ある程度予想されていたことではあったが、エリザベス二世の戴冠式の催されたこの年、BBC日本語部は渡英してくる日本著名人の訪問ラッシュに見舞われることになった。そして、その訪問ラッシュがいっきに激しさの度合いを増しはじめたのは皇太子の訪英前後からだった。まるで「英国詣で」をすることが一流文化人や一流政治家になるために課せられた必須の通過儀礼かなにかであるかのように、日本各界の名士らが続々と渡英してきはじめたのだった。もちろん、それら著名人らに、どうせ渡英するなら女王の戴冠式の催される前後の時期に合わせてという思いがあったこともそんな事態になった原因のひとつだった。
一群の訪英者のリストの中にはNHK番組のレギュラーとしても知られた藤浦洸、同じくNHKの「歌のおばさん」として名を馳せた松田トシ、柔道家の小泉軍司、作家の火野葦平、小糸のぶ、森田たま、日本コロンビア社長の秦米造、同じく財界人の大倉喜七郎、陶芸家の浜田庄司、民俗学者の柳宗悦といったような名前も見かけられた。いうまでもないことだが、この時代に一般の日本人が渡英するのは、経済的な問題をはじめとする諸々の制約上ほとんど不可能なことだったから、それら訪英者らは皆なんらかのかたちで特権層に属するか、そうでなくても特別なバックグラウンドをもつ人々ばかりであった。
英語学の権威として数々の英語辞書類の編纂に携わり、やがて東京外国語大学の学長をも務めた日本の語学界の重鎮小川芳男もその頃にイギリス入りした一人だった。小川芳男はイタリアのローマ、スイスのベルン、フランスのパリを経て、4月26日早朝に空路ロンドン入りすると、すぐその足でBBC日本語部を訪ねた。この時すでに東京外大の助教授という要職にあった小川芳男は、名目的には英語学関係の専門研究やそれに必要な情報収集をおこなうための逗留ということで渡英してきたのではあった。だが、戦後の復興期のことで、まだ容易には日本人研究者を受け入れることのできない当時のイギリスの社会事情、さらにはイギリスに劣らず厳しい日本側の経済状況などもあって、英国での小川の落ち着き先や滞在費その他にはおのずから様々な制限が伴わざるをえなかった。
したがって、日本国内ではそれなりに名の知れていた小川芳男といえども、かなり長期にわたるものではあったにしろ、事実上は英国視察旅行とも観光旅行ともつかぬ中途半端な状況下での訪英に甘んじざるをえなかった。より率直に言えば、とにかくイギリスに渡りさえすれば、なんとか自分の専門研究につながる身の落ち着き先やそのための糸口を探し出すことができるだろうから、まずは行動あるのみだというのが、その時の小川芳男のいつわらぬ心境なのでもあった。
なんのコネもなく単身中国大陸に渡った頃の自分の思いと重ね合わせ、そんな小川芳男の心情をすぐさま察知した石田は、当面自分の部屋に身をおきながらロンドンでの生活をはじめたらどうかともちかけた。その日の午後には松本俊一駐英大使に同行し、皇太子出迎えのためサウサンプトンへと出立しなければならなかったので、石田は手短にその状況を伝え、小川に即刻決断のほどを促した。小川のほうもそんな石田の好意的な申し出を渡りに舟と受け入れ、ロンドン到着のその日のうちに小川は石田の借りている部屋に転がり込むことになった。そして、ロンドンでの生活に慣れ、安くて住みやすい部屋が見つかるまでの間、小川は石田のところで寝起きするようになった。
ロンドンをはじめとするイギリスの生活事情全般に深く通じ、様々な情報や人脈をもち、しかも実践的な英語やフランス語・ロシア語などを自在に操る石田の存在は、頼れるもののほとんどいなかったその折の小川にしてみれば願ってもないことであった。石田は専門的な研究者としての体系的な学問を積んでいるわけでもなかったし、その学歴も旧制高校卒業で名門大学卒の小川には遠く及ぶべくもなかったけれど、庶民の間で用いられる活きた英語やイギリス人の生活風習に深い関心があるという意味からしても、二人はずいぶんとウマが合った。
ロンドンの生活にいくらか慣れた小川が自分の下宿先を別に定めそこで暮らすようになってからも、石田はなにかと彼の世話をやき、ことあるごとにその便宜をはかってやるようこころがけた。優れた研究者として日本ではすでにひとかどの地位を得ていたにもかかわらず、小川の向学心や好奇心はなおも旺盛そのもので、けっして尽きるところを知らなかった。その博覧強記ぶりも、「さすがは学者だけのことはある」と石田を唸らせるに十分なものであった。
そして、そんな小川が、ロンドンの各所をめぐり歩いて庶民の使う英語を調べようとしたり、ウエールズやスコットランド地方をはじめとするイギリス各地の英語を実地に体験学習しようとした時などは、石田の労を厭わぬ協力やアドヴァイスがこのうえない助けともなった。小川がタイムズ紙の本社を訪ねてエドモンド・ブランデンに面会したり、オックスフォードに出向いてスパルディンに対面したりしたときも、石田は自らの人脈を通じその調整役を務めたりもした。それが縁となって、石田は帰国してからもずっと小川芳男と隠れた親交を続け、小川が東京外国語大学の高名な教授となり、さらには同大学の学長となったあとも、陰にあってその仕事の一部をそれとなく手伝ったりもする間柄だった。
ロンドン入りしてまだ日も浅い5月14日のこと、小川芳男はBBC日本語放送にゲストとして出演し、「ロンドンの演説広場」という当該番組のなかでハイド・パークのスピーカーズ・コーナーを実際に訪ねた時の感想などを驚きをもって語ったりした。また、それから3ヶ月ほどのちの8月6日と8月17日には、小川は再びBBC日本語放送に登場し、「本場の英会話」というテーマで英国社会の各階層における英語会話の実状などについて興味深い解説やレポートなどをおこなった。小川がそんな番組にゲスト出演し日本の聴衆を魅了した陰に、石田達夫のひとかたならぬサポートがあったことはいうまでもない。
イギリス滞在期の2人には人知れぬそんな関係があったため、石田は心からの親しみをこめて小川芳男のことをのちのちまで「小川君」と「君」づけで呼んでいた。石田が他界する3年ほど前のことであったが、信州穂高町有明の石田邸を訪ね、なにかと話し込んでいた際に、たまたま小川芳男のことが話題にのぼったことがあった。その時のこと、石田翁は、「外大の学長も務めた小川君は、たしか仕事かなにかで南アメリカに渡ったんだよね。そして、その旅先で客死してしまったんだよ。残念なことにね……」と、なにやら感慨深げに呟きながら椅子から立ち上がった。そして書架から4、500ページほどの厚さの本を1冊取り出してきたのだった。1967年に大学書林から刊行されたその本のタイトルは「巷の英語」というもので、その筆者は小川芳男となっていた。
随所にエリザベス女王の戴冠式当時のイギリス社会の様子などについても述べられているこの「巷の英語(English on the Street)」は、知るぞ知る名著であった。その時もあらためてページをめくらせてもらったのだが、隠語を含めた庶民の言葉を細大漏らさず扱ったその内容といい、その魅力的な書き口といい、実に柔軟そのもので、外大学長も務めた高名な英語学者の執筆した本だとは想像しがたいくらいであった。むろん、石田が取り出してきた1冊は著者の小川芳男がのちに彼に贈呈したもので、その労作が、ロンドンでの彼ら2人の出逢いとそれに続く親交、さらにはその間の一連の出来事を通して得られた諸々の知識をベースにして生まれたことを証し物語る貴重な存在にほかならなかった。
「巷の英語」の363ページには小川がロンドンに到着したばかりの頃の想い出の一端が述べられている。皇太子がウオータールー駅に到着するのを知った小川は同駅まで皇太子を迎えに出向いた。そして、サウス・ハンプトンで皇太子が読み上げた英語の声明文に、英語の一教師という立場柄のこともあって、ひとからならぬ関心を抱きながらじっくりと耳を傾けた。そして、そんな小川もまた、18歳という年齢からすると実に立派なものだとしかいいようのない皇太子の英語の発音に聴き入りながら、皇太子に対するバイニング女史の英語教育の見事さを想った。
その時の様子について、小川は、「2、3の新聞が声が小さいなどと書いていたが、前夜マージャンを楽しまれたあと、2、3回の下読みをしただけであれ以上のスピーチを期待することは、期待するほうが無理であろう」と書いてもいる。著書中ではそのことについてはいっさい触れられていないが、小川はロンドンに到着したばかりだったわけだから、皇太子のウオータールー到着情報を含めた皇太子一行の動向について、彼がサウサンプトンまでお迎えに出向いた石田達夫や藤倉修一らから細かな情報を得ていたことは想像に難くない。
小川はまた、「私はロンドンに到着以来、年輩の人や若い人といろいろ話をしてみたが、女王に対する若い人の感じなど、実に人間的な愛情にあふれたものだと感じた。よく、日本で皇室は家長だと言われていたが、なんとなくへだたりを感じないわけにはいかなかった。ところがこの国では、このへだたりは全く感じられない。そしてエリザベス2世に対する国民の感情は、女王の立派な人格と態度に対するものなのである。尊敬と愛情をかねたものだが、愛情のほうが強い感じを受ける」とも述べている。それがその際の彼の新鮮かつ率直な思いでもあったのだろう。
さらに小川は、非公式のときには、王子や王女といったロイヤルファミリーらが裏口から自由かつ気軽に買物に出かけ、市民と自然に接してる様子などについても感動をこめて述べ語り、戴冠式というものについても、「戴冠式というのは、いうまでもなく王冠を戴くとともに人民への奉仕・義務・愛を女王が誓う式である」と記すことを忘れなかった。イギリスに到着したばかりの小川が、英国民とロイヤルファミリーとの関係にあらためて驚きの目を見張ったときの様子を、それらの一文からは偲ぶことができる。
その本をあらためて手にした老翁は、いささか悪戯っぽい表情を見せながら、「あの頃はよく小川君を案内していろんなところに行ったんだけどね。当時の彼の正統過ぎる英語は、文字通りの意味でのイギリスの巷にあってはあんまり通じなくってさ……。でもねえ、そんな小川君がこうして『巷の英語』っていうとても洒落ていてしかも立派な内容の本を書き残したんだから、この世の中ってつくづく面白いもんだと思うんだよね」と懐かしそうに語ってくれたものだった。
5月になるとNHK番組でも日本国民に広く知られていた徳川夢声がイギリス入りした。そもそもNHKが名物アナウンサー藤倉修一をBBC日本語部に派遣したのは、エリザベス女王の戴冠式の日本向け実況放送を彼におこなわせるためであった。藤倉はNHKでの長年の経験と独特の感性や話術を活かしBBC日本語放送でさまざまな番組を担当したが、あくまでそれらは彼に期待されていた本来の仕事ではなかった。そして、そんな藤倉修一に対抗するかたちで、戴冠式の実況放送のためにTBSから送り込まれたのがほかならぬ徳川夢声なのだった。いうなれば、エリザベス女王の戴冠式の場を巌流島がわりにして、藤倉武蔵と徳川小次郎の一大決闘がおこなわれようとしているわけであった。
だがそうはいってみても、日本では藤倉修一が司会を務める番組に徳川夢声はしょっちゅう登場もしていたので、当然2人はごく親しい仲でもあった。そもそも藤倉が前年の12月末に日本を発つ前、送別会で挨拶をしてくれたのはほかならぬ徳川夢声であった。だから、夢声夫妻がロンドンに到着したとき藤倉は空港まで出迎えに行った。さらに皮肉なことには、徳川夢声夫妻の滞在したホテルが藤倉の下宿先のすぐそばという偶然までが生じもした。だから、英国版巌流島の決闘を前にしても、相手に対するライバル心はさっぱり高まりをみせなかった。
それどころか、決戦を前にしたある日、徳川小次郎が藤倉武蔵の本拠地であるBBC日本語部を訪ね、BBC日本語放送に生出演するという珍妙な事態もおこったりしていたから、見せかけだけの馴れ合い決闘に発展しかねない有様だった。短期間とはいえ、ロンドンのホテル住まいが性に合わず不自由さを覚えたらしい夢声老は、ホテルでの朝食を終えるとすぐに藤倉の下宿部屋にやってきた。まるで夢声は藤倉の下宿部屋をNHKのサロンかなにかと勘違いしているのではないかと思われるほどで、藤倉がはるばる東京から持参してきた貴重な日本茶を遠慮なく飲みあさり、これまた貴重な茶菓子を次々とむさぼる有様だった。しかも、藤倉がBBC日本語部に出勤しているあいだ、夢声老は来るべき戴冠式の日の決闘相手の机を勝手に使って自らの仕事を進め、決闘に備えて秘策を練る始末でもあった。
徳川夢声も当時デンスケと呼ばれた録音機を持参してきてはいたが、録音機そのもの性能の悪さにくわえ機械操作に不慣れな夢声老のミスなどもあったりして、TBSのそのデンスケはよく故障を起こした。そんな時、夢声老は、「すまんのですが、お宅のやつをちょっとばかり拝借させてもらいますわ」といって、NHKのデンスケを何度も借用したのだった。その表情にはほんとうにすまなく思っている様子などすこしも感じられなかったが、どうしても藤倉はその要請を断ることができなかった。TBS派遣の夢声が故障した自らのデンスケのかわりにNHKのデンスケを借用するということは、巌流島の決闘を前にして鍛錬中の徳川小次郎が、自分の刀の切れ味が悪いのでちゃっかり相手の藤倉武蔵の刀を借りて鍛錬を続けるようなものなのだったが、夢声老にはまったくもって悪びれたところは感じられないのだった。
石田達夫自身はもちろんそれまで徳川夢声との直接の面識はなかったのだが、藤倉修一の紹介によって夢声夫妻とも親しく交流することができるようになった。トーキー映画が普及する以前の無声映画の時代においては高名な活動弁士として一世を風靡し、また、その後も各種ラジオ番組にレギュラーとして出演、日本国内では誰ひとりとして知らない人のいないほどに活躍をしてきたこの稀代の人物と、母国から遠く離れたロンドンの地で回り逢うことになろうとは、それこそ奇縁としかいいようのない出来事であった。

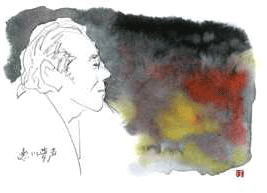
 RSS
RSS