その日石田が講演をすることになっていたのはユニバーシティ・カレッジだった。マートン校やベイリオル校と並び英国最古の歴史と伝統を誇るこのカレッジは、カーファックス塔の立つ大きな十字路を曲らずそのまま400メートルほど直進したところに位置していた。予定していた時刻よりもかなり早目に目的地周辺に着いたので、時間の調整かたがた、石田は大通りをはさんでユニバーシティ・カレッジの北側斜向かいのところにあるセント・メアリー教会に立ち寄ってみることにした。13世紀に建てられたこの教会の中央には高さ62メートル、127段の尖塔があり、威容を誇るその塔上にのぼると、オックスフォードの街並みを鳥瞰図そのままに一望できることで有名だった。
以前にも一度足を運んだことのあるそのセント・メアリー教会の塔上に立ち眼下の街並みを眺めやっているうちに、奇妙な感慨がその胸を覆いはじめた。かつて一度この塔上に立った時は、この学問の府とはまるで無縁な通りすがりのひとりの旅人の身にすぎなかった。しかし、今度はその時とは違っていた。二度目のこの時は、たとえごく限られた時間内での他愛もない中身の講演にすぎないにしろ、ともかくもオックスフォードの学生たちとの間に縁が生じてこの町にやってきたのだった。
まだ重たい晩冬の大気のもとにあって、多数のカレッジやその関係諸施設のひしめくオックスフォードの街並みはどこか沈み込み押し黙っているような感じであった。そして、そのことがかえってオックスフォードという学問の府を威厳ある存在として演出しているかのようにも思われた。そんな光景を眺めやる石田の脳裏を、なぜか遠い日々の想い出がはや送りのフイルムのコマのように慌しく駆けめぐった。久々に甦る一連の回想シーンの中には博多の芸人町の貧乏長屋の一隅に寝起きする幼い日のおのれの姿もあった。その頃の幼い自分が曲がりなりにも成長を遂げ、ユニバーシティ・カレッジでの講演を前にしてオックスフォードの街並みを見下ろしているのは、ある意味で奇跡以外のなにものでもないように思われてならなかった。あらかじめ自然体でことに臨もうときめていた彼に特別な緊張などはなかったが、それでも講演を前にしてその胸中にそんな感慨が湧き上がってきたのだった。
ユニバーシティ・カレッジのゲート・タワーの内側通路脇には、どういうわけかイギリスで最も人気のない国王だったとかいうジェームズ2世の彫像が置かれていた。石田はそのそばを通り抜け奥のほうへと歩を運んだ。あらかじめ指定されていたカレッジの中の講演会場へと向かう石の階段は驚くほどに擦り減っていた。オックスフォードのカレッジ群の中でも最古の建物のひとつと伝えられるだけのことはあって、その中に漂う独特の雰囲気には底知れぬ存在感が潜み息づいているようでもあった。擦り減った石段や石の手擦りのありさまを通して、700年をはるかに超える歳月のなかにおいてその階段を昇降し、やがて大きな世界へと飛翔していった数知れぬ学徒らの姿を想い描いた。
講演の会場に当てられたのは建物の最上階にある講義室のひとつだった。ほどなくその部屋を探し当て、温かく自分を迎え入れてくれた責任者の学生に会ってまずは簡単な打ち合わせをすませた石田は、おもむろに尋ねた。
「お手洗いはどちらでしょう?」
軽い緊張感といささかの冷え込みのために尿意をもよおしたからだった。
「そうですねえ、お手洗いは一階にあります。でも……」
「でも……?、なにか不都合でもあるんでしょうか?」
「いいえ、そうではありません。一階までわざわざお降りになるのもご面倒でしょうから、もしも小用のほうでしたら……」
そこまでいうと相手は石田のほうを見ながら悪戯っぽい笑みを浮かべた。
「ええ、もちろん、簡単にすませられるほうなんですが……」
「それじゃですね、この階の奥のほうにいらっしゃると、いまはほとんど使われていない古いシンクがあります。もちろん、水はちゃんと出ますからそこをお使いください」
なんとも意外な返事に呆気にとられる石田に向かってその学生はさらに付け加えた。
「我々学生もそうしていますから、どうぞご遠慮なく!」
「じゃその古いシンクはもうほとんど使われていなんじゃなくって、いまも大いに使われているわけなんですね!……では僕もこれから活用させてもらうことにします」
「ははははは……」
すぐに状況を悟った石田の切り返しに相手も一瞬笑い声をあげた。
そのあとすぐに問題のシンクのところへと足を運んだ石田は、水栓をひねってジャージャーと水を流しながら用足しをすませた。威厳に満ち伝統に彩られたオックスフォードのカレッジ学生らの柔軟このうえない対処ぶりに、石田はすくなからず感動を覚えた。おそらくはそのシンクの使い方もまたカレッジの伝統のひとつになっていたのであろうが、変に考え方によってはなんとも見上げたものでもあった。
講演会場では学生を主体とした40人ほどの聴衆が石田の登場を待っていた。司会担当の学生によって、石田の経歴やその日講師としてユニバーシティ・カレッジに招待した経緯など予備知識として必要な事柄が一通り紹介され終えたあと、拍手に促されて彼は壇上にのぼった。パディントンからオックスフォードへと向かう列車の中で考え出したアイス・ブレーカ、すなわち、その場の雰囲気を和らげるための講演冒頭の軽いジョークを、咄嗟に彼はほかのものに切り換えることにした。むろん、それは先刻の想いもよらぬ体験のゆえであった。
「東洋の野蛮国日本からやってきたイエロー・モンキーは、この壇上にのぼる直前、いささか緊張を覚えましたので、この階の奥のシンクにおいてコンディションを整えなおしてまいりました。まさかそんなシンクでの風変わりな儀式が、この歴史と伝統と栄光に満ちみちたオックスフォード・ユニバーシティ・カレッジにおいて私がおこなう記念すべき最初の務めになるだろうとは、夢にもおもってもおりませんでした」
石田がそこまで言いおえると、会場がどっと湧いた。そこで彼はさらにたたみかけた。
「ただ幸いなことに、その立派な儀式を通しまして私はこのカレッジで学ぶ皆様方の仲間入りをすることができたわけであります。皆様方のその驚くべき柔軟さこそが世界に名だたるイギリスの叡智の根源なのであり、イギリスの栄光の秘密であったのだと、今日初めて私は明確に悟ったのであります」
聴衆からは笑い声が漏れ、そのあと会場は大きな拍手に包まれた。即興のアイス・ブレーカーの効力のほどは絶大であった。
「このつたない講演において、私は皆様方から戦前の日本と戦後の日本の状況について思うところを述べるようにとのご依頼をうけました。戦前、私の仲間、イエロー・モンキー一族の棲むモンキー・ランドは、その一族の纏め役を昔から世襲してきた貴種ザルの威光をずる賢く利用した柄の悪い取り巻きの将軍ボスザルや政治屋ボスザルどもによって支配されてきました。彼らによって、イエロー・モンキー魂の美学とかいう非現実的な精神論を巧みに吹き込み煽りたてられた私たちの一族は、浮かれそして調子に乗って他種族の棲む周辺のモンキー・ランドを荒しまわりました。ところが、やがてホワイト・ゴリラ族を中心とする異種族の猛反撃をこうむるところとなり、新型ゴリラ爆弾を二発も落とされて降伏のやむなきにいたりました。それからほどなく、大きなパイプをくわえたホワイト・ゴリラの大ボスが郎党ゴリラを引き連れてやってきて、有無をいわさずボスザルならぬボスゴリラの座に君臨するようになりました。ただ、困ったことに、そのホワイト・ゴリラ一族は皆様の一族のご親族筋にあたってもいるようなのです」
悪戯っぽい表情を浮かべながらそう話を続けたあと一瞬の間をおくと、すかさず会場の一隅から誰かの声があがった。
「戦争のあと我々一族はホワイト・チンパンジーに、そしてあなたがた一族はイエロー・チンパンジーに進化したんですよ!……チンパンジーのほうがゴリラよりちょっとだけは知性的ですからね!、まあ人間には少々劣るかもしれませんが……」
「では、いまからは一頭のイエロー・チンパンジーとしてホワイト・チンパンジーの皆様に向かって話をさせていただくことにします。人間ではないっていうことになりますと、お互いちょっとだけ気が楽にはなりますよね」
そう石田が応じると、また会場に笑い声が響いた。講演者の石田と聴衆の学生らとの間に阿吽の呼吸が生じはじめたのはもはや疑うべくもないことだった。
石田は自分の生まれや育ちをはじめとする様々な体験を交えながら、まず、戦前の日本の文化や政治的あるいは社会的な状況について善悪両面から率直な意見を述べた。そしてそれに続いて、自らは上海にいたので戦時中の軍国主義下の日本国内の実状にはいまひとつ疎いところがあると断ったうえで、当時の日本国民の生活状況や心理状況、さらには沖縄戦の悲劇や米軍による都市部の無差別爆撃、原爆投下による広島や長崎の悲惨このうえない状況などについて、正直な感想を述べた。また、当時の日本軍部の指導下で起ったアジア各地での残虐な行為については、それらの事実を知らされずにいた自分を含む一般日本国民の愚かさを素直に認めるとともに、国民の一人としてその非を詫びた。
そしてそのあとで、マッカーサー指揮下の米軍中心の進駐軍によって支配統治されるようになった戦後の日本社会の実態について、思うところをすこしずつ話しはじめた。だが、戦後の実情についての話になると、石田の口調はすくなからず慎重な響きを帯びるようになった。数こそ少なかったものの当時の日本にはアメリカ軍と戦線を共にし協力関係にあったイギリス軍も進駐していたし、また、彼自身マッカーサー司令部から特別な出国許可を得てイギリスにやってきていたわけだから、無意識のうちにも迂闊な発言を控えるように注意せざるをえなかった。
すでに新憲法は公布されていたものの、まだ独立国家としては承認されていない被占領国の人間であるがゆえのかなしさでもあった。しかもBBCという世界に広く知られる放送局の一員としての発言ということになると、そのなかに進駐軍批判めいた文言が含まれていて、なんらかのルートでそれがマッカーサー司令部に伝わったような場合、召還などの憂き目にあわないともかぎらなかった。
ところが、そんな石田の歯切れの悪さを察知した学生の一人が会場の皆の気持ちを代弁するというかたちで、一言彼に注文まじりの声援を送ってきたのだった。
「石田さん、ここはイギリスです。日本でもアメリカでもありません。だから、マッカーサーなどに遠慮せずにもっと自由に話してください!」
会場にはまた一斉に拍手が湧き起った。その激励によって気分がとても楽になった石田は、あらためて進駐軍占領下の戦後日本の実状について思いのたけを語りはじめた。もちろん、その話のなかには、連合国による占領行政によってかつての軍国主義から解放された日本国民一般の喜びの様子などもありはしたが、そのいっぽうで、随所に功罪相半ばするマッカーサー行政への痛烈な批判なども含まれていた。
石田がのびのびと戦後の日本について語りはじめたのを見極めた聴衆の学生らは、誰もが実に好意的な様子で熱心にその話に耳を傾け、それまでにもまして大きな拍手を送ってくれた。聴衆のなかでもひときわ目立って称賛の拍手を送ってくれた学生があったので、講演のあと石田はその学生のところへいってお礼の握手を差しのべた。すると、その学生は嬉しそうな顔で石田の手を握り返したあと、なんとも悪戯っぽい口調で一言付け加えた。
「石田さん、今日はどうもありがとうございました。実は私はアメリカ人留学生なのです。ホワイト・ゴリラにもチンパンジーなみの知性をそなえた者はいるわけなんです」
その意外な言葉を聞いて石田は苦笑せざるをえなかったのだが、こうしてともかくもオックスフォード・ユニバーシティ・カレッジでの講演は大成功のうちに終わったのだった。

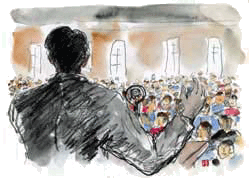
 RSS
RSS