秋が深まり冬の到来が間近になるとロンドンの街は霧の季節を迎えることになった。霧のロンドンといえばどこかロマンティックで、夜霧をついて恋人たちが忍び逢う姿を連想したくなる。実際、石田もそんな情景を心の奥に想い描きながらロンドンにやってきた。しかしながら、現実に彼が体験したロンドンの霧、なかでも深くて濃い夜の霧などはとてもそんな生易しいしろものではなかった。霧というともっぱら風に乗って山々や谷々に湧き昇る白くて涼やかな存在をイメージしがちだった石田は、ロンドンの霧の実態を知って正直なところ愕然とするばかりだった。どう贔屓目に見てもロンドンのそれにはロマンティックな雰囲気など感じられなかったからである。しかも厳冬期に入り人々が家々に篭りがちになるにつれて情況はますますひどくなっていった。
一口で言うとロンドンの霧はいわゆるスモッグそのものであった。車や各種工場などから吐き出される排ガスや煤煙に加え、大都市ロンドンの民家の屋根に立ち並ぶ無数のチムニー・ポッドからは終始煙が排出されもしていたから、風のない日など当時のロンドン上空に漂う煙の量ときたら想像を絶するものがあった。とくに冬場などはどの家庭も明々と暖炉の火を燃やし暖をとるのが常だったから、事態はいっそう深刻をきわめた。
寒い冬の日などにはその膨大な量の煤煙を構成する粒子の一つひとつを核とする微細な水滴が発生しそれらが中空を漂うことになる。それが有名なロンドンの霧の基本的な発生メカニズムであり、またほかならぬ濃霧の正体なのでもあった。石炭や薪の燃え盛る温かい暖炉の前でパイプをくゆらしあるいはお茶をすすりながら推理小説に読み耽るというのが、かつて石田が冬のイギリスに対して抱いた象徴的なイメージであったが、ことロンドンに関してはそういった光景は即刻不快なスモッグに繋がる行為なのであった。
霧のひどいシーズンなどには、直前まで見通しがきいていてもあっというまに濃霧が発生し、あたりはなにも見えなくなった。しかも日中でさえも手を伸ばすと指先が見えなくなってしまうほどの霧の深さだった。とくにひどい霧の日などはちょっと外出して戻っただけでワイシャツの襟が黒くなってしまったし、鼻の穴をハンカチでふくとやはりその白い布地が黒くなる始末だった。夜中などにふと目を覚まし、ベッドに横たわりながら明かりを点けて上を眺めやると、知らぬ間に窓の隙間などから流れ込んだスモッグのために天井が見えないといったようなことも起ったりした。信じられないことではあるが、当時のロンドンの濃霧、すなわちスモッグはそれほどに凄まじかった。
もっとも、その想像を絶する濃い霧のゆえに面白い光景を目にすることもあった。霧の深い夜など車掌らがバスを誘導する時などは懐中電灯ではなく松明が用いられていたのだが、何本もの松明が霧闇の中で揺れる有様はどこか幻想的で不思議なほどに美しかった。バスの誘導にわざわざ松明が用いられたのにはそれなりの理由があった。懐中電灯を用いた場合だと光が霧の中で散乱しボーッと輝くだけなのだが、松明だと、光輝部分も大きくしかも霧の中でも透過力のある赤色光が発せられるうえに炎の周囲に熱対流が生じて大気が揺れ動くから、運転手にも車掌の送る合図が認識しやすいというわけなのだった。
当時はまだスモッグという言葉こそ耳にすることはなかったが、まさにスモッグそのものだったロンドンの夜霧は、その言葉から連想させられるほどにロマンティックなものでないことだけは確かだった。しかしながら、そんなロンドンの冬の夜、通いつけのパブではお客の談笑や議義はいちだんと弾んだ。パブに出入りしはじめた頃のちょっとした緊張感やそれにともなうどこか不自然な身振舞いはすっかり影を潜め、石田は自分が日本人であることなどとくに意識にかけもせずごく自然にお店の人々や他のお客らとつきあえるようになった。
ロンドンではじめて迎えるクリスマス・イヴの夜、石田はイースト・エンドのパブに出向き、お店に集まってくる様々な国の人々とクラスを交し合いながら歓談を楽しんだ。あれこれと話が盛り上がり、ほどよくお酒もまわって誰の口からともなくクリスマス・ソングが飛び出しもするようになった頃、イギリス人と思われる一人の酔っ払いが石田の隣にすわり、他のお客たちにも聞こえるような大声で不意に話しかけてきた。
「メリー・クリスマス!……クリスマスはいいねえ、この夜だけはどんな民族出身の連中とも偏見なく楽しく一緒に過ごすことにしてるんだ!……ただなあ、それでも我慢できねぇーのはなあ、日本人とイタリア人なんだよなあ!」
なんとも矛盾に満ちたその言葉を耳にして、さしもの石田も返事に窮した。石田が日本人であることを知っているマスターやお客の一部はニヤニヤしながらウインクを送ったり、悪戯っぽく肩をすくめてみせたりした。
176センチと当時の日本人としては長身かつ大柄で、しかも流暢な英語を話し文化的なセンスもそなえもつ石田を、相手の男は日本人だとは思っていなかったのだった。背が小さくて小柄で出っ歯、そして異様に黄色い肌の色をしていて片言の英語を話すというのが、どうやらその酔っ払いの日本人観のようだった。せっかく盛り上がったその場の雰囲気を台無しにするわけにもいかないので、石田は適当に相槌を打ちながら無難にその場を凌き通した。
その冬にはやはり通いつけのパブでいまひとつちょっとした面白い出来事に遭遇した。年が明けた1950年1月の夜のこと、石田はBBC日本語部同僚の山本二三一とブッシュ・ハウス近くのパブで会い、仕事の打ち合わせがてら談笑に耽っていた。ちょっとしたBBC内での出来事に関する批評やイギリス人の国民性についての風刺、さらには社会情況がらみのいくらか批判じみた議論へと話が進展していったので、二人は英語での会話を日本語での会話に切換えた。日本語の会話だとBBC関係者を含むかもしれない周囲の客人たちに漏れ聞かれてたとしてもなにを話しているかわからないだろうから、そのほうが安全だと考えたのだった。
すっかりリラックスした気分になり調子にのった二人は、そつなく仕事をこなすための知恵や日本文化と英国文化の相違点、日英間の社会通念の各種ギャップなどについて、善悪両面からかなり率直な批評や議論を交わし続けた。そうこうするうちに喫煙したくなった二人はどちらからともなく煙草を取り出しはしたものの、生憎二人ともライターやマッチは持ち合わせていないことに気がついた。たまたまテーブルにも備えつけのライターもマッチもなかったので、お客の誰からか煙草の火を借ることにしようと日本語で話し合いながらそれとなく周囲のお客を見回した。
ちょうどその時だった。すぐ近くにいた中年のイギリス人男性がすーっと立ち上がり、吸いかけの煙草を手にしながら二人のところにやってくると、にこやかに話しかけてきた。
「ケトウの火でよろしければどうぞ!」
なんとそれは流暢な日本語だったのだ。石田と山本は一瞬言葉を失い、さらにはおのれの耳を疑いながら相手の顔をまじまじと見つめた。しかも彼ら二人が「ケトウ」というその意外な言葉の意味を理解するにはさらに時間が必要だった。しばらくして「ケトウ」が「毛唐」のことだと納得した石田と山本は、目を白黒させながらまたもや絶句する有様だった。
「毛唐」という言葉は日本人が欧米人を差別して呼ぶときの特別な表現用語だから、よほどの日本語通でないかぎりそんな言い回しなどできるはずがなかった。もちろん、相手はユーモアを込め二人を驚かすつもりであえて「毛唐の火」という表現を用いたのだった。そうだとすれば、その男性が石田らの会話を一部始終聴き取りその内容を理解していることは明白だった。もはやジタバタしても仕方がないと悟った二人は、素直に相手の好意を受け入れることにした。
「ええ、毛唐の火でも拝借できればありがたいです。なにしろ、我々はイエロー・モンキー、あるいはそれよりは多少増しなジャップなどという言葉で呼ばれる下等動物ですから……」
相手にうまく通じるかなと思いながらも石田がわざと日本語で応じると、その言葉を即座に理解した男は愉快そうな笑みを浮かべながらさらに言った。
「OK、では今夜から毛唐とイエロー・モンキーとは下等な者同士お互い友達になって仲良くすることにしましょう。ではその友好のしるしにこの毛唐の煙草の火をどうぞ!」
「どうもありがとう!……もし、毛唐の雄とイエロー・モンキーの雌が結婚でもして子供が生まれたら、ホワイト・ゴリラかなんかが生まれてくるんでしょうかね?」
そう切り返す石田の脳裏を一瞬、イギリス人と結婚したミサの姿がよぎっていった。相手の男はライターも所持している様子だったが、ここは友好の契りの儀式を兼ねてということで、石田はわざわざ自分の煙草の先を男の煙草の先端に近づけ火を移してもらった。そして二人はそのあと固い握手を交し合った。火を貸してくれたその相手は、戦前まで日本に長らく滞在し日本の大学で教鞭を執っていたこともある人物だった。まさかそんなところにそれほどまでに日本語に堪能なイギリス人がいるなどとは想像だにしていなかったので、石田と山本の驚きはひとしおだった。
かつて上海で石田ランゲージ・アカデミーを経営し自らも語学指導に携わっていた経験などを通じ、彼は、外国人が日本語を学ぶ場合その国民性に応じた一般的な傾向や特徴があることに気がついていた。むろん例外はあるものの、おおまかに見ると中国人はある程度まではすぐに日本語をおぼえるが何年経っても誤りを正そうとせず、また忘れてしまうのも早いように思われた。それに対して、ドイツ人やイギリス人はなかなか日本語をおぼえてはくれないが、いったんおぼえると、実に正確でしかも日本語についての知識も想像以上に深くて詳しいという特徴があった。この時に出合った人物も、そしてBBCのジョン・モリスもトレバー・レゲットもカニンガムもデイヴィスもみなその点では共通していた。
それにしても、時と場所と情況をわきまえたうえで、しかもユーモアと風刺を込めて「毛唐」という言葉を見事に使いこなすイギリス人とロンドンのパブで出逢い日本語での想わぬ会話を交わすことになった奇跡に、石田はすくなからず感動を覚えるのだった。
「まさに、壁に耳あり障子に目ありですね。でも、日本から遠く離れたこのロンドンにやってきてまでその諺そのままの事態に遭遇するなんて考えてもみませんでしたよ」
自分たちの話を近くで聞いていてどんな印象をもったのだろうといささか気にとめながら、石田はくだんの男にそう語りかけてみた。すると相手は悪戯っぽい表情を見せながら当意即妙としか言いようのない答えを返してきたのだった。
「私はすっかりお酒が回ってしまっていますから、耳に壁あり、目に障子ありの状態ですよ。だから、なんにも聞こえてなんかいませんし見えてもいません。そう……、なんていいましたっけね……、あっ、そうそう、いわゆる、見ざる、言わざる、聞かざるの状態ですね……」
見事な日本語を駆使してのそのウイットに富んだおとぼけぶりに、石田と山本はただただ脱帽するばかりであった。

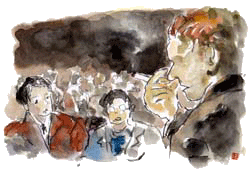
 RSS
RSS