「ミスター・イシダ……、あなたにもラジオ・ドラマに出演してもらうことにしますよ!、もちろん、ほかのBBC日本語部スタッフにもできるかぎりは協力してもらうことになりますけどね」
日本語部に勤務するようになってしばらくたった頃、レゲット部長から突然そう要請された石田は一瞬その耳を疑った。
「俳優の経験も声優の経験もまったくないんですけれど……。中国の青島にいた頃、伊勢志摩から海女を連れてきておこなった『真珠取り実演ショウ』なるものへの客の呼び込みくらいならやったことありますけどね」
「それだけ経験があれば十分でしょう。もともとみんな素人ですからね。これまでもBBCは各部局のスタッフに登場してもらいながら自前のラジオ・ドラマの制作を試みてはきたんですが、今後は本格的に取り組んでいこうということになりました。BBC本部も海外放送部門のボスのジョン・モリスもこの企画方針には大いに賛成しています。そんなわけですから、ドラマの内容が日本に関わるものであるような場合はとくに、その内容の検討や脚本の制作、演出を含めてミスター・イシダには大いに活躍してもらおうと期待しているんですよ」
「えっ?、じゃ、ドラマのシナリオ作成も、構成と演出も、そして声優としての出演もみんなBBCのスタッフだけでやるというわけですか!」
「もちろんです。当面シナリオは既に存在しているものを使うことになるでしょうが、日本語版の翻訳脚本は自分たちでつくらなければなりません。また日本語部が独自に日本の国を扱ったシナリオを作成してもかまいません。BBC本部局員を含めた他部局のスタッフらとも協力し合うことになってますから」
「面白そうなお話ですが、実際にうまくいくんでしょうか?」
「ちゃんと、番組制作全体を統括指揮するディレクターも配されることになっていますから大丈夫だと思いますよ」
「それにしましても、僕なんかドラマのイロハは言うに及ばず、脚本の読み上げそのものからしてまったくの未経験者なんですから……」
「そこをなんとか成功させるのも、我がBBCの優秀なスタッフの腕の見せどころというわけなんですよ!……それに、どうせなら、先々は、それぞれのドラマにそくした装束を纏い、実際にプロの役者が舞台上で個々のキャラクターになりきってドラマを演じているのと同様の状況をつくろうと考えています。舞台がわりに公園かなにかを利用しましてね。そのほうが我々スタッフも楽しんで参加できますし、その様子を録音して放送すれば、単にマイクロフォンの前で台本を読むよりもずっと迫真力がありますからね。ただ、準備不足で最初からそうする訳にもいきませんから、ここ当分はブッシュハウスの放送スタディオ内において声の演技のみをやってもらうことにしますけれどね」
「なるほど、そういうことですか。よくわかりました。それならぜひともチャレンジさせていただこうと思います。まずはベストを尽すように心がけてはみますので……」
いきなりのことで、内心なんとも覚束ないことしきりではあったが、石田としては当面そう答えておくしかなかった。
BBC本部、ジョン・モリス・海外放送部門ジェネラル・マネージャー、さらにはレゲット日本語部長らのそんな意向をうけて、石田をはじめとする日本語部スタッフらもそんなドラマ放送の企画と制作に大真面目で臨まざるをえなくなった。不慣れなことゆえ、当然、最初はなにかと不手際や失敗も少なくなかったが、このユニークなドラマ放送はサード・プログラムとしてBBCに定着し好評を博すようになった。なかでも日本語部においては、石田が帰国したのちにも後任スタッフらによってその制作が継承発展させられていくことになり、やがて日本語部ドラマの最盛期を迎えるに至ったのだった。
石田がそんな放送ドラマに関わり始めた頃は、T. Sエリオットやシェークスピア原作のポエティカル・ドラマが取り上げられることが多かった。それらのポエティカル・ドラマの演出や構成になにかと携わるにあたって、すくなからず参考になったのが、ほかならぬ日本の歌舞伎の世界だった。博多の芸人町で生まれ育ち、母親が筑前琵琶の師匠だった縁で幼い頃から劇場に出入りし、当時の歌舞伎役者らからもずいぶんと可愛がられたこともある彼は、歌舞伎の演技の流れとか呼吸とかいったようなものを知らずしらずのうちに学び身につけていたのだった。
イギリスのポエティカル・ドラマ作品にあらためて接するうちに、石田は、日本の歌舞伎というものも、五・七調のリズムを基調にしたポエティカル・ドラマのひとつにほかならないと思うようになった。役者が興奮した状態に入り、興奮が絶頂に達して台詞が言えなくなるか台詞そのものが意味をなさなくなる直前に踊りがそれを受け、さらに長唄や謡曲、語りなどがそれを引き取る――歌舞伎のもつそんな構成や呼吸の特徴を想い浮かべながら、BBCでのポエティカル・ドラマにそれらを重ね用いることを考えついたりもした。
石田が出演したBBCのラジオ・ドラマのひとつに「今だから話せる」というタイトルのドラマがあった。第二次世界大戦中のビルマ戦線の模様やその背景を回想録風に描き仕立てたドキュメンタリー風のドラマで、様々な階層の人物が登場し、敗戦前には言えなかった政治の舞台裏や庶民の想いなどを本音で語るというもので、石田は日本人役を一人で何役もやらされることになった。しかも、日本軍の軍医、日本軍兵士、日本の農民、さらには総理大臣など、様々な階層の人物をもっともらしく演じなければならなくなった。当然、それぞれの人物に応じて声色や語調、言葉遣いなどを変える必要があったので結構苦労も多かったが、その反面、いろいろな試行錯誤をおこないながらドラマの音声収録の醍醐味を存分に楽しむこともできた。
日本が苦境に立たされた大戦末期の総理大臣役を演じるにあたっては、わざわざ口の中に綿を押し込み咽の奥からそれらしい老いた声が発せられるように工夫したりする一幕もあった。戦時中に対連合軍宣伝放送をおこなった東京ローズの役をも演じるようにと要請されたが、男の石田が女性のローズの声色をしかも英語で真似るのは至難の業とあって、さすがにそればかりは辞退せざるをえなかった。東京ローズとは「アイバ戸栗ダキノ」というシカゴ生まれの日系二世で、カリフォルニア大学卒の美貌の女性だった。戦後、宣伝放送の責任を問われた彼女は米国で訴追収監され、その後半生は悲惨なものとなった。
このドラマにおいてはアメリカ人の日系二世男性の役もやってほしいと要請されたが、日系二世特有の言葉の抑揚を真似るのは難しいと思ったので、同じBBCに勤務するカナダ人の友人を引っ張り出し自分の代役を務めてもらった。幸いにもことは順調に運び、その放送ドラマはそれなりの仕上がりをみせたのだった。それに味をしめたらしい当の友人は、その後、キャサリーン・へップバーン主演の映画「旅情」(Summer-time in Venice)にも通行人を演じるエキストラとして出演し、石田を驚かせたりもした。単に驚いただけならまだよかったのだが、せっかくその映画の名場面にひたっていたのに、突然その友人の姿がスクリーンに登場したためたちまち現実の世界に引き戻され、興醒めにも近いような妙な気分になってしまう有様だった。
日本の地震をテーマにしたドキュメンタリー・タッチのドラマにも出演させられた。石田が受け持つことになったのは、イギリス大使館に雇われている日本人雑役夫の役柄で、突然地震が起こったために大使館員らの子供たちを誘導し裏手の竹林に避難する場面を演じることになっていた。この時は、たまたま不慮の事態が重なってしまったため、リハーサル抜きでほぼぶっつけ本番の演技をしなければならなかった。石田が登場するところではキューとしてブルーのランプが点灯されることになっていたのだが、そのランプが見にくい位置にあったうえにうまく点灯してくれなかったため、すっかりタイミングがずれ込んでしまい、なんとも惨憺たる結果に終わってしまったのだった。
変ったところでは、「虚無僧」というタイトルの一種の心理劇などに登場したこともあった。この時にはイギリス人ディレクターのサブ役をも務め、ドラマ全体の監修にも携わった。長崎のあるお寺に住むイギリス人男性とその日本人妻にまつわるドラマで、その大筋は、毎夜どこからともなく現れる虚無僧の吹く尺八の音を耳にした日本人妻が、やがてなぜか発狂し、自ら首を吊って死んでしまうというものであった。むろん、日本人妻とその虚無僧とはかつて恋人同志であったという伏線のあるドラマだったが、日本人の石田からしてもなかなかの出来栄えに見える作品であった。
虚無僧は実際には登場せず、もの悲しいまでに澄みわたった尺八の音色のみが虚無僧の存在をイメージさせるという構成で、当時の日本の尺八の名手の演奏録音盤から尺八の音は借用された。この時に石田が演じることになったのは、寺に住むイギリス人とその妻の世話をする高齢の使用人の役柄だった。そして、シナリオに従うと、彼の演じる使用人が最後の場面近くにおいて自ら縊死した日本人妻の死体を発見することになっていた。
死体を発見した使用人は、「だんなさん、だんなさん、大変です!」と日本語で驚き叫びながらイギリス人の主人にその事態を知らせるということになっていたが、石田が何度演じてみても、大変そうな声の響きには聞こえなかった。本格的な声優の訓練などまったく受けていない彼には、どう頑張ってみてもさすがにそのように凄惨な場面に立たされた人物を演じることばなど無理なのであった。ただ、だからといって、石田の代わりになれるような日本人がいるわけでもなかったから、さすがのディレクターも頭を抱え、すっかり困り果ててしまったのだった。
だが、幸いなことに、その時スタッフの誰かが妙案を考え出した。恐怖の絶叫をあげることができるような女優を急遽呼び寄せ、ちょっとだけシナリオを変更して、石田の演じる使用人の男の妻という設定で登場してもらうことにする。そして、彼女に死体の第一発見者になってもらい、恐怖の叫びを一声発してもらうことにすればいい。イギリス人でも日本人でも悲鳴なら似たようなものだから、なんとかうまくいくだろうというのであった。
すぐに、ひとりの女優がスタディオに呼び寄せられ、再びドラマの続きが収録されることになった。その女優は問題の場面に差しかかると、真に迫った形相を見せながら、「ヒエエーッ!」という、この世のものとはおもえないほどの絶叫を発したのだった。演技とは信じられないほどのその迫力に圧倒され、思わずギョッとした石田は、間髪を入れず、「だんなさん、だんなさん、大変です!」という台詞を吐いた。その時ばかりは彼の台詞のトーンもなかなかリアルで、無事、ドラマの収録は完了となったのであった。

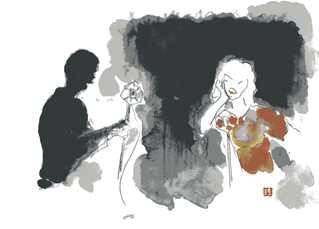
 RSS
RSS