ある奇人の生涯
「マセマティック放浪記」2002年12月25日
一年の終わりに
2002年も残りあと一週間ほどになってきました。とりとめもない手記であるにもかかわらず、この一年、「マセマティック放浪記」をご愛読くださった皆様方には心からお礼申し上げます。また、あわせて、よき新年をお迎えになられますように、心からお祈り申し上げる次第です。
ところで、来たる2003年の1月1日は水曜日です。そして、水曜日は私が筆を執るこの「マセマティック放浪記」の更新日にほかなりません。AICは年中無休が売り物のようですので、「マセマティック放浪記」は来年正月早々に新しい内容へと更新されることになります。縁起をかつぐわけではないのですが、ある意味でこれ以上のグッド・タイミングはないとも思われますので、来年の1月1日からはちょっとした新趣向にチャレンジしてみることにしました。
読者の皆さんにはご迷惑なことかもしれませんが、「ある奇人の生涯」という長編伝記実話小説を連載させてもらおうと考えています。いまのところ、一回につき平均十五枚程度の掲載を予定しているのですが、終了までにすくなくとも一年ほどはかかるのではないかと思います。ことによったら、それ以上の時間を要するかもしれません。横書きでの長編小説連載はどうなのだろうかという不安もありますし、段落や文章のリズムなどについてもいろいろと問題は多いのですが、いまやインターネット隆盛の時代とあれば、その潮流に乗って実験的に横書きでの小説掲載を試みてみるのも一興あることかもしれません。
ただし、もともとの原稿はいったん縦書きに打ち出してから、文体や文章のリズム、段落などの調整や手入れをしてありますので、お時間があり、かつ技術的に対応処理が可能な方は、テキスト部分だけをワードや一太郎に呼び込んで縦書きに変換し、段落などを通常の形式に直してお読みいただければ幸いです。筆者自身も一応校正はおこなうつもりではおりますが、勘違いやワープロ入力処理過程で起こるこまかなミスなどを完全に防ぐことはできません。またAIC編集サイドの人手不足などの事情もあって、通常出版物におけるような、編集部による十分な編集校正等の作業は望めませんので、ある程度の誤植や誤謬、不備などはお見逃し願うしかありません。
この伝記実話小説は、その題名からも想像がつきますように、昨年まで長野県穂高町の一隅に住んでいた石田達夫という稀代の奇人の生涯を描いたものです。昨年八月に他界したこの石田という人物については、マセマティック放浪記の中でもこれまで何度か書かせてもらったことがあります。「2000年04月26日・人生模様ジグソーパズル」、「2000年6月14日・ドラキュラ邸の宵」、「2001年04月25日・十三日の金曜日に」、「2002年04月03日〜2002年04月17日・ドラキュラ邸追想記(全3回)」などのバックナンバーをお読みくだされば、あらかじめおよその人物像は把握していだだけるのではないでしょうか。
小説の舞台は十数年前の信州穂高町に始まり、戦前の博多、東京、横浜、そして中国の天津、青島、大連、上海、さらには遠くエリザベス女王即位時前後の英国にまで及ぶことになります。登場人物も実に多様で、後半部においては若い時代の平成天皇をはじめとし、昭和史を飾った数々の有名人たちが実名で登場することにもなろうかと思います。まだそこまでは最終的な構想の詰めをおこなってはいないのですが、そのあと舞台は再び日本に戻り、一年前の穂高町で話が終わることになるでしょう。現段階でこんなことをいうのもどうかとは思うのですが、実録に基づく波瀾万丈の物語ですので、かならずや面白く読んでいただけるものと確信しております。
実を言うと、当初の予定ではこの伝記実話小説は、原稿用紙五百枚前後の長さに纏め、石田達夫翁の存命中に上梓するつもりでおりました。日本経済新聞社出版局の編集者との話し合いを通じて2001年までに同社から刊行してもらうように、ほぼ話もついていたのです。しかしながら、他の仕事で私が多忙をきわめたことのほか、多岐多様にわたる事実考証に多くの時間を要することなどもあって原稿の執筆が思うにまかせず、結局三分の一ほどを書き上げたところで足踏み状態になっていました。そして、そうこうしている間に石田達夫翁が他界してしまったのです。
亡き石田翁の霊を弔うためにもこの伝記小説をぜひ完成させなければならないと考えた私は、それまであった日経との話を振り出しにもどし、原稿枚数に制限を設けずにこの世紀の奇人の奇跡ともいうべき生涯の足跡を書き抜いてみようと決意したようなわけなのです。最終的に原稿用紙何枚程度でおさまるのかはわかりませんが、当初予定していた五百枚をはるかに超えるだろうことだけはまず間違いありません。なお、ご多忙なお身体ゆえ毎週とはいかないかもしれませんが、「自詠旅歌愚考」の挿絵でお馴染みの渡辺淳画伯に新作品のほうの挿画もお願いしようかと考えております。
書き下ろしにせず、AICですこしずつ公開しながら執筆を進めることにしたのは、ひとつにはAICで他の記事を書く場合に要するであろう時間をこの伝記実話小説の執筆に当てようと思ったからでもあります。しかし、それ以上に大きな理由は、様々な事情のゆえに世に知られることのなかったこの石田達夫という人物の途方もない人生を掘り起こし、インターネットという最新メディアを通じてそれを広く紹介することによって、昭和裏面史とでも呼ぶべき隠れた出来事の数々を一人でも多くの皆さんに知ってもらいたいと考えたからなのです。
そんなわけですから、先々は単行本にしてもらうつもりではおりますが、現段階では具体的なことは未定です。いずれにしろまだかなり先のことになりますので、じっくりと連載記事を読んでもらい、そのうえでとくに関心をもってくれるような出版社があれば、あらためて加筆修正をおこない、再編集をしてもらったうえで刊行をお願いしようかと考えています。
なお、これまで筆を執ってきた「自詠旅歌愚考」につきましては、「ある奇人の生涯」の記事連載の合間などに、月一回程度の割合で折々連載を続けさせてもらうつもりです。旅をテーマにしたこれまで通りの放浪記をときには一回読み切りでアップすることもあるかもしれませんが、石田翁の伝記執筆が完了するまでは、これまでのような複数回にわたる放浪記の掲載は控えさせていだだこうと考えています。
微力な身ではありますが、今後とも精神誠意執筆に励むつもりではおりますので、読者の皆様のご支援とご声援のほど、こころからお願い申し上げてやみません。
平成14年12月 本田成親 拝
「マセマティック放浪記」2003年1月1日
ある奇人の生涯 (1)
碌山美術館
「これからどちらへ?」―― 信州安曇野の穂高駅前で、手にした地図と観光案内板とを見較べながら気ままな旅の行程を考えていた私は、いきなり肩ごしにそう声をかけられた。「はあ?」と戸惑い気味に振り返ると、眼鏡の奥にいたずらっぽい笑みを湛えた一人の見知らぬ老人がじっとこちらを見つめていた。一瞬言葉に詰まって立ち尽す私に向かって、謎の老人は「昨日も私はあなたにお会いしましたよ!」と、追い伐ちをかけてきた。想わぬ展開に混乱をきたした私の様子を、老人は心底楽しんでいるかのようでもあった。生まれたばかりの樹々の緑が西陽をふくんでやわらかく輝く、ある晩春の夕刻のことである。
「あなたは昨日、碌山美術館のベンチでノートを片手になにやら想いに耽っていましたよね?」
「ええ、若葉は綺麗だし、陽差しもやわらかでとても気持ちがよかったので、ベンチに寝転ってボーッとしてました。でもどうしてそんなことを?」
「あのとき、私も客人を案内して碌山美術館を訪ねていましてね。それでたまたまあなたの寝そべっているベンチのそばを通り過ぎたんです。妙に印象に残っていましたんでね」
老人はそう言ってまた愉快そうに笑った。見るからに上質な麻織りのシャツを前開きにして着流し、太い黒縁のサングラスをかけたその姿には、不思議な存在感さえ漂っていた。どこか往年の黒澤明をも偲ばせる風貌のその老人を私はまじまじと見つめ返した。
旅の途中にあった私は、その前日、穂高駅に近い碌山美術館を訪ねたばかりだった。この美術館は、高村光太郎と並ぶ偉大な彫刻家、荻原碌山の業績を讃えて、昭和三十三年に建てられた。ツタの葉と蔓で覆われたチャペル風のレンガ造りの建物に魅せられてこの地を訪ねる人はいまもなお跡を絶たない。
安曇野の旧家の若当主、相馬愛蔵のもとに才色兼備でなる二十一才の相馬黒光が嫁いできたのは明治二十九年のことである。そのなみはずれた知性と美貌を武器にして、若いながらもすでに多くの文人や芸術家と交流のあった黒光は、嫁入り道具と共に一枚の絵画を持参した。「亀戸風景」というその一幅の風景画は、はからずとも彼女より三歳年下の青年荻原守衛の運命を大きく変えるところとなった。
姓は星、名は良というのが黒光のかつての本名だったが、女学校時代の師、星野天知が、「到底何かやらなければ成仏できそうもない光」を放つ彼女の瞳の輝きを「暗光」と呼んだことから転じて、「黒光」というその不思議な呼び名が生まれたのだという。「アンビシャス・ガール」として知られ、先練された都会的感覚の持ち主の黒光が安曇野に嫁してきた背景には、当時親交のあった国木田独歩や、彼女が傾倒していた田園詩人ワーズワースの影響もあったらしい。
キリスト教徒だった相馬愛蔵らが主宰する東穂高禁酒会に入会していた地元出身の青年荻原守衛は、その縁で美しく理知的な黒光を知るところとなり、彼女の鋭い知性と豊かな感性に圧倒された。なかでも、黒光によって教化され、芸術の世界へと眼を開きかけていた荻原守衛に一枚の油絵がもたらした衝撃は、その後の彼の人生を決定づけるほどに絶大なものであった。荒川河畔に牛が佇む様子を描いた長尾杢太郎筆の「亀戸風景」は、黒光への抑え難い思慕の念とあいまって荻原守衛の若い魂を激しく揺さぶったのである。守衛が芸術の道を志そうと決意したのはまさにこの瞬間であったという。いまも穂高の相馬家に所蔵されている「亀戸風景」の実物大写真が碌山美術館本館の入口近くに展示されている。
二十一歳になった荻原守衛は明治三十二年、相馬黒光の紹介のもと、巌本善治を頼って上京、明治女学校内の深山軒に仮寓した。そしてその二年後の明治三十四年、洗礼を受けて渡米し、ニューヨークの画学校に入学した。いっぽう相馬愛蔵夫妻も同じ年、穂高での生活に区切りをつけて上京、本郷の東京帝国大学前にあったパン屋「中村屋」を屋号ごと譲渡してもらい、その新事業の発展に努めることになる。当時の帝大生や上野の美校(現東京芸術大学)の学生たちの間で大評判を呼んだこともあって、中村屋は繁盛の一途を辿った。明治四十年には新宿追分に支店が開かれ、その二年後には新宿駅前に移転、現在の中村屋の基礎が出来上がった。文人や芸術家と幅広い交流をもつ黒光の才覚もあって、新宿中村屋はますます発展を遂げ、芸術家グループのサロン的役割を果すようにもなっていった。
ニューヨークには渡ったもののいまひとつ満たされぬものを覚えた守衛は、一時的に渡仏し、パリの画学校に入学する。そして、そこで運命的に出逢い心から感動した作品こそがロダンの彫刻「考える人」であった。「考える人」を目にして天啓に近い衝撃をうけた守衛は彫刻家になろうと固く決意する。
いったんニューヨークに戻って身辺の整理を終えた守衛は明治三十九年に再び渡仏し、彫刻の世界に没頭するようになっていった。美術雑誌に紹介された「考える人」の写真を一目見てやはりロダンに傾倒し渡欧していた若き日の高村光太郎と廻り逢い、互いに親交をもつようになったのはこの時代のことである。
ほどなく憧れのロダンに師事し、彫刻の腕に磨きをかけた守衛は、「女の胴」、「坑夫」などの秀作を次々に生み出していった。この頃から守衛は、「碌山」と号するようになるが、この雅号は、渡欧中に彼が愛読した漱石の小説「二百十日」に出てくる「碌さん」をもじったものであったという。しかし、その語調の中には恩師「ロダン」の名前のもつ響きが暗に込められているようにも想われてならない。明治四十一年、三十歳になった荻原碌山は、盟友高村光太郎が激賞した作品「坑夫」を携えて帰国する。現在碌山美術館に所蔵されているその作品を、当時の厳しい運搬事情を承知のうえで是非とも母国に持ち帰るようにと勧めたのも光太郎であったという。
帰国した荻原碌山は、相馬夫妻が営む新宿中村屋の二階に仮住まいし、東京で帽子屋を開いている実兄の援助で出来た近くのアトリエに通いながら、作品の製作にとりかかった。アトリエと言えば聞こえはいいが、実際には麦畑やトウモロコシ畑の中に立つ六畳一間ほどのバラック小屋だったらしい。
「愛は芸術なり。相克は美なり」という有名なロダンの芸術思想を継承した碌山は、激しく美しくも、いっぽうで救い難い葛藤と愛憎に彩られた世界に自らの魂を投じ、そこに彫刻表現の根源を求めた。愛の相克のもたらす美に文字通り命をかけていったのである。青春期に安曇野で出逢って以降、若くして他界するまで、碌山の相馬黒光に対する深い思慕は変わることがなかった。とくに、相馬愛蔵が安曇野に愛人をつくり黒光との不和が囁かれるようになると、碌山は黒光母子を連れて渡米することさえも考えたという。しかし、黒光はそんな碌山の激情を鎮め制するかのようにひたすら中村屋の家業に精魂を傾けるばかりだったため、碌山の煩悩は果しなく高まりゆくばかりだった。
自らの意志ではいかんともし難い胸中の苦しみを叩きつけるようにして、碌山は「文覚」、「ディスペア」、「労働者」といった作品を製作した。「文覚」は芸術としての彫刻が何たるかを初めて我が国に知らしめる歴史的記念作品ともなった。モデルとなった文覚上人は、北面の武士だった頃に恋慕した人妻、袈裟御前を誤って殺め、その苦悩のゆえに出家して仏門に入った歴史上の人物だけに、碌山には、黒光に対する自らの処し難い気持を重ね見る想いだったのであろう。絶望に悶える女の姿をテーマにした「ディスペア」は碌山と黒光の深い関係とそれに伴う複雑な事情が形を変え、類稀なる芸術作品へと昇華したものにほかならない。
明治四十二年の暮れ、自らの命の炎に避け難い翳りと揺らぎとを感じた碌山は、精魂を尽して一つの作品の制作に取りかかった。伝記の語るところによれば、塑像を作る粘土が凍結するのを防ぐため、毛布はおろか自分の着衣までも覆いとして用いた碌山は、暖房器具一つない貧しいアトリエの中で立ち震える有様だったという。
翌年の明治四十三年三月半ば頃に「女」と題されるその作品は完成した。完成後まもなく碌山のアトリエに案内された黒光の子供たちが、一目見るなり「あっ、母さんだ!」と叫んだというその塑像こそは、碌山最後の、そして明治期最高の傑作といわれる作品であった。膝を立て、両腕を後手に組んで豊かな乳房を誇示するかのように胸を張り、こころもち右へと首を傾け、両眼を閉じてわずかに口を開き、悩ましげに天を仰ぐその像は、まさしく相馬黒光その人の裸形そのものだったのだ。日本近代彫刻の名作「女」は、碌山と黒光が、その相克の深さにもかかわらずどこまでも心身を許し合う仲であったことをはっきりと物語っている。
「女」を完成してほぼ一ヶ月後の四月二十日、中村屋の奥にあった相馬家の居間で友人達と談笑中、突然に吐血した碌山は、それから二日後の早暁、相馬夫妻や駆けつけた多くの知己が見守るなかで絶命した。時に碌山三十二歳、天才にありがちな夭折であった。折しも奈良を旅していて碌山の臨終に立ち合うことのできなかった高村光太郎は、のちに「荻原守衛」という詩を詠んで次のようにその死を深く悼んでいる。
粘土の「絶望(ディスペア)」はいつまでも出来ない
「頭が悪いので碌なものは出来んよ」
荻原守衛はもう一度いふ
「寸分も身動き出来んよ。追いつめられたよ」
四月の夜更けに肺がやぶけた
新宿中村屋の奥の壁をまっ赤にして荻原守衛は血の魂を一升吐いた
彫刻家はさうして死んだ……日本の底で
息を引きとる直前、碌山は人目を忍んで黒光に一つだけ重要な頼みごとをした。碌山の葬儀が行われてから何日かのち、今は主なき碌山のアトリエに一人佇む相馬黒光の姿があった。黒光は死の床で碌山から秘かに手渡された合鍵で故人が愛用していた机の引き出しを開けて一冊の日記帳を取り出した。びっしりと歓喜や苦悩の文字の書き込まれたその日記帳の一枚一枚を黒光はむしりとり、深い想いを押し殺すようにして火にくべた。立ち昇る煙が天上遥かな碌山の魂に届けとばかりに、黒光は、情念の写し絵とでもいうべき紙片の数々を燃やし去っていったに違いない。
荻原碌山の遺骸の眠るひつぎは列車で信州穂高の実家に運ばれ、北アルプスの常念岳を望む安曇野の一隅に埋葬された。碌山の遺作「女」は、その年の秋の第四回文展において、「この一品をもって及第品中の最高傑作と断ずる」と絶賛された。日本近代彫刻の金字塔ともいうべき「女」は、荻原碌山が文字通りその命を賭け、最後の血の一滴までも絞り尽して完成させた作品だったのである。

絵・渡辺 淳
「マセマティック放浪記」2003年1月8日
ある奇人の生涯 (2)
出遇った相手は人食い老人!
その日碌山美術館で「文覚」や「女」をはじめとする彫刻作品を見たあと、私は中庭に出て、白塗りの大きな木製のベンチに腰をおろした。そして、ほどよく張りつめた精神をやわらかな木漏れ陽がここちよく包み暖めてくれるなかで、碌山と黒光という時代を超えた二つの魂の壮絶な愛の相克に遠く想いを重ねていた。
能力も人間としての器量もはるかに劣る私などにそんな命懸けの大ロマンがあったわけなどないのだが、身のほどにふさわしい幾つかのロマンの経験ならばそれなりになくはなかった。時代こそ違うが、すくなくとも自らのささやかな体験を重ね通し見ることによって、明治というまだ封建色の強かった時代に近代的な精神と感覚をもって生まれた二人の魂の不幸と、それゆえの愛の苦悩の深さを偲ぶくらいのことはできた。芸術史に残る一体の彫像としてお互いの魂を合体凝結させることによってしか、明治社会の執拗な呪縛を逃れ、新たな世界へと翔くことが許されなかった碌山と黒光の煩悶の一端は、おぼろげながらもわかる気がした。
彫像に修羅の涙を托しつつ
時を旅する若き碌山
そんな短歌まがいの戯言を胸の奥で呟きながら深い想いに耽っているときに、老人は私の脇を通りかかったらしいのだ。印象に残ったと老人が言うところをみると、よぼど情ない顔でもしていたのだろう。
「穂高駅でいまさっき客人を見送って帰ろうとしたら、あなたが立ってるんで声をかけてみたんですよ」
「はあ……」
なおも戸惑う私をまえに、老人はさらに言葉を続けた。
「今日これからのご予定は? よかったらしばらく私と話でもしませんか?」
「そうですねえ。これといってとくにありません。放浪に近いことをやっていますから」
「じゃ私がこの辺でも案内してあげましょう。これも碌山美術館のとりもつ悪縁と思ってね」
「う〜ん、じゃ、まあ折角ですからお言葉に甘えるとしますか……」
「気が向いたら一晩私の家に泊まってもらってもいいですよ。独り暮しですから誰にも気がねはいりません」
「そうですか、ちょっと考えてみますが、それじゃいくらなんでも御迷惑でしょうし、図々しいにもほどがあるという気がしますから……」
相手の申し出の意図を測りかねて困惑しながらも、すこし心の傾きはじめた私に向って、なんとも人を食った殺し文句が飛んできたのはその直後だった。
「遠来の客を見送ったこんな日の夜は、独り暮しの身にはいささか淋しくてねえ。そんなときには、一夜の宿を供するふりをして、道に迷ったうまそうな旅人をとって食うにかぎるんですよねえ……」
謡曲にある安達ヶ原の黒塚伝説を想わせるそんな言葉を吐いた老人は、いたずらっぽい眼で私のほうを見つめながらにやりと笑った。相手が妖艶な美女に化けていないのは残念だったが、黒塚伝説に登場する美女は鬼姿の化身で、鬼爺が美女に化けて人を食ったという話は聞いたこともないから、それはまあ無理な注文ではあったろう。相手がドラキュラなら、一応筋は通るが、すると、今度はこちらが美女に化けなければ向こうが納得するまい。ただ、残念なことに私にはその趣味はなかった。
物語の常道からはすこしばかりずれていたが、老人のその一言は私の体内に潜むある種の嗅覚を一瞬のうちに呼び覚ました。相手がただ者ではないと直感した私は、「どうご覧になってもうまそうには見えないでしょうが、よろしければどうぞ!」と切り返した。
老人の術中に自らはまるのは目に見えていたが、こちらもそれなりに人を食ってきた身なので、この際人に食われてみるのも悪くなかろうと、相手の誘いにあえて乗ることにしたのだった。
老人は駅前に駐めてあった自分の軽乗用車に私を乗せると、穂高駅からすこし離れたところにある大規模なワサビ園に向かって走りだした。そのワサビ園行きは私のほうが望んだことで老人の勧めによるものではなかったが、相手はこちらの要請に快く応じてくれた。ハンドルを握りながら、老人はジョークや洒落を次々に飛ばし続けたが、その切れ味にはどこか日本人離れした鋭さとセンスの高さが感じられた。
晩春の夕刻のこととあってワサビ園周辺には人影はまばらだった。清冽な水のながれる水路の張りめぐらされた広大なワサビ田そのものには風情を感じはしたが、観光客目当ての雑多な土産物屋やお世辞にも趣味がよいとは言えない種々の人工物、彫像群などには、言葉を失いひたすら苦笑するばかりだった。
伝説の大王窟と称する俄か造りの見るからに怪しげな洞穴や場違いの石組みのピラミッドを指しながら、「真面目に考えれば腹も立ちますが、出来そこないのジョークだと思えば結構楽しめるんですよ」といって、老人は愉快そうに笑った。
ジョークという意味での極めつけは、園内の一角にある大王神社とかいう祠の周辺の奇妙なたたずまいだった。狭いけれど曲りなりにも鳥居と祠をもつ境内には、創業者夫妻らを顕彰した何体かの銅像がものものしく立っている。そのすぐそばに仏像らしきものが並んでいるかと思えば、鳥居の左手にはちょっとした芸術作品風の「安曇野のこどもたち」という、健康そうな男女二人の児童を形どったブロンズ像が配置されていた。そして、それらすべてを嘲うかのように鳥居から数歩と離れていないところに置かれているのが、若い女性の裸体のブロンズ像だった。
「安曇野一帯には商売上手な芸術家もたくさんいましてね。芸術にかこつけて見え見えの作品を高く売りつけた結果がこの有様なんでね」
「大真面目に並べてあるぶん、よけいに笑いを誘われますね。これらの代物を憶面もなく売りつけた芸術家やブローカー連中への痛烈な皮肉を込めてのことなら、それはそれで見上げたものなんですがね」
「時々客人を案内してここを訪ねるときには、この見事なまでのアンバランスのもたらすジョークと風刺を楽しんでもらうことにしてるんです。うっかりすると折角の珍品を見落としてしまいますからねえ」
「彫像の作者たちには、いくらなんでもそれなりの自負はあたのでしょうから、この有様を目にしたらさすがに驚いたんじゃありません?」
「そんな繊細な神経でもあれば救いもあるんでしょうが、『恥は金なり』と開き直っているかもしれませんよ。どうせなら、大きなゴミ箱のそばにでも飾っておけば、もっとワサビが利くんですがね」
老人の言葉は辛辣だった。
「なにやら僕の全身にもワサビが利いてきた感じですよ。ここまでワサビが浸み透ってくると、辛過ぎて食べてもうまくありませんよね?、やっぱりこのワサビ園を訪ねてよかったなと思いますよ」
ちょっと意地悪気味な言葉を返すと、老人は愉快そうに笑ってさらにこう応えた。
「じゃ、そろそろ利き過ぎたワサビをすこしばかり洗い落しにいきましょう。実はすぐ近くにいいところがあるんですよ。ほんとうは、あなたをそこに連れていきたかったんです。利き過ぎたワサビもですが、あなたの身体についた泥のほうもしっかり洗い流してからでないと、食べられそうにないですからね」
「泥をとったらあとは、骨ばかりで、食べるところなんかありませんよ。もっとも、ちょっとやそっとでは私の泥はとれないでしょうけどね」
軽口を交わしながら、我々はワサビ田を右手に囲いこむようにしてのびる土手上の道を歩きはじめた。碌山美術館のような本物の芸術空間もあれば、このワサビ園のように珍妙な空間もある。そして、この老人のような不思議な人物も存在している。北アルプスの麓にそって長くのびる安曇野に私はある種の親しみをさえ覚えかけていた。
土手上をすこしばかり進むと何体かの道祖神が立ち並ぶ場所に出た。いまはこのあたりの土手道もすっかり整備され、ワサビ園観光コースの一部に組み入れられてしまっているが、当時はその付近まで足を運ぶ人はほとんどいなかった。老人は道祖神の前に立つと、いかにもそれらしく見えるが、これも新しく造って運び込んだ代物だと説明してくれた。道祖神はもともと古い集落をつなぐ道沿いに点在しているものだから、たしかに、地理的にみても不自然なこんな場所にそれらが数体も一緒に立ち並んでいるわけがない。近づいて石の刻面をよく観察してみると、たしかに新しい感じのものが多い。なかにはかなり古い造りのものもあったが、それだってはじめからここにあったわけではないだろう。
道祖神群の前を過ぎてすこし進むと急に左手の景観がひらけ、西方から流れてくる川が大きく北へと曲がる地点に出た。なにげなく川面に目をやった私は、次の瞬間思わず息を呑んだ。満々と水を湛えた万水川というその川の流れは深くそして速かった。北アルプスの綾線近くまで傾いた西陽に川面は美しく映えていた。眼下を流れる水は透明そのもので、三メートルほどはあろうかと思われるその水深と速い水の動きにもかかわらず、川底までがはっきりと透きとおって見えた。
水中には若緑色の美しい水草が繁茂し、下流方向に大きくたなびくようにしてゆらゆらと搖れている。水梅花とおぼしき小さな白い花が清流の中で身を清めるようにして点々と咲いていた。下流方向の両岸にはミズナラをはじめとする好水性の樹木が密生し、幅十メートルほどはある川筋全体を両側から覆い守るようにしてしなやかな枝を伸ばしていた。岸辺よりの水面にやさしく影を落とす樹々の緑も命にみなぎり、その葉の輝きは鮮烈そのものであった。
水辺に近い土手の斜面では、タンポポをはじめとする無数の黄色い花々が、野の虫たちを誘いかどわかすかのようにその鮮かな色を競っていた。上流左手の川岸に目を転じると、二、三軒の水車小屋が建ち並び、昔風の大きな木造りの水車が、時の流れに抗うかのようにゆっくりと回転していた。眼に飛び込んでくるなにもかもが美しかった。それは信じられないような光景だった。私も国内各地をずいぶんと旅しているが、人里近くにあって昔ながらの姿をいまも留める川を目にすることはめったにない。人手のほとんど加わっていない自然堤防をそなえ、いまでも日本古来の美しい姿を残す川を集落の近くに探すとなると容易なことではないに違いない。それなのに、昔の絵や写真の中にしか見ることのできないような川が突如私の眼の前に現われたのだった。
「僕はこの川が大好きでねえ、よく散策に来るんですよ。あのジョークいっぱいのワサビ園の近くにこんな川があるなんて意外でしょう?」
「そうですねえ。日本の昔ながらの風景が時間の淀みの中にたまたまとじこめられて残った感じもしますし、西洋の印象派の絵の中に見る田園風景にもどこか似たところがありますよね」
「身体の泥は落ちそうですか?、この川の水ならそれなりには泥も洗い流せるでしょう?」
「ええ、そうですね。お口に合うほどに身が清まるかどうかはわかりませんが、利き過ぎたワサビや長年の生活でしみついた泥の大半は落ちてしまいそうですね」
「すこしくらいは泥とワサビが残っているほうが独特の風味があってうまいから、ちょうどいいでしょう」
我々はそんな愚にもつかぬ会話を交しながら、万水川周辺を心ゆくまで散策した。もし自分一人だけでワサビ園を訪ねていたらこの素晴らしい風景に出逢うことはなかっただろう。私は、いまだ正体の掴めぬこの不思議な老人に内心深く感謝するばかりだった。
実をいうと、それから二、三年のちのこと、黒沢明監督の「夢」という映画を見ていた私は、ラストシーンの映像を前にして思わず声をあげそうになった。スクリーンいっぱいに広がる美しい川と水車小屋の風景は、忘れもしないこの万水川とその岸辺に並らぶ水車小屋の織りなす景観そのものだったからである。ずっとのちなってから、あらためてその老人と出逢いの際の想い出話をするうちに、その水車小屋だけは映画撮影のために黒沢監督がとくに造らせたもので、撮影終了後もそのまま残されたのだいうことが判明したのだが、いずれにしろ、それは私にとって忘れられない風景となった。

絵・渡辺 淳
「マセマティック放浪記」2003年1月15日
ある奇人の生涯 (3)
偉大なる創造空間?
駐車場に戻り車の座席にすわると、老人は、今夜は自分の家に泊まっていかないかとあらためて尋ねてきた。この老人が何者かを知りたいという思いが先に立ちはじめていた私には、もはやその誘いを断る理由などなかった。それまでの会話の端々から、相手が並々ならぬ語学力をそなえもっているらしいことだけは推察できた。ただ、質素な独り暮しだが、毎週三日働き残り四日は精神を満たすためにのんびりと遊び楽しんで暮していると笑う老人の真の姿は、まだ私にはまったく見えてこなかった。
まずは夕食をとろうということになり、老人の案内で「天満沢」という穂高町の西部山麓道路沿いにある老舗の蕎麦屋に行くことにした。老人の住まいはその蕎麦屋から遠くない赤松林の中にあるという。天満沢に向う間も彼はウィットと風刺に富んだ言葉を連発し続けた。体内から自然に湧き上がってくる感じの示唆に富んだそれらの言葉に、日本人離れした発音のかなり特殊な英語やフランス語の単語が織り混ぜられることからすると、この奇妙な人物が海外での生活経験を豊かにそなえもつことは明らかだった。
大ザルに盛って出される天満沢の蕎麦は、さすがに美味だった。お店の座敷の窓越しに夕闇の迫る安曇野を眺めやると、灯りはじめたばかりの民家の明かりが、どこか愁いを漂わせながら点々と瞬き輝いて見えた。
蕎麦を食べながら、老人はごく最近も通りすがりの大学生をからかった話をした。穂高駅から大きなザックを背負って山麓方向へと向う見知らぬ若者に、「あなたは横浜国大の横沢さんですね。これから穂高ユースホステルにいらっしゃるんでしょう?」といきなり話かけたというのである。一面識もない老人に名前や所属大学、さらにはその時の行き先まで当てられた大学生のほうはさすがに仰天したらしい。穂高駅からザック姿の若者が夕刻に向う場所は十中八九はユースホステルに間違いないし、ザックには大学名と当人の名前がマジックで記されていたからというのがその一件のタネ明かしなのだが、老人はどうやらいつもこの調子で「旅人を食って」いるらしかった。
「僕はシャーロック・ホームズが好きでね。ホームズ流に言えば、 『My dear Watson, this is just elementary!(ワトソン君、これはごく初歩的なことでねえ!)』という訳ですよ」
相手は簡単に事の次第を説明したあと、笑いながらそう話を結んだが、この最後のさりげない一言には、ずっとあとになって思うと、この老人の不思議な人生の解明に役立つ重要なヒントが隠されていたのだった。しかしながら、その時の私にはまだその言葉の背景を的確に読み取ることはできなかった。現代のホームズにはとてもなれそうにないというのはこの一事からしても明らかだった。
そば屋を出た私は案内されるままに老人の家へと向った。北アルプス山麓の深い赤松林の中にある洋風の屋敷には見るからに妖しげな気配が立ち込めていた。一瞬私はドラキュラ屋敷を連想したが、いまさら引き返す訳にもいかない。意を決した私は玄関の扉をおもむろに引き開けて家の中へと入っていった。
平屋造りの建物の中は簡素だが天井の高い洋風の構えになっていた。調度類もアンティークなものから現代風のものまでがいろいろと並んでいたが、明きらかに異国風のものが多かった。ただ西洋風の調度品ばかりでなく、東南アジアや中東風、さらにはアフリカ風やラテンアメリカ風の調度類までがいりまじっている感じでもあった。そして、この雰囲気からするとだとすくなくとも和風の妖怪は棲みついていように思われた。また、極力明るさを抑えた照明が室内に絶妙な陰翳を生み出しているのを見れば、この老人の美的センスの高さがおのずから偲ばれもするのだった。
いったんロングチェアに腰をおろして短い会話を交えたあと、私はトイレに立とうとした。すると、老人は、「この家のトイレにはいったら一時間は出てこられませんよ!」と言って意味ありげに笑った。案内されたトイレの前に立つと、なんとドアに「WORKS CREATIVE」と記されているではないか。WとCだけは赤い文字にしてもある。おなじ「W・C」でもこの「W・C」は、「創造的な作品群」あるいは「創造的な仕事の産物」であり、また「創造的な仕事の場」でもあるということらしいのだ。どれどれとばかりにドアを開けて一歩中に踏み込んだ私は、思わず驚嘆の声をあげそうになった。
広々とした造りのトイレの中央には西洋式の便器があり、その左手には木の棚があって、面白そうな本が何冊も並んでいた。簡単なメモ用ノートらしいものもある。便座にすわったままで本を手に取って読書に耽ったり、思策のすえにウーンとばかりに絞り出した独創的なアイディアをメモしたりもできるわけだ。ただ、そこまでならたまにある話で、そう驚くほどのことではない。私が目を奪われたのはドアの裏面を含めた前後左右の壁面と天井の五面の様相だった。
それらの面には珍しい大小のポスターや写真類、絵葉書類などが見事な構成と配列で貼りめぐらされていたのである。詩情豊かな自然の風物や海外の名所旧跡などの絵や写真、それぞれに物語を秘めた様々な男女の珍しい写真、さらに、見るからに独創的な芸術作品の写真や何枚かの美術展の酒落たポスターと、どの一枚いちまいをとっても、なんともいえないほどに味のあるものばかりだった。大小合わせれば二、三百枚はあろうかと思われる絵葉書や写真、ポスターなどが、オランダあたりの美しい花壇を連想させる構成とデザインで五つの面いっぱいに貼られている有様は、壮観の一語に尽きた。右側の壁面には手造りの文字盤をもつ花時計風の時計まで備えられており、まさにそれは「創造的作品」とでも呼ぶにふさわしいものであった。
私はとりあえず便座に腰掛けはしたものの、本来のその空間の用途など忘れてしまった状態で天井や四方の壁を順々に見回した。なるほど、こんな調子で絵や写真の一枚いちまいを眺めていたら、それだけでも一時間くらいはすぐに経ってしまうに違いない。そんなことを考えながら前方を見上げると、一枚の大きなポスター風写真が目にとまった。黒いグラスをかけた老人とおぼしき人物が風のような動きを見せて地上を走っている風変わりな写真である。写真の中の人物は不思議なまでの存在感と、それとは相反する不気味なほどに変幻自在な多様性とを同時に持ち具えているかのようだった。
しかも、驚いたことに、よく見るとその人物はほかならぬこの家の当主そのものだったのだ。老人の本質を見事に撮りきった写真家もさるものなら、このような不思議な動きを苦もなくやってのけるモデルのほうも相当なものである。私の好奇心はいやがうえにも掻き立てられるばかりだった。「トポスの復権」というタイトルの入ったポスターに目が行ったときも、私は思わずニヤリとした。「トポス」とは「場所」という意味である。老人はその美学に即し「トイレという場所の復権」を暗に唱えようとしていたのだろう。
ようやく本来の目的を想い出した私は、その一件を片付けたあと、何気なくロールペーパーに手を伸ばし、その一部をちぎりとった。そしてそれに目をやった途端、呆気にとられて、またもや息を呑み込む有様だった。なんとその紙片には青い色で英語のクロスワードパズルが印刷されていたのである。チャレンジされたからには受けて立つほかはない。かくして私はトイレからの脱出をはかるために難解なパズルに挑むという思わぬ事態に追い込まれるはめになった。
日本語のものだってクロスワードパズルはそれなりに難しい。まして英語のクロスワードパズルとなると、短時間での完答は容易ではない。しばらく考えてはみたが、どうしてもわからないところがある。このままだと夜が明けるまでこの便座に腰かけたままでいなければならない。この「WORKS・CREATIVE」空間のなかで、いつまでもロダンの「考える人」をみっともなくデフォルメしたような格好を続けていたら、私自身が老人の芸術作品の一部と化してしまうだろう。やむなく意を決した私は、三、四シート分のクロスワードパズルを犠牲にすると、新たにちぎりとった一枚のクロスワードパズルを手にしてトイレを出た。
おそらくは内心でニヤニヤしながらお茶の用意をしていた老人は、クロスワードパズルつきのロールペパーの切れ端を手にした私の姿を目にすると、
「ずいぶんとごゆっくりでしたねえ……私の創造空間を楽しんでもらえましたか?」
と愉快そうに訊ねてきた。
「ええ、存分に……。もうちょっとで便座にすわったまま硬直していたら、新作『考えるアホ』になってしまうところでした」
「ははは……で、そのクロスワードパズルは解けたんですか?」
「いや、それがまだなんですよ。せっかくですからお茶でも頂戴しながらゆっくり解いて、それからまたトイレに戻って排泄口を拭いてくることにします。その間しばし御迷惑をおかけしますが……」
「せっかく万水川の水で身についた泥を落としてもらいましたのにねえ。困ったもんですねえ……」
「こちらもちょっとくらいは防御策を講じておきませんとねえ」
そんなとりとめもないそんな言葉を交わしながら、我々はテーブルに着いた。紅茶を出してくれた老人は、カップの中のお湯にティーバッグをしばらく浸したあと、スプーンの先にティーバッグ本体をのせ、その上に馴れた手つきで付属の糸をぐるぐると巻きつけた。そして器用にティーバッグに残る水分を絞り出してみせた。
「ティーバッグ紅茶を使うときは、こうすると成分がうまく外に出るし、カップから出したあともベチャベチャしない。よく水切れしているから、もう一度使うときも都合がいいんですよ。まあ、以前は向こうにもティーバッグなんてものはありませんでしたけれどね。私も紅茶にはずいぶんとお世話になりましたから……」
感心してその手捌きを見つめる私に、相手はそう説明してくれた。ティーカップを持つときの慣れた手つきや「向こうにも」というその言葉のあやからしても、この老人が海外生活、おそらくは英国での生活体験をもつことは推測できた。
刻々と時をきざむ時計の針の動きとともに戸外の闇はどこまでも深まり、その闇の吐き出す黒い霧によってこの屋敷だけが外界から包み隠され、異次元の底へと沈み込んでいくみたいであった。どこか屋敷の近いところを流れているらしい小川のせせらぎの音だけが、この異界を現実界とをつなぐ唯一の細い糸のようにさえ感じられた。
その晩、我々は夜を徹して奇妙な対話を繰り広げた。嘘のなかの嘘にもみえて、この世でいちばんの真実のような、大詐欺師同士の対決にも似て、実は聖なる二人の高談のような、それはそれはなんとも不思議な歓談だった。対話の途中で何気なく席をはずした老人は、上質の厚い黒毛布を二つ折りにし、折り目の中央付近を首穴として切り抜き仕立てた手製のドラキュラ風マントに着替えてふいに現われ、私の背筋をぞくりとさせた。
二本の牙こそはえていなかったが、その風貌には映画で見る晩年のドラキュラ伯爵にも似た凄みがあった。しかも、屋敷の周辺に広がる深い林のどこかでフクロウが鳴くという望外のおまけまでがつく有様だった。どうやら、この魔宮から抜け出し、日常世界へと無事生還を遂げるには、こちらもそれなりの覚悟を決めて相手を化かし返すしかないように思われた。
盤面を激しく跳ねまわるパチンコの玉のように話はあちこちへ飛んだ。老人は想像以上に博識だった。その口からは、戦前の博多、京都、東京、さらには中国の青島、大連、上海での体験談や、戦後間もない頃の英国での生活体験についての話もでた。コナンドイル、アガサ・クリスティ、サマセット・モームなどをはじめとする英米文学作品についての造詣も驚くほどに深かったし、語学一般についての知識も並々ならぬものがあった。また芸術や文化について語るときの一語一語には、カミソリのような鋭さとナタのような重量感とが同時に込められている感じだった。その表現は日本人離れしたウィットとアイロニイに富んでいた。思わぬところで思わぬ有名人との出逢いの話が飛び出したり、歴史的な出来事に遭遇したときの想い出話が出たりして、私は何度も我が耳を疑うばかりだった。しかし、老人の言葉とその口調や表情には、現実にそれらを体験した者にしかもち得ないような、動かし難い真実味と重々しさが秘められていた。
嘘のようにみえて真実のような、真実のようにみえて嘘のような、どちらともつかない言葉のモザイク模様の中をさまよううちに、私は、モームの短編小説の世界の中に迷い込んでしまったような気分にもなってきた。目の前の人物が、嘘を真実に、真実を嘘に見せる天才ストーリー・テラーのサマセット・モームその人ではないかという錯覚さえおぼえるほどだったのだ。
寝室と書斎を兼ねた老人専用の部屋の壁には、国内外で広く活躍する芸術家、谷内庸夫の紙彫刻作品や、雑誌などでも知られる写真家、市川勝弘の作品などが配されていた。どうやらこの二人の若手芸術家たちも折々この穂高の「伏魔殿」に出入りしているらしかった。かつて彼らも、このドラキュラ老人の餌食になったのが縁でここを訪ねるようになったのだという。老人をモデルにしたトイレの中のあの不思議な写真は、カメラマンの市川が彼独特の手法で撮映したものだったのだ。
壁面の一隅には地元で建設業を営む素人カメラマンの作品だというモノクロの写真も飾られていた。花の蜜を吸う一匹の蝶が逆光に浮かぶ様子を撮影したものだが、その作品全体にはなんとも言えない生命の躍動感と体内の奥深いところを揺さぶる不思議なエロスが漂っていた。蝶と花と光と影という個々の構成要素が微妙に作用し合い、全体として美しい女体の肌を連想させるようなこの写真作品を、以前私はどこかで見かけたような気がしたが、その記憶はさだかではなかった。いずれにしろ、このような作品をさりげなく書斎に飾る老人の美的感覚は、なまじのものではないと思われた。
部屋の別の壁面には老人自身の作という一篇の酒落た英語詩「TREE」が黒のマジックでしるされもしていた。そして、その左手には、万歩計で測った日々の歩行の数を独自の処理法で樹形図化した不思議な模様が描かれていた。よく見ると横軸には日付を、縦軸には歩行距離数を配した一種のグラフになっていて、そのグラフの上辺のあちらこちらに赤い小さなマークがついていた。その意味を訊ねた私に、老人はいたずらっぽく笑いながら、本音とも冗談ともつかぬ調子で、それは性的衝動を覚えた日をマークしたものだと答えてくれた。
仕事用のデスクの上にさりげなく目をやると、何冊かの英文学の原書が置かれており、そのうちの一冊は開かれたままになっていた。それは「野郎どもと女たち」などの著作で知られるデーモン・ラニアンの作品のひとつで、どうやら翻訳作業の途中のようだった。話の端々から、英語がらみの仕事に相当関ってきたらしいことは推測できたが、書斎周辺の情況から察すると、どこにでもいるようなレベルのいわゆる「英語屋」ではなさそうだった。私自身も多少は海外著作物の翻訳経験もあり、英語でレポートを書く程度のことはやっていたので、そのことだけはすぐに想像がついた。

絵・渡辺 淳
「マセマティック放浪記」2003年1月22日
ある奇人の生涯 (4)
人生模様ジクソーパズル
狐と狸の化かし合いのような会話をいつ果てるともなく続けるうちに、夜はしんしんと更けていった。我々を包む大気とお互いの体の動きこそ靜かだったが、二つの精神と精神とは激しい火花を散らしてぶつかり合っていた。自らの肉体こそ現実に相手に食われることはなかったが、精神のほうはかなり相手の牙によって傷つき食い荒されてしまった感じだった。そんな中でタイミングをみはからっていた私は、単刀直入に老人のほんとうの職業を問いかけてみた。すると老人は、「そんな質問に一口で答えるのは難しいですね。あえて言えば『人間と人間のコーディネーター』ですかね」とまたいわく有りげに笑ってもみせた。
それでも容易には納得せずあの手この手で追及の矢を放ち攻めたてる私に、さすがの老人もいくぶん防御の手段に窮したらしく、その正体の一部をあらわしかけはした。しかし、それらはあくまでも相手の全体像のごく断片的なものにすぎなかった。驚くべきことに、生涯に四十六もの職業を体験したとも語る老人は、己の人生を系統だてて語る好みなどないと嘯き、どうしても自分の過去に興味があるというのなら、ジグソーパズルを解くように様々な話を繋ぎ合わせ、勝手に全貌をつかめばよいと笑って私を煙に巻いた。
老人は、十三日の金曜日には、自分の人生に大きく関わるような「変な人物」に出逢うことがよくあるのだとも語った。実を言うと我々が出逢ったのもたまたま十三日の金曜日だったのだ。光栄なことと思うべきかどうかはいささか疑問ではあったのだが、もしその言葉が事実だとすると、どうやら私もまた「変な人物」のリストの一端に名を留めることにはなるらしかった。ジグソーパズルを解くためにはこれからもまた何度かここにお邪魔しなけらばならないだろうと告げると、老人はニヤニヤしながらこう言い足した。
「またここを訪ねてくれるなら、なるべく十三日の金曜日にいらっしゃい。もし誰か他の人を一緒に連れてくるなら、まともじゃなく、なるべく変な人間のほうがいいですねえ。ただ、その時までこの屋敷が存在しているかどうかわかりませんけどね……」
相手の言葉を待つまでもなく、私のほうもまた、この不思議な空間は次に訪ねるときには霧のように跡形もなく消え去っているのではないかという思いをもちかけていた。
翌朝私は老人の案内で屋敷の周辺を見てまわった。屋敷を背後から囲い込むような深い赤松林と、赤松の間に密生する雑木やトゲのある蔓草類からなる薮は、山歩きになれたこの身でさえも踏み込むのを躊躇するほどだった。屋敷の東側には細い水路が一本あって、かなりの勢いで澄んだ水が流れていた。
もっとも、住居を直接に取り巻く庭そのものはよく手入れが行き届き、天気のよい日などはその一隅でティーパーティなどができるように、テーブルと椅子とがほどよく配置されていた。庭に生えている植物には食用や薬用から鑑賞用まで珍しいものが色々あったが、それらの植物の特性を十分に配慮した工夫がなされているところを見ると、老人の植物に対する知識は相当なものらしかった。
建物の外側に付属するかたちで老人自身の手造りだという小さな露天風呂なども設けられていた。夏などはこの風呂にお湯を引き込み、林や庭の草木を眺めながらのんびりと汗を流すのだという。その露天風呂の近くには枝ぶりのいい一本のエゴの木が生えていた。花の季節にはまだちょっと早すぎたが、エゴの木は時が来ると白い清楚な花を枝いっぱいにつける。
東京から折々命の洗濯にやってくる若手のコピーライターは、この風呂に入ってエゴの木を眺めるうちに、「エゴの木の下では何をしてもよい」というキャッチコピーを思いついたとのだそうである。エゴの木のエゴをエゴイズムのエゴに重ねたらしいこの洒落たコピーは、とことん我が道を行く感のあるこの不思議な人物の本質をも物語っているようで大変に面白かった。老人は愉快そうにそんな話を続けながら、大きな赤松が二、三本、ほどよい距離と空間をなして生えている庭の一角に私を導いた。
そこには白い太糸で網んだ大きく丈夫そうなハンモックが張られていた。むろん、ハンモックの支え網は赤松の幹にしっかりとゆわえつけられている。天気のいい日などはこのハンモックに体を横たえ、読書をしたり昼寝をしたりすると、涼しく爽やかで快適このうえないとのことだった。大人ふたりが乗ってもゆったりしているそのハンモックに揺られながら樹々の間越しに青い空を仰ぎ、とりとめもない想いに耽るのはたしかに最高の気分だった。その時には予想もしないことだったが、カナダ製であるとかいうこのハンモックには意外な運命が待ちうけていた。
もう数年前のことになるが、集英社文庫の宣伝ポスターに、ヤング・アイドルの広末涼子が白いハンモックに腰かけた大きな写真が登場したことがある。実をいうと、広末涼子とともに広く全国に紹介されることになったそのハンモックこそは、この日私が老人に勧められるままに乗ったハンモックそのものだったのだ。ポスター用の写真撮影をおこなったカメラマンの市川勝弘がこのハンモックのことをたまたま想い出し、彼の強い要請でハンモックは直ちに東京に移送された。そして、若者のアイドル、広末涼子とともに集英社文庫の宣伝に一役買ったのであった。
屋敷の周辺をひとめぐりした私は、十三日の金曜日を選んでまた老人の「人生模様ジグソーパズル」を解きにやってくることを約束し、ひとまずその場を辞すことにした。のちのちのこともあるので、別れ際に私は老人の名前を尋ねた。まさか「穂高町ドラキュラ伯爵様」という宛書きでお礼状を書くわけにもいかないだろうと考えたからである。すると、老人は短く一言、「石田達夫です」と名乗った。老人に見送られながら玄関を出るとき、確認の意味もあって、メールボックスにさりげなく目をやると、間違いなく、そこにはローマ字で「TATSUO・ISHIDA」と記されていた。
いったいこの石田達夫という老人はこれまでに何人の旅人を食べてきたのだろう。いろいろな世界で創造的な仕事をしている若い友人がずいぶんいて、仕事に行き詰ったりアイディアが枯渇したりしたときはヒントを求めて皆ここにやってくる、と語った老人の言葉はまんざら嘘ではないだろう。ふとしたきっかけでこの老人の毒気にあてられた若い旅人などは、その不思議な魅力にとりつかれ、再度この屋敷を訪ねることになったに違いない。老人のほうは、そんな旅人や来訪者の発するエネルギーの一部を相手に悟られることなく吸収しながら日々を生きているというわけなのだ。自らのことを人生のコーディネータだといって笑った老人の顔をもう一度想い起こしながら、私は石田邸をあとにした。十三日の金曜日に、あらためてまたジグソーパズルを解きにやってこようと固くかたく心の中で誓いながら……。
東京に戻った私は、お礼状とともに次のような一篇の詩を老人に書き送った。その一文をしたためながら、相手の手元に手紙が届く頃にはあの屋敷は影も形もなくなっているかもしれないなどという想像に浸ったりしたが、幸いなことにその心配は無用だったようである。
風の対話
別々のところから旅してきた
透明な風と風との出逢いのように
光りを発して
瞬時にお互いの体を通り抜け
そしてすぐさま別れました
嘘のなかの嘘のような
真実のなかの真実のような
古くからある話のような
誰も知らない奇談のような
大詐欺師同士の対決のような
聖なる二人の高談のような
それは不思議な出来事でした
どこかで聞いた小噺のような
初めて耳にする物語のような
リアリティなど皆無のような
しかしなぜか信じられるような
モームの語る世界のような
モームその人のおとぼけのような
それは奇妙な対話でした
十三日の金曜日というのは一年のうちに一、二度しかない。遊び心を起こした私は、暦を調べて十三日の金曜日をチェックし、なるべくその日には他の用件を入れないように心がけ、穂高の石田老人のもとを訪ねるようにした。老人によって課せられた「人生模様ジグソーパズル」を解くには正直なところかなりの時間が必要だったからである。しかし、私は執拗にそのパズルに挑戦し続けた。そして、その結果浮かび上がった老人の人生は破天荒そのものであった。
博多に生まれ、地元の旧制高校を卒業した老人は、東京でのバーテンダーを振り出しに、天津、台湾航路の船員、中国青島での香具師の秘書、外国銀行の大連支店職員、上海の日本海軍武官府国外情報担当官、日本語学校経営、ドイツ染料会社社員、ジーメンス社員、イタリー大使館大使秘書、上海賭博場用心棒、日本陸軍兵卒といったような職業を次々と体験する。
ここまででも驚きなのだが、その人生が真に劇的な展開を見せるのはなんとそのあとなのだった。上海で終戦を迎えた石田は、一時期アメリカ情報部の翻訳作業に協力させられたりしたあと帰国、焼け野原と化した東京に戻って呆然とするが、そこで、当時のBBC極東部長ジョン・モリスと奇跡的にめぐり逢う。それが縁となり、天運と才覚の赴くままに戦後初の民間日本人として渡英、BBC放送日本語部局のアナウンサー兼放送記者となり、六年近くにわたって放送史にも残る活躍をすることになった。
その間、エリザベス女王の戴冠式に昭和天皇の名代として渡英した皇太子(現天皇)を当時の松本駐英大使らとともに迎え、BBC放送日本向け定時番組のアナウンサーとして、戴冠式関係のニュースや皇太子の英国での御様子などを放送した。皇太子を案内してロンドン市内のあちこちをめぐり歩いたりもしたという。石田が英国滞在中に、民間の有名日本人が相当数訪英したが、その人たちの案内にはBBC放送日本語部局の局員が当たるのが当時のならいであった。そのため、石田は、「春の海」で知られる箏曲の宮城道雄、社会運動家の市川房枝、英文学の小川芳男などをはじめとする多くの著名人とも親交があったようである。
英国での仕事を終え帰国した石田は、予備校講師を務めたり、英会話学校を経営したりするいっぽうで、著名な英文学者などの依頼を受け、英米文学作品の翻訳に積極的に協力することになった。いわゆるゴースト・ライターの走りみたいなものである。コナン・ドイルやアガサ・クリスティの作品などをはじめとして、下訳を手がけた本は八十冊以上にのぼり、「風と共に去りぬ」の訳者として知られる大久保康雄などのような高名な翻訳家の仕事もずいぶんと手伝った。ただ、石田は自分の名が表に出ることを好まなかった。それだけの実力と実績をもちながらも、彼は終始一貫して蔭の存在であり続け、けっしてその名を表に出すことはなかったのだ。それはこの人物特有の美学によるものだったと言ってよい。
「僕は二流の一流にはなれるが本物の一流になれる人間ではない。また、たとえそれが可能だとしても一流になろうとは思わない」と、石田老人はあるときふとそう漏らしたが、私にはその言葉がこの人物のすべてを物語っているように感じられてならなかった。
石田は帰国後、ずっと東京で生活していたが、あるとき、当時信州大学の助教授をしていた英文学者の友人、加島祥造を訪ねたことがあった。そして、その折に案内された安曇野一帯の気候と風土が気に入った石田は、生涯独身の身軽さもあって松本に移住、その後さらに穂高町有明の地の一隅に居を構えるにいたったのである。穂高町に住みついてからも、時折この地を訪ねてくる人々を彼一流の「魔力」で魅了し親交をもつとともに、地元の文化人たちとも深い交流を結び、現在に至ったものらしい。
碌山美術館の取り持つ奇妙な縁でこの不思議な過去をもつ老翁と廻り逢った私は、冗談混じりに課せられた翁自作の「人生模様ジグソーパズル」を完成させるのに十年近くの歳月を要することになった。問題のジグソーパズルを解き終えたあと、私はその想像を絶するその人生模様の全容を伝記小説のかたちで記録に留めようと思い立った。石田達夫個人の生涯にまつわる物語ではあっても、見方を変えれば、それはひとつのすぐれた近代側面史にほかならないと考えられるからであった。
当初、石田翁はその人生について書かれるのを嫌がっていたのだが、私の再三再四にわたる説得が効を奏し、最後には「まあ、府中のドラキュラのあなたにならどう料理されても仕方がないだろう」という軽口を叩いて伝記執筆を諒承してくれた。類稀な人食い老人を解剖し料理するなどというチャンスにはそうそう恵まれるものではない。鋭さも切れ味もいまひとつの筆しか持たぬ身ではあるけれど精一杯の努力はしてみようと、私のほうも決意を新たにしたような次第だった。

絵・渡辺 淳
「マセマティック放浪記」2003年1月29日
ある奇人の生涯 (5)
波乱の人生は博多ではじまった
石田達夫という想像をはるかに超えたこの奇妙な老人の「人生模様ジグソーパズル」を完成させるには、どうしてもその生い立ちを明らかにする必要があった。なかなかそのあたりのことを明かしてはくれない相手に、いささかジリジリしたものを覚えはじめていた私は、何回目かの「十三日の金曜日」の訪問の際に、さりげなくそのあたりのことに水を向けてみた。すると、ようやく石田は久しい沈黙を破って幼少期から青年期にかけての出来事を語りはじめたのだった。ときおり遠い目をしながら、一つひとつ確かめるようにして昔の記憶をたどる石田の言葉を一語たりとも聞き漏らすまいと、私は懸命に耳をそばだてた。
はじめのうちどこか自嘲の影を帯び淀みがちだった石田の語調は、聞き手の私がうまく話の流れに乗るにつれて、軽快なテンポに変わっていった。厚く重たい「時間の覆い」の下に眠り隠されていた記憶の地層が、いっきにその意識の表層まで押し上がってきている感じだった。老人は、明らかに、長年意識の底に押さえ込んできた遠い日の自分の姿を解放することにある種の快感を覚えはじめている感じだった。石田独特の軽妙なジョークが想い出話のあちこちに飛び出しはじめたのが、そのなによりの証拠と言えた。
大正五年(一九一六年)は国の内外において大きな社会思想変動の兆しがあらわれはじめた年だった。国内のあちこちでは、東京帝国大学教授吉野作造の唱える民本主義思想を支柱とする大正デモクラシーの風が吹きおこり、徐々にその力は増大しつつあった。また、ロマノフ王朝末期の帝政ロシアでは、ほどなく全世界を揺るがすことになる革命政権樹立に向って、労働者を中心とする新勢力が、旧支配勢力との間で激しい闘争を繰り広げていた。
この年の二月十日に石田達夫は博多の商人町の一隅で誕生した。ただ、当時の様々な家庭的事情などもあって、実際に地元の役所に出生届けがだされたのは誕生日から一ヶ月半近くもたった三月二十六日のことだった。したがって戸籍上の出生日はそれと同じ日付けになっている。この世に生を得た直後から、どうやらその人生は波乱含みであったらしい。
「ちょうどロシア革命の年に生まれた身だから、体制に反抗的な気質をもっていても仕方ないのかなあ……。でもあの国の旧政治体制は僕が死ぬ前に崩壊してしまいましたねえ。僕よりも短命だったわけですよ……」と石田はよく語ってくれたが、それは彼のちょっとした勘違いで、実際にロシア革命が起こったのはその翌年の昭和六年のことであった。
母親はその界隈ではかなり知られた筑前琵琶の師匠石田旭昇で、隆盛期には常時百人を超える弟子を擁していた。女優、高峰三枝子の母で筑前琵琶師の高峰筑風と石田旭昇とは同門の間柄であったらしい。父親については、もともとは山口出身の流れ者で、いつしか母親のそばに居つくようになったようだと、石田は笑いながら語ってくれた。その話によれば、父親はなかなかの男前だったが、「色男、金と力はなかりけり」の諺を地でいくような存在で、表向きは母親の仕事のマネージャーを名乗っていたものの、要するに母親の「ヒモ」だったのだという。
「僕はヒモの子として生まれたから、ヒモに繋がれるのが嫌で自由に憧れるようになったのかもしれませんねえ」
「でも、お母様の臍の緒というヒモを切って生まれてきたわけですから、その気質は生まれつきなんじゃありません?」
「でもねえ、糸の切れた凧みたいになっちゃって、ふらふらと世間の風に流されて仕舞いには落っこちちゃう危険もあったわけで、そんなときはヒモも悪くないかなあって思ったりもしましたよ」
「このまえ写真見せてもらって驚いたんですけど、二十代の頃の石田さんって凄い美男子だったじゃないですか……。それって男前だったお父様譲りだったんじゃありません?……まあ、いまじゃ昔の面影はどこへやら、すっかり妖しいドラキュラ顔になっちまったようですけど!」
私はそう言ったあと、さらにもう一歩踏み込んでみた。
「あのぶんだと若い女の子にずいぶんとモテたんでしょうね。ほんとうのところは、その時代の石田さんにはヒモが十本くらい絡みついていたんじゃありません?……もしそうだったとしたら、お父様に感謝なさいませんとねえ」
「ヒモも十本くらい集まるとロープになっちゃいますからね。そうなると身動きできなくなってしまうから、ヒモは細いうちに断ち切るようにしてきましたよ」
「切れたヒモを見て泣いたり恨んだりした女性もずいぶんといたっていうことですね。もしかしたら時には泣かせた男などもあったりして?」
石田翁との親交を重ね昔の話を耳にしたりするうちに、もしかしたらこの人物は若い頃両刀使いではなかったのかと感じることもあった私は、単刀直入そう切り込んだ。すると、相手は、そんな追及を軽くかわし、はぐらかすような口調で応じてきた。
「本来ドラキュラの好むのは若い美女の血なんですから、それはどうでしょうね。でもまあ、いまは私が生まれた時の話をしているところですから、そんな枝葉の話は後回しにしてまずは本題に戻ることにしましょう。そうでないと、いつまで経ってもジクソーパズルは解けませんよ!」
「うーん、たしかに人生模様ジグソーパスルがいつまでたっても完成しないんじゃ僕も困っちゃうんですよね。十三日の金曜日がせめて毎月一回くらいのあるならまだいいんですが……」
もっと相手の核心に迫って知られざるかつての石田像をあれこれと引き出したいのは山々だったが、こちらとしても、ここはいったん追及の矛先のおさめどころだと思わざるをえなかった。ジグソーパズルの中核部のひとつにあたる幼年期の全貌が見えないことにはパズルの解決はおぼつかないからでもあった。
石田が幼少期を送ったのは下町の典型的な十二軒長屋の一角で、しかも色町のすぐ近くだったから、近隣の住人の職業もその暮しぶりも様々だったようである。家の向いは芸者の置き屋で、毎朝三味線の音が響き、迎えの車の到着を告げる「君香さん、お座敷き〜っ!」などといったような呼び声が折々聞こえてきたりもした。右隣りの住人は近くの劇場のお茶子さん、その一つ隣が畳屋さん、左隣りは、小唄のお師匠さん、その隣りが仕舞いの先生、さらにその隣は大工さんといった具合で、一番奥の大きな一軒屋には、朝顔と鴬の鳴声を日々愛でて暮す御隠居さんが住んでいた。また、長屋の前の路地を抜けて出た表通りには、醤油屋、駄菓子屋、家具屋、芋屋、医院などが軒を連ねて並んでいた。
私と出遇った頃にはどこか異国的な風貌を湛えているようにも見えた石田翁だが、幼い頃は何から何にまで純日本的な雰囲気に包まれた特殊な環境の中で育ったのだということだった。意外そうに聞き入る私の表情を楽しむかのようにして、彼は、自分は骨の髄まで日本的な文化に染まって成長したのだと、当時のことを懐しそうに回想した。
筑前琵琶の師匠という母親の職業のお蔭で、石田は幼少時代から博多の劇場の舞台裏や芸人、役者たちの稽古の場に自由に出入りすることができた。当時の博多にあった大博劇場と川端劇場という二つの劇場にはとくによく出入りしたらしい。歌舞伎や能、狂言といったような古典芸能には、それらがどういうものかも解らないうちから体感的に訓れ親しんできたし、子供ならではの特権で芸人や役者の控えの間をのぞきに行っては彼らに可愛がられもしてきたから、日本の伝統芸能特有の空気とでもいったようなものが、石田の身体には知らずしらずのうちに刷り込まれていった。
過もなく不過もない少年時代を送った彼は小学校を卒業すると名門の県立福岡中学に進学したが、四年生になる頃までに社会の情勢は大きく変わり、それまで比較的安泰だった石田家もその余波を大きく被むるようになっていった。
大正デモクラシーの時代が終り昭和の初期に入ると、国際的な経済停滞の影響もあって国民の間には将来の生活に対する強い不安感が高まった。若い学生や知識人たちは資本主義の矛盾を批判し新たな社会の建設を謳うマルクス思想に共鳴し、多くの社会主義運動家が生まれたが、それらの動きに危機感を覚えた政府や軍部筋は激しい思想弾圧の道を選択した。昭和三年には政治犯や思想犯を取り締る「特高」、すなわち特別高等警察が全国の都道府県に設置され、内務省の強力な統制のもと国民のなかに網の目のようにスパイ組織を張りめぐらした。拷問、虐殺を常套手段とした特高の思想弾圧は、社会主義思想や共産主義思想に対してばかりでなく、やがて一般の人々の自由な発言や活動にまで及ぶことになっていった。やはりこの年、中国で関東軍参謀の河本大佐による張作霖爆殺事件が起こり、それを契機に関東軍は満州占領に向けて着々と画策をめぐらしはじめた。
石田が福岡中学に入学したのはこの昭和三年のことだったが、その翌年の十月にはニューヨーク・ウォール街株式市場で株価の大暴落が発生、それが引金となって世界中が大恐慌に突入した。昭和五年に入ると日本国内の不況はますます悪化し、米や生糸の価格が極端に下落したこともあって、農村の人々の生活は悲惨このうえないものとなった。なかでも東日本一帯の農村の窮乏生活は深刻をきわめ娘たちの身売りが激増、東京などには公営の身売り相談所が開設されるという異常事態にまで発展した。そんな娘たちの多くは芸妓や娼妓の世界へと売り飛ばされていったという。
関東軍幹部が謀略をめぐらして中国瀋陽郊外の柳条溝で満鉄線を爆破し、悲惨な戦争へと向かって暴走しはじめたのは、昭和六年九月、石田が中学三年生のときであった。この事件を契機に日本軍部は満州全体に軍事行動を展開、すでに盲従の徒と化しはじめていた一般国民は、有無を言わさず暗い時代の潮流の中へと巻き込まれていった。いわゆる満州事変の勃発である。軍部の思惑によって惹き起こされた動乱に揺れるその中国大陸が、それから数年もしないうちに自分の人生に深く関わってこようなどとは、まだ十五歳の少年だった石田にとっては想像もつかないことであった。
不穏な空気が支配的になったこの時代にあって、人々の心を大きく捉え市民生活に予想以上の影響を与えたのは、トーキー映画の発明とその急速な普及だった。アメリカで発明され、昭和四年に我が国に初登場したトーキー映画は、大評判となってあっというまに全国に広まり、それまでの無声映画を圧倒しはじめた。そしてその二年後の昭和六年には、翻訳したセリフを画面に焼き付けるスーパーインポーズ方式を採用したマリーネ・デートリッヒ主演の「モロッコ」が上演され、大好評を博しもした。トーキー・システムを用いた初の邦画が公開されたのもこの年のことである。また、この頃までには、かなりの数の家庭に蓄音機が普及し、洋楽、和楽を問わず様々なレコードが市販されるようになって、庶民文化の様相が一変した。
もちろん、石田もまたそういった新しい文化の潮流の到来を心から歓迎したひとりであった。すべての面で早熟でもあった彼は、トーキー・システムの映画に感動し、スクリーンに映し出されるマリーネ・デートリッヒの姿に恋し、その声を耳にしてしびれ、遠く遥かな国々へと少年の夢を馳せらせた。そしてまた、蓄音機から流れ出る美しい歌声や胸にしみいる演奏に何度も何度も聴き惚れた。だが、なんとも皮肉なことに、そんな時代の流行は予想もせぬかたちとなって禍に転じ、中学生の石田の身に降りかかってきたのである。
各種レコードの出現やトーキー映画の登場、さらには種々の西洋文化の急激な移入によって大きな影響を被ったのは、日本の伝統芸能にかかわる人々だった。筑前琵琶の師匠として一家の生計を支えていた石田の母親旭昇にも当然のようにその余波は波及した。さらに折からの世界的な不況もそれに追い討ちをかけた。それまで、いつも百人前後はいた筑前琵琶の弟子の数は一挙に激減し、舞台の仕事などもほとんどなくなってしまったため、石田が中学四年生になる頃には、石田家の経済状態は深刻な状況に陥っていった。
父親はいろいろな仕事に手を出したが、その気性のゆえもあってことごとく失敗、状況は悪化の一途をたどっていくばかりだった。四人の妹まで抱える家の生計の一端を担うため、長男の石田は新聞配達をはじめとするいくつかの仕事を試みてはみたが、焼け石に水の有様であったという。
中学を卒業したら授業料がいらない高等師範に進み教師になってほしいというのが父親の希望であったから、石田もそのつもりで頑張った。ところが、卒業まで一年を残した四年生の終わりのこと、高等師範の入試は難しいのでまずは入試の雰囲気に慣れるため試しに普通高校を受験してみたらどうだろうという話が持ち上がった。そこで、戦後になって九州大学に併合された名門福岡高校文科フランス語科を小手調べのつもりで受けてみると見事に合格、想わぬ結果に大喜びした父親は、高等師範進学の話などまるでなかったかのように、福岡高校への進学を息子に命じたのだった。そして、たとえ石にかじりついてでも大学まで出してやるから頑張るんだと、日々石田を励ました。

絵・渡辺 淳
「マセマティック放浪記」2003年2月12日
ある奇人の生涯 (6)
かくして職業遍歴の旅路へと
「ところがねえ、たとえ石にかじりついても大学まで出してやるって言った当の父親がですよ……」
「どうかなさったんですか?」
「急に死んじゃったんですよ。僕が福岡高校の一年生のときにね」
老翁はちょっと皮肉めいた口調でそう言った。
「僕もずいぶん早くに両親を亡くした身なのでご苦労はわかりますよ」
「石にかじりついても大学を出してやるなんて言ってたけれど、結局、かじりついてはみたものの、その石の硬さに負けちゃんたんでしょう。そもそも、『石田』という石だらけの田んぼを意味する姓をもつ男が石にかじりつこうとすること自体、間違っていたんですね」
「はははは……」
話の深刻さにもかかわらず、石田の軽口につりこまれた私は思わず吹き出してしまった。すると相手はさらに調子にのって言葉をつないだ。
「おなじイシダでも『遺志だ!』ってわけですね。そんな希望的な遺志だけを置き土産にされたってあとに残された家族はどうしようもありません。現実は厳しかったんですから……」
「亡くなった原因はなんだったんですか、病気でも?」
「ええ、結核性の喘息が原因でした。当時、結核は不治の病と言われていましたしね」
社会的な大不況、母親の筑前琵琶の仕事の行き詰まり、そして父親の急死という三重の非常事態のために、石田家の経済状況は壊滅的状態に立ち至った。高等学校に通うかたわら一家の生計を支えなくてはならなくなった石田は、アルバイトその他の都合もあったので、母親や妹たちを引き連れ博多地区から福岡地区へと移住することにした。伝統的な商人町として栄えた当時の博多から城下町としての歴史をもつ福岡地区へ移住することは、昔の浅草周辺の下町から現代の丸の内や内幸町あたりへと移り住むにも等しい生活環境の変化をも意味していた。
異常としか言いようのない石田の職業遍歴が始まったのはこの頃からのことだった。なんとか苦しい家計を支えようと必死になった彼は、高等学校へ通うかたわら、いくつものアルバイトに手を出した。花火をはじめとする玩具類の販売を皮切りに、フルーツパーラーでのボーイのアルバイト、バーテンダーのアルバイトなどを次々と体験した。とくにこの時代におけるバーテンダーのアルバイトは、のちに精を出すことになる様々な客商売の基本を学ぶうえで、さらには人間とはなんたるかを学ぶうえでまたとない貴重な経験ともなった。
体格もよく体つきもスマートで、父親に似てたいへんなハンサムボーイだった若い彼は、女性にもずいぶんともてもした。当然、そんな彼をお目当てにお店にやってくる女性たちもすくなくなかった。だが、彼はそんな仕事だけに甘んじてはいなかった。カフェ・バー勤めのいっぽうでは、家庭教師や各種のパンフレット作成といったような堅い仕事を手掛けもしていた。一家の生計を支えるために硬軟両面を巧みに使い分けていのである。
昭和十年に旧制福岡高校文科フランス語科を卒業した石田は、その翌年、満たされぬおのれの心の落ちつくべき場所を求めて単身上京を試みた。東京に出て一旗揚げたいという思いも幾分あったようだが、たぶんそれだけではなかったのだろう。旧制高校での学業も優秀だった石田は、東京帝国大学や京都帝国大学といった学問のメッカへの強い憧れが胸中に渦巻くのをどうすることもできないでいた。家庭状況からして進学は不可能だとはわかっていたが、上京すればなにかしらの学問のチャンスにも恵まれるかもしれないし、すくなくとも最先端の文化の息吹にも接することができるだろうという密かな期待が胸中には息づいていた。
だが、この昭和十一年は、我が国にとって大激動の年でもあった。大きな内部矛盾を抱えた日本陸軍の皇道派と統制派との対立の激しさはこの年に至って頂点に達し、二月二十六日、皇道派の青年将校に率いられた約千四百人の兵士たちは、五十三年ぶりの大雪の中を突いてクーデターを決行した。世にいう二・二・六事件の勃発だった。
博多という古来国際色豊かな商人町で生まれ育ち、人間の機微に深く迫る伝統芸能の世界に幼少期から慣れ親しんできた石田は、一見仰々しい国粋主義や権威主義の背後に潜む薄っぺらな本質を若いなりに見抜いていた。だから彼は、その時代としては珍しいほどにリベラルな思想をもち、時流に染まることもなく行動した。皇道派だろうが統制派だろうが、横暴に振舞う時の軍部というものは、彼にとって深い嫌悪の対象以外のなにものでもなかった。
当然、彼は、東京の片隅にあって、突然の事件に大騒ぎする世間の有様をひとり冷ややかに眺めていた。「下士官兵に告ぐ」と記されたビラを目にしたり、「兵に告ぐ、今からでも遅くない」という有名なラジオ放送を耳にしたりしもたが、醒めた目をもつ二十歳の青年の瞳には、その後の軍部暴走の契機となったこの歴史的な事件も別世界の出来事のように映っていた。むろん、日本という国の行く末に漠然とした不安がないわけではなかったが、このときの彼の胸中には、国家の動向にかかわらず徹底した個人主義を貫いてこの暗い時代を生き抜こうという思いが募るばかりであった。
上京した石田がまず手を染めたのは牛馬の売買に携わるバクロウの仕事であった。うまくいけばそれなりの収益を見込めると期待してのことだったらしいのだが、海千山千のその世界は、さすがに二十歳そこそこの素人の手に負えるような甘い世界などではなかった。伯楽から転じたというバクロウという言葉は和語では「馬喰」とも表記されることがあるようだが、彼は馬を喰うどころか、逆に馬に喰われるはめになって、たちまち行き詰まってしてしまったのである。のちに石田が馬を喰うのではなく人を喰うほうへと趣向変えをするにいたったのは、このときの苦い経験が身にしみていたからなのかもしれない。
このバクロウの仕事と並行して、石田は、当時東京帝国大学の赤門前にあったカフェ・バーで働いていた。不遇な家庭的事情のゆえに大学進学の夢は断念せざるをえなかったが、旧制福岡高校時代にひたすら憧れていた東京帝大の正門前の店で働くことによって、帝大教授や帝大生らの姿をかいまみ、彼らのもつ文化的な雰囲気に接することを通していくらかでも自らの心を慰めようとしたからだった。
赤門前のそのカフェバーに勤めるようになった経緯についてはそれ以上詳しく語られることはなかったが、学問への道を絶たれた当時の石田の挫折感は想像以上に大きかったのではないだろうか。「僕は二流の一流にはなれるが本物の一流になれるような人間ではない。また、もしもそんなことが可能だとしても一流にはなろうとは思わない」というのちのちの彼の言葉の背景には、その折にうけた人知れぬ深い心の傷が大きく影響していたふしが窺えてならないからである。長年のうちに磨き上げられたその能力と有無を言わさぬ実力にもかかわらず、生涯を通じて彼が純粋に学問的な世界を敬遠しがちで、学術分野の専門家に対しいくらかの心理的なコンプレックスを抱いていたのは、その折の大きな挫折感に起因するものであったように思われてならない。
在京中、石田は赤門前のカフェバーのほかに銀座のカフェバーなどにも勤めたりもし、その仕事を通してダンサーをはじめとする幾人かの若い女性たちとも懇意になった。一七六センチという当時の日本人としては珍しい長身、すらりとした筋肉質の体躯、そして二枚目映画スターとまがうばかりの甘くて知性的なマスク、ある種の存在感を秘めた美声と話術――若年にしてすでに、彼には女性たちを瞬時に魅了してやまないすべての要素をそなえもっていたといってよい。石田が二十代だった頃のスーツ姿の写真が資料として一枚手元にはあるのだが、そこに写っている彼の姿は若い男優ともまがうばかりのスマートさなので、若い女性たちがほっておくようなことはまずなかったに相違ない。ただ、この時代に銀座で知り合った女性の一人とのちに遠く離れた異郷の地でたまたま出逢い、彼女によって苦境に陥った身を救われることになろうとは、さすがの彼もその時は想像だにしていなかった。
上京してまだ長くはなかったが、東京という大都会での生活にも慣れた石田には、上京時の深い挫折感とは裏腹に、へんな自信が湧きはじめかけてもいた。見方によっては魔都とも言える東京で価値観の異なる様々な人間と出遭った彼は、そのことを通していったん自らの人生観を低い視線で解体再構築し、そのうえであらためて自我観の確立を試みたのだった。そのお蔭もあって、彼は、身ひとつであるかぎりは、どんなところにおいても、また何をやっても生き抜いていけるという自負を抱くようになっていった。
人間としての根本的な誇りを捨てることはけっしてなかったが、そうでないかぎりは徹底してピエロを演じることも平気になった。むろん、晩年まで失われることのなかった生来のナルシスティックな気質や、若さのゆえの鼻っ柱の強さなどがすべて払拭されたわけではなかったのだろうが、彼自身にすれば、大きく一皮むけた気分ではあった。もっとも、現実の人生の荒波はそんな自信をも一瞬にして打ち砕きそうな激しさで次々と石田の身に襲いかかってきたのだが、そんなことなどつゆ知らぬ彼はしばし達観したような気分にひたったりもした。
皮肉なもので、世渡りのコツのようなものをそれなりに身につけるようになったことが、それまで体内で半ばまどろんでいた石田の気まぐれな性格をいっきに目覚めさせる結果となった。女性問題なども絡んで仕事仲間とのちょっとしたもめごとに巻き込まれた石田は、それまでの仕事がらみの人間関係をすべて絶ち切ることを決意、それからほどなく東京での生活を捨て京都へと移住した。移住といえば格好もつきはするけれども、その気まぐれな振舞いの結果あとに残された仕事仲間たちにしてみれば、彼の転居は突然の失踪みたいなものであったに違いない。ともかくもそうやって京都に身を置くようになった彼は、加茂川にほど近いあるカフェバーに勤めはじめた。父親譲りの流れ者の気質がむくむくと頭をもたげてきたからだと彼は笑って話していたが、たぶん半ば本音ではあったのだろう。
移転先として京都を選んだ理由については石田はべつだん詳しく話してはくれなかった。ただ、幼児期に日本の伝統芸能や伝統文化に親しんで育った彼に、その原点ともいえる京都の文化の雰囲気をしっかりと体感しておきたいという強い想いがあったことだけは間違いない。いまひとつ考えられるのは、西の学問の府、京都帝大の存在である。東京帝大赤門前のカフェ・バーに勤めたときと同様の内なる思いが彼の胸中には渦巻いていたのかもしれない。
京都でのカフェバー勤めはそれなりに順調ではあったのだが、その年、京都の街は加茂川の氾濫による大洪水に襲われて多数の民家が水浸しになり、大変な混乱に陥ってしまったのである。加茂川近くにあった石田の勤めるカフェ・バーも当然甚大な損害を被り、営業不能になってしまった。おかげで急に仕事口がなくなったばかりか、前月分の給料さえも支払ってもらえない状況になってしまったのだった。とくべつなツテなどもないうえに、そのような混乱した状況下にあっては、すぐに京都で新たな仕事口を探すことなど難しかった。結局、失業状態に追い込まれてしまった彼は、とりあえずもう一度東京へ戻ってみようと考えた。
ところが、困ったことに京都に出てきてそう時間も経っていない彼には預金など皆無で、しかも給料は未払いだったから、東京までの旅費さえ持ち合わせていなかった。なんとか給料を支払ってほしいとカフェ・バーの店主に掛け合ってみたが、洪水による多大な被害のために店主自身が生活費に事欠く事態に陥っていたからまるで埒があかなかった。困り果てた彼はついに非常手段にうってでることを決意した。
「ここはもうトンズラするしかないと思ったんです。お店の二階の小部屋に寝泊りしてましたから、泥水浸しになりボトルやグラス類の破片が散乱するお店に自由に出入りすることはできました。幸か不幸か……いや、私にとっては幸いでお店のオーナーにとっては不幸なことだったんですが、高い棚に並べてあった高級酒だけはそのまま無事に残っていたんですね」
青年時代を回想する老翁は、そこまで話すともう想像がついたろうとでも言いたげな表情でニヤリと笑った。
「深夜に店におりるとジョニウォーカー三本を無断で持ち出し、そのままその場から姿を消したんです。まあ、ジョニーウォーカーが三本あれば未払いの給料と相殺ということになるかと考えましてね……。もちろん、ほんとの私の身元なんか店主は知るよしもないんで、あとになってからしてやられたって気がついたってどうしようもなかったでしょう」
「なにか面倒な事態が生じたとき、差し引き勘定をしてエスケープするのがのちに石田さんの定番になった背景はそんなところにもあったんですかね。合理的というか狡知に長けているというか……。で、そのジョニーウォーカーはどうなったんです?。まさか無賃乗車してそれで車掌や駅員を買収したんじゃ?」
「二本は闇市みたいなところで売って換金しました。そのお金を東京までの旅費に充てたんですよ。残りの一本はたしか自分で飲んじゃいましたね」
「じゃ身ひとつで東京に舞い戻ったわけですね」
「舞い戻ったなんてそんな……迷い戻ったんですよ!……情けない話ですが」
そう言って自嘲気味に笑った老人はさらに言葉をつないだ。

絵・渡辺 淳
「マセマティック放浪記」2003年2月19日
ある奇人の生涯 (7)
行き倒れてなお運を掴む
「なんとか東京には戻り着いたものの、お金の持ち合わせは皆無に近く、身を落ちつけるべきあてもなかったんです。かつての仕事仲間のところへ顔を出せばまあなんとかなったんでしょうが、さすがにそれは私の美学が許さなかったんでねえ」
「美学っていうのもなにかと厄介なものなんですねえ。媚学だったらよかったでしょうに!」
「唯一当てにできる知人がいるにはいたんですが、訪ねてみると何処かに引っ越してしまっていて、転居先はわかりませんでした」
「でも女性にはもてたんでしょ、非常手段として、銀座あたりの街頭に立って今夜の獲物はどれにしようか、なんてやったりはしなかったんですか?……それとも、ドラキュラも若い頃は結構紳士の一面があったんですかね」
このときとばかりに、こちらも少々意地悪な質問を浴びせかけてみた。すると相手はすぐに切り返してきた。
「はははははは……、八歳くらいの女の子か八十歳くらいのバアさんになら話しかけられたんですけどね、それはさすがに……」
「非常事態なんですから、選り好みなんかしてはおられなかったんじゃないですか」
「それでねえ、たまたま目についたある蕎麦屋に飛び込んで、皿洗いや出前などの手伝いをさせてもらうように頼んでみたんです。蕎麦屋の主人は胡散臭そうに僕の顔をしばらく見ていたんだけど、ほんとうに困っているらしいと感じたのか、とりあえず雇ってくれましたっけ……。さすがに住むところもないとまでは言えなかったんで、適当なことを話して誤魔化しておきました」
「それで、蕎麦屋にはどのくらい?」
「いやあ、仕事はきついし、日給は微々たるもんですし、そのうえ寝泊りする場所がないときているんですから、とてもなんとかなるような状況ではありませんでした。蕎麦屋だから蕎麦くらいはたらふく食べさせてもらえるかと思ったんですけど、そうは問屋が卸さなかった。だから三日目にはその蕎麦屋を辞めちゃいましたよ」
「石田さんの四十六とかいう職業遍歴のなかにはこの蕎麦屋勤めも含まれているんですかねえ?」
「もちろんですよ、のちの大連でのことなのですが、半日だけっていうのもありましたっけ!」
「で、蕎麦屋を辞めたあとはどんなふうに?」
「いや、正直言ってまいっちゃいましたねえ。どうやってでも生きていけるなんてへんな自信を持ちかけた途端にそのザマでしょ。日は暮れるし、腹は減るし、そのうえ泊まるところさえもないといった文字通りの浮浪者状態に陥ってしまって、世間を甘く見た自分のアホさ加減がつくづく嫌になっちゃいましてね」
「私の知る石田さんにしてはずいぶんと謙虚な話ですねえ……」
「ふふふふふ……でもまあ、またすぐに世の中を甘く見るようになっちゃったんですけどね。ただまあその時はね」
「喉元を熱さ過ぎればなんとやらっていうやつですか……」
「なんて言うか、僕は悪運が強くてねえ……」
「でもですねえ、悪運の強い人に大型クリーナーみたいな勢いで運を吸い取られる周りの人たちはたまったもんじゃありませんね。こりゃ僕も気をつけなきゃ」
「そりゃあなた、もう手遅れですよ、いまさら気づいたってね。こちらは吸い取ったあなたの運をそのうち使おうと思って冷凍保存してあるんですから!」
相変わらず老翁の口は減らなかった。
それから二、三日というもの浮浪者同然の状態で公園のベンチで仮眠したりしながら、何かよい仕事はないものかと石田は横浜方面へと足を運んだ。小銭の持ち合わせももまったくなくなり、水を飲んだだけで石田はまる三日ほど何も食べていなかった。だから、横浜港そばの山下公園周辺に辿りついたときには過度の空腹と先行きの心理的不安とが重なって心身の疲労は極限状態にいたっていた。全身から力が抜けるのを覚えた彼は、とりあえず身体を休めようと山下公園内のベンチに腰をおろした。そしてその直後にそのまま失神し倒れてしまったのだった。
だが、そんな石田を天は見放さなかった。僕は悪運が強いと豪語した通り、絶望的ともみえる人生の危機にさらされたとき、不思議なほどに彼には天運が味方した。もちろん、ただ単に運の良さだけでは片付けることのできない石田特有のオーラみたいなものが周辺に作用を及ぼした結果ではあったのかもしれないが、たとえそうであったとしても、その強運ぶりは驚くばかりだったと言うほかない。
その日がたまたま十三日の金曜日であったのかどうかはうっかりして確認し忘れたが、人生の転機になるような人物や出来事に遭遇するのはなぜか十三日の金曜日が多かったという老翁の言葉にしたがえば、この日もそうであったのかもしれない。見方を変えれば、十三日の金曜日が彼にとって縁起のよい日になったのは、その日たまたま幸運に恵まれることが続いたため、あるときからは十三日の金曜日になると、なんらかの転機を求めて彼のほうから無意識のうちに積極的に行動するようになった結果だったとも考えられる。
その日の夕刻、ベンチ脇に倒れて失神している石田を発見し介抱してくれたのは、当時山下公園近くあった公共職業斡旋所(現在の公共職業安定所)の所長だった。近くの自宅に彼を運んだその人物は家族ぐるみで温かく疲れきった石田の身体を介抱してくれた。その甲斐あって、翌日には彼の体調は元通りに回復した。元気になった石田の姿を見て心から喜んだ所長は、彼の経歴と、山下公園で行き倒れになるにいたった経緯のほどを尋ねてきた。
「石田君といいましたね。立派な体格もしているし、それなりの教養もある人物に見えるんですが、あなた、いったいどうことでこんなことになったんですか?」
「ええ、福岡高校卒業までは博多界隈に住んでいたんですが、父親が急死してしまったんで残された家族のためにも頑張らなくてはならなくなったんです。そこで、どうせ働くなら地元ではなく、文化の香りに満ちた憧れの東京でなにかよい仕事を見つけたいと思ったんです」
「それで……?」
「でも就職のための下準備も何ひとつせず、ツテなどもまるでないままの急な上京でしたから、とりあえずはカフェバーのバーテンやダンスホールの裏方などをやるしかなくなりまして……」
「せっかく高等学校まで卒業したのにですか……それに、そんなことじゃご家族を支えることなんかできっこなかったでしょう?」
「ええ、まあ……。それで、もしかしたらと思ってバクロウの仕事の片棒も担いだりしてみたんですが、とても僕みたいな素人の手に負えるような世界ではありませんでした……」
「この厳しいご時世にあって、そりゃ君、いくらなんでもムチャというもんですよ」
「一応、英語とフランス語の基本だけは身に着けてきたんですが、それを表看板に掲げて何か仕事を探すという気にはなれませんでした。その英語やフランス語だって実務に使えるレベルには程遠いものでしたらから……」
「気持ちはわからないでもありませんが、名門福岡高等学校卒業の君が、いきなり上京してカフェバー勤めというのはねえ……。もしかしたら、自分の美男ぶりにすくなからず自信があったからなのかもしれませんけどね?」
所長はくったくのない調子でそう言った。
「でも、赤門前のカフェバーやダンスホールでの仕事はそれなりに面白かったんですよ。そのあと京都に移り、加茂川近くのカフェバーで働いていたんですが、先日突然に市街一帯が大洪水に襲われてしまいました。とくに僕の勤めていたお店のある周辺は洪水の直撃を被りまして……」
「働いていたお店も営業不能に陥ってしまって、それでやむなくまた東京に戻ってきたっていうわけなんですね?」
「ええ、あのぶんじゃ、すぐには給料を支払ってはもらえそうにありませんでしたし、だからといって、いつのことになるかわからない店の復旧を待っているわけにもいきませんでした。京都に移ったばかりで貯えもまったくありませんでしたから……」
「それでどうしたんです?」
「お店の人には申し訳なかったんですが、結局、身ひとつで夜逃げを敢行するしかなかったんです」
「東京まではどうやって……、旅費もかかったでしょうに?」
「給料を払ってもらえないことはわかっていたので、どさくさに紛れ、無断でお店のジョニーウォーカー三本を持ち出しました。そしてそれらを適当に換金処分して東京までの旅費を工面したんです」
石田は命の恩人とも言うべき職業斡旋所長の問いかけに正直に答えた。二十歳にして既に世の中を斜めに見据えているところはあったにしても、のちにみる彼特有のおそるべき風貌や人を食った会話の片鱗などそのときの様子からはまだ窺い知ることができなかった。そんな彼に所長はさらに問いつづけた。
「東京に戻ってきて、そのあとどうしたんですか?」
「もちろん、泊まるところも一時的に身を寄せるところもありませんでした。いきなり姿を消すようにしてもとの仕事仲間との縁を断ち京都に移ったわけですから、前に働いていたカフェバーにまた顔を出すなんてことはとても……」
「それで、横浜方面にふらふらと?」
「いえ、どうしても当座のお金が必要でしたから、たまたま目にした蕎麦屋に飛び込み、なんとか出前の手伝いでもやらせてもらえないかと頼み込んだのです。でも、結構重労働な上にコツの要る仕事で、しかも雀の涙みたいな報酬とあっては三日ともちませんでした。蕎麦くらいは只で食べさせてくれるだろうという目算も外れてしまって……」
「あまりにも無計画で無鉄砲な振舞いだったようですから、自業自得と言ってしまえばそれまでなんですが、それでも、倒れた場所が山下公園だったというのは、不幸中の幸いだったかもしれませんね」
「ええ、お蔭で助かりました。今回ほど人様の情が身にしみたことはありません。蕎麦屋を辞めたあとは浮浪者の生活そのものでした。公園の片隅のベンチなどで時々身体を休めたりしながら、着の身着のままの姿でふらふらとここまでやってきました。横浜に来れば何か仕事が見つかるかもしれない、せめて食べ物くらいにはありつけるかもしれないと思いながら……」
「気を失って倒れているあなたの姿を見つけたときは驚きましたよ!」
「山下公園にやってきたところまでは憶えているのですが、そのあとのことは何が何だかさっぱり……。極度の空腹と疲労のため突然に全身の力が抜けそのまま意識がなくなってしまったんです。お恥ずかしいかぎりなんですが」
石田とそんな会話を交わしたあと、しばらく何事か考え込んでいた所長は、はたと思い当たったような表情であらためて口を開いた。
「あなたは長身でスマートだし、高等学校卒業という立派な学歴もあって、しかも英語とフランス語の素養もそなえてもいるんですから、選り好みしなければ働ける場所はありますよ。昨日も話しましたように、私はたまたま近くの公共職業斡旋所の所長をやっていますから、近いうちに正式に何か仕事を紹介してあげましょう」
「行き倒れの身を介抱してもらっただけでも感謝し尽くせない思いですのに、そこまでご心配くださるなんて、なんとお礼申し上げてよいものやら……」
石田はかしこまってそう答えた。人を食って生きているなどと公言して憚らない後世の彼の姿など嘘のような謙虚さであった。
「石田さんといいましたね。あなたは台湾航路の貨物船に乗って仕事をする気はありませんか?」
「はい、この際ですから、どんな仕事でも……。それに、もともとひとつの場所にじっとしているのが好きなタイプの人間ではではありませんから……」
「そうですか、それじゃ話は早いですね。郵船会社に就職できるように私が斡旋してあげましょう」
「そんなことお願いできるんでしょうか」
「海は大丈夫ですよね……はじめのうちは船酔いしたりするかもしれませんが?」
思わぬ展開に意表を突かれ、しばし考え込んだあと、おもむろに彼は答えた。
「ええ、船に乗った経験はほとんどないんですが、環境適応力はあるほうですのでしばらくすれば慣れると思います」
「そうですか、じゃ、さっそく近日中に手続きをとることにしましょう。実際に船員として乗船してもらうのは年が明けてからになるとは思いますが」
「願ってもない話ですから、是非宜しくお願い致します」
「まあ、それまでの間は簡単なアルバイトか何かを紹介しますから、それで食いつなぎながら、時間のあるときに海運についての勉強でもしておいてください」
この職業斡旋所長とのなんとも不思議な廻り逢いが発端となって、石田は波瀾万丈の人生航路の直中へと船出していくことになったのだった。だが、その航路の前途に待ちうける数奇な運命に若い石田の想像が及ぼうはずはむろんなかった。当時としては高学歴といってよい旧制高校卒業者で、しかも英語とフランス語の素養が一定程度あることを知った所長は、その能力を高く評価し、台湾や中国大陸方面への航路を保有する日本近海郵船に彼の就職を斡旋した。かくして石田は、翌昭和十二年(一九三七年)に貨物船の船員となり、中国大陸という広大な大地に足跡を刻むための願ってもない糸口を掴んだのだった。

絵・渡辺 淳
「マセマティック放浪記」2003年2月26日
ある奇人の生涯 (8)
新たなる船出
石田が日本近海郵船所属の貨物船の船員となった昭和十二年(一九三七年)は、世界をゆるがす大激動の発端となった盧溝橋事件が勃発した年でもあった。同年七月七日夜、北京郊外における日本軍の夜間演習のあとに起こったこの事件を契機にして、日中両国は本格的な戦争状態へと突入した。
この夜の演習終了時に突然闇の中で数発の銃声が響き渡った。その直後、たまたま一名の日本軍兵士が所在不明になったため、ただちに主力部隊が出動する騒ぎとなった。所在不明となっていた兵士は、実際にはトイレに入っていただけで二十分後には無事発見されたのであるが、それをまたとない契機と睨んだ日本軍は翌日未明には中国軍を攻撃し、盧溝橋の架る河の左岸を制圧した。
七月九日には日中間でいったん和解協定が成立したが、日本政府と陸軍は表向きには不拡大方針を掲げながらも、そのいっぽうでは、関東軍ならびに国内三個師団を現地へ派兵すると表明した。そのような日本軍部の動向を知った中国側の反日感情は日増しに高まり、ついには蒋介石や中国共産党も抗日戦を叫ぶようになっていった。日本軍はこれを中国侵攻の絶好の機会と判断し、七月二十八日には中国軍に対して総攻撃を開始した。
日本陸軍内部の強硬派主導の謀略に基づく意図的な開戦というのが一連の事態の真相で、その後八年にわたり凄惨な日中戦争が繰り広げられることになったのだが、当時の国際世論の手前もあって、日本政府や軍部は「戦争」とはいわず「事変」という表現を用いつづけた。だが、日露戦争以来、戦時のみに設けられることになっていた大本営が「事変」においても設置できるように法的な改革がおこなわれ、この年の十一月二十八日には悪名高き「大本営」が宮中に設置されるにいたった。
石田が日本近海郵船の船員となったのはこの年の始めだったので、まだ日中事変は勃発してはいなかったが、内外の世相の不穏な動きを鋭く感じとっていた彼は、船に乗って広い洋上に身を浮かべ、その息苦しさから解放されることを心から願うようになっていた。
その年が明けてまもなくのこと、石田は横浜港で日本近海郵船所属の僚船に同乗し、自分の乗る船の待つ小樽港へと向っていた。冬の海はひどく荒れており、船は絶間なく激しいローリングとピッチングを繰り返した。船内特有のむっとするような異臭の洗礼もひどく彼を苦しめた。船が東京湾を出て外洋に入ると、まるでそれが通過儀礼でもあるかのごとくに、激しい吐き気と頭痛とに襲われ、幾度となくその対応に窮する羽目になった。
だがそういった悲惨な状態にもかかわらず、石田は後悔の念などひとかけらもいだいてはいなかった。一時的なその苦しみを克服することができさえすれば、幼い頃から密かに憧れてきた海の向こうの未知なる世界へと間違いなく足を踏み入れることができるからだった。ひどい船酔いにのたうちまわりながらも、その胸の奥底にはほのかに輝く希望の光が灯りはじめていた。一見コワモテな感じのする海の男たちが、実は人一倍心優しく、信頼に値する存在であるとわかったことなどもすくなからず彼の心の支えとなった。
さんざん船酔いに苦しんだ石田がなんとか船外の様子を眺めてみようかという気になったのは、横浜港を離岸した翌々日のことであった。船はちょうど津軽海峡へとさしかかろうとしているところだった。津軽海峡を東から西へと向かう船上には、激しい吹雪が、冷たい荒潮の飛沫とまじりあいながらこれでもかといわんばかりに叩きつけていた。それはあたかも波瀾に満ちた石田の前途を象徴でもするかのような光景であったが、その時の彼にはなぜかそのことが心地よくさえ感じられもした。いま一度人生を出なおすためにあらためて禊(みそぎ)をうけているような気分だった。
まだ足取りこそおぼつかなかったが、それでも船の揺れにいくらかは慣れてきた石田を船長は特別にブリッジに招き入れてくれた。前方から吹きつける無数の雪片と次々に寄せ来る大浪を船体ごと叩きつけるようにして切り分け進む船の有様は、どこか狂気じみてもおり、それでいてまた勇壮そのものでもあった。船長は操舵輪を航海士に任せると、彼に向かって鄭重な口調で話しかけてきた。制服に身を固めた船長の身振舞いには、「海の紳士」という言葉に恥じないだけの威厳と気品とが溢れていた。
「どうですか、はじめて乗る貨物船は?」
「ええ、鹿島灘から三陸沖にかけてのあたりを通過しているときにはひどい吐き気と頭痛に襲われまして、どうにもなりませんでした。そんな状態が永遠につづくのではないかって思ったりもしまして……」
「ははははは……、そりゃまあ無理もないですね。いきなりこの冬の荒海の航行というわけですからね」
「でも、船室でさんざんのたうちまわっていたら、不思議なもので幾分楽にはなってきたんですよ。もちろん、まだ頭は痛いし、身体の調子もいまひとつで、とても食事などうけつける状態ではありませんけれど……」
「台湾航路の貨物船に乗るらしいですね。まあ、それだったら、二、三週間もすれば身体も慣れてきますよ。それに、こんな時化模様の日ばかりじゃないですからね。海が凪いでいて、すばらしい朝日や夕日、あるいは素敵な星空などが見られることだってありますからね」
ひどい揺れのなかでも床面にぴたりと足が吸いついた感じで、さりげなくバランスをとりながら前方を睨む船長の姿に、石田は不思議な感動を覚えさえした。
「こんな視界不良のなかでよく操船ができますねえ?」
「そりゃまあ、長年の経験といいますか……、それに、海図をもとにした専門的な位置確認の方法もいろいろとありましてね。また、吹雪で視界不良とはいっても、一瞬ですが、時々、本州や北海道の陸地の影が見えたりもしますから、それによってもおおよその位置はつかめます。夜間航行だっていつものことですからね」
「暗夜航路っていうわけですか。そういわれてみますと、昨夜だって夜間の航海でしたものね」
ブリッジ内の作業デスクには詳細な書き込みのある大きな海図が一枚広げられていた。船長はさりげなくそのほうに視線を落としながら言った。
「なにごとも経験ですからね。奇妙なもので、ある種の勘っていいますか、そういったようなものが身についてくるんですね」
相変わらず船長の言葉は鄭重そのもので、若い石田はそのぶんかえって身の引き締まる思いだった。その言葉の一つひとつには命がけで海に生きる者ならではの気概のようなものが感じられてならなかった。
突然、大きなローリングとピッチングの複合攻撃に襲われた石田は、おもわずブリッジの壁面によろけかかった。しかし、船長や航海士はすぐに姿勢を立て直し、なにごともなかったかのように操船を続けていた。それを目にした彼の胸中には畏敬の念さえも湧いてくるありさまだった。生来鼻っ柱の強いその身にしてみれば、なんとも珍しいことではあっが、それは、海という悠久の存在がそれとなく石田にかけた魔術のなせるわざだったのかもしれない。
「いま下北半島の大間崎沖を通過しました。大間崎は本州最北端にあたる岬ですね。それと、もうすこし視界がよいときなら、ほどなく右手に函館山が望めるはずなんですが……。でも、この様子だとちょっと無理かもしれませんね」
「どこのあたりなのかはわかりませんが、時々右手に北海道のものらしい山々の白い影が霞んで見えてはいましたよね」
「そうそう、エイの尾ビレの右側にあたる部分ですね」
「はあ……?」
「ああ、北海道のかたちって、どことなく魚のエイに似ているでしょう。その尻尾の右ヒレにあたるところっていう意味ですよ。亀田半島といいますけどね」
船長はそう言いながら海図のほうに近づくとその一端を指さした。
「なるほどそういうことですか……」
そう応えながらあらためて北海道のかたちを確認する石田の胸に、突然、不思議な感動が込み上げてきた。これまでただ遠く漠然とした存在にすぎなかった北海道が目の前にあって、ほどなく自分はその地の要港小樽に初の一歩を刻むことになる、しかも、その地を起点にした船旅の前途には、日本海、東シナ海をはるばる越えたところにある広大な大陸が待ってもいる――船酔いの辛さも忘れ、しばし彼はそんな思いにひたっていた。山下公園での行き倒れの一件を境にして、おのれの人生航路を吹き抜ける風向きが大きく変わってきたらしいのはどうやら確かなことのようだった。
やがて船は津軽半島の突端、竜飛岬の沖合いを通過して日本海へと入った。大陸から日本海を越えて吹き寄せる北西の季節風に煽られて、海面は大きく波立ち、小山のようにうねっていた。なぜか船が日本海を沖合いに向かって進むにつれ雪は小降りになってきて、そのぶん視界がひらけてきた。沖合いの暗い水面一帯からは大量の水蒸気が絶間なく立ち昇り、それらが重く低く垂れ込めた黒雲の中へと次々に吸い込まれていくところだった。船がうねりの頂点に達するごとに、石田はその重々しい光景に憑かれたように見入っていた。
黒と灰色だけの寒々とした世界であるにもかかわらず、そこに広がる海と空には何物かを新たに生み出すエネルギーが無尽蔵に秘め蓄えられているように思われてならなかった。暗い海面からさらに暗い上空へと向かって激しく立ち昇る水蒸気は、その途方もない創造のエネルギーを象徴しているようにも感じられた。黒と灰色の織りなすモノトーンの世界こそが生命の躍動する色彩豊かな世界の隠れた演出者であることを石田はあらためて実感していた。そして、おのれの今後の人生においては、ある種の確信と意志を抱きながら、けっして臆することなくモノトーンの世界に踏み込んでいこうとひそかに決意した。
モノトーンの世界に正面きって身を投じることがなければ、その向こうに広がる色彩豊かな実りの世界へと飛躍するなどもともと不可能なことである。「身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ」という昔ながらの教訓が、それまでになく新鮮なものとなって石田の脳裏に浮かび上がってもきた。彼の人生全体からすれば、まだ薄皮がほんの一皮むけた程度にすぎなかったのかもしれないが、ささやかな脱皮をまたひとつ経験したことだけは確かだった。
そのあと石田は船室にもどって乗組員用ベッドですこし眠った。再び目が覚めたときには、船はどこかの半島の先端にあたるらしい岬をまわろうとしているところだった。こころなしか、船の揺れは小さくなった感じだった。断崖に取り巻かれたその岬の背稜一帯は純白の雪に覆われていて、岬の先端のすこし沖合いの海中からは、黒々とした巨岩がひとつ天に向かって屹立(きつりつ)していた。鋭く切り立つその岩の頂き付近は氷雪に覆われており、みるからに神々しい感じだった。
その光景にみとれている石田に、甲板員のひとりが、「あれが積丹半島の神威岬(かむいみさき)、そしてあの大きな岩が神威岩ですよ」と教えてくれた。彼にすれば、一度か二度その名をどこかで聞いたくらいの知識しかなかったが、初めて目にする神威岩の偉容はなんとも感動的なものであった。長年の嵐雪(らんせつ)や風浪による侵食に耐え、毅然(きぜん)として海中に聳えるその奇岩の孤高な姿は、無言のうちに人間のあるべき理想の姿を暗示しているかのようにも思われた。小樽入港が間もないことを告げるこの天然の海標を石田は以降何度も目にすることになったのだが、その時眺めた神威岩の荘厳な光景はとりわけ心に残るものではあった。
日本有数の商港小樽は、初めての船旅になにかと戸惑いの多かった若い石田を温かく迎え入れてくれた。小樽港の岸壁に横づけになった貨物船のタラップを降り、北の大地に初めての足跡をしるす彼の感慨はひとしおだった。肌を刺す寒気には一瞬さすがにたじろぎもしたが、胸の奥に灯る一条の希望の光がその寒気から彼の身体を守ってくれた。
運河沿いに立ち並ぶ石造りや煉瓦造りの巨大な倉庫群の周辺は、真冬の季節であるにもかかわらずそれなりの活況を呈していた。折から国内外が大不況に陥っていた時代でもあったので、小樽港のすくなからぬ賑いぶりはいささか意外でもあった。港湾近くの日本近海郵船の出張所で関係者と挨拶を交わし必要な事務手続きを済ませたあと、石田はゆるやかな上り坂の道をたどって繁華街のある小樽駅方面へと歩いていった。満足な防寒コートも防寒靴も持ち合わせない身には、積雪で凍りついた路面を吹き抜ける夕風はひどく冷たくも感じられた。歩きなれない夕暮れの雪の坂道は想像以上につるつると滑って何度も転倒しそうになった。だが、それにもかかわらず、彼の心はたとえようのない不思議な解放感に溢れていた。そして、そんな彼を、海の男たちのたむろする酒場の灯はこのうえなく優しく温かく迎え入れてくれたのだった。
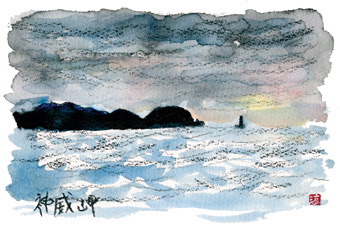
絵・渡辺 淳
「マセマティック放浪記」2003年3月5日
ある奇人の生涯 (9)
基隆への初船旅
石田が乗船することになったのは「氷川丸」という三千トンの貨物船だった。氷川丸というと、かつて米国航路に就航していた日本郵船所属の客船で、現在は横浜港岸壁に繋留され観光スポットのひとつになっている「氷川丸」のことを思い浮かべる人もあろうが、もちろんそれとは別の船である。この氷川丸という貨物船は、当初、小樽―基隆(キールン)、あるいは小樽―高雄(カオシュン)間を結ぶ航路に就航していた。北海道と当時日本の支配化にあった台湾とを直接に繋ぎ、両地域間の物資の運搬にあたるのがその主要な役割だった。
石田はこの貨物船にタリーマンとして乗り組んだ。タリー(tally)とは船荷証券、すなわち、発送貨物の届け先、発送人、内容、重量、特記事項などを記載した書類のことであるが、通常の荷札などもふくめてみなタリーと呼ばれている。そして、タリーマン(tally-man)とはそれら船荷証券をもとに積荷の内容や重量その他の詳細を検閲管理する係員のことをいう。船の運行に直接関わる仕事ではないために、一定の書類管理能力や計算力、語学力などがあれば、操船関連技術の資格を持たない者であってもその任務に就くことは可能であった。
氷川丸が出航するまでのあいだ、タリーマンとしての基本的な仕事内容を学んだりチェックしたりしながら、石田は出航の日を待っていた。タリーマンの仕事が多忙なのは母港や寄港地での貨物の積み下ろしの際だけで、航行中はそれほど忙しいというわけでもなかった。したがって、必要とあれば、目的地へと向かう間にまだ不十分な業務関係の知識などを学び補うこともできたので、その点についての不安はあまりなかった。
氷川丸が小樽を出港したのは、一月中旬の早朝のことだった。寒さは相変わらず厳しかったが、冬の日本海にしてはわりあい波の穏やかな日のことであった。港を出た船は積丹半島を左手に見て進み、半島突端の積丹岬や神威岬をまわり終えると、一路南へと向かって大きく舵をきった。氷川丸船員としての初航海をまるで励まし祝福でもしてくれているかのような神威岩のたたずまいが、石田にはなんとも印象的に思われた。
横浜から小樽へと向かう過日の初航海のときと違って視界は思いのほか良好で、船の揺れもずっとすくなかった。南下する船の左手遠くには白雪を戴いて輝くいくつかの峰々の姿が望まれた。どうやらそれらはニセコ連峰の山影のようだった。はるか沖合いの海上から目にする北の大地の白い山並みにすくなからぬ感動を覚えながら、この新たな人生航路への旅立ちにいたるまでのいきさつを、石田はあらためて不思議なおもいで顧みていた。
もちろん、彼には、目に飛び込んでくるものの何もかもが珍しくもあり興味深くもあった。だから、好奇心に誘われるままに船内をあちこち移動しては、いろいろなものを覗いたり触ったりしてまわった。ところが、船が奥尻島の近くを通り抜け、津軽海峡の西側沖合いへと差しかかる頃になると、船の揺れが急に大きくなってきた。先日の航海のときほどではなかったが、新米船員の身にはやはりこたえた。たちまち吐き気を催した彼は、青ざめた顔でトイレへと飛び込んだ。船酔いの洗礼をまがりなりにも受け流すことができるようになるまでにはまだ時間がかかりそうだったし、ましてや、揺籃(ゆりかご)の中の赤子のようにピッチングやローリングを笑顔で楽しめるようになるまでには、さらなる訓練と経験とが必要なようだった。
船長や甲板長の配慮もあって、身体が船に慣れるまでは自分のペースで自由に行動しても構わないということになっていた。だから、石田はトイレを出たあと、いったん乗員室の自分のベッドに潜り込んで横になり、ひたすら酔いがおさまるのを待った。そして、再び気分が安定するとベッドから起き上がって事務室に戻り、なにげなく書類をめくってみたり、船窓越しに外の光景を眺めてみたりした。一刻でもはやく船内での生活に慣れようと彼は彼なりに必死であった。容易にはめげないチャレンジ精神こそが彼の持ち前でもあった。のちにみるようなその並外れた環境適応能力は、ひとつには生来の資質もあったのだろうが、それ以上に、そのような不屈の意志によって積み重ねられた数々の経験に負うところが大きかったに違いない。
繰り返し襲ってくる船酔いと戦いながら、気をまぎらわすかのように船窓から外の光景を眺めやっていると、ひときわ大きく美しい山影が突然視界に飛び込んできた。まるで海面から直接聳え立っているかのようにして見えるその山は、広大な山麓から山頂までがすっぽりと純白の積雪に覆われており、なんとも神々しいばかりのたたずまいだった。幸いなことに風浪はかなりおさまってきていたので、彼は船室を出ると、北西の季節風の風下側にあたる左舷のなかほどに立ってその光景を食い入るように見つめつづけた。
なんという山なのかよくわからなかったのでそばを通りかかった甲板員にその名をたずねてみると、「あれは鳥海山ですよ。昔から船乗りたちの間では航海の目印として知られる山だったみたいですね」と教えてくれた。あれが有名な鳥海山なのかと思いながら、石田はあらためてそのはるかな山容を仰ぎやった。まだ船舶技術が現代のように発達していない時代、船乗りたちは海上から目視できる各地の特徴的な山々の影を位置や方向確認の目印として用いてきた。北前船全盛の時代などに、この鳥海山が最上川河口の要港酒田へと向かう舟人たちの目印になっていたことは、地理か歴史の時間に教わって知っていた。
しかし、それまでの彼にとって、そのような知識は実感の伴わぬ「単なる知識」にすぎなかった。いにしえの舟人たちとおなじように、海上から鳥海の山影を目にすることができたいまになってはじめて、かつてこの山がもっていた重要な役割や、それが海の男たちに与えたであろう安堵感の深さを身をもって感じ取ることができた。彼の乗る氷川丸は三千トンもあったが、北前船時代やさらにそれ以前の時代の和船が小さくてその性能も航海技術も貧弱であったことを思うと、日本海の荒波に文字通り命を賭けた昔日(せきじつ)の舟人たちの気概というものがつくづくと偲ばれもした。
二日半ほどをかけて日本海を航行し終えた氷川丸は、対馬海峡を通過し、五島列島の西沖合いを経て東シナ海に入った。幾分かは身体が海に慣れてきた感じではあったが、まだ本調子というにはほど遠かった。そもそも、船上生活における本調子とはどのようなものであるのかが新米船員の身にはまだとんとつかめてはいなかった。
大陸からの季節風の吹く真冬のことだったから、東シナ海もまた新米クルーの石田を優しく迎え入れてはくれなかった。先輩船員らの話からすると大時化(おおしけ)というほどのことではないらしかったが、彼にしてみれば、初めて目にする東シナ海の風浪の有様は大時化のそれとなんら変りのないものだった。
相変わらず不規則な上下動をつづける船上にあって、彼は、氷川丸での就労がきまったあとにちょとだけ読みかじった船舶史の記述を思いおこしたりもした。奈良時代から平安時代にかけ十数次にわたって大陸に派遣された遣唐使船団は、この東シナ海の荒波をこえて大陸との間を往復した。当時の遣唐使船は、気密甲板をもたず風浪に対してもきわめて安定の悪い平底の小型木造帆船だった。しかも、風まかせの航海を余儀なくされていた関係で、北西の季節風の吹き荒れる晩秋から真冬の時期にかけて復路をたどるのが普通であった。
遣唐使団員の生存帰還者が全体の四分の一ほどにすぎなかったのは、とくに復路における遭難率がきわめて高かったためだと言われているが、この冬の東シナ海の荒れようをまのあたりにして、彼は、そんな危険をおかしてまで渡唐し、唐代の文化の真髄を持ち帰った当時の人々の執念と決意のほどに心底感嘆を覚えざるをえなかった。
東シナ海を南南西に縦断し台湾のほぼ北端に位置する基隆(キールン)に入港するまでには、東シナ海に入ってからさらに二、三日ほどを要した。はじめはなかなか胃が受けつけてくれなかった食事も基隆が近づく頃にはそれなりには取れるようになっていった。小樽を出港した当初は食事のメニューになどまるで関心がなかったが、あらためてテーブルを前にしてみると船の食事は思いのほか豪華だった。北海道産の新鮮な魚貝類はいうまでもなく、肉類や野菜類もそれなりに供されており、大不況下における庶民の食卓の有様からすればそれは贅沢このうえないもののようにも思われた。空腹と疲労のあまり山下公園で行き倒れになったときのことを考えると、雲泥の差と言うべきだった。
船は琉球列島のはるか西方海上をひらすら南下しつづけた。あと一日足らずで基隆に到着するという頃になると、冬の海上であるにもかかわらず、ずいぶんと気温が上がり、海上もすっかり穏やかになってきた。長袖シャツ一枚でも平気なほどで、厳冬期の小樽の凍てつくような寒さがいまはうそのようだった。気温の上昇を肌で感じとるにつけ、確かに自分が母国を離れ、遠い南の異郷の地へと近づきつつあることをあらためて実感したりもした。ふと思い立って目指す基隆の位置を地図上で確認してみると、ほぼ北緯二十五度線の上にあることが判明した。北回帰線の一度半ほど北にあたる地点だから、太陽の日周軌道が南回帰線寄りに移動している時期とはいえ、基隆港が近づくのにつれて気温が上がってくるのも当然のことだった。
台北の東北東三十キロほどのところにある基隆は天然の良港に恵まれているため、当時から台湾随一の交易基地になっていた。北海道産の諸物資を満載した氷川丸は、風浪との格闘に疲れた船体をしばしのあいだ休め癒しでもするかのように基隆港に着岸した。三方を山々に囲まれた深い入江の奥に位置する基隆港は、折からの小雨に煙って全体的に霞んでみえた。基隆というところが年間を通じてほとんど雨模様の天候ばかりの土地柄だということを、そのとき石田はまだ知らなかった。
基隆港に着いた彼を待っていたのはタリーマンとしての海外での初仕事だった。起重機で次々に船倉から下ろされる貨物の荷札を船荷証券の原本と照合確認し、不備のないように細心の注意を払いながら積荷の陸揚げを差配した。その作業が終わると、今度は逆に台湾から小樽へと運ぶ貨物の船積みが待っていた。まだ不慣れの点も多かったのでいくつかの小さな不手際はあったけれども、最終的にはすべての業務をうまく処理することができた。新米タリーマンとしては上々の仕事だといってよかった。
大量の貨物の積み下ろしや燃料その他の補給のために何日かを要したので、石田は仕事の合間を縫って基隆の街並みを散策した。当時の台湾が日本の支配化にあったとはいえ、目にするものはなにもかもが異国情緒にあふれていて、彼の好奇心をいやがうえにも煽り立てた。連日雨が降りつづいているのが気になりはしたが、ここはもう日本本土ではないという思いからくる解放感と大きな心のときめきは、その陰鬱さをおぎなってなおあまりあるものだった。
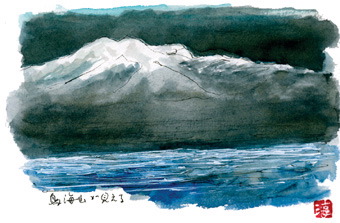
絵・渡辺 淳
「マセマティック放浪記」2003年3月12日
ある奇人の生涯 (10)
荘厳なる海上のドラマ
北海道と台湾の間を何度となく貨物船に乗って往復するうちに、いつしか季節も冬から春、そして春から夏へとうつりかわっていった。当初はずいぶんと船酔いに苦しめられていた石田もいまではすっかり船上での生活に慣れ、タリーマンの仕事をそつなくこなせるようになっていた。持ち前の能力を発揮しはじめた彼は船員仲間からも信頼されるようになり、なかでも中年のボースン(甲板長)などには、石田、石田となにかにつけて我が子のように可愛がられるようにもなった。航行中、かぎられた船内の空間しか動きまわれないことをべつにすれば、衣食住も保証されており、余計な出費もかからないとあって、それなりにお金の貯えもできたから、とくにこれという不満もおこらなかった。
この年の七月に北京郊外で発生した盧溝橋事件をきっかけに、事実上の日中戦争、「日華事変」が勃発したのだが、氷川丸の船員たちにまではまだその余波は及んでいなかった。軍部が主導する政府の方針に煽動され、国内では中国への侵攻を支持する世論が高まりはじめていたが、すくなくとも小樽と台湾間の貨物輸送にあたる氷川丸の運行にはなお直接的な影響はあらわれていなかった。
ラジオのニュースや入港時に見る新聞の報道などで事変の急速な進展をある程度把握はしていたものの、船上での新たな生活にいそしむ石田には、その非常事態もどこか遠い世界の出来事であるかのように感じられてならなかった。もともと軍部というものの体質が大嫌いだった彼は、中国侵攻を支持する新聞やラジオの論調や、それを後押しするかのような世論の沸騰を苦々しくも思っていたから、意識的に無関心を装おうようにしてもいた。
現在では台湾随一の工業都市になっている高雄(カオシュン)にも時々氷川丸は入港した。高雄は昔から知られた台湾南西部の港湾都市で、幅一キロ、長さ九キロほどにわたって発達した砂洲からなる旗津半島が天然の防波堤となって、基隆と並ぶ一大良港が形成されていた。市街の中心を情緒豊かな仁愛河などが流れ、市内から十数キロ離れたところに蓮花潭(リエンホワタン)という美しい淡水湖などもあるこの高雄が石田はとても気に入った。伝統ある道教寺院の三鳳宮(サンファンゴン)なども、はじめてその地を踏む者の目にはずいぶんと珍しく興味深いものに思われた。
日本にくらべ気温はずっと高かったけれども、雨模様の日がほとんどの基隆と違って天候に恵まれることもすくなくなかったので、寄港時の仕事の合間などには、運動不足の解消をかねて極力散歩に出かけたりもした。歴史的な意味でのその正当性はともかく、当時は日本による徹底した統治がなされており、また日中戦争の勃発している中国本土からは遠く離れていたこともあって、高雄一帯はなおどこかのどかな雰囲気に包まれていた。太平洋戦争に突入すると、平和に見えたこの高雄も南方戦線の中継基地として戦乱の大渦に巻き込まれていくことになったのだが、のちのち起こるそんな世界の大激動などまだ誰も予想することなどできなかった。
小樽と基隆、あるいは小樽と高雄間を往復する船上から目にする折々の風景も、タリーマンに転身した石田の心を十分に慰めてくれた。氷川丸に初乗船したのは真冬のことで荒れ模様の日もすくなくなかったが、季節がうつるにつれて快適な航海に恵まれるようにもなった。横浜港から小樽港まで時化(しけ)のなかを初航海したとき、その船の船長から、「海が凪いでいて、すばらしい朝日や夕陽、素敵な星空などが見られることだってありますよ」と言われたが、その言葉に偽りはなかった。広大な海は息をのむような自然のドラマに満ちみちており、実際その有様は石田の想像をはるかに超えるものであった。
石田がまず驚いたのは、海洋にみる生命の豊かさだった。海がひどく荒れているときでさえも、陸地から遠く離れた海の上では大小の海鳥たちが頻繁に活動を繰り広げていた。それらの海鳥たちのけなげな姿を眺めているうちに、それぞれの厳しい環境に適応して生きるこの地球上の命というものいとおしさにあらためて想いが及んだ。
――荒海をものともしないそれらの海鳥たちだって、あの小ぶりな体で大嵐や厳寒に耐えながら生き抜くのは、けっして容易なことではないだろう。人間をはじめとする陸上の生き物たちがやがては土へと還っていくように、一生を終えた海鳥たちのほとんどは海へと還っていくに違いない。地上で息絶えるものもあるのだろうが、たぶん大多数の海鳥たちは海上に屍(かばね)を浮かべ、やがて磯辺に打ち寄せられて朽ち果てたり海中に没したりしていくのだろう――それまで海鳥の末期など考えたこともなかった彼の脳裏をそんな想いがよぎったりするのも、船上生活という特殊な環境に身をおくようになったからこそであった。ある日ついに海上で力尽き、だた一羽息絶えた姿をさびしく波間にゆだねるであろう海鳥の運命を想うとき、懸命にいまを生き抜くその有様がいっそうけなげに、しかしまたこのうえなく切なく感じられもするのであった。
鯨やイルカの群にも航海中に何度となく遭遇した。あるときは悠然と、またあるときは驚くほど敏捷(びんしょう)にと、状況に応じて自由自在に水中を泳ぎまわるそれら海の哺乳類たちの姿にみとれることもすくなくなかった。飛魚の大群のただなかを航行することもあったが、そんなときには、誤ってデッキの上に墜落した獲物が食卓にのるという望外の僥倖(ぎょうこう)に恵まれたりもした。基隆港や高雄港で碇泊中の氷川丸の船側に寄って来る熱帯系のカラフルな魚たちの姿も石田の目を楽しませてくれた。彼はそれまで釣りというものをまったくやったことがなかったが、船員仲間に教わって舷側から釣り糸を垂れると、海神様の特別サービスででもあったのか、次々に魚のほうから勝手に釣り針に掛かってくれもした。ただ、ビギナーズ・ラックも度を超えると有難迷惑なもので、たまには正体不明のグロテスクな生き物が掛かったりして腰を抜かしそうになり、その事後処置に窮するようなこともあった。
海の生き物たちの演じる命のドラマも素晴らしいものであったが、船上で眺める大空の景観もまた感動的なものであった。好天の日に海上から眺める朝日や夕日の幻想的な美しさにに石田は何度も息を呑んだものだった。水平線から昇り水平線へ沈んでいく太陽というものを、彼は船に乗るようになってはじめて目にすることができた。なかでも、西空や西の海面全体を真っ赤に染めながら東シナ海の水平線の向こうに沈んでいく夕日を目にすると、胸の奥が知らずしらずのうちに熱くなりもした。かなしいまでに美しく荘厳なその輝きは、壮大なロマンをその胸中に深々と刻み込んでいった。赤々と燃えさかる西方の水平線のはるか彼方で、何ものかが自分の魂を呼び誘っているような気がしてならなかったけれども、いったいそれがなんであるのか彼にはまだはっきりとわかってはいなかった。
日没後しばらくして西の空を彩る黄緑色の黄道光の輝きも神秘的だった。満月のときなどはそれに合わせるようにして東の水平線から大きな月が昇ってきた。低い角度で射し込む月光を浴びて海面には黄色い帯状の輝きが走り、無数の波頭がきらきらと揺れ躍った。そして月が高く昇ると、こんどはゆるやかにうねる海面全体が見る者の魂を吸い込むような青白い光を放ちはじめるのだった。
また、月の出ない夜は夜で、一つひとつ丁寧に磨き上げたよいうな星々が天空いっぱいに満ち渡り、無数の蛍を想わせるような明滅を見上げる空のいたるところで繰り広げた。
そして時々、明るい流れ星が長い尾を曳いて遮るもののない大空を我がもの顔に横切った。舷側に目を転じると、まるで夜空の星々の瞬きに呼応でもするかのように、舳先で切り分けられた海水のあちこちが青緑色の光を放って煌き揺れてもいた。海の蛍、夜光虫の見せる神秘的な輝きだった。
晴天の下での航海が何日もつづくときなどは、北海道から台湾へと南下するにつれて北斗七星の高度がだんだんと低くなり、逆に北上するにつれその高度がしだいに増していくのが印象的だった。星の知識などほとんど持ち合わせてはいない石田だったが、北の空に舞う北斗七星や夏季南天高くにかかる蠍座くらいは、見分けがついた。
石田が氷川丸に乗るようになってから一年が過ぎた。初乗船の頃に船酔いで苦しんだことなどとても信じられないほどに彼はすっかり海上での生活に順応していた。タリーマンの仕事も十分に板につき、すこしばかりは給料も上がって、母親や妹たちのために定期的に仕送りをすることができるようにもなった。そんなわけだから、表向きはすべてが順調に進んでいるように思われた。いや、順調というよりはむしろ単調という表現を使ったほうがよいくらいに、たんたんと時間は流れていった。
だが、このときすでに見えないところでは確実に変化が生じはじめていたのである。軍部による徹底した情報管理のために、一般国民はまだ中国本土で拡大しつつある戦乱について詳しいことを知らされてはいなかった。ドイツのトラウトマン駐華大使の懸命な仲介に蒋介石以下の国民政府府首脳も和平交渉再開に応じる気配を見せはしたが、日本軍による南京攻略を境にして、近衛首相の率いる日本政府内強硬派の戦線拡大方針にはもはや歯止めが掛からなくなっていた。
国民政府など無視して中国侵攻を進めるべきだとする近衛首相ら強硬派と、対ソ戦に備えて国民政府と早期に和解しておくべきだとする陸軍参謀本部との対立は、結局、政府強硬派の押し切るところとなってしまった。そして、昭和十三年(一九三八年)一月におこなわれた「爾後国民政府を相手にせず」という近衛首相の宣言によって、両国間の和平交渉は打ち切られるに至ってしまった。全面降伏をしないかぎり蒋介石政府とはいっさい交渉はしないという日本政府のこの強硬姿勢によって、日中戦争は長期戦に入り泥沼化していくことになったのだった。
当然その戦乱の余波は中国本土のみにとどまらず、日本国内やその関係地域すべてにまで及ぶところとなっていった。そして、北海道と台湾とを結ぶ貨物船氷川丸にも思わぬかたちでその影響があらわれることになった。波瀾多き星のもとに生まれついた石田達夫という当時二十二歳の青年の運命にとってそれがどのような意味をもつことになるのかは、むろんわかろうはずもないことだった。

絵・渡辺 淳
「マセマティック放浪記」2003年3月26日
ある奇人の生涯 (11)
落日下の決断
中国大陸における日中両国間の紛争が激化の一途をたどるにつれて、日本本土と大陸との間には軍需物資をはじめとする大量の物資運搬の必要が生じてきた。そのため、軍部指導下の政府は、民間会社所属の船舶の航路にも様々な管理統制をくわえるようになっていった。そして石田らの乗る貨物船氷川丸も当然その影響を被ることになった。氷川丸はそれまでの小樽と台湾を結ぶ航路を離れ、横浜、神戸、天津(テンチン)をつなぐ、いわゆる三角航路に就航することになったのである。
もっとも、この世の中というもの何が幸いするかわからない。この就航路の変更は石田自身にしてみれば、願ってもないチャンスの到来を意味していた。軍部の宣伝やそのお先棒を担いだ当時の報道に煽動された人々と違って日中戦争の拡大を素直に喜ぶ気にはなれなかったが、そのおかげで自分の乗る船が中国大陸の一角、それも天津という歴史的な都市の郊外にある港に寄港できるようになるというのは、彼にとっては望外の展開であった。長年の憧れでもあった中国大陸にほどなく第一歩を刻むことができると知ってその胸はすくなからずときめいた。小樽と台湾間の海上往復にもすっかり慣れてきたこともあって、氷川丸での生活にもいくぶん単調さを感じはじめていた時期でもあったから、新たな展開に対する期待はひとしおだった。
氷川丸が寄港することになった天津港、より正確にいうと天津郊外にある塘沽(タンクー)港は、山東半島と遼東半島に囲まれた渤海湾の奥まったところに位置する華北随一の港だった。かつて日本から隋や唐に向かった遣隋使や遣唐使一行の船なども最初はこの付近に接岸したといわれている。船員という身分でもあるため当然その行動半径に一定の制約があるだろうとは予想されたが、ともかくも初めて足を踏み入れることになるロマンに満ちた中国大陸の存在は、二十二歳になったばかりの多感な青年の胸をこのうえなく激しく掻き立てた。
天津へと向かう氷川丸が渤海湾へと入ると、石田は胸中に渦巻く興奮をどうやっても抑えきれなくなっていた。もうここは日本じゃないだ、日本じゃないんだ!――感動のあまり思わず彼はそう呟いていた。その目には海の中に引かれた幻の国境線までもがはっきりと見えるような気がしてならなかった。渤海湾を奥まで進むとやがて船は白河という大河を遡行しはじめた。両河岸の向こうには広大な塩田が広がっており、白河はその塩田地帯の中央をくねくねと蛇行しならがのびていた。悠然と流れる白河をしばらく遡っていくと目的地の塘沽港が現れた。氷川丸はこの塘沽港におもむろに入港すると、まるで大陸への航海にともなう緊張を解くかのごとくに碇泊した。塘沽に入港したのは、三千トン近い大きさのある氷川丸では直接天津まで白河を航行することが無理だからだった。
外国映画が大好きであった石田は、往時の大女優マリーネ・デートリッヒ主演の名画「上海特急」などの感動的なシーンを通して、中国大陸のあちこちで繰広げられてきた壮大な歴史ドラマやそれにゆかりの各地の景観に深く魅了されるようになっていた。なかでも、当時アジアきっての国際文化都市だった上海への憧れはひとかたならぬもであった。塘沽から汽車に乗って天津まで行き上海特急の映画そのままに北京発天津経由の特急列車に乗り換え、一路南下をつづければ上海に行くことができると想像するだけで、彼の胸は激しく燃え立ち高鳴った。
まだ小樽と台湾間の航路を往復していたころ、哀しいまでに美しい夕日を船上から眺めながら、しばしば石田は奇妙な想いに襲われることがあった。赤々と燃えさかる西方の水平線のはるか彼方で何物かが、こちらに来いとばかりに自分の魂を呼び誘っているような気がしてならなかった。いったいそれが何ものであるのか、その時はまだ彼自身にもはっきりとはわからなかった。だが、ついにこの天津郊外の塘沽港に寄港することがかなったこの日、はからずも彼はそれが何であるのかを自覚させられることになったのだった。あえて言葉にするなら、それは、「大陸に沈む華麗かつ荘厳な夕日の誘惑」とでも形容すべきものであった。
日没が近いため貨物の積み下ろしは翌朝に行なうということになったので、石田は上甲板のデッキにもたれかかり、西空に沈んで行く太陽とその光の中に浮かぶ光景をひとり呆然と眺めていた。話には聞いていたが、それにしてもそれはなんとも壮大な景観だった。見渡すかぎり広がり続く塩田のあちこちには、マストや煙突、それにブリッジの上部だけをのぞかせながら動いていく大きな汽船の影が見えた。直接には白河の河面は見えなかったので、まるで塩田の中を幾隻もの船が直に航行しているかのような感じだった。塩田のあちこちにはまだ働いている人々の姿が点々とあって、その人たちのすぐそばを通り過ぎる汽船は、まるで挨拶でもするかのように、時折ボーッ、ボーッとその汽笛を鳴らした。
しばらくすると、真っ赤に燃え輝く太陽は遠く長くのびる地平線の真上へとおりてきた。そして、とてつもなく巨大な真紅の円盤と化しかとおもうと、一帯の塩田を赤々と染めながら地平線のむこうへと沈んでいった。それほどまでに大きく鮮やかな夕日を目にするのは石田にすればむろん初めてのことだった。まるで中国大陸の広大さを誇示でもするかのようなその幻想的な夕日は、その心に向かって悪魔の囁きにも似た誘惑の言葉をさりげなく、しかし繰り返し繰り返し語りかけてきた。
――中国大陸は素晴らしいんだぞ!……おまえまだ若いんだろう、それならもっともっと大きな夢と自由を求めて羽ばたいてみたらどうなんだい?、波瀾万丈の人生を求めて未知の世界に飛び込むならいまがチャンスだぞ!――彼にはそんな落日の囁きがはっきりと聞こえてきた。
そのとき突然うしろから誰かが近づいてくる足音がした。振り向いてみるとそれは氷川丸の事務長だった。丸顔でずんぐりした身体つきの事務長は、絵に描いたようなお人好しの人物だった。小さな眼を子供のようにキラキラさせながら事務長は石田に話しかけてきた。
「どうだい、すごいだろう?、日本ではまず見られない光景だから……」
「ええ、感動で言葉もないくらいです」
「今晩は上陸しないのかい?」
「塘沽には何があるんです?」
「何にもないねえ。汽車で天津まで行けば面白いところもあるけどな」
「事務長さん、もしも船を下りて中国に住みたいと思ったらどうすればよいんですかねえ?」
「どうするもこうするもありゃしない。さっさと船を下りてそのまんま帰ってこなけりゃいいんだ!」
事務長の返事はいたって簡単だったが、むろん、彼は冗談のつもりでそう言ったに違いなかった。だが石田はそうは受取らなかった。塘沽の夕日の囁きにすっかり魂を奪われた彼は、その言葉を胸の奥で真剣に受けとめていた。
石田の心は大きく揺れた。様々な状況を考え合わせるとき、無断離船のような思いきった行動をとるには塘沽寄港のなったいまが絶好のチャンスでもあるように思われた。しかしながら、それはずいぶんとリスクが大きいうえに、結果として氷川丸の船員仲間にひとかたならぬ迷惑をかける行為であることも明らかだった。ましてや、自分を息子のように可愛がってくれているボースン(甲板長)やお人好しの事務長、行き倒れの身を介抱し日本近海郵船への就職を斡旋してくれた横浜の職業斡旋所長のことなどを考えると、申し訳ないという気持ちがつのるばかりで、さしもの石田にも容易には決断がつきかねた。
だが、そうこうするうちに社会情勢はますます抜き差しならぬ方向へと進んでいった。石田の乗る氷川丸が、横浜、神戸、天津をつなぐ三角航路に就航するようになったこの年の四月には国家総動員法が公布され、我が国は本格的な戦時体制へと突入した。国家総動員法は戦時における国防目的遂行のため、戦争に必要な人的および物的資源を国家が全面的に管理統制することを狙いとしたもので、この法律の公布により、民間船舶会社などに所属する者の身分管理は一段と厳しいものへと変わっていった。したがって、いくら石田が青年期特有の一途な思いと決断のほどをを上司に告げ、どんなに懸命に離船を願い出ようとも、容易にはそれを聞き入れてもらえるような状況ではなくなってきていた。
ちなみに述べておくと、女優の岡田嘉子と新協劇団の演出家杉本良吉の二人が手に手を取ってソ連への亡命を敢行したのはこの年のことだった。二人は樺太の日ソ国境地帯に国境警備官の慰問のために出向いたあと国境見学にでかけ、国境線に近づくと脱兎のごとき勢いで雪の国境線を越えてソ連領へと逃走、そのままソ連への亡命を願い出た。杉本は当時壊滅状態にあった日本共産党再建のためコミンテルンと連絡を取る使命を帯びていたとも言われるが、ソ連入国後に同政府当局によってスパイと断じられ、愛の決死行もむなしく、異国の地で銃殺された。いっぽうの岡田嘉子のほうは対日放送のアナウンサーなどを務めながら戦後ソ連で演劇活動を再開し、亡命後四十四年を経た昭和四十七年(一九七二年)に日本へと帰国した。
その後何度も塘沽港に入港し赤い夕日を眺めるごとに石田の心の葛藤は深まっていくばかりだった。しかしながら、そんな葛藤にいつまでも心身を委ねておくわけにもいかなくなってきた。社会状況の緊迫化にともない、ついに彼は、そのまま氷川丸に船員として留まりつづけるか、それとも夢を追うべく思いきって中国大陸に身を投じるかの選択と決断を余儀なくされることになったのだった。
国家総動員令が発令されて以降、国民生活における軍部主導の統制管理は日増しに強まり、大陸への物資補給に不可欠な船舶とその船員に対する様々な規制や拘束はひどくなるいっぽうだった。そんな社会状況下にあっては、石田があえて中国大陸への思いを貫き通すとすれば、考えられる方法はただひとつしか残されていなかった。その唯一の道は過日の事務長の言葉にあったように氷川丸からの脱走をはかること、いますこし穏やかな言い方をすれば、塘沽港入港時に天津まで遊びに出かけるという口実を使って下船し、そのまま行方をくらましてしまうことだった。
横浜の職業斡旋所長の紹介でタリーマンとなってまだ一年半余、氷川丸が三角航路に就航するようになってからまだ三ヶ月ほどしか経っていないときのことだったが、彼はついに氷川丸からの脱走を決意するにいたった。運命の岐路におけるその選択が吉とでるのか凶とでるのか、神ならぬ身には知る由もなかったが、若さと滾(たぎ)る血潮とのどちらかに賭けるなら、波瀾万丈の運命の待ちうける世界か、そうでなくてもその予感に満ちみちた世界を選択したほうがましだと考えるようになったのだった。
塘沽港に碇泊中の氷川丸から脱走した経緯やその後の状況について、あるとき石田は詳細に語ってくれたことがある。いつものように互いに軽口を交えながらの談話を通してのことではあったが、その悲喜交々(ひきこもごも)の脱走秘話はなんとも興味深いものであった。
「じゃ、真っ赤な夕日に誘われて脱走を決意したっていうわけですか、中国大陸の夕日って男殺しなんですねえ――それも、黙って坐っているざけで若い女性を悩殺したとかいう男を殺しちゃうっていうんですからね!」
「そのまま船に乗ってたらどんどん拘束が強くなるばかりで、最後にはまるで自由がなくなっちゃうと思いましてね。それにすべてに横柄な軍部のやりかたというものが大嫌いでしたからね。そのときは予想もしていませんでしたが、あのまま氷川丸に乗っていたら、のちに戦局が悪化した時点で海の藻屑と消えていたかもしれませんね。たしかあの貨物船も無事ではなかったはずなんですよ」
「結果的には地獄からの脱走になったわけですね?」
「制海権も制空権も失うことになるなんて当時は誰も考えていませんでしたが、最終的にはそういうことになったんですね」
「それはともかく、氷川丸に見切りをつけてドロンしてしまった……よく決断がつきましたね」
「リスクはあっても脱走を決行するならいましかないと思い定めました。徴兵検査は丙種合格でしたから、すぐに軍隊に召集される心配はなかったですしね」
「まさか、演出家の杉本良吉と女優の岡田嘉子の亡命劇の真似をしようって思ったわけじゃないんでしょ?」
脱走の陰にそれを手伝った女性の存在でもあったのではないかと勘ぐりながら、私は意地悪な質問をぶつけてみた。すると相手はこちらの意図を見透かしたかのような笑みを浮かべながら、こともなげな調子で答えてきた。
「あの連中は二人一緒で、しかも使命感をもっての逃避行だったんでしょ。こちらは男独りで、動機ときたら、ただ単に夢を追いかけ中国各地を放浪し、いろいろと見聞したいだけのことでしたからね。それにですね、あの二人の亡命劇について知ったのはずっとあとになってからでしたよ」
「で、かんじんの石田さんのほうはいったいどうやって脱走を?」
「脱走っていいますけどね、実際は脱歩でした。走って逃げたんじゃなく、スーツケースをひとつ持って堂々と歩いて塘沽の駅まで行き、汽車で天津へと向かったわけで……」
「ハハハハハ、脱歩ですか。脱臼まではいかなくてよかったですね」
「そもそも、そんな大袈裟なことをやったわけじゃないんですよ、ごく自然にね!」
「自然にっていったって、どうせ石田さんのことだから、また何か突飛なことでも?」
「いやいやそんなことはない。塘沽港で下船するとき、例の事務長に行く先と目的を訊かれたんですけどね、天津あたりまで女を買いに行くって答えておきました。それまでの一年半余、結構真面目に仕事してましたから、信用はありましたんでね」
「最後にその『信用』の預金を全部遣い尽してしまった!」
「いや、その預金じゃ足らずに大借金をしてしまったというところですかね……。お人好しの事務長のアドバイスをそのまま実行したんですから」
「そりゃ事務長もショックだったでしょうね。じゃあ、もちろん、本物の有り金のほうは全部持って?」
「そりゃもう……二度と船に戻るまいと決意したわけですからね」
興味津々といった表情で耳を傾ける私を前にして一杯お茶を飲むと、一瞬、苦笑とも自嘲ともつかぬ微笑を湛えながら、石田は遠い記憶を呼び覚ますようにしてさらに言葉をつないだ。

絵・渡辺 淳
「マセマティック放浪記」2003年4月2日
ある奇人の生涯 (12)
計算違いの脱走劇
現代の我々日本人は天津と聞くとすぐに夜店などで売っている天津甘栗のことを想い出すのだが、実際には天津の街並みのどこを歩きまわっても甘栗を売っている光景に遭遇することなどまったくない。たぶん甘栗のもととなる中国産の栗が天津港経由で日本へと輸入されていたため、そんな商品名が人々の間に定着したのではなかろうか。いずれにしろ、その一事をもってしても天津が中国屈指の貿易港であることがわかろうというものである。
七世紀の初め隋の煬帝が大運河を開通させると天津は物資輸送の中枢地となり、十世紀後半の北宋とそれにつづく金王朝の時代には軍事拠点となる大要塞が設けられた。そして十三世紀後半に元王朝が都を北京におくとその玄関口として天津はますます発展し、現在も古文化街にその面影を留める天后宮などが建立された。さらに十五世紀の明代には壮大な天津城が建設され、頻繁に外国船も寄港する一大貿易港へと発展を遂げた。
しかしながら、近代に入ると天津は世界の列強国による攻勢の嵐にさらされるところとなった。アロー号事件を契機とする第二次アヘン戦争において英仏連合軍の侵攻をうけて清は敗退、その後に締結された北京条約に基づき天津は欧米各国に対して開港されるにいたった。そして天津の中心部を抜けて渤海湾に流れる白河の両岸には、イギリス、フランス、アメリカ、ドイツ、ロシアなどの租界地、すなわち外国人居留地域が次々と設けられ、西洋風の建築物が建ち並ぶようになっていった。さらに、一八九四年に起こった日清戦争後には日本も同地に租界を建設するにいたった。
盧溝橋事件を発端にして日中戦争が勃発すると、日本軍はこの天津を含めた華北一帯の広範な地域を占領するという強行策に打って出た。兵站(へいたん)を無視したこの戦略はやがて中国軍のゲリラ戦を主体とした反撃に遭い破綻をきたすことになっていくのだが、石田が氷川丸からの脱走を決意した昭和十三年(一九三八年)の時点では、一時的に日本軍が圧倒的に優勢を保っていたため、天津周辺の治安には表面上問題はなかった。
女を買いに天津まで行ってくると告げて氷川丸をあとにした石田の心はさすがに痛んだ。翌日には氷川丸船内が大騒ぎとなるだろうことは目に見えていた。ぷっつりと消息を絶った自分の身を案じて、あの人のよいボースンや事務長らが捜索のために乗組員を指揮しながら右往左往する姿が脳裏にはありありと想い浮かんだ。突然の不測の事態に困惑し、出港日時の変更などを含めた問題の処理にどう対応しどう責任をとったものかと途方に暮れる船長の様子なども想像できた。新たな旅立ちを志して天津駅へと向かいながらも、そのいっぽうでは何食わぬ顔で船に戻ったほうがよいのではないかという思いにとらわれかけたりもした。
だが、そんな弱気の虫に抗うように彼は脱走の決断にいたるまでの経緯をもう一度思い起し、こんなにも意志薄弱で優柔不断な有様なら先々の人生に展望はないと自らの心を煽り立てた。そして、この自分の不当行為は表面的にはお世話になった氷川丸の船員たちへの裏切りだが、日中戦争勃発にともなう船員の身分や行動の管理強化のありかたに根本的な責任はあるのだという、自己弁明とも責任転嫁ともつかぬにわか仕立ての理由づけをしてみたりした。そうでもしなければ、過去のしがらみを断ち切り新たな世界へと飛躍することなどおぼつかないという気がしたからでもあった。
日中開戦による華北一帯の不穏な状況もその時の石田には幸いした。日本人の多い租界地をはじめとして天津市街やその近郊周辺は見かけ上平穏を保ってはいたが、日本人に対する中国人の潜在的な憎悪は日々増大していくばかりだった。だから、街のどこかで日本人の一人や二人が行方不明になったとしてもそうそう驚くべき状況ではなくなっていた。
石田が天津の街に女を買いに出かけ、そのままプツリと消息を絶ったとしても、最終的には何らかの不運な事故に巻き込まれたものとして処理されてしまう可能性が大きかった。
さんざんお世話になった氷川丸関係者には申し訳ないかぎりではあったが、そんなふうに事後処理が進めばベストなのだがとも内心彼は期待した。もしかしたら事務長が過日夕日を眺めながら自分と交わした会話を憶えていて、冗談のつもりで言ったあの言葉を文字通りに受取りそのまま実行に移したのだと気づくことはあるかもしれないが、状況が状況だから相手だって絶対にそうであるという確信まではもてないだろうとも考えた。
天津駅に着くと、石田はそこからすぐに特急列車に乗り、夢にまで見た上海へと向かうつもりだった。いっきに上海入りすることによって、氷川丸脱走という事態の重さに揺らぐ心に踏ん切りをつけようと思ったからだった。だが、事は彼の計算通りには運んでくれなかった。その前途には「上海特急」どころか、「上海超々鈍行」による各駅停車の旅路が待ち受けていたからである。憧れの上海入りを果たすには、さらに遠い遠い道のりを歩かなければならなかった。
その日天津駅に到着したのが夕刻のことで、上海行きの最終特急列車がすでに発車してしまっていたのがそもそも歯車に大きな狂いの生じた原因だった。めざず上海行きの特急列車に乗るには翌日まで待たなければならなかった。やむをえないので、石田は以前に一、二度会ったことのある若い中国人女性に連絡をとって街で会い、一夜をともにしようと考えた。中国語がわからない彼は、たとえ一夜のことではあっても片言ながら日本語のわかる彼女の助けを借りることができればと思ったからだった。下手に天津在住の日本人と接触し、脱走を企てている事実を知られたりしたら面倒なことになるという警戒心も働いていた。
美人で気立てのよいその中国人女性は快くそして心底温かく彼を迎え入れてくれた。優しい彼女の笑顔と可憐で従順な立ち振舞いを目にして、それまで張りつめていた緊張の糸が一度に緩みほぐれる思いだった。石田は彼女と一緒に近くのお店で食事をとりながら、その場でのさりげない会話の中で、翌日には列車に乗って上海方面に行くつもりであることを伝えた。彼女はどこか淋しげな表情を浮かべはしたものの、それ以上彼のおかれている状況を問い詰めるようなことは何も言わなかった。ゆっくりと食事を終えたあと、二人は天津市街の場末にある宿屋へと向かっていった。
その夜、石田はその可憐な女を何度も何度も激しく抱いた。甘いマスクで若い女性にずいぶんもてたとはいっても、かねがね異性に対してどこかクールなところのある彼にすればそれは意外なほどの激しさだった。たぶん、そうすることによって完全に退路を断とうという思いも心の奥にあったのだろう。やわらかく温かい女の身体を狂ったように抱きしめ、折々全身を貫く陶酔感に時を忘れて溺れひたりながらも、彼は折々かすかに覚醒する意識の片隅で、これでもう引き返すことはできなくなったと感じていた。
女のほうもそんな石田に、時に切なく時に激しく応じてきた。優しい獣と化した男の命の鼓動を吸い込むように受け入れながら、全身全霊を傾け寸刻を惜しむようにしてそれに共鳴する彼女の妖艶な姿には、生命体というもののもつ神秘のすべてが集約されているといってもよいくらいだった。石田が果てると、女は彼の命の滴の最後の一滴までも吸い尽くそうとするかのように、自ら激しくそして妖しく挑みかかった。その甘美な攻勢に翻弄され抗すべきすべを失った彼は、女のなすがままに身を任せて歓喜とも慄きとも撼えともつかぬ不可思議な感覚に酔い痴れ、まるで失神でもするかのようにそのまま深い深い眠りに落ちた。
翌朝石田が目覚めたとき、女の姿はもうどこにもなかった。現金や金目のものをすべて入れておいたスーツケースも一緒に消えていた。愕然としながらおのれの甘さを呪ってもみたがすべてはあとの祭りだった。自分を信頼してくれていた人々を欺いた直後に、うかつにも信頼した相手から見事なまでに欺かれる――自業自得だといってしまえばそれまでだったが、いささか自意識過剰気味なところのあった彼にすれば、頭上から懲らしめの鉄槌を振り下ろされた感じだった。男というものの愚かさと女というものの底知れぬしたたかさを思い知らされた気分でもあった。
いささか自嘲気味ではあったけれどもその時の切迫した状況についての記憶をかみしめるようにしながら、石田はなおも事後談を語り続けた。事実は小説より奇なりとはいうが、その経験談はどこまでも興味深いものであった。
「その女をすっかり信用しちゃったために、見事にやられちゃったんですね。スーツケースごと持ち金のほとんどを盗られちゃって……。朝になって気づいたときには女はドロンしてたって寸法です。まさかあの優しくて従順可憐な女がって思ったんですが、あくまで現実は現実だったわけでして……」
「そりゃ困ったでしょ、のちのドラキュラ翁もまるで幼児なみのガキキュラじゃないですか?」
「そう言われても仕方ないですね、そのときは確かにオッパイ吸ってたわけですからね」
「ハハハハハハ……」
相変わらずの妙意即答にこちらが笑い転げるのを横目にしながら、石田はさらに先へと話を進めた。
「そこでさんざん宿屋の主人と掛け合ってみたんですが、どうにも埒(らち)があきませんでした。そもそも言葉が通じないんで身振り手振りに頼るしかありませんでしたから」
「もしかしたら宿屋の主人もグルだったとか?」
「たぶんそうだったんでしょう。不当な日中戦争で中国人の間には反日感情が高まっていたわけですから騙されて当然だったんですが、若さのゆえもあってそのへんについてはまるで無警戒でしたね」
「それでどうしたんですか?」
「まるで言葉が通じないとあって……、もしかしたら通じないふりをしていただけなのかもしれませんが……、それはともかく、仕舞いには暴力沙汰にもなりかねない状況になってきましてね。だからといって、大騒ぎになっているだろう氷川丸にいまさら戻るわけにもいきませんでしたから」
「もし船に戻っていたら、吊るし上げにされたあげく、最後は海中に放り込まれていたかもしれませんね」
「それで、いったんは日本の領事館に駆け込んで善後策を相談しようかとも考えました」
「でもそれじゃ脱走したことがバレちゃいますよね」
「そうなんですよ。若者ゆえの無謀さに身を任せて飛び出してはみたものの、脱走者でしかも不法入国者でもあるわけですから、それが明らかになったら本国送還という最悪の事態にもなりかねませんでした」
「結局泣き寝入りってわけですか?」
「さすがに狸寝入りするほどの余裕はありませんでしたよ。だから、スーツケースは諦めることにしました。とても領事館なんかに相談には行けませんでした。当時はいっぱしの大人だと思っていたんですが、いま振り返ってみると、とにかく若くて世間知らずで、無防備そのものだったですね」
懐かしそうにそう語る石田の静かな表情からは、六十年というその後の歳月の刻みもたらした人生の旅路の奥深さが読み取れた。

絵・渡辺 淳
「マセマティック放浪記」2003年4月9日
ある奇人の生涯 (13)
上海特急のロマンはいずこに?
石田はかねがね自分は人一倍悪運が強いのだと言ってはばからなかったが、天津で窮地に追い込まれたこのときでさえも天運はまだ彼を見放しはしなかった。もっとも、そんな強運の背景には、並外れた状況適応能力の高さと、非常事態に直面するほどに冷静さと沈着さを増すという彼の性格的な特質があったと言うことはできるかもしれない。裏を返せば、それは「行き当たりばったり」に振舞うことをなんとも思わない天性の資質でもあったのかもしれないが……。
石田はふるびた記憶の糸を丁寧に繋ぎ手繰るようにしながら、その後の事態の推移についてさらに語り続けた。
「頭を冷やしながらとりあえず天津の街を歩きまわりました。大金はすっかり盗まれてしまったんですが、幸いなことに、洋服のポケットの奥に盗られずにすんだお金がいくらか残ってましてね」
「その中国人の女性にも温情のかけらはなお残っていたということでしょうか?」
「さあ、それは……。ただ、そのお金のおかげで一時的に飢えだけは凌ぐことができました。人間、胃袋の中に何かはいっていさえたらそれほど絶望的になるものではありません」
「でもですねえ、現代では当面食べるだけのものはあっても近い将来の生活不安におののいて絶望する人々が少なくないですからねえ」
「まあ、時代や社会背景の違いということもあるんでしょうけれどね」
「それで、どうやってその窮地から?」
「知人はまったくいないし、たとえ誰かいたとしても下手に日本人と接触すればかえってまずい展開になってしまうかもしれませんでしたからね。でも、所持金も残りわずかということになると、当然、なんとかしなきゃならいっていう気持ちにはなります」
「まさか、また山下公園のときみたいに行き倒れになったんじゃないでしょうね!」
「自然と足は天津駅へと向かっていました。駅というものはいつも何かの始まりを暗示してくれますからね。終着駅っていう言葉もありますけど、その場合でも駅そのものが目的地であることはない……やっぱりそこから何かが始まるのが普通です」
「人生の終着駅は天国や地獄への旅路の始発駅っていうこともありますしね」
「駅のベンチに腰掛けてしばらく考えていました。特急で上海までいくつもりだったんですが、もうそれだけのお金の持ち合わせがない……、当面、上海行きはあきらめなければなりませんでした。もっとも、だからといって塘沽に近い天津に長居しているのは危険でしたしね」
そう言い終えてから一口か二口紅茶をすすると、石田は再び口を開いた。相手に合わせてティー・カップを手にしていたこちらも、また耳をそばだてた。
「駅であらためて鉄道路線図や時刻表を見ているうちに、一刻も早く列車に乗ってとにかく持っているお金で行けるところまで行こう……あとのことはそれから考えることにしようかって……」
「また例の石田流の行き当たりばったり主義ですね!……あとは野となれ山となれっていうわけですか?」
「時刻表で確認すると、憧れの上海特急がまもなく発車することになっている。慌てて切符売場に行くと、有り金をはたいて青島(チンダオ)までの乗車券を買い求めました。上海行きはあきらめるしかないけど、せめて日本人が多く住む青島(チンダオ)まで行ければなんとかなるんじゃないかと考えたわけですね」
「それって、やっぱり、例のマリーネ・デイトリッヒ主演の映画『上海特急』の影響だったんでしょう?、映画の力って凄いですね!」
「もちろんあの映画のせいだったわけなんです。途中の済南(チーナン)まで上海特急に乗って南下し、済南で山東半島方面行きの普通列車に乗り換え、そこからひたすら東に向かうと青島に着くわけですが、そこまでの切符を買うと文字通りの文無しになってしまいました。天津から済南までの区間の上海特急も一番安い席にしたんですが……」
「それでも、とにかく念願の上海特急に乗ることができたわけですね。石田さんにすれば、満願成就じゃなくって半願成就ってところだったんでしょうが……」
「あの映画の助演者にアンナ・メイ・ウォンというすごく魅力的な中国人女優がいましてね。上海特急に乗ったらあんな素敵な女性に会えるんじゃないかって期待もしたわけです」
その言葉を聞いた途端、思わず意地悪な質問が口から飛び出した。
「だって石田さん、前夜、チャーミングな若い中国人女性にコロッと騙され大金を盗られたばかりだったんでしょう、なのに性懲りもなくそんな期待をもったんですか?……もう二度と中国美人の魅力的な笑顔には騙されないぞと心を引き締めたのかと思ったら!」
「ふふふふふ……、まあ男っていうものは何回騙されても懲りないものですからね。それに、中国人女性だってやっぱりほんとうに素敵な人もいますから……」
「それにしても立ち直りがあんまり早過ぎません?」
「いやいや、実を言いますとね、あそのあとが大変だったんですよ。マリーネ・デートリッヒもアンナ・メイ・ウォンもどっかいっちゃいましてね」
「とにかく石田さんが夢にまで見た上海特急に乗れたわけですね」
「ええ、切符を買ったのが発車五分前で、発車時刻ぎりぎりに列車に乗り込みました」
そこまで話を進めると、石田はあらためて記憶の整理でもするかのようにしばし口をつぐみ、遠い目をしてなにやら深い想いに沈んでいった。ビデオフィルムを前後に巻き動かしながらその中のある映像をを引き出すときのように、石田の脳裏では記憶の中の映像が時間軸にそって激しく行きつ戻りつしている感じだった。その様子をさりげなく眺めながら勝手に相手の胸中に想像をめぐらせていると、過去の時空への往復を終えたらしい石田は、あらためてこちらの顔を見つめなおすと再びその口を開いた。
「憧れの上海特急に飛び乗ったのはいいんですが、乗ってみて驚いたんですよ。こんなはずじゃなかったってね!」
「といいますと?」
「映画の中の上海特急はもっともっとロマンティックでした。マリーネ・デートリッヒもアンナ・メイ・ウォンもゆったりしたコンパートメントのやわらかいシートに腰をおろして、ほれぼれするほどに長くて美しい両脚をのばしていました。ですが、私の乗った車輛ときたら……」
「ちっともロマンティックなんかじゃなかったとか?」
「映画では、上海特急の機関車には大きな鐘がついていて、汽笛がわりにその鐘がカランカランと音を立てていあたのが印象的でした。牛が一頭前方の線路の真中にすわっていましてね、いくら鐘を鳴らしても動こうとしないシーンなどもありました。いかにも大陸的でのどかな感じの特急ですが、乗っているお客はスパイだのゲリラだので、結構ロマンとスリルとがありました」
「それで、石田さんの乗った現実の上海特急のほうはどうだったんです?」
「ぎゅうぎゅう詰めのゴミ箱みたいなものでした」
「じゃ、石田さんもとうとうゴミになってしまったわけですね。結局、上海特急にまで騙されたってわけですか?」
「ははははは……まあ、そういうことになりますね。ひとつの車輛が十区画くらいに仕切られていましたから、一応はコンパートメントだったのでしょうが、問題はそのお粗末さなんですよ。日本の普通の寝台車から清潔さ、やわらかさ、居心地のよさといったようなものを全部取り除いた状況を想像してみてください。それが私の乗った上海特急だったんですよ」
「うーん、なんとなくは想像がつきますが、いまひとつイメージが……」
「木製の骨組みだけで出来た小部屋といった感じで、寝台車の二段ベッドにあたる部分がベッドのかわりに木製の二段ベンチになっていました。要するに上下二段のベンチが向かい合わせになってになったかたちで、四つベンチが並んでいるわけですよ。みんな粗末な板張りで、もちろカーテンもクッションもありません。座席部の板だってそれ以上汚れようがないくらいに汚れていました」
「そんなにひどかったんですか?」
「しかも、それぞれのベンチには十人くらいの乗客が身を寄せ合うようにして腰掛けていました。だから、下のベンチに腰掛ける人たちの眼前には上のベンチに腰掛けている人たちの足先がぶらさがっている有様でした。しかも、向かい合うベンチとベンチの間の通路にも人が立っていました。そのうえ荷物がそこらじゅうに転がっていましてね。その荷物も、薄汚れた布で包んで簡単に紐でしばっただけのものや剥き出しのものなどがゴチャゴチャと置かれていました。人間と荷物とが区別もつかないほどに混在していたわけです」
「ワン・コンパートメントに人間だけでも四、五十人ですか!……それじゃ夢もロマンも一瞬にして吹き飛んでしまいますよね。それでどうなさったんですか?」
「ただただ呆気にとられて、人間と荷物の間に身を小さくして立ちすくんでいました。いつ列車が動き出したのかさえ憶えていません。列車が天津を出て二、三十分経つうちに、どういうわけか私は徐々に名ばかりのコンパートメントの奥のほうへと押しやられていきました。奥のほうというのは要するに窓ぎわのほうのことなんですが、これは不幸中の幸いでしたね。窓ぎわは多少なりとも空気の流通があるので息苦しさが緩和されたんです」
「憧れの上海特急に乗ったばかりに、酸素不足で息がつまり天国超特急になったりしたんじゃやりきれませんものね」
「本物の天国に行けるんだったら、そりゃ我慢もしましたけどね。アンナ・メイ・ウォンがブルゴーニュ産の高級ワインを注いでくれる秘密の楽園とか……」
「それじゃまるで、昔はやった歌の文句そのまんまの『天国よいとこ一度はおいで、酒はうまいし、姉ちゃんは美人だ……』の世界じゃないですか!」
「ははははは……。天国はともかく、さらにありがたかったのは、上段のベンチに腰掛けていた連中がより一段と身体を寄せ合って一人分のスペースをつくり、私に上がって腰掛けろと言ってくれたことです。言葉はわからなかったんですが、身振り手振りで言わんとするところは察しがつきました」
「そんな状況のもとではアンナ・メイ・ウォンの笑顔よりもそのほうがずっと有難かったとか?……まあ、まるで花より団子みたいな話ですね」
「それで、私は憶えたての片言『謝々』を繰り返しながら上段ベンチの窓ぎわに腰掛けたんです」
「ともかくも座席が確保できて一息つけたわけですね」
「ベンチに腰をおろすことができ、周囲の状況に馴れてくると、それまでの緊張が疲れとなってどっとあらわれ、眠くなってしまったんです。そのまま眠り込んでしまいました」
「気がついたら乗り換え駅の済南を過ぎてしまっていたとか?」
「いや、さすがにそれはなかったんですが、その前にもう一騒動あったんです。なにせ脱走中の身でしたからね」
相手の記憶の根底をできるかぎり揺すぶり、忘却の淵にある想い出をなんとか甦らせようとするこちらの魂胆を知ってか知らずか、次々に当時の出来事を脳裏に呼び戻しはじめたらしい石田の話はさらに続いた。

絵・渡辺 淳
「マセマティック放浪記」2003年4月16日
ある奇人の生涯 (14)
そしてついに青島へ
どのくらいの間眠り込んでいたのかは定かでないが、突然ハッと目が覚めた。列車が駅に停まる直前の微妙な振動の変化のためか、プラットフォームから聞こえてくる駅員の大声のせいであったらしい。石田の意識が覚醒しはじめたとき列車はすでにプラットホームに停っていた。高らかに駅名を伝える駅員の声が流れてきた。彼の耳にはその声が「タンクー、タンクー」と連呼しているように聞こえた。
――タンクーというからにはここは塘沽に違いない、列車は南に向かって走っていたから、もう一度塘沽を通過するのは当然だ――そう考えた彼は無意識のうちに身を縮め、両眼だけを皿のようにしながら薄暗いプラットホームの様子を窺った。
その時、窓越しにプラットホームの上をコツコツコツと急ぎ足で歩く靴音が響いてきた。なんだか聞きなれた感じの靴音だった。さりげなくそちらのほうに視線を送ると、列車からすこしばかり離れたところを何度も往復する一人の男の姿が目にとまった。それは背の低い小太りの男だった。次の瞬間石田の心は動顛した。
――あれはもしかしたら事務長では?、いや、まさかそんなはずはない!、でも確かにあれは事務長だ、乗っていた船の事務長だ!……なんでまたあの事務長が?――柄にもなく石田は大パニックに陥った。
――青二才の自分を人一倍可愛がってくれた事務長、海の話をはじめとしいろいろなことを教えてくれたあの事務長が無分別に船から脱走した自分の身を案じてわざわざ駅まで捜しにきてくれたのだろうか?……それとも、冗談のつもりであのとき脱船の手口をほのめかしたことがこの結果につながったとその責任を感じ、必死になって捜索に出向いてきたのだろうか?――あれこれと想像をめぐらす石田の胸はとめどもなく動揺した。
「いっそうのこと、すぐにも下車してごめんなさいと謝るべきだろうか。でもそうしてしまったら、折角脱船した意味がないからやはりこのまま行ってしまったほうがよいのではないか――とまあ、ハムレットなみに思い悩みましたよ」
なかなか決断がつかず迷いに迷ったそのときの心理状態を、石田はまるでもう一度その場に戻りでもしたのような昂揚を見せつつそう語った。
「結局、どんな決断をしたんですか?」
そのまま列車に乗り続けることにしたのだろうと予想しながら話の続きを促すと、彼は意外な答えを返してきた。
「いやね、ここまで心配してくれるんじゃ、やっぱり素直に謝っていったん身柄を事務長に委ねることにするかって決心したんですよ。それで腰掛けていた上段ベンチから急いで飛び降りたんです」
「えっ、ほんとにそうしたんですか?……信じられない!」
「ところがですね、飛び降りた瞬間、よろよろとして通路の床の上にいた三、四歳くらいの男の子の足をもろに踏みつけてしまったんです。男の子はギャーアッて悲鳴をあげ、火がついたように泣き出してしまいました」
「そりゃ、まるで計算外のことですよね。困ったでしょう?」
「慌てた私は、ゴメン、ゴメンと日本語で謝りながら、子供の足を懸命にさすってやりました。周囲の人たちは皆私たちの様子を眺めていましたが、悪意のある視線ではありませんでしたね。子供も泣きやんで皆もほっとしたみたいでした。そこで私は昇降口に向かおうとあらためて立ち上がりかけました」
「列車から降りようと?」
「ええ……。ところがなんと、その瞬間、発車を告げる機関車の鐘がカランカランと鳴りだしたんです。大慌てで昇降口に駆け出そうとしましたが、混雑のために思うようには動くことができなくって、そうこうするうちに列車が走りだしてしまったんですね!」
「あれまあ、なにが幸いするかほんとうにわからないものですねえ」
「そうなんです、それでその後の私の人生は決まってしまったんです」
「結果的に脱走は成功したというわけですね!」
「ハハハハハ……」
「でもねえ石田さん、いくら事務長が寛大な人だったとしても、船長やボースンほかの乗組員の手前もあったでしょうし、国家総動員令の発せられたのちのことでもあったようですから、そこで降りていたら職場放棄と脱走の罪で処罰されていたかもしれませんよ。いずれにしろ危機一髪だったってわけですよね」
「それがねえ……、あとでよくよく考えてみると危機十髪くらいだったかもしれないんですよね」
「はあ?」
その言葉の意味を即座には解しかねてそう訊き返すと、石田は笑いながらあらためて言わんとするところを説明してくれた。
「最近なにげなく中国の詳しい地図を眺めていて気づいたんですが、北京から天津、済南を経て上海へと向かう鉄道は塘沽を通過しないんですよね。そうだとすれば、私が塘沽だと思った駅は途中のべつの駅だったことになります。もしもわたしがあの駅で見かけた人物がほんとうに事務長だったとすれば、彼はわざわざ私を探しに塘沽からかなり離れたところまでやってきたことになるんです。冷静になって考えてみると、まさかそこまではやらなかっただろうとね。実際には人違いだったんでしょうが、脱走の途中ということで心理的にもひどくナーバスになってたんでしょう」
「石田さんでも心理的パニックに陥ったことがあったんですね、いまの姿からは想像もつかない話ですけどね。もしかしたら人違いじゃなかったかもしれませんよ。塘沽港の船のほうじゃ大騒ぎになっていたでしょうから、全員で手分けしてあたり一帯を捜しまわっていたとか……。それに連帯責任ということもありますしね」
「何かの事故に遭ったものなのか、それとも意図的な脱走なのか船の者にははっきりとはわからないわけですから、そりゃ大変だったでしょうね。ずいぶん迷惑をかけたんだろうなとは思います、氷川丸の運航そのものにもね。タリーマンは重要な仕事でしたから……」
「石田のバカヤローッとか船員たちが叫んでいたかもしてませんね」
「人生ってごく些細な偶発事によって左右されることがあるわけで、あとで考えてみるとなんだか馬鹿にされたようで腹も立ってくるのですが、でもまあ奥が深いといえば確かに奥が深いともいえますね」
「ともかくも塘沽の真っ赤な夕日に全責任を転化した石田さんは、足を踏みつけてしまった幼児の鳴き声に救われて済南経由で再度青島行きを決意することになったわけですね」
「そうそう、そこであたらめてもう行くしかないと開き直り、当初の予定通り青島へと向かうことにしたんですよ」
そこまで話すと石田はしばらく押し黙り、その間に一杯の紅茶をすすって喉を潤した。そんな老翁の様子をさりげなく眺めやりながら、私は若い頃のその姿にあらためて想像をめぐらせた。素晴らしくハンサムでスタイルも抜群だが、かなり自己主張の強い、小生意気なナルシシスト気味の青年で、一見したところでは内向的だがそれにもかかわらず志向性はきわめて強い――それが心中で密かに想い描いた青年期の石田像であった。
私の知る晩年の石田には、他人を交えて談笑するときも、常に話題の中心となるのが自分に関する事柄や自分のよく知る範囲の物事でないと気がすまないようなところがあった。それはこの人物にまたとない魅力をもたらす長所であると同時に、気の合わない人から嫌われる理由ともなる最大の短所でもあった。半ば冗談まじりに石田のそんな一面をこちらが指摘したりすると、彼自身もそのことをはっきりと自認していたものだから、若い頃のその人物像についてのそんな推測はそう的はずれではなかったに相違ない。
もう引き返すことができないと悟った石田は、済南(チーナン)で山東半島方面行きの列車に乗り換え、当時多くの日本人の住んでいた青島へと向かった。所持金を騙し盗られ上海までの旅費が足らなくなったがゆえの不本意な青島入りだったが、黄昏の空のもとに広がる青島の街並みはそんな石田を慰めいたわるかのようにして迎え入れてくれたのだった。偶然の成り行きとはいえ、魔都と呼ばれた上海に直接向かわずこの風光明媚な青島の地を訪ねることになったのは、のちのちの彼の人生にとって結果的には幸いした。だが、気まぐれな運命の仕組んだそんな人生ゲームの行く末をこの時の彼が知ろうはずなどむろんなかった。
黄海に臨む膠州湾の東に位置する青島は、石田が想像していたよりもはるかに文化的で詩情にあふれ、しかも驚くほどに美しく整然とした港町であった。一八九一年、清の北洋艦隊が膠州湾を基地にした際に青島の町の建設がはじまり、その六年後の一八九七年に山東半島を侵攻したドイツが同地を租借地とすると、その一帯の統括支配を強化するために欧州風港町としての市街整備が大々的に進められた。個々の民家や街路は当時のドイツの町をそのまま模して構築されたため、石と煉瓦造りの赤い屋根の家々が海を見下ろす緩やかな傾斜地に整然と立ち並び、しかもそれらの街並みは豊かな樹々の緑や海の風景と見事なまでの調和をみせてのび広がっていた。ドイツ人たちによる青島の町の建設は、徹底した自然との融合を念頭に入れながら計画的に行なわれたため、その景観は当時からたいへんに素晴らしいものだったようである。
一九一四年にサラエボでオーストリアの皇太子フランツ・フェルナンドが暗殺されたのが契機となって第一次世界大戦が勃発すると、日英同盟を結んでいた関係で英国は日本の参戦を求めてきた。そして、それを中国大陸への勢力拡大の好機だと判断した日本政府は、青島周辺に要塞を築き守備についていたドイツ軍の攻撃を開始した。艦船七十余隻に二万人の軍勢をもって攻める日本軍に対してドイツ守備軍は同盟国オースリア・ハンガーリー帝国の巡洋艦一隻とその兵員四百人を合わせた四千四百名の寡勢で立ち向かい、二ヶ月余にわたって果敢に善戦したがついに敗れ、以後青島は日本の支配下に入ったのだった。
この戦いに参戦したオーストリアの巡洋艦カイゼリン・エリーザベト号(皇后エリーザベト号の意)に関してはちょっとした逸話がある。暗殺されたフェルナンド皇太子は一八九三年に三週間にわたって日本を訪問したことがあったが、そのときのお召し艦だったのがほかならぬこの巡洋艦カイゼリン・エリーザベト号であった。しかも、運命の皮肉はそれだけでは終わらなかった。
一九一四年にも日本を親善訪問したこの巡洋艦はそのあと上海へと向かい同地に碇泊していたが、たまたまその時に第一次世界大戦が勃発した。当時オーストリアはドイツと同盟関係にあったため、カイゼリン・エリーザベト号は急遽青島に移動してドイツ軍と合流、親善訪問したばかりの日本の軍隊と戦闘をしなければならないという予想外の事態に遭遇した。結局、同巡洋艦は青島沖で自爆沈没し、艦をあとにした四百名の乗組員は上陸してドイツ軍とともに要塞にたてこもり日本軍と戦った。
日本軍に敗れ捕虜となったドイツ人とオーストリア人たちは日本各地の捕虜収容所に移送され、それから五年間ほどわたって捕虜生活を送ったあと釈放された。その捕虜たちの中には洋菓子バウムクーヘンで知られるユーハイムの創立者であるユッフハイムなどのような人物もふくまれていたという。解放されたあと、ユッフハイムは横浜でユーハイムを開店、その後同店は神戸の三ノ宮に本拠を移したのだそうである。
第一次大戦にともなう日独戦の際にも青島の町はドイツ人によって建設された当時の姿のまま無傷で残り、第二次世界大戦終了にともない日本の支配から解放されたあとも美しい街並みは昔のままに保存された。その後、人口七百万の大都市にまで発展した風光明媚な青島やその一帯は現在も中国有数のリゾート地となっている。
ともかくも石田はそんな青島の駅に降り立った。ポケットの中にはもう小銭一枚さえ残っていなかった。それからどうするかなどまるで考えていなかったし、また考えようにも考えられるような状況でもなかったが、天津などと違って駅の構内を行き来する人々には日本人の姿が数多く見られ、また、いろいろな案内表示などにも日本語が多用されているのはせめてもの救いであった。とりあえず言葉が通じ周辺の状況が読み取れるということは、そのときの石田のおかれている切迫した状況からするとたいへんに心強いことであったからである。

絵・渡辺 淳
「マセマティック放浪記」2003年4月23日
ある奇人の生涯 (15)
夜の繁華街に青い鳥が!
当時の青島の駅は中世の小城か古いカトリックの教会を想わせるかたちをしていて、中央と左右にそれぞれ一基ずつ先端の鋭く尖った六角錐状の屋根をもつ尖塔が配されていた。とくに一番大きな中央の尖塔の頂きには十字架が高々と掲げられており、その一点からしてもこの青島というところが中国の都市のなかにあって文化的に異色の存在であることは明らかだった。
不思議な感慨にひたりながら青島駅構内のベンチでとりあえず一息ついたあと、宵闇の迫るなかを石田は近くの繁華街のほうへと向かって歩きだした。現在では孫文の異称「孫中山」にちなんで中山路と呼ばれている夜の繁華街一帯にはなんとも異国的でロマンティックな雰囲気が漂っていて、初めて目にするそのどこか幻想的な光景に彼はたちまち魅了されてしまった。
だが、なにぶんにも彼はもはや無一文の身ときていた。しかも、天津で上海特急に乗車してからはなにも食べていなかったから、青島の夜の繁華街の美しさに心を奪われはしたものの、しばらくすると空腹感に襲われそれどころではなくなってきてしまった。かつて横浜の山下公園で極度の空腹のために行き倒れになったときのことが脳裏に甦り、そうなるまえにどこかでちょっとでも食べ物でも恵んでもらえないかという淡い期待を抱きかけたりもした。自業自得の事態とはいえ青島到着早々に物乞い同然のことをするなど情けないかぎりであったが、ともかくもその場を凌ぐにはそうするのもやむをえないことだった。
ところが自らが悪運の強さと言って憚らないその強運のゆえに、このときもまた淡い期待が「濃い現実」にかたちを変えて彼の眼前に立ち現れた。その日も十三日の金曜日だったのかという問いかけに、それについては明確な記憶はないけれど、たとえ十三日の金曜日ではなかったとしても「銀曜日」くらいのことはあったのかもしれないと石田は笑って切り返してきた。
南北一キロほどにわたってのびる繁華街の中ををふらふらと歩いていると、「青い鳥」というネオンサインが突然目に飛び込んできた。しかもそれは中国語ではなく日本語で「青い鳥」と表示されたネオンサインだった。場所が青島なので「青い島」じゃないのかとあらためて確認しなおしてみたが、間違いなくそこには「青い鳥」という日本語の文字が表示されていた。
それはダンスホールのネオンサインだったのだが、まじまじとそのネオンサインを見つめやった石田は、わざわざ「俺の」という二文字を青い鳥のまえに付け足し、内心密かにもしかしたらこれは「俺の青い鳥」じゃないかと呟いていた。まったくの偶然のこととはいえ、そんな切羽詰った状況のなかで、青い鳥というなんとも思わせぶりな日本語の文字と出遭うこと自体なんともできすぎた話ではあったが、事実は事実に違いなかった。
彼はそのネオンサインに誘い導かれるようにしてダンスホールの中へとはいっていった。東京でカフェバー勤めをしていた頃、当時大流行していた銀座などのダンスホールに足繁く通い折々アルバイトで裏方などをやったりもしていたから、ダンスホールのシステムや内部の事情には通じていた。彼にすれば、まずは一杯の水でも恵んでもらえれば有り難いというのが本音であった。実際に踊るつもりならチケットを買ってダンスフロアに入らなければならなかったが、当時のダンスホールではダンスフロアーの外に立ってダンスを眺めながら水を飲むだけなら只ですませることができたからだった。
ところが、一杯の水を求めて飛び込んだそのダンスホール「青い鳥」で、石田は予想もしていなかった幸運にめぐりあうことになったのだった。不慮の事態続きの長旅に疲れ果てた彼を迎えるべく、青い鳥が待ってくれていたというのである。その経緯とそれに続く一連の展開を懐かしそうに語る彼の表情は、不思議なほどに明るく輝いて見えた。
「ほんとうに水だけ飲ませてもらおうって思ったんですか?――そのダンスホールで誰か可愛い女の子でも探し出し、巧みな会話とダンスのテクニックとでタラしこんで一時的にでも面倒を見てもらおうという魂胆だったんじゃないでしょうね!」
そう突っ込みを入れると、愉快そうに笑いながら相手は意外な答えを返してきた。
「ハハハハハ……、バレてしまったかって言いたいところですけどね、実際にはそこまでやる必要はなかったんですよ。青い鳥が一羽ホールの中を飛んでいましたんでね」
「はあ?……青い鳥が飛んでたんですか?」
思わせぶりなその言葉の含みを汲み取りかねてそう問い返すと、石田はこちらのいささか困惑気味な表情を楽しみでもするかのように言った。
「とりあえず青い鳥に入ってみますとね、男たちの相手をして踊っている女性はみんなプロのダンサーばかりでした。当時は頻繁に国際ダンスコンクールなどが開かれていましてね、国内外を問わず社交ダンスが盛況を極めていたんですよ」
「それでどうなったんですか……お金がないから石田さんは踊らなかったわけでしょう?」
「なんとそのホールのダンサーの中にベティがいたんですよ。いやあ、偶然もいいところでしたからさすがに驚きましたね。東京にいる頃にカフェバーや銀座のダンスホールで一緒に働いていた女の子でね、背の高いきっぷのいい娘でもともととても親しい仲でした。まさか彼女が青島に来ているなんて考えてもいませんでしたからね……」
「人間の青い鳥だったってわけですね。それでそのベティっていう女性は外国人だったわけすか?」
「いや、れっきとした日本女性なんですが、当時は、東京の銀座をはじめとする各地の繁華街ではカフェバーやダンスホールが大流行でしてね、そこで働く粋な女性たちはわざと洋風の名を名乗っていたんですよ。芸妓さんの源氏名みたいなものですね」
「へーっ、そうだったんですか。ぜんぜん知りませんでしたねえ、そんなこと……」
応答こそそっけなかったが、こちらにすれば、厚い記憶の古層の下に圧し固められていたドラキュラ老人の青春の化石を運よく掘り当てた気分だった。
「一踊りし終えて休んでいるベティに声を掛けると、さすがに彼女のほうも驚きましてねえ。どうして石田さんこなところにいるのって……」
「そりゃそうでしょうよ。それで、その晩はベティさんのところに転がりこんだわけですね、青い鳥の庇護のもとに……」
「助かったって思いましたよ。とりあえず簡単にこちらの事情を説明しましてね、彼女のおごりで食事を取らせてもらいました。そのとき何を食べたのかはもう憶えてはいませんけれどね」
「もちろんその晩はベティさんのところにお世話になったんですよね」
問い詰めるようにそう念を押すと、老翁はこちらの読みをずすように軽く首を振った。
「確かにベティの家には泊めてもらったんですけどね、彼女のほうはその晩わざわざ友達のところへ泊まりにいったんですよ。気性の激しい女の子でしてねえ、ダンスホールでダンサーをやってはいてもそのへんのことはとてもしっかりしていました」
「ふーん、そうだったんですか……、でもしばらくはベティさんの家に居候してたんでしょう……、すると彼女はその間ずっと友達の家に寝泊りしてたというわけですか?」
もう一歩踏み込んだそんな問いかけに対し、石田は言葉を濁しストレートには答えてくれなかった。だが、たとえ一時的なものではあったとしても、その後の二人の間にはそれなりの関係が生じていたと考えるほうが自然であるようにも思われた。
天主教堂という教会やその周辺のたたずまいに象徴されるように、東洋のものとはまるで異なる青島の街並みの美しさに石田はすっかり魅了された。青島港やその周辺一帯の変化に富んだ海岸美の素晴らしさも彼の心を感動させた。さらにまた青島市街の北東に位置する山東半島の中央部や先端部には奇岩奇勝に恵まれた風光明媚な山々や道教寺院太清宮など風変わりな観光スポットが点在していて、石田の美的関心や知的好奇心を存分に満たしてもくれた。中国各地で繰り広げられている日中間の熾烈な戦闘などにはまるで無縁な、それはそれはなんとも平和で心安らぐ光景だった。
まったくの偶然に導かれてのことではあったが、自然美と人工美とが見事に調和した青島というこの町にやってくることができた幸運を彼は胸の奥でしみじみとかみしめた。憧れの上海入りを断念したわけではなかったけれども、しばらくの間この青島に身を落ち着けてみることに異存はなかった。そんな青島の町での一年前後にわたる生活の様子についても、石田はさらに詳しく話してくれた。当時青島は日本の植民地と化していたわけだから、歴史的な観点に立って当時の出来事を振り返ってみるとき、かならずしもそれらすべてを肯定すべきではないかもしれない。しかしながら、当時日本の占領支配化におかれていた国外の町ならではの人々の生活の様子は、話を聞く者の立場からすれば実に興味深いものではあった。
「そんなわけで、ともかく青島での生活が始まったわけですが、いま思うとそれはそれでなかなか面白かったんですね。貴重な体験といいますか……」
「文無しの石田さんは、生活費を稼ぐためにいったい何をやり始めたんですか?、まさかいつまでもベティさんに面倒をみてもらうわけにもいかなかったでしょうし……」
「もちろん何もしないわけにいきませんでしたよ。母親の世話になりながら死んだ親父のザマを見ていて、女性の紐になるのだけは絶対に嫌だと思ってましたからね。青島に住むようになってしばらくは例のダンスホールの青い鳥で裏方なんかをやっていました。当時の人間としては身体も大きなほうでしたから、用心棒なども兼ねましてね」
「ひゃは!……用心棒ですか、まさかドスか拳銃なんかを隠し持っていたというわけじゃなかったんでしょう?」
「ハハハハハ……、さすがにそんな物騒なことはしなかったですよ。私は身長が一七六センチあって一見大柄で強そうに見えましたから、ホールにいるだけでよかったんです。実際にはすこしも強くなんかなかったんですが、しつこいお客がいるときなどはベティらのようなホール勤めの女性ダンサーのガードとして役立つことはありました」
「石田さんはダンスは結構うまかったんでしょう。女性客の相手なんかはなさらなかったんですか?」
「見よう見真似でまあまあ踊ることはできたんですが、時代柄もあってダンスホールに踊りにやってくる女性の一人客というのはそうそうはありませんでした。だからそんな機会はほとんどもてなかったですね。お客は男性ばかりで、たまに女性がいたとしても連れの男性がいるのが普通でしたから……」
石田はそう言って苦笑したが、その口ぶりから想像すると、ダンスそのものはその頃かなり得意だったようである。

絵・渡辺 淳
「マセマティック放浪記」2003年5月7日
ある奇人の生涯 (16)
大物香具師の右腕になる
青島ビールなどでも知られる青島は衣食住の環境にもずいぶんと恵まれていて、実際に暮らしてみると想像していた以上に過ごしやすいところだった。青島市街やその郊外周辺の様子も一通りのみこめ、新しい生活のリズムにも慣れてくると、それをみはからいでもしていたかのように、ベティは石田にちょっと風変わりな人物を紹介してくれた。懐かしそうに彼が語ってくれたその人物にまつわる話はなかなかに面白かった。
「そうこうするうちに、ベティから大阪屋さんを紹介されたんですよね」
「大阪屋っていうと、デパートかなんかのことですか?」
「いやあ、そうじゃなくて人間なんですよ」
「はあ?……てっきりお店かなにかの名前だとおもいましたが……、でどんな?」
戸惑いながらそう問い返すと、石田は愉快そうに笑いながらその人物のことを詳しく説明してくれた。
「大阪出身ということで大阪屋を名乗ってたんでしょうかね。興行師、いわゆる香具師の大親分でしてね、青島のあちこちに旅館なども経営していました」
「ありゃま……船員からこんどは香具師の子分に転身ですか!」
「ははははは……、でもねえ、単なる子分っていうわけじゃなかんたんですよ」
「じゃ、いきなり幹部クラスにでも?」
「ベティの口利きに加えて、一応は旧制高校卒業の学歴もあり、ある程度語学もでき経理の知識もあるというわけでしたから、結局、その香具師の大親分の秘書になったんです」
「美人秘書じゃなく美男秘書ですか……、なんだかちょっと場違いなような?」
「いやいや少しも場違いなんかじゃありませんよ。はまり役でしてね……なにしろ文字通りに大阪屋さんの右腕になったんですからね!」
そう言って悪戯っぽく笑う石田のほうを少々困惑顔で眺めやると、相手はここぞとたたみかけるように言葉をつないだ。
「なぜって、その大親分は実際に右腕がなかったんですよ。出入りが原因で右腕なくしたらしいんですがね……、まあそれはともかく、なかなか面倒見のいい人でしたね」
「ははははは……、正真正銘の右腕っていうわけですか!……、でも石田さん、もしもその人物の欠けたほうの腕が左腕だったら、そううまくは務まらなかったかもしれませんね」
私は半ば笑い転げならがそう応酬した。
「まあ、香具師連中の総元締めの秘書としていろいろな書類を作ったり、各方面との交渉や契約に携わったり、会計を担当したりしましたよ。秘書になってしばらくすると、すっかり信用されるようになりましたから、当面の生活にはまったく困らなくなりました」
「いやあ、いくらドサクサまぎれとはいえ、石田さんがそんな変った仕事についたことがあったとは意外でしたね。会計担当っていうことは、要するに金庫番もやってたっていうことですよね」
「金庫番は大袈裟でしょうが、まあ、似たようなものだったんでしょうかね」
「天津の中国人女性に盗られてしまった分の大金を、青島の香具師の親分の金庫からちゃっかり取り戻すなんてことは考えてみなかったですか?」
「いやあ、それは考えませんでしたよ。発覚して両手落ちなんぞにされてしまったらたまったもんじゃありませんからね。それに、そんなことをしなくても十分生活は成り立つようになっていましたからね」
「日中戦争が激化せず、すべてがそのまま順調にいってたら、そのうち香具師の石田親分なんぞが誕生していたかもしれませんね」
「そしたら、あんたに秘書になってもらって、いまごろは跡目相続なんかをしてもらったりしていてねえ」
「でも石田さん両腕があるから、右腕にも左腕にもなれませんよね」
「それならせめてこの右足にでもなってくれれば……」
時々痛みが走って近頃思うように動かせなくなってきているとかいう右足を擦りながら、相変わらず石田は軽口を叩き続けた。
「それはともかくとして、そんな秘書生活ばかり送っていてとくに退屈ということはありませんでしたか?」
「いや、実を言うと秘書としての事務的な仕事ばかりやっていたわけじゃないんですよ」
「じゃあ、大親分の右腕がわりになって大立ち回りにも一役買ったとか?」
「ははは……、いくらなんでもそれはねえ。そんなことになっていたら、いまごろこうして生きてなんかいませんよ」
「とするといったいほかにどんな仕事を?」
「いろいろな興行などで、ハンドマイク片手に呼び込みやアトラクションの実況解説なんかもやってましたね。言葉巧みに客引き文句を並べ立てたりしましてね」
「お祭りのときなんかによく見かける見世物小屋のあれとおんなじような?」
「そうそう、まさにあれとおなじですよ。さあさあ、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい、いまこれを見そこなったら皆さん一生後悔するよ!――なんて調子でね。でも、はじめはさすがに気恥ずかしかったですね」
「石田さんは博多の芸人町で育ったっていうお話でしたから、もともと十分にそんな資質があったんじゃないんですか?、それに、青島でのその経験がずっとのちになって、イギリスのBBC放送でのアナウンサーの仕事に活かされたとかいうことだって?」
イギリスにおけるずっとのちの石田の活躍ぶりについて断片的ではあるがそれなりには知っていたので、少々意地悪だとは思ったがあえてそんな質問を浴びせかけてみた。
「うーん、それはあるといえばあるような、ないといえばないようなものなんですが……」
「それで、具体的にはどんな風な興行をやってたんですか?」
「たとえば、伊勢志摩地方の海女さんなんかを連れてきて、大きな水槽の中で真珠採りの実演なんかをやらせるわけですね。日本人と中国人両方のお客を呼び込んでおいて、歯の浮くような解説文をもっともらしい調子で読み上げるんです。すると、それを中国人の通訳が、中国語に同時翻訳して聞かせるわけです」
「なかなかのもんじゃないですか!……、でその海女さんの真珠採りの実演は好評だったんですか?」
「ええ、なかなかのものでしたよ。とくに中国人たちにはとても珍しかったようで、ずいぶんと見物人も多かったです」
「最後には水槽に銀貨かなにかが投げ込まれたりしたんじゃないですか?」
「そうそう、そんなこともたまにはありましたね」
「石田さんが海士になって伊勢志摩の海女さんと一緒に潜るなんてことは……まあ、いくらなんでもなかったんでしょうね」
「それはあなた、たとえ僕が泳ぎが得意だったとしても、フンドシや海パン姿じゃとても絵にならないでしょう!」
「絵はもちろん金にさえもなりませんよ、そりゃ!」
「それでね、メインの催し物のある周辺には他の香具師仲間が集まって、チマチマした出し物を並べて一斉に興行を行うんですよ。まあ、一種の相乗効果を狙って雰囲気を盛り上げようってわけですね」
「そのへんは日本のお祭りの興行とおんなじですね」
「興行地のすぐそばには日本人向けのダンスホールもありましたが、そこでは浴衣を着てハワイアンを踊ったりもしてましたよ。いま思うとなんだか妙な取り合わせでしたけれどもね。ハワイアンじゃなくってジャパニアンというか……」
「そうだったんですか。なんだか異国での興行ならではの特別な雰囲気が感じられますね。叶うものなら一度見てみたかった――とは言っても、その頃僕はまだ生まれてませんけどね」
「まあ、香具師の興行が順調にいってるときはいいんですがね、そういかなくなることもままありましてねえ。青島というところはよく大雨が降るところで、とくに日本が梅雨の季節を迎える頃にはむこうも一ヶ月以上にわたって雨が降るんですよ。その年の雨はとくにひどくてねえ……」
「やっぱり雨が降ると興行はうまくいきませんでしたか?」
「洪水が起こるほどの降りかたでしたから、ぱったりと客足が止まってしまうんですよ。すると香具師連中はやることがなくちゃうから、毎日毎日、猪・鹿・蝶の世界にいりびたるわけです。もちろん、お金を賭けてですよ……。僕は花札が好きじゃなかったから、もっぱら入口のところに立って警察がやってこないかどうか見張る役目をしてましたけどね」
「じゃ、毎日毎日フラワーカード・パーティのガードマンをやってたんですね……ははははは、それで大雨はおさまったんですか?」
そう茶化しながらさらに話の先を促すと、再び石田はその後の経緯を面白おかしく語りだした。
「この年の大雨はとくにひどかったうえに、一ヶ月以上続いた雨がやんだあとも一帯は赤土が多いため川口の水がひどく濁ったんです。海女の実演用の大水槽には川水を使ってたんですけど、ひどい濁りをとるため浄水用のミョウバンをいくら入れても水は澄んでくれない。結局、興行は不可能になり、香具師グループもいったん解散せざるをえなくなってしまったんです」
「香具師たちも花札どころじゃなくなったわけですね」
「そうそう、それで僕は大阪屋の事務処理を手伝うかたわら、家具店で店員をやったりもしはじめたんですよ」
「まさか怪しげな家具売ってたわけじゃないんでしょうね?」
「ははははは……、そこはドラキュラ家具店じゃなかったですから、商品はまともなものでした。まあ、それはよかったんですが、そのときになってやっかいな問題が持ち上がったんです。日中戦争がますます激化してきましてね、青島のある山東半島は軍事上の要衝であるため軍部もその確保に懸命になりはじめたんです。そんな要衝ですから、中国側のゲリラによる襲撃などが起こるだろうことも予想もされ、青島周辺に住む民間日本人の安全は保証されなくなってきていました」
「それで退去命令が出たわけなんですね。せっかく青島に落ち着きかけたのに、石田さんにとってはまた計算違いの事態になってしまった……」
「そうなんですよね、民間人は日本へ引き揚げろという強制退去命令が出されました。貨物船から脱走してまだ一年も経ってない頃のことですから、いくらなんでもこのままおめおめと日本に帰れるかと思いましてね」
軍部の打ち出した青島からの民間人強制退去命令はすっかり石田を困惑させた。そのまま日本に戻ったのでは元も子もないばかりでなく、運が悪ければ氷川丸からの脱走による職場放棄の責任を追及されるおそれさえもあった。そんなわけだから、なんとしても彼は中国のどこかに当面の退避場所を探し出さねばならなかた。上海へと向かいたいのはやまやまだったが、鉄道や船舶による青島から上海方面への交通にはすでに厳しい規制が敷かれてもいたため、それは叶わぬ話であった。切羽詰った状況に追い込まれ身の振り方に迷う彼に願ってもない話を持ち込んできてくれたのは、ある香具師仲間の男だった。

絵・渡辺 淳
「マセマティック放浪記」2003年5月14日
ある奇人の生涯 (17)
それぞれのツテで満州へ
「結局それでどうすることになったんですか……、そこでまた石田流の悪運の強さが一役買ったとかいういつもながらの展開にでも?」
進退窮まったときの状況を語る石田には、「悪運の強さ」という文句を持ち出してその後の話の展開を促せばよいと悟っていた私は、わざとそう相槌を打った。
「幸い、わりと親しくしていた若い香具師仲間の男がいましてね、彼がツテを頼って大連に行くといいますのでね、僕も彼に同行することにしたんですよ。大連で彼の仕事の手伝いをするという条件でね」
「大連方面はまだ日中戦争の影響は及んでいなかったんですか?」
「山東半島の向かいの遼東半島先端に近い大連は、当時日本が実質支配していた満州の南部に属する都市で、満鉄本社などもそこに置かれていましたからまだ安全だったんです。青島から大連に渡る船も頻繁に出ていましたしね」
「そうだったんですか。それで、その香具師の男がフーテンの寅さんの前身だったなんてことはありませんよね!」
「ははははは……、もしもそうだったら、寅さんまでは無理としても、僕もいまごろフーテンのドラさんくらいにはなっていたかもしれませんがね。いや、名前が達夫だから、フーテンの達さんか……」
「それで、舞台はいよいよアカシアの大連に移るというわけですね。でも、憧れの上海からはどんどん離れていくいっぽうだったわけじゃないですか?」
「そうそう、それでね、やっぱり自分には上海というところは縁がないのじゃないかって思いかけてましたね」
「大連へはむろん船で?」
「ええ、もちろんそうです……やはり一九三八年のことですね。僕と同様に日本には戻らず、ツテを頼って中国北部方面へと移っていった者がずいぶんといましたね。皆いったん船で大連に渡り、そこから満鉄などを利用して満州各地へと散っていったんです」
「大連行きの船に乗ったとき、かつての船員生活が懐かしくなりませんでした?」
「敗軍の将は兵を語らず……じゃなくって、脱船の男は船を語らずですね」
そう言い終えると、石田は一瞬ニヤリと笑ってこちらの顔を見た。
「タリーマンの仕事をまたやりたくなったとかってことはなかった?……でもまあ、またもや大連港で脱走劇が繰り広げられたんじゃ船のほうだってたまったもんじゃありませんものね」
こちらがそんな意地悪な質問をすると、相手はすぐに切り返してきた。
「いや、その前に船のほうがね……何丸っていったか船名はもう忘れてしまいましたけどね……その船なんか私の顔を見るなり、仲間を裏切ったおまえなんかを乗せてやるのは嫌だって……」
「ははははは……船にまでそんな嫌な顔されたんですか」
「それで、大連に渡っていろいろやったあと、タリーマンではなく外資系の銀行マンになっちゃったんですよ」
「はあっ?……銀行マンですか!……まさか、銀行のガードマンをやってたっていうんじゃないでしょうね?」
眼前の石田翁が銀行マンとして働いていた姿などとても想像できそうになかったので、私は思わずそう訊き返した。
「いや、ちゃんとした銀行マンになったんですよ。それもアメリカのちゃんとした銀行のね……、まだ日米開戦前のことでしたからね」
大連に渡ったあとの石田の暮らしぶりについての質問をいったんそこで留めおくと、私はわざと話を脇道へとそらしてみた。たまたま青島に流れついた石田にとって文字通りの「青い鳥」となってくれたベティという女性のその後の身の振り方が気になっていたからだった。
「じゃ、ベティさんも一緒に大連方面にでも?」
そう水を向けると石田はこちらのそんな言葉を予想でもしていたかのようにすぐに応じた。
「お互い明日のことはわからない身でしたから、身の振り方は別々に考えていくしかありませんでした。我が身の面倒をみるだけで精一杯でしてね」
「じゃ、ベティさんはどちらに?……日本に戻ったとか……」
「いや、ベティは大連経由で満州のハルビンへと移ってそこで働くようになりました。やっぱり日本には戻りたくなかったんでしょうね。もちろん、ツテがあるとかで、ハルビンへと行ったわけです。青島から大連へと渡る船便も別々でした」
「じゃ、石田さんとは青島で別れたままに?」
「ええ、大連とハルビンじゃかなり離れてますからね。ただ、その後もしばらくはお互いに手紙や電話などを通しての連絡はあったんです。それに、満州には何人か双方に共通の知人などもいましたから、そんな人を介して互いの近況などが伝わったりもしましてね」
「まったくお互いの消息が知れなくなったというんじゃなくてまだよかったですね」
「ただ……」
「ただ……どうしたんですか?」
その「ただ……」という短い言葉に容易には測り難い含みを感じた私は、とりあえずそう訊ね返した。
「なかなかの美人だったけど、おっそろしく気丈な女でしてね。ダンスホールなどで自分にしつこく言い寄る男あったりして、しかもその相手が金や権力はあるけどなんとも嫌な奴だったりすると、呆れるような仕打ちをやってのけてました」
「そりゃまた、いったいどんな仕打ちを?」
「踊っている最中などにキスをしながら、あらかじめ自分の口に含んでおいた葡萄の種などを舌先を使って相手の男の口の中に押し込んでしまうんです。自分に気があると思って男のほうがついついいい気になり、葡萄の種をそのまま呑み込んでしまうのを見はからって……」
「へえ……葡萄の種を口移しで呑み込ませるわけですか……。で、その行為にいったいどんな策略が込められていたっていうんですか?」
一言も聞き漏らすまいと耳をそばだてながら、私はそう話の先を促した。
「そのあとすぐに、キスしたとき自分の金の入歯がはずれて相手の口に入ったのをそのまま呑み込んでしまっから弁償しろとふっかけ、それなりの額のお金を巻き上げたりしていましたね。大勢他人がいる前で堂々とそんな要求をするんですから、たとえ男のほうがハメられたと気づいても、結局、お金を払わざるを得ない……しかも、その後は、したたかな女だというわけで相手は二度と近づかなくなるっていう寸法です」
「それはまたなんとも驚いた手口ですねえ!」
「確かにしたたかではあったんですがね、自己防衛のため意図的にしたたか女を演じているところも十分にありましたよ」
「それが、当時の国際社会の社交場を独りで渡り歩きならが逞しく生き抜く女の知恵でもあったんでしょうね」
「そうなんですね。大陸の都市部の繁華街でいろいろなお客相手に働く日本女性は程度の違いこそあれ皆芯は強かったです。でもねえ、ベティの気性の激しさは別格でしたよ」
「それでも石田さんには優しかったんでしょう?」
「優しかったっていうより、ごく自然に接してくれていたっていうところでしょうかね」
そう言ってしばらく言葉を切ったあと、石田はベティという女性の気丈さを物語る凄まじいエピソードをいまひとつ紹介してくれた。
「ベティがハルビンに移ってからの話なんですがね、どう断っても彼女にしつこく迫ってくるロシア人がいたらしいんです。そして、とうとうあるとき不意に自宅に押し入られ、有無を言わさず強姦されそうになってしまったそうなんです。いま風に言うならきわめて悪質なストーカーだったってわけですね」
「それはまた……、それで勇敢に一大活劇を演じたとか?」
「いや、相手はロシア人の大男ですからとても力づくではかなわないと思ったんでしょう。ベティはいかにも彼女らしい非常手段をとったんです。意表を突くというありふれた言葉じゃ言い表わせないような手段をね……」
「うーん、ちょっと想像がつきませんが……」
「なんとそのとき彼女はとっさに台所に飛び込み包丁で自分の指先を切ると、大声で喚き叫びならが、激しく吹き出す自分の血液を相手の身体中になすりつけたというんです。さしもの相手もその凄まじい形相をまのあたりにし、強姦を断念して退散したのだそうですがね……」
「いやはや、そりゃまた凄まじいかぎりですね……」
驚きのあまり私がそう言ってしばし口をつぐむと、石田翁は最後に遠くを見つめ直しでもするかのような表情を浮かべ、一言ぽつりと呟き添えた。
「話が時間的に前後してしまうんですが、ベティはね、終戦になるまえにハルビンで死んでしまったんですよ。たぶん最後は一人ぼっちだったんでしょう、胸をやられていましたからね……。いくら気丈とはいえ、いろいろな思いが彼女の胸中を駆け巡りはしたんでしょうね。実際に僕がその死を知ったのはずっとあとになってからのことなんですがね。その事実を知ったときはさすがに悲しかったですね。お世話になりながら、結局、僕は何もしてはやれなかった……」
なんの衒いもなくそんな感情を素直に述べ語る石田の姿は、毒舌と皮肉の塊そのもののようないつものそれとはおよそかけ離れたものであった。幻術や妖術の厚いヴェールで何重にも覆い隠されたこの不可思議な老人の心の奥をほんの一瞬だが覗き見たような思いだった。
老翁の「ただ……」というはじめの呟きの背後に隠されていたそんな重たい現実の存在を知って、しばし私は黙り込んだ。いや、そうやって黙り込みながらも次の展開を語る相手の言葉を待っていたというのがほんとうのところではあったのかもしれない。石田達夫というこの奇人の波瀾に満ちた人生劇場の舞台は、実際、まだ第一幕が終わったばかりに過ぎなかったからである。

絵・渡辺 淳
「マセマティック放浪記」2003年5月21日
ある奇人の生涯 (18)
大連での初仕事は?
天津や塘沽の東側に位置する広大な渤海湾は、黄河の河口のすこし南側付近から北東に伸び出る山東半島と、朝鮮半島の付根あたりから西南方向に突き出る遼東半島とによって深々と抱かれるかたちになっている。石田がそれまで滞在していた青島が黄海に面する山東半島中部の港湾都市だったのに対し、彼が新たな生活を送ることになった大連は遼東半島のほぼ南端に位置する港湾都市であった。昭和十三年(一九三八年)の初秋のこと、石田は青島で共に仕事をしていた香具師の男に同行し、当時北方の真珠とも謳われていたこの美しい港町大連へと渡ったのだった。
「アカシアの大連」と称されていたことからもわかるように、市街のいたるところに見事なアカシアの並木道の見られるこの都市は、いまでこそ中国屈指の交易の中心地になっているが、一九世紀末頃までは青泥窪(チンニーワー)と呼ばれるごく小さな漁村であったらしい。日清戦争終結直後の明治二八年(一八九五年)四月に締結された下関条約によって、遼東半島一帯はいったん日本に割譲されることが決定した。ところが、この下関での講和条約に対してロシア、ドイツ、フランス三国による激しい干渉がおこなわれた結果、翌月の五月になって日本は遼東半島を清に返還するのやむなきに至った。
日本による遼東半島の植民地化をまんまと阻止することに成功したロシアは、それから三年後の明治三一年(一八九八年)には清から同半島の租借権を獲得、青泥窪一帯を商港として、また半島最先端に位置する旅順を軍港として大々的に開発整備することを計画した。ロシアが長年の悲願としていた南下政策を遂行するにあたって、遼東半島はそのための基地建設にとって格好の地点でもあったのだ。
初代市長に就任したサハロフは青泥窪に建設中の新都市を「ダルニー」と命名した。「ダルニー」というロシア語は日本語になおすと「遠大」を意味する言葉なのだそうだが、そのような背景からしても当時のロシア政府が遼東半島に託した「遠大な夢」への期待のほどが偲ばれるというものだろう。
ダルニー市の建設に際してはパリの都市構造を模した街造りが行なわれた。現在もその姿を留める円形の中央大広場から放射状にのびる十条ほどの街路には、複数の円形街路が何重にも同心円状にクロスしている。この独特の都市の骨格構造は、実際、市街建設の当初から美しいパリの街並みを彷彿とさせるようなものであったらしい。ただ皮肉なことに、ロシアによる港湾都市ダルニーの建設着工の二年後に勃発した日露戦争は、おおかたの予想に反して日本軍の勝利に終わった。その想わぬ敗戦の結果、ロシア軍をはじめとするロシアの主勢力は遼東半島から撤退せざるを得なくなったのだった。
そして、ロシア撤退後の明治三八年(一九〇五年)九月に日露間で締結されたポーツマス条約により、日本は遼東半島の租借権をロシアから承け継ぐことになったのだった。以降、ダルニー市は日本によって管轄統治されるようになり、市街の最終的な整備建設などもロシア人らの建設作業を承け継ぐかたちで日本人技師らが担当することになった。中国語で発音するとダルニーというロシア語の音声の響きに似ているかという「大連」という地名が新たな都市名に指定されたのは、この年のことであったという。もちろん、サハロフが命名したダルニーという都市名はその時点で世界地図上から消滅した。
すでに日中戦争が激化していたとはいっても、石田が大連に移ったのは満州に日本の傀儡政権が樹立されたのちのことで、しかも大連は日本政府による実質的な満州支配の中枢に当たる都市だったから、その安定した繁栄ぶりは大変なものであり、また中国在住の日本人にとってはこのうえなく安全なところでもあった。遼東半島の最端部には日清日露両戦争史にその名を残す一大軍港の旅順などもあり、大連は当時日本軍の支配化にあった同軍港の東隣に位置していたから、二重の意味でその安全は保証されていた。
満鉄という略称で知られるこの時代の満州鉄道は一応鉄道会社の形態を装いはしていたものの、事実上は日本政府の隠れ蓑ともいうべき巨大かつ強力な特殊組織体で、満州全土の裏の支配機構として隠然たる力を揮っていた。そしてその特別な組織体である満鉄の本社が置かれていたのもほかならぬこの大連の地であった。
初めて踏む大連の地ということもあったのだろうが、自然の風物と人工の造形物とが見事に調和したその街々の美しさに石田はすくなからず感動した。モンスーン型気候の大連は日本と同様に彩り豊かな四季にも恵まれていたから、その点からしてもなにかと心を癒される思いであった。主だった通りや橋、市内中心部の町々、各種重要施設などにはすべて日本名がつけられており、地名だけからするとまるで日本本土のどこかの都市にいるかのような錯覚を起こすほどであった。パリをモデルにした都市構造をもつうえに当局による管理統制が十分に行き届いてもいたため、街並み全体がいささか整然としすぎているきらいはあったけれども、どこか温かみに欠けていて違和感を覚えて仕方がないというほどのことでもなかった。
石田がいまひとつ心を奪われたのは大連の星空の美しさだった。澄みきった秋の夜の大気越しに眺める無数の星々の輝きは不思議なほどに彼の心に迫ってきた。氷川丸の船上よりかつて仰ぎ見た満天の星空も素晴らしかったが、この大連の夜空を刻々とめぐる群星の煌きにはそれとはまた一味違う趣があるように感じられてならなかった。なぜかそのときの彼には、頭上に明滅する星明りのひとつひとつが遥かな天上界に位置する未知の集落の家々にともる無数の灯火であるようにさえ思われた。そして、それらの灯火のかたちづくる悠久の集落こそは、やがて何時の日かおのれの魂の行き着くことになるであろう窮極の地であるに違いないという気さえしてくるのだった。
石田にすれば、そもそもこうして大連の街並みの一角から静かに夜空を仰ぎ見ているおのれの姿そのものが信じられない有様だった。運命の悪戯であったとはいえ、独り博多から上京し、様々な紆余曲折を経たあと横浜の山下公園で行き倒れになり、それがきっかけとなって遥々この大連の地までやってくることになろうとは、想像してみようにも到底想像できるような話ではなかった。
実際、ちょっと自分の生き方に自信をもちかけるようなことがあると、次の瞬間には必ずと言っていいほどに、その自信のほどを根底から打ち砕かれてしまうような予想外の事態が発生した。そして。これまで何度となく繰り返されてきたそんな一連の状況が今後の自分の人生においてもなお重ねがさね起こり続けるのであろうという気がしてならなかった。裏を返せば、そんな思いを抱くようになったことそのものが、内面における青年石田の大きな成長を物語っているのかもしれなかった。
貨物船の船員として働いているときはささやかながらも折々仕送りを続けていた博多の母親や妹たちとも、脱船者となって大陸に足を踏み入れて以降、まったく連絡が取れなくなっていた。これから先どのような運命の変遷が待ちうけているのかなど見当のつこうはずもなかったが、ともかくもこの大連の地でなんとか生き抜いていくための方策だけは講じなければならなかった。おのれの消息とここにいたるまでの経緯を伝え、とりあえず博多の家族の者たちを安堵させるためにも、安定した生活のすべを確立することは当面のなによりの急務ではあった。しかしながら、状況的にみてそれを実現するのがそう容易なことではないのも明らかであった。
青島で知り合った香具師の男の仕事を手伝うという条件で大連に同行してきた手前もあったので、石田はその男とともに大福餅と中華饅頭の製造販売の仕事にとりかかった。元手となる資金は二人合わせていくらかの手持ちがあったから、大福や饅頭を製造するのに必要な道具や類や仕事場、当面の住まいなどを男のツテ先の者に提供してもらい、少々お門違いとしか言いようのない彼ら二人の大連での初仕事が始まったのだった。
相棒の香具師の男は大福餅や中華饅頭つくりの経験が多少ともあったようなのでまだしもましだったのだが、その道にはまったくの素人だった石田のほうは失敗に次ぐ失敗の連続で目も当てられない有様だった。皮肉な話ではあったが、青島で香具師の親分の右腕を務めさえしたという彼も、こんどの仕事に関しては、相棒の男の右腕はおろか、左腕にさえもなれそうにない状況であった。いくらかは仕事に慣れたあとでさえも彼の手になる大福餅や中華饅頭などは本来ならとても商品になるようなしろものではなかったのだが、それでも二人は出来上がった品物をすべて自転車に積み込み、大連の中心街や満鉄関係者の住む街へと出向いては不出来を承知で売り歩いた。商品の品質改善はある程度稼ぎがあってからでも遅くないという開き直った思いもあってのことだった。
上野駅をモデルにしたという当時の大連駅の周辺では、列車の昇降客相手に大声を張り上げてくだんの品物を売り捌いた。青島での香具師の興行における言葉巧みな客寄せの技術がここではそれなりに役に立った。列車の昇降客の場合には一度きりのお客がほとんで、たとえ大福餅や中華饅頭の出来が悪くてもあとで文句を言われることなどはまずなかったから、まあまあの売上にはなった。だが、一日中昇降客のある現在の大都市の駅などとは違い運行列車の本数にも鉄道利用のお客の数にもおのずから限度があったから、一定以上の売上を期待するのは無理であった。
大連駅の西南方向すぐのところには連鎖商店街という、多数の大商店が軒を連ねる商業地域が広がっていたが、本物の大福餅や中華饅頭の売られているそんなところではとても勝負になりそうになかったので、はじめからそこでの商売は避けるようにした。そして、そのかわりに大連駅前から南にのびる路面電車の通り伝いに常盤橋まで下り、そこから東西方向にのびる別の路面電車の線路沿いに東の方向に進んだところにある大連中央広場付近へと出向いたりした。
この円形大広場の周辺には各種の官庁や銀行などが建ち並んでいたが、それらのなかにあってひときわ目立つのが、広場の南側中央に位置する満鉄経営の大連「大和ホテル」であった。ルネッサンス様式の建築で知られるこの大ホテルは、当時から全設備が完全な西洋式で、百余の客室のほか、三百人収容の大食堂などを有していた。そこからさらにしばらく東にいったところに建つ堂々たる石造りの満鉄本社と並んで、それらの建物は日本による実質的な満州支配の象徴的な存在でもあった。また、大和ホテルや満鉄本社の南側に位置する地域には、現在も同地に残る大連病院や終戦後撤去された大連神社などが、やはり日本当局の関係者の手によって建設運営されていた。
どう考えてみても大福餅や中華饅頭がマッチするような雰囲気の場所ではなかったのだが、いつの時代も酔狂な人はいるもので、そんな大連の中心街においてさえも時々商い中の彼らを呼びとめる声がかかったりすることはあった。もともと馬鹿売れするなど望むべくもない状況だったから、とりあえずは赤字にならなければ上々だと考えるべきではあった。
大連の中心地や繁華街からすこし離れたところには満鉄関係者らが多数住む閑静な住宅街があった。彼らはそんな住宅街などにも赴き、大声で「ダイフクモチーッ、チューカマンジュー、安くてうまいダイフクとチューカマンジューだよーっ!」と連呼しながら、懸命に稼ぎを増やそうと努めてみた。しかしながら、どう足掻きまわってみたところで素人商売は所詮素人の商売にすぎなかったから、思い描いていたほどの大儲けなどできるはずもなかった。それどころか、しばらくすると売上も落ち込み、朝早くから夜遅くまでずいぶんと苦労の多い仕事の続くにもかかわらず、その日をぎりぎり食いつなぐのが精一杯の有様となってきた。そのさき季節のほうも厳しい冬場に向かうとあっては、とてもそのままでは身がもちそうになく、なんとかして打開策を考え出さねばならないと焦り始めはしたものの、これという決定的な方策も見つからぬままいたずらに時間だけが流れていった。

絵・渡辺 淳
「マセマティック放浪記」2003年5月28日
ある奇人の生涯 (19)
コーリャン畑に見た孤独地獄
大福餅や中華饅頭売りの仕事がはかばかしくないこともあったので、石田は時間をみてはほかにもいろいろなことをやってみた。生涯を通じて四十余種にのぼるとかいう彼の無茶苦茶な職業遍歴のなかで、就業していた期間が最短だったと本人が笑う職業がひとつある。それがこの大連時代にたまたま体験したチンドン屋の仕事だった。その役回りは太鼓打ちだったのだそうで、太鼓担当の男が突然に急病で倒れたため、急遽、石田が代役として借り出されたようなわけだった。太鼓打ちの役柄は結構体力が要るかというので、当時としては大柄な身長百七十六センチの彼に白羽の矢が立ったものらしかった。
音感やリズム感はけっして悪いほうではないと自負していた石田は、なんとかなるだろうと思いその仕事を引き受けることにした。晩年の石田翁を見るかぎりでもその音楽センスは相当なものだったから、その話を持ちかけられたとき彼がそう思ったのも無理のないことではあったかもしれない。身のほど知らずと言ってしまえばそれまでなのだが、ともかくもそんなわけで、クラリネットや笛、鐘などを担当する仲間三人と共にチンチンドンドン、チンドンドンとやりながら大連の中心街に威勢良く繰り出していったのだった。
「結構大きな太鼓でしたからね、それなりに重量もあったんですよ。でもまあ所詮太鼓のことだから、ちょっとだけ練習すればなんとか様にはなるだろうってタカを括ってました」
石田はそう言ってしばし苦笑したあと、即席チンドンマンのその後の経緯を正直に語ってくれた。
「ところがね、そこはやはり素人のこととあって、年期の入った他の三人と呼吸を合わせるのがとても難しいんですよ。しかも、歩きながらのことですから、うまくリズムがとれないんです」
「チンチンチン、ドンドンドン、チンチンチンチンドンドンドンって三・三・七拍子の応援調になってしまったりして?」
「それだったらまだよかったんですが、へんなタイミングでドンドンと太鼓を打ち鳴らすものだから、まるで調子はずれの演奏になり、他の三人がしらけてしまってね…」
「あらかじめ、ちょっとくらいは練習したんでしょ?」
「練習するにはしたんですがね、あくまでもその時は静止した状態だったうえに、他の三人が私に音を合わせてくれてもいましたからね」
「実際に街中を練り歩きながら演奏するとなると、そうそう上手くはいかなかったってわけですね」
「それなりに重い太鼓を身体の前に抱え、前方に注意を払いながら全身でバランスをとってバチを揮いながら進むわけですから、初心者には容易なことではありません。歩くのだって必死ですから、他の仲間三人の演奏に合わせるどころか、その楽器の音でさえ聴き取れなくなってしまう……」
「営業妨害もいいところですね、それじゃ!」
「通りすがりの人たちが、私の調子はずれの太鼓の音を聴いて笑い出す始末でね」
「やっぱり、新米チンドン屋に見えたんでしょうね。でもせめてもの救いは、そのメチャクチャ下手な太鼓担当の若い男が背のスラっとしたハンサムボーイだったことだとか?」
「街の人々にどんな風に思われたのかはわかりませんが、ひとりだけ浮き上がって見えたことは確かでしょうね」
「それで結局どうなったんですか?」
「どうにもならなかったんですよ。まだ、調子はずれでも太鼓を打ち鳴らしながら歩けるうちはよかったんです。実際には想像していた以上の重労働でしてね、二、三時間もすると息切れさえしてきました。太鼓を支える背中や首筋は痛くなるし、バチを持つ手は上がらなくなってくるし・・…」
「想像以上に大変だったんですね!」
「その激務に耐えるのは並の体力では無理だということを痛感しました。そうこうするうちに全身にひどい疲れが出てまるで仕事にならなくなり、結局、二日間働いただけで首になってしました」
「で、二日分のアルバイト料はもらえたんですか?」
「うーん、どうでしたかねえ、はっきりとは憶えていないんですが、まったく仕事にはならなかったわけですから、たとえ日当を支払ってくれるって言われたって辞退したんじゃないかって思いますよ」
「石田さんにしてはなんと謙虚な!」
「いまだったら、人材採用時におけるあなた方の判断ミスだから、二日分の日当はしっかり頂戴致しますって開き直ったりしてねえ」
「ははははは・・…、それ以前に、いまの石田さんだったら誰も雇ってなんかくれはしないでしょうけどね!」
大福餅や中華饅頭の販売をはじめとし、手を染めた仕事がどれもこれもうまくいかないことなどもあって、美しく豊かな町であるはずのこの大連での生活に石田はどうしても馴染むことはできないでいた。そして、とうとうある日突然、何もかもが嫌になってしまった石田は、思い立ったように大連駅で列車に飛び乗ると、奉天すなわち現在の瀋陽(シエンヤン)方面に出かけていった。奉天で下車した彼は市街を急ぎ足で通り抜けると、なるようになれという開き直った気分になってひたすら北に向かって歩き出した。当時の満州ならではの広大な畑地のなかを体力と気力の赴くままにあてどもなく突進しはじめたのだった。
思惑通りには運ばないうえに拘束ばかり多い仕事も嫌、迫り来る戦争の足音も嫌というやり場のない思いが募り、自暴自棄の状態になってしまってもいたから、真の意味で我が身の自由と精神の解放が得られるなら野原の中で人知れず野垂れ死んでも本望だとさえ考えかけていた。悪運が強いと豪語することの多い石田の常の姿からすれば想像もつかないことではあったが、この時ばかりは実際にそんな追い詰められた心理状態にあったらしい。ひとつには、その時点ではまだ彼は自らの運の強さというもに確信を持てる段階に至ってはいなかったからなのだろう。
石田はどこまでも続く広大なコーリャン畑の中を歩きに歩いた。何時間くらい歩き続けたのかはいまとなっては定かでないとのことであったが、ともかく太陽が西の地平線に沈むのも気にせずにどこまでもさまよい歩き続けたのだった。歩き始めたときには、もうどうなっても構わないという気持ちだけがひどく先走ってしまっていたから、文字通り身ひとつのままで飲み物も食べ物もなにひとつ携行してはいなかった。
歩けども歩けどもコーリャン畑が尽き果てることはなかった。コーリャン畑が続いているということは、すくなくとも人跡があるということを意味してはいたのだが、奉天市街をあとにしてからというもの、人馬の影を目にすることも人家を見かけることも実際問題としては皆無の有様だった。そんな状況の中を夜空に舞う北斗の輝きを標(しるべ)にして北へ北へとしゃにむに歩き続ける石田の胸中に、突然、それまで予想だにしていなかった奇妙な想念が渦巻きはじめたのだった。それは、「人間にとっての自由の大きさと人間にとっての孤独の大きさとは、互いに正比例するものである」というなんとも切実かつ体感的な思いであった。そのくらいのことは理屈でならこれまでも十分すぎるくらいにわかってはいたが、自らの身体をもってこれほどまでにそのことを痛感するのは初めてのことであった。
世間のしがらみを逃れようとしてコーリャン畑の中をより遠くへと進んで行けば行くほどに、自由の度は増すものの、その代償としてやり場のない寂しさと深い孤独感とがどんどん大きくなっていく――その極限にあるのは、たぶん、道に迷った砂漠の旅人同様の孤独な中での死にほかならないことだろう。だからといって世俗の中へと引き返せば、寂しさや孤独感は少なくなるかわりに、そのぶん自由が失われる。おのれの胸中深くで右へ左へと大きく揺れ動くそんな心理的振り子の振動は、もはや彼自身の力では制御不可能な状態にまで至っていた。
あたりはすっかり暗くなり冷たい夜風が吹きぬけるばかりで、三百六十度どちらを見渡しても人工の明かりらしいものはまったく見当たらなかった。そのまま行き倒れになってしまっても誰にも見つけてなどもらえそうになかったし、盗賊などに襲われたりしても助けなど求めようがない状況でもあった。しばらくするうちに、石田には自分を取巻く夜のコーリャン畑がそのまま地獄の果てまで続いているかのように感じられはじめた。いや、もはやその真っ暗なコーリャン畑そのものが無間孤独地獄にほかならないように思われてならなかった。
そのとき初めて彼は真の意味での人間の孤独というものがなんたるかを察知した。見えないところで他人に支えられる経験をしてきたにもかかわらず、さらにまた、過去何度かいざというときに様々な人に助けられてきたにもかかわらず、なお心の底のどこかでは独力で生き抜いてきたと錯覚していたおのれの傲慢さがいまさらながら無性に悔やまれてならなかった。なんとも皮肉な展開ではあったが、そう思う彼の両目にはうっすら涙さえも浮かんできた。そして、その時点で石田はもういちど奉天に引き返すことを決意したのだった。体力の限りを尽くして彼は夜のコーリャン畑の中を奉天の町のあるとおもわれる方角に向かって走りに走った。それでもなかなか奉天の街の明かりは見えてこなかった。
ようやく遠くに市街の灯が見えてきたとき、石田はわれにもなく胸が熱くなるのを感じていた。無事に戻ってきてよかったという思いが沸々と身体中に込み上げ、それに伴うようにして両目からとめどもなく涙が溢れ出てくるのをどうすることもできなかった。奉天の市内に戻り着き、街をゆく人の姿を目にした時には、それがどんな相手であろうとも即座に抱きつき、その温もりを確かめたい思いであった。
この時の経験はその後の人生にずいぶんと役立ったと、石田はあるときしみじみと語ってくれたものだった。複雑な人間関係や面倒な仕事などがもとで大きなトラブルがあったときなどでも、あの孤独地獄に較べればこの程度のことはたいしたことないと辛抱することができるようになったとのことであったが、実際、この出来事を契機にして彼は大きく変貌を遂げたのだった。

絵・渡辺 淳
「マセマティック放浪記」2003年6月4日
ある奇人の生涯 (20)
自作自演の茶番劇
人間の運命とはなんとも不思議なものである。コーリャン畑の一件があってからほどなくして、その後の人生を大きく変える千載一遇のチャンスが石田の身に訪れた。香具師まがいの仕事をこのまま続けていても埒があかないと思った彼が、たまたまもうすこしましな仕事はないものかと摸索し始めた時のことでもあった。仕事を手伝うという条件で同行してきた香具師の男への義理だてもある程度はすんでいたので、新たな働き口を探してもほぼ問題ない状況になっていたことも幸いした。
ある日石田がなにげなく新聞に目を通していると、たまたま、「英語の堪能な日本人青年を求む」という求人広告が目にとまった。しかもその広告主は当時アメリカでも屈指の大銀行として知られていた「National City Bank of New York」の大連支店であった。その頃大連の人々の間では、この銀行は「花旗銀行」という別称で呼ばれていたという。日中間ではすでに戦争状態が続いていたが、まだ日本とアメリカとは開戦していない時期のことだったので、日本の支配下にあった大連などには、欧米の一流銀行の支店が置かれ、取り引き業務が遂行されていた。
正直なところ、外国銀行の業務に支障なく対応できるほど英語に通じているなどとは思ってもいなかった。ただ、旧制高校で英語とフランス語の基礎学習は一通り積んできていたし、氷川丸のタリーマンとして時には英文表記の船荷証券などを扱ったりもしてきていたから、時間をもらえればなんとかなるかなという自信はあった。それに、もともと語学そのものが嫌いではかったことも、彼が大胆な振舞いにでる一因とはなった。
この際多少図々しくてもやむをえないと開き直った彼は、一世一代の大芝居に打って出ることを決意した。石田らしいと言ってしまえばそれまでだが、なんとも呆れたことに、彼は、日中戦争激化の余波で青島から強制疎開させられてしまった自らの立場を大胆かつ巧妙に利用することを思いついたのであった。
それからほどなく彼は花旗銀行、すなわち、ナショナル・シティ・バンクに電話をかけた。時代の流れもあって当時の同銀行大連支店は日本人の個人顧客や日本関係企業相手の業務が主になってきていたから、電話に出た相手はごく普通の日本語で応じてくれた。
「はい、こちらはナショナル・シティ・バンクでございますが……」
「突然のお電話で申し訳ありません。私は青島避難民団の委員長を務める大川と申します。少々お願いしたい儀がございましてお電話を差し上げたのですが……」
石田は意図的に声のトーンを変えながらすました口調でそう告げた。そもそも青島避難民団などというものがはっきりした形で存在しているかどうかさえ定かでなかったし、たとえそのような民団組織あったとしてもその委員長が大川などという人物であろうはずなどなかったが、彼はあくまでも平静を装ってそう名乗った。
「そうでいらっしゃいますか。それでどのようなご用件でございましょうか」
相手の女性の対応はあくまでも鄭重そのもので、石田が一芝居うっていることなどにはまるで気がついていない様子だった。
「求人広告を拝見したのですが、そちら様では現在英語に堪能な日本人青年をお探しでいらしゃいますよね?」
「ええ、たしかに英語に堪能な日本人青年を募集中ではございますが……」
「それで、もうどなたかお決まりでございましょうか?」
「少々お待ちくださいませ。担当者に状況を確認致してみますので」
そう言って相手はしばし電話口を離れた。石田は内心でまだ採用者が確定していないことを祈りながら、再び電話から声が流れるのをじっと待ち続けた。
「お待たせ致しました。まだ採用確定者はいないようでございますが……、それで、何かお訊ねの儀でも?」
石田はここぞとばかりに蛮勇を奮い立たせて切り込んだ。
「実は、私どもの青島避難民団に優秀な青年がおりましてね。石田達夫君というのですが、彼をそちら様にご紹介申し上げたいと思いましてね。青島から強制退去させられ大連に移ってきたのですが、急なことでこちらではなかなかこれといった仕事がみつからず彼も困っていたところでございまして……。ところが折よくそちら様の求人広告が目にとまったものですから、是非私からも彼を推薦申し上げたいと考えましてね」
「さようでございますか……。上司にその旨を伝えてみますので、いましばらくそのままお待ちくださいませ」
「よろしくお願い致します」
しばらく電話が途切れたあと、再び先刻の女性の声が響いてきた。
「お待たせ致しました。では大川様、その石田さんとかおっしゃるお方に当銀行まで面接試験を受けにお出でになるようにお伝え下さいませんでしょうか。一応、履歴書なども用意くださったうえでお願い致します」
「有難うございます。石田君もとても喜ぶと思います。現段階では彼の英語の実力はきわめて堪能といえるほどではないようなのですが、読み書きの基礎はしっかり身につけているようですので、多少時間を頂戴できればそれなりには能力を発揮するようになるだろうと思います」
「わかりました。面接にあたる上司がどう判断するかはわかりませんが、その旨は伝えておきますので……。ともかく、明日面接にお出でくださるように申し上げておいてください」
「特別なご配慮を賜わり感謝に堪えません。では当人にそのように伝えておきますので、宜しくお願い致します。突然不躾なお願いを致したりして、大変申し訳ありませんでした」
「いいえ、どう致しまして……」
相手がそう言い終わるのを待って、石田はそっと受話器をおろした。そして、なんとか破綻なく一芝居を演じ終えられたことにほっとしながら、本来の自分に向かって「それでは石田君、明日はナショナル・シティ・バンクに面接に行ってきたまえ!」と自嘲気味に呟きかけた。もちろん、そのあと翌日の面接に備えて対応策を練りはしたが、実際の面接となると誤魔化しがきかないだけに小手先の小細工が効を奏するかどうかは大いに疑問で、さすがの彼にも確信はもてなかった。ただ、裏を返せば、そこまで策を弄せざるをえなかったのは、「どうしてもこの際シティ・バンクに採用してもらいたい。このチャンスを逸したらもう二度とこのような機会に恵まれることはない」という切羽詰まった思いのなによりの証でもあった。
翌日石田は面接を受けるためにインターナショナル・シティ・バンクに出向いた。インフォメーションの担当者は女性だったが、幸いなことに、声の調子から判断するかぎり前日に電話で応対してくれた人物とは異なっているようだった。
「私は石田達夫と申しまして、昨日、青島避難民団委員長の大川様の仲介があってこちらの銀行に面接に伺うようになった者でございますが……」
内心の緊張を抑えながら、彼は相手にそう来意を告げた。さすがに心の片隅にはうしろめたい思いが残りはしが、事ここに至っては運を天に任せて開き直るしかなかった。
「当社の行員採用面接でございますか?」
「ええ、そうです。大川様の強いご推薦がございまして……」
ご推薦もへったくれもあったものではなかったが、自らが描いた筋立てにのっとって有能かつ実直な青年を演じきるしかもはや道は残されていなかった。
「わかりました。少々お待ち下さいませ」
とくに訝しがる様子もなくオフィスの奥へと引っ込んだその女性は、ほどなく再び姿を現すと、にこやかな表情を見せながら石田をオフィスの中へと案内した。第一段階はまずもって彼の計算通りの展開となった。
面接に応じてくれたのはアメリカ人の支店長で、その脇に通訳担当の日本人男性が坐っていた。正直なところ、内心ハラハラしていた石田は、その通訳が女性ではないことを知ってすくなからず胸を撫で下ろした。むろん彼がもっとも惧れていたのは、前日電話を受けてくれた女性が現れ、自作自演の茶番劇の舞台裏が見えみえになってしまうことだった。前日の電話では声のトーンと口調を意図的に変えていたとはいえ、絶対にバレないという保証はなかった。
面接が行なわれたのは応接間のような特別な個室においてではなく、行員たちが通常業務を遂行しているフロアの一角においてであった。そんなわけだったから、面接の様子は仕事中の行員たちにもほぼ筒抜け状態であった。面接が始まる前、さりげなく石田は行員たちのほうに視線を送った。海外の銀行とあってか行員のほとんどは外国人で、日本人らしい行員の姿はごく少数のようであった。フロアのずっと奥のほうに先刻のインフォメーション担当の女性とは違う日本人とおぼしき女性の影が見えたが、それが前日電話で応対してくれた人物であるかどうかは確認のしようもなかった。
ただ、たとえその女性が同一人物であったとしても、彼女の坐るデスクは自分のいる場所から相当離れたところに位置していたので、そう慌てることはないとも考えた。面接を受けている最中にいくらか自分の声が漏れ響くようなことがあったとしても、そのことだけから前日来の茶番劇の裏事情が発覚してしまう可能性はほとんどないだろうと思われたからだった。
面接の冒頭で、アメリカ人支店長は、前日に青島避難民団委員長の大川という人から推薦のあった石田達夫という日本人青年はあなたのことかと確認はしてきたが、青島避難民団や大川なる人物などについてそれ以上詳しく訊ねてくることはなかった。相手がアメリカ人で、日本人社会の事情に疎かったことなどもそれなりに幸いした。もしも面接担当者が日本人で、中国の日本人社会の動向に通じていたとすれば、青島避難民団なるものの実態や大川なる人物との関係などを詳細に訊ねられたりし、そうこうするうちにしろどもどろになっていたかもしれなかった。アメリカ人支店長にすれば、面接対象となっている人物の日本人としての社会背景などどうでもよく、その実務能力と本質的な人物評価にしか当面の関心がなかったから、その点は石田にとってなんとも有り難いことだった。おまけにこの日はたまたま、彼にとってツキのある十三日の金曜日でもあったのだった。
「マセマティック放浪記」2003年6月18日
ある奇人の生涯 (21)
晴れて外国銀行員に!
求人広告には「英語が堪能な日本人青年」とあったので、直接に英語による面接がおこなわれるのだろうとあらかじめ覚悟だけはしてきていた。だが、前日の電話で予防線を張っておいたのが効を奏し、相手側が一定の配慮をしてくれたものなのか、通訳つきの面接になったのは石田にとって幸いだった。それでも面接が始まるとすぐにあれこれと英語の知識や業務経験などを問われたりしたので、このぶんでは採用してもらうのはまず無理だろうなという悲観的な思いが胸中をよぎった。前日来のひとかたならぬ身心の緊張もそんな思いに拍車をかけた。
いつもの姿からは想像もできないほどにがちがちになっていたそんな石田の心がほぐれたのは、ちょっとしたことがきっかけだった。面接してくれたアメリカ人の支店長が、話の中で突然「draft」という英語の意味がわかるかと尋ねてきたのである。その英語に心当たりのあった石田は、一瞬の間をおいたあとで、「それは船の喫水線を意味する言葉だと思います」という答を返した。しばらく貨物船に乗っていた関係で「draft」という言葉に「喫水線」という意味のあることを知っていたので、真っ先にそのことが閃いたのだった。
通訳を介して彼の答えを聞いた支店長は、突然大きな笑い声をあげながら、「Why do you know such an odd thing ?」と問い返してきた。次の瞬間には、通訳の男もそばの行員たちも大爆笑におちいった。米国人にもあまり馴染みのないそんな特殊な事柄をなんで日本人の青年が知っているのかと、相手は不思議にも感じおかしくも思ったらしかった。支店長が尋ねたのは、おなじ「draft」でも、銀行取引で用いられる「為替手形」あるいは「小切手」という意味のほうだったのだ。
石田の答えはピントはずれではあったけれども、結果的にはそのおかしなやりとりによって彼の気分はすっかり楽になった。そんな彼が次に尋ねられたのは「a bill of lading」という言葉の意味だったが、今度はすぐに、その英語は「船荷証券」のことを意味しているのだとわかった。いや、わかったもなにもない、貨物船で船荷証券を扱うタリーマンの仕事をやっていたのだから当然すぎる話ではあった。
いくぶん調子づいた彼は、貨物船氷川丸に乗ってタリーマンの仕事をしていた経緯を支店長に伝え、「draft」という英語に「喫水線」という意味があることを知っていたのはそんな背景があったからだということも一通り説明した。もっとも、山下公園で行き倒れになったことが契機でタリーマンになったことや、塘沽港で氷川丸から脱走したことなどについてはまったく触れなかった。
大連に流れてきたあと、大福餅や中華饅頭の製造販売に手を染めたり、一日だけチンドン屋をやって首になってしまったりしたことなどについても、むろん黙ったままだった。青島避難民団委員長推薦の「英語に堪能で有能」なはずの日本人青年が、たとえ一時期のことではあってもそんな仕事をやっていたというのも変な話ではあったので、伏せておくにこしたことはないと考えたからだった。調子に乗って下手にそんな話をしたりし、その話の流れなどから、青島避難民団委員長大川なる人物の存在やその人物による前日の推薦電話などの背景に話題が及び、挙げ句の果てにそれらのすべてが石田自身の自作自演であったとバレたりしたら、それこそも元も子もないことではあった。だから、どうあってもそんな最悪の展開だけは避けなければならなかった。
幸い、アメリカ人の支店長は好男子の石田のことがすっかり気に入った様子だった。どうしてもこの銀行に採用してもらいたくて一芝居打ったことはともかく、彼のほうも、もしも運良く採用されたなら心底与えられた業務に勤しもうと決意を固めていたので、その熱意がそれなりに相手に伝わりもしたのだろう。また、瀋陽郊外の広大なコーリャン畑での一件以来、いくら強がってみても自分ひとりの力だけではこの世を生き抜いていくことなどできないと悟らされ、それまでになく謙虚な気持ちにもなっていたから、そのぶんよけいに好感をもたれたのかも知れなかった。
幸運の女神はそんな石田を見捨てなかった。彼は無事その日の面接試験に合格し、支店長直々にさっそく翌日から出勤するようにと要請された。かくして彼は、大連の中心街、中央広場近くに位置する一流外国銀行 National City Bank of New York、別称、花旗銀行に晴れて勤務することになったのだった。行員のほとんどは外国人で、日本人の行員は石田のほかには数人しかいなかった。だから、彼が大芝居を演じたときにそれとは知らず電話の相手をしてくれた女性が誰であったかもすぐにわかったが、彼女のほうはまったくそのことに気がついていない様子だった。しばらくは聞き覚えのあるその声を耳にするたび内心ぎくりとさせられはしたが、やがて新たな職場の雰囲気にも馴染み、そんなことなどまったく気にする必要もなくなった。
初任給は当時のお金で二十円ほどだった。彼は勤務しはじめるとすぐに、まずタイプライターの猛練習を始めた。その有様は、支店長以下の行員たちが驚き呆れるほどに凄まじいものであったらしい。タイプライターをごく短期間でマスターすると、彼は信用状の処理をはじめとする各種銀行業務の猛勉強にとりかかり、それらのイロハを驚くべきはやさで修得した。もちろん、英会話の修得や英語の書類を的確に捌くための訓練と学習も卒なくこなした。「自分の人生を振り返ってみても、あの銀行に勤めていた時ほど死に物狂いで勉強したことはありませんでした。とくに語学には能力のすべてを尽して取り組みましたねえ。英語だけでなく、フランス語やドイツ語、ロシア語などにも……」と晩年石田は回顧しているが、実際その通りであったのだろう。
仕事に賭けるその熱意や実務能力の高さはすぐに支店長以下の上司の認めるところとなり、一ヶ月後には彼の給料は二倍の四十円になったというが、そのへんの対応はいかにも能力主義の外資系銀行らしいところだった。
先任の日本人行員らは多少英語はできたものの、全般的な基礎学力のほか、日本語による文章表現能力や、高度な英文書類の事務処理能力ということになると、新人とはいえ、しっかりした高等教育を受けている彼のほうがずっと上であった。「英語に堪能で有能な日本人青年」を自ら演じてこの銀行に採用された石田ではあったが、もはやその看板に偽りはないと断言してよいほどにその能力は磨き高められていった。それはまさに「水を得た魚」という表現そのままの状況でもあった。
さらにまた、日本軍部による中国北部地域の実質的な支配が強まる社会情勢のもとでは、欧米系の諸銀行といえども各種書類の多くを日本語によって処理しなければならない事態に迫られていた。必然の結果として、その業務を的確にこなせるのは行員のなかでも石田だけだということになり、彼の能力に対する評価は日毎にどんどんと高まっていった。そして、驚くべきことに、石田の給料は二年後の一九四〇年までに初任給の十倍にも及ぶ二百円という高額にまで達していた。
当時の日本人としては大変な高給で、社会の要職にある五十代、六十代の人々でもよほど特別な地位にでもないかぎりそうそうは手にすることのできない高額給与だったのだが、若干二十二歳の青年が、思わぬことからそんな特別待遇を受けることになったのだった。すでに国家総動員令の公布されていた日本国内では、一九三九年に物価統制令が敷かれれ、労働者の賃金も現状維持のまま強制凍結されることになったから、能力のある人間がどんなに仕事に貢献しても給与が増えるなどということは考えられなかった。その点からしても石田の昇給ペースは異例をきわめるものであった。
国家総動員令公布下における日本国民の厳しい生活状況がまるでよそごとのように、大連でナショナル・シティ・バンク勤めをはじめてからの石田の生活はそれまでになく充実し、まさに幸せそのものであった。あえて不満を探すとすれば、それ以前の仕事の場合とは違って、毎日きちんと背広を着用しネクタイをしめて出勤しなければならなかったため、少々窮屈に感じられることくらいであった。しかも、石田は、その一件に関してもいかにも彼らしい発想のもとに、うまく立ち回ることを企てたのだった。
「贅沢は敵」という政府主導のスローガンがすでに国民の間に浸透し、質素と倹約をモットーとする風潮が支配的になっていた日本社会では、カーキ色をしたシンプルなつくりの国民服が奨励されるようになっていた。国民に単一の行動を強いる軍国色が大嫌いなはずの石田が、なんとその国民服を着て出勤しはじめたのだった。日本国民はなるべく国民服を着用するようにという指示が日本政府から出されているから、自分もそれに従ったまでだという表向きの理由を、銀行の上司たちも認めざるをえなかった。だが、石田の本音は、手間のかかるうえに窮屈なスーツ姿で通すよりは身体の動きが自由で着るのも容易な国民服姿のほうが楽だというだけのことであった。まさに「逆転の発想」という言葉がぴったりの石田流戦略の勝利であった。
彼が国民服姿で出勤しはじめると、他の先輩日本人行員らは、「なんともいい心がけだよね、石田さん。我々も見習わなきゃいけないよね」と口々にその行為を称えた。それに対して、アメリカ人やロシア人の行員らは、「石田さん、その服なかなか似合っているよねえ」と外見的な面からの評価下し、また、中国人行員らは、「石田さん、それいくらだったの?」と値段を尋ねてきたのだった。ただそれだけのことではあったけれども、日本人は精神面のことを重視し、アメリカ人やロシア人はルックスのことを中心に考え、中国人は経済的な側面から評価を試みようとするのが、彼にはなんとも面白く感じられてならなかった。

絵・渡辺 淳
「マセマティック放浪記」2003年6月25日
ある奇人の生涯 (22)
老虎灘での至福な生活
ナショナル・シティ・バンクに勤務当時、石田は大連郊外にある老虎灘(ラオフータン)というところに住んでいた。大連中心街の南東方向六、七キロのところに位置する老虎灘は現在では開発整備が進み近代的な観光地になっているが、その頃はまだ豊かな自然がそのまま残る風光明媚な入江で、実に落ち着いた雰囲気の漂う土地柄であった。アメリカ人やイギリス人のほか、ロシア人やフランス人、ギリシャ人、中国人などが混住するとても国際色豊かな地域で、満鉄関係者などのような日本人家族らの多く住む大連中心部の住宅街などとはずいぶんと趣きを異にしていた。だから、日々の通勤に際しては、まず馬車に乗って最寄りの路面電車の駅まで出向き、そこから電車に乗って銀行のある大連市の中心部まで通っていた。
石田がわざわざ日本人居住者の少ない老虎灘を選んだのは、ひとつには、彼の勤務する銀行の何人かの行員やその家族らが住んでおり、それらの人々との日常的な交流を保つにはそのほうが好都合だからであった。だが、それ以上に大きな理由は、せっかくの機会なので、日本的な環境や雰囲気に支配されている地域を極力避け、国際性豊かなところで自分とは価値観の異なる多くの外国人と接しながら暮らしたいと考えていたからだった。猛勉強の成果もあってすでに英語は不自由なく使いこなせるようになっていたから英語中心の生活にまったく不便は感じなかったし、また、フランス語やロシア語などのような外国語を日常生活を通じて自然に修得するうえでも老虎灘は格好の場所であった。
日中戦争の激化や、それに伴う国際社会からの日本に対する批判が日毎に高まるなか、日本社会はますます閉鎖性を強めていきつつあったから、その息苦しさから逃れることができるという意味でも老虎灘での生活は彼にとって大きな救いではあった。
予想にたがわず、老虎灘での生活は石田にとってこのうえなく甘美で充実したものとなった。休みの日や、そうではなくても夜になると近くに住むロシア人やフランス人、ギリシャ人、中国人などが彼の家に次々と遊びにやってきた。すっかり経済的にも安定したおかげで広い庭のある立派な家を借りて住むことができるようになっていたから、来訪者たちと毎晩のようにその庭で盛大なパーティを催すことができた。豊富な食材を用いてバーベキューなどをやりながら、友人のロシア人の演奏する素晴らしいバラライカの音色に耳を傾けたり、皆で様々な国の歌や民謡を唄い合ったり、諸々のゲームに時を忘れて興じたりする満ち足りた日々の生活は、文字通り夢とも幻ともまがうばかりではあった。
とにかく、皆が驚くほどの高給を取っていたから、客人や友人たちに心ゆくまで振舞っても経済的に困るようなことはまったくなかった。何かの時に備えてそれまでになく十分な貯えをもつこともできた。こんなにも幸せな日々がいつまでも続いていていいものだろうか?――実際何度もなんども自分自身にそう問いかけもしたほどに、老虎灘での生活は恵まれたものであった。
もちろん、石田は高給をよいことに遊びほうけてばかりいたわけではなかった。銀行での実務や欧米人行員との日常的な付き合いを通して彼は英語力を磨きに磨き、またそのいっぽうで老虎灘在住の多くの外国人たちとの親交を重ねながら、ロシア語、フランス語、中国語などを次々とマスターしていった。もともと語学に対する資質に人一倍恵まれていた彼は、この時期にのちの一大飛躍につながる高い語学力を身につけることに成功したわけなのだが、それが将来どのように役立ちどのような展開につながるかなど、まだ当人には想像もつかないことであった。
しかし、大連における石田の平穏で満ち足りた生活とは裏腹に、国際情勢の不穏かつ複雑な動きはやがて第二次世界大戦の勃発へとつながる緊張を生み出していきつつもあった。一九四〇年九月、ベルリンで日独伊三国同盟が調印成立すると、国際間の緊張の度は一触即発の状態にまで高まった。すでに日本軍は南方資源の確保を目的に北部仏印(フランス領北ヴェトナム)を侵略し、国際戦線の拡大をはかりつつあった。三国による軍事同盟の合意内容は、日本、ドイツ、イタリアがアジアとヨーロッパにおける新秩序確立のための国家的活動をすること、つまりは周辺国家を侵略することを相互に認め合い、日中戦争や欧州の戦争にまだ参加していない第三国から日独伊同盟三国のいずれかが攻撃や干渉を受けた場合には相互に援助協力し合うことを約したものであった。
この日独伊三国軍事同盟の成立を境に米国の対日姿勢はいっきに硬化し、日米関係の悪化は決定的になってしまった。そしてその影響は徐々にだが石田の身辺にも及びはじめた。まだ日米開戦前年のことでもあったので、石田の勤める銀行の業務に直接的な支障は生じていなかったけれども、ますます日米関係の亀裂が深まり近々戦争さえも起こりかねないという状況になってきていたので、場合によってはナショナル・シティ・バンクの閉鎖や大連からの撤退もやむをえないとする空気が銀行幹部たちの間に流れはじめたことは確かだった。
ふと思い立って、石田は、民間人の立ち入りが厳しく制限されている大連西隣の軍港、旅順港周辺にも足を伸ばしてみることがあったが、遠目にもただならぬ緊張ぶりが窺われるばかりであった。平穏そのものの大連老虎灘での生活の背後に忍び寄る戦乱の影に、さしもの石田も次第に心を重くしていくばかりだった。だが、それでもまだ、数年後の母国日本やその国外占領地の悲惨このうえない姿にまでは想いを及ぼすことができなかった。
大連でのそんな石田の生活に大きな転換を迫る思わぬ出来事が起こったのは、それからほどなくのことであった。その当時、石田の勤める銀行では日本人を妻にもつコーカサス系の男性がブックキーパーとして働いていた。なかなかに有能な人物で、やはり老虎灘に住むその銀行員夫妻と若い石田との間には年齢差を超えた親交があった。そしてその夫妻の間には当時十八歳になるとても利発な美しい一人娘が存在した。その娘は日本語がうまかったうえに、二十四歳の石田とは年齢もそう違わなかったことから、二人はよくウマが合い、なにかにつけて一緒に遊んだり行動したりもしたものだった。彼女の両親もそんな二人を終始温かく見守り、とくにその行動をあれこれと干渉するようなことはなかった。
三方を山に囲まれた深い入江の老虎灘はこのうえなく変化に富んだ奇岩奇勝にも恵まれ、水がとても綺麗で海水浴や磯遊びなどにもってこいだったから、石田たちは周辺の磯辺でよく一緒に泳いだり、探検家気取りであちこちを散策をしてまわったりしたものだった。そのハーフの娘は美人だったばかりでなくとても気だてもよくて、口にこそ出しはしなかったものの、石田の胸中では彼女に対するひとかたならぬおもいが徐々にだが募っていきつつはあった。いっぽう、彼女のほうも、相手が知性的でハンサムなうえに若く有能な銀行マンとあっては何の不満のあろうはずもなく、時を追うに連れて内心では石田にぞっこんという感じになっていった。
だが、互いに好感を抱き合いながらも、ともに理知的で抑制のきく一面をもそなえていた二人は、一線を越えることはもちろん、ひとかたならぬお互いの慕いさえも伝え合うことはなく、いたずらに時を送るばかりであった。胸の内で真剣に相手のことを慕い合う男女の心理というものはもともとそういうものなのかもしれないが、石田のほうは彼女に対してはこれまでになく慎重だった。彼にすれば、相手が親しい職場の同僚のまだ純真な愛娘とあっては、そうそう安易に軽率な振舞いに出るわけにもいかないという事情もあって、いつになくおのれの心を律することしきりであった。
昭和十五年(一九四〇年)の夏も終わりに近いある休日のこと、彼女は、石田に向かって、二人だけで一日ゆっくり泳ぎにでもでかけないかと誘いかけてきた。よく晴れた静かな日のことで波も穏やかだったし、その無邪気にも見える呼びかけを断るような理由もとくになかったので、いつもの調子で彼は喜んで彼女の誘いに応じることにした。
すでに述べたように、黄海から寄せる荒潮によって侵食された奇岩が多数屹立する老虎灘一帯の景観は当時なかなかの偉容を呈してもいた。現在では近代的な観光地として道路や各種設備の整備が進み、大連周辺のリゾート地のひとつとして国内外から訪れる観光客も跡を絶たない状況になっているが、風光明媚で海水浴の適地であったとはいっても、その頃はたいへんに静かなところで特別な日をのぞいては人影もまばらであった。
軽食を用意し早朝に集落をあとにした石田たちは、入江沿いの静かな磯辺へと出た。そして、とくに人目につきにくい岩陰の地点を選んで水着に着替えると、二人並んで仲良く沖のほうへと泳ぎ出した。たまたま満潮前後の時間帯だったこともあって潮の流れは緩やかだった。
二人は互いに手を繋いだり離したりしてはしゃぎ戯れ合いながら、岸辺から少し離れたところに浮かぶ岩の小島へと泳ぎ渡った。小島に泳ぎ着くとすぐさま先に立った彼女は、意外なことに、水際からほぼ垂直に切り立つ高さ五メートルほどの崖をよじ登りはじめた。いったいどうするつもりなのだろうと石田のほうは一瞬戸惑いを覚えもしたが、彼女に促されるままにそのあとに続いた。まるであらかじめルートハンティングをすませてあったかのような彼女の軽やかで的確な動きの意味するところを、迂闊(うかつ)にもその時の石田はまだ察知していなかった。彼女のあとを追って這い上がったその小島の上部はやはり巨大な岩盤によって形成されてはいたが、予想外に小広くしかも平坦な地形になっていた。

絵・渡辺 淳
「マセマティック放浪記」2003年7月2日
ある奇人の生涯 (23)
二人だけの小島
全島岩からなっているとはいうものの、ちょっとした木立もあるその小島の上部は世間から完全に隔離された二人だけの別天地だった。こんなところにこんな秘密の場所が隠されていたなんて、石田にとってはなんとも思いがけないことであった。
「ナーシャ、いったい、いつごろからこの場所のこと知ってたの?」
その卒のない行動ぶりから、彼女がこの秘密の場所にやってきたのはこれが初めてではないと感じた石田は、あらためてそう問いかけた。ナーシャとは彼女の名を省略した愛称で、彼は彼女のことをいつもそう呼んでいた。
「ふふふふふ・・…。びっくりしたでしょ、石田!」
美しい顔にいたずらっぽい微笑みを浮かべながら、ナーシャは得意そうにそう答えた。彼女は彼のことをいつも「石田、石田」と呼び捨てにしていたが、べつに悪気があってのことではなかったし、へんにあらたまって「石田さん」などと呼ばれるよりもそのほうがかえって気楽でさえあった。
「うん、さすがに驚いたよ、こんな静かなところがあったなんて」
「私は石田が老虎灘にやってくるずっと前から、そう、幼い子どもの頃からここに住んでるでしょ。だから詳しいのよ、このあたりのこと……」
「ふーん、じゃ、その頃から時々ここには来てたわけ?」
「昔からこのへんじゃよく泳いでたし、それにね、あるとき、家によく出入りしていた地元の親しい老人がこの場所のことをそっと教えてくれたのよ」
「それで、ある時にここに来てみたっていうわけなんだ!」
「そうそう、もう五、六年は前のことだったと思うけど。私、もともと探検ごっこ大好きでしょう。だからここがすっかり気に入っちゃってね……」
「道理で崖をすいすいと登ると思ったよ。そんなこと全然知らないから、最初は見ていてハラハラしたんだよ。なんでこんな小島の上になんかよじ登ろうとするんだろうって……」
ようやく謎が解けた石田は、そう言いながらナーシャのそばに近寄ると、そっとその肩に手を当てた。すると水に濡れた彼女の髪がその手の甲にかすかに触れた。そのこそばゆい感覚を妙に心地よく思いながら、半ば目をそらすようしして、石田はナーシャのしなやかな肢体を盗み見た。その大部分は水着に覆われていたけれども、陽光を浴びて眩く輝く十六歳の娘の白い肌は一瞬息を呑むほどに美しくそして魅惑的だった。
「私ね、ずっと前から、一度石田をここへ連れて来ようって思ってたの。ようやく思いが叶って嬉しいわ」
「ほんとにいいところだとねえ!、この島の上ってけっこう広いようだけど、いったいどうなってるの?」
石田は内心の熱い慕いと動揺を押し隠すかのようにそう言った。
「この小島のことなら、私、隅から隅までよく知ってるわ。いまからすぐ案内してあげるわよ」
ナーシャはそう応じると大きく息を吸い、それから軽く胸を張った。水着の胸部を突き上げるようにして鋭く力強く盛り上がる二つの膨らみが石田の目にはなんとも眩しかった。見るからに毅然としていてまだ一度も男というものを近づけたことのない、だがそれでいて、男の手と唇の近づくのをいまや遅しと待ち焦がれてもいる清らかな乙女特有の矛盾の象徴そのものを、彼はそこに見る思いだった。
何をしようと人目につく心配などまったくないところだったから、その気にでもなればナーシャを意のままにすることなどわけもなかった。だがそれでもなお、彼はおのれの心を懸命に律した。映画の二枚目スターさながらの美男子だった石田は、東京でカフェバー勤めをしていた頃から女性にはずいぶんともてたから、むろん女性経験もそれなりにあった。だが、石田はこの十六歳の美しい娘に対してはこれまで常に紳士的に振舞ってきた。だからこの時も、彼は男の本性ともいうべき狼の牙を自ら剥くようなことはしなかった。力の弱い個体に対しては自らけっして牙を剥いたりすることのないという本物の狼にも似たその優しさが、彼女を大きくそして切なく包み込んでいたといってよい。
男はみんな狼だなどとよく言われるが、真の意味での狼の気質をもつ男であればあるほどに強い自制心をもつようになり、どんな相手に対してもすくなからぬ敬意をもって接するようになるものだから、心底愛するようになった女性に対してはむやみやたらに手を出すようなことはない。ところが、いっぽうの女性にすれば、そのことがつれない振舞いにも、また煮え切らない態度にも映ったりすることがすくなくない。二人だけになる機会がこれまでにも数多くあったにもかかわらず、常に石田が彼女に対して紳士的に振舞ってきたのは、彼がナーシャを掛け替えのない存在として深く愛するようになっていた何よりの証ではあった。
「ナーシャ、じゃ、ちょっと、この小島のなかの素敵なスポットを教えてくれるかい?」
彼女の胸や肢体のまばゆさに堪えかねた彼は、あえてそう促した。すると彼女はにこやかに微笑みながら、我が意を得たりとばかりにすぐその催促に応じた。
「いいわ、じゃ、あとについてらっしゃい。そんなに広くはないけど、眺めもいいし、松の木なども生えていてあちこちに木陰もあったりするから、のんびり過ごすには最高のところよ」
先に立つナーシャのなんとも俊敏な動きにちょっとした感動を覚えながら、彼はそのあとに続いた。
「この島の上、全体的には意外なほどに平なんだね」
「向こう側にむかってちょっとだけ傾斜していて、あちこちに大きな岩の凹凸はあったりするけど、全体は想像以上に平なのよね」
「島の周りはどちらの側も崖になってるんだよね?」
「そうなの……。黄海から寄せる荒波に削られて島全体が切り立った断崖に囲まれてるわ。さっきのところだけはなんとか登れるようになっているけど、それでもけっこう高さがあって危ない感じでしょ?」
「そうだよね……。なるほど、この島の上って、ナシャーの言ったとおりけっこう木が生えたりしてるんだ。磯辺からこの小島眺めてるだけじゃわかんなかったけど……」
「ほら、あの大きな岩を越えれば反対側に出るわ。けっこう眺めがいいのよ」
彼女のあとを追って表面の温もった大きな岩を越え、さらに小ぶりの岩と岩の間をすり抜けると、先刻二人で登ってきた崖とはちょうど反対側にある断崖上に出た。ちょっとした岩棚になっていて、心地よい潮風が岩角にぶつかるようにして下から激しく吹き上げてきた。波は穏やかそのもので、眼下にはかぎりなく青く透明な海面が広がっていた。近くには地元の漁船の影などもなく、はるか遠くの沖合いにかなり大きな貨客船らしい船影がひとつ見えるだけだった。
「見晴らしがいいでしょう、ここだったら大声でなにか叫んだって大丈夫だわ」
「そうだねえ、なんて叫ぼうか……日本軍部のバカヤローッとかね!」
「石田は軍隊嫌いなんだ?」
「うん、嫌いだよ。でもね、だんだん軍隊は嫌いだ、戦争は嫌いだっておおぴらには言えない雰囲気になってきているんだ」
「そうらしいわね。でもここだったら、思いきりバカヤローッて叫んだって誰にも聞こえないわ」
「ナーシャのお母さんは日本人だし、ナシャーも日本語とても巧くて日本人そのものだけど、お父さんはロシアの人だよね。お父さんとても素敵な人だけど、もし戦争がこれ以上ひどくなったりしたら、銀行だって閉鎖になり、みんなバラバラになちゃってナーシャとも会えなくなるよね」
このとき石田はその場の会話の流れからそんな言葉を軽い気持ちで吐いただけで、とくに深い思いをそれに込めていたわけではなかった。だが、その言葉を耳にした彼女の顔はこころなしか一瞬こわばったような感じであった。すぐにその表情はいつもの明るい笑顔に戻ったので、彼はそのかすかな心の翳りの裏に隠された深い意味を読み取ることはできなかった。
彼女は石田のそんな言葉にはとくに何も答えず、からかうような調子で言った。
「じゃ、私は、石田のバカヤローッて叫ぼうかしら……、石田には聞こえちゃうけどね!」
「おいおい、ナーシャ、なんで僕がバカヤローなんだい?」
「バカヤローだからバカヤローなのよ!……ふふふふふ」
あとで思えばなんともうかつなかぎりではあったが、悪戯っぽい笑顔と茶目っ気たぷりの口調の陰に秘める哀しい胸のうちと、それゆえの強い決意のほどに、彼はまだまったく気づいていなかった。心の奥の大きな痛みを抑え平静を演じることにかけては、十六歳のナーシャのほうが彼よりもはるかに上手ではあった。
沖を行く遠い船影に気づくと、彼女は言った。
「石田……、石田は船に乗ってたことがあるって言ってたよね?」
「うん、氷川丸っていう貨物船に乗ってタリーマンやってたよ。船荷の管理をする仕事をね」
「ふーん、それでどことどことへ行ったことがあるの?」
「横浜や小樽などの日本の港と台湾の港とを結ぶ航路だったから、基隆や高雄には行ったことがあるよ。そのあと天津の塘沽港にも寄るようになったから、天津周辺なんかもよく知ってるけどね。まあそんなところかな」
塘沽からの脱走劇のことが走馬灯のように彼の脳裏をよぎったが、もちろんそのことについては一切触れなかった。
「上海は行ったことある?」
「いや、一度行ってみたいとはいつも思ってきたんだけど、まだ行ったことがないよ」
「そうなんだ。あの船、上海にでも行くのかしら……。けっこう大きな船でしょう?」
「そうだねえ、大連からも上海行きの船がいろいろ出てるみたいだから、もしかしたらあの船も上海に行くのかもしれないな。でもなんで?……上海に行ってみたいわけ?」
「ううん、べつにね……。私は大連のこの老虎灘が大好きだから、上海なんか行くきたくない。石田は?」
「上海特急という映画などを見たせいでね、上海には昔から憧れてたから、やっぱりいつかは行ってみようと思ってる。でもね、いまはまだ大連に住んでいたいな……」
「私もね、上海ってどんなところかなっていつも思ってはいたんだけど……、でも、なぜかいまはもう上海なんかどうでもいいの」
ナーシャのさりげないそんな言葉をとくに変だとは感じることもなく、石田は軽く聞き流した。その言葉の背後に二重三重の含みが隠されていようなどとは、彼は想像だにしていなかった。

絵・渡辺 淳
「マセマティック放浪記」2003年7月9日
ある奇人の生涯 (24)
美少女脱皮
世間から隔絶されたその小島のあちこちには、ちょっとした木陰や直射日光を避けて横になるのにほどよい岩陰などもあった。一通り小島の散策を終えると、石田とナーシャは日の当たる平らな岩の上におもいおもいの格好で寝そべり、こころゆくまで日光浴を楽しんだ。夏の太陽は強烈だったが、二人の若い肌はその刺すような陽光の一部をほどよく吸収し、そしてまたその一部をほどよく弾き返しもした。この日の太陽は、まるでそんな二人の輝くような肢体だけを照らし出すために存在でもしているかのようであった。
日光浴を終えると、木陰になっているところへと移り、そこの岩に二人並んで横になった。そして、これまでに観たり聴いたりしたことのある音楽や映画の話をしたり、お互いの身にまつわる昔話を交わしたりした。お互いの将来の抱負などについてもあれこれと語り合った。他の誰にも邪魔されることなく、そんなふうにして二人だけで過ごしたひと時はこのうえなく満ち足りたものであった。いや、石田自身は心底そう感じていたが、真に満ち足りた時を送ることができたと考えていたのは、実際には彼のほうだけだったのであろう。
いっぽうのナーシャの胸中には、容易には鎮めがたい深い想いと、のるかそるかの賭けに托す彼女なりの緻密な計算とが人知れぬ底流となってうごめいていた。だが、石田はそんな複雑な彼女の胸中にまったく気がついていなかった。見方を変えれば、それほど見事にこの日のナーシャは自らの本心を押し隠し通し、何事もなく振舞う自分を演じきってみせていた。
日はまだ高かったが、そろそろ老虎灘の磯辺へと泳ぎ戻ったほうがよいのではないかと考えた石田は、「そろそろ帰ろうか……」とナーシャを促しおもむろに立ち上がった。彼女はちょっとだけ躊躇いの表情を浮かべたが、それでもとくに彼の言葉に逆らうこともなく、あとに続いて身を起こした。先に立った石田は来たときのルートを逆に辿り水辺へと降りるつもりで、午前中によじ登ってきたあたりの断崖の上へと出た。そして、下へと降りるための足場を確認しようとして何気なく海面を覗き込んだ。
次ぎの瞬間、思わず石田は我が目を疑った。彼らが二人だけの静かな時を送っている間に、小島のまわりではとても信じられないようなことが起こっていた。こともあろうに、海面が十数メートルも下方へと移動してしまっていたのである。
「こ、こんな馬鹿なことが……」と呟きながら、慌てふためいた様子で彼はうしろにいるナーシャのほうを振り返った。すると、そんな彼の困惑したような様子を見て、彼女は不思議そうに訊ねた。
「いったいどうしたのよ、石田?」
「そのう……なんて言うか、海が、海面がずいぶんと下のほうになっちゃってるんだよ!」
「そんなにひどく海面がさがっちゃってるの?」
「うん、ほらナーシャ、見てごらんよ、目も眩むような高さになっちまってるんだ!」
石田にそう声をかけられるのを待って、彼女のほうもそろそろと眼下はるかなところにある海面を眺めやった。
「ほんとねえ、いつのまにかずいぶんと……」
「驚いたなあ……こんな大変なことになっちゃってるなんて思ってもみなかったよ!」
「そうねえ石田、これじゃ、危なくてとても海面までは降りられそうにないわね」
「うっかりしてたなあ……、干潮時になると大きく海面下がることはわかってたんだけど、そんなことすっかり忘れてしまってたよ。いったいどうしたものかなあ……」
「そうだわねえ、いますぐにここから降りるのはちょっと……」
石田の言葉に合わせでもするかのように一言だけそう口を開くと、なぜかナーシャはそのまま黙り込んでしまった。彼のほうもそんな彼女の戸惑った心中を察して、一瞬黙り込んだ。
地理的な関係もあって、黄海北部沿岸一帯の干満の差は世界でも一、二を競うほどに大きいことで知られている。大潮の頃にはとくに干満の差は著しく、時にはゆうに十メートを超えることもあった。老虎灘で暮らすようになってからは、干満時のそんな海面の変化を幾度となく目にはしてきていたが、それは直接自分の生活に大きな影響を及ぼすようなことはなかった。まして小島を取り巻く海面の水位が干潮時になると極端に下がることなど、彼にとってはまったく関心外かつ計算外のことだった。
さらにまた運の悪いことに、その日はたまたま大潮の時期に重なってもいたから、干満の差が著しく大きかった。だから、石田らが戻ろうとしたときにはすっかり潮が引いてしまい、午前中この島に泳ぎ渡った時に比べると、海面は十メートル以上も低くなってしまっていたのである。
いっぱんに断崖というものは登るよりも降りるほうが難しい。しかも、ほぼ垂直に切り立つ岩壁にしがみつくようにして十数メートルも下まで降りきらなければならないとあっては、何事もなく眼下の海面にまで到達するのは容易なことではなさそうだった。それでなくても断崖の基底部には鋭い角をもつ大小の岩々が露出していたから、無理して降りる途中で滑落でもしたら到底無事にはすみそうにもなかった。たとえ石田のほうがなんとかその断崖を伝い降りることができたとしても、体力に劣る女性のナーシャにはそんなことなど土台不可能なことのようにも思われた。
予想だにせぬ成り行きにすっかり困り果てた石田は、不慮の事態を眼前にして不安に襲われているに違いない彼女の顔を、自らは平静を装いながらおそるおそる振り返った。下手にそこで慌てふためいたりしたのでは男としての顔が立たないばかりか、いっそう彼女の心を不安に陥れるばかりでもあった。だから、彼はおのれの心を落ち着けようと必死だったが、その実は、なんとか打開策を見つけることができないものかと焦るあまり、パニック寸前といってもよいような心理状態にあった。
石田は内心の動揺を押し隠しながら、囁くような調子でナーシャに言った。
「ここから降りるのはちょっと難しそうだね。仕方がないから、べつのところに行ってどこかもうすこし降りやすい場所を探してみようよ。きっとそんなところが見つかるさ。まあ、そんなに焦ることなんかないさ」
むろんそんな彼の言葉は、その胸中のあたふたした思いとはまるで逆の、その場しのぎの慰めにすぎなかった。そもそも、この断崖上に登ってくるのでさえも、いま自分たちが立っている地点へと向うルートしかないことは、この小島の地形に詳しいナーシャが誰よりも熟知しているところだった。
石田はナーシャがその言葉に応じてくるのを期待してなどいなかった。ところが、驚いたことに、彼女は彼の顔を真っ直ぐに見つめなおすと、思わぬ言葉を返してきた。
「なにもそんなに慌てることなんかないでしょ?、どうせなら、また潮が満ちてくるまでここで待っていましょうよ!」
「えっ……、また潮が満ちてくるまでだって?」
そんなことなどまるで念頭になかった彼が、意表を突くナーシャのその一言に一瞬戸惑いを覚えながらそう問い返すと、彼女はきっぱりと言ってのけた。
「潮が満ちてくるまでまだずいぶんと時間があるでしょ……、せっかくだからそれまでの時間を二人だけで存分に楽しむことにしましょうよ!」
燃えるような瞳の輝きをともなって放たれたその言葉の矢は、石田の心臓をまがうことなく貫いた。その必殺の一矢のために彼の心身が完全に麻痺したのを見て取った彼女は、「いいでしょう、石田?」とだけ短く言うと、もう相手に逃げようがないことを確めでもするかのように、彼のそばにぴったりと身を寄せた。そして、どこか思い詰めた表情のなかにも静かな微笑を湛えながら、澄んだ両の瞳で彼の顔をじっと見上げた。
まるで見えない糸に五体を操られている人形でもあるかのように、石田はその両手をナーシャの背中にまわすと、そのしなやかな身体をこのうえなく優しく、しかも不思議なまでに力強く抱き寄せた。男というものをまだ一度も受け入れたことのない少女に特有な芳香が、石田の心をいやがうえにも掻きたてた。相手の心のすべてを捉えきったと確信したナーシャは、さりげなく目をつむると、これがとどめとばかりに、その美しく引き締まった唇をそっと彼の口元に差し出した。
妖麗なひとりの女への脱皮を決意し、その変身の時はこの場をおいてはありえないと思い定めた美少女は、全身から目に見えない魔法の銀糸をこれでもかと言わんばかりに繰り出し続けた。そして、その妖艶な糸に心身をからめとられた石田に、もはや行動の選択の余地などあろうはずもなかった。彼は吸い寄せられるようにして、いつしか自分の唇を相手の唇に重ねていた。
それは、それぞれの体内に長きにわたって堰き止め蓄積されていた切なく激しい二つの感情が自制という名の堤を切り破っていっきに融合した瞬間だった。しばらくして一度そっと唇を離したあと、石田は無言でナーシャの顔を見つめやった。彼女の目はこころなしか潤み、右頬には一筋の涙が流れていた。「ナーシャ……」、そっと囁きかけるようにそう言うと、彼はもう一度力を込めて彼女の肢体を腕の中に強く引寄せた。ひたすらうち震えるような切なさと愛おしさがそんな石田の全身を激しく貫いた。

絵・渡辺 淳
「マセマティック放浪記」2003年7月16日
ある奇人の生涯 (25)
岩上の恋
外界から完全に隔絶された時空のもたらす静寂に見守られるようにして、二人は長いながい抱擁を交し合った。そのあと、いったんその抱擁の手をゆるめると、手に手をとって先刻まで横になっていた岩陰へと引き返した。再びその場所に戻ると、無言のまま、またじっと互いの顔を見詰め合い、全身が甘く切なくしびれるような抱擁をもう一度繰り返した。そしてそれが終わると、どちらからともなく崩れ落ちるようにして岩の褥(しとね)に身を横たえた。二人の間にはもうそれ以上お互いの気持ちを確認し合う言葉など不要だった。時間が止まり、彼らを包み込む大気は、「二人だけの孤独」の世界を演出するために他者の侵入をいっさい許さない透明なバリヤーと化した。
恥じらいの翳をどこかに残しながらそっと目をつむって身を寄せるナーシャの胸に、石田はこのうえなく優しくその指先を伸ばしやった。優しくはあったが、その指先にはまた男という動物の性(さが)のもたらす欲望のすべてが凝縮もされていた。水着の下の弾力のある膨らみのすこし尖った頂きに指先が達した瞬間、彼女は歓喜とも慄(おののき)きともつかない小さな声をあげると反射的に身をよじらせた。それを目にしてより激しく本能を煽られた彼の指は、彼女の身体の動きに遅れじと素早く動いて、執拗に二つの胸の膨らみを追いかけ、さらにはそのしなやかな肢体の奥深いところに隠された命の泉へと迫ろうとした。おのれの滾る欲望のゆえなのか、逃げると見かせて巧みに誘い惑わす妖精の幻術のゆえなか、それとも古来男女の間に宿命づけられてきた暗黙の儀式性のゆえなのか、もはや当の石田にもよくはわからないままにそんなイタチゴッコがしばらく繰り広げられた。
お互いの動物的本能を煽り高め合うようなそのイタチゴッコの決着を求めて、ついに石田の手がまだ誰にも知られていないナーシャの命の源泉に辿り着いた瞬間、彼女は言葉にならない声を上げ、もはやこれまでと観念したかのようにひときわ大きく身悶えした。そして、自らの聖域のすべてを空け渡すかのようにその身体の動きを止めた。石田はそんな彼女の濡れた水着を小刻みに震える手でそっと脱がすと、すぐに自らも生まれた時のままの姿になって半身を起こし、彼女の身体をいたわるように抱き寄せた。その白く引き締まった裸体は眩いばかりに美しかった。すっかり上気したナーシャの身体から伝わってくる温もりを愛おしさともやるせなさともつかぬ気持ちで受けとめながら、石田は、一瞬、これから行なおうとしているおのれの行為の重さとその業の深さを想った。
まだどこかに固さを残してピンと張り立つ両の乳房は、熟れようとしてなお自らの力では熟れきれずにいる思春期の少女に特有な至純さと危うさとをそなえていた。石田はその乳房の頂点にある輝くようなピンクの突起にそっと唇と舌先をあて、それを優しく吸い寄せた。そして二人は互いの身体を半ば重ね合うようにして還り道のない陶酔の世界へと崩れ落ちていった。
少女への訣別の瞬間のもたらす心身の不思議な興奮と、そのために避けることのできない痛みとの交錯するなかで、ナーシャは心から愛する石田の腕に深々と抱かれ、そしてついに一人の女へと脱皮した。石田はそんなナーシャを優しくしかしどこまでも狂おしく愛撫し、体内から突き上げてくるような随喜の末に果て去った。
美しい蝶と化したナーシャは、脱皮の痛みなどすこしも感じてはいなかったかのように、何度も何度も抱擁と愛撫のかぎりを求めてきた。まるでそれは明日にも石田がこの世からいなくなってしまうとでも思っているかのような激しさだった。その哀願にも似た熱い誘いにいまさら抗するすべなどあろうはずもなく、忘我の淵に深く身を託した石田は、いつしか一匹の野獣となりはて、弾むような美獣の肉体の生み出す歓喜と幻夢とを嬉々として貪り喰った。
いっぽうのナーシャも、そんな石田の灼熱しきった命の化身を体内深くに呑み込みながら、先刻まで清純な少女だったとは想われぬほどの妖艶さで、絶頂にあって陶酔する相手の呻きに共鳴した。どんなに歓喜の声をあげどんなに悶え狂おうと、誰かに漏れ聞かれたり覗き見られたりする心配はなかった。岩の褥をべつにすれば、何から何までが、二人の織りなす究極の生命のドラマとその舞台とに相応しかった。いや、岩の褥さえも二人には温かくそしてこのうえなく柔らかものに感じられた。
もう明日はないとでも言わんばかりの激しさで妖しく挑みかかるナーシャの姿は、まるで、若い石田の盛り立つ命の証を一滴も残さずに吸い尽くしてしまおうとしているかのようであった。いつしか攻守が逆転し、相手の攻勢に圧倒され翻弄されるばかりになった彼は、一匹の獣としての誇りも抗うすべも忘れて束の間の至福と悦楽に酔い痴れ、そして快い疲労の底へと沈み込んだ。
すべてを尽した愛の戦いを終えて放心しきった二人は、脱力しきった互いの身をそのまま寄せ合うようにして静かに目をつむった。その有様は、命を賭してどこまでも急流を遡上し、産卵のための交尾を終えて力尽き流れに漂う雌雄二尾の鮭の姿をも彷彿とさせた。ただ、鮭のそれと明らかに違うのは、この恋がまだ始まったばかりだということであった。燃え盛る二つの心と心の、さらにはその肉体と肉体の慄き撼えるような交接がまだこれからも幾度となく繰り返されるだろうことを遠のく意識の中で想いつつ、石田は深いふかい眠りへと陥った。
二人が目覚めた時、すでに太陽は大きく西空に傾き、刻々とその赤味を増していくところだった。爽やかな風が小島の上を吹き抜けはじめ、裸体のままで横たわっている彼らにとっては涼しすぎるくらいであった。ずいぶんと時間が経ってしまったことに気づいた石田は、いつにもなく慌てた様子でナーシャを促した。
「ナーシャ、眠っているうちにすっかり日が傾いちゃったみたいだよ。急いで帰らなきゃ!」
「そうみたいね。でも夏の日脚は長いから気にすることはないわよ、石田……」
意外にも、彼女のほうはとりたてて慌てた様子もなくそう答えた。
「でも、あまり帰りが遅いと、ナシャーのお父さんやお母さんだって心配するんじゃないのかい?」
「大丈夫よ。父と母は早急に片付けなければならない用事があるとかで出かけていて、今日は帰りが遅くなるって言っていたわ。両親には石田と一緒にのんびりと海水浴してくるって伝えてもあるし、二人とも石田のことは信用してるから……」
ナーシャにそう言われた石田は一瞬言葉に窮した。すると、彼女はそんな彼の複雑な胸中を察するかのように言葉を繋いだ。
「いいのよ、石田、そんなことなんか全然気にしないでね。両親には関係ないことなんだもの……、これって私と石田の二人だけの問題なんだから!」
「……」
なおも返事に戸惑う彼の顔をどこか憂いを含んだ表情でじっと見つめると、心底哀願するように彼女は言った。
「それよりもお願い、石田、帰る前にもう一度だけ抱いて……」
「それはいいんだけど、でもナーシャ、いくらなんでももうこの時間だから……。それに、これからだってまたいつでも会えるわけなんだし……」
六歳年上の大人としての分別を示すつもりで石田はそう諭しかけた。するとナーシャはちょっとだけ微笑みを浮かべ、甘えるような仕草で軽く首を振りながら、
「今日は今日、明日は明日……だから、今日できることは今日のうちにしておいたほうがいいってことだってあるでしょ?」と言った。そして、石田の身体にもたれかかりながらその胸に深々とその愛くるしい顔を埋めた。
再び湧き上がった激情が石田の全身を瞬時に貫き、またもや彼の理性のすべてを解体させた。抑制という名の呪縛から解き放たれ、先刻にもまして本能の権化と変じ果てた彼は、夏の夕日を背にしながら狂ったかのようにひたすら彼女を抱き求めた。奇妙なことではあったのだが、その肉体を強く抱きとどめようとすればするほどに、そしてその魂を懸命に追い求めようとすればするほどに、愛おしいナーシャの心身がまるで実体のない虚像のような存在と化し、どこか遠くへ逃げ失せてしまいそうな思いがしてならなかった。それでもなお石田は、ナーシャという存在の確たる証を手に入れたいと願うがごとくに、彼女の身体を激しく愛撫し続けた。それに応じるナーシャのほうもまた、石田への愛おしさが募れば募るほどに、切なく儚い思いへと駆られていくばかりだった。たぶんそれは、一時の快楽と昂揚をともなう「愛」という名の業深い営みに、古来例外なく宿命づけられてきた代償のようなものであったに違いない。
二人がそれぞれの水着を纏い帰途に着こうとする頃には、赤々と燃え立っていた夕陽も西方の山影に姿を隠し、西空一帯は黄昏色に染まっていた。小島の断崖の縁に立って下を眺めやると、ナーシャの言葉を裏付けるように、あれほど低いところにあった海面が大きく上昇し、眼下四、五メートルのところにまで達していた。先に立った石田が海面まで降りるルートのステップを探そうとすると、それを押し留めるようにナーシャは言った。
「石田、この崖の上から直接海に飛び込みましょうよ。ここにやって来た帰りにはいつも私そうしてるから!」
「えっ…・・大丈夫なの・・…ここから飛び込んでも?」
「すっかり潮が満ちてきたから大丈夫よ。ほら、すぐそこに岩棚が張り出したところあるでしょ、あの真下は深くなってるから飛び込んでも平気なの!」
「へえ、そうなんだ!……じゃ、そうしようか、そのほうが手っ取り早いから」
「どうせなら二人でしっかり抱き合ったままで飛び降りてみることにしない?」
「そりゃ、面白いかもね、折角のことだから……」
思いがけない彼女の誘いに一瞬躊躇いを覚えはしたが、とくに危険はないことを確認すると、彼はそう答えてその岩棚の端へと進んだ。そして、あとから来たナーシャと向かい合って立つと、しっかり抱き合ってもう一度だけキスを交わした。それから二人はそのままの態勢でしばし呼吸を整えると、一、二、三の掛け声とともに岩棚を蹴って空中に飛び出し、足先のほうから勢いよく海中に突入した。いったん水中に沈み再び海面に浮かぶ上がるまで二人はしっかりと抱き合ったままだった。
夕潮のなかをゆっくりと泳いで老虎灘の磯辺に戻ると、彼らは岩陰に置いてあったそれぞれの衣服入りの袋を手にし、水着姿のままで集落のほうへと歩きだした。ちょっとだけ身体が冷えはしたものの、堪えられないほどの寒さではなかった。肩を並べて家路に着いたが集落の入口近くに着くまでなぜかナーシャは無言だった。集落の入口に戻った二人は、周囲に人目がないことを確かめると、もう一度熱いキスを交わした。
海寄りの集落の入口からは石田の家のほうが近かった。自宅のすぐそばで来ると、石田はまだしばらく彼女と一緒にいたいという気持ちを抑えながら、ナーシャにとりあえず別れの言葉を囁きかけた。
「今日はどうも有難う、ほんとうに素敵な想い出ができたよ。また近いうちに会うことにしようね……。じゃ、今日のところはこれでね!」
「そうね、私もとても楽しかったわ。また、ゆっくり会えるといいわね……。石田もまた元気で頑張ってね……、じゃ、さよなら・・…」
ちょっと淋しげな笑顔を浮かべてそう言い残すと、ナーシャはこころもち足を速め、見送る石田を振り返ることもなく夕闇の中に消えていった。そんな彼女の目から二筋の涙が溢れ出し両の頬を濡らしていたなどとは、石田にはさらさら想いもよらぬことであった。

絵・渡辺 淳
「マセマティック放浪記」2003年7月30日
ある奇人の生涯 (26)
さよならも言わないで
たまたま三連休をとっていたため、石田は翌日も翌々日も出勤はせずに、読書をしたり音楽を聴いたりしながらのんびりと自宅で過ごした。ナーシャはどうしているのかなという思いが絶えず胸中を駆けめぐりはしたが、敢えて自分のほうから連絡をとることはしなかった。前日の夢かとまがうばかりの出来事を思い返すにつけても、気まずさとも気恥ずかしさともつかぬ複雑な心理がはたらいて、自分から彼女の家に電話をかけたりするのは気が引けたからだった。ナーシャのほうからなにか連絡はないものかと内心では期待はしていたが、彼女のほうからも二日間なんの音沙汰もなかった。きっと彼女も自分とおなじような気持ちでいるに違いないと想像をめぐらし、石田はおのれの心を慰めた。
小島での一件があってから三日目の朝、石田はいつにもなく緊張した面持ちで家を出た。老虎灘から大連の中心街にある勤務先の銀行へと向かう時も、いつもの時刻に乗る馬車と路面電車をわざとやりすごし、そのあとの馬車と電車に乗った。いつも乗る馬車や電車だと、かねがね親しくしてもらっているナーシャの父親イワノフと顔を合わせる可能性が大きかったからだった。なにも知らない彼女の父親からにこやかに朝の挨拶をされたりしたら、少なからぬ心中の罪悪感のゆえに、唯々戸惑い対応に窮してしまうような気がしてならなかった。
オフィスに着くと、さりげない様子でイワノフのデスクのほうを窺いながら石田は自分の席に坐った。意外なことに、盗み見るような彼の視線の先にイワノフ姿はなかった。時間にはとても几帳面なはずなのに今日はどうしたのだろうと思ったが、なにかの事情で急に休暇でもとったのかもしれないと考えなおし、彼はとりあえず一日の業務にとりかかることにした。イワノフの姿が見えないことに一瞬ホッとする反面で、もしかしたら彼女の身になにか不測の事態でも起こったのかという危惧が脳裏をよぎったが、彼はその二つの思いを胸の中で押し殺し、素知らぬ顔で業務に就いた。
何気なく近づいてきたアメリカ人支店長に信じ難い事実を告げられたのはその直後のことだった。支店長は、いささか躊躇いがちな口調ながらも、手短に、そしてはっきりと彼に向かって言った。
「Mr. Ishida……, I'm afraid I have to tell you something sad!(石田君、君に悲しい報告をしなければならいんだ)」
「What do you mean, sir ?(いったい何があったんでしょう、支店長?)」
悲しい報告をしなければならないと言われた石田は怪訝な顔でそう問い返した。
「Our able clerk, Mr. Ivanov suddenly left this office three days ago.(三日前のことなんだがね、有能な行員だったイワノフ君が突然会社を辞めてしまってね)」
「What ? ……, you've said Mr. Ivanov left the office ?(なんですって?……イワノフさんが辞職したですって?)」
ナーシャの父イワノフが突然銀行を辞めたと聞いた彼は、いくらなんでもそんなことがあろうはずがないとばかりに、相手の言葉を確かめなおした。すると、支店長は自分の言葉に間違いがないことを強調しきながら、さらに驚くべきことを彼に伝えた。
「Yes, I mean it, Mr. Ishida……. Mr.Ivanov and his family have already gone to Shanghai.(その通りなんだよ、石田君……イワノフ君と彼の家族はもう上海に行っちゃったんだよ)」
「They've left for Shanghai?……unbelievable!(あの人たちが上海へと向かったですって?……いくらなんでもそんなこと!)」
イワノフ一家はもう上海へと旅立ってしまったのだと話す支店長に向かって、石田は信じられないという表情を浮かべながら、半ば叫ぶような調子でそう言った。だが、支店長はそんな彼を宥めでもするかのような口調で言葉を継いだ。
「But it's just true, Mr. Ishida!(でもねえ、石田君、それはね、まぎれもない事実なんだよ)」
「What happened to them? Why didn't they tell me anythig about it ?(いったいあの人たちに何が起こったっていうわけですか?……それに、なんで僕にはなんにも話してくれなかったんでしょう?)」
「I think they were afraid of making you feel so sad, and so they've gone there without saying good-bye to you. They all loved you very much, I believe, Mr. Ishia.(きっと君をあんまり悲しませたくないって思ったんだろうね……、だから彼らは君にお別れの言葉も残さないまま上海に行ってしまったんよ。石田君、僕はね、彼らはみんな君のことが大好きだったと思うんだよ)」
「But……(でもそんな……)」
石田はそこまで言いかけて思わず絶句した。この時点に至ってようやく、彼には、老虎灘の小島でナーシャが何気なく吐いた言葉やさりげない振舞いの裏の意味がはっきりと読み取れたからだった。あの日の彼女の一挙一動はすべて計算し尽くされたものだったのだ。次の瞬間、彼の胸には遣り場のない悲しみがどっと込み上げ、その両目には涙が滲んだ。おのれの不覚を悔やんでみたが、もはやすべてがあとの祭に過ぎなかった。
しばらくしてなんとか気持ちを落ち着けた石田は、支店長や一部の同僚行員たちからイワノフ一家が上海へと旅立つまでの詳しい経緯を聞かされた。日中戦争が激化の一途を辿り、日米、日露関係なども日増しに悪化していくなかで、ロシア人のイワノフは、どうやらかなり以前からこの大連で働き続けることに少なからぬ不安を抱きはじめていたらしかった。日本政府の政策や日本軍部の意向が色濃く影を落としている大連にあっては、近い将来時局がいっそう緊迫化した場合、白系ロシア人のイワノフやその一家に弾圧や差別の手が及ぶことは目に見えていた。さらにまた、もしも日米開戦のような最悪の事態が発生した場合には、ナショナル・シティ・バンクそのものがこの大連からの撤収を余儀なくされるに違いなかった。
そのような事態に至ったら支店長ら米英人は母国へと引き揚げればよかったが、すくなくともイワノフ一家はそうするわけにはいかなかった。母国ソビエト連邦が東欧に侵攻してきたドイツに対し警戒を強めつつあったうえに、自由主義社会の空気を吸ったことのある海外在住ロシア人に対して厳しい思想弾圧がなされているのがスターリン政権下のソ連の実態だったから、たとえ帰国しても悲惨な運命が彼らを待ちうけていることは明らかだった。そんな状況下にあって、結局、イワノフは家族とともに国際都市上海へと移住する道を選んだのだというのだった。
上海に移住するため銀行員を辞めたいとイワノフが願い出たのは二十日ほど前のことだったらしいが、親交のある石田らにはそのことは内密にしておいてほしいととくに支店長に頼んだのだそうだった。どうせお互い悲しい思いをするのなら、せめて直前まではこれまで通りに親しい友として楽しく愉快な日々を送り、上海へ向かう日がきたら見送りもなにも一切うけずに家族だけで黙って大連を去るようにしたいというのがイワノフの意向だったのだ。石田にすればどうにも居たたまれない思いだったが、それはイワノフ流の男の美学とでも言うべきものだったのだろう。
衝撃的な事実を知らされて、石田の胸中は乱れに乱れた。これまでにもいろいろな経験積み、父親の死など大小いくつかの悲しみを乗り越えてきた石田だったが、そのときの心の痛みはそれまでの人生では味わったことがないほどに激しく辛いものだった。当然のことだがその日はほとんど仕事が手につかなかった。愛おしいナーシャの面影と激しく狂おしい小島での一日の想い出が、いつ果てるともなく、繰り返し繰り返し彼の脳裏を駆け巡った。
その実務能力と冷静沈着な仕事振りを高く評価され、アメリカ人支店長からいまや最も信頼される行員となっていた彼も、この時ばかりは失恋の痛手におのれを忘れて悲しみ悶える一介の青年に過ぎなかった。
どうみても仕事にはならなかったその日の業務をなんとか終えると、石田は大急ぎで老虎灘の自宅へと戻った。そしてすぐさま普段着姿に着替えると身を焦がすような想いで独り無人の磯辺へと降り立った。晩夏の夕日のなかで静かに輝く海も、さわさわと磯辺に寄せ来る青潮も、そして前方に浮かんで見えるあの岩の小島もみな先日のままだった。だが、あの愛くるしいナーシャの姿を探し求めることだけは最早できない相談だった。せめてその影でさえもと念じてみたが、所詮それは虚しい願いに過ぎなかった。力なく磯辺を歩きながら、石田はナーシャの内心の想いを読み取れなかったおのれの不覚を悔い悲しんだ。
あとになって思えば、あの日のナーシャの言動の一つひとつがなんとも暗示的であった。小島の断崖の上から沖を行く船を見ながら、「上海は行ったことある?」とか、「あの船上海にでも行くのかしら……。けっこう大きな船でしょう?」とか尋ねかけてきたナーシャの言葉の裏に込められた想いにもっと早く気づくべきであった。「上海に行ってみたいわけ?」という自分の問いかけに、「私は大連のこの老虎灘が大好きだから上海なんか行きたくない。石田は?」とさりげなく答えたナーシャの姿が、いまとなってはこのうえなくいじらしかった。
おそらくナーシャは潮が大きく引いたときにはあの小島の断崖を降りることができなくなるのも計算済みだったに違いない。自分との最初で最後の愛の一日を永遠に忘れ難いものへと演出するため、ナーシャは内なる悲しみをこらえつつ知恵のかぎりを尽して自分をあの場所に誘ったに相違ない――そう振り返る彼の胸はただもう張り裂けんばかりであった。はじめて唇を重ね合ったとき彼女の頬を伝い流れた涙の意味を悟れなかった己の無神経さが返すがえすも恨めしかった。
遣り場のない悲しみにくれながらとぼとぼと磯辺を伝いに歩くうちに、彼は二人だけの想い出の地となった小島のそばにやって来ていた。海を挟んで浮かぶ小島の断崖は折からの夕陽を浴びて黄白色に輝いていた。先に立って崖を攀じ登るナーシャの姿をあらためて偲びやりながら、彼は再び深い想いへと沈んでいった。
汚れなき処女から一人の妖艶な女への脱皮を決意し、その舞台に眼前の小島を、そして脱皮の儀式に不可欠な相手にほかならぬ石田を選んだナーシャは、一世一代の儀式の果てに永遠の別離が待つことを承知で狂おしく燃え立ち、少女への訣別を図ったのだった。それが男との初めての交わりであるとは信じられないほどに喜び悶え、自ら挑むようにして繰り返し繰り返し石田の愛撫を求めたのも、すべての事情が明らかになってみれば至極当然のことではあった。おそらくは両親のイワノフ夫妻もナーシャの石田に寄せる思慕の深さを知っていて、上海への旅立ちを前にした最後の一日に賭けようとする娘の姿を黙認していたのではないかとも推測された。
そんなことだと知っていたらナーシャにも、そしてイワノフ夫妻にも、もっともっと心のこもった対応をすることができたのにと嘆いてみたが、どんなに後悔してみても最早どうにもならないことだった。支店長にさえ上海の移転先を告げずに大連を去ったイワノフ一家にしてみれば、よほどの決意と覚悟とがあってのうえのことだったに違いなかった。

絵・渡辺 淳
「マセマティック放浪記」2003年8月6日
ある奇人の生涯 (27)
決断の時来たる
石田翁はその遠い日の出来事のことを「岩のような恋」という独特の表現を用いて懐かしそうに回想した。いまでこそ老虎灘での一連の事態の顛末を青春を彩る掛け替えのない想い出として振り返えり、冷静に述べ語ることもできるのだろうが、当時の石田翁の傷心の深さには計り知れないものがあったに違いない。いつもの人を喰ったような口調がすっかり影を潜め、しんみりとした語り口に変ったことからしても、その頃の苦悩の大きさが偲ばれようというものだった。
「まさに『岩のような恋』という表現がぴったりな話だったんですね」
とくに他意もなくそう問いかけると、老翁はちょっとはにかみ気味な笑みを浮かべておもむろに答えた。穂高のドラキュラ翁を自称する昨今のこの人物にしてはなんとも珍しいことであった。
「岩だらけのところで岩のように固く結ばれたところまではその通りだったんですが、そのあとがねえ……」
「そうですよね、それからほどなく、その岩が思いもかけず砕け散ってしまったっていうわけですからなんともはや……」
「そうですねえ……、砕け散ったというか海中深く沈んじゃったっていうか……」
「なるほど、海中深く沈んじゃった……、二人で抱き合って断崖の上から海中に飛び込んだままになっちゃたっていうわけですね」
「そうそう、岩のような恋がその重さに堪えかねて海底深くへブクブクと……」
「それで石田さん、結局、そのあとどうなさったんですか?」
「どうもこうもないんですね。なにしろ、一家の移住先が上海とわかっているだけで、あとは何の情報もないわけでなんですから」
「それじゃ、肝心の仕事だって手につかなかったでしょう?」
「ええ、まったく手につかなくなってしまいましたね。とてもよくしてくれた支店長には申し訳なかったんですけれど、もう銀行の仕事なんかどうでもよくなっちゃったんですよ」
「石田さんがそこまでショックを受け、思い詰めるとは……。何事にも超越的な現在の石田さんの姿からすれば、とても想像がつきませんけれどね」
「そりゃ私もまだ若かったですから、そのぶん純粋なところもありましたしね」
「いまでもある意味で石田さんは純粋ですよ」
「そんなことを言ってくれるのはあなたくらいのものですよ」
「ははははは……、べつに青春の秘話を聞き出そうとしておだててるわけじゃありませんからね。それで、その失恋の痛手は想像以上に大変なものだったんでしょうけれど、お蔭でしばらく回転が滞り気味だった石田さんの運命の歯車がまたまた大きく回り始めたとかいうことに?」
「ええ、実際そうなんですよ。人生なにが幸いするかわらないものですね。それからほどなく私も一大決心をすることになったんですが、それはナーシャという存在があったからこそだったのかもしれませんね」
「そうでなければまるで違った人生になっていたとでも?」
「たぶん……、ただねえ……」
「ただ……どうしたんですか?」
「結局のところ、ナーシャには二度と逢うことはできませんでしたけれどね……」
「じゃ、老虎灘のあの日が文字通り最後の一日となってしまったわけですか?」
「ええ、そうなんですね……」
こちらの問いかけに石田翁は短く呟くようにそう答えると、謎のような微笑みを浮かべながら、まるで自らに何事かを言い聞かせでもするかのように軽く頷いた。それからしばらく老翁は両手を軽く組んで額に当てながらなにやら思いに沈んでいたが、やがて再び口を開くとその後の経緯を語り始めた。
イワノフの突然の辞職と一家の大連離脱を知った石田の驚きと悲しみは大変なものだったが、いまひとつ彼にはなんとも複雑な思いがあった。ナーシャらが移住した先がほかならぬ上海だったからである。日本にいる時分から憧れてやまなかった国際都市上海へと渡るという夢を彼はまだ捨ててしまったわけではなかった。塘沽から天津へと出たときも、天津から斎南経由で青島に向かったときも、ベティとの再会がきっかけで青島に住み着いたときも、そして日中戦争激化の影響でやむなく大連へと移住したときも、けっして彼の脳裏から上海への憧れが消えることはなかった。要するに天運が彼に味方してくれないだけのことだった。
ただ、大連のナショナル・シティ・バンクに勤めるようになってからの生活は、人間的にも経済的にもそして環境的にもそれまでになく恵まれたものだったから、いつしか不満らしい不満もなくなり、あれほどに強かった上海への思い入れも表面的には影を潜めていたのだった。しかしながら、実際にはその思いはなお彼の心中深くにおいて絶えることなく燻り続けていたのである。
イワノフ一家が突如大連から姿を消してからというもの、まるで仕事が手につかなくなった石田の胸中で、それまで燻っていた思いが再び激しい焔となって燃え上がったのは当然のことであった。上海に行きたい……いや、なんとしても上海に行かなければならない!――老虎灘の小島の一件があってから半月と経たないうちに石田はそう決意を固めるよ
うになっていた。イワノフ一家の転居先も皆目わからぬ有様とあっては、上海に向かったからといってナーシャに再会できる保証などまるでなかった。だが、たとえ千分の一、万分の一の確率であったとしても、その僅かな確率に賭けてみるほうが何もしないでこのまま大連にいるよりはましであるようにも思われた。また、もしもナーシャとの再会が叶わなかったとしても、上海という国際都市のもつ独特の雰囲気に触れ、その文化の香りを吸収することがきればそれだけでも十分に心が満たされるのではないかという気さえした。
自分の能力を高く評価しこれほどにまでに優遇してくれた支店長に辞職を申し出るのは、石田にとってさすがに辛いことではあったけれども、そのことを別にすれば他に障害になるようなことはなかったから、長年の夢だった上海行きを決行するにはまたとないチャンスだった。高級で優遇されていたため、既に彼には経済的にも十分な貯えができていたから、上海への渡航費に事欠くようなことはなかった。それどころか、上海に渡ってもしばらくは何もしなくても生活していけそうだったし、ことによったら、ちょっとした事業を起こすことだってけっしてできない相談ではなかった。
秋風の吹き始めた九月半ばのある日、遂に意を決した石田は支店長に突然の辞意を申し出た。支店長はちょっと困惑し淋しそうな表情を見せはしたものの、そうなることをいくらかは予想していた感じだった。イワノフ一家がいなくなったあとの気の抜けたような石田の仕事振りを見ていて、支店長は彼の胸中にある程度察しがついていたらしかった。上海へ行くつもりなのかと支店長に問われた彼は、正直にそのつもりだと答えた。どんなに慰留されたとしても最早石田にはそれに応じるつもりはなかった。その断固たる決意のほどを察知した支店長は、しばしの沈黙のあと、永遠の弥勒の微笑みにも似た静かな笑みを浮かべながら「OK, Mr.Ishida……Good luck in your future!」とだけ短く言って石田の辞意を諒承した。
まだ日米開戦までには一年ほどある時期のことではあったが、両国間の緊迫した政治情勢から推してその先どういう事態が起こるのかもう誰にも予想がつかなくなっていた。だから、ナショナル・シティ・バンクの支店長にしても、たとえ石田を引き留めたとしてもその将来を責任をもって保証することは難しいと考えざるをえなかったのだろう。ともかくも、こうして石田の上海行きは現実のものとなったのだった。旧制福岡高校在学中からこのかた上海へと渡ることを夢見ながら何度も挫折してやまなかった彼に、思わぬかたちで遂にそのチャンスが到来したわけだった。それはまさに運命の皮肉としか言いようのない成り行きであった。
九月いっぱいで銀行を辞め直ちに上海へと向かうことにした石田は、大急ぎで身辺の整理にとりかかった。老虎灘で親交を深めた多くの友人や知人たちに上海へと移住することになった経緯を告げ、お別れのパーティを開いてお互いの将来の無事と繁栄を心から祈りあった。集まってきた友人や知人たちは、誰もが石田との別れを惜しんで心のこもった言葉をかけ、仲間の一人であるロシア人の奏でるバラライカの響きに合わせて別離の歌を唄ってくれた。
香具師の男と一緒に青島から大連に渡り不慣れな仕事に手を染めた頃からすると信じられないほどの生活の変容振りだったが、その恵まれた生活を敢えて捨て、魔都とも呼ばれる上海にこれから彼は向かおうというわけだった。上海に知人など皆無だったし、それなりの貯えはあったにしてもその後の生計を立てる確実な当てが何かあるわけでもなかったから、全く不安がないと言えば嘘になった。冷静になって考えてみると、上海に行ったからといってナーシャと奇跡的に再会がなる可能性は万分の一どころか億分の一すらなさそうであった。
だが、上海へのこの旅立ちを横浜の山下公園で行き倒れになった当時の有様や、天津で所持金を盗まれて途方に暮れ辛うじて青島に辿り着いた時の状況などに比べれば、両者の間に天国と地獄ほどの差があることだけは確かだった。石田は憧れの上海の様子にあれこれと想いめぐらせながら己の心を奮い立たせた。

絵・渡辺 淳
「マセマティック放浪記」2003年8月13日
ある奇人の生涯 (28)
憧れの上海へ
九月下旬のある日の朝、石田は想い出深い大連の街をあとにした。見送りはすべて辞退し、大連港から上海へと向かうフェリーには一人だけで静かに乗り込んだ。憧れの上海に向かう晴れの船旅であったし、所持金も十分にあったから、一等船客となって上海までおよそ千キロの航海をゆったりとした気分で楽しもうと考えた。
汽笛をひとつ大きく鳴らして大連港の岸壁を離れたフェリーは大連市の位置する小半島の先端を北から南へと回り、ほどなく老虎灘の沖合いへと差しかかった。船首に向かって右手のデッキ上に立った石田は、ひとかたならぬ感慨にひたりながら住み慣れた老虎灘の奥深い入江のほうを見つめやった。そして、楽しかった友人知人たちとの生活を振り返りながら胸中でいま一度お別れの言葉を呟いた。
ナーシャと二人であの幻夢のような一日を過ごした小島の影も遠くにではあったがはっきりと望まれた。あの時ナーシャと肩をならべて小島の断崖上から沖を行く船を眺めていた自分が、まだわずか一ヶ月しか経っていないというのに、こうして船上から逆に小島を眺めやっていることを思うと、つくづく人間の運命とは不思議なものだという感慨が湧いてくるのだった。
石田の乗る船はやがて大連や旅順のある遼東半島の島影をあとにし、青島のある山東半島の先端部沖合いを通過して黄海のなかほどへと進んでいった。塘沽、天津、青島、大連と、渤海湾周辺の各地ををめぐり暮らした歳月がいまとなっては懐かしかった。それらの歳月が将来自分の人生にどれほどの意味と影響をもつものかについてはまるで想像がつかなかったが、すくなくともその間の生活が助走となって上海への旅立ちが実現したのはまぎれもない事実であった。ずいぶんと遠回りしたみたいではあったけれども、そのいっぽうで得たものも少なくなかったから、それはそれでよかったのかもしれないと石田は己に言い聞かせた。
上海までは二日余の船旅だった。貨物船に乗って北海道の小樽と台湾の基隆や高雄との間を往復していた時に比べれば雲泥の差のあるなんとも優雅な航海でもあった。たまたま台風の季節には当たっていたが、幸いにも穏やかな晴天に恵まれ波も静かで、まさに海路の日和といった感じであったし、豪奢な一等船室でのこのうえなく気ままな寝起きは、なんとも快いかぎりであった。マリーネ・デートリッヒやメイ・ウォンなど往年の名女優の登場する映画「上海特急」に魅せられた彼が、結局は上海特急ではなく上海行きフェリーの一等船客となって上海に向かうというのは皮肉と言えば皮肉な話ではあった。だが、天津で所持金のほとんどを盗まれ、そのあと青島へ向かおうと残り僅かな小銭をはたいて乗車した上海特急三等客車の凄まじい光景に較べれば、まさにその船旅は天国を行くようなものであった。
黄海から東シナ海へと入った船は、大連を出港してから五十時間余の二日目の昼頃には長江の河口付近に到達した。そして、どう見ても海洋の一部としか思えない広大な河口をしばし遡行すると、水郷地帯として名高い蘇州周辺に向かって分岐する長江の支流黄浦江へと船首を向けた。目指す上海はこの黄浦江を南へ向かって十数キロほど遡行したところに位置していた。船が黄浦江に入るのを待ちきれぬかのように、石田はそそくさと船室を出るとデッキ上に立った。そして、吹き抜ける風に身を委ねながら、「ナーシャ、とうとう僕も上海にやってきたぞ!」と胸の奥で叫んでみた。
幅五百メートルほどの黄浦江をしばらくゆっくりした速度で遡ると、やがて右手前方にちらほらと建物の影が見えはじめた。なおも船が奥へ奥へと進むにつれて、視界に入る建造物の数もだんだんと増えてきた。またそれに合わせるかのようにすれ違う船舶の数もずいぶんと多くなった。その様子からして、船が目指す上海周辺に近づきつつあるのは明らかだった。
それからしばらくすると河岸沿いに立つ建築物の数がいっきに増加した。そして黄浦江全体が大きく左手にカーブし、蘇州江かと思われる小河がそこから右手に分岐する地点に差しかかった途端、大小様々な建築物が互いの存在を誇示し合って林立する壮大な光景が大きく眼前に迫ってきた。それまで単なる知識でしかなかった摩天楼という言葉の意味するところを彼が初めて実感した瞬間だった。
それらのほとんどは西洋風の建造物で、これまで彼が見慣れてきた都市の光景とはまったく異なるものであった。もちろん、洋風建築物ならそれまでにも日本各地や天津、青島、大連などでずいぶんと目にしてきてはいたが、その数の多さといいその規模の壮大さといい、過去に経験したものなどとは到底較べものにならなかった。まだ船上にあったにもかかわらず、石田はその光景に圧倒された。
上海か、これが憧れの上海か……、ようやく夢が叶ったぞ!――心中で小躍りしながらそう呟き終えると、石田は大きく両手を広げ船上を吹き抜ける大気を吸い込めるだけ吸い込んだ。するとまるでそれに呼応でもするかのように、熱いものが身体の奥底から激しくそしてとめどもなく込み上げてきた。あらためて顧みてみると遠いとおい道のりではあった。だが、厳しい思想統制がおこなわれ、生活の自由が失われつつある日本国内の時流に鑑みるならば、どんなに遠回りをしたとは言ってもこうして夢が実現したぶん自分は幸運だと思うのだった。けっして信心深いとほうだとは言えない石田だったが、さすがにこの時ばかりは神仏に深く感謝したい気持ちであった。
前方に建ち並ぶ建物群の影がその大きさを増すにつれて彼の乗る船と黄浦江河岸との距離はぐんぐんと縮まっていった。そして、それからほどなく航行を終えた船は、高らかに入港を告げる汽笛を鳴らすと、外灘(バンド)と呼ばれる黄浦江沿いの地域に近い一角にゆっくりと接岸した。それはまた、それまで以上に波瀾に満ちた新人生の扉がおもむろに開かれた一瞬でもあった。
おもむろにタラップを踏みしめながら下船した石田は、埠頭に降り立つと携行した大小のトランクをいったん地上に置き、胸中の興奮を抑え鎮めるかのように大きく呼吸を整えた。まだ九月末のこととあってか、南方に位置する上海の陽射しはなお強烈で、湿度もかなり高かった。大気の爽やかな大連からやってきたばかりなので多少は暑さがこたえはしたが、貨物船員として小樽・台湾間を往復していた頃にもずいぶんと経験したことなので、それほどまでには気にはならなかった。
それからしばらく、彼は黄浦江沿いの埠頭周辺の様子を眺めやっていた。あたりを取り巻く空気のすべてが、それまで体験してきたものとは明らかに違う感じだった。一口に言うならば、それは、これまでになく開放的で、どこまでも明るく自由な雰囲気を湛えた大気なのだった。まだ船から降りたばかりで上海市街にも足を踏み入れてもいないのに、そんな印象を覚えるというのはなんとも不思議なことだった。
上海には友人や知人など誰もいなかったので、ともかくいったんどこかに身を落ち着ける場所を探さなければならなかった。当然のことながら周辺の地理などまださっぱりわからなかったから、たまたま通りかかった人力車を呼びとめると、まずはそれに乗り込み、自分を上海の中心街へと連れていってくれるように依頼した。埠頭のある外灘から上海の中心街一帯にかけての大通りの両側には、ネオ・バロック風やネオ・ルネッサンス風、アール・ヌーヴォー風、さらにはアール・デコ風といった建物などがそれぞれに偉容を競って建ち並び、まさに国際都市上海の面目躍如という風情であった。
その時の石田にはそれらの建造物個々の建築様式の相違などまだよくわかりはしなかったが、初めて目にするその街並みの光景には唯々驚くばかりで、どうみてもそこが東洋の街であるなどとは信じられないのだった。賑やかな街路にあふれる人々の服装もずいぶんとモダンかつカラフルで、それらがどこの国の人なのかまでは見分けがつかなかったものの、その多くが西洋人であることだけは疑うべくもないことであった。
欧米列強国の租界地の中央を東西に貫く大通り沿いの上海中心街には当時からヨーロッパ風の豪華なホテルが建ち並び、世界各国から訪れる数々の旅行者やビジネスマンらの交流と憩いの場になっていた。現在では南京東路、南京西路と呼ばれているその街路の中ほどで人力車を降りた石田は、近くにめぼしいホテルを探し出すと、そのフロンに向かって足をはやめた。弱冠二十四歳の石田ではあったが、大連での銀行勤めのお蔭で当面ホテル代に困るようなことはなかったし、同僚行員や老虎灘での諸外国人との交流を通し英語・フランス語・ドイツ語は言うに及ばず、ロシア語や中国語にさえもある程度は通じるようになっていたから言葉に不自由することもなかった。だから、目指すホテルが欧米系一流ホテルであろうと、またフロントマンが何語で応対してくれようと彼には臆することなどまるでなかった。
たまたま対応してくれたフロントマンにしばらく滞在したい旨を英語で申し出ると、どこか日本人離れした感じの石田の様子を即座に見取った相手は、快くその申し出を受け入れてくれた。チェックインを済ませると、ボーイに先導され、見事な吹きぬけ構造をもつホールを抜け、エレベータに乗って高層階にある部屋へと案内された。それは想像していた以上に立派な部屋で、そんなところに泊まるのは石田自身も初めてのことであった。
外気温や湿度の高さに較べるとホテルの中はずいぶんと爽やかで快適そのものだった。上海の欧米系一流ホテルや劇場、ビルディングなどには当時から既に大型空調設備が導入されており、そのお蔭で上海のような高温多湿の地域でも建物内ではとても気持ち良く過ごせるようになっていた。その頃の日本にはまだ空調設備など存在していなかったから、石田にはそのシステムそのものがたいへん素晴らしく、また物珍しく思われた。
ホテルの部屋の窓から眺める上海市街の景観は感動的だった。眼下に広がる広大な街並みや大きくうねりのびる黄浦江の遠景を見つめながら、いつしか石田は深い想いに沈んでいった。彼の脳裏をよぎったのはほかならぬあのナーシャの姿だった。
――いったいこの上海の街のどこにナーシャはいるというのだろう。上海にはやってきたものの、いまの自分は彼女を探すなんの手掛かりもなんの手段も持ち合わせてなどいない。まるでそれは大海の中から特別な一滴の水を探し出すようなものではないか!――そう考えると石田はとめどもなく悲しい気分になるのだった。この際奇跡をと念じたいのは山々だったが、こうして上海にやってこられたこと自体が一つの奇跡でもあったわけだから、そのうえさらに奇跡をと望むのは虫のよすぎることだった。実際また、天運のほうも、そんな彼にそれ以上優しく微笑みかけてくれるほど甘くはなかった。
心理的な緊張や思わぬ興奮からくる疲れなどもあって急に睡魔に襲われた石田は、そのままベッドに倒れ込むように横たわると、周辺の散策に出るのも夕食をとるのも忘れ、唯々ぐっすりと眠り込んだ。どのような事態が待ち受けていようとも明日からはこの上海で生き抜いていかなければならない彼にとって、それは未来との戦いを勝ち抜くに必要な活力を貯えるための眠りでもあった。

絵・渡辺 淳
「マセマティック放浪記」2003年8月20日
ある奇人の生涯 (29)
租界の申し子上海
古代文明発祥の地として何千年もの歴史をもつ中国において、上海という土地が発展の道を辿り始めたのは想いのほか新しい時代のことだったようである。その歴史資料に基づくと唐代以前の上海は沼、湿地などがいたるところに散在する漁村地帯であったらしい。ただ、黄浦江と長江の河口近くに位置するという立地条件が中国内陸地と東シナ海沿岸各地とのとの交易の基点として最適だったため、唐の時代に入ると徐々に周辺の干拓が進められ、唐代末期の十世紀以降は港町として発展していくようになったという。南宋時代の十三世紀後半になると貿易の監督官庁が上海に設置され、とくに十三世紀後半になって上海県の県都として市街地が建設整備されると、その存在は国内外から次第に注目されるようになっていった。
十四世紀の元の時代になって始まった綿花の栽培はやがて一帯の主要作物となり、さらに明の時代の到来とともに起こった綿織物工業は一躍上海の重要産業となって、上海の発展に貢献した。いまの豫園商場地域に相当する上海県城が当時の上海市街域であったのだが、発展を遂げたとはいってもまだその市街域の規模は小さく、現在の上海の大きさに較べるとごく小さなものにすぎなかったようである。
上海が現在目にするような大都市へと変貌を遂げはじめたのは、一八四二年のアヘン戦争で清が欧米列強国に破れ、上海の開港を余儀なくされて以降、いわゆる租界時代に入ってからのことだった。アヘン戦争が終結し一八四三年に南京条約が締結されると、一八四五年のイギリス租界を皮切りに、アメリカ、フランスなどが次々に租界と呼ばれる特別な居留地域を上海に設置するようになった。また一八七一年の日清修好条約締結以降は日本人も欧米の租界地内に居留を許されるようになり、一八九四年に始まった日清戦争後の下関条約締結以降、日本も欧米列強国と同等の権利を獲得するところとなった。日清戦争以前の日本は英、米、仏などのように独自の「日本租界」というものを設けず、英米の共同租界地に邦人居住者が住むというかたちをとっていた。ただ、日清戦争後日本領事館がフランス租界地域より虹口南部に移転してからは、その周辺一帯が日本人租界と呼ばれるようになった。
これらの租界地は警察権、行政権ともにそれぞれの列強諸国に属する治外法権地域となっており、当然、清朝の支配が及ぶことはなかった。また上海の租界は外国政府が中国人の土地所有者から直接に土地を購入して設置するという独特の様式の外国人居留地で、香港などのように外国政府が中国政府から土地を借りうけるいわゆる「租借地」ではなかった。上海が「魔都」という二文字を冠し「魔都上海」と呼ばれていた背景にはそのような租界地特有の複雑な事情などがあったのだった。
各国の租界地は交易が盛んで人々の出入りが激しかったにもかかわらず、租界地を所有するそれぞれの国が警察権を持っていたため、犯罪の取り締まりそのものがきわめてルーズで一貫性にも欠けていた。したがって華やかな街の発展の陰にあって各種犯罪の横行も絶えなかった。諸外国が半ば公然とアヘン売買や賭博、売春といった行為等に手を貸していたばかりでなく、中国各地から難民が大量に流入していたことなどもあって犯罪の温床化が進み、日本人居留民などは身の安全を守るため一種の結社である自衛集団を構成したりする有様だった。そして、そのような上海の裏社会に漂う特異な雰囲気が「魔都」というイメージを生み出してもいたのである。
もちろん、諸外国の租界の存在にはそのようなマイナス面もあったものの、長期的かつ全体的な展望に立つと、のちのちの中国の発展に大きな貢献をすることにもなった。各国の租界地が文化交流や各種貿易の拠点となったため上海には大量の外国資本が流入し、国際貿易都市として経済的にも文化的にも奇跡的な飛躍を遂げることになり、現在目にするような中国最大の経済都市上海の礎が出来上がったからである。第一次世界大戦以降は、銀行、商社、製造業などに関係した日本資本が続々と上海に進出し、同地は我が国の対中国貿易における一大根拠地にもなったのだった。そのため、日本人居留民の数は年々増加の一途を辿り、一九三〇年代の終わり頃までには上海在留外国人のうちの三分の一以上を日本人が占めるという状況になった。そして、それら日本人たちの住む日本租界では寺社をはじめとする日本様式の建物などが次々に建造され、日本語を使った日本様式の生活が送られるようになっていった。
上海にはじめて租界地を設けたのはイギリスで、一八四五年、現在の人民広場のあるあたりから黄浦江河畔の外灘にかけての一帯に外国人居留地区を造営した。このイギリス租界は当時の上海の北部(現在の蘇州江沿岸部にかけての一帯)、西部(現在の虹橋地区)、そして東部(現在の黄浦江沿い外灘地区)へと拡大発展し、商業の一大中心地となった。また、イギリス租界に三年遅れて設置されたアメリカ租界は蘇州江北側の虹口地域一帯を中心にして広がり、蘇州江および黄浦江沿岸の港を生かして上海の工業地帯として発展した。そして、のちにそれら二つの租界は英米共同租界として一体化し、ますます発展を遂げていくことになった。
この英米共同租界東部の外灘地区にはその時代の上海の繁栄を象徴する洋式の様々な建物が立っていた。租界時代の建造物群のうち往時の面影を留めて現在も残っているものには、サッスーンハウス(現和平飯店北楼)、ジャーデン・マセソン商会(現上海市対外貿易公司)、上海クラブ、大英帝国領事館、パレス・ホテル(現和平飯店南楼)などがあるが、当時それらの建物はいずれ劣らぬ威容をもって栄華の極みを誇っていた。また、中西部にあったパークホテル(現国際飯店)や華僑飯店(現金門大酒店)、蘇州江河口北岸のブロードウエイ・マンション(現上海大厦)、アスター・ハウス・ホテル(現浦江飯店)などもその時代の上海を代表する壮麗な建造物であった。
英米租界よりも遅れて生まれたフランス租界は、上海県城域(現在の豫園商場一帯)の西側から英米租界の南側にかけて細長くのびるかたちで発展した。そして最終的には上海県城の北側をぐるりと取り囲む地域もフランス租界の一部となった。フランス租界は英米租界とは一線を画し共同租界となることがなかったばかりでなく、市街地の機能としても異なる役割と雰囲気を保っていた。英米租界が商工業の中心地として発展していたのに対し、フランス租界地区は静かな住宅地域となっており、フランス式建物や住宅が特有の風格と風情を湛えて並んでいた。ネオ・バロック様式のフランスクラブ(現花園飯店)やアール・デコ様式のキャセイ・マンション(現錦江飯店北楼)、スペイン風集合住宅の上方花園や新康花園、クレメントアパート(現克菜門公寓)、ノルマンディ・アパート(現武康大楼)、法国総会、法国公園など、どれをとってもフランス文化やその周辺文化の粋とも言うべき建物ばかりだった。それらの建造物類の多くはいまも同地に残っていて、東洋のパリと称された当時のフランス租界の面影をなおも留めて伝えている。
上海の租界は往時の帝国主義の悪しき一面を象徴するものでもあったのだが、およそ百年にわたる租界時代に上海の中国人たちは海外の文化や生活様式に身近に接することになり、その結果、独立心や冒険心、自由な思想への憧れなどを強く抱くようになっていった。そしてそのような状況のなかで身に着けた国際人としての感覚がその後の上海の経済発展土台となり、今日の中国の一大繁栄へとつながったことからもわかるように、租界には中国の近代化に貢献した一面もあったのだった。
石田が上海入りした翌年の対英米開戦後、日本軍が英米共同租界やフランス租界を占領したことにより、百年にわたる上海の租界時代は事実上終焉を迎えることになったのだが、その間に築かれた上海という国際交易都市に咲き開いた文化の華は、なにはともあれ素晴らしくかつ魅惑的なものではあったのだ。
そんな租界時代の終焉間近な時期に上海入りし、爛熟した上海の文化を目にすることのできた石田は、ある意味で大変に幸運だったとも言えた。彼はそのまましばらくホテルに滞在することにし、翌日からはホテルを基点に上海の主要な繁華街や租界地域を一通り廻り歩いた。まずは上海の地理やその土地柄に慣れること、そして次には自分の生活感覚に合う住居地域を探し出しそこに適当な住まいを確保することが当面の急務だった。もちろんナーシャのその後の状況が気になってはいたが、なんの手掛かりも方策もないままにこの人種の坩堝とも言うべき上海で彼女の一家を探し当てるなど到底不可能なことだったから、その件に関してはひたすら奇跡の到来に賭けるしかなかった。
ホテルを出た石田は現在の南京東路にあたる大通り沿いに外灘方面へと向かって歩きだした。メインストリートやそれと交差する大小の街路沿いにずらりと建ち並ぶ銀行、大商社、ホテル、デパート、レストラン、映画館、劇場、遊技場、各種商店などを一つひとつ感慨深げに眺めながら、彼はゆっくりとした歩調で広い歩道を進んでいった。舗装された街路を折々悠然と走り抜ける車にはこれまで目にしたことのないような洒落た形をしたものなどがあって、その光景もまた彼の好奇の目を楽しませてくれた。そもそも広い歩道全体の構造やデザインそのものがなんとも洗練されていて、一歩いっぽ市街を踏み進む石田の心を不思議なほどに魅了し高揚させてくれた。日本国内の都市よりはずっと開放的だった青島や大連のそれにもはるかに増して上海の街の開放感は大きなものに思われた。なるほど上海には魔都と呼ばれる一面もあるのかもしれないが、自由な空気の代償として魔都の側面が生じるものだとするならば、それはある程度やむをえないことではないかという気もした。
英米仏などが警察権と行政権をもつ上海の租界地域には、当時まだ日本政府や日本軍部の偏狭な政策の影響は及んではいなかった。すでに日本租界なども設けられていて上海在留外国人の三分の一ほどを日本人が占めるようになってはいたが、欧米諸国の租界地に住む人々と共存しなければならない事情もあったから、日本色のみに上海全体を染め変えてしまうというわけにもいかなかった。したがって、大なり小なり東アジア各地にその影を落としはじめていた軍国日本の息苦しい空気にその時まで上海はなお無縁な存在でもあった。軍部主導の日本的な規制や風潮に大きく距離をおくことができたのが、そんな石田の大きな開放感の要因となっていたのは確かだった。前日初めて上海の埠頭に降り立ったときに理由なく感じたあの自由な空気もそう考えてみると納得のいくことであった。
外灘地域に出るといったん蘇州江の河口周辺へと北上した。そしてアール・デコ様式のブロードウエイ・マンション(現上海大厦)やアスター・ハウス・ホテル(現浦江飯店)、さらにはアール・ヌーヴォー風のロシア領事館などを彼は不思議な感動を覚えながらあらためて眺めやった。それらは前日船が黄浦江を遡上し上海に近づいたとき真っ先にその威容を現わした建物群だからだった。眼前で蘇州江を吸収し大きく右手にカーブしながら悠然と流れる黄浦江の川面には大小の船々が浮かび、それらの一隻一隻がまるでおのれの意志を高らかに主張でもするかのように思いおもいの方向に航行を続けていた。
蘇州江の河口周辺をしばし散策し、そこから引き返すと左手に黄浦江を望みながら外灘地域を南下するメインストリート(現中山東一路)を豫園などのある上海県城の方に向かって歩いてみた。左手の黄浦江側は長さ一、二キロほどの細長い緑地公園になっており、右手には一九〇〇年から一九三〇年代にかけて現像されたネオ・バロック・スタイルやアール・デコ・スタイルの建物をはじめとする諸様式の壮麗な西洋風建物群が並んでいた。かつて映画や写真で目にした光景がまさに現実のものとなって石田の眼前に広がっているのだった。
その景観に圧倒された彼は息を呑む思いでしばしその場に立ち尽くした。なかでもネオ・バロック様式の香港上海銀行(現浦東開発銀行)やアール・デコ様式のサッスーン・ハウス(現和平飯店北楼)、パレス・ホテル(現和平飯店南楼)などのどこか厳かでしかも異国情緒に溢れるたたずまいはその心の底に深くそして強く焼きついた。それは上海以外のところではけっして見ることのできない風景に違いなかった。そんな素晴らしい光景を目にすることができただけでも上海にやってきた甲斐があったという思いが彼の脳裏をよぎっていった。

絵・渡辺 淳
「マセマティック放浪記」2003年8月27日
ある奇人の生涯 (30)
日本租界とフランス租界
翌日と翌々日は米英共同租界の北東部の虹口周辺を中心とする日本人居留地域にも出掛けてみた。英米共同租界やフランス租界などと違って日本人居留地域にはもともと租界としての明確な区画が存在していたわけではなかったが、日本総領事館が虹口に移転してからはその周辺に日本人居留民の住宅街が建設されるようになり、いつしか一帯は日本租界と呼ばれるようになっていた。
日本租界には日本にも縁の深い魯迅が密かに生涯最後の三年間を過ごした住居や、自店員名義でその住宅を借りて魯迅に供した有名な内山書店などもあった。石田が上海入りした時には魯迅はすでに他界していたのだが、彼が住んでいた大陸新邨はなおその瀟洒な姿を留めていた。この大陸新邨は、一九三一年に大陸銀行上海信託部が資本投資して建設した赤煉瓦造り三階建ての住居用テラスハウスだった。魯迅を陰で支えた内山官造は元大学目薬の営業員だったが、一九一七年同地に書店を開業、当初はキリスト教関係の書籍のみを扱っていた。その後、実質的に店を一人で管理していた妻の美喜子が営業を拡大したこともあって、内山夫妻が魯迅と親交をもつようになった頃には上海でも名高い書店となっていた。
その近くには、当時日本軍が使用していた広大な射撃訓練場(現魯迅公園)や知恩院、西本願寺、東本願寺、上海神社、福民総合病院、上海歌舞伎座、北部小学校などのほか、日本居留民団本部、大小の日本人アパートのような日本色の濃い呼称のついた建物や施設が並んでいた。もっとも、それらの建物や施設の構造までもがすべて日本風であるというわけではなかった。
たとえば一九二四年に造られた知恩院は、細かな装飾や彫刻の施された石造りの支柱と
アーケード式ベランダをもつイスラム風の壮麗な建築物だった。鮮やかな色彩をしたアラビアタイル張りの美しい壁面を眺めながら、石田は、この堂内で僧侶らが読経したり仏典の講釈をしたりしたらいったいどんなことになるのだろうと想像をめぐらしたりもした。やはり一九二四年に日本人医師の頓宮寛が開いたという福民病院は想像していた以上に立派な六階建ての近代的総合病院で、魯迅の妻の許広平が出産したのをはじめとし、彼の親族や知人たちの多くがこの病院で診療を受けていたというのも十分に頷けた。
邦人上海居留民団子弟のため一九〇七年に創立されたという北部小学校は、重厚な石造り四階建ての美しい構造をもち、窓が多く採光も十分な感じで、古びた木造やバラック造りの校舎がほとんどの日本本土の小学校などとは比較にならぬほどに立派なものだった。
一九二四年にワトソン清涼水工場を改造して開設された上海歌舞伎座にも立寄ってみた。やはり立派な造りではあったが、日本の歌舞伎座などとは外観がまるで異なっていたため、博多の芸人町で生まれ幼い頃から歌舞伎の世界に慣れ親しんで育った石田は、正直なところすくなからぬ違和感を覚えもした。
この時は外観を眺めるだけにとどめたが、上海に定住するようになってからというものは、当然、石田はこの上海歌舞伎座にも幾度か足を運んだ。外観とは違ってその内部は階上四百席、階下六百席の花道つき純日本式劇場となっていて、折々本土から公演に訪れる歌舞伎役者たちの名演技に邦人上海居留民を中心とする観衆はみな深く魅了されたものだった。厳しい思想統制が敷かれ、重苦しい雰囲気に包まれはじめていた日本国内と異なりなお自由な空気の漂っていた上海にあっては、歌舞伎役者たちも独特の開放感を感じながら伸びのびとした演技を披露できるようでもあった。
内山書店や福民病院からほど近いところにある多倫路周辺には様々な市が立ち並び結構な賑いを見せていた。この多倫路界隈には様々な文人や各界の名士らの仮寓や隠遁所などがあちこちにあるということだったので気の向くままに付近を歩きまわってみたが、独特の風情と存在感を湛えた煉瓦造りの店舗や住居が棟々を連ねて立ち並び、かねてから美観や美的センスには人一倍こだわりのある彼もそれなりに心惹かれる思いだった。当時中国人作家たちの溜まり場にもなっていたABC喫茶店やクンフェイ珈琲店などもこの近辺に位置していた。
どこか身を落ち着ける場所を探そうとしていた彼は、日本租界地区内にある日本人アパートや日本人居留民団本部なども一通り訪ね歩いてみた。日本人アパートなどは当時本国ではまず目にすることのできない超モダンなデザインをもつ多層構造の建物で、その建築センスに彼はすくなからず感嘆した。日本居留民団本部は三階建てのがっしりした石造りの建物だった。当初、石田はその居留民団本部を訪ね、貸部屋についての情報もらったり仕事の斡旋をしてもらったりしようかと考えた。しかし、日本租界を見てまわるうちに、いろいろと新たに思うところが生じ、結局、そこを訪ねて貸部屋情報を得たり仕事の斡旋を受けたりすることはやめた。
日本租界一帯に住む日本人たちは皆日常的に日本語を使って生活していた。だから、付近の商店街では日本語が飛び交っていて、様々な看板類なども日本語で表記されたものがほとんどだった。この時期には上海の外国人居留者の大部分を日本人が占めるようになっていたから、それは当然の成り行きではあった。したがって、日本租界のどこかに部屋を探しそこに住めば、まだ東も西もよくわからぬ上海の地ではあっても不必要に不安を感じることなどなく生活できるはずであった。
だが、既に大連の老虎灘でも外国人に取り巻かれて暮らしてきた経験のある石田には、この国際文化都市上海にやってきてまで、日本的な習俗や価値観、生活感覚などに捉われながら生きることが必ずしも意義あることだとは思われなかった。もはや語学に関してはなんの不自由もなかったし、諸々の外国人と生活を共にすることにもまったく不安はなかったから、長期的に考えてみた場合、むしろ日本租界以外の地域に住いを求めたほうが賢明であるような気がしてきたのだった。また、万に一つのナーシャとの再会を期したり、たとえそうでなくても彼女に関するなんらかの情報を入手できるようにするためには、フランス租界か米英租界に住んでいたほうがよいようにも感じられた。
石田が最後に訪ねてみたのはフランス租界だった。英・米租界が誕生して間もない一八四八年、上海駐在フランス領事としてこの地に降り立ったモンティーニは清朝の出張機関長である上海進台の呉健彰に対して自国にも租界の開界を許可してくれるように申請、その結果、翌一八四九年に上海県城域(現在の豫園商場一帯)とイギリス租界とに挟まれるかたちで初期フランス租界は誕生した。その後、フランス租界はイギリス租界の南側に東西に細長くのびるかたちで大きく発展、最終的には上海県城の北半分をぐるりと取り囲む地域全体が同国租界の一部となった。商業の中心地として一大成長を遂げたイギリス租界や港湾を活かし工業地帯として開発の進んだアメリカ租界と違い、当初からフランス租界の大部分は環境に恵まれた閑静な住宅街として発展した。そのため、フランス様式の建物や住居が立ち並び、フランス庭園やパリ風の街路に囲まれた上海随一の理想的な生活空間区となっていた。
フランス租界に一歩足を踏み入れた途端に、石田はその街並み一帯に漂う誇らかな文化の香りに圧倒された。そして、なにゆえにこの租界地区が東洋のパリとも称されているのかが理屈抜きでわかるような気がしてきた。ネオ・バロック様式のフランスクラブ(現花園飯店)やアール・デコ様式のキャセイ・マンション(現錦江飯店北楼)などの偉容を目の当りにして感嘆したり、法国公園(フランス公園)の美しさに見惚れたりしながら付近をあちこちと歩きまわるうちに、彼はなんとしてもこのフランス租界の住宅街のどこかに小さな部屋でも借りて住みたいものだと思うようになった。爽やかな大気や洗練された独特の雰囲気をはじめとし、なにもかもが自分の感覚にしっくりとくるこの街で暮らせるなら、住む部屋そのものはどんなに古くて狭かろうとすこしも構わないとも考えた。
フランス租界にはキャセイ・マンションのほかにクレメントアパート(現克菜門公寓)やノルマンディ・アパート(現武康大楼)といったモダンな集合住宅や、上方花園や新康花園のようなスペイン風ガーデンハウスなどもあり、それぞれに風格と風情があって魅力的なことこのうえなかった。ただ、さすがに石田もそんなところに住もうとは思わなかったし、たとえ住みたいと思ってみたところで住めるはずなどあるわけもなかった。彼にしてみれば、当面、そんな高級住宅の立ち並ぶ街々の片隅にでも身を置くことができるならそれだけでも満足であった。
フランス租界のすぐ隣りは上海県城であったが、その城域内にある豫園とそれを取り巻く中国古来の商店や民家のたたずまいにも石田はすくなからず心惹かれた。モダンなフランス風文化と古い中国の伝統文化とが明確に一線を画しながらも互いに接し合い共栄している有様は実に不思議なものでもあった。歴史の悪戯と言ってしまえばそれまでだったが、そのなんとも奇妙な取り合わせが彼はいたく気に入った。まさに国際都市上海の「際」という一文字にふさわしい光景だったからでもある。
明代の一五五九年に造営された豫園は「都市のなかの山水」と称えられる名園だった。もともとは刑部尚書を務めた藩恩という人物の菜園であったが、その息子の藩允端が晩年を迎え静かに余生を送る父親のために庭園に造り変えたものだった。孝行息子の藩允端などとはまるで違って孝行するいとまさえもなく父親をなくし、母親にも心労ばかりかけることの多かったおのれが「豫悦老親(老親に悦びを与える)」の意を暗に含むとも言われるこの豫園にひとときの安らぎを求めて散策するという運命の皮肉を、内心で石田はついつい苦笑せずにはおられなかった。そして、すこし生活が落ち着いたら母親と二人の妹をこの上海に呼び寄せようと思うのだった。
初めて訪ねる豫園の景観は想像していた以上に素晴らしいものだった。方形に近い荷花湖上にに架る九曲橋と湖面に浮かぶ湖心亭との絶妙な取り合わせなどの背後には、人工のものとは言いながらも、長いながいこの国の歴史の重みと彩りが秘められているように感じられてならなかった。また、大仮山という築山や会景楼と呼ばれる望楼からの眺望も息を呑むばかりで、文字通り絶佳の一語に尽きた。欧米や日本の租界地とは見るからに雰囲気の異なるこの園内を今後も折々徘徊することになるだろうと予感しながら、彼はしばし雑事を忘れてその美しい景観を楽しんだ。
豫園のすぐ西側に広がる商店街も壮観を極めた。清代からの老舗や伝統的な造りの大店舗が階を重ね軒を連ねて立ち並び、異様なまでの活況を呈していた。雑多な日用品は言うに及ばず、珍奇な漢方薬から見たこともないような食材、真贋入り混じった得体の知れない骨董品から古書類までと売られている商品も多種多様で、まさに中国数千年の歴史の縮図を垣間見る思いだった。
豫園を中心とする上海県城域をあとにした石田は、再びフランス租界に引き返すと閑静な住宅街や公園地帯を西に向かって通り抜け、同租界に一輪咲く異色の大麗華とも巨大な悪の華とも言うべき大世界方面へと足を向けた。そして、黄昏の迫る街路を感慨深げに踏みしめ歩きながら、その胸中で「身を落ち着ける場所はやはりこのフランス租界をおいてはないよな」と呟き、上海での新たな生活にこれまでとは違った人生の展開を期すことにしようと、あらためて己の決意を固めるのだった。

絵・渡辺 淳
「マセマティック放浪記」2003年9月10日
ある奇人の生涯 (31)
上海裏社会と大世界
フランス租界の一角に位置する大世界(ダスカ)は、まさに上海の夜の街に咲く巨大な一輪の妖花という形容がぴったりのところであった。色とりどりの鮮やかなネオンと照明に彩られた、美しくも妖しくもある奇妙な形の建物にまず石田はその目を奪われた。左右に大きくのびる複雑な構造の数階建ての建物があって、その中央には、まるで巨大な仏舎利塔を近代的にデフォルメしそれに螺旋階段や何層もの展望台を付設したような望楼らしきものが立っていた。大世界の建物やその周辺一帯の歓楽街を漂い包む華やいだ雰囲気にはどことなく洗練されたところがあって、東洋的な風土の醸し出す情緒とはまるで異なるものが感じられた。
その光景を一見した石田は絢爛たる光の渦の煌きの奥に底知れぬ闇の存在を直感した。しかしながら、同時にまた、目の前の光の渦に自ら巻き込まれ、どこまでも溺れ耽ってみたい気分でもあった。遠い東洋の地に移植された西欧の魔木が枝いっぱいに享楽の花を咲かせ、それに群がる者どもを次々に痺れ呆けさせようとしていると知りながら、なおその誘惑に抗しきれない人間の性というものをつくづくと不思議にも思うのだった。かねがね噂に聞いていた魔都上海の魔都たる所以をこの大世界という妖麗な夜の花の放つ甘い香りは何よりもよく物語っていると言えた。
どこらともなく流れ響いてくるジャズの演奏に思わず石田は足を止め、その哀調を秘めたメロディーとリズムにしばし耳を傾けた。そして心の底まで沁み透るようなその響きにどうにも抗することのできなくなった彼は、まるでそれに誘い導かれるようにして大世界の建物の一角にある階段を上った。ジャズの演奏の漏れ響いてくるお店はすぐに探し当てることができた。しばし躊躇ったあと意を決した彼がそのクラブ風の店の洒落た造りのドアの前に立つと、自ら手をわずらわせるまでもなく中国人ボーイの手でさっとドアが開かれ、彼は店内の一隅にあるテーブルへと案内された。
十分に計算し尽くされた照明に浮かぶ店内の光景に、石田は少なからず感嘆した。まだ
上海に不案内な身ではあってもこの地にはもっと大きくもっと高級なクラブがいくらでもあることは知っていたし、大世界という歓楽街の一隅に位置する店ということもあったから、店内の雰囲気にはそうそう期待はしていなかった。だが、個々のテーブルや椅子をはじめとする調度品や装飾品のすべてが重厚そのもので、しかも、きらびやかなチャイナドレスに身を包んでテーブルをめぐり、にこやかにお客に語りかける女性たちはみなそれぞれに美しくしかも気品に満ちみちていた。彼はそんな店内の様子をさりげなく窺いながら通されたテーブルに腰を落ち着けると、とりあえずカクテルを注文した。
店の奥あるステージでは数人の外国人たちによってジャズの生演奏が行なわれているところだった。ヴォーカル、サックス、トランペット、ドラム、ピアノのどの音をとってもゾクゾクするような迫力で、当時の日本などではまず聴くことのできない本格的な演奏だった。それまでにジャズに慣れ親しむ機会がそれほどあったわけではなかったのだが、石田はその音に酔い痴れその響きにひたすら圧倒されるばかりだった。
ジャズの演奏の合間には、英語、フランス語、ロシア、中国語などで談笑する声が店内に飛び交い、まさにアジアの最先端を行く国際都市上海の面目躍如というところだった。この夜たまたま石田が覗き見たのは、大世界、さらには上海という都市全体に蠢く光と陰の世界からすればごくささやかな部分、しかもごく健全な一面にすぎなかったが、それでもなお彼の心はどこか妖しくときめきたち、不思議なまでの興奮に包まれた。そしてこれが彼の上海歓楽街における遊興体験の第一歩となった。
英米租界やフランス租界が誕生し商工業が急速な発展を遂げるようになると、上海には福建省や広東省をはじめとする中国各地から船員や港湾労働者、各種商人、難民、さらには暴徒たちまでが大量に流入するようになった。そして、彼ら移民や流民たちは出身の郷土単位の互助組織を構成し、それらがさらに拡大して幇(パン)と呼ばれるより大規模な組織体を形成するようになっていった。上海に七つあったと言われる幇はその後いっそう統合が進み、最終的には紅幇と青幇と呼ばれる二大秘密結社となって上海一帯の裏社会を支配するようになった。第二次世界大戦後になって中国共産党によって上海が解放される以前には、黒社会とも称されていたそれらの幇に属する者の数は当時三百万前後だった上海の人口の四分の一にも及んでいたという。その秘密結社の一つ青幇の本拠地が置かれていたのは、ほかならぬこのフランス租界の大世界一帯なのだった。
青幇の大亨(大親分)であった黄金栄、杜月笙、張嘯林らは租界時代の上海では知らない者など誰ひとりいない存在だった。そのなかでも一番の頭領である黄金栄は、もともとフランス租界の警察の密偵を務めていたが、その有能な仕事振りをフランス租界行政当局に買われついには警察署長にまでのぼりつめた。そして、フランス租界の実質的な監察者であるその特権を最大限に活用し、幇会三宝(幇の三資金源)とうたわれた烟、賭、娼、すなわちアヘン、賭博、売春の三事業に奔走、驚くほどにほどに巨大な財力と権力とを築き上げた。その黄金栄が一九一七年にフランス租界内のこの地に造り上げたのが一大娯楽施設の大世界にほかならなかった。
大世界は映画館、劇場、演芸場、賭博場、各種レストランやクラブ、酒場、鍼灸院、さらには売春窟、アヘン窟までと、ありとあらゆる遊楽施設のある一大総合娯楽センターで、近くには競馬場(現人民公園)などの施設もあった。映画、京劇、中国雑技、演奏会、各種イベントにはじまり、諸々の賭博やアヘンなどの麻薬取り引き、秘密のものから公然なものにまでいたるまでの様々な売春と、人間の心身を慰め安らわせてくれたり、その本能的な興味や欲望を満たしてくれたりする催し物や行為の数々が昼夜を問わずに繰り広げられていたのである。
黄金栄がその財力にまかせて造営したのは大世界歓楽街ばかりではなかった。上海師範大学に隣接している現在の桂林公園は当時は黄家公園と呼ばれていて、黄金栄が自分の両親の墓碑などを築き置いた花園であった。その広さや園内の華麗きわまりない景観は租界時代における幇という組織の表裏両面にわたる絶大な支配力をこのうえなく象徴してもいた。
上海浦東で生まれたという杜月笙は地元の果物屋などで働いているときに青幇に入会、黄金栄にその能力と手腕を買われて頭角を現わし、黄金栄を継ぐ青幇の大頭目となった。国民党の蒋介石と通じ、フランス租界内の公館や東湖賓館、錦江飯店などが彼の上海での活動拠点になっていた。杜月笙は一九二九年に幇会の頭目が興した近代的な銀行としては初めての中匯銀行を設立、フランス租界内のアヘン業者や賭博売春業者のもつ莫大な資金を一手に吸い上げた。一九三四年に完成をみた中匯銀行ビルはその頃の上海においては有数の眺望を誇る高層建築でもあった。ちなみに述べておくと杜月笙は終戦直後に香港に亡命している。
浙江省生まれの張嘯林は杭州に出て裏社会に関係をもつようになり、その後上海に出て青幇に入会した。そしてアヘン取り引きなどを通じて黄金栄、杜月笙らに次ぐ青幇の大頭目となった。ただ、張嘯林は、杜が国民党支援のために上海を離れ重慶に滞在している間に日本軍と結んで自らが上海に君臨しようとしたため、国民党政府や杜一派の怒りを買って暗殺された。
幇会三宝と称されたアヘン、賭博、売春という三つの資金源のなかでもアヘンは幇の最大の資金源であった。金、杜、張の三人の大頭目は一九二五年に力を結集して大公司を設立し、上海のアヘン市場の独占を図りもした。租界各地には「燕子窩」という異名で呼ばれるアヘン窟が存在していたが、なかでも金陵東路や寧海東路一帯はアヘン窟の一大密集地であった。アヘンを取締まろうという動きも皆無だったわけではないが、現実問題としてそれを実践することはほとんど不可能な状況だった。中国人たちの住むいわる華界では軍閥警察がアヘン取り引きをバックアップしていたし、フランス租界内では黄が署長を務めるフランス警察が全面的にアヘン業者を支援して、租界自体が莫大な利益を得るという構図になっていたのだから、アヘン取締りに手をつけるなどできるはずもなかったのだった。
杜月笙がその理事長に就いていたころの大公司は事実上中国全土のアヘン市場を支配していた。一九三〇年代における大公司の年間アヘン取り引き量は最大で二〇〇〇トンにものぼり、フランス租界行政当局、公司、軍閥の三者のそれぞれに転がり込む収益は当時の中国の貨幣価値で一億元を悠に超えるものであったという。
漏れ響いてくるジャズの演奏に誘われてその夜石田が初めて訪れた大世界のお店は、それなりに風格もあり、そこに集うお客もその応対にあたる従業員も一見したかぎりでは洗練された感じの人々ばかりであった。だが、彼が我を忘れてジャズの演奏に聴き入っている間にも、大世界周辺のどこかでは数々の賭博が開かれ、アヘンの大取り引きの相談が進められ、さらには売春が行なわれているはずだった。しかも、西欧資本主義の洗礼を受け善い意味でも悪い意味でも爛熟しきったそんな上海の租界文化にも、暗い争乱の影が刻々と忍び寄り、その繁栄を次第に脅かすようになってきていた。石田が憧れの上海にわたり、同地においてその後六年にもわたる生活を始めたのはそのような時代のことであった。

絵・渡辺 淳
「マセマティック放浪記」2003年9月17日
ある奇人の生涯 (32)
看板書きから海軍武官府へ
石田が部屋を借りて住みついたのは上海県城に近いフランス租界の一隅だった。昔は宦官たちが住んでいたところであったという。フランス租界が設けられて間もない頃に造られた洋風住宅の中の一室で、既にかなり老朽化が進んでおり、けっして自慢できるほど綺麗な部屋ではなかったが、一人か二人で住むのには十分な広さがあったし、生活に必要な設備類も一通り揃っていたのでとくに不便は感じなかった。
その場所からは、フランス租界内の名所や豫園、上海商場、市内最大の繁華街南京東路、さらには散策に適した黄浦江沿いの外灘一帯もごく近かったので、暮らしやすいことこのうえなかった。部屋の中を自分で勝手に改造したり、壁面に好みの絵を描いたり装飾を施したりしても構わないというのも、彼にとってはたいへん都合のよいことだった。幼い頃から独特の感性と美観とを具え持っていた彼は、自分の住む部屋の空間を意表を突くようなデザインに仕立て上げるのが好きだった。
住居が決まると、その次ぎにやらなければならないのは仕事探しだった。多少の貯えはあったのですぐに困るようなことはなかったけれども、だからといって何時までも何もしないでいるというわけにもいかなかった。もちろんナーシャのこともすくなからず気にはなっていたが、消息を知るための手掛かりが皆無である以上、それについては最早どうすることもできなかった。そのままだと、日々の生活に追われたり、新たな人事との様々な出逢いを重ねたりするうちに彼女への切ない慕いも徐々に薄れ、やがてはその面影が想い出の世界の彼方へと遠のいてしまうのではないかとも危惧されたが、それはそれでやむをえないことかもしれないと考えもするのだった。
石田が上海で最初に手掛けた仕事は、たまたま親しくなったユダヤ系ロシア人の経営するお店での看板書きだった。中国人や上海在住の日本人を相手にするには漢字表記の看板や商品案内書きが必要だったし、欧米人相手には英語、フランス語、ドイツ語、ロシア語などによって記された看板や案内書きが不可欠であった。国際都市上海で商売の繁盛を図るには多様な言語を併記した各種の看板類がなくてはならなかったのだ。たまたまそれらの言葉に通じていて、しかも人一倍器用で美術的な感性を具えもった彼は、商店主たちにしてみればなんとも重宝な存在に違いなかった。
いっぽうの彼にはまた、ユダヤ系ロシア人の経営する店の仕事を手伝い、そのことを通して上海在住のロシア人たちと知り合いになれれば、ナーシャ一家の消息についてなんらかの情報が得られるかもしれないという淡い期待などもあった。この頃の上海には、ヨーロッパからのユダヤ人難民と並んでロシア人流民がすくなくなかったからである。石田がそんな仕事に手を染めるに至った背景には、いまひとつ彼なりのそんな思いもあったのだった。
石田の看板書きや商品案内書きの仕事振りはなかなかに好評で、ロシア人店主からもずいぶんと喜ばれた。ただ、ナーシャ一家のその後の消息に関しては結局のところ何一つ手掛かりになるような情報を得ることはできなかった。しかも、運命の悪戯とでも言うべきか、しばらくそのような日々を送っているうちに、彼の身に思わぬ転機が訪れることになったのだった。
ある夜のこと、彼はたまたま足を運んだ外灘地区のホテルのバーで外国人のお客二人を伴った日本海軍の軍人とおぼしき人物と隣席する機会があった。その日本人は抑揚のない棒読み調の英語で懸命に相手に話しかけようとしていたのだが、その英語は発音からしていかにもたどたどしく、二人の外人はずいぶんと理解に苦しんでいる様子だった。加えてまた、その軍人らしい人物は外国人らの話す英語をほとんど聴き取れずにいる感じでもあった。余計なお節介をするのもどうかとも思い、しばらくは素知らぬ顔をしていたのだが、あまりに相互の意思の疎通がうまくいかないのを見かねた石田は、ついついほっておけなくなり、敢えて助け舟を出すことにしたのだった。
突然石田が話に割り込んできたことに一瞬彼らは驚きもしたが、外国人たちは彼の流暢で品格のある英語と日本人離れした身振舞いにいたく好感を覚えたらしく、すぐさま安堵した様子でにこやかに応じてきてくれた。日本海軍の軍人とおぼしきその日本人もそんな石田の登場を渡りに舟と思ったらしく、とくに嫌な顔もすることなく彼のほうを振り向いた。そして、半ば苦笑するような調子で、「君、よかったら間に立って通訳してくれないかい?」と話しかけてきた。
そんな成り行きのもと、石田はごく自然なかたちでその場の会話の通訳を務めることになった。日本人のほうは海軍武官府に務める上村という海軍大尉で、二人の外人は英国商社勤務のイギリス人社員だった。話の内容そのものは国際情勢についての軽い情報交換程度のもので、興味深くはあったけれどもとくに極秘とするような性質のものでもなかったから、彼はことさら緊張したり気負ったりすることもなくその場の即席通訳を務めることができた。
上村海軍大尉はイギリス人たちとの話が一段落したあと、石田にそれまでの経歴を問い掛けてきた。石田は福岡高校を卒業してからしばらく東京で働いていたこと、そのあと小樽と台湾間の航路に就航していた貨物船氷川丸のタリーマンとなったこと、それから青島での生活を経て大連に移りそこでナショナル・シティバンク・オブ・ニューヨークの大連支店に勤務したこと、そして最近思うところあって上海に移り住むようになったことなどを手身近に伝えた。もちろん、横浜の山下公園で行き倒れになったこと、天津郊外の塘沽港で密かに乗り組んでいた貨物船から脱走したこと、青島で香具師の右腕となって働いていたことなどのような、不都合かつ誤解を招きそうなことについては一言も触れないでおいた。
一時的なことだったとはいえ石田にその場を助けけもらった上村大尉は、当然、彼の語学力に強い関心をもった。まだ日米開戦前のことだったがドイツやイタリアをのぞく欧米諸国との対立が日増しに深まっていた関係で、既にこの時期日本国内では敵性外来語廃止の気運が高まり、煙草の銘柄名の「ゴールデンバット」や「チェリー」などはそれぞれ「金鵄」や「桜」に改名された。また、音階を表わす「ドレミファソラシド」は「ハニホヘトイロハ」に、さらに野球の「ストライク」は「一本」にといった具合に外来用語廃止の動きはエスカレートしていきつつあった。だが、国際都市上海においてはおのずから事情は異なっており、在留邦人などに対してそんな馬鹿げた規制をするわけにもいかなかった。
上海事変後、日本軍部は、フランス租界や英米共同租界の外側に大きく広がっていた華人居留域に実質的な傀儡政権を誕生させて一帯の支配を強化した。そのため、この頃には日本軍部やその支配化の勢力に周囲を取り巻かれ、フランス租界と米英共同租界はすっかり孤立したかたちになっていた。だが、それでもなお上海の主要部を占めるそれらの租界地を支配し日本化することはまだできずにいた。
それどころか、外国、なかでも欧米諸国の動向を知り、それらの国々に関する諸々の情報を収集するうえで、欧米要人との直接間接の接触のなお可能な上海という都市は、日本軍部にとってもたいへん重要な存在だった。そして、その情報収集の中枢にあったのが当時の日本海軍武官府であった。当然のことだが、そのためには、外国語、なかでも英語やフランス語、ドイツ語、ロシア語などのできる日本人で、しかもそれなりに信頼のおける人材がどうしても必要であった。だから、上村大尉の目に、英語のほかフランス語やロシア語にも通じる石田との出逢いが願ってもない幸運に映ったのはごく自然なことであった。
それからも何度か石田と会いすっかり親しくなった上村大尉は、しばらくすると、日本人には稀なその実践的語学力を活かし、ぜひとも海軍武官府で働いてくれないかと相談をもちかけてきた。もしも海軍武官府側が石田のそれまでの経歴行状をあらかじめ詳細に調べ上げていたならば、さすがにこのような勧誘はなかったかもしれない。しかし、日中戦争が激化し米英との対立が日増しに深刻化していく状況の下では、海軍武官府当局といえども、そこまで調べを進めて当該人物が適格であるか否かを判断する時間的余裕も組織的能力も持ち合わせてはいなかったのであろう。
もちろん、石田は軍隊というものがけっして好きなわけではなかった。だが、海軍武官府の責任者が自分の能力を認めてくれたうえに、仕事まで与えくれると申し出てくれたことについては、けっして悪い気分はしなかった。ユダヤ系ロシア人の経営する店で看板書きや商品案内書作りをするのも捨てたものではなかったが、外国語の翻訳や通訳に関わることのできる海軍武官府での仕事は知的という意味でもより魅力的だった。それに、海軍武官府で働いたほうが収入も大きく生活も安定するにきまっていたし、まだ上海に知人や友人がほとんどいない状況を考えると、様々な人脈をつくるうえでもそうしたほうが得策であるように思われた。また、陸軍などの幹部に較べて海軍の幹部たちのほうがずっと発想が自由かつ柔軟であることにもすくなからず好感をもつことができた。
結局、石田は上村大尉の申し出を受け入れ、日本総領事館内や日本租界の海軍陸戦隊本部に拠点の置かれている海軍武官府で働くことになった。最初に彼に割り当てられた仕事は主に英字新聞各紙や各種英文雑誌類のモニターであった。欧米の英字新聞や英文雑誌に隅々まで目を通し、欧米諸国の軍事情勢や政治経済情勢にかかわる記事、日本に対する海外世論の動向や対日批判、各国の対日政策方針などについての記事を的確にピックアップして翻訳整理し、それらを情報収集の担当官に提出するのが具体的な仕事の内容であった。ときには担当官から打ち合わせの場に呼び出され、私的な意見を訊かれたり特定の記事についてのより詳細な説明や関連情報を提供するよう求められたりすることもあった。
全体としては地味でそれなりに根気のいる仕事ではあったが、判断ミスなどが原因でなんらかの責任を直接取らされるような立場ではなかったし、世界の趨勢をいながらにして垣間見ることもできる特殊な業務だったから、飽きたり疲れたりするようなことはほとんどなかった。それに、日常業務を通して文化や芸術に関する海外の様々な記事などを読み漁ることも可能だったので、ある意味で石田には願ったり叶ったりの一面もある仕事だった。むろん、ユーモアや風刺に富んだ記事類を目にするのもいつものことだったから、たとえそれが日本人を痛烈に風刺したようなしろものであったとしても、仕事中にそれらを見ながら人知れず笑い転げることなどもしばしばだった。

絵・渡辺 淳
「マセマティック放浪記」2003年10月1日
ある奇人の生涯 (33)
ケーキと札束の関係は?
海軍武官府で働いていた頃の石田に対する待遇や報酬は、当時上海に住む一般民間人のものからすると相当に恵まれたものだった。あるとき老翁は、こちらの問いかけに応じ、ちょっとしたエピソードを交えながらそのあたりのことを面白可笑しく語ってくれたことがある。
「海軍武官府で働いていたときの給料はよかったんですか?」
「ええ、仕事のほうは頭脳労働で労働環境にも恵まれていましたし、報酬もけっして悪くはなかったですよ。そのときの給金を現在の貨幣価値に換算するのはちょっと難しいんですけどね」
「当時のお金でどのくらいの額だったんでしょう?」
「それがですねえ、なにしろ給料は軍票で支給されていましたからねえ……。その頃はすでに上海においては日本軍部の支配力がずいぶんと強くなっていましてね、日本軍が発行する軍票が一種の通貨として通用するようになっていたんです」
「軍票ですか……、なんだかピンときませんが……」
「軍票は当時の日本紙幣に似せたデザインでしたが、表面に赤字で軍用手票という文字が印刷されていました。確か百円、五拾円、拾円と、いろいろな額面の軍票がありましたね。もっと小額の軍票もあったかもしれません」
「そうだったんですか……、いまの時代では考えられない話ですね」
「支給された軍票は現地通貨に換えることもできたんですが、中国の通貨に換金するとびっくりするほどに分厚い札束になったりてしまいましてね……、そう、七・八センチほどの厚さのずっしりした札束なんかにもね。お蔭でずいぶんと贅沢な生活ができるようになりましたよ」
「そうですか、でもあんまり分厚い札束になってしまうのも困りますよね。持って歩くのも容易じゃないでしょうから」
「そうそう、それでまた想い出しましたよ。ちょっとした失敗談をね」
石田翁は意味ありげな苦笑を浮かべながらいったん言葉を切ると、テーブルの紅茶を一口すすり、そのあと私がお土産に持参したケーキにフォークを入れながら呟いた。
「そうなんですよ、ケーキ、あのケーキのことを時々想い出すんですよ……」
「はあ?……軍票の話からいきなりケーキの話になっちゃったんですけど、なにかそれら二つに関係でもあったんですか」
さっぱり事情を呑み込めずに困惑顔でそう問い返すと、老翁はケーキを頬張りながら悪戯っぽく笑って言った。
「札束とケーキとは直接関係有るような無いような話なんですがね。海軍武官府で働くようになってしばらくしてからのことですが、仕事の帰りに知人からケーキを五・六個貰いましてね。当時はなかなか手にはいらない上等のケーキで、それを箱ごと風呂敷に包んで帰途についたんですが、その途中で軍票を地元通貨に換金しました。さっき話したように、ずっしりした分厚い札束になっちゃうんですから、とても財布には収まりきれません。たまたま鞄はもってませんでしたから、紙袋に入った札束をケーキの箱と一緒に風呂敷に包んだんです」
「ははははは……、それでようやくケーキと札束の関係が納得できましたよ。確かに関係が有るあるような無いような話ですね。まあ、ケーキのいい話と言いますか……」
こちらがそう茶々を入れると、老翁は景気のよい話はそこまでだとでも暗示するような表情を見せ、それからまた口を開いた。
「夕刻ちかくのことだったんですがね、南京東路にさしかかった時、突然、『ドロボーッ!、ドロボーッ!』って叫ぶ女の声がしたんですよ。振り返って見ると、必死の形相で抵抗する中国人老婆の手から若い男が包みのようなものひったくろうとしているところでした。すぐに私はそのほうに駆け寄よったのですが、もう一息というところで男はその老婆から包みを奪い取ると勢いよく走り出しました。老婆はまた『ドロボーッ!』と一声叫び必死に男を追いかけようとしました。でも、足が思うように動かないみたいなんです。履いている靴の形やその足の形からして彼女が纏足であることは明らかでした」
「それで、石田さんが代わりに?」
「そうなんです。咄嗟の判断で老婆に自分の風呂敷包みを預けると、私は男のあとを追って駆け出しました。『まてーっ!、こらまてーっ!』って叫びながらね。でもねえ、『まてーっ!』って言われて、はいそうですかって待つ泥棒なんかいるわけがありませんよね。なんであんな時に『まてーっ!』なんて叫ぶんですかねえ」
「ははははは……、でも、『はーい、なんでしょうか?』なんて返事が戻ってきたりしても逆に困ってしまいますものね」
「相手が曲がり角などで逃げ場を探してキョロキョロしたりし、そのぶん逃げ足が遅くなったこともありましてね、ひったくり現場から四・五百メートルほど走ったところでなんとか追いつきかけたんですよ」
「首尾よく男を御用にして一件落着ってわけにはいかなかったんですか」
「落着するにはしたんですけど、旅客機が海中か山中に不時着したような落着の仕方でしたよ」
「はあ?……いったいそれでどんな落着の仕方を?」
「なんとか私が追いつきそうになると、男は老婆から奪った包みをいきなり路上に放り投げ、また一目散に逃げはじめました。私がその包みを拾っている間に男のほうは角を曲がりとうとう姿が見えなくなってしまったんです。ただ、ともかくも包みを取り返すことができたので、まずはよかったと思いながら老婆の待つところに戻ったんです」
そこまで話が進んでくると、さすがにその結末は私にも読めてきた。
「するともう老婆はそこにいなかったってわけですね!」
「そうなんです。どこを探しても彼女の姿が見えないんですね。しばらくは変だなあと思いながらあたりを見回していたのですが、そのあとようやく、あっ、やられた!……と思ったんです。慌てて手元に残った包みを開けてみると、なんと中身はボロキレと紙屑と小石だけだったんですね」
「グルだったわけですね。でもなかなかの策略と演技力ですね!……なにからなにまで計算づくというわけで」
巧妙な手口にいささか感心もしながら話の先を促すと、石田翁は自嘲するかのようにさらに話し続けた。
「あとでよくよく考えてみますとね、そもそも老婆が『ドロボーッ!』って日本語で叫んだところからして変なんですよ。あの老婆は中国人だったから、反射的に出た言葉なら中国語になるはずなんです。あれは、あらかじめ私が日本人だってわかっていてやったことですね。それに、逃げたほうの男だって、ほどよく私を引きつけることのできる速さで逃げておいて、そこで包みを投げ出したんです。相棒の老婆が姿を隠すことができるだけの時間稼ぎをしてね」
「なるほど、それはしたたかですねえ。咄嗟のことだから、そこまで考えている余裕なんかありませんものね。ただ、そうだとすると、相手は石田さんが軍票を現地通貨に換金しているあたりから目星をつけていたんでしょうか?」
「そうだったのかもしてません。換金したのは南京東路のその現場からそう離れていないところでしたから……。もしかしたら、かなり以前からマークされていたのかもしれません。海軍武官府から住まいまでの帰りには毎日ほぼ同じルートをとっていましたからね」
「それじゃ石田さんも相当に頭にきたんでしょうね!」
「なんとしもその老婆を助けてあげなきゃっていう義侠心をおこして必死に男を追いかけたわけですから、そりゃ腹も立ちましたよ。怒りがおさまったあとも、悲しくなったり淋しくなったりしましてね。まあ、騙されてお金を盗られたのは初めてじゃなかったわけですけれども、上海に行ってから個人的に親しくなった中国人たちは皆信頼できる人たちだっただけにとても残念で……」
「一口に中国人といっていも、当然、いろいろな人がいたんでしょうからね」
「まあ、いぽうでは日本人が中国を侵略し、いたるところで好き勝手に振舞い中国人を弾圧していたわけです。海軍武官府で英字新聞などをモニターさせられていたわけですから、上海の日本人居留民たちとは違って、海外には日本の中国侵略を批判する厳しい世論があることも知ってました。ですから、あとになって考えてみると、仕返しに何をやられても文句は言えないという一面もあったんですね。ただ、そうは言っても生身の人間ですから、騙されたことはやっぱり悔しかったですね」
石田翁はそう言って苦笑した。いまでは海千山千の風貌をそなえたその口からそんな昔の失敗談を聞くのは、また一味も二味もあることだった。
「まんまと大金をせしめたその一味はさぞかし大喜びしたことでしょうねえ」
「そうかもしれませんがね、実を言うと、こちらにすればお金よりもケーキを盗られたことのほうが残念でねえ……」
「はあ?……ケーキを盗られたことのほうがショックだったですって?」
「ははははは……、そうだったんですよ。お金のほうはね、結構余裕がありましたし、海軍武官府で軍票支給してもらえばまたいくらでも手にすることができたんですが、当時の上海ではあの特製ケーキはたとえお金があってもなかなか購入できないものでしたから、そりゃ悔しかったですよ」
「なんとまたそれは意外な!」
「その晩は家に帰ってからもケーキのことばかりが頭にこびりついて、床に就いてからもなかなか眠れませんでしたね」
「その頃、二人の盗人どもはケーキでも食べながら、嬉々としてお金の勘定でもしてたんでしょうね」
「あれからも何度となくそのケーキの夢を見たりしましたよ。そうでなくても、ケーキを食べる機会があるごとにあの日のことを想い出しましてね。どんな美味しいケーキを食べても、あの時のケーキの味には及ばないような気がしましてね」
「だって石田さん、そのケーキを実際には食べてないんですから、味なんかわかるはずないでしょう?」
「理屈上はそうなんですがね、妙なものでなぜかそんな思いがしてならないんですよ。食い物の恨みは恐ろしいって言いますけど、本当ですね、ははははは……」
石田翁はそう言って笑いながら、その苦い想い出話に区切りをつけた。

絵・渡辺 淳
「マセマティック放浪記」2003年10月8日
ある奇人の生涯 (34)
緊迫する世相の中で
石田が上海に渡った翌年の一九四一年には満州映画協会の専属女優李香蘭と東宝の人気スター長谷川一夫とが共演した映画「支那の夜」が日本国内で大ヒットし、その哀調を秘めた主題歌「蘇州夜曲」は国内外で大流行をきたした。その頃すでに上海を拠点に活動していた李香蘭はこの年の二月に東京日劇に出演したが、各種規制の厳しくなってきていた国内事情にもかかわらず開場一時間前から観衆が殺到し、劇場周辺は大混乱に陥った。
その顔立ちからして当時は中国人だと思われていた彼女は、李香蘭という女優名で一世を風靡したのだが、実は満州生まれの日本人であった。山口淑子という本名が明かされたのは戦後になってからのことで、その後彼女は母国で国会議員となって活躍するようになるのだが、当時はまだごく一部の関係者を除いてその素顔を知る者はいなかった。のちに上海で李香蘭と直に接する機会に恵まれることになる石田にとっても、その時はまだ彼女は雲の上の存在に等しかった。
上海に渡った翌年の秋のこと、海軍武官府上司の配慮によって、石田は海軍の飛行艇に乗り一時的に本国に帰国する機会を得た。初めて乗る飛行艇の乗り心地は想像していたほどに快適とは言えなかったし、眼下の眺望を存分に楽しむことのできるような状況でもなかったが、現代と違い航空兵をのぞいて特別なポストにでも就いていないかぎり航空機に搭乗することなど不可能な時代だったので、彼の感動はひとしおだった。荒波を掻き分けて海上を航行する船などとは違って、驚くほど短時間で眼下に広がる東シナ海を一跨ぎし、本土上空へと到達したのも驚きだった。
ごく短期の本土滞在ではあったが、この時久々に目にした日本社会の変容ぶりに石田は少なからず衝撃を覚えた。彼が大陸に渡って生活するようになってから四年足らずのうちに、日本の社会は信じ難いほどに厳しい統制下におかれてしまっていたからだった。新聞報道や人々の噂によってある程度予想はしていたものの、上海という当時東アジアで一、二を誇る国際都市に住みはじめた者の目からすれば、軍国色一色に染まった日本社会の有様は善くも悪しくも異様そのものに感じられた。
それまでの小学校は国民学校と改名され、「皇国民の錬成」が初等教育の第一目標に掲げられるいっぽう、児童らは少国民などと呼ばれ、錬成の名のもとに学校生活のすべてを管理統制されるようになっていた。また、日中戦争の長期化と拡大にともなう物資統制や大量徴兵のため、各種肥料や農業労働力が極度に不足し、それに旱魃による不作なども加わって米穀の生産量が激減していた。そのため厳しい配給制度が設けられ、米穀類ばかりでなく、木炭、酒、砂糖、マッチ、食用油などの生活用品すべての流通が通帳制や切符制によって管理されるようになっていた。
巷では「八紘一宇」の精神とその延長上にある「進め一億、火の玉だ!」のスローガンが高らかに唱えられ、共同体の強化と思想統制、国民の相互監視を狙った隣組制度なども発足していた。また、厚生省は「優生結婚報国」の文字入りポスターの掲示を全国的に展開し、強壮な日本国民を育てるため「健全な男女同士の結婚」を奨励、そのために国民優生法という法律を制定施行するまでに至っていた。
そんな国内の変貌ぶりをつぶさに目にした石田は、内心、もしも自分のような人間がこのまま本土に定住し生活するようになったりしたら、軟弱な敵性思想をもつ非国民として徹底的に糾弾されることは間違いないだろうと思うのだった。そして、奇跡とも思われる気まぐれな運命の導きによってたまたま自分が上海という異郷の地に在留していることを心底有り難く感じもした。本国の人々の容易ならぬ生活状況を無言の内に察知した彼は、息苦しく逼迫した日々を送る母親と妹二人の心中を想い、彼女らを上海に呼ぼうと決意した。いったんそう意を固めると三人を説得しただちにその手筈を整えるのにそう時間はかからなかった。
幸いこの時期邦人が大陸に移住することは国策として奨励されてもいたし、とくに身内が先に大陸に居留している場合などはとくに渡航が容易だったから、格別問題になるようなことは何もなかった。当面、経済的にも安定はしていたから、しばらくは家族の面倒をみることも可能であった。一時帰国を終え石田が上海へと戻ってしばらくしてから、彼の家族三人は上海へと渡ってきた。彼は家族との同居は考えず、別に部屋を探してやりそこに彼女らを住まわせた。異国の地への突然の移住であったにもかかわらず、家族らの顔が本土にいる時よりも明るく生気に満ちて見えることが彼にはとても嬉しかった。
しかしながら、石田の家族が上海に移ってきて間もないこの年の十月、日本国内で想わぬ事態が発生した。いわゆる、ゾルゲ・スパイ事件の発覚と、それに伴う二人の大物被疑者の逮捕がそれであった。朝日新聞社の特派員として上海に派遣されていた尾崎秀実は、コミンテルンから対日情報収集のために同じく上海に派遣され、中国の左翼文化運動にも加わっていたリヒャルト・ゾルゲと知り合い、深く意を通じ合うようになった。その後日本に渡ったゾルゲは駐日ドイツ大使館顧問の要職におさまり、いっぽうの尾崎は近衛内閣の嘱託となった。
尾崎秀実は日本政府の軍事政策とそれに基づく日本軍の動向を察知して事実上ソ連のスパイだったゾルゲに伝え、ゾルゲを介してその情報はさらにソ連当局へと伝達された。リヒャルト・ゾルゲの最大の任務は、ソ連がドイツと開戦した場合に日本が日ソ中立条約を破棄して背後からソ連侵攻に踏み切るかどうかを探知することであった。ゾルゲは尾崎秀実を通して得られる情報やドイツ大使館の動向、日本国内世論の論調、日本の対米関係などを総合して一九四一年中には少なくとも日本軍の対ソ侵攻はないと判断し、その旨をモスクワのソ連政府に打電通報したのだった。このゾルゲからもたらされた情報により、ソ連は全軍をヨーロッパの対独戦線に投入することができたとも言われている。
関係者の動向を内偵しスパイ容疑を固めた日本政府当局は、まず尾崎秀実を検挙、続いてリヒャルト・ゾルゲを検挙し、治安維持法、国防保安法、軍機密保護法等違反の罪状で告訴した。ゾルゲ・スパイ事件の発覚は必然的に外国人との接触を持つ日本人の監督と監視視強化へとつながり、当然その影響は上海の日本人社会にも及ぶところとなっていった。尾崎秀実とリヒャルト・ゾルゲはそれから二年四ヶ月後の一九九四四年二月に処刑された。
むろんゾルゲ事件の詳細については何も知らされていなかったし、たとえある程度の状況を知っていたとしても、直接その事件が海軍武官府での自分の仕事に影響を及ぼすことになろうなどとは、その時の石田には想像もつかなかいことだった。だが、ずっとあとになってからよく考えてみると、上海の海軍武官府での仕事がなんとなくギクシャクしはじめたのはゾルゲスパイ事件発覚後しばらくしてからのことであった。まず外部から持ち込まれてくる英文関係の情報資料が激減した。さらにまた、なぜか海軍武官府の軍人上司との意思の疎通がそれまでほどスムーズではなくなってきた。時折、上海在住の欧米人と接触して米英両国の世論や軍事的動向についてなんらかの情報を直接聞き出せないかとも持ちかけられたが、その指示にはどこか取ってつけたようなところがあり不自然な感じだった。そもそも、諜報活動のイロハも知らない素人の身に重要情報の収集などできるはずもなかった。
十二月に入ってほどなく、突然石田は海軍武官府での定期的な仕事を解かれた。業務上助力が必要な時は臨時で働いてもらうようにしたいし、なにかの都合で海軍武官府による身分保証等が必要な場合にはいつでも遠慮なく相談にくるようにとのことではあったが、表向きのそんな言葉の裏になにか特別な事情があるらしいという推測だけはついた。ただ、武官府での定期業務を解かれたほんとうの理由については知るよしもなかった。
ずいぶんと時間が経ってからすべての事態が明らかになるのだが、この時期、上海の海軍武官府や日本領事館幹部、駐留日本陸軍幹部らは大変な緊張状態に置かれいた。かなり以前から対米関係が一触即発の状態にあるらしいことがそれとなく伝わってきていたからである。ゾルゲ事件のような事件の芽をあらかじめ摘むためにも、重要情報をもつ日本人が外国人といたずらに接触して情報を流すことや、逆に日本にとって不利な情報などを日本人が外国人から伝え聞くようなことだけはどうしても防がなければならなかった。
また、近々日米が開戦するに至れば、その時点で上海の英米共同租界やフランス租界には日本軍が進駐し、事実上その支配化におかれることは必然だった。そうなると、もはや海軍武官府による上海での米英諸国の情報収集が意味をなさなくなるのも当然の成り行きだった。さらに、上海が完全に日本軍の支配下に入れば、本土からそれまで以上に日本人が大量流入するのは目に見えており、いっそうの情報の管理統制を進めていく必要上からも、海外情報の収集能力の高い民間人が米英メディアなどの重要情報源に接することができるような状況は極力排除しなければならなかった。
石田自身は武官府での定職を解かれた理由を「自分にはジェームズ・ボンドばりのスパイの能力がなかったからですよ」と笑いながら説明してくれたが、突然の解雇通告の背景にはそのような抜き差しならぬ様々な国家的事情があったものと思われる。海軍武官府での高報酬の仕事のため当面の暮らしを凌ぐげるくらいの貯えはあったから、すぐにも別の仕事を探さなければならないような状況ではなかったが、いずれにしても新たな仕事の展開を考えなければならないことだけは確かだった。
そして、「ニイタカヤマノボレ1208」の暗号打電に続き「トラトラトラ」の暗号返電が空中に飛び交うことになった運命の日、一九四一年十二月八日が訪れたのは、彼が海軍武官府での英文モニターや英文翻訳の任務を解かれてからわずか四日後のことだった。

絵・渡辺 淳
「マセマティック放浪記」2003年10月15日
ある奇人の生涯 (35)
仏印進駐から真珠湾への道
石田が上海に渡った一九四〇年九月から海軍武官府での職を解かれた一九四一年十二月初旬にかけては、たまたま日本の外交が重大な岐路に立たされていた時期でもあった。近衛内閣府や陸海軍統帥部においてどのような外交政策議論がなされ、いかなる国際情勢の下で国策の検討と選択がなされつつあったのか当時の一般国民は知る由もなかったが、様々な難問が交錯するその対外工作の舞台裏は容易ならざるものがあった。
激化するいっぽうの日中戦争を一刻も早く制するために、日本軍は当時フランス領だった北部仏印(北ヴェトナム)から華南を経由する蒋介石政府支援物流ルートを遮断する必要に迫られた。この時期すでにフランスはドイツに降伏、事実上その支配化におかれていた関係もあって、仏印総督は日本との宥和を図るのが得策と判断、蒋介石支援ルートを遮断してほしいという日本政府の要請を受け入れた。そして、日本軍は支援ルートの遮断が厳守されているかどうかを確認するという名目で一九四〇年九月北部仏印に進駐した。
ドイツの本土侵攻を怖れていたイギリス政府も、日本との関係好転を狙い、同年の七月にビルマから中国雲南省を経由するもうひとつの蒋介石支援ルートを遮断することで日本政府と合意した。しかし、日本軍部による弾圧と暴政からの中国人民の救済や自国の通商権益確保の意図などもあって、アメリカだけは強硬な姿勢で対日政策を展開、日本軍の中国からの完全撤退を主張するいっぽうで、物資や資金に窮する蒋介石政府を全面的に支援した。そんなアメリカの対日強硬姿勢に促されたイギリスは、折からの独ソ開戦によりドイツ軍の自国侵攻はなくなったという判断も契機となってそれまでの対日宥和政策を対決政策へと転換、十月にはビルマからの蒋介石支援ルートを再開した。そして、蒋介石政府に対する各種軍需物資の補給を強化したほか、アメリカの対中国一億ドル借款供与にならいイギリスも一千万ポンドの借款資金の供与に踏み切ったのだった。
日中戦争の泥沼化に加え、鉄・石油・ゴム輸出制限などをはじめとする米英の対日強硬政策によって追い詰められた日本政府は、いっぽうでは日米交渉を友好的に進展させようと画策しながらも、一九四一年七月、南部仏印(南ヴェトナム)サイゴンへの進駐を強行した。南部仏印一帯に産するゴムと米を確保することが当面の日本政府の狙いだったが、いざというときに備え、石油資源に恵まれた蘭印(オランダ領インドネシア)やゴム資源などの豊富な英領マレーシア侵攻の足掛かりをつくるのも南部仏印進駐の目的だった。
かつて協調外交政策を提唱したがその政策が様々な圧力要因によって破綻、政界を引退していた幣原喜重郎などは、ことの重大さを察知し、当時の首相近衛文麿に面会して南部仏印進駐策を必死に諌めようとしたが、国威発揚と国民の団結を標榜する軍部に担ぎ上げられるのみで、実質的な外交判断能力も政策決定権も持ち合わせていなかった近衛にはもはや事態の進行をとどめることなどできなかった。
欧米列強国の東南アジア植民地を睨んだ日本政府のこの南進政策に当然米英両国は猛反発し、直ちにアメリカは自国内の日本資産を凍結、それにならってイギリスとオランダも日本資産の凍結を敢行した。さらに、それからほどなくアメリカは日本への石油輸出の全面禁止を断行した。アメリカ、イギリス、中国、オランダによ対日包囲網は、英語表記によるそれらの国名の頭文字を順に並べとってABCD包囲陣などとも称された。
国益上からしてもアメリカはこの時期すでに対日宥和政策をとる必要がなくなってきていたのだが、アメリカがそれほどの強行策に出ることはあるまいと踏んでいた近衛らは、ここに至って初めて予想以上の事態の悪化に驚いた。ようやくことの重大さを悟った近衛文麿は滞日十年余の知日家だった駐日米国大使ジョセフ・グルーの仲介でルーズヴェルト米大統領と頂上会談を行ない、妥協点を模索して事態の収拾を図ろうと考えた。アメリカ大使のグルー自身も、極端な国粋主義者と狂信者を除く大多数の日本人は、ある程度日本の顔が立つ合意が成れば満州を除く中国各地や仏印からの撤兵に賛成する判断していた。グルーの働きかけもあって、ルーズヴェルトのほうも野村三郎駐米大使に対し、「アラスカのジュノーにおいてなら近衛首相とともに三、四日を過ごし、お互い誠意をもって話し合うことは可能だ」という趣旨のメッセージを送っていた。
近衛文麿はグルーと協力し日米開戦を回避しようと必死に画策したらしい。満州を除く中国と仏印から期限つきで撤兵すること、アメリカが対独戦争を開始してもドイツに加担しないこと、撤兵完了後には新たな日米通商条約や航海条約を締結する用意があること、さらに両国間の交渉が合意に達した場合には詔勅をもってその事実を国民に知らせることなどを米国側に内々打診もしていたようである。
しかしながら、当時の米国務長官の極東顧問スタンレー・ホーンら対日強硬論者の働きかけでハル国務長官一派は対日宥和政策の放棄を大統領に進言、ルーズヴェルトがその提唱を受け入れた結果、アメリカ政府の対日姿勢は豹変し、一方的な日本の妥協がないかぎり、日米開戦の回避は困難な状況に立ち至った。
日本に対する石油輸出の全面禁止は、結果的に日米開戦に慎重な態度をとっていた海軍の態度をも一変させた。石油の全面供給停止が続けば二年以内に国内の石油備蓄は底をつき、海軍の艦船そのものの航行が不能になることは目に見えていた。また、艦船や航空機建造能力をはじめとする日米両国の国力差を考えると、時間が経つほどにその力関係に較差が生じ、日本が不利になることは明らかだった。自軍の戦闘能力が奪われ一方的に封じ込められることを危惧した海軍はついに、対米開戦覚悟で石油資源確保を狙う蘭印侵攻もやむなしと決断するに至ったのだった。
陸海両軍の首脳が対米開戦論に傾くなかで開かれた九月六日の御前会議では、今後とるべき国策についての討議が行なわれた。諸資料によると、あらかじめ用意された政策原案は以下のような三項目からなっていた。
(一) 自存自衛のため十月下旬の対米英蘭戦争開戦を目途にして万全の準備を行なう。
(二) 十月下旬開戦の準備に並行して外交手段を尽し米英に日本の要求を呑ませる。
(三) 外交交渉を尽して事態の打開を図り、十月上旬頃に至ってもなお日本の要求が貫徹できそうにない場合には直ちに対英米戦争の遂行を決断する。
それらが開戦を含みとした国策原案であったことは言うまでもない。どう見ても戦争準備完遂が最優先であるとしか思われないこの国策案に、原嘉道枢密院議長は、「戦争準備遂行が主論なのか、外交交渉重視が主論なのかを伺いたい」とその立案者の真意を質そうとした。しかしながら陸海両統帥部の総長は沈黙を守り、その質問に正面からは答えようとしなかった。その時、昭和天皇は原枢密院議長の疑問をもっともだと擁護して両総長の沈黙に遺憾の意を顕にし、「四方の海皆同胞(はらから)と思ふ世になど波風の立ち騒ぐらむ」という明治天皇の歌を引き合いに出しながら、自分も極力平和を望んでいると表明したと伝えられている。
主戦派の陸海両軍統帥部首脳はその天皇の意思表明に狼狽しきったと言われるが、その言葉にもかかわらず、結局、その原案はどちらともとれる曖昧な内容のまま御前会議において国策とすべく決定がなされた。もともと曖昧なままで原案を通すのが軍部主戦派の当初からの狙いでもあったのだった。
この国策決定により、近衛内閣は十月中旬まで幾度か日米交渉の開催を模索し続けたが、ついに両国間の調整は不調に終わり、外交交渉は暗礁に乗り上げた。そのような八方塞がりの状況を前にして陸軍は即刻開戦をすべく激しく近衛首相に迫ったが、海軍のほうは、対米戦争やむなしという空気には包まれつつあったものの自らの責任で開戦に踏み切るだけの自信はなく、最終的な決断を近衛首相に一任するという態度をとるに至った。
万策尽き果て開戦の決断を迫られた近衛だったが、それでもなお対米英戦争の道を選ぶことが適切か否か判断がつかなかった。その信憑性は定かではないが、伝えられるところによると、そんな煮えきらぬ近衛の様子を苦々しく思った東條英機陸軍大臣は、「人間たまには清水の舞台から飛び降りることも必要ではないか」と迫ったという。それに対して近衛は、「個人としての人間なら人生のなかでそういうこともあるかもしれないが、一億の国民と万邦無比の国体を有してきた国家がやることではない」と反論したと言われている。結局、対米開戦か否かを自ら決断することを放棄した近衛内閣は十月十八日総辞職した。
後継内閣の首班を誰にするかで重臣会議はもめにめたが、実質的な首相奏薦権をもつ内大臣の木戸幸一の支持により、結局、東條英機内閣が成立、東條は首相のほか陸相と内相をも兼任することになった。皇族の中には東久邇宮のように、「東條は日米開戦論者である。このことは陛下も木戸内大臣も知っていることなのに、木戸がなぜ開戦論者の東條を後継内閣の首班に推薦し、天皇陛下がなぜこれをご採用になったか、その理由が私にはわからない」という批判的な意見を持つ人もあったけれども、東條内閣成立の流れをおしとどめることはできなかった。
実質的な国策決定権を握っていた陸海統帥部では開戦の準備が進められており、大本営連絡会議においてはおよそ次ぎのような内容の三案が提出された。
(一) 戦争は極力回避し、将来の巻き返しを期しながら当面はひたすら難局に耐える。
(二) 開戦を直ちに決意し、政治や戦略上の諸々の施策を開戦準備に集中する。
(三) 戦争決行の決意のもとに作戦準備を完璧に調整遂行するいっぽうで、外交政策を続行し、それにより米英との妥協の道を模索するように努める。
一案にまっさきに反対し、二案を強く支持したのは陸軍同様の判断に傾いていた海軍の長野修身軍令部長であったが、他の海軍関係者が外交政策含みの疑義を呈し、結局この会議では折衷案の第三案を採択するに至った。そして、外交交渉展開のタイムリミットは十一月三十一日二十四時までと決定された。また、対米外交交渉成立の条件として、南部仏印からの撤退をせずに日米相互妥協を図る甲案をまず提示し、米国がそれを呑まない場合には、南部仏印からの撤収と引換えに対日石油禁輸を解禁するという乙案を提示するという方針がまとめられた。そしてその会議で決定した内容をもとにして以下のような趣旨の「帝国国策遂行要領」が定められた。
一、 大日本帝国は現状の危局を打開して自国の存続と自衛を完うし、大東亜共栄圏の新秩序を建設するため、この際対英米蘭戦争を決意し、次ぎのような処置をおこなう。
(一) 武力を発動する時期を十二月初頭と定め、陸海軍は作戦準備を完遂する。
(二) 対米交渉は別記の要領(前述の甲乙両案提示のこと)に基づいておこなう。
(三) 独伊との提携の強化を図る。
(四) 武力発動の直前に泰(タイ)との間に軍事的に緊密な関係を樹立する。
二、 対米交渉が十二月一日午前零時までに成功するならば、武力の発動を中止する。
大東亜共栄圏の建設という東南アジア侵攻を正当化する大義名文が掲げられたのはまさにこの時であった。そしてこの国策要領に従い東條内閣は来栖三郎をアメリカに特派し外交交渉に当たらせたが、アメリカ側は日本の暗号電文を傍受解読していたため、交渉以前から日本側の用意している甲乙両案の内容を知っていた。そして、すでに対日強硬姿勢に転じていたアメリカ国務長官コーデル・ハルは十一月二十六日、来栖に対して「ハル・ノート」として知られる次ぎのような厳しい対日要求を突きつけた。
(一) 中国及び仏印から日本の陸海軍及び日本の警察は全面的に撤退すること。
(二) 近隣国としての日中間の特殊かつ緊密な関係を放棄すること。
(三) 日独伊三国同盟を破棄すること。
(四) 中国における蒋介石政権以外の一切の政権を否認する。当然、満州国や上海周辺の汪精衛政権もその対象に含まれるものとする。
日本の傀儡国家とはいえ満州国だけは是認しようという動きが国際的には高まってきてもいた時期だけに、日本の大幅な譲歩を求めるこの米側の要求は予想以上に強硬で当時の日本としては到底受け入れられるようなものではなかった。そして、外交による平和的な事態の収拾はこの時点で遂に絶望的となったのだった。天皇の意向によって召集された最終的な重臣会議において、米内光政は、「ジリ貧を避けようとしてドカ貧に陥らぬよう、十分の御注意を願いあげます」と奏上、また若槻礼次郎は、「現下の状況で戦争をすることは憂慮に堪えない」と言上もしたというが、結局、趨勢を抑えることはできなかった。
十二月一日の御前会議において最終的に対米開戦が決定され、天皇からも、「このような事態に至ったのは残念だがやむを得ないことである。どうか、陸海軍は十分に協調して事態に対応するように」という趣旨の言葉が発せられた。
アメリカも開戦が間近なことは察知していたが、十二月八日を期して日本軍はマレー半島に上陸し、千島列島のヒトカップ湾を密かに発していた日本海軍起動艦隊は、「ニイタカヤマノボレ」の暗号電指令を受け、ハワイ真珠湾の先制攻撃を敢行した。日本海軍空母から飛び立った飛行艇群は同湾に集結中のアメリカ太平洋艦隊に攻撃を加え、猛攻に次ぐ猛攻によって同艦隊に壊滅的な打撃をもたらした。出撃機から送信された「トラトラトラ(我攻撃に成功せり)」の暗号電は大本営の陸海両軍首脳を歓喜させ、それに続く戦果の発表は一時的には日本国民を熱狂させるところとなった。
この真珠湾攻撃は米国への宣戦布告なしの奇襲攻撃であったと言う理由で、のちのちまで国際法違反として日本は厳しく非難され続けることになったし、米国も自国を有利に導くためにその世論を最大限に利用した。しかし、近年の外交資料等の研究により、日本外務省から打電された訓令があまりに冗長で解読処理に手間取ったこと、ワシントンの日本大使館に常軌を逸した職務怠慢行為があったことの二つが、米側への宣戦布告書の手交が遅れた直接の原因であったという事実も明らかになってきている。
なんとも皮肉なことであるが、対米開戦に踏み切るにあたり、同盟国として頼りにしていたドイツ軍は、ちょうどこの時期、モスクワ制圧を直前にして猛吹雪に襲われ、戦線の縮小と大幅な撤退を余儀なくされているところだった。同盟国の戦況がいっきに不利な状況へと転じようとしている矢先に、日本は開戦の道を選んだのだった。欧州戦線の情報不足とドイツ軍の力量の過大評価が日本の判断を誤らせたのだった。
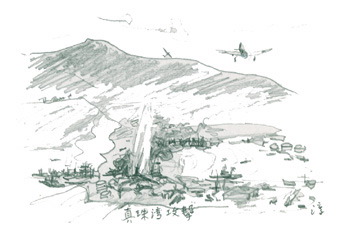
絵・渡辺 淳
「マセマティック放浪記」2003年10月29日
ある奇人の生涯 (36)
石田ランゲージスクール
対米英開戦のニュースは直ちに上海にももたらされたが、石田はそれを醒めた気持ちで受けとめていた。上海の日本租界周辺は本国と同様に戦勝気分に湧きかえっていたが、もちろん彼はそんなムードに身を委ねるつもりなど毛頭なかった。戦火が拡大していくばかりの現況と海軍武官府勤務の際に海外の報道を通して目にした日本の国力分析レポートなどから判断すると、先々の戦争の展望にはむしろいちまつの不安さえ抱かざるをえないからだった。しかし、いったん激しく動きだした時流というものは行き着くところまで行かなければとどまることはありえない。どんな困難があろうともとにかくこの上海で地歩を固め、やがて起るであろう戦時の混乱にも負けずに生き抜こうと、彼は彼なりに決意を新たにするのだった。
米英との戦争に突入すると、当然、上海の米英共同租界やフランス租界は事実上日本軍の管理下に入り、十九世紀半ばからほぼ百年にわたって続いた上海の租界制度はついに終焉を迎えることになった。ただ、上海の街並みの様子や国際交易都市としての様相がすぐに大きく変貌したというわけではなかった。もちろん欧米系の上海居留民が即刻強制退去を命じられたり、直ちにその資産を凍結されたりするようなこともなかった。日本の友好国であるドイツやイタリア関連の企業は開戦前よりもいちだんと上海に進出するようになり、ドイツ系やイタリア系の居留民の数はむしろ増加の傾向をたどった。地理的にみて上海が日中戦争や対米英戦争の最前線から遠く離れており、当面直接に戦火が及ぶ可能性がないことも上海の存続に幸いした。
一九四二年の三月頃までには、東南アジアに侵攻した日本軍はマニラ、シンガポール、ジャカルタ、ラングーン、ニューギニアなどを占領して支配化におさめた。そして大本営によるその劇的な戦果の発表は国民を勝利に酔わせ、日本国中にこのうえない歓喜と熱狂の嵐をもたらした。もちろん、それがつかのまのぬか喜びに終わろうなどとは、真の米国の国力を知るごく一部の指導者を除いてはまったく予想などしていなかった。
ちょうどそれと時を同じくするように、上海には、軍需物資や国民生活物資がらみの仕事を通じて一攫千金をもくろむ日本人が本国から大量に流入しはじめた。以前からの日本人居留民と違い、新たに流入したこの日本人たちは国際性に欠けていたうえに、戦勝ムードをよいことに現地の人々に対し傍若無人な振舞いを見せることも少なくなかったから、生活の秩序を破られた先住の日本人たちからさえも顰蹙(ひんしゅく)を買ったり厳しく非難されたりする有様であったらしい。
ただ、好むと好まざるとにかかわらず、日増しに日本色の濃くなる上海で暮らす欧米系や中国系の人々にとっては、一定レベルの日本語を身につけることが当面の急務となったばかりでなく、日本語ができるかどうかが死活問題につながりかねない状況にさえなってきた。だから、外国語のできる石田に個人的に日本語を教えてほしいという依頼などがちらほらと舞込んでくるようになってきた。そして、そんな情況の変化に着目した彼は、どうせならこの際思い切って小さな語学学校を開いたらどうだろうと思い立った。たとえささやかな規模のものではあっても自らの手で語学学校を立ち上げるなど、上海移住当初は想像だにしてみないことだったのだが、皮肉にも戦争の拡大という異常事態がそんな想定外の道を彼に開いてくれることになったのだった。事情が事情だったからすくなからず複雑な気分ではあったけれども、結局、彼は、現実に日本語修得を必要としている人々がいる以上、開校をためらうことはないのではないかと考えるようになった。
語学学校とはいっても当初は小さな日本語塾みたいなものを想定せざるをえなかったから、石田は南京路に近いフランス租界の一隅にちょっとした教室用の部屋を借り、まずはそこをベースに活動を始めることにした。そして、ともかくも「Ishida Language School」という看板を掲げ、英、独、仏、中国語等を介して日本語を教えるということを記した広告ビラを作成した。もちろん、そのビラには、英、独、仏、中国語でその旨を併記しておいたが、いまひとつ石田らしいのは、「授業料は無料とする」という一文を付け加えたことだった。
日本人居留民の戦勝熱からは一歩引き、冷静なスタンスをとっていた石田だったが、けっして本来の意味での愛国心がなかったわけでも、また日本文化に対する愛着がなかったわけではなかった。本質的な立場からの日本文化に対する深い思い入れなどは、その生涯を通して彼の心中に脈々と流れ続けていたといってよいだろう。この時石田は本気で、上海在住の外国人に日本語を教えることにより、すこしでも日本のために役立つことができればよいと考えていた。だから無料で日本語を教えることにためらいはなかった。
生活のほうはそれまでの貯えでまだ当分は凌いでいける見込みも立っていたし、そもそも彼は生来基本的な生活に必要な以上の蓄財に勤しむような性格の人間ではなかった。ところが、どこの国の人々でも感じることはおなじのようで、「授業料は無料とする」という文言がかえって人々の強い警戒心を喚び起こしたらしく、彼の心からの配慮にもかかわらず受講を申し込んでくる者は皆無であった。
「只ほど高いものはない」とはよく言ったものであるが、はからずも石田は、その言葉のより奥にある「只ほど怖いものはない」という人々の無言の思いをいやというほどに知らされるところとなった。彼自身は「只ほど有り難いものはない。何かあったらそれはその時!」という精神で生きてきたから、正直少々拍子抜けした感じだった。開店休業ならぬ開校休業状態ならまだいいが、いくらなんでも「開校廃業」に終わってしまったのでは格好悪いことこのうえない。このままでは石田美学の沽券(こけん)にも関わるというわけで、ものは試しと授業料有料化に踏み切り、生徒募集の広告ビラも作りなおした。そして、看板からも「授業料無料」の表示を消した。
皮肉なことにその効果は絶大だった。あれよあれというまに国籍も階層も様々な老若男女の生徒たちが次々と集まり、評判が評判を呼んでIshida Language Schoolは大変な盛況をみせるようになっていった。初めのうちは経営者兼講師として主に英語を使いながら自分一人だけで日本語を教えていた石田だったが、想像していた以上に急激に生徒数が増加したため、自力のみでは手に負えなくなってしまったのである。ついには教室の規模を大幅に拡大し事務局を設ける必要が生じ、それに伴って専任の教師や事務員を相当人数雇わざるをえなくなっていった。
この石田の外国人向け日本語学校は、人種の坩堝となっていた当時の上海の姿を象徴するかのように、最盛時には三十四カ国にもわたる外国人生徒約五百名を有するほどの規模にまで発展した。石田は若くて有能なオランダ人女性秘書を雇い、対外的な交渉や業務上必要な直接的身辺管理は彼女に任せるようになった。新たに雇用した教師たちもそれぞれに個性的で能力も優れていたが、その中の一人に当時五歳の男の子をもつなかなかに知的で美しい女性がいた。母親が出勤するときにはその幼い子供も一緒にやってくることが多かった。可愛らしい顔をしたその男の子は石田にとてもなつき、「石田のおじちゃん、石田のおじちゃん」と言いながらいつも彼のことを父親のように慕い続けた。石田のほうも我が子のようにその男の子を可愛がった。
その幼い男の子の名前はミッキー・カーチス、のちに日本でロカビリー歌手として登場し一世を風靡したあのミッキー・カーチスにほかならない。ちなみに述べておくと、石田がかつて見せてくれたアルバムには、その頃の幼いミッキーの写真や二十代の頃ギター片手に大々的にデビューした見るからにハンサムでスマートな青年ロック歌手ミッキー・カーチスの写真なども貼られていた。
日本語学校の望外の成功によって石田は人も羨むような多額の事業利益を得るようになった。しかしながら、彼はその収益を蓄財し必要以上に財力をつけるつもりなど毛頭なかった。そもそも、そんな成功がいつまでも続くだろうなどとも考えていなかった。蓄財欲と飽くなき事業拡大欲にはほとんど無縁であったところをみると、もともと彼は事業家向きの人間ではなかったのだろうし、また事業家としての自分の能力の限界というものをはじめから熟知もしていたのでもあろう。
あの奉天郊外の夜のコウリャン畑で孤独地獄を体験してからというもの、彼は人間というものが自分一人の力だけでこの世を生きることなど不可能なことを痛感していた。そしてそれ以来、大連での銀行勤めのときもそうであったように、万事においてなるべく多くの人々と生きる喜びを分かち合うことができるように心がけてきた。だから彼はまず、雇っている教師や秘書、事務員などの給与のアップやその他の労働条件の向上をはかった。さらにまた、少しでもそれらスタッフの生活の向上につながるような福利厚生面になるべくお金を使うように心がけた。スタッフの給与は能力給にしたが、それは彼が大連でナショナル・シティバンクに勤務し、押し掛け就職にもかかわらず自らの能力を高く評価してもらい、日本本土では考えられないような高給を支給されるよになった経験があったからだった。
雇用条件がよければスタッフたちも労を厭わず気持ちよく働いてくれるから、それがまた通ってくる生徒たちに好印象をもたらし、評判が評判を呼んで石田の日本語学校はますます繁栄の一途をたどった。教務のほうはすべてスタッフに任せ、自らは学校の経営に専念することも可能ではあったが、彼は教壇に立ち生徒たちと直に接することをけっしてやめようとはしなかった。また、もともと無料で日本語を教えようと思い立ったのが学校盛況の発端となった経緯などもあったから、授業料未払いの生徒があっても別にそれを責めたり厳しく取り立てたりするようなこともしなかった。
石田自らが担当するクラスにユダヤ人の女の子が通ってきていた。ある時、たまたま必要があって彼女の名前を呼ぶとその子はなぜかすぐには反応を示さなかった。三度ほど繰り返し名前を呼んだところでその女の子は慌て戸惑ったように反応し立ち上がったが、その様子から、その女の子がもともと生徒として氏名登録されている女の子とはどことなく違っていることに石田は初めて気がついた。瓜二つの双子の姉妹が授業料節約のため一人分の入学手続きをしたうえで交互に教室に通ってきていたというわけなのだったが、その裏事情が判っても彼は素知らぬ顔で騙された振りをし続けた。べつに姉妹の一人のほうを無料にしてやっても構わなかったが、そうすると他の生徒との公平さを欠くことになるし、当人たちもかえって周囲に対してバツが悪くなり学校に通ってきづらくなるだろうと考えたからだった。他の生徒に較べ半分くらいしか授業を受けていないわけだから、結局彼女たちのほうにだってそれなりの苦労があるに違いないと感じたのも、それを黙認した理由のひとつだった。
上海という特別な社会の中における望外の成功で得た利益は同じ上海社会の中へと還流させるのが最善だと確信した石田は、まっとうな事業家なら設備投資や運営資金用貯蓄、さらには事業拡大費へとまわすはずの余剰資金を、上海市内における各種文化活動の支援や歓楽街での遊行のために惜しげもなく使いまくった。もともと零からの出発だったのだから、再び零に戻っても悔いはないし、そうなったらそうなったでまたなんとか生きていくさ、という開き直りに近い思いがいっぽうにあったことも事実だった。まるで中国禅宗六租慧能の「人間もともと無一物」という有名な言葉に導かれでもするかのようなその日々の振舞いのゆえに、いつしか彼は上海社交界の名士としての地位を手にするようになっていた。
Ishida Language School の校長兼経営者として名声を馳せるようになった石田の噂を、同じ上海のどこかに住んでいるはずのナーシャが耳にしている可能性は皆無ではないと思われた。石田の胸中にも、それを知ったナーシャからなんらかの方法で連絡があるかもしれないという淡い期待のようなものがなくはなかった。しかし、結局、ナーシャに関する情報は何一つ得られるままいたずらに時は流れ、やがて訪れた新たな身辺の変化にともない、もはや彼女の面影を懐かしい想い出の一つとして記憶の一隅に留め置かざるをえない状況を迎えざるをえなくなったのだった。

絵・渡辺 淳
「マセマティック放浪記」2003年11月5日
ある奇人の生涯 (37)
新たなる出逢い
望外の日本語学校成功のお蔭で、はからずも上海の名士の一人として名声を馳せるにいたった石田は、さまざまな催し物などがあるときなどには各方面から真っ先に招待されるようになった。そして、それにともない、一大享楽街の大世界周辺は言うに及ばず、市内の高級ホテルや高級クラブなどにも頻繁に出入りするようになった。そんな華やかな日々のなかにあって、彼はたまたま外灘地区にあるパレスホテル(現和平飯店)に何日か滞在することになった。当時のパレスホテルは上海では最高級のホテルの一つで、そこに出入りしたり宿泊したりすることのできる人々は欧米系の要人や日本軍幹部、あるいは民間資産家などごく一部の特別な階級に属する人々にかぎられていた。
そして、そんなパレスホテルのロビーやラウンジ、レストラン、バー、ギャンブルコーナーなどを気の向くままにめぐり歩いても、それがすこしも不自然に感じられないほど洗練された身振舞いをすっかり彼は体得し実践していた。一七六センチという当時の日本人には珍しいほどの長身、二枚目スターなみの甘いマスク、ジョークや風刺を織り交ぜた知的な話術、そして日本人離れした抜群の語学力もそんな彼をいちだんと際立たせるのに一役買っていた。
ホテル滞在中のある日、なにげなくフロントロビー付近を通りかかった石田は、どこからともなく自分に向けられている誰かの視線のようなものを感じた。はっとしてあたりを見まわした彼の目に飛び込んできたのは、ホテルのフロントに立つ一人の美しい女性の姿だった。互いの目と目が合った途端に石田の全身を電撃のようなものが貫き走った。相手の女性は彼の心中を即座に察知でもしたかのように無言で軽く会釈しながら微笑みかけてきた。まるでその微笑みに操られでもするかのようにとりあえず彼もどこかぎこちない微笑みをもって応じ返した。その瞬間、まだ一言も言葉を交わしていなかったにもかわらず、二人はそれぞれに、互いの心と心が凛とした一筋の強い魂の糸で結び繋がれるのを確信し、また実感した。まさに運命のなせる不可思議な業(わざ)と言うに相応しい男女二人の出逢いであった。
視線を合わせたまま、一瞬、間を見計うようにその場に佇んだあと、まるで見えない糸に手繰り寄せられるみたいにして石田は彼女のほうに近づいていった。そして、たまたまお客の出入りのすくない時間帯でもあったのを幸いに、彼女に向かって初対面の挨拶を兼ねた軽妙なジョークまじりの短い一言を投げかけた。見るからに洗練され、日本人離れした感じの女性ではあったが、明らかに彼女は日本人だと思われた。しかし、自分の思いをさりげなく込めたキレのよいジョークをごく自然に発するには、日本語より英語のほうがずっとふさわしいと考えた彼は、流暢な英語で彼女に向かって話しかけてみたのだった。
すると彼女は悪戯っぽい笑みを満面に湛えながら、これまた見事な英語と洒落た言葉の一太刀をもって彼の言葉を受けかわした。それをまた逆手にとって彼がもう一歩深く切り込むと、彼女のほうはこともなげにその切り込みを再度鮮やかに受け流した。時間にすればごく短い間のことにすぎなかったのだが、そのウイットとエスプリに富んだ会話を通して二人は内心互いに、相手の人となりが初めに直感した通りであることを確かめ合った。石田が相手に名を訊ねると、彼女は「流れ者のミサ」と名乗って、男心を揺すぶらずにはおかないその魅惑的な瞳を、妖しいまでの光を内に秘めつつ一瞬きらりと輝かせた。
しばらくすると外国人の宿泊客がチェックインのためにフロントに現れたので、石田は彼女と会食でもしながら一度ゆっくりと話そうという約束だけを取りつけ、いったんその場をあとにした。よどみのない英語を駆使し、てきぱきとした態度で接客する彼女の様子をいま一度振り返りながらホテルを出た彼は、久々に満ち足りた気分で黄浦江沿いの公園地帯を歩きだした。ミサと名乗るその女性との想わぬ出逢いが彼の心をいやがうえにも浮き立たせていた。そこは彼もまだ若く、煩悩もけっしてすくなくない男であった。
それから二日後の夜のこと、仕事を終えてホテルを出たミサと南京路の一角で待ち合わせた石田は、行きつけの中華レストランに彼女を案内した。そして、コースものの本場中華料理に舌鼓を打ちながら、まずは自己紹介をかねてお互いのこれまでの人生などについてあれこれと語り合った。
面前に坐る彼女の姿やその磨き抜かれた身のこなしを目にしながら、石田はあらためてその知的な美貌と溢れでるような気品とに感嘆するばかりだった。それまでにも美人と評判の女性たちとすくなからぬ付き合いのあった石田だが、その彼にしてから、心底綺麗だと驚嘆し、才色兼備という言葉はまさに彼女のためにあるのではないかと思ったほどだった。その群を抜く美貌は、精神的にも身体的にもひとりの人間として十分に成熟しきった、そして社会的にも完全に自立を遂げた女性ならではのものに違いなかった。まだ徹底した男性優位の社会だったその時代の日本女性としてはきわめて異色な存在だったといってよい。
パレスホテルのフロントで目と目が合った瞬間から、直感的に相手のなかに自らとおなじニオイを嗅ぎ取っていた彼と彼女のことだったから、たちまち二人は意気投合し、その会話はごく自然に弾んでいった。ただ、まだ出逢ってまもないこととあって、さすがに言葉遣いだけはお互い丁寧だった。フロントで初めて短い言葉を交し合ったときと違って、もちろん今度はお互い日本語での会話だった。
「いきなりレディに歳を尋ねるのはちょっとどうかと思うんですが、ミサさんは何年生まれなんでしょう?……まさか紀元前の生まれじゃありませんよね。僕のほうは一九一六年の博多生まれなんですが……」
「私はladyなんかじゃなくってreadyのほうですから、遠慮なさらずなんなりと訊いてくださって構いませんよ。私は一九一五年生まれ、もちろん紀元前ですから、石田さんより一歳年下ということになりますね。生まれはいまの千葉県あたりだったような気がしますが、なにしろもうずいぶんと遠い昔のことなので忘れてしまいましたわ」
「ははははは……、紀元前のことじゃ、確かに千葉県はもちろん、日本って国だってまだありませんでしたものね」
実際には石田よりも一歳年長だったミサが、巧みな会話の受け流しを通して自分のほうが一歳年下だととぼけるその有様に、彼は笑い転げながらも、内心さすがだと思うのだった。そこでさらに彼はミサに問いかけた。
「ミサさんは一昨日初めて会ったとき、確かご自分のことを『流れ者のミサ』だなんて名乗りましたけど、流れ者になる前のミサさんはどこにいらしたんですか?……いくらなんでも竜宮城だったなんてことは……」
「東京麻布鳥居坂の東洋英和女学院っていう私みたいな時代のヒネクレ者を教育する専門学校を卒業するまでは、まあ、おとなしく東京周辺で暮らしていました。でもね、私、幼い時分からずいぶんと勝気な性格でしてね。だから、東洋英和卒業が間近になった頃から、なんとか国外に飛び出して未知の世界で思うがままに生きてみたいって考えるようになったんです。もちろん特別なツテもなく女一人で海外に渡るにはそれなりの覚悟もいりましたけれどね」
「東洋英和のご出身ですか。それじゃ、ずいぶんと自由な校風の中で外国文化や語学の勉強などもなさったんですね。道理で見事な英語を!」
「ところがですね、伝えきくところによると、敵性語や敵性思想排斥運動とかの煽りをうけて、昨年、東洋英和女学院の『英』の字を『永』に変えて東洋永和女学院という学校名になったんだそうですよ。バカバカしいったらありゃしないんですけど、英国憎けりゃ『英』の字も憎いってことなんでしょうね。ただね、英語やフランス語が上達したのは上海にやってきて多くの欧米人と親しく交流するようになってからですね」
「それじゃ、東洋英和を卒業したあと単身上海に?」
「ええそうなんです。思想統制は厳しくなるいっぽうでしたし、女性の人格や権利などは軽視されていくばかりでしたでしょう。だから、私ばかりでなく、自立心が強く自由な空気に憧れる女性たちはずいぶんと上海に渡ってきたんです。もちろん、身に振りかかるいろいろな危険は承知の上で……」
「ご両親は心配なさらなかったんですか?、おそらくはずいぶんと大切にお育てになられたんでしょうから……」
彼女の身体から自然に溢れ出るような気品は、幼い頃からのその育ちを通して形成されたものに違いなかった。そのことを直感した石田は敢えてそう訊ねてみた。
「私は三人姉妹の長女でしてね。妹たち二人は私なんかと違って誰もが認める日本的な美人で、しかも性格もとても優しく穏やかだったんです。ただ、それにくらべて私のほうは男勝りなうえに、社会にも親に反抗的で、おまけに美人でもなんでもないときていましたから、自分から国外に飛び出したことを両親だってかえって喜んだんじゃないでしょうか。厄介払いができたって……。そのまま日本にいたって働き口もないし、嫁にも行くようなところもないということで両親がやきもきしましたでしょうから……」
そんなミサの言葉を耳にして、石田は思わず呆れるような口調で言った。
「いくらなんでもそんなあ!……、妹さんがた二人のことはよくわかりませんが、それはともかく、ミサさんが美人じゃないっていうなら、この世に美人なんていませんよ。この上海じゃ、ミサさんずいぶんと評判になっているんじゃないんですか?」
「文化的に洗練された上海にはそのぶん素敵な女性も多いですから、私なんかとてもとても……。知性も品性もない性悪女としてなら話はべつかもしれませんけれどね」
ミサはそう言うと、引き締まった口元にかすかな笑みを浮かべ、悪戯っぽく両の瞳をきらきらと輝かせた。そのなんとも蠱惑的(こわくてき)な表情に石田は心身ともに成熟しきった大人の女性ならではの底知れぬ魅力を感じるのだった。

絵・渡辺 淳
「マセマティック放浪記」2003年11月19日
ある奇人の生涯 (38)
上海幻夢
その夜の二人だけのデートを契機に、石田とミサの関係は急速に深まっていった。以心伝心というか、一をもって十を知るというか、生来おなじ波長をもちそなえた二人が親密の度を増していくのに余分な言葉や余計な舞台装置など不必要だった。出逢った瞬間から、いや出逢うまえからそうなるように運命づけられていたことを物語るかのように、二度目のデートのときからは軽口をまじえた敬語抜きの自然な会話を交わすようになり、ともに戸外を散策するときなども、どちからともなくぴったりと身を寄せ合いながら歩くようになっていった。そして、お互いのことをミサ、タッツァンとも呼び合うようになった。彼も彼女も生来多趣味ではあったが、文化的なセンスも、音楽や絵画などの好みも、そのほか諸々の興味の対象も不思議なほどに一致していた。
ハンサムなうえに一七六センチという長身でスマートな体型の石田と、ハッとするような美人で身長一六八センチほどのスラリとした体躯のミサが二人並んで街なかを歩く姿は当然のように人目を惹いた。当時の平均的な日本人の体つきからすればともに群を抜いた長身であるうえに、身につけていた衣服もセンスのよいものだったから、まるで男女二人の映画スターかなにかが上海の街並みをめぐりつつ、詩情豊かなその風情を楽しんでいるかのような印象を与えさえもした。もちろん、石田がいまや日本語学校を大々的に経営する上海きっての名士であり、ミサが上海一流ホテルの知的で有能な美人スタッフであることを知る人もすくなくはなかった。
ただ、そこに至るまでに様々な修羅場をくぐり抜け、すでに二十六歳と二十七歳の自立した大人になりきっていた石田とミサとの間柄は、よくある恋人同士のそれとはまるで異なるものであった。ある意味で、二人の交際ぶりは初めから通常の男女の関係を超越していたと言ってよかっただろう。
二人はなによりもまずお互いの精神の自由と自立した生活スタイルを十分に尊重し合った。上海そのものはなお平穏そのものであったが、戦時下のこととあって将来の展望などまったく立たない状況にあったし、もともと今日のことは今日、明日のことは明日にという信念で生きてきた二人だったから、深い関係をもつようになってからも同棲したり結婚したりするなどということはまったく考えもしなかった。
そもそもミサにはたくさんのボーイフレンドがあった。晩年、石田は当時のことを振り返りながら、「なにしろミサには外国人男性をはじめとし、星の数ほどボーイフレンドがいましたからねえ。とにかく綺麗でしたから、男どもが次ぎから次ぎにまとわりついてきましてねえ……」と笑いながら話してくれたことがあったが、実際その通りだったのだろう。星の数ほどだったかどうかはともかくとしても、異性との交際という点では石田のほうもけっして彼女にひけをとらなかったようである。とくに上海の名士となってからというものは、ホテルやクラブでのパーティー、各種コンサートや観劇会などの機会を通じて彼に近づいてくる女性たちは跡を絶たなかった。そして、上海社交界のマドンナとうたわれるロシア人女性や中国人女性らをはじめとする数々の美女たち相手に浮名を流したりもしたのだった。
だが、出逢ってほどなく石田とミサの間に築かれた特別な信頼関係は、精神的な意味でも肉体的な意味でも互いを取り巻くそういった華やかな異性の存在を超越したものになっていった。その関係は、愛しい恋人同士のようでもあり、気のおけない友人同士のようでもあり、血を分けた姉弟のようでもあり、さらには生死の境をともにさまよった戦友のようでもあった。実際そうであったからこそ、そんな二人の不可思議な関係は、その後六十年にもわたる波瀾に満ちた歳月を越え、八十五歳で石田が他界するまで続いたのだった。「ミサとの関係は、かつての恋人同士だったなんて言うよりは、腐れ縁もいいところだったと言ったほうがよいのかもしれませんね」と苦笑しながら語ってくれた石田だが、裏を返せば「腐らせようにも腐れようのなかった縁」だったというふうにも考えられないこともなかったろう。
時々互いの温もりが恋しくなると、二人は上海のとあるホテルの一室にこもりきりになり、いつはてるともない激しい抱擁に身を委ねた。それぞれを取り巻く数々のボーイフレンドやガールフレンドの影を互いの背後に見ながらの抱擁は、そのぶんだけいっそう二人の体内の情欲の炎を大きく燃え立たせ、せめてその刹那だけも相手の心身をおのれの鎖のもとに繋ぎとめ意のままにとことん蹂躙しようとするサディスティックな思いを掻き立てた。恋多き身の男女にしてなお、そのような灼熱の愛欲をもたらすエネルギーが残されていることそのものが不思議といえば不思議であったが、ともかくもそれはまぎれもない事実ではあった。
数々の恋を重ねた一人の女としてこのうえなく磨きあげられ成熟しきったミサの身体は、弾力に富む石田の肉体をやさしく柔らかく包み込んだかと思うと、まるで真綿でジワジワと締めつけでもするかのようにいたぶり弄んだ。いまにも気が遠のきそうな感覚に酔い痴れながらも、石田のほうも必死にそれに堪え、一瞬の緩みを突いて逆に攻勢に転じると、相手の身体の波打つような動きを両腕で押さえ封じ込めるようにして、自らの全身を前後に激しく揺すり立てた。するとミサもついには体内に滾(たぎ)り昂ぶる命の鳴動を抑えきれず、歓喜の声を漏らしては悶え狂った。
昂揚の高みをすぎ、やがて満ち足りた虚脱と空白の時が訪れると、二人はお互いの体温を確かめ交換し合うかのように無言のままじっと静かな抱擁を続けた。そして心身の奥までを新たな生気で洗い清め終えると、この二人ならではの軽妙なジョークを交えながら、それぞれのこれからの生き方や時代の展望、様々な文化的問題などについていつ果てるともなく語り合った。
パレスホテルでの仕事がオフの時など、ミサは石田の経営する日本語学校に見学を兼ねて顔を出し、たまには臨時の講師を務めたりすることもあった。外国人への対応に慣れており、しかも日本できちんとした教育を受けて育った彼女は、そんな時などなかなか見事な講義ぶりをみせもした。ただ、私的な関係を必要以上に学校の中に持ち込むと他の講師たちへ好ましからぬ影響や印象を与えることが懸念されもしたため、よほどの緊急時をのぞいてはミサが講師の役を引き受けることはなかった。
この一九四二年の六月、山本五十六連合艦隊司令長官率いる日本海軍は、大小三百五十隻の艦船、航空機一千機、将兵十万をもってミッドウエイ海域での戦闘に臨んだが、事前の情報戦での敗北や戦略的な失敗が原因で米国機動部隊に大敗し、大型空母四隻、重巡洋艦一隻、主力航空機三百余機、将兵三千五百名を失った。そしてそれを境に太平洋全域での制空・制海権を急速に奪われていくことになった。
対米戦開戦当初は破竹の勢いを誇った南太平洋方面での日本軍の進攻も、ガダルカナル島の攻防戦で圧倒的な兵力を誇る米軍に大敗したのを契機として、次第に敗勢へと転じることになった。ソロモン海域で日本陸海軍は米軍となおも死闘を繰り広げたが、十一月頃までには一帯の制空・制海権を完全に喪失し、補給を断たれたガダルカナル島の日本兵はジャングルの中で飢えとマラリアに苦しみながら次々と死んでいった。同島をめぐる攻防戦での日本軍戦死者二万四千名のうち、餓死者・病死者は一万五千名以上を占めていたといわれている。
十二月も終わりに近づく頃、大本営はガダルカナル島放棄を決定、翌年の二月までに残存兵をブーゲンビル島に撤退させるが、以後、日本軍は南方戦線で敗退と孤立の一途をたどることになった。大本営はこのガダルカナル島撤退を「転進」と発表し、ミッドウエイ海戦大敗のときもそうであったように厳しい報道管制を敷いて国民の目から敗戦の事実を隠そうと画策し続けた。
対米戦争の最前線においては、このときすでに決定的な敗北とそれにともなう悲惨な事態が日本軍将兵の身に次々と生じていたにもかかわらず、上海にはまだその切迫した情況はまったく伝わってきていなかった。だから、旧来の欧米租界地域が事実上日本軍の支配統制下に入ったとはいえ、上海の経済的あるいは文化的な繁栄ぶりにはなお大きな変化は生じていなかった。一部の欧米人たちが間接的情報として日本軍敗退の事実を知っていた可能性はあるが、たとえそうであったとしても華やかな上海社交界にそのことが及ぼす影響はまだ皆無に近かった。
上海で一、二を争そうクラブなどで大々的な欧米風のパーティなどが開かれる時などには、石田は必ず主催者から招待を受け、列席を求められるようになった。一定以上の格式ある欧米風パーティには夫妻揃って臨席するか、そうでなくても男女ペアをなして参席するのが暗黙の儀礼になってもいたから、石田は綺麗なことこのうえなくしかも洗練された感性をそなえもつミサを同伴するのが常とはなった。
フォーマルスーツと洒落た社交ドレスをそれぞれ見事に着こなした二人が腕を組んで会場入りしようとすると、「Mr. and Mrs. Ishida……」と石田夫妻の来場を告げるアナウンスが高らかに流された。もちろん二人は実際には夫婦ではなかったのだが、そのような公式の場においては堂々と「石田夫妻」として振る舞い通した。二人の来場アナウンスが会場いっぱいに響き渡ると、ステージの一角に陣取る楽団員たちは石田夫妻専用のテーマ曲を演奏しながらその栄誉を称え、先客たちは皆盛大な拍手をもって彼らを迎え入れた。いまや二人は押しも押されもせぬ上海社交界の名士となっていた。
盛大なパーティの場で石田らは当時の上海社交界の大物たちとの出逢いとそれにともなう様々な交流を楽しみ、それが一時の仇花にすぎないとは知りつつも、人間という奇妙な生き物の夢と欲望と虚栄とが織りなす華やかな世界に酔い痴れた。石田はその時代に上海の名花として名の知れ渡っていた美女や賢婦たちと対等の立場で親しく接する機会を得たし、ミサはミサで一流の社交センスをもつ美男や知性溢れる紳士たちと忌憚ない会話を交わし、親交を結ぶことができるようになった。
石田が上海にやってきた当時は、一世を風靡した名女優の李香蘭などは雲上の存在以外のなにものでもなかったのだが、そんな彼女とも席を接して酒杯を交わしたり、ジョークを飛ばしながら親しく話をすることができるようになった。実際、李香蘭とは様々なパーティの場で一緒になることがすくなくなかったし、たまにはどちらからともなく誘い合い、二人だけで静かな歓談の時をもつこともあったのだった。

絵・渡辺 淳
「マセマティック放浪記」2003年11月26日
ある奇人の生涯 (39)
日本語学校閉鎖命令
厳しい情報統制下にある日本国民にはその事実は公表されていなかったが、一九四三年も半ばにさしかかる頃には、太平洋戦線全域において日本軍は大小の敗戦を重ね、四方からジリジリと追い詰められはじめていた。いっぽう、頼みの同盟国ドイツやイタリアもヨーロッパ戦線で連合軍の猛反撃に遭って防戦いっぽうに追い込まれ、その包囲網をどんどん狭められつつあった。そのような情況下にあって日本軍は中国の江南地方進攻作戦を大々的に展開、米英軍の反攻に備えて同地方一帯の支配を拡大しようと試みた。そして、それにともない、上海在留の欧米民間人や日本人に対する管理体制も強化されるようになっていった。なかでも欧米系外国人とかねがね親交のある在留邦人のほとんどは、有無を言わさず日本軍部の厳しい監視下におかれるようになった。
欧米系外国人との親交を理由に憲兵から身におぼえのない嫌疑をかけられ、一方的な追及を受けたり、不当な弾圧を被ったりする上海在留邦人の数はこの時期を境に急増した。そして憲兵隊や日本軍傀儡政権下の警察組織による取締りは熾烈をきわるようになり、やがては、米英系の外国人とはもちろんのこと、オーストラリア人やロシア人相手に短い会話を交わすことさえも禁止されるという異常な事態に発展した。しかも、ついうっかりその禁を破ったりすると、スパイ容疑という大仰な罪状のもとに身柄を拘束されたりすることもすくなくなくなった。
とくに、それまでに多くの米英系外国人と親交のあった在留邦人などは、危険人物というレッテルを貼られ強制的に日本へと送還されるようにもなった。そのため、知名度が高く、外国人とも交流の多い文化人や芸能人などで、本国へと強制送還される者は当然かなりの数にのぼった。それらの中にはあの李香蘭(以前に書いたように彼女は実は日本人であった)やその関係者なども含まれていたが、そのような事態に至ったのは、軍幹部の間に、文化人や芸能人などというものは戦時下の緊迫した社会においては無用の長物以外のなにものでもないとする判断があったからだった。
ただ、この時期になって軍部が上海における日本人と欧米人と接触を嫌うようになったのには、いま一つ大きな理由が存在していた。大本営要員をはじめとする日本軍幹部たちは、すでに劣勢に負い込まれつつあった日、独、伊、三国の実態が一般国民に漏れ伝わることを極力危惧してもいた。したがって、連合国側軍事情報の入手が容易な在留欧米人を通じて同盟国側の不利な戦況が邦人らに伝わる可能性がとくに高い上海では、厳しい情報統制を敷く必要に迫られていたのである。スパイ容疑などという大仰な罪状を振りかざし、憲兵らが上海において在留邦人と在留欧米人との接触を取り締まろうとしたのは、単に日本軍の軍事機密が漏れることをおそれたばかりでなく、自軍の劣勢を隠すというやむにやまれぬ背景があってのことだった。
石田の経営する日本語学校に突然三人の憲兵が踏み込んできたのはそんな折のことであった。上海在留邦人の行動全般に対する統制が急激に厳しくなったときから、いずれそのようなことが起るであろうと内心覚悟していた石田は、ついに来たかという思いでその憲兵たちに対面した。三人の中で一番の年長者らしい三十代後半かと思われる男は、どこかに蔑視と憎悪に近いの感情のこもった態度と、かなり横柄な口調をもって石田に問いかけてきた。憲兵であることを表わす襟章や腕章をそれとなく誇示し相手を威圧する振舞いがどうにも鼻について仕方なかったが、石田はあえてそんな自分の思いを胸中に抑え込んだ。
「この学校の経営者の石田達夫に会いたいのだが、いまいるかね?」
「はい、私がこの学校の経営責任者の石田達夫でございますが」
石田がそう答えながら立ち上がると、頭のてっぺんから爪先までを一瞥するような視線を送りながら、その憲兵はさらに続けた。
「この上海ではずいぶんと羽振りがよいそうだけど、いったい君はいま何歳なんだ。日本語学校の経営者といったってまだ二十代の若造みたいじゃないか!」
「はい、年齢はいま二十七歳でございますが……。そんな私になにか御用でございましょうか?」
石田は鄭重な口調でそつなくそう応対した。すると相手はみるからに彼を嘲笑するような表情を浮かべ、吐き捨てるように言った。
「二十七歳の分際で学校の経営者か……、まあ、たいしたもんだなあ。不良外国人を大勢集めて金儲けして、上海の名士気取りとはなあ!」
「いえ、べつにそんなつもりはありませんし、もともと、上海在住の外国人に日本語を教えることは日本のためにもなると思ってやったことなんですが……」
「開戦前の一時期海軍武官府で働いていたそうだが、あそこを辞めたあとでまたずいぶんとよいところに目をつけたもんよなあ。その点だけはおおいに褒めてやってもいいな!」
「だがなあ、調子に乗るのもいい加減にしたらどうなんだ……、こんな国賊まがいのことをやらかしてなにが日本のためなもんか!」
若い憲兵の一人が上官の言葉の続きを受け繋ぐようにそうたたみかけてきた。その声には明らかに恐喝に近い響きがこもっていた。
「いきなり国賊まがいといわれましても……。けっしておっしゃるような意図があってこの学校を開いたわけではありませんし、ここで日本語を教えることが日本の国益に反しているなどとも思われないのですが……」
もともと当時の軍人というものの考え方に心からの好感を持つことができずにきていた石田は、精一杯の弁明をしようとして、静かな口調でそう言葉を返した。だが、その言葉の抑揚のもつ微妙な高低の奥に鋭く彼の敵意を読み取った相手の憲兵は、いっきに怒りに近い感情を顕わにしながら声高に宣言した。
「欧米人に敵性言語を使いながら日本語を教えたり、敵性言語を介して不良欧米人どもと交流すること自体、国賊行為なんだ!、なにが日本のためなもんか!、ここが本国なら敵性言語を崇める敵性思想の持ち主としてお前なんか即刻逮捕投獄されるところなんだぞ!」
「講師が英語やドイツ語、イタリア語、フランス語、ロシア語などを使いながら日本語を教えるのがそんなにいけませんか?、それに、英語やフランス語はともかく、ドイツ語やイタリア語などは敵性言語ではないと思うのですが……」
石田がそう言い終えた途端に、憲兵はやおら手にしていた軍刀の鞘の先端を彼の胸元に突きつけ、ニヤリと意味ありげな笑みを浮かべた。そして顔を強張らせる石田の喉元のあたりを軽く小突くようにしながら、顎をしゃくりあげるようにして言った。
「そもそもこの上海で得体の知れない欧米人と付き合うこと自体が利敵行為やスパイ行為に相当するんだ。つべこべ言うとスパイ罪で逮捕するぞ!、お前一人くらい即刻逮捕して収監するか、最前線に送り込むなど簡単なことなんだぞ!」
そのあまりに無茶苦茶な言い分と横暴な態度に内心憤りを覚えながらも石田はあえてその感情を抑え、憲兵らが突然その場にやってきた理由を訊ねてみようと考えた。ほんとうのところは訊ねなくてもその理由はほぼ推察がついていたが、それでもやはり相手の用件の内容を確認するのは当然の筋道というものだった。だが、その思いをすぐには言葉に出しかね、しばし彼は沈黙に身をゆだねた。
「……」
すると、そんな石田の胸中を察知でもしたかのようにあらためて彼の顔を見すえた相手は、ここぞとばかりに傲然と言い放った。
「この学校を即刻閉鎖したまえ。これは軍の絶対命令だからな。それから、英米系やロシア系の外国人との交際もいっさい禁止する。もしもこの命令を厳守できないなら直ちに強制連行するからそう覚悟しておくんだな。また、敵性欧米人と交流のあった日本人はみな近々上海から退去し日本へと戻ってもらうことになる。そして本国で軍事教練と国家思想の再教育を受け、敵性思想をすべて洗い流してしまうようにしなければならない。いいな、学校閉鎖完了の期限は明日までとする。それ以上の猶予は断じて認められない!」
そう宣告し終えると、三人の憲兵たちはいかにも勝ち誇ったような様子で軍靴の音を響かせながら立ち去っていった。なんともひどい話ではあったが、あとに残された石田にはもはや抗すべきすべなどあろうはずもなかった。その日から翌日にかけて、急遽、彼は雇用していた教師たちや多くの生徒たちにやむえをえない事情を説明し、学校の閉鎖とそのための諸々の後始末に奔走するところとなった。
最盛時には三十六ケ国にわたる外国人生徒五百人を有していたIshia Language School は、こうして短い繁栄の日々をあっけなく終えることになってしまった。学校経営で多大の収入はあったが、あえてそれを残さず使いきり、非常時に備えて資金を貯えることをしてこなかった石田は、当然、学校閉鎖とともにそれまでのような収入がなくなってしまったから、もはや上海の名士の地位に留まることなどできるはずもなく、憲兵らがやって来た日から一週間を待たずして一介の日本人上海浪人に転落した。
しかし、もともとこういう事態もあるに違いないと予測していたから、彼自身にはさしたる悲壮感や絶望感などまったくなかった。幸いその時までには、上海に移住してきた 母親や二人の妹たちも、それぞれの特技を活かしささやかながらもなんとか自力で生活するができるようになっていたから、とりあえず自分の身の振り方さえなんとかすれば当面とくに問題はなかった。食うやくわずの事態に直面するのは過去一度や二度のことではなかったから、たとえその日暮らしの身になっても慌てることなどなかったし、また、なんとかなるものだという開き直りもあった。「まあ、人生とはこんなものよ!」とその不運を笑い飛ばすだけの度量がすでに石田にはそなわっていた。それにまた、以前とは違って、彼には、どんな不遇な情況にあっても互いに心を支え合うことのできるミサというまたとない大きな存在までもがあった。

絵・渡辺 淳
「マセマティック放浪記」2003年12月3日
ある奇人の生涯 (40)
スパイ容疑で逮捕する!
横暴な憲兵たちに突然押しかけられ、彼らから一方的な訊問をうけたのはミサもおなじであった。しかも、ミサに対する憲兵らの追及は石田のそれにくらべてはるかに厳しいものであった。外資系のパレスホテルに勤務していたミサはそれだけでも様々な欧米人、なかでも米英人と接したり一緒に仕事をしたりする機会が多かった。また、「当時ミサには星の数ほどボーイフレンドがいた」という石田の言葉通り親交のある欧米人はすくなくなかったし、さたには、おなじ欧米人でもそれなりの要職にある人物やその家族がほとんどだった。知的で英語やフランス語も堪能だった彼女にすれば、そんな欧米人たちと政治的な問題や国際情勢などについて会話を交わすことなど日常茶飯事でもあった。
だが、当然、ミサのそんな型破りの行動と自由奔放な生活ぶりは憲兵隊によって徹底的にマークされるところとなった。ミサの勤務中、パレスホテルに数人の憲兵がずかずかと乗り込んできたのは石田が日本語学校を強制閉鎖させられてから間もない日のことであった。彼らはまずホテルの支配人を呼びつけ、ミサがホテルの奥で仕事中であることを確認すると、すぐに彼女をフロント・ロビーに連れてくるように命令した。
呼び出し要請に応じてミサがフロント・ロビーに出向くと、軍服に身を固め居丈高に立ち並ぶ男たちの姿が目にとまった。彼らの姿を一目見ただけで彼女にはそれが憲兵隊員であることがすぐわかった。石田が日本語学校を閉鎖させられたことを知った時点で、ミサは遅かれ早かれ自分のところにも憲兵がやってくるだろうと予想していた。心の準備のできていた彼女は毅然とした態度で憲兵たちの前に立った。それでなくても男勝りで気性の激しい彼女が、かすかな微笑を湛えながら凛然と佇む姿はヴィーナスかなにかの再来を想わせるほどに美しかった。
ミサは憲兵らに軽く会釈をし終えると、相手の顔を見すえ、鄭重な口調のなかにも敢然とした響きを込めて話しかけた。
「私に何かご用でございましょうか。お呼びだということですので参りましたのですが?」
その堂々とした態度と類なき美貌とに一瞬圧倒された憲兵たちは、沈黙したまましばしその場に釘付けになった。そして、それから、あらためて気を取り直しでもしたかもように、一番の責任者と思われる一人が口を開いた。その男の口から飛び出したのはなんとも唐突な一言だった。
「お前をスパイ容疑で逮捕する!」
我が耳を疑うかのように心中深くでその言葉を反芻したあと、ミサは逆に問いかけた。
「どういう根拠で私がスパイ罪を犯したとおっしゃるのですか?……また、いったいどのようなスパイを働いたとおっしゃるのですか?」
「お前はいろいろなアメリカ人やイギリス人と交際し、我が国の重要な情報を流しただろう!」
「私はこのホテルで働いていますから確かに外国人とのお付き合いはありますし、上海にやってきて以来親しくなった様々な外国人の友人や知人もいます。でも、だからといって、どうして私がスパイだということになるんですか。そもそも私は日本の軍事機密などなにひとつ存じませんよ!」
すると相手の憲兵は、ミサがかねがね顔見知りである二、三の日本軍幹部の存在をそれとなく臭わせでもするかのような口振りで憎々しげに言った。
「お前はそれとなく重要な軍事情報をあの方々から入手できる立場にある。あの方々はお前がスパイだなんてまったくご存知ないから、つい油断していろいろ大切な話などをなさる可能性があるんだ。お前はそれを米英人に流しているんだろう!」
「冗談もいい加減にしてくださいよ。どんな情報を誰に私が流したというんです。それに、あなたのおっしゃるその方々とは、いったいどなたとどなたのことなんですか?」
「……」
ミサの鋭い逆襲に憲兵たちは互いに目配せしならが一瞬口ごもり、おおっぴらに軍幹部の名前をあげることを躊躇った。憲兵たちにしてもなんの確証もなくそれらの人物の名前を口にはできない弱みがあった。下手にそんなことをし、それが問題の人物たちに伝われば逆に自分たちの立場が危なくなるおそれがあったからだった。
「まったく身におぼえのない嫌疑をかけられたのでは私だってたまったものじゃありませんわ。私が女だからって舐めてかかるはやめていただけませんでしょうか!」
鄭重ななかにも厳しい響きのこもったミサの追撃に、相手は思わず低く呟くような口調で言った。
「この売女(ばいた)めが……。もっともらしい口をききやがって……」
「売女とはなんですか。仕事柄もあってお付き合いしている男性は確かにいろいろとございますけれど、あなたがたから売女などと軽蔑呼ばわりされるようなことをやっている覚えはまったくございません」
「こんな時世に毛唐野郎と付き合っている女なんて、それだけでも国賊ものの売女だろうが!……違うかあ?」
「そうだ!……お前のような国賊売女を懲罰するのも我々の任務なんだぞ!」
部下の憲兵の一人が相槌を打つようにそう口を挟んだ。
「私はスパイだの国賊だのと責められるようなことはいっさい致しておりません。それに、私のことを売女などとおっしゃるなら、中国人や一部日本人婦女子に対して平気で強姦をおこなったり暴行をはたらいているあなたがた軍人のほうだって野獣集団なんじゃじゃありませんか!」
あくまでも毅然としたそんな彼女の態度に業を煮やした相手は、ついに半ば叫ぶような調子で宣告した。
「帝国軍人に対してなんたる侮蔑……おまえを連行して徹底的に調べればスパイであることはすぐにわかることなんだ!、これから即刻憲兵隊本部におまえを連行する!」
「やましいことなどなにもやっていないんですから、あながたたに連行されるつもりはありません。私がスパイを働いたという証拠がどこにあるというんですか。なんの証拠ないじゃありませんか!、それに、誇り高い帝国軍人だとおっしゃるなら、もっと人間としての品格とというものを大切になさったらどうなんですか!……とにかく、もう私は仕事に戻ります」
当時の状況からして、素直に連行に応じれば、第三者の目がないのをよいことに身におぼえのない自白調書を捏造されたり、拷問にさらされたり、強姦や暴行をうけたりすることは目に見えていた。そんな事態になるくらいなら、女の意地にかけて自ら命を絶ったほうがまだしもましだと思ったミサは、その時すでにとこととん抵抗する覚悟を決めていた。
「逃げようたってそうはいかないんだ!……そこを一歩でも動いてみろ、容赦なくお前を撃ち殺すぞ、いいか!」
そう言いながら、相手の憲兵は腰から短銃を抜き取り、威嚇するようにその銃口をミサのほうに向けると、すぐさま彼女を拘束するよう顎で部下の男たちを促し動かそうとした。だが、それはまさに彼女が待っていた瞬間でもあった。ミサは短銃を構える憲兵のほうにすばやく近づくと、その銃口に自らその胸をぴたりと寄せ、相手の両眼を見すえて叫んだ。
「あなたの名前と所属をきちんと名乗りなさい。そして私がスパイだと確信があるならこの場で即刻射ち殺しなさい。それから、かねがね私をご存知の軍幹部の方々に、スパイ容疑で私を射殺したと報告しなさい。さあ、おやりなさい、あなたがたが正しいというなら、まわりの人も大勢見ているこの場で堂々と私を射殺しなさい。そのつもりで短銃を抜いたんでしょう!」
先刻からの騒ぎを聞きつけてホテルのロビーに集まった人々は、憲兵たちとミサとを遠巻きに取り囲み、その成り行きハラハラしながら見守っていた。日本人と中国人と欧米人との入り混じったその人々にも聞こえるように、彼女はいっそう挑発の度を強めながらさらに叫んだ。
「射ち殺しなさいよ!、そうでないと、私はあなたがたのこの不当な行為を軍幹部に報告しますよ!」
そう啖呵を切ったあとしばし無言の睨み合いが続いたが、ミサの思いがけない抵抗に相手はいささかたじろいでいる感じだった。怒り心頭に達した相手が発砲するかもしれないことを覚悟で胸元に突きつけられた銃口を見下ろす彼女の目には、かすかだがその筒先が小刻みに震えているのが見てとれた。
これだけ人目のあるなかでミサを射殺などしたら、彼女が懇意にしている軍幹部らにまで克明な情況報告がいくことは間違いないなかった。そもそも、そんなことをしたりしたらホテル側だって黙っているはずがなかった。そうなれば、彼ら憲兵の身だってそのままではすまないだろうことは明白だった。まただからといって、命がけでこれだけ毅然と無実を主張されたあととなっては、彼女を連行し密室状態のもとで不当かつ不正な調書を捏造するという姑息な手段に訴えるわけにもいかなかった。いまさら彼女を拘束してみても一連の事の次第が問題の軍幹部たちに伝わることは目に見えていた。
のるかそるかのミサの大博打は結局のところ効を奏した。苦々しい表情を浮かべ、彼女の顔を睨みつけながらもその憲兵は短銃をおもむろに鞘に収めた。そして、なんとかその場を取り繕い、ホテルから引き揚げる苦し紛れの理由づけでもするかのように、
「国際的なホテルの中のことでもあり、お客にも迷惑がかかるから今回は引下るが、今後また怪しい行動を取るようなことがあれば、断じて許さないからそのつもりでいろよ!、かねがね気の強い女だとは聞いていたが、それにしてもこれほどとはなあ……」と捨て台詞を吐くと、いかにもいまいましげな様子を全身に漂わせながら部下とともに立ち去っていった。
その後は、ミサのほうも、一人でいるところを急襲され拘束連行されたりすることのないように慎重に行動するよう心がけた。その甲斐あってか、それともミサの気性の激しさに圧倒されてか、幸いにも再び憲兵らが彼女の前に立ち現れるようなことはなかった。
石田翁が他界する一年ほど前のこと、たまたま高齢のミサさんに直接お会いし、当時の情況について詳しく聞く機会があったのだが、その時の話によると、パレスホテルでの憲兵との間のやりとりは、実際、女の意地を賭けた生死五分五分の大博打であったという。銃を突きつける相手の手に力がこもるのを何度も感じながら、その度ごとに、内心では今度こそ撃ち殺されるなという思いに襲われ、激しく緊張する有様だったのだそうである。

絵・渡辺 淳
「マセマティック放浪記」2003年12月17日
ある奇人の生涯 (41)
シーメンスから伊大使秘書に
憲兵らによって日本語学校を有無を言わさず閉鎖させられ、軍部から危険分子視されるようになった石田は、まだその身柄こそ拘束されていなかったが、そのままだと本国に強制退去させられるか、さもなければ懲罰の意味を込めて現地徴兵されるおそれが生じていた。そのため彼は大急ぎで対応策を講じる必要に迫られた。幸い彼の日本語学校の生徒にはドイツ人も多く、また、短い期間であったとはいえ上海社交界に名を馳せていたこともあって、ドイツ大使館やその周辺筋には知人がすくなくなかった。そこで彼は当面の身の処し方として、どこかドイツに深く関係する職場に斡旋してもらい、そこで働くことを思い立った。日本の同盟国であるドイツ公館筋の仕事をしていればそれなりの大義名分も立つし、憲兵隊といえどもドイツ公館サイドの了解なしに自分を連行したり強制退去させたりすることはできないだろうと考えたからだった。
当時上海に置かれていたドイツ大使館のツテで新たに石田が就いたのは、ドイツ・アルバイト・フロント(Deutsche Arbeit Front)顧問という一風変った仕事であった。建前としては、上海に進出しているドイツ企業に必要な人材の斡旋をしたり、ドイツ企業と現地在住のドイツ人や日本人、中国人、ユダヤ人、ロシア人などとの間をとりもったり、両者間に生じたトラブルの対応にあたったりする部署の相談役ということだったが、その実態はあってなきがごときポストではあった。だがそれでも、生活をするのに困らないほどの給料はちゃんと支払われもしたし、身分保証も十分になされていた。
日本語学校強制閉鎖のほとぼりがさめるまでドイツ・アルバイト・フロント顧問の仕事に従事したあと、石田はやはりドイツ大使館の知人の紹介でドイツ企業シーメンス上海支社に日本人顧問として就職、さらにはおなじくドイツ系の染料会社インダス・グレーンなどの顧問をも兼任した。大連のシティ・バンクにおいてそうであったように、それらドイツ系会社においても彼は短期間でめきめきと頭角をあらわし、ドイツ人支社長をはじめとする会社の幹部からも大きな信頼をうけるようになっていった。もちろん、憲兵隊や地元傀儡政権下の警察などからは陰で密かにマークされ続けていたに違いなかったが、直接にそれら官憲の手が彼の身辺に及ぶようなことはなかった。
厳しい報道管制がなされていたため公表されていはいなかったが、この頃になると同盟国側の戦況はいたるところで悪化の一途をたどりはじめ、一部の事情通の間では悲観論が囁かれるようにもなっていた。あまり多くは語られることがなかったけれども、ヨーロッパのドイツ・イタリア戦線が連合国側の反撃にあい徐々に不利に転じつつあるらしいということは、会社の幹部たちの会話の断片や業務の様子などからそれとなく感じとることはできた。ただ、それでも大戦の最後まで直接戦火にさらされることのなかった上海は、その時期まだ表面上は平穏で、南京路周辺の繁華街や大世界一帯の享楽街はなおそれなりの繁栄を保っていた。
シーメンスの支社長は日本人顧客や中国人要人を接待するときなどは、いつも必ず石田をその料亭やクラブに同行し、その応対にあたらせた。支社長はなかなかにこまやかな配慮の持ち主で、ドイツ流のマナーやエチケットを押し通したり押しつけたりするようなことはなく、たとえば日本人を接待するときなどには、自らはもちろん、部下たちにも日本風に振舞うようにあらかじめ命じたりしてもいた。そして、そのような場合にそなえて日本風のマナーやエチケットをドイツ人幹部に指導するのも石田の仕事のひとつであった。マナーやエチケットは国々によって大きく異なるから、母国の慣習にとらわれず常に臨機応変に対応すべきだというのが支社長の持論だったが、自己主張が強く自国の伝統に固執しがちなドイツ人気質を思うと、その支社長の柔軟な思考は意外なものにさえ思われた。
ただ、現実には真似しようにも真似することのできない生活習慣なども存在していた。その典型的な事例が食後に爪楊枝を使用する日本人の風習だった。事実上上海が日本の支配下に置かれるようになってからは、日本風料亭は言うに及ばず、それが中華料理店であれ西洋レストランであれ、日本人を接待したときには食後に必ず爪楊枝が出されるようになっていた。そんな情況の下において、ドイツ人と日本人が向かい合って会食したあとに見られる光景はなんとも奇妙かつ滑稽なものであった。
食後に爪楊枝が配られると日本人らは皆一斉にそれを受取るが、当然いっぽうのドイツ人たちのほうは皆それを不用だと辞退したものだった。そして次ぎの瞬間、日本人たちのほうは一斉に大きく口を開け、手にした爪楊枝の先で歯をほじくりはじめるのだが、それに対してドイツ人たちはちょっと困惑したような表情を浮かべながら、半ば不思議そうにそんな日本人たちの様子をじっと見守るというのがお決まりの光景だったからである。長い伝統と生活習慣の違いのゆえに生じるそのなんとも対照的な有様を目にしながら、石田は内心苦笑するばかりであった。
さすがの彼も食後の爪楊枝の使い方までドイツ人たちに教え込むことはできなかった。ドイツ人たちだって歯に食べ物がはさまることはあるだろうから、そんなときにはそれなりの対応をしているのだろうとは思ったが、すくなくとも食事のあとごとに爪楊枝みたいなもので歯をほじくる習慣のない彼らに、そんな日本人風の奇習を真似してもらうわけにはいかなかった。
ドイツ大使館筋、さらにはシーメンス社やインダス・グレーン社などでその語学能力や事務処理能力、的確な対外交渉能力などを高く評価されていた石田の噂はイタリア大使館にも伝わるところとなった。そのため、しばらくすると、ドイツ大使館員を介してイタリア大使館から石田に同大使館に勤務してくれるようにとの要請があった。シーメンス支社長は彼の能力を惜しんだが、せっかくの話をむげに断るわけにもいかず、結局、石田はイタリア大使館の大使秘書に就任した。そのお蔭で、いっそう身の安全は保証されるようになったけれども、同盟三国の極秘戦時情報を入手しやすい立場だけに、憲兵らがその不用意な行動を逆手にとって彼をおとしめにかかるおそれはあった。だから、彼も言動には慎重を期すことをこころがけた。
もっとも、このイタリア大使館勤務はその後の石田の運命に善い意味でも悪い意味でも皮肉な結果をもたらした。彼が大使館勤務をはじめた一九四三年の後半頃まではヨーロッパ戦線の情況が直接上海の大使館にまで影響をもたらすことはなかったが、翌年の一九四四年になると、ヨーロッパでの戦況の余波が遠く上海にも及ぶようになり、その結果予期せぬ事態が起ってしまったからである。
石田が大使秘書になった当時はまだヨーロッパの本国ではムッソリーニ政権が存続中だったから、イタリア大使館もそれなりに活発に機能しており、大使の仕事もすくなくなかった。彼も大使秘書としての業務を手際よく処理し、ことあるごとに力を尽して大使をサポートしようと心がけたから、その仕事ぶりに対する大使館の評価は高く、当然のことながら報酬も十分なものであった。
ところが、翌年になると、イタリア大使館内の雲行きがみるからにおかしくなってきたたのだった。折々不安と困惑の入り混じった表情を浮かべ、落ち着かない様子で考え込む大使の様子からも、ムッソリーニ政権下のイタリア本国が相当に厳しい状況におかれているらしいことは察しがついた。実際、この時期、連合国側の反撃攻勢に遭ってイタリア軍はずるずると敗退を重ね続け、追い詰められたムッソリーニ政権はついに崩壊、三国同盟の一角を担っていたイタリアは降伏するのやむなきに至った。だが、ナチス・ドイツはすぐさまイタリア各地を制圧してムッソリーニを保護下におき、パトリオ政権がそのあとを継承することになったのだ、イタリアはもはや政治的にも経済的にも完全に破綻した状況となった。そして、その影響をもろに被って上海の大使館そのものがうまく機能しなくなり、大使館員のやるべき仕事もほとんどなくなってしまったのだった。
大使秘書の仕事を解職こそされなかったものの、本国からの活動資金供給が途絶えがちになった大使館は職員の給与を大幅にカットするようになった。当然、石田の給料も半分以下にカットされ、やがては解雇通告もないままにほとんど給与が支払われない情況になってしまった。そしてそうこうするうちに、午前中出勤するだけで、午後は帰宅しても構わないと言い渡される事態にたちいたったのだった。上海にやって来た当時のような余分な貯えなどなかったから、とりあず生きていくためには何かほかの仕事をもやざらるをえなくなった。やむなく、大使館側に、午前中出勤したあとは何かほかの仕事に携わってもよいいかと相談をもちかけると、もちろん自由に何をやってもらってもかまわないというそっけない返事が戻ってきた。
そこで石田は早速他の仕事を探しにかかった。だが、午前中だけイタリア大使館で働いて午後から別の職場に出向くとなると、どうしても午後からの仕事のほうが中途半端になってしまう。そのため、現実にはこれというところを探すのは思ったほどに容易ではなかった。
もう一度シーメンスのようなドイツ系の会社にとも考え、あれこれ奔走をしてみはした。だが、まだイタリアほどではなかったにしても、ドイツもまた連合国の猛反撃によって既に劣勢に立たされ、戦況好転の見込みなど立たない状況になっていた。しかも、太平洋、大西洋、たインド洋は言うに及ばず、東シナ海や日本海の制海制空権までがほとんど連合国側の手に握られようとしていた。そのため、海上封鎖が現実のものとなりはじめ、ドイツ系企業といえどももはや業務遂行そのものが困難な情況になっていた。もちろん、だからといって、いまさら上海の日本人社会やその傘下の職場に飛び込み、軍部の監視下のもと、戦時思想にあまんじながら息を潜めて不承不承生きていく気にもなれなかった。そして、結局、そんな石田が潜り込むことにしたのは、いかにも彼らしい、しかし普通の人々の感覚からするとなんとも意外としか言いようのない仕事場だった。

絵・渡辺 淳
「マセマティック放浪記」2003年12月24日
ある奇人の生涯 (42)
大使秘書が賭博場の用心棒を!
結局、石田が第二の仕事として選んだのは、あの歓楽街大世界の一隅にある賭博場の用心棒であった。もっとも、用心棒とはいっても、ドスや銃器類を隠し持っていていざというときに身体を張って賭博場の親分を死守するあのヤクザまがいの用心棒ではなかった。賭博場をめぐって客と店との間や客同士の間に起こる大小のトラブルに割って入り、話し合いをもって穏便に処理したり、官憲の調べをあらかじめ察知して賭博関係者の逮捕を防いだり、急な手入れに備えて周辺を見張ったりするのがその仕事内容だった。
「いくらイタリア大使館があってなきがごとき状態になっていたとしても、大使秘書と賭博場の用心棒とを兼務したとは驚きですね!……どうやってそんなところへ?」
取材の際、当時の話を聞きながらこちらがそう尋ねてみると、老翁は悪戯っぽい笑みを湛えながらも、静かな口調でそのへんの事情をかなり詳しく語ってくれた。
「いまの時代からすると信じられないことかもしれませんがね、当時の上海の政治や経済の情勢からしますとね、もう仕事の種類に貴賎などの差別をつけておられるような状況じゃなかったんですよ。詰まるところ、支配する立場と支配される立場があるだけでね……。過酷な支配を受けていた中国人らは、日本軍部とつながりのある一部特権階級を除いては、その苦しい時代を生き抜くために、善悪を超えて知恵を働かせその身を守り続けなければならなかったんですから」
「それはたぶんその通りだったんだろうとは思いますが、そうは言ってもあまりに大使秘書と賭博場の用心棒とではかけ離れているような……」
なお納得がいかないでいるこちらの口振りをまるで諌(いさ)め諭しでもするかのように石田翁は言葉を続けた。
「いいですか……、かつてのフランス租界だって英米租界の場合だって、結局、各国の領事館当局は、賭博や麻薬売買、売春などの胴元である紅幇や青幇などの中国人大親分と裏で密接な関係を持ち、莫大な利益の分け前を本国へと持ち返っていたんです。当時の上海の繁栄というものは、表面的には別物に見える各種金融業や貿易業、ホテル業、飲食業、サービス業の発展、さらには文化芸能関係の興行等の隆盛を含めて、すべてが賭博、麻薬、売春と表裏一体の関係にあったんですよ」
「じゃ、日本語学校の経営も、ドイツ・アルバイト・フロントやドイツ企業支社の顧問も、大使館秘書も、そして賭博場の用心棒も、本質的には大差などなかったとでも?」
まだ十分には納得がいかない思いでさらにそう問いかけると、
「ちょっと極端な言い方に聞こえるかもしれませんが、すくなくとも当時の私の目からすると、そういうことになりますかね。フランス租界や英米租界までが日本軍部とその傀儡政権とによって支配されるようになってからというもの、表向きは賭博、麻薬、売春などに対する取締りが厳しくなりはしましたが、それは中国人筋や日本以外の外国人筋にその利益の多くが流れるような場合で、結果的に日本に莫大な利益が還流するようなケースには目をつむったままでしたからね」と老翁は答えた。
「結局、公衆道徳や社会生活の健全化というのは建前で、要は利権を握ることだけが狙いだったということですね」
「そうなんですよ。官憲による賭博場の手入れだって、賭博そのものをやめさせるというよりは、現場を急襲し捜査という名目でその場にある金品や客のもつ所持金、宝飾品類を根こそぎ持ち去り、それで私腹を肥やそうというのが当局関係者の本音だったわけですから……」
「それで、石田さんはどんな筋の賭博場の用心棒をやったんですか?」
「たぶん青幇傘下の中国人親分が仕切る賭博場だったとおもいます。日本語学校を経営していた頃からの付き合いでなにかと気心の知れた中国人が何人もいましたので、彼らに紹介してもらいその仕事場に潜り込んだんです。出入りするお客には中国人のほか、日本人もずいぶんいましたよ。日本人客には結構有名な芸能人や宝塚から流れてきた元関係者などもいましたね。そのほかに、ユダヤ人やロシア人などの姿もかなりの数見られましたよ。その賭博場の儲けがどこにどう流れていたのかまでは私の知るところではありませんでしたけれどもね」
「賭博そのものをやったととかいうなら話はわかるんですが、それにしても、賭博場の用心棒というのはまたどんな風の吹き回しで?……、ヤクザなみに身体を張っての用心棒ではなかったとはいっても、やっぱり石田さんのいまの姿とはどうしても結びつきませんが……。まさか、英語やドイツ語で啖呵を切る必要があったわけでもないでしょうにね?」
「東京でのカフェバー勤めや青島でのダンスホールの裏方のような仕事、さらには香具師の大親分の秘書など、それまでにも世の中の裏の世界にかかわる仕事をやって生き抜いてきてますからね、賭博場の用心棒という仕事にもべつだん偏見などありませんでしたよ。中国人なんかはとくに、みんな必死でその苦難の時代を生きていたわけなんですからね」
「どんな賭博がおこなわれていたんですか?……、石田さんも賭博でちょっとは儲けたとかいうことも?」
「賭博場では様々な種類の賭けがおこなわれていました。現代においてもよく見られるような西洋式の賭博もあれば、サイコロ賭博や花札といったような日本風の賭博などもありましたね。ただ、私自身は競馬とドッグレース以外の賭け事は嫌いでしたから、自らそれに手を染めることはありませんでした」
「じゃ、もっぱら見張り役とトラブルの調停役だったということですか?」
「ええ、そうですね。それとね、開戦直後からは事実上日本人が上海を牛耳っていたわけですから、賭博場に日本人の見回り役がいるというだけで、お客にはもちろんのこと、組織の異なる中国人や他の外国人系の裏社勢力にも警戒心がはたらいたんですね。だから、変な騒動が起ったりすることがあまりなくですんだんです。それからもうひとつ、日本人が賭博場にいるということだけで、日本人や外国人の金持ちのお客たちが安心して出入りできるという利点があったんですね。そうやって上客が顔を出してくれれば、賭博の胴元としては願ったり叶ったりですからね」
「なるほど、それじゃ、石田さんは睨みをきかしながら賭博場や賭博場のある大世界界隈を歩きまわっていたんですね。それで、黒いサングラスなんかかけてですか?」
穂高駅前で初めて声をかけられたときの石田翁のどこか凄みのあるサングラス姿を想い起こしながらそう問いかけると、一瞬、相手はこちらの予想を裏切って申し訳ないとでもいったような笑顔を見せながらさらに答えた。
「いやいや、サングラスなんかかけていませんでした。にこやかな顔を見せながら、あくまでも紳士的に振舞ってましたよ。ここは安心して賭けに興じることができる場所だとお客におもってもらえるようにとね……。欧州のカジノだって、ラスヴェガスのカジノだって名の通った賭博場というのは、お金は動くけれど見るからにいかがわしいっていう感じはしませんよね。当時の上海の賭博場は欧米人の影響を受け、それなりに洗練されていましたから、日本風のサイコロ賭博や花札賭博やる場合だって大テーブルを前に腰掛けてやっていたわけで、日本のヤクザ映画に出てくるような異様な雰囲気はありませんでしたよ」
「なるほど、言われてみるとそれはそうですよね。僕もラスヴェガスの賭博場は一、二度のぞいたことがあるんですが、暗い感じなどまったくありませんものね。現代のラスヴェガスなんて、アメリカで一番安全なところだなんて言われたりしているくらいですから」
「それとね、身長が一七六センチある僕は当時の日本人としては、そしてまたアジア人としては珍しいほどに大柄でしたから、そのことだけで賭博場に出入りする人々に無言の威圧感を与えてはいたようですね。べつに武術のたしなみがあるわけでもありませんでしたし、武器を隠し持っているわけでもありませんでしたから、ほんとうに殴り合いの喧嘩なんかになったらコテンパンにやられていたでしょうね」
「なるほど……、用心棒の石田さんは強そうに見えたけど、実は張子の虎だったというわけですね。ただ、相手が勝手に強そうだと思い込んでくれたおかげで、カジノ仕込みのポーカーフェイスを貫き通し、結果的に張子の虎でも役に立ってしまったと……」
「ははははは……、まあ、そんなところですね。ただ、官憲による手入れの情報や、警察の回し者などについての情報は、それまでにいろいろな方面と付き合いがあったせいでいちはやく入手することができました。まあ、もちろん袖の下を渡してのことではありましたんですけど、ともかくそのおかげで何度もうまく捜査の手を逃れることはできました」
「それで、用心棒の報酬のほうはどうだったんでしょう?、『用心棒』の芯の部分が実のところ空洞になっていたっていうわけですから、バレたりしたら目も当てられないことになっていたんでしょうが……。喧嘩の弱い用心棒じゃ、次ぎから皆になめられて仕事になんかなりませんものね?」
こちらの意地悪な問いかけにも石田翁は悪びれることなくたんたんと答えてくれた。その表情はむしろこちらの質問に応じることを心から楽しんでいるかのようでさえあった。
「幸いというか、最後まで化けの皮は剥げなくてすみましたんで、生活していくには困らないほどの報酬はもらえました。それに、賭博場はなんと言っても夜が仕事の主たる時間帯で、みな適当に食事を取りながらお客の相手を務めるわけですから、夕食代なんか自分で払うことはまずありませんでしたね」
「でも、賭博場の仕事は結構夜遅くまであったわけでしょう。たとえ張子の虎なみの中身が空洞な見かけだけの用心棒だったとしも、賭博場の営業が終わるまでは帰るわけにもいかなかったんでしょうね。翌朝の大使館出勤に響かなかったんですか?、いくら開店休業状態の大使館だったとはいいましてもね?」
「それがですね、年が明け、一九九四年になってしばらくすると、イタリア大使館そのものが閉鎖状態になってしまったんです。連合国がイベリア半島に上陸し、防衛にあたったドイツ軍はじりじりと内陸部への撤退を余儀なくされていましたから、日本の傀儡政権との関係で上海におかれたイタリア大使館には存在意義がなくなったんです」
「じゃ、イタリア大使秘書という仕事も自動消滅というわけで?」
「もちろんです。それで、結局のところ、賭博場の用心棒の仕事に専念することになったんです」
「イタリア大使館秘書からいっきに賭博場の用心棒に転落ですか、なんとまあ!……でも、それ以上にヤバイ仕事の手伝いなんぞはなさらなかったんでしょうね?」
麻薬取り引きや売春斡旋がらみの仕事のことをそれとなく暗示しながら、そう尋ねると、
「あのような状況ですから、もちろん、麻薬取り引きに手を染めようと思えばそうすることができたかもしれません。周辺にはアヘンの常習者もずいぶんといました。でも、麻薬関係の仕事には絶対に手を出しませんでしたよ。売春のほうは、あれは中国人の組織がやっていたことで、日本人がその組織にかかわり、そこから金銭を得るようなことはほとんどありませんでした。とにかく、賭博場の芯の空っぽな用心棒どまりがまあよいところではあったんでしょう」と言って、石田翁はどことなく自嘲気味な笑みを浮かべた。
「それで、その賭博場の用心棒の仕事は終戦時までずっと?」
「いえいえ、そうそう事は無事には運びませんでしたよ」
「じゃ、また、予想外の事態が起ったんですか?」
「予想外というわけではなかったんですが、とうとう僕のところにも来きたんですよ。あれがね……、現地の警察による賭博場の一斉手入れの翌日にね……」
石田翁はそこまで話し終えると、いったん言葉を切ってキッチンへと向かって立ち上がった。

絵・渡辺 淳
「マセマティック放浪記」2004年1月14日
ある奇人の生涯 (43)
現地徴兵で軍隊へ
この一九九四年の十月下旬、フィリピン奪回を目指す日本海軍連合艦隊は「捷一号作戦」を実行に移し、戦艦武蔵、大和、長門、金剛を中心とした海軍最強の編成艦隊を組んでレイテ湾突入を敢行した。しかし、米海軍機動部隊の猛攻撃に遭ってレイテ湾突入を阻止され、五日間ほどにわたる周辺海域での大激戦のすえに武蔵をはじめとする戦艦三隻と空母四隻を喪失した。戦艦大和は撃沈を免れたものの、主力空母四隻をすべて失った結果、この時点で日本海軍機動部隊は事実上消滅した。
このレイテ沖海戦に際しては海軍航空部隊によって神風特攻隊が編成され、劣勢となった国の運命を賭けて戦闘に初出動することになった。二五〇キロ爆弾を装着した零式戦闘機が機体もろともに敵艦隊に体当たり突入するというこの決死的攻撃は当初米軍に恐怖と戦慄をもたらしはしたものの、結果的には大勢に影響を及ぼすことはなく、日本海軍は壊滅的敗退を余儀なくされたのであった。
おなじくこの年の十一月下旬にはマリアナ海域から発進したアメリカの爆撃機B29が東京を初空襲し、以後、日本本土の各地は容赦ないB29の猛爆撃にさらされることになった。客観的に見て、もはや日本の敗戦は必至という状況に追い込まれていたにもかかわらず、日本軍部はその事実をなお隠蔽し大多数の国民の目を欺き続けていたが、さすがにこの時期とになると戦況の極端な悪化を薄々感じとりはじめた者もすくなくはなかった。石田の仕事場である上海の賭博場に日本軍傀儡政権下の中国人警察官らによる一斉摘発の手が入ったのはちょうどそのような時期のことだった。
手際よくお茶の準備をすませてキッチンから戻った石田翁は、こちらの要請に応じてその時の手入れの様子やその後の状況についてさらに詳しく語ってくれた。
「多数の中国人警察官が突然賭博場に踏み込んできましてね、有無を言わさず中国人従業員や中国人客、欧米系のお客らを次々に逮捕し連行していきました。ただ、私をはじめとする日本人従業員や日本人客には彼らは手を出しませんでした」
「そうだったんですか。じゃ石田さんご自身はとくに身柄を拘束されることもなく、無事にすんだわけですね。でも、さっき、確か『とうとう僕のところににも来たんですよ』っておっしゃってましたが、いったい何が来たっていうんですか?」
「翌日にはいわゆる『赤紙』、すなわち、徴兵令状が届いたんですね。僕は危険分子として憲兵隊などからマークされていましたから、すべては計算通りだったんでしょうね」
「現地召集だったわけですね?」
「ええ、僕は徴兵検査は丙種合格でしたから、甲種、乙種合格の人たちに比べて徴兵される可能性は本来すくないはずでしたし、たとえ徴兵されるにしても、一度本国へ強制退去させられ、本国のどこかの部隊に召集されることになるだろうと考えていたんです」
「ところがいきなり現地召集ということになってしまった……」
「全般的な状況からしていずれ徴兵令状が届いてもおかしくないとは思っていたんですが、現地召集になるとまではね……。現地召集には懲罰の意図が込められていることがすくなくなかったんですよ。かねてから僕に狙いをつけていた憲兵隊が陰で動いて、ここぞとばかりに徴兵令状を突きつけてきたのでしょう」
「なんだかんだと逃げまわっていた憎き石田達夫をいまこそ存分に懲らしめてやるってわけだったんですね!」
「もちろん軍隊は大嫌いでしたから、内心、癪で癪で仕方ありませんでしたが、そればっかりはもう逃れようがありませんでした」
「懲罰を受けたのは石田さんだけで、賭博場に出入りしていた他の日本人たちにはとくに厳しい処罰などなかったんですか?」
「いえ、そうじゃありませんでした。結構名の通った連中がお客として出入りしていたんですが、不良遊技場で不良外人との交際があったという理由で、ほとんどの者が本国へと強制退去させられたんです。その中には李香蘭や、『湖畔の宿』の歌で知られる高峰三枝子のダンナなんかも含まれていましたね。この頃になるともう、直接賭博場とは関係なくても、外国人とちょっと交流があったというだけでどんどん本国へと退去させられてましたね」
「それじゃ、もしも現地で徴兵されていなかったら、石田さんも日本へと送り返されていたわけですね?」
「間違いなくそうなっていたでしょうね」
「しかし、賭博場の手入れの翌日には赤紙が届いて現地召集とは、なんとも手際がよいというか……、憲兵隊の意図が見え見えですね。当然、憲兵隊に逆らったミサさんが石田さんと付き合っていることなんかも相手はとっくにチェック済みだったんでしょうから、何から何まですべて計算ずくだったんですね」
「その背景が実際にどんなものだったはいまさら知るよしもありませんが、徴兵の裏に一物あったことは確かでしょうね」
「それで、徴兵されて現地入隊したあとの軍隊での生活はどんなものだったんでしょう?」
さぞかし厳しい試練が待っていたのだろうと想像しながらそう尋ねると、老翁は何事かを考え込むかのようにしばし口をつぐんでから、半ば吐き捨てるように言った。
「想い出したくもないですね。くだらないとしか言いようのないものでしたよ!」
実際のところ、石田翁は終戦までの一年間ほどの軍隊生活についてはあまり多くを語りたがらなかった。正直なところ、そんな老翁にあくまでしつこく食い下がり、その時の状況を根掘り葉掘り聞きだすのもどうかという思いはした。だから、こちらもすくなからず気おくれはしたのだが、それでも、せめておおまかな様子くらいは知りたいと考えなおし、あえて質問をぶつけ続けた。すると、老翁は一度は困ったものだとでも言いたげな表情を浮かべはしたものの、なんとか言葉をつなぎながら、ある程度の状況を語ってはくれたのだった。
「上海で召集されたあとはどちらへ?」
「南京に連れていかれ、そこで新参兵としての軍事訓練を受けさせられました」
「南京事件のあったあの……?」
「そうですよ。古参兵や下士官たちは、なにかというと、チャンコロを何人やったとかいった類の自慢話なんかをしてましたね。まあ、当人たちにすれば武勇伝のつもりだったんでしょうけれどね」
「チャンコロって、当時の中国人に対して日本の軍人などが用いた蔑称ですよね?……、まだ幼なかった頃のことですが、田舎でおこなわれる宴会の席などで兵隊帰りの大人たちがその言葉を使うのを何度も耳にしたことがありますよ。当時の軍人たちが中国人大衆を人間扱いしてなかったことがよくわかるような……」
「僕は中国人たちとも親交がありましたからね。内心では、よっぽど当時の日本軍の古参兵や下士官らのほうがその蔑称に相応しいと思ってましたけれどね」
「それで、もっとも階級の低い新兵として入隊し厳しい教練を受けることになったんですよね?」
「実を言いますとね、僕は旧制高校を卒業していますから、その気なら訓練を受けたあとすぐにも下士官になることはできたんです。でも、軍隊の下士官なんかには絶対になりたくありませんでした。だから、あくまでも高等小学校卒ということで押し通したんです。そのため、それ相応の待遇のところへ配属されたわけですよ」
「でも、石田さんが高等小学校卒なんかじゃなく、旧制高校卒で知的な仕事に就いていた人間だっていうことは上官にはわかっていたんじゃないんですか?」
「はじめのうちはともかくとしても、しばらくしてからは学歴を詐称していることは相手にもわかったに違いありません。ただ、おなじ学歴詐称とはいっても、通常のそれとはまるで逆の詐称だったわけですから、上官からもそれを責められたりすることはありませんでした。むしろ面白がっていたのではないでしょうか。ずっとのちになってからのことなんですが、たまに将校らに呼ばれ、彼らの話相手をさせられるようなこともありましたから」
「でも、高学歴を隠し通したことはけっして得にはならなかったんじゃないですか?、階級社会の軍隊ではすこしでも位の高いほうがそのぶん苦労がすくなくてすんだでしょうに!」
「でもねえ、学歴をたてにすこしでも早く下士官になって楽しようなんて思ってもみませんでしたね。いまさら損得の問題として考えてみたってまるで意味のないことなんですが、まあ、結果的にはプラス・マイナス両面あったと言うべきなんでしょうかねえ」
「わざわざ一兵卒に甘んじ通したなんて、現実主義の石田さんからすると意外な感じを受けないでもないんですが……。まあ、それはともかく、そのプラス・マイナスと言いますと、いったいどのような?」
「そこまで計算していたわけじゃないんですが、あの時に学歴を正直に申告し下士官になっていたら、懲罰の意味をも兼ねて早々と最前線の激戦地に送られ、たぶん戦死してしまっていたでしょうね。僕を現地徴兵した憲兵隊のほんとうの狙いはそのあたりにあったのかもしれません」
「なるほど、そういうことですか……、それも石田さんならではの悪運の強さで?」
「ははははは……、そう言えないこともないんですが、ほんとうの悪運の強さはもっとあとになってから発揮されることになるんですよ」
「そうなんですか……。それはともかく、じゃ、下士官にならなかったことのプラス面はそうだったとして、いっぽうのマイナス面にはたとえばどういうことが?」
「そりゃもう、新兵の戦闘訓練の名目のもとに、古参兵らのストレスの捌け口として、それから一年近くというもの、連日連夜、殴る、蹴る、罵るにはじまる暴力の嵐にさらされ、とんでもない無理難題の山に苦しみ続けさせられましたよ」
老翁はそう語ったあとで、軍隊入隊時から終戦に至るまでの想い出の一端をさらに披露してくれた。

絵・渡辺 淳
「マセマティック放浪記」2004年1月21日
ある奇人の生涯 (44)
軍事訓練の名のもとに
軍事訓練をうけていた時期の出来事などいまさら想い出すのも嫌だという表情の老翁だったが、その重い口からそれでもいくつかの話を聞き出すことはできた。意図的に記憶の古層に沈め押し込められている当時の苦い想い出をほじくりかえすのはけっして本意ではなかったが、この際やむをえないことではあった。
「それで、その軍事訓練というか、戦闘訓練はどんな様子だったんですか?」
「そうですね、まあ、たとえていうなら、泳いで太平洋を渡れって命令されているようなものでしたかね、いや、歩いて太平洋を渡れっていわれているようなものだったのかな?」
「ははははは……、それで石田さんは沖の小島くらいまではなんとか歩いて渡れるようになったとか?、でも、もっと以前にその技術を修得していたら、ナーシャさんと一緒に大連の老虎灘の小島に渡るときも服を脱いで泳いだりしなくってもよかったでしょうに!」
老翁の軽口にこちらも軽口をもって応じると、あいてはさらに切り返してきた。
「でもねえ、もしもそうだったら、あの一生一代のロマンスは起こらなかったかもしれませんね。あのとき二人とも普通の服を着たまま島に渡っていたらあんな風なことにはならなかったかもしれないでしょう?」
「でもその場合、石田さんがナーシャさんを抱きかかえるか背負うかして海面を渡ることになったでしょうから、十分ロマンスに発展する可能性はあったんじゃないんですか……、ただまあ、それは冗談としまして、戦闘訓練はそのくらい大変だったっていうわけですね」
そう言って脱線気味の話をとりあえず元に戻そうとすると、老翁も素直にそれに応えてくれた。
「まずはじめに、軍服と軍靴を着用し銃剣その他の装備を携行したまま、連日連夜行軍したり寝起きしたりする訓練を受けたのですが、いきなりの経験ですから辛くて苦しいの一語に尽きましたね。その間に靴を脱ぐことさえも許されないわけですからね」
「話には聞いていましたが、実際大変だったんでしょうね?」
「あまりに激しい訓練のせいで体調が悪くなったりすると、むやみやたらに殴られたり蹴飛ばされたりしましたね。このくらいのことに堪えられないようでは実戦では死んでしまうぞと怒鳴られ、理不尽な暴行を加えられるわけです。またたとえ指示された通りに行動したとしても、結局は訓練を受けている全員が下士官や古参兵からありとあらゆる罵詈暴言を浴びせかけられ暴行のかぎりを尽されるわけなんです。軍事訓練というよりは、軍事訓練に名を借りた古参兵らの鬱憤の発散の場とでも言った感じでしょうね」
「それでなくても反抗的だったんじゃないかと想像される石田さんなんかはずいぶんと殴られたんでしょうね」
「東北出身の古参兵がいましてね。その男からは一年間近くほとんど毎日殴られっぱなしでしたよ。『高等小学校を卒業しているのにこの程度のこともわからんのか!』って口癖のように喚きながら殴ったり蹴飛ばしたりするんですが、毎日素手で殴っていると自分の手も痛くなるものですから、厚手のスリッパで頭や両頬を力いっぱい何度も殴られたり、木刀や竹刀で打ちすえらえたりすることもしょっちゅうでしたね」
「もちろん、その間は無抵抗ですよね?」
「内心は怒り狂っているわけですが、ちょっとでも反抗的な態度を見せると、自分だけでなく他の仲間たちも際限なく痛めつけられるわけなんです。軍規では上官の命令には絶対服従しなければならないことになってましたから、事情がどうであろうとひたすら堪えるしかありませんでした」
「嫌なことを想い出させて申し訳ないんですが、殴る蹴るのほかにもいろいろと理不尽な行為にさらされたとか?」
「そうですね、懲罰に軍服を着たまま頭から水をかけられ、寒い屋外にそのまま一晩放置されるとか……雨中訓練や寒中訓練の一環だと称しましてね。あと、何時間にもわたって不自然な体勢をとり続けるように命令されるとか、動物なみの奇声を発し続けるように強制されるとか、むりやり裸にされて卑猥な行為のポーズをとり続けさせられるとか、まあ、いろんな懲罰がありましたよ」
「軍事訓練とは直接関係ないシゴキがずいぶんとあったわけなんですね?」
「もちろん、そのころ、南太平洋方面の戦線においては、すでに日本軍は私たちの受けていた軍事訓練などとはくらべものにならないほどに悲惨な状況におかれ、ほとんどの兵士たちが生き地獄そのものの世界をさまよっていたわけです。そのことを考えると文句は言えなかったのかもしれませんが、むろんそんな情報は中国の日本軍にはまだ伝わってきてはいなかったはずですしね。それに、南方戦線では上官も下士官も兵士もみな一様に生死の境をさまよい、ほとんどの兵士が戦病死し、奇跡的に生還した者も地獄の苦しみを味わったわけですが、それとはまるで状況が違っていたわけですからね」
「太平洋戦争の末期の沖縄周辺における日米両軍の激闘の模様だって中国の日本軍筋に届いていたかどうかは疑問ですよね。幹部クラスの一部上官はそんな状況を把握していたのかもしれませんが、一般の兵士にまで沖縄戦の具体的な状況が伝わるわけなどなかったでしょうから」
「私の場合は、徴兵される前にイタリア大使館秘書の仕事がなくなってしまったりしたことや、それまで付き合いのあった外国人らを介してちらほら耳にする噂などから、なんだか雲行きがおかしいなというくらいのことは感じていました。でも、南方戦線の詳細な情報や入隊後に起こった沖縄戦の模様などを耳にすることはありませんでしたね」
そこで一呼吸をおいたあと、石田翁は急に想い出しでもしたかのように、いまひとつ醜悪なある出来事についての話をしてくれた。
「入隊してから半年以上たってからのことなんですが、時々将校連中から呼ばれて彼らの話相手をするようになったんです。たぶん、どこからかそれまでの私についての情報が流れ、ほんとうは高等小学校卒じゃないことがわかってたんでしょうね。それはよかったんですが、ある夜のこと、将校たちのとことろへと行った帰り、一部の下士官や古参兵らのいる部屋のそばを通りかかったんです。すると、中から若い女の悲鳴のようなものが聞こえてきました。いったい何事だろうと立ち止った次ぎの瞬間、ドアが開いて一人の軍曹が現れ、私の顔を見ると意味ありげにニヤリと笑ったんです。相手はトイレかなにかに行こうとしたところだったようなんですが、何を思ったのかすぐさま私を部屋の中に引き入れました」
「いったい何が起こっていたんですか?」
「中には下士官や古参兵など数人の男たちがいて、どこから連れてきたのかはわかりませんが、一人の若い中国人女性を素っ裸にして、有無を言わさず次々に強姦を繰り返しているところでした。一見したところとても綺麗な中国人女性だったように記憶してますが、言葉にならない叫び声や呻き声をあげ必死に抵抗する彼女をいたぶり弄びながら、男たちはおのれの性器を丸出しにして順繰りに襲いかかっていたんです。とても直視できるような光景ではなかったので、おもわず目をそむけてしまいました。誇り高き日本軍人などとは程遠い数匹の野獣の群といったところでしたね」
「それで石田さんはどうしたんですか?」
「見るに堪えかねてすぐに部屋を出て行こうとしたんですよ。ところが、その中に例の古参兵もいましてね、その男が私の腕を掴むと、おこぼれに預からせてやるからお前もヤレっていうんです。むろん私は辞退、いや拒絶しました。すると、彼は、『これは上官の命令なんだ、新参兵の分際で上官の命令に逆らうとは何事だ!』と凄んできたんです。他の男たちはそれを聞いてゲラゲラ笑ってましたよ」
「結局、石田さんも彼らと同罪に?」
少々意地悪な質問とは思ったけれども、ここまでくるともうやむをえないと考え、そう確認してみようとした。すると、なんということを言うんだとばかりに、老翁はすぐさま首を振って、さらに言葉を繋いだ。
「直立不動の姿勢をとり敬礼をすると、『たとえ上官のご命令ではあっても、こればかりは従うわけにはまいりません。他言は致しませんからどうか私をお見逃しください』と告げたんです。すると、相手は悪意に満ちた笑みを満面に湛え、それから『お前はそれでも日本男児か?、日本男児ならちゃんとついとるべきもんがついとるんだろうが!』と居丈高に叫ぶと、私の胸ぐらを掴み、顔面を二度ほど激しく殴りつけてきました。それでも我慢して不動の姿勢をとり続けていると、今度はパンツごとズボンを引きずり下されてしまいました」
「それでむりやりその女性のところへ連れていかれたとか?」
「いえ、さすがにその男たちの中の一人が見かねたとみえ、『こいつはたぶんインポなんだろうさ。わざわざいい思いをさせてやろうっていうのになあ。まあ、使えるような状態じゃなさそうだからもう放してやれよ』と言ったんです」
「助け舟っていうにはあんまりな言葉ですし、そもそも、そのインポっていう表現、当時の日本人の間で使用が禁止されていた敵性言語にほかならないようにも思われますけどねえ……」
冗談を言うのはいささか不謹慎な気もしたが、話の向きが向きなのでその場の雰囲気をちょっとばかり変えようかとそう茶々を入れると、老翁もそれに応じてまた軽口を叩いた。
「インポって表現はもちろん敵性言語ですから、本来なら『直立不動拒否症』だとかいったように表現すべきだったんでしょうね」
「ははははは……、いったいなんですかそれは?」
「まあ、その一時的な『直立不動拒否症』のお蔭でともかくも私はその場を逃れることができたんです」
「まさかあとになってから、やっぱりあのとき上官の命令に従っておけばよかったなどと後悔したりはしなかったんでしょうね?」
「あなたのご期待にそいたいところではあるんですが、さすがにそんなことはなかったです。私が部屋を出る時に一瞬目にしたあの中国人女性のなんとも言えない表情がいまも忘れられませんよ」
「と言いますと?」
「そうですね……、なんと言いますか、先ほども話しましたようにその中国人女性はみるからに知的な感じの美人でしたし、たぶんそれなりに育ちもよい女性だったのでしょう、さんざん強姦され人間としての誇りもなにも踏みにじられてしまったあとだというのに、彼女は毅然として男たちのほうを睨みつけていました。その目に涙のあとがあったどうかは記憶にありませんが、その表情や姿には、表面上はどんなに辱め穢されたとしてもそれだけはけっして犯されたり穢されたりすることのない、天性の誇りとも気品ともいったようなものが感じられたんですね。『どんなに辱められても私は人間なんです。そして、あながたのような野獣が私の身体をどんなに侮蔑し貶めてみても、私の心の中までは断じて穢すことはできないんです。やれるものならやってごらんなさい』と彼女の双眸が語っているように感じられてならなかったのです」
「結局、その女性はどうなったんでしょう。解放されたんでしょうか?」
「さあ、どうなったのかは私にはわかりません。もしかしたら、あのあとで処刑されたのかもしれません。もちろん気にはなっていましたけれども、そこにいた下士官や古参兵にどうなったのかなどと訊くことはできませんでしたから……」
「なんだか嫌な出来事を想い出させてしまいましたね。申し訳ありませんでした」
「……」
老翁はこちらのそんな言い訳じみた言葉には何も答えず、そのあとしばらく深い沈黙に身を委ねたままだった。

絵・渡辺 淳
「マセマティック放浪記」2004年1月28日
ある奇人の生涯 (45)
南京から漢口へ
一九四五年に入ると国内外各地での戦況は著しく悪化し、日本本国もまたその例外ではなくなっていた。この年の一月十九日には、阪神地方や川崎、明石などの軍需工場がB29による爆撃のために大きな損害を被り、つづいて翌二月の初めには神戸一帯が空爆にさらされ、その被害はますます拡大の一途をたどった。さらに二月の半ばには米軍艦載機二千機による関東、東海地方に対する大空爆が決行され、日本本土の人々は直接戦争の恐怖に直面させられるようになった。
三月中旬に入ると米軍は徹底した焦土作戦をとるようになり、多数のB29が飛来して大量に焼夷弾を投下、東京、名古屋、大阪、神戸などの大都市は次々と猛火に包まれ、人命と建物家屋の双方に甚大な被害が生じる事態となった。また、三月下旬に沖縄戦が始まると圧倒的に優勢な米軍はたちまち周辺各島を制圧して沖縄本島を包囲、四月一日を期して本島に上陸し、多数の民間人を巻き込んだ凄惨このうえない戦闘の火蓋が切って落とされた。そして、この沖縄戦参戦のため決死の航行を続けていた日本海軍の象徴、戦艦大和は、四月七日、沖縄へと向かう途中、薩南諸島西方海域において撃沈された。四月以降はB29による本土各地の空襲も日常化し、連日連夜の空襲警報に日本国民はなすすべもなく怯え逃げ惑う有様ともなった。
いっぽう、たまたま時を同じくするように同盟国ドイツも末期的状況を迎えていた。四月二十七日にソ連軍によってベルリンが包囲されると、その直後の三十日、ヒットラーは愛人エヴァとともに自殺した。そして翌五月二日にはベルリンが陥落し、同月八日にはドイツは全面降伏した。ドイツが降伏した結果、孤立無援となった日本は「一億総玉砕」のスローガンのもとに、もはやまったく成算のない戦いを続けるしか残された道はなかった。その無謀かつ無益な戦いの象徴ともいうべき沖縄本島決戦は、日米両軍と一般住民を合わせ二十余万人の尊い犠牲者を出したすえに、五月二十五日、沖縄守備軍司令部のおかれていた摩文仁ノ丘直下の洞窟内での守備軍令官牛島満中将の自害をもって終結した。
太平洋戦史においてよく知られているように、この時期、米国は密かに開発を続けていた原子爆弾を完成、その実験をニューメキシコで実行するための準備を着々と進めていた。そして、その周到な準備は七月十六日の世界初の原爆実験成功へと繋がり、さらには広島、長崎への原爆投下という悲劇的事態へと発展していくことになった。
一九四五年に入ると、中国全土に展開する日本軍も、毛沢東指揮下の共産軍のゲリラ戦による猛反撃や米空軍による激しい爆撃などにより、各地で苦戦を強いられるようになっていた。最前線に立つ部隊などは補給路を断たれ、飢えと疾病と敵襲の恐怖とにさいなまれながら、苦難に満ちた絶望的な行軍を続けている有様だった。そして、現地で召集され南京で戦闘訓練をうけた石田が、同じく現地召集の他の新兵らとともに充員として急遽軍務に就くように命じられたのは終戦も間近なそんな時期のことだった。総勢五百名ほどの新兵からなる彼らの部隊は、具体的な任務も最終的な行き先も告げられぬままに南京をあとにすることになった。
七月上旬のある日の未明、石田ら新兵は、うむを言わさぬ上官の命令のもと、南京の長江沿いの埠頭に接岸した船の狭い船室の中に重なり合うようにして詰め込まれた。それでなくても暑い盛りのことだったので、その蒸し暑さや息苦しさときたら筆舌に尽くし難いほどであった。南京を発った船は長江を遡り、蕪湖、安慶方面へと向かい始めた。米軍による空爆やゲリラからの攻撃を恐れてか、南京を出発してからしばらくは甲板に上がって船外の景観を眺めることも許されなかった。あまりの蒸し暑さに堪えかね、河水の飛沫でびちゃびちゃに濡れた通路に転がり出てそこに身を横たえる者が続出する有様だった。
一応かたちだけの食事は出されたものの誰もがそれには口をつけようともせず、ひたすら飲料用のお湯を欲しがった。だが、お湯の配給はすくなく喉が渇いて仕方がなかったため、しまいには、中国人の船員から密かにお湯を買って飲んだり、手洗い用の水を盗んできてはそれを口にしたりする者も現れる始末だった。
ひどい暑さや飲み水の問題もさることながら、いまひとつ大変に苦労したのが大便の処理だった。甲板の片隅に直径三メートルほどのばかでかい盥桶みたいなものが置かれており、それがトイレの役割を果たしていた。中には水が張られていて、先客らの尿の混じったその水の表面のあちこちには大小硬軟様々な排泄物がこれ見よがしに浮き沈みしていた。その大きな盥桶の縁に腰と尻をおろして用を足すのであったが、船そのものも大盥の中の糞尿混じりの水も激しく揺れ動くうえに、盥の縁を除いては掴まるものもまったくない有様ときていたから、時折バランスを崩して盥桶の中に背中から転落する者も現れたりした。間違ってそんな目にあったりしたら一巻の終わりだから、排便に際しては仲間の誰かに身体をしっかりと支えてもらい必死の思いでことに臨むのが実状だった。
南京を出て二、三日は昼夜兼行で航行を続けていたが、そのあとは米軍機による空襲を避けるために夜間だけの航行にかわった。昼間は上陸して長江沿い各地の避難所に退避し、夜になると船に戻ってなお長江を遡行し続けた。時折上空を米軍機の編隊が通過していくことはあったが、十分に警戒がなされていたせいか、石田らの乗る船が直接攻撃にさらされるようなことはなかった。また、幸いんことに、夜間航行をするようになってからは航行中船の甲板や舷側に立ったりしても叱責されるようなこともなくなったので、早朝や夕刻の薄明かりの中で長江の雄大な流れを眺めつつ遠い想いに耽ることができるようにもなった。
一面濁流に覆われた長江ではあったが、遡行の途中一箇所だけ進行方向右手寄りの流れが青く澄んで見えるところがあった。毎日毎日濁った河面ばかりを眺めてきたので、その青さは石田にとって妙に印象的だった。中国人船員にここだけどうして水が澄んでいるのかと尋ねてみると、そこからすこし遡ったところに?陽湖(ポーヤン湖)方面から流れてくる河との合流地点があるからだということであった。?陽湖(ポーヤン湖)については話に聞いているだけでむろん見たことなどなかったが、長江へと流れ込むその水の澄んだ色から察するすると、ずいぶんと綺麗な湖なのだろうと想像されもした。?陽湖方面から流れ込んでくる河との合流地点を過ぎると、左岸のほうに高々と切り立ち聳える山影が見えはじめた。それらの山々の名前こそはよくわからなかったが、その景観は船上の石田の目を十分に楽しませてくれた。
南京を出港してから一週間余の船旅のあと最終的に上陸したのは武漢の地の一角をなす漢口であった。時折米軍機の来襲はあったものの武漢一帯はなお日本軍の支配下におかれていたので、石田たち一行は漢口の部隊宿舎に無事落ち着くことができた。幸いなことに漢口の宿舎は水の豊富なところだったので、水槽の脇に立って思いのままに全身を洗い清め、汗と渇きと不慣れなトイレに苦しみ抜いた悲惨な船旅の疲れを一息に癒し流し去ることもできた。
水については何も言うことがなかったが、漢口の部隊宿舎での食事はお世辞にも褒められたものではなかった。戦争末期の逼迫した状況下のことでもあったので食べられるだけましであり、文句など言える筋合いではなかったが、そうは言ってもそれに慣れるまではずいぶんと苦労を重ねなければならなかった。おそろしく籾の混じったままのご飯は容易には喉を通ってくれなかった。籾の数のほうが多いくらいなのでそれらを取り除くわけにもいかず、それらを歯で噛んで中身だけを飲み込み籾殻は吐き出すしかなかったが、歯に当たったり挟まったりして食べにくいことこのうえなかった。だからといってのんびり時間をかけたりしていると、食べ終わらないうちに食事時間が終わってしまうから当然必死にならざるをえなかった。
ところが、その一帯での軍隊生活に慣れている先輩兵士たちは、その籾混じりのご飯をそう苦もなく平らげていた。無数の籾を相手に悪戦苦闘してる新兵たちの誰もが、はじめは不思議そうにその様子を眺めたものだった。どうやら彼らはあまりしっかりとは噛まないで、ほどほどのところで籾殻ごと飲み下している感じであった。そこですこしずつ彼らの真似をしてみているうちに、ほどなく石田自身もそう苦労せずに籾混じりご飯を胃袋におさめることができるようになった。武漢一帯には水牛が多かったこともあって食事には水牛の肉も出されたが、これがまた新兵たちにとっては難物であった。水牛の肉はひどく固いため噛み砕くのが容易でなく、顎が痛くなりもした。だからといって残すわけにもいかないので目を白黒させながらむりやり飲み込むと、てきめん消化不良を起こし七転八倒の苦しみに襲われる結果となった。
古参兵たちは相変わらず将校たちの目の届かないところで新兵たちを殴り苛め続け、憎悪に満ちた目でなにかにつけては無理難題を吹っかけてきた。新兵を痛めつけるのはまるで自分たちの特権だと言わんばかりの横暴ぶりであった。古参兵たちが新兵らに勝手気ままに暴力のかぎりを尽す裏には、七年も八年も激戦の地に身を置き続けたことによって鬱積した鬱憤を晴らそうとする彼らなりのやむにやまれぬ事情もあった。
当然のことだが、万事に不慣れでモサモサしている新兵の様子が、彼らにはなんとも目障りで癇にさわることこのうえなかったのだろう。また、それまで内地や外地の安全で恵まれた環境の中でのうのうと暮らしてきた者たちに対するやり場のない嫉妬や怒りが彼らの胸中には渦巻いていもいた。さらには、戦地で諸々の残虐な行為に遭遇しながら長い軍隊生活を送り続けているうちに一種の感覚的な麻痺が生じ、そのために常軌を逸した行為を自らの力では抑制することができなくもなっていた。もちろん、新兵らにすればたまったものではなかったが、新兵を虐待することでしか心の苛立ちを鎮めることのできない古参兵たちもまたその意味では戦争の被害者なのであった。
無抵抗の新兵を無残なまでに殴打したり蹴飛ばしたりしながら陶酔しきっている古参兵を目撃するのはもはや日常茶飯事になっていたし、石田自身がその対象にされたのも一度や二度ではなかったが、如何に理不尽なものではあっても上官の命令は天皇陛下の命令そのものであるとする軍規のもとではそんな行為から身を守ることなどできようはずもなかったのである。古参兵から被った虐待に対して新兵がなんらかの仕返しをするとすれば、戦闘時においていわゆる「うしろ弾」をくらわせることくらいしかなかったのだった。

絵・渡辺 淳
「マセマティック放浪記」2004年2月11日
ある奇人の生涯 (46)
強運と悲運のはざまにて
漢口に着いてからほどなく、石田らの新兵部隊に軍令が下された。彼らが命じられたのは、北京まで出向き軍馬を引き連れて漢口まで戻るという特別な任務だった。馬の取り扱いなど知らないに等しい新兵らに、日毎に激しさを増す米軍機や毛沢東指揮下の八路軍による猛攻をかいくぐりながら、片道千三百キロにも及ぶ漢口と北京間を往復し軍馬を連れてこさせるなど正気の沙汰の命令とは思われなかった。そもそもそんな危険をおかして遠路はるばる軍馬を連れ戻ったとしても、そのことにどれほどの意味があるのか疑問でもあ
った。あえて勘ぐれば、懲罰含みの命令であるとも受取れないこともなかった。
だが、上官の命令は絶対的なものだから、結局のところ、部隊の誰もが黙々とその命令に従うほかはなかった。戦局が悪化した太平洋戦争終末期の日本軍の軍令やそれに基づく軍事行動などには、悲壮な精神論がやたら強調されるのみで合理性に欠けたものがすくなくなかったため、戦線のいたるところで犠牲者が続出した。この時に石田らの部隊に下された命令もけっしてその例外ではなかったのだった。
皮肉と言えば皮肉な話だが、石田らの部隊がいよいよ漢口を出発しようという当日のこと、結果的にはその後の生死をわけることになった運命の分岐点が意外なかたちをとって彼の身に訪れた。入隊して以来、連日の猛訓練にともなう不摂生が祟ってその時までに彼の両足はひどく水虫におかされてしまっていた。それまで我慢に我慢を重ねてきていたのだが、すでに尋常の状態ではなくなっていたのである。その両足はどちらも五本の指が互いに癒着して拳みたいに固まってしまい、痛みや痒みばかりでなく出血などもあって、現実問題として長い行軍に堪えらえるような状況ではなくなっていた。ただ、それでも石田自身は命令に従って仲間たちと一緒に漢口を出立し、力のかぎりを尽して歩けるところまでは皆について行こうと覚悟を決めていた。あとは野となれ山となれという、半ばやけっぱちな気分でもあった。
部隊の出発前に、一応、希望者に対して軍医や衛生兵らによる簡単な健康状態のチェックがあったので、石田はたとえ一時的な気休めではあっても何かしら水虫の薬でも貰えないものかと思いその診察を受けた。ところが、たまたま石田の足の状態を診てくれた軍医はそのあまりに異常な病状に驚き、すくなからぬ好意をもって、せめて数日くらいは出発を遅らして治療にあたるようにと勧告し、急遽そのように手配してくれたのだった。部隊の他の者たちに申し訳ないという気持ちがしなくもなかったが、結局、数日してから後を追うつもろだと仲間たちに伝え、軍医の指示に従ってその日の従軍を思いとどまった。
石田翁は、「生まれつきの悪運の強さですよ」と自嘲気味にこの時の話をしてくれたのだが、結果的はこの水虫の極度の悪化が彼の一命を救うことになったのだった。実際、「水虫様々」と白癬菌に心底感謝するしかないような一連の成り行きで、悪運の強さのゆえの命拾いと老翁が笑うのももっともなことであった。
数日後に新兵からなる先発部隊の後を追うというつもりでいたのだが、結局、北京方面への後続部隊出動の命令は下らぬまま、いたずらに時は過ぎていった。一新兵に過ぎなかった石田にはむろん知るすべもないことであったが、米軍機によるさらなる猛爆撃と一大攻勢に転じた八路軍の急襲により、すでに北京と漢口を結ぶ軍事輸送路はいたるところで寸断され、後続部隊が容易に進軍できるような状態ではなくなっていたのである。
その惨状が明らかになったのはずっとのちになってからであるが、本来なら石田がともにその命運を委ねるはずであった部隊は、その時までにほぼ全滅に等しい状況に陥っていた。のちに判明したところによると、五百人ほどの部隊員のうち生還したのは僅か数人程度にすぎず、残りの兵士たちは皆非業の死を遂げたのだという。実際、人間というもの何が幸いするかわからない。ほとんど死ぬ運命にあったはずの石田は、こうして辛くも生の道へと押し戻され、その後に続くさらに数奇な人生航路へと突き進むことになったのだった。
この年の七月二十六日、ポツダム宣言がおこなわれ、連合国側は日本に対して無条件降伏をするように通告した。そして、それに呼応するように翌二十七日、蒋介石指揮下の国民政府軍も日本軍に対する一斉攻撃を開始した。さらにその十日後の八月六日には広島にウラニウム型原爆が投下され、それから二日後の八月八日、ソ連軍は日ソ不可侵条約を一方的に破棄して満州への侵攻を開始した。そして、翌日の九日にはとどめを刺すかのように長崎に二発目のプルトニウム型原爆が投下された。
異常なまでに悪化した水虫の治療を受けながら、石田が漢口の兵員宿舎に一時待機していたのは、終戦間近のそんな時期のことであった。もちろん、広島や長崎に原爆が落とされたことなど知るわけもなかったし、ましてや終戦が近づいていることなど石田には想像もつかないことであった。ただ、なんとも奇妙なことに、なお漢口に残されている石田ら一部の新兵たちは竹槍の訓練を受けさせられたりもした。いざという時には玉砕覚悟で迫る敵と戦わなければならないから、竹槍の訓練は絶対に欠かせないという触れ込みであったが、全体的な戦況のわからない石田らには、銃剣の訓練を差し置いて今更なぜそんなことをしなければならないのか、なんとも合点がゆかなかった。
石田にとって生涯忘れることの出来ない悲しい事件が起こったのは八月十四日のことであった。現地召集され新兵として戦闘訓練を受けるようになって以来、彼には寝起きを共にしてきた同い年の友人があった。それは、慶応大学中退の経歴をもつ舟村という新兵であったが、その育ちのよさもあってか、やることなすことのすべてにおいて石田以上に要領が悪かった。育ちのよさに対する妬みや憎しみなどもあって、当然、新兵の舟村は古参兵の鬱憤晴らしの格好の対象となり、やはり毎日のように殴る蹴るの暴行を加えられていた。石田もずいぶんと殴られ続けたが、彼に対する暴虐や侮蔑の数々はより凄まじいものであった。
お互い兵士としては落ちこぼれにすぎない存在だったが、それゆえにまた相通じるものもあって、石田と舟村とはいつしか深い心の絆で結ばれるようになっていた。もちろん、二人ともそれなりの教育を受け、過去それなりに知的な生活を体験してきていたから、ずいぶんと話も合った。他の兵士たちの目を避けながら、過去に見た外国映画の名作やそれまでに読んだ文学作品などについて、二人だけで密かに話し込むこともしばしばだった。不当な暴行などを受けたあとなどは、お互い慰め合い励まし合うこともすくなくなかった。
ただ、舟村はかなり身体が弱かった。新兵としの教育と訓練を受け、石田とともにやはり南京から漢口に連れてこられたのだが、その途中でもずいぶんと苦しそうな様子を見せていた。漢口から北京に向かうように石田らの部隊に命令が下った際も、病気がちな彼はすっかり体調を損ない体力が弱っていたので、結局、そのまま漢口の宿舎で待機するように命じられ、その指示に従って部隊には同行していなかった。そして、そんなお荷物的存在の彼は、その理由如何にかかわらず、いっそう古参兵らの侮蔑と嘲笑と暴行の対象にされるようになったのだった。殴られ蹴られたばかりでなく、最後には、性的な嫌がらせをはじめとし、その人格を根底から否定されるような凌辱のかぎりにさらされる状況へと発展した。悔しさに堪えかね、毎晩のように苦悶しすすり泣く彼をなんとかしてやりたいとは思ったが、宿舎では同室でなかったこともあり、石田にできることにはおのずから限界があった。
八月十四日の朝のこと、兵員宿舎のトイレ付近で突然なにやら騒がしい声がし、それに続いて一部の兵士や士官らが慌しくその場に向かう気配がした。そして、それからほどなく、石田に耳にも誰かがトイレの中で首を吊って死んだらしいという報せが飛び込んできた。それを聞いてはっとした彼は、もしやと思い大急ぎで現場に向かって走り出した。友人の舟村でないことを心中で祈りながら、人だかりができているトイレのそばに駆けつけてみると、すでに死後硬直を起こした様子の一人の兵士の縊死体が担架に載せられ衛生兵らによって搬出されようとしているところだった。
石田の予感は的中した。それはほかならぬ舟村の無残に変わり果てた姿だった。まわりの制止を振り払うようにして担架の脇に近寄ると、彼は友の頭部にかけられた白布をめくり、青黒く空ろな色になり果てたその顔を覗き込んだ。そして、片手で遺骸の胸のあたりを揺すりながら、「舟村君、舟村君、なんでこんなことになったんだっ!」と大声で叫び号泣した。やり場のない怒りと悲しみがとめどもなく込み上げてきたが、最早石田になすべきすべのあろうはずもなかった。
当時の軍隊では、古参兵などによる暴虐に堪えかね自ら命を絶つ者もすくなくなかった。だから、そのような事態が起こった場合の軍隊内での事後処理にはそれなりに手馴れたものがあって、石田の個人的な想いなどにはまるで無関係に、どこか事務的かつ機械的な手筈のもと、舟村の遺体は所轄の安置所へと運び去られていった。
そして、石田の哀しみもさめやらぬその翌日の八月十五日、ついに運命の時がやってきた。言うまでもないことだが、それは日本がポツダム宣言を受け入れ、無条件全面降伏に踏み切った日にほかならなかった。重要なラジオ放送があるというので兵士たちは通信隊の設置したスピーカーのある宿舎の一角に集められ、低く途切れ途切れな感じで流れる玉音放送に耳を傾けさせられた。だが、石田をはじめとするほとんどの兵士たちは、その放送の内容をはっきりと聴き取ることはできなかった。ただ、将校らの様子をはじめとするその場の全体的な雰囲気から、日本の全面降伏をもって戦争が終結したのだということだけは、誰の目にも明らかだった。
不思議なことだが、善い意味でも悪い意味でも日本が敗れたことに対する感慨のようなものはほとんど湧いてこなかった。放送を聴き終え解散したあとも、兵士たちの間には戦争が終わったことをとくに一喜一憂するような様子は見られず、奇妙な脱力感だけがひたすら現場の部隊やその関係者たち全体を支配していた。
そんな状況の中で、石田はあとわずか一日だけ我慢しておれば自ら命を絶つこともなくてすんだであろう舟村のことを何度も何度も想い浮べた。自らの悪運の強さを思うにつけても、たった一日の違いで無残な最期を遂げた舟村の天運のなさが無性に悔しく、そして胸がはりさけるほどに悲しくもあった。

絵・渡辺 淳
「マセマティック放浪記」2004年2月18日
ある奇人の生涯 (47)
光明と悲哀のさなかにて
この日を境に日本軍は次々と武装解除され、銃砲等はみな国民政府軍に引き渡された。一日にして敗者へと転じた日本軍に対する中国側の応接は、想像していたよりもずっと鄭重であった。武漢周辺に滞在する日本兵や民間日本人は上海に移動し、上海から引き揚げ船で母国へと送還される旨の通達がなされたが、輸送手段の問題などもあって全員がすぐに上海へと移るというわけにもいかなかった。
敗戦が明らかになってほどなく、「中国にいる日本人は、民間人を含めて全員玉砕するか、さもなければ集団自決しようという動きがある」という噂が一部の者たちの間で広まった。はからずもそんな噂を耳にした石田は暗澹とした気分になりかけたりもしたが、幸いそれは単なる噂だけのことに終わり、全員玉砕や集団自決といった愚かな行為が現実に決行されるようなことはなかった。敗北を潔しとしないごく限られた軍部筋やその協力者たちの中にそのような強硬論を唱える者があったのかもしれないが、冷静に考えてみるならば、それが無意味な行為であることは誰の目にも明らかであったからだろう。
とうとう自由の身になったんだ!、重苦しい軍国主義の時代から遂に解放されたんだ!――そんな思いがひしひしと胸中に湧いてきたのは敗戦から二、三日してからのことであった。正直なところ日本の敗戦をひどく憂い悲しむ気持ちなどその時の石田にはまるでなかった。非国民と言われようと、いまさらそれがなんなのだという思いだった。上海へと移動する手筈が整うまでの間とくにやることもなかったし、もはや兵士として行動を束縛されることもなかったので、漢口の周辺を気の向くままに散策してまわったりもした。八月の太陽はまだ強烈そのものだったが、そんなことはまるで気にならなかった。
それまでの厳しい拘束がまるで夢かなにかであったかのような気分であちこちを自由に訪ね歩くうちに、石田はかつて見たゴーリキー原作の映画「どん底」の一場面を想い出した。ジャンギャバン主演のその映画の終わり近くに、惨憺たる苦渋の末に絶望の淵から解放され自由の身になった恋人たちが全身を歓喜の念にうちふるわせ、至福の想いに酔い痴れながらあたりかまわず歩きまわるシーンがあった。そして彼はその場面にいつしか自分を重ね見ていたのであった。恋人たちが登場する映画のシーンと違って彼の場合は自分独りだけだったが、桎梏(しっこく)の苦しみから解放された喜びは彼らのそれに勝るとも劣らぬという想いがしてならなかった。
川のほとりに出て堤防沿いに歩いているうちに、たまたま一人の日本軍将校が川面に向かって釣り糸を垂れているそばを通りかかった。人の近づく気配を感じてその将校がうしろを振り向きかけた時、石田は反射的に直立不動の姿勢をとり、威儀を正して思わず敬礼をしそうになった。しかし、次ぎの瞬間、その脳裏を、かつての将校といえども戦争が終わったいまでは一兵卒と同等の身分すぎないのだという思いが電光のごとくによぎった。
我に返った彼は、敬礼しかけた右手をまるで何かを掴みそこねでもしたかのようにおろし、いったん直立不動の姿勢をとりかけた下半身の力を大慌てで抜くと、如何にも不自然な感じで再び歩き出した。将校のほうもそんな石田の奇妙な動作を見てはっと感じるところがあったみたいで、一瞬驚き戸惑ったような表情を浮かべると、また何事もなかったかのように川面のほうに向き直った。
彼には相手のなんとも複雑な心境がはっきりと読み取れた。その将校には申し訳なかったが、それまで絶対的服従と一方的な敬意の表明を強いられていた上官を無視しそのそばを通りすぎることができるというのは、何物にも換え難い快感であった。そしてまた、古参兵らからもう殴られずにすむことも、さらには、すっかり威信を失い空ろな姿を見せる彼らを無視してそばを通りすぎることができるのも、ながらく虐げられ続けてきた身からしてみればなんとも快いことだった。ただ、そんな快さのいっぽうで、あとたった一日を待つことができなかったがゆえに、救い難い絶望と屈辱にまみれたまま自ら命を絶ったあの舟村の無念さが偲ばれてならなかった。
しばらくして武漢の漢口から上海に戻った石田は、徴兵されたあとも借りたままにしてあった以前からのフランス租界の部屋に身を落ち着けた。彼が不在の間は上海でなお生活を続けていた母親や妹らが時折訪ねては部屋代の支払いや部屋の掃除などをしてくれていたので、当面寝泊りするだけならとくに問題はなかった。
ただ、当然のことだが、敗戦の日を境に、上海の街では日本人と中国人の立場はすっかり逆転してしまっていた。元軍人も民間人も日本人はすべて、資産や家財のほとんどをうち捨て、身ひとつに近い状態で日本へと引き揚げなければならなかった。敗戦国民の当然の末路と言えばそれまでだったが、ほんのすこし前まで日本軍の軍事力を盾に中国人や欧米系居留民に対し横暴に振舞ってきただけに、逆の立場におかれた日本人の有様は、そのぶんいっそう惨めなものであった。
もともと上海に在留していた日本人引き揚げ者らに加え、上海から出港する引き揚げ船に乗ろうとして中国各地から大勢の日本人が集まってくるために、引き揚げ船に乗るのも順番待ちで、誰もがすぐに母国へと帰れるような状態ではなかった。その結果、引き揚げ船の発着埠頭のある黄浦江沿いの外灘地区や蘇州江(呉松江)周辺をはじめとする上海の街は、乗船の順番を待つ日本人たちで溢れかえることになった。もちろん引き揚げ船の輸送力には限界があったので、乗船できるまでの待機期間のほうも数ヶ月から一年に及ぶ場合がすくなくなかった。
そんな日本人引き揚げ者たちにとって一番問題となったのは当座を凌ぐための食料の確保と、そのための資金の調達であった。もはや日本人たちはなんの力ももたない状態になっていたから、食料は中国人から入手するしかなかったが、中国人たちはそんな日本人引き揚げ者の足元を見透かし、容易には食料の供給に応じてくれなかった。それまですべての面で散々日本人によって収奪され続けてきたことへの恨みなどもあったから、よけいに事態は深刻であった。
なんとも皮肉なことではあったが、そこに石田の出番がやってきた。すでに述べてきたように、彼にはかつて親交を結んだ多くの中国人の友人や知人がいたし、大世界周辺の賭博場で働いたりしてもいたから、上海の裏社会を牛耳る連中ともある程度は通じていた。そこで彼は、日本人たちと中国人たちとの間に立ち、乗船を待つ引き揚げ者たちのために当座の食料や資金を調達する役割を担うことになったのだった。石田のことだからとくに商才などがあったとは思われないのだが、「強運の持ち主」の名に違わず、この非常事態ともいうべき場に及んでもなお時運は彼に大きく味方した。藁をも掴む思いでなんとか生き延びるための食料を求めようとする日本人たちのために、彼は意外なまでの働きをすることになったのである。しかも、その働きを通して彼自身にもそれなりの利得があるというおまけまでついていた。
何ヶ月にもわたって引き揚げ船への乗船待ちをする日本人たちが食料その他の当座の必需品を入手するには、持ち物を売り払うか、さもなければ物々交換という手段に頼るしかなかった。しかも、すっかり足元を見透かしきっている中国人や欧米人バイヤー相手のことだから、所持品を売るとか物々交換に供するとかいってみても、そうすること自体けっして容易な話ではなかった。だから、そんな日本人たちにとって、中国人らに顔が利き、しかも風貌や言動からしても十分に信用のできる石田の存在は、まさに「渡りに舟」だと言えた。
資産や家財のほとんどをなげうち、わずかな所持品だけを携行して本土への帰還をひたすら待つ日本人たちではあったが、それでもいざという時に備えて、貴金属類や美術骨董品、高価な衣類などを所持しているものはすくなくなかった。また、長年にわたって上海に在住していた日本人などの場合は、それなりの質と量の物品類を所有しており、たとえ只同然の値段であったとしても住まいを引き払う前にそれらを処分してしまいたいとも考えてもいたから、石田のもとにはずいぶんと多くの品々が集まった。
彼は処分を依頼されたそれらの物品を知り合いの中国人や欧米系外国人のところに持って行き、極力高値で換金したり、なるべく多くの食料品や生活必需品と交換するように努力した。そして売上金や入手した食料品等のうちのいくらかを利ざやとして受取りはしたが、けっしてあこぎな振舞いはしなかった。だから、日本人たちからもずいぶんと感謝されていた。
意外なことではあったが、日本の美術工芸品がもっとも高値で取引され、しかもよく売れた。なかでも、葛飾北斎、北川歌麿、安藤広重らの浮世絵は引く手あまたで、結構な値段で飛ぶように売れた。それらの浮世絵が本物であるのか贋物であるのかなど、石田にも相手のバイヤーたちにもまるで判断がつかなかったのではあるが、敗戦のために急遽中国での住まいを引き払わざるをえない日本人の目玉放出品ということで、その商品価値を疑う者はほとんどいなかった。
石田の受取る利ざやは歩合から考えるとけっして多くはなかったのだが、物品処分の仲介依頼がひっきりなしの状態であったため、結果的に手にした利益は相当な額にのぼることになり、そのお蔭で彼はむろん、母親や妹たちも上海での当面の暮らしに困るようなことはなかった。そして、そんなブローカーまがいの生活を送りながら、そのいっぽうで彼自身も本土へと引き揚げる準備を整えはじめたのだった。
正直なところ、本土へと引き揚げるのは気乗りがしなかった。日本以外のどこかで暮らすことができるものなら、どんな苦労と困難が待っていようともそうしたい気持ちでいっぱいだった。だが、さすがにこの時ばかりはそうすることは不可能であった。母国から伝わってくる噂によると、米軍の攻撃により日本全体が壊滅的な損害を被り絶望的な状態にあるとのことで、無事に本土へ帰還してもなんの光明も求めることなどできそうになかったから、彼の心はひたすら重くなるばかりだった。
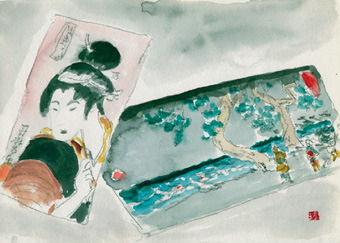
絵・渡辺 淳
「マセマティック放浪記」2004年2月25日
ある奇人の生涯 (48)
本土帰還と中国残留と
石田が兵役についていた間もミサはホテルで働き続けていた。だから彼は上海に戻るとすぐに彼女と連絡を取り、何度も二人で逢っては先々の身の振り方を話し合ったりもした。石田とミサとの親交そのものにその後の生涯を通じてなんら変るところがなかったが、この時期を境にして石田の内面には微妙な心理的変化が起こったのだった。一口にいうと、それは女性に対する極度の性的関心の薄れと性行為そのものの忌避であった。その後まったく女性との性的な関係をもたなくなったというのではなかったようだが、彼の心中に性というものに対するある種の違和感が生じかけていたのは確かだった。過去あれほどに女性相手に浮名を流した石田からは考えにくいことであったが、現実にその身に起こった予想外の事態に彼自身どう対処したらよいものか見当がつかなかった。もちろんミサとの性的な関係においてさえもそれは例外ではなく、以前ほどの激しさをもって彼女を抱くことができなくなっていた。
軍隊での生活を送るうちに何度か目にした古参兵や下士官たちによる女性強姦の場面、なかでもあの若くて美しい中国人女性が強姦されていた場面と、それにもかかわらず彼女の見せた恐ろしいほどに澄んだ超越的な双眸の輝きが石田の脳裏には焼きついて離れなかった。そしてそんな情景を想い出すにつけても、女性を前にして理性を失ったときの男というもののもつ、暴力的かつ野獣的なサガというものがどうにも堪え難いもに感じられてならなかった。また逆に、そんな男の本能的な獣性をいやがうえにも煽り立てる女性のセックスアピールというものにも一種の嫌悪感を覚えはじめたのだった。勘の鋭いミサは、石田のそのような内的変化をもちろんすぐに感じとっていたが、あえてそれを責めたりするようなことはしなかった。石田との精神的関係のほうがはるかに重要だと考えた点でも、さすがにミサは大人の女であった。
もしかしたら石田生来の隠れた資質のなかにホモセクシャルな一面があったのかもしれないし、また、見かけ上の体格の立派さとは裏腹にけっして頑健とは言い難い身体の持ち主だった彼には、強靭な心身をもつ男性というもに対する潜在的なコンプレックスがあったのかもしれない。そして、意識にのぼることなく体内深くで眠っていたそんな資質の一部が、中国での様々な体験を通し想わぬかたちをとって表面化してきたと言えないこともなかった。もっとも、石田のそのような一面はけっしてマイナスにのみはたらいたわけではなく、見えないところで彼の諸々の才能や抜群の美的センスというものに大きく寄与していたに違いない。実際、のちに迎えることになるその人生の一大飛躍をとことん支えた原動力の一端は、案外そんなところにあったのではないだろうか。
一九四六年に入り自らの本国帰還の日が近づくにつれて、石田は日本人引き揚げ者のために食料調達や資金調達をする仕事からも徐々に手を引きはじめつつあった。彼がそうせざるをえなくなった裏には、この一時期、上海の米国情報部に呼ばれ、日本や中国関係の情報文書の翻訳や解読を手伝わされていたという事情などもあった。もとシティバンクの行員で英語のうまい日本人だという情報はどこからか米軍筋にも流れていたらしく、上海から引き揚げるまでの期間そのような業務に協力するように要請されていたのだった。
夏も盛りに入り、いよいよ本土への引き揚げも間近になったある日のこと、ミサと逢ってあれこれと話し込みながら、何時頃本土に引き揚げるつもりなのかと尋ねると、彼女からは意外な返事が戻ってきた。なんとミサは、いまさら日本には帰るつもりはないと言い出したのだった。自分だってそうしたいけれど、こんな状況下ではそんなことできるわけがないだろうと反問すると、彼女は、今後は日本人としてではなく中国人として上海で暮らすのだと言い張った。中国語もうまく中国の事情にも通じているうえ、いろいろな中国要人とも交流のあったミサのことだから、本気で中国人になりっきて暮らすつもりならそれも不可能なことではないだろうとは思われたが、それ以上にこの時の石田が感じたのは、いざという時に見せる女性というもの本質的な強さであった。いくら彼が説得してみたところで彼女の意志は微動だにしそうにもなかった。
説得を諦めた石田は自分の部屋をミサに提供し、上海を引き揚げることにした。中国人になって暮らすのだと覚悟のほどを語ったミサではあったが、敗戦後に起こった日本人強制立ち退きの煽りを喰って、ミサはそれまで住んでいた部屋を引き払わなければならなくなっていた。そのため、彼女は大急ぎで新たな住まいを探す必要に迫られていた。だから、石田が引き揚げたあと、かわりに自分がその部屋に住むことができるというのは文字通り願ってもない話だった。むろん、その一件についての相談は二人の間ですぐにまとまり、あとは直ちに実行に移すための手筈を整えるだけのことになった。
石田の部屋の壁にはなんとも奇妙な絵が描いてあった。それは一匹の猿がマスターベーションに耽っている絵であった。その猿のどこか滑稽でしかも自己完結的な姿はほかならぬ石田自身の姿を暗示しているとも言えたし、男というもののどうしようもない愚かさを象徴しているとも言えた。石田は引き揚げ船に乗ることの決まった日が近づくと部屋を空ける準備を終え、それからあらかじめ用意してあった顔料と筆を取り出すと、壁の猿の絵に重ねるようにして、「You bitch!」と大書した。「売女めが!」とか「性悪女めが!」とかいった侮蔑の意味をもつこの英語をわざと石田が書き残したのは、ある種のミサへのあてつけにほかならなかったが、裏を返せば、ミサならば自分のそんな振舞いを平然と笑って受け流すことができるだけの度量があるだろうとの確信がもてたからでのことでもあった。
一九四六年の夏も終わりに近いある日のこと、石田はいよいよ引き揚げ船に乗ることになった。母親や妹たちは彼とは別の船ですぐあとから帰国することになっていた。日本人の乗船者は二、三日前から埠頭近くのテント村の一角に集合し待機するように指示が出ていたので、石田は蘇州江(呉松江)沿いの引き揚げ船埠頭へと向かう前にミサに部屋の鍵を渡し、その後の無事を祈りながら静かに別れを告げた。気丈なミサもそのときばかりはさすがに淋しそうだった。
まだ夏場ということもあって、乗船後に赤痢や疫痢などの伝染病が起こったりすると大変なので、出発前には乗船者をいくつかのグループに分け、全員を対象とした検便がおこなわれたが、その方法たるやなんとも荒っぽいものだった。横一列に整列して両手を地面に着け、ズボンやスカートを半分脱いでお尻をまるだしにしたまま待機していると、看護婦や衛生兵らがやってきて、そのままの姿勢で「あー」と大声を出しながら肛門の力を緩めるようにと指示を出した。そして次ぎの瞬間、彼らは箸か細い木ベラみたいな木片を肛門に差し込むと、手際よく少量の便を採取した。
もちろん男女の別なくその採便は実施されていたが、婦女子であっても頭を丸刈りにし男装している者がすくなくなかったため、一見しただけでは男か女か見分けがつかない有様だった。婦女子らが男装をしていたのは、中国各地から遠路はるばる上海の引き揚げ船埠頭までやってくる間に、無法化した状況の下で盗賊その他の連中に襲われたり暴行されたりするのを防ぐためだった。日本軍がかつて中国人婦女子に対して犯したのと同じ行為を日本人婦女子が逆に被るおそれは十分にあったし、実際、あちこちでそのような事態が生じていた。
採便の方法も、そして軽い痛みを伴う採便後のお尻の不快感も相当なものであったが、採取した便を検査する方法もまたちょっとしたものではあった。先端に採取した便のついた細長い木片は何本も一緒に同じ試験管に差し込まれ、そのうえでその試験管中の便に試薬かなにかを加え、光にかざして細菌が混じっていないかどうかが検査された。むろん、一人ひとりの便を別々の試験管に入れて検査するだけの時間と必要備品がないための非常処置だったが、おかげで、菌が発見された場合でも誰が保菌者であるかをすぐに特定することは不可能だったから、そのグループ全体が足止めされたりするという笑うに笑えない事態も起こった。
乗船に際してはほとんどの者が米国人看護婦らによってDDTの白粉を何度も何度も頭から吹きかけられた。いまでこそ大量のDDTの人体への散布は有害であるとされているが、当時は安全だとされていたこともあって、全身が真っ白になるくらいに同剤がふりかけられた。乗船直前の携帯品の検査もなかなかに厳格だった。携帯品検査は米兵や中国兵によって繰り返し繰り返し行なわれた。列をなして並び、自分の番がやってくると、一・五メートル四方ほどのシートの上に所持品のすべてを並べさせられた。一定量や一定数以上の品物を持って乗船することは許されなかったので、たとえあれこれ苦労して貴重品を携行してきても、結局、この段階で必要最小限のもの以外は放棄せざるをえなくなった。もっとも、なかには背嚢の肩帯などに巧みに貴重品を縫い込んだりして検閲突破を試みるずる賢い者もいたりした。石田自身はこれといった貴重品などまったく携えていなかったので、とくに検閲にひっかかるようなことはなかった。
引き揚げ者輸送の任にあたったのは、戦時中なんとか撃沈されずに残った日本の客船や貨物船、さらには元日本海軍の艦船などだった。元海軍所属の軍艦の場合、その武装が解かれていることはもちろんだった。たまたま石田が乗り込むことになった引き揚げ船は終戦直後に完成したため実戦には配備されなかったとかいう駆逐艦であった。かつて台湾の基隆や中国本土の天津と北海道小樽とを結ぶ貨物船の乗員をやっていた石田にすれば、船に乗ることそのものは手馴れたものであったけれども、細長い船体をもち高速が出るように設計された駆逐艦の構造を実際目にするのは初めてのことだったから、さすがになにもかもが物珍しく感じられた。
駆逐艦はもともと多くの乗客や大量の荷物を載せるようには造られていないから、ベッド類や広い船室のようなものは装備されていなかった。だから、乗船した引き揚げ者たちは狭い甲板やごちゃごちゃした機械類の間に身を寄せ合うようにして座り込み、本土までの長い船旅に耐えるしかない有様だった。
甲板の一角に腰をおろし出航準備が整うのをひたすら待つ石田の脳裏を複雑な想いがよぎっていった。ナーシャを追ってのことではあったとはいえ、大きな夢と希望を抱きつつ海路はるばる大連から上海へとやってきて、摩天楼の聳え立つその景観をはじめて目にしたときの感動はなんとも忘れ難いものであった。その時のことを想い出すにつけても、そ
れから六年を経たこの日、その摩天楼群を背にして上海を離れ、もはや夢も希望も抱くことができそうにない本土へと重苦しい気分で引き揚げようとしている自分の姿がつくづく情けなくやりきれないものに感じられた。そして、中国人になりすましてでも上海に残ろうと決断したミサの胸中がそれなりには理解できるような気がしてならなかった。

絵・渡辺 淳
「マセマティック放浪記」2004年3月3日
ある奇人の生涯 (49)
佐世保湾浦頭へ
引き揚げ船に振り当てられた駆逐艦「楠木」が上海の埠頭を離岸したのは黄昏時が過ぎ、もう宵闇が迫ってこようかという時刻のことだった。出航を告げる高く鋭い汽笛の音をあたりに響きわたらせながら、駆逐艦は黄浦江へと進み出た。もう二度と上海の街並みを目にすることなどないだろうと思うと、悲しくもあり淋しくもあった。上海での六年間にも及ぶ生活の中で起こった様々な出来事が、彼の脳裏を慌しく駆け巡った。船尾方向へと徐々に遠ざかり宵闇の中へと消えて去っていく摩天楼群の影を眺めやりながら、「さらば上海、我が愛しの上海……」と彼は胸のなかで呟いていた。そしてまた、その呟きの中の「上海」という一語には、毅然として上海に残ることを決意したミサや、上海ではついに再会することなく終わったあのナーシャの姿なども重ねられていた。
不可思議な運命の糸の導くところによって、ミサとはのちに意外なかたちで再会することになるのであったが、この時の二人にすれば、いずれ再会の日が訪れることになろうなどとは想像もつかないことであった。また、上海という都市に話をかぎるなら、実際問題としても石田にとってはこの日がその見納めともなったのであった。その後の生涯を通じて、二度と彼が上海の地を踏むことはなかったからである。ましてやナーシャについてはいまさら言うまでもないことではあった。
石田らの乗ったその駆逐艦は実戦配備こそされなかったものの、終戦直後に完成したばかりの最新鋭艦だというだけのことはあって、時速二〇ノット前後の高速での航行することができた。だから、速度という点においては、石田かつて乗っていた貨物船などとは雲泥の差があった。エンジン音を高らかに響かせなら他の船をどんどん追い抜いていく有様は爽快そのものだったが、狭いスペースに身を寄せ合いながら立膝をして固い鉄の甲板の上にじっと坐っているのはけっして容易なことではなかった。一等船客となって大連から上海へとやってきたときの優雅な船旅に較べると、それは悲惨このうえないものであったが、それでも、新兵として召集されたあと南京から漢口まで長江伝いに運ばれたときの船旅にくらべればまだしもましなように思われた。
高速で走る駆逐艦の甲板に坐らされていた関係で、引き揚げ者で鮨詰め状態たっだにもかかわらず、折々吹き抜ける風に身を委ねることができたのは幸いだった。南京から漢口へ向かった際の大盥状トイレに泣かされた石田は、この引き揚げ船のトイレはどうなっているのだろうと乗船時からいささか気になっていたが、その問題についてはそれほど危惧するには及ばなかった。もちろん、もともと駆逐艦に設置されているトイレでは間に合うはずもなかったので、多数の引き揚げ者の乗船にそなえ船尾には特別に臨時トイレが用意されていた。
船尾から両舷端外側の海上に突き出す感じで複数の仮設トイレが設置されていて、正規の乗員以外の乗船者たちはそのトイレを使うようにと指示された。ちょっとした緊張を味わいながら、しっかり張られた太いロープ伝いにこのトイレに辿り着き、便座下の長方形の穴を覗くと、真下には猛烈な勢いで泡立ち流れ走り去る河水や海水が見えた。穴から下に落っこちたらそれこそ一巻の終わりだったが、便座もしっかりしており不意の揺れにそなえて掴まる取っ手もついていたから、よほどふざけたことでもしないかぎりまずそのような心配はなかった。
後方へと激しく流動する河水や海水とそれらの飛沫の跳ね交う様を眼下に眺めながら、雑念を払うがごとくに大小の用足しをするのはなんとも爽快な気分ではあった。だがそのいっぽうで、塘沽、天津、青島、大連、上海、南京、漢口、上海と移り暮らしながら築き上げた過去八年間にわたる中国大陸での想い出までがそれと同時に己の体内から一挙に流れ消え去るような、奇妙な幻覚に陥ったりもした。
駆逐艦はいっきに長江を下り東シナ海に入ると、ほぼ東に向かって進路をとりはじめた。すでに夜が更けてからのことだったので、ほとんどの者にはその船がどちらの方角に進んでいるのか皆目見当がつかなかったけれども、東シナ海を航行する貨物船の乗組員を務めた経験をもつ石田にはすぐにおおよその航路の推測はついた。たまたま夜空には北極星をはじめとする星々が出てもいたので、それらの位置をもとにして船の進行方向をつかむのは容易なことだった。また引き揚げ船の入港先が佐世保であることもあらかじめわかっていたから、海図を思い浮べながら上海から佐世保までの航路全体の概要を予測するのに手間はかからなかった。
長江の河口から東シナ海をはさんで真東の方向に位置するのは九州の薩摩半島のあたりである。ところが、東シナ海のなかほどから九州西岸寄りにかけての海域を黒潮の分流である対馬海流が絶間なく北上し続けているから、真東に向かう船は緩やかなカーブを描いて自然に北へと流される。そして、九州西岸の天草諸島沖合いあたりに到達したところでいっきに対馬海流に乗って北上すれば、目指す佐世保港はすぐである。上海から佐世保までおよそ千キロ前後、この高速の駆逐艦ならまる一日ほどの船旅だろうと思われた。
夜空には星々が美しく輝きわたっていたが、海上には相当なうねりがあった。そのため、細身の駆逐艦はひどいローリング(横揺れ)を繰り返した。舳先で鋭く大浪を切り分けながら高速で前進できるような構造になっているせいか、ピッチング(縦揺れ)は想いのほかすくなかった。だが、それはあくまで船に乗りなれた石田にとってのことで、めったに船に乗る機会などなかった一般引き揚げ者たちにしてみれば、どちらの揺れであろうとも拷問以外のなにものでもなかった。まして、立膝をして互いに身をすぼめた状態でそのままじっと坐り続けなければならないときていたから、病弱者でなくても、船酔いその他のために気分の悪くなる者が続出した。婦女子や子供らをはじめとする者たちの泣き声や苦悶の声が飛び交うなかではあったが、それでもなんとか大事にはいたることなく船上の夜は明けた。
やがて舳先方向の水平線から朝の太陽が昇ってきて海上を照らし出した。しかし、「見よ東海の空高く旭日高く昇る時」などという愛国行進曲の勇ましい冒頭の一節が単なる皮肉にしか聞こえないほどに、どこか無残な朝の太陽の輝きだった。東海ならぬ西海にあって、朝日に照らされる船上に半ば無言のままぐったりとして坐り込むのは、旭日の名のもとに夢を追って大陸に送り出され、旭日の名の衰えのゆえにすべての夢を捨て、追われるようにして大陸をあとにした人々の一群にほかならなかった。
朝食の時間がくると艦員によってピッ、ピッ、ピッ、ピッ……という呼子が鳴らされ、一斉に食事をとるようにとの指示が出されたが、喜んでその指示に従うものはかならずしも多くはなかった。しかもその反応の鈍さは、ただ単に船酔いや一時的な疲労のために食欲がないからというよりは、敗戦により大陸での生活基盤をすべて失った悲しみと、帰国後の暮らしに対する不安との二重の苦悩に根差しているのは明らかだった。
それなりに揺れはしたものの船はエンジン音も高らかに佐世保へと向かって走り続けた。石田はトイレに立ったついでに右舷側へと足を運び、手すりに身を寄せながら海上を眺めやった。もうかなり九州本土に近づいているはずだったが、まだその遠影らしいものは見えなかった。どうせ見えないなら、このままずっと見えないままでいるほうがいいという、いささか屈曲した想いなども胸中に渦巻いていた。
時折、舷側近くの水面までイルカらしいものの影が近づくのが見られたが、かつてずいぶんと見なれた光景だったので、石田自身はそう興奮するようなこともなかった。ただ、たまたま船と並行するかたちで海面上を滑空する飛魚の姿は面白かった。かつて石田が乗っていた貨物船などの場合には、船と同方向にむかって飛魚が飛ぶとどんどん船を追い越す感じで滑空していったものだが、ほんらい駆逐艦として設計されたその引き揚げ船上から眺める飛魚の様子はいささか異なるものだった。飛魚たちはまるで石田の乗る船と並んで飛行するような飛び方をした。なかには船よりもすこし速く飛び去るものあったが、逆に遅れをとり、海面に着水してしまうものもあった。
べつに飛魚らが船と速さ較べをしているわけでもなかったが、そんな飛魚の飛行様態ははからずも引き揚げ船の船速の大きさを物語っているのだった。さすが駆逐艦というおもいもしたが、いっぽうでは、その速度に遅れをとる一部の飛魚がまるで世界の時流に取り残されるであろう自分の姿を象徴でもしているかのように感じられてならなかった。
太陽も西の空へと大きく移動しかかった頃のことだったろうか、進行方向左手にいくつかの青く大きな島影が見えてきた。それらの島影を一瞥した石田には、それらの島々が五島列島であるとすぐにわかった。貨物船に乗って小樽と台湾の基隆の間を往復していた当時、同列島の沖合いを何度となく通過したことがあったからだった。口々にあれはどこの島だろうと問い尋ねる引き揚げ者たちに、石田は何度となくあれは五島列島だという説明を繰り返した。大陸での生活が長く、どちらかというと褐色に近い風景を見慣れてきた引き揚げ者らの目には、青々とした五島列島の島影があらためて鮮烈なものに映ったようだった。甲板のあちこちに坐る引き揚げ者たちのなかには、なんとか無事に祖国へと辿り着いたことを知って感極まり、本土上陸に先だって歓喜の涙に咽ぶ人々もすくなくなかった。
上海を出てほぼ二十四時間を経た頃、引き揚げ船は船寄鼻と高後崎にに挟まれた狭い水道を通って佐世保湾に入った。そして湾内をほぼそのまま東進し、佐世保軍港とはすこし離れたところに位置する東彼崎針尾村浦頭港(現在の佐世保市針尾北町)の沖合いに碇泊した。その頃、佐世保湾内の浦頭は舞鶴港などと並んで、中国大陸各地や朝鮮半島、台湾、東南アジアなどから母国帰還者を乗せて入港する引き揚げ船の専用港となっていた。いったん佐世保湾内に碇泊はしたもののすぐに埠頭に接岸し下船することは許されず、何日もそのまま船上で過ごさなければならなかった。入国手続きの処理能力やそれにともなう検疫の態勢などには一定の限界があったため、次々に入港する引き揚げ船にはどうしても接岸の順番待ちをしてもらわなければならないからだった。

絵・渡辺 淳
「マセマティック放浪記」2004年3月10日
ある奇人の生涯 (50)
母国の土を踏む
佐世保湾内では想像していた以上の数の引き揚げ船が碇泊したり移動したりしながら接岸の順番を待ち続けていた。敗戦直後の一九四五年十月から四年半ほどにわたって、中国、旧満州、朝鮮半島、台湾、東南アジア各地などから、百三十万人を超える民間人や元軍人などが引き揚げ船に乗って佐世保を目指し、佐世保湾東部に位置する浦頭の地に上陸した。その後この地には浦頭引揚記念資料館が設けられ、当時の状況を現在に至るまで伝えている。同資料館は全国から寄せられた寄付金などをもとに佐世保市が建設にあたり、一九八六年五月にオープンした。
一口に引き揚げ船とはいっても、船の種類も大きさも驚くほどにまちまちだった。小さくて速度も遅い米軍の上陸用舟艇などにぎゅうぎゅう詰めにされたまま東シナ海を渡って佐世保に辿りつく引き揚げ者もすくなくなかったから、最新鋭の駆逐艦に乗って帰還することのできた石田などはその点でも恵まれていたと言うべきだった。
実際引き揚げ船の状況は相当に悲惨なものであったようで、乗船前の検疫にもかかわらず出航後に船内でコレラ感染者などが大量発生し死者が続出したほか、栄養失調が原因で母国上陸を目前にして衰弱死する者もあとを絶たなかった。記録の物語るところによると、引き揚げ船入港開始から二年八ヶ月経た一九四八年六月までの間に佐世保引揚援護局が処理した遺体数だけでも、三千七百九十三体にのぼったという。石田がその事実を知ることになったのはかなりのちのことになるが、彼よりもすこし遅れて上海を発った妹のひとりも、佐世保へと向かう引き揚げ船上で病が悪化しそのまま息を引き取ったのだった。
上陸許可がおりるまでの間、船上の引き揚げ者たちは時間をもてあましながらじっと辛抱を続けるしかなかった。眼前に本土の港が見えているというのに、上陸できぬまま碇泊した船上にただじっと坐ってひたすら待機するというのは、ある意味で苦行に近いことでもあった。詳細は掴めなかったが、周囲の人々の囁き噂するところなどからすると、石田の乗る駆逐艦上でも、衰弱して死亡したり重態に陥ったりした者が何人かは出たようであった。
時間を潰すために時々石田は舷側に立って船のまわりの海中を覗き込んだりもした。大きなクラゲが近くの水中を悠然と泳いでいたり、大小様々な魚類が群をなして眼下の船腹近くに寄り添うように集まってきたりするので、それらを眺めて気をまぎらわせるのも悪くはないと思ったからだった。元軍人の引き揚げ者らの中には、飯盒を取り出してそれをゲートル(巻脚絆)の一端や有り合せの紐の先などに結びつけ、船側から海中におろしてクラゲや小魚を掬っては退屈しのぎをしようとする者もあったりした。
かつて台湾航路の貨物船に乗っていた頃などは、基隆港などで船が碇泊している間に舷側から釣り糸を垂れ、釣りあげた魚を食べたりしてもいた。だから彼はせめてそんな釣りの真似事でもできないものかと思ったりもしたが、釣りの道具など持参していようはずもなかったから、そんなことは不可能だった。もっとも、どんな場合にも容易周到な人間はいるもので、もともと用意していたものなのかそれとも船員あたりから入手したものなのかはわからなかったが、釣り糸を垂れる者たちも現れたりした。
その様子をじっと脇から眺めていると、時折ちょっとした魚が釣れたりもした。文句の言える筋合いではなかったものの、船上で出される食事には皆いささか辟易していたから、見るからに活きのよさそうな魚を手にして、彼らはそれを料理したらさぞかしうまかろうと喜色満面であった。さりげなくそんな有様を目にしながら、正直なところ石田も内心で舌なめずりをしそうになったが、その時になって突然彼の脳裏にある光景が思い浮んだ。そして、次ぎの瞬間にはすっかりその食欲は醒めきってしまっていた。
その原因は船尾に特設された例のトイレにほかならなかった。佐世保湾内に碇泊して検疫の順番待ちをする間も乗船者たちはそれらの臨時仮設トイレを利用せざるをえなかった。船が河や海を高速で走っている時は排泄物がたちまち眼下の奔流に呑み込まれ、すぐに消え去ってしまうのだったが、波が静かで潮の動きも緩やかな湾内に碇泊した状態で大勢の者が次々に排泄をするとなると、船の周辺がおのずから好ましからぬ浮遊物だらけになってしまうのは必然の成り行きだった。しかも、その浮遊物が細かく砕け散ったものなどを群をなした魚どもが食べている様子を、石田はトイレに行った際に目撃してしまっていた。
さらにまた湾内には同様の状態の引き揚げ船が多数浮かんで順番待ちをしている状況ときていたから、周辺の魚どもがなんらかのかたちで異常な量の浮遊物の洗礼を受けている可能性は大きかった。もちろん、海水の浄化力はたいへんなものだから、現実にはそれほどに心配することもなかったのかもしれないが、心理的にはどうしても受け入れ難いものがあった。
ともかくもそんな船上で何日か待機したあと、ようやく順番がまわってきて石田らは浦頭への上陸を許された。乗船時よりも厳格な検疫を受け、そこを無事通過すると待ち構える看護婦らからまたもや全身にDDTを浴びせかけられた。検疫官は検疫に先立ち、「ご苦労様です」と引き揚げ者たちに声をかけたが、その声を耳にしてようやく帰国がなったと安堵し、その場で泣き崩れてしまう者もすくなくなかった。
検疫が終わると特別に定められた引き揚げ者用の入国手続きをすませ、引き揚げ証明書などの交付を受けたあと、やっとのことで学校か何かの建物らしい臨時宿泊所に案内された。こうしてようやく浦頭の地で帰国の第一歩を踏むことができたのであったが、石田自身には、結局日本に戻ってきたかというどこか諦めに近い思いがあるだけで、特別に深い感慨のようなものは湧いてこなかった。
臨時宿泊所のトイレは異常なほどに混んでおり、その近くには順番待ちをする男女の長い列ができるほどだった。もしかしたら、それは、苦労の末に母国へと辿り着いたという安堵感がもたらす緊張の緩みのゆえの一時的心理現象かもしれなかった。列に並んだあと順番がやってきたので空いているトイレを確認しようとしてトントンとドアをノックすると、中からは「おう!、なんだ?」といういささか横柄な応答が返ってきた。
てっきりトイレの中にいるのは中年の男だろうと思っていると、用足しを終えて出てきたのはなんと頭を丸刈りにし男装した若い女性だった。敗戦のため苦労して中国の奥地から命からがら逃れてきた女性などは、表面的に男装しているばかりでなく、身振舞いや言葉遣い、さらには声色まで男を真似て身を守ってこなければならなかった。どうやらその習慣が反射的に出たもののようだったが、石田にも女性たちのそんな苦労の一端はわかっていただけに、その有様がどんなに不自然で珍妙なものに映っても、それを冷笑する気などにはなれなかった。
浦頭港や臨時宿舎のある一帯はかなり大きな島様の地形になっているらしく、とても大きなアーチ状の木橋が水路を跨ぐ感じで内陸側へと架っていた。夕方になると、その橋の上から。どこからともなくやってきた子供たちの歌う日本の歌曲や童謡の調べが聞こえてきた。どうやら、その子供たちは、引き揚げ者を慰問するためにその橋の上で日本の歌を合唱するように指示されていたらしいのだが、たとえそうであったとしても、しみじみと胸に響くその懐かしい歌声は不思議なほどに聴く者の魂の奥底まで沁みいった。浦頭港に上陸しても特別な感慨はなかった石田であったが、その子供たちの歌声を聞いていると、さすがに、生まれ育った母国の温もりとでもいうべきものを感じざるをえなかった。
臨時宿泊所に何泊かしたあと、引き揚げ者援護局からいくばくかの現金と鉄道乗車券を支給され、石田ら引き揚げ者はそれぞれの故郷へと帰っていくことになった。宿泊所近くに架るその大きな木橋を渡りしばらく歩くと鉄道の駅があった。列車は足の踏み場もないほどの混雑ぶりを呈しており、乗れるだけでも幸いだと思わなければならない有様だったが、佐世保周辺から彼が生まれ育った博多まではたいした距離ではなかったので、蒸し暑い車内での辛抱もほんの一時のことにすぎなかった。博多駅に着いた石田は駅のホームの水道の蛇口に近づくとまずは手と顔を洗い、それからごくごくと渇いた咽を潤した。なぜか自分でも不思議なほどにその水が美味しく感じられた。
戦災の直後とあって博多の街並みはすっかり荒れ果てうらぶれて、かつてのような活況はどこにも見られなかった。摩天楼の立ち並ぶ国際都市上海から戻ってきたばかりだったからその思いはひとしおだった。街を行く人々の姿はどこか殺伐としていて、その様子には余裕というものがまったく感じられなかった。
あとから帰国する母や妹たちの当面の落ち着き先を下見しておく必要もあって、生まれ育った下町の長屋周辺を訪ねてもみた。その一帯もまたすっかり活況が失われてしまっていたが、幸い、昔の大家や一部の住民は健在で、すっかり成長し大人になった石田を驚きと親しみの目をもって温かく迎え入れてくれた。ひとつには、上海に移住したあとも母たちが以前一緒に暮らしていた下町の人々と互いに連絡を取り合い、なにかと世話を焼きあっていたお蔭でもあったが、ともかくも昔馴染みの人々の人情は身にしみた。
粗末なものではあったけれど、とりあえず身を落ち着ける小部屋なども提供してもらえることになったから、そのまま博多に住まうことも可能ではあった。ただ、そうするにしても、これから先いったい何をやって生きていくかが第一の問題であった。すぐに博多で適当な仕事が見つかるだろうとも思われなかったし、またそれまで苦労して積み重ねてきた語学力やその他の知識経験をうまく活かせるような職場がそうそうあるだろうとも考えられなかった。
いろいろと思案を重ねた末に、結局、石田は再度東京へと向かうことを決意した。焼け野原と化したと報じられている東京のことだから、上京すればなんとかなるといったようなものではないことは承知だったが、博多の下町にそのまま埋もれたままになっているよりは幾分ましかもしれないという気もしてならなかった。もちろん、かつで横浜の山下公園でそうだったように行き倒れになるおそれもなくはなかったが、現状を打破するにはともかくも行動に踏み切るほかはなかった。それにまた、山下公園で行き倒れになった頃に較べれは石田は能力的にみても精神的にみても数段成長を遂げていた。
それからほどないある日のこと、東京へと向かう混雑した列車の中に石田の姿が見かけられた。広島も神戸も大阪も、そして名古屋も横浜も、途中の車窓から眺める日本の大都市の姿は惨憺たるものであった。各地の田園風景などにはそう大きな変りはなかったし、戦災を免れ無傷のままで残されている京都周辺のようなところもあったが、日本の都市部の被った損害の甚大さが並大抵のものではないことは、車窓の向こうに見る光景を通して十分に推察がついた。
――このぶんだと東京はもっと悲惨な状況におかれているに違いない。いまさらそんな東京に出かけて行って、いったいどうなるというのだろう。絶望的な光景をまのあたりにして途方に暮れるだけではないのか。今一度上京してみようと決断したこと自体が誤りだったのかもしれない――迷いとも戸惑いともつかぬそんな複雑な想いが彼の胸中を駆け巡った。それまでの波瀾に満ちみちた人生をさらに上回る劇的な展開が行く手に待っていようとは、さしもの石田もこの時はまだ夢想だにしていなかった。
ほどなく東京に到着するという頃になって、石田は上海に独り残ったミサのことを想い浮かべた。そして、どんな苛酷な運命が彼女を待ち受けているかもしれないにしても、彼女が選んだ道はそれなりに適切だったのかもしれないと感じもした。あの激しい気性、あの洗練された感覚、そしてあの並外れた能力と行動力からして、彼女がいまこの日本に戻ってきたりしたら、たちまち身の置場に窮してしまうだろうことは目に見えていたからだった。そして、その時まだ彼は何も知らないでいたが、上海で暮らすミサの身にも、運命の悪戯とも言うべき想わぬ展開が生じかけていたのだった。

絵・渡辺 淳
(「ある奇人の生涯」第一部・完)
