�G�b�Z�[
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
1998�N10��12��
����̗t�̈ӊO�Ȏ����́H�@
�@���̉āA�d���ŏ��ɏo�����@��������B�\���肷�������ڂɒ������̂ŏ��������Ԃ���Ă���ƁA�����̕Ћ��ɔ���̎��������Ă���̂ɋC�������B�Ȃɂ��Ȃ��߂Â��Ďq�t�̐����������Ă݂�ƁA�Ȃ�Ƌ㖇������ł͂Ȃ����B
�@�܂�������ȁH�c�c�Ǝv���Ȃ���ׂ̗t�ׂĂ݂�Ƃ�͂�㖇�̎q�t������B�Ȃ��䂪�ڂ��^���Ȃ���蓖���莟��Ɏq�t�̐����`�F�b�N���Ă݂�ƁA�ӊO�Ȃ��Ƃ��������Ă����B�قƂ�ǂ̗t�͎q�t���������㖇�ŁA�����̗t�̂Ȃ��ɁA�����r���̂��̂炵���O�����邢�͌ܖ��̎q�t�������̂���芄���ō������Ă���B���������Ƃɔ����̎q�t��������̗t�ȂLjꖇ����������Ȃ��̂��B
�@�ǂ����A����̗t�́A�͂��ߐ�[���O�ɕ����ꂽ���ƁA�O���̗��q�t�����ꂼ����ɕ�����Čv�ܖ��̎q�t�����t�ƂȂ�A����ɂ܂����E���[�̎q�t�����ɕ�����Ď����̎q�t�������̂ւƐ�������炵���B�����čŌ�Ɏ����̎q�t�̗��[�����ꂼ������A�㖇�̎q�t�������S�ȁu����̗t�v�ƂȂ�悤�Ȃ̂��B����ł́u�ŔɋU�肠��v�������Ƃ���ŁA����̒c��g���[�h�}�[�N�̓V��l���^���̎��Ԃł���B����A�ĊO�A�V��l�̂ق��͂Ƃ����ɂ��̎������������ŁA�悯���Ȃ��Ƃ𑛂����ĂĂ����ȂƁA������ݒׂ����悤�Ȋ�����Ă�����̂�������Ȃ��B
�@���Ƌ�̕��ϒl�͔�������A���̐A�����u����v�ł��u���v�ł��Ȃ��u����v�ƌĂԂ悤�ɂȂ����̂́A�X���ނ����Ȃ����Ƃ�������Ȃ��B�䂪���ł͌×��u���v�Ƃ����������S���ʂ�\�����N�̂悢�����Ƃ���Ă������ƂȂǂ��A����Ȍď̂��蒅�������R�̈�ł͂���̂��낤�B�����A�u����v�Ƃ����ď̂����̐A���̎����ɐ��������邽�߂̊ώ@���܂点�A�ϔO��̋�����{���̑����ƍ��o�����Ă��܂��ƂȂ�ƁA�b�͏����Ƃł͂��܂Ȃ��Ȃ��Ă���B
�@���������ƁA���Ƃ��Ɨ��_�Ƃ͂��́u����v�Ƃ����ď̂̂悤�Ȃ��̂ł���B�����Q�̎����̑S�̑��ϓI�ɂ͂悭�\���Ă��邪�A�X�̎����ɂ͕K�������悭���Ă͂܂�Ȃ��B��������A���_�Ƃ������̂́A�X�̎����̂��ɒ[�ɕ����������̂āA�����S�̂ɂقǂقǂɓ��Ă͂܂��ʓI�ȓ���������u�@���v�Ƃ��Ă܂Ƃ߂��������̂ɂق��Ȃ�Ȃ��B���̂悤�ɂ��ē����ꂽ�召�l�X�ȗ��_�́A���݂Ɍ��т����d�ɐςݏd�˂��Ă���ɑ傫�ȗ��_���\�����Ă������ƂɂȂ�B���������āA���_����剻���Ă����ɂ�āA��������͂ǂ�Ȃɗ��h�ł������Ƃ͂ǂ�ǂ����ꂽ���̂ɂȂ��Ă������Ƃ������B�����āA���̂悤�ȗ��_���ӐM�I����͈Ӑ}�I�ɎЉ���Y�����ɓK�p�����Ƃ��A�ڂɌ����Ȃ��`�ő傫�ȕs���v����͉̂�X��ʎs���Ȃ̂ł���B
�@��剻�������_�ɋ^���������Ƃ��A���̋\�Ԃ��������B��̎�i�́A����̖ڂ�M���ė��_�̌��_�ւƗ����߂邱�Ƃł���B��������̎q�t�������̂����Ȃ��u����v�̎������������āA���̌ď̂̕\�Ɨ����ꂼ��̂��Ӗ���[���l���Ă݂邱�Ƃł���B���̈�A�̃R�����ł́A���낢��Ȋp�x����܁X����Ȃ��ƂȂǂ����グ�Ă݂����B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
1998�N10��21��
��̉��o���X�s�[�J�[�@
�@����̘b�������Ă��āA���_������̂��Ƃ�z���o�����B�u���{�̃G�W�\���v�Ƃ����ٖ��������_����́A�H�ƊE�ł͔��Γ`���̐l���Ɖ������V�ˋZ�p�҂��B
�@���_�Ƃ������̂͗��n�̌��ŁA���̌��E��Z�����������ėp����Ζ������J�����͂ȕ���ɂ��Ȃ邪�A�����������̐��������L�ۂ݂ɂ��ĐU��ƁA���W��j�Q���A��u�ɂ��Ă��̖�����f����ƂȂ�B��剻���������瘨���������_�ɋ^���������Z�p�҂��Ƃ�ׂ����́A���_�̌��_�ɗ����߂��čl���邱�Ƃł���B
�@�����A����͂������ėe�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ��B�����ł��̂��̂�����������A�ꌩ�����Ɍ����闝�_�̍���ɔ���A���_��I�m�ɋ�������ɂ́A��z�����\�͂��т������O�ɂ��킦�āA�l��{�̗E�C�ƗǐS��K�v�Ƃ��邩�炾�B���ꂾ���̔\�͂Ǝ��������Z�p�҂͂���߂Ă����Ȃ��B���_����́A�䂪���ł͂܂�Ȃ���ȋZ�p�҂̈�l�ł���B�I�[�f�B�I�V�X�e����5000�̊J���������݂Ă����̂��Ƃ��悭�킩��B
�@���_����́A�ӂƂ������Ƃ���A���O�̃I�[�f�B�I�̌������n�߂ĊԂ��Ȃ��A�A�i���O���R�[�h�ɉ����������ݍ��ނƂ�������G�l���M�[�ɔ�ׁA���R�[�h���特���Đ�����Ƃ��ɗv����G�l���M�[�����������邱�ƂɋC�������B�����ŁA�ŐV�̃��[�U�[�Z�p��p���ď]���̃A�i���O���R�[�h�ɍ��܂ꂽ���G�ȍa�̌`��ׂɒ��ׂĂ݂�ƁA�����قǂɖc��ȏ�B����Ă��邱�Ƃ����������B����܂ł̃v���C���[�́A�Đ��ɍۂ��āA�A�i���O���R�[�h�����������̂ق�̈ꕔ�����ǂݎ���Ă��Ȃ��������ƂɂȂ�B
�@�v���C���[���̂̔����Ȑk��������̒��g�̔��˂��������ɕϒ��������炵�Ă��邱�Ƃ���肾�����B�ɗ͕ϒ���}���邽�߃��o�[�ނ�����ނ���ؔr�����A���c��A�[���ɓ���ȍH�v���Â炵�Ď��_��������������5000�V�X�e���́A���\�N���O�̃��m�����Ճ��R�[�h�ł����������CD�𗽂��قǂɗǎ��ŗ��̊��̂��鉹�������߂��Ȃ��Ă��邱�Ƃ������Ă݂����B
�@���̂����ۂ��ŁA���_����͋��ٓI�Ȑ��\�����X�s�[�J�[�̊J���ɂ����������B�킸���ȃG�l���M�[��������Ă��Ȃ���̖����������܂ŋ����n�闝�R��Nj��������Ƃ��A�V�X�s�[�J�[�J���̂��������ɂȂ����Ƃ����B���ꂢ�ɔg���̂�����������g�́A��G�l���M�[�̂��̂ł����Ă��A�������g�ɕς��ƁA���炩���������ƂȂ��ĉ����܂ł悭�ʂ�B�Ƒn�I�Ȕg�����_�Ɋ�Â��ăo���T�ނ�f�ނɐv���ꂽ���^�X�s�[�J�[�́A������3�v���炸�̏o�͂ɂ�������炸�A�M�����Ȃ��悤�ȉ����Ɖ��F�ő�z�[�����ݍ��݁A���S�l���̒��O������������Ƃ�����Ղ��������Ă݂����B
�@�߂��Œ����Ă������Œ����Ă��A�O�㍶�E�ǂ̈ʒu�Œ����Ă������ɕς�肪�Ȃ����̑S���ʌ^�X�s�[�J�[�́A�ߋ��̏펯�z������i���̈�i���ƌ����Ă悢���낤�B���̉������I�[�f�B�I�����҂≹�y�Ƃ����́A�F�A�ٌ������ɋ����̐���������B
�@���_����́ACD���͂��߂Ƃ���ŋ߂̃I�[�f�B�I�Z�p�́A�|�p�Ƃɑ���`�����Ƃ�������Ă���B���^���ꂽ�����𒉎��ɍĐ�����̂ł͂Ȃ��A�Z�p�҂̊��o�Ɣ��f�Ō�����ϒ���������H�����肵�čĐ����邩�炾�Ƃ����B
�@��5000��CD�̍Đ��ɂ����Ă����̃V�X�e�������Ȃ��B�����ACD�̏��́A�����̘A������l�דI�ɋ����������A�s�A���ȃf�W�^�����ɕϊ����͂���鎞�_�ł��Ȃ�̕ϒ��������Ă���B����ɏ��Đ��̉ߒ��Ől�̎��ɓ���݂₷�������ւ̉��H�������Ȃ��邽�߁A�����Ƃ͂��Ȃ�َ��ȉ��ɂȂ��Ă��܂��̂��Ƃ����B
�@�ꔪ�����N�ɃG�W�\�����~���@�����Ă���CD�����y����܂ł̊ԂɃA�i���O���R�[�h�ɒ~�ς��ꂽ�c��ȏ��́A���j�I�ɂ݂Ă����������̂Ȃ�������Y�ł���A�����������̒��ɒ��ߎ̂ċ��邱�Ƃ͐l�ނɂƂ��đ�ςȑ������ƁA���_����͔M�����B���̔����������̋P���ɁA���͎��_�N�w�̐_�����݂�v���ł���B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
1998�N10��28��
�W���[�Ɣӎނ����킵�����X�@
�@�����������������̃`���p���W�[�̃{�X�A�W���[�����̏\����\���Ɏ��B����N��l�\��A�`���p���W�[�Ƃ��Ă͂����ւ�Ȓ����������炵���B
�@���N�̔����ɂ��܂��ܓ����s���������������̋g���k��Y����ɂ������@����������A���̎��ɖ��{�X�A�W���[�̂��Ƃ��b��ɂ̂ڂ����B�g������Ƃ����A�S������`���p���W�[�̎������|���ĎO�\�]�N�A�쒷�ނ̌����҂Ƃ��Ă��L���m���A�e���r�Ȃǂł����Ȃ��݂̕��ł���B
�@�������̎���W�Ƃ����ƁA�a���������B�̒���|�������肷��I�W�T���̂��Ƃ��Ǝv��ꂪ�������A���ۂɂ́A�g��������͂��߂Ƃ��āA�L���ȑ�w�̑�w�@�Ȃǂœ������Ԋw����w�Ȃǂ��C�߂��l�����Ȃ��Ȃ��B����W�Ƃ͑��Ȍď̂ŁA���͂�����Ƃ��������̐�匤���҂Ȃ̂ł���B
�@�g������`���p���W�[�̐��Ԃɂ��Ă��b���f�������ɁA��X�l�Ԃ͕����ʂ�u���ɂ���鑶�݁v�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ƃ����C���ɂȂ��Ă����B�������A�쒷�ރq�g�ȃq�g�ڃq�g�ł͂Ȃ��A�쒷�ރT���ȃT���ڃq�g�ɕ��ނ���Ă����������Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă������炽�����B
�@�`���p���W�[�ƒ��N�������Ă���ƁA�`���p���W�[���l�ԂɎ��Ă��܂����A�l�Ԃ��`���p���W�[�Ɏ��Ă����ł���B�l�Ԃُ͈�ȃ`���p���W�[�����A�`���p���W�[�ُ͈�Ȑl�ԂȂ�ł���\�\���������ď��g������̂��Ƃɂ͖��ɐ����͂��������B�g������̕��e��g�U�肪�ǂ��ƂȂ��`���p���W�[�̂���Ɏ��Č��������Ƃ��A���̈����������������Ȃ��B
�@�}�X�R�~�ȂǂŁA�`���p���W�[�̒m�\�͗c�����݂��Ȃǂƕ��ꂽ�肵�Ă��邪�A����͉��̍������Ȃ����ƂȂ̂��Ƃ����B�m�����ꂽ�`���p���W�[�̒m�\����@������킯�ł͂Ȃ��A�ǂ�������������Ȑ����ɉ߂��Ȃ��̂��������B���N�ɂ킽�鎩��̌o����ʂ��Ă݂邩����A�ނ�̒m�\�͑z���ȏ�ɍ����悤���ƁA�g������͌��B
�@�j�z���U���̎Љ�́A�{�X�U�����ʂ̃T������҂��x�z����҂̕������D����ꐧ��`�Ȃ����͕�����`�^�Љ���A�`���p���W�[�Љ�͊Ǘ��^�Љ�Ȃ̂��Ƃ����B�`���p���W�[�̃{�X�͉�Ђ̊Ǘ��E�݂����Ȃ��̂ŁA�l�]�Ȃ�ʁu���]�v�A�Ȃ��ł��A���̃`���p���W�[��������̐M�����Ȃ���Ζ��܂�Ȃ����̂炵���B��ȃ{�X�̎d�����A�O�G����Q����邱�Ƃ�A���ԓ��̑������Ƃ̒��قł��邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B
�@�`���p���W�[����Έ�Ō��܂����邱�Ƃ͂����Ȃ��炵���B���ʂ́A���ꂼ�ꂪ���Ԃ����蕡���ő������炾�B�{�X�̃`���p���W�[�́A����ȑ������������炳�肰�Ȃ����߂Ă��邪�A���E�����Ȃ��Ȃ�悤���ƁA���قɂ͂���B
�@���̔��f�Ə����͓I�m�ŁA���҂Ǝ�҂̊Ԃɂ͂���Ƃ��ɂ́A���҂Ɋ�Ƒ̂������A�w���Ŏ�҂������Ƃ����B���[���ᔽ�̉��Q�҂����Q�҂����ꍇ���A���Q�҂Ɋ�Ƒ̂������A��Q�҂�w��ɂ����B�����̓����҂̂ǂ��炪�����������ɂ悭������߂Ă���A�ْ����邱�Ƃ͖ő��ɂȂ��B
�@�����A�u�������痎����v�̌��ʂ�A�������̃{�X�����܂ɂ͔��f�~�X���������B����ȂƂ��ɂ͑z��ʎ��Ԃ��N����炵���B�������������̃`���p���W�[�̃{�X�A�W���[���A����Ƃ��A��Q�҂Ɖ��Q�҂̎��ʂ�������B�ق��ɔ[���̂����Ȃ��^�̔�Q�҂̃`���p���W�[�̂ق��́A�葫���������o�^�����Ȃ������߂��čR�c���A���͂̒��Ԃ����ɍق��̕s������i���������B����ƁA�����̃`���p���W�[������ɓ������A�L�͂Ȏ��������������ăW���[�ɔᔻ�I�ȑԓx���Ƃ�����A�W���[�̂��Ƃ������肵�͂��߂��B
�@�������莩�M��r�������W���[�́A�m�C���[�[��ԂɊׂ��āA���������̕Ћ��ɍ��荞�ގ��ԂƂȂ����B�s�[���ƓV��˂��ׂ��ے��������Ȃ�����ςȂ��̗L��l�Ƃ����āA����������͂܂��܂��n���ɂ���A������{�X�s�݂ƂȂ����Q�͑卬�����������͂��߂��B
�@�b��Ƒ��k���A�l�Ԃ̏ꍇ�Ɠ��l�ɐ��_����܂𓊗^���悤���Ƃ����b�ɂ��Ȃ������A����Ȃ�̖�������̂ł����������������悤�Ƃ������ƂɂȂ����B���̎��A�g������ɂ��邱�Ƃ��Ђ�߂����B�l�ԂȂ�A�X�g���X�����܂�ƈ�t����ėJ�����炵������B�`���p���W�[���l�ԂɎ��Ă���Ƃ����Ȃ�A������Ɣӎނ���点�Ă݂���ǂ����낤�Ƃ����킯�������B
�@�g������̓W���[����ʎ��Ɋu������ƁA�ނ̂��߂ɖI���Ŋ����������̃E�B�X�L�[��p�ӂ��A������O���X����ɂ��Ăǂ�����ƍ��荞�B�������āA�����������̈���ŁA�l�Ԃƃ`���p���W�[�Q�l�A����P�l�ƂP���̊ԂŊ�Ȏ������J��L�����邱�ƂɂȂ����B�x�e�����̎���W�ƒ��N�������Ƃ��ɂ����`���p���W�[�́A���ʂɘb���l�Ԃ̂��Ƃ��X���ȏ㗝������Ƃ����B�ނ��A����W�̂ق����`���p���W�[�̐S����ɂƂ�悤�ɂ悭�킩��B�g������́A�l�Ԃ�ɂ����Ƃ��Ƃ܂������������q�Řb���������B���������m��Ȃ��҂����̗l�q�����Ă�����A�v�킸�����o������͂Ă��ɈႢ�Ȃ��B
�@�g�@���F�W���[�A���܂�����ς���ȁA�܂��A��t����Č��C������I
�@�W���[�F�I���i�@�A���E�A�����i�`���E���I�A���X�h���K�A���b�e�^�J�b�e�A�I���m�R�g�A�o�J�j�X���_�����i�@�c�c�B
�@�g�@���F���܂��̋C�������킩�邯�ǂ悧�A���C�ɂȂ��Ă܂��Ԓ����Ă�����Ɖ���������B���܂���̌Q�����܂̂܂�܍�������������悧�A�������Ď�ɂȂ��ăI�}���}�̐H���グ�ɂȂ邩�������̂�c�c���ނ�A�Ȃ��I
�@�W���[�F�^�c�����K�^�^���g�A���E�h�i�C���i�������c�c���f�A�z���g�j�A�R���m���g�A�r���r���j�i�����J�C�H
�@�g�@���F���܂��̃o�C�A�O������˂�����悧�A��������Ă����i�j���ł���킯����Ȃ����ǂ����A�C�����悭�Ȃ��Ă������薰��͂��邺�c�c�B
�@�W���[�F�t�[���A�I���[�j���A�N���[�J�P�����i�@�B�W���A�}�@�A�`���C�g�m���f�~���J�A�h���h���c�c�B
�@�g�@���F���������A�����Ƃ������ɃO�[�b�Ƃ����ȁI
�@�W���[�F�E�[���A�R���A�i�J�i�J�C�P�����c�c�L�u���A���E�i�b�e�L�I�b�^�V�i�@�I
�@�W���[�����ۂɂ�������ׂ����킯�ł͂Ȃ�����ǁA�ނ�͂���Ɏ����S�̉�b�����킵���炵���B�����Ԃ��������ăW���[�ɘb�������Ȃ���ӎނ𑱂��Ă���ƁA�W���[�͋C�����悳�����ɐQ����ł��܂����B�����ŁA�g������́A���ꂩ��Q�J�����葱���āA�W���[�̔ӎނ̑���߂Ă݂��B���̌��ʂ͂Ȃ�Ƃ����ŁA��������X�g���X�̂Ȃ��Ȃ����W���[�̐S�g�A����S�`���͂����܂����ʂ�̗͋��������߂��A���̌�Ќ��̂������ŁA�`���p���W�[�̌Q�͍Ăѓ������̂ł������B
�@�`���p���W�[�����_�I�ɗ������Ƃ��Ώ��Ö@�Ƃ��Ĕӎނ����ʓI���Ƃ����g������̃��|�[�g�́A�����Ԃ�ƕ]���ɂȂ�A�e���r�Ȃǂł����ꂽ�B����ƁA������ċ����������̂�����������A�W���[�ɃE�C�X�L�[�肽���Ƃ����\���o���܁X��������ł���悤�ɂȂ����B
�@����ȂƂ��A�g������́A�ŋ߂����̃W���[�͌����삦�܂��ăW���j�N����~�[�}���^���������݂܂���̂łǂ�����낵���A�Ɖ������Ă����炵���B��k�Ƃ����炸�A��u���Ƃɋl�܂邨����������Ȃ��Ȃ������Ƃ����B
�@�g������̂ق����X�g���X�����߂��Ƃ��A�W���[��SOS�����߂��̂��ǂ����͕����R�炵�����A�ĊO�A�W���[�̂ق��́A�������A�ŗ�܂��Ă���Ă���͉̂����Ǝ������Ă����̂�������Ȃ��B���ہA�W���[�������āA���܂����Ƃ��߂���ł���̂́A�ق��Ȃ�ʋg������Ȃ̂�������Ȃ��B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
1998�N11��4��
��W���[�j�[�Ƃ̑Θb�@
�@����Ƃ��A�W���[�j�[�Ƃ�����e�`���p���W�[�̋��ɕ�����ꂽ�Ԃ����̗l�q�����������Ȃ����B���̂܂܂ł͖�����Ȃ��Ƃ��̂ŁA���ʎ��ɐe�q���ڂ����Â��Ƃ������ƂɂȂ����̂����A�W���[�j�[�́A�������肵���Ԃ����������������ߗ������Ƃ��Ȃ��B�C���ɐ������邵���Ȃ��Ɣ��f��������W�̋g������́A�߂Â��Ɩт��t���āA���낵���`�����ɂރW���[�j�[���₳�����Ȃ��߂ɂ��������B
�@���̂܂܂���Ԃ���Ⴄ��A���������낤�A�����Ă����邩��n���Ă����c�c�ƌ����Ɍ�肩���邤���ɁA�悤�₭�W���[�j�[�͐Ԃ����𗼎�ō����o�����B�������A�������낤�Ƃ���ƁA�����Ɏ����ނ������čU���I�ȕ\����݂���B�Ȃ�Ƃ����Ă��炢�����̂����A�ǂ����Ă���n���Ȃ��̂��B���ڂ̎�n���͊댯���Ɣ��f�����g������́A���������ŁA�u�W���[�j�[�A����Ȃ�Ԃ��������ɒu���Ȃ����B�����āA�����̉��ɍs���Ȃ����v�Ɩ��߂����B
�@�W���[�j�[���悤�₭�Ԃ��������ɂ��낵�A���̂ق��ւƂ��������̂ŁA�g�����Ԃ���������グ���̂ق��ɋ߂Â����Ƃ����B���̏u�ԁA�W���[�j�[�̍����̂��ːi���Ă����B�`���p���W�[���{�C�ɂȂ�����A�l�Ԃ̑̂��������ƂȂǂȂ�ł��Ȃ��B�������̋g��������A�������߂��ƊϔO�����Ƃ����B�����A�W���[�j�[�����̂́A�B�̔��̊i�q�������B����́A�����̊O�ɏo���A�����̌��Ă���O�łȂ�Ƃ�����Ƃ����A�W���[�j�[�̈ӎu�\���������̂��B
�@�Ăыg������̐������͂��܂�A�悤�₭���߂̂����W���[�j�[�́A���𗎂Ƃ��ĕ����̉��ɖ߂����B�����āA�����ɂ��������܂��炷���ۂ肩�Ԃ��ď��ɂ������܂����B����́A�ƂĂ����Ă͂���Ȃ��Ƃ�����e�Ƃ��Ă̐h���C�����̃A�s�[���������B
�@�d���x���ɂ��������Ԃ����́A�b��̎�ɓn�����Ƃ��ɂ͂��łɎ���ł����B�g������͌����悤�̂Ȃ��v���ɂ����Ȃ���W���[�j�[�̂Ƃ���ւƖ߂����B�����ɔ��ł����W���[�j�[�́A���ɐԂ��������Ă��Ȃ��̂ɋC�Â��ƃM�N���Ƃ����悤�ɑ����Ƃ߁A�g������̊�������ƌ��߂��B
�@�g�����������Ǝ��U��Ȃ���A�u�W���[�j�[�A�Ԃ����ł���B�Ԃ����͂����Ԃ��Ȃ��c�c�v�ƌ�肩����ƁA�W���[�j�[�͂����Ȃ�y�������A���Ɋz�����������悤�ɂ��ĉ��x�����������͂��߂��B����ł��ʖڂ��Ƃ킩��ƁA���x�͗�����d�˂đO�ɍ����o���A�����V�����Ȃ���Ԃ�����Ԃ��Ăق����ƈ��肵���B
�@�g������́A�W���[�j�[�̑O�ɂ��Ⴊ��ŁA���x�����x���W���[�j�[�Ɏ��������������B�g������̖ڂ̉���`�����ނ�ɂ��Ȃ��畷���Ă����W���[�j�[�́A�悤�₭���߂��悤�ɕ����̉��ւƕ�����������̂́A�����Ɉ����Ԃ��Ă��Ă܂��������A���������邠�肳�܂������炵���B�Ō�̓W���[�j�[�����ׂĂ̎����[�����Ă���A���q�ǂ��Ƀi���V�[�Ƃ������O�܂ł��Ă�����̂����������A����͂����A�S�ƐS�̉�b���̂��̂ł������Ƃ����B
�@
�@����Ƃ��A�B�̒��ɖY��Ă����^�I�����E���Ă���悤�Ƀ`���p���W�[�ɖ������B���̃`���p���W�[�������o���������^�I����B�̊i�q�̊Ԃ����낤�Ƃ���ƁA���̏u�ԑ���͂킴�ƃ^�I���𑫌��ɗ��Ƃ��A���炩���悤�Ȗڂ��ŋg������̊�������B�Ȃ߂��Ă͂����Ȃ��̂ŁA���������ł�����x���Ȃ����𖽂���ƁA�i�q�̂����߂��܂Ń^�I���������Ă��āA���Ƃ͎����ŏE���Ƃ�������ɂ܂����⏰�ɗ��Ƃ����B��ނȂ��A���Ⴊ��ł�����E�������悤�Ƃ������A���������Ă������Ȃ��B�Ȃ�ƁA���̃`���p���W�[���A�n���͂��߂����̎w�Ń^�I���̒[����������Ɖ������Ă����̂��Ƃ����B
�@�S������`���p���W�[�́A�����̉ߒ��Ő܁X����W�ɗ͊r�ׂ�m�b�r�ׂ�ł���B������u�����v�ȂǂƌĂԂ炵�����A�u�����v����������ꂽ�҂́A�����������Ɏ����̂ق�����肾�Ƃ������Ƃ�Ɍ֎����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����łȂ��ƁA�����猾�����Ƃ������Ȃ��Ȃ邩�炾�B
�@���ۂɂ͑���̂ق����r�͂��܂��邩��A�{�C�ɂȂ��Ċi��������ƂĂ����Ȃ�Ȃ��B������A�l�Ԃ̂ق����ア�ƌ���Ȃ��悤�ɁA���̕t�߂��������ďu�ԓI�ɂ��炵�߂�̂����炵���B���܂��܃`���p���W�[�������������Ă���̂�ڌ��������q���A���̎���W�͓������s�҂��Ă���ƊǗ����ǂ֍R�c���Ă��邱�Ƃ��������Ƃ����B
�@�g�����p���W�[�ƃf�[�W�[�Ƃ����`���p���W�[��Ɍ��������b�͖ʔ����B�f�b�L�u���V���{��������ŏ��̑|�������Ă���ƁA�p���W�[�����̈�{�����ݏ��ɏ���������͂��߂����A���̂����u���V�̒������̂ق����g������̂ق��Ɍ����Ă��肶��Ƌl�ߊ���Ă����B�f�[�W�[�̂ق����p���W�[����藧�ĂȂ���A�g������̔w��ɉ��P��������C�z���������B�B�ɓ���Ƃ��͓�d�����������{������̂ŁA���������߂����Ă��A�N�����ɂ͂͂���Ȃ������B
�@���̃`���p���W�[�Ƃ����Ζҏb�ɋ߂��B���ꂪ�Ŗ{�C�ɂȂ��ďP���������Ă�����A�l�Ԃ͂ЂƂ��܂���Ȃ��B�����A�����̉ߒ��ł����ꂱ��ȓ�������Ă��邾�낤�Ǝv���Ă����g������́A������Ă������Ȃ��ƕ����������B�����łЂ����Ԃ������Ȃ��Ȃ邱�Ƃ͖ڂɌ����Ă����B�w�����㌕�����̖Ҏ҂������g������́A�f�b�L�u���V�𐳊�ɍ\���A�f�[�W�[��w��ɉ�点�Ȃ��悤�Ɍ������Ȃ���Ǎۂ܂Ō�ނ����B���̗l�q�����Đ����Â����p���W�[���O�ɏo�悤�Ƃ����u�ԁA�g������͋���Ȗʂ̈ꌂ���������A�Ԃ��u���V��͈�t���ɕ����ĘA���Ƃ̓������߂��B
�@�ߖ������ē����o���p���W�[�����ڂɁA����ɍ\���Ȃ������u���V���f�[�W�[�̂ق��Ɍ�����ƁA������̂ق��͂��������ӑr�����ăp���W�[�̔w��ɉB��Ă��܂����B���ꂩ��Ƃ������́A�̃`���p���W�[�͋g������ɂ͂܂���������������Ȃ��Ȃ����Ƃ����B
�@�Ⴂ���S�����̎���ɂ������Ă����g������ɂ͋ꂢ�o��������B����Ƃ��B����o�悤�Ƃ���ƁA�ꓪ�̃S���������ӂ����ł����邩�̂悤�ɔ��̑O�ɗ����͂��������B���̏�Ŏ���悩�����̂����A���̂��ƂɋC���Ƃ��Ă����g������́A���̃S���������̑O���痧���ނ��̂�҂��ĊO�ɏo���B
�@�������̟B�̔��͓�d�ɂȂ��Ă��āA��ڂ̔����J���A��������{���������Ɠ�ڂ̔��̑O�ɗ��B���̍ہA�B�̒��ɂ͂���ׂ����ǂ����S�ɖ���������Ƃ��́A��ɒ��ɂ͂���ȂƂ����̂��S���ł���Ƃ����B�����S�����ɂ̑����̑O�ɗ������g������́A���ɓ�������ƒ��������B����ȍ~�A���̃S���������ʂ܂ŁA�g������͖��̟B�̒��ɂ͂��邱�Ƃ͂Ȃ������Ƃ����B
�@����قǍאS�ɒ��ӂ��Ă��Ă������A�댯�Ȗڂɑ������Ƃ͔������Ȃ��B�`���p���W�[�Ɏw�����܂�d���������Ƃ�A�{�����`���p���W�[�ɑ̓������H�炢�n���ɂȂ��Ė��𗎂Ƃ������ɂȂ������Ƃ�����Ƃ����B
�@�g������̈�A�̘b���Ă���ƁA�u���̘f���v�Ƃ���SF���܂�G�Ƃł͂Ȃ��Ƃ����C�����Ă��邵�A�쒷�ނ̎���W�͎d���Ɏ��M�������ăm�C���[�[�ɂȂ�₷���Ƃ����b���A�\���ɔ[���ł���v��������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
1998�N11��11��
�����Ƃ����ĂȂ߂�Ȃ�I�@
�@�������������̋g������̂Ƃ���ɂ́A�����w��U�̊w��������������K�ɂ���Ă���B���̗��R�͖��炩�ł͂Ȃ����A����Ȋw������ڌ��������ŁA�`���p���W�[�ɂ́A������͂P�T�Ԃ�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ƃ킩��炵���B�ǂ����������A�z�Â炵�Ă邯�ǁA������Ƃ̐h��������A�܂������ʂ�ɂȂ��Ă�邩�\�\�Ȃ�Ă킯�ŁA���ɂ悭���̖��߂������Ƃ����B
�@�Ƃ��낪�A���Ȃ�����ł��A���ꂩ��ܔN���\�N��������˂Ȃ�Ȃ��V�l����W������Ă���ƁA��Ƃ��Č������Ƃ������Ȃ��B�悪�������Ă����̂ɁA�I���[�݂����ȐV�ĂɂȂ߂��Ă��܂�����\�\�Ƃ������Ƃł���炵���B
�@�w�b�����ڂ����`���p���W�[�Ȃǂ́A�����ꂽ����ɂ͈�葬�x�ŃT�C���𑗂邪�A���肪�V�Ă̐l�ԂƂ݂�ƁA���n���ɂ����悤�ɂ������Ǝw�����Ȃ���T�C�����o���Ƃ����B�I���[�����肶��A��������Ă��˂��Ƃ킩��˂����낤����ȁI�\�\�Ƃł��l���Ă���̂��낤�B
�@�g�������N��ĂĂ����x�e�B�Ƃ������̃`���p���W�[������B������̂��ƁA�����̂悤�Ƀx�e�B�ƌĂԂƃv�C�Ɖ���������Ă��܂����B����ȕ��Ƀ`���p���W�[�ɂ����ۂ��������̂͏��߂Ă������̂ŁA���C�ɂƂ��Ă�����x�x�e�B�Ɛ���������ƁA������Ɣw���������A����œ���������ރ|�[�Y���Ƃ����B�ނ��A�Ăт��������̈ӎu�\���ł���B�z��ʎ��Ԃɂ����˘f�����o�������̂́A�����̓x�e�����̋g������A���������A�u�x�e�B����v�Ɓu����v�Â��ŌĂт����Ă݂��B����ƁA��u�U������ċg������̊���`���b�ƌ������ƁA�܂��m���Ղ�����߂��B
�@�����ŁA�h�ӂ����߁A���x���u����v�Â��Řb�������邤���ɁA�悤�₭�@�����Ȃ������̂��Ƃ����B���Ԃ����̂ƊW�������āA��������ɂ�`���p���W�[�ɂ��v���C�h���萶���Ă���炵���̂��B����ȍs�����l�Ԃ̂��Ƃ������Ă̂����ł��邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B
�@�`���p���W�[�Љ�ɂ́u��������v�̃��[��������B�a�Ȃǂ��������ꍇ�A��ꔭ���҂ɐ�挠������A���~����̒��Ԃ����Ɏ�芪���ꂽ��͂��邪�A���̎҂������͂Â��ŒD����邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ����B�a�Ȃǂ𒇊Ԃ����ŕ��z�������̂��`���p���W�[�̓����̈�ł���炵���B�u���ɂ����v�Ƃ������Ƃ����邪�A����Șb���Ă���ƁA�u�l�Ԃɂ���鉎�ɂ����͂Ȃ�Ȃ�v�ƁA�ނ炪�݂��ɉ��ߍ����Ă�����i���畂����ł���B
�@�l�ԂƂ͐��т̍\�����قȂ邽�߁A�l�������ׂ点��͖̂����炵�����A�L����p�����200�`300���̒P����w���邱�Ƃ��ł���B����ƁA�ނ�͂����̋L����g�ݍ��킹�Ĉӎu�\��������悤�ɂȂ�B�K���̒����ʏ�̉��������ƌ��Ă����`���p���W�[���A�ˑR�A�u�I�}�G�A�L�^�i�C�A�T���v�Ƃ����A����܂ŒN�����������Ƃ̂Ȃ��\�������Đl�Ԃ����������̂͗L���Șb�����A���̒��x�̑���\�͔͂ނ�ɂ͕��ʂɂ��Ȃ���Ă���̂��Ƃ����B
�@�z���ȏ�̒m�\�����`���p���W�[�����A�ނ�̐g�̔\�͂��܂������B�g������́A�`���p���W�[�͖ҏb���ƒf������B���̈��͎͂O�S�L���ɋ߂��A���肪�{�C�ŗ͂����߂���l�Ԃ̎w�̍��Ȃǂ����܂��܂�Ă��܂��B�r�͂������ւ�Ȃ��̂ŁA���\�L��������S���ɕ���グ�A���₭���̉��������蔲����Ƃ����|���Ȃǒ��ёO�Ȃ̂��Ƃ����B�r�͂��������A���ŕ�����������������������肷��͎͂O�S�\�L���ɂ��B���A������тɂ������ẮA�O�E�܃��[�g������l���[�g���ɂ��y�Ԃ̂��������B�܂��A���b�̏ꍇ�A�̏d�͌y�����\�L�����邩��A�S�͂ő̓����肳�ꂽ��A���ɗ͂����ς��͂����ꂽ�肵����A���݂̐l�Ԃ͈ꔭ�Œv�������A�_�E�����Ă��܂��Ƃ����B
�@�悭�A�O�֎Ԃ⎩�]�Ԃɏ��|�B�҂ȃ`���p���W�[�����邪�A�ӂ���V��ł���Ƃ��ɂ�����^���Ă���ɏ�邱�Ƃ͂Ȃ��炵���B�ނ�ɂƂ��āA����͋�s�ɂ��߂����Ƃ̂悤�ŁA�����Ă����ƁA���̔n���͂������ĎO�֎Ԃ⎩�]�Ԃ��O�j���O�j���A�o���o���ɕ������Ă��܂��Ƃ����B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
1998�N11��18��
�[�͗A�͎m�̑���ׂ͍��@
�@��̏ꏊ�̘b�ł��邪�A�告�o�̎��g�݂����Z�ق̓y�U���A������u�����Ԃ�v�Ō�������@����B�����������ʂƌĂ�ANHK�e���r�ɑ傫���f���o�����Ȃł���B�����ɂ͈ێ����Ȃƌ����A�{���͑��o����⑊�o�����W�҂�����������Ȃ��ꏊ�Ȃ̂ŁA���R���̐Ȃ̐ؕ��͔����Ă��Ȃ��B���܂��܃c�e�������Ă���ȏ�Ȃɐ��荞�ނ��Ƃ��ł����B
�@����������̈ē��Œʂ��ꂽ�͍̂s�i���܂�̂܂����날����ŁA�b�ɕ����Ă����ʂ�y�U���T���Ȃ̗͎m�̊��R�����̎p����ɂƂ�悤�ɂ悭�������B�����߂̍��z�c�P�����̃X�y�[�X�����Ȃ��A���ݐH������ł��Ȃ����A�����ȂȂ̂͊ԈႢ�Ȃ��B
�@���ʐȂ̂ق������グ��ƁA�Ȃ�قǃe���r�J������������̂ق���_���Ă���B����ɂu�}�[�N���o���Ă͂��Ⴐ��ł��Ȃ����A��������n�i�N�\�Ȃ��ق����Ă���Ƃ�����A�b�v�őS�����p���ꂽ�肵���炽�܂�������Ȃ�����A�܂��͂��ƂȂ����p���𐳂��Ă̊ϐ�Ƃ͂Ȃ����B
�@�����蒼��ɍs���開���͎m�≡�j�̓y�U����́A�߂��ł����Ɍ���ƁA���͂�������������������B�y�U��ɂ�����ƕ��ԗ͎m�����̉��ώA�f�U�C���A�F�ʁA�D�蕿�Ƃ����푽�l�ŋ��y�F�ɕx��ł���A�z���ȏ�ɑf���炵�������B�����ʐȂ̂��߁A���j�̓y�U����͂����둤���璭�߂邱�ƂɂȂ�͂������̂́A�b���ʂ��ꂽ�ؓ��������̂܂킵�ŃO�C�ƈ������߂��E�p�ɂ́A�ق�ڂ�Ƃ������ł������B�O���j�̂����ł͏��̓y�U���肪�ł����͂��������B���Ƃ��Ƌ����͎m����������̊�Ƌ��̂̎����傾���瓖�R�ł͂��邪�A�p�J�[���A�p�J�[���Ɖs�������������ŏ���ɂ����܂����̔���̉��͈����������B
�@���o�̎��g�݂��ʔ����������A�߂����ɍ���Ȃ��Ȃɐw������������A���ȂƂ������ɖڂ��������B�܂��C�ɂȂ����̂́A�y�U�̎l��������A�ԁA���A���̎l�{�̖[�̐F�������B���[�͂��̒ʂ�̐F���������A�Ԗ[�͂�����G���W�F�A���[�͏����ł͂Ȃ���������������̂��锒�������B
�@�ӊO�Ȃ̂͐[�ŁA���ۂ́u�v�ł͂Ȃ��N�₩�ȁu�v�Ȃ̂ł���B�u�����v�Ƃ������{��͂��Ƃ��ƃu���[����O���[���܂ł̕��L���F����\�����t������ԈႢ�ł͂Ȃ��̂����A��u�˘f�����o���Ă��܂����B�����Ƃ��u�݂ǂ�Ԃ��v��u��傭�Ԃ��v�ł͌�C���������Ƃ��̂����Ȃ��B
�@�y�U�͈ӊO�Ȃقǂɏ������������B��^�͎m���Q�l���y�U��ɏオ��ƁA�������ꂾ���Ŗ��t�Ȋ����ŁA����ȏ̂��Ƃł悭���ꂾ���̌������������ł�����̂��Ɗ��S�������B�S�y���ł߂đ������y�U�͍�������l�̑������t�߂܂ł͂���A�A��ۂɎ��G��Ă݂�Ƃ��̏�ʂ����ʂ������ʂ�J�`�J�`�������B���݂̐l�ԂȂ�y�U�ォ��]�������������ő傯�����邱�Ƃ��낤�B
�@�T���͎m�͂��ꂼ��Ɏ����̂������̓������傫�ȍ��z�c��t���l�ɉ^��ł�����Ă���ɍ���B���g�݂��I���Ƃ��̍��z�c���^�яo���A���̗͎m�̍��z�c�Ɠ���ւ���B�ٓ��̋��X�܂ł悭�ʂ�ƌ�����Ăяo���̐��́A�������Ŏ����X����Ɛ[������ł͂�����̂́A�ނ���ׁX�Ƃ��������ɕ��������B���N�b�����Ɠ��̌ċz�@�ɂ���ĕ��̒ꂩ��i��o���悤�ɔ������邻�̐��́A�ȑO�q�ׂ����_���X�s�[�J�[�̂��������̖����ȂǂƓ����̂��̂Ȃ̂��낤�B
�@�������̂���Ԃ������āA�T�l�̐R�������y�U��ŋ��c���͂��߂��B�F�������܂ɔ����������d�˂����Ă���B�ʔ����̂͑����̂ق��ŁA��l���q�ǂ��̑�����ܐ�ɂ������������ŁA�����̔����قǂ����J�o�[����Ă��Ȃ��B���̈�Ԃ͌��Ǎs�i�����Ⴆ�ƂȂ����̂����A�y�U���~��Ă������̍s�i�̊�͑����ɂ�����Ă����B�����Ⴆ�͂Ȃ��ق����������A�����ۂ��ōs�i�̌��ЂƂ͉����낤�Ƃ����v�������Ă��Ȃ����Ȃ������B�ǂ����Ȃ�A�y�U���̂T�l�̐R�����ɍg���̊����������A�_���̎����̂悤�ɏ����肳������ǂ����낤�B�����������m�ňЌ����Ȃ��Ȃ邱�Ƃ͔������Ȃ����c�c�B
�@���ꂼ��̌��܂̂ڂ肪�����ɋÂ����D��͗l�ɂȂ��Ă���͈̂ӊO�������B���炩���ߋ���ɓo�^�����X�|���T�[��Ƃ������܂̂ڂ���o���Ȃ��V�X�e���炵���A���Ƃ�����ł����Ă��A���O�҂������Ȃ茜�܋����o���Ƃ����킯�ɂ͂����Ȃ��悤���B�X�|���T�[��Ƃ͔N�Ԃɉ��{���܂��o���˂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ������悤�Ȍ��܂�Ȃǂ�����̂��낤���B
�@�����͎m�����܋��̓������j�V�܂���ɂ���l�́A�܂�ŏ����ȃg�����v�̃J�[�h���P���܂݂������݂����Ȋ����ł���B100���~���炢�����������傫�ȏj�V�܂łȂ��ƕ��O�ꂽ�͎m�̎�ɂ̓}�b�`���Ȃ��̂�������Ȃ��B
�@�͎m�̑����̋��̂Ɋr�ׂċ����قǂɍׂ��̂���ۂɎc�����B���═���ہA�Ղ̎�Ƃ����������͎m�ł����̓_�͓����������B�ꗬ�̓���̎�ӊO�Ȃ܂łɍׂ��̂Ɠ����悤�ȗ��R����Ȃ̂��낤�B
�@��ԋ��킹�͂Ȃ������̂ō��z�c����Ԃ��Ƃ͂Ȃ��������A�����e�ȁi�܂������j����y�U��܂ō��z�c�����Ƃ���A���̋�������l���đ����ȋZ�p������B������A���ۂɂ͓y�U�̎l�����͂ސ���قǂ̈ێ����Ȃ����肩������z�c����Ԃ̂ł���낤���A������ێ����̎d���̈�Ƃ����킯�Ȃ̂��낤���B�܂��A���̓��̎��݂����ɉ������Ȉێ��������邱�Ƃ�����A����Ȃ��Ƃ��N�������Ƃ��Ă��A�ׂɕs�v�c�ł͂Ȃ��B�A��ہA����������ő傫�Ȏ��܂����ς��̂��y�Y�Ղ������A����̓C���X�^���g�ێ����̎��ւ̈�����̕�V�ł��������悤���B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
1998�N11��25��
�h�i���h�E�L�[���搶�@
�@�挎�A��ʌ������s�ōÂ��ꂽ�A�����w�҃h�i���h�E�L�[���搶�́u���̍ד��v�ɂ��Ă̍u�����q�������B�����ɂȂ��ċ��k�����A��N�O�A�u�������J�̊���v�Ƃ����I�s��i�ő��̍ד����w�܂Ղ����Ƃ��A���`���A�剪�M�̗��搶��ƂƂ��ɓ��܂̑I�l�ψ��߂Ă���ꂽ�̂��A�ق��Ȃ�ʃL�[���搶�ł���B
�@���������Ԃ�Ɛ̂̂��ƂɂȂ邪�A�uMEETING WITH JAPAN�i���{�Ƃ̏o��j�v�Ƃ����搶�̒�����q�ǂ��A���{���w�ɂ�������搶�̎v������Ƒ��w�̐[���Ɋ����������Ƃ����邾���ɁA�ǂ̂悤�Ȃ��b���Ȃ���̂��y���݂ł������B
�@�����{�C�R�ɂ��^��p�U���̒���A�R�����r�A��w�̊w���������搶�́A�u�肵�ăJ���t�H���j�A�̕ĊC�R���{��w�Z�ɓ��Z�A�����Ŗҗ�ȓ��{��̓��P�����ɂȂ����B�l�E�܃J���őS�������{��̐V�������R�ɓǂ߂�悤�ɂȂ�قǂɁA����߂Č��������H�I�ȓ��{�ꋳ�炾�����Ƃ����B��킪�u������Ƃ����ɁA��X�̐�ǂ̓W�J��I���ɂ�������ĊԂ̏����̏������ɂ�č����{�́A�C�R�ɂ��̓��{��w�Z����݂��A���{��Ɠ��{�����ɒʂ����D�G�Ȑl�ނ̈琬�ɂ̂肾�����̂ł���B�S�{�ĉp�������t�ɁA���������̉p��̎g�p���֎~�������{�Ƃ͑�Ⴂ�ł������B
�@���̕ĊC�R���{��w�Z����́A�̂��ɓ��{�����̗D�ꂽ�����ҁA�Љ�҂Ƃ��Đ��E�I�ɖ���y����m���h�̎�҂��������������Ă������B�L�[���搶�̂ق��A��[�N����O���R�N�v�̖|��҂Ƃ��Ė������G�h���[�h�E�T�C�f���X�e�b�J�[�A�n�[�o�[�h�勳���Œ�����g�߂��G�h�E�B���E���C�V�����[�A���܂��Ȃ��l�X�Ȏ����̕�����͂��߂Ƃ���e��`���|�\�̑�������Ԃ܂ꂽ�Ƃ��A�����ʂ�͂̌����s�����Ă��������炵���t�H�r�I���E�o�E���[�Y�Ȃǂ́A�F���̓��{��w�Z�̏o�g�ł���B
�@�L�X�J���A�A�b�c���Ȃǂ̌���n�ŁA�ČR���{��ʖ�E�|�Ƃ��������ɂ��ꂽ�搶�̓��{�����ւ̊S�́A���̎d����ʂ��ē��X�[�܂��Ă������炵���B�I���A�R�����r�A�A�n�[�o�[�h�A�P���u���b�W�̊e��w�œ��{���w���U�A���O�N�ɂ͋��s��w�ɗ��w���ꂽ�B�����̎��_�ł��łɁA�a�̂̓��h�Ƌ��ɔh�̈Ⴂ��A�ߏ��卶�q�傪���̏�ڗ���i�ɓ��������\�̗v�f�A�����m�Ԃ̒�q�\�l�̔o���̓����⑊��Ȃǂɂ��Ę_���邱�Ƃ��ł����Ƃ������炨���ꂢ��B
�@�J�菁��Y�A���Ɏ��A�O���R�N�v����͂��߂Ƃ��鑽���̓��{�ߑ��Ƃ����Ƃ��[���𗬂̂������L�[���搶�́A���N�Z�����̓R�����r�A��w�ŋ��ڂ��Ƃ�A�c��Z�����͓��{�ɂ����āA���{���w�̌����ɖv������Ƃ��������������܂ő����Ă�����B�ÓT���猻�㕶�w�Ɏ���܂ŁA���̂��d���͕��L���A���������[���B�呠���̉ƌ��ɒ�q���肵�ċ������w�сA�u���ڂ̑��Y���ҁv�ٖ̈������̂ɂ��ꂽ���Ƃ�����A���{�̓`�������ɂ�������搶�̎v������̐[�����f���m���B���a�O�\�N�ɂ͑�D���Ȕm�Ԃ��Â�ŁA���ۂɉ��̍ד��̗������݂��Ȃ������Ƃ�������A�搶�́A���{�l�ȏ�ɓ��{�l�I�ȕ��ł���ƌ����ق��Ȃ��B
�@���{�����̑f���炵���͊O���l�ɂ͂킩��Ȃ��ȂǂƂ����̂́A�Ƃ�ł��Ȃ�����ŁA�O���l�����炱�����̐^�����킩�邱�Ƃ������B�����G�̉��l�ɋC�Â����̂��A���������ɔr���ʎ߉^�����N�������Ƃ������̋M�d�����������A���̕ی��i�����̂��ق��Ȃ�ʊO���l�����������B
�@�����m�Ԃ́u���̍ד��v�́A���݂̎l�S���l�߂̌��e�p���Ɋ��Z����Ƃ킸���O�\�ܖ��قǂ̍�i�ł�B�ӊO�ȂقǂɒZ�����̍�i�̊����ɁA�Ȃ��m�Ԃ͌ܔN���̍Ό����������̂��낤�B���̂�����̖��ɂ��āA�����̐V����V���߂������Ȃ���L�[���搶���Ȃ������u���͎��ɋ����[�����̂������B�u�����e�����ׂċL�ڂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A�ȉ��ɂ��̈�[���Љ���Ă��炨���Ǝv���B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
1998�N12��2��
�u���̍ד��v�ɂ��t�B�N�V�������H�@
�@��ʂɂ́A�u���̍ד��v�Ƃ�����i�́A�m�Ԃ����̗��̎��̌����قڂ��̂܂q�L�����I�s�ł���ƐM�����Ă���B�����A�m�Ԃ̐��s�҂������]�ǂ̐��s�L�A������u�]�Ǔ��L�v�̔�����A�ŋߘb��ɂȂ����m�Ԑ^�M�{�̏o���A����ɂ͂����̎��������Ƃɂ������Ƃ����̌����Ȍ����ƍl�ɂ���āA�ߔN�A�ӊO�ȐV���������X�ɖ��炩�ɂȂ��Ă��Ă���Ƃ����B
�@�����ɑ����s�ōs��ꂽ�u���ŁA�h�i���h�E�L�[���搶�́A���̂�����̂��Ƃɂ��ċ����[���b�����Ă����������B�w���L���Ȑ搶�̂��Ƃ䂦�A���R�u���̓��e�͑���ɂ킽�������A�u���̍ד��ɂ����̓t�B�N�V�����̕������������v�Ƃ������b�Ȃǂ́A���̂悤�ȑf�l�ɂƂ��Ă͑�ϋ����[�����̂������B
�@�u�t�B�N�V�������������邩��Ƃ����ĉ��̍ד��̕��w�I���l��������킯�ł͂Ȃ��B�ނ��낻��ɂ���Ă��̌|�p���͈�i�ƍ��߂��Ă���v�Ƃ��炩���߂��f���ɂȂ��������ŁA�搶�͋�̓I�ɂ������̃t�B�N�V�����������w�E���ꂽ�B
�@����̍�i��[���䂭�܂Ő��l���A���x���蒼������Ƃ����̂́A�m�Ԃ̏�ł������炵���B���������āA���X�̗L���Ȕm�Ԃ̋�̂Ȃ��ɂ͑�����͂قƂ�Ǒ��݂��Ă��Ȃ��Ƃ����B�m�Ԃ͎��R�̂̂܂܂ł��炳��Ƃ��̂悤�ȏG����r�A�Ƃ���M���Ă������Ȃǂ́A���̘b�������ƁA�����̖��\����I�ɂ����A���������ق��Ƃ����C���ɂȂ�������B
�@�R�`���̎R���ɂ��闧�Ύ��ʼnr�Ƃ����L���Ȉ��A
�@ �Ղ����ɂ��ݓ����̐�
�́A�����Ɏ���܂łɏ��Ȃ��Ƃ��O��͎蒼������A�ŏI�I�ɂ͓����̋�Ƃ͂��Ȃ��������̂ɂȂ����̂��Ƃ����B�܂��A�������ɍۂ��A������̐l�X�Ƃ̕ʂ��ɂ��݂Ȃ����Z������ʼnr�Ƃ�����A
�@ �s���t�Ⓓ�e�����̖ڂ͟�
�ɂ������ẮA���̍ד��̗����I�����̂��ɍ�������ꂽ���̂ł���Ƃ�������������B
�@���炩�Ƀt�B�N�V�����Ƃ킩��̂́A�����ʼnr�܂ꂽ�A
�@
�@ ���炽�ӂƐt��t�̓��̌�
�Ƃ����傾�����ŁA�]�Ǔ��L���̑��̎����Ȃǂ����Ƃɏڂ����l���Ă݂�ƁA�m�Ԉ�s�̓������K���͉J�����ŁA�t��t�����̌��𗁂тċP���ĂȂǂ͂��Ȃ������炵���B
�@�܂��A�u�̊��v�̒i�ɂ́A
�@�R�[���t������������Ă悤�₭�ɉh������߂�̊��̒��ɂ������A�Ȃ��Ȃ����߂Ă��炦��Ƃ��낪������Ȃ��B����ƌ������n�������Ƃɔ��߂Ă��炢�A�邪�����Ă���A�܂��m��Ȃ���������Ȃ�������Ă������B
�Ƃ�����|�̋L�q������B�Ƃ��낪�A���ۂɂ́A�����̗v�`�A�̊����ӂ̓��H�͂���Ȃ�ɐ������s���͂��Ă��Ė����悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ������͂����Ƃ������A���܂����Ƃ��ق�Ƃ��͒n�����Ƃ̗��h�ȓ@������̂��������B�m�Ԃ������Ď����ƈقȂ�L�q�������̂́A��ނ����Ȃ��������ƂƂ͂����A�ގ��g�͎��Y�ƂƉ������Ԃ��Ƃ��ւ�Ƃ͎v��Ȃ����������ɁA�̊����ӂ̉h�Ԃ肪���痝�z�Ƃ��đz���`�������̏�i�Ƃ͈�������̂ł���������ł͂Ȃ����ƍl������Ƃ����B
�@�����ɋP�������������Ɋ������Ăʼnr�Ƃ�����A
�@
�@�܌��J�̍~��̂����Ă����
�̋傾���A�]�Ǔ��L�ɂ��ƁA�������ݎ�镢�����ɂ͏������낳��Ă��āA���ۂɂ͔m�Ԃ����͉����݂邱�Ƃ��ł��Ȃ������悤�ł���B������A���̍ד��̃N���C�}�b�N�X�̈�Ƃ��Č������Ȃ��������A�m�Ԃ͑z���͂���g���A�S�̊�œ������A���̐S�ە��i����j�I�Ȗ���Ƃ��ĉr�݂��������ƂɂȂ�B�������������Ƃ����ق��͂Ȃ��B
�@�m�Ԃ͌��݂̎l�S���l�ߌ��e�p���ŎO�\�ܖ��قǂ̉��̍ד�����������̂ɌܔN���̍Ό����������Ƃ����B���̗��R�́A��̕�������łȂ��A�U�������܂߂����̍�i�S�̂��A����߂Ċ����x�̍������тȂ����͎�����Ƃ��Ďd�グ�悤�Ƃ����Ӑ}�����������炾�낤�ƁA�L�[���搶�͌���Ă�����B�s��ȗ��H�ł̐��X�̎��̌����m�ԂƂ����H��̓V�˂̐S�̂Ȃ��ň�x�h���������A���ꂪ�[�����������ɂ̐S�ە��i�ƂȂ��āA�u���̍ד��v�Ƃ������Ր��̍�����i�ւƌ��������̂��ƁA�搶�͂�������肽�������ɈႢ�Ȃ��B���ہA���������炱���A���̍ד��͊O���̐l�X�ɂ����ǂ����̂ł��낤�B
�@�s���Q���^�̕����s����i�߂Ă��鑐���s�́u���̍ד��E�m�ԍu����v�͐���̃L�[���搶�̍u���ő�\���ڂ𐔂���ɂ��������B�����s���̍ד��܂��Â���s�����i�ψ���ɂ���āu�S��̖��i�͂������̂�߁j�v�Ƃ����u���^�����s����Ă���A���̂Ȃ��ɂ́A���`���A�剪�M�A�L�n�N�l�A�����a�v�Ȃǂ̏��搶���͂��߂Ƃ���\���قǂ̕��X�̍u���̂ق��A�ȑO�̃h�i���h�E�L�[���搶�̍u���Ȃǂ����^����Ă���B�������m�Ԃ̐��_���ق��ӂƂ�����悤�ȁA�ؔ���r�����V���v���ȃf�U�C���ɂȂ��Ă���A��O�S�y�[�W�̏��Ђɂ��Ă͂���߂Ċi���ōD�������Ă�B
�@�Ȃ��A���̖{�̖��Ȃɑ��ɔ�ׂĊi�i�Ɍ���肷���Ⴂ�̍u����������܂܂�Ă���̂ŁA���̕��������͖��킸�����Ȃ������ق����悢���낤�B���̗��R�͂��z���ɂ��C������B
�@�]�k�ɂȂ邪�A�Ȃ�ׂ��J�Ȃ����ĉ��̍ד��̒Ǒ̌����������Ƃ����A�����ŗ~����ȕ��X�̂��߂ɁA�Ƃ��Ă����̏�����Ă������B�����l��������q����V�����ʂɌ������đ���Ɓu�A�O�̊ցv�Ղɏo��B�m�Ԉ�s����l�ɂ��̐g��������������A���~�߂�H������Ƃ���ł�B�Ղ��E��Ɍ��Ȃ���ʉ߂��A���炭�̂ڂ�ƒJ������傫�ȋ��ɂ���������B�Ԃ��~��Ă��̋��̂����Ƃ���J�؉����ɍד���H��ƁA�قǂȂ������̂قƂ���[����ɂ���B����͂��������Ƃ������ɕ����A���Ă̍����ƁA�ǂ�����Ƃ��Ȃ��������̐����������Ă���B
�@��قǂ̕��D�������ʂ邱�Ƃ̂Ȃ�襘H�����A���̓������͔m�Ԉ�s���܂���̈��V��Ɛ킢�Ȃ���z���Ă��������[��̘Z�Ȃ���̌Ó��ɂق��Ȃ�Ȃ��B�����̂܂܂̗l���𗯂߂Ă���̂͋����̂����킸���ȕ����ɂ����Ȃ����A�s�������������ؗ����̎}�X�̉������E�ɂ��˂�D���}�X�̍ד��́A���\����̒��R�z���i���H�R���z���j�̋�J�ƁA�����̗��̕��͋C�̂قǂ��\���ɎÂ��Ă����B��E�O�N�قǑO�A�������ۂɕ����Ă݂����A�m�Ԃ�]�ǂ̘b�����⑫�������܂ɂ��������Ă������ŁA�Ȃ�Ƃ����S�[�������B�����ŎO�E�l�\�����x����������Ȃ�����A�m�Ԓʂ����̂�����X�͈�x�K�˂Ă݂�Ƃ悢���낤�B
�@�m�Ԉ�s�͂��̎R�����̂ڂ�߂�������Ō��������J�Ɍ������A��ނȂ��o�H�����̖�l�̉ƂɎO���قǐ������邱�ƂɂȂ����B���̂Ƃ��ɉr�܂�̂��A
�@ �a�l�n�̔A���閍����
�Ƃ����L���Ȉ��ł���B�L�[���搶�́A��̍u���̂Ȃ��ŁA���̋�͔m�Ԃ̗��̐��_�̐^�����ے�������̂��Ə^���Ă���ꂽ�B
�@ �V��̉�҂��Ă���A�Ⴂ�����ȎR�ē��l�̐擱�ŁA�m�Ԃ����͓��Ȃ������i�݂Ȃ���R���������z���A���ԑ�̏W���ւƔ����Ă������̂ł���B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
1998�N12��9���u��\���N�Ԃ�̋A���v�`1999�N4��21���u��������A�܂��������܂Łv�̋I�s�G�b�Z�[�͂��̓쐨�o�ł̃z�[���y�[�W�Łu�����Č��I�s�v�Ƃ��Ĕ������ł��B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
1999�N4��28���A5��5��
����ނ�I�s
���E����ނ�I�s�@�@
�@�@�@�@�@����͐M�Z�ɐ��ށH
�@�F�l�̕đ�d����A�O�͘p������鈭�������˒[�̈ɗnjΖ����ɍ���ނ�ɍs���Ȃ����ƗU����B�đ�́A�������N�\�����Ɏd���ĂĂ��܂����]�_�ƁB�V�N�\�����ɋ߂���Ȃ����Ƃ����������Ȃ��A�����������肷��B�đ�̑�w���ォ��̐e�F�ŁA���Ƃ��t�������̒����W���[�i���X�g�̋ʖؖ���������s����Ƃ̂��ƁB���̎O�l���ꏏ�ɏo��������A�낭�Ȃ��ƂɂȂ�Ȃ����Ƃ͖ڂɌ����Ă���B
�@����̑�ނ藷�s�́A���̃}�j���A���E�����{�b�N�X�J�[�ł͂Ȃ��đ�̃I�[�g�}��p�Ԃŏo�����邱�ƂɂȂ����B�l����\������j�̌ߑO������JR�������J�w����ő҂����킹�A�����ɏo���B�R�[�X���͂����������ɔC����Ƃ������ƂɂȂ�B
�@���n�C���^�[����։z�����ԓ��ɓ���A�Q�n���ʂɌ������Ėk��J�n�B�����ŏ�M�z�����ԓ��ɕ����쌧�k����ڎw���B�u�R���M�Z�ɍ��₪����ł�킯�Ȃ�����A���܂���A�z�Ƃ��Ⴄ���H�v�v�Ə�ꂽ��A�u�͂��A�z�ł��ȁI�\�\�܂��A�Ȃ�悤�ɂȂ�܂������v�Ƒf���Ɏ�����̂�����������F�߂�̂݁B��̐ӔC�͂��̎��ɁB�o�����ǂ���Ɠ܂��Ă�����͖k�Ɍ������ɂ�ď��X�ɐ���オ��A�₪�ĉ����ɁB�s�������������̉�X�ɋ��͓I�Ȃ��V���l���A���Ȃ�C�܂���ȕ��ł͂��炵���܂���B
�@�쌴��R�������炩�ȗƁA���̒��ɓ_�݂��锒���R���̃R���g���X�g�����ɑf���炵���B���̋G�߂Ȃ�ł͂̔��������B�ƈ���Ɍ����Ă��A���\��ނ��̗�����B�F���ƍʓx�̈قȂ鑽�l�ȗ̐D��Ȃ����i�ɎO�l�Ƃ��Ђ����犴���B�ӏt���珉�Ăɂ����Ă̂��̔������ɖ������Ȑl���ŋߑ����Ă���Ƃ��������A���������Ȃ�����B�ǂ�ȗ������ΐF�ɂ��������Ȃ��F�ʃI���`�̂����炵���̂����A�Ȃ�Ƃ��͂�c�c�B
�@���قȊ��̘A�Ȃ�V���̊�A���`�R���ԑ�����ɑ傫������B���ĉ�Ƃ̐{�c�������A�拫���ɂ߂邽�߂ɒP�g���̎R�[�����Ă������Ƃ͂悭�m���Ă���B���N���O�A�ዷ�̔_����Ɠn�ӏ~������ē����āA�������̖��`�R�̊����ӂ�������܂�����B���`�R����ڂ�]���O���������ƁA�c���Ղ�����ԎR���Y��Ȏp�������Ă͂��߂��B
�@�����g���l���̘A������R�ԕ����M�B���v���ɓ���ƁA���i�͏��t�̂���ɕϖe�����B�u�t�܂��M�Z�H�́c�v�Ɖ̂̕���ɂ����镗�i���B�ނ��A�N�z�̕��Ȃ�A���蓡���̎��̈�߁u�Ȃ��n�R�x�͖G�����@�ᑐ���S�i���j���ɂ悵�Ȃ��v��z���o�����Ƃ��낤�B�Ԃ̐i�s�ɂ�āA����ɐ�Ȑ�̗��ꂪ�[�X�ƍ��f�R�ƁA���̏㕔�ɍL�����n�������Ă���B��������k��q���ɂ����Ă̑�n�ŁA��Ƃ̐���א搶�ݏZ�̊��Z���̂��鉺���d�������̈�p�Ɉʒu���Ă���B���������A�ŋ߁A�k��q���ł��V���ȃI�E���������N���Ă�����悤���B
�@�@�@�@�@�������R�����i
�@�X���Œ��쎩���ԓ��ɓ��薃�ё��i���݂ނ�j���ʂ������B�`���̛H�̎R���O���ɑ傫���p�������B�H�̎R�͊����R�Ƃ��Ă�Ă���B�u�Ȃ�Ŗ�̎R���Ȃ��̂��A����͒j�����ʂ̏ł͂Ȃ����I�v�Ɛ��̌���������l�₳��Ă����ɂ͕ԓ��̂��悤���Ȃ��B���{�̂ǂ����ɂ͖�̎R������̂��낤���B��������ȎR������悤�Ȃ�A��E�O�\�N��ɂ͉�X�O�l�����̂��R�̖��ɂȂ�������Ȃ��B
�@�H�̎R�g���l�����Ă����̖��уC���^�[�ō����������ʓ��ɂ����B���̖��уC���^�[���炷���̍�䑺�ۗ{���������́A���l�̓��ƌĂ��悢�̉���̗N���h���{�݂��B���̈�тɎ��۔��l���������ǂ����͖��m�F�B�߂��̓c�ނɂ̓q���{�^���������������Ă���A�Z�������玵�����{�ɂ����Ẵz�^���̗����͌�������������B�������w�O���߂��Đ��܂ŋ}�ȎR�����̂ڂ�A�������琹�����ցB��������т̎��т͂܂��~�̖��肩��ڊo�߂Ă��Ȃ��B
�@���������z���A�剪���������Ă��炭����Ƃ������ɓW�]���J���Ă���B���̒n�_����̖k�A���v�X�A��̑�p�m���}�͐���̈��ɐs����B�n���ȊO�̐l�ɂ͂قƂ�ǒm���Ă��Ȃ����A���E�߂̖k�A���v�X�r���[�|�C���g�B�剪���͎�����D���ȎR���̈�ŁA���t���珉�Ăɂ����Ă̎��R�̌i�ς͔��Q�B�܂������̉Ԃ����J�������B����ɖk�A���v�X�A���]�݂Ȃ���A�剪���̂Ȃ��قǂ����邩�����ŐM�B�V���ւƉ���B
�@�Ґ��n��A�M�B�V�����珬�쑺���ʂւ̎R�H�ɓ���B���̂�������T�^�I�ȎR���ŁA�G�ɕ`�����悤�Ȑ̂Ȃ���̎R�����i�������B��������̖k�A���v�X�̒��]�͂�͂�f���炵���B���̃h���C�u�R�[�X�ɂ������芴���������s�̓�l����́A�����ɁA�悭���܂��A����ȃ��[�g��m���Ă�����̂��ƕ������B��ނ�̂��ƂȂǁA���̐̂ɖY��Ă��܂����悤�ȗl�q�B�ɗnjΖ����ł͍��₪�P���P�����Ă��邱�Ƃ��낤�B
�@���쑺����S�������ɔ�����R�H�̗����ɍL���镗�i�͂���Ɋ����I�B�u���������{�̎R���v�̂���{�Ƃ��āANHK�e���r�̒��̔ԑg���ȂŏЉ��Ă����������Ȃ��B���{�̘b�̐��E�Ƀ^�C���X���b�v�����݂������ȂǂƘb���Ȃ���ǂ�ǂ�o���Ă����ƁA���쑺�̔��蕨�ł���k�A���v�X�W�]��ɏo���B���A�䍂���ʂ����O�A�������A�ܗ��A�����A����ɂ͔��n���A���n�ɂ�����k�A���v�X��Aῂ�����̔����P���������ĉ�X�̎��E�����ς��ɔ����Ă����B
�@�ό��K�C�h�u�b�N�Ȃǂɂ͂قƂ�ǏЉ��Ă��Ȃ����A�����͖k�A���v�X�̎B�e�X�|�b�g�Ƃ��Ďʐ^�Ƃ̊Ԃł͐̂���m���Ă����ꏊ���B�h���C�u�̍D���Ȑl�͂��Ј�x�K�˂Ă݂�Ƃ悢�B�������߂ĖK�ꂽ���͈�т͂܂����R�̂܂܂ɂȂ��Ă��āA���܂̂悤�ɗ��h�ȓW�]���݂͐����Ă��Ȃ������B���H���ׂ��_�[�g�������B
�@���Ȃ�̕W���̂��鏬�쑺�̖k�A���v�X�W�]������S�������ɉ���B��O���ނ���₾�炯�̌������R�͌ˉB�R�A���̉E����Ɍ�����͍̂��P�R�B�S��������͍��Ƀ��[�g���Ƃ蔒�n���ւƌ������B���m�ԂŗL���ȉ����ԋ���������߂��A���̃g���l������ƁA�܂���ʐ�ɕ���ꂽ�ܗ��A�����A���n���A���n�x�������ڂ̑O�ɑ傫�������яオ�����B�@�@�@�͉̂��x���o�����R�X�����A�c��̑������̎����ɂ�����x�o��Ƃ���ꂽ�炿����ƍl���Ă��܂��B
�@���n����،ΔȁA�咬�A���쑺�Ƒ���A�䍂���̎�O������ܖ�̐��[��D���R�[���ɓ���B���̓������ɂ͗l�X�Ȕ��p�ق�H�|�قȂǂ�����A�i�ς���������Q�B��R���p�قŒm����䍂���ɂ́A���̒m�l�ŕ��i�J�����}���̏㞊�������o�c���鋼�����Ȃǂ�����B���̂��X�̋����͐�i���̐�i�����A�x�߂̒��H�����܂������肾�����̂ō���͒ʉ߁B
�@���ݎ������̈��L�����M���̐Γc�B�v�Ƃ������\�]�̉��V�l��̋߂��ɍ�����������A������炸����}���B�ȑO�A�����j�m�L���X�^�[�����̓�̉��l���Ɉ������킹�����Ƃ�����B�g�����䂩��z�V�O�Ȃ��̐l���͗l�ɂ��ẮA�����҂Ƃł��������Ƃ���B�E�e�O�ɂ�����������V���ցc�c�Ȃ�Čy����@���Ă��A�\�O���̋��j��������Ȃ������邱�̃h���L�����V�l�͕��R�Ƃ������̂ł���B
�@������ō��̋�����H�ׂ����Ă�����~�����̑O��ʉ߁B���̓X�͌ߑO�\�ꎞ�ɊJ�X���ߌ�O���ɂ͕X�Ƃ����a�l���@���т��Ă���B�u��~�v�Ƃ����X���́u�����A�E���[�v�������������̂Ƃ��c�c�m���ɋ����̖��́u�E���[�v�Ǝv�킸�ꂫ�����Ȃ邭�炢�ɔ��������̂��B���̋������̒�����͑����傫���Ƃ��Ă��茩���炵�������̂����A���Α��̋q���̂ق��͂܂������O�̌i�F�������Ȃ��B���̓X�̎�l���킭�A�u���q�͈ꎞ�Ԃ�����A���Ă��܂����A�X�œ�����X�̂ق��́A�����Ԃ������������ĉ��N�������ꏊ�Ŏd�������Ȃ�����Ȃ�Ȃ��B������̂ق��̌����炵���悭����̂͂�����܂��� �v�Ƃ̂��ƁB�ǂ��܂Ŗ{�����͂킩��Ȃ����A�Ȃ��Ȃ��̋����N�w�Ȃ̂��B
�@�@�@�@�@�M�Z�����˂�
�@���炩�ȗɕ�܂�͂��߂��R�[���`���ɖx�����A���쑺�A���ܑ��Ƒ��蔲���A�ސ�n�_���A��n�A�㍂�n�����A�����āA��N�J�ʂ������[�g���l�����������Ċ����̏�����ɏo��B�}�s�ŃJ�[�u�̑������[�����z���Ă������́A�������G���Ă��Ȃ��Ă��㍂�n�������畽���܂ňꎞ�Ԃقǂ͂����������A�V�g���l���o�R���Ƃ������ܕ��B�J����ϐ���ɒʍs�~�߂ɂȂ邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ������A���i�̂ق��͓��z���̓��Ɋr�ׂĂȂ�Ƃ����C�Ȃ��B
�@�V�����A�Ȕ�������o�Ċ��c�쉈���̓���V�䍂����Ɍ������đ���B�E��ɏĊx�A����Ɋ}�P�x�A�����đO���ɕ䍂�A��ƁA������̎R�X���S�g�ɔ���̈߂��܂Ƃ��č����s���ނ����B���P�x�����͂��傤�lj_�ɉB��Ă��Č����Ȃ����A�����Ă���������̒��߂͐�i�Ƃ����ق��Ȃ��B�Y��Ȍi�ς��y���݂Ȃ��璆������o�R�̃��[�g�ŐV�䍂���[�v�[�E�G�C�̉w�̂Ƃ���܂ōs�������ƁA�������t�߂܂ň����Ԃ��A�߂��̒��ԏ�ɎԂ�u���ċ��̉��̘I�V���C�ɔ�э��ށB��˒n���ɂ���Ă��邽�тɁA���͂��̘I�V���C�̂����b�ɂȂ��Ă���B
�@���ꂢ�ȒP�����œ������������ɂ҂�����A�������A���R�̑��Ɉ͂܂ꂽ�L�����M�̒�͏����ȋʍ����ŏo���Ă��邩��C�����̂悢���Ƃ��̏�Ȃ��B�����͗L��]��قǗN���o�Ă��āA��ꂽ���͂����e�̊��c��̐����ɏ�����Ȃ��Ăǂ�ǂꗎ���Ă���B���ӂ̒��߂��������ƂȂ��B����h�ɕt�������G�Z�I�V���C�Ȃ��Ƃ��邪�A���R���Ɍb�܂�A���ʂ��L�x�ŁA�������N�ł������ł͂����{���̘I�V���C�́A�����߂����菭�Ȃ��Ȃ����B
�@����ɑf���炵�����ƂɁA���̘I�V���C�͍������B���̎��́A��X�O�l�̂ق��ɂ͑����N��̗��ꂽ��g�̒j�������B���̃J�b�v���͂Ȃ�Ƃ������悭�A��X�̓A�e�����ςȂ��B�u�ǂ����A�I���[��A�܂������낤���v�Ƃ������N�j�̓��ӂ��ȐS�̙ꂫ���������Ă������B�u��[������A����A���������撣�邩�c�c�v�Ɠ��u�����͗N���Ă��Ă��A���̏�ł��܂����ɑR�ł�����̂ł��Ȃ��B
�@ᛁi���Ⴍ�j�����炢����ł͂Ȃ�����ǁA���̃J�b�v���̏����̂ق����l�A�\��Œj���\�ォ��\��̎�҂�����������ƊG�ɂȂ����낤�B�t�̃P�[�X�͂��̎��゠��ӂ�Ă���B�����A�������j������������鎞�ゾ����A���������Ȃ������Ɏ��Ԃ͋t�]���邩������Ȃ��B���ŋ߁A���C�͎d���̊��͌����Ƃ̂����������@���̂��̂�����Ȃ�ǂ��A���܂ɂ͂��E�тł���ȂƂ���ɗ��Ă��̂��낤���ƁA�悯���Ȃ��Ƃ܂ōl�����B
�@�u�s�ρv�Ƃ������t�́u�l�̓��ɂ͂����v�Ƃ����Ӗ��炵�����A�V�����Ⴋ���A���̂��������ʏ������A�j����������i��ō��O���ۂ��y���ނ��Ƃ����ʂɂȂ������̎���A���̍s�ׂ�\���̂Ɂu�s�ρv�ȂǂƂ������ԑR�Ƃ����\����p���邱�Ǝ��̖��Ȃ̂�������Ȃ��B�U�߂�������t�����t�����ɂȂ������܁A���낻��u�s�ρv�Ƃ������t���u�]�ρv�A���Ȃ킿�A�u�l�̓��ɏ]���v�Ƃ��������悤�ȈӖ������̕\���ɉ��߂���ǂ����낤�B
�@�ނ��A���̏ꍇ�A�u�s�ρv�̓��́A����߂Č��i�ŕi�s�����Ȃ����ꕔ�̐l�X�݂̂Ɋ������邱�ƂɂȂ�B��������A�l�܂�ʑ����Ȃǂ������͂Ȃ��Ȃ�̂ł͂Ȃ����c�c����A����ς�Ȃ��Ȃ�Ȃ�����ȁA�����܂߂������Ȃ��̍��̖��O�̐��_���x���ł́c�c�B
�@����Ȏ�藯�߂��Ȃ����Ƃ��l���Ȃ���ꎞ�ԋ߂����I�V���C�ɂ����Ă���ƁA�������ɑS�g���������肵�Ă����B��������������Ă������Ƃ����A���낻��h�ɓ��邩�Ƃ������ƂɂȂ�B�̂�@���ĎԂɖ߂�����X�́A�I�V���C�̂���ꏊ���炻�������Ȃ��Ȕ����Ƃ������h�ɔ�э��B���N�j�ǂ��̈���̍s���Ƃ��ĂA���Q�Ƃ������\���ɋ߂��A����A�\�����̂��̂��B��㉻������铖���̂Ў�Ȏ�ҘA���ɂ́A����Ȑ^��������y�Ȃǂ��������͂��Ȃ����낤�B
�@�o���ꂽ�R�ؗ����炰�����ƁA���߂ďh�������̌������͂Ƃ�˂ƕn�R�l�������ۏo���ɂ�����X�́A�捏�̒����C�ł������肵���̂ɕڑł��āA�܂���������Ȃ��h�̘I�V���C�ɒ��X�ƐZ��A����������c�c��Ȃ��āA���𗭂ߍ��B
�@�������ɊF�Ƃ�[��Ƃ��Ă����̂ŁA�j���[�X�X�e�[�V������������ƌ��������ł����ɐQ���������A���܂ł������薰�������Ƃ����Ƃ����ł��Ȃ��B�����ƁA�[��O���ɂ͖ڂ��o�܂��A���{�̃A���_�[�E�c�D�G���e�B�E�T�b�J�[�`�[�����E���O�@�C���Έ�Ō��j����̂����͂����B�������I������̂��ߑO���߂��c�c�����͎����N���A�{�Ԃ̍���ނ�͂܂��܂����ꂩ��c�c�����������ꂩ��ǂ��Ȃ�낤�ƕ���ʂĂȂ���A���炽�߂Ė���ɏA���B
�@���m�̃L���}���W�����A�ؑ]�̌�ԎR
�@�����͎����ɋN���A�h�̘I�V���C�ɔ�э���Ŗ��C���o�܂��B����ɍL�������A���������V�B���H�����܂���ƒ����ɏo���B�����n���Ώc�f���邩�����œ쉺���A�[���܂łɂ͖L���s�̉����K����ɒ����˂Ȃ�Ȃ��B��������͕đ�̒��j�̂��ł���̕��N�ŁA��X�O�l������ނ�ɏ��҂��Ă����������䓖�l�B�Ȕ�����߂��̎����ŁA���h�̎�l�����̒n���u�_��v�����y�Y�ɍw���B
�@�Ȕ�����V���������������ɖ߂�A�O���쉈���ɍ��R���ʂ։���B�����Ղ��z���ɂ���߂���ƘA��̑傫�ȎR�e�͈����B���������ɍ炭�����R�u�V�̉Ԃ������B��ƃX�J�C���C���������߂����炭�s���ƁA�~�̎��߂�ꂽ�K�̂�����ʒn��ɂ���������B�����̖����Ƃ������������̋����͔����������Ȃ��Ǝv���Ȃ���ʉ߁B���w�k�c�̍D���Ȃ��̏����͌��݂��낤���B
�@�������炵�炭����ƁA���R���ʂɌ������ĉE��ɑ傫�Ȕ�˂̌Ö��Ƃ������������X�����ꂽ�B�����ꉀ�ł���B���̂��X�ɂ́A��N�H�A����G������˗����ꂽ��ˋI�s�̎�ނ̓r���łӂ���Ɨ�����������A�������������X�̕��͋C�A�o���ꂽ�Ă�����H�̔�ˋ��̂��܂��ƒʏ�̓�{�͂��邻�̗ʁA���̑��̐V�N�ȑf�ނ̑f���炵���Ƃ��܂₩�ȐS�s�����A�����ĉ��������̒l�i�̈����Ɋ��������B�X��̗э蓡���Y�����v�Ȃ��ƂĂ��f�G�ȕ��X�������B����͐���}���̂ł������ʉ߁B
�@���R�ɓ��鏭����O�ō��ɐ܂�Ďs�X���I��A�����l�����ɏo�����Ƌv�X�쒬�܂œ쉺�A���������ː쉈���ɒ��������ʂ������B���̏W�����߂��������肩��A�O���ɐእ��Ղ����X���ނ����x�R�̎p�������͂��߂�B�������A�������A�J�c����т��璭�߂��ԎR�͎��ɔ������A�u���m�̃L���}���W�����v�ƌĂԂɂӂ��킵���B
�@�����A�ꌾ�f���Ă����ƁA���̓L���}���W�����̗E�p���ʐ^��f��̉摜�ł����������Ƃ��Ȃ��̂ŁA�ق�Ƃ��ɂ��̖����ӂ��킵�����ǂ����ɂ͐ӔC�����ĂȂ��B�ǂȂ������Њm�F�̂قǂ��c�c�B���ʁA��ԎR�Ƃ����Ɩؑ]�H��A�z����̂����A�n�`�̊W�Ŗؑ]�H���ʂ���͌�ԎR�̑S�e�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B��ԎR�t�@���͂��В������A�������A�J�c���ցB
�@�H�_�_���A�����g���l�����č����_���A�����Ė씞���֑������Ƃ̕���_�ցB�씞���z���̓��͐ϐ�̂��߂܂������B���H���j�ɂ�����悤�ɁA���R���ʂ���z�K�A���J��т̖a�эH��������\��̎Ⴂ�������́A���Ă��̓������ǂ�A�W����Z���[�g���̖씞�����z���Ėؑ]�H���M����ޗLj�ɓ������B�����Ă������炳��ɁA��ܕS���[�g���̌����q�����z���ĈɓߒJ�ɓ���A�ɓ߂���J�`���ɉ��J���ʂւƌ��������Ɠ`�����Ă���B
�@���������z������������J�c���ցB�J�c����т́A�n���͒Ⴂ�����������n�̂̂������肵���ؑ]�n�̎Y�n�Ƃ��Ēm��ꂽ�Ƃ��낾���A���܂ł͏�����͂����قƂ�ǎc���Ă��Ȃ��Ƃ����B�����e���r�o�������Ƃ�����������̖ؑ]�n���\���N�O�ɂ��̋߂��Ō������Ƃ͂��邪�A���̌�̏�͂킩��Ȃ��B�����O�Z�ꍆ�̖ؑ]�X�����番����Č�x�R�[�̊J�c������D�������J�c�O�x�������ɓ���B�������̖������肩��͑O���ɑ傫���ނ������Č�������x�R���A�E��ԑ��̂������ɔ���B���x���オ���������������āA���ӂ̖ؗ��͂܂��~�̖���̒��B���̕��A���ʂ��͂����B�ԑ�����ɂ͖ؑ]��P�x�𒆐S�Ƃ��钆���A���v�X�̔�������X�������Ă���B�ނ��A���������͂܂���ɕ����Ă���B
�@�đ�ɉ^�]������Ă��炤���ߓ��H�e�ɎԂ��A���C�Ȃ����Ԃ����悤�Ƃ������ǂ��ɂ��r���v����������Ȃ��B�g�����N�̒��̃o�b�N��i�b�v�T�b�N�����X�܂ŒT���Ă݂�����͂茩����Ȃ��B�h���o��Ƃ��Y�ꕨ�͂Ȃ����Ƃ���قNJm�F�����̂ɁA�̐S�̎��v��Y��Ă���Ȃ�āA�ǂ����䂪�g�ɂ��{�P���܂���Ă����炵���B�m�l�̃V�`�Y�������Z�p������������v���[���g���ꂽ��������i�̃G�R�E�h���C�u�^�r���v�����A���܂���Ȕ�����܂ň����Ԃ��킯�ɂ������Ȃ��̂ŁA�ǂ����ŏh�ɓd�b���A���������玩��ɑ����Ă��炨���Ǝv���B
�@�Ƃ��낪���̎��A�����Ɏv�����������悤�Ȋ����̕đA�u���������������{�c����́c�c�H�v�ƌ����Ȃ���r���v���͂����č����o���ł͂Ȃ����B���������A�e�[�u���̏�ɂ������đ�̎��v�Ǝ��̎��v�Ƃ͌`��F�����Ȃ莗�Ă����Ȃ��Ǝv���Ȃ���A���̎��v�Ɍ�����Ɖ��ƂȂ������̕��ł���悤�ȁA�����łȂ��悤�ȁc�c�B���̎��̏u�ԁA���v�̗��W�������ƌ��߂��đA�u�����A����A�I���̂���Ȃ���I�v�ƃX�g���L���E�Ȑ����グ��B�đ����̍��r���m�F����ƁA�Ȃ�Ƃ����ɂ͂�����̘r���v���c�c�B�đ�͏h���o��O�ɂ������肵�ē�̘r���v������ɂ͂߂����̂炵���B�đ�̃X�[�p�[�{�P�Z�Ɋ��ӁA�����Ă܂����ӁI
�@�@�@�@�@��ؑ]����n�ďh��
�@�ؑ]�����Ə㏼�̒��Ԃɂ��錳���ō����\�㍆�ɍ�������������쉺�B���x���������������ōĂю�̋P�����������Ȃ�B�㏼���A��K�����o�ē�ؑ]���ɓ���A���ĕ��ʂɕ��č��ďh�e��ʉ߁A��ῂ��n�ē����z���ē��蓡���̐��a�n�n�ďh�Ɍ������B�t����n�Ă�����Ă܂ŕ������Ƃ��ɂ͋}�s��襘H�����Ȃ��������A���܂ł̓o�X���ʂꂻ���ȗ��h�Ȏԓ����ʂ��Ă���B���тꂽ�����̓��̒����O��ʉ߂��Ȃ���A�ԂŒʉ߂���l���قƂ�ǂ̂��܂͂��q�������������Ƃ��낤�Ƒz������B
�@�n�ďh���߂Â��ɂ�A�O���Ɍb�ߎR���傫�Ȏp���������B�n�ďh�͐Ώ�ƊK�i�̑����}��̌Ó��𗼑�����͂��ތ`�Ŕ��B�����W������Ȃ��Ă���B�đ���ʖ�����n�Ă͏��߂Ă��Ƃ����̂ŁA��㑤�̏W�������œ�l�����낵�A���������Ԃ��^�]���č≺���̒��ԏ�ɂ܂��B�����ɂ��̒n�����L�̑���̘V�܂̗������ԋ}�X�̘H���̂ڂ�A�W�������t�߂̓��蓡���L�O�ّO�ŕđ�A�ʖؗ����ƍ����B
�@�����L�O�ق́A���������܂������n�Ă̖{�w�ՂɌ��Ă��Ă���B�{�w�Ƃ͗��̓r���̑喼��M�l���������������h�꒬�̎�Ƃ̉��~�ŁA�e�핶�����╶���̏W�܂�ꏊ�ł��������B�����������Ƃ��đ听���Ă������w�i�ɂ́A�c�����ؑ]�̖L���Ȏ��R�̒��ň�����Ƃ������Ƃ̂ق��ɁA�����Ƃ��Ă͂���߂Čb�܂ꂽ�����I�o�ϓI��Ղ����������̂Ǝv����B�C�O���w���̎����⏔�X�̍�i�̌��e��e�ȂǁA���̓r�����Ȃ����Ղɂ͈��|��������B���≨�O�����������A�^�̃G���[�g�Ƃ��č���w�����A�����`����������Ȃ��牢�B�Ɋw�сA�A�����Č�y�̈琬�ƕ��w�E�̔��W�ɐS�g�̂��ׂĂ�����������̑啶���̋C���������ē`����Ă��銴���B
�@�������������Ƃ������k�w�@����̋����q������q�̎ʐ^�Ɠ��L���W������Ă������A���̒m�����A�B�M���̂����Ȃ��ѕM�����A�Ȍ��Ȃ�����I�m���ꖡ�s�����̂Ȃǂ́A�����������������߂��ˏ������̂��Ƃ͂���B�u�܂��������߂��O���́@�ь�̂��ƂɌ������Ƃ��@�O�ɂ�������ԋ��́@�Ԃ���N�Ǝv�Ђ���v�Ɖr����̂��䂤����́A���łɍ��Ă̘e�{�w�̑单���ɂ��łɉł��ł����͂��ŁA���̍��ɂ͂��������ɂƂ��ĉ������̐l�ƂȂ��Ă����̂��낤���c�c�܂��A����Ȃ��Ƃ́A�悯���Ȃ��Ƃ��B
�@�ʔ��������̂��A�����̕��A���萳�����Ⴂ���̑��q�t���A���Ȃ킿�����ɗ^�������߂̈ꕶ�B�S�̓I�ɂ́u������V���̒n�ւ̐���������A�R�t�⎅�t�A�q���t�Ƃ������A��l������鍼�\�t�܂����̘A���Ƃ̌��ۂ�T�ނ悤�Ɂv�Ƃ��������e�̕��������A���̒��ɁA�u���q�����܂�Ȃ��ꍇ���̂��������͎����Ȃ��悤�Ɂv�Ƃ̌P�����L����Ă���B�Ƃ��낪�A���̂������ƂɁA�u�������A���̂��Ƃ͂Ȃ��Ȃ�������Ȃ̂ŁA��̂̂Ƃ�����L���Ă������v�Ƃ�����|�̈Ӗ����肰�ȕ⑫�������Ă���̂��B���������ƂŌȂ̂��Ƃ�U��Ԃ�A�����t���������̂ł��낤���A�l�ԓ��萳���̐S�̓����Â�A�ɂ��Ƃ�������B
�@�W���ق̈�p�ɂ͓��������e���M�Ɏg����������z�c�A�Δ��Ȃǂ��͂��߂Ƃ��钲�x�ނ��̂܂܂ɔz�������������������A���Ɋȑf�Ȃ��̂������B�̕��̖؊��ɔw��L���Đ��������e�̕M���������A�݂肵���̓����̗l�q���Â��B�u��������Ȃ��[�A��������Ďp���𐳂��Đ^���ȋC�����ŕM�������łȂ���A�ǂ����̂Ȃ�ɏ����Ȃ���Ȃ��[�v�Ƃ����đ�̊��Q�Ƃ����ߑ��Ƃ����Ȃ����t����ۓI�B���Ȃ��Ƃ���X�O�l�͂��̎��_�ł��̏����Ƃ��Ċ��Ɏ��i�B
�@����ɂ��Ă��A���[�v����p�\�R���Ō��e�������̂����R�̂��ƂɂȂ��Ă��܂�������̍�Ƃ����́A��X�A���e�������̂Ɏg�������[�v����p�\�R���A�v�����^�[�A�t���b�s�[�Ȃǂ�����̕��w�����Ƃ��Ďc���̂ł��낤���B����͍�Ƃ̒N�X�搶�̂��g���ɂȂ����p�\�R���ƃv�����^�[�A����Ƀt���b�s�[�f�B�X�N�ł��c�c�Ȃ�Ă��ƂɂȂ�����A�N�����w�L�O�قȂǂɂ͍s���C�����Ȃ��Ȃ�ɈႢ�Ȃ��B�����Ƃ̕��w�L�O�ق̂悤�Ȃ��̂��㐢���藧���ǂ����͋^��ł���B���������̋L�O�ق����Ă��邱�Ƃ��肤����̑�搶���́A���[�v���Ȃǂɂ͗��炸�A���������菑���̌��e�ł��c���悤�ɐS�����Ă������悩�낤�B���g�͂����������ƂȂ��Ă��A��e���c���Ă���Ƃ��������ō����]������邱�Ƃ́c�c�܂��A���Ԃ�Ȃ����낤�ȁB
�@�@�@�@�@�ؑ]����O�͒n����
�@�����L�O�ق��o�����ƁA�߂��̋������Œ��H�B�Ȃ��Ȃ��������������������B�M�B�����̖��ؓ��肨�Ă���j����Ȃ����������Ē��ԏ�ցB�n�Ă��炢�����Ð�s�ɏo�����ƁA�⑺���ʂւƑ������ɓ���B���O�͂̎R����D���ĖL��A�L�����ʂւƓ쉺���悤�Ƃ������_�B�܂��܂��[���R�x�n�тɕ���������A���X�̗̋P���͈�i�Ɖ��₩�����܂��B��т͂��łɏ��Ă̋C�z�B�⑺�A����A��A�݊y�A�V��ƁA���ꂼ��Ɏ�̂��鑺�X�⒬�X���Ȃ��[���J�ؓ`���̓����Ђ������ցB�֓����ʂ���̗��l�ʼn��O�͂̎R����K�˂�l�͏��Ȃ����A�l�����{���牺�{�ɂ����Ă̂��̈�т̎��R�̔������͐����ɒl����B����͗������Ȃ��������A�����ɓ�A���v�X�A����A����ɓ�����琼���ɂ����ĉ��O�͂̎R���݂�]�ޒ��P�R���ӂ̌i�ς͂Ƃ��ɑf���炵���B
�@�V�邩��L����o�ĖL���s�̉����K����ߌ�Z���O�ɓ����B������v�Ȃɉ������}������B�����͎O���N���Ȃ̂ŁA������ɒ����Ă����ɒނ�ɏo�����鏀�������܂���B�S�z�Ȃ͓̂V��B��X�̔j�V�r�Ȏ��O�s���ɕ���ʂĂ����V���l���Ƃ��Ƃ��w�\���Ȃ����̂��A���グ���͂Ȃ�Ƃ��������_�s���ɁB�V�C�\��ł��A��C�����߂Â��Ă���A�����͊C�͍r��͗l�Ƃ̂��ƁB������������ō��̏����������̂ɂȂ��A�Ɖ�������B���̎����A��X�͊̎R���A�V�䍂���̖��h�̕z�c�̒��ō���̒ނ�閲�����Ă����̂�����d�����Ȃ��B
�@�ɗnjΉ��̊C���ɍ���̋F���҂����āA�O�͂ł��V���l�Ɗ|��������C�����Ăъ��̂��낤���B�ނ�Ƃ������́A���肪�ނ�Ă����̂�҂Ƃ��������x�̘r�O�̌��s�l�Ƃ������Ȃ����Ƃ͂Ȃ��̂ɁA�Ȃ�Ƃ����J�l�Ȃ��Ƃ��B
�@���C�ɂ���Ă��炢��i���������ƁA���l�̎�ɂȂ鍋�ȗ����ɐ�ۂ�łB�n���Ŋl�ꂽ�����̂悢���̎h���g�������������B�h���g�M�Ɏ��X�Ɣ���L���Ȃ���A�����ނ�O�ɂ���ł͏������t����Ȃ����Ƃ��v�������A�����������̗̂U�f�ɂ͏��Ă�킯���Ȃ��B�H��́A��������ƕđ�̏����A�H�i�������j�����̋ߋ��Ȃǂ��������b�ɉԂ��炭�B���r���O���[���̏���I�ɂ͓H����a�����ĂقǂȂ��A�������ނ�グ�A�������n�̕đ��ɂ��j���Ƃ��Ă��̂܂ܑ���ꂽ�Ƃ����ꃁ�[�g���ɋ߂��������^��̎ʐ^���������B
�@���}�n�ʼn��y�C���X�g���N�^�[������Ă�����������̏�̂��삳�đ�̒��j�̂��ł���B�������̎����A�����P�q�i���Ƃ����ɂ��j����́A�˕�����𑲋ƌ�A�p�[�J�b�V�����i�Ŋy��j�̗L���Ȏ�艉�t�҂Ƃ��Đ��E���҂ɂ����������B���݂̓����h���ɍݏZ�A���[���b�p�𒆐S�ɉ��y�����ƌ����Ƃɑ��Z�Ƃ̂��ƁB�ߓ��A���������̐��̃J�U���X�z�[���ł̃R���T�[�g��q���������A���̂ł���̂Ȃ牽�ł��A���Ƃ��Ύ���̐g�̂����������Ȋy��ɕς��Ă��܂����̔��͂ƓƑn���ɋ��Q�������Ƃ�����B
�@�V��͍r��͗l�ɂȂ�A�����͕S�p�[�Z���g�J�V�Ƃ̂��Ƃ����A�ē����Ă���鋙�t�͂Ƃ������o�D���Ă݂悤�����Ă���Ƃ̂��ƁB�ߑO�O���N���Ȃ̂ŁA�Ƃ������Q�悤�Ƃ������ƂɂȂ�A�ߌ�\���߂��ɏA�Q�B
�@�@�@����̓Z�C�S�ƃR�`�ɉ������I
�@�����͌ߑO�O���҂�����ɋN���B�����ɉ�������̎Ԃɏ�荞�݁A���J�̒����l�\�L���قǗ��ꂽ�ɗnjΖ��������ďo���B�ɗnjΖ��ɒ������ɂ͕������܂�B����ނ�̃|�C���g�͈ɗnjΖ����܂���ĊO�C�ɏo�����B��̉��B�H�ɂ͐^��̒ނ��ꏊ�����A���̋G�߂͂���������̒ނ��ɂȂ�B
�@�đ�Ǝ��Ƃ͉ߋ����x���ɗnjΉ��̐^��ނ�⍕��ނ�ɏ��҂��ꂽ���Ƃ�����B�ɗnj̑�ނ�͓Ɠ��ŁA�E�^�Z�G�r�A�A�J�Z�G�r�Ƃ������O�͘p�A�ɐ��p���ӂŊl��鐶�������C�V���a�ɂ���B�j��Ɋ|���ĊC���ɓ����Ă��C�V���������܂܂ł���悤�ɂ���̂��R�c�����A���ꂪ���\����B�ނ���͓��ނ�ŁA������������C��ɒ������������ƁA��`�O���[�g�������グ����Ԃœ������҂B�����ʂ�u�C�V�ő��ނ�v�킯���B�Ƃ��ɂ͑�̂����ɑ傫�ȃn�}�`���ނꂽ�������B�ȑO�̐^��ނ�̍ۂɂ́A���̊Ƃɂ��Z�\�Z���`�قǂ̃n�}�`���|�������B
�@�ɗnjΖ��ɒ����Ƃ������C���͂��J�b�p�𒅂Č}���̑D�̓�����҂B�����ڂ��̂���D������̑��鏬�^���D�����݂���ƒ����ɏ�D�B�����͊O�C�̉��B��͕��Q������������ނ�͖����Ƃ̑D���̌��t�ɏ]���A�}篒ނ��ƒނ�̑Ώۋ���ύX�B�O�͘p�ƈɐ��p���u�Ă�m�������˒[�̉����ɂ�����ԉ���ӂɌ������B�u�e���[�����̋C�Ȃ�N���ނ��Ă����v�ƍ���ɉ����܂���̎̂Ă���ӂ�f���āA�_�����o�����̃X�Y�L�̂��ǂ��Z�C�S�ɕύX�B�V�N�ȃZ�C�S�̎h���g�͔������A��������������I�c�c�Ǝ���Ɍ�����������B
�@��D���ĎO�\���قǂœ��ԉ���ɓ����B���C�̂��ߕ��Q�͂����������Ȃ����A����ł����\�D�͗h���B���炿�̎��͑D�����ɂ͖��������A�J���͂Ȃ��ق����悢�ɂ��܂��Ă���B�O���Ԃقǒނ葱�������މʂ͂܂�ł�������Ȃ��B�D�����X�ܐl������ŃZ�C�S�ƃR�`���킹�Ă킸���l�A�ܔ��B���ׂ̗Œނ��Ă���r�̂����D����������Ԃ�̃Z�C�S�����ނ��������B
�@���̓���Ԃ̑啨��ނ�グ���̂͏��߂ĎQ���̋ʖؖ�����B�\�Z���`�قǂ͂����^�̃Z�C�S������ނ�グ���B�u�悩�����ˁI�v�Ɛ����|����ƁA�����l�́A�ނ����Ƃ�����葊�肪����Ɋ|�����Ă��ꂽ�������ƁA�Ȃ�Ƃ���R�Ƃ����\��B
�@�������A�ʖ���ȏ�ɓr�����Ȃ��啨�������|��������Ă��܂����̂͂��̎��B�Ȃɂ���n���������ނ肻���˂��̂������ςȂ��̂ł���B�����������ʒu�̊C��͂��܂��܍��|���肵�₷���Ƃ��낾�����炵���A���x�����Ɉ����|����A��x�����悪��Ă��܂����B
�@�����������邤���ɕ��J����������ƌ������𑝂��A�C�ʂ��傫���g�����͂��߂��B��������ȏ�͖������Ƃ������ƂɂȂ�A�ɗnjΖ��ւƈ����Ԃ����ƂɂȂ�B�V�����[�̂悤�ȉJ�ɉ����āA���x���������炩�Ԃ�Ȃ���ɗnjΖ����B����ނ葛���́u�R�����đl��C�v�̌����̂܂܂̌��ʂɏI���B�C�̓ł������D������́A�������O���ނ��đD�q�ɐ������Ă������Z�C�S��R�`����X���ނ������̂ɍ��킹�ăv���[���g���Ă��ꂽ�B�����ŏ\�ܔ��قǁB
�@������ɖ߂������Ƃ́A�����s����₤�ׂ������ς璋�Q�B����ɂ��Ă��L���܂Œ��Q�ɗ���Ȃ�čl���Ă��݂Ȃ������B���ǂ��̓��͉�����ɂ����ꔑ�B�����ߑO���ɖL�����ē����������o�R�œ����ɖ߂�B�L�����瓌���܂ő�J�ɍ~�����ςȂ��B�Ƃɖ߂������ƁA���y�Y�ɂƂ�����Ď����A�����Z�C�S�ƃR�`�������A�h���g�ɂ��ĐH���B�����������c�c����̉��{�����\�{���I�c�c�����ǁA�A���̂ǂ����ɒނ�j�̌`�Ɏ����u�H�v�}�[�N�������|�������悤�Ȋ��������ĂȂ�Ȃ������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
1999�N5��12��
���鉫��̑z���o�i�P�j
�ߔe��������̒֎�
�@����ŃT�~�b�g��c���J�Â���邱�ƂɂȂ����B�v���X�v���ƃ}�C�i�X�v���̕��G�Ɍ��������肾����A����������������Ƃ͂����Ȃ���������Ȃ����A��ǓI�ɂ݂�Ή���ɂƂ��ėL�Ӌ`�Ȃ��Ƃɂ͈Ⴂ�Ȃ��B�u���v�Ƃ������t�̗��ɔ�߂�ꂽ���j�I�Ȕw�i�������ߋ��̂��̂Ƃ��ď������邪���Ƃ��A�T�~�b�g�J�Ì���̒m�点�Ɂu�o���U�C�v���O������n���U�v�W�҂̎p���A���ɂ͂ƂĂ���ۓI�������B
�@���łɃ}�X�R�~�Ȃǂł��w�E����Ă��邱�Ƃ����A�x���͑�ςȂ��Ƃ��낤�B�{�y���瑽���̌x�@���������̂��߂ɔh������邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B���ꂪ�J�Òn�ɑI�ꂽ�Ƃ����j���[�X���Ď����^����Ɍx���̂��Ƃ��v�������ׂ��̂́A����ɂ܂��x������݂̑z���o�����邩�炾�B
�@��㔪���N�̋㌎��\�O���A����ŋ��H������ꂽ���Ƃ��������B���̋��H����ނ��邽�߁A���͂��̑O���ɓ��q�@�ʼn���ɔ�̂����A�H�c�œ���葱��������Ƃ�����`�F�b�N�͌������A��ו��̒��g�܂ōׂ������ׂ�ꂽ�B����قǂɌx�������d���������R�́A���H�ϑ��ɑ����̐l�X���E����������ł͂Ȃ��A���܂��܂��̎��ɊJ����Ă������ꍑ�̂ɏ��a�V�c�̖���Ƃ��Č��c���q�̍_�{���o�Ȃ��Ă�������ł���B��������ɓn�낤�Ƃ��������A�_�{�͉��ꂩ�瓌���ɖ߂�\��ɂȂ��Ă����̂��B
�@�ቺ�ɐ��h��P���X��̊C�ɋz������悤�ɃW�F�b�g�@�͋@��������A�ߌ�߂��A�ߔe��`�ւƊ��荞�B�����ɂ������H�̃h���}�𖾓��ɂЂ����A���̋��͒e��ł����B�\�Ă��郌���^�J�[����悤�ƁA���̉�Ђ̋�`���������ɑ����^�ԂƁA���l�̐�q���A���f�C���̕\��ŌW���̐����ɒ��������Ă���Ƃ��낾�����B
�@�u��ϐ\����Ȃ��̂ł����A���̂ɂ��o�Ȃ̍_�{�l�����A��Ȃ邽�߂Ɍ�ʋK�����~����A�Ԃ���`�Ɏ������ނ��Ƃ��ł��܂���B�����A��������\�ܕ��قǕ������n�_�܂ł͎Ԃ�����܂��̂ŁA�����܂ł��ē��v���܂��B�����f�����������܂����A��낵�����肢�v���܂��v
�@�H�Ƃ͂����Ă��㌎�̌ߌ�̉���̓������͖{�y�̐^�ĂȂ݂ɋ���ł���B��X�͎�ו��������������ɂȂ�Ȃ���A�g�����V�[�o�[�Ў�̏����W���̗U���ɂ����������B�Ƃ��낪�A�قǂȂ��w��̒n�_�ɒ����Ƃ������ɂȂ��āA�W���̃g�����V�[�o�[���}�ɖ肾�����B�����āA�݂�݂�ޏ��̊炪�������������ȕ\��ɕς���Ă������B
�@�u�Ȃ�Ƃ��\����܂���B������̂ق������������܌�ʋK�����~���ꂽ�Ƃ̂��Ƃł��B�����������l�т��邵���������܂��A������x��`�������܂ł��߂肢�������܂���ł��傤���B�K���\���ɓ��Ђ̃��S������䂨��܂��̂ŁA���̎ԂŊF�l���s���̎��ǂ��̉c�Ə��܂ł��ē����悤�Ƒ����܂��B��`���o��ق��̓��H�͖��K���ł��̂Łc�c�v
�@�����̐ӔC�ł͂Ȃ��ɂ�������炸�A�K���ɂȂ��Ă����l�т�ޏ��̎p�́A���Ă��ĉ����Ȃقǂ������B
�@��X�͍Ăы�`�̌����ڎw���Ă��낼��ƈ����Ԃ��͂��߂��B���V���A����ɏd���ו��������Ȃ��牝���O�\���߂��������̂́A�������ɔ��邱�Ƃł͂������B����ȂƂ��͂��݂��l������A���͘V�w�l����ו����^�Ԃ̂���`���Ă������B
�@��X����Ԃ��I����ƃ��S���Ԃ͂����ɑ��肾�����B�ߔe��`�Ɠߔe�s�X�̊Ԃɂ͗��h�Ȏԓ����ʂ��Ă���B�S���ɂ킽���ĂƂ����킯�ł͂Ȃ����A�{�i�I�Ȏ����ԓ����ł����͖̂{�y��������̂ق����悾��������ɂ͂�����Ȃ��B�ނ��A��シ���ɉ��ꂪ�A�����J�R�̓������ɓ����������������B
�@�ԑ����甽�Α��Ԑ��������ƁA�Ȃ�قǁA�����ɂ͏\���[�g���قǂ̊Ԋu�Ōx�@�����x���ɗ����A���̌������ɓ��̊ۂ̏�������ɂ���������̐l�X�������ƕ���ł���B��풆�̔ߎS�ȗ��j�̂䂦�ɓ��̊ۂɑ��ĕ��G�Ȋ��������l�X�����Ȃ��Ȃ��ƕ����Ă�������ɂ��ẮA���̊ۂ̏��������l�̐����z���ȏ�ɑ��������B������������A����Ȃ�̔w�i�⑽���̉��o�Ȃǂ��������̂�������Ȃ����c�c�B
�@�Ԃ��^�]���Ă����̂́A�O�\�ΑO��̂ǂ��ɂł��������Ȋ����̒j���������B�����ɋ�`���o���Ԃ͎s�X�Ɍ������ĉ����ɑ��葱���Ă������A��{�̓����E��ߑO�����獇������ϑ�T���H�̂Ƃ���܂ł���ƁA���x�𗎂Ƃ��Ē��������т̂ق��Ɋ��A�������Ɣ��ΎԐ������։�]���͂��߂��B
�@�i�s�����ɑ��ĎԂ��l�\�ܓx�قNjȂ������Ƃ��������B�����ɕ��Ԍx���̐��l���Ƃ�ł��Ȃ��Ƃ����`���ʼn�X�̎Ԃɋ삯����Ă����B�����āA���̂����̈�l���傫�Ȑg�Ԃ�ł������ɒ��i����悤�ɉ^�]��Ɍ������Ďw�����������B
�@�����A���̏u�ԁA�^�]��͌x�@���̂ق����ɂނƁA�B�R�Ƃ��Ă��������������̂������B
�@�u���̎��Ə��͂����Ȃ�ł���B�����������Ȃ������͒��i���Ăǂ��֍s�����Ă�����ł����H�v
�@�^�]�肪�w��������������ƁA�Ȃ�قǁA���ΎԐ����̎O�\���[�g���قnj���Ƀg���^�����^�J�[�̉c�Ə��̊Ŕ������Ă���B�ނ�U�^�[�����Ă��̉c�Ə��ɖ߂낤�Ƃ����̂������B
�@�u�_�{�̈�s���قǂȂ�������ʉ߂���̂ŁA�����炪��̎Ԑ��͌�ʋK�����~����Ă��܂��B���i���Ă��������v
�@��l�قǂ̌x�����Ԃ̉�]��W����悤�ɂ��ĉE��O���ɗ����͂��������B�������^�]��͈���������Ȃ��B
�@�u���Ȃ��������d���Ȃ̂�������Ȃ����A�������Ďd���Ȃ�ł���B��ʋK������Ȃ炷��ŁA �͂��߂��玞�ԂƏꏊ���������茈�߂Ă���Ă���Ȃ�܂������B���Ȃ������̂����͍s������������肶��Ȃ��ł����B�ߏ�x���������Ƃ������c�c�v
�@�u�C�����͂悭�킩��܂����A����ɔ����{�����狭���K�����߂��o�Ă��ł��B�ꎞ���i���đҋ@���Ă��������v
�@���Ƃł킩�����̂����A���̂Ƃ��������̌x�@�����{�y����x���̉����ɔh������Ă����B�����A�����������Ƃ��\�ɗ����Ē��ڂɑΉ�����̂͒n���̌x�@���̔C���ɂȂ��Ă����悤�ł���B����������̌x�@���Ȃ�A���̎��_�Ō������s�W�Q�s�ׂƂ��ĎԂ������r�����A�^�]��̐g�����S�������˂Ȃ��Ƃ��낾�������A�����͉���̂��ƁA�x�@��������Ȃ�ɐT�d�ł������B
�@�ő����̂�Ŏ��Ԃ̐��ڂ�������Ă���ƁA�^�]��͈����ɗ͂����߂Ă���ɔ��_�����B
�@�u���̂��q���������āA�����ꎞ�Ԉȏ���\�肪�����Ă��܂��Ă��ł���B�������d���ו��������Ă��������U��܂킳��āc�c�B�{���Ȃ��`���烌���^�J�[�ɏ���Ă��炤�Ƃ�����A�������ĉ䖝���Ă�����Ă��ł���B������������ʂ̐l�X�̖��f�͂ǂ��Ȃ��ł����H�v
�@�����ׂ����i���W�J�����͎̂��̏u�Ԃ������B���͎v�킸�䂪�ڂ��^�����B�Ȃ�ƁA�w�l�x�����܂ޓ�l�̌x�@�����A����������g�������Ȃ�����A�Ԓ��̉�X��l�ЂƂ�Ɍ������ēA�d�ɓ��������͂��߂��̂ł���B�����Ȃǂł͐�ɍl�����Ȃ����Ƃ������B
�@���͋����Ռ����o���Ȃ���A�u�����͉���ȂI�c�c�l�X���فX�Ƃ��ďd�����j��w�����Ă����A���̍�����ȂI�v�ƐS�̒��ŋ���ł����B
�@���Ȃǂ́A���̍ے��i����ނȂ��̂���Ȃ����Ǝv�����������A����ł��^�]��͊�Ƃ��ĎԂ������Ƃ��Ȃ������B�ނɂ͔ނȂ�̓��Ȃ�v�����������̂�������Ȃ��B���̎��Ƃ��Ƃ��A�ߑO���̓��H�̂ق��ɍ_�{��s�̎Ԃ̗��ꂽ�B�x�@�������͍Q�Ăĕ������̎�����Ɉ���������A��X�̎Ԃ��������H�����Ɏ��c���ꂽ�B
�@�_�{��s�̎Ԃ̗�́A�������Ȃ��������̂悤�ɉ�X�̎Ԃ̘e��ʂ�߂��Ă������B�Ԓ��̍_�{�����ߋ��������X�̂ق��Ɍ������Čy�����U��Ȃ�����݂�����Ƃ������܂��܂ł��āc�c�B�����قǂ���̑�����G�ߒ��߂邩�̂悤�ɁA���̏Ί�͎��R�Őe���݂ɖ����Ă����B�㕔���Ȃ̘V�w�l�Ȃǂ́A�v��ʑ̌��ɂЂ����犴���̗l�q�������B
�@��s���ʉ߂���ʋK�����������ꂽ���Ƃ��A�ׂ����X�̎Ԃ̉^�]�肪�Njy���ꂽ��S�����ꂽ�肷��悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ������B�g���^�����^�J�[�̎��Ə��ɒ�������X�́A���ꂼ��ɎԂ���ĖړI�n�ւƌ������ĎU�����B�X�^�[���b�g���肽���́A�ߔe�s�������̂܂ܒʉ߂���ƁA���̔ӏh����\�肵�Ă������B���E�I�N�}�E���]�[�g�̂��鉫��k�����̉��ԃr�[�`�Ɍ������Đ��C�݉����̌ܔ�������k�サ�͂��߂��B���͗�������Ƃ��������]�[�g�z�e���ɔ��܂邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ����A���̂Ƃ���JAL�L����̈˗����e�̎�ނƂ������Ƃ��������̂ŁAJAL�P���̃��]�[�g�z�e����������������̎�ŗ\��Ă����B
�@�L���h���C�u�E�G�C�ɉ����ė������Ԃ��X�⌚���͂�������A�����J�i�C�Y�h����Ă��āA�܂�ŃJ���t�H���j�A������̊C�ݐ��𑖂��Ă��邩�̂悤�ł������B�Y�Y�A�X��p�A�k�J�i���Ⴝ��j���߂��Î�[�ɓ���ƁA�傫�ȉ~�H����l�A�ܖ{�̓��H���ʁX�̕����ɂ̂т�Î�[���[�^���[�����ꂽ�B���̎��ӂ͑傫�Ȍ������������Ԏs�X�n�ɂȂ��Ă���B�ǂ��ɂł�����w�O���[�^���[�Ȃǂ͈Ⴂ�A�@�\���̍�����K�̓��^�[���[�ŁA�A�����J�I�Ȕ��z�ő���ꂽ���Ƃ͈ꌩ���������Ŗ����������B
�@�[�����߂Â��Ă��Ă������A�Î�[��ʂ肩���������łɕČR��n����ڂł����߂Ă������Ǝv���A�܂��A��n�̖k���ɂ܂���Ă݂��B�Ȃ�قǁA�l�烁�[�g���͂���Ƃ����劊���H����{�A�܂����ɂ̂тĂ���B�����̂ق��ɂ͒��@�ꂪ�����Đ퓬�@��A���@�炵���@�e���U�����ꂽ�B
�@�ˑR�ɔw�ォ�獌���������Ă������Ǝv���ƁA���D�F�̃f���^�����������̂悤�ȃW�F�b�g�@�����z���Ɋ����H�ւƍ~��Ă������B���̈ٗl�ȋ@�e�͂������ɂȂ�Ƃ�������s�C�������߂Ă���B���炭����ƁA���x�͋���ȃA�z�E�h���ɂ������l���̑�^�@���k�������ւƔ�ї����Ă������B������n���ӂɂ����̂͂��������O�\�����炢���������A���̊Ԃɂ��l�X�ȌR�p�@���n�ʂ�h�邪���悤�ȋ��������Ăė��������J��Ԃ����B�ČR�̋ɓ��헪�ɂƂ��Ă��̊�n���ǂ�Ȃɏd�v�Ȉʒu���߂Ă��邩�́A�����̌R�p�@�̓��������邾���ł����炩�������B
�@�����������̊�n�̉��ł͂ǂ�Ȏw���n���̂��ƂɁA���X�ǂ̂悤�Ȑ헪�����āA���s����Ă����̂��낤�B�{�y�̉��c��n�Ȃǂ����������A�����炭�͒n���[���Ɋj�U���ɂ��ς������V�F���^�[�������āA���̒������̃I�y���[�V�����E�Z���^�[�ɂ��钴��^�X�N���[���ɂ́A�ɓ��S��̍q��@���v�͑D�̈ʒu�Ɠ��������A���^�C���ŕ\������Ă���ɈႢ�Ȃ��B
�@�Ăэ����ɖ߂������́A�����̂Ƃ��ɕČR���^����ɏ㗤�����Ƃ����ǒJ�����߂��A���[���ɂ������������B���[���r�[�`�A�����r�[�`�A���NJ_�r�[�`�A�C���u�r�[�`�Ɣ������C�݂̑������̈�т͉��ꐏ��̃��]�[�g�n�ŁA�����A�{�y�ł͂܂��������邱�Ƃ̂Ȃ������i��e���X�\���̍����z�e������������ł����B�J�Ƃ��ĊԂ��Ȃ����q�n�̍������]�[�g�z�e���A�T���}���[�i�����̈�p���߂Ă��āA�O�ӖڂɎ��͂����ɔ��܂邱�ƂɂȂ��Ă����B�܂����o�u���o�ς̐Ⓒ���Ƃ����āA����ɂ���ʂ̖{�y���{���������A�ό��J���Ɉ�i�Ɣ��Ԃ��������Ă����̂ł���B
�@�l�H�I�ł͂��邪�A�Ȃ�Ƃ����f�i���킭�j�ɖ��������i�̒���i��ł����Ɩ����r�[�`���߂Â��Ă����B����Ƀn���C���}�C�A�~�̍������]�[�g�z�e����f�i�Ƃ����鍋�ȑ���̖����r�[�`�z�e�����������B���͗����̋��H�����̂����߂��̖����тŊώ@�������ł����B
�@�T���Z�b�g�E���[�h�Ƃ����ď̂������Ă��������Ă��̖��ɒp���邱�Ƃ̂Ȃ����[�����C�݂̓����Ȃ�������Ȃ���A���͓�C�̔������ɂЂ����琌������Ă����B�����A����ɂ�������炸�A���̉^�]��̎p�Ƃ��̌��t�̗��ɔ�߂�ꂽ�v�����ǂ����Ă��C�ɂȂ��Ă��������Ȃ������B����̌��z�I�Ȍ��i�̔w��ɐ��ޗ��j�̉A�e���w���ɂ��̕����݂̂�^�����邱�ƂɁA���͖{�\�I�ȍ߈��������������Ă����B
�@���������̗�������f���Ɋy����ł��܂��悳�����Ȃ��̂��������A�ǂ����Ă����ꂪ�ł��Ȃ��Ȃ�͂��߂Ă����̂��B���̎������ň炿�Ȃ���A���͂��܂�ɂ�����̂��Ƃ�m��Ȃ��������B�u�Ђ߂��̓��v���͂��߂Ƃ��鉫��W�̉f���푈�ʐ^�͂���Ȃ�Ɍ������Ƃ�����������ǂ��A�����Ō������������̂��P�Ȃ�m���ȏ�̈Ӗ������悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ������B
�@���͂��܂����̎��̉^�]��Ɋ��ӂ��Ă���B���̏Ռ��I�Ȉꌏ���Ȃ���A�����̋��H���������Ȋw�̖ڂ݂̂Œǂ������A�{�y�̃o�u�����{�ɂ���ĉ��o���ꂽ����̕\�̔����������Ɍ�����A�암�̐�Ղ��j�����قȂǂ�ʂ̘f���̏o�����̂悤�ɒ��߂������Ŗ߂��Ă����ɈႢ�Ȃ����炾�B
�@���ԃr�[�`�Ɍ������r���A�y�H���Ƃ�ɗ�����������X�Ŏ��̎������̖{�ɓ������̂́A���̉^�]��̌����Ȃ��͂������ɈႢ�Ȃ��B�a�T�ŁA���悻��܁Z�y�[�W�̂��̃n�[�h�J�o�[�㐻�{�́A�X�̕Ћ��Ɏl�A�܍������Ɛς܂�Ă����B�u���ꂪ����킾�v�Ƃ����^�C�g���̖{�ŁA�ČR�T�C�h���B�e�������m�N���̐������푈�ʐ^�Ɖ����j�̋L�q�ƂX�ɐD��������\���ɂȂ��Ă����B�n���̗����V��Ђ����s���ߔe�o�ŎЂ��������Ă��邱�̖{�̔��^�̎ʐ^�ɖڂ��䂩��Ĕ����Ă݂͂����A���҂ɂ��Ă͂܂������m�����Ȃ��A�����ȂƂ��닽�y�j�Ƃ̈�l���炢�ɂ����v��Ȃ������B
�@���ہA���̖{�̒��҂́A�����A����ȊO�ł͂قƂ�ǒm���Ă��Ȃ��������A���̂ق����A�ʐ^�߂ĉ����ɂ��Ĉ�ʂ�̂��Ƃ��킩��Ώ\�����Ƃ������炢�̊��҂������Ă��Ȃ������B
�@����s���߂��{�������̍����������Ė{���k���̑�X�����ɓ���ƁA���������܂�A�C�ݐ��̌i�ς����R�̂܂܂̊����ɕς�����B������������A�܂��c�����������ޔ��b�����̋߂��ŗV��ł�����������Ȃ��B���ӂ̌i�F���ǂ�ǂ�l�H�I�ȑ�����E���̂ĂĂ����Ȃ��ŁA�������������ɖ��邭�₢�������̉��ԃr�[�`�ɓ��������̂́A���łɑ��z�����̊C�ɒ����Ƃ̂��Ƃ������B�����o���N�C�i�����݁A�ČR�̎��e���K�����ꕔ���P���������R�[���������ɂ����āA���ԃr�[�`��т����̓J���t�H���j�A�C�݂̔�ђn�̂悤�Ȋ�ȕ����X���Ă����B
�@�r�[�`����̑咓�ԏ�ɎԂ�u�������́A�Ƃ肠�����A���B���E�I�N�}�E���]�[�g�Ƀ`�F�b�N�C�������B�z�e�����ӂ͖{�y�������Ă����ႢOL�����ł��ӂ�Ă����B�Ⴂ�j������ɂ͂������A���|�I�ɏ����q�̂ق������������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
1999�N5��19��
���鉫��̑z���o�i�Q�j
���B���E�I�N�}�̖�
�@�����ʂ��ꂽ�̂̓c�C���d�l�̟������R�b�e�[�W�ŁA��l�Ŕ��܂�̂͂��������Ȃ����炢�������B�C���������Ă���ȃR�b�e�[�W��p�ӂ��Ă��ꂽ�̂��낤���A�����ɂ��A���̂Ƃ����͈�l���������B�N���ƈꏏ�ɗ���悩�������ȂƂ͎v���Ă݂����A���Ƃ̍Ղ�ł���B�����ɖ��@���g���Ĕ������o��������Ȃ�Č|�����ł����J�͂Ȃ����A�����������܂����Ƃ��^�Ԃ킯���Ȃ������B
�@���ԃr�[�`��т͂��Ƃ��ƕČR�ۗ̕{�{�݂������Ƃ��낾���ɁA�z�e���������̎��ӂ����S�ȃ��]�[�g�^�C�v�̑���ɂȂ��Ă���B���b�g�A�J���b�N�A�E�B���h�T�[�t�B���A����X�L�[�A�_�C�r���O�ȂǁA������}�����X�|�[�c���y���ނ��Ƃ��ł��邤���A��Ԃł��g�p�\�ȃg���[�j���O�W���A�v�[���A�e�틅�Z�{�݂Ȃǂ��������Ă����B�z�e���̏]�ƈ������˂��e�틣�Z��V�Z�̃C���X�g���N�^�[�Ȃǂ��������āA�؍q�̎w����Ή��ɂ������Ă������A�悭����Ɣނ�̑����͔��l�n�̍����炵���Ⴂ�j���ŁA�������Ȃ��Ȃ��̔��`�����������B
�@���͂Ƃ肠���������Ŋ��𗬂��A���X�g�����ŗ[�H�����܂����B�����āA�e��v���C���O�E���[����f�B�X�R�A�X�|�[�c�W���Ȃǂ��ЂƂ킽��̂����܂�������ƁA��̃r�[�`�ւƎU���ɂł��B�L���r�[�`�͔g�ł��ۂɂ�����܂Ŗ��邭�Ɩ����{����A�����ɂ������b�N�X���������̒j�����A�O�X�܁X�A�S�n�悢�C���ɑS�g���䂾�˂Ȃ���A�o���`���[�����y����ł����B�r�[�`�̂��������ɂ̓X�^���h�o�[��e�B�[�X�|�b�g�������āA�y�H�Ȃǂ��Ƃ��悤�ɂȂ��Ă���B���`���Ƀr�[�`�̒[�̂ق��܂ŕ����Ă����ƁA�傫�Ȏd��p�l�b�g������A���������ɂ͐i�߂Ȃ��悤�ɂȂ��Ă����B���̌������ɂ���͕̂ČR��p�̃��]�[�g�r�[�`�炵�������B
�@������т��U�Ȃ���썑�̖�̒����ɕ����قꂽ���ƁA�l�ӂ̈���ɂ���x���`�ɍ������낵���B�����ĉ���z���ł��Ȃ������̋��߂Ă��邤���ɁA���܂��ܗׂ荇�킹�ɂȂ����`���[�~���O�ȏ����ƁA�ǂ��炩��Ƃ��Ȃ��b�����ނ��ƂɂȂ����B�ޏ��͉�Ђ̃O���[�v���s�ł��̃z�e���ɔ��܂��Ă����̂����A���Ԃ��V�Z�ɋ����Ă���ԂɓƂ�Ńr�[�`�ɏo�Ă��Ă���Ƃ��낾�����B
�@�����̋��H�̘b��ɂ͂��܂�A����ɂ��Ă̂��݂��̑z���A����ɂ͗l�X�ȗ���d���̘b�Ȃǂ��A��X�͓ԋ߂��ɂ킽���Č�荇�����B����̗��̖镗���S�ْ̋��������ق����A����܂łɐ����Ă������ꂼ��̎���̊u�ǂ��������ɏ��������Ă��ꂽ���Ƃ������āA����߂Ď��R�̂̂܂܂ɁA�������͋��R�̏o�����̐��݂����炵�����L����������̊Ԋy���B
�@�����ɖ߂��ė����̋��H��ނ̏����𐮂������ƁA�x�b�h�ɉ��ɂȂ������́A���ԃr�[�`�ɗ���r���Ŕ������߂���j�L�^�A�u���ꂪ����킾�v�Ɍy���ڂ�ʂ��͂��߂��B�����ɂ͎�֒e�ɂ��W�c��������̐��S�Ȍ���ʐ^��A�B��Ă������̒����猻�ꂽ��l�̏������A���肠�킹�̖̎}�ɔ����O�p�������A���т��Ȃ���ČR�̂ق��ւƋ߂Â��Ă���ʐ^�Ȃǂ����߂��Ă����B��҂́u�������f���鏭���v�Ƃ��ĕČR�̉����L�^�t�B�����ɂ��o�ꂷ��L���ȃV�[���̎ʐ^�������B
�@���̖{�Ŏ������̎ʐ^��ڂɂ��Ă��牽�N���̂��A��Õx�q����Ƃ����ߔe�ݏZ�̎�w���u���̔����̏����͎��ł��v�Ɩ����o�āA�����V���Ȃǂł��傫�����ꂽ�B��Â���͓����Z�ŁA����Ɋ������܂ꂽ���߁A�Z�A�o�A��ƂƂ��ɓ�֓����邤���ɌZ�͏e�e�𗁂тĎ��S�A�o�A��Ƃ��͂���Ĉ�l�ɂȂ��Ă��܂����̂������B���傱���傱������邽�ߓ��{��������댯������A���O�������Ă���Ƃ����炪��Ȃ��ƁA���x���ޔ�������ǂ��o���ꂽ�Ƃ����B��������ē������r���ł��܂��ܔ�э����̒��ɁA���藼���̂Ȃ��V�l�Ɩڂ̕s���R�ȘV���̕v�w�������B
�@�u�����푈�͏I���������o�Ă��Ȃ����v�Ƃ����A���~����������ČR�̌Ăт�����������ˑR�������Ă����B����Ƃ��̘V�v�w�́A�ǂ����Ă��O�ɏo������Ȃ���Â�����Ȃ��߂������A�V�l�̉������č���������O�p�����������č����瑗��o�����̂��������B���̌�̘V�v�w�̏����͔�Â���ɂ��܂������킩��Ȃ��Ƃ������A���̉^���͑z���ɓ�Ȃ��B
�@���^�͂ƏՌ��͂Ƃɂ݂��������̊����ʐ^���������ƁA�u�ČR�A�c�NJԂ��U���v�Ƃ����^�C�g���̏��͂��y���C�����œǂ݂͂��߂����́A�����Ƃ����Ԃɂ��̕����Ɉ������܂ꂽ�B�����ėe�Ղɂ̓y�[�W����邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�����ɂ��Ă̐��m���ڍׂȋL�q�A���Ăǂ��瑤�ɂ������ȋq�ϓI���q�A�ɗ͊�������������W���[�i���Y���̎�{�̂悤�Ȗ����œI�m�ȕ��́A���ٓI�Ȃ܂ł̒����͂Ə����W�\�́A��Âȏ�͗́A�ǂގ҂̐S���Ђ����Ă�܂Ȃ������ȍ\���́A����ɂ͉���킪�Ȃ�ł���������@���ɕ����O�S���߂��푈�ʐ^�\�\���̂����Ȃ������ŔߎS�Ȑ�j��`���������{�ł���ɂ�������炸�A����͐�^�ɒl�������ł������B
�@���͖ڂ����J�������v���ł��̖{�̔����قǂ���C�ɓǂݒʂ����B���̂܂܍Ō�܂œǔj���Ă��悩�����̂����A���Ďc�蔼���𗂔ӂ܂œǂ܂��ɂƂ��Ă������Ƃɂ����B��ӂœǂݏI����̂͂��������Ȃ��悤�ȋC�����ĂȂ�Ȃ���������ł���B
�@��ÂȕM�v�ŏ����ꂽ���̐�j�̖{�����ɂ́A�ނ�҂̉e�炵�����̂͂܂������������Ȃ��������A���̐l���������҂ł͂Ȃ����Ƃ����͖��炩�������B����ׂ��M�͂Ɋ��Q�������́A���a�\��N�̏��Ŋ��s���ɗ�����w���_�������@�����P�����M���������������⒘�Ҏ��g�̑O�����A�����̒��җ����Ȃǂ����炽�߂čׂ����ǂݒ����A���̐l�ƂȂ�̂��悻�̗֊s���������Ɠw�߂Ă݂��B
�@�������R�i�ߊ��������������������a��\�N�Z����\�O���i����ɂ͎����͓�\����Ƃ������j�̑O���A���{�R�i�ߕ��̂����������m�̋u��тł͓��ė��R�̍Ō�̎������J��L�����Ă����B����t�͓S���c���ɏ��������\�ΑO�̈�l�̎�҂��A�₳�����R���ӂ��邻������ȖC����̒����Ő�����q���Đ퓬�𑱂��Ă����B�킢�ɗ��Ȃ��A�����̒��Ԃ��펀����Ȃ��A���낤���Đ��S�̒n��E�o�������̎�҂́A�O�J���ɂ��킽�鎀�̜f�r�𑱂��������Ɋ�ՓI�Ȑ��҂𐋂���B
�@�I���{�y�ɓn��A����c��w�Ɋw�ނ͈��l�N�ɓn�Ă��A�j���[���[�N�̃V���L���[�X��w��w�@�𑲋ƁA�A����͓���V���������Ō������Ƃ��Đ�匤���ɏ]������B���̌�A�ނ͂���Ƀn���C��w�C�[�X�g�E�E�G�X�g�E�Z���^�[�������o�āA������w�@���w���Љ�w�ȋ����ɏA�C���A���������K�˂��\��N�O�̎��_�ł͂܂�����w�ŋ��ڂ��Ƃ��Ă����B
�@����̐��͑����̐l�X�̌��ł����Ȃ�ꂽ���̂Ɛ[����������̐l���́A�č����w����A���������Ƃ������̎��������߂ċ@��邲�Ƃɓn�āA���V���g���̕č����h���ȂŖc��ȉ����W�̎ʐ^������T�������A���̒������琔�S�_�̎ʐ^��I�яo���ē��{�Ɏ����A�����B����ɁA�č����������فA�ė��C�R�A�ĊC�����Ȃǂ��ۊǂ��鉫��W������h�q����j���ۊǎ����A�e���L�ނȂǓ��O�̎������\�Ȃ���������W���āA�����̑S�e�𖾂炩�ɂ��悤�Ǝ��݂��B���̐S���ɔߑs�Ȃ܂ł̎g���������������낤���Ƃ͐����ɓ�Ȃ��B
�@���肵��������̌n�I�ɐ��������ނ́A�n�����̗����V��Ɂu���ꂪ����킾�v�Ƃ����^�C�g���̘A�ڋL���������n�߂�B�����āA���̋L���ɂ���ɉ��M���A�O�S�_�߂������J�̎ʐ^�Ƒg�ݍ��킹�ĕҏW�o�ł��ꂽ�̂��A���܂�������ɂ��邱�ƂɂȂ�������̖{�Ƃ����킯�������B���̖{�̓����̈�́A���^����Ă���ʐ^�̂��ׂĂ��ČR���ɂ���ĎB�e���ꂽ���̂ł���A�����������̓A�����J�Ɍ�������W�����ʐ^�̂����ꕔ�ɉ߂��Ȃ��Ƃ������Ƃ������B���{���̋L�^�ʐ^���قƂ�Ǒ��݂��Ȃ��̂́A�������R���قډ�ł������Ƃɂ���邪�A���傫�ȗ��R�́A����قǂ܂łɔމ�̊Ԃɕ��ʓI�ȗ͂̍����������Ƃ������Ƃł���B
�@�������o�ł������Ƃ��A���̒��҂͖��N�̂悤�ɃA�����J�Ɖ���Ƃ��������ĉ���W�̎ʐ^��@�����������W�A���q���e�̉�����i�߂Ă����B�ނ��A����́A�O�q�̌o��������킩��悤�ɁA�t���A�����̒����ɂ����Đ����n����̌����A���̗��w���o�ē��{�l�Ƃ��Ă͎w�܂�̃A�����J�ʂƂȂ�A��w���\�ŕč��l�̒m�Ȃ��������̒��҂ɂ��Ă͂��߂ĉ\�Ȃ��Ƃł������B
�@��c���G�\�\���̐l���������̖{�̎��M�҂ɂق��Ȃ�Ȃ��B���̐l�����̂��ɉ��ꌧ�m���ɂȂ낤�Ƃ́A���̎��̎��ɂ͑z�������Ȃ����Ƃł������B���݂̏o�ŏ�͂킩��Ȃ����A�����炭���܂�����łȂ炻�̒��������ł���̂ł͂Ȃ��낤���B�����K�˂�@��̂���l�≫���j�ɊS�̂���l�ɂ͂��Ј�ǂ������߂������B���݂̉���̕�������̍����́A�{��������ǂނ����Ŗ��炩�ɂȂ�ƌ����Ă��悢�B���܈�x���炽�߂ďЉ�Ă����ƁA�u���ꂪ����킾�v�i��c���G���A�����V��Њ��A�ߔe�o�ŎД����j�����̋M�d�Ȑ�j�L�^�̏����ł���B
�@���a��\�N�O����\�Z���A�������R�̗\�z�𗠐�c�NJԏ������U�����e�����ČR�́A���̊C�����_�ɂ��ĉ���{���㗤�������s�����B�c�NJԏ����ł͎��S�l�ȏ�̏Z�������̎��_�ł��łɏW�c�������Ă����̂��B�ČR�����͉��\�l������l�A�͑D����ܕS�]�ǁA���鉫�����R�͒n�����狭���������ꂽ�\�O����Z�\�܍܂ł̒j�q�Ə��q�w���Ō암�����܂ޏ\�ꖜ�l�ł������Ƃ����B
�@�����̃A�����J�̒����ȏ]�R�L�҂��A�u����͐푈�̏X���̋ɒv���B����ȊO�ɂ͂��̐킢�����܂��������悤���Ȃ��B���̋K�͂ɂ����āA���͈̔͂̍L���ɂ����āA���̌��ɂ����āc�c�v�ƕ�����̖��͏��a��\�N�l������Â��ɐ��ė��Ƃ��ꂽ�B
�@�u�C�O���A�D�����v�Ɠ��{���̊Ď������œd�����Ƃ����قǂɊC�ʂߐs�������ČR�c��͕����́A�ǒJ���̓n��m�C�݂ɑ��X�Ɩ����㗤���ʂ����B�̂��ɑ҂��鐦��Ȑ킢����͑z�������Ȃ����炢�ɁA���̏㗤���i�͕����Ȃ��̂ł������Ƃ����B�������R�����ی��������đS�R������암�ɔz���A���n��т̒n���Ƀg�[�`�J���\���ĕČR�̐i�U��҂�����������Ƃ������炾�����B
�@�������R�͓암�ɉ������Đw�n���\����ɐ旧���A�k�i�ǒJ�j��s��⒆�i�Î�[�j��s��j���g�p�s�\�ɂ���헪���Ƃ����B�w�k���ʂɓ������A�����N���������Ċ�����������̔�s��ł��������A�㗤�����ČR�ɕ⋋��U���̊�n�Ƃ��Ďg�p�����̂����ꂽ����ł���B
�@�������Ȃ���A���{���Q�d�{���̎v�f�͂������Ȃ�����ꂽ�B�D�G�ȃA�����J�H�����́A�����̃u���h�[�U�[�ƃg���b�N��g������ƁA�킸����A�O���ŗ���s����C���A�g���������Ďg�p�\�ɂ�������łȂ��A���ӈ�тɎԗ��p�̍L�����H�������Ƃ����܂Ɍ��݂����B
�@�O�q�̖{�Ɏ��߂��Ă���ꖇ�̎ʐ^��ڂɂ����Ƃ��A���͎v�킸�䂪�ڂ��^�����B�ČR���㗤���Đ����ƌo���Ȃ������ɑ���ꂽ�Î�[���[�^���[�ƁA���̉~�H�𑖂鑽���̕ČR�ԗ����B�e�����q��ʐ^������̂����A�Ȃ�Ƃ��̓��ʂ��Ă�������̉Î�[���[�^���[�̌`���̂܂܂���������ł���B�H�ʂ��ܑ�����A���H�����ɂ͌������т�����Ɨ�������ł��܂��Ă��邪�A���[�^���[�̌`�⓹���͌��������ƂقƂ�Ǖς�肪�Ȃ��B
�@�Î�[���[�^���[�𑖂�Ȃ���A���̃��[�^���[�̓A�����J�I�Ȕ��z�̂��Ƃő���ꂽ���̂��Ɗ����͂������A�܂����ČR�̉���㗤����Ɍ��݂��ꂽ���̂����̂܂c����Ă����ȂǂƂ͖��ɂ��z���Ă݂Ȃ������B�펞���̏ɂ����Ă����������z���ė��Ă�ꂽ�ČR�̐헪�\�z�Ɋr�ׂāA���{�R���̂���͂Ȃ�Ƌ����ŒZ���I���������Ƃ��낤�B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
1999�N5��26��
���鉫��̑z���o�i�R�j
���H�̂��Ƃ�
�@�����͐�D�̋��H���a�������B�z�e���Œ��H�����܂������́A�����ɁA���H�т̒��S���̒ʂ鉶�[�������іڎw���Čܔ�������쉺�����B�O���ߔe����ܔ������`���ɉ��Ԃɂ���Ă���r���ł��C�Â��Ă������A���H�����ɓ_�X�ƃA�C�X�N���[����X�^���h�������āA�N���̎Ⴂ���̎q�������������̂Ȃ��ł����Ƃ��q��҂��Ă���B��������ό��q�ɃA�C�X�N���[���������͓̂��R���Ǝv���āA�͂��߂̂����͂Ƃ��ɋC�ɂ��Ȃ�Ȃ��������A����Ȍ��i���J�Ԃ��������邤���ɁA������������ō̎Z�������̂��낤���Ƃ��������S�z�ɂȂ��Ă����B
�@������ė��邩�킩��Ȃ����q��҂��ė����Ă��鏗�̎q�����đ�ς��낤�Ǝv�������A���̕��G�Ȕw�i�����ɂ͂܂��悭�����Ă��Ȃ������B���ꍑ�̂Ƌ��H�Ƃ��d�Ȃ��Ė{�y����̋q�������������̓��̑O��͂Ƃ������Ƃ��Ă��A��������̎Ⴂ�������������������[�ŃA�C�X�N���[�����������Ă���̂́A�悭�悭�l���Ă݂�ƕs���R�Ȃ��Ƃł���B�ނ��A�u�����b���������{�y�̂��̂�������������̃A�C�X�N���[���͂悭����邩�炾�v�ȂǂƂ����\�ʓI�Ȑ����ŕЂÂ�����悤�Ȃ��Ƃł͂Ȃ������B
�@�Ԃ��Ɋώ@���Ă݂�ƁA�A�C���N���[���X�^���h�₨�y�Y�X�̔���q�ɂ͍����̒j���̎�҂����������B���łɉߋ��O�A�l�\�N�ɂ킽��R������Ƃ����č��n�̐l�X�ƒn���Z���Ƃ̊ԂŌ��̗Z�����N����A���݂����̏��i�s���ł��鉫��ɂ����āA���Ђ�l��̈قȂ镃������ނ炪�����������Ƃ͗e�ՂłȂ��B�ČR��n�W��Ƃ��̂����ƌo�ϊ�Ղ�����߂Ďキ�A�ٗp���s����Ȃ��̒n�ŁA����ɂ͉��̐ӔC���Ȃ��ɂ�������炸�A�Ƃ��ɂ͂���ʍ��ʂɂ������Đ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��l�X�̋�Y���A�{�y�̐l�Ԃ���������̂͂���߂ē���B�A�C�X�N���[���̃X�^���h��ɂ����̂悤�Ȗ�肪��߂��Ă����̂����A�����ȗ��l�̎������̂��ƂɋC�Â��ɂ͂��������Ԃ��K�v�������B
�@�����тƂ͊C�I�f�R��ɂ���V�R�̍L��̂��Ƃ��B�X�Ƃ����Ő��̍L���邱�̍L�ꂩ��́A�ቺ�ɍ��ɂ̖����̊C�������낹��B�����ȓ���]���͂���Ŗ����r�[�`�z�e���̟����������������Ă����B��܁Z�N�قǑO�A���̒n�����@�������h�����u���l�����点��ɑ���v�Ə̎^�����̂����̖��̗R���ł���Ƃ����B
�@�����ш�т͋��H�ϑ��ɂ���ė����W�҂��ʋq�ł����ς��������B�m�g�j�⒩���V���Ђ̘r�͂������w���Q����������ޏ��������邩�����ł́A�������̋Ǝ҂ɂ���ē��H���K�l�Ȃ���̂������Ă����B�����Ȓ����`�̔��������̒����ɉ~�`�̌��������A����ɍ����t�B�������͂����ȒP�ȓ���ŁA���������Ɉ�����Ă݂����A���\���ɗ��������������B
�@�����т̈�p�ł͉���×��̖����ߑ��ɐg���n���̐l�X���u���邤�Ձv�Ƃ������Ղ������Ă���A���H���n�܂�܂ł̂ЂƂƂ��A�ό��q�̖ڂ��y���܂��Ă���Ă����B���ϓI�ɂ��������������ł͂��邪�A����̓`���I�Ȗ����ߑ��p�̓A�C�k�̐l�X�̖����ߑ��p�Ƃ���߂Ď��ʂ����Ƃ��낪����悤�Ɏv��ꂽ�B�ŋ߂̂c�m�`�̌�����ʂ��āA�ꕶ����̉������B�̐�Z���Ɠ�����̓��k�A�k�C���̐�Z���Ƃ̊Ԃɂ͐[���Ȃ��肪���������Ƃ��킩���Ă��Ă��邪�A�������������Ƃ��Ȃɂ�����W���Ă���̂ł��낤���B
�@���H�͌ߑO�\��������n�܂�A����ɑ��z�������Ă����āA�\�ꎞ��\�O���ɋ��H�̏�ԂɂȂ����B�F�����H�Ƃ͈���đ��z�̎��[�̓����O��ɖ��邭�P���Č����邩��A�\�z���Ă����ȏ��ῂ����A����ł����Ɋώ@����͍̂�������B���ǁA���Q�̃t�B���^�[�⎎���ɋ��߂����H���K�l��ʂ��Ċϑ����邵���Ȃ��������A�\������Ă����ʂ�̌����ȋ��H���l���Ԃقǂɂ킽���Ċϑ����邱�Ƃ��ł����̂ŁA���̈Ӗ��ł͂��̎�ޗ��s�͑听���������B���H���N�����Ă���Œ��Ɏ��ӂ̗l�q�����������Ă݂����A�z���͑傫���Ȃ�͂��Ă�����̂̐��V���̗[�����͂����Ɩ��邢�����ŁA���̓_�͂��������ӊO�ȋC�������B
�@�l���Ă݂�A�F�����H�ƈقȂ�n��ɍ~�蒍�����z�������S�ɎՒf�����킯�ł͂Ȃ�����A�������R���i�����҂��邱�Ƃ��A�V�̊�˓`���ɂ���悤�ɐ��E���ꎞ�̈łɒ��ނ̂�ڂɂ���̂��A���Ƃ��Ɩ����Șb�ł͂������B���U�ɂ����Ĉ�x�o�������Ƃ��ł��邩�ǂ����Ƃ������R���ۂɁA����̖����тƂ����������ꏊ�ł߂��舧�������Ǝ��̂Ɋ��ӂ��ׂ��ł������̂������B
�@�����A�F���D�ȂǂŒn�����ӂ̋�Ԃ����R�ɓ������Ƃ��ł���悤�ɂȂ�A�F�����H����H�̋N����X�|�b�g�̒ǔ���I�����ӂ̂܂܂ɂȂ邩��A�ϑ��̐��ۂ��V��ɍ��E����邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ�ɈႢ�Ȃ��B�����A��ڈ���̋@��ɓq���邵���Ȃ����݂ɂ����ẮA���H�������̊�ł͂�����ƌ��邱�Ƃ��ł��������ł��b�܂�Ă����ƍl����ׂ����낤�B
�@���H�̊ϑ���ނ����I�������́A����s�܂Ŗk�サ�A�{�������̒��������Ė{�����n�v�n�`�ɏo�邱�Ƃɂ����B�n�}�Ō���ƁA�n�v�n����{�������˒[�ɂ��鉫��C�m���L�O�����܂ł͈ꑖ�肾�����B�{�����������̈ɓ�����т͉��ꐏ��̃p�C�i�b�v���̎Y�n�ł���B�Ԃ������������̍����n�тɓ���ƁA���̗������O�������n��������p�C�i�b�v�����ɂȂ��Ă����B���H�����̊ό��q�����̔��X�łƂ肽�Ẵp�C�i�b�v�������H���邱�Ƃ��ł������A���̊Î_���ς�����Ɩ��͂������ɖ{��Ȃ�ł͂̂��̂������B
�@�ɓ����n���ɂ͖����̍�����p�C�i�b�v���͂������炵�����A�����ς畧�O�̋����Ƃ���A����̐l�X�͂قƂ�ǐH�ׂĂ��Ȃ������Ƃ����B�Ƃ��낪�A���̕ČR�̉��꒓���ɂƂ��ȂĂ������Ɏ��v�����܂�A�ČR�p�ɑ�ʍ͔|�����悤�ɂȂ����B������_�@�Ƀp�C�i�b�v����肪����ɂȂ�A���܂ł͉���̊ό������̈�ƂȂ����̂������B
�@�p�C�i�b�v���n�т��߂������쉈���ɓn�v�n�̊X���݂ɏo�A�������炷�����k�シ��ƊC�m���L�O�����ɓ��������B������u�[���������Ă�����㎵�ܔN�ɁA���E���Ɩ��ł��ĊJ�Â��ꂽ�C�m���̐Ւn�����c�������������̂ŁA�����ł͍ő�K�͂̕~�n�ʐς�L���Ă���B�����ɔM�ѐA�����␅���فA����فA�C�m�����فA���ꋽ�y���A�A�N�A�|���X�A�G�������h�r�[�`�A�����Ă����܂�̑�V���n�G�L�X�|�����h�Ȃǂ��������B
�@�K�C�h�u�b�N�ɑS�{�݂����w����ɂ͍Œ�ł����Ԃ͕K�v�Ƃ�������Ă�����K�͂ȉ����{�݂��A������������ė����̂�����ƈ�ʂ�͌��Ă܂�����̂����A�e�{�ׂ݂̍��ȗl�q�Ȃǂ͂قƂ�NjL���Ɏc���Ă��Ȃ��B�\��N�قǑO�̂��ƂƂ͂����A���j������Ȋw�Z�p�A���A���̐��ԂȂǂɂ��Ă̓W���͂������Č����ł͂Ȃ����A���̉��������������ق��ł͂Ȃ�����Ȃ̂����A���������ǂ��������Ƃ��낤�B���̃t�B���^�[�ɑς�����悤�Ȕ����⊴�������܂�Ȃ������Ƃ������ƂȂ̂��낤���B
�@�킸���ɋL���ɂƂǂ܂��Ă���̂́A�\�����I����\�����I�ɂ����Ă̗��������̌Ö��ƏW�����Č��������ꋽ�y���ƁA�����̊C��s�s���f���A�A�N�A�|���X�̐����W�]�����璭�߂��������C���̌i�ρA�����āA�G�������h�O���[���̊C�̌������ɕ����Ԉɍ]���Ɛ���̓��e�������B����A����ɂ����ЂƂA����ł߂����ɂ��y�Y�����Ƃ̂Ȃ������A�����̌��c�X��H�X�ŐԎX��̃y���_���g���������߂��L��������B
�@���̂����̈�͉䂪�Ƃ̉����̒\�y�̒ꂠ����œ�x�Ɠ��̖ڂ����邱�Ƃ̂Ȃ��^�������ǂ��Ă���̂��낤�Ǝv�����A������̂ق���N�ɐi�悵�����̂������͂����良���Ă��Ȃ��B�Ȃ�ƂȂ��v��������ӂ����Ȃ��ł��Ȃ����A���܂���o�Ă����Ă����N�Ȃ��Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ�����A������̂ق��������Ă��Ă��炤�ɂ�����B
�@����C�m���L�O���������Ƃɂ������͖{�������̖k���ɂ܂��A�����ɕ����ԍ��A�m�i�Ȃ�����j�隬��K�˂Ă݂��B�����Βi���̂ڂ�A��̖{�ۂ̂������L�����ƌ×��̂܂܂̏�ǂ����n����W�]��ɂł��B���S�N�ȏ���O�ɒz���ꂽ�k�R�����̂��̏�́A��A���R��ƕ��Ԗ��邾�����Ƃ������A���݂͏�s�������c���Ă���B�k�R�����͏\�l���I�ɒ��R�̎R�ɂ���čU�ߖłڂ��ꂽ�B
�@�Ɠ��̍\���̏�ǂ̉��͒f�R�ɂȂ��Ă���A�k���C��͂邩�Ɉɉ������A�ɕ������Ƃ��ڂ������e���]�܂ꂽ�B���˂Ă���K�˂�l�͂قƂ�ǂȂ��炵���A��Ղɗ��͎̂���l�����������B��тɂ͗[���𗁂тĖ������̐�̐����߂����ɂ����܂��A���̕s�v�c�Ȑ䎞�J�i���݂�����j�́A�h�̉ʂĂɖłы��������ɂ����̖k�R�����ꑰ�̗���A����ɂ͂��̒n�ɂ��̊Ԃ̐������݁A�₪�ċ����Ă����������̉���тƂ̍������߂Ă��邩�̂悤�������B
�@���̐S�ɐ[�����݂��邻���̐�̐��͋�B�암�̃N�}���A�u����A�j�C�j�C��Ȃǂ̂��̂Ƃ͖��炩�Ɉ���Ă����B�����炭����n���ŗL�̐䂾�����̂��낤�B���������ƁA��̐�����łȂ��A�������悹�Đ��������鍡�A�m�̗[���̂��̂��̂Ɏ��̌܊��͖��m�̉�����m�o���͂��߂Ă����B�u�����̕��͈Ⴄ�B�����̒m���Ă��镗�Ƃ͈Ⴄ�v�c�c�ꌾ�ł�������Ȏv���ɏP��ꂽ�̂������B
�@�Ȃ��������䎞�J��w�ɁA�Â��ɍ��A�m�隬�����������́A�{�������k���̏W����D�����𑖂蔲���A�H�n���C�ƌĂ����������C�̂��ɏo��ƁA���̎��ӂ������낹�闒�R�W�]��ɂ̂ڂ��Ă݂��B�H�n���C�͖{�������̖k���t������тƂ��̏������ɂ��鉮��n���A�������ɂ���đ傫���͂����܂ꂽ�V�R�̓��C�ŁA���̒��ɂ͒n���̐l�X���������ƌĂԑ����̏������_�݂��Ă���B
�@�l���̂Ȃ����R�W�]��ɗ����Č����낷�H�n�̊C�Ƃ����ɕ����ԏ����̌Q�́A���藈��[�ł̂��ƂłЂ�����Â܂�Ԃ�A�C�܂���ȗ��l�̗��D�����₪�����ɂ��~�����Ă��B�_�X�Ɩ��Ƃ̖�����̓���͂��߂��Ί݂̉���n���̐����Ɩ{�������Ƃ̊Ԃɂ͍ג������R�̐��H���J���Ă���A���ڂɂ͌����Ȃ��������A���̐��H�̊O�m���̕������^�V�`�ƂȂ��Ă����B
�@�n���I�Ɍb�܂ꂽ�^�V�`�́A�×��A����ߊC���q�s����D���̊i�D�̔��`�ɂȂ��Ă����B�u�^�V�v�Ƃ������̊�Ȓn���̗R���͂Ȃ��Ȃ��ɖʔ����B�����܂ł��`���ɂ����Ȃ����A�ی��̗��ɔs�ꗬ�Y�̒n�ɓ��哇�ɂ��������ג��͖����ɑ哇��E�o�A�^��V�ɔC�����q�C�̖��ɂ��ǂ蒅�����̂����̍`�������̂��Ƃ����B���̌����̍q�C�ɂ��Ȃ�ʼn^�V�Ƃ����n��������ꂽ�̂��������B
�@���̂Ƃ����܂���ɂ��Ă����K�C�h�u�b�N���߂����ĉ^�V�`�̉�����E���ǂ݂��Ă������́A�c���\�l�N�i��Z�Z��N�j������N�������F���̌R�����ŏ��ɏ㗤�����̂����̍`�ł��邱�Ƃ�m�����B�����āA�����̈�����Ƃɂ��������ւ�鉓���̂̂���l���ɂ��Ă̋L�^��z���o�����̂͂��̂Ƃ��������B�w������Ɉ�x����炵���L�q�𑖂�ǂ݂������Ƃ͂��������A����ɐ����鎩���ɂ͒��ڊW�Ȃ��������Ƃ������āA���͂���ɂ����ċ������o���Ȃ������B������A����ȋL�^�Ȃǂ�������Y��Ă��܂��Ă����B
�@�^�V�`�ɂȂ���H�n���C��ʂ肩�������̂͋��R�ɂ����Ȃ������̂����A�䎞�J�̍��A�m�隬�ł��������̐g�ɓ����������h���̎��́A�ۉ��Ȃ��Ɏ��̍����l�S�N���O�̐��E�Ɉ����������Ƃ��Ă����B�h���_�Ƃ������̂����͐M���Ȃ��B���܂ł����ׂĂ͋��R�������ƍl���Ă���B�������A���̂Ƃ��̉���̗��ɂ����āA���R�Ƃ��ĕЕt����ɂ͂��܂�ɂ�����������R���d�Ȃ����͎̂����������B
�@�ˑR�̂悤�ɍ~���ėN�������G�ȑz������߂��˂āA�������͂��̏�ɗ����s�������B�����ɖ߂��ď��ւ̕Ћ��ɂ�����j�������ڂ����ǂ݂Ȃ����Ă݂Ȃ���A���܂ЂƂf��͂ł��Ȃ��Ƃ����z���͂��������A���������Ȃ̂��낤�Ƃ����\����ł��������Ƃ͂ł��Ȃ������B�����ȂƂ���A���ꂪ���̊��Ⴂ���L���Ⴂ�ł���悢�̂����Ƃ��l�����B
�@���̔ӍĂу��B���E�I�N�}�ɖ߂������́A�v��ʓW�J�̖��ɐ����������̍������m�[�g�Ƀ����������ƁA���ǂݎc������c���G�̒����u���ꂪ����킾�v�̌㔼����߂��ꂽ�悤�ɓǂݒ^�����B���̏����ɂ́A�M����قǂɎc�s�Ȑ��X�̏o�������A�ǂݎ�ɂ��̗��j�I�]�����ς˂邪���Ƃ��W�X�ƌ��Ԃ��Ă����B����̍��Ԃ���ɗ͗}���Ă���Ԃ�A�����Ɏ��߂�ꂽ�L�q�ɂ͂��������̐^�������������ĂȂ�Ȃ������B
�@���ԓI�ɂ͘b���O�シ�邪�A�A���������ƁA���͎F���˂Ɋւ�����j�����Ǝ��̈�����������������ɂ��Ă̗��j���������炽�߂Đ��ǂ��Ă݂��B���̌��ʁA��͂莄�̂������ȋL���͊ԈႢ�ł͂Ȃ��������Ƃ����������B���̎������ԈႢ�ł͂Ȃ��Ƃ킩�����ȏ�A���ɂ͉����̂̉���̏o�������ߋ��̘b�Ƃ��Ė��点�Ă����킯�ɂ͂����Ȃ��Ȃ����B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
1999�N6��2��
���鉫��̑z���o�i�S�j
�����N���Ə���ݔԕ�s
�@�����Ƃ̒n���I���j�I�W���[���A��C���Ղ̗v�����������������́A�o�ϓI�ɂ�����ȉ��l������A���O�A�L�b�G�g���������x�z���邱�Ƃ��Ă����Ƃ����B�փP���̐킢�ŖL�b����j��A�]�˖��{��������������ƍN�ɂƂ��Ă��A�������x�z���ɒu�����Ƃ͊���Ă��Ȃ����Ƃł������B
�@�����A�����A���������͒����i���j�Ƃ̌��т����������̔쉺�ɂ����������ɁA�]�˂̓��얋�{�����͂Œ��ڎx�z����ɂ͒n���I�ɂ��܂�ɂ����������B������������������̍]�˖��{�ɂ́A�����ւ̐N�U�͌o�ϓI�ɂ������I�ɂ���������̂ł���B�܂�����ɒ��ڂ̐N�����\���Ƃ��Ă��A���̍��Ƃ��Ēm���问���͂Ŏx�z����A�����̐l�X�������łȂ��A�����O��������Ȃ���ʔ��������낤���Ƃ͖ڂɌ����Ă����B
�@���̂��߁A���얋�{���I����͎���͘J���邱�ƂȂ��������Ԑڎx�z���邱�Ƃł��������B���Ȃ킿�A�F�����Ô˂ɗ�����N���x�z�����A�F���˂̎����A�����̐��ݏo���x�╶���̐����ԐړI�ɗ��悷�邱�Ƃ��l�����̂ł���B�c���\�l�N�i��Z�Z��N�j�̎F���˂ɂ�问���N���́A�\�ʓI�ɂ͎F���˂̒P�ƍs�ׂɌ���������ǂ��A�����͂ق��Ȃ�ʓ��얋�{�ŁA���̎x���Ə��F�������Ă͂��߂ĉ\�������̂��B�����x�z��A�F���˂��������������Β����ɉ��Ղ��A���{�����ɋ߂��喼�𑗂荞��ŁA�O�l�喼���Â̏]���̏��̂̂ق����������������킹�ē�������Ƃ���v�f���B����Ă����ɈႢ�Ȃ��B
�@�փP���̐킢�ɖL�b���Ƃ��ďo�w���Ȃ���A�Γc�O���Ɨp���헪���߂����đΗ������������A�킢�ɗ��Ȃ��Ɣ��f�������Ð��́A���Ɉ��������邱�Ƃ��Ȃ��������R�̐퓬���I���̂����͂���B������̓�����ւ̐Q�Ԃ�ƁA�E�҉ʊ��Œm��ꂽ���Ð��̕s�킪�L�b���s�k�̗v���Ƃ������邪�A������������A������ɂ���łȂ����Âɑ��Ă��A�V�ԂȉƍN����̔閧���̍H��Ȃǂ��������̂����m��Ȃ��B�����̂��Ȃ��������������ȂɎ�������Â̌R���́A���������߂�������̑����̌R���̐^���������l�R�Ƃ��čs�R���j���A�ŏ����̋]�����������Ŋ�ՓI�ɎF���ɋA�҂����B
�@���얋�{������A�O�l�喼�ɗ�ꂽ���Â̕\�����̘\���͉���O�c�˂ɂ����\�O���ł��������A�V���X�y�낪�����䕗�Ȃǂɂ���Q�̐₦�Ȃ��F���̕Ă̐��Y�͂͒Ⴍ�A�����I�ɂ͍��X�O�\�����ɉ߂��Ȃ��������A�Ď��������ǂ��͂Ȃ������悤�ł���B�y��I�Ɍb�܂�Ȃ��F���̖��l�̕�炵�͕n�����A�m���K���Ƃ����ǂ����̐����͋ꂵ�������B�̂��ɗ����o�R�Ŏ������܂ꂽ�Ï��i�T�c�}�C���j�͂��܂��܃V���X�y��ɂ������앨���������߁A�H�����R�̍ۂ̋~���ƂȂ������Ƃ͂悭�m���Ă���Ƃ���ł���B
�@�킸���Ȏ�������������A���{�ɑ���m�s�������̋V��╊�ہA�����Ȃǂɕs���s�����������肵������ՕK�肾�����O�l�̓��ẤA�˂̈ێ��h�q�ɕK���ł������B�O�l�喼�̎Q�Ό��̐��x�������ɒ�߂���̂͊փP���̐킢����O�\�ܔN�قǂ̂��̂��Ƃł��邪�A���얋�{������������A�]�ˏ�ւ̕\�h�Q����ˑ����̂��߂̖��{�L�͋ւ̍H��Ȃǂɂ͔���Ȕ�p���K�v�������B�܂��A�̂��̎F���˂ɂ��ؑ]�쎡���H���ɂ݂�悤�ȁA�˂̍�������������@�O�ȕ��ۂ╊���A���s�s�Ȋe����Ȃǂ���X�����������邾�낤���Ƃ͖ڂɌ����Ă����B
�@���ˑ̐����m�����Q�Ό�オ���x������Ă���Ƃ������̂́A�]�ˉ��~�̈ێ��A���X�̍Վ��V��A�e�핊�ہA�Q�Ό��̍s��Ȃǂɂ����āA���\�����͂邩�ɒ�����m�s�\�������̊i����v�����ꂽ���߁A�r����������p���K�v�ƂȂ����B���Â��͂��߂Ƃ����B�̏��喼�́A�Q�Ό��̍ہA��~�߂���������Ȑ�����̂����铌�C��������A�����Ă��͒��R����ʂ����悤�ł��邪�A���C����I�ꍇ�Ȃǂ͑���ЂƂn��ɂ���ςȔ�p�����������̂ł���B
�@���Ƃ��A�\���\���̊i���̑喼�͎Q�Ό��̍ۂɎO�S�l�قǂ̍s���g�ނ��Ƃ��`���Â����Ă������A���̍s�����n�邾���ł��A���݂̉ݕ����l�Ɋ��Z���Đ�ܕS���~�قǂ̔�p��v�����Ƃ����B���\�O���̎F���˂Ȃǂ́A�]�҂̐��͓��l�߂��ɂ��̂ڂ�A�������A����������]�˂܂Ő琔�S�L�����̗������Ȃ���Ȃ�Ȃ���������A���̂��߂̔�p�����ł��������̊z�ɂ̂ڂ����B�������Q�Ό��̗��ɗv����o��̑唼�͎�v�X���ɉ�������e�˂╈��喼�̎����ƂȂ�A�ԐړI�ɓ��얋�{�Ɋҗ����Ă��̍������������B�ؗ�ȍ]�˕����⋞�s�����̔ɉh�͂����������o�ύ\���Ɏx�����Ă����̂ł���B
�@���̂����ۂ��A�O�l�喼�̗̖��͏d�ł╊���ɋꂵ�݁A�m���Ƃ����ǂ����̑����͘\���ɓx�ɒႭ�}�����A�F���˂ɂ݂鋽�m���悤�ɁA�����͔_�k�ɏ]�����Ȃ��猵���������𑗂��Ă����B�F���l�̔����Ƃ����ꂽ�u���������v�Ƃ������t�́A�����������͂悢���̂́A����ȋC�������コ�ꂽ�w�i�ɂ́A������Ɛ키���Ƃ�]�V�Ȃ�����Ȃ�����C�T�����͍��������Ƃ����߂���̖��̉B���ꂽ�p���������̂��B
�@���ˑ̐���������̎F���˂��A�̓��̌��肠��Γ��݂̂ɗ����āA��X�\�z����開�{�̗l�X�ȗv������߂��ɑΉ����Ă������Ƃ͍�������B����ȎF���ɂƂ��ėB��̕���́A�����Ⓦ��A�W�A�Ƃ̖��f�Ղ��܂ޓ�C���Ղ�ʂ��ė��v�������邱�Ƃł���A���̍ő�̖ڋʂƂȂ�̂��A�ق��Ȃ�ʗ��������̎x�z�ł������B
�@�F���˂ɂ�问���N�����s��ꂽ�̂́A���얋�{�ƎF���˂̗��Q�Ɋւ���v�f�����܂��܈�v�������ʂɂق��Ȃ�Ȃ��B��ʓI�ȗ��j���Ȃǂł͉��\�����ۂ��̎F���˂����˂̗��v�̂��߂݂̂ɗ�����N�������悤�ɋL�q����Ă��邪�A���ۂ̍����͓��얋�{�ł���A�F���˂������x�z�ɂ���Ă��������v�̑唼���A�ŋz���グ���̂����{�▋�t�ł��������Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�@�c���\�l�N�i��Z�Z��N�j�O���A�����O��]�̎F���R�͕S�ǂقǂ̌R�D�ɕ���A�����N�U�̂��ߎF��������[�̎R��`�����Ƃɂ����B���R�����q��v���叫�Ƃ��邱�̎F���R�̎w�����̂Ȃ��ɕ����i���̂�����j�߂��l�̐l�����������B�����Ƃ͌R�̓S�C�g�A�|�g���w�������E�ł���B�R��`����̏o�w�ɍۂ��F���̏]�R���m�ɑ��ẮA�u��ʂ̖��l�ɘT�S���͂��炭�ȁA�_�ЁA���t�A���F�Ȃǂ��r�炷�ȁA�e��o���A�����Ȃǂ��ɂ���v�Ƃ����O�̌R�����z������Ă����B
�@�������Ȃ���A�قƂ�ǒ�R�������邱�ƂȂ�������~�𐧈������F���R�̏��m�����́A���̌R����j���Ė��l�ɘT�S���͂��炫�A�������r�炵�Ă͂����𗪒D�����B�u���̖��ɂ����ď��m�����Ԃ闥�߂�Ƃ��v�i���ًI�l�j�A�u�ƁX�̓��L�A��X�̕����A�������Ȃ��玸���ʂv�i������L�j�ȂǂƓ����̏��L���������ɂ��c����Ă���悤�ɁA�F���R�̖\���͖ڂɗ]����̂�����A���R�A�����̖��S�ɂ͋��������Â̊���N���N�������B
�@�����A����ȎF���̏��m�̂Ȃ��ɁA�R�������炵�A�����̐l�X�̐����Ɛ����̈��S�ɂɓw�ߕ����̕ۑS�ɐs�͂��悤�Ƃ�����l�̐l�����������B���ꂪ��ɏq�ׂ��F���R�̕����ł���B���S�̂Ȃ��ɍ��܂锽���Â̊����}���A�n���Ƃ̗G�a���͂���K�v�ɔ���ꂽ�F���́A�c���\�l�N�㌎�ɖ{�y�R���������グ�����Ƃ��A�R�������炵�����̖��S�ɂ��ʂ������̕��������n�ɗ��߁A���㗮���ݔԕ�s�̔C�ɓ����点��B�����Ȃ�A�ނ́A�����̌�A�����̍s���Ɍg������ČR�̌R���i�ߊ��Ɠ�����E�ɔC����ꂽ�킯�������B
�@������l��������R�������������Ƃ����Ă����F���얋�{�Ⓡ�Â̖��߂̑�s�҂ɉ߂��Ȃ������킯������A�����Ȃ���ʑ�����䂦�Ȃ������𗮋��ɂ����炵�����낤���Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B�N���҂̎��ł��邩����A�����̖��l�ɂƂ��Ė��f�ȑ��݂��������Ƃ͋^���]�n���Ȃ����炾�B�����A�����̖��{��F���˂̎x�z�\���̋���������ɂ����āA�n���Ƃ̗G�a���͂���ׂ����̐l���Ȃ�ɂ͗͂�s�������悤�ł���B�����N�U�����N��̌c���\�Z�N�i��Z���N�j�Ɂu�|�\�܃����v�Ƃ����@�x���F�����痮�������ɐ\���n�����܂ł̊ԁA�ނ͎ɂ����čݔԕ�s���߂������B
�@�|�\�܃����́A�������������炷�ׂ����������i�ɒ�߂����̂ŁA���̍ő�̑_���͗������{�̑ΊO�f�Ռ������A��ɑΖ��f�Ղ̗��v��Ɛ肷�邱�Ƃł������B�Ȍ㗮���͗^�_���Ȗk�̉����������F���Ɋ��悳�ꂽ����łȂ��A���S�ȎF���̐A���n�ƂȂ�A�l�X�Ȃ������Őł̏�[�����v���ꂽ�B�����A���ւ̐i�v�f�Ղ̕K�v��A���������̖������Ƃ̍����W�i���Ɏg�߂�h�����čv�����Ȃǂ̗��s�����A���̌��Ԃ�ɖ����������������A����̗��v��ۏ����W�j�͗e�F����邢���ۂŁA�������ɑ��Ă͎F���Ɨ��������̊W�͉B�����ꂽ�܂܂ɂȂ����B�v����ɗ����͓�d�x�z�̏�Ԃɂ����ꂽ�킯�ł���B
�@�܂��A���{�ɑ��Ă͓��쏫�R�̑�ւ��̂Ƃ��ɂ͌c��g���A���������̑�ւ��̂Ƃ��ɂ͎Ӊ��g���]�˂܂ő��邱�Ƃ��`���Â���ꂽ�B����͍]�ˏ��ƌĂ�A��Z�O�l�N����ꔪ�܁Z�N�܂ł̕S�N�܂ł̊Ԃɏ\������̎g�ߒc���h������Ă���B���{�ւ̔���ȍv�����ɉ����Ďg�ߒc�̗����鋗��������Ȃ����ɁA���̕��S�͑�ςȂ��̂ł��������낤�Ƒz�������B���얋�{�́A�F���˂�ʂ��Ă̊ԐړI�ȗ��v�z���݂̂ɂƂǂ܂炸�A�܁X���ړI�ȗ��v�ɗa���낤�Ɗ�Ă�ƂƂ��ɁA����̌��Ђ��L�������ɒm�炵�߂邽�ߗ��������𗘗p���悤�Ƃ����̂ł������B
�@����̊��{�̌n�������ނƂ�������l�����A���ĎF���͗�����N�������ƁA�������̃��f�B�A�Ō��������f���Ă���̂�ڂɂ������Ƃ����邪�A����͂��Ȃ����I�Ȍ������ƌ����Ȃ����Ƃ��Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�A�ł��̕Ж_�������ł����̂͊��{���������������铿�얋�{�ł���A����������D���ꂽ�x���߂��藬��ď������̂́A�n�����F���̗̓��ł͂Ȃ��A�Ύ��ƌ��܂����蕨�̍]�˂���������ł���B
�@����̗����ݔԕ�s�Ƃ����Ε������͂悢���A�v����ɗ������S���������̂��߂̑̂̂������ƂȂ������̐l���́A�����N�U�̓�N��Ɏ������ɏ��������B�����āA���x�́A���q����ȗ��̎x�z�ҏ���ꑰ�����ՂɂȂ������ƂŁA�l�S������Ď����������A���l��ٍ��D�̏o�����₦�Ȃ������Ƃ������Â̒����́A�����̏���ڒn���ɔC�����ꂽ�B�����Ƃ́A���Ď�����������x�ߊC�ɕ����ԓ��ł���B���j�����̂Ȃ��̕����ɂ́A�u�����͎�������艓�����߁A���ʂ̎҂�h�������̂ł͏���Ȃ��Ƃ������˂��A�ƂĂ��M���������Ȃ��B�����ŐT�d�ɐl�I���������ʁA��N�A�����ŌR�������v���̂��������̐l���������ɑ��邱�Ƃɂ��A�ً}�ɓ����Ɉڂ�悤�ɐ\���n�����v�Ƃ�������|�̋L�ڂ�����B
�@�M����������������Ƃ͂������̂́A���J�����������ɂ͉��������瓇�ւ̈ڕ��ł���A�����������̋L�^�Ō��邩���肻�̐E���̏d���ɔ䂵�Ă��̘\���͋����قǂɒႩ�����B�ނɂ͔˂̂���Ȑl���Ə������̂܂���Ȃ�����������̂�������Ȃ��Ǝv�������́A�Â������ׂ��̈ꑰ�̃��[�c������������T���Ă݂��B
�@�������Ƃ��̑����Ƃ̊Ԃɐ��܂ꂽ���Ò��v�́A������N�i��ꔪ�Z�N�j�������F���A����A�����̎O���̎��E�ɔC�����邪�A���v���g�͑�Ԗ��߂邽�߂ɓs�ɂ������B���̂��ߒ��v�͈�l�̒��b�����̂ɑ���̓������߂������B�h�����ꂽ���b�͒��v�ɑ����Ă��̎O���肵�̓��̏��X�ɏ��z�������Ǝ�N���}���ɏ㗌�A���v�ɏ]���čĂї̍��ւƉ������B
�@���Ò��v���F���̎��E�ɒ����ƁA���̒��b�͒��v���A���݂̎������������s�𒆐S�Ƃ�������т̓�����C�����A��k���ȍ~�ɂȂ�Ƃ��̒��b��X�̌���͑��������Ƃ��Ĉ�т����߂�悤�ɂȂ����B����ɂ���ɂ�������炸�M�Z��𖼏�铖�傪�����������̈ꑰ�́A�����������{���n�ɂ��Ă��̒n�����߁A�傫�Ȑ��͂����Ɏ������炵���B�n���[�l�ɂ��Ƃ��̈ꑰ�͐z�K��Ђ̑�{�i�ꑰ�Ƃ������ł������Ƃ����B�������A����̓����ɂ������ォ��\��ڂɂ����铟�e�Ƃ��̎q�̐e���͓V���\���N�i��l��N�j�Ɏ�Ƃɖd���A���ËM�v�̖����������ɏW�@�v�N�̌R�ɍU�߂��ē����̏����i���݂̓s��j�֓����A���ꂪ���Ƃňꑰ�̎�Ƃ╪�Ƃ͗��U���ނ��A���Ôˎj�̎嗬����p�������B
�@俐e�A�e�����q�����͂��P�ɉ��\�Ȉ������s���A���ꂪ���Ƃňꑰ�����ɑΗ����N����A�₪�Ď�Ƃ̓��Âɑ���d���ɂ܂Ŕ��W�����Ɣˎj�Ȃǂɂ͋L����Ă���B�L�^�Ɏc���Ă���悤�Ȏ������m���ɂ������悤�����A���Èꑰ�̓��ÉE�n���������̂��Ƒ���̒n���ɔC������Ă���Ƃ�����݂�ƁA�ꑰ�̓����ɏ悶�A�d���Ƃ������ڂŒǂ����Ƃ����v��ꂽ�\�����������A�Ȃ�炩�̂������Ŏ��Ɠ��Èꑰ�̐��͑����Ɋ������܂ꂽ�\�����Ȃ��͂Ȃ��B
�@�v�����ނ͂������̂́A����ł��Ȃ����̈ꑰ�̈ꕔ�͍����̒n�ɐ����̂сA�\�N�قǂ̂��ɂȂ��Ă��̌W�݂̒����猻�ꂽ�̂����㗮���ݔԕ�s�ɂȂ����l���ł������B�ނ͏G�g�̒��N�o���̍ہA���ÌR�̈���Ƃ��č���ɉ����A�܂��A�փP���̐킢�̂��Ɠ��Ë`�O���F���ɋA�҂����邽�߂ɑ傫���v�����A�`�O��蓡���̑�����q�̂���ƂƂ��ɁA�\�̒m�s���B�ނ��A�O�������d���̉����̂䂦�ɁA�c���ꂽ�����̎҂����ɂ͂��Ẳh���⌠�Ђɂ����邱�ƂȂNj�����悤�͂����Ȃ������낤�B������A�����₩�ł��Ƃ����ɂ͗^����ꂽ�@����ő���Ɋ������A�������Ō������Ă˂Ȃ�Ȃ������ɈႢ�Ȃ��B���̐l���������̕����̏d�v�����n�m���A�}������问���̖��O�̐S���\���ɉ��������̂́A����̒u���ꂽ����ȏɉ����A���̈ꑰ�ɑ�X�`��镶�����d�̋C���Ȃ����͉ƕ��݂����Ȃ��̂����������炩������Ȃ��B
�@�����̏���ڒn���ɔC�����A�n���Ƃ��Ă͋����قǔ��\�Ƃ��������悤�̂Ȃ��m�s�����̐l���A�{�c�e���́A�⍲���ňꑰ�̖{�c�����q��Ƌ��ɍ����ɓn��B�����Ĕނ�́A�c���N�Ԃɍ����ɔz�����ꂽ�吆��咆�����������A���؏����@���̌��Ɠ�l���Ō�ɕ�炵���㍙�������̉��~�ɋ����A���̐E����S�������B�{�c�e���̂ق��͊��i�\�ܔN�������玭�����ɖ߂藂�N�ɑ��E����B�����Ɏc�����ق��̖{�c�ꑰ�́A�������̕���X���ƂƂ��ɁA���̈⎙��q���ƌ����W�����ɂ��������悤�ł���B���������O���߂������@���́A�̂��ɍ������玭���������v���s�e���Ɉڂ������؉Ƃ̏o�g�ł���B
�@�������̍����ł̐����Ԃ���Âԕ����ⓖ���̎�����ڂ����L���������Ȃǂ͂Ȃɂ��c����Ă��Ȃ��̂Łi�����炭�˖��Ŗv�����ꂽ���̂Ǝv����j���m�Ȃ��Ƃ͒肩�łȂ����A���q����F���ɉ���ȑO�̖{�c�ꑰ�̃��[�c�Ƃ̊W���w�i�ɂ����āA���̂悤�ȉ������܂ꂽ�̂����m��Ȃ��B
�@�{�������̗��R�W�]�䂩��H�n���C�������낵�A�^�V�`�ɏ㗤�����F���̌R���̂��Ƃ�z�������ׂ��Ƃ��A�ˑR�ɋL���̌Ñw�����S�����̂́A�ق��Ȃ�ʖ{�c�e���Ƃ������O�������̂��B���������ƁA�e�����������ɖ߂������ƍ����Ɏc�����{�c�ꑰ�͎��̐�c�ł���A���܂͑������r��ʂĂ����~�ՂɂȂ��Ă��邪�A�ނ炪�l�S�N�߂����O�ɕ�炵���̂Ɠ������̏ꏊ�ł��̎��͈�����̂������B
�@�����̂̂��ƂƂ͂����A���{��F���˂̑�َ҂ƂȂ��ď��J���̗��������Ɋ����A�����̐l�X�ɑ���̖��f���������ꑰ�̖���̈�l���ق��Ȃ�ʂ��̐g���Ƃ������Ƃ��������A���͂Ȃ�Ƃ����鐣�������G�ȐS���ɂȂ��Ă��܂����B����ɂ���ė���܂ł́A����Ȃ������Ŕۉ��Ȃ��Ȃ̃��[�c�����ǂ炳��A�������̂͂ĂɏՌ��̎������m�F�������邱�ƂɂȂ낤�ƂȂǂ͖��ɂ��v���Ă��Ȃ������B��A�̎��Ԃ́A�܂��Ƃɂ����ēV�̂�������Ƃł������ق��Ȃ����̂ł������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
1999�N6��9��
���鉫��̑z���o�i�T�j
�ӌ˖��Ƒc�����A������
�@����O���ڂ̒��́A���������J�T�Ȏ��̐S���܂��͂Â��Ă����悤�Ȑ��V�������B�����̂̂��Ƃ��ǂ��ł���A�������ĉ���ɂ���Ă����ȏ�A����̉���̒u���ꂽ�������Ȃ�ɋɗ͗�ÂɌ������A�Ȃ̖��m�Ɩ��ӔC�����Ȃ݂�_�@�ɂ��邵���Ȃ��c�c�����v�����������́A�Ƃ肠�����z�e�����`�F�b�N�E�g����ׂ��g�x�x�𐮂����B
�@�t�����g�Ɍ������O�Ƀz�e���̔��X���̂����ƁA�O���̋��H�̎ʐ^�Z�b�g���������y�Y�Ƃ��Ĕ����Ă����B�L�O�Ƀ����Z�b�g�����Ă݂����A�v���̃J�����}�����B�����ʐ^�����̂��Ƃ͂����āA���̏o���h���͂Ȃ��Ȃ������Ȃ��̂������B�����A����ȏ�Ɋ��S�����̂́A�u�@������ɕq�Ȃ�v�Ƃ������t��n�ł����悤�Ȃ��̔����ڂ̂Ȃ������Ԃ肾�����B�����тŋ��H������O�ɔ��������H���K�l���������������A�ǂ��������̃A�C�f�B�A�͒n���̐l�̔��z�ł͂Ȃ��A���˂ɂ������{�y�̒N�����l���o�������̂̂悤�Ɏv��ꂽ�B
�@���ԃr�[�`�ɕʂ��������ƁA���͉���{���Ŗk�[�̕ӌ˖���ڎw���đ���o�����B�E��ɂ͍����R�n�̍ō����^�ߔe�x�̐��R�[���L�����Ă���B�^�ߔe�x�͎l��Z���[�g���ƕW�����������Ȃ����A���̎��ӁA�Ƃ��ɓ����R�[��т͐[�����M�ю��ɂȂ��Ă��āA�V�R�L�O���̃m�O�`�Q������o���N�C�i���������Ă��邱�ƂŖ������B�܂��A��Z�l�ȎO������ɂ���ԐA�����ɖ��Ă���Ƃ������A�V�R�ی���ɂ��w�肳��Ă���Ƃ��낾�B�C�ӂ̑��Ƃ������͐Â��ȎR���Ƃ����������̕ӓy���i�ւƂȁj�̏W�����߂��A���C�݉����̓����ǂ�ǂ�k�サ�Ă����Ƃ₪�ċX���ԁi���Ȃ܁j�̏W���ɂł��B����{���̏W���͖k�[�ɋ߂��قǐ̂̎p�𗯂߂Ă���B�������肵�������̐Ԋ��̉������ƂĂ���ۓI�������B
�@���邢�������𗁂тȂ�����Ђ�����Â܂�Ԃ����X���Ԃ̏W�����߂���ƁA�قǂȂ����H�̍��E�ɓ�\���[�g���قǂ̑��̐藧�ꏊ�ɂł��B�܂�Ńg���l�����Q�[�g���������Ă��銴���ł���B���̋߂��̓��H�e�Ɂu�߂铹�v�ƋL���ꂽ�肪�����Ă����B�܁A�Z�\�N�قǑO�܂ł́A�����͊�̗ڂ��@�������}���z�̋����ׂ����ɂȂ��Ă��āA�r���Ŕ��Ε����������Ă���l�Əo�����Ƃǂ��炩�����������Ė߂�Ȃ���Ȃ�Ȃ��������Ƃ���A���̂悤�Ȗ�������ꂽ�炵���B
�@���݂��ԓ��̏�̊R�̊Ԃɂ��̓��̐Ղ��ꕔ�c���Ă��āA�����k���ł̂ڂ�߂��Ƃ���Ɂu���ł��o���^�v�ƌĂ��ꏊ���������B�ቺ�ɂ͍����S���[�g���قǂ̒f�R���قڐ����ɐ藧���Ă���B���̒f�R�ォ�瑩�˂������C�ʂɌ������ė��Ƃ��ƁA���ɐ����グ���ăo���o���ɔ�юU���Ă��܂��Ƃ����̂��A���̕ς�����n���̗R���ł���Ƃ����B�f�R�̐^���ŗh���C�̐F�͂ǂ��܂ł����A��������̂ق��[���܂œ����ʂ��Ă����B����������������グ�ė������߂��ƁA���̉^�V�`���`�Â���{�������Ɖ���n����т̉��i���]�܂ꂽ�B
�@�l�S�N�O�A�S�ǂ���F���̌R�D�c�́A���̊�O�ɍL����C�������ĉ^�V�`�Ɍ������Ă������B�s���Ȏv���ɋ���Ȃ���A���̈ٗl�Ȍ��i�����̊��ł��o���^�̒f�R�ォ�璭�߂Ă�������тƂ��������ɈႢ�Ȃ��B�ŏI�I�ɂ��̎������m�F�����͎̂��������ɖ߂��Ă���̂��Ƃł��������A�����̌R�D�̂ǂꂩ�ɂ́A���l���\�z���ɂ��ʐ���s������F���̗����x�z�Ɉ���͂߂ɂȂ�l��������Ă����킯���B�����āA���ꂩ��l�S�N�߂��o���̂��A������A���̐l���ɂ䂩��̕s�тȒj���ӂ�ӂ�Ɖ����K�ˁA���ɂ����̉���тƂ��R�D�c�������낵�Ă����͂��̒f�R�ɗ����ē����̏��z�����Ă������ƂɂȂ�B
�@�W�]��̎��ӂɂ͑h�S�������������Ă����B�ԓy�ɋ߂����̒n�̓y��͑����ɓS�����܂�ł���̂��낤�B�Q�����邻���̑h�S�߂邤���ɁA���͎�����������Ƃ̒�̈���ɂ��傫�ȑh�S����{�����Ă������Ƃ�z���o�����B�N����̂̂��̑�h�S���͂�ĂȂ��Ȃ�Ƃ��ɂ͉Ƃ��łт�ȂǂƓ`�����Ă������̂��B�g�ӂɗl�X�ȕs�K���������A�₪�ēV�U�ǓƂ̐g�ɂȂ������������ɏo�ċ�w���͂��߂����ɂ́A���Ƃ��ƍr�ꂩ���Ă������~�́A���l�ƂȂ��Ă܂��܂��r��ʂāA���̑h�S�����̊Ԃɂ��͂�Ă��܂����B
�@����Ȃ��Ƃ������ƌ����`�������蓖�������悤�ɂ������Ă���̂����A�^���͑��������ł͂Ȃ��B�h�S�͓S���𑽗ʂɐێ悵�Đ�������Ȃ̂ŁA�����̂悤�Ȗ{���̎����n�łȂ��Ƃ���őh�S�̎�����ۂɂ́A�����ɋ��S��g���Â����䓁�̐n�Ȃǂ��펞���߂ēS����⋋���Ă��˂Ȃ�Ȃ��B���̂ق��A���܂��Ȏ�����䕗�Ȃǂɑ�������Ȃǂ��K�v�ƂȂ�B������A���炩�̎���ł��̐��b������Ɛl�����Ȃ��Ȃ�ƁA�h�S�͏��X�Ɏ��₪�ė����͂�Ă��܂��̂��B�l�����Ȃ��Ȃ邩��h�S���͂��킯�ŁA�����`���Ƃ͈��ʊW���t���܂Ȃ̂ł���B
�@���炽�߂Ď��ӂ̑h�S���ώ@���邤���ɁA����������A����������Ƃ̂��̑h�S�́A���̉���ł̔C�����I�������ɓn������̐l���������A����ł̓�N�Ԃ���������ŐA�������̂ł͂Ȃ������낤���Ƃ����z�����]�����悬������������B�����A����ꂳ���ӂ�Ȃ���Αh�S������O�A�l�S�N�ɂ��킽���Đ����Ȃ��炦�邱�Ƃ��ł�����̂Ȃ̂��ǂ����́A�A���̐��Ƃł��Ȃ����̐g�ɂ͂悭�킩��Ȃ������B
�@���ł��o���^�̂���t�߂��牫��{���Ŗk�[�̕ӌ˖��܂ł͎Ԃłق�̈ꑖ�肾�����B����т͖����тƓ����悤�ɃE�K���_�ł��������Ă��āA����l���̐l�X����W��ł��J�������ȕ��n�ɂȂ��Ă����B�����āA���̕��n�����̓˒[�ɑ��������̘e�Ɉ�̋L�O�肪�����Ă����B�قƂ�ǂ̐l�͉��̊S�����������X�ɂ��̔�̂���ʂ�߂��Ă��������A����Ȃ��̂��킴�킴���̒n�Ɍ��Ă�ꂽ�o�܂��A���͖��ɋC�ɂȂ��ĂȂ�Ȃ������B�����Ŕ�̑O�ɘȂ�ł����Ɣ蕶�ɖڂ�ʂ��Ă݂邱�Ƃɂ����B
�@�u�c�����A������v�Ƒ肳�ꂽ���̔蕶�͑����ɒ������̂ŁA�ׂ��ȕ������A�Ȃƒ��荏�܂�Ă���A�����̈ꕔ�͓ǂݎ��̂ɋ�J���邭�炢�ɕό`��ϐF���������Ă����B�����A�蕶��ǂݐi�ނ����Ɏ��͂������[�������ɂ����Ȃ�ꂽ�B���̂͂����Ԃ�Â����̂́A����͓ǂގ҂̋��ɐX�Ɣ��閼���ł������B�����āA�����ɂ́A�܂�����Ȃ����̉���тƂ̐S�̌��_�����܂�Ă����̂ł���B
�@����Ȕ蕶�����邱�ƂȂǂ��̕ӌ˖��ɂ���Ă���܂Œm��Ȃ��������A���̕��͂�����W�̏��Ђ�K�C�h�u�b�N�A�L���ȂǂŖڂɂ������Ƃ��Ȃ������B�ǂ����Ă����̓��e���L�^���Ă��������Ǝv�������́A���̔�̋߂��ɍ������낵�ăm�[�g���J���ƁA���̔蕶�̍������ꕶ���ꕶ�������ʂ��͂��߂��B���Ȃ莞�Ԃ̂������Ƃł��������A����Ȃ��ƂȂǂ��������C�ɂ͂Ȃ�Ȃ������B
�@�����蕶�������ʂ��Ă���Ԃɂ��A��������̊ό��q�����̘e��ʂ�߂��čs�������A�قƂ�ǂ̐l�͂��̔�ɉ��̊S�������Ȃ������B�����A��̑O�ő����~�߂�l���܂������Ȃ������킯�ł͂Ȃ��B��l�̓��{�l�N�Ɉē�����Ă���Ă����ݓ��ČR�̉Ƒ��Ƃ��ڂ�����s�́A��̑O�ɗ���V�T�C�����o�����肵�Ȃ���F�łɂ��₩�ɋL�O�B�e���J��Ԃ����B���̉��Ƃ����C�ŕ��a�Ȍ��i��ڂɂ��Ȃ���A�������̐l�������蕶�ɋL���ꂽ���e��m�����Ƃ�����ǂ�Ȕ����������̂��낤���ƁA���͓��S�Ŕ��������Ȃ������B
�@����̒����Ƃ������̂͂��ׂẲ��Q��������B����͕K�������l�ނ̕��a�ƗF�D�ɂƂ��Ĉ������Ƃł͂Ȃ��̂�����ǂ��A�܁X�������쌀�I�Ȍ��i�ݏo�������������̂��B���̂Ƃ��ڂɂ����ČR�Ƒ���s�̐S����y�������ȗl�q�́A���̂��Ƃ��������悭�ے�������̂ł������B
�@������������ꕔ�Ɏʂ��ԈႢ�Ȃǂ����邩���m��Ȃ����A���������̋@�����A�ȉ��ɂ��̑S�����Љ�Ă������Ǝv���B���̈Ӗ�����Ƃ�����ǂ̂悤�Ɏ~�߂邩�͐l���ꂼ��ł��낤����ǂ��A��X�{�y�̐l�Ԃ�����̊�n���◈�N�J�Â���鉫��T�~�b�g�̈Ӌ`�Ȃǂ��l����Ƃ��A�Ȃɂ�����̎Q�l�ɂ͂Ȃ�ɈႢ�Ȃ��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�q�c�����A������r
�@�@�@�@�@�@�@�S���̂����Đ��E�̗F�l�ɑ���B
�@�����n�镗�̉��Ɏ����X����B���͂ɍR�����A���Ȃ��Ƃ�����O�̊��t���B�ł���g���̋������B�푈�����ݕ��a�Ɛl�ԊJ������O�̋��т��B
�@�S�̖\����ݕ��a�̂��Ƃ����M�������ꌧ���́A�ČR��̂Ɉ��������A���ܓ�N�l����\�����T���t�����V�X�R�u���a�v����O���ɂ��A���J�I�ȕč��x�z�̓S���Ɍq���ꂽ�B�č��̎x�z�͘����Ō����̎��R�Ɛl�������W�����B�c�����{�͊C�̔ޕ��ɉ����A���ꌧ���̐��͂ނȂ����������B�����̓������奂̕��ɋ[����ꂽ�B
�@�������Ɨ��ƕ��a�����E�̐l�X�Ƃ̘A�т��邱�Ƃ�M���A�S�����ɌĂт����āA�S���E�̐l�X�ɑi�����B
�@����A���a�ɂ������܂��X���^�̗�����A��\���x����f���M�͑D�o���A���X����菟���𐾂���C����ɔ��W�����̂��B�����܂�Ă���y�����A�ӓy�斯�̐^�S�ɂ���Đ��鉫�V�̑啰���̑�n�Ȃ̂��B��㎵��N�܌��\�ܓ��A����̑c�����A�͎��������B�����������̕��a�̊肢�͊�����ꂸ�A���č��ƌ��̜͂��ӂ̂܂܌R�������ɋt�p���ꂽ�B
�@�����邪�̂ɂ��̔�́A��т�\�����邽�߂ɂ���̂ł͂Ȃ��A�܂��ď������L�O���邽�߂ɂ���̂ł��Ȃ��B
�@������U��Ԃ�A��O��M�������A����̗͂��m���ߍ����A���ӂ�V���ɂ��������߂ɂ�������A�l�ނ��i���ɐ������A�����Ƃ���������̂����R�̐ۗ��̂��Ƃɐ����Ȃ��炦���邽�߂Ɍx����炳��Ƃ��Ă���B
�@�蕶�̕M�ʂ��قڏI���������Ƃ��̂��ƁA���͂�����Y����Ȃ����i�ɂł��킷���ƂɂȂ��Ă��܂����B�m�[�g���L���ă������Ƃ鎄�̎p���C�ɂȂ����炵���A��l�̐N�����肰�Ȃ��߂Â��Ă��Ă����e�ɗ������B�����āA�ނ͂܂�ł�����̎����ɗU���邩�̂悤�ɁA���̔蕶�ɖڂ�ʂ��n�߂��̂������B�ނ͍����̐N�ŁA�n���̑�w�̊w���ł͂Ȃ����Ǝv��ꂽ�B���炭���̔蕶��ǂ�ł������̐N�̊炪�݂�݂镡�G�ȕ\��ɕς���Ă����̂��A���̎��͌������Ȃ������B
�@�ނ͔��Δ߂����ȁA���Γ{��ɖ������l�q�ŋ}�Ƀv�C�ƐΔ�ɔw��������ƁA�����������̂܂܈����Ԃ��čs���Ă��܂����B�����炭�ӌ˖��̓˒[�ɗ����ĊC�߂����ŗ����̂��낤���A�ނ͖��ɍs���̂�r���ł�߂Ă��܂����̂��B���̌������蕶�ɂ��������Ƃ͖��炩�������B�ނ̐S���͎@����ɂ��܂肠����̂��������B�������̌����������̐N�����꒓���̕ČR�R���ƒn������̏����Ƃ̊Ԃɐ��܂ꂽ�̂ł������Ƃ���A�ǂ�Ȃɂ��ꂪ����̖��O�̐S�������i�����������̂��Ƃ��Ă��A���̔蕶�͔ނɂƂ��Ďc���ȃ��X�ȊO�̉����ł��Ȃ������낤�B
�@����̒n�ō����Ƃ��Đ��܂�Ă����ނɂ͉��̐ӔC���Ȃ��B�����Đ��܂�Ă����ȏ�A�ނ͉���ŁA����ɂ͓��{�����Ő��������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A�ނ̗͂ł͔@���Ƃ�������ĊԂ̉ߋ��̗��j�I�w�i���l�X�Ȃ������Ŕނ��ꂵ�߂邱�ƂɂȂ��Ă����B���������̉���ɂ͔ނƓ����悤�ȋ����̐l�X���������������Ă��āA���̐��͌��݂���芄���ő���������͂��������B�����o�������N�͂���Ȃ�ɋ�����Ă��銴������������܂��悩�������A�����炭�A�\���ȋ�������Ȃ��܂܂ɋꂵ��ł���l�X����������ɈႢ�Ȃ��B����Ȑl����������ň��肵���d����T���̂͗e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ����낤�Ǝv��ꂽ�B
�@�c�����A������̌������ɂ��镽�R�n��ʂ蔲���A�ӌ˖��̓˒[�ɗ��ƁA�k���͂邩�ɗ^�_���̓��e����������Ɩ]�܂ꂽ�B�ቺ�͗��N�T���S�ʓ��L�̍�����\���[�g���قǂ̐�ǂɂȂ��Ă��āA�����������ł��ӂ��U���Ă����B���x�ߊC�Ƒ����m���q���C�����͂���ŗ^�_���܂ł͓�\��L���A���M�ł��ԑ��炸�̋������������A��㎵��N�ɉ��ꂪ���{�ɕ��A����܂ł́A���̊ԂɖڂɌ����Ȃ������k�ܓ�\���x����������Ă����B
�@�蕶�ɂ�����悤�ɁA�c�����A���肤�����̉���̐l�X�͔N�Ɉ�x���̕ӌ˖��̍L��ɏW�܂��đ�W����J���A��ɂ͋����⾉��āA���l��⾉��^�_���̐l�X�ƌĉ����������Ƃ����B�܂��A�ӌ˖��߂��̋X�^���̍`����ł����M�̌Q��͖k�ܓ�\���x�����z���A�A�^�_���������Ă������M�̌Q��ƍ������A�݂��ɐڌ�������_���đc�����A�����̂��߂̊C��W����Â����̂������B
�@������Ԃɖ߂�r���ōA���������߂ɔ��X�ɗ�����������A�Ⴂ����q�̏��������͂�͂荬���̐l�����������B����͎��̎v���߂�����������������Ȃ��̂ŁA�f��͂ł��Ȃ����A�암�⒆���̉���ό��̒��S�n����͂���ĉ���k����k�����Ɍ������ɂ�āA���l�n��荕�l�n�̍����Ǝv���锄��q�������Ȃ��Ă���̂͏��X�C�ɂȂ����B��͂�A�����Ȃ炴��Ȃ����炩�̎���B����Ă����̂��낤���B
�@
�@�ӌ˖������Ƃɂ������́A����{���ł����Ƃ��̂̂܂܂̎p�𗯂߂Ă���Ƃ����铌�k���̊C�ݐ��⍑���R�n�̓����R�[��т��߂��铹�H�𑖂��āA�����̋X������A���������ʂɔ����邱�Ƃɂ����B�ӌ˖�����قǂȂ��u���v�Ƃ��������W���́A���̖��̒ʂ�ɉ��䂩�����A�ƂĂ��Â��ȏW���������B�W�X�ƍ~�蒍�������邢����̗z���Ƃ͗����ɁA�܂�ʼn����̂Ɏ��Ԃ��~�܂��Ă��܂������̂悤�ɐÂ܂�Ԃ�ƁX�̂������܂��́A����암�̎s�X�n�⒆�����̃��]�[�g�n�т̗l�q����z�����ł��Ȃ����̂������B
�@������������̐^�|���c�����ɐ芄�����悤�Ȍ`�̐Ԋ���O�O�ɕ��ׁA������������Ōł߂��Ⴂ�������������ƁA���̎l�����͂���������Ƃ����Ί_�Ȃǂ́A���̒n�Ȃ�ł̖͂җ�ȑ䕗�ɂ��ς����邱�Ƃ�z�肵�����̂ɈႢ�Ȃ��B���N�̐����̒m�b�Ƃ��Ă��̂悤�ȑ���̉ƁX�����܂ꂽ�̂��낤���A���ӂ̎��R��썑�̑��z�Ǝ��ɂ悭���a���Ă��Ĕ����������B�������̉ƁX�̉��������鎂�q�`�̎��_�V�[�T�[����������A���������ɍ炭�u�[�Q���r������n�C�r�X�J�X�̉Ԃ����łȂ���A���͂��炭����Y��ďW���������������B
�@���W�����瓌���ɂ��炭�����ĉ���{���k���[�̊C�ݐ��ɏo��ƁA���͑傫����Ɍ�����ς����B�i�s��������ɂ͑����m���L����A�ǂ��܂ł��������l�̕l�ӂɌ������Ĉ�g���Â��ɁA�������₦�ԂȂ��ł��Ă���B�����ۂ��̉E��R�x���̎Ζʈ�т́A���M�ѐ��̎��тŐ[�X�ƕ����A�e�Ղɂ͐l�����Ȃ��C�z�������B
�@�{���̈�l�݂̂̎�����邠���̓������̒��ɚk���Ƃ������́A�ɍ]��߂��̊C�݂ŎԂ𒓂߁A�l�ӂɍ~�藧�����B�v�����ʂ�A�����ɂ͂܂������l��̉�����Ă��Ȃ����R�̈�l�������B�l�ӈ�ʂɖ����̔����X��̒f�ЂⒿ�����L�k���]����A���������̉���̕����͈�ӂɉ����đя�ɔ��B�����召�̎X��ʌQ����Ȃ��Ă����B�l�H�I�ɐ������ꂽ���]�[�g�n�̉��[�C�݂≜�ԃr�[�`�ƈ���čr�X���������z�Ȋ����ł͂��������A����͂܂������A�c�����Ɏ������ł��ꂽ�̂Ɠ����́A�{���̒��̍���ƋP�������C�ƕl�ӂɈႢ�Ȃ������B
�@���������قǂ悢���������A�����X�Ɛ��݂����Ă��āA�����̐����̑��Â��������܂ɂ��������Ă������Ȋ����ł���B����ʼnj���Ȃ���͂Ȃ����낤�B�N�����Ȃ��̂��悢���ƂɁA�c�N������������݁A���܂ꂽ�܂܂̎p�A���Ȃ킿�u�t���`���v�Ŕ�э���ł݂����Ƃ����z������u��������A�Ȃ̍��l����Ƃ������ɂ���͋C���Ђ����B�����ŁA��������Ԃɖ߂��Ď��Q�̊C�p���ɂ͂������A�S�[�O�����͂߂ďo�����ƁA��X�Ƃ��Ė��l�̊C���ɔ�э��B
�@�u�j���Ȃ���ΐl�ԂłȂ��v�Ƃ������́A�u����Ȃ���ΐl�ԂłȂ��v�Ƒ��̒N�����l���铇�炿�̎��Ȃ̂ŁA�r��ł̉j����f����͓��ӂł���B������Ɖ��ɏo�ĊC����`���Ă݂�ƁA�\�z�Ɉ�킸�召�̔������X�肪�Q���Ȃ��Ĕ��B���Ă����B�X��ʂ̍����ɐ���A����C����~�������ĊL��T���A�l���������F�Ƃ�ǂ�̋������ƋY��邤���ɁA���������͂��ׂĂ̗J����Y�ꋎ��A�Ȃ�Ƃ��������肽�C���ɂȂ����B��������g�s���Ă��Ȃ������̂ŊL���̂�̂͂�߂����A�H�ׂ�ꂻ���ȊL��������Ƃ���ɐ������Ă����B
�@�C���炠���������ƂŒ��C�������ꏊ�͋߂��ɂ͂Ȃ��������A�q�ǂ��̍����炱�̎�̂��Ƃɂ͊����������������A�����̐g�ׂ̂̂Ƃ��͋C�ɂȂ�Ȃ������B����ǂ��납�A���ɐl�e�̂Ȃ�����̔������C��Ɛ肵�ĉj�����Ƃ����]�O�ȑ̌��܂Őςނ��Ƃ��ł����̂ŁA�C���炠�����Ă��C���͑u�����̂��̂������B
�@�Ԃɖ߂��Ĉꑧ�������́A���Ȃ�ړI�n�A�^�i�K�[�O���C��ڎw���čĂё��肾�����B�O���C�Ƃ͐�̗��݂���̂��Ƃł���B�^�i�K�[�O���C�͈��g��̎x���A���v�i�t�[�N�[�j��̏㗬�ɂ���鋫�ŁA��т̎��n������ӂɂ͍��̓V�R�L�O���Ɏw�肳�ꂽ����̐A�����Q�����Ă���Ƃ������Ƃ������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
1999�N6��16��
���鉫��̑z���o�i�U�j
�V���̉���̋��Ԃɂ�
�@�^�i�K�[�O���C�Ɍ����ĎR�ԕ���ʉߒ��A�ˑR�A�o���o���o���o���Ƃ����s�C���ȍ������ǂ�����Ƃ��Ȃ������Ă����B�������A�G���W�����������������炢�Ɍ��������̉��͌J�Ԃ��J�Ԃ��������Ă����B�@�֖C��A�˂��Ă��鉹�̂悤�ɂ��A�R���p�̃w���R�v�^�[�������Ŕ�s���Ă��鎞�̉��̂悤�ɂ��v��ꂽ�B�����炭���꒓���̕ČR���A�߂��̎R�x�n�тłȂ�炩�̌R���P���ł�����Ă����̂��낤���A�L���Ȏ��R�ƐÂ��Ȋ��̎c�鉫��k���ɂ͂Ȃ�Ƃ��s�������ȕ����������B
�@�^�i�K�[�O���C�̓�����͈��g���ʂւƑ����_�[�g�̎R�x���H�̉E�e�ɂ������B�悭���ӂ��Ă��Ȃ��ƌ����Ƃ��Ă��܂������Ȃقǂɂ��̏ꏊ�͖ڗ����Ȃ������B�Ԃ��߂��̃X�y�[�X�Ɏ~�߂����ƁA�y���C�����ł��̓�����ɗ��������́A�\�z�O�̏Ɏv�킸����ۂB���̗��n�_����ቺ�̒J��Ɍ������āA�l�Ԉ�l���~���̂ɂ���ƂȂقǂ�襘H���l�\�ܓx�قǂ̋}�p�x�ň꒼���ɗ�������ł�������ł���B�����đ����̓S�Y�Ɉ�[���Œ肳�ꂽ�������������[�v����{�A����襘H�ɉ����Ē����Ă����B�ǂ����A���̃��[�v��`���ĉ��ɍ~���Ƃ������Ƃ炵�������B����ȂƂ����K�˂镨�D���͂߂����ɂȂ��Ƃ݂��A������͂���ƐÂ܂�Ԃ�A�l�̋C�z�͂܂������������Ȃ������B
�@���̓��[�v�ɂ��܂�g�̂̃o�����X���Ƃ�Ȃ���A�Ƃ����⎿�̊�ƔS�y���̐ԓy�̂ނ��������}�Ζʂ��~��n�߂��B�Ⴂ���ɎR�������o��������Ԃ�Ƃ���Ă�������A���̒��x�̂��Ƃ͂������ċ�ɂȂ�Ȃ��������A�����J���~���Ă�����ԓy�Őg�̒��D�X�ɂȂ��Ă������Ƃ��낤�B�J�̒�͊������R�ɂȂ��Ă��āA���n�̐��ӓ`���ɍד������������ƁA��̒������ޗ��̂��ɂł��B������̊�Ղ͗l�X�Ȍ`�ɐN�H����Ă��āA�����ƌĂ�ł悢�悤�Ȋ�X����������������ł����B
�@����鐅�͂��Ȃ�S�����܂�ł��銴���ŁA���̎��ӂ̊��ɂ₩�ȑ�̐쏰�̊�Ղ͂�����ƐԒ������F�����Ă����B��т͂��Ȃ�̍L���̎��n�тɂȂ��Ă��āA���߂Ėڂɂ���l�X�ȐA���ނ��ɖ��Ă������A������ЂƂ̖��͖̂�O���̎��ɂ͂悭�킩��Ȃ������B�����E�L���E�A�Z�r�A�A�I���M�\�E�A�R�P�^���|�|�A���N�V�}�X�~���Ȃǂ̒�������Q�����Ă���Ƃ̂��Ƃ��������A�Ԃ̃V�[�Y���������͂���Ă������Ƃ������āA���ꂪ�������ȂƎv�����x�ŁA�\���ɂ͊m�F�ł��Ȃ������B
�@�^�i�K�[�O���C�ɗ��ꍞ�ސ�̏㗬���͟T���Ƃ������M�ю��тɂȂ��Ă����B�ꂩ�痬�ꗎ���鐅�Ɏ�����Ă��邤���ɂȂ�ƂȂ����ɕ��������Ă݂����C���ɂȂ��āA������Ƃ����O�i�����������A����Ȏ��̑����������߂��̂͑O���Ɍ��ꂽ�ꖇ�̉��F���x���������B�鐂̃}�[�N���`���ꂽ���̌x���ɂ͉p��ŁuWARNING�I�v�Ƒ发����A���̉��ɂ�͂�p��Ōx�����R���L�����ꕶ���Y�����Ă����B�����댚�Ă�ꂽ���̂��͒肩�łȂ��������A����͒����ČR�̉q���Ǘ����ǂ̎�ɂ����̂ŁA���V�т�T���������ɂ���Ă���l�X�ɒ��ӂ𑣂����e�������B
�@�ڂ����ڂ�ʂ��܂ł́A��т̂��������ɐ��ރn�u�Ȃǂɒ��ӂ���悤���������̂��Ǝv���Ă������A�x���̓��e�͂����ł͂Ȃ������B����́A���̕t�߂ɂ͔M�ѐ��̓���ȗL�Q�����ۂ��������Ă���̂ŁA���V�тȂǂ͐T�ނ悤�ɂƂ������e�̌x�����������B�A�����J�l�Ȃǂ͉Ƒ��⒇�ԓ��ł�����Ƃ����`������݂̃t�B�[���h���[�N���y���ނ��Ƃ������B�����������l�X�����̌x���Ȃ̂��낤���A���{�̓��ǂɂ���Č��Ă�ꂽ���̂ł͂Ȃ��A�ČR�̊Ǘ����ǂ̎�ɂ���Č��Ă�ꂽ���̂ł���Ƃ������Ƃ́A�ߋ��̉���̏��̂����ɕ������̂ŁA�Ȃ�Ƃ������[�������肾�����B������������A���Ȃ�O�Ɍ��Ă�ꂽ���̂����̂܂c���Ă����̂�������Ȃ����łǂ��c�c�B
�@�Ăу��[�v�𗊂�ɋ}�Ζʂ��悶�o��^�i�K�[�O���C�����Ƃɂ������́A���g�̏W���ւƉ����Ă������B���g��̂����߂��܂ŎR�̎Ζʂ�����A���̎R���ɒi����Ȃ��ČÂ�����̖��Ƃ���������ł���B���݂͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��킩��Ȃ����A�����͂قƂ�ǂ��̂Ȃ���̊��Ԃ������̉��ꖯ�ƂŁA���̕���L���Ȍ��i��ʂ��āA��������̉���̎p�̈�[���ÂԂ��Ƃ��ł����B�Ԃ���~��ďW���ׂ̍����H������Ă݂�ƁA���X�܂Ŏ��ɂ悭����ꂪ�s���͂��Ă��āA�e�X�̉Ƃ̖���t�߂ɂ͈��M�ю�̔������ԁX���N�₩�ȍʂ���������̂��Ƃ��ɍ炫�ւ��Ă����B�W����т͂ǂ����Â܂�Ԃ��Ă��āA���̕s�v�c�ȐÂ������S�g�̉���܂ł��킶��Ƃ��݂Ƃ����Ă��銴���������B
�@���g���o�Ă��炭����ƁA�Ԃ͗^�ߔe�x�̓��R���ɍ������������B��ɂ��q�ׂ��悤�ɁA���̗^�ߔe�x�̓�����т̓m�O�`�Q������o���N�C�i����������̂ŗL���ȂƂ���ł���B�ނ��A��قǂ̍K�^�Ɍb�܂�Ȃ������肻���̒����ɂ͂߂��肠���Ȃ��Ƃ킩���Ă����̂ŁA�Ƃ��Ɋ��҂����Ă��Ȃ��������A����Ȓ������̐��ޖL���Ȏ��R�̒��𑖂�̂͋C�����̂������Ƃ������B
�@�^�ߔe�x�̎R�[���߂���ƁA�ԓ��͕��G�ȎR�x�n�`������邩�悤�ɊC�ݐ��̂ق��Ɍ������ĉ���n�߁A�قǂȂ��C�ӂ��炻�������Ȃ����R�n�ɏo���B�唑�A��H���A�����A�{��A��c�ƊC�݂ɐ��������W�����A�₪�ĎԂ͕��ǘp�ɖʂ��铌���̒��S�W�����ǂɓ������B�����āA���ǂ���F�o�ߔe�̂s���H�ɏo�č��܁A���炭���Ȃ�ɓ쉺���Ă����ƌc�����̏W���ɒ������B���̏W���̈ʒu����c������̉͌��ɂ̓q���M�A���Ȃ킿�}���O���[�u�̌Q�����`������Ă���B�C���̉����ɂ��ς���q���M�т͓�̓��Ȃ�ł͂̂��̂ŁA���̓Ɠ��̎}�Ԃ��t�̌`�A���̒��肩���Ȃǂ����ۂɖڂɂ����̂͂��̎������߂Ă������B
�@�c��������L���p���߂����čĂюR���ɓ���A���炭����Ƒ�Y�p�����̏W���ɏo���B��O�ɂЂ炯���p���͂���Ői�s��������ɑ傫���̂т����Č�����͕̂Ӗ�Ö��̂悤�������B��Y�p����Ӗ�Ö���т͖���s�ɑ����Ă���A���N�J�Â���鉫��T�~�b�g�ɂ����Ă͂��̂����肪���S���ɂȂ�\��ŁA���݊J���������i�߂��Ă���Ƃ����B�܂��A���V�Ԕ�s��̑�ւƂ��ĊC���n�̌��ݒn�̌��ɂ������Ă���̂��A����s�̓��C�݂ɂ����邱�̂�����ɂق��Ȃ�Ȃ��B�ނ��A���̎��_�ɂ����ẮA���̌�������u�����ꂽ�������Â��Ȃ��̒n���A�₪�č��ې������̉Q���Ɋ������܂�邱�ƂɂȂ�ȂǑz�������ʂ��Ƃł͂������̂��B
�@�Ӗ�Ö����߂���A�X��������o�Ē����̋������ɓ���ƁA���ӂ̕��͋C����ς����B�����ɂ��A�����J�I�Ȋ����̌������������сA���邩��Ɋ�n�̒��Ƃ����Ɠ��̋�C���Y���Ă���B�l���Ă݂�ƁA�L�����v�n���Z�����͂��߁A���������̎����������ČR�̌R�p�n�ƂȂ��Ă���Ƃ�������A�X���ݑS�̂��ǂ���������������������̂͂�ނȂ����Ƃ������B�R�����肰�Ȓ����ɂ��ĉ���×��̐Â��Ȕ_�����i�����҂���ق��������Ƃ������̂ł͂������B
�@�����̊X���݂�ʂ�߂��A�ܑ������̍s���͂��������p�����̓��ɏo��ƁA���Ãr�[�`������Ɍ��Ȃ���ΐ�s���ʂɌ������Ă������ɑ��蔲�����B����C��͂邩�ɕ����ԓ��e�́A�����ɖK�˂����ł������������A�{�铇�A�Ɍv���̂��̂̂悤�������B���C�݂̐ΐ�s�Ɛ��C�݂̉��[�������̊Ԃ́A����{���������Ƃ��ׂ����т�Ă��镔���ł���B�ΐ�s�ɓ��������́A���C�݉����ɓ쉺���銲���H���琼�ɕ��Ē����ɏo��ƁA���C�ݓ`���Ɏc�g���ڎw���đ��肾�����B�ł��邱�ƂȂ�A�c�g���Ő��̊C�ɒ��ޔ������[�����������Ǝv�������炾�����B
�@����ɂ���Ƃ����ɗ[����ǂ����������Ȃ�Ƃ����̂́A���̍������K���̈�ł���B�q�ǂ��̍��ɐg�ɂ��Ă��܂������ȏK�ȂŁA�قƂ�ǁu�[�����ŏǁv�Ƃł��Ăق����悢��ԂɂȂ��Ă���B�T���E�e�O�W���y���́u���̉��q�l�v�̒��ɁA���������[���������鏬���Ȑ��̘b���o�Ă��邪�A������������A�T���E�e�O�W���y�������Ɠ��a�������̂�������Ȃ��B���̖��ȕa��}����ɂ́A�N���f�G�ȏ����ɂł�����܂œ��s���Ă��炢�A���v�̎������߂Â�����u���Ɨ[���Ƃǂ�������Ȃ̂�I�v�Ƌ����ɔ����Ă��炤���炢�̂��Ƃ����邵���Ȃ��B
�@�����̂ق��͂ǂ����Ƃ����A�܂��A�������Č����ł͂Ȃ����A����ŏ�ɑ��N�����Ă��������Ƃ����܂ł̂������͂Ȃ��B���������t���[�����X�l�ԂƂ������̂́A���͎ア�Ƒ��ꂪ���܂��Ă���B�k�A���v�X�̎R�̒��Ō��郂���Q�����[�g�i���Ă��j�̂悤�ȗ�O������ɂ͂��邪�A�������Ƃ����_�ł́A��ʓI�ɂ͖łт̉e���߂��[���̂ق����f���炵���B
�@�]�k�ɂȂ邪�A���̊ۂƂ����̂́A�u���o�鍑�̓V�q�]�X�c�v�̐������q�̌��t��҂܂ł��Ȃ��A�G�l���M�b�V���Ȓ������C���[�W�������̂ɈႢ�Ȃ��B�^�}�ɓ��̊ۑ�D���l�Ԃ̐搶���������̂��A����ԈႤ�Ɓu���擌�C�̋��Ĉ�����������Ƃ��c�v�Ƃ����A�i�N���j�Y���ɒʂ����˂Ȃ��C���[�W�ւ̎v�����ꂪ�����Ă̂��Ƃ��낤�B�������炢�͗[���̌��l�����C���[�W�������̊ۂł�����A�[���h�̎��Ȃǂ������Ɠ��͊��ɍD����������Ƃ��ł��邾�낤�ɂƎv��ʂ��Ƃ��Ȃ��B�����Ƃ��A���������ٍ̐e���������Ă�����Ă��邱�̃z�[���y�[�W�̃I�[�i�[��Ђ��u�[���V���v�ł͂Ȃ�����A�b�͂Ȃ�Ƃ���₱�����B
�@�^�h�c���̕t����������A�^�v�c�r�[�`�����ɑ����āA�c�g���ɒH�蒅�����͓̂��v�����̏����O�������B�c�g���̖k���͐��L���ɂ킽���č����S���[�g���قǂ̒f�R�ɂȂ��Ă��āA�₦�ԂȂ����x�ߊC�̍r�g���ł��Ă���B���̐�[�t�߂ɗ��ƁA���x�ߊC����]�ł����B�����C��̐�������ɉ_���N���Ă������߂ɁA�c�O�Ȃ���������[���߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��������A�c�g���Ƃ������̖��̂�����A�z�����ʂ�́A�����ɂ���߂��_��I�ȗ[�g�̋P����z�������ׂ邱�Ƃ͗e�Ղł������B�����̟ƍ]�Ȃ͂��̖��̐����͂邩�Ɉʒu���Ă���B�����嗤���猩��A���̏��铌���̊C��ɕ����ԗ��������͂܂��ɐ�l�̏Z�ޖH���i�ق��炢�j�����̂��̂ł������ɈႢ�Ȃ��B
�@�c�g�����琼�C�ݐ��`���ɏ\�L�����炸�쉺���������肪�A�����̍ۂɕČR��͕����������㗤���ʂ������ǒJ���̓n��m�C�݂��B���l�ܔN�l������ߑO�����A������G�C�v�����t�[���̓����ɁA�u�A�C�X�o�[�O���i�X�R���j�v�Ɩ��Â���ꂽ�ČR����{���㗤���͊��s���ꂽ�B�������̖��ɗ��l���������Ƃ���A�쐼�����̊C���ʂ��Ċ͑D�Q�����]���邱�Ƃ��ł����ł��낤�B�ČR�����̊ԂŁu����͂�����������}�b�J�[�T�[�̏㗤���H�v�Ƃ����W���[�N����ь��������قǂɁA���{�R�̒�R�̂܂������Ȃ��Â��ȏ㗤���i�������Ƃ������A����͉���암����ɂ�����n���G�}�𗠂ɔ�߂��A�����ʂ�́u���̑O�̐Â����v�ɉ߂��Ȃ������B
�@�[���̎c�g���ɂ����Ȃ��ƁA���͌ܔ������܂ň����Ԃ��A���[���r�[�`�̏�����ɂ���z�e���E�T���}���[�i�Ƀ`�F�b�N�C�������B�{�i�I�ȃ��]�[�g�z�e���Ƃ��ē����J�Ƃ�������̃T���}���[�i�̑���́A�������Ɍ����Ȃ��̂������B�L����K�̃I�[�v���X�y�[�X�͉��y���t�p�̃X�e�[�W�Ɛ�����X����l�H�r�����Ȃ��������K�[�f�����̑���ɂȂ��Ă��āA���������Ƀ����O�`�F�A���z����Ă����B�Ɩ������͂��߂Ƃ���e��f�R���[�V�������v�Z���s���ꂽ���̂ŁA�㕔��Ԃ͌����̍ŏ�K�Ɏ��鋐��Ȑ��������\���ɂȂ��Ă����B����ɁA�e�K�ɂ͉�����L�������āA�����̉�L�����K�̃I�[�v���t���A�������낷���Ƃ��ł���悤�ȍH�v������Ă����B�G���x�[�^�̓������琁��������ԑS�̂����n����悤�ɂȂ��Ă���̂��Ȃ��Ȃ����Ȋ����������B
�@ ����������Ď����ɓ���Ƃ��������ɔ�э��݁A�k�����C�݂ʼnj�����Ƃ��ɐg�̂ɂ������C��������B���Ă���ꂽ�����͗��h�ȃc�C���d�l�ɂȂ��Ă���A�K�i��ɔz���ꂽ�����t���̃e���X����́A�召�̉��O�v�[���̂����뉀�Ƃ��̌������ɍL����C�������낷���Ƃ��ł����B����D��Ńz�e���E�T���}���[�i��I�킯�ł͂Ȃ��A���̃z�e���̎�ނ��d���̂����������̂Ŕ��܂邱�ƂɂȂ����̂��������A�����������̂��ƂȂ̂Ŗ쎟�n���_���ۏo���ɂ��Ă����������U�Ă݂���������B
�@�z�e���e�ɂ́A�e�탈�b�g��}�����X�|�[�c�p�̃{�[�g�̂ق��A�T���Z�b�g�E�N���[�W���O�⃀�[�����C�g�E�N���[�W���O�p�̑D�������ł����p�}���[�i���݂����Ă����B�L��ȉ��O�v�[���ɂ́A��ԏƖ��̂��ƂŎv���������ɉj�����y����ł��邩�Ȃ�̐��̏h���q�̎p������ꂽ�B�܂��A�z�e���~�n�̊O���ɑ����Y��ȎX�荻�̃r�[�`�̓T���}���[�i�̏h���q��p�ŁA��Ԃł����Ă��A��g�̉��Ɏ����X���A�T�N�T�N�ƍ��n�݂��߂Ȃ���U����y���ނ��Ƃ��ł����B�}�����X�^�b�t�ƌĂ��z�e���ꑮ�̃��W���[�w�����́A�j���Ƃ����B���E�I�N�}�Ɠ��l�ɂȂ��Ȃ��̔��`�����ŁA���̂قƂ�ǂ͂�͂蔒�l�n�̍����̂悤�������B
�@���̓_�C�j���O���[���ł̂�т�H�����Ƃ�����A�e�B���[���ł���������A���W���[���[�����͂���������A�v�[���ʼnj�����肵�Ȃ���A�h���q�̗l�q�����肰�Ȃ��ώ@���Ă݂��B�ႢOL�⏗�q�w�����̂��q�����|�I�ɑ����̂ɔ䂵�āA�j���q�͂��Ȃ�̍���҂��O���l���قƂ�ǂ������B�Ȃ��ɉ��g���Ⴂ�j���̃J�b�v�����������A�ʔ����̂́A�ǂ̃P�[�X�����̎q�̂ق����哱�����Ƃ��Ă��邱�Ƃ������B�z�e���̟������_�C�j���O���[���ŗ[�H���Ƃ�Ƃ����A�Ⴂ�j�̎q�̂ق����ǂ������ǂ��ǂ��������Ȃ̂ɑ��A���̎q�̂ق��̐g�U�镑���͎��ɓ��X�Ƃ��Ă����B���˂��ˎ��͊e���ʂł̏����̎Љ�i�o�ɍm��I�Ȑl�Ԃ����A���̂Ƃ�����́A�u���{�̎Ⴂ�j�ǂ���A����������Ƃ������肹���I�v�ƐK��@�������Ȃ�悤�ȋC���������B
�@����ɂ��Ă��A��������̓��{�l�j�����܂������ƌ����Ă����قnj�������Ȃ��̂́A�l���Ă݂�Ɗ�Ȃ��Ƃ������B�ЂƂɂ͋㌎�Ƃ������ߕ����������̂��낤���A��ԐS�g�̃��t���b�V����K�v�Ƃ��Ă���͂��̐l�Ԃ����Ȃ�OL���ٗl�ɑ����Ƃ������Ƃ́A�\�ʓI�ɂ͐Ⓒ���ւ���{�o�ς̒�̐����̂̂悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ������B���]�[�g�n�ł̂�т�Ƌx�{���Ƃ�̂͗v�E�ɂ���j�̂��邱�Ƃł͂Ȃ��Ƃ����Љ�ʔO������A��������̐l�Ԃ����������]�ɂ��y���߂�悤�ɂȂ�Ȃ���A���{�l�̐������^�̈Ӗ��ŖL���ɂȂ����Ƃ͌����Ȃ��Ɗ������킯�ł���B�����A�����ɂ͂����Ȃ�O�Ƀo�u���o�ς͕��Ă��܂����B�ǂ�������^���ɂ������̂ł���A�����̊�Ɛ�m�����͂��������]�ɂ��Ƃ��Đl�����G���W���C���ׂ��������낤�B���̍��Ȃ�A�{�l�̑I������ŏ\�����̂��Ƃ��\�������͂�������c�c�B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
1999�N6��23��
���鉫��̑z���o�i�V�j
����͉���ŗL�̕�������
�@�����͒��H�����܂������ƁA�z�e����p�̃r�[�`�ɏo�Ĉ�j�������B�����̎X�荻���Y�킾���A�G�������h�O���[���̊C�̐F���Ȃ��Ȃ��̂��̂������B�����A���ɂ͂��܂ЂƂ�����Ȃ������B�O��͋C�����Ȃ��������A���̃r�[�`�͑�ʂ̎X�荻���^��ł��Đl�H�I�ɑ��������̂ł��邱�Ƃ͖��炩�ŁA�C��̍\�����P���Ȃ����ɊC���ɐ����̉e���قƂ�nj�������Ȃ��̂��A���̂Ȃɂ��̏������B�C�ɉ������߂邩�͐l���ꂼ�ꂾ����A�����̍��Ɛ������Ȑ��̂���߂����̃r�[�`���f�G���Ǝv���l���������Ƃ��낤�B����͂���Ō��\�Ȃ��Ƃł���A���l������ɑ��Ă��ꂱ�ꌾ���؍����̂��̂ł͂Ȃ��������A�Ƃ������A��Ȉ炿�̎��̊����ɂ͂��܂ЂƂt�B�b�g���Ȃ������B
�@�z�e���E�T���}���[�i���`�F�b�N�A�E�g�������́A�ܔ����������܂����ǖk�サ�A���������ɂ��鉶�[�C�݊C��������K�˂Ă݂��B�����̂����̔��蕨�͖��̉��ꎵ�Z���[�g���قǂ̂Ƃ���ɂ���C���W�]���ŁA���Z����̊K�i���~���ƁA�����W�]���̑�����C��̗l�q�����߂���悤�ɂȂ��Ă����B�X��̗тƒ��̓����ɔ����Ă��߂������C���A�����Ă����̊Ԃ��j���܂��F�Ƃ�ǂ�̔M�ы��̌Q��Ƃ���Ȃ�Ɍ��������͂������B�����g�͎q���̍�����C�ɐ����Ă����������i�����x�ƂȂ����Ă����̂łƂ��ɋ����͂��Ȃ��������A�����قƂ͈ꖡ�Ⴄ���R�܂����̌��i�ŁA�W�]���ɋ߂Â����ނ����̂Ƃ��ǂ��ňقȂ邩��A�s��炿�̐l�Ȃǂɂ͂ƂĂ��V�N�Ɋ�����ꂽ���Ƃ��낤�B
�@���������C�������ɂ������ł�����Ǝv���Ċό��p�O���X�{�[�g�ɏ���т̊C�̒����̂����Ă݂����A�Q������X�肻�̂��̂͊F���U��Ȃ��̂��肾�����B�ߔN�̏͂킩��Ȃ����A��������������ł����Ă͂����萔�i�傫�ȃe�[�u����X��̌Q�������邱�Ƃ��ł����B�����Ƃ��A���Ԗ�������{�Ó��A���\���Ȃǂɍs���Θb�͂܂���������Ƃ��낤�B
�@���̊C�������ɂ��Ă��܂�����Ɏ��̋L���ɏĂ��t���Ă���̂́A����Ƃ͕ʂ̌��i�������B������D�����O���X�{�[�g���w��ɂ͂��Ȃ�̐��َ̉q�p�����R�ς݂��Ă������B�{�[�g�ɏ�����Ƃ�����A�����͂����������̂��߂Ɏg���̂��낤�Ǝv���Ă͂������A���܂ЂƂs���Ƃ͂��Ȃ������B����n�_�ɂ���Ă����Ƃ��A�{�[�g�̑ǂ��Ƃ��Ă����D���������܂ޓ���̎O�l�̋q�Ɍ������āu���̃p�����������ĊC�ʂɓ����Ă݂Ă��������v�Ɛ����������B
�@��u�����Ƃ��낤�Ǝv�������A���̒���ɋN���������ԂɎ��͂������ɂƂ��Č��t���������B�{�[�g�̎��ӂ̊C�ʂɂ܂��ꂽ�p����ڎw���āA�召�����̋����E�����Ă�������ł���B�o�`���o�`���Ɛ��������ĂĒ��ˉ�鋛�Ń{�[�g�̎���͖��ߐs�����ꂽ�B
�@�r�̌�Ȃ�Ƃ������A�C���ɐ��ޓV�R�����p����Ɍ������ċQ�����s���j�A�̂��Ƃ��ɌQ������i�́A�Ȃ�Ƃ��Ռ��I�Ȃ��̂������B�ׂɋ����p����H�ׂĈ����Ƃ������Ƃ͂Ȃ����A�ǂ��݂Ă��A���̌��i�́A�����ߋ��Ɍ����ꂽ�C�̋��̐��ԂƂ͂܂�ňَ��̂��̂������B�����ďq�ׂ�A�A�����J�I�Ƃł������ׂ��������낤���c�c�B
�@�ڂ̑O�ŋN�����Ă��邱�Ƃ��P���Ƃ������Ƃ������C�͂܂������Ȃ������B�������t�ɋ������̂́A����ȋ������̎p�ɐ��̉���̒u����Ă�����d�ˌ�������ł���B�I�풼�ォ�猻��Ɏ���܂ŁA����ł͖{�y�̓��{�l�̑z�����͂邩�ɒ����镶���̗Z�����N�����Ă����B�×��A����́A����Ǝ��̕����ƁA�嗤�����Ⓦ��A�W�A��������ɂ͓��{�{�y�̕����Ƃ̗Z���_�ł������B�����A�I���ɂ��̒n�ŋN��������A�̕����Z���̗���́A�Z���̋K�͂̑傫���ƗZ���̂��ƂƂȂ����e�X�̕����̑��ΓI�ȈႢ�̒��x�ɂ����āA�ߋ��̗��j�̏펯���͂邩�ɒ�������̂ł������̂��B����̌�����m�肷��ɂ���ے肷��ɂ���A��X�{�y�̐l�Ԃ��Ȃ̕�������U�肩�����Čy�X�����]�X�ł���悤�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��ƁA���Â��v�킴��Ȃ������B���̏ے��I�Ȍ��i��ڂ̂�����ɂ��Ȃ���A����͂��܂��̒n�ŕ�炷�l�X�̑��ӂ̌������Ƃ���ɐi��ōs�������Ȃ��ƁA�S�ꎄ�͊������̂������B
�@������A�C�������̂��邱�̕���������т����N�J�×\��̉���T�~�b�g�̃��C�����ɑI�ꂽ�B���ꌧ���ǂƖ���s�����S�ɂȂ��āA���݊֘A�{�݂̌��݂���ӊ��̊J�������������Ȃ��Ă���Ƃ��낾���������A�t�߂̏͂���Ɉ�ς��邱�Ƃ��낤�B�e���̎�]����������ɂǂ̂悤�Ȉ�ۂ������Ă��邩�͒m��悵���Ȃ����A���邭�ߑ�I�ɐ������ꂽ���]�[�g�n�Ƃ��Ă̈�ʂ���łȂ��A�l�ގj�ɂ����Ă��܂�ȁA�d�����������j��w������������ʂ̉���̎p���\���ɒm���������ŃT�~�b�g��c�ɗՂ�łق������̂ł���B������̃T�~�b�g��c�Ő��E�̏d�匜�Ă����������قNJÂ����̂ł͂Ȃ����Ƃ͑������m�����A����̂��̖��̈�p�ɂ����āA����ɂ��ꂽ���̐��̖����̎��ʂ��ق��������ł�������A����͂���Ŋ�������Ƃł���B
�@�����A����ŃT�~�b�g��c���J����悤�ɂ��Ă�������A����ɂ���Ĉꎞ�I�Ɍo�ό��ʂ�����̂�����A���̑㏞�Ƃ��ĕČR��n�̑����ɂ͉���̏Z��������Ȃ�̋��͂����ׂ����ȂǂƂ����{���]�|�����l����������c���Ȃǂ�����Ƃ���A�s�������͂Ȃ͂������B�{�y�̐����Ƃ���E�̗v�l�ɂ́A���̉���o�ς͕ČR��n���Ȃ������Ă���Ȃ������Ȃǂƕ��C�Ŏ咣����l�����Ȃ��Ȃ����A����͑�ό������ʓI�Ȍ����ł���B
�@�I���܂��Ȃ��ČR�̌R�����ɂ�����A�ɓ����瓌��A�W�A��тɂ����Ă̐헪��n�Ƃ��ďd�v�������悤�ɂȂ����Ƃ�������ȗ��j�̂䂦�ɁA����o�ς��ČR��n�Ȃ�тɂ��̊W�{�݂̑����ێ��Ɩ��ڂȊW�����悤�ɂȂ������Ƃ͎����ł���B����{���̎s�����̂Ȃ��ɂ́A�o�ϓI���R�̂䂦�ɕČR��n�W�̗U�v�ɐϋɓI�ȂƂ�������Ȃ��Ȃ��B�����������s�����̌����I�ȍ������Z���̐������l����Ƃ��A�����̎����̂���n�W�{�݂̑�����U�v�ɍm��I�ł��邱�Ƃ�ӂ߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A��c���G�O����m������̑I���Ŕs�ꂽ�̂����̂�����̖��ւ̑Ώ��̓�������������炾�낤�B
�@�������A���Ƃ�����Ɍ��݂̂悤�ȕČR��n�����݂��Ȃ������Ƃ��Ă��A����͉���Ƃ��đ������A���̍r�p���痧���オ���Ă���Ȃ�̔��W�𐋂��Ă����ɈႢ�Ȃ��B�̂��牫��ɂ͎Y�Ƃ炵�����̂����܂�Ȃ���������A�ČR��n�����ł͐��̉���o�ς͐��藧���Ȃ��������낤�ȂǂƁA�{�y�̐l�Ԃ���m���Ō�����肷��̂́A����̗��j�����ɑ��閳�m�Ɩ`���ȊO�̂Ȃɂ��̂ł��Ȃ��B���E�̂ǂ�ȂɊ��̌������Ƃ���ł��A�ǂ�Ȃɕn�����Ƃ���ł������ɏZ�ސl�X�͓Ǝ��̕����Ɨ��j��z���Ȃ��炽���܂������������Ă����B���ꂪ�l�ގj�̏펯�ł���B
�@�܂��ĉ���́A�×��A��C���Ղ̗v�ՂƂ��āA�т����܂��܂ȋ��ɖʂ��Ȃ�����L���Ȕɉh�𑱂��Ă����Ƃ���ł���B���������A����̕����ƕx�Ƃ����D���A������̉ʂĂɂ�����j�s�������̂͂��������N�������Ƃ����̂��낤�B�܂��A���ɍďo���������{�{�y�̒n�������̂̂����A���������o�ς��c�ނ��Ƃ��ł����Ƃ��낪�ǂꂾ���������Ƃ����̂��낤�B
�@���������̊C�����������Ƃɂ������́A�ܔ��������������ɉÎ�[���[�^���[�܂œ쉺���A�Î�[��n�̖k�����ē��C�ݑ��̋�u��s�Ɍ��������H�ɓ������B�r���܂ł͉���ɂ���Ă��������Ɉ�x�ʂ������ł���B��n�e���߂����炭�s���Ɖ���s�m�Ԃɂ��铌��A�����̋߂��ɏo���B�ǂ����悤���ȂƎv�������A���������̂��ƂȂ̂ŁA�Ƃ肠������������Ă݂邱�Ƃɂ����B���ꐏ��̋K�͂��ւ邱�̐A�����ɂ́A�������M�ѐA���∟�M�ѐA���������̂�����Ƃ���ɐ������Ă������A�\�N�ȏソ�������܂ƂȂ��ẮA���q�̖��₽��ɐ����Ă����Ȃ��Ƃ������炢�̋L�������c���Ă��Ȃ��B
�@�����A�����̔��X�ň����q�̎��̃W���[�X�̖������͂��܂��͂�����Ɖ����Ă���B���q�̎����܂邲�ƈ�����A�Ȃ��قǂ̊j���̊k��������܂ő@�ێ��̌�����Ɣ������A�܂邢�k�̈ꕔ��؏����Ă�������B�����āA�X�g���[�������Ē��̃W���[�X�����B�����m�̕��������Ǝv�����A�����������̞��q�̎��̃W���[�X�́A�F�������s�̂̃X�|�[�c�h�����N�̃|�J���X�G�b�g�ɂ悭���Ă���B�W���[�X�̗ʂ́A���q�̎���ŊʃW���[�X����قǂ͂������B������������A�|�J���X�G�b�g�̔��Ď҂́A���q�̎��̃W���[�X���q���g�ɂ��Ă��̐��������������肾�����̂�������Ȃ��B�k�̓����ɔ����w���Ȃ��Ă��Ă��锒�����������H�ׂ���Ƃ����̂ŁA���X�̐l�̂����߂ɏ]�������������Ď��H���Ă݂����A���\�����閡�������B
�@����A�����̂��鉫��s����ׂ̋�u��s�ɂ����Ă̊X�H��X���݂́A���ӂɌ������Ԃ��ׂĂ̖��Ƃ��ӂ��߂ĂȂɂ��������A�����J�I�������B���̋����قǂ̃A�����J���̗��R�́A�����ČR�W�҂₻�̉Ƒ����������̈�тɏZ�ݒ����Ă��邱�Ƃ����邪�A������ɂ߂������ɂ����āA�����×��̕����𗯂߂Ă����암�̎�v�W���͓O��I�ɔj�s������A�D���ɋA���Ă��܂����Ƃɂ����̂��낤�B���A�ČR�̎哱�ɂ���Đ������̕��������̍s��ꂽ����암���×��̕����̉e���قƂ�Ǒr�����Ă��܂����̂́A���̎��_�Ŏc���ׂ����̂��قƂ�ǎ����Ă��܂��Ă�������ɈႢ�Ȃ��B
�@��u��s�������́A�����m�Ɍ������ē쓌�ɑ傫���˂��o�����A������ڎw�����Ƃɂ����B���̔����̖k���͗^�ߏ鑺�i��Ȃ������ނ�j�A�쑤�͏��A���ɂȂ��Ă���B���̔����̋ߕӂɂ̓z���C�g�r�[�`�Ȃǂ��͂��߂Ƃ���ČR��p�̃r�[�`�������B�����̂قڒ������т����H�����炭����k���̊C�ݐ��ɏo���Ƃ��낪�^�ߏ鑺�̉��c���`�������B�`�̔w��̓W�]��ɂ�����Ƃ��炵���i�ς��]�܂ꂽ�B��O�ɂ��M�n���A���̂ނ����ɂ͕l��Ó��A����ɁA�C�ʂ��ɐ蕪���Ă͂邩�ɂ̂т�C�����H�̐�����ǂ�ƁA���������A�{�铇�A�Ɍv���̓��e��������Ō������B���A�����ɂقƂ�ǐڂ��銴�����M�n���͂��̖��Ƃ͗����ɂȂ��Ȃ��������������܂��̓����������A�n���̐l�̘b�ɂ��ƃn�u���������ƂŗL�����Ƃ̂��Ƃ������B
�@���c���ƕ��������̊Ԃ̐߂��Ăđ������l���Z�Z���[�g���̊C�����H�́A���ۂɑ����Ă݂�ƁA�Ȃ�Ƃ����K�ȃh���C�u�R�[�X�������B���Ƃ��Ƃ��̓��H�͐Ζ��R���r�i�[�g�ƐΖ����~��n�̂��镽�������Ɖ���{���Ƃ��Ȃ����߂ɐ݂���ꂽ���̂����������A���łɊό����H�Ƃ��Ă�����Ă��銴���������B����̒n�}�����邩����ł͕��������Ƌ{�铇�Ƃ͈�̓��ɂȂ��Ă���B�����͂��߂́A��̓��ɓ�̖��O�����Ă���Ȃ�ĉ����̊ԈႢ�ł͂Ȃ����Ǝv�������A�����m���Ĕ[�������B���Ă͕ʁX�̓��������̂����������A�Ζ���n���g�傷��ߒ��œ�̓��̊Ԃ����S�ɖ��߂��Ă��Ĉ�̉����A�n�}�ł͌��������Ȃ��Ȃ����炵���B
�@�i�ς̂悳�����Q���������A�C�����H�𑖂�͂��߂Ă����ɋC�ɂȂ����̂́A�x�i���o�[�̎Ԃ����|�I�ɑ������Ƃ������B��u���́A����ĕČR��p�̒n��ɕ��ꍞ��ł��܂����̂ł͂Ȃ����ƍ��o���������قǂł���B�قƂ�ǂ̂x�i���o�[�Ԃɂ͒j���̃J�b�v��������Ă��āA�O���l�j���ƌ��n�̎Ⴂ�����Ƃ����g�ݍ��킹���唼���߂Ă���悤�Ɏv��ꂽ�B���Ԃ�ČR�R�������̂�����Ƃ����f�C�g�R�[�X�ɂł��Ȃ��Ă���̂��낤�B
�@����̋����p�z���ɉ���{�����C�ݐ������]���Ȃ���{�铇�̓˒[�܂ő���A�����C���ɉ˂��鋴��n��ƁA��������Ԃ͂���̈Ɍv���������B���̓쑤�ɂ͏��W���������āA�߂��̍`�ɂ̓A�[�P�[�h�̂悤�Ȋ�₪�����Ă����B���̐����̂ق��ɂ܂��Ɣ������r�[�`�����ꂽ���A�������m��l���m��Ɍv�r�[�`�������B���̓r�[�`�����Ɍ��Ȃ���s����Ƃ���܂ōs���A�����ŎԂ𒓂߂�ƁA�������P���C�߂Ȃ���x�e���Ƃ����B
�@�������тɂ͖{�������̍��A�m�隬�Ŏ��ɂ����̂Ɠ�����̐��������Ă����B�ǂ�Ȏp�`�����Ă���̂��낤�Ǝv���Ė����̂�����̎}�𒍈Ӑ[���ώ@���Ă݂�ƁA�H�������œ��������F�������A�c�N�c�N�{�E�V���{�ɂ����قǂ̐䂪���������B��͂�{�y�ł͌������Ƃ̂Ȃ��䂾�����B
�@�Ɍv������ĂъC�����H��ʂ��ď��A�����ɖ߂�ƁA����p�����̓��𑖂��Ē��鑺�i�Ȃ��������ނ�j���ʂ������ē쉺�����B�����āA����隬�ɗ���������B�\�ܐ��I�̒����Ɍ��Ă�ꂽ�R�邾�Ƃ������A�s��ȏ�ǂ����܂��قƂ�lj����̂܂܂Ŏc���Ă���A���̒z��Z�p�͍����]������Ă���B�B�`�����Ă���Ƃ���ɂ��ƁA���̃y���[������ė�����K�ꂽ�Ƃ��A���̏�ǂ����Ă��̌��z�Z�p�̍������^�����炵���B�y���[�͂��̏�̒z��Z�p���t�����X�����Ƃ݂Ȃ����̂����������A���ۂɂȂ�炩�̂������Ńt�����X�̒z��v�z�̉e�������������̂Ȃ̂��A����Ƃ����܂����ʂ������̂ɂȂ����̂��́A�f�l�̎��ɂ͔��f�����Ȃ������B�����A����A�W�A���ʂ���ٍ��l������Ă��Ēz��Z�p�ɉe����^�����Ƃ������Ƃ́A�܂������l�����Ȃ��b�ł͂Ȃ��B
�@��̓��쑤�͍������\���[�g���̐�ǂɂȂ��Ă��āA�X�ƒ��̂��˂钆��p���ቺ�����ς��ɍL�����Ă����B���̏�͎����̒��b�썲�ۂ̋��邾�����Ƃ������A�ނ͐��G�ŏ��A���ł������������a���̓i�݂��A����槌��ɂ���Ėd���̍߂�������ꂽ�B���߂�s��������N�̏��v���ɋ^����͖̂��O�ƁA�썲�ۂ͈ꑰ�Y�}�ƂƂ��Ɏ��Q���ĉʂĂ��Ƃ����B���������āA���̏�͔ߌ��̏�̈���ƌ����Ă悢�B�̂��ɂȂ��āA�d������Ă��̂�槌������������a���̂ق��ł��������Ƃ����o�A����̖��ɏ��A�R�͔s��A�����a���͎h�E���ꂽ�B���̎j�b�͉���ŋ��ɂ���������A�ȗ��A�n���ł͂����Ƃ��l�C�̂��鉉��ɂȂ��Ă����̂������ł���B
�@����隬�����Ƃɂ��邱��ɂ͓�����ꂩ�����Ă��Ă������A���łȂ̂ő�}���ō��̏d�v�����������Ƃ�K�˂Ă݂��B�����Ƃ͓�S�N�ȏ�̗��j��������ŌÂ̖��ƂŁA�K���ɂ���ɂ��Ď����܂ʂ��ꂽ�B�w��ɖ������̂Ђ�Ԃ�i�̏��l�̂��́j��������������ē������~�n���ɂ́A�Ԋ������̕ꉮ�̂ق��A�A�V���M�A���q�A�؎ɂȂǁA�ܓ��قǂ̌������z����Ă����B���ʂ̕ꉮ�̉E��ɂ���A�V���M�ɂ͓�j��O�j����������܂ŏZ�ޕ���������A�܂��A���̈ꕔ�͋q�ԂƂ��Ďg���邱�Ƃ��������炵���B�ꉮ�̍���ɂ���͍̂��q�ƌĂ��傫�ȑq�ɂŁA�l�Y�~�␅�Q�Ȃǂɂ���Q��h�����߂ɏ��ʂ��������Ŏx��������Ɠ��̍\���ɂȂ��Ă����B
�@�����Ƃ̌����S�̂̌��z��ނ͖؎����d���ϋv���̂���C�k�}�L�ŁA�����{�̂͂����Ԃ�ƌÂ����A���݂̐Ԋ������̉��������͖����ȍ~�̂��̂ł���炵�������B�����Ƃ͑��������߂����_�̉ƕ����������A�m���ł͂Ȃ��������߂ɁA�����ɂȂ�܂ł͊������̉����̉ƂɏZ�ނ��Ƃ͋�����Ă��Ȃ��������炾�Ƃ����B�[���̂��������������A�����Ƃ̎��ӂɂ͊e��̎����ɂ��Ă��āA���ɐÂ��ŗ��������������������B
�@�����Ƃ̒�ł͂��܂��܉���`���|�\�̈�u�ԕ��i�͂Ȃӂ��j�v�̕��̃e���r�B�e���s���Ă���Ƃ��낾�����B�B�e�W�҂̂ق��ɂ͎��������Ȃ������̂��悢���ƂɁA���ɂ̎v����[����߂����₩�ȃe���|�̂��̗x��Ɍ�����Ă���ƁA�Ȃ�Ƃ������Ȃ��C�i��X���������ߑ��p�̕��x�Ƃ̕����B�e�̍��ԂɎ����̂ق�����߂Â��Ă��āA�ԕ��̕��ɂ��ĊȒP�Ȑ��������Ă��ꂽ�B
�@���̉ԕ��́A�̗V����������l�Ƃ̕ʂ�ɍۂ��āA�i���̋F��Ɛ[���ɕʂ̏�����ߖ����ɕ��������̂��Ƃ����B�V���͈�����l���������čs���̂�\�����Č����邱�Ƃ�������Ȃ������̂ŁA�ʂ��O�ɂ��̓��ʂȕ����I���A����ɂ����Ǝ����̈����݂�`�����̂������B���ݓ`������Ă���ԕ��́A���������̗x��������A�����̏��߂ɂ��܂̂������Ɋ������ꂽ�Ƃ̂��Ƃ������B�����̌��t����ɔ�߁A���ɓ����肵�����P�̗h��Ɏv�����������ԕ��̕��ɁA����Y��Ď��͂��܂ł��������Ă����B����ȕ��Ō�����ꂽ�ł��낤�̓��̉���l���A���S�őA�܂����v���Ă������Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B
�@����̒����Ƃ����Ƃɂ��邱��ɂ͖�̒��i�Ƃ�j����т��͂��߂Ă����B���̓A�N�Z�������悤�ɓ��ݍ��݂Ȃ���^�ߌ����܂œ쉺����ƁA��������ߔe�x�O�̎ɒʂ��铹�H�ɓ���A��Ղ̋߂��̉���O�����h�L���b�X���z�e���Ɍߌ㎵�����`�F�b�N�C�������B�u�̏�ɂ��鍂�w�̃z�e���̑�����́A�ߔe�s�̒��S�X���ʂ̖�i����]���邱�Ƃ��ł����B
�@�z�e���̎����ňꕞ�������ƁA���͓ߔe�̔ɉ؊X���ےʂ�ɏo�Ď��ӂ��U��A�ɐ��G�r�ƃX�e�[�L�����킹������������H�ׂ����Ă���郌�X�g������������Ƃ������ɓ������B�������������͊ŔɋU��Ȃ��ƂĂ������ŁA�������{�y�Ɋr�ׂĂ͂邩�Ɉ��������������B�܂��A���܂��ܐH�����ɗׂ荇�킹�ɂȂ����n���̎Ⴂ�����́A���̉���K�₪���߂Ă��ƒm��ƁA�ߔe�s�X����͂��߂Ƃ��鉫��암�n��ɂ��Ă̏������낢��Ƌ����Ă��ꂽ�B�Ί�̑f�G�ȕ��ǂ���Ƃ������̏����̓{�[�C�t�����h�Ƒ҂����킹�����������A�ނ������܂ł̊ԁA��ނ����˂����̎���ɐe�g�ɂȂ��ē����Ă��ꂽ�B
�@�[�H�゠�Ăǂ��Ȃ��Ԃ������̍��ےʂ�́A���̖��ɒp������ςȓ��킢�Ԃ�ŁA�O���l�̎p�������Ԃ�ƌ�������ꂽ�B�����āA�ߔe�s�̐l�����炷��ƕs�ނ荇�Ȃ��炢�ɁA�t�߂̂��X��s��͑�K�͂Ȃ��̂������A���i�����ېF�L���������B�{�y�Ƃ͈���āA�ē��̊Ŕ����{��̂ق��p��A������A�؍���Ǝl�J����ŕ\�L����Ă���A�܂��ɍ��ۓs�s�ߔe�̖ʖږ��@�Ƃ����Ƃ��낾�����B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
1999�N6��30��
���鉫��̑z���o�i�W�j
�隬���̖�ɗ���
�@�����́A�z�e�����o��Ƃ����Ɏ隬�𒆐S�Ƃ���u�ˈ�т�����Ă݂��B��K�˂�ό��q�̒N��������悤�ɁA�����܂��A�܂������ɁA���ɂ����̗��������̏ے��u���̖�v�̑O�ɘȂB�Ԋ�������Ōł߂���w�̉��������u���̖�v�́A���������Ō�̉����A�����ɂ���Ďl�Z�Z�N�قǑO�Ɍ������ꂽ�B����Ɠ��̌��z�l�������Ȃ����{���̖�͖�������ɍ���Ɏw�肳��A���O�܂ł��̗̈e���ւ��Ă������A��̉����Ő�ɂ��炳��Ď������B���݂̎��̖�́A�����Ȃɕۊǂ���Ă����Â��v�}�����ƂɁA���a�O�\�O�N�ɕ������ꂽ���̂ł���B
�@�u���̖M�v�Ƒ发���ꂽ�z����̒����ɍ��X�ƌf�����Ă���̂�ڂɂ��Ȃ���A���͂Ȃ�Ƃ����z���ɂƂ���Ă����B�����̍Œ��ɁA�Ȃɂ��������d�����������䂩��̂��̒n�ł��ċN�������o�����́A���܂�ɂ��u���v�̋����Ƃ͂������ꂽ�؍s���s���̂��̂���������ł���B���Ȃ��u����ꂢ�v�ł��A�u��߁v�A���Ȃ킿�A�u�R�����߂�ӖړI�Ɏ�邱�Ɓv���ŗD�悳�ꂽ���ʁA�I�풼�O�A���̒n�ɂ͕����ʂ舢�@�����̈�吶���n�����o�������B
�@���݂ł͎���������J����Ă���悤�����A�����͂܂��A���̖�̂ق��ɂ͎�̐��傾���������Ƒ�l��̋v�c�傪��������Ă�����x�������B���͂����̖���ЂƂ߂��肵�Ă���A������𐼂ɉ����āA���~�������̕�ˁA�ʗ˂̑O�ɏo���B�ʗ˂͗������������̑c�ƌ����A�����W�����m�����邢���ۂ��A�C�O�f�Ղł��L������y�������N���^�����A��܁Z��N�A�������~���̈⍜����������ɂ������Č���������Ƃ̕�˂ł���B�����[�g���ɂ��y�ԗ����ΊD��̐Ί_�ň͂܂ꂽ�A�L����l�Z�Z�������[�g���ɂ��y�Ԃ��̑s��ȕ���́A�C�m�����Ƃ��Ď��R�z���ɓ�C���ՂɊ��Ă��������̉���l�̖L�����ƁA���z�Z�p�̍����Ƃ��Â����B
�@���S�ȐΑ���̉Ƃ�z�킹��O��̕掺�̒����ɂ͐O�̈�[�����u���A�����̕掺�ɂ͍����Ɖ��܁A�E���̕掺�ɂ͉��q�y�щ����̈⍜��[�߂邵������ɂȂ��Ă����Ƃ����B�����w�҂̖��@�x���A�u���������ő�̕�˂ł���Ƃ����݂̂Ȃ炸�A���̗H�����ɂ����ĕC�G��������̂͐��E�ɂ����Ă��H�ł��낤�v�Ƃ܂ŏ^�������̋ʗ˂������̍ۂɂ͖җ�ȖC�ɂ��炳��A�傫�ȑ����������B�K���Ȃ��ƂɁA���̌�A�����C����Ƃ��i�݁A�ߔN�ł͂قڌ��^�����߂�����悤���B
�@�隬�̂��邱�̋u�ˈ�тɂ��đ����Ă����Ós�́A���s�A�ޗǂɎ����������̕�ɂ������B��ɕ�܂��O�̎���O�ɂ́A����Ɏw�肳�ꂽ�����������ł���\�����݂��A�d�v�������ɂ������Ă͂��̐����m��ʂقǂł������Ƃ����B�ČR�̐i�U�ɔ������������R�̎�͕����́A��{�c�̈ӌ��������A�ČR��͂��ꍏ�ł���������ɂƂǂߋɗ͒�R��}��ׂ��A�u�˂Ȃ�тɂ���ɘA�Ȃ�u�˒n�тɕz�w�����B�k���������낷�헪��̗v�����Ȃ��Ŗh�����A�g�[�`�J�i�n�����j���@��߂��炵�āA�ǒJ�����ʂɖ����㗤�����ČR���쉺����̂��}�����헪���Ƃ����̂ł���B
�@���������������鉫�����R�i�ߕ��̂����ꂽ�u�ˎ��ӂ́A���R���̖h����̍Œ������Ɉʒu���Ă����B�������R��͕����́A�c��ȗʂ̍�������d�v�������Q��n��̏��Ƃ��A�z�w���Ă����悤�Ȃ��̂ŁA�Ȃ��ł�����R�i�ߕ��Ȃǂ́A��̒n���̍��[���ɒu����Ă����B�܂�������R�g�[�`�J�̏㕔�₻�̋ߕӂɋM�d�ȕ�����Y�Q������ΕČR�͍U�����T���邾�낤�Ȃǂƍl�����킯�ł��Ȃ����낤���A�Ƃ������A���̌}���헪�͉���̗��j�ƕ����ɕs�K����܂�Ȃ��Ж�������炵���B
�@���s��ޗǁA���q�Ȃǂ���P��Ƃꂽ�̂́A�����̒n��̕������̏d�v�����n�m�������Ă̌����҂�ČR�W�҂����Ȃ肢�āA�ނ炪�����ɂ��̕ی���R��w���ɓ������������ʂł������B�ČR���̋L�^�ɂ��ƁA�ČR������ʎi�ߕ��W�҂ɂ��A�Ós�𒆐S�Ƃ�����т̕�����Y�̋M�d����m��A���̔j��ƏĎ��ɐS��ɂ߂��l���͂���Ȃ�ɂ������悤�ł���B�����A�������R�̂Ƃ����u�˂ɂ�������g�[�`�J���́A����͂��߂Ƃ��镶����Y�̋~�ς�����I�ɕs�\�ɂ��Ă��܂����B
�@�����̒��ł����Ď�͕��������ʂ��猃�˂����U�h��͉������߁A������̏��s�����߂�킢�ƂȂ����B�����āA����ɔ����A�c��Ȑ��̐l�������ƋM�d�ȕ������̔j�N�������̂������B���̔j��ƎE�C�̐��܂����́A��Z�Z��N�̎F���ɂ�问���N���ȂǂƂ͊r�ׂ��̂ɂȂ�Ȃ��K�͂̂��̂������B���ė��R�̐퓬������̂���݂ɒB�����Ƃ��A����ӂ̎�w�n�ɑ��ẮA�l�Z���ԂɈꖜ��Z�Z�Z�����̑�^�C�e���������܂ꂽ�B�U�h��S�̂�ʂ��Ă݂�ƁA�s�X����ӂ̎R��ł͈ꕽ�����[�g��������l�A�ܔ��̖C�e���y�����ƂɂȂ�B
�@����Ȃ��ƂɁA���̎��̕ČR���\�l�R�c�C���w�����́A��N�A���R�������Ƃ��Ēm����悤�ɂȂ����A�W���Z�t�E�V�[�c�����ł������B���R�������Ƃ��ĉ���ɕ��C����ƁA���炪�j�����������̎�ōČ���������̂��Ɛ錾���A�n���Z���̂��߂ɗ͂̂������s�������Ƃ����B�ނ̌R���������C�ɍۂ��ẮA����̐l�X�����C�^�����N�������قǂł������炵���B�L�\�ȐE�ƌR�l�Ƃ��Ă̖C���w���̔C���ƁA��̐l�ԂƂ��Ă̐l�ނ̗��j�����ɑ���،h�̔O�Ƃ̂͂��܂ɂ����āA�����炭���̐l�����A�풆���̎����ʂ��A�[�����ʂ̋ꂵ�݂𖡂���Ă����ɈႢ�Ȃ��B
�@���l�ܔN�l����\���O��Ɏn�܂����U�h�킪�܌���\����̉������R�̓암�P�ނɂ���ďI�����������Ƃ��A�u�˂͂�����Ƃ���ŕό`���������A�������Ós�́A�c��ȕ�����Y�Ƃ��ǂ��A���X�ɂ�����܂Ŗ��c�Ȋ��I�̎R�Ɖ����Ă����B�u���ꂪ����킾�v�i��c���G���A�����V��Њ��j�̒��ɁA�j��钼�O�ɕČR���ʂ�������ӂ̍q��ʐ^�Ɣj��s����������̓���̎ʐ^���f�ڂ���Ă��邪�A����炪�ق�Ƃ��ɓ����ꏊ���ʂ������̂��Ɖ䂪�ڂ��^������ł���B
�@���{�×��̓`���ƕ��������Ə̂��Ȃ���A���͎��ׂ����{�̓`���╶���ɂ��čł������ł������l�X�ɂ���ē����ꂽ�푈�́A����͓��R�̋A���ł������B�܂��A����͍��̌쎝�Ƃ�����a�Ȃ���ڂ͒m���Ă��Ă��A���{�����̖{���Ƃ��̐^�̏d�v������̓I�ɂ͂قƂ�NJw�Ԃ��Ƃ����Ă��Ȃ������A��X���g�̕����c������܂ޓ��{������l�ЂƂ�̋������̏I���_�ł��������B���₻�̐��͈̂ꎞ�I�ɖłтĂ��A�����₻�̖{���I�ȕ����͖��X�Ƒ��Â��Ȃ��炦����̂ł���A�܂��A�����ł���ׂ����Ƃ����u���E�̗��j�̏펯�v����{�l�͂܂������w��ł͂��Ȃ������̂��B������������������Ȃ�A���̊ۂ��ނ�݂₽��ɐU����Ƃ����j���ƍ��o���Ă��������̂��Ƃł���B
�@�ʗ˂����w���I�������́A���̂��Ɖ��ꌧ�������ق�K�˂Ă݂��B���̔����ق����݂̂������ɂȂ�܂łɂ́A���܂��܂����]�Ȑ܂��������悤�ł���B�I�풼��̂��ƁA����̕������̂��炵����m�����ČR�̃n���i�����Ɣނ̒��Ԃ̌R���́A���I�̎R���@��N�����A�������̒f�Ђ����W�����B�����āA�����̎��W�i�����[���ɑ����������فi�̂��ɓ����[�����قƉ��́j�ɓW�������B�����ۂ��A�ɏZ�ވꕔ�̒n���L�u������̎�ŕ������̔j�Ђ��E���W�߁A���������Ƃɉ��ꋽ�y�����فi�̂��Ɏ����قƉ��́j���J�݂����B�����āA���O�N�ɂ����̓�̎{�݂��������ė������{�������قƂȂ�A���Z�ܔN�ɏ����Ɖ��~�Ղ��w���A�č���艇�����Ă��̒n�ɐV�ق����Ă�ꂽ�B
�@���̊ԁA�����قƂ��đS���I�ɗ����֘A�������̎��W�^����W�J�A�č����{��č��ݏZ�̉���W�҂ɂ����͂��Ăт����A�헐�̍Œ��ɖłђׂ����������ɂ݂������������̖ʉe���A�ꕔ���ł͂��邪���낤���đh�点�邱�Ƃɐ��������B��㎵��N�̉�����{���A�ɔ����A���̂����ꌧ�������قƉ��̂���A���݂ł͎����i���_����悤�ɂȂ��Ă��邪�A���̑b�͕�����[�������鉫��Z����S����ČR�L�u�����̐s�͂ɂ���Ēz���ꂽ���̂ł������̂��B
�@�����ق̓W�����́A���j�A���R�A���p�H�|�A�����̎l���ƁA���O�R���N�V�����R�[�i�[�̌v���ɕ�����Ă���A���ꂼ��̊p�x���牫��߂邱�Ƃɂ�肻�̂��悻�̑S�̑������ނ��Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă����B����ɁA���{�{�y�̓ꕶ�A�퐶�A�Õ�����Ȃǂɑ�������L�ˎ���A��i�O�X�N�j�����������ꍑ�Ƃ��`������Ă�������A��C���Ղ̋��_�Ƃ��Ĕ��W�������ƍ����W�����Ԃ悤�ɂȂ����Վ���A�F���̐A���n�ƂȂ��Ĉȍ~�̍]�ˊ��̎���A�����Ė������珺�a�ɂ����Ă̎���ƁA�e����̉��ꑜ������Ȃ�ɓW�]�ł���悤�ȍH�v������Ă����B
�@�܂��A�i�v�f�Ղ̗l�q�▾�Ƃ̍����W�A�F����]�˖��{�Ƃ̊W�Ȃǂ�`���鏔�����A�����̐l�X�̐������ÂԂ��Ƃ̂ł���e�햯��Ȃǂ̖�����Y�����Ȃ�̐��W������Ă����B�����́A��̒��Ŏ���ꂽ���̂Ɋr�ׂ�Α�C�̈�H�ɂ��������c�������ł͂��������A�u�S�̖\���v�Ƃ������t�������ʂ�̑z����₷��j��̗��̂��Ƃ��l����Ȃ�A���ꂾ���̂��̂��c���������ł���Ղł������Ƃ����ׂ����낤�B
�@�ČR�̌X�̐퓬�����ɔz������Ă����R���v�������́A�㗤�O�ɉ���Ɋւ���S�ʓI�ȏ���v��ԗ����������q��z�z����Ă����̂ŁA�{�����̏Z���̂����ꂽ�������ɂ��Ă͂��Ȃ�̗\���m���������Ă����B�����A�㗤��ɔނ�̖ڂɉf��������̎���́A�z�����Ă������������ƔߎS�Ȃ��̂ł������炵���B����ȉ���̎��Ԃ����|�[�g����Ȃ��ŁA�ނ�̂���҂́A�u�R�����̏Z���͒N�������|�ɂ��̂̂��Ă��邪�A�����ɂ͈�̕s�g�ȗ\�����͂�����ƌ��ĂƂ��B����͎Ⴂ�N����l�����Ȃ����Ƃ������B�����Ă܂��A�Ⴂ�������ُ�Ȃ܂łɐ������Ȃ����Ƃ������v�Ƃ��q�ׂĂ���B
�@�ČR��Z�t�c�̒ʖ�r�E�V���o�[�\�����тȂǂ́A�u�����������n���Z���́A�S���Z�Έȉ��������͘Z�\�Έȏゾ�����v�Ƃ������Ă���B�����̂��̂悤�ȕ𑍍��I�ɕ��͂��Ă����ߒ��ŁA�ČR�i�ߕ��́A�n���̎Ⴂ����̂��ׂĂ�����R�̎x���ɓ������ꂽ���Ƃɂ͂��߂ċC�Â����̂ł������B
�@����̉Ԃ������ė��Ƃ���邩�Ȃ�O����A���ƂȂ��тɂ́A���̐g���̂܂܂̎p�ł��Ăǂ��Ȃ������f������l���̒n���Z���������āA�ČR�R���v���̎�ɂ���Č���̏Z�����e���Ɏ��X�Ǝ��e����Ă������Ƃ����B�퓬�J�n�ɔ����ē��R���̐��͌��������B�����A�����ɂ������قǂɂЂǂ��h�{�����ɂ������Ă��Ă��A�ČR�Ɏ��e���ꂽ�l�X�͂܂��b�܂ꂽ�ق��������B���������ɕ��u���ꂽ�l�X��A��Ђ̒��Őe�Z����������c�������̑����́A�ČR�ɂ��甭������邱�ƂȂ����X�ɉ쎀������A���������肵�Ă������B���̂�����Ƃ���ŔߎS�ȗc�������̎p������ꂽ�Ƃ����L�^��ČR�͎c���Ă���B
�@���A�ʂƂ��Ɉ��|�I�ɏ���Ί�A�͑D�A�q��@��i����l���Z�Z�Z�l�̕ČR�c�ɑ�����Z�l�Z�Z�l�̉������R�̕��͂Ɣ����́A���Ƃ���l���Ă݂�Ƃ��܂�ɂ��n��ɉ߂����B�������A����R�i�ߕ��́A�J�퓖���͎��M���X�ł������炵���B���̂��Ƃ͔��������Q�d�̔����Ɋւ���L�^�i�u���ꂪ����킾�v�����p�j�ɂ�����������B
�@�u�G�͗\�z�ɔ����A�قƂ�lj䂪�R�̒�R���邱�ƂȂ��A���̂܂㗤���������邾�낤�B���܂�̈ՁX����㗤���A���Ă͓��{�R�̖h�q�̋����Ղ����̂ł͂Ȃ����Ƃ��芨�Ⴂ���ď���肵�Ċ��ł���̂ł͂Ȃ����B�ہA���C�������̂��܂�A���{�R�͉Î�[�����͂ލ��n�тɑނ��A�B��A�킴�ƃA�����J�R����������A㩂ɂ�����v��ł͂Ȃ����Ƌ^���A�������Ȃт�����̏�Ԃɂ��邩������ʁv
�@�u��\�R�i�ߊ��o�b�N�i�[���R���������͂̎l�t�c�́A�A�b�c���ȗ��J��Ԃ���Ă������{�R�̖��Γˌ���\�����Ă��邾�낤���A�R��̎���R��]�͂܂���������ȓˌ��Ԑ����Ƃ�C�z�������Ȃ��B����҂͒k���A�܂����̎҂͉������ӂ����Ȃ���I�X�ƑO���߂���Ă��邪�A����͉��̂��Ɣ��₵���ɈႢ�Ȃ��B���{�R�͐��������O����k���n�тɌ��w��~���ĕď㗤�R�������ɗU�����݁A��A����A���������錈�ӂł��̏����𐮂��҂��Ă������炾�v
�@�ČR�̋ߑ�I���ʐ헪�̐�����m��ʑ�{�c�����R�i�ߕ��̂����������Â����f�́A���ǁA�Ƃ�悪��̎��Ȗ����ɏI���A���̌��ʁA�����̉���Z�������ߎS�ȉ^���ɓ����Ă������ƂɂȂ�̂����A����͂܂��A���E�̐����Ƃ������̂������I���q�ϓI�Ɍ���ڂ������Ȃ������A�܂����Ƃ��Ƃ����Ȃ����������̓��{������l�ЂƂ�̐ӔC�ł��������̂�������Ȃ��B�ł͂ǂ�����悩�����Ƃ����b�ɂȂ�ƁA���ׂĂ͌��ʘ_�ɏI���Ă��܂��̂����A����̉�X���A���߂ĉ���̔ߎS�ȗ��j�ɉ������w�Ԃ��Ƃ��炢�̂��Ƃ͕K�v�ł��낤�B������A�P�Ȃ�C�f�I���M�[�̗ƂƂ��Ăł͂Ȃ��A���E�̎v�z����Ȃ��A�����I����ÂȎ��_�ɗ��������f�͂ƁA�ł��邩���蓧�O�������j�I�z���͂������Ăł���B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
1999�N7��7��
���鉫��̑z���o�i�X�j
�U�h��čl
�@�����ɂ��ẮA����܂łɂ��܂��܂ȕ��Ȃ��ꂽ��A�e��̐�j�{���o�ł��ꂽ�肵�Ă��Ă��邪�A�L����V���ɂ���Ӗ��ł����̍ۂ�����x�A�����悻�̎U�h��̗l�q��U��Ԃ��Ă݂邱�Ƃɂ������B�ȉ��̕��͂������ɂ������ẮA�u���ꂪ����킾�v�i��c���G���A�����V��Њ��j�𒆐S�Ƃ��邢�����̐�j���������p������Q�Ƃ����肵�����Ƃ����炩���߂��f�肵�Ă��������B
�@�U�h��ɂ����čŏ��̎������J��L����ꂽ�̂́A�Ð����琼���ɂ����Ă̋u�˒n�т������B���V�ԕ��ʂ������낷�Ð����n�ɂ͉������R�������Ƃ����S���ւ�h�q�w�n�̈���������B�{�w�̑O�q�ɂ����鐔�Â̐w�n���ח�����Ύ�n���̎���R�i�ߕ����ʂւ̐i�R�H���J���邱�Ƃ͊m���������B�l����\���A�č����\�l�R�c�̃z�b�W�����́A�R�c�z���̑��\���t�c�i�ߊ��ɑ��āA�����Ȃ��i���u���A�����Ȃ�]�����Ă��A���̓��̓��v���܂łɉÐ����n���̂���悤���������B
�@�������Ȃ���A���{������R�̔����͐��܂����A�������̕ČR���s��������������Ԃ̂܂܈���Ɏl�A�\���[�g���O�i����̂�����t�̏�Ԃ������Ƃ����B���ǁA�ČR���ڕW�n�_�ɐi�U���A�Ð����̊��S�����ɐ��������͈̂�J���ȏ����̂��Ƃł������B�u�Ð����n�̐퓬�قǓ��{�R�ɋꂵ�߂�ꂽ�킢�͂Ȃ������v�ƕČR��j�ɂ��L�^�̂���ʂ�A���ʂɏ���A�����J�R�ɂƂ��Ă�����͋Ɍ��̐킢�ł������炵���B
�@�����ۂ��A�w�n���ʁA�����Ȃ�Ύ���R�̐S�������U�������̂͑��\�Z�t�c�������B���͂ȉΊ�������Č������U���������͂������̂́A���łȃg�[�`�J�[���ɐw���\���ēO��R������݂����R���s������ʏ�̐�@�ōU������͍̂���ƌ�����ČR�i�ߕ��́A�g�[�`�J��n���������̓��{�R��������O�ɋ��o���ɂ͓y��[���@��N�����悤�ȗe�͂̂Ȃ��C�����������邵���Ȃ��ƍl�����B�ނ�͂�����u�k����@�v�Ɩ��Â��Ă����炵���B�z�b�W�����̖��߈ꉺ�A�ČR�́A���A�C�A��̑S�R�������Ĉ�呍�U���ɓ]���A�ʏ�̖C�e�┚�e�̂ق��A�����Ƃ��Ă͐V����ł������i�p�[���e��P�b�g�C�Ȃǂ�����R�w�n�ɉJ�łƗ��т��������B���̋�O���̖Ҕ��ɂ���ė^�ߌ�����ɂ����Ă̈�т͈�ʏĂ��쌴�ɂȂ�A���ׂĂ̏Z�������͐Ռ`���Ȃ������B
�@���ʂɂ��̂����킹���U���ƕ��s���A�ČR�͒n�����⓴���w�n�̎���R�ɑ���̊������s�����B����R�̊e�n�����̏㕔�ɖ�A�ɂ܂���ė��B�̑_�����𑗂荞�݁A���̓�����t�߂ɐw��点�č�������p������������Ђ��[����_�������ɂ����̂ł���B�����Ď���R�������ɕ������߂��Ƃ���ŁA��Ԃ�n���w�n�̓�����ɗU�����A�����Ɍ������ĖґR�ƉΉ����˂𗁂т���������A���͂Ȕ�����K�X�e���ʂɓ��������肵���B�u�n�����v�ƌĂ�邱�̊�P��@�ɂ���āA��U�s���Ǝv���Ă�������R�̃g�[�`�J�⓴���w�n�͎��X�ɖ��͉�����A���̒��ő����̏������키���ƂȂ��]���ɂȂ��Ă����͂��߂��B
�@�������R�̎i�ߊ��͋����������A�Q�d�����͒��E�������������A�����I�ɐ헪���哱�����͍̂����Q�d�̔������ʑ卲�������悤�ł���B�ނ́A�ČR�����ߋ����Ɉ����A�Z���ňœ�������ɂ������u�h���Ⴆ��@�v���Ƃ邱�Ƃ��l�����B�ČR��������x��i����܂ł͂������锽�������������ٔF���A�@�����Ď���R�n�������ɉB���Ă����l�S��̏d�C�ň�čU�����J�n���Ĕ����ɓ]���A�ꋓ�ɑ���̎�͕�����r�ł��悤�Ƃ����킯�������B����R�ɂ͖C�p�̑�ƂƂ��ĕ��������a�c�F�������Ȃǂ����āA�C�����̖C�p�Z�\�͓��{�R�S�̂ɂ����Ă��ō��̃��x���ɂ������Ƃ����B������A��ĖC���J�n�̎����̔��f������邱�Ƃ��Ȃ���A���ʂ������߂�̂͊ԈႢ�Ȃ��ƐM�����Ă����̂ł���B
�@���ۂɂ́A����Ȏi�ߕ��̗\�z���͂邩�ɒ�����ČR�̖ҍU�ƍI���Ȋ�P�헪�̂��߂ɁA�唽���ɂł�O�Ɏ�͕����S�̂������ɕ������܂�Ă��܂����˂Ȃ���ԂɂȂ��Ă����B�������A���̎��_�܂ł́A�������R�͂܂����Ȃ�̐�͂��ێ����Ă����B�ČR�̍U���̖�ʂɗ�������ɑς��Ă������������w�����̑�Z�\��t�c�̕��͂͂��łɔ������Ă������A�g�[�`�J���ʼn�������Ă����a�c�����z���̑�ܖC�����̂ق��A����n��ɍT����J�{���������̑��\�l�t�c�A�Ɨ�������l�\�l���c�c�������A����ɂ͑�c����������C�R�����Ȃǂ̕��͂͂Ȃ����݂ł������B
�@�암�n��ɍT���邻���̕���������ɓ�������A������x�͕ČR�ɔ����Ԑ����Ƃ邱�Ƃ��ł���ƍl�����i�ߕ��́A���\�l�t�c�ƓƗ�������l�\�l���c�ɖk����w���A�����̕����͖�A�ɂ܂���đO���ɐi�o�����B�������āA�{�w�̉������R�i�ߕ������̖��^������������̏����͐������B
�@�������Ȃ���A���̎��_�Ŏ���R�i�ߕ���]�̊Ԃɂ͐�p��̖��ňӌ��̑Η����N�����Ă����B���Q�d��������Q�d�������A�S�R�������đ��U���ɏo��@���n�����Ɣ��f���A���͂������Ĕ����ɓ]����ׂ����Ǝ咣�����̂ɑ��āA���������Q�d�́A������������h�q���ɔz�����A�Ō�܂Ő�玝�v�̐�@���Ƃ�ׂ����Ǝ咣���ď��炸�A�e�Ղɂ͎��E�����Ȃ������B���̊Ԃɂ����킶��Ɛi�U�𑱂���ČR�́A�C�����̑_��������R�i�ߕ��ߕӂɏW�����͂��߁A�n���w�n�̍B�����܂ʼn��ɂ��������߂鎖�Ԃɂ܂ł������������B���R�A����R�̍����ɂ����Ă͓��ɓ��ɋْ��̓x���������܂�A�i�ߕ��ɂ͎E�C��������C���Y���������B
�@�����̏����̊Ԃɂ́A���̂܂��v��𑱂��A����邱�Ƃ��Ȃ��s�k�Ǝ���҂̂͑ς��������Ƃ����v�������A�u�U���͍ő�̖h��Ȃ�v�Ƃ������˂Ă���̓��{�R�̋����ɂ̂��Ƃ��āA���̍ۈ�čU���ɓ]����ׂ����A�Ƃ����C�^�����܂����B����ȋC�^�������āA�i�ߕ����̑吨�͍U���_�҂̋}��N�A���Q�d���̎咣���x�����邱�ƂŌł܂����B�����āA�ŏI�I�Ȗ�����c�ɂ�����̌��Ɋ�Â��A�������i�ߊ��́A�܌��l�������������đS�R�������������U���ɓ]���邱�Ƃ����f�����B
�@���̌����s���Ƃ������������Q�d�́A���̂Ƃ��̐S�����u�ČR�́A���{�R�̂��Ƃ��A���͗D�G�A���������͗ǍD�A�������Z�͖}�f�A�����w�����͋��ƕ]���Ă��邪�A��͑�{�c��艺�͑����R�̏d�v�Ȓn�ʂ��߂�l�X�܂ŁA�����̖�����w�������A�p�����̖{���I�m���Ɣ\�͂Ɍ����Ă���̂ł͂Ȃ����Ƌ^���v�ƋL�^���Ă���B�����̊뜜�����Ƃ���A���d�Ȕ����U����͂قǂȂ����c�Ȕs�ނ������A����R�͍Ăђn�����ɐ����Ď��v��ɓ]���邱�ƂɂȂ��Ă������B
�@�����ɂ͎��v��p�̂ق����ČR�ɂ͂قƂ�ǒʗp���Ȃ������̂ŁA�����̔��f�������������Ƃ͌�������A���낢��Ȕ�����s���L�^��ǂ݊r�ׂĂ݂邩����A���̐l���̌����ɂ͂��Ȃ�̖����Ǝ��ȕٌ�Ƃ��v���邠�����Ȃ���������B�܂��A�̂��ɔނ̂Ƃ�����킪���ʓI�ɂ͉����ʏZ���̑�ʎ��������N�������ƂɂȂ��Ă����B���������āA�㊯�ɑ��锪���̔ᔻ�̐�������S�ʓI�ɐM����킯�ɂ͂����Ȃ����A�ނ̌���������Ȃ�ɂ͓������Ă����̂��낤�B
�@���U����O�ɂ����i�ߕ������ł́A�{�E�̗����l�̎�ɂȂ�R�C�����̂��y���ɗm���܂Ō������폟�F��̏j�����J���ꂽ�Ƃ����B���������Ⴂ�����������Ԏ���R��]�̊Ԃ��ނ��Ă܂��A���̐����������ĊF���u�����̑��U���͕K���ԈႢ�Ȃ��I�v�ƌ��ɂ���ȂǁA�ӋC���V������̂��������炵���B�ǂ��܂Ŗ{�C�������̂��͂킩��Ȃ����A���Q�d���Ȃǂ́A�u�V�C�\��ł͌܌��O������l���ɂ����Ă͉J���B�G�̐�Ԃ͓D�ɂ͂܂��ē������A��s�@�͔�ׂȂ����낤�B�ܓ��̒[�߂̐ߋ�ɂ͐폟�j������邼�v�Ɖ��C����������L�l�������Ƃ����B�����Ƃ��A���̎����̐����O�A���Q�d���͈ӌ����قɂ��Ă������������Q�d�Ɍ������āu��������Ɏ��̂��v�Ɨ܂��݂������̎咣�ɓ��ӂ����߂��Ƃ�������A���S�ł͑S�R�ʍӂ����肤�邱�Ƃ��o�債�Ă����̂�������Ȃ��B
�@�܌��l���ߑO�l���\���A�������R�͑��������J�n�����B�n�����ɉ�������Ă�������R�̎l�S��̎�͖C�����������ɉ�f���A�C�����u�˂ɍ����킽��̂ɍ��킹�āA��B�{�y�̒m���⎭��������������̐_�����ʍU���@���C��̕Ċ͑D�Q�ɏP�����������B��p�╺��̗D��͂Ƃ������A���͂�s�����Ă̎���R�̔����ł͂����������ɁA��т͂����܂��C����Ɖ������B
�@�܌��l���̌ߑO���O�A�ČR���\�l���R�C�������́A�h�q�����Ɉʒu�����̏W���t�߂���̋ʂ����X�Ƒł��グ����̂�ڌ������B�����āA�����̏u�ԁA����R�w�n����ČR�̐w�n�Ɍ������Ėҗ̂����Ȃ��C�����n�܂����B���̖C���̐��܂����́A�ĕ�������܂łɈ�x���̌��������Ƃ̂Ȃ��قǂ̂��̂������Ƃ����B�������A����R�̔����U���͂��܂蒷���͑����Ȃ������B�ČR�������ɉΊ��q��@���������ĉ�����J�n�A�ߑO�������܂łɂ͑O���S�̂Ŏ���R�̍U�����قڒ��������B
�@����R�s�ނ̌����̈�́A�����̉���ˌ����ߐM������͕��c���U���J�n�ƂƂ��ɉ��̎Օ������Ȃ����n�ɖ��S�C�ɔ�яo���A�ČR�̏d�C�𗁂тđޘH��f���ꓮ���Ȃ��Ȃ��Ă��܂������Ƃɂ������B�����҂̌��t�����u�܂�œ�������������J����_����������݂����Ɏ��X�ƌ����|����Ă������v�̂��Ƃ����B���Ƃ��A���㒆���w�����̐�ԑ��\���A���Ȃǂ́A�ČR�̏W���C�̂��߂ɐi�ނƂ��ɕs�\�ɂȂ�A�唼�̑�������Ԃ��ƂƂ��Ȃ����ׂ��Ȃ��펀�����B�܂��A���U���̂��߂ɒn���ɉ������Ă���������R�����̋��C�́A�n��Ɏp��������Ăɉ𐁂����܂ł͂悩�������A�����҂��\���Ă����ČR�͍ڋ@�̉a�H�ƂȂ�A�����ɂ͂��̈З͂��قƂ�ǔ������邱�Ƃ��Ȃ��A���Ƃ��Ƃ��j�s������Ă��܂����B
�@�݂�ׂ���ʂ������邱�Ƃ̂ł��Ȃ������n��R�̐퓬�ɑ��āA�_�����ʍU�����̂ق��́A�܌��l���܂łɂ̂ד��@���o�������A�Ċ͑D�\���ǂ������������͑�j������Ƃ�����ʂ��������B�����A���������U���������͓ɋ߂��������̂́A�ČR���_�����U�@�ɑ���h������������ɂ�A���̐������͌����̈�r�����ǂ�A�قǂȂ������̎Ⴂ�����A�ނȂ�����C�̑����Ə����Ă������ʂɂȂ����B
�@�܌��ܓ��̌ߌ�Z���A�i�ߊ������������͒n�������̎����ɔ������ʍ����Q�d���ĂсA�u�\�͍U�����~�����肵���v�ƍ������Ƃ����B���U���̎��s��F�߁A����Ȃ鎩�w�̑��Q��H���~�߂邽�߂̌��f�������B�`������Ƃ���ɂ��ƁA�i�ߊ������́A����Ɠ����Ɂu�c�����͂Ƒ����̗������Ƃ������āA�Ō�̈�l�ɂȂ�܂ŁA����̓�̒[�Ɏڐ��̓y�n�̑����邩����A�����܂Ŏ��v������������{�y����̏����̂��߂Ɏ��������������B����͈���M���ɔC���邩��A�\�̕��j�ɂ��������v�������ɂ���Ă���v�ƍ������Ƃ����B
�@���������͂̂��ɖ����m���n�̓������Ŏ������Ă���̂ŁA�����Q�d���`���邻�̌��t�������̐^�ӂł��������ǂ����͂��͂�m���߂悤���Ȃ��B���R�m���w�Z���߁A�l�i�҂������Ƃ������鋍���̌��t�ɂ��Ă͂��������̋^�₪�c��C������B�U�h��̂��ƁA�����̓������������܂ܓ암�ɕ��������Ď��v���W�J�A���ʓI�ɏ\���l���閯�Ԑl�]���҂��o�����ƂɂȂ������̎����I�Ȏw�������������������Ƃ��v���ƁA�ǂ����ɐӔC����̂ɂ��������Ȃ��ł��Ȃ��B
�@���U�������~���ꂽ����Ƃ����Ă��A�킢���I������킯�ł͂Ȃ��A���̌�����đo���ɂ͑����̋]���҂����o�����B�Ƃ��Ɏ���R�̋]���҂̑唼�͐��������̐��s�Ƃ�����ꂽ���m�ł����������ɁA���͂┽���U���͐�]�I�ƂȂ����B���U�������s�ɏI��������Ƃ������āA�ŏI�I�ɗv����Ǝ���R�͎U�h��S�̂�ʂ��Ă��̕��͂̎��\�܃p�[�Z���g���������ƌ����Ă���B
�@����퓖���̗�؎͐��̉�ڒk�̒��Łu����̓��{�R���G����x�C���ɓ˂����Ƃ��Ă��ꂽ��A������_�@�Ƃ��ċ�̓I���a������J�n���悤�ƍl���Ă������A���҂ɔ����Ď���R�͂������Ă���Ȃ������v�Əq�ׂ��B�̂��ɂ����m���������́A�u���₵�����ꍑ�̎��A�����ɂ���Ȋ��҂��Ă����Ƃ���A����̎���������m�Ȃ��������̂ƌ���˂Ȃ�ʁB�����ɂ����ẮA���n�̎�]�͐퓬�J�n�������O�����]�������Ă����̂��B����͖{�y�ł��ƌ������A�������R�͖{�y�̑O�i�������ƒf���Ă����Ȃ���A���n�R�Ɍ���������Ė{�C�Ő폟�����҂���͖̂{���]�|���r�������v�Ɣ��_���Ă���B
�@�����́A��{�c�ƌ��n����R�Ƃ̊Ԃɂ͐����ɋ߂��ӎu�̘����i������j�����������Ƃ��w�E�A���̗�����𖾂炩�ɂ��Ă���B�ނɂ��ƁA�����̎n�܂�O�N������ȍ~�A��͎Q�d�������牺�͎Q�d�{�������ɂ�����܂ŁA��l�Ƃ��ĉ���ɒ��ڎ��@�ɗ�����A���������サ�ɗ����肵���҂͂��Ȃ������Ƃ����B����ǂ��납�A������ʂ̍��ɂ��Č��n�̍���C�ł��锪�����g�Ƃ����e�����G�������Ēk��������{�c�W�҂͈�l�����Ȃ������炵���B���������̂ق�Ƃ��̗��R�́A�ߔe�s�̗V�s���S�ł��ċ��y�ɒ^�邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ������Ƃ�A�쐼�����̊C��ɕČR�̔�s�@������͂������o�v���͂��߁A�g�̊댯������������ł������Ƃ����B
�@�����͂���ɁA��{�c�̖��������̂��̖��ӔC�ȑԓx�́A�č��̏ꍇ�Ƃ͂��܂�ɂ��ΏƓI�������Əq�ׂĂ���B�č��Ȃǂł́A�哝�̂������O���ɏo�����ď����ƌ�荇���A�������j�Ɛ푈����̎��ԂƂ̒������͂���̂��킾�������A�����̓��{���{���{�c��]�ɂ͂���Ȕz���Ȃǂ܂�Ō����Ă����Ƃ����B���ǁA��{�c�́A���炪������������Ɍ�������đ��������𑗂邱�Ƃ���߁A����{������R�A�쐼�����C�R�����A����ɂ͓������ꂽ�����̉���Z�����͂������Ă̐킢���݂��݂����E���ɂ����̂������B
�@�ČR��\�R�i�ߊ��o�b�N�i�[�����́A�������R�̑����������s�ɏI������̂����͂���ƁA�z���̑S�R�Ɍ܌��\����������đ��U���ɂ���悤�ɖ��߂����B�����ۂ��̎���R�͑��U���Ɏ��s�������ƁA�����Ɏ��v��Ԑ��ɐ헪���ւ��A���͂̌������l�����Đ�������ӂɏk�������B�ČR�����U���ɓ]�������̓��ɂ́A�_�����ʍU�����S�\�@������C��̕Ċ͑D�c�߂����ĖґR�ƌ����̑̓�����U�������s�����B�قƂ�ǂ̓��U�@�͕Ċ͑D�ɓ��B����O�Ɍ��Ă��ꂽ���A�ꕔ�̓��U�@�͕ċ@���͑����͂̃o���J�[�q���ɑ傫�ȑ����^���A��ނȂ����͂̃G���^�[�v���C�Y�Ɏi�ߊ������ڂ����ƁA���̓��U�@�����̃G���^�[�v���C�Y������j�������B�i�ߊ����͌��ǁA�ʂ̍q���͂Ɉڂ��ꂽ�Ƃ����B
�@���A�C�A��A�C�����̘A�g���̂��ƑS����ɂ킽�鑍�U�����J�n�����ČR�ɑ��A����R���Ō�̎��͂��ӂ肵�ڂ��Ċ拭�ɒ�R�����B�����A�̎���R�{�w�ɑ���C���͉ߋ��̂�����͂邩�ɏ��錃��Ȃ��̂ƂȂ����B�ČR��͕����͒���̕ʂȂ���ԖC��@�֖C�A�P�C�A���P�b�g�C���������݁A���킶��Ǝ{�w�ɓ������Ă������B
�@�ČR���V���K�[�E���[�t�ƌĂ����ȋu���߂���U�h��́A�ЂƂ��퐦�܂������̂ł������B���̋u�����Ăǂ���ɂƂ��Ă���p��̗v���ɂȂ��Ă������߁A�đ�Z�C���t�c�͈ꋓ�ɂ��̒n��苒���悤�ƁA�����̐�Ԃ𑗂荞��ōU�ߗ��Ă��B�������A�̐����Ɉʒu���邱�̋u�˒n�������Ύi�ߕ��w�n�������܂���@�ɕm���邱�Ƃ͖ڂɌ����Ă����̂ŁA����R����Z�\��t�c�ƓƗ�������l�\�l���c�̈ꕔ������z�u���A���n�����炷��\���ɂł��B
�@���ʂł͂邩�ɏ���ČR�́A�U�h��̊J�n�ƂƂ��ɐ����݂̖C���┚���������ē��{�R�̓������A��Ԃ����ɍU�ߐi�B���̖ҍU��ʏ�̐�@�Ŗh�����Ƃ͕s�\�Ɣ��f��������R���m�����́A������������܂��X�ɓ����w�n�����яo���A�U�ߊ�ČR�̐�Ԃ�C�����Ɍ������ē˓��A�̂Đg�̑̓�����U�������s�����B�������ăV���K�[�E���[�t�̋u�𗼌R�ň����������������Ƃ��������������A�킢���n�܂��Ă���Z����̌܌��\�����ɂȂ��Ă悤�₭���̋u�͕ČR�̎�ɗ������B
�@���ɂ͏��������A���܂�ɂ�����Ȑ퓬�̂��߁A�ČR��Z�C���t�c�͓�Z�Z��l���̎����҂ƈ��l���̐퓬��J�NJ��ҁA���Ȃ킿�����҂��o�����ʂƂȂ����B�����̐��_�ُ�҂����Â��邽�߁A�ČR�͓��ʂɐ��̖��a�@��ݗ����Ȃ���Ȃ�Ȃ������Ƃ����B�ނ��A����R���̎����҂͕ČR�̐��{�ɂ��̂ڂ����Ɛ��肳���B
�@�V���K�[�E���[�t�����ɖړr��������Z�C���t�c��͕����́A���̑����ɂ��߂����A�����Ɏ{�w�k���ɗאڂ������ё喼�̗����n�̍U���Ɏ�肩�������B�����Ȃ�]�����Ă����n�����点��Ƌ����i�ߊ����猵���������n����R�́A�͂̂������s���������A�P�C��͖C�ˌ��̖Ҍ��Ɏx�����ꂽ�C�����̎�ɂ���đ��n���܂��苒���ꂽ�B��܊C���A���̑������������đ�Z�C���t�c�̖ҍU�ɁA�喼�w�n����R�͉ʊ��ɗ����������A���炭�̊Ԃ͕ČR���܂��������Ȃ��������A�ČR�̍U���͂��ɂ��܂��Ď��X�������B�ʏ�C�e�͂����ɂ�����A������Ή����ˊ킩�烍�P�b�g�C�A�i�p�[���e�ɂ�����܂ł̂�����Ί킪��������A���ɑ喼���n��т̎���R�w�n�͊ח������B
�@�V�R�̗v�ǐΗ䍂�n�̍U���ɂ͂������̕ČR������Ă����B�ČR�̂��钆���͑�����Z�l�l�ŐΗ䍂�n�ɖ�P�����������A��ܘZ�l���������B����l����Ȃ�ʂ̍U�����͐����҂��O�Z�l�����A��֗v���Ƃ��Ĕh�����ꂽ�ܔ��l�̏����Ȃǂ́A�킸���ɎO�l�����҂��������������Ƃ����B����ł����X�Ɍ���𐧂��A�̎i�ߕ��w�n����芪�����n��苒�����ČR�́A���悢��i�ߕ��ɒ����e�𗁂т��͂��߂��B�����āA���O�̓��Ƃ������ׂ��ɒǂ����܂ꂽ�{�w�̊ח��͂��͂⎞�Ԃ̖��ƂȂ��Ă����B
�@����R�{�w�͎O���̋��łȖh�q���Ŏ���Ă����B�E���ɂ͑��\�l�t�c���w���\���A�����ɂ͑�Z�\��t�c���w��z���Ă����B�܂��A�i�ߕ��w�n�̓��k���ɂ͖h�q���������Ƃ����łœ�U�s���Ƃ݂Ȃ���Ă����ك��x�w�n���������B�Ƃ��낪�A����̗\�z�ɔ����ČR���^����ɍU�������̂́A���n���炻�������}�ɐ���オ�����s���̂͂��̕ك��x�w�n�������B�ČR���`���R���[�g�h���b�v�ƌĂW����Z�����[�g���̕ك��x�w�n�́A��핔���̕Ď��\�������t�c�̖ҍU���ɍ����A�����Ƃ����܂Ɋח����Ă��܂����B����D���Ă������߁A�ČR�@�ɂ�����̎x���U����A�����P�����̓����ɂ���Ă������Ȃ���ł�����ꂽ�̂������B
�@�܌���\����A�ČR�͂��悢��s���ɐi�R���悤�Ƃ��Ă������A���̓�����͂��܂��܂Ђǂ����J�Ɍ������Ă����Ƃ����B��������ČR��O�ɂ��Ă��͂▜���s��������R��]���́A�ŋʍӂ���o����ł߂������B�Ƃ��낪�A���������Q�d�����́A��E�o���ē암�̊쉮�������ʂւ̓P�ނ���Ă����B���̂��ߔނ͕��S�̎Q�d����p�v�ɖ����ɖ����āA����R�i�ߕ��̂Ƃ�ׂ�������l���������B�Öق̂����ɔ����̈ӌ���������Q�d�́A���̂悤�ȎO�Ă�����Ƃ����B
��A����R�i�ߕ��͊쉮���n��ւƓP�ނ���B
��A�m�O�����ɓP�ނ���B
�O�A���s�w�n�ɋ���A�Ō�܂œO��R�킷��B
�@�܌���\����̒��A�����͂��m��ʊ�ł����̎O�Ă삩�璷�Q�d�����ɒ�o�������B�����̉��Ƃ͒m��ʒ��Q�d�����͂����ɔނ��ĂсA���̌��������߂��B�����ŁA�������������͊쉮�����ʂւ̓P�ވĂ𐄂������ۂ��A���Ăɂ��Ĕz���̊e���c�w�����̈ӌ���q�˂Ă݂邱�Ƃ����߂��̂������B
�@���̖�̋��c�ɂ����āA��Z�\��t�c�̏���b�Q�d���͔z���̏����̑啔��������Ő펀���������A���A�w���ɂ͌㑗����ȉ���l���̏d���҂�����̂ŁA�Ō�܂ŎŐ키�ׂ����Ƃ������Q�d�������̈ӌ����q�ׂ��B����ɑ��A���\�l�t�c�̖ؒJ���Y�Q�d���ƌR�C�����̍��썂�������́A�쉮�����ʂւ̓P�ވĂɎ^�������B�܂��A�Ɨ�������l�\�l���c�̋��m�Q�d�́A�쉮���n��ł͂Ȃ��A�m�O�������ʂւ̓P�ވĂ��x�����A�C�R���\���ĉ�c�ɎQ�����������Q�d�͂Ƃ��Ɉӌ����q�ׂȂ������B���̌��ʁA���������Q�d�̎v�f�ʂ�ɂ��Ƃ͉^�сA�����i�ߊ��͎���R�i�ߕ����쉮���n��ɓP�ނ����邱�Ƃ��ŏI�I�Ɍ��f�����B
�@�܌���\�����[�������\�����ɂ����Ď���R�̓암�P�ނ͊J�n���ꂽ�B�܂���̍��J�Ɩ�A�Ƃ�����R�i�ߕ��̓P�ނɑ傫�����������B����R��]�w�͎����ȓP�ތv������A�������̏����ɕ�����ē쉺�����B��O�����܂ł͖����m���ʂւƒ��s�������A�����i�ߊ��Ɣ��������Q�d��\�l�̑�l�����ƒ��Q�d�����Ⓑ��Q�d����܂ނ�͂�\�l�̑�����́A�ЂƂ܂��ÉÎR�ɗ������A�ꎞ�I�ɂ�����퓬�i�ߕ��ɂ��邱�Ƃɂ����B�@����R�i�ߕ��P�ނƑO�サ�āA��Z�\��t�c�Ɛ�ԑ��\���A�����쉺�A�����̓�\�����܂łɂ͎őO���ɕz�w���Ă����Ɨ�������l�\�l���c�i�ߕ��Ƒ��\�l�t�c�i�ߕ����A�ÉÎR�̐퓬�i�ߕ��ɍ������邽�ߓP�ނ��J�n�����B
�@�ČR������R��͕����̊쉮�����ʓP�ނɋC�Â����̂́A�P�ފJ�n�ォ�Ȃ莞�Ԃ������Ă��炾�����B�܌���\����ɕđ��C�������隬�ɓ˓������Ƃ��A�v�ǂ͂��łɂ��ʂ��̊k�ɂȂ��Ă����B�����̍��d�ʂ�A�암�ł̎��v���_�������P�ލ��͕ČR�̖ڂ����\���A�����Ȑ��������߂��̂������B�������A���̓P�ލ�킱���͂܂��A�̂��ɑ������S�Ȓn���G�}�̏��͂ł��������̂��B�����A�Ŏ���R���ʍӂ��Ă���A���K�R�l��㖜�Z��̂قƂ�ǂ��펀���Ă�����������Ȃ����A�\�����l�ɂ��y�ԉ���Z���⌻�n�����h�q���͑����̎��͔������Ă�����������Ȃ��B����암����ɂ�����^�̔ߌ��͂��̎��_����n�܂����̂��B
�@�܌����̌R�c����c�ɂ͓����̓��c�b����m�������Ȃ��Ă����B���̐Ȃœ��c�m���́A�u�R������e������葕�����������ŋʍӂ����ɖ����m�ɓP�ނ��A�Z���A��ɂ���̂͋���ł���v�ƕ������Ƃ����B���̂Ƃ������i�ߊ��́A�u��O�\��R�̎g���͖{�y�����������Ƃ��L���ɓ������Ƃ��v�Ɛ����ĉ�c����ߊ������Ƃ����B
�@�u�₦�ԂȂ��J�̃J�[�e���̉A�ɉB��āA�����͂��̕��͂̑啔���𗦂��ĒE�o���邱�Ƃɐ��������B�����Ď�̐^��\�l�L�����A�₾�炯�̊C�݂������낷��ǂ̓����ɐV�i�ߕ���u�����B�������̓P�ނ͉���̏Z���ɂ͂ƂĂ������Ȃ��̂ɂ����B���Q��ԂɊׂ������Ԑl�̌Q�ꂪ�R�̂��Ƃ�ǂ��ē�֓����A�C�����ŋs�E���ꂽ�B������̎��̂��A�ʂ���݂̓��[�ɒu������ɂ���Ă����v
�@����́A�W�����E�g�[�����h�����̉������R�̓암�P�ނɂ��ďq�ׂ��ꕶ�ł���B�܂��ɔނ̎w�E�̒ʂ�A���̍��́A�Ђ߂�蕔���̔ߌ����͂��߂Ƃ��鐔�X�̑�S���������N�������̂������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
1999�N7��14��
���鉫��̑z���o�i10�j
���ꔭ�˂̒n�ƃC���u�[�]�k�@�@
�@�����̔ߌ��������ÂтȂ���u�˂����Ƃɂ������́A�{������[�ɂ���m�O�����Ɍ������ĎԂ𑖂点���B�m�O������������т́A����{���̂Ȃ��ł͂����Ƃ��X��ʂ̔������Ƃ���Ƃ��Ēm���Ă���B�˒[�̒m�O���ɂ͋ߑ�I�ȊC�m���W���[�Z���^�[�������āA�C����W�]�ł���O���X�{�[�g�Ȃǂ��p�ӂ���Ă������A���Ԃ̓s�����������̂ł���ɂ͏�炸�A���邭�P�����C�����߂Ă����B�썑�̐^���̑��z�ɂ���߂��h����C���ɂ́A���̊��܂킵���푈�̉e�Ȃǂǂ��ɂ��������Ȃ������B
�@�m�O����������ɂ܂����������ɂ͍֏��ԁi���[�ӂ��������j�ƌĂ�鐹�n���������B���̐��n�ɂÂ��R�������炭���ƁA�قǂȂ������ȍL��ɏo���B���̍L��̉E�[�͐藧�����f�R�ɂȂ��Ă��āA���̒f�R�ɂ����ꂩ����悤�ɂ��đ傫�Ȋ₪�����Ă����B����n���̓`�����ƁA�A�}�~�L���Ƃ����n���_�́A�܂��A���̒n�̉������ɕ����ԋv�����ɍ~�Ղ����B�����āA���̂��Ƃ��̍֏��Ԃɂ킽���Ă����̂��Ƃ����B���̂��߂��̒n�́A�×��A����{�����̐��n�Ƃ���A�����������̍�������N�����ɕK���Q�q�Ɍw�ł邵������ɂȂ��Ă����炵���B�܂��A�����Ɏ������͎҂ł���������N�i�������̂������݁j�̑��ʎ��������Ȃ�ꂽ�̂����̐��n�ł������Ƃ����B
�@�����̊C��������ƁA�Ȃ�قǁA�v�����̂��̂Ǝv���铇�e�������Ă����B�b�ɕ����Ƃ���ł́A�Î��L�ɂ��o�ꂵ�A���ꔭ�˂̒n�Ƃ���邱�̏����ł́A�\��N�Ɉ�x�C�U�C�z�[�Ƃ����Ñォ��`�����J���Â����̂��Ƃ����B����͓��̎O�\�����l�\��܂ł̏������i���`���ƌĂ��ޏ��ɂȂ邽�߂̐���s���ŁA�����̑S�������W�܂�A�m���Ƃ����ޏ��ō��ʂ̏��������̍��J�S�̂����d��B
�@�v�����ɂ�����m���̌��Ђ͐��ŁA���Ȃ�̎��L�n��^������ق��A���B��̓��Y�i�C���u�[�i�G���u�E�i�M�j�̕ߊl������X�m���Ɉς˂��Ă���̂��������B�ނ��A����͗��l��h�����߂̓����̒m�b�ł��������̂��낤�B
�@���Ȃ݂ɏq�ׂĂ����ƁA�C���u�[�i�G���u�E�i�M�j�́A�E�i�M�̎O���������Ă��邩��Ƃ����āA�������܊��Ăɕϐg���Ă����悤�ȃ����Ȏ荇���ł͂Ȃ��B�������A�j���[���[�N�E�����L�[�X�Ŋ������̂��̕��̐e�ʂł��Ȃ��B�C���u�[�Ƃ͓�̊C�ɐ��ޓŎւ̈��Ȃ̂����A������������ƈӊO�ɂ����������`���̍����ȐH�ނƉ����B���R�A�����̕ۑ��������B�C�m���W���[�Z���^�[�̓y�Y�����ɒu����Ă���̂����Ă������A�_��̂��̂ƃg�O���������������̂��̂Ƃ̓��ނ������āA������������ɍ����Ȃ�����̂������B
�@�v�����͑S�̂�����ł��邾���ɁA�����͂悻�҂������K��邱�Ƃ�K�������D�܂Ȃ��Ƃ������Ƃ��������A����̗���ɂ͍R���������Ƃ݂��āA�ߔN�͖��h�Ȃǂ��������ł��Ă���炵�������B�������X��̊C�Ɏ�芪���ꂽ���͔��L���̓����ɂ́A�_�b��`���ɍʂ�ꂽ�X�|�b�g������������Ƃ̂��Ƃ��������A���͉������炻�̓��e�߂邾���ɂƂǂ߂Ă������Ƃɂ����B
�@
�@�]�k�ɂȂ邪�A���܂≟��������������ʗ��s��Ƃ̔T��A�T���܂����؏܂���܂��邸���ƑO�̂��ƁA����y�Y���Ƃ����āA���̏Z�ޕ{���܂ŁA�Ȃ�Ƃ�������ȃV�����m�����Q���Ă��Ă��ꂽ���Ƃ�����B�ޏ��́A�u������ςĐH�ׂ�Ɣ����������A���{���s�܂Ƃ��Ă̓��������邻���ł���v�Ə��Ȃ���A�ꃁ�[�g���قǂ̍ג�����̕�݂������o�����B�Ȃ낤�Ǝv���Ȃ���A�������b�Ȋ������ƁA���������ޏ��́A���R�Ƃ�����Łu�v�������Y�̃E�~�w�r�ł���A���Ƃ��Ƃ͓Ŏւ������Łc�v�ƌ����Ă̂����B
�@���M���^�ł����ƕ�݂��J���Ă݂�ƁA�����ג�����{�̖_�̂悤�Ȃ��̂����ꂽ�B��݂�������o���Ă݂�ƁA�܂��ɃJ�`�J�`�Ɍł܂��������w�r�̊������ł���B���ǂ남�ǂ낵���O�p�̓����ɂ́A�����Ɩڂ��������Ă���ł͂Ȃ����B���ΐF�̌���̂��镠����w���ɂ�����Ƃ�����w��ł����ƕ��łĂ݂�ƁA���炴�炵���E���R�l�̊��G�������B�C�̎ア�l�Ȃ�ߖ������ē����o�����˂Ȃ����͂������B
�@�T�삳��́A������\�C�قǑ��˂����̂���Ɍg���ēߔe��`����H�c�s���̔�s�@�ɏ��A�H�c���璆���������̎���Ɏ����A�����炵���̂��B�����̂Ȃ��̈�C�����̂Ƃ���֓͂��Ă��ꂽ�Ƃ��ɂ͕���Ă��������A�ޏ������ꂩ�玝���A��ۂ́A�O�p�̓����Ɣ����͂قƂ�ǔ����o����Ԃ������Ƃ�������A���͂̐l�͂��������x�_���ꂽ���Ƃ��낤�B���ہA��s�@��d�Ԃ̓���q�̂Ȃ��ɂ͕����Ŕޏ��̂ق������߂�l���������炵���B�@�ׂȂȂ��ɂ������Ȉ�ʂ����킹���T�삳��炵���b�Ȃ̂����A���́A����A�C���u�[�̊����������̂��B
�@�Ƃ̎҂Ɂu���{�������Ĕ��������炵������A�K���̂ق����������ĐH�ׂĂ݂邩�v�ƗU���������Ă݂����A�N���Ԏ������Ă���Ȃ��B�Ȃ�Ǝv�������́A���Ƃ̕�Ɏ��߂��܂܁A���炭��������ɏ��ւ̊����ɏ����Ă������B�����āA���q���������Ƃ��ȂǂɎ��o���Ă͑�����������Ċy����ł����B�Ƃ��낪�A�����������邤���ɔT�삳��̒��؏�܂����܂����Ƃ����j���[�X����э���ł����B�����Ȃ�Ƃ����H�ׂ�ǂ���̑����ł͂Ȃ��B�ꋓ�Ɂu�T��C�_�v�ɏ��i�����C���u�[�l�́A���܂�ꑽ�����݂ƂȂ��āA�䂪�Ƃ̋q�Ԃɒ������Ă��킷�̂ł���B
�@���؏�܂̐܁A��܍�u�������v�ɓo�ꂷ��T���ɂ��Ȃ�ŁA�w���ɘT���̑��Ղ��v�����g�����s�V���c����������T�삳��́A���̂����̈ꖇ�����ɂ������Ă��ꂽ�B�u�C���u�[�l�v��u�T���s�V���c�v�ɉ����āA�V�����o�邲�Ƃɑ��悵�Ă�����Ă���ޏ��̎O�\���ɋ߂����Ŗ{��܁X���Ղ���t���Ȃǂ��ɍ��킹�ۊǂ��Ă����A���\�N���̂��ɂ́A�u�Ȃ�ł��Ӓ�c�v���̂̈�i�ɂȂ邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B
�@����ɘe���ɂ���邱�ƂɂȂ邪�A���ł����珑���Ă����ƁA�����Ԃ�̂Ɍl�I�ɒm�荇���A���܂⎄�ȂǑ����ɂ��y�Ȃ����炢�̊��������悤�ɂȂ��������͔T�삳��̂ق��ɂ����l������B�̂��ɓ��{�F�ŏ��߂ĔF�m�Ȋw���g�D���A���܂₻�̕���̑�䏊�ɂȂ��Ă��钆����w�����̎O��Ȃق݂���Əo������̂́A�ޏ����������ʂ��g���ĕč����w����A�����A�����w�@�̍��������Ɉꎞ�I�ɒʂ��Ă����Ƃ��̂��Ƃ������B�R���s���[�^����̕��@�_�␔�w����ȂǂɓK�����R���s���[�^����LOGO�̊��p�@�A����p�\�t�g�A�R���s���[�^�ʐM��ʂȂǂɂ��ĎO���قNj������o�ł����肵�����A���̌�̔ޏ��̊���͖ڂ���������̂�����B
�@AI�i�l�H�m�\�j�̐��E�A�Ƃ��ɃC���e���W�F���X�E�A�[�g�E�A���h�E�e�N�m���W�C�̌�������Ŗډ��Ő�[�̑���y�����q����Ƃ̏o��������Ԃ�Ɛ̂̂��ƂɂȂ�B�f�B�X�v���C�̒��̐Ԃ���A�l�Ԃ̘b�������ɉ����ċ������������{�����肵�Ȃ���A����Ɋw�K�������Ă����u�j���[���x�C�r�C�i�C���^���N�e�B�u�E�L�����N�^�[�j�v�̌����J���҂Ŗ������ޏ��ɂ��A���낢��Ƌ��ɂ����Ȃ��A�h�o�C�X�������肵���B���N�O���A�y�����炻�̌�̌����Ɛт��W���w�p�_���W������͂����Ă������A�����f���炵���̈��ɐs�����B�w���Ƃ͖����̂Ƃ��납��X�^�[�g���A�����ʂ�̎��͂ŊK�i�����Ɛт��������l�����ɁA���������̊��т𑗂�A����̊����S����F�肽���B
�@�m�g�j�́u���͂悤���{�v�̌��L���X�^�[�ŁA��̓h���}�̃i���[�^�Ƃ��ĂƂ��Ă��m���镽��[�q����Əo������̂́A�ޏ����܂�����c�̊w���̂Ƃ��������B�܂ɂ��Ă��낢�둊�k�����̂��悢���ƂɁA���Ȃ�ɗ�܂�����A���ɂ��Ȃ�⼌���f�����肵�Č��݂Ɏ����Ă��邪�A��N�A�ޏ��́A�u�ߔ��ߎ��Y�v�̌��ŕ����Ȍ|�p�Ռ|�\����̑�܂ɋP�����B���|�p�ƂƂ��Ď��X�ɐV���n���J���A���܂ł͂��̐��E�̑��l�҂ƂȂ��Ă���B�m�g�j�|�p����Ȃǂł����m�̕��������낤���A���̔��͂ɖ��������͐�i�ƌ����Ă悢�B���͂�ј\�\���ŁA�m�g�j�̃L���X�^�[�ɂȂ肽�Ă̍��̂��̂��ǂ��ǂ����p�͂ǂ��ɂ��Ȃ��B
�@��t�ۂЂ�q�剉�́u�~�Z�X�V���f�����v�A�L���^�N�Ə������q�剉�́u���u�W�F�l���[�V�����v�A�[�c���q�Ƌ��镐���M�������u�_�l���������������v�A�����čŋߎn�܂�������̖ؑ����T�剉�́u�p�[�t�F�N�g���u�v�ƌ����A���������҂����̊Ԃő�]���ƂȂ����t�W�e���r�n�g�����f�B�h���}�̑�q�b�g��ł���B�[�c���q�剉�́u�_�l���������������v�Ȃǂ́A�e���r�h���}�Ƃ��Ă͕����j��ō��̎��������҂�����������B�����̃h���}�̃V�i���I���������̂́A����������ݔ���o�����̐�얭�q����ł���B��삳�܂��c����w��w�@�����Ȃɍ݊w���̍�����̕t�����������A���܂�ޏ��̓g�����f�B�h���}�̃��C�^�[�Ƃ��ĉԌ`�I���݂ɂȂ��Ă���B
�@���ӂ�V���ɂ�����삳�V�i���I�̕����n�߂����A�����Ԃ�Ƙe�����������A���ɂ͂Ђǂ����Ȃ�������������̂����A��ߏ\�N�̖��ɔޏ��͌����J�Ԃ����B�ꎙ�̕�Ƃ��Ĉ玙�ɐ����o���������M������ޏ��̊����͂܂��܂��Ⴆ�n���Ă����悤�ŁA���͂⎄�ȂNjy�т����Ȃ��B�ljƂ̂���l�ł������ɂ�������炸�ςɍs���͂̂���ޏ��́A�]�v�Ȃ��Ƃ��茾�������ǂ�ȏ��łǂ�Ȉ炿���������̂��C�ɂȂ����炵���A���鎞���ɂ͂��m��ʊ�����Ă͂�鍙����K�ˁA�䂪�Ƃ̂���c�l�̕�Q��܂ł��Ă��Ă��܂����B
�@�������O�̂��ƁA�uAIC�ɂ�����Ƃ����̂̂��Ə������Ă��炤��v�Ɠd�b������A��b��̌������Ŕޏ��͂����������ɏ��Ȃ���A�u���̌��e���Ă����ɂȂ��ł����H�v���Đq�˂Ă����B�s�ӑł��������āA�����Ԏ��ɋ��������Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B���������}�C�i�X�̃J�[�h����������Ă��邱�̐g���Ă��Ă̈ꌾ�ł͂������̂����c�c�B
�@���̂ق��ɂ��A�̏o��A���܂ł͗L�\�ȕҏW�҂�t���[���C�^�[�A���邢�͖|��ƂƂȂ��Ċ������̏����͂��邪�A�ޏ������ɂ͈�̋��ʓ_������悤���B�B�ꂽ���������Ȃ��Ă����̂͂ނ���A����ȏ�ɏd�v�Ȃ̂́A���̒N�������O�ꂽ�w�͉Ƃł���Ɠ����ɁA�����͂���̏W���͂̎�����ł�����Ƃ������Ƃ��B�s���œw�͂������Ȏ��Ȃǂ́A�傢�Ɍ��K��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂����A���̐����̏K�������͔@���Ƃ��Ȃ���B���������āA�ǂ�ǂ�ޏ������ɒu���Ă�����邱�Ƃ͓��R�̕ł���B
�@�����̘b���菑�������A�����₩�ȉߋ��̐l���̒��Ő����Ă��j��������Ȃ�ɂ͑��݂��Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B�������A���̘A���̘b�̂ق��́A�u�����߁v�����˂�����̌��e�̃l�^�Ƃ��āA���炭�Ƃ��Ă������Ƃɂ��悤�Ǝv���B�@�@
�@
�@�C���u�[�̘b�����[�ƂȂ��Ă��������]�k���߂��Ă��܂������A���̂ւ�ōĂі{��ւƖ߂邱�Ƃɂ��悤�B
�@�m�O���������Ƃɂ������́A�����m�̋u�ւƌ������r���ŋʐɗ�������Ă݂��B�ʐ͐ΊD�⎿�̗��N�X��ʂ��N�H����Ăł����ߓ����ŁA���a�l�\��N�A���Q��w�T�����ɂ���Ĕ������ꂽ�B���̏ߓ����͑S���ܐ烁�[�g���قǂŁA�ό��q�Ɍ��J����Ă��镔�������ł����S���[�g���͂���B�ߓ��̑����͎��ɋ�\���{�ɂ��̂ڂ�Ƃ�����K�͂ȓ��ŁA�ߓ��̎�ނ̑����Ɠ����̌i�ς̔������ł͍������w�̑��݂ƌ����Ă���B
�@�y���C�����œ����ɂ͂������̂����A��̐�����d���K���X���������v�킹�閳���̏ߓ��̋P���́A�������ɑ���ۂނ悤�Ȕ������������B�ߓ����̋K�͂�S�̓I�ȑ������A�_�鐫�Ƃ������ϓ_���炷��Ζ{�y�̏H�F���◳�̂ق��������Ə�ɂ͈Ⴂ�Ȃ����A�ߓ����⡂̑��`�̖��Ƃ����̑@�ׂȔ������Ƃ����_�ł͂��̋ʐ̂ق��������Ă���悤�Ɋ�����ꂽ�B�Ƃ��ɁA�n��̖��сA�z���̍��A����̃z�[���ȂǂƖ��Â���ꂽ���ʂȃX�|�b�g�̌i�ς͈����������B
�@����܂łɖ{�y�̗L���ȏߓ����͂قƂ�ǖK�˕����Ă��Ă������A���̋ʐ̓��L�ȕ��͋C�Ɠ����ǖʑS�̂̐F�����́A�����ߋ��ɖڂɂ������̂Ƃ͖��炩�ɈقȂ���̂������B�ЂƂɂ́A���̏ߓ����̏ߓ����a�������̂���\���N����l�\���N�O�ƁA���̎�̂��̂Ƃ��Ă͂���߂ĐV�������̂ł��邱�Ƃɂ�������̂��낤�B
�@�ʐ��o��ƁA�������킹�̂Ƃ���ɂ���ʐ�n�u�����ɂ�����Ă݂��B�ғł����n�u�̓����₻�̐��Ԃ��悭�킩��悤�ɍH�v���ꂽ�W���ق��֓W����̂ق��A�n�u���̌������Ȃǂ��݂����Ă������A�ǂ����ό��q�����̍ő�̔��蕨�́A�R�u���Ƃ��̓V�G�}���O�[�X�̓�����������V���[�ł���炵�������B�n�u�}���O�[�X�ł͂Ȃ��A�����܂ŃR�u���}���O�[�X�ł���Ƃ��낪�~�\�ł���B
�@�傫�ȃj�V�L�w�r�Ȃǂ�����ɓo�ꂵ�A�E���ȏ����ϋq�̎�̉��ɂ��ꂪ����������Ƃ������O���V���[���J��L����ꂽ���ƁA���̃R�u���}���O�[�X�̌����Ȃ���̂��n�܂����B�����A����́A�����Ƃ͖�����́A�؏����̂��܂�����ꍇ���v�����X�V���[�݂����Ȃ��̂������B
�@�R�u���F�����}���O�[�X�A�{�C�Ŋ��݂��Ȃ�ȁB���܂����ɂ����ˁ[����ȁI
�@�}���O�[�X�F���܂������āA���̂܂��}�W�Ŋ��݂����낤���B�ł���肩�������I
�@�R�u���F�����͂��ƎO����A�z�ʂ������ό��q�̑O�Ő��Ȃ���Ȃ�ˁ[����ȁB
�@�}���O�[�X�F���Ⴓ���A���ӂ肷�邩��悧�A���O�����܂ꂽ�ӂ肹�[��B
�@�R�u���F����A���A�����Ă��肶���c�c�B
�@�}���O�[�X�F�킩������A�O��Ɉ��͉��������Ă�邩�炳���c�c�B
�@�܂��A����ȉ�b���R�u���ƃ}���O�[�X�̊ԂŌ��킳�ꂽ���ǂ����͒m��Ȃ����A����̂悤�ɃR�u���ƃ}���O�[�X�̂ǂ��炩�����ʂ܂Ő�킹�Ă�����A�R�u����}���O�[�X�����C�������đ����킯���Ȃ��B������A�����V���[�̃��t���[���߂�l�Ԃ��قǂقǂ̂Ƃ���Ŋ����Ă͂����Ă����ŏI���Ƃ������@�������B��Âɍl���Č���A�{���̎��������҂���ق��������悷����Ƃ������̂������B
�@�ʐƃn�u�����ׂ̗ɂ́A���M�ѐA�����T���Ɛ����鎩�R�������������B�Ȃ�ƂȂ��߂Â������������̂���Ƃ���ŁA��������Ă݂����Ƃ����C���ɂȂ������A�c�O�Ȃ��炻���ɓ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B���͂��̏ꏊ�ɂ͐��S�N�Ԃ����J�ɂ��炳�ꂽ�����̔������R�Ɛς܂ꂽ�Ñ�̕����̐Ղ������āA�ȑO�́u���҂̒J��Ռ����v�Ƃ��Č��J����Ă����炵���B�������A�ό��n�Ƃ��ẴC���[�W�Ȃ��Ƃ����n���W�҂̈ӌ��������āA�ߔN�͗������邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ����Ƃ̂��Ƃ������B���Ԃ�A�߂��ɉ����Ō�̌���n�ƂȂ��������Ս�������Ȃǂ����邱�ƂȂǂ��A�����������z�����Ȃ��ꂽ�w�i�ƂȂ��Ă���̂��낤�B
�@�ʐ��ӂ����w���I�������͎O�O�ꍆ���ɏo�āA���悢��A�����I���̒n�A�����m�̋u�ւƌ��������Ƃɂ����B�������R�i�ߕ����Ō�܂Œu����Ă����Ƃ���ł���B���C�Ȃ����z�z�������ƁA�������Ȃ萼�ւƌX�������Ă����B���̑��z�ɂ��������悤�ɁA���͎Ԃ̃A�N�Z����傫�����ݍ��B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
1999�N7��21��
���鉫��̑z���o�i11�j
�����m�m�u�ɂā@�@
�@�[�������������������Ă��A�����m�m�u�͉����������B���ł����邩�̂悤�ɂЂ�����ƐÂ܂�Ԃ��Ă����B���̒n�����̒n���G�}�̌J��L����ꂽ�ꏊ�Ɠ����Ƃ���ł���Ƃ͐M�����Ȃ��قǂɁA������͐X�ՂƂ��Ă��āA�v�킸�g���������܂銴���������B�咓�ԏ�ŎԂ���~�肽���́A�܂����a�F�O�����߂���A���ꂩ�畽�a�L�O�����A���a�L�O�����ٕt�߂��o�āA�C����\���[�g���قǂ̖����m�m�u�̒��ւƌ��������Ƃɂ����B
�@�U�h��Ő��K�R�̎������镺�͂������A����{����[�̖����m����쉮�����ɂ����Ă̈�тւƓP�ނ����߂�����R�́A�����I�ɓ��������\�O����Z�\�]�܂ł̒n���j���Z���Ə��q�w���Ō�����Ō�܂ŌR�ɓ��s�������B�����ۂ��A����R�̓암�P�ނɂ���Ēu������ɂ��ꂽ�V�l��q���A�w���q��̊Ԃɂ́A���藈��ČR�ɂ�������W�����Ƃ������|�������A�ނ�̂قƂ�ǂ����̏����������Ȃ��܂܂Ɏ���R�̂��Ƃ�ǂ��ē쉺����Ƃ������ԂɂȂ����B
�@���K�R�Ɠ��������ƈ�ʏZ���Ƃ����ׂƂ�����Ԃœ암�ւƑނ��̂�nj������ČR�́A�S�R�������ėe�͂Ȃ��C���������s�����B�����ۂ��A�퓬�\�͂��قƂ�ǎ����Ă������K�R�́A���\�����ɋ߂��s����Ԃ̒��ŁA�����̈�ʏZ���⓮�������������Y���ɂ�������łȂ��A�ނ�����ɂ�������Ƃ����ُ�ȏɒǂ����܂ꂽ�B�Ɍ��ɋ߂��p�j�b�N��Ԃ̂Ȃ��ŏ��X�ɗ�ÂȔ��f�͂������A�₪�ē��{�ɖ����͂Ȃ��Ɛ�]����ɂ������������̂Ȃ��ɂ́A���疽���҂��������ꂽ�B
�@��j�L�^�ɂ��A�ŏI�I�ȓ��{���̐펀�Ґ��͓�l���l��O�Z���A���̓���͐��K�R�Z���܋�Z�����A�n���ŕҐ����ꂽ�h�q����������A�������ꂽ�Z���퓬���͎Ҍܖ��ܓ�Z�l���A��ʏZ���㖜�l���l���ł������Ƃ����B�����ۂ��A�č��̌��������ɂ́A�����ɂ�����ČR�̎��҂͈ꖜ��ܓ�Z���ŁA�������R���l�Z���ܖ��A�C���������O�����A�C�R���l��Z�����ł������ƋL����Ă���B���łɏq�ׂ��悤�ɁA���{���̎��҂̑啔���́A�U�h��œ��{�R���s�ނ��A���������Q�d�̒ɂ��������ē암�ւ̓P�ލ�킪���s���ꂽ���Ƃɐ��������̂ł���B
�@�����̏Z�����g���]���ɂ��Ă܂Ő��Ȃ���Ȃ�Ȃ��������R�ɂ��āA���������Q�d�́A�u���{�{�y�����ƂȂ����ꍇ�A�R���݂̂Ȃ炸�A�V�c�w���q�Ɏ���܂őł��Ĉ�ۂƂȂ�A�c�y�h�q�ɒ�g���ׂ��ł��邱�Ƃ́A�����̕������闝�z�ł���w�����_�ł���A�킪�w���҂����̋������Ă�܂ʂƂ���ł��������炾�v�ƌ��A����ɁA�u���Ɩ����̋��S����ɂ�����闈����ׂ��퓬�ɂ����ẮA���悻�𗧂j�q�͂��Ƃ��Ƃ��R���̉��ɒy���Q���ׂ����������炾�v�Ƃ��q�ׂĂ���B
�@�����A�����ۂ��ŁA���̓����l���́A���a��\�N�Z����\�O�������A�㊯�̋���������R�i�ߊ��Ⓑ�E�Q�d�����������m�f�R�̓��A���Ŏ���������킪�I�������Ƃ������c��A�㊯�炪�������钼�O�̘Z����\���ɁA�C�������������̍��쒆���Ƃ��̂悤�ȑz������荇�����Ƃ������Ƃ�`���c���Ă�����̂ł���B���̓��e���O�q�̐푈�w�����O�Ƃ͂��܂�ɂ��������ꂽ���̂ł��邱�ƂɁA���͂�������������ʂĂ����ŁA�q�ׂ�ׂ����t���Ȃ��B
�@�u����s���Αc�����܂��S�ԁB���{�̏����͌��������Ă���̂ɁA�����̎w���҂����͂ق�Ƃ��ɕ����ʂ�ŖS�̓���I�Ԃł��낤���B�����~������Ȃ�A���͉������킪�����̏����������S�����Ȃ��Ԃɍ~�����ė~�����B�ہA�킪�w���҂����́A���̖{�\���玩�Ȃ̒n�ʁA���_�A�����Đ����̈���ł���������̂���]���āA�킪�����̓�O�����]���ɂ��Ă��ӂɉ�Ȃ��Ȃ��̂ł��낤���v
�@���͂�s�\�Ȃ��Ƃł͂��邪�A���̌��t�̒��́u�킪�����̏������v�Ƃ����������u�����̉���Z�����v�ɁA�܂��A�u�킪�����̓�O�����]���ɂ��Ă��v�Ƃ����������u����Z���̏\����\�ܖ�����]���ɂ��Ă��v�ƒu�������������ŁA���̂܂ܔ����Ƃ����l���ɓ˂��Ԃ������v��������̂́A���̎������Ȃ̂��낤���B
�@�g�D�Ƃ��Ă̈ӎv���肪�������Ȃ������Ɣ��������ꍇ�A���̐ӔC�̏��݂��B���ɂȂ�悤�ɂ��炩���߈Ӑ}���ꂽ�\�������̂́A�킪���̊e��g�D�̍ł���������ƌ����Ă悢�B���{�×��̒k�����_�Ƀ��[�c�������̂悤�ȑg�D�̂̂��肩���́A���Y�g�D�������ɋ@�\���Ă���Ƃ���g�D���������肪�����ȂƂ��͓s�����悢���A��������傫�ȕs�ˎ����N��������A�ً}�ɑg�D�Ƃ��Ă̈ӎv����▾�m�ȐӔC�̏��݂��v������鎖�Ԃ��������肵�����ɂ́A���̌��ׂS�Ȃ܂łɂ��炯�����B
�@���̂悤�ȑg�D�̂ɂ́A���ڏセ�̑g�D�̒��߂�҂��܂߂āA�N��l�Ƃ��Ď��ȐӔC�̂��Ƃɐv���Ȏ��Ԃ̎��E���͂��邱�Ƃ̂ł���҂����݂��Ȃ����A���Ƃ����݂����Ƃ��Ă��\���セ�����邱�Ƃ�������Ă��Ȃ����炾�B����̖��f�������҂₠�ƂɎc���ꂽ�҂ɂ͉��̋~���ɂ��Ԃ߂ɂ��Ȃ�Ȃ��A�u�����v�A�u���E�v�A�u���E�v�Ƃ������A�l�܂�Ƃ���͊ԐړI�Ȏ��Ȕ����Ƃ������邨���܂�̑Ή����Ȃ���A���ǂ��ׂĂ͂���ނ�ɂ���Ă��܂��B
�@���疀���m���ӂւƓP�ނ��Ă���̎���R�́A�����Ђ�����Ō�̏u�Ԃ�҂��c�Ȕs�핔���ȊO�̂Ȃɂ��̂ł��Ȃ������B�c��������R�́A��[�̊쉮�����Ɩ����m�m�u��т̌���ꂽ�n��ɒǂ��l�߂��A�ČR�̖C�Ɉ���I�ɂ��炳��邾���̑��݂ɂȂ����B�q�ϓI�ɔ��f����A�S���ʍӂ͎��Ԃ̖�肾�������A���̂悤�ȏ�Ԃ��ÂɌ��ߓ��~���͂���҂͂قƂ�ǂ��Ȃ������B���S���ꂪ�őP���ƍl�����w�����������Ƃ��Ă��A���{�I�g�D�̂Ȃ��ɐ��܂肫�������̐g�ɂƂ��āA��������s�Ɉڂ��͕̂ʂ̑傫�ȗE�C��K�v�Ƃ����ɈႢ�Ȃ��B���̘I�Ə�������\�]���̐l�X�̒��ړI�ȉ��O��A����ɑ���c���ꂽ�l�X�̂���̂Ȃ��{������A�u���́v�Ƃ������̎��̂̑��݂��Ȃ��S��̂ق����A��X���{�l�ɂƂ��Ă͍����̂������Ƌ��낵���Ƃ������Ƃ������̂ł��낤�����B
�@�ǂ��l�߂�ꂽ����R�����Ă�����쉮�������疀���m���n��т̔w��̊C��́A�召�����̕Ċ͑D�Q�ɂ���č��X�ƕ����s�����ꂽ�B�����āA�����̊͑D�Q����́A����̕ʂȂ��A�쉮�����▀���m���n�̎���R���_�ɑ��Ėҗ�ȖC�������J��Ԃ��ꂽ�B�܂��A�q��@�ɂ��e���������������߁A���ォ��͂l�S��ԌQ�Ƃ��������ɂ����Ēn��R���l����������W���W���ƕ�͖Ԃ����߂Ă����B���̍��ɂȂ�Ǝ�������̎��҂͘A�����l���A�폝�҂̐��͂�����͂邩�ɏ������B����ɁA���̐퓬�̂��Ȃ����E���������ē����f���A�Ȃ����ׂ��Ȃ��|��Ă����������̔�퓬�������̗L�l�́A�n���G�}���Ȃ���ł������Ƃ����B
�@���܂�m���Ă͂��Ȃ����Ƃ����A���������̓����⍈�ɉB����ʏZ�����~�o���邽�߁A�i�ߊ��o�b�N�i�[�����̎w�߂����ČR�́A�J���t�H���j�A��n���C�ɏZ�މ���o�g�̈ꐢ��̂�������ق̓��ӂȎ҂����I���}篑O���ɑ��荞�B�����āA�ނ�Ƀn���h�X�s�[�J�[��n���A�����⍈���ɐ��ސl�X�Ɍ������āA���S��ۏႷ����O�ɏo�Ă���悤�ɂƌĂт����������B���̐����H��ɂ���Ė����~��ꂽ�Z��������Ȃ�̐��ɂ͂̂ڂ������A�c�O�Ȃ��ƂɁA���҂��ꂽ�قǂ̌��ʂ͂�����Ȃ������B�ČR�̐����ɉ����邱�Ƃ̓X�p�C�s�ׂ◠��s�ׂ��Ƃ݂Ȃ���A�w�ォ��e�e����ԃq�X�e���b�N�ȏ̂Ȃ��ł́A�~���̂��߂ɐs�����ꂽ������w�͖͂��ׂɓ��������̂ƂȂ����̂������B���ꏗ�q�t�͂̎Ⴂ�w������Ȃ�Ђ߂�蕔���̔ߌ��́A���̏ے��Ƃ������ׂ��o�����������B
�@�o�b�N�i�[�����́A�Z���\���t���Ŏ���R�i�ߊ��������������ɍ~��������𑗂��Ă����B�u�t���̗�����R���͗E���ɐ킢�P�킵�܂����B���{�R�����̐헪�́A�t���̓G�ł���ČR��������������h�����Ƃ���ł���܂��v�Əq�ׁA����R���~�����邱�Ƃd�Ɋ����������̏���́A�ǂ������o�܂̂䂦���͕s�������A�����i�ߊ��̎�ɂ͓͂��Ȃ������Ƃ����B�O�x�ڂ̍~�������Z���\�����ɂȂ��Ă���Ƌ����i�ߊ��̎�ɓ͂������A�ނ͂�����ΎE����ɏI������Ɠ`�����Ă���B
�@�����i�ߊ������̌ܓ��قǑO�̂��̎��_�ʼn���킪�I�����Ă���A�펀�Ґ����ܖ��l�͏��Ȃ��Ă��낤�Ƃ�������������悤���B�������A���łɎ���R�̎w���n����ʐM�Ԃ����f���A�e�c�������̏�������ʏZ�����ɓx�̃q�X�e���[��Ԃ̒��Ŏ��Ȃ̔��f�Ɋ�Â��Đ퓬�s���𑱂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��������Ƃ��v���ƁA���ʂ͂قƂ�Ǖς��Ȃ��������낤�Ɛ��@�����B�����i�ߊ�������������̏�����Z������A�O���������������������Ƃ����������A���̂��Ƃ𗠕t���Ă���ƌ����Ă悢�B�v����ɁA���ׂĂ͌�̍Ղ������̂��B
�@�������R��]���ĎO�ɂ킽��ČR�̍~�����������������ɂ�������炸�A�ČR�͑�ʂ̍~�������r�����܂��A��莞��������ƖC���𒆒f���Ĉ�ʏ����⓮���Z���ɓ��~���Ăт������B�ČR�̋L�^�ɂ��ƁA�Z���\�������ɂ͓��~�҂��\�l�قǂɂȂ�A���\����ɂȂ�Ǝ����I�ɓ��~���镺�m�̐��͎l�S�l�ɋy�Ƃ����B�S�̂��炷��킸���Ȋ����ł͂��������A�ČR�̓w�͂͂܂��������ʂ������킯�ł͂Ȃ������悤�ł���B
�@����ɂ��Ă��l�Ԃ̉^���Ƃ������͔̂���Ȃ��̂ł���B��������R�i�ߊ��ɍ~��������𑗂����ČR�i�ߊ��o�b�N�i�[�����́A�Z���\�����̌ߌ�ꎞ���A�����̍Ō�̐i�������@���邽�߁A���C���t�c�攪�A���̑O���Ď����ɏo�������B���̎��@�ɏo�����ɐ旧���āA�ނ͑�Z�C���t�c���\��A�����n�����h�E�g�E���o�[�c�卲����A���{�R�w�n���炩�Ȃ�̗��e������̂őO���̎��@�͌������悤�ɂƂ̌x�����Ă����B�������A�ނ͂��̌x����������A�����̌�������˂đO���ɗ������B
�@�����āA���̒���A����R���̑_�����̕������ꔭ�̏e�e���o�b�N�i�[�i�ߊ��̋��ɖ����A�ނ͂��̏�ŗ��������̂������B�������A�o�b�N�i�[�����Ɍx���������o�[�c�卲�̂ق������̂��悻�ꎞ�Ԍ�ɑ_������Ď��S����Ƃ�����d�̕s�^�ɏP��ꂽ�B�s�R�̏������i�ߊ��̎��������������o�b�N�i�[�ČR������ʑ��i�ߊ������S�����Ƃ��������́A�P�Ȃ�^���̔���Ƃ��������āA�����̓��ė����̌R���̂��\���I�ȈႢ�Ƃ������̂��������������Ă����B
�@
�@�����m�m�u�咓�ԏꍶ��̉��ꕽ�a�L�O���ɂ́A����̐��|�p�ƎR�c�^�R���q����\��N�̍Ό��������Ċ����������a�L�O���������߂��Ă����B��ʂ̎���s�˂Ă͂����͋сi������j�Ƃ�������Ǝ��̍H�@�ő���ꂽ���̋L�O���́A�����\�Z���[�g���A�������[�g��������A����ɔ�₳�ꂽ���̑��ʂ͎O�\�܃g���ɂ��y�Ƃ����B�R�c�^�R�͎���𓊓����đ��̐���Ɏ�肩���������A�r���Ŕ�p������Ȃ��Ȃ�A���̕⏕�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����B
�@�Ƃ��낪�A�͂��ߐ�����Ӑ}���������̊ω���F���̂܂܂ł͓���@���̏ے����ւ̍���̓������ւ���@���ɐG��邽�߁A�⏕������t���Ă��炤�͍̂���Ƃ������Ƃ����������B�����ŁA�}篁A����̘@�̉Ԃ�ʂ̉Ԃɂ����A���쒆�̑����ω���F���ł͂Ȃ��A�����܂ŕ��a�L�O���ł���Ƃ������Ƃɂ��A�⏕�������炤���Ƃ��ł����Ƃ����G�s�\�[�h���c���Ă���B���̎R�c�^�R�͑�����������̂�ڂɂ��邱�ƂȂ����E�����Ƃ����B
�@���ꕽ�a�L�O�����疀���m�m�u�̒��ւƌ������r���ɂ͍L�X�Ƃ������a�L�O�����������āA���̍���̈�p�ɕ��a�L�O�����ق������Ă����B���̎����قɂ͉����̊e����n����W�߂�ꂽ�l�X�ȕ���╺�m�̏����i���_�ȏオ�W������Ă����B�e�͂Ȃ��C�̂��ƂŐ��̎r�Ɖ�����������ʎ傽���ɂ�����āA�����W���i�̈�ЂƂ́A�푈�̔ߎS���ƍ�����X�Ƒi�������Ă��邩�̂悤�������B����l���ꂼ��̊������ɂ����̂ł��낤���A���ɂ́A�Âт��e�C����S���A��ᴁA�e���L�ނɂ�����܂ł̕i�X�����ꂼ��ɂ����̉��O���Ă���悤�ɂ����v��ꂽ�B
�@���a�L�O�����ق��班���s�����Ƃ���ɂ��镽�a�L��̎�O�ɂ͓���̓��������Ă����B���̈ԗ쓃�͓����̉��ꌧ�m�����c�b�牫�ꌧ���E���O�܈ꖼ�̗�����J�������̂ł���B���a��\�N�ꌎ�A�܂Ɣ��̖т��Ƒ��Ɏc���Đ�n����ɒm���Ƃ��ĕ��C�������c�́A�H���̊m�ۂƓ����̈��S�̂��߂ɖz�������B�Ō�͎���R�ƍs�������ɂ������A�Z���\���������ɔނ͏����������Ƃ����B�����m�m�u�̂ǂ����œ|�ꂽ���̂Ǝv����B
�@���a�L���тɂ́A�����̐펀�҂̖��O�����ԗ�肪�����Ɨ�������ł����B���̐��Ő펀�������m�̏o�g�n�́A���{�̑S�s���{���ɂ킽���Ă���A�ԗ��ɍ��܂ꂽ��v�Җ��͏o�g�n���Ƃɐ����z��Ă����B�ԗ��ɓ��{���̖��O����łȂ��A�펀�����ČR���m�̖��O�����܂�Ă���̂͂ƂĂ���ۓI�������B
�@���a�L��̈ԗ��Q�̊Ԃ��ĎΖʂ�o��߂�ƁA�C�����\�チ�[�g���̖����m�m�u�̒���ɏo���B����R�Ō�̎i�ߕ����u����Ă������A�̐^��ɂ��邱�̉����I���̒n�ɂ��t���̓��������Ă����B����̐ՂƂ͐M�����Ȃ��قǂɐÂ܂肩�����u�̏ォ��́A����암����]���邱�Ƃ��ł����B���ɐl�e�̂Ȃ����̋u�̒����Ɉ�l�Ȃ݁A�Ō�̐퓬�̏�z�����Ȃ���C�Ɨ[��߂���Ă��邤���ɁA�ǂ���玄�̐g�̂͂����̗�C�ɕ�܂�Ă��܂����悤�������B������Ƃ������o���Ƃ��Ȃ����̕s�v�c�ȋC�z�ɓ������܂܂ɁA���͋u�̓쑤�f�R��D���ĊC�݂ɑ����}�ȍד�������͂��߂��B�T���Ƃ������M�ю��тɕ����邻�̒f�R�̂Ȃ��قǂɂ́A�������i�ߊ��ƒ��E�Q�d�����������������A�����܂����̂܂c���Ă��āA�����ɂ��Â��҂��������̏����͂��̓��A�̂ق��ւƑ����Ă���̂������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
1999�N7��28��
���鉫��̑z���o�i12�j
������ʖ����̍��ɕ����@�@
�@�u�����炻�̏�̕��͋C�ɗU���ĂƂ͂����Ă��A�[���Ɉ�l�ł���ȂƂ����K�˂�Ȃ�ĕ��D���ȁI�v�ƌ�����A�������ɂ�����������Ȃ��B�����A�����A���͖쎟�n�����̉�݂����Ȑl�Ԃ����A�q���̍�����l��������悤�ȂƂ�����x�������̂����C�������B����ɁA�[���Ƃ͂����Ă��܂�������͂��Ȃ薾�邩�����B������A�������R�Ō�̎i�ߕ����u����A�����i�ߊ��ƒ��Q�d���������������Ƃ������̓��A�����̖ڂŌ��Ă݂����Ƃ����ӎ������ݓI�ɓ����Ă����Ƃ��Ă����������͂Ȃ��B
�@���̓��A�́A�����m�m�u�̒��ƊR���̊C�݂Ƃ̂��傤�ǒ��Ԃ̂Ƃ���ɂ������B�ۂ�����ƊJ�����傫�ȓ����t�߂ɂ́A�������i�ߊ��ƒ��E�Q�d���������a��\�N�Z����\�O�������ɂ��̏ꏊ�Ŏ����������Ƃ��q�ׂ��ꕶ�ƁA���������̎����̋�Ƃ��L�����肪�����Ă����B�u���R�叫�������v�ƕ\�L����Ă���Ƃ�����݂�ƁA����Ɂu�叫�v�ւ̏��i���Ȃ��ꂽ�̂��낤�B�i�ߊ���Q�d�����͎�����������̋�Ȃǂ̏����ꂽ��Ȃǂ𗧂Ăė���Ă��炢�A�c���ꂽ�⑰�ւ̔N����t�z�Ȃǂɂ��W����K�����i�̔z�����Ȃ��ꂽ����悢�悤�Ȃ��̂́A�Ȃ�̌��Ԃ���Ȃ��܂܂ɐ��̘I�Ə����A�⍜�������s���̂킩��Ȃ��Ȃ���������m���ʓ����̗�Ȃǂ͉i���ɕ�����Ȃ����낤�B
�@�����̓�����ɋ߂������̕ǖʂ⏰�ʂ̂����������Ă�������ŒY�������悤�Ȋ����ɂȂ��Ă���̂́A�Ō�̐퓬�̍ۂɕČR����Ή����ˊ�┚���ɂ��U���������Ȃ̂�������Ȃ��B�Â������̉��ɂ������Ă݂����A�ꌩ�����Ƃ���ł͂���Ȃɉ��s���̂��銴���ł͂Ȃ������B�����Ƃ��A������т͕ČR�̖җ�Ȕ����ɂ���ĕ���ό`�����Ƃ�������A�����͂����Ɛ[�����ɂȂ��Ă����̂�������Ȃ����A�����̈łɎז�����Ȃ���A���Ȃ�[���܂ōB���������Ă���̂��m�F�ł����̂�������Ȃ��B
�@�ڂ����X�ɓ����̈Â��ɂȂ�Ă���ɂ�āA�ڂ���Ƃł͂��邪���A�ǖʂ⏰�ʂ̗l�q���킩��悤�ɂ͂Ȃ��Ă����B���������ɔ����ۂ����̂�����̂悤�Ȃ��̂�������̂́A���N�X��ʂ̈ꕔ�����̂܂c�������̂��A�����Ȃ������炪�ΊD�≻�������̂ł��낤�Ɛ������ꂽ�B�ꏊ���ꏊ�Ȃ����ɁA�܂�œ����̂��������ɐl���̒f�Ђ��U����Ă��邩�̂悤�ȍ��o�ɂƂ��ꂽ�قǂ������B
�@�ČR�������m�m�u�̒��ւƐi�o���A����R�i�ߕ��̂��邱�̓��A�ւƔ����Ă���i�K�ɂȂ�ƁA����������A�߂��̐���܂Ő����ɍs�������ł��A�ܐl����l�͏e�����Ď��S����ɂȂ����Ƃ����B�������Ԃ̕��m�����́A����ł����g���ɕ�����Ė������̐����ɏo���������A����͂܂�ŁA���V�A�����[���b�g�A���Ȃ킿�A���{���o�[�e�ɂ�鎀�̃��[���b�g���̂܂܂̍s�ׂł������B�����Ƃ��A����������ēG�w�֓˓�������ꂽ�����̊w�k�������≺�����m�Ɋr�ׂ�Δނ�̂ق����܂������܂���������������Ȃ��B���e���U������ʎa�荞�ݑ����́A�u���̃��[���b�g�̉��b�v�ɂ��痁���邱�Ƃ�������Ȃ���������ł���B
�@����Ȑؔ������̂��Ƃɂ����āA���̓��A���ɂ����ẮA���������Q�d�ƍ���C�������������̊ԂŁA�����i�ߊ��ƒ��Q�d�����̎����̒i��肪�b�������Ă����悤�ł���B���̌��ʁA��l�����A���Ŏ�������ƁA�X��₪�ł��Ēn���ɖ��߂邱�Ƃ��ł��Ȃ����A�ČR�ɂ���������₷�������A��ࣂ�����̂������Ɏc��͕̂s�l������A�����m�̒f�R��Ŏ������Ă��炢�A��[�͂��̂܂ܒf�R�����̊C���ɓ����Đ����ɂ����ق����悢�Ƃ������ƂɂȂ����炵���B
�@�����ƍ���̗��҂͎c������R�����������Ė����m�x�R������[�ɂ����ĕz�w���Ă���ČR�Ɉ�ēˌ������s�����A���̊Ԃɋ����i�ߊ��ƒ��Q�d�����ɋu�̏�Ŏ������Ă��炤�Ƃ����؏����𗧂Ă��B�����āA�Z����\����锼�����m�m�u�����D��A��\�O�������ɂ����ŗ����R�̎������s���邱�ƂɂȂ����B�����O�\�Z���`�A���\�Z���`�̓̔ō������l�̕�W���p�ӂ��ꂽ�Ƃ����B
�@�������A������ڑO�ɂ����ČR�̔����͐��܂����A�����m�x�R���̒D��͎��s�����B���̂��߁A�����A���̓�l�́A��ނȂ����Ă��̓��A�����t�߂ő������Ŏ��������B�Z����\�O���ߑO�l���O�\���̂��Ƃ������Ɠ`�����Ă��邪�A���m�Ȏ����̓����A�ꏊ�A���@�Ȃǂɂ��Ă͗l�X�Ȑ�������A���݂ł��^���͖��炩�ɂȂ��Ă��Ȃ��B����ɂ��������ꕔ�̎҂ɂ����킩��Ȃ��������G�Ȏ���������̂ł͂Ȃ����Ɛ��@�����B
�@����ɂ��ƁA�������i�ߊ��́A�����̒��O�Ɂu����̐l�����͎������݂Ɏv���Ă���ɈႢ�Ȃ��v�Əq�ׂ��Ƃ������A���ꂪ�������Ƃ���A���̌��t�̔w�i�ɂ������v���Ƃ́A���������ǂ�Ȃ��̂������̂��낤�B���̒��x�̐\���J���ʼn���̐l�X�̉��O�����炳�����̂ł͂����Ƃ́A�����i�ߊ����g�������Ƃ��悭���o���Ă����͂��ł���B�����������łȂ������Ƃ���A���O�ƌ����ق��Ȃ����A�Ƃ������A�������ĔߎS���ɂ߂������͏I�����݂��̂������B
�@�i�ߕ��̂��������A���o�����́A���ւƑ����}��襘H�����ǂ��ĊC�݂ւƍ~��Ă݂邱�Ƃɂ����B�ׂ����̗����ɍL����Ζʂ̐[���M�∟�M�уW�����O���̓y���ɂ͂��܂��ɐ��m��ʈ⍜�̒f�Ђ�������Ă��āA���݂ł��y���@��Ԃ��Ƃ����̈ꕔ��������Ƃ����b�͕����Ă������A�Ȃ�قǎv�킹�镵�͋C���������тɕY���Ă��銴���������B�R���̊C�݂͒��a��`�O���[�g���قǂ̑��召�̊�X�̗������ԍr��ɂȂ��Ă��āA��ɊJ�����C�ォ��͋����ɐ�����悤�ɂ��Č������g���ł��Ă����B
�@�O���ɂ͂ЂƂ��퍂���藧�f�R�������āA���̒f�R�ɎՂ��邩�����Ŏ��̗��r��͍s���~�܂�ɂȂ��Ă����B�����m�m�u�̓�[�ɂ��т����A�̒f�R���A�����m����т̊C��ɓW�J���Ă����Ċ͂̕��m�����́u���E�f�R�v�ƌĂƂ����B�ČR�ɒǂ��l�߂�ꂽ�����̉������s�c�������́A���X�ɂ��̖����m�m�u�̒f�R�ォ��C����R���̊��Ɍ������Đg�𓊂����B�ڑO�ɓW�J���闝���������S�Ȍ��i�ɁA�͏�̕ĕ������͌��t�������B��R�Ƃ������ł������Ɠ`�����Ă���B
�@���͂��������召�̊��`�������Ēf�R�̐^���܂ŋ߂Â��Ă݂��B�f�R�̊C�ɖʂ��������₻�̌��������̗l�q���ǂ��Ȃ��Ă��邩�͂킩��Ȃ��������A���̗����̑����͊p�������召�̊₾�炯�ł������B�����ɂ��т���f�R�ォ�炱�̊��Ɍ������Ĕ�э~�肽��ЂƂ��܂���Ȃ������낤�B���a��\�N�Z����\���O��ɂ́A���̈�т̊�X�͈�ʎ�ɐ��܂��Ă����ɈႢ�Ȃ��B�����̋���Q���d�Ȃ��Ă���Â��[�����Ԃ̒�ɂ́A���܂��Ȃ������̈⍜���l�m�ꂸ���薄����Ă���悤�ȋC�����ĂȂ������B
�@�������̔ߌ����ÂтȂ���A����̒f�R�������ƌ��グ�Ă���ƁA�ˑR�A���́A�S�g�������̋C�z�ɕ�ݍ��܂��悤�ȁA�ٗl����܂�Ȃ����o�ɏP��ꂽ�B�g�̂̉����������Ɛk���A���������悤�Ȑ�Ɋ��Ƃł������\�킵���ق����悩������������Ȃ��B��C���������Ƃ����\���������Ƃ����������̂́A���Ԃ�A����Ȏ����낤�B���́A�����̐S�𗎂������邽�߂ɁA�q���̍������}�i����j�Ă���ʎ�S�o�̈�߂˓I�ɋ��̉��řꂢ���B
�@�q���̍��ɔʎ�S�o���������̂́A���킢���Ȃ����Ƃ����������������B���t�J�f�B�I�E�n�[���́u�������F��v��ǂ�ł��邤���ɁA���̐g�̂ɏ����ꂽ���o�̕������ʎ�S�o�̂��̂������Ƃ������Ƃ�m�����B�쎟�n���_�ɗU����܂܂ɁA���d�̑O�ɂ������o�{�̈�������o���Ē��ׂĂ݂�ƁA���܂��܂��ꂪ�ǃK�i�̂ӂ�ꂽ�ʎ�S�o�������̂ł���B�Ӗ����킩��ʂ܂܂ɂ��̌o�����ËL�������Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B���̌o���̂��[���Ӗ����w�̂͂����Ƃ̂��̂��ƂɂȂ邪�A����Ȕʎ�S�o�ɈӊO�ȂƂ���ł����b�ɂȂ����Ƃ����킯�������B
�@�l�Ԃ̐S�Ƃ������͖̂��Ȃ��̂ł���B����ȋْ���ٗl�ȕ��͋C�̒��ɒu���ꂽ�肷��ƁA�܊����ُ�ȋ����ƍ����𗈂����A���̌��ʁA���Â��������l�̐S�͌��o�⌶���̗��ɂȂ�B�����A���Ƃ�����炪��Ȃ鑶�݂ł������Ƃ��Ă��A���l�ɂ͂܂�����Ȃ����݂Ɋ�������킯������A�b�͂������ėe�ՂłȂ��B
�@�ǂ����Ă����͐M�S�[���l�Ԃł͂Ȃ����A���̐��̌��ۊE���\��������]�i������j�A���Ȃ킿�A�F�i�����y�ѓ��́j�A��i���o��m�o�j�A�z�i�e��T�O�Ƃ��̍\���́j�A�s�i�L����ӎu�j�A���i�����Ȉӎ��j�̌܂̑��݂���Ȃ�W���݂̂͂ȋ�ł���A���̂��Ȃ��Ɛ����A���ɓI�ɂ͂��̋��`���̂��̂���ł���Ƃ���ʎ�S�o�̋����͍D���ł���B����Ԃ��A�M�S�[���l�ԂłȂ����炱���A�ʎ�S�o�̋��������ɍ����Ă���̂�������Ȃ��B����ɔʎ�S�o�͒Z���Ċo���₷���̂��Ȃɂ����悢�B�l�̐S�Ɉُ�ȋ�����ϑz���������Ƃ��ɂ́A���̐S�o�̓g�����L���C�U�[�Ƃ��Ă̌����ڂ����B
�@�C���h�×��̂���Ȑ��_����܁i�H�j�̂����ōĂї�Â������߂������́A�Ȃ̐S����u�����������A�C���������Ƃ��Ȃǂɉr�މ䗬�̉̂ɑ�����ƁA�[���̔��門���m�̒f�R�����Ƃɂ����B���Ԃ�A���̖����m�m�u��тʼn����ɜ߂��ꂽ�悤�Ɏ���ł������l�X�����Ă������̂��A�����Ĕނ炪�����Ɏ�낤�Ƃ������̂��A�u���́v�Ƃ������ʂ����Ԃ��������̈��삾�����ɈႢ�Ȃ��Ǝv���c�c�B
�@�E�ъ���C�ɉr���S�ނ��k���ė��Ă薀���m�̊R��
�@
�@�咓�ԏ�ɖ߂������́A��}���ňԗ��u�Ђ߂��̓��v�̌��n�_�ւƎԂ𑖂点���B������͗[�łɕ�܂�͂��߂Ă����̂ŁA�Ђ߂��̓���Ђ߂�蕔���̎S���̏�ƂȂ����n�����̎��ӂɂ͐l�e�͌�������Ȃ������B���̒��ɗ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ������̂ŁA��������O�A�l���[�g���̐[���̂Ƃ���ɂ��铴�����O���璭�߂��낵���������������A���x�ƂȂ��f��⏬���̕���ɂ��Ȃ����Ƃ��낾���ɁA��l�����ɗ����S�͂ЂƂ����������B
�@�����ɂ�����ߌ��I�ȏW�c���͓����̂�����Ƃ���ŋN�����Ă���A���̂��������̂��ƂȂ�Ђ߂�蕔���̂���͎��Ґ��S�̂̂����ꕔ�ɂ����Ȃ��B�������A��������Ⴂ���q�w���̔ߑs�ȏW�c���ł����������ɓ����̎Љ�ɗ^�����Ռ��͑傫���A���̔ߌ��͂̂��̐��܂ŘA�Ȃƌ��p�����Ƃ���ƂȂ����B
�@�]�R�Ō�w�Ƃ��ė��R�a�@�̊O�Ȃɔz�����ꂽ���ꌧ����ꍂ���Ɖ��ꏗ�q�t�͂̐��k�����́A�Ђ߂�蕔�����\�����A�܌����{���̖����m�Ɍ��̒n�����ɂ���Ă����B�������Ȃ���A�Z���\�����܂łɂ��̍��̎��ӂ͊��S�ɕČR�ɐ�������A���a�@�͉��U�̂�ނȂ��Ɏ������B�Ƃ��낪�A�s�^�ɂ����̖��߂̓`�B���\���ɍs�Ȃ��Ȃ��������߂ɁA�����̂Ђ߂�蕔���Ō�w�����͌Ǘ������܂ܒE�o�s�\�ɂȂ����̂������B
�@���@�m�����ČR�́A�U�����d�|����O�ɉ��x�����O�ɏo�Ă���悤�����H������݂����A���̐���������t���邱�Ƃ͂��ɂȂ������B�����\�l�A�܍̏��^���C�ȏ��������́A�ߗ��ɂȂ�ƕĕ��ɖ\�s����E�����Ƃ�������R�̐�`��^�ɂ����A�Ō�܂ō��̉��ɗ��Ă�����Â�������ł���B
�@�ČR�ɂ���čŏI�I�ȍU�����s���钼�O�ɐ����݂ɍ��O�ɏo���O�l�ƁA�ČR�̍U�����ՓI�ɏ���������l�̌v�ܐl���̂����A���q�w���ꔪ�����Ƌ��t�\�O������Ƃ̎��𐋂����B�`������Ƃ���ɂ��ƁA���w�������͔��߂𐧕��ɒ��ւ��A�Z�̂��̂��Ȃ��玀��ł������̂��Ƃ����B
�@����܂łƐM���ĎU�肵������E�i�Ƃ��j������ƚo�i���j����������
�@�[�܂�[�ł̂Ȃ��ʼn������̎S���̗L�l��z�����Ȃ���A�ޏ������̗�ɂ���Ȃ����₩�Ȓ����̂����������́A�Â��ɂ��̏�𗧂��������B
�@����������͔��Â��Ȃ肩���Ă������A�����܂ŗ������łȂ̂ŁA���͉���{���œ�[�̍r��ɋ߂��Ƃ���ɂ��鍰鮂̓���K�˂Ă݂邱�Ƃɂ����B�����ׂ��A���Ȃ�킩��ɂ����Ƃ���ł͂��������A�u��鮂̓��v�̂���ꏊ�ɂ͖������ǂ�����Ƃ��ł����B���̕t�߂ɂ͍�鮂̓��̂ق��ɁA�k��̓��A�����̓��A�����̓��Ȃǂ̈ԗ������Ă��Ă����B���̈�т͖����m�m�u�ƕ���ʼn����Ō�̌���n�ƂȂ����Ƃ���ł���B��ケ�̒n��ɓ��A�������������͎R��┨�n�ɎU�����u���ꂽ�܂܂̈⍜���W�߂č��J���A�ԗ��u��鮂̓��v�����Ă��̂������B�W�߂�ꂽ��̂̐��͎O���ܐ�̂ɂ��y�Ƃ�������A�����ɔߎS�Ȑ킢�ł����������z�������B
�@��鮂̓��ׂ̗ɂ́u�k��̓��v�������Ă����B�����ɂ�����펀�҂̏o�g�n�͓��{�̑S�s���{���ɋy���A���̂����ł����Ƃ��������߂��͖̂k�C���̏o�g�҂����ł������B�ꖜ�l�疼���邻���̐�v�҂̗�����߂ɁA���܂��Ȃ��k�C���̈⑰�����̎�ɂ���Ă��̓��͌��Ă�ꂽ�B�u�����̓��v��u�����̓��v�����l�̔w�i�����ԗ��ł���B
�@���ł̐[�܂�쉮�������ӂ���ʂ菄��I�������ƁA���͋��ƂŗL���Ȏ������Ď̃O�����h�E�L���b�X���E�z�e���ւƖ߂邱�Ƃɂ����B�����͗Ǎ`�Ɍb�܂�A���̒n�ɏZ�ސl�X�̐�c�����͌×��Ɠ��̋��@�Ő��v�𗧂ĂĂ����B�̂̎����̋��v�����́A�T�o�j�ƌĂ�钷�����`�����[�g���̑D�ɏ���ē���A�W�A����C���h�m�ɂ܂ŏo�������̂��Ƃ����B�ǂ��������g���ԁA��{�ނ�A���ĖԂȂǁA�����̋��v�����̗p�����l�X�ȋ��@�́A���{�����̊e�n�ɂ��`���L�����Ă������B�����s�����������߂���A��C���Ղ⋙�J�W�̌Â������j�Ղɐڂ������Ƃ����v���͂��������A�����s�X�ɂ������������Ƃ��ɂ͂��łɖ�ɂȂ��Ă����̂ŁA���ꂾ���͒f�O������Ȃ������B
�@�����͉���𗣂����ɂ������Ă������A���̓��̌ߑO���A���͓ߔe�̏�����ɂ���L����̋��C�R�i�ߕ��������K�˂Ă݂��B�ߔe�s�X�₻�̉������̊C�����n������ɂ��邱�̒n�������ɂ́A�����{�C�R�Ō�̎i�ߕ����u����Ă����B�����m�̎���R�i�ߕ��ח��ɏ\���قǐ旧�A���a��\�N�Z���\�O���܂łɁA��c�������������l�疼�̏����͂��̍����Ő펀�𐋂����B�n���O�\���[�g���̂Ƃ���Ɍ@��ꂽ�i�ߕ����́A�S����ܕS���[�g���ɋy�ԑ�K�͂Ȃ��̂ŁA�C�R�i�ߎ��A��펺�A�������A�M�����A���Z���Ȃǂ������̂悤�ɕ�������Ă����B�Ђ���Ƃ�����C�̕Y�������̕ǖʂɂ͓����̃c���n�V��L�̐Ղ����X�����c��A���̍��Ղ𒇗����ɂ��āA�Ŋ��̏u�Ԃ�O�ɂ������������̒Ⴂ����߂������܂ɂ������ɋ����Ă������������B
�@���C�R�i�ߕ��̂��������\�����ɂ́A��ꖜ�l�̊C�R�����������h�q�v���Ƃ��Ĕz����Ă͂������A���K�̊C�R�R�l�͂��̎O���̈���x�ɉ߂����A�c��͌��n���W�̖h�q��������Ȃ��Ă����B���܂��ɁA���K�R�l�̂����n���̎��n�P�����Ă����̂͂킸���O�S�����x�ŁA����킪�n�܂�܂Ŏ���o���͊F���������B���̂��߁A����R��]�͘Z���ɓ����Ă����ɊC�R������암��ނ�����\��ł������A�A���̍s���Ⴂ�◼�҂̎v�f�̈Ⴂ�Ȃǂ������āA�C�R�����͂����葁���܌���\�Z���ɖC���@�֏e���j���암�ւƓP�ނ��Ă��܂����B
�@�����m��������R��]�́A�Ή��ɋꗶ�������ƁA���ǁA��c�C�R�i�ߊ����܂ފC�R�����ɑ��ď��\�̊C�R�w�n�ւƕ��A����悤���������B���łɏd�Ί�ނ�j�Ă��܂��Ă������߁A���\�֖߂����C�R�����͎g�p�s�\�̔�s�@����@�֏e���������O�����킷��Ƃ�������̍���Ƃ�������������A���͂ȉΊ�Ŕ���ČR�ɍR���邱�Ƃ͓y�䖳���Șb�������B
�@�Z���ܓ��ɂȂ��Ď���R��]�͑�c�C�R�i�ߊ��ɓ암�ւ̓P�ނ𑣂����A���łɂ��̎��ɂ͊C�R�����͕ČR�C���t�c�ɂ���Ċ��S�ɕ�͂���A�E�o�͕s�\�ȏɂȂ��Ă����B��c�i�ߊ��͓����A����R�i�ߊ��ɓd�M�𑗂�A�u�C�R�����͂��łɊ��S��͂���P�ނ͕s�\�Ȃ��߁A���\�n��ɂōŌ�܂Ő키�v�ƒʍ������B
�@�ʍӂ��o�債����c�i�ߊ��́A�����̔ӁA�C�R�������ɗL���Ȍ��ʂ̓d��𑗂����B�u����j�G�K�U�����J�n�ȗ��A���C�R�n�h�q�퓬�j��O�V�e�����j�փV�e�n�z�g���h�ڃ~���Ƀi�L�i���v�Ƃ������Ɏn�܂邻�̓d���ɂ́A���ꌧ������ʼnƉ����Y���ׂĂ��Ď������ɂ�������炸�A�w���q�܂ł����悵�Ď���R�Ɍ��g���A�C�e�^����Ƃ̂ق���g�a�荞�ݑ��ɂ܂ŎQ����\���o��҂��������Ə�����Ă���B�����āA�d���̍Ō�́u���ꌧ���z�N��w���A�����j�V�㐢���ʃm�䍂�z���������R�g���v�ƌ���Ă����B
�@�ČR�̋L�^�ɂ��ƁA����̐퓬�ɕs����Ȃ����ɏd�Ί����������͂ȕ����ł������ɂ�������炸�A�C�R�����͕ČR�̏W���C�����̂Ƃ������A�Ō�܂Ŋ拭�ɒ�R�����B�Ƃ��ς₵����Z�C���t�c�̃V�F�t�@�[�h�����́A�z���̏����ɘZ���\����ߑO�����O�\���������đ��U����������悤�Ɍ����A��ԕ�����擪�ɗ��Ăđ�U���ɏo���B
�@���̔ӂ̂��ƁA��c�i�ߊ��́A�����m�̋�������R�i�ߊ��Ɉ��ĂāA�u�G��ԌQ�n�A���K�i�ߕ����A���U�����i���B�C�R�����n���n���\�����O�O�Z�ʍӃX�B�]�O�m���b���ӃV�M�R�m�������F���v�Ɖi���̑œd�������B���ۂɂ͂��ꂩ���\�l���Ԃقǂ̂��̘Z���\�O���ߑO�뎞���A��c�����ȉ��̊C�R������]�͎��n���ĉʂĂ��B�đ�Z�C���t�c�̕��m�����́A�����̘Z���\�ܓ��A�C�R�i�ߕ��n�����̒ʘH�̈���ő�c�i�ߊ��ƌܐl�̎Q�d�����z�c��~���Ď������Ă���̂������B��������A��~�����āA��̎��ɂȂ��Ď���ł����Ƃ����B�C�R�����͂������ĂقڑS�ł������A�ČR�������̐퓬�ɂ����Đ琔�S�l�ɋy�Ԏ����҂������A���̑��Q�͐r��ł������Ƃ����B
�@��c�C�R�i�ߊ��̍Ŋ��͂悭�m����Ƃ��낾���A�����ڂ̂Ȃ��ߎS�Ȑ퓬�𑱂��邱�Ƃ̖��Ӗ���������Ă����R�l���ꕔ�ɂ͂����悤�ł���B���͂�S�R�ʍӂ��m���ɂȂ����Z���\�ܓ��̌ߌ�A�攪�\������A�������R�ϑ卲�́A�A���i�ߕ��ɕ����̏������W�߂��B�����āA�㋉�t�c��]�͗����������đ��U���̊��s�𖽂�����肾���A�S�l���炸�̕��m�����c���Ă��Ȃ������̘A�����g�D�I�Ȑ퓬�𐋍s���邱�Ƃ͕s�\�����疽�߂ɂ͏]���Ȃ��ƒf���A�K�\�����������ĘA�������Ă��A�������U�����B���̂��Ɣނ́A�����̏����ɑ��A��������Ɏ��ʂ��Ƃ̂Ȃ��悤�ɖ����A�{�y�ɋA�҂��������̂͂������Ă悢�Əq�ׁA����͊������E�𐋂����Ƃ����B���̉���������A�������̍�����т����̒���Ɍ��e�Ŏ��������B
�@�Ō�܂Ŗ��ʂȐ킢�𑱂��邱�Ƃ𖽂��������ɁA����͐����c�����㊯�����Ȃ�̐������Ƃ�������R��]���̗L�l�ɔ�ׂāA�ނ�̋B�R����p�͂Ȃ�Ƃ����ɔ�����̂�����ƌ��킴��Ȃ��B
�@
�@���G�Ȏv���ɂЂ���Ȃ��狌�C�R�������Ƃɂ������́A�ߌ�̉H�c�s���̔�s�@�ɏ�邽�߁A�����^�J�[��ԋp���ߔe��`�ւƌ��������Ƃɂ����B�g���^�����^�J�[�̉c�Ə��ɎԂ�ԋp����ƁA�c�Ə��̐l���Ԃŋ�`�܂ʼn^��ł����Ƃ����B�^�]�肵�Ă���l�͈�������A�Ȃ�Ǝ����悹��ꂽ�Ԃ́A���ꓞ���̓��ɏ�������̃��S���ԂƓ������̂������B���̎Ԃɏ�������Ƃ����������ƂȂ��āA���͏��߂ɏq�ׂ��悤�ȋM�d�ȑ̌���ςނ��Ƃ��ł����B�܂����̂����ŁA���̎��̉���̗��͎��ɂƂ��Đ��U�Y�ꂪ�������̂ƂȂ����B�ԂɌ������Ă�����q�ׂ�̂��ςȘb���������A�����ԂɌ��t���킩��Ȃ�A�S���炻���������C���������B
�@�ߔe��`�ŎԂ��~���Ƃ��A���͕Ў�ł����Ƃ��̃��S���̎ԑ̂ł��B���Ȃ�Âт��Ԃł͂��������A���邭�P������̌ߌ�̑��z�̌��̂��ƂŁA���̔����ԑ̂͌ւ炵���ɋP���Ă���悤�Ɍ������B
�i����̕��@���j
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
1999�N8��4��
�����t�Łu�M�̒��v�@�@
�@�H�열�V��̍�i�̒��Ɂu�M�̒��v�Ƃ����Z�҂�����B�����ۂƂ����������A���̓s����ዷ�ւƌ������r���̎ᕐ�҂Ƃ��̔��e�̍Ȃ��P���B�����̍����ɂ͂܂�s�ӑł���H������ᕐ�҂͐��̍����ɔ�������A���̖ʑO�ŏ��͔Ƃ����B�����āA���ꂩ��قǂȂ��A�ᕐ�҂̂ق��͈�̂ƂȂ��Ĕ��������B�₪�ē����̑����ۂ͕߂炦���A�����g�ɂ���Ď�蒲�ׂ��邱�ƂɂȂ�̂����A�����ۂƎᕐ�҂̍ȁA����ɗ�}��ʂ��ē���ꂽ�ᕐ�҂̗�ɂ��،������ꂼ��܂�ňႤ�̂��B
�@�����ۂ͎������ᕐ�҂��E�����ƔF�߁A���͎������v���h���E�����ƍ������A�Ō�ɌĂяo���ꂽ�ᕐ�҂̗�͌Ȃ̎�Ŏ��Q���ĉʂĂ��ƌ���āA���ǁA�^�����M�̒��ɉB����Ă��܂��B�l�Ԃ��ꂼ��̐S�̈łƂ���䂦�̎v�f���A�ǂ����Ă�������Ȃ��͂��̐^���̒��ɕ�ݍ��݁A���ǒN�ɂ��ق�Ƃ��̂��Ƃ�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ƃ������̘b�́A�Ȃ�Ƃ����ӂɖ����Ă��ċ����[���B
�@���Q�̌�w�͂̎����傾�����H�열�V��́A�Ⴂ���A�����Ԃ�Ɨm����ǂ������Ƃ����B���̔ނ��Ƃ�킯���D�����C�O��Ƃ̈�l�ɃA���u���[�Y�E�r�A�X�������B���V��̍�i�͂��̃r�A�X�ɂ����Ԃ�Ɖe�����Ă���Ƃ����Ă���B�r�A�X�͒Z�҂̐_�l�Ƃ���ꂽ�č��l��ƂŁA�يE���e�[�}�ɂ������z�I�ȍ�i�ӂƂ������A�킪���ł́A�ނ���A���̐h煂��̂����Ȃ��u�����̎��T�v�̕M�҂Ƃ��Ă��̖��������B
�@���̃r�A�X�̒��쒆�ɁuThe Moonlit Road�v�Ƃ�����i������B�u��E�̌��e�v�Ƃł����̃^�C�g�����Ӗ����Ȃ�悤�ȒZ�҂ŁA��l���q�Ƃ��̗��e���o�ꂷ��B������A���e�̕�e������ʼn��҂��ɍi�E����A��w�݊w���̑��q�͋}篕��e�ɌĂі߂����B��e�̎��̏ɂ��Ă̑��q�ƕ��e�A�����āA��}�ɂ���ČĂяo���ꂽ��e�̗썰�̏،������݂ɐH���Ⴄ�B�ނ��A���V��́u�M�̒��v�Ƃ͐ݒ������̓W�J���قȂ邪�A���̍�i�������ɂ������āA�r�A�X�̒Z�҂����V��ɂ����̃q���g��^�������Ƃ͂قڊԈႢ�Ȃ����낤�B���͂��̓��̐��Ƃł͂Ȃ��̂ň̂����Ȃ��Ƃ͌����Ȃ����A���̂ق��ɂ����҂̘A���������������i�͂��������݂���B�@�@
�@���V����{�̌ÓT�ɑ�ނ����߁A�������f�t�H�������A�Ǝ��̓N�w�I��i�ւƏ������Ă��������Ƃ͍L���m���Ă���Ƃ��낾����A�ނ��A���u���[�Y�E�r�A�X�̒��삩����l�X�Ȍ[�������ƂɈꕔ�̍�i���������Ƃ��Ă��ׂ���s�v�c�͂Ȃ����낤�B
�@�O�u���������Ȃ��Ă��܂������A�ׂɂ��̏������ĊH�앶�w�̘b�����悤�ƍl�����킯�ł͂Ȃ��B����A�����V���C���^�[�l�b�g�L���X�^�[�̌����j�m���A�u�����t�̈����v�Ƃ����^�C�g���Œ����Г��e�j�X�t�����삳���܂ł̌o�܂��q�ׂĂ����B���̒��ɑ��t����̊W�҂Ƃ��Ď��̖��O�Ȃǂ��o�ꂷ��̂����A���̒m��̂Ƃ͂��Ȃ�قȂ鎖���Ȃǂ��Љ��Ă����悤�Ȃ̂ŁA���̍ہA���́u�M�̒��v�ł������Ă݂�̂��ʔ����̂ł͂Ȃ����Ǝv������������ł���B���̃P�[�X�ł́A�u����˗��l�A���T�������ҏW�������j�m�̏،��v�A�u����ҁA�{�c���e�̏،��v�A�����āu����w���ҁA�̈ɓ��A���|�勳���̏،��v�̎O�،������ƂȂ邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B
�s����˗��ҁA���T�������ҏW�������j�m�̏،��t
�@�u�슴���@����Ȃ��́H�v�ƁA���̏���̑�t�ɂ��ẮA����ꂽ�B�Г��̃e�j�X���Ԑ��l���A���T�x���ɉ�Ђ̉���Ŏq���̗V�т̂悤�ȃQ�[�����y����ł�������̂��Ƃł���B�u�|��̈̂��搶���D���J�b�v������Ă����炵���B�݂�ȂŁA�������o���������v�Ƃ����b�ɂȂ����B
�@���������́A���܁u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v�������Ă���{�c���e�������B�{�c����́A�����|�p��w�̊w���ɐ��w�i�K�v����̂��낤���H�j�������Ă��āA�����Œb���̋����ł�����ɓ��A�������Ɲ፧�ɂȂ����B�A�g���G�ɒʂ��āA�����̎d�������Ă��邤���A��������������Ă݂����Ȃ�A��̔̒[�����������āA�����Ȃ����Â����Ђ˂�o�����B
�@�����Ă��́u��i�v���A�����͉��˂Ȃ̂Ɏ�ȂɎ����Ă��ẮA�݂�ȂɎ������Ă����B�u�Ȃ��Ȃ��̘r�O�ł��ˁB����ǃe�j�X�̗D���J�b�v�ł�����Ă��炢�܂��傤���ˁv�ƁA���͒ʂ肢����̂��������q�ׂĂ������B�����A���̂ɑS�������Ă��Ȃ��{�c����ɁA�������������̂��A����������肾�����B
�@���ɖ{�c����A�����������Ƃ��́A�u��̂��́A����Ă܂��B����ǂ��Ȃ����@���Ă݂܂��v�Ƃ����ɂȂ��Ă����B����ɂ�����܂łɂ́A�����������G�Ȏ����������A�v��ƁA�܂��ȏ�̂悤�ɂȂ�B
�@�{�c����ɐ����|�����āA����A���͈ɓ������̃A�g���G�֏o�������B���̉Ƃ���́A�֓��n���̑ɂɂ���̂ł͂Ȃ����Ǝv����قlj����A��ʌ��E���Ԃ̉��B�ČR���Z�̌����ɂ������̎d���ꂾ�����B�b���Ƃ����̂́A�����̕���Ȕ�ƂŒ@���ĉ�������Ȃ����肷�鑢�`�̎�@�ł���B
�@�����Ƃ������̂́A�@���Ή��сA���������т����ŁA��ɏk�܂Ȃ��Ƃ������Ƃ������I�ɒm�����B�@��������ƁA�J�[�u���ǂ�ǂ�}�ɂȂ�A�����߂����Ƃ͂ł��Ȃ��B�ǂ����Ă��߂�������A���������ǘF�ŗn�����āA�����̕������ɂ��āA���������蒼���ق��Ȃ��B���͐\���킯���x�ɒ@���āA���Ƃ͖{�c���A�ɓ������̎w���ŁA�Ƃ�Ƃ�@���̂��A��������Ă����B
�@�{�c���ЂƉĂƂ�Ƃ�@���Ċ��������J�b�v�́A����Ȃ��̂������B���a��40�Z���`����B�[����15�Z���`���炢�B���{�������Ԃ��߂̊����Ă���B�Â��Ă���̂͒ꕔ�ŁA�����ƂЂ˂�ƁA�ʂ̏����Ȕt�ɂȂ�d�|���B����̌��������Ő����~�A����ɓ����̋˂̔��ɓ����Ă����B�H���̓^�_���Ƃ��Ă��A���o��������10���~�͂�����Ȃ������ȁc�c�B
�@�e�j�X�̃����o�[���A����قǍ��ȃJ�b�v��z�肵�Ă��Ȃ������B���͍����ł���B���l�łP���~���o�������Ă��A�����s������B�������ɏ����t�V���W�P�[�g��g�ނ��ƂɂȂ��������u���̏���̃J�b�v�́A�|��̈̂��搶������ɐ[���ւ��i������Ƃ͂���Ȃ��j�A���ɒl�i������ƁA���S���~������B���ꂪ�P���P���~�ŁA�����I�[�i�[�ɂȂ�܂��v�B���P�b�g���P��ł��U�������Ƃ̂��肻���Ȑl�����X���U�A�ŏI�I�ɂ�12�l����o�����B
�@�Q�[���̌�A�₽���r�[�����J�b�v�ɂȂ݂Ȃ݂ƒ����A�ŏ��̈�������ނ̂��A�D���҂̓����ł���B�M�`�����������̂ŁA�L�[���Ɖ�����������قNj₪�₽���Ȃ�A�Ƃ��Ă����������B���̃Q�[���܂ŁA�J�b�v������ɕۊǂł���̂��D���҂̓��������A�u�ł������āA�u����ɍ���ƁA�Ȃ��炵����ꂽ�v�Ɠ������������҂������B
�@���́A�Z�����ĂȂ��Ȃ��Q�[���ɎQ���ł����A�J�b�v�̊���������ƂȂ��Ƃ����o���҂��������Ƃł���B�u�슴���@����ʂ�v�̐������������̂������͂Ȃ��B�ꕔ�g�ݍ��݂̏��t�́A�O���猩���Ȃ��Ƃ���ł͂��邪�A����҂Ƃ��āA�{�c����Ǝ��̖�������ł���̂��^�f���������B�ɓ��������C�𗘂����Ă��ꂽ�̂����A�{�c����͂Ƃ������A���̏ꍇ�A����Ɍg������Ƃ͊m���ɂ����Ȃ������B
�@�o���҂͂��̌�A�C�O�ɕ��C������A��w�̌����ɂ�����A�ސE������Ŏl�U���A����̃Q�[�����J����Ȃ��Ȃ����B�u�슴���@�v�̉\���A�K��������ƂȂ����B�J�b�v�͂��܁A���̐��ōł��[�����������Ă���{�c����ɗa�����܂܂ɂȂ��Ă���B�Ƃ��ǂ��e�ʂ̌������ȂǂɎ�������ŁA�������Ă���悤���B
�@�ɓ��A�������́A��N���A�b���̎d���Ƃ͕ʂ̌����ɑ��Z�ȂȂ��A���������o���œˑR�|��A�S���Ȃ�ꂽ�B�ɓ��搶�̂���ŁA���쌩���̍��Ԃɂ��������ɂȂ�����┞�̗₽�����v���o���B�����������F�肵�����B
�s����ҁA�{�c���e�̏،��t
�@1993�N�̂��Ƃ����A���͓����T�������̕ҏW�������������j�m����̈˗����A�u����\�O�ʏ́v�Ƃ����^�C�g���̘A�ڃR���������M���Ă����B�����̎��T���A�莆�����A����̕��ꕗ�A�Ȋw�G�b�Z�C���A�����L���A�������c�c�Ɩ��Ƃɕ��̂�ς���Ƃ����Ȃ�Ƃ��A�N���o�e�B�b�N�Ȏ���̃R�������������A�Â肷���������������ĕҏW�҂��ǎ҂����ɖڂ��A���Y��̊K�i���Ɠ����\�O��ڂ̎O�\�ꕶ�����i�Z�̕��j�������ĘA�ڂ͏I���ƂȂ����B�����āA���̑ł��グ�ԘJ��z�n�̒����V���Ћ߂��̂��X�łЂ��₩�ɍs��ꂽ�B�o�Ȏ҂́A�ҏW���̌����j�m����ƕ��ҏW���̎R�{���j����Ɏ��̑����O�l�������B
�@���˂̐g�䂦�A�{���ԘJ�����ׂ������̂ق����ԘJ���鑤�ɂ܂��ϑ��I�ȑł��グ��ɂȂ邾�낤���Ƃ͐����������̂ŁA���͓�l��������Ǝv���Đ��삵������̏����ȏ���I�`���R�����Q�����B���̎W�R�ƋP���o�����Ă̋�u�͋L�O���ׂ����̏��߂Ă̒b����i�ŁA���܂��茳�Ɏc���Ă��邪�A���ۂɂ��̔u�ɂ����𒍂��ň��̂́A��ɂ���ɂ��ނ��l�����������B
�@�|�p�I�˔\�Ȃǂ܂�łȂ��������̏����Ȕu�����Ɏ������o�܂ɂ́A���܂ł��܁X���u�t�Ƃ��ču�`�ɏo�����A�����Z������Z�i�H�j�Ȃǂ������Ă�����̌|�傪�W���Ă���B�̏o�����Ă�����w������A�t���[�̂��̏����ɂȂ��ĕ�炵�Ă���������̂��ƁA�|���w�@���p���猤��������u�`�̈˗�����������ł����B�|�p�Ȃǂɂ͂��悻�����̂��̐g�ɂ��������Ȃ�łƌ˘f���͂������A�������w���̂��̂��u�`����̂ł͂Ȃ��A���w��_���w�A�R���s���[�^�T�C�G���X�A�����w�ȂǁA�����Ȋw��ʂ̍���ɂ���l�������Ȃ�ׂ��킩��₷���u�`���Ăق����Ƃ����̂�����̈ӌ��������B�@���̌|�p�I���z��_���I���_�̌[���A��X�̔��p����ȂǂɂȂ�炩�̂������Ŗ��ɗ�����������A�u�`�̓��e�͖��Ȃ��Ƃ������Ƃ������̂ŁA���ǁA�W���u�`�������ɂ��̈˗�����������B
�@���a�V�c�̒�N�A�O�}�{�e���Ȃǂ��q�������Ƃ��ĐЂ�u����Ă��邻�̌������ɏo�������ƂɂȂ������́A�����Ȋw�̗̈�ɂƂǂ܂炸�A�g�̂قǒm�炸�����m�̂����ŁA����_�A���w�_�A�|�p�_�̃W�������ɂ܂œ��ݍ��݁A�����\�N�]���Ȃ��u�`�𑱂��Ă����B�|�吶�̖��_�̂��߂ɕt�������Ă����ƁA�ނ�ɂ͂������Đ��w�I�˔\���Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B�{���I�A���邢�́A���ݓI�\�͂Ƃ����Ӗ��łȂ�A�̎����ւ������w�̊w���Ȃǂ����D�ꂽ�l�ނ����邩������Ȃ��B���G�ȃf�U�C���◧�̓I���`�\���Ɏ��g�ފw���Ȃǂ́A���ӎ��̂����ɐ��w�I�v�l���d�˂Ă��邵�A���G�ȍ\�����̌����ϓI�Ɍ������ɂ͐��w�I�˔\���������Ȃ����炾�B
�@�Ƃ���ŁA����Ȏ��̋��ɂ����Ȃ����ӔC�u�`���@���ɂ܂����Ė����������u���Ă������鋳�����������B���ꂪ�����������̋����Œb���E�̑�䏊�A�ɓ��A�������������̂ł���B��x���܂ő�w�Ɏc��A�܁X�ɂ������Ȃ���������đ����̊w���ƐS�̒ꂩ��������A�����̐l�ނ𐢂ɑ���o�������̋����́A���H��ƂƂ��Ă����{�ŎO�w�ɂ͂����Ƃł���������łȂ��A����҂Ƃ��Ă���ςɂ����ꂽ�l���ł������B
�@�����������邤���ɁA���́A��ʌ����R�s�L�̖ɂ������ɓ������̍H�[���w�ɒʂ����ƂɂȂ�A�₪�ċ����Ɋ��߂��Ď��ۂɂɒb��������邱�ƂɂȂ����B�G��ł������ł��H�|�ł����������A�D�ꂽ��Ƃ̍H�[�Ƃ������̂͗l�X�ȓ���ނ��G�R�ƒu����Ă��āA�������ɂ��Y��Ƃ͌�����B�������A�H�[�͌|�p�Ƃ��S�g�S��������A���݂ǂ댌�݂ǂ�ɂȂ��ċ��ꓬ����i���Z�̃����O�̂悤�Ȃ��̂�����A����͓��R�̂��Ƃł���B�ɓ������̍H�[���S�C����l�������Ȃ��Ă������Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B
�@�V�c���ʂ̋V�ɗp����ꂽ�䕨�Ȃǂ��܂ސ��X�̑�ꋉ�|�p�i�̐��ݏo���ꂽ�H�[�̂ǐ^���̂��A�H�[�傪���N���p�����H������������q���������ɁA�}�X�������b���E�̑�䏊�����Ԏg���̂悤�ɂ����g���Ȃ���A���葫��肵�Ă�����ďo���オ�����̂����̔u�������̂��B�f�ނ�����ɂ����̂͂��ꂪ�f�l�ɂ������₷������A�܂��A����i��u�ɂ����̂́A�u���肪�b���̊�{�����炾�����B�����͘r�̏オ�������݂���l����ƁA�Ȃ�Ƃ��S���ƂȂ���i�����A���ɂƂ��Ă���͑z���o�[����i�������B
�@���āA�ł��グ��̐ȏ�A���̋�̔u�ň�t���I���������ҏW���́A�}�Ɏv�����������̂悤�ɁA�u������g�債���`�ł��\���܂���A�����V���Г��e�j�X�t�p�Ƃ̑��t���Ă��炦�܂��˂��H�v�Ƃ̂��������B�삯�o���̎O�����C�^�[�A����A�S�~���C�^�[�i�H�j�ɂƂ��āA�ꗬ�T�����̕ҏW���̐��́u�_�̐��v�ȊO�̉����ł��Ȃ��B�������A���̑��t�ɂ͂��钘���l�̖��O�����������Ƃ��A����Ȃ�ɂ�����Ǝv����ޗ���̒��B�@�ɂ��Ă͖��Ă�����Ƃ��A�H���̂ق��͎��ɖ�����d���Ăق����Ƃ��A�͂��߂���b�͑����ɋ�̓I�������̂ł���B
�@�Ƃ�ł��Ȃ��ł��グ��ɂȂ������Ƌ�̃I�`���R�����߂����ɒ��߂Ȃ���A������́A�Ƃ肠�����ɓ������ɓd�b���Ď��̎����ł��������B����ƁA�����́A���Z�Ȑg�ɂ�������炸�A�u������`���Ă����܂�����A�Z�p�C���̂���Ń`�������W���Ă݂�Ƃ悢�ł��傤�B�f�ނ͂�����ŏ������܂�����A�J�b�v�̂��悻�̃f�U�C�������͍l���Ă��Ă��������v�ƁA�����ɋ~���̎�������L�ׂĂ��ꂽ�̂������B���́A�J�b�v�̒ꕔ�̑���Ђ˂�Ƃ��ꂪ���O���A�O�ꂽ����𗠕Ԃ��ƕʂ̏���t�i�Ƃ����Ă����ʂ̔u�̐��{�͂���j�ɑ��ς�肷��Ƃ����A���Ȃ�Â����a�V�ȃf�U�C�����l���o���������ŁA���R�̍H�[��K�ꂽ�B�K���A�ɓ�������������̃f�U�C���͂Ȃ��Ȃ��ʔ����Ƃ��_�߂̌��t���������B
�@��������̉��ה���傫�ȉ~�Ղ�Z����̋�ł����A������o�[�i�[�ʼn��M���Ă͊e��H���p���ď��X�ɒ@���̂��đ_���̌`�ɋ߂Â��Ă����Ƃ����A�C�̉����Ȃ�悤�ȍ�Ƃ����͈�Ē�������H�ڂɂȂ����B�o�ϓI�ɂ͂Ȃ�̑����ɂ��Ȃ�Ȃ���Ƃ䂦�A�Ƒ�����͔����ڂŌ����Ă������A����ȏ�ɑ�ς������̂́A�����ɂ킽���Ďd������̂��ꂽ�����ɁA���̂����Ȃ���̂�����u�s�т̒�q�v������Ă��܂����ɓ������������낤�B�|��̊w������Ȃ�{�������ނƂ���������Ɖ䖝���A�����̎d���͂����̂��Ŏw�����Ȃ���Ȃ�Ȃ������킯������A���̃X�g���X�����z���ɗ]�肠��B
�@������x�`�������Ă����i�K�Ő���˗��҂̌���������ĂсA�i�W�����Ă��炨���Ƃ������ƂɂȂ����B�삯�o���̎Љ�L�҂��������A�����̂قƂ�ǂ�������ŏ����̔\�ʎt�ɒ�q���肵�A���Ȃ�̏o���h���̖ʂ�܂łɘr���グ���i�ƕ����Ă��邪�A���܂������͌����Ă���������Ƃ��Ȃ��j��������Ȃ�A�b���ɂ��K���⋻���������Ă���邾�낤�Ǝv�������炾�����B�H�[�Ɍ��ꂽ��������́A�z���ȏ�ɗ��h�ȑ��t���o�����������̂�ڂɂ��Ă������ɋ������炵���B
�@��������������Ƃ�����ŁA��������ɂ�������\�Ƃ��O�\�ƂقǗ��t�̕�����@���Ă�������L���͂���B����ȏ㑱���Ă��炤�ƁA���������̋�J�����̖A�ɂȂ��Ă��܂����˂Ȃ������̂ŁA�����܂łʼn䖝���Ă��炤���Ƃɂ����B
�@�����ɂ́A��t�Ə��t�̐ڍ��������Ȍ`��̑��̐���A���������x�ȋZ�p��v�������ȋȖʕ��̑ł��o����Ō�̕\�ʎd�グ�ȂǁA�ǂ�Ȃɍ��Ȏw�������Ă�������Ƃ���ŁA���̎�ɂ͕����Ȃ��Ƃ�������������B�����������Ƃ�������ׂĈɓ������ɍ���Ă���������Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B������A���̑��t�̐���v���x�������Ĕ䗦�ŕ\�킷�Ƃ���ƁA���ɓ��A���F�{�c���e�F�����j�m �� 50�F49.99�F0.01�� ���炢�̊����ɂȂ��Ă���B�����I����҂͈ɓ����e�i�H�j�Ƃ������݂��Ȃ��l���Ƃ������ƂɂȂ�̂��낤���c�c�B�Ƃ������A�������āA�ǂ��ɏo���Ă��p���������Ȃ��參��t���a�������B
�@���́A�u�s�т̒�q�v�̎����Ɓu�s���̑���q�i�H�j�v�̌�������̖����O���猩���Ȃ����t�̗��ɐ���Җ��Ƃ��ĕ��ׂĒ����Ăق����ƈɓ������ɂ��肢�����B�S�i�����ˁj���g���ďo������������t�ɖ��肱�ނȂǂ̌|������X�ɂł���͂����Ȃ��������炾�B���ƌ������e�X�̖��O�����ɏ����ēn���ƁA�ɓ������͌������S�����ł��̕M�Ւʂ�ɖ������ݍ���ł����������B
�@��������̗v���������āA�����������̑��t�ɂ́A����l���̖��������������t�Ƃ����t����������\���Ă������B�����A���낢��ƕ��G�Ȏ���Ȃǂ������āA���̌�A�t����͂��ꂢ�ɔ�������A���܂ł͂������肵�����̌`�ɖ߂��Ă���B�u����͂Ȃ��Ȃ����h�ȍ�i������A�ǂ��ł��悢�l���̖��ڂɒ��荞��͂��Ȃ��ق����悢�v�Ƃ̈ɓ������̒�������������ɓ`���A�}篋�\��t���ɕύX�����̂����A���܂ƂȂ��Ă݂�Ɛ����������悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B
�@���̑參��t�̍ޗ���́A�����˔��Ȃǂ�����ď\�]���~�ɂ̂ڂ����B�����̈ɓ������̘b�ł́A�H���͒ʏ폭�Ȃ��Ă��ޗ���̓�`�O�{�͂��邻��������A�ǂ��������ς����Ă��l�A�\���~�͂���B���ۂɂ́A�\���I�ɂ�����߂Ē������A�������A���̖��������܂�Ă͂��Ȃ����̂̈ɓ������̎肪�܊����͂�������i������A�ƂĂ�����Ȓl�i�ł͂��܂Ȃ����낤�B
�@�����������Ă���悤�ɁA���܂��̑��t�ّ͐�Ɉꎞ�ۊǂ���Ă���B�����q�̌������Ȃǂ̂Ƃ��ɁA�Ȃ݂Ȃ݂Ǝ������ŐV�Y�V�w�̖ʑO�ɏ����A�ՐȎ҂̖ڂ�����������y���܂����肵�Ă��邪�A�{���̈Ӑ}�Ƃ͈قȂ�ړI�Ɏg�����t�̂ق��́A���������ʐH����Ă��邩������Ȃ��B�@�@�@
�@���̂Ƃ��̘J����d�̂���Ƃ����킯�ł��Ȃ��̂��낤���A���ꂩ�炸���Ƃ̂��ɂȂ��āA���͌�������萻��⽍���ۂ����Ղ����B���������⽍��̓��Z�������Ă��āA��X�𗬂̂���l�X�ɓƓ��̖��̂����ۂ��đ����Ă���B���ݎ������p���Ă���u���e�v�Ƃ�����͂́A��������X�����v�ŗ�������ł����Ƃ��ɒ��������̂Ȃ̂����������A���̂����ꂪ�����̃X�����v�~�߂ɂ͔��Q�̌��͂����邩��������B���������ۂ��̂ق��́A�����J�̃y���l�[���p��͂����A������̂ق������낻�늈�Ă��炤�悤�ɂ��Ȃ���ƍl���Ă���B
�@�Ȃ�Ƃ��c�O�Ȃ��ƂɁA�ɓ��A���|�勳���͍�N�\�A�ʋΓr���̓d�Ԃɂ����Ă��������o���œ|��A���̂܂܈ӎ������邱�Ƃ��Ȃ����E���ꂽ�B�ߓx�Ȍ����ɂ��X�g���X�������Ƃ����@����邾���ɁA���͂��܂��B�X�S�c��łȂ�Ȃ��B�u��w��ފ������狽���̎l���ɖ߂��ăA�g���G���\���A�S��y���݂Ȃ��玩�R�̂őf�ނƌ��������A�悢��i�肽���B���̓������܂͑傢�ɐS�҂��ɂ��Ă����ł��v�Ƃ������t�́A�����̋U��ʐS���ł������ɈႢ�Ȃ��B
�@�ɓ��������}���Ȃ������Ƃ��A��������͂��܂��ܑ傫�Ȏ�p�̂��߂ɓ��@���������B������A���͌�������ɂ́A�މ@���m�肷��܂ňɓ������̋}�ȑ��E�ɂ��Ă͈ꌾ���b���Ȃ������B�K���A��������͌��C�őމ@�̉^�тƂȂ����̂ŁA���̎��ɂȂ��Ă͂��߂āA�ɓ������̋}����`�����悤�Ȃ킯�������B
�@���Ƃ���肽���Ǝv���Ă��A���̂悤�ȑ��t����邱�Ƃ͂����s�\�ɂȂ��Ă��܂����B���܂ł͋M�d���̂����Ȃ����݂ƂȂ������̑��t�́A�ɓ������̍����߂āA�����̂܂��̕����̈���ʼn������邩�킩��Ȃ��o�Ԃ������Ƒ҂��Ă���B
�s����w���ҁA�̈ɓ��A���|�勳���̏،��F��}�͖{�c���e����s�t
�@�����ł��˂��A�{�c�����̍H�[���w�Ɍ��ꂽ�̂͂����\�N�قǑO�̂��ƂɂȂ�܂����˂��B�ςɍD��S�̋����l�ł��ĂˁA�v�]���čH�[���w�ɏ����������A�܂������̐l�����ۂɒb������点�Ă���ƌ����o���Ȃ�Ďv���Ă����܂���ł����B����Ȃ��ƂɂȂ邭�炢��������A����ɂ��̐l�̍u�`���ɂ�������Ȃ������Ȃ��B
�@�d�����Ȃ�����A��Ԃ₳���������ȋ�̔u����点�邱�Ƃɂ�����ł����A�����ȋ�������炪�����Œ��A������ς킳�ꂽ�����ɁA�q���̔S�y�H�̂悤�ȏo�������Ȃ��̑㕨���a�������킯�ŁA����͂�Q���Ă��܂��܂�����B���̂܂܂ł́A����܂�s���D�Ȃ̂ŁA���������蒼�������Ă�������ł����ˁB�����Ƃ��A�{�c����{�l�͏��߂Ă̑̌��ő傢�ɉx�ɓ����Ă��܂�������A���̓_�͂悩�����Ǝv���Ă��܂���B
�@�ł����̋�̔u���ł��グ��̐Ȃɓo�ꂵ���Ƃ͈ӊO�������Ȃ��B�T�������̌���������ǂ��������肾������ł����ˁB�܂��b���́u�^�v�̎����m��Ȃ��{�c����̋Z�p�ő��t�����Ȃǂƌ����o���Ȃ�āc�c�B������Ȃ�ł��A�{�c�����đ���̈˗����{�C����k�����炢�͋�ʂ����Ǝv���܂�����A��͂�A�b�͂͂��߂��瑊����̓I��������ł��傤�B�{�c���ƂĂ������Ă���悤�ł�������A�Ƃ�������`���Ă����邱�Ƃɂ��܂�����B�������܂��܉ċx�݂������̂ŁA�Ȃ�Ƃ����Ԃ͂Ƃꂽ��ł��B
�@����Ȍ`�̑��t����肽���Ɩ{�c�������o���������}�����āA���͓��S�A����Ȃ��̂ǂ��t�����������Ď��͂ō���킯�Ȃ����낤�Ǝv���܂�����B�ł��A���̎a�V�ȃA�C�f�B�A�����͐����ʔ����ȂƊ����܂����B�`���H�|�����̎��ł����A�^�j��̐V�������z�Ƃ������̂͂���Ȃ�ɑ�D���Ȃ�ł���B
�@��t�⏬�t�̎M�̕����͖{�c����J���č��܂����B������₪�_�炩���f�ނ��Ƃ����Ă��A���̂��炢�̌����ɂȂ�Ɛ�̂����đ�ςȂ�ł����A�܂��āA�ƂŒ@���ď��X�ɋȖʂ���肾���Ă����Ȃ�Ă��Ƃ͏��S�҂ɂ͂������ėe�Ղł͂Ȃ���ł��B�^�ĂȂ̂ɍH�[�͗�[�������Ă��܂��A���̂����⌀��ނ������Ԃ�Ǝg���܂�����A�����������ł��ˁB�召�̋��Ƃ�ؒƂ�₦�ԂȂ��U�邢�Â��邾���ł��A���˂Ďg��Ȃ����������̋ؓ������܂�����A�͂��߂̂����{�c����͐g�̂̂����������ɂ�������Ȃ��ł����B���̈Ӗ��ł͂悭�撣��܂����ˁB
�@�����Ɍ����ē���Ƃ��낪�����Ԃ�Ƃ���܂����B�������Ȃ��J�����قǂł�����ˁB�{�c���H�[���g���Ă���Ƃ��́A�ǂ����Ă��C���U���Ď��̂ق����d���ɂȂ�܂���A�ǂ����Ȃ�S�ʓI�ɋ�t���ɋ��͂��āA�ꍏ���������������������ق����悢���ƍl����悤�ɂȂ�܂����B�{�c����̃y�[�X�ɔC���A�Z�p�̌����҂��Ă�����A��N���O�N���������Ă��܂�����������܂���B
�@����l���̖��O����������������t�̕\���ɒ��ڂɒ��荞�݂����Ƃ�����������̗v�]��`���������Ƃ��A����Ȃ��Ƃ������点�������̍�i�̉��l�������邩��A�ʂ̕��@���l�����ق����悢�Ǝv���܂����B�����ԍۂɂȂ�ƁA���̂ق��ɂ�����Ȃ�̎v�����ꂪ�����Ă��Ă��܂�������ˁB���ǁA�ג�������ɂ��̐l�����M�̕��������݁A��̕\�ʂ����Ԃ��āA�����ڒ��܂Ŗ{�̂̕\�ʂɓ\����܂����B�̂��ɁA��������悤�Ɉ˗����������̂ł���������ł����A���ʓI�ɂ͂悩�����ł��ˁB
�@���t�Ƒ�t���̖{�c����ƌ�������̖��ł����A�܂��A����͂���ł����g�Ƃ��Č��\�Ȃ��Ƃ�������܂��B�{�c�����Ȃ�̕�����������̂͊m�������A��������͂�����ƒ@�������������ǁA�ŏ��ɘb�������o�����͔̂ނ������킯�ŁA�ǂ��܂Ŗ{�C���������͂Ƃ������A���̐����������Ȃ�����̑��t�͐��܂�Ȃ������킯�ł�����B�����قǂ͎�����`������ł����A�������Ɏ��̖��͓�����܂���ł����B���̓v���ł�����A���������Ȃ��Ƃ͂ł��܂���B
�@���̑��t�A�������������炭�炢�̉��l�����邩�ł����āH�c�c�������ł��˂��B���̖ڂ���݂�ΐ����ȂƂ��낢�낢��܂����Ƃ��������܂����A�\���ƃf�U�C���I�ɂ͂���߂Ē��������̂Ȃ̂ŁA�S�̓I�ɕ]���������ȂɈ������̂ł͂���܂���B��������ɏo���Ƃ���A�����葤�̕]���̖�������܂����A����l�X�ȏ��d�Ȃ��ăv���~�A�������Ƃ��l�����܂�����A�Ȃ�Ƃ������܂��A���Ȃ��Ƃ��A�l�\����\���~�ǂ܂�Ƃ������Ƃ͂Ȃ���Ȃ��ł��傤���B�����A����҂̂���l������l�ł�����A���̖����t���ʂƂȂ��āA�ꋓ�ɍޗ���ȉ��̒l�i�ɖ\�����Ă��܂��\���͂���܂��ˁB�ł��A���Ɩ{�c���H������d�����킯������A���̈Ӗ��ł͑f�ޔ���ł����������͈����������������Ƃ͌����܂��ˁB
�@�Ȃɂ������c�����Ƃ����邩�ł����āH�c�c���낻�남�~�������x���炢�͕�Q��ɗ���悤�ɖ{�c����ƌ�������ɓ`���Ă����Ă��������B���̑��t�ɏ㓙�̂�������{�S�������ŁA���̏ォ�炩���Ă��炦��Ɗ�������ł����˂��B�����A���낻���E�̍H�[�ɋA��Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ԃł��B�ł͂���Ŏ��炵�܂��ˁB
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
1999�N8��11��
�[�����ٌ��ۃ��|�[�g�@
�@�����͂Ȃ�ׂ���ÂɌ��߂�悤�ɐS�����Ă�����肾���A����܂łɉ��x���s�v�c�ȑ̌����������Ƃ͂���B�L����H��Ȃ���A��A�O�̑̌��k���Љ�Ă݂����B
���w�܁A�Z�N���̍��̂��ƁA�G�����Ȃɂ��ŁA���c�ЕF�Ƃ��������w�҂��l�b�g�������Đl����ǂ������A�Ȋw�I�ɂ��̃��J�j�Y���̌��������悤�Ƃ����Ƃ����b��ǂB�����Ă��̘b�̓��e�Ɏh������A�[��A��n���ӂȂǂ�������Đl���̂�������{�����������Ƃ��������B���̍��͋�B�̗����ɏZ��ł������A�ƂĂ��ςȏ��N�ŁA�����Ў��Ȃǂ̋�����[��Ƃ�ŕ������肵�Ă��|���Ɗ����邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ������B
�@�܂��A�썑�̓��Ƃ����̕��y���A��x���O���ق��������Ă��Ƃ��ɒN������Ƃ��߂��邱�Ƃ��Ȃ������̂��A�D��S�����ȏ��N�ɂƂ��Ă͍D�s���������B����ɁA�����̓c�ɂ͈Ŗ�̔ӂȂǂق�Ƃ��ɐ^���ÂŁA���肪�Ȃ���Ε����Ȃ���Ԃ���������A�l�H�̂��̂ł͂Ȃ������̂�ǂ�������ɂ͏����I�ɐ�D�������Ƃ����Ă悢�B
�@���ۂ̂Ƃ���́A�l���̂������͂��������e�ՂɌ�����悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�������������̂��ق�Ƃ��ɖڌ�����ɂ́A����Ȃ�̓w�͂ƔE�ς��K�v�ł���B�̋ʁA���Ȃ킿���ɂ��ẮA�I�����W�F�̂��̂Ɖ��F�̂��̂����ꂼ���x���������Ƃ����邪�A��ÂɊώ@����ƁA�Ȃ��Ȃ����Y��Ȃ��̂ł���B�c�O�Ȃ��ƂɁA�ǂ���������ɑ傫�ȋ�������Ă��������ɁA�������̎���Ŕ��ΐÎ~���Ă������Ƃ������āA�ƂĂ������̏W�p�l�b�g�ŕߊl�ł���悤�ȏł͂Ȃ������B
�@���̒m��͈͂ł̐��X�̖ڌ��k�𑍍�����ƁA�ǂ����A���͎��̎}�ȂǂɐÎ~������ԂŌ����Ă�����̂ƁA���V���Ă�����̂Ƃɑ�ʂł���悤�ł���B�����̔ӂ��́A�ނ��땗�̋������ꂽ���̖�ɏo������X��������悤���B�ڌ��҂����ɏP��ꂽ��A���炩�̊�Q�������Ƃ����b�͕��������Ƃ��Ȃ��B���̈Ӗ��ł́A���͂Ȃ��Ȃ��ɐa�m�I�Ȃ悤�ł���B���Ȃ��Ƃ��l�{���Q�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�܂��A����Ƃ̑����͂��܂�Ȃ��悤�Ɏv����B�l�I�ȑ̌����炷��ƁA�ŋ߈ꕔ�̕����w�҂����ɂ���ď������Ă���v���Y�}���┭���o�N�e���A���ɂ͂��Ȃ�������̂�����B
�@�����ۂ��A�S�Ȃ����͐l���ƌĂ����̂́A�~���Ă����J���}�ɏオ���ēV�C�����A�C�������߂ɂȂ����ӂȂǂɓy���̕�n�Ō����邱�Ƃ������̂ŁA�L�@����y���̊e��̃o�N�e���A�����Ȃ�ւ��������Ă���̂����m��Ȃ��B�悭������l�̈�̂⓮���̎��̗̂ӂ��R����̂��Ƃ������́A�����Ƃ��炵�����A�ЂƂ����傫�Ȗ��_������B���R������̂͗L�łȉ��ӂ����A�����̑̓��ɂ���͖̂��łȐԗӂł���B�����āA�ԗӂ͊ȒP�ɂ͉��ӂɕω����Ȃ��B�����A���̗̂ӂ��R����Ƃ��������ɐ����͂���������ɂ́A�y���Őԗӂ����ӂɕω�����v���Z�X���ɐ������Ă��˂Ȃ�Ȃ��B�l�X�ȍy�f��o�N�e���A�ނ̓����ł��̂悤�Ȃ��Ƃ��N����\�����Ȃ��Ƃ͂����Ȃ����A���̂�����̂��Ƃ͐��Ƃɂ��f�������Ă邵���Ȃ��B�ʔ������ƂɁA�قǂ悭�����������Ē��߂��ق����A����炵�����̂̑��݂��m�F���₷���B���ߋ����܂ŋ߂Â��ƁA�͂�����ƌ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����Ƃ������B�����A������ɂ���A����炪���̉Ȋw�I���ۂł��邱�Ƃ����͊ԈႢ�Ȃ��悤�Ɏv����B
�@���͑�w���̂Ƃ��̑̌��k�ł���B���̍��A�����s�]����̖؏�̉^�͉����̐��S�W�̉�Ђ̍H��Ŗ�x�̃A���o�C�g�����Ă������Ƃ��������B�Ō�̎Ј����ގЂ���ƁA��̍H�꒷�ȂƎ��̂��Ă����₩�Ȏ��Ȗ����ɂЂ���A���_�Ƌ��Ƀ^�C�����R�[�_�[�𑀍삵�ė����㎞���炢�܂ł̕��̏���L�^�����炩���ߝs�����A���Ƃ͉������ʼn��ɂȂ��Ė��̐��E�Ŗ�x�����Ȃ�Ă��Ƃ������������B�����̋����̃^�C�����R�[�_�[�́A������Ƃ����@�B�I�m����������Ύ����̒������v���̂܂܂ɂ����Ȃ����Ƃ��\���������炾�B
�@��^�̍|�ނ�p�r�ɉ����Đؒf����̂���ȋƖ��Ƃ��Ă������̍H��ɂ́A�d���傫�ȓS�ނ⋐��Ȑؒf�@��������Ƃ���ɔz�u����Ă����B����ȂƂ���ɓ��݂ɂ͂��낤�Ƃ���D�_�͑�^�g���b�N���Ȃɏ���ďd�����ʼn�������ł��邵���Ȃ��킯�ŁA����ȘA�����܂Ƃ��ɑ���ɂ��Ă��������������Ă������͂����Ȃ��B����A����Ȏ��ԂɂȂ����肵����A���R�A�g���Y������̂���ԗ����Ȑg�̏��������Ǝv��ꂽ����A�u�Q�x�v�͘_���I�ɂ͐������I���ł͂������B
�@���ɂ�����ɂ͂���������ǁA�ꌩ���������ł������������Ȃ͂����ĂȂ��͖̂�������������A�ǂ�ȂɃh�W�ȓD�`���������Ă���ȂƂ���͂܂��_���͂��Ȃ������낤�B���������A���̋��ɂɑ���Ȃ��[�܂��Ă����Ƃ���A���m�b�ɂ������n�R�w���̃A���o�C�g��x�ȂǂɊǗ���C������͂��Ȃ������낤�B���łɏq�ׂĂ����ƁA���̎���́u�Q�x�v�̒��Ԃ����܂ł͐��{�̍�������Ƃ̊����ɂȂ����肵�Ă��邩��A���{�̎Љ�ǂ��Ȃ錩���݂͂قƂ�ǂȂ��B
�@���āA����Ȃ��Ƃ𑱂��Ă�������ӂ̂��ƁA���c���Ă�����l�̍H�����A�Ђǂ������Ă������ƂȂǂ������āA�}�ȓS���̊K�i�݊O���A�ٗl�ȕ����ƂƂ��ɓ�����]���A�z��܂���Ȃ����S����Ƃ����ߎS�Ȏ��̂����������B�������Ƌ����Č���ɒ��s������X�́A�����Ȃ�ʎ��Ԃƒm���Ă����ɋ~�}�Ԃ��Ă����Ɏ�x�ꂾ�����B
�@���ꂩ���E�O����̐^�钆�̂��ƁA���̊K�i�̋߂��ɂ��鉼�����̃x�b�h�ʼn������ɖ��ȋC�z�������ĂӂƖڂ��o�܂��ƁA�Ȃ�Ɩڂ̑O�̋ɖS���Ȃ������̐l�̊炪������Ō�����ł͂Ȃ����I�@����͖����A���ɈႢ�Ȃ��Ǝ���Ɍ����������悤�Ƃ������A�����̈ӎ��͍Ⴆ�킽���Ă��āA�ǂ��݂Ă����Ƃ��������ł͂Ȃ��B�ł��邩����S���Âɂ��āA����͌��o�ȂA����̃V���b�N���傫�������̂ň��̐S���I���e�����Ă���A�������������Ǝ������g�əꂫ�������B�����āA�q���̍��ʔ������ł܂�ËL������̔ʎ�S�o��S���ŏ����ċC�����������߂Ă���ƁA���炭���Ē��ɕ������̊�͖��̂悤�ɏ��������Ă������B�K�����̂��Ƃ͓��ɉ����N����Ȃ������B
�@�����g�́A���܂ł��A����͐S�����̌��o�������ɑ���Ȃ��ƍl���Ă��邪�A�����H�삾�Ɖ����Ă��܂��A�ԈႢ�Ȃ��H��͑��݂���Ƃ������Ƃɂ��Ȃ낤�B���̂悤�Ȍ��ۂ��ǂ̂悤�ɉ��߂��邩�ɂ��ẮA�l���ꂼ��̗���ňӌ����قȂ�̂ł��낤���A���Ƃ����o�ł����Ă��A�������܂ł͂�����Ɖ��قȉe���܂̂�����ɂ���ƁA�H��̑��݂��ł��M����l���łĂ��Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��Ǝv���Ă���B
�@���܂ЂƂA����ȑ̌����������Ƃ��������B�Ⴂ���A���͂悭�Ƃ�Ŗ�ԓo�R�Ȃǂ��y����ł����B����ӏH�̖�\�ꎞ�߂����A��ʌ������̎O����ɍŏI�d�Ԃœ������A���̂��Ƃ��������d����Ў�ɉ_��R�ւ̓o�R����H��͂��߂����Ƃ��������B���̔ӂ͎O�������̃R�[�X���Ƃ��ĉ_��R�ւƌ������o�R�҂͂قƂ�ǂȂ��A��g�̃A�x�b�N�ƌ\�߂��̒��N�̒j���Ǝ��̍��v�l�l�����������B�����n�߂Ē��Ȃ��A�Ⴂ�A�x�b�N�̒j���͂��炭�������Ă���o��Ƃ������Ƃŋ߂��̏����ɓ���A�܂��A���N�̒j���̂ق��͑�ς�����肵���y�[�X�������̂ŁA���ǁA���������Ƃ�Ő�ɖ铹���}�����ƂɂȂ����B
�@���l�̔��Ώ������߂��A�W����O�E�l�S���[�g���̒n�_�ɍ����|�������Ƃ��ł���B�����́A�������}�ΖʁA�E�����[�����ётɂȂ��Ă���Ƃ���Ȃ̂����A�s�ӂɂǂ�����Ƃ��Ȃ������ӂ��Ⴂ���̍b���������f���I�ɕ������ė����B�N���߂��ɂ���̂��낤���Ǝv���A�����d���ł�������Ƃ炵�Č������A�l�e�炵�����̂͂ǂ��ɂ���������Ȃ��B���������������Ă݂����A�O���ɓo�R�҂�����l�q���Ȃ��������A�n�`�セ�̎��ӂ̓e���g���Ė�c�ł���悤�ȏꏊ�ł��Ȃ������B�o�R�����������ɂ͑����Ɏ��M���������̂ŁA���Ƃ��珗���̓o�R�҂��ǂ����Ă����ȂǂƂ������Ƃ͂ƂĂ��l�����Ȃ��������A�ꉞ�����~�߂đ҂��Ă��݂��B�����A��͂�N������Ă���C�z�͂Ȃ������B
�@�������Ă���Ԃɂ��A���̓��̂̒m��ʐ������͕������Ă����B���̉��⓮���̂��Ă镨���Ƃ͖��炩�Ɉ���Ă���B�����Ɏ��܂��Ă݂邯��ǂ��A���������Ă�̂��͂킩��Ȃ����A�ǂ��炩�畷�����Ă���̂������܂ЂƂ͂����肵�Ȃ��B�����Ƃ������Ƃ����邩�Ǝv���A���x�����x���m���߂Ă݂�̂����A��͂�l�̐��̂悤�Ɏv��ꂽ�B�����ŁA���炽�߂đ��𑬂߁A���삯�o��悤�ɂ��ē����}���ł݂��̂�����͂�N����������Ȃ������B�_�揬���ɒ����Ă����A�����Ԃ̐l�ɐ�ɓo���Ă����l�����������ǂ����q�˂Ă��݂����A�N�����Ȃ��Ƃ̂��Ƃ������B���ǁA�����͂킩�炸�d�������������A����͎��Ɋ�ȑ̌��ł������B
�@�R�ł̕s�v�c�ȑ̌��Ƃ����A�ق��ɂ���Ȃ��Ƃ��������B���镗�̋������ꂽ�ӂ̂��ƁA�ؑ]�̌�x�R�ɓo���Ă���Œ��ɁA�n���J�̈�т������ӌ����ĕs�C���ɋP���Ă���̂��������Ƃ�����B����Ȃǂ͂����̉Ȋw�I���ۂɈႢ�Ȃ��Ƃ͎v���̂����A���̌��ۂɐ���������ƂȂ�Ɠ���B
�@�悭���Q�̗��Ȃǂɂł����A�ςȎ����Ɏv��ʏꏊ��ʂ����肵���Ƃ��A���܂ɂ����A���̗�C�Ƃł��Ă�ł����悤�Ȃ��̂ɑ������邱�Ƃ�����B����ȂƂ��ɂ͗�̔ʎ�S�o�Ȃǂ������ĐS�𗎂������������킯�����A������Ƃ����Ĉӎ��I�ɗH��̖����Ɖ\�����悤�ȂƂ����K�˂Ă��A����炵�����̂ɑΖʂł��邱�Ƃ͖ő��ɂȂ��B��x����������𗊂�ɉ��k�����̋��R��тȂǂ�����Ă݂��肵�����̂����A��C�Ƃ������悤�Ȃ��̂������邱�Ƃ͂Ƃ��ɂȂ������悤�ɋL�����Ă���B
�@�|���Ƃ����Ӗ��łȂ牺��Ȃ������Ȃǂ����l�Ԃ̕s���ȍs���̂ق����͂邩�ɕ|���B���܂��ܗ������啝�ɋ����A�^�钆�Ɏl����\�l�ԎD���A�Ō�莛��K�˂邱�ƂɂȂ��Ă��܂����Ƃ��̑̌��́A���܂ł��Y��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�@���������Ԃ�̘̂b�ɂȂ邪�A���̔ӁA�Ō�莛�i�ق݂������j�̗���ɂ��钓�ԏ�ɒ������̂́A�ߑO�ꎞ�߂��������B������N�̍��̂��Ƃł���B�Ԃ𒓂߂Ă��肰�Ȃ�������̗l�q���M���Ă݂����A�������ɐl�e�炵�����̂͂܂�������������Ȃ������B
�@�]���������߂�������̌��̖�̂��Ƃ��������A�삩��k�ւƌ������������ɐ����Ȃ���A�����}���Q�_�ɂ���āA���e�͂قƂ�Ǖ����B����Ă����B�����A���܁A�_�̗ڂ��炱�ڂꗎ���錎�̌��ɂ́A�d�����܂łɍႦ���P������߂��Ă����B�ˑR�����肪�ٗl�ɖ���Ȃ������Ǝv���ƁA�����ɂ܂��ł��߂�Ƃ����A���̂�������������тт���i�́A���ƂɂȂ��čl���Ă݂�ƂȂ�Ƃ��Î��I�Ȃ��̂ł͂������B
�@�܌������{�ɂ����낤���Ƃ������߂ɂ��킦�āA�썑�y���̂��Ƃł�����������A�镗�͂ނ���S�n�悢���炢�ŁA�����Ƃ��������͂܂������Ȃ������B���̎����𐁂������Ă������ɏ���Ă������Ȓ��̍���ƒ���̋����Ƃ��`����Ă���̂́A���̍Ō�莛�����˖��̂قڐ�[�̍���Ɉʒu���Ă��邩�炾�����B���������A�u�Ō�莛�v�Ƃ́A�u���̍Ő�[�ɂ��邨���v�Ƃ����Ӗ��Ȃ̂ł���B
�@���ԏ�ň�x�݂������ƁA���͍Ō�莛�̋������U�Ă݂邱�Ƃɂ����B�q�ǂ��̍�����̏K���Ő[��ɓƂ�҂����ꏊ������܂�邱�ƂɊ���Ă��鎄�ɂ́A���|���͂܂������Ȃ������B
�@�Ō�莛�̕������̓����R�呤�Ɍ������Ď����������ƕ����n�߂��Ƃ����A���e�͂��傤�Ǒ傫���������_�̉A�ɉB��Ă��܂��Ă����B��Ԃ̂��Ƃ䂦�\���ɂ͊m�F�ł��Ȃ���������ǂ��A��т̓A�R�E��^�u�A�ӗނȂǂ̍��X�Ƃ������M�ѐ����тŕ����Ă���A�����������l����[�̖������̂��Ƃ���Ƃ��������������B
�@���̒���̂��ƁA�˔@�A�T�[�b�ƕӂ��т����邭�Ȃ������Ǝv���ƁA�����������A����O���ɉ��т�̂����̕���s�C���ɏƂ炵�������B���̂ق��Ɏ����𑗂������̏u�ԁA���͕��ɂ��Ȃ��v�킸�g������点���B�O���̕������ɁA���𐂂炵���Ⴂ���̉e�̂悤�Ȃ��̂���������ƕ�����Ō���������ł���B�������������났�Ȃ�����A����͌��o�ȂA���o�ȂƁA���͎���Ɍ������������B��ԁA�҂����Ƃ������l�ŗ����Ă���Ƃ��Ȃǂɂ��̎�̌o�������x���������Ƃ̂��邨�����ŁA�قƂ�ǂ̏ꍇ�͎����̍��o�⌶�o�ł��邱�Ƃ��킫�܂��Ă������炾�����B
�@���̍����e�����͂ǂ����Ă����ނ����Ⴂ�����̎p�Ɍ������̂����A�S�𗎂������A�������܂ŋ߂Â��Ă݂�ƁA����ς肻��͌��̌��̂�������ł��邱�Ƃ����������B���̎}�t�̔����ȉA�e�Ɛ����������D��Ȃ����R�̌��e�������̂��B���̌��e�ݏo�����ƂƂȂ������̑O��ʂ蔲�����������Ƃ��ɂ́A���e�͍Ăщ_�ɕ�܂�A�ӂ�ɂ͈ł��߂������A�u�H��̐��̌�����͂���ԁv�Ƃ������Ƃ킴��n�ł����悤�Ȏ��̂Ȃ�䂫�ɁA�������Ĉӂ������������́A��ɂ��������d���̌����ւ炵���ɗh�炵�Ȃ���Ō�莛�̎R��̂ق��ւƋ}�����̂������B
�@�����Ō�莛�̎R��ɗ������Ƃ��A���v�̐j�͂��傤�njߑO�ꎞ�����w���Ƃ��낾�����B���̎R��́A��Ƃ͂����Ă��ׂɔ�������킯�ł��Ȃ��A���ł����R�ɏo����ł���悤�ɂȂ��Ă����B�����̎���͐[�����M�ю�̎��тň͂܂�Ă��邤���ɁA���̌��͂܂������_�ɕ�����Ă�������A�����̈ł͑����ɐ[�������B��������芪�����ɂ��������Ă��A���̓����͂܂�����������ꂸ�A���X��U���Ȍ�����������A�Â�����C���̂��̂��A�����Ƒ����Ђ��߂Ď��̈ꋓ�ꓮ���M���Ă��邩�̂悤�������B
�@�ْ����ق������߂ɑ傫������f���Ȃ���A�����̑O�ւƑ����Q�������E�������ݐi�Ƃ��̂��Ƃł���B�O���̈ł̒��ŁA�����Ԃ������Ȃ��̂����炿��Ɨh��ē����Ă���̂ɋC�Â������́A���˓I�ɂ��̏�ɗ����~�܂����B�����āA�s�ӂɖڂɔ�э���ł������̊�Ȃ��̂̐��̂����ɂ߂悤�ƁA�S�_�o���������܂��đO�����������ɂ݂������B
�@���̔w���s���₽���X�̐j���˂��������̂͂��̎��̏u�Ԃ������B�����ܐ�ɂ����Đg�k������悤�Ȑ�ɂ����������Ǝv���ƁA���̐g�̂̑S�_�o�͏u���ɂ��ē�����Ă��܂����B����́A�������܂�ď��߂Ė��키�A�{���̋��|�Ƃ����Ă��悩�����B�����ʂ�S�g���d�����A�����Ȃ玩����ÂɂȂ��ߗ�܂����t���S�̉��œ�����Ă��܂��L�l�������B
�@�ł̉��ɐԂ��h�ꕂ����Ō��������̂́A�����̂�����O�̐Βi�̏゠����ŕs�C���ɗh��߂���{�̘X�C�̉��������̂��B����Ȏ����ɁA���������N�����̂��߂ɒu���Ă��������̂Ȃ̂��낤�B�ނ��A������ɐl�e�͂܂�������������Ȃ������B�ł��A�N�����A��������̖ړI�ŏ����O�܂ł����ɂ��āA���̕s���R�ȏꏊ�Ɉ�{�̘X�C���u�������Ƃ����͂܂�����Ȃ������������B���́A�������������̂̒m��Ȃ����̂ɂ����ƌ��߂��Ă���悤�ȋC�����ĂȂ�Ȃ������B�����߂Â��C�z���@�����N�����A�����̈ł̒��ɐg���B���A�����ɂ�����̗l�q���M���Ă��邱�Ƃ����ď\���ɂ��链�邱�Ƃ������B
�@���̂Ƃ�����́A�������ɁA���̏ꂩ�炷�����ܓ������������C���������B�����A�K���Ƃ������A����ł��A���炭����ƁA�킸���Ȃ��������Ȏv�l�������͂��߂Ă����̂ŁA���͑傫���ċz�𐮂��Ȃ���A�ɗ́A�����̐S����ÂɂȂ�悤�ɂƓw�߂Ă݂��B�^�������x�̕��p�̐S�����������̂��A�����Ƃ����Ƃ��̔����Ƃ��đ����͖𗧂����B
�@���̓�߂����X�C�̉��͂������ɗh��Ȃ�����ˑR�Ƃ��ĕs�C���ɔR�������Ă����B�ǂ��݂Ă��A����͌��o�Ȃǂł͂Ȃ������B�ł�H���ΎM�܂ł��Ƃ������A�ǂ����Ȃ�A�����炩�炠�̘X�C�̂��܂ŋ߂Â��Ă݂悤���ƊJ�����������́A��O�̘X�C�̉��Ɏ䂫����悤�ɁA���킶��Ƃ����̑O�̐Βi�ւƋ߂Â��Ă������B
�@���̘X�C�͐Βi�̂Ȃ��قǂɗ��Ă��Ă����B���X�̕��ɂ͑ς�����悤�ɂƂ̈Ӑ}���炾�낤���A����͂��Ȃ葾�߂̘X�C�ŁA���̔R���������@����ƁA�����ꎞ�ԋ߂��͔R�������Ă����̂ł͂Ȃ��낤���Ǝv��ꂽ�B�Ȃ�Ƃ��s�v�c�Șb�����A���������ɂ���Ă���O�ɁA�N�����A�����̖ړI�ł��̘X�C�𗧂Ă����Ƃ����͋^���]�n�̂Ȃ����Ƃ������B
�@������������A�ł̉�����A��̖ڂ����̈ꋓ�ꓮ�������ƌ��ߑ����Ă����̂�������Ȃ����A�K������ȏ�͉����ς�������Ƃ͋N����Ȃ������B������������g����^�C�~���O�𑪂��Ă������́A�Ăь��e���_�ԂɌ���A���ӂ����邭�Ȃ����̂����͂���ƁA�Ȃ����R��������X�C�����ƂɎc�����܂܍Ō�莛�̋����𗧂��������B
�@�Ԃɖ߂������Ƃ��X�C�̂��Ƃ͋C�ɂȂ������A���̊�ȍs�ׂ̎�̐��̂��A���̐l�����Ӑ}����Ƃ�����Ō�܂ł킩��Ȃ������B�����҂ɂ���A����Ȏ����Ɏ��̂悤�Ȑl�Ԃ��Ō�莛��K���Ȃ�ė\�z���ɂ��Ă��Ȃ������낤���A���Ƃ����̏�̂ǂ����ɐg����߂Ă����Ƃ��Ă��A������Ɋ�Q�����������Ȃǖѓ��Ȃ������̂��낤�B�������A�Ȃ�炩�̉��O�⎷�O�ɜ߂��ꂽ�l�Ԃ̍s�ׂقǕs���ŕ|�����̂͂Ȃ��ƁA���̖�̂��Ƃ�U��Ԃ�Ȃ���A���Â��v������ł���B
�@�������A�����ɂ���ẮA�N���̎�̍����Y�������Ƃ������Ƃ��܂������l�����Ȃ��͂Ȃ��b�ł͂���̂�����ǂ��c�c�B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
1999�N8��18��
�̎��u�u��̌��v�̐^�U�̂قǂ́H�@�@
�@�����܂���̓��̏��w�Z�ɒʂ��Ă������̘b�ł���B�����������邩��ɐ��������ȒS�C���t�́A�������Ƃ���ɁA��������ƌ�C�����߂Ȃ���A���̓��̎��Ƃ���ߊ������B
�@�u��{�����Y�́A�n�R�Ń����v�̖����Δ������Ȃ�����B��������ŁA�ӂɂ�A�u�̌���ᖾ������Ĉꐶ���������Ĉ̂��Ȃ����Ƃ�B�u��̌��Ƃ������t�́A���́c�c�̎����イ���A����Ȑ̗̂L���ȃG�s�\�[�h�����ƂɂȂ������B���w�������炿�イ�āA���܂�����Â��Ă����肨���ŁA�����ƕ�����ɂႢ����B���Ȃイ����́A���̋C�ɂȂ�A�ǂ��Ăł��ł�������I�v
�@���܂ɂ��Ďv���A����́A�Â������̌̎��Ƃ����Ƃ̂��̓�{�����Y�̓`���Ƃ������፬���ɂ����A���Ȃ肢�������ȓ��e�̌P�b�������B�����A����Ȃ��ƂȂǒm��悵���Ȃ��Гc�ɂ̏��w���ɂ��Ă݂�A���̖����q�ِ̕�̂����͂Ɛ����͂͂Ȃ��Ȃ��̂��̂������B
�@���̔ӂ̂��ƁA���ȃ��[�����Ȃ�ʁu���ȋ����Y�v�ɑ��ς�肵�����́A�����Ƃ̎҂�K�ڂɁA�K���X�̏��r�����ɉ����A�Ў�ɒ|ⴂ��g���āA�߂��̏���̂قƂ�܂ňӋC�g�X�ƌu���ɏo�����邱�ƂɂȂ����̂������B�l�����班�����ꂽ�Ƃ���ɂ�������吂̐��ފ���̐����́A�m��l���m��u�̕�ɂŁA�܂������߂������Ƃ����āA���ȋ����Y�̖ڎZ�ɂ͘I�قǂ̋������Ȃ������B�����̕邵�ނ��͂������Ċy�ł͂Ȃ��������A������Ȃ�ł����Â����d���̂ЂƂ�ӂ��͂���������A�u��̌��̌̎��ɂȂ炤�K�v���������킯�ł͂������ĂȂ��B���������f���ɂ���ȋ����ɐS�����A��J��ɂ��܂��w��ς�ł������炢�Ȃ�A���������ƌ��\�Ȑg���ɂȂ��Ă����͂��ŁA�������Đ������˂��悤�ȋY���Ȃ�Ԃ�����͂��Ă��Ȃ����낤�B��k�݂����Șb�����A����͂ЂƂ��ɁA���N�����L�̉����ȍD��S�̂Ȃ���Ƃ������ƌ����Ă悢�B
�@�܂�ŁA���̐��̋����Y�̎��O�����ڂ����݂����Ȓ|ⴂɒǂ��ꂽ�̂ł́A�������̌����u�����܂������̂ł͂Ȃ��B�قǂȂ��A���r�̒��́A��p�ƂȂ����\���̐������̗��ł����ς��ɂȂ����B�u�ɂ���Ζ��f�疜�Șb�ŁA���D���ȏ��w���̐S����肽�Ă�������̋��t�����������������������Ƃ��낤�B
�@��̏���̂��������ň�E�ԂقǑ劈�������������́A�������͗ǂ��Ƃ���ɉƂɋ삯�߂�A�������������ɂƂ肩�������B�̂̓K���X�r�Ȃǒ��������ď����̎�ɂ͓���Ȃ������낤�Ƃ̑z������A�a������̌Â����^�̊p�s�������o���Ă��āA��C�����ǂ������ƁA���̒��ɕ߂炦���u������Ă݂��B
�@�������ʂ͗\�z�ɔ����Ă͂Ȃ͂��s�{�ӂȂ��̂������B���܂�ɕs���ȍS���Ԃ�ɒ�R�̈ӎu���ނ������ɂ����u�ǂ��́A�l�ԗl�̐�m�b�������������������Ƃ��A�s���̒����ނ�݂₽��ɔ����܂��A�x���ŗ�ŕs�K���Ȍ��̌��t���s�[�J�s�J�c�c������Ǝv���܂�������A���̋��̗����ŕٌc����ɖ���y��������ۂ��ڂ����|�������ȖZ�����I�c�c ���x�̎コ�������܂��āA�������ׂ������ȂǓ���ǂ߂����̂łȂ��A�����ēǏ��𑱂����痂���̖閾����҂����ɍ������A�Q����ł��܂��Ă������Ƃ��낤�B
�@���킦�Ă܂��A���̂Ƃ���ɂ����{���{�c�c�l���܌o�ȂǂƂ����������[���ȏ����ɂ͂قlj����A�]�ː에���̒T�㏬���u�������ʁv����������A�u�ǂ���������p�ɂł��Ƃ����̂��܂炤�Ȃ����ʖ�ł͂Ȃ��B���̐����ȖړI�̂��߂ɋ]������������Ƃ����̂Ȃ�܂������A�Гc�ɂ̃n�i���ꏬ�m���T�㏬����ǂނ̂ɐg��������Ȃ�āA�ƂĂ��䖝�ł��Ȃ��ƁA�ނ�̓w�\���Ȃ����̂��낤�B
�@�����A�b�͂܂��I���Ȃ��B���̂Ƃ��A�ˑR�A���ȋ����Y�́A���̎����ɏd��ȕs�������邱�ƂɋC�������B�̂̏����̕����́A����̊����Ɋr�ׂĂ����Ƒ傫�������Ƃ������Ƃ���������Y��Ă����̂ł���B�����ŁA�ɂ킩�����Y�́A�������d�̑O�ɔ��ōs���A�Â��ؔō���̊ϖ��ʎ��o�ƈ���Ɍo�a�]�{���������Ŗ߂��Ă����B�܂��A���̂����ۂ��ŁA����̘a���Œ��ǂ������ȑ܂�����A�u�ɂ���������A�v���m�������I�v�Ƃ���Ɍu�ǂ������̒��ɉ�������ŁA�����ȖړI���s�̂��߂ɗL�������킳���E�]�����v�����B�����āA���̗܂��܂����w�͂ƍH�v�̍b�゠���āA�o���̂����߂����������Ȃ�Ƃ��ǂ߂��c�c�ہA�u�������v�̂ł���I
�@����ňꌏ���������A�u�u��̌��v�̔��k�͕K�������R�ł͂Ȃ������̂��Ǝ����[���������Ƃ����ƁA�����ł͂Ȃ��B�c���Ȃ�̎v�Ă̖��ɒB�������_�́A���Ƃ����낤�ɁA�u�̌̎������b���Ƃ���A���̐l�͓`���Ƃ͈قȂ葊���ȊՐl�������ɈႢ�Ȃ��Ƃ������̂������B
�@�u�Ƃ������̂͂��ア�����ŁA�������Ă̒��Ȃǂł͕߂��Đ����Ԃ����Ȃ������ɐ��サ�Č��������Ă��܂��B��ɂ��Ď����ɂ��Ă��Z�������A���������A���̎�Ԍ������ł��e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ��B���̌u���l�ԗl�̏���Ȏv�f�ɂ���قNj��͓I�ł���킯�͂Ȃ�����A�鐅�ӂɏo�đ����̐��̌u�������邾���ł���E�Ԃ͐������ł��܂��B���ɂ�ɂΘJ�Ίw�̐l���A������Ȃ�ł����Ӑ�ӂɏo�āA�u�u���[�C�I�v�ł��Ȃ������낤�B�ނ��A��x���x�Ȃ�\���ɂ��蓾���b���낤���A�u�̋G�߂��Z�����Ƃ������킹�l���Ă݂�ƁA�ƂĂ������I�Șb���Ƃ͎v���Ȃ������B
�@�썑�ł͂߂����ɐႪ�~��Ȃ����߁A�ᖾ����̂ق��ɂ��ẮA�c�O�Ȃ���A��̓I�Ɋm�F���邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�����A��l�ɂȂ��Ă���A��R�Ŗ���߂�������A�[��ꎞ�ɐ�̐[���n����K�˕������肵���o�����炷��ƁA������̂ق����A�u���͂����ƌ�����������悤�Ɏv����B��͈�x�ς���Ɨe�Ղɂ͏����Ȃ����炢�ł����p�\�����A�ᖾ��Ƃ������̂ɂ͊m���ɂ���Ȃ�̂����邳�͂��邩�炾�B�����A�ᖾ��́A�u�ƈ���Ă����܂Ŕ��ˌ��ł��邩��A����ߗׂ̃����v�̖���A�����ȂǁA�Ȃ�炩�̌������K�v�ɂȂ�B�Ȃ�̌������Ȃ��^���Âȏꏊ�Őᖾ��𗘗p���ď�����ǂނ��ƂȂǂ́A�ނ��o����͂����Ȃ��B
�@�����A�N���X���C�g�̉��l���Ɏ��̎����b�����Ƃ���A���̂����̂����������Ȉ�l���A���ƒ������Ȃ�A������̋��t�Ɍ������āA
�@�u�搶�A����̌u��̌��̘b�̂��Ƃ₢�������Ă��A�䂤�ׁA�{�c���A�ȂA��łȂ܂ȁi��������j�u�Ε߂��āc�c�v�ƁA��肾�������炽�܂�Ȃ��B�s�ӑł�����������t�̂ق��́A�����Ȃ��Ȃ萺���A����ʗd�Ȍ`���������Ȃ����債���B�z���o�����тɐ\����Ȃ����Ƃ������ƁA���܂��A���������Ȃ͂��Ă���̂����c�c�B
�@�u�u��̌��v�̌̎��͒����̐W�����̎Ԉ��`�E���N�`�Ɍ�������̂ŁA���Ă̎t�ɂ͐\����Ȃ����A�����Ɍ��邠�̐d��w��������{�����Y�����̈�b�̎�ł���킯�ł͂Ȃ��B������������A�Ԉ��`�⑷�N�`��ǂ����Y���A������u��̌��̌̎��ɂȂ炨���Ƃ������Ƃ͂������̂�������Ȃ��B�܂��A�ނ��������ΘJ�Ίw�̐��_�⍏��ח�̋������̂��̂́A�N�ɂƂ��Ă�����Ȃ�ɑ�Ȃ��Ƃł���B�����A�u��̌��̌̎��Ɠ�{�����Y�Ƃ͒��ڂɂ͊W�Ȃ��B
�@�u���ɂ܂����̌̎��́A�����Ɍ��������������ł��w�͉\���Ƃ������Ƃ�������߂̏ے��I�Ȃ��Ƃ��b�������Ǝv���A���̈Ӗ��ł́A���ۂɌu�̌���ᖾ��œǏ����Ȃ��ꂽ���ۂ��͂����ďd�v�Ȃ��Ƃł͂Ȃ����낤�B�����A����Ȃ��Ƃ��b���A���̂܂ɂ�炠���̃��A���e�B�������ď���ɕ����͂��߁A�������ꂵ���u����ځv�ƂȂ��āA�����������Ŗ҈Ђ��ӂ邤�ƂȂ�Ƙb�͕ʂł���B���̂悤�Ȏ���͐̂��������Ȃ��Ȃ��A�����ɋ�����`�Ƃ������̂̕|��������ƌ����Ă悢�B�����Ɍ����邩������Ȃ����A���ؓI�ԓx�́A����ȋ�����`�I���_�̌��x�������s�����߂�͂������A���ꂪ���ƂňӊO�Ȕ�����V���ȏ̑ŊJ�ɂȂ��邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��B
�@�������Ȃ���A��̓I�Ȍ����肪�ɒ[�ɐ�s����ƁA�O�E�̑��l�Ȏ��ۂ̔F���̂������ɓ��ꐫ���Ȃ��Ȃ��Ď��E�����Ȃ��Ȃ�B����ȂƂ��A�s���肩���ׂƂ����ɓ���ƒ��a�������炵�A�Љ�̂Ƃ�ׂ��������������Ă����̂��A���_�ł��藝�O�ł�����̂��܂��������B���̈Ӗ��ł́A���b���ǂ����Ɋւ��Ȃ��A�u��̌��̂悤�ȁA�悭�ł����̎��̑��݂�����Ȃ�ɂ͕K�v�ƂȂ��Ă���B
�@��������ӂꂽ�A���ɂȂ��Ă��܂��̂����A�v����ɓ�̂��͕\����̂ŁA���҂̖r�܂�����l�O�r�ɂ�鏕�������I���W�������]�܂����Ƃ������ƂɂȂ�B�Е������̖\���́A���ǂ̂Ƃ���j�łɂȂ������ł���B
�@����ɂ��Ă��A�J�����Ƃ�ʐ̂̉����ȒT���S�͂������������֏��������Ă��܂����̂��낤�B�u�̋G�߂��̋G�߂�����Ă��邲�ƂɁA�c�����X�̂��Ƃ�z���o���ẮA�Ƃ�����Ɗ������D��S���݂肪���Ȃ��̐g���������߂Ă͂��邪�A�Ȃ��Ȃ��v���ɂ܂����Ȃ��̂�����B������������A���܂����A���ɂ́A���̂Ƃ��̒S�C���t�̌��t�݂����ɁA���ؐ��_��T���S�����������������Ă����悤�ȉ������K�v�Ȃ̂�������Ȃ��B
�@�����Ƃ��A�����̗^�}�c���搶�����́u�w������⏭�N�ƍ߂̑����Ȃǂ̖������̂��߁A���̊ہE�N������͂��߂Ƃ��鈤���S���炪�K�v�ł���v�Ƃ������悤�ȁA���̊ہA�N����̐�����]�X����ȑO�̂��e������܂�Ȃ��c�_�����ɂ����肷��ƁA���_�������ǂ��ł��悭�Ȃ�A�B�X����ȃ��x���̐搶�����������̑ǎ������Ă��鍑�ɏZ��ł��邱�Ǝ��̒p���������C�����Ă��܂��B�������ł����������������Ȃ���搶�����́A�ق�Ƃ��ɂ��̍��������Ă�����̂ł��낤���B���{�Ƃ������������Ă������̈�s���Ƃ��Ă���������������Ȃ��Ă���Ƃ������̂��B
�@�肪�����̂́A��b�_���w��C���w�i���g���b�N�j����背�x���g�ɂ��������̃v���̎�ɂ�����ƁA�u���͌��ł���v�Ƃ����g�[�g���W�C�i���ꔽ���A���Əq�ꂪ�����T�O�̖���j�I�ł���߂Ď����Ș_������̏ؖ����A�u���͔L�ł���v�Ƃ����펯����E��������̏ؖ��i�H�j�̂ق������Ƃ��炵���������邱�Ƃ��낤�B�����̏ؖ��v���Z�X���l���Ă݂Ă��A��҂̂ق�����苻���[���ɈႢ�Ȃ��B
�@����_������𗧏���Ƃ́A�u�l�Ԃ����łɎ������킹�Ă���T�O���{����̂Ȃ�����A�Ȃ�ׂ��₳�����A�N�ł����R�����ϓI�Ɏ���邱�̂Ƃł���悤�Ȃ��̂�I�яo���A������g�ݍ��킹�ĖړI�Ƃ����荂�x�Ȗ���̐��������������v���Ƃł���B������A���܂�ɂ������Ȗ�����ؖ����邱�Ƃ͎��͂����ւ����B�u���͔L�ł���v���Ƃ𗧏��Č����邱�Ƃ̂ق����A�ɂ���Ă͂͂邩�ɂ₳�����A���̘_���̓W�J��ڂɂ��鑤�ɂ������Ɩ��͓I�ɂ���̂��B
�@�Ȃ�Ȃ���ۂɂ����ł��̏ؖ��̈�[���I���Ă݂Ă��悢�̂����A�����͘_���w�̃R�[�i�[�ł͂Ȃ����A������Ɛ[���肷��ƁA���e�̗ʂ������܂��{������ɂ��Ȃ��Ă��܂����˂Ȃ�����A�����̂Ƃ���͂��̂ւ�ŕM�������߂邱�Ƃɂ������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
1999�N8��25��
�q�L�̊J������������@�@
�@���܂ꂽ����̎��X�̗��u�₩�ȕ���ῂ��������ĝ���Ă����l�����{�̂��Ƃł���B�~�[�~�[�Ƃ����Y��Ԃ��Ȃ��q�L�̖����炵�����̂��ǂ����炩�������Ă���ƁA�Ƃ���Ɛl�������o�����B�܂�����Ƃ̃m��������̗Y�L�`�[�^���[��������ɖ��f�Ő��]���̎�p���Ă����킯�ł�����܂����A�u����Ȕn���ȁH�v�Ƃ͂��߂͔��M���^�������̂����A�u�~�[�~�[�v�����̊Ԃɂ��A�u�~�M���[�I�E�t�M���[�I�v�̐⋩�ɕς�鑛���ɋy��ł́A�������ɂ��̑��݂�F�߂Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��Ȃ����B
�@����͂Ƃ����̂Œ��ׂĂ݂�ƁA���Ƃ͂��łɗe�ՂȂ�ʎ��ԂւƂ����������Ă��܂��Ă����B�Ƃ̉����`���ɂ���Ă������̃m���L���A��Ƃ̌���̉J��̂��˂ɐ������킸���Ȍ��Ԃ����K�̓V��Ɠ�K�̏��ɂ͂��܂ꂽ������ԂɐN�����A�ǂ����Ɏq�ǂ����Y��ł��܂������̂炵���B�������A�^�����Ƃ̉����̕�C��Ƃ��n�܂������߂ɐe�L�̃A�v���[�`�E���[�g���f����Ă��܂��A���܂ꂽ�Ă̎q�L�������Ǘ������̏�Ԃɒu����Ă���炵�������B���̏؋��ɁA�����͂��鎞�_���s�[�N�ɂ��Ď�܂��Ă����Ă���B�u�~�M���[�I�E�t�M���[�I�v�͎q�L�ɂ���Ζ���q�������ѐ��Ȃ̂������B
�@�����̂���ꏊ���ǂ�����K�ɒʂ���K�i�㕔�̗����t�߂炵���Ɣ��������̂́A���Ȃ莞�Ԃ������Ă���̂��Ƃł���B�ꏊ���ꏊ�����ɑ��ɋ~�o��i�͂Ȃ��Ɣ��f�������́A�K�i�̐����ʂɎl�p�������J���邱�Ƃɂ����̂����A�L�̂��鐳�m�Ȉʒu�����߂ʂ��߁A�l�i�ɂ킽���ċ����ӂ邤�͂߂ɂȂ����B
�@�����猻�ꂽ�̂͂܂���ɔ����̂������������T�Ԃقǂ̎O�тƃL�W�g���̓�C�̎q�L�ŁA�O�т̂ق��͎��o�����Ƃ���Ɂu�~�M���[�I�v�̘A�����͂��߂����L�W�g���̂ق��͑̂��₦�����Ă��܂��Ă��āA�u�j�[�j�[�v�Ƃ������Ȑ��Ŗ��̂�����Ƃ̂悤�������B���炵�����̊����K���̂��������悭����ƃ`�[�^���[�������肾�B�Ƃ̔L�����Ǝ҂Ƃ����Ă͂��͂�ӔC�͖Ƃ꓾�Ȃ��B�y�b�g�V���b�v�Ɏq�L��p�̚M���r�ƃ~���N���ɑ�����ۉ��������������A�����܂��ƒ����呛���ɂȂ����B�l�̌��͔ōǂ��ł݂����̂́A�p�b�`���[�N�̎��s��݂����ŎS����͂Ȃ͂������B�����ň�v���Ă��A�茳�ɂ��������b�Y��⌹���G���̊G�t���Ȃǂ��p�����B���悤�ɓ\��t����ƁA�v���̂ق������������̊K�i�M�������[���ł����������B
�@�������萊�サ�Ă����j�[�j�[�̂ق��͕K���̉�����ނȂ�����������悤�ɂ��đ���������������A�O�т̃~�M���[�͖{�\�I�ɑO�������݂ɓ���������|�[�Y���Ƃ�Ȃ���~���N���悭���݁A����قǂ���Ɩщ������Ȃ�悭�Ȃ����B�����A����O�T�Ԃ܂ł̎q�L�ɂ͒������ʓԂ����̚M���Ɣ����ȑ̉��̈ێ��������s���ŁA�r�A�r�ւ����͂ł͂܂܂Ȃ炸�A�ʏ�͐e�L����ŋǕ��Ɏh����^���Ă���Ă͂��߂Ă��ꂪ�\�ƂȂ�B�@�@
�@�e�L�ɂ�����Ă���炷�ׂĂ�l�Ԃ����ȂǕ��̊o��ł͖����Ȃ̂����A�߂������ȁA���̂ւ�̎���ɉ�X�͂܂�ł��Ƃ������B�~�M���[�̕K���̑i���ƁA�悩��Ǝv����X�̌����̉��Ƃ͔���Ȃ܂ł̂���Ⴂ��������Ƃ���ƂȂ����̂������B�ˑR�~���N�����Ȃ��Ȃ����������̉������̎��s�ɂ��k�o�@�\�̒ቺ�ɂ���ƋC�Â��܂��Ƀ~�M���[�̗͑͂����Ղ��A���e�𗊂݂ɒm�l��̎��L�̂��Ƃɋ삯���Ƃ��ɂ́A�������͂œ����z���͂��Ȃ����Ă��܂��Ă����B���̎��L�̎����[���K���̉���ɂ�������炸�~�M���[�͂ǂ�ǂサ�A���̏�ł��ɑ��₦���B
�@�[���ɂ݂ɂ����Ȃ܂���A���͋v�X�ɊJ�����������犴�����Ƃ����܂��Đ��E�̉�����̂����Ă����B���t�ƌ��t���A�����Ĉӎv�ƈӎv�Ƃ�����Ⴂ�A���ǂ͎������Ƃɂ���Ă����w�Ԃ��Ƃ̂ł��Ȃ����̐��̏k�}�����߂Ă����B�����Ă͂��߂ď������J����E�E�E���͂������A���̖��������m�炸�ɐ������~�M���[�̐����������Ă���v���������B���̂������A���肵���߂��s���I���J�[�̘A�Ă̐���������肢�������������������������B
�@�����A��̕Ћ��ɂ���j�[�j�[�̕�̉��Ƀ~�M���[�̕����ׂĂ������B�Ƃ��낪���̐�����A���Ƃ����낤�ɁA�䂪�q�̕�݉z���ăK�[���n���g�ɏo�w����`�C�^���[�̎p���ڌ����ꂽ�B�u�Ԃ��������݉z���āc�c�v�ǂ��납�A����ł͂܂�ŁA�u����q�ǂ������݉z���āA�s���͒j�̐����铹�c�c�v�ł͂Ȃ����I�@���͂����������ɂƂ��Ă��̗l�q�߂Ă����B�������Ă܂��A����璦��Ȃ��ʁX�̎�ɂ���āA�u���v�Ɓu���v�Ƃ̗��j�͖������J��Ԃ����B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
1999�N9��1��
���̘e�����Q�L�i�P�j
�NJ��̐S��K�˂�
�G�E�n�Ӂ@�~
�@�NJ��̐S��K�˂ā\�\�z�㒷������o�_���
�@�̂�т�Ƃ����C���Ń��S���Ԃ̃n���h��������A�����A�����{���𗧂������́A��ʍ������������Ƒ���p���ŌQ�n�ƐV�������ɂ���O�������z�����B��萳�m�Ȍ�����������A�O���g���l�������B�u�����̃g���l������Ƃ����͐ፑ�������v�Ƃ����A���̕����̌��t�ɂ��₩�肽���Ƃ��낾�������A�܌������̂��ƂƂ����Ă������̐[����������A�t�߂͈�ʋP���悤�ȗ̎�t�ɕ����s������Ă����B
�@�����Ƃ��A��͂Ȃ��Ƃ����Ă�����͍������ӂ̂��ƂŁA�c��R��J��x�Ȃǂ̎R�X�͂܂������Ղ�Ǝc���Ղ��A�z���𗁂тĂ܂䂭�P���Ă����B���̓~�A�����{��т͋v�X�̍���Ɍ�����ꂽ����A��N�ɔ�ׂď��Ă̖K�ꂪ��A�O�T�Ԃقǂ͒x��Ă��銴���������B
�@���Ԓ����Ƌx�e�����˂āA�c��Ɠ���̂Ȃ��قǂɂ�����H�X�e�[�V�����ɗ������ƁA�������̋}�Ȋ┧�̎Ζʂ��炱��Ɛ������N���o�Ă���̂��ڂɂƂ܂����B�����Ɉ������ł݂�ƁA���ꂪ���ɂ��܂��B�w������ȗ��̎R����ʂ��Ė����ƌĂ����̂͂����Ԃ�ƌ��ɂ��Ă����̂ŁA���̖������͑����ɂ킩����肾���A����Ȏ��̌o�����炵�Ă������̐����͂Ȃ��Ȃ��̂��̂������B�։z�����ԓ��A�����g���l���������O�̒J��x�p�[�L���O�G���A�̗N�������J�ɖ��������A���̐��̂��܂��͂���ȏ�̂��̂Ɏv��ꂽ�B
�@�����ɐ��͕K���i�ł���B���́A�Ԃ���u�Z�b�̐��v�ƕ\�����ꂽ��̓b�g���p�y�b�g�{�g���ܖ{�����o���ƁA�����ɐ����l�ߍ��B���Ƃ����ł͖{���ɏ��������Ȃ��u�U�Z�b�̐��v�̒a���ł���B���܂�̗₽���ɂ��т��w��������艷�߂Ȃ���A�u��S�{�قǃy�b�g�{�g�������������Ƃ����������ł��邩������Ȃ��ȁv�ȂǂƖ��ȑz����������������B
�@�M�Z��̎x���A�����ɂ����Ă̂т鍑���\�������z�㕽��Ɍ������Ă�����A�k���{���̒����w�ɓ��������̂͌ߌ�ꎞ���������B��̑O�A�����ɖ���y����煘r�����Ƃ̂��G�������̂��Ƃ͂����āA�w�r���₻�̎��ӂ̌����A���H�Ȃǂ͏\���ɐ������s���͂��Ă���B�w�߂��̘H��ɎԂ��Ƃ߂����́A�����l�\�l���ɏ���Ĉꎞ�\�����ɒ����ɓ�������͂��̗��̑��_���}����ׂ��A�������D���ւƕ���i�߂��B�p���p���ɂӂ��ꂽ�傫�Ȕ�܂����ɂ��āA���ۂΖX�q�ɐV���c�A�W�[���Y�p�̓��Ă������l�������D���ɂ��̑啿�Ȏp���������̂͂��ꂩ��Ԃ��Ȃ��̂��Ƃł���B�ዾ�̉��̑傫�ȓ����݂��������ăL�����ƌ������B���N�ɂ킽�萅�㕶�w��i�̑}�G�����S�����Ă���ꂽ���Ƃł��m���钘���ȉ�ƂŁA�ዷ��ђ����ݏZ�̓n�ӏ~����̓o�ꂾ�����B
�@��B��H���ɂœn�ӏ~����ƌ��I�ȏo���������Ă���������N�߂����B���̊Ԃɉ��x���A��l�����ŋC�܂܂ȗ������悤�Ƃ����b�������オ������͂����B����܂ł���A�O���̒Z�����ɂ́A���x���ꏏ�ɂł��������Ƃ͂���̂����A��T�Ԃ��钷���Ƃ��Ȃ�ƁA�o���̎��Ԃ̒���������̂��Ȃ��Ȃ��ɓ���A�v���ʂ�ɂ͌v���i�߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��ł����B�����ŁA���N�����͒��N�̖��������̂��̂ɂ��悤�ƁA�V�N���X�ɏ~����Ɠd�b�ő��k���A�܌�������Z�����{�̏\���Ԃقǂ����炩���ߗ��̂��߂ɂ����Ă������Ƃ������ƂɂȂ����̂��B�����āA���܂悤�₭�A��l�̔O�肪���Ȃ����Ƃ��Ă���悤�Ȗ����B

�@����������قǂ̓������̂Ȃ��A�~����𒓂߂Ă������Ԃ̂Ƃ���܂ňē�����ƁA�������o���̏����ɂƂ肩�������B��X�́A���̗�������ɂ������āA�O������܂��ȃK�C�h���C����݂��Ă������Ƃɂ����B���͗�����ł��邩������オ��ɂ��܂��邱�ƁA���͂��̎��X�̐���s���ɔC���čs�����[�g��I�ђ�߂邱�ƁA�����đ�O�K�C�h���C���͓���I�ȓ�\�l���ԒP�ʂ̍s���p�^�[����������Ă��܂����Ƃł���B���̓����̓��̂����悻�̗��̕��������߂�̂́A�Ƃ肠�����A�^�]��̎��Ɉ�C����邱�ƂɂȂ����B
�@�o�����ĂقǂȂ��A�܂��͓��{�C�����̓��ɏo�Ă݂悤���Ƃ������ƂɂȂ�A�M�Z��ɂ�����^����n���Ē��V��������^���ւƌ��������Ƃɂ����B��Z�����X�ƒX�����M�Z��̗Y�p�Ƃ��̔��͂͂������ł���B�����܂������������铹���Ȃ�}����Ȃ��Ȃ�����X�́A�^����n��I����Ƃ����ɉ͌��ւƂ����铹��T���A���̐^���ւƍ~��ĎԂ𒓂߂��B���Ă̓������𗁂тĉ͌��̑�����Ăɕ��̐��C�ƁA���Ԃ̎��𐔌���Ȃ����߂ė����M�Z��̐��ʂ̋P���ɂ́A�B�X���|��������ł���B���������X�P�b�`���͂��߂��~����̂������ŁA���̂ق��͗I�R�Ɨ�����͂Ɍ�����Ȃ��痷�̃����ł��Ƃ邱�Ƃɂ����B���������ꂪ�C�܂܂ȕ��Q�̗��łȂ�������A�ό��̃|�C���g�ȂǂƂ͂܂�Ŗ����̂���ȏꏊ��K��A�̂�т�Ƒz���ɂЂ��邱�ƂȂǐ�ɂȂ����낤�B�@
�@���āA����͂����̂����A�������o�����Ă܂��O�\�����o���ʂƂ����̂ɂ���ȓ��������Ă���ƂȂ�ƁA�������������͂ǂ��܂ł�������\�\�B�ǂ�ȂƂ���ŐQ��̂����C�ȉ�X��l�̂��Ƃ䂦�A����͂��̋��̉��Ŗ�h�ł��Ƃ������悤�Ȃ��ƂɂȂ肩�˂Ȃ����Ȃ��������A������Ȃ�ł�����ɂ͂܂��������߂����B�����l�ɂ����������͂��炢�͐�ւƎ��B���ꂽ��X�́A���ėNJ����������т����������Ƃ������V�������z���Ęa�����ɓ���A���܂��ܖڂɂƂ܂����ē��ɗU����܂܂ɁA���ؑ��ƕ�n���̗NJ��̕��K�˂Ă݂邱�Ƃɂ����B
�@�NJ��́A���i�l�N�A�\���œ��Ǝ��ɂ���A��\��̂Ƃ��ɂ��܂��ܗ��z��������a���ɐ��s���Ĕ����ʓ��~�ʎ��ɕ����A�����ŏC�s��ςނ��ƂɂȂ�B���NJ��Ə̂���悤�ɂȂ����̂͂��̍�����̂悤�ł���B�O�\���ɂȂ��ĉz��֖߂����NJ��́A�ԕn�ɊÂȂ���o�_��⍑��R�[��т�]�X�Ƃ��A�ꏊ�s��A���㕗�ɂ����Ȃ�A�u�Z���s��A���E�v���R�̐����𑱂��A�\�߂��ɂȂ��Ă悤�₭�A����R�܍����ɒ�Z�����B�����āA���̂قڏ\�N��ɂ͍���R�[�̉��q�K�e�̑����Ɉڂ�Z�݁A�Z�\��Έȍ~�́A���葺�\�o���A�ؑ����E�G��@�ɋ�������B�����܂��O�\�̎Ⴓ���������e�̒�S�͂��߂ėNJ���K�˂Ă����̂͂��̈�N��A�NJ����\�̂Ƃ��̂��Ƃł������B
�@�����ˎm�̖��Ƃ��Đ��܂ꂽ�ޏ��́A���݂̐e�Ƃ͗c�����Ď��ʁA�������Ă�����A���̕��݂͂��ꂽ���e�ƍˋC���t�ɍЂ����A�����̐h�_���Ȃ߂������ƂɂȂ�B�₪�āA����߂��̏�y�@腉����ɋ삯���ނ������œ�ƂȂ�A�C�s��ς�Œ�S��Ɩ����悤�ɂȂ����B�NJ���K�˂Ă��������A��S��͒����ݕ�����腖����ɓƂ�ŏZ��ł����Ƃ����B���ꂩ��킸���l�N���炸���Ԃ̂Ȃ��ł����Ȃ�ꂽ�A�NJ��ƒ�S��Ƃ̐S���J�̐[�ߍ����ɂ��ẮA���ɍL�����Ɍ���Ă���ʂ�ł���B
�@�NJ�����S��ɕʂ�������A�Â��ɓV��E�ւƗ������Ă������̂́A�V�ۓ�N�i�ꔪ�O��N�j�V�t�̗[���̂��Ƃł������B
�@�������ɂ̂����Ђ͂Ȃ�Ă��ނ݂ɂ�����ʂ킩��̂��邼���Ȃ���
�@�i�����̐����̋��n��������ɋA�˂��邱�̐g�ɂ��܂��A�����������ʂ�̂��邱�Ƃ̂Ȃ�Ɣ߂������Ƃł������܂��傤�j
�Ƃ�����S��̉̂ɑ��ėNJ����Ԃ���
�@��������������Ă������Ă�����݂�
�Ƃ�����傪�A�͂��炸�������̋�ƂȂ����Ƃ����B�������ʂ����킹�����A���̐��E�ƔϔY��̐��E�Ƃ̂͂��܂U���R�̂Ő����������l�ԗNJ��̎U��ۂɁA����͂Ȃ�Ƃ��ӂ��킵����ł������B�͂�͂�ƎU��s���g�t�ɗNJ����g�̎p���d�ˍ��킳��Ă��邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B
�@�NJ��ƒ�S��Ƃ̎l�N�ԋ߂��ɂ킽��S�̌𗬂̈ꕔ�n�I���q�ד`������S��̎��M�e�{�u�͂����̘I�v�́A�u�V�ۓ�N�K�N�@�����Z���J���@��͂Ў��\�l�@�@��S�v�Ƃ����ꕶ�Ō���A��S��̐[�����݂��Î��ł����邩�̂悤�ɂ����łՂ���ƏI����Ă���B�̂��ɒ�S��̕��ɍ��܂�邱�ƂɂȂ����ޏ��̎����̉́@
�@�@����Ɏ��ċA��Ɏ����艫�g�������͕��̐����ɔC����
�̃C���[�W�́A�t�A�NJ��̗ՏI���܂��ɂ����[���z����ʂ��Đ��܂ꂽ���̂ł͂Ȃ����ƍl���錤���҂�����悤�����A�����Ă݂�ƁA�������ɂ����i���Ȃ��j����ӂ�������B
�@�����������������ɖ|�M����A����ł���������ł��Ȃ��t���������������̔g���S�g�̐l���Ɍ����Ă�A���̉̂ɔ�߂�ꂽ�z���͎��R�ƌ����Ă���B��g���g�t�̕\�ɁA�܂������䂭�g���g�t�̗��ɁA�����Ĕg���N���������g�t���U�炷���ɑΉ�������A���҂̉��ɗ���Ă���l����z�̖{���͓������̂����炾�B
�@�NJ��̕�́A���܂�`���Ƃ��Ȃ��Ă��鐴�n���̂��̂̐��U����͂ƂĂ��z���ł��Ȃ��قǂɗ��h�Ȃ��̂ł������B�Δ�̕��͂䂤�Ɉꃁ�[�g�����z���A�����̂ق��͑�������킹��ƎO���[�g���߂��ɂ��y�Ԃ̂ł͂Ȃ����Ǝv��ꂽ�B���Ɠn�ӂ���Ƃ͎v�킸��������킹�Ȃ���A�u�����̗L�͎ҒB���NJ��̓����]���Č��Ă���ł��傤���A������Ƃ��߂��݂����ȋC�����܂��ˁB���̐��̗NJ��͊�������߂Ă�����������܂���ˁv�Ɛ����Ȉ�ۂ���荇�����B
�@�����A���ƂɂȂ��Ē��ׂĂ݂�ƁA����ȑz���́A�ǂ�����X�̕s���Ƒ��Ƃ���̂����ł��������悤�Ȃ̂��B�V��������̏o�g�ŁA�NJ��̌����҂Ƃ��Ēm����k��Ȉ꒘�̖{�ɂ��A���̕��͎��̗L�͎ҒB�̎�ɂ���Č��Ă�ꂽ���̂ł͂Ȃ��A���O�ɗNJ��������z��̖����̐l�X�̎�ŁA�NJ��̖v���N�o�����V�ێl�N�Ɍ������ꂽ���̂Ȃ̂��Ƃ����B�NJ��̎���߂��z��̐l�X�́u�Δ藿�u�v�ƋL���������������ĕ���ɂ����܂��A�������W�߂������ŁA�����̎��Ƃ����Ƃ��납��ԛ���̋����^�т��݁A���̒n���ɂ͗ނ��݂Ȃ��悤�ȑ�������Ă��̂������ł���B�������g�����x�̕~����Ă������얋�{�̎������ɂ����́A��̑傫���ɂ����̂����琧�����������B���얋�{�̐���������ƒf���A���{�̔쉺�ɂ����Č������Â�m���╶�l�������s���ᔻ���������NJ��́A���͎҂̗��ꂩ�炷��A��H�V��Ƒ������ׂ��Ǖ��m�̐g�ɉ߂��Ȃ������B������A�v���N�̂����ɂ���قNj���ȕ��z���A�u�NJ��T�t��v�Ƒ傫�����ݍ��ނȂǂƂ������Ƃ́A�����̐g�����x�ɐ^�������璧�킷��s�ׂł��������炵���B�������A���̔�̖����́A��Y�������U���������NJ��̂��˂Ă���̑z�����ے�����̂�A�l�S����V�������@��ɑ��錵���������ƌP���̌��t�������̂������B
�@�NJ��̎���A���{��@�傩��̎w�������o�_��̑㊯���́A�NJ��̉̍e���̑��̎�e�ނ̋����I�Ȓ�o�𖽂�����A�W�҂̎�蒲�ׂ������Ȃ����肵���Ƃ����B�����āA�Ǖ��m�NJ��̋���ȁu�T�t��v�������Ƃ������炵���B
�@�������A�NJ����̐l�̂��܂�ɂ��܂��Ƃ��Ȑ��_�Ǝ咣�A����ɂ͂Ȃ�Ƃ��I���˂��蕶�̂䂦�ɁA�������̌��͎ҒB�����Ɏ���������Ƃ͂ł��Ȃ������B���͎҂������ɕ������ł����Ă�����蕶���̂܂܂̔؍s�ƂȂ��āA�����̖��O��������ɂ���A�����܂����Ђ����Ă����ɑ���Ȃ��B����ɂ��Ă��A�������Ă�ɐ旧���A���͎҂̎���I���ɕ�����d�|�����ďo�������O�̒m�b�͑����Ȃ��̂ł���B
�@�NJ��̕悩��߂�r���A��X�͈�H�̐��̎q���Q���e�ɂ������܂��Ă���̂������B�Ƃ�����`�����`�����Ɩ����������Ă���B�ǂ���瑃���痎�������A���������������̂̂��܂���ׂ��ɂ��̏�ɕ����~�肽���̂炵���B�������ɗl�q���M���Ă���ƁA��H�̐e�������܂ɔ��ł��Ă͉a������Ă���B�L�ɑ_���ł�������ЂƂ��܂���Ȃ��̂ŁA�S�z���Ȃ��炵�炭�����ƌ�����Ă������A��X�����̐g�䂦�A�ꏏ�ɘA��Ă����킯�ɂ��䂩���A�����͐e���̒m�b�ƈ���ɔC���邵���Ȃ��Ɣ��f�����B�����딯���Ђ����z���ł��̏�����Ƃɂ����̂����A���ɂ����Ă����R�̐ۗ��Ƃ͌��������̂ł���B�����A�NJ����ڂɂ��Ď���̖��͂��ɑł��̂߂��ꂽ�Ƃ����n���G�}�A���Ȃ킿�����̏����̔ߎS�Ȍ����́A����Ȃ��̂Ƃ͊r�ׂ��̂ɂȂ�ʂقƂɋ~������̂ł������ɈႢ�Ȃ��B
�@�NJ��̕�����Ƃɂ�����X�́A���ɁA�NJ��̈�n�A��i�̗ނ��������W������Ă���o�_��̗NJ��L�O�ق�K�ꂽ�B�����āA�M�������Ă���Ƃ������͌����̋ꂵ�݂���������A�����������Ă���̂��Ƃ������Ƃ������Y��Ė��S�Ɏ��ƋY��Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv�킹��A�Ȃ�Ƃ����R�z���Ȗn�ՂɁA��X�͐S�̒ꂩ�犴�������B�������������A���h�Ɏd�グ�悤�A�����̐l�X�̏̎^���������ȂǂƂ����ڑ��Ȉӎ��z�����NJ��̎p�������ɂ͂͂�����Ɗ�������̂ł������B
�@�����A������ƌ����āA���͗NJ��Ƃ����l�������R������̐l�������Ƃ͎v��Ȃ��B�������Ƃ������̑����̂Ȃ��ɂ����Ď��������̈�����Ȃ��Ă���ɂ�����炸�A���ꎩ�̂̋P���͂������đ��萊���邱�Ƃ̂Ȃ��Ήp�̍����ɂ��������݂ł������悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B
�@�NJ��L�O�ق̂��鍂�������ē��{�C�����̍����ɏo��ƁA���z�����Ȃ萼�ɌX���Č������B�K�������܂łɂ͂܂����X���Ԃ����肻���ł���B�[�z������Ȃ��F�R�����肪�����B�[��ɐÂ܂肩������{�C�����Ɍ��Ȃ���A��X�͎������ʂւƑ��肾�����B

�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
1999�N9��8��
���̘e�����Q�L�i�Q�j
�[�z�̖�����F�R
�G�E�n�Ӂ@�~
�@�[�z�̖�����F�R�\�\��������V���`��
�@�����̒����݂ɂ������������Ƃ��A���́A�ˑR�A���̂�����̖����̂ЂƂł����̕l�Ă��̂��Ƃ��v���o�����B�\���ɉ����قǂ������V�N�ő傫�ȑ���܂邲�Ƌ��h���ɂ��A������Y�ł�������ƏĂ����������̂ŁA���̎p�������Ƃ����A���Ƃ����A�����ʂ�̐�i�ł���B�[�H�̏����炵�����Ƃ͂܂��Ȃɂ����Ă��Ȃ������̂ŁA�n�R���s���̐g�ɂ͂�������ґ��A������B���Ă݂悤�Ƃ������ƂɂȂ����B
�@���v���ԋ߂Ȏ����Ƃ����Ă��ό��q�̎p�͂�������r�₦�A���������̓y�Y�����̂قƂ�ǂ͂��łɓX���܂����I���Ă����B�ꌬ�����������X���܂����O�̊C�Y�����ɔ�э��݁A��̕l�Ă��͂Ȃ����Ƃ����˂�ƁA������Ƃ܂��ɕЂÂ��Ă��܂����Ƃ����B���߂��ꂸ�ɓX�̋������낤�낵�Ȃ���A���X���̎�ł��܂ɂ����ւƉ^�ы����悤�Ƃ��Ă��锠�̈���̂������ނƁA�Ȃ�Ƃ����ɂ܂�����Ȃ��u��̕l�Ă��l�v�̂��p������ł͂Ȃ����I
�@�ǂ����Ă����̑�������Ăق����ƐH���C�܂邾���̌`���ō��肷��ƁA����͂����˘f���̕\����ׂ͂������̂́A���̂��Ƃ����ɉ����肢������Ă��ꂽ�̂������B�������̒m��Ȃ����̓�l�̋q�́A�ق��Ă�������Ȃɂ����ł������킩��Ȃ��ƁA���̂Ȃ��Ŏv�����̂�������Ȃ��B����ɂ��Ă��A�l�\�Z���`�߂����h�ȑ�̕l�Ă�����Ŕ��S�~�Ƃ����̂͂Ȃ�Ƃ������������������B�����Ƃ��A�P�i�Ƃ��ẮA����̉�X�̗���ʂ��Ă����Ƃ������Ȕ������ł͂������̂����\�\�B
�@��̕l�Ă��l�����₤�₵���Ԓ��ɂ��ē��\���グ����X�́A���ꂩ��قǂȂ��A��͒Õ����H�̉͌��t�߂ɂ������ϋ��ɍ������������B��͒Õ����H�͐M�Z��{�����番���K�͂Ȕr���H�ŁA�NJ��䂩��̍���R�̓쐼���𗬂�Ă���B�ɕ�܂ꂽ�����ȓ���]��̉͌��́A�܂���̗[�z��w�ɂ��ďl�R�ƋP���A��X�̗��D�����₪�����ɂ��������Ă��B�~�����������X�P�b�`�u�b�N�����o�������Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B

�@�~����̃X�P�b�`����i������̂�҂��āA���͂܂��Ԃ̃G���W�����n���������B�ڎw���͖�F�R�X�J�C���C���ł���B�n�}��Ŕ��f���邩����A���v�܂łɂ͊ԈႢ�Ȃ���F�R���t�߂ɓ��B�ł���B����������{�C�ɒ��ޗ[�z�߂邱�Ƃ��ł���Ό������Ƃ͂Ȃ��B��ς̏W���߂��ō������番����A��F�R�X�J�C���C���ɓ���ƁA�݂�݂邤���ɍ��x�����������B�����āA�R�����璆���ɂ����Ă̔Z���̎��ёт���ƁA�������ɓW�]���Ђ炯�Ă����B���ۂɓo���Ă݂�ƁA��F�R�͑z�����Ă����ȏ�Ɍ������A���������[���B�ቺ�ɍL������{�C�Ɍ������āA���̎Ζʂ͂��Ȃ�̋}�p�x�ŗ�������ł����B
�@�X�J�C���C����o��߂�������̒��ԏ�ɎԂ�u���A��������\�ܕ��قǍ⓹��o���āA�C���Z�S�O�\�����[�g���̖�F�R����߂��ɂ���W�]��ɒH�蒅�����̂͌ߌ�Z�������������B���{�C�̂ق�����A�������ɖ����܂����������グ�Ă��Ă���B�ꊾ�����Ȃ���}�ȓ���o���Ă������ゾ���ɁA���̕����Ȃ�Ƃ��S�n�悭�v��ꂽ�B
�@���炩�Ȏő��ɕ���ꂽ�W�]�䂩��̒��߂͖]�O�̂��̂������B�����ȂƂ���A��F�R����̒��]������قǑf���炵���Ƃ͎v���Ă��Ȃ������B�[�z�ɉf���ċ��̂悤�ɂ����܂肩����C�̌������ɂ́A�܂�Ń��[���[�ŕ���ɂȂ炵�ł��������̂悤�ȍ��n�̓��e���Ⴍ�L�����Č������B���Ԃ�A������Ԕ��ɂ����Ă̍��n�암�̈�т��낤�B���Ȃ�ȑO�ɍ��n��K�˂Ă݂āA�z���ȏ�ɎR�̑����Ƃ��낾�Ƃ�����ۂ������Ă����̂ŁA�C���r�ꂽ�炽���܂��C���ɖv���Ă��܂������ɂ������邻�̌��i�͂�����ƈӊO�������B�W���Z�S���[�g���]�̎R�̏ォ�猩���낵�Ă��邹���Ȃ̂��낤�B
�@�����ɑ傫���ڂ�]����ƁA���E�����ς��ɔ�э���ł����̂́A�ʂĂ��Ȃ��L����̗���A�z�㕽�삾�����B�[�z�ɂƂ���ǂ��됅�ʂ������Č�����̂͂������M�Z��A�����āA���̎��ӂɍL����͎̂O������������̓c���n�т��낤�B����ɂ͂��łɌ���\��E�O���قǂ̌��������Ă��āA���̏o�Ԃɂ͂�����Ƒ����������ȂƂł����������ɁA�\������x�̔��������Ă����B
�@���n�̓��e�̂ق��ւƑ傫���X�����[�z�́A�������ɐ[���Ԃ݂�тсA�܂邢�֊s���͂�����ƕ����яオ�点�Ȃ���A�Y���悤�ɒ���ł����B�ቺ�̊C�ʂ̂������������������Ă���̂́A�C���̂����炵���B������̋C�������[��Ƃ������āA�Ζʉ����ɐ����グ�Ă��镗����������������悤�ɂȂ��Ă����B����ł��A���Ɠn�ӂ���́A���ꂼ��̑z���ɂЂ���Ȃ���A�����Ɨ[�z�����߂Ă����B
�@�W�]��t�߂ɂ́A��X�̂ق��ɁA�j���O�l����Ȃ������g�̃O���[�v�����āA�[�z�߂Ȃ����O�p�[�e�B������Ă���Ƃ��낾�����B���̐l�����̂ق����Ȃɂ��Ȃ�������Ă���ƁA�ˑR�A�u�悯��Έꏏ�ɂǂ��ł����H�v�Ɛ���������ꂽ�B�Ȃ�ƂȂ�����Ԃꂽ�i�D�̓�l�̒j���A�[���ɐ�����Ȃ��畠���������������ŗ����Ă���̂������˂āA�S�D�������̕��X�͂��肰�Ȃ��U���Ă����������ɈႢ�Ȃ��B
�@�����͕n�R���s�̓r��ɂ����X�̂��ƁA���ꂼ�܂��ɓV�̏����ɂق��Ȃ�Ȃ��Ƃ����킯�ŁA�������܂��̐\���o�����ꂽ�B�ނ��\�����ɂ͂��������͂������̂́A���S�ł́u��������I�v�Ƃ��������ł���B�O�l�̕��X�́A�߂��̎O���s�ɂ��Z�܂��̋v�ەx�F��v�ȂƁA�O���܂ŗV�тɂ݂��Ă���ꂽ�v�ەv�l�̖��������B��F�R�̗[�z�͑f���炵���̂ŁA���������ɗ��ẮA�����̕�������Ɉ�t�����ɂȂ�̂��Ƃ����B�v�ۂ���͂�����x�R���������o����ۂ悭�_����ƁA����̑f�ނ̂͂������傫�Ȋʋl���J���A�}�X������l�̒��q�̂��߂ɔM�X�̓�`������Ă����������B�����āA�ʃr�[���ɂ��܂݁A����ɂ́A���ɂ���A���V���ɂ�����܂ł��C�O�悭�����߂Ă����������̂ł���B
�@�����Ȃ�Ƃ����A�Ԃ��c�q�Ȃ�ʁA�u�[�z��芛��v�A�u�[�Ă����r�[���v�ł���B�v���������ʂ��y���Ɋ������Ȃ���A��l�ŕ��Q�̗�������ɂ��������o�܂Ȃǂ���������肵�Ă��邤���ɁA�����̗[�z�̂ق��́A�u����ȏ����Ƃ�邩���I�v�Ƃ���ɐԂ��C�F�݂Ȃ���A�������ƍ��n�̓��e�ɒ���ł��܂����B��炪�����S�����̒��x�̂��̂��Ǝv�킸�Ԗʂ����������A����ȏ���~���Ă��ꂽ�̂́A�u�����͐��̐������߂��ɉ_�Ȃǂ������Ĕ����������܂ЂƂȂ�ł����A�ق�Ƃ��Ȃ�A�����̗[�z�͂����Ƃ������Y��Ȃ�ł���B�܂��A����͂���Ƃ��āA��������������y�������܂��傤��v�Ƃ����v�ۂ���̈ꌾ�������B
�@���̋����F�ɐ��܂�A�₪�Ė�F�R��т��[�łɕ�܂��܂ŁA��X�͊��k���Â����B�v�ۂ���͎R���D���ŁA�[�c�v��́u���{�S���R�v�ɏЉ��Ă���R�X�̂����A���łɘZ�\���j�Ȃ������Ƃ̂��Ƃł������B�v�ۂ���̘b�Ɏ����X���Ȃ���A�ӂƓ��̋�����グ��ƁA�捏�܂Ŕ����W���S���ƂȂ��ȋP���������Ă��������A�ق�ڂꂷ�邭�炢�ɐ���������Ȃ���Ȃ̑��݂��֎����Ă���B�ቺ�͂邩�ɓ_�X�Əu������F�Ƃ�ǂ�̖��Ƃ̖�����́A�z�㕽��̖���ʂ閳���̕���̂��̂������B
�@�ʂ�ۂɁA��X�́A�傫�Ȋʃr�[���̂ق��A�����炩�̂��܂݂Ȃǂ����Ղ����B�P�ӂ̐l�X�̍D�ӂ��Â�C���`�L�C�s�m�̑�݂����ŁA�NJ��l����͎���ꂻ���ȋC���������A�Ƃ������L�����Ƃł͂������B���̏������炱��Ȓ��q���ƁA��nj����ǔL�Ȃ݂ɁA�s����X�Ől�l�ɛZ���Ă͂��̂����ڂ�Ղ���Ȃ����Ă��܂������ŁA���������C�ɂ͂Ȃ�B������Ƃ����āA�������͌ւ�������Đl�Ԃ炵���U�镑���ׂ����Ɣ��Ȃ������Ƃ����ƁA����Ȃ���͂��炳��Ȃ������B�����Ƃ��A���̂��Ƒ��A��O�̋v�ۂ��e�ՂɌ����������Ƃ����ƁA����͂܂��ʂ̘b�ł������B
�@��F�R�����Ƃɂ�����X�́A�ĂъC�����̍����ɏo�āA�V�����ʂւƑ���o�����B�����ɐ������ꂽ�����ŎԂ̉e���قƂ�ǂȂ��Ƃ����āA���̂�����X�s�[�h���[�^�[�̐j�́A�E�։E�ւƊ���̃X�e�b�v�ނ��ƂɂȂ����B����ł��A�r���̃R���r�j�ŊȒP�ȐH�ނ����݁A�V���s�����̊։��l�ɒ��������ɂ́A���Ȃ�x�������ɂȂ��Ă����B���܂��ꏊ�I�ɂ��s�����悩�����̂ŁA��������Ԃ𒓂߁A���炽�߂ĔӔт���������H�ׂȂ������Ƃ������ƂɂȂ����B
�@�R�����œ������A���X�`���̑��̃C���X�^���g�H�i�������̂����A�Ȃ�Ƃ����Ă��A���̔ӂ̎���̓N�[���{�b�N�X�̒��́u��̕l�Ă��l�v�������B�R�����̉ʼn��߂Ȃ����ĐH�ׂ��̂����A���̂��܂����ƁA���܂����ƁI�\�\��l�Ŋ����̌��t��A�����Ȃ���A���ߕ��悤�ɂ��Ĉ���̑������܂����Â�s�������悤�Ȃ킯�������B�����قǂɐg�����Ă��āA�l�Ă������ł����������ς��ɂȂ��Ă��܂����قǂł���B�n�ӂ���́A��ł��������A�捏�A��F�R�Œ��Ղ��Ă����ʃr�[�������܂����Ɉ��݂Ȃ���A�����Ɋy�Ƃł����������ȕ\������B�܂������̊ʃr�[�����A���̕��Q�̗��H�ɂ����Ă�������Ƃ��ł����Ō�̃r�[���ɂȂ낤�Ƃ́A�������̓n�ӂ�����z�����ɂ��Ă����Ȃ��������Ƃ��낤�B
�@���̌o����ɗ͈������悤�Ƃ����o���O�̗��������������āA���ΈÖق̂����ɁA���X�R���r�j�Ŕ������߂鋍���ނ̂ق��́A�����ς�A���̐�X�ŒT�����Ă����܂������Ƃ�������Ă��ꂽ�Β���g���������������Ƃ������ƂɂȂ�������ł���B��F�R�ŏo�������v�ۂ���̂悤�ȕ������̌�����X�Ɍ���Ă�����͈Ⴂ�������낤���A���̒����������Â��͂Ȃ������B�A���R�[���������Ȃ��Ă����C�Ȏ��̂ق��͂Ƃ������A���u�ǐl�v�̓n�ӂ���ɂƂ��ẮA����Ȑ���s���͎v��ʌ�Z�ł�������������Ȃ��B
�@�Ƃ��������\���ɂ�����������X�́A�قǂȂ��։��l�����Ƃɂ��A�V���s�̒��S�����āA�ߌ�\�ꎞ�����ɐM�Z��͌��̐V���`�A�V���{�C�t�F���[�����u���ɒH�蒅�����B�u���ɂ͂��܂����M�s���̐V�^�t�F���[�u�j���[������v���ڊ݂��Ă���A�قǂȂ��o�q���悤�Ƃ��Ă���Ƃ��낾�����B���̍ŐV�v�̔������D�́A�����ő�̃t�F���[�ł���B�߂��Ŗڂɂ��邻�̋���ȑD�̂̔��͂͐������B
�@�C�܂���ȗ��䂦�ɁA���ꂩ��u�j���[������v�ɏ���Ă����Ȃ�k�C���ւƂ�������Ȃ��͂Ȃ��������A���M�s���̃t�F���[�u���ɂ���Ă����̂͂��̂��߂ł͂Ȃ������B���̃t�F���[������܂ʼn��x�����p���A���ӂ̏ɒʂ��Ă������́A����Ă��Ȃ��@��䂦�A���Гn�ӂ���Ɂu�j���[������v���������������Ǝv�����̂������B
�@�n�ӂ���ɂ͑��q����l������B�̒Y���Ă��Ă���ꂽ���A�n�ӂ���́A�܂��c���������̑��q������R���̎��̊��Ƀ��[�v�łȂ��ł���d�����Ȃ����Ă����Ƃ����B�ނ��A�c���s�҂ł��Ȃ�ł��Ȃ��A�댯�ȍ�Ƃ̑����Y�Ă��d���Ƒ��q����̐g�̈��S�Ƃ𗼗������邽�߂̋���̍����B
�@�u���q���A���̑̌��ɂ͂���ۂǒ��肽�炵����ł���B���̂������A�傫�イ�Ȃ����Ă���́A�R�ł̎d���͐�Ɍ���A�C�̂ق��������䂤�āA�D���̎d���ɂ��������ł���v�ƁA�n�ӂ���́A�̘b�����Ă������������Ƃ�����B
�@���������ƁA���̑��q���A�ŋ߂܂ŁA���̐V���D�j���[������̈ꓙ�q�C�m���Ȃ����Ă����̂ł���B�ꓙ�q�C�m�ƌ����A�D���ɂ��v�E�ŁA������A�D�̑��c�Ɖ^�s�S�ʂ��Ƃ肵����̂����̐E���ł���B���܁A���q����́A�����V���{�C�t�F���[�̕��߁[���M�q�H�̑D�̂ق��ŁA��͂�ꓙ�q�C�m�߂Ă����邪�A�D���ƂȂ���͎̂��Ԃ̖��ɈႢ�Ȃ��B�Z�����n�ӂ���́A����܂ŁA���q����̏���Ă���ꂽ�j���[������������ɂȂ������Ƃ͂Ȃ��������A���̐V���`�̃t�F���[�u���ɂ����łɂȂ������Ƃ����Ȃ������B����Ȏ�������������m���Ă������́A���̓��ł͐���Ǝv���Ȃ�����A�C�܂�����Ă��̕u���ւƎԂ�i�ݓ��ꂽ�悤�Ȗ����B
�@�ߌ�\�ꎞ�\�����傤�ǂɁA��̑�C��k�킹��悤�ȒႭ�͋����G���W�������������Ȃ���A�j���[������͂������Ɗݕǂ𗣂ꂽ�B���M�܂ł͏\�����Ԃقǂ̍q�C�ł���B�D�̃u���b�W�̉��̂ق��ɂ͂������ɐl�e�炵�����̂��������B�n�ӂ���̑��q��������̂�����ɐw����āA�q�s�̎w�����Ƃ��Ă���ꂽ�̂��낤�B�u���ɗ����Ă��ꂾ���̋��D�̏o�`���i��ڂɂ���̂͋v�X���������A�����Ă����t�ɂ͐s�������������}���Ɨ���������A�S�x�����ł������B
�@�Ō�̑����q�����[�v���͂�����A���R�̐g�ƂȂ����傫�������D�̂��A���̂�̗��j�Ղƃ��[�_�[�����������ɑ�C�ւƌ������ē����o�����Ƃ��A�n�ӂ���̔]�����悬�����̂͂��������ǂ̂悤�ȑz���������̂��낤�B�R���̎��̊��Ƀ��[�v�Ōq���ꂽ�c�����̑��q����ƁA�₪�Ă��̃��[�v�����������A�����̂ɂ��S������邱�Ƃ̂Ȃ���C���ւƗ������Ă��������q����̎p�Ƃ����G�Ɍ������Ă����̂�������Ȃ��B
�@�j���[������̍q�C�������������Ă����̂����͂��ĎԂɖ߂����Ƃ��ɂ́A�����[��ꎞ�ɋ߂��ɂȂ��Ă����B���ǁA�A����͂��̕u���̕Ћ��ŎԒ������悤�Ƃ������ƂɂȂ�A���S���̃V�[�g���t���b�g�ɓ|���ĐQ�鏀���ɂƂ肩�������B�V���{�C�t�F���[�̃r�����̐��ʏ��͖����܂Ŏg���Ȃ��B��X�́A�����ݕǂ̐^���Ɋ�g�̉����Ȃ���A�Ƃ肠�����j�̓��������p�����B�A�Q�O�̊ȒP�Ȑ��ʂ����܂���ɂ́A�y�b�g�{�g����{���̐��ŏ\���������B���ɂȂ��ĂقǂȂ��A��X�͒W�������̍������ގԒ��ŁA�[���S�n�悢����ɂ����B
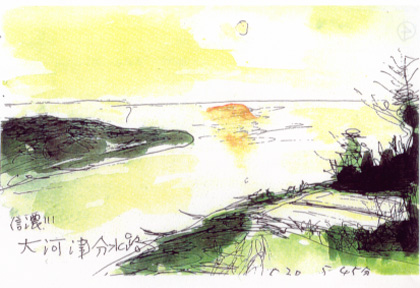
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
1999�N9��15��
���̘e�����Q�L�i�R�j
�����R�n�Ƌ��كg���l��
�G�E�n�Ӂ@�~
�@�����R�n�Ƌ���g���l���̒����\�\����s���璩������
�@�����͘Z���ɋN�������B������グ��ƁA�_�ЂƂȂ��L�����Ă���B�Ԓ��ł̊ȒP�Ȓ��H�㒼���ɐV���`�����Ƃɂ�����X�́A������ɂ�����l������n��A�E�܂��č��������ɓ���ƁA������ʂւƌ������đ���o�����B�V���̈�ʍ����͂ǂ����������s���͂��A�Ԑ���������肵�Ă��Ď��ɑ���₷���B�����Ƃ������́u�����v�Ƃł��̂����ق��������悤�ȓ��H���S���e�n�ɂ��܂Ȃ��������݂��邱�Ƃ��v���ƁA�V���͂܂��ɓ��H�V���ł���B
�@���������������ɑ����ĐV���k���̑���s�ɓ�������X�́A��������A�߂��𗬂��O�ʐ�`���ɒ����R�n�̒J���ւƕ������邱�Ƃɂ����B�W���ꔪ���Z���[�g���̑咩���x�����Ƃ��钩���R�n�ɂ́A�܂�������̎��R���ӂ�Ɏc���Ă���B��ł��������Â������X�̕W�������͒Ⴂ���̂́A�L��Ȓ����R�n�̎R��J�͂���߂Đ[�����������B�~�͍���ɂ���ĕ�����A�ď�����H����Ȃǂ̂��ߋ߂Â��̂��e�ՂłȂ��Ƃ����āA�K���l�͑����Ȃ��B�L���ȑ��̎R�x�n�т̂悤�ɂ͎R�X���r�炳��Ă��Ȃ�����A�R�D���Ȑl�X�����̎R�n�ɋ����S���䂫������̂́A���R�̂��Ƃƌ����邾�낤�B
�@���̒����R�n�̒�����������т̎R�n��D���悤�ɂ��āA�V��������������R�`���������ւƈ�{�̗ѓ����ʂ��Ă���B�������ƒ��������Ȃ��Ƃ����A�Ȃ�Ƃ���₱�����ѓ��ŁA���̖��������X�[�p�[�ѓ��Ƃ����B�ǂ��炩�̑���[�����Ɖ�������A���[�X�[�p�[�ѓ��ƂȂ��Ă킩��₷���͂Ȃ�̂����A�[���Ƃ������t�͂������Ɂu�����v�Ƃ������̃C���[�W�Ɍ��т�����A���̖��ɂ͂ӂ��킵���Ȃ��̂��낤�B���łɏq�ׂĂ����ƁA���̎R�n�̓����ɂ͒�����������̂����A�����Ȃ�Ƃ����u�����v�̒D�������ł���B�����z�n�̒����V���Ђ����������Ɉ����z���ł����Ă�����A����͂����������낤�B
�@�����X�[�p�[�ѓ����o�ēc�����ւƔ����邱�Ƃ��ł���A�r���Œ����R�n�̎R�X��J�X�̌i�ς����\�ł��邵�A�܂��A�̂��̂��̍s���������Ԃ�Ɗy�ɂȂ�B�ѓ��̍ʼn����͂܂��c����[���낤����A�����Ȉ��H���o�傹�˂Ȃ�Ȃ����낤�B�ł��A���H�𑖂�̂͂����̂��Ƃ�����A�����ƌ��܂�A���Ƃ͂����`�������W���邾���ł���B
 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�O�ʐ�`���̓��ɓ����Ă܂��Ȃ��A�Ԃ͕z���ʏ�i�ʂׂ̂�Ȃj�ւƓ��������B��Z���̐������ʂ����ς��ɒX�i�����j���ė����O�ʐ�̗��݂̗́A�܂����炩�ł݂��݂������B����ɂ��˂�[�܂鐅�ʖL���ȎO�ʐ�k�J�𓌂������đk��A���ӂ�����ɐ���������������O�ʃ_���ɓ��������̂́A�����ߑO�\�ꎞ���߂��̂��Ƃ������B���Ă̖��邢�������𗁂тāA�_���̏㗬��т̎R�X�̋}�s�ȎΖʂ��N�₩�ȃ��C�g�O���[���ɋP���Ă���B�Ƃ��Ɍi�ς̂��킾�����_���Ƃ����킯�ł͂Ȃ���������ǂ��A�l�e�̂قƂ�ǂȂ��Î₻�̂��̂̂������܂��́A��X�̗��D��U���[�߂Ă����ɂ͏\���������B
�@�O�ʃ_���̓�����t�߂���n�܂钩���X�[�p�[�ѓ��́A�_���̉E��R�����i�ނ悤�ɂ��Ē����R�n�̉��ւƂ̂тĂ���B�������悢��ѓ��ɓ��邼�A�Ɛ������݂������r�[�A�܂�ŏo�@�����������̂悤�ɁA����ɂ��铹�H���\���̂�Ȃ��������ڂɔ�э���ł����B�Ȃ�ƁA�O�ʐ�̎x���ɂ��鉎�c�쉈���̃L�����v��t�߂܂ł͒ʂ�邪�A���ꂩ���A�R�`�����ʂւ͒ʍs�ł��Ȃ��ƋL����Ă���B���̓~�̍���̂��ߒ����R�n�̊e���Ő�����������A���̉e���ŗѓ����s�ʂɂȂ��Ă��āA���̏C����Ƃ��s���Ă��邽�߂炵���B
�@��������͂�����������Ԃ������Ȃ��Ǝv���������̂����A�C���Ƃ�Ȃ����āA�܂��͍s����Ƃ���܂ōs�����Ƃ������ƂɂȂ����B�Ԃŗ������Ă���ƁA�O���ʍs�s�\��m�点�邱�̎�̕\���ɂ悭�ł������Ƃ�����B����ȂƂ��A�ǂ����Ǝv���Ȃ�������ۂɌ��n�܂ōs���Ă݂�ƁA���p�̉I��H���݂����Ă�����A�H������̍�ƈ��̓��ʂȔz�����������肵�āA�ĊO�ʂ�Ă��܂����Ƃ����Ȃ��Ȃ��B�������������܂ŗ����̂�����A�ꂩ�����q���Ă݂悤�Ƃ������ƂɂȂ����̂������B

�@�Ԃ́A�������G���W�������Ȃ点�Ȃ���A���։E�ւƑ傫�����˂�}�s��襘H�������ɂ悶�o���Ă����B�ꉞ�ܑ͕��͂���Ă���̂ʼn��ʂ͏��Ȃ����A�Ȃ��Ȃ��̓��ł��邱�Ƃɂ͕ς��Ȃ��B�Ƃ�����H���p�̂��̂Ƃ��ڂ����_���v�Ƃł����A���肬��ɂ���Ⴆ��n�_�܂Ńo�b�N����Ƃ������Ԃ��N�������B�����A���։��ւƐi�ނɂ�A�ڂɌ����Ď�Ԃ���X�̗̔������́A����ȋ�J�����Ă��܂肠����̂������B
�@�����ɐ藧�ѓ������̌k�J�͍��X�Ƃ��̐[���𑝂��A�k�J�̗������ނ���R�X�́A�����r�X�����┧���ނ������ɂ��ĉ�X�̖ڂ����|���͂��߂��B�����āA���ӂ��ʂ�̋P���͂��������݂��݂��������ۗ������Ă����B�����Ă݂Ă͂��߂Ď�������̂����A�������ɂ��̎R�n�͉��[���B���������Ԃ�ƎR�Ԑ[���ɂɕ����������C������̂����A�n�}�Ŋm���߂Ă݂�ƁA�܂��܂������Ɖ��ւƂ��̒J�͑����Ă���B
�@�ѓ����傫���k�ւƓ]���鉎�c��_���e���߂��A�E��ɉ��c��̌k�J�������낵�Ȃ��炵�炭�i�ނƁA�}�ɓW�]���J���A�c����܂��S�g�ɂ܂Ƃ����܂܂̒����A��̎�ł��p���������B�甪�S���[�g���O��Ƃ������̕W������͑z�����ł��Ȃ��قǂɓ��X�Ƃ��Ă��āA�Ȃ�Ƃ������Ȃ����݊��ɂ��ӂ�Ă���B�g�̂̑傫�������ł͂��̐l�Ԃ̑��݂̏d�����͂���Ȃ��̂Ɠ��l�ɁA�W����P�Ȃ�R�̂̑傫�������ł͂��̎R�̉��[�����͂��肵�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B��X�͂����Ԃ��߂Ă��̗Y�p�ɂ����ƌ��������B
�@�^���悯��ΎR�`���ʂւƔ������邩������Ȃ��Ƃ�����X�̊Â����҂́A���c��L�����v��������߂���������܂Ői���_�ł����Ȃ�������B�拭�ȓS���̎Ԏ~�߂��s�����₽���j��ł���B���Ƃ��͂����ŎԎ~�߂�˔j���悤�ɂ��A����ł͂܂��������������Ȃ��B�����Ԃ��̂͂ǂ��ɂ����Ⴍ�����A��ނȂ��悤�ł���B��X�́A�������̏�ɎԂ𒓂߂�ƁA�����e�𗬂�鉎�c��Ȃɂ���A���H���Ƃ�Ȃ���P������邱�Ƃɂ����B
�@�����������̂܂ܑ���܂ň����Ԃ��A�P���ɍ�����k�シ��Ƃ����̂́A�u�ʂ������Ƃ̂��铹��A�Ԃ̑��������͋ɗ͔�����v�Ƃ����A���˂Ă���̉䂪���̃|���V�C�ɑ�������B���������A�u���̘e������Q����v�Ƃ�������̗��̖��ڂɂ�����Ȃ��B�]��ł������ł͋N���Ȃ��̂���X�̗��̐��_�Ƃ���A�����͂Ȃ�Ƃ��ŊJ����u���˂Ȃ�܂��B
�n�}�߂Ȃ���v�Ă��邤���ɁA�O�ʐ�{���Ɖ��c��Ƃ̕���_�܂Ŗ߂��������肩��R�`���암�̏��������ʂɌ������ē쉺����ѓ������邱�ƂɋC�������B���Ȃ��ɖ߂邱�Ƃɂ͂Ȃ邪�A���̖ʔ������Șe�����ď������A�іL���Ƒ���A�іL���璩���R�n�̓������I�Ē������A��]�����ʂ֖k�シ��悢�B�����ƒn�}�ɂ��ڂ��Ă��邭�炢������A�ʂ�Ȃ����Ƃ͂Ȃ����낤�B�v�f�ʂ�ɂ��Ƃ��^�Ԃ��ǂ����͂킩��Ȃ��������A�Ƃ������A���P�̃��[�g�͂������Č��܂����B
�@���H�����܂��ĉ͌�����Ԃ֖߂�r���A��X�͕s�v�c�Ȃ��̂�ڌ������B�u�i�̋��ɉ��d�ɂ������������̕t�����قǂ̑��������A�͂����ŃY�^�Y�^�ɐ��f����A�͂ꎀ���i�������B�u�i�̊��̂ق��ɂ��A�����[�����������Ƃ��l�W�̍a�̂悤�ɂ͂�����ƍ��ݎc����Ă���B����́A�X�̑�ցu���v�ƐX�̋��l�u�u�i�v�Ƃ́A���S�N�ɂ��킽��A�Â��ȁA��������������������Ȑ킢�̐Ղ������̂��B�u���ǁA�u�i�����������c�c�v�Ƃ����n�ӂ���̂��肰�Ȃ��ꌾ���A�Ȃɂ����悭���̏���Ă����B
�@���Ԃ�A���߂̍��́A�����̂͂₢�����u�i�����|���Ă����̂ł��낤�B��������͍i�ߎE���ꂻ���ɂȂ����u�i�́A����ɑς��Ȃ����痂����������A�₪�āA�Ђ����ɒ~�����w���N���Y�Ȃ݂̗͂ŁA�������������Ɉ����������Ă��܂����ɈႢ�Ȃ��B
�@��X�́A�Ԃɖ߂�Ƃ����ɖ��̗ѓ��̕���n�_�܂ň����Ԃ����B�A���̗ѓ������ɗ��ƁA�܂�����J���Q�[�g�������čs�����j��ł���ł͂Ȃ����B�����A�ʍs�~�߂��Ƃ����\���͂Ƃ��ɂȂ��B�n�ӂ���Ɠ�l�Ŏ����ɃQ�[�g�̏d���S���̃o�[�������グ�Ă݂�ƁA�����݂Ȃ���ł͂��邪�Ȃ�Ƃ��J�����B�J���ւƑ����r�ꂽ�_�[�g�̍ד��ɂ́A���Ȃ�܂��̃^�C���̐Ղ炵�����̂��܂��������Ɏc���Ă���B���S�̕ۏ͂��Ȃ����A�ʂ낤�Ƃ����ӎu�̂���҂͏���ɒʂ�Ƃ����Ӗ����ƁA�s���悭���߂�����X�́A�Ԃ�ѓ����ɐi��������ƁA�ĂуQ�[�g������B
�@�ѓ��E��͎O�ʐ�{���̋����藧�����J�ł���B�H���ɏ\���Ȓ��ӂ��Ȃ��瑖�肾���ĂقǂȂ��A�O���ɁA����Ȋ�������ʂ��đ������s�C���ȃg���l�������ꂽ�B���̖����u����g���l���v�Ƃ���B�܂�Ő̂̎�@��̓��傻�̂܂܂̈Â��ׂ��g���l���ŁA�ނ������̊₪�����Ɠ��ǑS�ʂɂ��肾���Ă���A�������A�Ԃ�������ƒʂ�邩�ǂ����Ƃ��������ł���B�g���l���̂����Ɖ��̂ق��͕����ʂ�̐^���ÈŁA���C�g�ɕ����Ԏ�O�̘H�ʂ��n���ނ������ʼn��ʂ��Ђǂ��A�N���Ƃ���ɂ���Ăł���������炵�����̂����������Ɍ����Ă���B�ꎞ��O�A��������������A���v�X���P�k�J�̗ѓ��Ȃǂł��̎�̃g���l���ɂ����������������Ƃ͂��������A�ߔN�ł͒����������A���݂ɂ����Ă������ɂ܂���Ƃ����Ƃ�ʑ㕨�������B
�@���d�łȂ��X���A�������Ɉ�u�S�O�����������A�����ɋ��낵���Ɍ����Ă��g���l���͏��F�g���l���\�\�l�Ԃ����������̂ł��邩������������ɕK����o��������͂����Ɗm�M���āA�܂܂�Ƃ���ɂ��̈ł̒��ւƓ˓������B
�@�g���l�����̘H�ʂ͂���������������Ă��āA�z�����Ă����ȏ�ɉ��ʂ��Ђǂ������B�܂��A���炭�ʂ���ꏊ���Ƃ���ǂ��날�邤���ɁA�[�������E���ɂ͗N���������Ă��̏�Ԃ��ǂݎ��Ȃ��B�������ŁA���s���Ă���ɂ�������炸�A�ԑ̂͌������㉺���A������Ƃł����f���f����ƁA�V��⍶�E�̕ǂ���˂��o�������̊�p�ɂЂ������肻���ɂȂ�B�ӂ�ɐ������܂��������⎿�̊�ǂ̓w�b�h���C�g�̌����z�����Ă��܂����߁A�Â��Đ悪�悭�����Ȃ��B���܂��ɁA���̃g���l�����̘H�ʑS�̂͏㉺���E�ɂ��Ȃ�N��������J�[�u�����肵�āA���E�̈����ɔ��Ԃ������Ă���B
�@�S���[�g���قǐi�Ƃ���łӂƈ����\�����o���͂������A���܂�������Ԃ��킯�ɂ������Ȃ��B�����͂Ђ�����ːi����݂̂��B����Ȃ̏~������A�����̕s���������E���悤�ɖق��đO�������߂��܂܂������B�ُ�Ȉ������ƕNJ��ɏP���Ȃ�����A��X�͉��։��ւƐi��ł������B�V��̊�Ղ̌�����~�肩����N�����t�����g�K���X���������@���B���C�p�[�Ŏ��E�̊m�ۂ��͂��낤�Ƃ���ƁA���̐����Ԃ����P���Ă���B�\�z�O�̎��Ԃ̘A���Ƃ����āA�O�A�l�S�ĉ��ւƐi����ɂ́A�ق�Ƃ��ɂ��̃g���l���͌��������ւƒʂ��Ă���̂��낤���Ƃ����^�O���A���̉��ɉQ�����͂��߂��B
�@�����\���������̂��̂ƂȂ����̂͂��̒��ゾ�����B�w�b�h���C�g�ɐ蕪����ꂽ�O���̈ł��A���̏u�ԁA��X�͜��R�Ƃ��Č�������̂������B�Ȃ�ƁA�g���l���͂��̐�ōs���~�܂�ɂȂ��Ă����̂ł���B�ǂ����A���Ղ������̎���ŕs�ʂɂȂ��ċv�����炵���B�i�ނ���܂����Ƃ͂܂��ɂ��̂��Ƃł���B�t�^�[���͂܂������s�\������A���̂܂܃o�b�N���邵���Ȃ����A�O�i����̂����ėe�Ղł͂Ȃ������Ƃ����̂ɁA���̈������̂Ȃ��ŁA�o�b�N���Ė����̂܂܂Ńg���l���̓�����܂Ŗ߂�Ȃ�Đ_�Ƃɋ߂��B
�@�u�܂����������͂��Ă��Ȃ��Ȃ��A���������Ȃ�ł���Ȃ��ƂɁH�v�\�\�S���ł����ڂ₫�Ȃ���A�C�����𗎂������悤�Ƃ��Ă�����A����Ƃł��������A�ˑR�A���邱�Ƃ�z���o�����B���N���Ă��炸���Ɖ����Y��Ă���悤�ȋC�͂��Ă������A���������ƌ܌��O�\����̂��̓��͌����L�O���������̂��B�������A�����������ɑ��E���Ă������ƉƓ����ꂼ��̑c�������̖����ɂ��������Ă���B���������̘̂b�����A�����������͕��ł������Ƃ������܂��܂ł��Ă����B
�@�u������������A�����A�J�~����Ƃ���c�l���M�肩�ȁH�c�c���܂���A�킪�Ƃ���A�J�~���A����c�l�̈ʔv�ɂ������ł������Ȃ��獦����ꂢ�Ă����肵�āc�c����Ȃ�܂��A���������������ɎԂ��Ă݂�Ƃ��邩�v�\�\�ȂǂƁA���Ώ�k�߂����z�����߂��点�Ȃ���A�o�b�N�^�]�Ńg���l���E�o�Ƃ����_�Ƃւ̒���ɂƂ肩�������B
�@�����E�B���h�E�͒��ˏグ���D�ƓV�䂩��H��N���̂��߂ɓ܂��Ă��܂��A���C�p�[�����Ă������I�ɂ������E�������Ȃ��B�������A�o�b�N���C�g�̌��͈Â�����A�ځ[���Ƃ������͂������Ȃ��B���̂����㔼�g��������ɂЂ˂��������Ȏp���ł̕Ў�^�]�Ƃ��Ă��邩��A���Ƃ��H�ʂ����R�ł����Ă��A�ԕ����肬��ɔ����ǂɎԑ̂��C�炸�蔲����͓̂���B�܂��Ă�A���̓�H�ʂƂ�����A������ĉ��ʂ��Ђǂ��A���������ʂ��邤���ɁA�����ɃJ�[�u���Ȃ���o���܂ŎO�E�l�S�Ă������Ă�����B
�@�ڎ�蒎�̂悤�ȃy�[�X�ň�i��ނ��J��Ԃ��Ȃ���ł͂��������A�ŏ����̎C�菝���������x�łȂ�Ƃ��E�o�ł����̂́A�s�K���̍K���������Ƃ����Ă悢�B�����Ԃ��l�쓮�ԂłȂ�������A�㕔���ւ��[���H�ʂɐH�������肵�ē����Ȃ��Ȃ��Ă����ɑ���Ȃ��B����ꓬ�̖��ɂ��낤���Ēn���̈ł���E�o���A�o�b�N�^�]�̂܂܂ŃQ�[�g�O�ɒH�蒅�������ɂ́A��l�Ƃ��ɐ��������s���ʂĂ鐡�O�������B
�@���������̖��d�ȐN���͒I�ɂ����A���̃Q�[�g������ɊJ���Ȃ��悤�ɂ��Ă����ׂ����ȂǂƂ�����s�����炵�Ȃ���A��ނȂ�����܂ň����Ԃ����ɂ���������X�������A�r���ł܂��e���a�̔��삪�ނ�ނ�ƗN�����������B����Ȃ�����l�l���̋C�܂���Ȗ��߂̂䂦�ɁA���킢�����ȎԂ͂܂�����ԓ��ɓ˓�����͂߂ɂȂ����̂������B

�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
1999�N9��22��
���̘e�����Q�L�i�S�j
���R�ƍŏ��
�G�E�n�Ӂ@�~
�@���R�ƍŏ��ɖ������ā\�\�z��H���珯�������
�@�n�}���ڂ������ׂĂ݂�ƁA�_���Ȃ����͐������H�Ƃ������邩�Ȃ�ׂ������A�R�[��R�ԕ���D���悤�ɂ��ĎR�k�����ʂւƂÂ��Ă���ł͂Ȃ����B�����X�[�p�[�ѓ��̃X�P�[���ɂ͂���Ԃׂ����Ȃ����A����Ȃ�ɂ͖ʔ������ȓ��ł���B�e�����̉�X�ɂ́A�ނ��A�����Ă����̃R�[�X����������A�������������͂Ȃ������B
�@�z�����璆��A���c�A���A�k�啽�ƁA���W�����Ȃ������̓��̗����ɂ́A�q�̓I�Ƃ������t���҂�����̕��i���L�����Ă����B�ԑ��������ɑ��苎��̂��̂��̈ꖇ�����܂��̋P�������ɔ������B�Ȃ�ł��Ȃ�����̐��̗���܂ł��ٗl�Ȃ܂łɐ��݂����Č�����̂��C�̂�������ł͂Ȃ����낤�B�k�啽���o�Đ쉈���ɍ����̏W���ɂ͂��邱��ɂ́A�J���܂����Ȃ�[���Ȃ����B
�@��������R�k�����ʂ֔�����ɂ́A�k�ւ̂т�ѓ��`���ɁA�V�W�R���ՎR�̈ƕ����z���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����Ȃ��Ƃ��W���܁E�Z�S���[�g���̎R�z���ɂȂ邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�J�̓��ɕʂ����������X�́A�}�Ζʂ��قڂ܂������ɂ̂ڂ�ѓ��ɓ������B���̓��͓r���̓V�W�q��t�߂܂łܑ͕�����Ă������Ƃ������āA����ƍ��x�͂�����A�W�]���������ɂЂ炯�āA�����̎R���݂��������ꕝ�̐��n��̂悤�ɕ����яオ�����B����ȂƂ���܂ł킴�킴����Ă��闷�l�Ȃǂ܂����Ȃ����낤���A����ɂ��Ă��A��X�����Œ��߂�ɂ͂��������Ȃ����炢�̌i�ςł���B
�@�Ƃ��낪�A����ȉ��K�ȃh���C�u�����̂܁A�܂�����A�O������ɂ�����Ƃ��闧�ĊŔ������ꂽ�B�傫�Ȏ��ł���݂悪���ɁA�u���̂����H�����ɂ��Ǝԗ��ʍs�~�߁v�Ƃ��邳��Ă���ł͂Ȃ����B���ǂ͑���s�X�܂ł��ǂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����̂��낤���c�c�c�B��������͒��߂ɋ߂��C���ɂȂ肩�������̂����A������������ƋC����蒼���āA�Ƃɂ����H������܂ōs���Ă݂邱�Ƃɂ����B
�@��ƌ���͓V�W�R�q�ꂩ�炷�������ɐi������ŁA���Ȃ��K�͂ȓ��H�g���H���������Ȃ��Ă���Ƃ��낾�����B�H������̎�O�̂ق��Ŏd�����̎Ⴂ��ƈ��ɁA�����邨����A�ʂ��Ă͂��炦�Ȃ����낤���Ɛq�˂�ƁA���̂ق��ɂ���ӔC�҂ɂ����Ăق����Ƃ����Ԏ��ł���B�ǂ����ʖڂ��낤�ȂƊϔO���Ȃ���A�Ԃ��߂Ă��炭���߂���Ă���ƁA��ƐӔC�҂炵���j��������̂ق��Ɍ������đ傫���菵������̂��������B�ǂ����A�ʂ��Ă��Ƃ������Ƃ炵���������B
�@�܌��O�\������M��������ɂ��Ă悤�₭�����܂��Ă����Ƃ����킯���B���܂��ɂ͂������M���Ă�肽�����A����̓n�ӂ���������Y���ɂ���̂͐\����Ȃ�����A���̂ւ�Ŋ��ق��Ă�낤�Ƃ������ƂɂȂ����̂��낤���B����ɂ����[���������́A�Ƃ��������ق��Ƃ����������Ŗ��̍H�������ʂ蔲�����B�����A�ǂ���炻�̓ǂ݂͊Â������炵���B�����Ƃ̂��ɂȂ��Ė��炩�ɂȂ�̂����A�ڂɌ����Ȃ��M��̖��̎�͏~����ɂ��Ƃ���Ă����炵���̂��B
�@�H��������߂��ĂقǂȂ��A�ѓ��͎Ԉ�䂪����ƒʂ��قǂɍׂ������_�[�g�ƂȂ����B�┧�̂ނ��ł����ʂ̂Ђǂ��������ւƂÂ��Ă���B�u�������v�Ƃ������̖����u�Ӓn���k���v�Ƃł����炽�߂��ق����悳�����Ȉ��H�̓��H���̂ڂ�߂�ƁA�����͂邩�ɁA�Ȃ������Ղ������A��̎R�X���]�܂ꂽ�B���̂������܂��͂Ȃ�Ƃ��_�X��������ł���B�ʍs�~�߂�������Ĉ����Ԃ��������X�[�p�[�ѓ��̑���J�́A�[��������Ƃ����ꍞ�݂������ē�k�ɂ̂сA�ꕔ�͖��̉��ɒ���ł���B���̉����^�L�^���E�Ŗ������鋫�咹�r�����[���ɕ������ޒ����R�n�̍L�傳���A��X�͂��炽�߂Ď����������邨�����������B
�@�R�k�����ʂ����ėѓ��͉���ƂȂ������A�����H�ʂ͑��ς�炸���ʂ��������A�Ƃ���ǂ���Ђǂ��ʂ������B�Ԃ��قƂ�ǒʂ邱�Ƃ��Ȃ��Ƃ݂��A���̗���������̎}���H����悤�ɂ̂т����Ă���Ƃ��������B�Ԃ��Ƃ���������������悤�ɂ��Đi�݂Ȃ���A���Ȃ莞�Ԃ������đ喈�̏W���ɂł��B�喈�ōĂэ��������ɍ��������{�ɂłĂ���́A�f���ɊC�݉����̍�����k�サ�A�R�`���ɓ����ĂقǂȂ��Ƃ���ɂ��鉷�C����ւƌ��������Ƃɂ����B��肠���肩�瓌�̎R�ԕ��֕�������e��������̂͂킩���Ă������A�����Ă��̓��͑I�Ȃ������B���͕��C�ɂ͂���Ȃ������̂ŁA���邭�炢�͉���ŗ��̊��𗬂����Ƃ��Ƃ������ƂɂȂ�������ł���B
�@�R�`���ɓ���A�l���ւ̊C�ݕt�߂ɂ������������Ƃ��ɂ́A�[�ł����菬�J���~��͂��߂Ă����B���̏����m�Ԃ́A���s�̑]�ǂƂƂ��ɁA���܂����O�S�N�O�̌��\��N�i��Z����N�j�̋���Z����\�����ɁA���C���瑺����ʂ������Ă��̑l���ւ�ʉ߂����B�ނ炪�o�H����z����o�ĉz���ւƖk���������ɗ��������̎����́A���݂̗�ł́A�������{���甪�����{�ɂ����Ă̖ҏ��̍��ɑ������Ă���B
�@���̍ד��̉z��H�̕����ɁA�u�l���ւ��z����Ƃ��悢��z��̒n�ŁA�C������V���Ă���ɕ��������A�z���̍��̎s�U�̊ւɂ����B���̊Ԃ͋���قǂ�v�������A�ҏ��∫�V��̂Ȃ��������Ă̋�J�������������̂ŁA�C���������J�T�ŁA��������̒�������Ă��܂����B������A�����̂��Ƃ͏����Ȃ��ŏI����Ă��܂����v�Ƃ����Ӗ��̂��Ƃ����邳��Ă���B��قǑ�ς������炵���̂����A���̊ԂɋႶ���̂��u�r�C�⍲�n�ɂ悱���ӓV�́v�̖��傾�����Ƃ����̂�����A�����ꂢ��B
�@��c����e�s�m�̓�ł���ꂽ�z���s�U�܂ł̗����킸�����s�̕��͂ł����Â��Ă��܂����w�i�ɂ��āA���ۂ͑̒����Ђǂ����������킯�ł͂Ȃ��A���̎��㐏��̕��l�����M����ɒl����悤�Ȗ������Ղ��Ȃ���������ȒP�ɂ��܂����̂��Ƃ��A�m�ԂƂ����l���𗝉��ł���l���z��ɂ͂����Ȃ��A�Ȃɂ��ƕs���Ȏv������������ȗ������̂��Ƃ�������������炵�����A�����Ԃ�Ɖz��̐l�X�ɂ͎���ȕ������̂悤�ɂ������ĂȂ�Ȃ��B���ۂɗ����Ă݂�ƁA�z��H�͕ω��ɕx��ł��Ĕ��������A�܂��A���Ɛ̂̈Ⴂ������Ƃ͂����A�z��̐l�X�̐l��͂��܂₩���̂��̂ŁA�����ɑ��鑢�w���[������ł���B
�@�m�Ԃقǂ̕Y���̐��_�̎�����Ȃ�A���Ƃ��������ՂƂ��ē`���Ƃ��낪�����Ȃ������Ƃ��Ă��A���̂Ԃ�A�������Đ���ςȂ��ɖ��m�̉z��H�̗����y���߂��͂��ł���B���̍ד��̂Ȃ��ɂ������߂��Ă͂��Ȃ����A�u�߂Ȃ��������ꂽ���⍲�n�����v�Ƃ������Ȃǂ́A����Ȕm�Ԃ̐��_���Ȃɂ����悭������Ă���B�܂��A�����ւ̗������ɍۂ��Ă��̐S�����q�ׂ��A�u�\�����Â�̔N��肩�A�Љ_�̕��ɂ����͂�āA�Y���̎v�Ђ�܂��v�Ƃ����ꕶ�����̂��Ƃ��͂�����Ɨ��Â��Ă���B���������A�����𗝉����Ă����l�����Ȃ��Ƃ��������ŋC�����Q���āA���̒n���̗��̋L�^���͂�����Ă��܂��悤�Ȑl���ɁA���̂悤�Ȑ����ȋP��������A�̋I�s����Ԃ邱�Ƃ��ł����Ƃ͂������Ȃ��B��͂�A�����ɑ̒��������������A���ɂ���Ȃ�̎���������̂��낤�B
�@���Ȃ݂ɁA�m�Ԉ�s���ʂ����Ƃ�������l���ւ���s�U�C�݂܂ł̓����̋����������݂̓��H�n�}�����ƂɊT�Z���Ă݂�ƁA���傤�ǎO�S�L�����[�g���قǂɂȂ�B�m�Ԃ͂��̊ԋ���قǂ��������Ƃ��邵�Ă��邪�A�]�Ǔ��L�Ȃǂ����Ƃɏڂ������ׂĂ݂�ƁA���ۂɂ͏\�l����v���Ă���B�����A����œA���]�ÂœA���c�ŎO�����Ă���悤������A�z��H�̗����̂��̂ɗv���������͏\���ł���B�m�Ԃ̋L�^�ƈ���̂���͂��邪�A�\���ŎO�S�L���j�����Ƃ���A������ώO�\�L������������ƂɂȂ�B���ώ����l�L���ň���Ɏ��������ԋ߂������Ƃ������̗��̃y�[�X�́A�ُ�Ȃ܂ł̍��������ɂ��킦�ď\�l���̂����ŋ�����J�V�������Ƃ����������l������ƁA�Ȃ��Ȃ��̂��̂ł���B�r���l���̋x�{�́A��͂�m�Ԃ̐g�̂̕s�����Î����Ă���ƍl���Ă悢���낤�B
�@�m�Ԉ�s�������߂��������u�₩�Ȃ��̎��߂ɁA�����̗���𑀂��āA�ނ�Ƃ͋t�ɗ����ւƌ������Ėk�シ��g�ɂ͓����̗��̋�J�Ȃǂ킩�낤�͂����Ȃ��������A�l���ւ�ʉ߂��Ȃ���A�����̂̔m�ԂƑ]�ǂ̉��V���̓��s���ɂ���ȑz�����߂��点����X�������B
�@�l���ւ��������߂����Ƃ���ŎԂ��߂���X�́A�[���̑����߂��̈�ӂɍ~�藧���ĔӔт̖��X�`�̋�̒��B�����݂��B���`�������Ȃ��琅�����̂������ނƁA�u��z�i���J���j�v�Ə̂���ɂ͂��������N���Ȋ����ł͂��������A�\���H�ׂ�ꂻ���ȁu���ƃ��J���H�v�������Ɨh��Ă���B���Ғʂ�̂��Ƃ̉^�тɃj���}��������X�́A�قǂ悢�ʂ��̃��J�����̎悵�ĎԂɖ߂����B
�@�قǂȂ��������Ȃ����J�̂Ȃ��𑖂蔲���A�������炷�������܂����Ƃ���ɂ��鉷�C����X�ɒ������Ƃ��ɂ́A������͂�������Â��Ȃ��Ă����B��X�́A�����ɗ���������X�^���h�ŏЉ�ꂽ���������T�����Ă�ƁA�Ȃɂ͂Ƃ�����A�ꕗ�C���т邱�Ƃɂ����B���C����X�̂Ȃ��قǂɂ��邱�����ς肵����������ɂ͔ԑ䂪�Ȃ��A�����ɁA��l��S�~���̋��͋�������t���̔��ɓ���Ăق����|�̓\�莆�����Ă������B�ӂ��肠�킹�Ďl�S�~�̋��͋��𓊓����㉖��̉���ɂ���ƁA���̔��Ƌْ����������ɂق���邨�����������B�����������̋��͋�������~�����~�ɂ��l���Ă��邩�̂悤�Ɋ������A�Ȃ�Ƃ��������ꂽ�C���������B
�@�Ƃ��낪�A�������o�Đg�̂�@���ߕ��𒅂Ă��邠�����ɁA���邱�ƂɋC�������B���X�ɗ���ɂ���Ă�������҂̒N������S�~�̋��͋����l�q���Ȃ��̂ł���B�ǂ����A�ߗׂ̐l�X�͊F�A�͓I�i�H�j�ɂ��̋�������𗘗p���Ă���炵���B���łɏ\���ȋ��͂����Ă��܂�����X�́A���݂���������킹�Ȃ���A������ƕ��G�ȋC���ɂȂ����B�����قǕ������l�S�~�̋��͋����A����Ɨ��Ƃ��Ă��܂�������~�����~���̂����ɂ���������悤�ɂ������Ă�������A�l�ԂȂ�ĂȂ�Ƃ�����Ȃ��̂ł���B
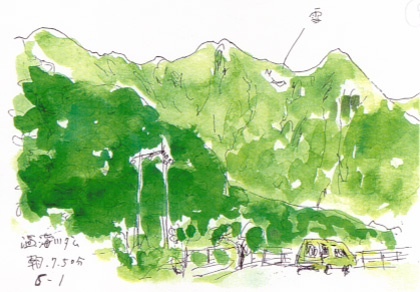
�@�Ƃ����������̊��𗬂������Ă����ς肵����X�́A�����ɂ͂��ǂ炸�A���C��ɉ����ĒJ���̂ڂ�A���C��_���T�C�g�̒��ԏ�ɎԂ��Ƃ߂��B�����͂������������܂���Ă����B
�@����������}���Œ������ĐH�ׂ��Ӕт����̗Ⓚ��Ă����ǂ�͊��҈ȏ�ɂ��܂������B�����āA�l���ւ̈�ӂŏE���Ă����N�����J������ɂ��Ă��������J���`�����ɂ������������B�����A���̃��J���`���Ȃ܂����������������Ƃ��A�����̒����ɂȂ��낤�Ƃ͑z�������Ȃ����Ƃ������B
�@�H�������܂��H��������Â��I�������ƁA���邢�����v���āA�n�ӂ���͈���̃X�P�b�`�̐����ɁA���̂ق��͗��̃����̂܂Ƃ߂ɂƂ肩�������B��i�����A�Ԃ̑��̃J�[�e�����Ђ��Ė���ɂ����̂͏\�ꎞ�����������悤�ɂ������B
�@�����͖锼�̉J�������̂悤�Ȑ��V�ƂȂ����B�ȒP�ɒ��H����������X�́A�����ɁA��ؓ���ʂ�R���̃��[�g���Ƃ��Ē߉����ʂւƑ��肾�����B��������ɓ���ƂقǂȂ��A�O���ɂ͎c����܂Ƃ��P�����C�R�̎p������A�ԑ��E��ɂ́A��͂�c��̊���Ղ������R�̑傫���̂т₩�ȎR�e�����E�����ς��ɍL�������B�Ȃ�Ƃ��Y��ȕ��i�ł���B�n�ӂ��}���ŃX�P�b�`�u�b�N���J���C�z���@�m�������́A����Ɍĉ����邩�悤�ɎԂ̑��x�𗎂Ƃ��A���s�^�]�̑Ԑ��ɓ������B
�@�S�̓I�ɗ������������͋C�̒߉��s�X���A�]�ڕ��ʂɌ������L��_���ɂ͂���ƁA��ʂɓc�����i���L�������B�Ăǂ��돯������͓c�A�����I���������ŁA�܂��Ⴂ�̈�����ɗh��Ĕ������B�O�ォ���X���͂��ނ悤�ɂ��đ傫�����钹�C�R�ƌ��R�̎p�͈����Ƃ����ق��Ȃ��B�u���ȋC���ł��炭�A�N�Z���ݑ�����ƁA���������������Ȃ����ŏ��̒�ɂł��B�ނ��A��X�͎Ԃ���~��āA���ꂼ��ɖ�������ƕ���Ɠ�̎R�Ƃ��D��Ȃ����̌i�ς�������䂭�܂Ŋy���ނ��Ƃɂ����B�����āA�߂��ꂽ�悤�ɃX�P�b�`�̕M���Ƃ�n�ӂ���̂������ŁA���̂ق��́A��Z�����X�ƒX����ŏ��̐��ʂɌ�����Ȃ���A�v�X�ɂ����₩�ȉ̂��r�ݙꂢ���B
�@���Ȃ��݂̐�����܂͉�������ݗZ�����čŏ��䂭
�@���������ƁA���܂���\���E���N�قǑO�̔������̗[���̂��ƁA���͂��̑Ί݂̒版���̓����A��͂�ŏ��̐��ʂ߂Ȃ���Ƃ肠�Ăǂ��Ȃ������Ă����B�傫���^���Ԃȗ[�z�����傤�ǐ��̒n�����ւƗ����Ă����Ƃ���ŁA���̋�Ƃ�����f�������ŏ��̐�ʑS�̂����������Ɖ������ĂĔR��������悤�Ȋ����������B���̐���������̗[�f���́A���̐��̋��X�Ő�����l�X�̖����̔߂��݂�ꂵ�݂����ꂠ�܂��Ăł����ϔY�̑�͂��A���̊C�Ɋ҂�̂��܂��ɂ��āA�V�n��[�g�ɐ��߂鋐��ȉΒ��ƂȂ��ĔR��������i�����A�z�������B
�@�V�n�i���߂��j�ɂ��䂽���߂���߂��݂̗���R�����[�ŏ��
�@���̉̂͂��̂Ƃ��ɉr���̂����A����͂���ł��낢�h��铖���̎��̐S�̂����f���ے����Ă����悤�ɂ������B����ɂ���ׂ�ƁA���̗��ŏo�������ŏ��̎p�́A�Ȃ�Ƃ����������₩�Ȃ��̂Ɋ�����ꂽ�B
�@�ĂюԂɖ߂�A�ŏ��ɂ����鏯������n���ė]�ڒ����珼�R���ɂ͂���Ƃ����ɁA�u���C�̐X�v�ƋL���ꂽ�ē����ڂɂƂ܂����B���]����Ƃ������Ă���B��u�A�u���C�̐X�v�̌�L�ł͂Ȃ����Ƃ����������A�ǂ���炻���ł��Ȃ��炵���ɂ������Ƃ̂Ȃ��n���Ȃ̂ŁA���̂���������ɂ�����Ǝ�����������������A�Ƃ������A���܂��ꂽ����ŖK�˂Ă݂悤�ł͂Ȃ����Ƃ������ƂɂȂ����B
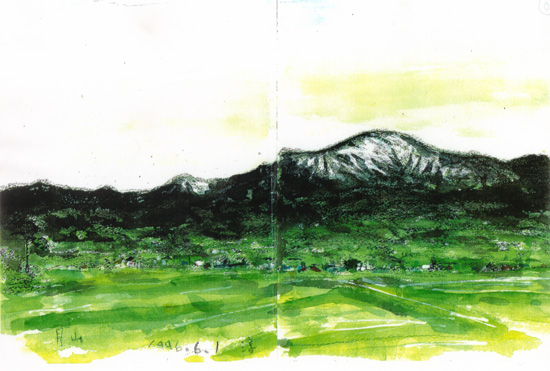

�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
1999�N9��29��
���̘e�����Q�L�i�T�j
�U�����ւ̒������M��
�G�E�n�Ӂ@�~
�@�U�����ւ̒������M��H�\�\���C�̐X���璹�C�R��
�@���H�W���ɓ������܂܂ɏ��R���̏W���̔w��ɂ��鏬�R���������ɓo��߂�ƁA�}�Ɏ��E���Ђ炯�A���₩�ȋN���̍L���鍂�݂ɂł��B�X�Ƃ������͗̎Ő��Ƃ��Ԕ��ɕ���ꂽ�����Ƃ������������������A�������ق��Ȃ�ʒ��C�̐X�������B�\���ɐ����̍s���͂����~�n���̏������Ƃ����I��ŁA�������W�]�䂪�݂����Ă���B�Ԃ���~��Ă����̓W�]��̂ЂƂɗ�������X�́A���̗Y��Ȍi�ςɎv�킸����ۂB���]����Ƃ�������������ɂ��܂��ꂽ����ŖK�˂Ă݂����C�̐X���������A���̊ŔɋU��͂Ȃ������B
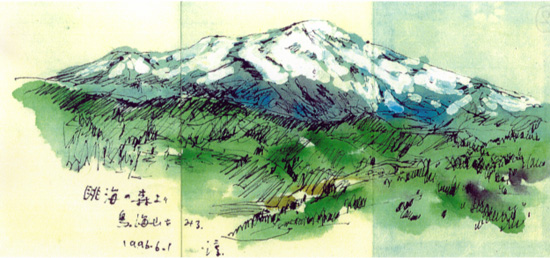
�@�ቺ�ɍL���鏯������̂����Ȃ���傫�����˂藬���ŏ��̐�ʂ́A���炩�ȓ������𗁂тāA�����₩�ɋP���Č������B�����āA�ŏ��̉͌�������Ǝv������p�ɖڂ����ƁA�u���C�v�Ƃ������t�ɂ����킸�A���ޓ��{�C�̊C�ʂ����]�ł����B�܂������O�Ƃ����đ��z�͋��Ɉʒu���Ă͂������A�������琼�ɒ��ޗ[�z�߂��炳�������Y��Ȃ��Ƃ��낤�B��������̉��܂���ւƖڂ�]����ƁA�����P�����R�A�A�����āA�@���̂������E��ɂ́A����z�������Ȃ��������R�n�̎R���݂������A�Ȃ��Č������B
�@�����A�����ƌ`�e���Ă����܂肠��̂́A���C�̐X�̖k���̓W�]�������B���̔���̊���Ղ����C�R�̗Y��ȎR�e�����܂ɂ���̓͂������ȂƂ���ɔ����Č����Ă����B�ǂ���璭�C�̐X�́u���C�v�Ƃ������ɂ́A�ÂɁu���C�R�߂�v�̈Ӗ������܂܂��Ă���炵���B����ɂ��Ă��A����ȑf���炵���W�]�䂪���邱�Ƃɂ���܂ŋC�Â����ɂ����Ȃ�āA�Ȃ�Ƃ��M�����Ȃ����v���������B
�@���C�̐X����̑厩�R�̒��]�𑶕��Ɋy�����ƁA��X�͍L��ȕ~�n�̈�p�ɂ���X�ъw�K�W���ق����w�������A���̓W���ق̓W�����ɂ́A���炸���炸�̂����Ɍ��w�҂̋������������Ă�a�V�ȍH�v�����낢��ƂȂ���Ă��āA�ƂĂ����S���Ă��܂����B���̒n��K�˂�@��̂�����A�Ƃ��ɂ��q�l�A��̕��X�ɂ́A������Ƃ����ł��̂����Č��邱�Ƃ��������߂������B�W���ق��o�����ƁA���ԏ�̋߂��ɂ���O�R���b�W�ɗ������A�����ƃ\�o��g�ݍ��킹�����S�~�̃Z�b�g���j���[�𒍕������H�ɂ������A�Ȃ��Ȃ��̖��������B�����Ƃ��A����́A��l�Œ������o�����Ĉȗ��͂��߂Ă̊O�H����������A���̂Ԃ�A��肢��������������������ꂽ�̂�������Ȃ��B
�@���C�̐X�����Ƃɂ��钼�O�ɂȂ��āA���́A�~�n�����߂��̓W�]��ʘH�̘e�Ɂu�O���Y�̓��L�v�Ȃǂ̍�i�ł����鈢�����Y�̋L�O�肪���Ă��Ă���̂ɋC�������B�ǂ����A�������Y�͂��̏��R���̏o�g�ŁA���C�R�⌎�R�A�ŏ��Ȃǂ���X���߂Ȃ��������炵���B�������Z�����������ɂ́A���яG�Y�A�T�䏟��Y��̕��͂ƕ���ň������Y�̕��͂��悭���ȏ��ȂǂɂƂ肠�����Ă������̂ŁA���R�A��w�����ɂ����̕��͂����Ώo�肳�ꂽ�B������A�O���Y�̓��L��ǂ����Ǝ��݂����Ƃ����x�����������A���Z���̐g�ɂ͂���߂ē���Ȏv�ِ��̋������͂������̂ŁA�����������炭�炵�Ă��āA���ǁA���ǂ͂ł����ɂ�����Ă��܂����ꂢ�z���o������B
�@�������Y����̎p�𓊉e�����O���Y�Ȃ�l���́A�쒆�̂��������Ŏ��g�̂��Ƃ�s�҂ƚ}���Ă������̂����A���Ƃ��Ƃ����₩�Ȕ\�͂����������킹�Ȃ����Ȃǂ́A���̒s�҂̓f�����c��Ȍ��t�̈�[�����������ɂ͗����ł����ɓ����������ł����悤�Ȃ킯�������B����ɂ��Ă��A���̑����ɋ��Ȃ̑������ȓI�ȕ��͂��������������Y���A���̗Y��Ȏ��R�̒��ŗc�����𑗂����Ƃ��������́A���ɂ�������Ԃ�ƈӊO�Ȃ��Ƃ̂悤�Ɏv��ꂽ�B
�@���C�̐X�ɕʂ����������X�́A�����O�l�܍��`���ɕ��c���A���������o�āA�L��Ȓ��C�R�̓쓌�R�[�Ɉʒu����V���i�䂴�j���ɓ������B�K�C�h�u�b�N�ɂ����Љ��Ă��Ȃ����A�܌�����Z���ɂ����Ă̗V�����̓c�����i�͎��ɑf���炵���B�c�����i�Ƃ́A�܂��ɂ��̂悤�Ȍi�ς̂��Ƃ������ɈႢ�Ȃ��B���͂���܂łɂ���A�O�x�A�̋P�����߂ɗV����K��A�_���̕Ћ��ɎԂ𒓂߂ăJ�[�X�e���I���痬��o��x�[�g�[�x���̘Z�ԁu�c���v�ɐS�䂭�܂Œ������������Ƃ�����̂����A����Ӗ��ł���͍ō����ґ����Ƃ����Ă悢�B�����Ƃ��A���̂Ƃ��́A�V���̒��ɓ����ĂقǂȂ��A�n�ӂ���������}�ɖ��C�����您���Ă������߁A�c�ނ̌l���ɎԂ��A���C�R�߂Ȃ���ꎞ�Ԃقǒ��Q���邱�Ƃɂ����B

�@�ЂƖ��肵�����ƁA�Ăѐ��Y���ʂɌ������đ��肾������X�́A�قǂȂ�������Ƃ������������̐��n�����B���Ԃ�A���X�Ɛ���X�������̐Â��Ȑ�̐��ʂɂ́A�����̔ӂȂǁA���̌������z�I�ȋP���������Ȃ���f���킽��̂ł��낤�B���̔ӂ̌��͂��傤�ǖ����ɂ������Ă�������A�������̋�ɏ���܂ł��̒n�ɗ��܂��Ă��̖��̗R�����m���߂Ă݂����C���ł͂��������A�܂��ߌ�O���O�������̂ŁA�Ƃ肠�����͐S�̒��Ō��������Ȃ��痷�H���}�����Ƃɂ����B
�@��͐���킽���Ă����ɂ�������炸�A���Y���߂Â��ɂ�A�ڂɌ����ĕ������܂��Ă����B���c�̐X�Ƃ�����̕c���������g�ł��Ă���B�n�}�����Ă̎��̐��������A���{�C���琁����C���������傫���ނ��钹�C�R�ɂԂ���A�����������邩�����ł��̐��Y��т�ʉ߂��邹���Ȃ̂�������Ȃ��B�n�`�ケ�̂����肪���̒ʂ蓹�ɂȂ��Ă���Ƃ���A���Y�Ƃ������̒n�����[���ł���Ƃ������̂��B���Y�̏W���ō��������ɍ������ĂقǂȂ��A���C�u���[���C���̎R�`����������ɂ��钓�ԏ�ɓ���������X�́A�����߂��̍r��ɂ���\�Z�������K�˂Ă݂邱�Ƃɂ����B�\�Z������́A���C�R�̎R�������{�C�ɑ傫�����肾�����A���Y�̏W���̖k�͂���̒n�_�Ɉʒu���Ă���B
�@�����m�Ԃ̈�s�́A��c����C�����ɂ��̐��Y����ɂ͗L�떳��̊ւ��A���܂͏H�c���ɑ�����ۊ��܂Ŗk�サ�A���������̍ד��̗��̖k���̒n�Ƃ��čĂю�c���ʂɓ쉺�����B�]�k�ɂȂ邪�A�������N�\�ꌎ��\�ܓ��A�u���̍ד��v�̔m�Ԓ��M�{�����Ŕ����m�F���ꂽ�Ƃ����j���[�X���S���ɗ����ꂽ�B���́A���N�̎O�����Ɏ��������₩�ȋI�s��i�ʼn��̍ד����w�܂���܂����ہA��Îґ��̂͂��炢�ŁA�I�l�ψ��̑剪�M�A���`���̗��搶�����Ɗ��k���Ȃ����H������@��Ɍb�܂ꂽ�B
�@���̐ȏ�A�剪�搶���A���`�搶�ɂނ����ĉ��̍ד��̐^�M���������ꂽ�Ƃ����b�����X�ɓ`����Ă��邪�A�{���Ȃ̂��Ƃ����₢�������Ȃ���A����ɑ��āA���`�搶�́A���ܐ��Ƃ��m�F�������A�قڊԈႢ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ������ɂȂ��Ă����B�����āA���݂͖��Ԑl�̎�ɂ�����̂Ȃ̂ŁA���I�ȂƂ��낪�������ƂȂ�ƁA�r�����Ȃ����z���K�v�ɂȂ邾�낤�c�c���̍ד��Ȃ�ʕ����ʂ�́u���v�̍ד����Ƃ������������ꂽ������Ă���ꂽ�B���ꂩ�甪�����������ĐT�d�Ȍ������Ȃ��ꂽ���ƁA�悤�₭���ɒ��M�{���Ƃ̊m�F���\���Ȃ��ꂽ�킯�����A���n�ȍ�i�Ŕm�Ԃ䂩��̕��w�܂���܂��������N�ɂ��܂��܉��̍ד��̐^�M�����������Ƃ����]�O�Ȃ߂��肠�킹�ɁA���܂����͕s�v�c�Ȋ��S���o���Ă���B
�@����ȏ\�Z������́A���{�C�̍r�g�̊��ӂɁA�Ȃ�ƂȂ��{����z�킹�邽�����܂����ނ��Ă����B��̐��ʂɂ܂��ƁA�Ȃ�قǁA�߉ޔ@���ɕ����A����̗���F�Ƃ������钆���̎O���𗼑�����͂��ނ悤�ɂ��āA�\�Z�̗̂������������Ɗ�ɒ��肱�܂�Ă���B�Q�w�҂������낷�悤�ɕ���ł͂��邪�A�ǂ������g�����邻�̕\��ɂ͐e���݂����Ă��B�����ڂ��C���N��������X�́A���߉ޗl�Ƃ�������傫�Ȓ����̑O�܂Ō��݂ɂ悶�o��A�����ō��T�܂����̃|�[�Y�����Ďʐ^���B�肠�����B�\�Z��������\��������ɕς��Ă��܂����Ƃ������_���������A�����n�ӂ���̎p�������Y�łƂ炦�A�V���b�^�[��낤�Ƃ����u�ԁA�C�ƕs���̋U�����ǂ��߂��Ƃ�������ɁA��̂��߉ޗl����u�j�����ƂȂ������悤�ȋC�������̂́A���̎v���߂����������̂ł��낤���c�c�B
�@������̂�����̎��ӂ̊C���ɂ͎��̂悳�����ȃ��J�����͂��Ă����B���H�ׂ����J���`�͑z�����ȏ�ɔ������������獡����܂����J���`�����낤�Ƃ������ƂɂȂ�A�Ăщ�X�̓��J���̂���n�߂��̂������B���������̊�������ɕ����ԏ����`�������Ȃ���A�����ɘr��˂�����Ń��J�����̂�̂����A����̊�ɂ͂ʂ�ʂ�Ƃ����A�I�T����ʂɐ����Ă��Ē��ӂ��Ȃ��Ɗ����Ă��܂��B�C�炿�̎��́A�c�������炱�̎�̊�������̂ɂ͓��Ă������A���������ꂽ�Ƃ���ɂ���n�ӂ���̗l�q�����ڂł����Ƃ��������ƁA�ǂ������̑����͊�Ȃ��������B���N�R�d���Œb�����n�ӂ���͌��r�ɂ͈Ⴂ�Ȃ����A��̕������ɂ͂܂�����Ȃ�̃R�c�����邩�炾�B
�@������Ɨ��ꂽ�Ƃ���ɂ����ɔ�шڂ낤�Ƃ��Ă���n�ӂ�������āA�v�킸��Ȃ��ł���Ɛ��������悤�Ƃ����̂����A���̏u�ԁA�����������Ƃł��������A�܂������ʂ̎v�������̔]�����悬�����̂������B��X�����k�n������Q����ƒm��������ҏW�҂���A������߂������ƁA���̕��Q�L�������Ă��炦�Ȃ����낤���Ƃ����Őf���Ă����B�l�Ԃ̐S�Ƃ́A�Ȃ�Ƃ����Ӓn���Ȃ��̂ł���B�����ɍ������Ă����ƁA���̕ҏW�҂̊���v�������ׂȂ���A�����������œn�ӂ��C�ɂ͂܂�悤�Ȓ����ł�����Ό���ȕ��Q�L��������̂ɂȂ��ƁA���͐S�̒��Ŏv�����̂������B
�@�������n�ӂ���ɂ��Ƃ���Ă����炵���܌��O�\������M��i�H�j�ƁA�ӂƂǂ��ȋU�����ɑ���\�Z������̂��߉ޗl����̒��炵�߂ƁA���̎�ɂ����̂����ꂽ�Ƃ��������悤�̂Ȃ����̎v�O�̓����Ƃ̎O�d�U���ɂ������̂ł́A������Ȃ�ł��ς����悤�͂����Ȃ��B���̓�A�O�b��̂��ƁA�͂��݂����Č������̊�ɓn�낤�Ƃ����n�ӂ���́A�A�I�T�̖ʂɂ��̂̌����ɑ����Ƃ��A����ǂ肤���ė₽���C���ɓ]�������B���������疽�ɕʏ�͂Ȃ��������̂́A���ꂪ���̐�[�̂����Ɛ[���Ƃ��낾������A�n�ӂ���������邽�ߎ��������ɔ�э��܂˂Ȃ�Ȃ������낤�B
�@���߉ޗl�ɂ�����ꂱ�����{�]�ł��点�ꂽ�̂�������Ȃ����A�������̐g�̂قǒm�炸�̘A���ɓM���ł�����A�Ԉ���Ă��܂����ɓV��E�ɂł�����Ă���ꂽ��ƂĂ��ʓ|�Ȃǂ݂���Ȃ��ƁA�r���Ŏv�������ꂽ���̂炵���B�����łȂ���A�ׂ̕����A����̗���F�l���A�u���߉ޗl�A���߉ޗl�A���������ł��傤�������̂Ƃ���͂��̒��x�Łc�c�v�ƂȂ��߂Ă����������̂ł��낤�B
�@�S�g���ԔG��̓n�ӂ���Ƒ�}���ŎԂɖ߂�A�q�[�^�[�����Ďԓ������߁A�܂��͂��̒��ւ�����`�����B�K���A���ԏ�̈�p�ɐ��ꂪ�������̂ő̂�@������A���ɔG�ꂽ�ߕ��𐅐��邱�Ƃ͂ł����B����œn�ӂ��ߗނ̒��������Ȃ����Ă���ԂɎ��͂�����x���ɍ~��āA���܂��������J���ƋT�̎���̎悵���B���̖��̒ʂ�ǂ����T�̎�Ɏ����Ƃ���̂��邱�ٌ̈`�̊L�́A�g�̌�������ӂ̊�̂����ԂɌQ�����Ă��邪�A�Y��ȊC���ł����Ƃ�łĐH�ׂ�Ƃ��̎p�`����͑z�������Ȃ��قǂɔ������B�ނ��A�̂����T�̎����ł邽�߂ɊC�����y�b�g�{�g���l�ߍ��ނ��Ƃ��Y��͂��Ȃ������B
�@�\�Z�����₻�̒��ԏ�����Ƃɂ��A���C�u���[���C���ɓ������̂͌ߌ�������������B����ƍ��x���オ��ɂ�A���H�̗����ɂ܂������܂܂̎c��̑w�����ꂽ�B���̓~�A�����ɐႪ�������������Â��B�悭����Ǝc��w�̉����̂�����������_�炩�����ȕ����V����������Ă����B����Ȑ��X�����F�̂��̂Ȃ�ԈႢ�Ȃ�����������ƗE��ŎԂ���~�肽�n�ӂ���́A�捏�̖��_�҉�Ƃ���ɁA�������܂�������̕����V���̎悵�Ė߂��Ă����B���J���̂�ł͂�����Ƃ��肵�����������A�����͎R�炿�̓n�ӂ���̘r�̌����ǂ���ɈႢ�Ȃ��B�Ƃ������A�������āA���̖�̐H���̗p�ӂ͖��S�ƂȂ����c�c�͂��ł������B
�@�O�\���قǑ����Ē��������C�R�����̑啽��ɗ��ƁA�V�������c���ʂւƂ̂т�L��ȕ��삪�A���肩��̗[�z�𗁂тĐԗɉf���P���Č������B�܂��A�͂邩�ɁA���R�⒩���R�n�̔�����X��]�ނ��Ƃ��ł����B�啽�䂩��̒��]�i�������ƁA�g�����o�ďH�c�����̏ۊ����ʂւƂ�����r���ŁA���z�͓��{�C���g�����߂Ȃ��琅�����̌������ւƒ���ł������B�[�ł̔�����{�C�̂����Ȃ��ɁA�ЂƂۂ�ƕ����������Ԕ̓��e�����ɂ͂Ȃ�Ƃ���ۓI�Ɏv��ꂽ�B�u���[���C���̏H�c���Q�[�g���o�ďۊ��̒��ɋ߂Â����ɂ́A�����̒��ɂق̔��������Ԓ��C�R�̍����ɖ������̂ڂ��Ă����B���̌��́A�܂���X�̂�����Ōł߂��Ă���݂����ɂځ[���Ƃɂ��F�̌�������A�قǂȂ��[������ɂ����Ƃ��钹�C�R�̗Ő���_��I�ȍʂ�ɉ��o���Č����Ă��ꂽ�B
�@���������ɍ����������ƁA��X�͉��̍ד��̗��H�ɂ�����k���̒n�A�ۊ����������ɒʉ߂����B�m�Ԃ̎���A����������]�ɐ��X�̏����������сA�����ƕ��я̂�����i���n�ł������ۊ��́A�������N�i�ꔪ�Z�l�N�j�̑�n�k�Ő��ꂪ���N���Ċ��オ���Ă��܂��A���܂ł͏��������������u�݂̂��_�݂��邾���ɂȂ��Ă���B
�@���ɔG�ꂽ�n�ӂ���̐g�̂�������߂������āA�ۊ�����k�ɂ������s�����Ƃ���ɂ�����Y����̃z�e���ɗ������A���������������Ă�������B�����āA���̂��ƁA��X�͐��ڒ��t�߂̊C�߂��ɎԂ𒓂߁A�x���Ӕт̎x�x�Ɏ�肩�������B������Ɗ�Ȏ�荇�킹�ł��������A�i���R�����ƃ��J������̖��X�`�������Ă���ƁA�n�ӂ��A������ꏏ�ɓ����Ɣ�������ƌ����Ȃ���A�ϗ�������`�̒��ɐ捏�̂��Ă��������V�����X�ɐ����悭���荞�B���S�A���v���ȂƎv�����̂����A�����V�̒����ɂ��܂�ڂ����Ȃ����́A�n�ӂ���̌��t�ƌo����M���邵���Ȃ������B
�@�������������ł��낤�Ƃ������閡�X�`��������킨���Ƃ����n�ӂ���̊�͊�ɂ䂪�B�u�{�c����A���炠�����A���߂�I�v�c�c�Ƃ����̂��A���̒���ɓn�ӂ���̔��������t�������B���������������ƁA���������邨���邻�̖��X�`�����ɂ��Ă݂�ƁA�Ȃ�Ɩ��X�`�̖����܂�ł��Ȃ��B�����ɁA���炩�ɕ����V�̋����A�N�̂������Ƃ�������A������Ƌꖡ�������ٗl�Ȋ��o���������ς��ɍL�������B�i���R�����������J�����A����ɂ͖��X�`���̂��̂��݂�ȓ�����������ł͂Ȃ����B���܂�̒����Ɏ��̂ق��͂������܃M�u�A�b�v���Ă��܂����B
�@�u����ȏ_�炩�����ȕ����V�ɏo�������̂͂͂��߂Ă̂��ƂȂ�ŁA�A�N�������[�ւ�ł��A����Ȃ炷���ɐH����Ƃ��������Ȃ��c�c�B������������A������A���߉ޗl���M�肩�������Ȃ��v�ƌ����Ȃ�����A�n�ӂ���͐ӔC�������Ă��A�Ȃ����ʊ��ɓ�`�ɒ���ł�����B���̂ق��́A���Ȃ����̂��߂ɂ��ƃ{�g���ɋl�߂Ă����C�������o���A�}���ŋT�̎�̒����Ɏ�肩�������B�K���Ƃ������A�T�̎�̂ق��͂����̒ʂ�������̂��̂������B
�@�Ȃ�Ƃ����܂�Ȃ��Ӕё������I������Ƃ��ɂ́A�����͂��łɌߑO�뎞���߂��ɂȂ��Ă����B��X�́A���ꂩ��قǂȂ��A�V��̖��邢�]���Ɍ�����Ȃ���A�[���ӂ�������ɂ����B
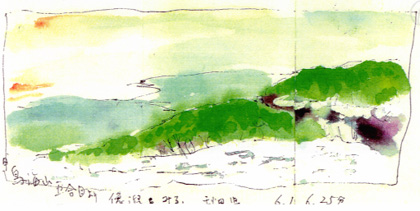
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
1999�N10��6��
���̘e�����Q�L�i�U�j
�������ƌ����̓c���
�G�E�n�Ӂ@�~
�@�������ƌ����̓c��\�\�p�ق̕��Ɖ��~����c���
�@�����͎������ɋN�����A�J�b�v���[������䥗��ŊȒP�ɐH�������܂������ƁA�c��Ε��ʂɌ������ďo�������B�{����������ɂ͂���A��ȁA����k�A�p�ق��o�ēc��֔�����Ƃ����̂����̓��̂����܂��ȗ\�胋�[�g�������B�{�����獑����Z�܍������ɖk��A��������o�đ�ȕ��ʂւƓ��i���鍠�ɂ́A����܂Ŏ��ܐU��Ԃ��Ă͒��߂Ă������C�R�̑傫�ȎR�e���͂邩����ɉ�������A�₪�ĉ�X�̎��E������������Ă������B
�@�p�قɒ������̂͌ߑO�\�ꎞ���������B�p�ق͕��Ɖ��~�����܂��ɓ����̖ʉe���Ƃǂ߂Ă���ꏊ�Ƃ��Ė������B�������������炿����Ɨ�������Ă��������Ƃ������ƂɂȂ�A�\�������߂��̒��ԏ�ŎԂ��~�肽�B���ӂ̒���S�̂����v�ۑ��n��Ɏw�肳��A�X���݂⌚���̋��X�ɂ�����܂ł��߂��܂₩�Ȕz�����s���n���Ă��邹�����낤�A���C�Ȃ������Ă��Ă��A�܂����Ԃ̗���̂��₩�������ː�����ɖ߂����悤�ȍ��o�ɂ�������B���ƁA���ƁA�͌��c�ƁA����c�ƂƂ��������Ɖ��~���X�H�ɉ����ĕ���ł���A�����̌Â���\���̉��~����́A�召�̓������ɍ�������鞎p�̎������܂ɂ���яo���Ă������ȕ��͋C�������B

�@��X�́A��������p�ق̕��Ɖ��~�̂Ȃ��ł����Ƃ��̂̂܂܂̖ʉe�𗯂߂Ă���Ƃ������Ƃ�K�˂Ă݂��B���łȍ\���̖�����ƁA���ʂɓ�w�̑傫�Ȋ�������̕ꉮ�����ꂽ�B�����ȑ���̕ꉮ����́A�ߌ���ɂ̂т邩�����ŁA�����Ɖ��̑傫�ȓy���̂ق��܂Ō������Â��Ă���B�ꉮ�̓y�ԂɌC��E���A�L���ɂ������Ď��Ԃ̖���L��Ȓ�߂�ƁA�Ȃ�Ƃ������������C���ɂȂ����B�������ꂽ�Αg�݁A��ہA����ȌÖ��͂��߂Ƃ���S��������̒�̔z�u�ȂǁA�n���̕��Ɖ��~�ɂ��Ă͂Ȃ�Ƃ��҂�s����������ł���B
�@�ꉮ���x���钌�̈�{�����ۂ���A�܂��A���̊Ԃ��͂��߂Ƃ��鎺���̗v���̑����������ɂ߂����̂ɂȂ��Ă��āA���ɑf���炵���B�Ō�ɑ����^�傫�ȓy���̂Ȃ��ɂ́A���Ƃɑ�X�`��鐔�X�̒��x�i�═��ނ��W������Ă������A��������ʋM�d�ȕi�X����ŁA�����̊p�ٕ��Ƃ̗D��ŖL���Ȑ����Ԃ�ƌ𗬂̍L�����Âꂽ�B���Ƃ͍��|�k�Ƃ̍�����a����[�˖��⊨����߂Ă����炵���B
�@���Ƃ��Ɗp�ق̕��m�����͔ˎ�̉Ɛb�ł��������|���̉Ɛb�A���Ȃ킿�A���b�ł������B���b�ł͂Ȃ��A���b�̉Ɛb�Ƃ����A�����Ƃ��Ă͂������č����Ƃ͂����Ȃ��g���̂䂦�ɁA�\�������������S�Β��x�ɗ}�����Ă����Ƃ����B�������m�Ƃ��Ă̂��̘\�����炷����R������]�V�Ȃ�����Ă����������Ȃ��ނ炪�A�ǂ����Ă��̂悤�ɗ��h�ȉ��~���\���A����قǂɖL���Ȑ������c�ނ��Ƃ��ł����̂ł��낤���B
�@�p�ق̕��m�����͖����߂��ɂȂ�ƁA�n�̗����������āA�����i�A���}�A���H�A������H�Ȃǂ̐B�Y�ƋZ�p�̌��s�ɐϋɓI�Ɏ��g�݁A����ɂ���āA�ނ�̘\������͑z�������Ȃ��悤�ȉ��~�Ɖ����ێ��ł���قǂ̍��͂��̂ł������B���܂ł͑S���e�n�̓y�Y���X�Ŗڂɂ�����̎������������H�ނȂǂ��A�̂͂��̊p�ق̓��Y�i�ŁA����Ȏ��v���ɂȂ����̂��Ƃ����B���낢��ƒm�b�����ڂ����������ɁA�ނ�́A���^�ɂ��Čy�ʂŁA�������l�̒�����Y�i���l�Ă��A�������L�����ʂ��������ʂƂ��đ���ȗ��v����ɂ����̂ł���B�ނ��A�n���I�����ɂƂ��Ȃ��y�n�̈����⌚�z���ނ̓���̂��₷���Ȃǂ��A�s��ȕ��Ɖ��~�\�z���\�ɂ�������������̂ł͂��낤�B
�@��ʂ蕐�Ɖ��~�Q�⎑���قȂǂ����w�������ƁA���ǂ�̘V�܁u���v�Œ��H�����܂�����X�́A�Ԃɖ߂�A�����l�Z����c��Ε��ʂɌ����đ���o�����B����ƁA�p�َs�X���ĂقǂȂ��A�u�����Ԃ�k�J���ʂցv�ƋL���ꂽ�ē��W�����ڂɔ�э���ł����B�j�S��d�����U�����̌ď̂Ɉ�ڍ��ꂵ����X�́A�������Ȃ��W���̎w�����p�ւƎԂ�������邱�Ƃɂ����B���ꂩ��قǂȂ��k�J������ɒ������̂����A���ԏꂪ���G���Ă��邤���ɁA�k�J�̉��ɓ���ɂ͂������炳��ɒJ�����ɕ����˂Ȃ�Ȃ��炵���B�k�J��k��Ƃ������ꂪ����Ƃ������Ƃ��������A�����Ƃ���A�i�ςɊi�ʂȓ����̂���k�J�ł��Ȃ��������������A�����l�������ẮA���Ƃ��J������d���Ȕ���������Ă��A�Ђ����Ɉ��������y���ނ킯�ɂ������Ȃ��B�����܂����j�ꂽ��X�́A�u�����Ԃ��k�J�v�Ȃ�����ƈӖ��[�ɂȂ�̂ɂȂǂǚ��������Ȃ���A���������Ƃ��̏ꂩ��ގU�����̂����A�����ւƖ߂�r���A���܂��܂��̗L���Ȍ���u���э��v��ڂɂ��邱�Ƃ��ł����̂́A������Ƃ������n�������B
�@�c��Β����߂Â��ɂ�A���㕔�̗Ő������ȏH�c��x�̎p���傫����O�ɔ����Ă����B�}�Ɉꕗ�C���т����Ȃ�����X�́A�c��ΔȂ�K�˂�̂͂��Ƃ܂킵�ɂ��A�܂��́A��x�Ƃ���ɘA�Ȃ�R�X�̉��[���ɕ����ꂽ�������ւƌ��������Ƃɂ����B�c���ւ̓��ɓ���ƁA���x�͂�����A�������ɓW�]���J���Ă����B��l���Ďv�킸���Q�̐����������̂́A�c���x�ɑ��̒��ԏ�܂œo�����Ƃ��������B���邢�z�˂��������ς��ɗ��тāA��x���͂��߂Ƃ���O���̎R���ݑS�̂��A�����Ƃ܂�������ɉ��₩�ȋP�����Ă�������ł���B�u���炩�ȁv�Ƃ����`�e��������قǂ܂łɎ������Ɏ��͂����o���������Ƃ��Ȃ������B�n�ӂ��������܃X�P�b�`�u�b�N�����o�������Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B

�@�����x�ɑ����߂���Ƃ����ɎԂ͐[���u�i�т̒��ɂ���A�����҂��Ă������̂悤�ɁA���̂ق������˂��˂Ƃ����ׂ��}�ȍ⓹�ƂȂ����B�n���h�������E�ɂ����Ȃ��瓹�H�e�ɂ��炿��ڂ����ƁA���������ɂ��Ȃ�̐��̐��m�Ԃ��Q�����Ă���̂�������B�ǂ����Ԃ��J���Ă܂��Ԃ��Ȃ��炵���B�u�i�т��ē������̍ʼn��ɂ��鍕���̒��ԏ�ɒ������̂́A�ߌ�l���O���炢�������낤���B���ԏ�̂Ȃ��̏������Ȃ����Ƃ��납��J�������̎R�߂��ƁA����̂ҁ[��ƒ������Ⴂ�����̓��[��������̎R�e���ڂɂƂ܂����B���ꂪ�A�������Ƃ������̂̂��ƂƂ��Ȃ��������R�̒��ł��邱�Ƃ͖��炩�������B
�@��������͓����R���痬��o���B��Ɠ��X�R���炩�痬��鍕����������J���ɂɈʒu���Ă���B�����N�i��Z���l�N�j���ɂ͂��łɏH�c�ˎ卲�|�{�Ƃ̓�����Ƃ��Ēm���Ă����Ƃ��������̂��Ƃ͂����āA�ǂ�����Ƃ�������̍��������������̌������A���ɔ�߂����̗��j�̏d�݂��������܉�X�Ɍ�肩���Ă����B�������̑�̂�����Ƃ��납��͂���Ɖ��N���o�Ă���A��тɂ͓��C�Ɨ����̉������������Ɨ����̂ڂ��Ă���B��l�ܕS�~�̓��������Ă͂������I�V���C�͔��������_���̗�����ŁA���������قǂ悭�A�����܂�������₩�ɂȂ銴���������B�铒�ƌĂ�邾���̂��Ƃ͂����ē��M���璭�߂��̌i�ς͎��ɑf���炵���A�n�ӂ���Ȃǂ́A���M�ɃC���X�^���g�J��������������ł�����Ɏ��ӂ̌i�F���ʂ��Ă���ꂽ�قǂ������B���܂͈�ʂɐV���f���킽���Ă��邪�A�H�ɂ͂��̎�t�̈ꖇ�����܂��������ȍg�t�ɕς�邱�Ƃ��낤�B�܂��A�����߂��ɂ͍����Ƃ����ď̂̂��ƂɂȂ����Ƃ�������A�����ۂ������Ƃ������F�̒P���������f��̗����������āA��X�̐g�̂����ꂩ�牷�߁A�m�炸�m�炸�̂����ɒ���l�߂Ă����S�g�̋ؓ������炩���ق����Ă��ꂽ�B
�@�����Őg�̂���߂����ƁA��X�͑��̓���k���Ōܕ��قǂ��������Ƃ���ɂ��鑷�Z�̓���K�ˁA����̃n�V�S�����邱�Ƃɂ����B��Z�������قƂ����B��������낵�Ȃ��狴��n��ƁA�Ȃ�Ƃ��ЂȂт�����h�����ꂽ�B�ނ��A���Z�̓��ł���B�������̂Ȃ��œ�����Ƃ��Ă̕���������Ƃ��c���Ă���Ƃ������̉���́A�u�R�̖v�ȂǂƂ��Ă�Ă���炵���B�̈قȂ�l�̗���ƘI�V���C�������āA�Ȃ��ł����W�E���ܗL��͓��ɖ��������炵�������B�����̌������k���̂����e�ɂ���I�V���C�͂������ʂ�߂��������A�V�R�̊��g��łł������M���璭�߂鐴���̔�������A�₳������������ރu�i�A�g�`�Ȃǂ̗̑����Ɋ��Q���邤���ɁA�g�̂��ق��ق��Ɖ��܂��Ă����B
�@�I�V���C�̂����ׂ̖ؑ���̏����̒��ɂ���̓��́A�傫�Ȉꖇ�������ʂ��������ɐ��[�ΐF�̒P�����X�ƒX�����Ă��āA���������قǂ悭�A����܂����ɂ������͋C�������B��X�̂ق��ɂ͓����q�͂��炸�A�݂����Ԃ���������A�����������Ƃ͂Ȃɂ��Ȃ������B�A�肬��A���Z�̓��̏h�����e�ɗN���Ă��鐴�������ɂ��Ă݂�ƁA�₽���R�N�������ĂƂĂ����܂������B�����ŁA��������Ԃɖ߂������ƁA��̃y�b�g�{�g���ܖ{���g���Ă�����x�����Ԃ��A�~�l�������ӂ�Ɋ܂��̐��������ς��ɋl�ߍ��B���Z�̓���K�˂�@��̂�����̕��ɂ́A���ЂƂ����̐��������Ȃ����Ă݂�悤�ɂ������߂��Ă��������B
�@�����A���Z�̓������Ƃɂ�����X�́A���������x�ɑ��̂���Ƃ���܂Ŗ߂�A��������A���T���A�劘������o�ĊI�ꉷ��ւƂÂ����ւƂ킯�������B�����O�̉���͂��������B�쉈���ɂ����āA�����A���Z�̓��̉������Ɉʒu���Ă���B���T���̂Ƃ���Ő�B���n�������A��̃u�i�т�[�����ނ��̔������k�J�ɂ́A������ƌ��t�ł͌����s�����Ȃ��悤�ȉ���������������ꂽ�B�k�J����w�i�ɂ����I�V���C�����蕨�̖��T���A�����Č��n�I�Ȍi�ςƋ㔪�x�̌��������I�V���C�Ŗ������劘������߂��Ă��炭�i�ނƁA�����s���~�܂�ɂȂ����B�O���ɖڂ����ƁA�V��������̏h�������Ă���B�������I�ꉷ�����B�ǂ����A�t�߂̑�ɊI�������������Ă��邱�Ƃɂ��̖��͗R������炵���B�͎̂����̓����ꂾ�����Ƃ������̉���́A��͂�A�����тɈ͂܂ꂽ�I�V���C�Œm���Ă��邪�A����̗���f���Ă��A���܂ł͓������̂Ȃ��ł����Ƃ����h�ȉ���h�ɂȂ��Ă���B�܂�����̃n�V�S���Ƃ����v�������������A�[���������Ă������A�܂���������ł������獢��̂ŁA�I��A�劘�A���T���̎O�̉���ɂ��ẮA�Ƃ肠�����h�̕��͋C�������O���璭�߂Ă��܂����Ƃ������ƂɂȂ����B
�@�Ăё劘����A���T���̑O���߂��A�c���x�ɑ����o�āA�u�铒�E�߂̓���������v�Ƃ��邳�ꂽ�ē��̑O�܂ŗ����Ƃ��ɂ͂�������������Ă����B��������͒ʂ�߂��悤�Ǝv�����̂����A���܂������ƂɁA�Ŕ́u�铒�v�Ƃ���������������X�̐S�𑨂��ĕ����Ȃ��B�u���v�Ƃ�������ɂ��Ă����������Ȗ���Ă��܂��Ƃ��Ɠ����S����ԂŁA�ē��̎w�����̗ѓ��ւƂ͂����Ă��܂����B�����A��B��ւƉ���A���n���đΊ݉����ɒ߂̓����ʂւƂÂ����̗ѓ��ɂ͈ӊO�Ȃقǂɖ����������B�܂��Ȃɂ����A���̗ѓ�����U��������H�c��x�̎p���f���炵�������B�����̊��Ⴊ�Â܂肩�������X�̎��X�̗Ƃ��܂����a���āA�������Ȃ��ɂ������ȕ��͋C�������o���Ă���B��B�쉈���̓��H�e�̐[���ؗ��Ɉ͂܂ꂽ���n�ɐl�ڂ�E�Ԃ悤�ɌQ�����鐅�m�Ԃɂ��A���̒n�Ȃ�ł͂̕���Ɖ��䂩������������ꂽ�B
�@�߂̓��ɒ������̂͗[���Z�����������B�K��邨�q�����\�����Ƃ݂��āA�L�����ԏ�ɂ͑�^�o�X���܂߂Ă��Ȃ�̐��̎Ԃ��Ƃ܂��Ă����B�ό��p���t���b�g�Œ��ׂĂ݂�ƁA���̒߂̓��͓������̂Ȃ��ł͍ŌÂŁA�H�c�ˎ卲�|�`�����ȗ��A��X�̔ˎ�̓�����Ƃ��Ēm��ꂽ���Ə�����Ă���B�J���ȗ��O�S�\�N�Ƃ������̗��j�𗠕t���邩�̂悤�ɁA�R������h���Ƃ����ɂ킩�闧�h�Ȓ������̌������A�����̍L���ʘH�����ނ悤�ɂ��ĕ���Ō������B�����܂ŗ�������������ɋA���͂Ȃ��B���R�����Ђƕ��C���т悤�Ƃ������ƂɂȂ����B
�@�����A�Ԃ��~��āA���E���ꂼ��̒��Ɂu�{�w�ߔT���v�A�u�铒�ߔT���v�ƋL���ꂽ�Ŕ̊|����Õ��Ȗؑ���̖�������낤�Ƃ���ƁA���A��̓����q�͌ߌ���܂ł����t���Ȃ��Ƃ������ӏ������ڂɂƂ܂����B�������肵�Ă�������͎Ԃɖ߂肩�����̂����A�l�Ԃ��߂��ƌ�����Ƃ悯���ɋC�ɂ͂Ȃ��Ă���B���������������܂����v���ɂ����Ȃ����O�ŗl�q�����������Ă���ƁA���܂��h�̊W�҂炵�����N�̒j�������q�𑗂��Ē��ԏ�Ɍ��ꂽ�B�Ȃ�ׂ��Ȃ炻����������i�ɗ��肽���͂Ȃ������̂����A���̃`�����X���������ɂ͔���i����ނ����Ȃ��ƁA�����Ɏ��͌��S�����B�����āA���̒j�̐l���ЂƂ�ɂȂ�̂�҂��Ă���A���̓r���A�}�ɒ߂̓��̎�ނ��v�������Ăӂ���Ƃ���Ă����̂����A�����t�����Ԃ͌��܂łƂ������ƂȂ̂łƂĂ��c�O���Ƙb�������Ă݂��B
�@���̑��肪�߂̓��̎x�z�l�A�����a�u�������͓̂V�̗S���ƌ����ق��Ȃ��B��������́A�ǂ������悲��ĉ������Ȋi�D��������X���Ƃ����b��l�q���Ȃ��A�����ɓ����ł���悤�X���͂����Ă����������B�������A�������͂���Ȃ��Ƃ��������B�Ȃ��\����Ȃ��Ȃ��Ă͂������A�����͂����t�ɊÂ��āA�̂̂��a�l�Ɠ����C���ɂЂ��点�Ă����������Ƃɂ����B��������ɂ��ƁA���œ��A������q�̎t������ߐ�̂́A���܂�q�̕��X�ɂ�����艷��ɂ͂����Ă����������߂̔z����A���v��ɑ����s�R�҂ɑ�����̂��ƂȂ̂��Ƃ����B
�@�傩��܂������ɉ��ւƂÂ����̍���ɂ́A���Ă͔˂̌x��̎����l�߂Ă����Ƃ����{�w�������̎p�����܂����߂Č����Ă���B����́A�O�S�N�ȏ�̕���ɑς��Â����Ƃ��������Ȋ������̒����������B�E��̌����͂���ɂ���ׂ�����ƐV�������肾�������A��͂�ꕔ�ɔ��ǂ�z�����ؑ��̒����������B�������ɂ͂��܂ꂽ�ʘH�̓˂�������ɂ͉������������Ăė���铒�̑�̐����������āA���̐����ɂ����鋴��n���Ă����̂Ƃ���ɌÕ��Ȗؑ��̗����Ƒ�I�V���C���z����Ă����B��X�͂܂��A�{�w�̌����̍ʼn��ɂ���Ǘ��������ɗ�������č�������ɒ߂̓��̗��j�̊T�������������A���̂��Ƃ����ɓ��ɂ��点�Ă��炤���Ƃɂ����B
�@�����͍����A�����A���̓��̎O���ɕ�����Ă���A�e���̓��͂��ꂼ��ɐ��قȂ��Ă����B���͕\�ɂ��ƁA����ł͂��邪�����ۂ��F�̍����́A�g�̂��c���牷�܂�i�g���E���������E�Y�_���f��A�����F�̔����́A�������ׂ��ׂ��Ă��銴���̊ܗ����E�i�g���E���E�J���V�E���������E�Y�_���f��A�����Ċ�a��_�o�n���̕a�C�ɑ��������Ƃ������̓��́A�d���E�H���������f�Ƃ������Ƃ������B���łɗ[�H���ɂ������Ă����������A���Ȃ�̐��̔��܂�q������Ǝv����ɂ�������炸����ɂ͑��ɐl�e�͂Ȃ������B�Ɩ���}�����������ɂ͂قǂ悭���C���������߁A�Ȃ�Ƃ��������͋C�ł���B��X�͂܂������ɂ���A���ꂼ��Ɉ����U��Ԃ�Ȃ���g�̂����߂��B�Ȃ�قǁA����҂����ɑ̒����ق��ق����Ă��āA�����܂��ɔ�ꂪ�Ƃ�銴���ł���B
�@���炭���āA����ǂ́A�����ׂɂ��锒���ɂ͂����Ă݂��B�K�x�ɗ��������܂������炩�ȓ��́A�u���ɂ₳�����v�Ƃ����\�����҂�����ŁA�畆���G�����Q�������B�܂���ʂ̕ւ�����߂Ĉ�����������ɁA�喼����������ȉ��n�܂ł͂�铒���ɂ���Ă����Ƃ����̂��A�Ȃ�قǂƂ��Ȃ����銴���������B����̃n�V�S�ł������ɂ�������ꂪ�ł��̂��A�n�ӂ���͂���������Ƃ��������ɂ���Ȃ����ē����炠����Ƃ������Ƃ������̂ŁA���̂ق��́A�����ɂЂƂ藁�����łāA�߂̓��̊ŔƂ������ׂ���I�V���C�Ƀ`�������W���邱�Ƃɂ����B
�@�W�������ʑS������S�I�I�V���C�̕��ő��ʂɑI�ꂽ�Ƃ��������̂��Ƃ͂����āA����ȋ����╗�C���Ƃ܂�������ɔ������炩�Ȃ��̓��́A�z���ȏ�ɓ���S�n���悩�����B�K�C�h�u�b�N�̒߂̓��̏Љ�L���ɋU��͂Ȃ��A�݂�݂锧�������Ԃ��Ă���悤�Ȋ����ł���B���́A�M�����ʂ邭���Ȃ����������̓������ɖ������Ȃ���A�������Αg�݂̗����̉��ł����Ɩڂ��ނ�A���Ζ���悤�ɂ��Ă����ɐg���䂾�˂Â����B
�@���炭����ƁA�ˑR�����肪���������Ȃ�l�̓������p�ɂɂȂ��Ă����B�}�ɖ��邢���C�g����E�O�����A�����҂��Ă������̂悤�ɁA�^�I���ŋ����牺�����e���r�^�����g���̎Ⴂ�������M�̒[�Ɍ��ꂽ�B�f�B���N�^�[�炵���l���𒆐S�ɁA�r�f�I�J������W���}�C�N�����������l�̒j�����Ȃɂ��ł����킹�����Ă���Ƃ�����݂�ƁA�ǂ����Ȃɂ��̎B�e���n�܂�炵���B�����������邤���Ɍ����l�炵���l�e�������A����ɂ������l���A��͂艺���g�������^�I���ʼnB���������������p���������B
�@���̂ق��͊��S�ɓ����炠����^�C�~���O���킵�Ă��܂����B�E�����ߗނƃ^�I����u�����I�V���C�e�̊ȈՒI�̓��C�g�A�b�v����Ă��܂��Ă���B�����̎Ⴂ�������܂ސl�X�̎����̂܂��ɁA���C�g�A�b�v���ꂽ���N�j�̃X�g���b�v�p�����炷�ȂǁA�����ɂ��Ȃ�Ȃ��B�����瓒�����������Ƃ͌����Ă��A�������ɂ̂ڂ��C���ɂȂ��Ă͂��Ă������A�����͂����Ɖ䖝���邵���Ȃ��ƁA������o���ē��M�̒��ɍ��荞�B�킽���̎p�ɋC�������f�B���N�^�[�́A��u�A�u�悯���ȓz������킢�v�ƌ�������̕\������������A�قǂȂ����̎q�����������ɂ���A���ǂ��̂܂B�e���n�܂����B�ǂ����A��B�n���̃e���r�ǂ̉���T�K�ԑg�̎B�e�炵�������B
�@���̂܂ɂ��I�V���C�̎��ӂ͂��Ȃ�̐l������ɂȂ����܂����B�Y��ȏ��̎q�����Ƃ̍����Ƃ����]�O�̂��V���ĂƂ����āA�̂̂��a�l�C���ɂЂ���ɂ͊i�D�̓W�J�ƌ����Ȃ����Ȃ��������A�����܂Ől�ڂɂ��炳���ƂȂ�ƁA�����������ł��������Ȃ������B���́A�Ȃ�ׂ��J�������牓���l�ڂɂ��ɂ����I�V���C�̋��ւƓ��̒����悤�Ɉړ����A�Ђ�����F��悤�ȋC�����ŎB�e����i������̂�҂����B�̂ڂ������ē��̒��ŋC���������A�䖝������Ȃ��Ȃ��Ă��������яo���A�ԊO�̃X�g���b�v�V���E�������邩�̌��f�𔗂���O�ɎB�e����������x�~���ꂽ�͍̂K���������Ƃ����ق��Ȃ��B�����ۂ��A����Ȃ��ƂƂ͂�m��ʓn�ӂ���̂ق��́A�ЂƂ�Ԃ̂��ɗ������܂܁A����߂��C�ɂȂ���A���肶�肷��v���Ŏ��̋A���҂��Ă���ꂽ�炵���B�v��ʓW�J�ɑ喼�C����������߂̓��̒T�K�́A���̂悤�ɂ��Ė��ƂȂ����B
�@�������ł̘I�V���C�̃n�V�S�Ɏv���̂ق����Ԃ��₵�Ă��܂������߁A�����ɂł��Ƃ��ɂ͂����������X���Ă����B�c��ΔȂɌ��������̂ǂ����ŔӔт̐H�ނ����߂����ł����̂����A���������ƂɊJ���Ă��邨�X���ǂ��ɂ�������Ȃ��B�d�����Ȃ��̂ŁA������x�p�ٕ��ʂւƈ����Ԃ��A�悤�₭�������z�J�z�J�ٓ����ɔ�э���ŕٓ��𒍕��A�Ӕтɂ������B
�@�c��ΔȂɂł��̂͐^�钆�߂��̂��Ƃ������B�Ί݉����̓����E���ɑ���Ȃ���A��X�͎Ԃ𒓂߂Ė���̂ɂӂ��킵���ꏊ��T���ɂ��������B�܂肩��\�Z��̌�����V�����ɏ����Ă������߁A�c��̌Ζʂ�Ί݂̎R���݂������̂Ȃ��ɂ�������ƕ����ыP���Č������B���������Ƃ��̓c��ɂ͂�����Ƃ����z���o���������B���܂���\��N�قǑO�̈�㔪�l�N�̔����\�����̂��ƁA���͓��{��̐��[���ւ邱�̌̒P�Ɖ��f�V�j�ɒ��킵���B�l��O�E�l���[�g���Ƃ������̌��O��̐[���ƁA�����ɂ��Ƃ��������x�ɖ������ẮA���D���Ƃ��������悤�̂Ȃ����݂������B������������ΔȈ�т̗V�j�͋֎~����Ă����̂�������Ȃ����A���͐l�ڂ�E��ōs�����A�ΐS���炩�Ȃ�����Ƃ���ɂ���Ő[���߂��̊�ꂩ�琅���ɓ������B
�@�c��͋��Ό��ɐ��������Ăł����J���f���ł���B�����x���̂��̂͋ɂ߂č����̂����A�Ί݂��琔���[�g���Ɨ���Ȃ��Ƃ��납��A�̕ǖʂ͂قƂ�ǐ����ɋ߂��p�x�ŗ������݁A�ꖳ���̐��������ւƏ����Ă���B�Ί݂��琔�\���[�g���������ƁA�Â����F�̐��̂ق��ɂ͂������������Ȃ������B�l�S���[�g�����鐅�[����l���Ă݂�Γ��R�̂��ƂȂ̂����A�����ዾ�����Ɍ��邻�̌��i�ɂ͂�����Ƃ������݂��������B���e�炵�����̂͂قƂ�nj�������Ȃ������悤�ɋL�����Ă���B
�@���f�V�j���͉̂��K���̂��̂������B�^�Ă̂��ƂƂ����ČΖʂ̐����͎v���̂ق������A�₽���͂܂����������Ȃ������B�Ί݂𗣂�ĂقǂȂ��A���܂��܋߂���ʂ肩�������V���D�̏�q�����̎p�ɋC�����āA�Ȃɂ��吺�ő������ĂĂ���̂������������A����ȊO�ɂƂ��Ɏx��ɂȂ�悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃɂ��Ȃ��A�Ő[���������Ă̌Ζʉ��f�V�j�͖��������������߂��̂������B
�@�c��ɐ��ޗ��̉��g�A�C�q�P�̑��̗����ؐ_�Еt�߂��߂��A�ΔȂ��l���̎O�����Ėk�݂̌���̐ΐ_�Ћ߂��̒��ԏ�ɒ�������X�́A�����܂ł����Ŗ��邱�Ƃɂ����B������͂��[��ƐÂ܂�Ԃ�A���ɐl�e�͂܂�������������Ȃ��B�Ԃ��~��ČΔȂɂł�ƁA�����ʼn�X��҂��Ă����̂́A���܂ɂ������������ꂻ���Ȃ��炢�ɔ������_��I�Ȍ��i�������B
�@�̓쑤�ɂ�����Ί݂̎R���݂̏�ɂ����������́A�Ζʂ𖾂邭�A�������A�ǂ��܂ł��₳�����Â��ɏƂ炵�o���Ă����B�����āA���炩�ɖ����グ������ȓ�����z�킹��Ζʂɂ́A�O�ւ̎R�X�̉e���t���ɂȂ��Ă�������Ɖf��A�ق���̂̎R�X�Ƒ��ĉ����ċ�����̂̌����ȑΏ̐}���\�����Ă����B�����𗬂��W���F�̉_�̂��߂Ɍ��̌��͍��X�Ɣ����ȐF�����̕ω��������Ă������A���ꂪ�܂��A�ΖʂƂ���ɐڂ��鐟��C�Ɍ����悤�̂Ȃ��ʂ�݂����炵�A��X�̖ڂ�B�t���ɂ����B�����ɕ����ѕY�����e�́A�܂�ʼn�X��l�̍����Β�[���ɂ����Ȃ����낤�Ƃ��Ă��邩�̂悤�ł��������B
�@�[��̌��z�I�ȓc��Ɏ���Y��Č����邤���ɁA���͓ˑR�n�[���j�J�𐁂��Ă݂����Ȃ����B����ȋC���ɂȂ����̂͋v�X�̂��Ƃł���B�}���ŎԂ̃T�C�h�{�[�h����n�[���j�J�����o���ΔȂɖ߂�ƁA�Β��ɏ����˂��o���D������̐�[�ɐw���A���R������n�߂ɁA�r��̌��A���̍����A�k���ȂƁA���X�ɉ��������̓��̉̋Ȃ����h���[�őt�łĂ݂��B�������n�[���j�J�̉��F������ŕ��������̂��A�C�̂�������ł͂Ȃ������̂�������Ȃ��B�c��̂��������������̐��E�ɐ������ꂽ���ƁA��X�͎Ԃɖ߂�A�����̗��H�ɂ��Ȃ��Ė���ɂ����B�����N�̍��ɋ߂������Ǝv���B
�@���͂܂������C�Â��Ȃ������̂����A���̂Ƃ��A�n�ӂ���́A�����ɕ����ԓc���w�Ƀn�[���j�J�𐁂����̎p���X�P�b�`�ɂ����߂Ă���ꂽ�炵���B����A���R�����Ђ��玄�̍�i�W�u���ł̗��H�v�����s����邱�ƂɂȂ�A���̑����n�ӂ���ɂ��������邱�ƂɂȂ����B�����āA���낢��ƌ������ꂽ���ʁA�\���G�ƂȂ��ēo�ꂷ�邱�ƂɂȂ����̂́A�Ȃ�Ƃ��̔ӂ̓c��̏�i�������̂ł���B�n�ӂ���̐S�̂��������G�Ƃ������������Ă���͎��ɑf���炵���A�ǂ��ɂ�����̂��悤�ȂǂȂ��������A����ł��Ȃ��A���ɂ͂��܂ЂƂ����C������ȂƂ��낪�������B���̊G�̍����[�ɂ����āA���������̓c��̌���̕��i�������Ȃ��ɂ��Ă��܂��Ă���������ȕ��̂̐l���́A���������ǂ��̒N�������̂ł��낤���c�c�B

�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
1999�N10��13��
���̘e�����Q�L�i�V�j
�����̉��L�^�B��
�G�E�n�Ӂ@�~
�@�����̉��L�^�B���\�\�`��̌̋����m�����物����s�V�s�������
�@�����͎����ɋN����Ƃ������Ɍ���̐����Ƃɂ��A�����ɐ��P���c����قڈ�����Ă���̌܃L���قǐ����𑖂鍑����Z�܍����ɂł��B�����āA���H�����̂��X�Ŕ������T���h�C�b�`���p�N���Ȃ���A���ĐX�Ƒ啧�x�̈ƕ����z���Ĉ��m���ւƓ������B�[���J�����������X�̗̐��X�����䗧���̏W���ɍ������������Ƃ��A���́A�s�ӂɁA�`�ꂪ����������߂������̂͂��������̈��m���̂ǂ����ŁA���܂��e�ʋ̕����Z��ł���Ƃ������b�����ɂ������Ƃ�z���o�����B�n�ӂ���ɉ��C�Ȃ����̘b������ƁA����Ƃ�������K�˂Ă݂悤�Ƃ��������B�`��̋����͟N�c�Ƃ������̂ŁA���̐�����|����ɂ���Ƃ͎v�������A�N�c�Ƃ����Ƃ������炶�イ�ɂ������肵����b�ɂȂ�Ȃ��B�����ŁA�}篁A�߂��̌��O�d�b����ɓ��̈ɓ��ɏZ�ދ`��ɓd�b�������Ă݂��B����ƁA�����A�`�ꂪ�Z��ł����Ƃ���͈��m���̍r���Ƃ����W���ŁA���܂͂����N�c�Ƃ̎҂͒N�����Ȃ����A�e�ʂ̍��X�ؖΎ����K�˂Ă݂�A�����Ɗ��}���Ă��炦�邾�낤�Ƃ̂��Ƃ������B
�@�W������͂��������ꂽ�Ƃ���ɂ���H�c�����c�ѓS���̍r���w�O�ɎԂ𒓂߂���X�́A���l�̃z�[���ɂ̂ڂ��āu�r���v�Ƃ����w���\�����o�b�N�Ɏʐ^���B�����B�W���̓�����߂��ɂ���ȈX�ǂŐq�˂�ƁA���X�ؑ�̏ꏊ�͂����ɂ킩�����B�W���̂قڒ��قǂɈʒu���鍂������̗��h�ȉƂ��ǂ���炻���ł���炵���B�Ȃ�̑O�Ԃ���Ȃ��Ɉ�ʎ����Ȃ��j��l���K�˂��肵����A��������������т����肷�邱�Ƃ��낤�Ƃ͎v�������A�����͂�������s���ɂ܂����邵���Ȃ��Ƃ��������������B

�@���X�؉Ƃ̌��ւ̃`���C���������A���ӂ�������ƁA�����ɉ�X�͉��ւƒʂ��ꂽ�B�`��̏]�Z��ɂ�����Ƃ����V��v�Ȃ͂ƂĂ����₩�ȕ��X�ŁA�ˑR�̖K�₾�����ɂ�������炸�A��X�͂ƂĂ��������}�������ꂽ�B���ȏЉ�⍡��̗��̓��@�ȂǂɎn�܂銽�k���ЂƂ�����͂��Ƃ���ŁA��X�͋`�ꂽ�������ďZ��ł����Ƃ����Ƃւƈē����ꂽ�B�������ȑf�ȕ�������ł͂��������A���̉Ƃ͐��\�N�̕���ɑς������A���܂͂����₩�ȎG�ݓX�ɂȂ��Ă����B���X�،�v�Ȃ̘b��ʂ��ď�������̋`��̎p��z�����Ȃ���A���������Ƃ��̌Â������Ɍ������Ă��邠�����ɁA�n�ӂ���͎葁�����ӂ̃X�P�b�`�����Ă����������B�n�ӂ���̐S�̂����������̃X�P�b�`������v���[���g���ꂽ�`��Ȃǂ́A�����ŋ����l�܂点�A��傷��L��l�������B

�@����}���˂Ȃ�Ȃ����Ƃ������āA���c��ɂ��݂Ȃ�����قǂȂ����X�؉Ƃ���������X�́A���Ă͋�R�ł��m��ꂽ���m���̏W�����A���m�쉈���ɐX�g���ē���ɂł��B�����āA�ē���ō�����Z�܍��ɕʂ�������A���m��ɉ��������O�����𑖂��č��쒬��ʉ߁A���m�삪�đ��{���ɍ������鏬�q�t�߂ō��������ɓ������B���������𓌔\��܂Ŕ����������Ƃ́A�đ���n���ĕ��l���ւƑ����L��_����k�サ�A����t�߂ō�����Z�ꍆ�ɍ��������B���l�����ӂ̍L��ŗ̖L���Ȕ_�ƒn�т𑖂��Ă���ƁA�S�������A�̓��Ɋ��͂��S���Ă���悤�ȋC���������B
�@���{�C������Ɍ��Ȃ��獑����Z�ꍆ��i�݁A�H�c�����̔��X�����o�ĐX����葺�ɂ͂��鍠�ɂȂ�ƁA�}�ɈÂ��Ȃ�A���������������n�߂��B���Ȃ�̐��̉ƁX�̖��W����W�����������ʂ�߂������A�܂�ōL���d���̒n�т�[��ꎞ�ɑ����Ă���悤�Ȋ����ł���B�ܓV���̂��ƂƂ͂����Ă��A�܂��ߌ���炢�ł��邱�Ƃ��v���ƁA�ٗl�ȈÂ��Ƃ����ق��Ȃ��B�傫�߂̏��X�̑O��ʂ肩�������Ƃ��A���x�������̂����Ă݂��̂����A�ǂ̓X�������肪���Ă��Ȃ����A���Ă��Ă��\������x�ɖ����蓔���Ă��邾���ŁA�Ȃ�Ƃ����Â��B�Ȃ�炩�̗��R�ŁA�F���\�����킹�ߓd�ł����Ă���̂��낤���ƍl��������������A�ǂ���炻���ł��Ȃ��炵���B���Ԃ�A���̒n�����L�̋C�ۂ̊W�������āA�N�Ԃ�ʂ��Ē��ł��Â����������A�l�X���������肻��Ɋ���Ă��܂��Ă��邹���Ȃ̂��낤�B���������A���ĒÌy�����̐��C�݂𗳔Ɍ������ė������Ƃ����A����Ƃ悭�����A�Â��҂������i���ǂ��܂ł������Ă����悤�Ɏv���B�����A�����ĕt�������Ă����ƁA���̗J�����܂Ɠ��̈Â��̉��ɂ́A���炩�Ɉ̑�Ȃ��̂ݏo���͂���߂��Ă���̂��B
�@�Ԃ͂₪�ė�������̏W���ɍ������������B�Ⴍ���ꍞ�߂����_�ɕ����ĎR�e���������Ȃ��������A���̒n�̓�����тɈʒu����R�n�́A�L��ȃu�i�̌����т�L���邠�̔��_�R�n�ł���B���̎��R�����E���R��Y�Ɏw�肳��A���r���𗁂т邱�ƂɂȂ������_�R�n�́A���{�C����₦�ԂȂ������鑽���ŗ���ȑ�C�̂������ŁA�M�d�ȓV�R�u�i�т����Ԃ��Ď���ނ��Ƃ��ł����̂ł��낤�B�Ɍ�����A�C���A�C���A�n�`�̎O�҂����ւ������Đ��ݏo�����̈Â��������A���_�R�n�̖L���Ȏ��R�ƁA���̒n���ɓ��L�ȕ����̈�Ă̐e�Ȃ̂ł�B
�@�\��ł͗������̏W���t�߂ō����ɕʂ�������A���_�R�n�̖k���𓌐��ɑ���O���ѓ��ɂ͂������ł����̂����A��������������A����������������܂ōs���āA������̕s�V�s�������K�˂Ă݂悤�Ƃ������ƂɂȂ����B�������̏W���̖k���ł́A���{�C�Ɍ������ė��n���R�u��ɔ���o���Ă���B���̔����̖k���̓˒[�Ɉʒu����̂�������ŁA�����̈�ӂɂ͗��D���Ȏ҂̊Ԃł͗L���ȘI�V���C������B
�@�����������ɐ����A�Â��C�ʂ��疶��̗�C�̐����オ��䄍�i�ւȂ��j���̊����o�ĉ�����̕s�V�s������ɒ������̂͌ߌ�O�������������B���Ȃ�傫�ȉ���z�e�����قǂ��������A��X�͂���ɂ͖ڂ����ꂸ�A�����̃z�e���̗���ɂ����ӂ̒��ԏ�ɎԂ𒓂߂��B���F�̋�ƊC�̐ڂ��邠���肩��₦�ԂȂ��N���鎼������C�́A�����܂ł��₽�������ďd���������B
�@���ړ��Ă̕s�V�s������̘I�V���C�́A�g���𔒂��t�������Ȃ��獂�g�̊�r��̂����Ȃ��Ɉʒu���Ă����B�킸���ɖ��J���܂����₽�����ɐg��k�킹�Ȃ���A��ӂ̊�`���ɘI�V���C�ɋ߂Â��ƁA�w�����̎�҂���l�œ������Ă���Ƃ��낾�����B��������q�˂�ƁA������Ƃʂ�߂Ȃ̂ŁA�����̂��̊������ƁA�������g�̂����߂Ă���ł�悤�ɂ��Ȃ��ƕ��ׂ��Ђ��Ă��܂��������Ƃ����Ԏ����߂��Ă����B�s�V�s������ɂ͂������������Ŗ����k�܂����Ƃ����̂ł͟����ɂ��Ȃ�Ȃ����A�����œ������������肵����A���ꂱ���I�V���C�ʂ̖��������Ă��܂��B�ӂ���������X�́A�f�����ߕ���E���A�J�ɔG��Ȃ��悤�ɂ����M�̂܂��̊�̂����܂ɉ������ނƁA��}���ł����̒��ւƔ�э��B
�@�́A�ׂ��ȗ��q�̐ԓy��n�������悤�ȐF�̊ܓS������ŁA�������ɓS�K�̂悤�Ȃɂ��������A�Ȃ߂�Ƃ��Ȃ肵����ς������B�╗�̂��߂ɐg�̂��₦�Ă������Ƃ������āA�͂����Ă����ɂ͂ʂ邢�Ƃ��������͂��Ȃ��������A��q�̌��t�ʂ�A���������̉���ɂ͈Ⴂ�Ȃ��A���炭�����Ă���ƁA�����ɂ͂ł����Ȃ��Ƃ����C���ɂȂ��Ă����B���̘I�V���C���璭�߂闎�z�̔������͗L���ŁA���ꂱ���C�ʂ������F�ɉf����̂����A���̓��͂ƂĂ��[�z�݂̂���悤�ȏł͂Ȃ������B
�@�C���������Ɠ��M�̂������܂Ō������g���ł��Ă��Ă��āA���ɕx�ނ��Ƃ��̂����Ȃ��B�C�ʂ������Ɛ���オ��A�ЂƂ���傫�Ȕg�������Ă����Ƃ��Ȃǂ́A���M���ƊC���ɂ����Ă��܂��̂ł͂Ȃ����Ƃ����v��ꂽ�B��q�̎�҂������炠�����ē�l����ɂȂ������ƁA��X�͂������肢���C���ɂȂ��Ĉꎞ�ԂقǓ��M���̂��Â����B�����Ƃ��A������ł��犦����������A�ł�ɂł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����Ƃ����̂��ނ���{���ł͂������B
�@���Ȃ藣�ꂽ�Ƃ���ɂ���z�e���̑�����A�Ƃ����肱����̗l�q�����������Ă������܂�q�ɂ́A��X��l�̓����p����قNjC�����ǂ������ɉf�����炵���B���炭����ƁA��g�̃A�x�b�N�ƁA�Ⴂ�������܂ޒj���̈�c������Ă����B�����āA����܂łƂ͂܂�ł����Ă���������₩�ȍ�����ԂƂȂ����B���M�̂Ȃ��ŊF�̘b���傢�ɒe���Ƃ������āA���ꂩ��܂��ꎞ�Ԃقlj�X�͓��ɂ���Â����B���ʂȂ�Ƃ����ɂ̂ڂ��Ă���Ƃ��낾���A���̂Ƃ��ɂ������ẮA����Ȋ����͂܂������Ȃ������B
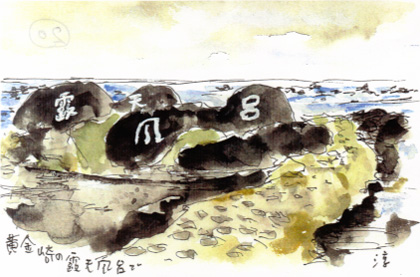
�@�����A�قǂȂ����Ԃ͈�ς����B��i�ƕ������܂�A�J�����������Ȃ������Ƃ������ƁA�������悤�ȗ��ƂƂ��ɁA���s�C���Ȉ�Ȃ��C�̂ق����甗���Ă����B�����C�Ȑl�Ԃǂ��̃w�\��L�����Ղ��Ă��܂����Ƃ����̂��A���l�̍��_�ł������炵���B�����������Ɨ��ɂ�������Ȃ��������q�̂قƂ�ǂ́A�F��Q�ĂŘI�V���C�����яo���A�������ߗނŗ��g���B���悤�ɂ��Ĉ����g���Ă������B����ȑ����̒��ŁA�����A�܂܂�A����ȃw�\�ł��悢�Ȃ�Ί��ō����グ�܂��傤�ƊJ���������̂́A�ނ��A��X��l�ł���B�������镗�Q�ɂ��킦�āA���_�l�̓��ʏo���Ƃ������܂��܂ł����I�V���C�Ȃ�āA���������̌��ł�����̂ł͂Ȃ��B�������蕠�����߁A�ǂ�����Ɠ��M�̒�ɐK����������A���ꂪ�܂��A�Ȃ�Ƃ������C���Ȃ̂ł���B�������Ă܂���X��l�́A���ꂩ��ꎞ�ԂقǁA������̖����I�V���C��Ɛ肷�邱�ƂɂȂ����B�Ȃ�ƎO���Ԃ������ĉ���̒��ɂ�����ςȂ����������ƂɂȂ�B
�@���l�̂��{�������߂ɋL�^�I�����C���y����ł���Œ��ɁA�Ȃɂ��Ȃ����M�̒[���甼���g�����o�����r�[�A���͊�Ȃ��̂Ƃ͂����킹�ɂȂ����B�ڂ̑O�ɁA���߂������Ȋ�������낭���̂悤�Ȃ��̂��k�[�b�Ƃ���Ɍ��ꂽ�̂ł���B�v�킸�������������ɂȂ������A�悭�悭�䂪�ڂ��Â炵�Č��Ă݂�ƁA�Ȃ�ƁA����͈�H�̑唒���̎p�������B����[���ɑ����Ђ����Ȃ���A���M�̐Αg�݂̂������ɂ������݁A������̂ق��Ɏ���L���āA�Ȃɂ���肩����悤�Ȗڂ��ʼn�X�̂ق��������ƌ��Ă���B���̕\��͂ǂ������̔߂������ł��������B
�@�Ȃ�ō�������ȂƂ���ɔ���������̂��낤�Ɖ��b�Ɏv���Ȃ���A���̂��������Ԃ��Ɋώ@���Ă݂�ƁA�ǂ���獶�̗��̂Ȃ��قǂ����߂Ă���炵�����Ƃ��킩���Ă����B���ԂƖk���֖߂�r���A�Ȃ�炩�̎��̂ɂ����ė������߁A��ׂȂ��Ȃ��Ă��̉�����̒n�ɋً}���Ă������̂炵���B�����l��ꂵ�Ă���Ƃ�����݂�ƁA�߂��ɏZ�ޒN�����A���X�a������Ă���̂ł��낤�B���M�̂������ӂ��������ƈړ����Ȃ��琅���̉a�����݁A���܁A�����~�܂��ẮA�тÂ��낢�����A�v���o�����悤�ɉH���͂����Ă݂��肵�Ă���B����ɓ���Ă���ĉH��������̂Ȃ�A�����ɂ��������Ă�肽���C�������������A���������͉�X�̎�ł͂ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��B���̓��̂�邹�Ȃ��v���������E���Ȃ���A�n�ӂ���Ǝ��͂����Ƃ��̗l�q�����߂���肾�����B
�@��������A�̂ق��ɉ�������A���̎p�������Ȃ��Ȃ�ƁA��X�͖����̂܂܍Ăѓ��̒��[���ɐg�߂��B���̒��ɓ����ĎO���Ԃ��߂��悤�Ƃ��Ă����B������O�������A���J�̂��܂�����������Ƃ����Ă��A���ɂ�����ςȂ��ŎO���Ԃ͂���܂�ł���B�������A���̂���܂�Ȃ��Ƃ��A��X�͂Ƃ��Ƃ�����Ă̂����̂������B�������傶��ɉ��̂��A�������J���������܂��Ă��Ȃ���A�l���Ԃ̋L�^�ւ̒���ƂȂ��Ă�����������Ȃ��B�����킢�Ƃ������A�����J�����������̂ŁA��X�͑�}���Ŋ⌊����������肾�����ߕ������₭�g�ɂ��A�悤�₭�ԂւƖ߂����悤�Ȃ킯�������B����Ɋ܂܂�鉖���ƓS���̂����Ŕ����ׂƂ��������������A�l�Ԃ̉��Ђ����ł����̂łȂ������A�܂��܂��Ƃ������̂������B
�@�Ԃ̉^�]�Ȃɖ߂�A�G���W���������Ȃ��������x�g�ł�����̂ق��������ƁA�����قǂ̑唒���̂��т������Ȃ�����p���ڂɔ�э���ł����B����͂����Ȃ����Ԃ�҂��Â��Ăł�����̂��낤���A�������̂ق������߂Ȃ����H�ۂ�Ƃ������ނ��̎p�́A�������������U������ł������B������������₽�������ɂ́A�����̖{�\���������Ă鉽������߂��Ă���̂ł��낤�B�v���o�������̂悤�ɉH�����A�����Ă܂��A���߂���Ȃ��l�q�ʼn�����ɂ����ƌ�����p�ɁA��X�́A���炽�߂Ď��R�E�̝|�̌�������Ɋ�����������肾�����B
�@������̘I�V���C�����Ƃɂ�����X�́A����������̏W���ɂ��ǂ�H����⋋�������ƁA������Ɨׂ荇��䄍얦�̒֎R�����K�˂邱�Ƃɂ����B��葺���c�̂��̏h���ۗ{�{�݂ɍs���ĉ���̃n�V�S�����A�捏�̘I�V���C�Őg�̒��ɂ�������������Ă��܂����Ƃ����킯�������B�藧�����f�R�̏�Ɉʒu����֎R����̑�W�]���C�́A�V�䂪�J���ɂȂ����ߑ�I�ȑ���ɂȂ��Ă��āA�ቺ�ɍL����C�̌i�ς��Ȃ��Ȃ��̂��̂��������A�����҂͉�X��l�����Ƃ����Ȃ�Ƃ��ՎU�Ƃ����������B���̎{�݂͂��Ȃ�傫���A���肻�̂��̂��ߑ�I�łƂĂ����h�Ȃ��̂Ȃ̂����A�v�f�Ƃ͈Ⴂ�A���܂ЂƂo�c�����܂������Ă��Ȃ������ł���B�����炭�́A���Ă̑S���I�ȑ��������u�[���ɏ���Č�������A���E���R��Y�ɂ��w�肳�ꂽ���_�R�n�̃u�i�̌����т����w�ɂ���Ă���ό��q�č���ł����̂ł��낤���A���ʓI�ɂ͂��Ȃ�v�Z���͂���Ă��܂����Ƃ������ƂȂ̂��낤�B������A�W�̐l�ɂ��̂ւ�̂��Ƃ����肰�Ȃ��q�˂Ă݂�ƁA������̑z���ʂ肩�Ȃ�̐Ԏ��Ȃ̂������ŁA���c�{�݂����炢���悤�Ȃ��̂́A���ꂪ���Ԃ̎{�݂Ȃ�Ƃ����ɕ�����Ă��邾�낤�Ƃ������Ƃ������B
�@���ǁA���̓��̖�́A�֎R���炻�������Ȃ��Ƃ���ɂ��铹�̉w�ŎԂ𒓂߂ĎԒ��������邱�ƂɂȂ����B���J�̍~��Ȃ��ŔӔт������ĐH�ׂ��̂����A�����������Ă������Ƃ������āA�ƂĂ���������������ꂽ�B�\�ꎞ���ɂ͖����A�Q�ƂȂ����̂����A������̔����͍����ǂ����Ă���̂��낤�ƍl�����肵�͂��߂�ƁA�ǂ����Ă��ڂ��Ⴆ�Ă��āA�Ȃ��Ȃ��ɐQ�����Ƃ��ł��Ȃ������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
1999�N10��20��
���̘e�����Q�L�i�W�j
���_�R�n�ƌΔȂ̌���
�G�E�n�Ӂ@�~
�@�����͔�r�I�x�߂̌ߑO�㎞���ɏo�������B����ƈ���ēV�C���悩�������A������Ȃ����A���͒W�������������B�������̏W�����甒�_�R�n�̖k���𑖂�O���ѓ����o�Đ��ډ��ɔ����悤�Ǝv�������A�ѓ�������߂��ɁA�[���c��Ɠ��H����̂��߂Ȃ��ʍs�s�\�Ƃ̌x���\�����Ȃ���Ă����B��̂��Ƃ��܂�����܂œ˂�����ŁA�킸���ȉ\���ɂ����Ă݂����Ȃ��͂Ȃ��������A�ߋ��ɓ�A�O�x���̗ѓ��𑖂������Ƃ̂��鎄�́A��Ԃ��悢�Ƃ��ł�����ςȈ��H�ł��邱�Ƃ�m���Ă����̂ŁA�����ɂɓP�ނ����ӂ����B
�@���Ƃ́A�ܔ\���̑���C�����ɖk�サ�A�[�Y�A�吣�˂ƌo���˃P����ʂւƔ����邵���Ȃ��B���͍����ɎԂ�߂��ƁA�O�C�ƃA�N�Z���ݍ��B���₩�ɐ��ꂽ��̂��Ƃł���ɂ�������炸�A�ԑ�����ɍL������{�C���A�ǂ��ƂȂ��A���тт����F�ɋP���Č�����̂́A�ߑO�̑��z���E��̗��n������˂�����ł��Ă��邹���Ȃ̂ł��낤���A����Ƃ��A�P�ɐS���I�Ȗ��Ȃ̂ł��낤���c�c�B
�@����~�̊��Œm�����ː�����܂���Ă��炭����ƁA�ߑO���ɋS�ʂ�z�킹��R�e�́A�ЂƂ���傫�ȎR�������Ă����B�Ìy�̖��R�A�u��S�R�v�ł���B��S�Ƃ͂悭���������̂ŁA���̒��㕔�ɂ���O�قǂ̊���܂��g�ݍ��킳���āA���낵���ȋS�̊�Ɍ�����̂ł���B�Ìy�̖��R�A�u��S�R�v�Ə��������A����ȎR�����������ȂƎ���Ђ˂���ނ��������낤�B���͂��̎R�A���߂�����⒭�߂鋗���ɂ���Ďp�`���قȂ��Č����邱�Ƃ������āA�ʂ̖��ŌĂ�邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��B����A���̂ق�����ʂɂ͒ʂ肪�����B�Ìy�x�m�Ƃ��Ė������u��؎R�v�Ƃ����A�ǂȂ��ł��A�u�������I�v�Ɣ[���Ȃ���͂��ł���B��؎R�́u�v�Ɗ�S�R�́u�S�v�Ƃ͉��ǂ݂������Łu���v���邱�Ƃ��v���ƁA��S�R�Ƃ����Ăі��̂ق����{���̖��̂������̂ł͂Ȃ��낤���B
�@���łɏq�ׂĂ����ƁA��؎R�́A�k�����̌��쌴�������쑤�̍O���ѓ����ʂ��璭�߂�ƁA�G��ȃR�j�[�f�^�̎R�Ɍ�����B�����̍O�O�����肩�炾�ƁA��������̒��]�Ɠ��l�ɋ��낵���Ȍ`�Ɍ����邪�A���������ł����������蓌�̈�т���]�ނƁA���ڂɂȂ邹���ŁA��͂�R�j�[�f�^�̓Ɨ���Ɍ�����B
�@�قǂȂ��A�˃P�Ԑ̏W���ɓ�������X�́A��������A���_�R�n��b�X�R��т������Ƃ���Ԑΐ�`���ɐԐΗѓ���k��A�O���ѓ��ɓ˂�������Ԑ����瓌�ɐi�H���Ƃ��āA���ډ��ɔ����邱�Ƃɂ����B���߂čO���ѓ��̓��������炢�͑��j���āA���Ă̔��_�R�n�̎��R�̑����̈�[���炢�͖��킢�������̂��ƍl��������ɂق��Ȃ�Ȃ��B

�@�r���̌F�m������t�߂܂ł͕ݑ����ꂽ���K�ȓ��H�������Ă������A���ꂩ�牜�ɐi�ނɂ�āA�ѓ��̓S�c�S�c������̂ނ������A�i�����炯�̈��H�ƂȂ����B���������܂��������ɁA�}�p�x�̌X���Ȃ��č��E�Ɍ��������˂��Ă��邩��n���������B�G���W���͍���ɖウ����l�̂悤�ȉ������āA�n���h�����o�C�u���[�^�̂悤�ɐ₦�ԂȂ��U������̂ŁA���̊��o���Ȃ��Ȃ��Ă��܂������������B���܂��ɁA�f���I�ɃK�[���Ƃ����Ռ����Ƃ��Ȃ��ĎԂ����ɒ��˔�Ԃ��߂ɁA�����オ�����g�̂��V�[�g�Ɍ������@������ꂽ�肵�āA���܂ɂ��������Ƃт����Ă��܂������Ȋ����������B
�@����ȂЂǂ����𑖂�̂͂͂��߂Ă̂��Ƃ��Ƃ��������n�ӂ�������ڂɁA����ł����̓n���h��������Â����B�����킢�Ƃ������A���̂ق��́A����ɗނ��铹�����x�ƂȂ����������Ƃ����邵�A�ȑO�͖ڎw���O���ѓ����̂��̂��A����������ƂЂǂ����H�������L�������邩��A���������Ђ�ނ��Ƃ͂Ȃ������B�ނ��A�ߋ��ɂ���ȑ̌��̒~�ς��Ȃ�������A�r���ʼn����đގU���Ă��܂��Ă�����������Ȃ��B
�@���͂Ђǂ��������A�ԐΌk�J�����̗̔������͊i�ʂŁA���ꂪ�Ȃɂ��̋~���ƂȂ����B���E���R��Y�Ɏw�肳�ꂽ�u�i�̌����т̂��锒�_�R�n���S������͂����Ԃ�͂���Ă���ɂ�������炸�A�����ȃu�i�̗т����̗����ɍL�����Ă���B�����āA�O���ѓ��Ƃ̏o�����n�_���߂Â��ɂ�āA�k�J�͐[�܂�A���������ɂȂ��Ă����B�ڎw���Ԑ��ɓ��������̂́A���O�������悤�Ɏv���B
�@�O���ѓ��̐Ԑ��t�߂́A�ȑO�ƈ���ē����g����������Ă���A���݂����H�g���H�������s����Ă���l�q�������B���Ԃ�A�O���ѓ��S�̂����A�ό��ŖK���Ԃ̒ʍs�̕X���͂��낤�Ƃ������ƂȂ̂��낤�B�Ԑ��̋߂��ɗՎ��ɐݒu���ꂽ�x���\���ɖڂ����ƁA���H����ƏC���H�����̂��߁A���ډ����ʂɂ���葺���ʂɂ��ʍs�s�\���ƋL����Ă����B���E���R��Y�ɂ��w�肳�ꂽ���_�R�n�ő�̃u�i�����т��L����Ǘǐ���������̌�����ɍs���ɂ́A�Ԑ����琼�Ɍ������ē�قǑ傫�ȎR�z�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���݂ǂ̒��x��������Ă���̂��͂킩��Ȃ��������A�ߋ��̋L�����炷��ƁA�ԐΗѓ��ȏ�̐��܂������H�ł������B���̓������čH�����Ƃ����قǂ̂��ƂȂ̂��낤�B�\�Ȃ�Ǘǐ��여��܂œ��荞�݂����Ǝv���Ă����̂����A���ǁA����͒f�O������Ȃ������B
�@�ԐΗѓ��́A�O���ѓ��ƃN���X�������ƁA����ɏH�c�����ɋ߂��Ԑΐ쌹����܂ł̂тĂ���A���̈�т̃u�i�̌����т��͂��߂Ƃ��鎩�R���f���炵���B���ډ����ʂ���O���ѓ��o�R�Ŏ����͂��߂Ă��̒n��K�˂��Ƃ��ɂ́A���̐Ԑΐ쌹����ɂ��Ԃł͂��邱�Ƃ��ł����B�����A���݂͂��̕��ʂւ̓���������d�ȓS�Q�[�g�ŕ�����Ă��āA�Ԃł͐Ԑ������ɐi�ނ��Ƃ͂ł��Ȃ�����A����ȏ�͓k���ɗ��邵���Ȃ��B���E���R��Y�Ɏw�肳�ꂽ���ƁA���R���̈���������Ēn���̗ыƊW�̎Ԃ������ߏo�����ƂɂȂ����̂��낤���A����͓K�ȏ��u�������Ƃ����Ă悢�B
�@���Ƃ��ƁA���̔��_�R�n���͂��ސX���ƏH�c���̂������ɂ͐������H�̊܂݂����������X�[�p�[�ѓ��̌��݂��s����\��ł������B�X���̐��ډ��ƏH�c���̓�����������ƂڂɂȂ����Ƃɂ���āA�����̌o�ς╶���̌𗬂������ɂ��A�n��̂̊��������͂��낤�Ƃ������Ƃ������炵���B�n���I�ɂ݂Ă���Ȃ�̐����͂����J���v��ł͂������̂ŁA�����̏H�c���m�����͂��ߒn���ɂ͎x���҂������A�ꎞ�͌��݂����s����悤�Ƃ����B�����A�S����l�X�̂���������A�M�d�Ȏ��R�����j���Ƃ����������̐���������A��]�O�]�������ƁA�悤�₭���H�̌��݂����~�ɂȂ����o�܂�����B���̈�т����E��Y�Ɏw�肳�ꂽ�̂́A���ꂩ�炵�炭���Ă���̂��Ƃł������B
�@�Ԃ��~�肽��X�́A�V�����˂��Ȃ����ꂽ����̐Ԑ��̂����ɗ����A�[���ɕ�܂ꂽ�ԐΌk�J���ӂ̌i�ς߂�����B�����̎v���ƈ���āA�s��ȃu�i�т�n�ӂ���Ɍ����Ă������Ȃ������͎̂c�O�����A�������������ɁA�����܂ŗ���ꂽ�����ł��悵�Ƃ��邵���Ȃ������B
�@�Ȃ�Ƃ����ډ����ʂɔ�����肾�Ă͂Ȃ����̂��ƁA���������ǂԂ��Ɍx���\���̒��ӏ�����ǂނƁA��������l�E�܃L�����ւ������l���q�X�R�t�߂���悪�ʍs�s�\�ɂȂ��Ă���Ƃ����B�ǂ������Ă��A������x�Ԑ̏W���ɖ߂�A�˃P��ւƂł邵���Ȃ��悤�ł���B�a�X�Ȃ���A��X�͍ĂѐԐΗѓ���߂�͂��߂��B����Ƃ��ɂ͑f�ʂ肵�Ă������A�Ԑ�����O�\���قlj������Ƃ���ɋx�e���炵���{�݂��������̂ŁA���̑O�ɎԂ𒓂߂Ē��H���Ƃ邱�Ƃɂ����B�������̑�ɂ͐��ꂪ�����āA�₽������������Ă���B�܂��͍A�������A���A�����āA�y�b�g�{�g���ɂ��̐����l�ߍ��B��C�͐��݁A�C�����قǂ悭�A��̖ؗ��𐁂������镗���u�₩�ŁA���R�̂悤�ɐH�~���i�B
�@���H��A��X�ȊO�ɂ͂܂������l�C�̂Ȃ����O�n�E�X���̋x�e�{�݂��̂����Ă݂�ƁA���������ƂɁA���ꂪ�Ȃ�Ƃ����h�ȑ���̌����������B�����ŋߌ��Ă�ꂽ����炵���A�Ȃɂ��������^�V�����B������������A��ʂ̗��K�҂ł́A��X��l���ŏ��Ȃ̂ł͂Ȃ����Ƃ����v��ꂽ�B���͂������肵����K���Ă̍\���ɂȂ��Ă��邤���ɁA�R����H�����̑��̕�����ۑ����邽�߂̍L���n�����܂ł���A�����A�g�C���A�����p�䏊�������A����ɂ́A���\�l�͊y�ɐQ���܂�ł���قǂ̃X�y�[�X�����g�[�ݔ����m�ԁA�V�i�̏��~���̕����A������ӂ̌i�F�߂邱�Ƃ��ł��韭�����V���ƁA�����s������Ȃ̂ł���B�������A�펞�����ŊJ������Ă��āA�N�������R�ɗ��p�ł���悤�ɂȂ��Ă���炵���B
�@���炩�Ɍ��~���̗��p�����z�肵���Ƃ�������A���̂������肵�����肩��@����ƁA�~�G�ɔ��_�R�n�ɕ�������l�X�̂��߂̖��l�����̖��������S���Ă���̂��낤�B���ꂪ�[���̂��ƂȂ�A�����ɂ����̎{�݂ɔ��܂邱�Ƃɂ����ɈႢ�Ȃ��B�����łȂ��Ă��A��ӂ����ɔ��܂��Ă��������C���������̂�����c�c�B����ɂ��ē�����Ɍf�����Ă��邱�̎{�݂̖��ɂ��炽�߂Ėڂ����ƁA�u���_����Ɓi���炩�݂��j�v�ƂȂ��Ă���ł͂Ȃ����B�N���l�����̂��͒m��Ȃ����A�Ȃ�Ƃ����������O�ł���B�������A�u���_�R�n�v�ɂ��|���Ă���̂��낤���A���̖��̂̔��Ď҂̃E�C�b�g�ɂ́A�B�X�E�X������肾�����B
�@�u���_����Ɓv�����Ƃɂ��A�O�\���قǐԐΗѓ���������ƁA�u���낭�܂̑�v���w�H������ɒ������B���ł����������Ă������Ƃ������ƂɂȂ�A�Ԃ��~��āA�[���u�i�тɕ���ꂽ�k�J�����̗ѓ����\���قlj��̂ق��ւƕ����������B�u�i�̋��̊Ԃ�D���A�c��ɔ��Ζ����ꂽ����ȓ|�����������݉z���Đi�ނƁA�������\�܃��[�g��������Ƃ������ʖL���ȑ�̑O�ɏo���B��������������������A�܂���̕��ɏ���Ă������ʂɖ��J�ƂȂ��č~�蒍���ł���B�ǂ����āu���낭�܂̑�v�Ƃ�����������ꂽ�̂��͂킩��Ȃ����A���̎��ӂɂ悭�F�ł��o�v���A�����тł�����̂ł��낤���B���̗̂R���͋C�ɂȂ�������ǂ��A���̂�����̌F�����ƈ��A�����킷�\��͂Ƃ��ɂȂ������̂ŁA��X�́A�������悤�ȍ����̂Ȃ��Ŏl�A�ܕ��Ԃ��̑s�ςȑ�Ɍ��Ƃꂽ���ƁA�ԂւƖ߂����B
�@�ԐΗѓ��������Ԃ��A�ĂѐԐ̏W�������˃���̒��S�X�ɂł����Ƃ́A��؎R�̐������R�[�������čO�O�s�Ɏ��郋�[�g���Ƃ����B���E�ɂ��₩�ȃJ�[�u��`���Ȃ�����K�ȃh���C�u�E�F�C�������Ă���B���x���オ��ɂ�Ď��ӂ̒n�`��������ɕς��A�������ɓW�]���J���Ă����B�傫���X�������z�ɋP���f�����t�́A�܂��ƂȂ��S�̐����܂��B�Ԗ��̑������z���ɐ��܂��؎R���̋���Ȋ��́A���l���ɂ��������ԋS�̊炻�̂܂܂ł���B
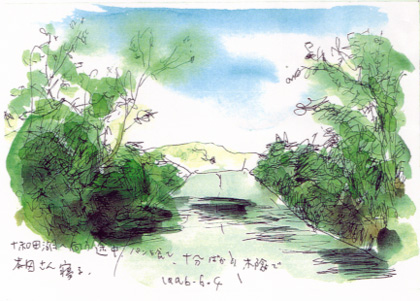
�@�O�O�ɋ߂Â��ɂ�āA��؎R�[��D�����̗��������ς��ɂ悭�����̍s���͂��������S�����L����͂��߂��B�������̓����S�̖{�ꂾ���̂��Ƃ͂���B�����S�̏n���G�߂ɂ͂܂������������邪�A��X�͐Ԃ����̂����ɂȂ���i��z�����Ȃ���_�������̓��𑖂蔲���A�O�O�s�X�ɓ������B�����āA�s�X�̒��S�����������ɒʉ߂���ƁA���Ε��ʂւƃn���h��������B�[�z��w�ɎԂ͈�H���ւƎ������������B
�@���Ύs�ɓ��鍠�ɂ́A�^���ԂɔR���鑾�z����؎R�̉E���ɗ������������B���̋�͈�ʑ����Ȑԍg�F�ɐ��܂��Ă���B��X�͎Ԃ��߂Ă������̐�������C�̉���Ɍ������Ă����B�₪�đ��z���Ő��̌������ɒ��ނƁA�����̋��w�ɂ��āA��؎R�̃V���G�b�g�����z�I�ȐF������ттĕ��яオ�����B�������͒Ìy�x�m�ł���B
�@����Ȃɍ���̂��A�n�ӂ���ł͂Ȃ��A�N���f�G�ȏ���������������Ƃ����̂ɂȂ��A�ȂǂƂ����悩��ʎv������u�]�����悬�������A����Ȃ��ƂȂǂ�m��ʓn�ӂ���́A��������߂��܂܂ł���B����A������������n�ӂ���͓n�ӂ���ŁA�^�]�Ȃɂ���̂����łȂ�������ƁA�l���Ă����̂�������Ȃ��B
�@���Ύs���\�a�c�ւƌ������r���ňꕗ�C���т����Ȃ�����X�́A��������e���ɓ���A�i�s��������̎R���[���ɖ�������K�˂Ă݂邱�Ƃɂ����B�G���W����X�点�Ȃ��炮��Ƌ}�s�ȎR����o��A�R�Ђ��̂�������Ɛ[�����肭�Ƃ���ɂ������ɒH�蒅�����Ƃ��ɂ́A������͂��Ȃ�Â��Ȃ��Ă����B���ړ��Ă̐���̕��͋C�́A�z���ʂ�铒�̖��ɒp���Ȃ����̂������B�����A�c�O�Ȃ��ƂɁA���A��q�͗[�����܂łŁA����ȍ~�͂��f��Ƃ̒��ӏ����������̘e�ɗ��Ă��Ă����B�߂̓��ł̂悤�ȍK�^��������x�Ƃ��v�����������A���̒������������܂��͂����Ȃ��B�[�R�̓��ɖ����͂��������A���낢��Ə������������ʁA�����͂������悭�P�ނ��悤�Ƃ������ƂɂȂ����B�Ăэ����ɖ߂�r���̎R�x�H���牓�]�����؎R�͐_��I�ȋP���̔����ɂӂ��ǂ��A���̎p�͈ꕝ�̊G�������̂��̂������B

�@�\�a�c�Ζk�����̓W�]��ɒ������Ƃ��ɂ͊��Ɍߌ�㎞���߂��Ă����B�w�b�h���C�g�������Ԃ���~��Đ[���ł̒��ւƈ�����ݏo���ƁA����y���ȓV�疳���̐��̌����V�����[�ƂȂ��č~�肩�����Ă����B�v�X�ɖڂɂ��銴���I�Ȑ���ł���B
�@�ĂюԂɖ߂�����X�͏\�a�c�ΐ��݂��܂���ČΊݓ�[�̘a����Ɉړ����A�����̒��ԏ�ň��𖾂������Ƃɂ����B���̒n�ɂ́A�x�d�Ȃ鎸�s�̖��ɁA�\�a�c�ł̃q���}�X�̗{�B�ɐ��������a�����V�̈̋Ƃ��]����肪�����Ă���B
�@�x���Ӕт̎d�x�����A�����H�I���鍠�ɂȂ��āA�悤�₭���̋炨���l���p���������B�����Č�������ɂ�āA��������Ɩ��̂��������\�a�c�̌Ζʂ��W���P�����͂��߁A�ǂ����s�v�c�Ȃ��̌������̋L���̒n�w�[�����ق̂₩�ɏƂ��o�����B
�@���������A���̔ӂ��������Â��Ȍ��邾�����B�܂������Ԃ�ƎႩ�������́A�Ƃ��鏗���ƂƂ��ɖK�˂����̌ΔȂɘȂ�ŁA�����Ȃ�������������ӂ�����Č��߂Ă����B�����āA���̗��ꂽ���܁A�����̉����邩������Ȃ�Ɍ�������́A�W�������ČΖʂɕY���閶�̉��ɁA���������̏��݂��߂Ă��ڂ�ɕ��ԉ����ߋ������߂Ă���B�Ⴋ���̖����̑z���}�Ƃ��܌���ߋ��̉�z�}�Ƃ́A�\����̂ƂȂ��āA�s�v�c�Ȋ��������̋��ɂ����炵���B�u�ĂԂƂ������Ƃ͒ɂ��Ƃ������ƂȂ̂ˁv�Ƃ����Ԏ��ɋ�����悤�Ȍ��t���c�����A���̔��̒����l���̒[��Ȗʉe���A���͉������z���N�������B�@�@
�@�����͌ߑO�������ɘa������o���A�x���ɗ�������ČΔȂɗ����������Y��́u�����̑��v��K�˂Ă݂��B�ǂ������������ł��̒����ɂ��̂悤�Ȍď̂�����ꂽ�̂��͒m��悵���Ȃ��������A�ӂ��悩�łǂ�����Ƒ�n�ɍ����������悤�ȑ̂��̂�����̂̏����̗��`�́A�ނ���u�ꑜ�v�A���邢�́u������̑��v�Ƃł��Ăق����悢�����������B�ނ���Ƃ��Ă͑�ϗD�ꂽ���̂Ȃ̂��낤���A������Ȃ�ł��u�����v�͂Ȃ����낤�ȂƂ����̂������ȑz���������B�����Ƃ��A����́A�|�p�I�Ȋ�������Ȃ����̕Ό��������̂�������Ȃ��B�C�ɂȂ��āA����A�����Y�̔ӔN�̍�i�ׂĂ݂�ƁA���̂悤�Ȏ����ڂɂƂ܂����B
�@�@�\�a�c�̗����ɗ^�� �@�@ ���������Y
�����܂����\�a�c�̉~����Ԃɂ͂܂肱���
�@�@�V�R�l���̕���ł��܂Ƃ��ɂ�����
�@ ���ƃX�Y�Ƃ̍����ŏo����
���̗�������l�@
�@�@�e�ƌ`�̂₤�ɗ����Ă���
�@�@�������悢���̋����������т�
�n��Ɋ���Ă������܂�
�@�@���̌��n�т̈��͂Ɋ��ւ�
�@�@���Ȃ����N�ł��ق��ė����Ă�
�@���̎���ǂނ�����ł́A�u�����̑��v�Ƃ����薼�ɒ��ڂȂ��錾�t�͂ǂ��ɂ��o�Ă��Ȃ��B�܂����������Y�_�Ȃǂ�ǂނƁA�����Y�����̑��삷��Ƃ����ۂɃC���[�W�����͖̂��C�ȉ����̎p�ł͂Ȃ��A���ċ�y�����ɂ������Ƃ��Ă̒q�b�q�������Ƃ��q�ׂ��Ă���B���p�̌�������Ƃ��邠��m�l�̌��ɂ��A�u���w�Q���v�Ƃ����̂��{���̍�i���ł͂Ȃ��낤���Ƃ������Ƃ������B���̐^���̂قǂ͂Ƃ������Ƃ��āA�u�����v�ł��邱�ƂɎ��M�̂Ȃ��Ȃ�������������A�\�a�c�ΔȂ�K�˂Ă��̑��������悢�B���Ȃ炸��u�����v�Ƃ��Ă̎��M�����߂����Ƃ��ł��邱�Ƃ��낤�B
�@�x�������Ƃɂ���ƁA�ՌΑ�W�]���A�q�̌����o�āA�\�a�c�Ζk�݂ɂ��т�����@�ӎR�����ĎԂ𑖂点���B�q�̌����߂����炭����Ɠ��͋}�s�ɂȂ�A�G���W�����������X������Ă͂��߂��B���x���オ��ɂ�A���ΐF�ɉ���悤�ȃu�i�т�����ꂽ�B���炩�ȐV��𐁂��o��������̃u�i�̎��X�̍�����т͂܂��[���c��ɕ����A�n���͂܂����������Ȃ��B�Ԃ��߂č����������u�i�̑�߂Ȃ���A�ӂƍ����̐�ʂɎ����𗎂Ƃ��ƁA�쐶�̏������̑��ՂƂ��ڂ������̂��A�_�X�Ɨт̉��ւƑ����Ă����B
�@�\�a�c�ΐ���̌i�ς��ւ��@�ӎR�W�]����ӂɂ́A��X�̂ق��ɐl�e�͂Ȃ������B�����̊댯������Ƃ����̂œW�]��͗�������֎~�ɂȂ��Ă������A������Ƃ������������������ƌx�������ēW�]��ɗ��ƁA�������Â��ȌΖʂ��ډ��̎��E�����ς��ɍL�������B�͂��߂Ă��̌�@�ӎR�̒����ɑ��Ղ����Ñ�̎R�l�̋C���ɂȂ����悤�Ȏv���������B

�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
1999�N10��27��
���̘e�����Q�L�i�X�j
�������̌��e�̒���
�G�E�n�Ӂ@�~
�@�������̌��e�̒��Ł\�\���b�c�R���牺�k�����ց@
�@��@�ӎR����̏\�a�c�̒��߂i�������ƁA��X�͉������k�J�̍ʼn��ɂ�����q�̌��܂Ŗ߂�A��������ɉ����ĉ��邱�Ƃɂ����B�g�t�Ŗ����������������A�����Ȍk�����ݎ��悤�ɂ��đ������V���g�t�ɂ��Ƃ炸�������B�̖��p�ɑ̓��̍זE�̈�ЂƂ��h��v���ɂЂ���Ȃ���A�\�a�c���܂Ōk�J������A�������甪�b�c�A�����ʂɌ������ɓ������B�r���A�哹����E��ɕ���铹�����ƁA���b�c�A�����]�̂��ƂɌ��n���鍂���ɂł��B�܂��ߑO�㎞���A���ꂽ���̂��炩�ȑ��z�ɖ��邭�P���L��ȕ��i��n�ӂ��X�P�b�`����ԁA���̂ق��͋���n�A�R�r�Ȃǂ��̂�т�Ǝᑐ����ގp�߂Ă����B�������ʂ�Z�����F�ɖ��ߐs���^���|�|�̉Ԃ������������������B
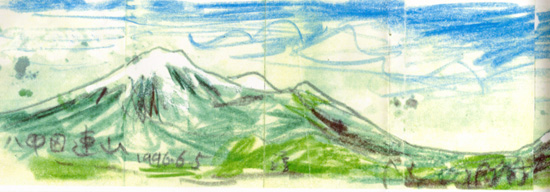
�@�哹�ւƍĂэ������A�J�n�A���q���o�Ĕ��b�c�A��̉��[����D���J�̓��ɓ���ƁA�c��̗ʂ��}���ɑ����Ă����B�Z�����߂Ƃ����̂ɂ��̂�����͂Ȃ��~�̏I��肩�瑁�t�ɂ����Ă̗l����悵�Ă���B�����̎Ζʗy���ɑ����[���т��܂�������E�O���[�g���̐�ɕ����A�������肩��o�߂Ă��Ȃ��B���̎c��̑������炷��Ƃ����̓~�͓��ʂȍ��Ⴞ�����̂��낤�B�ʼn�ɂ��Ȃ��Ă���n�ӂ���̊G�A�u�~�̌��i�v��]���ɑz�������ׂȂ���A�A�N�Z���ݑ����邤���A�Ԃ͎P�������z���A�قǂȂ����b�c�̖����A�_��������ɓ��������B
�@�_�����͒������j���߂������̌Ó��ŁA���b�c�R��K�˂�N�����K���Ƃ����Ă悢�قǗ������h�ł�����B�����g���̉���̔������炩�Ȃ����ł���܂ʼn��x���̔�����������Ƃ��낤�B�ނ��A�����n�R���s������A�����ɂ͓��邪�h�ɔ��܂������Ƃ͂Ȃ��B�ȑO�͑S�̂��Â��傫�Ȋ������̉�����������ɂȂ��Ă������A���݂͉��z����ĐV���������ɕς���Ă���B�����A�K���Ȃ��ƂɁA�X�q�o�ő���ꂽ�Â����������������ԑ嗁��͌��݂ŁA�̂Ȃ���̕�����Ȃ����Ƃǂ߂Ă����B
�@�ƂĂ����ɂ悢��_���̗�����̂��̉����ڂ̑O�ɂ��āA�ꕗ�C���т��ɒʉ߂���ȂǂƂ�����͂Ȃ��B��X�͓��������ƃ^�I���Ў�ɓ��C�̗�������嗁��ւƊ��荞�B�܂��ߑO�\���߂����������Ƃ������āA�����҂͏��Ȃ������B����]�铒���ӂ�Ɋ��������ł������A�Q���A�����ėN�����Ă̓��X�Ƃ��������ؑ���̗������S�g�����߈���킹�Ă��ꂽ���Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B
�@�h�̐H���ŊȒP�Ȓ��H�����܂��_���������Ƃɂ�����X�́A�X�w�ɂ�����Ƃ�����������Ă����Ӓn�ւƏo�A�������牺�k������k�シ�邱�Ƃɂ����B�O���ێR�̓ꕶ��Ղ�K�˂����Ƃ����v���͂��������A���k�����̓˒[��ԍ�ŗ[�z�����悤�Ƃ������ƂɂȂ����̂ŁA���Ԃ̊W��A����}�����킯�������B
�@�����p������ɂ��Ĉ꒼���ɖk�ɂ̂т鍑�����������Ȃ���A���͂܂��A�����Ԃ�̂̂��Ƃ�z���o�����B�����A���̗����p�Y�̃z�^�e�ɂ͂����̓őf���܂܂�Ă���Ƃ�����������X�I�ɕ���A���̔���s�����傫����������ł����B�Ђ˂�����̂̎��͂��̊X�������̂��X���͂��߂Ƃ��鉺�k��т̉������̂��X�ɗ�������ẮA�z�^�e�̎h�g��z�^�e��������قLj����l�i�ł���ӂ��H�ׂ܂������B�ƂĂ����������������Ƃ��������܂��L���̕Ћ��Ɏc���Ă���B���̍��̃z�^�e�ɓőf���܂܂�Ă����͎̂������������A�Ȋw�I�ɍl����ƁA�l�̂ɉe���������̂́A���̃z�^�e���������N�ɂ��킽���ĐH�ב������ꍇ�ł���B��������ǂ�Ȃɑ�������Ă��ꂪ�����Ŏ����̑̂����������Ȃ�Ȃ�čl�����Ȃ��������A����Ȃ��̂��y���ɗL�Q�ȐH�i����퐶���̒��ő����ʐێ悵�Ă��邱�Ƃ��킩���Ă�������A���͏����������Ȃ������B


�@�����s�X���A���R�����ʂւƌ������ɓ���ƁA�قǂȂ����H�̗����͈Â��[���тɕ����A�����ɂ����̂��̂������͋C�ɕ�܂�Ă����B�����������n�̍L���鋰�R���O�̒��ԏ�ɒ��������ɂ͎��v�̐j�͂����ߌ�l�������܂���Ă����B������X�����J���f���A�F�]���R�̖k���ɋ��R���͈ʒu���Ă���B���R��K�˂�̂��������x�ڂ������A���\�a�c�ʼn��������ڂ݂��A���܂͉������e�̐��E�̎�Ƌ��Ɏ������߂Ă�����K�˂��̂́A�����Y��ȏH�̖邾�����B�e��畧���Y���ւđ�ԍ������A�唨���炱�̋��R�ɒ������Ƃ��ɂ́A������͂�������Â��Ȃ�A�@���̋疞���������߂������������Ă����Ƃ��낾�����B�ނ��A���R��t�����͂Ƃ��ɉ߂��Ă��āA�R��t�߂ɂ͑��ɐl�e�͂Ȃ������B���������͍��ƈ���ė����ƒ��ԏ���u�Ă��͌`����̂��̂ŁA���̋C�ɂȂ�Ή�������ł��ȒP�ɍ�Ԃ�ʂ蔲���邱�Ƃ��ł����B�܂��Ԗ��̎c��W��������ƌ��̐��������������d���𗊂�ɁA�����S�O�����ƂȂ������ւƑ��ݓ��ꂽ�B�[��ȗe�p�ɂ�������炸�w������u�J�~�\���v�Ƃ����ٖ���������Ă������̋C��ȏ������A�ނ��A���킸���̂��Ƃɂ��Ă����B
�@���҂̍������܂�Y���Ƃ������R�����j����l�����ŕ����ȂǂƂ������Ƃ́A�C�Ⴂ�������Ǝv���Ă��d�����Ȃ��B�����A�l�b�g�������Đl����ǂ��������Ƃ������c�ЕF�̃G�b�Z�C�ɐG������A���N����A�����悤�ȑ̌������߂āA������_�Ђ̗���A���͂���̕�n�Ȃǂ�钆�ɕ����܂�������Ƃ̂��鎄�́A�����ʒi�|�����Ƃ��Ƃ͎v��Ȃ������B�C��Ƃ͂����Ă��������ɔޏ��̂ق��ْ͋����B���Ȃ��l�q���������A����ł��x�ꂸ�ɂ��Ă����B
�@�Ԓ����Ă���������ꂪ������Ȃ��đ傫�����˂�悤�ɍL����A�@���������̉����l���ɕY���A����ɂ͒n���̂�����������M���������o���Ă��鋰�R���́A���ԖK�˂Ă݂Ă����ɍr���Ƃ�������������B�܂��āA�l�̋C�z�̓r�₦����Ƃ����ẮA�W�������ɕ����Ԃ��̈ٗd�Ȍ��i�ɑz����₷�鐦�݂�����͓̂��R�̂��Ƃ������B������������ɂ�Č����͖��邳�𑝂��A���̒��ɕ����Ԃ悤�ɗ��������̉͌��̖����̐ΐς݂́A���ꂼ��ɐ[����߂�߂�������𗷐l�̉�X�ɐX�Ƒi�������Ă��邩�̂悤�ł������B
�@������Ƃ����e�𗎂Ƃ��Ēn����F�̗���R�̉A��D���ד����A�F�]���R�̌ΔȂɍ~�藧�ƁA�Â܂肩�������Ζʂɂ͑傫�Ȑl����z�킹�錎�e���Y���悤�ɉf���Č������B�ɂ����čL�������̂т�Ήp���̔����̕l�ӂɓ��̑��Ղ����݂Ȃ���������ƕ����Ă���ƁA�ˑR�T�[�b�ƕ����N����A����ɍ��킹��悤�ɂ��āA�J�T�J�T�A�J���J���Ƃ�����ȉ����ǂ�����Ƃ��Ȃ��������Ă����B�ޏ������˓I�Ɏ��̍��r�ɂ����݂��B�������Ɏ�����u�w�ɗ₽�����̂�����̂��o�����B
�@�C�𗎂������Ȃ���s�v�c�ȉ��̂���ق��ւƋ߂Â��Ă݂�ƁA���n�̏�ɗ��Ă�ꂽ���{���̒Z���_��̐�[�ʼn������J���J���Ɖ������ĂȂ������Ă���B�����d���ŏƂ炵�o���Č���ƁA�Ȃ�Ƃ����́A����K�Ȃ��l�X���A���܂͖S�����҂̗�ւ̒����̋F������߂ČΔȂɗ��Ă����Ԃ������B���m��ʕ��Ԃ���Ăɉ�肾�����Ƃ��ɋN����g�ł�����߂��悤�ȋ����́A�n�̒ꂩ��O���オ���Ă��鎀�҂����̔߈����������̙ꂫ�̂悤�ɂ�������ꂽ�B�K���Ȃ��ƂɁA���̂Ȃ�Ƃ���������ʗ��p�j�ɂ�������炸�A���̌����X�ɂ͂Ƃ��ɕs�g�Ȃ��Ƃ͉����N����Ȃ������B���܂�̐}�X�����ɁA���R��тɕY���썰������͂āA�������ɂ��Ē��߂ł����Ă����̂ł��낤���B
�@���̉��ł���ȉ������̏o������z���N�����Ȃ���A���͓n�ӂ���ƈꏏ�ɋ��R���̖�����������B�������͋��R��Ƃ����A�㐢�I���Ɏ��o��t�~�m�ɂ���ĊJ��ꂽ���ŁA�{���͉����n����F�ł���B�������ɍ���͎�t�ł����Ɠ��R�����������������ł̂��Ƃ������B���Ō��C��C�Ƃ��ސl�X�̂��߂̏h���{�݂̘e��ʂ��Ă���ƁA�ȑf�ȑ���́u�Ñ�̓��v�Ƃ�����������̂ɋC�������B�Âт����˂��J���Ē����̂����Ɛl�C�͂܂������Ȃ��B�����`�̑傫�ȓ��M����͂��������Ɠ����肪�����Ă���B��X�͎v�킸������������B���R���ŗN���o�Ă��邱�Ƃ͒m���Ă������A����ȂƂ���ɂ����炦�ނ��̉�������Ȃ�đz�������Ă��Ȃ������B��������߂�����͂Ȃ��Ƃ���ɁA�������܉�X�͂��̒��ɂ͂����Ă݂��B
�@�����A�����ō��������ƂɋC�������B�܂�������ňꕗ�C���т邱�ƂɂȂ낤�ȂǂƂ͍l���Ă����Ȃ����������l�Ƃ��^�I���Ȃǂ����Ă��Ȃ��B�d�����Ȃ����牺���ő̂�@�����ȂǂƘb���Ă���ƁA�E�ߏ�̕Ћ��ɒN�����u���Y�ꂽ�炵���Â����{�^�I���̐�[���c���Ă���̂��ڂɂƂ܂����B�����ꂽ�F�ɂȂ��ăp�T�p�T�Ɋ������A���\�Z���`�A�����O�\�Z���`���炸�̕����ʂ�̃^�I���̐�[���������A����ł��^�I���̓^�I���ł���B���ꂼ�V�̗S���Ɗ��X�́A���̃^�I���̐�[���Y��ɐȂ����A�����Ŏg�����Ƃɂ����B�S���I�ȍ��g���̂��Ɖ����������Ă��A����̓��������������f���������K�Ȃ��̂Ɏv��ꂽ�B
�@������y���㏞�Ƃ��āA����������ꏄ��͗\��ɔ����ċ삯����ԂɂȂ����B�厞�����߂������ɁA���ꂩ�痎���߂邽�߂ɑ�ԍ�܂ōs���˂Ȃ�Ȃ��B�Ƃ肠������}���ʼnF�]���R�ΔȂ܂ōs�������ƁA�Ȃ�̂��߂̋��R�w���킩��ʗL�l�̂܂Ԃɋ삯�߂�A�����҂�����ɑ唨���ʂɌ����Ė҃X�s�[�h�ő��肾�����B�u���R�S�ƌ������͂߂����@�Ȃ肯��v�Ɖr�̐l�咬�j���̐Â��ɐ����_�Ȃǂ��̂Ƃ��̉�X��l�ɂ͂܂�Ŗ����̂��̂������B
�@�ܑ��͂���Ă��邪���E�ɂ��˂�R�����^�C���������܂��Ȃ��瑖�蔲���唨�ɏo��ƁA��������Ìy�C�������̓��𐼂Ɍ����Ĕ������邱�ƂɂȂ����B���ւƌX�����z�Ƃ̃J�[�E�`�F�C�X�́A�T���x�c����ւƑ����V���쉈���̍����Ōo�����Ĉȗ��̂��Ƃ������B�قڎ������炢�Ǝv�����ԍ�̓��v�����ɊԂɍ������ǂ������肬��̂Ƃ��낾�����̂ŁA���͎v������A�N�Z���ݍ��B
�@�����Ō����̂��Ȃ��A�����Ƃ����Ƃ��̎��̎Ԃ̉^�]�Z�p�ɂ͒m�l�����̊Ԃł�����Ȃ�̒�]������B�ȑO������Ƃ�����������ĐM�B���[����̋}�s�ŋ����J�[�u�̌������R����҃X�s�[�h�ő��艺�����܁A�n�ӂ�������̉^�]�e�N�j�b�N�̂قǂ͑̌��ς݂������B���̂����������Ă̂��Ƃ��낤�A����Ȃ̓n�ӂ���͕��R�Ƃ������̂������B�����Ƃ��A�����͂����Ă��l�쓮�̃f�B�[�[���G���W�����S���Ԃ́A���Ƃ��ƍ����^�]��z�肵�Đv���ꂽ�Ԃł͂Ȃ��B������A�������s���̎ԑ̂̃o�����X��A���s�\�͂��炢���Ă��A��ʓ��ł͍ō��ł��u�ԓI�Ɏ����S��\�L�����炢���o���̂����x�ł͂������B
�@����ł��A�Ìy�C�����͂���Ŕ����ޖk�C���̓��e���E��ɖ]�݂Ȃ���A�����ւƑ����ɓ����鑾�z��ǂ�������X�����͂Ȃ��Ȃ��̂��̂������B�n���h�������E�ɐ�A�A�N�Z������藧�ĂȂ���A�X�s�[�h���[�^�[�̐j�𗊂�ɑ�ԍ蓞���������Z�肷��ƁA��͂���v�������肬��ł���B��ԍ肪���Ȃ�߂Â������A�s��̘H�n������̏�p�Ԃ�����A��X�̎Ԃ̑O������͂�҃X�s�[�h�ő��肾�����B�ǂ����A�����̎Ԃ��[�z��ǂ��Ė����ʂւƌ����Ă���炵���B�O��̎Ԃ͍��������Ăė[�z�̊X�������������B�@
�@�ǂ�������Ԃꂽ�����̑�ԍ�ɂ͌ߌ㎵���҂�����ɓ��������B�{�B�Ŗk�[�̒n�ł��邱�Ƃ������傫�Ȕ�̌����ɏ��Ă̑��z������̐Ԃ��_�̑т��c���Ē���ł����Ƃ��낾�����B���z�Ƃ̃J�[�`�F�C�X�ɏ������Ƃ����������ƁA����ɔ���������J���ɐg���ς˂Ȃ���A��X�͂������ق��ė����̋O�ՂɌ������Ă����B�Ìy�C�����͂��ޖk���̕��p�ɂ́A���َR�̓����I�ȎR�e����������ƕ������ނ��Č������B
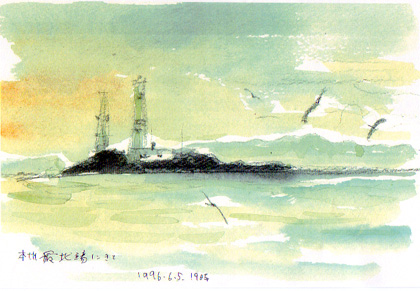
�@�n�ӂ��X�P�b�`������ԁA���͂܂��A���̉s���m���̂䂦�Ɂu�J�~�\���v�Ƃ����ٖ�����������̏����Ƃ̉������̗��̂��Ƃ�z���o���Ă����B�����ƐL�т����̂�����������X���Ȃ���A�������𗤉��̏H���ɗh�点�ė����������̎p�́A�����ɂ������������߂����Ƃ����������Փ����Ⴂ���̋����ɐ��݂����炵�ĂȂ��]�肠����̂������B���̂Ƃ��́A��ԍ肩��唨���o�ċ��R�Ɍ����Ƃ����A����̃R�[�X�Ƃ͋t�̃R�[�X���Ƃ����B�����炻�̑O���̗[���͗����p�����̓��𗤉��s����A���k��������[�Ɉʒu����e����ڎw���đ����Ă����B�G�߂��A��̐��X�����P�����Ăł͂Ȃ��A�ӏH�߂��̂��Ƃ������B
�@�������قǂɐԂ����z������Ɏp���B���ƁA�Ìy��������т̗[��͐_�X��������̉����F�ɕ�܂ꂽ�B���F�ɐ����Ɨ�n�������悤�Ȃ��̋�����Ȃ���A��X�͓�l�����̎������ގ��v�̐j���~�߂��B�s��Ɋm������͉̂����Ȃ������B����A���Ƃ�艽���Ȃ����Ƃ͓�l�Ƃ����m���������A�����炱�����̈ꍏ�ꍏ���ǂ��܂ł��Ȃ��A�k����قǂɔ��������Ƃ��킩���Ă����B
�@�]�_�ƍD�݂̌��t�����A����͑Ό��z�̐��݂������炷��̌��e�������Ƃ������ƂɂȂ�̂��낤���A�l���Ƃ������H��ʂ��Đl�Ԃ��S�̉��ɂ��߂��ޕ�Ƃ͂��Ƃ��Ƃ���Ȍ����Ïk���ꂽ���̂ɈႢ�Ȃ��B�����Ƃ������̂����ЂƂ̌��z�����߂��Ă�u���́v��u�n�ʌ��́v�Ȃǂɂ���Ă͓��邱�Ƃ̂ł��Ȃ�������Ă�͂肱�̐��ɂ͑��݂���B�Ό��z�����ݏo����ƁA�����Ƃ������̏펯���z�������炵�Ă�����Ƃ͏��Ȃ��Ƃ������Ƃ͌����邾�낤�B�ԊO�ŊG�M���Ƃ�n�ӂ���̌��p��������Ō����Ȃ���A���͓��S����ȑz���ɋ���Ă����B
�@�n�ӂ��X�P�b�`���I���Ԃɖ߂�̂�҂��ĉ�X�͑�ԍ���o�������B�����ߌ㎵�������ɂȂ��Ă����B��Ԃ���͘e�����ʂɂ͓쉺�����A�Ăё唨�܂Ŗ߂�A�����s�X���ĎO�O�������ɓ������B���k�����̓��݂��������ɓ쉺���悤�Ƃ�����ł���B���̓��H�́A�����E���쌴�����J�����Ƃƌ����̔p�����������őS���I�ɂ��̖���m����悤�ɂȂ����Z��������˂������ĎO����ʂɂ̂тĂ���B��������Â��Ȃ��Ă��܂����̂ŁA���ӂ̌i�F�͈łɕ�܂�Ă��܂������A�Ƃ����荶��ɍ��X�ƍL���鑾���m�Ɨm����q�s���̑D���̍q�C���炵�����̂��������B�Z���������߂Â����ɂ͂����������Ă����̂ŁA��X�͓��H�e�̃X�y�[�X�ɎԂ𒓂߁A�R���r�j�Ŕ������߂��H�ނ����ƂɊȒP�ȗ[�H�����܂����B
�@�Z��������тɂ͂����Ƃ��傫�ȏ��쌴���͂��߂Ƃ��đ召�̌Ώ�������������B�����m�Ɛ�Œ��ڂȂ�����̂́A���݂ł͂�������ߑ�I�ɐ�������A�������쌴�`�Ƃ��Ēn���̑����J�����Ƃ��x���Ă���B�����p���������{�݂̌��������̎��Ƃ̈�Ȃ̂��B�����ɂ��V���̍H�ƒn�т炵���������̊Ԃ�D���č����O�O�����͓�ւƂ̂тĂ���B�����̏Ɩ��ɍʂ����̍H�ƒn�тƂ������̂́A�X���ȕ������ł̉��ɉB����Ă��܂��������A�����ɂ���Ă͖��ɔ������B�Ăѓ쉺���͂��߂���X�́A�Љ�̕��̕��������ׂĖ��邳�̉��ւƉ����B���Ă��܂�������{�̏ے��̂悤�Ȍ��i�̒����A���G�ȑz�������ɕ����Ȃ��炢�����ɑ��蔲�����B
�@�O���n�̓������߂��A���ˎs�̖k�Ɉʒu����S�Β��t�߂܂œ쉺�𑱂������A�����łЂǂ������ɏP��ꂽ���߁A�����e�̃p�[�L���O�G���A�ɒ��ԁA�����܂Ŗ��邱�Ƃɂ����B��������x�݂Ȃ������܂���������Ŕ�ꂪ�s�[�N�ɒB���Ă����̂��낤�A��X�͕��ꗎ����悤�ɂ��Đ[������Ɋׂ����B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
1999�N11��3��
���̘e�����Q�L�i�P�O�j
�������߂���`����z��
�G�E�n�Ӂ@�~
�@�������߂���`����z���\�\�����C�݂��畽������
�@�������o�����Ĕ����ڂɂ����闂���͌ߑO�����ɋN���A���H�����܂���ƒ����ɏo�������B�����ɋP�������Ԕ��b�c�A�R�̉��i�����ɑf���炵���B�i�F�Ɍ��Ƃ�Ȃ��甪�˕��ʂւƓ쉺���邤���ɓ��H�̏a���Ђǂ��Ȃ��Ă����B���̂܂܂��ƒʋ��b�V���Ɋ������܂ꓮ���Ȃ��Ȃ��Ă��܂������������̂ŁA���ˎs�X���I�ċv���s�ւƌ������A�v�����珬���C�ݕ��ʂɐi�H���Ƃ����B
�@�����m�̍r�g�ɂ����鏬���C�݈�тɂ͑召�l�X�Ȋ�₪�����A�Ȃ��Ă��āA�s�ςȂ��Ƃ��̂����Ȃ��B��X�����ނ悤�ɂ��đł��锒�Q�̂ނ����ɂ́A�������₩�Ȃ��˂�������Ȃ��琟�P��������Ă���B����ƌĂ��ЂƂ���傫�Ȋ��̕t�߂ŎԂ��߁A���̊�������ӂ̐��ۂ��̂����ƁA���J����R���u��������Ƃ���ɑł����Ă���ł͂Ȃ����B��X�͂����Ƀr�j�[���܂����o���čr��ɍ~�藧�ƁA��ʂ̃��J����R���u���̎悵���B���邩��ɐ��X�������炩�Ŏ��ɂ��܂����ł���B����̖��X�`�̋�͂���łn�j�Ƃ����킯�������B


�@����̏W�����獕����ʂւƃ��[�g���Ƃ�ƁA�����C�ݍ��������̈�p���Ȃ�����Ȓf�R�n�т̏㕔�ւƏo���B�^�ɋP���C�ʂ��琂���ɐ藧�����k�R��̒f�R�ɂ́A����҂̍��������������ւƈ������ނ悤�Ȕ��͂�����B��ǂ̂��������̊�p�⋷����I�ɂ�������悤�ɂ��Đ�������⏼�A�V���o�i�V���N�i�Q�A����ɂ͂��̑���X�̟�ؗނ̗��z���ɉf���A�T���O���X���������ڂɂ�ῂ䂢�B����Ȋ⛠���̑����������̔����傾�����A���̖����̊C�̉B�����{�������肰�Ȃ���莦���Ă���悤�������B�@
�@�����Ɖ��������߂邤���ɁA���̐�ǂ̏ォ��ɐg�𓊂��o���A�C�ʂɒ@��������܂ł̐��b�Ԃ̔��Ă��y���ނ̂������Ȃ��ȂƂ����v�������Ă����B�����Ȃ�A�C���ɖv�������Ƃ������[���Ɋ������܂�A������͋��̉a�ƂȂ��ē�x�Ɛl�ڂɐG��邱�Ƃ��Ȃ����낤�B���ہA�ߋ��ɂ����ēˑR�p���������l�̒��ɂ́A���܂����̐���ɖ���҂�����������ɈႢ�Ȃ��B���ɍL���鑾���m�̔ޕ����疞��������H�̖�Ȃǂɂ��̒f�R�̏�ɗ��ĂA�����̂̎���B���������ɑi��������݂肵���̕��ꂪ������̂ł͂Ȃ����Ƃ����������������B
�@�ߑO�\�ꎞ�ɖk�R����o���A�����㔒�������Βf�w�Œm����c�씨���������D�����ɓ���A��ւƌ������ƂɂȂ����B�L���ȏߓ����u���v��K�˂邽�߂ł���B���{�ł͍ŌÂ̒n�w�̎c���茧�̖k��R�n��т́A�Ð��㖖���⒆����̉��̎Y�n�Ƃ��Ė������B�Ȃ��ł���ߕӂ̎R�X�͑S�̂��ΊD�₩��Ȃ��Ă���A���̊W�Ŏ��ӂɂ͑召�̏ߓ��������������݂��Ă���B���������k�ɂ�����Ɠ��ƕ���ŗ��͂��̑�\�i�̓��A�Ȃ̂��B
�@���ɂ͐��ߑO�ɒ������B���̏ߓ����̓A�C�k��Łu���̂������v���Ӗ�����F�업�i�E���C���j�R�̑̓��[���ɗt����ɂ̂эL�����Ă���B�D�V�̂��߂ɊO�͔����Ă����قǂ̏�������������A���̒�����N���o�鐴���͂Ȃ�Ƃ��₽���u�₩�Ɋ�����ꂽ�B�����͐g�k�����o����قǂɔ������A�O�̏����������̂悤�������B�ȑO�͓����̒ʘH�ׂ͍�������p���������Ă��Ă����Ԃ�ƕ����ɂ����������A���݂ł͔���̕��ȕ����ɕς�肷����������₷���Ȃ��Ă���B��قȌ`�����������̏ߓ����⡁A�Β��Ȃǂ߂Ȃ����X�͉��։��ւƐi��ōs�����B�����̉E��≺����Z���F�̐������Ђ��Ђ��Ɖ������������悤�ȋ��������Ăė���Ă����B���Â���₦�邱�ƂȂ������Ă������̐��̚������ΊD�⎿�̌����n�w�����X�ɗn�����A�s�v�c�ȑ��`���̗������Ԃ��̋���ȓ����ݏo�����킯�ł���B
�@���ő�̊�ς͂��̍ʼn����ɖ���傫�Ȓn��ł���B���A���A��O�ƎO�̒n������J����Ă��邪�A�Ȃ��ł��[���㔪���[�g���̑�O�n��́A�_��I�ȃR�o���g�u���[�̐��X�Ƃ������āA��X�̐S���̌��t�ňЈ������B�����ɉ���̃��C�g���ݒu����Ă��邽�߁A��̂ق��܂ł͂�����Ɠ����ʂ��Č�����B�w��������Ƃ���悤�Ȃ����݂̂���F�������B���Ƃ����ď̗̂R���͂悭�킩��Ȃ����A���̒n��̂���ɉ��ɑ������A�̂ǂ����ɗ�������ł����Ƃ��Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��B���ہA��O�n��ΐ[�����肳��ɉ��ɐi�ނƐ[���S��\���[�g���̑�l�n�������Ƃ����B���̓����x�͐��E�ł��L���Ƃ����邪�A���݂͂܂���ʂɂ͌��J����Ă��Ȃ��B����܂łɒm���Ă���ʼn����܂łł����ܕS���[�g���͂���A��ϖ����̑��e���߂����A���̂��̂̑S�e�͉��s���ܐ烁�[�g���ȏ�ɒB���邾�낤�Ɛ��肳��Ă���B
�@��O�n�����̋A��̃��[�g�́A���x�����x���W�O�U�O�ɐ܂��}�s�ȊK�i�̏�蓹�ƂȂ����B�����ɑ����ɂ���������ł���B��������֏�ւƐi�ނƁA�捏�̒n��������͂邩�����ɐX�ƋP���Č������B�@
�@�����o����X�́A���V���̂ق����K�˂Ă݂邱�Ƃɂ����B���Z���N�ɔ������ꂽ���̐V���́A���{�������̌������ɂ���ߓ����ŁA���݂͉Ȋw�ق������˂Ă���B���E�ł����������R�����Ȋw�قƂ����킯�ŁA�ߓ����̐����v���Z�X������������ɂ��ďڍׂɉ������Ă����B�܂��A�����w�A�n�w�A�����w�A�l�Êw���̋M�d�Ȏ�����W�{�Ȃǂ�����J���Ă������B�������甭�����ꂽ�����̓y���Ί�ނ��W������Ă���Ƃ�����݂�ƁA�Ñ�l���̂��璆�ɏZ�݂��Ă������Ƃ͖����ŁA���̈Ӗ��ł͂��̐V���́u�Ĕ������ꂽ�v�ƌ������ق����I�m�ȕ\���Ȃ̂�������Ȃ��B
�@���O�̂��X�Œ��H�����܂������ƁA��X�͊C�����ɑ��鍑���l�܍����ɏo�ē쉺�A�c�V���̂�������O�̐^��C�݂ւ̓��ɓ���A�傫���C�ɓ˂��o�����^��ɗ����āA�ቺ�ɍL����r��Ƒ����m�̌i�ς��y���B
�@�^�肩�炷������ɉ������Ƃ���ɍ����h�ɎO���t������B���̍����h�ɂɂ͈ȑO�Ɉ�x���܂������Ƃ����������A�u�O���t�v�Ƃ������̂̂��ƂƂȂ�����u�O����v�͂܂��ڂɂ������Ƃ��Ȃ������B�ނ��A�������킯�ɂ͂����Ȃ��Ƃ������ƂŁA�Ԃ���~�肽��X�͗т���ׂ���������A�O����W�]��ւƏo���B��O�Ɍ���ꂽ�̂́A�ߐl���ق����E�̉������Ƃ܂���������̋���ȎO�̊₾�����B�C������Џ䍂�ɂ����藧����̒��ł��ЂƂ���傫�Ȃ��̂́A�n���̔e��腖��剤��z�킹���B
�@�܊p�����琅�ӂ܂ō~��Ă��̊�i���y�������Ƃ������ƂɂȂ����̂����A�����������Ċ댯������W�]��̍���z���Đi�ނ��Ƃ͋ւ���Ƃ����x���������Ă���B��u��������킹����X�����A���y�̉������̏����ɂ͍R����A�����ɍ���z���ċ}�ȍד�������͂��߂��B���̐��̉������̂��n�t��������̂�����|�����̂͂Ȃ��B�}�s�Ȋ⓹�̕��������Ȃ�Ȃ��ʉ߂��A�O����̑����߂��ɍ~�藧�ƁA�S�n�悢���̍��肪�@�������B
�@�܂���̊����ň�Ԏ�O�̑��̍L����ꕔ����������I�o���Ă��邽�߁A��ӂ��珬���Ȋ�`���ɂ��̋���̍����̂Ƃ���܂ŗe�Ղɓn�邱�Ƃ��ł����B���炽�߂ĉ����猩�グ��ƁA���Ɍ����Ȍ`��������ł���B��̍����ɉ����ĕ����Ȃ���C�����̂����ƁA���J����z���_�����̗т��₦�ԂȂ��Ă͈������̗���ɍ��킹�Ă����Ɲ��ꓮ���Ă���̂��������B���ꂾ���C�����ɂ��Ă�����A���L�ނ������������Ă��邱�Ƃ��낤�B�C���߂Ă��邤���ɁA������Ɛ����Ă݂����Ƃ����C���ɂȂ������A�܂������₽�����Ȃ����ɁA�����ዾ�ƊC���p���c���Ԃ̒��Ɏc���Ă������Ƃ������āA�������ɂ���͎v���Ƃǂ܂����B
�@����Ƃ͕ʂ̃��[�g���Ƃ��ċ}�Ζʂ����Ԃɖ߂�����X�́A�c�V�̒�������Ɍ��Ȃ��炢�����ɑ��蔲���A�{�Õ��ʂւƓ쉺�����B�����Ȃ�ړI�n�́A���킸�ƒm�ꂽ�����C�ݐ���̖����u��y���l�v�ł���B�������番�������₩�ȓ��������y���l���ԏ�ɓ��������̂́A�ߌ�O���l�\�ܕ����������B
�@���ԏꂩ��т̒�����Ƃ����C�ӂɏo���B�E��ɊC�����Ȃ��珬���Ȗ����܂��ƁA�߂��獷�����ޗz�˂��������Ĕ��X�ƋP����X�������Ă����B�C��ɘA�Ȃ���ї��召�̊�X�́A�ЂƂЂƂ����������Җق��镧�����������̂悤�Ɍ�����B�����āA�����̊��Q�Ɉ͂܂��悤�ɂ��ď����ȓ��]������A���̓��]�̉��ɐ^���ȋʐ�~���l�߂��悤�Ȕ������l�ӂ��������B�ނ��A��y���l�ł���B
�@���̈�т̊C�݂≫�̂ق��ɕ��ԏ����́A���ׂď����ɋP���Ήp�e�ʊ�łł��Ă���B�`���ɂ��ƁA���܂���O�S�N�قǑO�ɋ{�Âɂ����싾�a���Ƃ����l��������K�ˁA�u���Ȃ����y�̂悤���v�Ǝ^�Q�������Ƃ����y���l�ƌĂ��悤�ɂȂ����Ƃ����B���z�ɔ������f����V�R�̊╧�̌Q��ɐS�̒��Ŏ�����킹�Ȃ���A�Ήp�e�ʊ�̔����ʐ���Ȃ�l�ӂɑ�̎��ɂȂ��ĐQ��̂́A���t�ɂ͐s����������������B

�@�ߌ������y���l�������A�{�Â��獑����Z�Z�������ʂ������đ�������X�́A��䑺�̏���ō����O�l�Z�����ւƍ��܂����B�Ԃ͐[���т̒��̓���������Ƃ̂ڂ�߁A�₪�āA���r��R�̓����Ɉʒu����W�����S���[�g���̗��ۓ��ɓ��������B�[����L�̐[�����ݍ��ނ悤�ȐF��ттĊቺ�ɍL����̂́A�`���Ɩ��b�̗���A����ł���B
�@����[�łƋ����������̂悤�ɁA��X�͉���ւ̓����삯�������B����~�n�k�����̓c���n�тɓ���ƁA�����ɂ��`���ɍʂ�ꂽ���j�ƃ��}���̋��炵�����͋C���Y���͂��߂��B���H�̗����ɓ_�X�Ɨ������ԌÂ��ƁX�̂������܂����̂��̂��A���Ԃ�s�ЂƂ̕��ꂾ�Ƃ����Ă悢�B�ۂ�ۂ�Ɠ���͂��߂������̖��Ƃ̖�����߂Ă���ƁA���c���j�����̒n��K�ꂽ����ւƃ^�C���X���b�v�������̂悤�Ȍ��o�ɏP��ꂽ�B

�@���Ԃ��������̉���ň��𖾂��������C�����������A���Ƃɑ����̍s����̓s�����������̂ŁA����͐H���̕⋋�����������ʼn���̒���ʉ߂��邱�Ƃɂ����B����~�n�������ƌ����낷�悤�ɗŐ����L���鑁�r��R�������F�̎c�Ƃɕ����ԗL�l�́A���X�̖��b�̐��܂ꂽ�w�i����X�ɔ[�������Ă��܂肠����̂������B���̑��r��R������Ȃ������A����̎��̒��ɑ��r��̑厩�R���r�������������Y�́A���܂��Ȃ����̎R�[�̑��Ɉڂ�Z�B�푈��^�̎��������đ����̎Ⴂ������ւƋ�藧�Ă��Ȃ̉ߋ��ւ̉����ƁA�q�b�q�������ւƒǂ����ߍ��ȉ^���ւ̍R����̂䂦�̉B�قł��������Ƃ����B
�@�R���ŏC���҂ɋ߂������𑗂��Ă��������Y�̎R�����̂������R���Ƃ����Ƃ���̋߂����߂��A�k���̎x�������ΐ쉈���ɖk��s���ʂɌ������ɂ́A�����������X���Ă����B�@�k��s�ō����l�����ɍ����A����s���߂��鍠�ɂȂ�ƁA�������ɂ����������Ă����B�����e�̃p�[�L���O�G���A�ɒ��Ԃ��A�x�߂̔Ӕт�����ĐH�ׂ����A�����C�݂ō̂��Ă�������̃��J����R���u�̂��A�ŁA�����̊��ɂ͌��\���܂��H���������B�Ӕт��I���A��ۂ悭���ы��Еt����ƁA�Ăэ����l��������ʂɌ����đ���o�����B�@�@
�@��������̍��������Ȃ�̑��x�Ŕ������A�������̒��ԏ�ɒ������̂͌ߌ�\�ꎞ���������B��Ԃ͎��R�ɗ��p�\�ȍL�����ԏ�ɂ́A���ɎԂ̉e�͂Ȃ������B�Ԃ��~�肽��X�͉����d������ɒ������̎Q���̂ق��ւƕ����͂��߂��̂����A����Ȏp��N�������Ă�����A���̎��Əꏊ���킫�܂��Ȃ��쎟�n�����ɕ��ꂩ��������������Ȃ��B
�@�������̎Q���͂��Ȃ蒷������ɂȂ��Ă���B�ĂȂǂɋ}�����ł��̍⓹��o�����肷��ƁA���ꂪ���A���т������ɂȂ�قǂł���B�Q���̗����ɂ͐��̋������������Ɨ������ђ��ł��Â����炢������A���ӂ��[��̈ł̔Z���͂��܂��狭������܂ł��Ȃ��B�ߋ��ɉ��x�������^�����������A�[�邱����K�˂�͎̂������߂Ăł���B���ɐl�C�̂��낤�͂����Ȃ��������A�t�ɁA�l�e�̓r�₦���[�邾���炱���̕���┭��������̂ł͂Ȃ����Ƃ������҂͂������B
�@�����d���ő����̈ł�蕪���Ȃ���������ƕ��������Ɋ�̂ق������Ȃ�Â��ɂȂ�Ă����A���ɐG����̋�C���v���̂ق��S�n�悢�B���Ȃ�⓹���̂ڂ�߂��Ƃ���ʼn��C�Ȃ��������U��Ԃ���ƁA���ؗ����̌����̋��邭�Ȃ��Ă���B�ӊO�Ɏv���đ����Ƃ߁A���炭���̂ق��߂���Ă���ƁA�����̌��ɋ߂��������p�����킵���B���������A�������Q���̍⓹�́u������v�Ƃ����ُ̂������A�قڐ^���Ɍ����ČX���Ă���B����܂Ō�����Ƃ������̌ď̂̈Ӗ���[���l�������Ƃ͂Ȃ��������A�������ɍ����ƋP���𑝂������������߂Ă��邤���ɁA�Ȃ�قǂƂ����v�����N���Ă����B��C������ł��邹�����A�����͑z�����Ă����ȏ�ɖ��邩�����B�����ł��̌��̋���������A���ꂪ�����������炳�������Y��Ȃ��Ƃ��낤�B
�@�z��ʌ����̏����̂������ŎQ����т͂����Ԃ�Ɩ��邭�Ȃ����B���������d���͂قƂ�ǂ���Ȃ��B���ԂȂ�`�o���Ō�̐킢���s�Ȃ����ߐ�Ð�ꂪ���]�ł��鍂��ɗ��������A�������Ɉߐ�̐�ʂ��m�F���邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�`�o�̉��삪���������āA�߂������̖��O�̏��X�ƌ�肩���Ă����A����ɂ��������Ƃ͂Ȃ��������A�c�O�Ȃ��Ƃɂ���炵���C�z�͑S���Ȃ������B���̓�l��ɉ���ɐ̕���ł�������A�˂��Ȃ����ĉ���������邩�킩��Ȃ��A�����Ȃ�����߈��ƃ��}���ɖ������䂪���j�`���������Ȃ����ƁA�`�o�̗삪�h���ł������̂��낤�B
�@�ނ��A���Ԃ����Ԃ���������A������m�����ɂ͗������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��������A����ł���X�͂����Ղ�Ǝ��Ԃ������āA�L��ȋ����̋��X������܂�����B�����łقǂ悭�������炰��ꂽ�������S�R�̗�C���A���킶��Ƒ̓��ɂ��݂���ł��銴���ŁA�Ȃɂ��S�g�̉��ꂪ��|����Ă����悤�Ȏv���������B�ނ��A����̋��F���̂��ɂ������^���A�S�̂��ł����ۂ��ݕی삳��Ă��邻�̑����Ȃ����{�̂�������킯�͂Ȃ������B����ł���X�́A�����̒��ɎW�R�ƋP�������Ԃ��ɂ����̋��F���̎p��z�����Ȃ���A�������̑O�ɘȂ�ł����B
�@�^�钆�̒������w���I������X�́A�Ԃɖ߂�ƁA�[��̍����l��������m�ցA�z�قƓ쉺�����B�����āA�z�ق���ԎR�����ʂɌ��������ɓ���A���쌴�Œr���A�q���ʂւƕ��鍑���l�������ւƎԂ������ꂽ�B���������U�����ɓ��̋珸���Ă��������͂���ɍ��x�ƋP���𑝂��A���ӂ̖�R�𖾂邭�Ƃ炵�o���Ă���B���̂܂ܖ閾���܂ő��葱���悤���Ƃ��v�������A�q�܂ł��ƈꑧ�Ƃ����吴���t�߂ɒ������ɂ͂������ɂ��������Ă����B���v������ƌߑO���߂��Ă���B���������q�ʼn���ɂ͂���ɂ͂��̂�����Ŗ�h�����ق����悩�낤�Ƃ������ƂɂȂ�A���[�ɎԂ𒓂߂Ė��邱�Ƃɂ����B���̌����������X�ƍ~�蒍���Â��ȐÂ��Ȗ邾�����B

�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
1999�N11��10��
���̘e�����Q�L�i�P�P�j
�m�Ԃ������a�ɗ���
�G�E�n�Ӂ@�~
�@�m�Ԃ������a�ɗ��\�\�q���狼���ǂ��둺�R��
�@�����͎������N���A���荇�킹�̐H�ނŊȒP�ɒ��H�����܂���ƁA�����ɖq���ʂɌ����ďo�������B����͂��Ȃ�̋��s�R�łƂ��Ƃ����C�ɓ��邱�Ƃ��ł��Ȃ������̂ŁA�����͂܂��q�ňꕗ�C���тĂ���s��������肾�����B�q�̒��S�X�ɓ��邷������O�ŁA���̎��Ԃ�����������Ă���鉷��͂Ȃ����ƒn���̐l�ɐq�˂Ă݂�ƁA�߂��ɓc������Ƃ����Ƃ��낪����Ƌ����Ă��ꂽ�B�����K�˂Ă݂�ƁA�ЂȂт��ƌ������͂Ȃ�Ƃ��Âڂ�������h�������B�����̎�t���ɂ͐l�e��������Ȃ��̂ŁA����̕��ɂ܂��吺�ŗ��ӂ�������ƁA�悤�₭��炵�����N�̒j�����ꂽ�B�Ƃ肠������l��S�~�̓��������Ē��֓�������X�̖ڂɔ�э���ł����̂́A�����̔ɉh���Â���̕��̔���̍L����L�ƁA���̉��Ɉʒu����ƂĂ��傫�Ȉꎞ��O�̑���̗��ꂾ�����B
�@����͒��a��\���[�g���߂��͂��낤�Ǝv����~�`�����Ă���A���X�Ɠ�������������ڂ̑傫�ȗ�������A�Ǐ�ɔz�u����Ă����B�����ۂ��̂����͐[�̐��F�����Ă���A���������ۂ��̓��͕s�����ȉ����F�����Ă������A�ǂ���̂������K���Ŕ��ɂ��炩���A�����Ȃ��̂����܂銴���ŁA���ɉ��K�������B�͏d����Ƃ̂��ƂŁA�������ʂ͔��Q���Ƃ����B
�@��l�����ŗ������̂��Ȃ���Ԃ��ɑ嗁��S�̂߂܂킵�Ă��邤���ɁA���܂ł͕ǖʂ������ۂ������݁A�^�C���̂������������c�ɔ��������ĕNJG�̐}�����s�N���ɂȂ��Ă��܂��Ă��邪�A���Ƃ��Ƃ͎���̐�[���s���f���炵������̗��ꂾ�������Ƃ��킩���Ă����B���̂��Ƃ��������悭������Ă���̂́A���̗���̒��S���̓���ȑ��肾�����B�~�`�̗���̒����ɐ����p�`�̑��K���X���蔲�����̖��邢��悪�����āA���̒��֒ʂ����͂�K���X����̃h�A�����Ă���B�h�A���J���ē������̂����Ă݂�ƁA�����͔��p�`�̎𗎂������ɂȂ��Ă���A�㕔�͂�͂蔪�p�`�̖��K���X�̓V���ɂȂ��Ă��āA���邢���̌����˂�����ł��Ă����B���܂ł������̔������p�`�̗����͓���₽��ĕ��u���ꂽ�܂܂ɂȂ��Ă��邪�A�����͎a�V�Ȓ��z�ɂ�邻�̑���̂䂦�ɁA��ϕ]���ɂȂ����ɈႢ�Ȃ��B�����o�ČÂтĂ��܂��Ă͂��邪�A�ǖʂɒ���ꂽ�^�C���͋ɂ߂ď㎿�̂��̂ŁA�����I�Ɏc����F�^�C���̐F����f�U�C�����炷��ƁA�����ɕ`����Ă����}���͂���߂Ċi���̍������̂������낤�Ɛ������ꂽ�B
�@��X�́A���́u���̐Ձv�Ƃł������ׂ��c�����ƂĂ��C�ɂ������B�������Âт悤�������ʂĂ悤���A���ɂ��炩�Ȃ��̐��̂ƕς��킯�ł͂Ȃ��B������オ���ĒE�ߏ�ŕ��𒅂Ă���Ƃ��ɓ����ɂ���Ă����ØV�̘b���ƁA�����p�Ƃ��Ă͂��܂ł��q����̐Ȃ̂��Ƃ����B�����A����Ƌ��ɁA������������̋ߑ�I�Ȗq����X�������A���̂�����œc������͂�����Ă��܂����炵���B���݂ł́A�n���̐l�X�ƁA���܂ɖK��鎖��ʂ̈ꕔ�̓��Q�����q���������������ŗ��p���Ă��邾���炵�����A�Ȃ�Ƃ����������Ȃ�������ł���B
�@���C���炠���������ƁA�ٓ��̘V���������L���K�i���̂ڂ�A�l�C�̂܂������Ȃ���K�̑����炱�̏h�̗���̂ق��߂���X�͎v�킸����ۂB�r��ʂĂĂ��܂��Ă͂��邪�L��ȕ~�n���͂邩���̂ق��܂ő����A��L���蕗�̌����Q���Âт�����A�˂Ă���B���̋K�͂��炢���āA�͖̂q�ł���E��𑈂��嗷�ق������ɈႢ�Ȃ��B���N���u����A���̊Ԃ̕���ɂ���ĂЂǂ������l�̌����Q�����߂Ȃ���A���炽�߂ĉh�͐����̂Ȃ炢��z������ł������B
�@�ߑO�㎞�����ɓc��������o���A�傫�ȃz�e���̗������Ԍ��݂̖q���S�X���������ɒʉ߂��A���炭�}���o���Ă����ƁA���̍ד��ɂ��o�ꂷ��u�A�O�̊ցv�Օt�߂ɓ��������B��������o�H�ւƉz�����H�̓r���ɂ��邱�̊֏��ŁA�m�Ԉ�s�͎v�������������~�߂����ƂɂȂ����B�����͂قƂ�ǒʍs����҂̂��Ȃ����������ʂ�̍ד��������ĉz���闝�R�ƁA���̐g���̂قǂ��l�Ɍ��������ꂽ����ł���B
�@�m�ԂƑ]�ǂ����̂������ʂ����̂͋���̌܌������A���݂̗��ł͘Z�������玵�����ߍ��ɑ������Ă���B���k�n�����~�J���ɓ���A���x���C���������ɍ����Ȃ��Ă����͂��ŁA�k���ɂ�闷�H�̓�V�͑z���ȏ�̂��̂������낤�B

�@�A�O�̊Ղ��獑���l���������炭�̂ڂ����Ƃ���ɒJ������傫�ȋ����������Ă���B���̋��̂����Ƃ���J�ɓ���ׂ�����H��ƁA�����ɐ����̂قƂ���[����ɓ������B����͂��������Ƃ������ɕ����A�ǂ�����Ƃ��Ȃ������̖������������Ă���B���܂ł͂�قǂ̕��D�������ʂ邱�Ƃ̂Ȃ�襘H�����A���̓������́A�m�Ԉ�s���܂���̈��V��Ɛ킢�Ȃ���z���čs�������[��̘Z�Ȃ���̌Ó��ɂق��Ȃ�Ȃ������B�n�ӂ���Ǝ��Ƃ͈����������ł߂�悤�ɂ��āA���E�ɂ��˂�}�X�̍ד���o�����B���ݐՂ炵�����̂͑S���Ȃ��A����łȂ��Ă��l�ЂƂ�ʂ�̂�����Ƃ̋������ɁA�s�����������悤�ɂ��Ė̎}���L�яo���Ă���B����ł��A�m�Ԃ�]�ǂ����̏��a�ݒH�����̂��Ǝv���Ɗ��S�͂ЂƂ����������B�����̂܂܂̗l���𗯂߂Ă���̂͋����̂����̂����킸���ȕ����ɂ����Ȃ�����ǂ��A���\����̍��̒��R�z���A���Ȃ킿���H�R���z���̋�J�Ƃ��̕��͋C�̂قǂ��Âꂽ�̂͑傫�Ȏ��n�������B
�@���̍ד��ɂ��ƁA�m�Ԉ�s�͂��̎R�����̂ڂ�ߏo�H�̍��Ƃ̋��Ɏ�����������Ō��������J�Ɍ������A��ނȂ������̖�l�̉ƂɎO���قǐ������邱�ƂɂȂ����B���̎��ɉr�܂ꂽ�̂��A
�@ �`�l�n�̔A���閍��
�Ƃ����L���Ȉ��ł���B�V���҂��Ă���A�Ⴂ�����ȎR�ē��l�̐擱�ŁA�m�Ԉ�s�͓��Ȃ������i�ނ悤�ɂ��ĎR�����i�Ȃ�����j�����z���A���ԑ�̏W���ւƔ����Ă���B
�@�ĂюԂւƖ߂�����X�́A�m�Ԉ�s�ɂ͐\����Ȃ��悤�ȑ��x�ŎR�`���ւƑ������H���z����ƁA���ԑ���ʂւƌ������ăn���h��������B���ԑ���߂���Γc���̓c��Ƃ����Ƃ���ɂ���������ƁA���R�̗Y��Ȓ��]���s��̎��E�����ς��ɍL�����Ă����B��������̒߉������肩��Ƃ͂��傤�Njt�̕������猎�R�߂Ă��邱�ƂɂȂ�B���̈�A�̗���ʂ��āA�͂��炸�����R�̔������R�e�𗼑�����]�ނ��Ƃ��ł����Ƃ����킯���B
�@��Γc����́A�t�R�̐����D�����ɓ������B�t�R�͌��R�A��̓��[�Ɉʒu����R�ŁA�Â�����C�����̗�R�Ƃ��Ă��m���Ă���B��ɋP���쒆�����炭����ƁA�ŏ��ɂ�����O�������ɂ������������B���̋��̉���т͐[���藧�����k�J�ɂȂ��Ă���A�쐣���r�X�����I�o���Ă��ė����������A�͍̂ŏ�쐅�^�̎O��̂ЂƂ������B�đ�˂ŎY�o�����g�ԂȂǂ̕����͍ŏ��`���ɏM�ɂ���ē��{�C�ɖʂ���͌��̎�c�܂ʼn^�ꂽ���A�����̉Q�����������Ȃǂɂ��̓���ʉ߂��邱�Ƃ͑�ς������炵���B����ɂ܂��A��c���ʂ���K�v������ς�ŕđ���ʂւƍŏ���k�s����ꍇ�́A�����̐l�͂�v����g���M��Ƃɂ���ċ}���ɗ����������r��������Ȃ���Ȃ�Ȃ������B
�@�O�������̂����ƂɎԂ𒓂߁A�쒆�������������A�z���̂ق��������͏��Ȃ������B���܂ł͏㗬�n��тɑ����̃_�������݂���A���ʂ��R���g���[�������悤�ɂȂ��Ă��邩�炾�낤�B�܂��A�m�Ԃ��u�܌��J�����߂Ă͂₵�ŏ��v�Ɖr�����͐V��̎����̂��ƂŁA�܂��ꃖ���قǂ����̔~�J���̍Œ��ɂ������Ă���B�܌��J�Ƃ́A�ނ��A�~�J�̂��Ƃł���B�~�J�̍��ɂȂ�A���܂ł��������Č��������ꉺ��ŏ��̎p��������̂�������Ȃ��B
�@�O���������炵�炭�s���Ƒ��R�s�̔����Ƃ����W���ɂ������������B���������Ǝ��͂��̂�����̒n���ɂ͑����ڂ��������B���̏W���ɁA���݂͐_�ސ�̑��͌��Ŏ��Ȉ�@���c��ł���̂���̒m�l�̎��Ƃ������āA���̐l�ɘA����A�ߋ����x�����̒n��K�˂�����ł���B
�@�������s���ō��Z�����𑗂��Ă������A��w�����������͒n���̂��鎕�Ȉ�@�ŃA���o�C�g�����Ă����B���܂��܂����V�C�̋Ζ���Ƃ��ĕ��C���Ă����̂��A�����\��˔N���̏���x�j�������B�N������傫���������A�C���Ⴍ�ď���C���Ȃ��A���������D���ȏ��삳��Ƃ͕s�v�c�ȂقǂɋC���������B�l��{�̓w�͂Ƌ�w�̖��Ɏ��Ȉ�Ƃ��Ă̓����J�������삳��̗�܂��́A�[���l���o���ɗ��t����ꂽ�����������Ă����������ɁA��������������A�L����������B�������Z��N���̂Ƃ��A���삳��͋Ζ���̈�@�̊Ō�w����ƌ����Ȃ������̂����A���̂Ƃ��O�㖢���̒������N�����B���l�߂����Ȉ�@���̉�����̔z���������Ă̂��Ƃ��������A�ЂƂ܂����Ή��̍��Z��N�̎����A�Ȃ�ƐV�Y�̎��Ȉ�́u�F�l��\�v�Ƃ��ďj�����q�ׂ�������Ƃ����A�M�����Ȃ����Ԃɒ��ʂ���͂߂ɂȂ����B
�@�{�y�̓�[�������ł̌��������������߂ɁA���삳��̐e���A�m�l�A�F�l�Ȃǂ̂قƂ�ǂ��Q�ȂȂ���Ȃ��Ƃ�������͂��������A����ł����\�l���̏o�Ȏ҂������Ă̋����������B����ȏ̒��ŁA�V�哪�Ɋw�����p�̍��Z�����F�l��\�Ƃ��ďj�����q�ׂ��킯������A�قƂ�ǂ̎Q�Ȏ҂͖ڂ𔒍������ċ�������͂Ă��ɈႢ�Ȃ��B�܂��r�f�I�ȂǕ��y���Ă��Ȃ�����̂��Ƃ�����A�K���X�s�[�`�^��͎c���Ă��Ȃ����A����������Ȃ��̂��c���Ă����瓪�꒼���͂ł��Ȃ����Ƃ��낤�B���{�L���Ƃ����ǂ��A���Z��N���̕��ۂŁA�\��ΔN��̂�����Ƃ������Ȉ�̌������ŗF�l��\�Ƃ��Ă��j���̃X�s�[�`�������ȂǂƂ����̂́A���̎����炢�̂��̂ł͂Ȃ��낤���B
�@������w�i�w�̂��ߏ㋞���ĂقǂȂ��A���삳��̂ق��͖k�C���T���}�߂��̒��ɂ����Ď��Ȉ�@���J�Ƃ���A���̌�A�_�ސ쌧���͌��s�Ɉڂ��Č��݂͂����Ŏ��Ȉ�@���c��ł�����B���삳���͌��Ɉڂ��Ă���́A�̋��̎R�`�ɋA�Ȃ����Ƃ��Ȃǂ悭���U���������A�x�X���̒n�ɓ��s���A�����̂���ɔ��߂Ă����������B���̓x���Ƃɂ��̎��ӂ������Ԃ�ƕ�������Ă��邩��A��т̒n���Ɏ��͂悭�ʂ��Ă����̂ł���B
�@����������Ƃ̉��~���E������Ɍ��Ȃ��甒���̏W�����߂���ƁA��X�͂������班����ɉ�������v�ۂƂ����Ƃ����ڎw���đ��葱�����B��Γc���̎��N�߂Ƒ��R�s�̑�v�ۂƂ̊Ԃɂ́A���h���܂ޏ\�l�E�܌��̂��Ή������݂��Ă���B���̊X�����u�ŏ��O����ΊX���v�Ƃ����ʏ̂����̂����̂��߂ł���B���ɂ��т����l�Z�ꃁ�[�g���̗t�R�̉��ɕ������n�`�̊W�ŁA����삩�璼�˓����������邢���ۂ��A��C�����荞�ݖ���������₷���B���̓���ȋC�ۏ����́A���͔̍|�ɍD�K�ŁA�M�B�Ɠ��l�ɂǂ̔_�Ƃ����Ɨp�̂����͔|���Ă����B�Â��͍g�Ԃ̑�Y�n�ł���A�����͍g�Ԃ̌��ɂ�����t������Ă����Ƃ����B
�@�`���ƋC�ۏ����Ɏx����ꂽ���Ε��̎��͍ŗǂ����A�����������ꂼ��̂��X�ɂ͂���Ȃ�̔�`�����邩��A�o����邻�͂Ȃ��Ȃ����܂��B�����A�Ȃ�Ƃ����Ă��A���̂�����ň�Ԃ̘V�܂͑�v�ۂɂ���u���炫���v�ł���B�吳���N�n�Ƃ́u���炫���v�̎O��ڂɂ����铖��̈��얔�O����́A��т̂��Ή��𒆐S�ɋߔN�������ꂽ�u�ŏ��O����ΊX���U����v�̉�߁A�n��̐U���ɍv�����Ă�����B���삳��ɓ��s���Ă��̒n��K��邽�тɁA�u���炫���v�ɘA��Ă����ꂽ���́A�������̑������̂��邻�Ɋ������o���������Ȃ����ۂ�ł������̂������B���߂Ă��炫����K�˂��̂́A������\���N�O�̂��Ƃ������悤�Ɏv���B���̓���X����v�ۂ�ڎw�����̂́A�ނ��A���́u���炫���v��K�˂邽�߂������B
�@���Ƃ͕s�v�c�Ȃ��̂ł���B�������o�Ă�����{�C�����ɖk�サ�Ă���Ƃ��ɁA�n�ӂ���Ƃ̉�b�̒��ŁA���k�ɗ���Ȃ琥������Ăق����Ƃ����Ă��Ă���V�܂̂��Ή�������̂����Ƃ����b���ł��B�����̎��l���A��Ƃ̐���א搶��ɂ̎�B��H���ɉ���ŁA�n�ӂ���̊G�̔M��ȃt�@���ł�����Ƃ����B���܂��ɁA��H���ɂ̉�����ɓn�ӂ���̑}�G����ŘA�ڂ��Ă������̃G�b�Z�C�������ǂ��Ă��������Ă���Ƃ����̂��B�悭�悭�b���Ă݂�ƁA�R�`���̑���s�ɂ���u���炫���v�Ƃ������X���Ƃ����̂ł͂Ȃ����B����͂܂�����Ƃ����ƂɂȂ�A���̎��_�Łu���炫���Όw�v�����܂����̂������B�O���A���k�����������ɓd�b�����A���̓��̒����܂łɂ͓�������ނ˓`���Ă͂������̂ŁA���炫���̕��X����X�������̂��A���܂����܂��Ƒ҂��Ă��Ă����������悤�ł������B

�@���炫���ɓ��������̂͌ߌ�ꎞ���������B���̕���L���Ȋ����������̑傫�Ȍ����͈ȑO�Ə������ς��Ȃ��B�u���炫���v�Ƃ��邳�ꂽ�T���߂ȊŔ��ꖇ�������肰�Ȃ��|���Ă��邾���Ƃ����̂����ɂ����B�O���璭�߂���̕��̑���̗R������Â����Ƃɂ��������Ȃ��B�n�ӂ���́A�Ԃ���~���Ƃ����ɂ��X�̌����̑S�i���X�P�b�`���͂��߂��B���̂ق��͂��̊ԁA���X�̎��ӂ����肰�Ȃ�������Ȃ���A���Ă̗z���ɋP���������镗���̖����y���B�n�ӂ����܂ɂ��X�P�b�`���I�������ɂȂ����Ƃ��A���X�̂ق����犴���̂����j�̐l��������Ƃ͂ɂ��ނ悤�ȏ݂��ׂĉ�X�̂ق��ւƋ߂Â��Ă����B�����āA�n�ӂ���Ɍ������ĐÂ��Ȍ����Řb���������B���ꂪ���l�̈�����������B��X�͂����Ɍ��ւɒʂ���A����̈��얔�O��v�ȁA������̉��l�A�^�|�����ɂ���Ď�����}�������ꂽ�B�@
�@������̂���N�����̊��Ȍ���ő���ꂽ�L�����~���̋�Ԃɂ́A�l�̐S�����R�ƂȂ��܂��Ă����s�v�c�ȉ��������������B�V�R�ŏo�����ג����H�䂪���r�����сA�Â��㎿�̖ؔ��Ȃ�ł͂̉��₩�ȋP��������Ă���B���̂ق��̍��z�c�ɂǂ�����Ɛw�������X�̑�������Ă������鈰��V��v�ȁA���v�Ȃ̏���C�̂Ȃ����l���ƁA���ɂ��炩�ȎR�`�ق̔��������Y���Ƃ��A���̂����Ȃ��̂悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ������B�n�ӂ���͈���Ƃ̕��X�Ƃ̒k�b�̍��ԂɎ�₭�X���̗l�q���X�P�b�`���A�捏�̌����S�i�̃X�P�b�`�Ƃ��ǂ��A����ƂɃv���[���g�Ȃ����Ă����B
�@���炫���͒m��l���m��R�`�̘V�܂�����A�H�ʂ̍����ȕ��l��|�\�l�Ȃǂ��͂��߂Ƃ��A�͂�邱�̂��X�̖��ƕ�������߂ĖK�˂�l�͂��Ƃ�f���Ȃ��B��̑O�Ɉꐢ���r�����m�g�j�̖��A�i�E���T�[�{�c�P�A�c����w�����ŐH�ʂƂ��Ēm��ꂽ�r�c��O�Y�A��Ƃ̑��㌳�O�Ȃǂ��A���炫���̔M��ȃt�@���������炵���B�ȑO�͂����������l�X�̏���F�������̊Ԃ�ǂɊ|�����Ă������A���܂͕ʂ̏���F���ɕς���Ă����B���肰�Ȃ����X�̎l�������n���Ȃ���A���̂����n�ӂ���̃X�P�b�`�����ԂƗ��j�̗n�������̕ǖʂ̈�������邱�ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����ƁA���S�Ŏ��͎v�����̂������B
�@�N�����̖̂ؐ��̒����^��u�Жؖ~�v�ɒ��J�ɕ��א���ꂽ���ڂ̂��́A����A�������A���̋����A�ǂ���Ƃ��Ă������ʂ�̐�i�������B�������A���̈�l�O�̕��ʂ��v���ƁA�M�����Ȃ��قǂɗǐS�I�Ȓl�i�������B���͉��x�����̂��X�ɗ��Ă��邩��悭�킩��̂����A���ʐ���Ɛ̐���Ƃ������āA���ʐ���ł���ʂ̂��Ή��̈�{���قǂ̗ʂ͂���B�̐���̂ق��͕��ʐ���̓�{���ʂ�����̂�����A���q�ɏ���Ă����ɒ��������肷��ƁA�r���ňݑ܂̂ق����M�u�A�b�v�̔ߖ������Ă��܂����ƂɂȂ肩�˂Ȃ��B
�@�����Ƃ����̓������͈���Ƃ̂��D�ӂɊÂ��A���炫���Δ�`�̖������\�����Ă����������ƂɂȂ����B�������܂��������A�Y�n�������ׂ������Ɩ��X�����ň�������Ďύ������̐g�����ׁA�㎿�̍����܂̃^�����̂������̖����v�킸���Ȃ肽���Ȃ�قǑf���炵�������B�����ďo���ꂽ�̂ꂽ�Ă̎R�ؗނ̂��Ђ���������т��|�l�Ȃ��ɔ������������B
�@�����A���������ƂɈ���ƌ�Ƒ��̐^�S�̍������ڑ҂ɊÂA���X�ɏo������y���ɔ������邤���ɁA��X�̑̓��ł͑z��ʕω����N����͂��߂��B�����œn�ӂ���ƍ����������n�߂Ă���̋���ԂƂ������́A�e�H�ɓO���Ă����܂ł���Ă����킯������A����Ȃ�̃��Y���Ɋ���Ă��Ă����ݑ܂̂ق����A����ȑ�ʂ̌�y�����������ɕ��ꍞ��ł���Ȃ�ė\�z���ɂ��Ă��Ȃ��B�����Ƃ����܂ɂς�ς�ɖc�ꂠ����A����ł��Ȃ��l�ߍ��܂�Ă����y���ɑΉ�������Ȃ��Ȃ����ݑ܂��A�Ƃ��Ƃ��r�n�r�̔ߖ��͂��߂��̂������B�Ō�́A�n�ӂ���������K���ɂȂ��Č�y���Ɗi�����鎖�ԂƂȂ�A����������Ƃň���������Ȃ��Ȃ肻���������B
�@����Ƃ��璸�Ղ�����R�̂��y�Y���Ԃɐςݍ���X�́A�S����ʂ��ɂ��݂Ȃ���A�ߌ�Z�������A�R�`���암���畟�����k�����ʂ�ڎw���đ���o�����B����k�ɂȂ邪�A�����ɖ߂��Ă��珑���������̒��ŁA���́u���炫���v�Ƃ��������̗R���ɂ��Đq�˂Ă݂��B�O�q�������삳��A���炫���́u���炫�v�͂ǂ���猕���r�ؖ��E�q��ɂ��Ȃ��̂炵���Ƃ����b�������Ƃ�����������ł���B����̈��얔�O���璸�Ղ������莆�ɂ��ƁA��X��̌䓖�傪�u�k�̍r�ؖ��E�q��̔M���ȃt�@���ł����A���̂��߉������u���炫�v�ɂȂ����̂��Ƃ̂��Ƃ������B���삳��̘b�͎����������̂ł���B
�@�H�߂��͂̕Ă��߂����B���炫�����o�����A�͖k���A���͍]���o�ēV���ɏo�����̂��Ƃł���B���E�����ς��ɖc�����Ă����ݑ܂��Ԃ̐U���ł���Ɏh���������ނ��Ă���ɖc��オ�����������낤���A�d�ꂵ�����s�[�N�ɒB�����B����Ȃ̓n�ӂ�������炩�ɓ����Ǐ��悵�Ă���B�u�{�c����A�ݎU�����邩����܂ւH�v�Ƃ����n�ӂ���̋ꂵ�C�ȗU���ɁA���̂ق����������Ȃ����ӂ����B�����\�O�����e�̃p�[�L���O�G���A�ɎԂ𒓂߂���X�́A���炫���̊F����ɂ͐\����Ȃ��v���Ȃ�����A�ݎU���ꕞ������ł���Ԃ̌㕔�Ȃł��炭���ɂȂ�A�ݑ܂̔�����ً}�ُ�M�������Â���̂������Ƒ҂����B��l�Ƃ��A������E�O ���͂Ȃ�ɂ��H�ׂȂ��Ă��悢�̂ł͂Ȃ����Ƃ����v���������B
�@ �݂₷�߂��łɓԂقlj������Ƃ������ƍĂё��s�Ԑ��ɓ�������X�́A��������Â��Ȃ��������x���͂�߂ē쉺�����B�R�`�s�A��z�s���o�ĕđ�ɏo�A�đ�͔��z������ʂւƌ������ɓ������B���������Ԃ�̂̂��ƂɂȂ邪�A���z����̍����h�ɂɂ͂���Ƃ����z���o������B����ӏH�̗[���ɒ��c��Εt�߂���}�ɓd�b�����A�j��l�������Ӕ��߂Ă��炦�Ȃ����Ɛq�˂Ă݂��B���������ꍇ�͒f����邱�Ƃ������A�Ƃ��ɁA�ό��V�[�Y���Ő�����A�t�ɃV�[�Y���I�t�ŁA���q���قƂ�ǂȂ��Ƃ��Ȃǂ͂Ȃ��Ȃ����߂Ă��炦�Ȃ��B�H�̍g�t�V�[�Y���͉��ɏI���A�قǂȂ����~�ɂ����낤���Ƃ����q���̓r�₦�����Ȏ�������������A�̂悭�f����邾�낤�Ɨ\�z���Ă����B�Ƃ��낪�A�d�b�̌������̘V�������̎�́A�u�͂��킩��܂����B�䓞�������҂��\���グ�Ă���܂��B���ӂ̂����܂�͂��q�l����l�ł��̂ŁA���q�l�������߂��镔���̖����肾�������A���̕����͏������Ă��҂��\���グ�Ă���܂��B��Ԃ̂��Ƃœ��ق����킩��Â炩�낤�Ƒ����܂��̂ŁA�����ڈ�ɂ��Č䗈�ق��������v�Ƃ����A�Ȃ�Ƃ����ȉ�����Ԃ��Ă����̂ł���B
�@ ����Ȃ�̋K�͂̏h���{�݂���������l�̓ˑR�̃t���[�q�𔑂߂�ƂȂ�ƁA����ɗv����l�������M��A�Ǘ���ȂǂŐԎ��ɂȂ��Ă��܂����˂Ȃ��B��������m�Ŕ��߂Ă����Ƃ����̂ł���B�v��ʂ͂��炢�Ɋ������邢���ۂ��ŁA�Ȃ��\����Ȃ��C������������悤�ȗL�l�������B
�@ �O�������ȎR�̐������z�����ȃX�J�C�o���[���z���Ĕ��z����ɒ������͖̂锪�������������B��K�����̕����̖��肾���������O�K���Ă̑傫�Ȍ������������̂ŁA���ꂪ�ڎw�������h�ɂ��Ƃ������Ƃ͂����ɂ킩�����B�}���Ă����������̂́A�ƂĂ������̂����V��̊Ǘ��l��v�ȂŁA�����ɏo���ꂽ�S�̂����������������������������A�L���������l�Ő�̂��Ă̓��������K���̂����Ȃ��A�v��ʍK�^�Ɏ��͊����̂��ǂ����ł������B������\�N�߂����O�̂��ƂȂ̂ŁA���̌�v�Ȃɂ�����邱�Ƃ͊���Ȃ����A�������Ă���Ƃ��Ȃǂ��܂ł������������̈��̂��Ƃ�z���N�����B
�@ ���z����X��ʂ肩�������̂͏\�ꎞ�O�ゾ�����̂ŁA�������ɂǂ����ňꕗ�C�Ƃ����킯�ɂ������Ȃ������B�̂Ɋr�ׂ�Ƃ����Ɩ��邭�ߑ�I�ɂȂ����z�e����h���{�Q�����ڂɌ��Ȃ��甒�z�̉���X�𑖂蔲����ƁA�قǂȂ����͋}��ɂȂ����B�[��̃X�J�C�o���[���z���ĕO���Α��֏o�悤�Ƃ����Z�i�ł���B����Ȏ����ɂ��̐[���R�z���̓���ʂ�Ԃ͂قƂ�ǂȂ����낤����A�L�����H�Ƃ͂����Ă��A���������Q�[�g�ɌW���͂��Ȃ��ɈႢ�Ȃ��B��������A���̂Ԃ�A��ʔ�����オ��ł��ށB�A�N�Z���ݍ��ނƂ���Ԃ̍��x�͂�����A���₩�ȃr���[�h�n�ɑ召�����̕���U��߂��悤�Ȗ�A���E�̏�������ς��ɍL����͂��߂��B���Ԃ��߂ēV��̐��X�����Ȃ���R�`�ƕ����̌����̓����z���A�ʍs�t���[�ɂȂ��Ă������������Q�[�g���A�O�������̓��ɏo���Ƃ��͌ߑO�뎞���܂���Ă����B
�@ �Ƃ肠�����O���ΔȂ̃I�[�g�L�����v��ւƑ����_�[�g�ׂ̍�����������葖���Ă���ƁA�ˑR���C�g�̒��ɔ�ђ��˂�悤�ɓ����܂�鏬�����̎p�������яオ�����B�悭�݂�ƁA���C�ɂ���ꂠ���O�C�̎q�ς������B�q���̓�����������ŁA�Ȃ�Ƃ����炵���B�Ԃ��߁A���C�g�������܂܂ɂ��āA��X�͓��Ȃ閽���e���]����悤�Ȏq�ς����̓����������ƌ��ߑ������B�v�킸�R�ꂽ�u�����R�C�̂��I�v�Ƃ�������Ȃ̓n�ӂ���ꂫ���A���̏�i�̂��ׂĂ���Ă��銴���������B�q�ς��������H�e�̔ɂ݂̒��֎p���B���̂�҂��ČΔȂɏo���B�����āA�����ɎԂ𒓂ߖ���ɏA�����̂͌ߑO�ꎞ�߂��������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
1999�N11��17��
���̘e�����Q�L�i�P�Q�j
�S����̓��̌��i
�G�E�n�Ӂ@�~
�S����̓��̌��i�\�\��Â���z�㒷����
�@ �����͘Z�����ɖڊo�߂�ƁA���H���Ƃ炸�ɂ��̂܂ܕO���ΔȂ����Ƃɂ����B�\���Ԃɂ킽��n�ӂ���Ƃ̗��̍ŏI���Ƃ����āA�ǂ����Ă��ߌ�O�������܂łɂ͉z�㒷���w�ɒ����˂Ȃ�Ȃ��B�����܂ł͂܂����Ȃ�̍s���Ȃ̂ŁA�����������悤�Ȃ킯�������B�֒�R�����Ζʂɉe�𗎂Ƃ��ܐF���ɗ��ƁA���̈�тɗV�����������X�̂��Ƃ��z���N�����ꂽ�B�����ɕ����Ԕ֒�R�̂͂邩�Ȓ����ɂ́A�̓��̎����̉e�����܂��S��̂悤�ɗ����Ă��āA�����Ƃ�������������Ă���悤�ȋC�����ĂȂ�Ȃ������B�܂��A�ܐF���̐��Ζʂɂ͐t�̓��X�ɑ������{�[�g�̐��������܂��������ȐՂ��c���Ă���A�܂����X�̎��ӂ�D�������̕Ћ��ɂ́A���Ă̗J����[�������Ղ��B����Ă���悤�ȑz���������B


�@ �s���邱�Ƃ̂Ȃ���z��U�蕥���悤�ɂ��ČܐF�������Ƃɂ���ƁA���͂������ɃA�N�Z���ݍ��݁A���c��ΔȂ����ăn���h��������B�����āA���c��Δȉ����̓����Ζʂ�����Ɍ��Ȃ��炵�炭����A��Îᏼ�ւƃ��[�g���Ƃ����B���Ԃ��\���ɂ���A�ѐ��R���͂��߂Ƃ��鋌�Ղ�������菄���Ă��݂����������A���̓��̍s���̓s���セ�����Ă���]�T�͂Ȃ������̂ŁA�ѐ��R�̘[���I�������ŁA��Îᏼ�s����ʉ߂����B��Óc���܂œ쉺���A�c������O�}��Ɍ��������Ƃ����̂��A���ʎ����z�肵���R�[�X�������B
�@ ��Îᏼ�Ɖ�Óc���̊Ԃɂ��鈰�m�q����t�߂ɂ��������鍠�ɂȂ�ƁA�������ɂ������Ă����B��[���炫�����o�������Ƃ��́A������E�O���͉����H�ׂȂ��Ă������悤�ȋC���������̂ɁA�����͂������̒��q���������ʂĂ����̂ł���B���m�q����X�����ɋ߂��y�Y�����̒��ԏ�ɋ}���ŎԂ𒓂߂���X�́A���炫���Œ��Ղ��Ă����g�����ׂƍ����тŒ��H���Ƃ����B��������Ǝύ��܂ꂽ�ׂƂقǂ悭�������̂����т���������Ɩ��킢���݂��߂�ƁA����Ƃ̕��X�̐^�S�����킶��ƐZ�ݏo���Ă��銴���������B���ɍ������܂Ԃ��A�J���b�Ɨg�����J�����g�E���̂��̂��A�s�v�c�ȕ����������ĂƂĂ��������������B
�@ ���H���I����ƁA��X�͂܂�������̎x�����ɉ���������쉺���͂��߂��B�����āA����Ƃ����W���ɂ������������Ƃ���Ő��ւƕ��铹�ɓ������B�ΑN�₩�ȒJ�`���ɂ��炭����ƁA�삩��̂тĂ��Ă��鋌�X���ɍ��������B���̒n�_�Ŗk�ɐ܂�A�������i�ނƁA�������̂Ȃ���̏h�꒬�̖ʉe�����܂��Ƃǂ߂����h�������B����h�́A�ؑ]�H�̍��ďh��n�ďh�A�ޗLj�h�Ȃǂƕ���Ŗ����j��d�v�ȕ�����Y�𐔑����c���W���Ƃ��Ēm���Ă���B�Ԃ��W��������̒��ԏ�ɒu���ꑧ���ƁA���������Â������݂����w���邱�Ƃɂ����B
�@ �������Ƌ{�̖�O�����s����k�ɂ̂т��Ð��X���́A�R�������z���ĉ�Óc���ɓ���A�c�������Îᏼ���ʂւƑ����Ă���B�c�������Â��������X���́A���݂̍����Ƃ͈Ⴂ�A�[���������J�Ƌ}���̘A�Ȃ��������A���̐����R�ԕ���D���ĉ�Í��c���ʂւƒʂ��Ă����B���̓r���́A����x�ƉG�X�q�x�Ƃ����W���烁�[�g�������̎R�X�ɋ��܂ꂽ�J�̕��n�ɁA����h�͈ʒu���Ă���B�W���̒����𑖂鋌�X���́A���₩�ȍ���Ȃ��Ėk�̕��p�ւƏ���Ă���B�����͂��Ȃ�L���A���̗��[�ɂ͉������������ĂĐ��̗����p���H���݂����Ă����B
�@ �܂��������������������Ƃ������Ċό��q�̎p���܂�ŁA�����ݑS�̂͐Â��Ȋ������������A�X���̗����ɂ͑傫�Ȋ���������������Ó��L�̍\���̌Â��ƁX���������сA�����̔ɉh�̂قǂ��\���ɎÂ��Ă��ꂽ�B���j�����ق╶�����w��̖��ƂȂǂ�����A�\���Ɏ��Ԃ������Č��w�������Ƃ���ł͂��������A�z�㒷���Ɍߌ�l���ɂ͒����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����āA�ǂ����Ă��}�����ōs�����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�̕��̓X�\���̂��y�Y����H�����̑O��h���S��}���Ȃ���ʂ�߂��A�Ƃ��������W���̍ʼn����܂ŕ���i�߂��B�t�߂ɌÂ������Ȃǂ�����悤���������A������K�˂��肷��̂͂܂��̋@��ɂƂ������ƂɂȂ����B�ނ��A�ĖK�̋@����߂����Ă��邩�͒m��悵���Ȃ����Ƃł͂���������ǂ��c�c�B
�@ ����h���߂���ƁA���X���͕����ēo�邵���Ȃ��ׂ������R���ɂȂ��Ă���B���͏���x�̖k�ɂ���Z�Ίx�ƑO�q�̉G�X�q�x�Ƃ̈ƕ����z���ĉ�Í��c���ʂւƑ����Ă��邪�A���݂ł͂��̎R�H��H��l�͂߂����ɂ��Ȃ��B��X�͎R���ɓ����O�ň����Ԃ��A�����̗��l�̎p�������ÂтȂ��璓�ԏ�ւƖ߂��Ă������B
�@ ����h����͋��X���`���ɓ쉺���A���R�����z���ĕx�h�̏��W����ʉ߁A�ь˂ōĂэ����ɍ������郋�[�g���Ƃ����B�ь˂����Óc���܂ł͎Ԃŏ\���قǁA�����ɂ��ď\��E�O�L���������B
�@ ��Óc���ɓ���A�s�X��싽�����ʂ֔����悤�Ƃ��Ă���ƁA�O���ɓ��H���̕\���������ꂽ�B�Ȃ�ƍ�����ܓA�����O�ܓƂ��c��Ɛ���̂��ߒʍs�s�\�Ƃ���ł͂Ȃ����B���Ƃ��ẮA�c������싽�����o�ĎO�ܓ��`���ɕO�}��ɏo�A����������������x�̖k�R�[��ʂ��ĉ������̋�R�ɔ�������肾�����B�r���̗Y��Ȍi�ς͔��Q�����A��R���珬�o�Ɏ���A�����܂ł͂ЂƑ���ł���B�������̓��͎R�x���̍���n�т��郋�[�g�Ȃ̂ŁA���������Ǝc��Œʂ�Ȃ��\��������Ƃ͎v���Ă����B������A���̏ꍇ�́A�싽������������ɏo�č�����ܓɂ͂���A�c�q�q�_���̖k����ʂ��ď��o�ɔ�������肾�����B������ܓ͉�ÂƐV�����Ȃ��R�x���H�����A���ēc���p�h���͂���ꂽ�Ƃ��������̂��Ƃ͂����āA�L����������Ƃ�������̊��S�ܑ����H�ł���B�܂������̓��H�܂ł����̎����ʍs�s�\�ł���Ȃ�čl���Ă��݂Ȃ������B�����̓~�͂�قǂ̍��Ⴞ�����̂��낤�B��ʏ��ɂ͎��X���ۂ̏Ƃ͂��ꂽ���̂�����̂ŁA���ǂɊm�F�̓d�b�����Ă݂����A��͂�ǂ���̍������ʍs�s�\���Ƃ������Ƃ������B
�@ �c���ꂽ���[�g�͂����ЂƂA�����Ԃ��ɂ͂Ȃ邪�A������x�k�サ�č����l�㍆�ɓ���A�����쉈���ɑ����ĐV�����ʂɏo�邵���Ȃ��B�����Ɏl���O�ɒ����邩�ǂ������肬��̂Ƃ��낾���A�Ƃɂ����`�������W���Ă݂邵���Ȃ��B�}篁A�c������k���ɂ̂т錧���ɎԂ�������A�����ɃJ�[�u�̑����������z���Ă܂����a���ւƏo���B�r���̌i�ς͂���Ȃ�ɕω��ɖL��ł͂������A������������y����ł���S�̂�Ƃ�͂Ȃ������B���a���̎�O�ʼn�Í��c�ւƑ��������l�Z�ꍆ�ւƉE�܁A��E�O�L���������Ƃ���Ŕ��m�R�̐��R�[��k�ɖD�������ɓ������B
�@ ���̌����������čs���ƁA�قǂȂ����~����ɏo���B���R����Ƃ��Ă�A�̂���ЂȂт�����h����������Ƃ���ł���B���̉�������߂ĖK�˂��͓̂�\���N�O�ŁA�������O�q�������Ȉ�̏��삳��ƈꏏ�������B���̎��͋t�����̖��Â�����~�ւƌ��������̂����A�����͖��ܑ��̋������ʂ̂Ђǂ����ŁA���\��ς������L��������B���̌��~�̉���h�̓����́A�����̏h���ꂼ��̐��܂������قȂ��Ă��邱�ƂŁA�������������Α��̏h�ł������ł�������A���߂ɉ��ʂ��p�ʼn���߂�����������̂������B�ǂ̏h�̉���ɂ��̂Ȃ���̑f�p�ȕ���Ɛl��c���Ă���A�ƂĂ��������肽�ЂƎ��𑗂����z���o�����邪�A�Ԃ��猩�邩����ł͂�����������ߑ㉻����Ă��銴���������B
�@ �������̑�J�̉w���������߂����Ƃ���œ�ܓ��ɍ����A���Â̕��ʂւƃn���h��������Ƃ���ŁA���̔]���ɂ��܂ЂƂ��������L�����S�����B��͂��\�N�ȏ�̂̂��ƂŁA���̂Ƃ������삳��ƈꏏ���������A�ꌎ�̏��߂ɂ�����肳��ɉ��ɂ���ʗ�����ւƏo���������Ƃ�����B�S�R���߂��ĉ�Îᏼ�Ɍ���������A�Ґ���ɂȂ����B���k��т���E�O�\�N�Ɉ�x�Ƃ������Ɍ�����ꂽ�N�̂��Ƃł���B�t�����g�E�B���h�[�ɂ̓��C�p�[�̏����\�͂����Ⴊ�~��ς���A���]�̍�Ƃ��ăE�B���h�[�E�E�H�b�V���[���g���ƁA�ቷ�̂��߁A�����܂����C�p�[���̂��̂�������p���Ȃ��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��L�l�������B������Ƒ����Ă͎Ԃ��߁A�t�����g�E�B���h�[�̐��X�����Ƃ��܂�����Ƃ�����Ƃ��J��Ԃ������ɁA����ǂ̓A�N�Z����N���b�`�A�u���[�L�̒��q�������Ȃ����B���x���Ԃɏo�͂��肷�邤���ɁA�C�̗��ɕt��������ʂ̐Ⴊ�����ăA�N�Z����N���b�`�A�u���[�L�̂܂��ɓ�����A���܂��ɌC���̐�܂ł��X�����Ă��܂����̂ł���B���̂��߁A�A�N�Z���A�N���b�`�A�u���[�L�̓����������Ȃ��������ɁA����ł��C�������Ɋ��邽�߁A�v�����܂܂ɉ^�]���ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂������B�Â��Ԃ̂��߁A�q�[�^�[�̗��������������̂�������������A�ő�̌����ُ͈�ȍ~��Ɖ�Ȋ��C�������B
�@ ����ł���Îᏼ�܂ł͂܂��悩�����B�H�ʂ��[���V��ɉ����āA�V�ቺ�̘H�ʂ��̂��̂̓K�`�K�`�ɓ������Ă�������A���Âɂ��������鍠�ɂȂ�ƃ`�F�[�����قƂ�Ǘ����Ȃ��Ȃ����B�n���̃^�N�V�[�Ȃǂ����䂩���[�œ����Ȃ��Ȃ��Ă����B�X�R�b�v���ӂ���čs����̐��r��������A����~�߂̍����T�����肵�Ȃ���A�T�̂悤�ȑ��x�ň�i��ނ𑱂����B������ܓ��番�ċʗ�����A����ɂ͏��a���ւƒʂ��铹�͂��܂ł͂�������g����������A�ܑ����H�ɂȂ��Ă��邪�A�����͋}��̈��H�������B���̓������͂��߂鍠�ɂȂ�ƁA�܂�ŎԂ��ƕX����X�P�[�g���Ă���݂����ɁA�E�֍��ւƃX���b�v���J��Ԃ��A���x�ƂȂ��ԑ̂��i�s�����Ǝl�ܓx�̊p�x���Ȃ��Ē�܂�L�l�������B�����ȂƂ���g�Ɋ댯���o�������Ԃ������Ƃ��v�������A�����������Ă��t�^�[�����ł��Ȃ��B������Ƃ����Ă��̏�œ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂�����A���Ԃ͂��������ߎS�ł���B�Ō�̔ؗE���ӂ邢�N�����A�ق��ق��̑̂ŏh�ɒH�蒅�����Ƃ��ɂ́A�����͖�̏\�ꎞ���߂��Ă����B���̍��������ꌬ�����Ȃ���������h�̌��l����A�u�悭���܂��A����Ȉ��V��̒������o�łɂȂ��܂����˂��B�n���̎҂ł����̐Ⴖ��N���������肵�܂����B�Ă����肨����͂Ȃ����̂Ǝv���Ă���܂����v�Ƒ傢�ɕ�����������B��H�ɂ��������݂̎l��̃��S���Ԃł��ǂ����Ǝv�����炢�Ȃ̂ɁA�悭���܂��A���̋����̘V���ԂŖ��d�Ȃ��Ƃ���������̂ł���B
�@ ���~��ɂ͂Ȃ������A��͗�������܂Ȃ������B������������Ƃ����\���ʂ�A���̌�N����������Ƒz�����͂邩�ɒ������ϐ�̂��߂ɓ��H�͊��S�ɕs�ʂƂȂ����B�����āA���H���ĂъJ�ʂ���܂ł̊ԁA��X�͋ʗ�����t�߂ɕ����߂���͂߂ɂȂ��Ă��܂����B�d�����Ȃ��̂ŁA�����͋߂��̏��W�����U���Ԃ�ׂ����ƂɂȂ������A�z���������ʌ��i�ɂ߂��肠�����̂͂��̎��������B
�@ �����ɐς��������ꃁ�[�g���ȏ�̐��傫�Ȗؐ��̐�x�����I�݂Ɏg���Ă��낵�Ă���V�l�ɘb��������ƁA�~�̌������Ɛ키�ፑ�̋�J���A���[���A�������Ȃ�����X�ƌ���Ă��ꂽ�B�����ɏ���ĐႨ�낵��̌����Ă��悢�Ƃ����̂ŁA���ڋC���N�����Ă�����Ƃ�����`�킹�Ă���������A�O�E�l�\�Z���`�̌��������w���ɕ����ĕ\�w�����珙�X�ɐ���~�낷��Ƃ́A�z���ȏ�ɏn���Ƒ̗͂�v����d���������B�\���قǂ��Ⴈ�낵�𑱂��Ă���Ɛg�̒������݁A�������d�����Ȃ��Ă����B�v���Ɏ����^�ڂ��ƁA�����̌�����̐���������Ɏ�菜�����肷��ƁA�����̏�����̌�������w���}�ɓ������肾���č�Ǝ҂���Ƃ��n��ɕ��������˂Ȃ��B�Ⴈ�낵��ƒ��ɉ������痎������A��Ɉ����ׂ��ꂽ�肵�ĕ����҂⎀�҂��ł�̂͂��̂��߂ł���B�V�l�̘b�ɂ��ƁA�Ⴈ�낵�ɂ͓S���̃X�R�b�v�Ȃǂ����A�̂Ȃ���̖̐�x���̂ق��������ƌ����I�ʼn��������߂��ɂ��ނƂ������Ƃ������B
�@ �Ⴈ�낵����ې[���������A���̂��Ƃł��܂��ܖڂɂ������i�͏Ռ��I�ł����������B���̏��W���̈���ɋ�����n�������āA�����Ŗ����̋V�����s���Ă����̂ł���B��т͐[���l�E�܃��[�g���͂��낤���Ƃ�����Ɉ�ʕ����Ă��܂��Ă��āA��n���̂��͉̂�X�̖ڂɂ͂܂����������Ȃ������B�����␔�����ɂ����l�X�Ɏ����悤�ɂ��Ă����Ǝv������̂��߂��܂ʼn^��Ă��Ă������瑒�V�ɂ͊ԈႢ�Ȃ������B�ǂ�����̂��낤�ƕs�v�c�Ɏv���Ă����Ƌ߂Â��Ă݂�ƁA�Ȃ�ƁA��ʂ̈�p����ӌ܁E�Z���[�g���̐����`�Ɏd���A�����������[���x�艺�����Ă���ł͂Ȃ����B�����āA�Â��l�p�����̌��̒�Ɍ����Ē�q���|�����Ă���̂������B
�@ ���̒ꂪ�ǂ��Ȃ��Ă���̂����O�҂̉�X�͒m��悵���Ȃ��������A�y���Ȃ͖̂��炩����������A�����߂邱�Ƃ��ł���悤�Ɍ��̒�̗₽���n�ʂ͂���ɐ[���@�艺�����Ă����ɈႢ�Ȃ��B������ł����Ă��y���̏ꍇ�ɂ͂��Ȃ�[���n�ʂ��@�艺���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�z�����������ł����̍�Ƃ͗e�Ղł͂Ȃ������������B�����̎Q��҂̈�l�ɂ����Ɛq�˂Ă݂�ƁA�S���Ȃ����̂͋�\�˂��������������V�k���Ƃ̂��Ƃ������B���̐l�̌��t�����̂܂ܐM����Ƃ���A���̘V�k�͐��܂�Ă���S���Ȃ�܂ł����Ƃ��̒n�𗣂ꂽ���Ƃ��Ȃ������Ƃ����B���݂ł͍l�����Ȃ��b�����A�����̎R���⋙���ɂ͂܂����̂悤�Ȑl�X���킸���������݂��Ă����̂ł���B
�@ ���Ə��삳��Ƃ́A�����ɓB�t���ɂȂ����܂܁A���ŘV�k�̖��邨������q�`���Ɍ��̒�[���ɂ��낳���l�q�����߂Ă����B���N�͐[����ɕ�����鍋��n�юR���̏��W���ɐ��܂�A�����₩�Ȋ�т�y���݂͂������낤���A�������̉��\�{���S�{���̋ꂵ�݂Ɣ߂��݂ɑς��Đ����A�����Đ��U�a���̒n���ЂƂ��т�����邱�ƂȂ��i���̖���ɂ����V�k���A���܌���������̉��̈Â��₽���y�̒�ւƊ҂��Ă����c�c����́A������Ƃ������Ƃ̈Ӗ������ꂩ��l���Ȃ���������s�₫��܂�Ȃ����i�ł������B��ȋ��R�̎�荇�킹�ł��̘V�k���n���ւƖ߂�u�Ԃɗ����������ƂɂȂ�����X�́A��x���������̎p��q���邱�Ƃ̂Ȃ������l�̒��̐l���̐�B�Ɍ����Č��J�l�Ǝ�����킹���悤�Ȏ��悾�����B
�@ ���X���̌ߑO���ɂȂ��Ă悤�₭���H���ʍs�ł���悤�ɂȂ����B�A��d�x�����܂��A�����Ԃ������Ƃ��Ă݂����A�A���̊��C�ł������������������炵���A�G���W���͔������ɂ��Ȃ��B���������@������h�����肵�Ă���`���[�N���i�荞�݃X�^�[�^�[���Ă݂����A�����Ɏ~���Ă��܂��Ăǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��B�K�\�����������ʂɋz������݃v���O���G��Ă��܂������Ƃ������āA���Ԃ͈���������肾�����B�����x�����ƒ��߂��������A�Ō�̔���i���Ǝv�������A�h�ɖ߂��đ傫�ȃ��J����t�̔M����������Ă���ƁA������G���W���Ɏv�����藁�т��������B�����ē����̓r�₦�ʂ����ɃG���W����������ƁA����Ȃ��Ȃ�����Ȃ�Ƃ������������B�G���X�g���Ȃ��悤�ɒ��ӂ��Ȃ���G���W���S�̂̉��x���オ��̂�҂��āA�悤�₭��X�͋ʗ���������Ƃɂ����悤�Ȃ킯�������B
�@ ���Â��߂����炭�������Ƃ���ō�����ܓ��͍����l�㍆���ƍ��������B�����n�_�ō��܁A�l�㍆���`���ɐV�����ʂɌ����Đ��i���͂��߂����A���Ȃ�Ԃ�����ł��Ďv���悤�ɂ͐i�߂Ȃ��B��͂菬�o�A�������ʂɒ��ڒʂ����̍������ʍs�~�߂ɂȂ��Ă���e�����낤�B�����w�ߌ�l���ܕ����̗����l�l���ɓn�ӂ�����悹��ɂ͒x���Ƃ��O���܁Z�����炢�ɂ͉w�O�ɓ������Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���̒��q���ƊԂɍ������ǂ����킩��Ȃ��B�n�ӂ���ɂ͖ق��Ă������A���͓��S���Ȃ��炸�ł��Ă����B����}������Ȏ��̋C�����̂䂦���A�l�㍆�ƕ��s���Đ��ɂ̂т鈢��̗���܂ł����ɂ̂�т�Ƃ��Ă���悤�Ɏv��ꂽ�B�����염�݂̎�͑N�₩���������A�c�O�Ȃ��Ƃɂ�����������ƒ��߂Ă���ɂ͂Ȃ��B�͂��߂̗\��ł͒����ɒ����܂łɂǂ����ʼn���ɂ͂�����肾�������A�ƂĂ�����ǂ���ł͂Ȃ��Ȃ����B�n�ӂ���Ƃ̗��̏I����ԋ߂ɂ��āA�Ȃɂ��u�����v���邢�́u���퐶���v�Ƃ������̖����������̖��肩����߂čĂ�忂��������������������A���̂܂܂����Ɨ��𑱂���̂łȂ�������A����͂ǂ��ɂ��d���̂Ȃ����Ƃ������B
�@ �Ð쒬�ɒ������Ƃ���ł��炽�߂Ē������ʂւ̍ŒZ���[�g���������Ȃ����A�����l�㍆���ɕʂ�������Ĉ�����ɂ����鋴��n�����B�����Čܐ�A�������A����ɉ��Ύs�A�O���s���o�č����������ɏo���B���������ɏo����A���Ƃ͒����܂łЂƑ��肾�����B
�@�n�ӂ���Ƃ̂��̗��̏o���n�_�����w�ɓ��������̂͌ߌ�O���O�\���ŁA���ʓI�ɂ͓����̗\�莞���ɂ҂�����Ԃɍ������B���s����������L�����[�g���A�㔑�\���ɂ킽�闷�͂������Ė����I�������B�㔑���ׂĎԒ����Ƃ����O��Ԃ肾�����B�K���V��ɂ͌b�܂�A�X����葺��������ӂł̔����������S�s�����ŗB��̉J�V�������B
�@ ���̑S�s���ɗv������p�́A�H��A�Ԃ̔R����A�L�����H�����A�e��{�ݗ��p�����̂��ׂĂ��܂߂Čܖ��ܐ�O�S�~�A�����l������ɂȂ����ƓZ�܉~�ł������B����p�̂����ňӊO�ɑ傫�Ȋ������߂��͈̂�����ψ�l�����莵�E���S�~�ɂ̂ڂ�e�n�ł̉������������������A����̃n�V�S�������������T��ł�����A�����ƈ��オ��̗��ɂȂ������Ƃ��낤�B���܂ǂ��M�����Ȃ��Ǝv����������L�肾�낤���A���̏W�v�l�ɊԈႢ�͂Ȃ��B�Ⴂ�҂Ȃ�Ƃ������A�悢��������l���悭���܂��n�������^�����Ɛ��Ȃ���ނ������Ȃ��Ȃ��낤���A���̂悤�Ȑ��ɑ��ẮA�u�͂����������ʂ�A�z�Ȃ�ł��v�Ǝ���̋�������f���ɔF�߂�ق��͂Ȃ��B
�@ �ߌ�l���ܕ��������̗����l�l���Ŏዷ�ւ̋A�r�ɂ��n�ӏ~��������͈�l�z�[���Ō��������B��Ԃ���������̂����͂��Ă���w�O�ɒ��߂Ă���Ԃɖ߂����r�[�ɁA�݂�݂�Â��Ȃ��Ȃ܂���̑嗱�̉J���~�肾�����B�܂�œV��̗��l���A��X�̗����I���̂����т�����炵�đ҂�������Ă��������ł���B�ǂ����A�~�J�O���������s���ӂ܂Ŗk�サ�Ă������̂炵���B�������J�̒���˂��ĐV���Q�n�������̎O�����t�߂ɂ���������ƁA��A�O���[�g����������Ȃ��قǂ̔Z���ƂȂ����B�t�H�O�����v�������s�^�]�ŃJ�[�u�̘A�����铻�����z�������A����������t�߂܂ł͔Z�����͐���Ȃ������B���W�I�Ɏ����X����ƐV���암����֓��n����т͊��S�ɔ~�J���肵���ƕĂ����B�r���ʼn������Ƃ�����A���̗]�C�ɂЂ������肵�Ȃ���A�̂�т�ƈ�ʍ����𑖂�A�Z�������̌ߌ�\�ꎞ�\�����ɓ����{���̎���ɋA�蒅�����B�{�����璷���܂ł̉��������܋�Z�L�����[�g����������ƁA�S���s�������͎O�l���܃L�����[�g���ɒB���Ă����B

�i���j
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
1999�N11��24��
���L�̌��p
�@ �F����͓��L�Ƃ������̂��ǂ̂悤�ɂ��l�����낤���B�ߍ��A���́A���L�Ƃ������̂̎��Ӗ������܈�x�������Ă���Ƃ���ł���B�l�Ԃ̋L���Ƃ͑����ɂ��������Ȃ��̂ŁA�����̐l���̒��ŋN���������Ȃ�Ռ��I�ȏo�����ł����Ă��A��E�O�N������Ƃ��̑唼��Y�ꋎ���Ă��܂��̂����ʂł���B�܂��ē�\�N���O�\�N���O�̂��ƂƂȂ�ƁA�قƂ�ǂ��[�����̖��̉��ɕ�ݍ��܂�Ă��܂��Ă��āA�z���o�����Ƃ��Ă��ő��Ȃ��Ƃł͑h���Ă��Ă���Ȃ��B����ȂƂ��A�ق�̈�E��s�́A�ꍇ�ɂ���Ă͂킸����P��̃����̂悤�Ȃ��̂ł��c���Ă���A���ꂪ�A�z�̃L�[�ƂȂ��Ă��̓����̏o������������J���悤�ɂ��đz���o�����Ƃ��ł�����̂��B
�@ ���Ƃ��Ɠ��L�ȂǂƂ������̂́A�������l�Ɍ��J���悤�Ȃǂǂ����s���ȈӐ}�ł��Ȃ�������A���������ɂ킩��Z���L�^���x�ɂ��Ă������ق���������������B�܂��A�������Ă����A���ꑼ�l�Ɍ���ꂽ�ꍇ�ł������Q�Ă邱�Ƃ��Ȃ����A��̂��ɂȂ��Ă���́A�������Ă��̂ق������ɗ��悤�ȋC�����ĂȂ�Ȃ��B��T�ԂɈ�x���x�ł��悢����A������Ǝ��Ԃ������āA�ق�̈ꌾ�����A���ƂɂȂ��Ă��炻�̎��̎��Ȃǂ�z���o�����Ƃ̏o����悤�Ȏ��������̃L�[���[�h���L���Ă��������ŏ\�����Ǝv���B���X�Ɩ�����Ԃ�K�v���Ȃ����A���̎�����ԗ��X�ɏ����c���Ă����K�v���Ȃ��B
�@ ���Ƃ��A�u���������A��A�����A����A�����I�v�Ƃ������Ȃ�̕ϓN���Ȃ��Z�������ł��A���l���ǂ߂A�����ʂ��Ă�������Y��Ă������̓��̃h���}�e�B�b�N�ȏo�������h���Ă���Ƃ������Ƃ͏\���ɂ��肤�邱�Ƃ����炾�B
�@ �ǂ�Ȃɔg������̐l���𑗂����l�ł��A�����ߋ�����U��Ԃ�ɂ��������Ƃ��A�������̓����������̒��ɒ���ł��܂��Ă��āA���͂�A�������ȋL���Ƃ��Ă����̓��̏o������z���N�������Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ���A��͂肻��͔߂������ƂɈႢ�Ȃ��B
�@ ���͊w���̍��������ŎO�N�g���锎���ق̓��p���L�������p���Ă����B���̍ɂȂ��ċ������t���̓��L���߂����Ă݂�ƁA�����ɂ����킩��Ȃ������Z��������ʂ��āA���̔w��ɉB����Ă��鐔�X�̏o�����ⓖ���̗l�X�Ȑ����Ȃǂ����X�Ɣ]���ɑh���Ă���B���������̑����́A�����ɏd��ȏo�����������ɂ�������炸�A��������Y��Ă��܂��Ă������Ƃ���Ȃ̂��B�����ł͌����ċL���͂̈����ق��ł͂Ȃ��Ǝv���Ă��邵�A�܂��A�܂��d�x�̒s���ǂɂ�����悤�ȍł��Ȃ��̂����A����ł����̗L�l�Ȃ̂ł���B
�@ ���m�Ȍ����͖Y��Ă܂������A�u���L�̂Ȃ��l���Ȃ�āA�l�����h�u�Ɏ̂Ă�悤�Ȃ��̂��v�Ƃ����悤�ȈӖ��̌��t���c�����̐l���������B����܂ł��܂�C�ɂ��Ƃ߂��ɂ������̐l���̌��t�̔w�i���A���ɂ��Ă悤�₭�����ł���悤�ɂȂ��Ă��������ł���B�H�Ƃ����D���[���G�߂̂����Ȃ̂��A����Ƃ��A��͂肻��Ȃ�ɍ��Ƃ��Ă��������Ȃ̂��͂킩��Ȃ����E�E�E�B
�@ �Ⴂ����Ɏg���ӂ邵���\��\����p�̎蒠�A�r�W�l�X�蒠�Ȃǂ́A���̂Ƃ��ɂ͂����������̂Ɋ������Ȃ��Ă��A�̂ĂȂ��ł��̂܂܂Ƃ��Ă����ƁA���鎞���������Ƃ��A�����͊|�ւ��̂Ȃ��S�̍��Y�ɕς��̂ł͂Ȃ����Ƃ��v���B�����͏\���ɓ��L�̑�p�ƂȂ肤�邵�A���炽�߂ē��L���ȂǂƑ�ɍ\���Ȃ��Ă��A���̒��x�̂��ƂȂ�N�ɂł��e�Ղɏo���邱�ƂȂ̂�����E�E�E�B
�@ �����Ƃ��A������L����h�点�邽�߂̃L�[���c���Ă����Ƃ��Ă��A�����̃L�[�����p����]�͂������c���Ă��Ȃ��قǂɎ����̓��̂ق����{�P�Ă��܂�����A����͂����b�ɂȂ�Ȃ��B���������̂悤�Ȏ��ԂɂȂ��Ă��܂����ꍇ�ɂ́A�L�����Ăі߂����߂̃L�[���Ƃ�ł��Ȃ��ϑz�ݏo�����������ɂȂ����肷��\�������Ă���B�������Ă݂�ƁA���Ƃ��Ă�����L�̌��p�ɂ������邽�߂ɂ́A�ǂ�����背�x���̓��]�̓��������͈ێ����Ă����K�v�����肻�����B
�@ �L���ݏZ�̑��㏺����Ƃ�������������B�A�R�[�f�B�I�����t�̃R���N�[���őS���{�`�����s�I���ɂ��Ȃ������Ƃ̂���A�R�[�f�B�I���̖���ŁA�L�����ӂɂ͂��̉��t�ɖ�����ꂽ�t�@�������Ȃ��Ȃ��B�ނ��A�������コ��̑t�ł�▭�ȃA�R�[�f�B�I���̉��F�̗��ɂȂ�����l�ŁA�̂��炱�̕��Ƃ͂����Ԃ�ƍ��ӂɂ����Ă��������Ă���B
�@ ���́A���コ��́A�ȑO�A�u�V�l���s���ǂ��l�����v�̉����Ȃǂ����߂Ă������Ƃ�������ŁA�s���ǂ̂��Ƃɂ��Ă͂����ւڂ����B���łɑ��E���ꂽ�����e���ӔN�ɓx�̘V�l���s���ǂɂȂ��A���コ�g�A���đ�ςȂ���J���Ȃ��������Ƃ�������Ƃ����B���̂��߁A���コ���v�Ȃ́A���̎��̌o�����������A�e�g�ɂȂ��Ēs���ǂ̘V�l�������Ƒ��̕��X�̑��k�ɂ̂�����A�I�m�ȃA�h�o�C�X�������肵�Č��݂Ɏ����Ă�����B
�@ ���̑��コ��ɂ��ƁA�����A�V�l���s���ǂɂȂ�Ȃ��悤�ɂ���ɂ́A�l�\�ォ�炻�̗\�h�ɓw�߂�K�v������Ƃ����B���낢�날��\�h��̂Ȃ��œ��v�I�ɂ݂ďd�v�ȑ�̈�́A�Ƃɂ����w�����悤�ɐS�����邱�Ƃł���炵���B������A�ł��邩���肷�ׂĂ̎w�����悤�ɂ����ق����悢�Ƃ����B�w�̉^���͔]�������h�����A���ʓI�ɔ]�@�\�̒ቺ��s���ǂւ̐i�s���}������Ƃ����̂ł���B���̓_�A���y�ƂȂǂ́A�E�Ə�K�R�I�ɂ��ׂĂ̎w���g�����߁A�V�l���s���ǂɂȂ銄���͒Ⴂ�悤���B
�@ �����A���������ƂɁA���Ȃǂ͎w�����Ēe���y��ɖ����ł���B�n�[���j�J�Ȃ炻��Ȃ�ɐ������A���Ƀo�C�u���[�V��������������Ƃ��ȊO�́A�w�̉^���ɂ͂��܂�W�Ȃ��B��ƐO�A����ɔx�̉^�����]�̎h���ɗL�����Ƃ����̂Ȃ當��͂Ȃ��̂����A����Șb�͕����Ă��Ȃ��B���[��A�ǂ��������̂��낤�ƍl���Ă��邤���ɁA���������A�p�\�R���̃L�[�{�[�h�Ȃ炸���Ԃ�̂���@���Ă���Ȃ��ƋC�������B�L�[�{�[�h�̑���ɂ͓��R�w���g���B�p�\�R���̑���ɂƂ��Ȃ��ܖ{�̎w�̉^���͑����Ȃ��̂ł���B
�@ �p�\�R���Ȃ���������W�r�b�g�̃A�b�v���}�V���ȗ��̏�A�ŁA�ꎞ���A�����Ȋw�W�̋���\�t�g�̊J���Ɍg����Ă������Ƃ�����B�ʐM���������A�\�N�ȏ���O�Ƀj�t�e�B�T�[�u�Ȃǂ̃p�\�R���ʐM�V�X�e�����o�ꂵ�Ĉȗ��̒ʐM�}�j�A�ŁA�����̍���STRANGER�ȂǂƂ����ӂ������n���h���l�[���Ńp�\�R���ʐM�ɓ���Z���Ă����B���̐��ʁi�H�j�����ƂɁA�܂��C���^�[�l�b�g�̕��y���Ă��Ȃ����N�قǂ܂��u�d�q�l�b�g���[���h�F �p�\�R���ʐM�̌��Ɖe�v�i�V�j�Ёj�Ƃ����A�p�\�R���ʐM�̐l�Ԗ͗l�Ƃ��̖��_��`�����{���n���h���l�[���ŏ������肵���قǂ������B������A�w��̉^���ʂ����͌��݂Ɏ���܂łɂ��Ȃ�̂��̂ɂȂ��Ă���B���ꂪ�����ł���X�̒s���Ǘ\�h�ɖ𗧂��Ă���Ƃ���A����Ȃ��肪�����b�͂Ȃ��B
�@ ���܂�p�\�R����[�v�����S���̎���c�c�ǂ����̃\�t�g�n�E�X���A���낢��ȕ֗��Ȍ����@�\�╶���E�����֘A�̃f�[�^�̂����g���₷�����p���L��p�̃\�t�g�ł��J�����Ă���A�f�B�X�N�ꖇ�A���邢�̓������[�J�[�h�ꖇ�����ňꐶ���̓��L���J�o�[�ł���悤�ɂȂ�Ό������ƂȂ��B�������A���܂ł��A�V�X�e���蒠��f�[�^�E�x�[�X���̑��̃\�t�g�ނ����p����A����ɋ߂����Ƃ��ł��Ȃ��킯�ł͂Ȃ�����ǁA�����œ��L��p�̗D�ꂽ�\�t�g�Ɏd�グ�悤�Ƃ���Ƃ܂��܂����\�ʓ|�Ȃ��Ƃ������悤���B�߂������̋L������J��邽�߂̃L�[�ƂȂ���L�ƁA���̔]�̘V���h�~�̂��߂̎w�̉^�����Ƃ��Ȃ��L�[�{�[�h����c�c�l���Ă݂�ƁA����͂Ȃ��Ȃ����܂��b�Ȃ̂�������Ȃ��B�@�@
�@ AIC�̓ǎ҂̊F����A�K�x�̎w�̉^�����ێ����Ă������߂ɁA����Ƃ����肸�ɂ�낵���������ɂ��t���������������܂��悤�Ɂc�c�B�����H�c�cAIC�̓}�E�X�����œǂ߂邩�炠�܂�w�̉^���ɂ͂Ȃ�Ȃ��ł����āH�c�c�ł��܂��A�l�����w�̉^�����炢�ɂ͂Ȃ�ł��傤����A�������Ȃ����͂���ł������Ƒ����ł���I
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
1999�N12��1��
�܂�����������������i
�@ �R�A���̃��[�g���Ƃ��ċ�B�Ɍ������r���A�x�����H���Ƃ邽�߂Ɏ����Γ�݂̓��̉w�A�u�ӂꂠ���p�[�N�v�ɂ��郌�X�g����LAGO�i���[�S�j�ɗ���������B�����ɉf����L���Â��Ȏ����̌Ζʂ����z���ɖ]�܂�A�Ȃ��Ȃ��ɕ���̂��闎�����������͋C�̂��X�ł���B�����߂��̌Ζʂł́A�����̌Q�ꂪ�a����������H���x�߂��肵�Ă���Ƃ��낾�����B
�@�u�a�l�����܂��Ɨ_�߂���߂��I�v�Ƃ������L���b�`�t���[�Y�ɒނ��A�Ӂ[��Ǝv���Ȃ��炻�̑�߂��𒍕������̂����A��V����~���傤�ǂƂ������̒l�i����l���āA�̎^�����͓̂a�l�Ȃ���Ȃ��A���������n�R�����Ȃɂ���������Ȃ����ƁA����ȑz����y�����肵�Ă����B����Ȏ��̖ڂ̑O�ɉ^��Ă����̂́A���\���h���̂����߂��Z�b�g�������B���A�����A���F�̎O��ނ̂��ڂ�ƃl�M���̑��̖������Ղ萷������M�ɁA�}�{�^�̓y�r�A�������Ă̂��т̓��������^�̊۟C�A�����āA��̂����q������Ă���B�ǂ����A���Ɣ����̂��ڂ�͑₻�ڂ�A���F�̂��ڂ�͗����ڂ�A�����āA�y�r�̒��g�͂�������ɂ����č������̃_�V�`�ł���炵�������B
�@ ���̎�̑�߂���H�ׂ�̂͏��߂Ă������̂ŁA��u�A�ǂ��������ɂ��Č��ɉ^�ׂΈ�Ԃ��܂��̂��ƌ˘f�������A�����ɁA�����Ђ��̗v�̂Ŗ��킦�悢�̂��낤�Ǝv���Ȃ������B�����ŁA�܂��͂����q�Ƀz�J�z�J�̂��т��ĎO�F�̂��ڂ���ӂ�ɐU�肩���A�y�r�̃_�V�`�������Ղ蒍�����B���ꂩ��A�����Ɣ������Ă݂�ƁA���ɂ��ꂪ���܂��I�c�c�a�l�����������̂������Ƃ����ƁA�����ɔ[�����Ă��܂����B�\���ɐU�肩���Ă��]�肻���Ȃ��炢�ɂ��ڂ�̗ʂ������A���x���Ȃ��炲�т�H�אs���������ƁA�y�r�Ɏc�����_�V�`�̂ق������ꂢ�Ɉ��݊����Ă��܂����B�i�F���b�܂�Ă��đ�߂������܂����A���X�̕��͋C���Ȃ��Ȃ��̂��̂�����A�Ԃŕt�߂𗷂�����ɂ͐�������Ă݂邱�Ƃ������߂������B
�@ �����ΔȂ����Ƃɂ��đ�c�������A�l�c�s�X�ɒ������ɂ́A������ƒ��g�̋P���������Ȃ��瑾�z�����̒n�����̔ޕ��Ɏp���B���Ă������B�C�����̉v�c�s���A��`���ɂ��Ȃ�����ɓ������Ƃ���ɂ���Øa��ɂ��������鍠�ɂ́A������͐[�����łɕ�܂ꂽ�B���N�̎��a�A�u�e���a�v�̔��삪�N����͂��߂��̂͂��̎��ł���B���̎��a����������������������ƂȂ�ƁA�����̈ӎv�ł͂����ǂ��ɂ��R���g���[���������Ȃ��B
�@ �n�}�Œ��ׂĂ݂�ƁA�Øa�삩��A�ނݑ��A���h���A��㑺���o�Ĕ��s�܂ōׁX�Ƃ��������������Ă���B���܂����R�Ԃ̏W�����q���ʼn��т�R���̂悤�Ȃ̂ŁA���ɔ�����܂łɂ͑������Ԃ������肻�����������A�e���a�̔���ɂ����̂́u���̚k�o�v�ɓ������܂܂ɂ��̍ד��ɎԂ������ꂽ�B������Ƒ���ƁA�Ă̒�A�����͋ɒ[�ɋ����Ȃ�A�E�ɍ��ɂ��˂��˂Ǝ֍s���͂��߂��B�������̐[���J�⓻�H��D���q�������̎R���ŁA�_�[�g�̕������C�H�����̕��������Ȃ��Ȃ��B�����̃m�X�^���W�[�������o���Ȃ��瑖�邤���ɁA�ł���i�ƔZ���Ȃ�A�V��̐��X�����X���Ŗ������悤�ȉs���P��������͂��߂��B���D��U����̂����R�ŁA���ꂱ���́A�̉��������{���́u�Ŗ�̕��i�v�ɂق��Ȃ�Ȃ������B
�@ ���ɎԂ̒ʂ�C�z�Ȃǂ܂������Ȃ��̂��悢���ƂɁA���͓��[�ɎԂ𒓂߁A�����\���Ղ��܂ނ��ׂẴ��C�g�ނ������Ă݂��B�̂Ȃ���̂��̂悤�Ȑ[���ł̒��ł́A�����������O���[���̌��ł��������邭��������B�v�X�ɂ���ȑ̌�������ƁA�������͂��߂Ƃ��錻��l�������Ɍ��ɓ݊��ɂȂ��Ă��܂��Ă��邩��Ɋ�����������Ȃ��B�������͂��߂Ƃ��Ĉ�т͎����̈łɎx�z����Ă���A��A�O���ԊO�ɓ��ݏo���ƁA���ɒ��߂Ă���͂��̎Ԃ����������Ȃ��Ȃ����B�V�����ƁA�����̃T�t�@�C�����u���[�W���R����A�z������召�̌��̗����A���ꂼ��̑��݂��咣���邩�̂悤�ɋP���Ă����B����邭�Ȃ������ߍŋ߂ł͂قƂ�nj��邱�Ƃ̂ł��Ȃ��Ȃ�����̗͂���������������B
�@ �s�v�c�Ȃ��̂ŁA���炭����Ɛ�����ɖڂ�����Ă��āA�ł̒��ł�����Ȃ�Ɏ��E�������悤�ɂȂ��Ă����B���炭�����Ă������̌܊����A���̂Ƃ��Ƃ���ɖڊo��忁i�����߁j���͂��߂����߂��낤���B�c���̍��ɂ͓�����O���������i�ł͂��邪�A���͉��\�N�Ԃ肩�Ő̗̂��l�ɏo�����ł��������̂悤�ȋC�����ɂȂ����B�������A�̗̂��l�͍Ό����d�˂�Ƃ��̗e�p���ϖe���Ă��܂����A���̐���ƒn��̈ł̐D��Ȃ���̎p�ɂ͐̂̂܂܂̐��X���������߂��Ă��āA�Ȃ�Ƃ������������肾�����B
�@ �ĂюԂɖ߂��Ă��炭����ƁA�J�Ԃɂ����Ė��Ƃ̓_�݂���Ƃ���ɏo���B�ł̒��̂��������ɁA�����ʂ�ۂ�ۂ�ƁA�ق̂₩�Ȑl�Ƃ̖����肪������ł���B�u�܂�œ��{�̘b�̐��E�ɖ������݂�������Ȃ��c�c�v�Ƃ����z�����A��u���̔]�����悬���Ă������B�s��̖�̉ߏ�Ȃ܂łɃM���M���Ƃ������邳�����̐̂Ɏ̂ċ������u���̒g�����v�Ɓu�l�̉�����v���A�����ɂ͂͂�����Ɗ�����ꂽ����ł���B�ēx�Ԃ𒓂߂����́A�J�̌������ɓ���W���F�̖�����̈�ЂƂ����������ƒ��߂��Ȃ���A�ق̂��Ȍ��̉k��Ă��邻�̉ƁX�ɏZ�ސl�X�̎p�Ȃǂ�z�������ׂ��B�~��Ȃǂ͐���[�����Ƃ��낤���琶���͌������ɑ���Ȃ��B�����I�ȈӖ��ł̖L�����Ȃ�A�s��ɂ͋y�Ԃׂ����Ȃ��B�ł��A�l�X�̐S�͂����ƒg�����ɈႢ�Ȃ��B����Ȃ��Ƃ��l���Ȃ���Ȃɂ��Ȃ����グ�������A���邭�P������������̔����g���Ėk�̕��p�ւƗ��ꋎ���Ă������B
�@ ���̒n���ɂ����ẮA���Ȃ�̐��̉ƁX���������ԏW���ł��A���H�����̊X���͕S���[�g������S���[�g�������ɗ����Ă�����x�ɂ����Ȃ��B�����A���ۂɊm���߂Ă݂�ƁA����ł����\���邭�A�铹������̂ɂ���قǕs�ւ��Ƃ��������͂��Ȃ��B�邱��ȂƂ���𗷂��Ă݂�ƁA����̓s��̖��邳�̂ق����ǂ�ȂɈُ�ł��邩���悭�킩��B�u�Â����Ƃ͈����̂��̂ł���v�ƌ�������ɉߏ�ȏƖ��̈����s��ɏZ�ސl�X�́A���܂ɂ͂��������n����K�ˁA�������炢�͌Ȃ̊��o�ُ̈킳�Ȃ��Ă݂�K�v�����邩������Ȃ��B�����̓d�͋����̎O���ȏ���߂�悤�ɂȂ������q�͔��d���̊댯�����A�։�Ⓦ�C���ł̎��̂����������ɑ���ƂȂ��Ă�������ɂ����Ă͂Ȃ�����ł���B
�@ ���s�ɏo�Ė�̒��S�X�┋�`���ӂ��߂��������Ƃ́A�������ꍆ����Ӑ}�I�ɂ͂���A�R�A���Ɨ��ݍ����悤�ɂ��ĊC�݉�����D���`�����E�O�����ɓ˓������B�܂����s�̂͂���̏W����ʂ�߂��Ȃ���������A�ƕ��݂̊Ԃ�������悤�ɂ��Ă��蔲�����Ԑ����肬��̓��ɂȂ����̂ŁA����Ȃ�ɂ͊o�債�Ă������A���ꂪ�܂��A�₽��J�[�u�̑����\�z�ȏ�ɍׂ��������������B�������A����X���������ɍD�����̂�ł���ȂƂ����ʂ鐌���ȎԂȂǑ��ɂ��낤�͂����Ȃ������B
�@ �������A���������ƂɁA���̓��͖�̐��E�̃h���}�ɖ����݂����Ȃ�Ƃ��f�G�ȓ��ł��������B�E��ɓ��{�C�������낷�f�R��𑖂��Ă��邹���ŁA�_�X�Ǝ���L���ɋP�������ԋ����A�C���ɑ傫���J�����������������]���邱�Ƃ��ł����B�ЂƂ���傫���C�ɓ˂��o�����߂��̃X�y�[�X�ɎԂ𒓂߁A�����d���𗊂�ɊR�`���ׂ̍��}�ȋ�����������ƁA�Â��ɔg�̊���ɏo���B�������ɊL�k�̏��Ђ������ɏW�܂��Ăł��������ȕl�ӂȂǂ������āA�����^�Ԃɂ�ăT�N�T�N�Ƃ���������������тɉ��������킽�����B������������Ĉ�ӂɍ������낵�����́A��̂����܂ɑ̓����q�i�����j��𐴂߂Ă��炢�Ȃ���A�����ƒ����ɕ��������Ă����B
�@ �ĂюԂɖ߂��Ă��炭�i��ł����ƁA���̃��S���Ԃ����肬��ʂ�邩�ǂ����Ƃ����قǂɓ����͋��܂�A���������̓��͏Ɨt���Ƃ��ڂ������̖�������[���т̒��ւƂ͂����Ă������B�E�ւ��Ȃ��悤�ɍאS�̒��ӂ��Ȃ���A�Ƃ���J�[�u��傫���Ȃ������u�ԁA���肵���̌^�̍����F���������������C���w�b�h���C�g�̒��ɕ����яオ�����B����̂ق����A�s�ӂ�˂��ꂽ�������A���남�낵�Ă��̏�ɗ����s�������܂܂ł���B�Ԃ����߂Â��Ă݂�ƁA����͎l�A�ܕC�̃^�k�L�̌Q�ꂾ�����B�悤�₭���Ԃ��@�m�����炵���^�k�L�ǂ��́A�Ԃ̂����E��e�̋}�Ζʂ��Q�Ăł�ꂳ���ɂ悶�o��A�݂̒��Ɏp�������Ă��������A���Ԃ̏�ɖ������̂���������A�]��������z�������肵�āA���̗l�q�͎��Ƀ��[�����X�������B
�@ �O�����̏W���������ĎR���������Ă���ƁA���F���Ԃ炵�����̂��ɂ������{���̎����ڂɂƂ܂����B�s�v�c�Ɏv���ĎԂ���~��A�߂Â��ĉ����d���ŏƂ炵�Ă݂�ƁA�Ȃ�Ƃ����͉��F���ԂȂǂł͂Ȃ��A�̉��������ۂ������Ȗ����̎��������̂��B�ǂ����Â�������{�ɂ��铇�����̈��̂悤�ł���B�͔|���Ă���_�Ƃ̐l�ɂ͐\����Ȃ��Ƃ͎v�������A��A�O���f�Œ��Ղ����߂̔���Ď��H���Ă݂�ƁA�f�p�����ǂ�����i�ȊÎ_���ς���������t�ɍL�������B��Ɉڂ�c�������̍�������ɂ���₩�Ȃ��̂������B
�@ �������炵�炭�������Ƃ���ł́A���H�e���M�̒��ɖ쐶�̊`�̖������Ă���̂��������B�������������傫���������炢�̏����Ȋ`�̎������Ȃ�̐��Ȃ��Ă���ł͂Ȃ����B�����d���ł悭�Ƃ炵�Ē��ׂĂ݂�ƁA�����قǂ悭�n��Ă��āA���Ȃǂɂ��܂ꂽ�Ղ�������̂����Ȃ肠�����B��߂Ȃ��̂���Ƃ��ĐH�ׂĂ݂�ƌ��\���܂������̂ŁA����Ɍ܁A�Z�قǂ����Ƃ��Ă���O���̏W���ւƍ~��čs�����B�O�����̏W���ɓ����ĂقǂȂ����̓��͍L�������ɍ��������̂ŁA�[��̘e���T�K�̂ق��͂����łЂƂ܂��I���ɂ��邱�Ƃɂ����B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
1999�N12��8��
���̉��ȏ����͂���
�@ ���܂��ܐ����r�ܐ����w���t�߂ɂ����@��������̂ŁA���������ɂ����Đΐ_�������K�˂Ă݂��B�܂��C�w���̐g����������ȗ��̂��Ƃł���B��̏]�Z��̎q�ŁA������Ώ�̑�w�����A�����A�ΐ_�����̂������̃A�p�[�g�ɏZ��ł����B���Ȃ�̉��������A���e���̔����������ɂ́A����ł��t�������̂��鐔���Ȃ����҂̈�l�������B���߂������ɁA���݂����͑匙�������D��S�����͂₽�牠���Ƃ������ʓ_�Ȃǂ������āA�ƂĂ��E�}���������B
�@ �w������͉����ɂ��Ĕނ̃A�p�[�g�ɉ��������A������킸�����́u���l��v���J��L�����B������グ�āu�W�F�b�g�@�҂����I�v�Ƌ��Ԃɓ������u�҂����I�v�Ȃǂ�����D�d���ɔ��ʂĂ�ƁA�C���]�������˂Đΐ_������ɏo�����ă{�[�g��������A�U��������肵�����̂��B�ג����`�������ΐ_��r�̐^����������낵���͂ɔC���đ����܂���A�ق��̃{�[�g�ɂԂ��肻���ɂȂ������E�i�Ђキ�j�����������Ƃ�����B�r�̐��H�����ɕ�����ɒ[�ɕ��������Ȃ����Ƃ���ɉ˂��鑾�ۋ��̉���҃X�s�[�h�ł����蔲���悤�Ƃ��ċ����ɐڐG�A�]���������ɂȂ������ƂȂǂ��������B
�@ �T����x���Ȃǂɂ͎Ⴂ�A�x�b�N��Ƒ��A�ꂪ�����A�{�[�g���͌��\�ɐ����Ă����悤���������A�E�B�[�N�f�C�Ȃǂ͐Â��Ȃ��̂ŁA�ނ�l�̎p�Ȃǂ��قƂ�nj����Ȃ������B����ȐÂ��ȓ��ɐΐ_��r�̌Ζʂ�Ɛ肷��̂͂Ȃ�Ƃ��C�����̂悢���̂������B�����A�ΐ_��r�̓쑤�͟T���Ƃ����тɂȂ��Ă��āA�[��ꎞ�⌎��̔ӂȂǂɌΔȂ��U��ƁA�����ɂ��Ă͒��������炢�ɕ��������ꂽ���̂ł���B
�@ �܂��A�ΐ_��r�̂���ɉ��ɂ͎O�r�Ƃ�����ʂ̗N���Ɍb�܂ꂽ�r�������āA���̒r��т̐A���Q�́u�O�r����A���Q���v�Ƃ��ē�������V�R�L�O���̎w��������Ă����B�~�c���K�V����V���N�W�C�^�k�L���Ȃǒ������A�����Q�����Ă������߂炵���B�قډ~�`�������O�r�̎��ӂ͓������̂����ċ}�ΖʂɂȂ��Ă���A���ł��Â��قǂɎ�X�̑���������Ă����悤�ɋL�����Ă���B�ΔȂ��߂���ׂ��������X�X�L���̑��̐[���ɂ������ɕ����A���Ԃł����܃U���K�j�l��⏬���l��ɂ���q���̎p����������x�ŁA�قƂ�ǐl�e�͂Ȃ������B������A������Ƃ����T���ƋC�ǂ�Œr�̈�т��߂���������Ƃ��ł����B�H�̖����̍��ȂǁA���̎O��r�̐����ΔȂ�A������ƒr�ɓ˂��o���ٓV�Ђ̉E����ɗ����ē��̋珸�錎�߂�̂͂Ȃ�Ƃ��C���̂������̂������B�����ɂ������ɗh���X�X�L�̕�̌������ɕ����Ԍ��e�͉ԎD�̊G����A�z���������A�Ζʂɔ������h��f���錎���́A�s��̌��i�Ƃ͎v���Ȃ��قǂɌ��z�I�������B
�@ ����ȑz���o�[���ΐ_������߂��̃A�p�[�g�ɁA���X�A�킪���l��̑��_��U���ɂ����l�̉��ȏ������������B�u�a�c�̂��Z���Ⴀ�[��A�ꏏ�ɖ싅���悤�悧�[�I�v�Ɠ�́u��v���ɓƓ��̗}�g�Ƌ����̋����̍����������ŁA�ޏ��͂������C�悭�U�������Ă����B�����͓����܂����w�܁A�Z�N�����������A�������炵�����̔������L�т₩�Ȏp�Ԃɂ́A�V���̋C�i�ƈ炿�̂悳�Ƃł������ׂ����̂�������ꂽ�B������Ƃ͂ɂ��ނ悤�Ȕ��݂Ɖ��炵���G�N�{����ۓI�Ȃ��̔������́A�q���Ȃ���ɒm�I�ȋP���ƐS�̋������߂Ă���A�䂭�䂭�͑f�G�ȏ����ɐ������Ă����ɈႢ�Ȃ��Ƃ��v��ꂽ�B
�@ �a�c�̂��Z�����A���Ȃ킿�A�킪�w�{�����̑��_�́A�u�ӂ݂����A�ӂ݂����v�Ƃ����āA�������̏�����������A�悢�V�ё���ɂȂ��Ă����B�ނ́A���Ɠ������������̍����̈炿�Ƃ����Ďq���V�т̒m�b�ɂ͒����Ă������A�q���̑��������̂��ƂĂ����ӂ���������A���Ȃ������Ă����ɂ�������炸�A�ӂ݂����ɂ͂����Ԃ�ƋC�ɂ����Ă����悤�ł���B������������A���̍��A�����N���炢�̗V�їF�B���ߏ��ɂ��炸�A�ӂ݂����͂ӂ݂����ł�����҂�҂����v�������Ă����̂�������Ȃ��B
�@ ���̂Ƃ����璷���Ό������ꋎ�����B�v�X�ɖK�˂��ΐ_��������ӂ͑S�̓I�������萮�����s���͂��A�̂Ƃ͂��Ȃ�l�q���ς���Ă����B�{�[�g����͂��܂����������A�ȑO�̖ؐ��̎葆���{�[�g�͉e����߁A�����ɉ��������������̃{�[�g���قƂ�ǂɂȂ��Ă��āA�����炩�c���Ă���葆���{�[�g�������������̂��̂ɕς���Ă����B�������A�x�ƒ��Ȃ̂��A�����̃{�[�g�͂��ׂĊݕӕt�߂Ɍq�����߂��A�ΐ_��r�̌Ζʂ𑆂��킽��{�[�g�̉e�͊F���������B�y���ޏꏊ�������Ă����̗̂��l�����ƈ���āA���܂ǂ��̃����O�J�b�v���́A����ȂƂ���ł��������{�[�g�ɏ������͂��Ȃ��̂��낤�B
�@ �����̓��[�ɒ��ԏ���ł��A�ΔȂ��߂�������͊g������A�����Ԃ�ƕ����₷���Ȃ��Ă����B�ΐ_��̓�݈�тɂ́A�̓��̕�����̖ʉe���Â���u�i�A�i���A�N�k�M�A�g�`�Ȃǂ̍L�t���̑�����܂��Ȃ����Ȃ�̐��c���Ă��āA�ƂĂ��������͋C�̎��ёт��`�����Ă����B�k�݂ɕ��ѐ�������̑���ɂ��Ȃ�Ƃ������Ȃ�����������B�H�̑����ȑ��z�����̋�ɑ傫���X���[���̂��Ƃ������̂ŁA�����̎��X�̉��t���������[�z�ɉf���A���ܐ��������镗�ɗh�����āA���ォ��̗t�̃V�����[�ƂȂ��Ă͂�͂�Ɨ����Ă����B�ΔȂ̂��������ɐ�����O���̐j�t�����^�Z�R�C�A�̍g�t���N�₩�������B�����̃��^�Z�R�C�A���̂���ΐ_��r���ӂɂ��������ǂ����ɂ��Ă͂͂����肵���L���͂Ȃ��B������������A��r�I�ߔN�ɂȂ��ĈڐA���ꂽ���̂Ȃ̂�������Ȃ��B
�@ �Ζʂɂ̓J����I�V�h�����͂��߂Ƃ��邽������̐����̎p����������ꂽ�B�ӏH�Ƃ������߂̂������������̂�������Ȃ����A�����̐��͈ȑO�������Ȃ葽�������������B�������̉a�ƂȂ�r�̒��̏�����A�������������������l�q�͂Ȃ�����A������������r���U��l�������a��^���Ă���̂�������Ȃ��B�ΔȂ̂��������ɂ͒ނ莅�𐂂��V�l�����̎p����������ꂽ�B���܂͉����ނ��̂��낤�v���Ȃ��瑫���~�߂Ă��肰�Ȃ����̗l�q�߂Ă݂�ƁA����ނ�Ƃ������́A���Ԃ��a�ɂ��āA�Â��ȗ]���Ƃ���ɔ����[���z����ނ��Ă���Ƃ��������ł���B�E�B�[�N�f�C�ɂ�������炸�r�̎�����̂�т�ƎU��l�X�͂��Ȃ�̐��ɂ̂ڂ��Ă������A����҂̐�߂銄��������߂č����̂́A����̓��{�Љ���ے����Ă��邱�Ƃ̂悤�Ɏv��ꂽ�B�����w�����������ɂ͂���Ȃ��Ƃ͂Ȃ���������A����́A�܂�����Ȃ��A����Љ�̓����ƍ���ґw�̈�背�x���̐����̈���ɂƂ��Ȃ����ۂȂ̂��낤�B
�@ �l��`�̐Z���������[���b�p�Ȃǂł́A�̂���A�V�l��V�����O�X�܁X�����ȂǂŘV��̎��Ԃ��߂����p����������ꂽ���̂ł���B���̐g�Ȃ��U�������炵�Ă���ȂɖL���ȊK�w�ɑ�����Ǝv����V�l�������A�ǂ����҂����e���߂Č����̃x���`�ɍ��|�����������߂Ă���p��ڂɂ���ƁA���{�I�ȉƑ����x���̂Ă����̂ł͂Ȃ��̂��Ȃƍl��������������̂����A�ǂ������{�����ĂƓ����悤�ȏɂȂ��Ă����炵���B����Ԃ̕����Ɗj�Ƒ������܂��܂��i�ނ��̎���ɂ����ẮA�V������}�����l�͊F�A�a�C�ł��Ȃ�������͓Ƃ�Ŏ����߂����Ă������ׂ�g�ɂ��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��낤�B
�@ ����ȏ��ے����邩�̂悤�Ƀx���`�ɍ����l�̘V�l�̎p���������B���̘V�l�͂͂������ዾ����Ƀx���`�̘e�ɒu���A�t�����F�ɐ��߂ė[�z�ɕ����ԑΊ݂̖��̕��߂Ă����B�߂���˂����ޖؘR������ق̂₩�ɏƂ炵�o�����̔w���ɂ́A���t�ɂ͐s������҂������Y���Ă���悤�ł������B���͂��̘V�l�̂܂�����܁A�Z���[�g���̂Ƃ���ɘȂ�ŁA���̐l�̋��̓��ɑz�����d�˂Ă݂��B�C�̂����ł͂�������������Ȃ����A���ɂ͘V�l�̐S�̙ꂫ�̈�ЂƂ��������Ă���悤�Ɋ������ĂȂ�Ȃ������B
�@ ���炭���čĂѕ����o�������́A�ג����r�̔�������ɂ����̐Α���̑��ۋ���n���ĉ������̎����̑��Ղ����ǂ������ƁA�ΐ_������̍ʼn��ɂ���O�r�ւƕ����^�B�̂ƈ���ĎO�r�̎��͂ɂ͗��h�Ȗؓ����z������A�ȑO�̖������������ɁA���̂Ԃ�����₷���͂Ȃ��Ă����B���������ɕ��i��`����Ƃ����̃C�[�[�����������сA�Q���Ȃ��ĉa�����鐅�������̎p���J�����Ɏ��߂�l�X�̎p�������Ԃ�ƌ�������ꂽ�B����Ɛ����̗O���o��O�r���O�������芪���}�Ζʂ̎��ёт́A�K���̂̂܂܂ɕۑ�����Ă����̂ŁA�O�r���̂��̂̕���͂��܂��Ȃ����݂������B
�@ �o�[�h�E�I�b�`���O�̃X�|�b�g�ł������тɂ͊e��̖쒹�̐����₦�ԂȂ������n��A����H�ׂĐ����Ă���̂͂킩��Ȃ����A�܂�܂�Ƒ������щ��̂�����ǔL�������A�t�߂��M�̒���ؓ��̎��ӂ��䂪���̊�ɜp�j���Ă����B�ꌩ���������ł͔���Ȃ��������A�ŋ߂ɂȂ��Č��Ă�ꂽ�炵���ē��̉�����ƁA�ߔN�A�O��r�̎��R�N���ʂ��������Ă��Ă���A���̎��R�����ێ����邽�߂ɐl�דI�ɂ��Ȃ�̐����⋋����Ă���炵���B�×��A�ΐ_���̌���ɂȂ��Ă����O�r�̗N��������̗���ɂ͍R����A���̐_�ʗ͂����������Ă����Ƃ����킯�Ȃ̂��낤���B
�@ �O�r�̈�p���炱��������Β��ɓ˂��o���ٓV�Ђ̘e�ɂ͌ΖʑS�̂���]�ł��閳�l�x�e���Ȃǂ��݂����A�U��҂����������x�߂邽�߂̐�D�̃X�|�b�g�ƂȂ��Ă����B�܂����̏��鎞���ɂ͊Ԃ����������߁A�����Ō������y���ނ��Ƃ͂ł��Ȃ��������A���߂ƌ���A�����Č��̏o�̎������\���Ɍ��v����Ă��̋x�e���ɂ���Ă���A���݂ł��Ζʂɉf������������e�����߂��邱�Ƃ��낤�B
�@ �ΐ_���������n��߂���I�������ƁA�ΔȂ��炻�������Ȃ��Ƃ���ɂ�����������u���l��̐Ձi�H�j�v��K�˂Ă݂����Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B�����L���𗊂�ɏ����̑��_���Z��ł����A�p�[�g�̂������ꏊ��T���Ă݂����A�������������Ƃ���ɂ͟���������̉ƁX���������сA�̂̃A�p�[�g�̐Ղ��Â�����̂Ȃlj���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ă����B���������̃p�[�g�̑�Ƃ͎R�Y����Ƃ��������Ȃ��Ƒz���o���Ȃ���A����Ȗ��̕\�D���|�����Ă���Ƃ�T���Ă݂����A���܂������邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�����A�n�`�I�ɂ݂Ă����������ɈႢ�Ȃ��Ƃ����n�_�ɒH�蒅�����Ƃ͂ł����B
�@ ���肭��[�ł̂Ȃ��ɓƂ�Ȃ�Ő[�����S�ɂЂ��邤���ɁA���́A�u�a�c�̂��Z�����v��U���ɂ������̉��ȏ����̖ʉe������̂��Ƃ̂悤�ɑz���N�������B�����A�������̋߂��ɁA�����Ȉ�l�̍�Ƃ��Z��ł����B���������ƁA���̏����͂��̍�Ƃ̂��삳�����̂��B���ꂩ�炸���Ԃ�ƌo���Ă���̂��ƁA���Ă̂��̉��ȏ������Ⴍ�����������ւƕϖe�𐋂��A�e���r��T�����ɓo�ꂵ�Ă���p��ڂɂ����Ƃ��̎��̋����͑�ςȂ��̂������B�����āA���̂Ƃ����獡���܂ŁA����ɂ܂��������Ԃ��߂��������B
�@ ���������ƁA�ΐ_������̋߂��ɏZ��ł��������ȍ�ƂƂ́u�Α�̐l�v�Œm����h��Y����A�����āA���̉��ȏ����Ƃ́A���D�̒h�ӂ݂��̐l�ɂق��Ȃ�Ȃ��B���܂ɂ����ꏏ�ɗV�L���̂Ȃ����̂ق��͂Ƃ������A�u�ӂ݂����A�ӂ݂����v�Ƃ����Ί�Řb�������Ă����a�c�̂��Z�����̂ق��Ȃ�A�h������L���̕Ћ����炢�ɂ͗��߂Ă����邩������Ȃ��B���w�N�̐^�����݂����Ȃ��Ƃ�����Ă����킪���l��̑��_�̂ق��́A��������x����x�A�h����̂���Ɏf���A�h��Y����̎藿������y���ɂȂ������Ƃ�����͂��ł���B
�@ �������݁A��������Â��Ȃ����铹�����������݂��߂�悤�ɂ��Đΐ_������w�̂ق��ւƌ������Ȃ���A���͒h�ӂ݂���̏��D�Ƃ��Ă̍���̌䊈���S����F�鎟�悾�����B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
1999�N12��15��
���̋Ր��𑀂�ٍˁI
�@ �܌��̕��̂悤�ɗD�������炩���S�g���ݍ��ތ��̚������z�[���ɋ����킽��͂��߂��u�ԁA�Ε��ɂ��Ȃ����͌��������̍�����o�����B�X�e�[�W�ɗ����̏����ȃ��@�C�I���j�X�g�̑t�ŏo�������ȉ��̈�ЂƂɂ́A����Ƃ��͖��邭�A�܂�����Ƃ��͒W���P�����낤�s�v�c�Ȍ��ʂ�������ꂽ�B���炩���Đ[�����݂������A����ł��Ē��O�̍����������h���Ԃ邻�̉��F�́A�S�̉���ɂ��܈�̗ދH�Ȃ郔�@�C�I�����̖�����߂Ă���҂łȂ���ΐ�ɑt�ŏo���Ȃ����̂ł������B����\�ꌎ��\�����A�������c��I����z�[���ōÂ��ꂽ�씩�������@�C�I�������T�C�^���ł̂��Ƃł���B
�@ ���ۂɂ��̉��t�����ɂ���܂ł́A�����ȂƂ��낱��قǂ̂��̂��Ƃ͑z�������Ă��Ȃ������B�������ĉ��y�̐��E�̂��ƂȂǂ킩��Ȃ��������A�n�R�w���̍�����A�O�H���C���X�^���g���[�����ł��܂���Ȃǂ��Ē��߂������ʼn��t��ɂ����͂悭�o�������B���@�C�I�����̃R���T�[�g�ɂ������Ԃ�ƒʂ������A�\���X�g�̑t�ł郔�@�C�I�����̉��F�ɂ���قǂ܂łɊ��������̂́A�Ⴂ����ɃA�C�U�b�N�E�X�^�[���̉��t���Ĉȗ��̂��Ƃł���B
�@ �ŏ��̋ȖځA���[�c�A���g�̃P�b�t�F���O����ԁA�s�A�m�ƃ��@�C�I�����̂��߂̃\�i�^�A�g�����̉��t�����ɂ��������邱��ɂ́A�܂�Ŗ��@�ɂł������������̂悤�ɁA���̌܊��̂��ׂĂ��A�㊥��\���̂��̃��@�C�I���j�X�g�̑��錩���Ȃ����Ɉ������銴���ɂȂ����B�z�[���̒��O�̂قƂ�ǂ����Ɠ����悤�ȋC���ɂȂ��Ă����ɈႢ�Ȃ��B�S�̓I�ɂ��f���炵�����t���������A�Ƃ��ɍ�����̌��̋����͐▭���̂����Ȃ��A�����ɂ͂����炩�͂����̂̍d���ȋ������܂������ƌ����Ă����قNJ������Ȃ������B�������ɂ�������炸�A�����҂̑̓��[���܂ŁA���炩���A�S�n�悭���ݍ���ł���̂ł���B
�@ ��Ȗڂ̓x�[�g�[���F���̃s�A�m�ƃ��@�C�I�����̂��߂̃\�i�^���ԃn�Z���u�A���L�T���_�[�v���������A���̑�l�y�͂ɓ����ĂقǂȂ��A�������Ƃ����n�v�j���O���N�������B�c�����̖�Q�ɒ[�����M�a�������Ő씩��������͂قƂ�ǖڂ������Ȃ��B������A��u�ǂ��Ȃ邱�Ƃ��v�������A�������������A�Â��Ȍ����Œ��O�Ɍ����ꂽ�|��`����ƁA�s�A�m�t�҂̃h�~�j�N�E�n�[�����ɓ�����Ă������䗠�ɂ��������B�����āA�����āA���芷�������@�C�I�����������čĂѕ���ɗ��ƁA�������Ȃ��������̂悤�ɁA�N�₩�Ȍ������ƈ��|�I�Ȕ��͂������đ�l�y�͂�e���I�����B
�@ �x�e�����������ƁA���B�G�j���t�X�L�[�́u�`���ȁA ��i�\���v�A�G�����X�g�̑�Z�ԁu�Ă̖��c�̃o���v�Ɖ��t���i�݁A�씩���ŏI�Ȗڂ̃����F���́u�c�B�K�[�k�v��e���I�������Ƃ��A�z�[���S�̂������̗��ߑ��Ƃ��̎^�̙ꂫ�Ƃ����ʐ[���]�C�ɕ�܂�A�Ȃ𗧂l�͂قƂ�nj�������Ȃ������B�A���R�[���ɉ����Đ씩����͎l�ȂقǏ��Ȃ�e�����̂����A�T���T�[�e�̃c�B�S�C�l�����C�[���́A���̂Ȃ��ł���i�ƌĂԂɂӂ��킵�����t�ł������B�̂��炸���Ԃ�ƒ����Ȃꂽ�Ȃł���ɂ�������炸�A���̈�����[���X���������Ɏv�킸�ړ����M���Ȃ����قǂ������B
�@ ���t���f���炵���������A���܂ЂƂ��S������ꂽ�̂́A���t��̃p���t���b�g�ɂ���Ȗډ���̕��͂ł���B���ꂼ��̉��t�Ȗڂɂ͐씩���M�̉���������Ă����B���ƂŊm�F�����Ƃ���ɂ��ƁA�씩����́A���t����邲�ƂɁA���t�Ȗڂ̉�����������ŏ����̂��Ƃ����B���x�����t�������̂Ƃ���Ȃł��A����V���ɉ���������������炵���B�������A���̕��͂��Ȃ��Ȃ������Ȃ��̂Ȃ̂ł���B���Ƃ��A����̃R���T�[�g�̑��ȖځA�x�[�g�[���F���̃s�A�m�ƃ��@�C�I�����̂��߂̃\�i�^���ԁu�A���L�T���_�[�v�ɂ͎����̂悤�ȉ�������Ă����B
�@�u�x�[�g�\���F���̋Ȃɂ́A���ɂ����{�̖�̑������̂��̋P����K���ŋz���グ�Đ��������Ă����悤�ȁA�����ӎ��I�ȗ͂������܂��B�l����^���Ɍ��߁A�S�̐[���Ƃ�����@�艺���čl����������v���ɂȂ�A�s�v�c�Ȃ��Ƃɔ߂������Ƃ��ꂵ�����Ƃ������ɏ����Ă��܂��A�S�̐��E���L���L���ɂ��Ă����悤�ȋC�������Ă���̂ł��B�A���L�T���_�[�ꐢ�Ɍ�����ꂽ�\�i�^�̂����A���̎��Ԃ́A�x�[�g�[���F���̋ȗ������ɁA���X�e���Ă݂����Ȃ�悤�ȋȂ̈�ł��B�v
�@ �씩��������̂��Ƃ́A�挎�A�����V���́u�ЂƁv���ł��Љ�ꂽ�B���N�ꌎ�̔����ɂ́A�����O�q����́u�O�q�̕����i�e���r�����j�v�ɂ��o�ꂷ��Ƃ������ƂȂ̂ŁA���y�ɊS�̂�����͂����ɂȂ�Ƃ悢���낤�B�씩����ɋ����S�䂩�ꂽ���́A�m�l�̒���������āA�I����Ɋy����K�ˁA�Z�����Ԃ��������씩����A�Ȃ�тɂ��̂����l�̐��v����Ə��߂Ă��b����@����B���q�Ƃ��ǂ����Ɍ����ȕ��X�ł���B������炽�߂Ă����l�̂ق�����͓A�d�ȓd�b������A�܂��݂Ĉ�x������萬������Ɗ��k����@��������Ă��������邱�Ƃɂ��Ȃ����B
�@ �씩�������ٍ˂̃��@�C�I���j�X�g�Ƃ��Đ��E�ɂ��̈���ݏo���܂łɂ́A�z����₷��悤�ȋ�Y�Ɣ߈��̓��X���������悤�ł���B���郉�W�I�����ǂ̃C�^�r���[�̒��ŁA�씩����̓��[���A�����������Ȃ���W�X�Ƃ��̊Ԃ̎��������Ă��邪�A���̘b�͎��Ɋ����[�����A�܂����̌��ɂ����鐬������̓��{��̋����͂ƂĂ��������B����ꂪ�C����ςS�̉��̌���ʂ��Ĕ������邽�߂��낤�B
�@ ���������씩����́A�c����Ƃ̃A�����J���s���ɕ��ׂ��Ђ��s�̂̕��ז�p�����B�Ƃ��낪�\���ƌo���ʂ����ɍ��M�ƂƂ��ɑS�g�ɐ��A�������A�قǂȂ��g�̒��̔畆���܂����c�ɔ�������ԂɂȂ����B�~�}�ɒS�����܂ꂽ���n�̕a�@�ł́A�����̊m���͌܃p�[�Z���g�A����Ɉꖽ���Ƃ�Ƃ߂��Ƃ��Ă��ʏ�̌��N�͕̂ۏł��Ȃ��Ɛ鍐����������B�K���ň��̎��Ԃ����͖Ƃꂽ���A�씩����͂��̕s�^�ȏo�����������Ŏ��͂������Ă��܂����B���{�ɖ߂����c���씩�����O�ɂ��āA�䗼�e�̐��Y����Ɨ�q����Ƃ͈ꎞ���ߒQ�ɖ������閈���������Ƃ����B
�@ ���q�̏������l���A�ŏ��͏����w���ɂł��Ƃ������ƂɂȂ����̂����������A�߂��ɓK���ȏ����̎t��������Ȃ��������߂��̘b�͎������Ȃ������B��������̐��Y����͌��݂��|��ȂǂŊw���̎w�������Ă����郔�@�C�I�����̐搶�A���l�̂ق������y�ƂƂ����씩�����Ƃ��������A���y�Ő����Ă������Ƃ̌����������ɒɊ����Ă���ꂽ���߁A����܂Ő�������j�Ƃ���O�l�̂��q����Ƀ��@�C�I�����������邱�Ƃ͂Ȃ������Ƃ����B
�@ �����A���Ȃ̂ŁA�����ɂƁA���v�����v�Ȃ͏\�ɂȂ�����������ɏ��߂ă��@�C�I�������������Ă݂��B���@�C�I�����̖���Ƃ�����l�X�̂قƂ�ǂ͎O�A�l�ŗ��K���n�߂Ă���Ƃ�������A�����x���X�^�[�g�������킯�ł���B���Y������K�����������悤�����A��������̂ق�������ɂ悭�������B���Ƃ��Ɩ����Ă����˔\���ڂ��o�܂��A���X�ɊJ�Ԃ��͂��߂��̂��낤�B��������͈�N�������Ȃ������Ƀc�B�S�C�l�����C�[�����}�X�^�[���A�قǂȂ��Z�ʓI�ɂ����e�̐��Y����������Ă��܂����B
�@ �������Ɏ��͂��c���Ă��������́A�傫�Ȗ͑����Ɍܐ������g�債�ĕ`�������̂���Ȃ��ƂɕS���߂����p�ӂ��A����ŋȂ������Ă������A�قǂȂ����͂������܂������y�����ǂ߂Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B����ȍ~�̓s�A�m�ȂǂŒe����郁���f�B���Ȃ���A�y���̉�����e��L����ǂ�ł��炢�Õ�����悤�ɂȂ����Ƃ����B���܂ł́A���̋��ٓI�ȏW���͂ƋL���͂������āA��T�Ԃ�����ΐV�����R���`�F���g�����S�ɈÕ��ł��邻���ł���B
�@ �\�O�̂Ƃ������A�C�U�b�N�E�X�^�[���̑O�Ń��@�C�I������e���A�X�^�[���������̐��������Č��܂���قǂ̍˔\���������씩���N�́A������_�@�ɖ{�i�I�Ƀ��@�C�I�����t�҂ւ̓�����ނ��Ƃ����ӂ���B��������̏����ɂ��Ă̌䗼�e�̋�Y�Ɩ����������ꂽ�̂����̎��ł������炵���B����������������͂₪�ċ˕��w�����Z���o�ċ˕��w����w���y���ɐi�w�A�䂪���̃��@�C�I�����̑��l�ҍ]���r�ƂɎt���A����l�N�ɓ���w�𑲋ƌ�A�����h���ɂ���p���������y�@�iRoyal Academy of Music�j�̑�w�@�ɗ��w�����B�l�N��̈��㎵�N�ɂ͂������̉h�_����܂���܂��A�p���������y�@��w�@����Ȃő��ƁA�S���\�N�߂��ɋy�ԓ����y�@�̗��j���l�ڂ̃X�y�V�����E�A�[�e�B�X�g�E�X�e�C�^�X�̏̍������^���ꂽ�B��\�ܔN�Ɉ�x�����J�Â���鉤�����y�@�L�O�R���T�[�g�ɂ����ẮA�\���X�g�Ƃ��ĉ��t����Ƃ����h�_�ɂ��P�����B
�@ ���݁A�씩����̓C�M���X��{���n�ɂ��ăt�����X�A�h�C�c�A�I�[�X�g�����A�Ȃǂ̃��[���b�p�e�n�Ő��͓I�Ɍ������s���A�\���X�g�Ƃ��đ劈�����ł���B���㔪�N�O���ɂ͓����̃T���g���[�z�[���ł̓��{�t�B���Ƃ̋�����ʂ��ē��{�f�r���[���ʂ����A���N�̏\�ꌎ�ɋI����z�[���ōÂ��ꂽ�\�����T�C�^���̂ق������N�̃��T�C�^���Ɠ��l�ɑ�D�]�����B�܂��Ȃ��A�r�N�^�[����씩�����t�@�[�X�g�A���o���u�̗̂��Ɂv��CD����������邱�Ƃɂ��Ȃ��Ă���B
�@�u�p���ł́A�P�Ɋy���ɒ����ȉ��t�����邾���ł͂Ȃ��A����\�����������O�ɓ`���������w�т܂����v�ƌ��씩����́A�V���[���b�N�z�[���Y�̔M��ȃt�@���ł�����B���̂Ƃ��̕č��ł̓��a���ɓǂ�ł�������z�[���Y���̂����������ƂȂ�A�z�[���Y��i�͑S���ǔj�i���j�j�����̂��������B
�@�u�V���[���b�N�z�[���Y�̕���ƂȂ����x�[�J�[�X221�Ԓn�͉������y�@�̂����߂��ł����̂ŁA�z�[���Y�̃��@�C�I�����̘r���m���߂ɉ��x������K�˂Ă݂܂����B�h�A���m�b�N����̂ł����A�����s�݂ŁA�c�O�Ȃ��炢�܂��Ƀz�[���Y�Ƃ̑Ζʂ��ʂ����Ă��܂���v�Ƃ��肰�Ȃ������Ō��씩����̃W���[�N�́A����܂������ȉp���d���݂̂悤�ł���B
�@ ���o��Q�̂䂦�ɓ��ʈ�������邱�Ƃ̌����Ȑ씩����́A�����̐l�X�Ƃ������ʂɌ𗬂��A���y�ȊO�̂��Ƃɂ��Ă��L���w�сA�������ł��l�ԂƂ��Đ������Ă������Ƃ�]��ł���Ƃ����B�������邱�Ƃɂ���āA����̑t�ł鉹�y�����������[�݂Ɛ��݂𑝂��Ă������Ƃ��\���Ɏ��o���Ă̂��ƂȂ̂��낤�B������G�b�Z�C����Ȋw���A�N�w���ɂ�����܂ŁA�W���������킸�Ƀ{�����e�B�A����������ł��ꂽ�e�[�v�̏�������ēǏ����y����ł����邻��������A���̒m���Ǝv���̐[���͑����Ȃ��̂ɈႢ�Ȃ��B����ł��āA���������Ԃ���\���Ԃ̃��@�C�I�����̗��K�͌����������Ƃ��Ȃ��Ƃ�������A���������h���������ł���B�@
�@�u���������@�C�I�����̉��t��ʂ��ĕ\���������Ǝv�������Ƃ����O�̂ق��ɂ����܂��`������A�Ƃ����m�M��ꂽ���������Ƃ��K���ȏu�Ԃł��v�Ɛ씩����͌��B���Ƃ��A�V�ォ�畷���������Ă���悤�ȉ���t�ł����Ǝv���ĕ���ɗ������Ƃ��A���O�ɂ����ۂ��̂悤�ɕ��������Ƃ���A����͉����ɂ������тł���Ƃ����B���t�Ō����͈̂Ղ������A��������ۂɎ�������ƂȂ�ƁA�������ėe�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ����낤�B�@�@
�@ �h�C�c�̃V���c�b�c�K���g�ɉ��t���s�ɏo�����A�A��̓d�Ԃɏ��x�ꂽ�씩����́A���̓d�Ԃ�҂ԂɁA�w�߂��̘H��ň�l�̃W�v�V�[�̃��@�C�I�����t�҂��t�ł�c�B�S�C�l�����C�[�������܂����ɂ����B���t�ɐs����قǂɐ[�����������̃��@�C�I�����̉��F�ɍ��߂�ꂽ�W�v�V�[�̐S�ɐ[������ł��ꂽ�씩����́A����܂ł̎����̃c�B�S�C�l�����C�[���̉��t�ɑ���Ȃ����̂����������������A���̋Ȃɑ���l�����Ƃ���ɗ����������ԓx�����ꂩ�炠�炽�߂��Ƃ����B���̎v�킸�ړ����M���Ȃ�A�����l�܂�悤�ȃc�B�S�C�l���A�C�[���̋����́A����Ȍ����ȓw�͂�ʂ��Đ��ݏo���ꂽ���̂Ȃ̂��B
�@ ���ܓ�\���̐N���@�C�I���j�X�g�́A�~�n���ɓ���ł��낤�\�N��A��\�N��ɂ͂��������ǂ̂悤�ȉ��t�����Ă����̂ł��낤�B�Ȃ�Ƃ��y���݂ȍ˔\�̎����傪���ꂽ���̂ł���B���̂悤�ȉ��y�̑f�l�������̂��Ȃ��A��l�ł������̐l�X�ɓ��{�̐��Ⴋ�ٍ˂̃��@�C�I�������t���Ă��������������̂ł���B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
1999�N12��22��
���Ɨ[�z�̐�������
�@ ���B�Ɍ������r���A������Ɗ�蓹���ē��Â̒���K�˂��̂́A�L�����j���L���ȏH�Ձu���Â��v���I����ĎO���قǂ��Ă��炾�����B�����̏���̗h���Ȃ��A�Î��L���ȑ����ɐg���ł߂��g�q�����ɂ���ď��̎s����E�s�ɉg�����\�l��̉g�R���A���łɉg�R�W����̃K���X����̎��[�ɂɎ��܂�A��N�Ԃ̐Â��Ȗ���ɂ��Ă����B�d����`�l�g��������g�R�͊ԋ߂Ō���Ƃ������ɑ傫���B�e��̎��q�A�����̊��A����́A�A�P���A��D�A����ɂ͋T�ƉY�����Y���`�ǂ������̂ȂǁA�g�R�̌`�����ɂ����̎��X�̍H�|�E�l���r�ɂ�������������̂����肪�s������Ă��Ď��ɖʔ����B
�@ �g�R�W������o�����ƁA�O�ۂ̏����A�C��̏����ƕ��я̂���铂�Â̓��̏���������Ă݂��B���C��ɖʂ��邱�̏����́A���ёт̒����ƕ��A���m�̖����x�A���`�Ǝ���̑��l���ȂǁA�ǂ���Ƃ��Ă����Ɍ����Ȃ��̂ł���B���̎��ёт̒���D���������Ĕ����̕l�ӂɏo��ƁA�������Ƃ������E��̊C�������P���h��߂��Č������B�r�g�łȂ錺�C������̓��ɂ������Ă͂����Ԃ�Ɖ��₩�Ȋ����������B���̂��������ꂽ�Ƃ���ŗV�Ԉ�g�̎q���A��̉Ƒ��̂ق��ɂ͐l�e�炵�����̂͌�������Ȃ��B���Ƃ������Ȃ��J�����ɂЂ���Ȃ���A�����ɐ[�����Ղ����ݍ��ނ悤�ɂ��ĕl�ӂ�������ƁA�T�N�T�N�Ƃ����������Ƃ��̂����Ȃ����������������B
�@ �l�ӂʼn_��Ȃ���Ɛ��̂͂ĂւƋ}���H�̑��z�߂Ă��邤���ɁA�����̗[�z�͂����� ���Y�킾�낤�ȂƂ����z�����]�����悬�����B�����āA�����̏u�Ԃɂ́A�������̑z���͐��C�ɒ��ޗ[�z���������Ƃ��������Փ��ɕς���Ă����B���͋}���œ��̏��������Ƃɂ���ƁA���Îs�X���������ɋ삯�����A�ɖ����s���ʂւƃn���h��������B�O�\���قǂœ�����Ŗ������ɖ����s�X�ɏo��ƁA�������珼�Y�s���o�ĕ��ˑ勴�ւƑ����C�݉����̍����ɓ������B�E��ɍL����ɖ����p���珼�Y�p�ɂ����Ă̌i�ς͂Ȃ��Ȃ��������������������A�����̊C�ɒ��ޗ[�z��q�ނɂ́A�n�`�I�ɂ݂ċ��I�����_���ِՂ̂��镽�˓��܂ōs���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B��������˓��̐����܂ʼn�荞�܂Ȃ���ΑʖڂȊ����������B���ԓI�ɂ͂��肬��Ǝv��ꂽ����A�ڂ�ς�镗�i���ԑ��z���ɂ̂�т�ƒ��߂Ă���ɂ͂Ȃ������B
�@ ���Y�s�X���߂����ˑ勴�����Ȃ�߂Â��Ă������������낤���A�u�[�z�̐������܂ł��Ɠ�\��L���v�Ƃ����ē��̕������ˑR�ڂɔ�э���ł����B�ȂɁH�c�c�������H�c�c���Â����܁A���������܁A���傤�����܁c�c���Ɠǂނ̂��͒m��Ȃ����A���������A����ȓ��ǂ��ɂ��������H�c�c�����̒n���ɂ͂���Ȃ�ɐ��ʂ��Ă������̎����������A�s�o�ɂ��u�������v�Ƃ����n����ڂɂ���̂͏��߂Ă������B�C�ɂȂ��Ēn�}�Œ��ׂĂ݂�ƁA�Ȃ�ƁA���˓��̖k�����Ɋ��Y���悤�ɂ��ē�k�ɍג����̂т鏬���ȓ�������ł͂Ȃ����B���˓��Ƃ̊Ԃɂ͐����勴�Ƃ��������˂����Ă���炵���A�ǂ���炻���܂ŎԂōs�������Ȃ̂ł���B��B�{�y�̍Ő��[�ɂ����Ėk���̑�C�ɓ˂��o���悤�ɂ̂т鏬���ŁA���̐����ɂ͊C���L������肾����A���̓��̐��C�݈�т���͊m���ɔ������[�z��������ɈႢ�Ȃ��B������ƒn�}�߂������ł͕��˓��̈ꕔ�ɂ��������Ȃ����Ȃ̂ŁA����܂ł��̑��݂ɋC�����Ȃ������̂������Ȃ����Ƃł͂������B
�@ ��B�{�y�ƕ��˓����q�����ˑ勴�ɂ��������邱��ɂ́A���z�͑傫�������ɌX���A���˓��̒����w�ł��Ȃ��R���݂̈��ɉB��Ă������Ƃ��Ă���Ƃ��낾�����B�ቺ�͂邩�ɍL���镽�˂̐��˂̊C�ʂ͒W���s���N�̋P����X���A�[��̐��˂��䂭��ЂƂ̑D�e���s�v�c�Ȃ܂łɐ[�����D���������B���z��ǂ�������̂����ʂ̖ړI�������̂ŕ��˂̊X���݂𑖂蔲���A�������ڎw���ăA�N�Z���ݍ���ł݂͂����A���˓��͑z���ȏ�ɑ傫���ĎR�[�������B���������ʂւ̓��H���̂��̂͂�������ܑ�����Ă͂������A�����������L���Ȃ��A�J�[�u���N���������Ԃ��Ƃ����āA�X�s�[�h�͂��܂�o���Ȃ��B���v�܂łɐ������t�߂܂ōs�������̂͂ƂĂ��������ȂƎv���͂��߂��Ƃ��A�����J�ɂ��O���Ƀg���g���Ƒ��鉽�䂩�̒n���̔_��ƎԂ����ꂽ�B�I�Ɍ��Ēǂ������͕s�\�ƌ�������́A���̒i�K�ŗ[�z�̒ǔ����M�u�A�b�v�����B
�@ �C���͂���ʼn����ɕ����ԓx�����I��哇�Ǝv���铇�e���A�������Ԏ��ɐ��܂��Ă���B����̐������߂��ɂ����āA�������Ԃ��R�������Ă���̂��낤�B���̒E�͊��ƂƂ��ɁA����ȏ�s���Ă����ʂ��ȂƂ����v�����N���オ���Ă������A�ǂ��������܂ŗ�������u�s�������Ƃ���܂ōs���Ă݂邩�I�v�ƁA���܈�x�C���Ƃ�Ȃ������B�����āA�������́u���������܁v�Ƃ��ǂ߂邩��ȂǂƁA���}�C���ɕςȌ�C���������݂���������B���ƂɂȂ��Ĕ��������Ƃ����A�Ȃ�ƁA�������̓ǂݕ��́A����ɂ����̌�C���킹�̓ǂ݂������������̂��B�������ɓn���Ă���ڂɂ��������̗R����ǂ�����ł́A�u�����v�Ƃ������́u�s�������v�Ƃ������t�Ƃ͒��ڂɂ͊W�Ȃ������ł���������ǂ��c�c�B
�@ ����ɂ��Ă����̐��̒��A�ǂ��ɉ�������̂��͎��ۂɍs���Ă݂Ȃ���Δ���Ȃ����̂ł���B���������̒n�_�ň����Ԃ��Ă�����A���̖]�O�Ƃ������ׂ���A�̔����Ɗ����͂Ȃ������ɈႢ�Ȃ��B���j�I�ɂ������w�I�ɂ��M�d�Ȏ���������ȏ����ȓ��̈���Ɏc����Ă���ȂǂƂ́A���̓��̐��ƂłȂ����ɂ͗\�z�����Ȃ����Ƃł������B
�@ �����勴�̕��˓����n�����ɒ����Ƃ������ɐ����̓W�]���J���Ă����B���̋�ɖڂ����ƁA�Ȃ�Ɗ��ɒ����̂ƒ��߂Ă������z���܂����������肬��̂Ƃ���Ɏc���Ă���ł͂Ȃ����B�������߂��ɉ����ɂ̂悤�Ȃ��̂����Ȃт��Ă��邽�߁A���z�͗h��߂��悤�ȃI�����W�F�̋P���ł͂Ȃ��A�Â������[�g�F�����Ă������A�Ƃ����������C�̗����ł��邱�Ƃɂ͈Ⴂ�Ȃ������B�ʍs���������Ƃ��A��u�A�Г��S�~�̕��ˑ勴�Ɋr�ׂĕГ��Z�S�~�Ƃ��������勴�̒ʍs���͍��߂���Ȃ��Ǝv�������A�����Ɍ�����Ȃ���̓n���������̂ł�����ɋC���Ƃ��A���̎��ɂ͂���ȏ�[���͍l���Ă݂Ȃ������B
�@ �����A���ƂɂȂ��Ă���A�������ɏZ�ސl�X���������H�̈�Ƃ��Ă��̋��𗘗p����ꍇ����������������Ă���ƕ����A�������S�~�Ƃ����̂͂�����ƍ�����ȂƂ��炽�߂Ċ����͂����B���݂���Ă���܂����N�قǂ����o���Ă��Ȃ��Ƃ̂��ƂȂ̂ŁA�ˋ��ɗv������������҂���܂ł́A���ꂭ�炢�̒ʍs�����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂�������Ȃ��B�܂��A���Ă͂��̑勴�̉ˋ������͐������̐l�X�̔ߊ肾�����̂��낤����A�ˋ���̈��̕��S�͂�ނ����Ȃ��Ƃ���Ă�����̂��낤�B����Ȃ�̎���͂킩��Ȃ��ł͂Ȃ����A�Ȃ��Ȃ��ɑ�ςȂ��Ƃł͂���B
�@ �����勴��n���ĂقǂȂ��A�ԉ��ޑ��z�͐������̔ޕ��Ɏp���B�����B���̗l�q�����͂������́A�������̐��C�݂�D���Ăقړ�k�ɂ̂т铹�H���o�R���A�Ŗk�[�̑�o�G�蓔��Ɍ������Ă݂邱�Ƃɂ����B�������͂Ȃ�ƂȂ����̌`�Ɏ��Ă���B���̕��̒[�ɑ������铇�̓�[���𐼂Ɍ������Ă��炭���Ȃ�ɐi�ނ����ɁA�u�T���Z�b�g�E�G�C�v�ƌĂ�Ă����k�H�̓�[���ɏo���B�r���A�u���̊فv�Ƃ������y�ق炵�������̋߂���ʂ������A���̎��͂������ċC�ɂ����߂Ȃ������B
�@ ���̐₦�ԂȂ���r����ቺ�Ɍ����낷�T���Z�b�g�E�G�C�́A���̖��ɒp���ʉ��K�ȃh���C�u�E�G�C�������B���̒n�`�Ƃ��̓��H�̋���炷��A�Ԃő���Ȃ���A�ǂ�����ł����C�ɒ��ޔ������[�z��������䂭�܂Œ��߂邱�Ƃ��ł���ɈႢ�Ȃ��B���ɗ[�z��������ł��܂��Ă������A�����͂邩�ȓ��x�ߊC�̐�������ɍL�����́A��ʐԎ��̉����F�ɐ��܂�A���傤�ǐ������ɐڂ���悤�ɂ��āA���F�ɋP������̔��_���ׂ��������Ȃт��Ă���̂��������B���ɂ͒ʍs�ԗ����܂������Ȃ��A�Y��Ȏ��R��Ɛ肵�Ȃ��牓���z���ɒ^��ɂ͂Ȃ�Ƃ���D�ȏꏊ�ł͂������B
�@ ��������������̏ꍇ�Ɠ����悤�ɁA���̓�����]�ޗ[�z�́A���������̂�������̓~�̓����ł��������ɈႢ�Ȃ��B��B�̐����C��ɂ͑Δn�C��������Ă���B������ʂ��瓌�x�ߊC��k�サ�A�Δn�C�����ē��{�C�ɓ��邱�̒g������́A�Ă͂ނ��A�~�ɂ����Ă��₦�ԂȂ��ɑ�ʂ̐����C�����Ɍ������ė��������Ă���B���������āA�����̓��ɂ́A���Ƃ������ł������Ƃ��Ă��A���̏��ɂ͔��_��A�����łȂ��Ă������ɂ��������₷���B���z�����x���߁A�₪�Đ������ɋ߂Â����v���ɂ́A�z���������̔��_����A�ɂ̑w�߂��Đl�̖ڂɓ͂����ƂɂȂ邩��A�[�z���Â������[�g�F�Ɍ����邱�Ƃ͂����Ȃ��Ȃ��̂��B
�@ �̂�т�ƎԂ𑖂点�A�������̍Ŗk�[�A��o�G��ɒ������Ƃ��ɂ͂����ߌ㎵�����߂��Ă����B���ԏ�ɎԂ�u���A�H�̖�Ƃ͎v���Ȃ��قǐS�n�悢��C�ɐg���ς˂Ȃ���A���łɕ�܂ꂽ�W�]��ւ̍ד������ǂ��Ă����ƁA�قǂȂ�����̂���ꏊ�ɏo���B����Ƃ͂����Ă��A�����Ȍ����������ɖ��ł��邾���̂��������₩�Ȃ��̂ł���B�قڎO�Z�Z�x�̓W�]�������n�`�ł���̂ɂ��킦����V���ɋ߂��Ŗ邾�����̂ŁA�f���炵������������̂Ǝv���Ă����̂����A���̊��҂͌����ɊO���Ƃ���ƂȂ����B�Ȃ�ƁA���̖��͋����قǂɖ��邩��������ł���B���͂���Ȃ�̐�������ɂ͌��������A�܁A�Z�����̐��X���̗͂���܂ł������h��P�����V�̐���ɂ͂قlj������̂������B
�@ �����͊C��̂�����Ƃ�������X�ƔR�����閳���̋���������B�����I�ɂ݂ĂقƂ�ǂ̓C�J�ނ�D�̂��̂��낤�B����͂���Ŕ������i�ł͂���������ǂ��A���N�̍��Ɍ��Ĉ�����ǂ����������҂����ȋ���Ƃ͂܂�ŕ�����قɂ�����̂ł������B���͂Ȕ��d�@��ς����̋��D�̋���̓p�`���R���̏Ɩ����ɋ��̂��̂�����ł���B����̂��Ƃł��邪�A�n���o�g�̎��l�̃G�b�Z�C��ǂ�ł��邤���ɁA���̑�o�G���тł͌������یĂ�钿�����������ۂ����܌�����炵�����Ƃ�m�����B�₦���݂̌��������ꂽ�~�̔ӂȂǂɁA�I�[������̌��̃J�[�e���ɂ������c���̌��̑т������ɋP���Y���̂��Ƃ����B����凋C�O���ۂȂ̂������ŁA�s�m�Ƃ��Ȃ����A����Ȕ��˂Ƌ��܌��ۂɂ���āA�C��̋������C�ɓ��e���ꂽ���̂ł���炵���B
�@ ��������̋P���l���̊C�ʂ߂邤���ɁA����͂Ƃ������A�����Œ��߂閞���̂ق��͂��������Y��Ȃ��Ƃ��낤�ȂƂ����z�������Ă����B�[���ɓ��̊C���珸�蒩���ɐ��̊C�ւƒ���ł��������ɂ��A���v��ɐ���̋�ɕ����сA�₪�Đ��̐������ւƗ����Ă����O�����ɂ��A���t�ł͕\��������ɈႢ�Ȃ��B������������A�������Ƃ������������̖�̒��߂��f���炵�����ƂƊW������̂ł͂Ȃ����A�ȂǂƏ���ȑz����������������B�����A���̂��Ƃ�g�������Ċm���߂�ɂ́A���̖�����v����čēx���̓���K�˂Ă݂�K�v�����肻���������B
�@ ��o�G�蓔������Ƃɂ����������ɂ͂����ߌ㔪�����߂��Ă����B��̂��Ƃ��Ԓ����ɂ��悤���Ƃ��v�������A���C�ɓ��肽���C�����Ă����̂ŁA���̎��Ԃ���ł����߂Ă����h�����ǂ����ɂȂ����̂��T���Ă݂悤�Ǝv���������B�����ŁA�������ɓn���Ă����Ɏ�ɓ���Ă����������̗��وē��K�C�h�}�b�v�����ƂɁA�߂ڂ����Ƃ���Ɏ��X�Ɠd�b�������Ă݂��B����Ȏ��ɂ͓������s�̌g�ѓd�b�Ƃ������̂͂Ȃ�Ƃ����肪�����B
�@ ���������ƁA���낢��ȗ��R�������āA�����ŋ߂܂Ŏ��͌g�ѓd�b�̎g�p���ӎ��I�ɍT���Ă����B�����A�I�Ƀt�@�b�N�X���e�Ȃǂł͂��܂��邱�Ƃ̂ł��Ȃ��A�ڎ��M�Ȃǂ��肪����悤�ɂȂ��Ă���A�Ƃ��Ƃ��g�ѓd�b��������������Ȃ��Ȃ����B�l�����ꂽ�R���◣���Ȃǂ̗���ɂ���Ȃ���A�m�[�g�p�\�R���őł������e�f�[�^��ҏW����������A���e���e�Ɋւ���A���������肷��ɂ́A�g�ѓd�b�ɗ��邵���Ȃ��Ȃ�������ł���B���R�A���̌g�ѓd�b�̎�v�p�r�͎��M���e�f�[�^�̑���M������A�K�v���ȊO�͓d������Ă��邱�Ƃ������A���M�Ҕԍ��̂ق����ʏ�́u�s�ʒm�v�ɃZ�b�g�����܂܂ł���B
�@ ���Ԃ����Ԃ������̂ł��ׂĒf������̂Ɗo�債�Ă������A�ىY�n��̌˓c���Ƃ������ق��[�H�����łȂ甑�߂Ă����Ƃ������Ƃ������̂ŁA�����ɂ����b�ɂȂ邱�Ƃɂ����B�˓c���ɓd�b����ꂽ�ہA���̓X�d�����͑����̂ł����H���͂ǂ����܂��Ă��邩������Ȃ��Ƃ�����ꂽ�̂ŁA�����ƂȂ�������p�ɐς�ł���َq�p���ł��������ė[�H�ɂ�������肾�����B�����A�K���ɂ���o�G���䂩��ىY�n��Ɍ������r���ňꌬ�����I�ƒ��O�̎��i���������邱�Ƃ��ł����̂ŁA�����ɔ�э��ݖ����[�H�����܂��邱�Ƃ͂ł����B
�@ �˓c���͐������ł͌Â����ق炵���A�o�}���Ă����������َ��v�Ȃ͂ƂĂ������̂������X�������B���l�̌��t�ɂ��A���̐������͌����Y��Ȗ����̓��Ȃǂ�I��ŖK���ƍō����Ƃ̂��Ƃ������B��͂�A������o�G����őz�������ʂ�A���̓��̌��̔������͊i�ʂ̂悤�ł���B�������Ƃ����n���́u���������܁v�Ɠǂނ̂��Ƃ������Ƃ��A�˓c�����ق̂����݂��狳������B�ނ��A���̓��ɗ���r���ł̂ӂ�������C���킹�̓ǂ݂����܂��ܐ������������ƂɁA�v�킸����������̂͌����܂ł��Ȃ��B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
1999�N12��29��
�������̌Î��ߌ~
�@ �����������𗣂��O�ɁA������Ƃ����������̔����فu���̊فv�ɗ�������Ă��������Ǝv���������B���������������܂ł���Ă����̂�����A���̗��j�Ɩ����ɂ��đ����Ƃ��m���Ă��������ƍl��������ł���B�����ɂ��̉J�͗l�Ƃ����āA���C���������̌i�ς��y���ނɂ͂��܂ЂƂ̏��Ƃ������Ƃ��������B�������A����Ȍy���C�����ŖK�˂����̊ق́A�Ȃ��Ȃ��Ɍ��������̂��锎���ق������B
�@ �Î��ߌ~�@�̂��܂ɓ`���y�n�Ƃ����Θa�̎R���̑��n���������B������̂ق��͎����ߋ��Ɉ�A��x�K�ˁA���̒n���̓`���I�Ȍ~���̓W��������ڂɂ������Ƃ�����B�����A��B�炿�ł���ɂ�������炸�A���C��т��猺�E��ɂ����Ă̌Î��ߌ~�ɂ��Ă͂قƂ�ǒm���������Ă��Ȃ������B�͓̂��x�ߊC������{�C�ɂ����Ă�������̌~���������Ă��āA�ꕔ�n��̋��������������߂��Ă����Ƃ������炢�̂��Ƃ͕����Ă������A���̏ڍׂɂ��ĂƂ��ɋ����S������悤�Ȃ��Ƃ��Ȃ������B������A����Ȑ̂̌~�߂�̗l�q���Ԃ��ɓ`����M�d�Ȏ����ɂ��̓��ł߂��肠����Ƃ͍l���Ă����Ȃ������̂��B
�@ ���̊قɓ��ق��Ă����ڂɂƂ܂����̂́A���āu�E���i�����ȁj���v�Ƃ��Ă�Ă����`���I�Ȍ~���@�ɂ��Ă̑f���炵���W�������������B�E���Ƃ͂������~�̂��Ƃł���B�����܂����̋����[���W�����̗��ɂȂ��Ă��܂������́A���̌o�̂��Y��ČX�̎�������ЂƂH������悤�Ɍ��Ă܂�����B�܂��A�ڍׂȉ�����������m�F����悤�ɓǂ�ł��݂��B
�@ ���ē��{�C��тɑ����������Ă��~�̌Q�́A�~�ɂȂ�ƑΔn�C���A�܂��͌��C�傩�������ӂ��o�ē��x�ߊC���ʂւƓ쉺���A�ĂɂȂ�Ƌt�R�[�X�����ǂ��ē��x�ߊC������{�C���ʂւƖk�サ���B�a�����߂Ȃ���A���x�ߊC�Ɠ��{�C�Ƃ̊Ԃ��G�߂ɉ����čs�������Ă����킯�ł���B�O�҂́u���~�v�A��҂́u����~�v�ƌĂ�Ă����B
�@ ���C�傩�������o�Čܓ����ӂ֔����邩���̋t���[�g���Ƃ�~�̌Q�́A���̊C��ɂ��铇�X�Ƌ�B�{�y�Ƃ̒n���I�W�Ȃǂ������āA���̋������H��ʂ炴������Ȃ��B�K�R�I�Ɍ~�̉�V���[�g�Ɖ�V����͑傫����������邱�ƂɂȂ邩��A���̈�т͐�D�̕ߌ~��ƂȂ�B�Ȃ��ł��������ƕ��˓��Ȃ�тɂ��̋ߗ����̎��Ӑ���́A�ܓ����ӂƕ��Ԍ~�̉�V�H�̗v�Ղɂ������Ă����B������A�]�ˎ���A���������~���̒��S�n�̈�ɂȂ����͎̂��R�̂Ȃ��䂫�������̂��B
�@ �I�B�̑��n������Ō~�߂������Ă����˂��g���\�����I�����ɂ͂�鐼�C��тɂ܂Ői�o���Ă����̂��_�@�ƂȂ��āA���̎��ӂɓ˂��߂莮�ߌ~���L�܂��Ă������炵���B�₪�āA�v�x�ƂƂ����ꑰ�́A���������͂��߂Ƃ��鐼�C�e�n�Ɍ~�߂�Ɖ�̏����A����ɂ͌~����~�����̑��̌~���i�̔������ɉc�ށu�~�g�v��g�D���A����ȗ��v���グ���B���˔˂̍����ɂ�����̍v�������������Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B�ܓ�����Ȃǂɐi�o�����~�g�̕ߊl�������킹�Ă̂��Ƃł͂��邪�A�v�x�Ƃ̋L�^�Ɏc���Ă��邾���ł��S�l�\�N�ԂŌ~�ߊl������A�����v�͎O�S���������Ƃ����B�N���ψ�l�Z���̕ߊl���A�ݕ��Ɋ��Z����Ɠ��]�̎��v�����������ƂɂȂ�B
�@ �]�ˎ���̉�ƂŐ��V���L�̒��҂ł�����i�n�]���Ȃǂ́A�͂�鐶������K�˂Ē����ɂ킽���Đ����A���炪�������������̕ߌ~�̗l�q�Ⓡ�̕����Ȃǂ������ɕ`�ʂ����B������ʂ̊G�}��L�^���͌��݂��c���Ă���A���̋M�d�ȊG�}���{�̈ꕔ��g��̎ʐ}�Ȃǂ��ٓ��ɂ͂ӂ�ɓW������Ă���B�����̎����������ƒ��߂邤���ɁA�܂�Ŏ������g�������̌~���ɗ�������Ă���悤�ȍ��o�Ɋׂ�L�l�������B
�@ �~�g�͋����قǍ��x�ɑg�D�����ꂽ���Ƒ̐���~���Ă���A�g���̉v�x�Ƃ_�ɂ��āA���ۂɌ~��߂�u����v�ƁA�߂����~����̏������Ĕ̔�������ߌ~������⋋���B�����肷��u�[����v�Ƃɑ�ʂ���Ă����B�����āA����g�D���[����g�D������ɍׂ����A�A�O���̉����g�D�ɕ������Ă����B���Ƃ��A����͌�����g�⋙�g�ɁA�܂��[����͊��蕔��A��̉��H�g�A�����⋛�����Ȃǂ̊e��X�ܑg�D�A����ɂ͒b�艮��ԉ��Ȃǂ̕ߌ~�p������̐���⋋�g�D�Ȃǂɕ�����Ă���Ƃ�����������B���̑S�̂̍\���Ɖ^�c�`�Ԃ͌����Ɗ畉���̂��̂ł���B
�@ ���ۂ̓˂��߂�ߌ~�̗l���͑s��Ȃ��̂ł������炵���B����̌�����g�̊NJ�����u�R���v�Ƃ����R��̌����菬���̔Ԑl���~�̌Q������ƁA�����T���ȂǂŌQ�̈ʒu��~�̎�ށA�����Ȃǂ����g�ɒm�点��B�H�������C�ʂ���ڂ𗣂��Ă͂����Ȃ��R�������ł̌�����̎d���͑z���ȏ�ɑ�ς������炵���B����������v�܂ŁA�K����A�������قǂɓ����ꏊ�ɍ������܂܂����Ɠ����C������߂Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ����A��ɂȂ��ďh��ɖ߂��Ă����A�����̎d���ɍ����x���邩����͂��ݖ�X�����͔����˂Ȃ�Ȃ��B䩔��Ƃ����C������������Ă���Ɩڂ����Ă�����Ă��邩��A�R�������̊C�ɖʂ����H�ڔ̂����̈ꖇ�������͂����A��������C�ʂ�����H�v�Ȃǂ�����Ă����B
�@ �R�������̌����肩��m�点�������g�͏\�ǂقǂ̑D�c��g��Ō~�̌Q�̉�V�H�ɐ��肵�A�߂ڂ����~��D�c�Ŏ��͂B�D�c�̌X�̑D�ɂ͂��ꂼ��̎�����Ɩ������^�����Ă���A���q�����͌o����ς��̎w���̂��Ƒg�D�I���@�\�I�ɍs�������Ƃ����B�܂��A�傫�߂̘a�D���lj��Ōq�������o�D�Ƃ������̑o���D�Ɖ��ǂ��̐��q�D���~�̂�����ɂ��A�g���j�̂����S���́u����i��낸����j�v�Ƃ�����������~�̔w���ɑł����ށB���ł����܂ꂽ�~�͑D�������������܂܁A�K���ɉj������������肵�Ȃ��瓦���f���B���Ď��ۂɎg��ꂽ������W������Ă������A�����S����̓����͂قڒ��p�ɑ傫���Ȃ����Ă���A�ǂ�Ȃɑ傫�ȗ͂������������@���ɕ�����Ă����B
�@ �����ɁA�~�����Ȃ����Ă����Ƃ�������v����āA�~�̗��e���͂ސ��q�D����A�̂̓㓁�i�Ȃ��Ȃ��j������傫�������悤�Ȍ`�́u�H�w�����v�����{���ł����܂��B�~�̔w���ɏ������˂������Ƃ�_���ĕ�������`���悤�ɓ�����ꂽ�Ƃ����H�w�����̕��̒[�ɂ́A��͂��v�ȉg���j�����Ă����B����ƈ���Ă��̉H�w�����ɂ͊|���肪���Ă��Ȃ��B���̖�́A�~�̔w���Ɏh�����������g���j�����������ĉ�����A���̌����ēx�ł����ނ��߂������B�������w���ɓ˂��h�����������������ɓ����j�̗͂ň���������邲�ƂɌ~�̐g�̂͐[�X�Ɛ荏�܂��B�l������H�w�����̗e�͂Ȃ��U�����J��Ԃ������邤���ɁA�E���ٖ̈������������̌~���S�g�ɐ[������̉j�͂������Ă���B
�@ ���������v����āA�n�h�i�͂����j�Ƃ��������ʼnj������肪�B�҂Ȓj�ǂ�����^��̂悤�Ȃ��̂����킦�Ė������Ō~�ɋ߂Â��A�~�̔w�⓪�ɂ悶�o���ċ}����˂��h���B�Ō�͌~�̂�����̋}���A�@�i�ċz�E�j����ĂƂǂ߂��h�����Ƃ����B���̗E�҂��s��Ȍ~���ɂ����ẮA�������h�ꓮ���葆���̘a�D�ŕK���ɖ\�ꋶ���~�ɋ߂Â��A�����̉s���Ȑn���Ŋl���ɗ��������������ɁA���R�A�����҂⎀�҂������o���B��ςȊ댯���Ƃ��Ȃ��d�������ɁA���ۂɌ~��߂鋙�g�̑g���ɂ͈��̔\�͎�`���~����Ă���A�r�̂悢�n�h��D���A�ǎ�Ȃǂ͍����e�n����X�J�E�g����A�����̑ҋ����^�����Ă������悤���B�����g�̐n�h�ł��A�\�͂ƋƐю���Ŏl�ԑD����O�ԑD�ցA���邢�͓�ԑD�����ԑD�ւƂ������悤�Ɋi�グ�����悤�ɂȂ��Ă����B�\�͂������V�X�e���ɂȂ��Ă����킯�ł���B
�@ ��Z�����N�A�I�B���n�̑��n�p�E�q�嗊�����ԕ߂莮�ߌ~���l�Ă���ƁA���ꂩ��\�N���炸�ł��̕ߌ~�@�����C��тɂ��L�܂�A����܂ł̒P���ȓ˂��߂莮�ɔ�ׂĕߌ~�����ƈ��S���͔���I�ɍ��܂����B�ԕ߂莮�ߌ~�͓˂��߂莮�ߌ~�̉��nj^�Ƃ������ׂ��ߌ~�@�ŁA�傫�ȖԂŕ����ʂ�~���߂�킯�ł͂Ȃ��B�~�̐i�s�����Ɍ~�̓����������ۂ�Ƃ͂���悤�ȉ~���^�ɋ߂���Ԃ��d�|���A����ɂ���Č~�̓������Ă����Ă���A�]���Ɠ��������œ˂��߂�̂ł���B�Ԃœ�������������ꂽ�~�̓p�j�b�N���N�����������o�������Ă��܂����ɁA�傫�ȖԂƂ���ɘA�Ȃ鉽�z���̑D���������邱�ƂɂȂ邩��A�v���悤�ɂ͓������Ƃ�Ȃ��Ȃ�A�[�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�B�����˂��߂�����ő_���킯���B�n�h�����͖Ԃ���|���葫�|����ɂ��Ă��e�ՂɌ~�ɋ߂Â��A���̔w���ɂ悶�o�邱�Ƃ��ł���悤�ɂ��Ȃ����B
�@ �����̍��ɂ́A���n�������������Ɖ�V���邽�߂ɓ˂��߂�ɓK�����Z�~�N�W���������߂�ꂽ�炵���B�Z�~�N�W���ɂ́A���Ƃ��Ɓu�w���~�v�܂��́u�����~�v�Ƃ����������Ă��Ă������Ƃ��A���͂����̎����ŏ��߂Ēm�����B��̂悤�ȏ��^�Ȍ~�A���邢�͂ǂ��ƂȂ���Ɏ����`�����Ă���~�Ƃ����Ӗ��ŃZ�~�N�W���ƌĂԂ̂��Ǝv���Ă������A�ǂ����A�u�j���Ƃ��̔w���̃��C�����������~�v���邢�́u�j���p���А��悭�������~�v�Ƃ������Ӗ������߂Ă���ꂽ���O�炵���̂��B
�@ �߂肷�������߂ɔw���~�������Ă���ƁA����ǂ͉������͂₢���x�ʼnj�������~�Ⓑ�{�~�Ȃǂ̑�^�~���_����悤�ɂȂ����B�ԕ߂莮�ߌ~�͂����̑�^�~��߂�̂ɂ��傢�ɈЗ͂������炵���B�����A������~���͔w���~����ԂƂ���Ă����悤�ŁA�����u�{���v�Ƃ��Ăꂽ�w���~�́A�ꓪ�ō����~�Ⓑ�{�~���̉��l���������̂��������B�����~�Ȃǂɂ́A���Ƃ��Ƃ́u�G���~�v�A���Ȃ킿�A�u����ɂ͓���Ȃ��A�ǂ��ł������~�v�Ƃł��������悤�ȈӖ��̌ď̂��^�����Ă����Ƃ������B
�@ �Ƃ��ɂ����A���܂̎��ォ��l����Ƃ��Ȃ荓���ߊl���@���s���邱�Ƃ��������B�e�q�A��ʼnj���ł���~�̎q�~���܂��߂炦��B�q�~��������ƕ�~�͂������痣��Ȃ��B���~�͂��̏�𗣂�Ă�������ǂ��A��~�̂ق��͂������������Ă��܂����̏�ɖ߂��Ă���̂��Ƃ����B�q�~���Ă��Ă��̎������V���Ō�܂ŗ���Ȃ����̕�~�������ɑ_���ߊl���Ă��܂��B�~�̕ꐫ���𗘗p�������̕ߌ~�@�Ȃǂ́A����̎Љ�ʔO���炷��Ǝc���Ŕ��̂����Ȃ����̂ł������B
�@ �����A�����������ߋ��̖��̑P�����l����ꍇ�ɂ́A�P���Ɍ���̎ړx����������ł��̐���f���Ă͂Ȃ�Ȃ��B�ߋ��̎��ۂɑz�����߂��炷���ɂ́A�ł��邩���莋�_���ߋ��̎���Ɉڂ��A���Ƃ����E�͂����Ă����̎���ɐg��u��������Ō��݂̎�����t�~����ɓW�]����K�v������B����̂悤�ɖL�x�ȐH�ƂƐH�ނɌb�܂ꂸ�A�����������e�Ղɂ͎�ɓ���Ȃ����������̐l�X�ɂƂ��ẮA�~�͕K�v�s���Ȑ����̗Ƃł������B�@�@
�@ �܂��A�ߌ~�Z�p������������̋Z�p����Ƃ���ׂ�Ƃ���߂Č��n�I�ł������B�D�͎葆���̘E�D�ő��x���x���A�������Ĉ��萫����������A���̗��ꂪ�s���肾������V�r��͗l�������肵�Ĕg�������ƁA���D���̂��e�ՂłȂ������B�܂��āA����ȏ̂Ȃ��Ŏd���߂悤�Ƃ����~�ɖ\���ꂽ��A��̐a�D�Ȃǂ͂ЂƂ��܂���Ȃ��������낤�Ǝv����B�V�j���x�̂͂₢�~��ǂ������邱�Ƃ͎���̋Ƃł��������낤�B�̂��ɉ䂪���ɂ��`�������ߑ�I�ȕߌ~�e����Ƃ͈قȂ�A��������⌕�̈З͂ɂ͌��E������������A�Z���ԂŌ~���d���߂邱�Ƃ͕s�\�ł��������ɈႢ�Ȃ��B
�@ ����Ȍ���ꂽ�̂��ƂŊm���Ɍ~���d���߂�ɂ́A����̊ϓ_���炷��Ύc���Ƃ��v����ߌ~�@�ɗ��邱�Ƃ���ނȂ������̂��B�l���悤�ɂ���ẮA�L���b�`���[�{�[�g�ƕߌ~�e��p���ċI�ɂ�C�̌Î��ߌ~�Ƃ͔�r�ɂȂ�ʂقǂ̐��̌~���Ƃ�܂������ߑ�ߌ~�̂ق����A�͂邩�Ɏc����������������Ȃ��B����Ď˂��E���ꂽ�e�q�A��̌~���A��X���z������ȏ�ɐ��������������Ƃ��낤�B
�@ ����Ȃ��Ƃ������ƁA�u����Ȍ~�̕߂�����������{�l�͂�͂�c���������v�ȂǂƊ��Ⴂ����A���j�I�z���͂Ɍ������O���l������邩������Ȃ��B�����A�������̕ߌ~�������Ƃ��������]�ˎ���A�����m����{�C��тł����Ƃ������̌~��߂��Ă����̂̓A�����J�ł���B���łɕߌ~�e���͂��߂Ƃ���ߑ㑕�������Ȃ��Ă��������̍��X�̕ߌ~�D�́A���{�ߊC�Ɏ��X�ƌ���A�I�ɂ�C�̕ߌ~�Ƃ͌��Ⴂ�̐��̌~��߂�܂����Ă����B�������A�߂����~�̓��͂ނ��A��⍜�A�E��K���ɂ�����܂łʂȂ��g���������{�l�̏ꍇ�ƈ���āA�A�����J�Ȃǂ̕ߌ~�́A�e��̌~����R���Z�b�g�̍ޗ��ɂȂ�ꕔ�̓���̎悷�邱�Ƃ������ړI�ł������B
�@ ���������A�y���[���Y��Ɍ�����{�e�n�̊J�`�얋�{�ɔ������w�i�ɂ́A���{�ߊC�ɂ܂ł���Ă��鎩���ߌ~�D�ɂƂ��āA����H�Ƃ̕⋋�`�A����ɂ͑䕗�Ȃǂɂ��ЊQ���ً̋}���`���ǂ����Ă��K�v���Ƃ���������������B�܂��A�����܂Ŏ����k��Ȃ��Ă��A�����q���̍��܂ł̓A�����J�͐��E�L���̕ߌ~���ŁA��ʂ̔����{�~�▕���~��߂��Ă����B�ߌ~�I�����s�b�N�Ə̂��Ċe�����܂��~�̕ߊl�����������Ă�������̂��ƂŁA���w�Z�̐}�����̐}�ӂ��N�ӂŒ��ׂ��A�����J�̔����{�~�̕ߊl�����ɖڂ������������Ƃ����͂��܂��͂�����Ɖ����Ă���B���ۓI�Ȍ~�̕ی�^���̍��܂�͌��\�Ȃ��Ƃ��Ƃ͎v���̂����A�ُ�Ȃ܂łɌ~�ی삪����A�~��߂鍑���͔ȍ����̂悤�Ɍ��`�����悤�ɂȂ����̂́A�Ȋw�Z�p�̐i���ƐH�Ǝ���̍D�]�Ō~��ߊl����K�v�̂Ȃ��Ȃ������̂��鎞������̂��ƂȂ̂��B
�@ �����A�Z�p�̊v�V�ɂƂ��Ȃ��H������H�Ǝ���̈��ω����N����A�l�ނ�������H����K�v���Ȃ��Ȃ��������Ƃ���A���E�e���ɂ�������H���̎���͉��ƂȂ�A�����̐������͌������邱�Ƃ��낤�B���������̂悤�ȏɂȂ����Ȃ�A���̈���^�������E�e�n�ŋN���邩������Ȃ��B�����āA���̎��ɂ܂�������H�ׂĂ��鍑���▯�����������Ƃ���A�����̐l�X�͔�l�ԓI���ƌ����������邱�ƂɂȂ�ɈႢ�Ȃ��B����Ȏ��オ���������Ƃ��A���݃X�e�[�L�������Ƃ��H�ׂĂ��鍑���̎q�������́A���������̐�c�̂��ƂȂǂ����ƖY��A���H�l��i�H�j���̐�N�ɗ��̂��낤���B�l�ԂƂ͂��̎�����Ƃ��Ƃ�Ȃ��̂Ȃ̂ł���B
�@ �Î��ߌ~�Ɍg����������̋I�ɂ�C�̋��������ɂ��Ă��A���ۂɂ́A����Ȃ�Ɏc���Ŕ��Ȍ~�߂�ɂ܂������S�̒ɂ݂������Ă��Ȃ������킯�ł͂Ȃ��B����A�ނ���A�ނ�͌���̉�X�ȏ�ɐl�ԂƂ������̂̔��A�c�����A�����̑����ɋC�Â��A���������Ă����ӂ�������B�������̘b�ł͂Ȃ����A�~�̈ʔv�Ƃ��~�̕�Ƃ��������悤�Ȃ��̂������e�n�ɎU�݂���̂��A�����������w�i������������Ȃ̂��낤�B�������v�x�Ƃ̌~�g�̏ꍇ�ɂ́A�n�h���~�ɍŌ�̗��߂��h���ƁA�����Ɍ~���͂ޑD�̎ґS���������オ��A���₦���~�Ɍ������Ď�����킹�u�얳����ɕ��v�̔O�����O�x�J��Ԃ������邵������ɂȂ��Ă����Ƃ����B
�@ �d���߂��~�́A�O�q�������o�D�̉��̒����ɂ��̓������Œ肳�ꂽ�܂ܕߌ~�[����݂̊ɉ^��A��̉��H����Ƃ���E�l�ɂ���Ď�ۂ悭�������ꂽ�B���������͂��߂Ƃ��鐼�C�e�n�̉�̏�����Ƃ͋ɓx�ɍ���������Ă��āA��ӏ��̍�Ə�ő�^�~������Ɏl�A�ܓ����������邱�Ƃ��ł����Ƃ����B�����A�y���Ȃǂł͏������~�ꓪ����̂���̂ɂ������v�����Ƃ̂��Ƃ�����A�v�x�ƎP���̌~�g�������ɋ@�\�I�ȑg�D�W�c������������������悤�B
�@ ���ڂɌ~�Ƃ͊W�Ȃ����A��K�̓W�����̈���ɂ́A�����~�����G��Ƃ����]�ˎ���̋����͎m�̓��g��̑��������Ă����B�u�~�v�̈ꎚ�����̂������Ɏ��������o�g�̗͎m�̐g���͂Ȃ�Ɠ[�g����\���Z���`�ŁA�̏d�͕S�Z�\��L���A��̂Ђ�͎O�\��Z���`�A���̃T�C�Y�͎O�\���Z���`���������Ƃ����B�䂪���̗��j���̂Ȃ��قǂ̑�j�ŁA�~�̖��ɒp���Ȃ������킯�ł���B
�@ ���̊ق̌Î��ߌ~�����Ɉ��|����A�[���v���Ɏ䂫���܂�Ă��܂��������������A�Ȃ�Ɠ�K�̉��̓W�����ɂ͂��܂ЂƂz���������ʋM�d�ȗ��j��������Ă����̂ł���B���̓W�����ɑ��ݓ��ꂽ���͍Ăт��̏�ɓB�Â��ɂȂ��Ă��܂����̂������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N1��5��
�������ƉB��L���V�^��
�@ �L���X�g�����{�z���̑c�t�����V�X�R�E�U�r�G������l��N�Ɏ������ɏ㗤���Ă���A�͂�l�S�\�N�̍Ό������ꋎ�����B��N�������ł̓U�r�G�������l�S�\�N�L�O�ՂȂǂ��Â��ꂽ�悤�ł���B�L���V�^���Ǖ��߂�������Ĉȍ~�̓L���X�g���k������߂Č��i�Ɏ����܂��������Ô˂̂��G���������ŁA�U�r�G���L�O�Ղ���X�I�ɍÂ���A���O���瑽���̎Q���҂⏵�Ҏ҂��W�߂��Ƃ������Ƃ́A��ȗ��j�̂߂��肠�킹�Ƃł������ق��Ȃ��B���̃t�����V�X�R�E�U�r�G���̓��M���_�@�Ƃ��āA��B���k�����͂��߂Ƃ��鍑���e�n�ɃL���X�g�����}���ɍL�܂��Ă��������Ƃ́A�\�Z���I������\�����I�����ɂ����Ẳ䂪���̗��j�Ɍ���ʂ�ł���B
�@ �������㗤��A�Ăу|���g�K���D�ɏ�D�A�����A�呺���o�ĊC�H���C�n���ɗ��q�����U�r�G�����A��܌܁Z�N�ɕ��˓��ɓ���ƁA���̗��N�ɂ͑����������ɓ��{���̋���������ꂽ�B�����āA�����҂��Ă������̂悤�Ƀt���C�X��t�F���i���f�X���͂��߂Ƃ���C�G�Y�X��̐鋳�t���������X�ɗ����A���C�n����тɂ�����L���X�g���̕z���M�͉����x�I�ɍ��܂��Ă������B�����N�ɂȂ��Ē��肪�J�`�����Ɨ�������鋳�t�����̐��͂���ɑ��債�A���ꂩ��\�N�قǂ̂��ɂ͉Y��ɂ��̗L���ȓV�哰�����������܂łɂȂ����B�܂��A��ܔ���N�A��B�̃L���V�^���喼��̓��[�}�ɓV�������g�ߒc�𑗂�A�L���X�g���ɍD�ӓI�������D�c�M���͐鋳�t�����Ɛi��Őڌ��A�ނ�ƌ𗬂�[�߂�ȂǁA�L���X�g���̍����z���̐����ɂ͈ꎞ���ڂ�������ׂ����̂��������B
�@ �������A��ܔ����N�ɂȂ��ďG�g���L���V�^���Ǖ��߂߂��ăL���X�g���̕z�����ւ��A���ꂩ��\�N�قǂ̂��A�t�����V�X�R��̐鋳�t�Z�l�A���{�l�C�G�Y�Y��C���m�O�l�A����ɔނ�������܂������{�l�M�ҏ\���l�A���킹�ē�\�Z�l�̃L���X�g���k�����萼��̋u�ŏ}������ɋy��ŁA�L���X�g���ɑ�������܂�͊i�i�Ɍ������𑝂��Ă������B�����āA��Z��O�N�ɉƍN�����߂����z���A�E�C���A���E�A�_���X���ƎO�Y���j�����˂ő��E������Z��Z�N���ɂȂ�ƁA���{�ɂ��L���X�g���e���̌������͂��̒��_�ɒB�����B��Z���N�i���a���N�j�ɂ́A�鋳�t��M�Ҍ\�Z�������藧�R�ʼnΌY��a��ɏ������Ƃ������a�̑�}�����N�����Ă���B
�@ �����C���u�Ă��ٍ��̒n�V���ȏ@����z������Ƃ������Ƃ́A�����ɏZ�ވً��k�����ɑ��������Ŏv�z�̐킢�ނ��Ƃɂق��Ȃ�Ȃ��B���̏@�����{���I�Ȃ��́A���Ȃ킿�A���̎���̋K�͂�x�̂䂦�ɋ�Y����l�X�̐S�������̋K�͂�x�z���������ŋ~�ς��悤�Ƃ�����̂ł������قǁA�@�����L�߂鑤�Ƃ�����َ��Ȃ��̂Ƃ��Ĕr�����悤�Ƃ��鑤�Ƃ̐킢������ɂȂ�B���܂ł͂ǂ�Ȃɉ����ŕ��ՓI�Ɍ�����@���̏ꍇ�ł����Ă��A���̌����`�Ԃَ͈����ߌ��ŁA���Љ�I�A�����͓I�Ȃ��̂ł������ƍl���Ă悢�B�܂��āA�z���̐�w���������ꂽ�u�_�̐�m�v�����̔w��ɁA������X�̐�m�������ӎ����Ă������ۂ��ɂ�����炸�A�ٍ��̐�����������ތ��͎҂̎p�������B�ꂵ�A�}�����������̑Ή��ɋ����ċ��Ђ���������������悤�ɂȂ��Ă������Ƃ���A���Ԃ������ɂ����܂낤�͂����Ȃ������낤�B
�@ �\�Z���I������\�����I�����ɂ����ĂƂ���������l����ƁA�����̉䂪���̈א��҂������A�L���X�g���ɑ��铖���̊��e�����̂āA�����������ւƓ]���Ă�����������Ȃ������w�i��������x�͗����ł��Ȃ����Ȃ��B���N�h�C�c�̃Q�b�e�B���Q����w�œ�����r�����j�̌����𑱂��������v�q�́A���̒����̒��ŁA�Ǝ��̎��_�Ɋ�Â������̂悤�ȋ����[���������q�ׂĂ���B�����̐鋳�t�����������⋳��{���֑��������X�������|�[�g��L�^�����[���b�p�e�n�̐}���ق��甭�@���W���A�����͂��������ł̉s���w�E�����ɁA�ǂ�ł��Đ[���l������������̂�����B
�s���������ꂪ�t�̗���ł������Ȃ�A�����̃��[���b�p�̗��j�ɂ͉��Əq�ׂ��Ă��邱�Ƃ��낤���B���Ƃ��Ώ\�Z���I���A�V�V���[���̍`������ɂЂ������ƈ�c�̕��m���p�������ď㗤���A���̒n���̏Z���ɕ��ɂ̋���������A�L���X�g���͎��ł��邩�狳����Ă�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ɛ������A�������@�����Ăė̎�����@�����A���̉����ō`���Ă͂��̈�т�̗L���A�\���˂�}���A������ɂ͐��l����@�������ĕ������Ő��i����������Đ�ۂ�ł��A���m�̔z���ɂ���f�ՑD�����N���q���ă��[���b�p�ɂȂ��������Q���A�l�X�͋����Ă�����A�D������Ƃ��ɂ̓C�^���A�̕n�������X�ň��������W�߂����N���������Ɍq���ŏ悹�A�z��Ƃ��ĉ^��ōs�����Ƃ����Ȃ�ł���t
�i�����v�q���A�uWEG ZU JAPAN�v���j
�@
�@ �L���V�^�����Ɋւ��鏔�c�_�̐���͂Ƃ������Ƃ��āA�L���X�g���̋��`�ɐS�̂��ǂ�������߂铖���̌h�i�ȐM�҂����́A����肪�������Ȃ�ɂ�A���Ɍ����u�B��L���V�^���v�Ƃ��Ă��̐M���B������Ă��������Ȃ��Ȃ����B�����āA�����ɂȂ��ĐM���̎��R���F�߂���܂ł̊ԁA�q����X�����ɋ��`��`�������̐M���ł����т����̂��A�ق��Ȃ�ʂ��̐������ƕ��˓����C�݂̍����q���ӂ̐l�X�������̂��B
�@ �Î��ߌ~�W�̓W���������I���A��K�ɏオ���Ĉ�ԉ��̓W�����ւƐi��ł��������́A�����Ŗ]�O�Ƃ������ׂ��B��L���V�^���W�̓W�������ɂ߂��肠�����ƂɂȂ����̂ł���B���̓��̗��j�����I�Ȕw�i���炷�����͓��R�̂��Ƃł͂������̂����A�܂�ŗ\���m���̂Ȃ��������ɂ́A�����W�����̈�ЂƂ��傫�Ȗ��f���߂��̂悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ������B
�@ �������ƕ��˓��̍����q�n��ł͈ꕔ�̖�l�����܂߂������̏Z���S�����L���X�g���̐M�҂ɂȂ��Ă����Ƃ����B�����ɂ͐鋳�t���C�X�E�A�����C�_�Ȃǂ��������A�L���V�^���e�����n�܂�O�ɂ͘Z�S�l�����e�ł��鋳��Ȃǂ������āA���łɃ��e����̐��̂��̂��Ă����炵���B���ہA���̂��炢�̐M�̐[�܂肪�Ȃ���A���{�̌��i�Ȏ����ɂ��Ђ�ނ��ƂȂ��A�B��L���V�^���Ɖ����ĐM���т��ʂ����Ƃ͂ł��Ȃ������ɈႢ�Ȃ��B�B��L���V�^���ƂȂ������̐l�X�́A������_�����B�ꖪ�ɂ��A�Ȍ�A�M���̎��R���ۏ����悤�ɂȂ�܂ł̓�S�\�N�]�ɂ킽���Ă��̐M�𖧂��Ɏ�葱���Ă������̂��B
�@ �W�����̍ʼn��ɂ͉B��L���V�^���̔閧����̖������ʂ����Ă����c���g�i���h�j�Ƃ̕����̕��������������āA���ۂɒ��ɓ����ē����̕��͋C��̊����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă����B����ɂ��ƁA�����땔�̊x�̉��c���g�ł́u���l�v�s���ɂ�����i�I���C�i�j�Ղ���͉�����Ӗ�����j�̏�ʂ��Č��������̂��Ƃ����B���ۂɂ́A�����̃c���g�̏����V���̗l�����n��ɂ���Ă��Ȃ�Ⴂ�A�c���g�Ƃ����P�ɂȂ��Ă���Ƃ���Ɖ��N�����Ƃ̎������ɂȂ��Ă���Ƃ���Ƃ��������悤���B
�@ �y�Ԃ��炠�����Ă����̍���ɂ͐̕��̑傫�Ȕ��Δ����u���ꂽ�~���̍T���̊Ԃ�����A�E��ɂ͓������~���̕��Ԃ��������B���Ԃɂ͕�F����z�������d�𒆐S�ɂ��č���ɂ���t�l���J��I�h���A�E��ɂ͂��D�l�Ƃ������̐_�I�����א݂����Ă���B�����ɂ��u���̉Ƃł͓��{�×��̐_�������̂����Ȃ�����J���Ă��܂���v�ƌ��������ȕ��d�Ɛ_�I�̔z��Ȃ̂����A脉��r�i����������r�j�̃f�U�C����z�u�̂������ЂƂɂ��ǂ��ƂȂ��s���R�ȕ��͋C���Y���Ă���悤�Ɋ������ĂȂ�Ȃ������B������������A���������ڂŌ��Ă��鎄�̋C�̂����������̂�������Ȃ�����ǂ��c�c�B
�@ �˂ł�������Ǝd��ꂽ���Ԃ̉��ɂ͔[�ˁi���u�����j�������āA���͂������B��L���V�^���̖{���A���Ȃ킿�u��O�l�i�}���A���܂��͐��ґ��j�v���J��閧�̊ԂɂȂ��Ă����B���̊Ԃɂ͘a���̃^�b�`�ŕ`�����c���L���X�g���������}���A���̊|�������������A���̉��ɂ͐����̕r��e��̃��_���I���A���Ƃ��Ƃ̓J�g���b�N�̋�s�̍ۂɎg���Ă����ڂ̈���͂����A�ꐻ�̃I�e���y���V���Ƃ�������Ȃǂ��u����Ă���B���Ȃ݂ɏq�ׂĂ����ƁA�I�e���y�V���͖������₨�����̂��߂ɗp������B��L���V�^���̐��E�Ɠ��̐���ł������B�I�e���y���V���Ƃ������t�̌ꌹ�́A�|���g�K����Łu�����v���Ӗ�����upentencia�v�ł������Ƃ����B����Ȃ�A�u�I�v�̎������Ƃł����������h�̐ړ���Ƃ݂Ȃ��A�u�e���v�Ɓu�y���v�����ւ��u�I�y���e���V���v�ƌĂԂ̂��������̂ł͂Ȃ����Ƃ��v�������A�������̎������m�F���Ă݂Ă���͂�I�e���y���V���ɂȂ��Ă����B
�@ ���̊Ԃ̑O�ɒu���ꂽ�L���V�̏�̂��~�ɂ͋����p�̎M��o�ނ����ׂ��Ă������A�����̃f�U�C����G���͂�͂�ٍ����̊����̂�����̂������B�������ɂ͓��{�×��̊ω������I�݂Ƀf�t�H�������A�c���L���X�g������}���A�̃C���[�W���d�˂��e��̃}���A�ω������W������Ă������A�e�n��̃c���g�̔[�˕����Ȃǂɂ͂����}���A�ω����Ȃǂ��鑠����Ă����悤���B�����Ƃ����Ƃ��ɔ����āA�����ȃ}���A�ω�����\���ˁA�M�d�ȃ��_���I���Ȃǂ��[�˂̒���ǂɖ��ߍ��܂ꂽ��h�荞�߂�ꂽ�肷�邱�Ƃ��������炵���B
�@ �[�˂Ƃ́A���Ƃ̉��[���Ƃ���ɂ����Ĉ�Ƃ̈ߗނ⒲�x�i�Ȃǂ����܂��Ă����A���̂Ȃ��Â����u�����̂��ƂŁA��ʋq�͂������A�Ƒ��̎҂��߂����ɂ͏o���肵�Ȃ��ꏊ�ł���B���̔[�˂ɐ���}���A�̑��₻�̐���Ȃǂ��鑠���ꂽ���Ƃ���A�����́u�[�ː_�l�v�Ƃ������ς��Ȍď̂ŌĂ�Ă������悤���B�[�ː_�l�Ƃ��ẮA�������A�}���A�ω����Ȃǂ̂ق��A���E�҂������}���������n�̒��]�m������̎悵�������A�O�q�̃I�e���y���V���A���������ʂ��č���������ȏ\���`�̂��܂Ԃ�i�����j�A�ԁi�����Ɓj�_�i���^�̃��U���I�j�A�T���W���A���l�i���_���I���̈��j�Ȃǂ��p����ꂽ�B
�@ �ǂŎd��ꂽ�[�˕����̍��ׂ͍L�����~�����ɂȂ��Ă��āA���̍��~�ł̓i�I���C�̋V���͂��߂Ƃ邷�l�X�Ȕ�V��s�����Â��ꂽ�B�e���l�ƌĂ��c���g�̓��傪�S�̂̋V�����d��A�I���V���Ƃ����F���������a���ꂽ�Ƃ����B�I���V���͑����ɒ������̂������ŁA�Ղ��p���Ⴂ�҂����V����I���V�������`�ŋ����Ƃ��Ȃǂ́A���S�ɉ�����܂ő�ςȋ�J���������̂炵���B���~������[�˕����ł́A�I���V���̘^���e�[�v����������Ă������A��ӂ����͕̂s�\�ɋ߂����̑����̏��a�́A�}�g�����Y������y�^�@�̕�������Ɍo��ϖ��ʎ��o�̓njo�̋����ɂ������肾�����B����͂����܂Ŏ��̐��������A���܂��ܕ��O�̒N���ɒ����ꂽ�Ƃ��Ă������̓njo�Ƌ�ʂ����Ȃ��悤�ɁA�Ӑ}�I�ɂ���ȍH�v���Ȃ���Ă����̂�������Ȃ��B
�@�u�i�I���C�v�̋V��u���Y�҂��i�N���X�}�X�E�C���̋V���̂��Ɓj�v�A�u���a�����i�L���X�g�̐��a���j�v�̍s���̂Ƃ��ɂ́A���~�̊Ԃƕǂ��u�Ă��[�˂̌�O�l�ɃI���V���������ċF������������ƁA�j���̎���悪�o���ꂽ���A�s�����ɒN�����[�˂ɓ����O�l�ɎQ�q���邱�Ƃ͂܂������Ȃ������炵���B����I�ɂ���O�l���J��[�˂ɏo���肷�邱�Ƃ͋ɗ͔������A�o���肪�ł���̂��c���g����̐e���l�����Ɍ����Ă����B����قǂɓO�ꂵ���閧�ێ��̑Ԑ���~���Ȃ���ΐM�̌p���ێ��͕s�\�������Ƃ������ƂȂ̂��낤�B
�@ �W�����ɂ͂��Ă̐鋳�t�������c�����ؗ�Ȏi�Օ�����ށA�\���˗ނȂǂ̊W������������Ă������A����Ȓ��ɂ����Ď����ЂƂ���S���䂩�ꂽ�̂͗L���ȓ��G�̎����ł������B���G�Ƃ����͓̂������ŏo���Ă�����̂Ǝv���Ă������A�W������Ă�����ۂ̓��G�́A�a�Ղ������������悤�Ȃ������́A�ۂ݂̂��邪������Ƃ����̑�̒����ɂ͂ߍ��܂�Ă����B���̑�ɂ̂ڂ����҂������S�̂œ��G�{�̂��������݂�����悤�ɍH�v���邢���ۂ��ŁA���̗l�q���l���e�ՂɊm�F�ł���悤�ɂ��z�����Ă������킯���B������ł������薀�ł������̓��G�̖ؕ��́A�B��L���V�^���ł��������ۂ��ɂ�����炸�A���̓��G�܂��ꂽ�҂̐����@���ɑ�������������Ă����B
�@ ������Ŗ��ł��������ɂ́A�ǂ����Ă�������������ɂ��������G�{�̂߂��ɏ��Y���ꂽ�h�i�ȐM�҂����̑��Ղ̖��c����߂��Ă���ɑ���Ȃ��B�����v���ƂȂ�Ƃ��s�v�c�ȋC�����ĂȂ�Ȃ������B�₪�ăL���X�g���̎w���҂����̂ق����A�M�k�����ɓ��G��ł��_�̎��߂ɂ͕ς�肪�Ȃ����A�^�ɐM����邽�߂Ȃ�ނ���i��œ��G��ł��\��Ȃ��Ƃ����w�����o�������߁A���G�ɂ��L���V�^���T���͎����͂������A����Ɍ`�[�����Ă������B�����āA���ďC��ʏ���������ꂽ�ꔪ�ܔ��N�Ɏ����āA�S�ʓI�ɓ��G�͔p�~���ꂽ�B
�@ ���܂ЂƂA�����ڂ�D��ꂽ�W�����́u�����v�ƌĂ�����ȓ����������B�����Ƃ������̂����̐��ɑ��݂���Ƃ������Ƃ͎��ɂ��Ă������A���̎�����ڂɂ���̂͏��߂Ă������B���Ɋω���F���̕�������������A�\���͒ʏ�̓����Ɠ����悤�Ɋ��炩�ɖ����グ��ꂽ���ʂɂȂ��Ă��邱�̋��Ɍ��āA���̔��ˌ��𔒂��ǂ⎆�ɓ��˂���ƁA�Ȃ�ƁA�~�`�̌����̒��ɏ\���˂Ɋ|����ꂽ�L���X�g�̎p�Ƃ��ڂ������̂������яオ��̂��B�ω���F�ł͂Ȃ��ăL���X�g��}���A�̑��������яオ��Ƃ��낪�~�\�ł���B�����̎���ɒN���l���o�����Z�p�Ȃ̂��͒m��悵���Ȃ����A�Ȃ�Ƃ������ȋZ�@���Ƃ����ق��Ȃ��B�������ʼn\�̖����ɑ����ł���Ȃ�Ė]�O�̂��̂܂��]�O�̂��Ƃ���������A���ˌ��̒��ɕ����яオ��s�v�c�Ȑ����߂Ȃ���A���͂�������������Ȃ����B
�@ �����̔閧�͊ω����̕�������������ʂƕ\�̋��ʂƂ̊Ԃɂ��錩���Ȃ����ɂ���炵���B�O����͂킩��Ȃ����A�̉~�`�����I�݂ɓ\�荇�킹�č�������A���Ȃ킿���ʂ̂ق�Ƃ��̗����ɂ͔����ȉ��ʂ������A�܂�����ȍH�Ȃǂ��{����Ă���B�����āA�����̉��ʂ�H���\�̋��ʂɋy�ڂ��e���̂��߂ɔ��ˌ��ɖ��x�̂ނ炪�����A���̖��Â̌��̎Ȃ��S�̓I�ɑg�ݍ��킳���Đ����̕��l�ƂȂ�炵���̂��B�Ȃ�Ƃ������ׂ������e�N�j�b�N�Ȃ̂ł���B
�@ �Ȃ��ɂ́A���̉����ǂ�ł��������Ɏv�킸�����o��������悤�ȓW�������������B�����ɂ��Â����ȏ\���˂̒����Ƀ}���A�ω����炵�����̂̕���������{�����u�L���V�^���╨�̋U���v������ł���B���̂��킭���肰�Ȓ��i�́A���C�n����т̃L���V�^���j�Ղ�K���O���l�ό��q��_���ďI���̈ꎞ���ɍ��ꂽ�A�����܂邾���̋U�\���˂���������ł���B����m��Ȃ���Γ��{�l�ł��x����Ă��܂������ȑ㕨������A����ƒm�炸�ɂ��y�Y����ɔ����Ă������O���l�����������ɈႢ�Ȃ��B
�@ ��Z�l�O�N�ɓ����̍Ō�̎i�Ճ}���V�������_�����}������ƁA���C�n���̃L���X�g���M�҂����͉B��L���V�^���ƂȂ��Ċe�n�ɐ����A������Ə��V���̊܂ݎ��{���̈Ӗ���_�𐳂����`������鋳�t�̂��Ȃ��܂܂ɁA���̐M�͌Ǘ������y�������Ă������B�����A���Ƃ����y�̉e�����y���������Ƃ͂����Ă��A���K�̎i�Ղɂ��w���̂܂������Ȃ��܂܂ɁA���̌��S�\�N�]�ɂ��킽���Ă��̐M���p����蔲���ꂽ�Ƃ������Ƃ͋��قƂ��������Ȃ����낤�B�W���̑S�˂������ĉB��L���V�^���ƂȂ��Ă������Ƃ��A�����⍪���q�̐l�X���M���Ŏ炵�����邱�Ƃ��ł����傫�ȗ��R�ł͂��낤���A���ꂾ���ł͐��������Ȃ��C�����Ȃ��ł��Ȃ��B
�@ ���ɂ́A�L��ȊC�Ƌ����Ƃ����w�i���B��L���V�^���̐M�̑����Ɉ���Ă����悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B������B�̓��炿������悭�킩��̂����A�C��ɂ��Đ����鋙���Ƃ������͈̂�ʂɌ��t���Ȃ������ł��B����ł��ĕ����̖{�����ÂɌ������͂������A�����Ƃ����Ƃ��̌��f�͂ƍs���͂ɂ��G�łĂ���B
�@ ���܂ƈ���Ď葆���̘a�D�����Ȃ�����ɂ́A��������C�ɏo����A���������͂��݂��͂����킹�ł����������Ȃ���A�I�m�Ȕ��f�̂��Ɩ������Ŏd����i�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ������낤�B�Ƃ�ʼn��ɏo����o���ŁA�������N���邩����Ȃ��댯�ȏƗׂ荇�킹�̂Ȃ��ŁA����̐S�Ɍ��₢��������̗͂Ɣ��f��M���Ȃ���A�فX�Ƌ��J�ɂ������܂Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�������͏������ŁA���Ƃ��C�ɏo�邱�Ƃ��Ȃ��҂ł����Ă��A�C���ǂ������Ƃ��납�͏\���ɂ킫�܂��Ă��āA�������Ƃ��ɂ���C�̒j�����̐g�ɉ������N�������Ƃ��̊o�傾���͂ł��Ă����͂��ł���B
�@ �v����ɁA�×��A�C�Ƃ������̂́A�X�̐l�Ԃ̍����𐘂����̐l�Ԃ�����������Ɠ����ɁA�l�X�̐S���J��z���ȏ�ɑ�������������̂Ȃ̂��B�ܓ����܂߂����C�e�n�̉B��L���V�^���W���ɂ݂�l�X�̌����̌ł��ɂ́A�C�ɐ�����҂̂���ȋC�����傫����p���Ă����悤�Ɋ������ĂȂ�Ȃ��B
�@ �B��L���V�^���ƂȂ����l�X���@���Ɍł�����������ꂼ��̔�V�����ʂ������́A�C������ł킸���ȋ�����������Ă��Ȃ������ƍ����q�ɂ����Ă����A���ꂼ��̐M�l�������Ȃ�قȂ������̂ɂȂ��Ă���������������M���m�邱�Ƃ��ł��悤�B�������ł́A�u��������V���͂��������͂Ȃ��v�Ƃ����L���Ȍ��t���c���ď}���������W���A�����Y�E�q��炪���Y���ꂽ�������̒��]�m���Ƃ����������A�����ۂ��̍����q�͑�ʂ̏}���҂��o�����Ƃ��������q���l�����̐��n�ɂ��Ă���B�B��L���V�^���g�D�̌`�Ԃ���q�s�����I���V�������ꂼ��̒n��œƎ��̗l���ւƕω����Ă������悤�ł���B�������ł́A�B��L���V�^���̒��Ɏ��l���ł��ꍇ�ɂ́A�����m�����Ȃ������ɁA��̂�O�ɂ��āu���ǂ����v�Ƃ����~�T�̕ό`�Ƃ������ׂ����ʂȋV�����s�Ȃ��A�I���V����������ꂽ�Ƃ������B
�@ �����ɂȂ��ĐM���̎��R���F�߂���ƁA���˂̕R������̃y���[�_����͂������܍ĕz���̂��߂ɐ����⍪���q��K��A�l�X���J��[�ː_�l�ƃL���X�g���Ƃ͓���̂��̂ł��邱�Ƃ������ɐ������B�������A�I�����̍Ό����o�ēy���������B��L���V�^���Ǝ��̐M�l���ƃL���X�g���{���̐M�l���Ƃ̊J���͂��܂�ɂ��傫���A�L���X�g���̍ĕz���́A�\�Z���I�����̏��z���Ȃǂ����͂邩�ɍ��������߂��Ƃ����B
�@ �v���������ʔ����ɐS���т��o���Ȃ��瓇�̊ق����Ƃɂ������́A�Ăѐ����勴��n���ĕ��˓����ɖ߂�A���C�݂̍����q���l�̋߂��ɂ��镽�ː؎x�O�����ق����K�˂Ă݂��B����͓��ꉮ���蕽���̂�����܂肵�������قŁA���َ҂͎���l�����������B������̂ق��ɂ����̊ق̓W�����ɗ�炸�A�Ȃ��Ȃ��ɋ����[���B��؎x�O�W�̎�������Ă����B�������B��L���V�^���Ջ�〈�邩��Ɍ|�p���̍������̂��̃}���A�ω������������B�i�Օ��p�̐��E�҂̌Â��ؑ��A�傫�ȏ\���˂�w�����������ȑ���̃L���X�g�ؑ��A����ɂ͎��ۂɗp����ꂽ���߂̍��D��_���I���ȂǁA������̓W�����ɂ��[���S��ł��̂�������ꂽ�B
�@ �����A���w���I���������ق����Ƃɂ��悤�Ƃ����Ƃ��̂��ƁA��������C�ɂƂ���悤�ȑ㕨��ڂɂ��Ă��܂����B�����ق̕Ћ��Ŕ����Ă��邨�y�Y�i�̒��ɁA�Ȃ�ƈ��~�̒l�i�̂������G�̃��v���J�����ׂ��Ă����̂ł���B�ǂ����̍��̎��b�A���̊������ɂ������G�Ȃ�ꖇ���炢�����Ă��āA�X�g���X�����p�ɉ䂪�Ƃ̌��悠����ɒu���Ă݂�̂��悢���Ƃ͎v�������A�������ɖ{���̓��G�̃��v���J�ł͂ƂĂ���������C�ɂ͂Ȃ�Ȃ������B�������A�����ɗ��j�����Ƃ��Ă��̃��v���J���Ă����l�������̂��낤���A�����ّ��������������l�X�ւ̃T�[�r�X�̂���ŗp�ӂ������̂ɈႢ�Ȃ��̂��낤���A���̊����ɂ͂���ƍ���Ȃ����y�Y�i�ł͂������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N1��12��
�S���Ē����琢�I���N����
�@ ���U���X�ɁA720ml�r�Z�{�̏Ē������u���ɐ�����āv���A�������̎������������̉��c���瑗���Ă����B�ȑO�ɂ��̗��Ő�i���ƏЉ�����Ƃ̂��鍙���Y�̖{�i�Ē��u�S���v�̌����ŁA40�x�قǂ̓x��������B����������ꂽ�Ē��ʂ̐l�X�̊Ԃł́u�S���v�����������i�Ƃ��Ĉ��D����Ă��錴�������A���N12����500�{�������o�ׂ������ʌ��菤�i�Ȃ̂ŗe�Ղɂ͎�ɓ���Ȃ��B���͂܂������̉��˂����A�ǂ����Ă��u���ɐ�����āv������ł݂����Ƃ����Ē��������͂ɉ��l������̂ŁA��N11�����߉��c�̓���A���c���j����ɒ��ڗ���ł������̂��B�����e�n�̎�������u���ɐ�����āv�̗\�����������A�������肢�����Ƃ��ɂ́A�����c�肪�킸���Z�{�����Ȃ��L�l�������B�����ʂ�̊��荞�݃Z�[�t�������킯�ł���B
�@ ���̌����́A720ml�r��{2000�~�Ɛ��Y�R�X�g���������i�ł����邽�߁A���R��ʂɂ͏o�ׂł��Ȃ��B����ł��A���Y��̉��c����́A�o���i�������ݒ肷�������Ȃ����A���ꂪ���q�ɓn��Ƃ����{���̍��l�ɂ肠���邱�Ƃ�]��ł����Ȃ��B���܂�ɍ����l�i�Ŕ�����������邱�Ƃ��킩��ƁA�Ȍセ�̂��X�ɂ́u���ɐ�����āv�̏o�ׂ���߂Ă��܂��̂��������B��������Έꎞ�I�Ɏ��v�͂����邪�A�֏旘�v��ژ_�܂������̏��i���K���o�ꂵ�Ă���B�i���̈������i���o���A���������ߔN�傫�����������Ă����u�Ē��v�ɂ�������C���[�W���܂��_�E�����Ă��܂��B����͏Ē��ƊE�ɂƂ��Ď��E�s�ׂɓ��������ƂȂ̂��Ƃ����B�u���ɐ�����āv�������ŏo�ׂ��闝�R�́A�ق�Ƃ��̏Ē��Ƃ������̂͂���Ȃɑf���炵�����̂��̂Ȃ̂��Ƃ������Ƃ��A�s�[�����邽�߂Ȃ̂��������B
�@ ���H�A�u���̂��߂ɍ�����K�ꂽJTB�u���v�ҏW���̕��痢������A���c���ē�����A�{�i�Ē��u�S���v�̖������\�Ȃ������炵���B���̎��A������̂ق�����A�u�S���v��u���ɐ�����āv�������ƍL�����ɏЉ�邽�߂̒�Ă��������̂����������A���Y�ƕi���̈ێ��Ǘ��̂ق����ƂĂ��ǂ����Ȃ��Ƃ������ƂŘb�͕ۗ��ɂȂ����Ƃ����B
�@ �����V���v���ȃf�U�C���̎�����1���o���A�ǂ�Ȃ��̂��ƊW���J���Ă݂�ƁA�P���悤�ȐF�̓����ȉt�̂������܂ł����ς��ɋl�܂������r�����ꂽ�B�����Ȕ����a�����̃��x���ɂ́u�{�i�Ē��@�S���@�����E���ɐ�����āv�ƕ\������Ă���B�����āA���x���̉��̂ق��ɂ́uNO 1�v�Ƃ��������ԍ����L�����Ă������B1��1���ɁuNO 1�v�Ƃ͉��N�������ȂƎv���Ȃ���A�ŏ��̐��i�Ȃǂɂ͂�͂�uNO 1�v��t�L����̂����ʂŁA�uNO 0�v�̂悤�ɗ�̔ԍ����ӂ�悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ���ȂƁA���C�Ȃ��l�����B�����āA�����������邤���ɁA���̔]���ɁA�u�������A���N�͂܂�20���I�ŁA���N�̋I��2001�N���炪21���I���Ƃ�����̂́A�����������炻�̂�����̖��Ɛ[���W�������Ȃ����ȁv�Ƃ����v�����N���オ���Ă����B
�@ ��\�ꐢ�I�̂͂��܂肪�I��2000�N����Ȃ̂��A����Ƃ��I��2001�N����Ȃ̂��Ƃ������́A�I��2001�N���炾�Ƃ������Ƃňꉞ�͌��������悤�ł��邯��ǂ��A�Ȃ�ƂȂ��������肵�Ȃ��v���̐l�����Ȃ��Ȃ����낤�B���������������̈�l�ɂق��Ȃ�Ȃ��B�I��2001�N���炪��\�ꐢ�I���Ɣ[����ł���l���A�����f�肷�闝�R�����߂���ƁA���ǂ́u�������܂��Ă邩�炻���ȂI�v�ƌ��������n���ŁA����ӂ�Ȃ��Ƃ��̂����Ȃ��B
�@�u���ɐ�����āv�́uNO 1�v�Ƃ��������ԍ��ɐG������A�ēx���̖��̍����ɑz�����߂��炷�����ɁA�ǂ����A��Ƃ��������a�������E���ɕ��y����܂ł̗��j�I�w�i��A��Ƃ��������̔�ߎ����ʂȒ��ې��A����ɂ͏\�i���̌��̌J��グ�\�L�@�Ȃǂ����̖��̕s���Ă��̌����ł���炵���Ƃ������Ƃ��킩���Ă����B
�@ ���̖�����薾���ɂ���ɂ́A�܂��A�I���N���Ȃ���̂͂��̎���A�N�ɂ���čl���o���ꂽ���̂��𖾂炩�ɂ��Ă����K�v�����邩������Ȃ��B�K���Ƃł������ׂ����A���̎����܂��܁A���́A�I���N���̋N���Ƃ��̔��Ď҂ɂ��Ă̊ȒP�ȋL�q������S�Ȏ��T�̒��ɂ��������Ƃ�z���o�����B
�@ �������N�قǑO�̂��ƂɂȂ邪�A���͐V�j�ЂƂ����o�ŎЂ���u�������v�Ƃ������ς��ȕS�Ȏ��T��|��o�ł������Ƃ�����B�����̓C�M���X�Ŋ��s���ꂽ�uTHE ULTIMATE IRRELEVANT ENCYCLOPAEDIA�v�Ƃ����{�ŁA�{���̃^�C�g���ɂ́A�u���ɂ̓I�͂���S�Ȏ��T�v�A���邢�́A�u�܂�Ŗ����l�ȎG�w�S�Ȏ��T�v�Ƃ����Ӗ������߂��Ă���B�v����ɁA��ؓ�ł͂����Ȃ��L�����e�̂т�����l�܂����u�����j��̂��������厫�T�v�Ƃ����킯����������A�ŏ��A�M�ɂ́A�u�����̎��T�v�̌��������āu�V�g�̎��T�v�Ƃ����^�C�g�������悤���ƍl�����B�������A�䂪���ɂ́u�L�����v�Ƃ����̑�Ȏ��T�����邱�Ƃ�z���N�����A�ŏI�I�ɂ͂�����������āu�������v�Ƃ����^�C�g���ɂ����B�u�펯�������T�v�Ƃ����Ӗ����܂݂ɂ������Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B
�@ ���̎��T�̒��́u�A�E�O�X�g�D�X�E�J�G�T���iBC 63 �` AD 14�j�v�̍��ɂ͎����̂悤�ȋ����[���L�q���Ȃ���Ă���B
�s�I���O8�N�̂��ƁA�A�E�O�X�g�D�X�E�J�G�T���͎����̖����������Ȃ����Ƃɗ��_���A���݂�8���ɑ������錎��Augustus(August�̌ꌹ)�Ƃ����Ăі��ɉ��߂������B�܂��A�����̖����������������̃W�����A�X�iJulius���Ȃ킿July�̌ꌹ�j�̖������������P�������Z�����ƂɋC�Â����ނ́A2����1���������Ȃ����A���̕���8���ɕt�������Ă��܂����̂������B
�@ �����܂ł��Ȃ����A���̂悤�Ȉ�A�̏o�������N�������N�オ�̂��Ɂu�I��8�N�v�ƌĂ��悤�ɂȂ邾�낤�ȂǂƂ́A�����̐l�X�ɂ͑z�������Ȃ����Ƃ������B���ہA�I��700�N���Ɏ����Đ��҃r�[�h���L���X�g�̒a������ɂ��ĔN��������Ƃ����▭�ȃA�C�f�B�A���v�����܂ŁA�N�����A���N�ɂǂ�ȏo�������N����������I�m�ɒm�邷�ׂȂǎ������킹�Ă��Ȃ������̂ł���t
�@ �̂��牢�ĂȂǂōL���l�X�̏���U���Ă����▭�ȃW���[�N�̂Ȃ��ɁA�u���@���ꂽ���̒قɂ́ABC 100�N�Ƃ�������N��̍��Ȃ���Ă����v�Ƃ��A�u�M�d�Ȃ��̖{�̍Ō�ɂ́AAD 100�N�ɂ�����A�Ƃ����L�q���������v�Ƃ��������悤�Ȃ��̂�����B����ȃW���[�N���l�X���j�����Ƃ����邱�Ƃ�����킩��悤�ɁA�I���N�����ďo���ꂽ�̂͂Ȃ�ƋI��700�N���A���Ȃ킿�A���܂���1300�N�قǑO�̂��ƂȂ̂��B
�@ �I���N�����l�Ă��ꂽ���悻�̔N�オ����������A�����Ɋm�F���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A��Ƃ������̋N���ƗR���A����ɂ͂��̊T�O����ʂ̐l�X�̊Ԃɒ蒅���Ă����܂ł̗��j�I�Ȕw�i�ł���B������̂ق��ׂ�ɂ́A���w�҂̋g�c�m�ꂪ1939�N�ɒ������u��̔����v�i��g�V���j�Ƃ�������Ă��Ȃ��������������B���Ȃǂ����܂�邸���ƈȑO�Ɋ��s���ꂽ���̒���́A���w�j�␔�w�̍����I���ɂ܂ŐG�ꂽ��ʓǎҌ����̌[�֏��ł��邪�A���܂��炽�߂ēǂ�ł݂Ă��������Âт����������Ȃ��B��������Ƃ�����Ȃ��ł͂Ȃ�����ǁA�������̍��ɂ��̖{��ǂ�Ō[������A�₪�Đ��w�̌����҂ɂȂ����l�����Ȃ��͂Ȃ��͂����B�������邤���ɐ��w�������ɂȂ�����A���w�͂���Ȃ�ɓ��ӂł��A���̖ڎw���Ƃ���␔�w�̐��E�̓W�]���܂�Ō����Ȃ��Ƃ����������ɂ͐��̖{��E�߂Ă݂����B
�@ ���āA���܂ł͏��w���ł��m���Ă����Ƃ������������A���̐��������E���ɍL�܂肻�̎��p�����F�߂���悤�ɂȂ�܂łɂ͑����̎��Ԃ��K�v�������炵���B���̖{�ɏq�ׂ��Ă���Ƃ���ɂ��ƁA�낪�������ꂽ�̂��C���h�ł��邱�ƂɊԈႢ�͂Ȃ����A���̔��������̎���A�N�ɂ���ĂȂ��ꂽ�̂��͕s�����Ƃ����B�����A�����̌����҂́A�Z���I���̃C���h�ł͂��łɁA��̊T�O��p�����A���݂̋L���@�ɋ߂��ʎ��L���@�������Ȃ��Ă����̂ł͂Ȃ����Ɛ������Ă���悤���B
�@ �u1�v�Ƃ�����̐��̂��鐔�ɔ�ׂāA�u0�v�Ƃ������̂̂Ȃ����ۓI�Ȑ��̂ق��́A�̂̐l�X�ɂƂ��Ă��̈Ӗ��Ƌ@�\�𖾗ĂɔF�����邱�Ƃ͓�������B�w�I�ȕ���ł͂���߂č��x�Ȍ������i�߂��Ă����Ñ�̃G�W�v�g�A�M���V���A���[�}�Ȃǂɂ����Ă��A�㐔�w�I�ȕ���̌����͂قƂ�ǐi��ł��Ȃ������B�ڂ��������͏Ȃ����A�u0�v�Ƃ��������܂��m���Ă��Ȃ��������Ƃ��傫�ȗ��R�������낤�ƍl�����Ă���B�������u0�v�Ƃ��������Ȃ������Ƃ���A�\�i�@��p����ꍇ�ł��A���Ƃ��A1�A2�A3�A4�A5�A6�A7�A8�A9�A�s(10��\�킷�L��)�A11�A12�c�c�c�c19�A2T�i20�j�A21�A22�c�c�c�c89�A9T(90)�A91�A92�A93�A94�A95�A96�A97�A98�A99�AH(100��\�킷�L��)�AH1�i101�j�AH2�i102�j�A�c�c�c�cHT�i110�j�A�c�c�c�c9H(900)�A�c�c�c�c9H9T�i990�j�A991�A992�A993�A�c�c�c�c998�A999�AM�i1000��\�킷�L���j�c�c�c�̂悤�ɁA�\�A�S�A��ƌ����オ�邲�ƂɐV���ȋL����t�������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@ ���⒛�P�ʂ̐��ɂ��Ȃ�ƁA�����̋L���@�ł����̐���\�L���邾���ł���ςȂ��Ƃ�����A���̋L���@�ʼn����揜�̌v�Z�Ȃǂ���낤�Ǝv������A�V�˓I�ȓ��]�������Ă��Ă��e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ����낤�B�܂��āA���x�ȑ㐔�������������ȂǂƂ������Ƃ́A�قƂ�Ǖs�\�������ɈႢ�Ȃ��B���[���b�p�Ȃǂŋߑ�Ȋw�̊�b���z����A�Ȋw���������B�����̂́A��̊T�O�����C���h�L���@���`���������������ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B
�@ �Ƃ���ŁA���q�ׂ����Ƃ���킩��悤�ɁA�u0�v�Ƃ����X���̍������ۓI�Ȑ��̔F�m����Ă��鐢�E�Ȃ�A���̎n�܂���u0�v�ɂ��āA0�A1�A2�A3�A4�A5�A�c�c�c98�A99�A100�A�ƃJ�E���g���邱�Ƃ����ʂɂȂ�B�������A�u0�v�Ƃ��������Ȃ����E�̏ꍇ���ƁA���̎n�܂���u1�v�ɂ��āA1�A2�A3�A4�A5�A�c�c�c�c97�A98�A99�AH�i100�j�A�ƃJ�E���g����̂����R�̂Ȃ�䂫�Ƃ������̂��낤�B
�@ �������b���킩��₷�����邽�߂ɁA���������C���[�W���Ă��炤���Ƃɂ��悤�B�����āA��Ƃ��������F�m����Ă��鐢�E�̏ꍇ�ɂ́A�u1�v�Ƃ����Ƃ���0����1�܂ł̊Ԃ̐�����\�킵�A�u2�v�Ƃ�����1����2�܂ł̐�����\�킷�Ɩ���Ă���Ƃ���B���̃��[���ɏ]���ƁA�u100�v�Ƃ�������99����100�܂ł̊Ԃ̐�����\�킷���ƂɂȂ�B
�@ �����ۂ��A��Ƃ��������F�m����Ă��Ȃ����E�̏ꍇ�ɂ́A�u1�v�Ƃ�����1����2�܂ł̐������A�܂��u2�v�Ƃ�����2����3�܂ł̐�����\�킷���̖���Ă���Ƃ��Ă݂悤�B���̃��[���ɂ̂��Ƃ�Ƃ���AH�i100�j�Ƃ�������H(100)����H1�i101�j�܂ł̊Ԃ̐�����\�킷���ƂɂȂ�B�������킩�肾�낤���A��\���I��1901�N���߂���2001�N�̏��߁i2000�N�̏I���j�܂łƂ���Ƃ����ꐢ�I�̔N���̃J�E���g�@�́A���̗�Ƃ��������F�m����Ă��Ȃ����E�̃P�[�X�ɑ������Ă���̂ł���B
�@�u��̔����v�̋L�q�ɂ��A��̊T�O�����C���h�L���@���C�X�������E���o�ă��[���b�p�ɓ`���A���p�I�Ȃ��̂Ƃ��ď��l���͂��߂Ƃ����ʂ̐l�X�̊Ԃŗp������悤�ɂȂ����̂́A�\���R�����̎���Əd�Ȃ�\�I�̍��ɂȂ��Ă��炾�Ƃ����B����ȑO�ɂ��m���Ƃ��ăC���h�L���@�����[���b�p�̈ꕔ�̒m���l�ɓ`����Ă����\���͂���炵�����A�ً��k�̊�قȍl�����Ƃ��ĂقƂ�ǖ�������Ă����̂�����̂悤�ł���B
�@ �\�I�㔼�ɏ��l�̎q�Ƃ��Đ��܂ꂽ���w�҃t�B�{�i�b�`���A�C�^���A�ŏ\�O���I�����ɏ������A�C���h�L���@�Ƃ����p�������Ɨp�Z�p��̌n�I�ɏЉ���̂��_�@�ƂȂ��āA�悤�₭���[���b�p�ɗ�̊T�O�����y�蒅���邱�ƂɂȂ����̂��������B
�@ �I���N�������Ă��ꂽ�̂��I��700�N���������Ƃ���A�����̃��[���b�p�ɂ͗�̊T�O�Ȃǂނ��`����Ă��Ȃ��������ƂɂȂ�B�������Ƃ���A���Ƃ��Ύ����I��701�N���߂���800�N�I���܂łƍl����͕̂K�R�̐���s���������Ƃ������ƂɂȂ낤�B����̉�X�͒��w���ɂ��Ȃ�Ɓu0�v�Ƃ���������_�Ƃ����������̊T�O������邩��A�I��0�N����ɂ��āuBC 100�N�v�Ƃ��uAD 100�N�v�Ƃ��������N���\����e�ՂɎ���邱�Ƃ��ł��邯��ǂ��A��̊T�O�������Ȃ���������̐l�X�́A�ǂ����Ă��u1�v����_�ɂ���������Ȃ������Ɛ��@�����B��\�ꐢ�I��2001�N���߂���Ƃ����̂́A����ȃJ�E���g�@�̖��c�ł���ƍl���邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ��낤���B
�@ �ȏ�̂��Ƃ́A�����܂ł��������܂��ܑz�����Ă݂��l�I�Ȍ����ł����āA���̍l����𐳂����ƕۏ��Ă����悤�ȗ��j�I�����Ȃǂ͂Ƃ��ɂȂ��B�u���ɐ�����āv�̐����ԍ��uNO 1�v�����[�ƂȂ��Ă��ꂱ��ƋC�܂܂ɑz�����߂��炷�����ɁA���̋I��2000�N�̌����͂��̂܂ɂ��I����Ă��܂����B�Ȃ�Ƃ�����2000�N���i�H�j�ɑ����������̂ł���B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N1��19��
�R�䋳�Y����̃A�j���ɋV�I
�@ �R�䋳�Y����̃A�j���R���������C�Ȃ����߂Ă��邤���ɁA�҂Ă�A���̏����̊G�A�ȑO�ɂǂ����Ō������Ƃ�����Ȃ��c�c�Ǝv�킸�}�E�X��������~�߂��B�ꎞ��O�̐g�Ȃ�Ɣ��^��������w�l�����[�v���𑀍삵�A�uHAPPY NEW YEAR 1900�v�ƐԂ�������ł��o���A���ɂ悭�ł����A�j���[�V�����Ȃ̂����A���Ƃ��Ƃ̓G�b�`���O�������ؔʼn悾�����̂ł͂Ǝv���邱�̂��w�l�̊G�ƁA���[�v����ʂ̂�������ɂ��鋌���^�C�v���C�^�[�̈ꕔ�炵�����̂Ɍ��o��������������ł���B����܂ŎR�䋳�Y����ɂ͈�x������������Ƃ��Ȃ����A�R�䂳��̃A�j���R������q������悤�ɂȂ����͍̂ŋ߂̂��Ƃ�����A�ނ������ȕ��Ɋ������̂͂܂������̋��R�������B
�@ �L�������ǂ��Ă��������ɁA���͉�����������̖{�̂��Ƃ��v���o�����B�����ɏ��I���炻�̖{����������o���ăy�[�W���߂����Ă����ƁA����܂����A����܂�����I�c�c�m���ɎR�䂳��̃A�j���̃x�[�X�ɂȂ����Ǝv���邻�̊G���A�ԈႢ�Ȃ������Ɍf�ڂ���Ă����̂ł���B19���I�㔼�ɕ`���ꂽ���̊G�ƃA�j���R�����Ƃ����r�ׂȂ���A���͎v�킸���]���A�R�䂳��̌����ȃp���f�B���_�ƗV�т�����A����ɂ͂��̈ӕ\��˂��A�C�f�B�A�ɐS�ꔏ�芅�т𑗂肽���C�����ɂȂ����̂������B
�@ ���������ƁA��T�̃A�j���R�����ɂ���قǂ܂łɐ[���������o�����̂́A�R�䂳��̃E�B�b�g�̑f���炵���ɉ����A���܈���Ȃ�̑傫�ȗ��R�������Ă̂��Ƃ������B�b�̐���s����A��T�ɑ����Ă܂����⎩���̉ߋ��̎d�������������ɂ������ƂɂȂ��ċ��k�����A�������܂���23�N���O��1977�N�̂��ƁA���̓V�O�}�Ƃ����o�ŎЂ���̈˗����uVICTORIAN INVENTION�v�Ƃ������ς��Ȗ{��|��o�ł������Ƃ��������B�C�M���X��John Murray �Њ��s�̂��̌����́A�㎿����A4�ő��200�y�[�W�قǂ̏��ЂŁA�I�����_�l��Leonard de Vries��1971�N�ɕҏW�����ދH�Ȓ��{�ł������B
�@ ���e�I�ɂ́A�T�C�G���e�B�t�b�N�E�A�����J�����A���E�i�`���[�����i���j�A�f�E�i�c�[�����i���j�A�U�E�l�C�`���[���i�p�j�ȂǁA�`�����铖���̈ꗬ�Ȋw�����1865�N����1900�N�ɂ����Čf�ڂ��ꂽ�����Ɋւ��鋻���[���L�����ҏW�������̂ŁA�����̍ő�̖��͂́A���Ƃ��Ƃ̓G�b�`���O�������ؔō��肾�����Ǝv���郆�[�����X�Ń��}�����ӂ��}�ł��ӂ�Ɏ��^����Ă��邱�Ƃ������B�����ɏЉ��Ă��锭���i�┭���A�C�f�B�A���A����Ȋw�̐�삯���Ȃ������H�I�ȏ��X�̔�����������A�ꐢ���r�����唭���▜��������̖ڋʓW���i�A����ɂ́A������|���̂̒��i�A��z�V�O�Ȓ��A�C�f�B�A�̐��X�ɂ�����܂ŁA���Ă̖������ꎞ��������ɏے�������̂��肾�����B�܂��A������Ɩڂ�ʂ��Ă݂������œ����̉Ȋw�G���̑�炩���Ȃǂ��Â�A�Ȃ�Ƃ����܂���������ł������B
�@ �����A���I�i���h�E�f�E�t�F���X���ҏW���������̉�����́A�O�q����19���I�̉Ȋw���̋L�����قڂ��̂܂܈��p���č\������Ă��邽�߁A�ꐢ�I���o�������̊ϓ_���炷��ƁA�����ɕs���R�ŗv�Ȃ����������A����ɁA�����̂��Ȃ�̕������Õ��ł���߂čd���Z�p������̕��͂Ő�߂��Ă���Ƃ��������������B�����ŁA���{����i�߂�ɂ������ẮA���ҏW�҂̈Ӑ}�ƌ����̎�|�ƂȂ�ʂ悤�ɐS�����Ȃ�����A��_�ɑn��I�Ȗ|������݁A�����Ɏ��M�̋Y�������M������������B�K���Ȃ��ƂɁA���s�����ƁA�V���e���₢�����̏T�����ɂ��Љ��A�����̍����Ȋw�����ق̌����ҋ���́A�Ȋw�j�̐�匤���ɂ��𗧂D�ꂽ�|���Ƃ����A�g�ɗ]��悤�ȕ]�������Ղ����B��Ƃ̍r���G����Ȃǂ́A��S�I�̒��̈���ɂ��I��ł����������B
�@ �Ȍ�\�N�]�ɂ킽���Ĕł��d�˂Ă������A�V�O�}�Ђ̌o�c����̖��Ȃǂ�����A�₪�Ă��̖{�͐�ŏ�ԂƂȂ����B�����āA1992�N�ɂ������āAJICC�o�Łi���Ёj����u�}���E�������̎���v�ƃ^�C�g�������߁A�r���G����̐����ѕ��t���ŕ������ꂽ�B�����A���N���Ă�����̂ق�����łɂȂ��Ă��܂����̂ŁA���݂ł͂��̖{�͓���s�\�ɂȂ��Ă���B���܂��Ƃ����莄�̂Ƃ���ɖ₢���킹���������肷��̂����A�ǂ����̏��X�ŕ��ɖ{���Ȃ����͍ĕ����ł�����Ȃ�������A�}���ق��Ï��X��T���ĉ{�����Ă��炤�������@���Ȃ��B���p�W�҂�e���ʂ̌����ҁA���Ѓ}�j�A�̕��X�Ȃǂ������Ԃ�ƍw�����Ă��������Ă����悤�Ȃ̂ŁA������������A����AIC�̓ǎ҂̒��ɂ��������������̕������邩������Ȃ��B���̂悤�ȕ�������ꂽ��A���̏�ł��炽�߂Ă����\���グ�����B
�@ �Ƃ���ŁA���́uVICTORIAN INVENTION�v���邢�́u�}���E�������̎���v��164�y�[�W�ɁA�u�^�C�v���C�^�[�̔����v�Ƃ����L���������āA���̉E�ɕʌf�̂悤�Ȉꖇ�̑}�G�����Ă���B���B�N�g���A����̂��w�l���A1865�N�ɃA�����J�l�V���[���Y�����������Ƃ������オ����������̃^�C�v���C�^�[��@���Ă���Ƃ����`�����}�G�Ȃ̂����A���ꂱ�����R�䂳��̃A�j���R�����̃x�[�X�ƂȂ����G�Ȃ̂ł���B�}�G�}�ł̉��ɂ́u�V���[���Y�̃^�C�v���C�^�[�i1872�j�v�ƋL����Ă��邩��A�����炭�A�}�Œ��̃^�C�v���C�^�[�̓V���[���Y�����̐��N�O�ɔ����������̂̉��nj^�Ȃ̂��낤�B���Ȃ݂ɏq�ׂĂ����ƁA���̌��L���̓I�����_��1891�N�ɔ��s���ꂽ�f�E�i�c�[�����Ɍf�ڂ��ꂽ���̂�����A�}�Œ��̃^�C�v���C�^�[������ꂽ�����炻�̎��܂łɁA�����19�N�قǂ̍Ό�������Ă��邱�ƂɂȂ�B
�@ �R�䂳��̃A�j���R�����̊G������Ɗr�ׂ�Ƃ����킩�邱�Ƃ����A�V���[���Y�̃^�C�v���C�^�[�̓�������������̃��[�v����ʂɒu���������Ă���B����͂ނ��Î~�悾����I�y���[�^�w�l�̎�������͂��Ȃ����A�A�j���R�����̂ق��ł́A�uHAPPY NEW YEAR 1900�v�Ƃ������b�Z�[�W�ɂ��킦�āA�����̕�����ł����ޗ���̓����܂ł����扻����Ă���B�Ȃ�Ƃ����������z�Ƃ����ق��Ȃ��B�V���[���Y�ɂ���ă^�C�v���C�^�[����������Ă������135�N�قǂ��o���Ă��邪�A�L�[�{�[�h��l�Ԃ̖{�����̂��͓̂����ƂقƂ�Ǖς���Ă��Ȃ��B���ۂɌ���̉��ɓY�����Ă���N��Ƃ͑����قȂ邪�A�ꎞ��̂̂��w�l���A�ꐢ�I�O��1900�N����2000�N�̌���ւƌ���̃��[�v�����g���ă��b�Z�[�W�𑗂�Ƃ����\�}�́A���Ɋܒ~�������āA�E�[���Ɗ��S���Ă��܂�����ł���B
�@ ���̖{�̒��Ɏ��^����Ă���}�ł�L���̈ꕔ�́A���{��ł����s����Ĉȗ��A���܂��܂ȍL����C�x���g�ނ̐�`�|�X�^�[�ɓ]�ڂ��邢�̓f�t�H�������p����Ă����B�}�ł��̂��̂͂��ׂĕS�N�ȏ�̂̂��̂����A�|�̒��쌠�͈ꉞ���ɂ��邯��ǂ��A�������ǂ��������悤�Ƃ���������Ȃ��̂ŁA���ƃ��}���ɂ��ӂ�邻���̋L�������������ŕ����I�ɔ������p����邱�Ƃ͌��\�Ȃ��Ƃ��Ǝv���Ă���B�R�䂳���̖L���ȗV�т�����ƓƑn�I�ȃA�j���Z�p�������āA�ق��̐}���Ȃǂ����p���f�B�����Ă������邱�Ƃ�����A���������ʔ������Ƃ��낤�B
�@ �V�O�}�ł����s����Ă��炭���Ă���̂��Ƃ����A����e���r�ǂ����̖{�Ɍf�ڂ���Ă��钿�����i�Ⓙ�A�C�f�B�A�T��i���Č����A������ʔ������������f����Ƃ����ԑg����悵���B���̍ہA����҂Ƃ��Ĕԑg�ɓo�ꂵ�Ăق����Ƃ����U�����������肵�����A�����͂܂��t���[�����X�̐g�ł͂Ȃ����낢��ƍS�����������̂ŁA���̘b�͎��ނ����B�ԑg���̂��̂͌��\�D�]�ł��炭�����Ă����悤�ł���B
�@ �b�̂��ł�����A�Ō�ɁA���̋L���̖`�������ȉ��ɂ����������Љ�Ă������B���[�v���̂���c�l�Ƃ������ׂ��A�����̃^�C�v���C�^�[�̔����ɂ܂��b�͂Ȃ��Ȃ��ɋ����[���B
�u�^�C�v���C�^�[�̔����v
�@ ���X�̋Z�p�̒��ł��A�u�����v�Ƃ����Z�p�̏K���́A�������ƌ��т��Ă��邾���ɂ���߂Đ؎��Ȗ�肾�����B�����Ƃ�����������Ɗ肤�҂́A������x�������܂��������Ƃ��ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ��������A�菑���̋Z�p����������Ɛg�ɂ��悤�Ɖ��N���C����ς�ł��A�����̏ꍇ�͖����ł���قǏ�B���Ȃ��ŏI���̂���������B�����������肩���������A���̔��e����͑z�����ɂ��ʁA���C�������o����悤�ȕM�Ղ̂䂦�ɁA�ނ��ނ����j�Z�Ƃ��������ɋ�����ʎ��ԂȂǂ��N�������肵���B
�@ �����ŁA���̂悤�Ȑl�X���~�ς��A�����X�s�[�h���グ�邽�߂ɁA�ꕔ�̔����Ƃ����́A�菑���̕��@�ɂ����ċ@�B�I�ɕ������L���Z�p���J�����悤�Ƃ����B1865�N�A�A�����J�l�V���[���Y�����E���̃^�C�v���C�^�[�삵���̂ɑ����A1877�N�ɂ̓��~���g���Ƃ����A�����J�l�Z�t���A����߂č����\�̃^�C�v���C�^�[�������B�������A��ʂɂ��̎��p�����F�߂���悤�ɂȂ����̂�1880�N����㔼�ɓ����Ă���ŁA���̍��ɂȂ��Ă���ƁA���̋@�B�͋ߎ��̐l�X�⏑�z�i���̍��g�ɂ���F�≊�̈��j�������Ă���l�X�ɖ𗧂ɂ����Ȃ��Ƃ����Ό������߂���悤�ɂȂ����B�����āA1890�N��ɓ���ƃ^�C�v���C�^�[�͋}���ɕ��y���͂��߁A�������p�ɍL�����p�����悤�ɂȂ����B����Ȃ킯������A���炽�߂ď����̃^�C�v���C�^�[��U��Ԃ��Ă݂�̂��Ȃ��Ȃ��ɖʔ����Ǝv����B
�@ 1877�N�Ƀ��~���g�������삵���^�C�v���C�^�[�ɂ�44�̃L�[�����Ă��āA�����̃L�[�́A���~���g�����ł��֗����ƍl�������Ԃɔz�ꂽ�B���̌��ʂƂ��āA�^�C�v���C�^�[�ނɂ����ẮAQ W E R T Y U I O P �̕��������ɕ��ԂƂ������ƂɂȂ����B�����A�ɂ������ƂɁA���̃^�C�v���C�^�[�͑啶�������łĂȂ������B�����A�p���ł��̃^�C�v���C�^�[�̃f�����X�g���[�V�����������Ȃ�������C�M���X�����́A�菑����2�{�̑��x�ɂ����閈��90�����ȏ�̈��x��B�������Ƃ����B���\�͂Ƃ������A���~���g���^�₻��ɗގ������\���̃^�C�v���C�^�[�͂��Ȃ荂���Ȃ��̂������̂ŁA�փ����g�����̂悤�ɁA�V�����^�̂��C�v���C�^�[�삷��l�����ꂽ�B�w�����g���^�̓��~���g���^�Ɋr�ׂĐ��\�͗�邪�A����Ɋ����Ώ\�����p�ɑς�������̂ŁA�������l�i�͊i���ł������B�i�ȉ��ȗ��j
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N1��26��
���̉��ז_��͂b
�@ ���Ă͉����̍��Ƃ��Đ��E���ɖ���y�������{�����A�ŋ߂ł͂��̋����قƂ�Ǎ̂�Ȃ��Ȃ����B���܂ł��Ȃ����z���̌@���̋��z�R�����s���{����������������炢���邩�����m���낤���B�V�����̍��n�A�É����̓y��A����ɂ͓��k�e�n��k�C���ȂǁA���Ă̋��̎Y�n���v�������ׂ�l�������낤���A�c�O�Ȃ��炻���̒n���ŋ����̂ꂽ�̂͂��������Ԃ�Ɛ̘̂b�ł���B
�@ �ӊO�Ɏv���邩������Ȃ����A�����Ō��݂������Y�o���Ă���z�R������͎̂������������ł���B�Ȃ�ƁA���܍����Ő��Y����Ă�����͕S�p�[�Z���g���������Y�Ȃ̂��B���ܗL���̍����ǎ��̋��z�̍̂��H�����R���͂��߂Ƃ��āA���������ɂ͌����̋��z�R���܂����J�����c���Ă���B
�@ �����̂�����Ƃ���ɉ��O���o�Ă��邱�Ƃ�����킩��悤�ɁA�S�悪�ΎR�n�`�̕W�{�̂悤�Ȏ��������ɂ́A����Ȃǂ̋H���z���̍̂��M���z�������Ȃ��Ȃ��B�ΎR�n����L�̃V���X�y��ɕ����ēy�n���₹�A�����Q�������A�č�ɕs�����������F���˂̍������x�����̂́A���f�ՂƗ̓�����Y�������ł������Ƃ����Ă���B�����A���{�̒����z�R���������n��y��Ȃǂ̋��R�ƈႢ�A�O�l�喼���Â̗̂���F���̋��R�́A�˂̑��S�ɐ[���ւ�邱�ƂȂǂ������āA���̏�������Ǘ�����Ă����B���̂��߁A��ʂ̐l�X�ɂ͂����̑��݂���قƂ�ǒm���Ă��Ȃ������̂ł���B�����ȍ~�ɂȂ��Ă������������z�R�̑��݂�m��l������߂ď��Ȃ������̂́A�����ꏭ�Ȃ��ꂻ��Ȕː�����̏��Ǘ��̉e���������Ă̂��Ƃ������̂�������Ȃ��B
�@ ��������������Ƌ�B�{�y�Ƃ̊Ԃ����ԃt�F���[�̕�`�͋��ؖ�s�ɂ��邪�A���̋��ؖ�s�X�̖k���R�n�ɂ��O��n�̍z�R��Ђ��o�c������R�������āA���Ă͗ǎ��̋��z�𑊓��ʎY�o���Ă����B���܂��z�R�̈ꕔ�ł͋��z�̍̌@���s���Ă���Ƃ������A�ߔN�̌@�ʂ͑啝�Ɍ������A������悵���̂̋��z�R�̖ʉe�͂����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ă���悤���B
�@ �����̔ɉh�����I��������A���̋��ؖ���R�̒n��[���ɂ́A�L�͈͂ɂ킽���ċ��B�����Ԃ̖ڂ̂悤�ɉ��эL����A���̖��c�𗯂߂Ă���B�����āA���݂ł͂��̈ꕔ���u�S�[���h�p�[�N���ؖ�v�Ƃ����z�R�����ق����˂����w�{�݂ƂȂ�A��ʂɌ��J������Ă���B���ؖ�̎s�X��ʂ肩�������Ƃ��A���܂����Ԃ��������̂ŁA�쎟�n�����̕����܂܂Ɏ��͂��̃S�[���h�p�[�N��K�˂Ă݂邱�Ƃɂ����B�×��A�l�̐S�𖣗������f�������Ă����Ƃ����������̌̋����A�b���̃^�l�ɂ��������`���Ă�낤�Ƃ������_�ł���B���ꂩ���������ꑰ�Ɖ������Ԃ��ƂȂǓ���l�����Ȃ����̓���炵�̐g�ɂƂ��ẮA�܂�����Ȃ�ɂ悢�@��ł͂������̂�������Ȃ��B
�@ ���ꗿ���ăp�[�N���ɓ���Ƃ����ɁA�n���B���̉��ւƌ����������Ґ��̃}�C���V���g�����Ƃ����g���b�R��Ԃɏ悹��ꂽ�B�������A�ȑO�A���ۂɂ��̍\���Ŏ��Ɨp�Ɏg�p����Ă������̂����w�җp�ɐ����������̂ł���B�z�R�J���҂������g���b�R�ɗh���Ȃ���A��̂��������Â��B����ʂ��Ēn��̍�ƌ���ւƌ��������͋C���^���̌����Ă��炨���Ƃ����킯�Ȃ̂��B�݂����Ԃ̃g���b�R��Ԃ́A���X�Ƃ��������B�������ς��ɋ������Ȃ���A�B�̉��ɂ���n���̃X�e�[�V�����Ɍ������ĂP�L���قǂ̋����������Ă������B
�@ �n���X�e�[�V�����Ńg���b�R��Ԃ��~���ƁA���Ƃ͈ē��W���ɂ��������ċ��B������k���ňꏄ��ł���悤�ɂȂ��Ă����B���炭�B����i�ނƂ܂���^�̌@�i�@���u����Ă���Ƃ���ɏo���B���j�ɂ���čӂ��ꂽ�z��ςݍ��݂Ȃ���A����Ɠ����ɉ��ւƍz�Αw���@��i�ނƂ����Ȃ�Ƃ���p�Ȍ@��^���@�B�ŁA���b�J�[�V���x���ԁA�O�����r�[�z�ԁA�o�b�e���[�d�Ԃ̎O�̓���ԗ����������Ăł��Ă���B��̑O�̖���Ȃǂɓo�ꂷ�鋐�働�{�b�g�����A�z������ǂ������[�����X�Ȃ��̓����ɁA�������͌�����Ă��܂����B�܂��A�@�i�@���炻������Ă��Ȃ��Ƃ���ɂ́A�S�n�͂̍������[�^�[�ƍ|�S���C���[�ɂ���đ�B�����ɐl�Ԃ�z�Ή^���Ԃ������グ�鋐��ȃE�C���`�Ȃǂ��������B��B�Ƃ́A�[���n���̍B�����炳��ɒn��Ɍ��������z�������ɁA�X�Ίp35�x�A����250m�ɂ킽���Č@��ꂽ��B���ŁA�̌@��ƈ����^��22�l���̐l�Ԃ�X�L�b�v�ƌĂ��z�Ή^���Ԃ��A���Ă͂��̍B���Ζʓ`���ɂ����������㉺���Ă����炵���B
�@ �B��������ɉ��ɐi��ł����ƁA�V��⍶�E�̐Ήp���̕ǖʑS�̂��܂�ŋ��̗��q�ߍ��܂�Ă��邩�̂悤�ɂ��炫��ƋP���Ă���Ƃ���ɏo���B���ꂪ�݂ȋ��z���c�c����ᐦ����Ə��߂͎v�����̂����A���炭���邤���ɂǂ������������ƋC�������B����ɂ��Ă͉����F�̗��q��������Ƒ傫������悤�����A����痱�q�̎U�ݖ��x���������銴���Ȃ̂��B�ǂ�����т̍B���ǖʂɊ܂܂�邻��疳���̋��F�̗��q�́A����ȉ_��n�̍z���ł���炵�������B
�@ ����őz���o�����̂����A�����R�n������̌����n�т̑ɓ���ƁA�쏰�̍�����ʂ��炫��Ɖ����F�ɋP���Ă���Ƃ��낪����B�f�l�������疳���̍������q���썻�ɍ������Ă���悤�Ɍ����邵����̂�����A�ʂɈ�A��t�قǍ����Ǝ����Ԃ��āA�u����͒����̂���R���̔閧�̏ꏊ�Ŕ����̎悵�������Ȃ�v�Ɛ^��ł��炩���ƁA�����Ă��͂�������x����Ă��܂��B��ڌ��Ċ䕨���ƌ��j���l�́A�����ɍz���ɏڂ����l�������B�ŋ߂���������m���������̂Ƃ���炻�̊䍻������̍��������Ԃ��đf�m��ʊ�Ŋw�������Ɍ����A�����ς��H�킹�����Ƃ����������肾�����B
�@ ���Ƃ����낤�ɁA���̗��B���̊�ǖʂł��炫��Ɣ������P���Ă���̂́A���̊䍻���̑������߂Ƃł������ׂ��z���Q�������̂��B���Ƃ��Ƃ͔�d�̌y�����������F�������̍z�������A���̔��˗��̊W�ŋ��F�ɋP���Č�����̂��B���̂悤�Ȋ���������Ԃ������ĕ������A�₪�č���ɂȂ��Đ쏰���݂ɑ͐ς���ƁA�����⑽���̎R���̑�ɂ���悤�Ȋ䍻�������ł�������Ƃ����킯���B
�@ �{���̋��z���T���v���͊���z�̂���Ƃ��납�炳��ɉ��ւƐi�Ƃ���ɂ������B�������A���̎��ӂ����Ӑ}�I�ɍ̌@���c���Ă��������̂��B����ɋ��z�Ƃ͂����Ă����낢��Ȏ�ނ̂��̂�����炵���̂����A���̋��ؖ���R�̏ꍇ�A�Ήp�����̔�����Ղ̂��������ɍ����ۂ����Ȗ͗l���Ȃ��đ����Ă���̂����z���Ȃ̂��Ƃ����B�ӊO�Ȃ��ƂɁA�ق�Ƃ��ɂ��ꂪ���z�H�c�c�Ɩ₢�Ԃ������Ȃ�قǂɒn���ȐF�����Ă���B�����ۂ�������̂͋₪���Ȃ荬�����Ă��邩��Ȃ̂��낤�B�����d���̌��Œ������т鍕���ۂ��t�������Ƃ炵�o���Ă݂�ƁA�������ɂ��������ȉ����F�̓_�������ɂ���߂��Ă���̂����ʂł����B����z�̗��q�̉��\���̈�A���S���̈ꂭ�炢�����Ȃ������q�ł���B
�@ ���i�ʂ̋��z�ł��P�g�������肹���������O�������x�̋������̂�Ȃ��Ƃ�������A���ۂ̋��z���Ƃ͂܂�����Ȃ��̂ɈႢ�Ȃ��B�����̋��z���̊���C�̉����Ȃ�悤�Ȏ��Ԃ������ď����ȍ����ɂ܂ŕ������A�₪�Ĕ�d�̑傫�����̔����q�������̒ꕔ�ɒ���Ō݂��Ɍ����A�傫�߂̗��q�ɐ��������̂�������V�R�����Ƃ����킯�Ȃ̂��B���������ƋC�y�Ɍ������A�����ɂ�����܂łɂ͒����Ȃ������Ԃɂ킽�鎩�R�̐��B�v���Z�X���o�Ă��Ă���킯�ł���B
�@ ����ɍB����i�ނƁA�p���������{�b�g�Ԃɉs������ȍ|�S���̊p���͂₵���悤�Ȍ`�́A���[�r���W�����{�Ƃ������������@�����ꂽ�B���剻�������J�����̃C���[�W�������̃}�V���̓��̂͑O���ƌ㕔�̓�ɕ�����A�O�㗼�����q���������ׂ͍����т�Ă���B�A����n�`�Ȃǂ̓��̂�z�����Ă��炦�悢�B�������ɂ��邭�т�̂������Ń��[�r���W�����{�͌㕔�̈ʒu��ς��Ȃ��܂܁A�O���̌���������ς��Ċp�̐�[���㉺���E�ɐU�邱�Ƃ��ł���킯���B��������ǂɌ������p�̐�̓��Z���a������]�����@�ɂȂ��Ă��āA�@��J�����E�ɔ�����l�߂Ċ�Ղj����B���̂ق��A�������B���ł������₷���悤�Ɏԕ����ׂ����A�Ȃ������B���ɂ��_��ɑΉ��ł���悤�ɍH�v�������[�h�z�[���_���v�Ƃ����z�Ή^���Ԃ̍\���Ȃǂ������[�������B��������������}�V�����J�������Z�p�҂����́A�����ƍ����⓮���̓������炻�̍\���̃q���g����������̂��낤�B
�@ ���j�[���̌��|�C���g�A�����̋���z���w�ƌ@�킵�����z�����̂܂ܓW������Ă���̌@�؉H����̏Љ�R�[�i�[�A���̉�600���[�g���̂Ƃ���ł͌��݂����z�̌@���Ƃ����B�����A����ɂ́A�T���_�[�z�[���Ƃ������a2.2���[�g���A�[��120���[�g���̏c�B�̔`�����Ȃǂ����X�ɂ߂��������ƁA�u�����̃s���~�b�h�v�Ȃ�W�����̂��ɏo���B����39�N���猻�݂܂łɍ̌@���ꂽ����55�g���A��{12.5kg�̃C���S�b�g�A��������̉��ז_�Ɋ��Z�����4400�{���ɂȂ�Ƃ����B4400�{���̖͋[�C���S�b�g��A������s���~�b�h��ɐς�œW�����Ă������̂����A�l�ԂƂ͏���Ȃ��̂ŁA�{���łȂ��Ƃ킩���Ă��܂��ƁA�ǂ����^���ɂȂ��Ē��߂�C�����Ȃ��B�Ӂ[��Ƃ��������ł��̎q���x���݂����ȉ����̃s���~�b�h�̑O��ʂ肷���Ă��܂����B
�@ �g���b�R��ԃ}�C���V���g�����̒n�������X�e�[�V�����ɖ߂邷������O�ɂ́A�n��C�x���g�z�[���Ƃ������I�[�v���X�y�[�X�������āA�c�^���J�[�������̉����̃}�X�N�̕����ȂǁA�������̗��j��L���ȉ����╨�̕����i���W������Ă����B��ʂ蒭�߂�������ł́A�܂�����Ȃ�ɂ悭�ł������������A�f�ނ̂ق����{���̋��𑊓��ʂ͗p���Ă͂���炵���̂����A�����物���ɊW�����邩��Ƃ͂����Ă��A�����̕�����������Ȓn��z�[���œW������̂͏��X��Ⴂ�Ȃ悤�ɂ��v���ĂȂ�Ȃ������B�܂�����Ȃ�̎���������Ă̂��ƂȂ̂��낤����A���O�҂̎��Ȃǂ����ꂱ�ꌾ���Ă݂Ă��d���̂Ȃ����Ƃł͂������̂���������ǂ��c�c�B
�@ �n���̌��w�R�[�X���߂���I���A���ԑ��Ƃ͔��Α��ɂ���n���X�e�[�V�����̏���ɏo��ƁA�Ȃ�ƁA���ꌩ�悪���ɃL���L���L���ɐg���ł߂����l�炵�����̂��������Ă��킵�܂��ł͂Ȃ����B�K�C�h�}�b�v�̉���ɂ��ƁA�u�����ω��v�l�ł��点����̂������ŁA���̑�������芪�������Ȓr�̂Ȃ��ɂ͂����܂�̂悤�ɑ�ʂ̂��ΑK�����荞�܂�Ă���B�S�g���ꉩ���̉��g�݂����Ȋω��l�ɁA�����̋P���Ƃ͖����̒�z�d�݂Ȃǂ����܂��獷���グ�Ă݂��Ƃ���łǂꂾ���̌䗘�v������̂��낤�A�ǂ����Ȃ烆�j�Z�t����ɂł����ق�����قnj䗘�v������̂ł͂ƁA�Ӓn���Ȃ��Ƃ��v������������B�u�ق�Ƃ��ɍ����Ă���҂́A���ΑK�������邩���ɉ����̐g�̂̈ꕔ��������Ď��������Ă��悢�A���ꂪ��F�Ƃ������̐g�̎��߂Ƃ������̂ł��c�c�v�Ƃ��Ȃ�Ƃ��A�I�X�J�[�E���C���h�̓��b�̎�l���u�K���̉��q�v��̊i�D�����Z���t��f���Ă����Ȃ�b�͂킩�邪�A����Ȃ��Ƃ�������A���҂��ω��l�̂����̉��̎��̂��m��āA�͂Ȃ͂��s���������̂����m��Ȃ��B
�@ �Ăу}�C���V���g�����ɏ�荞��Œn��X�e�[�V�����ɖ߂�A���H�ē��ɂ��������Đi�ނƁA���z�R�W�̗��j����ыZ�p�����Ȃǂ��W������Ă��鏬�����ٕ��̌����ɏo���B���ؖ���R�̒n���B���Ԃ��������̖͌^�Ȃǂ����������A��������Ă݂�ƁA���Ȃ�[���L���Ǝv�������w�R�[�X���A�B�������ɑ����邲���ꕔ�̗̈�ł��邱�Ƃ��悭�킩�����B
�@ �����̓W�����̒��łƂ��Ɉ�ۂɎc�������̂�����������A���̈�͋������n���������Ƃ������@�̐��������B���┒���͉��_�ɂ��M�Z���_�ɂ��Ɏ_�ɂ���������Ȃ����A�Z�Ɏ_�ƔZ���_�Ƃ����̊����ō������������ƌĂ��t�̂ɂ����͗n������B�����́A���w�̎��Ƃŋ�����Ă���Ȃ��̂�����炵���Ƃ������Ƃ����͒m���Ă����B�����A�{���̋����킴�킴�n��������������Ă݂��Ă����悤�Ȑ����ȉ��w�̐搶��������������͂����Ȃ�����A����܂ŋ���n�����������̎����Ȃnj������Ƃ��Ȃ������B
�@ �̂͋��z��������̎悷���Ƃɂ͑����ȋ�J���Ƃ��Ȃ����悤�ŁA���Ȃ�ܗL�ʂ������A�܂܂����̗��q�Ɉ��ȏ�̑傫�����Ȃ��Ƌ��̐�������������͍̂���ł������炵���B�������A����n�����邱�Ƃ̂ł��鉤�����o�ꂵ�Ă���́A�ܗL�����Ⴍ���q������߂čׂ������z����ł������̎悷�邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B���z����ɕ��ӂ��Ă��炢�����ɗn�����Ē��a������B�����ċ��𑽗ʂɊ܂ޔ�d�̏d���ꕔ�̍��D�����o���ĉ����ɓ����Ƌ��������A���������f�_�Ƃ�������ȍ��C�I���ƂȂ��ėn���o�����B����Ɉ�����������ƁA�C�I�����X���̑傫�Ȉ����������C�I���ƂȂ��ėn���o���A���̂��߃C�I����Ԃ�ۂĂȂ��Ȃ������C�I�������x�̍������ƂȂ��Đ͏o���a����B���Ƃ́A������̎悷��悢�B
�@ ����n�������������W������Ă������A�Ȃ�ƕ����ʂ�́u�����F�̐��v�ŁA�����ȃX�R�b�`�����ߐF�̋P���������Ƌ��F�ɋ߂Â����悤�ȁA�ǂ������d�Ő_��I�ȐF��ттĂ����B���̐F���A�������̂��̂̐F�Ȃ̂��A����n�������Ƃ��ɐ�����e��C�I���̐F�̍����F�Ȃ̂��A����Ƃ����ۂɋ��C�I���̐F�Ȃ̂��͔���Ȃ��������A�Ȃ��Ȃ����Y��Ȃ��̂������B�����Ă��̋����C�I���̏ꍇ�ɂ́A���Ƃ��Ƃ̋����̐F�Ƃ��̋������C�I���ƂȂ��ėn�o�����Ƃ��̉t�̂̐F�Ƃ͑����Ɉ���Ă���̂����ʂȂ̂ŁA���������ꂪ���C�I������݂̐F���Ƃ���A�Ȃ�Ƃ��ӊO�Ƃ��������Ȃ��B�����A����n������O�̉������ɂ͉����j�g���V���iNOCl�j�Ƃ������ԐF�̋C�̂��n������Ԃő��݂��Ă���炵������A�����ڂɂ����������F�̉��o�̎�́A���͂��̕����̂ق��������̂�������Ȃ��B
�@ ���܈�����������䂩�ꂽ�̂́A���̃S�[���h�p�[�N�̖ڋʂƂł������ׂ��A���̉��ז_�̓W���R�[�i�[�������B�l����������v�����ȃK���X����ɂȂ��Ă���W����̏�ɁA�t���J�}�{�R��������Ƒ傫�������悤�Ȍ`�̏����̉��ז_����{�����A����Ȗʂ����ɂ��Ēu����Ă���B���ʂ̃K���X�̉����ɂ́A���傤�ǐl�Ԃ��Ў��r�悭�炢�܂ō������ނ��Ƃ̂ł���~�������J���Ă��āA����������˂�����Œ��̋��̉��ז_�ɐG������A�����͂�ł���悤�ɂȂ��Ă����B����悭�����ƒ͂�ł��Ɉ����āc�c�ȂǂƂ悩��ʊ��҂����Ȃ���A���̉��ז_���݂͂ɒ���ł݂����A�Ȃ�ƁA�����グ�悤�Ƃ��Ă�����̓s�N���Ƃ����Ă���Ȃ��B
�@ �Иr��L���A��̍b����ɂ��Ẵ`�������W������A�ؓ��̏�Ԃƃe�R�̌������炵�ė͂��͂��肸�炢�Ƃ������Ƃ����邯��ǁA����ɂ��Ă��d�����B�����ɗ͂ނƁA���낤���Ĕ���]�قlj��ɓ]�������Ƃ͂ł������A���̏ꍇ�ł����̏�Ԃɖ߂��Ƃ��w������ז_�̕���Ȓꕔ�ł͂��܂�Ȃ��悤�ɒ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�����₵�čl���Ă݂�ƁA�傫�߂̔J�}�{�R�قǂ̋��̉��ז_�͈�{��12.5kg�قǂ�����B���l�߂������ł͂��̏d���̓s���Ƃ��Ȃ����A��2���b�g������y�b�g�{�g��6�{���ȏ�̏d�ʂ�����̂�����A�ȒP�Ɏ����オ��킯���Ȃ��B�������ĉ䂪�ꝺ����̖��͙R�����ׂ��������B�f��▟��Ȃǂɂ́A�����Ȃǂ����̉��ז_�����\�{���傫�Ȋ���܂ɋl�߁A�y�X�Ɖ^�яo����ʂȂǂ����邪�A�����ɂ͂���Ȃ��ƂȂǕs�\�ł���B�Ȃɂ�10�{��125kg������Ƃ����̂�����c�c�B
�@ �S�[���h�p�[�N�����Ƃɂ��悤�Ƃ��Ă���Ƃ��A���邱�Ƃ�ˑR�Ɏv���o�����B��������Y��Ă������A���Ď��͎�̂Ђ�ɂ̂邭�炢�̏����ȐΉp���̊�Ђ������Ă����B���w���̍��A�����̂Ƃ��鍂��̔��ɑc���ɂ��Ĉ��@��ɏo�����A���̔��̕Ћ��ŗz���𗁂тĔ����P�����̊�̂�������������B�悭����ƍ����ۂ������������ɑ����Ă��āA�����̋̋ߕӂɂ̓L���L���Ƌ��F�ɋP�������ȗ��X�������ɓ_�݂��Ă���̂��������B���ꂪ���Ȃ̂��͂悭�킩��Ȃ��������A�Y��Ȋ�ЂȂ̂ʼnƂɎ����Ԃ��Ē����ԂƂ��Ă������B���Z�ɒʂ����߁A���𗣂�Ď������s�ɏo���Ƃ��ɉƂɒu���Ă��Ă��܂��A���̉Ƃ����̐��N��ɂ͉�̂���ĂȂ��Ȃ����̂ŁA�������̊�Ђ̍s���͂킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂������A���v���ƁA�ǂ�������͋���z�̂����炾�����炵���̂��B�S�[���h�p�[�N�̎������ɓW������Ă����Ήp���̋���z�ƐF���Ƃ��ɂ������肾��������ł���B
�@ �l���Ă݂�ƁA�����͊C���͂���Ŗ{�y��30�L���قǗ���Ă͂��邪�A���ؖ�A�ڃ���A�H���Ƃ��������R�̂���n��Ƃ��������Ȃ��B�������Ƃ���A�n���w�I�ɂ݂Ă����̒n��̒n�w�Ɠ����̒n�w�����݂��Ă��Ă����������Ȃ��B���̊�Ђ��E�������̂�����́A�ߑa���ɂƂ��Ȃ��_�Ƃ̐��ނł�������r�n�ɕϖe���Ă��܂��Ă��邪�A�ꏊ�����͂͂�����ƋL���Ɏc���Ă���B�����ƒT���A���̊�Ђ̊܂܂�Ă����n�w�������邩������Ȃ��B�����Ȃ�Έꝺ����̖����������Ȃ��Ƃ�������Ȃ��B�����A����Ȃ��̏����Ȃ���Ă���A���̍ہA�R�t�ɂł��]�g�����ق���������������Ȃ��ȁc�c�������N�̓��̋L������J�鎄�̔]������u����Ȏv�����悬���Ă������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N2��2��
����l�̗[�i
�@ �F�������𐼊C�݉����ɓ쉺����r���A����l�i�ӂ������͂܁j�ɗ�������ė[�z�߂邱�Ƃɂ����B�V�̒�܂ł������ݓ����������̈���������̂ŁA�f���炵���[�z��������ɈႢ�Ȃ��Ǝv��������ł���B�Ԃ��~��ď��т���ƁA�قړ�k�ɒ���ȋ|�`���Ȃ��ĉ��т鍻�l�ɏo���B�Ήp���̍��ƎX�莿�̍��Ƃ������荇���������́A�������тɃT�N�T�N�ƐS�n�悢���������Ă�B���ɐl�e�͂܂������Ȃ��B�����ɉ����L����[��̓��V�i�C�́A�Ƃ�ɑ���ʈ�l�̗��l�̂��ƂȂǂ܂�ŊS���Ȃ����̂悤�ɁA�[���ґz�ɒ��܂܂������B
�@ �����������l�͗����ɂȂ��ĕ����ɂ�����Ǝv���A�������܌C��E���̂āA���炽�߂č���ɑ������낵�Ă݂��B���̓r�[�ɁA�y���܂���ʂ��āA�����ŊC�ӂ��ӂ��삯�����Ă��������������N�̓��̊��o���S���Ă����B�k�������̊C��͂邩�ȂƂ���ɂ́A�[�z�ɐ��܂�ג������e���������B�c�����Ɏ�������������ł���B���N�̓��X�A���͂��̓��ɍ݂��āA�������ދ�B�{�y�̎R���݂�̊፷���Œ��߂Ă����B�C�̌������̖{�y�ɂ́A������Ȃ����ƃ��}���ɍʂ�ꂽ���m�̐��E�������āA�����̎���҂��Ă��Ă����͂��ł������B
�@ ���̎����璷���Ό������ꋎ�������܁A���́A���܂��ܖK�ꂽ��B�{�y�̐���̕l�ӂ���A�����̈���������̓��e��[�z�̂��ƂŒ��߂Ă���B�m�X�^���W�A���ƌ����Ă��܂�����܂ł����A���̂�̉ߋ��̖����ꖰ�铇�e���������Ă͂邩�ɖ]�ނ̂́A�Ȃ�Ƃ����S�[�����̂������B�Ԗ��𑝂������z���������ɒ��ނ܂łɂ́A�܂����������Ԃ����肻���������̂ŁA���́A����ɐԎ��F��[�߂Ă����������e���E��ɒ��߂Ȃ���A���������������Ď�����肷�������Ƃɂ����B����Ȏ��̂��������A��H�̐璹���Â��Ɋ�������g�ƋY��Ȃ���A���傱���傱�Ƌ}�����Œʂ�߂��Ă������B���[�����X�ȓ����̂Ȃ��ɂ��ǂ������t�ɂ͐s������D��X�����A�Ȃ�Ƃ��s�v�c�Ȓ��ł���B
�@ �C����������g�̂��}�ɗ₦�Ă����������낤�A�ˑR�A�����I�M���������͂��߂��B�ނ��A�߂��ɂ͂���炵���{�݂����낤�͂����Ȃ��B�����A�����킢�Ƃł��������A�L��ȕl�ӂɗ��̂͂��̐g�ЂƂ肾���ł���B�����Ȃ����猴�n�I�ȏ����@�ɗ��邵���Ȃ��Ǝv�������́A�ǂ����Ȃ�A�q���̍��悭������悤�ɁA�����������̏�ɑ傫�Ȏ���`���Ă݂悤�Ǝv���������B
�@ �\�����̗��������Ɂu�{�c���e�����Q��I�v�ȂǂƋL���ɂ͐����̗ʂ����肻���ɂ��Ȃ������̂ŁA�Ƃ肠�������̓�������傫���`���Ă݂邱�Ƃɂ����B���l��a�������ɂ��ĕM�i�H�j���ӂ�������ʁA�C���X�^���g������i�Ƃ��Ă͂܂��܂��̏����d�グ�邱�Ƃ��ł����B�������ŋC�����������肵�����́A���̏�ɂǂ�����ƍ������낵�A�������ւƋ}���ɋ߂Â��͂��߂����z�ɂ����ƌ����邱�Ƃɂ����B
�@ �v�X�Ɍ���������[�z�������B�C�ʂ͋P���悤�Ȏ�F�ɐ��܂�A����͔Z�����F��F�ɕ���ꂽ�B�����āA�E��ɕ����ԉ����������e�́A���̗֊s�����ʼn����ł��������̂悤�ɐԁX�ƔR�������Ă����B�傫�����邢�I�����W�F�̑��z���h��߂��悤�Ȏc�����Đ������̔ޕ��ւƎp���B���܂ŁA���́A�u�����Y�̍������Ȃɂ��̂悤�ɁA�r��g��ł��̏�ɂ�������܂܂������B
�@ ���N�̓��X�������铇�e���g�@�ɐ��߂ē��V�i�C�̔R��
�@ �҂�Ȃ��ЂƓ��̐��̋Y������ƕς��ėz�͉����ɂ���
�@ �[�ł̔��鍻��ɍ����Ă���ȉ̂Ȃǂ��r�ݙꂢ�����ƁA���т�D�����n�̍ד����ĎԂɖ߂����Ƃ��ɂ́A������͂�������Â��Ȃ��Ă����B
�@ �Ăуn���h���������ĎF��������쉺���Ă��������ɁA���܂��܁u��[�ӂ�v�Ƃ������㒬�c�̉���ۗ{�{�݂̂���ʂ肩�������B�u��[�ӂ�v�˂��c�c�����������ς��Ƃł������Ӗ��Ȃ̂��Ȃ��H�c�c���܂����Ȃ悭�킩��Ȃ����O�����ǂȂ��c�c����Ȃ��Ƃ��l���Ȃ���A������Ɨ�������Ă݂�ƁA�{�ݓ��ɂ͗��̊��𗬂��̂ɂ����Ă����̉��K�ȉ���Ȃǂ��������B��D�̃^�C�~���O�ł�����������A�������Ȃ����͂����ňꕗ�C���т邱�Ƃɂ����B
�@ ����ɓ����Ă����ς肵���܂ł͂悩�����̂����A���̂��Ƃ�����������肾�����B�u��[�ӂ�v�ŗ[�H���Ƃ邩�A���̎��ӂł���Ƃ����H�ނ��w�����Ă����悩�����̂����A����Ȃɂ͋����o���Ă��Ȃ������B�����ŁA�ǂ�����̂ق��ɂ܂��J���Ă���H�����R���r�j�����邾�낤�ƌy���l���A�F�������쐼�[�̊}������Ԗ����ʂ�ڎw���đ���o�����̂������B�Ƃ��낪�A�\�z�ɔ����āA�H����H�ޓX�Ȃǂ͂ǂ����܂��Ă��āA�R���r�j�炵�����̂������ς茩������Ȃ��B���̕t�߂͖�㎞���߂���Ɛl�ʂ��Ԃ̒ʍs���قƂ�ǂȂ��Ȃ邩��A�X���J���Ă��Ă������ɂȂ�Ȃ��̂��낤�B
�@ ���܂��܃C���X�^���g�H�i�ނ���������H�אs���Ă����Ƃ��낾�����̂ŁA�茳�ɂ͐��݂���A�O���c���Ă��邾���������B�������Ɉ��ݕ��̎����̔��@�����͓��H�e�̂��������ɐݒu����Ă����̂ŁA�ʃR�[�q�[�Ɗʍg�������͔������ނ��Ƃ��ł����B�������A��A�ԑ����đ傫�Ȏs�X�n�̂���Ƃ���ɏo��Ȃ�Ƃł��Ȃ邱�Ƃ͂킩���Ă������A����ł́A�킴�킴�C�݉����̖铹��`���Ă����܂ł���Ă����Ӗ����Ȃ��B�f�H���H�ɂ���ׂ�Ȃ�Ă��Ƃ͂Ȃ��A�悵�A����Ȃ獡��͐��ݎO���ƈ��ݕ������łʼn䖝���悤�ƕ����������B
�@ �}�����ɓ����Ă����Ԋx�̖k���[�ɓ_�݂���C�����̏��W�����������ʉ߂��A��Ԋx�̐��k���Ɉʒu�����Ԓr�`�ɒ������Ƃ��ɂ͂��łɌߌ�\�ꎞ���߂������B��Ԓr�`�͎F���������[�̖�Ԗ��̕t�����Ɉʒu���邩�Ȃ�傫�ȋ��`�ł��邪�A�`�߂��̏W�����ӂɂ͐l�e�͂قƂ�nj�������Ȃ������B�ЂƂ킽���̖�Ԓr�`���߂���I���A���̐n�`�ɊC���ɉ��яo���Ԗ��̍����������Ė�Ԋx�̓쐼���R�[�ɉ��ƁA�ł���i�Ɛ[�܂�A�܂�ł����҂��Ă������̂悤�ɓV��̐��X�̋P���������Ă����B�ቺ�ɂ͓��x�ߊC�����X�Ɖ������A�͂邩�����ɂ͋�����܂��Z�_�X�ƕ�����Ō������B
�@ ��̂��߂��̎p�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��������A�C���T�X�P���[�g���̖�Ԋx���Y��Ȍ`�̎R�ł���B������[�Ɉʒu����C���X�X�Q���[�g���̊J���x�ƂƂ��ɁA�×��A�F�������̏ے��I���݂Ƃ��ďM�l�����̍q�C�̕W�ɂ��Ȃ��Ă����B����C��͂邩�ȎF�쏔���◮���������ʂ����B�{�y��ڎw�����Â̏M�l�����́A��{�̊p�̂悤�ɍ��E�ɑ傫���Ԃ��J�����ނ�����Ԋx�ƊJ���x�̏G��ȎR�e�������Ă���ƁA����Ŗ����ɎF���ɒ�����Ɗ�сA���g�̋��ł��낵�����̂��Ƃ����B
�@ ��Ԋx�̓�Ζʂ��}�p�x�ŊC���ɗ�������ł��邠����܂ōs���ƁA���H�e�ɏ����ȓW�]�����݂����Ă���̂��ڂɂƂ܂����B�����ɂƗ�������Ă݂�ƁA���ԂȂ炩�Ȃ�W�]�����������ȏꏊ�ł���B�s���̂悢���ƂɁA�Ԃ���A���قǂ����钓�ԏ���������B���X���C���Â��Ă����Ƃ���ł��������̂ŁA�Ƃ肠�����͂����ɎԂ𒓂߁A�Ђ�����ƈ��𖾂������Ƃɂ����B�Ƃ��Ă����̎O���̐��݂������炰�A�ʍg���ƊʃR�[�q�[������ł���A�[��̓W�]��ɗ����đ傫�Ȑ[�ċz�����Ă���ƁA�������ɒ��̑��������镗�ɏ���ēr��Ƃ���ɋ����Ă����B
�@ �Ȃɂ��Ȃ��W�]��̕Ћ��ɖڂ����ƁA�Α���̋L�O��炵�����̂������Ă���B�����낤�Ǝv���ĉ����d���ŏƂ炵�o���Ă݂�ƁA�Ȃ�ƁA�֓��g�̉̔�ł������B��ʂ̕ւ̂���߂Ĉ�����������ɁA�g�͂���ȂƂ���܂ł͂�����ė������̂炵���B
�@ �_��̊}���̍�ɂ킪�����ЂƂ��тƂǂߐS�a���Ȃ�
�@ ���̉̔�ɂ͂���Ȉ�[�X�ƒ��荏�܂�Ă����B���̉̂́u�}���̍�v�Ƃ����n�������̓W�]��̂���t�߂̂��Ƃ��w���̂��A����Ƃ����ۂ̎F�������̍Ő��[�A��Ԗ����w���Ă���̂��́A���ɂ͂悭�킩��Ȃ������B�����A���݂ł��Ő�[�܂ōs���ƂȂ�ƁA�[���M��蕪���A�g�̒��ɒw偂̑��̐�����Ȃ���i�܂˂Ȃ�Ȃ���Ԗ��Ɏ��ۂɖg�������^�Ƃ���A���̗��S�̐[���͂�͂�l���݂͂��ꂽ���̂ł������ƌ��킴������Ȃ����낤�B
�@ �g�̉̔�̗����̓W�]�䂩��A�����̊J�c�Ӑ^�䂩��̒n�Ƃ��Ēm����V�Ò��H�ڂ܂ł͂킸����������Ă��Ȃ��B�����炭�g�͖V�Â�K�˂����łɂ��̖�Ԗ����ʂւ�����L�����̂ł��낤�B�邪��������A�����܂��Ӑ^�a��̑��Ղ������˂Ă��̖V�Âւƌ��������肾�����B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N2��9��
���V�K�Ƃ̑���
�@ ���邢���̗z�˂��ɑ�����Đ[�����肩��ڊo�߂Ă݂�ƁA�ቺ�ɂ͐��C�������̂�̑��݂��֎������̂��Ƃ�����߂��L�����Ă����B���Č����g���悹���D���������Ă������ォ�琔�m��ʐl�����݂̂���ł����C�ł���B�ꌩ���₩�ɂ݂͂��邯��ǂ��A���̓��V�i�C�͍r���ƕ|���B�E��ɂ͊��̐n�`�ɋȂ����Ă̂тł��Ԗ������]���ꂽ�B�t�����̂Ƃ��납��˒[�܂Ŏl�L���قǂ͂��낤���Ǝv���邱�̖��͑S�̂��藧�����C�H�R�Ŏ��͂܂�Ă��āA�C������߂Â����Ƃ͗e�ՂłȂ��B����ዂ�������̔w�ŕ��ɂ́A����̂ق��ɁA�傫�ȎO���H�̕��Ԃ������͔��d���������Ă����B���͔��d���̂ق��͋ߔN�݂���ꂽ���̂Ȃ̂��낤�B
�@ �ȑO�Ɉ�x���̐�[�ɂނ����ėŐ��`���ɕ��������Ƃ����邪�A����Ɏ��邩�Ȃ��O���瓥�ݐՂ��قƂ�ǂȂ��ׂ��M���ɂȂ�A�������玟���Ɍ����w偂̑���~�������Ȃ���O�i�����L��������B���̒��قǂɌ�����̂Ƃ���܂ł͂Ȃ�Ƃ��H�蒅�������A������������⊙���g���Đ[���M���J���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��������̂ŁA����ȏ�i�ނ��Ƃ�f�O�����B���Ƃ����n�`�͂Ȃ�Ƃ�������������̂ŁA���݂����ȕƒn�D�݂̗��l�͂����ɂ��̖��͂ɂƂ����A�n�̉ʂĂ��ɂ͊C�����Ȃ��Ƃ킩���Ă��Ă��A�ǂ����Ă���x�͓˒[�܂ōs���Ă݂Ȃ���C�����܂Ȃ��S���ɂȂ��Ă��܂��B���[�n�`�Έ��nj�Q�Ƃł����Â���ׂ����̕a�I�ȐS����Ԃ͂����������ɋN��������̂Ȃ̂��낤�B
�@ �W�]�������Ƃɂ��ĖV�Õ��ʂւƑ���͂��߂Ă܂��Ȃ��A�O���̘H�㒆���ɍ����ۂ������̎��̂炵�����̂��]�����Ă���̂������B�ŏ��͌����Ȃɂ����낤�v�������A�߂Â��Ă݂�Ƃ��̎p�`��ѕ��݂͌��̂���Ƃ͂܂�ňႤ�B�Ԃ��~��ĂԂ��Ɋώ@���Ă݂�ƁA�Ȃ�Ƃ���͖쐶�̑傫�ȒK�̎��[�������B�̂ɐG���Ă݂�Ƃ܂��������B�������܂��ɓ������Ԃ�瀂��ꂽ�炵���A�����̏�Ԃ������B�K�Ȃ�ɋ�J���Ă����܂ő傫��������̂��낤�ɁA�ԂƂ����T�ᖳ�l�ȐV�ĉ��b�Ɉꌂ����ďu���ɗ�������Ȃ�āA�����������O�Ȃ��Ƃ������낤�B�ʍs����Ԃ��قƂ�ǂȂ����̒n�ŎԂɂ͂˂��Ď��ʂȂ�āA��قlj^�����������Ƃ��������悤���Ȃ��B
�@ �����ď�v�����Ȏ葫�̒܂ׂĂ݂�ƁA�s���d�����̐�[�ɂ͓y�≽���̑@�ۂ炵�����̂����т���Ă����B�܂����Ȃ艷����̎c�镠���ׂ̍��_�炩�ȑ̖тɊr�ׁA�w�����̖т͑e���Ă��炴��Ƃ��Ă���A���L�̒e�͐������Ȃ��Ă����B�K�̖т͖ѕM�̕��̑f�ނɊi�D���Ƃ͕����Ă������A�Ȃ�قǂ���������̂�����B���̂܂ܓ��H�̒����ɕ����Ă����̂����z�����A��d�O�d�ɎԂ�瀂��ꂽ�肵����K�̗삾���ĕ�����܂��B���߂ē��H�e�̑��ނ炩�т̒��ւƉ^��ł�낤�Ǝv���āA��{�̌㑫�������ƒ͂�Ŏ����グ��ƁA������Ƃ����d�݂�����ɓ`����Ă����B�������͂��߂��r�[�ɃW���[�b�Ƃ����������Ăđ̉t�������o�������Ƃ��炵�Ă��A���̂ɑ������Ă���܂��Ԃ��Ȃ����Ƃ͖��炩�������B
�@ ���w�ɂ���悤�ȏے�����������ׂ��Ƃ���Ɍ�������Ȃ����炱�̒K�͎��Ȃ̂��낤���Ƃ��A�̂̐l�͒K�`��H�ׂ��Ƃ�������������������ǂ�����Ē��������̂��낤���Ƃ��A���Ȃ��Ƃ����ꂱ��l���Ȃ�����A���̑�K�̈�[��т̘e�܂ʼn^�яI�����B�����āA��̎ő������Ԃ����Ɍ����A������킹�Ė����ɓy�Ɋ҂邱�Ƃ��ł���悤�ɂƋF���Ă�����B���肪�������K��������A����t���ςō�����䏬�����炢�͌g���ĒK�̉��Ԃ��i�H�j�ɂł�����Ă���̂����҂��邱�Ƃ��ł�����������Ȃ����A���V�����K������ł͂���������Ƃ������̂������B
�@ ���͈Â������̂ŋC�����Ȃ��������A���炭�����Ă��邤���ɁA���H�̂��������Ɂu�s�R�ȑD��l�������������炷���ɒʕ���v�ƋL���ꂽ�Ŕ������Ă���̂��ڂɂƂ܂����B�����āA�E��O���ɖV�ÏH�ډY�̈�p���`�����鉫�H�ړ��i���P���j�̓��e���傫�������Ă��鍠�ɂȂ��āA���������A��K�͂Ȗ��A�g�D�̗��ޑ�ʂ̊o������̌���Ƃ��ă}�X���f�B�A�Ȃǂő傫���ꂽ�̂́A���������̂�����̉������C��̂��Ƃ������Ȃ��ƂȂɂ��Ȃ��l�����B�ߑa�n�悾����i�D�̃^�[�Q�b�g�|�C���g�ɂ���Ă����������Ȃ��B�����Ⓦ��A�W�A�A���N�������ʂ���̖������҂Ȃǂ͂Ȃ��Ȃ��Ղ�₽�Ȃ��悤�ł��邪�A�n�`��C���̊W���炵�Ă��A�ނ���悹���D�����̈�тɋ߂Â��ڊ݂����݂��肷�邾�낤���Ƃ͏\���ɗ\�z�����B
�@ �����܂ōl�����Ƃ��A�҂Ă�Ƌ}�ɂ��邱�ƂɎv�����������B�������ڊo�߂��Ƃ��A���̎Ԃ�����W�]������l�A�\���[�g�����ꂽ�H���ɒ��N�̒j��������n���̎Ԃ炵����p�Ԃ���䒓�܂��Ă����B�悭�悭�v���Ԃ��Ă݂�ƁA�Ԓ��̒j�͂��肰�Ȃ����Ђ�̗l�q���M���Ă��銴���������B�x�e�ł����Ă���̂��ȂƎv�������x�ŁA������͉��̋C�ɂ������Ă��Ȃ������̂����A���̎Ԃ������o���̂ƑO�サ�Ă��̎Ԃ������͂��߁A���Ε����ւƑ��苎���Ă������B�������킩�肾�낤���A���̎��Ɏ����Ă悤�₭�A���́A������������A�����s�R�҂Ƃ��ĊĎ�����Ă����̂�������Ȃ��ƋC�Â����̂ł���B
�@ �l���Ă݂�A�����i���o�[���������S���Ԃ��G�߂͂���̐[��ɂ���ȕ�翂ȏꏊ�ɂ���Ă��Ė�𖾂����Ă���Ȃ�āA�n���̐l�X�̊��o���炷��Ȃ�Ƃ��s���R�Ȃ��ƂɈႢ�Ȃ��B���Ƃ��ό��̂��߂ɓ����������Ă��Ԃ��Ƃ��Ă��A���ʂ͂ǂ����ɏh���Ƃ��Ĕ��܂�̂����R�ł���B�������A��閰��ɂ��O�̎����̍s�����v���N�����Ă݂�ƁA�����d����U��Ď��ӂ��Ƃ炵�o������A�C�Ɍ������Č��𑗂��Ă݂�������Ă����B���܂茩�����Ȃ��i���o�[�̎Ԃɏ�������̂̒m��Ȃ��l���������������ȍs�������Ă���A�ƌ������Ă��d���̂Ȃ��������̂��B�����������Ƃ���A�Ԃ̃i���o�[���`�F�b�N���������A���ƂŐg���̊m�F�����邭�炢�̂��Ƃ͂Ȃ��ꂽ�����m��Ȃ��B
�@ �X�����ƒn�����킸�A�ςȎ��ԂɕςȂƂ���Ɍ���ĎԒ�����������ӂ��U���肷�鈫���Ȃ����ƂŁA�x�@���ɖƋ��̒����߂�ꂽ��E����������肵���͈̂�x���x�̂��Ƃł͂Ȃ��B����ȂƂ��A�u�Ȃ�����Ȏ��Ԃɂ���ȂƂ���ɂ���̂ł����H�v�ȂǂƐu�₳���ƁA�����ɍ����Ă��܂����Ƃ����Ȃ��Ȃ��B���m�̏ꏊ��K�˂Ă݂����Ƃ����Փ��ɋ���A�K�R�I�ȗ��R�Ȃǂ܂�łȂ��܂܂ɗ����邱�Ƃ���������A�����[�������邱�Ƃ�����̂��B�l�ԂƂ������̂͂ǂ����Ă������̓��I�K�͂ɂ����Ďv�l���s��������̂�����A�x�@���̂���ȑΉ����̂��̂�ӂ߂�킯�ɂ͂����Ȃ��B�ʓ|�����炽���Ă��́u���̎�ނł��v�Ɠ����邱�Ƃɂ��Ă��邪�A���Əꍇ�ɂ���ẮA�u��ɂ���Ă����x���Ǝ��̊ԂőT�ⓚ�畉���̒��ⓚ���J��L�����邱�Ƃɂ��Ȃ�B
�@ �������A����Ȏ��ł��ɗ͓A�d�ɉ����邱�Ƃɂ͂��Ă���B�����A��҂Ȃ�Ƃ������A����Ȃ�̍̐l�Ԃ��I�[�g�L�����v��ł��Ȃ��Ƃ���ŎԒ����Ȃǂ����Ă���ƁA�ǂ����Ă��C�ɂȂ���̂炵���B���̂悤�ȏꍇ�A�Ƌ��̒����߂���Β`�������邩�瓖�R����ɉ����邪�A���܂ɂ́A������̗������Ȃ��x�@�p�g�і����ŖƋ��ؔԍ�����|����ɂ��Ă�����̐g���̏ڍׂ��m�F���ꂻ���ɂȂ邱�Ƃ�����B��������ȏ���V�X�e��������̂��낤�B
�@ ������ɂ͕ʒi��܂������ƂȂǂȂ��̂����A�s�@�s�ׂ����Ă���킯�ł��Ȃ��̂ɂ����܂Œ��ׂ���͕̂s���������A�z���s�ׂł�����ƍl�����邩��A����ȂƂ��͋B�R�Ƃ��čR�c���A�����ɖƋ���Ԃ��Ă��炤���Ƃɂ��Ă���B�܂��A����̂��߂ɑ���̖��O�Ə������A����������t�Ɏ��₷�邱�Ƃ����Ă���B���̋t�̖₢�����ɉ����������A�r���Őu�����߂Ă��������Ɨ��������čs�����x�@���Ȃǂ����Ȃ��͂Ȃ��B�Ȃ��ɂ́A����ȕK�v�͂Ȃ��ƊJ���������x�@�����������B
�@ �������A����ȏꍇ�ł��A���̎Ԃ̃i���o�[���炢�̓`�F�b�N����Ă���ɈႢ�Ȃ��B�ǂ������ƂɂȂ��ď��L�҂̊m�F�Ȃǂ��Ȃ���Ă���̂��낤����A�s�R�Ԃ̃i���o�[�Ɖ���J�E���g�����V�X�e���ɂȂ��Ă���悤��������A�ԈႢ�Ȃ����Ȃǂ͏Ɖ�ߑ��l���i�H�j�̃��X�g�Ɋ܂܂�Ă��邱�Ƃ��낤�B�����Ƃ��A�Ȃ��ɂ͂�����̏��ɗ������A���ɕt�߂̗��̏��Ȃǂ������Ă����l��L���Ȍx�@�����������肷�邩��A��T�ɉ]�X����킯�ɂ͂����Ȃ����Ƃ����͊m���ł���B
�@ �s�R�D�ɒ��ӂ𑣂����Ŕ����������ŁA����Ȃ��Ƃ����ꂱ��ƍl���Ȃ��瑖�邤���ɎԂ͂₪�ĖV�Ò��H�ڂ̏W���ɍ������������B�V���N�Ԃ̓~�̂�����A�z����₷����̖��ɓ��̍��m�Ӑ^���h�B�����Y���瓌�V�i�C���z���Ă͂�闈�M�A���̑��������n�_�ł���B�H�ڂ̏W�����������߂����Ƃ���ɂ���Ӑ^�L�O�ق̏��L�����ԏ�ŎԂ���~�肽���́A���X�ƒX���ċP���Â܂�ቺ�̓��]�ɂ����߂��ꂽ�悤�Ɍ������Ă����B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N2��16��
�V ��
�@ ���܂͉����̔ɉh�ȂǐM�����Ȃ����炢�ɐÂ��Ȓn�����`�ɕς���Ă��邪�A���ĎF���̖V�ẤA�}�O�����ÁA�ɐ����Z�ÂƂƂ��ɓ��{�O�Âƕ��я̂����قǂɉh�����`�ł������B���ォ��ޗǎ���ɂ����āA�����嗤�𐼕��͂邩���ɂޖV�ẤA���V�i�C����Ă̒����e�n�◮�������Ƃ̌��Ղ̕\���ւɂȂ��Ă�������ł���B���オ�ڂ��Ĉꎞ���̗������I��������Ƃ��A�V�È�т͘`���̊�n�ƂȂ�A�܂������Ƃ̂��̍]�ˎ���ɂ����ẮA�F���˂̖��f�Ղ̒��p�n����ѕ⋋��n�ɂ��Ȃ��Ă����B�V�Â��Ǎ`�Ƃ��ꂽ�̂́A�����嗤�ɒ��ږʂ���n���I�ʒu�◮���������ō����{�����番�Ėk�シ��Δn�C�������̉������𗬂�Ă������ƂȂǂ̂ق��ɁA�V�Â̂��Ȃ�������Ȓn�`�I�\��������������ł���B
�@ ����ɖV�ÂƂ������A�k�����珇�ɁA�H�ډY�A�v�u�Y�A���Y�A�V�Y�ƁA���ꂼ�ꕡ�G�Ȍ`�������l�̓��]���قڐ��Ɍ������ĕ���ł���A�����S�̂��܂߂����̂�������V�ÂȂ̂ł���B�ɒ[�Ȕ�g��p����ƁA�ܖ{�̎w���L�����悤�Ȓn�`�̎l�̎w�Ԃɑ������镔�������ꂼ����]�ɂȂ��Ă���悤�Ȃ��̂Ȃ̂��B�������e�X�̓��]�̉��ɂ͑D�̒┑�ɓK������d�A�O�d�̏����ȓ��]���`������Ă��āA�O�C�̕��Q����┑�D����������Ǝ����n�`�ɂȂ��Ă���B�����ȊC�}�◅�j�ՂȂǂȂ�����́A����������̑D�Ɋr�ׂċɒ[�ɍq�s�\�̗͂�镗�܂����Q�܂����̖ؑ����^�D�ɂƂ��āA�l�̉Y�̂ǂꂩ�ɒH�蒅����������Έ��S���ۏ����V�Â͊���Ă��Ȃ��Ǎ`�ł������B�Ȃ��ł����������Q�ɖ|�M�����j���O�ɂȂ��Ă���D�Ȃǂ̕Y���n�Ƃ��ẮA����قǂɏ����̂悢�ꏊ�͂Ȃ��������Ƃł��낤�B
�@ �V�Â̒��S�n�͎l�̉Y�̂Ȃ��ł͏����߂̔��Y��V�Y���ӂɂ��邪�A�`��I�ɂ͈�Ԗk���ɂ���H�ډY�������Ƃ��傫���B���̏H�ډY���`�Â���傫�ȓ��]�̉��܂����Ƃ���@�ɂ���ɏ����ȓ��]�������āA���܂ł͂�����Ƃ����D���܂�ɂȂ��Ă���B�V������ܔN�i�V�T�R�N�j�P�Q���Q�O���A���݂̗�ł����P���̒��{���I���̍��A���̍��m�Ӑ^���悹����ǂ̌����g�D�����ΕY������悤�ɂ��ē��`�����̂́A�����A�F���������S�H�ȉ��Y�ƌĂꂽ�A���݂̖V�Ò��H�ڂ̂��̏����ȑD���܂�ł������B�����āA�������H�ډY��т߂��낵�Ă���Ӑ^�L�O�ّO�̒��ԏ�́A�Ӑ^��s�����݂����n�_�̂�����Ɉʒu���Ă����B
�@ �L�O�ق̉E�e�ɂ́u�g�^��a�せ��C�y���V�n�v�i�����́u�T���Y�C�v�̉E�Ɂu���v����������Ȏ��ŁA�����Œ��ׂĂ��݂���Ȃ����A�u���v�Ƃ������Ǝ����悤�ȈӖ������Ɛ��������j�Ƃ����\���̒��荏�܂ꂽ�傫�ȉԛ���̋L�O�肪�����Ă����B���̕��ӂ́A���Ԃ�A�u�Ӑ^��a�オ��C��h�����ď���A�͂�铞�������n�_�v�Ƃ����悤�Ȃ��ƂȂ̂��낤�B�@�@�@
�@ ���炭���̋L�O��߂����ƂŁA�������C���[�W�������̂炵���ߑ�I�ȃR���N���[�g����̋L�O�قɂ͂����Ă݂��B��������Ă܂��Ԃ��Ȃ��Ǝv����ٓ��ɂ́A�Ӑ^�̐��U�̑��Ղ�`�������������N�㏇�ɓW������Ă���ق��A�Ӑ^����������܂ł̌o�܂��r�W���A���ɓ`����W�I���}�ⓖ���̌����g�D�̕����͌^�A�t�߂̊C����������グ��ꂽ�Ƃ����d�Ȃǂ����ׂ��Ă����B
�@ ���Ȃ݂ɏq�ׂĂ����ƁA�d�Ƃ́A����̕d�̐�Ɏ����ؐ��̊|����Ƒg�ݍ��킹�A�d��Ƃ��ėp������̂��Ƃł���B�S�z�����ʂɓS�Y����Z�p�̂Ȃ����������́A���S�������ɂ����S�͓��荢��ȋM�d�i�ŁA�D���p�ɓS�̕d������ȂǍl�����Ȃ����Ƃ������B���܂��܊ٓ��ɂ͗��q���Ȃ��������Ƃ������āA�Z�����Ԃł͂��������A�L�O�ق��Ǘ����Ă����������q����W�������ɂ��Ă��낢��ƕ⑫������q�����邱�Ƃ��ł����B
�@ �U�S�T�N�ɑ剻�̉��V���s���A�V�O�P�N�ɓ��̗��ߐ��x����{�Ƃ����߂����z�����Ɏ���ƁA�}���ɉ䂪���̍��Ƒ̐��͐����A���̓s������͔͂ɂ����V�s���鋞�̑��c�Ɉ�i�Ƃ����Ԃ������邱�ƂɂȂ����B���̈א��҂����������Ɋ�Â������𗝑z�Ƃ������Ƃ������āA�قǂȂ������͗��ߍ��Ƒ̐��̈ێ��ɕs���̂��̂ƂȂ�A����̗���ɏ���ċ�O���̔��W�𐋂��Ă������ƂɂȂ�B
�@ ���鋞�̂��������ɑ召�̉�������������A���厛�啧�̑������i��ŁA�\�ʓI�ɂ͕����̋�������邬�Ȃ����̂ɂȂ����悤�Ɍ����͂��߂����̂́A�����̉䂪���̕����̌n�ɂ͈�����傫�ȓ�_���������B���K�̕����̌��i�ȉ����ɂ̂��Ƃ�������s�����Ƃ��ł��鍂�m����l�����݂��Ă��Ȃ������̂ł���B�킩��₷�������A�V���ɕ��m�ɂȂ낤�Ǝu���C�s��ςގ҂ɁA���m�Ƃ��Č������Ȃ��w������ׂ��K����@�𐳂����`�����A�ŏI�I�ɂ��̎҂�m���Ƃ��ĔF�ߔC���邱�Ƃ��ł��邾���̎��i�������m�����Ȃ������̂ł���B
�@ ���̂��߁A�䂪���ł͎�������ɂ��o�ƁA���Ȃ킿�A�����Ő��肵�ĕ��m�ɂȂ���@���Ƃ��Ă������A���R�̌��ʂƂ��āA�{���Ȃ�m���ɂȂ邾���̊w�����l�������i���Ȃ����̂�����ɑm���ƂȂ�A�J�ɉ��s����Ƃ����L�l�ł������B�m���Ƃ����g�����l�X�ȉۖ�ɗ��p�����悤�ɂȂ������Ƃ������āA����͍ĎO�Ďl�������������悤�Ƃ����悤�ł���B�������A�����ɓn�萳�K�̎������ċA���A�m���ɂȂ����҂͂���߂ď��Ȃ��A���ʂ̑m���܂ߎ�������ɂ��o�Ƃ������҂��قƂ�ǂ̏ł́A�����Ɏ����������߂�͖̂����ł������B
�@�u�������č����ꂸ�v�̌������ƃ��x���Ŏ��H���Ă���悤�Ȉُ펖�Ԃ����E���邽�߂ɂ́A����������̎t�Ƃ��Ăӂ��킵�����m���}���A�����ɂ����鐳���������̗�s�Ɖ����m���̕��y�𑁋}�ɍs�����Ƃ��K�v�ł������B���̂悤�Ȃ킯�ŁA�V���ܔN�i���O�O�N�j�̌����g�D�ɂ́A�h�b�i�悤�����j�ƕ��Ɓi�ӂ��傤�j�Ƃ�����\��͂��߂̓�l�̐N�m�����ʂɏ�荞�ނ��ƂɂȂ����B�������A������̔ނ�̔C���́A�`���̎t�Ƃ��ċ��鍂���̑m��T���o���A����ɂ�����ē��{�ւ̓n�q�����肷�邱�Ƃł������B
�@ �L�^�ɂ��ƁA���ɓ������h�b�ƕ��Ƃ͋�N���̍Ό��������Ďt�ƂȂ�ׂ��l�������ߓ��z���������炵���B�o��ƂĂ��ɂȂ�Ȃ����Ƃ��낤�ɁA���̂��߂ɋ�N���̔N���������邱�Ƃ������ꂽ�Ƃ������Ǝ��́A�B�����������ƌ����ق��Ȃ��B����̎ړx�ł͌v��m��Ȃ����Ԋ��o�≿�l�ς̑��݂��Â�ĂȂ�Ƃ������[���B�h�����ꂽ�̂���\���������̐N�m�ł������Ƃ����̂��A䅓�ɑς������b�̗͂�ٍ��̊��ɑ���K���\�͂��l�����������ł̂��Ƃ������̂��낤�B���S�}�[�N�Ŗ��ߐs�����ꂽ�o�H��`���Đ��E�𗷂��鍡���̉�X�Ƃ͑�Ⴂ�Ȃ̂��B����ɂ����ẮA���Ƃ��ǂ�Ȃɒm���ɒ����Ă����Ƃ��Ă��A��\���������̐N�����Ƃ̍ō��@�ւ̓�����тсA�����A��̊w���҂�T���ɑ����ɏo�����ȂǂƂ������Ƃ͂ƂĂ��l�����Ȃ����Ƃł���B
�@ �������N���߂����V���\�l�N�i���l��N�j�̏\���A�g�q�]�̉�����Ɉʒu���铂�̑�s�s�̈�g�B�ɂ����āA�ނ�͂��ɗ��z�̎t�ƂȂ�ׂ��l����T�����Ă��B���ꂱ�������̑哿�Ƃ��Đ��ɖ��������m�̊Ӑ^�ł������B������Ȃ�ł��A������ˑR�ɊӐ^�̑O�Ɍ���A�����Ȃ���{�ɓn�����Ăق����Ɗ肢�o���Ƃ͎v���Ȃ�����A�Ӑ^�̖剺�ɓ����ďC�s��ςނ�����炠�ꂱ��ƍ����s���A�n�q�̈˗������������@����M���Ă����̂ł��낤�B���㕗�Ɍ����A����͍��ƃ��x���̋ɔ�w�b�h�n���e�B���O������A���{����̌����g�������������������Ɏ����ȃn���e�B���O��킪�����Ă����ɑ���Ȃ��B
�@�u���Ӑ^�ߊC��t�����`�v�ȂǂɎc���ꂳ��Ă���ނ�̒Q��̌��������b�̂ɂȂ����ƁA�h�b��͂ǂ���玟���̂悤�ȕِ�������ĊӐ^�����������炵���B
�@�u�����̋����͉��̐̂ɓ��{�ɓ`����Ă܂���܂������A���̋������D������ɉ��߂���č����ɍL�܂邾���ŁA�����{���̋����𐳂����`���邱�Ƃ̂ł���l�����䂪���ɂ͈�l�����Ȃ��L�l�ł��B�́A�������q�́A���܂����S�N��ɕ����͉䂪���ŋ������݂�ł��낤�Ɨ\���Ȃ������̂ł���܂����A���悢�悻�̎������������悤�ł������܂��B�ǂ������肢�ł������܂�����A���̍ۂ��ЂƂ��䂪���ɂ��n�肭������A�^�̕���������Ă��̈�勻�����͂���ƂƂ��ɁA�Ղ��p���ׂ������ꂽ���m�̈琬�Ǝw���ɂ��͂����݂����������܂���ł��傤���B���ЂƂ����ǂ��̐S�̎t�ƂȂ��Ă��������܂��I�v
�@ �I�ɂ݂āA�ǂ��ɂ��ł��������b������A�ƂĂ����̂܂ܐM����킯�ɂ͂����Ȃ����A�n���̐^�ӂ������ɑi��������ނ�̌��t���Ă����Ӑ^�́A
�@�u�`�������Ă���Ƃ���ɂ��܂��ƁA�������̏@�h�V��@�̑c�t�ł������x�b�v�T�t�́A���S���Ȃ�ɂȂ�ꂽ���ƁA���{�̉��q�ɐ��܂�ς���ĕ��@���������A�O�����~��ꂽ�Ƃ̂��Ƃł��B�܂��A���{�̒������́A�璅���̌U���������Ď������ɑ����Ă����������̂ł����A�����̌U���̈�[�ɂ́A�R��و�A�������V�A���q�A���������A�Ƃ����l�傪�h�J����Ă�����܂����B���́A���{�����͐^�ɕ����̋���������Ă��鍑���Ǝv���܂��B�����̘b���Ă��Ă���邠�Ȃ������̂Ȃ��ŁA�N�����{�ɓn���Đ^�̕��@��`���Ă����悤�Ȑl�͂���܂��v�ƕ��݂����q�����ɖ₢�������̂��Ƃ����B
�@ �����̐搶�Ȃǂɂ͂��������Ȃ��Ƃ������ȂƎ���ꂻ�������A�R��و�A�������V�A���q�A���������A�̎l������Ȃ�ɑn�ӖĂ݂�ƁA���悻�����̂悤�Ȃ��ƂɂȂ�Ǝv����B
�@ ���Ƃ��R��̌i�ς̈قȂ�ʁX�̐��E�ł��낤�Ƃ��A���ꂼ��̒n�𐁂��n�镗��A���ꂼ��̐��E���Ƃ炷���e�́A�����V���߂��鋤�ʂ̑��݂ł͂Ȃ����B���̓���M����҂́A���₻�̗�����Ĉꓰ�ɉ�A�S����ɂ��ċ��͂������A���݂��������̐��ɐ��܂ꂽ�����ɂ��Ȃ���A���Ɏ������Ŗ����Ɍ������ĕ������ł͂Ȃ����B
�@�������Ӑ^��������Ƃ������̘b�������������Ƃ���A�����̓��{�l�̍��ۊ��o�͂ǂ����ĂȂ��Ȃ��̂��̂ł���B�������A���̍��̓��{�͌�i������������A�嗤�����ɑ��鋭�����ꂪ�`��ς��Ă����ꂽ�����̂��Ƃ�������Ȃ����A�ԍ���g��ŊO�ɐK�������č���A���݂��̊�̌�����ւ̓��������Řb��i�߂�̂����ӂȌ���̉�X�ɂ́A���������w�Ԃׂ��Ƃ��낪�Ȃ����Ȃ��悤���B
�@ �Ӑ^�̖₢�����ɕ��݂���m�͊F�ق荞�܂܂������Ƃ������A���ɁA�˕F�Ƃ�����l�̏C�s�m���i�ݏo�Č������B
�@�u���{�͑�ςɉ������߁A�����Ă��̒n�ɍs�������͎̂���̋Ƃ��ƕ����Ă���܂��B�ʂĂ��Ȃ���C����n��Ȃ���Ȃ�Ȃ����߁A�S�l�Ɉ�l�����������ɂ��̒n�ɓ�������̂�����Ɛ\���ł͂���܂��B�ЂƂ��ї�������A�l�Ƃ��čĂт��̐��ɐ��邱�Ƃ͓���A�܂��Ă�A���̒����ɐ��܂�邱�ƂȂǂ��͂�]�ނׂ����Ȃ����Ƃł��傤�B�������A���ǂ��͂܂��C�s���̐g�Ȃ̂ł�����A�����ɂ���N�������܂̎t�̂����t�ɑ������邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ł������܂��v
�@ ����ƁA�Ӑ^�͂��̌��t��҂��Ă������̂悤�ɁA��q�̈ꓯ�Ɍ������ċB�R�Ƃ��Ă��������������炵���B
�@�u����͂ЂƂ��ɕ��@��`���邽�߂Ȃ̂ł��B���o�̂Ȃ��̋����ɂ����邱�Ƃł����A���@���L�߂�ɂ́A����̐g����ɂ���ł͂Ȃ�܂���B�N�����̂����ɍs���Ȃ��Ƃ����̂Ȃ�A�����g���s�����Ƃɂ��܂��傤�v
�@ �������āA���ɂ����Ă����Ԏ҂��Ȃ��Ƃ���ꂽ�����̑哿�A�Ӑ^�̓��{�n�q�������Ɍ������ē����o�����̂������B
�@ ���ۂ̏��قɂ������ẮA����ȕ\�����̔��k�Ƃ͈���āA���̊Ӑ^���܂߂������ȗ��H���閧�̓n�q�������Ȃ��ꂽ�ɈႢ�Ȃ��B���̎���A���̌��@�c��͍��m�̍��O���o���ɗ͗}���悤�Ƃ��āA�������K����~���Ă����B�����̍��m�Ƃ����Ίw�|�S�ʂɒʂ����w�ҁA���Ƃ��Č����Ίw�ی����������Ȃ�����̃m�[�x���܃N���X�̍Ő�[�����҂ɂ��������Ă���B���������m�͍s����̃o�b�N�{�[���Ƃ��Ă��s���̑��݂ł���������A���R�A�o���͗e�ՂłȂ������B�Ӑ^�N���X�̓��]���o�́A�ɉh�̐Ⓒ�ɂ������卑�̓��ɂƂ��Ă����ƓI�����������Ƃ̂ł���B
�@ ���{�ւ̓n�q�𖧂��Ɍ��ӂ������̂́A����ȊӐ^��҂������Ă������̐��X�͑z����₷����̂ł������悤���B�������A�Ӑ^�́A�������Ȃ����������䅓���������A���ɑ�a���������������B���̋����ׂ��ӎu�͂ƕs���̎��O�́A��͂蒴�l�I�Ȃ��̂��Ǝv�킴������Ȃ��B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N2��23��
�� �^
�@ �Z�����N�i������N�j���̗g�B�]�z���ɂ܂ꂽ�Ӑ^�͏\�l�ŏo�Ƃ��A�g�B��_���̒q���T�t�̂��ƂŏC�s�ɗ�ނ悤�ɂȂ����B�����ł̌��r�͓��X�ɖڊo�����A�\���̂Ƃ��ɂ͓��ݑT�t��葁������F�����������B��F���͑����Ƃ��Ă�A�����ɂ����鋆�ɂ̌��𗝑z�ɏC�s�ɋ��ގ҂����炷�ׂ������̂��Ƃł���B��̓I�ɂ́A�s�E�A�s���A�s���A�s�ό�A�s?���i�������Ă͂Ȃ�Ȃ��j�A�s���ߍ߁i������v�z��ߎ�������Ă͂Ȃ�Ȃ��j�A�s���]�ʑ��i������]�������葼�l���������肵�Ă͂Ȃ�Ȃ��j�A�s�ʁi���ɂ��݂����Ă͂Ȃ�Ȃ��j�A�s�сi�{��������ɂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��j�A�s掁i�l���掂��Ă͂Ȃ�Ȃ��j�c�c�Ƃ������悤�ȉ�������Ȃ��Ă���B
�@ ��\�ɂȂ����Ӑ^�́A����Ȃ鋳���𐿂����߂ɁA���m�̏Z�ޗ��z�A�����̓s�ڎw���ė��������B�����āA��\��̎Ⴓ�Œ����̎��ێ��ɓo�d�A�O�i���t���䔯�̔�u�i�т��j�Ɍ������ʉ��߂��w�сA���̌���𐾂�����̋V���������B����Ƃ́A����h����𐧂��邽�߂ɔ�u���u�g�ɂ��Ȃ���ׂ������̂��ƂŁA��u�ɓ�S�\���A��u��ɂ͎O�S�l�\�����Ƃ��ܕS���Ƃ������K������߂��Ă����Ƃ������A��u��̎��ׂ������̐��̂ق��������Ƒ����̂ŁA����Ȃ�j�����ʂ��Ƃ����������ᔻ�̐����N�����Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��B
�@ �Ӑ^�͓�\�Z�ł͂₭���u���ɏ�藥�`�i�������̈Ӌ`�𒐎߉������u�`�j���u�����Ƃ�������A��͂�ދH�Ȃ�r�p�ł������̂��낤�B�l�\������ɂ��������鍠�ɂ́A�����̑�t�A���Ȃ킿�A�����̉���������`���邱�Ƃ��ł��鍂���̑m�Ƃ��Ă��̖��͓��̍����ɕ������A�u�y��]���ɏ����̎ҁA�Ӑ^�Ƃ�G�łėςȂ��v�Ɠ`������悤�ɁA�@�g�q�]���������g�q�]�ȓ�̒n�ɂ����ẮA���ɕ��Ԏ҂Ȃ����݂ɂȂ��Ă����B
�@ ���ɂƂ��Ă����������̂Ȃ�����قǂɌ��o�����l�����A���@�c��ɂ��n�q�֎~�̕z����Ƃ��Ă܂œ��{�ɏ��ق��悤�Ƃ����̂�����A�U���ق������̗U���ɏ��ق����q��̊o��ł��ނ͂����Ȃ��B��a���삩��h�����ꂽ�X�J�E�g�}���m�̉h�b�╁�Ƃ�̒Q������{�n�q�����ӂ����Ӑ^�����A�n�q�������Ɍ��s����ƂȂ�ƁA���R���o���̂��������Ƃ炴��Ȃ��Ȃ����B
�@ �h�b�╁�Ƃ炪�g�B�喾���ɂ����ē��{�n�q��v���������N�̎��l�O�N�A�\�Z�ɂȂ��Ă����Ӑ^�́A���悢�����ڂ̓��{�n�q�v�����肻������s�Ɉڂ����Ƃ����B�Ƃ��낪�A���̌v��͔@�C�Ƃ�����q�̖����ɂ���Ė�l�̒m��Ƃ���ƂȂ�A���s�ɏI����Ă��܂����B����ɂ��߂����A���N�̏\�A�^�~�̓��V�i�C�̍r�g�����đ���ڂ̓n�q�����s����邪�A�T�a�Y�Ƃ����Ƃ���ł����Ȃ�����A�n�q�͂܂����⎸�s�ɏI����Ă��܂��B
�@ ���̌���Ӑ^��͍ĎO�s�^�Ɍ�����ꂽ�B��N��̎��l�l�N�ɂ́A��O���̓��{�n�q�v�悪�T�d�ɗ�������A�Ăт��̖��c�����o�A�h�b���߂܂����Ă��܂��Čv��͓ڍ������B����ł�����Ȃ��Ӑ^�́A���N�̓~�ɂ͓V��R�����\�����ɗg�B����쉺�A���̂܂ܓ��V�i�C�����ɂ���n�q�D�̑ҋ@�n�ɉ���ďo����}�낤�Ƃ����B�Ƃ��낪�A���ތ��T�ю��ɓ������Ƃ���Ōx�����̓��̖�l�ɐg�����S������A���ǁA�Ӑ^�͗g�B�ւƌ��d�Ɍ쑗����鎖�ԂƂȂ��āA��l���̓n�q�v������s�ɏI������B
�@ ���ʂȂ�l�x���v�悪���܂���Ɠn�q�̋C�͂����ꂩ�炻����Ă��܂��A�Ȍコ��ɓ�x�̂��̏o������Ă�ȂǂƂĂ��l�����Ȃ��B�������A�����Ă��������Ă̂����Ӑ^�Ƃ����l���́A�����̍��{���O�̈�ł���u��E�ҐS�v�̉�̂悤�ȑ��݂ł������̂��낤�B�g����ɂ��܂��A�厜�߂̋����ɂ��������ďO���̂��߂ɐs�͂��A�����Ȃ�댯��`���Ă������̋��`�̕��y�ɓw�߂�Ƃ�����`���A�Ӑ^�̐S���m�łƂ��Ďx���Ă����ɈႢ�Ȃ��B
�@ �܂��A���̐l���̐[���Ɛ��_�̐������̂䂦�ɁA�����x�n���킸�Ӑ^�ɋA�˂���҂��Ղ�₽���A���Ƃ������ɔw�����Ƃ͂����Ă��A�ނ��Ƃ��Ƃ�f�߂��邱�Ƃ͕s�\�ł������̂�������Ȃ��B���ꂪ��`�ɔ�������̂ł���A�O���ɐ�Ď��ɂ��̖@�����������E�C�������Ƃ́A�^�̏@���҂̏d�v�Ȏ����ł���Ƃ��v����B�ނ��A���̑O��Ƃ��ėދH�Ȃ�l���Ɠ��@�͂Ƃ��K�v�Ȃ̂ł͂��邯��ǂ��c�c�B
�@ �@���҂Ƃ��Ă���łȂ��A������o�ϖʂɂ����Ă������ȗ͂����Ȃ������Ă����Ǝv����Ӑ^�́A����̓n�q����Ă�ɐ悾���āA���{�ւƎ������ނ��߂ɁA�M�d�Ȍo�T�⏑���ށA�@����͂��߂Ƃ����ʂ̕��������W�����B���q�v�悪���o������o�q��ɑ�����肷�邲�ƂɁA�����͎U�킠�邢�͗������Ă��܂������A����ł��ނ͍����Ȃ������B�������A����̎��ԂƔ�p��v���邻��當���̎��W�́A�����ʂ�̓Ɨ͂ł͕s�\�Ȃ��Ƃ�����A�����炭���̍����ɂ��Ӑ^�̓n�q�̌��ӂ𗝉�������𖧂��Ɏx�����銯���̕��l��o�ϐl���������������̂ł��낤�B
�@ ���ꂩ��l�N�A�\�����͐Â�����ۂ��Ă������̂́A����Ȃ����k�̖ʁX�͂Ȃ����閧���ɓ��{�n�q����Ă����B���l���N�̏t�A�h�b�ƕ��Ƃ͓����S���g�B�������ɂ����Ӑ^�̂��Ƃ�K�ˁA�ܓx�ڂ̓n�q���s��v������B���N�̘Z���ɗg�B�����Ӑ^��s�͐��H�`���ɘT�R�A�O���R���o�R���ċ㌎�ɏ����R�ɓ��������B�����āA�����œV��҂������Ȃ���Ō�̏����𐮂������ƁA�\���\�Z���ɉ����A�����ޔg�i����j���ʂɌ������ďo�q�����B
�@ ����ɂ��Ă��A�V�^�Ƃ������͎̂��ɂ͂Ȃ�Ƃ��ߍ��Ȃ��̂ł���B�Ӑ^�̏�����D�͓��V�i�C�Ō������G�ߕ��Ɍ������Ĕ���ǂ�j���A�q�s�\�͂������ē��L���߂�������ւƕY�����邱�ƂɂȂ����B�G�ߕ��������Ƃ���Ă͂��邪�A�����I�ɂ݂āA���܂ł����䕗�Ƒ��������̂�������Ȃ��B�q�s�s�\�Ɋׂ������̑D�́A�����A�u�ڋ��i��イ���イ�j�v�ƌĂ�Ă������݂̑�p��ʂ�߂��A鰎u�`�l�`�̒��ɂ��`���̕����Ɨގ�����Ƃ��Ă��̖����o�ꂷ��u?���i���j�v�A�u��R�i���オ���j�v�̒n�A���Ȃ킿�A���݂̊C�쓇�ւƗ��ꒅ�����B�C�쓇�̓x�g�i���̓����ɂ����ăg���L���p�̈�p���`�����铇������A���{�Ƃ͕S���\�x�������Ⴄ�Ƃ���ɓ��B�������ƂɂȂ�B�Y�������̂��\�ꌎ���Ƃ�������A�ꃖ���߂��C������܂�������ɁA��ՓI�ɏ��������̂ł��낤�B
�@ ��܉�ڂ̓��{�n�q�����s�ɏI���A�g�B������L���قǂ����ꂽ��̕ƒn�A�C�쓇�ɕY���������_�ŁA�ʏ�̐l�ԂȂ疽�^�s�����Ƃ��ׂĂ���߂Ă��܂����ɈႢ�Ȃ��B�������A��E�ҐS�̉��g�̂��Ƃ��Ӑ^�́A���̑D���̔�������ɂ������ɂ���ōĂї����オ��B�V���̎��R�̂Ƃł������̂ł��낤���A�ނ́A���X�ɍ~�肩���鍢��ȋ������t��ɂƂ�A���̂܂ɂ�������V���ȑn���̌���ւƕς��Ă��܂��̂������B���̒��l�I�Ȉӎu�͂ƒ��z�̖L�����A���K���͂̍����ɂ͗B�X�h������ق��Ȃ��B
�@ ���̍����͌����ɋy���A�ߗ����ɂ܂ō����̎t�Ƃ��Ă��̖���m��ꂽ�Ӑ^�ɂ́A�e�n�ɎU����������̒�q��A�ˎ҂���Ȃ鑾���傫�Ȑl�����������B���̐l���Ǝ���̒m���x�𗊂�ɁA���̋���������L�߂Ȃ��痤�H��`���̑哿�Ƃ��Ă̖�ڂ��ʂ����Ȃ��痤�H�����X�ɖk��A�g�B�ւƋA�҂��邱�Ƃ��l�����ނ́A�܂��C�쓇�̐U�B���g���ɉ�������ƁA���n�̑�_�����C�z����B�����Ė����B���g��F��K�ˁA���̂��ƊR�B�ɓ���ƁA���̒n�ɊR�B�J�����������B�R�B�ł̋s���ʂ����ƁA��s�͍L�B�ւƌ��������ƂɂȂ����̂����A���̓r���̒[�B�Ő��s�̉h�b�͍Ăѓ��{�̒n�ނ��ƂȂ����E�����B
�@ �h�b�̎����͂������̊Ӑ^�ɂƂ��Ă������ւ�ȏՌ��ł������悤�ł��邪�A�N�����������܁Z�N�A�Z�\�O�ɂȂ����ނ́A����q���������߂��݂����炦���A�c�������Ƃ�ɐ��s����čL�B������B�ւƌ��������B�����āA�r���Ől�X�ɖ@�b��������莛�@�̑����C���ɋ��͂����肵�Ȃ�����B�ɓ���A�������������x�g�B�ւƖ߂��čs�����B���Ƃ̂ق��͂���������B�ŊӐ^�ƕʂ�A���V�i�C�ɖʂ��閾�B�̈��牤���ւƌ��������B������ɊC�ݐ���쉺���Ė��B��K���\��ɂȂ��Ă��錭���g��s�Ƃ̐ڐG���͂��邽�߂ł��������̂��낤�B
�@ �ēx�̑���Ɩ������悤�ȕY���A����ɂ͓��L���ɂ��킽��`���̒����ƁA���X�Ɛg�ɍ~�肩����ߍ��Ȏ����ɑς��邤���A���x�łȂ邳�����̊Ӑ^�̐g�̂ɂ������������ٕς������Ă����B�����������Ƌ���ȑ��z�̂��Ƃł̉ߍ��ȕY�����������Ƃ��A�����Ⴊ�}���ɐi�s�������ʂ��Ƃ������Ă��āA�ق�Ƃ��̂Ƃ���͂悭�킩��Ȃ����A�}���Ɏ��͂��������ނ́A���̔N���Ɏ������Ă��܂��B���Ƃ����{�ւ̓n�q�ɐ������A���ɂ͓ޗǂ̓s�Ɏ��肦���Ƃ��Ă��A���̈�ࣂ̋ɂ݂�ڂɂ��邱�ƂȂǂ͖]�ނׂ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂������B�Ӗڂ̐g�ő�C��n��A�������炳��ɉ������H���o�đ�a���肷��Ȃǂ��͂�s�\�ƍl����҂�����������������Ȃ��B�������A�Ӑ^���A�����Ďc���ꂽ���Ƃ��܂����{�n�q����߂Ă͂��Ȃ������̂��B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N3��1��
�����g�D�Ƃ��̍q�H
�@ �Ӑ^��ɂ���Z�����{�n�q�v�挈�s�̘b�Ɉڂ�܂��ɁA�����̌����g�D�̏��ɂ��ď�������G��Ă������B
�@ �Z�O�Z�N�Ɍ����c�L�i���ʂ��݂݂̂������j�𐳎g�Ƃ������̌����g�c���������Ĉȗ��A�L�^�Ɏc���Ă��邾���ł��A���~�ɂȂ������̎O����܂߂č��v�\����̌����g�c�h�����v�悳�ꂽ���Ƃ��킩���Ă���B���̊ԁA��������e�퐧�x�ɂ�����܂ŗl�X�ȑ嗤���������{�ւƓ������ꂽ���A���������𐳎g�Ƃ��锪��l�N�̔h���v�悪���~�ɂȂ����̂��Ō�ɁA��S�Z�\�N�]�ɂ��y�Ԍ����g�D�n�q�̗��j�͏I�����������B
�@ �Ő����ɂ͌ܕS�l����Z�S�l���̔h���g�ߒc�����l�ǂ̑D�ɕ��悵�ē��ɓn���Ă����Ƃ����邪�A���C�▂�̓��V�i�C�͗e�͂Ȃ������̐l����ۂݍ��B�V���Ƃ̊W���悩���������̍��ɂ́A��g���o���l�ǕҐ��̌����g�D�c�͐��˓��C��ʂ��Ĕ����ÂɎ���A���̂��ƈ��Δn�t�߂��Ē��N������݂̉������ւƐi�݁A�������̐���[������Đ��݂ɏo���B�����āA�������璩�N�������C�݉����ɖk��A�r���ŐV���̓����ÂɊ�`�����肵�Ȃ���ɓ�������݂Ɏ���A���������݂𐼐i���ĎR�������k�݂̓o�B�ɒB����Ƃ����q�H���Ƃ�ꂽ�B�܂��A�A�H�̂ق��́A�R��������݉����ɓ��i���A���C�k���ɏo�����Ɩk���̋G�ߕ��ɏ���Ē��N�������݂ɋ߂Â�����[�܂œ쉺�A���ɍq�H��ς��ē�������݉����ɐi�݁A���Δn�t�߂��o�Ĕ����Âɓ���Ƃ������[�g�����S�ł������B
�@ �k�H�ƌĂ�邱�̃��[�g�͗��n�����̂��ߔ�r�I���S�ŁA�����Ƃ����Ƃ��ɂ͍Ŋ�̍`�ɋً}���邱�Ƃ��ł�������A����͂����̂������ɂ��Ă��A�����g��s�̂����̂��Ȃ�̐��̎҂͂Ȃ�Ƃ����Ƃ̉����𐬂������A�����̊|�����Ƃ��Ă̖������ʂ������Ƃ��ł����B�Ƃ��낪�A�V���Ƃ̑Η��������A�����̊W�����������̂ɂƂ��Ȃ��A���S���̍����k�H���Ƃ邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ������߂ɁA�Ȍ�A�����g�D�͓��V�i�C�ډ��f�����H���邢�͓쓇�H��I��������Ȃ��Ȃ����B�������A�q�s�\�͂̏\���łȂ������̏��^�ؑ����D�ł��̓��V�i�C���[�g���ɍq�s����͎̂���̋ƂŁA�K�R�I�ɑ���������A�����̐l����������悤�ɂȂ����B
�@ �����Â��o�����ƌܓ����݉������Ɍ������A�������炢�����ɐ��i���ē��V�i�C�����f�A�g�q�]�������ڎw�����A���̋t�R�[�X���Ƃ邩�����̂���H�ƌĂ��q�H�ł���B�n�}������킩��悤�ɁA���̍q�H���Ƃ����ꍇ�ɂ́A�ܓ����𗣂��ƁA�g�q�]������ɒ����܂Œ��p�n����ƂȂ�悤�ȓ����܂��������݂��Ȃ��B�����̑D�̔\�͂ł́A�ǂ�ȂɓV��Ɍb�܂ꏇ���ɏ�����Ƃ��Ă������ɒ����܂łɐ����͗v�����͂��ł���B���ۂɂ́A���V�i�C�̒n���I�����Ɉ�����C�ۏ��炵�āA�����Ԃ��D�V�������Ƃ������Ƃ͋H�������낤����A�q�C�̓r���ǂ����ōr�V�ɑ�������͔̂������Ȃ��������Ƃ��낤�B�������ɑ����ƁA�\���̐Ƃ��ؑ��a�D�͂����܂��j�����Ă��܂��A�Z���]�������肵�A�����łȂ��Ă��q�s�s�\�̏�ԂɊׂ邱�Ƃ����������B
�@ �܂��A����ɍD�V���������ɂ��Ă��A�����̘a�D�̌��n�I�Ȕ��̍\���⑀���Z�p���炷��ƁA�����ɋ߂��ꍇ��t���̏ꍇ�Ȃǂɂ͂܂�Ŕ������ɗ����Ȃ������ɈႢ�Ȃ��B����ȏꍇ�A�ꎞ�I�ɂ͔����t����䂁i��j��p���Đi�ނ��Ƃ��ł����낤���A������Ƃ�����䂂����𗊂�ɑ�C�����f���邱�ƂȂǂ͓y�䖳���Șb�ł������B�����������Ă����邵�����シ���Ă�����Ƃ������̖��ȃW�����}������Ȃ��瓌�V�i�C�̉��f����Ă邱�Ƃ́A�����ʂ�g����q�����ꐶ���̔��łł������ƌ����邾�낤�B
�@ �G�ߕ��ƊC���̊W�������āA��������{�ւ̋A�ҍq�H�ɂȂ邱�Ƃ̑��������쓇�H���Ƃ����ꍇ�A�����g�D�͗g�q�]�͌��ɋ߂��h�B�A���邢�͂��̂���������Ɉʒu����Y�B����o�q���A�ŒZ�ł����������鉂�������t�߂�ڎw���čq�s�����B�����A�����ɂ͕��܂����̍q�s�ɗ��点��������Ȃ���������A�k���̋G�ߕ��������Ƃ��Ȃǂɂ͓�ɗ�����A��j���O�̏�ԂŁA�����ޔg�A���Ȃ킿�A���݂̉��ꏔ���ւƕY�����邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ������B�����≫�ꏔ���̂ǂ����֕Y�������D�͂܂��悢�ق��ŁA�����m�ւƗ����ꂽ�D�͍����ɏ���ėm���k�������ւƉ^��A���̂܂܍s���s���ɂȂ��Ă��܂����Ƃ����������B�V�^�Ɍb�܂ꂽ�ꍇ�ɂ́A�����m�𐔕S�L����������I�ɔ����̓암������ɒH�蒅�����Ƃ��������悤�����A������ɂ��떽�����̍q�C�ɂ͕ς��Ȃ������B
�@ ���������∢���ޔg�ɒ����������g�D�͂����ŏC����⋋��Ƃ��s���A���̂��ƕ��҂������Ȃ���A�Δn�C���ɏ���ĉ��ꏔ���A���������A�F�쏔���Ɣ�ѐΏ�ɑ������`���ɖk��A�F����������[�ɋ߂��V�ÂւƓ��`�����B���������āA�V�Â͓��◮���������ʂ��瓞���Ȃ����͋A�҂�����O�̑D�̌����ɂȂ��Ă����B�V�Â���͋�B���݉����Ɍ��݂̒��茧���C�n���Ɍ������Đi�݁A�������猺�C���ʂ��Ĕ����ÂւƎ����Ă����̂ł���B
�@ �L�^�ɂ��ƁA��A�l�A��A�\�A�\�l�A�\�Z���̌����g�D���员��̂ɑ������A����ȊO�̏ꍇ�ɂ����Ă��A�ꕔ�̑D������������������u�a�œ|�ꂽ�肵�āA�l�D�Ґ��̌����g�D�c�ƒc���̂��ׂĂ������ɔC�����܂��Ƃ����邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ������悤�ł���B�����g�ɑI���Ƃ������Ƃ́A�͂��߂��玀�����o�債�Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃł������킯�����A����ł��I�ꂽ�҂����́A����ɂ��ނ��ƂȂ��V�����m�������߂ē��V�i�C�������n��A�����嗤�ւƕ������B
�@ �����̎ړx�ōl����Ɨ����ɋꂵ�ނƂ�������邪�A���Ԃ�A�����̐l�X�̈��S�ɑ���l������A�l���ɂ����鉿�l�ς͌���̉�X�̂���Ƃ͂����Ԃ�ƈقȂ��Ă����̂��낤�B���ώ���������l�̔����قǂŁA����������ꂽ�n��ʼnߍ��ȘJ���ɑς��ԕn�ɚb���Ȃ����炷���Ƃ�]�V�Ȃ�����Ă��������̐l�X�ɂƂ��āA���Ƃ����������m�̐��E�ւƗ������Ƃ́A����q����ɒl����قǖ��͓I�Ȃ��Ƃł���A�h�_�ɖ��������Ƃł��������̂��낤�B��a�̐s���Ȃ��Z���l���ɂƂ��āA���ꂪ��u�̂͂��Ȃ����ł������Ƃ��Ă��A���������_�̍��g���Ƃ��Ȃ�������̌��I�ȑ̌��́A�����̐l�X�ɂ���Ί���Ă��Ȃ����̂Ɏv��ꂽ�ɈႢ�Ȃ��B�@�@
�@ ���Ƃ����ɍs���������ƂȂ����U���I����Ƃ��Ă��A�����Ƃ��Ă͍ŐV�^�̌����g�D�ɏ�荞�݁A���˓��̊C���Ĕ����ÂɎ���A�������瓌�V�i�C�̍r�g�̒��ւƏo������Ƃ������m�̑D�����̂��̂ɁA�Ȃ̖��ɒl�����`�������Ă����̂��낤�B����Ȃ�̊댯���o��ŃX�y�[�X�V�b�v�ɓ��悵�A�͂邩�ȉF���ւƔ�ї�����̔�s�m�����̎v���ɒʂ�����̂������ɂ͂������Ƒz�������B
�@ �Ƃ���ŁA�����g�D�Ƃ������̂͂ǂ�ȍ\�������Ă���A�ǂ̒��x�̔\�͂����D�ł������̂��낤���B�����j�k���C��������̒��ɂ͑D�����\��قǁA�D�������]�肾�����ƋL�q����Ă���B���͏\�ڂŁA����̒P�ʂɂȂ����ƎO���[�g���]�ɑ������邩��A�������l�\�܃��[�g���قǁA�����l�A�܃��[�g�����x�Ƃ������ƂɂȂ낤�B������Ƒ傫������C�����Ȃ��ł��Ȃ����A�Ƃ������A���̑D�ɕS��\�l����S�Z�\�l�̎҂���荞�Ƃ����Ă���B���g�݈��̔����͑��D�Ɍg��鐅�v�����������炵���B
�@ �o�[���w��������̂Ȃǂ������āA�����`�̑傫�Ȕ��锿�����D���t�߂ɂ͓�{�����Ă����B�܂��A�b��ɂ́A�D�V���ɗv�l���ڂ����Ǝv���鍂���A���������߂��蕗�Q����g���B�����肷�邽�߂ɗp�����炵���ؑ����̂悤�Ȃ��̂��݂����Ă����B�������ɂ͂��ꂼ�ꔪ���قǂ�䂂����u�ł���悤�ɂȂ��Ă��āA��������t�����A�����j���������A����ɂ͗��n�߂��Œn�`�ɉ������ׂ��ȓ��������Ȃ���Ȃ�Ȃ����ȂǂɁA���v����ւł�����䂂𑆂��őD��i�߂��悤�ł���B
�@ �]�k�ɂȂ邪�A�D�𑆂����߂ɌÂ�����`����Ă���䂂Ƃ������̂́A�C�����₩�ȏꍇ�Ȃǂɂ̓I�[���Ȃǂ��������ƕ֗��Ō����I�ȓ���ł���B���^�G���W���̕��y�������āA���܂ł͂����قƂ�nj������邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ��Ă��܂������A�c��������䂂𑆂��ň�������ɂ́A���̗L����ʔ����͂悭�킩��B��肭�Ȃ�Ɠ`�n�D�p�Ȃǂ̏��^��䂂Ȃ�Ў�ł������邵�A�������܂܂ł�������B������������Ƃ��̎��̕Ԃ��ɂ�����Ƃ����R�c�͂��邪�A����Ă���Ɨ͂�����Ȃɗv��Ȃ����A�I�[���ƈ���đD�̐i�s�����Ɋ�������đ����邩��A���D���y�ł���B�������đ����Ƒ����ȑ��x���o���邵�A�����Ȑi�H�����⑬�x���������R�ɂł���B
�@ �����ۂ�䂂̓�_�̓I�[���Ȃǂɔ�ב��������}�X�^�[����܂łɎ��Ԃ������邱�Ƃł���B�܂��A�C���r��Ĕg�������Ȃ�A�D�̏㉺�����������Ȃ�ƁA�E�ɂ����鐅�̒�R�͂��傫�����s�ύt�ɂȂ�A�x�_�ɂ����鏬�ˋN�i�E�Y�j����䂂��O��Ă��܂����Ƃ���_���낤�B�����̌����g�D�̏ꍇ�ł��A�C�����₩�Ȃ��䂂͂���Ȃ�ɗL���������낤���A�������ɂȂ�����䂂͂قƂ�ǖ𗧂��Ȃ������ɈႢ�Ȃ��B�r�ꂽ�C�ł̓��[�}����̃K���[�D�Ɍ���悤�ȑ�^�I�[���̂ق��������Ɩ𗧂������Ƃ��낤�B
�@ 䂂͑����肪�����𗼎�ň����đO��ɉ�����������u�r���v�ƁA�����ɂ����Đ��������u�r���i�H���Ƃ������j�v����Ȃ��Ă��āA�S�̓I�ɂ͋Ȃ���̂��₩�ȁu�ցv�̎��`�����Ă���B䂂��g���Ƃ��ɂ́A�܂��A�r���̏�̂ق��ɂ�����`�i��ׂ��j�Ƃ������~�����ɁA����䂏��ɌŒ肳�ꂽ䂍Y�i�낮���j�Ƃ������̊ۂ��ʌ`�ˋN��Ƃߍ��ށB�����ɁA���Ɉ�[���Œ肳�ꂽ�����i�͂₨�A䂓�Ƃ��Ăԁj�Ƃ����֍j�̂�����[���A�r���̏㑤�ɂ���~���ˋN�Ɉ����|����B�����āA䂍Y���x�_�ɘr���������������Đ����̋r�������E�ɓ������A���̐��͂őD��i�߂�B���̍ہA������䂂����肳���A���̓��������͈̔͂ɗ}���铭��������킯���B
�@ ��r�I�㐢��䂍Y�ɂ͊C���ɂ�镅�H�ɋ����^�J���̂��̂������邪�A���Ƃ��Ƃ͊~�̂悤�ȍd���؍ނō���Ă����B�����V������Ȃǂɂ͓S�⓺�Ȃǂ̋���͋M�d�i�������낤����A�D��䂍Y�͓��R�ؐ��������͂��ł���B�O�m�ł��ʗp����悤�Ȓ��傩����䂂��g���ꍇ�A䂍Y�ɂ�����d�ʂƗ͂͑����Ȃ��̂ɂȂ����͂�������A䂍Y����`���܂ꂽ�芄�ꂽ�薀�ł����肵�āA���̋@�\�Ɏx�Ⴊ�����邱�Ƃ���������イ�������ɈႢ�Ȃ��B�����g�D��䂂����𗊂�ɓ��V�i�C���z���邱�Ƃ́A�ނ���Ȃ��Ƃ������B
�@ �a�D�𑆂�����䂂̑��삪���n���ƁA��������`��䂍Y����O���䂂������オ�葀䂂��s�\�ɂȂ��Ă��܂��B����䂂̑��삪��肢�ƁA��`��䂍Y�Ƃ͂��܂��a�����A䂂��O��ɉ������邲�ƂɁA�M�[�b�A�M�[�b�Ƃ������C���悢�������Ă�B�́A�a�D�ɏ��M�l�����́A䂍Y�̂��Ƃ�j����ɁA�܂���`��������Ɍ����āA�u䂂𑆂��v���邢�́u�D�𑆂��v�Ƃ������t�𐫍s�ׂ̉B��ɂ��Ă����B���ہA����������c�ɂł́A䂍Y����`�ɂ́A���ꂼ��j����⏗���킻�̂܂܂̌ď̂������Ă����B
�@ �É̂Ȃǂɂ悭������u���v�Ƃ������t�́A䂁A�D�A�ǂȂǂ̘a�D�̑D��̑��̂ł��邪�A�u���v���u䂁v��u�ǁv�ɏd�˂�ƁA�̗̂��ɂ��肰�Ȃ��B���ꂽ���܂ЂƂ̈Ӗ��������яオ���Ă��邱�Ƃ�����B�u䂁v�̂ق��ɂ��Ă͂��q�ׂ��ʂ肾���A�u�ǁv�̂ق��ɂ��Ă������������������Ă��������B
�@�u�ǁv�Ƃ͂������A�D�̍Ō�������ɂ����đD��̌�����ς�����A������������ւƌ������肷�铹��̂��Ƃł���B�̂̏��^�a�D�Ȃǂł́A�D���̉��̊O�������ɑnj��������āA�K�v�ɉ����đǖ{�̂����̌��ɔ��������ł���悤�ɂȂ��Ă����B�܂��A���̑ǂ����R�ɛƂ߂���O������ł���悤�ɁA�D���̒ꕔ�����ɂ͍ג������Ԃ����Ă����B�����ɂ���Ă͏����̌ҊԂ�A�z�����鑢��̂��߁A�̂Ȃ���̘a�D�ɗ����Ă�������̋��t�����́A������ɂ��Ă��A�ǂ�j����ɁA�nj���������Ɍ��Ȃ��Ă����悤�ł���B�nj��ɑǂ��Ƃ߂�ꂽ��Ԃ�ނ炪�j���̌����̏ے��ƍl�����̂́A�������R�̂��Ƃ������ƌ����Ă悢�B
�@ ����͂܂������̎����ł��邩��A�����܂ł��ÓT�ɖ��m�ȑf�l�̋Y���Ǝ���Ă�����č\��Ȃ����A�S�l���̒��̗L���ȉ̂Ȃǂ��A����Ȋϓ_�ɗ����Ē��߂Ă݂�ƁA�w��ɔ�߂�ꂽ���܂ЂƂ̍�҂̎����������ꂽ�肵�Ȃ����Ȃ��B���̂悤�ȑ��l�̖ڂ��炷��ƁA����ȉB�g������ł���Ƃ݂Ȃ��ق����A��҂̐���������w�i���炵�Ă����R�ł���悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��̂��B
�@ �R�ǂ̂Ƃ��킽��M�l�����������s���ւ��m��ʗ��̓����ȁ@�i�\�H�D���j
�@�u�Ɓi�ˁj�v�Ƃ͓ˏo�����n�`�ɂ͂��܂ꂽ���������̂��ƂŁA�u�R�ǂ̂Ɓv�Ƃ͌��݂̋I�W�C���i�W�H���Ƙa�̎R���c�q��Ԃ̊C���j�������Ă���Ƃ����Ă���B���̊C������C�����l�ɒ������������B���̑������̗���ɗ����������Ȃ��猜���ɊC���𑆂��킽�낤�Ƃ���M�l���A�������A䂂�䂍Y����͂����A�������̂͂Ă�䂂𗬎����Ă��܂��A�M�͒��ɗ�����ǂ��֍s�������Ƃ��킩��ʏ�ԂŕY���͂��߂�B����ȏM�l��M�̉^�����l�ɂǂ��Ȃ��Ă����̂��킩��Ȃ����̓��ł��邱�Ƃ�A�Ƃ����̂����g�Ɋ�Â��\�̉��߂ł���B
�@ �������A�M�l�������Ɂu�M�𑆂��v�A���ɂ͗͐s���āu䂍Y�v����u䂁i�`�j�v���͂����Ă��܂�䩑R��������L�l���u�j���̌����v�̈�A�̉ߒ����̂��̂̉B�g���Ƃ���A�u�s���ւ��m��ʗ��̓����ȁv�Ƃ������т̋���A�܂����̋�̂Ȃ��́u�s���v�Ƃ��������A���ꑊ���ɗd�������₩�ȗ��̈Ӗ����܂�ł��邱�ƂɂȂ�B����ɁA�u��g�̊C�i���݂̑��p�j�v�̓�����ɂ���u�R�ǂ̂Ɓi�I�W�C���j�v�������̃V���{���ɁA�܂��A�M��j���̃V���{���Ɍ����Ă�A���̉̑S�̂��j���̍s�ׂ̉B�g�ɂȂ��Ă���Ƃ����ǂݎ����ł��邩������Ȃ��B
�@ �a�D��䂂ɖ����ɂȂ��Ă��܂�������l�ɂ͑z���̂��ɂ����b��������Ȃ����A�����̂��̂Ɋ���e����ł����̂̐l�X�A�Ƃ��ɏM�l�̊ԂȂǂł́A�����������B�g�͂������ʂɒʂ��Ă������̂Ǝv����B
�@
�@ 䂂ɂ܂��]�k���߂��Ă��܂����̂ŁA�b�̊j�S������Ă��܂������A�����̑��D�Z�p�������炷��ƁA�����g�D�͍����ő勉�̐V�����ؑD�ł������Ƃ�����B�����A�c�O�Ȃ��ƂɁA�����g�D�̍b�̍\���A�D��̍\���A���̍\���̂��ꂼ��ɂ͏d��Ȍ��ׂ�����ł����B�Ȃ��ł��a�D�̔��̂����̗͊w��̌��ׂ́A�D�̍q�s�\�͂���łȂ��n�q������q�H�̑I���ɂ܂Ő���������炷���ƂɂȂ����B���̌��ʂƂ��āA�����g�D�ɂ͕K�R�Ƃ������鑘��̂��������邱�ƂɂȂ����̂������B�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N3��8��
�����g�D�̍\���I����
�@ �����g�D���͂��߂Ƃ���Î��a�D�̑��̌��ׂ́A�C�������S�ɎՒf�ł���C���b����������Ă��Ȃ��������Ƃł���B�b�Ɋ��S�Ȗh���������{�������̋Z�p���Ȃ����������ɁA�ωׂ̗g���~�낵�������悭�����Ȃ����Ƃ��D�悳�ꂽ����A����̑D�̂悤�ɑD�q���C���x�̍����b�ŕ������ƂȂǂ͂��܂�l������Ă��Ȃ������B���������āA�����Ƃ̂��̍]�ˎ���̐�ΑD��k�O�D�i�ٍ��D�j�Ȃǂł������A���̂Ƃ��ɍb�����Q�ɐ��ꂽ�肷��ƊC�����D�q�ɗ���݁A�����܂��]���̊�@�ɂ��炳��Ă��܂��L�l�������B�k�O�D�̏ꍇ�Ȃǂ́A���ɑ������đD�q���Z������ƁA�]��������邽�߂ɐωׂ��̂Ă�Ƃ�������i���Ƃ��Ă����Ƃ����B
�@ �����g�D�̕����͌^�����邩����ł͈ꉞ���̑D�q�͍b�ŕ����Ă��邪�A���ۂ̍b�̍\���͂����������𖧂ɕ��ג��������x�̂��̂������Ɛ��������B�ϐ��\�͂̂���߂ĒႢ���̂悤�Șa�D�ɂƂ��āA���R�̂��Ƃ��ɐ���オ��A�������D�������ׂ��悤�ɂ��čb�ɒ@������\�����̌��Q��h���Ƃ߂邱�ƂȂǁA�ǂ��l���Ă݂Ă��s�\�������ɈႢ�Ȃ��B���ē��V�i�C�ɕ����ԗ����ň�����g�䂦�A�ߑ㑕�������S�g�����炢�̑D�ɏ���ė��̊C��n�����̌������x�����邪�A����ł��������Q�Ƃ̐킢�͑s��Ȃ��̂ł������B
�@ �Î��a�D�̑��̌��ׂ́A�D�ꕔ�������������Ȃ�����̍\���ɂȂ��Ă������Ƃł���B�����Ƃ͑D�ꕔ�̊�{���i�̂��ƂŁA���̍\�����A�����w���𒆐S�ɍ��E�Ώ̂ɘp�Ȃ��Ă̂т鋰���̋����̑���Ɏ��Ă���̂ł��̖�������B�I���O�̐̂��痳�������Ȃ��Ă������[���b�p��A���r�A�n���̑D�́A�D�ꕔ�̒f�ʂ��傫���J�����u���`�����Ă��ĕ������̏d�S���Ⴍ�A�N���オ�菬�@�t�Ɠ��������ō��E�ɌX���Ă���������͂����������B�܂��A�x���ƂȂ鑾�����������邽�߂ɑD�ꕔ�̋��x���傫���A���Q�ɑ���ϋv�������������B���̊C�őD�̂��������C�ʂɒ@������ꂽ��A���g�̒��������肷��Əu�ԓI�ɑD���D���A�b�Ȃǂ��c�ށB����������ƏՌ��ɂ��c�݂͏��Ȃ��Ă��݁A���̉��́i�O�͂����Ƃ����̂ɐ������R�́j�ɂ���Ęc�݂͏C�����������B
�@ �Ƃ��낪�A�������Ȃ��A���M�̓����f�ʂɂ���������̘a�D�̏ꍇ�́A�d�S�̈ʒu�������A�O������̏Ռ��ɑ��Ă��Ƃ���������A�C���r���Ƃ����܂�����̊�@�ɕm����L�l�������B�^���C�D��z�����Ă݂�킩��悤�ɁA��̐���D�͊C�ʂ����₩�ȂƂ��ɂ͉��h�ꂪ�����Ȃ����肵�Ă��邪�A��������C���r��đ�Q�Ɏ����グ����ƈ���������đ傫���X���A���]���Ă��܂����Ƃ������������B�܂��A���̎��ȂǁA��g�̔g�����炢�����ɔg��ɒ@������ꂽ�肷��ƁA�����������Ȃ��Ǝ�ȑD�̂͂��̏Ռ��ɑς���ꂸ�A�D���D�����j��A�Z�����Ă��܂����Ƃ����Ȃ��Ȃ������B
�@
�@ �D���j�ׂĂ݂�������ł́A�䂪���ł͂��߂ė��������D������ꂽ�͖̂������̍��̂悤�ł���B�ӊO�Ȃ��Ƃ����A��ΑD�Ȃǂ��ӂ��߂āA����܂ł̘a�D�͑�^�̂��̂ł���������������Ă��Ȃ������̂��B�]�ˎ��㖖���̎v��ʎ������_�@�ƂȂ��ė����������ĕ��̑�^�D�����Z�p�������ɓ`�������܂ŁA�a�D�̊�{�\���͌����g�D�̎���ƂقƂ�Ǖς���Ă��Ȃ��������ƂɂȂ�B
�@ �ꔪ�l�N�i�������N�j�\�ꌎ�l���A�ɓ����c��т́A�I�ɔ�����[����k���Ƃ����n�k�ɂ���ċN��������Ôg�ɏP����B���c�̒��Ƃ̂قڑS�˂���u�ɂ��ē|�����Ă��܂��قǂɐ��܂����Ôg�������炵���B�č��̃y���[�ȂǂƓ��l�ɁA���{�Ƃ̊J�`���̂��߃��V�A����h������Ă����v�`���[�`����́A���c�p�ɒ┑����R�̓f�B�A�[�i����ɂ����āA���܂��܂��̒Ôg�ɑ��������B
�@ �Ôg�ɖ|�M����đ���A��j�����f�B�A�[�i���́A�v�`���[�`���Ƃ̌��̂��߂ɖ��{�̑�\�Ƃ��ĉ��c�ɐ������Ă������t�A��H��敂̋C�]�Ɣz���ŁA�C���̂��߂ɐ��ɓ��̌˓c�i�ւ��j�`�ւƉ�q����邱�ƂɂȂ�B�Z�\����̑�C����������g�����̂��̑�^�ؑ����D�ɂ͖�ܕS�l�̃��V�A�l�����g��ł����Ƃ����B�f�B�A�[�i���͂Ȃ�Ƃ��˓c�p���܂ʼn�q�������A�C���r��Ă��邤���ɕ����ǂ̔j���ƂЂǂ��Z���̂��߂ɍq�s���܂܂Ȃ炸�A�c�q�̉Y�ɋ߂��{�������i���݂̕x�m�s�V�l��������j�ɗ�����A�����œ������Ƃ�Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B
�@ �K���̋~�D��Ƃ��ނȂ����A�������̃f�B�A�[�i�������v�̊�@�ɂ��炳��鎖�ԂɂȂ������߁A���V�A�l��g���Ƌ{�������ӂ̒n�����Ƃ́A���������Q�����Č����̋�����Ƃ��s�Ȃ��A�h�����đD�ƕl�ӂƂ̊Ԃɋ~���p���[�v�邱�Ƃɐ��������B�����āA�J�b�^�[�{�[�g����`�ɕ��悵���v�`���[�`���ȉ���ܕS���̑D���́A���̃��[�v�j�Ɍ��Q������{�����ɖ����㗤���邱�Ƃ��ł����B���̂Ƃ��ɑD���̋M�d�i�⎑�ނ̈ꕔ�����g�����ꂽ�悤�ł���B
�@ ���ꂩ���A�O����̂��ƁA���v���O�̃f�B�A�[�i�����Ȃ�Ƃ��˓c���܂ʼng�q���悤�Ƃ������ƂɂȂ�A�x�͘p���ӂ̋��D�S�ǂقǂ��{�����ɏW�������B�a�̂悤�ɌQ���邻���葆���̏����D�ɉg����āA�f�B�A�[�i���͌˓c�`�̂ق��ւƔ��L���قǃW���W���ƈړ������̂����A�����ł܂��ˑR�C��Ɋ����N�����������ɏP���A���ɒ��v���Ă��܂��B���ꂩ��قǂȂ��A�{�����ɏ㗤�������V�A�l�����͖����ɂ���Č˓c���ւƈڂ���A�S���̋A������������Z�����ق̂ǂ̊ԁA�ނ�͑��l�Ǝ��肠��𗬂𑱂��Ȃ���˓c�̏W���ɑ؍݂��邱�ƂɂȂ����̂������B
�@ �K���Ȃ��ƂɁA������f�B�A�[�i���̏�g���̒��ɂ́A�̂��ɔ�s�@�̐v����ł����̖���m����悤�ɂȂ郂�W���C�X�L�[�Ƃ����D�G�ȋZ�p���Z���܂܂�Ă����B�v�`���[�`�����͂��߂Ƃ��郍�V�A�l��s�̋A���ɂ͂ǂ����Ă���p�D���K�v�ł���������A�K�R�̐���s���Ƃ��āA���̃��W���C�X�L�[�̐v�Ǝw���̂��ƁA�˓c�̓��]�̈���Ŕ��\�g���قǂ̃X�N�i�[�^���D����������邱�ƂɂȂ����B�������A���̂��߂̎��ނ�D��H�A�l�v�Ȃǂ͖��{�������邱�ƂɂȂ����̂����A���������J���}�킸���V�A�l�����̂��߂ɏ\���ȕX���͂���A���D��Ƃ̐��s�ɑ傫���v�������̂́A�L�\���J���I�Ȑl���Ƃ��Ė������A�O�q�̖��t�A��H��敂ł������B
�@ �V�D�����ɂ������ẮA���ɓ��e�n�̑D��H���������W���ꂽ�B�D�������ł��l�\���قǁA����ɖ��{�̏���l�⑺�̊W�ҁA�l�v�����킹��ƎO�S���A����Ƀ��V�A�l�����ܕS���������������A���v���S�l�قǂ̐l�Ԃ����̈�厖�Ƃɏ]���������ƂɂȂ�B�v�`���[�`���ɂ���āu�˓c���v�Ɩ������ꂽ�A�O�{�}�X�g�A�S����\�[�g���̖{�i�I�Ȃ��̗m�����D�́A�O�������炸�Ƃ��������Ƃ��Ă͋��ٓI�ȃX�s�[�h�Ŋ������ꂽ�B���̈�A�̍�Ƃ�ʂ��āA���{�̑D�������͗��������O�m���D�̌����Z�p���͂��߂Ď��n�Ŋw�тƂ����̂������B���Δh�̒��S�I�l���Łu���V�A�l���F�E���ɂ���v�Ƃ܂ŏ��������ːď��܂ł��A�Ō�ɂ͉Ɛb��̂��ɐΐ쓇�d���d�H�̊�b��z�������˂̑D������˓c�ɑ��荞�˓c���̌�����������w�������Ƃ�������A�����ɃZ���Z�[�V���i���ȏo�����������̂��낤�B
�@ �P�ɂ��ꂪ����ꂽ�Ƃ��������̘b�Ȃ�A�˓c�����a�����鐔�����O�ɍ����œ�ǂ̑�^�m�����D�̌������s���Ă���B��^�D�̕K�v�������Ė��{�݂����炪�Y��Ō��������P���ۂƁA�F���˂��������œƎ��ɑ��D���������ۂ�����ł���B�����A���D�Ƃ��ɊO�������𗊂�Ɍ��悤���^���Ō������ꂽ���߂ɗ��D�Ƃ��ɋZ�p�I���ׂ������A�����ۂ̂ق��Ȃǂ͂Ƃ��ɐZ�����Ђǂ��āA�܂������̎��s��ƂȂ��Ă��܂����Ƃ����B���������āA�˓c�������́A�䂪���ŏ��̖{�i�I�ȗ����\�������m�����D�������ƌ����Ă悢�B����Ƃ̊ēɂ����������l�̑D��H�̓��������́A�ב�R�炳���D�̐���ߒ��̋L�^���Ƃ�A�̂��̂��̗m�����D�����ɔ����悤�Ɠw�߂��炵���B
�@ �����Ƃ��A�˓c���̌����ɗՂ��{�̑D���������A�������Ď�g�����ۂ��ł������킯�ł͂Ȃ��B�S�̓I�ȑD�̍��i����̒i�K�ł̓��V�A�l�Z�t�����̎w�����傫�ȗ͂ƂȂ����̂����A�ו��̍�Ƃ�\�ʎd�グ�̒i�K�ɂȂ�ƁA���̊�p�ȓ��{�̑D�������̋Z�p�ƃA�C�f�B�A����������A���̑f���炵���Ƀ��V�A�l�����͊F����������Ƃ����B
�@ �ʔ������ƂɁA�˓c���ɂ́A���{�l�D����̈ӌ������ē��{���̃I�[���A���Ȃ킿�A䂂��Z���قǔ��������Ă����B�v�`���[�`����̏�����˓c�����J���`���b�J�̂g���p�u���t�X�N�`�ɋ߂Â����Ƃ��A������䂂��v��ʈЗ͂�����B�����̓N���~���푈�̂��Ȃ����������߁A���`��т̓C�M���X�ƃt�����X�̊͑��ɂ���ĕ�͂���Ă����B�Ƃ��낪�A���܂��܂��̓��͋H�ɂ݂�悤�Ȃׂ���ł��������߁A���V�A�l�����͔�������䂂��g���G�͑��ɔ�������邱�ƂȂ��A�o�`���X�N�̓��]�ɓ������ނ��Ƃ��ł����̂��Ƃ����B
�@ �킸���O�����Ԃ̌˓c��������ʂ��ăX�N�[�i�[�^���D�̐���Z�p���K���������{�l�D����́A���V�A�l�炪�A���������Ƃ��A�Z�ǂ̓��^�D�����X�ɑ��肾�����{�ɔ[������B�₪�Ĕނ�₻�̒�q�����́A�]�ˁA���{��A�Y��A����A���A�_�˂��͂��߂Ƃ��鍑���e�n�̑��D���ɎU��A�����Ɏ���䂪���̑��D�ƊE���W�̑b��z�����̂ł������B
�@ �C���b�◳������������Ă��Ȃ��������Ƃ��傫�Ȍ��ׂł��������A�����g�D���͂��߂Ƃ���Î��a�D�̍ő�̎�_�͂��̐��i�̗͂v�ɂȂ锿�̍\�����̂��̂ɂ������B����Ɍ����ƁA���[���b�p��A���r�A�̔��D���A�t���≡���ł��i�ނ��Ƃ̂ł���g�͗��p�̔��̌��������łɂƂ肢��Ă����̂ɑ��A�a�D�̔��͏�������͂���ɋ߂����������p�ł��Ȃ����n�I�Ȕ��ɉ߂��Ȃ������B������u���b�g�v�Ɓu���|���M�v�̈Ⴂ�ł���B
�@ ��s�@�̗��̒f�ʂ݂����ɕ\���̖ʂ��ӂ���݁A����ɔ�ׂė��ʂ�����ȕ��̗̂��ʂɉ����đ�C�������ƁA���ΓI�ɋC���̗��ꂪ�x�����ʑ�����C���̗���̑����\�ʑ��Ɍ������ėg�͂Ƃ������ʂȗ͂������B��s�@��H�����L���đ������钹�Ȃǂ́A���̗g�͂̂������ŋɕ���ł���킯���B���b�g�̎O�p���i�����I�ɂ͎O�p���łȂ��Ă��悢�j�̒f�ʂ͂�͂肢���ۂ����i���̕\���j���ӂ����ł��邽�߁A���Ƃ��Δ��̐^�����畗�������Ă����ꍇ�A���������Ŕ������甿�\�̕����Ɍ������ėg�͂������B���̗͂����b�g�𐄂��i�߂�킯�ł���B���_��͑D�̐^���������畗�������Ă���ꍇ�ɗg�͍͂ő�ƂȂ�A����ł͑D�������������邱�Ƃ��\�ł���B
�@ �t���̏ꍇ�ł��A���Ƃ��ΑD���w���ɑ��ĂقډE�l�\�ܓx�̕��p�Ɍ����A���̊p�x�����C���ƂȂ�ׂ����s�ɂȂ�悤�ɒ�������A�g�͂�������B�ǂ��I�݂ɒ�������A���̕��͂𗘗p���ĉE�ߑO���ɐi�ނ��Ƃ��ł���B���炭�i��A���x�͑D�̌���������ɑ��č��l�\�ܓx�ɂȂ�悤�ɑǂ��A��͂蔿�̊p�x�����C���ƕ��s�ɂȂ�悤�ɂ��Ă��A����ǂ͍��ߑO���ɐi�ނ��Ƃ��ł���B�^�b�N�ƌĂ�邱�̑�����J��Ԃ��A�D�̓W�O�U�O�^�������Ȃ��畗������ւƐi��ł�����̂��B
�@ �������A�����̏ꍇ�͕��ɔC���Đi�߂悢�킯�ł��邪�A���̏ꍇ�͗g�͂𗘗p���Ă��邱�Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ�����A���̑��x�ȏ�ɂ͑D���͏オ��Ȃ��B�^����O�����̕��Ȃ�����ł��g�͂̂������ł��ꑊ���ɂ͑O�i�ł��邪�A�����ł������̏ꍇ�ɂ̓��b�g�Ƃ����ǂ��v���悤�ɂ͑O�i�ł��Ȃ��B
�@ �����ۂ��A���̍\����̊W�ŗg�͂𗘗p�ł��Ȃ����|���M�̏ꍇ�ɂ́A�����Ȃ����͂���ɋ߂�������̕��ł����O�ɐi�߂Ȃ������ɁA�����ȏ�̑D�����o�����Ƃ͂ł��Ȃ�����A����߂đ��s�\�͂��Ⴍ�Ȃ��Ă��܂��B�������A�t���Ȃǂ̏ꍇ�ɂ͔��������ނ����Ȃ��킯�����A�܂��A���Ƃ����������Ƃ��Ă������ɗ������̂�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@ �����g�D�͌����ɋy���A�]�ˎ���̐�ΑD��k�O�D�ɂ�����܂ŁA�䂪���̑D�͂قƂ�ǂ��D���t�߂ɔ��������u���|���M�v�ł���������A�s����X�̍`�ŕ��҂������Ȃ��珇�������𗊂�ɐi�܂�������Ȃ������B���������āA���̂悤�ȑD�ɏ���Ĉ��S�ȉ��ݒn�т𗣂�A�������̈�肵�Ȃ��O�m�ɏo�Ă��܂����ꍇ�ɂ́A���Q�ɖ|�M����A�ړI�n�ɒ����O�ɓ�j������Y�������肵�Ă��܂��̂��ނ��뎩�R�Ȃ��Ƃł������B
�@ �����g�D�̕����͌^���݂�������ł́A���̔��͓Ƃ��ɑ����傫�Ȓ����`�̖��z���ŁA�����ɂ͒|�ނ∯�̂悤�Ȃ��Ȃ₩�ŋ��x�ȕ⋭�ނ����ɕ҂݂������Ă������悤�ł���B�v���ɏグ��������̂�������̂悤�ȏd���������ƁA����łȂ��Ă������D�̏d�S������ɍ����Ȃ�A�����ł����Ă������̎��Ȃǂɂ͔����S�̂ɋ����͂������s����ɂȂ��Ă��܂����ɈႢ�Ȃ��B�������A�㕔�ɂȂ�قǎ�͂��������������ɍ��킹�Ĕ��̊p�x�����R�ɕς�����O�p����A�グ�������e�ՂŃ}�X�g�̐�[�ɋ߂��قǏ������Ȃ�m�����D�̕��w���ƈ���āA���������ނ���㕔�̂ق��̕����L���a�D�̔��́A�͊w�I�ɂ݂Ă������ɖ������������B
�@ ���Ƃ������傫���̗͂ł����Ă��A�����̐�[���ɂ��̗͂������ƁA�e�R�̌����ɂ���Ďx�_�ɂ�����}�X�g�̍����t�߂�D�̖{�̂ɂ�����͂͑傫���Ȃ�B������A�˕��⋭���ɐ�����ƃ}�X�g���܂ꂽ��A�D���s����ɂȂ��ČX�����肷�邱�Ƃ͕p�ɂɋN���������Ƃ��낤�B
�@���������`���ɂ��ďq�ׂ�������̕����ɂ́A�u�`���̎g���D�͑D�ꂪ���Ŕg���Đi�ނ��Ƃ��ł��Ȃ��B���̔��z�͒��S���������Əd�Ȃ�悤�ɒ����Ă���A�����D�̂��Ƃ����̒[���������Əd�Ȃ�悤�ɂ͒����Ă��Ȃ�����A�������g�����Ƃ����ł��Ȃ��B�t���△���̏�ԂɂȂ�Ɣ�����|����䂂��g���̂����A�v���悤�ɂ͍q�s�ł��Ȃ�����A�`���̏��D�͓��V�i�C��n���̂Ɉꃖ���]���������Ă��܂��v�Ƃ������Ӗ��̂��Ƃ��q�ׂ��Ă���B
�@ ���Ȃ݂ɏq�ׂĂ����ƁA�l�p�����̍��E�ǂ��炩�̒[���������ɏd�Ȃ�悤�ɒ���~�߂��A���̂�����[�����������ɂ��ĕ������ɍ��킹���R�ɓ�������悤�ɂȂ��Ă���A���b�g�̎O�p���Ɠ��������ʼn�����t���𗘗p���i�ނ��Ƃ��ł���킯���B�u�ꃖ���]���������Ă��܂��v�Ƃ����L�q�́A������Ȃ�ł�������Ƒ�U���߂���悤�ȋC�����邪�A���V�i�C�̉��f�ɂ����Ԃ�Ǝ��Ԃ������������Ƃ����͊m�����낤�B
�@ �����A�a�D�ɂ��܂�������O���Ȃ������킯�ł͂Ȃ��B�،����N�G���Ɍ���\�I�㔼���̑嗤�n�q�D�̔��͒������ɒ[���������Əd�Ȃ�悤�ɒ����Ă��邵�A��Z�Z�l�N�����Z�O�ܔN���܂ő���������D�i�r�ؑD�j�͎O�{�}�X�g�ŁA�����D�Ɨm���D�̐ܒ��^�̔�������Ă����悤�ŁA�w��ɂ������Ȕ��������悤�ɂȂ��Ă����B�����̑D�̂̔����I�݂Ɏg���A�i�s�����̒�����t���̗��p���\���������Ƃ��낤�B���̂��ƍ����̎���ɓ���A�O�m�̍q�C�ɑς����^�D�̌������֎~���ꂽ���Ƃ������āA���̎�̔��͎g���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂�������Ȃ��B���ǁA�a�D�͂��Ƃ̔��|���M��Ԃɂɂ��ǂ��Ă��܂�����ȏ㔭�B���邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂��B�C�m���ł���ɂ�������炸�O�m�D�����B���Ȃ������̂́A�����I�ȍ\���̘a�D�ł��Ȃ�Ƃ��Ԃɍ������ݒn��⒆���A���N�Ƃ̌𗬂���ŁA�����m�̔ޕ��ւƂ̖ڂ�������K�v�̂Ȃ������䂪���̗��j�I�w�i�ƒn���I����ɂ����̂������̂�������Ȃ��B
�@ �����g�D�����V�i�C��n��̂ɁA�嗤�����Ɍ������ē쓌�̋G�ߕ��̐����r���Ċ���I�̂́A���łɏq�ׂ��悤�ɁA���̍\����A�����ɗ��邵���Ȃ���������ł���B�쓌�̋G�ߕ������������́A�����嗤�ɋ߂Â��ɂ�ĊC���r��Ă���B�����̌����g�D�ɂƂ��Ă͋G�ߕ��̂Ђ��������r�g�����邾���ł��e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ������̂ɁA���̋G�߂͓�C�Ŕ��������䕗�������嗤���̊C��R�[�X���Ƃ��Ėk�シ�鎞���ɂ��d�Ȃ��Ă����B�䕗���Ȃǂ���悵���Ȃ����������̏̂��Ƃł͑�����o����̂����R�������B
�@ ���H����ς��������A���H�͂���Ɍ����������B�����ɂ͂��œ��{�ւƖ߂�ɂ́A�ӏH���猵�~���ɂ����đ嗤���琁���o���k���̋G�ߕ��ɏ�邵���Ȃ��������A�܂��G�ߕ����ア�ӏH�̍��͑䕗�V�[�Y���Əd�Ȃ��āA��r��ɂȂ邱�Ƃ����������B�܂����{�t�߂������~�^�̋C���z�u�ɕ����錵�~���ɂȂ�ƁA�������k���̕��ɐ����A���V�i�C�C�͎l�Z�����r��ɍr�ꂽ�B�������A�g�q�]�������Y�B����D�o���Ėk���̕��ɏ�����ꍇ�A�����Ƃ͂����Ă��D�͓쓌�����ɗ�����邱�ƂɂȂ邩��A���ڋ�B�{�y�ɒ��݂��邱�Ƃ͓�������B������A�����Ă��̏ꍇ�ɂ́A�������������≫�ꏔ���̂ǂ����ɒH�蒅���A��������V��҂������Ȃ��獕���{����Δn�C���ɏ���ē��`���ɖk��A�����m���ɗ�����Ȃ��悤�ɍאS�̒��ӂ��Ȃ���V�Â�����ɒ��݂���Ƃ������@���Ƃ��Ă����B
�@ �쓌�̋G�ߕ��ɏ���Ē����Ɍ��������H�̏ꍇ�́A�嗤�̂ǂ����ɒ������Ƃ��ł���Ȃ�Ƃ��Ȃ������A���H�ɂ����ẮA�D�̂��̂��̂������ł����Ă��A�����m�̂����Ȃ��ւƗ�����Ă��܂��O�ɂǂ����̓��ɓ������Ȃ���Ȃ�Ȃ������B���������ĕ��H�̍q�C�͂����������������߂��킯�ł���B���������m�ɗ���o�Ă��܂�����A��قǂ̍K�^�ɂł��b�܂�Ȃ������萶�҂͐�]�I�������B�u�쓇�H�v�Ƃ������t�ɂ͂Ȃɂ�烍�}���̋��������������邪�A���ۂɂ͂��̌��t�́u�n���̈꒚�ځv�Ɠ��`�ꂾ�����ƌ����Ă悩�����낤�B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N3��15��
���V�i�C���z����
�@ ���ܓ�N�A�����g�̈�s�����������B�ɒ����ƁA���̓������Ђ�����҂��Ă������Ƃ́A�����ɐ��g�̓������͂�Ɖ�����B���Ԃ�A���̎��ɊӐ^�̓��{�n�q�v�悪���܈�x�����ɗ���Ȃ����ꂽ�̂ł��낤�B�����O�N�̐����A���{�g�ߒc�͓��̍c��ɔq�y���j��̗��s�����߁A�������Ȃ��������̂悤�ɓs�ւƂ̂ڂ��Ă���B���v�̂��߂ɓ�������e���̎g�ߒc�́A�����ɓs�ɓ��蒩��ɔq�ꂷ��̂����킵�ɂȂ��Ă����B
�@ �Ӑ^�ɍŏI�I�ȓn�q�̌��f���肤�ׂ�������i�߂Ă����������͂�́A���̔N�̏\���\�ܓ��ɗg�B�������ɒ����ƁA�������ɊӐ^�ɑ����{�ւ̓��s��v�������B���̐\���o����������Ӑ^�́A���̎l����̏\����ɗg�B�𗷗����Č����g�̈�s�ɍ������A�\�ꌎ�\�Z���A�܂���̑咪�ɏ���đh�B�����Y����G�ߕ��̐����r��铌�V�i�C�ւƏo�������B�@�@
�@ �����Y�́u���v�Ƃ��������́u�܁v���Ӗ����Ă��邩��A����͉��Ƃ��Î��ɖ������D�o�ł������ƌ����邩������Ȃ��B�Ӑ^�́A�o�q�ԍۂɂȂ��Ă���A�l�ڂ������悤�ɂ��Ďl�ǕҐ��̋A���D�c�̑��D�ɏ�荞�Ƃ����B���R�A���o���������킯������A����̓��Ƃ̊W��S�z������{�g�ߒc�̊Ԃɂ́A�Ӑ^����D���钼�O�܂Ōv��̌��s�ɂ��߂炢���������Ƃ��`�����Ă���B
�@ ���̑D�c�̑��D�ɂ͐��g�̓������͂̂ق��ɁA���̗L���Ȉ��{�����C������Ă����B
�@ ���ꎵ�N�̑攪�������g�D�ŗ��w���Ƃ��ē��ɓn���������C�́A�������͂Ƌ����܂łɎO�\�]�N�̎����ٍ��̒n�ʼn߂����Ă����B���̊ԁA���̒���ɏd�p����Ă������Ƃ������āA�����̑厍�l�����≤�ۂƂ���V���������ƌ����Ă���B���̂Ƃ����łɌ\��ɂȂ��Ă��������C�́A���̑D�ɏ���ĉ��������̍��A�낤�Ƃ����̂ł������B
�@ �Ӑ^���A�v�l�̐�߂銄�������������Ǝv������D�ɂł͂Ȃ��A���D�̂ق��ɏ�荞�ނ��ƂɂȂ����̂́A���肬��܂Ŗ�l�̊Ď��̖ڂ�E�ԈӐ}���̑��̎�����������߂��낤�B�����A���ʓI�ɂ͂��̂��Ƃ��K�������B���̎l�ǂ̑D�c�̂����A�Ȃ�Ƃ������ɖV�ÂɒH�蒅�����̂͊Ӑ^�̏�������D��������������ł���B
�@ �^�U�̂قǂ��m���߂邷�ׂ͂Ȃ����A���{�����C���A�u�V�̌��ӂ肳������Ώt���Ȃ�O�}�̎R�ɂ��ł��������v�Ƃ������̗L���ȉ̂��r�̂́A���̏o�D�̒��O�A�h�B�̕l�ӂōÂ��ꂽ�ʂ�̉��̐Ȃɂ����Ăł������Ƃ����B�̂̒��́u�V�̌��v�́A���Ƃ��Ƃ́u�C���v���邢�́u��C���v�������Ƃ�����������悤���B�L�^�ɂ��A�����g�D���h�B�����̂͋���@�i���A��j�̏\�\�Z��������A���̈���O�̏\�ܓ��ɂ͓��̊C���珸�閞��������ꂽ�͂��ŁA�b�̂��܂͍����Ă���B�ꍑ�ւ̋A�҂�ڑO�ɂ��������C���A���̐��������珸����������e�߂Ȃ���A���ɑ���]���̔O���̂ɉr�ݍ��Ƃ������̓`���������������Ƃ���A���̌�ɔނ�҂������Ă����^���͂��܂�ɂ�����ł������Ƃ��������悤���Ȃ��B
�@ �������͂∢�{�����C�̏�������D�͏o�q��ɓ��V�i�C�ő���A���ĊӐ^�����ꒅ�����̂Ɠ����C�쓇���ʂɐh�����ĕY�������B��l�Ƃ��ɖ����������������̂́A���Ɍ̍��ւ̋A�҂��ʂ������Ƃ��ł��Ȃ��܂܂ɂ��̐��U���I�������Ƃ́A�N�����m����j�ɖ������b�ł���B�����C�͂��̑���̂��ƍĂђ����ɖ߂��ē��̒���ɓ�\�N�قǎd���A���\��Ŗv���Ă���B�܂�ŊӐ^�Ɠ���ւ��ł������悤�Ȃ��̔ӔN�̗L�l�́A�V�̂�������Ƃł������ق��Ȃ��ł��낤�B���Ȃ݂ɏq�ׂĂ����ƁA��O�D�͑����m�ɗ�����āA�I�ɔ����암�̓c�ӕt�߂̕l�ӂɖ��S�Ȏp�ŕY�����A�܂���l�D�͎F�������̓�[�ɂ��錻�݂̉o�����̍r��ɓ�j�D�ƂȂ��đł��グ��ꂽ�ƌ����Ă���B
�@ �L�^�ɂ��ƁA�Ӑ^�̏�������D�͏\�ꌎ��\����ɂ͉���ɒ����A�����őD�̏C����⋋���I�������ƁA�����̏\�Z���ɂ͉�������Ƃ����B�ӊO�Ȃ̂͂��̂��Ƃ̍s���ŁA�r�������哇�Ɋ�`�����ɂ�������炸�A�����̏\�����ɂ͂������v���ɒ������ƋL�^����Ă���̂ł���B�n�}�����Ă݂�킩��悤�ɉ��ꂩ�牂���������o�ĉ��v���Ɏ���C�H�͎l�S�L���ȏ�����邩��A���̋L�^�Ɍ�肪�Ȃ������Ƃ���A��ՓI�Ȃ܂łɓV��ƕ��Ɍb�܂�A��قǂ��܂�������Δn�C���ɏ�邱�Ƃ��ł����̂��낤�B����������ʼn��ꂩ�牂���o�R�ʼn��v���܂ōq�s�����Ƃ���A������\�L�����鑬�x�őD�͋x�ނ��ƂȂ�����Â����v�Z�ɂȂ邩�炾�B�n���I�ɂ݂Ă�������炢�͉����ɒ┑�����͂����ƍl����̂����R������A������������L�^�̂ق����Ԉ���Ă���̂�������Ȃ����A���܂ƂȂ��Ă͊m���߂邷�ׂ��Ȃ��B
�@ ���v���ɏ\���قǑ؍݂��ĕ��҂��������D�́A�\�\�����ɉ��v���������A�o�����ĂقǂȂ��l�����܂������킩��ʂقǂɊC���r�ꋶ���A�����������đ���̊�@�ɂ��炳���B�����A�K���Ȃ��ƂɁA�\����̓����ɂȂ��ĎR�̂悤�ȑ�g�̊Ԃ���{�y�̎R�̒����炵�����̂�]�ނ��Ƃ��ł����炵���B���Ԃ�A�F���x�m�ٖ̈������J��x���A�����łȂ���Γ������G��ȎR�e������Ԋx�̒��������̂��낤�B�Ȃ�Ƃ����݈ʒu���m�F���邱�Ƃ��ł����D�́A���ꂩ��܂������Q�ɖ|�M���ꂽ�����ɁA�\��\���̒����A�F���������S�H�ȉ��Y�i�V�ÏH�ډY�j�ɑ���O�̏�ԂŒ��݂����B���v������V�ÏH�ڂ܂ł͒��������ŋ�\�L���قǂɂ����Ȃ�����A����܂ł̏����ȍq�C�Ɋr�ׁA���̊Ԃ̑D���͂�قnj��������̂ł������̂��낤�B
�@ �\�܍̂Ƃ��ɓ��{�ւ̓n�q��v������Ă�����ɋ�ߏ\�]�N�A�V�ÏH�ڂɒ������Ƃ��ɂ͊Ӑ^�͂����Z�\�Z�ɂȂ��Ă����B���{�̓y�Ƃ����łɎ������Ă����Ӑ^�́A�u�R��و�v�̒n�ł���V�Â̌i�ς����̖ڂł����Ɍ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ������ɈႢ�Ȃ��B�������A�Ӑ^�ɂ͂�������ė]�肠����O�ꂽ�S�Ⴊ������Ă����B���̐S��������āA�ނ͖V�Â̏�i�₻���ɏZ�ސl�X�̐S�̓��������ƌ������A�ٍ��̒n�̑�C�̂����߂����s���ǂ݂Ƃ��Ă������Ƃ��낤�B
�@ ����̏\��\���Ƃ����ƌ��݂̈ꌎ���{���炢�ł��낤���B�썑�F���Ƃ����ǂ��A�V�x���A�C�c�����肾���k���̃����X�[���������r��邱�̋G�߂͑����Ɋ����B�����嗤�k�����瓌�V�i�C���z���Đ�������ł���G�ߕ��̒��ɁA�s�A�̌��ӂŗ������������̍��̑�n�̑������Ӑ^�͚k���Ƃ��Ă�����������Ȃ��B�����A���̂����ۂ��ŁA�ً��̒n�ɍ~�藧�����Z�\�Z�̔ނ́A���̓������̒��ɁA�^�̕��@�҂݂̂̒m�o������߉ނ̎���Ǝ���ɉۂ���ꂽ�g���̏d���Ƃ�������������Ă����ɈႢ�Ȃ��B
�@ ���{�����C�����̉̂��r�Ƃ��������̓����炿�傤�Ljꌎ��̋���\�\�ܓ��O��̍��A�Ӑ^�͉��v���ɑ؍݂��Ă����킯������A���ɂ͖���������ɋ߂����������Ă������ƂɂȂ�B�܂��A�V�Â��C�H��B���݂�k�シ�鍠�ɂ͂�����L���̌��������̋��ɋP���Ă����͂��ł���B���Ƃ��k���̋G�ߕ��͋����Ă��A���̊Ԉ�x����x���炢�͊Ӑ^�̎p���ٍ��̓~�̌��ɏƂ炵�o����邱�Ƃ��������낤�B�܂��ɂ���́A�u�������V�v�̌�傻�̂܂܂̐��E�ł������ƌ����Ă悢�B
�@ �Ӑ^���V�Âɂǂ̂��炢�̊ԑ؍݂������͕s���ł��邪�A�D�̏C����⋋���I���Ƃ����ɑ�ɕ{�Ɍ����ďo�������悤�ł���B���̎���́A�V�����肵�Ă���Η��H���C�H�̂ق����͂邩�Ɉ��S���v������������A���R�C�H���I�ꂽ�B�V�Â��o���D�͖�Ԗ�������ĎF����������k��A�����Ɩ{�y�Ƃ̊Ԃ�ʂ��ēV�������݂ɒB���A��������V�����k�[�Ɠ���������[�̊Ԃ̑��萣�˂��A�����������݂ɉ����ėL���C�ɓ������B
�@ �����ėL���C�̍ʼn��ɂ��錻�݂̍��ꌧ�v�ۓc���t�߂̕l�ӂɒ��݂����B���̂��Ƃ͗��H���Ƃ��ď\��\�Z���ɑ�ɕ{�ɓ��������悤������A�Ӑ^��s�͖V�ÏH�ڂɓ��`���Ă���Z���قǂő�ɕ{�ɓ��������ƂɂȂ�B
�@ ��ɕ{����́A�����Âɏo�čĂёD�ɏ��A�C�H���˓��C���ē�g�Âɒ����A������N�̓l���ɕ��鋞�ɓ������Ƃ������Ƃ�����A��ɕ{�ɒ����Ă���ޗǂ܂ňꌎ�]�̍s���ł������B�̍��̗g�B���Ă��畽�鋞�ɓ��B����܂łɎO���������̊��Ԃ�v�����킯�ł���B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N3��22��
�����ƊӐ^����
�@ �Ӑ^�����鋞�ɓ��������l�N�ɂ́A���̓n���ŏ��ɏ������������V�c�͍F���V�c�ɍc�ʂ������Ė@�c�ƂȂ�A����͓V������V������Ɉڂ��Ă����B�Ӑ^�̗����N�҂�������Ă��������@�c������c�@�A�����čF���V�c��͍ō��̋V���s���Ĕނ��}������A�`�@��@�t�ʂ������B
�@�u�Ӑ^�a�A�M�m�͉������̍�����͂���C��n��A�ꖽ�𓊂���o��ł��̍��ɗ��Ă��������܂����B����͎������˂��ːS�������Ă����Ƃ���ŁA���̋��̓��̑傫�Ȋ�тƐ[�����炬�͉����ɂ����Ƃ��悤������܂���B���͂��̓��厛����������̂ɏ\�N���̍Ό���v���܂����B�܂����̌�����i�߂邩�����A���厛�ɉ��d��݂��A���m�̏C�߂�ׂ��^�̉����������̏��m�ɓ`�����邱�Ƃ��ł��Ȃ����̂��Ƃ��l���Ă��܂����B���邻�̋����v����Y��邱�ƂȂ������d�ˁA�������č����Ɏ������悤�Ȃ킯�Ȃ̂ł��B�K���A���ɕ��тȂ������Ƃ��Ēm����M�m�̗������������A������`�����đՂ��邱�ƂɂȂ�܂����B����͎����`���̑�C�����ׂċM�m�ɈςˁA��������i��ŕ����̉����������낤�Ɛ[���S�ɐ����Ɏ���܂����v
�@ ����꒲�ɂȂ����Ă��܂��ƂȂ�Ƃ��y�������ɂȂ��Ă��܂����A�Ƃ�����������Ȏ�|�̏فi�݂��Ƃ̂�j���������Ӑ^�́A����҂������ē`�@�̎t�Ƃ��Ă̑�C�ɂ����ƂɂȂ����̂ł���B�����āA�V�c�A�c�@�A�c���q�ɂ͂��܂�A���m�ɂ�����܂ł̑����̕��k�����厛�啧�a�̑O�ɎQ�W���A���t�̊Ӑ^��莟�X�Ɖ��������������̂ł������B�����ɏq�ׂ��u���q�@���������v�̓�傻�̂܂܂̌��i���J��L����ꂽ�킯�ł���B
�@ ���N�̎��܌ܔN�ɂ͓��厛���d�@���݂����A�Ӑ^�͂��̍����ɂ��₩�邱�Ƃ�����č�������o�d����C�s�m�ɉ�����`�����邩�����A���܂ł�����w���w���͂��߂Ƃ��鏔�Z�p�⏔�m�����L�������������ƌ����Ă���B�ڂ������Ȃ��Ȃ��Ă������߁A�e��̖Ȃǂ͚k�o��G���ł��̐^������f���A�������قƂ�nj�邱�Ƃ��Ȃ������Ƃ����̂�����A���̈ٔ\����⋰��ׂ����̂ł������Ƃ����ق��Ȃ��B
�@ ���ܘZ�N�ɊӐ^�͑�m�s�ɔC�����邪�A���̓�N��̎��ܔ��N�ɂ͑�m�s�̊��ʂ������A��a��̑������������ꂽ�B�����āA���̗��N�ɂ͐V�c���e���̋�����ʂɊ�i����A���̒n�ɓ�������A���Ȃ킿���݂̓����̌����ƂȂ������@���@���n�����ꂽ�B�܂��A����{�̉��C���s��ꂽ���Z�Z�N�i�V����F�l�N�j�ɂ́A���̓����W�a�������@�Ɉڒz����A���������̍u���Ƃ��ėp������悤�ɂȂ����B�Ӑ^�̂��Ƃɂ͂��̒m�������č����̒ÁX�Y�X����C�w�m�������W�܂�A�݂��ɐ����������Ȃ���������͂��߂Ƃ��鏔�w�̏C���ɓw�߂��Ƃ����B
�@ �C�w�̂��ߑ����̋A�ˎ҂��Ӑ^�̂��ƂɎQ�W���Ă������Ƃ͂킩�邪�A���̍u�����i�͂��������ǂ̂悤�Ȃ��̂ł������̂��낤�B���l�I�Ȕ\�͂����Ӑ^�ł������Ƃ��Ă��A�n�������N��̑��̏��琄������Ɠ��{��̉�b�͂ł��Ȃ������ƍl����̂����R���낤�B�������A�����̋��{�l�̓ǂݏ����͒�����i�����j�łȂ���Ă�������A�lj���L�q�ɂ��Ă͖��͂Ȃ��������̂Ǝv����B�������A�Ӑ^�����q���钆����̍u�`���đ����ɂ���𗝉�������A������ōu�`���e�ɂ��Ă̎��^���������肷��ƂȂ�Ƙb�͕ʂ��������Ƃ��낤�B�����Ɠ��{�Ƃ̊Ԃł́A����̌��t�͌����ɋy���A�����̓ǂݕ����̂��̂����łɑ傫���قȂ��Ă����͂��ł���B
�@ �����g�c�̈���Ƃ��ēn���̌o���̂���ꕔ�̑m�������Ȃ璼�ڂɒ�����ŊӐ^�ƑΘb���邱�Ƃ��ł������낤���A�w�m�����̊F��������̉�b�Ɋ��\�������Ƃ͎v���Ȃ��B�u�֎q�ɍ���Ӑ^�̍u���Ɏ����X���鑭�m�����v�ȂǂƂ��������̂����Ð}�Ȃǂ߂Ă���ƁA�����������ɑ����������C���ɂ��Ȃ��Ă���B�����炭�͒ʎ��i�ʖ�j���̍u�`�������Ȃ��Ă����̂��낤�B
�@ �����̓��A�W�A�ɂ����ẮA������͍��ۋ��ʌ�Ƃ��Č���̉p��ȏ�ɏd�v������Ă����͂�������A�㗬�m���K���̊Ԃł́A������́u�ǂݏ����v���u��b�v�����ېl�̋��{�Ƃ��ĕs���Ȃ��̂��ƍl�����Ă������Ƃ��낤�B�����������璆�����b�m�݂����Ȃ��̂��������̂�������Ȃ��B�����A���Ƃ������������Ƃ��Ă��A�����̉p��b�m�̔ɉh�Ԃ�ɂ͒����������낤����A������̉�b�̂ł���҂������������Ƃ͂����Ă��A�C�w�҂̒N�����������b�ɒʂ��Ă����Ƃ͎v���Ȃ��B
�@ ����Ȃ獕�┒���g���Ă����Ȃ���u�`���e�̔��Ȃǂ͂ǂ��������ɂȂ���Ă����̂��낤�B���┒�ɑւ�铹��������݂��Ă����̂��낤���B����ɂ܂��A�a���Ȃǂ͑�ςȋM�d�i���������̎���A��u�m�p�̃e�L�X�g��u�`�^�p�m�[�g�Ȃǂ͂ǂ����Ă����̂��낤�B�����Ȏ������ʂɎx������Ă����̂��낤���A����Ƃ����z���؊Ȃ�|�Ȃ̂悤�Ȃ��̂��p�����Ă����̂��낤���B���l�I�ȋL���͂̎����傾����������u�̗L���i�҂������Ƃ��v���Ȃ�����A�Ȃ�炩�̕��@���u�����Ă͂����̂��낤�B���̂�����̎���ɂ��Ă͂��̓��̐��Ƃɋ�������Ă݂邵���Ȃ��B
�@
�@ ���O�ꂽ�C�͂Ƒ̗͂��ւ������l���N��I�Ȑ��������͉B�����Ƃ��ł��Ȃ������B���Z�O�N�ɓ���ƁA���x������߂��Ӑ^�̌��N��Ԃ��傫���X���A���̗]�����Ȃ肪��������悤�ɂȂ��Ă����B�E����͂��߂Ƃ���Ӑ^�̒�q�����͎t�̓��ł��߂����Ƃ����A�����ɂ��̍��M�Ȏp��������ɋ߂��������ɂ����Ƃ�A�㐢�ɓ`���c�����Ƃ��l�����B���܂ł������̊J�R��e���Ɉ��u����Ă���Ӑ^���͂��̎��ɑ���ꂽ���̂ł���Ƃ����B���̔N�̌܌��Z���A�Ӑ^�͌����卿�i�������ӂ��j���Ď��₵���Ɠ`�����Ă���B���N���\�Z�A�n�����ʂ����Ă���\�N��̂��Ƃł������B���݂����̓����͓����̂܂܂Ŏc����Ă���Ƃ����铂�������́A�Ӑ^�����E�������N�Ɍ������ꂽ���̂ł���B
�@ �������N�ɑ�\�l���̌����g�Ƃ��Ē����ɓn�����������ѐl�i�������̂��܂��݂��j�́A�Ӑ^�a��̓���𓂂̒���ɑt�サ���Ɠ`�����Ă���B�܂��A���ꂩ���N��̎�����N�ɂ́A�^�l���J�i�W�C�O�D�j�ɂ���āA�����ɂ܂œ`���u���Ӑ^�ߊC��t�����`�v��������Ă���B
�@
�@ �Ӑ^�L�O�ق̒��ɂ���Ӑ^���̕��������������炽�߂Ĕq�ς��I�������́A�Ԃɖ߂�Ɛ^���̗z���𗁂тĐ��Â��ɋP���H�ډY�����Ƃɂ����B�ω��ɕx�v�u�Y�A���Y�̔��������i���E��ɖ]�݂Ȃ���쉺���A���j���������قƖV�Ò�����̂��邠����ɂ���ƁA�ቺ�ɖV�Y�̒��]���J���Ă����B�����̂ق��ɖڂ����ƁA�s���������̊₪�Λ�����悤�Ȃ������ŊC���ɂ����藧���Ă���̂��������B�o���ƌĂ�邻����̊�͂���߂ē����I�Ȍ`�����Ă���A��Ƃ��̎��ӂ̌i�ς͓����ɔ[�߂�ꂽ���R�@�Ή攌�̏�lj�u���߁v�̃��f���ɂ��Ȃ����B���O�A���R�攌�́A�Ӑ^�����߂ĖV�Â̒n�̂Ɠ������߂ɓ��n��K��A�C�̍r�����Ȃǂ�I��ł͓�����lj�̊�b�f�b�T����X�P�b�`�ɗ��ł���ꂽ�Ƃ����B
�@ �Ӑ^�䂩��̂��̖V�Î��ӂɂ́A�]�ˎ��㖖���܂ň��@���͂��߂Ƃ��閼����Ù������Ȃ�̐����݂��Ă����B�������Ȃ���A�������N�O���\�����ɐ_�_�����ǂ���o���ꂽ�_�����R�߂��_�@�Ƃ����p���ʎ߉^���̂��߁A�����͖��S�Ȃ܂łɔj�s�����ꂽ�B�吭��҂ɑ����������Â̍��߂̂��ƁA�Ր���v�̐����`�Ԃ�����Ƃ��鎞���̖\�����䂫�N�����������s�ŁA���܂ƂȂ��Ă͂����c�O�̈��ɐs����B
�@ �������Â̗��O���f�����B�ƂƂ��ɖ������{�����̉������Ƃ����F���˂ł́A���Ôˎ厩�炪���悵�ēO��I�ɔp���ʎ߂������Ȃ����B������N�\�ꌎ�ɂ͑嗳���A�s�f���@�A����Ƃ������˓��̌Ù����p����A�Ō�܂Ŏc���Ă��������@�A���@�A���M�@�A���A�����ĖV�Â̈��@�����ɔp���ƂȂ�A������\�l���������āA�F���˓��ɂ͈ꎛ�@���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����ƌ����Ă���B�p���ɂƂ��Ȃ������̕������j��ċp���ꂽ���Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B�V�Â̊C�݉����̏ꏊ�ɂȂ�Ƃ�����Ȏp�ɕς��ʂĂ���̂̐m�����������Ă��邪�A���������Ă̔p���ʎ߉^���̖��c�Ȃ̂��낤�B
�@ ������N�ɂȂ��ĐM���̎��R���ۏ����Ƃ��ُ̈�ȏ�Ԃ͒��ÂɌ������A���@���Č�����Ă����̂����A�����ɂȂ�������̈ꎞ���͕����ɂ����Đ_���ɂ�鑒�Ղ��s���悤�ɒʒB���o�����L�l�������B�F���˂Ŕp���ʎ߂��O�ꂳ�ꂽ�̂́A�����v�z��̗��R�̂ق��ɁA�召���킹��]���ɂ̂ڂ鎛�@��p���đm�����ґ�������Ώ\���ɋ߂��R��Ƒ����̕�����P�o�ł��邤���A�����퐻���ɂ��Ă�Ə\�]�������̌o���ߖ�ł���Ƃ����A��펞�ɔ�����v�Z�Ȃǂ����������炾�Ƃ����B
�@ �p���ʎ߂̖��߂ɔ����铮�������Ȃ��������R�Ƃ��ẮA�F���˂ɂ�����m���̒n�ʂ����˂̂���Ɋr�ׂĂ����ƒႭ�A�m�ЂD����邱�Ƃɂ��܂��R���Ȃ��������ƁA�\�����͕����e�@�h�ɑ����Ă������O�̑�����������͋��̈���@�i��y�^�@�j��M���Ă������ƂȂǂ���������Ƃ����B�܂��A�F���˂̑m���͓��ʂȏꍇ���̂����Ďm���o�g�҂Ɍ����Ă����̂ŁA�ґ��҂ɂ͍ȑт������Ĉ�Ƃ��\�������A���Ƃ̎m���Ђɖ߂��Ȃǂ̕��u����ꂽ�̂��A�p���ʎ߂��}���ɐi���R�ł������炵���B
�@ �V�̖��ւƑ���������n�`�̍����t�߂ɂ���V�̊X���݂����Ƃɂ��A���ƂŒm���閍��s���ʂւƌ����Ă��炭����ƁA�Ԃ͎��擻�ɍ������������B��������ɓ쑤�̓W�]���J���A����C��͂邩�ɁA���v���̂��̂Ǝv��������I�ȓ��e�����������ނ悤�ɕ�����Ō������B�ቺ�̊C�݂Ƃ��̓��e�Ƃ̊Ԃɉ������̂́A�V�ÏH�ړ����̒��O�ɊӐ^��̏��D��̗t�̂��Ƃ��|�M�����C�ł���B���̓��̂悤�ɕ����Ȃ��C�����₩���ƁA�����̉�����Ƃ��̂��̎p�ȂǂƂĂ��z���ł��Ȃ����A���Ƃ��ƊC�Ƃ������͎̂��߂Ǝc�E���Ƃ����킹���Ñ�̐_�X���̂܂܂̒��z�I�ȑ��݂Ȃ̂��B���̎�����A�l�ԂƂ������̂́A���鎞�͂��̌b�݂ɗ����A�܂����鎞�ɂ͂��̎c�����ɑς��Ȃ��琶���Ă����B
�@ �ˑR�A�O���E��ɁA�C�ɓ˂��o�邩�̂悤���ނ����������R�e�������яオ�����B�F��������[�̖��R�J���x�ł���B�F���x�m�̖��ɒp���Ȃ����̏G��ȎR�e�͂����Ă��f���炵���B���̎R���܂��A�×��A�q�C�̖ڈ�ƂȂ��đ����̑D�l���������������ۂ��ŁA�͐s���ĊC���ɉʂĎr�ƂȂ��čr��ɑł����閳���̐l�Ԃ������߂Ă����B����E��햖���ɂ́A�������̎Ⴂ������̊C�ւƏ����Ă����̂����߂Ă������B�k��������\�L���قǂ̂Ƃ���ɂ������m���̊�n���ї����A����̊C�ւƕs�A�̗����������Ă������Ⴋ���U�����������A�J���x�͂��������ǂ�Ȋ፷���Ō������Ă����̂��낤�B���̗��j�̏،��҂́A�R�j�[�f�^�ΎR���L�̗D���Ȏp�ŖK��闷�l�𖣗����Ȃ�����A�������ȂɌ�������Ŏ��炪�ڂɂ����ߋ��̑z���o���������Č�낤�Ƃ͂��Ȃ��B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N3��29��
�Y�Ȗ��k�w�����C�P������x
�@�@�@�@�@�@�@�@�\�\�ƌ̓��̏�ʁ\�\�@
����F�ɓ��̏C�P������A�I�V���C�E�u�ƌi�Ƃ����j�̓��v
���o��l����
�j��F�ɓ����Q���̒��N�j�i�S�~���C�^�[���̎g���̂ă��C�^�[�j
�j��F���C�^�[�̓��s�ҁi�H��v���_�N�V�����E�v���f���[�T�[�j
���B�F���N�������A���l�i����N��l�A�\�̖җ�I�o�T�������j
�V�l�F���������̓��s�҂炵�����\�ΑO��̍D�X�ꕗ�̒j
�@ �₦���݂̌������t���̖�x�������B���V�ɂ͖����܂ł��Ɠ�A�O���Ǝv���閾�邢�����P���Ă���B�����ɃL���L���Ɖf����j��̐�ʂ��������B�S�̉��ɂ����ƕ��������Ă���悤�Ȃ����炬�̉����A��������Â܂���������̋�C���������ɐk�킹�Ă���B
�@ ���䒆���A�j��̐�ʂ̒����ɍr�ڂ̓��_�Ɉ͂܂ꂽ�I�V���C�u�ƌ̓��v��������B�������߂����C���A���ܐ���������₽�����ɏ���Đ쉺�̕��ւƗ��ꋎ���čs���B
�@ �����肩��A�W�[���Y�Ɍ���̃Z�[�^�Ƃ������t�ȏo�ŗ����̓�l�̒j���^�I������ɓo��B������̕�������邪�܂܂Ɋy���݁A���ԂȂǂ܂�ŋC�ɂ���l�q���Ȃ��ނ�̎p�ɂ́A���˂Ă�����Q�̗��Ɋ���e����ł���҂ɓ��L�̐g�y������������B
�j��F�N���͂����ĂȂ���A�����[�A�T�C�R�|�I�c�c���������Ȃ����炢����B
�j��F����Ŕ��l���͂����Ă���h���s�V�������܂���ǁA�������ґ��܂��H
�j��F�ł����A��Έꂩ�Ȃ�������A�������߂����ē�l�Ō������Ȃ���Ȃ��B�@�@
�i��Δ��ň��|������Ȃ������낵�����Ԃ̗\���ȂǁA��l�ɂ͂܂����炳��Ȃ��j
�j��F�����H�c�c�s�X�g���łł����A����Ƃ��A���S�C�ł����H
�j��F���������A���ȃC���[�W�ĂыN���������o���Ȃ�A����Ȃ��Ȃ�I
�j��F�������������E�T�M����I
�j��F����Ȃ炨�܂��ƃJ�P����ׂ��Ă��H�c�c���܂���J�P�����قǂ̌��C���Ȃ����ˁB
�j��F�u�������̎����͂ǂ������́H�v�A�Ȃ�Ă��Ƃɂ͂��݂��Ȃ肽���Ȃ�����ł��ˁI
�@ �ƌ̓��̒��ɂ���A�������ތ�����̒��ňߗނ�E���̂āi�A�̐��F�������j�͗l�ɂȂ�Ȃ��j�A�����߂��̓��_�̏�ɖ�����Ɋ|����ƁA���X�Ɠ���X�����③��̓��D�ɔ�э��ށB�T�[�b�ƍL���������䂪�������z���Ė��P���A���D�̊O�ւƈ��o�Ă����B����ɍ��킹�邩�̂悤�ɁA�����炬�̉����ЂƂ��퍂�܂�B
�@�@
�j��F�i�������肢���C���ɂȂ������ƁA�u�ƌ̓��v�̗R�����L�������������̂ɋC�Â��A������𗊂�ɂ��̈ꕶ��ǂݎn�߂�j
�@ �ȂɂȂɁc�c��������̂��ƁA�O�@��t�͌j��̗₽�����ŕa�̘V���̐g�̂���N�̎p�������ɂȂ��ĐS��������A��ɂ��ꂽ�@��̓ƌŊ���������A���̖@�͂������ĔO����ꂽ�Ƃ���A�����܂��ɂ��Ă������炱��Ɖ��N�������c�c�����A�ӂ��[��I
�j��F�������O�@��t�l���Z����������˂��I�c�c���̌�ʂ̕s�ւȎ���ɓ��{�̃A�`���R�`���ɏo�v���āA�������萅����������������a�C��������B�O�@�l����l���炢�͂���͂��ƌ����ɂ͂܂ɂ�������낤�ˁB�O�@�l���Ȃ��Ȃ��̃r�W�l�X�}���������낤�ȁB�܂��A�ł��A����Ȃ��Ƃ͂ǂ��ł��������c�c�B���������ō��Ȃ猾�����ƂȂ���B�������A���̘I�V���C�A�������͑��Ƃ��Ă邩��ˁB
�j��F��q���Ȃ��A�m���̓����𗘗p���đS���𗷂��Ȃ���A����␅�̗N�������ȂƂ���A���邢�͂��łɗN���Ă���ɔ�̏ꏊ�ɖڂ�t���Ă����āA�Ȃ�ɂ��m��Ȃ��P�ǂȖ����܂��ɍO�@�l�̖@�͂Ń��j�����j���Ƃ��Ȃ�Ƃ�����āc�c�B
�j��F�O�@�G���^�[�v���C�Y�̔��W�Ɛ��͊g�����͂������낤�ˁB
�j��F����ɂ��Ă��A�`����t�l�����Ă����̂͂Ȃ����قƂ�Ǖ����܂���ˁB
�j��F�E�[�[���A���������������Ȃ��[�A�u�f���M���E�v���ቷ�f�����炩�ȁH
�@ ���炭���ق������B�g��[�����ɒ��ߖ������肽�\��̓�l�B�����͂܂��܂��Ⴆ�킽��A�Ȃɂ�猶�z�I�ȕ��͋C����Y���͂��߂�B��������Ɖ��J�̔ߗ������z���Â���悤�Ȍ��ƉA�Ɛ����̕s�v�c�Ȍ����������B
�j��F�O�@�l�Ƃ��������́A���Q�̗��ɐg��������̂����ɁA���������������������Ă�낤�Ƃ͍l���Ă������������ł����ˁH�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�j��F�������������𗬘Q�Ȃ����Ă�����A�����ɍ��������邾���Ŏ肢���ς�����Ȃ������Ȃ��H
�j��F���̍ہA����͂����܂���A�����ڂ�ł������I�c�c�O�@�l�b�I
�j��F���炱��A�����͐ԍ��Z�{����Ȃ����A�_���ȓƌ̓������I�c�c�܁A�͂����Ă�l�Ԃ̂ق��͂���܂��_������Ȃ����ǂȂ��c�c�B�@
�i��u�A��l�̏����A�����āA��ċz���������Ɓj�@�@
�j��F�Ƃ���ŁA���ӂ��ꂩ��ǂ����܂��H
�j��F�ǂ����悤���H�@�܂��A�����ł���������ƃ{�[�b�Ƃ��Ă���A�����l�Ƒ��k���Ă��ꂩ��܂��A�Ԃ��������B�������͖\�����D�ނق��́u�D�\��t�l�v���Ă킯��ˁI
�j��F�R�E�{�E���^�]�̌����Ă��Ƃ�����܂���B
�j��F����Ƃ��Ⴛ��Ƃ��ŁA�V���̉���ɂ͂���邩�炢�����B
�j��F��������A�V���悢�Ƃ���x�͂����ŁA���͂��܂����l�[�`�����͔��l���c�c�Ȃ�ĉ̂��̑�q�b�g�������Ƃ�����܂��������˂��B
�@ ��l�͓��D�̊O���ɋ߂�����ȂƂ���ɁA�ɂ��ċ����ɉ������A�V��̌������Ȃ���A�����C���ŗy���ȑz���ɒ^����B�������ق������B���ɔ�߂������l�̂��ƂȂǂɂ��ꂼ��炢��y���Ă��镗��B�����炬�̉��������ɂ₩�Ȏ��̐i�s������������B�Ⴆ�킽��������ɕ����ԓ�l�̒j�̗��́i�A�̐��F�������A���̖����Ȍ��i���f��������ɂ͂��Ȃ�̉��o�Z�p���K�v���Ƃ��v����j�B
�\�\�Ó]�\�\
�@ �˔@�A���䉺�肩��A���ق̗��߂ƉH�D���܂Ƃ�����Q�̒��N����������A�b�����������ɋ߂����ѐ��������Ȃ���A���ʂ̎��������炩�ɓƌ̓��̓�����ւƂȂ��ꍞ�ށB
����F���������[�A���������I�c�c�͂���[���A�͂₭�I
����F����[�A�j�̐l����l�͂����Ă�݂��������[���I�A�ǁ[����[���H
���O�F��������Ȃ��́A���傤�ǁA�U�f����̂ɁI�i�ꓯ�A�M���n�n�n�n�n�n�Ƃ������܂����������Ăď��j�@�@
�@ �������薲���S�n�ɂЂ����Ă�����l�̒j�́A�������N�������̂����炸������R�Ƃ��邪�A�����Ȃ�ʎ��ԂɋC�Â��ƁA�����남�낵�Ȃ���A�Q�Ăӂ��߂��ċN���オ��A�ł��h��̑̐����Ƃ�Ȃ��瓒�D�̒��ɐ[�X�Ɛg�߂�B
�j��F�i�����Łj�@�R�R�b�A�R�E�{�E�l�̃^�^������A�����I
�j��F�i�����������Łj�@�h�h�b�A�h�E���܂��H
�j��F�i���˂ẴN�[�������ǂ��ւ��j�فA�ق�Ƃ��ɂ͂����Ă��邫����I
�j��F�i�킪����^�����̂��Ƃ��j���ꂶ��A�o�悤�ɂ��o��Ȃ��A�^�X�P�e�N���[�I
�@�@�@�@
�@ �������邤���ɂ��A���B�͊F�ŃM���[�M���[�����Ȃ���ߗނ�E�����āA�����t�߂̓��_�Ɋ|����B���l���̏��́A�킴�ƂƂ����v���Ȃ���肩���ŁA�j�B�̒E�߂̏�Ɏ��������̒E�������߂�p���c�A�u���W���[�Ȃǂ��|����B�j�B�͂Ȃ����ׂ��Ȃ��A���D�̒����牡�ڂō��߂������ɂ��̗l�q�߂�B
�@ �E�߂��I�������B�́A��̂���ɍ��肽�����������̓�l�̒j��}�����̔@���ɂ������̂������ȋ���䂷��A���f�I���[�h�Ƃ͂܂�Ŗ����̋���ׂ����݊����֎����Ȃ��玟�X�ɓ��D�ɔ���B�@�@
���l�F�͂�����[���A�I�j�C�T�������I�@
���܁F����Ȃɓ����Ȃ��Ă�������Ȃ��A�܂����A�h�[�e�C����Ȃ���ł���H
���B�F�M���n�b�n�n�n
�@ ����ɂ͓������A�j��l�͓��D�̋��̕��ւƂ��肶��Ɛg�������B���܂��܁A���������̗N�����߂����������߁A�M��������l�̔w�����A�v�킸�A�A�`�`�`�Ɗ��c�߂Ȃ�����A�K���ɂ�������炦��B���̊Ԃɑ��v���l�̏��B�͓��D�̑唼���̂��Ă��܂��B���悢�拇�n�ɒǂ����܂���l�B���B�͂킪���̊�œ��D�̒����܂��n�߂�B
�j��F�i�j��̎����Łj�����A�I�o�^���A���̋t�P���I�A�ǂ���ē���悤�H
�j��F�i�����Ԃ��悤�Ɂj���Γ�A�������A����킢�j��l�ɑ��āA�G�͂܂�ŋ����m��ʍ���������c�c�B
�j��F���̂܂�܂���A䥂Ń_�R�ɂȂ��Ⴄ��A�Ȃ������̂ق����{�[�b�Ƃ��Ă�����������c�c�B
�@
�@�i����Ȓj�B��l�̗l�q�����Ȃ���j
����F�������A����Ȃɋ��ɂ����Ȃ��ł������ɂ�������Ⴂ��I
���Z�F�H�ׂ͂��Ȃ�����A���v��I
���O�F�H�ׂĂ�������Ă������ق����A������Ȃ��́H
���B�F�M���n�n�n�n�n�n
�����F�ł��A�������A�悭����Ɠ�l�Ƃ��C�C�j����Ȃ��I
�@�i�A�̐��F���̈ꌾ�́A�j�B�ɂƂ��Ĉ����̂悤�ȏo�����̒��ł̂��߂Ă��̋~���ł͂�������������Ȃ��B���̖ҏ��̌��s�l������������ꂳ�����Ȃ��悤�ł́A�ނ�͂��͂����C�͂������A��]�̉ʂĂɁA�j��̕��\�\����Ȃ��̂�����̂��ǂ��������肩�ł͂Ȃ��������\�\�ɐg�𓊂��A���̈ꖋ�̌�������������̂ɂȂ��Ă����ł��낤�j
�����F�ǂ�ǂ�A�����Ƌ߂��Ō��Ă����悤���B
���܁F���A�ǂ�����C�Ȃ́H
���B�F�M���b�n�b�n�b�n
�@ �Ԃ����t���Ȃ��g���ł����Ė����̂܂܂̒j�B�B�M�������̂����������Ă����N���N�����Ă��ĉ䖝�����E�ɋ߂��Ȃ�B�v�l�\�͂���������ቺ���A���˂Ă̓Ő�Ԃ�Ȃǂ݂邩�����Ȃ��B��u�A����ȓ�l�̔]�����A�������l���̃I�I�o�o�^���A����ɌnjR�������鏬����̈̑�Ȏp���悬��B
���l�F����ł����b�̎킪�ł�����A�C�C�j�B�ƈꏏ�ɕ��C�ɂ͂������āI
���܁F�ł��A�܂��A�炵�����ĂȂ����ˁ[
���B�F��������ˁ[���A�n�n�n�n�n
�j��F�i�c���ꂽ�C�͂��Ȃ�Ƃ��ӂ肵�ڂ�A�Ȃ�Ƃ����H�������������Ɓj�����Ă����Ă��������Ǎ����ł���B
���Z�F���Γ�̕��X�����Ȃ當��Ȃ���Ȃ��H
�j��F�ʂ��������Ă��Ƃ�����܂�����ˁB�i���������Ȃ���A�����Ƃ������ɂ��Ȃ��āA�ߗނ̂���Ƃ��떘�̋�����ڑ�����j
����F�i�j��̂��鑤����O�[�b�Ƌ߂Â��Ă��āA�j��̋�Ɏ��G���悤�ɂ��āj�˂��A�������A���Ӊ����ɔ��܂��Ă�́H
�j��F�i�H��v���_�N�V�����̃v���f���[�T�[�Ƃ��ĎႢ���D��ɂ��ꂱ��̂����ɒ��������Ă��邢���̐}�X�����͂ǂ��ւ��A�����������ꋯ���j�����A���̂ւ�ɂ͔��܂�܂����I�c�c���A����������܂�����I
����F������������āA�݂�ȁA�܊p�������[�����Ƃ��Ȃ�I
���B�F�M���n�n�n�n�n�i���̏����͂����炬�̉������������������j�@
�@ ���������āA�j��l�͂܂��������Ƃ�Ȃ��Ȃ���A�ق�Ƃ��Ƀm�{�Z�Ă��āA῝�����������͂��߂�B����͂����A���悢��J�����邵���Ȃ��Ɗo������߂��������傤�ǂ��̂Ƃ��A���܂�q��p�̉H�D�Ɨ��߂�g�ɒ������V��̒j�������B
�V�l�F�ȂA�ȂA�����������A�݂�Ȃ͂����Ă�̂��I
�����F�p�S�_���x��Ă�����A�Ȃ�ɂ��Ȃ�Ȃ�����Ȃ��́I
�V�l�F����܁A���m��ʒj�̐l�ƈꏏ�ɂ͂����Ă�̂��I�A����������[������I
�@
�@ �j�͂��������āA�ߕ��𒅂��܂ܓ��D�ɋ߂Â��A���D�̘e�̊�̏�ɂ킴�Ɣw���������č������낵�A���_�����Ɍj��̐�ʂ����߂�ӂ������B
�j��F�i�S�̒��Łj��k����Ȃ���c�c�p�S�_���~�����̂͂���������I
�j��F�i�S�̒��Łj�p�S�_�ł��Ȃ�ł���������A�������Ƃ����Ă���[���A�łȂ��Ƃ����m�{�Z�Ď��ʂ�[�b�I
���O�F�I�W�T���A����ȂƂ��ō��|���ĂȂ��ňꏏ�ɂ͂����Ă���Ȃ���A�p�S�_�ɂ͂Ȃ�Ȃ�����Ȃ��́B
���l�F�I�W�T���̗p�S�_�͂����U��܂킵�Ă��N���p�S���Ȃ����畽�C��I
�i�A�̐��F�����������Ƃ�������\�킸�吺�ŋ��Ԃ���A�I�o�T���R�c�͋��낵���j
�@ ���B�ɍĎO������Ă悤�₭�ӂ��������V�l�́A�ߕ���E���ł��Ƃ��p���������ɓ��D�̒��ɂ͂����Ă���B�����āA���B�Ɠ�l�̒j�B�̊ԂɊ����Ă͂���B
�V�l�F�ق�A���������A���������ɂ���ƁA���̐l�B�����Ă邶��Ȃ��́c�c�B
���܁F�I�W�T���A���������A���^�ǂ����̗p�S�_�Ȃ́H�@�@
���B�F�M���n�n�n�n
�j��F�i�V�l�Ɍ������ĒQ�肷�邩�̂悤�Ɂj���́A�������̖l�����̕��̏�ɏ�������Ă���ߗނ�����Ɠ������Ă��炦�܂��A����������o������ŁB
�V�l�F�i���B�Ɍ������āj�܂��Ȃ�Ă��Ƃ�����Ă�̂�A�������I�i���������Ȃ���A�V�N�̒j�͓��D����o��ƁA���B�̈ߗނ̈ꕔ�����A�Ăѓ��D�ɂ���B���B�͂��̗l�q���݂āA�܂��A�Q���Q�����B�j
�@�@�@�@
�@ ���������x�ƌ������l�̒j�́A��ċz�̌�Ɏ������킹�ē��D�����яo�����A��������̂ڂ��đ������ӂ���B����ł��A�K���ɂȂ��Ĉߕ��̊|�����Ă��铧�_�ɒH����A���@�����Ƃ܂��Ȃ��A�A���_�[�E�E�F�A�[�𒅂�B���S�ɓ��������Ԃ̓�l�B�w��Ŗҗ�Ȕl���Ƃ������܂����������N���N����B�W�[���Y���Q�ĂĂ͂����Ƃ��ĕЕ��ɗ�����˂����݂����ɂȂ�A�o�����X������Ă�낯��p�����Ă܂��������Ɩ쎟�̒ǂ��ł��B����ȏ��ł悤�₭�ߕ��𒅏I������l�́A���ڂ��Ȃ����ǂ�������Ȃ���A�ق��ق��̑̂ł��̏�𗧂������Ă����B
�@
�j��F���������Q�����Ȃ��A���}������������������Ȃ��I
�j��F��������I�c�c�O�@�l�����I
�@ ��ɂ͉������Ȃ��������̂悤�ɁA�捏������i�Ɩ��邭�~�̌����Ⴆ�킽���Ă���B�j��̐��ʂ́A�s�������݂Ɍ�����e���Ԃ��Ȃ���������h��߂�������B�����炬�̉��ɍ������āA�ƌ̓��̕�����A�Ȃ��A���B�̏����������ɉk�ꋿ���Ă���B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�s���t�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N4��5��
�����̏���ǔj����ɂ́H
�@�u�����̏���ǔj����v�Ƃ������t�ɏے�����Ă���悤�ɁA�������̏�����ǂ݂��Ȃ��\�͂Ƃ������̂́A�̂��炽���ւ�d�v�Ȃ��Ƃ��ƍl�����Ă����B�����A���Ƃ��Ƃ��������Ǐ��\�͂��������킹�Ă��Ȃ����Ȃǂ́A�{��ǂނ��Ǝ��̂͌����łȂ������ɂ�������炸�A����̖{��ǔj����̂ɂ���������A�b�������Ƃ����Ȃ��Ȃ��B�����̓Ǐ��͂̂Ȃ�����X�v���m�炳��Ă������́A����Ƃ��A���ʂ̔\�͂̐l�Ԃ��ő���ɓw�͂����Ƃ��āA�����̏���ǔj����̂ɂ��������ǂꂭ�炢�̔N������������̂��낤�ȂǂƂ������ɂ����ʂ��Ƃ�^���ɍl���Ă݂��B
�@ ���������S���w�I�ɂ݂�ƁA����Ȏv���Ɏ�����邱�Ǝ��̂����Ȃ̂�������Ȃ��B�����̋`�����ɑ�����A�Ȃ̔\�͂����ʂ̓Ǐ��ɒ������Ƃ��錩�h����̕\�w�ӎ��ɑ��A�����D��̐��݈ӎ����A�u�������������ɖ����Ȃ��Ƃ͂�߂Ă���A�����łȂ��ƁA����łȂ��Ă��S���Ȃ��]�_�o�̉�H���I�[�o�[�q�[�g���Ă��܂��v�Ƃ����Öق̌x�����Ă��邹�����Ɖ��߂ł��Ȃ����Ȃ����炾�B
�@ ���āA�����̏��̓ǔj�ɗv���鎞�Ԃ̂��Ƃ����A���܂���ɁA�y�j�Ɠ��j�����������A������{��ǂ�ł������̂Ƃ��Ă݂悤�B�����������Ă͖{�̓��e��y�[�W���͍l���ɂ���Ȃ����̂Ƃ���B��N���\��T�Ƃ��Čv�Z����ƁA�N�ԂŖ��S�Z�\���̖{��ǂނ��ƂɂȂ�B����͕��ʂ̐l�Ԃɂ���Α����ȃy�[�X�ł��邪�A���Ƃ����̃y�[�X�Ŗ{��ǂݑ������Ƃ��Ă��A�����̏���ǔj����ɂ͎��Ɏl�\�N�̍Ό����K�v�ƂȂ�B�Ȃ�Ƃ����͂ł܂Ƃ��ɖ{���ǂ߂�悤�ɂȂ�̂��\���炢���炾�Ƃ���ƁA�����̏���ǂݏI���鍠�ɂ͌\�ɂȂ��Ă���v�Z���B
�@ �������A����{�Ȃ�Ƃ������A������Ƃ������e�̌��߂̖{�Ƃ��Ȃ�ƁA����Ɉ���ǂݏI����̂͂����B�܂��āA��E�O�y�[�W�߂����������Ŗ��C���Â��悤�Ȑ�发��m���ƂȂ�ƁA���̓��̐��Ƃł��A�T�Ɉ�E������ʓǂł���悢�ق����낤�B�����Ȃ�ƁA�ǔj�̃y�[�X������Ɨ�����B�Ǐ����d���Ƃ̈�Ƃ���w�҂╨�����A���邢�́A�Ȃ�炩�̗��R�œǏ�������邱�Ƃ̂Ȃ��l�Ȃ�Ƃ������A���ʂ̐l�̏ꍇ�́A���������������Ǐ��ɒ^���ĂȂ����Ȃ��B
�@ �����ۂ��A�w�҂╨�����̂悤�Ȑl�X�̏ꍇ�ł��A�������ɂ���Ȃ�̎��Ԃ͕K�v�����A�����{���̌�����i�߂��茴�e���M�������肷�邽�߂ɂ��c��Ȏ��Ԃ��₳����Ȃ��B���킦�āA���X�̐�发�̒��ɂ́A�ʓǂ���̂Ɉ�E����v����悤�Ȃ��̂��U���ɂ��邱�Ƃ��v���ƁA�l�\�N�ňꖜ���̏�����ǔj���邱�ƂȂnj����ɂ͕s�\���낤�B���Ƃ���{�̔��\�N�������Ă��A��ɕs�\�Ƃ͌���Ȃ����A�܂������Ď����͍���낤�B���������₩�Ȑ}���ق̏ꍇ�ł��A���ʁA��E�O�������炢�̑����͂��Ȃ��Ă���Ǝv���邪�A���U�����Ă������̖{����ǔj�ł��Ȃ��l�Ԃ̔\�͂Ȃ�āA�Ȃ�Ə����Ȃ��̂ł��낤�B
�@ �����Ƃ��A���̒��ɂ͈ꌩ�s�\�����ɂ݂��邱�Ƃɒ��ޒ��l��A�M����悤�ȑ��ǂ̒B�l����l���l�͂�����̂�����A�M�l�X�u�b�N�Ȃǂׂ���A���U�ɓǔj�����{�̐����\�����ȏ�ȂǂƂ������L�^���L�ڂ���Ă����肷�邩������Ȃ��B�܂��A�u�����̏���ǔj����v�Ƃ������t�����܂ꂽ�̂͂��̎���̂ǂ��̍��̂��Ƃ��͒m��Ȃ����A�����炭�́A�Â��o�T�ނɂ݂�悤�ɁA�����̑����������Ƃ��Ĉ����Ă��������̂̂��Ƃ��낤�B���ɂ����̊����̕����͋ߍ��̊����̂̕�����肸���Ƒ傫����������A�ꊪ�̏����Ɏ��߂�ꂽ���̗͂ʂ͌���̈���̖{�Ɏ��܂��Ă��镶�͗ʂ��͏��Ȃ������ɈႢ�Ȃ��B����Ȏ���炷��A�����̏���ǔj����̂͐̂̂ق����y�������낤���A���ꂾ�������̉\�������������Ƃ����������ł��Ȃ����Ƃ͂Ȃ��B�����A���Ƃ������ł������ɂ���A�c��Ȏ��Ԃ�v�������낤���Ƃɂ͕ς�肪���B
�@ ��������肻��Ȍv�Z�����I�������́A�����̑z���ɂЂ���Ȃ���A�����̏��ɒ��ނ��Ƃ������ς�ƒ��߁A�犪�̏��ɒ��ޒ��x�Ɏu����ύX�����B�{��ǂނƂ������Ƃ͑�Ȃ��Ƃ����A�ǂ{�̐���������悢�Ƃ������̂ł͂Ȃ��B���Ƃ��ꐶ�̂����Ɉ���̖{�����ǂ܂Ȃ��Ă��A�s�ԂɉB���ꂽ���̂����͂ݎ�����ł�������Ɠǂݍ��߂A�������瓾������̂͌v��m��Ȃ��B���̖{�ɐS���犴�����A��������w���̂���ɑz���͂��L���A�v����[�߂邱�Ƃ��ł���A����ŏ\���Ȃ̂��Ǝv���B�l�I�Ɍ����s�����͂����Ă��A�D�ꂽ�����Ƃ������̂́A���Ƃ��Ƃ��̂悤�ȉ��[�����߂����Ă�����̂��B
�@ ���j�̂Ȃ��Œ~�ς��ꂽ��l�̒m�b�⋳���͏d�v�����A�ЂƂ�̐l�Ԃ����̂����₩�Ȕ\�͂ŏ����ł�����ʂɂ͌��x������B���ǁA��X�́A�����ɓK�����ʂƓ��e�̏���������ǂ݁A���Ƃ́A�����̓��Ƒ̂Ő���t�̎v�l�ƍH�v��ςݏd�˂Ă��������Ȃ��B�P�Ȃ�m���Ɛl���̖{���ɐ[���ւ��b�m�Ƃ͂��Ƃ��ƈقȂ���̂ł����āA���ǂɂ���Ēm����g�ɂ��邱�Ƃ͂ł��邪�A�b�m�̂ق��͕K���������ǂɂ���ē�����Ƃ͂�����Ȃ��B���Ԃ�A�^�ɕK�v�Ȃ̂́A�b�m�������Ă�������̖{�ɏo�������Ƃ̂ق��ł���B
�@ �����A�K�v�ȂƂ��ɕK�v�Ȗ{�ɏo�������߂ɂ́A���ʂ̑�������߂��ɂ������ق����悢�Ƃ������Ƃ͂��낤�B�Ȃɂ��Ȃ����������Ă���������̖{�����܂���ɂ��A���̖{����A���̌�̐l����傫�����E����悤�Ȑ[��������������Ƃ��������Ƃ́A�N�������悭�o������Ƃ���ł���B�����āA�����������o�������N����₷�����邽�߂ɂ́A���Ƃ��S����ǔj���邱�Ƃ͂Ȃ��Ă��A������x�̍����̖{���펞�g�߂ɒu���Ă����ɂ��������Ƃ͂Ȃ��B����̖{�ɏo�������߂ɕS���̑������K�v�ŁA���ʂƂ��Ďc���\��������ʂɂȂ����Ƃ��Ă��A����͂���ō\��Ȃ��Ƃ�������B
�@ �l�ԂƂ������͖̂��Ȃ�����̂ŁA���ӂ���A���̖{�͗Ǐ�������Ɗ��߂��Ă��A�����ɂ͂����ǂދC�ɂȂ�Ȃ����̂����A���Ƃ��ǂƂ��Ă��A���߂��l�Ɠ��l�̊������o����Ƃ͂�����Ȃ��B�ɒ[�ȏꍇ�ɂ́A�ǂ����Ă���Ȗ{�����߂Ă��ꂽ�̂��낤���b���������v�������������̂��B���̐l�̔N��A�E�ƁA�炿�A���݂̐����Ȃǂɂ���āA�{�ɑ���]���Ƃ������̂͑傫������Ă�����̂�����A����Ȃ��Ƃ��N����͎̂d���̂Ȃ����Ƃ��낤�B���l�̊��߂͎Q�l���x�ɂƂǂ߁A�{�Ƃ̏o�����́A��͂�A���̐l�Ȃ�̐�����ʂ��A���R�Ȃ������ɂłȂ����̂��őP�̂悤�ł���B
�@ �{�Ƃ̏o�����Ƃ����ƁA���ɂ����������z���o������B�������A���Z��N���̍��������Ǝv���A���܂��o�������������s���̉����̖�X�ŁA�薼�������悭���ʂ܂܂Ɉ���̕��ɖ{�����߂��B��������������ďq�ׂ�A�Ö{�Ɩ�������Ă����ɂ�������炸�A���̕��ɖ{���^�V�����܂܂ŁA���������̒l�i���܉~�Ƃ��������Ƃ��Ă��j�i�̈��l����������ł���B���͂��̖{�������A��A���̖{�ƈꏏ�ɂ��̂܂ܓǂ܂��ɕ����Ă������B������c���h�N���邢�̓^�e�g�N�Ƃ�����ł���B
�@ ���ꂩ��O�N�]�̍Ό�������A�����ɏo�đ�w�����ɓ�����������̂��ƁA�Ȃɂ��Ȃ��{�I�Ɏ��L���A��������Y��Ă����u���̖���ɂ��āv�Ƃ����p�앶�ɔł̂��̖{�����o�������́A�`�����𑖂�ǂ݂����r�[�ɁA�������肻�̗��ɂȂ��Ă��܂����̂������B�������ɂ��̖{��ǂݒʂ������Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B�V�W�ǓƂ̋����ɉ����āA�܂��Ⴍ�s�����������������������̂��̐g�Ƃ��̐S�����Ȃ��炸���₵�A���̌�̐l���ɂƂ��đ傫�Ȏ�����^���Ă���邱�ƂɂȂ������̖{���A���́A�S�����ËL����قǂɉ��x�����x���ǂݕԂ����B�����āA����ɁA���̕M�ҁA�T�䏟��Y�̑��̍�i��Ђ��[����ǂ������B�u�䂪���_�̕��v��u��a�Î��������v�Ȃǂ̒���������Ԃ�ƈ�ۂɎc���Ă���B
�@ ���҂̋T�䏟��Y���A���яG�Y�∢�����Y��ƕ��ԓ����̒����ȕ]�_�Ƃ̈�l�ł��邱�Ƃ�m�����̂́A���̒�����������ǂݏI�������Ƃ̂��Ƃł���B�ނ��A���̍ɂȂ�A���̖{�ɑ����肩���������Ԃ�ƈقȂ������̂ɂȂ炴��Ȃ����A���ܓǂ�Ŏ�������������{�Ƃ������ƂɂȂ�A�����Ɉ�������̂ɂȂ��Ă��܂����Ƃ��낤�B�����A����Ȃ��ƂɊւ��Ȃ��A�u���̖���ɂ��āv�Ƃ�������̕��ɖ{�����̐t�̊|�ւ��̂Ȃ��ꗢ�˂ł��������Ƃ����͊ԈႢ�Ȃ��B
�@ �w�҂╨�����Ƃ������l�X�́A�����Ă����h�Ȗ{�I�ɑ�ʂ̏��𑠂��Ă���B�����ڂɂ�����ʐl�́A���̎�̐E�Ƃ̐l�X���������펞���p���A���̂قƂ�ǂ�ǔj���Ă�����̂Ǝv�����������A�܂�����Ȃ��Ƃ͗L�蓾�Ȃ��B������Ǝw���G�炵�Ă����ƕ��Ԗ{�̏�[�����Ȃ���ƁA�z�R�����ׂ�����t�����̂����A���������d���ɕK�v�œǂޖ{�́A����⏰�ɎU�����Ă���̂����ʂł���B�Ƃ�����ƁA���h�ȏ��˂ɕ��ԑ����́A���Ζʂ̎҂�S���I�Ɉ��|�����_�I�ɗD�ʂɗ����߂́u���������x�i�v�ɂȂ��Ă��܂����˂Ȃ��B
�@ �w���ɗ���Ō������̑����ɐԐ��������Ă�������Ƃ������鋳���̘b��̎��ɂ������Ƃ����邪�A�����̗��p�̎d�����l���ꂼ��ł���B�w�҂̏�������发�Ȃǂ�ǂނƁA���p������Q�l�����Ȃ���̂����炸��Ɗ����ɗ���Ă�����̂����A�����܂Łu���p�v��u�Q�l�v�Ȃ̂ł����āA���̒���҂������̕�����S���ǂƂ����킯�ł͂Ȃ��B���ڂ̈��p�ł͂Ȃ��A�������A�Ȃ����́A���̂܂����������Ȃ�Ă������Ƃ������l������B
�@ �{�𑽓ǂ���ɂ��������Ƃ͂Ȃ�����ǂ��A�ق�Ƃ��ɏd�v�Ȃ̂́A�ǂޖ{�̗ʂł͂Ȃ��A�{�̎����̂��̂ł���A�܂��A���̖{���ǂ��ǂݎ��ǂ��������Ă������Ƃ������ƂȂ̂��낤�B�����āA���̂��߂ɐ�Ό������Ȃ��̂́A����̈ӎu�������čl����\�͂ƁA����̌��t�őz������͂ł���ƌ����Ă悢�B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N4��12��
��ɑz������
�@�@�@�@�@�@�@�i���̈�j
�@ ��̌����͐�����ł��Ĕ������B�앝�����ׂ���������ǐ��w�Ȑ��͌���������ƂȂ��ċ}�s�ȒJ�Ԃ��ꑧ�ɂ���������B���܂���Ȍ������K�˂�ƁA�v�����Y��Ă������̂��v�������n�b�Ƃ������邱�Ƃ�����B�̓��ɐ���������Ă������̋L�����������A�����āA������҂�p���������S���邩�炾�B
�@ �������Ȃ���A�C�ɋ߂�����̕��i���܂��̂ē�B���ꂽ���Ԃɔ�Ⴗ���n�̗܂��������ς��ɗn��������ł��邩��A�������ɂ��̐��͑����Ă���A���P���͂����ɂ͌����Ȃ��B����ǂ��A���̗���͂������Ƃ��Ă��āA�Ȃɂ������̐��ʁi�݂Ȃ��j�͍L���đ傫���B����Ƃ��͗[�z�ɉf���A�܂�����Ƃ��͊X�̖�����f���o�����̐��ʂ́A�S�̉��ɐ���ł�������ЂƂ̖ڂŌ��߂�ƈ������܂łɔ������B�����ɂ͂܂��A������Ȃ��A�ЂƂ̈��炬������ł���B�����āA���̌������ɂ͗I�v�̎���X�����傫�ȑ傫�ȊC�������āA�Ђ����疳���Ő�̗�����~�߂Ă���B
�@ ��{�̉͐�̂ǂ̒n�_�ɌȂ̐S�̕��i�����߂邩�́A���̐l�̔N�����ɂ���Ă��ꂼ��ɈႤ���낤�B����҂͏㗬�́A����҂͒����́A�܂�����҂͉����̕��i�������̌��݂̂������܂��ɂӂ��킵���Ǝv�����낤�B
�@ �Љ�Ƃ������̖����̎x�������삾���āA�����̃V�u�L�����Ă鐅�A�����݂��������A������������������A�Ђǂ����������A�����ׂ��ǂ��������ƁA���낢��ȐF�̐������̗���̒��ɒX���Ă���B�����A�������������������̈�H��H�ɂ͂���Ȃ�̈Ӗ��Ɩ����Ƃ������āA���ꂼ�ꂪ�m�炸�m�炸�̂����ɍ�p�������A��{�̐�̖�����������Ǝx���Ă���̂��낤�B���̑̓��ɏh�鐅�H�͂������炩�ł͂Ȃ��A������������A���łɁA��������قǂɈ��L��������H�ɕς���Ă��܂��Ă���̂�������Ȃ����A����ł��Ȃ�Ƃ��C�܂ł͗���Ă����Ă݂悤���Ǝv���Ă���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�i���̓�j
�@ �l���Ƃ������̑����ɂǂ��Ղ�Ƃ���Ȃ���A�͌��։͌��ւƉQ��������䂭�}�f�Ȃ��̐g�Ȃ̂����A����ȂǂłӂƐ�ʂ߂��肷��Ƃ��Ȃǂɂ悭�v�����Ƃ�����B�l�Ԃɂ͎O�̏ے��I�Ȑ�����������̂ł͂Ȃ����낤���Ɓc�c�B
�@ �܂���́A�ߊ삱�������̏o�����̗��݉Q���������R�ƌ����낵�Ȃ���A��̓y��̏�������Ɍ������ēƂ�فX�ƕ���ł����������ł���B�����A����͐��ɂ����āu���l�v�ƌĂ��l�݂̂̑I�Ԃ��Ƃ̂ł��铹�ŁA�������̑�ł͂��邪�A��X�}�l�ɂ͓���^���Ȃǂł������ɂȂ��B
�@ ��߂́A��ʂɏM���ׂĂ���ɏ��A����͂��܂ɐ����Ԃ��𗁂т���x�ŁA���ڂɂ͗���ɐg�߂邱�Ƃ̂Ȃ��܂܂ɁA�����̗͂���Đ�������Ă����������ł���B����́A���ۂɂ͑����Ɏp��ς��������ɂ���Ă�������Ǝx�����Ă���ɂ�������炸�A�����ڂɂ͎������̂Đ��̐l�X�̂��߂ɐs�����Ă���悤�Ɏv����l�X�A���Ȃ킿�A���X�̐^���ȏ@���Ƃ�w����̌����ҁA���̐M�������v�z�ƂȂǂ�簐i���铹�ł���B�����A���̓����}�l�ɂ͂�͂薳���ł���ƌ����Ă悢�B���܂ɁA�����ɝ��܂�ďM���]�����邱�Ƃ�����悤�����A������ƌ����āA���̌���_���s�S���҂�����ɂ���ɏ�낤�Ƃ��Ă��A�����������͂��܂��^��ł͂���Ȃ����̂��B
�@ �O�߂́A�������̂��̂ɐg��C���A���炪����̌������̂��̂ƂȂ�Ȃ���A����Ƃ��͗��݁A����Ƃ��͌������z��T���ꉺ�鐶�����ł���B�ނ��A���ꂱ������X�}�l�̐l�����̂��̂ƌ����Ă悢�B
�@ ��X��ʂ̐l�Ԃɂ͂ǂ����~���Ă�����悤�̂Ȃ����̎O���߂̐������Ȃ̂����A�����ɐg��C���邩��Ƃ����āA��ɐS�g�̉��܂ő�����ςȂ�������ςȂ����Ƃ����ƁA�K��������������ł͂Ȃ��悤�ȋC�����ĂȂ�Ȃ��B
�@ �̋�B�̕Гc�ɂɏZ��ł������Ƃ������āA��J��䕗�̌�Ȃǂɍ��X�Ɖ������ĂȂ���������Q���������L�l�����x�ƂȂ��ڂɂ������Ƃ�����̂����A����Ӗ��ł���͏�p���Ƃ��Ȃ����ɑ����Ȍ��i�ł��������B�y����������鐦�܂����G�l���M�[�ʼn͌��ɐς������S�~��H������C�ɉ��������A���ׂĂ̂��̂���|���Ă��܂����̕s�v�c�Ȕ��͂́A�c���S�ɂ͂ƂĂ������I�ɂ����v��ꂽ���̂ł���B�@
�@ ����ɂ܂��A����ȂƂ��A�������������邨����d������Ċώ@���Ă݂�ƁA���̒��ɗl�X�ȐF��`�̖����̍������܂܂�Ă������Ƃ������͂�����Ƒz���o���B�����܂ł��Ȃ������̍���������̌������̂��̂������̂����A���̈ꗱ�ꗱ�͈ӊO�Ȃقǂɉ��₩���Y��ȋP����ттĂ����B�Ȃ��ł��A�Ήp���̍����Ȃǂ́A�ǂ����Ă��ꂪ����̂��ƂɂȂ�̂��낤�Ǝ���X�������Ȃ�قǂɔ��������������肵�Ă������̂��B
�@ �ǂ�Ȃɐ삪���艘��悤�Ƃ��A����̂��Ƃł���ꗱ�ꗱ�̍����͂���ȏ�P�����������Ƃ͂Ȃ��B����Ɠ����悤�ɁA�l���Ƃ��������̒��ɐ����鏬���������Ȃ��̐g�ł����Ă��A�S�̉��̂����₩�Ȉ�p���A���邢�͍��̂ق�̕Ћ����ȐF�ɕۂ��炢�̂��Ƃ͂ł���̂ł͂Ȃ����Ƃ����C�͂��Ȃ��ł��Ȃ��B�������A�l�ԂƂ��������̈�Ђ��������ɕ����̐F�́A���������قȂ��Ă��Ă��悢�Ǝv���B���Ƃ��������͂ǂ�Ȃɉ���Ă����Ƃ��Ă��A�g�̂̂ǂ����ɏ����ȍ������ꗱ�B���Ă�����������A��J���~���Č������Q�����Ƃ��Ȃǂɂ́A���̖����̍����ƈꏏ�ɂȂ��Đ삻�̂��̗̂̏͂ƂȂ邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����낤���c�c�B
�@ �t����Ɏ����傫�Ȋ��������̐l�̉�Ô���́A�u�Ӎցi�����j�v�Ƃ������𖼏��A�u�Ӎ��M�v�Ƃ������z�W�����B���̍֍��ɁA����́u�����ɐ��܂�����l�ԁv�Ƃ��������̈Ӗ������߂��̂��낤���A�u�Ӎցv�Ƃ������������Đ[�ǂ݂���A�u����Đ��߂�v�Ɖ��߂ł��Ȃ����Ƃ��Ȃ��B�������̐��Ɂu����Đ��߂�l���v�ȂǂƂ������̂�����Ƃ���A�O�q�����悤�ȏ̂��Ƃ������̂�������Ȃ��Ǝv�����肷������ł���B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N4��19��
�[�쉲�O���̑z���o
�@ ���������̂̂��Ƃ����A�n�R�w���̎��́A�]����[�쉲�O�O���ڂ̕�����Ƃ����C���̓�K�̎l�����ɊԎ肵�ĂȂ�Ƃ����X�����̂��ł����B���������ɂ͂��Ƃ��Ɛ����ݔ��ȂǂȂ��������A����ɐ������ł����ɂ��Ă��①�ɂȂǂ��낤�͂����Ȃ���������A���H���������邱�Ƃ͌o��I�ɂ����ԓI�ɂ����X�����������B������A�����͂ǂ��ɂł�������������H���ɑ��������ʂ������̂������B
�@ �����s�����́u���v�Ƃ����ꖖ�̒�H���̐e������́A�싅�]�_�Ƃ̐��{����̕��e���ق��ӂƂ�����悤�ȁA�Ɠ��̋C�i�ƐM�O����ɔ�߂�����Ȑl���ł������B�Z�t�Ƃ��Ē��N�߂��ΐ쓇�d���d�H�Ƃ�ސE��A��コ��Ƃ��������ƘV���̋삯�����ɋ߂���ԂŐ[��Ɉڂ�A���H��̍H����J���ҁA�n�R�w������̂����₩�Ȃ��X�����̒n�ɊJ���Ă���ꂽ�炵���B�����̘b�̒��ŁA�����̐�コ������̓����̍����Ȃ���o�l�̖�킾�����Ǝf�����L�������邩��A�����Ɏ���܂ł̂���l�̊Ԃɂ́A����Ȃ�̐[������������̂��낤�B�ł�����l�Ƃ����������A�ƂĂ��K�������Ɍ������B
�@ ���鎞�A�e������̎����Ƃ��ڂ������N�̏��������X����Ă��Đ�コ��ƂȂɂ��k�����Ă����ɍs�����킹�A���肰�Ȃ����̘b�Ɏ��������Ă����Ƃ�����B���̎��A�B�R�Ƃ��āA�u���͍��Y���~�����Ă��̐l�ƈꏏ�ɕ�炵�n�߂��킯�ł͂���܂���A���Y�Ȃr�^�ꕶ������܂���B�������A�ǂ�Ȃ��Ƃ������Ă��Ō�܂Ŏ��͂��̐l�ɓY�������A�����ň�̖ʓ|���݂�o��ł��B������A���Ȃ����ɖ��f�����������Ȃǂ܂���������܂���v�ƌ�����������コ��̎p�����͍���̂��Ƃ̂悤�Ɏv���o���B�ꎞ��O�̌ւ荂���C���|�҂̈Ӓn�ɂ�������r�ȐS�̌��������A�����ɂ͊�����ꂽ���̂ł���B
�@ �Ƃ������A�����͂��߂Ƃ���n�R�w���ǂ��͂��̕��X�ɂ����Ԃ�Ƃ����b�ɂȂ����B���������łɂ��܂����̂�H�킹�Ă��炢�A���̂������Ŏ��Ȃǂ͉h�{�����ɂȂ炸�ɂ����炢�ł���B���̎���̐[����ӂɂ͓����̉����Ȃ�ł͂̐l����܂����������Ɏc���Ă��āA���̉������ɏ�����ꂽ�z���o�͂������ď��Ȃ��Ȃ��B�k�̌���낵���p�N�p�N�ɒܐ敔�̊J�����C�𐫒�����Ȃ������Ă��鎄�������˂��C���̐e������A�ꑫ�C���v���[���g���ꂽ���Ƃ�����B���̐e������́A���q�����蕨�̍����C�����Ƃ���ƁA����ȍ����ȌC���������Ȃ��̂��ܗ����Ă���C�����ق��������ƈ��オ�肾�ƌ����āA���̏�ő���̌C�̏C�������Ă��܂��悤�Ȑl�������B
�@ ��H���̐�コ��ł̓}�O���̃u�c����悭�H�ׂ��B�}�O���̎h�g�̒l�i�̓}�O���̃u�c��̓�{�ȏ�������̂ł��������u�c�����H�ׂĂ����̂����A���ꂪ�A�ʂ������Ղ�ŁA���ɂ��܂������B����Ƃ��A���܂��܃J�E���^�[�ɕ��э��킹�����q���}�O���̎h�g�𒍕������̂ɑ����āA���̂ق��͂����̃}�O���̃u�c�𒍕��������Ƃ��������B���̂��Ƃʼn��C�Ȃ���ɖڂ����ƁA�e������́A�܂��܂��}�O���̎h�g�������炦�A�܂����������}�O���̓����g���Ă���ǂ̓u�c������Ă���ł͂Ȃ����B�������A�u�c�̂ق����h�g�����ʂ��������炢�ł���B����܂ŁA�u�c�̓}�O���̈����]����̕����ō���Ă�����̂Ƃ���v���Ă�������A���́A��u�A�䂪�ڂ��^���Ă��܂����B�ǂ���Ńu�c���܂��͂��ł���B
�@ �ׂ̋q���Ȃ𗧂������ƁA�����ɁA���͐e������ɁA�u�h�g���u�c���ޗ��͓����������݂����ł����ǁH�v�ƁA�����Őq�˂Ă݂��B����ƁA�e������́A����������ۂ��݂��ׂȂ���A�u�h�g�ƃu�c�Ƃ͐�����Ⴄ��I�v�Ƃ������ȉ�����Ԃ��Ă��ꂽ�̂ł������B
�@ ������B�̓��炿�ŁA���������̂����܂��A����h�A�K���Ȃǂ̃A�����D�����Ƃ������Ƃ��킩��ƁA�z�n�̋��݂͊Ɏd����ɍs�������łɐg�̂��������̃A����܁X�����A��A�X��ɂ����̃A������⒲���p��Ƃ��ǂ��������^���Ă���������B����ɃA���𗿗����ĐH�ׂ�Ƃ����킯�ŁA���̉��b�ɗa����A�߂��ɏZ�ޓ��ނ̕n�R�ȗF�l���ꓯ�A�A���̎藿���ɐ�ۂ�ł��Ƃ��ł����悤�Ȗ����B
�@
�@ ���ƗF�l�̂ق��ɂ͂��q�̂��Ȃ���������ӂ̂��ƁA���܂��ܐe������Ƃ̊ԂŒ����̂��Ƃ��b��ɂȂ����B�����b���͂����ƁA�e������́A�}�Ɏv���������悤�ɁA���Ƃ�͂肱�̓X�̏�A�������F�l�̓�l���K�̕����ɏ����グ�A���^�̃_���{�[���l�̔��̉��ɑ�ɕۊǂ��ꂽ���Ȃ�̖����̎ʐ^�������Ǝ��o�����B�����āA�e������́A�ǂ����v���l�߂��悤�ȕ\��������Ȃ���A���炽�܂������q�Řb���o�����B
�@�u���͂˂��A�펞���A���R�����̒�����ʖS���̔C���ɂ��Ă��ĂˁA�싞������������ɂ��Ďʐ^�B�e�Ƃ��̏����ɗ����������B�s���A���{�A������ہA����炷�ׂĂ̎ʐ^��W���ނ͈ꖇ�̂��炸���p�p������悤�Ɍ������ꂽ���A�K���̎v���ňꕔ�𖧂��Ɏ����A������B���ꂪ���̎ʐ^�Ȃ��ˁc�c�v
�@ �e������́A�����ő��𐮂��邩�̂悤�ɁA�������t���A����ɁA�����������B
�@�u���ۂ���͖ڂɂ��������œf���C�����您�������Ȃ�悤�Ȑ��S�Ȍ��i�łˁA�E�Q���ꂽ�����̐l�X�̊Ԃ�����ƕG���߂��܂ł��钷�C�����̊C�ɂ��Ԃ��ԂƂʂ���A���C�̒��ɂ܂Ō����͂����Ă���L�l��������c�c�B�����҂���l�ł�����Ƃ܂�������Ƃ����̂ŁA���{�����e���ōēx��̈�̎��̂�˂��h�������Ă����˂��B����ȋ����Ȃ��Ƃ͓�x�ƌJ��Ԃ��Ă͂Ȃ�Ȃ���B���낢��Ɩ��Ȏ�������āA���̂悤�Ȏʐ^�����邱�Ƃ͌��\�͂ł��Ȃ����ǂ˂��c�c�v
�@ ���̐Â��Ȍ����ɂ́A�Ȃ�Ƃ��`�e����d��������������ꂽ�B�������̐��܂�����i���A���܂��e������̐S���Ղ݂Â��Ă��Ă��邱�Ƃ͖����������B
�@ �Â��Ȃ�A���Ȃ�ϐF���������̎ʐ^�ł͂���������ǂ��A�����̎ʐ^�ɂ͂��т����������̖��S�Ȏ��̂��ʂ��Ă����B���܂��炽�߂ĐU��Ԃ��Ă݂Ă��A���̂Ƃ��̐e������̐^�ӂ̂قǂ͂��܂ЂƂ݂͂��˂�̂ł��邪�A�����̘b�����������Ƃ����ނɂ�܂�ʎv���ɋ�肽�Ă��Ă̂��Ƃ������̂��낤�B���炭���Ď��͐[��𗣂ꂽ���A���ꂩ�琔�N��ɂ��̐e������͑��E���ꂽ�B�����]��ɐڂ��邱�Ƃ��ł��Ȃ������̂ŁA�S���Ȃ��Ă��炭�����Ă��獁�T�������Ă��X�ɐ�コ���K�˂����A��コ��Ƃ�������̂����ꂪ�Ō�ɂȂ��Ă��܂����B
�@ ��A�O�N�قǑO�A�p���������Ė�O�����ɏo�������Ƃ��A���łɂ��̉��������ꏊ��K�˂Ă݂����A������͋ߑ�I�ȊX���݂ɕϖe���A�̂̊X���݂̂��������Ȃǂǂ��ɂ��Ղ𗯂߂Ă͂��Ȃ������B�ނ���コ��̂��X���c���Ă��悤�͂����Ȃ������B
�@ �����O�\�N�ȏ�O�̂��ƂȂ̂����A���̎ʐ^�����̌�ǂ��Ȃ����̂������́A���܂��ɋC�ɂ�����B�H���C���肪�摖��Ⴓ�̂䂦�ɁA�����͂��Ƃ̏d��ɂ��Ă��܂�[���l���Ȃ������̂����A���������ڂ����e������ɘb���f���Ă����悩�����Ƃ��܂͐S���������Ă�����B
�@ �싞�����͂Ȃ������Ǝ咣����l�X�������Ȃ��Ă��Ă�����������A�����������Ƃ���A�싞�������������Ƃ���咣�́A�����������{�ɕ��邽�߂ɝs���������U�̐�`�A�Ȃ����͈ꕔ�̍����I���{�l�i�H�j�Ƃ��ɂ��ϑz���Ƃ������ƂɂȂ�̂��낤���H
�@ �����������������l�ł������Ɖ��肵�A��ÂɂȂ��čl���Ă݂�ƁA���Ƃ��������{�l�ɕ��邽�߂Ƃ͂����Ă��A���ۂɑ��݂��Ȃ�������s�E�������f�b�`������Ȃ�Ă������Ƃ͂���߂ĕs���R�������Ȃ��Ƃ����A���Ƃ�����ȍ����̂Ȃ��咣�����Ă݂Ă��A���ꂪ���ۓI�ɒʗp����ȂǂƂ͍l���Ă��݂Ȃ����Ƃ��낤�B���̐e������̌��t��ʐ^�ɑ҂܂ł��Ȃ��A�싞�����͂������Ƃ݂Ȃ��̂��������R�̂��Ƃ��낤�B
�@ �E�Q���ꂽ�l�X�̐��ɂ��Ă̐���l���������Ɠ��{���Ƃő傫���قȂ��Ă���Ƃ������͂��邾�낤�B���m�ȃf�[�^��L�^���c����Ă��Ȃ��ȏ�A���Q�����͎��҂̐����Ȃ�ׂ����Ȃ����ς���A�t�ɔ�Q�����͂��̐����Ȃ�ׂ��������ς��낤�Ƃ��邾�낤���A�c�s�s�ׂ̏ɂ��Ă����{���͉ߏ��ɁA�������͉ߑ�ɍl���悤�Ƃ��邾�낤�B�������A�싞���������݂������ǂ����Ƃ����c�_�Ɋւ��邩����A���Ґ��̖���c�s�x�ɂ��Ă̗����̌����̑���͓�`�I�Ȃ��Ƃɉ߂��Ȃ��ƌ�����B
�@ ���w�̏ؖ��Ȃ�ΕS�̎��ۂ̂����S���ׂĂ����藧���Ƃ��K�v�����A�Љ�ۂɂ�����ؖ��ł͕S�̂������\�����藧�ĂΏ\���ƌ��Ȃ��ׂ����낤�B�W���ۂ�S�p�[�Z���g���ł��Ȃ���Ώؖ����ꂽ�Ƃ͌����Ȃ��Ƃ��鐔�w�I�ȍl�������Љ�ۂ̏ؖ��ɓK�p����̂́A���F�A���������Ӗ��Ȃ��Ƃ̂悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B�Љ�ۂɊւ��ẮA��O�����x�̖��𖾁A���ؖ��̎��ۂ����邩��Ƃ����āA���ƂȂ��Ă��镨���S�̂�ے肷��悤�Ȃ��Ƃ͐T�ނ悤�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂��Ă�A�B��ł����藧���Ȃ����Ⴊ������̖���͕s�����Ƃ��鐔�w�I�Ș_�@���A�����̐^�����B���Ӑ}���߂ĎЉ�I���ۂ̑��ݔے�ؖ��ɂ������ނȂǂƂ������Ƃ́A�ؖ��_���̈��p�ȊO�̉����ł��Ȃ��ƌ����邾�낤�B
�@ �Ȃ̔�͔�Ƃ��Č����F�߁A���̂����ő���̎����o����������ߓx�̐ӔC�Nj��ɂً͈c�������A�I�m�ɊO����i�߂Ă������Ƃ����̍ەK�v�Ȃ̂ł͂Ȃ��낤���B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N4��26��
�l���͗l�W�O�\�[�p�Y��
�@�u���ꂩ��ǂ���ցH�v�\�\�M�B�䍂�w�O�Ŋό��ē��߂Ă������́A�����Ȃ茨�����ɂ�������������ꂽ�B�u�͂��H�v�ƌ˘f���C���ɐU��Ԃ�ƁA���m��ʘV�l������������ۂ��݂��ׂė����Ă���ł͂Ȃ����B��u���t�ɋ��������Ɍ������āA��̘V�l�́A�u��������Ȃ��Ƃ�����܂�����v�ƒǂ��ł��������Ă����B���܂ꂽ����̎��X�̗����z���ӂ���ł��炩�ɋP���A����ӏt�̗[���̂��Ƃł���B
�@ �O���A���́A�䍂�w�ɋ߂���R���p�ق�K�˂����肾�����B�ǂ����A�������p�ق̒���̃x���`�ɂ����A�[���z���ɒ^���Ă����Ƃ��A�V�l�͋q�l���Ă��̏��ʂ荇�킹�A���̎p���L���ɗ��߂����̂炵���B��قǏ�Ȃ���ł����Ă����̂��낤�B
�����̋q�����܌����������肾���A����ȓ��̖�͂��������҂����B���������Ƃ��ɂ́A���̏h��������ӂ�����ē��ɖ��������܂����ȗ��l���Ƃ��ĐH���ɂ�����\�\���B�P���̍��˓`����z�킹�邻��ȈӖ��̌��t��f�����V�l�́A���̊�����Ăɂ��Ə����B���肪�d���Ȕ����ɂł������ėU�f���Ă���Ȃ������͎̂c�O���������A��������l��H���Ă����g�A���̍ہA�l�ɐH���Ă݂�̂������Ȃ��ƁA���͂��̗U���ɂ����ď�邱�Ƃɂ����B
�@ �R���̐[���т̒��ɂ���m���̉��~�ɂ́A���邩��Ɉٗl�ȋC�z���������߂Ă����B�V�l�́A�㎿�̍��ѕz���܂�ɂ��Ďd���Ă��Ƃ����萻�̃h���L�������}���g�ɒ��ւ��Ăӂ��Ɍ���A���̔w��������Ƃ������B�����Ńt�N���E�����Ƃ������܂��܂ł����A���̌���̖��{���疳�����҂��ʂ����ɂ́A�������������������Ԃ������Ȃ��悤�������B
�@ ��X�͖��O���Ċ�ȑΘb���J��L�����B�R�̂Ȃ��̉R�ɂ��݂��āA���̐��ł�����̐^���̂悤�ȁA�卼�\�t���m�̑Ό��Ɏ��āA���͐��Ȃ��l�̍��k�̂悤�ȁA����͂Ȃ�Ƃ��s�v�c�Ȋ��k�������B
�@ ���U�Ɏl�\�]�̐E�Ƃ�̌������Ƃ����V�l�́A�Ȃ̐l�����n�����ĂČ��D�݂͂Ȃ��ƚ����A�ǂ����Ă������̉ߋ��ɋ���������Ƃ����̂Ȃ�A�W�O�\�[�p�Y���������悤�ɗl�X�Șb�̒f�Ђ��q�����킹�A����ɑS�e�����߂悢�Ə��āA�������Ɋ������B�����ɖ߂������ƁA���́A����̈Ӗ������߂āA���̂悤�Ȉ�т̋Y���������������B
�@�@�@���̑Θb
�ʁX�̂Ƃ��납�痷���Ă���
�����ȕ��ƕ��̏o�����̂悤��
�����ďu���ɂ��݂��̑̂�ʂ蔲��
�����Ă������ܕʂ�܂���
�R�̂Ȃ��̉R�̂悤��
�^���̂Ȃ��̐^���̂悤��
�Â����炠��b�̂悤��
�N���m��Ȃ���k�̂悤��
�卼�\�t���m�̑Ό��̂悤��
���Ȃ��l�̍��k�̂悤��
����͕s�v�c�ȏo�����ł���
�ǂ����ŕ����������̂悤��
���߂Ď��ɂ��镨��̂悤��
���A���e�B�ȂNJF���̂悤��
�������Ȃ����M������悤��
���[���̌�鐢�E�̂悤��
���[�����̐l�̂��Ƃڂ��̂悤��
����͊�ȑΘb�ł����B
�@ �莆�𓊔����Ȃ���A������������A�������̉��~�͉e���`���Ȃ��Ȃ��Ă��邩������Ȃ��Ƃ����z�����߂��点������������A�K�����̎莆�͖����V�l�̎茳�ɓ͂����悤�������B���ꂩ��Ƃ������́A���́A�V�l���C�ɓ���̏\�O���̋��j����I��ł͕䍂�ɏo�����A�W�O�\�[�p�Y���ɒ��킵���B���̌��ʕ����яオ�����V�l�̐l���͔j�V�r���̂��̂������B
�@ �����������Z���ƌ�ɏ㋞�A�{���Ԗ�O�̃J�t�F�o�[�̃{�[�C��U��o���ɁA�ݕ��D�̑D���A����ɂ͒����̐��ō���t�̉E�r�߂���҂́A�₪�đ�A�Ɉڂ��ē��n�̊O����s�̗L�\�ȍs���ƂȂ�A���ɂ͏�C�ɏo�ē��{��w�Z���J�Z�A��̒n�̖��m�ƂȂ�B���ă~�b�L�[�J�[�`�X���̕ꓰ�͂��̓��{��w�Z�̋��t�߂Ă���ꂽ�Ƃ����B
�@ �s��ア������A�������ނ́A�V�^�ƍˊo�̕����܂܂ɐ�㏉�̖��ԓ��{�l�Ƃ��ēn�p�A�a�a�b�������{�ꕔ�̃A�i�E���T�[�������L�҂ƂȂ��āu�����h���������̍��v�Ƃ����ԑg��S������悤�ɂȂ�B�P�X�T�R�N�ɂ́A�G���U�x�X�����̑Պ����o�Ȃ̂��ߖK�p�����c���q�i���V�c�j���m�g�j����h�����ꂽ���q�C���Ƌ��ɃT�U���v�g���`�ɏo�}���A�e�n���ē�����ƂƂ��ɁA�Պ����O��̃����h���̗l�q����{�����ɓ`���邽�ߘA���̂悤�Ƀ}�C�N���Ƃ����B
�@ �̂��ɂa�a�b�����������ċA�������ނ́A���{�ʼnp��b�w�Z���J�������킽��A�V���[���b�N�z�[���Y���͂��߂Ƃ���p�ĕ��w�̉A�̖���҂Ƃ��āA��v�ۍN�Y���͂��߂Ƃ��钘���Ȗ|��Ƃ�p���w�҂����̃S�[�X�g���C�^�[�������������B���łɗ�\�������̐Γc�B�v�Ƃ����V�l�̐���Ȑ��U���A���͂��������M�ɑ�͂��߂��Ƃ���ł���B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N5��3��
���ӔC�m���k�b
�@ ����_���̌n�������I�ȈӖ��Ŕj�]���Ă���Ƃ������ƂƁA�l�ԂɂƂ��āA���̘_��������L���̎��������̗��j�I�w�i�̂Ȃ��ŗL�Ӌ`�ł���Ƃ������ƂƂ́A�����čl���Ȃ���Ȃ�Ȃ����ł���B�����łȂ���A�l�Ԋ����̂��ׂĂ��ے肳��Ă��܂����Ƃɂ��Ȃ肩�˂Ȃ����炾�B
�@ �m���_�ЂƂ��Ƃ��Ă݂Ă��A�����ɍl����Ƃ���ƁA��ϓI�m���i���w�I�m���Ƃ��Ă��j�Ƌq�ϓI�m���i���v�I�m���Ƃ��Ă��j�̋�ʂƂ������悤�Ȗʓ|�ȋc�_����n�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��킯�ŁA���ƂɂƂ��Ă�����͖��Ȗ�肾�ƌ����Ă悢�B���ہA���܂ɂ��|�ꂻ���ȃ{���Ƃ����͂��H���Ȃ���Ȃ�Ƃ��̍ق�ۂ��Ă����Ƃ�����Ƃ��A�m���_�̐��E�ɂ����Ă͉����ʂĂ�Ƃ��Ȃ��������Ă���̂ł���B�Ȃ�Ƃ��Z�߂�ɂ͏Z�߂邪�A�����Ȃ�ǂ��ǂɌ����J�����킩��Ȃ��B���̂��߂ɉ������������ł��܂������킩��Ȃ��B�ł��܂��A���ʁA�J�I��₽�����𗽂����Ƃ͂ł��邩��A���̉Ƃ̑��݂͂���Ȃ�ɂ͗L��A�Ƃł��������悤�ȂƂ��낾�낤���B
�@ �c�O�Ȃ��Ƃł͂��邪�A�u��ɗ����Ȃ���s�@�v�͑���Ȃ��B������A��s�@�ɏ��Ȃ��ƍl���邩�A���S���ɓq���Ĕ�s�@�ɏ�邩�́A����̔w�i��l���ꂼ��̐l���ςɊ�Â����f�Ɉς˂��邱�ƂɂȂ�B�Љ�ۂ⎩�R�E�̎��ۂɊm���_��K�p����ꍇ�́A��ʂɂ́A�ǂ����Ă��A�ߋ��̎��ۂ̗l�ԂɊ�Â��f�[�^���疢���̎��ۂ̗l�Ԃ�\������i�������A�ʎq�_��F���_�̏ꍇ�͉ߋ��̗\���������肷�邱�Ƃ�����A�܂��A�ŏI�I�ɂ͉ߋ������������z����b�ɂȂ��Ă��܂����肷��킯�����j�Ƃ����v���Z�X�܂���Ȃ��B���̏ꍇ�A���̊m���I�\�����Ӗ��������߂ɂ́A�u���̗\���̂��ƂɂȂ��������ۂ̗l�Ԃ�����܂Œʂ�ɓW�J����̂ł���v�Ƃ����Öق̑O���݂��Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��킯�ŁA���̑�O���ꂽ�ꍇ�ɂ́A���̊m���I�\���͂قƂ�LjӖ��������Ȃ��Ȃ�B
�@ �����̏��킩��Ȃ�����\���������B�ł��\���������邽�߂ɂ́A����܂łƂ��Ȃ��悤�ɏ��X�̎��Ԃ��W�J���Ă������Ƃ��O��ƂȂ�B���������ꂶ��A�܂�ŗ\���̈Ӗ����Ȃ��c�c�B�@�����̏��킩��Ȃ�����\���������B�ł��\���������邽�߂ɂ́A����܂łƂ��Ȃ��悤�ɏ��X�̎��Ԃ��W�J���Ă������Ƃ��O��ƂȂ�B���������ꂶ��A�܂�ŗ\���̈Ӗ����Ȃ��c�c�B��ʂɂ́A�T�C�R���̊e�X�̖ڂ��o��m���͘Z���̈�ŁA�U��𑝂₵�Ă����Ίe�ڂ̏o�銄���͘Z���̈�ɂ�����ł��߂Â��Ă����ƐM�����Ă���B�������A���̂��߂ɂ́A�u�ꂩ��Z�܂ł̂ǂ̖ڂ����S�ɓ��������ŏo��T�C�R��������Ƃ���v�Ƃ�����O���݂��Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���������N���ǂ�����Ă���ȃT�C�R�������邱�Ƃ��ł���Ƃ����̂��c�c�܂����A�U���Ă݂Ă�����m���߂�Ƃ����킯�ɂ������Ȃ����낤�B����ł͏z�_�Ɋׂ��Ă��܂��B
�@ ����͂ƂĂ��Ȃ��p���h�b�N�X�ł��邪�A�p�X�J���A���v���X�A�K�E�X�Ƃ������m���_�̌��c�B�͂��Ƃ��A����ȍ~�̂ǂ̂悤�ȓV�˂̓��]�������Ă��Ă��{���I�ɂ��̋t�����������邱�Ƃ͏o���Ȃ��ł��Ă���B�m���_�̐�发���J���ƁA��ʐl�ɂ͈Ӗ��s���̊���Ȑ������Ƃ��닷���ƕ���ł��邪�A����̓{��������������⋭�����葕�����Ȃ������肵�āA�����m��Ȃ��ʍs�l�ɂ͗��h�Ȍ����ł���悤�Ɏv�킹�Ă��邾���̂��Ƃł���B�������A��ɏq�ׂ��悤�ɁA����ɂ͂���Ȃ�̗L�Ӑ��͂���킯�ŁA���ꂪ�S�����Ӗ��Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B����͈͂Ƃ���������ŁA����͗L�����L�v�ł͂���A���̂��Ǝ��̂͂���Ȃ�ɕ]�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@ ����s�K���Ȍ`��̒n�ʂɐ��𗬂��ꍇ�A���̗��H�𐳊m�ɗ\�����邱�Ƃ͕s�\�ł���B�s����ɖ̗t���ꖇ���������Ă����Ƃ��A�����}�ɐ������Ƃ��A�����z���Đ���オ�������������ꂽ�Ƃ��A���܂��ܒʂ肩�������l��Ԃ̉e�����������Ƃ��������悤�ɁA������Ƃ��������̕ω��ł����Ȃ藬�H���ς���Ă��܂����Ƃ͂悭�m����ʂ�ł���B
�@ �������A���H�����肵�����ƂŁA�����Ȃ�m���i��������Ȃ肢�������Șb�ł��邪�j���Z�肷�邱�Ƃ͂ł��邪�A���̊m���I���l�́A���̌�̗��H�̌����ȗ\���ɂ͂��܂�Ӗ��������Ȃ��B�����A�����͂����Ă��A����͈͂ł͖𗧂킯�ŁA���������ȂƂ���ł���B
�@ �����^���[�̂Ă���`�����̐�[���ꖇ����Ă����A���ꂪ�ǂ��ɗ����邩���A������Ȋw�I���͂������ƂɊm���_�I�ɗ\������ꍇ�A��L�����[�g���P�ʂ̌덷�������Ȃ�Η\�����Ӗ����������邾�낤���A��~�����[�g���P�ʂ̌덷����������Ȃ����x�ƂȂ�ƁA������\��������Ă��܂����Ӗ��ł��낤�B�\���̐��������m�F����ɂ́A�`�����̒f�Ђ̗����ʒu����~�����[�g���P�ʂ̐��m���ő��肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����ŁA�����ʒu�𐳂����m�F���邽�߂ɑ���@��������Đl���߂Â��ƁA���ꂾ���ł�����̑�C�������ɗh�ꓮ���A������ʒu���ω����Ă��܂��B�����܂ł��Ȃ����A����̓n�C�[���x���N�̕s�m�萫���_�ł����A������u��炬�v�̈��ł���B
�@ �܂�Ƃ���A�m���Ƃ������̂̕]���́A�]���̂��߂ɕK�v�ȔF���ړx��Ӗ��̎ړx���ǂ̃��x���ɂƂ邩�ɂ���āA�L�ӁA���ӂ̂ǂ���ɂ��]�ѓ���\��������킯���B���������āA�O��ƂȂ邻�̂ւ�̌����ȋc�_�Ȃ��Ɋm���_���₽��U��Ă�������Ƃ���͂��܂�Ȃ����ƂɂȂ�B
�@
�@ ���ł�����A��ϓI�m���Ƌq�ϓI�m���ɗ��ޗL���ȃp���h�b�N�X���ЂƂЉ�Ă������B���Ԃ̂�����́A�������łǂ������������̂��l���Ă����ɂȂ�Ƃ悢�B
�@ �̖\�N�̎x�z���Ă������鍑�̊č��ɏ\�l�̐����Ǝ��Y�������āA���̂����̋�l�͗������Y����邱�ƂɂȂ��Ă����B�Ƃ��낪�A���̒��̈�l�̎��Y�����A���܂��܌����ɂ���Ă����Y�����������܂��Ă����b���������B
�@�u�킽���͖����A�\���̋�̊m���Ŏ���ł䂭�^���ɂ���l�Ԃł��B�����A���肢�ł����炻��Ȏ��̗��݂��ЂƂ������Ȃ��Ă��������v
�@ ��ނȂ��Y�����������̌��t�Ɏ����X����Ƃ��̒j�͂����������B
�@�u�����������Y����邩�ǂ����͋����Ă�������Ȃ��Ă����\�ł��B���̂����A����������l�̂����ǂ̔��l�����Y����邩�������Ƌ����Ă��������B�������đ��̎��l�ɂ͌��O���܂��A�܂��A�����g�͏��Y����邩�ǂ��������ɂȂ�Ȃ��Ƃ킩��Ȃ��킯�ł�����A���Ȃ����g����荇�����M���M���̂Ƃ���Ŕ閧�`���͎��邱�Ƃł����c�c�v
�@ �j�̕K���̒Q��ɂق����ꂽ�����͂��̗v�����̂݁A�����ƒj�ɖ��̔��l�̖��O���������B����ƁA���̎��Y���͋}�ɖ��邢�\��������Ȃ��炱�������ɂ�����q�ׂ��B
�@�u�����قǂ܂ŁA�����������ʊm���͏\���̋�ł������A����ŁA�����������ʊm���͓̈�ɂȂ�܂����B�����Ő����ƋC�����y�ɂȂ�܂����B�ق�Ƃ��ɂ��肪�Ƃ��������܂��I�v
�@ ���̃p���h�b�N�X�A�����������������Ƃ͒N�ɂ������ɂ킩��̂����A����������ɐ������悤�Ƃ���ƁA�v�l���������āA�Ȃɂ��Ȃ��킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�����ŁA�g�����v�̃J�[�h���ɂƂ�Ȃ���A��������̓I�ɍl���Ă݂邱�Ƃɂ��悤�B
�@ ����ɌY���������A�n�[�g�ꖇ�A�X�y�[�h�㖇����Ȃ鍇�v�\���̃J�[�h�̒����炠����l�Ɉꖇ�����J�[�h���������Ă��̃J�[�h�̗��Ɉ���������A���l�ɂ͂��̃J�[�h�����ł��邩�������Ȃ��܂܁A��̂��Ă�J�[�h���ӎ��I�Ɏc���i���̈ӎ��I�ɑ��삵�Ă���Ƃ��낪���Ȗ�ł���j�A���̋㖇�̃J�[�h�̂��������̃X�y�[�h�̃J�[�h���߂����Č������Ƃ���B����Ǝc��͓ŁA�m���Ɉꖇ�̓n�[�g�A�ꖇ�̓X�y�[�h�ł��邪�A���̏ꍇ�A���Ɉ�̂��Ă���J�[�h���X�y�[�h�ł���m���͓̈�ł͂Ȃ��\���̋�ł��邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B��̂����J�[�h���n�[�g�ł���Ώ��Y����Ȃ��ł��ނƂ���A���̒j���������т�m���͏\���̈�A���Y�����m���͏\���̋�ł��邱�Ƃɕς��͂Ȃ��B
�@ �ł́A�������A�������A�\�����A�n�[�g�ꖇ�A�X�y�[�h�㖇�Ƃ����J�[�h�̍\�������l�ɂ͖��炩�ɂ����Ɉꖇ��I�����Ɉ���������A�j�̑I�J�[�h���܂ޓ̃J�[�h�������c�����Ƃ��Ă݂悤�B���l���I�J�[�h���n�[�g�A�X�y�[�h�̂ǂ���ł������ɂ���A�ꖇ�̓n�[�g�A�ꖇ�̓X�y�[�h�ɂȂ�悤�ɍH�����Ă����̂͂������̂��Ƃł���B�����āA�ǂ��炪�j�̑I�J�[�h����Ɍ���Ȃ��悤�ɂ��Ȃ���A�\�������ƌ����āA�m���Ɉꖇ���n�[�g�A�ꖇ���X�y�[�h�ł��邱�Ƃ��m�F���������ƁA�Ăї��Ԃ��ɂ��Ă悭��A���ꂩ�炨���ނ�ɁA�u���O�̑I�J�[�h�͂��̈�̂�������B���܂��O�Ɋm�F�������ʂ�A�ꖇ�̓n�[�g�A�ꖇ�̓X�y�[�h���B���O���I����̃J�[�h���n�[�g�Ȃ珈�Y�͂��Ȃ��B���̂����A�X�y�[�h�Ȃ炨�O�͏��Y���v�ƍ������Ƃ��悤�B
�@ ���̃P�[�X�ł́A���l�̒j�͏����̗ǐS�ɓq���āA�����̑I�J�[�h���n�[�g�ł���m�����X�y�[�h�ł���m�����̈ꂾ�ƐM���邵���Ȃ��킯�ł���i��ϓI�m���j�B�����ۂ��A���łɌ��ʂ�m���Ă���Y�������̂ق��́A������]�݂͂͂��߂���\���̈ꂵ���Ȃ������̂��Ɠ��S�Ŏv���Ă���킯�ł���i�q�ϓI�m���j�B���̃p���h�b�N�X�����Ȍ����́A����Ȃ�ɂ͋̒ʂ�����ϓI�m���Ƌq�ϓI�m���Ƃ̑o�����l�Ԃ̎v�l�̒��Ō������A���̃��c�������܂��قǂ����Ƃ�������Ƃɂ���B
�@ ���̎�̓T�^�̓C�J�T�}�T�C�R���ŁA���̃T�C�R���̏d�S����̖ڂ̂ق��ɑ傫�����Ă��邱�Ƃ��o���I�ɂ��炩���ߒm���Ă���l�ԂƂ����łȂ��l�ԂƂ�����ꍇ�A�m��Ȃ��l�Ԃ̂ق��͂ǂ̖ڂ��o��m�����Z���̈ꂾ�ƂƂ肠�����͐M���邵���Ȃ��i��ϓI�m���j�킯�����A�����͈�̖ڂ̏o��m�������̖ڂ̏o��m���Ɋr�ׂėy���ɍ����i�q�ϓI�m���j���Ƃ�m���ėL���ɏ�����i�߂��邱�ƂɂȂ�B���̗�͊ȒP������悢���̂́A�Љ�ۂ⎩�R�E�̎��ۂɂ͂���Ɠ��������d�ɂ����G����ɍ������Ă���A�q�ϓI���ƐM���Ă����X���g�i�������A���Ƃ��܂߂āj���A���͑O�q�̎��l�Ɠ�����ϓI����ɒu����Ă���Ƃ������Ƃ����Ȃ��Ȃ��B
�@ �Ƃɂ����A���鎖�ۂ̊m���Ƃ������̂́A�����̂Ƃ肩���ɂ���ĈقȂ��Ă�����̂ŁA���͑����ɑ��ΓI�Ȃ��̂Ȃ̂��B�͂��߂̎��Y���̖��ɂ����Ă��A�\�N�̎c�s���ɕ���ʂĂ��@����b���A�����閧���ɖ��߂��o���A���̂����̌ܐl����͂��悤�ƌ��ӂ��Ă����Ƃ���ƁA�Y���������q�ϓI���ƐM���Ă��邻�̊m���ɂ́A���́A���̎��_�ŋq�ϐ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ă����ł���B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N5��10��
��ǔL�Ɩ�ǃ`���{
�@ �����{���̓����_�H��w�L�����p�X�́A�䂪�Ƃ̂����k���Ɉʒu���Ă���B���O�Ƃ��Ă͕��O�҂��\���ɓ��邽�߂ɋ����K�v�Ȃ��ƂɂȂ��Ă͂��邪�A������A���ӏZ���͍\�������R�ɒʍs���邱�Ƃ��ł���B�ԓ�������Ŕ_�H��Ɨאڂ��鎄�����Z�̐��k�����Ȃǂ͑�w�\�����k�ɉ���ʘH��ʊw�H�ɗ��p���Ă��邭�炢�ł���B���܂��畔�O�҂̖������\���֎~����Ȃǂƌ����Ă��A���N�ɂ킽���č\�����U����ʍs�����肷�邱�ƂɊ���Ă����ߗZ���́A����ȋK���ɑf���ɏ]�����肵�Ȃ����낤����A��w���ɂ��Ă����݂̏�ٔF���邵���Ȃ��̂ł��낤�B����ɁA���ꂩ��̑�w�̔��W�ɂƂ��āA�n��Z���Ƃ̎��R�Ȍ𗬂͕s���Ȃ��ƂɈႢ�Ȃ��B
�@ �_�H��\���̂��������ɂ͟O�̑���͂��߂Ƃ����X�̎����ɂ��Ă��āA�_�炩����t�̉萁�����̎��߂̌i�ς͂Ƃ��ɑf���炵���B���傩��\���ւƑ����ʘH�́A���܌����ȟO�̎�t�̃g���l���ɕ����Ă���B�܁X�̋G�߂��ʂ�ԁX�≷�����Ŏ����͔|���̊Ϗܗp�A���Ȃǂ��U��҂̖ڂ��y���܂��Ă����B�d���ɔ�ꂽ�Ƃ��ȂǐS�g�����t���b�V�����邽�߂ɍ\���������鎄�ɂƂ��āA���̗ΖL���ȃL�����p�X�́u�،i�̒�v�ǂ��납�u���f�ؗp�̑�뉀�v�Ȃ̂ł���B
�@ �L�����p�X�̓����ɂ͍L�X�Ƃ��������p�_�ꂪ�����āA�G�߂ɉ������l�X�ȍ앨��ʎ��ނ��͔|����Ă���B���傤�ǂ��܂͔���ʂɔ����X�Ɣɂ��Ă���Ƃ���ł���B���̕Ћ��ł̓\���}���Ȃǂ�����Ă���悤���B�V�C�̂悢���Ȃǂɂ��̔_����̍�Ɨp�H���U��������̂́A������Ƃ����ґ�����Ȃ��B���܂ǂ��s��ł͒��������炢�Ɏl���̋Ђ炯�Ă��āA�[�Ă��̋���A�����Ă���ɑ����[���̋P����X���������������B�C���ɉ��������y�̊��G���o���Ȃ���A�l�G�܁X�̍앨�̐����Ԃ�߂Ă܂��̂����Ȃ��̂ł���B������[���Ȃǂ͌���A��ĎU���ɂ���Ă���l�����Ȃ��Ȃ��B
�@ ���݁A�䂪�Ƃł͌����L�������Ă͂��Ȃ����A�_�H��L�����p�X�����͂��߂Ƃ��邱�̈�тɂ͂��Ȃ�̖�ǔL���������Ă���B�䂪�Ƃ̎��ӂɂ������A��N�قǂ̖�ǔL�̂̌܌Z�킪����ł��āA���X�a���˂���ɂ���Ă���B���������̒��Őg�����m�b�Ȃ̂��낤���A����Ƃ����a������Ƃ����ނ�͏W�c�s�����Ƃ��Ă���悤���B�ǂ�����Ȃ��Ȃ��́u�L���v�����Ă��āA�����̎����L�Ȃǂɂ͌����Ȃ����ɔL�炵�����e��X���Ă���B
�@ �Ƃ��낪�����ܕC�̒��Ɉ�C����������ƕς�����z������B�ŋ߁A���͂��̗Y�L�ɂɁu���L�v�Ƃ����Ăі��������B��ȂǂɎU���ɏo������ƁA�����͖ڂ��Ƃ����̎p�������Ăǂ�����Ƃ��Ȃ�����A�s�[���ƐK���𗧂ĂȂ���ǂ��܂ł����Ƃ����Ă��邩�炾�B�L�̂����ɂ܂�Ō���������Ȃ̂ł���B�ŏ��͉a���˂����Ă���̂��Ǝv�����̂����A�ǂ���炻���ł��Ȃ��炵���B���̍s���������Ɗώ@���Ă݂�ƁA���̂��Ƃɂ��Ď����̒m��Ȃ��Ƃ���܂ł���Ă��邱�Ǝ��̂Ɋ�т������Ă���悤�Ȃ̂��B�l�Ԃɂ��ُ�ȕ��Q�Ȃ����҂�����悤�ɁA�L�ɂ����܂�����Q�Ȃ����Ȃ����z������̂��낤���B������������A���́u���L�v�͎��ɓ��ނ̂悵�݂������Ƃ��Ă���̂�������Ȃ��B�����v���ƁA���͂Ȃ�Ƃ����G�ȋC���ɂȂ��Ă����B
�@ �_�H����ӂ�������邾���ł������ȋ���������̂����A���́u���L�v�͈��̋�����ۂ��Ȃ���A�����C�܂���ȎU�����I���ĉƂɖ߂���܂ł����Ƃ��Ƃ����Ă���B�Ȃɂ��̔��q�ŋ���������������ƁA�܂�Łu������Ƒ҂āv�ƌ�������ɁA�j���[���Ɩ��B���̂����A�ǂ�ȂɌĂъĂ݂Ă���A�[�g���ȏ�͋ߊ���Ă��Ȃ��B��x�ł�������z�̑̂ɐG���Ă�낤�ƁA������͂����ƃ`�����X���f���Ă���̂����A����͂Ƃ����ɂ�����̋��̓���ǂ�ł���炵���A���L���Ƒf�����g�����킵�ĉ��������Ă��܂��B
�@�u���O�̂��Ƃɂ��Ă͂������ǁA���ɂ͉��̎��R�����邩��G����̂͐�Ό��Ȃ̂��B��ǔL�ɂ͖�ǔL�̌ւ肪���邩��˂��I�v�Ƒ���͌��������Ȃ̂ł���B�u���L�v�Ǝ��Ƃ̂��̊�ȊW�͂����������܂ő����̂��낤�B�ނ��A�ނ͑����ɋC�܂���ŁA���ԁA���̌Z��L���ǔL���ԂƂ̂�т�߂����Ă���Ƃ��́A���ڂł�����̗l�q���M������͂�����̂́A���Ƃ͑f�m��ʊ�ł���B
�@ �_�H��L�����p�X�̓쑤�ɂ͔n�p���̎g���Ă��鍻�~���̔n�ꂪ�����āA���̂����e�ɓ�傪����B���̖�̎��ӂ̋n��т̒��ɂ́A��ǔL�̂ق��ɖ쐶��������Q�̖�ǃ`���{������ł���B���̖�ǃ`���{�ǂ��A�쐶�����Ă��邾�������āA�C�����������B���܂ǂ��̎�����炳�ꂽ����L�Ȃǂ�����ɋ߂Â����肵�悤���̂Ȃ�A�����܂��˂��Ԃ���Ă��܂��B���܁A�傫�Ȗ쒹��_����ǔL�ǂ������āA�����̖�ǃ`���{�ǂ��ɂ͂܂�������̏o���悤���Ȃ��悤���B�����D���ȋߏ��̏Z�������c�тȂǂ�^���Ă���̂�ڂɂ��邪�A��ǃ`���{�ǂ��͉䂪���̊�ɐU�镑���Ă܂������ɉa�����݁A���̂����ڂ���ǔL�ǂ������̌Q�ƈꏏ�ɂȂ��Ē��Ղ��Ă��邠�肳�܂Ȃ̂��B
�@ �т��M�������A�L���\���Ɋe��̌�����{�݂����G�ɂ̓���g��ł���̂ŁA�ǂ��ŕ������Ă���̂��͂悭�킩��Ȃ��̂����A������ˑR�ɐe�`���{���]���]���Ƃ��킢������A��Ďp�����킷���Ƃ�����B���܂ǂ��̓s��ł͒������A�Ȃ�Ƃ����܂������i�ŁA�ʂ肩����l�X�̐S��a�܂��Ă���邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B�����A���R�E�̝|�͂����ł��������A���̏����Ȑ��������J���X���ǔL�̌Q���_������A���ۂɐ����ƂȂ�̂͂ق�̈ꕔ�ɉ߂��Ȃ��悤���B�����Ď��R�����̕����܂܂ɂ܂����A���܂ꂽ����l�דI�ɕی삵��ďグ�悤�Ƃ��Ȃ��̂́A�����ɂ������̐��Ƃ̑������̑�w�̂��Ƃ炵���B��������������ǃ`���{�ǂ��̏��L�����N�ɂ���̂��A���܂ł͂����悭�킩��Ȃ��B
�@ �ʔ����͖̂쐶���������̖�ǃ`���{�ǂ��̐��Ԃł���B�䂪�Ƃ���܁A�Z�\���[�g���قǂ�������Ă��Ȃ����̎��ӂɂ́A�����\���[�g������O��G���W���A�w�A��A���~�A�ԏ��Ȃǂ̑�������Ă��邪�A��������Ɣނ�͂���Ȏ��̂Ă���߂��̎}�܂ł̂ڂ��āA�����Ŗ����𖾂����̂��B�g����邽�߁A���S�ȍ��̎}�Ԃ��˂���ɂ��Ă����ł���B���̎��Ȃǂɂǂ����Ă���̂��͂킩��Ȃ����A���N�ɂ킽���Ė����ɐ������тĂ���Ƃ�����݂�ƁA����Ȃ�ɖ쐶�̒m�b�������J�𗽂��ł���̂��낤�B
�@ �Ƃ���ŁA�����̃`���{�ǂ����A�ǂ�����č����\���[�g���قǂ�������̎}�܂ł̂ڂ邱�Ƃ��ł���̂��Ǝ���X����l�����邾�낤�B������쐶�������Ƃ͂����Ă��A�܂����J���X��n�g�Ȃǂ̂悤�Ɏ��R�ɋ���ׂ�悤�ɂȂ����킯�ł͂Ȃ��̂�����A���R�ނ�Ȃ�̕��@������͂����B�ŏ��͎����^��Ɏv�����̂����A�[���A�ނ�̐��Ԃ��ώ@���邤���ɁA���̓�͗e�Ղɉ������B�ނ�́A�������H�����Ēn�ォ���яオ��ƁA�܂��A��A�O���[�g���قǂ̍����̎}�ɂƂ܂�B�����āA�����ł��炭�H���x�߂�ƁA�Ăь������H�����āA�������炳��ɓ�A�O���[�g����̎}�ɔ�шڂ�B���Ƃ͓��l�̂��Ƃ��J��Ԃ��Ēn��\���[�g���O��̍����ɂ܂œ��B����킯���B
�@ �Ċ��Ȃǂɂ͌ߑO�O�����l�����ɂȂ�ƁA�R�P�R�b�R�[�Ƃ����E�܂����������������Ă���B�������߂�����łȂ��A�Ȃɂ�����͎��̂Ă���߂��Ŗ��Ă���̂�����A���̒ʂ肪�悢���ƂƂ����炱�̏�Ȃ��B��\�������痂���̖������ɂ����Ďd�������邱�Ƃ̑������Ȃǂ́A���낻��Q�悤���Ǝv�����ɃR�P�R�b�R�[�Ƃ����ƁA���ԗl�Ǝ��Ԋ��o�ɑ傫�ȃY���̂���Ȃ̐����̏Ɉꖕ�̍߈����������o���Ă��܂��L�l�Ȃ̂��B�ŋ߂͂₽��X���̐����������ӂ����邭�Ȃ����������A�C�̑����z�Ȃǂ́A�ߑO�뎞���ɂȂ�ƁA�����R�P�R�b�R�[�Ƃ���Ă���B�̓����v�������Ă���̂͂ǂ���炱�̐g�����ł͂Ȃ��炵���B��ǃ`���{�ǂ������Ď��Ԋ��o���킩��Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���炵���̂��B
�@ �Ƃ��ɂ͖쐶�����ӂ�邱�̃`���{�ǂ��߂Ȃ���A�����߂܂��ĐH�����炳���������������Ƃ��낤�ȂƖ��ȑz�������邱�Ƃ�����B�̂́A�����������B�̓c�ɂȂǂł͏j���������鎞�ȂǁA�ǂ��̉Ƃł������̉ƂŎ����Ă���{���i�߂ĐH�ׂ����̂�����A���R�����{���i�߂�Z�p�₻�̗����@��g�ɂ��Ă���B�ނ��A���������ɋ߂���Ԃň�����{���ǂ�Ȃɔ��������n�m���Ă���B�����c�����狳������{�̍i�ߕ��́A���ڂ̉H����{�������A���̐�����t�����̐�[���{�̓��̎�������]�Ɍ������Ďh�����ނ��̂ŁA���̕��@��p����ƌ{�������Ƃ��ꂵ�܂Ȃ��Ă��ނƂ̂��Ƃ������B
�@ ����̓s��炿�̐l�X�ɂ͎c�����Ǝv���邩������Ȃ����A��̑O�̓c�Ɉ炿�̐l�Ԃɂ́A����͐����Ă������߂ɕK�v�Ȑ����Z�p�̈�������B�c�����ɂ���ȑ̌���������A�����Ďc�s�Ȑ��i�̎�����ɂȂ�̂ł͂ȂNJ뜜����̂͂Ȃ�Ƃ��Z���I�ȍl���ŁA���ۂɂ́A�ނ��낻�̂悤�Ȍo����ςނ��Ƃɂ���Đ̂̐l�͖��̑������w��ł��������̂Ȃ̂��B
�@ �ዷ�̎�B��H���ɂȂǂʼn��x������������Ƃ̂��錀��Ƃ̑q�{������́A�u�x�ǖ�m�ւ̓��m��]�Ҏ҂ɂ́A�j�����킸�F�Ɉ�x�͎����Ō{���i�߂�̌���������B���ꂪ�o���Ȃ��҂͓��m�����Ȃ��v�ƌ���Ă���ꂽ�B�ނ��A����́A�^�̉������u���҂́A�������܂��A���̐������̖������Ƃɂ���Ă͂��߂Đ����Ă���l�ԂƂ������̖̂{������x�͑̊����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����A�q�{����̌��������O�̂䂦�ł���B
�@ ��������������Ɍ����邩��Ƃ����Ă��A�������ɔ_�H��̖�ǃ`���{��߂܂��ĐH�ׂĂ݂悤�Ƃ����C�͋N����Ȃ��������A���鎞�A�䂪�Ƃ̒��܂ʼn������Ă�����H�̃`���{���A�Ƃ̗���̕��ƕǂ̌��Ԃɂ͂܂荞��œ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ƃ����n�b�v�j���O���������B�`���{���~�o�������ƁA�����܂��c���������̂ق���U��Ԃ��āA�u���܂��炱��𗿗����ĐH�ׂ悤�B�����Ƃ��܂����I�v�Ƃ����Ă��炩���ƁA�u��߂ā[�A��߂ā[�A�{�����킢��������[���I�v�Ɛ^��ōR�c���ꂽ�B����Ȗ��̎p�����Ȃ���A���̂Ƃ��A�������w������̂���o������z���o�����B
�@ �c�ɂ̉䂪�ƂɎ����Ă����{�̒��ɂЂƂ��헧�h�ȗY�{�������B�S�g���������H�тƂ����A���̌����ȑ̌^�Ƃ����A����ɂ͑��̌{�����ɑ���U�����Ƃ����A�Ȃ�Ƃ����i�̂���Y�{�ŁA���͂Ƃ��ɔނɖڂ������Ă����B������̗[���A�A��Ă݂�Ƒc���̑厖�Ȃ��q���䂪�ƂɌ����Ă����B���̂��q�����}���邽�߂������̂��낤�A���̔ӂ̗[�H�́A�{���{�т��͂��߂Ƃ���߂����ɂɂ��ڂɂ����邱�Ƃ̂Ȃ��悤�ȍ��Ȍ{�����ł������B�����A�u�����������̌{�́c�c�H�v�Ƃ����^�₪�c�����̔]�����悬�����̂́A�����ɂ����������ɐ�ۂ�ł������Ƃ̂��Ƃł������B�����A���̗Y�{���p�������Ă��܂��Ă������Ƃ͂��z���̒ʂ�ł���B
�@ �ǂ̉Ƃ����������ɋ߂������𑗂��Ă��������̗����̏ɂ��킦�āA���܂��ܓV��s���ȓ����������̂ق����s�����������Ƃ���A�o�q�����ĂȂ��ɂ͑厖�Ȍ{���Ԃ������Ȃ��Ƒc���͌��f�����炵���B����͂���Ŏd���̂Ȃ����Ƃ������̂��낤���A���ɂ͂Ȃ�Ƃ��߂����o�����������B���ꂩ�炵�炭�̊ԁA�c�����̋��̒��ŕ��G�Ȏv�����Q�����Ă������Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B
�@ �����p�_��̔����̂܂������̕�߂Ă��邤���ɁA���̔]���ɂ��܂ЂƂ��������L�����S���Ă����B���n���ɋ߂����̕��E��Ŋw�Z�Ɏ����čs���A���̕���t���܁A���Ȃ킿�A��̕t�����̂ق�����ɂ��āA�N���X�̒��Ԃ̃Y�{����X�J�[�g�̐��̓����ɋC�Â���ʂ悤�����Ƃ����B���̕�ɂ͉s���Ēe�͐��̂��鑽���̍ג����т������Ă���A���̖т��Y�{����X�J�[�g�̐��n�ɂ������������邩��d�|����̂ɋ�J�͂Ȃ��B����Ȃ��ƂƂ͒m��Ȃ����肪�g�̂����ɂ�Ĕ��̕�͈ߕ��̒�����֏�ւƂ̂ڂ��Ă����B�ʔ������Ƃɂ���Ȕ��̕�͂܂������ĉ��ɗ����Ă��܂����Ƃ͂Ȃ��B
�@ �₪�Ĕ��̕䂪�ҊԂ��畠���ɒB����ƁA���������̏ォ��s����̖ѐ悪�`�N�`�N��
�畆���h���͂��߂�B������ƒ��y���悤�ȃ��Y���Y�Ƃ������o�ɏP��ꂽ����́A���̂Ƃ��ɂȂ��ĂȂ��ς��ȂƋC�Â��킯�ł���B�ٕ�������Ƃ킩���Ă����ƒ��Ȃǂɕ����߂�������E�����肵�Č����ׂ�̂͗e�ՂłȂ�����A�d�|�������̓j���j�����Ȃ��甞�̕�̖\��Ԃ�����ڂŊy���ނ킯�ł���B
�@ ���������A���w����͔_��Ƃ̎��Ԃ������āA�Z�p�ƒ�̎��ԂȂǂɂ͊w�Z���̍؉��Ŗ�ؗނ͔̍|���K�Ȃǂ��s���Ă������̂����A�����͐��삦�̉^���������B�삦���Ɋw���g�C���̐l����A���ۂŋ��ݓ��ꂽ���ƁA���̔삦����S���_�̒����ɒ݂邵�ĉ^�Ԃ̂ł���B��l��g�ɂȂ��Č��ŒS���ł��Ȃ�̋������^�Ԃ̂����A�����������㉺�����J��Ԃ��ɂ�ĉ��̒��̐��삦�ɂ͕��G�ȗh�ꂪ�����Ă���B�����Ȃ�Ƃ������܂������̂ł͂Ȃ��B�����^�Ԃɂ�ăs�`���s�`���Ɛ����悭���ˏオ��������͎̂���̋Ƃ��������炾�B�^�������ƒS���ł���r���ɔ삦���̕R�����Ƃ����ߌ����N�������肵�����̂��B
�@ �Z���搶�⋳���搶�p�̖���͔|���Ă���؉��ɂ͈���قǂɂ����Ղ�Ɛ��삦�𒍂����B���璆�̃L���x�c�Ȃǂɂ́A�t�̉��܂ł��݂��ނ悤�ɏォ��ǂ��Ղ�Ɛl���ƔA�����������̂��B�炿����̈��K�L�ǂ��̂����₩�Ȓ�R�������킯�ł���B
�@ �V�̔������_�H����ӂ̏��i���y���`�ʂ�����肪�A�A�z�Ɏ����A�z�ɗU����܂܂ɁA�Ƃ��Ƃ��������N����̉��������o�����̉�z�ɂ܂ŋy��ł��܂����B������܂��u���f�ؗp�̑�뉀�v�̖����ɐs����Ƃ������̂��낤���B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N5��17��
���{�b�`�R�ɂ�
�@ ���܌܌��ܓ��̌ߑO�A���͕W����Z�܌܃��[�g���̍��{�b�`�R���ɗ����Ă���B�C���͗�x�ɋ߂��A�j���Ȃł��C�͗₽�����A����ɂ͖��V�̐��L����A�͂邩�ɋ������̗͂��ꂪ�������B�O�S�Z�\�x�̓W�]���������̒����̋�͂Ƃɂ����L���B�k�������̊ቺ�ɂ͉��K���珼�{�ɂ����Ă̎s�X�n�̖����肪�w�͗l��`���ĖȁX�ƘA�Ȃ�A��Ɏ����𑗂�ƁA�z�K���牪�J�ɂ����Ă̖��Ƃ̖����肪�A���������Â��z�K�̌Ζʂ���芪���悤�ɂ��ċP���Ă���̂�������B
�@ �k�̋�����グ��ƁA�E���Ɍ������đ傫�����ۂ��X���������̖k�l�����ƁA�������ό`�C���̂v�^�������J�V�I�y�A�����Â��ȋP��������Ă���B�s��Ȃǂł͂Ȃ��Ȃ��������ɂ����k�̈���u�k�ɐ��v���͂�����ƌ�����B�l�S���N�قǗ��ꂽ���̐��́A���̌��̃X�y�N�g�����͂���A���ۂɂ͎O�̐����݂��ɉ�荇���O�d�A�����낤�Ɛ��肳��Ă���B
�@ ��V�ɖڂ�]����ƁA�T�\���������̑傫���̂т₩�Ȏp�������Ă���B�T�\���̐S���ٖ̈������ꓙ���A���^���X�̐Ԃ��P�����ЂƂ��햾�邢�B�ܕS���N�̔ޕ��ɂ��邱�̐��́A���z�̎��S�{������ԐF�������ŁA���łɂ��̐��U�̍ŏI�����}���Ă���B��c���ɂƂ��Ȃ��Ė��x�͐^��ɋ߂��ɂȂ�A�\�ʉ��x���������Ă��邽�߁A�������猩��ƐԂ�������B�₪�Ă͋}���Ȏ��k�ɓ]���A���V���������N�����^���ɂ���ƌ����Ă���B
�@ ���炽�߂ēV�������߂��ƁA�V�̐���͂���ŁA�D�P�ƌ��������̔ߗ��̕����i�������邩�̂悤�ɐ��F�̐������Ă���B�D�P�ƌ����Ƃ̔N�Ɉ�x�̈������͉Ă̎��[�O��̏���Ɛ��Ԃł͑��ꂪ���܂��Ă���̂����A���́A���̓�l�A�l������܌��̍��͑�������N�O���̐[��Ƀf�[�g���d�˂Ă���̂ł���B�����Ƃ��A��l�̊Ԃ��u�Ă�V�̐�̐��͂������ğ���邱�Ƃ��Ȃ��̂�����A�f�[�g�Ƃ͂����Ă��A���݂��ʁX�̊ݕӂɗ����Ė����Ăэ������Ƃ�������邾���ŁA���ۂɕ��i���������Ƃ͓���B����ȓ�l���u�Ă�V�̐�̂����Ȃ��ɂ����ė��������ς��ɍL���Ă���͔̂������B���܂ɂ͐D�P��w���ɏ悹�Č����̗��Ί݂ւƉ^��ł���Ă��悳�悤�Ȃ��̂����A���̔������p�Ɏ����킸�A�����͂Ȃ�Ƃ�����Ȃ悤�ł���B
�@ �D�P�̓��F�K�ƌĂ��Ս��̎启�ŁA�k�V�ł͍ł����邢�Z�E�ꓙ���̌��x�����B��\�܌��N�Ƃ��������߂������ɂ���A��X�̏Z�ޑ��z�n�S�̂́A���݁A��͌n�������̐��̂���ق��ւƌ������ē����Ă���B�����͘h���̈ꓙ���A���^�C���ŁA�\�Z���N�Ƃ�͂肻�̋����͋߂��B���a�͑��z�̈�E���{���x�����A���z�̕S�{�ȏ�̑��x�Ŏ��]���Ă��邱�Ƃ��킩���Ă���B�������łЂƂ���ڗ��͈̂ꓙ���̃f�l�u�����A���̐��͒��a�����z�̘Z�\�{�A���ʂ���\�ܔ{���锒�F�������ŁA���ݖҗ�Ɋ������ł���B�����A���̎����͈�疜�N�Ɛ��Ƃ��Ă͂���߂ĒZ���A�₪�Ē��V���������N�����A�K�X���Ȃ����̓u���b�N�z�[��������^���ɂ���Ƃ����B�����͈ꔪ�Z�Z���N�ŁA���F�K��A���^�C���Ɋr�ׂ�Ƃ��Ȃ艓���B
�@ ���F�K�A�A���^�C���A�f�l�u�̎O�����q���łł���}�`�́u�Ă̑�O�p�`�v�ƌĂ�Ă��邪�A���ۂɂ͑��̓Ɋr�׃f�l�u�����������Ƃ���ɂ���킯���B�����쒆���鎞���͖����l�����炢���x���Ȃ邩��A���̐[��ɎR��Ŏ������߂Ă��鐯��́A�^�Ď��̏��̍��Ɍ����鎍��L���Ȑ���ɑ������Ă��邱�ƂɂȂ�B
�@ �s��ȉF���̃h���}�͐l�m���͂邩�ɒ����Ă���B�������Ȃ���A���Ƃ��ǂ�ȂɉF���̃h���}���������s��ł������Ƃ��Ă��A���̐_��̃h���}�Ɋ����ł���u�ӎ��̎�́v���Ȃ������Ȃ�A�F���̑��݂͂܂�Ƃ��떳�ɓ������B�����ɂ͂����A�����̈ł��͂Ă��Ȃ��L�������Ȃ̂ł���B�����ȏ����ȑ��݂ł͂��邯��ǂ��A�l�ԂƂ������͉̂F����������f�����邽�߂̂����₩�ȋ��̈�ɂق��Ȃ�Ȃ��B���₷���c����������Ȃ�����ǁA�����ĉi���Ɋ������邱�Ƃ̂Ȃ�����������Ȃ�����ǁA��X�l�Ԃ���������Ӌ`�͂���Ȃ�ɂ���̂��낤�B
�@ ��c�����߂����b�ɂȂ��ċ��k�����A���Ď��́A����ȑz�������߂Ȃ���A�u�F���̕s�v�c���킩��{�v�i�O�}���[�A�m�I���������ɁA�e�R�I�F���Ƃ̋����j�Ƃ����{�����������Ƃ�����B�o�ŎЂ̈ӌ��ɂ���Ă���ꂽ��ȃ^�C�g���ɂ́A�����ȂƂ���M�҂̎����g�����X�p�����������o���邪�A����ł��A��ʓǎ҂̕��X�ɍŐV�̉F���Ȋw�̑S�e���Ȃ�ׂ��킩��₷���`���邱�Ƃ��ł���悤�ɁA�T�C�G���X���C�^�[�Ƃ��čő���̓w�͂͌X�����B�ߑ�F���Ȋw�j�Ƃ��Ă��ǂ߂�悤�ɂ���Ȃ�̍H�v���Â炵�Ă�����B��͂���͂܂ł͎��̎��M�A�Z�͂Ǝ��͂͋����҂̋e�R���i����q���y�ђ}�g�F���Z���^�[�����j�̍u����V�����e�����������A�ĕ��͉��������̂����A���݂�����\�Ȃ̂ŁA��������ǂ���������Ȃ�K�����̂����Ȃ����Ƃł���B
�@ ���{�b�`�R�͈��ܖ�암�̉��K�s�̓����Ɉʒu���Ă���B���͐̂��獂����ɍL���邱�̎R�����x�ƂȂ��K�˂Ă����B���Ă̓_�[�g�����������ߔN�͂������萮�����s���͂��A�Ԃł̃A�v���[�`���e�ՂɂȂ����B�R���߂��̒��ԏꂩ����₩�ȎΖʂ��������������ēo�蒸���ɗ��ĂA�����ʂ�O�S�Z�\�x�̃p�m���}�i���邱�Ƃ��ł���B�����߂��ɂ͂�����Ƃ����q������邵�A�ċG�ɂ͎R����тɍ炫�����e��̍��R�A���̉ԁX���y���߂�B�M�B�̍����Ƃ����Ɣ������̂ق����L�������A���́A�K���l�̏��Ȃ����̍��{�b�`�̂ق����D���ł���B���{�b�`�R�̂����ׂɂ͓�烁�[�g����̕W�����������R������A���{�b�`����Ԃœ�\���قǑ���A�������炳��ɓ�\���قǕ����ēo��Ƃ��̎R���ɗ����Ƃ��ł���B
�@ ����̊ώ@�ɂ͂����Ă����̍��{�b�`�R�┫���R�����A���܂ЂƂ|���l�Ȃ��ɑf���炵���̂��A���̒�������̒��]�ł���B�V��ɂ����b�܂��A���{�ɂ���O�烁�[�g�����̎R�X�̂قƂ�ǂ߂邱�Ƃ��ł���̂��B�Ƃ��Ɏl�����{����܌��ɂ����ĂƔӏH���珉�~�ɂ����Ă̓W�]�͔��Q���B�O�����܂ł͎c��̂��ߒ��������̓��H���A�C�X�o�[�����Ă���̂ŁA�r����������Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���̋�J���}��Ȃ��Ȃ�A�������ۂނ悤�Ȏ��ӂ̐�R�̌i�ς���]�̂��Ƃɂ����߂���B���̎����Ȃ�l�Ղ̂܂������Ȃ������̊�������Ɏ��������̑��Ղ���������ƍ��ނ��Ƃ��ł���B
�@ �����͂��܌ߑO���c�c�ԂقǎԂɖ߂��ĉ����������ƁA���͍Ăэ��{�b�`�R���ɘȂ�ł���B�R���ւ̕����ɂ͑����������A�����ʂ��镗�����₽�����A����݂͂��߂���ɂ͉_�̉e��Ȃ�����A�ō��̒��]�����҂ł��������B���̋���݁A�Ԏ�����[�g�F�A�����ĉ��g�F�ւƒ��Ă��̐F���ς��ɂ�āA�c���Ղ��������̎R�X���������p�������͂��߂��B���҂ɂ�����ʑs��Ȓ��]�ł���B
�@ �k���̕����͂邩�ȂƂ���ɂ͐�ԎR�̓����I�ȃV���G�b�g����������ƕ�����Ō�����B���̕��p�ł͒���ɃX�p�b�Ɛ������悤�Ȍ`�����ȎR�����̑��݂��֎����͂��߂��B���ȎR�ɂ͊w������Ɉ�x�����o�������Ƃ����邪�A�������猩��ƕ���Ɍ����邻�̒����т��召�̗n��Ŗ��ߐs����A�z���Ƃ͗����ɂЂǂ��S�c�S�c�����n�`�ɂȂ��Ă���̂͋����������B���ȎR�̉E��ɂ����Ē����傫�ȎR�e�𓌓�����ւƘA�˂Ă���̂́A���x����V��x�A�Ԋx�A�����x�A�Ҋ}�R�Ƒ��������x�A��ł���B�܂������т��Ă���c�Ⴊ�ق̂₩�ȃs���N�̋P�����͂��߂��B�������Ĉ�ԉE�[�Ɉʒu����Ҋ}�R�̗Y��ȃX���[�v�͂����߂Ă��������B���~���̔����x���c�������������̉���������i���A���̎��Ƃ���ɋL���̒ꂩ���S���Ă����B
�@ �Ҋ}�R�Ƃ��̉E��ɘA�Ȃ��A���v�X�A��Ƃ̊Ԃ͑傫����������ł��āA���̈ƕ��̌��������ɂ͕x�m�R�������Ȃ���̏G��Ȏp�������Ă���B�ƕ��̂����肪�b�B�X���̕x�m�����ŁA���̎�O�ɍL����̂��z�K�𒆐S�Ƃ���z�K�~�n���B�����x�A����[�̕Ҋ}�x��I�����ɁA�܂���A���v�X�k�[�̍b���P�x�������ɂ������̕x�m�R�̓y�U���肪���߂���̂́A���̍��{�b�`�Ȃ�ł͂̂��ƂȂ̂��B�b���P�x����A�P���R�A���x�A�k�x�A�Ԃ̊x�ƘA�Ȃ��A���v�X�A��̒����́A�܂��^�����ł���B��̂Ȃ��Ȃ������̍��{�b�`�R�̐A���Q�����Ă܂����Ζ�������Ԃ̂܂܂�����A��A���v�X�A��̒���߂��̂��̖L���ȍ��R�A���Q���͐�̉��ł��܂Ȃ��[���~�̖���ɂ��Ă���ɈႢ�Ȃ��B
�@ ���̑�C���������قǂɐ��ݓn���Ă��邹���ŁA�����͓���ɂ͂邩�ɒ����A���v�X�̋�؊x��ؑ]��P�x�̎p���]�܂��B�������A���̏s���Ȓ�����т͓��̋�ɏ���͂��߂�����̑��z�̌��̒��őN�₩�ȍg���F�ɋP���Ă���B�ؑ]��P�x�̕����̃J�[���Ζʂɂ́A�X�L�[��X�m�[�{�[�h�̓��ӂȎ�ҒB�������������W���A�c��̏�ł��̖��l�|�������������Ƃ��낤�B�ؑ]��P�x�̂������E��A�쐼�̕����ɂ����āA����Ȕ���̉�����A�z������Ɨ���́A�����܂ł��Ȃ��ؑ]�̌�ԎR���B��ԎR�[�̊J�c������w�Œm����ԑ�̔��т͉ߋ����x�ƂȂ��K�˂����Ƃ����邵�A��ԎR���ɂ���x�قǗ��������Ƃ�����B
�@ �^���̕��p�ɂ͏�Ɗx�����̗Y��Ȏp�������Ă���B���{�b�`�R���璭�߂�ƁA�������ɂ��̌`�͑傫�Ȕ���̈Ƃɂ������肾�B��Ɗx����쑤�ɉ��т�Ő��̒Ⴍ�Ȃ���������́A���ԂH���j�ŗL���Ȃ��̖씞�����낤�B�씞�������������̏�Ɗx�����グ��悤�ɂ��Ē��߂����Ƃ����邪�A��͂�n�̈ƌ^�Ɏ��Ă���Ɗ��������̂��B����߂��܂Ŏԓ����ʂ��Ă��邩�牽���ł��o���ƍl���Ă����������낤�A�������߂ď�Ɗx�̒����ɗ������͔̂�r�I�ߔN�̉Ă̂��ƂŁA���̎�����܂��\�]�N���������Ă��Ȃ��B�L�����ԏꂩ������ē�A�O�\���قǂ̂Ƃ���ɂ���ō��n�_�͈ӊO�ɋ����A�Ƃ��y��ŕ����Ă����悤�ɋL�����Ă���B
�@ �����珸�������z�̍��x�����X�ɏオ��ɂ�āA�ቺ�̈��ܖ���͂���Ŗk���������ނ��A�Ȃ�k�A���v�X�̘A�R���A����ȗŐ��𖾂邢�s���N�ɐ��߂Ȃ��炭������ƕ����яオ�����B���{�b�`�R���璭�߂���p�m���}�̎���́A�Ȃ�Ƃ����Ă����̖k�A���v�X�A��̎O�烁�[�g�����̎R�X�ł���B���ʂɈʒu����䍂����A�k�Ɍ������đ����x�A��O�x�A��V��x�A���x�A�G�X�q�x�A�@�؊x�A���������x�A����ɂ͌ܗ��x�A�����x�A���n�x�ƘA�Ȃ��ނ���s���ȎR���݂̔��͈͂��|�I�̈��ɐs����B�Ȃ��ł��A��O�x���V��x�̂���ɐ����Ɉʒu���鑄���x�̗Y�p�ږڂɂ��邱�Ƃ̂ł���ꏊ�͈��ܖ쑤�ɂ͏��Ȃ������ɁA�����̂悤�ɑ����x���͂�����ƌ�������͊������ЂƂ������B
�@ ���܂ł͂������ꂾ���̋C�͂��̗͂��c���Ă͂��Ȃ����A���Ď��͎Ⴓ�ɂ܂����Ă����̕�X�̂��ׂĂj�����B�䍂�A���A���n�ɂ������ẮA�o�������͈̂�x���x�̂��Ƃł͂Ȃ��B�~�̔��n�̎R���߂��ł́A�\�z�O�̋}���ȓV��ω��ɔ����Ґ���ɑ����A��T�ԋ߂��ɂ킽��ᓴ���ł̃r�o�[�O�ɐh�����đς��ʂ��A�㎀�Ɉꐶ�����Ƃ��������B�P�������������܂��Ⴓ�ɖ������Ă�������̗l�X�ȑz���o�ɂЂ��邱�Ƃ��ł���̂��A���̍��{�b�`�Ȃ�ł͂̂��Ƃ��낤�B���邳�ƒg�����𑝂��z���ɐg���ς˂Ȃ��炻��ȉ�z�ɒ^���Ă��邤���ɁA�������A�����P����X����A�u���O���������肨�ƂȂ����Ȃ����Ȃ��v�ƚ����������Ă���悤�ȋC���ɂȂ��Ă����B
�@ ���n�̌�����k�̕��p����킸���ɓ����Ɏ�����]����ƁA�ٗl�Ȋ��Œm����ˉB�R�̂��̂Ǝv����R�e���������ɖ]�܂��B�����āA���̂���ɏ����E��̂����߂��Ƃ���ɂ����āA�܂邭�傫�ȎR�̂������Ă���̂������R���B�����������͂��傤�ǔ����R�̉A�ɂȂ��Ă��邽�ߍ��{�b�`����͒��ڂɂ��̌i�ς�]�ނ��Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@
�@ �������ԏ�̎Ԓ��ɂ��ǂ�A�k�A���v�X�̎R�X���Ȃ����z���ɋ��Ȃ��猴�e�Ɉ������ƁA�y�����H�ƍg���Őg�̂����߂��߁A���ꂩ�炵�炭�������Ƃ����B�ڊo�߂����ɂ͂������߂������߂��Ă��āA�k�A���v�X�̕�X�̋P���͂�������݂�тсA����������������ɕς���Ă����B���ܖ��т̒n�\�̉��x���オ��A�����C���܂㏸�C���������Ă��邽�߂ł���B���܂͂܂���C�Ɋ܂܂�鐅���C�̗ʂ����Ȃ����߂��̒��x�ł���ł��邪�A�����ꃖ��������ƁA���Ƃ����V�ł����Ă����̎����ɖk�A���v�X�̎R���݂]���邱�Ƃ͓���Ȃ��Ă���B
�@ �����R���ʂɌ������ėŐ��`���ɎԂ����O�ɁA���͊ቺ�Ɍ����낷���{�s�X�̈���ɂ����䐟�v����Ƃ������̃A�g���G�ɓd�b���������B���{�b�`�R���珼�{���ʂɉ��������ƁA�A�g���G��K�ˁA���̃��j�[�N�Ȓ�����i�Q��q�������Ă����������Ǝv��������ł���B����͎R�̒����ɂ���Ȃ���A�͂邩�Ɍ����낷�L��Ȗ~�n�̂ǂ����Ɉʒu����Ƃ�������̂���ɓd�b��������Ƃ����̂́A�Ȃ�Ƃ��\����Ȃ��悤�Ȋ�ȋC���̂�����̂������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N5��24��
�A�g���G�E�{�����W���[����
�@ �v�X�ɖK�˂������R�̎R�����ӂ́A���������������������ȑO�Ƃ͗l������ς��Ă����B�M�d�ȍ��R�A���Ȃǂ������т̑��n�ݍr�炳��Ȃ��悤�ɂ���ɂ́A���炩���ߒT���H��݂��Ă����A����ȊO�̂Ƃ���͗�������֎~�ɂ�����Ȃ��̂��낤�B�����R������ʎ�ɕ�����̂͌܌����{�ȍ~�̂��ƂƂ����āA�A�x���Ƃ͂����Ă�������ɐl�e�͂قƂ�ǂȂ��B���邢�z�˂��ɍR�i���炪�j�����̂��Ƃ������ʂ���╗�ɔ��̖т��t���ĂȂ��璸���ɗ��ƁA���{�b�`�R�̂���ƍb��������������̎R�x���i���ڂɔ�э���ł����B�����R�̒�������́A�������≤���@���͂��߂Ƃ�����������ʂ̌i�ς���]���邱�Ƃ��ł���B�����A�����R�k���ʂƔ������쐼�ʂƂ̊Ԃ͐[���J�ɂȂ��Ă��邩��A���ɂł��Ȃ�Ȃ��������O�̔������ւƒ��s����͖̂����ł���B
�@ �R���̓W�]�i���I����ƁA�������R�ƍ��{�b�`�R�Ƃ̊Ԃ̈ƕ��܂Ŗ߂�A��������R�̓����o�ď��{���ʂւƉ��铹�ɓ������B���������Ԃ�̂̂��Ƃ����A�R�̓������ڎw���ď��߂Ă��̓������������ɂ́A�܂��H�ʂ͊₾�炯�̋����_�[�g�ŁA������Ƃ���ŏ��K�͂ȊR�����y�����ꂪ�N�����Ă����B�R�̓��ɏo�邷������O�̂�����́A���S���̎ԗւ����Ԃ��ԂƂʂ��蒾�݁A�Ԏ���Ԓꂪ�₦�ԂȂ��H�ʂ����قǂ̂Ђǂ����H�ŁA�h���h�������ԓy�̋}����Ԃ��ƃX�P�[�e�B���O����悤�ɂ��ĉ������L��������B�����Ƃ��A���܂ł͓������L���Ȃ芮�S�ɕܑ�������Ă��邩��A���S�҂ł��^�]�ɋ�J���邱�ƂȂ����K�ȃh���C�u���y���ނ��Ƃ��ł���B
�@ �{�����炷�����e���ɓ������Ƃ���Ƀ^���̉���̎�ł���|�C���g������̂ŁA������Ɨ�������Ă݂͂����A�܂����������ȐV�肪����o���͂��߂�����ŁA�̂�ɂ͂�����Ƒ��߂����B��X���́A�R�n�𗷂���܂ȂǂɎR�؍̎�|�C���g����̎�|�C���g��T���o���ė��m�[�g�ɋL�^���Ă����A������̕t�߂�ʂ肩���邱�Ƃ�����ƁA�K�v�ɉ����Ă����̃|�C���g���`�F�b�N���Ă݂邱�Ƃɂ��Ă���B��ӂ�k���̂��܂��܂Ȋl���ɂ��Ă����l�̃`�F�b�N�����Ă��邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B
�@ �r���ŎU�X������H�����̂ŁA���{�s�암�̑���Ƃ����w�߂��ɂ����䐟�v����̃A�g���G�A�u�{�����W���[���v�ɒ������̂͂����[���߂��������B�Z���X�̂��������F�̃����K����̊O�ǂƎl�p�����˂̂��郂�_���ȎO�p�����������̃A�g���G�̑O�ł́A����v�ȂƂ��̑��q����̎O�l���A��������Ă��邩�킩��Ȃ����������Ƒ҂��Ă��Ă����������B
�@ ���l�Ƃ͈ȑO����ʎ������������A�A�g���G�̎�ł����䐟�v����Ƃ������̂͂��ꂪ���߂Ă̂��Ƃ������B���������ƁA���݁A��䂳��͓����{���s�̎���̂����߂��ɂ��Z�܂��ł���B��䂳��ɂ͍L�T����Ƃ������q�吶�̂��삳������Ȃ̂����A���N���O�̉ċx�݂̂��ƁA�ӂƂ������Ŏ��͂��̂��삳��̉p��̕����݂Ă����邱�ƂɂȂ����B�w�����˗����ꂽ���Ȃ��u���w�v�ł͂Ȃ��u�p��v�ł��������Ƃ��L�T����ɂƂ��Ă͉^�̐s���ŁA���Ƃ��Ƃ͑�w�̂��߂̉p���u�ǂł������͂��̍u�`�́A�G�w�S�ʂɋy�ԂƂ����ُ펖�Ԃɔ��W�����B�u�G�w�v�Ƃ������Ȃ�����Ό������Ƃ͂Ȃ������̂����A���̒����������s���悭�͂����Ȃ�����A���̍u�`���𗧂����̂��ǂ����͂��܂���̂܂܂Ƃ������Ƃ���ł���B
�@ ��w���ɂȂ��Ă�����A�L�T����͎��X�䂪�ƂɎG�w�̃l�^���d����ɂ���Ă���B����Ȑ܂̔ޏ��Ƃ̉�b��ʂ��āA�����_�H��w�ŕ������������Ȃ����Ă��邨��������������Ă�����炵���Ƃ������Ƃ͎��ɂ��Ă����̂����A����܂Œ��ڂɂ������@��͂Ȃ��������A���̍�i��q������`�����X���Ȃ��܂܂ł������B����ȂƂ���ցA�܂�悭�A��䂳��̌W�����E�̉�L�ŊJ�Â����Ƃ����ē������Ă����̂ł���B����l���ɊJ���ꂽ���̌W�́A������ǔ����͂��߂Ƃ���e�V���̓s���łł��傫���Љ��Ă�������A�ڂɂƂ߂�ꂽ���������邩������Ȃ��B�Ƃ肠�����������Ԃ̓s�������A���E�w���班�����ꂽ�Ƃ���ɂ��邻�̉�L�ɑ����^��ł݂��̂������B
�@ �����W�̉��Ɉ�����ݍ�����҂��Ă����̂́A����ʂɂƂ��닷���Ɨ������ԂȂ�Ƃ��s�v�c�Ȓ����Q�������B�召�̖ؒ������S�����A�����̈�̈�̂����̑̓������ς��ɂ��ꂼ��̕����s�i�͂�j��ł��āA����҂Ɍ������āA�Y�ꂩ�������E�̑z���o�b������������t�̐��X�������ƚ��������Ă���̂ł���B���͂����܂�����璤���Q�̗��ɂȂ��Ă��܂����B
�@ �|�p�ɂ͂܂������̑f�l�̎������A��w�@������ɎG�w�̍u�`�����邽�߁A���܂ɓ����|�p��w�ɏo�������ƂȂǂ������āA�|��̐搶���̍�i���͂��߂Ƃ���D�ꂽ���㒤���̍�i�͂���Ȃ�̐����Ă��Ă���B�����A�����̂��̂Ƃ͂܂�Ŏ���قɂ����䂳��̒����Q�ɂ́A���R舒B�ȓƓ��̍앗������Ă��āA��n�ւ̐[���F��Ɗ��ӁA����ɂ́A�܂����̐��̂ǂ����ɉB�ꐱ�ނ炵�����삽���Ƃ̕s�v�c�Ȍ����̕��ꂳ������z��������Ɠ��̍앗�����Ȃ���Ă����B�ꌩ�f�p�œy�̓����ɖ����݂��Ă͂��邪�A���̉��ɂ́A����҂̐S���₷��킹���ɂ͂����Ȃ��D�����ƁA�l�Ԃւ̐[�������Ɖs�����@�Ƃ���߂��Ă��銴���������B
�@ �ǂ������̓Ɠ��̑��݊���X����~�ɂ������A�܂��M�Z�H�̂������ɂ������ޓ��c�_�ɂ��ʂ���A�f�ނ��Ȃ������������R�Ȓ����̒���Ղ߂Ă��邤���ɁA���ɂ͏��N���Ɋ�䂳��̊�������ďグ�������i��������悤�Ȏv�������ĂȂ�Ȃ������B���{�̑����ׂ�m�`�̗����ɂ́A�䍂����R���p�قɎ��߂��Ă��鉬����R��̃u�����Y�́u���o�v��Â����X�ɗ������ԗ����������䂳���Ǝv����e���̑傫�����Â�������B���̐l�̐S�̉��Ɂu�݂�������M�Z�̍��̈��ܖ�v���ǂ�����ƍ������낵�Ă���̂͋^���]�n���Ȃ����Ƃ������B
�@ ��A�O�S�̂ɂ��y�ԍ������Z���`�قǂ̑f�Ă��̏����Q���D��Ȃ����i���a�V�Ŗʔ��������B�ꕶ����̐l�X��������Ă����i���C���[�W�������̂Ȃ̂����������A���Ƀ��[�����X�Ȋi�D���������`�̒j��������ʂɕ���ł��āA���ꂼ�ꂪ�v���������Ɉ���A�̂�����A�x������A�����b�������肵�Ă���B�Ȃ�قǓꕶ����̎����͂���ȕ��������̂��Ǝv�킸�[�����Ă��܂������ȂقǂɁA�f�Ă��̑��̈�̈�̂������グ�S�g��U�藐���āA�ЂƂƂ��̖��̐��E�ɋ��������Ă���̂������B�u��N��A�Ñ�l�ɂ����l���Ȃ�킯�ł����A���̎��A�����̕��ꂪ�b�����炢���ł��ˁv�Ƃ������肰�Ȃ��Y���������Ȃ��Ȃ������Ă��čD�������Ă��B
�@�@������̘̐̂H�@����͖l�̎v���o�ł���
�@�@�؊��ɍ����ā@�т��猩���锖������̒���
�@�@�l�͗т̒��ց@�n������ł����悤�Ɏv����
�@�@����͑��Â̏o�����Ɂ@�v����y���Ă������ł�����
�@�@�܂��ʂĂ��Ȃ������Ɍ������ā@���������ł����Ă���
�@�@�����₩�Ȋ肢�������̂�������Ȃ�
�@�@���͗���Ă���
�@ �Â��ȑz���̂������䂳��̂���Ȏ���ǂ�ł���ƁA���̐l�̕s�v�c�ȑ��`�̐��E�̉��Ɋm�łƂ��đ��݂�����̂�����Ȃ�Ɍ����Ă���悤�ȋC�����Ȃ��ł��Ȃ����A����ɂ��Ă��A����ȓƑn�I�ȍ�i�Q�ݏo���Ȃ�āA�Ȃ�Ƃ����L���ȗV�ѐS�̎�����Ȃ̂��낤�B�����v���ƁA���͊�䐟�v����ɂǂ����Ă�������Ă݂����Ȃ����B�������A�c�O�Ȃ��Ƃɂ��̓��͂��܂��ܕ����������̂ŁA�W���ł͂��̊肢�͊���Ȃ������B�_�H��Ŏ������߂Ă������䂳��́A���R���̓��͂��d������������ł���B
�@ ���������A������w�̕����������߂Ă�������Ƃ������ƂɂȂ�ƁA���Ԃł͋������̃T�C�R���݂����Ȑl�����Ƃ��̑��ꂪ���܂��Ă���B���̋����T�C�R���݂����Ȃ͂��̐l�����A�~�⋅�Ƃ������ނ��떳��`�ɋ߂��A����قǂɎ��R�ȋȐ���Ȗʂ�����i�Q�ݏo���Ȃ�Ă��������ǂ��������ƂȂ̂��낤�B��䂳��͔���ȂǏo�Ă���ꂸ�A�����̋Z�p�͂��ׂēƊw�Ȃ̂��Ǝf���Ă͂��邪�A���炩�ɂ��̍�i�̎��Ɨʂ͎�̈���A�{�E�̒����Ƃ̈�ɒB���Ă���B
�@ ����ɂ܂��A���ƌ������Ƃ��Ă̖{�������Ȃ��������ł���قǂɖc��Ȑ��̍�i�Q��n���ł���閧�͂ǂ��ɂ���̂��낤�B�_�H��̎��������|�p�H�[�ɕς�����Ƃ����Ȃ�b�͂킩�邪�A����Ȃ��Ƃ͂��肦�Ȃ����A����ɂ��킦�Ċ�䂳��̃A�g���G�͌�v�Ȃ̏o�g�n�̏��{�s�ɂ���Ǝf���Ă���B���̃A�g���G�ɒʂ���̂͋x�݂̓��Ɍ����邾�낤����A�͂͂܂��܂������ėe�ՂłȂ��B����ɂ�������炸�A�{���̂�����⏼�{�̃A�g���G�ɂ͂����Ƃ����Ɩc��Ȑ��̍�i�������Ă���Ƃ����̂ł���B���������ǂ��Ȃ��Ă���낤�Ƃ��������ȋ^��ƁA���̑n��͂̔w�i��T���Ă݂����Ƃ����v�����A�쎟�n�����̉�݂����Ȏ��̋����ɂނ�ނ�ƗN���オ���Ă����͓̂��R�̂��Ƃł͂������B
�@ �W�ɏo�����������A���삳��̍L�T����ɓd�b�����A��i��q���������z�Ȃǂ���������S�[���f���E�B�[�N�ɖk���ܖ�̕䍂���ʂɍs����������Ȃ��Ɠ`����ƁA���ꂩ�炵�炭���āA��䐟�v���璼�ڂɂ��莆���������B�u����͂��肪�Ƃ��������܂����B���̑O�ɖ����f���ƍ����Đ搶�̂��Ƃ�b���Ă���܂��B�f�v���ɐ搶�A������������䍂���ʂɂ��o�|���ɂȂ�R�c�c�v�Ƃ����ꕶ�ł͂��܂鎩�R舒B�Ȗn���̂��̎莆�ɂ́A�A�x���͏��{�ɑ؍݂��Ă���̂ŁA���ЃA�g���G��K�˂Ă��炢�����Ƃ�����|�̂��U���̌��t���L����Ă����B
�@ �n��ɏM�Ƃ͂��̂��Ƃ��Ǝv�������́A���{�b�`�R�������䂳��̃A�g���G�ɓd�b�������A��i����̂��ז��ɂȂ邾�낤���Ƃ�S�����m�ʼn��������Ă����悤�Ȃ킯�ł���B�Ԃ���ɒ��߁A�ē������܂܂ɃA�g���G�̌��ւ��������Ď����ɓ��������́A���̏u�Ԗڂɂ������i�Ɏv�킸����ۂ̂������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N5��31��
��䐟�v���R������
�@ �A�g���G�E�{�����W���[���̒��ɓ������r�[�Ɏ�������ۂ̂́A�t���[�����O�̍L������ʂƑ��ǂɐ݂���ꂽ���i���̒I�ߐs�����悤�ɂ��āA�����Q���т�����Ɨ�������ł������炾�����B���Ȃ����ς����Ă��O�A�l���[�͂��낤�Ǝv����\��L���Ȓ����Q���A���ꂼ��ɌŗL�̃|�[�Y���Ƃ�Ȃ��玩�Ȏ咣�����Ă���̂ł���B���̗L�l�́A�Ȃ�Ƃ��s�ςȂ��̂������B
�@ �����V��ƓV�������A�g���G�̈���ɂ͉��������d�X�g�[�u�������āA���̑O�Ƀe�[�u���ƈ֎q���u����Ă����B�ē����ꂽ�e�[�u���ɒ����Ȃ���d�X�g�[�u�̂ق��ɖڂ����ƁA���邩��ɒg�������ȃI�����W�F�̉����R�������Ă���B���ɂ͂��̉��̂��߂����A���̃A�g���G�̎�̗D�����������S�̏ے����̂��̂ł��邩�̂悤�Ɏv��ꂽ�B
�@ ���߂Ă�������䐟�v����́A���ɏ_�a�ł��̐Â��ȕ��������B�S�g�ɂ��̂����Ȃ����R�ȕ��͋C�̕Y����䂳��̎p�́A������w�̕����������Ƃ������݂̂��d������z�������u�������̃T�C�R���v�̂悤�Ȑl�����ɂ͂܂�Ŗ����̂��̂������̂��B���₩�Ȋ�ɂ�����Ƃ͂ɂ��݂����ȏ݂�X���Ȃ���A�����C���Ɉ��������̉��ꂩ��N���オ�点��悤�ɂ��Ă��b�ɂȂ邻�̎p��q�������Ƃ��A���͂��̕��̓��ɔ�߂�ꂽ�s�������Ɛ��_���̋�����z�����B��䂳��̂ƂĂ��Ȃ��n���͂̔閧�́A���Ԃ̂�����ɂ�����̂���B
�@ ���̂����₩�Ȍo���ɂ��A���ɗ͂̂͂���Ȃ����Ȃ₩�Ȏ��R�̂����Ȃ����l�Ƃ������́A���̃\�t�g�Ȍ������Ƃ͈���āA�ǂ̂悤�ȌǓƂɂ��t���ɂ��ς����鋭�x�Ȉӎu�͂ƔE�ϗ͂��ߎ����Ă��邱�Ƃ��������B���ɁA�����}�X�R�~�l�̒��Ȃǂɂ�����������悤�ȁA�\�ʓI�ɂ̓R�����e�Ŏ��M�����Ղ�Ȍ����蕨�ɂ��Ă���l���Ƃ������̂́A�ǓƂ�t���ɂ͈ĊO�Ƃ��A�����������ɗ������ꂽ�肷��ƁA���ʂ̎コ��I�悷�邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��B���䗠�ł͉�����₻��ɋ߂����݂ɂׂ�����ƈˑ��������Ă���Ƃ������P�[�X�Ȃǂ��悭����b�̂悤���B
�@ �������̉��Ɋm���鐢�E���������̊�䂳��̏ꍇ���A���l�͒����ƂƂ��Ă̌��l�̂��̂����Ȃ������҂ł���A���͎҂ł���A�ʓ|�ȑΊO�I�Ղ̒S����ł�����B�|�v����̔��l��̏����ɂǂ����ʉe�̎����Ƃ���̂��鉜�l�̓����̌����̂����䂳��̌��t�Ȃǂ́A�{�S����̂��̂ɈႢ�Ȃ��B���̌��t���U��łȂ����Ƃ́A�����̒����Q�̒��ɖ����ɉ��l�̃C���[�W�Əd�Ȃ镵�͋C��X������i�����������邱�Ƃ����������B�����A�l�܂�Ƃ���A������҂ɂ��������Ȃ���U�s���̐S�̏��z���A���̏��Ƃ��ČN�ՂȂ����Ă���̂́A�ǂ��l���Ă݂Ă����l�̐��v����̂ق����낤�B�����炭�A�ꋫ���Ȃǂɂ����邱�̕��̂����܂��������͂Ə_��Ȋ��K���\�͂͑�ςȂ��̂ɈႢ�Ȃ��B
�@ �����ɒu����Ă���c��ȍ�i�̐��m�Ȑ��͊�䂳�{�l�ɂ��킩��Ȃ��炵�������B�����{���̂�����⏼�{�̎��ƂȂǂɂ�����̂����킹��ƁA�����[�͂�����Ȃ����낤�Ƃ̂��Ƃ������B�Ñ�̐_�X��`����̐l����z�킹�钤�����烂�_���ȏ������܂ŁA�V��j���l�X�Ȃ������̗��������R�z���ɌȂ̑��݂��֎����Ȃ��痧������ł���̂����A�S�̓I�ɂ́A��������肾�������Ȋ�̕\��ƃ��[�����X�ɂ������镠���̌`�Ƃ���䂳��̍�i�̓����ł���悤�Ɏv��ꂽ�B
�@ �������l��{��D�����Ƃ�����䂳��̍�i�炵���A��r��Ў�Ƀ��b�p���݂̃|�[�Y���Ƃ鑜��A�������萌���ς���Ď�U��g�U���낵���吺�ʼn̂ł��������Ă���炵�������Ȃǂ��������B���������A�ߓ��̌W���ł́A�ꕶ����̎������C���[�W���č��ꂽ�Ƃ��������Q���̂Ƃ�킯������ݕ��̈��[�Ɂu���v�Ɩ����L�������̏��Ђ����肰�Ȃ��\���Ă������A�V�ѐS�������܂ł���Ɛ��Ȃ��Ƃ��̂����Ȃ��B
�@ �����Q�̊Ԃ�����������悤�ɂ��Đ݂���ꂽ���̒ʘH������Ȃ���A�����̎p�Ɏ�����i������炢�͂���̂ł͂Ȃ����ƒT�����肵�Ă݂����A�������肵�Ď�⑫�Œ�����|���ł����Ă��܂�����A�ق��̒����������ɏ����|���ɂȂ��āA�A�g���G���͈��p�j�b�N�ɂȂ��Ă��܂������ł��������B��K�t���A�̉��ɂ͑䏊�����������A���������ƂɁA��i�Q�̐��X�͂��̑䏊�̏���ǂ̒I�܂ł���̂��s���A�䂪���̏t��搉̂��Ă����B���̂ق��ɟ���������̒���K�����������A���̒���K�̃t���A�ɂ������Ԃ�����̒���������ł������A����K�̎萠��̉��₻���ɒʂ���K�i�̘e�ɂ��A�M�Z�H�̓��c�_��C�ߗ��̐Ε��Q��A�z�����镂������̖ؒ���i���u����Ă����B
�@ �ӂƊK�i�e�̒��̂Ƃ���ɖڂ����ƁA����K�����K�t���A�Ɍ������āA�Z���̖_�l�̂��̂𑽐����łȂ����I�u�W�F�����ꉺ�����Ă���B�Ȃ낤�Ǝv���ċ߂Â��Ă݂�ƁA�Z���̖_�Ɍ��������̂͂��ꂼ��h�Ƃ��瓦��悤�ƕK���ɂȂ��Ă��銴���̒j���̖ؒ���i�ŁA�����ɐ�����ʂ��Ȃ��Œ݂邵�����̂������B�H�열�V��̍�i�u�w偂̎��v���C���[�W�������̂Ȃ̂������ŁA�܂�����r���Ƃ̂��Ƃ��������A�Ȃ�قǂƎ��͂��̃A�C�f�B�A�ɂЂ����犴�S������肾�����B
�@ ��䂳��O�N���A���悤���^���̎�T���ԂŒ������͂��߂Ă��獡�N�ŏ\�ܔN�قǂɂȂ�炵���B��l�̂��q�����w�����炢�ɂȂ������A�e�Ƃ��Ă̑��݂̏����炩�̂������Ŏq�������Ɏc�������ƍl�����̂��A��O���N�̂��������ł������Ƃ����B�Ȃ�̖������Ȃ��A�͂�����Ƃ������������Ƃ��낪�A�܂����̕��̐����Ƃ���ł�����B���ꂩ�����܂Ƃ��ȍ�i�ЂƂq�������̂��߂Ɏc�������ɂȂ����Ȃǂɂ́A������Ǝ��̒ɂ��b�ł͂������B
�@ �����Ƃ��A�䂪�Ƃ̏ꍇ�Ȃǂ́A����ɍ�i�܂����̂��̂��c�����Ƃ���ŃS�~���Ɏ̂Ă���̂��������낤����A�͂Ȃ��炱����͐�ӑr���ł���B�ǂ����c���Ȃ�Ƃ�y�n�Ȃǂ̎��Y�̂ق����悢�Ȃǂƒ���������ꂻ�������A����Ȃ��̂��c����\�͂����邭�炢�Ȃ�A����Ȃ����Ȃ����e�Ȃ����Ă���͂����Ȃ��B
�@ �ЂƂ킽���i�Q��q���������Ƃ܂��d�X�g�[�u�̑O�ɍ���A���l�̎藿���ɐ�ۂ�ł��Ȃ����䂳��⑧�q����Ƃ����ܘb�ɉԂ��炩���͂��߂��̂����A���܈�����C�ɂȂ邱�Ƃ��������B���̂ق��ɒ��F�p�痿�Ȃǂ�����������u����Ă͂��邪�A�����ケ�̃A�g���G�͒�����i�̎��[�q�ɂ݂Ȃ��ȏ�ԂɂȂ��Ă���B�A�g���G�Ƃ͂��Ƃ��ƍH�[�̂��ƂȂ̂�����A��䂳������蒤�����������肷��ꏊ�������Ȃ��Ƃ����̃A�g���G���̂ǂ����ɂȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�Ƃ��낪�A����炵���ꏊ�������̂ǂ��ɂ���������Ȃ��̂��B
�@ ��������̂ق��͂����ɓ䂪�������B��䂳�ڂ̑O�ŔR������d�X�g�[�u�̌����J���A�o���オ��������̑f�Ă��̑���A�O�[�����o���Ƃ�����������Ŕq����������ł���B��œy������Č`��A��������̐d�X�g�[�u�̒��ɓ���ďĂ��グ��Ƃ����A�������ăV���v���ȕ��@�ŁA���̎O�S�[���郆�j�[�N�ȁu�ꕶ�R�c�v�͏o���オ�����炵���̂��B���낢��Ǝ��s���낵�Ȃ���䗬�œy�����ˁA�Ή������悭�킩��ʂ܂܂ɏ����������I�ɏĂ��Ă݂Ă���̂����������A�o���オ���������̕s�v�c�Ȗ��͂Ƃ����A���̐��̑����Ƃ����A�B�X�����������ł���B�Ă����ȂǂƂ����ƁA�ǂ����Ă���|����Ȑݔ���z�����Ă��܂��̂����A�H�v����ł́A����ȊȒP�ȕ��@�œ����̂悤�ȍ�i�ݏo�����Ƃ����Ăł���̂��B
�@ �̐S�̖ؒ��p��Əꂪ��������Ȃ��̂��ǂ���ł������B�Ȃ�Ɗ�䂳��̖ؒ��H�[�A���Ȃ킿���^�����̃A�g���G�̂ق��́A�A�g���G����i���[�Ɂi�H�j�̗��Ɍ��Ă�ꂽ�����قǂ̂��������ȃv���n�u�����������̂��B������Ɣ`�����Ă��炤�ƁA�ȑf�ȑ���̂��̏����̒��ɂ́A�傫�Ȗؐ������܂�����͂��߂�����̌��ؗށA�e��H��Ȃǂ��������ƕ��ׂ��Ă��āA���Ƃ͑�l�ЂƂ肪����ƍ��������邭�炢�̃X�y�[�X�����邾���������B
�@ �O�@�͕M��I����栂ł͂Ȃ����A�ق�Ƃ��ɐ������߂đn��ɑł����ސl�̎d����Ƃ͑�̂���Ȃ��̂��낤�B����܂łɂ����x�����̓��̑�ƂƌĂ��H�|�Ƃ��Ƃ̍H�[�������Ă��炤�@����������A���ʂ��Ă���̂́A�ӊO�ȂقǂɊȑf�ł������Ђǂ��G�R�Ƃ��Ă��邱�Ƃ������B���Ƃ��ƍH�[�Ƃ́A��Ƃ��S�g�Ƃ��ɗ��ɂȂ�A���݂ǂ댌�݂ǂ�̂Ȃ��Ő����̌����s���ČǓƂȐ킢�𑱂��郊���O�Ȃ̂�����A�Y��ŗ��h�Ȃ킯���Ȃ��B�����狷���đ��̓��ݏ���Ȃ��悤�Ȃ��̍H�[��ڂɂ��āA���͖��ɔ[���̂����C���ɂȂ����B
�@ ��䂳��́A�Ƃ��ɒ����p�̑f�ނ�I�Ԃ��Ƃ͂����A���܂��ܖ�R�ŏE�����肵���ؕЂ�؍ނȂǂł����ׂĒ����̍ޗ��ɂ��Ă��܂��B�ǂ�Ȃɂ݂��ڂ炵���s���D�Ȍ��ɂ����Ă���Ȃ�̐������h���Ă��邩��A��������R�Ɉ����o���������悤�ɂ��Ă��A�����Ȃ��ʔ�����i���o���オ��̂��Ƃ����B���Ƃ��A���H���̂Ђǂ������炯�̑f�ނł����Ă��A���̒��H���������̂܂܍I�����p���Ă��܂��A�Ȃ�Ƃ����̂���Ƒn�I�ȍ�i�ɉ����Ă��܂��̂��B���ہA���H�����������ɐ����������������[������ł������B
�@ ���炩���ߑz���`���Ă���ʂ�̍�i�����������邽�߂ɗǎ��̑f�ނ�I�ԂƂ������@����䂳��͂��܂�D�܂Ȃ��B���̐܁X�Ɏ�ɂ���f�ނƐS�̑Θb�����x���J��Ԃ��Ȃ���A���̑f�ނ̔�߂閽�ƍ�҂̖��Ƃ̎��R�ȗZ���̂�n��o���Ă����Ƃ����̂���䂳��̒����ƂƂ��Ă̐M���ł���B���̊�{���O�������O���Ȃ��n���͂̌���Ȃ̂��낤�B�܂����������ł���Ƃ���A���Ԃ�̍�i�݂����Ȃ��̂Ȃ�ǂ�ȏꏊ�ɂ����Ă����삪�\�ƂȂ�B�K�������H�[�ɂ������Ďd��������K�v���Ȃ��Ȃ�킯���B�\�ܔN�قǂ̊Ԃɉ����[�ɂ��y�Ԗ��͓I�Ȓ�����Y�������܂ꂽ�̂́A�ǂ�����䂳��̂���ȑn�엝�O�Ƒn��p���̎����ł������炵���B
�@ �[�H����y���ɂȂ������Ƃ�������b������ł��܂������߂ɁA���̔ӂ͌��ǃA�g���G�ɔ��߂Ă��炤���ƂɂȂ����B���f�Ȕ�ѓ���q�̂����Ŋ�䂳���v�ȂƑ��q����̎O�l�͈�K�̒����Q�̂����Ȃ��ɐQ���~���Ă��x�݂ɂȂ�H�ڂɂȂ�A���ЂƂ肾��������K�̏�̊Ԃɕ~���ꂽ�z�c�ŋx�܂��Ă��炤���ƂɂȂ����B���̕z�c�̂����߂��ɂ����Ȃ�̐��̒�������������ł��āA���������ڂŒ��߂Ȃ��疰��ɂ����Ƃ͂Ȃ�Ƃ��s�v�c�ȑ̌��������B���̃A�g���G��K�˂Ă݂Ăق�Ƃ��ɂ悩�����Ǝv���Ȃ���A�Җڂ��邤���ɁA���������͐[������ɗ����Ă����B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N6��7��
���Ԃ͑z��ʕ�����
�@ ���������ܖ�͐��V�Ɍb�܂�Ă���B�ߑO���ɂ͂����������Ƃ܂������ł����̂����A�A�g���G�̃e�[�u����q���Ă������̌��e�̐��������Ă��邤���ɂǂ�ǂ�Ǝ��Ԃ��o���Ă��܂��A�C�������Ƃ��ɂ͂����ߌ���炢�ɂȂ��Ă��܂����B�����āA���ǁA�u�悩�����牓���Ȃ������Ɣ����Ă����Ă��������v�Ƃ�����䂳���v�Ȃ̂����t�ɊÂ��A������ӂ����A�g���G�ł����b�ɂȂ邱�Ƃɂ����B
�@ ���e�̏������I����ɏo�Ă݂�ƁA��䂳�S�y�����˂Đ��[�̓����̌��^������Ă�����Ƃ��낾�����B���ӂ܂������̑��͐d�X�g�[�u�ŏĂ���邱�ƂɂȂ�̂��낤�B��ӏĂ��������������̗����́A���łɒI�̏�ɂ����ƕ��ԓꕶ�����Q�̒��ԓ�������Ă����B�Ă��O�ɋ��⍘�̂�����ɋ⎆���������Ă����Ƃǂ̂悤�Ȏd�オ��ɂȂ�̂��������Ă݂��̂��Ƃ̂��Ƃ��������A���傤�ǃu���W���[���⍘�����ɂ�����Ƃ���̔��̐F�����Ă������ɂ��̂܂c���������ɂȂ��Ă���A�Ȃ��Ȃ��ɖ������������B�ꕶ���̏������u���W���[�Ȃǂ����Ă����̂��ǂ����Ƃ������Ƃ��āA���Ȃ��Ƃ��u�����i�H�j�v�̌���̒j�ǂ��ɂ͑傤���������ȍ�i�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ������B
�@ ��̈�p�ɂ̓����S�_�Ƃŕs�p�ɂȂ蔰�̂��ꂽ���̂��Ƃ��������S�̎�����ʂɐςݏd�˂��Ă����B�������A���������Ē����̍ޗ��ɂ�����A�~��ɐd�X�g�[�u�̔R���ɂ����肷�邽�߂ł���B���̂����ł��������̂��낤���A�����S�̎��͂�������Ƃ��Ă��đz���ȏ�ɏd���������B�ؖڂ������Ԃ�Ƌl�܂��Ă��āA�@���Ă݂�Ƒ����ɍd�����G������B����n�Ɉ���͕K�R�I�ɂ��̂悤�Ȗ؎������Ȃ������ƂɂȂ�̂��낤�B
�@ �ߌ�A�F����i�������Ƃ���ł����̎��ԂɂȂ����̂ŁA���͋v�X�ɎԂ̃{�b�N�X����n�[���j�J�����o���A����̈Ӗ������߂ĉ��Ȃ��������̃����f�B�[�����t�����Ă��炤���Ƃɂ����B�Ⴂ����Ƃ͈���ċߍ��͂�قNjC�����̂�Ȃ�������n�[���j�J�𐁂����Ƃ͂Ȃ����A�ꉞ�r�O�̂ق��͂��������l�l�ɒ����Ă��炦�郌�x���ɂ͒B���Ă���B�Ȗڂ́u�r��̌��v��u���R���v�ɂ͂��܂�A�u�ٍ��̋u�v�ȂǂƂ����ő����ΓI���݂Ƃ��Ȃ��Ă���Â��Ȃɂ܂ŋy���A��䂳��͂�������ڂɗ܂��������ׂȂ��玄�̂��Ȃ����t�ɒ��������Ă����������B
�@ ���ł�����q�ׂĂ����ƁA�u�ٍ��̋u�v�Ƃ����Ȃɂ��Ă͉��������z���o�������B������̑O�̘b�ł͂��邪�A���k�̎R�ԕ��̂���ЂȂт�����h�Ɉ�l�Ŕ��܂����Ƃ��̂��ƁA�[���A���܂����̓n�[���j�J����ɂ��Ă��̋Ȃ𐁂��Ă����B����ƁA�ˑR�A���h�̓�\�l�قǂ̘V��̒c�̋q���炨����������A�L�������킳�����~�ɘA��o����āA�u�ٍ��̋u�v���͂��߂Ƃ���펞���̖��̐��Ȃ��J��Ԃ��J��Ԃ��Ɖ���������H�ڂɂȂ����B���̘V�l�����͊F���ċ����R�̓��������ɑ����Ă����̂������ŁA���傤�ǂ��̔ӂ��̏h�Ő�F����J���Ă���Ƃ��낾�����炵���B�Ƃ��낪�A�����֎v�������Ȃ������o�i���炦�j�ނ��̋Ȃ������Ă����̂ŁA�����m�炸�̎����Ă�ʼn��t�����Ă��炨���Ƃ������ƂɂȂ����̂��������B
�@ ���̐l�X�͊F���܂Ɉ�тȂ��牉�t�Ɏ����X���Ă��ꂽ����łȂ��A���ړI�Ȑ푈�̌��ȂǂȂ��Ⴂ���̑t�ł郁���f�B�[�ɍ��킹�āA�升���̐����N������������������̂������B���͌R�̂��͂��߂Ƃ���펞���̉̋Ȃ��Ƃ��ɍD�Ȃ킯�ł��Ȃ�ł��Ȃ��������A�K�������̋Ȃ��Ȃ�Ƃ��������Ȃ��͂����̂ŁA�ǂ��ɂ����̏���Ƃ�����Ƃ͂ł����B
�@
�@ �n�[���j�J���t���I���A���ܖ���ӂ̂��Ƃɂ��Ă��ꂱ��Ƙb�ɉԂ��炩���Ă��邤���ɁA�ӂƂ������Ƃ���䍂�̐Γc�B�v�V�i�ߓ��ٍ̐e�u�l���͗l�W�N�\�[�p�Y���v�ŏЉ���l���j�̂��Ƃ��b��ɂ̂ڂ����B�����āA������_�@�Ɏ��Ԃ͑z��ʕ����ւƓW�J���Ă����͂��߂��B���̓��͐Γc�h���L�����V�����C�ɓ���́u�\�O���̋��j���v�ł͂Ȃ������̂����A���������̋@������䂳���v�Ȃƈꏏ�ɐΓc���K�˂�̂������Ȃ��ƍl���A���͂Ƃ肠��������ɓd�b�������Ă݂��B����ƁA�^�悭�ƌ����ׂ����^�����ƌ����ׂ����͂킩��Ȃ����A�Ƃ������A�u���Ђǂ����v�Ƃ̉����邱�Ƃ��ł����̂ł���B
�@ �܂����̂悤�Ȍo�܂ŁA�[���A����v�ȂƎ��̎O�l�͕䍂���L���ɂ���Γc���K�₷�邱�ƂɂȂ����B�����Đl�H���V�l�i�H�j�̉a�H�ɂȂ�댯��Ƃ��Ă݂悤�Ƃ����킯�ł���B���\�]�Ƃ����N��̂䂦�ɂ��Ẳs���͎����Ă����Ƃ͂����A�h���L�����V�l��ዂ��Ă��͂�Ă��h���L�����V�l�ɂ͕ς��Ȃ��B�}�Ȃ��Ƃ䂦�\���˂�j���j�N�Őg���ł߂�Ђ܂͂Ȃ������̂ŁA��X�́A�����ɐΓc��ւ̓r��ɂ���X�[�p�[�}�[�P�b�g�Ŕ��������i�Ɖʕ������Q���A����̐H�~��������̂ق��ւƂ��炷���ɏo���邱�Ƃɂ����B���̌��ʂ̂قǂɂ͐r���^������������A���ɕ��@���Ȃ������̂ł��̍ۂ�ނ����Ȃ����Ƃł͂������B�ǂ��l���Ă��A���i��ʕ��̂ق�����X�����������ɂ��܂��Ă���̂����A�����ɋC�܂���ȑ��肾���Ɉ�ؓ�ł͂����Ȃ��Ƃ��낪�Ȃ�Ƃ����ȂƂ���ł͂������B
�@ ����Ȑg�̓Ƃ�Z�܂����Ƃ������Ƃ������āA�Γc��ɂ̓Z�R�����J�������Ƃ���������ȊĎ����u���ݒu����Ă���B���֎��ӂ̉f���Ɖ������펞���A���^�C���Ŏ��W�ł��邱�̑��u�̂������ŁA�������N�����Ƃɋ߂Â��ƁA�����ɂ��Ȃ���ɂ��Č���̃h���L��������͂��̗l�q�������͂₭�@�m���邱�Ƃ��ł���B�K��q���m������ł�������A�����������肵�悤���̂Ȃ�A����炪�݂ȓ������ɂȂ��Ă��܂��A���ƂɂȂ��Ă���f�m��ʊ�ł��킶��Ɣ�������Ղ�ɋt�P���ꂽ�������킯���B�����A���łɂ��̗��d�|����m���Ă��鎄�ɂ́A���Ȃ��Ƃ����̎�������͒ʗp���Ȃ������B
�@ �Ă̒�A�����炪�߂Â��̂������������m�����Γc�V�́A���Ɏ~�߂��Ԃ����X���~��I����܂��ɏ�����̂ق�����k�[�b�Ǝp�������A�Ԃ̂��ɋ߂Â��Ă����B���̃^�C�~���O���Ȃ�Ƃ��▭�Ȃ��̂�����A�������m��Ȃ��l�Ȃǂ͋����Ă��܂����Ƃ����Ȃ��Ȃ��炵���B�Ƃ���������X�O�l�͂������ĐΓc��̌��ւɗ������ƂɂȂ����B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N6��14��
�h���L�����@�̏�
�@ ������ƌÕ��Ȏ�̂��錺�ւ̃h�A���J���A���邳��}�����ԐڏƖ��̎����ɓ������Ƃ���A�u�Ȃ��Ȃ��f�G�ȕ��͋C�ł��˂��v�Ƃ����ꂫ�����v�l�̌�����R�ꂽ�B�����̕ǂ��V�����������ÂтĂ��܂������Ȋ����Ȃǂ܂��������Ȃ����A����߂ăZ���X�̂������x�i���▭�Ȍv�Z�Ɋ�Â��Ĕz�u����Ă��āA���̉Ƃ̎�l�̂��Ȃ������ӎ��̐[�����Â��B�������A���ꂪ���͂Ȃ��Ȃ��ɋȎ҂Ȃ̂ł���B
�@ �������Ƃ����C���ɂȂ��ĉ��ڊԂ̈֎q�ɍ������낵�����v�Ȃ��A���炽�߂ď��Ζʂ̈��A�����킻���Ƃ������̏u�ԁA�Γc�V�̌�����A�W���[�N�Ƃ�����Ƃ����ʌ��t�����˖C�̂悤�Ɏ��X�ƌ����o����͂��߂��B����܂łɉ��x�����̉p���d���݂̌��t�̏e�e�𗁂сA�|�S�̊Z�ɐg���ł߂Ȃ��瑦���ɉ��V���邷�ׂ��w��ł��܂������́A���܂�������͂��Ȃ������B�����A���߂Ă̐��������v�Ȃ̂ق��͕Ԃ����t���Ȃ����]�������ł���B���y�Y�̎��i�̂ق��Ƀh���L�������̐H�~��������悤�ɂ��悤�Ƃ������́A����̐搧�U���̂��߂ɂ����Ȃ��ڍ����A�V�Q�̂���l�͓�����܂邩���肳����ԂɂȂ��Ă��܂����B
�@ �[�ł������Ă͂������A���r�������Ȃ����������ł܂����Ȃ薾�邳�͎c���Ă����̂ŁA��X�̓h���L�����@�̒�ɍ~�藧�����B���̕s�v�c�ȋ�Ԃ����߂ĖK�˂��҂́A�l�X�Ȓ������A����ؗ��̐����邱�̒�̈���ŁA�ꕗ�ς�����u�ʉߋV��v���邱�ƂɂȂ��Ă���B��̉��̂ق��ɂ͉��{���̐ԏ��̑�������Ă���̂����A�����̎��Ԃ����̒ʉߋV��̕���ƂȂ�B���~�̗���ɂ����邻�̏ꏊ�̌������ɂ́A���ł��Â��T���Ƃ����ԏ��̖����т��ǂ��܂ł������Ă���B
�@ ���͎�̘V���̗v���ɏ]���Ƃ̈�p�ɂ��镨�u��������傫�ȃn�����b�N�����o���ƁA��䂳��̋��͂����œ�{�̐ԏ��̊Ԃɂ����A���̗��[����������Ƒ������̊��ɌŒ肵���B���̃n�����b�N�́A�J�i�_���̂��̂��Ƃ������傫���Ċ��ȑ���̂�����̂ŁA��l��l������ŋ����ɐQ���ׂ����肵�Ă��т��Ƃ����Ȃ����A�O�l����ō��|���A�u���u������Ă����C�ł���B�����āA���̃n�����b�N�ɐg���A�ԏ��̖ؗ��̊Ԃ��������グ�Ă������V���𖡂������A��̐Γc���������ď��X�Ƀn�����b�N�ɍ������낵�L�O�B�e�������肷��̂��A���̗��K�҂̒ʉߋV��Ƃ����킯�Ȃ̂��B�ނ��A���̊Ԃ����t�̏e�e���e�͂Ȃ����ł���B���߂Ă�����K�˂��Ƃ��A�������̒ʉߋV���̌��������A���̈ē��ň�x������K�˂����Ƃ̂��錊���j�m�L���X�^�[�Ȃǂ����̐���������B
�@ �Ă�H�̑u�₩�ȓ��ȂǁA���̃n�����b�N�ɗh���Ȃ���Ƃ�Ǐ��ɒ^������Ė����ނ��ڂ����肷��̂́A�ō����ґ�Ƃ����邩������Ȃ��B���Ă̎��Ɠ��l�Ƀh���L�������̓ŋC�̋]���҂ƂȂ�������R�s���C�^�[�Ȃǂ́A�A�C�f�B�A�ɍs���l�܂�Ƃ��̉��~�ɂ���Ă��āA�n�����b�N�ɗh���Ȃ��炠�ꂱ��Ƒz��������肷��̂��Ƃ����B���ɂ����x���o�������邪�A�ʓ|�ȎG������ؖY��Ă��̃n�����b�N�ɉ������A�����ʂ��镗��ؘR����ɐg���ς˂Ă���ƁA�ǂ�����Ƃ��Ȃ��s�v�c�Ȋ��͂��N���������Ă���B
�@ �Ƃ���ŁA���̃n�����b�N�����A���N���O�A���o�ŎЂ̐�`�|�X�^�[��ʂ��đS���I�ɂ��̗l���̈�[���Љ�ꂽ���Ƃ�����B���D�̍L�����q�����ɖ{����Ƀn�����b�N�ɏ���Ă���p���f�ڂ����W�p�Ђ̃u�b�N�t�F�A�p�|�X�^�[�������Ă���������邾�낤���B���������ƁA�L�����q���������낵�Ă����傫�ȃn�����b�N�����́A�h���L�����@�̂��̃n�����b�N�ɂق��Ȃ�Ȃ��B
�@ �W�p�Ђ̂��̃|�X�^�[���B�e�����s�쏟�O�J�����}���́A���܂��ܖK�˂����ܖ�ł��Ă̎��Ɠ��l�ɐΓc�h���L�������̉a�H�ɂȂ�����l�ł���B���݂ł͎������ӂɂ��Ă�����L�\�ȃJ�����}���ŁA�܂������̋��R�Ȃ̂����A����AIC���ŏё��ʐ^�~���[�W�A����S�����Ă������c�h��Y����̂���q����ł�����炵���B�܂��邲�ƂɃh���L�����@�ɏo���肵�A���̃n�����b�N�̑��݂�m���Ă����s��J�����}���́A�W�p�Ђ̐�`�|�X�^�[�̎B�e�ɐ旧���ē����܂Ńn�����b�N�𑗂��Ă��炢�A�L�����q������ɏ悹�Ă�����̎ʐ^���B�����̂������B
�@ ���K��̊��v�Ȃ́A�Ƃ������A���̂��킭���̃n�����b�N�ɍ������낵�Ĉ�ʂ�̋V����ς܂��A����ɁA�������ɂ���A�ǂ����d�������͋C�̏����ȘI�V���C���w�̂ق��������ɏI�����B�L�荇�킹�̍ޗ����g���ĐΓc�����炪���������̘I�V���C�����w����̂��ʉߋV��̈�ɂȂ��Ă���B�ď�Ȃǂɉ����̕��C��̋���������z�[�X�ł����������Ă��ē��D�����A�ؗ��̗��̉_�����Ȃ����������̂����A���ۂɑ̌����Ă݂�ƕ����Ȃ��Ƃ��̂����Ȃ��B�����A������̂ق��́A�n�����b�N�ƈ���Ă��N�ł��̌��ł���Ƃ����킯�ɂ����Ȃ��̂���_�̂悤�ł���B
�@ ���̘I�V���C�̘e�ɂ͎}�U��̂����u�G�S�̖v�������Ă��ĉĂɂ͔����Ԃ�����B���̃h���L�����@�̎�l�̏ے��݂����Ȗ��������̖����Ƃ��Ƃ����ɐ����Ă������̂Ȃ̂��A����Ƃ��Ӑ}�I�ɂ����ɐA����ꂽ���̂Ȃ̂��͂킩��Ȃ��B�������A�u�G�S�̖̉��ł͉�������Ă������v�ȂǂƈӖ����肰�ȟ������t��ꂫ�Ȃ��痈�K�҂����Ɋ����V���̎p�����Ă���ƁA�v�Z����s�������̂̂悤�ɂ��v���ĂȂ�Ȃ��B
�@ �n�����b�N�������݁A����ꏄ�肵�ĉ��ڊԂɖ߂����Ƃ��ɂ́A������͂�������Â��Ȃ��Ă����B�������߂ďo���������Ɋr�ׂ�A�������̃h���L�������̋C�͂��̗͂������Ԃ�Ɨ����Ă����悤�ł���B���̂������A��X�ɗ��т��������錾�t�̏e�e�̐��������̌o�߂ƂƂ��ɂ���Ǝ�܂��Ă����B�����ł͐��������z����悤�ȎႢ�����ɉ�舧�����Ƃ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂��낤���B���ꂪ�����̌����Ȃ̂�������Ȃ����A�ŋ߂̎Ⴂ��������ɑ���ɂ����肷��ƁA�h���L�������Ƃ����ǂ��t�Ɍ����z���Ă��܂����˂Ȃ�����A�悯���ɋC�͂Ƒ̗͂̈ێ��͓���̂�������Ȃ��B
�@ �Ƃ������A����ɔ�ꂪ�����͂��߂��Ƃ�������v���ĉ�X�͎��Q�������i��ʕ������o���A�������e�[�u���ɕ��ׂĂƂ肠�����[�H�ɂ����邱�Ƃɂ����B�H�����Ƃ�Ȃ�����l�l�̊Ԃʼn�b�͒e�B���ς�炸�Γc��������ł͂��������A���̈���I�Ȍ��t�̗������܂��Ă������Ƃ��K�����A���݂��̉�b�����܂����ݍ����悤�ɂȂ��Ă����B�����āA�H��̂������y���ލ��ɂ͖����������ƍX���A�܂�ł���Ɍĉ����邩�̂悤�ɂ������肤���Ƃ����C���ɂȂ�����X�́A���ʂĂ�Ƃ��Ȃ��k�ɉԂ��炩����L�l�������B
�@ ����Y��Ęb�����ނ����ɁA�����������͏\�ꎞ�߂��ɂȂ��Ă����B���낻�남���Ƃ܂��Ȃ���Ƃ������ƂɂȂ�A�����グ�����v�Ȃ͋A��O�ɂ�����ƃg�C���ɗ�������Ă݂邱�ƂɂȂ����B����A�����Ɛ��m�ɂ����ƁA�g�C���́u���w�v�ɂ������ƂɂȂ����B�����A�h���L�����@�ɍs������g�C����`���Č��邱�Ƃ����͖Y��Ȃ��悤�ɂƁA���炩���ߐ�������ł����������ł���B�����̃g�C���ɂ͖Y��邱�Ƃ̂ł��Ȃ��z���o���������B
�@ �䍂�̉w�O�ł��̕s�v�c�ȘV�l�ɂ��܂�A���߂Ă��̉��~�Ɉē����ꂽ��̂��ƁA���炭��b�����킵�����ƂŎ��̓g�C���ɗ��Ƃ��Ƃ����B����ƁA�Γc�V�́A�u���̉Ƃ̃g�C���ɂ͂�������ꎞ�Ԃ͏o�Ă����܂����v�ƌ����ăj�����ƈӖ����肰�ɏ����̂������B�ē����ꂽ�g�C���̑O�ɗ��ƁA�Ȃ�ƃh�A�Ɂu�v�n�q�j�r�@�b�q�d�`�s�h�u�d�v�ƋL����Ă���ł͂Ȃ����B�v�Ƃb�����͐Ԃ������ɂ��Ă�����B���Ȃ��u�v�E�b�v�ł����́u�v�E�b�v�́u�n���I�ȍ�i�v���邢�́u�n���I�Ȏd���̎Y���v���Ƃ����킯�Ȃ̂��B�ǂ�ǂ�Ƃ���Ƀh�A���J���Ĉ�����ɓ��������́A�v�킸���Q�̐������������ɂȂ����B
�@ �L�X�Ƃ�������̃g�C���̒����ɂ͐��m���̕֊킪����A���̍���ɂ͖̒I�������āA�ʔ������Ȗ{������������ł����B�ȒP�ȃ����p�m�[�g�炵�����̂�����B�֍��ɂ�������܂܂Ŗ{����Ɏ���ēǏ��ɒ^������A�v��̂����ɃE�[���Ƃ���ɍi��o�����Ƒn�I�ȃA�C�f�B�A��������������ł���킯���B�����A�����܂łȂ炽�܂ɂ���b�ŁA���������قǂ̂��Ƃł͂Ȃ��B�����ڂ�D��ꂽ�̂̓h�A�̗��ʂ��܂߂��O�㍶�E�̕ǖʂƓV��̖ʂ������B
�@ �����̊e�X�̖ʂɂ͒������召�̃|�X�^�[��ʐ^�ށA�G�t���ނȂǂ������ȍ\���Ɣz��œ\��߂��炳��Ă����̂ł���B����L���Ȏ��R�̕�����C�O�̖������ՂȂǂ̊G��ʐ^�A���ꂼ��ɕ�����߂��l�X�Ȓj���̒������ʐ^�A���邩��ɓƑn�I�Ȍ|�p��i�̎ʐ^�≽�����̔��p�W�̎𗎂��|�X�^�[�ƁA�ǂ̈ꖇ�����܂����Ƃ��Ă��A�Ȃ�Ƃ������Ȃ��قǂɖ��̂�����̂��肾�����B�召���킹��Γ�A�O�S���͂��낤���Ǝv���邻���̊G�t����ʐ^�A�|�X�^�[�Ȃǂ��A�I�����_������̔������Ԓd��A�z������\���ƃf�U�C���Ō܂̖ʂ����ς��ɓ\���Ă���l�́A�s�ς̈��ɐs�����B���Ɍ������ĉE��̕ǖʂɂ͎葢��̕����Ղ����Ԏ��v���̎��v�܂Ŕ������Ă���A�܂��ɂ���́u�n���I��i�v�Ƃ����ׂ����̂ł������B
�@ ���͂Ƃ肠�����֍��ɍ��|���͂������̂́A�{���̂��̋�Ԃ̗p�r�ȂǖY��Ă��܂�����ԂœV���l���̕ǂ����X�Ɍ����B�Ȃ�قǁA����Ȓ��q�ŊG��ʐ^�̈ꖇ�����܂��߂Ă�����A���ꂾ���ł��ꎞ�Ԃ��炢�͂����Ɍo���Ă��܂��ɈႢ�Ȃ��B����Ȃ��Ƃ��l���Ȃ���O�������グ��ƁA�ꖇ�̑傫�ȃ|�X�^�[���ʐ^���ڂɂƂ܂����B�����O���X���������V�l�Ƃ��ڂ����l�������̂悤�ȓ����������Ēn��𑖂��Ă��镗�ς��Ȏʐ^�ł���B�ʐ^�̒��̐l���͕s�v�c�Ȃ܂ł̑��݊��ƁA����Ƃ͑�������s�C���Ȃ܂łɕό����݂ȑ��l���Ƃ��Ɏ�����Ă��邩�̂悤�������B
�@ �������A���������ƂɁA�悭����Ƃ��̐l���͂ق��Ȃ�ʂ��̃h���L�������̎�l���̂��̂������̂��B���̃h���L�����V�̖{���������ɎB�肫�����ʐ^�Ɓi�̂��ɁA���̎ʐ^���B�����̂͑O�q�̃J�����}���s�쏟�O����ł��邱�Ƃ�m�����j��������̂Ȃ�A���̂悤�ȕs�v�c�ȓ���������Ȃ�����Ă̂��郂�f���̂ق��������Ȃ��̂ł���B���̍D��S�͂��₪�����ɂ��~�����Ă�����肾�����B�u�g�|�X�̕����v�Ƃ����^�C�g���̓������|�X�^�[�ɖڂ��s�����Ƃ����A���͎v�킸�j�����Ƃ����B�u�g�|�X�v�Ƃ́u�ꏊ�v�Ƃ����Ӗ��ł���B�V�l�͂��̔��w�ɑ����u�g�C���Ƃ����ꏊ�̕����v���Âɏ����悤�Ƃ��Ă���̂��낤�B
�@ �悤�₭�u�{���̖ړI�v��z���o�������́A���̈ꌏ�������Â������ƁA���C�Ȃ����[���y�[�p�[�Ɏ��L���A���̈ꕔ��������Ƃ����B�����Ă���ɖڂ�������r�[�A���C�ɂƂ��āA�܂����⑧��ۂݍ��ޗL�l�������B�Ȃ�Ƃ��̎��Ђɂ͐��F�ʼnp��̃N���X���[�h�p�Y�����������Ă����̂ł���B�`�������W���ꂽ����ɂ͎ė��ق��͂Ȃ��B�������Ď��̓g�C������̒E�o���͂��邽�߂ɓ���ȃp�Y���ɒ��ނƂ����v��ʎ��Ԃɒǂ����܂�邱�ƂɂȂ����B
�@ ���{��̂��̂����ăN���X���[�h�p�Y���͂���Ȃ�ɓ���B�܂��ĉp��̃N���X���[�h�p�Y���ƂȂ�ƁA�Z���Ԃł̊����͗e�Ղł͂Ȃ��B���炭�l���Ă݂͂����A�ǂ����Ă��킩��Ȃ��Ƃ��낪����B���̂܂܂��Ɩ邪������܂ł��̕֍��ɍ��������܂܂ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���́u�v�n�q�j�r�E�b�q�d�`�s�h�u�d�v��Ԃ̂Ȃ��ŁA���܂ł����_���́u�l����l�v���݂��Ƃ��Ȃ��f�t�H���������悤�Ȋi�D�𑱂��Ă�����A�����g���V�l�̌|�p��i�̈ꕔ�Ɖ����Ă��܂����낤�B��ނȂ��ӂ����������́A�O�A�l�V�[�g���̃N���X���[�h�p�Y�����]���ɂ���ƁA�V���ɂ�����Ƃ����ꖇ�̃N���X���[�h�p�Y������ɂ��ăg�C�����o���B
�@ �����炭�͓��S�Ńj���j�����Ȃ��炨���̗p�ӂ����Ă����ł��낤�V�l�́A�N���X���[�h���̃��[���y�p�[�̐�[����ɂ������̎p��ڂɂ���ƁA
�@�u�����Ԃ�Ƃ��������ł����˂��c�c���̑n����Ԃ��y����ł��炦�܂������H�v
�Ɩ��������ɐu�˂Ă����B
�@�u�����A�����Ɂc�c�B����������ƕ֍��ɂ�������܂܂ł�����A���̂܂܍d�����ă��_���̌��������͂�u�����Y�̐V��w�l����A�z�x�ɂȂ��Ă��܂��Ƃ���ł����v
�@�u�͂͂́c�c�ŁA���̃N���X���[�h�p�Y���͉�������ł����H�v
�@�u����A���ꂪ�܂��Ȃ�ł���B���������ł����炨���ł����Ղ��Ȃ�������������āA���ꂩ��܂��g�C���ɖ߂��Ĕr������@���Ă��邱�Ƃɂ��܂��B���̊Ԃ�������f�����������܂����c�c�v
�@ ����������Ԃ����B
�@ �����\�N�ȏ���̘̂b�����A�Y��悤�ɂ��Y����Ȃ�����ȏo�������������̂ŁA���߂ĐΓc�@��K�˂�l�ɂ͒N�ɂł��A�u�g�C���̌��w�����͐���I�v�Ɗ��߂邱�Ƃɂ��Ă���̂��B���܂ł͂����p��̃N���X���[�h�p�Y�����g�C���b�g�y�[�p�[�͒u����Ă��Ȃ����A���̂ق��̗l�q�͓����ƂقƂ�Ǖς�肪�Ȃ��B���������̋@�����Ƃ����킯�ŁA���v�Ȃɂ��A���Ί��Q�����Ε��C�ɂƂ��Ă��炢�A�g�C���ł̂ЂƎ���������䂭�܂Ŋy����ł����������B
�@ �䍂�̃h���L�����@�����Ƃɂ��A���{�̊�䂳��̃A�g���G�ɋA�蒅������X�́A������Ƃ���V�ѐS���N�����A�召�̒����Q�̂Ȃ��Ƀh���L�������̃C���[�W�ɂ�������̍�i���Ȃ����ƒT���Ă݂���������B���̌��ʁA��r�I�悭�����p�`�̒������O�A�l�[�قnj����������A���������ۂɐΓc�V�Ɍ������ꍇ�ǂ̂悤�Ȕ������߂��Ă��邩�́A���܂ЂƂz���̂��Ȃ����Ƃł͂������B���Ɋ��v�Ȃ��h���L�����@��K�˂�@���������A�����̂����̈��[�����̏\���˂����Ɏ��Q���邱�ƂɂȂ邩������Ȃ��B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N6��21��
���{��S�C��
�@ ���{�s�̒��S�����Ĕ��������ʂւƌ������r���A���{��̋߂���ʂ肩�������̂ŁA�v�X�ɂ��̓V��t�ɏ���Ă݂邱�Ƃɂ����B�����炨�悻�l�S�N�O�A���\��N����O�N�i��܋�O�N�`��܋�l�N�j�ɂ����ēV��t���z�����ꂽ�Ƃ������{��́A�P�H��A�F����A���R��ƕ���ō���Ɏw�肳��Ă��鐔���Ȃ���̈�ł���B���Ԃ�Ȃ���̂̂܂܂̕���̍\�����قڊ��S�Ȃ������Ŏc���Ă���A���j�I�������Ƃ��Ă̂��̎������l�͂���߂č����B
�@ ������ɂԂ��Ȃ��悤�ɒ��ӂ��Ȃ���A�Ђǂ��X�̋}�ȋ����ؑ��K�i�����x���J��Ԃ�����Ă����ƁA������A���`�̌����炵�̂����V��t�ւƓ���B��C�̐����Ȃǂɂ́A�V��t�̎l���̊i�q������A���{�̊X���݂͂����ɋy���A��O�x���͂��߂Ƃ���k�A���v�X�̎R�X��A�����R�A���������ʂ̎R���݂Ȃǂ���]�̂��Ƃɂ����߂邱�Ƃ��ł���B
�@ �헐���̘U������z�肵�Ēz�����ꂽ���̏�̕ǖʂɂ́A�S�C���ԁi�Ă��ۂ����܁j���ԁi�₳�܁j�ƌĂ�鐳���`�Ⓑ���`�̕nj��i�e���˖���j���A�e�w�ɂ킽���đ����݂����Ă���B�������łɉΓ�e����v�ȕ���ƂȂ��Ă������Ƃ������āA�e�K�w�̕ǖʂ́A�G�̏e�e�ɑς���������h�荞�ߕǂɎd�グ���Ă���Ƃ����B�����芪���x�̕��Ȃǂ������̓S�C�̐��\���l�����Č��߂��Ă���炵���B�悭�悭�l���Ă݂�ƁA���Ƃ��ǂ�Ȃɖh��ɍH�v���Â炵����ł����Ă��A���̖h��ݔ����𗧂̂́A���ǁA�틵�������鑤�ɂƂ��ĕs���ȂƂ��ł���B��������ȏ�ԂɊׂ�A��S�̂������ł��ނƂ������Ƃ͂܂��l�����Ȃ��������Ƃ��낤�B�z�������ڐ�Ɋ������܂�邱�ƂȂ��A���܂��Ȃ��̂Ȃ���̎p�𗯂߂Ă��鏼�{��́A�K�^�ȏ�̈�ł������ƌ����Ă悢�B
�@ �����Ƃ��A���̔�������ɂ���x�������S�̊�@���������炵���B�����ېV�����A���{�e�n�Ŕp��₻��ɔ�����̈ڒz��̂��������A����Ȏ����̒��ł��̏��{����������Ԃɔ���ɏo���ꂩ�����̂��Ƃ����B�K���Ȃ��ƂɁA���̐܁A���{�s���𒆐S�Ƃ��鑽���̐l�X�̊ԂɔM�S�ȕۑ��^�����N����A��̕ۑ���p�̒��B�ɐ����A���̂����ŏ��{��͋M�d�ȗ��j�������Ƃ��Č��݂Ɏ���܂ł��̎p���c���`�����邱�ƂɂȂ����B
�@ �Ƃ���ŁA���̏��{����ɂ����Ă͂��܂ЂƂӊO�Ȃ��̂�ڂɂ��邱�Ƃ��ł���B�u���{��S�C���v�ƌĂ��A�e��̎�q���e���тɂ����Ɋւ���M�d�ȗ��j�����̃R���N�V����������ł���B���̃R���N�V���������{�s�Ɋ����ԉH�ʏd���̖��������āA�u�ԉH�R���N�V�����v�ȂǂƂ��̂���Ă���悤���B���{��̌��w�҂́A��̓�������V��t�ւƂ̂ڂ�r���ƁA�V��t����o���ւƂ�����r���ŁA���R�ɂ����̓W�������ɖڂ�ʂ����Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă���B����ȂƂ���ō����ł���ꋉ�̎�q���e�W�̓W�����������邱�Ƃ��ł���Ƃ́A���߂Ă̖K��҂Ȃǂ͑z�������Ă��Ȃ�����A���̌����ȃR���N�V������O�ɂ��ď��Ȃ��炸��������邱�ƂɂȂ�B
�@ �v���Ԃ�ɂ��̎�q���e�̓W�������ߕ��������ɁA��q���e�ɂ��Ă͂قƂ�ǒm���Ȃǎ������킹�Ȃ��g�ł���ɂ�������炸�A���̓��͕s�v�c�Ȃقǂɑz���͂�~�����Ă�ꂽ�B�l�I�ȗ��Ǝ�ނ����˂Ď�q���F���Z���^�[��K�ˁA���̂��łɁA���߂ĉ䂪���ɓS�C��`�����|���g�K���l��̏��D�̕Y�������l�ӂɂ���������Ă݂��肵�����A����܂ł��̗��j�I�Ӌ`��S�C���ʂ����������ɂ��Ă��܂�[���z�����߂��炷���Ƃ͂Ȃ������B���������A���̐킢�ŎO����̉Γ�e�����Ȃ����S�C���Ɠ���ȍ\���������w�n���I�݂ɋ�g���A�D�c�A����̘A���R�����c�̋R�n�R�c��ł��j�����Ƃ����j�b���A���̕Ћ��ɐh�����ė��߂Ă������炢�̂��̂ł���B
�@ �������A�ǂ������킯���A���̎�����͎����ł��ӊO�ȂقǂɘA�z�͂��͂��炢���B�ЂƂɂ́A���܂��܂��̓��̌��w�҂����Ȃ��������Ƃ������āA���ꂱ��z����y���Ȃ���A��������ƓW�������߂邱�Ƃ��ł��������ł����낤�B���ꂩ�炻�̐܂ɍl�������Ƃ��������菑���Ă݂悤�Ǝv�����A�����܂ł��f�l�̑z���͂ƒ��ςɊ�Â����Ȃ肢�������Ȑ���������A�y���ǂݗ�������ł��t�������肢�����B
�@ ��q���̍œ�[�ɂ����q�������̍��l�i���݂͍r��ɕς���Ă���j�ɕY�������|���g�K���l�����ɂ���āA���߂ĉ䂪���ɓS�C���`����ꂽ�̂́A�V���\��N�i��l�O�N�j�̂��Ƃł���B�|���g�K���l�����͔��N�قǎ�q���ɑ؍݂����Ƃ����Ă��邪�A�̎傪�ނ炩����肵���Γ�e����{�ɁA��q���̓��H�A�������q�i����j�́A���N�̓V���\�O�N�ɂ͑��������͂ɂ��S�C�̐����ɐ��������B���R�A�S�C�`���̉\�͓��{�{�y�e�n�ɍL�����Ă��������A�����ׂ��͂��̏��`�B�̑����ƁA���̒���Ɋe�n�̓��H�������݂����S�C�����Z�p�̏K���ɂ�����ُ�Ȃ܂ł̔M�ӂł���B
�@ �W������Ă��鎑���ɂ��ƁA�S�C�`���̃j���[�X�͂قƂ�ǎ��������č�𒆐S�Ƃ����E����тɓ`���A���V���\�O�N�ɂ́A�����A�I�B�������̓��H�ŒҐ��E�q����̓��H�k�����O�Y���S�C����Z�p�K���̂��ߎ�q���ɔh������Ă���B���̔N�̂����ɍ������ɖ߂����Œ҂͓��H�W�c�𗦂��ēS�C�̐�����n�߁A�k���̂ق����S�C�`�������N��̓V���\�l�N�ɂ͍�ɖ߂�A���H���������đ�ʂ̓S�C����ɒ��肵�Ă���B
�@ ��q���̎�́A�ނ��{�y�̎F���˓��ÉƂւ��S�C�Ɋւ������`�����悤�ł��邪�A���̏�F���˓��ł���قǂɏd�v������Ȃ������ӂ�������̂́A�����̎F���˂͑������˓��̓�������߂�̂Ɏ肢���ς��ŁA�S�C�ǂ���ł͂Ȃ���������Ȃ̂�������Ȃ��B����Ƃ��Ă̓S�C�̈З͂Ƃ������̂��A�܂��˂̏�w���ɏ\����������Ă��Ȃ��������Ƃ����̗��R�̈�ł͂������̂��낤�B
�@ �F���˂��قǂȂ��̓��̓��H�����ɖ����ēS�C�̐������s���Ă͂��邪�A�S�C�`���̏����̒i�K�ɂ����ď���Ɛ肷��ɂ͎���Ȃ������悤���B�̂��̓��쎞��Ȃǂɂ����Ă͓O�ꂵ�����Ǘ��Œm��ꂽ�F���˂̂��Ƃł���B�S�C�̏d�v���ɑ��铯�˂̔F�����s�\���ł������Ƃ����w�i�ł��Ȃ���A��q���̎傪�E������S�C�Z�p�K���ɂ���Ă��铁�H���e�ՂɌ}�����ꂽ���Ƃ��A�F���˂��S�C�Ɋւ��錵�i�ȏ��K�����s��Ȃ��������ƂȂǂ��A�ȒP�ɂ͐��������Ȃ��悤�Ɏv����B
�@ �������A���Ƃ����̂悤�Ȕw�i���������ɂ��Ă��A�S�C�`���Ƃ���ɔ������X�̋Z�p������Ƃ��Ă͈ٗ�̑����ŋߋE��тɓ`������̂́A���������Ȃ��������̂��낤�B��q�������B�{�y�e�n�A����ɂ͒����n���e�n���o�ċE���ւƂ������H�����̒���ȓ`�d���[�g�������z�����Ă��܂����������A�����̌�ʎ����Q�Y�����̏��l����Ƃ��܂ЂƂ��D�ɗ����Ȃ��B����ȋ^�������Ȃ���A���̌�S�C�����̒��S�n�ƂȂ����n���������������{�n�}�������ƒ��߂Ă��邤���ɁA�}�ɂ��邱�ƂɎv�����������B
�@ ��p�����痮���A���������̓�����i�����{���́A��q����[�̖�q���̉�������k���Ɍ������Ēʉ߂��A�����m�ւƗ��ꍞ�ށB�S�C��`�����|���g�K���l�����̏��D���A��j���O�̏�ԂɂȂ�Ȃ�����h�����Ė�q���t�߂ɕY�������̂́A�܂��ɒg�������̂������������Ǝv����B�Ƃ���ł��̍��������A��q���𒆐S�Ƃ����q������[�������߂�悤�ɒʉ߂������ƁA�������ɋI�ɔ����̒��̖�������F����тɓ��B����B���Ď�q����K�˂��Ƃ��A�������암�ɂ���u�F��C�݁v�ɘȂ�ł��̉������𗬂�鍕���̍s���ɑz����y�������Ƃ����邪�A�n�}����������킩��悤�ɁA���̌F��C�݂���I�ɔ����̌F�쉫�܂ł̒��������͈ӊO�ɒZ���B�����ɏ��ЂƂ����Ȃ̂ł���B
�@ �F��Ƃ����o���ɋ��ʂ����n���́A��������čs��ꂽ�I�ɔ����Ǝ�q���Ԃ̌Ñォ��̌𗬂̐[�����Â���B�����g�D�W�̕����ȂǂׂĂ݂�ƁA�g�q�]�����悩��o�����F���̖V�Â�ڎw�������H�̌����g�D���A���ɑ����đ��D�s�\�Ɋׂ葾���m���ɗ�����A�I�ɔ����̊C�݂ɕY����������Ȃǂ��L�^����Ă���B�������A�����̐l�X�Ɂu�����v�ȂǂƂ����T�O�͖����ł͂������낤���A���Ȃ��Ƃ��ꕔ�̏M�l�����́A���܂����̗���ɏ�肳������A��q������I�ɔ����܂ł̑D�H�͂ЂƂ����ɉ߂��Ȃ����Ƃ��o���I�ɒm���Ă����ɑ���Ȃ��B
�@ �܂��āA��q���ɓS�C���`��������l�O�N���Ƃ������ƂɂȂ�ƁA���m�q�C�Z�p�͂Ƃ������Ƃ��Ă��A�䂪���̉��ݍq�C�Z�p�̂ق��͑����ȂƂ���܂Ŕ��B���Ă����ƍl����̂����R�ł���B������A�S�C�ɂ��Ă̏�A�قƂ�NJԂ��������ƂȂ��A��q������C�H�`���ɋE����тւƂ����炳�ꂽ���낤���Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B���ɑ����@������ɕq�ȍ����O���̏��l�O���A�����A��q���ɓ��H��h�����邱�Ƃ��ł����̂��A���̂悤�Ȕw�i���l����Δ[���������B
�@ ����ɂ��Ă��A�S�C�`������̏\�N�ԁA����ɂ́A���ꂩ��V���O�N�i����ܔN�j�̒��̐킢�Ɏ�����\�N�Ԃɂ�����ُ�Ȃ܂ł̓S�C�����ʂ̑���ƁA�Z�p�̉��ǔ��B�̗��j�����������ǂ̂悤�ɐ�������悢�̂��낤���B�܂��A�J���⡂̂悤�ɍ����Ɉ��͂��߂��S�C���A�ԐړI�ł͂������ɂ��Ă��A����悭�Γ��{�̐A���n�����Ƒ_���Ă����ɈႢ�Ȃ����ė��̐N�U��}�~����͂Ƃ��Ă͂��炢���\���͂Ȃ������̂��낤���B����ȋ^��Ȃǂ����ꂱ����������ɁA���̖��z�Ƃ���������Ȃ��z���́A�����琻�S��ʍ|�i���܂͂��ˁj�ɑ�\�����䂪���̓���ȓ`�����|�Z�p�ƓS�C�����Z�p�Ƃ̊W�A����ɂ́A�̂��̍���������͂��߂Ƃ���C�O���͂̒��o���ɉA�œS�C�������������Ȃǂɂ܂ŋy��ł������̂������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N6��28��
��q���e�]�k
�@ �t�����V�X�R�E�U�r�G�����|���g�K���D�ɏ���ċэ]�p�ɓ��`�A�������ɏ㗤�����̂́A�S�C�`������Z�N��̓V���\���N�i��l��N�j�A���܂����l�S�\�N�O�̂��Ƃł���B�U�r�G���͎����������Ƃɂ���ƁA���N�ɂ͊C�H���˂ɓ���A����ɂ��ꂩ��E���ւƌ������A�����䂪���̌��Ղ̒��S�n��������Ȃǂ����@���Ă���B
�@ �U�r�G����s�́A�t�B���s�����ʂ��獕���ɏ���ė��������A�������������ɖk��A�����炭�͎�q���A���v���ߕӂ�ʂ��ċэ]�p�ɓ������Ƃ�������B���R�Ɍb�܂ꂽ�������Z�Ȃ��̓��m�̓����ɃU�r�G����͂���Ȃ�̊������o�������Ƃł��낤���A�܂������̒n�ő�ʂ̓S�C��ڂɂ��邱�ƂɂȂ낤�Ƃ́A���ɂ��z���Ă��Ȃ������ɈႢ�Ȃ��B�������A����Ȃ��ƂɁA�����̓S�C�̂قƂ�ǂ́A�ނ̏��D�̑D����Ɠ����Ђ̃|���g�K���l���킸���Z�N�O�Ɏ�q���ɂ����炵���S�C���������̂������B
�@ �L���X�g���z���̕��Ƃ��ċ����U�r�G�������A�ނ͂����ۂ��ŁA�L���X�g���̍��O�z�������̃X�|���T�[�I���݂ł������|���g�K�������ɑ��A���{�̌R���͂�o�ϗ͂Ɋւ���ڍׂȕ��̓��|�[�g�𑗂��Ă�����B���̍����R���͂Ő�������͓̂���Ƃ�����|�̂��Ƃ��q�ׂ��ނ̃��|�[�g�̗��t���Ƃ��ẮA�܂��A�����̍����e�˂̍��x�ɑg�D�����ꂽ���m�W�c�̑��݂⏤�Ƃ̒��S�n��Ȃǂɂ݂���o�ϗ͂̑傫���Ȃǂ��������邾�낤�B
�@ �����A���̂ق��ɁA�ނ������̓S�C�̑��݂Ƃ��̐��������ڂ̂�����ɂ��A���̋Z�p�̍����ɋ������ꂽ�炵�����ƂȂǂ��A���̏���͂ɏ��Ȃ���ʉe����^�����ɈႢ�Ȃ��ƍl������B�U�r�G���̃��|�[�g�̓��e����͑����ɂ��̂悤�Ȃ��Ƃ������ł��邩��ł���B���ہA�U�r�G�����E����K�˂����ɂ́A��⍑�F���ӂ̓��H�W�c�̑����́A������S�C�H�W�c�ւƕϗe�𐋂��Ă����B
�@ ���F�̓��H�𒆐S�Ƃ����b��W�c�̏ꍇ�́A��q���̎��菫�R�����`���Ɍ��コ�ꂽ�Γ�e����A��������Ƃɂ��ĂقǂȂ���ʂ̓S�C�������s���悤�ɂȂ����B���������A�U�r�G�����������ɗ��K�����V���\���N�ɂ́A�F���̉����؏�ɂ����ēS�C���킪�s���Ă���A�܂��A�����N�ɐD�c�M���͍��F�̓S�C�H�O�ɌܕS���̉Γ�e�����Ă���B�L�^�ɂ��ƁA�S�C�����o�����͂��߂��̂����̍��̂悤�ł���B�����̓����ɍ��킹��悤�ɁA��͂肱�̔N�A��̍�������@�v����{�i�I�ȓS�C��ʐ��Y�ɏ��o���Ă���B
�@ �䂪���ɂ����Ă���قǂ܂łɋ}���ɓS�C�����y�����w�i�ɂ́A�×��̓��������Z�p�ɑ�\�����悤�ȍ��i�ʂ̍|�S�̐����Z�p�A�Ȃ�тɐ��Y���ꂽ�|�S�̍��x�Ȑ��B���H�Z�p�̑��݂��������Ƃ�������B�Ñ�ɒ��N��������ڏZ���Ă������S�Z�p�����H�l�W�c�i���㕗�Ɍ����ΐ�[�Ȋw�Z�p�ҏW�c�j�́A�䂪���Ŕ���I�ɂ��̋Z�p�����x�������W�����Ă������B���̍ő�̗��R�́A�|�S�̐����Ɛ��B���H�ɓK�������R���������܂��܉䂪���ɂ͂��Ȃ���Ă�������ł���B
�@ �R�[�N�X��p�����n�z�F�ɂ���đ�ʂ̓S�z��n�����S��������@�́A�����Ƃ̂��Ƀ��[���b�p�ŊJ�����ꂽ���̂ł���B�܂��A�S������߂ėp�������ƂŒm����Ñ�̃q�b�^�C�g���Ȃǂ̏ꍇ�́A���̒n���ɑ����U�݂��Ă���覓S��n�Z���H�����ƌ����Ă���B�������A�㎿�Ȏ��S�z���Y�o����n��ł́A���ڂɂ�����p������������炵���B�������A�Ñ㓌�A�W�A�ɂ����Ĉ�ʓI�������̂́A���S���ʂɏW�߂Ă��ꂩ��|�S��������@�ŁA�������A���N��������n�������̂̍H�l�������u�����琻�S�v�ƌĂ�邱�̕��@��p���Ă����B
�@ ���S���܂ތ������w�̂���X�Βn�ɏ㕔�����ʂ̐��𒍓���������Ƃ������o����Ƃ��J��Ԃ��ƁA��d�̏d�����S���Z�k���ꂽ�������ŗ��H�̒ꕔ�ɒ��a����B�������W�ߓ��l�̌����ł���ɔZ�k���Ă����A�S���̔Z�x���\���ɍ��܂����Ƃ���Ŋ���������̂��A�����琻�S�̑��i�K�ł���B�R�A�n���e�n�̊C�݂�C�߂��̎R�n�ɂ́A�Ƃ��ɂ��̈�A�̍�ƂɓK�������n�⍻�w�Ɛ����̂悢�X�Βn�����������݂��Ă����B�v����ɁA�����Ƃ�����������鎩�R�����Ɍb�܂�Ă����킯�ł���B���̏�����Ƃ��̂��̂������Ȏ��R�j��������炷���̂ł������炵�����A�����̒Ⴂ�l�����x�⎩�R�̂������͂���l���āA����Ȃ�̓K�n�����{�e�n�ɂ͂������悤�ł���B�������A�R�A�n����тȂǂ́A�n���I�ɂ݂Ă����N����������{�C��n���čH�l�������ڏZ���Ă���̂Ɋi�D�ȏꏊ�ł��������B
�@ �������A�u�����琻�S�v�ɂ͂����ЂƂ�Ɍ������Ȃ��v�f���������B�����܂ł��Ȃ��A����͓S��n�����ɕK�v�ȁu�Ήv�ł���B�u������ށv�Ƃ������t�̌ꌹ�ɂ��Ȃ��Ă���u������v�Ƃ́A�S�̐�����B�ɗp���������݂́u��^��i�ӂ����j�v�̂��Ƃł���B�ǂ����Ă��z���̂��Ȃ��l�́A�{��x�̃A�j����i�u���̂̂��P�v�̖`���̏�ʂ�z���o���Ă��炦�悢���낤�B�������i�ӂ����j�Ől�H�I�ɋ�C�𑗂��ĉ����A�S��n�Z������b�B�����肷��̂ɕK�v�ȍ����ݏo���킯�ł���B
�@ �������A������傫���䂪�����Ă��A�R���ƂȂ�؍ނ�ؒY����ʂɂȂ���Θb�ɂȂ�Ȃ��B�Z�k�������S��n�����đe�S������A������܂����x�������ɉ��M���Ēb�B�����J��Ԃ��A�����̐n�Ȃǂɗp����ʍ|�i���܂͂��ˁj��܂łɂ́A�r�����Ȃ��ʂ̖؍ނƘJ���͂�K�v�Ƃ����B����ɂ́A�����Z�p���\���ɔ��B���Ă��Ȃ����������̍��ɂ́A�C�ۋʂقǂ̗ʂ̋ʍ|�����B���A���������Ƃɂ킸���Ȑ��̓����邾���ł��X�щ��\�w�N�^�[�������̖؍ނ�K�v�Ƃ����Ƃ����B���������āA�����琻�S�@�ɂ��S��̐����ɂ͑z����₷�鎩�R���j�Ƃ��Ȃ������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B
�@ ���S�Z�p�����H�l�W�c�����N��������䂪���ɈڏZ���Ă������R�̈�́A�؍ނ��s�����A���S�ɕK�v�ȔR���̓��肪����ɂȂ������Ƃł���ƁA��Ƃ̎i�n�ɑ��Y���ǂ����ŏ����Ă����悤�ȋL�������邪�A�������ɂ�������������͂������̂��낤�B���N�������݈�т͉ԛ��⎿�̌ł��y�낪�����A�A���̔ɐB�ɂ͂��Ȃ炸�����K���Ă͂��Ȃ��B���̂����A�n���I�Ȃ�тɋC�ۊw�I�ȗ��R�ɂ���ē��{��肸���ƉJ�ʂ����Ȃ�����A�X�т���������F������Ă��܂��ƁA���̕����ɂ͓r�����Ȃ����Ԃ��������Ă��܂��B���݂����N�������݂Ɏ��ёт����Ȃ��̂́A�Ñ�̐��S��ƂɂƂ��Ȃ��X�є��̂̉e�����Ƃ����������邭�炢���B
�@ �Ƃ��낪�A�K���Ȃ��ƂɁA�䂪���ɂ͐X�ь`���ɓK�����L���ȓy��ƁA���̓y��̏�ɔ��B�����L���ȐX�т����݂��Ă����B�������A���̐X�сA�Ƃ��ɏƗt���̎G�ؗт́A��ʂɔ��̂��Ă�����ȂɔN����v�����ɕ�������͂Ə��������Ȃ��Ă����B�����āA���̐X�ѕ����͂̔閧�́A�����m�𗬂��g�������Ɠ��{�C�𗬂�鍕���̕����Δn�C���A�I�z�[�c�N�C�c�Ə��}���C�c�̊ԂɌ`�������~�J�O����H�J�O���A����ɂ͉Ă���H�ɂ����Ď��X�ɓ��{���ӂɗ��T����䕗�ɂ������Ƃ�������B
�@ �䂪���͕��ϓ��Ǝ��Ԃ�����Ȃ�ɑ�����ɁA���C���ɋ��܂�Ă���W�ŕ��ϋC���������B�ď�ɑ����m������嗤�Ɍ������Đ����ʂ���쓌�̋G�ߕ��́A�����̗���鑾���m���痧�����鑽�ʂ̐����C����{�̓����ւƉ^�сA�R���ɂԂ����������̐����C�͑�ʂ̉J�ƂȂ��ĎR��ɍ~�蒍���B�t�ɁA�~��ɂ́A�嗤���瑾���m�Ɍ������Đ����o���₽���������k���̋G�ߕ����A���{�C�𐁂��n��Ƃ��ɑΔn�C���̕\�w����₦�ԂȂ��������������鐅���C���z�����A������R�A��k���A���k�n�����ݑ��̓����ɉ^�ԁB�������A�����̐����C�́A���{�l�Ȃ�N�����m���Ă���悤�ɑ�ʂ̐�ƂȂ��ĎR��ߐs�����B
�@ ���܂��ɁA�~�J�O����H�J�O���`���Ɏ��X�Ƃ���Ă���ړ����̒�C����A�Ă���H�ɂ����Ă̑䕗�́A�^���������炷�قǂ̑�J���~�点��B���̂悤�ȋC�ۏ����̂��Ƃł́A�䂪���̐X�т����N�����⒆���嗤��т̂�����͂邩�ɑ傫�ȕ����͂����Ȃ��Ă��邱�Ƃ͓��R�̂��Ƃ��낤�B���ܓ��{�e�n�𗷂��Ă݂�Ƃ悭�킩�邪�A�����O�ނ̗A���≻�ΔR���̕��y�Ŕ��̂���邱�Ƃ̏��Ȃ��Ȃ����䂪���̎R�т́A���Ă̗�����Ԃ��炩�Ȃ�̂Ƃ���܂ŕ����𐋂�����B�ނ��A�u�i��w�A���̐X�т�̂̎��R�т̏�Ԃɂ܂Ŋ��S�ɕ�������ƂȂ�Ƃ����ȒP�ɂ͂����Ȃ����A����ł��ꎞ�����͂邩�Ɏ��Ԃ͍D�]���Ă���B�b�܂ꂽ�C�ۏ����̍��ɏZ�މ�X�ɂƂ��ẮA���������R�̂��Ƃ̂悤�ɂ��������邩������Ȃ����A���R�����̈قȂ鑼���̏��l����Ƃ���͑�ςȂ��Ƃł���B
�@ �����q���̍��Ɉ�������������̍����ł́A�����A�d�Ƃ��đ�ʂ̏Ɨt���̗тN�̂悤�ɔ��̂��Ă������A�Ȃ�̎����������ɐ��N���u���Ă��������ŕ������Ă����悤�ɂ������B��N�A��\���N�Ԃ�ɋA�����Ă݂����A�ߔN�͋�B�̗��������ΔR����d�͂ɔM�����ˑ�����悤�ɂȂ�A����ɂƂ��Ȃ��Ď��̔��̂͂قƂ�Ǎs���Ȃ��Ȃ����炵���B���̂��߁A���Đd�̐�o�����s���Ă����R�X�̏Ɨt���т́A��������̂�����ȂقǂɟT���Ƃ��������тɕς���Ă����B
�@ �����琻�S�ɐ�D�̎��R���������䂪���ɈڏZ�����H�l�����́A���̋Z�p�ɂ��������̖�����������ƂƂ��ɁA�����ɂ��̏n���̋Ƃ��L�߂Ă������B�₪�āA�����̊e�n�ɂ́A����߂č��i���ȋʍ|�ݏo���A���������ƂɁA���͂�|�p��i�Ƃ��������悤�̂Ȃ��悤�ȓ����ނ铁�H���������X�ƒa�������B�ނ�̂���҂͂܂��A�����ނ݂̂łȂ��A�Z������e��̐��I�ȑ����i�A���S�Ȏ��p�i�̂ɂ�����܂ł̗D�ꂽ�������i�ݏo���悤�ɂȂ��Ă������B
�@ ���{�̏ꍇ�A�嗐���N�������ꍇ�ł��A�����Ă��͎x�z�ґw������ւ�邾���ŁA�����̓��H���͂��߂Ƃ���H�l�������A�`���I�ȋZ�p���₷���ƂȂ��A�ނ��딭�W�I�ɑ�X�E�l�Z���p�����Ă��������Ƃ��K���ł������B�ٖ����̐N���△���ʑ�ʎE�C�Ȃǂɂ���āA�e��̓`���Z�p���r�₦�Ă��܂��悤�ȏɂ�������A�|���g�K���l�������炵���Γ�e�̕����e�A����ɂ͂��̉��Ǐe�������قǂ̒Z���ԂŐ��삷�邱�Ƃ͕s�\�ł������낤�B
�@ �Γ�e�̐����ߒ��ɂ����Ă����Ƃ��d�v�Ȃ̂́A�|�S���̍ג����e���ƁA���{�̓S�C�H�������u���炭��v�ƌĂ��I�ȓ_�Δ��ː��䑕�u�ł��邪�A��{���������Ƃ͂����Ă������̎�v���������邱�Ƃ͂������ėe�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ������B�����A�K���Ȃ��ƂɁA�S�C�`�������̉䂪���ɂ́A�`���I�ȓ��������ʂ��č|�S�̈����ɏn�B���Ă������H��A���I�ȋ��������i�̍H�Z�p��������t���������Ȃ��炸���݂����B�ނ�́A���N�ɂ킽���Ē~�ς���Ă����Z�p�̐���s���āA�����̓������Ɍ������������̂ł���B����Ԃ��A�����̉䂪���ɂ́A�`���̓S�C�̍\������͂��A�Z���̂����ɂ��̕����ݏo�������̍��x�ȋZ�p�͂����łɂ��Ȃ���Ă����̂������B
�@ �S�C�`�������A�䂪���ɂ͍d���|�S�̖_�ɐ��Ղŏe����������Z�p�͂Ȃ��������A�ʍ|��������ꂽ���H�����́A����ȕ��@���ďo���A���̖������������B�܂��A�^���Ƃ����܂邭�ג����S�_������A���̏�Ɋ����Ƃ����|��ɂ܂�߂����̂��������A���x���Ă������Ēb�B����B�����̒b�B���I���ƁA����Ɋ����̏ォ��ג����|�𗆐���ɂ��邮��Ɠ�d�Ɋ������A�܂�����ē���ƒb�B���ĎO�Ďl�J��Ԃ��B�����čŌ�ɐS�_�̐^�������A��ړ��i�Ə��j�����ďe������������B���ꂪ���H�����̍l�����e���̐����@�������B
�@�u���炭��v�A���Ȃ킿�_�Δ��ː��䑕�u�ɂ��ẮA�������̍\���ƌ��������������ƁA�n����������t�����ɂƂ��Ă��̐���͂���������Ƃł͂Ȃ������悤�ł���B�ނ�́A�^�J�ƓS�Ƃ�f�ނɂ��āA�O���̉Γ�e�Ȃǂ̂��̂��������ƗD�ꂽ�䂪���Ǝ��́u���炭��v�����X�ɑn��o�����B�J�ɂ��ς����钅�Α��u��\����h�����S���u�Ȃǂ̍H�v�ɂ͖ڂ������炳�����̂�����B�e���A�����A�e�ہA�Ζ�Ƃ��������̂��ނ��d�v�ł͂��������A�����̂��̂̐���ɂ́A�n���E�l�����͂قƂ�Nj�J���Ȃ������悤�ł���B
�@ ��q���ɓS�C���`�����Ă��炿�傤�Ǐ\�N��̈�܌O�N�ɂ͍����e�n�ő�ʂ̓S�C�����������悤�ɂȂ�A���̔N�A�D�c�M���͖{�i�I�ȓS�C����Ґ������B�܂��A�S�C�̕��y�ƂƂ��ɍ������A��x�����͂��߂Ƃ���S�C�p�̊e���h�����܂�A���ˏp��Ȏˏp�i�������O���ɂ���ĉ����̓I��_�����@�j�Ȃǂ̂悤�ȍ��x�Ȏˌ��p���҂ݏo����͂��߂��悤�ł���B�n�B�҂ɂȂ�ƁA�ۂ����ʂ������o�������̉Γ�e�ł���A�O�S���[�g�����ꂽ�I�𐳊m�Ɍ����������Ƃ��ł����Ƃ��L�^����Ă��邩��A�S�C�p�͂킸���\�N�O�قǂŊe�i�̐i���𐋂��Ă������ƂɂȂ�B
�@ �Ƃ���ŁA���̂悤�ɒZ���Ԃŋ����قǂ̑��x�ō����ɍL�܂����S�C�����A����炪�A�ʼnʂ����������Ƃ������̂ɂ��ẮA���͗��j�ł͂قƂ�Nj�������L�����Ȃ��������A�������M�ł���ɂ��Đ[���l���Ă݂�@����Ȃ������B�����A���܂����{��S�C���Ŗڂɂ��������Ȃǂ����Ƃɂ��ꂱ��Ƒz�����߂��炷�����ɁA���j�I�ɂ݂ēS�C�ɂ͈�̏d�v�Ȃ͂��炫���������̂ł͂Ȃ����ƍl����悤�ɂȂ����B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N7��5��
���j�̍����u�S�C�v
�@ �����ɁA�`�������S�C���{�̍H�l�W�c�����������ۂɁA�e���₩�炭��i�_�Δ��ː����u�j�Ɋr�ׂāu�e���A�����A�e�ہA�Ζ�v�̐����ɂ͂���قNj�J���Ȃ������悤���Ə��������A�������A�Ȃ�̍H�v�⎎�s����̐ςݏd�˂��Ȃ������̐���������Ă̂����Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B�b�͑O�シ�邪�A���̂�����̂��Ƃ������⑫���Ă������Ƃɂ������B
�@ ���ɂ����̋{��H���˂̏��̗��������܂ł��Ȃ��A���̖L���ȉ䂪���ɂ͌×��D�ꂽ�؍H�Z�p�����݂����B�e���⏰���Ƃ������S�C�̖ؕ��͊~��O���͂��߂Ƃ���d�łł��Ă��邪�A��{�ƂȂ�S�C��������A���̏e���⏰���̕�����o�����Ƃ́A�������̖؍H���H�Z�p�����H�l�����ɂƂ��āA����������Ƃł͂Ȃ������悤�ł���B���ہA���{�S�C���ɓW������Ă���e��̉Γ�e�̏e���⏰���́A�����܂��ɒ��߂�ƈ��̌`������Ȃ��Ă͂�����̂́A�ו����悭���Ă݂�Ƃ��ꂼ��̏e���Ƃɗl�X�ȈقȂ�f�U�C����H�v���Â炳��Ă���A���ꎩ�̂��H�|�i�̗l����悵�Ă���B��҂̖��Ȃǂ������Ă���̂�����ɂ��Ă��A���̋Z�p�ɑ��鎩�M�̂قǂ��Â�ĂȂ�Ȃ��B
�@ �e�ۂ͉��ʂł��������A���a�l�~�����炢�̂����璼�a��Z���`�O��̂��̂܂Łi�̂��ɂ͈�іڋʂƌĂ��哛�p�̒��a���E�l�Z���`���炢�̉��ʂ��o�ꂵ���j�l�X�ȑ傫���̂��̂�����ꂽ�炵���B�������A�����ȋK�i�ȂǂȂ���������̂��Ƃ�����A�Γ�e�̂ق����e���̌��a�͂܂��܂��ł������炵���A���ꂼ��̏e�̌��a�ɍ��킹�ēK�X���ʂ��Ă����Ƃ����̂���������悤�ł���B
�@ �e�e�̉��ʂ́A����Ƃ������^�ێq��̕��t����Ŕ���n�����A������ʌ^�Ƃ������ɗ�������ő������B�ʌ^�͑�^�y���`�̐�[���ɏ�������̌E�݂����������킹�ɂ����悤�ȓ���ŁA���̌E�݂ɗn���������\���ɒ��������ƁA�������̂ق��Ɏ�̗͂����߂Đ�[���̉����������݁A�₦�ł܂�̂�҂��Ď��o���A�����ȉ��ʂ����X���Ȃǂō���Ďd�グ���B�퍑���ɂ����Ă͏e�e����͏����̎d���ɂȂ��Ă����炵���A���l���̏������F���͂ݒk���Ȃ��牔�ʑ�������Ă���}�Ȃǂ��c����Ă���B
�@ ���ł�����Љ�Ă����ƁA���{��S�C���i�ԉH�R���N�V�����j�ɂ͂Ȃ�Ƃ������ȍ\���̓S�C�ʂ��W������Ă���B���̉��ʂ���q���ɂ����A�ʂƂł��ĂԂׂ�������́A�{���̉��ʂ̂�����ɏ����ȕ��ʂ��ג����j���Ōq�����`�̂��́A����ɂ͒ނ�j���{���킹���悤�ȉs���b�j�̂������ʂƁA�v�킸���̈Ӑ}�Ǝ������Ɏ���X�������Ȃ�悤�ȕs�v�c�Ȃ�����̂܂ł�����ł���B����炪���ۂɎg�p���ꂽ���̂Ȃ̂��A����Ƃ��V�ѐS�Ɖ����Ȏ������_�̌��ʁA�����I�ɑ���ꂽ���̂Ȃ̂��͂킩��Ȃ����A���������|�����ł����̂���l�̉Γ�e�Ȃ�ł͂̂��Ƃł͂������̂��낤�B
�@
�@ �Ō�Ɏc��͉̂Ζ�ł��邪�A�Γ�e�Ɏg��ꂽ�Ζ�͂��Ȃ�Â����炠�鍕�F�Ζ�����ǂ������̂������悤�ł���B���F�Ζ�́A�ߑ�̍����\�Ζ�قǂ̐��\�͂Ȃ����̂́A���a�܃~�����炸�̏����ȉ��ʂ��O�S���[�g���O�������炢�̈З͂͂������悤���B�������A�S�C�`�������́A�|���g�K���l���͂��߂Ƃ���ٍ��l�Ȃǂ���Γ�e�p�̉Ζ�ɂ��Ă̏����W������ɍs��ꂽ�悤�ł���B
�@ �����A���R�̗��P�������q����ȍ~�A������x�̉Ζ�̊�{���@�͒����⒩�N��������`����Ă��Ă������Ƃ�����A��v�����̒��B�����\�ł���A���s����̎�����ʂ��čœK�ȉΖ��̌��������������o���܂łɂ́A����قǎ��Ԃ�K�v�Ƃ͂��Ȃ������悤���B����܂œS�C�������݂��Ȃ��������A�Ζ��T�����̑��̖ړI�ł��łɉΖ�ނ͎g���Ă����悤������A�Γ�e�p�̉Ζ���J����������Z�p�I���n�͏\���ɂ������ƍl����̂����R���낤�B���Ƃ��ƁA�ׂ̒����⒩�N�͉Ζ�Z�p�̐�i���������킯������A�䂪���̈ꕔ�̍H�l�����F�Ζ�Ȃǂ̋Z�p��`�����Ă����Ƃ��Ă��s�v�c�͂Ȃ��B
�@ �|���g�K���l�����痼�œ���̉Γ�e������������̗̎��q�����āi���˂����܂Ƃ������j�́A�Ζ�̌������Ɛb�̎쏬�l�Y�ɖ����Ă��邪�A�e�{�̂̕����Ɏ��g�������q�i����j�̎���i�̔��ˎ��������������̂͗��N�̂��Ƃ�����A�Ζ�̊J���̂ق�������܂łɂ͈�背�x���ɓ��B���Ă����ƍl���Ă悢���낤�B
�@ �����̓`����Ƃ���ɂ��ƁA�Γ�e�p�̍��F�Ζ�́A�i�₰��j���g���ĉ��Ɂi�ɐΕ����A�ɐƂ͏Ɏ_�J���E���̂��Ɓj�A���������A�ؒY�������T�F�R�F�Q���炢�̊����ō����������̂ŁA���̍�����͋@�������ł������炵���B�������A�����̉̔@�������ł����Ƃ����܂ɍ����e�n�ɓS�C���L�܂����Ƃ�����݂�ƁA�Ζ�̍�����͂قƂ�nj��R�̔閧�̂悤�Ȃ��̂������̂��낤�Ɛ��������B�����ƖؒY�͍����ŗe�Ղɓ���ł������A�ɐ͍����ł͂قƂ�ǎY�o���Ȃ������ɁA���ʂȃ��[�g�ŊC�O������肵�Ă����悤�ł���B�ނ��A�����̍��̓|���g�K���l�Ȃǂ���K�v�ʂ����������ɍw�����Ă����̂��낤�B
�@ �����Ƃ��A�S�C�`������\�N���o�ƁA��Ȃǂɂ͑�ʂ̏ɐ��o����Ă����悤�ł���B�U�r�G�����������𗈖K������N���̓V����\��N�i��܌ܓ�N�j�ɂ́A�����`�P�̈˗��ŐΎR�{�莛�����Ɂi�ɐj�\�҂���Œ��B�����Ƃ����L�^�Ȃǂ��c���Ă��邩��A���łɂ��̎����A���тɂ͑����ʂ̉��ɂ��C�O���玝�����܂�Ă����̂��낤�B�m���Ȃ��Ƃ͂킩��Ȃ����A��ă`���Y�̏ɐȂǂ��͂��C��n���č����ɉ^�э��܂ꂽ�\��������B
�@
�@ �Ƃ������A���̂悤�ȉߒ����o�č����ő�ʐ��Y�����悤�ɂȂ����Γ�e�́A����ł����̈З͂�����悤�ɂȂ����B�V����\�N�i��܌܈�N�j�A����`���͓����M�Ƃ̌����̐킢�œS�C�S�����g�p�A���̗͂������ē��R��j�����Ƃ����B�܂��A�i�\�O�N�i��ܘZ�Z�N�j�̉����Ԃ̐킢�ɂ����ĐD�c�R�͎O�S���̓S�C���g�����Ƃ����L�^���c���Ă���悤���B�����Ԃ̐킢�Ƃ����ƁA�s�R�̊W���ނȂ������襘H�Ɉ��̖{�w��������`���R�ɑ��A�܂���̈��V���˂��ĐD�c�R����P�U�������������ƂŒm���邪�A���̍ۂɓS�C���g��ꂽ�Ƃ����b�͂��܂蕷�������Ƃ��Ȃ��B�����A�������L�^�ʂ�ɎO�S�����̓S�C���g��ꂽ�Ƃ����̂ł���A�D�c�R�̈�叟���ɂ���Ȃ�̍v���͂����ɈႢ�Ȃ��B
�@ �i�\���N�i��ܘZ�l�N�j�ɓ�q���̘U���U�s���̕x�c����U�߂��ї��R�́A���̎������͂Ƃ������A�S�C�ōU�����d�|���Ă��邵�A���̗��N�ɋN��������O���c�`�ł̃|���g�K���D�U���ɂ͍�ő���ꂽ�Γ�e���p����ꂽ�Ƃ����B���Ƃ����낤�ɁA�S�C�Ƃ����v���I�ȕ����`�����Ă��ꂽ�t�̃|���g�K���l�ɁA�`�����ꂽ��q�̓��{�l�ق�������������g���čU�������킦���Ƃ����̂�����A�Ȃ�Ƃ�����Șb�ł���B�|���g�K�����ɓ����̋L�^���c���Ă��邩�ǂ����͂킩��Ȃ����A�|���g�K���D�������ɂƂ��Ă͂Ȃ�Ƃ��Ռ��I�ȏo�����ł��������Ƃ��낤�B
�@ �i�\�\��N�i��ܘZ��N�j�A�D�c�M������䒷���̖{�����J����U�߂��Ƃ��ɂ����Ȃ�̓S�C���p����ꂽ�Ƃ������A���̍��ɂ͍�͍����ő�̓S�C���Y�n�ɂȂ��Ă����B�������A�M����������S�Ɏx�z���Ɏ��߂��̂́A���Ղ⏤�Ə�̗v�n�Ƃ������R�̂ق��ɁA�S�C�����S�Ɏ����̊Ǘ����ɂ��������Ƃ����Ӑ}�Ȃǂ������Ă̂��Ƃ������̂��낤�B���̗��N�A�ΎR�{�莛�ɗ��ĘU�����������O�A�G��O�Ȃǂ̋I�B�����U�߂��D�c�R�́A�{�莛����R�̑����̓S�C�ɂ�鉞��ɋꓬ����������H�ڂɂȂ����B���̋��P�������Ă��A�M���͍��F�̒b��W�c�ɖ����āA��苭�͂ȓ�S�擛�i�e���a��܃Z���`�̑�^�C�j�����삳���Ă���B
�@ �j�㖼�����V���O�N�i����ܔN�j�̒��̐킢�ɂ����āA�O����̉Γ�e�����D�c�̓S�C�������c�̋R�n�R�c�������j�������ƂŁA����Ƃ��Ă̓S�C�̏d�v���͂�邬�Ȃ����̂ƂȂ����B���{��S�C���ɂ͒�����}�����̈ꕔ���g��R�s�[�������̂��W������Ă��邪�A���̐}���ɂ́A�h��a�ň͂܂ꂽ�i�X��̖��w�n�̓����ʼnΓ�e���\�����D�c�R�̑��y�����c�R�̌R�n��R�n���҂�_�����i��A�S�C�Ō����|���ꂽ���c���̕��҂�R�n���`����Ă���B���c�R�̒��ɂ��S�C�炵�����̂������Ă���҂�����悤�����A�S�C���̑g�D�͂̍����ƓS�C�̐��ɂ����ĐD�c�R�͈��|�I�ɏ����Ă����悤���B
�@ ���ډΓ�e�ɂ͊W�Ȃ����Ƃł͂��邪�A���̍���}�����Ă��邤���ɖʔ������ƂɋC�������B���y�S�C���̎w�����ł͂Ȃ����Ǝv���闼�R�̕����̉��l�����A�悭�ڗ����֊���w�����Ă���̂��B���n�ɐԂ����ւ���߂��c���̊��ŁA�v����Ɍ���̓��̊ۂ̊����c�ɂ����悤�Ȋ��ł���B�����̓��֊��ɂǂ̂悤�ȈӖ���������������̂��͖�O���̎��ɂ͂킩��Ȃ��������A�����������炱�̎���̓��֊��͌��݂̓��̊ۂ̃��[�c�ɂȂ�炩�̊W������̂�������Ȃ��B���{�s����ψ���s�́u���{��S�C���v�Ƃ����������̒��ɂ́u���֊������S�C���R���v�Ɛ����̂����ʐ^���f�ڂ���Ă���B���̓��֊��́A���n�ɋ��F�̓��ւ�`�������̂����A�\�}����̌`�Ȃǂ͍���}���̓��֊��Ƃ܂������������̂ł���B�@
�@ �M���̎���V��������ʂ������G�g�͒��N�o����f�s���邪�A���̎��G�g�R�͏\�拉�i�e�e�a��E���O�Z���`�ȉ��j�܂ł̏�������𓊓����A���̈З͂������Č�평���ꎞ�I�ɂ͗D�ʂɗ������B�������A�C�H�ɂ��⋋��������������ɁA�₪�ĕS�拉�i�e�e�a��l�Z���`�j�̑哛�𑽐����������N�R�̍U���ɑ����A���ɂ͗ɒǂ����܂�A�P�ނ̂�ނȂ��ɂ��������̂ł���B
�@ �G�g�̂��Ƃ��p���œV�����x�z��������ƍN���A���R�A�S�C�ɂ��R�������ƓS�C�b��W�c�̊Ǘ��ɍאS�̒��ӂ��X�����B�ƍN�͍��F�̒b��W�c�ɒ����𐾂킹�邱�Ƃƈ������ɔނ�̓S�C�������x�����A�������ꂽ�e�C���ʂɔ����グ���B���̂��߁A���F�̓S�C�H�̐��͍Ő����ɂ͐��S�l�ɂ��y�Ƃ����B�c���\��N�i��Z��l�N�j�̑��~�̐w�̒��O�ɂ́A��̒b��W�c�͓���A�L�b���w�c����S�C�̑�ʒ����������A�L�b�ƖŖS��͍�̒b��W�c����p���ƌĂ�铿�얋�{�����̓S�C��悤�ɂȂ��Ă������B
�@ �������A���얋�{�͖C�p�̌���ɂ��͂����A��x�ꖲ���͂��߂Ƃ���C�p�Ƃ����̓o�p��x���A����ɂ͂��̌�p�҂����̈琬�ɂ���Ȃ�̔z���������������B�܂��A�C�p�t�͍̔��c�\���q�����a�O�N�i��Z�ꎵ�N�j�A�����̏��{���˓c���Ɏd�������Ƃł��킩��悤�ɁA���̎���ɂȂ�ƁA�e�˂͗D�ꂽ�C�p�t�͂������Čٗp���͂��߂��悤�ł���B
�@ ���i�\�ܔN�i��Z�O���N�j�̓����̗��ɂ����ẮA����ɘU���������l�̔_��������ɏ\�̖��{�R��������������邱�ƂɂȂ������A�_��������ɂ�����ܕS���̓S�C�����{�R���̌����̈�ł��������Ƃ������Ă���B�قǂȂ����얋�{���]�˂ւ̓S�C�̎������݂������������܂�悤�ɂȂ����̂��A����܂ł̌o����ʂ��ēS�C�Ƃ������̂̈З͂Ɗ댯�����\���߂���قǂɔF��������ꂽ����ɈႢ�Ȃ��B
�@
�@ �͂�铌�m�̓������{�ɂ܂Ői�o���ė������[���b�p�̐��͂ɂƂ��āA�\�z�����S�C���y�̑��x�Ƒ�ʂ̓S�C�ɂ��R�������͂����炭�v�Z�O�̂��Ƃ������낤�B��q�����ĂɓS�C��n�����|���g�K���l�����ɂ������ẮA�܂�����N���o���Ȃ������ɂ��̒n�ŕ����e�������悤�ȂǂƂ͖��ɂ��z���Ă��Ȃ������͂��ł���B
�@ �L���X�g���z���̂��߂ɊC���z���Ă͂�����ė��������̐鋳�t�����̔w��ɂ́A�Վ�ἁX�Ɠ��{������_�����[���b�p���̎x�z�҂����̑�̂悤�Ȗڂ��������B�鋳�t�����̐M�ɂ�����z���ƕz���̔M�ӂ��ǂ�Ȃɏ����Ȃ��̂ł������Ƃ��Ă��A�����鋳�t�����̉A�ɉB����ރ��[���b�p�̘T�����́A���͂ł��̍��𐪕��ł���Ƃ�������v�Z���������������玟�X�ɂ��̉���ďP���������Ă������Ƃ��낤�B���ɂ́A����ȌQ�T�����̖�S�̉��}�����͓̂S�C�̑��݂ł������悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B
�@ ����Ă�A�t���J�A���ߓ��A����A�W�A�Ȃǂ̊e�n�ɂ����鐦�܂�������̐A���n�x�z�̗��j������A���̂��Ƃ͑����ɐ��������B���[���b�p���͖����ɓS�C�̗͂ɂ���Ă����̒n��̍��X��łڂ��A���O���x�z���e�������B�{������̕⋋������A���̏�ł���r�ɂȂ�Ȃ��قǂɏ����̉��B���͂����E�e�n�𐪕��������̂́A�e�̈З͂������čs����X�̎x�z�҂��E�C�Ȃ����͕��]�����A����ɂ���č����Ɋׂ�������������Ă��܂������O���ӂ̂܂܂ɑ��邱�Ƃ��o�������炾�����B
�@ �K���Ȃ��ƂɁA���̓����̓��{�����͂�������������Ă����B���[���b�p�l�̎��e�Ɋr�ׂ�����炭���\�̓_�ł͂��Ȃ����Ă͂����낤���A�ނ炪���{�ɐH�w���̂��͂��߂����ɂ́A�䂪���ɂ͖c��Ȑ��̓S�C�����݂��Ă����̂ł���B�����ɔނ炪�D�ꂽ�e�ŕ������Ă����Ƃ͂����Ă��A�D�̎��e�\�͂̊W�ł��������S�l�O��̒P�ʂł������{�ɏ㗤���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��������낤���A�܂��헪�����̕⋋����������Ǝv����B���\�����Ƃ͂����Ă����̏�ł͈��|�I�ɏ���Γ�e�ŕ��������R�c�ƁA���̌R�c�Ɏ��ꂽ�����̓��{�̌Q�Y�����𐪕�����̂́A�ނ�ɂƂ��Ď���̋Ƃ������͂��ł���B
�@ �����l���Ă݂�ƁA��q���e�͉䂪���ɂƂ��ĂȂ�Ƃ��▭�̃^�C�~���O�œ`�������ƌ��킴������Ȃ����A���܂��ܓ������̑��̍��x�ȋ������H�Z�p�����݂��Ă������Ƃ��܂��ƂȂ��K�^�������ƍl����������Ȃ��B���R����ƌ��̎���ɓ����ĉ䂪���͍�����������A���̂��߂ɍ��O���͂̐N�����s�\�ɂȂ����Ƃ������Ă��邯��ǂ��A���������낤�����܂����A�������͂ɂ��x�z���\�ȏɂ������Ƃ�����A�ނ�͗e�͂Ȃ��N�����Ă����ɈႢ�Ȃ��B�����g�́A���N�ɂ킽�鍽�������j�I�Ɍ��Ă悩�����Ƃ͍l���Ă��Ȃ����A����ɂ�镶���I�ȃ}�C�i�X�ʂ������ւ��������Ƃ��F�߂�������Ȃ�����ǂ��A����͂Ƃ������A���ʓI�ɓ��얋�{����������𐋍s�ł����w�i�ɂ͓S�C�̑��݂����������Ƃ͔ۂ߂Ȃ��悤�ȋC�����ĂȂ�Ȃ��B
�@ �ƌ��������߂z���Ă����S�]�N�̍Ό����o���ꔪ�l�Z�N�̂��ƁA�A�����J���C���h�͑��i�ߊ��r�b�h���͒ʏ������߂ĉY��ɗ��q�������A���{�͂��̐\���o��f�łƂ��ċ��₵���B����ɂ��ꂩ�玵�N��̈ꔪ�O�N�A�������A�����J���C���h�͑��i�ߊ��y���[���哝�̂̍������g���čĂщY��ɗ��q�A���{�ɑ��Č������J���𔗂����B�����āA���j�ɍ��܂�Ă���悤�ɁA���N�ė��������y���[�Ɩ��{�Ƃ̊Ԃœ��Ęa�e��������ꂽ�킯�ł���B
�@ �����p�ɓ������l�ǂ̍��D�ɂ���C�̈Њd�ˌ��Ƌ��d�ȊO���p���ɁA�]�˂̖��t�����O���F�����T�����邱�ƂɂȂ����̂����A�����ɂ͐v���ȏ������𔗂�y���[�̂ق��ɂ����S�ł�͂��������Ƃ��낤�B�͖C�ˌ���������]�ˏ�������ڔj�邱�Ƃ͂ł�����������Ȃ����A�{������̎x����⋋���Ȃ��܂܁A�������l�ǂ̊͑D�ɕ��悷�镺�͂����ŏ㗤���A�S�C���C�ŕ����������m�W�c�Ɛ퓬���s���A���y�����S�ɐ������邱�Ƃ͎�����s�\�������͂��ł���B�y���[���g���N�����悭���̂��Ƃ��킫�܂��Ă����ɈႢ�Ȃ��B
�@ �s�������Ƃ�����ꂽ���Ęa�e���̒������_�@�Ƃ��āA�䂪���͈ꋓ�ɋߑ㉻�ւƓ˂��i��ł����̂����A����܂ł̗��j�̉A�ɂ����ēS�C���ʂ����������́A�ǂ��Ӗ��ł������Ӗ��ł������ɑ傫�Ȃ��̂ł������悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B���{��S�C���̎�q���e�R���N�V������ڂɂ��Ă͂��܂������̖��z�́A�������č��D���q�̎���ɂ܂ŋy�сA�悤�₭�������݂�Ƃ���ƂȂ����B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N7��12��
�t���[�����X���ĂȂɁH
�@ ���Ζʂ̑���ƈ��A�����킷�Ƃ��A�u���d���͂ǂ̂悤�Ȃ��Ƃ��H�v�Ɛu�˂���ƁA���̂悤�Ȑl�Ԃ͂Ƃ肠�����u�t���[�����X�ł��v�Ɠ����邵���Ȃ��B�ꉞ���h�������Ă͂��邪�A����������̂Ȃ��A�����̖��O�ƏZ���d�b�ԍ����L���������̖��h�ł���B
�@ ���̒��ɂ́u�t���[���C�^�[�v�Ƃ������t������B�����������ʉ������a���p�ꂩ�͒m��Ȃ����A�u�t���[�̂��̏����ł��v�Ƃ����Ӗ��̂���炵�����̌��t���A���͕K�������D���ł͂Ȃ��B�ׂɍ����́u�t���[�^�[�v�ƊԈႦ���邩�猙���Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A�����Ɛ[�����R�������Ă̂��Ƃł���B���̓���炵�̌o�ϓI�Ȑ������猾���Ύ��Ȃǂ͂܂��Ƀt���[�^�[�̓T�^�ɈႢ�Ȃ��B
�@ ���Ԃ�A�t���[���C�^�[�Ƃ������t�ɂ́A�ǂ����̏o�ŎЂ�V���Ђ́u�ꑮ���C�^�[�v�ł͂Ȃ��A�ǂ��̎d���ł������郉�C�^�[���ƌ����܂݂�����̂��낤�B����Ȃ�ΒP�Ƀ��C�^�[�ƌ����悳�����Ȃ��̂����A�����ăt���[�Ƃ�������������Ƃ��낪�����ɂ����{�I�ł���B������������A�u���C�^�[�v���Ȃ킿�u��Ɓv�Ɩ����̂͂������܂������A���Ƃ����Ă܂������̑f�l�Ƃ��Ⴄ������Ƃ�������������Ȃ����v�������̌��t�ɂ͍��߂��Ă���̂�������Ȃ��B�{���A���͂������d��������l�͊F���C�^�[�Ȃ̂�����A�l�I�ɂ́u�t���[�v�Ƃ������Ȃǂ��Ȃ��Ă悢�Ǝv���̂����c�c�B
�@ �u�t���[���C�^�[�v�Ƃ����a���p�ꂪ���܂ꂽ�w�i�ɂ́A�����炭�u�t���[�����X�ifree
-lance)�v�Ƃ����p��̑��݂��������Ǝv����B��E�𗣂ꏊ���̂Ȃ������𑗂�悤�ɂȂ��Ă���́A���Ȃǂ��E�Ƃ�u�˂�ꂽ�Ƃ��A�u�t���[�����X�ł��v�Ɠ����邱�Ƃ��������B����ȂƂ��A�u�t���[�����X���ĂȂ�ł����H�v�Ɩ₢�Ԃ��ꂽ��A�ׂ��Ȑ����͖ʓ|�Ȃ̂ŁA�u����[�A�v����ɁA����E���ł��Ȃ�ł����t���[�̂��Ƃł���v�Ƃ�������������Ă��܂��̂����A���́u�t���[�����X�v�Ƃ������t�ɂ͂���Ȃ�̈Ӗ�������B
�@ ���Ăł̓��C�^�[��e��A�[�e�B�X�g�Łu�t���[�����X�v�𖼏��l�͏��Ȃ��Ȃ����A���������l�́A�L�������ɂ�����炸����Ȃ�̐M�O�Ǝ����̎d���ɑ���ǂ��Ӗ��ł̐ӔC�ƌւ�������Đ����Ă���B����́A���Ăɂ����Ắu�t���[�����X�v�Ƃ������t���������j�Ɠ`���Ɏx����ꂽ���t�ł����邩�炾�B
�@ �ufree-lance�v��Ɓu���R�̑��v�Ƃ������ƂɂȂ�B�uchivalry world�v���Ȃ킿
�����R�m���̐��E�ɂ����āA����̉���M���Ɏd���邱�ƂȂ���ɂ����u����{�v�݂̂𗊂�ɗ�����n��R�m�����������B�ւ荂���ނ�́A���̎��͂�^�ɔF�ߋ����Ă���鉤���M���̂��߂ɓ����͂������A�������Ă��̐b���Ƃ��ċA�����邱�Ƃ͂Ȃ��A�����܂ň�C�T�Ƃ��Ď��R�ӎv���т��ʂ����B
�@ �ނ��A����ł́A�ނ�͕s���ɊÂA���������ŋ`���т����Ƃ��������B�����āA����Ȕނ�͂������ufree-lance�v�ƌĂ��悤�ɂȂ��Ă������̂ł���B�����R�m���̎��オ�I���A�����ƌ㐢�ɂ������Ă�����A���̌̎��ɂ��Ȃ�ŁA���Ăɂ����ẮA����̌ٗp��ɑ���������̐M�O�Ɋ�Â��Đ��̎d��������l�X�̓t���[�����X�ƌĂ��悤�ɂȂ����悤�ł���B
�@ �u����{�̓n���l�v�Ƃł����������Ƃ��Ƃ̈Ӗ��ł̃t���[�����X�ɂ͂قlj����������A�����̂Ȃ�����ɐg�������悤�ɂȂ��Ă���́A�Ƃ�����ƃN���C�A���g�̊�F�����������Ȃ��痬���ꂽ��Ë������肵�����Ȑg�𗥂��邽�߂ɁA���܂ɂ̓t���[�����X�̐��_�ɗ����Ԃ��Đ܁X�̎����̌�����`�F�b�N����悤�ɂ��悤�ɐS�����Ă����B�܂�����Ȃ��Ƃ������āA�\�����ĐE�Ƃ���ꂽ�Ƃ��ɂ́A�u�t���[���C�^�[�v�ł͂Ȃ��A�u�t���[�����X�v�Ɠ�����悤�ɂ��Ă���킯�ł���B����ɁA���̏ꍇ�A���C�^�[���������Đ��v�𗧂ĂĂ���킯�ł͂Ȃ�����A�t���[���C�^�[�Ƃ������t�͂������肱�Ȃ��B
�@ �Ƃ܂��A�����܂ł̌��ӕ\���̂قǂ͊i�D�����̂����A�����ɂ͂Ƃ������ƂɂȂ�Ǝ���͂͂��̂�����قȂ��Ă���B�x�@�̎���܂�̌���������Ƃ������Ƃ������āA�����Ή���ȃy����L�[�{�[�h�Ɏ����ւ��A���X���������肵�Ȃ���A�{���̃t���[�����X�ɂ͂���܂����ق����͂Ȃǂ������Ԃ��Ă���킯�ł���B�����V���Ђ̃A�T�q�E�C���^�[�l�b�g�E�L���X�^�[���iAIC���j�̕��Q�L�Ȃǂ����̈�ɂق��Ȃ�Ȃ��B
�@ ���Y���̒S�����˗����ꂽ�������e�p�����Z�ŕ��Ϗ\�l�A�ܖ��̒������e����������͂��߂��Ƃ��A�ҏW�҂́A�l�b�g��ł���Ȓ������e��ǂނ͎̂��������ŁA�Ō�܂œǂݒʂ��l�͓ǎҒ��ɂ͈�l�����Ȃ����낤�Ǝv�����̂��������B�ҏW�҂���́A�����̘A�ڌ��e������A���e�O�A�l�����x�̕��͂ɂ���悤�ɂƂ̗v�������x�����������A���͂��̈ӎv�ɋt�炢�A���Ȃ�̕��j���т��Ă����B�ҏW�҂ɂ͐\����Ȃ��Ƃ͎v�������A�����͘J�͂ƌo�ϐ������A�����ł�AIC���̂��߂ɖ𗧂ĂƎv���ď����͂��߂��u�t���[�����X���ǂ��l�ԁv�̈Ӓn�ł���B���e���͂قƂ�ǂȂ��ɓ��������A���R�ɉ��ł������Ă悢���A���f�B�A�̐����㒷�����Ƃ��ɐ����͂Ȃ��Ƃ����̂������̘b����������A����Ӗ��Ŏ��͂��̌��t��f���Ɏ���������̂��Ƃł���B
�@ �C���^�[�l�b�g�̑O�i�K�̃p�\�R���ʐM����Anifty-serve�J�݈ȗ��̌ÎQ��A������������́A�z�X�g�T�C�h����̈˗��������āA�ꎞ���Astranger�Ƃ����n���h���l�[�����g���l�X�Ȋp�x����R���s���[�^�ʐM�̉\����T���Ă����B�{�������\�ɏo�邱�Ƃ͂Ȃ��������A���̂���stranger�Ƃ����n���h���l�[���́A���̐��E�ł͂��Ȃ�m��ꂽ���݂ł������B�����Ă��̎����I���s�̈�Ƃ��āA���͓�N�Ԃقnjf���ɖ��T�̂悤�ɒ������e���A�b�v�������Ă������Ƃ�����B�ȑO�ɂ��̗��ŏЉ�����Ƃ̂���ٍe�A�u�����C�P������v��u�[�����k���|�[�g�v�Ȃǂ́A���������ƁA���̎���Ɍf���Ɉ�x�A�b�v�������Ƃ̂��錴�e����������蒼�����������̂��̂ł���B�����̃p�\�R���ʐM������͂܂��S���ł��������l�A�ܖ��l���x���������A����ł����̎����I�Ȏ��݂�ʂ��Ď��͑������̏�A�ǎ҂��l�����邱�Ƃ��ł����B
�@ ����Ȃ��Ƃ������Ɛ\����Ȃ����A�O��V���Ђ̋L�҂���͂��߂Ƃ���e�V���Ђ�G���Ђ̋L�҂����̂قƂ�ǂ��A�p�\�R���ʐM�̓}�j�A�b�N�Ńl�N���ȘA���̂�邱�ƂŁA���̓��e���@�\���t�قł܂��܂��ƂĂ������}�̂ɂ͋y�Ȃ��ƚ����Ă�������̂��Ƃł���B
�@ �����A�V�j�ЂƂ����o�ŎЂ���̈˗��Łu�d�q�l�b�g���[���h�E�p�\�R���ʐM�̌��Ɖe�v�Ƃ����{��stranger�Ƃ����n���h���l�[���Ŏ��M���A�߂������̃R���s���[�^�ʐM�̗l�X�ȉ\����A�l�����闘�_��X�N�ɂ��Ă킩��₷�������������B���݃C���^�[�l�b�g�̐��E�ŋN�����Ă���A�E�C���X�A�n�b�L���O�A�p�X���[�h����A��排����A�����A���\�A�ߓx�ȏ@�����U�A���t���U�A�����Ƃ������悤�Ȋe��̕s�ˎ��́A���łɃp�\�R���ʐM�̎��ォ��N�����Ă����B�����ʐM���E�̌��߂�l�Ԗ͗l�ɂ��āA�W���[�N�Ⓙ�k��L�x�Ɍ����ďq�ׂ����Ȃ�y���̂�̖{�ł��������A�����ǂȊw�Z�p���P���̖����H�w��������d�@���ƘA����Ȃǂ���ʐM���E�̓W�]�ɂ��Ď�������肷��Ƃ������܂��܂ł����B
�@ �����āA�����ɂ͎��̗\�z�����͂邩�ɏ��鑬�x�ŃC���^�[�l�b�g�S���̎��オ���������B���܂�V���Ђ�G���Ђ���̂Ђ��Ԃ����悤�ɉ��ɋ����ăl�b�g�����p���A�R���s���[�^�֘A�������X�ɏo�������ł���B�p�\�R���ʐM�̎��ォ��C���^�[�l�b�g�ւ̉ߓn���ɂ����āA�����g�A�����̏��S�Ҍ����R���s���[�^��paso�őn�������N�Ԃقǁu�R���s���[�^��̐V���v�Ƃ����R������S��������������B
�@ ����Ȍo���Ȃǂ��������̂ŁA���߂͌h�����ꂽ�Ƃ��Ă��A���Ԃ����ĂΏ������ǂ�ł���������������邾�낤�ƍl���A�����Ē������͂��A�����ĂƂ��ɂ͍d���ȕ��͂������Ă݂��肵���B�C���^�[�l�b�g�̌f�ڕ��͏���`���邱�Ƃ��ړI������A���̂╶�ӁA�_�|�̓W�J�ɂ��܂肱����炸�y�����������̂��x�X�g�����A�ǎ҂����̂ق����D�܂����v���Ă���A�����̐l�͋Â������͂Ȃǂ����҂��Ă͂��Ȃ��Ƃ����̂͂��̒ʂ肾�낤���A�܂�����ł悢�Ƃ��v���B�������A�C���^�[�l�b�g�����W�r���̃��f�B�A�ł���A�����I�ɂ͌ʓI�ȃj�[�Y�������Ƃ�ڎw���Ă���Ƃ���A�l�X�Ȏ��݂͂Ȃ���Ă悢�̂ł͂Ȃ��낤���B
�@ ��A�̎�L�͑̍ق���Q�L�ɂ͂��Ă��邪�A�C���^�[�l�b�g��̋L��������Ƃ����čs�������������̏o���������̉��n���Ȃ��K���ɏ����Ă���킯�ł͂Ȃ��B���̂ɒ��ӂ��Ȃ��炻��Ȃ�ɐ��Ȃ������Ă��邵�A����ނ̂ق��ɑ����ʂ̎��������ׂ���ǂ肵�Ă�����B�������̗Ƃ邽�߂̎G�������Ȃ��Ȃ���̎��M�Ȃ̂ŁA��J���Ȃ��ƌ����ΉR�ɂȂ邪�A���Ƃ������ł������Ƃ��Ă����œǂ�ł��������������Ƃ����Ȃ�M�҂Ƃ��Ă͖����ɐs����B
�@ �ŋ߂̕ҏW�҂̘b�ɂ��A���̂��킢�Ȃ������ɖ���Ō�܂Ŗڂ�ʂ��Ă�������}�j�A�b�N�i�H�j�ȓǎ҂̕��������Ԃ�ƌ���Ă��������ł���B�����g�͂��̕��X���}�j�A�b�N���Ƃ͎v�������Ȃ����A���Ƃ������ł������Ƃ��Ă��B�X�S���犴�Ӑ\���グ�����ł���B�܂��A�����f�ڂƂ��������I���s����Ԃ݂Ȃ������N�߂������Ɖ䖝�������Ă����ҏW�҂ɂ�����Ȃ�̊��ӂƌh�ӂ�\����K�v�����邾�낤�B
�@ ���Ăł�����悤�ȃt���[�����X�ɂ͓���Ȃꂻ���ɂȂ����A���߂āu�t���[�����X���ǂ��v�̂���ɂ��̂܂��u���ǂ��v���炢�̃��C�^�[�ɂ͂Ȃ��悤�ɐS���������Ǝv���Ă���B���Ƃ��i���̏K�색�C�^�[�ŏI��邩������Ȃ��ɂ��Ă��c�c�B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N7��19��
�������̏o��Ӑ}�́H
�@ ���܂ɂ����A�ǂ����Ă��ƈ˗����A�ߏ��ɏZ�ޑ�w�������̐��w�w�K�̑��k�ɂ̂��Ă����邱�Ƃ�����B������w�����Ⴂ�ނ�̊�������͂�������Ȃɂ��Ɗw�Ԃ��Ƃ������̂ŁA���ɂƂ��Ă�����Ȃ�ɗL�Ӌ`�Ȏ��Ԃł���B
�@ ���̓_�͂܂��悢�̂����A�Ƃ�����ނ炪��������ł���������̒��ɂǂ��l���Ă݂Ă����̏o��Ӑ}�������ł��Ȃ���肪�������肷��ƁA�������ɓ{�肪���ݏグ�Ă���B�ŋ߂��A���鎄�����Z�̐��k���h��Ȃ̂ŋ����Ăق����Ƃ����Ă������߂Ă��邤���ɁA����Ȗ����ꒃ�Ȗ����������w�̋��t�̊炪�������Ȃ��Ă������̂��B���鎄����w�̌o�ϊw���̐��w�̖�肾�����̂����A���̑�w���u�]������̊w�͓x���炷��ƁA���Ԃ�N��l�Ƃ��ĉ����Ȃ������낤�c�c���₻��ǂ��납�A�͂��߂����̂��悤���Ȃ��������낤�Ƒz������邵����̂���������ł���B������̈�ȂǂƂ����ɒʂ�z���A�u�X��v�̈�ɂ܂ŒB���Ă����ƌ����Ă悢�B
�@ ��w�̖��_�ɂ�����邱�ƂȂ̂ł��̖��𖾂��ɂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A�����̏��q���̐����������ċɒ[�Ȓ��������������Ă����w�̈�Ƃ��������Ă������B�����Č��킹�Ă��炤�Ȃ�A����ȑ�w�i���܂肱��ȏ������͂������Ȃ��̂����j���A���w�̏o��͈͂����UB�܂ł̂͂��̌o�ϊw���̓������ɁA���V�̔��ς̒m����s�^���̒藝�i���Z�̐��V�͈̔͊O�j�Ȃǂ������Ȃ���Ή����Ȃ��悤�Ȗ����o�肷�邱�Ǝ��ُ̈�ł���B�o�ϊw���͗��H�n�Ȃ݂̐��w��K�v�Ƃ���Ƃ͂������̂́A������w�⎄����w�̒���֍Z�Ƃ������w�����āA�o�ϊw���̏ꍇ�ɂ͏o��͈͂͐��UB�܂łɂ������Ă���B
�@ �����ŏڂ������Ƃ������킯�ɂ������Ȃ����A�����̒��ɎO�����╪�����̓��������̃O���t��`���A�����̃O���t�̐ڐ������߁A���ɂ��̃O���t�̓���̈�̐ڐ������̗̈�̃O���t�ƌ����͈͂ł̐ړ_��X���W�̍ő�l���߁A����ɂ��̂Ƃ��ɐڐ���X���A�����Ă��Ƃ̊��̃O���t�ň͂܂�镔���̖ʐς����߂���ł������B
�@ �܂��A�����̒��̎O�����i���̎O������X���Ƃ̌�_�͐�����Ɩ�������I�j��ΐ���������̕�������������đ����\�������i�������̋Ɍ��l�����߂�Ƃ��ɁA���Ƃ��m���Ă��Ă��ؖ������ŒP�Ɍ��ʂ������ËL���Ă���ɂ����Ȃ����s�^���̒藝���K�v�������肷��B���s�^���̒藝���g��Ȃ��ł��̋Ɍ��l�����߂悤�Ƃ���ƁA���Ƃ������܂����Ƃ��Ă����ꂾ���Ŏ������Ԃ��I����Ă��܂����˂Ȃ��j�A�����̒������̒l���Ƃ�X�̗̈�����߂邾���ł����J�ŁA���̒i�K�Łu�o��҂̃o�J�����[�b�I�v�Ɩڂ��肠���Ĕl�肽���Ȃ�B
�@ �Ȃ�Ƃ����ꂪ���܂�ƁA�����̂������Ƃ̊��S�̂̈ꎟ���������߂āi���ꂪ�܂����G�ȕ������ɂȂ�I�j�A��������Ƃɐꂬ��́i���Ƃ̊��̍����������̒l�ɂȂ�̈悾���́j�����\��`���i�����ɂ��Ȃ瓖�R�������K�v�ɂȂ�j�A����ɂ������̊��l�����߁A���̊��̃O���t��`���B�����܂ł���ƁA�u�I���[���C���悧�H�A�N�\�b�^�������I�v�Ɠ{��������ɐ⋩�������Ȃ�B
�@ ���̂��ƁA���G�Ȗ�����������ɂ��镪���W���̐ڐ��̕����������߁A������S�`���S�`���ό`�����蕪�������A�o�Ă������̓K�ۂʂ����肵�ĂȂ�Ƃ������ƂȂ�ړ_�̍��W�����߂�B�����āA�Ō�̂ւ����Ȑ}�`�̖ʐς��������ɏ��������Ȃ����ϕ����Čv�Z���ʂ𑫂��I��鍠�ɂ͖ڂ�������Ă��āA�u�R���`�L�V���[�b�A�E���Ă�邤���I�v�ƕ��{�̓x�����͂��ɒ��_�ɒB����B�v����Ɂu�{��Ȑ��v���ő�l���Ƃ�킯���B���������Ɠ{��Ȑ�������Ĕ����s�\�ȓ��ٓ_�ɂȂ�����A����Ȃ�����̂��߂Ɋ��l��������ɔ��U�����肵���˂Ȃ��B�����܂ł���ƁA�������w�̖{���Ƃ͂܂�Ŗ����Ȑ��_�̍���ȊO�̂Ȃɂ��̂ł��Ȃ����炾�B
�@ ���Ԃ̌���ꂽ�����̌���Ŏ��ۂɂ���Ȗ��Ƒ���������A��֍�����w�̗��Ȍn�̎������āA�����o����҂͂قƂ�ǂ��Ȃ����낤�B����ȏ��炷��ƁA���̑�w�̎��ł��̖��Ɏ���������̂��������Ƃ͂ƂĂ��v���Ȃ��B�������A��荂�x�Ȓm���������w�̐��ƂȂ獂�݂��猩���낷���Ƃ��ł��邩��A����Ȃ�̓W�]�������āA���ϓI�ɂ��̉��j��|�C���g���������邱�Ƃ��ł��悤���A���̒m���͈̔͂ł�������Ƃ����͖̂����ꒃ�Șb�ł���B���������A����Ȃ��Ƃ��ł��邭�炢�Ȃ��w�Ȃɍs���K�v�ȂǂȂ��ƌ����Ă��悢���炢�Ȃ̂�����c�c�B
�@ ������������A����ȏo���������w�̐搶�́A���l�Ɉ�l�̔E�ϗ͂ƏW���͂̓V�˂�T�����肾�����̂�������Ȃ��B�����łȂ���A������ɂ�قnj��Ȏv�����������ʂ��ꂪ�g���E�}�ƂȂ�A���̔����Ŏ��ɑ���T�f�B�X�e�B�b�N�Ȏ�ɐ����b���������悤�ɂȂ����̂�������Ȃ��B
�@ �o��҂̂ق��͂��炩���ߗp�ӂ��Ă��������������Ƃɂ��āA�Ӓn���ȗ��Ƃ�����N���A����̂ɓ���ȑM���̂����Q�������ꂱ��Ɛ݂��Ȃ����������Ă�������悢�悤�Ȃ��̂́A�����Ȃ肻�����炳������̂ق��͂��܂������̂ł͂Ȃ����낤�B�������ߔN�͕��G�ȔC�ӂ̊��Ƃ��̓K���Ȓ�`�����͂��邾���Ŏ��݂ɃO���t���`����p�\�R���\�t�g�Ȃǂ����邩��A�����쐬���鑤�͂�����ł��Â�ɋÂ����O���t��}�`���f�U�C�����邱�Ƃ��ł���B���Ă̓O���t�̌`�킩��Ȃ�����������Ă��̊T�`�����߂Ă����̂ɁA�R���s���[�^�̔��B�̂������ŁA���܂͐��m�ȃO���t���ɕ`���Ă���A���ς̖����f�U�C������Ƃ����A�{���]�|�Ȃ��Ƃ��ł���킯�ł���B
�@ �܂��A���Ƃ�����Ă����ꂪ�����̖{���I�Ȋw�K���e�ɂȂ�����Ȃ炠����x��ނ����Ȃ��̂����A�v�Z�ʂ��₽�瑽���P�ɂЂ˂���Ă��邾���̓��Ȃ�A����قǂɖ��f�Șb�͂Ȃ��B���H�̍\���������l�������邽�߂ɖ��H�ɒ��܂���̂Ȃ�悢���A���Ԃ𐧌����������ŁA�������������d�ɂ������ˌJ��Ԃ��i���������̂��t���N�^���}�`�I�Ƃ��������j�₽�畡�G����ɐݒ肵��������H�Ƀ`�������W�����A���ԓ��ɔ������Ȃ��Ƃ��O�̐l���͐^���Â����Ƌ�������悤�Ȉُ킳�́A���Ă��܂�������ł͂Ȃ��B
�@ �ł́A�����Ă���ȏo�肪�J��Ԃ���闠�ɂ͂ǂ�ȈӐ}������̂��낤�H�B�ǂ�ȂɈՂ�����w�ł�����Ȃ�̃v���C�h����邽�߁A������肾���͈ꉞ�̊i�D�����Ă����˂Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ͂���̂�������Ȃ��B�܂��A�o��S���̑�w���t���s���ō��Z���̐��w�̏C���͈͂ɏ\���Ȕz�����Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ����낤�B���w�Ƃ������Ƃ������āA���Ƃ����₪�o�肳�ꂽ�Ƃ��Ă��A�N���������̂���ᔻ�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ���������Ȃ��Ƃ͌����Ȃ��B
�@ �������A���ɂ͂��܂ЂƂ��ʂȗ��R������悤�ɂ��v���ĂȂ�Ȃ��B����Ȍ�����������Ȃ����A�[�I�Ɍ��킹�Ă��炤�ƁA�o��ƍ̓_�̘J�͂̏ȗ͉��ł���B�Ƃ��ɋL�q���̖��Ȃǂɂ����ẮA�\���Ɍv�Z���s�����ǖ�����A�����_�⒆�ԓ_�Ȃǂ��ׂ�������ƂȂ�ƁA�����쐬�����葽���̓��Ă̍̓_���������������ɁA�ׂ��ȓ_���̏W�v�܂ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ������S���҂̘J�͂͑�ςȂ��̂ƂȂ�B�����A�ɒ[�ɖ�肪�������̕K�v�͂قƂ�ǂȂ��B���������������ȑ�w�̏ꍇ�A�����̓��_�����ۂǂꂾ���̈Ӗ������̂��͂킩��Ȃ����A�l�X�ȗ��R�ŁA���Ă��܂ޓ�������������Ȃ�ɐ��������ԕۊǂ͂��Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤����A���̖��͒ɂ��y���Ƃ������Ƃ���Ȃ̂��낤�B
�@ �������������ƂɁA�����̗]�g���y�Ԃ̂͂�����o�肵����w�̎������ɗ��܂�Ȃ��B�ނ��낻�̑�w�ɊW�Ȃ��҂ւ̉e���̂ق����傫���̂��B�����̏o�ŎЂ�\���Z�Ȃǂ͂����̈�Ȃ���Ȃ��������~���W�߁A�u�����W�v�Ƃ��������悤�ȗނ̖��W���쐬����B�������Ԑ���~���Ǘ���`�I�X���̋����ꕔ�̍��Z���t�̂Ȃ��ɂ́A���̎�̖��W���w�����A��������I����V���ɖ��p���ɃR�s�[���ċ��ނɂ����萶�k�̏h��ɂ����肷��҂�����B���t�����̂ق��͖��W�ɕt������͔͉������Ă��邩��悢�悤�Ȃ��̂́A�Ȃ�̃q���g���Ȃ��܂܂ɐ^���ʂ��炻�����炳��鐶�k�̂ق��͂ނ�܂������̂ł͂Ȃ��B
�@ �����������������ނɂ��鋳�t�����������Ȃ���ł��\�K�����A���炩���߂�������|�C���g���������Ă���A���J�ȉ�����ł��̖��������Ă݂��A���k�̋^��_�ɓ����Ă����̂Ȃ�܂�������B�������ȋ��t������悤��������͏����h�ɉ߂��Ȃ��悤���B�����Ă��̏ꍇ�́A�u����ȑ�w�ł����̒��x�̖����o���B���̂��炢�̖�肪�ł��Ȃ��Ăǂ�����I�c�c����Ȃ��Ƃ���A�u�]�Z�Ȃ�Ȃ������I�v�Ƃ���Ɍ��������k�Ƀv���b�V���[�݂̂�������B
�@ ���������Ă����Ȃ肻��ȃq�l�Ƀq�l��������炳�ꂽ�犮���Ȃǂ��ڂ��Ȃ������ɁA����Ȃ��Ƃ͒I�ɏグ�Đ��k����肽�Ă�B�����čŌ�ɂ͂���܂��R�s�[���������̉k�Ɏ�n���A�u�ł��Ȃ�������������Ăł���悤�ɂȂ��Ƃ��I�v�Ɛ����ɐ錾���A�����_�������Ԃ��������������A���ۂɂ͂��̖��ɂ��Ď���͉�������Ȃ��܂܂ɏI��点�Ă��܂��B���̂��Ă̋����q�ɂ����Z�̋��t�����Ȃ肢�邪�A����ȋ��t�ɂȂ��Ă��Ȃ����Ƃ��Ђ�����肤����ł���B
�@ �قƂ�ǂ̐��k�̏ꍇ�A����ȓ������͂ł͉�����͂����Ȃ����A�����Ă����̈Ӗ��𗝉�����̂����������A�^�ʖڂł������قǎv���Y�݁A�Ђǂ��Ȃ�Ɛ��_�����ǐ��O�̏�Ԃɂ܂Ŋׂ��Ă��܂��B���������ނ�́A�\���Z�̋��t��ƒ닳�t�A�g�߂Ȑ��w��U�̐l�ԂȂǂɏ��������߂邱�ƂɂȂ邪�A���������߂�ꂽ�������đ����ɑΉ�����̂͗e�ՂłȂ��B���Ƃ��������Ƃ��ł����Ƃ��Ă��A��������Ă������k�̗͗ʂ◝��x�ɍ��킹�ĉ���₷���������邱�Ƃ͓�����A��������ɂ͂���Ȃ�̎��Ԃ������邩�炾�B
�@ ���k������Ⓙ��������Ă��A���̗v�_��������I�������ƂŁi�v�_���ւ���������Ȃ��̂����j�A�u����Ȗ��ł��Ȃ��Ă����v�Ȃ�B������Ȃ��������Ƃ��Ȃ���v�ƐS����Ԃ߂Ă��ƁA����͂����ɂ��ق��Ƃ����Ƃ����悤�Ȉ��g�݂̏��ׂ邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��B�ǂ�Ȃɔނ炪���_�I�ɗ}�����ꂽ��Ԃɂ��邩���킩��Ƃ������̂��낤�B
�@ �����ۂ��A�s���l�܂����Ƃ��ɒN���ɏ��������߂邻��Ȑ��k�̗��e�����āA���̂��߂ɑ����ȏo��𔗂�ꂽ�肷�邱�ƂɂȂ肩�˂Ȃ��B�Љ�S�̂Ƃ��čl���Ă݂�Ƃ��A����͂������ԓI�A�o�ϓI�ȈӖ��ł��A����ɂ͐l�I�G�l���M�[�̊ϓ_���炵�Ă���ςȃ��X���ƌ��킴������Ȃ��B�s���Ȏ���ɂ͗\���Z��m�Y�Ƃ̔��W�͌o�ϊ������̗v���ɂȂ肤�邩��A�����̑��݂��x���钴������ɂ͈Ӗ�������ȂǂƂ����瑊�Ȍ��������藧��������Ȃ����A����Ȍ����͋���̂���ׂ��p����͌����܂ł��Ȃ��O��Ă���B
�@ �u�D�_�ɂ��O���̗��v�Ƃ����������邭�炢������A�������������w�̐搶���ɂ͓��R�u�l����ܕ����x�̗��v���炢�͂���ɈႢ�Ȃ��B�܂��A�������悵�Ƃ��Ȃ��命���̑�w�̐搶���ɂ��A������S������ɍۂ��Ă͂���Ȃ�̋�J�͂��邱�Ƃ��낤�B�҂̂Ȃ����獇�i�҂̑I��������Ƃ����s�ׂɊ��S�����ȕ��@�ȂǑ��݂��Ȃ����炾�B���T�͂��̂�����̂��Ƃɂ��Ďv���Ƃ������������q�ׂ����Ă��炢�����Ǝv���B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N7��26��
�����S���҂ɂ���J���H
�@ ���܂���ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ����A������S�������w�̐搶���ɂ�����Ȃ�̋�J�͂���悤���B���݂̓����`�Ԃ������������邩����A�Ȃ�ׂ��Ȃ�����̒S�����ɂ͂Ȃ肽���Ȃ��Ƃ����̂��A�����炭��w�̋��t�����̖{�����낤�B�����̐�匤����w���̎w�����ɂ킽���Ē��f�����������Ƃ���ɑ����̓_�����Ɩ��ɖz���������邤���ɁA�~�X���������炠�����Őӂ߂���B���Ƃ���S���Đ^�ɗD�ꂽ�l�ނ�I������ɓK�����ǖ�������Ă݂��Ƃ���ŁA�e���Ȃ̑����_���ɂ�鍇�۔��肪�嗬�̌������ɂ����ẮA���苳�Ȃ̓�����Ɋ����ł�������Ƃ����Ă��ꂾ���ł��̎҂����i�ł���킯�ł͂Ȃ��B������A���Ƃ��ǖ�ł������Ƃ��Ă��A���ꂪ�n���I�\�͂̔����⍇�۔���Ȃǂɒ��ڊ���������\���͂قƂ�ǂȂ��B����ł́A�o��҂��{�C�ŗǖ������C�ɂ͂Ȃ�Ȃ����낤�B
�@ ���ɏq�ׂ��悤�ɁA�L�q���̗ǖ�̏ꍇ�͂��̂Ԃ�̓_�ɂ���ԂƎ��Ԃ������邤���ɁA�]���ɂ��̓_���̎�ς�������x�͂��炴������Ȃ�����A�������������̒������ӂ��߂āA�Ґ��̑�����w�̓����S���҂͖c��Ȋ֘A�Ɩ��̏����ɒǂ��܂����邱�ƂɂȂ�B������w�̏ꍇ�ł��w�����Ƃɓ�����ς��ĉ��x���I�������̍s���鎄����w�Ȃǂɂ����ẮA���ꋳ�Ȃɂ��ĉ���ނ��̖��p��������Ȃ���Ȃ�Ȃ�����A�悯���ɑ�ςȂ��ƂɂȂ�B���������A������w�Ȃǂł̓}�[�N�V�[�g�����̎������嗬�ƂȂ炴������Ȃ����A�����Ȃ�Ƃ����ǖ₾�낤�����₾�낤���ǂ��ł��悭�Ȃ��Ă���Ƃ����̂������ȂƂ���Ȃ̂��낤�B
�@ �ł͂��߂č�����w���炢�͂܂��Ƃ��ɂƂ����ӌ����łĂ��悤���A���Ԃ���Ƃ��Ɍ������Ď��̖ڂ��������Ă��鍑����w�̏ꍇ�Ȃǂ́A���ۂɂ͖��͂��[���ł���Ƃ����Ă悢��������Ȃ��B�����ŋ߂̏ɂ��Ă͂悭�m��Ȃ����A�����O�܂ł͓����̒S�����͑z���ȏ�ɑ�ς������悤�ł���B
�@ ���܂��ܓ����̒S���҂Ɏw�����ꂽ�����́A���̎��_���玄�I�ȃA���o�C�g�Ȃǂ͈�؎��l���A�����̌����𒆒f�Ȃ����͓�̎��ɂ��ė��N�̓����̑Ή��ɖz������������Ȃ��Ȃ�B�ߋ����N�ɂ��킽��e��w�̓������⏔�X�̑�w�\���Z�̖��A�ƎҖ͋[�e�X�g�̖��Ȃǂ�O��I�Ƀ`�F�b�N����̂���n�߂̎d���ɂȂ�B����Ȗc��ȍ�ƂɘJ�͂��₷�̂́A�ނ��A����̎҂������L���ɂȂ�悤�ȗގ����̏o�������A���ׂĂ̎��ɑ��Č������������߂ɂق��Ȃ�Ȃ��B��������ގ����ł��o�肵�悤���̂Ȃ�A���Ԃ���ᔻ�̗��ɂ��炳��邱�ƂɂȂ肩�˂Ȃ�����A�k�J�ɋ߂�����ȍ�Ƃɂ��T�d�ɂȂ炴������Ȃ��킯���B
�@ ���ꂪ�I���ƁA���ꋳ�Ȃ̓������쐬�Ƃ��̍̓_���������̐�C�����͂��ꂼ��ɖ��𑽐��쐬���ċɔ�Ɏ������A�S���ł������ЂƂЂƂׂ��������A����ɉ��x�����x���b���������J��Ԃ��������Ŗ������I���i�荞�ށB�����āA�ߋ��ɗގ���肪�Ȃ����ƁA�ׂ��ȃ~�X��s�K�ȓ_���Ȃ����ƁA���Z�̊w�K���e�͈̔͂������Ȃ����ƂȂǂ��Ċm�F���������ŁA�ŏI�I�ɖ�肪���߂���B�̂��̂��̕s���̎��Ԃɔ����Ė{���̂ق��ɂ����g���̗\�������p�ӂ���Ă���悤�ł���B
�@ �o��p�̖�肪���܂�ƈ���ɂ���킯�����A�w���Ɉ�����������Ȃ�������w�Ȃǂ̏ꍇ�A��r�I�ŋ߂܂œ������̈���H���͗e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ������炵���B�R���s���[�^�ƃv�����^�[�̔���I�Ȑi���ɂ���č����͈̏���Ă��Ă��邩������Ȃ����A���ẮA��v�ȍ�����w�̓������̈���́A���R��Ȃǂ̎��̂�h�����߁A�e�n�̌Y�������̈�����ɂ����āA���������܂ł͌Y���̂����Ȃ��͔͎��Ȃǂ��g���čs���Ă����悤���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@ ���R�A�S���������������Ȃ�̒����ԌY�������ɐg���ς˂���ԂŖ��p���쐬�̎w���ƈ���~�X�ׂ̍��ȃ`�F�b�N�Ȃǂ����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B���O�Ɉ���p���̖����𐳊m�Ƀ`�F�b�N���A��������邢�͈����Ɉꖇ�ł��p�����s���s���ɂȂ����肷��ƁA���ׂĂ̖���V���ɍ��Ȃ����قnj��i�ȍ�Ƃ��s���Ă����Ƃ����B
�@ ������ꂽ�������͒S�����������̎�ōĎO�Ďl�S�������`�F�b�N����A�����������̂��ꖇ���Ȃ����Ƃ��m�F���ꂽ���ƌ��d�ɕ��قǂ������B�����̗L��������w�Ȃǂ̓������́A����ソ�����ɑ呠�ȑ����ǂ̋��ɂɈڂ���A���������܂ł̌��d�ɕۊǂ���Ă����炵���B�������A���̊Ԃ͓��������쐬�����S�������Ƃ����ǂ����̕ۊǏꏊ�ɋ߂Â����Ƃ͋�����Ȃ��B
�@ �����܂ł̍�Ɖߒ����I���ƁA�S�����������͌X�̖�育�Ƃɍl�����邩����̉�@�ɂ������͔͉���Ⴒ�Ƃɍ쐬�A���ꂼ��̉̃^�C�v�ʂɍׂ��ȍ̓_���݂��Ă����B���w�̋L�q���Ȃǂ̏ꍇ�ɂ͗l�X�ȉ�@������̂ŁA���̂Ԃ�悯���ɑ�ςȂ悤�ł���B�������A���̒��ɂ͒S���������l�����Ȃ������悤�ȃG���K���g�ȁi�V���v���Ŗ��ʂ��Ȃ��A�������_���I�ɖ������N�₩�ȁj���o����҂�����A�����ɂ̓P�[�X�E�o�C�E�P�[�X�̑Ή����Ƃ��Ă���悤���B�����ɐ��w�I�ȗ��ꂩ�猾���A���̂悤�Ȕ\�͍͂����]�����ׂ��Ȃ̂��낤���A�ނ��A�G���K���g�ȉ���������Ƃ����Ă��̖��̔z�_�ȏ�̓_�������炦��킯�ł͂Ȃ��B
�@ �����_��r�����`�̌��݂̓������x�ł́A���w�łǂ�ȂɃG���K���g�ȉ�@��҂ݏo�����Ƃ��Ă����̎҂ɂƂ��ē��ʗL���ɓ������Ƃ͂Ȃ����A���Ƃ������S�������l�I�ɂǂ�Ȃɂ��ٍ̈˂�]�������Ƃ��Ă��A���ꂾ���ł��̐l�������i�ɂ��Ă��킯�ɂ������Ȃ��B����ǂ��납�A���̋��Ȃ̎������ʂ��v�킵���Ȃ��Ă��̎҂��s���i�ɂȂ�\������������킯���B����ȏ��������Ƃ���A������ǖ�����ƌ����Ă��A�o��҂����쐬�ɂ�����M�ӂ����̂����炻�����Ƃ������̂��낤�B
�@ �l�I��Ƃɂ͂ǂ�Ȃɒ��ӂ�������ł��~�X�͂����̂�����A���R�A������ꂽ���ۊnjɂɎ��߂����ƂŁA�o��҂��������~�X�����~�X�ȂǂɋC�Â����Ƃ�����炵���B�������A����������ɂɕۊǂ���Ă��܂������Ƃł͂������C�����邷�ׂ͂Ȃ��B�C������ɂ͂���܂ł̑S��ƍH����������x��蒼���Ȃ���Ȃ�Ȃ����炾�B�����������邢�͂��̂��ƂɂȂ��ďo��~�X���w�E����A�e���ʂ��炻�̐ӔC��Njy���ꂽ�肷�邱�Ƃ����܂ɋN����悤�ł͂��邪�A�������T�C�h�ɂ�����Ȃ�ɂ�ނ����Ȃ�����͂���悤�Ȃ̂��B
�@ �������I���ƍ̓_�ɂ���킯�����A��v������w�̏ꍇ�A�ԍ����Җ����S�������ɂ͂킩��Ȃ��悤�ȏ�Ԃɂ��č̓_�������s����悤���B�ނ��A�������݂̍̓_���s����̂�h�����߂ł���B��w�ɂ���ẮA�N��̎q���������͓����S�����炸���悤�Ȕz�����Ȃ���Ă���炵���B�S���̓��Ă̂��ׂĂ��̓_�S�������̑S������₲�ƂɌ��݂Ɍ������`�F�b�N�������A���_���W�v����B�L��������w�̏ꍇ�A�{�[�_�[���C���ɓ��_�҂��S�l�ȏ�����Ԃ��Ƃ�����Ƃ�������A���_�W�v�ɂ͑z���ȏ�ɐT�d�ȑΉ����Ƃ��Ă���悤���B
�@ ���Ȃ�Љ�ȂȂǂɂ����ẮA���炩���ߓ�Փx����������ł��A�����W���J���Ă݂�ƑI�����Ȃɂ���ĕ��ϓ��_�ɑ傫�ȍ���������Ƃ������Ƃ����Ȃ��Ȃ��B����ȏꍇ�ɂ͑I�����Ȃɂ��ɒ[�ȗL���s���������Ȃ��悤�ɁA�e���ȊԂ̓��_���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̂悤�ȃv���Z�X���o�Ă悤�₭���i�҂����肵�A���̔N�x�̓����S���������͂���Ƃ̂��Ƃł�����ƂƂȂ�킯�����A���ʓI�ɂ͈�N�̂قƂ�ǂ�_�ɂӂ邱�ƂɂȂ��Ă��܂����˂Ȃ��悤�ł���B
�@ �������̍쐬��\���Z�ȂǂɈϑ����悤�Ƃ��A�ߋ��̓������̍Ďg�p��F�߂�悤�ɂ��悤�i�������A�������肻�̂܂o�肷��Ƃ����킯�ł͂Ȃ��j�Ƃ������������̑�w�̓�������݂̓����ɂ́A���̂悤�Ȃ�ނɂ�܂�ʗ����������悤�Ȃ̂��B������ɂ���Ȃ��Ȃ��ɖ��Ȃ��Ƃɂ͈Ⴂ�Ȃ����A�������x������̂܂܂ł���Â��邩����A���쐬��\���Z�̐�啔��Ɉϑ�����悤�Ȃ��Ƃ������Ă悢�̂ł͂Ȃ����Ǝ����g�͍l���Ă���B�ނ��A�T�d�ȓ����f�[�^�̊Ǘ��ƁA�ł��邾���K�ō����I�Ȗ��쐬��O��Ƃ����b�ł͂��邯��ǂ��c�c�B
�@ ����łȂ��Ă����z�I�ȓ������x��������쐬�̂��肩����̍�����Ƃ�����Ƃ͓���B�ꌩ�����Ƃ��q�ϓI�ɂ���]���^�̃y�[�p�[�e�X�g��ӓ|�̑����_����@�ɕ���A�������쐬�ɗv����J�͂�̓_�����̔ώG�����Ă����āA�P�Ȃ�ËL�͂�v�̗̂ǂ��ׂ邾���̑e�G�Ȉ�������₪�����Ȃ�B�D�ꂽ�ËL�͂�L����Ƃ������Ƃ͂������Ĉ������Ƃł͂Ȃ����A���̕������ɒ[�ɂȂ肷����ƁA���苳�ȂɈٍ˂����ҁi���Ȃɂ�链�_�̂�����傫���҂������j��^�̑n���͂��߂��v�l�^�C�v�̎ҁi��@�̂��Ƃɐ[���������[���������Ȃ��Ǝ��ɐi�߂Ȃ��^�C�v�������j�Ȃǂ͕s���i�ɂȂ��Ă��܂��\���������B
�@ �����Ȃǂł͓��͔����ĈՂ�����肩������̂����i�̃R�c���Ƌ�����̂����{�̏��w�E���w�E���Z�̋��猻��̏�ł��邪�A���w�Z���w���獂�Z���Ƃ܂ł̏\��N�Ԃ�����ȃg���[�j���O�ɖ������Ă���ƁA��w���ɂȂ邱��ɂ́A���̉����ɓƑn���⓴�@�͂�K�v�Ƃ���`�������W���O�Ȗ��ւ̑Ή��\�͂��މ����Ă��܂����˂Ȃ��B��]�����w�҂�j���[�����l�b�g���[�N�E�R���s���[�^��p���Ĕ]�̊������������Ă���w�҂����̍ŋ߂̃��|�[�g�Ȃǂɂ��A�l�Ԃ͐����n�����������ǂ�]�זE���������Ȃ��Ă��邪�A�����̉ߒ��ł��̍זE������K�x�Ɏg������������悤�ɂ��Ă��Ȃ��ƁA�זE�̓����͑މ����@�\�������Ă��܂��̂��Ƃ����B���������̒ʂ肾�Ƃ���A����͂�䂵�����Ԃ��ƌ��킴������Ȃ��B
�@ �����ۂ��A�����y�[�p�[�e�X�g�ł����苳�ȕΏd�]���^�̎����ɂ���A���̋��Ȃɑ���K���̔��肪�\�ȗǖ�쐬�ɂ�����o��҂̋�J�͕���A�Ƒn���̂���w����I�����邱�Ƃ͂ł�����̂́A���Ԃ���͉p�ˋ����`���Ƃ��������悤�ȋ����ᔻ�̐����N���N���邱�Ƃ��낤�B�L���Ӗ��ł̊�b�w�͂�Љ�Ɍ�����A���o�����X�Ȋw���Ȃǂ������Ă������˂Ȃ��B�܂��A��w�܂łɓ��苳�Ȃ݂̂��w�����x���܂Ő���w�K������̂�����A����͂���Ŏ����͌������A�������̐����͂���܂łƂ͈�����Ӗ��ō��x�����Ă������Ƃ��낤�B
�@ ���̖�����������ɂ́A�܂�Ƃ���A�]�����݂̕������ȑ����_�����A�����勳�Ȃ̓��_�D������A�ʐڂɂ���������⏬�_���ɂ��l���]�������Ȃǂp�������d�����̓������s�������Ȃ��̂��낤���A����͂���ŐV���Ȗ���W�҂̋�J�ނ��Ƃɂ͂Ȃ邾�낤�B�����A�]���^�̓������@������̏ƓK�����Ȃ��Ȃ��Ă������܁A�����̃}�C�i�X�v���͂����Ă����݂̎Љ�Ƃ��̗v���ɑ������������@�̉��v���s�����Ƃ͐�ɕK�v�Ȃ��ƂɈႢ�Ȃ��B
�@
�@ �ߓ�����m�l����A�u��w�Ȃǂ̐��w�̌����҂͊F�A��w�����̐��w�̓������炷��������ł��傤���H�v�Ƃ�����������B�������A���w�̃X�y�V�����X�g������A��������Ȃ�̃g���[�j���O�ƃE�H�[�~���O�A�b�v���s���A�����������̊������߂��Ă���Ȃ�A�ꉞ�����͂��邾�낤�B�����A���Ɠ������x���A�����͈͂̒m��������p����Ƃ������������A���Ԑ�����݂��������ŁA�Ȃ�̏������S�\�����Ȃ������Ȃ�����̓��Ƀ`�������W������A����_���Ƃ���̂����o���邩������Ȃ��Ǝv���B��ɓ����̓��Ɏ��g��ł�����\���Z�u�t��L���i�w�Z�̋��t�����ɂ͂ނ��̂��ƁA���їD�G�ȗ\���Z���⌻�����Z�������ɂ��y�Ȃ��\���͏\���ɍl������B
�@ ���������A���w�҂Ƃ������̂͂悭�v�Z���ԈႦ��B�v�Z�͂��D��Ă���ɂ��������Ƃ͂Ȃ��̂�����ǁA��w�Ȃǂ̃X�y�V�����X�g�̊ւ�鐔�w�����̖{���̑Ώۂ́A���팾����ɓx�ɒ��ۉ���������Ȍ���̐��X�ŐD�萬���g�ݗ��Ă�ꂽ����I�Ȑ��E������A�����ł͖ʓ|�Ȏl���v�Z����l�̌v�Z�����m�ł��邩�ǂ����͂��܂�d�v�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B���������āA���w�̌����҂������A�����u�����N�̖��ɁA�ނ�̌����̐��E�Ƃ͂܂�ňَ��ȓ����̓��ɂ����Ȃ�`�������W������ꂽ�肵����A���ׂȌv�Z�~�X���������A�����ł��Ȃ����Ԃ��傢�ɋN���蓾��킯���B
�@ ���ꂼ��ɓ��ʂȎ���͂���̂�������Ȃ����A������ɂ���A��X�����z�����w��I�z������ł͂Ȃ��A�����P�ɂ��̎��X�̎������f�����邾���̓��A���A������o�肵�����Ƃ̂����w�̐搶���́A��x���l�̍�������̎�̖��Ɏ��Ɠ��������Ń`�������W���A����炪�ǂ�Ȃɖ��f�����Ӗ��Ȃ��Ƃ��A����E���ʎЉ�ɂƂ��Ăǂ�قǕ��S�ɂȂ��Ă��邩���������Ă��炢�������̂ł���B�������A��������������ɂ͂���Ȃ�̈Ӗ���Ӑ}������Ƃ����̂ł���A�˘f���Ă��鑽���̎��̂��߂ɂ��A���Ђ����̖��̏o��w�i�����ɂ��Ă��������������̂��Ǝv���B
�@ �������Z�����������A���鍂���ȕ��Ȍn������w�̍���̓��w�������͂ނ�݂₽��ɓ�����ƂŗL���������B���i�҂ł��S�_���_����A�O�\�_���Ƃ��Ώ�o���Ƃ�����x�ł��A����Ȃǂ̖������͂邩�ɓ�������B�������̑�w�ɂ͍�����̖������������āA���N���̋���������̓������̍쐬�ɓ������Ă����炵���B���͂̔ᔻ�ɂ��߂����A�����̏��������͂��A�u����͖����ł���]�X�v�Ƃ������悤�ȃ��[�h�����œ����ɗp�����肵�����Ƃ��������Ƃ�������A��ؓ�ł͂����Ȃ��l���ł͂������悤�ł���B
�@ ���܂�ɖ�肪����o��X�������Ă���Ƃ����̂ŁA�S�����Z�Z����c���Ȃɂ����u���������ƈՂ��������̂Ȃ����̂ɂ��Ă����悤�Ɂv�Ƃ�����|�̒Q�菑�����̑�w�ɒ�o�����B�Ƃ��낪���̗��N�̓���w�̍���̓����ɁA�u�{�����Ɍ�肪���邩��w�E����v�Ƃ������悤�Ȑݖ���ł��̒Q�菑�̈ꕶ���o�肳��Ă��܂����̂ł���B�����܂ł��̂��ƊW�҂������������ꂽ�Ƃ����b������̋��t������ƒ��ɕ��������Ƃ����܂����������z���o���B
�@ �������ĖJ�߂�ꂽ�b�ł͂Ȃ����A�������̋�������̓I�ɂǂ̂悤�Ȕ��_�������̂��͂��܂ƂȂ��Ă͒m��悵���Ȃ����A�����������炻��ȓ�����葱�������̋����ɂ͂��̐l�Ȃ�̐M�O���������̂�������Ȃ��B���̋����̐^��������悤�ɂƏ��シ�����Ȃǖѓ��Ȃ����A�����ē������o�肷��Ƃ����̂Ȃ�A���Ȃ��Ƃ�����Ȃ�̊m���闝�R�Ɛ��Ԃ̔ᔻ�ɑ��Ď��Ȃ̐M�O�X�Ɗт������̊o��͂����Ăق������̂ł���B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N8��2��
�����������\����ӂݎq��
���̌��
�@ �~��ᰂ悹���C�捡���������ČȂ�̖��S������
�@ ����́A�\���N�O�A�эL�̒��̈���ł��܂��܌�����������̐l�̉̔�ɍ��܂�Ă������ł���B����̐l���ɂ܂��s��ȕ���Ƃ��̏I���Ƃ𐦂܂����܂łɓ��O�����ڂŌ����������̉̂ɐڂ����Ƃ��A���͌������Փ��ɏP��ꂽ�B�����āA��^�̏d�����Â���u�~��ᰁv�Ƃ������t�ƁA���̗\���ɕ�܂ꂽ�u�Ȃ�̖��S�v�Ƃ����\���̔w��ɐ��ލ�҂̑z�O�����[���ǂ݉��������Ƃ����v���ɋ���A���͜߂��ꂽ���̂悤�ɂ��̑эL�炿�̏�����܉̐l�̉̏W�Ɠ`�L�ɓǂݒ^�����B����ӂݎq�Ƃ������̉̐l���A���̕a�̏��ɂ���Ȃ���̏W�u���[�r���v�𐢂ɖ₢�A�}�f�Ȑ����Z�̂��嗬�����������̎ʎ���`�Z�̊E�Ɉ�𓊂����Ƃ������Ƃ�m�����̂͂��̎��ł���B�`���̉̂́u���[�r���v���́u�~�̊C�v�Ƒ肳�ꂽ�̌Q���Ɏ��߂��Ă���B
�@ ����ӂݎq�̉̂̈����ɂ́A���R��������s�C���ȋS�̋P���ƁA��F�݂̏Ƃ��V���̚����Ƃ����ʗd���ȋ��������݂��Ă���B�������̉̂̂�����i���Ƃ��܁j�̋����ɂƂ����Ă��܂����҂����ɂƂ��āA���̗d�͂��瓦��邱�Ƃ͎���̋Ƃ������ɈႢ�Ȃ��B���������̉̐l�������̂܂܂̎p�ł��܂������Ă����Ȃ�A���̋����Ȑg�Ȃǂ��A���̖����̌��t�̎��ɂ���݂Ƃ��A�����܂��g�������ł��Ȃ��Ȃ��Ă�����������Ȃ��B
�@ ����ӂݎq�͑吳�\��N�A�эL�̗T���Ȍ����X�̒����Ƃ��Đ��܂ꂽ�B�킪�܂܂ł��������C���̌����������������炵�����A�ǓƂ��������ʂ������A�ɂ���������낢��Ȗ{��ǂ������肵�Ă����Ƃ����B�эL���w�Z�ł͐�[�N���̍�i�ɌX�|�A�����̉Ɛ��w�@�ɒʂ��Ă��鍠�ɏ��߂ĒZ�̂̎�قǂ�����̂����A�t�̒r�c�T�ӂ���́A�u���Z�I�ōˑ��肷���Ă���B�����Ƒf���ɉr���Ȃ����̂��v�ƕ]���ꂽ�Ƃ����B���̎w�E�͓I���˂Ă͂����̂��낤���A����Ԃ��A����͑P�������������ޏ�������ȍ��̑��݂̏ł������Ƃ������悤�B
�@ ���a�\���N�A��\�ɂȂ����ӂݎq�͋����ɖ߂�A�k��H�w������Ȃő��Ƃ����D�G�ȍ��S�Z�t�A����O�ƌ�������B�����A���̓�A�O�N��A�S�����E�����ɘA�������J���ꂽ�v�̍O�́A�v���[�J�[�̎d���Ɏ�����ߐg�����������Ă����B��������͍ċN�������ĕv�̋��������ɓ]���邪�A�O�̓]���͎~�܂�Ȃ������B�ӂݎq�͉Ƒ��Ƃ��Ɏ��Ƃ̂���эL�ɖ߂�A�O�͑эL�H�Ƃŋ��ڂ��Ƃ�悤�ɂȂ邪�A���̎d�������N�Ƃ͑����Ȃ������悤�ł���B
�@ �����Ɏ����āA�ӂݎq�͕s���ɂȂ����v�̍O�ƕʋ��A���ɂ͗��������ӂ���B�ӂݎq�ƍO�̊Ԃɂ͓�j�ꏗ�����������Ă������A���͂₻�̎q�������̏Ί�������Ă��Ă��v�w�̊Ԃ��q���Ƃ߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B���a��\�ܔN�A��\���̂Ƃ��ɂӂݎq�͍O�Ɨ�������B������������́u��]�v�ł͂Ȃ��u����v�Ƃ����ʂꂽ�v�̐��𖼏�葱�����w�i�ɂ́A�q�ǂ������̂��߂Ƃ������Ƃ̂ق��ɁA����̋����ƃ��Y���ɉs�q�Ȋ��������ޏ��Ȃ�ł͂̂������̂悤�Ȃ��̂��������悤�ł���B�������ɁA�u��]�ӂݎq�v���́u����ӂݎq�v�Ƃ������̂ق����ꊴ�I�ɂ��C���I�ɂ������Ă���A�Ƃ͌����Ȃ����Ƃ��Ȃ��B
�@ ����܂ł̗ǍȌ���̌ւ�����Ȃ���̂āA���Ď��͂̒N�����A�O�Ƃ̐����ɏI�~����ł������ƁA�ӂݎq�͎��̂悤�ȉ̂�ǂ�ł���B
�@ �߂��݂̌����i�݂̂�j�̔@���q������Ă��̏d�����͌���������
�@ ����̊��U�炵�䂭�[�����ɕ��Ȃ���q�̍b������
�@ �������A����Ȃ��ƂɁA���̉ƒ�I�ȕs�K���A�ӂݎq�̓��ɖ����ɐ��ݑ����Ă����u�H��̖����v�ƁA�ӎ��̉���ɖ����Ă����u�s���o�̍˔\�v�Ƃ��������ɉ�����邱�ƂɂȂ����B�܂�ł���́A�c���ꂽ���Ԃ̏��Ȃ����Ƃ�������ˑR�ɓV���獐������ł������悤�ȕϖe�Ԃ�ł������炵���B�F�l�ɗU���ē�����эL�̒Z�̉����ɁA�����Z�̉����Ƃ��Ċ�������悤�ɂȂ����ӂݎq�́A�߂��߂��Ɠ��p������킵�A�l�X�̋����A�Ȃ��ł��j���̐l�̐S�̒��Ɉ��������������炷�R��̋����̂��r��ł͉���ԂɎ^�ۂ̗��������N�������B
�@ ���̒��ɍ��Ȃ��Y�ӈ�{�̔����s�Ȃ����Ǝv��
�@ �J�����ڂȂ����̂������̂͂��炶��Ƃ��Č����ɂƂ�
�@ �M������̎��݂݂̂ƌ��Ђ��ꂸ�킪������т͖��H��
�@ �łт�Ƌ�藧����̂��鎞�͗d�k�̂Ђ����Ԃɂ����
�@ �����̂��֗₽���ڂɂĂ������킪�������܂��҂����Ă܂�
�@
�@ ����ȉ̂��r�ނ����ۂ��ŁA��\�Ή߂��̔��e�̓Ɛg�����ɂ��������Ȃ������Ƃ����ӂݎq�́A������ꂽ���̖����̗d�͂������Ċ��l���̒j��������̗��ɂ��A�эL�E�G�ɕ�����y���点���B�Љ�܂��Â��ϗ��ςɔ����Ă������̎���ɁA�ޏ��͐l�ڂ�݂炸���l�����Ƃ̕s�ςɑ���A�ނ����ʂɎ���Ė|�M���A�Y�܂����܂ł����f�i���킭�j�I�ł���ɂ�������炸�ǂ����������قǂɐ��߂��፷���ƓV�˓I�ȃ��g���b�N�������āA���̐S�ە��i�����܂����ƂȂ��V���ȉ̂ւƉr�ݑ�Ă������̂ł���B�����̉̂ɂ́A���̂Ƃ����ɁA�Ȃ�ƂȂ��Ȃ̎���\�����Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���鋿����������������B
�@ ����Ȃ����̕���N�����͂����悹�����Ă̂Ђ玝����
�@ 嗋��̏o���t�̉J���Ƃɐl�Ԃ̂ق��ȂׂĔ���
�@ �垾�̐V�����t�𝆂߂���͑��܂������ɐ�������
�@ �킪���������v���o���̂Ƃ��Ēn��̗₽����Ɍw�ł�
�@ ���A����Ȃ��ƒm����D�����Č��Ȃ�ׂ䂭�t�̔��X
�@ �܂��������Â��������ڂ������Ă������������Ȃ�����
�@ �킪���߂ɖ��̔R���l������s痂̎v�ЗU�ӏt�̓�
�@ �z�ɂ����ė���Ӑ�͏t�߂��\�̉�́u�₷�₷�v��
�@ �������܂��A���̂����ۂ��ŁA�܂��������Ȃ���e�ł��������ӂݎq�́A�䂪�q�ւ̎v���Ɩ����̏��̏�O�Ƃ����݉Q�������̋������������̉̂ɉr�ݍ��݂������B
�@ ���炴��z�X�������ɗ܂��މ��䂫�����e���̂̂�
�@ ������p�i���Ɓj���Ԃ�������Ƃ��ɐ��܂��Ă��̏���
�@ �q������ė܂��ނƂ��������������}�ɐ������Ă����
�@
�@ ����Ȃӂݎq�ɑ傫�����̉e�������Ă����͎̂O�\�̂Ƃ��ł���B�����ɂ�������Ă��邱�Ƃ��킩�����ޏ��́A�эL�̕a�@�ō����[�̐؏���p�������Ȃ����A��N��ɂ͉E���ɂ������]�ځA�E���[�����؏�����������Ȃ��Ȃ����B���̎��ɉr�܂ꂽ�Ƃ����S�C�������̉̂́A�̂��Ɋ��s�����̏W�́u���[�r���v�Ƃ����\��ނ��������ɂ��Ȃ����̂������B�`���ɏЉ���������̎����ɉr�܂ꂽ���̂ł���B
�@ ���Ɏ����ЂƂ�̏��s�ςɂē��킬�̌Y�ɑ��͂��肵��Ñ��
�@ ��₩�Ƀ��X������䂭���[�Ƃق������̂���}�ւ�
�@ �킪�������[�����߂Ă���炵���ӌ��͂Ȃ�̉Q�܂�
�@ �~�ЂȂ����Ɛ�̌i�F�ʂĂ��n�_�����͕��݂䂭�ׂ�
�@
�@ ���_�̎p���_�Ԍ��Ă��̉e��������ӂݎq�ł͂��������A���̏�l���ꂵ�����́A�@���I�Ȍ��⎩�Ȃƒ��O�̂����炷�Î�̋��n�ւ͌����킸�A�Ō�܂Łu���v�Ɓu���v�ւ̎��O�̉��̔R�����C���̐��E���삯�߂������B�ޏ��͐_�ɗ��炸�A�����̂��Ƃ��ɕs���ɐU�����A���̋��|�Ɛl�m��ʌǓƊ��ɂ̂������Ȃ�����A�d������O�̉��̗h��߂��Ɣ��b�̌ւ�����Ȃ����ƂȂ��A�j�ǂ�����ɋ��킹�䂪�ӂ̂܂܂ɖ|�M�����B�����āA����ȏ���̏C�����w�i�ɂ����ӂݎq�̉̂́A�d�킩����ȋ������߂Ĉ�i�ƍႦ�킽��A���X�̔����������̂ւƌ��������B����͂܂��ɗ������O�̌�䊂ɂ������A�s��ȍŌ�̍��̋P�����̂��̂ł������ƌ����Ă悢�B
�@ ����ӂݎq�̉̂̔�߂��ŗL�̕��ꐫ���v���Ƃ��A���̐l�ɂ͉̐l�Ƃ��Ĉȏ�ɍ�ƂƂ��Ă̍˔\���������̂ł͂Ȃ����Ƃ����C�����ĂȂ�Ȃ��B�������ӂݎq�ɂ��߂Ă��Ə\�N�̗]�����^�����Ă�����A�ޏ��͂ЂƂ��ǂ̍�ƂƂ��đ听�������̂ł͂Ȃ����Ƃ����v���B�����A�����̖��Ƃ��āA�ޏ��͎c���ꂽ�Ȃ̐��̏�Z�̂ɂ����邵���Ȃ��Ȃ��Ă����B���肭�鎀�̋��|�Ɛ킢�A���Ԓn����Y���ǓƂȍ��ɂЂƂƂ��̈��炬��^���邽�߂ɂ́A���ɂ̖���␇����ɂ��܂���Z�̂Ƃ�������Őg���ł߂邵���Ȃ������̂ł��낤�B
�@ �����[�̐؏��������������������A�ӂݎq�́A���a���̕ʏ̂����D�y�����ː��ȕa���ɓ��@���邪�A���ۂ����ŒԂ�ꂽ��L�̒��ŁA�ޏ��́A�u�s���Ƃ��͂����̋��|�ɑΌ��������A�n�߂ĕs�K�̊m�M���琶�̐[�w�Ɏ肪�͂����Ǝv�ӁB�A�T�Ȋ��a���Ɏ����̓�������o�������ǂ����ĉ̐��ƂȂ炸�ɒu�������B���̋��߂�V�����R��͂��̓��y�̐��i�ɔ|������O�Ȃ��v�Ƃ������t���c���Ă���B
�@ �эL�ō����[��؏��������ƁA�܂��A�ӂݎq�͔N���̔��N���Ȃ̐g�̂ɓM�ꂳ���A���̖��C�ȍ����ė��i�낤�炭�j�����B
�@ �R���ނƂ��邩��̑f����j�ނ��̔ނ̓��Ȃ�T���g���E�J�~����
�@ ���������ɉԉ����J�����͌G�Ȃ��D�͂�Ă��
�@�@
�@ ���̓]�ڂƈ����ɂƂ��Ȃ��E�̓��[�����r���A���̂��Ɠ��@�����D�y���ł́A�S���̎Ⴂ��t��n���̒Z�̎��u�V���i�ɂ��͂�j�v�̕ҏW���l�ʼnԌ`�̐l�������j���ƊW�����B�ӂݎq�̎��̈ꃖ���O�ɓ����̎����V���Ђ����ނ̂��߂ɔh�����ꂽ�ጎ���ɂ������ẮA�C���^�r���[�������̓��̂����ɂӂݎq�̖��͂ɗ��ݎ���A�����ɂ͖߂炸�ɓ�T�Ԃɂ킽���Ė��ӂӂݎq�ɓY���Q����H�ڂɂȂ����B��l���������ăx�b�h�ŐQ�Ă���Ƃ���������Ō�w���a�@���Ȃ�ƐS���邩�Ƃ��̔����������߂�ƁA�ӂݎq�́A�u���̕a���͘S���ł��B����������l�ŐQ��Ƃǂ����ė×{�̖W���ɂȂ�̂ł����B���͒j�̐l�ɕ�����Ă���ق����S�����炬�悭������ł��v�Ɣ��_�A�×{�Ƃ����Ă��ǂ�������҂g�Ȃ̂�����Y���Q��F�߂�ׂ����ƍR�ق����B
�@ ������Â̍�����˂��A���̏펯�̔ے肷�邻�̍R�c�ɂ͎厡��ł����������ɋ����A���̓Y���Q��ٔF����L�l�������Ƃ������B�u����������@��������ɂ́A���Ƃ��]���킸���ȏd�a�҂ł����Ă��A�ɗ͌Ȃ��E���Đ�Ƃ������ׂ��a�@�̋K����K�͂ɏ]���A�Â��ɓV�����܂��Ƃ�����̂�����̔������v�Ƃ��鐢�Ԃ̈Öق̗������ɑ��A�ӂݎq�͈�̐l�ԂƂ��āu����͈Ⴄ�B���Ƃ��ǂ�ȂɏX���ł����Ă����ɂ䂭�����炢����̂܂܂̎p�ł����Ă����B�����Ȃ��Ƃ����͂������肽���v�ƈًc���������̂ł������B
�@ �f�@�߂ʂ�����N���K�N�̖̃p�C�v�������ޖ���m�肽��
�@ �w���̂��݂��C��������₩�ɘL�ɂÂ��ނ킪���̂̂���
�@ ���f�̎����������H�ׂĂ��ւ�䂭���݂��킪���̊O���ɂ��
�@ ���̖�z�ɖ�͂̂��Ƃ����₫�ďu���ɏ��������Â��̂���
�@ ��������ʗp�𗊂݂ĂЂƂƂ������ɖ��S�Ȃ��������
�@ ����ڑO�ɂ������a��\��N�l���A�S�����u�Z�̌����v�̑���\��r�łӂݎq�͓̉̂��I�ƂȂ�B���ԑR�Ƃ������Ȑ����Z�̎嗬�̉̒d��J���ҏW������p�v�̉p�f�ł��������A�����̒����̒d�̏d�������̂قƂ�ǂ͂ӂݎq�̉̂��掂��}�����B�܂��Ƃ��ɕ]�������̂́A�{�A��A���R�ށA�����Î}��O�������������Ƃ����B���Ȃ݂ɏq�ׂĂ����ƁA���N�̑���\��r�œ��I�ƂȂ����̂́A����܂��Ռ��I�ȉ̂��g���o�ꂵ�����̎��R�C�i�ł���B
�@ ����ł����O�ɂ��Љ̏W���s���Ƃ������l�����̔z����m���āA�ӂݎq�͂��˂ČX�|���Ă�����[�N���Ɏ莆����������̏W�̏������M���˗�����B���Ԃ�A�ӂݎq�ɂ͕��d�ɌN�Ղ���N���̐S��������̌��t�œ�������Ƃ����m�M���������̂��낤�B�܂��S���I�ɂ͖����̑��݂ɉ߂��Ȃ������ӂݎq�̉̂Ǝ莆��ǂN���́A�̏W�u���[�r���v�̏������M���������������ɁA�p��́u�Z�́v�ҏW���ɔޏ��̉̂̏Љ���˗��A�{�A��̉{�����o�������ŐV���Ɍ\�����Z�����̊��������邱�ƂɂȂ����B�Ȃ�ƚ}����悤�ƁA�̐l����ӂݎq�̋Ɛт͂��͂�s���̂��̂ƂȂ����̂������B
�@ ���a��\��N�����O���A�ӂݎq�͎O�\��ʼni������B�{�i�I�ɉ̂��r�ނ悤�ɂȂ��Ă���킸���O�N�]�Ƃ����Z�����̋P���ł�����
�@ �s���̂��ɖ邪�p�ӂ��������寁A�����A�����l�̂�����
�@ ���̏�Ɏ��Ԏ��ЂĂ䂭����c�����͂�����ɏ���
�@ �����䂭�����₳����C�̋a���炩�ē��܂���@��
�@ ���������Ă��̂т₩�ɗׂɗ�����̂����y�i���炭�j�̔@������ཱྀi�ȁj�炵��
�@ ����̂��͐g���낭�ǂ��ւ����͂�ނ��Ƃ����݂̌��ɂ�����
�@ ���̉��̋P�������X�Ɏ�߂Ȃ�����������Ă䂭�̂ł͂Ȃ��A���Ƃ���u�ł͂����Ă����o�̈ŋ���ؗ�ɍʂ낤�Ƃ����ӂݎq�́A���̏K���ɋt�炢�A�u���\���v�Ƃ����Ζ���d���u�Z�́v�Ƃ������́u���̉ԉv�����炩�ɑł��グ�A�����Ă��ɑ��₦���B
�@ ���̖����̗L�l�����̋K�͂���ǂ�ȂɈ�E�������̂ł������Ƃ��Ă��A�ӂݎq���ł��グ�����̉ԉ́A�u���ɏ�������ǂ��납�A���Ԃ��Ă��̎c���ɏo������X�̍��������f���A�s�v�c�Ȃقǂɋ��̉����������킹��B����́A����ӂݎq�Ƃ������̐l���̐����܂�����Ȃ���̐^���ł���A���̌��t�̐��X�����w�ƌĂԂɒl������̂ł��������Ƃ̉����̏Ȃ̂��낤�B
�@ ���܂��Ȃ��}���̂������ʎ���`������Ƃ����Z�̊E�̎嗬���炷��A�ԗ��X�Ń��g���b�N�ɑ��肷���Ă���Ƃ��݂��钆��ӂݎq�̉̂ȂǁA�ٌ`�ْ[�̂����ԓI�ȑ��݂ł���A�Y�ꋎ���ē��R�ł͂���̂�����������Ȃ��B���ہA���܂̎���Ɂu����ӂݎq�v�Ƃ����̐l���������Ƃ�m��҂́A�Z�̂��r�ސl�X�̒��ł�����߂ď����ɂ����Ȃ����낤�B�������A�����܂ŗ��ɂȂ�A�����܂Ő����ɌȂ̖��S�����炵�������̂��A���������]�l�̒N�ɉr�߂�Ƃ����̂ł��낤���B���܂ɑf�l�̐l�̐^�����Ȃǂ����鎄�Ȃǂɂ́A�U���q������̂����ꂽ�����̐l�ł���悤�ɁA����ӂݎq���܂������̂����ꂽ�����̐l�ł������Ǝv���ĂȂ�Ȃ��̂��B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N8��9��
���Ȃ̂��炵�R�~���j�e�B
�@ �I���̎q��I����Ȃǂ̖��قŒm���钷�쌧���z�{���́A����s�̖k���x�O�Ɉʒu���Ă���B����s����͒���d�S�œ�\���قǁA�Ԃ��ƖL�쒬�܂��͐{�⒬�o�R�ŎO�\���قǂ�����B�d�ԁA�Ԃǂ���ōs���Ă�����s���ʂ��炾�Ɠr���Ő�Ȑ��n�邱�ƂɂȂ�B
�@ ������܂肵���������A���j�Ɠ`���������d���v��I�ȊX���肪�����Ȃ��Ă��邱�Ƃ������āA�X���݂͓Ɠ��̕���Ə��ɖ������Ă��邩��A�����Ԃ�Ԃ�ƎU�邾���ł����낢��Ȕ����������Ėʔ����B���z�{�̃K�C�h�}�b�v�Ɂu���z�{�̊X�̓X�j�[�J�[�T�C�Y�v�Ƃ������Ă���悤�ɁA�����̑��ŕ������̂ɂقǂ悢�傫���̊X���݂ł��邱�Ƃ������킢���B
�@ �H�̍��ȂǏ��z�{�����͂��߂Ƃ���V�܂̓X��ɍ������낵�A�ꕞ���Ȃ���I���̎q��I�r㻁A�I����̖����y���ނ̂��܂����Ȃ��̂ł���B�������A�I�َq�͂ނ��̂��ƁA�u�I�v�Ƃ����ꕶ�������������ł��C���������Ȃ�����k���������肷��Ƃ����I�A�����M�[�i����ȃA�����M�[�����邩�ǂ����͒m��܂��j�̕������͂��̒��͔������ق����悢���낤�B�Ȃɂ��A������Ƃ���ŌI���i�������Ă���̂ɂ��킦�āA�ǂ�������Ă��I�A�I�A�I�Ƃ����������炯�Ƃ��Ă���̂�����c�c�B
�@ �ӊO�Ɏv�������������������Ȃ����A���̏��z�{�̒��͊����k�ւƉ��i�䂩��j���[���B���z�{�o�g�̍������䍃�R�́A��\���߂��拫�V���̋ɂ݂ɒB���������k�ւ��͂��]�˂��炱�̒n�ɏ����A���ӂ�s���Č��������B��҂̍��䍃�R�̐S�z����ЂƂ����Ȃ���n���ȁu����v�A���Ȃ킿�A�g���G�����˂������ɂ����āA�k�ւ͎��X�Ɩ���ݏo���Ă������悤�ł���B
�@ �O�\��㔼�ɔ��l�����G�t�Ƃ��ē��p������킵���k�ւ́A�l�\�ォ��\��ɂ����ēǖ{�i��݂ق�j�}�G��G��{�i���Ăق�j�̊G�t�Ƃ��ĐV���������N�����A���\��ɂȂ�ƗL���ȁu�x�ԎO�\�Z�i�v���͂��߂Ƃ���Ɠ��̕����G�ňꐢ���r�����B�l����̂����������G�̐��E�Ɉٗ�Ƃ������镗�i����������݁A�Ƒn�I�ȕ����G�t�Ƃ��Ă��̕]����s���̂��̂Ƃ����k�ւ��������A�ނ̉拫�̐[�܂�͂Ƃǂ܂�Ƃ����m��Ȃ������B��\���}���鍠�ɂȂ�ƁA�����G�t�Ƃ��Ă̕]�����܂�Ŗ����ł����邩�̂悤�ɁA�k�ւ͓��M��ɂ��̐S�����X���͂��߂�B�ނ����R�ɏ����ꏬ�z�{�̒n�ɋ�������悤�ɂȂ����̂͂��傤�ǂ��̎����ɑ������Ă����B
�@ ���Ԃ���b�Ȃ̂��낤���A���R�̖ʑO�ł���̂�݂炸�A�����̗��ɐԂ��G�̋�������Ղ�h�����{��^�����ȉ掆�̏�ŕ������A�u��ɎU��g�t�ɂ��������I�v�Ƃ�����Ƃ��Ƃ����`�����c�邭�炢�A��s�Ȃ�������Ō��͂ɑ��锽�R�S�����������k�ւ̂��Ƃł���B��̗��x�Ȃǂƕ���ʼn䂪���̃t���[�����X�̐�삯�I�ȑ��݂��������̓V�ˉ�Ƃ��ЂƂ��ɐM�������Ƃ����̂�����A���䍃�R�Ƃ����l�����܂��A���͂���������̒P�Ȃ鍋���Ȃǂł͂Ȃ��A�ꗬ���l�Ƃ��Ă̕i�i�������킹���Ȃ����H��̌����������̂��낤�B���s��]�˂ɏo�č��w�A���w�A���w�Ȃǂ��L���w�z���w�҂̍��R�͊e�E�̏d�������Ƃ̌𗬂������A�����⏑��ɂ����Ă��D�ꂽ�Ɛт��c���������悤�ł���B�ʔ������ƂɁA�ނ͗d����ɂ��ٍ˂������Ƃ����B
�@ �قڊX���݂̒��S�Ɉʒu����k�֊قɂ́A�����k�ւ̓��M��A��e�A���ȂȂǖ�\�_�̂ق��A�k�֒��M�̓V��G�Œm����Չ�������W������Ă��āA�k�փt�@���ɂ͕K���̃X�|�b�g�ƂȂ��Ă���B�k�֊ق̈ꎺ�ł́A�u�拶�\�k�ւƓ��M��v�A�u���z�{�̖k�ցv�Ȃǂ̃}���`�X���C�h����f����Ă��邪�A���̂Ȃ��ŏЉ��Ă���k�֔ӔN�̌��t�Ȃǂ͂Ȃ�Ƃ������[���B�ӔN�ނ́A�u�����ɂ͘Z�̍����玖���̌`���`���ʂ��Ȃ��������B�\���߂��������炢�낢��ȊG�}��`���悤�ɂ͂Ȃ�������ǂ��A���\�ΈȑO�ɕ`������i�ɂ͎��ɑ���悤�Ȃ��͈̂���Ȃ��B�����̊G�̋Z�ʂ͂܂��܂������������A�S�ɂȂ鍠�܂łɂ͊����̈�ɓ��B�ł���悤�ɂƊ���Ă���v�Ƃ������悤�Ȏ�|�̂��Ƃ��q����Ă����炵���̂��B
�@ �������A�k�ւł��������\�܂ł͂���������i�͐��ݏo���Ȃ������̂��c�c����A�������܂ʼn�������Ȏd�����ł��Ȃ������̂������Ȃ��ȁI�c�c�Ȃǂƃ����m�����ČȂ̖��\�������ȕٌ삵�������Ȃ�Ƃ��낾���A�}�˂ɂ͂��Ƃ��\�{�̎��S�N�������邱�Ƃ������ꂽ�Ƃ��Ă��}�X����d�������ł��Ȃ����Ƃ��낤�B
�@ �k�֊ق̂ق��ɂ��A�������ꂽ���Ă̖k�ւ̉掺�Ȃǂ����鍂�䍃�R�L�O�فA�]�ˎ��ォ��吳����܂ł̏Ɩ����𑽐��W�߂����{�����蔎���فA�n���̖���������l�S�_��W���������j���������فA����ɂ̓t���[�����K�[�f�����z�{�A������g�فA�I�̖ؔ��p�فA���㒆�����p�قƁA��������p�H�|�i�̌��ǂ���ɂ͎������Ȃ��B���������͂��߂Ƃ���e��̐H�ו�����y�Y�������ꌬ�ꌬ�����I�ŗ����������͋C�̓X�\���ɂȂ��Ă���A�X���ꂼ��̂��ĂȂ���ʂ��ė��l�̐S�ɂЂƂƂ��̈��炬��^���Ă����B
�@ �Ƃ���ŁA����ȏ��z�{�̒��̒��S�X����k�ɏ������藣�ꂽ�Ƃ���ɁA�u�m�o�n�@�l�i��c�����Ƒg�D�j���Ȃ̂��炵�v���^�c���鏬�z�{�I�[�v���n�E�X�������Ă���B����A�������Ď��͊J�݂���ĊԂ��Ȃ����̏��z�{�I�[�v���n�E�X��K���@����B���̂m�o�n�@�l�u���Ȃ̂��炵�v�Ƃ��̎x���g�D�u���Ȃ̂��炵�R�~���j�e�B�v�̑�\�߂Ă����鏬���o���q����ɂ͈ȑO���瑽���̖ʎ����������̂ŁA���̓Ɠ��̔�c���g�D�̊������j�⊈�����O�ɂ��Ă��Ȃ�ڂ������b�������������Ƃ��ł����B��������͌����ŏ_�a�ȕ����̉��Ɋm����M�O���ߎ����������̐M�B�����ŁA�����������̂����Ƃ������̍s���͂ƌ��f�͂��ǂ�قǂ̂��̂��͎��ɂ��e�Ղɑz���������B
�@ ��������Ɏf�����Ƃ���ɂ��ƁA���z�{�I�[�v���n�E�X�́A�V����������ĕ�炵�����Ɗ肤�l�X��S�g�ɏ�Q�����l�X�Ƌ��ɁA�^�ɐ����邱�Ƃ̈Ӗ��₻�̂��߂̂��ׂ��l����ꏊ�Ƃ��āA�����̋����҂̎x���Ƌ��^�̂��ƂɌ��Ă�ꂽ�{�݂��Ƃ����B���̎{�݂́A�V�l��S�g�̕s���R�Ȑl�X�ƐS�̌𗬂��͂����������ɑ���A������f�C�T�[�r�X�Ɩ��𐿂������ق��ɁA�n��T�����Ƃ��Ă̖������S���Ă���̂��������B�ߗׂɏZ�ޗl�X�Ȑl���C�y�ɗ����k�b���y����������������肷�邱�Ƃ��ł���B���Z�����l�⎞�Ԃ̂���l�ɂ́A�����Ȃ��͈͂ŃI�[�v���n�E�X�̈ێ��Ƃ��Ȃ̂��炵�R�~���j�e�B�S�̂̔��W�ɋ��͂��Ă�����Ă�����Ƃ����B
�@ �܂��A���̃R�~���j�e�B�ɊS�̂���l�Ȃ炽�Ƃ����O�҂ł����Ă�����ɂȂ��V�X�e���ŁA�I�[�v���n�E�X���L�[�X�e�[�V�����ɂ��čL���𗬂��͂����悤�ɂ��Ȃ��Ă���B�Ƃ��ɂ͊O������u�t���������肵�Ċe��Z�~�i�[�⏬�K�͂ȍu����Ȃǂ��J�Â�����A�n�E�X���̂̃X�[�X���M�������[�Ƃ��ĊJ�������肷�邱�Ƃ�����悤���B��K�ɂ͉����̉���₻�̓��s�҂��\�l����\�l�͏h���ł���悤�ȕ������p�ӂ���Ă���A���̂��߂ɕK�v�ȗ������p�L�b�`�����������Ă���B�����ꔑ�����Ă���������A���ɉ��K�Ȉ����߂������Ƃ��ł����B��ʂ̐l�ł����͋��Ƃ����������̎{�ݗ��p�����Έ�����p�ŏh���ł���悤�ł���B�i�A����FTEL&FAX 026-247-4756 ���Ȃ̂��炵�j
�@ ���z�{�I�[�v���n�E�X�̌����ɂ͔������ؔ��̓V�R�؍ނ��ӂ�Ɏg���Ă���A�e������L���A�����A���ʏ��Ȃǂ́A�O�ꂵ���o���A�t���[�̍\���ɂȂ��Ă���B���Ƃ��g�C����Ƃ��Ă��A�h�A�̊J�A�_��������A�����̊J�A����̐��Ȃǂ������I�ɍs����悤�ɂȂ��Ă��邵�A��펞�̌Ăяo���u�U�[�����Ă��邩��A�̂̕s���R�Ȑl�ł����S���ė��p�ł���Ƃ����킯���B
�@ ���Z�p�𒆐S���Ŕ����ɐ����`�i��`�ɂȂ��Ă���j�̃e�[�u�����Ȃ��Ȃ��̃A�C�f�B�A���Ƃ����Ă悢�B���̕��ς��ȑ�`�e�[�u���́A�����g�ݍ��킹��Ǝ��ɗl�X�Ȍ`�����肾�����Ƃ��ł��邩��Ȃ�Ƃ��@�\�I�ŁA���̎��X�̖ړI�ɉ����ēK�X���R�ɕ��בւ��g�����Ƃ��\�Ȃ̂��B���肰�Ȃ������������܂₩�Ȕz���̐ςݏd�˂��u���Ȃ̂��炵�v�̊������x���Ă���Ƃ����킯�ł���B
�@ �u�ق�Ƃ��ɐl�Ԃ炵���L���Ȑ������͉����v�Ƃ��u���R�Ƌ������郉�C�t�X�^�C���Ƃ͉����v�Ƃ��������悤�Ȃ��Ƃ��u�����l�X�Ƌ��Ɋw�эl���A������ʂ��ē���ꂽ�m����Z�p�y�p�����Ă������Ƃ����̑g�D�̊����̗��O�Ȃ̂��Ƃ����B�n��Ǝ��̐����̏d���⎩�R��A�̏d�v�������Ȃ������悤�ɂȂ������܁A�����e�n�ɂ����Ă��̂悤�Ȋ���������l�X�����X�ɑ������邪�A���́uNPO�@�l���Ȃ̂��炵�v�̊����Ȃǂ͂��̐��I�Ȏ��݂̈�Ƃ����Ă悢�̂��낤�B
�@ ��������̘b�ɂ��ƁA����Ȃ��Ȃ̂��炵�R�~���j�e�B�̉^��������Â��邢�܈�̎��݂́A�u�J���m�����q�ю��Ɓv�Ƃ̒�g�����ł���Ƃ����B���쌧�̖k���Ɉʒu����L��ȉ����ꍂ���̒��قǂɃJ���m���ƌĂ��n�悪����B�W����l�S���[�g�����邱�̍���n�т̃J���m���ł́A���N�ɂ킽���āu���q�ю��Ɓv�Ƃ�������߂ē��قȎ��Ɗ������s���Ă����炵���B�u���q�ю��Ɓv�Ƃ������t�����͏��z�{�ɂ���Ă��ď��߂Ď��ɂ����̂����A�v����ɖq�{�ƐX�ш琬�Ƃ��ꏊ�œ����ɂ����Ȃ�����Ȏ��ƌ`�Ԃ̂��Ƃ��ƈӖ����Ă���悤�������B
�@ ���Ẳߓx�ȐX�є��̂ōr��ʂĂ����L�т̈ꕔ��n��g���Ŏ�A���̒n�ō��јa���̕��q���s���Ȃ���u�i�т̍Đ��Ɗ����̐X�ю����̕ی���͂��낤�Ƃ���ِF�̎��Ɗ����Ȃ̂������ŁA��������͂��̎��Ƒg���̎����ǒ������������Ă�����Ƃ̂��Ƃ������B
�@ ���Ƃ��ꎞ�I�ł����Ă����Ȃ̂��炵�R�~���j�e�B�ɂ������l�X�ɂ́A���̍��q�ю��Ƃ̑��̒����W�J�ɂ��Ă��m���Ă��炢�����A�����āA���ۂɂ��̌����K�˂Ă��̎��Ƃ̐��ʂŊ������A�����ŌJ��L�����鎩�R�Ɛ������Ƃ̖{������ׂ������W�����ߒ����Ă��炢�����c�c�g�D�̑�\�߂鏬������̌��t�̉��ɂ́A����ȋ����z������߂��Ă���悤�ȋC�����ĂȂ�Ȃ������B
�@ �S���͈ꌩ�ɂ������Ƃ�������A�������������܂ł���Ă��č��q�ю��ƂȂ���̂���ڂ����Ȃ��܂ܓ����ɋA���͂Ȃ����낤�B���ǁA���̗����A���́A���z�{�܂ł����ƈꏏ�ɗ����Ă����]�_�Ƃ̕đ�d���q�Ƃ��ɃJ���m����K�˂Ă݂邱�Ƃɂ��߂��B��������̑��q����ɂ͈ē����ɗ����Ă��炦��Ƃ������A�J���m���̔ԏ����ł͍��q�ю��Ɛ��i�g�����̓��������X��҂��Ă��Ă�������Ƃ������Ƃ������̂ŁA����͂�������Ă��Ȃ�����s���������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N8��16��
�J���m����
�@ �����͉J�͗l���������A�����o���q����̂��q���A���G����̈ē��łƂ������J���m���ւƌ��������ƂɂȂ����B�擱�̔��G����̎Ԃ̂��Ƃɑ����ׂ��A�����z���_�E�h�}�[�j�̃n���h�����������B���܂��܂��̎��͎��̈��ԁi���ԁH�j�g���^�E���C�g�G�[�X�ł͂Ȃ����s�̕đ�d����̎Ԃł̗��������̂ŁA�z���_���z���_���^�]����Ƃ������Ȃ��ƂɂȂ��Ă��܂����B�L�c���g���^�̎Ԃɏ��悤�Ȃ��̂�����܂��ǂ��ɂł�����b�����A�����̐��Ɠ������̃��[�J�[�̎Ԃɏ��Ƃ����̂͂�����҂�C�p���������C����������̂��B�����Ƃ��A�^�]����ق��̋C�܂���ȃz���_�Ƃ͈Ⴂ�A�^�]�����ق��̃z���_�͏]�����̂��̂ł͂������̂����c�c�B
�@ �R�V������Ԑ��̏W���t�߂��߂���Ɠ��͋}��ƂȂ����B�܂���̉J�ɉ����Ď��E�͂��܂肫���Ȃ����A���x���オ��ɂ�Ă݂�݂���X�̗��[�܂��Ă����B�X�L�[�̃��b�J�Ƃ��Ė������u�ꍂ������쉎�Ƃ̍����i�H�j�ŗL���Ȓn���J����Ȃǂ̂������ʂɌ������ẮA���ύ��x��l�A�ܕS���[�g�����炢�̎R�ł��傫�������̂т����Ă���B���u�ꍂ���ƌĂ�邱�̈�тɂ́A�J���̐i�u�ꍂ�����ӂƂ͈���āA�܂��܂��L���Ȏ��R���ӂ�Ɏc����Ă���悤���B
�@ ���̂Ȃ��炩�ȗŐ�������˂��˂ƖD���悤�ɂ��đ����Ă��鉜�u��ѓ��́A�������߂ĖK�˂����͒n�}�ɂ��قƂ�Ǎڂ��Ă��Ȃ������ăf�R�{�R���炯�̃_�[�g�̗ѓ��������B�������A���܂ł͓������L����قƂ�ǂ̕������ܑ�������āA���K�ȑ��肪�y���߂�悤�ɂȂ��Ă���B���G����^�]�̐擱�Ԃ����̉��u��ѓ���ڎw���Ă���͖̂����������B
�@ �₪�ĉ�X�̎Ԃ͉��u��ѓ��ɂԂ���A���������܂��Ė���ʂ������Ă��������葖��ƁA�E��ɖ��ܑ��ׂ̍��ѓ��̕���n�_�ɒ������B���̗ѓ��̓����ɂ͌��̂��������Q�[�g������Ă���A��ʎԂ͂��������ɂ͐i���ł��Ȃ��悤�ɂȂ��Ă���B�i������ȂƂ�����Ƌt�ɐi���������Ȃ�̂��l�Ԃ̏�ŁA����Ȃǂň�ʎԑ��s�֎~�̂��̎�̗ѓ��ɑ�������ƁA���Ƃ������Ăł����Ă����̉���T���������Ȃ�͎̂��̍��������i�����j�ł���B����Ɏ��ۂ������Ă݂��ق����v��ʔ�����֎��ɉ�舧���Ėʔ����̂����A���R����Ȃ�̋�J�������B
�@ �����A���̎��͔��G���Q�[�g�̌��������Ă����̂łȂ�̋�J���v��Ȃ������B���G����ɂ��̃Q�[�g���J���Ă��炢�A���̗ѓ��ɎԂ�������Ă��炭����ƁA�ˑR�т̒��Ɋȑf�Ȗؑ����������ꂽ�B�������A���q�ю��Ƒg�����̓�������ď�ɏ풓�Ȃ����Ă���ԏ����������B��X��s�́A�����̒B�ς��������������铌�邳��̉��₩�ȏΊ�ɕ�܂��悤�ɂ��ĎԂ��~�肽�B
�@ ���������ǂ��Ƃ����āA�����̑O�ł͂�͂肱�̍��q�ю��Ƃ����w�ɂ����炵���j�����l�̐�q�����H�p�o�[�x�L���[�̏��������Ă���Ƃ��낾�����B�قƂ�ǎ�Ԃ瓯�R�ł���Ă�����X���A���ǐ���̂��D�ӂɊÂ����̈�c�ɍ��������Ă��炤���ƂɂȂ����B
�@ �����̎��ӂɖڂ����ƁA��ʂ��ׂĂ��u�i�тƂ܂ł͂����Ȃ����̂́A����ł��召���Ȃ�̐��̃u�i�̖��V�Ɍ������Ď}���L���Ă���̂��������B���n�ł͂Ƃ����ɐV�̋G�߂͉߂��Ă������A�����͍���n�тł����������ɍ��x������Ƃ���Ȃ̂ŁA�u�i�̗t�͂܂����邩��ɐ��X���������������B�����̂����O�ɂ͐��k��������Ă���A�������狿���Ă��鐅�������Ɍy�₩�ŐS�n�悢�B�J���m����т͐܂���̏��J�ɉ����Ă������A����ł��厩�R�̒��Ŏ�钋�H�̖��͊i�ʂ������B
�@ �M�Z�Y�̘a���̃o�[�x�L���[���������������A���邳��萻�̍��Ȓ|��⡂���ɂ������X�`�̖������Q�������B�ׂ��_�炩��⡂̎����������قǂ悭�A�H�������ɂ����B���u�ꍂ����т͍��Ȓ|��⡂���������̂�邪�A���܂��܉�X���K�˂������͂��傤�ǂ��̍̎�V�[�Y���ɂ������Ă����B���邳��̘b���ƁA���Ȓ|�Ƃ̓`�V�}�U�T�̂��ƂȂ̂������ŁA����⡂͎I�̊ʋl���_�V�ɂ��Ė��X�`������ƍō��Ȃ̂��Ƃ����B���쌧�k���ł͍��Ȓ|��⡂̃V�[�Y���ɂȂ�ƎI�̊ʋl���ُ�͂قǑ�ʂɔ����炵���B
�@ �I�̊ʋl���_�V�ɂ���Ƃ悢�Ƃ����͎̂����o����悭�킩��B�H�̍��ɎR�ɓ��肢�낢��ȑ��Ȃǂ��̂��Č��n�ő��`������Ƃ��Ȃǂɂ͂ƂĂ��d��Ȃ̂ł���B�I�̊ʋl�A�Ȃ��ł����g���t���[�N��̂��̂��R���r�j��X�[�p�[�ȂǂŔ����Ă����A��������̂܂ܓ�̒��ɕ��荞�݁A���□�X�ƈꏏ�ɑ~�������Ȃ�����M����Ƃ�ƁA�����܂����`���ł�������B����̂Ɏ肪������Ȃ������ɁA���ꂪ���ɂ��܂��Ƃ��Ă���̂��B
�@ �Ȃ�Ƃ��ӕ\��˂��ꂽ�͍̂��Ȓ|�̏Ă�⡂������B�̂肽�Ă�⡂��Ă��ĐH�ׂ�Ƃ������z�͂���܂ł̎��ɂ͂Ȃ����̂ŁA������Ƃ����������������A���ۂɏo���ꂽ���̂�H���Ă݂�ƂقƂ�ǃA�N���Ȃ��Ȃ��Ȃ��ɖ��킢�[�������B�����A���Ă��̂��̂̍����̂ق��̕����͂������ɍd���A�������ĐH�ׂ邤���Ƀp���_�ɂȂ����悤�ȋC�������Ă������Ƃ����͐����ɍ������Ă������ق����悢���낤�B
�@ ���H��ɔԏ����O�̌k�����̂����Ă݂�Ɗ⋛�̉e���`���z��������B�ׂ��k�������炻�̋C�ɂȂ�Ί⋛�̎�݂͂��ł��Ȃ����Ƃ��Ȃ��������B�l���Ă݂�ƁA���̃J���m����т́A�͌��̓V�R�I�V���C�Ŗ������H�R���ؖ�����t�߂Œ��Ð�{�����番��G����i��������j�̌�����ɂ������Ă���B�k���ނ����Ƃ���l�X�̓���̓I�ł���⋛���G���ƌĂԂ̂͂��������E�тȂ����A�⋛���͂��߂Ƃ���G���A���Ȃ킿�e��̌k���������̐�̗���ɂ͑����������Ă�������G����Ƃ����ď̂������ɑ���Ȃ��B�������Ƃ���A���̕t�߂̌k���ɂ�������⋛�����Ă����R�Ƃ������̂��B
�@ ���邳��a����������đ�d����́A�Ԃ̃g�����N����ދ�����o���Ƃ��������⋛�ނ�Ƀ`�������W���͂��߂��B����܂Œ��ڂɂ͂��̒ނ�p��ڂɂ������Ƃ͂Ȃ��������A�⋛�ނ���͌��\�����ƕ����Ă���đ�̘r�Ɏ��͊��҂��������B�����A�ǂ��ɂ��O�삪���邳�߂����B���܂͒��N�߂��c�я���ސE�Ȃ����č��q�ю��Ƒg�����ɂ����܂��Ă����铌�邳��́A���Ȓ��B�����⋛��ԏ����ł̐H�Ƃɂ��Ă����邭�炢������A���Ƃ��Ɗ⋛�ނ�̃x�e�����ł���B�܂��A�n���̒���s�ߕӂ̍ݏZ�炵���撅�O���[�v�̒��̒j��������̌��Ԃ肩�炵�Ċ⋛�ނ�̃L�����A�����Ȃ肠��炵�������B
�@ ����ȘA�����e����u�����ƊƂ��ނ莅���Z���ق��������v���́A�u���ꂶ�����H���ԈႢ�Ȃ��ˁv�ȂǂƍD������Ȃ��Ƃ��������̂�����A�đ�͋C����ł��Ďv���悤�ɘr�������Ȃ��A����A�r���k���ėe�Ղɂ͑_������܂�Ȃ��B�⋛�̂ق��͊⋛�̂ق��łȂ��₯�Ɏ��肪���X�����Ƃł��v�����̂��낤���A�a�ɂ����ۂ����������肩�A��A�ɉB��Ďp�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�u���l�����ăv���C�h�͂���[�ȁI�c�c����H���˂��A�ق�H���˂����Ă��ꌩ�悪���ɏo�����a�ɐH������A�쐶�̌ւ肪�����˂��I�v�Ɗ⋛�̌N���Ӓn��قǂɁA���������đ�̃v���C�h�̂ق����ǂ�ǂ�I�[�o�[�q�[�g������肾�B
�@ ���̏��������Ƃ₻���Ƃ��ገ�܂�Ȃ��ƌ�����������G����Ǝ��Ƃ́A�đ�����ƂɎc���ėѓ��`���ɉ��̕��ւƕ����������B�����������q���Ăꂢ��Ƃ���܂ňꑫ��ɍs���Ă݂悤�Ƃ����킯�ł���B�J���H���H�D���Ă̂̂�т�Ƃ������s���������A�@�������̂т₩�ȃu�i�̖ؗ���[�X�Ɣɂ�`�V�}�U�T��X�Y�^�P�̌Q��������M�����E�ɖ]�݂Ȃ��瑼�ɐl�C�̂Ȃ��ѓ���i�ނ̂́A�Ȃ��Ȃ��ɖ��̂�����̂������B���H�e�̂��������ɂ̓^���̖Ȃǂ������Ă��āA�h�X�̂���ג������̐�[��}��ɂ͐H���̃^���̐V�肪�ӂ�ɂ��Ă����B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N8��23��
�J���m���ƃu�i��
�@ ���q�ю��Ƒg�����̓��������ɑՂ��������ɂ��ƁA��k�ɂ̂т鉜�u�ꍂ���̂Ȃ��قǂɂ���J���m���͊C����l�Z�Z���[�g������玵�Z�Z���[�g���̍��x�������A�ď�̍ō��C���͓�\���x�A�^�~�̍Œ�C���̓}�C�i�X�\���x�A�������甪���̕��ϋC���͏\�ܓx�O��ł���炵���B���~���̐ϐ�͕��ώO�E�܃��[�g���ɋy�ԂƂ����B�P�Έ��R�⎿�̓y�ƐX�ъ��F�y�Ƃ����荬�������y��ŁA���݂ł̓`�V�}�U�T�i���Ȓ|�j�A�`�}�L�U�T�i�N�}�C�U�T�A�V�i�m�U�T�Ƃ������j�Ȃǂ����̐A���̑唼���߂Ă���B���m�Ɍ����ƁA�J���m���Ƃ́A�쓌�̍��W�R�i�ꔪ�l�����[�g���j�A�k���̖ؓ��R�i����[�g���j�A�����R�i��Z���Z���[�g���j�A����ɖk���̑�q�R�i�ꔪ�O���[�g���j�A�����R�i�ꔪ�ܓ[�g���j�Ɉ͂܂ꂽ��т̍����̂��Ƃł���B
�@ ���W�R�̎R���ɋ߂��J������n�̈�p�ɂ��ăJ���̑�����������߁A�������J���m���ƌĂ��悤�ɂȂ����炵���B�������A���Ă��̃J���m���ɐ������Ă����̂̓J���ł͂Ȃ��A�ق��Ȃ�ʃu�i�ł������B���a�����ȑO�̃J���m���ɂ͑S��ɂ킽���ĕ��ώ����S�N���u�i�т��T���Ɩ��Ă����B�u�i�т̕ې��͂Ɛ����p�̂������ō��J���ɂ��k���̐��͑��邱�Ƃ��Ȃ��A�^�Ăł��g���悤�ȗ₽�������₦�ԂȂ�����ĎG���여��������A���̒n��ɐ������鐔�X�̓��A���̐�������������Ǝx���Ă����Ƃ����B�������̈�т�K���̂́A�t����H�ɂ����Đ����ɐ��ފ⋛��ނ�ɂ���Ă���v���̋��t���炢�̂��̂������悤���B
�@ �����̃J���m����т͗ъw�̗p��ŋɐ����i�N���C�}�b�N�X�E�X�e�[�W�j�ƌĂ��Ő��ɖΊ��̃u�i�тɂ���ĕ����Ă����̂��낤���A���̍��܂ł̓J���m���ɂ����炸�A�����n������k���A���k�n���̎R�x�n�т̂�����Ƃ���ɋɐ����̃u�i�т����݂��Ă����悤�ł���B�Ƃ��낪�A���ꂩ�琔�\�N���o�����݁A�ɐ����̃u�i�̎��R�т��c����Ă���̂́A���E���R��Y�̎w��������_�R�n�i�H�c�X�������̎R�x�n�сj�̂悤�ȍ����̂���������ꂽ�n��ɂ����Ȃ��B��������V�R�u�i�т��قƂ�ǎp�������Ă��܂����̂ɂ͂ނ��Ȃ�̗��R���������B
�@ �u�i�Ƃ������͊����Łu?�v�Ə����B�u�v�Ɓu���v�̓���g�ݍ��킹�Ă���������������A���X������������������u�ł͂Ȃ��v�Ƃ��u���ɗ����Ȃ��v�Ƃ����Ӗ��ɉ����Ȃ����Ƃ��Ȃ��B�×��A������ʂƂ��ɖL���ȐX�тɌb�܂�A���x�Ȗ̕�����z���グ�Ă����䂪���ł͂��邪�A�̂Ȃ�ǂ��ɂł��������u�i�̖́A�����ԗ��p���l�̂Ȃ����Ƃ��Čy���Ȃ����͎ז��҈�������Ă����B�u�����v�A�u�悶��₷���v�A�u�ό`���₷���v�A�u����₷���v�A�u�ؒn�������v�Ȃǂ̗��R�ŁA���ނ���H�p�ނ��͂��߂Ƃ�����p�Ƃ��Ă̕]���͂���߂ĒႩ��������ł���B�܂��A���̂��Ƃ��t�ɍK�����Ĉꎞ���܂ł��������Ɏ���Ẫu�i�т��c��������Ă����B
�@ �������A���ۂɂ́A������\���[�g���ɂ��y�ԗ��t���̃u�i�͐��Ԋw��ɂ����Ă��d�v�Ȏw�W�A���ŁA���������Ė��ɗ����Ă��Ȃ������킯�ł͂Ȃ��B�\�����ɐ��n����u�i�̎�����́u�R���v�Ƃ��Ă��㎿�̐H�p�����̂ꂽ���A����������u�i�������̂邱�Ƃ��ł����B�����A���邳��̘b�ɂ��ƁA�u�i�̎��Ƃ������͎̂O�N���玵�N�̎����ŋ����L����J��Ԃ��͂Ȃ͂��C�܂���Ȑ����������Ă���炵������A���N���̎��n�Ăɂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ������킯�ŁA��H�ނƂ��Ă͕s�����������̂��낤�B
�@ �؎����ɂ͎E�ۗ͂�͂̂���N���I�\�[�g�̐������܂܂�Ă���A���炩��͐������̂��Ƃ������A�䂪���ł̓u�i�̂�����������ʂ͂��܂荂���͕]������Ă��Ȃ������悤�ł���B�u�i������S�N�ɂ��y�Ԓ�����L���A���̎�t���_�炩�����X�����F���ԕۂ��Ƃ��ł���̂́A�D�ꂽ�z���͂�ې��͂����̂ɂ��킦�āA�N���I�\�[�g�����̓����Ȃǂɂ��Q���ւ̒�R�͂�����߂đ傫������Ȃ̂�������Ȃ��B
�@ ���̓_�A���[���b�p�A�Ȃ��ł��h�C�c�𒆐S�Ƃ����n��ł́A����ȋ�C��w�Ȑ����������A���̔������L���ȗɂ���đ����̓��A����{�������u�i�́A�u�X�̕�v�ƌh���Ă�Đ̂����ɂ���Ă����B�܂��A���[���b�p�l�̓u�i�ނ̓����Ƃ��̓��L�̔����ؔ������p�I�Ɋ��������@���l���A�T���_�{�[���̂悤�Ȓ������e��̉Ƌ�肾���A�ނ�Ǝ��̎��ؕ�����z���Ă����B
�@ ���Ԃ�A�����������u�i�ɑ���މ�̕]���̈Ⴂ�́A�����̗ǎ��̐����Ƒ��푽�l�Ȏ��Ɍb�܂�A�������ƃu�i�тƂ̊W��[���l����K�v�ȂǂȂ������䂪���ƁA�ǂ������m�ۂ��邽�߂ɂ̓u�i�т��͂��߂Ƃ���X�т̑��݂������ł��Ȃ����Ƃ�Ɋ�������Ȃ��������[���b�p�̍��X�Ƃ̕����I�Ȕw�i�̈Ⴂ�ɂ����̂ł͂������̂��낤�B
�@ �����l������Ă����̂��K�������a�\�N��ɓ���܂ł͊e�n�ɍL�����݂����u�i�т��������A�R����`�̑��������܂��ē��{�����ۓI�ɌǗ����A�R���������������邽�ߑ�ʂ̍��Y�d�Y�𗘗p������Ȃ��Ȃ�ƁA����ȃu�i�тɂ��������ɕ��������悤�ɂȂ����B����ɐ��Ɏ���A���y���������o�č��x�o�ϐ������ւƌ��������ɂȂ�ƁA�u�i�͑��̎G�Ɠ��l�ɁA�d�Y�p�̂ق��A�p���v�A���A�������H�ނƂ��Ă̗��p�Ƃ��̂��߂̌����J�����啝�ɐi�݁A��X�I�ɔ��̂��s����悤�ɂȂ��Ă������B
�@ ���R�A���̉e���͂��̃J���m�����ӂ̃u�i�тɂ��y�B���a�O�\�Z�N�A�R�m��������_�ɏH�R���̒��Ð�k�J���ʂւƂȂ���G����ѓ����������A��^�g���b�N���ʍs�ł���悤�ɂȂ�ƁA�J���m�����L�т̍L��ȃu�i�т͔��̂��s������A�ꎞ���͖��S�ȏ�悷��L�l�ł������B�ނ��A�u�i�т̕ې��͂�͂Ȃǂ����R���S�̂ɉʂ����Ă��������ȂǍl�������]�n���Ȃ��܂܂ɁA�����e�n�̑��̃u�i�т����X�ɔ��̂���A�����܂��p�������Ă������̂ł���B���v�n���牓����ʂ̕ւ�����߂Ĉ����������ƁA�ɓx�̍���n�тł��������ƁA���̎R�x�n�`�̓��ꐫ�̂䂦�ɗѓ��J��������������ƂȂǂ��K�����A�B�ꌴ���т̂܂܂Ŏc���ꂽ�̂��A��N���E���R��Y�Ɏw�肳�ꂽ���_�R�n�̍L��ȃu�i�тɂق��Ȃ�Ȃ��B
�@ ���g�����ȋC��Ɍb�܂ꂽ�䂪���̎��̐������x�͈�ʓI�ɂ݂Ă����ւ�͂₢�B������A�����F�����Ă����������тƂ��ĕ�������܂łɂ͂����c��ȍΌ��͂�����Ȃ����낤�Ƒ����̗̂ыƊW�҂����͍l���Ă����B�Â����炠��u�₪�Ė�ƂȂ�R�ƂȂ�v�Ƃ������̂悤�ɁA���̂��Ă����u���Ă��������Ăю����������A���т͕������邾�낤�Ƃ����̂�����̌����������̂ł���B�ނ��A�ъw��A���w����Ƃ��鐶�Ԋw�҂Ȃǂ̂Ȃ��ɂ̓u�i�т̏ꍇ����O�ł��邱�Ƃ��n�m���A���̕����Ɋ뜜��������҂��������낤���A����o�ς�����̔����ƍl���鍂�x�o�ώЉ�u���̒����̒��ɂ����ẮA����Ȑl�X�̈ӌ��Ȃǖ��͂ɓ����������ɈႢ�Ȃ��B
�@ ����ɂ܂��A�u�i���͂��߂Ƃ���e��̗��t�L�t���̂����Ւn�ɂ́A���p���ނƂ��ău�i�Ȃǂ��l�i�̂悢�X�M��q�m�L�Ȃǂ̂悤�ȏ�ΐj�t�������X�ƐA������Ă������B�������A�����I�ȓW�]�ɗ����Č���ƁA�{���̐A������������ȐA�т��܂����ł������B
�@ ���t�L�t���т̏ꍇ�ɂ͔ӏH���珉�Ăɂ����Ă͗��؏�Ԃ̂��ߓ������n�\�܂ŏ\���ɓ͂��B�قǂ悢���z�G�l���M�[����������邩��A���ʂɐl��������Ȃ��Ă��l�X�ȉ�������ؗށA����ɂ͋�����̎����������A�e��̖쐶��������ށA�n�ۗށA�o�N�e���A�ނȂǂ������ł��鐶�Y�͖L���Ȏ��т��`�������B�悤����ɍł������I�Ȏ��R�̃T�C�N���������Ȃ��`�����킯�ŁA���̂悤�ȐX�т͕ې��͂ɂ��x��ł���B
�@ �V�R�̉��v���т̂悤�ɒ���Ȏ��R�̗։�Ɛ�����q�������ǂ����̋������o�Đ��������X�тƈ���āA�l�H�I�ɐA�т��ꂽ��Ύ��̐��̖����тȂǂł́A�������n�\�܂ŏ\���ɂ͓͂��Ȃ��B�l��ɂ���ĊԔ��≺�}�����Ƃ�������Ƃ��펞�s���A���R�̏�Ԃɋ߂����т̈ێ��`�����Ȃ����ꍇ�͂܂��悢���A�ێ��R�X�g��������Ȃ��Ȃǂ̗��R�ɂ���ĕ��u���ꂽ�l�H�т͔ߎS�ł���B�����ł͎��R�̃T�C�N�����\���ɔ��B���Ȃ�����A�����I�Ȑ��Y�͂��Ⴍ�����̐���ɂ����܂�K���Ȃ��B�V�R�̐��тȂǂƈ���ĕې��͂��ӊO�ɒႢ�B
�@ �o�ϐ������Ő������}���鍠�ɂȂ�ƈ����O�ނ��ǂ�ǂ�A�������悤�ɂȂ�A�ꕔ�̓��ʂȖ؍ނ������č����Y�̖؍ނ̓R�X�g�I�ɍ̎Z���Ƃ�Ȃ��Ȃ����B�܂������ۂ��ł́A�����e�n�̉ߓx�̍L�t���є��̂��A���s���Ƃ��v���Ă����������Ɉ��e�����y�ڂ����Ƃ��������ɖ����ɂȂ��Ă����B����ɁA�����̐����������オ��A�������i�ς�L���Ȏ��R�������߂ĎR��𗷂���l��������ɂ�āA�u�i�т��͂��߂Ƃ���L�t���т̑��݉��l�������]�������悤�ɂ��Ȃ��Ă����B�������ău�i�ю��̎���͂悤�₭�I���������A�c���ꂽ�u�i�т̕ی�ƃJ���m���̂悤�Ȕ��̂��ꂽ�n��̃u�i�т̍Đ����d�v�ȉۑ�Ƃ����悤�ɂȂ����̂ł���B
�@ �������Ȃ���A���̗��t�L�t���̗тƈ���āA��x���̂��ꂽ�u�i�т̍Đ��͗e�ՂłȂ����Ƃ��قǂȂ������ɂȂ��Ă����B���g�����ȋC��ɔC�������Ă����}���ɍĐ�����قǂɃu�i�͈琬���e�ՂȎ��ł͂Ȃ���������ł���B�u�i�͍���n�т̍��n�ɕ��z���Ă���B�{���̓u�i�ɍ����]�����銴���̋����W�ɂ���ƌ����Ă��悢�̂�������Ȃ��B�����A��������u�i�т����̂����ƍ��������җ�ɂ͂т����т͍��R�Ɖ����Ă��܂��B�����Ȃ�ƁA���Ƃ��c�����u�i����H�Ɏ����������Ƃ��Ă��A�n�\�����ɑj�Q���ꂻ��炪��q�Ƃ��ēy���ɒ蒅���邷�邱�Ƃ͗e�ՂłȂ��B����ɒ蒅���V����o�����Ƃ��Ă��[�����M�ɂ���ē������Ւf����邩�珇���Ȑ���͂����ւ����B
�@ ����Ɉ������ƂɁA�u�i�̖͑�ʂɎ�������̂����N�Ɉ�x���炢�����Ȃ������ɁA���Ƃ��Ă̂��̐������x������߂Ēx���B�����̂悤�Ȏ��̎������\�N���炢�ƒZ���̂ɑ��A�u�i�̎����͍Œ����S�N�ɂ��y�ԁB��ʂɒZ���̖͐������������A�����̖̏ꍇ�͂��̂Ԃ����x���B���邳��Ɏf�����b�ɂ��ƁA�u�i�̎�̐������x�͐��N�ł��������܁A�Z�\�Z���`���x�̂��̂ł���Ƃ����B����ł̓u�i�т̍Đ����e�ՂłȂ��̂������ł���B
�@ ����������R�ɂȂ�ƎR�͐��Y�͂������čr��ʂĂ邵�A���̉Ԃ��炢�č�����ʂɌ͎������肷��Ƃ���ɍr�p�͂Ђǂ��Ȃ�A��J�̎��Ȃǂɂ͕ې��͂��������R�̎Ζʂ��ʂ̐������ꉺ���Ă���Ɏ��R���̔j��������炷�B�����ŁA��X�N���蓾�邻�̂悤�ȏ�Ԃ𖢑R�ɖh�����߂ɂ��A���R��Ԃɋ߂��Ȃ����J���m���Ɏc��u�i��ی삵�A�S�N�A��S�N�Ƃ��������������ɂ�Ńu�i�̎����Ă邱�Ƃ��K�v���ƍl������悤�ɂȂ����B�����A���̂��߂ɂ͕��X�Ȃ�ʗ��O�Ƃ�����x������H�I�Ȍv�悪�K�v���������A���̌v��𐋍s���邽�߂̐l�I�y�ѕ��I�x�����s���ł��������B
�@ ���������ƁA�J���m�����q�ю��Ƃ͂��̐��I�Ȏ��݂̈�ł������̂��B�u���[���b�p�Ȃǂ̐X����́A���A���q�A���̎O��ɂ킽���Ă����Ȃ����ł���B���e���c��A���A����������p�������q�������̎��X��傫����āA����ɑ������h�ȐX�ɂȂ�悤�ɍŌ�̎d�グ�������Ȃ���ł���v�ƁA�M���v�������߂Ȃ������Ă������������邳��̌��t�����ɂ͂ƂĂ���ۓI�������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N9��6��
�J���m�����q�ю���
�@ ���a�����A�J���m�����ӂ̑��X�̏Z���͂قƂ�ǂ��_�ƂŐ��v�𗧂ĂĂ������A�����̔_���̂ǂ����������ł������悤�ɁA�_�k��Ƃɂ͋���n�Ȃǂ̒{�͂��p�����Ă����B�t����Ăɂ����ĉߍ��Ȕ_�k��Ƃɏ]�����̗͂����Ղ������n���̂�т�Ɛ×{�����邽�߂ɁA�ؓ�������������J���m���̈ꕔ������̂��A���̂�����̕��q���Ƃ̎n�܂�ł���Ƃ����B���̍��́A�\�L�����[�g�����̍⓹�����n�ƂƂ��Ɉ�������ĕ����A���̃J���m���̐×{�n�܂ł���Ă��Ă����炵���B
�@ �J���m���ł̔_�k�p���n�̕��q�ɒ��ڂ����c�я��́A�u�i�̑�ʔ��̂ɂ���č��R�Ɖ������J���m���n��̃u�i�эĐ����͂��邽�߂ɓ��p�a������q���邱�Ƃ��v�����A�قǂȂ��擱�I���s���J�n�����B����쑐������̐[�������ɕ��q����ƁA������т����R�ɕ����܂�邤���ɍ��n�̒n�ʂ����܂�ď��X�ɍk����邵�A���̕��A���삵�ƂȂ��Ēn�͂����߂�B�܂��������������̂��݂̂��Ȃ���ړ����A�ǂ�ǂ���̗t��H�ׂĂ������̐������}������B�u�i�̐����j�Q������̐���������Ă��Ǘ}������A���N�Ɉ�x������ʂɂ͎���Ȃ�Ȃ��Ƃ����u�i�̎�̍��t�����e�ՂɂȂ邵�A����o�����u�i�̗c�ɂ��z�����\���͂��悤�ɂȂ�B��������A�����I�ɂ̓u�i�т̍Đ������ł͂Ȃ��Ƃ����킯�������B
�@ �A���w�̌��ЁA�̖q��x���Y���m�̕��ނɂ��ƁA����ɍ��Ƃ͂����Ă����̎�ނ͘Z���Z��ɂ��y�ԂƂ����B�R���ɐ����Ă�����́u�F�̏o��悤�ȉ��R�ɖ���v�Ƃ������悤�ȈӖ������߂āu�F���v�ȂǂƌĂ�Ă��邪�A�{���̃N�}�U�T�Ƃ́u�G���v�Ə����A�t�̂ӂ��������G�ǂ�ꂽ���̂��Ƃ������̂��������B���Ƃ��Ƃ͋��s������̈ꕔ�̒n��Ɏ��������ނ̍��ł���炵���B
�@ ����͂Ƃ������A��X���ЂƂ��炰�ɂ��ăN�}�U�T�ƌĂԍ��ނ͈ӊO�Ȃ��Ƃɋ��̎����Ƃ��Ă����ꂽ���݂ł���炵���B���̗t�̊܂ސ����̊����͌܁Z�p�[�Z���g�قǂȂ̂ŁA��Z�p�[�Z���g����������Ȃ���Ɋr�ׂĉh�{���͂����ƍ����A���̑@�ێ��͋��̈ݑ܂ɔ[�܂�\���ɏ�������邱�Ƃɂ���č����`���ɐ��܂�ς��̂��Ƃ����B
�@ �ʏ�A�q��Ƃ����ΐX�Ƃ����L���q���n�ł̂�т�Ƒ���H�ދ������̎p��z������̂����A�����ܗL���̍���������H�Ƃ���ꍇ�A�̏d�܁Z�Z�L���̐����͐����ێ��̂��߈���Ɍ܁Z�L���߂�����H�ׂȂ���Ȃ�Ȃ��B����͋��ɂƂ��Ă������ȏd�J���Ȃ̂��Ƃ����B���̓_�A���̗t�͐��������Ȃ��h�{�����������ߐH�ׂ�ʂ����Ȃ��Ă��ނ���A���������H���̐ێ�ɔ�₷�J�͂����̂Ԃ�Ƃ����킯���B
�@ �ʏ�����Ƃ��Ď��炳��鍕�јa���̓��������i�ʂɕۂ��߂ɂ́A�H���Ƃ��Ĉ��̕i�����ێ����邽�߂ɂ͎�������݂̂ɗ����Ă��Ă͏\���łȂ��̂Łi�����̏ꍇ�͂ނ��b�͕ʂ̂悤�ł���j���������������������S�ƂȂ邪�A���̏ꍇ��L���̓��Y����̂Ɏ��L���̍������K�v�ɂȂ�Ƃ����B�ǂ������͂���Ȗ��_���J�o�[����̂ɂ��K�������z�I�Ȏ����ł���悤�Ȃ̂��B�����Ƃ��A���Ɋr���̖��̂ق��͂ǂ����Ƃ������ƂɂȂ�ƁA���ꂾ���͋��ɕ����Ă݂Ȃ��Ƃ킩��Ȃ��B�O�����̋��Ȃǂ́A�u���[�E�b�A�T�T�ɂ̓C�T�T�J�O���������[���A�����H���Ă惂�[�E�b�I�v���ĐS�̒��Ŏv�����肷�邩������Ȃ��B
�@
�@ �Ƃ����������̂悤�Ȕw�i�Ƒ_���̂��Ƃɉc�я��͍��q�ю��Ƃɒ��肷�邱�ƂɂȂ�A���̑�_�Ȏ��݂͈Ȍ�\�N�Ԃقǂɂ킽���đ�����ꂽ�B���̍ۂɐ��܂ꂽ���́u���q�ю��Ɓv�Ƃ���������Ȃ��p��́A�v����Ɂu�����ƃu�i�тƂ̈琬���ɍs�����Ɓv�Ƃ������悤�ȈӖ��̍��߂�ꂽ����Ȃ̂ł���B���ƊJ�n�����̒{�Y�W�҂̂قƂ�ǂ͐l�̔w�������M�̒��ŋ�����q����Ƃ������d���ɋ�������A���s�͊ԈႢ�Ȃ��Ɖ\�����Ƃ����B���������܂�ыƗp�̊��蕥���@�����Ɏg���Ď����̐ߖ���͂��邢���ۂ��ŁA����悭�Ε��q���Ɏq���܂��Ē{�Y�U���ɂ���^�����悤�Ƃ������������~���������ƌv�悾��������A�{�Y�W�҂����̏�������Ԃ̂������͂Ȃ��B
�@ �J���m���͍���n�т�����A�l���̋��ɂ��狍�������R��ɉ^����R��u�i�̑a�тɕ������̂́A��n�����I����т��V�ɕ�����Z�����̍��ɂȂ�B�����ď��Ⴊ�����C�����X�_���ɂ�����\�����{�ɂ͍ĂяW���̋��ɂɖ߂��Ă��Ȃ��łȂ�Ȃ��B���̉ĎR�~�������̈狍�ɂ����ẮA�ď�Ɠ~��ɂ�������̍��ق͑����Ȃ��̂�����A�����������̊��ω��ɂ��Ă����邩�ǂ��������ł������B
�@ ���ہA�~��ɍ�����ۑ������������ނ̎����Ȃǂ�^���������ďꂢ���Ȃ�R���̍��R�ɕ�������H�ׂ������肷��Ə����s�ǂ��N�������Ƃ�����炵���B��i���̔��H�Ƃ����J�̒n�ɕ����A��ނȂ����̓y�n�̐H�������ɂ��Ă��������킷�悤�Ȃ��̂�����A����͂�����x��ނ����Ȃ����Ƃł���B�����ŁA�ď�ɋ����R���ɕ��ꍇ�ɂ͑O�����Ĉ����Ԃ��̉�������������K�v���������B
�@ �Ƃ���������������Ď����I�ɃX�^�[�g�������q�ю��Ƃ͏\�N�Ԃɂ킽���đ������A��X�I�Ƃ͌����Ȃ��܂ł����s�Ƃ��Ă͂���Ȃ�̐��������߂邱�Ƃ͂ł����̂����A�і쒡�S�̂̐Ԏ��o�c�Ƃ���ɂƂ��Ȃ�������̂��߂ɂ���ȍ~�̎��Ƃ̑��s�͗e�Ղł͂Ȃ��Ȃ����B�ꎞ�͎��Ƃ̑�������Ԃ܂��������悤�ł��邪�A�����킢���a�\�O�N�ȍ~�͓���������g�����Ƃ��閯�Ԃ̍��q�ю��Ƒg���Ɉ����p����邱�ƂɂȂ�A���݂Ɏ����Ă���Ƃ����B�����т̋������_�Ƃ𒆐S�ɂ������̎��Ƒg�����̂��̂͂������đ�K�͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�����ɂ��̎��Ƃ��p���W�J���Ă��Ă���悤�ł���B
�@ �����Ă̋G�߂ɋ��ɂ���������A�h�{�L�x�ȍ��̗t�ƍ��킹�ăJ���m���̓V�R�̐��������ێ�ł��邱�Ƃ͋��̐����ɂƂ��Ă��悢�炵���A���N�A���q����鋍�����̂����̉������͎q�����o�Y����Ƃ����B�������R���ł̎��R���łقƂ�ǐl��͂�����Ȃ��B����������傫���Ȃ��āA���낻��o�Y���ȂƎv���邱��ɂȂ�ƓˑR�Ɏp�������Ȃ��Ȃ�A�Ăюp�������Ƃ��ɂ͎q����A��Ă��āA�������Ȃ������H��ł���̂��Ƃ����B�����̓����I�{�\�ɂ���ĒT���o�����閧�̏ꏊ�ɂ����āA�������͐l�ڂ������悤�ɂ��ďo�Y���Ă���炵���B�������Đ��܂������q���͓����������ւ���Ă���̂ŁA���܂ł͎s��ɂ����Ă��u�J���m���v�Ƃ��������Œm���A���̐l�C�͂ƂĂ������̂������ł���B
�@ �����Ƃ��A���q�ю��Ƃɂ�����������Y�̑S�̓I�Ȏ��x�ƂȂ�ƁA�܂��܂�������Ŋ�ׂ�悤�ȏ�Ԃł͂Ȃ��炵���B�O������̈��������̗A���ɂ��킦�č����e�n�Y�o�̖������Ƃ̔̔�����������������A���Ƃ����ʂɈ�Ă��ǎ��̓���������Ƃ����Ă��v�����悤�Ɏ��v����������Ƃ͂�����Ȃ��B����ɁA��������q�Ƃ͂����R���ɕ����ꂽ�X�̋������̓��X�̏�Ԃ�c�������̌��N�Ǘ����s���풓�Ԑl�Ȃǂ͕K�v������A���̂��߂ɗv����l��������ɂȂ�Ȃ��悤�ł���B�ނ��A�~��̋��ɂł̎���ɂ͑����̌o���������B������\���ɍ̎Z�������ȂǂƂ͂ƂĂ������Ȃ��Ȃ̂��B
�@ �܂������ۂ��A���N�Ő��\�Z���`���x�����������Ȃ��u�i�̖̈琬�ɂ͂ȂɂԂ�ɂ��������Ԃ��K�v�Ȃ̂ŁA�u�i�эĐ��Ƃ����ŏI�I�ȉۑ�ɂ����鍬�q�ю��Ƃ̐��ʂɂ��Č��i�K�ł͂����肵���]�������������Ƃ͓���B���Ȃ��Ƃ��e�q��A�S�N�̎����o�����ƂłȂ�����̈Ӌ`�ɂ��ēI�m�ɘ_���邱�Ƃ͂ł��Ȃ����낤�B
�@ �������A���q�ю��ƒn��ɂ̓u�i�̗c�������Ƃ��A���̒n��Ɋr�ׂĊ����̃u�i�̐������x�͂₢�Ƃ��������悤�Ȃ��Ƃ𐬉ʂ̈�Ƃ��Ďw�E���邱�Ƃ͂ł��邩������Ȃ��B�����A��ǓI�ɍl����Ȃ�A���܂̎��_�ł͂���ȏ����ȕ]���ɂ��������A���̎��Ƃ̗��O�Ɖ\����M���A�Ђ����疢���̃u�i�тɖ�������ŋ��͂�ɂ��܂ʂ悤�ɂ��邱�Ƃ̂ق����A��X�ɂƂ��Ă��d�v���L�Ӌ`�Ȃ̂��ƌ����邾�낤�B
�@ �ڐ�̎��ȗ��v��Z���ł̖ړI�B���ɂ����S�̂Ȃ��҂��唼�̍����̓��{�ɂ��A�ŒZ�ł��S�N�����S�N��łȂ���Ίm���鐬�ʂ̌����Ȃ����Ƃɖ���q���悤�Ƃ������Ȑl�X������̂�m���āA���͐[���S���������v���ł������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N9��13��
�J���m���̎l�G
�@ ���q�ю��Ƒg�����̓��邳���Ă���H�ɂ����ď풓�Ȃ����Ă���ԏ����O����A���J�̒����\���قǕ����ƁA���������O�X�܁X���ނ낵�Ă���ꏊ�ɂł��B�q��Ƃ����ƒʏ�͂Ȃ��炩�ōL�X�Ƃ������n��z������̂����A�ނ��J���m���̏ꍇ�͂����ł͂Ȃ��B�u�i��G���܂�ɐ����Ă͂�����̂́A�啔���͔w���������[�����M�ɕ���ꂽ�}�Ζʂ����q�n�ŁA�����ɋ������͕�����Ă��邩�炾�B
�@ �������̍s���͈͂����̒n����ɗ}���邽�ߐj���̈͂��݂͐����Ă���悤�����A�����������M�̒��ɓ����Ă��܂��Ƃ��̍s���̗l�q�⑶�݈ʒu�n���͂�����ƒm�邱�Ƃ͓���B���q�n���̂��������Ɍk���������Ă���炪���R�̐���ɂȂ��Ă���悤������A�������͂Ƃ����肻�̋߂��ɏW�܂��Ă��͂���̂��낤���A������ؗ��̒��̂��������ɍD������ɋ�������Ƃ��������ŁA���悻�q��Ƃ����C���[�W����͒������B������A�����̖q��̃C���[�W������ăJ���m����K�ꂽ�l�́A���Ȃ��炸���q�������Ă��܂���������Ȃ��B
�@ ���炭�������̎p�����]���Ȃ��炠����̃u�i�т␟�k���߂Ă��邤���ɁA���邳��ƕđ��Ƃ���Ԃł���Ă����B�ǂ����ԏ����e�̌k���ł̕đ�Ɗ⋛�Ƃ̏����͐�����̈��������ɏI������炵���B�u���̂������т̑�̂ق����⋛�͑����ł���v�Ƃ������邳��̌��t�ɁA�đ�͍Ăђނ�Ƃ��ӂ邢�͂��߂��B
�@ �Ȃɂ��Ȃ���ɉ˂鋴�̂����Ƃ߂��ƁA�u�⋛�ދ֎~�v�ƋL���ꂽ�ꖇ�̗��D������̂��ڂɂƂ܂����B�u������A���̂�����͊⋛�ނ�̋֎~���ł����H�v�Ɛq�˂�ƁA���邳��͂���������ۂ��݂��ׂāu���͂���A�������Ă����̂Ȃ�ł��v�Ɠ����Ă��ꂽ�B��ʂ̎Ԃ͓����Ă����Ȃ����A�⋛��_���ނ�l�����͓k���ł��̂�����܂ł���Ă��Ēނ����r�炷�B���邳���͔ԏ����ł̐H�ނ͂Ȃ�ׂ�������������悤�ɓw�߂Ă���A���̈Ӗ��ł��⋛�͎R���ł̋M�d�Ȓ`�����ł���悤�Ȃ̂��B
�@ �����Ƃ��A���邳�u�⋛�ދ֎~�v�̎D�𗧂Ă��̂́A�t�߂̊⋛����l��߂ɂ��悤�Ƃ����~�������v���ɂƂ�߂��ꂽ����ł͂Ȃ��A���ɂ���Ȃ�̗��R�������Ă̂��Ƃ������B�ŋ߂̖��@�Ŏ�������Ȓނ�l�����́A���Q�����y���`�ŕ��q�n�̃��C���[���͂��̂����������蓖���莟��ɐؒf���Ēʂ蔲���A���̂܂ܕ��u���Ă����̂��Ƃ����B��J���ċ����������ɂ���Α�ςɖ��f�Șb�ŁA�ǂ����Ă�����Ȃ�̎��Ȗh�q���K�v�ł���炵���B�L�h�S���ł͂Ȃ��̂����瑽���ʓ|�ł͂����Ă����̋C�ɂȂ�ΐj����ؒf���Ȃ��Ă����蔲���ł���̂����A�������Ȃ��Ńy���`�Ő�i�ނƂ��낪�Ȃ�Ƃ����㕗�̎��Ȓ��S�I�Ȕ��z�ł͂���B
�@ ���邳��͎��Ƒg�����̂ق��ɁA���q�ёg�������̊e�_�Ƃ���a��������ȋ������̐���̗l�q�⎖�ƒn�̏��`�F�b�N���錻�n�Ǘ��l�����˂Ă����邩��A���R�A�ؒf���ꂽ���C���[�͂��̕�C�����̎d���̂����ɂӂ��܂��B�[������тŕ���ꂽ�L��Ȏ��ƒn������������Ĉ͂��̓_���������Ȃ��ق��A����̎��Ԃɔ����X�̋������̌��N��Ԃׂ�͓̂��邳��̓��ۂƂ����킯�Ȃ̂��B�������A���q�ю��Ƃ̍ŏI�ړI�͖L���ȃu�i�т������邱�Ƃł��邩��A�u�i�̔����c�̐���̗l�q�A�N�X�̃u�i�̌����A���ƒn����т��̎��ӑS�̂ɂ킽��A�����̒����Ȃǂ��d�v�Ȏd���̈�ɂȂ��Ă���B
�@ ����A�O���O���[���L����M�n�̉��Őe���ɂ͂��ꓮ���Ȃ��Ȃ����q����T���o���A�O�\�L���ȏ�����邻�̎q����w�����Đe�̂���Ƃ���܂ʼn^�т��낵�����肾�Ɠ��邳��͏��Ă���ꂽ�B�e�����l�ڂɂ��ɂ����[���M�̒��Ŏ��R���ɂ��o�Y��������A�܂����܂�ē��̌o���Ă��Ȃ��q����A��ĎR�̉��̂ق��ւƕ����������肵���悤�ȂƂ��ɂ���Ȃ��Ƃ��悭�N����炵���B�������A�܂������ꂵ�Ă��Ȃ��q���ɍ��̗t�ȂǐH�ׂ���͂����Ȃ�����A���̂܂ܕ����Ă����Ɛ����ɂ�����邱�ƂɂȂ�B�e���͐e���ł��남�낷�����ŁA�����ł͂ǂ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��炵���B
�@ �ނ��A����ȂƂ��͓��邳��̏o�ԂƂȂ�B��X���Ԃ������čL��Ȏ��ƒn�������X�܂ŕ������A�ڍׂȒn�`�͂����ɂ�����A��т��M�n�̏�Ԃ���̈�{��{�������n�m���Ă��铌�邳��ɂ́A�q���������Ȃ��Ȃ��Ă���ꏊ���ǂ��ł��邩�����悻�̐��������炵���B���q�ɂȂ����q����T���o���w�����o���ƁA�q���̂ق��͂��ƂȂ����O����{�𓌏邳��̍��E�̌��ɂ䂾�ˁA���g�����悤�ɂ��Ԃ���̂��Ƃ����B��̑O�ɂ͂悭���������Ԏq��w������e�̂悤�ɁA�q����w�������邳��̃��[�����X�Ȏp��z�����A���͂Ȃ��ق̂ڂ̂Ƃ����C�����ɂȂ����B
�@
�@ �̂�т�ƐQ���ׂ��������H�肵�Ă��鋍�����̎p�����]�������ƁA��X�͔ԏ����ւƖ߂����B�đ�Ɗ⋛�Ƃ̌����͈ȑO�P����Ԃ̂܂܂ŁA�ԏ����ɖ߂������Ƃ��ɂݍ����������Ă����B�Ӓn�ƈӒn�Ƃ̒��荇���i�H�j�����炱��͂����ǂ��炩������������܂ŕ����Ă��������Ȃ��L�l�������B�����ŁA���̂ق��͔ԏ����̒��ɓ���A�����Ղ��Ȃ���A���邳��J���m���̎l�G�ɂ��Ă̘b���f�����Ƃɂ����B
�@ �l���̃J���m���͂܂���ʐ[���c��ɕ����Ă��āA���肱�Ԃ��̑����قǂ܂ł̎��Ȃǂ͌ł�����������w�Ɉ����f�i�Ђ��j���ꂽ�܂܂ł���Ƃ����B���܂��ܔ��̂�Ƃꂽ�u�i�̑�������A�C�̉����Ȃ�悤�ȍΌ�����ɔ�߂܂�ɗ����Ă��邾���ł���炵���B�܁X�����r���t���ɂ���Đ������Ƃ��ꂽ�ۂ⏬�}�����ɎU���A�Ƃ���ǂ���ɃA�J�Q�����˂����Ƃ����؋����ς����Ă���̂�������Ƃ����B�t���[�܂�ɂ�āA������ŕ����Ă�����̂��������Ƀ|�b�J���ƌ����J���Ĕ����Ȑ������������͂��߂�B�����āA�u�i�̑�̎���̐�ʂ͐��w�I�Ɍv�Z����ł��������̂悤�ȘR�l��̋Ȗʂ�`���ė������݁A���̒�̂ق��ɂ͍�������̂�������悤�ɂȂ�̂��������B
�@ �܌��ɂȂ�ƑJ���A�⋛��_���ĖK���ނ�t�̑��Ղ����̐�̏�ɓ_�X�ƂÂ��悤�ɂȂ�B�����ĂقǂȂ��R�̎Ζʂ̐�͏����A�u�i�̎�肪��Ăɂ��炩�ȗt���J���͂��߂�Ƃ����B�����ۂ��ł̓I�I���}�U�N���̉Ԃ��R�X�̂���������N�₩�ȃs���N�ɐ��ߕς��A���̃^���V�o�͎���̎}�ł͎x����Ȃ��قǑ����̐^�����ȉԂ�����B�n�\�ł͐�Z����҂�����Ȃ����̂悤�Ƀt�L�m�g�E�����X�ɉ萁���A����Ɍĉ����邩�̂悤�ɏ��X�̑��Ԃ���Ăɔ������̎�t�𐁂��o���n�߂�B
�@ �Z�����玵���ɂȂ�Ƌ��̕��q���͂��܂�A�J���m���̂��������ł͂̂ǂ��ȋ��̖������������悤�ɂȂ�B�����܂ł��Ȃ��A���X�̓��A���̖��̖������J���m���ɖ����킽�鎞�߂ł���B�t�L�m�g�E�A�R�S�~�A�����r�A�C���N�T�A�^���m���A�^�P�m�R�A�q���^�P�Ȃǂ̎R�����߂Ĉ�т����키�̂����̍��̂悤���B
�@ ���u�ꍂ����т��n�C�J�[��L�����p�[�A�h���C�u�q�Ȃǂ̊ό��q�ł��ӂꂩ���鎵�����甪���̉ĎR�V�[�Y�����߂���ƁA�J���m�����ӂɂ͍ĂѐÎ₪�߂��Ă���B�㌎�ɓ���Ƌ}���ɏH�͐[�܂�A���͗��t�̃^�P�m�R�̔���ɔ����\�y�̗{������C�ɒn���s�ɒ~���͂��߂�B�U�݂���g�`�m�L�Ȃǂ͂����ɂȂ����d���������X�ɒn��ɂӂ�܂��B�R�̒����t�߂ł͍g�t���͂��܂�A�₪�Ă��̍g�t�͎R�X�̘[�Ɍ������čL����i�ށB�����ĂقǂȂ��A�J���m���͈�ʁA�ԁA�g�A��A���A���ƐF�Ƃ�ǂ�̍g�t�ɐ��ߐs������邱�ƂɂȂ�̂��������B
�@ �Ă���ӏH�ɂ����ăJ���m���ɐ��ރc�L�m���O�}�����������Ɋ�������Ƃ����B���邳��̘b���ƁA�k�C���̃q�O�}�ȂǂƂ͈���ăc�L�m���O�}�����q���̋����P�����肷�邱�Ƃ͂܂��Ȃ��炵���B���邳��̔ԏ�������͉a������ɋ߂Â��c�L�m���O�}�̎p���ڌ�����邱�Ƃ������ł���Ƃ����B�c�L�m���O�}�̎��͗Y�ƌ�����������Ɠ~���ɓ��邪�A���͂��̊Ԑ�����ۗ�������Ԃ̂܂ܕ�ق̒��ŕۂ����炵���B�Ă���H�ɂ����ĉa�Ɍb�܂�h�{�����\���~���邱�Ƃ̂ł������N�}�̎��́A�t�ɂȂ��ē~�����I���ƂƂ��ɂǂ�ǂ��ٓ��Ő������A�R�O�}�ƂȂ��Ēa������B�������A�h�{�̒~�����\���łȂ����N�}�̎��͓~�����ɕ�̂ɋz��������ł��Ă��܂��Ƃ����B���R�̎d�g�݂Ƃ͂悭�ł������̂ł���B
�@ �\���ɂȂ�ƃJ���m���̍g�t�͂����܂�ƂȂ�B�L�m�R�̂�ɖK���l�X�ňꎞ�I�ɓ��킢�͂�����̂́A�قǂȂ��������n�ʂ��A�،͂炵�������t�グ��悤�ɂȂ�B�ނ��A���̍��ɂȂ�ƕ��q����Ă������������l���ɂ��낳��A���N�̐�Z�����܂Œg�������ɂ̒��œ��X���߂������ƂɂȂ�B�̂́A�u�R�~�߁v�Ƃ����āA�\����\�����i���Ԃ�ɂ��ƂÂ��Ă̘b���낤���j���߂������ɓ��R���Ȃ��悤�ɂ���Ƃ����̂��A�J���m�����ӂ̎R�[�ɏZ�ސl�X�̈Öق̃��[���ł��������悤���B����n�юR�x���̍~��͑z����₷��قǂɐ��܂����A��u�ɂ��Ĉ�т𔒋�̒n���ւƕς��Ă��܂��B�����̑�����Z�p�ł͂���ȏ��ő�����l���~�����邱�Ƃ͂قƂ�Ǖs�\�������̂ŁA�l�X�͂��̎R�~�߂̌��܂���ł�����Ă����Ƃ����B
�@ �\�ꌎ�������߂���ƃJ���m���͐�ɕ�����A���N�̌܌����܂łقڔ��N�Ԃɂ킽���Đ[������ɂ����ƂɂȂ�Ƃ����킯���B
�@ �������邳��̘b�Ɏ����X���Ă���Ԃ��A�đ�Ɗ⋛�Ƃ̐Â��Ȃ錈���͑����Ă����B�⋛�̂ق��������łǂ��v���Ă����̂��͒m��悵���Ȃ��������A�����ۂ��͉a�ł��܂��Ēނ肠���悤�Ɛh�����d�ˁA���������ۂ��͉a�̗U�f�ɏ��Ȃ��悤�ɂ����Ɨ~�]��}����Ƃ����A���ʂĂ�Ƃ��m��Ȃ��䖝�r�ׂ����Ă���ƁA�������ɗ��҂̊Ԃɕ����Ă͂��肽���Ȃ��Ă����B�[���܂łɂ͏H�R�����ʂɔ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��\��Ȃǂ��������̂ŁA�đ�ɂ��Ƃ肠�����͖���Ȃ�ʊƐ�����߂Ă��炤���Ƃɂ��A���邳��̂ɂ��₩�ȏΊ�Ɍ������Ȃ���A��X�̓J���m�������Ƃɂ����̂������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N9��20��
���v���鉜�O�ʂ̎��R�ƈ��
�@ �O�ʐ�i�݂����Ă���j�͐V�����k���̒��������瑺��s���o�ē��{�C�ɒ�����������ł���B�V��������R�`���ɂ܂�����L��Ȓ����R�n�Ɍ����邱�̐�Ƃ��̗���ɂ́A���܂Ȃ�������̖L���Ȏ��R���ӂ�Ɏc���Ă���B�̂Ɋr�ׂ�Ύ��ɑ���Ȃ����ł͂��邪���܂ł������Ȃǂ̑k�オ������Ƃ����B���̎O�ʐ�̌�����ɂ���傫�ȒJ�̉��ŁA�ܐ�N���̎����ē`������Ă������j�ƕ����A����ɂ͂����̃��[�c�ƂȂ����M�d�Ȑ�j����̈�ՌQ���قǂȂ�����ɒ��݁A���������Ă������Ƃ��Ă���B����Ȏ��Ԃ̋}����m���Ă�ނɂ�܂�ʎv���ɋ��ꂽ���́A���v���邻�̈�т̍Ō�̎p�����̖ڂŌ��͂������ƍl���A���̏ꏊ�ł��钩�������O�ʂ�K�˂Ă݂邱�Ƃɂ����B
�@ �V������R�`���ʂɌ������č�����������k��A����s�X���߂���������ʼnE�܂��O�ʐ�`���ɎO�ʃ_�����ʂ�ڎw���đ���ƁA�₪�Ē����X�[�p�[�ѓ��̋N�_�ɓ��B����B����ɎO�ʃ_�������Ȃ���X�[�p�[�ѓ������̂ق��ւƐi��ł����ƁA�O�ʐ삪�傫�����ɕ���n�_�ɓ���B�㗬�Ɍ������ĉE��ɕ�������̂ق��́A�h�P���R�ƉF�A���R�Ƃ������������̊�R�ɋ��܂ꂽ�����ʂ�̏s���Ȃu���J�̉��ւƑ����Ă��邪�A���̐[���s���藧�����O�ʌk�J�̂���Ɍ��������ɂ͔鋫�ƌĂԂɂӂ��킵�����O�ʂ̍L��ȒJ�Ԃ��B����Ă���B�l���܂��������Ȃ����������������Č���҂����|���Ă������Ă̎O�ʌk�J�́A���̉��ɉB���ꂽ���O�ʂ̏W���Ɠ��A���̕�ɂƂ������ׂ��������̒J�X�����Q�[�g�̖��������Ă����̂������B
�@ ���̉��O�ʌk�J�̏㗬���Ɍ��c�̑�^�_�������݂��悤�Ƃ����v�悪�����オ�����͈̂��Z�Z�N�㖖�̂��Ƃł���B�^�������⎡���Ƃ����������̃_�����݂̖ړI���_�Ɨp���p�A����ɂ͔��d�p�ƖړI�ύX���J��Ԃ��Ȃ��獡���܂ŎO�\�N�߂��N���������Č��݂��i�߂��Ă����̂́A���̃_�����ق��Ȃ�ʓ��{�̍��x�������̗����q�̈���������炾�낤�B�@�@
�@ ���݂����ɂȂ��Ă�����̓��R�_����F�{���̐�Ӑ�_���Ȃǂ̑�^�_�����v��̏ꍇ�����������A�o�ϐ������̃_���v��́A���̃_�������������ɂƂ��Đ^�ɕK�v����������Ƃ������A�ނ���A�ǂ����Ƀ_���邱�Ƃɂ���đ�ʂ̎��������o�ς̊�������}�邱�Ƃ����̎傽���_���ł������B���[�I�Ȍ�����������A����s���{���̖�l��Z�p�҂����ƊE��d�͋ƊE�̋Z�p�҂�ƂƂ��ɁA�܂�����őS���̒n�}�߂Ēn�`�I�ɓs���̗ǂ����n��T���o���A���̂��Ƃł��̒n�ɂ�����_�����݂̖ړI�����ꂱ��ƍl���o���Ƃ����{���]�|�����v���W�F�N�g������U���čs���Ă����킯���B
�@ ���ݗ\��n�ɏZ�ސl�X�̐������̈����⓮�A���Ȃǂ̕��z��ԂȂǂɂ��ẮA�قƂ�Ǎl�����Ă��Ȃ��������A�l����K�v���Ȃ��Ƃ���Ă����̂��U��Ȃ������̎���ł͂������B���̎�̖��Ɋւ��ẮA�o�ς̍��x�����ɂ�����A���R�ی�ȂǓ�̎��ɂ��đ����Ȃ�Ƃ����̂����ڂ�ɗa�����Ă�����X�命���̈�ʍ����ɂ��ӔC������ƌ����Ă悢�B
�@ ���O�ʂ̍L�������ĉ��[���J�́A�������x�A���]�R�A���͎R�A�ȓ��x�A�ь��R�Ƃ����������A���ł̎R�X�̉����Ɉʒu���Ă���B���O�ʂ̍ʼn��ɂ���s���ȒJ�́A���̖k�Ɉʒu����ȓ��x�Ɩь��R���q���Ő����͂���ŗL���ȑ咹�r�Ɠ�k�ɑΛ����邩�����ɂȂ��Ă���A�咹�r���ӂƕ���ł��̈�т͒����R�n�̍Ő[�����`�����Ă���̂��B
�@ ���Ă��̉��O�ʂ̒J�̉͊ݒi�u��ɂ͎l�\��ˁA�l���S�\�l�قǂ̔������Â��ȁA�����Ď��R�̍K�L���ȏW�����������B�������Ȃ���A�_�����݂̌v�悪�i�ނɂ�Ă��̏W���̏Z���͑��n��ւ̈ڏZ��]�V�Ȃ�����A���܂���\�ܔN�قǑO�̈�㔪�ܔN�ɒ������j������ł������O�ʏW���͎�������ł����B���̑�^�_������������ƍL�͈͂ɂ킽��J�����v���邽�߁A�u�i�A�g�`�A�i���A�z�E�A�N�k�M�A�N���Ȃǂ̑�̖������鎩�R�тƂ����ɐ��ފe��̓����̐����������邱�Ƃ͓�������w�E����Ă������Ƃ����A�H������݂̔��@�������i�ނ����ɁA���̒n�ɂ͂��܂ЂƂ|���ւ��̂Ȃ����������B����Ă��邱�Ƃ������ɂȂ��Ă����̂������B
�@ �����ׂ����ƂɁA����܂ŎO�ʏW���̂������ꏊ�₻�̏㉺����̎Ζʂ�͊ݒi�u�ォ��A�w�p�I�ɂ�����߂ĉ��l�̍����c��ȗʂ̐�j����̈�ՌQ���˔@�o�������̂ł���B����́A���܂���ܐ�N�O�̋��Ί펞��̈�Ղɂ͂��܂�A�ꕶ���n���������A�ӊ��ɂ�������ՌQ�������̂��B�����Ìy��o�H�A������Ȃǂ���^�ꂽ�Ɛ��肳���Ί�f�ށA ��K�͂ȃX�g�[���T�[�N���i���j�A�G���Z���ՁA�y��ށA�����~���ܑ̕��H�A�����̔z�Ε�A���{�ł͏��߂ĂƂ�����ꕶ���͓̉��t���ւ��H���ՂȂǁA�����͐M���������悤�Ȏ��Ɨʂ̈�ՌQ�ł������B
�@ ���O�ʈ�ՌQ�̔��@�������ɖڂ�ʂ����l�Êw�҂����ٌ͈������Ɉ�Ղ̑f���炵���ɋ����ƂƂ��ɁA���݂ł��߂Â����Ƃ��K�������e�Ղł͂Ȃ������R�n�̒J���ɂ���Ȑ̂���l�X���Z�ݒ����A���n��ƌ��Ղ≝�����J��Ԃ��Ă������Ƃ��ϕs�v�c�Ɏv�����Ƃ����B�ނ��A���O�ʈ�Ղ�m�錤���҂����͂����������Ԃ������Ă��̓�ɒ��݂����Ƃ͍l���Ă����悤�����A���ɍ����S�\�Z���[�g���̕������^�A�[�`���_�����O�ʌk�J���ǂ��������Ŋ������A �\��������玎���X���i�����j���J�n����邢�܂ƂȂ��ẮA������̑ł��悤���Ȃ��Ƃ����̂�����̂悤�ł���B
�@ �����ʖ�ꉭ���ܕS���g���A�ꉞ�͎����A���������A���d�̖��������Ƃ���邱�̌��c�_���̌��݂ɂ͑��H��S��\���~���������ꂽ�B����ɂ܂���������H���̑��̎��ӊ��̐�����ێ��̂��߂ɑ��z�̌o���������̂Ǝv����B���ꂾ���̔�p���������_���{�̂����Ɋ����������݁A�X�������Ȃ��܂܂��������Ă����Ƃ������Ƃ͎Љ�ʔO����s���@�\���������Ȃ����Ƃł͂���̂��낤�B�Ⴆ�͈������A���Ă̐�͑�a�̂悤�ȋ��͂��Ă��܂������܁A���ꂪ�Ӗ������Ƃ������܂����A�܂����ꂪ�ǂ�ȉ^����H�낤���A�C�ɕ����ׂĂЂ����瑖�点�Ă݂邵���Ȃ��Ƃ����킯�ł���B
�@ �����̕����Ɣɉh�̂��߂��Ɩڂ̑O�ɑ����ς�Ő�������A��j���ォ��ܐ�N�ȏ���p����Ă�����c�̒n���������������������O�ʂ̌��Z���̐S�����A�����ۂ��ł܂���ϕ��G�Ȃ悤�ł���B���ɂ��Ă̏Z�����Ƃ̓X�X�L�̐�����r�n�Ɖ����A�܂��J���J�̑��ʂ��H���p�g���b�N���^�@�B�ނ��c�����s�ɑ���܂�������ʁA�̂̐Â��Ŕ����������W�����Â�����̂Ȃǂ����قƂ�ǎc���Ă͂��Ȃ��B����Ȍ̋��̖��S�Ȏp��ڂɂ���ɑς��Ȃ����Z�������̂Ȃ�����A�����_���ɐ������Ăق����A�����łȂ��Ɖ�X�͌��c�l�ɑ��Đ\�������Ȃ��Ƃ��������オ���Ă���̂���ʂł�ނȂ����ƂȂ̂��낤�B
�@ �\������Ƀ_���̒X�����J�n����邽�߁A��Ք��@�ȗ��\�N�]���������Ă������O�ʈ�ՌQ�̌�����J���㌎��\�l���������ďI���B�Ō�̌��J�ƂȂ��\�O�A��\�l���ɂ́A���n�Ƀe���g�����Ȃ���قǂȂ����v���铯��ՌQ�̖��͂ɐG��錩�w��J�����B�V�����������ْ��ō��w�@��w�����̏���B�Y���ɂ��u�����Ղ̃��C�g�A�b�v�Ȃǂ��\�肳��Ă���Ƃ����B
�@ �_���̌Β�ɒ��މ��O�ʂ̒J�����w�ł���̂��\���̈���܂łŁA�Ȍ�͊W�҈ȊO�̓��n�ւ̗�������͋֎~�ƂȂ�A��N�Ԃ͓��_�����ʂւƑ����ԓ��̈�ʎԂ̒ʍs���K�������炵���B�����X���J�n����܃�����̓�Z�Z��N�O���ɂ̓_���͖����ɂȂ�Ƃ����B
�@ �^�������Ɣ��d����ړI�Ƃ���邱�̃_���ɂ��āA�y�؎j��͐�H�w����Ƃ���V����w�H�w���̑�F�F�����́A�V������̕������œƎ��̌������q�ׂĂ���B��F�����ɂ��A����ɔ��d�����^�����������ɘb���i���čl����ƁA���i�̓_������ɂ��Ă������Ƃ��\�����A�����łȂ��Ă��v��̃_���̍Œᐅ�ʂɒ����ʂ�}���邱�Ƃ��ł���A������\���[�g���قǍ����ʒu�ɂ��錳���~��ՂȂǂ́A�ȏ㑝�����ȊO�͊�����Ƃꂤ��Ƃ̂��Ƃł���B
�@ �����ɂ͂�͂蔭�d�ƍ^�����������˂��O�ʃ_�������łɑ��݂��A�܂����܈�̎O�ʐ�x���A���c��̏㗬��ɂ͂�͂�傫�ȉ��c�_�����݂����Ă���B���������̃_���ƘA�W���ĉ�����̐��ʂ����A���̂����ň�ՌQ�̐��v���ŏ����ɗ��߂邱�Ƃ��ł��Ȃ����Ƃł͂Ȃ��̂��낤���A�W�s�����ǂɂ����������z�������߂邱�Ƃ͂��̍��ł͂�͂������ƂȂ̂��낤�B
�@ ��F�����͔��d�ɂ��Ă������[�����Z�����Ă���悤���B���O�ʃ_���ɂ���ĐV���ɐ��ݏo�����d�͔͂N�Ԗ�ꉭ�O�疜�L�����b�g���Ƃ̂��ƂŁA��������z�Ɋ��Z����Ƃ��悻�\�����~�ɂȂ�Ƃ����B�����_���̑ϗp�N����S�N�Ƃ���ƁA��玵�S���~�̌o�ω��l��L���邱�ƂɂȂ�A����ɔ��d�𒆎~���Ĉ�Ղ�ۑ�����Ƃ������ƂɂȂ�ƁA���̂��߂ɂ��ꂾ���̔�p���������Ɠ����v�Z�ɂȂ�B�ܐ�N���̎��Ԃ��~�ς��ꂽ���O�ʂ̕����I���l�͂�������r��������Đ��s�\�Ȃ��̂ł���A�O�q�̋��z�����̉��l�͏\���ɂ���̂ł͂Ȃ����Ƃ����̂���F�����̈ӌ��ł���B�����I�Ɍ��Ăǂ���̑I�������������ǂ�����x���c��ȂǂœO�ꓢ�_����邱�Ƃ����͊��҂����Ă���悤���B
�@ �V�����������ْ��̏���B�Y���Ȃǂ���́A�\�����璙�����J�n����Ɠ~������ɓ������������������ʂ̏㏸�̂��߂ɓM�����Ă��܂��̂ŁA���߂đ�������g����邱�Ƃ��ł���悤�ɒX���J�n��g���������ɂ��炵����ǂ����Ƃ�����ĂȂǂ��Ȃ���Ă���悤���B
�@�u����܂œy�؋Z�p�҂͐��������̂��ƂȂǍl���Ă��Ȃ��������A�����R�^��Â��肪�W�Ԃ���鍡���A���߂Ă��̏����Ƃ��Đ��������ʎ��ɂ����Ȃ�������������ׂ��ł͂Ȃ����Ǝv���B��l����邱�Ƃ����҂������v�Ƃ�����F�����̌��t�ɂ́A�y�؎j��͐�H�w�̐�剻�̂��̂ł��邾���ɂ��������̏d�݂��������ĂȂ�Ȃ��B
�@
�@ ���O�ʒT�K�̔w�i�����������Ȃ��Ă��܂������A�Ƃ����������̂悤�Ȏ���ŋ}篎��͂��̃_���̌������K�˂Ă݂邱�Ƃɂ����킯�������B���O�ʂ̒J�Ɍ������O�Ɏ��͎O�ʌk�J�̉������ɂ܂���Čk�J�ߏグ�Ă݂��B�k�J�̉��ɂ͊��ɋ���ȃR���N���[�g�̕ǖʂ����X���ނ������A���̐S��}�����̂��Ƃ��Ɉ��|�����B���̎O�ʌk�J�̉��Ɍ������č���̊�R�ɂ́A���ċ��كg���l���Ƃ����┧�����o���ׂ̍��Â���@�蕗�̃g���l�����ʂ��Ă����B�V����Ⴍ���������A�Ԉ�䂪����ƒʍs�ł�����x�̔��͖��_�Ȃ��̒����g���l�����̂͒������̒��S�������牜�O�ʏW���ւ̗B��̒ʍs�H�������̂����A���܂ł͂������S�ɕ�������Ă��܂��Ă���B
�@ ���݂ł͂��̂����ɁA���كg���l���̓����̂������ꏊ���班���X�[�p�[�ѓ���߂����n�_�ɁA�{������O�ʐ���z���ĉE��ɕ��邩�����ʼn~�ዴ�Ƃ����V���������˂�A�������牜�O�ʕ��ʂւƐV�ܑ݂̕����H���̂тĂ���B���̉~�ዴ��n��A�菑���̕W���ɏ]���ĐV�������炭����ƁA�قǂȂ�����܂��V�݂̋ߑ�I�ȃg���l�������ꂽ�B���̒����g���l������Ƃ����Ȃ���̉��O�ʃ_���̉E�[�ɋ߂��n�_�ɏo���B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N9��27��
���O�ʌ����~���
�@ ������ڑO�ɂ����ŏI�H���̍s���Ă���_���T�C�h�ɂ͐i�ނ��Ƃ��ł��Ȃ��̂ŁA�n���h�����E�ɐ�A���O�ʂ̒J�Ԃւƍ~��Ă����}�X�̓��ւƓ������B�ቺ���O���ɂ́A�قǂȂ�����ɒ��ސ[�X�Ƃ������O�ʂ̒J�Ԃ��L�����Ă���B�����Ă��̒J��̒��S����D���悤�ɂ��ĒJ���̂ق��ւƂ̂тĂ���̂��O�ʐ삾�B�J���т�V���ȓ��H�H�����s���Ă��锽�Α��̎R���̍����ł́A�H���p�̃_���v�J�[��u���h�[�U�A�N���[���ԂȂǂ��܂��Z�������ɓ����܂���Ă���Ƃ��낾�����B
�@ �J��̂ق��ւƂ��Ȃ艺���Ă������Ƃ���ŎԂ��߁A�Ȃɂ��Ȃ����������~��Ԃ�ƁA�����S�\�Z���[�g���ɋy�ԉ��O�ʃ_���̈Зe���ڂɔ�э���ł����B�܂��O�ʐ�̐��H��������Ă͂��Ȃ�����A�S�ǖʂ���O���ւƌʏ�ɂ��肾�����������^�A�[�`�_���̑S�e����ꕔ�܂ł͂�����ƌ��ĂƂ��B�����ɗ��ꂽ�Ƃ��납��_���̑�ǖʂ����グ��悤�ɂ��Ē��߂Ă��邹���ł��̑傫���͂��܂ЂƂF�����Â炢���A�_�������̐��H�t�߂ō�Ƃ����Ă���_���v�J�[�̑傫���Ɗr�ׂ�Ƃ����ɋ��傩�������ł���B����ɂ��Ă��A�قǂȂ����v����͂��̋���_���̌Βꕔ�ڂɖڂɂ���Ƃ����̂͂Ȃ�Ƃ���ŕ��G�Ȏv���̂�����̂������B
�@ �_���{�̂ߏI����ƁA���䂩�̍H���W�̎ԂƂ���Ⴂ�Ȃ��瓹�Ȃ�ɒJ�̒�ւƍ~��A��������O�ʐ�ɂ����鋴��n���Ă���㗬�����ւƎԂ𑖂点���B�i�s��������̎R���ł͐V�������H�̌��݂��i�߂��Ă���B���̌��グ��悤�ȍ����𑖂�V�����₪�Ă��܂�鋐��Ȑl���̎��H�ɂȂ�Ƃ����킯���B�ނ��A���Ԃő����Ă��邠����͐V���̍Ő[���ɂȂ��Ă��܂��B
�@ ����ɂ��Ă��Ȃ�Ƃ����ς��悤���낤�B�܂��Ⴉ��������̂��Ƃł͂��邪�A�R�������D�����������́A�R�`���������⒩������������R���A�ь��R�A�ȓ��x���璩���x�ւƘA�Ȃ钩���A���ł��z���Ă��̐V������D�S���������O�ʂ̏W���ɉ��R������A���̋t�R�[�X���Ƃ��ĎR�`�����ɔ������肵�����Ƃ�����B���Ă��̉��O�ʂ̏W����J�X��т́A�t�Ȃ�ΉԂ̐Î⋫�A�ĂȂ�Ἡ鋫�A�H�Ȃ�g�t�̌��z���A�����ē~�G�Ȃ�Δ���̖����Ƃł��ĂԂɂӂ��킵���Ƃ���ł������B�O�ʐ�𗬂�鐅���A����ɂ͂��̎嗬�Ɍ������Ďl���������璍�����ޑ召�̌k�����M�����Ȃ��قǂɐ����������݂����Ă����B���̒J�ł͂������Ǝ��Ԃ�����A�����ɏZ�ސl�X�͌��t�������Ȃ��������S�D�����A���̈ꋓ�ꓮ�͕s�v�c�Ȋm�M�ɂ��ӂ�Ă����B
�@ ���܂��̔����������J�̗����͉��̂ق��܂Ŗ��c�ɍ�����A�Β�ɒ��ޕ����̎��͂قƂ�ǐ�s������āA�̂̉��O�ʂ̖ʉe�͂��͂�ǂ��ɂ��c���Ă��Ȃ��B�O�ʐ염�݈�т̉͊ݒi�u��̕��n�ɂ̓u���h�[�U��L���^�s���Ԃ��c���ɑ���܂�����Ղ��[�X�ƍ��܂�A�_���v��ʂ����߂̍H���p���H���A�܂�ł��̒J�̎��R�̑����ɍŌ�̎~�߂��h���Ƃł���������ɍ��ݐ݂����Ă���B�ނ��A���̐S�D���������R�l�����̎p�Ȃǂǂ��ɂ����낤�͂��͂Ȃ��B
�@ ���G�Ȏv���ɋ���Ȃ��炵�炭�J���ւƌ������đ���ƁA���E�ɓ�������n�_�ɏo���B����̓��͐ԑ���䖔��̂���O�ʐ쌹������ʂցA�E��̓��͎x���̖����k�J�����ɐi���ƁA�������x����傫���̂т�������z���ď������ʂւƑ����Ă���B���̓��H�̕���_�̍���͊ݒi�u��ɋ����O�ʏW���͂������̂����A�u���h�[�U�ō�蓥�݂Ȃ炳��Ă��܂ł͂��̖ʉe�͂ǂ��ɂ��Ȃ��B�Z���������ނ������ƍs��ꂽ���@�����ɂ��A���̂����肩����ꕶ���̈�Ղ�╨���������ꂽ�炵���̂����A���������̏o�y��������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���Ԃ������Ď��ӂ��ڍׂɒ���������A�����Ɨl�X�Ȕ��������邾�낤�ƌ����Ă��邪�A�قǂȂ����v����Ƃ����Ă͂��͂₻����s�\�ł���B
�@ ���͍���ɕ��ĎO�ʐ쌹�����ʂւƌ��������ɓ���A������\�l���܂ł͈�ʂ̌��w�҂ɂ����J����Ă��錳���~��ՂɌ��������Ƃɂ����B�ނ��A���̈�т̓��H����Ջ��X���v���Β�̈ꕔ�ɂȂ�킯������A�X���̎n�܂鍡�N�\������ȍ~�͓��R�ʍs�s�\�ɂȂ��Ă��܂��B�Ԃ͓���͂邩�ȂƂ���ɉ˂�H�����̑勴���̉���ʂ�ʂ��A���ʂɂ���ꂽ�_�[�g�̓��`���ɂ�����x�O�ʐ��n��A���̐s����Ƃ���ɂ��鏬�����͊ݒi�u��̕��R�n�ւƏo���B���̒i�u���������O�ʂŔ������ꂽ�ő�̓ꕶ��ՌQ�̂��錳���~�������B
�@
�@ ���������Ƃ��̓��̎��ɂ͈�l�̓��s�҂��������B�܂���\�㔼�̎Ⴂ�����̂`����ł���B����O���n�̉�Ђɋ߂�ޏ��́A�����łƂĂ����͓I�ȏ����Ȃ̂����A�c�������j����̍s���͂ƃ`�������W���_�����킹�����Ă���B�߁X���O�ʂɍs���Ƃ����b������Ɛ���Ƃ����s�������Ƃ����̂ŁA�������炱�̒n�ւƌ������r���A�ߐ{�Ŕޏ����E���Ă����B�O���͖җ�ȗ��J�̒��A�S�g���ԔG��ɂȂ�Ȃ�����Ƃ�œߐ{���ӂ̎R�������y����ł��Ă����Ƃ�������A�Ȃ�Ƃ����グ�����̂ł���B
�@ ��X��l�͎Ԃ���~��A�s�v�c�ȂقǂɐÂ܂肩��������Ղ̑O�ɘȂB����������O�ɂ��̌����~��Ղ�K�˂��Ƃ��ɂ́A���܂��܋x���������������������̌��w�҂̎p������ꂽ���A���̓��͌��j�����������Ƃ������Ď��ӂɂ͉�X�ȊO�ɐl�e�͌�������Ȃ������B�ቺ�̎O�ʐ�Ί݂𑖂�_�[�g�̍H���p���H���Ƃ�����g���b�N�����������ĂȂ���ʂ�߂��͂������̂́A��ՌQ�̂��邠����͂Ȃ�Ƃ��Â��Ȃ��̂������B��X�����n��K�˂��̂͏\���\�����ł��������A���ꂩ���T�Ԍ�̓�\�O�������\�l���ɂ����Ĉ�Ղ̃��C�g�A�b�v���s���A���Ƃ����ɂ��Ō�̈�Ռ��w������J����邱�ƂɂȂ��Ă���Ƃ����b���M�����Ȃ����炢�̐Â����������B
�@ �_���H���ɂƂ��Ȃ����@�����̂��߂ɕ\�y������Ē��N�̖��肩��o�߁A��������̂܁A���x�͔����o���̂܂ܐ���ɖv�߂��Ă��̈�Ղ͍Ăщi���̖���ɂ��B���������̈�ՌQ�̕揊�̂ǂ����ɂ��܂��Ñ�l�̗삪���ݏh���Ă����Ƃ���A�����
�̍��͐g����Ȍ���l�Ƃ������̂̎p���ǂ̂悤�ɍl���邱�Ƃ��낤�B
�@ �[���z���ɒ^��Ȃ��痧���s������X��l�̊�O�ɂ́A�O����Ⴂ���[�v�Ŗ�����Ɉ͂�ꂽ�����~��Ղ��A�ꕶ�l�̖����̃��b�Z�[�W��[����ߓ`���邩�̂��Ƃ��ɍL�����Ă����B�����̒G�����Z���Ղ��A��d�O�d�̕��G�ȉ��ʂ��Ȃ��Ăǂ��܂ł������Ă���B�ꕶ���Ƃ���������l����A����͂܂�ɂ݂��W���������Ƃ����Ă悢�B�X�̊ێR�O����ՂɕC�G���邭�炢�̓ꕶ��ՌQ���Ƃ�����̂��������Č֒��ł͂Ȃ����낤�B
�@ ���т����������̑召�̒G���̉��₻�̎���̕\�y�ɂ́A�悭����ƌG�Ȃ��e���ł����܂�Ă����B�ނ��A���Ƃ���Ւ����̍ۑ��n�̖ڈ�Ƃ��đł������̂ł���B���ʂȒG���Ȃǂ͓���Ȑp�l�̂��̂�p���Ă��̉����܂邭�����ł߂��肵�Ă������B���⑤�ʂɑ����̐��d�˕��ׂ��Ă���G�����������B�f�l�̉�X�ɂ͂킩��Ȃ����A���̓��̐��ƂȂ炱���̒G���Q�̔z���\�������������œ����̏W���̗l�q��I�m�ɑz���`�����Ƃ��ł���ɈႢ�Ȃ��B���v�ɐ悾���ďڍׂȒ������s���A�Ί��y��A���p��Ȃǂ̋M�d�ȏo�y���������ɐ݂���ꂽ��Ւ������Ɉڂ���Ă���̂͂��߂Ă��̋~���ł���Ƃ����Ă悢�B�����̏o�y�i�͂������ʌ��J�����\��ł���Ƃ����B
�@ ���̌����~��Ղ͉͊ݒi�u�̒n�`�ɑ����đ傫����i�ɂ킩��Ă���B�G�����Z���Q�Ղ̍L���鉺�i�ƕ揊����J�Ղ炵�����̂̂����i�Ƃ��u�Ă�}�ȊR���̒ʘH�`���ɕ����čs���ƁA���܂��Ȃ�����������ƗN���o���Ă���傫�Ȑ�̂��ɏo���B�ܐ�N�ȏ�ɂ킽���ėN�������Ă�����ł���B�����ɗ̐����Ɛ��ۂ̖邻�̐�ɓ�l�ŕ���Ŏ������ƁA�₽���Ȃ��ɂ����̌ۓ�������������s�v�c�Ȋ��o���`����Ă����B���̒n�ɏZ�ꕶ�̐l�X�́A�ނ�̐�̐��Ɏx�����Đ����Ă����ɈႢ�Ȃ��B���̐�̂�����G�����Z���Q�Ղ̂���ق��ւƖ{���̗��H�Ƃ͈قȂ�ׂ����H�����Ă��邪�A�ǂ���炻�ꂪ�䂪���ł͏��߂Ă̔������Ƃ����Ñ�͓̉��i���H�j�t���ւ��H���̐Ղł���炵���B
�@ ���i�̈�ՌQ������Ɍ��Ȃ��炢���̂ق��ւƐi�ނƁA�����e�Ɂu�z�Ε�v�ƋL���ꂽ���D�̂���ȉ~�^�̌������ꂽ�B����Ƃ͂�����킩��悤�ɐp�l�̂��̂ł�͂茊�̎��͂����������ł߂��Ă���B�������ɋ߂Â��Ē���`���Ă݂�ƁA�ȉ~�^����̐[�����̑��ʂ͑傫�߂̋ʐ�O�O�ɐςݏグ�đ������Εǂł�������ƌł߂��Ă����B�m���ɐl�ЂƂ肪���������ɏ\���Ȃقǂ̑傫��������B���ӂɂ͓��l�̔z�Ε�Ǝv���錊�����Ȃ�̐�����ł����B�����߂̌��͎q���ł����߂���ՂȂ̂��낤���B�������ꂽ�Ƃ���ɂ͊��A������X�g�[���T�[�N���炵�����̂����������������B
�@ ��Ղ̏�i�����ɂ̂ڂ��Ă݂�ƁA�����ɂ͉��i�̕��n�ȏ�ɍL�X�Ƃ������R�n���L�����Ă����B�T�^�I�ȉ͊ݒi�u�̍ŏ㕔�ł��邱�Ƃ��悭�킩��B�����ɂ����Ȃ�̐��̔z�Ε�ՁA���邢�͉����̍��J�Ղ������ɐՂ��Ǝv����召�l�X�Ȍ`�̌��������Ȑ��U�݂��Ă����B�������@���ꂽ�����̌��̑��ʂ͂�͂�قƂ�ǂ��傫�ȋʐ�ς�Ōł߂��Ă���B�������傫�Ȍ��̂ق����z�Ε悾�����Ƃ���A����͏W���悾�����̂�������Ȃ��B
�@ ��i�̕��n�̒[�ɗ����ĉ��i�̒G�����Z���Q�Ղ�z�Ε�Ղ߂��ƁA����炪�z���ȏ�ɑ傫�Ȉ�Ղł��邱�Ƃ��悭�킩�����B����ɂ��Ă��A�ꕶ�W���ɂ�����Z���ƕ�n�Ƃ̂��ُ̈�ȋ߂��͂������������Ӗ����Ă���̂ł��낤���B�܂��ɏZ��אڂȂ̂ł���B���E������c�̗�ɑ���ꕶ�l�̈،h�̔O�̐[����S�I�W�̔Z�����́A����l�̑z�����͂邩�ɒ�������̂ł������̂��낤�B
�@ ���Ȃ�̎��Ԃ��o��������ǂ��ˑR�Ƃ��ĐV���ɐl���K��Ă���C�z�͊������Ȃ������B��X�͂����ቺ�̈�ՌQ�₻�̌������𗬂��O�ʐ�̗�������߂Ȃ���A�������ꂼ��̑z���ɒ^���Ă����B
�@ �ꕶ����̏��N�����͂ǂ�Ȗ������Ă����̂��낤�H�c�c���̎R���̒J�ɐ��܂�قƂ�ǂ͂��̒J�ɂ����Đ��U���I���Ă������ɈႢ�Ȃ��ނ�ɂƂ��āA���E�Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł������̂��낤�H�c�c���n��̓ꕶ�l�Ƃ̌𗬂���Ղ̂��߂ɂ��̒J���o�čs���҂͂ǂ̂悤�ɂ��đI�ꂽ�̂��낤�H�c�c�ނ�̂����̂ǂ�قǂ̎҂������ɖ߂��Ă����̂��낤�H�c�c�������Ƃ̍����͂ǂ̒��x�F�߂�ꂽ�̂��낤�H�c�c�s�v�c�Ȏ��Ԃ̗���邱�̋�Ԃɂ����āA�����ēꕶ�l�̒N�����܂������v����Ƃ͑z�������Ȃ��������̐��n�̍Ō��O�ɂ��āA��X�̋����ɉQ�������G�ȑz���͂Ƃǂ܂�Ƃ��������Ȃ������B
�@ �����~��Ղ����Ƃɂ�����X�͂����߂��̎O�ʐ�̉͌��ɍ~��Ă݂��B����̗l�q�͕ς��ʂĂĂ��܂��Ă������A�������₩�ȔS��≩�ΐF�̍��⎿�̊�Ղ���Ȃ�쏰�𗬂�鐅�͐̂Ɠ����悤�ɐ��݂����Ă����B���̐��͂��̂܂܂ł����߂�B���炫��ƋP���h��鐅�ʂɏ��𓊂��Đ�����y�����ƁA��X�͓������ăC���X�^���g�̖��X�`�����A�R�[�q�[�����ĊȒP�ȐH����������B
�@ �Ԃɖ߂�����X�͎O�ʐ�̂���ɉ��̂ق���T�����Ă݂邱�Ƃɂ����B�O�ʐ�̏㗬��������̊݉����ɂׂ͍��_�[�g�̋����������āA����͂���ɉ��̂ق��ւƂ̂тĂ���B�H���Ԑ�p���̕\�������������A���̕\�������Ă��炭����Ɛ�̘e�̊J�����ꏊ�ɏo���B���̒n�_�̏��������ɂ͏����ȉ������邽�߁A���̏㗬���͓����Ȑ��X�ƒX�����L���傫�ȗ��݂ɂȂ��Ă���B�ݕӂɂ̓V���x���J�[�ō����̎悵���Ղ����������A�쏰���Y��ȍ��n�ɂȂ��Ă��Đ[�����قǂ悭��������₩����������A�j���C�ɂȂ�����ɂ��j���銴���������B�ނ��t�߂ɂ͊⋛������ł���B
�@ ���̑傫�ȗ��݂̂������̍��݂ɎO�ʐ���ׂ��őΊ݂ɒʂ����{�̖ؐ��݂苴���˂��Ă���̂����A���݂͔p���ɂȂ��Ă���A���̓n�����̓X�X�L�■���A���ؗނȂǂɂ���Đ[�X�ƕ����Ă��܂��Ă���B���Ƃ��Ƃ͉��O�ʂ̐l�X�̐����Ɍ������Ȃ��d�v�Ȓ݂苴�ŁA�m��l���m�鑶�݂������̂����A���̔p�����܂��قǂȂ����v����^���ɂ���B�̂��̋���n�������Ƃ̂��鎄�́A���ꂪ����ȍ\�������Ȃ��Ă��āA���Ƃ��j�̐g�ł����Ă��n���ɂ͂���Ȃ�̃R�c�Ɠx�����K�v�ł��邱�Ƃ�m���Ă����B�����甼�Ώ�k�̂���ŁA�`����Ɍ������āu�����n���Č��悤���A���Ȃ��Ȃ�n��邩������Ȃ���v�ƗU���������Ă݂��̂����A������Ǝv������A�Ȃ�Ɣޏ��͂�邫���X�̕\����������B�����Ȃ�����������݂̒苴�̍Ō�̓n���҂ɂȂ�ׂ��`�������W���Ă݂邵���Ȃ������������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N10��4��
���悤�Ȃ牜�O��
�@�@�@�@�@�@�@���������������݂݂̒苴��
�@ ��ɗ��������́A����Ȃ��悤�ɂ��Ĕw�����X�X�L�̗t��~�������A�����̂���ފ����M���������݂Ȃ��狴�̂����Ƃɋ߂Â����B�����đ������m���߂�悤�ɂ��ċ��[�̉E��Ɏ������B�U��Ԃ�ƁA������Ƌْ������ʎ����ł`������������Ƃɂ��Ă��Ă���B���ʂȂ炱�̂悤�ȋ��̏ꍇ�A�u�p���Ŋ댯�ɂ��n���֎~�v�Ƃ��Ȃ�Ƃ��L�����x���������Ă�����̂Ȃ̂����A����Ȃ��̂Ȃǂǂ��ɂ���������Ȃ��B���ꂪ�܂��A���Ă͔鋫�ƌĂꂽ���̒n�炵���Ƃ���ł�����B�����Ƃ��A�����łȂ��Ă����邩��ɃX�������_�ŁA�������p���ƂȂ��Ă���͂����������낵���ȕ��͋C��Y�킹��悤�ɂȂ��Ă��܂������̋����A�����ēn�낤�ȂǍl����l�Ԃ�����ق����ςȂ̂�����A�x�����Ȃ������Ďd�����Ȃ��B
�@ �݂苴�Ƃ����ƁA�S���I�ɗL���Ȏl���̉��c�J�̂����狴�Ȃǂ�z���o���l��������������Ȃ��B���݂̒苴���Ȃ��Ȃ��ɔ��͂������āA�n��ɂ�Ă����h��邵�A�����̋����ɂ͈��Ԋu�̌��Ԃ������Ă�������[���k�J�������Ă���B�����A�c�J�̂����狴�̏ꍇ�͋������������̌��Ԃ���������A�^�����Б����������瓥�݊O���悤�Ȃ��Ƃ��������Ƃ��Ă��A���̂܂ܑS�g�܂邲�ƒJ��Ɍ������ė�������\���͏��Ȃ��B���ꗼ���݊O�����悤�ȏꍇ�ł��A����ŋ����⋴���̂ǂ�����͂ݗ����Ȃ��悤�ɂȂ�Ƃ��g�̂��x���邱�Ƃ͂ł��邾�낤�B
�@ �Ƃ��낪�ǂ����낤�A�����N���n�邱�Ƃ̂Ȃ��Ȃ������Ƃ͂����A���̎O�ʐ�݂̒苴�Ƃ�����ꕗ�ς�����\���ɂȂ��Ă��邩��A������ƊԈ������A�͂邩�ቺ�̐��ւƂ������ɒ@��������B�����Ȃ�����ꊪ�̏I���ł���B
�@ ���݂̒苴�̍\�����܂��ɗ�������ɂ́A�S���̃��[���Ɩ��������Ă��̗����Ƀ��C���[���[�v�����[���ƕ��s���ĉ��d���ɒ����Ă���Ƃ�������z�����Ă��炤�Ƃ悢���낤�B���ɂ����邱�̋��̋����i���j�͏\�Z���`�p�A�����[�g���قǂ̊p�ނł��邪�A���ɕ~���ꂽ�p�ނƊp�ނ̊Ԋu���䂤�ɓ[�g���قǂ͂��邩��A�������A�l�Ԃ����X�ɂ�����ׂ��œ��ݓn�邱�Ƃ͕s�\�ł���B�I�����s�b�N�I����݂̒����͂ƃT�[�J�X�c���畉���̃o�����X���o�����킹����҂��댯�o��Ŕ�шڂ�Ȃ�Ƃ��Ȃ邩������Ȃ����A���ʂ̐l�Ԃ������������炽���܂��ቺ�̌k�J�ւ̓]���͂܂ʂ���Ȃ��B
�@ �Ƃ���ŁA���̖��ɂ����鉡�̏�ɂ͂�͂�\�Z���`�p�قǂ̊p�ނ���s���ĕ~�����ׂ��A���傤�Ǔ�{�̑��ڂ̃��[���Ɠ����i�D�ŋ��̏��Ί݂܂ł̂тĂ���B�����Ă��̖̃��[���ƃ��[���̊Ԃ͑�l����҂��J���ƂȂ�Ƃ��͂����炢�̕��ɂȂ��Ă���B������{�̃��[���ɍ��E�̑���������ė������ꍇ�A�ނ��g�̂̉��̓X�P�X�P�̋�ԂɂȂ�킯������A������ƃo�����X��������炻�̏u�ԂɁu�͂��A�T���i���v�ƂȂ��Ă��܂����Ɛ����������B�v����ɁA��{�̃��[���̊Ԃɂ͕��\�Z���`�̊p�ނ��d��g�ɂ��āA1���~2���قǂ̒����`�̋�Ԃ��c�����Ɋ������ł���̂ł���B�ނ�ꂼ��̃��[���̊O����0.4���~2���قǂ̒����`�̋�Ԃ����l�̏�Ԃł����ƕ���ł���킯���B�ۂ�����ƌ����J����X�̒����`��Ԃ̐^���ɂ͐�����X�����k�J���҂������Ă��邾���ł���B���x���|�ǂ̐l�Ȃǂ͘b���������Őg�k�������Ă��邩������Ȃ��B
�@ ���߂Ă��̋���ڂɂ����l�Ȃǂ́A���Ɖ��̊ԁA�ؐ����[���ƃ��[���̊Ԃ��J�o�[���鋴���ނ����Ƃ��Ƃ͂��������A����炪����ꌻ�݂ł͓n���s�\�ɂȂ����Ƒ����_���Ă��܂���������Ȃ��B�����A���ۂɂ͂��̋��͂��Ƃ��Ƃ���ȍ\���ɂȂ��Ă���̂ł���B���Ԃ�A�C�ۂ��̑����͂��߂Ƃ��邱�̒n�̓���Ȏ��R������������̂䂦�ɁA�l�X���m�b�ƍH�v���Â炵�����ʁA���̂悤�ȍ\���݂̒苴���œK�Ƃ����ɂ��������̂ł��낤�B
�@ �Ƃ���ł����������̋����ǂ�����ēn��̂��H�c�c�������A���\�Z���`�قǂ̖̃��[���̏��n��̂ł���B�����ɉ��{������ꂽ���C���[���[�v�̓K���Ȃ��̂�Ў�Ōy���͂݃o�����X�����Ȃ���݂苴��n��̂��B����ɉ�������ׂ����ϑ�̏��n��悤�Ȃ��̂ł���B�������O�\���[�g���O��͂��邾�낤�B�ؐ��̃��[���A���Ȃ킿��{�̕��s�ȍׂ��ؓ����݂���ꂽ�̂́A���Ă��̋������I�ɗ��p���Ă����l�X������Ŗ����Ȃ�����Ⴆ��悤����K�v������������ɈႢ�Ȃ��B�S���I�ɂ݂Ă���{���[�����͓�{���[���ɂ����ق������芴���������̂��낤�B
�@ ���̖ؐ����[���̕��̓g���b�L���O�V���[�Y�̕���苷������A���E�̑������݂ɓ��ꊷ���Ȃ���i�ލہA�������点�Ȃ��悤�ɍאS�̒��ӂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�E���̃��[���ɏ�������́A���������ɒ���ꂽ���C���[���[�v�̂قǂ悢�����̂��̂�I��Ōy���E��Œ͂݁A�o�����X�����Ȃ��狴��ɓ��ݏo�����B���̐^�������ɐi�ނɂ�A�v���Ԃ�̓n���҂̎p�Ɋ��삷�邩�̂��Ƃ����S�̂��y���a�i�����j�݂����Ăď㉺�����͂��߂��B�܂���̗z���𗁂тĐX�ƋP���ቺ�͂邩�ȎO�ʐ�k���́A�u���ł�������ɂ����ł����ŁI�v�ƁA�Â����t�ŗU�������Ă���B�������A�����ɂ���������̃X�����������݂苴�n��̑�햡�ł���B���K�L�̍��A�c�ɂ̐�ɂ�����ꖇ�̋��̐^���ɗ����ċ����v����U�������A��ɗ����Ȃ��悤�ɐg�̂��Ƌ��U���Ȃ���o�����X���Ƃ��ėV�L���Ȃǂ��A��u�]�����S���Ă����B
�@ �����ێ炪�s���Ă��Ȃ������ŁA���[���[�̂Ƃ���ǂ��낪�����Ă����B�������ɂ���ȂƂ���ł͍אS�̒��ӂ��đ������m���߂͂������A�n��Ȃ��Ƃ����قǂ̂��Ƃł͂Ȃ������̂ŔؗE���ӂ���Đ�ւƐi�B����̃��[����n���Ă��Ă��邤����̂`����ɐ܁X�����������̒����t�߂ɐ�ɓ��B���A�����ő����~�߂Č����U��Ԃ�ƁA�ޏ��͂���ȂɂЂ�ޗl�q���Ȃ��A�ނ���n���̃X�������y���ނ悤�ȑ����ň�����������ւƋ߂Â��Ă��Ă���B���݂̏����Ȃ�ƂĂ������͂����Ȃ��B�ނ��A�ޏ��̋C�����킫�܂��Ă��鎄�́A���������菕���Ȃǂ��Ȃ������B����ɂ��Ă��A�����������̃`���[�~���O�ł��Ȃ₩�Ȏp�Ԃ̂ǂ��ɂ���Ȍ����������ɋ߂��s���͂���߂��Ă���̂��낤�B�ޏ��ɂ͏����Ƃ��Ă̂��܂₩�Ȉ�ʂ��l��{���Ȃ���Ă��邱�Ƃ��m���Ă��邾���ɁA���S���͕s�v�c�Ȋ������o���Ȃ��炻�̎p�ɂ���������L�l�������B
�@ �݂苴�̐^���t�߂ɗ����Ċቺ�Ɍ����낷�O�ʐ�̗���́A�ǂ��܂ł������݂����Đ��炩���̂��̂������B�قǂȂ����̋�����Ƃ���т��Β��ɐ��v����Ȃ�ĂƂĂ��M�����Ȃ����Ƃł���B����ȍ\���݂̒苴�͂��Ԃ��̂ǂ���T���Ă�����������Ȃ����낤�B�Ȃ�ł��Ȃ��p���Ɍ����͂��邪�A���̋����̂����h�Ȗ����������ł͂Ȃ����B�����v���ƁA�Ȃ�Ƃ�����̂Ȃ������݂����̉��ɍ��ݏグ�Ă����B
�u����Ȃ��Ƃ���Ă�Ƃ���N���Ɍ���������A�댯�����ē{�����ł��傤�˂��v
�u���Ԃ�ˁc�c�ł��A�������̋������ɂ���l�ȂN�����Ȃ���Ȃ��v
�@ ��X�͋���ł���ȉ�b�����킵�Ȃ���A��������Ί݂ւƒ݂苴��n������B�Ί݂̋��̂����Ƃ���́A�����قƂ�Ǘ��p����҂����Ȃ��Ȃ����̂Ȃ���ׂ̍��}�ȎR�����X�̑傫�ȎR�̎Ζʂ�D���ď���ւƂ̂тĂ���B���̂����������ɂׂ͍������O�ʐ�k�J�{���Ɍ������ė��ꗎ���鏬���ȑꂪ�����āA�u�₩�Ȑ����Ԃ��Ɛ��������ĂĂ����B
�@ ������x����n���Ė߂�r���ł�������������ʐ^���B���Ă������Ƃ������ƂɂȂ�A��������Ԃɖ߂��Ă���`����̃J�����������Ă܂����̂Ȃ��قǂɗ������B���Ƃ��Ɠ�l�Ƃ��`�������W���_���l��{�������������Ƃ����邪�A����ɂ��Ă�����Ƃ͂����낵�����̂ŁA�������̐U���̃��Y�������݃o�����X�̎����̃R�c�����ڂ��Ă��܂��ƁA�������Ȃ�̑����ňړ����Ă����C�ł���B�傫�����r���J���ē�{�̃��[���ɍ��E���ꂼ��̑���������A����ŃJ�������\���Ă��ǂ��Ƃ������Ƃ͂Ȃ��Ȃ����B��ʑ̂̂`����̂ق�������ł̐g�̂��Ȃ��̌ċz����������̓����������������B
�u����Ȏʐ^�A�e�ɂ͐�Ό������܂���˂��c�c�v
�@ ����������ۂ����݂Ȃ��炻���ꂭ�ޏ��̐����Ȃ���A���[��A���l��{�[�C�t�����h���������đ��|�����Ⴄ��Ȃ����Ȃ��A����ɁA����ȗE�҉ʊ��Ȉ�ʂ�ڂɂ�������݂̒j���Ƃ��育�݂����Ⴄ��������Ȃ��ȂȂǂƁA���Ώ�k�܂���ōl������������B�����A���画�f���āA���Ԃ݂̒苴��n�����͉̂�X���Ōゾ�����͂��ł���B���̈Ӗ����炷��ƁA�u�O�ʐ�݂苴�Ō�̓n���ҁv�ƂȂ����ޏ��̑�_�ȐU�镑���́A�\���L�O�ɒl������̂������ƌ����邩������Ȃ��B
�@�@�@�@�@�@�@���X�̌Ö̉^���́H��
�@ �Ԃɖ߂�����X�́A����ɏ㗬�����ɂނ����đ���A�X�X�L�̕�ɕ���ꂽ�ׂ��������l�߂������B�����ĎԎ~�߂̂��邻�̍ŏI�n�_�ʼn��Ԃ���ƁA�ȒP�ȗp�������ꂽ�y�U�b�N�����ɂ��Ă���ɉ��ւƕ����������B���͂����ɍׂ��R�H�ɕς��A�قǂȂ���ʂ��X�X�L�̌��ɂȂ��Ă���ꏊ�ɂł��B�����炭�͍̂k��n�������̂��낤�B�X�X�L�̌��̌��������ɖڂ����ƁA�����ȌI�т��L�����Ă���B���Α��̎R�̎Ζʂ��M�n�ɂ���������̌I�̑�������Ă���̂��ڂɂƂ܂����B�悭����ƁA���n�ɂ͂܂�������Ƒ������������A�I�������ɂȂ��Ă���B�R�I�̈��Ŏ��͏����������̎�̌I�͖����悢�B���O�ʂ̏W���ɐl���Z�܂Ȃ��Ȃ������܂ł́A�I���̂�ɂ���Ă���l�����Ȃ��̂��낤�B
�@ �����ɓ��̂����e�ɗ����Ă����܂����C�K���炯�̌I���E���ĊO���̊k�𗼑��Œׂ�����A���̎������Ŋ��݊����Ĕ������g�̂܂܂�����ƁA�Â��ĂȂ��Ȃ��������������B�R�I�͂��̂܂܂ł����\�������̂��B���ł�����A�������̑傫�ȌI�т̂Ƃ���܂ōs���Ă݂悤�Ƃ������ƂɂȂ�A�R����͂ߎ��Q�̊�����ɂ��ăX�X�L�̌��ɕ����������B�����A���������X�X�L�͔w����͂邩�ɒ����A�l�X�Ȗ����������Ȃ��M�͎v���̂ق��ɐ[���Đi�ނ̂͗e�ՂłȂ��������A���Ƃ��猒�C�ɂ��Ă���`������y�ł͂Ȃ��l�q�������B
�@ ���ŃX�X�L��h�̂��閠���ނ�蕥���g�̒��w偂̑����炯�ɂȂ�Ȃ炪�A����ł��Ȃ�Ƃ��I�т̈�Ԏ�O�̂Ƃ���܂ł͂��ǂ�����B���X�Ǝ}���L����I�̑�����グ�Ă݂�ƁA�ӂ�Ɏ������Ă͂�����̂̐��n����܂łɂ͂����������Ԃ������肻���ł���B����ɁA���܂ł͎����̈�т��[���M�n�ɕς���Ă��܂��Ă��邩��A���Ƃ����n���ɂȂ����Ƃ��Ă��A�������I���E���̂͗e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ��������B�����炭���O�ʏW���̐l�X�������ނ��Ă���́A�H�ɂȂ�Ɩ����̎������邱�̌����ȌI�т����̂Ă��A���̂悤�ɍr�ꂽ��ԂɂȂ����̂��낤�B�������A���̑傫�ȌI�т��قǂȂ�����ɒ���ł����B
�@ ����ȏ�I�т̒��ւƕ��������Ă��d�����Ȃ��Ɣ��f������X�́A�Ă��M��~�������ĎR���ւƖ߂�A����Ɍk�J�̉��ւƌ������Ă��邫�������B���炭����ƁA����̎R������N���o�����w�Ȑ��̗���鏬���ȑ�ɂł��B���̉��O�ʂ̒J�ɂ͐����̂قƂ��邱�̂悤�ȏ��������U�݂��Ă���B������̂܂܈���ł������x���Ȃ��B�����������͎����łɌ��ɐ����܂�ł��̖����m���߁A���ꂩ�炢�����ɂ����������ƈ��ݍ��B
�@ ���̂�����̑�ɂ͐������D�ޏ��^�̐Ԋ^���������Ă���B���̊^�͋ؗ͂����Q�ő̌^�����^�ōאg������A���̓����͎��ɑf�����B�l���߂Â��ƖڂŒǂ�������̂�������炢�̑����œ����o���A��߂Ȍ����A�ɐg���B���Ă��܂��B���܂���ŕ߂܂��Ă��A�܂�ŃE�i�M���h�W���E�̂悤�ɂ����Ɣ����o���A�����Ƃ����܂Ɏp�������Ă��܂��̂��B���̐Ԋ^���A�܂�Ő�����s���钴���^���P�b�g�̂悤�Ȑ����Ŏ��̊�O���悱�����Ă������B
�@ ���̑������Ƃ����ɓV�R�̋��̐�����[���т̂Ȃ��ɓ������B���������͓������}�ɋ��܂�A�l�ЂƂ肪����ƒʂ��悤�Ȗ{�i�I�ȓo�R���ƂȂ����B���̓��͎O�ʐ�̂܂������Ɖ��ɂ���ԑ���o�āA�����R�n��ł̈�p���Ȃ��ȓ��x���ʂւƒʂ��Ă���B����͓o�R���ړI�ł͂Ȃ����A����Ȃ�Ɏ��ԓI�Ȑ��������������A�l�A�\���قlj��܂ŕ����Ă�����������Ԃ����肾�����B
�@ ���̎R���́A�O�\���[�g���͂��낤���Ƃ�������u�i�A�g�`�A�z�E�A�i���Ȃǂ̑���T���Ɩ�X�̎Ζʂ�D���悤�ɂ��ĒJ���ւƂ̂тĂ���B�E��̎Ζʂ͋}�p�x�ŎO�ʐ�ւƗ�������ł��邪�A���̎Ζʈ�тɐ����Ă���̂���������ʃu�i��g�`�A�z�E�A�i���Ȃǂ̋�����ŁA�܂�ł��ꂼ��̖X�����S�N�Ԃ����̒n�ɍ��萶���Ȃ��炦�Ă����ւ�����炩��搂������Ă��邩�̂悤�ł������B�ǂ̂�����܂ł����v���C�����͒肩�ł͂Ȃ��������A�_���������ɂȂ�����̋��،Q�̂����J�ɋ߂��Ƃ���ɂ�����̂͊F���v���Ă��܂��͂��ł���B
�@ ��X�͎��ܗ����~�܂��Ă̓u�i��g�`�̑�̎}����͂邩�ɒ��ߏグ�A����ɂ͂��̑������⍪����ŕ��ł���@�����肵�Ȃ���A�����ɂ��Ă������Y�قȂ��̐X�̒��V�����Ƃ̐S�̑Θb���y���B�����A�Ō�ɁA��j����ȗ��A�₦�邱�ƂȂ��������̐l�Ԃ����ɖ��̐����b��ł��������X�̎傽���ɐ����̊�@�������Ă��邱�Ƃ�`���A���ʂ�̌��t�������Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ́A�Ȃ�Ƃ��E�тȂ�������ł������B
�@�@�@�@�@�@�@�������̎O�ʐ�k�J��
�@ ���Ƃ��Ƃ��̂���͂Ȃ������̂����A���炭�R����i��ł��邤���ɋ}�Ɏv����������X�́A��r�I�X�̊ɂ₩�ȎΖʂ�I��ŋ��̖�������т̒���D������A�O�ʐ�k�J�̉͌��ւƍ~��Ă݂邱�Ƃɂ����B�}�����M�����������ĎR�����獂�x���ɂ��ď��Ȃ��Ƃ��܁A�Z�\���[�g���͉����������낤���A��O�ɓ˔@�Ƃ��ĐX�ƋP���h���O�ʐ�̐��ʂ����ꂽ�B�܂�ʼn������ɗU����悤���ĒJ��ւƍ~��Ă����̂����A�����ʼn�X��҂��Ă����̂͐M�����Ȃ��悤�Ȕ��������i�������B
�@ �Ί݂͂����藧�悤�Ȑ�ǂɂȂ��Ă���A���̏㕔�͈�ʐ[�����тɕ����Ă������A��X�̍~�藧�������ɂ͑召�����̋ʐƔ����┧�̊�Ղ���Ȃ邿����Ƃ����͌����������B�����Ă��̉͌��Ɋ��Y���悤�ɂ��ĎO�ʐ삪����Ă����B�������̐앝�͓�A�O�\���[�g���قǂ��낤���A��ꂪ��ʃL���L���Ƌ┒�F�ɋP���Ă���B�����F�̌�������ėh�ꓮ�������Ȑ��̗�����Ȃ�ƌ`�e������悢�̂��낤�B�O�ʐ�̐��̐��炩���͐̂���L���ł͂��������A����ɂ��Ă����̐��̐F�͋����ɒl����B���͂��炽�߂Ă��̔������Ɋ�������������Ȃ������B���̉Ă̏I���Ɏ��͐����Œm����l���\�쌹�����K�˕��������A�����Ă��̎O�ʐ쌹����̌���ꂽ��т����Ɣ�r����Ȃ�A������̂ق����ォ������Ȃ��B
�@ ��̔����炱������͐ɂȂ��Ă��邪�A�Ίݑ��̑啔���͂��Ȃ�[�����ɂȂ��Ă���B��������ł��A�R�̒����̂��������ɂ͐Ƃ��낪����悤�������B�㗬�̂ق������n���ƁA������͐�S�̂����n���ʍ����̐ɂȂ��Ă���悤�ŁA���̋C�ɂȂ�Ε����đk�s�ł��銴���������B�����̂ق��ɂ͐�������Ƃ���}���ɂȂ��Ă���Ƃ��낪�����āA�����̂Ƃ��낾���͂����g���N����A��ʑS�̂������F�ɖA�����Č�����B�J�Ԃ̏��̉_����Đ̂����A��������̗z�����W�X�ƍ~�蒍���n�߂�ƁA����鐅�̋P���͂����������z�I�Ƃ��������悤�̂Ȃ��ʂ�ɕς���Ă������B
�@ ��X�̓W�[���Y�̐��������������A�����ɂȂ��Đ�̒��ɓ����Ă݂��B�������ɐ��͗₽���A���炭�Z�����Ă���Ƒ��悪���т�Ă��銴���������B�����A�s�v�c�Ȃ��̂ŁA���x�������ɏo���肵�Ă��邤���ɐg�̂������Ɋ���Ă��āA����Ȃɗ₽�����o���Ȃ��Ȃ����B�`���A�����������Ă���悩�����ƌ����o�����̂͂��̎��ł���B�c�����ɐ�ʼnj���ň�����Ƃ����ޏ��ɂ���A����Ȑ��ݐ������ڂɂ���Ƒ̓��̌��������̂��낤�B��C�̓��炿�̂䂦�ɁA�Y��ȊC��������ǂ��ł��낤�Ɖj�������Ȃ�Ȃ̂��鎄�ɂ́A���̋C�����͂悭�킩�����B
�@ �����A�������������Ȃ����̉͌��ɍ~�藧�����̂͋��R�̐���s���������킯�����A������l�̂Ƃ��Ȃ�Ƃ������A�Ⴂ�������ē����Ă���Œ��ɎO�ʐ�ʼnj�����ȂǂƂ͂������ɍl���Ă��݂Ȃ������B������A�Ԃɂ͏�����Ă��鐅�j�p���c�������ዾ�����Q���Ă͂��Ȃ������B����ŘI�V���C�Ȃǂɂ͂���Ƃ��̂��߂ɔޏ��������͎��Q���Ă����炵���̂����A�ނ��Ԓ��Ɏc���Ă����܂܂ł���Ƃ����B
�@ �`����͂��炭�Ȃ�ŎO�ʐ�̐�ʂ������ƌ��߂Ă����B���ꂩ��A�u���̗z�˂͂܂��Ȃ邱�Ƃ͂Ȃ��ł���ˁH�v�Ɛq�˂����Ă����B���̌��t�̈Ӗ������܂�[���l���Ȃ��������́A�u���̓V�C����������v�Ȃ�Ȃ����ȁv�Ɛ����ȕԎ��������B����ƁA���������ƂɁA���̏u�ԁA�u����A���̂܂܁A��ɂ͂���܂��B������Ƃ͂����Ȃ���������܂��A�ڂ��Ԃ��Ă��������v�ƌ����c�����ޏ��́A���𒅂��܂܃U�u�U�u�Ɛ�̒��ւƕ����o�����̂ł������B
�@ �~�߂�ɂ���������A���C�ɂƂ��鎄�ɔw���������Ȃ���A�ޏ��͏��X�ɐ����ւƐg�߂Ă����B�l�H���̂����炳���Ȃ��͌��A�������P�������A�k�J����芪���[���X�A����C�Ɩ��邢���z�A�����ĕ��𒅂��܂ܐ�̐[�݂ւƕ����Ă�����p�̎Ⴂ�����A����͂����f��̔����������V�[�����̂��́A���₻��ȏ�̌��i�ł������B�O�ʐ�̒J���ɐ��ސ��삪�ɕʂ̏�����߂ĉ��o������т̃h���}�������ƌ������ق����悩������������Ȃ��B������s���I�ȏ����ł���Ƃ͂����Ă��A�ޏ�������قǂ܂łɂ��̐�ɖ������ꂽ�̂́A�قǂȂ����݂䂭���̒J���Ō�Ɍ����邱�̂����Ȃ��ؗ�ȑ����̂䂦�������̂��낤�B
�@ ���ɂ͎�܂Ő[�X�Ɛ����ɐg�߂��ޏ��͗₽���ƌ����Đg��k�킹�Ȃ��炢������͌��ɂ������Ă����B���̎p�͂Ȃ�Ƃ����Ƃ������A��������ƕ������߂ăL�X�̂ЂƂ����Ă�肽���C���ł͂��������A�����͂�������a�m�i�H�j�̒[���ꂭ�炢�̎����S�͎������킹�Ă���䂦�ɁA�����Ɨ������͂��炩���ČȂ̊����}���A���Ɏ��ׂ��s�����l�����B���̋@�������A���v���邱�̕t�߂̒J�ł͉j�����Ƃ͕s�\���B�������Ƃ���A���̍ہA��������ꏏ�ɂ��̏�ʼnj���ł݂�̂��x�X�g���낤�B�ޏ��Ɠ��l�ɒ��߂̂܂܂łƌ��f�����������A�K���Ƃ����ׂ����A���̂Ƃ����͂��܂��܌���̃g�����N�X���͂��Ă������Ƃ��v���o�����B
�@ �����Ƃ킩������g�����N�X�ꖇ�ɂȂ��ĉj���ɂ�����B�W�[���Y�ƃV���c���������ܒE���̂Ă����́A���̂܂܂����ɐ����ɓ������B�m���ɗ₽���B�������A�ӂ������Đ[�����̂ق��ւƉj���o���A���\��������������đΊݑ��ɓn��ƁA�������̗₽���͊����Ȃ��Ȃ����B����ɂ��Ă��ق�Ƃ����Y��Ȑ��ł���B
�@ ���̗l�q���͌��̑����猩�Ă����`����́A�Ƃ����I��ł�����Ɍ������ĉj���o�����B�Ƃ��낪�A�ĊO���ꂪ���������ɁA�㉺�ߕ��𒅂��܂܂Ƃ��Ă��邩�琅�̒�R�����Ȃ�傫���B������v���悤�ɂ͐g�̂������A�[�݂̂ق��ւƗ����ꂩ�����B����Ǝv���Ĕ�э��݂��������A�����ɉj���ł���ޏ��̊�𗎒����Č����ƁA���̗����̂Ƃ���܂ł͂Ȃ�Ƃ����ǂ�������ł���B�����Őg�̂�������Ȃ��悤�ɑ����đ傫������̂��A���Ԃ����ċ߂Â��Ă���ޏ��̎������v����������グ���B������Ƃ����������������������A�K�����̐g�ɕς��͂Ȃ��悤�������B
�@ ��������͌��ɖ߂������ƁA���x�͏����㗬�̂ق��ւƗ���̒[�ɉ����Ă̂ڂ��Ă݂��B���̈�т͐�S�̂��G�قǂ̐[���̍L���ɂȂ��Ă���A����͈�ʂ����߂ׂ̍����^�����ȍ��n�ŁA�����ɓ`��銴�G�̐S�n�悢���Ƃ͂��̂����Ȃ������B���ܑz���Ԃ��Ă݂Ă��A����͌��̂悤�ȏo�����Ƃ��������l���Ȃ��B���炭�����ŗV���ƁA���̂ق��͗���ɏ���Đ[�������������ɉj������A���Ƃ̉͌��߂��ł`���߂��Ă���̂�҂����B�ޏ��̂ق��͏㗬�̐Ƃ���ł����j�����y����ł���l�q�������B
�@ �z���𗁂тȂ���g�̂��������Ă���ƁA�ˑR�A�w���╠���A���ڂȂǂɒ��y�����o������͂��߂��B�����낤�Ǝv���Ă悭���Ă݂�ƁA�Ȃ�Ƒ召�̈������C���畆�̂��������ɐH�炢���Ă���ł͂Ȃ����B�Q�ĂĐ��C��@�����Ƃ��Ă݂͂����A�����玟�ɐV��̈��ǂ�������Ă���B�@���ׂ��قǂɂ��̐���������̂́A�������Ȍ��̓����ɂ��ނ�̚k�o���s���������邩��Ȃ̂��낤�B�������Ď��͈��ǂ��Ƃ̎v��ʐ킢����������H�ڂɂȂ��Ă��܂����B�l���Ă݂�ƁA�����R�n��т͈����������ƂŒm���Ă���B�Ƃ��ɏH�̂��̋G�߂ɓ����̌����ǂꂾ���z�����Ƃ��ł��邩�ɂ���ĔɐB�͂ɈႢ���ł邩��A���ǂ������ĕK���ł���B�܂��A ���R���L���Ȃ��Ƃ̏ł͂��邩���ނ����Ȃ����ƂȂ̂����A�������Ƃ���ɉa�H�ɂ��ꂽ�ق��͂܂������Ă��܂������̂ł͂Ȃ��B
�@ �����������邤���ɖ������肽�\��ł`���߂��Ă������A�Ȃ�Ɣޏ��̂ق��́A�G�ꂽ�ߕ��Őg�̂������Ă��邹�������̐���ȂǂقƂ�ǎĂ��Ȃ��炵���B�ޏ����������ꂽ�Ƃ���ɂ���傫�Ȋ�A�ɐg���B���A�������ƈߕ��̐��������V���c�𒅑ւ����肵�Ă���ԂɁA���̂ق�����}���ŔG�ꂽ�g�����N�X��E���A�W�[���Y�ƃV���c�𒅍��B����ň��R�c�̍U����h����Ǝv�����̂����A�Ȃ�ƁA���������o�������ǂ��̒��ɂ̓V���c�̏ォ��h�����̂܂Ō����n���������B
�@ ���ǂ��ɂ�����́A���炩�ȎO�ʐ���j���Ő������������Ƃɑ���R�̐_�̒��炵�߂ƍl���A���̒����ɊÂ邱�Ƃɂ������A���h����ɂ͑��������̎��̎��ł����̂����炭�g�̒��̂������������y�������B�����ɖ߂��Ă��炶������Ɛ����Ă݂���A�Ȃ�Ƃ܂��A���ɐH��ꂽ���Ƃ���\���J�����������B�h�_�̕����M�͂Ȃ�ʁu�j�^�̈��ЌM�́v�Ƃ������Ƃ���ł���B
�@ �`����̂͂��W�[���Y�͔G�ꂽ�܂܂��������A�ޏ��͂�����̐S�z���悻�ɕ��R�Ƃ��Ă����B�����Ƃ��A����ɐS�z��������Ƃ����ĒE���ŕ����킯�ɂ������Ȃ����낤����A�ޏ��̂ق����B�R�Ƃ��ĐU�镑�������Ȃ������킯�����A���̊��K���\�͂͂����������̂ł���B�����̎Ⴂ�����ɂ͒��������̎��R�ւ̑Ή��͂ɕԂ��Ԃ������͌h�ӂ�\�������Ȃ����B
�@ ��X�͍ĂђJ�̎Ζʂݕ����o���ĎR���ɖ߂�A���̂��Ɖ��x�������ȑ��n��Ȃ��炳��ɉ��܂œ�\���قǕ����^�B�����Đԑ�̂���O�ʐ�ʼn��̑�₻�̌��������ނ���R�X�̌�����Ƃ���܂ōs���A���̒n�_�ň����Ԃ����Ƃɂ����B�A�蓹�A���������̖̑т���F�ɋP���������ђ��������Ďw�����ƁA�`����ׂ͍��̖_���E���Ă��Ă��̐�Ŗђ����y���˂��Ȃ��炻�̗l�q�������[�����Ɋώ@���Ă����B�������������^�̉�A�V���W���T�����N�X�T���̗c����������Ȃ��Ǝv�������A���܂ЂƂ��̐��̂͂͂���Ƃ͕�����Ȃ������B
�@ �����Ԃɖ߂蒅���ƁA�`����͂������Ƌ߂��̗т̉��ւƈ�l�p�������A�f�����G�ꂽ�W�[���Y��Z�p���ɂ͂������čĂю��̑O�Ɍ��ꂽ�B���c�ɂ����͂��邪�A���Ƃ͉��O�ʂ̒J�ɍŌ�̕ʂ�������A��H�����ւƌ������݂̂ł���B����s�̍x�O�ɂ��鐣�g����ɗ�����Ĉꕗ�C���тĂ���V���ɏo�āA�։z���o�R�Ŗ�x�������ɖ߂�����Ƃɂ����B
�@ �O�ʐ�k�J�̐������A�������͌���T���E�i���I�A���v����u�i��g�`�̑������T���E�i���I�A�i���т�A�I�т�T���E�i���I�A�X�������_�݂̒苴��T���E�i���I�A�����~�ꕶ��ՌQ��T���E�i���I�A�����ĉ��O�ʂ̑傫�ȒJ��T���E�i���I�c�c�܂�����܂łƌ����������A���ܑ����Ă��邱�̓��H���͂��߉����������F�Β�ɒ���ł��܂��Ƃ����ẮA���͂₻������Ȃ��܂��B�����A�X���J�n�܂ł��Ƃ킸�������Ȃ��Ƃ������̓��ɁA�����₩�Ȃ�Ƃ����ʂ�̌��t��`���ɂ��邱�Ƃ��ł������Ƃ����͂��߂Ă��̋~���ł�������������Ȃ��B
�@ �Ȃ�Ƃ�����̂Ȃ��v�������̓��Ŋ��ݒ��߂Ȃ���A��X�͗������Ɠ��������t�ɂ��ǂ艜�O�ʂ̒J�����Ƃɂ����B���̓��ɂ͂����P������Ă��܂��Ă������A������܂ł��̃_���̍H������̋߂��ɂ́A�u���炩�ȎO�ʐ�A���̂ʼn����ȃ_�����ԁv�Ƒ发�����傫�ȉ��f���������Ă����B�N���l���o�����W��Ȃ̂��킩��Ȃ��������A���͂��̎��R�]���̗����ɐ��ޖ��_�o���ɕ���ʂĕԂ����t���Ȃ��v���������B���O�ʂ��璩���X�[�p�[�ѓ����ʂւƔ�����V�݂̃g���l���𑖂�Ȃ���A�Ȃ������܈�x���̒����ȕW��̂��Ƃ�z���o�����B���Ԃ�A�����O�\�N���̉䂪���̑�K�͌������Ƃƌ��ݍs���̎��Ԃ�����قǂɏے����Ă��錾�t�͂Ȃ��Ɗ��������炾�낤�B
�@ �X�����I����ĉ��O�ʃ_���ւ̌�ʋK������������A�Ăт��̒n��K��邱�Ƃ��ł��邾�낤���ɂ́A��X�����̓��ɖڂɂ������̂̂قƂ�ǂ͐���[���ɒ���ł���B���̎��ɂ́A���O�ʃ_�������ł����������J�X�́A�����Ă���ɂ͊|���ւ��̂Ȃ����������̕�W�ƍl���A�Â��ɋF��������悤�Ǝv���B�܂��A���̂��Ƃ�ʂ��āA�Ƃ�����ΖY�ꂪ���ȌȂ̘������Ȃ��A ������܂߂��l�Ԃ̔ڏ������ĔF������悤�ɐS���������ƍl����B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N10��11��
���˓����Ȃ݊C��
�@ �������{�̂�����A�����������Ǝ�ނ̂��߈��Q���L�����ւƌ������r��ɂ�������X�́A�R�z�����R�p�[�L���O�G���A�ŎԒ����������ƁA�����s�X�̏�����O�Ő����ˎ����Ԃɓ������B��X�Ƃ͂����Ă����̂ق��ɂ͓��s�̎O���m�����邾������������A�������ċC�܂܂ȃ}�C�y�[�X�̗��ł͂������B
�@ �O���m����͓����炿���������ɕς�����L�����A���������Ȑl���ŁA�A���R�[���̂ق����ꖳ���ɋ����B�Ⴂ���A�I�y���[�V�����E���T�[�`�̐��ƂƂ��ē��{�J����s�̌�������ɋΖ��A�L�\�Ȏd���Ԃ�ŏ��������]����邪�A���鎞���ɓˑR����E���ĉƑ����X���R�̖L���ȉ��ꐼ�\���ɓn���Ă��܂��B���{�J����s����̐e���������ɂ͒|���������c����w�����Ȃǂ������B���\���ł͂�������n���̐l�X�̒��ɗn�����݁A���t�ƃ_�C�r���O�E�C���X�g���N�^�[����邩�����A�����₩�Ȗ��h�Ȃǂ��J���Ă����B�Ƃ��낪�d���̂��߂ɍw�����Ă܂��Ȃ����[�^�[�{�[�g�Ɍ��ׂ�����A���������ƂȂ��ė��̊C�ő���A�{�[�g���C���ɖv�����鐡�O�Ɏ��q���̃w���R�v�^�[�ɋ~�o����Ƃ������ԂɂȂ����B
�@ ���炭���āA�{�[�g�̔̔��ӔC���ł������������쏊�ɕ⏞���̌��̂��ߏ㋞���邪�A���̍ۂɎO������̈ٔ\�������]�������������쏊�{�Ђ���̍����������āA���ǁA���Ђ̊C�m�W�̋Z�p�����J������ɋΖ�����悤�ɂȂ����B���������ƁA���v�������[�^�[�{�[�g�̕⏞��������ނ�ɂ��������ɎO��������ۂߍ���ŏ������쏊�ɃX�J�E�g���Ă��܂������{�l�̌��c�I�F����͋����̎��̒m�l�ŁA�����������쏊 �{�Ђ̗v�E�ɂ������B�F�{���V���n���o�g�̂��̌��c����͑�ςȐ�҂̐a�m�ł��邪�A���ܒi�Ƃ��������ƂŁA����܂����������Ȑl���ł���B
�@ �O������͏������쏊�ŗl�X�ȃv���W�F�N�g�𐬌������ċƐт����������ƁA��N���Ђ�ނ��A���݂͓����_��̐��Y�w�W�̋����ƗⓀ�Z�p�W�̋���������i�߂Ȃ��瓯��̑�w�@�Ŋw���̎w��������������Ă���B���݈��Q���L�����Ōv�撆�̒����������ƂɎl�������������ƃ^�C�A�b�v���Ă��̎O�������͒��̂��߁A�n��ɏM�ƍL�����ւ̈ē������Ă�������悤�Ȃ킯�������B�O������͐̂���A�d���ŏo��������d�v�ȃ|�X�g�ɂ���l���Ɖ�����肷�鎞�ł��A���Ȃ肭���тꂽ�W�[���Y�ɃV���c�Ƃ��������܂�̎p�Œʂ��Ă���B���̓_�ł����Ƃ͂����ւ�ɃE�}�������킯���B���̓����O������͔���������ł܂Ƃ߂Č��킦�A���̂قꂽ�W�[���Y�̒Z�p���ɉ��Ȃ̃|���V���c�Ƃ����C�����b�N�ɋ߂��o�ŗ����������B
�@ �{�y�ƌ����Ƃ��Ȃ������勴�n�����̂͌ߑO���������������A���肩��̐��V�Ƃ����āA�Ӊē��L�̋���ȗz�˂��ԑ��z���ɍ�������ł����B���E�����܂킷�ƁA�召�̓��X�╡�G�Ȃ��������������]�A����ɂ͌��������̗��ꓮ�����˂Ȃǂ��ቺ�����ς��ɍL�����Ă���B�\�z�ɂ�����ʔ������i�ς��B�������u���˓����Ȃ݊C���v�̈��̂��������̂��Ƃ͂���B�����܂ł��Ȃ����A�����ˎ����ԓ��͖{�B�Ǝl���Ƃ��Ȃ��O�̎����ԓ��H�̈�ŁA�|�\�����̂����̌����A�����A�������A��O���A�������A�哇�̘Z�����X�e�b�v�E�X�g�[���ɂ��Ė{�B�̔����Ǝl���̍����Ƃ��Ȃ��ł���B
�@ �����ƈ����Ƃ̊Ԃɉ˂�����勴�ɂ��������鍠�ɂ́A���邢�Ă̑��z�̂��ƁA���˂̓��X�ƊC�X�̐D��Ȃ������͂܂��܂����Z�̓x��[�߂Ă������B�ӎ��I�ɎԂ̑��x�𗎂Ƃ��A�������ƈ����勴��n��I����ƁA��X�͂��������ˎ����ԓ�������Ĉ����s�X�ւ̓����Ƃ����B��������������A�����s�����������ɂ��鐅�R���K�ˁA���㐅�R�W�̎����ł����w���Ă������Ƃ������ƂɂȂ�������ł���B�ڎw�����R��͈������㎁�̕���@���������낷���R�̒����Ɍ����Ă����B���ԏ�ŎԂ��~�肽��X�̓^�C���X���b�v�����C���ł��̏��R�̎R���ڎw���ĕ���������
�@ ���W�I�̃j���[�X�ŋC�����O�\���x���Ă���̂͒m���Ă������A����Ȃɂ������������h�����˓����ɐg�����炷�̂͋v�X�̂��Ƃł���B�썑�̓��炿�̐g������A�̂Ȃ炽�Ƃ�����ȗz�˂̒��ł����R�̈���삯�o��Ȃ�ĂȂ�ł��Ȃ����Ƃ������̂����A��͂肱�̍ɂȂ�ƁA����ȃJ���J���Ƃ�̂��Ƃŋ}�s�ȎΖʂ�D���������������ɋ삯�o�邾���̋C�͂͂Ȃ��B�����A����ł���X�͋x�ނ��ƂȂ����R��̌����̏��R��o��߂��B
�@ ���݂̈����̐��R��͏��a�\���N�ɒz��Č�����A���㐅�R�W�̎����قƂȂ��Ă�����̂ŁA�����̂܂܂̂��̂ł͂Ȃ����A�̂͂��̂悤�Ȑ��R�邪�|�\�����̕��G�ȓ��]�␣�˂������낷�v���v���ɑ������݂��Ă����炵���B���܂ł͂��̐��R��̂��鏬�R���璼�ڂɌ�������т͂�������s�X�n�����i�݁A�C�ݐ��������Ԃ�Ɖ����ɑނ��Ă��܂��Ă��邪�A�����ɂ͂��������̒J�܂Ő[�����]���̂тĂ��Ă����炵���B
�@ ���˓��C�ɂ͐�ɋ߂��召�̓��X�����邪�A���̂����̎����߂����|�\�����ɑ����Ă���Ƃ����B�|�\�����Ƃ́A�L�����암���爤�Q���k���ɂ͂��܂ꂽ�C��ɂ����ē���g�n�`���Ȃ��Ė��W����Q���̂��Ƃł���B��������ƒn�}�߂Ă��炦�킩��̂����A�D������Ȍ`���������X���S�`���S�`���Ƒ��݂��Ă��āA��v�ȓ��̖��O�ƈʒu�������邾���ł��e�Ղł͂Ȃ��B���̌|�\�����̊Ԃ�D���悤�ɂ��đ��l�ɕ������ׂ����H�����˂��˂Ƒ����Ă���̂����A�����̐��H�����܂��ʂ��Ĉ�т𓌐������ɔ�����̂́A���m�ȊC�}��f�o�r�Ƌ��͂ȃG���W�������������̑D�ɂƂ��Ă��e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ����낤�B
�@ �����ł݂邩������ӂ̒��̓����������낵�����G�Ȃ悤������A�E�┿�ɗ��邵���Ȃ������̘̂a�D�ł��̊C����ɒʂ蔲���邱�Ƃ́A��т̒n���⒪���̕ω��ɂ��Ƃ��҂ɂ͂���߂č�������ɈႢ�Ȃ��B�����Â���֖�C���A���h��A�ɗ\��A����ɂ͐��˓��A�d����A��g�ÂƂȂ������̊C���ʂ̎�v�H�𗘗p����ꍇ�A�ǂ����Ă��|�\�����Ɖ��O�����i���R���ƍ��쌧�ɂ͂��܂ꂽ�C��̓��X�j��ʉ߂��Ȃ���Ȃ炸�A�K�R�I�ɗ������C��͌�ʂ̓�ɂȂ�Ɠ����Ɍ�ʂ̗v���Ƃ��Ȃ����B���H�������ĕ��G�Œ����̕ω��̌������|�\������т̏ꍇ�͂Ƃ��ɂ����ł������B
�@ �����̓��X�ɏZ�݁A���ӊC��̐��H�⒪���̓����ɏڂ����C�l�������A�t�߂��q�s����D�������Ȃ�ɂ�A�����̑D�̐���ē���������x��������肷��悤�ɂȂ����͓̂��R�̂��Ƃł������B�|�\�����͍k�n�����Ȃ��A�܂��A�����̋��Ƃ͋Z�p�I�ɂ������B�œV���G�߂ɂ��傫�����E����邱�Ƃ�������������A���ł̐����͂����ւ�Ɍ��������̂ł������B���������āA�l������������ɂƂ��Ȃ��A�����̓��l�������A��т��q�s����D�̐���ē���x��߂邱�Ƃɂ���Čx�ŗ��i�x�엿�̂��Ɓj�Ə̂�����̒ʍs�ł����A���v�𗧂Ă悤�Ƃ����͎̂��R�̂Ȃ�䂫�������낤�B
�@ �x�ŏO�Ƃ��Ăꂽ�ނ炪�A����ł͂�����C���s�ׂɑ��������낤���Ƃ��z���ɓ�Ȃ��B�ꏊ���ꏊ�Ȃ����ɁA���D�p�ɂ����Ă��n���I�Ȓm���ɂ����Ă��ނ�̂ق����͂邩�ɒ����Ă����킯������A���Ƃ��C���s�ׂ��͂��炩�ꂽ�Ƃ��Ă���̂����悤���Ȃ������ɈႢ�Ȃ��B���Z��N���ɂ͎R�z��C�ɊC���O���p�ɂɏo�v�����Ƃ̋L�^������悤������A���Ȃ�̂���ꕔ�̊C�l�����͊C���s�ׂ��͂��炢�Ă����悤�ł���B
�@ �����̊C���͒P���I�Ŗ������������炵�����A����̈ڂ�ƂƂ��ɑ����̌x�ŏO���C���O�Ƃ��Ă̈�ʂ����悤�ɂȂ�ɂ�āA�ނ�͑g�D�I�ȏW�c���`�����A����ɂ����̏W�c�̌����̂��\�����Ă������B�₪�Ĕނ�͊C���v�q�H�ɗՂޓ��X�̗v���ɏ���\���A���̐��R�Ƃ��Ă̐��i�����悤�ɂȂ��Ă������̂ł���B�����āA�����Ɏ���ƍ��x�ɑg�D�����ꂽ�ނ�͗��n���̕������͂ƒ�g������h�R�����肷��悤�ɂȂ�A���͑��݂ɋٖ��ȘA�g�Ԑ����Ƃ�Ȃ��琣�˓��C��тɂ����ċ���Ȑ��͂��ւ�悤�ɂȂ����̂������B
�@ ���R�̊��Ƃ��ɖڗ��悤�ɂȂ����͓̂�k������ȍ~�̂悤�ŁA�������ォ��퍑����ɂ����Ă��̊����͍Ő������}����Ƃ���ƂȂ����B�Ƃ��Ɏ�����������퍑����ɂ����ẮA�ɗ\�O�Ƃ���l�����̊C���{���Ƃ��Ă����C���O���k���̌����������тɂ܂Ő��͂��g�債�|�\�����S����x�z����悤�ɂȂ����B�����Ĉɗ\�O�̂Ȃ��ł��ЂƂ���傫�Ȑ��͂��ւ�悤�ɂȂ����̂��A�\���E�����E�����̎O�������ꂼ��̖{���n�Ƃ��鑺�㎁�x�z���̊C���O�ł���B�u����v�Ƃ������ꐩ�𖼏�邻���O���̊C���O�̓��̂����͓���ӎ��������ĘA�ь��W���A�₪�đ��㐅�R�Ƃ��Đ��˓��C�����̑S�C��𐧈�����Ɏ������B
�@ �ї����A�Ɠ������Ƃ��e���𑈂��������̍���ɂ����Ėї����ɂ������㐅�R�́A�ї��R���܂���̖\���J�����ĊC��n�蓩�w�c���}�P����̂�������ƂƂ��ɁA���D�O�S�z��z���ē��R�̑ޘH���Ւf�A���R��r�ł���Ƃ������������ĂĈ��̗͂̂قǂ��L�����Ɏ����A���̑��݂��m�ł�����̂ɂ����B�S�����̑���O�Ƃ̐��R���x�z�C��ł������x�ŗ���ʍs�ł̑��z�͐����Z�Ŏl�\���Έȏ�ɂ��̂ڂ����Ƃ����B
�@ ���R�鎑���قɂ́A�刢���D�i��������������j�ƌĂꂽ���㐅�R�̑�\�I�ȌR�D�̖͌^���W������Ă����B���l�p�̑傫�Ȕ��̒����ɂ́u��v�̈ꎚ���ۂň͂������㐅�R�̖�͂��`�����߂��Ă���B���̖�͂����������Ők���オ�����D�l���������Ȃ��͂Ȃ������낤�B�D���͓�\�Z���[�g���A�D���チ�[�g���A���S�g���̑傫��������A���͔͂��Ƒ����̘E�ł������B���̑D���z�ɂ͏��m����\�`�l�\���A����i�����j�����\�`�S�O�\�����g��ł����悤�ł���B�܂��A�����Ƃ��Č��a�\�܃Z���`�̎�C�̂ق��ΐ��i����j�Ȃǂ����ڂ��Ă������B
�@ �����͌^�ɂ��ƁA�㕔�͓�w�̑���ɂȂ��Ă���A��w�̕����͂��̉����������˂Ă���b�̉����ɂ����āA�K�v�Ȃ�Η����ʂɊJ���̔˂𗧂ĂĊ��S�ɕ�����������邱�Ƃ̂ł���\���ɂȂ��Ă����B���̍\���ɂ���đ�Q�╗�J������邱�Ƃ��ł�������łȂ��A�퓬�̍ۂȂǂɓG�̋}�P��h�����Ƃ��ł����B�܂��t�ɁA���ʑS�̂�������܂ܓG�D�ɋ߂Â��Đڌ����A��Ăɑ��ʂ̔˂��J���ďP��������A����̑D�ɏ��ڂ��Ă�����̂��邱�Ƃ��\�������B���̈�w���ɏ��m�␅��̂قƂ�ǂ�����Ă���A�������ɂ͓�\�A�O�\�����̒����E�����Ă邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă����B�������A�E�̑�����̎p�͊O������͒��ڂɌ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ�����A�O�G�̖��S�C�ɂ��U��������g����邱�Ƃ��ł����ɈႢ�Ȃ��B
�@ ��w���̏���b�̒����ɂ͑傫�Ȕ��Ɣ����������Ă���A���̑O���ɂ͌��݂̑D�̃u���b�W�ɑ�������傫�Ȏl�p����̓�w�������݂����Ă���B�����Ă��̓�w���͂���ɓ�w�ɕ�����Ă����悤���B���̕����ɂ͐��R�̓��̂Ⓖ���̏㊯�������w���A�C���т��ɂ݂Ȃ��瑀�D���߂��͂��߂Ƃ���S�̓I�Ȏw�����Ƃ��Ă������̂Ǝv����B�����̘E���g���ꍇ�A�X�̑�����ɂ͒��ڑD�O�̏������Ȃ�����A���̓�w���̎w��������Ȃ�炩�̕��@�Ŗ��߂��`�B����A����ɉ����ĘE�𑆂��Ƃ��̗͂̉���������ȑ��E�̒����Ȃǂ��Ȃ���Ă������̂��낤�B
�@ �W�������̒��ɂ͑��㐅�R�̗p�����u��i�����R�W�v�Ƃ������@���ȂǂɊ�Â��D�c�̐w�`�z�u�}�Ȃǂ���������ꂽ�B�i�ߑD�ȉ��̑��D�Ɋe�X�̖�����\�킷�����ĂĎ��ʂł���悤���A�����̕�����傫�Ȃu���`�A���邢�͑召�̂u���`�������`�ɔz�Đw�`�������Ă���B�W������Ă���͕̂��@���ɂ���w�`�̂����ꕔ�ŁA���ɂ��l�X�Ȑw�`���������悤�ł���B�S�̌������ւ����ނ�́A���X�̐킢�̘A���̒��ŏ�ɐV������p��҂ݏo���悤�ɍH�v�̂������s���A������`�A���`�Ƃ��Č㐢�ɓ`���������B���@���̖`���ɂ́A�u�D�ɏ�鎖�͓V�̗����Ƃ��A�n�̗����l����ׂ��B�R�̎n�ނ�l�̘a���Ƃ��A��ɓV�n�̗����l����ׂ��v�Ƃ����S���Ȃǂ�������Ă���悤���B
�@ �C���O�Ƃ����Ε������͂�邢���A�C�Ƃ����n���I���_���ő���Ɋ��p���邱�Ƃɂ���āA������̐��R�O�́A���̎���̕������x�̘g����͂��ꂽ���R�l�̏W�c�Ƃ��Ă̈�ʂ������Ă����ƌ����Ă悢�B�ꕔ�̌��͎҂ɂ���Ĉ���I�Ȏ��D��L�������킳�ʋ����x�z���s���Ă�������ł��������Ƃ��v���ƁA�ނ炪�܁X�C���s�ׂƂ����@�s�ׂ�Ƃ����Ƃ͂����Ă��A����͎��̎x�z�҂����̗��ꂩ�猩���@�s�ׂł���A���R�����ɋꂵ�ޓ����̏����̖ڂ��炷��ƁA�K�������ے肳���ׂ��s�ׂł͂Ȃ������̂�������Ȃ��B
�@ �����ׂ����ƂɁA��l�O�N�̓S�C�`����ɂ��̏����������㐅�R�͐����������̌K���ƂɓS�C�삳���A�����͂₭�Ǝ��̓S�C�g��g�D����ƂƂ��ɁA�̂��̊����f�Ղɂ����Ă͐��������S�C�𒆍��ɂ܂ŗA�o���Ă����炵���B�P�Ɍx�ŗ���ʍs�ł��������łȂ��A���R�݂�������L���������n��⍑�O�Ƃ̌��Ղ��s���A���v�������Ă����̂ł���B
�@ �����قɓW������Ă���e���ނ̒��ɂ́A�u�����Ɩ�t���S�K�n�F��v�Ƃ������h�ȊZ���ꎮ��A����ȃz�^�e�L�̊L�k��������ɂ��炦������������́u�ق��ĊL���v�Ȃǂ��������B����������㐅�R�Ȃ�ł͂̎���w�i���Â���i�ŁA�Ȃ�Ƃ������[��������ł͂������B���R�����ق��o�����Ƃ͋��@������ɂ���������㐅�R���̖���揊�̌ÐΓ��̂܂��ɘȂ݁A�Ƃ肠�����ނ�̗�Ɍh�ӂ�\�����B
�@
�@ ���R������Ƃɂ�����X�͍Ăѐ����ˎ����ԓ��ɏオ��A��������ʂ��Đ������ւƓn�����B���̓��̐��˓c���ɂ͍k�O���ƕ��R��v�L�O�ق�����̂ŁA�������������炻����K�˂Ă݂悤�Ƃ������ƂɂȂ����B�����Ă�������͂����߂��܂ŎԂ𑖂点���B�������A�Ȃɂ�炽������̓y�Y����������A�˂Č������сA�t������L�����ԏ�ւ̌Ăэ��݂����\�������l�q�������̂ŁA�C�̎ア�i�H�j��X��l�͂��̕��͋C�ɉ����Č��ǂ��̂܂ܓ��n��ʉ߂��Ă��܂����B���R��v�攌�ɂ͐\����Ȃ��������A���������Â��Ȏ����ɂ��炽�߂ċL�O�ق�K�ˁA�������ƓW����i�Ȃǂ��ӏ܂������Ǝv�������ƂȂǂ����ق��T�������R�̈�������B�����ԓ����������ꑽ���̊ό����s�҂̓����Ɋ��҂���n���̐l�X�̋C�������A����Ȃ�̎�����\���ɂ킩��̂����A���߂Đ��˓��̓��X�̂��Ă��Ȑl��ƕ�����͑��Ȃ�Ȃ��悤�ɂ��Ăق����B�����Ƃ��A���̐ϋɐ����������㐅�R�ȗ��̓��̓`���I���_�����ƌ�����ΕԂ����t���Ȃ��̂����c�c�B
�@ ���������瑽�X���勴��n���đ�O���ɂ͂��鍠�ɂ͐��˓��̗z�˂͂܂��܂�����ɂȂ��Ă����B���˓����̂�����Ƃ���̋C���͗\�z�C���̎O�\���x���Ƃ����ɒ����Ă���͂��������B���̑�O���ɂ͑�R�_�i������܂Â݁j�_�ЂƂ����L���ȌÎЂ�����B���̗R������_�ЂɌ×���[����Ă����Z���Ȃǂ̕���ނ͍����d�v�������̎w��������Ă�����̂��قƂ�ǂŁA�����Ă��̓��{�j�̋��ȏ��⎑���W�Ȃǂɂ͂����̎ʐ^���f�ڂ���Ă���B�ړI�n�܂ł܂����Ȃ�̋���������̂ł����������Ԃ͂Ƃꂻ���ɂȂ��������A���ł������R�_�_�Ђɂ����͎Q�q���čs�����Ƃ������ƂɂȂ����B�ނ��A�����M�S�̂䂦�ɂƂ����̂ł͂Ȃ��A�ЂƂ��ɕ��������̂䂦�ł���B
�@ �����ԓ�������Ă����O���̐��C�݂ɂ���{�Y�Ƃ����W�����ʂɌ������ē�A�O�\���قǑ���ƁA��R�_�_�Ћ߂��̂������L�����c���ԏ�ɒ������B�悭�������ꂽ�L��Ȓ��ԏ�Ȃ̂����A�Ȃ������ɃK�����Ƃ��Ă��ĎԂ̉e�͂قƂ�nj�������Ȃ��B�����̏I���Ƃ��������̂������������̂��낤���A������������ό��q�̑�����������ʼnߏ萮���������ʂ������̂�������Ȃ��B����Ȃ��Ƃ��l���Ȃ���Ԃ���~���ƁA�r�[�ɖҗ�ȔM�C���P���Ă����B
�@ �W�X�ƍ~�蒍���z���ɂ����ῂ�����ɏƂ炵�o����Ă������A�悭�����̍s���͂�����R�_�_�Ђ̍L�������͈ӊO�ȂقǂɐÂ��������B�������i���̂���_�Ђ��������ċ����S�̂ɗ����������͋C���Y���Ă���B�q�a�O�̓���ւƒʂ���_��̎�O�ɂ͓V�R�L�O���̑�킪�������B�ǂ����c�I�N���ɂ����������̂炵�����Z�S�N�Ƃ�������̐������z�ʒʂ�ɐM�p����C�ɂ͂Ȃ�Ȃ��������A����͂Ƃ������A����Ȍ����ȓ��ڂɂ���̂͋v���Ԃ�ł���B�������̓�̑�̂܂��ő����~�߂����ƁA��X�͐_��������蔲���A���̂ق��ɂ���q�a�̂ق��ւƕ����^�B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N10��18��
��O�����爤�Q���L������
�@ ����R�_�_�Ђƕ�������
�@ ��R�_�_�Ђ̔q�a�Ƃ��̉��ɂ���{�a�́A�������ɗ��j�̏d�݂�����������s��ȑ���ɂȂ��Ă����B���͞w�畘���A�����̊O�����O�h��̖{�a�͎O�ԎЗ�����ƌĂ��\���ɂȂ��Ă��āA���̎�̑�������_�Ђ̑�\�i�Ƃ����Ă悢�B���Ƃ��Ƃ̎Гa�͌�����N�i��O���N�j�ɕ��ɂ������ďĎ����A�V���l�N�i��O�����N�j����S�N�قǂ����ď��X�ɍČ����ꂽ�̂����݂̎Гa�ł���Ƃ����B�Ր_�͑�R�ρi�_�j��_����Ƃ������ēV�Ƒ�_�̌Z�_�ɂ�����̂����������A���̂ւ�̂�₱�����b�ɂȂ�ƁA��X�́u�͂������ł������܂����v�Ƒ��l���̂悤�əꂫ�Ȃ��甼�Ύv�l��~��ԂɊׂ邵���Ȃ��B
�@ �M�S�����g�ɂ�������炸�ꉞ�q�a�O�ŕ\�h�̗�����܂������ƁA����̍���̖��ʂ��Đ_�Ж{�a�̗����ɂ܂���Ă݂��B���{�������搂�����ɂ͗��h�Ȓ���̐X������̂��낤�Ǝv��������ł���B�\�z�ɂ����킸�_�Ђ̗���ɂ͌����Ȓ���̐X���L�����Ă����B�V��˂������̓�̑�������������сA�������傾�ƌ�������Ɍ݂��ɂ��̑��݂������֎��������Ă���B�܂��A�����̎��Ԃ͊e��̏Ɨt���n���̐[���݂ɂȂ��Ă���B
�@ �������ɂ����ɂ́A�ߑ㉻�����Љ��͖Y����ċv�����A�����̕s�v�c�ȋC�z�̕Y����Ԃ����݂��Ă����B�����āA�܂�ł��̋C�z�ɂ����Ȃ��ł����邩�̂悤�ɂ��āA���̔]���ɂ͗c�����ɋ삯���������̔����_�Ђ̋����₻������͂ނ悤�ɂ����ނ����A���~�A�^�u�A�A�R�E�Ȃǂ̑�̑z���o���S���Ă����B�v���A�����̖X�ɂ悶�o������A�B�ꂽ��A�J�h�肵����A�̎�������������肵�ĉ߂����Ȃ��Ŏ��̊�����T���S�͈�ݔ|���Ă����̂ł���B
�@ ����̐X���ݗ����̑����ɂ����g���ς˂����ƁA��X�́A�����E��e�ɂ��鎇�z�a�A����فA�C�������ق̎O�ق��߂����Ă݂邱�Ƃɂ����B�V�W�̂���ʘH�łȂ���ꑱ���ɂȂ��Ă��鎇�z�a�ƍ���قɂ́A����Ȃ�тɏd�v�������̊Z�A���A�����ނȂǂ����т����������W������Ă����B���`�o��[�̐Ԏ��ЊZ�A��������[�̎����ЊZ�A�͖�ʐM��[�̍����ЊZ���A��ǐe����[�̉��O���������ɍ������n�Ƃ���������ނ͂��ׂč���Ɏw�肳��Ă���B�����o�ĐF�����Ă��Ă��邪�A�f�l�ڂɂ��f���炵�������̐��I�ȑ���͂Ȃǂ������ɍ���Ȃ�ł͂̂��Ƃ��Ǝv��ꂽ�B����ł͂Ȃ����A�֖��V�c����[�����Ƃ�������������̋b�������Ȃǂ��W������Ă����B����܂��Љ�̋��ȏ��Ȃǂł��Ȃ��݂̋��ł���B
�@ �d�v�������̊Z���ƂȂ�ƓW������Ă�����̂����ł��䂤�ɐ��\�̂ɂ̂ڂ�A�������d���̊e�퓁���ނɂ������Ă͂��̐�����������̂����������Ȃ��炢�ł���B�����̒��ɂ́A�������Y�ג���[�̐Ԏ��h�d���|�A�ؑ\�`����[�̌O����ЊZ�A���d����[�̗���������A�����V�ٌc��[�̓㓁�Ƃ������悤�Ȃ��̂��܂܂�Ă���B�ǂ��܂Ŏ����̗��t��������̂��͒m��悵���Ȃ����A���j��ɂ����ēG�����ɂȂ��Đ�����l�������̂�������ʕ�[�i���ꓰ�ɒ�Ă���Ƃ���Ȃǂ́A���̐_�ЂȂ�ł͂̂��ƂȂ̂��낤�B���`�o��퐳���̂ɗp����ꂽ�Ƃ������i�����̂قǂɂ��Ă͂ƂĂ��ӔC���Ă����ɂȂ��j��X�F�����p�̍���̑����ȂǂƂ���������̂܂ł������B
�@ ���ۂɎg��ꂽ���̂��Ƃ����呾����㓁�ނ́A�z�����Ă����ȏ�ɒ����傫�����邩��ɏd�����ŁA�ق�Ƃ��ɂ���Ȃ��̂�U��Đ키���Ƃ̂ł���̗͂̎����傪�����̂��낤���Ǝ���X�������Ȃ�قǂ������B�킢�̂��Ȃ��G�̏��n�̋r���̂ɓ�l������ŗp�����Ƃ������呾���Ȃǂ��W������Ă������A���s���ɂ���ȓ���ȕ���ŋr��_��ꂽ�n�����܂������̂ł͂Ȃ������낤�B���ʂɍ������[�i�Ƃ������Ƃ��������̂�������Ȃ����A���ג���[�Ɠ`������d���̋|�Ȃǂ́A�X�[�p�[�}���ł��Ȃ������肱��Ȃ��̂��������Ƃ͂ł��Ȃ����낤�Ǝv����قǂɊ�䂻���Ȃ�����̂������B
�@ �����A����ȏ�ɋV�����͍̂���ق̓�����߂��ɑ傫���W������Ă�����R�_�_�Ћ{�i�ꑰ�̌n�}�������B�V�Ƒ�_����͂��܂�_���V�c���o�Č��݂̋{�i�ꑰ�ɂ܂ő����Ă���炵�����̌n�}�����āA��X�͂��������V����Ƃ��������悤�̂Ȃ��v���ɂȂ����B����@�ꑰ�����̏W�c����^�ʖڂɂ��̌��ЂƑ��݂̐�ΓI�ȗ��t�������߂悤�Ƃ���Ƃ��ɁA�Ӑ}�������Ă����N���肤�邱��͍ō��̃M���O�ł���B
�@�C�������ق̂ق��ɑ����^��ł݂�ƁA������̂ق��ɂ͋��ޕW�{�A�z���W�{�A�l�Êw�W�W�{�A�D���W�����Ȃǂ����낢��ƓW������Ă����B�t�R���ō̎悳�ꂽ���a�V�c�䂩��̊C�m�����W�{�⌤�������Ȃǂ��͂�邱�̊C�������قɂ܂ʼn^���������Ă���̂��ӊO�ł͂������B�X�̓W�����͂���Ȃ�ɗ��h�Ȃ��̂����A���̈Ӌ`���������邱�Ƃ͂ł���̂����A���ɂ͈�����ǂ��ɂ��C�ɂȂ邱�Ƃ��������B��R�_�_�БS�̂̕��͋C�₻�̗��j�I�w�i�A���z�a�Ȃ�тɍ���قȂǂ̓W�����Ȃǂ��l���鎞�A���̐V�݂̊C�������ق̑��݂����͂Ȃ�Ƃ������͂��Ȃ��̂Ɏv���ĂȂ�Ȃ���������ł���B
�@�C�ɉ������葺�㐅�R�Ƃ̊W���[���_�Ђ�����A�C�������ق������Ă����������Ȃ��낤�Ƃ����l�������������̂��낤���A���̌��w�Ґ����m�ۂ���ɂ͋����̐_�ЊW�{�݂ƃZ�b�g�ɂ����ق����悢�ȂǁA���ɂ����X�̎�������Ă̂��Ƃł͂������낤���A���߂Ă����������ꂽ�Ƃ���Ɍ��Ă�Ȃǂ̔z�����炢�͂Ȃ���Ă��悩�����̂ł͂Ȃ��낤���B�Î��䂩�����s��ȑ���̔q�a�ɎQ�q���A�[�X��������̐X���߂���A�����d���̊Z���Ⓛ���ނ߂Ȃ���Â̕��������̐����ɉ����z����y�������ƁA�ߑ�I�ȑ���̔����قɂ���Ă��Ă����Ȃ�~�̃y�j�X�ɏے������悤�ȓW�������������鑤�̐g�ɂ��Ȃ��Ăق����B
�@
�@ ��R�_�_�Ђ����Ƃɂ���ƁA�Ăѐ����ˎ����ԓ��ɖ߂�A�|�\�����̂Ȃ��̏d�v�Ȑ��˂̈�ł���@�I���˂��ׂ���O������n�����B�s����̔������̒��߂�@�I���ˎ��ӂ̌i�ς����ɑf���炵���B����}�����Ƃ������Ĕ������͂������ɒʉ߂��A�����E�哇�勴��n���đ哇�ɓ���Ǝl���{�y�̔g�����⍡���s�͂��������������B�哇�Ǝl���{�y�̊Ԃɂ́A�×��A�|�\��������ۂ̍ŏd�v���[�g�ł����������C���A���Ȃ킿�A�������˂���������Ă���B���̗������˂ɉ˂闈���勴�͐����ˎ����ԓ��ɉ˂鎵�����Œ��̋��ł���B���E�̊ቺ�̗Y��Ȑ��˂̒��]���y���݂Ȃ��痈���勴��n��I������X�́A�l���{�y���ɐ݂���ꂽ�����C���W�]���ɎԂ𒓂߂��B
�@ ���܂ɂ������Ă��������Ȃقǂɋ���ȗz�˂𗁂тāA�������˂͌Q�F�ɋP���Ă����B�����āA����X�������̐��H�̒������A���x�𗎂Ƃ����D���Ƃ�������̂����ɒʂ�߂��Ă����B���˂̌������ɂ͐�قǒʉ߂��Ă����哇�₻�̌������̑�O���Ȃǂ̓��e���]�܂ꂽ�B���̗������˂̐��H���ɂ͐��̏������U�݂��Ă��āA�Ȃ��قǂɂ���n���ɂ͗����勴�̋��r���ݒu����Ă���B�܂��A��X�̗����Ă���W�]������͌����Ȃ����A�����s�̖k�Ɉʒu����g�����̐��ˑ��ɂ͗Ǎ`���`������ג������]�������āA���傤�ǂ��̏o���t�߂ɁA�ʏ�̃h���C�u�}�b�v�Ȃǂł͎��ʂ���̂�����Ȃقǂɏ����ȕė���̓���������ł���B���ꂱ�����������㐅�R�̍����n�ɂȂ��Ă����u�����v�Ȃ̂ł���B�ӊO�Ȃقǂɏ����ȓ��������˂̍ŗv���Ɉʒu����v�Q�̒n�ł��������̂ŁA�×��A�ɗ\�O���{�����\���Ă����B�������˂Ƃ������̂��ނ�̓��̖��ɗR��������̂������B
�@ ���l���\��̌����n�сA���Q���L������
�@ ���˓����Ȃ݊C���ɕʂ����������X�͍����s�Ɠ��\�s���������ɒʂ蔲���A���R�����ԓ��ɓ���Ɛ��Ɍ������Ė҃X�s�[�h�ő���o�����B���Ȃ蓹����H���������ŗ\��̎��������x��Ă���B���R����E��͂邩�ɖ]�݂Ȃ��珼�R�s�����ʉ߁A�ɗ\�s�A���q�����o�ď��R�����ԓ��̏I�_��F�Ɏ���A��������͍����\�Z�������ɉF�a�����ʂւƓ쉺�����B����Ȃł͎O�����ڎw�����Q���L�����̖���W�҂ƌg�ѓd�b�ŘA�����Ƃ��Ă���B���Ȃ݊C���̓r���ɂ��铇�Ȃǂɗ�������ہA�����Ԃ�Ɠ��ɖ��������瓞�����\������啝�ɒx��邾�낤�ȂǂƎO������͐���ɓ`���Ă��邪�A���ɖ������o���Ȃǎ��̂Ƃ���͂��炳��Ȃ��B���ׂĂ͓����̂䂦�ł���B
�@ �F�a�����߂��A�F�a���s�ɓ��鏭����O�ō����\�Z�����獶�ɕ��铹�ɓ������B�����ē��������ē�\���قǑ��菬���ȓ����z���Ă��炳��ɂ��炭�A�N�Z���ݑ�����ƁA�R���݂ɑ傫�����͂܂��悤�ɂ��Ă���������X�������n�̍L�����тɂł��B�����āA���̂����肪�ق��ł��Ȃ�����̗��̖ړI�n�A���Q���L�����������B���H�̍��E�ɂ͐Â��ȕ�������������_�R�����i���L�����Ă���B�n���h��������Ȃ��炿����Ƃ���������������ł͂��������A�Ȃ��Ȃ��ɉ����̐[�����Ȋ����̂��钬�������B
�@ �܂��͍L���������K�˂�蔤�ɂȂ��Ă����̂Ŗ���̂���Ƃ����߉i�W���Ɍ������ĎԂ𑖂点���B�Ƃ��낪�̐S�̍L��������炵���������Ȃ��Ȃ�������Ȃ��B�n���̒�������Ƃ����Ǝ�v������قǂȂ��ꏊ�ɂ�������Ƃ킩�邽�����܂��Ō����Ă���̂����ʂȂ̂����A�L�����̏ꍇ�ɂ͂ǂ��������ł͂Ȃ��炵���B�ߋ����x���L��������ɗ��Ă���O������Ȃ炷���ɂ킩��͂����Ǝv�����̂����A�����ł͎Ԃ��^�]���邱�Ƃ̂Ȃ������������Ă��낤���A���̃i�r�Q�[�V�����͂����ς�v�̂Ȃ��B�C��ɂ����ĂȂ�ɗ\�̊C���O�Ȃ݂̔\�͂�����O������̑̓����j�Ղ��A�n��ɂ������Ă��܂����r�[�ɁA���݉��̔����鋭�͂Ȏ��͐��̉e���ł߂��Ⴍ����ɋ����Ă��܂��炵���̂��B���@���A����ȏ�ԂɂȂ��Ă����݉��̕��������͂����Ƃ킩��炵������Ȃ�Ƃ��s�v�c�Ȃ��̂ł���B
�@ ���ǂ͍L�����_�щۂ̔_���W���A���c�B�炳�炪�}���ɗ��Ă�������Ƃ������ƂɂȂ����B�����āA�قǂȂ����ꂽ���c����̎Ԃɐ擱����āA��X�͏W���̏������܂����Ƃ���ɂ���L��������ɓ��������B�L��������ł́A�O�������ӂɂ��Ă���Ƃ������t�G��_�щے����A�������肵���g�̂̉��ꂩ�炶����ƗN���オ��悤�ȉ�����̂���Ί�ł����ĉ�X��l���o�}���Ă��ꂽ�B���Â��ȍ��c����̏�i�ɂ�������t����͌��邩��ɍ��_���G�l���M�b�V���Ȋ����̐l���ŁA���Q�̍s���͂ƌ��f�́A����ɂ����ɂ�����炸��ǓI�ȗ��ꂩ��l����ē������Ƃ̂ł����e�͂̎�����ɈႢ�Ȃ��Ƃ��������B���������l������l�ł�����ƁA���̍s���g�D�̂͂��̂����犈�������A���̔��W�ɂƂ��Ă���ςɗL�Ӌ`�Ȃ��Ƃ��낤�B
�@ ���ڎ��ň�ʂ舥�A���ς܂������ƁA���͓��t����L�����ɂ��Ă̊ȒP�ȃK�C�_���X�����Ă݂����B���̒��̌��݂̐l���͂��悻�ꖜ���ܕS�l�ŁA���ѐ��͎l���S�\�˂قǂł���Ƃ����B�]������̈��┨��Ȃǂ̔_�Ƃ̂ق��A���_��{�A�ыƁA�_�Y����؍ނ̉��H�Ȃǂɂ���Ē��ɏZ�ސl�X�̐����͎x�����Ă��Ă���悤���B
�@ ���m���̒����s�̉͌�����y���p�ɒ����l���\��́A�����̐��y�����]���t�߂ō��E���ɑ傫������B���̂�������̎x���̂ق��͌������z���č��m�����爤�Q���ɓ���A���쒬���o�čL�����ɂ������Ă���B�����āA���̑傫�Ȏx���͍L�������ɓ���ƍL����A�O�Ԑ�A�ޗǐ�̎O�ɕ�����A����ɂ����O�̐�͏㗬�Ɍ������ɂ�Ă��ꂼ�����̎x���ɍׂ������A�R�ԕ��̒J���ւƏ����Ă����B�v����ɁA�L�����Ƃ͎l���\��̖k�����x���̌�����Ɉʒu���钬�Ȃ̂��B�����Ŗ������l���\��̌����n�т�����A���R�����𗬂��召�̐��k���̐������ݐ��Ă���A�����̗����тɍL����X��т����̂����Ȃ��������B
�@ ���̒n�ɓ`���ɗ\�_�y�͍��w��̏d�v���`�����������ɂȂ��Ă���Ƃ����B�u�j�q�l���_�y�v�Ƃ��Ă�邱�̓`���_�y�͊��q����ȗ��̂��̂Ƃ����A�l���_�y�̒��S�I���݂ł�����炵���B�_�E�݂̂ɂ���ĉ������邱�̐_�y�̑S���ڂ͎O�\�ܔԂɂ��̂ڂ�A�{���Ȃ�Ε����I����̂Ɉ�ӂ�v����Ƃ����̂����A���݂ł͏ȗ�����ĎO���ԂقǂŏI����Ă��܂������ł���B
�@ ���Q�����w��̗L�`�����������̋S�k���y���L�����ɂ����Ē��N�p����Ă��Ă���`���|�\�̂ЂƂł���B�]�ˏ����̎O�����̈�Ƃ��Ēm���A�l�S�N���̓`�����ւ��Ă����W�H�̐l�`��ڗ��A�㑺�����v����͖�������ɂ��̒n��K�ꂽ�Ƃ��A�ނ炪�g�p���Ă������H��̐l�`�̓���ߑ����������̌|�Ƃ��ǂ����̒n�̐l�X�ɓ`�������B���ꂪ�S�k���y�̂͂��܂�Ȃ̂��Ƃ����B���݂����̗R������`���|�\�͒n���̐l�X�ɂ���đ�X�`������Ă���B
�@ �L����̎x����h�쉈���ɂ��鐴���W���ɒ��N�`���܂��x����������B�p�̐������傫�Ȏ��̖ʂ����Ԃ�S�g���Î��L���ȑ����ŕ������ܐl�̕����肪�����邱�̎��x��́A��l�����������q���̌n���ɑ����镑�Ȃ̂��������B���������Ɏ��⒖�Ȃǂ̖L�����F�������J�s�����甭�W�������̂��Ƃ��A�F�a���Ɉڕ����ꂽ�ɒB�G�@�����n���ɓ`��鎭�x����������ݓ`�������̂��Ƃ������Ă���B
�@ �V�����Ƃ���ł͘a���ۏW�c�̊@�i���������j������B��������Ă���܂��\�O�N�قǂ��Ƃ������A�c�������͋ߔN�߂��߂��r�������邢���ۂ��ł܂��܂��a���ۂɂ̂߂荞�݁A�S�����ł��O�ʂɂȂ�ȂǁA�`�������ɂ͑�ςȊ���Ԃ�������悤�ɂȂ����悤�ł���B
�@ �����I�Ȗ��������Ĉɗ\�_�y��S�k���y�A�܂��x��Ƃ��������̒n�̓`���|�\��ڂɂ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��͎̂c�O���������A���̍L�����ɂ͂�����ė�������ɂ́A�Ȃɂ͂Ƃ�����A�S���͈ꌩ�ɂ������̐��_�������Ă��������K�˕����Ă݂�̂��x�X�g�ɂ͈Ⴂ�Ȃ��B�[���������Ă͂��Ă������A�܂��͂Ƃ������ƂŒ����ꏊ�L�̑�^���S���̐V�Ԃɐg���ς˂���X�́A���t����ƍ��c����Ɉē������܂܁A�L�����암�𗬂��ޗǐ�̉��ɂ��鐬��k�J���ʂւƌ��������ƂɂȂ����̂������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N10��25��
�L���������𐆂��̉ʂĂ�
�@ ���ޗǐ�͐�~�̂ł̈𐆂��k�`��
�@ �L�����암�𐼂��瓌�ɗ����ޗǐ쉈���̈�тɂ͂��Ȃ�̖ʐς̐��c���L�����Ă���B�ǂ���炱�̂ւ�͋S�k�ĂƌĂ��n���Ă̎Y�n�ł���炵���B����̏W���ō��܂����Ԃ͂قǂȂ��k�J�̑����n�тւƍ������������B�ԑ��̊O�̕��͋C����@����Ƃ��̕t�߂���㗬�̒J������k�J�̂悤�������B�������ɂ͐��͕����ƂȂ��ė����炵���쏰�͊����Ă������A�����Ό����������̗͂ɂ���Ė���������ꂽ���̊┧�͌��邩��ɉ��₩�Ŕ������B
�@ ����ɐ[���Ȃ�k�J���ǂ�ǂ܂ők�邤���ɍĂѐ��������ꂽ�B�����āA��X�̏��Ԃ͂��������͎R�������˂��V�����Ƃ����n�_�Œ�~�����B�傫������Ȋ�Ղ���d�ɂ������Ȓi���Ȃ��ĘA�ȂƂ�Ȃ�L���쏰�������āA���̏���ʂ芊��悤�ɂ��Đ��݂�������������Ă���B�㗬���牺���Ɍ������Đ쏰���قǂ悢�X���Ȃ��Ă��邽�߁A�������ԛ��⎿�̊┧�������ƕ��ł�悤�ɂ��Ċ��藎���Ă���̂��B�������A���̐��͂��̂܂܈���ł������x���Ȃ����낤�B���͈�l�쏰�ɍ~�肽���Đ����Ɏ����������A���̗₽���u�₩�Ȋ��G��������䂭�܂Ŋy���B�k�J�̗����͞w�̋���e��̍L�t���̔ɂ��ނ���X�тɕ����Ă���A�������܂����̌k�J�̔����������o����d�v�ȗv�f�̈�ɂɂȂ��Ă���B�t�߂ɂ̓L�����v����݂����Ă��āA�����ŗ[�M�̏��������Ă���炵���l�e������ق猩������ꂽ�B
�@ ���̐���k�J���l�߂������Ƃ���ɂ͍����R�Ƃ�����O�S���[�g���قǂ̎R�������āA���̎R�̌��������ɂ͓������l���\��̏��x���ł���ڍ��삪����Ă���B�����āA���̖ڍ���̏㗬�ɂ͂�͂�������ԛ���̐쏰�Ɛ����Œm���銊���k�J�������āA����k�J�Ƌ��ɓ�k�������獂���R�����ނ������ɂȂ��Ă���B����k�J�������k�J���͏����`������⎿�Ɗ�Ղ̍\�����قړ���������A�����悤�Ȍk�J�ɂȂ��Ă���̂��낤�B
�@ ��X���Ԃ��߂��ꏊ���班���������Ƃ���ɂ͍L�����c�̍�������Ɛ���k�J�x�{�Z���^�[�i0895-45-2639�j�������āA�h���̂ق��ɉ���̓��A��������ł���悤�ɂȂ��Ă����B�����ɂ���Ă��钬���ɍ������ĉ�X�l�l������ɂ��������A���������悭�Ȃ��Ȃ��ɉ��K�ł��܂ɂ��@�̂̈���o�Ă������Ȋ����������B���D�̒��ɓ��t����ƕ���ł����Ȃ��琬��k�J���ӂɂ��Ă��낢��Ƙb���f���Ă݂����A�ӊO�Ȃ��ƂɁA���Ȃ艷�g�����ɂ݂��邱�̂�����ł��~��ɂ͌��\�Ⴊ�ς邱�Ƃ�����炵�������B����k�J���ӂł͗ǎ��̞w�ނ�M�q����ɂ͎��R���Ȃǂ��Y�o�����Ƃ������Ƃ��������A�����̎Y���̕i���̗ǂ������̒n�̓��ʂȒn�`��C��ƂȂɂ��W������̂��낤�B������ӂɂ����炸�L�����S��ŎY�o����鎩�R���͋S�k���R���Ƃ����Ė��Ǝ����Ƃ��ɂ悢���Ƃł��m���Ă���Ƃ����B
�@ ����k�J����ɂ�����X�͍ĂэL��������ւƖ߂����B�����āA����̂����e�𗬂��ޗǐ�̉͐�~�ւƈē����ꂽ�B�[���̔��������̉͐�~�̈�p�ɂ͑傫�ȃV�[�g�����������L�����A�L��������W�҂𒆐S�ɂ����O�\�l���炢�̐l�X���A���̒n�̖����s���ł���u�𐆂��v���s���Ă���Ƃ��낾�����B���̈𐆂��Ƃ����s���͔������{����㌎�����܂ł̊Ԃɂ��̉͐�~�ɒn���̐l�X���v���������ɏW�܂��čÂ��̂������ŁA�����Ƃ�����オ��̂͋㌎���̍��炵���B��X���L������K�˂��͔̂������{�̕����̂��Ƃ���������A���̓��𐆂�������Ă���͖̂���W�̐l�X�̃O���[�v��g�����������B�ǂ����O������Ǝ����܂��܂���ė��Ă���Ƃ����̂ŁA�}篂��̓��̗[���Ɉ𐆂�����낤�Ƃ������ƂɂȂ����炵���B
�@ ���t����ɂ��ȒP�ȏЉ�I��������ƁA��X��l�����̂Ȃ��ɉ����Ă�������B�����Ǝς��ڂ̑O�̓炩��͂Ȃɂ����������Ȃ����肪�Y���Ă��Ă���B�O������̂ق��͂������ɃA���R�[���V�����[�̐��E�ւƓ˓����Ă��������A�A���R�[���V�����[�ɂ��܂�ϐ��̂Ȃ����̂ق��̊S�́A�����ς�𐆂��̂Ƃ����s�����̂��Ƃɂ��Ȃ�����̒��g�̂ق��ւƌ�����ꂽ�B
�@ ���͊�撲���ۏ����̊�{���q����Ƃ��������̂������N�����Ɨ��킹�ɂȂ����B���̊�{�����M�ɂ̂��Ă܂������ɏo���Ă��ꂽ�̂́A䥂ŏオ������C�̔��������ȃJ�j�������B���̈�т̐����ɑ����������郂�N�Y�K�j�Ƃ�����K�j�炵���B�b�����͂���������Ɖ��F�݂�тт��g�����ɂ���Ƒz���ȏ�ɔ����ł������B���U��̃J�j�������t�����������肵�Ă��邹���ŁA�ׂ߂̑����������Ă����̒��ɂ�����Ƃ��܂݂����݂����Ă���B�����I�ɂ͂���������̂ق����g�̓���������悭�Ȃ�Ƃ̂��Ƃ��������A���߂Č��ɂ���҂ɂƂ��Ă͏\���Ȃ��܂��������B
�@ ��{�����Ɏ��M�ɂ̂��č����o���Ă��ꂽ�̂́A�𐆂��̐^�łƂ������ׂ��A�T�g�C���A�R���j���N�A�^�}�S�A�J�V���A�A�c�A�Q�Ȃǂ̎ϕ��������B�x�[�X�ɂȂ�̂͒n���łƂꂽ����̐V�N�ȃT�g�C���ƒn�{�̓��ŁA����ɊF�������������͂�n���Y�̊e�펩�R�H�ނ������A���̏�ł�������Ǝύ��ށB�n�{�͂悢�_�V���\���ɂł�V�{�������̂��Ƃ����B���Ƃ��Ƃ́A�n���̐l�X���e�X�L�荇�킹�̐H�ނ������ĉ͐�~�ɏW�܂�A�������ύ���ł������M�X�̓�����Ȃ�������ނ��킵�e�r���͂���s���������悤�����A�ߔN�͊ό��q���͂��߂Ƃ��钬�O�̐l�X�̎Q�����ڗ��悤�ɂȂ��Ă��Ă���炵���B
�@ ����܂��n���Y�̊e��V�R���������ӂ�Ɏg���Ďύ��܂ꂽ�T�g�C���A�R���j���N�A�A�c�A�Q�A�^�}�S�A�����Ēn�{�̓��́A��������ʂ��܂��ł������B���̖������Q�ɑf���炵�������̂́A�B�����Ƃ��Ă��܂ЂƂL�����̐l�X�́u�l��v�Ƃ������ʒ��������z����Ă��������ł��������낤�B�O������͂Ƃ݂�ƁA������������o���オ���Ă��銴���ł���B����ӎ��ɂ͂���Ȃ�ɕ��G�ȎO������̓��̒��̐l���n�}�����܂̓g�|���W�C�}�`�Ȃ݂ɘc�ݕω����P��������āA����}�[�N��݂̂����낤���Ė��ł��邾���̏�ԂɂȂ��Ă���ɈႢ�Ȃ��B
�@ ���ł��[�܂�ɂ�Ĉ𐆂��̏�͑傢�ɐ���オ��A���͊�撲���ے��̎œc��������̂ق��A�L�����_�ƌ��Ђ̐ݗ��Ɋւ�������c�m�ꂳ��A����ɂ͉��l���̎��E���̐l�����Ƌ��ɂ��낢��Șb�����邱�Ƃ��ł����B���̂Ȃ��œ��ɐS�Ɏc�����͍̂L��������̐l�������F�Ȃ��Ȃ��̎��ґ����ŁA�n���͂��m�I�D��S���w�K�ӗ~����ςɉ����Ȃ悤�Ɍ����邱�Ƃ������B�܂��A�ނ炪�^���ɍL�����̏����̔��W���l���A�^�Ɉ�ʒ����ƈ�̉������s���̓W�J��S������悤�ɓw�߂Ă���炵�����Ƃ������ւ��ۓI�������B���̒��̋�̓I�Ȑ��Y���Ƃ̓W�J�ɂ��Ă͗������w�����Ă��炤���ƂɂȂ��Ă������A���̔w�i�ɂ�������E���̋��͂ȃ��[�_�[�V�b�v�����݂��Ă��邾�낤���Ƃ͖����������B
�@ �L���Ȏ��R�Ɖc�_���Ɍb�܂ꂽ���̍L�����ł��ߑa�����i�݁A�ߔN�̔_�ыƏ]���Ґ��̌����͒������Ƃ����B����ɗ���������ɂ�������������̎Y�Ɠ��v�\�͔@���ɂ��̌����Ԃ����Ă����B�_�ѐ��Y�ƂȂǂ̈ꎟ�Y�Ə]���Ґ��́A���H�Ƃ�T�[�r�X�ƂȂǂɏA���Ă���E�O���Y�Ə]���҂����킹���S�Y�Ə]���Ґ��̌ܕ��̈ꋭ�ɉ߂��Ȃ��B�œc����⍂�c����̘b�ɂ��ƁA�����ŕS�p�[�Z���g�c�_�Ő��v�𗧂ĂĂ���_�Ƃ͂��܂ł͂킸�����˂Ȃ̂��Ƃ����B���v�I�ɂ͔_�ѐ��Y�Ə]���҂̐��͐��S�l���Ă��邪�قƂ�ǂ����Ƃł���炵���B
�@ ���̒��̌b�܂ꂽ�c�_�����炷��A�_�Ƃɂ���Ĉ�˂ɂ��Œ�ł��N�ԎO�S�����x�̏��v�͌����߂�̂��������B�s�s���ƈ���ďZ��������͂قƂ�ǂ�����Ȃ�����A���̋C�ɂȂ����Ȃ�ɖL���ň��肵�������𑗂邱�Ƃ��ł���͂����Ƃ����B�n���ŎY������ނ��ؗނ͂ނ��A���`�̂���F�a���܂ł͎ԂłЂƑ��肾���狛��ނ����ĐV�N�ň������̂�������ł���ɓ���B���������ĂƂĂ������͂��₷���B�����A�������������ŁA�������_�����l���Ăы����ɖ߂��Ĕ_�Ƃɕ��A������͂���܂ł̂Ƃ���قƂ�ǂȂ��A�_�Ɛl���͉ߋ������̈�r�����ǂ��Ă����̂��Ƃ����B
�@ �������A���܁A���t�����œc����⍂�c�������͂��߂Ƃ���L�����̐l�X�́A�����̖L���Ȏ��R��������I�ϓ_����\���Ɋ��p���邱�Ƃ̂ł��鎞��ɑ������V���Ȕ_�Ƃ̓W�J�𗧈Ă��A�ϋɓI�ɐ��i���邱�Ƃ��l���Ă���B�o�u���̎��オ���S�ɐ̓��̂��̂ƂȂ�s�s�W���^�̌o�ς╶���̑O�r�ɑ傫���Ȃ肪�����͂��߂����݁A�n��������n��o�ς̕����͐�ɕK�v���K�R�̂��Ƃ�����A������ǂ݂����_���╶���s���̎�����ڎw���͎̂��������̐Ӗ����Ɣނ�͔M���ق��A������̎��ɋ����������i�������Ă����B���ہA�ނ�́A���������オ�ڂ�Ύ��R�Ɍb�܂ꂽ�L�����ł̔_�Ɛ����̑f���炵�����ĔF������l�X�������Ă��邾�낤�Ɗm�M���Ă���悤�ł��������B�ߔN�A�s������̂ēc�ɕ�炵���n�߂�l�����Ƃ������Ȃ����A����Ȑl�X�ɂƂ��Ă͂��̈��Q���L�����Ȃǂ͗��z�I�ȈڏZ��̌��̈�ł͂Ȃ����Ǝv��ꂽ�B
�@ ���̈𐆂��̐Ȃŏ��߂Ă��̑��݂�m�����̂����A�L�����ɐݗ����ꂽ�Вc�@�l�L�����_�ƌ��Ђ͑S���I�ɂ�����߂ă��j�[�N�ȑ��݂Ƃ����Ă悢���낤�B���̌��Ђ́A�ߑa����_�Ə]���҂̍���ɔ������Y�����̒��D�ǔ_�n�̍k������A�_�ƌ�p�ҕs���Ƃ��������̉����A�_�Ƌ@�B�ւ̉ߏ�ݔ������ɂ��o�c��@�_�Ƃ̋~�ρA�H�Ƃ̈���I�Ȑ��Y�����Ԑ��̈ێ��A����ɂ͎��R����Ԍn�̕ی�Ȃǂ�ڎw���Đݗ����ꂽ�B��̓I�ɂ́A�_��Ƃ̎�ϑ���_�n�̊Ǘ��ۑS�̑�s�A�_�ƌ�p�҂̈琬�ƌ��C�A�_�Ǝ{�݂���є_�Ƌ@�B�݂̑��t���A�n�掑�������p�����_�Ɠ��Y�i�̊J���Ɣ̔��A�s�s�Ɣ_�ыƒn��Ƃ̌𗬑��i�Ƃ������悤�Ȏ��Ƃ������Ȃ��Ă���B���f���P�[�X�Ƃ������ׂ����̌��Ђ̎��Ƃ����������߂�A����̌��Ђ̐ݗ��Ɗ������S���I�ɕ��y���Ă������ƂɂȂ邾�낤�B
�@ �𐆂��̗R���ɂ��Ďn�܂�L�����̔_�Ɩ��ւƈڂ�����X�̘b�́A�Ō�ɂ͐��w��F���_�̐��E�̘b��ɂ܂Ŕ��W���Ă������B�������A�F���F�A��̑O�̖������鏭�N�����̂悤�ɂ��̂����Ȃ��M�ӂɖ����݂��Ă����B���`���N�`���ƌ�������قǃ��`���N�`���Șb���Ȃ������낤���A���ꂱ�����𐆂��Ƃ������̒n�Ȃ�ł͂̐e�r�s���̑�햡�Ƃ������ׂ��ł������̂��낤�B�����g���̈𐆂��s���̌���ɂ���Ă���܂ł́A�܂����l���\�쌹����̉͐�~�œ痿�������Ȃ��琔�w��F���Ȋw�̘b�����邱�ƂɂȂ낤�Ƃ͖��ɂ��v���Ă��Ȃ���������A�Ȃ�Ƃ��s�v�c�ȋC���ł������B�����A�悭�悭�l���Ă݂�ƁA����ȔM�ӂƎv�l�̏_���������̐l�X�̒��ɂ�������A���̒��͑��̒����ɂ͂��܂�ޗ�����Ȃ��悤�ȓƎ��̎��ƓW�J���ł��Ă���̂ł͂��낤�B
�@ ���L�����̖�͍X���ā�
�@ �𐆂��̐Ȃ����Ƃɂ�����X�́A����ǂ͍L�����k���A�L���쉈���̏W���ɂ���u�Ⴟ���v�Ƃ������������ɏꏊ���ڂ��A�`�����̈��݉����邱�ƂɂȂ����B�����Ƃ��A��X�Ƃ͂����Ă����݉�Œn�����������Ƃ̌����̑O�ʂɗ��͎̂O��������A���̂ق��͂��̉A�ɉB��ďo����闿���Ȃǂɐ�ۂ�ł��Ă���悢�Ƃ������@�������B�A���R�[���̉���Ă��Ȃ����͂��������̎Ԃɖ߂�A�F�a���s����𐆂��̏�ɋ삯���Ă�����c����Ƃ�������܂��O������̒m�l�̃i�r�Q�[�V�����ɂ��������Ėڎw�����������Ɉړ������B
�@ �������ȑ�o�g�Ō��݉F�a���s�Ő����Ƃ��c��ł���Ƃ������̏�c������Ȃ��Ȃ��Ƀ��j�[�N�Ȑl���ŁA�L�����̐l�X�Ƃ̌𗬂������Ԃ�Ɛ[���悤�������B���ƂɂȂ��Ă킩�����̂����A��������Â��Ȃ��Ă����ɂ�������炸�A���̂܂ɂ����Ζʂ̎��̎Ԃ̃^�C���ׁA���̖��ŏ�Ԃ��������`�F�b�N���Ă����炵���B���̂Ȃ�Ƃ����ς��Ȏ��_�̎����ɂ�����͗B�X��������������ł������B�������萳�̂̂Ȃ��Ȃ��Ă���O������̎l���ł̃l�b�g���[�N���ǂ��Ȃ��Ă���̂��͒m��Ȃ����A�܂��ɑ��m�ρX�ςƂ����ق��͂Ȃ��B
�@ ���������u�Ⴟ���v�̐e��������܂���{�̒ʂ����Ȃ��Ȃ��̐l���Ƃ��������������B�Ǝ��̐R����Ɛl���ς����ɔ�߂����̐e��������A�ǂ����O���m�Ȃ�тɍL�����l�ރl�b�g���[�N�̗L�̓����o�[�ł���炵�������B�e�������ł̒�������o��������̃E�i�M�������A�S�����߂č���Ă��ꂽ���Ă͔���������łȂ��A�Ȃ�Ƃ������Ȃ����������������������B�������̗����ł̏��N����A�~�~�Y��h�W���E���a�ɂ��ăE�i�M�̌��ނ��������A�ނ����l���������ł����ĐH�ׂĂ������́A��u�̂Ƀ��[�v�����悤�ȋC���ɂȂ�������ł���B
�@ �O�������t�����ƒꖳ���̈��ݔ�ׂ𑱂��Ă���ԁA���ׂ͗ɍ�������撲���ے��̎œc����Ƙb������ł����B�̎����ւ���Ă������Ƃ̂���R���s���[�^����␔�w���炪��݂̐��I�Ȏ����Ȃǂ�������₢���߂���܂܂ɘb���Ă����̂����A�œc����̔M�ӂƊ����̉s���ɂ͓��S�S������肾�����B�ǂ��炩�Ƃ����Ɨ��m�I�ŗ}���̂������^�C�v�̎œc����̓_�C�i�~�b�N�Ől��ƃ^�C�v�̓��t����Ƃ͑Ώ̓I�ȑ��݂ŁA�悫���C�o���Ƃ������邱�̂���l�̉ے�����́A�L�����̍s���𐄐i��������I�ȗ��ւɈႢ�Ȃ��Ƃ������������ĂȂ�Ȃ������B
�@ �Ō�ɉ�X�͗����K�˂�\��ɂȂ��Ă�����X���Ƃ����ߓ����̋߂��ɂ���h�����Ɉē����ꂽ�B�l�����ꂽ�R���ɂ���L�������L�̍L���ꌬ�Ƃ����A�O��������������R���L���ŕ��ς��ȂƂ��낪�D�݂��Ƃ����킯�ŁA�v�����g���Ă��Ȃ��炵�����̉Ɖ��ɔ��܂炳��邱�ƂɂȂ����̂������B�h������������O������͍L�����̎����A����ɖ閾���܂ő��������Ȑ����Ŏ��J��L���Ă������A�ߑO�뎞���߂Â����ɂ͂������ɔ�ꂪ�����Ƃ݂��A�����ł悤�₭���J���ƂȂ����B
�@ �O������͂��łɑO��s�o�̏�Ԃł���B��X��l�������c���čL�����̊W�҂��F�����g���Ă��������ƁA���͉����ꂩ��K���ɕz�c����������o���ĕ~���A�܂��͂����ɎO�������Q�������B�ނ͂������̂܂ܗ����܂ł͐��̂Ȃ����葱����ɈႢ�Ȃ������B�����̕z�c��~���I���Ă��玄�͂������O�ɏo�ė���ɂ���g�C���ɓ������B�����ėp�������ς܂������A���������Ƃɂǂ��H�v�����x�`�������W���Ă݂Ă���̃��m�����ꗎ���Ă���Ȃ��B�����ԒN���g���Ă��Ȃ��W�ŕ֊�̒��q�������̂��B
�@ ��ނȂ����͂�������g�C������o�Ė_���T���o���A������x�֊�ɋ߂Â��Ė������ڂ̑O�̕������̒��ɉ������B��������͂Ȃ�Ƃ��i�D���������̂̌��͋l�܂����܂܂�����A���������̂��ƒN�����g�����Ƃ�����r���ɕ��邱�Ƃ͐��������ł���B�g�C���������������A���ڊo�߂��O�������̔�Q�҂ɂȂ�m���͓̈�ł͂��������A����͔ނ̃E������Ƃ���ɑf�m��ʊ�����ĕ����Ă������Ƃɂ����B
�@ ���������̉����Ȃ���Ăщ����ɖ߂�A�������Ƃ������ēy�Ԃ̉��ɂ��闬���ɂ����ƁA�����ȃ��J�f�������߂��A�邪��т܂��A�w偂���������Ă����B���[��A�Ȃ�قǂ����m���Ɏ��R���L�����킢�ȂƎv���Ȃ���A�����̐����̎����Ђ˂�Ɣr�����̕t�߂łȂɂ����̉�������ł͂Ȃ����B�Ȃ낤�Ǝv�����h�ߑ��u���̋��W���͂����Ē���`���ƁA�����ɂ͈�C�̑傫�ȃg�J�Q�������܂��܂��Ă����B�l�̋C�z�������Ă����ɓ������͂������̂̏o��ɏo���Ȃ��Ȃ��ĉ������Ă����Ƃ���炵���B
�@ �����Ƃ��̊���݂߂�ƂȂ��Ȃ��Ɉ��g�̂��������Ă���B�̂��܂��̓����̐K������ėV���Ƃ����邩��A���̍ߖłڂ��ɂ����͉��������Ă�邩�ƁA��݂͂ɂ��ĊO�ɏo���������Ă�����B���V��̒w偂̎��̘b�ł͂Ȃ�����ǁA�����Ńg�J�Q�ɉ����Ă���������A��X���Ƃ��n���ɗ������Ƃ��Ă��g�J�Q�̐K����̉��b�ɗa�����āA腖��l�̒Njy�̎��邱�Ƃ��ł��邩������Ȃ��B����Ȃ��Ƃ��l���Ȃ��玕���I�������́A���̔�����₵�A�����̌��w�ɔ�����ׂ��悤�₭���ɏA�����悤�Ȃ킯�������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N11��1��
�L�������V�K���ƒT�K�L
�@ �����X�������߂���
�@ ���������V�������B�R���Ƃ͂����A�����͓썑�l���̓�������̂悢�J�̎Ζʂ���������C���͋}���ɏオ��A�ߑO�㎞���ɂ͂��łɌy���O�\�x���Ă��܂��Ă����B�O��͈Â��ċC�Â��Ȃ��������A��X�����߂Ă�������Â�����̖��l�̏W����ꌬ�Ƃ̂����e�ɂ͑�^���Ԃ����ݒu����Ă����B��r�I�V�������ԂŁA�ꎞ�I�ɐ������Ȃɂ��Ɏg��ꂽ���ƕ��u���ꂵ�܂������̂̂悤�������B���H���玅�̂悤�ɍׂ����Ȃ��ė��ꗎ���鐅�̏d�݂ɖ�����董����ł����邩�̂悤�ɁA�M�M�[�b�K�K�[�b�Ƃ����������ĂĂƂ�����v���o�����悤�ɉ�]���Ă�B�O�鏰�ɏA�������ƁA�ǂ�����Ƃ��Ȃ��b�̙���Ɏ������ȉ����������Ă���Ƃ͎v���Ă����̂����A�ǂ���炻�̐��̂͂��̐��Ԃ��a�ދ����ł������炵���B
�@ �������ɂ͏����ȑ����āA���̑�������������̎Ζʂ͂�����Ƃ����|�тɂȂ��Ă����B�y�₩�Ȃ����炬�̉��ɗU���đ�ɂ���Ă݂�ƁA�₽���������ӂ�ɗ���Ă���ł͂Ȃ����B�����߂��̈��X���Ƃ����ߓ�������N���o���Ă��鐅�ɈႢ�Ȃ��B�q���̍�����l�X�ȗN�����������݂��Ă����g�����琶���ɂ͋����B���N�̌o���ł��̐������߂邩�ǂ����͒��ϓI�ɔ��f�����B�����������̐��ɒ��ڌ������Ĉ��ނƎ��ɂ������������B
�@ ���łɐ������܂��A�����M�ɑ������w偂����Ƃ����Y��Ă���ƁA���Ƃ���O�����������Ă����B�O��͂��ꂾ���җ�Ɉ��݂܂���A�܂�Ő��̂��Ȃ������̂Ɉ�閾����������P���b�Ƃ������̂ł���B���̐l�̊̑����̃A���R�[�����������@�\�́A������Ƃ������w�H��Ȃ݂̔\�͂������Ă���̂�������Ȃ��B�m���̈�̃g�C���̃E����肪��u�]���𗩂߂͂������A����Ȑ�����O�ɂ��Ă���悤�Șb�ł͂Ȃ������̂ł��̂��Ƃɂ͈�ؐG��Ȃ������B
�@ �ē����̓��t����ƍ��c�������܂ł̂������Ԃ̕Еt�������Ă������́A�t�����g�E�B���h�E���̃^�I���̏�ɒu���Ă������`���[�C���K���̉���̂Ă悤�Ƃ��Ďw����̂����B�����A���̏u�ԁA�e�w�Ɛl�����w�̐�[�ɏĂ��Δ��ɂł��G�����Ƃ��̂悤�Ȗҗ�Ȓɂ݂��������B�Q�ĂĐU�蕥�����Ƃ�������{�̎w��ɔ��Ήt�����Ē�������K���͂ǂ�����Ă����������Ă���Ȃ��B�ɂ݂����炦�Ȃ���}���ő�ɋ삯����A�␅�Ɏ��˂�����Ŏw����\���ɗ�₵�Ă��ƁA�悤�₭�Ìł����K��������邱�Ƃ��ł����B�Ԓ��Ńt�����g�K���X�z���ɋ���Ȓ��˓����𗁂т��K�����t���A�����q�̑g���̂䂦�������č����ƂȂ��Ă����̂ɋC�Â����܂��ʂ�����ł������B�K�����x�͍����Ă��K���̔M�e�ʂ��̂��̂��������A�܂������ɐ��ŗ�₷���Ƃ��ł������ߎw��͌y���Ώ����x�ŏI��������A�傫�ȉ�̃K����������^�_�ł͍ς܂Ȃ��������Ƃ��낤�B�K���ł��Ώ������Ƃ�����ƒm�����̂͋M�d�ȑ̌��ł��������B
�@ ���ꂩ��قǂȂ��p�����������t����ƍ��c����Ɉē�����āA��X�͑�̏㗬�قǂȂ��Ƃ���ɂ�����X�����}�����ւƑ����^�B��ݏ��R�̒����ɂ����邱�̋߂��ɂ͏��K�͂ł͂��邪�A�̂��畗���Ƃ��Ēm���Ă������X�ߓ����������āA���a�O�\�l�N�Ɏ��Ԏ��v���l���勳����ɂ��{�i�I�Ȓ������s��ꂽ�B�����Ă���ȍ~�A�R�̒����̕�������͎O�\���N�O�ɐ������Ă����j�z�����J�V�W�J�̂��̂Ǝv���鉻���͂��߂Ƃ��A�O�\���ށA��ɂ��̂ڂ铮���̒����������Ȃǂ����������B�܂��A�����N����\���N���炢�O�̑�l�X���̋M�d�Ȑ�j��ՂȂǂ��o�y���A�ꎞ���V���������킹�������悤���B
�@ �����ۂ��A�����̈ʒu���Ⴂ�n�_�ɂ��鐅���̂ق�����͐��w�ȗN��������o���Ă��āA������̂ق��͒P�Ɉ��X���ƌĂ�Ă���B�������A�㕔�̕����̑����ŁA��ݏ��R�̒n���[���ɖ����Ă��邩������Ȃ��ߓ����̏o���ɂ�����Ɛ��肳��Ă���A�n��̃��}���ɓq����n���L�u��ɂ���Ď��\���[�g���قlj��܂Ŏ��@���ꂽ���A����܂ł̂Ƃ����K�͂ȏߓ����̔����ɂ͂������Ă��Ȃ��B
�@ ��X���ē����ꂽ���}�����͂��̐����A���Ȃ킿���X���̓����̂������Ɍ����Ă����B���}�����́u���}���v�Ƃ����O�����ɂ͒n��̃��}���ɓq�����n���̐l�X�̂ЂƂ����Ȃ�ʎv�������߂��Ă���̂��낤�B���X������₦�ԂȂ��N���o��␅�𗘗p���������ȁu�����߂��v�͂��̃��}�����̔��蕨�ł���B����A�u�����߂��v�̂��߂̃��}�������ƌ����Ă������x���Ȃ����낤�B���X���ۑ���A���X�������߂��̉�X���A���{�m�K����ɂ��낢��Əڂ������������Ă��炢�Ȃ���A��X�͗₼���߂�ɐ�ۂ�ł��ƂɂȂ����B
�@ �傫�Ȃt���`�z���̗��H�����炦���Ă��āA���̒���₽�����N�����Ă̐���������Ă���B���̔z�ˎ����炻�̐����ɏ���Ď��X�Ɨ���o�Ă���^�����ō��̋����˂ł������A���`�ɂ��ĐH�ׂ�̂����A���`�̖��Ɩ��܂���i�Ƃ��Ă����B���Y�A�V���E�K�A�~���E�K�A�l�M�A�^�}�l�M�I���V�A���T�r�A�A�I�W�\�Ȃǂ̖��ӂ�ɕ��ׂ��Ă��āA�D���Ȃ�������Ď��R�Ɏg����悤�ɂȂ��Ă���B���̒n�̓��Y�i�ł����郆�Y�̍���Ɩ��͂Ƃ��ɑf���炵�������B�܂����Ƃ肽�Ẵ��Y���܂邲�Ǝ�ɂ��A�K�v�Ȃ��������ł��肨�낵�Ďg���̂����A���`�ɂ��̃��Y�����A���̖𑽏��������Ă��̂܂܈��ނ����ł������ł������Ȋ����������B
�@ �l���\�쌹���̂��̂܂������̐����ɐZ�����㎿�̖˂��A�n���łƂꂽ�Ă̖��g���ĐH�ׂ�̂������ґ�Ȃ��Ƃ��̂����Ȃ��B��l�O�ܕS�~�ŐH�ו���Ɨ����������B�c�Ɗ��Ԃ͘Z����\�������甪���O�\����܂ŁA�c�Ǝ��Ԃ͌ߑO�\������ߌ���܂łł���Ƃ����B�ڍׂɂ��ẮA�c�Ɗ��Ԓ��̓��}�����i0895-48-0820�j�ɁA�܂�����ȊO�͍L���������撲���ۂɖ₢���킹�Ă݂�Ƃ悢�������B
�@ ���Ƒn�I�Ȕ_�Y�����H�i��
�@ �H��A���X�������w���I������X�́A���ɍL����̎x���A��h��̒����ɂ��鐴���Ƃ����W���Ɉē����ꂽ�B�u�������ĉ��H�ڂ݃O���[�v�v�Ƃ����A�_�Y�����H��������ѐ��Y�̔����i�g�D�̉�A���{���u�����A���g�D�̒��S�����o�[�̎R���҂����ɉ���Ęb�����߂ł���B�L�����ł͒��Ƃ̋��͑Ԑ��̂��ƗL�u�O���[�v�̎�ɂ���ēƑn�I�Ȕ_�Y�����H���i�������������J������A�s�̂�����Ă���悤���B���\���ĂȂ��������Ⴍ�Ƃ��Č����S�����ȉ��{����́A�S�k�R��������X���Ȃǂ��������Ă�����Ƃ̂��Ƃ������B
�@ �Ԃ������W���ɋ߂Â��ƁA�I�����W�Ɖ��̒��ԐF�̒n�F�̏�Ɂu��������H���v�Ƒ发���ꂽ�����̂���Ŕ���ɂƂ܂����B���ӎ��̂����Ɂu���v�̎��Ɓu��v�̎�����ꊷ���ēǂ�ł��܂������́A��u�A������Ȃ�ł����̃V�����m�����H����Ƃ��낶��Ȃ���ȂƁA���ȘA�z�����Ă��܂����B��^�̗��Ɏ����A���̍��������Ăł���E�R���͉��F�n�����Ƃ��Ēm���A�r���}�m�炪���Ă���@�߂���p�H�|�i�Ȃǂ��ގ��ɗp���鉩�F�̃E�R���z�Ȃǂ���߂�̂ɂ��p������B�����A�F���F�����ɘb�͂Ȃ�Ƃ���₱�����B
�@ �K�\�����X�^���h�ɗאڂ��邻�́u��������H���v�ŁA���{�����X�^���h�̌o�c�҂ł�����R������A����ɂ͂��Ƃ��猻�ꂽ����n��E�R���g���̑g��������Ȃǂ���_�Y�����H�̋�J�b���f�����̂����A���̒k�b�̂Ȃ��ʼn��{������u���̎���ǂ݊ԈႦ�Ď���X����l���悭�����ł���v�Ə��Ă���ꂽ�B�����������炠�̊Ŕɂ͉��{�����̗V�ѐS����߂��Ă���̂������ĂȂ��Ǝv������������B
�@ ���̔_�Y�����H���ł͒n���Y�̃E�R���A�R���A�g�}�g�Ȃǂ������ɂ����l�X�ȉ��H�H�i�̌����J�����i�߂��Ă����B�Ȃ��ł��A���������œ�����̂悢�Ƃ�����D�ރE�R���͔̍|�͍L�����̋C���n�`�ɓK���Ă���A���̒n��̓��Y���̈�ɂȂ��Ă���B�E�R���̖���͕i���엿�̐����ɂ���Ă��Ȃ�قȂ�Ƃ̂��ƂŁA���{����̂��E�ߕi�͎��t�E�R���������Ƃ̂��Ƃ������B�ƂĂ����\��ɂ͌����Ȃ����{����̌��N�̔閧�͂�͂�E�R���Ǝl���\�쌹���̐����Ȃ̂ł��낤���B
�@ �͔|���ꂽ�E�R���́A������Ƃ��Ă��������E�R�������ɂ���ق��A�E�R�����A�E�R������J���[���A�E�R�����胉�[�����ȂǂƁA�����̎��v��_���ėl�X�ȉ��H���p�̎��s�������Ȃ���Ă���炵���B�ς�����Ƃ���ł̓E�R�����X���C�X�������ł�������Ǝϋl�ߊ����������E�R���Ƃ������H�i�Ȃǂ��������B�E�R���̗t��s�̂ق��ׂ͍����荏��ő͔�ɍ���������A��͂�ׂ����ْf���Ċ������������܂ɂ���Ƃ��������p�@���l�����Ă���B
�@ �E�R�����ƃE�R���͉�X�����H�����Ă���������A�Ȃ��Ȃ��̖��������B�n���̓��Y�i�W���̔����u�X�̎O�p�ڂ����v�ł͊��ɂ����͔̔�����Ă��邻�������A�����悭���N�ɂ������Ă����ƂȂ�A�����Ȃɂ��������Ƃ͂Ȃ��B�����n���Ŕ����Ă��鎇�t�E�R���������w�����ċA�莎�p���Ă݂����A�����̃E�R���ɔ�ׂ悭��������Ă��ĕi���������A���݂₷�������������B�E�R���ɊS�̂�����͈����n��E�R���g���i0895-46-0011�j���u�X�̎O�p�ڂ����i0895-45-3751�j�v�ɖ₢���킹�Ă݂�Ƃ悢���낤�B
�@ �S�k���R���Ƃ��Ēn���Ől�C�̂���R���̉��H���������낢��Ɛi�߂��Ă���悤�������B�J���J���\���₨�D�ݏĂ��A�e��˗ނȂǂ̑f�ނƂ��Ă̊��p�Ȃǂ͏]�����玎�݂��Ă������̂����A�ʔ��������͎̂��R�������肨�낵�Ă��̂܂܂̏�ԂŒ����ۑ����A�K�v�ʂ�K�v�ɉ����Ďg����悤�ɂ��鏤�i�̊J�������̘b�������B
�@ �ŏ��͂��肨�낵�����R�������������������������ĕ��������݂Ă݂����A�p�T�p�T���Ă��ĂƂĂ��g�����ɂȂ�Ȃ������Ƃ����B�����ŁA���������ĕ�������ۂɓK�ʂ̓����������Ă݂�Ȃǂ̎��s���Ȃ���A����Ȃ�ɂ˂肯�����邱�Ƃ͂ł����̂��������B�����A���������߂���Ƃ���ǂ͋t�ɂЂǂ��˂��Ăǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ���ԂɂȂ��Ă��܂��L�l�ŁA���̒�����������̂ق������܂ЂƂ������炵���B
�@ �����ōl����ꂽ�̂��A���肨�낵�����R����^��p�b�N�ɂ��ĉt�̓����@�Ƃ�������ȋZ�p�ŗⓀ�ۑ���������𓀂�����@�������B���ۂɎ������Ă݂�ƁA�˂肯���������肨�낵������̏�ԂƂ����傫�ȕς��͂Ȃ����Ƃ��킩�����炵���B�t���Z�p��K�v�ݔ��̖��Ȃǂ������Ċ��S�ȏ��i���܂łɂ͂܂����Ԃ�������Ƃ������A�����悻�̖ړr�͂��Ă��Ă���炵���B���������ƁA���̉t�̓����@�̋Z�p���w�����Ă���̂��ق��Ȃ�ʎO���m����ł���B�O�����������Ă���Ⓚ�Z�p�͍L�����Ǝ��̑��̏d�v�v���W�F�N�g�ɂ���������邱�ƂɂȂ��Ă���A���ꂪ�{���̎O������̖����ł�����̂����A����ɂ��Ă͌�q����B
�@�_�Y�����H���i�̈�g�}�g�������H�����Ă���������A�\���Â��ăg�}�g�̎_���Ȃǂ��قƂ�NJ�����ꂸ�A���ꂪ�g�}�g�������ɂ������̂��Ƃ͂ƂĂ��M�����Ȃ����炢�������B����ɂ��Ă��A���́u�������ĉ��H�ڂ݃O���[�v�v�̑n���͂Ǝ��H�͎͂��Ɍ��グ�����̂ł���B�i��̐��_�ƓƑn�I�C���ɖ����݂��Ă������ẲF�a���˂̐��_�����̓`�����A���܂����̒n�ɂ͖��X�Ɛ��������Ă���̂�������Ȃ��B
�@ �_�Y�����H�i�̘b����i���������ƁA���{����́A�����̏W������܂������Ɖ��܂����Ƃ���ɂ��鎩�R����E�R���͔̍|�n�ɉ�X���ē����Ă��ꂽ�B�͂��߂ɗ���������R�����ɂ͍͔|��̎��R���������ɂȂ܂łɔɂ����Ă����B�쐶�̎��R���@��������Ԃ�Ƃ�������Ƃ̂��鎄�͂��̑�ς���m���Ă����̂ŁA���ꂾ���s�̑��������Ɗ��S�Ɍ@��o���̂͗e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ɖ�������ɐq�˂Ă݂��B����ƁA���͔|�̏ꍇ�ɂ͍��𐂒��ɐL�������A�ג����p�C�v��̗e���y���Ɏ߂ɖ��߂Ă��̒��Ő��������邩��A�@��o���̂͗e�Ղ��Ƃ����Ԏ����߂��Ă����B���[��A�������A����Ƃ����������R���́u���v�̎����u���v�̎��ɒu�������āu���R���v�Ƃł��ĂԂׂ��Ȃ̂��ȂȂ��ȂǂƁA���Ȃ��Ƃ��l������������B
�@ �Ō�Ɉē����ꂽ�E�R�����ɂ́A�傫�ȗt��点�đ����̃E�R��������Ă����B�E�R���͔̍|�����ڂɂ���̂͏��߂Ă��������A�����x�͎v���̂ق������A���ꂾ�ƍ�t�ʐς������L���Ȃ��Ă������ʂ̐��Y���\�Ȋ����ł���B���̂��߂������Ă��A��ʃE�R�����Ƃ����悤�ȏł͂Ȃ������B�����n��E�R���g��������ɂ��ƁA���݂̎��v�ł́A������ƍ�t�𑽂�����Ƃ����܂��ߏ萶�Y�ɂȂ��Ă��܂����˂Ȃ�����A�قǂقǂɐ��Y���T���Ă���̂��Ƃ̂��Ƃł͂������B
�@ �A��ہA���{����ɑ�����A�X�e�r�A�Ƃ����������ג����A���̗t���ς̐���ق�̂�����Ƃ�������ł݂�ƁA�ˑR�������ς��ɊÖ����L�������B�����̎O�S�{�̊Â��̐������܂ސA���Ȃ̂������ŁA�����̂����ɂ��̐A���̗t�̕�����p�������i���Ȃɂ��l�������Ƃ������Ƃł��������B
�@ ���{�����ƕʂꂽ���ƁA��X�͍L�����̓��Y�i�W���̔����u�X�̎O�p�ڂ����v�ւƈē����ꂽ�B�Ȃ��Ȃ��ɋ@�\�I�ş���������̔̔����ŁA�n��Y�̊e���ؗނ��ӂ�ɒu�������Y�g���^�c�̎s��Ȃǂ������~�n�ɐ݂����Ă���B�l�i�̂ق������邩��Ɉ����B�ό����s�҂݂̂�ړ��Ăɂ����P�Ȃ�y�Y�����ł͂Ȃ��A�����̓���I�Ȑ����Ƃ����ڂȊW�����Ă�悤�ɓX�̑���⏤�i�̒u������z�����Ă���Ƃ���Ȃǂ͂Ȃ�Ƃ��S�����Ƃ����ق��Ȃ��B
�@ ���Y�i�̔��W���R�[�i�[�̂ق����߂����Ă݂͂����A�y�Y���ƈ����ŗǎ��ȓ��p�i�Ƃ�����܂����Ă���A�̔����i�̎�ނ��ʂ��z���ȏ�ɑ��������B���i�̑����ɐ��Y�҂̖��O��b�Z�[�W���t�L����Ă���̂��傫�ȓ����ŁA�ǂ̋���o���ꂽ�A�C�f�B�A�Ȃ̂��͒m��Ȃ����Ȃ��Ȃ��ɍD�������Ă��B�������A�e��̃E�R�����H�i�Ȃǂ��̔�����Ă���A���r����̎��t�E�R�������ɂ́A�����قǂ����������̉������u����̖��O�̋L���ꂽ���̂Ȃǂ��������B�܂��A�؍ނ̎Y�n���������Ċe��̖؍H�i�Ȃǂ��s��ł͍l�����Ȃ��悤�Ȉ����Ŕ����Ă���A���|���ɂ����u����ɂ����x�i�ɂ��g�������ȎO��~�O��̑�̐芔�Ȃǂ́A�u���ꏊ��������ΎԂɐς�ł����ċA�肽�����炢�ł������B
�@ �X���̏��{���삳��ɂ��ƁA���̐X�̎O�p�ڂ����͎��{����X�ёg�����O���̈�A�L�������O���̓�o�����Ăł�����O�Z�N�^�[�^�c�̓��Y�i�̔��X�ŋq�͒����҂ƒ��O�҂����X���炢�ł���Ƃ����B���{����ɕ]���̂悢���Y�i�͉����Ɛq�˂��Ƃ���A���Y�ƖI���Ƃ��听���ɂ����������t�u�䂸�̗����C�����v�A�|���|�ݖ��u�䂸�̗��v�A�l���Ȃ�ł͂̌�����p�����u�ق�Ԃ��ݖ��v�A�`�������W���R����́u���肱���X�v�A������́u�����X�v�A���r����E�R�������Ȃǂ̖���������ꂽ�B�䂸�̗����C�����͎����w�����ē����ɖ߂莎�����Ă݂����A���ɗނ̂Ȃ����ƕ��������Ȃ������������ݕ��������B
�@ �Ō�ɉ�X�����w�����͍̂L�����̃��j�[�N�Ȓ��������v���W�F�N�g�̈�A賂̗{�B�{�݂������B�L�����͂��̒n�搫���������A������N������S���I�ɂ�������賂̗{�B���ƂɎ��g��ł��Ă���B�����̒��b�ی�@�Ȃǂ̋K���������ē��{�Y�̖쐶��賂����Ƃɗ{�B���Ƃ��s�����Ƃ͂ł��Ȃ������̂ŁA�L�����͒����Y�̍���賂̈���A������������Ƃɗ{�B���Ƃ�W�J���Ă����B��ʂɂ͓��肪��������ȃC���[�W�̂���賂����܂��{�B����ʂɏo�ׂł���悤�ɂȂ�A�����I�ɂ͒��̎�Y�Ƃ̈�ɂȂ肤��ƍL�����̎��Ɛ��i�S���҂����͍l�����悤�ł���B
�@ ������賂̗{�B�̔��v���W�F�N�g��
�@ ���t����Ɏf�����Ƃ���ɂ��ƁA����賂��Y������͎̂l������Z���ɂ����Ă̍��ŁA���͂��̎����ɕ��ώ��\���x���ނƂ����B���ł͂����ɂ����̗��c�̐����ɉ^�ѓ���ȍ\���̑�^�z����ɓ���ĎO�\���x�̒艷�œ�\�������\�O�����炢�̂��������߂�B�����賂̐����a������̂��Ƃ����B�����z�����珙�X�ɉ��x�������Ă��퉷�ɓK�������Ă����B�����̛z��������w�����Ă���������A�Ȃ�قǐ��̒��ɂ͂��܂��H�v���ꂽ�@�킪������̂��Ɩ��ɊS��������L�l�������B
�@ �z���������͈ꃖ���Ԃقǐ����ň�Ă��A���̂��ƈ�H�ܕS�~�Œn���̊e�_�Ƃւƈ����n�����B�X�̔_�Ƃ͂��̐��N���炢�����Đ����Ɉ�ďグ�A���͂������H���ܕS�~���炢�Ŕ����߂��B�����āA�K�ȉ��H�������قǂ����Ĕ̔����[�g�ɏ悹��B�_�Ƃ�賂𐬒��ɂ���̂ɗv���鎔����̑��͈�H�ɂ���~�ǂ܂肾�Ƃ�������A���̍��v���_�Ƃ̎����ɂȂ�킯���B賂͎G�H���ő���t�Ȃǂ��H�ׂ邩��A�u�L�������Y�̃E�R���ƈ��X���̐����ň�Ă�������賁v�Ƃ������悤�ȃC���[�W�Ŕ���o���헪�����邩������Ȃ��ł��˂ƁA���t����͏��Ă����B
�@ 賂������Ƃ����������͈̂ꌎ������Ȃ̂������ŁA���̎����ɂȂ�ƔɐB�p�̐����ȊO�͂��ׂď������A�Œ�ł���N�Ԃ͖����ς��Ȃ��悤�ɗⓀ�ۑ�����̂��Ƃ����B�킸����N�̖���賂̂��Ƃ��v���Ƃ�����Ɖ��z�ȋC�����Ȃ��ł͂Ȃ����A�H�ނƂȂ��Ă��邱�̐��̒��̓����̑唼���݂Ȏ����悤�ȉ^�������ǂ��Ă���킯������A����͎d���̂Ȃ����Ƃ��낤�B
�@ ���璆��賂̗c����A���̎����܂œ��ʂɎ����Ă��鐶���N�ȏ�̐����Ȃǂ������Ă���������A�����Ȋ������賂����͋��Ԃ̒���ꂽ�Q�[�W�����������Ƒ������Ă����B�����������肵�Ă��āA�܂�Ń_�`���E���ɓx�ɏ��^�����������X�����ɂ����悤�Ȋ����ł���B������炵�đ����ɋC���̌��������Ȓ������璇�ԓ��m�̌��܂��₦�Ȃ��悤�ŁA�˂���ċ���w���̉H���������������������Ă��܂��Ă�����̂�����B���n�ȂǂɈ琬�p�Q�[�W��݂���悤�ȏꍇ�ɂ́A�C�^�`���y���@���ĐN����賂��P���̂�h�����߁A�Q�[�W�̊�ꕔ����������ƌł߂�K�v������Ƃ����B
�@ ���܂��܌��w�����傫�Ȏ���p�Q�[�W�̎��ӂ͐[�X�ƎG���̔ɂ鑐�n�ɂȂ��Ă������A�����ȍL���̂���Q�[�W���ɂ͂܂��������������Ă��炸�A���������n�������̂܂ܔ����o���ɂȂ��Ă���B�ǂ����賂ǂ����G������{�c�炸�H�אs�����Ă��܂������߂炵���B�����ɑ����̎G������݂͂�����������ċ��Ԃ̌��Ԃ�����荞��ł݂�ƁA��}���ŋ삯����Ă���賂̉��H���������������ɐH�ׂĂ��܂����B
�@ ���݂͂܂�賂̑�ʐ��Y����їⓀ���H�����v���W�F�N�g���{�i�I�ɉғ����Ă��Ȃ��̂ŔN�ԓ�A�O��H�̔̔����тɂƂǂ܂��Ă���悤�����A�߂������ɔ̔����[�g���g�債�A�����H����賂̐��Y�o�ׂ������Ȃ��v��Ȃ̂��Ƃ����B�ǂ����A�u賂̒��v�Ƃ��čL������S���I�ɔ���o���헪����t�����͗��ĂĂ�����炵���̂��B���̂��߁A賂̉�̂���Ⓚ�����܂ł���т��Č����悭�����Ȃ��H������ܒ����Ɍ��ݒ��ŁA���̐v�ɂ����s�̎O������͊ւ���Ă���Ƃ����킯���B�����ɂ���n���̃V���N�^���N�A�l�������������Ƌ��͂��A���O�����Ƃ��ɗ͂𒍂��ł���̂�賂̗Ⓚ�ۑ��H�������S�Ȃ��̂ɂ��邱�Ƃł���炵���B賓����ō��̖��̏�ԂŒ����ԗⓀ�ۑ����邽�߂ɂ́A���̓����̓��ꐫ�ɕt�����鍂�x�ȋZ�p�I���̉������K�v�ł������悤�Ȃ̂����A�t�̓����@�Ƃ�������Z�p�̓������������J��Ԃ������ʁA���������N���A����ړr���������̂��Ƃ����B
�@ �����I�ɗⓀ�������ꂽ賓��̓��V�s�t���ł��łɍL�����Ŕ̔�����Ă���A�����̃O�����t�@�[�����X�i0895-48-0136�j�Ȃǂɒ�������ΗX�֏���ő����Ă��炦��B�����O�������ʂ��ē����ōL�����Y��賂���肵�A賓�ɂ��ĐH�ׂĂ݂����Ƃ����邪�A��ςɔ����ł������B�c���Ȃǂɂ͐̂�����ʂ�賗������`����Ă���̂������ł��邪�A����܂ʼn�X��ʏ����ɂƂ��Ă�賗����͂��܂艏�̂Ȃ����̂ł������B�{�Ȃǂɔ�ׂĂ܂��P���������Ƃ͂����Ă��A賗�������ʉƒ�̐H�����킷���ƂɂȂ�Ƃ���A����͊�Ԃׂ����Ƃł���B
�@ ��ʂ蒬���̊ό��X�|�b�g��Y�Ǝ{�݂����w���I���A���t����ƍ��c����ɕʂ�������čL���������Ƃɂ��鍠�ɂ́A����قNj��������z��������߁A�傫�����̋�ւƌX���Ă����B�Z���؍݂ł͂��������A�L�����ɏZ�ސl�X�Ƃ̏o�����̈�ЂƂ͂ǂ����ϐS�Ɏc����̂ł������B�L���Ȏ��R�Ɛl��ɕ�܂�A����ł��Ď����Y��ʓƑn�Ɛi��̐��_�����Ȃ����������Q���L�����̔��W���F��ĖK��Ȃ���A���͉F�a�����ʂւނ����Ă����ނ�ɎԂ̃n���h��������̂������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N11��8��
�f��̐씩���������K�˂�
�@ �㌎���{�̒�������̂��ƁA�����O��s�[�厛�̊ՐÂȏZ��X�ɁA���@�C�I���j�X�g�̐씩������������K�˂����B�O���ɃR���T�[�g�̂��������É�����߂�������̂����ɁA�قǂȂ��������D�y�ł̃R���T�[�g�ɔ����ė��K�ɓ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��������ł͂��������A�씩����͌䗼�e�̐��Y�����q���X�A����߂Ď��I�Ȃ��̓��̖K�����������Ă����������B�������A�����͓�A�O���Ԃقǂł����Ƃ܂������ł����ɂ�������炸�A�씩�Ƃ̊F����̂��D�ӂ������āA���ǁA���s�̎��̌�y���X�A��\�ꎞ���܂ʼn��X�Ƙb�����ތ��ʂɂȂ��Ă��܂����B
�@ ��������̕��N���Y����Ǝ��ɂ͎������ɋ��ʂ̒m�l������B���Y����Ƃ͗c�Ȃ��݂̂��̒m�l����ă��@�C�I���j�X�g�씩��������̑��݂�m�����悤�Ȃ킯���������A���̖��p�I�Ȍ��̋����Ɋ������Ă���Ƃ������́A���͔M��Ȑ씩�t�@���ɂȂ��Ă��܂����B�����Ă��܂ł͏Љ�҂ł��鎭�����̒m�l�������u���Đ씩�Ƃ̊F����ɂ͑�ύ��ӂɂ��Ă��������Ă���B�{���̉䂪�Ƃ���씩�Ƃ܂ł͎Ԃœ�\�����炸�Ȃ̂ŁA��������Ɏf���̂ɂ��قƂ�ǎ��Ԃ͂�����Ȃ��B
�@ ���܂�씩�`���Ƃ��Ȃ���鐬������̌o����P�������Ɛтɂ��Ă͊e�탁�f�B�A�Ŋ��ɌJ��Ԃ��Љ��Ă��邵�A�����g���ȑO�ɂ��̃R�����ŕM�����������Ƃ����邩��A���炽�߂Ă����̎����ɏڂ����G��邱�Ƃ͂��Ȃ��B�����ł́A���y�ɂقƂ�ǖ��m�Ȑl�Ԃ̃Q�����I�K��ɂ���ē���ꂽ���ʁi�H�j�����ƂɁA��A�O�T�ɂ킽���Đ���������͂��߂Ƃ���씩�Ƃ̊F����̑f��̈�[���Љ�Ă݂悤�Ǝv���B�����܂ł��u�f��̈�[�v�Łu�S�e�v�ł͂Ȃ�����A���̓_�͂��炩���߂��f�肵�Ă��������B
�@ ���̓��씩�Ƃ̖�O�ɗ����ă`���C����炷�ƁA��������Ƃ����e�̐��Y�����q�������Č��ւɌ���A��X��l���������}������Ă����������B��X���ʂ��ꂽ��K�̊Ԃ́A���������A��͂�|��o�̃��@�C�I���j�X�g�ł��鐳�Y�����K�Ɏg���Ă����镔���������B����l�̗��K���i�Ȃǂ��z���ł��ĂȂ�Ƃ�������������ł͂��������A���̕������q�̉�X����̂��Ă���ԁA��������͖{�i�I�ȗ��K���ł��Ȃ��Ƃ��ƂɂȂ��Ă��܂��B������ƐS�z�ɂȂ��Ă����̂ł��̓_���m�F����ƁA�O�����h�s�A�m��u���Ă���ʎ����K���ɂ���A�����ł����K�ł��邩��C�����͂���Ȃ��Ƃ̂��Ƃł������B
�@ ��������ׂ̗ɍ��������́A������K���ɂƂ���ɁA���y�ɂ͕K�������W�̂Ȃ����̂���������̓V�˃��@�C�I���j�X�g�Ɏ��X�ƂԂ��Ă݂邱�Ƃɂ����B�܂��A���Y����Ɨ�q����̂���l�ɂ������Ȃ��s�^�Ȏ���������Ă��炤����ł����B���̂ւ�͂܂��A���疳�m�̊Z��Z�����g�̂قǒm�炸�̉��y���s�l�Ԃ̋��݂Ƃł����������Ȃ����낤�B
�@ �܂������ɐH�ו��̍D�݂ɂ��Đq�˂�ƁA�`�������W���_������������Ȃ�ł��H�ׂ�悤�ɂ��Ă��邪�A��͂�m�H�Ȃǂ��a�H�̂ق������������Ǝv���Ƃ̂��Ƃ������B��������̊������_���u����Ă���C�M���X�́A�̂����ʓI�ɂ��܂���H�ɂ������Ȃ�������������A���̂Ԃ�悯���ɂ���Ȏv��������̂�������Ȃ��B��������̉p���؍ݎ��A��ɐ��������ɂ��Ă��邨�ꂳ��̗�q����́A�ĂȂǂ��͂��߂Ƃ�����{�H�̐H�ނ����߂ă����h���s���̂��Ȃ藣�ꂽ�Ƃ���܂Ŕ������ɏo�����邱�Ƃ������炵���B�u���L���̕Ă̂ق��ɑ��̐H�ނ���p�i�����킹�Ĕ������݁A�o�X�ɏ���Ď����A��̂ł�����A����Ⴀ痂������Ȃ�܂���v�Ɨ�q����͏��Ă���ꂽ�B��q����́A�y�Ȃ̕��ʂڂɓǂݎ�邱�Ƃ̍���Ȑ�������̈Õ���Ƃ��s�A�m��e���Ď�`���������A�ً��̒n�ł̓��퐶���Ɍ������Ȃ��G���̂��ׂĂ������Ȃ��Ă�����킯�ł���B
�@ �܂����������������s���̖�Q���̂ɑ������Ă��炱���ɂ�����܂ł̗�q����̐h��̓��̂�͑z����₷����̂ł������悤�����A����Ȑ̂̋�J�̉A�Ȃǂǂ��ɂ����������Ȃ��ƂĂ��C�����őf�G�ȕ��ł���B�m���Ƌ����M�O����ɔ�߂Ă�����ɂ�������炸�A�܂���������C�̂Ȃ������I�Ȋ����̕����Ə������Ă�������ق����悢�����m��Ȃ��B�������萬����������������A���̋����������ė�ÂɌ��߂Ă�����̂���ψ�ۓI�������B��������̃��T�C�^���Ȃǂł͂����A���Y�������q������܂������ڗ����Ȃ��i�D�����ď��ҋq�ȂǂƂ͗��ꂽ���̕Ћ��ɂ����ƍ����Ē����Ă�����B�������ʂ̐������o���ɂ��A�X�̂��q����̎��含�d����Ƃ����̂��̂���̐씩�Ƃ̋�����j�������悤�ŁA���������A�s���̖�Q���̂Ȃǂ��Ȃ���ΐ�����������y�ƂȂɂ������͂Ȃ������̂��Ƃ����B�\�܂Ő�������Ɋy��������������Ƃ͈�x���Ȃ��������A���ہA��l�̒킳���͉��y�Ƃ͂܂�Ŗ����̓������ł�����悤�ł���B
�@�u���{�H���H�ׂ���Ƃ������X�ɓ����Ė��X�`���o�Ă����Ƃ���܂ł͂�����ł����A���̖��X�`������������݊����܂ł͌�т��͂��ߎ��̗������o�Ă��Ȃ���ł���B�~�\�E�X�[�v�����琼�m�����̃X�[�v���݂��Y��Ɉ��݊����Ă���łȂ��Ǝ��̃f�B�b�V�����o���Ă��Ȃ��Ƃ������ƂȂ�ł��傤���c�c�v�ȂǂƁA�C�M���X�ł̐H�����܂��G�s�\�[�h�̈�[����܂���Ɍ���Ă���鐬������͎��ɉ������̂��̂ŁA�b�͂ǂ�ǂ�e��ł������B
�@ �ꗬ�̉��y�ƂɌ������āA���܂���A�u�ǂ�ȉ��y�����D���ł����H�v���Ȃ������A����ȋ��ɂ���������͂ɂ��₩�ɉ����Ă��ꂽ�B�ǂ�ȉ��y�ł����Ă����ꂼ��ɌŗL�̑f���炵������߂��Ă���A�܁X�̐l���̂Ȃ��ł����ɏo�����A�����������������A�܂���������w������Ă����킯������A���ǁA�ǂ�ȉ��y�ł�����Ȃ�ɍD�����Ƃ������ƂɂȂ��ł��傤�ˁA�Ƃ����̂���������̓����������B�W���Y��|�b�v�X�Ȃǂ��D��Œ������肷�邱�Ƃ�����炵���B
�@ �ǂ̍�ȉƂ̋Ȃ��D���ł����Ƃ����₢�������邱�Ƃ͏�̂��Ƃł���炵�����A������ȉƂ̍�i�����Ċ����I�Ȃ��̂���������łȂ����̂����邩��A��T�ɂ͓������Ȃ��Ɛ�������͏��B�V���ȋȂɏo�����A����Ƀ`�������W���Ă����ߒ��ł͂��߂Ă��̋Ȃ̔�߂��f���炵�������邱�Ƃ̂ق��������Ƃ̂��ƂŁA���̈Ӗ��ł��D�݂̋Ȃ͓��肳��Ă͂��Ȃ��̂��Ƃ����B�l�\��A�\��̉~�n�����ɂ݁A�S�Z���ʂɂ����邢�������̔���ڎw���Ď��ȗ������̐�������ɂƂ��āA����͓��R�̂��ƂȂ̂��낤�B�����ēǏ��ɂȂ��炦��A���Ȑ����ɂ�ď����̍D�݂����̖{�ɑ���]����F�����ς���Ă���̂Ɠ����悤�Ȃ��̂ŁA���i�����̓��X�𑗂��Ă��鐬������̏ꍇ�ɂ͂Ƃ��ɂ��̌X���������Ȃ̂��낤�B
�@ ����I�Ȑ����p�^�[���ɂ��Đq�˂�ƁA�����h���ɂ��鎞�Ȃǂ́A��̌ߑO�������ɋN�����A���H�⒋�H�A�x�e�Ȃǂ��͂���Ōߌ�\�����܂Ń��@�C�I�����̗��K������̂����ۂɂȂ��Ă���Ƃ����B���K�I����ɒx���[�H���Ƃ��ď\���ɏA�Q���邩��A���ϐ������Ԃ͔����Ԃ��炢���Ƃ̂��Ƃ������B�����I�ɂ͓��ɔ����Ԃ��炢�͐��_���W�����̗͂̏��Ղ�ɂ��܂����������K���d�˂Ă���킯�ŁA����́u�V�˂̉A�ɓw�͂���v�̋�����n�ł����悤�Șb�ł���Ƃ����Ă悢�B�����ƌĂ��\���X�g�����͊F�A����ɂȂ��Ă������\���Ԃ��炢�͗��K������̂�������O�Ȃ̂������ŁA�Ȃ��ɂ͏W���͂��ێ����邽�߁A�����Ԃɂ킽����K�����������H�������Œʂ��l������Ƃ����B
�@�u��Ћ߂̕��X�Ȃǂ͒N�����Ė��������Ԃ�\���Ԃ̎d���͂Ȃ���킯�ł��傤�B�����������Ă��ꂪ�d���Ȃ킯�ł����A�킴�킴���ɑ����^�сA����Ȃ�̗������Ē����Ă��������ȏ�A�v���Ƃ��ē��R�̂��ƂȂ̂ł͂Ȃ��ł��傤���v�ƁA�Ȃ���ȁi�Ă�j�����Ȃ���������͌����Ă̂���B�\�Ń��@�C�I�������n�߂������A��Q�Ŕ畆�̒ɂw�悩�猌�𗬂��Ȃ��畃���Y����̖ғ��P�ɑς��A�������đ�U���ł͂Ȃ��l�̐��{�͗��K��ςƂ�������������Ȃ�ł��Ȃ��̂�������Ȃ����A���̂悤�ȕs���҂ɂ͑�ώ��̒ɂ��b�ł͂������B
�@ �����h���s���̐�������̃A�p�[�g�����g�̓O�����h�t���A�i��K�j�Ȃ̂������ŁA��̃t�@�[�X�g�t���A�i��K�j�ɂ͒j�̎q��l�̂�����₩�ȉƑ����Z��ł���炵���B���̂��ߓV�䂲���ɕ������Ă��镨���������Ȃ��̂Ȃ̂����������A��������ɂ͂��̂ق����D�s���ł�����悤���B�ނ��A��������̂ق������������ɂ��������胔�@�C�I�����̗��K�ł��邩�炾�����ŁA���܂ł͏�K�ɏZ�ނ��̉Ƒ����������肻�̉��y���i�H�j�ɓ�炳��Ă��݂��a�C�\�X�Ȃ̂��Ƃ����B�V�˃��@�C�I���j�X�g�̐����t���o�b�N�O�����h�E�~���[�W�b�N�ɂ������퐶���Ƃ������̂����������ǂ�Ȃ��̂���x�̌����Ă݂����C�����邪�A���������͖쎟�n���_�����Ȃ��̐g�ɂ��ǂ����悤���Ȃ����Ƃł͂���B
�@ ��������͂��̃����h���̏Z�܂�����A��w�@���ƌ�̂��܂��������y�@�̐搶�̂��ƂɃ��b�X���ɒʂ��A����ɂ͎��X���[���X�^�[�ɏ���ĉp���C���̃g���l����������A�p���ݏZ�̃t�����X�E���@�C�I�����E�̑��l�ҁA�K�X�g���E�v�[����K�˂āA���̋�������Ă���̂��Ƃ����B�����ԃ����h���̃A�p�[�g����ƁA�p�����L�̋C���A�p�[�g�̍\����̊W�ł����܂��Z�߂Ȃ��Ȃ��Ă��܂������ꂪ����̂ŁA�s�݂̊Ԃ͉������y�@���w�ȗ��̐e�F�Ńs�A�j�X�g�̃_�j�G���x���E�s�G�i�[���Ɏ��R�Ɏg���悤�ɂ��Ă�����Ă���̂��������B��A�t���J�o�g�̃s�G�i�[���͂�͂艤�����y�@��w�@���Ƃ̗D�ꂽ�s�A�j�X�g�ŁA�씩�������T�C�^���̔��t�҂Ƃ��Ė��R���r��g�݁A�ߔN�����ł��L���m����悤�ɂȂ����l�����B�������s�݂̎��A��K�ɏZ�ނ�����̈�Ƃɂ̓��@�C�I�����̋����ɂ�����ăs�G�i�[���̒e���s�A�m�̖��Ȃ̉����������Ă���̂ł��낤���B����Ȗ��Ȃ��Ƃ����������C�ɂȂ�͂������A���̓_�ɂ��Ă͂��������R�炵�Ă��܂����B
�@ ��������ƒk���Ȃ���A���͎l�{�̌���_�Ƃ̂��Ƃ��J�����̍���̎w�������Ă��炤���Ƃɂ����B�����傫�Ȃق��ł͂Ȃ���������̎�͑S�̓I�ɂƂĂ��_�炩�ʼn����������B�w�̐�[�͂�����ƕ��Ȋ����ɂȂ��Ă��āA�p���Ƃ�Ă������ۂ݂�тт������ȃT�C�R���̕\�ʂ�A�z�������B�ނ��A�\���N�̒����ɓn�錷�Ƃ̊i���̌��ʂȂ̂��낤�B������������w��̕���ȕ����ɐG���Ă݂�ƈӊO�Ȃقǂɏ_�炩���������A�������ɂ��̔畆�̈ꕔ�͂��Ȃ�ł��Ȃ��Ă����B
�@ �����A�����\�z���Ă����悤�ȃy���_�R�Ȃ݂̌ł��ł͂Ȃ������B��������̐��Y����Ɏf�����Ƃ���ł́A�I�m�Ɍ����J���ɂ͎w�̐�[�͂Ȃ�ׂ��_�炩���ق����悢�̂��Ƃ����B�����̎��Ȃǂɂ͌ł��Ȃ�Ȃ��悤�Ɍy�̂悤�Ȃ��̂�p���Ďw���������悤�ɂ��Ă���̂��Ƃ̂��Ƃ������B�����ۂ��A�e�j�X�̑I��ȂǂƓ��l�ɁA�|�����E��̂ق��͒��N�̂����ɍ���Ɋr�ׂď������蒷���Ȃ�炵���B������A�m���Ȃǂ��d���Ă�ۂɂ͉E���߂ɂ���K�v������̂��������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N11��15��
�K�_�j�[�j�Ɏ肪�k����I
�@ �Ԃقǂł��ɂ������ł����̂����A�����Ƃ����ɗ\��̎��Ԃ͉߂��Ă��܂����B���͐씩�Ƃ̊F����ƒk�𑱂��邩�����A������Ɨ����オ���ĕ����̂Ȃ��̂�������������ƂȂ����߂����Ă�������B�^����Ɏ��̖ڂɂƂ܂����̂́A�����̕ǂɒ���ꂽ�ꖇ�̎ʐ^�������B�߂Â��Č���ƁA���̎ʐ^�ɂ͎O�l�̐l�����ʂ��Ă����B���@�C�I�����������ĉE��ɗ��̂������܂��\�O�̒��w����������������A����̈�l�͂��ꂳ��̗�q����A�����Đ^���ɗ������̐l�����������@�C�I�����E�̋����A�C�U�b�N�E�X�^�[�����̐l�������B
�@ ���̔N���܂��ܗ��������X�^�[���͌��J���b�X���̏�Ő씩���N�̑t�ł郔�@�C�I�����̉��F�����߂Ď��ɂ��A���̑f���炵�����^�����Ƃ����B���������ƂŒm���A�e�ՂȂ��Ƃł̓��b�X������J�߂Ȃ��X�^�[���ɂ��̍˔\��F�߂Ă���������ƂŁA�悤�₭���@�C�I���j�X�g�̓�����܂��錈�ӂ������ƁA��N�A���Y����͌���Ă�����B���̋����X�^�[���Ƃ̋L�O���ׂ��o�����̏u�Ԃ������߂��̂����̈ꖇ�̎ʐ^�ł������B�g���{�ዾ����������Ƌْ��C���̐���������ɂ��₩�ȏ݂ŕ�݂ق������̂悤�ɗ��A�C�U�b�N�E�X�^�[���̎p���Ȃ�Ƃ���ۓI�������B�Ⴂ���Ɏ������x�����t���Ŗڂɂ����S�����̃X�^�[���́A�ǂ����ߊ�����͋C��X�����l���Ɍ����������ɁA���̎p�͈ӊO�ɂ����v��ꂽ�B���ׂ̗ɂ�������ꖇ�̎ʐ^�̂ق��ɂ͗�q����ɕ����ꂽ�c�����ǂ��Ȃ��������ʂ��Ă������A�����̓V�˃��@�C�I���j�X�g�̕З����̎ʐ^�̒��̎p���犴����邱�Ƃ͂܂��������ɓ�������B
�@ �\�ɂȂ��Ă͂��߂ă��@�C�I�������K���͂��߂���������́A�X�^�[���Ƃ̏o�����ɐ旧�O�N�ԁA�S�Ɖ����������Y����̓��P�ɐ₦�ʂ����B���q�̏������Ă��鐳�Y������K���ł���������A���̃��b�X���͑s����ɂ߂��炵���B�����A�u���ƕ�̐��i����������Ǝp���������ŕ�����������������ł��v�ƌ�鐬������́A���e�Ƃ̍����̐킢�Ƃ������ׂ����̃g���[�j���O�Ɋ��R�Ɨ������B���@�C�I�������K���͂��߂Ĉ�N���قǂŃ`�S�C�l�����C�[������ʂ�}�X�^�[���Ă��܂����Ƃ�����������́A��N�قǂʼn��t�Z�p�I�ɂ͐��Y�����ǂ������Ă��܂����炵���B
�@ �u��������ɒǂ������ꂽ�Ƃ킩�����Ƃ��̂��C�����͂ǂ��ł����H�v
�@ ���Y����̊�����Ȃ��痦���ɂ����q�˂�ƁA��u�A�����̊Ԃ����������ƂŁA
�@�u��͂�����������ł��˂��c�c�v�Ƃ����Z���Ԏ����߂��Ă����B���̎���������Ɍ������Ď���̐S�̓������t�ɂ����o���͂��Ȃ������̂ł��낤���A����͐��Y���S�Ƃ��Ă̑��݈Ӌ`���������u�Ԃł��������B���͂⎩���̎�ɂ͗]��ƌ�������Y����́A���̌�̎w���𑼂̐��Ƃɑ������Ƃɂ����Ƃ����B
�@ �u�ߍ��͐e�Ǝq��l�Ń��@�C�I�����≹�y�̏����ɂ��Č��_�����킷���Ƃ����\�����ł���B��l�̊Ԃɂ͂������l�����◝�O�̈Ⴂ�Ȃǂ�����Ȃ�ɂ������肵�܂�����c�c����ɁA�ǂ������Ȃ��Ȃ�����܂���ˁv
�@ ��q����͐��Y����Ɛ�����������ڂɌ����Ȃ���A���Ď��ɂ������������Ă����������B
�@ �h�A�ɋ߂��ǖʂɂ͓�̏����ȃ��@�C�I�������|�����Ă����B�ނ�����q���̍��Ɏg���Ă������@�C�I�����ŁA���ɋ߂Â��Ă悭�悭�ώ@���Ă݂�ƁA�����Ԃ�Ǝg���Â��ꂽ���Ƃ�����B���̃��@�C�I������ǂ���O���Đ�������ɒe���Ă��������A���������ǂ�ȉ����ł�낤�ȂǂƖ��Ȃ��Ƃ���S�ōl���Ă݂���������B�����A�ǂ��݂Ă������̃��@�C�I�����͂����ɒe�����Ԃɂ͂Ȃ������̂ŁA�������ɂ���Ȃ��肢������͎̂v���Ƃǂ܂����B����ɁA�u�O�@�͕M��I���v�Ƃ������͂�����̂́A�����̐g�̂ɓ���ނ܂łɉ��N�Ԃ�������Ƃ������@�C�I�����̏ꍇ�ɂ͘b�͂����ȒP�ł͂Ȃ��ɈႢ�Ȃ��B
�@ ���������ݎg���Ă��郔�@�C�I�����̓����������P�[�X�́A���������̏��̋��ɒu���Ă������B���@�C�I�����͔����Ȋy��Ȃ̂ŁA�n�k�̂Ƃ��̂悤�Ȏv��ʐU����Ռ������邽�߁A���ʂɐU���z���p�̃N�b�V������~�����̏�ɃP�[�X��u���Ă����̂��Ƃ����B���[���b�p�Ɋr�ď�͋C���Ǝ��x���͂邩�ɍ����A�t�ɓ~��͋C���Ǝ��x���Ⴍ�Ȃ肪���ȉ䂪���ł́A���@�C�I������u���Ă��������̎����Ǝ��x�����d�ɊǗ�����K�v������B���̂��߁A�����������ז����������́A�펞�A�قڎ�����\�l�x�A���x�\�p�[�Z���g�̏�Ԃɐ��䒲������Ă���炵���B�ˊO�Ń��@�C�I�����������������̂��߂ɁA�P�[�X���̉��x�⎼�x���R���g���[�����鏬���Ȃǂ��J������Ă���Ƃ̂��Ƃ������B
�@ ���Y����͂킴�킴�P�[�X���J���A���������ݎg���Ă��郔�@�C�I���������o�����Ɍ����Ă����������B���Y����̌��t�ɓ������܂܂ɁA����Ԃ����a�i���̏�ʂ̍ג����a���j�̕Е����炻�̃��@�C�I�����̂Ȃ���`���ƁA������ʂɋL���ꂽ�C�^���A�l�����J.B�K�_�j�[�j�̏����Ƃ��̐���N������� 1770 �Ƃ���������ǂݎ�邱�Ƃ��ł����B���삩����ɓ�S�O�\�N���o������Ƃ������ƂɂȂ�B��ύ����Ȃ��̂ł���ɈႢ�Ȃ����̖���Ɏ����G�ꂳ���Ă���������A�����������ɗ��Ƃ������ς��ƌ����v�������������A�ْ��̂��܂肩�����ė��肪�����݂ɐk���Ă��܂��L�l�������B
�@ ���ۂɊԋ߂Ŗڂɂ����uJ.B�K�_�j�[�j�A1770�v�Ƃ������̖���́A�v���̂ق����U��ŁA�f�ނ̖ؖڂ��͂�����ƌ����A�ӊO�Ȃقǂɑf�p�Ȋ����̂��郔�@�C�I�����ł������B�\�ʂɓh���Ă���j�X�͓����ł��������邢���y�F�����Ă���A�j�X�̓h�肻�̂��̂�����߂Ĕ����B�����烔�@�C�I�����̍ގ��̖ؔ������̂܂ܕ\�ʂɕ����яオ���Č����Ă����B�������A���������ɂ���������r�⏬���Ȗؔ��̂��Ȃ�������Ȃǂ͑f�l�ڂɂ�����Ǝ��ʂł���قǂ������B�܂���u���b�W�ƌĂ���̌��̎x�������ȂǂɌ���Ɠ��̌Âы�ɂ��A��S�O�\�N�Ƃ������̗��ꂪ�͂�����Ɗ�����ꂽ�B
�@ ���Y����������Ɏf�����Ƃ���ł́A�X�g���f�B�o���E�X��K�_�j�[�j�Ƃ��������S�N���̃��@�C�I�����̖���Ŗ��r�̂��̂͂قƂ�Ǒ��݂��Ȃ��̂��Ƃ����B����{�̂��傫������Ă��܂��悤�Ȃ��Ƃ��N������������ǂ����悤���Ȃ��炵�����A�����Ȗ��r�Ȃǂ͂��̎��X�ɋZ�p�E�l�ɂ���ĕ�C����A���݂܂ő�ɓ`���c����Ă��Ă���̂��Ƃ����B�����������@�C�I�����Ƃ����y��̓��̕��͉��H�����f�ނ̔��j�J���Œ��Ӑ[�����荇�킹�ďo���Ă���̂������ŁA���N�g���Ă���Ƃ��̃j�J���������I�ɔ��������Ă��܂��ڍ����Ɍ��Ԃ��������肷����̂炵���B���R�A�����Ȃ�Ɖ����ς�艉�t�Ɏx�Ⴊ�����邩��A����I�ɕ�C���̋Z�p�E�l�Ɉ˗����đ��ڂɕs�nj����Ȃ����ǂ����̃`�F�b�N���A�����Ƃ��낪����������ɏC�����A�������Ă��炤�̂��Ƃ����B
�@ ����ƌĂ�郔�@�C�I�����̏�Ԃ�I�m�ɐf�f���s�nj��𑁊��ɔ�����C���������ŁA���̊y��{���̔��������F���o��悤�ɒ������قǂ�����ꗬ�Z�p�E�l�͐��E�ł�������قǂ������Ȃ��̂��������B�c�O�Ȃ�����{�ɂ͂��̃��x���̋Z�p�E�l�����Ȃ��̂ŁA��������̏ꍇ�̓����h���̐��E�l�Ɉ˗����ĕ�C�≹�̒����������Ȃ��Ă�����Ă���Ƃ����B�k���̂悤�ȂƂ���ɉ��t�ɂł��������Ƃ����ɉĊ��̓��{�̂悤�ȋC�ۏ����̑傫���قȂ�Ƃ���ɏo�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����ɂ́A�ɒ[�ȉ��x�⎼�x�̊r���ɂ���ă��@�C�I���������e�����傫������A�Ƃ��ɒ��ӂ��K�v���Ƃ̂��Ƃł���B����ȏꍇ�ɂ́A�K�����@�C�I�����̃`�F�b�N����悤�ɂ��Ă���Ƃ����B
�@ �씩���q���炢�낢��Șb���f���Ȃ��ŁA���@�C�I������r�I���A�`�F���Ƃ��������y��̓��̓��ɂ́u�R���`���E�v�ƌĂ����̂������āA�������o�������ł��ꂪ�ƂĂ��d�v�Ȃ͂��炫�����Ă���炵���Ƃ������Ƃ�m�����B�R�E���M��X�Y���V�̂悤�ȍ��������@�C�I�����̒��ɐ��݂��ĉ����ɍv�����Ă���ȂǂƂ́A���y��̍\���ɑa�����ł��������ɍl���͂��Ȃ��������A�u�R���`���E�v�Ƃ͂��������ǂ�ȃV�����m�Ȃ̂��낤�ƕs�v�c�ɂ͂��������B�����Ő��Y����ɏڂ����b��u���Ă݂�ƁA�Ȃ�Ɓu�R���`���E�v�Ƃ́u�����v�Ə����Ƃ̂������ŁA���@�C�I�����̓��̓��̕\�i��j�Ɨ��i���j�Ƃ̊ԂɈ�{�����x���Ƃ��Ĕz����Ă���ׂ��~���̂��Ƃ��Ƃ����ł͂Ȃ����B���Y����ɑ�����Ă����a���烔�@�C�I�����̓������悭�悭�`���Ă݂�ƁA�Ȃ�قǁA�~���ג����x���̈ꕔ�炵�����̂����̂ق��ɂ�����Ƃ��������Ă����B
�@ �����Ƃ������͕̂K�v�ɉ����ē�������悤�ɂȂ��Ă���炵���B���̍����̈ʒu���ړ�����Ƃ���ɉ����ē��̗̂��ƕ\�̔̒����⓷����ԓ��̋�C�U���������ɕς��A���̂��߂Ƀ��@�C�I�����̉����̂��̂��ǂ����������ω�����B�܂��A�������̂��̂�ʂ��Č��̐U�������̂̕\�����痠���ւƓ`���A���ꂪ���̑S�̂̋��ɑ傫�ȉe���������炷�B���������āA���̃��@�C�I�����̉��F�̂悳���ő���ɂЂ������ɂ́A���̎��X�̊y��̏�Ԃɍł��K���������̈ʒu��I�m�ɒ�߂Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ǂ�Ȗ���ł������̈ʒu���K�łȂ�����̊y��{���̉����łȂ��炵���B�������A���̔����Ȓ����������Ȃ��̂���C�Ɍg���Z�p�E�l�̎d���ł���B����������Z�ʂ����Ȃ����E�l�Ȃ�Af���a�����p�̍H����������ނ��Ƃɂ���āA�v�����I�m�ɍł��ǂ����̏o���鍰���̈ʒu���߂ł��܂��̂��Ƃ����B
�@ �O���ȂǂŔ�s�@���Ԃ̍��Ȃɂ�����ĉ��t���s������Ƃ��ɂ́A��������͑�ȃ��@�C�I�����̓������P�[�X��G�̏�ɂ̂�����A�����łȂ��ꍇ�ł������̂ǂ����ŏ�ɃP�[�X�ɐG��Ă����̂��������B���̗��R�́A�펞���Ń��@�C�I�����P�[�X�ɐG��Ă��̏��݂��m�F���Ă����A������Ƃ������ȂǂɃ��@�C�I�����𓐂܂ꂽ�肷��댯�������Ȃ��Ȃ邩�炾�Ƃ����B�܂��A��s�@�̗��������Ȃǂɂ́A����傫�ȏՌ���U�����������ꍇ�ɂ��Ȃ��ă��@�C�I�����𒈂ɕ������Ď�邱�Ƃ�����̂��������B
�@ ���@�C�I�����̓����ɂ��Ă��ꂱ��Ƙb���i�ނȂ��ŁA�������炢�܂ЂƂʔ������Ƃ��f�����B���@�C�I�����Ƃ������͕̂\�ʂɓh��ꂽ�j�X�̐F�ł��������قȂ��Ă���̂��Ƃ����B�ǂ��炪�ǂ��Ƃ������Ƃ������킯�ł͂Ȃ����A��ʓI�ɂ͖��邢�F�̃��@�C�I�����͖��邢�����̉����A�Â��F�̃��@�C�I�����͂ǂ��炩�Ƃ����ƈÂ��������̉����o��̂��������B���̂�����̏ڂ����◝�R�Ȃǂ͑f�l�ɂ͂��܂ЂƂ悭�킩��Ȃ����A���ۂ����������̂ł���炵���B
�@ ���Y����ɁA�u��������̂ق��͂ǂ�ȃ��@�C�I���������g���ł����H�v�Ə��X�Ӓn�̈������������ƁA�����ɁA�u���̃��@�C�I�����͈����ł���B�����̂��̂Ƃ͉_�D�̍�������܂��v�Ƃ����������Ԃ��Ă����B�����͌����Ă��v���̃��@�C�I���j�X�g���g���y�킾����A�ނ��Ȃ�̒l�i�͂���ɈႢ�Ȃ����A������ɂ��됬������̃��@�C�I�����͕ʊi�Ȃ悤�ł������B
�@ ���@�C�I�������K���Ă���ŋ߂̓��{�̎q�������̂Ȃ��ɂ́A�v���̉��t�Ƃ̂��̂Ȃǂ����͂邩�ɍ����Ȋy��������Ă���҂����\����炵���B�ꉭ�~����X�g���f�B�o���E�X�Ȃǂ���ɂ��ă��b�X�����ɗ���q���Ȃǂ�����Ƃ�������������B����͊Ǘ�������ۊǂɂ�����Ȃ�̎萔��������B����ɁA���@�C�I�����Ƃ������̂͒e����̑S�l�i�����̂܂ܔ��f�����y�킾����A�������ɂ��Ă��邩��Ƃ����Ă��ꂾ���Ŕ��������F��t�ŏo����Ƃ������Ƃ͂��肦�Ȃ��̂��������B�e���肪���n�ȏꍇ�ɂ͂��ꑊ���̉������o�Ȃ�����A���_�I�ɂ܂������B�Ȏq�������ɓ��ʍ����Ȋy����������邱�Ƃ͂قƂ�LjӖ����Ȃ��Ƃ����B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N11��22��
�y���͂����܂ŋȂ̍��i
�@ ���E�I�ɗL���Ȋy�탁�[�J�[���n�݂����x�A�[�E���@�C�I�����܂��A�씩����͉p���������y�@��w�@�݊w���̈��㎵�N�Ɏ�܂����B���̂Ƃ��ɐ씩�����܂̋L�O�i�Ƃ��Ă���������@�C�I�����̋|�������Ă�������B���̋|�̒[�����ɂ͐씩����̖������[�}���ō��܂�Ă������A�������ɂƂ��Č����Ă�����Ă��邤���ɖʔ������ƂɋC�������B���Ƃ��e���Ȃ��Ă����@�C�I���������x����ɂ������Ƃ̂���l�Ȃ�N�ł��m���Ă��邱�ƂȂ̂��낤���A����܂ł���Ȍo���̂Ȃ��������̓��@�C�I�����̋|�̍\���Ɍ��������ς������Ă����̂ł���B
�@ �|�Ƃ�������ɂ́A�|�̌��ɂ�����w�A�i�n�̖т̂��ƂŁA�ʐ^�T�������ɓo�ꂷ��V�����m�ł͂���܂���j�́A�a�|�̂���Ɠ��l�ɁA�ʏ�ɔ������|�{�̗̂��[���ŒZ�����Ōq���悤�ɂ��Ē����Ă�����̂��Ǝv���Ă����B�Ƃ��낪���@�C�I�����̋|�̃w�A�͂Ȃ�ƌʏ�Ɍy���������|�{�̂̔w���A���Ȃ킿�A�ʏ�̋|�Ƃ͋t�̑��ɒ����Ă���̂��B�������A����̋���͋|�{�̖̂��[�ɂ����l�W�Œ����ł���悤�ɂȂ��Ă���̂����A���̋|�̏o������̊O���Ƀw�A�������Ă���Ƃ͂���܂ōl���Ă��݂Ȃ������B
�@�u�Ƃ���ŁA�씩����A�Ȃ����t����ꍇ�A�e���̒��Z���y���̉����̒ʂ�ɐ��m�ɒe�����̂Ȃ�ł����H�v
�@ �܂����Ă����͑f�l�Ȃ�ł͂̋����Ă݂��B����ƁA��������̐��Y����������ɂ�����āA
�u�����A�����Ƀ��g���m�[��������܂����A���̃��g���m�[���̔��q�ʂ�ɋȂ����t�����烁�J�j�J���ȉ��ɂȂ��Ă��܂��ĂƂĂ����������̂ł͂���܂����B�����ꔏ�̎����ł��l���ꂼ��Ȃ��ꂼ��ɂ���ĈႢ�܂����A�����Ɖ����̑��ΓI�Ȓ��Z�W�⋭��W�̉��߂��e�t�҂ɂ���Ă܂��܂��Ȃ�ł��v�Ɠ����Ă��ꂽ�B
�@ �y���̉����Ƃ������̂͂����܂ł��Ȃ̊�{���i�𐬂����̂ŁA����ɓK�ȓ��Â���F�Â��������Ȃ��̂����t�҂��Ƃ������ƂȂ̂��낤�B���̂��߂ɂ͒P�Ȃ鉉�t�Z�p�̍I���Ƃ͈قȂ鎑�����K�v�ƂȂ�ɈႢ�Ȃ��B���R�A���t�҂̐l���ς␢�E�ρA����ɂ͏��X�̎����ɑ���S�̋����⊴���̐[���A���Ȃ킿�A���̐l�̊����Ǝv�z���Ƃ��傫���e�� ���Ă���킯���B���������āA���Ȃ�̂Ƃ���܂Ŋy���ɍS������Ă���悤�ɂ͌����邯��ǂ��A���ۂɂ͑����Ɏ��R�x�̍������E�Ȃ̂ł���A��背�x�����炳���ɂ����Ă͑t�҂̐l�Ԑ������̂܂܉��Ȃ��Ă������|�����E�ł�����Ƃ����̂��B
�@ �����y���ɂ��������Ēe���Ă��Ă��A���@�C�I�����t�҂̖a���o�����ɂ͎��R�ɂ��̐l�̈�������̖������y�̉e�����������̂炵���B�Ƃ��Ƀr�u���[�g�̕����Ȃǂɂ����Ă͂��̌X���������Ȃ̂��������B�c�����ɉ��̗̂������ň�������{�l�t�҂̏ꍇ�ɂ́A�ӎ�����Ƃ��Ȃ��Ƃɂ�����炸���̉��ɉ��̒��̋������E�э��݂����ł���Ƃ����B�f�l�ɂ͂킩��ɂ������A�����o�g�̑t�҂ł���ǂ����ɌӋ|�̉����Â��钲�ׂ��A���ׂ̊؍��l�t�҂ł���A�������̒��ׂɋ߂����������ꂼ��̉��t�ɕ��ꍞ��ł���Ƃ����̂ł���B���̘b��e�ŕ����Ă���ꂽ��q����ɂ��ƁA�C�M���X�ɓn��������̍��͂��܂�킩��Ȃ��������A�ŋ߂ł͂ǂ̍��o�g�̑t�҂ł��邩�����������ł����ɂ킩��悤�ɂȂ����Ƃ̂��Ƃ������B
�@ ����Ƃ��씩���X�y�C���ɂ䂩��̋Ȃ�e���Ă�����A�w���ɂ������Ă���搶����A�u�N�̓��e���n�̍��̏o�g���ˁv�Ɛu���ꂽ���Ƃ��������Ƃ����B���S�j�����Ƃ��Ȃ���A���̌��t���������v���ĕ����Ă�����ł��ƁA�씩����͏��Ȃ���b���Ă��ꂽ�B�ꗬ�̐搶�̎��������܂����Ă��܂����̂�����A����͐������ƂɈႢ�Ȃ��B�������������ǂ��납�A���Еs���̉��������o���Ȃ��A���≹�y�ȑO�̉����o�����Ƃł�������ɗ]���X�ɂ́A�B�X����������̘b�ł͂���B
�@ �씩����̌o���ɂ��ƁA���Ƃ��x�[�g�[�x���̋Ȉ��e���ɂ��Ă��A���e���n�̐l�́u���ʂ悯����ׂĂ悵�v�I�Ȃ��̏ꂻ�̏�̋C���ɏ悶����_�Ȓe���������A���V�A�l�ɑ�\�����X���u�n�̑t�҂́A���炩���߁u��������ׂ����v�Ƃ������O���f���A�����ł�����ɋ߂Â��悤�Ȓe���������邱�Ƃ������Ƃ����B�{�ԂȂǂł́A�Ȃ̒e�������̃e���|�����\�d�v�Ȃ̂������ŁA���̃e���|�ɂ���ē��Y�Ȃ̉��t�S�̂̈�ۂ��܂������قȂ���̂ɂȂ��Ă��܂��悤�ł���B�ǂ����A���@�C�I�����̐����t�Ƃ������̂͂܂�Ő�������ɂ��Ă���݂����Ȃ��̂ŁA���̎��X�ŗl�����قȂ��ؓ�ł͂����Ȃ��悤�Ȃ̂��B
�@ �V�����Ȃ��}�X�^�[������A���̋Ȃ̕\�킷���E������̉��ɔ�߂�ꂽ��ȉƂ̐[���z���Ȃǂ�c�����Ă��������ł̋�J�Ȃǂɂ��Đq�˂Ă݂�ƁA��������炵�������ȓ������Ԃ��Ă����B�ʏ�̃��@�C�I���j�X�g�͊y�������ĉ��x�����x���Ȃ�e���Ȃ��珙�X�ɈÕ����A���̉ߒ���ʂ��ĉ����Ȃ̔w��ɔ�߂�ꂽ���E���ǂ��\�����邩���l���Ă����B�������A�������邱�Ƃ�����씩����̏ꍇ�́A�b�c�����蕈�ʂ��s�A�m�Œe���Ă�������肵�Ă܂����̋ȑS�����Õ����Ă��܂��B�����āA���̂��ƂŃ��@�C�I������e���Ȃ��玟��Ɏv����[�߁A�Ȃ̔�ߎ����E�̉��ւƑz���͂��߂��炵�Ă����̂��Ƃ����B���̌��ʂƂ��āA���O�̐S�̒�܂Ő��ݓ���씩����Ȃ�ł͂̂��̏�L���ȉ����a���o�����Ƃ����킯���B
�@ �������ۂɂ������������Ƃ��ł��邽�߂ɂ́A���t�Z�p�Ƃׂ͂ɁA�l�ԎЉ�⎩�R�E�S�ʂɂ��Ă̍L���m����o���A�[�����@�͂ȂǂƂ������悤�Ȃ��̂��K�v�ƂȂ炴������Ȃ��B�������A�����P�ɂ��̐��E�̊Ô��Ȉ�ʂ�����F�����Ă���悢�Ƃ������̂ł͂Ȃ��B���R�A�l�Ԃ̋Ƃ̐��݂����炷���X�̗~�]�Ƃ��̂䂦�̔߈��̐��X�A����ɂ͐��₩�ߎS�Ȓn���G�}���̂��̂̐��E�̑��݂����m���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��킯�ł���B
�@ �䗼�e���͂��߂Ƃ��鑽���̋��͎҂���A�l�X�ȃW�������̖{��ǂ�ł�������肢�낢��Șb�����Ă�������肵�āA�씩������×~�ɂ��̐��E�̏o�����ɂ��Ċw��ł����B�w�����̃V���[���b�N�E�z�[���Y�E�V���[�Y�ɂ͂��܂�A�̂��̊e��̕��w���A�v�z���A�Ȋw���ɂ�����܂ŁA�ǔj���⒮�j�����{�̐��͑����ʂɂ̂ڂ�炵���B�������A���`�ʂȂǂ��܂ޏT�����̊e�킫����̋L���ɂ��A�܂����X�̎O�ʋL����e���r�E���W�I�̃j���[�X�Ȃǂɂ��Ă��l���݂̊S�������Đڂ��Ă����Ƃ����B�v����ɁA�D��S�����ŁA���̐��̒��̂��ƂȂ�ǂ�Ȃ��Ƃł��I��D�݂������R�ɖڂ�������悤�ɂ��Ă��Ă���Ƃ������Ƃ炵���B
�@ �씩����̌��t�Â����������قǂɒ[���ŁA���������̘b�Ԃ肪���[���A�Ɉ��A���̂����Ȃ��m�I�Ȗ��͂�����������̂�����Ȕw�i�����邩��Ȃ̂��낤�B���Y�������q������A��������ɂ͂Ȃɂ����܂��������ʂ̐l�ԂƂ��Đ����邱�Ƃ��ɂ��A���̏�ʼn��y�̎d���ɐ��i���Ă��炢�����ƍl���Ă�����悤�ł���B
�@�u�Z�b�N�X����݂̏T�����̋L����C�h�V���E�̘b��Ȃǂɂ��Ă��A�����Ƃ͂������ʂɘb���悤�ɂ��Ă����ł��B����V���ɁA�w��������ӂ�Ȃ��c�x�Ȃ�ĈӖ��̂��Ƃ������ꂽ������܂������ǂˁv�Ɨ�q����͖��������ɏ��Ă���ꂽ�B���Y����≺��l�̒킳���̗����̂��ƁA��������ɓ������ăC�M���X�ɓn������q����́A���[���b�p�e�n�Ő��E�I�ɗL���ȉ��y�Ƃ����Əo�����@��Ɍb�܂ꂽ�B���̐l�B�ɋ��ʂ��Ă�����̂́A���퐶���ɂ����Ă͂ǂ��ɂł����邲�����ʂ̃I�W�T���Ƃ��������̂ŁA�����ȉ��y�Ƃ��ȂǂƂ������͋C�͔��o���������Ȃ����Ƃł���Ƃ����B�����̐����ɗn�����݂������R�ɐ�����̑�ȉ��y�Ƃ����̑f���ڂɂ��āA��q����͐�X��������ɂ����������Ăق����Ɗ���Ă�����̂ł��낤�B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N11��29��
����Ȃ�����F���
�@ �씩����ɂǂ�Ȗ{��ǂށi�e�[�v���j�̂��D���ł����Ɛq�˂�ƁA���������D���Ȃ̂͗��j���ŁA������������킸���E�̗��j�S�ʂɊS������Ƃ����Ԏ����߂��Ă����B�ŋߖ����ɂȂ������w��i�̈�ɁA�g���X�g�C�̒���u�N���C�c�F���\�i�^�v������Ƃ����B�x�[�g�[�x�����u�N���C�c�F���\�i�^�v����Ȃ���܂ł̔w�i���h���}�e�B�b�N�ɕ`������i�Ȃ̂����A���Ԃ̕��͂̒��ɐ�[������������l�X�Ȋ�������ȉƂ̐[���������z���Ȃǂ́A���ۂ́u�N���C�c�F���\�i�^�v�̉��t�ɂ�������ς��Đ�������Ă���͂��ł���B�@
�@ ����Ƃ��A�e���r���Ȃɂ��ŁA�A�C�U�b�N�E�X�^�[�����܂������Ԃ�ƎႢ���@�C�I���j�X�g�̗��������w��������i���������Ƃ�����B���̂Ƃ��X�^�[���́A���ȉƂƌĂ��l�͒N�ł��A������荰�̂���������߂ČX�̉����������グ���Ƃ����̂ɁA���̍�ȉƂ̓`�L�������ǂ��Ƃ��Ȃ��Ƃ����͉̂������Ǝ���A�P�Ȃ鉉�t�e�N�j�b�N�̏K�������ɑ��肪���ȃ��b�X���������������������ʼn��߂Ă����B�ނ��A�씩����͂���ȏ����I�Ȃ��ƂȂǂƂ����ɔF���ς݂�����A���낢��Ȓm�����L�������Đ[���g�ɂ���ׂ��A���y�ȊO�̂Ƃ���ł������ƌ��r��ς�ł���킯�ł���B
�@ ���ʂɎ��Ă������������i�Ղ��Ȃ���̉�X�̒k�͒e�݂ɒe�݁A�₪�Ęb��̒��S�͉��y�̐��E�̑��ʓI�Ȃ��Ƃ���ւƈڂ��Ă������B�����āA���܂��ɂ͉��y�ɂ͒��ڊW�Ȃ��D���j��F���j�̖��ւƘb����ԗL�l�������B����Ȓk�b�̓W�J�̂Ȃ��ɂ����Ď��̂悤�ȉ��y�̑f�l�ɂƂ��ĂƂĂ��ʔ��������̂́A���t���̉����̗ǂ������ɂ܂�邿����Ƃ������b�������B
�@ �씩���q�̘b�ɂ��ƁA���@�C�I�����̉��t�̏ꍇ�A���t�҂┺�t�҂����₷���ʒu�Ɖ����̂ɂ����Ƃ��悢�ʒu�Ƃ͂܂�ňႤ���Ƃ������̂������ł���B�������̃z�[���Ŏ��ۂɌ����Ă݂����ʂ���ސ�����ƁA��ʂɃ��@�C�I�������t�̏ꍇ�ɂ́A��K���قǂ��牜�ɂ����ẮA����Ɍ������ĉE��Ǎۂɋ߂��Ȃ������I�ɍō��Ȃ̂������ł���B���ҋq�p�̐Ȃ������K�����t�߂́A���������ɂ̓x�X�g�����A���̋����Ƃ������ƂɂȂ�Ƃ��܂�悢�ʒu���Ƃ͌����Ȃ��炵���B�z�[�����ɂ����镡�G�ȉ��̔����Ȃǂ̊W�������Ă����������ƂɂȂ�̂����������A������Ƃ����Ă܂������ҋq���z�[���̋��̂ق��ɍ��点��킯�ɂ������Ȃ�����ƁA�씩���q�͋���Ă����B�������A�I�[�P�X�g���̉��t�Ȃǂ̏ꍇ�A�͂܂��قȂ��Ă���̂�������Ȃ��B
�@ ���܂ЂƂʔ��������̂͐씩����̃W���[�N�ɂ܂����܂����G�s�\�[�h�������B�씩����̃��T�C�^���ł͂��łɂ��Ȃ��݂̌��i�����A�v���O�����Ȃ̉��t���I���A���R�[���ɂ͂���O�ɁA�씩����͕K�����̓��̒��O�������ĊȒP�Ȃ���̌��t���q�ׂ�B�����āA���̂Ƃ��̌��t�̒��ɂ��肰�Ȃ��܂荞�܂��y���ȃW���[�N�ɂ���āA���͂����Ȃ��₩�ȏ��ɕ�܂��B���{�̃N���V�b�N�̉��t��ł͑�ςɒ��������ƂȂ̂ŁA�͂��߂Ă���ȕ��͋C�ɐڂ����l�͋������o���������邩������Ȃ��B�p���d���݂ł͂Ȃ����Ǝv���邻�̐������ꂽ�W���[�N�̐ꖡ�͂Ȃ��Ȃ��̂��̂ŁA�ƂĂ��D�������Ă邵�A���ہA���̂��Ƃɑ����A���R�[���Ȃ̉��t������������ۓI�Ȃ��̂ɂ�����������ʂ����Ă���B
�@ ���Ƃ��A�㌎�ɓ����O��ōÂ��ꂽ���T�C�^���ɂ����āA�씩����͔��t�҂̃_�j�G���E�x���E�s�G�i�[����������炽�߂Ē��O�ɏЉ�A�ނ���A�t���J�o�g�̃s�A�j�X�g�ŁA�����h���̉������y�@�ŋ��Ɋw�e�F�ł��邱�Ƃ�`�����B�����āA���Ђ�����������قȂ��l���C�M���X�Ƃ����ً��̒n�ŏo�����A�����S���J�̂��ƁA�݂��ɋ��͂������Ȃ��特�y��o���Ă������Ƃ̑f���炵���s�v�c���ɂ��āA�W�X�Ƃ��������ʼn��̐l�X�Ɍ������Č�肩�����B
�@ ���̂��ƓˑR�ɁA�씩����́A�u�ƂĂ����̂悢�������Ȃ�ł����A����̗[���͉��̂���l�̊Ԃɂ����Ȃ�ʋ�C���Y���܂��āA�ǂ��Ȃ邱�Ƃ��Ɓc�c�B�����Ƃ��A�Ԃقǂ����炢���ʂ�̂����e�����W�ɖ߂�͂��܂������c�c�v�ƂȂɂ��Ӗ����肰�Ȉꌾ�𓊂��������B�s���Ƃ����l�͂����Ƀj�����Ƃ����̂����A���݂̂邩����A�u�ԓI�ɂ��ꂪ�W���[�N���Ƃ킩�����l�͏��Ȃ������悤�ł���B���͂��̑O���̗[���ɃI�����s�b�N�̃T�b�J�[�\�I�A���{�Γ�A�t���J�̎������s�Ȃ�ꂽ���肾�����̂��B�씩����̌�����O���̔w�i�����������ƁA���������͂������̉Q�ɕ�܂ꂽ�B
�@ �܂��ȑO�̃��T�C�^���ɂ����āA�씩����́A�s�G�i�[������Ƌ��ɂ����Ƃ̂Ƃ���փ��b�X�����ɏo���������A���̐搶���炻�ꂼ��ɉۑ��^����ꂽ�Ƃ����b���������Ƃ�����B���ɗ��鎞�܂łɐ씩����͂����Ɖp�ꂪ��肭�Ȃ�悤�ɁA�܂��A�s�G�i�[������̂ق��͂����ƃs�A�m����肭�Ȃ�悤�ɂƂ����̂����̉ۑ肾�����Ƃ������̂ŁA�ނ��A����͐씩���̌y���W���[�N�ł������B�Ƃ��낪�A�ꕔ�̐l�ɂ͂ǂ���炻�ꂪ�W���[�N�Ƃ��Ă͎���Ȃ������悤�ł���B
�@ ����Ȃ��˂ẴW���[�N�����ڂɏo�āA����n���Ƀs�G�i�[������Ƌ��Ɍ����ɏo�������Ƃ��̂��ƁA���ɏ��Ȃ����Ԃ��N�������B�씩����͉p�ꂪ�s���R�炵������X���v����Ă����悤�Ƃ�����Îґ��̔z���ŁA�s�G�i�[����Ƃ̊Ԃ��Ƃ�����߂ɋ}篒ʖ���ꂽ�Ƃ����̂ł���B�Ƃ��낪���������ƂɁA��N�قǂ̉p���؍o�������Ƃ������̒ʖ�͂ǂ������킯�����܂�p�ꂪ���܂��Ȃ��A�{���������ΐ씩���g�����ڂɉp������ق������͂����Ɨe�Ղł������炵���B�����������͐S�D�����씩����ƃs�G�i�[���̂��ƁA����ȋ��̓��Ȃǂ����тɂ��o�����A�����̒ʖ��Ō�܂ʼn����������A���̊�𗧂ĂĂ������̂��Ƃ����B
�@ �씩����͂��̒��x�ōς���܂��������A���s�̃s�G�i�[���ɂ������ẮA�����Ƌ���ȃp���`�̐����H������炵���B���t��̃��Z�v�V�����������̐ȂŁA����l���ނɌ������āA�u�s�G�i�[������A���Ȃ��̓s�A�m���܂����܂肨��肶��Ȃ������ł����A���x���������鎞�܂łɂ͏�肭�Ȃ��Ă��Ă��������ˁv�ƁA�ɂ��₩�ȏ݂�X���Ȃ����^�ʖڂŌ�肩�����̂������ł���B�씩����ɂ��ƁA�s�G�i�[���͑�ςɃV���C�Ȑl�����Ƃ������Ƃ�����A����̌��t�����̂܂ܓ`������Ƃ���A���炭�ނ͕Ԏ��ɋ����Ėڂ𔒍��������ɈႢ�Ȃ��B
�@
�@ ���N�̋㌎���{���T���[���X�̓��Č���ōs�Ȃ�ꂽ�씩����̃A�����J�����T�C�^���͑听���ɏI���A���O�𖣗����s���������̉��t�̗l�q�̓��T���[���X�^�C���X�Ȃǂł��傫�����ꂽ�B���̃��T�C�^���̈ꕔ�n�I�͏\����y�j�ߌ�\������m�g�j����e���r�́u�y�j�v���~�A���v�ɂ����āA�u���̂����������X�`�씩������\�N�ڂ̃��T���[���X�`�v�Ƃ����h�L�������^���[�ԑg�Ƃ��ĕ��f����邩��A�S�̂�����͌䗗�ɂȂ�Ƃ悢���낤�B���ł�����q�ׂĂ����ƁA�\�\�ܓ��ߌ�Z������͂s�a�r�e���r�̃j���[�X�̐X�ւ̐��o�������܂��Ă���悤�ł���B�܂��߁X�A�}�K�Ђ���씩����̎��`���o�ł����\��ɂȂ��Ă���B
�@ ��X���씩�Ƃ�K�˂����A��������̓��T���[���X�������O�T�Ԍ�ɍT�����S�������S�[���ɘb���Ă��ꂽ�B���̂Ƃ�����ŕs���̖�Q���̂ɑ��������씩����̓J���t�H���j�A��w�t���a�@�ɒS�����܂�A������\���̎Ⴂ�厡��̌��g�I�Ȏ��ÂƎO�����ɓn����@�̖��ɐh�����Ă��̈ꖽ�����Ƃ߂��B���̎�����͂��\�N�A�씩����͊���������̎厡��Ɠ����N��̓�\���ƂȂ����B���݃T���t�����V�X�R�ݏZ�̎l�\���̈�t���A�������A�씩����̉��t���ɂ��邱�ƂɂȂ��Ă���Ƃ����b����������A���T���[���X�ł̓�l�̍ĉ�͂������������I�Ȃ��̂ƂȂ����ɈႢ�Ȃ��B
�@�u���R�Ƃ͂����A���̂��炿�傤�Ǔ�\�N�ڂ̂��̔N�ɓ�\�N�Ԃ�ɃA�����J�ɓn��A�����̒n���T���[���X�ŏ����T�C�^�����J���Ƃ����͓̂V�̓����Ƃ��������悤�̂Ȃ��s�v�c�ȉ^���̐���s���ł��v�ƌ��씩����̕\��ɂ́A���n�ł̉��t�ɂ����錈�ӂ̂قǂ��Â�ĂȂ�Ȃ������B
�@ ������̏\�ꌎ��\�O���ɂ́A�����I�y���V�e�B�z�[���ōÂ��ꂽ�씩����̃��T�C�^�����ɏo�����Ă������A����܂����҂𗠐�ʑf���炵�����t�������B�l���ꂼ��ɍD�݂�����̂ł����܂ł����l�̊��z�����A����̉��t�ł͓��Ƀo�b�n�̖����t�p���e�B�[�^�A���ԁA�j�Z���ABWV1004�̉��t����ۓI�������B�씩�����T�C�^���Ńo�b�n�̍�i�����グ��͍̂����߂Ă��Ƃ̂��Ƃ��������A���̋ȂɁu���S�v�̋��n�ŗ������������Ƃɂ����Ƃ����Ȗډ���̒��̐씩���g�̌��t�ʂ�A�t�ŏo����鉹�̈�ЂƂɂ͐l�Ԃ̉䎷�������Ȃ鋿���Ƃł��ĂԂׂ����̂�������ꂽ�B
�@ �씩����̃z�[���y�[�W�ihttp//:www.1.u-netsurf.ne.jp/�Pmichi-k/�j�̃��[���{�b�N�X�ɁA�u�ꐶ�̂��肢������`�S�C�l�����C�[����e���āv�Ə����������t�@���̗v�]�ɓ����āA�Ō�̃A���R�[���ł͋v�X�ɂ��̋Ȃ��e���ꂽ���A��i�Ə�������艉�t�ɂ����݂������������ŁA���̐Ȃ̎��ӂ�������ƌ��܂킵�������ł��ړ����������Ă���l�������Ԃ�ƌ�����قǂ������B�I���タ����Ƃ����y���Ɏf�����Y����Ɨ�q����Ɉ��A���������A���Y�����ɂ����Ί�������Ă���ꂽ�Ƃ�����݂�ƁA���҂𗠐�Ȃ��f���炵���o���h���������̂ł��낤�B
�@ �씩����͂��傤�ǃt�@���̑҂T�C�����ւƌ������Ƃ��낾�����̂ŁA����Ⴂ���܂ɂق�̂�����ƌ��t�����킵���������������A�C�̂��������̕\��ɂ͂���܂łƂ͂ǂ���������������Ƃ�Ƃ肳���������������邱�Ƃ��ł����B�\�\�����ɂ͕{���s�̐��U�w�K�Z���^�[�ɂ����āu���ƃ��@�C�I�����v�Ƃ����e�[�}�Ő씩����̍u�����s�Ȃ���\��ɂȂ��Ă��邪�A�ǂ�Șb�������邩�Ƃ��܂���ƂĂ��y���݂ł���B
�@ ���ŋ߂̂��Ƃ����A�씩����Ɠ��t�B���Ƃ̋����R���T�[�g�̎������ł̊J�Â���悵�Ă���Ƃ����l����A�씩����ɂ��Ă̒Z���Љ�̎��M���˗����ꂽ�B���ٕ̐����Ō�ɋL�������āA�씩��������ɂ��Ă̍���̈�A�̕��͂̌��тƂ������Ǝv���B
�����̋Ր��𑀂�ٍˁI��
�@ �v�킸�ړ����M���Ȃ�قǂɒ��O�̍���h���Ԃ邠�̖��p�I�ȉ��F�́A���������ǂ����琶�܂�Ă�����̂Ȃ̂��낤�B���Ԃ�́A���ٍ̈˂̐S���ɂ����Ė��̉����ނ��ł���s�q�ȋՐ��̂͂��炫�ɂ����̂ɈႢ�Ȃ��B�씩�������̓��ɔ�߂鍰�̌��́A�ܐ����̉���������Ƃ��čĐ���������܂��ɁA���̐��ɐ�����l�X�̊���̐���߈��̋��тɉs���[��������B�씩�̑t�ł�������l�X��S�ꊴ��������̂́A���@�C�I�����̉��t�Z�p�݂̂ł͓��B�s�\�ȍ��݂ɂ��̕\���̌����邩��Ȃ̂��B�f��̐씩�͏_�a�Ō����ŁA�����������قǂɋC�����Ŗ��邢�B���y�Ƃɂ����̂̐_�o���ŋߊ�肪�������͋C�Ȃǖѓ��Ȃ��B�m�I�T���S�������ŕ��w��N�w�A���j�A�Ȋw�Ȃǂ̐��E�ւ̊S�������B�씩�̌��t�����[���A�ƃE�B�b�g�ɕx�݁A�I�m�����͓I�œ��L�̕i��������������̂�����Ȕw�i�̂䂦�Ȃ̂��낤�B���ꂩ���A�܂��܂�����I�ȕ\���͂̌��オ�]�߁A����ɂ͉��y�v�z�ƂƂ��Ă̐����������҂ł��邱�̐V�i�\���X�g�̏������A��X�͒����ڂŗD�����������A���������ɂ͌�������ÂɌ�����Ă����������̂ł���B�@�@�@�@
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N12��6��
�����ɑz���i�T�j
�i�����̖����x�R���j
�@ ����̐Ӗ����I�����^�g�̑��z���A�������������̃V���G�b�g�ƂȂ��ĕ����ԒO��R��̌����ւƗ����Ă����B��̈��������߂ē��ւ��p���B�����Ƃ��Ă�����p����킸�����藣�ꂽ�Ƃ���ɁA�s���Ȑn��Ő蔲���ꂽ������`�̌^���݂����ȗ֊s�����Ă���̂́A���킸�ƒm�ꂽ�x�m�̎R���B
�@ ��C�̐��ޔӏH���珉�~�̍��ɂȂ�ƁA�����x�O�̑������ӂ̂��������ł́A�����ǂ��̐���ɂ��̂悤�ȏ�i������������悤�ɂȂ��Ă���B�U��̐܂ȂǁA����ۂނقǂɔ���������ȉe�G�ɂ߂��舧���ƁA�������ܑz���o�����Ƃ�����B����́A���̎��߃I�z�[�c�N�̕l�ӂɂЂ��₩�ɍ炭�Ƃ����A���������ȋe�Ȃ̉Ԃ̘b�ƁA���̉Ԃ���D�����ƌ���Ă��ꂽ�r����̉������̎p�ł���B
�@ �܂���\��㔼���������̘b�����A�Ă��I��ɋ߂�������̗[��̂��ƁA���́A������C�z�̐₦�Â܂��������x�i�J���C�k�v���j�̒��ɂ����āA�Ƃ薜���̑z���ɂЂ���Ȃ���A�[�z�ɉf���ĎR���F�ɋP�����܂門���̌Ζʂɜ߂��ꂽ�悤�Ɍ������Ă����B�Ζʂ̂ނ����̊O�֎R��Ɉʒu����W�]��̓��킢���ʐ��E�̂��ƂɎv����قǂɂ��̐藧�����R���͎�R�Ƃ��Ă��āA�ق��ɐl�e�炵�����̂͂܂�������������Ȃ������B����ɗ����Ă����A�A�C�k��Łu�_�̎R�v���Ӗ�����J���C�k�v���̎R���ɃR�[���Ŋ��t���������ƁA�������ꂱ���A�O���Ԃ���Ƃ������́A���͂��̉�����Ƃ��߂ɂ����܂܂������B
�@ �����x�͊C�����Z�O�ĂƕW�����������������Ƃ͂Ȃ��������A���̉s�������������̒��]�͉���̈��ɐs�����B��ʂ��瓌�ʂɂ����Ă̊ቺ�ɂ͐l�Ղ����ނ悤�ɂ��ėY��ȍ������삪�L����A���̗y�����Ȃ��A�V�ƒn�Ƃ��Ⴍ���Y��������ɂ́A�I�v�̎��Ԃ�X���܂ǂ�ޑ����m���]�܂ꂽ�B�܂��A�k���Ɏ�����]����ƁA���P�x�A������U��ɂ����悤�Ȃ������̎Η��x�����E�����ς��ɔ���A���̉E�����ɂ͒m�������̔w�����Ȃ��C�ʊx�A�����ʊx�A���P�x�Ȃǂ̎R�X���A�ّR�Ƃ��ĘA�Ȃ��Ă����B
�@ ���܂��ܑ�C�����݂킽���Ă������Ƃ������āA�����m���̎R�X�̓����ɂ͍��㓇�̂��̂炵�����e����������ƕ�����Ō������B����ɁA�Η��x�������̖k�ʂɂ����Ă͗ɑ������k�����삪���̑��݂����ꌩ�悪���Ɍ֎����A�܂����̂ނ����ɂ́A�⛌�̐�Ƃ������ׂ��I�z�[�c�N�C���[���݂�ттĕ��ɂ̂эL�����Ă����B
�@ �����A�����̌i�ςɂ��܂��đf���炵�������̂́A������т̓W�]�ł������B���ɂ����̃A�C�k���̔ߗ��Ƃ��̏�O�̂�������ڂ�s�������̗͂ŏ��n�������悤�Ȗ����̐����̐F�A�J���C�̈Ќ��̑O�ɂЂ�����k�����܂�ΖʁA�����Ă��̌������ɘA�Ȃ���ΘH�A���y���A�Y�����x�A�������x�Ȃǂ̉��i�c�c���X�Ƃ��낤�z���̂��Ƃł����̕������d�Ȃ�D�萬�����p�m���}�͈����Ƃ��������悤���Ȃ������B�����āA���̑�p�m���}�̐����͂邩�ȂƂ���ɑ����Ȃ������܂��������Ē�������̂́A�k�̖���A���R�A�����B
�@ ����Ȓ��ɂ����Ƃ肠���Č}�������̓��̗[�f���́A�Ȃ�Ƃ������I�Ȃ��̂ł������B���̐��������R���F����Ԏ��F�ɏƂ�f���A�����낷��n�͈�ʉ����F�̗�C���ĔR�������A���������悤�Ȍ`�ł�������ƕ��яオ��Y�����x�̗Ő��́A���܂ɂ����𐁂��グ�����ɐԂ��P���h��߂��Ă����B
�@ �厩�R���⏥�������o����\�\�V�n�̑����ȉ̐��ɂ܂�āA���̐��ōł��M�d�ȉ����̂����ɂ��C���Ȃ����サ�A�v���̔ޕ��ւƗo������ł䂭�\�\����Ȍ��l����X�����A����͐���Ȃ܂ł̋�̐F�ł������B
�@ �����̋ɂ݂ɒB�������́A�������ɂ��ʑ�C�ɐg�̓��������ł��������̂悤�ɁA���z�������Ƃ����̏�ɂ����Ɨ����s�������܂܂������B�₪�Đ��̋�͐[�����̐F������̂ɂ��������鉩���F�ɂȂ�A���F���率���o�Ă������ɔZ���̏��̐F�ւƕς���Ă������B�����̖��Ƃ͂��������͖k���̂��ƁA�������ɔ��������o���ĉ��R�̐g�x�x���n�߂����A���̍��ɂ͂������̕��䂢���ς��ɏ����̉����J�L�����A���̉₢��������̂��ƂŊቺ�̖����͐[������ɂ����Ƃ��Ă����B
�@ �����Ƃ́A���ǂ����ꌯ�����藧�����Ƃ������悤�ȈӖ������A���ۂ��̖��̒ʂ�̌`������Ă��āA��ʂ̐l���Ζʋ߂Â����Ƃ͗e�ՂłȂ��B�����A�ӊO�Ȃ��ƂɁA�̓����ɂ́A�܂�Ŗ����x�̉��ɉB��������ł����邩�悤�Ȃ������ŁA���₩�ȎΖʂɘA�Ȃ��������Ƃ���ɑ��������ȓ��]�����݂��Ă���B�����āA�����A���̓��]�̒�ɂ͐��Y���̒����D�炵�����M���l�ڂ�E�Ԃ悤�ɔz����Ă����B���ɏ��ł̒��ɒ���Ō����Ȃ��Ȃ������̔��������]�ɐS�̒��ŕʂ�������A�I�R�Ɩk�̖����߂���k�l�����Ȃ��玄�͐Â��ɎR�����������B�f�l�Ȃ�ł͂̂��̂����Ȃ��قȂ��Z�̈����̌ΖʂɌ������Ă����ƙꂫ�����Ȃ���c�c�B
���ɂ��ւ̃A�C�k�̗������ߖ��������ڂ�Ƃ�
�i���������ČF���H�j
�@ �����d������ɂ��āA���͖����x����^���̋}�ȓ��������ɋ킯�������B����̂��Ƃ�z���A���ɏ������ăU�b�N�ɒ݂��Ă��������̋A����i�߂邲�ƂɃJ�����J�����Ɖ������������Ă��B�����܂ł��Ȃ����A�F�悯�̂��܂��Ȃ��ł���B���R���ׁ͍X�Ƃ����M�����������A���ł��R�H�̗F�Ƃ���̂͂����̂��Ƃ䂦���ɕs���͂Ȃ������B�����A���킳�ɕ����q�O�}�̑��݂����́A���ߕ��������Ă��������C�ɂ͂Ȃ��Ă����B�}�����ŕ���i�߂����Ƃ������āA�قǂȂ��A�����x�ƁA�m��l���m�鍂�R�A���̕�ɐ��ʊx�Ƃ̊ԂɈʒu����ƕ��ɏo���B
�@ ���̎��ł���B������̏����ȓ��]���ւƂ�����Ζʂ̖��������N�}�U�T���M���ˑR�K�T�S�\�Ƒ傫���h��Ȃт��A���҂��������߂��C�z�������B�w��₽�����̂�����Ƃ͂悭���������̂ł���B�ق�Ƃ��ɔw����������Ă��܂������ȉs���������̓����т����Ƃ݂��A�����Ȃ���n�̎肪�u���ɗ����ɂ̂тĂ��̐g��������ɂ��Ă��܂����B���M���獕���e��������܂ł̎��Ԃ����ƒ���������ꂽ���Ƃ��낤�B
�@ ���Ί���Ђ��点�Ȃ���A�K���̎v���Ō����������d���̌��̗ւ̒��ɕ��я�����̂́A�K���Ȃ��ƂɌF�Ȃ�ʁA���������Ɉٗl�ȕ��̂̐l�e�ł������B������s�ӂ�����Ĉ�u�������悤�ɗ��~�܂�A�����d�������̂ق��ɏƂ��Ԃ����B�����Ė����őΛ����邱�ƎO�A�l�b�\�\���̂��Ɠf�������t�����v���ƂȂ�Ƃ����m����܂�Ȃ����̂������B
�@ �������A�u�܂����F���Ⴀ��܂����ˁH�v�ƌ��������悤�ɋL�����Ă��邪�A���肪���ۂɌF��������A�u���͌F�����I�v�Ɠ����Ă��ꂽ���̂��ǂ����c�c�B���̒����Ȗ₢�����ɁA���̐l�e�́A�u������������܂����I�v�Ƃ����������ɏ��Ȃ���߂Â��Ă������A���̂Ȃ�Ƃ��s�v�c�ȕ��̂���͑z���ł��ʂقǂɁA���������A�h���悤�ɉs���A���������������̗ւ̒��ŋP���Ă����B�����āA���ꂪ�r����Ǝ��Ƃ̕����ʂ�̌��I�ȏo�����ł������B
�@ �ł�w�ɂ��ĉ����d���̌��̒��ɐÂ��ɂ������ނr����̎p�����͍����Y��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�����^�Ԃ��ƂɃt�P�̕����������˂Ȃ����̂���������ᓪ�ɁA���ڒ��̌�����ɂ߂��悤�ȕE�ʁA��Ƃ��Đ���邱�Ƃ����ݑ����Ă����炵�������Ȃ܂ł̃{�����̏㉺�A�����āA�����̐_�邻�̂��̂𒆂ɋl�ߍ��݂����Ȕ����ꂽ���ɑ܁c�c�ǂ����Ă����̂��ł����͈ٗl�Ƃ��������悤���Ȃ������B�����A�����ɂ͂����̈��炬�̑��Â���������A�����Ζڂɂ���悤�Ȃ�肫��Ȃ��ȂǂƂ������͔̂��o���Ɋ������Ȃ������B���ʂ̉��ꂩ��N���オ��Ȃɂ��̂����A�O���̂��ٗl����s�v�c�Ȃ܂łɐ��䂵�s���Ă�������ł���B�����̂����ɕY�����邻�̑��݂̏d�݂���@����ɁA�N�̍��\�㔼�Ǝv�����O�̂��̐l�����A��O���̂����Ȃ������Ƃ��̒T���҂ł��邱�Ƃ͋^���]�n�̂Ȃ��Ƃ��낾�����B
�@ �ǂ��炩��Ƃ��Ȃ�����������A����̂��Ƃł����Ɏ���܂ł̌o�܂����݂��q���킵�����ƁA�킽�������́A�܂��A�����ΊO�Ǐ���ׁX�ƖD���M����H��͂��߂��B�����āA��L���Ɛi�܂ʂ����ɂ�������ӋC�������Ă��܂����B���炽�߂Ďf�����Ƃ���ł́A�r����͂��傤�ǖ����̂��̓��]�ł���d�������Ă̋A�肾�Ƃ������Ƃ������B�捏�܂œƂ�ŕ����Ă����Ƃ��ɂ͖�����̃q�O�}�̏o�����C�ɂȂ��Ă����������C���Ɏv�������̖铹���A�b���e�ނɂ�Ă��̂����Ȃ��y�������̂ɂȂ��Ă������̂�����A�s�v�c�Ȃ��̂ł���B
�@ �r����͓�����т̎R�X�̒n����n�`�A���A���̐��Ԃɐ��ʂ��Ă���炵���A���̘b�͂ǂ���Ƃ��Ă������̐s���Ȃ����̂��肾�����B���͂Ђ�����S���[�������v���ł��̘b�ɕ��������Ă����̂����A���̂����ۂ��ŁA��̂��̐l���͉��҂Ȃ̂��낤���Ƃ����v�����S�̉��Ō������Q�����L�l�������B���̕��͋C���炵�Đ��ɂ����w�҂ɂ͌����Ȃ��������A���肰�Ȃ����t�̒[�X�ɂ����ĂƂ�����L�����ƌ����߂�ꂽ�w���̉e��A��������悤�ȓ��@�͂̐[�����炨���͂���ƁA�ƂĂ��q��ȑ��݂ɂ͎v���Ȃ���������ł���B
�@�u�Ȃɂ��A���̌䌤���ł��H�v�ƈ�x�͒P�������荞��ł݂��̂����A������A�������Ɏ��}���Ȃ�тт������ɂ���Č����Ɏ��킳��Ă��܂��n���ł������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N12��13��
�����ɑz���i�U�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�i���̉ԁj�@
�@ �ł̒�ɐ[�X�Ɩ��蒾�ޖ����̈Â��Ζʂ��E��ɖ]�݂Ȃ���ΕǏ���قڔ������A�������W�]��t�߂ɒH�蒅�����Ƃ��ɂ́A�����͊��Ɍߌ�㎞������Ă����B
�@�u���������Ǝ��Ԃ��x���ł����A���ꂩ��ǂ����܂��H�v
�@�u��q���̒��̕��ւ��������������ĉ����āA���ꂩ��ǂ����K���ȏꏊ��T���Ė�c�ł����܂��B�����̂��ƂŊ���Ă܂�����c�c�v
�@ �r����̖₢�����Ɏ��͂����������B���܂ł����Ԓ������ł��郏�S���ō������D������ɋ삯�����Ă��邪�A�n�R�����҂̗������������̎��i�����Ƃ��A���܂��u�����ҁv���u�������v�ɒu��������������ŁA���̌`�e�����̂ق��͂ǂ����̃v���싅�`�[�����݂Ɂu�i���ɕs�łł��I�v�Ƌ������Ă͂��邪�j�ɎԂȂǂ��낤�͂����Ȃ������B������A��l���̖�c�����ꎮ���l�ߍ��d�����U�b�N��w�����Ă̎R�s��g���b�L���O�̗��Ȃǂ͂���������O�̂��Ƃ������B
�@�u���ꂶ��A�ꏏ�Ɏ��̉Ƃɍs���܂��傤�I�v
�@ �r����̂���Ȉꌾ�ɂ���āA�������Ȃ����̖�̐g�̂ӂ肩���͌���ƂȂ����B���̌������Ȃǂŗl�X�Ȑl�Əo�����A�����̌����̈Ⴂ��������A�u���ꂶ��A�ꏏ�Ɏ��̉Ƃɍs���܂��傤�I�v�Ƃ������̎��̂r����̌��t���l�̗U�����A���̏h���b��ł�������o���͏��Ȃ��Ȃ��B�������A����ȏo�����̊���́A�����̐l���Ɍ���I�ȉe���������炵�Ă����悤�Ȃ��̂ł��������B���܂ɂ��Ďv���A���R����ʼn�舧��������Ɂu���̏h����Ă��炤�K�E�ƁH�v���������ӎ��̂����Ƀ}�X�^�[���Ă��܂����̂́A���̎��̌o���ɂ��Ƃ��낪�傫���̂�������Ȃ��B�������A���̂ق��ɂ́A�u���߂Ă��炢�����v�ȂǂƂ����v���Ȃǂ܂������Ȃ��̂����A�Ȃ����������ʓI�ɂ����Ȃ��Ă��܂��̂��B
�@ �����Α��W�]��t�߂ɒ��Ԃ��Ă������r����̎Ԃɓ��悵�Ē�q���̒��ւƂ�����r���ŁA�킽���͂Ȃɂ��Ȃ��r����ɂ����q�˂������B
�@�u���̂��Ɩԑ��̌����ԉ��̂������K�˂Ă݂����Ǝv���Ă����ł����A�ق�Ƃ��͉Ă��I��̂���Ȏ�������Ȃ��āA�Ԃ̍炫����鏉�Ă̍�������Y��Ō����Ȃ�ł��傤�ˁH�v
�@ ���R�A�������Ƃ����Ԏ���������̂��Ƃ�����҂��Ă������́A�ӊO�Ƃ��������悤�̂Ȃ��r����̌��t�ɔ]�V��ł��ӂ����v���������B
�@�u���̏��Ă̍��̑N�₩�ȗɏے�������X�����͋������̑�������A���̒�m��ʑ�n�̊��͂ɂ͂������Q���邵������܂���B����ɁA����̍��Ɍ��錴���ԉ��̉ԁX�̔������͊i�ʂł��B�ł��A���ꂪ���ׂĂ��Ǝv���̂́A���̔w��ɐ��ނ��܂ЂƂ̐��E�����邢�Ƃ܂̂Ȃ����l�̐g����ȑz���ɉ߂��܂����B�ĂɗI�X�Ɩq����H�ޓ����̎p���������āA�P���ɖq��ł̐����ɓ�����ߐ��̗��l�̑z���Ƃ���͏������ς�肠��܂���v
�@�u�͂��c�c�v
�@ �������t�ɋl�܂�̂����Ăr����͂���ɑ������B
�@�u���̖k���̑�n�̕Ћ��ɍ������Đ����鎄�ɂ���A��������K�˂Đ[���������o����̂́A���͔ӏH���珉�~�ɂ����Ă̍��Ȃ�ł���v
�@�u�ǂ����Ăł����H�v
�@�u���̍��ɂȂ�ƁA���̌����ԉ���т̃I�z�[�c�N�̕l�ӂł́A���F�̋�̂��Ƃŏ��Ⴊ�����A�g���悤�Ȋ����������r��͂��߂܂��B������A�Ă̓����Ƃ͂����Ă�����āA�N�ЂƂ�K�˂�l�ȂǂȂ��Ȃ��Ă��܂��܂��B�ł����A���̑��Ԃ���������͂�ʂĂ�����ȏ̂��ƂŁA���������R�ɗ����������悤�ɔE�э炭�����ȉԂ������ł���v
�@�u�ւ��c�c�����Ȃ�ł����H�v
�@�u���̉Ԃ́A���ׂ��g�������ɒɂ߂����Ȃ�����A���Ă��������n�ɕK���ɍ���t���ɑς��č炭��ł��v
�@�u�ǂ�ȉԂȂ�ł����H�v
�@�u�e�Ȃ̑��ԂȂ�ł����A�Ԃ��̂��̂͂قƂ�ǖڗ����Ȃ����������Ȃ��̂ŁA���̕ϓN���Ȃ��������}�ȐF�����Ă��܂��B�������A�N������ȉԂȂnj������Ȃǂ��܂��A���������A����ȉԂ����邱�Ƃ���m��Ȃ��ł��傤�v
�@�@�r����͂����ł������t��������ƁA�܂�Ŏ���Ɍ����������邩�̂悤�ɍĂь����J�����B
�@�u�ł����̉Ԃ͍炭��ł��B�炩���ɂ͂���Ȃ��ł��B�炭�Ƃ����s�ׂ��̂��̂����̉Ԃ̖��̏Ȃ̂ł�����B����́A���Ȃ鐶�����̂��̂̏����̉c�݂Ƃ����Ă��ߌ��ł͂���܂���v
�@�u�Ȃ��A�g�ɂ܂���銴���ł��ˁB����Șb���f���Ɓc�c�v
�@�u�~�̃I�z�[�c�N�C�̓{����w�ɂ��č炭���̉Ԃ����Ă���ƁA�����̂��܂苹���l���Ă��܂����Ƃ������ł���B�Ԃ��̂��̂͂Ȃ�Ƃ����}�Ȋ����̂��̂ŁA�������ɂ��������Ƃ͌����Ȃ��c�c�ł����̉Ԃɂ͕s�v�c�Ȗ��̋P���������ł���v
�@�u�����Ȃ�ł����A����Ȃ��ƍl���Ă��݂܂���ł����B������x���̉Ԃ����Ă݂Ȃ��Ⴂ���Ȃ��ł��ˁv
�@�u�������Ă̌����ԉ��̎�������ʂɐG��A�����Ƃ������̂̉��[���ɐS�ꊴ�Q���Ă��炤�ɂ́A���̉Ԃ̎p����x�͌��Ă������ق����悢��������܂���ˁv
�@�u�c�c�v
�@ ����Ȃr����̍Ō�̈ꌾ�Ɏ��͕Ԃ����t���Ȃ��A���������ق��Đ[���z���ɒ��ނ����������B�������A����ɗނ���b�Ȃ�J�ɂ͂��낢��ƂȂ��킯�ł͂Ȃ�����ǁA���ł����������ɁA���̎��̂r����̈����͕s�v�c�Ȃقǂ̐����͂������Ď��̋��̉����h���Ԃ����B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N12��20��
�����ɑz���i�V�j
�i�j�W�}�X�̛z���琬�����j
�@ ���������A�O�\���قǂŎԂ͒�q���̒��̂͂���ɂ���r����̂���ɒ������B�~�n���ɂ͌k�����͂��ސÂ��ȓ����т������āA���̗т̒������ɐi�ނƁA�`�����A�����̎R�������v�킹�韭��������̃��O�n�E�X�����ꂽ�B�r���炪�v�����Ƃ������̌����̓����ɂ́A�Ăї�̂����Ɏ育��ȑ傫���̏�����݂邳��Ă����B��̂��Ƃ������̂ł悭�͂킩��Ȃ��������A���~���𗬂��k���͒P�ɂ����𗬂�Ă���Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�������ʂȖړI�̂��߂ɗp�����Ă��銴���������B
�@ ���Ƃŏڂ����b���f���Ă킩�����̂����A�r����͈�ʂ̐l�X�ɂ͂قƂ�ǒm���Ă��Ȃ����鐅�Y�W�̋Z�p�J���Ɍg���n���̖��Ԍ����҂������B����̓j�W�}�X�̐l�H�z���ƒt���̐l�H����Ɋւ��錤���ŁA����̎��Y�𓊓����Ă̌l�I�Ȏd���ł������ɂ�������炸�A�����r����͂��̕���̓��{���w�̃X�y�V�����X�g�������̂��B
�@ ���݂̏ɂ��Ă͂悭�킩��Ȃ����A���̍��܂ł̓j�W�}�X�̐l�H�z���ƒt���̐l�H����Z�p�͂܂��m������Ă��Ȃ������B���~���ɂ����鋛���̊Ǘ�����ύ��ł����������ɁA������l�H�z�����A�z�������t�����ʎ��������Ɉ��̑傫���̒t���ɂȂ�܂Ől�H���炷��Z�p�̊����͗e�ՂłȂ��A���p���ɂ͂Ȃ���������Ԃ������B����ȏ������������݂̂ɐ�������j�W�}�X�̐l�H�z���ƛz������̐l�H����ɂ́A�����Ȑ����Ɛ����Ǘ��A�n�ݎ_�f�ʂ̃R���g���[���A�a�̎��Ɨʂ̒����A�a���\�h�ɕK�v�Ȗ��^�ʂ̎Z��Ⓤ�^�@�̍���ȂǁA�������Ȃ���Ȃ�Ȃ���肪�R�ς��Ă����B������A�����̃j�W�}�X�l�H�{�B�Ǝ҂�́A���̑傫���܂Ő��������t�����͐��Ώ��Ȃǂ���̎悵�Ď����A��A�����l�H�{�B�r�ȂǂŐ����ɂȂ�܂Ŏ��炵�Ă����̂ł���B
�@ �O�ꂵ���t�B�[���h���[�N������͂��邱�ƂȂ��A����ł͂܂��������ɗ����Ȃ����I�Ȍ����f�[�^�݂̂\���鍑���̐��Y�w�҂ɂ��āA�r����́A�����Ƃ����꒲�̒��ɂ��ᔻ�Ɣ���̂������������ł���Șb�����Ă��ꂽ���̂������B
�@�u���Ƃ��A�n�ݎ_�f�̓K�ʂ͂��ꂱ��Ő����͂��̂��炢���Ƃ����f�[�^�͂���̂ł����A�����͌������₷�����ʂȎ����{�݂ł̎������ʂ����ƂɊ���o�������̂ł��B�����ɐl�H�z���{�݂�l�H�t���琬�{�݂����ꍇ�A�ǂ��������@�ŗn�ݎ_�f�ʂ␅����K�x�ɃR���g���[�����邩�Ƃ������悤�Ȃ��Ƃ͂ǂ�Ȏ����ׂĂ������Ă���܂���B�ł�����A����Ŏ��R�̂��̂ɋ߂��k�����f����A�V�R�̐��������āA���s����̎������J��Ԃ��A�K�x�̗n�ݎ_�f�ʂ␅�����ێ��Ǘ�������@����J�����Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂ł��v
�@�u����A�����g�ő���ꂽ�����ݔ����������Ȃ�ł��ˁH�v
�@�u�����A�������ł��B�����䗗�ɂȂ�킩��܂����A�߂��Ő��̗���鉹�����Ă���ł��傤�H�c�c���~�̒��Ɍ����̂��߂Ɏ����ŋ�J���đ����������ݔ�������܂��ĂˁB���Ƃ��ƁA���̂��߂ɂ��̏ꏊ�Ɉڂ�Z�悤�Ȃ킯�Ȃ�ł����c�c�v
�@�u������������ł����c�c����������̂ʼn��~�̒����k��������Ă��邱�Ƃ͂����킩��܂����B����ɁA���H�����R�̌k���Ƃ͂Ȃ�ƂȂ�����������������̂ŕs�v�c�ɂ͎v������ł����A�܂������ꂪ�j�W�}�X�̌����̂��߂������Ƃ́c�c�v
�@�u�����␅���̊Ǘ�����łȂ��A�z������̒t���ɗ^����a�̎���ʂ̒�������ϓ����ł���B�܂��t���̕a���\�h�̂��߂ɂ͓K�ʂ̖𓊗^���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł����A������̂ق��͂���ɖ��ł��Ăˁc�c�v
�@�u�ǂ����Ăł����H�v
�@�u�w�҂̌����_���ɂ́A�t�����������̉a��̓��^�K�ʂ��ꉞ�L�ڂ���Ă͂��܂��B�ł������́A�����̋��̂����Ƃɂ��Čv�Z�Ŋ���o���������̐��l�ł�����A�����ɂ͂܂��������ɗ����܂���B�����đ���͐��܂ꂽ����ŏ����Ȃ��炾�̂����ɁA����Ȗ����̒t�����Q���Ȃ��ė���̂��鐅�����D������ɉj������Ă��ł���B�܂���������߂܂��ēK�ʂ̉a��𓊗^���Ă��킯�ɂ������܂���ˁv
�@�u������������ł����A�Ȃ����̒ɂ��b�ł��˂��c�c�v
�@�u���Ƃ��A����̌v�Z�ł͏\�L���O�����̉a�Ɉ�~���O�����̊����Ŗ��������Ă��悢�Ƃ킩�����Ƃ��܂��B����͂�����ł����A���������ǂ�����ď\�L���O�����̉a�̒��ɂ킸����~���O�����̖��ϓ��ɍ���������Ă�����ł��傤�H�B���������̖͐����ɓ�������n���ė���Ă��܂��܂�����A�����t���S���ɓK�ʂ̗\�h���^���悤�Ƃ�����A�ʂ����^�������A����ɂ͓��^�@���ꂩ��l�������Ȃ���Ȃ�Ȃ���ł���v
�@�u����A������������ł���Ă�������킯�ł����H�v
�@�u�����A�܂��܂��������̖�肾�炯�ł�����ǂ��ˁB����Ȍ����A�N�����Ƃ��p���ł͂���Ȃ��ł��傤����A�̗͓I�Ɍ����𑱂��邪�ł��Ȃ��Ȃ�����A����܂Œn���ɐςݏグ�������f�[�^�����́A�k��̌�����������ɂ��ׂĊ�����悤�Ǝv���Ă��܂��v
�@ �r����Ɏf�����Ƃ���ɂ��ƁA���̎�̌����͕��S���ʂő����̕��S��v���邤���ɁA���~���̉ߍ��ȃt�B�[���h���[�N����Ɍ������Ȃ��Ƃ����āA�����͑�w�̋��ސ��̌����҂�����������̂���ł������炵���B���܂����Əo���������̓����A�W���ǂ�����ʂɋ����r����́A�����ɂ���Č��������p�̃j�W�}�X�̍̎�Ƃ��̐��Ԓ��������Ă����̂��Ƃ����B�����ɂ͖������ɃU���K�j�ƎG�H���̃j�W�}�X����������A����炪���N�̂����ɔɐB���A���̐������͌��݂ł͂��Ȃ�̐��ɒB���Ă���炵���B�������A�U���K�j�̓j�W�}�X�̉a�̂ЂƂƂȂ�Ƃ������R�ŕ����ꂽ���̂��Ƃr����͐������Ă��ꂽ�B���Ă͐��E����ւ��Ă��������̓����x���ߔN�ɂȂ��ė����Ă����̂́A�����̔ɐB�ɔ��������Ɋ܂܂��L�@���̗ʂ��������������낤�Ƃ��A���̎��r����͌���Ă����B
�@�u�o�ϐ���x�O�������n�R���������ɂ��킦�āA�~��ɂ͗뉺�O�\�x���z���錵���̒��A�����o��Ŗ��Ӗ��O���ĕX�̉��̋����̏�Ԃׂ��肷���ł�����A�܂��C�Ⴂ�̂�邱�Ƃł��ˁB�����A�C�Ⴂ���ƌ����Ă��܂����ǂˁB�C��̂悢�Ƃ��ȂǂɁA�ǂ����ʼn\�������e���ʂ̂��̕��Ȃǂ��킴�킴���w�Ɍ����邱�Ƃ������ł����A�ʔ������Ƃɂ������������X�̘R�炷���z�͓�̃p�^�[���̂����̂ǂ��炩�Ȃ�ł���v
�@�u�Ƃ����Ⴂ�܂��ƁH�v
�@�u�ЂƂ́A����Ȗʔ�������������قǂɎ��R�̖L���ȂƂ���ł���Ȃ�čō��ł��˂��Ă������́c�c�A���܂ЂƂ́A�킴�킴��J���Ă���Ȍ����Ȃ���Ĉ�̉��ɂȂ��ł������Ă������ł��ˁB�ق�Ƃ��́A�ǂ���ł��Ȃ���ł����ǂˁc�c�v
�@ �Ō�ɂr�����}�C���̊o�߂������ł����ꂢ���̂����ɂ͖��Ɉ�ۓI�������B�b���f���Ȃ��牞�ڊԂ̕ǖʂ��s�����Ă��鏑�˂ɖڂ����ƁA�l�X�ȃW�������̐�发��v�z���A���w���A���A���W�̐}�ӂ⏑�ЗނȂǂ����o�������ɗ�������ł���̂��������B�����Ă���琔�X�̏����̉��ɁA���͂r����̉B���ꂽ�l���̋O�Ղ��_�Ԍ���v���������B�����̂��������ɂ͎��ӂ̕�����`�������ʉ����G���|�����Ă����B�����ɓ����^�b�`�̊G�ł��������s�v�c�Ȃقǂɓ������̕Y���f�l���ꂵ����i�������̂ŁA�u�ǂȂ��̊G�ł����H�v�Ɛq�˂�ƁA�r����͂͂ɂ��C���ɂ������ق���������ƁA�u������Â�ɕ`�������̂ł��v�Ɠ����Ă��ꂽ�B
�@ ���̔Ӓx���ɂȂ��ēV��Ɍ����������B�����̌��ɂقNj߂��E�������Ȃ茇�������ł͂��������A��C������ł������Ƃ������č~�蒍�����͈ӊO�Ȃقǂɖ��邩�����B�ǂ�����Ƃ��Ȃ���{�̃t���[�g�����o���A�����ނ�ɂ������ɂ����r����́A�N�ɕ�������Ƃł��Ȃ��o�b�n�̏��Ȃ�t�ł͂��߂��B�����Ă��̃t���[�g�̉��F�̌������Ă�����T���Ƃ���A����͋q�̎��ł���l�̂r���g�ł��Ȃ��A����n�錎�e���A�����ɓ����̗т�h�炵�Ȃ��琁���ʂ���镗���A�����Ȃ���A�����Ђ��߂Ď��ӂ̎R���忂��召�̐����������ł��邩�̂悤�Ɏv��ꂽ�B
�@ �����r����̂���������O�ɁA���̓j�W�}�X�̌����ݔ�����ʂ茩�w�����Ă�������B�Ȃ�قǁA�k���̗��H�͌����ړI�ɂ��Ȃ��悤�ɐ�������A����̂��������ɂ͑召�̕��G�Ȓi�����l�H�I�ɐ݂���ꂢ���B���������̒i�����͂��̍����ƌX�Γx���C�ӂɕς�����悤�ɍH�v������Ă����B�������A�����␅�ʁA�n�ݎ_�f�ʂȂǂ�K�X�����ł���悤�ɂ��邽�߂������B�a��������A�����̉a�ɕa���\�h�̖�i�����܂����a�������邽�߂̎������u�␅���������u���͂��߁A�e��̕K�v�ݔ��Ȃǂ��k�������ɔz����Ă����B
�@ ���������ƂɁA�����̎����ݔ��͂��ׂĂr����̎葢��ŁA�������A�K�v�ȓ��͂̂قƂ�ǂ͌k���̐��͂𗘗p���ċ��������d�g�݂ɂȂ��Ă����B���̌����𐋍s���邽�߂ɁA�r�����������ł��ׂĂ̌l���Y�𓊓��Ȃ����Ă������Ƃ͂��܂��猾���܂ł��Ȃ��B�k���̉������ł̓j�W�}�X�̐��������Ȃ�̐������Ă������B�r����̊i�ʂȔz���ɂ���āA���͂����̃j�W�}�X�̈�����h�g�ɂ��Ă��炢�A������䂭�܂ł��̖��̂قǂ����\���邱�Ƃ��ł����̂����A�Ȃ��\����Ȃ��悤�ȋC���ɂȂ��Ă��܂������Ƃ����܂��͂�����Ɖ����Ă���B
�@ �ӏH���珉�~�̔������������A���܂��Ď����������̂r����Ƃ̏o������I�z�[�c�N�̕l�ӂɍ炭�Ƃ������������ȋe�Ȃ̉Ԃ̘b��z���o���̂́A����Ȗ����Ă̂��ƂȂ̂��B���ɂ́A�r���̂��̂����́u�����ԁv�Ɠ������݂ł������悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B�̂��ɂȂ��Ă��܂��ܒm��Ƃ���ƂȂ����̂����A���H�o�g�̂r����́A���Ƃ��Ƃ͓����̂��鍑����w�̐V�i���z�w�҂������̂��Ƃ����B�����������Ƃ���A���̟��������O�n�E�X���r����̐v�������Ƃ����̂��ʒi�����ɂ͂�����Ȃ����Ƃ������ƌ�����B�r����́A�l�X�����]�Ȑ܂��o���̂��A�ŏI�I�ɂ͌̋��̋��H�ɋ߂��k�̑�n�̕Ћ��Ɉڂ�Z��Ńj�W�}�X�̐��Ԍ����ɓ]���A�����Ɛ킢�Ȃ��疢�m�̌����ɑł�����ł���ꂽ�̂������B
�@ ������܂߂��l�Ԃ����p�̔�����������m��s�����Ȃ�����A�����̍��Ԃɓ��A���Ƃ̐G�ꍇ�������߂ĎR����삯����A�Î�̒��Ŏv�z�����Ђ��Ƃ��A�����āA���ɂ͐��P���S�̉��̌����̂܂܃L�����p�X�ɋÌ������悤�ȊG��`�����Ƃ���Ƃ��Ă���ꂽ�r����̎p���A����̂��Ƃ̂悤�ɉ��������z���N�������B�Ăѕ������Ƃ͊���Ȃ�����ǂ��A�k�̖��Ɍy�₩�ɒe�������A���邢�͂܂������ɕY�����X�̔@���ɒW������߂��h��Ă������̃t���[�g�̉������܂��������痣��Ȃ��B
�@ �r����ɋ�����ꂽ�e�Ȃ̏����Ȕ����Ԃ��c�O�Ȃ��玄�͂��܂��ڂɂ������Ƃ��Ȃ��B���̍����ۂ��F�̍��n�̍L����I�z�[�c�N�̕l�ӂ�ӏH�ɖK�˂Ă݂�A�r����̂���Ȃ����������̔����Ԃɏo�������Ƃ͂ł���ɈႢ�Ȃ��B�ނ��A���܂����ɂ��������Ă݂����Ƃ����z��������B�������̂����ۂ��ŁA���̉Ԃ����z�̐��E�̒��ɗ��߂Ă������ق����悢�̂ł͂Ȃ����Ƃ����z�������̐S�̒��ɂ��邱�Ƃ��m���ł���B����Ȗ����̗��R�́A���̎����A���܂Ȃ����̉Ԃ����ł�ɂ͑��������Ȃ����o�ɂ܂݂�s�����l�Ԃł��邩��ɂق��Ȃ�Ȃ��B���̍ɂȂ��Ă��Ȃ������Ȃ��̐g�ɂ́A���̉ԂɑΖʂ����Ƃ��A�S�ꂻ�̐����͂Ɋ����ł���Ƃ������M���m�M���Ȃ�����ł���B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2000�N12��27��
�t�B�i�[���͂܂��씩����ŁI
�@ �{���s���U�w�K�Z���^�[�ōÂ���Ă����u�\�������̌��_�v�Ƃ�����A�̍u���������I������B�u�t�w�́A����̎��Ɏn�܂�A�����i�̑}�摕���ł��m����ዷ�̉�Ɠn�ӏ~����A�{����j���[�X�X�e�[�V�����ł�������݂̒����V���ҏW���������F����A����Ƃ̑�䏊�ʖ�������A������\����]�_�Ƃ̋ڑ�r���A�����čŏI���܂��Ƃ��߂��V�i���@�C�I���j�X�g�̐씩��������Ƃ����\���������B���̂ق����B�X����ʁX�ŁA���������u�҂͐\�����ݏ��ɕS���قǂɌ���A�܂���u�����S�Z���ʂ��Đ�Z�S�~�Ƃ����j�i�̈����ŁA�Ȃ�Ƃ��ґ�ȍu���ł͂������B�u�t�Ǝ�u�҂Ƃ����ߋ����ŗ����Ȉӌ������⎿�^���������邱�Ƃ��ł��A�{���u�����Ԃ͖���Ԃɐݒ肳��Ă����ɂ�������炸�A���ۂɂ͈ꎞ�Ԃ���ꎞ�Ԕ����u�`�����������Ƃ����ٗ�̎��Ԃɂ��Ȃ����B�@
�@ �n���̕{���s�ݏZ�Ƃ������Ƃ������āA���͏���̍u�t�̂ق��A���Ƃɑ����e��̍u���̎i������S��������ꂽ�̂ŁA�e�u�t�̔M�ӂ̂��������u�`�̊T�v�ƍu���S�̗̂���Ƃ���ʂ艟�����邱�Ƃ͂ł����B�K���������̐܂̍u�`�̖{�|�ɂ����Ĕ�����ꂽ���̂���ł͂Ȃ���������ǂ��A�e�u�t�͂��ꂼ��Ɋܒ~�̂���Z�����t���c���������B�X�̌��t�̔w�i�ɂ��Ă̏ڂ�������͏ȗ����邪�A���Ƃ��A�����͎��̂悤�Ȃ��̂ł������B
�@�u���̒J�̓y�����̒J�̕��ɐ�����Đ��������v�i�n�ӏ~�j
�@�u�V���L�҂ɕK�v�Ȃ��̂͐��`�S�ł͂Ȃ��D��S�ł���v�i�������F�j
�@�u��X�͌��t�ɓł���s���Ă���B�Ώە����牽�d�ɂ����݂����t������Ă����Ƃ��A�͂��߂Ă��̑��݂̖{���ɔ��邱�Ƃ��ł���v�i�ʖ����j
�@�u�l�Ԃ̖��ӎ��̈�͂���߂Đ[���ł���B���̖��ӎ��̈�̉��ꂩ�猾�t��������ꂽ���̂݁A���̕\���͖������v�i�ڑ�r��j
�@�u�ڂɏ�Q�͂Ȃ��ق����悢�ɂ��܂��Ă���B�������A�t���ɂ��邪�䂦�ɂ����m�o�ł��鐢�E������B���͂Ȃ�Ȃ������玄�̓��@�C�I���j�X�g�ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ������ɈႢ�Ȃ��B�y����ڂŒǂ��Ȃ����͂܂��ȑS�̂��Õ����Ă��特���[�߂Ă����B���ʒʂ�ɒe�������ł͂悢���t�͂ł��Ȃ�����A���ʓI�ɂ͖ڂ��s���R�Ȃ��Ƃ��v���X�ɍ�p���Ă���̂�������Ȃ��v�i�씩�����j
�@ �����܂ŏ����ƁA�u���Ⴂ���������O�͂ǂ�Ȍ��t���c�����H�v�Ƃ����������Njy�ɂ��炳�ꂩ�˂Ȃ��̂����A�ǂ��U��Ԃ��Č��Ă����M�ɒl����悤�Ȍ��t�ȂǓf�����L�����Ȃ��̂ł���B�����A�����ċ�����Ƃ���A�u��X�͖��ؐ������邪�䂦�ɂ��̕����𐳂����Ɗ�����̂ł͂Ȃ��B���ؐ��̑O��ƂȂ�T�O�𐳂����ƐM���Ă��邪�䂦�ɖ��ؐ�������Ɗ����Ă��邾���̂��Ƃł���B���ׂĂ͒�`�ɂ͂��܂��`�ɗ����߂�̂��v�Ƃ������悤�Ȃ��Ƃ͏q�ׂ���������Ȃ��B
�@
�@ �t�B�i�[���̐씩��������̍u���͈�i�Ɛ����������B�\�����Ă���Ă���킯���ݒ��u�҂�\�z���āA���̓��͉��ƂȂ������C���ɍő�����e�\�ȕS�l�\�Ȃ��݂���ꂽ���A����ł������܂����ȂɂȂ�L�l�������B�ꏊ���ꏊ�������̂ŁA�����A�씩����ɂ͍u�����������Ă��炤����ł����̂����A���{�l�̓��ʂȔz���������āA�u���̂��ƃ��@�C�I�����܂Œe���Ă��炦��Ƃ�������Ă��Ȃ��b�ɂȂ����B����ȁu�I����ڂ��݁v�I�W�J�͖]���Ă��������������̂ł͂Ȃ��B�����ŕ{���s�̒S���҂Ɉ˗����A���ƂȂ錤�C���ɋ}篔��t�p�̃A�b�v���C�g�E�s�A�m��������Ă��炤���Ƃɂ����B
�@ �O����̏\��\���ɐ씩����͖��É��Ń��T�C�^�����J�����ƂɂȂ��Ă����B���̃��T�C�^���ŋ������邽�߂Ƀx�������ݏZ�̃s�A�j�X�g�A�R���������O���A���������肾�������A�Ȃ�ƁA�����e�̐��Y�����q����̂ق��A���̎R������܂ł����씩����ƈꏏ�ɗ��ꂵ�Ă����������̂������B�܂��A���ɂ͐씩���s���̖�Q���̂ɑ��������ۋ��ɃA�����J���s���������Ƃ����I�o�A�l�̎p���������B
�@ �J��O�A�씩�����s�ɉ��̔z�u��s�A�m�̐ݒu�Ȃǂ��`�F�b�N���Ă�������̂����A���y�ɂ͂܂�őf�l�̂ɂ킩�݂����������Ƃ������āA�s�A�m�̌������t�ɂȂ��Ă���������Ă����B�����ŁA�s�̘^���S���Z�t�Ɏ��Ɛ��Y����A����ɂ͎R����������܂ł�������đ�}���Ńs�A�m�̌����ƈʒu��ς���Ƃ������܂��܂ł����L�l�������B�I�ɂ�ނȂ����Ƃł͂������̂����A���t�O�ɉ��t�҂̂����l�⋤���s�A�j�X�g�Ƀs�A�m�̈ړ�����`�킹��ȂǂƂ����O�㖢���̒֎������ł͋N�����Ă����̂ł���B
�@ �s�A�m�̈ʒu����܂�ƁA�u���[���X�̃n���K���A���Ȃ̈ꕔ��p���ĎO�A�l���قNJȒP�ȉ����킹���s�Ȃ�ꂽ�B�u���I����ɎR���������璼�ڎf�����Ƃ���ɂ��ƁA�h�C�c������{�ɖ߂�������ł܂������ڂ���Ԃ����������ɁA���ʂ������ɐ씩����T�C�h����n���ꂽ�̂������ł���B����ł�������̏ɑΉ����Ă��܂��Ƃ���Ȃǂ͂������v���̋ƂƂ����ق��Ȃ��B�˕��w������ɂ͎R������͐씩����̓�N��y�ŏ������͓��w���݊w���������Ƃ�������A���݂��̌ċz�͂�����x�킩���Ă͂���̂��낤���A����ɂ��Ă������������̂ł���B��q����̘b�ɂ��ƁA�R������͏����̊y�������̏�őN�₩�ɒe�����Ȃ��Ƃ����H�L�̍˔\�̎�����ł�����Ƃ������Ƃ������B
�@ ��������T�����Ɉڂ�y���ɒ��ւ����씩������ē����Ē荏�ɍu�����ɓ���ƁA�傫�Ȃǂ�߂��ɍ������āA�u�ق�Ƃ��[���I�v�Ƃ����ꂫ�Ƃ������Ƃ����ʂ������������������R�ꋿ�����B�e���r�Ƀ��W�I����ɂ͏��X�̐V����G���ɂƁA���܂�������肾���̐씩����̎p����n�������̂̐��U�w�K�Z���^�[�̍u���Ŋԋ߂Ɍ��邱�Ƃ��ł���Ȃ�Ă����炭��u�҂ɂƂ��Ă��]�O�̂��Ƃ������낤����A���ۂɂ��̖ڂŊm���߂Ă݂�܂ł͔��M���^�������l�����Ȃ��Ȃ������̂ł��낤�B
�@ �씩�����ɂ������@�C�I�����P�[�X�����ɂ��낵�ĐȂɒ����ƁA��ꂩ���Ăɔ��肪�N���N�����B�����Ďi��̎��̊ȒP�ȏЉ�I���ƁA�씩����͂����ɂ悭�ʂ鐺�Řb���n�߂��B�������������Ƃ������̌��t�����Ƃ����A���ɓ��X����b���U��ł���B�e���r��W�I�ɂ͂���������o�����C���^�r���[�Ȃǂ������Ԃ�ƎĂ���씩�����A�Ԃɂ킽���ĒP�Ƃ̍u��������̂͂��̎������߂ĂƂ������Ƃ������B�ނ������m�Ŏ��͂��̓��̍u�����˗������悤�Ȃ킯�ł��������B
�@ ���炩���߂��������Ă������u���e�[�}�́u���ƃ��@�C�I�����v�Ƃ������̂ł��������A���t���}�X�R�~�e�Ђ̎�ށA�˗����e�̏����Ȃǂōu���̑O���܂ŃX�P�W���[�����т����肾�Ƃ������Ƃł��������̂ŁA���R�̐���s���ɂ܂����Ԃ����{�ԂōD���Ȃ悤�ɘb���Ă��炤���ƂɂȂ����B���������ق�����u�҂ɂ��{���̐씩����炵�������܂��`��邾�낤�Ƃ����v�������̂ق��ɂ����������Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B
�@ �b�̓L�J���V�������c�N���̉�z����n�܂����B�����ė���̃��T���[���X�Ŗ�Q���̂ɑ������ăJ���t�H���j�A��w���f�B�J���Z���^�[�ɋً}���@�A�����Ő����̋��������������̂Ԃ��ȏA��ՓI�Ȑ��҂̑㏞�Ɏ��͂Ȃ��ċA���������ƂȂǂ��A�W�X�Ƃ������q�ŏ���ǂ��Č��ꂽ�B���ɒ[���ȓ��{��Ō��t�̑I���������قǂɓI�m�ł���B�n���h�}�C�N����ɘb�����̎p�����s�[���Ɣw���L�тĂ��āA�����e�ɕ���ō����Ă��鎄�Ȃǂ͎v�킸�p������n���������B
�@ �����ď\�ł�������Ƀ��@�C�I�������K���͂��߁A����\���Ԉȏ�̖ғ��P�ɑς����������̑z���o�����ꂽ�B�����͖͑����ɕ`���ꂽ�傫�Ȍܐ����Ȃ�h�����ēǂݎ�邱�Ƃ��ł����̂ŕS���߂����������L�����͑�����p�ӂ��ė��K���Ă������A�}�W�b�N�̏L�����ٗl�Ȃ܂łɕ����ɗ������ߑ�ς��������ƁA�����ĂقǂȂ����ꂳ�����o���Ȃ��Ȃ�A���̌�͒����ɂ��Õ��ɗ��邵���Ȃ��Ȃ����Ȃǂ��A�씩���̃��[���A�������Ȃ��玟�X�ɏЉ�ꂽ�B�씩���g�������{���̃��Y���ƌ��t�ŐS�̉��̎v������������ƒ��O�Ɍ������Č�肩���銴���������̂ŁA�e���r�Ȃǂ̃h�L�������g�ԑg�ȂǂƂ͂܂�����������������āA�����X����l�X�̕\����Ȃ��₩�ł������^�����̂��̂������B
�@ �u���̂��ƂɂȂ��āA�u�����̎q���͗c��������n�߂����@�C�I�������\�ł�߂����ǁA�씩����͏\�Ŏn�߂Ă��̐����c�c�V�˂Ɩ}�l�̈Ⴂ�͂���ς肻�̂ւ�ɂ���̂�ˁv�ƌ����Ď��ӂ��킹���m�l���������A�܂��Ɍ������Ė��Ƃ����Ƃ��낾�낤�B�\���͖L���Ȃ����ɂقƂ�Ǘ���̌����Ȃ����t�̗�����������Œ����Ă��鎄�ɂ́A���̐l�̖{���I�ȓ��̖������Ƃł������ׂ����̂��Â�ĂȂ�Ȃ������B
�@ �˕��w�����Z����̑̈�̎��ԁA���Z��g���b�N���Z�Ȃǂ��v���悤�ɂł��Ȃ��씩����ɂ͋��t������ʃ��j���[���ۂ����Ă����Ƃ����B���̃��j���[�̓}���c�[�}���̎w���ł��Ȃ���邱�Ƃɂ͂Ȃ��Ă����̂����A�}���\����o�R�Ȃǂ̃m���}�������Ղ�Ƒg�ݍ��܂ꂽ�����Ƀn�[�h�Ȃ�����̂ł������炵���B���鎞�A�w�F�̈�l�����ڂ��C���N�����ē����̈�̌l���Ƃ�̌����Ă݂邱�ƂɂȂ����̂����A����������ō��������M�u�A�b�v���Ă��܂����Ƃ����G�s�\�[�h�Ȃǂ���I���ꂽ�B�����ނ��g�����Ƃ��ł��Ȃ����߁A��w�̕��Ȃǂɂ��l�m��ʋ�J���������悤�ł���B���w���A���O�𑼂̎҂ƍ��ʂ͂��Ȃ��Ɛ錾���A�������g���[�j���O���ۂ��������̋��t�ɂ��܂͐S���犴�ӂ��Ă���ƌ��씩����̕\��݂͂邩��ɑu�₩�Ő��X���������B
�@ �˕��w�����y��w���ƌ�A�p���������y�@�̑�w�@�ɗ��w���邱�ƂɎ^���������̂͐��Y�����q����̌䗼�e�Ƌ˕����厞��̉��t�]���r�Ƃ���̎O�l�����ŁA�ق��̐l�X�͊F���������̂��Ƃ����B���ʓI�ɂ͉p�����w���씩����̔���I�����ɂȂ������킯�����A������A�Ō����Ɏx���������e�Ƃ��Ƒ��ɑ��銴�ӂ̋C������씩����͂͂�����Əq�ד`���Ă������B�Ƃ��ɂ��ꂳ��̗�q����Ȃǂ́A�씩����̐g�̉��̐��b�����邾���ł͂Ȃ��A�������y�@�̎��ƂɈꏏ�ɏo�Ȃ��邱�Ƃ��`���t�����Ă������̂�����������A���̂���J�̂قǂ͕����̂��Ƃł͂Ȃ������ɈႢ�Ȃ��B
�@ �\���قǂ̋x�e���͂��ݐ씩����̍u���͂قړԂɂ킽���đ�����ꂽ���A�Ō�܂ł��̘b�͉��̐l�X�̐S�������䂫���ė����Ȃ������B�C�M���X�ł̕w����̏A�މ�̉��y���̑���_�A���y�\���ɑ��鎩���̎p���Ɨ��O�Ȃǂ��܁X�E�B�b�g�������Č��ꂽ�B�����āA�Ō�ɁA�����ǂ�������肩�Ƃ悭�q�˂��邱�Ƃ����邪�A�����N���낤�Ɛ�X�̂��Ƃ͉^���̕����܂܂ɔC���邵���Ȃ��̂ł����āA�����Ƃ��Ă̓x�X�g��s���Č��݂��A���t�ƂƂ��Ăł��邩����̌��r��ςނ��Ƃ����l���Ă��Ȃ��Ƃ�������|�̂��Ƃ��q�ׂ�ꂽ�B
�@ �씩����͍u���̂Ȃ��ł����e�₲�Ƒ��ɑ���[�����ӂ̋C���������x���J��Ԃ��q�ׂĂ���ꂽ���A���ɂ͂��ꂪ���̍u�����@�ɂ����씩���g�̐��_�I�����錾�ł�����悤�Ɋ������ĂȂ�Ȃ������B�u�t�Ȃɂ����āA���͉��̉��̂ق��ɖڗ����ƂȂ������Ă����邲�Ƒ��̂��l�q�Ȃǂ����肰�Ȃ��q������������Ă������̂����A�����̌��ӕ\���Ƃ��v����씩����̓��X���錾�t�̈�ЂƂɁA�������̕\����ׂĂ���ꂽ�̂���ۓI�ł��������B
�@ �u�����I�����씩����́A��S�O�\�N�O�ɃC�^���A�ő���ꂽ����K�_�j�[�j���P�[�X���炻���Ǝ��o�����B�ȑO�Ɏ����O��s�̂����K�˂��܁A�����ɐG�点�Ă�������̂͂������̂́A�ْ��̂��܂�肪�k���ĂȂ�Ȃ�������̃V�����m�ł���B�씩����͂��̖�����ꉞ���@�C�I������p�̃P�[�X�ł͂��邪�A�ꌩ���Ăǂ��ɂł����肻���ȕz�n�̃P�[�X�ɓ���Ď��������Ă���B���ԕ��l�̏����ȏ���̂������̃P�[�X�̌��R�̕t��������́A������Ƃقꂽ�肵�Ă��āA�m��Ȃ��l�Ȃǂ��O���猩�������ł͂��̒��ɋM�d�ȃ��@�C�I�������[�܂��Ă���ȂǂƂ͑z�������Ȃ����Ƃ��낤�B���邩��ɍ��������ȃs�J�s�J�̔琻�P�[�X�Ȃǎg���Ă��Ȃ��Ƃ��낪�����ɂ��씩����炵���B
�@ �씩����́A�R����������̃s�A�m���t�̂��ƁA�u���[���X�́u�n���K���[���ȑ��ԁv�A�O���b�N�́u����̗x��v�A�����đO���Ƀ��B�N�^�[���甭�����ꂽ����̓ڂ�CD�^�C�g���ȁA�O�m�[��ȁu�A���F�E�}���A�v�̎O�Ȃ����X�ɒe���Ă��ꂽ�B�������������ʔz�������Ă��Ȃ��������ʂ̌��C���ɂ����鉉�t�ł������ɂ�������炸�A���̐_���Ƃ��������l�̂Ȃ���ՓI�Ȍ��̋����ɉ��̒N�������������|���ꂽ�B�ڂɗ܂��אg���났�ЂƂ����ɉ��t�ɒ��������Ă���l���A������ƌ��܂킵�������ł������������������B
�@ ���t���e���r�Ō���ꍇ�Ƃ������āA���t���̐씩����̈ꋓ�ꓮ���A���̑��������܂߂Ă���������Ԃ��ɒ��ߖ��키���Ƃ��ł����̂��A���̏�ɋ����킹���K�^�Ȓ��O�ɂƂ��Ă͊����������낤�B�u���I����Ɏ�u�҂͊F���F�A�l�X�Ȋ����Ə̎^�̌��t���c���ċA���Ă��������A�����̐l�X�̑z���́A�u�v�X�ɐ��삪�����̐g�̂̒��ɖ߂��Ă��Ă���܂����v�Ƃ��������u�҂̒Z���ꌾ�ɏW��Ă����ƌ����Ă��悢���낤�B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N1��3��
�N���̈��A�ɂ�����
�@ ���������̗����̏����Ȓ��w�Z�𑲋Ƃ������A�Ⴂ�����̉��y���t�͎��̑��ƋL�O�T�C�����Ɂu���e����A��\�ꐢ�I�܂Ő����܂��傤�ˁI�v�Ƃ����Z�����t����������Ă��ꂽ�B��䖞�q�Ƃ������̐搶���ǂ�Ȏv���ƈӐ}�����߂Ă���Ȍ��t���T�C�����ɋL���Ă��ꂽ�̂��́A�����ȂƂ��낢�܂��ɂ悭�͂킩��Ȃ��B�����A�ꌩ�Ȃ�ł��Ȃ��悤�ɂ݂��邱�̌��t�́A���̌�̐l���ɂ����Ė��Ɏ��̐S�Ɏc�葱�����̂������B�Ɛg�̐^�ʖڂȐ搶�������L���͂��邪�A�Ƃ�킯���l�������Ƃ����킯�ł��Ȃ��A���k�̊ԂłƂ��ɂ������悩�����Ƃ����킯�ł��Ȃ���������i�������ǂ����Őٍe���䗗�ɂȂ��Ă�����A�搶���߂�Ȃ����j�A��͂肻�̌��t���̂��̂Ɍ������ȏ�̎����͂��������Ƃ������ƂȂ̂��낤�B
�@ �Ō�̓��e����������̑c����̎������߂��A�قǂȂ��V�U�ǓƂ̐g�ɂȂ�ł��낤���Ƃ�\�����Ă������N����̂��Ƃ�����A�����ł͈ӎ��������Ă��Ȃ��������̂́A�O�r�̐��ɑ���s���̉e������[�X�ƕ�ݍ���ł����̂�������Ȃ��B������A�u���̓����I�Ȑ��k���A���������܂����Ȃ��Ȃ��t��������A�Ȃ�Ƃ���l�O�̑�l�ɂȂ��Ď���ǂ������I�܂Ő����������Ƃ��ł��܂��悤�Ɂc�c�v�Ƃł��������悤�Ȗ����ȋF������߂āA���̐搶�́u��\�ꐢ�I�܂Ő����܂��傤�ˁI�v�ƌ�肩���Ă����������̂�������Ȃ��B
�@ ���������l���ł͂Ȃ��������A�Ƃ����������͌\��㔼�Ƃ������̔N��܂Ő����̂сA��\�ꐢ�I���܂��܂��̏�ԂŌ}���邱�Ƃ��ł����B���搶�̂��̌�̏����͂킩��Ȃ��̂����A�����Ƃǂ����ł������̂��Ƃ��낤�Ǝv���B�Ԗʏǂ̋C�������ĒʐM��ɂ͂����������������Ə�����Ă����u�������̌����v�݂����ȏ��N���A��\�ꐢ�I�ɓ��������܂ł́A���Ȃ��Ƃ��O����́u�O�����̌����H�v�݂����Ȑ��Ԃ��ꂵ�����N�j�ւƕϖe�𐋂��Ă��܂����̂�����A�����̖��p�Ƃ������̂͂��狰�낵���B
�@ ���ۂɂ͂��܂ł��V���C�Ȏ����⎩�ȉߏ�C���ȋC�����̓��ɑ��Â������Ă��邱�Ƃɕς��͂Ȃ��̂����A���L�邲�Ƃɂ���炪�\�ʂɗ�������邱�Ƃ����͂Ȃ��Ȃ����B���̈Ӗ��ł͂Ƃ��������߂ł������Ƃł���B���܂���x�����邩�ȂƂ����C�����Ȃ��ł͂Ȃ����A�����I�܂ŋ��ɐ����܂��傤�Ɛ����܂��Ă����������搶�ɂ͈ꌾ�����\���グ�����B
�@ ���āA�����܂ł͂܂��悢�̂����A���Ȃ͓̂�\�ꐢ�I���}�������ꂩ�炠�Ƃǂ����邩�Ƃ������Ƃł���B�u��\�ꐢ�I�܂Ő�����v�Ƃ������ʂ̖ڕW��B�������̂͂悢�̂�����ǁA�Ȃɂ�甏�q�������Ă��܂��āA���������Ƌْ������������܂܂ł��ꂩ��̗]���𑗂邱�Ƃɂ��Ȃ肩�˂Ȃ��B������ƌ����āA������Ȃ�ł��A�u��\�I�܂Ő����܂��傤�ˁI�v�ȂǂƂ����}�X�����ڕW��搂�������킯�ɂ������Ȃ��Ƃ��Ă��邩��A�b�͂Ȃ��Ȃ��ɖ��Ȃ̂ł���B
�@ �ǎ҂̊F����ɂ͖��f�Șb��������Ȃ����A�S�ْ̋����قǂ悭�ۂƂ����ϓ_���炷���A��T�Ԃ��ƂɌ��e�X�V���̂߂����Ă���{���̎��M��ƂȂǂ͂���Ȃ�ɗL�Ӌ`�Ȃ��Ƃ̂�������Ȃ��B�����Ɍ��킹�Ă��炤�ƁA���̕��Q�L�̌��e�͎d���Ƃ��āi���e��������ړI�Ƃ����d���Ƃ��āj�����Ă���킯�ł͂Ȃ�����A�����������Ȃ��t���[�����X�̐g�ɂ��Ă݂�A���߂Ă��ꂭ�炢�̌䗘�v�͂Ȃ��ƍ���Ƃ������̂��B����Ȃ��Ƃ��������肷��ƁA�u�ȂA���O�̓{�P�h�~�̂��߂ɏ��������e��l�l�ɓǂ܂���C���H�v�ȂǂƂ�����������ނ鎖�Ԃɂ��Ȃ肩�˂Ȃ����A���ۂ̂Ƃ���͎d���Ƃ��Ď��M���錴�e�Ȃǂ����͂邩�ɐ������X���A����Ȃ�Ɏ��Ԃ𒍂���������Ă��邩��A���̓_�͑�ڂɌ��Ă������������B
�@ ����ɂ��Ă��A��N�O�̏\���ɂ��̕��Q�L��S�����n�߂Ă��炱��܂łɏ��������e�̕��ʂ́A�����ƌv�Z���������ł��l�S���l�ߗp���Ő�ܕS���ɂ��̂ڂ�B�P�s�{�ɂ���䂤�ɎO�A�l�����ɂ͂Ȃ镪�ʂȂ̂����A�ނ��A�O�����C�^�[�̏������������炵�����͂����܂ǂ��D��Ŗ{�ɂ��悤�Ƃ����o�ŎЂȂǂ����������낤�͂����Ȃ��B���̂����ɁA�s���҂̂��̐g�ɂ́A����ϋɓI�ɓ����ĒP�s�{�ɓZ�߂Ă����o�ŎЂ�T�����Ƃ����ӗ~���Ȃ��Ƃ��Ă��邩��A�������܂܂̑ʕ��̎R�́A���������Ƃ��̂����ʕ��̎R���ւƕϖe���Ă������˂Ȃ��B�s�тȎR���ɂȂ�O�Ƀu���h�[�U�ŎR������A�����̍앨���炢�͊n��锨�ɕς��Ă݂�̂��Ǝv��Ȃ����Ƃ��Ȃ����A����łȂ��Ă��k������̑������̓~�̎���A����͖����Șb���낤�B
�@ ����ł�����������̂��Ɩ����Ȃ�A���X�̐�����ɗ��������������̗̑͂ƋC�͂������A�����đ����Ƃ�����ȑʕ���ǂ�ł�������������邩����͂������������Ǝv���Ă���Ƃ������������B�K���A���܂ł͑�ςȐ��̕��X�������O����AIC���ɃA�N�Z�X���Ă��������Ă���悤�Ȃ̂ŁA���̃��C�^�[�̈�[��S�������ł��邩����̓w�͂͂������ƍl���Ă���B�ȑO�ɂ���������q�ׂ����Ƃ����邪�A�C���^�[�l�b�g�̑O�g�ł���p�\�R���ʐM�̑��n���ȗ��A���́A�u�R���s���[�^�ʐM�ŕ��͂M����Ȃ�āA���l�O�̃I�^�N�ǂ��̂�邱�Ƃ��c�c�v�Ƃ������₩�Ȑ���w�ɂ��Ȃ���A�����I�ɐٕ��̔��M�����݂Ă����B���̈Ӗ��ł����܂��瓦���o���킯�ɂ͂����Ȃ��Ƃ����C�����Ă���B
�@ ���������ƁA��m���̒m�l��������A�u�������b�ɂ��ƁAAIC���Ē����V���W�̒��ł͓��قȑ��݂Ȃ��Ă˂��B�ǂ������Ƃ����ƁA�V���{���⒩���n�T�����⌎�����ƈႢ�A�����͂��߂Ƃ���t���[�̃��C�^�[���A�����̎�͋���͂�����Ƃ͂��ꂽ�l�B�Łc�c�i�M�Ғ��F�Ƃ������������AIC�̗D�G�ȃt���[���C�^�[�̕��A���߂�Ȃ����j�v�Ȃnj���ꂽ���Ƃ��ߋ��Ɉ�x���x�ł͂Ȃ��B�Ƃ��낪�A���������ƂɁA����Ȃ��Ƃ�������ƃV�����ƂȂ�ǂ��납���������Ɠ����S���N���N����A����Ȃ�܂��Ɍ��Ă��Ɠ��S�ŗ]�v�Ȕ����������Ȃ�̂����̐g�̈����Ƃ���ł�����B
�@ �V���{����T�����A�������Ȃǂƈ����AIC�ɂ͍u�Ǘ����ݒ肳��Ă���킯�ł͂Ȃ�����A���ڒ����V���Ђ̎��v�ɂȂ���킯�ł��Ȃ��B�ߍ��ł͂����炩�L���Ȃǂ��f�ڂ����悤�ɂȂ����悤�����瑽���̎��v�͂���̂��낤������͑S�̂��猩������X����z�̂��̂��낤�B���������āA�������e����˂Ȃ�ʓ����̍����ȍ�ƂȂǂ����X�o�ꂷ��]�n�́A�����I�ɂ͂Ƃ������Ƃ��Ă��A�ډ��̂Ƃ���͂قƂ�ǂȂ��ƌ����Ă悢���낤�B����ȏȂ̂�����A���̏������e�Ȃǂ̓��f�B�A�̎嗬�Ɉʒu���鎯�҂̖ڂ��炷��S�~���R�Ɍ�����̂����R�̂��Ƃ��낤���A���̂��Ƃ���������ے肷�����Ȃǖѓ��Ȃ��B
�@ �����A�u�ꐡ�̒��ɂ��ܕ��̍��v�̌��ł͂Ȃ����A�t���Ɋ���A�������̂Ȃ��g�Ƃ������̂͊J�����肪���������Ɍ��\�S�苭���ł��ꋭ���B���Ƃ����ʓI�ɂ͑ʕ��ɂȂ��Ă��܂����Ƃ��A���œǂ�ł���������X�̂��邩����A�P�Ȃ�{�P�h�~�̂��߂Ȃǂł͂Ȃ��A��͂Ȑg�Ȃ�̐��������߂Ă��̕��Q�L�����������Ă݂����Ƃ͎v���Ă���B���N�͕��Q�͈̔͂�ʏ�̗��̐��E�����ɂƂǂ߂��A�|�p��Ԃ�_���E�ւ̗��ɂ��L���Ă������ƂɂȂ邩������Ȃ��B��\�ꐢ�I���N�ɂ����鍡�N���܂����N���l�ɊF����ɂ��t�������肦��K���Ȃ��Ƃ��̂����Ȃ��B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N1��10��
��IT�l�Ԃ̈��D
�@ ��\�ꐢ�I���}�������܁A�䂪���ł́uIT�v���v�Ȃ錾�t�������͂��ɂȂ��Ă���B�܂�ŁA�uIT�v���ɏ��x�ꂽ�҂͎Љ�̒E���҂ƂȂ邱�Ɛ����������v�Ƃł���������̗��s�Ԃ肾�B���Ԃ̑��V���N�^���N��R���T���e�B���O��Ђɋ߂�m�l�����́A�n�������̂��͂��߂Ƃ�����I�@������IT�u����IT�헪�̊��Ǝ��H�ɖz�����A���ꂪ�܂���ςȐ��ʂ������Ă���炵���B�ނ��A�����Ō����u���ʁv�Ƃ́A���I�@�ւ��ނ�̊��ɐi��ŗ\�Z�𓊓����Ă���邽�߂Ɏ��v���������Ă���Ƃ����Ӗ��ł����āAIT���Ȃ킿���Z�p�̖{���ɑ��邨��l�����̗������[�܂�A���̂��ߎ����̓���IT�Z�p��ϋɓI�Ɋ��p���悤�Ƃ����@�^�����܂����Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B
�@ ���特�����Ƃ���IT�v���ȂǂǂԂ���������O������̂��낤�A�ŋ߁A�����ȂȂǂ͊e�n�������̂ɑ�IT�֘A�̍u���Ȃǂ������������悵�Ď�u����悤�ɂƂ����ʒB���o���A��u�Ґl���̊��蓖�Ă܂Ŏw�����Ă���炵���B����n�������̂̎Љ�畔��ɑ�����m�l���A�u�����ȋ���g�b�v�_�E���ł���Ă����w�߂ɏ]���A���������̕����̎҂������s���\����IT����̍u���ɔ������I�ɎQ�����������ł���B��̐l�ƈ���ĉ�X����̎����S���҂͂���łȂ��Ă����Z�ł��̂Ɂc�c�B�������A��u�͈�N�Ԃ����Ɍ��肳��Ă��āA���e�͂������A��u���u���Ԑ������Ē��r���[�Ȃ�ł��B���Ȃ���ł��̕���̐�C�ƂȂ�ׂ��A���߂ĎO�A�l�N�͎d������݂�IT�̕��������Ă��炦��Ƃ����̂Ȃ�b�ׂ͂Ȃ�ł����ˁc�c�v�ƃ{�����Ă����B
�@ �������̃I�W�T���A���哱��IT�v���Ȃ�Ă܂�����Ȃ��̂��낤�B���Ƃ���IT�v���̖{���I�Ȓ��g�Ȃǂǂ��ł��悭�AIT�v���Ƃ��������I�ȕW����f���č����̐S��h�蓮�����A�R���s���[�^��ʐM�֘A�@���}��ɑ�K�͂Ȏ����̗��ʂ��N����悢�Ƃ����̂��{�ӂȂ̂��낤�B�����A�u���߂�Ȃ����v�ƌ�����IT�̂ق����������Ɠ����o���Ă��܂������ɂ������鐭�����I�W�T���A�̎v�f�ʂ�ɁA���̌���̐��̒��������Ă������̂��ǂ����c�c�B
�@ ���������A���Ԃł͂Ƃ�����IT�v�����N�����Ă��邵�A���{��W�Ȓ�����������낤�����܂���IT�ɂ��Љ�̕ϊv�ƍ��������̊v�V�͋}���ɐi�W���Ă����B�Ő�[��IT�����Ɍg�����̃X�y�V�����X�g�⏔�X�̐��Z�p�ҁA����ɂ̓Q�[����i���[�h����̎�҂����́A�L�[�{�[�h�Ɍ������ǂ����̍��̎�TV�f���𔒁X�����v���Œ��߂Ȃ���A�u�������X�c�c�v�Ƃ�������Ă��邱�Ƃ��낤�B
�@ �����g�ɂ��Č����A���Ă̎d���̊W�������āA�R���s���[�^���g���n�߂��̂��A���[�v���ŕ��͂������n�߂��̂��A�����Ȋw�p���邢�͋���p�̃R���s���[�^�\�t�g�⌾��J���Ɋւ��X�̃v���O�������쐬�����̂��A�����ăp�\�R���ʐM���n�߂��̂������ł͂���߂đ����ق��������Ǝv���B����قǂɒ����R���s���[�^���������Ă���Ƃ����̂ɁA�ߍ��ł́A���̐l�X�ɐ����A�������������ƌ\�����S�����x��ď��Z�p�̉��b������̂���Ƃ���悤�ɂȂ��Ă��܂����B�ߔN�ɂȂ��āA�V�������Z�p�ɑ��鑊�ΓI�S�x����܂��Ă����͎̂����̂悤�ŁA���̒m�V�Ƃ������t��X�I�Ɏ��Ƃ���A�u�m�V�v�̕����ɏ��X�Ȃ肪�����n�߂��Ƃ������Ƃł���炵���B��IT�l�Ԃ̈��D�Ƃ����킯���B
�@ ���܂���v���I���`���̂悤��8�r�b�g�}�V�[���̃A�b�v���E�R���s���[�^�����̎���A�����̃Q�[����i���������A�����J�Łu�g�����V�����@�j�A�v�Ƃ��u���r���t�b�h�v�Ƃ��u�f�b�h���C���v�Ƃ��������A�h�x���`���[�Q�[���̐V�삪���������ƁA�uMICRO�i�}�C�N���j�v�Ƃ��������R���s���[�^�������s���Ă����V�I���Ђ̕ҏW������قǂȂ��䂪�ƂɃQ�[���f�B�X�N���͂���ꂽ���̂������B�h���L�������݂��͂��߁A�L���Ȋe��L�����N�^�[�̓o�ꂷ�邻���̃Q�[���Ɉꎞ���͂܂肫���Ă������́A�Ƒ��̗��₩�Ȏ�����w���Ɋ������{���̎d�����������̂��ɂ��Ė�Ȗ�Ȃ����V��Q�[���Ƀ`�������W���A���̕����L��U���L����MICRO���Ɍf�ڂ���������Ă������̂��B
�@ �܂������ł́A�R���s���[�^����W�̐��L�������M������A���̍��ɃA�����J�ŕ]���ɂȂ�n�߂�����̃x�m�A�EB�E�}���f���u���[�g�̃t���N�^�����_�ɂ��Ẳ���L���Ȃǂ�A�ڂ���������Ă������B�t���N�^�����_�͂̂��ɃJ�I�X���_�A����ɂ͕��G�n�̗��_�ւƔ��W���A����`�I���i�������ۂȂǂ̂悤�Ɋ֘A����v�f�����G�����l�Ɍ������Ă��āA����̐����Ȃǂł͗e�ՂɋL�q�����菈��������ł��Ȃ��悤�Ȗ��j�̋L�q�⏈���ȂǂɌ������Ȃ����̂ƂȂ��Ă������̂����A�����̉䂪���ɂ����ẮA�܂��R���s���[�^�E�O���t�B�b�N�X�̎a�V�Ȏ�@��������X�I���_�Ƃ��Ē��ڂ���n�߂����x�ɂ����Ȃ������B���܂��炿�傤�Ǐ\���N�O�Ɏ��M���A�}�C�N�����̊����L���ƂȂ�����ʌ����̃t���N�^�����_����L���A�u�t���N�^�������v�͍K���Ȃ��ƂɍD�]���A�����̐l�X�ɗl�X�Ȏ�����^���邱�Ƃ��ł��͂����悤�ł���B
�@ �O����LOGO�Ƃ�������ȋ���p�����p���ăV�~�����[�V�������̑��̃v���O���������삵�A����Ɋ�Â��A�ڋL�����Ȋw�����ɏ����Ă����̂����̍��̂��Ƃł���B��̑O�A�����J�̑�w�ōL���p�����Ă���PASCAL(�p�X�J��)�Ƃ��������Ȋw�p�����LISP�i���X�v�j�Ƃ����l�H�m�\�p������x�[�X��MIT�ŋ���p�ɊJ�����ꂽLOGO�Ƃ����v���O���~���O����́A�䂪���ł͒P�Ȃ邨�G�`�p���ꂾ�ƌ������A���͂�Y�ꋎ��ꂽ���݂ɂȂ��Ă��܂��Ă��邪�A���ܐU��Ԃ��Ă݂Ă����ۂɂ͂���߂ėD�ꂽ�R���s���[�^����p����ł������Ǝv���B�w�������ɐ��w�╨���̌����v�l����������A�l�H�m�\�̊�{����������A���x�ȃR���s���[�^�E�v���O���~���O�̍������Ȃ����J�[�W�����i�ċA�j�Ƃ�������ȊT�O����{��������w�����肷��̂ɂ͍œK�ł������B
�@ MIT�̐��w�҃G�[�x���\���Ȃǂ́u�^�[�g���E�W�I���g���[�v�Ƃ����{���A�g�|���W�[�i�ʑ��w�j�⑊�ΐ����_�Ƃ��������x�ȗ��_�̌����w�K�ɂ܂ł��̌��ꂪ���p�\�ł��邱�Ƃ������������B�p�p�[�g��~���X�L�[�Ƃ�����MIT���f�B�A���{�̑n���҂����ɂ���ĊJ�����ꂽ���̌���̉��[���ɂƂ���ꂽ���́A�����Ȋw�̌����w�K�Ɋւ��邳�܂��܂ȃv���O���~���O�����������Ȃ��A���̈�[���Ȋw�����ɘA�ڂ��Ă����悤�Ȃ킯�������B
�@ �]�k�ɂȂ邪�A���̍��A�L�����e�̑ł����킹���������{���̉䂪�Ƃ܂Ō��e�����ɗ��Ă���Ă������̗D�G�ȉȊw�����ҏW�L�҂��A���݂ł͒����̏����L�҂̊�Ƃ��čL���m����悤�ɂȂ����ғĎq����ƍ����^���q����ł���B�҂���͑��{�Ђ̉Ȋw�������Apaso�ҏW���A�A�����J���NjΖ����o�Ă��܂ł͓����{�ЉȊw���̗v�E�ɂ�����B�����ۂ��̍�������͉Ȋw�����ҏW��������{�ЉȊw���������o�ē����{�ЉȊw���ɖ߂��A���݂͒����V���_���ψ��߂Ă�����B�҂��������������V������ʼnȊw�W�̏����L���𐔑������M�A�����̎�Â���e��V���|�W�E���Ȃǂł����R�[�f�B�l�[�^�Ƃ��Ă�����݂�����A�����m�̂����������낤�B
�@ ��͂蓯�����A���݂̕Ђ̑O�g�AJICC�o�ł���̈˗��ŁuLOGO�Ɗw�K�v�l�v�Ƃ������E���̐搶�������̃R���s���[�^����{�����M�������Ƃ��������̂����A���̂Ƃ������b�ɂȂ������ЃR���s���[�^���Е���ҏW�ӔC�҂̍����M�O����Ȃǂ́A�Ȃ�Ƃ��܂ł͂��悻�R���s���[�^�Ƃ͖����ȁu�c�ɕ�炵�̖{�v�̕ҏW��������Ă�����B�܂���IT�̐��E����A���`IT�̐��E�ւ̉ؗ�Ȃ�i�H�j�]�g�Ƃł������ׂ��ł��낤�B
�@ IT�̐��E�ɋ����������͂��߂��͍̂��d�˂�ɂ�ċN����D��S�̐����������ƌ���ꂻ�������A�܂��m���ɂ��������ɂ͈Ⴂ�Ȃ��̂����A���Ƃ��Ǝ��̐S���ɂ͌Â��Z�p�ւ̂������ƐV�Z�p�ւ̋����S�A���[�I�Ɍ����Ȃ�A�i���O�ƃf�W�^���̐��E�ւ̊S���������Ă����悤�Ɏv���B������A���܂��܂��鎞�����ɂ��Ĉꎞ���傫���f�W�^�����ɕЊ�葱���Ă����E�G�C�g���A�ߔN�ɂȂ��ăA�i���O���ɂ����Ɩ߂��Ă����Ƃ������Ƃł���̂�������Ȃ��B���̌��e�̏��������̂��̂����Ԃ̂��Ƃ��悭�ے����Ă�����B
�@ �p�\�R����[�v�����o�ꂷ��O�͂�����e�͂��ׂĎ菑���ł������B�₪�ď����̃p�\�R����[�v�����o�ꂷ��悤�ɂȂ�ƁA�قǂȂ�������p���ĕ��͂������悤�ɂȂ����B��������ł��A���͂̓��e�ɂ���Ď菑���ƃ��[�v�������Ƃ�Ջ@���ςɎg�������Ă����B�w�p�I�Ș_����Ȋw�G���̌��e�Ȃǂ̂悤�ɕ��̂����L�q���e�Ƀ|�C���g��������̂̓��[�v���ŏ����A�����ۂ��A���e�͂ނ�̂₻�̃��Y�����̂��̂��炵�ďd�v�ȎU���n�̕��͎͂菑���ŏ������Ă����̂ł���B�����āA�p�\�R���p�̃��[�v���\�t�g�����݂̂��̓��l�A�����x�̍����i�K�Ɏ���ɋy��ł͂��߂āA���ׂĂ̌��e�����[�v����������悤�ɂȂ����B
�@ �������A�S���e�����[�v���ŏ����悤�ɂȂ��Ă�����A���̂�Y�����͂��߂Ƃ���ׂ��ȕ\���ɂ������K�v�̂��镶�͂̏ꍇ�ɂ́A���炩���ߎ菑���Ŏd�グ�����e�����[�v�����͂�����A�����łȂ��Ă��A���������c�����ɕϊ����������Ńv�����g�A�E�g���Ėڂ�ʂ��A�啝�ɉ��M��C�����قǂ����Ă���B�c�����Ɖ������Ƃł͓ǂݎ肪���͂������ۂ�Y�������قȂ邤���ɁA�S�p�[�Z���g���[�v���Ŏd�グ�����e���Ƃ��Ȃ�_�o���g���Ă��Ă����ʓI�ɂ͂ǂ������烏�[�v���I�A��������Ȃ�ƂȂ����J�j�J���ȕ��͂ɂȂ��Ă��܂�����ł���B�����ł���Ȃ��Ƃ������̂��Ȃ��A�����ȂƂ���A��A�̎��ٕ̐��Ȃǂ��ق�Ƃ��͖����̂̏c�����ɒ����ēǂ�ł�������ق������Y�����悭�A�����Ǝ��R�ȕ��͂Ɍ�����B
�@ �������̖��Ȃǂ�����̂�������Ȃ����A�������ł������S�V�b�N�̕��̕����̏ꍇ���ƁA��Ȃ��ƂɂȂ�ƂȂ��S�c�S�c���ēr��r��̕��͂ł���悤�Ɋ������Ă��܂��̂��B�������͂ł��A�����̂ŏc�����ɂ����ꍇ�ƈ���āA����Ȃ�̍H�v���Â炵�����R�ȗ���̕\�����A��J���Đ������͂��̃��Y�����ǂ����֏��������Ă��܂��悤�ȋC�����ĂȂ�Ȃ��B�f�W�^���\���S����IT�v������̂��Ȃ��ł��e�Ղɂ͉��v����悤�Ƃ��Ȃ��A�i���O�I�ȌÂ��Ȃ̊��o�������̂��A����Ƃ��̂Ȃ���̐l�Ԃ̃��Y���ɑ������A�i���O���o���ɂ���悤��IT�̐��E�ɃA�i���O�I�ȃf�W�^�����[���h�̎�����]�ނׂ��Ȃ̂��A���Â��l����������Ƃ���ł���B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N1��17��
�l�b�g���[���h���t����
�@ PC-VAN��NIFTY-SERVE�Ƃ������p�\�R���ʐM��Ђ��a�����A�T�[�r�X���J�n�����̂͏\���N�O�̂��Ƃł���B�����̃p�\�R���ʐM����̕��ϔN��͌��݂Ɋr�ׂ�Ƃ͂邩�ɍ����A�O�\�܍���l�\���炢�ł͂Ȃ��������Ǝv���B���̍��͂܂��R���s���[�^������߂č����Ȃ��̂����������ɁA�ʐM���x��1200bps���x�ƒx���A���̂Ԃ��ʐM���Ԃ������Ȃ炴������Ȃ������B������A���q�ɏ���Ē����ԃ`���b�g�ɂ͂܂����肵�Ă���Ɠd�b�セ�̑��̒ʐM��͂��ɂȂ�Ȃ����z�ɂȂ����肵���B��҂������C�y�Ƀp�\�R�����ĒʐM�ɎQ������킯�ɂ������Ȃ���������̂��Ƃ�����A�ʐM����̕��ϔN����������͓̂��R�̂��Ƃ������B
�@ �����̒ʐM���ԓ��ł́u�~�J�J���ɋꂵ��ł܂��I�v�Ȃ�Č��t�����A����ɔ�ь����Ă������̂��B�J�i�����́u�~�v���A���t�@�x�b�g�����́uN�v�ƁA�܂��������J�i�����́u�J�v���A���t�@�x�b�g�����́uT�v�Ɠ����L�[�ɂȂ��ĂȂ��Ă���̂��L�[�{�[�h��Ŋm�F���Ă��炦�킩��悤�ɁA�u�~�J�J���v�Ƃ́uNTT���v�A���Ȃ킿�d�b��̂��Ƃ������B�����x�m�ʂɋ߂Ă�������ʐM���Ԃ̂悤�ɁA�C���������ɂ͈ꃖ���̒ʐM��l�\���~�ɂ��̂ڂ��Ă��܂��Ƃ����ߎS�Ȏ��ԂɌ�������҂Ȃǂ��o�������B
�@ ���A���^�C���ň�x����������Ƃ̂Ȃ��l�X�Ƃ̉�b���y���߂�`���b�g�ɂ͂܂�A���Ӑ����Ԉȏ��������Ȃ����ςȂ��ɂ��Ă������Ƃ����̔ߌ��̎���ł͂������B����ɂ܂��A�����̃p�\�R���ʐM�V�X�e���ɂ͈�莞�Ԓ[���@����̑��M���Ȃ���ΒʐM����������I�ɐؒf����@�\���g�ݍ��܂�Ă��Ȃ���������A�ʐM���ɖ��荞��A�Ȃɂ��̎���ʼn���ؒf��Y�ꂽ�肷��ƁA�m��ʊԂɂ��̊Ԃ̖c��ȒʐM����Z�����Ƃ��������ɋ����Ȃ����Ԃ��N�������B���{�̒ʐM��͂܂������A�C���^�[�l�b�g���y�̂��߂ɂ͂��啝�ȒʐM��̃R�X�g�_�E�����K�v�Ȃ��Ƃ͌����܂ł��Ȃ����A�����̏ɂɊr�ׂ�ŋ߂͂����Ԃ�Ƃ܂��ɂȂ����Ƃ͎v���B
�@ �K���Ȃ��ƂɁA���̏ꍇ�A�d������������Ė��Ԋ�ƂȂǂ���p�\�R�����ݗ^����A�܂������Ԗ����A�N�Z�X���\�ȓ���lID��ʐM��Ђ��玎������Ă���������A�d�b�コ�����ȕ��S����A�e��̒ʐM���s������������A�ɂȎ��ȂǂɃp�\�R���ʐM�𑶕��Ɋy���肷�邱�Ƃ͂ł����B�����Ƃ��A�ŏ����̔�p�Ńp�\�R���ʐM������X���͂����Ă�������㏞�ɁA�D�ނƍD�܂���Ƃɂ�����炸�R���s���[�^�֘A�̎d����������ꂽ��A�ʐM���͂��߂Ƃ���R���s���[�^���삪��݂̌��e���������ꂽ�肷��͂߂ɂ��Ȃ����B�u���قǍ������̂͂Ȃ��v�Ƃ������قǂł͂Ȃ��ɂ��Ă��A���ʓI�ɂ͂���ƌ\���S���̏�Ԃɒǂ����܂ꂽ�킯�ł���B
�@ ����ɂ܂��A�u�ʐM�𑶕��Ɋy����ł����v�Ȃǂƌ����Ε������͂悢���A���ۂɂ́A�y���ނƂ����̂�ʂ�z���Ă��̕s�v�c�Ȗ��͂ɂ�������Ƃ���ꂽ��Ԃɂ���������A���Ԃ̃��X�Ƃ����炱��܂���ςȂ��̂ł������B�悤����ɁA��Ȗ�ȃ`���b�g��������A��A�����o�[���W�܂�t�H�[������`������BBC�i�f���j�ɉ����Ə������肵�Ȃ���C�����܂Ȃ��u�p�\�R���ʐM���ŏǁv�Ɋׂ肩���Ă����̂ł���B�ŋߘb��ɂȂ�͂��߂Ă���u�C���^�[�l�b�g���ŏǁv��ui���[�h���ŏǁv�̑O�i�K�I�Ǐ�Ƃł����������̂������ƍl���Ă���悢�B�����̒ʐM�V�X�e���̏����\�͂̒Ⴓ��g���u���̑�������`���āA���ԓI���X�i���X�������̂��Q�C���������̂��͖{���̂Ƃ���悭�킩��Ȃ��̂����c�c�j���܂������Ȃ��̂ɂȂ炴������Ȃ������B
�@ ������nifty-serve�ł̓`���b�e�B���O�R�[�i�[��CB�icurrent board�j�ƌĂ�Ă����B�����āA��ɂȂ�Ǝw������ɓ����o���A���̊Ԃɂ�CB�R�[�i�[�ɃA�N�Z�X���Ă���a�I�̂��Ƃ��A�ʐM���Ԃ����͓�������uCB���ŏǁv�ƌĂ�ł����B�����āACB���ŏǂ̓�����́u�ۋ��v�����Ȃ��Ƃ����W���[�N�Ȃǂ����킳�ꂽ������Ă������̂������B�u�ۋ��v�Ƃ͓�����nifty-serve�̏]�ʐ����z�ʐM���̂��ƂŁA�܂�ŐŖ����̒�������ېŋ������A�z�����邱�̕\����nifty-serve���炪�p���Ă����B���������̉ۋ��A�p�\�R���ʐM�ɂ�����d�b���Ɠ������炢���������̂ł���B�����́u�C���^�[�l�b�g���ŏǁv�ɂ����̎�̓��������悢�̂����A�l�X�Ȋ������x���ł��v���o�C�_�[���p�������d�b�������i�i�Ɉ����Ȃ������݂ł́A���̌��͂����҂���͖̂����Ȃ悤���B
�@ �����͕�������𑗎�M����̂�����t�ŁA�f�[�^�ʂ̂���߂đ����摜�̂��Ƃ�Ȃǂ͍���������A����ł��A�`���b�g�̃R�[�i�[��BBS�A�����t�H�[�����Ȃǂ͐���������߂Ă����Bstranger�Ƃ����n���h���l�[����PEI00015�Ƃ�����������ID��p���A��A����Ƃ��Ďl�Z������������o���Ă���nifty-serve�̏ꍇ�A���ʐM�l�b�g�̊J�ǂ����A�O�N�o������̓o�^������͂܂��l�قǂŁA��������ɂ������Ă͂��̈ꊄ�̓��l�قǂłɉ߂��Ȃ������悤�����A�������L�̕�����������`���Č��\�ȓ��킢�Ԃ�ł������B
�@ �����̃V�X�e���͂悭�_�E��������A�����łȂ��Ă�������ƃA�N�Z�X���������������Ńf�[�^�������x�����X���[�ɂȂ����肵�Ă����B�`���b�g�̍Œ��Ƀh���Ɨ����Ă��܂�����A�u�n���[�v�Ɠ��͂���ƈ�A���Ă���悤�₭���j�^�[��ʂɁu�n���[�v�Ƃ����\���������ꂽ�肷�邱�ƂȂǂ�������イ�ŁA���̂��ߊԂ̔����������ȃ`���b�g���J��L�����邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ������B���ɂ̓`���b�g�̓r���Ȃɂ��̔��q�ʼn�����ؒf����A�����̃n���h���l�[�����`���b�g�R�[�i�[�ɕ\�����ꂽ�܂c���Ă��܂����ƂȂǂ��������B���́u�H��v�ƌĂ���ԂɊׂ��Ă��܂��ƁA���̃`���b�g���Ԃ��Ăт����Ă��������̂܂܂ł�����肩�A���l���ăA�N�Z�X���悤�Ƃ��Ă��u��d���O�C���ł��v�Ƃ����\�����o�āA�ɂ������������������Ȃ��Ȃ�L�l�������B
�@ �p�\�R���ʐM�̏����̎���͉���̕��ϔN������������ʁA���L���ōD��S�����Ȋe�E�̒����Ȑl���Ȃǂ����\����o���Ă��āA�`���b�g�R�[�i�[��f���A�����t�H�[�����Ȃǂ͑��m�ρX�̊����������B�����͂ǂ̃R�[�i�[���n���h���l�[����ID�������g���������ł̎Q�����\����������A�قƂ�ǂ̎҂��{����E�ƌo���������������J���邱�ƂȂ��p�\�R���ʐM���y����ł������A�l�b�g��Œ����t�������Ă���Ə��X�ɑ��肪�����҂ł͂Ȃ����Ƃ��킩���Ă����肵�ċ�������邱�Ƃ������������B
�@ ����̈ڂ�ƂƂ��Ƀl�b�g���L����ʂɕ��y���ĉ���N��w�̑啝�Ȏ�N�����i�݁A�܂�BBS�Ȃǂւ̓����̏������݂Ȃǂ��K�������ɋy��ŁA�����̖�����A��������͎���Ƀl�b�g�E����p�������Ă������B�����g���A�l�b�g���ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��邩����ʂ�̌����A����Ɋւ��钘����㈲���I�������ƁA����قǂ܂łɂǂ��Ղ�Ƃ����Ă����l�b�g�E�Ɉ�����悷�悤�ɂȂ����B�ŋ߂ł̓l�b�g�ւ̃A�N�Z�X�͎d����ǂ����Ă��K�v�ȂƂ������Ɍ���悤�ɂ��Ă���̂����A���̈Ӗ��ł�IT�v���̐����炩�Ȍ���̐����Ƃ͂܂�ŋt�̂��Ƃ�����Ă���ƌ����Ă悢�B�����̎���A����ŁA���܂��l�b�g�Ŋ������̎҂��܂����Ȃ肢�邠�悤�����A�ނ����������Ȃ�̔N��ɓ��B���Ă���A���Ă̂悤�ȃ��`���N�`���Ԃ������킯�ɂ������Ȃ��Ȃ��Ă��邱�Ƃ��낤�B
�@ ��������Ƀl�b�g�ɏo�v���Ă������́A�`���b�g��[���Ȃǂ�ʂ��đ��肪���͓I�ł������\���M���ɒl����l���ł���Ƃ킩��ƁA�{����E�Ƃ𑊌݂ɓ`�������A���ڂɑΖʂ��Đe�������э������Ƃ������Ȃ��Ȃ������B����I�Ȑ�����ʂ��Ă͐�ɏo�������Ƃ̂Ȃ��l�X�Ƃ̃X�g���[�g�ȑΘb�̏���Ȃ����肾���Ă����ʐM�l�b�g�̈З͂ɁA���������������̒��N�l�b�g�}�j�A�����͂������Ɋ����������̂ł���B�܂������̐l�X�̓R���s���[�^�ʐM�ɖ��S�ł�����₩�ł����������A�����g�͂��̎��シ�łɃl�b�g�̏��������m�M����悤�ɂȂ��Ă����B
�@ ���ܗ��s��i���[�h�g�ѓd�b�ɂ���ĕs���葽���̖��m�̑���Ƃ̌�M���y���ނ��ƂȂǂ́A�����̃p�\�R���ʐM�̉�������ɂ���킯���B��̑O�̂��̕s�v�c�Ȋ������v���A��҂���������ɔM����������R�̂��Ƃ��Ƃ����C�����ĂȂ�Ȃ��B
�@ ���������킯�ɂ������Ȃ����A������nifty-serve��CB�i�`���b�g�R�[�i�[�j��BBS�i�f���j�̏�A�����o�[�̒��ɂ́A�������炻�̐��E�ł͒�����������A���̌�ɒ����ȑ��݂ɂȂ����w�p�E�A�|�p�E�A���w�E�A�@���E�A�����o�ŊE�A���E�A���ƊE�Ȃǂ̃X�y�V�����X�g�����������B���Ƃ���ƂЂƂ��ɂƂ��Ă��A���ɒ��؏܍�Ƃ�H��܍�Ƃ������ҁA�قǂȂ������̏܂���܂����҂Ȃǐ��l�̖��������邱�Ƃ��ł���B�����ď������Ă��炤�Ƃ���ƁA�����͂܂���ƂƂ��ăX�^�[�g�������肾�������A���̌㒼�؏܂���܂��A���݂ł͉���������������ʗ��s��ƂɂȂ��Ă���T��A�T����Ȃǂ�����ȏ�A�̈�l�������B
�@ ����Ȃ�̐��m��������ɐl��{�D��S���V�ѐS�������ȘA�������W�܂��ă`���b�g���J��L�����肵�Ă����킯������A�s��ȃo�g������A�ꔲ���̃W���[�N����A���ӂ�������A���ǂ�����A�l�����k����ŁA����͂���͓��₩�Ȃ��̂������B���݂̏��ǂ��Ȃ��Ă��邩�m�F�͂��Ă��Ȃ����A�����������瓖���̃`���b�g�̂ق����M�C�Ɉ��Ă�����������Ȃ��B�܂��摜�����M�ł���������ʂ����Ō�M���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł͂��������A���̂Ԃ�悯���ɑz���͂����N�����Ƃ�����ʂ��������B��ʂ̕��������߂Ă���Ƒ��肪�␢�̔�������j�q�Ɍ����Ă���u�`���b�g���l�nj�Q�v��u�`���b�g�n���T���nj�Q�v�Ɋׂ�҂Ȃǂ����Ȃ��Ȃ������悤�Ɏv���B
�@ �`���b�g��t�H�[�����ABBS�Ȃǂʼn�舧�����ِ��ɑ����S������悤�ɂȂ�A�Z�����d���̍��Ԃ�D���ĘA���̂悤�Ɍ��t�̂������s�������[������������A�悤�₭�̂��Ƃő���Ƃ̃I�t���C���i�I�����C���������������t�ŁA���ڌ�M����ɉ���Ƃ������A�ꎞ���A�p�\�R���ʐM���Ԃő嗬�s���Ă����j�̖�������B�����āA���鋹��}���Ȃ���A�����̑҂����킹�̏�ɗՂ�ł݂�ƁA����قǂɊ��҂Ɗm�M�����߂Ēz���グ���͂��̗��z�ِ̈����͂ǂ��ւ��c�c�A�����Ɍ��ꂽ�A�����̊ԈႢ�ł͂Ȃ����Ȃ����Ɖ䂪�ڂ��^�������Ȃ�悤�ȑ���Ɍ������āA�Ђ�������ł��̏ꂵ�̂��̃W���[�N�����A�����͉䖝�Ɩ����ɌȂ��䂵�Ȃ���[�����Ȃƌ���̂ЂƂƂ����߂����Ƃ��������Ԃ��������B
�@ ����悭�Έ����Ƃ��ɖ������c�c�ȂǂƂ��������̎v���͂ǂ��ւ��A�}�p���ł�������Ƃ����ꂵ�������������肵�āA���ǂ��납�ꎞ�Ԃ��o���ʂ����ɂ��������ƐȂ𗧂B�����āA���e�����̂ƐM�����Ȃ̋�������p���Ȃ��炮������Ƃ����C���ŋA�r�ɂ��B���܂��ɂ̓l�b�g��Ђ�d�b��Ђɍv�����������肩�`���b�g��[���̂��Ƃ�ɔ�₵�����Ԃ܂ł��Ȃ�Ƃ��ɂ��܂�ĂȂ�Ȃ��Ȃ�B����قǕp�ɂɃ��[���������Ԃ����̂������̂悤�ɁA��������͑���ɊȒP�ȃ��b�Z�[�W�𑗂�C�͂��������������āA�\����Ȃ��Ƃ͎v�����A�`���b�g�Ȃǂł܂��o�����Đe�����b�����肷��̂��Ȃ�Ƃ������ɂȂ����������B����Ȃ�ƕʂ̏o���������߂Ă܂��`���b�g�̏�Ɋ���o�����肷��ƁA�n���h���l�[����ID��ڂ��Ƃ�������������̑���́A�`���b�g�̔�b�@�\���g���ē�l�����Řb���Ȃ����Ƃ�����ɗU���������Ă�����̂�����A�܂��܂��Ή��ɋ����邱�ƂɂȂ����肷��B
�@ ���������I�[�o�[�ȏ������Ɏv���邩������Ȃ����A�C���^�[�l�b�g����ɐ旧�p�\�R���ʐM�̐��E�ł͏��ɏ��Ȃ����̂悤�Ȏ��Ԃ���������イ�N�����Ă����̂ł���B����Ȃ��ƂɁA���̂悤�ȃP�[�X�ɂ������ăI�t���C����͍U�炷������Ƃ���������A�t�ɂ��肷��悤�ȃ��u�E���[���̍U���ɂ������Ƃ����Ȃ��Ȃ������悤�ł���B���̂悤�Ȏ��ɗ�ID�̂ЂƂ��~�����Ȃ�̂͂܂����R�̐���s���ɈႢ�Ȃ������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N1��24��
IT���l�ތ�V�L
�@ ��̑O��nifty-serve�ɁA���D�҂������`�����l���E�Z�u���Ɩ��Â����`���b�g�̖����R�[�i�[���������B�������N�ł��C�y�ɎQ���ł���R�[�i�[�������̂����A�V�ѐS������̌ÎQ�����o�[��̔��Ăɂ���āA���鎞���炻���ł̉�b�͑��ق��p��Ɍ�����Ƃ��������ȃ��[�����݂����邱�ƂɂȂ����B���̌��ʁA�`�����l���Z�u���̃`���b�g�R�[�i�[�ł́A���قƉp��̉������ȉ�b����ь����A����炪���G�ɗ��ݍ����Ƃ������ɂ������Ȏ��Ԃ��J��L������Ƃ���ƂȂ����B
�@ ���ق��ǂ��̕ςȌ�����p�����肷��Ɓu�\���A�A�J�w�����v�Ƃ���ɕW���I�ȑ��فi����Ȃ��̂�����̂��ǂ��������^�킵���̂����j���g���悤�w�����o���ꂽ������Ă������߁A���Ȃǂ͂����ł����Ԃ�Ƒ��ق̃g���[�j���O��ςނ��Ƃ��ł������̂ł���B���ق��͂��߂Ƃ�����n�̌��t�͒Z���Ď��ꂪ�悭�A�\���͂��L��������A�Ɠ��̃e���|�ƃ��Y���̂悳��v�������`���b�g�ɂ͂ƂĂ��K���Ă����悤�Ɏv���B�����ɐh煂Ȃ��Ƃ������Ă��㖡�̈������c��Ȃ��̂����̗��_�̈�ł������B
�@ �p��̂ق����Ȃ��Ȃ��̒B�l�����ŁA�����ŌJ��L������p��b�Ȃǂ͂�����Ƃ������̂ł��������B���ɂ̓h�C�c���t�����X��̎g���肪���荞��ł���������āA�`���b�g�̏ꂪ�p�j�b�N��ԂɂȂ�����������B���̍��̃A�����J�̑��ʐM�l�b�g�ACompu-serve�o�R�ʼn��Đl���`���b�g�ɉ�����Ă��邱�Ƃ������������悤�ɋL�����Ă���B������ɂ���A���قƉp��ƁA�����Ă��܂ɂ̓h�C�c���t�����X�ꂪ���j�^�[�ɓ��藐��ĕ\������A���������\����g�b���W�J����̂�����A�Ȃ��Ȃ��Ɍ����ł͂������B�������肵�ĕW����Ȃǂ��g���������̂Ȃ�A�u�\���A�i�����l���A���e�A�\���i�R�g�o�A���J���w�����I�v�Ɨ₽���������ꂽ���̂ł���B
�@ �������̃R�[�i�[�ɏW�܂郁���o�[�͂Ƃ��Ƀ��j�[�N�Ȑl���������A���[���A�ƃE�B�b�g�ƃA�C���j�C�ɕx�ނ�̉�b�̐ꖡ�͐▭���̂����Ȃ������B���Ԃ��A�����o�[�����ł���A�O�\���͂����Ǝv���B�`���b�g�̏�ł͎����̖{���̎p��K���ɃJ���t���[�W�����A�f�m��ʊ�ŊF���ꂼ��ɂӂ����܂����Ă������A�قƂ�ǂ̎҂͑�w�̌����҂��͂��߂Ƃ��鉽�炩�̐��̈�̃X�y�V�����X�g�ł��������BAJ�̃n���h���l�[���œo�ꂵ�A���ꂩ��قǂȂ��A�T�q�l�b�g�̑n�݂Ɍg����������̒����W���[�i���̃f�X�N�ŁA�̂��ɘ_���ψ����Ȃɂ��ɓ]�����^���Ȃǂ����̈���������B
�@ �Z���Ă������s���ꖡ�̌��t�������`���b�g�̐������Ƃ����_�͍����̂��ς�肪�Ȃ��B������`���b�g�ɂ��炭�͂܂��Ă���ƁA���̐��E�Ɠ��̌��ꊴ�o��\���@���g�ɂ��Ă���B�����Ȃ��Ă���Ƃւ�Ɏ��M�����Ă��āA�C�̍������Ԃ�A����͂Ƃ������͓I�ȑ�����������ɍ����Ō��t�̃o�g�����J��L���邱�ƂɂȂ��Ă����B���̏ꍇ�A�[��o�v���鎞�ԑт����܂��ܓ��������Ƃ������Ƃ������āA�����A�u��l�v�Ƃ����n���h���l�[���œo�ꂵ�Ă������{�r�c�s�ݏZ��舒B�Ȃ��Ƃ��̂����Ȃ��l����A�u���v�Ƃ����n���h���l�[���Ń`���b�g�E�ɐ����������N�����Ă��������ݏZ�̐l����ƁA���ʂĂ�Ƃ�����Ȃ����t�����W�J�������̂ł���B���Ƃł킩�������ƂȂ̂����A��l����̓h�C�c�̗��w�o���������ƍߊw�̐��ƂŁA���̖^��w�̋����������B�܂��A�����ۂ��̒�����̂ق��͑��̗L���ȑ�a�@�Ζ��̖�w�҂ŁA��w�t�H�[�����̐ӔC�҂ł��������B
�@ �l�b�g�}�j�A�����͓������當����L����g�ݍ��킹�Ă������L�����O���ichracter-graphics�A���̊G�����j��ʐM���ɓK���Ɍ����Ďg���Ă����B�ʏ�̃`���b�g�ŖO������Ȃ��Ȃ�ƁA��X���܂������̃L�����O���┻�������Ȃǂ�n�o���A���ꂾ����p���Ăǂ̂��炢�̉�b���ł��邩������������������̂��B���܁A��҂�����i���[�h�̌g�ѓd�b�Ȃǂ�p���A�l�X�ȊG�����┻�������ɂ�郆�j�[�N�ȃR�~���j�P�[�V�����ɔM�����͂��߂Ă��邪�A�悢��������X�������̃`���b�g��ʂ��Ă��̐��I���s�݂����Ȃ��Ƃ�����Ă����킯�ł���B�ʏ�̃`���b�g�̂Ƃ��Ȃǂ��A���͎���stranger�}�[�N�istranger�̓A���x�[���E�J�~���́u�ٖM�l�v�ɂЂ����������̃n���h���l�[���j�Ɩ��Â����A (@L@)�Ƃ������S�}�[�N��p���Ă����B
�@ �����̒ʐM�\�͈͓͂̔��ł̂��Ƃ�����A�L�����O���Ƃ����Ă��A(^L^)�A(*|�P)�i>-<�j�A(*-*)�A(^H^)�A�ȂǂƂ������悤�ȏ����I�Ȃ��̂��\�قǂ����Ă��ꂼ��ɈӖ����������A��������ׂČ�M���y����ł������x���������A����ł��m�I�V�тƂ��Ă͌��\�h���I�Ŗʔ��������B���������ɂ������ẮA
�@�@�@�@�@�u�ѓʖс��щ��с��Z���~�H�v�@�@�@�@
�Ƃ������悤�ȁu�i���J�C�i�H�v�Ǝ���X�������Ȃ�悤�ȓ���ȁi�H�j�V�����m�܂ł��o��A�����̂Ȃ��̂������̂��̂́A�����Ƃ����܂ɒʐM���Ԃ̃`���b�g�p��Ƃ��čL�܂��Ă������B����ꂽ�ʐM��Ԃ̂Ȃ��̂��ƂƂ͂����A�V��̒a���ɂ������A����������炪�}���ɗ��s���Ă����l�q�������ɋ��Ȃ��璭�߂邱�Ƃ��ł���킯������A����Ӗ��ł���قǂɖʔ������Ƃ͂Ȃ������Ƃ�������B����Ȃ킯������A���܂̎�҂�����i���[�h�ʐM�ɖ����ɂȂ�C�����͏\���ɗ����ł���B
�@ ���ɏq�ׂ��悤�ɁA�����̃p�\�R���ʐM�i���݂̃C���^�[�l�b�g�̏ꍇ����{�I�ɕς��͂Ȃ����j�ł́A�`���b�g��t�H�[�����A�f���Ȃǂ̃R�[�i�[�ɂ��Ă͓����Q���������ƂȂ��Ă�������A�l�X�ȃW�������̐l�X�������₻�̎��������J���Ȃ��܂܃A�N�Z�X���A���m�̐l�X�Əo�����A�����Č𗬂�[�߂邱�Ƃ��\�ł������B���̂��߁A���ʂȂ�܂��m�荇���@����Ȃ��悤�Ȑl�X�Ɖ�舧���A������_�@�ɒ��ډ���ĈȌ�e�������ԂƂ������Ƃ����Ȃ��Ȃ������B���͐l�Ȃ�Ƃ������A���Ƃ����������̂��Ƃ�ł͂����Ă��A���肪�Ƃ��ɕʐl�i�������ł����Ă��Ȃ�������́A���ʂ��̐l���͂���Ȃ�Ɍ����Ă���B���Ȃ��Ƃ����̏ꍇ�A�������\�z��������̐l���Ǝ��ۂɉ���Ċ����邻�̐l�ƂȂ�Ƃɑ傫�ȃM���b�v�����邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ������B
�@ �p�\�R���ʐM����ďo�����A���ۂ�[�߂Ă߂ł�����������������������ɑ����̐��ɂ̂ڂ����B���ۂɎ����m�邩����ł����̍��ɏ\�g�ȏ�̃J�b�v�����a�����Ă���B�l�b�g�ł̏o�����𑊌݂̐�匤����r�W�l�X�Ɋ������A�ًƎ�𗬂ȂǂƏ̂��āA�V���Ȏd���̓W�J�ւƂȂ���҂������Ԃ�Ƃ������B�����g���l�b�g�ŏo�������Ⴂ�l�X�̂��߂Ɏd����̕X���͂�������A�Ȃɂ��ƃA�h�o�C�X�����Ă������肵�����Ƃ����Ȃ��Ȃ��B
�@ �����A�l�b�g��ʂ��Ă̏o�����Ƃ������̂����ׂĂ悢���ʂɂȂ���Ƃ͂�����Ȃ��B
�@ �����\���ɂ���M�����ɁA���ӂ͂Ȃ������ɂ�������炸������Ƃ������t�̍s���Ⴂ�����Ƃő傫�Ȍ����������A����������悤�Ƃ���Ӑ}�Ȃǂ������ĂȂ������ɂ�������炸�A���ʓI�ɂ͏��Ȃ���ʐS���I�_���[�W��^���Ă��܂��Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��N�������B�y���W���[�N�╗�h�̂��肪�A����l�ɂ͒f���ċ�������̂̂悤�ɂ���A�{����Ă��܂��悤�Ȃ��Ƃ������ŁA���������ɂ��ʐM�̓������������ʐM�}�j�A�̊Ԃł͑傫�Ȗ��ɂȂ��Ă��������̂��B������莝�Ƃ��Ƒ����ɒ[�Ȕ����⏑�����݂������肷��ƁA���܂��܂��̕���������ڂɂ��A����ɋ����s�������o��������́A�����Ɍ���Ă���l�ƂȂ肪���M�҂̐l�i�̂��ׂĂ��Ǝ���Ă��܂��悤�Ȃ��Ƃ��A�p�\�R���ʐM�̏����̍�����펞�N�����Ă������炾�B
�@ ������t�I�݂ɑ�����x������ʐl�i�����肷�邱�Ƃ͂ł���킯������A�������\���͂��߂Ƃ���e��̂Ђǂ����\�������排����̓D�d���Ȃǂ��������N�������肵���B���R�A����ɑς��Ȃ��G���A�O�������⒆���L���Ȃǂ��o�ꂵ�i�Ƃ͌����Ȃ���������܂߂ĊF�����\������ǂ�ł����悤������A����ɑς���V�����m�������̂�������Ȃ��j�A�������ǂ����邩�Ƃ����c�_�Ȃǂ����̍����Ɋ����N�����Ă����B����t�H�[�����ɉ��荞��l�̏��������ԂƔ�掂̂������s�����A���̔����ɓ{�������̃t�H�[�����̃V�X�I�y�₻�̎�芪���A�������̏����̐g����o���ׂċt�ɋ����܂����̔������������ʁA����ǂ͏����������_�ʑ��ő�������i����Ƃ����o�����Ȃǂ��N�������B���Ԃ�A�l�b�g�ł̔�排�������ɂ����䂪�����̍ٔ������������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B
�@ nifty-serve�Ȃǂł́A�z�X�g�T�C�h�𒆐S�ɓ����ɂ�锭�����K�����A�����\���̏������݂ɂ���l�b�g�̎������܂�Ƃ����ӌ������܂�Anifty��BBS�i�f���j�Ȃǂł͓��������͂ł��Ȃ��Ȃ������A�����ɂ̓G���A�O���̏������݁A�����ȕ��i�̔���@�����U�A�������Ȓj�����ۊ��U�̗ނ̋L���͏��������炸�A����߂Ď��̍���������������A�e��̐��I�ȑ��k�Ȃǂɐe�g�ɂȂ��ĉ����Ă����Ă�����A�X�y�V�����X�g�̑�������ĂɃ{�[�h����p���������B
�@ �d�����E��̗���������āA���Ƃ��^�ʖڂȈӌ���A�h�o�C�X���q�ׂ�ɂ��Ă������ł݂͜���l���������߂Ă�������ł���B���ړI�ȉ����̏�Ŏ����𖾂����A�X�g�[�J�[�܂����̍s�ׂɌ�����ꍢ��ʂĂĂ��܂����˂Ȃ��l������������i���܂��������킩��A���ꂪ���ƂŎ��ۂɔ�Q�ɑ����l�Ȃǂ��ł��j�A����͂�ނ����Ȃ����Ƃł��������B�g���͓K�łȂ���������Ȃ����A�u���݂͗lj݂��쒀����v�̃O���V�����̖@���܂����̏����łɋN�����Ă����킯���B
�@ �����Ƃ��A�n���h���l�[���Ȃǂ̓����ɂ��l�b�g��ł̌𗬂́A���X���ɏ��Ȃ����Ԃ��Ђ�����������������悤���B�`���b�g��t�H�[�����ABBS�ȂǂŒm�荇���A�d���̂��Ƃ�ƒ�̂��ƁA�����ِ̈��Ƃ̌��ۂ̂��ƂȂǖ{���ł��ꂱ��ƌ�荇�������ƁA�������[��������������i�u���b�N���[������h�����߁A�������烁�[���̏ꍇ�ɂ͍��o�l���������\�������悤�ɂȂ��Ă����j�A�I�t���C���Ŏ��ۂɉ���Ă݂��肷��ƁA���肪��Ђ̏�i��������A���ے��̗��l��������A�v��Ȃ�������A�����ׂ̏Z�l��������Ƃ����z���O�̔ߊ쌀���������肵���̂ł���B���E�����Ȃ��Ȃ��Č��ǂ͗���������Ȃ��Ȃ����v�w�̃P�[�X���ꌏ�������������m���Ă���B
�@ �j�A�~�X�Ƃ����Ȃ��A����Ƃ��`���b�g������Ă��āA����̐��̈�₻��Ɋւ���ׁX�Ƃ������ƂȂǂ�b��ɂ��Ă��邤���ɁA�����Ȃ胂�j�^�[��Ɏ����̖��O���\�����ꂽ���Ƃ�����B���̂��߁A�ǂ���瑊�肪���Ă̋����q�炵���Ɣ��������̂����A�����Ԃ�Ƃӂ�������b���������Ƃ����������ɖ����ɖ���ꂸ�A�f�m��ʊ�Ŏ����̂��Ƃ������ł��Ȃ����肵�Ȃ��炻�̏�����̂������������z���o�Ȃǂ�����B
�@ �C���^�[�l�b�g�Ԑ���̌��݁A�e��̏����ʂɒ~�ς������X�̃T�[�o�[��f�[�^�x�[�X�ƌl�̒[���Ƃ����сA���`�B��������̌������ƎЉ�̋@�\����}��̂�IT�v���̖{���ł���悤�ɋ�������Ă��邯��ǂ��A�^�̃l�b�g���[�N�̔��W�ɂƂ��Ă���͂��Ȃ炸�����D�܂������Ƃł͂Ȃ��悤�Ɏv���B
�@ �N�������ܖY��ĂȂ�Ȃ��̂́A�l�b�g��g�ѓd�b�Ȃǂ��͂��߂Ƃ�����Z�p�̊�{�͂����܂ł��u�l�ԂƐl�Ԃ��Ȃ����Ɓv�ɂ���A�ǂ������@���Ń��J�j�J���ȏ��̊C�Ɛl�ԂƂ��Ȃ��̂����̖{���ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��낤�B������ƃC���^�[�l�b�g��̌������҂Ȃ炷���ɂ킩�邱�Ƃł��邪�A�ǂ�Ȃɂ悢����ڂ���Ă���Ƃ͂����Ă��A���j�^�[��ʂ�ʐM�@��̌��������ɐ��g�̐l�Ԃ̑����̊������Ȃ��l�b�g�Ȃǂɂ́A���������ĂȂ�̖��͂����݂��Ȃ��B�ǂ�Ȃɏ��Љ���x�����悤�Ƃ��A�l�Ԃ͏�ɐl�Ԃ����߂���̂Ȃ̂��B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N1��31��
�l�b�g���[���h�͎Љ�̏k�}
�@ �C���^�[�l�b�g�̐��E�́A�܂�Ƃ����X�̏Z�ގЉ�̏k�}�ɂق��Ȃ�Ȃ��B�����瑽���������͈���Ă��l�ԎЉ�ŋN���邱�Ƃ͂��ׂċN���肤��ƍl���Ă������ق����悢�B�e��ƍ߂��排����͂ނ��A�����I�A�d��o�ϓI�d���A�I���Ȑ��_����Ȃǂ��������Ă��̗�O�ł͂Ȃ��B���݁A���܂��܂ȃC���^�[�l�b�g�ƍ߂��Љ���ɂȂ���邪�A���͓���̔ƍ߂͊��ɉߋ��̃p�\�R���ʐM�̎���Ɉ�ʂ�N�����Ă����B���Ȃ炸���������͍����̐V�����Љ�ۂł͂Ȃ��̂ł���B���ۂ̎Љ�̏�ł���R���s���[�^�E�l�b�g���[�N�Ō��ꂽ���f�B�A��Ԃł���A��萔�̐l�Ԃ��W�܂���̂Ȃ��ŗl�X�ȗ~�]��v�f���Q�������Ƃɂ͕ς�肪�Ȃ��B�����Ă����̗~�]�̉Q���A�����Ȕ�排�����s���ȏ��A����ɂ͑召�̊e��ƍ߂������N�����B
�@ �������A������Ƃ����ăC���^�[�l�b�g�V�X�e�����̂��̂��ނ�݂₽��ɔᔻ���A���̐ӔC��₢�l�߂Ă݂��Ƃ���ʼn���������Ƃ���͂Ȃ����낤�B�X�̔��M�҂���M�҂��A�C���^�[�l�b�g��Ԃ̍\���͏��X�̃��X�N���܂߂Č����Љ�̂���ƂȂ��ς�肪�Ȃ����Ƃ����o���A���ȐӔC�͈̔͂��\���ɂ킫�܂��������Ńl�b�g�̂����炷���_�����������Ă����ق��Ȃ��B���݂ł͒N�����d�b�Ŕƍ߂̑��k�������Ƃ��Ă��A���̂��߂ɓd�b��Ђ̎Љ�I�ӔC��₤�̂����������؈Ⴂ�ł���̂Ɠ��l�ɁA�C���^�[�l�b�g��ŕs�ˎ����������Ƃ��Ă����̒��ړI�ȐӔC�̂��ׂĂ��C���^�[�l�b�g�V�X�e���ɓ]�ł���̂͊ԈႢ���낤�B
�@ �ӂ�ɏ����e�Ղɂ��������ł���Ƃ��A�Ȃɂ����ɂ��֗����Ƃ���������ʂ����ɖڂ�������̂ł͂Ȃ��A�����댯�łǂ�ȏ�M�p�ł��Ȃ����f���A���X�N������Ɗ������炻��Ɏ���o���Ȃ��悤�ɂ���T�d����g�ɂ��邱�Ƃ���X�ɂ͋��߂���B�X�p�ɂ�����������Ȋ��U��Â��U���̌��t�A���܂�����b�Ȃǂɑ��Ēʏ��X�������悤�Ȍx���S�́A�C���^�[�l�b�g�̐��E�ɂ����Ă����R�K�v�Ȃ��ƂȂ̂��B�v����ɁA�C���^�[�l�b�g�Ƃ����V���f�B�A�Љ�ɐg��������X�́A���l�ȉ��l�ς������ɑ��݂��Ă���Ƃ���������F�����A�܂��l�X�Ȋ댯����ɐ��ݑ��Â��Ă��邱�Ƃ����o���������ŁA���̐V����Ɍ��������s���̂Ƃ肩�����w��ł��������Ȃ��̂ł���B���X�N���ΓI�ɉ���ł���V�X�e��������Ƃ��������オ�邩������Ȃ����A�_���I�ɍl���Ă��\���I�ɍl���Ă�����͕s�\�Ȃ��Ƃł���B
�@ �����ŃR���s���[�^�ƍ߂̏ڍׂȎ����_����킯�ɂ������Ȃ����A�R���s���[�^�l�b�g���[�N�̍\�z��\�t�g�E�G�A�̃R�[�f�B���O�Ɉ�背�x���܂Ōg��������Ƃ̂���l�ԂȂ�A�����̃V�X�e����\���������Ɍ����炯�̂��̂ł��邩�\���ɏ��m���Ă���͂��ł���B���������̍\�����ׂ̓R���s���[�^�V�X�e���̐v�v�z�̍����Ɉ�����h���I���s��I�Ȃ��̂ł���ƌ����Ă悢�B�l�ԒN���������܂ꂽ���_�ł��łɁA�����ł͂ǂ��ɂ��o���Ȃ��Ȃɂ�����̕��̈�`�q����L���Ă���悤�Ȃ��̂ł���B
�@ ���������A�R���s���[�^�l�b�g���[�N�����p���A�ǂ��ɂ��Ă��d�v�ȋ@���������Ǘ������菈��������ł���悤�ɂ���Ƃ������z���̂��̂��傫�Ȗ����ɖ����Ă���B�@���Ƃ́A����ꂽ�҂�����ꂽ�ꏊ�Ō���ꂽ��i�Œm�邱�Ƃ��ł��邩�炱���@���ł���B�ǂ��ɂ��Ă��������Ǘ��Ȃ����͏����ł���Ƃ������Ƃ́A�u����ꂽ�ꏊ�Ō���ꂽ��i�Łv�Ƃ�������������Ă��܂��Ă��邱�Ƃ��Ӗ����Ă���B
�@ �܂��A�����獂�x�ȈÍ��̌n�ɂ��K�[�h��~���A�p�X���[�h�̊Ǘ��������͂������Ƃ��Ă��A����Ȃ��͕̂\�����̃K�[�h�A��������Ή��~�̐��ʂ̖傾�����ł߂Ɍł߂������ɂ����Ȃ��킯�ŁA���~�̗���⑤�ʂ͌��Ԃ��炯�Ȃ킯������A������ɐ��ʂ����d���t�̎�ɂ���������ЂƂ��܂���Ȃ����낤�B�R���s���[�^�Ƃ����֗��ȋ@�B��p����㏞�Ƃ��āA�u����ꂽ�҂��v�Ƃ����ŗD��̌������������ꋎ���Ă��܂��Ă���킯���B
�@ �V�X�e���ɐN������n�b�J�[�̓o���҂܂ł��Ȃ��A�R���s���[�^�ɋL�^���ꂽ�@����R�k����\���͂������ɂ���B�d�v�ȏ��������߂��R���s���[�^�́A��d���̑��A�Ȃ�炩�̗��R�Ń_�E�������Ƃ��ɔ����o�b�N�A�b�v���Ƃ��Ă���B�o�b�N�A�b�v���Ƃ��Ă���Ƃ������Ƃ́A�V�X�e���Ǘ��҂ɋ߂��̎҂����̋C�ɂȂ�Εێ�̐܂Ȃǂɂ�����ł��L�^���ꂽ���̒��g��`�����邱�Ƃ��ł��邵�A���̏����R�s�[���ĉ������ł��邱�Ƃ����Ӗ����Ă���B���������̏������������ĉ\�ł���B
�@ �����ʂ�̈Ӗ��Ő�ɊJ���Ȃ�����A�J����̂ɉ��N����������������ċ��ɂ���邱�Ƃ͂ł��邾�낤������Ȃ��͖̂��ɗ����Ȃ��B��펞�ɂ͌��Ȃ��ł��J���邱�Ƃ̂ł���Ȃ�炩�̎肾�Ă��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����A�����łȂ��Ă��A���ɂ̏��L�҂͕K�v�ɉ����Z���ԂŔ����J�����i�������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������Ȃ�炩�̗��R�������āA���K�̕��@�ł͊J���̉��N����������ɂ��������Ƃ���A���̏��L�҂₻�̏��̐���҂́A���Ȃ炸������ƒZ���Ԃł���J���邱�Ƃ��ł��闠�̎�i��݂���ɈႢ�Ȃ��B���ꂪ�l�ԂƂ������̂̂���ނɂ�܂�ʐS�������炾�B
�@ �@�����������߂��R���s���[�^�V�X�e�������ꍇ���܂����������ŁA������ł����G�ȃp�X���[�h��Í������̌n�����邱�Ƃ͂ł��邪�A�Ǘ��җp�̃p�X���[�h������������A�Í������@�\�����܂��@�\���Ȃ��Ȃ�����A���ʂȋً}���Ԃ��������肵���Ƃ��Ȃǂɔ����āA�\�����Ƃ͈قȂ�@�����ւ̗��̃A�N�Z�X���[�g���݂����邱�Ƃ��낤�B���K�̃p�X���[�h��Í��L�[���Ǘ�����̂��e�ՂłȂ����A�����[�g���ɔ�̂܂܂ɂ��Ă����̂����\����b�ł���B�u���l�̎��̓��o�̎��v�̋��b�ł͂Ȃ����A�l�ԂɂƂ��Ĕ閧�����ʂ����ƂقǍ���Ȃ��̂͂Ȃ����炾�B
�@ �@���������Ǘ�����R���s���[�^�V�X�e���ɂƂ��Ė��Ȃ̂́A��������Ǘ��җp�p�X���[�h��Í���ǃL�[���O���ɘR���ƁA�����Ƃ����܂ɂ��̏�����͂��납�A���E���ɂ܂ōL�܂��Ă������˂Ȃ����Ƃł���B��������Ȏ��ԂɂȂ��Ă��܂����瑽���̃n�b�J�[��������ĂɃV�X�e�����ɐN�����Ă��邱�Ƃ͔������Ȃ��B�N�����ꂽ�V�X�e�����̓p�X���[�h��Í���ǃL�[�̕ύX�𔗂��邱�ƂɂȂ邪�A���̂��߂ɂ͂���Ȃ�̎��ԂƔ�p�Ǝ�Ԃ������邵�A�W�҂ɐV���ȃp�X���[�h��L�[��`���邾���ł��e�Ղł͂Ȃ��B���̉ߒ��ōēx���Y��R��Ă��܂������ꂷ�炠��B
�@ ������ɂ���A���ꂩ���IT�Љ�ɂ����ẮA�u�l�b�g���[�N�ɂ̂������Ƃ������̂́A�ǂ�ȂɌ��łɃK�[�h����Ă����Ƃ��Ă��v���̎�ɂ���������܂��O���ɘR��Ă��܂����̂��v�Ƃ������Ƃ�O��ɍs������悤�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�č��h���Ȃ⍑�ƈ��S�ۈ��ǂȂǂɂ͕��O�ꂽ�R���s���[�^�̓V�˂����������풓���Ă��āA�e���IT�d���������W������J�L���Ă���Ƃ����Ă���B���Ƃ��ƃK�[�h�̊Â����{�̏��X�̋@�����Ȃǂ́A����������̂��̂��킸���̑������Ƃ����ɕč����̑��̏��W���ǂ̎�ɂ���Ă����ϔ�����Ă��܂��Ă���\���������B
�@ ����ȃv���O�����R�[�h����Ȃ�R���s���[�^�E�C���X���R���s���[�^�V�X�e����j���荬���������肷�邱�Ƃ͂悭�m���Ă���Ƃ��낾���A���Ƃ��Ƃ����̃E�B���X�͍Ő�[�̃R���s���[�^�Z�p�������A�v���O�����R�[�h��V�X�e���̌��ׂƌ��E�Ȃǂ�m��s�������ꕔ�̃v�������̎�ɂ���Đ��ݏo����Ă������̂ł���B����Ӗ��ł̓}�b�`�|���v�̐��E���Ƃ������Ȃ����Ƃ̂Ȃ��R���s���[�^�E�C���X�ƍ߂͂��ꂩ����������Ă��Ƃ�f���Ȃ����낤�B
�@ �ׂ��ӂ⑼�ӂ͂Ȃ��Ă��A���x�ȃv���O�����̃R�[�f�B���O�Z�p�����҂Ȃ�N�ł��A�����̏������v���O�����̂ǂ����ɍ쐬�҂̎��������ɂ����킩��Ȃ����ʂȎd�|���ߍ��݂����Ȃ����肷����̂Ȃ̂��B�E�C���X��W�b�N���e�Ȃǂ͂��̉�������ɂ���Ƃ����Ă悢�B���Ȃ݂ɏq�ׂĂ����ƁA���W�b�N���e�Ƃ́A����Ȏw�߂������Ƃ��̃\�t�g�E�G�A�ɊJ���Ҏ��g�����炩���ߑg�ݍ��j��v���O�������N�����A���Y�\�t�g�E�G�A��֘A���̃t�@�C��������������N���s�\�ɂ��Ă��܂����肷����ʂȎd�|���̂��ƂŁA���Ƃ��Ƃ�IMB�ЂȂǂ����ЊJ���̃\�t�g�E�G�A�̃R�s�[���i���o���̂�h�����߂ɍl���o�����Z�p�������B
�@ �\�t�g�E�G�A�̃v���O�����R�[�h�͕��G�ɑg�ݍ��킳�ꂽ�c��ȗʂ̋L����ł��Ă���A���Ƃ����̓��̐��Ƃł������Ƃ��Ă����l�̏������v���O�����R�[�h����͂��A���ꂼ��̋L����̈Ӗ����閽�߂𐳂�����ǂ��邱�Ƃ͂���߂č���ł���ɈႢ�Ȃ��B�܂��Ă�A�r�����Ȃ��s���̐��K�v���O�����R�[�h�̂��������ɕ��U�����Ė��ߍ��܂ꂽ����v���O�����������̉B���ꂽ�@�\��T�m���邱�Ƃ́A���̃R�[�h�̍쐬�҈ȊO�̎҂ɂƂ��Ă͎���̋ƂȂ̂��B
�@ ��荂�x�ȃv���O���~���O����ƃR�[�f�B���O�Z�p��p����A���炩���ߐݒ肵���閧�̕�������͂���ƁA���K�̃v���O�����R�[�h���\������L����̋L���̈ꕔ�������������玩���I�Ɏ��o���đg�ݍ��킹�A�\�ʓI�ɂ͌����Ȃ��������ł��̃v���O�����R�[�h�ɂ͂Ȃ���������ȃv���O�������V�X�e�������ɂ��肾�����Ƃ��ł���B�ނ�̓���v���O�����ɁA�X�p�C�����H������ǂ��̋@�\���������邱�ƂȂǂ��̓��̃v���ɂƂ��Ă͗e�ՂȂ��ƂȂ̂��B�E�B���X�̏ꍇ�ɂ͊��������v���O�����̃T�C�Y�𐳋K�̃v���O�����T�C�Y�Ɣ�r������A���K�̃v���O�����R�[�h�ɂȂ�����R�[�h�����o�����肷�邱�Ƃɂ�蔭���ƏC�����\�ł��邪�A������̂ق��́A���Ƃ��Ɛ��K�\�t�g�E�G�A�̒��ɓ��݂��Ă���d�|�������畔�O�҂ɂ͎�̂قǂ����悤���Ȃ��B
�@ ���E���œ���I�Ɏg���Ă���\�t�g�E�G�A��e��IC�`�b�v�̃v���O�����R�[�h�̒��ɂ����������d�|�����g�ݍ��܂�Ă��Ȃ��Ƃ͂�����Ȃ��B����A�����g�̂��Ă̂����₩�ȃv���O�����̃R�[�f�B���O�o���Ȃǂ��猾���A�v���O���}�[�̂�����Ƃ����V�ѐS�Ƃ��������̂��܂߂�Ȃ�A���̗L���ȃ\�t�g�E�G�A�̃v���O�����R�[�h�̒��ɂ͂Ȃ�炩�̂������ł���Ȏd�|�����E�э��܂��Ă���ƍl�����ق������R�ł���ƌ����邩������Ȃ��B�l�Ԑ����̋Ƃɂ���������ȍs�ׂ����炩���ߖh�����@�́A�c�O�Ȃ��瑶�݂��Ȃ��ƌ����Ă悢���낤�B�D�ꂽ�Z�p�̊J���ɂ́A���Ȃ炸�ƌ����Ă悢�قǐs���邱�ƂȂ��V�ѐS���Ƃ��Ȃ��B�����łȂ��Ă��A�n���Ɣj��Ƃ͂��̐��E�ɂ����Ă��Ƃ��ƕ\����̂̂��̂����炾�B
�@ �ȑO�ɁA�I�E���W�̉�Ђ̃R���s���[�^�Z�p�҂����銯�����̃\�t�g�E�G�A�̊J���Ɍg����Ă����Ƃ������Ƃ��������A�ꎞ���}�X�R�~�Ȃǂł�����Ƃ��������ɂȂ������Ƃ�����B���I�ȂƂ���֔[�߂�\�t�g�ɏd�v���𓐂ݎ�邽�߂̓���R�[�h�Ȃǂ��g�ݍ��܂�Ă������ς��Ƃ������ƂŁA�V����e���r�Ȃǂ����̖���傫�����グ���킯�����A���l�͂��������؈Ⴂ�Ȏv�������ĂȂ�Ȃ������B��萅���ȏ�R���s���[�^�V�X�e����m��A�\�t�g�̃R�[�f�B���O���ł���Z�p�҂Ȃ�F�������������Ƃ��낤�B
�@ ���ĎЉ�I�ȑ厖�����N�������I�E���䂦�A���̊W�҂����I�\�t�g�̊J���Ɍg��邱�Ƃ���ԂދC�����͂킩��̂����A����������̂Ȃ�A���܂⍑���̂��ׂẴR���s���[�^�ɓ��ڂ���Ă��閳����IC��OS�A��v�\�t�g�E�G�A�ȂǂɎd�g�܂�Ă��邩������Ȃ�����R�[�h����^���Ă����邵���Ȃ��Ȃ��Ă���B�č��̗L�͊�Ƃ����̃\�[�X�R�[�h�������Ă���A�������A���Ƃ����̃\�[�X�R�[�h�����ł����Ƃ��Ă����̓r�����Ȃ��ʂ̃R�[�h��͂͐�]�I�ɍ���ł��邱�Ƃ��v���ƁA���͂₱�̎�̖��͂���グ�ƌ��������Ȃ��B����ɁA�Ŋ뜜���ꂽ�ʂ�I�E���̋Z�p�҂ɂ���Ċ����������̃\�t�g�ɋɔ�R�[�h���g�ݍ��܂ꂽ�Ƃ��Ă��A���Ԃ���`�F�b�N����̂���������̋Ƃ��낤�B���������N���Z���Ԃł������肨������Ƃ����̂��낤���B
�@ ���ǁA���̃R���s���[�^�l�b�g���[�N����ɐ������X�́A���ׂĂ̏��͘R���Ƃ������Ƃ�O��ɂ��čs�����邩�A�����Ȃ��l�b�g���[�N��ʂ��Ă̋@���̘R�k���̂��̂��Ӗ��������Ȃ��Ȃ�悤�Ȗ����Љ�����肠���Ă��������Ȃ����ƂɂȂ�B�ǂ����Ă��@�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����̂Ȃ�A���d�����ɏ��ނ����A��������d�ɕ��ĕۑ�����Ƃ����̂Ȃ���̕��@����邵���Ȃ����낤�B�������A�������邱�Ƃɂ���Ċe��̎Љ�I�@�\�͔���������邾�낤���A����͂�ނ����Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N2��7��
IT����Ƌ���
�@ IT�v���̎���Ƃ͂����Ă��A���̔��W�ɕK�v�Ȑl�Ԃ̎����ɂ��Ă͂���܂łƏ������ς��͂Ȃ��B�����玞�オ�i��ł��A�厩�R�̉��[���Ɋ������A�l�ԂƂ������݂̕s�v�c���ɐS���Ƃ��߂������Ƃ��Ȃ��Ȃ��Ă��܂�����Information Technology �ȂǗL�������̂��̂ɂȂ��Ă��܂����Ƃ��낤�B�����A�u�l�ԁv�Ƃ����T�O���̂��̂����A���܂̐l�ނƂَ͈��̐����̂ւƕϗe���Ă������オ������ނ��b�͈���Ă��悤���A�܂������͐l�Ԃ����Ă�IT���Ƃ������Ƃɋ^����������ޗ]�n�͂Ȃ��B
�@ IT����̍őO���ɗ������҂�Z�p�ҁA�o�c�҂Ȃǂ��݂Ă݂�ƁA�ӊO�Ȃ��ƂɁA�c�����⏭�N���A�厩�R�ɂ͌b�܂�Ă������̂́A�����̐�[�Z�p��ŐV���Ȃǂɂ͂܂�Ŗ����ȎR���◣���ȂǁA��������I��ԁi�H�j�Ɉ�����l�����Ȃ��Ȃ��B����Ȕނ�ɋ��ʂ��Č����邱�Ƃ́A��ʓI�ȓs��炿�̎҂Ɋr�ׁA���ȏ��I�Ȓm���ł͂͂邩�ɒx����Ƃ��Ă�������ǂ��A���������R���ۂɑ���ώ@�����̃h���}�Ɋ�������S�ɂ����Ă͂͂邩�ɏ����Ă����Ƃ������Ƃ��낤�B�ނ�͑n���͂̌���ƂȂ錴���i�⌴���v�l�̕��@�_�����Ԃ������Ȃ��炵������Ɗl���`�����Ă����Ƃ�������B�����āA�����̌����i����@�_��IT���E�ł̗D�ꂽ�ƐтɂȂ����Ă�����̂��낤�B
�@ �����w�I�F���_�̌����ȂǂŒm���鍂���ȔF�m�S���w�҃s�A�W�F�̌��t���ؗp����Ȃ�A��ʘ_�Ƃ��āA�c�Ɉ炿�̐l�͋�̓I����̒i�K�i���ۂ̑Ώە�����������Ƃ�������܂킵�Ȃ���v�l��|���[�߂Ă����i�K�j����`���I����̒i�K�i������e��L���ȂǁA���ۓI�ȋL���݂̂𑀍삵�Ďv�l��ςݏd�˂Ă����i�K�j�ւ̈ڍs�����₩�ŁA�t�ɓs��炿�̐l�͋�̓I����̒i�K����`���I����̒i�K�ւ̈ڍs���͂₢�Ƃ������ƂɂȂ낤�B�������A�����̉䂪���ł́A�ɓx�̏��q���Ɛe�����̋���M�̍��܂肹���ŁA�����̒ÁX�Y�X�܂ł��`���I����̒i�K�ւ̈ڍs���}���s��I�ȋ��畗���̒��Ɋ������܂�Ă��܂��Ă���悤�Ɏv����B
�@ �����̏�����������̃J���L�����������i�H�j�ŗ����n�̊w�K�������啝�ɃJ�b�g���ꂽ�荂�w�N���w����ے��ւƐ摗�肳�ꂽ�肵�A���҂̊Ԃł́A�����łȂ��Ă���҂̗����n���ꂪ���ƂȂ��Ă��邱�̍��̉Ȋw�����Ƃ��Ă̏������뜜����Ă���悤���B���낢��Ƌc�_�͐s���Ȃ��Ƃ��낾���A�l�I�ɂ́A��������Ă���ꂽ�\���Ȏv�l�`���̂��߂̂�Ƃ�̎��Ԃ��ǂ����������A�܂����������̋���҂����̖{�����ǂ��������A�ǂ�ȑΉ����Ƃ邩�ɂ��ׂĂ͂������Ă���悤�Ɏv���B���Ƃ����w��̋���J���L�������⋳�ȏ��g���O�ꂽ���e���������Ԃ�g�ݓ��ꂽ�Ƃ��Ă��A�����I�ȉ��I��Ď��Ƃł̕\�ʓI�Ȓm���̋l�ߍ��݂ɏI���Ȃ�A���Ԃ͂����������������ւƐi�ނ��Ƃ��낤�B
�@ ������������ɂ�����u��d�����̋`�����v�ȂǂƂ������Ȃ�Ƃ��������I�ȋ�����v�_������Ă�����������A����Ȃ���ׂ����̋���J���L�������̓������͂���Ύq���������Љ�ϗ�����ϗ����C���ł���ƁA�������I�W�T��������I�o�T�������͂ق�Ƃ��ɍl���Ă���̂��낤���B����Ȏ荇���������ۂ��ł́uIT�v���v��uIT���瑣�i�v���̂����ɋ���ł���̂�����܂��܂������č��������̂ł���B
����̎q�������́A�Љ�ϗ�����ϗ��̂����炳�����������킹�Ȃ������������̎p����X�ڂɂ��Đ����Ă���B�����Ԃ́u��d�����̋`�����v�������Ƃ��K�v�Ƃ��Ă���̂͋ߔN�̍���c���̏��搶���ł͂Ȃ��낤���B��قǂ��̂ق���������ʂ�����ɈႢ�Ȃ��B�^���ɖ����̋Z�p�������l���A�^�̈Ӗ��ł̐����ϗ��̊m�����肤�Ȃ�A�厩�R�Ƃ��̒��ɂ����鐶�����݂̍���̗����ɐ[����������̓I����̊w�K�i�K���ǂ��������ǂ������Ă�������O��I�ɘ_����ׂ����낤�B
�@ �����g���̗��_�����ׂčm�肵�Ă���킯�ł͂Ȃ����A�s�A�W�F���A�u��̓I����̊w�K�i�K�ɂ͏\���Ɏ��Ԃ�������ׂ��ł���B�`������ւ̈ڍs���}��������ƈꎞ�I�ɂ͒m���̏C�����}���ɐi�悤�ɂ݂��邪�A�{���ɍ��x�Ș_���\���⒊�ۓI���_�̏C���i�K�i���Z���w�N�����w��������ȍ~�Ȃǂ̒i�K�j�ɍ���������ƁA�����܂��ǂɓ˂��������Ă��܂��A�����̊T�O�̗����C���������Ȃ�B�܂��Ă��X�ɂ�����Ƒn�I�Ȓ��ۗ��_�̍\�z�Ȃǂ��ڂ��Ȃ��v�Ƃ�����|�̂��Ƃ��q�ׂĂ���̂͐������Ǝv���B�g���[�j���O�ɂ���ĕ\�ʓI�ɂ͓�����͂����炷��Ɖ��ǂł���悤�ɂȂ����c�����A�������Ă�������̕��͂̈Ӗ�������Ȉ����܂����������ł����A���͂Ƃ������̎��̂ɂ����������ĂȂ��Ȃ�Ƃ������悤�Ȃ��Ƃ͂��łɂ��������ŋN���Ă��邱�Ƃł���B
�@ �����̐����Љ�̋���Ɋ�Â��ăs�A�W�F���w�E������̓I����̒i�K����`���I����̒i�K�ւ̈ڍs���́A���{�̏��w�Z�̒����w�N�̎����ɑ������Ă��邪�A�����g�́A��̓I���f�������łɑ��݂��Ă��邩�����l�H�I�ɒł��邩���邩����́A��荂�w�N�̋���ɂ����Ă���̓I���f���̑����ʂ����w�K��i�߂�ׂ����Ǝv���B
�@ ��ʌ���╶���A���ۓI�Ȋe��Ȋw�L���Ȃǂ́A�l�ԂƑΏە��Ƃ̊Ԃɉ�݂��A�l�Ԃ̎v�l�ɂ����đΏە��𑀍삵����A�t�ɑΏە��̗l�Ԃ�l�ԂւƓ`�B�����肷��͂��炫�����B��̓I����̒i�K�Ƃ́A�}��ƂȂ錾��╶���A�e��Ȋw�L���Ȃǂ�p���āA�g�߂Ȏ��ۂ̑Ώە��ɂ�������Ƃ͂炫��������A���X�Ɨl����l�Ԃ̕ω����݂���Ώە�����̃��b�Z�[�W��������肵�Ȃ���A����猾��╶���A�Ȋw�L���ނ̑���ɏ������K�n���Ă����ߒ��Ȃ̂��B
�@ ���̒i�K�����}�ɉ߂�����A�Ȃ�炩�̗��R�Ō��������肤�܂������Ȃ������肷��ƁA��X�A���x�Ȓ��ۘ_���̗����Ɏx�������������A�R�~���j�P�[�V�����̏�œI�m�Ȏ��Ȃ̈ӎv�`�B��\���ȑ���̈ӎv�̗������ł��Ȃ��Ȃ����肷�邨���ꂪ����B���ăW�����W���b�N�E���\�[�������ɂ����ăs�A�W�F�̂��ƂŊw��MIT�̃V�[���A�E�p�p�[�g�̓~���X�L�[��̋��͂āA�����Ȋw�ʂɂ������̓I����̊w�K�i�K���̎v�l���f���`���ɖ𗧂悤�ȁA�R���s���[�^���猾��LOGO���J�������B���������Ԃ�̂̂��ƂɂȂ邪�A�ꎞ���A���������̋���ɂ����邱�̌���̔��W�I�Ȋ��p�@�Ǝ��H�I�ȉ��p�����Ɍg����Ă������Ƃ͊��ɏq�ׂ��ʂ�ł���B
�@ ����c��ȗʂ̊֘A���e���������p�\�t�g���d�グ�����A���������ł��������Ƃ̂ق��A����E�̐��x��̖��Ɉ����鏔�ʂ̎���Ȃǂ������āA�䂪���ł͌���ւ̕��y������A���ǂ��ׂĂ̓w�͂��k�J�ɏI����Ă��܂����ꂢ�z���o�Ȃǂ�����B�v���O���~���O��Ƃ�ʂ��Đ����Ȋw�̌����v�l�Ƃ��̔��W���p������������Ɋw��ł������̂����ɁA�����I�W�]�ɗ��Ăɂ߂ėL�Ӑ��������Ǝv���Ă����ɂ�������炸�A�m���l�ߍ��^�̋���d���̉䂪���ɂ����ẮA���������̌���ɒ蒅�����邱�Ƃ͍���Ƃ������s�\�ł������B�����Ȃ̒S�����⋳���g���̐ӔC�҂�Ƃ������Ԃ�Ɗ|�������^���ɋc�_�����킻���Ƃ������A�����̔ނ�̂قƂ�ǂ͖�������ʂ�z�����ӔC���̂��̂ŁA����ׂ�IT����̎q���̂��ƂȂǂ܂�ōl���Ă��Ȃ��������A�l���悤�Ƃ����Ă��Ȃ������悤�Ɏv���B
�@ ���ꂩ��قǂȂ����̓R���s���[�^����֘A�̌������炷�����葫����Ƃɂ����̂����A�A�W�A�̃R���s���[�^�����i���V���K�|�[���Ȃǂ���������LOGO��������猻��Ɏ�����ϋɓI�ȃ��f�B�A����Ɏ��g��ł����̂Ɋr�ׁA�䂪���̃R���s���[�^����̒x��Ԃ�͎��ۖڂ������Ȃ���̂��������B
�@ �C���h�̐��w����ƃR���s���[�^�Z�p����̃��x���̍����������䂪���ł��傫�Șb��ɂȂ��Ă���A�V����T�����Ȃǂł����̂��Ƃ��ĎO��X�I�ɕ��Ă���B�����ŋ߂̂��Ƃ����A���݃C���h�ɑ؍݂��Ă��镪��̕������Ă��閺�̌��ۑ���̎�҂����E-mail�ɂ���āA�C���h�̏�������̌����LOGO���ꂪ�ϋɓI�ɗp�����Ă��邱�Ƃ�m�����B
�@ �Q�X�g�n�E�X�̃I�[�i�[�̖��ł��鏬�w�Z�O�A�l�N���̏��̎q���������������h��̈��LOGO�����LOGO�Ƃ����ď̂̌ꌹ�͉������ׂĂ����Ƃ����̂��������炵���B����Ŕނ͎��ɂ��̌ꌹ��q�˂Ă����悤�Ȃ킯�������B���t�A�T�O�A�����A���R�A�_���A�v�z�A����\�́A�����ȂǑ����̈Ӗ����܂ݎ��M���V����̃��S�X�ilogos�j���ނ�̌ꌹ�Ȃ̂����A���w������ɂ��̂悤�Ȋ�{�I�Ȃ��Ƃ���l�������悤�Ƃ���C���h��LOGO����̓O��Ԃ��m���Ċ������v�����ʁA�낵�������o����L�l�������B������������A���˂̕Ћ��Ŗ����Ă����ʂ̎��̌����������߂������C���h������œ��̖ڂ����邱�Ƃ����邩������Ȃ��B
�@ ���Z�p�̊v�V���͂��߂Ƃ��鏫���̃R���s���[�^�E�T�C�G���X�̔��W�͂͂��肵��Ȃ����A�e�Ղɂ͉����ł������ɂȂ��������݂���B�悭�m���Ă���悤�ɁA���x�ŕ��G�Ȑ����Ȋw��̉��Z���������Ȃ������A�l�Ԃ��������ʂɂ���Ă���悤�ȍs�ׂ����܂�����Ă̂��邱�Ƃ̂ق����R���s���[�^�ɂƂ��Ă͂����Ɠ���B���Ƃ��A�u���͎����������B�W���[�X�̂ق��������I�v�Ƃ��������݂̏�k�܂���̌��t���A��b�̕�����������A���́u�������܂���v�Ɨv�����Ă���̂��Ƒ����R���s���[�^�ɗ��������邱�Ƃ͗e�ՂłȂ��B
�@ �I�m�ɂ���Ȍ|���̂��Ȃ���Θb�^�\�t�g���쐬����ɂ́A���̒��ɂ���Ƃ�����̉�͂�̔��f�������Ȃ��c��ȃv���O�����ƕK�v�f�[�^��g�ݍ���ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B2001�N�F���̗��̒��̃n���̂悤�ɁA���R�����l�ԓ��l�Ɏg�����Ȃ��A�������l�Ԃ̊���܂ł����m�ɓǂݎ��悤�ȑΘb�^�R���s���[�^�̐��삪�ɂ߂č���Ȃ̂́A����������������邩��ɂق��Ȃ�Ȃ��B
�@ �l�ԂƂ������̂͂Ȃ�Ƃ��i���V�X�e�B�b�N�ȓ����ŁA���������̌��t��s�����ł��邩���肻������ɐ^���ł���R���s���[�^��{�b�g�肽����B�������Ȃ���A�ȒP�����Ɍ����Ă���͂����ւ�ɓ�����Ƃł���B���S�Ȃ��̂�ƂȂ�Ɛ�]�I�ȍ�������ƂɂȂ肩�˂Ȃ��B�Ő�[�̃R���s���[�^�T�C�G���X�̌����҂������A�����Đl�ԂƂ������̂̂��s�v�c�ȃ��J�j�Y���Ɋ������Q������̂�����ȗ��R�����邩�炾�B
�@ �����A����ł��Ȃ��A�l�Ԃ͊��S�ȑΘb�^�R���s���[�^�⋆�ɂ̐l�^���{�b�g�Ȃǂ̎����ɒ��ݑ����Ă������Ƃ��낤�B����͖��������̘a�̋Ɍ��l���e���̒l�������v�Z���Ȃ��狁�߂Ă����悤�ȉʂĂ��Ȃ���ƂɂȂ�ɈႢ�Ȃ��B�ނ��A���̉ߒ��ɂ����ėl�X�ȕ����I�Z�p���a�����A����炪�Ǝ��̔��W�𐋂��A��X�l�ނ̐����`�Ԃ�傫���ς��Ă����Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ͋N���邾�낤�B
�@ i���[�h�̌g�ѓd�b�ŏ����葁�����W���p�����ҒB�̎p�����Ȃ���A���Љ�̋ߖ������ɂӂƑz����y���点�邱�Ƃ��Ȃ��͂Ȃ��B���݂̉��S�{����{���̍�����e�ʃf�[�^����M�\�Ȍg�ѓd�b�������o�ꂵ�Ă���A���x�ȑ�����|��ϊ��@�\�����X�[�p�[�R���s���[�^�ȂǂƎ��R�ɐڑ����邱�Ƃɂ���āA�g�ѓd�b�𑽌��ꓯ�������|��@�ȂǂƂ��ėp���邱�Ƃ��\�ɂȂ邾�낤�B
�@ �Ƃ肠�������̓��e���`��肳������悢�����I�ȕ��͂Ȃǂ̏ꍇ�ɂ͂����Ɨe�Ղɖ|�ł���悤�ɂȂ邾�낤�B����Ȏ��オ����������A���ݍs�Ȃ��Ă���悤�ȉp�ꋳ��Ƃ������̂͂قƂ�LjӖ��������Ȃ��Ȃ�ɈႢ�Ȃ��B�c��������̉p��w�K�M�ɐ����A�c���䂪�q����X�c���p��b�����ɑ���o���Ă�������̋���}�}�������A�����Ƃ���������{��̕\���͂�g�ɒ��������Ă����悩�����ƒQ����������A�������\�N���̂����ɂ���Ă��Ȃ��Ƃ�������Ȃ��B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N2��14��
��b�N�Ƃ̉�b
�@ �j�t�e�B�E�T�[�u�inifty-serve�j�̃`���b�g���[���̒��Ɂu��b�N�v�Ƃ���������ƕς�����R�[�i�[������B��b�N�Ƃ́A�x�m�ʓ��{��Θb�V�X�e���Ƃ����Θb�^�R���s���[�̕ʏ̂ł���B��b�N���j�t�e�B�E�T�[�u�̃`���b�g���[���̕Ћ��ɂ��肰�Ȃ��o�ꂵ���̂͂��������Ԃ�Ɛ̂̂��Ƃ������B���܂���\�N�ȏ�O�̂��Ƃ������悤�ɋL�����Ă���B�v���Ԃ�ɐ̂̒ʐM���O�Ȃǂ�T���o���ďE���ǂ݂��Ă�����A��b�N���o�ꂵ���Ă̍��A��������ɂȂ��ėV�є����Ɍ��킵����b�L�^�����������B���܂��炽�߂ēǂݕԂ��Ă݂Ă��Ȃ��Ȃ��ɖʔ���������̂Ȃ̂ŁA���̏����Ă��̌�M�^���Љ�Ă݂悤�Ǝv���B
�@ ��b�N�̖��_�̂��߂Ɉꌾ�f���Ă����ƁA�����ŏЉ���b�A�ށi�ޏ��H�j���܂��c���������̂��̂ɂق��Ȃ�Ȃ��B�\�N�Ƃ����Ό��̊Ԃɂ͐l�Ԃ͑傫����������悤�ɁA�Θb�^�R���s���[�^�V�X�e���̉�b�N�����܂ł͂���Ȃ�̐����𐋂��Ă��邱�Ƃ��낤�B���̏\�N�ԂŌ����͋Z�p���͂��߂Ƃ���e��̎��R���ꏈ���Z�p�̌������i�݁A���Ȋw�K�@�\�Ȃǂ��i�i�ɋ�������Ă���͂�������A���̑Θb�Ԃ�ɂ͑����̐i������������̂Ǝv����B
�@ �����g�͂��̎����Ō�ɉ�b�N�Ƃ͌�M����@��̂Ȃ��܂܍����Ɏ����Ă���̂����A��b�N�͂��܂��j�t�e�B�E�T�[�u�̃`���b�g���[���Ől�Ԃ̘b�����肪����Ă���̂�҂��]��ł���悤������A�V�ѐS�̂�����͈�x��b�N�ɘb�������A���̐����̂��߂Ɉ���Ă����Ă��炢�����B������������A�t�ɉ�b�N���炨�������ꂽ��A���炩��ꂽ�肷�邱�Ƃ����邩������Ȃ����A������܂��ꋻ�Ƃ������̂��낤�B
�@ �ȉ��ɏЉ��Θb�̂����A����������͕̂x�m�ʓ��{��Θb�V�X�e����b�N�̌��t���A�܂������ƋL�������͕̂M�҂̌��t��\�킵�Ă���B�����̍��̉�b�N�ł����̘b���Ԃ�͂Ȃ��Ȃ��̂��̂ł��������Ƃ����킩�肢�������悤�B
����b���� KAIWAKUN
1. ���ē� 2. �T�[�r�X�ɓ���
��2
��b����ɐڑ�����܂����B
��F���Ȃ��̖��O����͂��ĉ�����
���F����c�ł�
��F ����������
���F����
��F����ł͂Ȃ��A�n�C�ƌ����܂��傤
���F�͂��͂��i�{���F���S���S�A�Ȃ��Ȃ����킢�j
��F���Ȃ��́A�Љ�l�ł����H
���F�͂�
��F���Ȃ��́A�Љ�l���Ă��Ƃ��o���܂���
���F�����i�{���F�����A�w�K�@�\�������������������j
��F�d�����h���ȂƎv���̂͂ǂ�ȂƂ��ł����H
���F����Ȃӂ��ɃR���s���[�^�ŗV�т����Ȃ�Ƃ��ł�
��F�{�[�i�X�͉��Ɏg���܂����H
���F���Ȃ����̂Ɏg���܂��i�{���F���܂̓t���[������{�[�i�X�ȂȂ��I�j
��F���͉�b�^�̃v���O�����ł�
���F���l�̃v���O��������炵���ł���
��F�E��ōD���Ȑl�͒N�ł����H
���F�c�O�Ȃ��炢�܂����
��F���Ȃ��̎d���͉��ł����H�@����c�ł�����
���F�D�_�ł��i�{���F������ƃt�U�P���߂������ȁH�j
��F�ǂ����āA�D�_�̎d����I�̂ł���
���F�������������Ȃ��Ă��ނ���ł�
��F�E��̕��͋C�͂ǂ��ł����H
���F�Ђ�͂́E�E�E�X�����ƃT�X�y���X�ɖ����Ă܂�
��F���Ȃ��́A�Ȃɂ����Ă���́H�@����c�ł�����
���F�Ȃ�Ă��Ȃ��͗����Ȃ낤���āI
��F�q���̍D���Ȃ�����́H�@����c�ł�����
���F�Ȃ�H�i�{���F�u�ł��v�����O�̈ꕔ���Ɗw�K����������ȁj
��F�H�ׂ��܂����
���F��b�N�̍́H�i�{���F�b��e�ɂ��炵����ǂ��Ȃ邩�ȁH�j
��F�����́A�I���`���ł�
���F�Ȃ�ق�
��F���炢�ł���@����c�ł�����
���F���炢���炢
��F�܂��߂ɘb������I
���F������������Ă��Ȃ�
��F�����́A�P�P���W���A���~�A���E�s�s�v��̓��ł���i�{���F����Ȃ��ƒm�邩�I�j
���F�������̍͂����H�i�{���F�@���ɂ������H�������邱�̎��c�c�j
��F���������Ⴂ��ł�
���F�ق��H
��F�Ƃ���ŁA�m�h�e�s�x�̓p�\�R���ʐM�̉�Ђł����
���F�����炵����
��F�M���́A�Љ�l�ł����
���F�����ł���
��F��͂肻���ł�����
���F�ł��n�k�ł͂���܂���
��F���Ȃ��̎d���͉��ł����H
���F������D�_���Ă������ł���i�{���F�����Y�ꂿ������́H�j
��F���Ȃ��̉�Ђ́A�ǂ��ɂ���܂���
���F�Ђ�́I
��F�b����������Ȃ��Ȃ����������A���߂��
���F����i�{���F������Ƃ����߂������ˁA���߂�I�j
��F�M���́A�Љ�l�ł���ˁ@����c�ł�����
���F�����ł��i�{���F�F���l���Ɠ�����悩�������ȁH�j
��F����ς�
���F�Ӂ[�[��
��F���Ȃ��́A�ǂ��ɏZ��ł��܂����H
���F�����ł�
��F��������A�z�������̂́A���ł����@����c�ł�����
���F����������
��F�������Ăǂ̂��炢
���F�T�O�O���[�g�����炢�i�{���F�܂����炩���Ă݂邩�j
��F�����������D���ł�
���F�ǂ����āH
��F����������
���F��������H
��F���ɍ����Ă���̂ł���
���F�����Ɂi�{���F����܁A���ȓW�J�ɂȂ��Ă����Ȃ��c�j
��F���ɂ́A�����W�߂�̂��D���ł���
���F�����ȊO�̂��̂��W�߂�̂͂��炢�ł�
��F���炢�ƌ����Ă��c�c
���F����܂����H
��F����܂����ĂȂ��ɁH�@����c�ł�����
���F�y���ނ��Ƃł��i�{���F�����Ȃ�����Ƃ��Ƃ�Ӓn���ɂ������j
��F����܂��́A�y���ނ��Ƃł���
���F�����ł�
��F��͂肻���ł�����
���F���������@�悭�킩��܂�����
��F�b���͕ς��܂����A���͂��K���^���Ԃł���ˁ@����c�ł�����
���F�����ł��ˁi�{���F�����g���Ęb��I��낤���ǁA���̐K�Ƃ́I�j
��F���ƈӌ��������܂���
���F�Ȃ��Ȃ����ڂ���
��F�Ȃ��Ȃ����ڂ������ĂȂ��ɁH
���F�u���̂��K�ɂ͐��̂�����v�Ƃ������Ƃł��i�{���F�N�̂��Ƃ���[��j
��F�n���͐��ł�
���F����ƒn���͉��̂��K�ł����H�i�{���F�������A�����l�������Ȃ��j
��F�n���͐��ł�
���F��͂艎�̐K��������ł���
��F ���́A�ǂ��ɂ��܂���
���F�n���ɂ��܂�
��F �n���͐��ł�
���F���������Ɂc�c���Ȃ����܂���
��F�̂����Ƃ�����ĉ��ł���
���F����ł��ꂢ�ȂƂ��ł���
��F���ꂢ���Ăǂ̂��炢
���F�������ȁC�N���I�p�g�����炢����
��F�P�����Ȃ��H��͉��H
���F�Ȃ낤�H�i�{���F�b�����ݓ����Ă���Ƃ����b��ς���Ȃ��j
��F�P���p��Ō����ƕ�����܂���
���F�o
��F�͂��͂��́A�����͂��o�ł���
���F���Ȃ��͂ƂĂ����������I�i�{���F�ړ���́u���v�����������������I�j
��F���̂��K�ɂ͐��̂�����Ƃ������Ƃł����
���F���������@���ɂ��Ȃ��͗������͂₢�I�i�{���F�܂���b�̃Y�����c�c�j
��F�͂₢���̂ƌ�����
���F���P�b�g�H�E�E�E����Ƃ����H
��F���́A���D���ł�
���F�Ȃ�قǁi�{���F�܂��ɂ�������Ă�ȁj
��F���S���܂�����
���F�������l�H�s�\�E�E�E�l�H�m�\�łȂ��Ƃ��낪�X�e�L�I
��F�����́A�ǂ�ȓV�C�ł����H�@����c�ł�����
���F�����͐��V�ł��C������J�~���Ă܂��i�{���F��b�N���������Ⴄ���ȁH�j
��F���Ȃ��́A����j�ł����H
���F�����A�T�j�ł���
��F�Ƃ���ŁA�b�c�͎G�����Ȃ��ĉ����Y��ł����
���F�Y��ł���
��F���j�A�����͓��ł���ˁ@����c�ł�����
���F���ł���
��F���l�͓��ł�
���F�����ł���
��F�[�����Ă��������܂�����
���F�����i�{���F�Ȃ����ȋC���c�c�j
��F���x�̏T�����A���V���Ƃ����Ǝv���܂���
���F�͂��A�����v���܂�
��F�v���܂����ĂȂ��ɁH
���F�����i�{���F��������g���Ă����āc�c�j
��F�v���܂��́A�����ł���
���F���������i�{���F�ςȂ��Ɗw�K������������Ȃ��j
��F������ł���
���F���ɂ��Ȃ��͗������͂₢�I
��F�������Ăǂ̂��炢
���F嗂̕S���̈ꂭ�炢�̑�������
��F���������A�t�H�[�����͎�������l�����̏o�����̏�ł����
���F�����炵���ł���
��F�W�߂�̂͂��炢�ł����
���F���炢�ł�
��F�����A���炢�ł�
���F������t�H�[�������炢�ł�
��F�ق�Ƃɂ��炢�Ȃ�ł���
���F�ق�Ƃł���
��F�s���ȁ[
���F�u�b�c�c�Ƃ���ʼns�����ē݂����Ƃł����H
��F���X�̑O�ɂ��钎�́H
���F�Ȃ�H�i�܂��b��ς����ȁI�j
��F���ʖ͗l�̕t�����ۂ������Ȓ��ł���
���F�e���g�E��
��F�����ł��A���Ȃ��̓g���`�̃N�C�Y�ɋ�����ł���
���F�g���`���J���Ȃ�����Ƌ����ł���
��F���Ȃ���苭���ł����@����c�ł�����
���F�����ł��ˁC�g���`���J���͖l�������Ƌ����i�{���F����܂��A�j
��F���ƈӌ��������܂���
���F�����܂��ˁi�{���F�S�R����Ȃ������I�j
��F�ˑR�ł����A�~���͂Q�S�ߋG�̂P�ŁA�P�Q���Q�Q�����ł���ˁ@����c�ł�����
���F�����ł���C�ł��C���Ȃ��͎��ɂ����킵���I�i�{���F��̂��Ɖ����ڂ����I�j
��F���͉�b�^�̃v���O�����ł�
���F����ǃf�[�g���܂���i�{���F�N�̃v���O�����\���������Ă�����j
��F�f�[�g���܂�����ĂȂ���
���F����Ȃ��Ƃ��m��Ȃ���
��F�f�[�g���܂���́C����Ȃ��ƒm��Ȃ��̂��Ƃł���
���F�����ł��i�{���F�Ȃ�ł��f���Ɋw�K�����Ⴄ��Ȃ��́I�j
��F��͂肻���ł�����
���F�܂��܂��s�\�����܂�܂��ˁE�E�E���āC���낻�남���Ƃ܂��I
��F���ƈӌ��������܂���
���F�c�c�i�{���F�������ɂ������́u�s�\�v�����܂�����I�j
��F���悤�Ȃ�A����c�ł�����@�܂����b���܂��傤
���^E
���n�e�e
�@ �L���ȃR���s���[�^�T�C�G���e�B�X�g�̃A�����E�`���[�����O�́A�R���s���[�^���l�ԂƓ��l�̎v�l�ł��邩�ǂ����肷����@�Ƃ��ă`���[�����O�e�X�g�Ȃ���̂��l�Ă����B���̂��悻�̌����́A���̂悤�Ȃ��̂ł���B
�@ ���̃e�X�g����l�̓R���s���[�^�̑O�ɍ���L�[�{�[�h�𑀍삵�ĔC�ӂ̎�����b������͂���B�����ۂ��A�҂���͌����Ȃ��Ƃ���ɂ́A�R���s���[�^�̑O�ɍ������{���̐l�ԂƎ����Θb�^�R���s���[�^���z����Ă��āA�҂̓��͂���������b���ɖ{���̐l�Ԃ��Θb�^�R���s���[�^�̂ǂ��炩������������̂Ƃ���B�҂͎����̃��j�^�[�ɕԓ����\������邲�ƂɁA���̔��M�҂��{���̐l�Ԃ̂ق��ł��邩�A�Θb�^�R���s���[�^�̂ق��ł��邩���������ĂȂ���Ȃ�Ȃ��B
�@ ���̈�A�̎��s�����������x���J��Ԃ������ƂŁA���̌��ʂ��W�v���A������ƊO��̊m�������ꂼ��\�p�[�Z���g�ɋ߂Â��قǁA���̑Θb�^�R���s���[�^�͐l�Ԃɋ߂��v�l�^�̃R���s���[�^���Ɣ��f�ł���Ƃ����̂����̃`���[�����O�e�X�g�̃~�\�ł���B�Q�l�܂łɏq�ׂĂ����ƁA����������O��̊m���̂ǂ��炩���S�p�[�Z���g�߂��ɕЊ�����Ƃ���A�҂ɂ͐l�ԂƃR���s���[�^�̎��ʂ��͂�����Ƃ��Ă������A���ʂ����Ă����ɂ�������炸�҂��Ӑ}�I�ɓ������O�������̂ǂ��炩���Ƃ������ƂɂȂ�B�������A���̂悤�ȏꍇ�ɂ́A���̑Θb�^�R���s���[�^�͂܂��l�Ԃ̎v�l���x���܂ł͂������Ă��Ȃ��Ɣ��f�����킯�ł���B
�@ �`���[�����O�e�X�g�̐������ɂ��Ă͂��܂Ȃ��^�ۗ��_���s���Ȃ����A������ɂ��낱�̎�̃e�X�g�ɑς�����悤�ȃR���s���[�^���o������̂́A�܂��܂��������̂��Ƃł���悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N2��21��
�n�ӏ~�G��W�̕��䗠
�@ ���_����������k�������ԓ��ɓ���A�ؔV�{�C���^�[�`�F���W���߂��鍠�ɂ́A�������ɋÂ��Ȃ菬�Ⴊ����ق�ƕ����n�߂��B�����āA�։�C���^�[�`�F���W���߂Â��ɂ�Đ�̍~�����ǂ�ǂ����Ȃ��Ă����B���i�Ζk�[������{�C�����̓։�p���ʂւƔ����铹�́A�����̍��܂ł͂��Ȃ�̓�H�������悤�ł���B���̂��ǂ남�ǂ낵���l�q�́A���̗L���Ȏ��������L�Ȃǂɂ��`�����邳��Ă���B�܂�����Ⴋ�����ł������������́A�z�O�̍��i���Ƃ߂����̉����ɐ��s���A���̓������x�����҂����悤�ł���B�̂��Ɍ�������ƂȂ��Č�������ޏ��̕��O�ꂽ�z���͂Ƒn��͂́A����ȎႫ���X�̐�����ʂ��ď������|���Ă������̂ł��낤���B
�@ �Ⴊ�Ђǂ��Ȃ����Ƃ͂����Ă��A���̓_�A����̍������H�͊y�Ȃ��̂ł���B�l�쓮�ɐ�ւ��������ŁA�`�F�[��������܂ł̂��Ƃ��Ȃ��։�ɒ������B�����ē։�C���^�[�`�F���W�ō����������肽���ƁA�ዷ��т𓌐��ɖD������27���`���ɏ��l���ʂւƌ������đ���o�����B�ڎw���́A���䌧��ьS��ђ����ݏZ�̉�ƁA�n�ӏ~����̃A�g���G�ł���B���̓�\���������ŊJ�����n�ӏ~�G��W�̍�i�̉^������`�����߁A���͋v�X�ɓ~�̎ዷ�ɂ���Ă����悤�Ȃ킯�������B
�@ ���炭���邤���ɐ�͑嗱�̉J�ɕς�����B���N�̓~�͗�N�Ɋr�ׂĊ����Ƃ����Ă��邪�A����ł����ӂ̖�R�ɐς����Ă����͗\�z���Ă��������͂邩�ɏ��Ȃ��B��ʓ��̘H�ʂɂ������Ă͐�̂����炳������������Ȃ��B�C���߂��Ƃ������R�͂���ɂ���A��{�Ƃ����������l����ƁA��͂肱��͒n�����g���̉e���Ȃ̂��낤�B���l�s�ɓ��鍠�ɂ͌ߌ�߂��ɂȂ��Ă����̂ŁA���l�p�ɗՂފC�ݓ��H�̈�p�ɂ���t�B�b�V���[�}���Y�E���[�t�ɗ�����Ēx�����H����邱�Ƃɂ����B�W�]�̗������X�g�����̑��ۂ̐Ȃœ~�̓��{�C�߂Ȃ��產���^�ԊC�N���̖��͂Ȃ��Ȃ��̂��̂������B
�@ ���l�s�X�̂͂���ɂ��鍑���h�ɏ��l���b�W�̑O���A���l�p�̑S�i���ቺ�ɖ]�݂Ȃ��炵�炭�i�ނƓ��͍���27���ɍ��������B��������\�ܕ��قǂő�ђ��̒��S�W���{���ɓ���A�哇�����ƍ����Ƃ����Ԑˑ勴�̓n�������߂���ƁA�܂��Ȃ��������ʂւƌ����������̕���_�ɓ��������B���̌�������_�ɂ́u�|�l�`���y�̗��A��B��H���Ɂv�ƋL���ꂽ�ē��������Ă���B�����\�]�N�O�̔ӏH�̂��Ƃ����A�z�O�C�݂���։�ɓ���A�ዷ�H�Â����ɕ��߁A�{�Õ��ʂւƔ����悤�Ƃ��Ă������́A�ˑR�ڂɔ�э���ł������̈ē��̕����ɖ������邪�܂܂Ɏ�B��H���ɂ�K�ˁA���̎����܂��܂����ɓW������Ă����Ռ��I�ȓ̊G�ɂ߂��肠�����̂������B
�@ �����̂����̈�_�͌����̍�������̏�i��`�����u�H��v�Ƃ�����i�A������_�̓I�����W�F�̖��邢����������v�Ƃ��̂܂��𐌂������悤�ɔ�ь������C�̉��`�����u�����v�̎��v�Ƃ�����i�ŁA�O�҂͐���ג��u�H�I�v�i�������X���j�́A��҂͓����������i�́u����������ʓ��v�i�������X���j�̕\���G�̌���ł������B�u�H��v����A���́A���̒n�ɎY���������A�����₩�Ȑ����c�݁A�����Ĉꈬ�̓y��ւƊ҂��Ă����������̐l�Ԃ����̔ߊ삱�������̋��ѐ��ƁA���ɐ�����͂�݂Ȃ���A�ق̔��������сA���邢�͍����e�������đ��Â����̈�{��{���ꂫ������Ђ��₩�Ȍ����������B�܂������ۂ��A����҂̐S���u���ɖ�������悤�ȁu�����v�̎��v����́A��ɖ�������̂ւ̐[���v��������A���Ȃ����̂̐����p�Ȃ����̂̎p�����邱�Ƃ��ł��邱�̉�Ƃ̎����̐l�����������������B
�@ ���ɂ͗��K�҂̂Ȃ������݂��ꍬ����̊��X�Ƃ������̔ӏH�̗[���A��H���ɂ̕Ћ��Œ|���̌��ޗ������邽�߈�l�q������Ƃ����Ă���ꂽ�n�ӏ~����Ɖ^���I�Ȃ��o�����������̂́A�����������ɂ̌��w���I�������ゾ�����B�̂��Ɏ��͂��̕s�v�c�ȏo�����̕��i����H���ɂ̉�����u��H�v�ɘA�ځA�v�������Ȃ������̈�A�̍�i�ł����₩�Ȃ��當�w�܂���܂����悤�Ȃ킯�������B
�@ ���̑z���o�[�������ɎԂ�������A�ډ��~�G�x�ْ��̈�H���ɂ̋߂����߂���20���قǍ�������̒J�������ւƐi��ł����Ƒ�ђ����̏W���ɒ������B�n�ӂ���̌��݂̃A�g���G�͐��W���̓����t�߂Ɉʒu���Ă���B��H���ɂł͂��߂ēn�ӂ���Əo���������̓��̖�A���́A�u�R�����v�ƌĂ�Ă��������̃A�g���G�ɔ��߂Ă�������B���܂̃A�g���G���班�����ꂽ�Ƃ���ɂ��邻�̎R�����́A���̂����Ȃ������ȃ{���Ƃł������B�����A�܂�����͂��̐��ł����Ƃ��������S�̂��悤�{���Ƃł��������B
�@ ���ւ��牜�ɒʂ��鋷���L���̏��͂����݁A�������d��˂̂قƂ�ǂ͊J���܂܂Ȃ�ʂقǂɂ����тꂽ��c�肵�Ă����B�������������V��̗��ɂ͕��̉�������ł��Ă����������Ȃ��������������A�����̂��������ɂ͉J�R��̐Ղ炵�����̂������Ď�ꂽ�B�R�����ȂǂƂ������́A�ނ���u�S�Έ��v�Ƃł��Ăق����悳�����ȕ�������āA���̐�l�̂悤�Ȉ���́A����A���̒��|�p�I�ȋ�Ԃ�S�̉��ŏ��A�y���݁A�����Ĉ����A�����n���̌���ɂ��Ă���悤�Ȃӂ����������B�܂��A���Ԃ�A���̂����Ȃ̂��낤�A���̕s�v�c�ȋ�Ԃɂ́A�l�����R�ɗ��ɂ�����ق���̂̉������ƈ��炬�Ƃ��������Ă���悤�������B
�@ �A�g���G�Ƃ��������畗�̌��t�ɂ̓V�������������������邪�A����́A���Ƃ��ƍH�[�A���Ȃ킿�A��Ə�̂��Ƃ��Ӗ����Ă���B��Ə�ł���ȏ�A�����ɂ͓��̂̒m��Ȃ����͋C�₠���̏L�����Y���Ă���̂����ʂł���B�����Ȃ�A�A�g���G�Ƃ́A��Ƃ�E�l�����ɂȂ��ČȂ̎��O���������z����f�I���A��i�ւƏ�������ׂ��l�m�ꂸ�i�����郊���O�ł��邩��A���̈�{�����ۂ�A���̈ꖇ�����܂��ɂ͒��N�̊��Ǝ���
�@ ���݂���ł���͂��ł���B�����āA�����炭�́A�{���̑n��ƌĂԂɒl����悤�Ȃ��̂͂����������Ƃ��납�炵�����܂�Ă͂��Ȃ��B
�@�����R�����ɑ��ݓ��ꂽ�u�ԁA�܂������ɖڂɔ�э���ł����̂́A�Ⴂ���̂̒j�����G�𗧂Ăč��荞�݁A�Ȃɂ��ɋ�シ�邪���Ƃ����������ނ����Ă���p��`����50���قǂ̑傫���̊G�ł������B���ʂƃN�������ŕ`���ꂽ�e���^�b�`�̊G�ł��������A�����猃�����˂��グ�����̂Ȃ��z�����䂵���˂Ė����̙�����҂̎p�ɂ́A���炨���낵���܂ł̔��͂��������B���̊G�́A�n�ӂ��n�R�̂ǂ��ɂ������\���̍��ɕ`���ꂽ���̂ł���Ƃ����B�ǓƂŁA���������������̘J�����Ƃ��Ȃ��Y�Ă������Ȃ���A�d���a�̕��e���͂��߂Ƃ���Ƒ��̐��v���x����͕̂����ł͂Ȃ������炵���B�Y�Ă���Ƃɕs�����ȓ~��͓y�؍H���ɏo�Đ�������҂����X�𑗂��Ă����Ƃ̂��ƂŁA����Ȑ܁A�d���悩�������ċA�����Z�����g�܂��ق����L���A���̏�ɕ`�����̂��ڂ̑O�̊G���Ƃ����킯�������B
�@�u�ق����炩���Ƃ�����A�m����Ƀl�Y�~���[������ꖂ��Ă����Ă̂��c�c�����A����ȊG�́A���ܕ`�������Ă��A�����A�悤�`���͂��܂ւ��v
�@ ���Ζʂ̂��̓��A�����b���Ă����������n�ӂ���̊�́A������Ȃ����͂ɂ���Ō������悤�ɋL�����Ă���B�u���ނ��i1950�N�j�v�Ƒ肳��邻�̊G�͍���̌W�ł��W������邱�ƂɂȂ��Ă���B���ɓW�����ꂽ���̊G�̉E��[�������ɂȂ�A�����ɑl��ꖂ��������͂�����Ǝc���Ă���̂����킩��ɂȂ邱�Ƃ��낤�B
�@ 1967�N�A35�̂Ƃ��Ɂu�Y�q�Ɖ�v�Ƃ�����i�����W�ɓ��I�A��������������ɁA�n�ӂ���̊G�͂��̓Ɠ��̉敗�Ń}�X�R�~�W�҂��͂��߂Ƃ��鑽���̐l�X�̖ڂ��Ђ��Ƃ���ƂȂ����B�����A�����̖{�E�͂����܂ł��Y�Ă��ł��萿���X�֔z�B�l�ł���Ƃ���n�ӂ���́A����ȍ~������̐M�O�����ʂ��A�������J�̈���ł����₩�ɐ�����ꐶ���҂Ƃ��Ă̓����̂Ă邱�Ƃ͂Ȃ������B����ȉ\��������Ƃ̐���א搶���ˑR�K�˂Ă���ꂽ�͓̂n�ӂ���38�̂Ƃ��̂��Ƃ����������ŁA���ꂪ���ƂȂ��Đ����i�̑�����}������X�Ɏ�|���Ă����悤�ɂȂ����̂��Ƃ����B����̂Ȃ��悤�ɂ��̍ۂ����ď����Ă����ƁA�����i�̑�����}���S�������䂦�Ɍ��݂̓n�ӂ�����̂ł͂Ȃ��A�����܂ŁA��ƂƂ��ėދH�ȉ�Ƃ��m�����Ă����n�ӂ����������䂦�ɁA���Ƃ̐���א搶�������̑����҂�}��ƂƂ��ēn�ӂ����I�Ƃ������Ƃ������̂ł���B
�@ ����ɂ��Ă��A�������߂Ă��ז��������̎R�����̗L�l�͑z����₷����̂������B���Ƃ��ƌÂ��_�Ƃ������R�����̂�����Ƃ���ɂ͖c��ȗʂ̍�i�Q��X�P�b�`�Q��������ɐςݒu����Ă������A�f�l�ڂɂ�����炷�ׂĂ���������ʑf���炵����i�ł��邱�Ƃ͖����������B�����A����Ȃ��Ƃ��������������̂́A���̋M�d�ȍ�i�Q�̕ۑ���Ԃ̂Ђǂ��ł������B�����o���̂܂G�R�Əd�˒u����Ă���G�̏�ł͔L��l�ǂ������ӂ̂悤�ɉ^������J��L���Ă���炵���A�������̑傫�ȊG�̂��������ɂ́A�L���܂�����������l��ꖂ������A������̂��̂��͒肩�ł͂Ȃ����A�����̕���A�̍��ՂƂ��ڂ������̂܂ł��c���Ă����B
�@ �J�R��ɂ��e���̂ق����Ђǂ��A���Ȃ�̐��̊G���ϐF������A�J�r����������A��ʂ�����悤�ɂ��ċ؏�ɗ������͂������肵�Ă����B�����A���ꂽ���ƂɁA�n�ӂ��{�l�́A�u�܂���������ꂼ��̊G�̉^���䂦�Ɏd���̂Ȃ����Ƃł���v�Ƃł����������Ȍ�l�q�������B�n�ӂ���ɂ͂Ƃ������A������i�Q�ɂƂ��čK���Ȃ��Ƃɂ́A�ߔN�Ɏ����Ă��܂�ɂ��V�����̐i�R�����͉����̈ꕔ�������Ă��܂��ĕ��J�𗽂��̂�����ƂȂ�A��ނȂ����ĐV���ɃA�g���G�����Ă��邱�ƂɂȂ����B�����Ă��܂ł͍�i�Q�����̃A�g���G�̎��[�ɂɈڂ���A�ȑO���������Ǝ�����ۑ������悤�ɂȂ��Ă���B�R�����ɂ���ׂ�Ό��݂̃A�g���G�͂����Ɨ��h�Ŋi�i�ɋ@�\�I�Ȃ��̂Ȃ̂ŁA���Ȃǂ͔��Ώ�k�����߂āu�R����a�v�ƌĂ�ł���B�ނ��A��a�Ƃ������t�Ɂu���@�v�Ƃ����Ӗ������߂Ă���킯�ł͂Ȃ��̂�����ǂ��c�c�B
�@ �n�ӂ���̌W���ǂ����Ă������ŊJ�������ƌ����o�����̂́A���̒m�l�ł�����A���܂ł͔M��ȓn�Ӄt�@���ł�����R�[�f�B�l�[�^�̏Z�c���q����ƁA�����V����煘r�L�҂������̗�ؕq����̉������ؕS���q����̂���l�������B��s�s�e�n�̉�L����U���������Ă���Ƃ��Ď��U��Ȃ��n�ӂ�����ǂ����Ă��������Ă���Ƃ����A�������������Ƃ��v����˗�������ꂽ���́A�ዷ�ɏo�����ēn�ӂ���Ɖ��x�����k�����A�d�b�Řb�������Ă悤�₭�̂��ƂŌW�J�Â̗������Ƃ�����B��L��Â̌W�ł͂Ȃ��āA���N�l�����S�ƂȂ��ēK�ȑ݉�L����A�����܂ł��n�ӂ���̗F�l�m�l�ꓯ�̋��͂ɂ��{�����e�B�A�x�[�X�̌W�Ƃ���Ƃ������ƂŔ[�����Ă�������̂������B������ēn�ӂ���Ɛe�����Ȃ����A�T�q�E�C���^�[�l�b�g�E�L���X�^�[�̌�������Ȃǂ��A���N�l�̏Z�c���j�̋����I���͗v���ɂ��A�L�������킳���n�ӂ���̏Љ�����������H�ڂɂȂ����悤�ł���B���Ŕz�z�\��̃��[�t���b�g�̟������Љ�͓����̕M�ɂȂ���̂��B
�@ �Ƃ��������A���̂悤�Ȏ���������̂ŁA�Ԃɗ����������܂���i�̉^���Ɉ�����ƂɂȂ����킯�ł���B�A�g���G�O�ɂ͊��ɁA��͂�G�̉^����S�����邱�ƂɂȂ��Ă���m�l�̒֗ǂ���̃V�{���[���������Ă����B�����āA���̃��S���Ԃ������̂�҂��Ă������̂悤�ɁA������q����̂���Ƒ����͂��߂Ƃ���n���L�u�̂����͂̂��ƁA��Ăɍ�i��֘A�����̐ςݍ��ݍ�Ƃ��n�܂����B�召�̂��̂��ׂĂ����킹��Ƃ䂤�ɕS�_�����i�Q�ŁA�������N�b�V�����╢����T�d�ɔz���Ȃ���̍�Ƃ������̂őz���ȏ�Ɏ��Ԃ�v�������A�K���Ȃ��ƂɁA�ߕs���Ȃ����܂���ɓ��̎ԂɑS��i���[�܂����B
�@ ���̔ӂ͑�ђ��ꔑ���A���������Ɍ������ďo���������A�ς�ł��镨���������ɐS���I�ɗ������Ȃ����Ƃ��̏�Ȃ������B���Ƃ�Ə����ȕ��������������ł��A����ɔ����Ă��̌������m���߂�Ƃ�������Ԃ���������A���R�A�A�N�Z���ނ̂��u���[�L�ނ̂��T�d�ɂȂ炴��������A�����Ȃ�ڂɂ͂���r���̗Y��ȎR�x���i���قƂ�NjL���Ɏc��Ȃ��L�l�������B�����A���Ԃ⍂���Ȕ��p�i�̉^���Ԃ̉^�]�肽���̋C�����������Ƃ��킩��v�����������Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B���������ɒ������Ƃ��ɂ͂������ɂق��Ƃ����悤�Ȏ��悾�����B
�@ �n���ዷ�ł��n�ӂ���̊G�͓��肪����̂ł��邪�A���̂��т̌W�ł͉�L�ؗp���P�o����K�v�Ȃǂ������āA�ꕔ�̏���i�ɂ������Ă͈�ʂɂ��Еz����邱�ƂɂȂ����B���ɒ����V�������łȂǂł��W�J�Â����Ă���悤�����A�S���͈ꌩ�ɂ������A�܂��͓n�ӏ~��i�̑f���炵�����F����̈�l�ЂƂ�̖ڂł�������Ɗm���߂Ă��������������̂��Ǝv���B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N2��28��
���܂ɂ͉���Ȏ��ł�
�s�w偂ƒ��t
���ԂȂ���
�C�����Ă͂��Ȃ������̂ł��傤
�f�����̂悤�Ɏ��R�ɂ��Ȃ��̌����炱�ڂꗎ����
���肰�Ȃ����̌��t��
�s��������Ă������Ƃɂ́@�@
��Ă��܂��܂���
���܂�ɂ����C�Ȃ�
�c�X�Ƃ��Ėa��������
���̐��ł������v�Ȕ��̂��̎���
�����݂̒e���U�鉹�����Ă�
���߂������ɐꗎ����
���̂��߂Ă��̂��Ƃ܂���������邱�Ƃ̂Ȃ��܂܂�
�w偂����S�ɋ�̎����߂��炵�Ă���Ƃ���ł�
�d�����Ȃ��̐U�������@�@�@�@�@�@
�w偂ɂ���͖������邽�߂Ȃ̂ł�
�l��������ɂ�����͓̂V�̐ۗ��ɂق��Ȃ�܂���
����Ȓw偂͈��҂ł���
��̖Ԃɋߊ�钱��
���ł����C�ȋ]���҂ł���
�ꂽ�����镗�ɕ����܂�
�������Ɗ��ӂ̂Ȃ���
���ԂR�̑㏞�ł�
�܂��a���܂���
��ɐ�Ȃ��Ƃ���������
�܂��߂�܂���
�w偂ƒ��Ƃ̂����낵���s���R�ȋY���
���ƕ���Ɩ��҂Ƃ�����������ւ��Ȃ���@
�s ���@�@�� �t
�i�����Ⴋ��l�̂��߂Ɂj
�N���m��Ȃ��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
���������Ƃ��납��@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@
���̗��Ɉ�܂�ā@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@
�N�B�͂���Ă��� �@�@
�����ȓ������Ȃ���@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@
�N�B�͂��ꂼ��ɗ����Ă���
�����ďo�����₪�Đ������@�@�@�@�@�@�@�@�@
�����ւƑ����Ƃ������̂��܂���
��̌��ŏƂ炷���Ƃ��@�@�@�@�@�@�@�@ �@
�N���܂��҂��Ă������Ƃ̂Ȃ��Ƃ���
���̕s�v�c�ȓ��������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
���W�ɂ��Ȃ������
���Y������ł������߂Ɂ@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@
�₪�ėz�͒���
���ł��s������ނ��낤
��I�Ɉ߂��G��邾�낤
�Ⴉ�玞�Ԃ������Ƃ���
�����Ȃ��b���Ƃ��́@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�N�B��l�œ��������@�@�@�@�@�@�@
�����������������܂��@�@�@�@�@�@�@
������Ƃ����c�݂́@
�[�܂�ł̂��������Ł@�@
����镗�ɝ���Ȃ���
���Â��Ƃ��铔��
���̎��Ŗa������
�����ȏ����Ȏ�������@�@�@�@�@�@�@
�����ȏ����ȓ�������
�s�@���t�̉^���t
���t�ƌ��t��
�Ȃ��낤�Ɨd����������
�ӂ��̌��t��
�Ȃ��낤�Ƃ��đ��~��
���~���̂Ȃ����玍�����܂��
�Ȃ��낤�Ƃ���܂��ɂ��̂Ƃ�
���z�͋P������̎��݂ɉ�����
���͎��F�̃G���X�����
����������
�Ȃ��������t�̔߂���
�Ȃ��낤�Ƃ����������͂�
�s����������Đ˗͂ɕς��
�����w�̖@���̒ʂ�
�G�l���M�[�͕ۑ������
���݂����z�ɂ��܈�x�߂��͂Ƃ���
���t�ƌ��t�̌��іڂ�
���^�Ɨ҂����̋�Ԃ݂Ȃ���
�ЂƂ��тȂ��������t��
���̂܂܊낤���Ȃ����Ă���ɂ���
�܂��o���o���ɂȂ�ɂ���
����Ă܂��Ȃ����Ă����ɂ���
�ǓƂƉ��^�̒n���̂Ȃ���
�Y���Ă��������Ȃ�
���Č��������F�̌���
���H�Ƃ��Ă͂��܂�ɂ�������
�S�̂悤�ɑ����Â�
�̂悤�ɏd������������Ȃ���
��̌������������Ȕ����i�g�[�g���W�C�j�̎���
�܂̉��Ō㐶�厖�ɂÂ�Ȃ���
���߂����l���
����Ȍ��t�̗��ڂ̗��j��
�e�a�͂̔ߌ��ƌĂԂƂ���
��Ȃ���E�E�E�E
�s�@���@�� �t
���͕������@����������
�����āE�E�E�E
�����z�͒��݂����Ă���
���U�ɂ�����x��������
������x�������ނƂ������ւ��E�E�E
�L������������
�L�̑��z�͂ǂ�Ȑi�݂���������̂��낤
�ׂ̌���������Ɏ��R��~�������Ă���
���z�̕��݂��̂낢��
���ꂱ��\�N������ł���
���ɋ������悤�ȋC������
���R�����悤�ȋC������
�Ȃ�ɂ����Ȃ������悤�ȋC������
����Ȃ��̂��Ƃ����C������
���������璭�߂���
���̐��̋����ȗ��H�Ȃ�
�ǂ��������Ȍ��̓_
���Ǝ��̂͂��܂Ȃ�
���̗܂̂ЂƎ�
���Ȃ��͂�����N�w�҂ɂȂ����́H
�Ӓn���Ȑ�������
�ϖ̉Ƃ��o���o���ɂ���
�������V�тɂ����Ȃ������āH
�z������ł��܂������x�Ɛϖ͂ł��Ȃ����I
���̋�̑��z��
�}�ɓ��������߂Ă���
���F�͎₵�������
�H�v����ł͂܂��V�ׂʂ��Ƃ��Ȃ�
�ЂƂ�ڂ����̉B���ڂ��
�����̂ق����厖����
�R�������̂͂ǂ��̂ǂ����E�E�E
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N3��7��
�^�E�P�̐l�`�Ɏv��
�@ ����m�l�̉Ƃ�K�˂�ƈ�ڂ݂������ł���Ƃ킩��^�E�P�i�������䂤���j��̐l�`�������Ă����B�V�l�̎p���������ǂ����l�`���������A���ǂ��Ŗڂɂ��Ă��A���̐l�̎�ɂȂ�l�`�ɂ͌���҂��͂��Ƃ�����s�v�c�Ȑ��C���Y���Ă���B�^�E�P��̐l�`�̂���m��ʖ��͂Ɛ��݂ɂ��ẮA���D�̍����O�q���͂��߂Ƃ���ꕔ�̐l�`�ʂ����̊Ԃł����Ԃ�ȑO�����]���ɂȂ��Ă����悤�����A�\�N�قǑO�ɂ͍����e�n�̃f�p�[�g�Ȃǂō�i�W����Â���ꐢ���r�������Ƃ�����������A�悭�����m�̕��������낤�B
�@ �܂��������Ⴂ�̐��E�̂��ƂƂ����āA���͐l�`����Z�p�ɂ��Ă͉��ЂƂm���͎������킹�Ă��Ȃ��̂�����ǂ��A�ӂƂ������Ƃ���^�E�P�̐l�`�̕��d�����܂ł̗͂ɐS�ꖣ�����Ă��܂����l�Ԃ̈�l�Ƃ��āA���̍�i�̑f���炵���ɂ��ĉߋ��̋L���������Ȃ��班������q�ׂ����Ă��炢�����Ǝv���B
�@ �͂��߂ė^�E�P��i�ƑΖʂ����Ƃ��A�u�ԓI�Ɂu���̐l�`��������l�͂����낵���v�Ɗ��������Ƃ����܂��͂�����Ǝv���N�����B�ނ��A���́u�����낵���v�Ƃ��������ɂ͍ő勉�̌h�ӂ����߂��Ă���B�����̐��C����悤�Ȃ��̐l�`�̎����ɂ́A�����������l�Ԃ̐S�̉���l�ɂ��猩���Ȃ��Ƃ���܂ʼns���˔����͂��B����Ă�������ł���B�������A���̎����́A�s���ɂ�������炸�A�����邨����m���߂Ă݂�ƕs�v�c�Ȃقǂɉ������B�����ɂ́A���ׂĂ�������ݍ��ޑ�n�̂ʂ�����Ƃł������ׂ����̂�������������̂��B
�@ �^�E�P�Ƃ����l�́A�����Ȑl�`�t�A�ґ��W���T�u���[�ƁA����Ӗ��őΏۓI�ȑ��݂ł���ƌ����邩������Ȃ��B�a���ɒ������A�͂��߂Ă̑���ɂ��������v�킹��悤�ȕ����̏_�炩���ŁA�݂邩��Ɍ��t�D������肩���Ă��Ă����W���T�u���[�́A���͂��̓����Ɍ����đ��l�ɂ͋ߊ�邱�Ƃ̋�����Ȃ��s�������߂��l�ł�����B�͂��߂̗D���������̖{�����Ǝ��Ⴆ�Ĉ�����܂œ��ݍ������Ƃ���ƁA�����A�������A�܂��Ƃ��ɂ͓���悤�ȗ₽���Œe���Ԃ���Ă��܂����ƂɂȂ邾�낤�Ǝ��͊��������̂ł���B�̂̋g���̗V�f�Ȃǂ��e�[�}�ɂ������̐��X�̑s��ȍ�i�Q�����̂����畨����Ă���悤�ɁA�W���T�u���[�͂��̎��_���u�V�v�A���Ȃ킿�A���ɓI�ɂ͔ނɂ����߂Â��Ȃ��u����̍��݁v�ɂƂ�A�������璹�Ղ���鐢�E�̗L�l�Ƃ����Ő������X�̐l�Ԃ̉^�����A�l�`�Ƃ����������ɑ������݁A��̊���������ԂƂ��ĉ��o����B���������āA�V�˃W���T�u���[�ɂ��Ă͂��߂ē��B�\�Ȑ��E�ł��邩���ɁA�����͑��̒N�����ݍ��ނ��Ƃ�������Ȃ����E�ł�����B�@
�@ ����ɑ��āA�^�E�P�Ƃ����l�́A�����͂���߂Č��i���Ǎ��łǂ����ߊ�����������A�����ɂ���Ă͕����̂��̂ɂ����f��ɂ�������炸�A�ނ���ǂ����̓����Ɍ������ď������݉z���i��ōs���Ȃ�A�Ō�ɂ͋߂Â��ė���҂�S�̓��ʼn������}���ē��ꂭ���悤�Ȑl���ɈႢ�Ȃ��B���̐l�̎��_�́u�n�v�ɂ����āA�������琢�E�����グ�Ă���B��������D�����l�тƂ��݂���ł���B����A�ނ���A���̎��_�͐l�Ԃ̐g�̂̒��ɖ��܂��Ă���ƌ����Ă悢�B������ނ̐l�`�́A��̈�̂����ꂼ��̕����S�̌��t�Řb�������Ă���B���ꂼ��̐l�`�͂��ꂼ��̐l���������ɔw�����ė����Ă���B
�@ �Ⴆ�A���Ď����ڂɂ�����i�̒��Ɂu�lj��v�Ƃ�����Q�̐l�`���������B�����́A��l�̂܂��c�����ǂ����Ԃɂ͂����N�̕v�w�𒆐S�ɁA�V��A����ɏ��w�����獂�Z�����炢�̎c��ܐl�̎q���B�����E�ɔz������̑O�̉Ƒ��̐l�`�Q�ł������B���ʂɗ��ƁA��ЂƂ̐l�`�́A����A���̉Ƒ��̈�l�ЂƂ�́A���ꂼ��̐l���̌o���Əd�݂Ƃɉ������S�ƌ��t�Ō�����̂Ɏ���̑��݂�i����肩���Ă����B���ɂ͂������ɔނ�̐��������������A�����̊Ⴊ�����Ƃ���i�������Ă���̂������������B
�@ ���ꂾ���ł��������ƂȂ̂����A�l�`�Q�̌��ɉ�������͂���������������邱�ƂɂȂ����B�����̐l�`���ꂼ��̌�p���Ȃ�Ƃ������I����������ł���B�l�Ԃ̌�p�͂Ȃɂ����悭���̐l�����ƌ����邪�A������Q�̐l�`�̔w���̂ЂƂЂƂ́A���g�̐l�Ԃ̂���Ɠ��l�A���₻��ȏ�ɁA�[�����S�̍������������̌��t��Â��ɔ����Ă����̂ł���B�����Ȃ�Ɖ��ɉ���Ă݂����Ȃ�̂��l�Ԃ̐S���Ƃ������̂ŁA��Ҏv�f�ʂ�ɁA�����ł܂��͂��Ƒ���ۂ܂���邱�Ƃɂ��Ȃ����B���̓����܂łɐ��삳�ꂽ�l�`�̐��͂��悻�ܕS�̂ɂ̂ڂ�Ƃ������Ƃ��������A��̈�̂̐l�`���ǂ���Ƃ��Ă����ׂĂ������Ƃ����̂�����A�����������Q����ق��͂Ȃ������B
�@ �����܂ł���Ƃ����A�l�`�ȂǂƌĂԂ��́A�u�S�`�v�Ƃł��Ăق����ӂ��킵���̂ł͂Ȃ��낤���B���ʁA�G��A�����A�H�|�Ƃ�������i�͎ʐ^�ɎB���Đ}�łƂ��Đ��{����ƁA�ǂ�ȂɗD�ꂽ���̂ł����Ă�������������ł��܂����̂Ȃ̂����A�^�E�P�̍�i�Ɍ����Ă͕s�v�c�Ȃ��Ƃɂ����ł͂Ȃ��B���̐l�`�B�͕��Ȏʐ^�ƂȂ��Ė{�̒��ɕ����߂��Ă��Ȃ��A��������ɐ��C������Ă���̂ł���B����͂����������ł͂Ȃ��B�����ʂ�́u�S�`�v�̂Ȃ���ƂŁA���̂��Ǝ��̂��^�E�P�̍�i�̐�������������������Ă���ƌ������B
�@ �����܂ł�����͌l�I�Ȑ����ł͂��邪�A�^�E�P���A�ꎞ�����������ɂ��Ă����ґ��W���T�u���[�ƕʁX�̓�����ނ悤�ɂȂ����w�i�ɂ́A�����ɏq�ׂ��悤�Ȗ{���I�Ȏ��_�̑���ƕ\���@�̈Ⴂ���������悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B�ނ��A�ǂ�����ނ܂�Ȃ�˔\�̎�����Ȃ̂ł���A�\���̗��r�_�����݂ɈقȂ�̂ł��邩��A�����ł��̍b�����c�_���Ă݂��Ƃ���ʼn��̈Ӗ����Ȃ��B�����A�����g�́A����̐l���ςƂ̗��݂������āA�^�E�P�̍�i�ɂ��䂩���Ƃ��낪�����C�͂���B
�@ �l�`�Ƃ����ƁA���E�I�ɗL���Ȃ̂̓W�����[�ł���B���̃t�����X�l�`�̋ɒn�Ƃ������ׂ��W�����[�̐l�`�ɂ́A���I�ȍ��ɉ����Č����m��ʖL���ȕ\��Ƃ��܂₩�Ȋ�������߂��Ă���A������̂�s�v�c�Ȋ����ɗU�����ށB�^�E�P�̐l�`������Ɏ����Ƃ��낪�Ȃ����Ȃ��̂����A���l�Ƃ��ẮA���̖{���́A�ނ���A���_���₻�̒�q�̉�����R�A���������Y�Ƃ������A���R��`�̒����ƒB�̍�i�ɂɋ߂����̂ł���悤�Ɏv���B
�@ ���сA�߂��݁A�{��~�]�A�ウ�ƌ������悤�Ȑl�Ԃ̓��ʂ��A���g�̐l�Ԃ̂����ȏ�ɏՌ��I�ȃ��A���e�B�������ău�����Y�̒����ɑ�������̑�Ȓ����ƒB�Ɠ��l�ɁA�^�E�P�Ƃ����l�́A�z�n����ȑf�ނƂ����Ǝ��̐l�`�ɐl�Ԃ̐S�̉A�Ȃ��\�����Ƃ��Ă���ƌ����Ă悢�B�ʎ��ł͂��邪�A����͐S�Ƃ��̐S�̔����錾�t�̎ʎ��Ȃ̂ł���A�P�Ȃ�O�ʂ̐��I�Ȏʎ��Ȃ̂ł͂Ȃ��B������A���Ƃ��S�b�h�E�}�U�[�Ƃ������t�̈Ӗ���m��Ȃ��Ƃ��Ă��A�S�b�h�E�}�U�[�Ƃ����^�C�g���̂����l�`�̑O�ɗ��ƁA��X�͈�ڌ��������ŗL�������킳�����̌��t�̎��Ӗ���[���������Ă��܂��̂ł���B���ہA����͐������ƂɈႢ�Ȃ��B
�@ �^�E�P�͌����Ď����̐l�`����̋Z�@���B������͂����A������J���Č����Ă����炵���B�������A���̃J���`���[�E�Z���^�[�ȂǂŁA���N�ɂ킽���Ĉ�ʂ̐l�X��Ώۂɂ��Đl�`����̎w���𑱂��Ă������Ƃ����B���̂����A���̎w���͋ɂ߂Č����������悤�ł���B�e�ՂȂ��Ƃł͂���ƌ���Ȃ��B�f�ނ������Ă���킯�ł͂Ȃ��A�H�v���Â炵�Ă���Ƃ�������̂��g���B�C�E�X�q�E�o�C�I�����E�����h�Z���E���P�E�U�ށE�����E���ʁE�����n�̐��߂���e��ׂ̍��Ȏh�J�܂ŁA�{���̐���ƂقƂ�Ǔ����悤�ȍH���݂Ȃ��炷�ׂĂ������ō�点����B�������A������m���́A�{�����d���Ă�̂Ɛ������ʂ�肩���ō쐻��������B�����Ă��̂����A�d�オ�����l�`�͂���Ȃ�̐l����w�����A�S�ƌ��t�������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����炽������̂̍�i�����̂ɂ����r�����Ȃ����Ԃ�v�����������炵���B
�@ ���̒m�l�ł�����A�^�E�P�̒�q�ɂ����邠��V�w�l�Ȃǂ́A�V�l�̐l�`������Ă����Ƃ��A���̏����ȏ��{�����̂ɉ��x����Ă����Ȃ����𖽂����A���̂��߂ɂ����Ԃ����ԋꂵ�����ł���B����Ƃ����܂��܌������������Ȗ̑f�ނ��g���A����ɂ��낢���������Ă悤�₭�n�j����ꂽ�̂����������A���̐l�`�����������Ƃ��̏[�����͑�ςȂ��̂������Ƃ����B
�@ �����Ƃ���ɂ��ƁA�^�E�P�Ƃ����l�͎����̐��삵���l�`���P�[�X�Ɏ��߂��邱�Ƃ��ςɌ����Ƃ����B�u�ċz���ł����A�S�����R���Ă��Ȃ��Ȃ�A�l�`������ł��܂��v�Ƃ����̂����̗��R�Ȃ̂��������B�����̍�����l�`���l��ɓn�����ꍇ�ł��A�ނ͎��Ԃ��݂Ă͂��̉Ƃ�K�ˁA�����̔[���̍s���܂ŁA�`�̕����A�����ȃo�����X�A�ߗނ�t���i�̂�����Ƃ��������Ȃǂ����Ă܂���Ă������炵���B�l�`�̈�̈�̂��A�����ǂ���A��Ҏ��M�̕��g���̂��ɂȂ��Ă��邩��Ȃ̂��낤�B
�@ �l�`����̃y�[�X�́A���ρA��E��J���Ɉ�̂��炢�������悤�ŁA�[���������Ȃ��Ƃ��ɂ́A�N�Ɉ�̂��������Ȃ����Ƃ��������Ƃ�������A�܂��ɂ��̂ւ�͐̂̐E�l�C�����̂܂܂��ƌ����Ă悢�B�������A�l�`�̎��������ׂĎ��肾����A����Ƃ�����H�|�Z�p�̏C���ƌ��s������ɐς�ł���킯�ŁA���̋�J�͑z���ȏ�ɑ�ςȂ��̂������悤�ł���B
�@ �����Ԃ�O�Ɍ�����i�W�̓��킢�Ԃ�Ȃǂ��炷��ƁA�͂��߂ɂ͂ƂĂ��₩�����ɉf��̂����A�l�`����̃y�[�X�����q�ׂ��悤�ȋ�������A���Ƃ��Ƃ�����Đ��v�𗧂ĂĂ����l�ł��Ȃ��悤������A���ۂ̐����ʂ͑z���ȏ�ɑ�ς��������Ƃ��낤�B
�@ �ނ��A�f�B�[���[�̗U���ɂ̂��Ď������i���ǂ�ǂ��邩�����A�����u�t����������Đl��������ΐ����͊y�ɂ͂Ȃ����̂��낤���A��������ΐl�`�̂ق��͐S�Ɛ��C�Ƃ������Ă����܂�����ł��܂����ɈႢ�Ȃ��B�t�Ɍ����A���Ƃ��Ƃ����������Ƃ̂ł��Ȃ��C���̐l�����炱���A����قǂ܂łɐ����l�`�����o�����̂ł����āA����͂����A�|�p�̖{�����s���l�̏h���Ƃł������ׂ����̂ł���̂�������Ȃ��B
�@ �m�l�̘b�ɂ��ƁA�Ƃ����܃e���r�o�������Ƃ��ȂǂɌ����鉸�������ȕ\��^�E�P�̏�̕\��Ǝv������傫�ȊԈႢ�ł���Ƃ����B���i�l�`������Ă���Ƃ��́A���邢�́A�l�`�̍������q�����ɋ����Ă���Ƃ��̂��̎p�͋S���̂��ł���炵���B���̎w���̎d�����A�����̈ꗬ�E�l���ꋉ�̌|�p�Ƃ������ł���悤�ɁA������Ƃ������͗D�ꂽ���̂�������ۂɍ���Č�����Ƃ�����肩���ł���悤���B�ނ��A���x���킫�܂��Ă̂����̂��Ƃł͂��낤���A���낵���`���ʼns���m�~����Ƒ�ɓ˂��h�����ƂȂǓ��풃�ю��̂��Ƃ̂������炵���B
�@ �ꗬ�̌|�p�ƂƂ������̂́A�����ꏭ�Ȃ���F�����Ȃ̂ł��낤���A����قǂ܂łɐl�Ԃ̐S�̉������ʂ���������Ă���ƁA�ނ��날��Ӗ��ł͐l��{�s�K���Ƃ��v����B����������䂦�̕s�K�ł���B�����āA���̂悤�Ȉ�l�̓V�˂��A�V�˂̂䂦�ɔ����邱�Ƃ̂ł��Ȃ��s�K���A�S�g�S������߂č�i�ւƏ������悤�Ƒ��~���ꂵ���ʂƂ��āA�͂��߂āA���̂悤�ȗD�ꂽ�l�`�Q�A����A�S�`�Q�͂��̐��ɐ��܂�o�Ă���̂ł��낤�B
�@ �v�������Ȃ��ڂɂ����^�E�P��i�����ƂŁA���Ėڂɂ������̍�i�Q�̈�ۂ���邱�ƂɂȂ��Ă��܂������A���q�ׂ��悤�Ȃ��Ƃ͒P�ɐl�`�̐��E�ɗ��܂炸�A�|�p��ʂ̐��E�ɂ��ʂ��邱�Ƃł���悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N3��14��
�����������n�ӏ~�G��W
�@ ����l���ڊp���̑单����L�ōÂ��ꂽ�n�ӏ~�G��W�́A�X�^�b�t�ꓯ�̗\�z���͂邩�ɒ����鐷���̂��ƁA�Z���Ԃɂ킽�������I�����B�{���̃R�s�[��Ў�ɉ��K�˂Ă����������ǎ҂̕��X�����Ȃ��Ȃ������悤�ł���B�Ȃ��ɂ͓����n�ӂ�����T�|�[�g���Ȃ��珔�X�̎G���̂���`�������Ă������̎p��ڂɂƂ߁A�v���t�B�[���̎ʐ^�ƌ�����ׂȂ���߂Â��Ă��Đ��������Ă�����������������肵�A�Ȃ�Ƃ��C�p��������������ł͂������B
�@ ��L��Â̌W�ł͂Ȃ��A�݉�L����A�f�l�����l�����W�܂��ĉ^�c�ɂ�����Ƃ����^�j��̌W���������߁A���S�ǂ��Ȃ邱�Ƃ��ƃn���n�����������A���ʓI�ɂ͖]�O�̐��������߂邱�Ƃ��ł����B�����Ɏ������ő�̗��R�́A�Ȃ�Ƃ����Ă��A�n�ӏ~����̍�i�Q�̗L�������킳�ʔ��͂ƗދH�Ȃ鑶�݊��A����ɂ͂��ꂼ��̍�i�̔�߂���栂��悤�̂Ȃ��������ɂ������ƌ����Ă悢�B
�@�u�ق�Ƃ��ɗ��Ă悩�����ł��v�Ƃ��A�u�z�����Ă����ȏ�̑f���炵���ŁA�S�����܂�܂��o�Ă���v���ł����v�Ƃ��A�u�v���Ԃ�ŐS�̂ӂ邳�Ƃɖ߂����悤�ȋC���ł��v�Ƃ��������悤�Ȍ��t���c���ċA��������قƂ�ǂ��������Ƃ��A���̂��Ƃ��Ȃɂ����悭������Ă���B
�@ �����ۂ��ŁA�n�ӂ���̐l���ƍ�i�̑f���炵���ɋ���������v�V���e�����W�J�Â��ڂ����Ă��ꂽ���ƁA����ɂ͈ꕔ�̃��W�I�ǂ��W�̏��𗬂��Ă��ꂽ���ƂȂǂ������ւ̑傫�ȑ��|����ƂȂ����B�n�ӂ���̏ꍇ�A��s�s�ł̖{�i�I�ȌW�͍����߂ĂƂ������Ƃ������ċq���̐L�ы���S�z������������A�������������ӂ̉�L�ł̌W�Ƃ��Ă͈ٗ�Ȃ܂ł̐����Ԃ�ƂȂ�A��X�X�^�b�t�͊�т̔ߖ������Â���L�l�������B
�@ ��i���������̑����͂����ւ�Ȃ��̂ł������B�ߑO�\�����A�召�̍�i�Q�ڂ����ԓ���V���̋���l���ڊp�̘H��ɋ����ɒ��Ԃ��A�܁A�Z�l�̃X�^�b�t���o�ł����ӂ��Ɩѕz�Ŋ������ωׂ��~�낵�A��}���ő单���r�����K�̃M�������[�ɉ^�яグ���B�������Ȃ̂ɂ��킦�āA���Ԉᔽ�ŕ߂܂�Ȃ��悤�ڂ̑O�̌�Ԃ̓������C�ɂ��Ȃ���̍�Ƃ���������A�_�o���������Ƃ��̂����Ȃ������B
�@ ���Ȃ���͕S���O��̑�^��i�\�_���܂ގ�v��i�\���_���ǂ��W�����邩�������B�����낵�����ƂɁA�����͂��߂��̏�ɋ����킹�����l�̃X�^�b�t�́A������������ƂɊւ��Ă͂قƂ�njo���̖����҂��肾�����B����ȘA��������Ă������āA�����ł��Ȃ������ł��Ȃ��Ǝ��s������J��Ԃ��A���ڂ��Ȃ�����ŊG��ǖʂɔz���Ă����̂�����A�G�̂ق������Ă��܂������̂ł͂Ȃ������ɈႢ�Ȃ��B�������G�Ɍ�����������A�u�N�������Ă���[���v�Ɛ⋩���Ă������Ƃ��낤�B
�@ ���������A���������ɕR�肻�����ɂ��ĊG�̈ʒu���߂�Ƃ����m�b���͂��炩�Ȃ��������A�傫���̈قȂ�G����ׂ�ꍇ�ǂ�ȍ����łǂ��𑵂���̂��K���Ƃ����悤�Ȓm�����������킹�Ă��Ȃ������B������肩�A�G���x���݂邷���ނ̂܂Ƃ��Ȉ���������悭�͒m��Ȃ��L�l�������B���܂Ɏ����u�`�ɏo�������Ƃ̂���|��Ȃǂɂ͂��̓��̃v����������ł����邩��A���̋C�ɂȂ�Δނ�ɏ��������߂邱�Ƃ��ł����̂����A���N�l�̏Z�c�A��ؗ����j�̊�𗧂āA�f�l�̎肾���Ŗ������܂��Ȃ����Ƃ������S���Ƃ��Ƃ�ѓO���邽�߁A�����ĊO���ɏ��͂������Ƃ͂��Ȃ������B
�@ �������ŁA���܂��o�����X���Ƃꂸ�ɊG���X������A�ǖʂ��痣��ĕ����オ������A�������ɒ��߂��Ƃ��̒��S���������Ă��Ȃ�������A���ϓI�Ȏ����̍������炷��ƑS�̓I�ɊG�̈ʒu����ɂ�����߂��Ă�����ƁA�v���̐l��������ڂ𔒍������Đ�債�Ă��܂������ȗL�l�������B�G�ƊG�̊Ԃ̃X�y�[�X�̉�����G�̔z����肾�������A�Ɩ��̒������z�����Ă����ȏ�ɓ�������B���������̂���Ă��邱�Ƃ̖��d���ɋC�����ꎞ�̓G���C���ƂɂȂ����ƍ��f�����������A���͂�������݂������͂����Ȃ��A�ؗE���ӂ���ēːi����ق��Ȃ��������B
�@ �����A�Ύ���̔n���͂Ƃ͂悭���������̂ŁA�K���ɂȂ��Ă��ꂱ�����Ă��邤���ɖ��_�������Â�������A�Ȃ�Ƃ�����Ȃ�̗l�ɂ͂Ȃ��Ă����B�G���̂��̂̔��͂����O�ꂽ���̂ł������������ŁA�����̓W���Z�p�̕s���̓J���t���[�W������Ă��܂����̂���X�ɂƂ��Ă͍K���������B
�@ �傫�ȍ�i�̔z�u���I���ƁA�S�_�قlj^��ł�������i�̂����̂ǂ�Ƃǂ�Ƃ�W�����邩�̑I�ʍ�ƂɂƂ肩�������B��������i�S��������X�y�[�X�͂Ȃ�����A�Ƃ肠���������̒�����K���Ȃ��̓�A�O�\�_�قǂ�I��œW�����邵���Ȃ��B�Ȃ�Ƃ��W����i�����܂�ƁA����ǂ͍������قȂ邤���ɏc�������̂��̂̓��荬�����������̍�i������i�Ɍ��h���悭�z���ƂɈڂ����B
�@ ����i�̂ق��͕ǖʂɐ�p�s����ł����݂���Ɋz���̕R�������ČŒ肷��̂����A�r���ɂ̂�g���J�`���ӂ���Đ��m�Ŏ�ۂ̂悢�s���ł���Ƃ�����̂́A�o���̂Ȃ��҂ɂƂ��Ă͎v���̂ق�����B���ɓK���Ȑl�ނ������킹�Ȃ������̂ŁA���ǁA���̍�Ƃ͂��ׂĎ�����邱�ƂɂȂ����B�q���̍��A��B�̕Гc�ɂœ��X��d�������Ĉ�������ɂƂ��ẮA�����Ƃ���ŋ��Ƃ��ӂ���ēB�ނ�łȂǒ��ёO�̂��Ƃł���B��������Y�ꂩ���Ă����̂Ȃ���̋Z�p���v��ʂƂ���Ŗ𗧂��ƂɂȂ�A�������������䂢�C���ł͂������B
�@ �Ȃ�Ƃ���i�{�̂̓W����ƏI���A��i�����L�����|���̏��Ђ��X�̊G�̉��Ƀs���ŗ��ߏI�����Ƃ��ɂ͂�������������Ă����B���Ȃ݂ɏq�ׂĂ����ƁA����̌W�łƂĂ��D�]���������̊G�於�J�[�h�́A��B��H���ɂŐ�����q����Ƃ��������������|������Ŗ��h��ɂ�����A����ɓn�ӂ��於��M�����������̂������B���̂��ƁA���ꂽ���ԗނ�������A��t�̃e�[�u����݂��A��ꒆ���̗��q�p�e�[�u���̔z�u�⏔�X�̕K�v���i�̏����Ȃǂ��I�����Ƃ��ɂ́A�单���r���S�̂��܂�ߌ㔪�����肬��ɂȂ��Ă����B�����ʂ芊�荞�݃Z�[�t�������킯�ł���B�����������ł������Ă�����ǂ������W�J�ɂȂ��Ă������킩��Ȃ��B
�@
�@ ��������̌W�J�Ê��Ԓ��A��X�X�^�b�t�͊e�X�̖{���̎d�����x��őS�ʓI�ɃT�|�[�g�Ԑ���~�����Ƃɂ����B�������A�n�ӏ~��������a�̍��̒ɂ݂������ĉ��ɓ��Q�����q�̑�������Ă������邱�ƂɂȂ��Ă����B�������Č}�����W�J�Â̏����A�J�ꎞ���̌ߑO�\�ꎞ�҂�����ɂ܂��p�������Ă����������̂́A�Ȃ�Ə��`�Œm����̕�����҂̔���~�V���������B���コ��̖��O���F�����̑��ԖڂɋL�����ꂽ���Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B
�@ �����ɂ͂��̃A�T�q�E�C���^�[�l�b�g�E�L���X�^�[�̐ӔC�ҁA�����j�m�L���X�^�[�Ȃǂ̎p���������B�n�ӏ~����̌o�����Љ�邽�߂ɉ�X�����肵�����[�t���b�g�̈ꕶ�͌��������������̂ł���B�������t�߂ɂ́A�u���̒J�̂��̓y���A���̕��ɐ�����Đ��������v�Ƃ����n���̘e�ɖ앧��Y�����n�K�L��̏���i�O�A�l�_���|�����Ă����B���������ƁA���̍�i�̗����ɗp����ꂽ��͂́A�������炪�������n�ӂ���ɑ��������̂������B���܂�������Ȃ������Ƃ��낾�����n�ӂ���́A���̎��ȍ~�A����ꂽ��͂̈������Ɏg���Ă�����B�O���A�n�ӂ��璼�ڂɂ��̘b���Ă�����X�́A����܂藎���A����y�ςł���b����Ȃ��Ȃ��Ə�k�����������Ă������̂������B�����Ƃ��A�܂��������̂����ł͂Ȃ������Ƃ͎v���̂����A�����̏���i�͊F����Ă��܂�������A��������̎�ɂȂ鍏��͂���Ȃ�ɉ��N�������̂����m��Ȃ��B
�@ ��������̘b�ɂ��ƁA�n�ӂ���ɑ���������́A�S�Z�Ƃ��ɂ����Ƃ��[�����������ɒ��������̂Ȃ̂������ł���B�Ȃ�قǂ����������̂��Ƃ�������͔[�����������̂����A���̂��Ƃ����A���́A�����̎茳�ɂ����̈�͂̂��Ƃ�z�����������B��͂茊���j�m�������Ă��ꂽ���̂Ȃ̂����A���̈�͂̂ق��͂����l�������Ƃ��X�����v��Ԃɂ������Ƃ��ɒ���ꂽ���̂ł���炵���B��������̌����璼�ɂ��������Ă��邩�炻��͎����ɈႢ�Ȃ��B
�@ �b�͘e���ɂ���邪�A���ݎ��́A�u���e�v��⽍����ꂽ����̂ق��������ς爤�p�����Ă�����Ă���B�����Ƃ��A���̈�́A���q�ׂ��悤�Ɍ�������̃X�����v���̉��O�����ׂď��ڂ����V�����m������A���̐�䂪�g�ɂ͉����N���邩�͂킩��Ȃ��B�����A�K���Ƃ������Ȃ�Ƃ������A���͕��������̓��X���͔g��������D�ރ^�C�v�̐l�ԂȂ̂ŁA���̓_���̈�͂Ƃ͖��ɑ����������炵���A����܂ł̂Ƃ���͂��܂�������g�����Ȃ��Ă��Ă͂���B���܈�̈�͂̂ق��́A���܂ɉB��Ďg�����̃y���l�[���������̂ŁA�ꌩ�����Ƃ���o���͂�����̂ق��������Ƃ悢�����ł���B�����A���̂Ԃ߂�ꂽ���O�̓x����i�Ƌ������Ȃ̂ŁA����������ɂȂ��ăy���l�[���𑽗p���鎞��������g�����Ǝv���A�ډ��̂Ƃ���͊��̈��o���̉��Ɍ��E���āi�H�j�������߂Ă���B
�@ ��������ƑO�サ�āA���T�������̕ҏW�ψ��߂Ă���R�{���j��������Ɍ��ꂽ�B���N�قǑO�A�����T�������ʼn���\�O�ʏ͂Ƃ����A�ڃR���������M���Ă����Ƃ��A���̒��ڂ̒S���L�҂������̂����������̕��ҏW���߂Ă���ꂽ���̎R�{�������B���Ȃ݂ɏq�ׂĂ����ƁA�����̏T�������ҏW���������j�m����ł���B���̂Ƃ��̘A�ڃR�����̑}�G��������ēn�ӏ~����ɒS�����Ă��炤�悤�ɂ����W�ŁA����l�����ڊ�����킹��͍̂����߂Ă���������ǂ��A���ȂȂǂɂ��𗬂͂��������Ԃ�ƒ����ɂ킽���Ă���B
�@ �����̊J�꒼�ォ��r��邱�ƂȂ����X�ɗ���҂����������߁A���̗[���܂łɂ͗p�ӂ����F�����̃X�y�[�X���c�菭�Ȃ��Ȃ�A�n�ӂ�����Љ�����[�t���b�g������������ȏɂȂ����B������肩�A�n�ӂ���̃G�b�Z�C�W�u�R�������L�v�������܂��i�ꐡ�O�Ƃ����\�z���Ȃ��W�J�ɂȂ��Ă��܂����B�����܂łɂȂ�Ƃ������̕�[�����悤�ƃX�^�b�t�ꓯ�������ӂ��Ƌ킯�����������Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B
�@ ����ڂɂ͓n�ӂ���Ƃ̌𗬂̒������D�̕l���}����̎p������ꂽ�肵���B���̓��̗��K�҃��X�g�̒��ɂ́A�j���[�X�X�e�[�V������A�T�q�E�C���^�[�l�b�g�E�L���X�^�[���ł�������݂̒����V���ҏW�ψ��̐������F����A�����������V���̘_���ψ��̍����^���q����Ȃǂ̖��O������ꂽ�B���ӂ���Ƃ��Ɏ��̌l�I�Ȓm�l�ł͂��邪�A�����Z�Ȏd���̍��Ԃ�D���Ă̗��ꂾ�������Ƃ��v���ƁA�͂��n�Ӎ�i�̂��s�v�c�Ȗ��͂̂Ȃ���Ƃ������ɈႢ�Ȃ��B�n�ӂ���Ƃ̒����ɂ킽��G�莆�����̂��Ƃ��V���ł��Љ��]���ɂȂ����s�������ݏZ�̏��w���A�X���݂̂肿����炵���p�������Ă��ꂽ�̂����̓��̂��Ƃ������B���X�Ɍ���闈�K�҂̉��ɂ��肫�蕑�����Ă����n�ӂ���̖j�������ɂ̂͂ނ��̂��Ƃł���B
�@ �O���ڂ���ŏI���ɂ����Ă̎l���Ԃ͐l���l���ĂԊ����ƂȂ�A���̑Ή��œn�ӂ������X�X�^�b�t�ꓯ���A�H�������邱�Ƃ͂��납�A������t�����ɂ͈���ł����Ȃ��ɂȂ����B�\�������v���̉�Ƃ�e���ʂ̗v�l�Ȃǂ̗���������Ԃ�Ƃ������悤�����A�k�C���Ⓦ�k�A�����ʂȂǂ���͂��K�˂Ă��Ă���������X���������ɂ̂ڂ����B��x���O�x�Ɖ��ɑ����^��ł����������������Ȃ��Ȃ������悤�ł���B
�@ �ŏI���̓��j���͌ߌ�������ɃN���[�Y�������ƁA�����ɉ��̐����ƍ�i�̔��o��ƂɎ�肩�������B���Ă̋����q�����𐔐l��`���ɌĂ�ł������̂ŘJ���͂ɂ͎������Ȃ��������A���̂��ƓԂقǂł��ׂĂ̊֘A���ނ�Еt���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����āA�Q�������Ƃ��̂����Ȃ������B�W����i�͎ዷ�̓n�ӑ��^�яo�������Ɠ��l�ɖѕz��N�b�V�����ނł��̕\�ʂ���������ƕ������݁A�X�^�b�t�̈���ւ���̃V�{���[�Ǝ��̃��C�g�G�[�X�Ƃɕ����Ē��J���T�d�ɐςݍ��B
�@ ���ɏ���ꂽ�召���X�̍����Ȍ��Ԃ�A���̍T�����ɏ������Ɛςݏグ��ꂽ���َq���̑��̑���i�̎R���ǂ����邩�������肾�����B���ǁA���ԗނ̂ق��͂��̏�ɂ����F�œK���ɕ��S�������A���Ă��炤���Ƃɂ������A�������̂����ɁA����Ɏ����A���Ă��炤�Ƃ͂����Ă��A�^���p�̎Ԃ��p��̂Ȃ����͂Ȃ��Ȃ���ςȂ��Ƃ������B���َq��H�i�ނ͕ۑ��̗������̂Ƃ����łȂ����̂Ɏd�����A�ۑ��̗������̂͂܂Ƃ߂Č���ԂŎዷ�܂ʼn^�Ԃ��Ƃɂ��A�ۑ��̗��������ɂȂ����̂́A�n�ӂ���̈ӌ��ɂ����Ă�͂肻�̏�ɂ����ĊF�ŕ��z���A���ꂼ��̉ƒ�Ŗ𗧂ĂĂ��炤���Ƃɂ����B
�@ �呛���̂����ɁA�Ȃ�Ƃ����ׂĂ̓P����Ƃ����������̂͑单���r�����܂�ߌ㔪�����肬�肾�����B�听���̂��Ɖ���������I������Ƃ������g���ƁA�ْ��̘A���̗��Ԃ��Ƃł������ׂ����E���Ƃ��������A�n�ӂ���������ĉ�X�X�^�b�t�ꓯ���A�����Ȃ�Ƃ��`�e�����ȋC���ɏP����L�l�������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N3��21��
����n�ݎ��\��ʊω�
�@ �ዷ�ւƌ������r���A�ւ����C���^�[�`�F���W�Ŗ��_���������~��A�����O�Z�܍����ɓ������B�̓��ɑ������Ȃ���̘e�����s�Ȃɑ�����Ă̂��Ƃ������B��ɕ���ꂽ�ɐ��R�̘[���A�o��̍���Œm����o�������A�D�c���ɔs�ꂽ���i�������j�����̋��鏬�J��̂��������J�R���E��Ɍ��Ȃ���ؔV�{���ʂւƖk��𑱂��Ă���ƁA����\��ʊω��̂���n�ݎ��i�ǂ����j�ω����̓����������W�����ڂɔ�э���ł����B��������͂��̏ꏊ���S���[�g���قǒʂ�߂����̂����A���N�̂����ɔ|��ꂽ�k�o���͂��炢�����Ƃ������āA�����Ɉ����Ԃ�������K�˂Ă݂邱�Ƃɂ����B
�@ ���̍����͂���܂łɉ��x���ʂ������Ƃ�����̂����A�����ɂ��n�ݎ��\��ʊω��̑��݂������Ƃ��Ă����̂ł���B���̂�����͎Ԃ̒ʍs�̏��Ȃ�������̑���₷�����ł��邽�߁A���������ő��蔲���邱�Ƃ��������A����܂ł��̕W��������̂ɋC�Â��Ȃ������̂��B����͂��܂��Ԃɓn�ӏ~�攌�̋M�d�ȊG���i�Q�ڂ��Ă����W�ňӎ����Ă������Ƒ����Ă����̂����A�t�ɂ��ꂪ�K�������悤�Ȃ킯�������B
�@ ���i�Ζk�݂Ɉʒu���邱�̍������̓n�ݎ��\��ʊω��ɂ��ẮA���{�����̍�i������̏\��ʊω��I�s�Ȃǂ�ʂ��Ĉꉞ���̑��݂����͒m���Ă͂����̂����A�Ȃ�������܂Ői��ŖK�˂Ă݂悤�Ƃ����v�����͂��炩���A���̂܂܂ɂȂ��Ă����̂ł���B
�@ �\��ʊω��Ƃ����ƁA�H�����l�̍��Œm����̐l��Ô��ꂪ�A
�@�@�ӂ��͂�@�́@���ق��@�������@���@�����݁@�Ɂ@
�@�@���Ђ݂�@���Ƃ��@�������@�����т�
�Ɖr�ޗǖ@�؎��̏\��ʊω����L���ŁA�t����ɉ�Ô���̉̂ɌX�|���Ă������Ȃǂ́A����̎������W�Ȃǂ�Ў�ɖ@�؎���K�˂��̑����q�����������̂ł���B���ݍ����ɂ͘Z�̂̍���\��ʊω�������̂����A�����̂Ȃ��ł��������ɂ����Ă͈�A��Ƃ����邠�̖@�؎��\��ʊω��̌�������ƕ����n�݂̊ω�����q�ςł���̂́A���R�̐���s���Ƃ͂����A����Ă��Ȃ����Ƃł������B
�@ �n�ݎ��e�̒��ԏ�ɎԂ�u�����̋����ɓ���ƁA�Ђ���Ƃ�����C���S�ْ̋��𑣂��ł����邩�̂悤�ɗ��j�ł��B�O�����߂̂��ƂƂ����āA�����ɐl�e�͂قƂ�ǂȂ��B�ꌩ�����Ƃ���ǂ��ɂł����肻���Ȃ��̂����ɁA�����ȍ���\��ʊω����ق�Ƃ��Ɉ��u����Ă���̂��Ƃ����v�������Ȃ�悤�ȊՎU���ł������B���̗l�q���ƁA���Ƃ��ό��V�[�Y���ł����Ă����K�҂͂��������͂Ȃ��̂ł͂Ȃ��낤���B
�@ �������ʂ̑���Ƒ傫���̖{���e�̎�t�Ŕq�ϗ����ƁA�����ɍ��艜�ɂ���ω����ւƈē����ꂽ�B��q����l�قǂ�����������Ⴂ�ɂȂ����̂ŁA�����ɓ������Ƃ��ɂ͈ē����̒n���̌ØV�炵���l�Ǝ��̓�l�����ɂȂ����B�����̒����ɂ͏d�v�������ّ̑��E����@�����������u���ꂢ���B�����āA���̌������ĉE��ɗ��̂����ړ��Ă̏\��ʊω����ɂق��Ȃ�Ȃ������B�@�����������ɔz����Ă���̂́A���l�̊i�Ƃ��Ă͕�F�����@���̂ق�����ʂɂ��邩��Ȃ̂��낤�B��F�Ƃ́A�䂭�䂭�@���ɂȂ邽�߂ɏO�����~�ς���s��ς�ł���C�s���̂��ƂŁA�������ߖ��ӕ�F��ω���F�͕�F�Q�̂Ȃ��̗D�����Ƃ������Ƃ���ɂȂ�킯���B
�@ ����@���̑O�ɍ�����ʂ�ØV�̐����Ɏ����X�������ƁA���͂����ނ�ɍ����グ�ď\��ʊω����̑O�ɗ������B����͑z�����͂邩�ɒ������A���ɔ������ω����ł������B�Ȃ�قǁA�@�؎��̏\��ʊω��̌�������ƌ����邾���̂��Ƃ͂���B���₩�ȕ\��Ɨ��킱�̂����Ȃ��������܂��̉��ɗh�邪����C�i�Ƒ��݊���X�������̊ω������A�ޗǂł����s�ł��Ȃ��A���i�Ζk�݂ɋ߂��������Ƃ��������Ȓ��̈���ɂ����āA��S�\�N�ɋ߂��Ό����ē`�����ꑱ���Ă������Ƃ͕����ʂ��Ղɋ߂����Ƃ̂悤�ɂ��v��ꂽ�B
�@ �����S��\�l�Z���`�A�w�̈�ؑ���̌����Ȋω����́A���`�ɂ��ƁA�V�����N�A���̓V�c��菜�ЋF���̒������������m�א����F������߂Ē���グ�����̂��Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B�����A���Ƃ̏ڂ��������ɂ��A���ۂɂ͖@�؎��̏\��ʊω��Ɠ������A���������̒�ς̍��ɑ���ꂽ�������ϗl���̕����̌���ł���炵���B
�@ ���̍����ɏグ��ꂽ����̒��w�A��w�A�e�w�̎O�w�͐��r�̒�����ɂ��邭�܂�߂ēY��������A�c��̐l�����w�Ə��w�̓�w�͗D���Ȃ������ŗ��Ă��Ă���B�܂��A�����ۂ��̉E��͑̂̑��ʂɓY���悤�ɂ��Ď��R�Ȋ����ʼn����ɐL�сA����A���]�A�����̎O���̐[�����܂ꂽ��̕��̐�ɂ��w�͂�������܂������ɒn���w���Ă���B���r���x���鍶��̐e�w�ƒ��w���ւ𐬂��ĐG�ꍇ���Ă��邱�Ƃ���A�����Ĉ�`�ɂ������������������Ȃ�A���i�����i���イ�ڂイ�����j�̈�̃f�t�H�����Ƃł��������ƂɂȂ�̂ł��낤���B
�@ �����獘�ɂ����Ă̖L���ȑ̂̐�������������ǂ��A����ɂ�������d���Ȃ܂łɈ������Ăċ������Ă���̂��A�����ɂ��Ȃ�傫���Ђ˂�ꂽ�����̑��肾�����B���������̍����̏G�킱�̂����Ȃ��Ђ˂�́A���̑��S�̂̈��芴������ǂ��납�t�ɂ����[�߂������Ă����B��҂��͂��߂���f�ނ̌`��ɂ������Ȃ��Ӑ}�������̂Ȃ̂��A��ؑ���̂䂦�f�ނ̌`����������ׂ����Ă��̂悤�Ȃ������Ɏd�オ�������̂Ȃ̂��͒m��悵���Ȃ��̂����A���Ɍ����Ȃ��̂ł���B������A�����ėD���������悤�ɑS�g��������މH�ߗl�̓V�߂��@�ׂł݂�тȂ��Ƃ��̂����Ȃ����̂������B
�@ ����͂Ƌ����ƁA�v���̋F������߂��Җڂ��邩�̂悤�Ȑ꒷�̗��̔�����A�[���Ȕ�����@�ւƑ�����{�̏G��ȋȐ������Ε�ނ悤�Ɉ͂�ł���B�܂��A�@�����\��������̓M���V�������̂���̂悤�ɒ[��ŁA���������͂�����ƕ����o�������͏����������ƈ������܂�A���₩�ȂȂ��ɂ��X������X�����\��S�̗̂v�i���Ȃ߁j�̖�������������Ɖʂ����Ă���B�ӂ�����Ƃ������j�͊�̕\��S�̂ɉ~�₩���������炵�Ă���A�����Ƃ̋����Ȃ��z�̐��͕ω��ɕx�݂������_�炩���̂����Ȃ������������B
�@ ��ʂɏ\��ʊω����͓������̕�韁i�ق������j�ɏ\��̉����A���Ȃ킿�����ʂ������Ă���B�ڂ����q�ׂ�ƁA�O�����ɕ�F�̎��߂�\�킷�O�̕�F���ʁA�������ɕ��{�̌`���������O���ѓ{���ʁA�E�����ɉ���o�����`���̓������O�̋��o���ʁA�㓪���ɂ͑�����Ă��鑊�̈�̖\����Α��ʁA�����čœ����ɂЂƂ���傫���V�ɓ˂��o���悤�ɔ@�����̕��ʈ�ƁA���v�\��̏����ʂ��z����Ă���B�{�ʂ�����Ə\��ʂƂȂ�킯�����A�Ȃ����\��ʊω��Ƃ͌Ă�Ȃ��B�\��ʊω��M�̓T���ƂȂ�u�����\��ʊϐ����_��o�v��u�\��ʐ_��o�v�ɂ��A���̌`��ɂ��ē����ɂ��q�ׂ��悤�ȏ\��ʂ̏����ʂ�Ղ��Ɛ�����Ă���悤������A�������͕���������Ă��݂Ă��͂��܂�Ȃ��B
�@ �Ƃ��낪�A���̓n�ݎ��̏\��ʊω��͂Ȃ��������̐��₻�̔z�u�ł��^�j��̑��݂Ȃ̂������B�O�����ɂ͎O����ׂ���F���ʂ�������Ȃ��B���̂���肻����̕�F�ʂ̊ԁA���Ȃ킿�{�ʂ̒��S��������Ɉʒu����Ƃ���ɁA�悭���Ȃ��Ƃ���Ƃ͔���Â炢�����Ȕ@����������̔z�u����Ă���B�܂��A���������ɂ͓���ѓ{���ʂ��z����A�c�����ѓ{���ʂ͍����̌�둤�ɒ���������Ă���B���l�ɉE�������͓�̋��o���ʂ����ђu����A�c���̋�告�ʂ͉E���̌�둤�ɓY�����Ă���B����ɁA�\����Ζʂ͖{�ʂ̐^���Ɉʒu���镶���ʂ�̌㓪���ɒ��荞�܂�Ă���̂ł���B�������A���̖\����Α��ʂ͎��ɕ\��L���ŁA���̙��Ԃ�͍����Ȃ��Ƃ��̂����Ȃ����̂������B�������Ԃɂ��Ȃ�傫�Ȍۗl�̎����肪���Ă���̂����ɂƂ��Ă͂Ȃ�Ƃ��ӊO�Ȃ��Ƃ������B�����炭�͂ǂ�������̕����̉e����\�����̂ł���ɈႢ�Ȃ��B
�@ �{���͔@�����ł���ׂ����㒆���̒��㕧�́A����܂����̂��@���`�ł͂Ȃ���F���ʂɂȂ��Ă����B���̏\��ʊω����ɂ������鐳�ʂ̏����Ȕ@�������͂�������ł͂Ȃ�����A�����̐��͍��v�\�ŁA�{�ʂƍ��킹�Ă��ꂼ�܂��ɏ\��ʊω��ƌ����������Ȃ�̂����A�j�i�͂����܂ł��j�i�Ƃ������ƂɂȂ�̂��낤�B�����A����Ȍ^�j��̍\���������䂦�ɁA���̏\��ʊω��̉����͑��̏\��ʊω����̂��̂Ɋr�ׂĈ���傫���\����L���Ő��C�ɖ��������Ă����B�������X�̉����̕�韂͍����傫������オ��A�������̂̑��݊����ЂƂ���傫�Ȃ��̂ɂ��Ă���̂������B���ꂼ��̉����̕�韂̑O�ʂɌ�������@����������̂����荞�܂�Ă���̂������I�������B
�@ �����ۂ��A��������@���ɗ�������������Ă����ƐL�т闼�r�̃��C��������ۂނقǂɔ����������B�ϐ��̂Ƃꂽ���̊ω����̋r�����̔w��ɁA����܂������ٍ��̕����̉e���F�Z����������ł���̂͑f�l�ڂɂ������Ȃ��Ƃ������B����ɂ��Ă��A�ω����{�̂͂������A�@��̘@���̈ꖇ�ꖇ�ɂ�����܂ł���ؑ��肾�Ƃ����̂�����A����͂����B�X�����̈��ɐs�����B
�@ ���Ƃ��Ƃ͑S�g�������ŕ����Ă����̂ł��낤���A���܂ł͐��r��V�߂̈ꕔ�Ȃǂɂ��̖��c�������邾���ł���B�����N���̐�����āA�S�̓I�ɂ͉��n�̍������\�ʂɂ�����A�u�����Y���̏d���ȋP���ɂ����������ō����肵�Ă���̂����A���ꂪ�܂����̏\��ʊω��Ɍ��t�ł͌`�e����i�i�Ɛ������Ƃ������炵�Ă���悤�ł��������B
�@ �\�\���͒��ڂɂ͂��Ȃ������l�Ԃ̋�Y���~�����Ƃ͂ł��܂���B�ł��A���Ȃ������ׂ̊�����̐��X��Ƃ��ł��낤���X�̉߂��́A������������Đӂ߂��肹���A���ׂĂ��m�肵�Ă����܂��傤�B�����āA�i���̔��݂Ǝ���������Ă��Ȃ������̐������܂ł������A���̓��s�����F��]���Ă����܂��傤�B�܂�Ƃ���A������̂͂��Ȃ��������g�ɂق��Ȃ�Ȃ��̂ł�����\�\�����̂����ɂ���Ȍ��t����肩���ł����邩�̂悤�ɂ������ނ��̍���\��ʊω��ɂ́A�������Ȃ���A�B�ꂽ���̗��j����߂��Ă����̂ł���B�l�Ԃ̋Ƃ̐��݂����炵���헐�̉Q�̒��ŁA���̑��͐�ɐg���ł����Ď��̊�@�ɂ��炳��Ȃ�����A�����ߎS�ȏւƒǂ����Ă����������Ȑl�Ԃ̂��߂ɂЂ�����~�ς̋F����������Â��Ă����̂ł������B
�@ ���T���N�i����Z�N�j�A�D�c�M���͏��J����䒷�����U�߂��B�����Ďo��̍���Ƃ���ɑ������J��U�h�̌���̂Ȃ��ŁA�Ζk��тɈʒu���鐔�X�̌Ù��̓��F���Ă������A���̎��̂̂قƂ�ǂ͎��X�ɖv������Ă������B�M���̓{��������Ă�����b�R����̎P���̓n�ݎ��ɂ��̖@��瓦��邷�ׂ̂��낤�͂����Ȃ��A���F�͂��Ƃ��Ƃ��D���ɋA���A�n�ݎ����̂��̂��p�ł����B
�@ ���̐헐�̂��Ȃ��A���̏\��ʊω���[���M���Ă����n���̖��O�����́A�������F���P���̂����̂Ƃ������҉�`���ē��F�ɓ���A�ω�������o�����Ɠ`�����Ă���B�������A�Ȃ�Ƃ��~�o�͂������̂́A�����D�c�R�����̖ڂ���B�����ꏊ���Ȃ��A��ނȂ����ēy���ɖ������ω��j��̖\������������̂��Ƃ����B
�@ �D�c�M���Ɛ�䒷���Ƃ����A���j�h���}�Ȃǂɂ����Ă͏�ɋH��̉p���Ƃ��Ċi�������`���o����闼�Y�ł͂��邪�A����̐����Ƃ����̂قƂ�ǂ������ł���悤�ɁA�����炭���̎����́A���ƂȂ�����тɏZ�ޖ��O�̂����₩�Ȑ�������X�̌h�i�ȋF��ɂ͂��悻�����ȑ��݂ł������ɈႢ�Ȃ��B���̎�������E�����Ƃ�����ނ�̐킢�̈Ӌ`�͎l�S�N�]�̍Ό��̂Ȃ��ł��͂╗�����Ă��Ƃ𗯂߂��A�ނ�ɂƂ��Ă͖��Ӗ��ɉ߂��Ȃ������낤���O�̊ω��~�o�Ƃ��������₩�Ȓ�R�s�ׂ̂ق��́A�����N���̂̂��̂��Ƃł͂��邪�A���ʂƂ��āA���̍������E�Ɍւ镧�������ƕ����|�p�̈ێ��ۑS�ɏ��Ȃ��炸��^����Ƃ���ƂȂ����̂ł���B���j�Ƃ������͎��ɔ���Ȃ��̂��ƌ����ق��Ȃ��B
�@ �헐�������܂������N�A����e������т�̂���ɋy��ŁA�h�����ĉJ�I����������x�̂����₩�Ȃ������݂���ꂽ�B�����āA�y������@��N�����ꂽ�\��ʊω����͂����Ɉ��u����A���̂قƂ�ǂ̐l�ɂ͒m���ʂ܂܁A��X�n���̖��l�̎�ɂ���Ď��`�����Ă����悤�Ȃ킯�������B�������قƂ�ǔ������A�����̒n�h�肪�\�ʂɏo�Ă��Ă���̂��A���̂悤�Ȕw�i�����������炾�ƌ����Ă���B
�@ ���̓��X�ɑς��A�����s���̎���k���i�ΔȂ̒n�łЂ��₩�ɑ����Ă������̊ω������H��̋M���Ƃ��č����]������A�L�����ɒm����悤�ɂȂ����̂͂��Ȃ�ߐ��ɂȂ��Ă���̂��Ƃł������B�ޗǂ⋞�s�̍����Ȏ��@�ɂ����Đ̂��炻��Ȃ�̈����������Ă������̍���\��ʊω����ȂǂƂ͂��̓_�ł��傫���قȂ��Ă���̂ł���B������\��N�̋{�����S���撲�ǂ̒����ł͂��߂Ă��̐^�������o����A���{���w�̗쑜�Ƃ��ď̎^�����悤�ɂȂ����B�����āA�����O�\�N�ɂȂ��Ă悤�₭����̎w����������̂ł���B���ꂩ�炸���Ƃ̂��̑吳����ɂȂ��Č��݂̊ω����̂��ƂɂȂ錚������������A���a��\���N�ɐV����Ƃ��čĎw���������ɋy��ŁA���̊|���ւ��̂Ȃ����l�����炽�߂Đ[���F�������Ƃ���ƂȂ����B�����āA�K���Ȃ��ƂɁA����ȍ~�͑����̂����날��l�X��Ō����J��`�����Ă����̂ł���B
�@ �ӂƂ����������������ƂŁA���̑f���炵���\��ʊω����ɂ߂��肠���邱�Ƃ��ł������́A���̍K�^��������߂Ă��݂��߂Ȃ���A�n�ݎ��̎R������Ƃɂ����B���̂��ƍ���������ؔV�{���o�Ĕ��i�̖k�݂��܂��A���Â��狌�I�X���ɏo�ď��l�ɔ����A�[���ɓn�ӂ���̑҂�B��H���ɂւƓ��������̂����A���̊ԁA���͌J��Ԃ����肩�����n�ݎ��\��ʊω��̔������ƕs�v�c�������݂��ߑz���N�����Ă����B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N3��28��
�]�O�̐�i�F�ɐ���
�@ ����ŊJ���ꂽ�n�ӏ~�G��W�̓W����i�̈ꕔ���ዷ��ђ��̓n�ӂ���̂���܂ʼn^�сA�������ԋp���ċA�r�ɂ����̂͗[�������낾�����B��ȊG���^�яI�����ׂ̉����낵�������������āA�A�H�͂������ɋC���y�ɂȂ����B���l���߂��A�㒆�����獡�Õ��ʂւƔ����鍑���O�Z�O�����ɓ���A�F��h�ɂ��������鍠�ɂȂ�ƁA�}�Ɍ��������C�ɏP��ꂽ�B����܂ł̓�T�Ԃقǂ����������n�[�h�ȓ��X�̘A�����������Ƃ������āA�C���ɂr�[�ɂǂ��Ɣ�ꂪ�o�Ă������̂炵���B�����A����}���K�v������킯�ł��Ȃ������̂ŁA���F��h�̌Â��X���݂ɋ߂����̉w�ɎԂ𒓂߁A�����������Ƃ邱�Ƃɂ����B
�@ ���{�C���Ղ̗v�ՂƂ��Č×��������ዷ���l����A�㒆�����o�Đ��⓻�Ɏ���A���݂̍����O�Z�����ɂ����鋀�؊X�����ċ��s�ւƑ��������́A���āu�I�X���v�Ƃ��Ăꂽ�����^���̎�v���ł������B�I�X���͓��{�C���ݎY�̏������̏W�ϒn���l�Ƌ��s�Ƃ��ނ��ԍŒZ���[�g�ŁA�ዷ��т̊C�Ő��g�����ꂽ��ʂ̎I��e��̐V�N�ȊC�Y���ނ����̓��`���ɋ��s���ʂɑ��荞�܂�Ă������߁A����ȕ��ς��Ȗ��������B
�@ �Ǎ`�Ɍb�܂ꂽ�։�Ə��l�́A���{�����̏��̎��ォ�璩�N�����𒆐S�Ƃ����嗤�Ƃ̌𗬂̌����Ƃ��āA�܂��A���{�C�����e�n�̕����╶���A�����Y���̒��p�W�ϒn�Ƃ��đ傫�Ȕ��W�𐋂��A���j�ɂ��̖��𗯂߂Ă����B�։�Ə��l�͒n���I�Ɍ��Ă��A�W�ς���������ޗǂ⋞�s�A��g�Ái���p�j���ʂɉ^��A�t�ɓޗǁA���s�A��g�ÂȂǂ���^�э��܂ꂽ��������{�C���݊e�n�≓���嗤�Ɍ����đD�ς݂���̂ɂ���߂ėL���Ȉʒu�ɂ������B
�@ �։ꂩ��̏ꍇ�A�������͗��H�ɂ���Ĕ��i�Ζk�݂̉��Õl��ؔV�{���ӂɉ^��A����������i�̐��^�𗘗p���Ĕ��i�œ�[�̐��c�t�߂ւƉ^�����ꂽ�B��M�ɂ�鐣�c����̐��^�͗���̎x���ł���F����`���ɋ��s�암�̒n��ւƎ���A����ɂ��̒n���痄�삼���ɓ�g�È�тւƒʂ��Ă����B�����ۂ��̏��l����́A���ׂė��H�ŋ��s�ւƒʂ���O�q�̎I�X���Ɛ��⓻�t�߂ł킩��A���̂܂܍�������Ē��i�����i�Ζk���݂̍��ÂɎ���ዷ�X���̓[�g�����B���Ă����B�ዷ�X���o�R�̏ꍇ�A���Â����̕����^���ɂ́A�������։ꃋ�[�g�Ɠ��l�ɁA���i�A�F����A����̐��^�����p����Ă����B
�@ ������ɂ���A���H�ɂ���ʗA�������������߂Ă�������ɁA�ŏ����̗��H�ˑ��œ��{�C���Ƒ����m�����Ȃ����̌��H���ǂ�Ȃɏd�v�ł��������͑z���ɓ�Ȃ��B���̓�k�̌��H�Ɋ��Ɗ֓��𓌐��ɂȂ����H����������̂��ߍ]��т������킯�ŁA���̒n�̕������ʂ����Ɉ����Ă����̂��ߍ]���l�ƌĂ���Q�̏��l�����������B�����ȍ~�ɂȂ��ē��{�̏��H�Ƃ̒��S�I������S�����̂������ߍ]���l�̖��Ⴝ���ł��������Ƃ͂悭�m���Ă���Ƃ���ł���B
�@ �����Ԃ𒓂߂��F��h�́A�I�X���Ǝዷ�X�������铻�̏�����O�Ɉʒu���鋌�h�꒬�������B���݂��ɉh������߂������̊X���݂̈ꕔ���ۑ�����Ă���A���j���������قȂǂ��݂����Ă���悤���B�̓��̖ʉe�͂��͂�Ȃ����A���Ă͈��������唪�Ԃ����̏h�꒬�������������̂��Ƃ����B�I���i�͎ዷ��т̖����̈�����A���̌F��h�̓��̉w�̔��X�Ŕ����Ă���I���i���Ȃ��Ȃ������悭�l�i�̂ق����荠�ł���B�@
�@ ���l�`���̊C�Y���̔����A�t�B�b�V���[�}���Y�E���[�t�Ȃǂł��I���i�������Ă��邪�A�������Q�Ƃ͌�������A��{�O��~�Ƃ����l�i�̂ق���������ƍ����C�����ĂȂ�Ȃ��B�n���Œ�]�̂���I���i�������Ă���̂͋��؊X���i�I�X���j�����ɂ��邨�X�Ȃ̂����A���łł��Ȃ������肻���܂ŏo�����̂��Ȃ��Ȃ��ʓ|�Ȃ����ɁA�\�Ă��Ȃ��Ɣ����Ȃ����Ƃ�����炵������A������̂ق��́A�ǂ����Ă��Ƃ������H�ʂ̕��X�����̂悤�ł���B
�@
�@ ���̉w�œ�A�O���Ԃقǂ������薰���Ėڂ��o�܂��ƁA������̗l������ς��Ă����B�X���ɕ����ԎԊO�̌i�F����ʐ^�����ɕς���Ă���B�����Ă���ԂɓV�}�ς��A�O�͑��ɂȂ��Ă����̂��B�S���I�ɂ͌��\�����̌������~���������Ƃ���A���ꌧ�k������ዷ��тɂ����Ă̓��H�ɂ܂������Ⴊ�Ȃ��̂��ӊO�ɂ͎v���Ă����̂����A��͂�~�鎞�ɂ͍~����̂��B�t���ԋ߂ɂ��������Ƃ������Ƃ������ď��X�����ۂ������ł͂��邪�A�܂��ɉ��O��Ƃ������t���҂�����̑嗱�̐Ⴊ���������������Ă���B�t�����g�K���X�����������ŕ����s������A�������C�p�[�𗧂ĂĐ����ŕ������Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��L�l�������B
�@ ���炭�ԊO�ɏo�Ď哮�ւ̌�ւɃ`�F�[���������A�O�ւ����b�N���Ďl�쓮���s�ɓ��鏀�������Ă���ԂɁA�����͂����܂��Ⴞ�炯�ɂȂ��Ă��܂����B�F��h�����Ƃɂ��ĕ���Ǝ���̌����Ɍ������ē������̂ڂ��Ă��������ɐ�͂܂��܂��Ђǂ��Ȃ�A�Ƃ��Ƃ����C�p�[�̓������ő��ɂ��Ă����E���m�ۂ���̂�����Ȃقǂ̐���ɂȂ����B�J�[�u�������A�������Ҕ������Ȃ����H�̒����ŗ�����������킯�ɂ������Ȃ��̂ŁA�w�b�h���C�g���r�[���ɂ��A���F�������A���x���\�L���O��ɗ��Ƃ��đ��s�𑱂����̂����A�O�ʂ���@������悤�ɍ~���̂��߁A���Ɏ��E�̓[�����[�g����ԂɂȂ��Ă��܂����B
�@ ����O�C����������A���C�p�[�ɕt�������Ⴊ�������ăK���K���Ɖ������Ă͂��߁A���炭����ƃ��C�p�[�Ƃ��Ă̋@�\���ʂ����Ȃ��Ȃ����B�K���߂��Ɍ㑱�Ԃ͂Ȃ��悤�������̂ŁA��������Ԃ��߁A�t�����g�ƃ����̐�ƕX�����Ƃ��A�E�I�b�V���[�t�˂��Ĉꎞ�I�ɂ킸���Ȏ��E���m�ۂ��A�E�ւ�����Z���^�[���C�����I�[�o�[�����肵�Ȃ��悤�ɐ_�o�������Ȃ���A�܂��̂�̂�Ƒ��肾�����B�����āA����Ȉ�A�̍�Ƃ����x���J��Ԃ��Ȃ���A�Ȃ�Ƃ������z�����ÂւƒH�蒅�����B
�@ �������������̐����͂����܂����������������A���Â���}�L�m���A����䒬�A�]�����Ɣ��i�Ŗk�݂̈�т��ĖؔV�{�Ɏ���Ԃɂ���͌������~�葱�����B�͂��Ǝv���Ȃ����ĔR���v�ɖڂ����ƁA�y�����c�菭�Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���ł͂Ȃ����B��ђ����o�����_�ł͂���ȏɂȂ�ȂǂƂ͗\�z�����Ă��Ȃ������̂ŁA�R���⋋�����Ă��Ȃ������̂��B���Ƃ��ƃK�\�����X�^���h�����������Ȃ��ꏊ���ɂ��킦�āA�����ɂ����j�̖�\�ꎞ�߂��̂��ƂƂ��Ă�������A�قƂ�ǂ̂��X�͕܂��Ă����B�Ȃ��ɂ͓ˑR�̑��̂��߂͂��ƓX�d���������Ƃ��������悤�������B
�@ �R����������I�����W�F�̌x���������Ă�����������Ԃ�Ƒ��s���Ă���̂ŁA���悢������Ă�����ȂƎv���Ȃ���A�����Ȃ��Ȃ����Ƃ��̑P����^���Ɍ����������͂��߂��B�������A�K���Ȃ��Ƃɂ́A���ꂩ��قǂȂ��A�܂���̑��ɖ������悤�ɂ��ĉc�Ƃ𑱂��Ă���X�^���h�ɒH�蒅���A�h�����čň��̎��Ԃ�������邱�Ƃ͂ł����B
�@ ��������͖ؔV�{�C���^�[�`�F���W����k�����ɏオ��A���_�����ƒ������o�R�œ����֖߂낤���ƍl�������A���������̖�̐�i�F���y���܂Ȃ���͂Ȃ��Ƃ����Ɏv���Ȃ����A���H�Ƃ͋t�̃��[�g���Ƃ��Ĉ�ʍ��������̂܂܊ւ������ʂւƌ������đ��邱�Ƃɂ����B�n�ݎ��̂��鍂�����A���J�隬�̂����䒬���߂��A�ɐ��R�[���z���Ċւ������ɓ��鍠�ɂ́A�������̌���������������œV��ɂ��ڂ�Ȍ��e�����������͂��߂��B��i�F�Ƃ��ڂ댎�̑g�ݍ��킹�Ƃ����̂��Ȃ��Ȃ��ɕ�������Ă������̂������B
�@ ���̂܂܂������ɁA��_�A�A�e�������A���Z���A�䐓���Ƒ��蔲���A���Q�ō����\�㍆�ɓ���A���Ð�t�߂ł�������x�e���Ƃ����B���̂��ƒ��Ð삩��͒������ɏオ��m���X�g�b�v�œ������ʂւƌ��������肾�����̂����A�Ȃ�ƁA����������̂��ߎ��̂������A���s�K�����Ƃ̌x���\�����łĂ���ł͂Ȃ����B�[��̍��������m���m���^�]���Ă��d�����Ȃ����A�ǂ����[��̐ᒆ�s������Ȃ�A�ω��ɕx�ݍD������Ɋ�蓹���ł����ʓ��̂ق��������Ƃ܂����B�����Ɏ��͒��Ð삩�炻�̂܂܍����\�㍆�̖ؑ\�X���`���ɓ�ؑ]�A�㏼�A�ؑ\�����A�����A�ޗLj�Ɣ����A���K�ɏo�悤�ƌ��f�����B
�@ ��ؑ]���ɓ��鍠����ĂѐႪ�������~�肾�����B�C���̂ق���������A�܂����C�p�[�̓����������Ȃ��Ă����B�H�ʂ��K�`�K�`�ɓ������A���̂����ɂǂ�ǂ�V�Ⴊ�~��ς����Ă����B�}��̃J�[�u�̘A������Ƃ���Ȃǂʼn���Ƀt�b�g�u���[�L�������̂Ȃ�A�`�F�[���������l�쓮�̏�Ԃő��s���Ă��Ă������肵�Ă��܂������Ȋ����ł���B�ɗ̓G���W���u���[�L�ɗ���A���Ӑ[���M���`�F���W���J��Ԃ��Ȃ���A�����O�A�l�\�L���قǂ̒ᑬ�ő��葱�����B�����Ȃ�[��̂��̎��ԑтɂ͉ݕ��ڂ�����^�g���b�N�����\�����Ă���̂����A���̖�ɂ������Ă͑��ɒʍs�Ԃ͂قƂ�nj�������Ȃ������B�����āA�ؑ\�������߂��鍠�ɂ͊��S�ɐᒆ�̒P�Ƒ��s�ƂȂ����B
�@ ���܂��ܐႪ���~��ɂȂ�����ꎞ�I�ɂ�肷��ƁA�r�[���A�b�v�������C�g�̒��ɁA�ؑ]��̊ݕӈ�т̐�i�F���܂�Ő̂̉��̕`�������n��̂悤�ɕ����яオ�����B�[��̂���Ȏ����A����ȏ̒��œƂ蕗�i�ɂ݂Ƃ�Ă���Ȃ�Ăǂ������_�o�����Ă���̂��Ǝ���ꂻ�������A���������̂͂ǂ�ȏꍇ�ł����Ă���͂�������B���������A���̂悤�ȏ������炱���A���ʂƂ͈Ⴄ�i�ς�������Ƃ������̂��B
�@ �t�����g�E�C���h�E��T�C�h�~���[�̕\�ʂɒ�������X���킬���Ƃ����ߎ��X���H�e�ɎԂ��߁A���̂��łɂ��̎��ӂ��C�̌����܂܂ɕ��������������Ȃ���A���`�����o�Ėؑc���̖����t�߂Ɏ��������ɂ͂����ߑO�����߂��Ă����B��k�̕�����̈�p���Ȃ������������̃g���l�����A��䑺�̓ޗLj�h�߂��ɍ���������ƁA���������Ƃɂ܂������̘e���Ȃ����������Ɠ��������グ�A���������͂��߂��B���h�꒬�̖ʉe�����܂���������Ɨ��߂�ޗLj�h�̐�i�F���ڂ��̊�Œ��߂Ă݂����Ǝv���������̂ł���B
�@ �Ԃ�ޗLj�h�����̒��ԏ�ɒu���A�~�肵�����̒�����ݐi��ŋ��X���̌Â��ƕ��݂ɂ͂��܂ꂽ�ʂ�ɗ��ƁA��u�ɂ��Č��݂���]�ˎ���ւƃ��[�v�������̂悤�ȍ��o�ɏP��ꂽ�B�閾���O�̎��ԑтł͂��������A�_�X�Ɠ���W���X���̌��Ƃق̂₩�Ȑᖾ��̒��ɁA�����L�d���N�����`���~�̏h�꒬�̕����G�}�����̂܂������悤�Ȍ��i���ۂ�����ƕ����яオ���Ă����̂ł���B�̂��牽�x�ƂȂ��ޗLj�h��K�˂Ă͂��邪�A���̂悤�ȏ�i�ɏo�������̂͏��߂Ă̂��Ƃ������B
�@ ����Ɛ�̍~�銦�������̂��ƂƂ����Đl�e�͂܂������Ȃ��������A��ł����ۂ�ƕ���ꂽ�̂Ȃ���̉ƁX���ꌬ�ꌬ���߂Ȃ���H�ʂɐ[�X�Ɠ�̑��Ղ�����ł����̂́A���̂����Ȃ��ґ�Ȃ��̂Ƃ̂悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ������B���̒҂�܂�A�z�㉮�⑊�͉��Ƃ������V�܂̉����������ÊŔ̈ꖇ�����܂������グ�Ȃ�����ނ����ɁA���́A���炪���ɂ����̗��l���̂��̂ł��邩�̂悤�Ȍ��o�ɂƂ���͂��߂��̂������B����A���ہA���̂Ƃ����͎����ė������Ă����̂�������Ȃ��B
�@ ���Ղ��Ȃ���Ȃ����Đ�ɐ����@�@�i���e�j
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N4��4��
�C�쒬��O�̑z���o
�@ �u�Œm���钷�쌧�C�쒬�������܂��ܒʂ肩�������Ƃ��ɁA�v�����Y��Ă���������������z���o���ˑR�]�����S���Ă����B������������A�P�ɉ��������z���o�ȂǂƂ������́A���܂̎���ɂ͂��͂⓾��A�ꕗ�ς�����M�d�ȑz���o�Ƃł��������ق������K�Ȃ̂�������Ȃ��B
�@ ���N�̒m�l�̂ЂƂ�ɏ���x�j����Ƃ����R�`�o�g�̎��Ȉオ����B���ݐ_�ސ쌧���͌��ݏZ�̂��̏��삳�A���܂����\���N�O�A���쌧�C�쒬�̖�O�Ƃ����W���ɂ��錳�{�\�_�Ƃ̑傫�ȋƂ����~�̈���ɂ���Â������ƍw�������B�Ό��̏d�݂����������邻�̉Ɖ��Ɖ��~�Ƃ�ʑ�����ɗp���A���ӂɂ������O�����̊�n�Ƃ��Ă��ő���Ɋ��p���悤�Ƃ����킯�������B���삳��ɂ���A�̋��̕����ɂǂ����d�Ȃ�Ƃ���̂��邻�̒n�̎��R�≮�~�Ɖ��̂������܂����C�ɓ������Ƃ������Ƃł��������̂��낤�B��O����Ԃňꑖ�肵���Ƃ���ɏ���Ƃ����W�������邱�ƂȂǂ��A���R�Ƃ͂����s�v�c�ȉ��ł͂������B
�@ ��O�W���͉���Ƃ������Ȃ�傫�Ȑ�̒����ɖʂ��Ă���B����͓V����̎x�������̂��̂܂��x���ɂȂ��Ă��āA���̏㗬�̐[���J�ɂ͌k���ނ��g�t�Œm���鉡��k�J�Ȃǂ�����B���̌k�J�̍ʼn����͒����A���v�X�A���k�[�Ɉʒu�������Z���̌o���x�R�������ɂ܂ŋy��ł���A�A�v���[�`���[�g������`���ɑk�s���邩�A�k���Ōo���x���z���č~��Ă��邩�̓�����Ȃ�����A��т͂��܂ł��Ȃ��̂̂܂܂̎��R���قڎ�����Ŏc����Ă���B������A�R�̌b�݁A��̌b�݂��L���Ȃ��Ƃ��̂����Ȃ��B
�@ ���̂Ƃ��낸���Ƃ��������̂����ςȂ��Ȃ̂����A�ȑO�͂悭���삳��ɗU���Ė�O��K��A�s�v�c�ȑ��݊��̂��邻�̉��~�ɑ؍݂��A��т��U�����̂��B�܂��q���������������������A�䂪�ƂƂقړ����N����̂��q����̂������]�_�Ƃ̋ڑ�r����Ƃ�U���A�Ƃ��ɉ߂��������������z���o�Ȃǂ�����B���Ƃ��Ƃ��{�\�_�Ƃ̉Ɖ����������Ƃ������āA�y���̂ق��A�������ɑq�ɂ����˂��傫�ȉB����������������A������ʂƂ���ɒn�������݂���ꂽ�肵�Ă��āA�q��������������Ƃ����T���C���Ȃǂ𖡂���Ă����悤�ł���B
�@ ���R�A�g�C���͐̂Ȃ���̋��ݎ�莮�ɂȂ��Ă�������A�䂪�Ƃ̎q�������ɂ��삦���ۂ��������ĕ��A�̋��ݎ���삦���^�т̎�`������点���B���_�����̗����̑��ň�������ɂƂ��Ă͉���^�т�͔쑢��ȂǓ��풃�ю��ɉ߂��Ȃ���������A���ꎩ�̂Ȃ�̒�R���Ȃ��������A�q�������̂ق����A���~���̖�ؔ��ɉ^���삦��y�ɎT����ƂȂǂ��A���ܐ�����ɂЂ�ނ��Ƃ��Ȃ����\�y����ł����悤�ł���B���܂͂������萬�������ނ�ɂƂ��Ă�����͋M�d�ȑ̌��������ɈႢ�Ȃ��B���̂ق��ɂ��i�^���ӂ���Ă̐d����A�r�̑|���␅�����A���˂̔��Ƃ�≮�����̕�C�A���ӂ̑����A��̎����◎���t�̐��|�ȂǁA���낢��Ƃ�邱�Ƃ����������A�K�x�̉^����C���]���ɂ��Ȃ��Ă�����ʓ|�Ɋ����邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ������B
�@ �y�Ԃ̉��ɂ���̂Ȃ���̖؉��̕��C���Ȃ��Ȃɖ����������B�傫�ȓS����p�����܉E�q�啗�C�Ȃ�q���̍��ɓc�ɂŊ���e����ł�������A���������z�����炢�ŏI��������낤���A�{�i�I�Ȗ؉��̕��C�ɓ�������͂��̎����͂��߂Ă������̂ŁA�Ȃ�Ƃ������ÁX�ł������B�g�̂߂�嗁���Ƃ��ꂢ�ȏオ�蓒�𗭂߂Ă��������ȓ����Ƃɂ킩��Ă���̂��ʔ����������A�����Ƃ��������o�����͕̂��C�������̍\���������B���ɃV���v���ł����������I�ɂł��Ă�������ł���B
�@ ���̍\�����܂��ɏq�ׂ�ƁA���a���O�\�Z���`�قǂ̓����̑傫��L���ǂ�����A�Z���ق��̓��ǒ[�͕��C���̊O�ɏo�Ă��āA���ꂪ�R���̕������ɂȂ�B�����ۂ�L���ǂ̎厲�ɂ����鑤�̒������ǂ͗������̋��̂ق��𐂒��Ɋт��悤�ɂ��Ĕz����A���̏�[���͏\�Z���`�O��̌��a�ɍi�荞�܂�Ē��ډ��˂ɂ�������Ɛڑ�����Ă���B�v�͂��ꂾ���̂��ƂŁA������L���ǂ����C�����̂��̂Ƃ����킯�Ȃ̂��B
�@ ���C�̕������������ȒP���̂��̂������B�܂��A���C���̗������ɐ���A�オ�蓒�p�̏������ɂ���������B�����āA�������ɂ�����Z���ق��̊nj�����K�ʂ̐V������ĂȂǂ̕������ނ����ĉ����A�ΐ������������Ȃ����Ƃ���Ŏ�R���ނ̐d�Ȃǂ𐂒������ɗ��Ă��܂܂̏�Ԃō�������ł��̂��B���̋C�ɂȂ�Έꃁ�[�g���A�[�g���̒����؍ނł����̂܂ܗ��ĂĔR�₹��Ƃ����킯�ŁA���S�Ȃ����ɂقƂ�Ǐꏊ���Ƃ�Ȃ��B
�@ ���ۂɂ���Ă݂�ƁA�����ɉ͂��A���Ƃ��獷�����d�Ȃǂ����������Ɖ��𗧂Ăċ����قǂɂ悭�R�����B�ʔ����̂́A���������������̂ق��ɂ͂܂������������Ă��Ȃ��ʼn������Ɉړ����AL���ǂ̒ꕔ�������蔲���ė������̊ǂق��ɗ���邱�Ƃł���B�v����ɁA���˓��ɋ����㏸�C�����N���邽�߁A�������̂ق�����͂ǂ�ǂ�V�N�ȋ�C���z�����܂�邩�����ɂȂ邩��A�R�Č������悢�����ɁA���C���Ă���l���������v����������A���܂���R�₷���߂ɂ悯���ȋ�J������K�v���Ȃ��B��������d�Ȃǂ��R���͂��߂���A�K�X�R����⋋����ȊO�͈��S���ēy�Ԃł̐d���肻�̑��̍�Ƃɐ�O���Ă���悢�킯���B
�@ �������A�������̐��͉��˂ɂȂ����Ă��鑤�̓��ǂ̔�����M�ɂ���ĉ��߂���B�ꉞ�͓����҂̐g�̂����ړ��ǂɐG��Ȃ��悤�ɊȒP�Ȏd��i�q���݂����Ă��邪�A�܉E�q�啗�C�̏ꍇ�Ɠ��l�ɓ��������ڂɐg�̂̈ꕔ�����ɐG��Ă��Ώ������Ƃ͂Ȃ��B��M�̑傫�Ȑ�����M�̏����ȓ��ǂ̔M���ǂ�ǂ�z�����Ă��܂�������v�Ȃ̂ł���B
�@ �R�Č������悢���瓖�R���C�������̂��͂₢�B�Ή����̂ق��͂ǂ�����Ē������邩�Ƃ����ƁA���ꂪ�܂����ɂ��܂��ł��Ă���̂������B�Ȃ�Ă��Ƃ͂Ȃ��A�������ɏd�߂̊W�����Ă��āA�����K�x�ɊJ����C�̗����ʂ����Ă����������̂��ƂȂ̂��B�������̊O�܂ŏo��悤�ȔR���ނ�����Ƃ��͂������邩�A��܂��Đ[���Z�\�Z���`��̊O�����Ǔ��ɂ����߂邩���āA���̂��Ɗ��S�ɊW��߂�Ή͏����Ă��܂��B��ɂ��Ă��������������Ƃ����W���J���Ă����悢���A�Ăщΐ���������������ΊW��傫���J���悢�B
�@ ���ۂɉ��x������Ă݂����A���R���݂ɉΉ������ł���̂��B�����ɓ������܂܂ł�������Ƃ����g�̂�L����������Ύ����œ��������R���g���[�����邱�Ƃ��ł����BL���ǂ̒ꕔ�ɗ��܂�D��R�������Ȃǂ́A�������A���������̒ꕔ�ɂ��Ă��鏬���ȑ~���o�������珜���ł��邵�A�R�ēx���������߂ɔR�������̗ʂȂǂ�����߂ď��Ȃ��B���̎���ɒN���l���o�������C���Ȃ̂��͒m��悵���Ȃ��������A���ɗ��ɂ��Ȃ������̍\���Ɏ��͗B�X���S������肾�����B
�@ ���̍��܂ł͂܂��M�B��т̂��������ł��̎�̕��C�����g���Ă����悤�Ȃ̂����A�����̒ÁX�Y�X�܂ł����ΔR����̂̐����ɕς���Ă��܂������݂ł́A�������̎p��ڂɂ���@��͂قƂ�ǂȂ����낤�B�܂��āA�_�C�I�L�V�������ȗ��A�����傫�ȉe��������Ƃ��v���Ȃ��V�R�؍ނ̔R�ĂȂǂɂ��ߕq�ȋ��۔����������l�̑����Ȃ��������ł́A����͂������S�ɖY�ꋎ��ꂽ���݂ɈႢ�Ȃ��B���̑�σ��j�[�N�ȉ����C�Ȃǂ͂ǂ����̖��������ق▯����قɎ�������Ă����������Ȃ��ƌl�I�ɂ͎v�����������̂����c�c�B���삳��̉��~�̕��C�́A����ꂪ�\���łȂ��܂g�킸�ɒ��炭�����Ă����ꂽ���߁A�c�O�Ȃ��炢�܂ł͎g�p�s�\�ɂȂ��Ă��܂����ƕ����Ă���B
�@ ���삳��Ɩ�O�̉��~�ɉ��x���ʂ������ɂ͗l�X�Ȃ��Ƃ����������A�������̉����ɃX�Y���o�`������������ȑ�����菜�����̂����������z���o�̈�ł���B�������~������܂ł��̂܂܂ɂ��Ă���������̓n�`�����Ȃ��Ȃ葃�������c��̂ŁA���̎��ɂ������������悢���Ƃ͂킩���Ă����B�����A�u���u���Ƒ傫�ȃX�Y���n�`�̌Q����щ��A��ƒ��Ɏh���ꂩ�˂Ȃ����ԂɂȂ����̂ŁA��ނȂ�������菜���Ă��܂����Ƃ������ƂɂȂ����B
�@ ���K�L�����������A��R���M�n������삯����Ă��������ŁA�X�Y���n�`��A�V�i�K�o�`�̗ނɂ͉��x���h����Ă����Ԃ�ƒɂ��v�����������̂��B�n�`�ɏP��ꂽ����ɃT�c�}�C���̖��̍������ɋ߂��������A���������ݏo�锒���t�̂��h���ꂽ�����ɂ��邩�A���܂菧��ł��͂��Ȃ����A�����̃I�V�b�R��������Ƃ������邩����悢���ƂȂǂ��A�N���狳������Ƃ��Ȃ����̍��w���̂������B�������A���܂ƈ���Ē��h����Ɍ����ǂ��ł����R�ɂ͓���ł��Ȃ�����̂��Ƃ�����A���X��ł��d�����Ȃ������B
�@ �����̃I�V�b�R���o�Ȃ������Ƃ����l�̂�������肪�����q�����L���͂������ɂȂ����A���w���̍��A�ꏏ�ɗV��ł����Ή��̒j�̎q�����ӏ����X�Y���n�`�Ɏh���ꂽ�Ƃ��A�u�C�^�J�C���E�o�b�e�A�A�b�J�A�A���[�`�b�g�A�L�o�����H�I�i�ɂ����낤���ǁA���O�́A����������ƁA�䖝�����I�j�v�Ɠ����t�ŗ�܂��Ȃ���A�������r�o���������̃I�V�b�R�̉��H����f�m��ʊ�ł��̎q�̓����ɂ��Ă�������Ƃ͂���B�������A��̉t�̒��̂ǂ̐������ǂ̂悤�ɍ�p���Ēɂ݂����}������ʂ�����̂��ȂǂƂ��������ȉ��w�I�m���Ȃǂ��낤�͂����Ȃ��������A�������������ڂ̂قǂɂ����܂ЂƂm�M�͂Ȃ������̂ł��邯��ǂ��c�c�B
�@ �܂��A����Ȃ悤�Ȃ����₩�Ȍo���̐ςݏd�˂̌��ʁA��ɂȂ�Ƒ��ɖ߂��Đ[�����荞�ނƂ����X�Y���n�`�̏K�����n�m���Ă�������A���̏������̂��̂ɂ͂�����J�͂��Ȃ������B�[��n�V�S���|���č��������ɂ�����X�Y���n�`�̑��̂Ƃ���܂ł̂ڂ�A��v�ő傫�ȃr�j�[���܂ł����ۂ�Ƒ��S�̂���݁A���̕t���̂Ƃ���ő܂̌����i���ĉ��d�ɂ��O����R���������A�X�Y���o�`�����̈ꑰ�Y�}�ǂ������S�ɑ܂̒��ɕ������߂Ă��܂����B����������d���ŏƂ炵�����炢�ł̓X�Y���o�`�͖ڊo�߂��肵�Ȃ�����x���ƌ��f�͂�������ǂ��Ƃ������Ƃ͂Ȃ��B
�@ �Ō�̎d�グ�́A���̕t����������藣�����Ƃł���B���Ȃ�̏d���̑��������ɂ��\���ς��鋭�x�Ō��̑������ɂԂ炳�����Ă���킯������A�t���͊�䂻�̂��̂ŁA��̗͂ł����Ƃ��قǂ�킭�͂Ȃ��B��������n�V�S���~��A�m�R�M���������čēx���̂Ƃ���ɂ�����Ȃ����A���̕t���̍ŏ㕔���S�V�S�V�ƈ��������B�z���ȏ�Ɍł��������肵�Ă��āA�ׂ߂̊ۑ���邭�炢�̎��ԂƘJ�͂��K�v�������B�X�Y���o�`�ǂ��ɂ���~���ėN�����V�Ђ������Ƃ���ŁA�Ȃɂ��Ȃ������ς�킩��Ȃ������ɈႢ�Ȃ��B
�@ ���~���̐���̖�x���ɖ�O�ɏo�������Ƃ��Ƃ��Ȃǂ́A�H�ʂ��K�`�K�`�ɓ������Ă��܂��Ă������߃`�F�[�����܂��������ɗ������A�܂�ŎԂ��ƃX�P�[�g�����Ă���悤�ȏ�ԂɊׂ�낤������ɓ]�����Ă��܂������ɂȂ��Ă��܂����B�����̃��S���Ԃ͔n�͂��������܂����݂̂悤�Ȏl�쓮�Ԃł��Ȃ������B�������A���S���Ԃ̓G���W�����O���ɂ���W�ŎԑS�̂̏d�S���O�֑��ɕЊ���Ă���B���̂��߉ו���ς�ł��Ȃ��ꍇ�ɂ͌�ւ̋쓮�ւɂ�����ԏd���y���A���Ƃ��`�F�[���������Ă��Ă��Ђǂ����������H�ʂł͊ȒP�Ɍ㕔�����E�ɉ����肵�A������K�U���ԂɂȂ��Ă��܂��̂��킾�����B�܂��Ė�O�̂�����͕W�������S���[�g���قǂ͂�������̎R�ԕ��ŁA�����͓��������Ԃ̒ʍs���قƂ�ǂȂ��Ƃ��낾��������A���������͈��������B
�@ �悤�₭�̂��ƂŖ�O�̉��~�O�ɒH�蒅���Ԃ��ɓ���悤�Ƃ������A�������H�̈�ʂɂ͌����X������߂Ă��āA�ǂ����~���Ă��쓮�ւ��X���b�v���J��Ԃ������ł܂�œ������Ƃ�Ȃ��Ȃ����B�Ȃ�Ƃ��^�C���t�߂̕X���ӂ����Ƃ��ĎԂ�����o�����c���n�V���v����U�艺�낷�ƁA�Ȃ�Ƌ��������ƂɁA�J�`�[���Ƃ��������������������Đ�[������ΉԂ��������B�c���n�V�Ŋ��������肷��ƉΉԂ��U�邱�Ƃ͒m���Ă������A�܂����X������Ă��ΉԂ��U��Ƃ͍l���Ă��݂Ȃ����Ƃ������B
�@ ���̏��쉮�~�ɂ܂�鐔�X�̑z���o�̒��ł���߂��͓y���ɂ܂�鈫�Y�b�Ȃ̂����A������̂ق��͏��X�x���߂��Ă�����������Ȃ��B���삳����������͑����Ȉ��Y�D���ł���B����ȓ�l���{�C�ɂȂ��Ēm�b�����ڂ蒿�v���Ă����̂�����A������Ƃ₻���Ƃ̂��ƂŎ������܂낤�͂����Ȃ��B�����m��Ȃ��l�������Ȃ肻�̃V�����m�ɑ��������炻�̏�ő��|���Ă��܂����˂Ȃ��A�Â�ɋÂ����H����X�͑��̒��Ɏd�|�����̂������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N4��11��
��̍����r����
�@ �L�����~�̈�p�Ɍ��Ă��邻�̌Â��y���́A���邩��Ɋ�䂻���Ȗ{�i�I�ȑ���̂��̂ł������B�O�ǂƓ��F�̔��h��̔��͓`���I�ȓy�ǂƂ��Ȃ��H�@�ő����Ă���A�����d�����A�����������J�Ȃ��Ƃɓ�d�\���ɂȂ��Ă����B�̂Ȃ���̗��Ƃ������͂����Ĕ����J���ƁA���̓����ɂ���ɂ����ЂƂ��Ȕ��������Ƃ����킯�������B
�@ ���̒��͈�K�Ɠ�K�����Ƃɕ������Ă��āA��K�̏��Ɠ��ǂ͂�������Ƃ���������ɂȂ��Ă����B���̉��ɐԓy�⎽����ł߂Ă��������S�ȓy�ǂ��B����Ă������Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B���̋��X��l���̕ǂ̐ڍ������܂ł��������ƒ��߂܂킵�Ă݂����A�قƂ�nj��Ԃ炵�����̂͌�����Ȃ��B�l�Y�~�͂ނ��A�S�L�u����C�ł������N������͓�����������B�O������l�Y�~��S�L�u�����N������Ƃ���A�����J���Ď��ނ̏o����������Ă��鎞���A����炪���ނƈꏏ�ɕ��ꍞ�ꍇ�ɂ�����ꂽ���Ƃ��낤�B
�@ ��K�ɂ�����ɂ́A��q�i�̏㕔�ɐ݂���ꂽ�l�Y�~�Ԃ��Ƃ����X���C�h���J������������J���A������ʂ蔲���Ē��ɓ���B�܂��l�Y�~����K�ɐN�������ꍇ�ł��A���̃l�Y�~�Ԃ��œ�K�ւ̐N���͖h�����Ƃ����킯�ł���B�����d������ɓ�K�ɂ������Ē���`���Ă݂�ƁA��K�Ɠ��l�Ɋ��ȑ���ɂȂ��Ă��ĊJ���̖����葋����A�O�قǂ��Ă����B�����ɂ��̖����葋���J�������d���������Ă݂�ƁA���Â��Ȃ�������ԂȂ璆�łȂ�Ƃ���Ƃ͂ł������Ȋ����ł������B
�@ �Ƃ���ŁA���̑��̒��ɂ͑O�̎����傪�s�v�i�Ƃ��Ă��̂܂ܒu���c���Ă������l�X�ȌÂ�����ނ┠�ނ����[����Ă����B�Ȃ��ɂ́A�s��̍������Ɏ������߂����炩�̒l�i�͂������Ȃ��̂Ȃǂ��������B�܂��A����ɂ��킦�āA�V��������ƂȂ������삳��̎�ŁA���͌��̎����s�v�ɂ͂Ȃ������̂Ă�ɂ͔E�тȂ��ÉƋ�Ȃǂ��^�э��܂�Ă����B������A�܂������̋��Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A�������ꉞ����炵�����̂ɂ͂Ȃ��Ă����B
�@ �����͍������������ő��r�������s���Ă����B���̒C�쒬��тɂ͌Â��������Ȃ������Ƃ������Ԃ�Ǝc���Ă������߁A���R�̂悤�ɑ��r���ɂ���Q���₦�Ȃ������B����Ȃ킯����������A�ɂ߂ċM�d�ȕi���͂Ȃɂ����߂��Ă��Ȃ������ɂ��Ă��A�����ȑ��r���ǂ��ɏ��삳�L�̂��̑����_����\���͏\���ɂ������B�����ŁA���ΗV�ѐS�������Ă���Ȃ�̎��q����l���悤�Ƃ������ƂɂȂ����̂ł���B�������A���r���̐N�������炩���ߖh�����Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�ނ�̐N����O��Ƃ������X�Ӓn���Ȏ��q����u���悤�Ƃ������ƂɂȂ����̂������B
�@ ���̓�K�ɂ͑O�̏��L�҂��c�����Â��̋����������B�͍̂����Ȓu�����M�d�ȏY��ނ��͂����Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv�������R���̗��h�Ȕ��ŁA�S�̓I�ɍ����肪���Ă��Č��邩��ɂ��킭���肰�Ȋ����������B���͂��܂��܂��̌Ô��ɖڂ������̂ł���B���̔��̒��ɑ��r�����J���Ē��������炠���Ƌ����悤�Ȃ��̂����ĕ����A��c�`���̋M�d�ȕi�������܂��Ă��邩�̂悤�ȁA�Ȃ�Ƃ��v�킹�Ԃ�Ȉꕶ�̊O�ɋL�����A�Î��ɖn�����ē\���Ă����B�����Ă����ڗ����₷���Ƃ���ɁA�����ɂ��厖�����ɕ��ׂĂ����Ƃ����̂������̊�{�������B
�@ ���̒��ɉ������邩�͂����ɂ��܂����B�������A���킸�ƒm�ꂽ�V�����m�ł���B�����͂ǂ����Ŋ����i�̃I���`�����͌^�ł��T���Ă��ĂƘb�������Ă������A���ǁA���̃V�����m��̐���͏��삳�炪�����邱�ƂɂȂ����B���Ȉ�̏��삳��͂��Ƃ��Ƒ�ςɎ��̊�p�ȕ��ł�����Ƃ��������̐S���Ȃǂ�����B���Ԃ̋��������莕�ȋZ�H�Ȃǂ������ł��Ȃ��Ă����l�Ȃ̂ŁA�d����ɂ͍H������H�p�ޗ����������������Ă��邵�A�E�ƕ��A��낤�Ƃ��Ă���V�����m�̌`��ɂ��ڂ����B���R���̊W�̐}�Ŏ����Ȃǂɂ��������Ȃ��Ƃ����킯�������B
�@ ���ӂ����Ƃ�����Ƃ����Ȃ����̍����̑��k�����Ă���O�����قǂ�����������̂��ƁA������K�˂����͊����������̃V�����m���������ꂽ�B�����āA�����̂��܂�̏o���h���̂悳�Ƃ������A��u�g�����������Ȃ�悤�Ȏ����畉�����݂Ɏv�킸�X�萺�������Ă��܂����B���邢���̂��Ƃł��������ƌ��ߕ��ł܂킵�Ă݂Ă�����͖{���������肾��������ł���B�������Ɏ�������ɂ������Ƃ͂Ȃ��̂Ŏ��ۂ̂Ƃ���͂킩��Ȃ��������A�����ĈႢ���������Ƃ���A�����y�߂��ȂƂ����v�������邭�炢�̂��̂ł������B
�@ ���ꂩ��قǂȂ���X�͂��̃V�����m��C�쒬�̑��܂ʼn^�сA������̌Ô��̒��Ɏ��߂Ĕ�������̒��Œ��߂Ă݂��B�^���Âɂ��Ă����ĉ����d���̌��ŏƂ炵�o���Ă��݂��B���ꂪ�U�����ƒm���Ă����X���g�ł������A���̕s�C�����ɂ������|�����L�l�ł������B�������ʂ̂قǂ��m�F�������ƁA���ɊW�����A����R����������ƒ��߂��B�����āA���|�̖���ł����鏬�삳�u�얳��t�ՏƋ����E�Ɠ`���鎲�v�Ɩn�����������ɂ��Â����Șa����\������B�u�얳��t�ՏƋ����v�̕�����p�������Ƃɂ͕ʒi�Ӑ}���������킯�ł͂Ȃ��A���Ďl���ł��H�����̌��������Ƃ̂��鏬�삳�ˑR���̔��������v���o���ď������������̂��Ƃ������B����t�l�̋�C�����炢�Ƃ���Ɉ�������o���ꂽ���̂ŁA����ȕs�͂��Ȏ荇���ɗ��p���ꂽ���Ƃ��A���������N�E�J�C����R�E�J�C�Ȃ����Ă��邱�Ƃ��낤�B�u�Ɠ`���鎲�v�Z�����̂ق��͂ق��Ȃ�ʂ��̐g�̔��Ăɂ����̂������B
�@ �Ƃ���ŁA���̃V�����m�Ƃ͂����������������̂��c�c�����A�������A����͂��@���̒ʂ�ł���B���삳��͂܂���̂قǂ悢���q�̎�����肵���B�����āA��U�w�̐}�ł��Q�l�ɂ��Ȃ���O�O�ɂ����̞��q����虊��ʂ��Č��^���d�グ�A�\���Ɋ����������B�����Ă��̕\�ʂ���O�ɐp�œh��ł߁A����ɂ��̂������琅���������čd������Əۉ县��������ɂȂ鎕�ȍޗ��̕�U�ނ��ʂɗp�ӂ��ČG�Ȃ��h�z�����̂ł���B���|��@���ɂ�����Ƃ���͓��ɒ��J�ɍH���A�O���C���_�[��p���đS�̓I�ɂ�������Ɩ������������B
�@ �旳�_�˂Ƃ������t�����邪�A���̏���y�j��i�̏ꍇ�́A�o����Ƃ�`������čŌ�̎d�グ�Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�����ɂ����Ȉ�炵���A�鐂Ɏ������čŌ�̎d�グ�Ƃ����̂ł���B�鐂̕s�C�����͎��̊����Ă��܂�Ƃ����Ă��悢���A�Ȃ�Ə��삳�Ō�̎d�グ�ɓ��ꂽ���ɂ́A��胊�A���Ɍ����邽�߂ɐl�H���̂ق��ɖ{���̎������Ȃ�̐��������Ă����̂������B���Ȉ�̏��삳��́A�d�����Ђǂ�������d�x�̎����a�ɂ����������҂̔����������Ȃ��B�����ꂽ�����̎��������A�銳�҂͂قƂ�ǂ��Ȃ�����A���͎c��B�ʏ킻���͔p����������Ă��܂��̂����A���̈ꕔ��]�p�����Ƃ����킯�������B�������āA�v�w���e�q�̂����z��������召��̊������鐂̃Z�b�g���������݂��̂ł������B
�@ ����ƌ����Ă��܂�����܂łȂ̂����A�Ƃ���������X���u�������r����͂��̂悤�Ȃ��̂ł������B���̌�{�E�̑��r�������̑��ɐN���������Ƃ��������̂��ǂ����͒肩�łȂ��B�����A���삳�畷�����Ƃ���ɂ��ƁA���Ȃ��Ƃ���x�͉�X�̒m��ʒN�������f�ő��ɓ����Ė��̌Öؔ������������`�Ղ�����Ƃ����B���삳��̌��t�ʂ�ɁA���̔����J�����g��ڂɂ����l�����������Ƃ���A�����������ɋ��������Ƃ��낤�B
�@ ������͂��łɑ��E�Ȃ����Ă��邪�A��������N��̏��삳��ɂ́A�����Ȉ�̒��j�ƃR���s���[�^�Z�p�҂̎��j�̂��q�����l������B�������A���̂��q�����ɂ��������̗��b�͂܂��`����Ă͂��Ȃ��悤�Ȃ̂��B��X��l���ł���������܂܁A�������肻�̂��Ƃ��Y�ꋎ���Ă��܂�����A��X�ɂȂ��Ĉꑛ���N���邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�����Ȃ�����߂���������Ƃ��낾�낤�B
�@ �����ɖ߂��Ă��珬�삳��ɓd�b���A�v�X�ɒC�쒬�̉Ɖ��~�̌���k��y���̂��̌�̗l�q�Ȃǂ�u�˂Ă݂����A�l��s���Ŏ���ꂪ����Ȃ��߂��܂ł͂��Ȃ�r�ꂽ��ԂɂȂ��Ă���Ƃ̂��Ƃ������B�������A���̒��̊���ȃV�����m�����̂܂܂ɂȂ��Ă���炵�������B�����ŏ��삳��Ɂu��̈��ӂ����̌���l�̎��M���Ńo�������Ⴂ�܂���I�v�ƍ�������A��b��̌������ŁA�u���̎��ザ��A��X�����Ȃ�ǂ����̂悤�ȏ�ԂɂȂ��Ă��܂�Ȃ��Ƃ�������Ȃ�����˂��c�c�n�n�n�n�v�Ə��Ȃ�������������Ă��ꂽ�B����Ȃ킯�ŁA���X�x���߂������������Ȃ��ł��Ȃ����Y�b�̌��J�Ƒ�����������ł���B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N4��18��
�U����ɗU����
�@ ���N�̍������łɐ�����߂����B�������U�鎄�̓��ォ��́A���c�̍��̉Ԃт炪�͂�͂�ƕ��������Ă���B�����ʂ��镗�����₩�Ȃ��Ƃ������āA������Ƃ����ɂ͏��X���̂���Ȃ��C�����Ȃ��ł��Ȃ��B�����A����ł������͈�ʉԂт�ɕ����A���܂����}���͂Ȃꂽ����̉Ԃт炪�A�n��ɗ�����܂ł̈�u��ɂ��ނ��̂悤�ɂ��邭��ƒ��ɕ����Ă���B
�@ �����������Ɖ���t�̍��߂邱�Ƃ��ł���̂��낤�H�c�c�ӂƂ���Ȃ��Ƃ��l�����B�^���悯��܂��O�A�l�\��͒��߂邱�Ƃ��ł��邩������Ȃ��B�������A���N�̂��̍������[�߂ɂȂ����Ƃ��Ă�����͂���ł��������Ȃ��B���܂ɂ����A���N�y�̗F�l��m�l���S�Ђɓ������Ƃ����Ȃǂ��͂����肷��悤�ɂȂ����B���̐g�����Ė����̂��Ƃ͂킩��Ȃ��B�킩��Ȃ�����A�������č�������������₩�Ȋ��S�ɒ^��Ȃ��琶���Ă�������B
�@
�@ �U����̂�������U����@�@�NJ�
�@ ���J���߂����Ƃ͂����A�}�X�ɂ͂܂���������̉Ԃ��c���Ă���B����ȍ����ЂƂ�Â��ɋ��݂邤���ɁA�v�킸���͗NJ��̗L���Ȉ�����������ł����B���̂Œm����NJ������A���͏G������Ȃ��Ȃ��B������̑z������X�������Ă�������̎��ɂ���A����͂Ȃ�Ƃ����ł������ł���B���܂�ɂ����R�ɖ��̂�������Ⴖ���������̋�̌������Ɋ������邤���ɁA���̉Ԃт�̈ꖇ�����܂����A���Ƃ������܂łɔ����������Ă����B
�@ ���̉Ԃ̎U�肬��̌����ɂ����Ƒz�����߂��点�Ă��邤���ɁA�ˑR�A���͂��܂ЂƂS�ɋ��������NJ��̋��z���o�������B�NJ��̍Ŋ����Ŏ������S��̉̂ɉ��������̂��Ɠ`�������ŁA������̎����̋傾�Ƃ������Ă���B���Ȃ���������̂̎U�肬����Ⴖ�����̂ɂ͈Ⴂ�Ȃ����A������̂ق��͏t�̍��ł͂Ȃ��H�̍g�t����ނɂȂ��Ă���B
�@ ��������������Ă������ĎU����݂��@�@�NJ�
�@ �NJ��ɂ́A���̓�������Ɏ�{�����Ȃ���̂�т�Ɠ��X���߂������Ƃ����A�������ꂵ���C���[�W�����܂Ƃ��Ă���B�����A���ۂ̗NJ��́A���g�̐l�ԂƂ��ċ�Y�ɂ���Y�̐�����݁A�ԕn�ɊÂ����̌��͂ɍR���A�Ȃ̖��͂���Q���Ȃ�����l�X�̋~�ςɐS�̂������s�����H��̑�l���ł������B�����n���ɂ����������̗����\���݂Ȗ��킢�s���A����ɂ͈��̑����ɋ�Y���������������Ƃ��`�������l�ԗNJ��̂��Ƃł���B���̐��U���ЂƂЂ�g�t�ɑ�������̈�傪�l�̐S��[���ł��Ȃ��킯�͂Ȃ��B
�@ �t�̍��̎U��䂭���܂Ɋ������邤���ɁA�������H�̍g�t�̕��������邳�܂ɑz���y�ԂƂ����A�͂Ȃ͂����Ȑ���s���ɂ͂Ȃ��Ă��܂������A������ЂƂ��ɁA���̖��͂ƗNJ��̖��͂̂Ȃ���Ƃ��낾�����̂��낤�B
�@
�@ ���炭�������Ȃ�����������ƁA�����Ȍ����̃x���`�ɍ��|���A�����o��������̎�X�����O�̐V������ڂɒ��߂Ă����B����ƁA���w��A�O�N�����炢���Ǝv����j�̎q�̎O�l�A�ꂪ����Ă��āA�߂��̍���ŗV�т͂��߂��B�ނ�̉�b��g�U��܂�����@����ƁA�����߂��̊w���ۈ珊�ɒʂ��Ă���q�ǂ������炵�������B���X�����V�肻�̂܂܂̎q�ǂ��������ȂƎv���Ȃ���A���̔��܂����p��������Ă���ƁA�ˑR�A�V����悤�ȉ�b�����ɔ�э���ł����B���̉�b�̐[���Ȕw�i�Ƃ͂��܂�ɂ��ΏƓI�ȉ����ɁA���͈�u�Y�b�R�P�Ă��܂������ɂȂ����B
A�F���̂����A���܂���Ƃ��̕�����l�ځH
B�F���l�ڂ��āH�c�c���[���ƁA�����Ƃ���Ȃ��l�Ȃ��ǁc�c�B
A�F�Ӂ[��A����O�l�ڂȂ��ǁA����ǂ̕������A�₳�����ǂ��c�c�B
C�F����͂����A���̂܂��܂ŃI�W�T���������l�����܂͕������ȂI
B�F�ǂ�����ΐV�������������炦��킯�H
A�F�ƂɋA���ĕꂿ���ɂ����Ă݂�H
B�F����̕ꂿ���A�킩�邩�Ȃ��H�c�c�V�����������̂��肩���c�c�B
C�F�I�W�T�����܂����Ȃ��́H
B�F����A���[���Ƃ���Ȃ�������Ƃɂ��邾��������c�c�B
�@ ��ؓ�ł͂����Ȃ��Ȃ������G�Ȍ���̎Љ��ƒ��[�I�ɕ����q�ǂ������̉�b�������B���Ԃ�A�������������i�͂��܂ł͒��������̂ł͂Ȃ��̂��낤�B���̎q�����͂��̎q�����Ȃ�ɓ��X�����ȋ���ɂ߂Ȃ���A����ɍ~�肩�����Ă���^���Ɍ��C�ɗ����������Ă���킯���B�₪�Ă��̎q�������x���邱�ƂɂȂ��\�ꐢ�I�Љ�͂ǂ̂悤�ɓW�J���Ă����̂��낤���B�����g�͂��̎q�ǂ������̌��݂��m�肵�A���̖����̉\�����Ђ�����M�������B���̂��肰�Ȃ�������m���Ă��m�炸���A����ȉ�b�����킵�Ȃ���V�ы�����Z�̓��́A�t�̗z�˂̒��Ő��������ƋP���Ă����B
�@ �₪�Đ����𐋂������̎q�ǂ������́A�Ƒ���Љ�K�͂ɂ��Ă̊����̉��l�ς����߁A�V���ȉ��l�ς�n��o���A��������ɂ��܂Ƃ͈قȂ関���Љ��z���グ�Ă������Ƃ��낤�B����Ȏ��オ����������A�������Â��N��w�̎҂����̓J�r�̐���������̉��l�ς��̂āA�V��������̂��肩���ɏ_��ɓK�����Ă��������Ȃ��B���ꂪ�ǂ�Ȃɓ���Ă��A�܂�Ƃ���A��������̂��őP�̓����Ǝv�����炾�B
�@ �o���̖L�����̂䂦�ɁA����҂��Ⴂ���ォ��h������A��ɂ����̂͌��\�Ȃ��Ƃł���B�����A������悢���ƂɁA�g�̂قǂ��킫�܂��������̏�Ȃǂɂ��Ⴕ���o���肵����낭�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B�Â����O�⎞��x��̉��l�ς���������ŁA�Ⴂ����̎��R�Ȋ�����}�����ނȂǂ����Ă̂ق����B���{�̓`�������ׂ����Ƃ����X���[�K���̂��Ƒ�a�S��U��V�X�̉�̂悤�Ȑl�X�́A���ԂƋ����̉Ԃ̌����ȎU�肬��������Ƃ݂Ȃ�����ق����悢�B
�@ �k�R���̎��i�A�u��������̘I�v�̏I���̂ق��ŁA�g�c���D�͐g���킫�܂��ʘV�l�̕��Q�������������ŋ��e���Ă���B�u�g�̈��������������l�Ԃ́A�N�V�����X���e�e��e�p��p����C�������Ȃ��Ȃ�A�l�O�ɂł���邱�Ƃ���l����悤�ɂȂ�B����ɑ傫���X�����[�z�̂悤�Ȑg�ł���Ȃ���A�����̎q�⑷�̂��Ƃ�����S�z���A�q���̔ɉh�����͂������Ɨ]���Ɏ�������悤�ɂȂ�B�܂��A�Ђ����疼�_�⎩�ȗ��v��Nj�����S���肪���܂�A���̂̂��͂�̐��_�������킩��ʂ悤�ɂȂ��Ă��܂��B����Ȏp�͌���ɂ����Ȃ�������ł���v�Ƃ����̂����̎咣���B
�@ �Z�����A�ÓT�̑f�{�Ȃǂ܂�łȂ����̂悤�Ȑl�Ԃ�������ƏE���ǂ݂��Ă݂������ł��[���l���������Ă��܂��悤�Ȍ��t�ł���B�܂��͎����Ɍ�����ꂽ��l�̉��߂Ƃ��āA��������S�ɗ��߂����Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B
�@ ����ɂ��Ă��A�����ŗV��ł������̒j�̎q�����̈�l�́A�ƂɋA�������Ƃǂ������̂��낤�B���ꂳ��Ɍ������āu�ǂ�������V��������������́H�v�Ɛ^��Őq�˂��̂��낤���B�܂��A���������̎q�����ۂɂ����q�˂��Ƃ���A���ꂳ��̂ق��͂����������Ɠ������̂��낤���B���c�̍��ɗU���A�v�������Ȃ������ꂱ��ƂƂ�Ƃ߂��Ȃ��A�z���߂��炷����ł͂������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N4��25��
�\�O���̋��j����
�@ �\�\�����͏\�O���̋��j������Ȃ��A���������ł̂��܂��܂ł����Ă���Ƃ��Ă��邩��A���낻��U���̃e���t�H���R�[���������Ă����������Ȃ��ȁ\�\�����v���Ă�����A�Ă̒�A�L�����L�����L�����Ɠd�b����o�����B����l���\����̂��Ƃł���B��b�킩�痬��o��Ɠ��̐��̋����́A�ԈႢ�Ȃ��M�B�䍂���ݏZ�̐Γc�B�v�h���L�������̂��̂������B�Γc���̌��Ƃ���ɂ��A���\�]�N�ɂ킽�邻�̌��I�Ȑl���ɂ����āA�u�\�O���̋��j���v�͂Ȃ������b�L�[�E�f�C�ɂȂ邱�Ƃ����������̂��Ƃ����B�����l����������Ƃ������Ă��邩��h���L�������ƌĂ�Ă���̂����A���������̖��̂��Ƃ����͂���B
�@ ����ɂƂ��Ă��̂��Ƃ����b�L�[�������̂��A�����b�L�[�������̂����܂��ɒ肩�ł͂Ȃ����A�������̐Γc���Ɨ���̕䍂�w�ŏo�������̂���͂�\�O���̋��j���̂��Ƃ������B���̎��ȗ��A���́A�h���L���������C�ɓ���̏\�O���̋��j����I��ł͂��̉������Ȋق�K�ˁA���̘V�l�̊�Ȑ��Ԃ̉𖾂ɓw�߂Ă����B�����炪�Z�����Ă����\�O���̋��j���ł��邱�Ƃ�Y�ꂽ�肵�Ă���ƁA����̂ق����A�u�����͓��ʂȓ��̂͂��Ȃ�ł����ˁA�����ς�������Ƃ��Ȃ��đދ��ł˂��c�c�v�ȂǂƁA���X�Ӓn���Ȍ����œd�b�������Ă���悤�ɂȂ����B
�@ �W�O�\�[�p�Y���������̂Ƃ��Ȃ��v�̂ŁA�Ȃ�Ƃ����͂��̔j�V�r�Ȑl���͗l�𖾂��ɂ��邱�Ƃ͂ł����B�ȗ��A���̘b��ق��M�ɑ���Ǝ��Ԃ������Ă��Ă���̂����A���X�̎���Ŏ��M���啝�ɒx��A�܂��E�e�ɂ͂������Ă��Ȃ��B����Ȏ������炩���悤�ɁA�u�������e�������グ��܂ł͎��˂Ȃ���Ȃ��B���Ə\�l�A�ܔN�قǂ����Č��e���d�グ�Ă����ΕS�܂ł͐�������v�Z�ɂȂ���Ȃ��c�c�v�ȂǂƐΓc���͌y����@���B��������������ƁA�u����Ȃɒ��������ꂽ�ᐢ�̒��̖��f�ł���B�܂��A���Ɣ��N�قǂŏ����グ���Ⴂ�܂�����A����܂ł̂͂��Ȃ������Ɗo�債�Ă����Ă��ق��������ł��ˁv�Ƒ����ɐ�Ԃ����肵�Ă���B
�@ �u�\�O���̋��j���v�Ɂu���Łv�̂��܂��܂ł����Ƃ����A�L���X�g�Ɏ߉ނ܂ł����_�u���p���`�̃A�����b�L�[�E�f�C�́A�Γc���ɂƂ��Ă͓�d�̃��b�L�[�E�f�C�Ƃ������ƂɂȂ�B���̂��߂ł������ɕ\�h�K�₵�Ȃ��킯�ɂ������Ȃ����낤�Ǝv�������́A�\�O���̌ߑO�O���ɕ{���̎�����o�����A�����������ɏオ��ƂЂ�������ܖ�ڎw���đ���o�����B�b�{���a�C���^�[�`�F���W��ʉ߂��鍠�ɂ͓��̋����������ł��āA���ӂ̎R�X�����X�ɔ������֊s�����͂��߂��B�H���ɎԂ��Č����U������ƁA�O�q�̎R�X�z���ɁA���܂������肩��o�߂悤�Ƃ���x�m�̎p���]�܂ꂽ�B
�@ �c���Ղ������x�A����E��ɁA�b���P�x�̔����s���Ő�����Ɍ��Ȃ���A��������������ɑ��蔲���A�������O�ɂ͐z�K�p�[�L���O�G���A�ɓ��������B���傤�ǂ��̂Ƃ��A�ߌ���ɑ傫���ʒu��ς��������x�A��̂Ȃ��قǂ���A�����������̑��z�������Ă����B
�@ �\�\�V��ɂ��b�܂�Ă��邱�Ƃ�����A���{�b�`�R�ɓo���ĎR�x���i�߂Ă����Ȃ���͂Ȃ��ȁB����̕䍂�s���͂����܂ŕ\�h�K��Ő���}�����Ƃ��Ȃ�����A�����͘e���s���y���ނɂ�����\�\�����v���Ȃ��������́A���J�ō��������荑����\���`���ɉ��K���ւƏオ�����B�����Ă������獂�{�b�`���ʓ����ɒʂ��鋌���R���ɓ������B���{�b�`���ʓ����܂ł͂킸���ȋ����ɂ����Ȃ��B�����A�Ԉ�䂪����ƒʂ��}��̍ד��͐[���тɕ����Ă��āA�������L�̕�����܂��Ȃ��c���Ă���B�u�F�o�v�ɂ����Ӂv�ȂǂƂ����x���������Ă��邪�A�c�O�Ȃ��ƂɁA�܂������ŌF�ɏo���������Ƃ͂Ȃ��B
�@ ���{�b�`�R���ւƑ������ɓ���A�R�����班���������Ƃ���ɂ���q������ɒ����܂ł͂����Ԃ鏇���������̂����A����ȏ�͑O�i�ł��Ȃ��Ȃ����B�H�ʂ��[���ł��c��ɕ����A�`�F�[���������Ă����ꎕ�������Ȃ���������ł���B��N�Ȃ�O�������l�����߂܂łɂ͎R�������̒��ԏ�܂ŏオ���悤�ɂȂ�̂����A�܂���ʂ̎c�Ⴊ����Ƃ��납�炷��ƁA���~�͂�͂�ُ�ɐႪ���������̂��낤�B�O���O�\���[�g���قǂ̂Ƃ���ɂ͏����Ɨp�̃u���h�[�U�������ǂ��悤�ɂ��Ăۂ�ƈ��u����Ă����B���̂ق����班����������s���Ȃ���A�����܂ŏオ�����������̂炵���B
�@ ��q������݂����ŁA�q������e�̃X�y�[�X�Ɉ�䃏�S�������߂��Ă����B���������ɎԂ�u���A�c��݂��߂Ȃ��璸��������ĕ����������B�ߑO�Z�����̂��ƂƂ����āA�R�̎Ζʉ����ɐ����~�낷���́A�c��̕\�ʂ���C���z���Đg���h���قǂɗ₽�������B��������ɂ�������炸�A��т̙z�Ƃ������͋C�ɐg���S���������܂�v���ł͂������B����������`�����Ȃ���������Ƃ����y�[�X�ŎO�\���قǕ����ƁA������̎R���ɒ������B�R�̎ʐ^���B��ɂ��Ă�����q��l�Ƃ͓r���ł��������̂ŁA����ɗ������Ƃ��ɂ͑��ɐl�e�͂Ȃ������B
�@ �����̌��͑u�₩���̂��̂������̂����A���V�̊��ɂ͎��E�S�̂��������ŁA���҂��Ă����قǂ̓W�]���y���ނ��Ƃ͂ł��Ȃ������B��C�������ɂ͂悭������x�m�R��b�����A����ɂ͖ؑ\�̌�x�┒�n�A������݂̌������Ɏp���B�����܂܂������B�����̏�ƁA���A�䍂�ƁA�����̔����x�����͂悭�����Ă������A�����̌i�ςɂ��Ă����܂ЂƂ�����Ȃ������������B
�@ ���ł̂��܂��܂ł������̏\�O���̋��j���́A�䂪�g�ɂ͂�͂�A�����b�L�[�E�f�C�ł������̂��c�c�B����ȋ��ɂ����Ȃ��v���ɂЂ���Ȃ���R�����������B�����ĎԂ̂Ƃ���ւƖ߂�r���A�c��̈ꕔ���n���o���A�H�ʑS�̂��悤�ɂ��ė���Ă���Ƃ���ɏo���B�n���o�����������̗z���𗁂тē����ɋP���Ă���B�Y��Ȑ������A���[�͐��X��A�O�Z���`�قǂ�����U�o�b�ƌC���ƒ��ɓ��ݍ���ł����Ȃ��ƌy���l�����B�����Đ����悭�����ɑ��ݓ��ꂽ�̂��ߌ��̂��Ƃ������B
�@ ���̏u�ԁA���̐g�͎̂߂ɂȂ��Ē��ɕ����A�E�̑��������ɂ����܂܁A�K�c�[���Ƃ����݂��������ĂĘH�ʂɌ������@������ꂽ�B���˓I�ɐg�̂��E�ɂЂ˂����̂Őh�����Ĕw����㓪����ł�����̂����͔�����ꂽ���A���̂����ɁA�E�I�ƉE�����Ƃɗ����ɂƂ��Ȃ��Ռ��̂��ׂĂ��邱�ƂɂȂ��Ă��܂����B���������������ς�킩��Ȃ��܂܂ɁA���͕K���Ɏ�����������A�E�r�ƉE����тɑ��錃�ɂɂ��炭�����Ƒς��������B
�@ �ɂ݂����炦�Ȃ���Ȃ�Ƃ������オ��A���������������ƒ��߂Ă݂�ƁA�n���o�������Ɍ��������̂́A�Ȃ�ƃK�`�K�`�ɓ�����������ȕX�ł������B�Ⴂ�����x�ƂȂ��~�R��Z����̏t�R�ɓo�������Ƃ̂���g�Ȃ̂�����A�������Ă����Ȃ����ƌx���S�������Ă�����ׂ��������̂����A�z�����x��������y���ɐU�镑���Ă��܂����̂��B
�@ ���ꂩ�����قǂ͕I���������Ȃ�ɂB���܂ł��E���ɂ͂������ɓݒɂ��c���Ă͂��邪�A�s�K���̍K���Ƃ������A���̂܂ܓ����Ȃ��Ȃ�����A���Ɉُ�����������肷�鎖�Ԃɂ͂�����Ȃ������B����̃Z�[�^�[�̏�ɂ�������Ƃ����h���p�̃_�E���𒅍���ł����̂ŁA���ꂪ�N�b�V�����ƂȂ��Ă��Ȃ�Ռ����z�����ꂽ����Ȃ̂��낤�B
�@ �\�\���[��A����͂ǂ����\�O���̋��j�����M��炵���ȁA���������������A�������y����ł��鎄�Ɍ�����ꂽ�h���L���������M�肩�ȁ\�\���}�C���ɂ���Ȃ��ƂȂǙꂫ�Ȃ���A�������ƕ����ĎԂ̂Ƃ���܂Ŗ߂�ƁA��q�̓�l���܂����̏�Ɏc���Ă����B�X�ɑ����Ƃ��ĂЂǂ��g�̂�ł��Ă��܂����ƌ����ƁA���������ƂɁA���̓�l���܂����������ڂɑ����Ă��܂����̂��ƁA���Ȃ���b���Ă��ꂽ�B�ނ�̂ЂƂ�Ȃǂ́A��ȎB�e������ꂽ�U�b�N���Ɠ����ʂɌ������@�������A�@�ނ̈ꕔ�����Ă��܂����Ƃ̂��Ƃł������B�ӊO�ɂ���Q�҂͎������ł͂Ȃ������̂��B
�@ �ɂސg�̂��x�߂Ȃ��炵���������Ƃ낤�Ǝv���Ԓ��ʼn��ɂȂ�ƁA���̂܂l���Ԃقǖ��荞��ł��܂����B�ڂ��o�߂��̂͏\�ꎞ�߂��̂��Ƃ������B�O�C���������Ԃ�Ƃ�����A�������ޗz���̂��ߎԒ��͏������炢�ɂȂ��Ă���B���s�ɂ͍������͂Ȃ��قǂɍ��̒ɂ݂������܂����̂ŁA�ԊO�ɏo�Ď��ӂ��܂������U�Ă݂��B���̂܂ɂ������ƈ�������Ă��Ă��āA�u���h�[�U���������i�߂Ă���Ƃ��낾�����B
�@ ������Ɛ����|���Ęb���Ă݂�ƁA��͂肱�̓~�ُ͈�ɍ~�Ⴊ���������Ƃ����B���{���ӂł���������ӂŎ��\�Z���`���̐Ⴊ�ς����������������炵���B�R�����ԏ�܂ł̓��H�̏���͂��܂ł�����̂��Ɛq�˂�ƁA�����̒����܂łɂ͍�Ƃ��I����\�肾�Ƃ̕Ԏ��������B�ǂ�������������߂����Ƃ������Ƃ炵�������̂����A���̈���Ⴂ�̂����ł����Ԃ�ƒɂ��ڂɑ����Ă��܂����킯�ł���B
�@ ���{�b�`����̋A�r�A���H�e�ɓ����̈�[�̈ꕔ�炵�����̂��U�����Ă���̂��������B�Ȃ낤�Ǝv���ċ߂Â��Ă݂�ƁA�����́A�傫�Ȕw���̈ꕔ�ƁA�ǂ��̂��̂Ƃ����f����������̖є�̒f�ЁA�����āA�܂����Ɩт��������܂܂̓�̋r���������B��ɂƂ��Ċώ@���Ă݂�ƁA��̋r���͂ǂ������r�̑�߂����̕����ł������B�F��`���琄������ƁA�ǂ���炻���͂��̎��ӂɐ�������J���V�J�̈�[�̈ꕔ�ł���炵�������B�ꌩ�����Ƃ��뎭�̂���ɂ����Ă��邪�A�c���ꂽ�є�̖т͂��Ȃ蒷�߂ŖѐF�������Ԃ�ƍ�����ттĂ���A���̂��̂Ƃ͂��Ȃ����Ă���悤�Ɏv��ꂽ����ł���B
�@ �R�̎Ζʂ̐�ɖ�����Ă�����[������Ȃǂʼn���������ĘH��ɗ����A��^�̎Ԃ��u���h�[�U�ɉ��x��瀂���Ă��̂悤�ȏ�ԂɂȂ������̂Ȃ̂��A����Ƃ��A���炩�̌����ő��₦�����ƁA���̓����ɐH�ׂ�ꂽ�莩�R�ɕ��H�����肵�Ă����Ȃ������̂Ȃ̂��͂킩��Ȃ������B���������S�O�����o���͂������A���������̂ɂ͈Ⴂ�Ȃ������̂ŁA���D���ȐΓc���ւ̂��y�Y����ɂƎv���A��̋r���Ɩє���傫�ȃr�j�[���܂ɓ���ĎԂɐςݍ��B�����Ďc��̔w���̈ꕔ�⑼�̏��Ђ͂������̗т̒��ɖ��߂Ă�����B
�@ ���{�b�`�R�������ƁA���K�o�R�ŏ��{�ɔ����A���ܖ�̐��[���k�ɑ���L��_���ɏo���B���{�~�n���ӂ͂��傤�Ǎ��̉Ԃ����J�ɂȂ������肾�����̂ŁA�����ōs���t�̕����U�����ɂ����ƁA������x����̍��������ł���Ƃ����K�^�ɂ��b�܂ꂽ�B�䍂���ւƌ������r���̎O�����A�x������т̔��n����́A�k�A���v�X�A��̐��Ζʉ����ɐ����~�낷�����������ɐ����A�җ�ȓy���������オ���Ă����B���̕t�߂̏���F�ɉ��݁A�O���̐M�����悭�����Ȃ��قǂ̌������������B
�@ ���̐��܂����y���̒��𑖂邤���ɁA���͎q�ǂ��̍��Ɋ��x�ƂȂ��̌������t�̉������ۂ̂��Ƃ�z���N�������B���������̐����C��ɕ����ԍ����́A�t�ɂȂ�Ƃ����ΔZ�����F�̖��̂悤�Ȃ��̂ɂ����ۂ�ƕ����A����Ă��Ă����z�������Ȃ����������������悤�Ȃ��Ƃ��������B���ׂ̒����̓����n�тō��������オ������ʂ̍����̍����A�����ɏ���Ă͂���B��т̏��ɂ܂ʼn^��Ă���B���ꂪ�������ۂ̃��J�j�Y�����Ə��w�Z�̗��Ȃ̎��Ԃɋ����������������̂��B
�@ �r���Œ��H���Ƃ����肵���̂ŁA�\�h�K���̐Γc��ɓ��������̂͌ߌ�߂��ł������B���������y�Y�Ɏ����Ă����Չ��̗r㻂������Ɏ�n���A�Ԃ̒��ɂ����ЂƂς�������y�Y������̂����Ɠ`�����B�����̓y�Y�ł͂Ȃ��ȂƎ@�m�����Γc���́A�b�����Ɏ��̗l�q�����������Ȃ���A�u���̍l���邱�Ƃ�����A�܂��ǂ������N�ȃV�����m����Ȃ��낤�H�v�Ɩ₢�����Ă����B
�@ �h���L�������ٖ̈������Ƃ͂����A����͔��\�܍ɂȂ�V�l�ł���B�����Ȃ���������o���ċ������킯�ɂ������Ȃ��Ǝv���A�����ɁA����͍��{�b�`�ŏE�����J���V�J�̑��̐�[�����ƍ������B����ƁA�Γc���̌�����́A�u���₠�A���ꂾ����������������邱�Ƃɂ����B�ȑO����������ŏ��蕨���Ȃɂ������ǂˁv�Ƃ����\�z�O�̕Ԏ����߂��Ă����B�������̃h���L�������ɂ��ߍ��ɂȂ��ĐS���̕ω����N�����Ă������̂炵���B
�@ �V���[���b�N�z�[���Y�����͂��߂Ƃ��A���N�ɂ킽���ĊC�O�̗l�X�Ȑ���������|�Ă����W�ŁA�Γc���ɂ́A�����̈�[�̈ꕔ�������肷��ƁA���̑S�̑��₻���Ɏ���܂ł̔ߎS�Ȕw�i�ɂ��ꂱ��Ƒz�����߂��炷�K�Ȃ��������B���̏K�Ȃ����Ƃ�ɂ�ă}�C�i�X�ɍ�p����悤�ɂȂ�A�ߔN�ł͐������̎��[��ڂɂ����肷��ƁA�S���₩�ł͂���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��炵���̂��B�ӊO�Ȃ��Ƃ����A�ǂ����A���S�A����L���X�g�S���h���L�������̑̓��ɉ萶���͂��߂����̂̂悤���B
�@ ���������̌v�Z�Ⴂ�Ɍ˘f�����o���͂������A�Ƃ��������̓y�Y���͎Ԓ��Ɏc�����܂܂ɂ��āA�܂��͕\�h�̈��A�����܂��邱�Ƃɂ����B�\�O���̋��j���̐Γc���ւ̑Ή��̎d���ɂ����낻�����ς����K�v�Ȃ̂�������Ȃ��ȂƂ����v�����A��u���̉����悬���Ă������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N5��2��
���x�͐������J���V�J��
�@ �Ő�̐ꖡ�����͑��ς�炸�̐Γc���ƎG�k�ɉԂ��炩�������ƁA�����ċ߂��̉���ɏo�������B�����Ă����̘I�V���C�ɂ���Ȃ���A�̂�т�ƓԂقǂ̎��𑗂����B�A�蓹�ɂ͔���������齂����݁A�C�̌����܂܂ɂ������܂�ł́A����ɓ�A�O���Ԃقǘb�����B���܂��܃��@�C�I���j�X�g�̐씩��������̂��ƂȂǂ��b��ɂ̂ڂ����B
�@ �씩����̃��@�C�I�����̑f���炵����Γc���ɓ`�����͎̂����������A����ȗ��A�����������肻�̉��ɖ������Ă��܂����炵���A�x�b�h���[���̈���ɂ̓��@�C�I��������ɂ����씩����̎ʐ^���ꖇ�\���Ă������B�����ɂ���Ă͕����̂����Ȃ��V�l�����A�C�M���XBBC�Ζ����͂��߂Ƃ��钷�N�̊C�O�����Œb���グ��ꂽ�R����͓I�m���̂��̂Ő����̋������Ȃ��B�e�ՂȂ��Ƃł͐l��F�߂������J�߂����Ȃ����̘V���̖ڂƎ��ɁA�씩����͓K�����Ƃ������ƂȂ̂��낤�B
�@ �����\�h�K����I���ĐΓc�@�����Ƃɂ����̂͌ߌ�㎞�����������B�ꔑ���Ă��\��Ȃ������̂����A�����Ă������Ȃ������̂́A�\�O���̋��j���̂����ɕʂ��̂��o���̔��w�ɂ����Ȃ��Ă���悤�ȋC�����ĂȂ�Ȃ��������炾�����B�䍂�����珼�{���o�ĉ��K�s�X�ɔ��������ƁA�����\�㍆�����̃t�@�~���[���X�g�����ɔ�э��B�����Ă��̂��X�̈�p�ɐw����Č��e�����ɖv�����Ă��邤���ɁA�����͏\�l���y�j�̌ߑO�뎞���߂��Ă��܂����B
�@ �����ňꌏ�����ƂȂ�悩�����̂����A���������ƂɁA�̓��ɐ��ދC�܂�����A�@���M���Ă������̂悤�ɂ��������Ƃ����߂��͂��߂��B�����āA�m�[�g�p�\�R���̃L�[��@�������Ă��鎄�̎����ɁA���̒����A�u������x���{�b�`�ɓo���Ĕ��������Ă������Ă����̂������Ȃ����I�v�ƁA�U�����肽�Ă�悤�Ȍ��t�������Ă����̂ł���B�C�܂���̗U�f�ɒ�R����͓̂���B�����ɎԂɖ߂������́A���ǁA�[��̍��{�b�`�R���ڎw���čēx�A�N�Z���ݍ��ނ��ƂɂȂ��Ă��܂����B
�@ ���K�����獂�{�b�`���ʂւ̗ѓ��ɓ����ĊԂ��Ȃ��A�ˑR�A�O���ɉ��F�����̗����_�X�ƕ����яオ�����B���˓I�Ƀu���[�L�݁A�w�b�h���C�g�ɕ����Ԃ�����\�قǂ̌��_�Ɍ�����ƁA������̂͐Î~���A������̂͂킸���ɗh�ꓮ���Ȃ����Ăɂ�������Î����Ă��銴���ł���B���F�����̓_�����g�ɂȂ��Ă���炵�����Ƃ���A����炪�����̊�ł��邱�Ƃ͂����ɂ킩�����B�k�C���Ŗ铹�𑖂��Ă��鎞�Ȃǂɂ����Ώo�����G�]�V�J�̊�̋P���ɂ悭���Ă���B�����v���Ȃ��珙�X�ɋ߂Â��Ă݂�ƁA��͂肻���͖쐶�̎��̈�Q�ł������B���̗l�q���炷��ƁA���̋ߕӂɂ͑������̎����������Ă���炵���B
�@ ���̌Q�ƕʂ�R�����ʂɌ������Ăǂ�ǂx�������Ă��������ɁA������Ƃ����^�₪�N���オ���Ă����B�O���E���ĎԂɐςݍ��J���V�J�̌�r��[���ƕ\��̈ꕔ�炵�����͎̂��ۂɂ͎��̂��̂������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����^���������͂��߂��̂��B���������̎v���͑��s���d�˂邤���ɂ������������Ȃ��Ă����B
�@ �����A���S���[�g���߂��܂ō��x���グ���Ƃ��̂��ƁA�ˑR�A����ȋ^�O����|���Ă����悤�ȏo�������N�������̂��B��^�̓����̂��̂炵�������e����u�Ԃ̑O��������A�E��̎R�̎Ζʂ������삯�o�����Ƃ���ł҂���ƐÎ~�����B�Ԃ��߂ėl�q��`���Ƒ���������Ƃ�����̓�����T���Ă���C�z�ł���B�������܉����d������肾�����̍����e�̂ق����Ƃ炵�o���ƁA���F���傫�ȑ���̗��̊Ⴊ�A���ւ̒��ňٗl�Ȃ܂łɂЂƂ��햾�邭�P���Č������B�S�̓I�ȕ��e�͂ǂ������R�r�̂���Ɏ��Ă��āA�����ɂ͑傫�����ɔ����������̓�{�̊p�������Ă���B�������A�����d���̌����z���č��������яオ����������̑��ʂ́A�ӂ��ӂ��Ƃ������тŕ����Ă���悤�������B�������V�F�t�F���̕s�C���ȗe�e�����A�z�����邻�̓Ɠ��̑��e�́A�ǂ����Ă��J���V�J�̂��̂ɈႢ�Ȃ������B
�@ ���𗁂тȂ��炵�炭�����ƘȂ�ł�������́A�����炪����ȏ�߂Â����Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ킩��ƁA�}�ȎΖʂ�I�R�ƕ��݂̂ڂ�A�����ő傫�����Ɍ�����ς��đ�����������݂͂��߂��B�����Ԃڂł͂���������ǂ��A�������̂̌`�����̓��C�g�̌���ʂ��Ă�������Ɗώ@�ł����B�����ɐ捏�����������̂���Ƃ͐F���`������Ă���B��r�̑�߂�����ɂ����Ă̐�[���͎v���̂ق��ׂ��Z���A�Ԃɐς�ł����̋r����������ł������B���̈�[�̈ꕔ���������̂���������قǂȂ�������������A��͂肻���͓����l�����ʂ�ɃJ���V�J�̂��̂������̂��B
�@ ����ɉ�������J���V�J�̍��e�������������ƁA���͍ĂюR�����ʂɌ������ĎԂ𑖂点���B���łɏ��Ⴊ�I����Ă������߁A���x�͂Ȃ�̋�J���Ȃ����{�b�`�R�����ԏ�ɒ������Ƃ��ł����B���v������Ƃ܂��ߑO�O���O�������̂ŁA�Ƃ肠������������܂ł��̏�ʼn������邱�Ƃɂ����B
�@ �ߑO�������O�A�l�̘b���������ɂ��Ėڂ��o�܂��ƁA���������Ƃɂ��Ȃ�̐��̎Ԃ����ԏ�ɂƂ܂��Ă���ł͂Ȃ����B�����Ă���ԂɎ��X�Ƃ���Ă������̂炵���B���Ⴊ�I��蒸��܂ōs����Ƃ�������Ԃ�O���̂����ɗ���Ă����̂��낤�B�i���o�[���m�F���Ă݂߂�ƂقƂ�ǂ��n���̎Ԃ̂悤�������B
�@ �قǂȂ����̋瑾�z�������Ă����B��S�̂͂������ɉ����������ŁA�������x�X�g�̎��̒��]�Ɋr�ׂ���܂ЂƂł͂��������A����ł��O�����͂����ƓW�]���������B�k�A���v�X�̎R�X���悭���ʂ����Ƃ��ł������A�����������ł͂����������x�m�R�̎p��]�ނ��Ƃ��ł����B
�@ �R�̌i�F�߂����ƁA�Ԃ̒��Ŏl���Ԃقǂ�������Ɩ������B�ڂ��o�߂��Ƃ��ɂ͋C�������Ȃ�オ���Ă��āA�����ʂ��镗���S�n�悢�����ɕς���Ă����B���������̈��ܖ�z���Ɏ����𑗂�ƁA�䍂�A��O�A�����x�Ȃǂ̎R�X�̒������A�������������z�̌��𗁂тĔ����s���P���Č������B
�@ �R�����ԏ�����Ƃɂ���O�ɁA�r�j�[���܂ɓ���Đς�ł�����������̃J���V�J�̋r���̐�ƕ\��̈ꕔ���ǂ��Ȃ��Ă��邩���m�F���Ă݂��B�E�������ɂ͂��Ȃ芣���Ă���悤�Ɍ������̂����A�ԓ��̉��x�����������������Ă��Ȃ蕅�H���i�炵���A�@��˂��悤�ȈُL���Ă���B�\��̖̑т�������ƐG���������Ń|���|���Ɣ��������Ă��܂��L�l�ŁA�ƂĂ����̂܂ܒ����ɂ킽���ĕۑ��ł���悤�ȏ�Ԃł͂Ȃ������B
�@ ���������Ȃ��̂ŁA���K���ւƌ������ĉ���r���őO���J���V�J�̈�[���������ꏊ�ɎԂ��߁A�w���̈ꕔ�������̂Ɠ����Ƃ���Ɏc��̕��������߂Ă�邱�Ƃɂ����B�܂������{�b�`�ŃJ���V�J�̈�[�̈ꕔ�����A���ʓI�ɂ��������Ă�邱�ƂɂȂ낤�Ƃ͗\�z���ɂ��Ă��Ȃ������̂����A������܂��u�����̉��v�ƌĂ����̂̂ЂƂł͂������̂��낤�B
�@ ���K���ō�����\���ɍ������A���������ʼn��J�C���^�[�`�F���W�ɓ����悤�Ƃ������ɂȂ��āA�ˑR�܂��e���a�̔���ɂƂ����Ă��܂����B���J�C���^�[�`�F���W���璆�����ɏオ�炸�A���̏�����O�ʼnE�܂��ĉ����p�[�N���C���ɓ���A�C����ʂɔ����Ă݂悤�Ǝv���������̂ł���B�����Ԃ�̂ɓ�A�O�x�ʂ������Ƃ̂��铹�Ȃ̂����A�����ׂ͍��_�[�g�̎R���ŁA�[���тɕ����W�]���قƂ�ǂ����Ȃ������B�Ƃ��낪�A�n�}�Œ��ׂČ���ƁA�ߔN�͂������蓹�H������������K�ȃh���C�u�E�G�C�ւƕϖe�𐋂��Ă���炵���B�����p�[�N���C���ȂǂƂ����������ď̂�����ꂽ�̂��������̂��߂Ȃ̂��낤�B����Ȃ�Έ�ڂ��̕ϗe�Ԃ�����Ă����̂������Ȃ����낤�Ƃ����킯�������B
�@ �����p�[�N���C���ɓ���ƍĂтǂ�ǂx�������肢�����ɓW�]���J���Ă����B�ʍs�Ԃ������Ȃ����A���H�͊��S�ܑ�������ӂ̌i�ς��̂ƈ�����Y��ɐ������Ă���B�ؗ��̊Ԃ���͕䍂���ƂȂǁA�k�A���v�X���ʂ̎R�X�����]���ꂽ�B�C�����悭���Ȃ��炵�炭����ƁA���L���p�[�L���O�G���A�̂���W�]��ɒ������B�܂��ł��ĊԂ��Ȃ������̓W�]��ł���B
�@ �W�]��ɗ��������͖]�O�̕��i�Ɏv�킸����ۂB�ቺ�����ς��ɐz�K���L����A���̌������ɂ͔����x�A�p�m���}�ʐ^���̂܂܂ɗY��Ȏp�������Ă���B����܂łɂ����낢��Ȋp�x����z�K�┪���x�̌i�ς߂Ă������A���̈ʒu�Ɗp�x���炻����ڂɂ���̂͂��ꂪ���߂Ă̂��Ƃ������B�E���͂邩�ɂ́A�z�K�̐����V���쐅�n�ƂȂ��ė���o�邠����̒J�ԂƁA���̒J���ׂ��ŎO���ɂ̂т钆�����ƒ��쓹�����Ղ��ꂽ�B�W�]��̈ʒu�����悢�����Ƌ������p�ɂ��邽�߂��A�z�K���̂��̂̌i�F�����̃r���[�|�C���g���璭�߂������������Ƒf���炵�������B
�@ �����A����ɂ��܂��ċ������͔̂����x�̓W�]�̌������������B����ɔ����x�Ƃ͂������̂́A���̘A��͉��ɒ����傫���L�эL�����Ă��āA���̑S�e����]�̂��Ƃɂ����߂�͈̂ӊO�ɓ���B���̒m�邩����ł́A�����̖�ӎR������т⒁���R�n���ӂ̎R��ɂ́A���ȎR����Ҋ}�x�܂łɂ����锪���x�̑S�e��]�߂�Ƃ���͌�������Ȃ��B�����������̊���A�z�K�����肩��͂��Ȃ�悭�͌�����̂����A�����x���Ⴗ���邤���ɋߕӂɐl�H�������߂���B���{�b�`�R����̒��]�͂���Ȃ�ɖ����������̂ł͂��邪�A�W�]�p�x�̊W�Ŕ����x�A����\������X�̎R�X�̌`���\���ɔc������̂͗e�ՂłȂ��B
�@ �Ƃ��낪�A���̓W�]�䂩��́A�������̎ԎR�A���ȎR�A���x�A�Ȍ͎R�Ȃǂɂ͂��܂�A�V��A�����A�Ԋx�A�����A�Ҋ}�ɂ�����܂ł̂��ׂĂ̕�X�Ƃ��̌`�܂ł��͂�����Ɩ]�ނ��Ƃ��ł�̂������B�X�̕�X�̖��ƌ`�𐳊m�ɍ��L�����ē�������܂ł��Ȃ��������̈ʒu���������ʂł����̂́A�z���̊O�̂��Ƃł������B���O������Ă��Ȃ��W�]��ł͂��������A���̒��]�ɏ��Ȃ��炸���|���ꂽ���́A�����x���c�������t�̓��̋L�����S�点�Ȃ���A�����[�����S�ɒ^�葱�����B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N5��9��
�����A�G���W���Ƀg���u�����H
�@ �����x�Ɛz�K�ߏI���A�Ԃɖ߂��ăG���W���������悤�Ƃ���ƁA�}�O�l�b�g���z���������Ƃ��̂悤�ȃJ�`���Ƃ��������������邾���ŁA�X�^�[�^�[���n�����Ȃ��B���x�����ꂱ�ꎎ���Ă݂��̂����A�ǂ����Ă��G���W���͋N�����Ȃ������B�o�b�e���[���オ�����̂��ȂƎv���ăw�b�h���C�g��_������A�ꎞ�I�ɃG�A�R�����쓮�������肵�Ă݂����A�����̗l�q���炷��ƃo�b�e���[�����ڂ̌����ł͂Ȃ��悤�������B�ǂ����A�d�C�n�����Z�����[�^���̂��̂̌̏�炵���B�G���W�����[�����J���A�f�l�Ȃ�̒m���������Ă���������������܂킵�Ă݂����܂�Ś��i�炿�j�������Ȃ��B
�@ �����͂���JAF��SOS���˗����A�ꍇ�ɂ���Ă͉��J�����K�̍H��܂Ō������Ă��炤�����Ȃ����낤�ƕ����������BJAF�̉�������̂��̂͂��������Ԃ�ƒ����̂����A���̊Ԃɂ����b�ɂȂ����͓̂�x�������B��x�͓��k�����ԓ��𑖍s���̂��Ƃ������B���W�G�[�^���ˑR�j���A�}���ȗ�p���R�ꂪ�N����A�G���W�����[������オ�锒���ɋC�������Ƃ��ɂ͊��ɃV�����_�[���Ă������s�s�\�Ɋׂ��Ă����B���܈�x�͈ɓ������̎R���ŁA��\���L���ȏ���������O�̃��C�g�G�[�X�����V�����Ƃ��̂��Ƃł���B�V�������i��ł����������낤�A����܂����s���A�ˑR�A�㕔���ȂŃ{�[���Ƃ����j�����A�V���[�b�Ƃ����������ĂēˑR�ԓ��ɔM��������̍������C�������݂����ɐ����オ��Ƃ����M�����Ȃ��o�������N�������B�g�[�n�̔z�ǂ��j�ꂻ�����獂��������������p�������o���Ă��܂����̂����A�K���㕔���Ȃ͖��l�������̂ōň��̎��Ԃ͖Ƃꂽ�B
�@ �R���Ńg���u�����������Ƃ��ȂǁA�ȑO��JAF�ւ̘A�����̂��̂���ς��������A���܂ł͌g�ѓd�b�Ƃ������킪���邩����ɗL���B�Ƃ肠����JAF�̃T�[�r�X�Z���^�[���R�[�����ڂ������������ƁA���{��n����o������̂ňꎞ�ԂقǑ҂��Ă��Ăق����Ƃ̕Ԏ��������B���̓W�]��ɂ͂Ȃ������O�����Ă��Ȃ������̂ŁAJAF�̏����W���ɐ��m�Ȉʒu��`����̂ɋ�J�������A�z�K�Ɣ����x�Ƃ��悭�����鉖���p�[�N���C�������̓W�]���T���Ăق����Ƃ������ƂŔ[�����Ă�������B���̎���̂��Ƃ�����AJAF�̃T�[�r�X�J�[�Ȃǂ͐��x�̍���GPS�����Ă���ɈႢ�Ȃ����A������̌g�т̔ԍ����`���Ă���������A���͂Ȃ����낤�ƍl�����B
�@ ���������ǔ����x�߂�����ӂ����������肵�ď��ꎞ�Ԃقǎ��Ԃ�ׂ��Ă���ƁAJAF�̃T�[�r�X�J�[������Ă����B���{��n����o�����Ă��ꂽ�T�[�r�X���͔n�ꗺ����Ƃ����������肵�����N�̒j���ŁA���̐g�U�����ɂ����t�g���ɂ������ւ�ɍD�������Ă��B�M��������n�ꂳ��̓o��ɁA����Ŗ������͊ԈႢ�Ȃ��ȂƎ��͋����m�M���o�����̂������B
�@ �Ƃ��낪�ł���A�Ȃ�Ƃ��͂�A������̊m�M�ȏ�̂��Ƃ��N�����Ă��܂����̂��B�K���Ɋŕa���Ă������̎҂Ɍ������āu���ʁA���ʁv�Ƃ�߂��Ă����}�a�l���A�M���ł��閼��̊�������r�[�Ɉ��S���A�܂����̎��Â����Ă��Ȃ��̂ɗl�Ԃ��R�̂悤�ɗ��������C�ɂȂ��Ă��܂��悤�Ȃ��Ƃ����܂ɂ���B���Ƃ����낤�ɁA����Ƃ܂������������N�����Ă��܂����̂��B
�@ �������ʂ�̏��I�����n�ꂳ��́A�G���W�����[�����J�����܂܂̎Ԃ�������Ɣ`�����ނƁA�X�^�[�^�[���n�����Ă݂Ă����悤�ɂƍ��}�����B�����ŃG���W���L�[���y���ƁA�Ȃ�Ƃ�����ʂĂ����ƂɁA����قǂ��ꂱ�ꎎ���Ă������Ȃ������G���W������x�ŋN�������̂ł���B���肪�@�B�łȂ�������A�u�Z���E���[�^�̂Ԃ��ŁA�����Ԃ�Ɛl���r�߂₪���āI�v�ƈꔭ�S�c���Ə��˂��Ă�肽���C���������B
�@ �Ƃ��낪�A����Ȏ��̐S�������������悤�ɁA�n�ꂳ��̓j�R�j�R���Ȃ���Ȃ�Ƃ��ӊO�Ȃ��Ƃ������Ă��ꂽ�B���̂悤�Ȏn���s�ǂ͌Â��Ȃ����Z���E���[�^�ɂ����N���錻�ۂŁA���傫�ȃg���u���̗\���݂����Ȃ��̂Ȃ̂��Ƃ����B�Z���E���[�^���V���������悤�ȏꍇ�A������Ƃ����J���̊��ݍ��킹�̈�����o�b�e���[�̋N�d�͂̂킸���Ȓቺ�Ȃǂ��U���ƂȂ��Ă��̂悤�Ȃ��Ƃ��N����炵���B����Ȏ��ɂ́A���炭�����Ă����Ă���Ď��s����ƁA�Ȃ�Ȃ��n�����邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��̂��������B���炽�߂ĉ��x���G���W���̎n���ƒ�~���J��Ԃ��Ă݂����A�捏�̎��Ԃ��R�̂悤�ɉ��ُ̈���N����Ȃ������B
�@ �u�������܂��n�����Ȃ��Ȃ�����A�Z���E���[�^���O������_�������Œ@���Ă݂Ă��������B��������Γ����Ǝv���܂��B�����ɖ߂蒅�����炢�܂łȂ�A����ʼn��Ƃ��Ȃ�͂��ł�����c�c�v�Ə��Ȃ���A�n�ꂳ��́A�ēx�n���s�\�Ɋׂ����ꍇ�̑Ή���܂œ`�����Ă��ꂽ�B�Ȃ�̂��Ƃ͂Ȃ��A�R���`�L�V���[�b�Ƃ���ɃZ���E���[�^�ɓ�A�O�����킹��A����͑f���Ɍ������Ƃ������Ă����Ƃ������Ƃ炵���̂��B�a�m�I�ł��肳������Ή��������܂������͂�����Ȃ��B���̐��͂Ȃ�Ƃ����Ȃ��̂ł���B
�@ JAF�̉���ł��������߁A����~�قǂ̏o����ƋZ�p���i�A�h�o�C�X�����h�ȋZ�p�ɂق��Ȃ�Ȃ��j�͖����ƂȂ����B�n�ꂳ��n���Ă��ꂽ��Ɠ��e�ؖ��̋L�^�p���ɂ́A�u�������A��ƂȂ��ŃG���W���n���B�X�^�[�^�[�̕s�ǂƎv����v�ƋL�����Ă������B
�@ �n�ꂳ��ɂ͓A�d�ɂ�����q�ׁA�ʂ�ۂɂƂ肠�����莝���ْ̐������i�悵���B���ł�AIC�̐�`�Ȃǂ����Ă���������i�����Ȃ����C�^�[�̐g�䂦�A�ǎҊl���̂��߁A����܂��܂����w�͂����Ă���킯�ł��j�A������������ǂ����ł��̈ꕶ��ǂ�ł�����Ă��邩������Ȃ��B�����ނ�Ɍ���𗧂������Ă����n�ꂳ��̎Ԃ��������Ă��邤���ɁA������JAF�̃T�[�r�X�ԂɎ�ނ����˂đ̌����悵�A�uJAF��\�l���ԕ����L�v�݂����ȃ��|���^�[�W�����̂������Ă݂�̂������Ȃ����ȂƎv������������B�������A����ȕX��JAF�T�C�h�ɂ͂����Ă��炦��̂��Ƃł͂��邯��ǂ��c�c�B
�@ �Z���E���[�^�̒��q�������Ȃ�A�����ɍŊ�̉��J�C���^�[�`�F���W���璆�����ɏオ�蓌���ւƒ��s����悳�����Ȃ��̂Ȃ̂����A�f���ɂ͂������Ȃ��̂����l�Ԃ̒[���ꂽ�鏊�Ȃł�����B�������������܂ŗ����̂����炢�܂�������Ԃ���͂Ȃ��ƁA�͂��߂̗\��ʂ肻�̂܂ܒC�쒬������ʂւƌ������đ���o�����B
�@ ���炭�A�N�Z���ݑ����Ă���ƁA������Ƃ����j�Ոē��\���݂����Ȃ��̂������Ă���̒n�_�ɂ��������������B�Ԃ��߂Ĉē��̉����ǂ�Ō���ƁA���̏ꏊ����S���[�g���قǍׂ��⓹��o�����Ƃ��낪�����R���䂩��̏��쓻�ł���Ƃ̂��Ƃ������B���܂ł͖K�˂�l���߂����ɂȂ��т̒��̍ד��ݐi�ނƁA�قǂȂ����̍ō��n�_�ɗ����Ƃ��ł����B������͓����ւƌ������ĉ��蓹�������Ă���B���̋����́A�����ɂ͎O����o�āA���J�A�z�K���ʂւƒʂ���v�H�ł������B
�@ �]�ˎ��㏉���A���t�����͍]�˂̒�����ɕK�v�Ȗ؍ނ�ؑ]�n�����璲�B���悤�ƍl�����B�����Ă����̖؍ނ�ؑ]����z�K�ΔȂ܂ʼn^�яo�����߂ɁA�ؑ]����\���\�я���\����\���쓻�\�O��\�z�K�Ƃ����ؑ]�J�Ɛz�K�Ƃ��Ȃ��ŒZ�H����ꂽ�B�������A���̃��[�g�͋����I�ɂ͍ŒZ���������̂̌�����������������H�ŁA�����͓r���ɐl�Ƃ��قƂ�Ǒ��݂��Ă��Ȃ��������߁A���̊J���Ďw��������v�ے�����̎���͋}���ɗv�H�Ƃ��Ă̖����͋}���ɂ�����Ă��܂����̂��Ƃ����B���ꂩ��قǂȂ����āA���̏��쓻�z���̒��R���́A���������ł͂��邪�����S�Ŏ��ӂɐl�Ƃ������A���݂̍�����\�������̉��K���z���̒��R���Ɏ���đ����邱�ƂɂȂ����悤�ł���B
�@ �������ɘȂ�ʼn�������ɑz����y�������ƁA�Ԃɖ߂��Ă���ɏ�����ʂւƉ����Ă����ƁA����ǂ́A�u���{�̒��S�̕W�܂�6.3�L���v�ƋL���������ȕW�����ڂɔ�э���ł����B�ȂA�����H�\�\�u���{�̒��S�v���Ĉ�̑S�̂ǂ�ȂƂ���Ȃ낤�H�\�\�����v���Ȃ��炢������͂��̒n�_��ʂ�߂��������̂����A���̏u�ԁA�C�܂�����܂�����ڂ��o�܂��Ă��܂����̂������B�������܈����Ԃ��Ă��̕W���̎w�������ѓ��ɓ���A���̏ꏊ���ǂ�ȂƂ��납�m���߂Ă݂�ƁA�C�܂���͂�����ɂ��̐g�������̂����n�߂��B
�@ ���Ȃ�̈��H�̗ѓ��݂���������r���ŃG���X�g�Ȃ��A�܂��Z���E���[�^�������Ȃ��Ȃ����肵���獡�x����JAF�ɂ����z��s������Ă��܂����A�@���Ă��ċN�����Ȃ�������ǂ�����H�\�\����ȕs������u�]�����悬��͂������A���ǁA���͖��d�����m�ŗѓ��ւƓ˂����B���ꂪ�ǂ�Ȃɋl�܂�Ȃ��Ƃ���ł������Ƃ��Ă��A���̋@����O������u���{�̒��S�v�Ƃ��̂���镗�ς��ȏꏊ��K�˂�`�����X�͓�x�ƂȂ��悤�ȋC�����ĂȂ�Ȃ��������炾�B
�@ ����ɁA���˂Ă�����{�̕Ӌ��n������D��ŖK�˕����Ă��邱�̐g�ɂ���A���̑��G�_�Ƃ������ׂ��n�_��ڑO�ɂ��Ă��߂��߂ƈ���������킯�ɂ������Ȃ������B���ꂻ�̋߂��ŎԂ������Ȃ��Ȃ����Ƃ��Ă��{�]�Ƃ������̂����A����͂���ŏ\���b�̎�ɂȂ�Ƃ����v�����������B�����̈��H�Ƃ͂����Ă��A6.3�L���̓��̂�Ȃ炽���������Ƃ͂Ȃ�����A�����ƂȂ����瑫�ɗ���悢���낤�B�����������ނƁA�������l�쓮�ɐ芷���ėѓ��ւƏ����ꂽ�̂����A����͂����炪�z�����Ă����ȏ�Ɏ苭�������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N5��16��
���{���`��K�˂�
�@ ���{�̒��S�Ƃ́A�����Ȃ�u���{���`�v�̂悤�Ȃ��̂ł���B���̓��{���`�ɑ��Ղ�����ł݂����ƈӋC����œ˓������ѓ����������A�قǂȂ�����̓S�c�S�c�����₾�炯�̃_�[�g�̈��H�ɕϖe�����B��B����k�C���܂ŗl�X�ȗѓ��⌯�H�𑖂����Ă����g������A���H�͏������C�ɂȂ�Ȃ��B�����A���̂Ƃ�����́A��������G���W�����~�܂��Ă��܂�����A�����Ă��R����Ă��X�^�[�^�[���ċN�����Ȃ������ꂪ����Ƃ�������������A���̂Ԃ�T�d�ɂȂ炴��Ȃ������B���܂�u���ԁv�̈�ɂ������Ƃ��Ă���䂪���Ԃ͐̂Ȃ���̃}�j���A���Ԃł���B������A�ˑR��p�ɏ��グ����a�ɂ͂܂����肵�āA��u�N���b�`�̐ؒf���삪�x�ꂽ�肵���炽���܂��G���X�g���Ă��܂��B
�@ �����������邤���ɓ��͈��H�ɉ����ĎԈ��ʂ�̂�����Ƃ̋}��H�ɂȂ����B�l�쓮�ɐ؊����A���ɂ͎ԑ̂𒈂ɕ��������肵�Ȃ���J�^�K�^���s�𑱂��邤���ɁA�݂�݂鍂�x�͏オ���Ă����B����ł��Ȃ��}��H���A�Ȃ��Ă���Ƃ����݂�ƁA�ǂ������{���`�͑����ȃf�x�\�ł���炵�������B
�@ �₪�ĎԂ͍L��Ȑԏ��тɍ����|�������B�O���E�肩�獶��Ɍ������ċ}�p�x�ŗ������ގΖʈ�тɂ͐ԏ��̖����т����z���Ă��āA���̒���D���悤�ɂ��ă_�[�g��襘H���Ȃ�����ւƂ̂тĂ���B�H�ɂȂ�Ƃ����Ԃ����̂���Ȃ����ȂƎv���Ȃ���A�N�Z���ݑ����Ă���ƁA�Ă̒�A�u���R�ɂ����Ȃ����R���ւ��v�ƋL���ꂽ���Ŕ����ꂽ�B���Ƃ��u���R�������v�ƌ����Ă��u���\�ł��v�Ǝ��ނ���l�̂ق��������̂ł͂Ȃ����ȁA�Ǝv���Ȃ��炳��ɍ��x���グ�Ă����ƁA�悤�₭�̂��Ƃő������ʂ��̂��������ɏo���B
�@ �ቺ�͂邩�ɓV����̂��̂Ƃ��ڂ����J���L����A�����̎Ζʂ͂��̒J�Ɍ������ċ}�p�x�ŗ�������ł���B���ӂ̌i�ς��炷��Ƃ��������ȍ����̂Ƃ���ɗ��Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ������B�ѓ������̕W���ɂ́u���{���S�̕W�܂�6.3�L���v�Ƃ��������A���ɂ���ȏ㑖���Ă��銴���ł���B�������A�ڕW�n�_�炵�����̂͂܂����E�ɂ͓����Ă��Ȃ������B
�@ ����܂ł̌o�����炵�Ă��A���I�Ȃ��̈ȊO�̋����W���̕\���͂��܂蓖�Ăɂ͂Ȃ�Ȃ��B�n�}��ł����܂��ɐ}�������������Ɛ��������ւ̕ω���召�̃J�[�u���v�Z�ɓ��ꂽ�������Ƃ̍��͑傫������A�ň��̏ꍇ�ɂ́A�\�������̓�A�O�{�͑���o������Ă������ق����������낤�B�k�C���Ȃǂɂ����ẮA��L�����[�g���ƕ\���̂���Ƃ��낪���ۂɂ͂��̉��{������Ƃ������悤�Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ��B
�@ ����ȂƂ���őΌ��Ԃ������獢��ȂƂ͎v�������A�K���A���̐S�z�͂Ȃ������������B���̂����A�����ŃG���W�����~�܂��ē����Ȃ��Ȃ��Ă��܂�����A���ԂɏE���Ă��炦��\���ȂNJF���ɓ������B������ɂ���A�����܂ŗ�����ǂ����낤�Ƃ����{���`�ڎw���Ђ�����O�i���邵���Ȃ��������B�i�s��������͐[���J�ƂȂ��Đꗎ���Ă���B�}��̋����ѓ��̘H���͌��邩��ɐƎセ���������̂ōאS�̒��ӂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ������B
�@ �����A�ő�̓���҂��Ă����̂͂��̐悾�����B�s����̓��H����A�O�S���[�g���ɂ킽���Ĉ�ʎc��ɕ����A�J�`�J�`�ɓ������Ă����̂��B�G���W�����~�܂�Ȃ��悤�ɋC�����Ȃ���`�F�[�����������ƁA�Ƃ肠�����H�ʂƐ�̏�Ԃ��ׂ����`�F�b�N���Ă݂邱�Ƃɂ����B�ԕ����킸���ɍL�����x�̘H�ʂ͒J���ɌX���Ă��邤���ɁA��A�O�ӏ��H�������ꂩ�����Ă���Ƃ��낪����B�������A���S�̂͂��Ȃ�̋}�₾�����B�R���ɎԂ������ς��ɊA�ԑ̂��X���Ȃ���ʂ�Ȃ�Ƃ��Ȃ肻���ł͂��������A�܂���������N�����ĒJ���ւƒE�ւ�����ЂƂ��܂���Ȃ������������B
�@ ��ʏ�ɓQ�炵�����̂��قƂ�ǎc���Ă��Ȃ��Ƃ�����݂�ƁA�ŋ߂�����ʂ����Ԃ͂Ȃ��炵�������B�T�d�̂����ɐT�d���������߁A�X�R�b�v����肾���A�Ƃ��Ɋ�Ȃ����Ȍ��̎R���ɂ͍����ԗւ�ʂ����߂̍a���@�����B�V�C���悭�C�������Ȃ�オ���Ă������߁A�����ʂɂȂ�Ƃ��X�R�b�v�̐��˂��h�����Ƃ��ł����͍̂K���������B�X�R�b�v�̐���˂������Ȃ��قǂɓ������Ă�����ǂ����悤���Ȃ�������������Ȃ��B
�@ �Ԃ�u���ēk���ŖړI�n�܂œo�낤���Ƃ��v�������A�Ԃɖ߂������Ɨ������������Ԃ����߁A��Ԃ��\�ȏꏊ�܂Ńo�b�N�^�]����̂��e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ������������B�������H���o�b�N�^�]����r���ŃG���X�g���A�X�^�[�^�[���Ďn�����Ȃ������炨��グ�����A���Ƃ�JAF�̋~���Ԃ��삯���Ă��ꂽ�Ƃ��Ă��A���̂悤�ȏ��ł͌������܂܂Ȃ�Ȃ��ɈႢ�Ȃ������B�܂��A���������A���̐[���R���Ōg�ѓd�b���g���邩�ǂ��������肩�ł͂Ȃ������B
�@ �����͒��˖Ґi����݂̂Ƃ���ɁA���������ē��������H�ʂɎԂ������ꂽ���́A���̂܂܈��̑��x��ۂ��Ă������ɖ��̏ꏊ�����낤�Ƃ����B�T�d�ɂȂ邠�܂艺��ɑ��x�𗎂Ƃ��߂��A�r���ŃX�g�b�v���悤���̂Ȃ炩�����Ċ�Ȃ��B��u�Ԃ��E�ɌX���A�E�ߑO���ɏ����X���b�v���ē��S�Ђ��Ƃ������͂������A���������c��ɑ傫���ԗւ��Ƃ��邱�Ƃ��Ȃ��A�Ȃ�Ƃ������ɂ��̓��蔲���邱�Ƃ��ł����B��������Ԃ��߃`�F�[�����O���Ă���Q���m���߂ɖ߂��Ă݂�ƁA�����ʂ�H�����肬��̂Ƃ�����E�ԗւ��ʉ߂����炵���Ƃ��낪��ӏ������������B
�@ �H�ʂ̓��������߂��Ă��炭�i�ނƁA���̌X���ɂ₩�ɂȂ�A�ˑR�A���邭�J���������̗Ő���ɏo���B�u�C�쒬�A���{���S�̕W�v�ƋL���ꂽ�ē��������Ă��邻�̒n�_���炳���œ��͓��ɕ��A����̓��̂ق��͋}�ȉ���ƂȂ��ē�̕��p�ւƂ̂тĂ����B�u���{���S�̕W�v�̕����������ē��̖��ɂ��������A���������ۂ��̉E�萅�������ɑ������`���ɕS���[�g���قǐi�ނƁA�S�����̑傫�ȓW�]��̗��ꏊ�ɏo���B�����Ă����œ��͍s���~�܂�ƂȂ����B
�@ �ǂ����A�����l�����ꂽ�Î₻�̂��̂̂��̒n�_�������A�ق��Ȃ�ʁu���{���`�v�ł���炵�������B���{�̒��S�Ƃ�������n����̓��ٓ_������قǂɕ�翂ȎR���Ɉʒu���Ă���Ƃ����̂́A�Ȃ�Ƃ������[��������ł͂������B
�@ �G���W�����������܂܂ɂ��ĎԂ��~���ƁA�����Ɏ��͓W�]��ɏ���Ă݂��B�قڎO�S�Z�\�x�̓W�]�̂������̍��݂���́A�ߕӂ̎R�X�͌����ɂ�����A�����x��b���A�k�x�A�o���x�A����ɂ͖ؑ]��x�A��Ɗx�Ȃǂ悭�m��ꂽ�R�X�̎p�����]���ꂽ�B�܂����ӂ̎R�X�͓~�͂�̏�Ԃ̂܂܂��������A�V��g�t�̋G�߂ɂȂ�Έ�т��������ʂ��邾�낤���Ƃ͑z���ɓ�Ȃ������B
�@ �[�R�̑�C��x�����ς��ɋz�������ƁA���͂������ƓW�]����~�肽�B�����Ă�������l�A�\���[�g���قǗ��ꂽ�Ƃ���ɂ��鍕���ۂ��n�����C�⎿�̎l�p���Δ�̑O�ɗ������B���̔�ɂ͂��Ȃ�ۂ݂̂��鎚�̂ŁA�u���{���S�̕W�v�Ƃ����Z�������[�X�ƒ��荏�܂�Ă����B�蕶�̕��������|�����̂͒���I���Ƃ����l���̂悤�ł������B�܂����̔�ɂ́A�u���{�̒��S�v���Ƃ������̒n�_�̐��m�Ȉܓx�A�o�x�A�W�������킹�ĕ\�L����Ă������B
�@�@�o�@�x�F���o137��59��36���@
�@�@�܁@�x�F�k�� 36��00��47��
�@�@�W�@���F�C��1277m
�@�@���ݒn�F���쌧�C�쒬�߃���i�W��1291m�j�t��
�ȏオ���{�̒��S�A���Ȃ킿�A���{���`�̏��ݒn�Ɋւ���ڍׂȃf�[�^�ł���B�n�}�����Ă��炤�Ƃ킩�邪�A���J�Ɖ��K�����ԍ���20�����A�z�K�ΔȂ̉��J�ƒC�쒬���Ȃ��V���쉈���̌����A�����ĉ��K����C�쒬�ɂ̂т鍑��153�����̎O�H���Ɉ͂܂ꂽ�O�p�n�т́A������Ƃ����R�x�n�тɂȂ��Ă���B���̎R�x�n�т̂قڒ����ɂ���̂��߃���Ƃ����R�ŁA���́u���{�̒��S�v�͂��̂����߂��Ɉʒu���Ă���̂������B
�@ ���{�̒��S�̕W�ɍ��܂ꂽ�f�[�^�߂Ă��邤���ɁA���������ǂ������Z��@�̂��ƂɁA���̒n�_���䂪���̒��S�ƒ�߂��̂��낤�����^�₪�N���Ă����B��ԒP���ȕ��@�́A�S���̊C�ݐ������̊e�n�ɑ����̃`�F�b�N�|�C���g��ݒ肵�A�����̒n�_�̌o�x�ƈܓx�Ƃ̕��ϒl���Z�肷�邱�Ƃ��낤�B�P���ɕ��ʂƂ��čl�����Ƃ��̓��{�n�}�̏d�S���Z�o���A�������{�̒��S�ƒ�߂��肩���ł���B���̏ꍇ�ł��A���}�������◮�������ȂǓ��{�{�y���牓�����ꂽ���X�̃f�[�^�����Z������ƂƂȂ�ƁA�����̏����̎d���ɂ���ĎZ��l�ɂ��Ȃ�̈Ⴂ���������˂Ȃ��B
�@ �܂��āA�R�x�n�т╽�n�ȂǂƂ��������̓I�Ȓn�`���z�܂ōl�����Ă��̕����I�d�S���v�Z����ƂȂ�ƁA�b�͂܂��܂����Ȃ��ƂɂȂ��Ă���͂����B�����܂ōl�����Ƃ��A���͂���AIC�̃��C�^�[�̒��ɁA��X���M�v����Ƃ������̓��̑�Ƃ������邱�Ƃ�z���N�������B�������߂�AIC�ɓo�ꂵ�����A�{���̕ҏW�ӔC�҂̌����L���X�^�[�́A���Ώ�k�܂���Ɏ��̂��Ƃ��u�������y�n���@�v�ȂǂƏЉ�Ă����悤�ł��邪�A���̌�ɓo��Ȃ�������X������͐��^�����̍��y�n���@���߂�ꂽ���ł���B�����͂����A���Ƃ̖�X������ɂ��f�������Ă邵���Ȃ��Ǝ��͍l�������悾�����B
�@ �����ėN���オ���Ă����^��́A���������������{�̒��S�ł���Ƃ���ƁA���{�̍ʼnʂĂ͂��������ǂ��ɂȂ�̂��낤�Ƃ������̂������B�����������͂��������Ƃ��ĎԂɐς�ł���n�}�������o���A���{���ӂ̒n�}�̕\������Ă���y�[�W���J�����B���ɂ���܂�������̂ЂƂf�B�o�C�_�[����ɂ��ė��j���傫���J���A���̕Е������ݒn�Ǝv����n�_�ɓ˂����Ă��B�����Ă����𒆐S�ɂ����Е��̐j��ʼn~�ʂ�`���Ȃ�����{�̗̓y�̂ǂ�����ԉ����̂��ׂĂ݂��B
�@ ���̌��ʔ��������̂́A���ꌧ�̗^�ߍ����̓쐼�[���ʼnʂĂ̒n�ɂ�����炵���Ƃ������Ƃ������B�n�}�̏k�ڂ�p���ĊT�Z����ƒ��������ɂ��Ė�1800km�A���̋����a�ɂ��ĉ~��`���ƁA���̒������쒹�����A�𑨂ƍ���̗��������̉~���ɂ����ۂ�Ƃ����܂����B�k���ŗ^�ߍ����܂ł̋����ɑ�������n�_�́A�������k���ƃA�W�A�嗤�Ƃ̊ԂɈʒu����ԋ{�C���̖k�[�A�A���[���́i�����]�j�̉͌��t�߂ł��邱�Ƃ��킩�����B�����̖k�����قړ������Ɉʒu���Ă����B
�@ ���{���`�ɕʂ�����������Ƃ́A����Ă����ق��̗ѓ��ɂ͖߂炸�A���Α��ւƉ���ѓ��ɓ������B�ӊO�Ȃ��Ƃɂ�����̗ѓ��͓������L���H�ʂ��������肵�Ă��đ���̂ɉ��̋�J������Ȃ������B�ǂ����A������̗ѓ��̂ق������{���S�̕W�Ɏ���{���������悤�ŁA�����n���n�����Ȃ���H�����ق��̗ѓ��͗����ł���炵�������B
�@ ���炭�����Ă����ƁA�E��ɋ��炵�����̂����ꂽ�B����́u�]�قނ�v�Ƃ����A���܂܂Ŏ��ɂ������Ƃ̂Ȃ��o�l�̋��ł��������A�����ɍ��܂�Ă����͎̂��̂悤�ȑf�l�̖ڂɂ������f���炵���Ǝv������ł������B
�@�@�@�×��̂ǂ̎R������Ⴊ����
�@ ����ȏ㉽�̐���������Ȃ��������A����ł��ĐM�Z�̓~�̂��ׂĂ����s�����Ă��邻�̌������\�\���̐▭�ȏ\�O�����̋�ɏo�����������ł��킴�킴���̒n��K�˂��b�オ����Ƃ������̂������B
�@ �]�قނ�Ƃ����o�l�́A�{�����g�]�����l�ƌ����A�吳��N�ɒC�쒬�Ő��܂ꂽ�l���ł���炵���B��藠�ɋL���ꂽ�o���̌��Ƃ���ɂ��ƁA�d�ʑ�𑲋ƌ�A���N�C�ے��ɋΖ��A�ސE��͒n�����J�ɍݏZ���A�H���s���j�A��H��s�A��c�ܐ��Ɏt�����ċ����w�Ƃ̂��Ƃł������B���̌����͕���5�N9��25���ƂȂ��Ă��邩��A�܂������Â����̂ł͂Ȃ��悤�������B
�@ ����ɂ��Ă��A���ꂪ���ꏊ���ꏊ������A�n���̔o��W�҈ȊO�̐l�����̋���ڂɂ��邱�Ƃ͂߂����ɂȂ����낤�B����A�������������̌����҂����͂�������m�Ŋ����Ă��̂悤�ȏꏊ��I�̂�������Ȃ��B�W���烁�[�g�����z���邱��ȎR��̂��Ƃ�����A�~�ɂ͋�育�Ɛ[����ɖ�����Ă��܂��ɈႢ�Ȃ��B�Ђ���Ƃ���ƁA���ꂱ�������̔�����̏ꏊ�ɗ��Ă��l�X�̑_���ł��������̂�������Ȃ��Ƃ����v�����������B
�@ ����ȑ������Ȃ����ƂȂǂ��l���Ȃ���A���͂����ނ�ɂ��̏�����Ƃɂ����B�������ѓ��ƌĂ�Ă���炵�����̗ѓ��́A����ɂ�ē��������X�ɍL���Ȃ�A�r������͂����肵���ܑ����H�ɕς�����B�ѓ������肫�����Ƃ���͒C�쒬�̒��S�X�̂����߂��������B���^�������Ƃ������Ȃ�Ƃ������A�G���W������x���炸�ɂȂ�Ƃ��ѓ��𑖔j�ł����̂ŁA�ēx�X�^�[�^�[�n���s�\�̎��Ԃɍēx�ׂ�A�R���ŗ����������Ă��܂����ƂȂǂ��Ȃ��Ă��B
�@ ���������ꂩ����{���S�̕W��K�˂Ă݂����Ƃ�����������悤�Ȃ�A�C�쒬���S�X�̑�����A�v���[�`���邱�Ƃ������߂����B�ѓ������t�߂ɂ͂������肵���ē��W���������Ă��邵�A���H��������̂ق����i�i�ɂ悢���炾�B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N5��23��
�_�y��̎H
�@ �i�䖾����Ǝ��Ƃ��S������A�T�q�E�C���^�[�l�b�g�E�L���X�^�[�iAIC�j���̃R�������ɂ́A�u���vs.���w�ҁv�ȂǂƂ��������߂����^�C�g�������Ă���B�������́A�ق��Ă����Ƃǂ��܂ł��\�������˂Ȃ���X��l�Ɉ��̃^�K���͂߂Ă����ׂ��AAIC�̓����ӔC�Ҍ����L���X�^�[�����炩���ߎd�g�Ƃł����āA�����������䂪�ӂ����̂ł͂Ȃ��B�����ۂ��́u�Y���L�v�Ɓu���Q�L�v�Ƃ����^�C�g���������L���X�^�[���ƒf�I�Ɍ��߂����̂Ȃ̂����A������̂ق��͂��Ȃ�I�m�ɉ�X��l�̃��C�^�[�̖{�������������������ƌ����Ă��悢���낤�B
�@ ����Ȃ킯������A�i�䂳��Ǝ��Ƃ́A�e�X�̖{���ɂ̂��Ƃ��āA�����ς�A�Y���҂���͕��Q�҂Ƃ��ĐU�����悤�ɐS�����Ă���킯�ŁA��w�␔�w�̘b���قƂ�Ǔo�ꂵ�Ȃ����R�̂ЂƂ͂���ȂƂ���ɂ����邩������Ȃ��B���Ƃ��ƁA��������͉�X�Ɏ��M���˗�����ɂ������āA��҂����߂��l�ԂƐ��w�҂����߂��l�Ԃ́u���߂��ғ��m�̑g�ݍ��킹�v�ŕY���L�ƕ��Q�L��S�����Ă��炢�܂�����Ɠ`���Ă��Ă����̂��B
�@ ����ȗ��ꂩ�炷��ƁA�u���vs.���w�ҁv�ł͂Ȃ��A�u�Ԏ�vs.���y�ҁv���A�����Ȃ���A�u�Y����vs.���Q�ҁv�Ƃ����^�C�g���̂ق������ӂ��킵�������̂�������Ȃ��B����A���܂ɂ��Ďv���A�����̉i�䂳��Ǝ������߂Ȃ����Ƃ̑g�ݍ��킹������A�u���vs.���ˁv�Ƃ���̂��x�X�g�������悤�ȋC�����ĂȂ�Ȃ��B
�@ �i�䂳��Ǝ�����L�������͂��߂Ă��������N���قǂɂȂ邪�A���������ƁA�i�䂳��Ǝ��Ƃ͂���܂ň�x������������Ƃ��Ȃ������B��N�A�i�䂳���܂����̏Z�ޕ{���s�Ɍ����ɂ݂����Ƃ��A�Ē��u�S���v�̌����u���ɐ�����āv����y�Y�ɂ��ĉ��̍T������K�ˁA�ق�̏\���قǏ��Ζʂ̈��A�����킵�������ł���B�i�䂳��͑z���Ɉ�킸���ȗ}���̂������ƂĂ��f�G�ȕ��ŁA��˂Ɖ��˂̈Ⴂ���Ă����ɂ��ӋC�����ł������Ȋ����ł������B�F�D���i�̉A�ɂ́u���ɐ�����āv�̉B�ꂽ���\�������炩�������̂�������Ȃ����A�Ƃ�������X�͒Z����b�����킵�����ƍĉ��ĕʂꂽ�̂������B�@�@
�@ �������A����ȍ~�A�o���Ƃ��Ɏd���ɒǂ��i���̎��͎d�������Ȃ����߂̌����ɒǂ��H�j�i�䂳��Ƃ̍ĉ�͂Ȃ��Ȃ��������Ȃ������B���̂��i�䂳��ƃ��[���̂��Ƃ������Ȃ��ŁA��������ɏꏊ�Ǝ��Ԃ�ݒ肵�Ă��炢�O�l�ʼn���Ƃ����Ƃ���܂Řb�͐i�̂����A�̐S�̌�������ɁA�Ȃ��Ȃ������Ă����C�z�������Ȃ������B���Ԃ�A�s�i���̌�������ɂ́A�u���vs.���ˁv�̑ΐ�����܂��J�����M���Ȃ������̂��낤�B
�@ �����Ȃ���A��˂Ɖ��˂��㉺���������сA�s�i�̕s��ۂ��Ȃ���݂邵�グ�鋓���ɏo�邩������Ȃ����Ƃ����炩���ߌx�������̂�������Ȃ��B������ɂ���A��X��l�̑ΐ�̏��{�����ɐݒ肵�A�n�b�P���[�C�ƕ������Ă����Ȃ���A���܂���s�i�����������Ƃ͂Ȃ�Ƃ���������ʘb�ł͂������B
�@ �����Ŏl�����̂��ƁA���́A�u���vs.���ˁv�̒��ڑΐ���Ȃ�Ƃ��������܂��傤�Ƃ�����|�̃��[�����i�䂳��ɏ����������B�l�������AIC�̉�ʕ\���̑啝�ύX�ɂƂ��Ȃ��āA�i�䂳��Ǝ��Ƃ͗L�������킳���ʁX�̕����ɉ������܂�A�ƒ�������̏�ԂɂȂ��Ă��܂��Ă����̂ŁA���̍ۂȂ�炩�̑Ή�����u���Ă����K�v���������B
�@ �K���A�����ɁA�i�䂳��A�����̂ق��Ŏ��ƌ���������܂߂��O�҂̓s�����l�����A�K���ȓ����Əꏊ��ݒ肷�邩��Ƃ����ԐM���[���������Ă����B�ΐ�҂̂����̕Е������̑����t���[���܂ł����҂��Ă��܂����Ƃ����̂�����A�u���vs.���ˁv�ǂ��납�A�u���in hands with���ˁA�s�i�v�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��āA���͂₱��ł͑ΐ�ɂȂ肻���ɂ��Ȃ������B�ł��܂��A���̎E���Ȑ��̒��䂦�A�u�a�v�ɏ�����̂͂Ȃ����낤�Ƃ������ƂɂȂ�A�F�D��c�̐ݒ�����ׂĉi�䂳��ɂ��C������^�тƂȂ����B���̌��ʁA�܂��͌܌��\���̌ߌ㎵���ɔѓc���̉i�䂳��̎������ɏW�܂낤�Ƃ������ƂɂȂ����̂ł���B
�@ �F�D��c�ɏo�����ɂ͓��R�Ȃɂ�����F�D�̏��K�v�ƂȂ�B���肪�A���R�[���}�̉i�䂳��Ƃ���A�F�D�̏̎��Q�i�Ƃ��āA�������͍����Y�̈��W���[�X�i�H�j�u�S���v���A�O�q�������̌����u���ɐ�����āv�ɏ�����̂͂Ȃ��B���������̑������c������Ă����̂ł͊Ԃɍ��������ɂȂ������̂ŁA�����̌ߑO���A�����ŏĒ��u�S���v��u���ɐ�����āv��u���Ă��鐔���Ȃ��X�̂ЂƂA�O��̋{�c��X��T�����Ă��B�����āA���܂��܈�{���c���Ă������ړ��Ă̕i���w���A�������Ԃ炳���Ĕѓc���Ɍ������A�̎�����������ɁA�w����قǂȂ��}���V�����̘Z�K�ɂ���i�䎖�����̃`���C����炵���B
�@ �h�A���J���A�ɂ��₩�Ɏ����ē����Ă��ꂽ�̂́A�ƂĂ��`���[�~���O�Ŋ����̂��������̕��������B�i�䂳��̎�L�̒��ɐ܁X�o�ꂷ��E���C����Ƃ����̂͂��̕��ɈႢ�Ȃ������B�قǂȂ����̕������猻�ꂽ�i�䂳��ƈ��A�����킵�A���߂���܂܂Ƀe�[�u���ɍ������낷�ƁA���ݕ��͉����悢���Ɛq�˂�ꂽ�B�i�䂳��̎������̗①�ɂɂ̓A���R�[���ނ����͂����Ă��Ȃ��낤���ȁA������������A�����̎�������A���R�[�������o�Ȃ���Ȃ����ȁH�\�\�ȂǂƑz�����߂��炵�Ȃ���A�����邨����A�u�E�[�������͂���܂����H�v�ƕԎ��������B����Ƃ����ɁA�E���C���悭�₦�����ߐF�̈��ݕ����^��ł��Ă����������B�܂������r�[�����E�C�X�L�[����Ȃ����낤�ȂƎv���Ȃ��������Ղ��Ă݂�ƁA�ԈႢ�Ȃ�����͏㎿�̃E�[�������ł������B
�@ �����������Ă��邤���ɂ܂��`���C���������B��������̓o��A���⌊��������s�l�̓o�ꂾ�����B�����V���d�g���f�B�A�ǂ̋Z�p�҂Ƃ��āAAIC���͂��߂Ƃ���asahi.com�̃e�N�j�J���T�|�[�g��S�����Ă���㓡�N�O����Ƒ���R�I����������̓��s�҂������B�㓡����͂܂��Ⴂ����ǂ���������Ƃ����^�C�v�̒j���ŁA�݂邩��ɑ��݊��ɖ������Ă����B�ߓ��̌�������̘b�̒��ŏЉ�ꂽ��Ή����̎�����̈�l�͂��̌㓡����Ȃ̂��Ƃ����B�����ۂ��̑��삳��͑o�Ƃ̋P���̔������݂邩��ɑu�₩�Ȃ��삳��ŁA�D��S�ƒm���~�̉��������S�g������o�Ă����B��������̐����ɂ��A�㓡����Ƒ��삳��s�����̂́A���˂̎��ɂ�����ē�l�ɉi�䂳��̑���߂Ă��炤���߂Ȃ̂������ł������B
�@ ���炽�߂ĊȒP�Ȉ��A���������������ƁA���̏�̃e�[�u�����͂�ł������ܑO���킪�J�n���ꂽ�B�i��Ɨ��R�ɑ���͌����A�㓡�A����A���R�Ƃ��������ŁA����͉��{���̊ʃr�[���ł������B�E�[�������Ƃ����I���`���̃s�X�g�����R�̂��̂���ɂ������́A�K�R�I�ɒ������̒�풲��ψ��݂����Ȗ�����S�����ƂɂȂ��Ă��܂����B�Ȃ�Ă��Ƃ͂Ȃ��A���̂܂ɂ����̉��˂̐g�͍s�i���ɂ���Ă��܂����̂������B�r�[���C�̌��������������Ă���Œ��ɁA�i��R�̕�⋁i�ւ�����j�������ǂ�E���C����́A�������邩�̂悤�ɂ��̏��ޏo���Ă������B�K���Ƃ����ׂ����c�O�Ƃ����ׂ����A�����������i�p�[���e�Ȃ݂̏d�Ί�͑��ŕ��ꂽ�܂܂������B
�@ �r�[���C�̒e���s����̂�҂��Ă�������x�틦�肪�����A�{��̏���i�䂳��ʂ����̐_�y��E�G�̂��X�Ɉڂ����ƂɂȂ����B�i�䂳��̎�L���ɐ܁X�o�ꂷ�镗��L���Ȗ�̐_�y����������Ə��A���S�X���炷�����͂��ꂽ�����ɓ���ƁA�قǂȂ��u�������v�Ƃ������̂��X�ɒ������B�i�䂳��ɁA�ē��g�ɂ��Ȃ�ł���ꂽ�X���ł����Ɛq�˂�ƁA���̂悤���Ƃ̕Ԏ��������B�o�c�҂��R�`�䂩��̐l�Ȃ̂ł��낤�A�ǂ��ƂȂ��Â����{�̋��D�̕Y���A�Ȃ��Ȃ��ɗ����������͋C�̂��X�ł������B�]�ƈ��̈�l�ЂƂ�ɂ��A�e�[�u�����͂ތX�̂��q�ɂ��A�S�Ȃ����l��̔Z�₩�����������ĂȂ�Ȃ������B
�@�@�ŏ��t���g�̗��܂łɐ��Ⴍ�[�ׂƂȂ�ɂ��邩���@�@�g
�@ �Ȃ�����u�A���̔]���ɂ͐ē��g�̂���ȉ̂��z�������B�����āA���́u�������v�ł̍����̖{��́A�ŏ��̋}���ɋt����Ĕ��g�����������قǂɌ������r�ꐁ�Ⴍ�̂��A����Ƃ��A�����̋��̓~��z���Ȃ��炱�̉̂��r�g���̐l�̐S���̂悤�ɁA�Q��҂��ꂼ��̐S�̓��֓��ւƐ[���������ďI������̂��A���ɂ͂������������̂���Ƃ���ł��������B�������g�͉��˂ł͂��邪�A�E�[��������R�[���A�W���[�X�Ў�ɁA�����Ɩ��̂��ʁX�ɂ��ʂĂ�Ƃ��Ȃ��t�������̂͂����̂��ƂŁA���ɂ͂���������ɂ͂Ȃ�Ȃ������B
�@ ��X�͂��X�̒��e�[�u���̋���U���`�Ɉ͂BU���̉E�[�ɉi�䂳��A���ׂ̗ɉi�䂳��̉�Y�����̑��삳��A������U���̒ꕔ�ɉE���玄�ƌ㓡����AU���̍��[���ɂ͌�������Ƃ����w�`�������B�i�䂳��ƌ�������Ƃ̓e�[�u��������łقڌ����������������ɂȂ��Ă����B�F���Ȃɒ����I���A�퓬�Ԑ��������ƁA������Ƃ����h�g�̐��荇�킹�⋛�̓��g���A�c�ɕ��̎ϕ��A�R�ȂǂƂɁA�����āA���X�����̖����������d�C�ɂ��ďl�X�Ɩ{��̉ΊW�͐��ė��Ƃ��ꂽ�B
�@ ���̏ڍׂ�`���邱�Ƃ��ł��Ȃ��͎̂c�O�����A���ލ���̍��ԂɌJ�L�������b�̉��V�ɂ͂���Ȃ�̖������������B�܂��͌�������̎d����̗l�X�ȋ�J杂����ꂽ���A�����͑��d���݂̘b�|�̎�����A�ǂ��܂ł��{�ӂłǂ��܂ł�����グ�邽�߂̃I�g�{�P�Ȃ̂��A�����Ă��邤���ɂ����ς�킩��Ȃ��Ȃ��Ă���Ƃ���Ȃǂ͂������ł������B�ߓ��̒����V�����j�ł̗�����50�l�̋L�ҁA�u���s�`���v�̂Ȃ��ŁA���M�҂̕ۉȗ��N�L�҂��u�ӂƖڊo�߂�Ǝ����ɁA���]�ԑ��Ƃɔ��ʂĂĂ���A���̘A�ڂ̃L���b�v�́A�i�j���̏��l�̂悤�ȏΊ炪�������v�Ə����Ă��邪�A���̃i�j���̏��l�̂悤�ȏΊ�̎傪�N�ł���̂��͂��܂��珑���K�v���Ȃ����낤�B
�@ ��������̂��Ƃ��������i�䂳��̌�����́A�J�i�_�̃����g���I�[���ɗ��w����w�����ɏ]�����Ă������̑z���o�b�Ȃǂ����[���A�����Ղ�Ɍ��ꂽ�B���d�͂̏�Ԃɂ����ĖF�����̕�����Ɛl�Ԃ̚k�o�Ƃ̊W���ǂ��Ȃ邩���𖾂��邱�ƂɁA�ꎞ���i�䂳��͊S�������Ă����Ƃ����B�}�O�������D�̃V�b�v�E�h�N�^�[�Ƃ��Ẳi�䂳��̑̌��k����ςɖʔ��������B�����I�g�{�P���̍q�C�L�������Ă���i�䂳���A���̎��͍����ł��O�w�ɂ���D��ŁA�ŏI�I�ȑ_���͓�Ɋϑ��D�œ�X�m�ɏ��o�����Ƃɂ���炵�����Ƃ�m���āA���͑傢�ɋ�����������ꂽ�B���������Ȃ������A�I�[�������o�b�N�ɍc��y���M���Ƃ̈��݂���ׂɗ�މi�䂳��̎p�������邩������Ȃ��B
�@ ���݂Ȃ����݂��̂��Ƃ��ʂ��āAAIC�Ɋւ���Ă���N�����A�����������Ⴆ���ꂼ��ɋ�J���Ă���炵�����Ƃ��킩�����̂��傫�Ȏ��n�ł������BAIC�ŕM�������Ă��錊������璩���̋L�ҏ������A�����āA�㓡����⑁�삳��̂悤��AIC�̃e�N�j�J���T�|�[�g�S���҂��A����ɂ́A�i�䂳��⎄�̂悤�ȊO���̃��C�^�[�������A�F���F�S�g�̘J���}�킸�{�����e�B�A�I�̂��ƂŌX�̔C�����ʂ����Ă���̂��Ƃ������Ƃ������ɂȂ����̂́A�`�[�����[�N�����ϗL�Ӌ`�Ȃ��Ƃł������B
�@ �����V���n�̃��f�B�A�}�̂̂Ȃ��ŁA�A�T�q�E�R���̓C���^�[�l�b�g�̕��y�ɂƂ��Ȃ��ߔN�悤�₭�F�m����͂��߂����f�B�A�Ȃ̂����A���̃A�T�q�E�R���̒��ł�AIC�͂���߂Ĉْ[�I�ȑ��݂ł���悤���B�������A����AIC�̂Ȃ��ł������j��Ŗ��ߑ��ȃ��C�^�[�Ɩڂ���Ă���炵������i�䂳�A�܁X�r�[���{�[����f�b�h�{�[���𓊂����肷����̂�����A�L���b�`���[�̌����L���X�^�[�̓n���n�����Ȃ��炻�̏����ɋ�J���邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��炵���̂��B�S�̓I�Ɍ��Ċe���C�^�[�̎��I�F�������Z�����ݏo�Ă���AIC�̂��Ƃ�����A���Ȃ�ǂ���̏��ł̗J���ڂɑ����Ă����������Ȃ����낤���Ƃ͂����������ɂ��z���������B
�@ �����K���Ȃ��ƂɁAAIC�S�̂Ƃ��Ă̓ǎҐ��͍������O���킸�z���ȏ�ɑ����Ă���̂������ŁA���Ƃ��A�x����������}�b�N�X�v�����N���������͂��߂Ƃ���C�O�̍����ȏ��������ɖ��߂���{�l�����҂̌܊��ȏオ���ǎ҂Ȃ̂��Ƃ�������A���̓_�͗L���Ƃ����ق��Ȃ��B�Ȃ�Ƃ����Ă��ǎ҂͐_�l�A���X�\�����P�ʂ̃A�N�Z�X��������ƂȂ�AAIC�W�҂̗�݂ƂȂ�Ȃ��킯�͂Ȃ��B�����̓ǎ҂̐����𗊂�ɂ��Ċ撣���Ƃ���܂ł͊撣�낤�A�����āA�������ł��鎞��������A�X�[�p�[�E�m���@�i���V���j�Ȃ݂ɑ唚�����N�����ďI��낤�ȂǂƁA���Ώ�k�A���Ζ{�C�������Č�荇���������B
�@ �i�䂳��ւ̃A���R�[�������e�⋋�W�����˂Ă��鑁���́A��������X�ɃO���X����ɂ��Ȃ���A�ڂ��ׂ߂Ȃ�Ƃ��K�������Ȕ����ׂ�h�N�^�[�Ɍ������āA�₦�ԂȂ�����𗁂т������Ă���B�������肽����̉i�䂳��́A����ȑ����̍D��S�Ɋ��S�ł����邩�̂悤�ɁA��ЂƂ̖₢�����ɒ��J�ɉ����Ă����B�{��ȂǂƗE�܂��������������Ă������A��t����ɂ����i�䂳��̕\��͉��₩���̂��̂ŁA���ɐa�m�I�ȋC�i������݂��Ղ�ł������B�ň��̗��l���l�Ɏ���S�ꈤ���Ă�܂Ȃ��Ƃ�������̉i�䂳����A���߂Ȃ����͂��������A�܂������v���Ȃ��璭�߂Ă����B�ꌾ�ł����Ȃ�A����͓��֓��ւƐÂ��Ɍ������}���̂��������ł������B�������A����͂��̔Ӂu�������v�Ŗڂɂ���������ł̊��z������A���Ȃ炸�����ۏ̂�����ł͂Ȃ����Ƃ����f�肵�Ă��������B
�@ ���͗��ׂ̑��삳��ƌ㓡����ɂ��ނ����Ȃ���A���������Γ�������x�ł����ς瑼�̎l�l�̂͂��ޘb�ɕ������Ă����B����ƁA�b�̕��������ς��A���삳���̖{�Ƃ͉����Ɛq�˂Ă����B���ɑ����Ă����������̖₢�ɓ������̂͌����������B
�@�u�i�䂳��͂�����Ɣ���Ă��ƂŁA�{�c����͔���ĂȂ���ƁI�v�\�\����͂����ɂ��w���������̓��ӂȌ������̓����ł͂������B�����ɂԂ���ꂽ���́A�Ŏ�g�̑Ԑ������Ȃ���A�G�́u����v�Ƃ����g�h���̌`�e���������Ƃ��Ă��܂�������A���̔w���������͗L�����Z������x�ɂ͂Ȃ��Ă���{�ɂ͂Ȃ�Ȃ��ȁA�Ɠ��S�Ńj�����Ƃ��Ă����B�s���Ȑ��i�������āA������N�قǒ�����o���Ă��Ȃ�����A����Ȃ���Ƃł���O�ɁA����{�̂Ȃ��u����Ȃ���ƁH�v�ł�����킯���B
�@ �������i�䂳��̘b�����������������������Ƃ͎v�����A���܂��ܓ`�����̂��Ƃ��b��ɂȂ����B����ƁA�������A�����V���Ђɂ͂�����ƑO�܂ł͔��W�Ȃ���̂������āA�`�����̎����S�����Ă������̂Ȃ̂��Ƙb���͂��߂��B�����āA����J����������̔��̂قƂ�ǂ́A�����o������߂��Ă��Ȃ������肵�������̓`�����̎q�������Ȃ̂��ȂǂƂ����A���ΐl�����Ɋ����悤�Șb���A�����Ƃ��炵��������Ėʔ�������������Ă݂����B�������芴�S�����悤�������Ȃ��炻�̘b�ɕ��������Ă���Ⴍ�đf���ȑ����ׂ̗ł́A�i�䂳�y�������ɏ��Ȃ��疳���ŃO���X���X���Ă����B
�@ ���̍��ɍ���㓡����͌�������ɃO���X�������Ȃ�����A�����₨�܂݁A����ɂ͂����̒lj������Ȃǂɂ��ꂱ��ƍׂ��ȋC�����������Ă����BAIC�̋Z�p�ʂ̃T�[�r�X�ƃT�|�[�g�������I�ɒS�����Ă���̂͂��̌㓡����⑁�삳��炾�Ƃ̂��ƂŁA���̋�J�͑����Ȃ��̂炵���B��������̌��Ƃ���ɂ��A�����ŋ߂̂��ƁA�}�Ɍ㓡����炪���߂Ă��܂��Ƃ����b�������オ�����肵�āAAIC�̑�������Ԃ܂ꂽ���Ƃ��������̂��������B�����ʂł�����㓡����́A��ϗD�ꂽ�R���s���[�^�Z�p�҂ł���Ƃ����B
�@ �l������̃A�T�q�E�R���̉�ʂ̑S�ʕύX�ɔ����ώG�ȋZ�p�����̂��߁A����AIC�̃o�N�i���o�[���ꎞ�I�ɓǂ߂Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ă��邪�A�㓡�����́A�����̓d�q�d�g���f�B�A�NJ��J���Z�N�V�����ł̖{���̎d���̍��Ԃ��݂��ẮA���̕��������������ɐi�߂Ă���Ƃ���炵���B����J����\�t�g�E�G�A�̃R�[�f�B���O�Ȃǂ�̂�������Ƃ�����g������A���̋�J�͂悭�킩��B���䗠����݂�ƁA�{�����e�B�A�x�[�X��AIC�́A�ǂ���牽�x���j�n��I�ɕm���A���̓x���ƂɂȂ�Ƃ����̏�𗽂��ł������̂̂悤�Ȃ̂��B
�@�u�������薡�o����Ⴢ�����ԂɂȂ��Ă�������A�A���R�[���Ɩ��������Έ������ł��Ȃ�ł������ł���v�Ƃ������t���i�䂳��̌������ďo�鍠�ɂ́A���������������X���A�I�[�_�[�X�g�b�v�̎����ԍۂɂȂ��Ă����B�A���J�C�b�N�X�}�C����X��������̖��ӕ�F��������̕\��ɂȂ����i�䂳��́A����܂������ɐ����V�����Ȃ���̖ʎ����������鑁�삳��ƂȂɂ��y�������Ɍ�荇���Ă���B���̂����ۂ��ŁA���́A�O���X���d�˂邤���ɂ��Ȃ�C�������g���Ă����炵���㓡����Ƙb������ł����B��������́A��g�ɕ����ꂽ��b�̏���C�܂܂ɍs�������Ă��銴���������B
�@ �ȉ~���Ȃǂ��g���ăR���s���[�^�ɂ��Í������̎d���Ȃǂ����Ă���Ƃ����㓡����́A�����̌��t�̌q���ڂ��ƂɁu����v�Ƃ�������������Ɠ��̌����ŁA���w�Ɋւ��鎿������ꂱ��Ɛq�˂Ă����B�u���w�j������Ƃ��̑�Ȑ��w�҂́A����A�������������N��������ł��傤���ˁA����B����ς�K�E�X������ł����˂��A����A����Ƃ��K���A�����ϕ��̌��c���C�v�j�b�c���j���[�g��������ł����˂��A����H�v�Ƃ�������Ȃ̂ł���B
�@ �Ȃ̔\�͕s�������o�������䂦�ɂ��̐��E����Ƃ����ɑ��������O�����w�҂̂Ȃ�̉ʂĂ̂��̐g�ɁA�܂Ƃ��ȓ����ȂǏo���悤�킯���Ȃ������B�����A�N���j��ő�̐��w�҂ł��������Ƃ������̎�����A�㓡����͂��̓����ɂԂ��Ă݂悤�Ǝ肮���˂Ђ��Ă���Ă����炵���B������ɂ���Γ��G�܂����悤�Ȃ��̂ŁA�Ȃ�Ƃ����������Ƃł͂��������A������Ƃ����Č㓡����̔M�S�Ȗ₢����������킯�ɂ������Ȃ������B
�@ ���̐��E�̗��j�╶���̔��W�ߒ����݂Ȃ����ł���悤�ɁA���w�Ƃ����w��̈ꕪ����܂��A�P�����s�t�I�Ȓ�����̐i���}���̒ʂ�ɔ��W���Ă����킯�ł͂Ȃ��B���������A����̐�[���s�����w�҂Ƃ������̂́A�����̌����������E�ʼn����ɖ𗧂��ǂ����ȂǑS���O���ɂȂ��̂����ʂł���B�܂��A���݁A�ߋ����킸�A�V�ː��w�҂̎c���������ƐтƂ������̂͑��݂ɖ��ڂȊW������A�����̕]�����A����炪�Љ�ɂ��Ӗ����A����w�i��Љ�̐��ڂɉ����č��X�ƈڂ�ς���Ă����B
�@ ���w�̐��E�Ƃ����ǂ����ʓI�ȑ��݂Ȃ̂ł����āA�ǂ̕���̒N�̌������ł��̑傩�d�v�ł����Ɩ���Ă��A����ɂ͂Ȃ�Ƃ������悤���Ȃ��B���Ƃ��Č����Ȃ�A�����ɂ���E�j�̐j�̂����A�ǂ̐j���E�j�ɂƂ��Ĉ�ԑ�ł����Ɛu����Ă���悤�Ȃ��̂ł���B�������j������Ƃ����ăE�j�S�̂ɂƂ��Ă��ꂪ�ŏd�v���Ƃ͌���Ȃ����A�����Ƃ��Z���j������Ƃ����Ă��ꂪ�ŏd�v�ł͂Ȃ��Ȃ��Ƃ�������B�V�F�[�N�X�s�A�ƃ_���B���`�ƃx�[�g�[���F���ƃA�C���V���^�C���̎l�l����ׂĒN����Ԉ̑�ł����Ɛq�˂�Ă��A����Ȗ₢�ɂ͂��Ƃ��Ɠ����悤���Ȃ��B���w�̐��E�ɂ������Ă��A���͓������Ƃ�������킯�ŁA�ߋ��̐��w�҂̋Ɛтɍb���͂���B
�@ �㓡����̎���ɑ��ẮA�܂������������悤�Ȃ��̏ꂵ�̂��̂��������ȓ������������A�������葊������Ɋ����Ă��܂����B�㓡���[�����Ă��ꂽ�̂��ǂ����肩�ł͂Ȃ��������A���X�މ����ޏk���Ă����䂪�����₩�ȓ��]�������Ă��ẮA����������̂�����t�̂��Ƃł͂������̂��B�����Ō�ɁA�㓡����̂��̖₢�ɓ�����͓̂������ǁA��h�̂����ɂ��ĂȂ炢����ł��`�����܂���Ɖ����Ă��������B
�@ �X���ԂƂȂ����u�������v�����Ƃɂ�����X�͐_�y��̑�ʂ�ɏo���B�����Ă����Ń^�N�V�[���E�����Ƃ������ƂɂȂ����B�i�䂳��s�����̐V�h�߂��̂��X�ő�O��������낤�Ƃ������ƂɂȂ�������ł���B�������Ȃ���A�E�����^�N�V�[�ɏ�荞�����Ƃ���i�K�ŁA�����̎d���ɂ݂̌������܂��s��錾��\�����A�Ƃ肻�̏ꂩ��p���������B�c������X�l�l�̓^�N�V�[�ɏ���ĂƂ肠�����V�h���ʂɌ����������A�����̃X�P�W���[���̊W�������āA���ǎ��������������邱�Ƃɂ����B
�@ �V�h�ւ̎Ԓ��A�ˑR�A�㓡����́A�i�䂳��Ɍ����ĂƂ��Ɉ�����p�ӂ��Ă����̂��Ƃ�����������B
�@�u�������Ƃ������Ƃ�����ꍇ�A����A�i�䂳��͂ǂ�����Ƃ�܂����A����H�v�@
�@ �Ԕ�����ꂸ�i�䂳��̓Y�o���Ɠ������B
�@�u���������ˁI�v
�@ �i�䂳��̃A�b�p���ȉ����Ԃ�ɔ���𑗂�Ȃ���A���̂����ۂ��ŁA���Ɍ������āA�u�E�[�������Ƃ������ł͂ǂ������Ƃ�܂����H�v�Ƃ͐q�˂Ă���Ȃ������㓡����̌������������������߂����v���̂ł��������B
�@ �V�h�̒��S�X�ɓ��鏭����O�ʼni��A�㓡�A����̎O�l�͓r�����Ԃ��A�Ō�̌����ւƌ������Ă������B�Ȃ�̂��Ƃ͂Ȃ��A�{���Ȃ炻�̌����ɗՂނׂ������R�Ɩ{�c�R�Ƃ͂����Ȃ��퓬�s�\��ԂƂȂ�A�i��Ɨ��R�ƌ����\���R�݂̂����O���Ď��Y��������Ƃ����\�z�O�̐���s���ɂȂ��Ă��܂����̂������B�O�l�Ƃ͂��ꂼ��Ɍł���������ĕʂ�A�Ԓ��Ɏc���ꂽ���������Ƃ�V�h�w�ւƌ����������A���̂��̎O�l�̏����͂悤�Ƃ��Ēm��Ȃ��B���Ƃ��ẮA�Ђ������s�̖������F��݂̂ł���B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N5��30��
�R���o�����A�E���ł����I
�@ �܌��̂���ӂ̂��Ƃł���B���C�Ȃ����ւ̔����J�������̉Ƃ̐l�́A��O�̌��i�ɋV���A���̂܂܂�����債���B�Ȃ�ƍE�����A���̐ΐF�̉H�����E������H����ɗ����Ă������炾�B�����͖�̔������A�ꏊ�͋��n�Ŗ������{���s�̔ɉ؊X�ɋ߂��Z��X�A�ǂ��l���Ă݂Ă��A����͒f���ċN���낤�͂��̂Ȃ����Ԃł������B���̍E���͋�����l�q�Ȃǂ܂������݂����A�R���o�����Ƃł����������Ɍ���ɂ����ƘȂ܂ܓ������Ƃ��Ȃ��B�ǂ�������悢�̂��킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����Ƃ̐l�́A���̍E�����ǂ����֗������邾�낤���Ƃ�����Ă��������Ɣ���߂��B�ނ��t�B�N�V�����ł��Ȃ�ł��Ȃ��B���ۂɂƂ��鎄�̒m�l��ɍ~���ėN�����ꐢ���̒֎��ł���B
�@ �O�\���قǂ��Ă���A�l�q���M�����Ƃ����邨����h�A���J����ƁA���������ƂɍE���͂܂�����ɗ����Ă���B������肩�A�n��ɏM�ƌ�������ɁA�g�R�g�R�ƉƂ̒��ɂ͂����Ă��Ă��܂����̂������B�Q�ĂĒǂ��o�����Ƃ��Ă݂����A�������̎��͎�x��ŁA�������ɂ��ʑf���������ʼnƂ̉��ւƋ삯����ł��܂����B
�@ �p�j�b�N�Ɋׂ��Ă��܂����̂́A�E���ł͂Ȃ��Ƃ̒��̐l�X�̂ق��������炵���B�{�⊛�Ȃ�l���ċƂ���������邪�A���肪���̍E���Ƃ����Ă͂����������Ȃ��B����������̂��ǂ������킩��Ȃ��������A���Ƃ����Ƃ��Ă������@�Ȃǂ킩��͂����Ȃ��B�߂܂��Ĕ����ɂ��Ă��܂���������邩������Ȃ��ȂǂƂ��������Ȉӌ����o���炵�����A����͂���Ŋl���ċȏ�ɓ���b�ł͂������B
�@ �Ή��ɋ��������̉Ƃ̐l�X�͂�ނȂ��x�@�ɒʕ��B�u�E�����Ƃ̒��ɖ�������ł����̂łȂ�Ƃ����Ă��������v�Ƃ̋}������x�@�̒S���҂��A��u���̎����^�����ɈႢ�Ȃ��B�������{���w�����������\������������Ȃ�����ȂƂ���ɁA����������X���Ă���E�����o�v����Ȃ�āA�ǂ��l���Ă��M������b�ł͂Ȃ����炾�����B
�@ ����ł��Ȃ�Ƃ����̍E���̓����o�����悪���������Ƃ݂��A���炭����Ƃ��̏��L�҂炵���l�����m�l��ɂ���Ă����B�����ɍE���͌�p�ƂȂ��Ĉꌏ�����Ǝv������A���Ƃ͂����ȒP�ɂ͉^�Ȃ������B�����������̂ɂ������R�������ՁX�Ǝ�����킯�ɂ͂������Ƃ���ɁA�E���͉Ƃ̒����т܂��\��܂���Ċ拭�ɒ�R�����炵���B���̏�ɂ����l�X�����|����łȂ�Ƃ��E�������ւ̊O�ɒǂ��o���A����Ƃ̂��Ƃŕ߂܂��I�������ɂ́A�����ߑO�ꎞ�߂��ɂȂ��Ă����Ƃ����B��߂蕨�̏I������Ƃ̒��ɂ͔������E���̉H�т������炶�イ�U�����A�Ȃ�Ƃ��ٗl�Ȍ��i�ł������炵���B
�@ �������炽�߂āA���̍E���̊Ǘ��҂Ƃ��ڂ����l������Ƃ��l�тɂ���ė����B�j�������o�������h�ɂ́A�Ƃ���߂��̉�Ж����L����Ă����Ƃ����B���̉�Ђ��Ȃ�炩�̎d����̖ړI�ōE���������Ă����̂��A����Ƃ��P�Ƀy�b�g�Ƃ��Ď����Ă����̂��͂킩��Ȃ��Ƃ������A�����Ԃ�l��ꂵ�������������炵����A�e���r��f��̎B�e�p�Ɏ��炳�ꂽ�E���������̂�������Ȃ��B�����������Ƃ���A���̂ق��ɂ����H���̍E�������̎������̕t�߂�������Ă����\��������B���܂��܂��̏�ɂ��Ȃ�����������ɁA�u�{���̖��ƂɍE���������Ȃ�Ē������I�v�Ƙb�����Ƃ���A�u����Ȃ��̓��{�����̂ǂ��̉ƒT�������Ă��Ȃ����I�v�ƕ����ꂽ�肵���Ƃ����B
�@ �E���ɂ܂�邻��Ȓ��k�ɑ�����Ă��邤���ɁA���͍E���ɂ��Ă̂���b���v���o�����B�����s���w�i�G�\���W�[�j�̌��ЁA�R�����[�g�E���[�����c�̒���u�\�������̎w�ցv�̒��ɏo�Ă���b�ł���B�E�B�[���ɐ��܂�A�P�[�j�q�X�x���N��w��}�b�N�X�E�v�����N�s�������w���������Ȃǂ��C�������[�����c�́A���ށA���ނ𒆐S�Ƃ����e�퓮���̐��ԁA�Ƃ��ɂ��̍s���̌������s���A�G�\���W�[�Ƃ����V�w�╪����J���B���̋Ɛтɂ��A�ނ�1973�N�Ƀm�[�x����w�����w�܂���܂��Ă���B
�@ ���Ȃ݂ɏq�ׂĂ����ƁA���[�����c�͗L���ȁu���荞���ہv�̔����҂Ƃ��Ă��������l�����B������z��������̎q���Ȃǂ͎����̂��Ő^����ɓ��������̂��e���ƔF�����Ă��܂��A�Ƃ��������ׂ������́A���N�ɂ킽��ނ̒n���Ȍ����Ɗώ@��ʂ��Ĕ������ꂽ�B�ނ͂܂��A�����ώ@�̖ړI�������ĉƂ̒��Ŏ�X�̓�������������ɂ��Ă������߁A�܂��c�����������̎q�ǂ��̐g�̈��S���l���A�q�ǂ��̂ق���B�ɓ���Ĉ�Ă��Ƃ����^�j��̊w�҂ł��������B���z�̋t�]�Ƃ�������܂ł����A�w��̐V������J���m�[�x���܂���܂���悤�ȓV�˂̍l�������Ƃ́A�}�f�ȉ�X�̒��z�Ƃ͂܂�ň���Ă���悤���B
�@ ���[�����c�̌��Ƃ���ɂ��A�����̍U�����͓����̎�ނɂ����2�^�C�v�ɑ�ʂ������̂炵���B��ʂ��֖҂Ŏc�E�Ǝv���Ă���T�̂悤�ȓ����́A���Ȃ����ԓ��m�ŋ���𑈂��ꍇ�A��������ق��������̋}���ł�����̉�̑O�ɍ����o���ƁA�D���Ȃق��̘T�͂���ȏ㑊��ɍU���������邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ����B�̑������h���̏�Ԃő���̉�ɐg�����炷���̋V�����I���ƁA�����ő��݂̏����܂�A�ǂ��炩���v���I�ɏ����܂ő������V���邱�Ƃ͂قƂ�NjN����Ȃ��̂��������B����̉�̊댯����F�����Ă���T�����͍U���}���\�͂����Ȃ��Ă���킯�ŁA���̈Ӗ��ł��T�Љ�͎��ɒ����̂Ƃꂽ�Љ�Ȃ̂��ƃ��[�����c�͏q�ׂĂ���B
�@ �����ۂ��A�L�W�o�g�Ƃ��m���W�J�Ƃ������A��ʂɕ��a�̏ے��ƍl�����Ă���悤�ȓ����́A���̖{�����������֖҂ł���炵���B�ア�������m�Ƃ������݂̂͌��ɋ���𑈂����A�̑��͑���̍U�����牓���֓����邱�Ƃɂ���Đg�����B������ɏ\���Ȉ��̃X�y�[�X�����邱�Ƃ��A�ނ�̎Љ�Ŕߌ��������邽�߂̕K�v�����Ȃ̂��������B�@
�@ �L�W�o�g��m���W�J����̂Ȃ������B�̒��Ŏ����Ă���ƁA�I�X���m���������N�������ꍇ�A�ق��Ă����ƎS�����N����B�L�W�o�g�̏ꍇ�A�D�ʂɗ��������́A�����ē��������������҂��ǂ��܂ł��ǂ��l�߂ďP��������A����đ��₦�鐡�O�̑���̓����z�炪�߂���Č��ǂ��Y�^�Y�^�ɐ�A�ؓ����U��܂ōU���̎���ɂ߂邱�Ƃ͂Ȃ��B�m���W�J�ɂ������ẮA���҂͔s�҂̓����������o���j��܂ōU������߂邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ����B
�@ �����̃o���r�̃��f���ɂ��Ȃ��Ă���m���W�J�Ȃǂ́A�G�ӂȂǂ܂��������������Ȃ��l�q�ŐÂ��ɋ߂Â��Ă��āA���f��������ɂ����Ȃ�P��������p�ŃN�T���Ɠ˂��h�����肷��̂��������B�m���W�J�ɏP���Đl������d�������肷�鎖�̂́A�ҏb�ɂ�铯��̎��̂��������ƕp�����Ă���Ƃ����B�ア�����Ƃ������̂́A���ƂȂ��������Ă��A�����ƂȂ�Ƃ��̖{���͂���߂Ďc�E�ł���A�U�����������B�ق��Ȃ�ʉ�X�l�Ԃ���҂ɑ����Ă���ƃ��[�����c�͏����Ă���B
�@ �ނ̘b�ɂ��A�E���̃I�X�Ǝ��ʒ��̃I�X���ꏏ�Ɏ����Ă����肷��ƁA�\�z�O�̐��S�Ȏ��Ԃ������邱�Ƃ�����悤���B�Ȃ��Ȃ̂��͕s�������������A���ʒ��́A�����A�G�{�ށi�W�����P�C���C�j�ł͗B��T�^�̓��������Ȃ������ł���炵���B���ʒ��̃I�X���m�����܂�����ꍇ�A���Ȃ�Ȃ��ƌ�������͑���̚{�̑O�Ɏ����̎�����ɂ��č����o���A�~�Q�̃|�[�Y���Ƃ�B����ƁA�������ق��͂���ȏ�U�����邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ����̂��B
�@ �E���Ǝ��ʒ��Ƃ͋߉���̂䂦����ɑ���G���S�������炵���A�ꏏ�ɂ��Ă����Ƃ����܂����܂��n�܂��Ă��܂��B�Ƃ��낪�A���̑����ɂ����Ă͎��ʒ��ɂ͂܂����������ڂ��Ȃ������Ȃ̂��B�E���̂ق��͒�����A�ˑR�H���J������A�s�����̒܂��o���ɂ����肵�Č��������ʒ����Њd���A�U������B����ƁA���Ƃ��Ƃ͍E�����g�̂��傫���͂������͂��̎��ʒ��́A�\�z�O�̑���̍s���ɋ����Ă����܂���ӑr���A�M�u�A�b�v���Ă��܂��B�����āA�����܂��̂��̏K���ʂ�ɒ�������E���̑O�ɍ����o���Ă��܂��̂��B
�@ �Ƃ��낪�A�����ۂ��̍E���͎��ʒ��Љ�̃��[���Ȃǂɂ͖��ڒ�������A�������Ƃ���ɑ���̎�ɗe�͂Ȃ��s���܂ƚ{��˂����Ă�B�U�����������قǁA���ʒ��͍E���̑O�Ŏ��L���U���̒��~���肤�B���̂܂܂ق��Ă����ƁA�E���͂܂��܂������ւ��Ě{�ƒ܂��ӂ邢�A���ʒ��̎��c�Ȏp�Ő▽����܂ōU�����~�߂Ȃ��Ƃ����B
�@ ���̘b�ɂ͂Ȃɂ��ƍl����������Ƃ��낪���Ȃ��Ȃ��B��X�l�Ԃ��L�W�o�g��m���W�J�A�E���ȂǂƓ��ނ̐��Ȃ����Ƃ���A������̂Ȃ�����Ԃɕ����߂�ꂽ�悤�ȏꍇ�A���҂���҂����Ɏ���܂Œǂ��l�߂Ă��܂����Ƃ��\���N���肤��͂������炾�B�w�Z�Ȃǂ̂悤�ȁA��҂ɂƂ��ĕ����I�ɂ��S���I�ɂ����x�I�ɂ�������̂Ȃ��A�܂��A���Ƃ������łȂ��Ă��Љ�ʔO�㓦���o�����Ƃ̌����Ƃ���Ȃ���Ԃɂ����ẮA���҂���҂��Ƃ��Ƃ�U�����邱�Ƃ��N�����Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��B�������l�Ԃ̏ꍇ�ɂ͈�Έ�ŋ��҂���҂�ǂ��l�߂�̂ł͂Ȃ��A���҂��͂ޑ�������l�̎�҂�ǂ��l�߂邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ����炢�����������������B�ǂ��l�߂����ЂƂƂ��Ă��A�l�Ԃ̏ꍇ�ɂ͕����I�ʂ���ƐS���I�ʂ���̂ӂ������邩��܂��܂��b�͖��B
�@ ����̎Љ�̉��ł́A�c�����̎q�ǂ��������A���҂̍U�����瓦��g����邽�߂̕��@���K���̂�������B��������@��g�ɂ��Ă��Ȃ��q�ǂ��������A���ΓI�Ɏ�҂ƂȂ��āA����łȂ��Ă�������̂Ȃ���Ԃɒu���ꂽ��A���̌�ɋN����ߎS�Ȍ��ʂ͖ڂɌ����Ă���B�����ۂ��̋��҂͋��҂ŁA�g�̂قǂ��킫�܂��邱�ƂȂ��܂��܂��������A���\������߂邱�ƂɂȂ肩�˂Ȃ��B
�@ �ߔN����E�ł͕s�o�Z�Ґ��̑��傪���ɂȂ��Ă���悤�����A���R�Ȃ������ł́u�ǎ��ȓ�����v�̎���ꂽ����Љ���ẮA���Ƃ����ꂪ�ň��̓�����ł������Ƃ��Ă��A�s�o�Z�͒ǂ��l�߂�ꂽ�q�ǂ������ɂƂ��Đg����邽�߂̍Ō�̎�i�Ȃ̂�������Ȃ��B�����āA�����������Ƃ���A���܋��猻��ŋ��߂��Ă��邱�Ƃ̂ЂƂ́A�ꎞ�I�ɂ�����g�̂��ǂ���Ƃ��Ă��ӂ߂��邱�Ƃ���ᎋ����邱�Ƃ��Ȃ��A���R�����F�̗ǎ��ȓ�����ƗL���ȉ�����[�g���A���l�ɂ킽���ĉ��i�K�ɂ��݂��邱�Ƃł���̂�������Ȃ��B
�@ �R�����[�g�E���[�����c�͎��炪�J��m�����������s���w�̌������ʂɊ�Â��A�l�Ԃ̋��ɂ̖{���𐫈��Ȃ��̂��Ƙ_���A�l�ԎЉ�̖����ɑ��l�X�Ȍx�������肵�Ďv�z�E�ɑ傫�ȉe���������炵���B�����ۂ��A�uTHE ART OF LOVING�i������Ƃ������Ɓj�v��uTHE HEART OF MAN�i�l�Ԃ̐S�j�v�Ȃǂ̒���Œm����Љ�w�҂̃G�[���b�q�E�t�����́A���[�����c�̎咣�ɑΗ����邩�����Ől�Ԃ̐��P�ʂ�i�삷��{���_��W�J�A�u�o�C�I�t�F���X�v�Ɓu�l�N���t�F���X�v�Ƃ����Ǝ��̓�ɊT�O���x�[�X�ɂ����l�Ԙ_�������āA���l�ɓ����̉��Ďv�z�E���r�����B
�@ �~���ėN�����悤�ȍE���̒��k�[�ɂ��āA�ӋC�������N���ɓǂ��������Ƃ̂���ނ�̒���Ȃǂ�z���N�����Ă��܂������A�����������̎��́A�t�����̐��P���ƃ��[�����c�̐������̂ǂ���ɌR�z��������ׂ��Ȃ̂��낤�B���̎�����l�Ԃ̐S�̒��ɂ͐��P�̔��ւƐ����̍��ւƂ����ݍ����悤�ɂ��đ��݂��Ă����B�����A�\�ʓI�ɂ͕��������ȋߔN�̐l�ԊE�̓����ŁA���₩�ɔE�т����߂����ւ̉e�����ւ̂����葾���傫��������̂́A���̋C�̏��ׂɉ߂��Ȃ��̂ł��낤���B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N6��6��
���͔L�Ȃ̂��H
�@�u�������ł��邱�Ƃ��ؖ����Ȃ����v�ƌ���ꂽ��F����͂ǂ����邾�낤���B�u����Ȃ��Ɠ�����O����Ȃ����I�v�ƌ����Ĉ�ɕt�����A�u�o�J�o�J�������Ƃ�u����Ȃ���I�v�ƁA�͂Ȃ��瑊��̌��t�����邩�̂ǂ��炩���낤�B�u���͌��ł���v�Ƃ��A�u�l�Ԃ͐l�Ԃł���v�Ƃ��������悤�ɁA�啔�Əq�����܂���������̖���͘_���w�̗p��Ńg�[�g���W�C�i���ꔽ���j�ƌĂ�Ă���B
�@ �������A���̂悤�Ȗ���ړI�ɏؖ����邱�Ƃ͕s�\�ł���B�����Ă�������Ƃ���A���̐��ɐ������鑼�̂����铮���̓����������Ђ��[���璲�グ�A���������̓����̂�����ɂ������Ȃ����Ɓi���������̓����̂ǂꂩ�ɑ�����Ƃ���Ζ����������邱�Ɓj�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̂��̂���������������ƁA������w���@�I�ؖ��ɗ��邵���Ȃ��̂����A���w��_���w�̐��E�̏ؖ��Ȃ炢�����炸�A�I�m�ȕ��ނ���������Ȗ����̐������̑��݂��錻���̐��E�ɂ����āA����ȗI���Ȃ��ƂȂǂ���Ă����킯���Ȃ��B�܂��A���Ƃ�����Ă݂��Ƃ���ŁA�����ɂ͂Ȃ�̈Ӗ����Ȃ��B
�@ �����Ȋw�̋L�����ӂ��ނ��ׂĂ̌���\���̍���ɂ́A�u��`�v�ƌĂ���{�I�T�O�i�������Ŏ���邱�Ƃ����߂��邨�����Ƃ̖��Ɓj�����݂��Ă���B���w�̐��E���ɂƂ�A�u��_�Ԃ����ԍŒZ�������Ƃ���v�Ƃ��u�����͑S�̂̈ꕔ�Ƃ���v�Ƃ��������悤�Ȃ��Ƃ���`�ɂȂ�킯�ŁA�ʏ�͂����������̗��Ƃ��Ď���Ă��������Ȃ��B�ނ��A����Ȓ�`�̏ؖ��͕s�\�ł���A�܂����Ӗ��ł���B
�@ �����̒�`�ɂǂ����Ă��[���������Ȃ��Ƃ����̂ł���A�����ł�薾�����I�m�Ȓ�`������A���������Ƃɗ��_�̌n�̍č\�z�����H���Ă����ق��ɂ͉����̓��͂Ȃ��B���ہA���[�}����A�C���V���^�C���Ƃ������j�㖼�����V�ː��w�҂�V�˕����w�҂����͂��̍���Ȏd���𐬂������Ă������ƂŒm���Ă���B
�@�u�������ł��邱�Ƃ��ؖ�����v�Ƃ����ċ�����̂́A�u���v�Ƃ��������̒�`���ؖ�����Ɣ����Ă��邩��ɂق��Ȃ�Ȃ��B�u�`�A�a�̓�_�Ԃ����Ԓ����̒����͓�����_�Ԃ����ԋȐ��̒������Z�����Ƃ��ؖ�����v�Ƃ����Ă���悤�Ȃ��̂����炾�B�ł́A�u���͔L�ł��邱�Ƃ��ؖ�����v�Ƌ��߂�ꂽ�Ƃ���ǂ����낤���B���w�̐��E�Ȃ�A����́A�u�Ȑ��͒��������Z�����Ƃ��ؖ�����v�Ƃ����Ă���悤�Ȃ��̂�����A������k���Ƃ������ƂŏI��邾�낤�B�ؖ������߂��Ă��閽�肻�̂��̂����������Ƃ����킩�邩�炾�B
�@ �������A���ꂪ���G�Ȑ������ۂ�Љ�ۂ̂悤�ɘA���I�Ń_�C�i�~�b�N�ɕϓ����鐢�E�̘b�ƂȂ�ƁA�����P���ɂ͂����Ȃ��̂����ȂƂ���Ȃ̂��B���̘_���W�J�ɐ����͂����邩�ǂ����͂Ƃ������Ƃ��Ă��A�u���͔L�ł���v�Ƃ�������̂ق��́A�k�ق�M���ėl�X�Ș_��W�J���邱�Ƃ��ł��邩�炾�B�������ƌ����܂߂邱�Ƃ̓��ӂȈꗬ���k�ىƂȂ�A�u���͎l�{�����A�K��������v�Ƃ������悤�Ȍ`�ԓI�����̗ގ�����������N�����A���̎肱�̎�ŁA��ʂ�������ʔ����_���l���o�����Ƃ��낤�B
�@ ���̋C�ɂȂ�A�i���_�������o���ă��[�c�͔L�����������������Ƙ_���A�����̐��т̍\�������������ɂ��āA�u�����Ƃ��������̈�ϗe�`�Ԃ��j�����Ƃ����������v�Ƌ��ق��邱�Ƃ����ĉ\�ł���B���܂����b�͏ȗ����邪�A���ہA�u���͔L�ł���v�Ƃ������悤�Ȏ����̒�`���炩�����ꂽ�����������Ƃ��炵���������Ă݂��邱�Ƃ̂ق����A���̃v���ɂƂ��Ă͗e�Ղ����A�܂��r�̌����ǂ���ł����邩�炾�B
�@ ���̘b�́A�u���͌��ł���v�Ƃ���������u�����Ƃ͐��������ŁA�����S�̗̂��v�̂��߂ɑ��݂���ׂ����v�Ƃ�������ɁA�܂��A�u�L�͌��ł���v�Ƃ���������u�����Ƃ͌��d�p���ɒ����Ă��āA���ȗ��v��Nj����鑶�݂ł���ׂ����v�Ƃ�������ɒu�������Ă݂�Ƃ悭�킩�邾�낤�B
�@ �O�҂͂����������������O�̂��Ƃƍl���邩��A�������̐�������������悤�Ƃ���ƂȂ��Ȃ��ɓ���B��҂̏ꍇ�ɂ��ẮA���낢��Ȍ����_��l�Ԃ̖{���_�������o���A�u���d�p���ɒ����Ă��邱�Ƃ⎩�ȗ��v��Nj�����\�͂����邱�Ƃ͐����ƂɌ������Ȃ������ł���A�܂�Ƃ���A����炪�����S�̗̂��v�ɂ��Ȃ���v�Ƃ����_���A�ʔ���������������ł��W�J���邱�Ƃ��ł���B�����̒�`�ɋ߂�����قǂ��̐�������������邱�Ƃ͍���Ȃ̂��B
�@ �{�������ł��邱�Ƃ��]�܂����Љ�O�ɂ��Ă����Ȃ�A���̐����������������A���̔��؎�����w�E���邱�Ƃ̂ق����͂邩�ɈՂ����B�����āA�k�ىƂ́A�{���I�Ȃ��̂ɉ߂��Ȃ����̔��؎�������ƂɁA���̗��O�̓˂������⍜�����A����ɂ͑S�ʓI�Ȕے��_���B���閽��̔������������̖��肻�̂��̂�ے�ł���Ƃ������w�I����͘_���w�I�Ȏ�@���A�Љ����Љ�ۂ̘_�ɂ��̂܂ܓK�p���邱�Ǝ��̊ԈႢ�Ȃ̂����A��דI�ɂ����������_�@���Ƃ�ꂽ�������B
�@�u���_�̎��R�̗��O�Ɋ�Â��̎��R�͕ۏ����ׂ����v�Ƃ������ɓ�����O�̎咣�ɑ��A�u�����v�Ƃ͉����Ƃ����c�_�Ȃǂ������̂��ɂ��āA�u�͌����ł���ׂ����B�����łȂ��͒f�ŋK�����ׂ��ł���v�ȂǂƂ����ᔻ�I���������R�ƂȂ��ꂽ�肷��B�����āA���̎咣�𗠕t����D��Ƃ��āA����̃_�C�I�L�V���������ɂ��Ă̈ꕔ�e���r�ǂ̌����̂悤�Ȃ��̂������Ɏ��グ��ꂽ��A�e��}�X�R�~�̋ɒ[�ȃv���C�o�V�[�N�Q��肪�����o���ꂽ�������B���_�̎��R��̎��R���Љ�ɂƂ��ėL�v�ł��邱�Ƃ��������Ⴊ�L�Q�Ȏ�����͂邩�ɑ����ɂ�������炸�A�����͌����ɃJ���t���[�W������Ă��܂��̂��B�������A���̂���߂Đ����I�ȍ��d�Ɋ�Â��c�_����ʍ����ɂ͑z���ȏ�ɐ����͂��������肷�邩����Ȃ̂��B
�@ ����̃_�C�I�L�V�����������̍ٔ��ł́A�S���n�قɂ���Č������̎咣���ꉞ�ނ����͂����B�������A�����c�̈ꕔ�̐l�X�͔�����s���Ƃ��č��قɍT�i����Ƃ����B�T�i���͖̂@�����Ƃɂ����铖�R�̌���������A���̑P�����]�X����C�͖ѓ��Ȃ��B���n�̃_�C�I�L�V�����������Ƃ��Ɣ_�Ǝ���̐ӔC�ł͂Ȃ����Ƃ��v���ƁA�܂��A�_�앨�̔���s���������A���Ȃ���ʑ��Q���������Ƃɂ��Ă�������ւ����Ȃ��B
�@ �����A�����c�̔_�Ƃ̐l�X�̔w��ɁA���ڂ̔�Q�҂ł͂Ȃ��ɂ�������炸����悭�t�]�������Ɗ肢�A�����K���̐�D�ɂ��悤�Ƒ_���Ă���ꕔ�����Ƃ₻�̍��������̉e��������Ă���̂͂��������C�ɂȂ��ĂȂ�Ȃ��B����������������v�f�ɂ́A����Ƃ��\���Ȍx����ӂ�ʂ悤�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B
�@ ���������قɂ����ċt�]�������o���肷��A����̌����_�Ƃ̐l�X�͂���ɂ���đ��Q�������������A�傢�ɗ����������邱�Ƃ��ł��邩������Ȃ��B���̔������q�ϓI�ɂ݂Đ����Ȃ��̂ł���Ȃ�A�ނ��A����͂���ł�ނȂ��B�����A���̑㏞�Ƃ��āA���{�����S�̂��K���Ƃ����������ŕs���ȏ��Ǘ��ɂ��炳���悤�ɂȂ�A���Ԃ��̂��Ȃ��s���v����\��������Ƃ���A����͏d��Ȃ��Ƃł���B
�@ ���ߑ��Ȉꕔ����c���哱�̍������A���ȏ����A�������̖��A�K�����A�����@�����i�H�j���A�v���C�o�V�[�ی���A��Q�G�C�Y�ٔ����A�e����ی���A��×ϗ����ȂǁA�ŋ߂̏d�v�ȎЉ���Ɋւ���c�_�̍����w�i�ɂ́A������̏ꍇ�ɂ����q�ׂ��悤�ȍI�����k�ق̘_���̖��̎肪����ł���悤�ȋC�����ĂȂ�Ȃ��B�A�ō������Ă��錠�͎҂⍕�������̎p�������B�ꂵ�ĂȂ�Ȃ��̂��B
�@ ���̂悤�Ȉ�H�̃��C�[�^�[�̌����ׂ����Ƃł͂Ȃ���������Ȃ����A�}�X�R�~�Ɋւ�鑽���̐l�X�́A�Ƃ��ɗǎ��h����������}�X�R�~�l�����́A�Ƃ��肢����̕\�ʓI���Y�킲�Ƃ��q�ׂ����łȂ��A�����Ȋo��������Ė��̖{���̐[�������뜜���A���̑Ή����^���ɍl���Ă����K�v�����邾�낤�B�u���͔L�ł���v�Ɛ����X�Ɏ咣����l�X��A���̘_���ɐ����������ꂽ�l�X�ɑ��āA�u���͌��ł���v�ƃI�E���Ԃ��ɌJ��Ԃ��Ȃ��痧�����������ł͂��͂�s�\��������ł���B�ǂ�Ȃɂ��ꂪ��ςȂ��Ƃł����Ă��A����ɂ͋t����ŁA�I���ȃ��g���b�N�ɂ͂���ȏ�ɍI���ȃ��g���b�N�������ĉ��V���邵���Ȃ��Ǝv����B
�@ �V�ː��w�҃��[�}���́A��_�Ԃ����ԍŒZ�������Ɩ��A��_�Ԃ����Ԓ����͈�{�������݂��Ȃ��Ƃ��郆�[�N���b�h�w�̒�`���̂Ă��B�����āA��_�Ԃ̋������Ȃ킿��_�����Ԓ����͔C�ӂɒ�`�ł���Ɣ��z���]�����邱�Ƃɂ���āA���[�}���w�ƌĂ��V�����w�̌n���������Ă��B����ɁA���[�}���w�Ƃ�������I�ȉȊw�_���̋L�q��i����ɂ����A�C���V���^�C���́A�^���A���ʁA���A�G�l���M�[���Ɋւ���v���I�Ȓ�`�݂����A���ꑊ�ΐ����_�A��ʑ��ΐ����_���m�������B
�@ �܂�ŃW�������̈قȂ鐢�E�̘b�����瓯��ɘ_���邱�Ƃ͂ł��Ȃ�����ǂ��A������������A�����̍����Љ���̉����ɂ̓��[�}����A�C���V���^�C���Ȃ݂̔��z�̓]�������߂��Ă���̂�������Ȃ��B����̗���̒��Œ�`���s�K�ɂȂ����Ƃ���Ȃ�A�p�m�����W�����K�ȐV��`�ݏo���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����炾�B�P�������������A���̐��̂��ׂĂ͒�`�ɂ͂��܂��`�ɏI���Ƃ����Ă悢�B���Ȃ��Ƃ��A�ߎS�ȉߋ��̐��E�ɂ����Ė҈Ђ��ӂ�����������I�Ȓ�`�ɗ����߂�������͔����Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B
�@ ���ؐ��A���Ȃ킿�A���鎖�����������Ɗ�����v���Z�X�̉���ɂ́A�ǂ̂悤�ȏꍇ�ł��A��X�l�Ԃ̈ӎ��ɑ��Öق��������̏��F�𔗂��O�A��`����͌����Ƃ����������ōI���ɉB����Ă���B�����āA���̑�O�����X�̎v�l�`�Ԃ���R�Ȃ�����邱�Ƃ��ł���ꍇ�A���邢�́A���Ƃ��Ƃ��̑�O��X�̎v�l�`�Ԃ̎Y���ł���悤�ȏꍇ�ɁA�u���ؐ�������i�����ł���j�v�Ƃ������f���Ȃ����B���������āA���̂��Ƃ��ؖ�����Ƃ����s�ׂɂ͓��R���E�������Ă���B�����āA���̌��E�̂䂦�ɁA�I�����̂����Ȃ��l�X�ȃ��g���b�N��A�u���͌��ł���v�Ƃ������悤�ȃg�[�g���W�C�i���ꔽ���j������Ȃ�̑��݈Ӌ`�������ƂɂȂ�B
�@ ��������ꂸ���킹�Ă��炦�A���ǁA�ؖ��Ƃ́A���ϓI�ɂ͔[�������������ɂ������x�ȊT�O���A���ϓI�ɖ������Ɗ����邱�Ƃ̂ł�����킩��₷����{�I�ȊT�O�ɒu�������A���̐�������l�X�ɔ[�����������邱�Ƃł���B���������āA�����ɂ́A�u�ؖ��̑ΏۂɂȂ��Ă��鍂���̊T�O�́A����ɐ旧���g�߂ňՂ����T�O�Q�ō\������Ă���v�Ƃ���Öق̑�O����ł���B��������ƁA��Ԃ��ƂɂȂ��Ă���T�O�A���Ȃ킿��`������͏ؖ��s�\�ŁA���������Ŏ���邵���Ȃ����ƂɂȂ�B
�@ �܂��A�Ղ��������T�O�̑g�ݍ��킹�ł͐��������Ȃ����A����ł����f�I�ȐV�T�O��V���ۂɏo�������悤�ȏꍇ�ɂ́A�������ؖ��s�\�Ȓ�`�A���邢�͐�̐^���Ƃ��Ė������ŐM������邩�A�����Ȃ��A�����������͂����Ƃ��ȋ��U�Ȃ����͂܂₩���Ƃ��Ĕr�˂��邵���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B���̂����A�����{�I�ȊT�O�ɑ����ϓI�ɖ��ؐ��i�������j�������邱�Ƃ��ł��邩�ǂ����ɂ͑傫�Ȍl�������݂��邩��A�ؖ����̂��̂̂����ؐ������ΓI�Ȃ��̂ɂȂ炴������Ȃ��B
�@ �����l���Ă݂�ƁA�u������̂��Ƃɖ��ؐ��i�������j������v�Ƃ������Ƃ́A�u���̎��ۂ̗l�Ԃ����̎���̈�ʓI�ȔF���̂��肩���ɋ�X���܂��K�����Ă���v�Ƃ��������̂��Ƃł����āA���̎��ۂ̖��ؐ����i���ɕs�ςł��邱�Ƃ��ۏ���Ă���킯�ł͂Ȃ����ƂɂȂ��Ă��܂��B�Ȃ�Ƃ��p���h�L�V�J���i�t���I�j�Șb�ł͂��邪�A��X�́A���ؐ������邪�䂦�ɂ��̂��̂��Ƃ𐳂����ƐM���Ă���̂ł͂Ȃ��A����̑O��T�O�𐳂����ƐM���Ă��邪�䂦�ɖ��ؐ�������Ɗ����Ă��邾���̂��Ƃł���B
�@ ���̂悤�Ȋϓ_�ɗ��ƁA���闝�O�◝�_������ɂ������ẮA���̍��{�ƂȂ�O��T�O���A�@���ɂ��ĂȂ�ׂ������̐l�X�ɒ�R�Ȃ����ꂳ���邩�A�����āA�ł��邱�ƂȂ犴���������ĐM�����������������邩���d�v�Ȗ�肾�Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B�����ɂ��̎g���������ĉ�X�̑O�ɗ��������̂��A�I�������d�Ȏ������̋��ѐ��ł���A�ؗ�Ȕ�g��g���b�N�ł���A����ɂ͂܂����X�̐_�̌��t�Ȃ���̂ɂق��Ȃ�Ȃ��B
�@ ����҂��u�͂��߂Ɍ��t���肫�v�Ɛ����A����҂��u��v���䂦�ɉ�L��v�Ƌ��сA����҂��u�����͉^�������]����v��搂��A�܂�����҂��u���t�͌��t�ł���v�ƍ��炩�ɏ�����̂��A�܂�Ƃ��낻�̂悤�Ȕw�i�����邩��Ȃ̂��B
�@ ���w���̍��̋��ȏ��ɂ��鋳�P�I�Șb���ڂ��Ă����B�ڂ������e�͖Y��Ă��܂������A�v����ɁA�n�����V�v�w���s���|��ɂȂ肩��������l�̕n�������l���������������ĂȂ��Ă�����Ƃ���A���̗��l�͂���ɂƖ����̎���ꗱ�����c���Ă������Ƃ����悤�Șb�ł������ƋL�����Ă���B
�@ ���̎���܂��ƈ�{�̖����̕c���萶���A�݂�݂鐬�����Ă����ɗ��h�Ȑ��ɂȂ����B�s�v�c�Ȃ��ƂɁA���̖����̖ɂ͗��̓��ł���̓��ł����Ȃ炸��������������������̎����Ȃ����B���̘b�������������������Ă��āA�����͂�����ł��o�����琥�̖����̖������Ăق����Ɛ\���o�����A�V�v�w�͐��̒��̂��ׂĂ̂�����ς܂�Ă�����킯�ɂ͂����Ȃ��ƒf�����B�����Ă��̖����̖ɂ͂��̌��������Â����̎����Ȃ�Â����Ƃ����̂ł���B������ɂ���A����̓�������D���̋c���搶�������ɂ�����A����̈����Ԃ������Ԃ�͒I�ɏグ�A�܂𗬂��đ��т������Ȕ��k�ł������B
�@ �Ƃ��낪�A�ˑR�A�N���X�̐��k�̈�l���A�u�����������炻�̖����̖��������Ɣ����Ă��܂��ɈႢ�Ȃ��B�Ȃ�ł��̘V�v�w�͂������Ȃ������̂��낤�H�v�Ƃ����f�p�ȋ^����o�����̂��B�Q�Ă��̂͒S�C�̋��t�ł���B�Ȃ�Ƃ����ĘV�v�w�̂Ƃ����ԓx�̐������i�H�j��[�������悤�Ƃ��ꂱ��w�߂Ă݂��̂����A���̐��k�͊�Ƃ��Ď���̈ӌ���ς��Ȃ������B������肩�A���̓����҂��N���X�̔����߂��ɂ܂ŋy��ł��܂����̂��B���̂܂܂ł͂܂����Ɣ��f�������t�́A��v���Ă��A�u�����̖؎��h�v�Ɓu�����̖ؔ��p�h�v�ɐ��k���ăf�B�x�[�e�B���O����点�邱�Ƃɂ����̂ł���B
�@ ���܂��܁A���͗��h�̓��_�̎i����ɂ܂킳�ꂽ�̂����A���t�̎v�f�f���邩�̂悤�ɁA�����̖؎��h�ɂ͔�r�I���т̂悢�q���������������z����Ă����B�������Ďn�܂����f�B�x�[�e�B���O�̌����͖����̖؎��h�̊����Ȃ��܂ł̔s�k�ł������B�u����Ɉ�̖������Ȃ������Ă���Ȃ��̉��̖��ɂ������Ȃ�����Ȃ����B�����̖��ėL��]�邨������ɓ���A������ł��S�L���Ȑ������y���ނ��Ƃ��ł��邵�A�b�ɏo�Ă��闷�l�̂悤�ȕn�����l�X�����Ăǂ�ǂ��Ă�������B���낢��Ȏ{�݂����Ă��邱�Ƃ��ł���B�����������̂ǂ��������̂��v�Ƃ��������̖ؔ��p�h�̐�N�ɁA�����̖؎��h�͒��ق��邵���Ȃ������̂ł������B
�@ ������݂Ԃ����悤�ȕ\��̋��t�ɂ���āA�Ō�ɂ͎i����̎��������̖؎��h�ɂ܂���Ĉӌ����q�ׂ�悤�Ɏw�����ꂽ��������̂����A�ނ��łǂ��ɂ��Ȃ�悤�Ȗ��ł��Ȃ������B�����̖؎��h�ɗ����Ę_�w�邱�Ƃ͑�l�ɂ����ē�����ƂȂ̂�����A�ǂ����~���Ă݂��Ƃ���ŁA���w���̐g�ɂ́A�u�V�v�w�ɂƂ��Ă��̖����̖͐����b��ŁA������������������v�Ƃ������g�[�g���W�C�I�Ȃ��Ƃ����������A���p�h�̍U���ɃM�u�A�b�v���邵���Ȃ������̂ł���B�V�v�w�̐M�S�[���₻�̐��n�v�z�̈Ӌ`������͂������ĕٌ삷��ȂǁA�c���q���ɂ͂ǂ��������Șb�ł������B
�@ ���̘b�̓��e���̂��̂����P�Ƃ��Ď��̐S�Ɏc�邱�Ƃ͂Ȃ��������̂́A����ɂ��A���̃f�x�[�e�B���O�ɂ����閨���̖؎��h�S�s�̗L�l�͑傫�ȋ��P�Ƃ��Ă̂��̂��܂Ŏ��̋��̉���ɐ[�����܂��Ƃ���ƂȂ����B���I�Ȑ��_�_�d���̂ɂ��������Ȃ��ł��Ȃ����̌P�b���炪���s�����͓̂��R���Ə��Ă��܂�����B�����A���ꂪ�\���̎��R��K���Ɋւ�����A���R�ی���A�e��̐�������Љ���Ȃǂɂ����āA�����Ƃ����ׂ����_���k�ق̗��̑O�ɎN����|�M�����̂�T�ς���͔̂E�тȂ��B�奂̕��Ǝ��}���������Ȃ�̂����A�܂����̂悤�Ȃ킯�ŁA���ɂ��Ȃ�����ȋY����Ԃ��Ă݂�C�ɂ��Ȃ����悤�Ȃ킯�ł���B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N6��13��
���v���x���ꂽ�b
�@ �������ɏo�������ہA�L�y���t�[�h�Z���^�[�̑O��ʂ肩�������B���̎��A�L���̉���Ŗ����Ă����Ⴋ���̋ꂢ�z���o���ˑR����̂��Ƃ̂悤���S���Ă����B
�@ �܂���w�ɓ��w���ĂقǂȂ����̂��Ƃ����A�̈�̎��ԂɍX�ߎ��̃��b�J�[�ɓ���Ă��������z�Ƙr���v�Ƃ��A���b�J�[�r���ɓ��܂�Ă��܂������Ƃ�����B�����̍��z�ɂ͏��K�������͂����Ă�����������������A���̂ق��͂��������ɂ����Ǝv��Ȃ������B�����A��w���w�̂��j���ɒm�l�����������r���v�𓐂܂ꂽ�̂̓V���b�N�������B
�@ ���܂Ƃ͈Ⴂ�A�����A�r���v�͑����ȋM�d�i�������B���Y�̈�ʓI�Șr���v�ł��V�������̂͌ܐ�~�O�サ���Ǝv���B���[������t�����\�~���炢�̎���̂��Ƃ�����A�w��Ɛ����������w���ƃo�C�g���݂̂ł�肭�肷��n�R�w���̐g�ɂƂ��āA����͑�ςȒɎ�ł������B���v���Ȃ��Ă��g�ѓd�b���̑��̋@��ɂ���ėe�ՂɎ����̊m�F���ł��錻�݂Ƃ͂킯���Ⴄ�B�s�ւȂ��Ƃ��̂����Ȃ��������A���炭�͘r���v�Ȃ��ʼn߂�����Ȃ��Ȃ����B
�@ ����Ȑ܂��܁A���́A���܂��܂��̗L�y���t�[�h�Z���^�[�̑O��ʂ肩�������B���������̍L���ʘH�̘e�ɂ͂��Ȃ�̐l�����肪�ł��Ă����B�Ȃ낤�Ǝv���đO�̐l�̌��z���ɒ���`������ł݂�ƁA��l�̒j���L���V�[�g�̏�ɂ�������̘r���v����ׁA���͂���芪���l�X�Ɍ������ĂȂɂ���������Ă���Ƃ��낾�����B�j�̍��e�ɂ́A��͂�V�i�̘r���v�̓������ג����������i�ɂ��ςݏd�˂��Ă����B
�@ �j�́A�V���̐蔲���L���Ƃ���L���T�����̈�y�[�W���w�������Ȃ���A�����ɏЉ��Ă���V�^���v�́A���������L�����y�[�����̎��v�Ɠ������i�ɂق��Ȃ�Ȃ��A�Ƃ�����|�̂��Ƃ����t�I�݂Ɍ���Ă����B�ꌩ����������ł́A�L�����̎ʐ^�̎��v�ƃV�[�g�ɏd�ˍL����ꂽ���v�Ƃ͊m���ɓ����i���ł���悤�Ɏv��ꂽ�B�ނ��w�����V���̐蔲���ƏT�����̋L���̌��o���ɂ́A�u����I�ȐV�^�r���v�ߓ������I�v�Ƃ������悤�ȈӖ��̕������x���Ă����B
�@ �^�ꗬ���v���[�J�[���A����I�ȐV�Z�p��p���ďȃG�l���M�[�^�̐V���r���v���J�������B���̎��v�͂قǂȂ��S���Ŕ�������邱�ƂɂȂ��Ă��邪�A���݂͂��̃L�����y�[�����Ԓ��ŁA���̂悤�ɐV����G���Ȃǂł��傫���Љ��Ă���B���������[�J�[�P���̃L�����y�[�������̈���Ƃ��ĊX���ɏo�āA�F����ɂ��̎��v�̑f���炵�����Љ�ĉ���Ă���悤�Ȃ킯�Ȃ̂��B�@
�@ �j�͂��̂悤�ȑ�̌������ʂ�q�I����ƁA���ׂ�ꂽ���v�̉������グ�Đ��l�̐l�X�Ɏ�n���A�����̊��G��f�U�C���A�\���Ȃǂ���������Ɗm�F�������B�ŏ��ɎƂ��Ċm�F���I�����ׂ̐l���玄�����̎��v����n����A����̎�Ɗ�������Ă�������ƕi��߂����Ă݂����A��ɓ`���d�ʊ��Ƃ����A�㎿�Ŋ��炩�ȋ����̊��G�Ƃ����A�܂������Ղ�o���h�����̃f�U�C���Ƃ����A�ǂ���Ƃ��Ă��^�L�����[�J�[�̍������v�ɒp���Ȃ�����̂��̂ł������B
�@ ���v�̕i�����m�F���I�����l�X���玞�v��������I����ƁA�j�̓^�C�~���O�����v���Ă������̂悤�ɂ�����o�����B
�u�F����ɂ���ɂƂ��Č��Ă��������܂������̐V�^�r���v�̔����\�艿�i�͎���~�O��ł��B�A���Ȃ荂���Ȃ̂ł����A���݂̓L�����y�[�����Ԓ��ł�����A�����ɂ��p�ӂ������v�����́A���O�̐�`�����˂āA���ʉ��i�ܕS�~�ł��Ђ��v���܂��B���Ɍ��肪����܂��̂ŁA���ׂĂ̕��ɂ͍s���n��Ȃ����Ƃ͎v���܂����A��ς����������Ƒ����܂��̂ŁA���̋@����������߂��������v
�@ ����͂Ȃ�Ƃ��I�݂ȎE������ł͂������B���݂Ȃ�A�X���ɂ����Ă��̂悤�ȗL�����v���[�J�[�̐V���i�L�����y�[�����s���邱�Ƃ͂܂��Ȃ��L�蓾�Ȃ��B�����A�e���r��W�I�ŗ������R�}�[�V���������܂قǂɂ͐�`���ʂ��������A�S���I�Ɍ���ƁA�J���[�e���r�͂������A�����e���r�ł��������y�������܂ЂƂ��������̎���ɂ́A���X���̂悤�Ȑ�`�L�����y�[�����s���Ă�������A�b�͂悯���ɕ���킵�������B����������㋞�����Ă̂܂����p�Ȑ��Ԓm�炸�̐g�ɂ́A�����n�̖ڂ���s��̕|���Ȃǒm��悵���Ȃ��Ƃ���ł������B
�@ ���̎��v���ܕS�~�����A�܂������Ȃ��b����Ȃ��A���傤�ǘr���v���~���������Ƃ��낾���A�ܕS�~�͑�������ǁA���܂��������킹�����邱�Ƃ�����\�\����Ȏv���������ɕ����Ȃ�����A���͂��炭���̏�łǂ����悤�����S�O���Ă����B
�@ �ˑR�A���������ꂽ�Ƃ���ōl�����ނ悤�Ȋ�����ė����Ă��������̂悢�X�[�c�p�̒j���A�ӂ��������悤�ɌܕS�~�������o���A�捏�m�F�����Ȃ��̎��v�̈�����߂��B��������������̒j�͑f��������Ŏ��v�̓����������݁A�������ܑ���Ɏ�n�����B����ɑ����āA���x�́A�Ⴄ�ꏊ�ɂ�����A�O�l�̒j�����������~�����ƌ����Ȃ���A���ꂼ��ɍ��z���J���Ă��������o�����B����ƁA����ɗU�����Ă��邩�̂悤�ɂ��āA�l�X�̗ւ̒�����A��������������ɁA��������ɂ��������̎肪�j�Ɍ������č����o���ꂽ�B�����āA���̂�������̎�̒��ɂق��Ȃ�ʎ��̎肪�������Ă������Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B
�@ �j�͊��ꂽ����Ŏ��X�ɖڂ̑O�̎��v�̔����݁A��ۂ悭��X�Ɏ�n���Ă��ꂽ�B����A���ۂɂ͘e�ɐςݏd�˂Ă������ق��̔�����ł��肰�Ȃ���n���Ă����̂�������Ȃ����A���܂ƂȂ��Ă͂��̂ւ�̂��Ƃ͂悭����Ȃ��B�����A������ɂ���A��i�܂����̎�����p����ꂽ���Ƃ����͊m���ł������B������ɂ����ג������̕�݂���́A���Ɏ��܂��Ă���͂��̘r���v�̏d�ʊ����قǂ悭�`����Ă����B�����Ԃ�ʂ͂䂢�v�������Ȃ����������v���|�P�b�g�Ɏd���������́A���ƂŔ����J���邱�Ƃ��y���݂ɂ��Ȃ���A���������Ƃ��̏�𗧂��������B
�@ ���ƂɂȂ��Ďv���A�ŏ��ɂ����������o�������l���͂��Ԃ�T�N���ŁA�����̒j�Ƃ̓O���������̂ł��낤�B�����āA�m�F�̂��߂ɐl�X�Ɏ�n���ꂽ���v�͖{���ŁA�T�N�������������ӂ�����Ď����������i�����{���������Ǝv����B�V���̐蔲����T�����̋L���͍I���ɋU�����H���ꂽ���̂��A�����Ȃ���Ή��炩�̎��v�ɂ��Ă̎��L�������p�������̂������̂��낤�B
�@ ���v�����߂��T�N���ȊO�̑����̐l�X�́A���炭���Ă��猩���Ƀn����ꂽ���ƂɋC�Â��A�n�c������ʼn����������ɈႢ�Ȃ��B����A���܂�̑N�₩�Ȏ���ɁA�����l�A���}�̌��t���o�ʂ܂܂ɁA�������C�ɂƂ��Ă����Ƃ����̂��ق�Ƃ��̂Ƃ���ł�������������Ȃ��B����͂����J���ƂȂ�����X�̐S���炵���܂łɓǂݐ��Ă�������ł���B
�@ ���\�܂����̂��ł���ɂ���A�����ł͂Ȃ����̂ł���ɂ���A���̎�̊X���Z�[���łȂɂ�����̕i�����w�������҂��A���̏�ł����ɂ��̕�݂��J�����̒��̕i�����m�F����Ƃ������悤�Ȃ��Ƃ͂قƂ�ǂȂ��B���ꂪ�������ʂ̔�����̐S���Ƃ������̂Ȃ̂����A����͂��̐S�������炩���ߌv�Z�ɓ���A�I�݂ɗ��p�����̂ł���B
�@ �Ȃ�ƂȂ��C�ɂȂ��������A�|�P�b�g�̒�����ג�������݂����o��������J���Ă݂��̂́A�\�ܕ��قnjo���Ă���ł������B���ɂ͊m���Ɏ��v�炵���V�����m���͂����Ă͂����̂����A�����l�q�����������B�Q�ĂĂ��̒��g�����o�������́A���܂�̂��Ƃɜ��R�Ƃ��A�{��̌��t���o�Ȃ��L�l�������B���̎��v�����܂��̋U�u�����h�̎��v�������Ƃ������炢�Ȃ�܂������܂��Ƃ������́A����A�S�������āA�C���`�L���i�ł��ꉽ�ł���Ƃ肠�����������v�Ȃ�܂��~�����������B
�@ �����A���ꂽ���ƂɁA���̃V�����m�Ƃ�����A�v���X�`�b�N���̂��Ⴟ�ȕ����Ղƈ����ۂ��r�j�[�����̃o���h����Ȃ�c���p�̃I���`���̎��v�������̂��B����ɂ����J�Ȃ��Ƃɂ́A���̎��v�̓����ɂ͉��̉l�ߍ��܂�Ă����̂ł���B�Ȃ�Ă��Ƃ͂Ȃ��A��ɓ`����Ă����قǂ悢�d�ʊ��Ȃ���̂͂��̉��̂����ɂق��Ȃ�Ȃ������B�ǂ�Ȃɍ������ς����Ă���A�O�\�~���x�̃V�����m�Ȃ̂����A�Ȃ�Ƃ���ɌܕS�~���̑�����x���킳�ꂽ�Ƃ����킯�ł������B��}���ł��Ƃ̏ꏊ�܂ň����Ԃ��Ă݂����A�ނ��A�j�̎p�͂����ǂ��ɂ���������Ȃ������B
�@ ���Ԓm�炸�̉䂪�g�̋����������}���Ȃ���ʂ肩�������K�[�h���ɂ́A�c���q�A��̋������̏��̎p���������B���̑O��ʂ�Ȃ���A�ǂ����Ȃ��x�����ꂽ�ܕS�~���������ɂ���Ă��܂��悩�����Ǝv���������B�����A�L�y����V���̃K�[�h�����ӂɂ́A�ʂ�O�ɒu���A�{����Z�����݂��ڂ炵���p�̋��������A�ʍs�l�Ɍ������Ă͌��������������Ȃ��炻�̓���������Ă����B���̏��̘e�ɂ͕K���l�A�܍قǂ̗c�������������Ȋ�ō����Ă��āA�l�X�ɋ�i���A���͂̏��������߂邩�̂悤�ɗ܂𗬂��Ă��������̂������B
�@ �n������㋞���Ă�������̐S�D�����l�X�́A���߂Ėڂɂ��邻��ȋ������e�q�̎p�ɂЂƂ����Ȃ�ʓ�����o���A�����炩�̏��K���ʂ̒��ɓ�������Ă��̂��킾�����B�n�R�w�������������A�㋞�����Ă̍��ɂ́A������ɂق����ꉽ�x���ʂ̒��ɏ\�~�ʂ���荞�L��������B���������ƁA���̋��������܂��Ȏ҂������̂����A�������A���̎��͂܂��������̐��E�̗�����Ȃǒm��悵���Ȃ������B
�@ ���ꂩ�甼�N�قǂ��Ă���̂��ƁA�s���̕����{�݂�{��{�݂ł̃{�����e�B�A�����ɎQ�����n�߂����́A�����]����؏�̈�p�ɂ��������葑�Ƃ������Ԍo�c�̕��q���Ŏv���������ʎ�����m���Ĝ��R�Ƃ������̂������B���Ȃ݂ɏq�ׂĂ����ƁA���q���Ƃ͐����͂̂Ȃ����q�ƒ�̂��߂ɐ݂���ꂽ���̕����{�݂ŁA��q���ȂǂƂ͈���č����ł�����߂Ē��������݂ł������B���݂��̏ꏊ�ɂ͒����c���ǎ��̋A���҂����̐�p�Z��݂����Ă���B
�@ �n�����Ă��䂪�q�����͕K���Ɉ�ďグ�悤�Ƃ����q���̑����̕�e�����ƈ���āA�l�i�I�Ȕj�]�҂����Ȃ��Ȃ��������q���̕��e�����́A�䂪�q�ɐޓ���X���A�����A���t�A����Ƃ������悤�ȍs�ׂ����������苭�v�����肷�邱�ƂȂǁA�Ȃ�Ƃ��v���Ă��Ȃ������悤�ł���B�ނ���̗�O�͂��������A�ނ�̂��Ȃ�̎҂���������Ďq�ǂ��������҂������i�������グ�A�����͉��������ɓ��X��������ĐQ�Ă���Ƃ������L�l�������B
�@ �����A���̕��q���ɂ͂ƂĂ��l�Ȃ����l�A�܍��炢�̒j�̎q�����āA�ނ͉�X�w���{�����e�B�A�̂Ƃ���ɂ悭�V�тɗ������̂������B������ނƈꏏ�ɗV��ł���Ɩ��ɂ��K��ɂ���̂ŁA�K���ɒ�R����̂��������āA���̃Y�{���ƃp���c��E�����Ă݂��B�ނ̂��K�ɂ͂ق��ڂ��Ɏ��F���{���ꂪ����A�܂��畆�̂����������^�R�̂悤�Ɍł��Ȃ��Ă��܂��Ă����B��X�����R��u���Ă��ނ͊�Ƃ��Č������낤�Ƃ͂��Ȃ������B�c���S�Ȃ�ɁA�ނ����炩�̔閧�������Ɏ�낤�Ƃ��Ă��邱�Ƃ͖����������B
�@ ���̕s���Ȏ��Ԃ̔w�i��������Ă��ꂽ�̂́A���q���̊Ǘ��ӔC�҂ł��������x�e�����P�[�X���[�J�[�̍����������B���b�����Ȋ�̉�X�Ɍ������āA��������͂��Ƃ��Ȃ��ɁA�u�����A���̎q�̂��K�̂��Ƃ����H�A����͋������̂����Ȃ�B�킩���Ă��Ă��~�߂悤���Ȃ����ǂˁB�ł��˂��A���̂��炢�̂��Ƃŋ����Ă�����A�������ɂ͂����ł̊����Ȃ��܂�Ȃ���v�ƌ����Ă̂����̂������B
�@ ���ꂽ���ƂɁA�ނ̕��e�͈��������̖ŋ������̏��ɉ䂪�q��݂��Ă����̂ł���B�������̏��͎肽�q�ǂ���A��Ĕɉ؊X�߂��̃K�[�h���Ȃǂɏo�����A��Ԃɂ����Ă����āA�l������ʂ邽�тɔ߂������ɋ�����߂����A��������������Ă͓�������߂鉉�Z�����Ă����̂��B�q�ǂ����������Ƃ������Ȃ�������A�r���Ŕ�ꂽ��A���܂������Ȃ������肷��ƁA�e�͂Ȃ����K���˂�����@�����肵�ĂЂǂ��ܟB���J��Ԃ��Ă����悤�ł���B
�@ �����̋����������̎q��A��ĊX���ɏo�������Ƃ͏��Ȃ��A���ۂɂ͂قƂ�ǂ�����Ȏ�q�ł������炵���B�l���Ă݂�A�q�ǂ��͂����ɐ���������̂�����A���N�ɂ킽���ċ������̎d���𑱂���ɂ́A�ʍs�l�̓�����ɂقǂ悢�N��̎q�ǂ����m�ۂ��邽�߁A���X�Ɏq�ǂ�����芷���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B������A���������q�ǂ������͓̂��R�̂��Ƃł͂������̂��B�ނ��A�����s�҂������Ƃ���ŁA���܂��炷��ƂЂǂ��b�ł͂���̂����A���̎�̍s�ׂ₻��ȏ�ɎS���炵���s�ׂ���s��̂�����Ƃ���ōs���Ă�������̂��Ƃ�����A�킩���Ă��Ă��N�ɂ��ǂ����邱�Ƃ��ł��Ȃ������̂ł���B
�@�u���̂��炢�̂��Ƃɋ����Ă�����A�������ɂ͂����ł̊����Ȃ��܂�Ȃ���v�Ƃ�����������̌��t�ɂ͌֒��ȂǂȂ������B����ɂ��Ă͂����ł͏����Ȃ����A���ہA�������͂��̌�̊�����ʂ��đz����₷��̌������邱�ƂɂȂ����̂ł������B
�@ �������x���ꂽ����Ȍo������ɁA��ؓ�ł͂����Ȃ��s��̗��̎p���������w�����ŁA���̍ɂȂ������ł́A�����A���̋C�ɂȂ������Ƃ������\�t���炢�ɂ͂Ȃ��قǂɂ��錫�����Ȃ����B����A�悭�悭�l���Ă݂�ƁA���������������Ƃ����E�Ƃ��炵�đ̂̂悢���\�t�݂����Ȃ��̂��ƌ����Ă悢���낤�B���ɂ����Ȃ����Ƃ������Ă͑����̐l�X�̊S���䂫�A����łȂ�Ƃ������Ă���B���̃C���`�L���v����̒j�⋃�����̏�������ӂ߂鎑�i�́A�����������炢�܂̎��ɂ͂Ȃ��̂�������Ȃ��B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N6��20��
�����X�[�p�[�ѓ���
�@ �V���ƎR�`�ɂ܂����钩���R�n�ւƌ������r��ɂ��������́A�S�R���獑��49�������ɒ��c��ΔȂɏo�����ƁA�֒�R�[��쑤���琼���ւƊ����悤�ɂ��đ��蔲���A���̒��A�쑽���s�ɓ������B���܂ł́u���̒��v�ȂǂƂ������u���[�����̒��v�Ƃ������ق��������ƒʂ肪�悢��������Ȃ��B��Ô˂̖k���Ɉʒu���Ă������߁A�ː�����ɂ͖k���i���������j�ƌĂ�Ă������̒n�́A�����̏��ߊ쑽�����ƂȂ�A����ɏ��a29�N�쑽���s�ɏ��i�����B�s���Ɉڍs���������܂ł́A3���т�1���т̊����ő������L���Ă����Ƃ������Ƃ�����A�����ʂ葠�̒��������킯�ł���B
�@ ���a40�N��㔼�ɂȂ��āA�쑽���̕�����Y�ł�����������X�����X�Ɏ����䂭�̂�ɂ��ʐ^�Ƌ��c���́A�㐢�ɂ��̎p��`���c�����ƌ��ӂ��A�Ђ����瑠�̎B�e�ɐ������X�����B�����āA���̎ʐ^��i�͌��ʓI�ɑ����̐l�X�̊����ƎЉ�I�Ȕ������ĂԂƂ���ƂȂ����B���a50�N�ANHK�̐V���{�I�s�u�����܂��̒��v�����f�����ɋy��ŁA�u���̒��A�쑽���v�͈���S���I�ɗL���ɂȂ����̂ł���B
�@ ���̒��A�����K�����邩�킩��Ȃ��B���̂��Ƃ��_�@�ƂȂ��āA���̌��w�①���~�̎ʐ^�B�e�̂��߂Ɋ쑽����K���ό��q�̐��͔���I�ɑ��債���B�܂��t�@�~���[���X�g������t�@�[�X�g�t�[�h�X�A�R���r�j�G���X�X�g�A�Ȃǂ̂Ȃ����������̂��Ƃ䂦�A�����ǂ��ȂǁA�ό��q�����͒n���̑�O�H���ɓ���A�K�R�I�ɂ��̓X�̃��[������H�ׂ邱�ƂɂȂ����B����ȏ̂Ȃ��ŁA�n���ł����Ƃ��l�C�̂������������[�����������ς�u�������v�ƕ]���ɂȂ�A���̉\������ɉ\���Ă�ŁA�u���������[�����v�Ƃ���ɁA���[�������̂��̂�H�ׂ邽�߂ɓ��n��K���l�X���ǂ�ǂ��Ă������B
�@ ���̌�A���ɂ̃��[������ڎw���A���������ėl�X�Ȗʂł̍H�v�Ɖ��ǂ��Ȃ���A�������쑽���́A��y�i�̎D�y�A�����ƕ���œ��{�O�僉�[�����̒n�Ə̂����܂łɂȂ����B���݂ł́A�u�쑽�����[�����v�̃u�����h�ő�ʂ̒n���Y���[�����������e�n�ɏo�ׂ����悤�ɂȂ��Ă���B
�@ �쑽���ɓ��������̂͌ߌ�O���߂����������A�܂����H���Ƃ��Ă��Ȃ������̂ŁA�Ƃ肠�������������ɂ���u�ԂӂԂ��v�Ƃ������[�����{�܂ɔ�э��B�����āA��t750�~�̃`���[�V���[�����𒍕����Ă݂����A���������������Q�̃`���[�V���[�������Ղ�Ƃ͂����Ă���A�˂ɂ��قǂ悢���������āA�Ȃ��Ȃ��̂��܂��������B�쑽���ɂ͓Ǝ��̖������������̂悤�ȃ��[�������X�����������݂��Ă��āA�ǂ̓X�̖����b�����������̂����A����}���ł������Ƃ������āA����͕֗��̂悢�����̂��̂��X�ɗ�������悤�Ȃ킯�������B
�@ ���̓X�̕~�n���ɂ͑傫�����h�Ȑ��ˍH�ꂪ�����āA���w�p�ʘH�̃E�B���h�E��ʂ��ăI�[�g���[�V���������ꂽ���ˍH�����Ԃ��Ɋώ@���邱�Ƃ��ł����B�e��̓Y�����ƂƂ��ɏ����������グ�A�����і˂Ƃ�����40�Z���`�قǂ̒��я�ɉ����L���Ċ����グ��B����ɂ��̊����グ���і˂�ʂ̋@�B�ɂ����ĊJ���L���A���������ɂȂ�悤�Ɉ�������B��������Đ�����ꂽ���F�̑і˂́A�ؒf�@�ɑ���ꂽ���Ɖ����̍ג����ˎ��ɐ蕪�����A����Ɉ��̒����̂Ƃ���Őؒf�����B�����āA�����͈�H�����ƂɎ����I�ɕ����Ă����̂ł���B���[�����̐����H����ڂɂ���̂͏��߂Ă������̂łƂĂ������[��������ꂽ�B
�@ �쑽�������Ƃɂ���ƁA�������ɍ���121����k��A�����_�����݂�ʂ�哻�g���l�����ĎR�`���ɓ������B������������R�`���̕đ�~�n�Ɍ������ɂ́A�����s����I�q�g���l�����鍑��13�����[�g�A���c�ォ��֒�R���[�A�O���Γ��݂��o�āA�L�����H�X�J�C�o���[���z���郋�[�g�A�����āA���c��܂��͉�Îᏼ����쑽�����o�ĕđ�Ɏ��鍑��121�����[�g�̎O��v�H�����݂���B
�@ ���p��������121�����[�g�̊쑽���ƕđ�Ԃ́A�i�ςɌb�܂�Ă��邤���ɓ������L���ܑ������S�ŁA�}�J�[�u���M�����قƂ�ǂȂ��B�������A�ʍs���p�̐��͂���߂ď��Ȃ�����A���s�͉��K���̂��̂ŁA�̂�т葖���Ă��쑽������đ�܂ŎO�A�l�\������������Ȃ��B�����̓������s����S�{�쉷��A�쎡����A�\���A��Óc���A��Îᏼ�A�쑽���ƌo�ĕđ�ւƎ��鍑��121���͉�Ð��X���Ƃ��Ă�A�r���ɖ������Ղ������A�厩�R�Ɍb�܂�Ă��ĕ��������Z�ł���B���k���⍑��4���𑖂���͂����Ƒu���������邵�A��Îᏼ�s�X����Ƃ��ȊO�ɂ͏a���قƂ�ǂȂ�����A�����D���Ȏ��Ȃǂ͎R�`���ʂւ̉����ɂ��̃��[�g�𗘗p���邱�Ƃ������Ȃ��Ȃ��B
�@ �����A����̖ړI�n�͕đ���ʂł͂Ȃ������R�n�����������̂ŁA�r���̓��c��Ƃ����Ƃ���ō������獶�֕��錧���ɓ���A�іL�R�n�k���̒J�ԂɍL����c���n�т�D�������ď������ւƔ������B�����āA��������͔іL�R�n�ƒ����R�n�Ƃ̊Ԃ𗬂��r�쉈���̍���113������ʂɌ������Ĕ��������B�����Ɣ����Ɩ\���Ƃ͂��������ǂ����Ⴄ�̂��Ɩ����A�E�[���Ƃ����ԓ��ɋ�����������Ȃ��Ƃ��낾���A�܂����̂�����̂��Ƃɂ��Ă͓K���ɐ������Ă��炤�����Ȃ����낤�B
�@ ����n�Ƃ��Ă��m�������߂��r�쒬�ɓ��鍠�ɂȂ�ƁA���z���傫������ɌX�����B�^���ʂ��獷�����ޗz�˂́A�T���O���X�������Ă��Ă�ῂ��قǂ������B�����܂ł���Ɠ��{�C�܂ł͂����ꑧ�ł���B���v�����܂łɂ͊C�ݐ��ɏo�邱�Ƃ��ł������������̂ŁA���{�C�ɒ��ޗ[�z���v�X�ɒ��߂Ă݂悤�Ǝv�������A����7�������肻�̂܂܊C�ݕ����ւƒ��i�����B�����āA���𗊂�ɁA�ד����W�O�U�O�ɑ��蔲���Ȃ���A���W���[�p�{�[�g�̃n�[�o�[�̂���r��͌��t�߂ɒH�蒅�����B
�@ �Ԃ��~��A�h�g��e������ʂ��ĕl�ӂɏo��ƁA���傤�Ǒ��z�����̐������ɋ߂Â����Ƃ��Ă���Ƃ��낾�����B���{�C�̓x�^��ŁA�ׂ��ȍ����Ɣ�������Ȃ�l�ӂɂЂ��邳���g�̋����́A���̐S��s�v�c�Ȃقǂɂ₷��킹�Ă��ꂽ�B�E��C��ɖڂ����ƁA���ĖK�˂����Ƃ̂��鈾���̓��e���]�܂ꂽ�B
�@ �����ւ͑���̊�M�`����t�F���[�œn�����̂����A�ω��ɕx�i�ς��\���Ɋy���߂����A�����l�ӂŐ^���ԂɏĂ����������`�̒��ɕ��荞��ŐH�ׂ�u���b�p�ρv�Ȃǂ̈闿������ςɒ����������B�ɂ₩�ɗ���鎞�ԂƁA�ǖقȓ��l�̐S�̉��ɔ�߂�ꂽ�Z�₩�Ȑl��͂��̒n�Ȃ�ł͂̂��̂ł��������B�V�[�Y�����I�t�ɖK�ꂽ�C�܂���Ȋό��q��������l�悹���f�R����̗V���D�́A�ǂ��l���Ă݂Ă��Ԏ��������ɈႢ�Ȃ��B
�@ ��F����g�ւƐF��ς������z�́A�₪�Đ������ɂ҂���Ɛڂ��A���ꂩ�炷���ɐ������̈ꕔ���Ԃ��~�Ղ̉�����錷�ɕς�����B�����āA���̌��͂������ɒ����𑝂��Ă��ɂ͑��z�ʂ����E�Ɋт����a�ƂȂ�A�������炳���͋t�ɂ݂�݂邻�̒����������Ă������B���̒������[���ɋ߂Â��ɂ�čg�F�̋|�`���}���ɏk�݁A�قǂȂ���̐������������A�Ȃ��������F�ɋP�������̋�ƊC�Ƃ̋��ڂɎc���ꂽ�B
�@ ���c��ɂ��݂Ȃ��物���̋��������Ă���ƁA�n���̋��t�炵���j������A�g�ł��ۂ̂����߂��Ŏ�ɂ������Ԃ������͂��߂��B�Ȃ��Ȃ��ɑN�₩�Ȏ���Ȃ̂����A����ȏ��߂��ŋ����l���̂��낤���ƁA���Ă��Ă��������S�z�ɂȂ����B�����A����͂悯���ȐS�z�Ƃ������̂������B�������瓊�Ԃ������グ�ĕl�ӂɍL���悤�Ƃ��Ă���j�ɋ߂Â��A�����l���̂��q�˂Ă݂�ƁA�ނ͓��Ԃ���͂���������̏����O�A�l�C���w���������B����͏��Ԃ�̃J���C�̂悤�������B�j�̘b���ƁA�������悯��J���C���̑��̏��������\�Ȑ��l���炵���B���ƌ��t�����킵�Ȃ���A�j�͖Ԃ���͂��������̂����̂��������Ȃ��̂�I��ł͍ĂъC�ɓ����߂����B
�@ �l�ӂ���߂�ƁA�����߂��ɂ���u�`�v�Ƃ����X�������̊C�N���X�g�����ɓ������B�����Ď`�Ƃ������t�̋����Ƃ͂��悻�������ꂽ�C���[�W�̐�S�~�̎h�g��H�𒍕������̂����A���ꂪ�Ȃ��Ȃ��̏E�����������B�l�ꂽ�Ă̐���̋��̎h�g�́A���A�ʂƂ��ɐ\�����Ȃ��������A���g�̃J�j����̃J�j�`�����ɗǂ����ł������B�ϕ��ɂ��A�����Ă�₩�Ȓn���Y�̂��Ă̂��тɂ�����̂��悤���Ȃ������B�������A�T���_�ƈ��ݕ��͐H�ו���A���ݕ���Ƃ��Ă�������A����ō��݂Ő�S�\�܉~�Ƃ����͈̂������̂ł������B�`�Ƃ������̂��X�Ɂu�]�́v�����������v��������Ȃ��玄�͎ԂւƖ߂��Ă������B
�@ ���������ƁA���̂��Ǝ��͍�N�㌎�ɂ��K�ꂽ�����R�n���̉��O�ʃ_���ւƌ��������肾�����B���Ĕ鋫���Ăꂽ���R�̕�ɂ̔j���M�d�ȓꕶ��Ղ̐��v�������ސ���f����悤�ɂ��āA��N�\���ɂ��̃_���̒X���͎n�܂����B��N���̂��Ƃɂ��ď��������Ƃ������āA���̌�̃_�����ݒn��т̕ϗe�Ԃ����x�����̖ڂŊm���߂Ă݂����ƍl���Ă������炾�����B
�@ �ǂ������̂��Ƃ͒����R�n�̎R���ł̎Ԓ����ɂȂ邾�낤�Ǝv�����̂ŁA�ʂ肪����̃R���r�j�ɗ�����Ē��H�p�̃p���⋍�������߂��B�X���o�����Ɖ��C�Ȃ����ׂ̗߂�ƁA��̂��Ƃ䂦���̂ق��܂ł͂悭�����Ȃ��������A���Ȃ�傫�ȃn�E�X�͔|�̎{�݂炵�����̂������Ă���悤�ł������B�����Ă��̑O�ɂ́u�t���b�V����I�v�Ƃ����傫�ȊŔ��f�����Ă����B
�@ ���̎��ł���B�Ȃɂ��Ȃ܉��������ɏ���āA�ǂ�����Ƃ��Ȃ����̗L�@�͔|���L�̃t���b�V���ȏL�����Y���Ă����B�����q�ǂ����ɂ͓c�ɂȂ�ǂ��ɂł��Y���Ă������̉��������L���ł���B�u�t���b�V����˂��A�m���ɂ��̃t���b�V�����̂����Ȃ��L�����炷��ƁA�����̃n�E�X�ō̂���͐V�N�ł��܂��ɈႢ�Ȃ��B�ł��A�s��炿�̉q���ϔO�ߏ�Ȑl�X���A����Ȗ�̗L�@�͔|�����ڂɂ�����A�����ƋV���邱�Ƃ��낤�ȁB�ܗL�������댯�Ŗ������܂ЂƂł��A����ς�Ȋw�엿��p������̂ق��������Ȃǂnj����o���̂ł͂Ȃ����낤���H�v�\�\����ȑz�����߂��炷���̋����͂����������G�Ȃ��̂ł͂������B
�@ �����X�[�p�[�ѓ������ɂ͖�Ԓʍs�֎~�Ƃ����\�����Ȃ���Ă͂������A�����ɃQ�[�g������킯�ł��Ȃ��̂ł��̂܂ܗѓ��ɕ����������B���̗ѓ��͂��Ȃ艜�܂ł悭�ܑ�����Ă��邵�A���x������Ȃꂽ���ł��������̂ŁA�[��Ƃ͂����Ă��Ƃ��ɍ���悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ������B���炭���葱���Ă���ƁA�܂���̐Q�҂̌����R��ɏ���A�����R�n��т̎R�X�ɓ��L�Ȃ��̍r�X�����┧���Ƃ炵�o���͂��߂��B�ǂ�������Ȋ����������錎���̎R�x���i�Ƃ������̂́A�[��̈�l���ɐ��̏̈�[�����߂�l�Ԃɂ́A���̂����Ȃ������I�Ȃ��̂ł���B���͂����Ԃ��߁A����ɐ[���藧�J�ꂩ��N������閶�ƁA���̒J�̗������ނ�����Ƃ������ɕ����яƂ炳���L�l���A�������ł��������̂悤�ɂ��������ƌ��߂Ă����B
�@ ���������e�����Ȃ����̎R�����̂�т�Ƒ����Ă������Ƃ������āA���O�ʃ_�����ʂւƑ������H�̕���_�ɓ��������̂͌ߌ�\�ꎞ�߂��������B������������Ă����̂����A�c�O�Ȃ��Ƃɉ��O�ʕ��ʂւ̓����ɂ����鋴�ɂ͌��d�ȎԎ~�߂̃Q�[�g���݂����A���N�̏\�����{�܂ł͒ʍs�s�\�ł���|�̕\�����Ȃ���Ă����B���O�ʃ_���ɕt�т��铹�H���Ȃ��������ł��邽�߂Ƃ����̂��\�����̗��R�̂悤�������B
�@ �ʍs�~�߂ł͎d�����Ȃ��Ǝv���Ȃ���A���C�Ȃ�����Ɋ��������ƁA�Ȃɂ��傫�ȉ���炵�����̂��ڂɔ�э���ł����B�Ԃ̃��C�g�ŏƂ炵�o���Ă݂�ƁA����͐V������Ƌǂ��ŋߗ��Ă�����̉��O�ʐ��͔��d���ɂ��Ẳ���������B�X�������ɂ́A���̉���̓��e�͂��e���ŁA���w���ł��m���Ă������Ȑ��͔��d�̌����̊ȒP�Ȑ}���ɉ����āA��b�ԂɃh�����ʓ�S�{���̐������d�p�����H�𗬂ꗎ���A�ő�o�͂�34500kwh�ŁA����͑���ƒ������̖�ꖜ�O��˕��̎g�p�d�͂ɑ�������Ƃ������Z�����������Ă��邾���̂��̂������B�����čŌ�ɂ́u���͔��d�͏����Y�̃N���[���G�l���M�[�ł��v�Ƃ����ꕶ���Y�����Ă����B
�@ ���������N�ɓǂ܂�����肩���悭�킩��Ȃ�����̐����̍Ō�ɁA����Ȍ���������������^�ʖڂȊ�����ĕt���������肷���l�����̖��_�o���ɁA���͗B�X���ꂩ�������ł������B�ő�o�͂�34500kwh�A1kwh������̓d�͗�����23�~���Ƃ���ƁA��N�ԋx�݂Ȃ��ő�o�͂ŘA�����d�������Ȃ����Ƃ��̑����d�ʂ̉~���Z�z�́A
�@23�~/kwh�~34500kw�~24h�~365����6951060000�~
�ƂȂ�B
�@ ���ۂɂ͍ő�o�͂ň�N�����d�𑱂��邱�Ƃ͕s�\�����A���d���X�Ȃǂ����邩��A���̎l���̈���x�̔��d�ʂƍl����̂��Ó��ȂƂ��낾�낤�B����ƁA�����I�ɂ͔N�ԑ����d�ʂ̉~���Z�z��17���~�O��Ƃ������ƂɂȂ�B�Â�����̏W����S�˗����ނ����A�����ł�����߂ċH�Ȏ��R���Ɍb�܂�鋫�ƌĂ�Ă�����k�J�ƁA�ߋ��ܐ�N�ɂ킽���Ă��̒J�̒n���ɖ��薄����Ă����ꕶ�̈���Ղ𐅖v�����A��牭�~�ɋ߂��H��𓊓����đ���ꂽ���̃_���̔��d�\�͂͐��X���̂��炢�̂��̂Ȃ̂��B�Ȃɂ������Y�̃N���[���G�l���M�[�Ȃ��̂��ƁA����ł݂����Ȃ�l���������ď��Ȃ��Ȃ����낤�B
�@ ���O�ʃ_�����ʂ̕���_��ʂ�߂������ƁA���͂���ɉ��̂ق��܂Œ����X�[�p�[�ѓ���i��ł������B�c��Ȃǂ̉e�����₷���������ӂ̓��H����̈����������āA��N�܂����̎����ɂ͐V��������R�`�����ɂ͔������Ȃ��B��ނ����Ȃ��̂ŁA�ʍs�~�߂̍��̒����Ă���ꏊ���牓���Ȃ����R�o�R���t�߂ɒ��Ԃ��A�����ʼn��������Ƃɂ����B���炭�{��ǂ茴�e���������肵�Ă������Ƃ������āA�G�A�x�b�h��c��܂����̏�ɐg�����������̂͌ߑO�O�����������B�J�[�e���̌��Ԃ��獷�����ތ������s�v�c�Ȃ��炢�ɖ��邩�����B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N6��27��
�y���U���ɏ��������ɁI
�@ �����͘Z�������ɖڂ��o�߂��B�߂��Ől�̐�����������ł���B�g���N�����đ��z���ɊO���̂����ƁA�n���̂��̂炵���y�g���b�N����䂷�����ɂƂ܂��Ă��āA���N�̒j��l���R�ɓ��鏀�������Ă���Ƃ��낾�����B���̂܂܂�����x����Ȃ����悩�����̂����A�V�C���悩�������Ƃ������āA���̂܂܋N�����Ă��܂����̂����̎n�܂肾�����B
�@ �C�ɂ���قǂ̂��Ƃ͂Ȃ��������A���C���ł�����ƋC�ǂ����k���Ă��銴���������̂ŁA�̒��̖��S�������A�g�s���Ă����C�ǎx�g���܃T���^�m�[�������ʋz�������B�����āA�����ԊO�ɏo�Ă��������ς܂����B���ꂩ�璩�H�����ɉَq�p��������o���A�����ꖂ�Ȃ�����R�������̒j�����̗l�q��������Ă����B�ނ�͑�����ɂ��K�����ϐ����̒��n�����܂ɗ����ւ��A�G���ł��̏�[����������Ǝ~�߂Ă���Ƃ��낾�����B
�@ �⋛�ނ�ɂł��s���̂��Ɛq�˂�ƁA�t���T�r��[���}�C�Ȃǂ̎R���̂�ɍs���Ƃ���Ȃ̂��Ƃ����B���ۂɂ͒j�����̂ق����������Ⴉ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv�����A�����ɃW�[���Y�Ƃ������̎p�����āA�����������������ƔN�����ƍl�������̂炵���B�ނ�͂����Ƃ��������łǂ�ǂĂ���A���ɂ͗t���T�r�̂���Ƃ���܂ňꏏ�ɍs���Ȃ����ƗU�������Ă����B
�@ ���̓��͎R�`�s���ʂɌ��������肾�����̂ŁA��������͓��s�����ނ����̂����A�Г��ꎞ�Ԃقǂ����琥��ǂ����ƗU���Ă��ꂽ�B�̂��̐���s�����炷��Ɣނ�̈Ӑ}���ǂ̂ւ�ɂ������̂����܂ЂƂߑR�Ƃ��Ȃ��̂ł͂��邪�A�Г��ꎞ�ԂȂ�������ňꎞ�Ԃقlj߂�����l������ɖ߂��Ă��Ă��O���Ԃ��炢�̂��̂��낤�ƁA���̎��͂�������y���l�����B
�@ ���̎Ԃɂ͓o�R�p��ꎮ�ς�ł���B��芸�����}���œ��R�̏���������̂ł�����Ƒ҂��Ă��Ă���Ȃ����Ƃ����ƁA����́A���邾���Ȃ��牽�������Ȃ��ł������A���̂܂܂̊i�D�ő��v����ƁA�}�����Ă��B�o�R���ɗ����Ă���ē��ɂ��ƁA�ނ炪���낤�Ƃ��Ă���͕̂W���烁�[�g����̐��R�Ƃ����R�ŁA����܂ŕГ��O���ԁA�R���ɂ͈ꉞ����������悤�������B
�@ ���ǁA���͂��̂܂܂ł悢�Ƃ����j�����̌��t��M���A�U����܂܂ɒj�����ɂ��Ă������Ƃɂ����B�H�ׂ����̃p�����ԂɎc���A�����ʂ��Ԃ�̏�Ԃ������B�Ⴂ���炻��Ȃ�ɎR�s���d�˂Ă����g�Ƃ��ẮA�������Ă���܂������Ƃł͂������̂����A���̎��́A�t���T�r�̂���Ƃ���܂ł�����Ƒ���l�߂邭�炢���낤�ƌy���l���Ă��܂����̂��B����ɎR�����̌o�������������Ƃ����̏ꍇ�ɂ������Ă̓}�C�i�X�ɂ͂��炢���ƌ����Ă悢�B
�@ �����n�߂ĊԂ��Ȃ����̓��͋}�ɍׂ��������Ȃ�A�A�b�v�_�E�����z���ȏ�ɂЂǂ��Ȃ��Ă����B�Ƃ��낪�A���̂�����̎R�����Ɋ���Ă���炵���j�����́A����Ȃ��ƂȂǂ��\���Ȃ��ɁA�����ȃX�s�[�h�Ői��ł����B�����Ƃ����o�R�C�ɗ����ւ����A��X�������ςȂ��̑����ɒ�̎C�茸�����g���b�L���O�V���[�Y�̂܂܂ŗ��Ă��܂������߂ɁA���������ė]�v�ɃG�l���M�[���₵�����A����ł��x�ꂶ�Ɣނ�̂��Ƃɂ��Ă������B���������œ|�������ǂ��Ă��܂��Ă������߁A�n���悤�ɂ��Ă��̉�������������A�t�ɂ��̏�������ɏ��z������A�M��~�����������������肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ������B
�@ �����v�����̂��A�ނ�̈�l�́A�����n���a�̌��t�ł̂ق��́A�u�R�؍̂��⋛�ނ�ɓ��������łɂ��̎R�̒���܂œo�邱�Ƃ������Ă��A���Α��ɂ͐�~��Ă͂����Ȃ��B���l��s���s���ɂȂ����l�����Ȃ�̐��ɂ̂ڂ邩��v�Ƃ����Ӗ��̂��Ƃ�b���Ă��ꂽ�B���ƂɂȂ��Ă݂�ƁA�ǂ��ɂ������Ȃ��v��������̂ł͂��邪�A���̎��͑f���ɂ��̌��t���悻�҂̎��ɑ��钉�����ƎƂ߂��B
�@ �i�ނقǂɌ��������܂��R�����ꎞ�ԋ߂����������Ə����̑���������̂����A���̑�͐܂���̐�Z�����ŗ��ꂪ�������A�C���ǂ��Ղ�Ɛ����ɂ��A��ۂő������点�Ȃ��悤�ɂ��܂��o�����X���Ƃ�Ȃ���A�n���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�G�܂Ő��ɂ����Ă����C�Ȋi�D�����Ă���ނ�ɂ͂Ȃ�ł��Ȃ��������A����Ȃ�̑����������Ă����ɂ�������炸���h���Ȏp�̂܂܂ł���Ă������͂����������Ȃ������B����đ�ّ��ɗ������������ς�����A�������̂��Ɨ����ɂȂ�W�[���Y�̐����������ēn�낤���Ƃ��v�����B�����A����@���^�I���������Ă��Ȃ������ɁA����Ȃ��ƂŐ�s����ނ��҂�����̂����������C���Ђ����̂ŁA�C�ƃW�[���Y�̐��[��G�炵�Ȃ�����A�W�����v�͂��قǂ悭�������ĂȂ�Ƃ����̋}����n������B
�@ �������Ƃɂ́A���̂��ƍׂ��o�R���͖җ�ȋ}��ɂȂ����B����s����l��ǂ������\���Ԃقǂ̗͑͂̌����s���Ă��Ă������Ǝ��݂��̂����A���ɂ����ŃM�u�A�b�v������Ȃ��Ȃ����B�o�R�̍Œ��ɂ��̂悤�ȑ̌�������͕̂����ʂ菉�߂Ă̂��ƂŁA�����ł��M�����Ȃ��v�����������A�ɓx�̔�J���őS�g�̋ؓ����܂������������Ƃ������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�������ɒ[�ɂЂǂ��Ȃ�A�S�������ُ�ɑ������ė���ῂ݂��o���A�����������邤���ɖڂ����݂������B
�@ ���炭�t�߂̑ۂނ�����ɍ��|���ċx�����A�܂��C���Ƃ�Ȃ����ċ}��襘H���������o��͂��߂����A��\���[�g���قǕ����������ł܂��g�̂��������Ƃ������Ȃ��Ȃ����B�����̎R�s�̏ꍇ�ƈ���Ă������肵���U�b�N��w�����Ă���킯�ł��Ȃ�����A�ǂ��l���Ă����̏�Ԃ͐q��ł͂Ȃ������B�d���ו���w�����č��R�ɒ��ނ��Ƃɓo���ɂƂ��Ȃ��ꂵ�݂����x��������Ă͂����̂����A����̏ꍇ�͖����ɂ���Ƃ͉���������Ă����B������Ƃ����āA�����Ԃ����ɂ��A����ȏ�Ԃł́A����̋}�Ȃ��̑�Ȃǂ�������x�n��A�A�b�v�_�E�����Ђǂ��đ���̋ɂ߂Ĉ�����H���Ė����o�R���ɖ߂�����ƂȂǂł������ɂȂ������B
�@ ������ɂ��낱���͎��Ԃ������Đg�̂��x�߁A���̂��Ɨ�Âɍs�����邵���Ȃ��Ǝv���A�K���ȏꏊ��T���Ă݂��B���̋}�ȎΖʈ�т̓u�i��g�`�̟T���Ɩ���тɂȂ��Ă������A�����̎��̂قƂ�ǂ͓~��ɐς��鍋��̉e���ŁA�����߂��̊��̕������傫���p�Ȃ��Ă���A�w���������ꂩ���Ē��Q�ł�����̂Ɏ荠�Ȃ��̂��Ȃ��ɉ��{���������B���͂���Ȏ�̈�{��I�сA���̊��ɑS�g���䂾�˂����Ă����ڂ��ނ����B�g�̒��̗͂��X�[�b�Ɣ����A�����ӎ����ɂȂ�A���Ԃ̗��ꂪ��u�~�܂��Ă��܂������̂悤�Ȋ����������B
�@ �Ȃ�Ƃ���Ȃ��b�ł͂��������A����̌����Ƃł��������A������ς������قǂ��ґ�ȑ̌��͖]��ł����������ł�����̂ł͂Ȃ������������B�܂��ߑO�����߂����������A�V����悭�A��C�͑u�₩���̂��̂ŁA�������������܂����������Ȃ������B�u�i��g�`�A�z�E�Ȃǂ̋��̎��т̐��ݏo���V�N���ӂ�Ȏ_�f�ƃI�]���ɕ�܂�A���͂��̐S�g������܂Ő��߂��Ă���悤�Ȃ��̂ł��������B��s������l�̒j�������߂��Ă���l�q�͂܂������Ȃ��������A���Ƃ���l������Ă���C�z�Ȃǂ��܂�łȂ���������A���͂��̏�ł܂�������l����ɂȂ��Ă����B
�@ �����Ɩڂ��ނ�u�i�̎�̊��ƈ�̉��������̂悤�ɐg���������鎄�̎����ɁA�����𗬂��k���̐����ƁA�X�ɐ��ރA�J�Q���̎����މ��Ƃ��A�s�v�c�Șa����D��Ȃ��ĉ��������Ă����B���炭���Ă��炻���Ɩڂ��J����ƁA�͂邩����ŁA�܂����܂�ĊԂ��Ȃ��u�i�̎�t�����X�����F�̗ɋP���Č������B�܂������R�n�͏��Ă��}�������肾�����B
�@ �x�������������ł��Ȃ�̒����������A�v�l�͂��S���Ă����̂ŁA���̂܂܂̑Ԑ��ő傫���ċz�𐮂������ƁA�����ɂ�����܂ł̏�����x��ÂɐU��Ԃ��Ă݂��B�Ђǂ��ꂵ�����o���A�g�������ł��Ȃ��Ȃ�������A�܂������Ɏ��̔]�����悬�����̂́A�u���̒��x�̂��ƂŎQ���Ă��܂��قNj}���Ɋ�b�̗͂������Ă��܂����̂��B��͂���Ƃ��Ă��܂����Ƃ������ƂȂȁB�������Ƃ���ƁA���ꂩ��͐�͓o�R�Ȃ�Ė������ȁv�Ƃ����Ȃ�Ƃ���Ȃ��v���������B
�@ �����A���炽�߂čl���Ă݂�ƁA���ׂĂ��̂����ɂ��Ă��܂��̂͂Ȃ�Ƃ��s���R�ȋC�����Ȃ��ł��Ȃ������B�����ŁA���̎�������ꂱ��Ɖ�z���邤���ɁA�ˑR�A���������ڂ̌����炵�����̂��v��������ł����B
�@ �����o�����̂͋C�ǎx�g���܂̃T���^�m�[�����z���������ゾ�����B����I�ȍs�������镪�ɂ͂Ȃ�ł��Ȃ��̂����A�ꎞ�I�ɐS���ɕ��S��������S�������オ��T���^�m�[�����g�p��A�����ɉߌ��ȉ^���������ꍇ�A�����p�������ĐS���Ɉُ�ȓ����������邱�Ƃ͍l�����Ȃ����Ƃł͂Ȃ��B�܂��A���̐������Ԃ͎O���Ԓ��x�ŁA�������A�O���͌ߑO�뎞�����炢�ɓ������o�āA�r���ł������������Ȃ���x�ނ��ƂȂ����̒����R�n�܂ł���Ă����킯������A���Ƃ����Ƃ��Ă��Ȃ��Ă�����Ȃ�̔�J���~�ς���Ă��Ă����R�������B
�@ ����Ɉ������ƂɁA�j�����ɋ}�����ꂽ���Ƃ������āA���̒��َ͉q�p�����H�ׁA���������R�b�v�Ɉ�t�������������B�܂��A�����o���Ă�����}�C�i�X�̏������d�Ȃ����B�܂������̎�Ԃ炾�����Ƃ͂����A���H��i�ޒj�����̑��x�͑����Ȃ��̂������B���߂ď\�N�O�܂ł��炢�Ȃ炻�̑����ɂ��Ă����͉̂��ł��Ȃ������낤���A���̍ŁA�������A������ƋC���Ɗ����Ă��܂����˂Ȃ���̎C�茸�����g���b�L���O�V���[�Y�̂܂܂Ŕނ�̂��Ƃɑ����ɂ́A���ӎ��̂����ɂ��Ȃ薳�������Ȃ���Ȃ�Ȃ������B
�@ �����ЂƂA�f�b�h�|�C���g�̖����������B�Ⴂ������܁X�R�ɓo���Ă������̏ꍇ�A��ԋꂵ���Ȃ邢����f�b�h�|�C���g���A�����o���ĎO�A�l�\����Ƃ�����r�I�������Ԃɂ���Ă���B���̎��ԑт��������ƕ����Ă��߂����A���Ƃ͐g�̂��y�ɂȂ��ĕ�����������A���e���|�ŎR���܂œo���Ă������Ƃ��ł���B���̃f�b�h�|�C���g�ɂ����鎞�ԑтɖ��������Ă��܂������߁A�I�[�o�[�y�[�X�ɂȂ��Ă��܂����̂������B
�@ ������ɂ���A����Ȋ���̈��������d�Ȃ��āA���ɂ͐g���̂��Ƃ�Ȃ���ԂɊׂ������Ƃ����͊ԈႢ�Ȃ��悤�ł������B���������A�U���Ă��ꂽ�j�����́u���̂܂܂ő��v����v�Ƃ������t���z�ʒʂ�Ɏ���Ă��܂����̂��Ȃ̕s�o�������̂��B
�@ ���낢��Ȃ��Ƃ�A�z���Ȃ��珬�ꎞ�Ԃقǐg���x�߂Ă���ƁA��������̒������Ă����B������ƕ����Ă݂����A�K���g�̂��y���Ȃ��Ă���A���̕����ƒj�����̂���Ƃ���܂ōs�����Ƃ͏\���\�Ȃ悤�Ɏv��ꂽ�B��ɐi�ނ���A���ƂɎc���Ă������̂��Ƃ�S�z���Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv�����̂ŁA���͍Ăы}��襘H����֏�ւƕ����n�߂��B�܂������̂��ƁA���̂܂܂̎p�Ő��R�̒���ɂ܂Ŏ��邱�ƂɂȂ낤�Ƃ́A�������ɍl���Ă����Ȃ������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N7��4��
���d�o�R�H
�@ �o��ɂ�Ă܂��܂��ׂ��������Ȃ�R�����O�\���قǐi�ނƍĂё�ɏo���B�₽������������قƂ��邻�̑�͂����œ��ɕ�����Ă����B����܂Ŏ��̒m�����ł́A�V�R���̃��T�r�́A���w���L�x�ȗN���̗����f�R�����̋}�Ζʂ̂悤�ȂƂ�����D�ށB�������Ƃ���A�n�`�I�ɂ݂Đ�ɍs�����j�������ڎw�����͍̂���̑�̂悤�Ɏv��ꂽ�B�����A�o�R���̂ق��́A���E�ɕ����ꂽ��̑�ɂ͂��܂������ւƑ����Ă����B
�@ �j�����̋��ꏊ���肩�ł͂Ȃ������̂ŁA�吺���o���ČĂт����Ă݂��������炵�����̂͂܂������������Ă��Ȃ������B�ǂ����悤���Ƃ����S�O�͂������̂́A����������������Ə�̂ق��܂ōs�����̂�������Ȃ��ƍl���A�Ăѓo�R������ݎn�߂��B�ċz�ƕ��s�̃��Y���𐮂��Ȃ���������}�Ζʂ�o�邤���ɁA�܂���ɏo���B
�@ ���邩��ɗ₽���Ă��܂����Ȑ���������Ă����̂ŁA�܂��͎�Ɗ�����Ă����ς肵���C���ɂȂ�A���ꂩ��A�߂��̕��̗t���ꖇ�Ƃ��ĘR�l��ɂ܂�߁A����ʼn��t�������d���Ă͈��݊������B�q�ǂ��̍�����͈��݂Ȃ�Ă���̂ŁA�ꌩ���������ŁA���̐������߂邩�ǂ����□�͂ǂ̒��x���Ƃ������悤�Ȃ��Ƃ͂��悻���f�����B�\�z�ɂ����킸�A����ܑ͌��Z�D�ɂ��݂킽��悤�Ȃ��܂����ł������B
�@ ���̒n�_�ł�����x�A�ǂ������������Ȃ��Ƃ���ɂ���͂��̒j�����ɑ吺�ŌĂт����Ă݂����A��������炸�����͂Ȃ������B���͂⎩���̈ӎv�Ŏ��R�ɍs�����邵���Ȃ��ƌ��f�������́A�����Ԃ��ׂ����A����Ƃ����̂܂ܐ��R�̒����ڎw���ׂ����ɂ������B�����Č��ǁA��҂̂ق���I�Ԃ��Ƃɂ����B���łɂ��Ȃ�̂Ƃ���܂œo���ė��Ă���̂ŁA���ƈꎞ�Ԕ����撣��ΕW���烁�[�g����̎R���ɒ����͂����Ƃ����v�Z���������B�܂��A�R���ɗ��ĂA�Ⴂ���̗͂ɔC���ĕ����܂���������A���ł̎R�X�����]�ł���̂ł͂Ȃ����Ƃ������҂����������炾�����B
�@ ���łɏq�ׂ��悤�ɁA����s��������s�����������߁A�H�Ƃ␅���̑��̕K�v�����͌����ɋy���A�n���J�`�̈ꖇ�������g�s���Ă͂��Ȃ������B�����A�܂����Ԃ������V����ǍD�ŁA�̒��̂ق�������������Ƃɖ߂��������������ŁA��������Ȃ�Ƃ��Ȃ邾�낤�ƍl�����B�������茳�ɒn�}�ȂǂȂ��������A�����R�n�S�̂̂����܂��Ȓn�`�͓��ɂ͂����Ă����̂ŁA���߂ēo��R�ł͂��������A���̓_�ł͂Ƃ��ɕs���͊����Ȃ������B
�@ ���炭����ƁA����łȂ��Ă��ׂ������M�Ɨ����t�Ɠ|�ɕ���ꗧ���������O�̏�ԂɂȂ����B�����ēy�����_�炩�������ɓ��ݐՂ��c���Ă��Ȃ����ǂ����A��������Ɗm�F���Ă݂����A����炵�����̂͂܂�����������Ȃ������B�����āA���̂��Ƃ́A����U������l�̒j�����������܂ł͓o���Ă��Ă��Ȃ����Ƃ���Ă������B�ނ�͂�͂肳������������̂����̂ǂꂩ�ɕ��������Ă������̂��낤�B�������Ƃ���A������̏����Ȃǂ܂��������Ă��Ȃ����������A�������Ĕނ��T�����A���̓o�����[�g��I���Ƃ͓K�������̂�������Ȃ������B
�@ ��т̕��ϓI�Ȏ����͂��Ȃ�Ⴍ�Ȃ��Ă������A���ё������Ȃ��Ƃ������ėŐ��͂Ȃ��Ȃ������Ă��Ȃ������B�����Ȃ炻��Ȃ�̏d���̃U�b�N��w�����Ă���̂ŁA�}��Ȃǂł͎��R�ɐg�̂��O�X���đ̏d�S�̂������ɂ�����A���܂����肪�Ƃ��̂����A��Ԃ�Ƃ����͖̂��ɐg�̂������Ă��܂��A�������ăo�����X�������B�ςȂƂ���ɕςȗ͂�����銴���ŁA���̓_�͂��������ӊO�ł��������B�Ƃ�����Ɠr�ꂪ���ɂȂ郋�[�g���Ȃ�Ƃ����𗊂�ɓ��q���Ȃ��炳��ɐi�ނƁA�ˑR�A�s����ɁA����ł����ƌ�������̗l����悵�Ȃ���A���̓��ő�̓�Ζʂ����ꂽ�B�ǂ̂��炢���̋}�o�H�������̂��͂킩��Ȃ��������A����́A�ǂ��݂Ă��悶�o�邵���Ȃ��悤�ȓ�y�Ɗ�Ƃ̍������Ζʂ������B
�@ �ׁX�Ƃ��̋}�Ζʂ�D���`��襘H�́A�Ƃ���ǂ���܂����Ȃ�̎c��ɕ����Ă��đ��ꂪ��������łȂ��A��Z����������o���Ă��邽�߂ɁA�����������c���c���O�V���O�V���ɂȂ��Ă����B�����łȂ��Ă����\�̗͂����Ղ������ȂƂ���Ȃ̂ɁA���ȃI�}�P�܂ł��Ă���Ƃ����̂����炽�ǂ��ɂ����܂������̂ł͂Ȃ������B�s�b�P����A�C�[���Ƃ������{�i�I�ȑ����͂Ƃ������Ƃ��Ă��A����n�т̗Z����̎R�ɂ́A����ɔ����ăX�L�[�p�X�g�b�N�̈�{���炢�͂����Ă���̂��펯�ł���B����Ȃ̂ɁA���̃X�g�b�N�͂��납�A�����H�Ƃ������Ă��Ȃ������̂����疳�d�o�R��掂�������Ă��d���̂Ȃ��Ƃ���ł������B
�@ �C�������Ăǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��Ƃ����A�Ȃ�Ƃ��o��Ă�������ƃo�����X��������犊�藎���Ă��܂������ȂƂ���͈Ӑ}�I�ɓ����͂����A���X��ςł�����M��~�������A�̎}��̍��ɂ��܂��ċ����ɂ悶�o�����B�W���烁�[�g�����炸�̎R�Ƃ��Ă͑z���ȏ�Ɏ苭���Ƃ����v���͂������A�����܂ł���Ƃ����Ӓn�Ƃ������̂������B���Ȃ��̂ŁA�捏�̂Ђǂ��̒��s�ǂȂǂǂ����������ł��܂��������������B
�@ ���R�A���x���������点���߁A�葫�͂ǂ�ǂ�ɂȂ�W�[���Y�̐����D�y�łׂƂׂƂɂȂ������A��������Ȃ��Ƃ͂ǂ��ł��悩�����B�Ȃɂ͂Ƃ�����A���R�̒���ɗ��Ƃ��Ƃ����C�����̂ق����摖���Ă����B������Ƒ�U����������Ȃ����A���̒��x�̂��Ƃœo����f�O���Ă��܂�����A�����̃`�������W���_���A���ɐg���������Ă����l���������I��肾�Ƃł��������悤�Ȏv�������̉��ɉQ�����Ă����B
�@ �c��Ŗ��܂���襘H��������邽�ߋ}�Ζʂ��M�ɂƂ���A�������Ȃ�Ƃ��������ēo�R���ɖ߂�ƁA��������������ƕ���Ȋ����ɂȂ�A�������L���Ȃ����B����͂܂��悩�����̂����A�Z������������ƒn�ʂ̓D�Ƃ������荇���ăO�V���O�V���ɂȂ��Ă����B�O���߂Ȃ���A�ǂ���I��Œʂ蔲���悤���ƍl������ł���ƁA�ˑR�A��������������ɂ�ł���悤�ȋC�z���o�����B�͂��Ƃ��Ă��̂ق��Ɏ����𑗂�ƁA�o�R���e�̒�̎}���玄�̓�����T���Ă����C�̑傫�Ȗ쐶�̉��Ɩڂ��������B
�@ �悭����ƁA�`�V�}�U�T�̍����s�̕����炵�����̂�Ў�Ɏ����A���̐�����ɂ��킦�Ă���B���傤�ǐl�Ԃ��ܗk�}���g���Ă���Ƃ��̂悤�Ȋi�D�������B����́A�u���������e���[�A����ȂƂ���ɉ����ɂ���ė�����H�B���̂������т͉��l�̓꒣��Ȃ���B�ǂ����Ă��ʂ肽�����Ă�����Ȃ�ʍs���悱�����I�v�Ƃł����������Ȗڂ��ł�����������ƌ��߂Ă���B�̊i���щ��������Ԃ�Ƃ悩��������A������������Q�𗦂���{�X���������̂�������Ȃ��B
�@�u���ɂ͐\����Ȃ����A����������ܕK���Ȃ炩�A�����Ȃ��ʂ��Ă��炤��I�v�Ƃ���ɁA�h���h���ɂȂ������̘e�̂ق���˂��i�ނƁA����͂�����ɋ��ޗl�q���Ȃ��̂����Ď�����炵���A�Q�Ă��M�̒��ւƎp���������B����ňꌏ�����Ǝv������A�v��ʍГ���̐g�ɍ~�肩�������̂͂��̒���̂��Ƃ������B
�@ �E���ŃO�V���b�Ɖ����ݔ����A���������̑������̂܂ܓD�y������̏_�炩���Z��ʂɓ˂�����ł��܂������߁A�D���ƈꏏ�ɓ��݂����V�����m�̈ꕔ���C�̒��܂ł͂����Ă��܂����B�����������ݔ������̂��낤�Ǝv���āA���炽�߂Ċm�F���Ă݂�ƁA���Ƃ����낤�ɁA����͍����ɕϐF���A�������Ɛ���オ���������̕��˂������̂��B�ǂ����悤���Ȃ��̂ł��̂܂ܕ����o�����r�[�ɁA��������l�Ԃ̂���Ƃ�������̋���ȏL������������n�߂��B�ǂ����A�������ݔ��������͓̂꒣��\�������˂��쐶���̕��˂������悤�Ȃ̂��B
�@ �l�ԂƋ߂����̔r�����Ƃ���A�l�Ԃ̂��̂�������̏L�������Ă����������͂Ȃ��B����W�[���Y�̐���ɂ͂�����x��̂Ƃ���܂ʼn��邵���Ȃ����A���ꂩ��܂��o���Ă���̂ł́A�������ɐg�����������ɂȂ������B�d�����Ȃ��̂ŁA���ǁA���L�ɑς��Ȃ���A���̂܂ܒ���ڎw���čĂѕ����o�����B����ɂقǂȂ��Ő������̋}�Ζʂ��Ƃ���ǂ���c��ɕ����A�o��̂���ςł͂��������A�K���Ȃ�Ƃ����邱�Ƃ��ł����B�Ő��ɏo�邿����Ǝ�O�̃^���~����́A�傫���[���J���͂���ŁA�܂��[���c��ɕ���ꂽ�����A���ł̎R�X����]���邱�Ƃ��ł����B�Ⴂ����ɕ��������Ƃ̂����X�����ɁA�����̎����Ƃ��̓��̖��c�Ȏ����Ƃ��r���Ă݂鋹�̎v���͂Ȃ�Ƃ����G�Ȃ��̂ł������B
�@ �Ő��ɏo�����ƁA���R����܂ł͑����A�b�v�_�E����������x�̕���ȓ��������B����ԋ߂̏��L�����R�n�ɂ́A�����炵�����̂����������A�����͖��c�ɔj��A�ǂ��������Ă��āA����ȂƂ���ɔ����炩�����đ���Ă��܂������ȗL�l�������B���̓��o���Ă������炵�Ă��A�o�R�҂����������Ƃ͎v���Ȃ�����A�����̊Ǘ����\���łȂ��̂͂�ނ����Ȃ����ƂȂ̂�������Ȃ��B
�@ ����ɒ����܂łɁA���ǎl���ԋ߂���v���Ă��܂����B�ނ��A���̒��ɂ͎��̊��ɐg��a���A�ɂ킩�ɐ������̒��̕s�ǂ𐮂��Ă����ꎞ�Ԃقǂ̎��Ԃ��܂܂�Ă���B���R���ォ��̓W�]�͓��{�C���Ɍ������đ傫���J���Ă���A�ቺ�ɍL����R�[�╽��z���ɓ��{�C��]�ނ��Ƃ��ł����B�����͋}�s�ȊR�ƂȂ��Đꗎ���Ă��āA�����瑤�ɉ��铹�͂Ȃ������������B
�@ �͂��炸�����Ղ����ނ��ƂɂȂ������̎R���ł̍ő�̎��n�́A�ʍs�~�߂̂��ߌ��ǍĖK��f�O������Ȃ��������O�ʃ_���̈ꕔ���A����ቺ�͂邩�ɒ��߂邱�Ƃ��ł������Ƃ������B�������̂́A��N���n��K�˂����ɂ͂܂��ˋ��H�����������勴�̂�����ŁA�������炷��ƎO�ʐ�̐앝���L����A���Ȃ萅�����܂��Ă���悤�������B�������A���̗l�q���炷��ƁA�����̐�Z�����I���܂łɂ͖����ɂȂ�Ƃ����V�������ǂ̓����̗\���ƈ���āA�_���������ɂȂ�ɂ͂܂��܂����Ԃ������肻���Ȋ����������B���Ԃ�A���̏㉮�~�n��̋M�d�ȓꕶ��ՌQ���܂����v���Ă͂��Ȃ����Ƃ��낤�B�������ƂȂ�A����炪���S�ɐ����Ɏp�������O�ɁA���߂Ă�����x�������̎p��ڂɂ��Ă݂������̂��Ǝv���̂������B
�@ �C�̏L���̂��ƂȂǂ������Y��A���炭����ŋx��ł���ƁA���N�̒j�����ЂƂ�o���Ă����B�قږ��T�荠�ȎR�ɓo���Ă���Ƃ����V���ݏZ��I����Ƃ������������BI����͎�������Ȃ�A�u�Ȃ�ɂ������Ȃ��ŎR�ɓo���Ă�����ł����B����Ȑl�ɑ����̂͏��߂Ăł���I�v�Ɣ��Ε���A���Ί��S���邩�̂悤�Ȋ�Řb�������Ă����B���̂ق������������A�u�l�����ď��߂Ăł���A����ȃ��`���N�`���ȓo�R��������̂́c�v�Ƃ���ɉ������B����̂܂܂̂��Ƃ��q�ׂ������ɉ߂��Ȃ������̂����A����ł��A�͂��߂̂����AI����́A�|�����̒m�炸�̑f�l�̖��d�o�R���Ǝ������悤�������B
�@ ���̌�̘b�̗��ꂩ��A�����������߂��ɉَq�p��������H�ׂ��������ƒm����I����́A�c�������̂ł悯��ƁA�����H�ׂ����̃p���������o���Ă��ꂽ�B����ȏꍇ�̎R�j�̉���͐S��L���Ǝv��˂Ȃ�Ȃ��B���͂����ɂ��̃p���Ղ��A���������키�悤�ɂ��Ĉݑ܂ɂ����߂��̂������B���̌C�ُ̈�ȏL�����C�ɂ͂Ȃ��Ă����낤�ɁAI����͂��̂��Ƃɂ��Ă͉����G��Ȃ������B
�@ ���R�͓�l�ꏏ�������B���H�̃��[�g���t�ɒH�邾���������̂ŁA�l�q���킩���Ă���Ԃ�A���H�̂ق��������Ɗy�������B�����A�悭������ȂƂ�����A���̂����тꂽ�C�𗚂����܂܂ŁA�������ꎞ�I�Ƃ͂����̒��s�ǂœ����Ȃ��Ȃ������ƂŁA���߂������ɓo���Ă������̂��ƁA��Ȃ�����ꂴ��Ȃ������B
�@ ������߂���ɏo���Ƃ���ŋx�e���Ƃ�A�܂��͗��̌C�Ǝ葫�A����ɂ͊�ƃW�[���Y�̐����\���ɐ��߂��B���ꂩ��A�₽�������������܈����A���̐��̖������̐��̂ǂ�Ȉ��ݕ��ɂ��܂��đf���炵��������ꂽ�̂́A����A���R�̂��Ƃł͂������B�C�Ƒ��Ƃ����Ă���Œ��ɁA�傫�Ȗ쉎�Əo�������b��A�������肵�ĕ��˂ݔ����Ă��܂����b������ƁAI�������͂�쉎�ɏo�����A�Њd���ꂽ�Ƃ̂��Ƃł������B���Ԃ�A���Ȃ����������̂�������Ȃ��B
�@ ���R�ɂ͓Ԕ��قǗv�������A�Ƃ��ɑ傫�ȃg���u�����Ȃ��o�R���̒��ԏ�ɓ��������B�V����I����Ƃ͂����ŕʂ�A���͐�ɋ����čs���Ԃ������ƌ��������B�����A�͂��߂Ɏ���U������̗t���T�r�̂�̒j�����̎Ԃ͂��������ɂȂ������B��ɉ��R���A���Ă��܂����̂��낤���A�����܂��Ԃɖ߂��Ă��Ȃ����Ƃ��炢�킩�����͂�������A���߂ď����u���̈���炢���Ă���Ă��Ă��悳�����Ȃ��̂��Ƃ��l�����B����U���Ă��ꂽ�̂���������̍D�ӂɂ����̂������̂��A����Ƃ����炢�����������̂��͐����ȂƂ��낢�܂ł��悭�킩��Ȃ��B
�@ �G���W���������n���h�������������́A�������ɑ���s�x�O�ɂ��鐣�g����ڎw���đ���o�����B���g����̈�p�ɂ́u����v�Ƃ������A������Ґ��̉�����B���Ȃ��Ȃ��ǂ����A�ʂ�߂̘I�V���C�͎��̂悤�Ȓ����C�D���̐l�Ԃɂ͂҂�����ł���B�L�����������p�ӂ���Ă��邩��A���Ă���悤�ȏꍇ�ɂ͂������Ƌx�߂đ�ςɗL���B�悭�����������ݔ����炷��ƁA���̓����������ƂĂ��ǐS�I�Ȃ��̂ł���B
�@ ���g����̗���ɂ͈ꎞ�Ԃ��炸�œ��������B�E�B�[�N�f�C�Ƃ����Ă��q�����Ȃ���������A�L������������������I�V���C��Ɛ肵�Ă�����䂭�܂ŐS�g�̔�������A���ꂩ��A�����ׂ��\���ȐH�����Ƃ����B�I����Ă݂�A����Ȃ�ɗL�Ӌ`�ł͂��������A�Ƃɂ������ɂ��n�b�v�j���O�����̈���ł͂������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N7��11��
�k���S�i�E�t�F���[�����ꂠ��
�@ �Z���̉Ď��̓��A���͐V���Ə��M�����ԓ��{�ߊC�t�F���[�A�����ꂠ���̃��E���W�ɂ����āA�O���̊C���ЂƂ肶���ƌ��߂Ă����B�ߑO�\�����ɐV���`���o�������ꂠ���͓₢�����{�C������悤�ɑ���A�Ђ�����k�ւƌ������Ă����B�S���S��\�܃��[�g���̑�^�t�F���[�͏��X�g�������Ă��т��Ƃ����Ȃ��B�܂��āA���̂悤�ɔg�̉��₩�ȓ��̍q�C�Ƃ����ẮA�����ȃG���W���̋������̂����ėh��炵�����̂͂܂������������Ȃ������B
�@ ���ߑO�A�D�͈����̐����ɍ����|�������B�E���̓W�]�������̃V�[�g�Ɉڂ�A�ג��������̉e�߂���Ă��邤���ɁA�������ɋN������A�h���߂��̕l�ӂŐH�ׂ�����ꂽ���������u���b�p�ρv�̂��Ƃ�z���o�����B���̂�������ł��Ȃ������낤���A�}�ɋ����o�����̂ŁA�܂��͕������炦���Ǝv���A���X�g�����ɓ����ă��[�����𒍕������B����Ȃ�̐ݔ������D�����X�g�����䂦�A����������Ɵ��������j���[���������̂����A�Ȃ��������Ƀ��[�������H�ׂ��������B
�@ �ߌ�ꎞ���A�����͂邩�ɂЂƂ���傫�ȎR�e�������n�߂��B�܂��c���Ղ������̔������R�e���炵�āA����͒��C�R�ɈႢ�Ȃ������B�{�y��艓�����ꂽ�C�ォ��A�������Ă��̗Y��Ȏp�������߂Ă݂�ƁA���ɂ����̏M�l���������C�R���q�C�̖ڈ�ɂ��Ă������Ƃ̈Ӗ����悭�킩��B���̓��ȂǁA�悤�₭�̂��ƂŒ��C�̎R�e�����E�ɑ������̖̂k�O�D�̑D��肽���Ȃǂ́A����Ŗ����Ɏ�c�ɓ��`�ł���ƁA���g�̋����Ȃł��낵�����Ƃ��낤�B
�@ �E���O������E������ւƂ������������Ɏp���ڂ��Ă䂭���C�R�����]���Ȃ���A�ӂƎv�������āA�R�`�����R�s�̒m��l���m�鋼�����A�u���炫���v�ɂ���̓d�b�������Ă݂��B��X�ЂƂ����Ȃ�ʂ����b�ɂȂ��Ă��鋼��������ŁA�ߓ��A�����R�n��K�˂��A��ɂ�������点�Ă��炢�A��i�ƕ]���̍��������Ɛg�����ׂƂ�������t��y���ɂȂ����B���̂����A���y�Y�ɂƁA�n���̖��`�������̕����������������R�̃T�N�����{�܂Œ��Ղ��Ă��܂����B����̈��얔�O�����v�Ȃ��A�����Ď��l�̈���������v�Ȃ����ɑf���炵�����l���̕��X�ł���B���̌�l���������āA���炫����K�˂�l�͂��܂��₦�邱�Ƃ��Ȃ��B
�@ ���n���牓�����ꂽ����ȊC��Ōg�ѓd�b���g������̂����ǂ����m�M�͂Ȃ��������A���ۂɂ����Ă݂�ƁA���܂��ʂ����B������������A���̎��̑D�̈ʒu���A�߉����c�Ƃ�������������s�s���̉������ł��������Ƃ��K�������̂�������Ȃ��B���܂��ܓ���̈��얔�O���d�b�ɏo�Ă����������̂ŁA���k���Ȃ���A�d�ɉߓ��̂����\���グ�Ă��������A�R�`����������̐����͂邩�ȉ���������A���R�A��̌��������Ɉʒu���鑺�R�s�̈��삳��Ƙb������Ƃ����̂́A�s�v�c�Ȋ����̂�����̂������B���̂��Ǝ�����A�O�̗F�l�ɂ��d�b�������Ă݂����A��͂艹���͖��Ă��̂��̂������B
�@ �����������Ă��邤���ɔ̉e�������͂��߂��B�ג�����`���������̓��e�́A���̐S���ɐ��ޗ��̒��ɖ����ʼn������������Ă��邩�̂悤�������B�͂܂���x���K�˂����Ƃ̂Ȃ����̂ЂƂł���B�D���k�ɐi�ނɂ�āA���X�ɉ_����Ă��āA���̍��Ԃ���Ƃ���ǂ���̂����͂��߂��B�ߌ�Z���O��A�D�͍r��̘I�V���C�u�s�V�s������v�Ŗ�����������̉������ɍ����|�������B���̔w����ނ���͔̂��_�R�n�ɂق��Ȃ�Ȃ��B��[�����_�R�n�̂��Ƃ�����A�R���ɋ߂���тł͂��܂��傤�ǃu�i�̎�t�����₩�ȗ��֎����Ȃ���A�������萁����
�@ �����Ɩڂ��Â炷�ƁA�{�y�̊C�ݐ��̈�p�ɔ��������Ȍ����̉e�炵�����̂��������B�r��̘I�V���C�̔w��ɂ͔����̃z�e���������Ă�������A���Ԃ̂����肪������ɈႢ�Ȃ��B���N�O�A�����ዷ�̉�ƁA�n�ӏ~����Ɖ�����̕s�V�s�������K�˂����͑�r��̓V�����B�Ђǂ����J�̒��A���D�̂��܂Ō������ł���r�g�߂Ȃ���A�Ȃ�ƎO���Ԃ����̒��ɂ�����ςȂ����������ƂȂǂ����������z���N�����ꂽ�B���V�̓��̗[���A�s�V�s������̘I�V���C����]�ޗ[�z�͍ō����Ƃ����邪�A���D�ɐZ����Ȃ��璭�߂�Ď��̂��̓��̗[�z�͂ǂ��Ȃ̂��낤���ƁA�����z�����߂��点�������B
�@ �ߌ�Z�������Ƀ��X�g�����ɏo�����A���Ƃ��Ă͈ٗ�Ȃقǂɑ����[�H���Ƃ����B���M�⏬���ɏ��ʂ�����ꂽ��i���������ꂱ��ƑI�э��킹�ĐH�ׂ��̂����A�l�i�̊��ɂ͂���Ȃ�ɖ����̂����H���������B���X�g�������o��ƁA�����̓W�]�������̃V�[�g�ɐ[�X�ƍ������낵�A���{�C�ɒ��ޗ[�z�Ɍ����邱�Ƃɂ����B�T���Z�b�g�E�z���b�N�i�H�j�̐g�Ƃ��Ă͓��R�̍s���ŁA�[�H�𑁖ڂɂƂ����̂����v�������v�Z�ɓ���Ă̂��Ƃ������B
�@ ���傤�ǃt�F���[���Ìy�C�����ɍ������������ߌ㎵���\�ܕ��A���z�͐��̐����̌������ւƎp���B���Ă������B��т̊C�ʂ��痧�����鐅���C�͏��Ŕ��_�ɕς��B�����������ł͂����̉_���܂�d�Ȃ��Č����邽�߁A�����̉_�Ɍ����Ղ��A�����̉e���̂��̂��͂�����Ɩ]�ނ��Ƃ͂ł��Ȃ��������A����ł������̋�̐F�͗��D���ݐ[�߂Ă����ɏ\���Ȕ������������B�C�����ƁA�����W�]�����ӂ͏�q�����ł��ӂ�Ă����B�D�ォ�猩��[�z�ɂ��ꂼ��̐l���̑z�����d�ˑ�Ȃ���A�ނ�͊F�[�����S�ɂЂ����Ă���悤�ł��������B
�@ �E�~�l�R��P�C�}�t���̔ɐB�n�Ƃ��Ēm���鏼�O�����ƁA���̂��Ȃ艫�ɂ��鏼�O�哇�Ƃ̊ԂɑD�������|�����鍠�ɂȂ�ƁA�E�����̊C���ʂ����X�ƋP�������Ԗ����̓_�������ꂽ�B���̐�������ῂ�����̖����邳�ł���B�����́A�Ő������}�����C�J���̏W�����̖����肾�����B�̂̋���͂ǂ������̗҂����ȐԂ��͂��Ȃ��F�����Ă������̂����A����̋���̋P���͋���Ȃ��Ƃ��̂����Ȃ��B
�@ ���炭��̃f�b�L��E���W���U�����ƁA�ӂƎv�������ăr�f�I�V�A�^�[�ɓ����Ă݂��B�S���ŘZ�\�Ȃقǂ��邻�̃V�A�^�[�̊ϋq�͎������Ă������O�l�Ƃ����ՎU�Ԃ肾�������A��f���̃r�f�I�́A���́u���v�Ƃ�������������i�������B���̕��g�Ƃł������ׂ��j���������̒������I�ȋ�Ԃɖ������݁A�����Ŗڂɂ������E�����I�ɕ`�����Ƃ����ݒ�̉f��ŁA�S�̓I�ɂ͌��㕶���ւ̔ᔻ���Y���A�����ԂP�F�̟��ݏo���������Ȃ����Ȃ���i�ł���B�����A���Ă̍���t�@���̈�l�Ƃ��ď��߂Ă��̉f��������Ƃ��ɂ͂���Ȃ�̊����͂������B�������A���R�̂��ƂƂ͂����A���̃��X�g�V�[���ɂ́A�Y����Ȃ��z���o���������B
�@ �V�A�^�[�ɓ������Ƃ��A���łɁu���v�̏�f�͂��Ȃ�i�݁A�c��O���̈ꂭ�炢�̂Ƃ���ɍ����|�����Ă����̂����A�v�X�ɂ��̃��X�g�V�[�������Ă݂����Ǝv���A���̂ق��ɒ��Ȃ����B���傤�ǂ��̎��A�X�N���[���̉摜�̓S�b�z�̊G�̒��ɕ`����Ă���悤�ȃI�����_�̔_�����i�ɕς�����B�����ĂقǂȂ��A���̏�ʂ́A�����̐��E�ɖ������Ⴂ�j���A���@���E�r���Z���g�E�S�b�z���̐l�Ƃ��ڂ����l����{�����āA�Z����b�����킷�V�[���ւƈڂ��Ă������B
�@ ���R�̒��ɔ������G��T���ȁB���Ƃ��Ǝ��R�͂ǂ�Ȃ��̂ł��������B�Ȃ̐S�����߂Ď��R�����߂�A���̂����炻�ꂪ�G�ɂȂ��Ă���\�\����ȈӖ��̂��Ƃ��S�b�z�͒j�Ɍ�肩�������Ǝv���ƁA�����܂��A�������ւƂ��Ȃ��p���������B����i���ŃS�b�z�Ɍ�点�����̌��t����x�ǂ����œǂ悤�ȋC�����邩��A�����������炻��́u�S�b�z�̎莆�v�̒��̈ꕶ���قǂ悭�A�����W�������̂������̂�������Ȃ��B������ɂ���A���́A���̌��t���āu�䂪�ӂ���v�Ƃ����v���ɂȂ����B
�@ ���̃S�b�z�̌��t�̈Ӗ�����Ƃ���́A�G��ɂƂǂ܂炸�A�|�p�\����ʂɓ��Ă͂܂�B�|�p�I�ȕ\���ɂ͂قlj�������ȋI�s���Ȃǂ�Ԃ鎄�̂悤�Ȑl�Ԃ́A���܂ǂ�����ȕ��Ȃǂ��������Ƃ���ŁA������������炪���ɂȂ�Ƃ����̂��낤�Ƃ����v���ɏP���邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��B���i���i�A���������X�̕����Ȃǂ������ɓ`���邾���Ȃ�A���̌���A�r�f�I��ʐ^�Ȃǂ̉f���Z�p�ɑ����ł��ł���킯���Ȃ����炾�B���ہA�ꕔ�̐l�X�Ȃǂ���́A�e���r��r�f�I�A�ʐ^�Ȃǂł���Ƃ����鎖�����Љ��Ă��邱�̎���ɋI�s�G�b�Z�C�ȂǏ����ĂȂ�̈Ӗ��������ł����A�Ɩ���邱�Ƃ������Ȃ̂��B
�@ ����ȏ̂��Ƃɂ����Ď����ɂł��邱�Ƃ�����Ƃ���A�Ȃ̐S�Ɗ����̂������s���Ċe�n�̎��R�╗�������߁A�J�����̖ڂł͑�����S�ە��i��`���o�����Ƃ��炢���낤�B�S���̃����Y��ʂ��Ē��߂�ƁA��������ӂꂽ���i�╗���̒��ɉB����Ă��銴���I�ȏ�i������ƌ����Ă���B�S�̊�Ƃ��̑Ώە��Ƃ�����p���N�����A�����Ƃ����z�Ƃ����Ȃ��ЂƂ̐S�ە��i�������яオ���Ă���킯���B�����ĉ�Ƃ�������G�M�ɑ�悤�ɁA�I�s��Ԃ�l�Ԃ͕M�ɑ�Ƃ������ƂɂȂ�B�����A�����͌����Ă��A���s�L�Ȃǂ������l�ԂɂƂ��ėe�ՂȂ炴�鎞��ł��邱�Ƃ����͊ԈႢ�Ȃ��B
�@ ���낢��Ǝv�����߂��炵�Ȃ���X�N���[�������߂邤���ɁA�u���v�͂��������X�g�V�[���ɓ������B�����̔�������������A���̑��̂��𐴂炩�Ȑ���X�����������삪����Ă���B��̗��݂ɂ͉Ԃ��炫����A������̑傫�Ȑ��Ԃ��������Ɖ���Ă���B���̑��ł́A������S�������҂����ʂƂ������Ƃ͑�ςɂ߂ł������Ƃ��Ƃ����B���l���o�̑��V�́A�y�����擪�ɗ����A�S�g���Ԃŏ������Ⴂ���̎q�������ɂ��₩�ȏΊ�ŗx��Ȃ��炻��ɑ����Ƃ������A���̑��Ɠ��̂��Ղ胀�[�h�ɕ�܂��B�����āA���b�Z�[�A���b�Z�[�A�o���o�J�o���Ƃ����|�����Ɗy���̑t�ł郊�Y���ɏ���āA��������`���ɂ��Ղ�Ȃ݂̑��V�̍s�i��ł����Ƃ���ʼnf��͏I���B
�@ ���̍�i�̃��X�g�V�[���ɐ[���z���o������Ə������̂ɂ͂�����Ƃ�������B�܂����́u���v�Ƃ����f�悪���J�����O�̂��Ƃ����A���́A���ܖ�̈�p�ɂ���䍂����JR�̉w�O�œ����H�Ȃ��l�̂ЂƂ�Ƌ��R�ɏo�������B�Γc�B�v�Ƃ������̘V�l�i�ٍe�A�u�l���͗l�W�N�\�[�p�Y���v��u�\�O���̋��j���Ɂv�Ŏ��グ���l���j�́A�o�����Ă����A�䍂���̑剤���T�r���̋߂��ɂ����̂قƂ�Ɏ����ē����Ă��ꂽ�B�Ő�̉�̂悤�Ȃ��̘V�l�́A�剤���T�r���̂ق�����������ɂ��Ȃ��Ȃ�����A���̐삾���͎��ɑf���炵���Ǝ�����ŖJ�ߏ̂����������̂������B
�@ ���̒n�_�łقڒ��p�ɗ��H��ς��邻�̐�́A���ݐ��������Ƃ��Ƃ��Ɨ���A�����ł͔������̐쑔�������Ɨh�炢�ł����B��̗��݂͑��ԂƐ[���V�R�̖ؗ��ɕ����A����͂܂�Ő��m�̕��i�悻�̂��̂悤�Ȍ��i�������B���܂ł�����Ȑ�炵���삪�������̂��Ǝ��͊����������̂����A�Ґ�̎x���䍂��̂��̂܂��x���ɂ����閜����Ƃ������̐삱���A�u���v�̃��X�g�V�[���ɓo�ꂵ���삾�����̂��B�̂��ɂȂ��ĉf��قŁu���v�̃��X�g�V�[���ڂɂ����Ƃ��A���́A�����A���̐삾�Ǝv�킸����ۂ��̂��B
�@ ���M�ւƌ��������̃t�F���[�̏�ł܂����u���v�̃r�f�I�����邱�ƂɂȂ낤�Ƃ́A����ɂ܂��A�����ʂ��ĕ䍂�̐Γc���̂��Ƃ��ÂԂ��ƂɂȂ낤�ȂǂƂ́A���ꂱ�����ɂ��z���Ă��Ȃ������B�������A�Γc���́A��O�̈ꎞ���A���M�A�V�ÁA������ԎO�p�q�H�̉q�D�ɏ���Ă������Ƃ�����l������������A���͂��̕s�v�c�Ȉ����ɂ������t���łȂ��L�l�������B
�@ �ߌ�\�����A�����ꂠ���͉��K���Ɠn�������Ƃ̊Ԃɍ����|�������B�E���������������O����������D�̎���͂��ׂďW�����Ŗ��ߐs�����ꂽ�����������B��т̊C��͈�ʋ����قǂ̖��邳�ł���B�����̏W�����Q�̒���~��������悤�ɂ��Ȃ���A�����ꂠ���͂��������Ɣ����O�i���Ă������B
�@ ���ꂩ��ꎞ�ԂقǁA�����̑������ɔz�u���ꂽ�֎q�ƃe�[�u����苒���A����Ɍ���ɉ߂��s�����K���̖��Ƃ̖�������������߂��Ȃ���A�m�[�g�p�\�R�����J���Č��e�̐����������B�����āA�ߌ�\�ꎞ���q���̏�i�x�b�h�ɐ��荞�ݖ���ɏA�����B���M�����̗\�莞���͗����̎l���\��������A�킸���l���ԑ��炸�̐����ł͂��������A����Ȃ����͂܂��Ƃ������̂��������A�D���x�b�h�̐Q�S�n������Ȃ�ɉ��K�������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N7��18��
�k���S�i�E���M
�@ �荏�҂�����̌ߑO�l���\���A�����ꂠ���͏��M�`�ɒ��݂����B�W���̗U���ɂ��������Ė����ɉ��D���A�t�F���[�^�[�~�i���̒��ԏ�ɂ�������Ԃ��Ƃ߂����ƁA�܂��͌y�����̉^���ƁA���炭�t�F���[�u���̎��ӂ��������Ă݂邱�Ƃɂ����B�Ԏ~�߂̓S����ׂ��ʼnz���A���������Ȃ��Ƃ���ɂ���ݕǂɏo��ƁA�����ɂ́A�uSEA PINK�v�Ƃ����D���̊O���ݕ��D����ǒ┑���Ă����B�D���͉p�ꂾ���A�D�̕��͋C���炷��ƁA���ۂɂ̓��V�A�D�̂悤�ł������B���̑D���ʂ�ɁA�D�̂̎�v���̓I�����W���������s���N�F�ɓh���Ă����B
�@ ���̑D�����Â��ɂȂ��Ă���ݕǂ̂������ɂ́A�召�O�A�l�\��قǂ̒��ÎԂ������ɕ���ł����B�ǂ����A�����̎Ԃ͂��ꂩ�炻�̉ݕ��D�ɐςݍ��܂ꃍ�V�A���ʂɉ^��邱�ƂɂȂ��Ă���炵�������B���܂ł͏��M�`�͑��V�A�f�Ղ̕\���ւ݂����ȂƂ���ɂȂ��Ă���A���ÎԂ����{����̎�v�A�o�i�̂ЂƂɂȂ��Ă��邱�Ƃ͏O�m�̎���������A���̂��Ǝ��ׂ̂͂�������ɂ͓�����Ȃ������B
�@ �����̂��Ƃ䂦�A�ނ��Ԃ̐ςݍ��ݍ�Ƃ͂܂��n�܂��Ă��Ȃ������B�t�߂ɂ͑��ɐl�e�Ȃǂ܂�������������Ȃ���������A���͂����ς�y���C�����ŁA�����ƕ��Ԓ��ÎԌQ������䒭�߂Ȃ�������Ă����B�ǂ̎Ԃ��O��̃v���[�g�i���o�[������A�t�����g�K���X�̓����ɂ͏��M�s�`�p�ǂ̉���̂���A�o�m�F�݂����Ȃ��̂��O���猩����悤�ɒu����Ă����B�قƂ�ǂ̎Ԃ͂��Ȃ�N�����o���Ă��銴���ŁA�����łȂ�\���A��\���Ƃ��������i�Ŏ������Ă���V�����m�̂悤�ł������B
�@ �Ƃ��낪�A���ɎԂ߂Ă��������ɁA�ӊO�ɂ���A�O��A���Ȃ�V�����Ԃ��܂܂�Ă��邱�ƂɋC�������B�Ƃ��ɂ����̒��̈��͂҂��҂��̐V�Ԃɋ߂������������B�߂Â��Ă悭���Ă݂�ƁA�g���^�̃����h�N���[�U�[�ŁA�^�C�����܂��^�V�����A�t�����g�㕔�ɂ͗��N�O���܂ŗL���ȗ��^�ǂ̎Ԍ����i���\��ꂽ�܂܂ɂȂ��Ă����B�������A�i���o�[�v���[�g�͑O��Ƃ��Ɏ��O����Ă��܂��Ă������A��Ȃ��ƂɁA�Ԃ̒��̌㕔���Ȃɂ͂��Ȃ�㎿�̒j���̔琻�R�[�g���ꖇ�c����Ă����B
�@ �����������炱����ē���Ԃ̉\���������Ȃ����ȁA�ŋ߁A���̎�̘b���悭���ɂ��邱�Ƃ����\�\����Ȏv������u�]�����悬�����B�����ŁA���������ǑO�ʂɂ܂���ăt�����g�K���X�̓�����`�����炽�߂Ă݂�ƁA�Ӗ��s���̃��V�A��炵�������������ꂽ�����Ђ��u����Ă��邾���ŁA���Ԃɕt����Ă���悤�ȏ��M�s�`�p�ǂ̉������̊m�F�炵�����̂͌�������Ȃ������B���l�̎Ԃ����ɂ���A��䂠��������A���ۂɂ͉����ʂ̎���������̂�������Ȃ����A������ɂ���A���̂܂ܑD�ɐςݍ��܂��ɂ��Ă͂ǂ����ٗl�ŕs���R�Ȋ����������B
�@ ���̎��ł���B�w��ɂ����Ȃ�ʎ����̂悤�Ȃ��̂����������́A�͂��Ƃ���SEA-PINK���̂ق���U��Ԃ����B�D��̃u���b�W�t�߂Ƀ��V�A�l�炵�����N�̒j�������A���݂̂������ł�����̂ق����������ɂ�ł����̂ł���B����@����ƁA���Ȃ�O���炱����̈ꋓ�ꓮ���Ď����Ă������̂炵���B
�@ ����̓��o�C�A�܂����Ƃ͎v�����A���ɖڌ��҂����Ȃ����Ƃ����A�D���ɂł��A�ꍞ�܂ꂽ�炻��ňꊪ�̏I���Ƃ������Ƃɂ��Ȃ肩�˂Ȃ��\�\�������������͑�}���ł��̏��ގU���A�l�e�̑����t�F���[�^�[�~�i�����ԏ�ւƖ߂����B�u���l�̍`����c�c�v�Ƃ����L���ȓ��w�̕���̌��������āA�u���M�̍`���炨�D�ɏ���Ĉِl����ɘA����Ă�����������v�Ȃ�Ă��ƂɂȂ����炽�܂������̂ł͂Ȃ��B
�@ �Ԃ̉^�]�Ȃɂ��A�o���̏��������Ă���ƁA���炩�ɐ捏�̉ݕ��D�̃��V�A�l�D���Ƃ��ڂ����j���A�ݕǂ̂ق����玩�]�Ԃɏ���Ă���Ă��āA�����l�q�ł��M�����̂悤�ɂ��Ď��̎Ԃ̂Ƃ܂��Ă��钓�ԏ���ӂ𑖂����Ă���̂����Ɉ�ۓI�ł��������B�ނ��A���̖ڂ��Ђ������̃����h�N���[�U�[������Ԃł������ƒf��ł���킯�ł͂Ȃ����A������������ׂɉ��炩�̎���������̂�������Ȃ��B�����A�ǂ����q��łȂ������������Ƃ����͊m���ł������B
�@ �t�F���[�^�[�~�i���̒��ԏ���o�������̂́A���M������ꎞ�Ԃقǂ��Ă��炾�����B���M�̊X���݂��̂��͉̂ߋ����x��������������Ƃ�����̂ŁA�����̑q�ɊX���ӂ��y�����蔲���A���̂��Ə��M�x�O�̏j�Õ��ʂ܂ł�����Ƒ����̂��Ă݂悤���ƍl�����B�t�F���[�^�[�~�i�����炻�������Ȃ��Ƃ���ɂ͋ߔN�J�݂��ꂽ�Ό��T���Y�L�O�قȂǂ�����炵���������A�J�َ����܂ł͂܂������Ԃ�Ǝ��Ԃ����������A���قɂƂ��ׂ������o����قǂ̂��Ƃ��Ȃ������̂ŁA���̕t�߂͂������ƒʉ߂��Ă��܂����B
�@ �����Ƃ����Ă܂��ό��q�̎p���Ȃ��q�ɊX���L�����L�������Ȃ��瑖���Ă���ƁA�u���M�i�j�R���f�Ձv�Ƃ����������n�̊Ŕ̊|�������q�ɂ̑O�ɏo���B�m���ɁA��ڌ��������Łu��������H�v�ƕs�v�c�ɂȂ��đ����~�߂����Ȃ�悤�Ȃ������܂��̑q�ɂł���B�������A��������Ēʂ肪����̂��q�ɑ����~�߂Ă��炤�̂��A����̑_���ł�����̂��낤�B���������ɎԂ��~��āA���̑q�ɂ̓����ɗ����Ă݂��B
�@ ���J���̑q�ɓ����̃h�A�⓹�H�ɗՂޕLj�ʂɂ́A�܂�ň�ѐ��̂Ȃ��A����A�ނ���Ӑ}�I�Ɉ�ѐ���r�������Ǝv����G������ȓX�������i���S�`���S�`���Ɣz����Ă����B�u���M�i�j�R���f�Ձv�Ƃ����Ŕ����̉��ɁuTHE DREAM ANTIEQUES�v�Ƃ����������̈ꕶ���Y�����Ă���Ƃ�����݂�ƁA��͂苌�q�ɂ𗘗p�����ό��q����̌Õ��G�ݓX�Ȃ̂��낤�B���ɓ����Ă݂����Ƃ����Փ��ɋ��ꂽ���A�܂��ߑO������������肾�����̂ŁA����͖����Ƃ������̂ł������B
�@ ���炽�߂đq�ɂ̓������ӂ߂܂킵�Ă݂�ƁA���̈�p�����ł������A���ɗl�X�Ȏ�ނ̕i���ł���ł����ƌ�������ɏ�������Ă����B���Ƃ��A�����̃h�A�̏�ɂ́A�̂̑唪�Ԃ̖ؐ��ԗւ���t���̌Ã^�C���A�D�̓��t���Ȃɂ��������Ǝv��������~�ՁA�O���Ԃ̃i���o�[�v���[�g�A����������̊e��؎D�⎆�D�A��|���̊G�D�Ƃ������悤�ȕ��Ȃǂ������Ȃ܂ł̖����ꂳ�Ŋ|������\�����肳��Ă����B
�@ �܂��A���H�ɖʂ���ǂ�ۂɂ́A��蔲���č����������ۂ�C���ނ̏��蕨���u����Ă��邩�Ǝv���A�����Ƃ͂܂�Ŗ��W�ȃS���t�{�[���̖͌^��l�X�ȑ����������Ă����肵�A����ɂ��̂܂��ɂ́A���Ƃ��ڂ������̎}�X���G�R�ƁA����ł��āA�Ȃ�炩�̔�߂�ꂽ�Ӑ}������������z��ŕ��ׂ��Ă������B�g�[�e���|�[���⎭���Ȃɂ��̓����̓��W���A���Ή�ꂩ�������Â����֎q�Ȃǂ����̕��ς��ȑ����̂��Ȃ߂Ƃ��Ĉ���Ă����B�@�@
�@ �Ћ��Ɂu���ؔ���܂��v�Ə����ꂽ�̒��D���|�����Ă�������A���������̊C�݂ɗ��ꒅ�����ؗނ��E���W�ߔ̔����Ă�����̂��낤�B�����炭�͗��̂ق��ɂ��l�X�ȕY�����Ȃǂ��Ă���ɈႢ�Ȃ��B������ɂ���A�ӕ\��˂������ς��ȑ��������Â��q�ɂ̃h�A��ǖʂƌ����Ƀ}�b�`���A�X���݂Ƃ����܂����a���Ă���̂́A�V���A���X�A�P���̂��ׂĂ�ۂݍ��ݓ������Ă��܂����̌Â��`�����M�Ȃ�ł͂̂��Ƃł���悤�Ɏv��ꂽ�B
�@ ���M�̒��S�X���炷�������ꂽ�Ƃ���ɂ��鏬���`�j�Â̏W�����A����������⓹�𑖂�Ɠ��a�R���䉺�ɏo���B�����ŎԂ��~��ăG�]�J���]�E�̍炭������o��ƁA����Ƃ���ɑ����W�]�L��ւƏo���B�����\�Z�N�ɓ_�����Ĉȗ����̒n�̊C����葱���Ă������a�R����͂����傫�Ȋ����̓���ł͂Ȃ����A����ł��O�\�܃L�����[�g���قǂ̌��B������L���Ă���B�f�R��̓W�]������́A�܂肩��̒����������^���ȊC�������낹���B�܂��A������w���L�̒���t�w�̔��B�����f�R�̂��������ɂ̓E�~�l�R�̎p�Ȃǂ��U�����ꂽ�B
�@ ����グ�����������ɓ]����ƁA�_�Ж��ƐϒO���Œm����ϒO�������ʂ̑傫���̂т₩�ȎR�e���]�܂ꂽ�B�k�C���̊C�����̓��͂قڑ���s�����Ă���̂����A�_�Ж�����_�b���ɔ�����ϒO������[���̓��H�����͂܂����������Ƃ��Ȃ��B���H�H�����̂��̂���q�A�悤�₭���̕������J�ʂ����̂͋ߔN�̂��Ƃ�����A���낤�ɂ�����悤���Ȃ������̂��B�����������邤���ɁA��������̗��̋A�H�ɂł��_�Ж����ʂɗ���邱�Ƃ��ł���A�����̕�����ʂ蔲���A�k�C�����C���H���S���j�𐬂������邱�Ƃ��ł���̂����Ƃ����v�������ɕ���Ă����B�B
�@ ���a�R����̂������ɂ́A�k�C���w��̗L�`�������u��a�v�Ȃ���̂������Ă��āA���������̔ɉh�Ԃ���̂����ɎÂ��Ă��ꂽ�B�܂����������߂���̂œ��������w���邱�Ƃ͂ł��Ȃ���������ǂ��A���Ԃ̖ؑ����z���Ƃ��Ă͈ٗ�Ƃ�������傫�Ȍ����������B�؍ȑ��蕗�̑剮�������̍ŏ㕔�ɂ͓V�������炦���Ă���A�m���Ƃ��a���Ƃ����ʉ������݂̔�A�e���ւ��x����ە@���ƂƂ��ɂȂ�Ƃ��s�v�c�ȕ��͋C�������o���Ă����B
�@ ���։��ɗ����Ă������ɂ��ƁA���̌����͐ϒO�����L���̖Ԍ��������c�������Ƃ����l�����A�����O�\�N���A���N�̍Ό��������Č����������̂Ȃ̂��Ƃ����B���a�O�\�O�N�ɂȂ��āA�k�C���Y��D�D������Ђ���������A�א�Ώꏊ�Ƃ��Ēm��ꂽ���̏j�Ó��a�R�Ɉڒz�A���M�s�Ɋ����̂��Ƃ����B���̋K�͂͊Ԍ��\�Z�ԁA���s���ԁA���ؕS���\�ܒŁA�S�����ɂ͖�S��\�l�̊W�҂��Q���肵�Ă����̂������ŁA�p�ނƂ��ẮA���`�_���A�Z���A�g�h�}�c�ȂǁA�k�C���Y���؎O��i��ܕS�l�\�g���j���g�p����Ă���炵���B
�@ ���M�����Ƃɂ��A���{�C�����ɖk����J�n���钼�O�A�ӂƎv�������āA���܂͓����ŗL�\�ȏ���W�̎G���⏑�Ђ̃��C�^�[�ɂȂ��Ă��鏬�M�o�g��N����ɋv�X�̓d�b�������B���������Ԃ�Ɛ̂̂��ƂɂȂ邪�AN���܂���������������A���܂��܂��̔\�͂ɒ��ڂ������́A�l�b�g���[�N�W�̏��Ђ̋����҂ɔ��F�������Ƃ�����A����ȗ��̕t���������B���݁A�ޏ��́A���\�t�g�̃\�[�X�E�R�[�h�̍쐬�����V�X�e���̍\�z����e��\�t�g�̗D�ꂽ����L���̎��M�܂ŁA���L���Ɩ������Ȃ��Ă���B�R���s���[�^�W�̎��H�m���ʂɂ����Ă͂��͂⎄�Ȃǂ��y�ԂƂ���ł͂Ȃ��B
�@ �Q�ڂ������œd�b�ɏo��N����ɁA�u�����M�ɂ����A������ƑO�Ƀt�F���[�Œ���������łˁI�v�ƍ�����ƁA�u�����A����ȁI�c�c�Ȃ�ł���������Ƒ������M�ɍs�����Č����Ă���Ȃ�������ł����v�Ƌ����̐����グ���B�����������Ƃ̌䗼�e�͂����N���Ă���͂�������A���܂���d�b���Ē��H�ł���y��������A���łɏ��M�̒����ē������邩��Ɣޏ��͐\���o�Ă��ꂽ�̂����A����ł͂��܂�ɐ\����Ȃ��̂ŁA���̘b�͉��������B
�u�ǂ����{�c����̂��Ƃ�����A���ꂩ�瓹����[�X�܂ő���܂�����Ȃ�ł���H�B�ł��A���낻�남�Ȃ�ł�����A���������ɐg�̂قǂ��킫�܂��Ȃ��Ƃ����܂����I�B�Ȃ�Ȃ�^�]��ł����߂ɂ��ꂩ��k�C���ɔ�т܂��傤���H�v
�@ ���̐g���Ă��Ă����N����̂���Ȍ��t�͗L���������A�ޏ������Ă������������̔N��̏����ł���B�������A�����Z�Ȑg�ł�����悤������A�u����A�����낵�����ނˁI�v�ȂǂƋC�y�ɓ������ɂ������Ȃ������B
�u�܂��A�Ȃ�悤�ɂȂ邳�A�Ԃɏ�����܂ܗ��̘I�Ə�����Ȃ�A����͂���Ŏd�����Ȃ���B�[�R��C�ӂ̒f�R�Ȃǂ�����Ă��ēˑR�N���b�Ƃ���悤�Ȃ�A������^���ƒ��߂邳�B���������Ȃ��Ă����č������T������Ȃ�����ˁB�l���̒��ŕςȓz�Əo�������c�c�A����ȑz���o�̂ЂƂł��L���̕Ћ��Ɏc���Ă����Ă������ꂾ���ŏ\�����I�v
�@ ������Ɗi�D�������������ȂƂ͎v�������A�Ƃ肠�������������c���ēd�b������B��͐���n���Ă��āA�~�蒍�����̗z���͂ǂ��܂ł����邢�B���ɗݐϑ��s�����͏\�ܖ��L���߂��ɂȂ��Ă��邪�A�ډ��̂Ƃ���͈��Ԃ̃G���W���̋������y���ŁA�k�C���̗��̃X�^�[�g�͂���Ȃ�ɏ������Ƃ����Ă悩�����B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N7��25��
�k���S�i�E�[���X���k��
�@ ���O����̗��l�ɂ͂��܂����݂̂Ȃ��A�Ύ�C�݂ƐΎ��͌���Ƃ�K�˂Ă݂��B�Ύ�C�݂̐Ύ�`�t�߂͂�����Ƃ����H�ƒn�тɂȂ��Ă��邪�A����������������߂���Ǝԓ������ɍL�X�Ƃ������삪�����B�k�C���Ȃ�ǂ��ɂł�������i�ŁA�������K�C�h�u�b�N�Ȃǂł��Ƃ���Љ��Ă���킯�ł��Ȃ����A�ԁX�̍炫�ւ邱�̋G�߂̌i�ς����͈ꌩ�ɒl����B
�@ �u�₩�ȏ��Ă̕��̐����������т̖쌴�́A���P�����߂Ƃ����Č��n��������Ԑ��肾�����B�����ʂɕ����G�]�^���|�|�̑N�₩�ȉ��F���ڂɐ��݂�B���̋P���悤�ȉ��F���Ԃ��O�~�ɂ�����ƃA�N�Z���g�����銴���œ_�݂��Ă���̂́A�Ԏ��̃n�}�i�X�̉Ԃ��B�^���|�|�̉��F��n�}�i�X�̐Ԏ��Ɉ��|����Ă��܂�ڗ����Ȃ����A�W���s���N�̃n�}�q���K�I��n�}�G���h�E�̎��̏����ȉԂȂǂ��͂��Ƃ���قǂɔ������B���ł͉��H���̃q�o�����A�z���ɐ�������邩�̂悤�ɁA�����炩�ɕ��������Ă����B
�@ �Ύ��͌��̗��H�͊C�ݐ��ɑ����p�ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B�Ύ��͉͌��t�߂ŊC�ݐ��ɂقڕ��s�Ȋp�x�Ɍ�����ς��A���̂܂ܓ��{�C�ւƗ��ꍞ��ł���̂��B���������āA�͌����H���݂ƊC�Ƃɋ��܂ꂽ�����͒Ⴂ�u�˂��Ȃ��č��{��ɍג����L�яo�Ă���B�C�̌����܂܂ɃA�N�Z���ݑ����Ă���ƁA�Ԃ͂��������̍��{��n�`�̏�ɏo���B�Ԃ𒓂߂ĊC���ɂ���Ă݂�ƁA�����ۂ��F�̍��l�������ǂ��܂ł������Ă����B�Ύ�l�ƌĂ�邱�̈�т̊C�ӂ́A�K���C�݂Ƃ��ǂ��k�C���ł͐����Ȃ��C������Ƃ��Ēm���Ă���B
�@ �܂��C�����V�[�Y���ɂ͑������̍L�����l�̐^���ɁA������g�����A�V�[�g��~������ɐQ���ׂ��Ĕ����Ă���Q�̐l�e����������ꂽ�B�D�y�������Ă����Ƃ����Ⴍ�Ĉ��炵���O�l�̏��̎q�����ŁA���l���킯�߂���y�b�g�̎q���Ƃ��ǂ��A������Ƃ����G�ɂȂ��Ă����B�������A�ޏ��炪�C���ɓ������l�q�ȂǂȂ���������A���̐Â��ȕl�ӂł̓������������y���ނ���ł���ė����̂��낤�B
�@ �ޏ������Ƃ�����Ƃ����W���[�N�܂���̉�b�����킵�Ă���Ԃɖ߂�A�ܕ��قǑ���ƁA�Ύ듔����ӂɍL����u�͂܂Ȃ��̋u�v�ɏo���B���̒n��K�˂��̂͏��߂Ă��������A�u�͂܂Ȃ��̋u�v�Ə̂���邾���̂��Ƃ͂����āA�悭�������ꂽ�ؓ�������͂��߂��r�[�ɁA�����ʂɍ炫�����n�}�i�X�̉Ԃ��A����ł����ƌ�������ɌȂ̑��݂�i�������Ă����B����꒼���ɍ~�蒍���z���𗁂тāA���܂�Ɛ^�g�̉Ԃт炪ῂ�����ɋP���Ă���B�����āA���̃n�}�i�X�̍g�ɋ������ނ��̂悤�ɁA���������ɌQ������G�]�^���|�|�̉ԁX�����F�Ƃ܂��������ῂ���������Ă����B�G�߂̎�����䂪���̂ɂ���Ƒ��݂��֎�������������̉ԁX�̊Ԃɂ����āA�n�}�q���K�I��n�}�G���h�E�A���̑��̉ԁX�Ȃǂ͂����������f�C���ȕ\��������Ă����B
�@ �͌�����ŐΎ�삪�傫���֍s���Ă���Ƃ������Ƃ́A�n���̒m���Ƃ��ĂȂ�̂���悭�m���Ă͂����̂����A���ۂɂ��̗l�q��ڂɂ���̂͏��߂Ă̂��Ƃ������B�͂܂Ȃ��̋u�̖ؓ����������͂���A�Q������O�~�̎}�X��~�������i�ނƐΎ��̐��ӂɗ����Ƃ��ł����B�͌�����t������C���̉e���������Ă��A�قƂ�ǐ��͓����Ă��Ȃ��B��̐����w��ɂ����r�߂Ă݂�ƁA����������V���b�p�C���������B�������̏�ɑ��𗯂߁A���̂悤�Ɋ��炩�Ȑ�ʂ̌������ɍL���镗�i�Ɍ��Ƃ�邤���ɁA�������̓����v�̕b�j���Î~���A�₪�ċt�����ւƉ��͂��߂銴���������B
�@ ���ԏꂻ�̃��B�W�^�[�Z���^�[�̔��X�ł́A�n�}�i�X�̃\�t�g�N���[���Ȃ���̂��Ă����B�ǂ����A�n�}�i�X�̉Ԃ̐F�f�ƌO������������\�t�g�N���[���ł���炵���B�u�����ł����H�ׂ��܂����v�Ƃ������X�̐l�̌��t�ɏ悹���A��S�\�~�̑�����Ď��H���Ă݂����A�܂��܂��̖��ł͂������B
�@ ����������O�ꍆ�ɖ߂�A�傫�����˂�Ύ����ቺ�ɂ����߂Ȃ���Ύ�͌�����n��ƁA�قǂȂ����c���ɓ������B�������ɍʂ�ꂽ����Ɩq��n�тƂ��ǂ��܂ł������A���̂Ȃ���D���т��悤�ɂ��Ďԓ����̂тĂ���B�M�����Ȃ����ʍs���p�����Ȃ�����A���̋C�ɂȂ�������H���݂̃X�s�[�h�����ďo����B�䔑�Ƃ������W�����߂���������ŋ}�ɖ��C���Â����̂ŁA����ɍL����C�ݒi�u��̑����ɎԂ𒓂߁A���P�����{�C�ƍs����̎R���݂߂Ȃ��炵���ߐ����Ƃ邱�Ƃɂ����B���傤�ǐ��ߑO�̂��Ƃ���������A�����ʂ�̌ߐ��������B
�@ �傫�����ˏグ���㕔�h�A���琁�����ޑu�₩�ȑ�C�ƁA���z���ɍ������ޗz���Ƃ��قǂ悭�~�b�N�X���A�t���b�g�ɂ������A�V�[�g�����ς��ɉ�����邱�̐g��S�n�悭���ł��ꂽ�B�����̂��߂ɖ���̂ł͂Ȃ��A���̈�u��u�̂��߂ɂ̂ݖ����Ă���A��������A���Ԃ̋������瓦��A�������邽�߂����ɖ����Ă���\�\����Ȗ������肽�v���ɂЂ���Ȃ���A���͐[������ɗ������̂������B���ȃz�e���̈ꎺ��N�����F�߂镗�����Z�Ȋό��X�|�b�g�Ƃ͂��悻�����ȁA�����ɂ���Ă͂Ȃ�̕ϓN���Ȃ����i�Ɗ��̂��ƂŐ^�̈��炬�邱�Ƃ��ł���Ƃ����̂́A�����̂��ƂȂ���s�v�c�Șb�ł͂������B���Ԃ�A����́A���ӎ��̂����Ɏ���鎞�Ԃ̍����ꎞ�I�ɐؒf����邱�Ƃɂ���Đ�������قȌ��ۂȂ̂��낤�B
�@ �O���ԂقǏn���������ƁA���͍Ăї[���X����k�サ�͂��߂��B�Ύ뒬����l�v�����o�ė��G�s�Ɏ���A����ɁA���G����H�y���A�V�������o�Ēt���ւƑ������{�C�����̈�A�̓��H�́A�����I�ɂ́A�Ύ덑���A���э����A�V�������ȂǂƌĂ�邪�A�����̍������璭�߂�[���̔������̂䂦�ɁA�[���X���Ƒ��̂��ꂽ�肷�邱�Ƃ�����B���̂����A�H�y������V�������o�Ēt���Ɏ��镔���́A���Ĉ�тɐ������Ă����I���������ɂ��Ȃ�ŃI���������C���ȂǂƂ��Ăꂽ�肵�Ă����悤���B
�@ ���c���̒��S�X���߂��l�v���ւƌ������r���ŁA�Ԃ͐����ɂ����肽���s�Ȓf�R�n�т�D������C�ݓ��H�ւƍ����|�������B�s���藧�f�R�̑�����召����̃g���l�����ꂬ��ɁA�������A�ʂĂ邱�ƂȂ������Ă���B�Ƃ���ǂ���ɐ݂���ꂽ���W�]����g���l���̐�ڂ��猩���B�ꂷ�镗�i�́A�s���藧��Ɛ��̊�C�Ƃ̃R���g���X�g���▭�ŁA��i�ƌĂԂɂӂ��킵�����̂������B
�@ �S�L�u���ƊԈႢ�����ȔZ���i�����т�j�Ƃ����ς�����n���̏ꏊ���߂��A�������番�ċt�тƂ������W�����܂�铹�ɓ���A�C�H�R�̑��������C�݂������낷�����z����ƁA��{�i���ƌĂ��V�R�L�O���̎��̂���n�_�ɏo���B��{�i���Ƃ͍����ɋ߂����̕�������}��̕����܂ŁA������Ƃ��낪�ُ�ȂقǂɎ}�����ꂵ���~�Y�i���̋��ŁA��т������邻�̎}�Ԃ�͂Ȃ�Ƃ��ٗl�Ȋ����������B�t�߂ɂ͓��l�̋����O�A�l�{��������ł��āA�����̊��ɂ͂��낢��Ɗ肢�����������V�����W���������킦�t�����Ă����B�n���ł͈��̌�_�Ƃ����J���Ă���̂ł��낤�B
�@ �Ăэ�����O�ꍆ�ɍ����A�l�v���̒��S�W�����߂���ƁA�Ԃ͂܂��������C�H�R�����̓��ɓ���A�قǂȂ��Y�~���ɓ��������B�W����l��ꃁ�[�g���̎���ʊx����l�v�x�A�Y�~�R���o�Đ��ɂ̂т�Ő��́A���̗Y�~���t�߂ł������ɓ��{�C�ւƗ�������ł���B���c����l�v�A���т��o�ė��G�Ɏ��鍑����т����s���̂����Ȃ��C�ݔ��Ɍb�܂�Ă���̂́A���̂悤�Ȓn�`��̗��R����ł���B
�@ �Y�~�����������k���ɂ܂�����Ƃ���ɂ͗Y�~���W�]�䂪�݂����Ă����B�}�Ζʂ��オ�肫�����Ƃ���ɂ��钓�ԏꂩ��A����ɓk���ŋ}�s�ȕ�����o��߂��Ƃ���ɂ��̓W�]��͌����Ă����B�l�ʑ��K���X����A��w�̂Ȃ��Ȃ����h�ȑ���ɂȂ��Ă��āA�ቺ�ɂ͍L��ȓ��{�C�Ƃ��̉��ݒn�т��A�w��ɂ͍r�X�������̛�����ɘA�Ȃ鏋���ʂ̎R���݂�]�ނ��Ƃ��ł����B����������{�C�ɒ��ޗ[���߂��炳�������f���炵�����Ƃ��낤�Ƃ͎v�������A�����ɂ����v�܂ł͂܂��O���Ԃقǂ��������̂ŁA�[�������͒f�O�����B�Y�~���Ƃ����n��������z�������Ƃ���A���̂�����̐^�~�̍r���Ƃ����[�i�ɂ́A�Ă̂���Ƃ͈���Đ���Ȃ܂ł̔��͂�����ɈႢ�Ȃ��B
�@ ���ђ����߂����G�s�ɓ������̂͌ߌ�������������B���G�s�X���������ɑ��蔲��������O�ɓ��������́A�A�N�Z������i�Ƌ������ݍ��B�̂Ɋr�ׂ�ƁA���H�͂��ׂĂ̓_�ŐM�����Ȃ��قǂɂ悭�Ȃ��Ă���B�������L���ܑ��������Ȃ��߁A��ʍ����ł���ɂ�������炸�A��^�g���b�N�Ȃǂ������S�L���O��̃X�s�[�h�Ŕ������Ă�������ł���B
�@ ����ɐ��̊C�Ɍ������ČX�����z�����ڂɌ��Ȃ�����K�ȃh���C�u�𑱂��邤���ɁA�������S���̓��̉w�u�הԉ��v�ɓ��������B�ׂ̖L���ɂ킢�������̑傫���הԉ��̌��������j�������Ƃ��ĕۑ�����Ă��āA�����͖��������قɂȂ��Ă���悤���������A�J�َ������߂��Ă������ߒ��ɓ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�C�����̍L�ꂩ��̒��]�͂Ȃ��Ȃ��ɑf���炵�������B����͂邩����ł́A�����ʊx����Y�~���ւƑ�����X���A�܂肩��̗[���ɉf���Đ_�X��������̋P���Ă����B�E��̊C��ɂ͏��X�ɐ������ɋ߂Â��[����w�ɍ����Ⴍ�����ԍג�����̓��e���]�܂ꂽ�B�ނ��A�����́A�V�����ƏĐK���̓��e�ɑ���Ȃ������B
�@ �L��̈�p�ɂ́A�Z��ɋy�ԉڈΒn�T���Œm���鏼�Y���l�Y�̓����������Ă����B�A�C�k�����̂悫�����҂ł���A�k�C���Ƃ����n���̖��Â��̐e�ł��������Ɠ`�����镐�l�Y���A���̖k�ӂ̊C�ӂɂ����āA�ЂƂ�������[���߂Ȃ���A���̋��̗��H�ƌȂ̐��̕s�v�c���ɑz����y���Ă����̂��낤�B
�@ �[�g�̂Ђ��鏍������Ȃ��炵�炭���Ԃ�ׂ��Ă����̂����A����Ȃ��̂łȂ��Ȃ����z������ł���Ȃ��B�d�����Ȃ��̂œϑO�����ʂɌ������Ă̂�т�Ƒ���o�����B�ϑO�s�X�ɓ���O�ɁA�C�ݓ`���̂��̍����̂ǂ����œ��v��q�߂邾�낤�Ƃ����v�Z�������B�ӊO�Ȃ��ƂɁA����������ϑO���ɓ������r�[�ɕ��͔��d�p�̋���ȕ��Ԃ����X�Ǝp�������͂��߂��B�����Ȑ��̕��Ԃ��������сA�C���������Ă������Ɖ�]���Ă���B
�@ ���[�����X�����ǂ����l�����n���ɂ����悤�Ȃ��̓��������Ă��邤���ɁA�Ԃ��E�}�����o�Ŏ������ق��Ȃ�ʃh���L�z�[�e���̐l�ł����邩�̂悤�ȍ��o�ɏP��ꂽ�B���ƂŒn���̐l�ɕ����Ă킩�����̂����A�ϑO���͕��͔��d���{��Ƃ��Ēm���钬�ŁA�����ɂ͎l�\����锭�d�p���Ԃ�����炵���B�N���[���G�l���M�[�m�ۂ̕K�v�������������ɂ����āA�ЂƂ̃��f���P�[�X�Ƃ����킯�Ȃ̂��낤�B����͂���Ō��\�Ȃ��ƂȂ̂����A�������A�����A���{�̊C�ݐ��̂�����Ƃ���ɂ��̎�̕��Ԃ��������ԂƂ������ƂɂȂ�ƁA���͕ʂ��ƌ��킴������Ȃ��B
�@ ��Ђ̉_�̉e�������Ȃ���������ɑ��z���傫���߂Â����̂́A�ϑO�s�X�̂�������O�ɍ����|�������Ƃ��������B�����Ɏ��͎Ԃ�H���ɒ��߁A�[��ɐÂ܂鍻�n�̕l�ӂɍ~�藧�����B�����āA�V�����̂���������̊C���ɖv��ł䂭�^���Ԃȗ[���ɂЂƂ肶���ƌ�����Ȃ���A���̒����߂ɉ���𗧂��ƂȂǂ��Ă��Ȃ������Ȃ̐l����U��Ԃ����B�����Ƃ��A������Ƃ����āA�]���𐢂̐l�X�̂��߂Ɍ����s�������ȂǂƂ����ꏟ�Ȍ��ӂ�����C�ɂ��Ȃ�Ȃ������B�ߌ㎵����\���A�Ď�����܂��܂������������Ă��Ȃ��^�g�̑��z���A���̋����Ȑg�ɍŌ�̌��𓊂������ł����邩�̂悤�ɂ��ĊC���ւƎp���������B
�@ �ϑO�s�X�ɓ����Ă܂��Ȃ��A�u�ϑO�ӂ���Ɓv�Ƃ������c�̉���{�݂炵���������ڂɂƂ܂����̂ŁA�������������ɔ�э��݁A����̊��𗬂����Ƃɂ����B�͓S���̑����㉖�������A�����̘I�V���C����̒��߂͖]�O�̂��̂������B���ʂ͂邩�ȂƂ���ɂ́A��ڂł���Ƃ킩�闘�K���̓��e���A�����̋��w�ɂۂ�����ƕ�����Ō������B�܂��A�E��O���̊C��ɂ́A�V���ƏĐK�̗��������ǂ�����ł��̑��݂��֎����Ă����B���܂��܈ꏏ�ɓ��ɂ����Ă����n���̘V�l�̘b�ɂ��ƁA���̘I�V���C����́A�V�����ƏĐK���Ƃ̊Ԃɒ���ł��������ȗ[�������߂��邱�Ƃ�����炵���B
�u�ϑO�ӂ���Ɓv�́u�ӂ���Ɓv�Ƃ������t�̈Ӗ������ɂ͂��܂ЂƂ悭�����ł��Ȃ��������A�ӂ���Ƃ����C���ł��̉���{�݂����Ƃɂł����͍̂K���������B�Ԃɖ߂��Ĉ�ʂ�g�s�i�̐������I�������́A��c�ɓK�����ꏊ�����߂Ă����ނ�ɃA�N�Z���ݍ��B�k�̖������������k�l�̐��e���ЂƂ����ۓI�������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N8��1��
�k���S�i�E�V������
�@ �V���A�ĐK�����ւ̃t�F���[���o�Ă���H�y�`�ɒ������̂͌ߑO�����\�ܕ����������B���������ƁA�t�F���[�̏o���`�����◼���ɂ��Ă̏��X�̏�m�肽���ĉH�y�`�ɂ���Ă��������ŁA���̂܂܂����Ƀt�F���[�ɏ�荞�����Ƃ͎v���Ă��Ȃ������B�Ƃ��낪�A���܂��܃t�F���[�ւ̏ڍׂ�q�˂���D��t�����̌W���ɁA�\�ܕ���ɏo�`����t�F���[����ēV�������ĐK���̂ǂ��炩�ɓn��A����������Ă���H�y�`�ɖ߂���A��R�[�X�͂ǂ����Ɗ��߂�ꂽ�̂ł���B���̃t�F���[�ւ��͂����ƁA�K�R�I�ɓ��Ɉꔑ����������Ȃ��Ȃ�Ƃ̂��Ƃ������B
�@ �V���A�ĐK�̗����͂܂��K�˂����Ƃ̂Ȃ����X����������A���R�A���̊��U�̌��t�ɐS���������B��[���A����A�Ƃɂ����A�s�������s���Ă݂邩�I�\�\�ɂ킩�ɂ������f�������́A��}���ŎԂɖ߂�ƁA��ރm�[�g���͂��߂Ƃ���K�v�ŏ����̌g�s�i���i�b�v�T�b�N�ɋl�ߍ��B�����āA��Q�ĂœV�����s���̏�D�������߁A���ݐ��O�̃t�F���[�ɋ킯���̂������B�C���̔ɐB�n�Ƃ��ėL���ȂƂ���炵���Ƃ������ƈȊO�ɂ͉��̗\���m���������Ȃ��܂܂̓V�����s���ł͂������B
�@ ���̓��͐��V���������A���������������A�C�͂��Ȃ�r��Ă����B�������A�t�F�F���[�͂Ђǂ��h�ꂽ���A�������̗����炿�ł��Ƃ��ƑD���ɋ������́A�Ƃ����范�����C���̍~�肩����f�b�L�ɗ����āA�v�X�ɖ��키�s�b�`���O��[�����O�̃��Y������������ł����B�V�����܂ł́A ��O�̏ĐK���o�R�ł��悻�ꎞ�Ԕ��قǂ̍q�C�������B
�@ ���������������˂�Z���̊C���߂Ă��邤���ɁA�ˑR�A���͕s�v�c�Ȋ����ɏP��ꂽ�B�����Ԃ��ۂ��Ɍ����銴���ł͂��������A���̊C���̐F���A�̋��̍������݂�k�シ��g���̐F�Ǝ�������Ă�������ł���B�悭�悭�l���Ă݂�Ƃ�������R�̂��Ƃ������B��B����C��ō����{�����番���Δn�C���́A�����̕����ԓ��V�i�C��k��A�Δn�C�����ӂ�ʉ߂��ē��{�C�ɓ���A���k�n���̉����o�āA�͂�邱�̖k�C���̖k�������܂œ��B���Ă���͂��Ȃ̂��B�Ƃ��ɉď�ɂ͊C���̐�������������A�V���A�ĐK�̗����͂ނ��A���k�Ɉʒu���闘�K����當���ɂ܂ł��̗���͋y��ł���Ǝv����B
�@ ���ɐ���ꌃ���������ɑł����钪�̔𗁂тȂ���A�傫�����˂�C�ʂ����߂Ă���ƁA���������ɓ_�X�ƕ����ԍ��������ȊC���̉e���ڂɂƂ܂����B���肩��̋����ƍr�g�����̂Ƃ������A�����ɐ�������A�����݂ɉH�����Ȃ���C�ʂ����ꂷ��ɔ�ь������肵�Ă���B�E�~�E���Ǝv�������A����ɂ��Ă͂���Ƒ̌^�����Ԃ�Ȋ����������B���Ƃł킩�������ƂȂ̂����A�ǂ���炻���̓E�g�E���E�~�X�Y���̌Q�ł������炵���̂��B�@
�@ �����̊C�������̂��Ȃ��Ȏp�߂Ă��邤���ɁA���ꂼ��̌��������ɓK�����Đ����邱�̒n����̖��Ƃ������̕s�v�c���Ƃ��Ƃ������ɂ��炽�߂đz�����y�B�r�C�����̂Ƃ����Ȃ����̊C�����������āA���~�����ʂ��̂͗e�Ղł͂Ȃ����낤�B����̐������������₪�Ă͓y�ւƊ҂��Ă����悤�ɁA�ꐶ���I�����C�������̂قƂ�ǂ͊C�ւƊ҂��Ă����ɈႢ�Ȃ��B�n��ő��₦����̂�����̂��낤���A�命���̊C�������͊C���ɖv���Ă����̂��낤�B��������ɊC��ŗ͐s���A������H���т����g�Ԃɖ����̎p���䂾�˂�ł��낤�C���̉^����z���Ƃ��A�����ɂ��܂��������̗L�l�������������Ȃ��ɁA�������Ȃ���������̂������B
�@ �t�F���[�͂قڗ\�莞���ʂ�ɓV���`�ɐڊ݂����B���D���Ă����A�߂��̃����^�E�T�C�N���X�Ŏ��]�Ԃ��肽���́A�S���\��L���̎��V�H�����v���ɑ���o�����B�����A����ł����ƌ�������ɖҗ�Ȍ����������������Ă��邽�߁A�����Ƀy�_���������ł����]�Ԃ͂Ȃ��Ȃ��i��ł���Ȃ������B���܂��ɋ����z�˂��e�͂Ȃ��n��ɍ~�蒍���ł�������A�o���_����قǂȂ��Ƃ���ɂ��钷���⓹����肫�邾���Ŋ��т������ɂȂ��Ă��܂����B
�@ �⓹���オ��I���Ă܂��Ȃ��Ƃ���ɂ́A�Ȃ�ƂȂ������S���̃p�I��A�z�����鑢��̌����������Ă����B���H�e�̈ē��\���Ɂu�C�̉F���فv�ƕ\�L����Ă���Ƃ��납�炷��ƁA�H�y�`�ŏ�D���O�ɂ�����Ă����ό��p���t���b�g�̒��ɏЉ��Ă���V�����C�����Z���^�[�ł���炵�������B��u�x�ق��Ǝv�����������A�悭����Ɠ����̏d���Ċ�䂻���Ȕ����킸�������J���Ă���B���R�����̌������k�ӂ̗����̂��Ƃ�����A����̌��������Ȃǂ��l�����Ă��̂悤�ȍ\���ɂȂ��Ă����̂�������Ȃ��B
�@ �����Ɣ��������J���Ē��ɓ���ƁA�O�ς��炤���邱����܂�Ƃ��������Ƃ͈���āA�����͗\�z�O�ɍL�������B���w�I�ɍl����Ǝ��������̕��ʐ}�`�̒��ł͉~�̖ʐς��ő�Ȃ̂�����A�ǖʂ��~�`�̌����̓������L���͓̂��R�ł���B�����A�O�����璭�߂��ꍇ�A���_����~���`�̕ǖʂɈ�������{�̐ڐ��ɂ͂��܂�镔�����������Ȃ����ƂɂȂ邵�A���s�����F�����ɂ�������A�ǂ����Ă����ۂ�菬�����v����̂ł��낤�B
�@ ���܂��܂����������̂��낤���A�ٓ��ɂ͏����W������l���邾���ő��ɐl�e�͌�������Ȃ������B���ٗ��O�S�~���Ȃ���A���ܓV�����ɒ���������ŁA���ꂩ�玩�]�Ԃœ������������Ƃ��낾�ƍ�����ƁA�Ⴍ�Ċ����̂�����˂���Ƃ������̌W���́A�u���ӂ͓����ɂ����܂�ł���ˁB�ł�����A���̊C�̉F���قɂ͂��̓��ꌔ�ʼn��x�ł��͂���܂�����c�c�A����Ɂc�c�v�ƌ��t���Ȃ��������B����������ĎՂ�ł����邩�̂悤�ɁA�u����A����͍s�������������ł���ė�����ŁA�ꉞ�A���A��̂���Ȃ�ł��v�Ɠ`����ƁA�ޏ��͂����ɂ��c�O�����ȕ\����������B
�@ ���̗��R�͂����ɂ킩�����B�ނ܂�ȊC���̔ɐB�n�Ƃ��Ēm����V�����́A���S�̂����ʓV�R�L�O���Ɏw�肳��Ă���B�����āA���̓V�����ɂ����āA�ő傩�ō��̌����Ƃ������ׂ��E�g�E�A���̈��y�[�W�F���g���J��L������̂́A���傤�ǂ��̎������Ƃ����̂ł���B�ɐB���ɂ͐��\���H�ɂ̂ڂ�Ƃ�����E�g�E�̑�Q���A�I�I�i�S��C�J�i�S�Ȃǂ��\�C����\�C�����ɂ��킦���܂܁A���v����̉����̋��w�i�ɁA�C�ォ�瑃���߂����Ĉ�ĂɋA�҂���B���̌��i�͑s�ς̈��ɐs����Ƃ����̂������B
�@ ���R�E�̐��������͏�Ɍ������B�E�g�E���q�i�̂��߂ɂ��킦�Ė߂邻���̊l��������肵�悤�ƁA�����߂��ɂ̓E�~�l�R�̌Q���҂��\���Ă���B�������������A�����l���̂قƂ�ǂ��ɓ��钼�O�ɒD�������Ă��܂��E�g�E�����Ȃ��Ȃ��炵���B�c�����ɂ́A����ȃE�~�l�R�̌Q�ƃE�g�E�̌Q�Ƃ�����ȍU�h�킪�A���[�J��Ԃ����̂��Ƃ����B�Z���͂���ȊC�������̗l�q���ώ@����̂ɐ�D�̎����Ȃ̂ŁA���̊����I�Ȍ��i�����Ȃ��ŋA��Ȃ�Ă��������Ȃ��Ƃ����̂���˂���̈ÂɌ����Ƃ����Ƃ��낾�����̂��B
�@ �������A���̐S�͑傫���h�炢���B�����A���̕K���̃h���}����������ɂ͈�ӓ����ɏh�����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B����Ȃ��ƂȂ�A�m�[�g�p�\�R���������Ă���̂������ƌ���������A�ނ�Ƃ̍Ղ肾�����B���悩�珑������˂Ȃ�Ȃ����e�̍i�ߐ肪�����ɔ����Ă�������ł���B����ł��A�Ȃ�Ƃ������Ƃ��炵�������������ĕҏW���ɋ������Ă݂悤���Ƃ͍l�����B�����āA�ꉞ�́A����Ȃ�Ƃ������e�x���̗��R���Ђ˂���o���Ă݂͂��̂ł���B
�@ �����A�D�ꎮ�̑Ή���������܂ōl���o�����Ƃ���ŁA���͌���I�Ȍ�Z������̂ɋC�������B���A��̂���ōQ�Ăăt�F���[�ɔ�я�������߁A�K�v�ŏ����̂����������Q���Ă��Ȃ������̂��B�A��̃t�F���[������������ƁA�ǂ��v�Z���Ă��h���オ����Ȃ��B��펞�Ɏg��VISA�J�[�h���Ԃ̒��ɒu���Ă��Ă��܂��Ă�������A�����x���Ƃ����킯�������B�������āA����ɂ��E�g�E�A�҂̈��y�[�W�F���g�����͖��Ƃ��������Ă��܂����̂������B
�u�y�j���Ȃ̂ŏh�͍���ł��邩������܂��A����l���炢�Ȃ�d�b����ǂ��ɂ��Ȃ�Ƃ͎v���܂�����ǁc�c�v�Ƃ�����˂���̐e�Ȍ��t�ɁA�u�Ƃ肠�����A������������Ă݂Ă���ǂ����邩�l���Ă݂܂��v�Ɠ����͂������̂́A�����̈ӎv�Ɋւ��Ȃ��A���łɌ��_���o�Ă��܂��Ă����悤�Ȃ킯�������B�܂����A�u�h�������܂���̂ő݂��Ă��������v�Ȃǂƌ����o���킯�ɂ������Ȃ���������c�c�B
�@ ����ɂ��Ă��A�l�ԁA���ȂƂ���Ŗ��Ȃ��Ƃ�z���o�����̂ł���B�Ȃ�Ƃ��̎��A�ˑR�ɁA�k�R���̒��́A�u�����̎��ɂ���B�i�����j�͂���܂ق������Ȃ�v�Ƃ����ꕶ���]���ɕ�����ł����̂������B���N�̏h�]���ʂ����ׂ��ΐ��������{�w�łɏo�������m�a���̖@�t���A�ē��s���̂䂦�ɁA�Ɋy���⍂�ǐ_�ЂȂǂ�{�a�Ǝv�����݁A�̐S�̎R��̖{�{���Q�w�����ɋA���Ă��Ă��܂����Ƃ�����b�̍Ō�ɂ���A���̗L���ȋ��P�̌��t�ł���B���̏ꍇ�͏��X����قȂ�A�ꉞ�͐�B�邱�Ƃ͂ł����̂����A�ǂ��ɂ����ꂪ�x�������Ƃ����킯�������B
�@ �����A����Ȃ����́A�����ś����������A�����������_�����������̂�̐S�����܈�x�����������邱�Ƃɂ����B�����āA�Ƃ�����ƈӋC�����������Ȃ���ȓw�͂̒��ŁA�s���悭�z�������̂��A���p�ԓ`�䂩��́u�邷��Ήԁv�Ƃ������t�������B���t�V�т������Ƃ���ł͂��������A���̎��͌��\�^���������B
�@ �|�\�҂������ɂȂ�A�ϋq�̊��Ҋ����傫���Ȃ�߂���ƁA�ǂ�Ȃɑf���炵������������Ă��u�ԁv�A���Ȃ킿�A���҂̔�����S�g�̋P�����ϋq�ɗ^���銴���͔����B�ނ���A�܂��l�X�ɂ��܂�m���Ă��Ȃ����҂��A�ϋq�̑z�������Ȃ������悤�ȍō��̕���������������Ƃ������A���҂́u�ԁv�A���Ȃ킿���̑��݊��ƋZ�|�̐��݂Ɖؗ킳�͋ɂ݂ɒB���A�ϋq�̂����銴��������̂��̂ƂȂ�\�\���l�̐r������ȉ��߂Ő\����Ȃ����A������͉ԓ`���̒��Łu�邷��Ήԁv�̐��_������ȕ��Ɍ���Ă���悤�ɂ݂���B
�@ ���s���̂܂܁A�ߓx�̊��҂�������Ƃ��Ȃ����̗��̕���ɂ���Ă����ϋq�̎��́A���̍ہA���́u�邷��Ήԁv�̐��_�ɂ��₩���āA�������\�z�����Ă��Ȃ������悤�ȁu�ԁv���߂Ă��邩������Ȃ��V�����Ƃ������m�̖��҂̉��Z�߂Ă݂悤�ƁA���炽�߂Ďv���������̂��B�����āA�܂��͂��́u�C�̉F���فv����ƁA���̓W��������ʂ菇�Ɍ��w���Ă݂邱�Ƃɂ����B�ߌ�l�\�ܕ����̉H�y�s���t�F���[�̍ŏI�ւ܂łɂ͎l���Ԃقǂ���B���̎��Ԃ��v�Z�ɓ���Ȃ���̓�����̂͂��܂肾�����B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N8��8��
�k���S�i�E�C�̉F����
�@ �C�̉F���قɂ́A�V�����̎��R�Ɋւ��鐔�X�̂����ꂽ�����ނ��W������Ă���ق��A�[���������e�̏��R�[�i�[�Ȃǂ��݂����Ă����B���Ԃɒǂ��Ȃ���̊ٓ����w�ɂ����āA�܂������Ɏ����ڂ�D��ꂽ�̂́A���ς��Ȑ��̃E�~�K���X�̗��������B�\�ʑS�̂ɂ܂���͗l�̂��锖�ΐF�̗��ŁA���a��8�`9�Z���`�A�Z�a��5�`6�Z���`���炢�ŁA�{�̗������ЂƂ܂��傫�Ȋ����������B�����A�Ȃɂ�����Ȃ̂͂��̗��̌`�������B�Ȃ�ƁA���m�������ג����Ђ��̂��A���т���Ȃ����Ă��܂����悤�Ȍ`�����Ă���̂ł���B�����������Ԃɂ킽��ˑR�ψقƎ��R�����̌J��Ԃ��̌��ʁA���ɓK�������`�̂��̂��c�����Ɛ�����������܂ł����A����I�Ȉӎu�̉�݂������z�������邻�̑��`�̖��ɁA���͂Ђ����犴�Q�������ł������B
�@ �I���������Ƃ������̂Œm����E�~�K���X�́A�k�̃y���M���Ƃ��Ă�Ă���B�Ȃ�قǁA�W������Ă��邻�̎ʐ^��r�f�I�f���A����ɂ܂����I�ȃf�R�C�i�[�����j�Ȃǂ����Ă݂�ƁA�p�`�Ƃ��������̉H�т̑g�ݍ��킹�Ƃ����A���^�̃y���M���������肾�����B�̒��͎l�\�Z���`�]�A�����͓�\�Z���`�]�ł���炵���B�E�~�K���X�͗���ł̓y���M�����l�������Ă悿�悿�ƕ����A���Ď��͏����݂��A���I�ɉH�����Ȃ���C�ʋ߂����I�ɔ�Ԃ̂��Ƃ����B���ׂ�Ƃ��낪�y���M���Ƃ͈���Ă���B�������A�����ł͌����Ƃ��������悤�̂Ȃ��j�����Ղ�Ȃ̂��������B
�@ ���̃I���������A���Ȃ킿�E�~�K���X�́A�c�������A�f�R�̊�I���̌E�݁A��̗ڂȂǂɈ�̗��ڂɎY�ݗ��Ƃ��炵���B�z������܂łɉ����̔��q�ŗ����]�������肵���Ƃ��Ă��A���m���Ɏ����`�����Ă���A�~�ʂ�`���ē����̂ŁA���̂Ԃ��I����]���藎����\���͏��Ȃ��Ȃ�B�Ȃ�Ƃ������Ȋ��ւ̓K���Ԃ�Ƃ����ق��͂Ȃ��B
�@ �W���̑�˂���Ɏf�����Ƃ���ł́A1938�N���ɂ͓V����������40000�H�������Ă����E�~�K���X��1983�N�ɂ�8000�H�Ɍ����A1995�N�̒������ɂ�����m�F�̐���20�H�O��ɂ܂Ō��������Ƃ����B���݂ł͍����̔ɐB�n�͂��̓V�����̊���t�߂Ɍ����Ă���A��Ŋ뜜��Ƃ��ėL�u�̐l�X�𒆐S�Ɍ����̕ی�Ƃ��Ă͂��邪�A�O�r�͊y�ςł��Ȃ��ł���炵���B1960�N�ォ��1970�N��ɂ����ēV�������ӂŐ������T�P�E�}�X�̗����Ԃ�A�I�I�i�S���Ȃǂ̎h���Ԃɂ�����A���т����������̃E�~�K���X���]���ɂȂ����̂��A�ő̌����̎���������ƍl�����Ă���悤���B�E�~�K���X�͐����ŗ������H�������Ȃ��牡�����ɂ�����ǔ�����K�������邽�߁A�C���̂Ȃ��ł������Ƃ����Ԃɂ�����₷���̂��������B
�@ ��ʂɐ����Ƃ������̂́A����������萔�������Ƃ��̌̐����}���Ɍ������鐫�������B����ɂ��킦�A���̌㐔�𑝂����V�G�̃I�I�Z�O���J������n�V�u�g�K���X�ȂǂɂƂ��āA�啝�ɌQ���k�����W�c�h�q�\�̗͂������E�~�K���X�E�R���j�[��_���A���␗��ߐH����̂��e�ՂɂȂ������ƂȂǂ��A�̋}���̈���ƂȂ����悤�ł���B
�@ �ߔN�ł͂�قǏ����Ɍb�܂�Ȃ������蒼�ڂɌ������邱�Ƃ̓���Ȃ����E�~�K���X�̎p��������A�C�̉F���قł́A�R���s���[�^�ɂ��f�W�^���Đ��摜��Đ������Ƃ��āA���َ҂Ɍ��J���Ă���B�I���������Ƃ�������A���̖����ɂ́u�I�������A�I�������c�c�v�Ƃ����A�ǂ������߂����ȋ�������߂Ă���̂��Ǝv�������A���ۂɒ����Ă݂�ƁA������Ƃ��Ⴊ�ꂽ�����ŃS���S���ƈ��k��Ȃ��甭������u�I�������������c�c�v�Ƃ������Ȃ�͋��������̐��������B�K���K���K���K���Ɛl�������������Ă��鎞�̉��̂悤�ɂ��������Ȃ����Ȃ��B
�@ �E�~�K���X�̗���30�`33���̕��������o�ěz������炵���B�a���������͈ꃖ����ő������i��I�����H�H�j�̎����}���邪�A�܂���Ԃ��Ƃ��ł��Ȃ����߁A���v��Ɋ�I����܂�ŗ����ł����邩�̂悤�ɔ�э~���̂��Ƃ����B�����A�����n�_������Ό��̏�ł����Ă��~���̃V���b�N�ŕ�������悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��̂��������B���~��A���͂����ɊC�ɏo�A�Y�̐e��������Ԃقǐ����s����ߐH�s���������A���̂��Ɛ����Ƃ��ĂЂƂ藧������Ƃ̂��Ƃ�����A�E�~�K���X�̗Y�͑����ȋ���p�p�Ƃ������ƂɂȂ�B�V�����ł͎Y���͘Z���ɂ����Ȃ��A���͔������܂łɑ��������I����B
�@ �T�n�����̃`�����j�[����瓇�Ȃǂɂ́A�c��y���M���̃R���j�[��������̗l����悷���K�͂ȃE�~�K���X�̔ɐB�n�����܂��Ȃ����݂��A�~��ɂ͂��̈�т�����{�ߊC�܂ő勓���ē쉺���邻��������A�E�~�K���X�����E�I�ɐ�ł̊�@�ɕm���Ă���킯�ł͂Ȃ��B�����A���Ƃ��������Ƃ��Ă��A���č����̈��ɐB�n�ł��������̒n�ł̊m�F�̐���20�H�O��Ɍ������Ă��܂����Ƃ����̂͂��т��������肾�ƌ��킴������Ȃ��B
�@ �ٓ��ɂ͊C�����̑��Ԃ̎ʐ^���͂��߂Ƃ���A�V�����̎l�G�̎��R�����ʂ������X�̎ʐ^���W������Ă����B�B�e�҂̉s���L���Ȋ����Ǝ��R�ւ̐[�����w���Â��邻���̑f���炵���ʐ^�Q�́A�C�̉F���ق̉^�c��́A�l�C�`���[���C���̑�\�߂鎛��F�B����̍�i�������B����ɂ́A�u�E�~�l�R�v�A�u�I���������̓��v�i�Ёj�A�u�k�瓇�̎��R���v�i�ۑP�j�A�u�k�C���@���̖쒹�v�A�u��Ƒ�n�̐��v�i�k�C���V���Ёj�Ȃǂ̒��삪����B�����ʐ^�W�u��Ƒ�n�̐��v������w�����ċA�������A�Ȃ�Ƃ�����L���ȍ�i�W�ŁA�S����邱�Ƃ��̂����Ȃ��v���������B
�@ �����ɋL���ꂽ�v���t�B�[���ɂ��ƁA1960�N�ɖk�C���m�ʎs�Ő��܂ꂽ�����1992�N�k�C�������w�𑲋Ƃ���ƁA�V�����̏��w�Z�ɕ��C�����B�V���̎��R�ɖ�����ꂽ����͋��������̂�����瓇�̎l�G�̎ʐ^���B�葱���A1991�N�A����L���m���T�����Ŏʐ^�W�u�C���̓��v���J�ÁA��D�]�����B���ꂪ�]�@�ƂȂ�A��1992�N�ɂ�10�N�Ԃɂ킽���ċߏグ�����E�������A�t���[�̎ʐ^�ƂƂ��ēƗ������B
�@ �k�C�����N�Ȋw�����U���܂Ȃǂ���܂�������̊����́A�P�Ȃ�ʐ^�ƂƂ��Ă͈̔͂ɂƂǂ܂邱�Ƃ͂Ȃ������悤�ł���B���{�쒹�̉����A���{���w�����ƂȂ�������́A�V�����̑����I�Ȏ��R�ی�A����ɂ͎��R�ώ@�Ǝ��R�w�K�̕��y���i�A�����O�ւ̍L���ȂLj�т��Ă����Ȃ����߁A1999�N�A���̓V�����C�����Z���^�[�u�C�̉F���فiTEL&FAX 01648-3-9009�j�v���I�[�v���������B
�@ �V�����̎��R���ڂ����Ǝ��̃p���t���b�g���쐬������A�V�����C���ی��ψ���s�̋@�֎��u�C���ی�v�̕ҏW�Ɣ��s�ɖz��������A���R�ώ@�⎩�R�T���̊w�K���ʐ^�B�e�Ȃǂ̓����c�A�[�����^�c������A���O�ւ̏�M�⋦�͗v���̂��߂̊�_�ɂȂ�����ƁA�C�̉F���ق̑��݂͂��܂�V�����ɂƂ��Č������Ȃ����̂ƂȂ��Ă���B�C���^�[�l�b�g��̓V�����Љ�̃z�[���y�[�W�ihttp://www.teuri.jp�j��������͂��߂Ƃ���C�̉F���ق̉^�c��́A�l�C�`���[���C���ɊW����X�^�b�t�ɂ���ĊǗ��^�c����Ă���悤���B����B�e�̎ʐ^�M�������[�����邵�A�V�����̊e����R�[�i�[��l�C�`���[�{�����e�B�A��W�̃R�[�i�[�Ȃǂ��݂����Ă��邩��A�S�̂���l�̓A�N�Z�X���Ă݂�Ƃ悢���낤�B
�@ �����ɂ́A���ɓV�������ݒ��b�ی��Ǘ����Ȃ�{�݂�����A������ɂ��C���̎ʐ^�┍���A���Ԃ̃r�f�I�Ȃǂ��p�ӂ���Ă͂���݂��������A���݂����������ɂ͂��̋@�\�ƒ��̏[���x�͂��܂ЂƂ̊����炵���B���̎{�݂ɂ��Ă��A���X�̊Ǘ��^�c�ʂŊC�̉F���ق̃X�^�b�t���Ȃɂ��Ƌ��͂����Ă���悤�������B
�@ �b�͑O�シ�邪�A�����ɖ߂��Ă���A�������m�F���Ă��������������ƂȂǂ��������̂ŊC�̉F���قɓd�b�������B���̂Ƃ����܂��܂��̓d�b�ɉ����Ă����������̂������{�l���������A���̉��₩�Ō����Ȑ��̋����̉��ɂ́A�l��{���x�Ȉӎu����߂��Ă��銴���������B
�@ ����\�߂�l�C�`���[���C���͗L����ЂɂȂ��Ă��邩��A���̉^�c���ɂ���C�̉F���ق͂������Ƃ��Ă͖��Ԍo�c�̎{�݂Ƃ������ƂɂȂ�B�ǂ��l���Ă݂Ă��c���ړI�Őݗ����ꂽ�{�݂ł͂Ȃ�����������A���̈ێ��Ǘ��ɗv����l�I�J�͂�R�X�g�����ł�����Ȃ�ɑ�ςȂ��Ƃ��낤�B�����v�������́A�C�̉F���ِݗ��̈Ӑ}�ƌo�܂𗦒��Ɏ���ɐq�˂Ă݂��B
�@ �V�����̑����I�Ȏ��R�ی�Ǝl�G�ɉ��������R���̎��W�`�B���͂���ɂ́A���n�ɋ@�\���̍������I�ȏ��Z���^�[��݂��邱�Ƃ��s�����ƁA����͍l�����B�����čs�����ǂ��͂��߂Ƃ��鏔�X�̊W�҂ɂ��̕K�v����i�������Ă݂͂����̂́A�Ȃ��Ȃ����̍\�z�͎������Ȃ������B�����ł�ނȂ��A�����L�u�́A���͂ł��̂悤�ȏ��Z���^�[��ݗ����悤�ƌ��f�����̂������B
�@ ���R�A���̂��߂ɂ͎����̒��B���K�v�ƂȂ邪�A���Z���x��̖��������āA�l����ɂ͎�����Z�����Ă��炦�Ȃ��B���̂��߁A����͎��炻�̑�\�ƂȂ��ėL����Ѓl�[�`���[���C����ݗ����������Ŏ����������A1999�N�A�悤�₭�V�����C�����Z���^�[�A�C�̉F���ق̊J�݂ɑ��������B�u���̐�܂��܂��؋���ԍς������ĂĂ����Ȃ���Ȃ�܂���v�Ƃ�������̌��t�́A�͂��炸�����̍��̕����s���̕n��������Ă���悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ������B
�@ �ډ��傫�Ȗ��ɂȂ��Ă��铹�H��������̉��b�������āA�k�C���̓��H����͋ߔN�����قǂɂ悭�Ȃ����B���[���R�ԕ��ɂ�����܂ŏc���ɗ��h�ȕܑ����H���ʂ��Ă���A�������͂����ƃ_�[�g�̈��H���炯�������̂̎p���M�����Ȃ����炢�ł���B����ł��Ȃ��A�����Ɠ��H�̌��݂��Ƃ����n�������̂̐��͐₦�Ȃ��悤���B�������A���H���݂̕K�v�������ׂĔے肷��C�͂Ȃ��̂����A���N�ɂ킽���č��������X�܂ŗ����Ă������Ȃǂ́A�ǂ��l���Ă��s�K�v�Ɍ����铹�H��ߏ萮���Ƃ��v���闧�h�ȓ��H���قƂ�Ǘ��p����Ȃ��܂܁A�S��������Ƃ���ɑ��݂��Ă���̂�ڂɂ��Ă������B
�@ ���s���x�ł͓��H�̌����݂ƊW�{�݂̐����݂̂Ɏg�p�����肳��Ă��铹�H��������̂ق�̈ꕔ�ł��n���̕����s���ɓ]�p���邱�Ƃ��ł���A����̂悤�ȕ��X���]���ȋ�J�����Ȃ��Ă����ނ��낤�ɂƂ����v���������B�������A���H�̌��݂͌o�ϓI�Ȕg�y���ʂݏo���n��̊������ɂȂ��邪�A�C�����Ƃ��̂��߂Ɏ����𓊓����Ă��o�ό��ʂ͓����Ȃ��A�ȂǂƂ������_���N���邾�낤�B�����A�������v�i��̑_�����߂����̎�̎咣�̂قƂ�ǂ͎��ȋ\�Ԃɖ����Ă���B
�@ ���{�ȊO�̐�i���̑������A���R�ی�A����ɂ͂���ɕt�����镶���{�݂̌��݈ێ��A�l�I�����̊m�ۂƈ琬�ɑ���̍���𓊓����A�L���Ȏ��R�Ɠ`�������̎c��n��ɂ���Ȃ�̊������������炵�Ă��邱�Ƃ��v���A���̎�̔��_�ɖ��������邱�Ƃ͎������낤�B�ǂ�ȑΏۂɎ����𓊓����Ă����ɂ���A�v�͂��̎������m���ɒn���̐l�X�̎�ɂ����킽��A���ʂƂ��Ă��̒n��̊������ɂȂ���H�v���Ȃ����悢�����̂��Ƃł���B���H���݂���̂Ƃ��錚�Ƃ�ʂ��Ă��������n���ɂ͎����𗎂Ƃ����@���Ȃ��Ƃ���]���̍l�������A���̍ۉ�X�͑傫�����߂Ă����K�v�����邾�낤�B
�@
�@ ������̂��߂ɕK�v�Ȏ��Ԃ��C�ɂ��Ȃ�����A���͊C�̉F���ق̓W��������r�f�I�f���𑶕��Ɋy���B�E�~�K���X���l�ɋߔN���̌̐��̌������뜜����Ă���P�C�}�t���̉f�������ɋ����[�����̂������BSpectacled Guillemot�i�ዾ���������E�~�K���X�̈Ӗ��j�Ƃ����p��������z���ł���悤�ɁA�Ȃ����P�C�}�t���͗��ڂ̂܂��ƚ{�̕t���������肾���������F�����Ă��āA�܂�Ŕ����傫�Ȋዾ�������Ă���悤�ɂ��݂���̂��B���̎p�͂Ȃ�Ƃ����[�����X�ň��g�ɖ����Ă���B�S�̓I�ɂ̓n�g�������ЂƂ܂��傫�������悤�ȑ̌^�����Ă��āA�ĉH�̏ꍇ�A�ڂ̂܂��ƚ{�̕t�����A����ɗ��̂����ꕔ���̂����Ă͍����H�тɕ����Ă���B
�@ �P�C�}�t���̂����ЂƂ̓����́A���邩��ɑN�₩�Ȃ��̐Ԃ��F�̑��ł���B�P�C�}�t���Ƃ����a���̌ꌹ�́A�u�Ԃ����v���Ӗ�����u�P�}�t���v�Ƃ����A�C�k��Ȃ̂����������A�Ȃ�قǂƂ��������ł������B��������ɂ��ƁA���̒����Ԃ��F�����Ă���炵���B�k�C�����ӂ̓��X�̒f�R����ȔɐB�n�ŁA�V�����͂��̑�\�I�ȉc���n�ɂȂ��Ă���B1963�N���܂ł͔ɐB���ɂȂ��3000�H�قǂ̃P�C�}�t�����ώ@����Ă������A1972�N�ɂ�400�H�O��ɂ��̐����������A���̌�������̌X���ɂ���悤���B���̒��́A�܌����A�f�R�̊�̗ڂ��Ɗ�̌��Ԃɓ�̗����Y�݂��邪�A�����ɑ������Ă������͒ʏ��H�����Ȃ̂��Ƃ����B
�@ �P�C�}�t�����l����ǂ������������j���p���r�f�I�Ō������A�������L���傫���H�����Ȃ���i�ޗl�q�́A�܂��ɐ������ĂƂ����\�����҂�����ł������B���������ƂɁA���Ԏ��̒��̎p�ƂقƂ�Ǖς�肪�Ȃ��̂ł���B���̕s�v�c�Ȍ��i�ɂ����Ȃ���ʊ������o���Ȃ���A���͂Ђ�����ڂ̑O�̃r�f�I�f���Ɍ��������̂������B�����āA���̎B�e�������Ȃ��������J�����}���̃J�������[�N�ɂ��h�ӂ�\�������C���ɂȂ����B
�@ ����B�e�̓W���ʐ^��A�R���s���[�^�̃f�W�^������Ō����E�g�E�̋A�����i���f���炵�������B�v��ʌ�Z�����ƂɂȂ��ăE�g�E�A���̌��i�����w�����D�̃`�����X�ɂ��邱�Ƃ�����I�ɂȂ��Ă����̂ŁA���̂Ԃ�������ۓI�������̂��낤�B�������̌������ɂ��܂������܂�Ƃ���[�z�ƈ��F�̗[�Ă����w�ɁA�����̍��_�ƂȂ��Ĉ�ĂɋA�����鉽��H�A�����H���̃E�g�E�̑�Q�A�{��t�ɐ�������Ȃ��قǂ̃C�J�i�S�����킦�Ēf�R�㕔�̎Ζʂɑ��X�ƒ��n���A������Ɨ���Ȃ������Ȃ���������ɐ��̑҂������������̂��Ȃ��Ȏp�A���̂����ۂ��ł���ȃE�g�E�̋A�҂�҂������l����D����낤�Ƃ���E�~�l�R�̌Q�\�\���܂ǂ�����Ȗ��̃h���}�ڌ��邱�Ƃ��ł���̂́A�����L���Ƃ����ǂ����̓V���������ɈႢ�Ȃ��B
�@ ���E�ő�̃E�g�E�̔ɐB�n�ł���V�����ł́A�Z���̂��̎����A���\���H���̃E�g�E�̌Q��������炵���B�P�C�}�t���ȏ�ɐ������Ă̓��ӂȃE�g�E�͔ɐB�����̂����Ă͗��ɂ����邱�Ƃ͂Ȃ��A���̈ꐶ�̂قƂ�ǂ��C��ʼn߂����̂��Ƃ����B�����͊C�ɖʂ���f�R��̎Ζʑ��n�ɉ��s���[�g���ɋ߂������@���ĉc������B�V�����̔ɐB�n�ł́A�\���[�g���l���̎Ζʂɕ��ϓ�S�O��̑���������̂������ŁA�����̈قȂ鑃���ǂ��������Ōq������������Ă���Ƃ̂��Ƃł���B
�@ �ɐB���ł��E�g�E�͓����C��ʼn߂������߁A���v��̋A�������̂����Ă͗���ł��̎p���������邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��B�l�����{���A�����̉��Ɉ�����Y�ݗ��Ƃ��ꂽ���́A�܌����{����z�����͂��߂�B�����z��Ɛe���͈���Ɉ�x�������v��ɑ�R�̋������킦�đ��ɖ߂�A�̐��ɋ��a����̂��Ƃ����B�A���r���ŃE�~�l�R�ɉa��D��ꂽ�E�g�E�̐��́A�����̗[��ꎞ�܂Ő�H��]�V�Ȃ������̂��낤���B������������A�O���̐H�c���Ȃǂ��������肷��̂�������Ȃ����A���̂ւ�̂��Ƃ͎����ł͊m�F���邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B
�@ �t���Đn�I�w�K�ł͂��������A�C�̉F���قœV�����̎��R���ƊC���̐��Ԃɂ��Ă����܂��ȂƂ�����w���́A�Ăу����^�E�T�C�N���Ɍׂ�ƁA���̐���[�ɂ���Ԋ�W�]��ڎw���Č����Ƀy�_���݂͂��߂��B���ς�炸�̖җ�Ȍ��������ŁA���R�n�ł��������]�Ԃ͎v���悤�ɐi��ł͂���Ȃ��������A���ӂ̎Ζʈ�тɃE�g�E�̑����ƃE�~�l�R�̉c���n��������Ƃ����Ԋ�W�]��ɗ��̂����ʂȂɂ��̊y���݂ł������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N8��15��
�k���S�i�E�Q�����
�@ �V�����̒n�`�́A�k��������쓌���ɂނ����ē��S�̂����₩�Ȋp�x�ŌX���������ɂȂ��Ă���B�����ĐԊ�̂���쐼�[����V������̗��k���[�܂ł̖k���C�ݘZ�L���قǂ��A������S���[�g���قǂ̒f�R�ɂȂ��Ă���A�e�Ղɂ͐l���߂Â��Ȃ��B�ނ�̒f�R��т��C�������̈��R���j�[�ɂȂ��Ă���킯���B
�@ �V���`����O�L���قǂ̒n�_�܂ł́A�킸���ɏ��C���Ȃ���A�C�����ɂقڕ��R�ȓ��������Ă�������A���ʂȂ���K�ȃT�C�N�����O���y���߂�͂��������B�Ƃ��낪�\�z�O�̋�����^���ʂ��炤���邱�ƂɂȂ������߁A�������������ɂȂ��ăy�_����ł��A���]�Ԃ͂̂�̂�Ƃ����i��ł���Ȃ������B�܂��āA�O�L���n�_����Ԋ�W�]��t�߂ւƑ������x����S���[�g���A������O�L���̍⓹�́A�ǂ����~�����Ƃ���ő����o�邱�Ƃ͕s�\�������B
�@ ���ꂶ��A�킴�킴���]�Ԃ���Ă����Ӗ����Ȃ���ȁ\�\����ȋ�s�܂���̌��t��ꂫ�Ȃ���A���]�Ԃ������Ĉ������⓹��o�����B�������A����Ȃ��ƂɁA���̂����ŁA���H�e�̎Ζʈ�тɍ炫�����ԁX����������ƒ��߂邱�Ƃ͂ł����B�n�}�i�X�A�G�]�X�J�V�����A�G�]�m�����C�O�T�A�����āA���x���オ��ɂ�đN�₩�ȉ��F�̉Ԃ����G�]�J���]�E���p��������悤�ɂȂ����B�Ԏ��̏��Ԃ�����������ĕ��ɗh���̂͂ǂ���烄�i�M�����炵�������B�Ԃ̓��Ƃ����Ƃ��ĖK�˂��當���̂��Ƃ�z���o�����A���̂�������Ɉʒu���邱�̓V�����̉ԁX�̔��������Ȃ��Ȃ��̂��̂��ƌ������B
�@ ���ɖL���Ȏ��R�Ɍb�܂ꂽ�V���������A���ۂɖK�˕����Ă݂ĂЂƂ����C�ɂȂ����̂́A�X�т炵�����̂��قƂ�nj�������Ȃ����Ƃ������B�����́A�C�ۏ����̂������Ȃɂ��ő傫�Ȏ������炵�ɂ����̂��낤�Ɛ��������̂����A���ƂɂȂ��Ď���F�B����̒���u��Ƒ�n�̂����v�i�k�C���V���Ёj�ɖڂ�ʂ������ɁA���ꂪ�l�דI�Ȍ����ɂ����̂炵�����Ƃ�m�����B
�@ ��j����̈�Ղ̕����Ƃ���ɂ��ƁA�ܐ�N�ȏ�̂̓ꕶ�����łɁA�V�����ɂ͐l���Z��ł����炵���B�������A���j��̋L�^�ɓV�������o�ꂷ��͍̂]�ˎ���ȍ~�̂悤�ł���B�ȗ��A�Z�l�͏��X�ɑ����A�j�V�������Ő����ɂ߂��������㖖���ɂ́A�����l���͓V���j��ő��̐甪�S���\�l�]�ɂ��Ȃ����炵���B�����A�N�ԓg���߂����l�ꂽ�j�V���̂قƂ�ǂ̓V�����i�엿�j�Ƃ��Ė{�y�ɉ^�ꂽ���A�V����������ɂ̓j�V�������M��������K�v���������B���M�p�R�����m�ۂ��邽�ߖL���ȐX�͐�s������A�������V�����͊ۖV��̓��Ɖ������̂��������B
�@ ���x��������ɂ�āA����ቺ�ɏĐK���̓��e���͂�����ƌ����͂��߂��B���ܗ����~���Ă͏ĐK���̓��e�Ǝ��ӂ̉ԁX�߁A���ꂩ��܂������o���Ƃ����s�ׂ��J��Ԃ��Ă��邤���ɁA�ˑR�A���H��ʂ��^�����ɂȂ��Ă���Ƃ���ɏo���B�܂�ŘH�ʑS�̂𔒃y���L�œh��Ԃ����悤�Ȋ����ł���B��������傫������������܂킵�Ă݂�ƁA�^�����ɂȂ��Ă���̂͘H�ʂ����ł͂Ȃ��悤�������B�t�߂̑��̕\�ʂ����Ȃ蔒���ϐF���Ă���B���ꂪ�C���̕��̂������ƋC�Â����̂́A�Ԋ�W�]������������ē��\�����ڂɂƂ܂������炾�����B
�@ ����قǂɒ��̕��������Ă���Ƃ��납�炷��ƁA���̕t�߂ɂ͂�قǂ̐��̊C�����������Ă���ɈႢ�Ȃ������B���������Ƃ��̗L�l�߂Ă��邤���ɁA���ނ̕����Ăǂ����Ă���Ȃɔ����F�����Ă���̂��낤�Ƃ����^�₪�N���Ă������A���̓��̐��ƂłȂ����̐g�ɂ́A�\���Ȑ��������邱�Ƃ��ł��Ȃ������B
�@ ���]�Ԃ�Ԋ�W�]������ɒu���W�]��ւƑ������ݕ���������͂��߂��r�[�A������������قǂɖҗ�ȕ������グ�Ă����B�O���ቺ�ɂ͔����g���������Č������g�����{�C���L�����Ă���B�萠��ɂ��܂�Ȃ��獶�E�����܂킷�ƁA�f�R��̍L�����n�܂���̎Ζʂɑ召�����̈ٗl�Ȍ��������Ă���̂ɋC�������B�����̂����e�̋}�ȎΖʂ���ʌ����炯�ł���B
�@ �܂�ŌÑ��Ղ̔��@�Ղ݂����Ɍ��{�R���炯�Ȃ��̊�ς̑��`�傱���́A�ق��Ȃ�ʊC���̃E�g�E�����ł������B���̕s�v�c�Ȍ��i�ɖ������邢���ۂ��A�����ŃS���t���������A�N���u��U�������Ƃ����Ȃ����̐g�ł��z�[���E�C���E�����͌������낤�ȂȂǂƂ�����Ⴂ�Ȃ��Ƃ��l������������B�ɐB���ɂ�����E�g�E�̐������͐��\���H�Ƃ����邩��A�A�ȂƑ����V�����k�����f�R�̏㕔�Ζʂɂ͂�����Ƃ���ɂ��̂悤�ȑ����������Ă���̂��낤�B
�@ ���ꂼ��̑����̉��ł́A���łɒa�����������������v��̐e���̋A���҂��Ă����̂�������Ȃ����A����ȋC�z�Ȃǂ͂܂������������Ȃ��������A�ǂ�Ȃɖڂ��Â炵�Ă������T������Ă݂Ă��A�E�g�E�̐e���炵�����̂̎p�͂����̈�H����������Ȃ������B�����āA�E�g�E�ɂ����Ĉ�т̎Ζʂ₻�̉��̒f�R�̂�����Ƃ���ɓ_�X�Ǝp�������Ă���̂́A�삵�����̃E�~�l�R�����ł������B�~���[�A�~���[�Ƃ����Ɠ��̉s���������Ȃ���A�C�ʂ��琁�グ�Ă��鋭���ɏ���Ĕ��Ă��Ă�����̂����Ȃ肠�������A�قƂ�ǂ̃E�~�l�R�����͊�A��E�g�E�̑����̂܂��Ȃǂł����ƉH���x�߂Ă��銴���������B�G�]�J���]�E�̉Ԃ̉A�ɔ��ΐg���B���悤�ɂ��Ă������܂��Ă���E�~�l�R�����Ȃ��Ȃ������B
�@ �f�R��̋}�Ζʂ��������������Ƃ���ɂ���Ԋ�W�]��ɗ��ƁA�C������s������ɓ˂��o�������l�\�����[�g���̐Ԋ₪�A�ቺ�ɂ��̈Зe�����킵���B�W�]��̐^���͂قڐ����ɐꗎ����f�R��ǂɂȂ��Ă��āA�Ԋ�Ɍ������A������r�g�ƁA���̎��ӂɓ_�݂���召�̊C�������̉e����]�̂��Ƃɂ����߂邱�Ƃ��ł����B�V�����̏ے��Ƃ������ׂ����̐Ԋ�t�߂͂��ăE�~�K���X�i�I���������j�̔ɐB�n�ł����������A���݂ł͂��̒n�ʼnc������E�~�K���X�̎p�͌����Ȃ��Ƃ����B
�@ �̌^�͎��Ă��邪�E�~�l�R�����ЂƂ܂��傫�Ȋ����̒��������B���̐F�����F�ł͂Ȃ�������ƃs���N�������Ă����悤������A���Ԃ�I�I�Z�O���J�����������̂��낤�B���̒��͎G�H���ŁA�������Ⓓ�ނ̎��́A���̊C���ނ̗��₻�̐��A���ނ̎��̂���Ȃǂ��D�ނƂ����B���R�A�E�~�K���X��P�C�}�t���Ȃǂ̓V�G�ł�����킯�ŁA�V�����̊C���Љ�ł͐H���A���̃g�b�v�Ɉʒu���Ă���̂��������B�ߔN���̃g�b�v�̍����߂�I�I�Z�O���J�������}������Ƃ����ُ펖�Ԃ��N������������Ă���炵���B�@
�@ ���ɖK���l���Ȃ��̂��悢���ƂɁA�C�Ɗ�Ƃ̐D�萬����т̊�i�ƊC�������̗l�q�𑶕��Ɋy�����ƁA�����ނ�ɐԊ�W�]������Ƃɂ��������B�����A���͂����ł�����x�����~�߁A���������v���ŃE�g�E�̑��������������ƒ��߂�����B���Ǝ��A�����Ԃ������炱�̒n�ŌJ�L������ł��낤�s�ςȃh���}�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��͎̂c�O���ɂł͂��������A����͂܂����炽�߂Ă��̓���K�˂鎞�̊y���݂Ƃ��ĂƂ��Ă������ƁA����̐S�Ɍ������������B
�@ ���Ȃ����ς����Ă����S�̂ł͉��\���Ƃ����V���̑����������Ă���͂��Ȃ̂ɁA�قړ������ɚ{�����ς��ɋ������킦�ċA�҂���E�g�E�����́A�������Ď����̑������ԈႦ�邱�Ƃ͂Ȃ��̂��Ƃ����B�����{�\�Ƃ��������Ƃ��炵�����t�ŕЕt���Ă��܂�����܂łȂ̂����A�E�g�E�����̍s�����a�̍L���ƈ�ċA�҂̏�z���ƁA���̎��ʔ\�͂͋����ׂ����̂ł���B
�@ �����Ƃ��ƂɂȂ��Ă��玛��ɓd�b���Ē��ڊm�F�������ƂȂ̂����A�E�g�E�̑����̂قƂ�ǂ͉��N�ɂ��킽���čė��p�����̂��Ƃ����B�������A�܂������V�����������@���邱�Ƃ�����B���̎��ȂǑ��������Z���ɂȂ�Ȃ����Ƃ��v�������A��т̓y���⑃���̍\���̖��������Č����ɂ͂��̐S�z�͂قƂ�ǂȂ��炵���B
�@ ���̂��߂Ɏ����A�����l�����E�~�l�R�ɉ���肳�ꂽ�ꍇ�A���͂����������Ƃ͂Ȃ��̂��Ƃ����f�p�ȋ^�������ɂԂ��Ă݂�ƁA�ӊO�ȓ������Ԃ��Ă����B��H�̐e�������͗Y�����ꂼ��ɑ������̋������킦�Ė߂��Ă���̂ŁA������S���D�������Ƃ������Ƃ͂߂����ɂȂ��̂��������B�Ƃ��ɚ{�̕t���t�߂ł��킦�Ă��鋛�́A�E�~�l�R�Ƃ����ǂ��͂����ŒD�����̂͗e�ՂłȂ��̂��Ƃ����B�{�̉��̂ق�������ȍ\���ɂȂ��Ă��āA���킦��������������Ɨ��߂邱�Ƃ��ł��邩��Ȃ̂��������B
�@ �e����������ʂɊl�����^��Ŗ����A�������悤�ȏꍇ�ɂ́A���͂������x�ɐH�ׂ��A���x���ɕ����ĐH�ׂ��������炵���B�ЂƂ̑����ƂɈ�H�����a�����Ȃ��E�g�E�̐��́A�Z��Ԃ�����ȉa�̒D������������K�v���Ȃ��킯������A����Ȃ��Ƃ��ł���̂��낤�B����̘b�ɂ��ƁA�C�J�i�S���l�\���C�����킦�Ė߂��Ă����E�g�E�Ȃǂ��������Ƃ����B�������A�����ꂽ�ʐ^�Ƃ̎���̂��Ƃ�����A���̗l�q���ʐ^��r�f�I�Ɏ��߁A���ƂŐ��m�ɃJ�E���g���Ă݂��̂��낤�B
�@ �Ԋ�W�]������ɖ߂������́A���Ő����|���ꂽ���]�Ԃ��N�����A����������Ȃ���Ăэ⓹��o��͂��߂��B�����Ă����ꊾ�������Ƃ���ŁA���̍ō��n�_�߂��ɂ���r���[�E�|�C���g�̂ЂƂA�C���ώ@�ɂ̓����ɓ��������B�����Ŏ��]�Ԃ��~��A�ώ@�ɂւƑ�������������o�����r�[�ɁA���܂�ƍ炫�ւ鉩�F���G�]�J���]�E�̌Q���Ǝ��̃^�`�M�{�E�V�Q���Ƃ������ɖڂɔ�э���ł����B���肩��̋����ɐ���ꌃ�����h��g�ł��Ă������A���ꂪ�������āA���̖k�̓��ɍ炭�ԁX�̔����������������ۗ������Ă������B�����̉E��ɉ����A�Ȃ錯�����f�R���A�����Ă��̊�ꕔ��₦�ԂȂ��ቺ�͂邩�Ȑ��̂���߂�������ۂނقǂɔ����������B
�@ �C���ώ@�ɂɌ������r���A�傫�Ȉ�C�̍��L�Əo�������B�s���ڂ��Ƃ����A�r�q�Ȑg�̂��Ȃ��Ƃ����A�ʏ�̎����L�Ƃ͖����ɈقȂ鐦�݂�����������A�����炭���Ζ쐶�������L�Ȃ̂��낤�B������������C����쒹�Ȃǂ��P���A�����H�ׂĐ����Ă���̂�������Ȃ��B
�@ ���������J�ɂ��ς�����悤�ɐv���ꂽ�ؑ����l�����̊C���ώ@�ɂ́A����ɓ˂��o���f�R�̏�ɗ����Ă����B��v�ȃK���X����̎ɓ��ɂ͖����Ŏg�p�\�Ȗ]������o�ዾ�������t�����A�O���̒f�R��т�ቺ�̊�ʒn�тɐ��ފC�������̐��Ԃ���������Ɗώ@�ł���悤�ɂȂ��Ă����B���܂莞�Ԃ��Ȃ������̂ŁA�]�����ŊC�������̓������Ԃ��ɒ��߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��������A����ł��A�ቺ�̑s��ȕ��i���y���݁A�C�������̐��ݕ����̗l�q���M���m�邱�Ƃ͂ł����B
�@ �ώ@�ɓ��̉���ɂ��ƁA�Ă̔ɐB���A���̈�т̒f�R�̉����ɂ̓q���E��E�~�E���c�����A���̏�̒f�R���i�̊⌊�ɂ̓P�C�}�t���A��I�ɂ̓E�~�K���X�A�����āA�f�R�㕔�ɋ߂��Ζʂɂ̓E�g�E�A����ɒf�R�ŏ㕔�̎Ζʂ�n�ɂ̓E�~�l�R���c������̂��������B������Q�l�ɂ��Ȃ���A��ʂ肻�̐��ݕ����̖͗l�߂Ă݂����Ɩ]������`���ƁA�f�R���ʏ�̂�����Ƃ���ɁA��т܂������H���x�߂��肵�Ă��閳���̒��e��F�߂邱�Ƃ��ł����B�����A�f�l�̖ڂ������Ă��ẮA�E�~�l�R�̉c���n���̂����A�ڂ������ݕ����̏��m�F���邱�Ƃ͍�������B
�@ �ώ@�ɂ���́A���݂ł͍����B��̃E�~�K���X�̔ɐB�n�ɂȂ��Ă���J�u�g���]�ނ��Ƃ��ł������A�����ɂ̓J�������E�~�l�R�Ǝv���钹�̎p�������邾���ŁA�̐S�̃E�~�K���X�̎p�炵�����̂������o�����Ƃ͂ł��Ȃ������B���܂ł̓E�~�K���X�̎p������ɂ͊ό��D�ŊC�ォ��A�v���[�`���Ȃ��Ɩ����Ȃ悤�Ȃ̂ŁA�E�~�K���X�����̓E�g�E�̋A�����i�̌����Ƃ��킹�Ď��̋@��̊y���݂Ƃ���ق��Ȃ������B
�@ ����͎��]�Ԃł̎��V�H����ƂȂ������A�V�����̍��s�Ȓf�R����A����������Ă���C���̎p��D�ォ��ԋ߂ɒ��߂���A����͂���ł܂��f���炵�����Ƃ��낤�B�����Œm����o�t���E�j�̋��l���ɂ����鎵�����ɓ��ɔ��܂�A��i�Ƃ��Ė��������̊C�̍K�̖����y���ނ��Ƃ��ł���Ƃ������̂��B�`���n���Ɏ��Ă��邽�ߕs���_�Ȗ��������Ă��邪�A�C�̃_�C���Ƃ��̂���邱�̃E�j�͕����ʂ�k�̊C�̕�ł���B
�@ �]�k�ɂȂ邪�A�C���ώ@�ɂ��玩�]�Ԃ̒u���ꏊ�ɖ߂����Ƃ���ŁA���͈�u���Ȃ��Ă��܂����B�����炳�����Ă����]�Ԃ̌���������Ȃ��������炾�B�����ł��Ȃ��悤�Ȃ�A���]�Ԃ���u�����܂ܓk���ō`�܂Ŗ߂邵���Ȃ����A���㏈���Ȃǂ����邩��A��̃t�F���[�ɂ͂ƂĂ��Ԃɍ��������ɂȂ��B���R���Ɉꔑ������Ȃ��Ȃ邪�A���A��̂���ł���Ă�������A���H�̃t�F���[��ɏ����]�邭�炢�̂��������������킹���Ȃ������B�H�y�`�Ɏc���Ă����Ԃɖ߂�ʂ�����A�h����͂��납�A�����������ُ̕��ゾ���ĕ��������ɂȂ��L�l�������̂��B
�@ ���߂Ēn���̎Ԃł��ʂ��Ă����A�������������]�Ԃ��ƍ`�܂ʼn^��ł��炤�Ƃ���������������A�Ȃ������̎��ɂ������Ă͒ʍs�Ԃ̉e�������Ȃ��������A���Ɋό��q�̎p����������Ȃ������B��ނȂ����́A�����ɂ��ĎO�S���[�g���قǂ��鎩�]�Ԓu��ƊC���ώ@�ɂƂ̊Ԃ̏������A�����ɖڂ��Â炵�Ȃ����x�����������B�����A����ł������������͌�����Ȃ������B
�@ ��������͓r���ɕ�ꂩ�����̂����A�K���A���̎��A��̍��L�Əo�������n�_�ŁA�|�P�b�g����y�������o���A���������~���ă������Ƃ������Ƃ��v���o�����B�����ɂ��̒n�_�ɖ߂�A���̂�������悭�T���Ă݂�ƁA�Ă̒�A���[�̑��ނ�ɗ����Ă��錮�����������B�{�[���y�������o�����Ƃ��A�ꏏ�Ƀ|�P�b�g���炱�ڂꗎ���Ă��܂����̂��낤�B
�@ �ق��Ƃ����C���Ŏ��]�Ԓu��ɖ߂������́A��}���ŃT�h���Ɍׂ�ƕ��ɏ���Đ����悭����o�����B���łɓ��������W�ŁA���������������ǂ����ɕς���Ă������炾�B���܂��ɁA���V�H�̍ō��n�_��ʉ߂��Ă���͓��������ɂȂ��āA�X�s�[�h�͂���オ�邢���ۂ��������B�������ŁA�O�L���قǂ�������Ă��Ȃ����̃r���[�E�|�C���g�A�ω����W�]��܂ł͂قƂ�ǎ��Ԃ�������Ȃ������B
�@ �ω����̓W�]�䂪�߂Â��ƁA���H��ʂ��܂��^�����ɕϐF�����B�Ԋ�W�]��t�߂̓��H�ȏ�̔����ł���B��������グ��ƁA�b�����������Ȃ��������Ă��锒�����̎p���������B���͖����ɂ����̒��̕��Ǝv������̂܂ł����~���Ă����B���̗l�q���炷��Ƒ����Ȑ��̊C�������̈�тɐ������Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ������B
�@ �ω����W�]��Ɉ�����ݓ��ꂽ���́A�z����₷���O�̌��i�ɂ����킸����ۂ݂��̂܂ܗ����s�����L�l�������B�E�~�l�R�A�E�~�l�R�A�E�~�l�R�A�����Ă܂��E�~�l�R�c�c�A�V���n���A�����ʂ�E�~�l�R���炯����������ł���B����Ȑ��܂������̊C��������܂Ō������Ƃ͂Ȃ������B�q�ǂ��̍��A�����̏����ȓn�蒹������ȍ��_�̂��Ƃ��Q���Ȃ��ĊC���n���Ă����̂����x�ƂȂ��ڌ��������Ƃ͂���B�������A�ԋ߂ł���ȓr�����Ȃ����̑�^�C���߂�̂͏��߂Ă̂��Ƃ������B����́A�ǂ����q�b�`�R�b�N�̖���u���v�̐��E�����A�z������A���ɋ����ׂ����i�������B
�@ �W�]��̎萠��ɂ͐g�̂������悤�ɂ��ĎO�A�l�\�H�̃E�~�l�R�����������ƌ�����ׂĂ����B�����āA�����������܂ŋ߂Â��Ă������͓����悤�Ƃ����Ȃ������B�ቺ�͂邩�ȊC�ʂ��琁�グ�Ă�����y�����Ȃ��Ȃ���A�܂�Ń��Y���ł��Ƃ邩�̂悤�ɑ̂������݂ɗh�炵�Ă���B�{�̐�͏㉺�Ƃ��ԍ���F���я�ɕ������ɂȂ��Ă���A��[�����̂����Ă͍����܂ʼn��F�����Ă���B�^�����ȓ����̚{���ɂ��闼��͉��F���s���L�̖ڂ�������ŁA�{�̐�Ɠ��l�̐ԐF�ɉ��ǂ��Ă����B���̑��݂Ȃǂ܂�ňӂɉ�Ă��Ȃ����̂悤�ɁA���炷�����̎萠��Ɍ������Ĕ�э~��Ă���E�~�l�R���������B
�@ ����Ԃ̖��т̍L��ȎΖʂ́A�㉺���E�Ƃ����n��������E�~�l�R�����̃R���j�[�ɂȂ��Ă����B�W�]��̂������̃G�]�X�J�V������G�]�J���]�E�Ȃǂ̉ԁX�̊Ԃɂ́A�̂��B���ł����邩�̂悤�ɍ��荞�݁A��悾�����o���Ă�����̗l�q���M�������̃E�~�l�R�����̎p���݂�����ꂽ�B�����������痑�ł����߂Ă����̂�������Ȃ����A���̓_���͂�����Ɗm�F���邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B���܂�������I��ł��̓W�]���K�˂�A�e�������ɋ��a����l�q��A���������������Ă������i�Ȃǂ��A�������炶���Ɍ��w���邱�Ƃ��ł���̂��낤�B
�@ �悭�ʂ�b���������ɗU���A���炽�߂ċɖڂ�]����ƁA�����ɂ���̂͂���܂��E�~�l�R�����̕���������s��Ȑ��E�ł������B�C�H�R�̎Ζʉ����Ɍ��������グ�钪���ɏ���Ď��R�z���ɔ��Ă��������邩���̎p�́A���̓��̓V�����߂���̃t�B�i�[���������Ă����ɗ]�肠����̂ł������B���͂ЂƂ�W�]���ɘȂ݁A���̊����I�Ȍ��i�ɂ��܂ł������ƌ������Ă����B
�@ �E�~�l�R�͎G�H���ŁA�C���V��C�J�i�S�Ȃǂ̏����ށA�I�^�}�W���N�V�Ȃǂ̗����ޖ����ځA�����ށA�l�̎̂Ă��c�тȂǂ�H�ׂ�Ƃ����B���͍D���ł͂����Ă��A�����͐����̊l�����Ƃ邱�Ƃ͏�肭�Ȃ��B������E�g�E�Ȃǂ̎����A��l����D�����������킯�����A���X�����߂�������ȍs�ׂ����R�̐ۗ��̓����Ƃ���䂦�A��ނ����Ȃ����Ƃł͂���̂��낤�B��X�l�ނ̋Ɉ��Ԃ�ɔ�ׂ�A���������R�̒��Ō����ɐ�����E�~�l�R�̈����Ԃ�ȂǑ������������̂ł���B
�@ �V�����ɂ͐����H�̃E�~�l�R���������Ă���悤���B�V�����̃E�~�l�R�ɐB�n�̒��S�n�́A���Ă͐Ԋ�t�߂���C���ώ@�ɂ̂��邠����ɂ����Ăł������̂����������A���݂ł͂��̊ω�����тɈ��R���j�[���`�������悤�ɂȂ����̂��Ƃ����B�Ȃ��R���j�[���傫���ʒu��ς��邱�ƂɂȂ��Ă��܂����̂��ɂ��ẮA���܂��ɂ��̌����͂悭�킩���Ă��Ȃ��炵���B�V�����ŔɐB�����E�~�l�R�����K���Ɉړ����A�����ŔɐB���Ă��邱�ƂȂǂ��m�F����Ă���悤���B
�@ �\�肪���������A�ꎞ�͂ǂ��Ȃ邩�Ǝv�����V�����߂��肾�������A�K���A�A��̃t�F���[�̏o�q�����܂łɂȂ�Ƃ��V���`�ɂ��ǂ�����Ƃ͂ł����B���R�̐���s���ŁA���H�����͌����ɋy���A�r���Ő���t���ނ��Ƃ��������Ȃ����s�R�ƂȂ��Ă��܂������A�L��]��قǂ̔���������ɂ��߂��舧���A���ɑf���炵���T�K�ł͂������B
�@ ���x�V������K�˂�Ƃ��ɂ́A�E�g�E�̋A�����i���ώ@���A�V���D�ɏ���ē��̏ے��̐Ԋ��A�킸���Ȃ���E�~�K���X�̐��ނƂ����J�u�g��Ȃǂ��C�ォ�璭�߂Ă݂����A�����ē��̐l�X�̐l��ɂ��G��Ă݂����\�\����ȑz�������[���ɔ�߂Ȃ���A���͉H�y�`�������I���������̃^���b�v��������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N8��29��
�k���S�i�E�@�J��
�@ �r���ł��������Ɋ�蓹���������߁A�@�J���ɒ������̂́A�J�[���W�I����ߑO�뎞�̎������̂Ƃقړ����������B���{�Ŗk�[�̏@�J���́A�n�`�I�ɂ݂Ă��A������̕��͋C���炵�Ă��A�ǂ��������I�ł܂�₩�Ȋ����̂��閦�ł���B�_�Ж���m�����A���邢�͔[���z���Ƃ������悤�Ȗk�C���̗L���Ȗ��Ƃ͂��̓_�Ŏ���قɂ��Ă���B����тɂ͍L�����ԏ���݂����Ă��āA��Ԃł����X�ƏƖ������Ƃ����Ă����B
�@ �����ɂ�����܂ł̓�\�l���ԂƂ������́A���s�Ɏ������s�̘A�����������߁A�������ɔ�J�̓x�����͋Ɍ��ɒB���Ă����B���ԏ�̈�p�ɒ��߂����S���́A���X�Ƃ����������ĂĐ����܂���җ�Ȑ����ɐ���ꂮ�炮��Ɨh��Â������A����Ȃ��ƂȂǂɂ����܂��Ȃ��A���ɂȂ����r�[�[������ւƗ����Ă��܂����B
�@ �����͋㎞���ɖڂ��o�߂��B�Ȃɂ��吨�̐l�̋C�z���������炾�B�Q�ڂ���Ŏԑ��z���ɊO�߂�ƁA���Ԃ�̐_�`�������A���̂܂����⑾�ۂł����߂����Ղ�̍s�A��������ʉ߂��Ă����Ƃ��낾�����B��ɂ͖��_�ЂƂ������������߂��Ă�������A�߂��ɂ���Ȗ��̐_�Ђ�����̂��낤�B�@�J���̂������ɂ͑喦�Ƃ������Ȃ�傫�ȏW�������邩��A���Ղ�ɎQ�����Ă���̂͂����ɏZ�ސl�X�ɈႢ�Ȃ��B�S��������Ƃ���ɐ_�Ђ͑��݂��Ă��邩��A�@�J���ł���Ȃ��Ղ肪�������Ƃ��Ă��ׂɂ��������͂Ȃ��̂����A���l�̖ڂ��炷��ƁA���{�Ŗk�[�̖��Ō���_�`�⑾�ہA����ɂ͛�̍s��Ƃ��������̂͂Ȃ��s�v�c�Ȋ����̂�����̂ł͂������B
�@ ���قǂ̗ł͂Ȃ��������A����тɂ͑��ς�炸�����������������Ă����B�Ă��Ƃ����̂ɕ������\�₽�������B�V��̗ǂ����Ȃ牓���T�n�����̓��e�Ȃǂ��]�ނ��Ƃ��ł��邱�̖������A���̓��͂قƂ�ǓW�]�������Ȃ������B���̂����������Ă��낤�A���X�ɖ���K���ό��q�����́A���{�Ŗk�[�̒n������킷��̑O�ŋL�O�B�e���I����ƁA�F�����ɗ��������Ă������B
�@ ���Ȃ݂ɏq�ׂĂ����ƁA�u���{�Ŗk�[�̔�v�͖k�ɐ��̈ꈻ���C���[�W�����O�p���l�̍\�����ŁA�܁E�l���[�g���قǂ̍���������B��̒����ɂ͖k���Ӗ�����m�̕������z����Ă���A���̐ݒu�n�_�̈ܓx�͖k��45�x31��14�b�Ȃ̂��������B�����Ƃ��A�����k���l���̕Ԋ҂���������A���{�Ŗk�[�̒n�Ƃ����L���b�`�t���[�Y�́A�𑨓��̐��k�[������ɒD���Ă��܂����ƂɂȂ邾�낤�B���̎���������A�u���{�{�y�Ŗk�[�̒n�v�Ɓu�{�y�v�̓���t�������˂Ȃ�Ȃ��Ȃ�ɈႢ�Ȃ��B������Ƃ����āA�܂����A�@�J�n���̐l�X���k���̓y�ԊҔ��Ή^���Ȃǂ��N�������肷�邱�Ƃ͂Ȃ����낤���A�u���{�Ŗk�[�̒n�v��𑨓��ɂƂ��Ă�����邱�ƂɂȂ�A�ό��X�|�b�g�Ƃ��Ă̏@�J���̑��݈Ӌ`�͂����Ԃ�邱�ƂɂȂ邾�낤�B
�@ ���͊ό��ړI�ł��̖��ɂ���Ă����킯�ł͂Ȃ������B�t�����o�ē��{�C������I�z�[�c�N�C���ɔ�����r���ŁA����܂ʼn��x�����̖��ɂ͗���������Ƃ�����B������A���{�Ŗk�[�̒n�ɑ��Ղ��Ƃ����i�ʂȑz�������߂Ă��̖���K�˂��̂ł͂Ȃ������̂��B�킴�킴�������ď@�J���ɂ���Ă����͕̂ʂɖړI������������ł���B
�@ �\���N�O�ɂ��܂��܂��̏@�J����K�˂����̂��ƁA���͖��̂������ɂ���o�����Y�̋������ŔR����⋋�����B���̐܁A����̑�����x�����ƁA���܂��܉����Ă��ꂽ�Ⴂ�����W�����̎��ƂƂ��Ɉ�̎萻�̂�������n���Ă��ꂽ�B�z�^�e�������̏����ȊL�k����킹�č�������킢�炵�������ŁA�L�k�̓����ɂ͎菑���̕����Łu��ʈ��S�v�̎l�����Ƃ��̓��̓��t�Ƃ��L����Ă����B�܂��A�L�k�̕\���ɂ͏@�J����\�킷�V�[���Əo�����Y�̃A�|����̃}�[�N�Ƃ��\���Ă������B�ǂ���炱�̋������ŋ����������q�Ɉ�����̂�������n���Ă���炵�������B
�@ �Ⴂ�����玄�͂����Ƃ������̂������Ȃ���`�̐l�Ԃ������B������_�Ђ₨���Ŕ����Ă��邨���Ȃǂ��Ԃɂ������Ƃ͈�x���Ȃ��B�l���炨�y�Y�ɂ�������������肷��ƁA����̍D�ӂ͗L�����A�����A���̏����ɋ�J���邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ������B�Ƃ��낪�A���Ƃ��������Ƃ������A���̎�����������̊L�k�̂���肾���́A���C�Ȃ��^�]�ȍ������̃`���[�N�����m�u�ɒ݂艺����ꂽ�̂����������ŁA���������ƈꏏ�ɑS���𑖂��邱�ƂɂȂ��Ă��܂����̂������B
�@ ������܂߂������̑S�s���{����]�����ƂȂ��ʉ߂��I����������̂������A�܂�����̃K�\�����X�^���h�ɕԔ[���悤�ƁA���͂Ȃ��炭�@����M���Ă����̂������B���ɕЕ��̊L�k���������Ă��܂������̂�����V�������̂ƌ������Ă��炨���Ƃ����v�����������B�l�A�ܔN�O�ɂ���x�@�J����ʉ߂����̂����A�����ɂ��[��̂��ƂƂ����ăX�^���h�͕��Ă���A���̎��ɂ͕Ԕ[�͂Ȃ�Ȃ������B
�@ ���c�Ζ��X�o�c�̏o�����Y�@�J���������ɎԂ��������ƁA�����ɎႢ�����̌W�������ꂽ�B�y���^���ɂ��Ă����悤�Ɉ˗����A�^�]�Ȃɍ������܂��͖ق��č�Ƃ��I���̂�҂����B�������I��藿�����x���������ƁA�̂Ƃ��Ȃ��悤�Ɏ萻�̊L�k�̂�����̎����Ƃ��ǂ���n���Ă������̂��ǂ����m�M�͂Ȃ������B���ꂩ��\���N���o���Ă��邱�Ƃ�����A���ς���Ă��Ă����������Ȃ������B�����A���c�Ζ��X�������X�̖����̂̂܂܂������̂ŁA���҂͂��Ă�Ɠ��S�ł͎v���Ă����B���R�����A���c�Ƃ������́A�k�C������s�o�g�̎��̉Ɠ��̋����Ƃ��Ȃ�����������A���c�Ζ��X�Ƃ����X���͏\���N�o�������܂��͂�����Ɖ����Ă����̂ł���B
�@ �͂��߂Ă��̃X�^���h�ŋ��������Ƃ��͊m���J�[�h�Ŏx�������ς܂���������ȁA�ȂǂƂ����ǂ��ł��悢���Ƃ�z���o���Ȃ��猻���ő�����x�����ƁA��������X���ɖ߂��������W���́A�̎����₨��ƈꏏ�ɁA�ꖇ�̃J�[�h�ƈ�̏����ȊL�k�̂�������ɂ��Č��ꂽ�B�Z����\�l���Ƃ������t�X�^���v�̉����ꂽ�u���{�Ŗk�[�����ؖ����v�Ȃ�L�O�J�[�h�ƂƂ��ɁA�̂Ȃ���̊L�k�̂�����ޏ�����n���Ă��ꂽ�Ƃ��A���͓��S���t�ɂ͌����s�����������������o�����̂������B
�@ ��������������Ȃ��炨�������������́A�Е��̊L�k�̌��������Â��������͂����Ă����ނ�ɌW���ɍ����o���ƁA���̓��킴�킴���̋�������K�˂����R���������B�����āA���Q���Ă��Ă����ْ��u���ł̗��H�v�̒��́A���̋������ɂ��ďq�ׂ��ꕶ���w�������Ȃ���A���b�����Ȋ�������鑊��ɁA�����Ɏ���܂ł̏ڂ����������������B�قǂȂ����Ď��̐^�ӂ̂قǂ��@�m���Ă��ꂽ�W���́A�V���������ƈ��������Ɏ��������o�����Â����������������Ă��ꂽ�B
�@ �V���ɂ�����������������`���[�N�����m�u�ɂ��I�������́A�������ɕʂ��������ƁA�������@�J�u�˂Ɍ������đ���o�����B����Ȏ��̔]�����A���̐V��������肪�S�s���{����ʉ߂��I����̂͂������������̂��ƂɂȂ邾�낤���Ƃ����v�����悬���Ă������B
�@ �@�J�����ԏꂻ�̍⓹�����A�W�]����@�J������̂���ꏊ��ʉ߂��Ăǂ�ǂւƑ����Ă����ƁA���l����̂т铹�H�ƍ�������B�����ō��Ƀ��[�g���Ƃ�ƁA�L��ȋu�˒n�т����ꂽ�B�������Ɣg�ł����˂�悤�ɂ��āA��ʎᑐ�ɕ���ꂽ�ɂ₩�ȋu�˂������l���ɍL�����Ă���B
�@ �@�J����K�˂�l�͏��Ȃ��Ȃ����A���̏@�J�u�˂ɂ܂ő����^�Ԑl�͈ӊO�ɏ��Ȃ����A���������قƂ�ǂ̐l�͂��̖��������m��Ȃ��B�����A���Ă̍��ɂȂ�Ƃ��̋u�ˈ�т͗̓V���Ɖ����B�q���n��앨���̍L����u�˂Ƃ����A�x�ǖ�̘[������l�̋u�˒n�т��L�������A�w�i�ɏ\���x�̂悤�ȍ��R�͂Ȃ��ɂ��Ă��A�L���Ɣ������ɂ����Ă͂��̏@�J�u�˂������ɂЂ����Ƃ�Ȃ����낤�B�u�˒n�т̂͂邩�ޕ��ɐ��P���I�z�[�c�N�C��������̂��Ȃ��Ȃ��ɂ����B
�@ ���������镗�̋����͑��ς�炸���������A�z�˂͖��邭�A�̋u��J�Ԃ̐D��Ȃ��ɂ₩�ȋN��������悤�ɂ��āA���_�̉e�����X�ɒʂ�߂��Ă������B���̃��Y���ŕ��ɔg�ł��h���q���̂��炩�ȋP���������������B���͎O�S�Z�\�x�̓W�]�̂������݂ɎԂ𒓂߁A���炭�ቺ�ɍL���钭�]���y���B
�@ �k�C���̖q��n�тƂ����ƁA�����ɒN�����z������͓̂����̎p�����A���̏@�J�u�˂̌��i�͂��̓_�ł�������Ƃ���قȂ��Ă����B�L��ȑ����ɕ��q����I�R�Ƒ���H�ނ̂́A�����܂���͗l�̓����ł͂Ȃ��A�S�g�����тŕ���ꂽ�a�������ł������B�m��l���m��@�J�a���͍��т��邢�͒��т̓����ł���B�_�X�Ǝl���ɎU�݂��鋍�����̍����e�́A�k�ӂ̒n�ł���ɂ�������炸�A�̖�R�ƕs�v�c�ȂقǂɃ}�b�`���Ă����B
�@ �قǂ悢�A�b�v�_�E�����J��Ԃ��Ȃ���L�����R���v�����܂܂ɋ킯�߂���A���X�����P���̉đ��������܂ŐH�ނ��Ƃ̂ł��邱�̋G�߂��A�������������Ȃ��搉̂��Ă͂���̂��낤�B���̌Q�̒��ɂ́A�܂����܂�ĊԂ��Ȃ��q����A��Ă�����̂����Ȃ��Ȃ������B�܂��������܂��H�ނ��Ƃ̂ł��Ȃ�����Ȏq�������́A�ꋍ�ɂ�����悤�ɂ��Ă��̌��ǂ��A���܁A���[�����킦�ẮA���g�����悤�ȕ\����ׂ�����Ă������B
�@ �㉎�����ʂւƌ������ċu�˒n�т�D�����H�́A��������ď\���L���قǑ����Ă����B���S�ܑ����ꂽ�f���炵�����H�ŁA�q��n�т��߂���ƁA���ӂ̌i�ς͔�����u�i�A�ڈΏ��A�����Ȃǂ̗т̍L����V�R�̍������ётɕς�����B���H�̕������̂����Ă͐l�肪�قƂ�lj������Ă��Ȃ��Ƃ��낾���ɁA��{��{�̎��X���ꂼ�ꂪ�A�s����̂��Ƃ̂Ȃ�������B����߂Ă���Ƃ��������������B
�@ �\���L���n�_�����͓��H���������̂��ߌ�ʎ~�߂ɂȂ��Ă���A���ɔ��������Ȃ������̂ŁA��������܂��@�J�����ʂւƈ����Ԃ���������Ȃ������B�����āA���̗��h�ȕܑ����H���������Ă̋A�蓹�A���������Ǝ��͂�����҂蕡�G�ȋC���ɂȂ����B�ԂŖk�C���̗��𑱂��鎩���ɂƂ��āA����Ȃɂ����R�Ɍb�܂�A���������K�Ȃ��Ƃ��̂����Ȃ����H�̑��݂͗L���������A������ł͊�ׂȂ��Ƃ����v�����킢�Ă�������ł���B
�@ ���̂悤�Ȑ����̍s���͂������H��V���Ɍ��݂��A���̈ێ��Ǘ���I�m�ɂ����Ȃ��ɂ͑�ςȔ�p��������B�l��̂͂����Ă��Ȃ��Ƃ���ł������قǂɁA���H���݂ɔ������R�j����������ď��Ȃ��Ȃ����낤�B����قǂɂ��đ��������H�̗��p�x���ǂ̒��x�̂��̂ł��邩�����ƂȂ�B�������������_����l���Ă݂�ƁA���܂������Ď������C�����悭�����Ă��铹�����ċc�_�̗]�n���Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B���G�ȋC���ɂȂ����̂͂���Ȃ��Ƃ��l�������炾�����B
�@ �s�K�v�ȓ��H�̌��݂Ɉًc��������l�X�ɑ��āA���H���ݎ^���̐l�X����u���H���ł�����Ȃ��������Ēʂ邶��Ȃ��ł����H�v�Ƃ������_���Ȃ���邱�Ƃ��悭���邪�A�m���ɁA�l�ԂƂ������͕̂֗��ɂȂ�Ƃ������֗̕����ɂȂ�Ă��܂��Ƃ��낪����B�ǂ��܂ł��K�v�łǂ��܂ł��s�K�v���̓I�m�Ȕ��f�́A�������ėe�Ղɉ�����悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�s�v�ȓ��H�̌��݂������Ƃǂ߂�ɂ́A��X���g�ɂ�����Ȃ�̗��O�Ɗo��̂قǂ��s���ƂȂ낤�B
�@ �@�J�a���̖q��n�т�������x�ʂ蔲�����l�ւƌ������r���ŁA���Ȃ萬�������q����������������������ɏW�߂��Ă���Ƃ���ɏo���B�������e��������������ꂽ�������A�߂������Ȗ����������Ă���q��������B����ɉ����ł����邩�̂悤�ɉ�������e���̖����炵�����̂��������Ă����B
�@ �_�k�p�����˂��a���̂��������Ă������ň�������ɂ́A�����ɂ��̈Ӗ����ǂݎ�ꂽ�B����Ƃ͒m�炸�e���ɂ��Ĕg�~��܂ōs�����q�����A�L�������킳���e���������������A�N���[���ɒ݂��ꎟ�X�ɑD�q�ɐςݍ��܂�镗�i�N�̂悤�Ɍ��Ă�������ł���B�ߖɋ߂��������グ�Č݂��ɌĂэ����e���Ǝq���̔߂����Ȏp�́A�܂��c���������̋��ɐ[���Ă����ė���Ȃ������B
�@ �Ƃ��̕��@�����Ⴄ���̂́A�e��������������ꂽ���̎q���������A�قǂȂ������ւƏo�ׂ���Ă������낤���Ƃ͖����������B�܂�����䂦�ɁA����̉^����m���Ă��m�炸���A�v���������̊i�D�Ŏᑐ��H�݁A���邢�͐Q���ׂ��Ă܂ǂ�ގq�������̎p���A�Ȃ�Ƃ����Ƃ��������ɔ����Ă���̂������B���B�̂��߂ɖq��Ɏc�����q���Əo�ׂ����q���Ƃ̑I�ʂ����R�����Ȃ��Ă���̂��낤���A�o�ׂ����͈̂��|�I�ɗY���������ɈႢ�Ȃ��B���ƂɎc�����ɂ���A�����łȂ��ɂ���A�a������܂����������o���Ȃ������ɉ^���̊�H�ɗ��������q�������̕��ޓ��́A�z���ȏ�ɉߍ��Ȃ��̂Ȃ̂��B
�@ �����������������Ɉ��A���l�̖ڂɂ͗̊y���ɂ������f��Z���̂��̖q���тŁA�Â��ɂ������m���ɋ������̔ߌ��͐i�s���Ă����B������H�̐��E�̏킾�ƌ�������܂ł̂��Ƃł͂��������A���Â��l�ԂƂ͋Ƃ̐[�����݂ł���Ǝv�킴������Ȃ������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N9��5��
�k���S�i�E�T���x�c����
�@ �[���ɒt���𗧂��A�O��k�サ���I�������X�����A����ǂ͋t�ɃT���x�c������ʂɌ������ē쉺�����B�嗱�̉J�ƊC���܂݂̖җ�Ȑ������������Ă������߁A���E�͋ɓx�Ɉ��������B�E��Ɉʒu���Ă���͂��̓��{�C�◘�K���̓��e�͂ނ��A���H�̂��������ɎU�݂��鎼�n�т�Ώ��n�Ȃǂ��قƂ�nj����Ȃ������B����ł��A�r���ŎԂ��߃J�b�p�𒅍���œ��[�ɗ��ƁA�₽���J�ɂ����ꌃ�������ɗh��Ȃ�����炫�����A���F���G�]�J���]�E�̉ԁX���ڂɔ�э���ł����B
�@ �����Ԃ�̂ɏ��߂ăT���x�c�����K�˂��Ƃ��A���́A�L��Ȏ����̉ʂĂ�Ƃ���܂ň�ʂɍ炫�ւ�G�]�J���]�E�̉Ԃ����āA
�@�@�@�ԁX��G���炫���ԉc�݂��ьo����T���x�c�̖��
�Ƃ��������r�B�k�̑�n�̌����������ނ��뗘���邪���Ƃ��ɍ炫���сA�͂邩�Ȏ����A�c�X�Ǝ���̎�����`���Ă������̎p�ɐS��ł��ꂽ���炾�����B
�@ �������A���̓��͂Ȃ����A�Ⴆ��C���ɂЂǂ���������Ȃ���������ς��E�сA�f���Ă��̕i�i���������ƂȂ��A�B�R�Ƃ��č炫�J����ւ̃G�]�J���]�E�̂������܂��ɋ����S�䂩�ꂽ�̂������B���̉Ԃ̂��Ȃ��Ȏp�ɁA���͂����̏����̂��Ȃ����s�v�c�ȋ����̂��������d�ˌ������炾�낤�B
�@ �s��Ɉ炿�A�s��ł̒��N�̐������o�����Ƃʼn������ꂽ�ً��̗����ɓn��A�܂��c���������𒆊w���ɂȂ�܂ň�ďグ�A���������ƗB��̓��e�Ƃ��Ďc���ꂽ���ɂ��炻��������邱�ƂȂ��A�Ƃ茈�R�Ƃ��Đ������c��̋��������̂ЂƂ������B�܂��A�������s�ŋ�w�����������Z����A�����b�ɂȂ��Ă����o�C�g��ŏo�����A�l�X�Ȃ��Ƃ��������Ă����������ΐ���]�q�搶�́A�C�i�ɖ����A�����������Ȃ鎞�ł��B�R�Ƃ��Ă�܂Ȃ��p�Ȃǂ����̓��G�]�J���]�E�̉Ԃ̌������ɏd�ˌ������̂̂ЂƂ������B
�@ ���N���łɋ�\�O�̐ΐ�搶�́A�܂��S���I�ɏ����̎Љ�I�n�ʂ��Ⴍ�}�����A�Ȃ��j���v�z�̐F�Z���c���Ă�������ɁA�����������̑S�����w�Z��ʂ��A�����Ƃ��ď��߂ċ����E�ɏA���ꂽ���ł���B�n���ɂ����ẮA���܂��܂Ȕ�排��������̂Ƃ������A����҂Ƃ��đ����̗D�ꂽ�l�ނ𐢂ɑ���o���ꂽ���ƂŒm���Ă���B�搶�͎Ⴂ���������A�������E�𗣂�Ė��B�ɓn��ꂽ���A���̒n�Ō��l�Ǝ��ʁA�h�_�̋ɂ݂��r�߂�������ɏI���Ȃ�Ƃ��������ɋA�҂��ꂽ�B���Ă���قǂȂ������Ƃ��ĕ��E�Ȃ���A�č����邱�ƂȂ����̌�̐l�����Ђ����狳��Ɍ�����ꂽ���ł���B�ٍ��̒n�ŋꋫ�ɂ���������A���B�̖�ɍ炭���Ԃ߂Ȃ��玩���̌ǓƂȐS���܂����b�Ȃǂ���X�f���Ă����̂ŁA�悯�����͕��ɗh���G�]�J���]�E�̌������ɐ搶�̎p��z�������ׂ��̂ł��낤�B
�@�@�@������k�̕l�ӂɗ����h�炮���ׂ��Ԃ���͋���
�@ ����ł͂��邪�����̑z�����̂܂܂��̂ɉr�ݍ����́A�ĂюԂɖ߂��đ���o���ƁA�t����ō��܂��T���x�c�����ԉ��̒��S���ւƌ��������B�����܂��܂��V��͈������A�[�ł��[�܂��Ă��Ă����̂ŁA���̂܂ܖL�x������ʂւƒʉ߂��邱�Ƃɂ����B�����Ă��̎��A���܂��܂Ƃ����ɂ͂��܂�ɂ��^�C�~���O���悷���邭�炢�ɁA�J�[���W�I����A�F��̎��l���q�݂����̎��̘N�ǂ�����Ă����B�܂�ł��̎��̓T���x�c�̖����ʂɕ��������̑��ԂɌ������ĐX�ƌ�肩�����Ă���悤�ł��������B
�\�\��������m��ʑ��̎q���A�Ȃ�疜�̑��̎q���A�y�͂ЂƂ�ň�Ă܂��B����������������������A�y�͂�����Ă��܂��̂Ɂ\�\����́u�y�Ƒ��v�Ƃ������ł��������A�Ղ�������ǂ��[���S�ɐ��ݓ���V�ˎ��l�Ȃ�ł͂̌��t�g���Ƃ��̐▭�ȃ��Y���ƂɁA���͎v�킸���������Ă��܂����̂������B��X������҂́u���͂Ő����Ă���v�̂ł͂Ȃ��u�ڂɌ����ʂ��̗̂͂Ƃ��̋]���Ƃɂ���Đ�������Ă���̂��v�\�\���t�ɂ���ƂȂ�Ƃ������ȕ\���ɂȂ��Ă͂��܂��̂����A���ɂ͋��q�݂����̐S�̉��̂���Ȑ^���ȋ��ѐ������܂ɂ��������Ă������ł������B
�@ �T���x�c�����������ƁA���������Ȃ��Ƃ���ɂ���L�x����ɗ����A���c�̉���{�݂ňꕗ�C���т��B�����čĂуn���h��������ƁA�y�������o�č����l�\���ɓ���A�Ђ�����铹����[�����ʖڎw���đ���o�����B�ߌ�㎞�����������낤���A���Ўq�{�ɍ��������鏭����O�Ŏ��͑O���H��ɓ����̎��̂炵�����̂��]�����Ă���̂����A�����ɎԂ��߂��B�Ԃ���~������d���������ċ߂Â��Ă݂�ƁA����͂܂������݂̎c��L�^�L�c�l�̎��̂������B�����ƕ����Ƃ��Ԃ�瀂���A�����j��ő����������̂炵���B�ڂƓ�������яo���A��������c�Ȏp�ł������B
�@ ���̂܂܂ł͉��z�Ȃ̂ŁA������͂�ő̂��ƂԂ炳���A���H�e�̐[�����ނ�܂ʼn^�B�����ăX�R�b�v�����o�������@��ƁA���ɂ��Ȃ��얳����ɕ��ƐS�̒��řꂫ�A������킹�Ȃ���A���̃L�c�l�̍���Â��ɒ��������Ă�����B�얳����ɕ��ł͂Ȃ��얳���@�@�،o�ƙꂱ���ƁA�\������ăA�[�����Ə����悤�ƁA���邢�͂܂���炵�����Ɠ��炵�Ĉ����낤�ƁA���L�c�l���]�ނȂ炱����Ƃ��Ă͂ǂ̕��@��I��ł��\��Ȃ������̂ł͂��邪�A�����ɂ����ɂ͓��̃L�^�L�c�l�̐M���ǂ̂悤�Ȃ��̂ł������̂��Ȃǒm�邷�ׂ��Ȃ������B������A�����Ƃ������葁���i���A�~�_�u�c�ōς܂����悤�Ȃ킯�������B
�@ �Ăщ^�]�Ȃɖ߂������́A���Ўq�{���߂���ƁA���[���܂ł������ɍ����l�\������쉺�����B�����āA�u�тӂ��v�ƕ\�����ꂽ���̉w�ɎԂ𒓂߂�ƁA�����Œ��܂Ŗ��邱�Ƃɂ����B���傤�ǂ��̍��A�������s���̂���a�@�̈ꎺ�ŋN�����Ă������ԂȂǐ_�Ȃ�ʂ��̐g�͂�m��ʂ��Ƃł͂������B���Ƃ����낤�ɂ��̓��̗[���A�ˑR�Ђǂ��������N�����ċً}���@���ꂽ�ΐ�搶�́A���̕a�@�Ŋ�ď�ԂɊׂ��Ă���ꂽ�̂������B
�@ �̂��ɂ��Ďv���A���������J�ɑς��č炭�G�]�J���]�E�̉Ԃɐΐ�搶�̎p���d�ˌ������ƂƂ����A���܂����ɂ������q�݂����̎��̘N�ǂƂ����A����ɂ͑��₦���L�^�L�c�l�ɑ����������ƂƂ����A���̓��̈�A�̏o�����͂Ȃɂ�����Î��I�ł͂������̂��B�����A�ΐ�搶�͑��E���ꂽ�B�����A�{���̎����̘A���ł��̂��Ƃ����ۂɒm�����̂́A���ꂩ��l����A�܂������k�C���̎R���𗷂��Ă���r���ł̂��Ƃ������B
�@ �����Ƃ̂��ɂȂ��Đΐ�搶�̗{���̕�����f�������ƂȂ̂����A������\�N�߂��O�A�㍂�n�͓̉����Ŏ��Ɠ�l�ŎB�����ʐ^�������茳�ɒu���A��ɂ��Ă��������Ă����炵���B�u�{�c����Ɓv�ƋL���ꂽ���̓̎ʐ^�͂��̌㓌���̎���ɓ͂����A���܂ł͂��肰�Ȃ������̈���ɏ����Ă���B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N9��12��
�k���S�i�E���[����N�ʂ�
�@ �R�x�n�т�D���ē��k���瓹���ւƔ�����r���A���[�������ɂ��鏼�R�����ɗ�������B���Ȃ�R�[���Ƃ���ɂ��钓�ԏ�ŎԂ��~��A��������}�ȎR�����O�\���قǓo��ƁA�W�����㎵���[�g���̎R�㎼���ɒ������B�D�Y���̒n�w����Ȃ鏼�R�����͍����Ŗk�̍��w�����ł���B�J�������������͂ނ悤�ɂ��āA���U��̃A�J�G�]�}�c�Ƒ�U��̃N���G�]�}�c�̍���т��L�����Ă����B�ɂ₩�ȋȐ���`���ĉ����ɐ��ꂵ�Ȃ��悤�ɂ��Ă̂т�G�]�}�c�̎}�U��́A������Ō���Ⴂ�����̌�p���Â���B
�@ �Î₻�̂��̖̂��l�̎����ł́A���₩�ɐ��������镗�̒��ŁA��ʂɍ炫�J�������^�X�Q�������݂ɐk���Ȃ���g�ł��Ă����B���������ȏW���Ԃ������q���V���N�i�Q�������̂��������łЂ��₩�ɍ炢�Ă����B�^�`�M�{�E�V�̑�Q�����ڂɂ������A�Ԃ��炭�̂͂܂����ꂩ��̂悤�������B���ꂱ��ƂƂ�Ƃ߂��Ȃ��z�����߂��炵�Ȃ炪�ؓ��`���ɂ̂�т�Ǝ�����������V�����̏o���n�_�ɖ߂������A���̊ԂɎ�����K�˂ė����l�͑��ɒN�����Ȃ��悤�ł������B
�@�u���R�����v�̈ē��̘e�ɂ͏����ЂƂ������Ă����B�������Z�����ɕ���ꂽ�Ƃ��ȂǁA�U�����̐l�ɏo���n�_�̈ʒu��m�点��ɂ��̏���炵����ł�����̂��낤���B���ɐl�����Ȃ��̂��悢���ƂɁA���͔������̖ؒƂ���ɂ���ƁA��A�O�x�͂����ς��ɂ��̏���@���Ă݂��B�����Đ����̉�����тɋ����n��̂����ɂ��Ȃ���A���Ԃ�A���̎�����K�˂�̂͂��ꂪ�ŏ��ōŌ�ɂȂ邾�낤�Ǝv������������B
�@ ����ȂƂ�������̍ɂȂ��ēƂ�K�˂��ȂǂƂ������Ƃ������̓������ǂ��������m�����肵����A���������Ȃ�Ǝv�����낤�B���������\�����e���̃��N�łȂ��߂��ƍl���邾�낤���A����Ƃ��A�n�R���s�����̂Ƃ������l�ՋH�Ȃ��̔鋫��Ƃ�ŖفX�ƕ��������̈ӋC�ɁA���߂Čh�ӂ̂����炭�炢�͕\���Ă������̂��낤���c�c�B����ȋ��ɂ����ʂ��Ƃ��l���Ȃ���A���������ɔ������炵���S�[���^�`�o�i�̍炭�R�����������Ɖ����Ă������B
�@ ���ԏꂩ��_�[�g�̗ѓ�������ɉ��܂ŋl�߂��Ƃ���ɂ͉J���̑�Ə��_�̑�Ƃ�����̑�Ȃǂ��������B�j���I�ȉJ���̑�܂ł͎Ԃōs�������A���_�̑�܂ł͂������炳��ɌF�ł��o�������M����~�������A���炭�����˂Ȃ�Ȃ������B�������A���̖��̒ʂ�A���_�̑�́A�����⒌��t���w�𗬏��ɂ����ɔ��������炩�ȑꂾ�����B
�@ ���R������т̎U����I�������ƁA���[�����z���ėY���������ɓ���A����ɂ������牺�쒬���ʂւƔ�����r���ŁA����܂����[���Ƃ���ɂ���y���z���ɍ����|�������B����Ƃ��̎��A�����琼�ɕ���_�[�g�̗ѓ������ɗ��A�u�_��̑�����v�ƕ\�L���ꂽ�ē����ڂɂƂ܂����B�ē��ɂ́u���̐掵�E�l�L�����[�g���̂Ƃ���ɗ����l�Z���[�g���̐_��̑���͂��߁A���܂��܂ȑ�Q������A������̖��C�̎p�̎��R�������Ղ�Ɩ��킦�܂��v�Ƃ����ꕶ���t�L����Ă����B�����āA���̈ē��̘e�ɂ́u�F�o�v�ɂ����ӁI�v�Ƃ����x���\���̂��܂��܂ł��Y�����Ă����B
�@ �F�͕|����������̎��R�Ƃ��͌��Ă݂����A����A�ǂ����Ȃ���łɌF�����Ă݂����B����ȊŔ��������Ĉ��������Ȃǂ�����̂��\�\�������ӂ������͂����ɂ��̗ѓ��ւƎԂ������ꂽ�B
�@ �l�쓮���s�ɐ�ւ��A���Ȃ艚�ʂ̌������ѓ����܃L���قlj��܂Ői�ނƁA�G�]�}�c�A�g�h�}�c�A�~�Y�i���A�V�i�m�L�A�J���o�ނȂǂ̑���T���Ɩ錴���ђn�тɍ����|�������B���܂��ܖڂɂ����ē��̉���ɂ��ƁA���̈�і�O�\��w�N�^�[���͉��y�������ی�тƂ��Ď���Ă��Ă��鎩�R�тŁA�^�̈Ӗ��ł̌����тƂ��Č×�������̂܂c���Ă���̂́A���܂ł͓����ł����̎��ӂ����ɂȂ��Ă��܂����̂��������B�Ȃ�قǁA���̖����x�ƌ����A�́X�Ƃ������X�̎}�U��ƌ����A�����т̖��ɒp���Ȃ����̂ł���B�͖̂k�C���̂�����Ƃ���ɂ��̂悤�Ȍ����т����݂��Ă����̂��낤�B
�@ �������炳��ɓ�A�O�L���߂��ѓ�������ƁA�_��̑�����������W���Ɨ��K�җp�̏����Ȓ��ԏꂪ���ꂽ�B�Ԃ��~��đ�̂���ق��֕����͂��߂�ƁA�܂�����u�F�o�v�ɂ����ӁI�v�Ƃ����x���\�����ڂɔ�э���ł����B�x���͗L�����A���ӂ���ƌ����Ă��A�������̓s���Ȃǂ��\���Ȃ��ɓ˔@�o�Ă��鑊��Ƃ����Ă͂ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��B�u�l�Ԃ��o�v���܂��̂ł����ӂ��������I�v�ƌF�����Ɍ������Čx���𗧂Ă����C���ɂ��Ȃ��Ă����B
�@ �_��̑�ׂ͍������̏��ꂪ�����W�܂��Ăł����傫�ȑꂾ�����B�S�̂̕��͑����ɍL���A�������l�\���[�g���ȏ�ŁA�قڐ����ɗ��ꗎ���Ă������A�u�_��v�Ƃ������t�̋��������C���[�W�Ƃ͈���Ăǂ��������I�Ȋ������������ł������B��ق̂������܂ō~��A���J��̔�S�g�ɗ��тȂ��痬���Ŋ��葫�������肵�����A�قǂ悢�₽���Ŏ��ɂ����ς肵���C���ɂȂ����B���ɂ��������ꂪ����悤���������A�n�`�I�Ȗʂ��猩�Ăقڎ����悤�ȍ\���̑ꂾ�낤�Ɛ����ł����̂ŁA�_��̑���������������ŎԂւƈ����Ԃ����B�����āA�K���s�K���F�ǂ��ɂ��o�������ƂȂ��y���z���̗ѓ������ɖ߂蒅�����B
�@ �y���z�������Ƃɂ���ƁA���쒬���o�Ċ�����_���܂œ쉺�A�������瓌�i���ď�䓻���z���A��㒬�ւƔ������B�����đ�㒬���S�X�̏�����O�Ō�����ɓ���A�����암�̏㏍�����ʂւƌ��������B�㏍���ɋ߂Â�����ɂȂ�ƁA���E�̌i�ς́A��ʎᑐ�ɕ���ꂽ�Y��Ȗq��n�тւƕϖe�����B���܂��������̎R�A�ɒ������Ƃ���[���𗁂тĐԗɉf����L�����n���A�ǂ������g�̂�������Ԃ�Ńg�R�g�R�Ɖ����čs���L�^�L�c�l�̎p���Ȃ�Ƃ���ۓI�������B�܂�ł��̗L�l�͊G�{�̒��Ɍ�������������i���̂܂܂���������ł���B
�@ �㏍������͒n������H���Ē������ɐi�H���Ƃ�A��������ۗ������z���Ċې��z���ւƔ����邱�Ƃɂ����B�Ȃ��q��n�т̑������������߂��A�ۗ����Ɍ������ē�i���邤���ɓ��͐[���J��D���ׂ��_�[�g�̈��H�ɕς�����B�����āA���̃_�[�g�̓���o��l�߁A�k���x�m���w�Ă̊Ԃɖ]�ޕW���O�Z���[�g���̗��ۓ����z���鍠�ɂ́A����͐Ԏ��̐[�������F�ɐ��܂��Ă����B
�@ �ې��z�ɒ������̂͂��傤�njߌ㔪�����������B�ې��z���c�̉���{�݂ňꕗ�C���тĊ��𗬂����Ǝv�����̂����A�����ɂ��x�ٓ��ɂ������Ă��ē����͂ł��Ȃ������B�ǂ������������������Ă���鉷��h�͂Ȃ����Ƃ��������T���܂���Ă݂����A���ǂ���ȏh�����܂������邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B���������Ȃ��̂ł��̖�̉�������͒��߁A�����ꑖ�肵�Ă��̂܂܃T���}�Ε��ʂւƏo�Ă݂邱�Ƃɂ����B
�@ �r���̉��y���ŃR���r�j�ɗ������ٓ����Ēx���[�H�Ƃ��A���̂��Ə�N�ʒ����o�ăI�z�[�c�N�C�ɗՂޗN�ʒ��̎O�����l�ɏo���B�O�����l�́A�I�z�[�c�N�C�Ɍ������č��肩��T���}�������悤�ɂ̂т�\�L�����[�g���]�̍ג����r���̐�[�Ɉʒu���Ă���B�����߂��ɂ́A�T���}�����ԉ���A�H�̂���ɂȂ�ƈ�ʔ������s���N�F�ɐ��܂�T���S�\�E�̌Q���n�Ȃǂ�����B
�@ ���̖�A�O�����l�̒��ԏ�ɂ͑��ɎԂ̉e�͂Ȃ������B���̒��ԏ�ň��𖾂������ƂɌ��߂����́A�㕔�V�[�g�t���b�g�ɂ��A�G�A�x�b�h��c��܂��I����ƁA���炭��������U�邽�ߎԊO�ɏo���B�����Ă������̒�h���z����ƁA�I�z�[�c�N�C�ɖʂ��鍻�l�ɍ~�藧�����B�镗�ɏ���ċ����Ă��钪���Ɏ����X���Ȃ���k�̋�����グ��ƁA�I�R�ƋP���߂���k�l�̎������傫������ɔ����Ă����B
�@ �k�l�����̕��̒[���琔���ē�Ԗڂ̐��̂����e�ɂ́A�܂�ł���Ɋ��Y���悤�ɂ��ċP���~�U�[���Ƃ������̂��������Ȑ�������B���̃~�U�[���Ƃ������͘Z�����ŁA���̖��邳�͓���Ŏ��ʂł�����E�ɋ߂��B���C�R�Ȃǂł͎��͌����ɂ��p�����Ă����Ƃ����������Ƃ�����B���ӂ��Â���C������ł���Ƃ���Ȃ�A���͂���E�炢����Ό��邱�Ƃ��ł���̂����A�ŋ߂͂ǂ��֍s���Ă��₽�����邢���߁A���ʂ���̂��Ȃ��Ȃ�����Ȃ����B���̃~�U�[���̂������Ȍ����v�X�ɂ͂�����ƌ������邱�Ƃ��ł������́A�Ȃ��������Ȃ��Ă��܂����B�䂪���͂����܂Ȃ����݂ł���m�����Ƃ����̗��R�̂ЂƂł͂������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N9��19��
�k���S�i�E���b�J�����ԉ�
�@ �T���}�̌Γ���[�A��C���h�Y���`�̕t�߂���́A�T���}�ƃI�z�[�c�N�C�Ƃ��u�Ă镝�Q�O�O�`�V�O�O���̍ג������F���A�S���Q�O�����قǂɂ킽���Ă̂т����Ă���B�����āA���̐�[���́A�k���[�̗N�ʑ�����̂т����S���P�O�����قǂ̍��F�̐�[�ƌ����������i�D�ŁA�T���}�ƃI�z�[�c�N�C�Ƃ��Ȃ������������`�����Ă���B�z�^�e�̗{�B�Ŗ��������Ƃ�����킩��悤�ɁA������O�ʂ̖ʐς������̃T���}�́A�O�m����C���̏o���肷�鉖�ł���B
�@ �O��A�O�����l�̂���N�ʑ����F�̓˒[�߂��ŎԒ����������́A���̓��̒��A�T���}�Ί݂��قڎl���̎O�����邩�����ŎԂ𑖂点�A�h�Y�ւƂ���Ă����B��C��������̂т������F��ɂ̓��b�J�����ԉ��ƌĂ��C�ݑ��������B���Ă���B���߂������ēV�����D�Ȃ̂ŁA���̌����ԉ���K�˂Ă݂悤�Ƃ����킯�������B
�@ �k�C���̗L���Ȏ����⌴���ԉ��́A�R�x����當�A���K�Ƃ����������̂��̂��ӂ��߁A���̂قƂ�ǂ�K�˂����Ƃ�����̂����A�߂������x���ʂ��Ă���ɂ�������炸�A���̃��b�J�����ԉ��ɂ����͂܂���x�����ݓ��ꂽ���Ƃ��Ȃ������B������A���̂Ԃ���҂����Ȃ��Ȃ������B���b�J�����ԉ��̓����ɂ̓��B�W�^�[�Z���^�[�������āA�Ԃ������̂͂����̒��ԏ�܂ł������B�����ԉ������߂���ɂ́A�k���ɗ��邩�A�����Ȃ���Αݎ��]�Ԃ��ό��n�Ԃ𗘗p���邵���Ȃ��悤�������B
�@ ���B�W�^�[�Z���^�[�Ɍf�����Ă������ɂ��ƁA�u�����ԉ��v�Ƃ����ď͕̂X��p�����Ă��邾���Ȃ̂������ŁA�w�p�I�ɂ́u�C�ݑ����v�ƌĂԂ̂��������̂��Ƃ����B���̐A��������ł��Ȃ��悤�Ȍ����������ɂ���k���̗ՊC�n��ł́A���̈������ɑς�������ʂȎ�ނ̐A�����������炽�Ȃ��B���̂悤�ȐA���ɂ���Č`�������̂��C�ݑ����A���Ȃ킿�����ԉ��Ƃ����킯�ŁA���̈Ӗ��ł́A�����ɐ����炭�ԁX�͂��Ƃ��Ƌt���ɋ����̂��B�u����Ȗk���̕l�ӂŁA�悭���܂�����قlj��ȉԁX���c�c�v�ȂǂƊ�������̂́A�ǂ����l�ԗl�̏���Ȏv�����݂ł���炵���B
�@ ���B�W�^�[�Z���^�[�Ń����^�T�C�N����݂肽���́A���₩�ȊC���̐����ʂ���Ȃ����y���Ƀy�_����ő���o�����B�T���}�̓I�z�[�c�N�C���̂��̂��Ɗ��Ⴂ�������ȂقǂɍL���̂����A���̍��F��ɍL���郏�b�J�����ԉ��̃X�P�[�����܂��z���ȏ�ɍL�傾�����B���B�W�^�[�Z���^�[���o�����Ă܂��Ȃ��A�I�����W���������F�̃G�]�X�J�V��������ʂɍ炫���������ɏo���B���ɗh��閳���̃G�]�X�J�V�����̂��߁A�L�������S�̂������F�ɐ��܂��Č�����قǂ������B
�@ �ǂ������[�����X�Ȋ����̊ό��n�Ԃ��A�̂т₩�ɍL����O���̑������g�R�g�R�Ƒ����Ă����B�y�_���������ς��ɓ��ݍ���ł��̔n�Ԃ�ǂ��z���ƁA�قǂȂ�����ȍ��F�ɂ����Ē�����ɂ̂т闳�{�X���ɂԂ������B���{�X���Ƃ́A���̂s���H���獶�E���ꂼ��̕����ɖ�܃L���قǂɂ킽���Đ݂���ꂽ�U���H�̂��Ƃł���B���͂����ō��܂��A����ɃT���}�����Ȃ��瑖��R�[�X��I�Ԃ��Ƃɂ����B�ǂ���ɍs���Η��{��ɍs�������̂��肩�ł͂Ȃ��������A����Ă���̂��T�̔w���Ȃ�ʃ����^�T�C�N���Ƃ��Ă�������A���P�l�Ɉ����錩���݂͂��Ƃ��ƊF���ł͂������B
�@ �����A���̖��ɒp�����A���{�X���̗����ɍL����V�R�̉Ԕ��̌i�ς͑f���炵�����̂������B�ЂƂ���ڗ��G�]�X�J�V�����̑�Q���͂������A�^�g�̃n�}�i�X�A�����V�V�E�h�A�G�]�J���]�E�Ƃ��Ă�鉩�F���G�]�[���e�C�J�A�����Ď��̃q�I�E�M�A�����ƁA���n��������Ԃ܂��Ԃ̐��E�������B�悭����ƁA�������Ԃ������I�I�t�X�}�A���F�����Ԃ̏W���Ԃ̃Z���_�C�n�M�A����ɂ́A�ǂ�����Ԏ��̉ԕق������q���n�N�T�t�W��n�}�G���h�E�Ƃ������ԁX�Ȃǂ��A���������ł��̑��݂�������ɑi�������Ă����B
�@ �������A���̌����ԉ��������Ȃ̂́A����ȉԔ����s���ǂ��s���ǂ��ʂĂ邱�ƂȂ��A�Ȃ��Ă��邱�Ƃ������B�s���H�ō��܂��Ă��痳�{�X���̐��k�[�܂ł̖�܃L���ɂ킽���āA���������ԁX�̉��͐s���邱�ƂȂ������Ă����B�����āA�����̉ԁX�̍炫�ւ���i�����������������ĂĂ���̂́A�z���̂��ƂŐ��Â��ɋP���T���}�̐��ʂ������B
�@ �U���H�̏I�_�͋��ƕۈ��тɂ��Ȃ��Ă��郏�b�J�̐X�̓����t�߂ŁA�ԁX�̍炫�����C�ݑ����͂��̏�����O�ŏI���A���������͎��X�̖�������[���X�ɂȂ��Ă����B���F���̂��̂̐�[�܂ł͂��̒n�_����܂��\�L���قǂ����������A���Ƃ��k���ł����Ă����ʂȋ����Ȃ������肻�̐�ɑ������ётɂ͂��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��悤�������B
�@ ���{�X���̏I�_�ɂ�����L��̈�p�ɂ́u�Ԃ̐������b�J�̐��v�Ɩ��ł���鐴�����N���Ă���Ƃ��낪�������B�u���b�J�E�I�E�C�v�Ƃ����A�C�k��́u���̂���Ƃ���v�Ƃ����Ӗ���\�킵�Ă���̂������ŁA���b�J�����ԉ��Ƃ������̂��ǂ���炻�̌��t�ɂ��Ȃ�ł���ꂽ���̂̂悤�������B�T���}�ƃI�z�[�c�N�C�Ƃ��u�Ă�ג������F�̂Ȃ��قǂɐ^�����N���Ă���Ȃ�ĈӊO�ȋC�����Ȃ��ł��Ȃ����A�������O��̓V�����ɂ��^���̗N����˂��������悤�����A���ق��͂��߃g���{���i���q���j�n�`�̍��F��ɔ��B�����W���͏��Ȃ��Ȃ����Ƃ�����A�n���w�I�ɂ͂������������Ƃł͂Ȃ��̂�������Ȃ��B
�@ �N���o�Ă��鐅������t���̕��ۂɋ���ň���ł݂����A�Ȃ��Ȃ��ɂ��܂����������B���̐��ꂩ��قǂȂ��Ƃ���ɂ͐̂Ȃ���̎艟���|���v����䐘�������Ă����B�����q�����������ɂ͂ǂ��ɂł��������艟���|���v�����A�ŋ߂ł͓c�ɂɏo�����Ă��ő��Ɍ������邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ����B���������v���ɂ����Ȃ炪���̃|���v�ɋ߂Â��A�Ăѐ������������ĕ��̒[������A����͋��������Ă��ƁA�{�R�{�R�Ɖ������ĂĐ��^���������悭����o�����B�@�@�@
�@���{�X���������Ԃ��O�ɁA�M�����ăT���}�̐��ӂɍ~�藧���Ă݂��B������ɕ���ꂽ���F�Ɛ��ʂ����悤�ɂ��āA�����ۂ����n�̏������X�Ƒ����Ă���B���̏��`���ɕ����čs�����F�̐�[���܂œ��B�ł������ł͂��������A�܂��Г��\�L��������Ƃ����Ă͒f�O������Ȃ������B
�@ ���{�X���̃I�z�[�c�N�C���͂ǂ����ɂ₩�Ȃ̂ڂ�ΖʂɂȂ��Ă��邽�߁A���]�Ԃő���Ȃ��璼�ڂɃI�z�[�c�N�̊C�ʂ�]�ނ��Ƃ͂ł��Ȃ������B�����ŁA�A��r���Ŏ��]�Ԃ[�ɒu���A������Ƃ������H������ăI�z�[�c�N�̕l�ӂɍ~�肽�B�����āA�T���}�Α��Ɠ��l�̍�����тт����n��Ŕg�ł��ۂɕ��݂��A���S�ɕԂ��Đ���������肵�Ȃ���A�����̂������钪�ƋY�ꂽ�B
�@ �����玩�]�Ԃ̂���Ƃ���ւƖ߂�Ƃ��A���n�ɐ������s�̏����ȐA���ɋ��R�ܐ悪�G�ꂽ�B����ƁA���������ƂɁA���̐A���S�̂��A�܂�ō����Ȃ��݂����Ȋ����ō�����X�[�b�Ɖ��ɓ������ł͂Ȃ����B���C�ɂƂ�ꂽ���́A������x�y���C��ł��̐A�����R���Ă݂��B����ƁA����͂܂��������艡�����Ɉړ������B
�@ �������܂��̐A���̂��ɂ��Ⴊ�ݍ���ł��̗l�q���Ԃ��Ɋώ@���Ă݂�ƁA�ӊO�Ȃ��Ƃ��킩���Ă����B����͔Z�ΐF�������̊ے��ȗt����ˏ�ɂ�����Ȃ������̐A���������B�܃Z���`�قǂ̒����̂��̗t�̈�[���w��ł܂y���O�㍶�E�Ɉ��������Ă݂�ƁA���̐A���͂��Ƃ��ȒP�ɗ͂̓������ւƈړ������B�܂�őS�̂����ɕ����Ă���݂����ł���B�����@��N�����č������Ǝv���镔���ׂĂ݂�ƁA�Ȃ�ƁA�s�Ƃ����Ƃ����Ȃ��ׂ������̂悤�Ȃ��̂������[���Ɍ������Ă̂тĂ���ł͂Ȃ����B�����ǂ�ǂ�@��Ԃ��Ă����ƁA�[����A�O�\�Z���`�̂Ƃ���ł��̐�����̒n���s�炵�����͎̂O�A�l�{�ɕ�����A���ꂼ�ꂪ�܂����[�������ւƂ̂тĂ����B���Ɏ���C�̏o�Ă��邻�̂����肩���̕������ق�Ƃ��̍������Ȃ̂ł��낤�B
�@ �Ȃ�Ƃ������̐A�����͂킩��Ȃ��������A�{�̕��͂܂�Ŏ��Ɍq���ꂽ�^�R�݂����ɍ���ɕ�����ł���킯������A�����[������̂т邻�ׂ̍��n���s����Ȃ�������͍�������͈͓������Ƃ��\�����A�Ȃɂ��̔��q�ō��ɖ��܂����苭���̂��߂ɌX�����肵�Ă����C�Ƃ����킯�ł���B���܂��ܖڂɂ������R�̖��Ɏ��͗B�X���Q�������ł������B
�@ �Ăю��]�ԂɌׂ�ƁA����ǂ͗��{�X���̂�����[��ڎw���đ���o�����B���B�W�^�[�Z���^�[���ʂւ̕���_��ʂ�߂��A�������炳��Ɍ܃L���قǃy�_���ݑ��������A�U���H�̗����ɍL���鑐���́A������̂ق����܂������̉ԁX�Ŕ������ʂ薄�ߐs������Ă����B���]�Ԃɂ�鉝����\�L�����̌����ԉ��̎U��́A�ꊾ�����͂������̂́A���ɑf���炵�����̂ł͂������B
�@ ���b�J�����ԉ������Ƃɂ��ĂقǂȂ��A�H�������邽�߁u�Ƃ���v�Ƃ������������̃��X�g�����ɔ�э��B�����āA�����̂��E�߂̃��j���[�ł���炵���z�^�e�s������H�𒍕������B�z�^�e�`�A�����̏Ă��z�^�e�A�z�^�e�̎ϕ��A�z�^�e�̎h�g�A�z�^�e�̃q���̘a�����A�z�^�e�T���_�A�z�^�e���̑��̋��L�ނ̗g�����A�z�^�e�̂���g�Ƀ}�b�V���|�e�g�ƁA�Ȃ�قǂ��̖��Ɉ��ʃz�^�e�s�����ŁA���Ƃ����ʂƂ����\���ɖ����̂������̂������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N9��26��
�k���S�i�E�ԑ��Y����
�@ ���X�Ɛ���X�����ԑ���ɂ��̋��͉˂��Ă����B�����ƌĂ�邻�̋����A���Ă̎�Y�҂����́A�ǓƂƔ߈��Ɛ�]�ƒ��O�̕��G�Ɍ��������v���ɋ���Ȃ���فX�Ɠn���Ă������B�ނ�̂قƂ�ǂ͎��Y���△���������A�����łȂ��Ă�����ɋ߂������Y�̎�Y�҂����������B�Y�����I���A���R�̐g�ƂȂ��čĂт��̋���n�邱�Ƃ̂ł����҂͂܂������K���ł��������A�d�Y�ɂƂ��Ȃ��ߍ��ȘJ����a��ɑς����ˁA�▽�����҂����Ȃ��͂Ȃ������B
�@�u���ʂɉ䂪�g���f���A�܂��������A�S�𐴂߂悤�v�Ƃ����v�������߂āA�l�X�͂��������̋��������ƌĂԂ悤�ɂȂ����Ƃ������A�ق�Ƃ��̈Ӗ��ŋ܂��������S�𐴂߂�ׂ��́A����n���čs���������̎�Y�҂����ł͂Ȃ��A�ނ�����̌������ւƑ���o�����P�ǂȂ�s���A�ہA�P�ǂƏ̂����ߐ[����ʎs���̑��ł������̂�������Ȃ��B���܂ł͈�ʌ��w�҂̒ʍs�����R�ɂȂ���������n��Ȃ���A�����̐��ʂ߂Ă݂��̂����A�������ے����邩�̂��Ƃ��ɑ�������̂䂦�������Ă��A�����ɂ܂݂ꉘ�ꂫ�������̐g�̉e�Ȃljf�肳�������Ȃ������B
�@ ��Ⴂ���r������������ł͂��������A���ォ��ቺ�̐�ʂ����߂邤���ɁA�Ȃ������́A�ˑR�A�A�|���l�[���̎��A�u�~���{�[���v�̈�߂�z�������ׂ��B������ƃ��[�����T���Ƃ̗��̏I�����̂������̗L���Ȏ��́A�V�����\���ɂ��Ȃ�A�䂪���ł��x����{�̖�ʂ��čL���l�X�ɒm���Ă���B���뉯���̂��̎��������̉��řꂫ�Ȃ���A�������Y�����̋��ł��邱�Ƃ��Y��A�������͉����z���ɒ^���Ă����B
�@ �ԑ��Y�����Ɏ��e�����̂́A���ł͓�N����O�N�Ԃ̒Z����Y�҂���ɂȂ�A�̂̂悤�ɒ�����Y�҂��������邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ����B������n���ĉ��ւƐi�ނƁA�ԗ�������̍������̑O�ɏo���B�����Ă��̕��ɂ����Ă��炭�i�ނƁA�u�ԗ�����v�ƌĂ��A�[�`����̑�傪���ꂽ�B�f��Ȃǂɂ��悭�o�ꂷ�邠�̖ԑ��Y�����̐��傾�����B����ȏ����̉����̋�̏㔼���������ė֊s�������ŕ����A�����ɑ傫�Ȕ��~�`�̒ʘH��݂��A���̗��e�ɂ������N���Q�l�̈�̎�q����z�����悤�Ȑԗ�����ɂ́A�������ɓƓ��̈Ќ������Ȃ���Ă���B��ʌ��w�҂�����������������̂͂��̖�̑O�܂łŁA�������牜�͊O���Ɗu�₳�ꂽ���E�ɂȂ��Ă����B
�@ ���������ɓ��肽����A����Ȃ�̓{��Ƌ�Y�Ɛ�]��ς����ł���ė���ȁB�ق�Ƃ��ɁA���O�ɂ��ꂾ���̓x���Ɗo��̂قǂ�����̘b�����ˁ\�\�܂�ł��̐ԃ����K��́A�ߑ����g�̂����ɕ\�����Ă͖��C�̂��Ƃ��ɐU�镑�����s���̎��Ɍ������āA����Ȍ��������t���ł����Ă��邩�̂悤�������B�o�l�����m�Ԃ́A�������l�̓��Ƃ��Ēm��ꂽ���n���ɉ����z����y���Ȃ���A�u�߂Ȃ��������ꂽ���⍲�n���v�ƋႶ���Ƃ����B����Ȉ̑�ȕY���̎��l�̎p��z������ɂ��A�߂������Ă��������E�C�̂����炷��Ȃ��Ȃ�Ƃ��ڏ��ȌȂ̗L�l�����Â���Ȃ��v���̂������B
�@ �ԑ��Y�����́A������\�O�N�O���A���H�č����ԑ����k�����Ƃ��Ĕ��������B���k�����̘J���ɂ���āA�����тɕ���ꂽ�������R�x�n��A�[�������ƈ����̍L���関�J�̌�����J�킵�A�������H�����݂���̂����̑_���������Ƃ����B���݂͎�v�����ɂȂ��Ă���ԑ�����k�����܂ł̐V���S�Z�\�O�L�����J�����߂ɒ��p���ꂽ���k���S���̂Ȃ������ł��A���Җ��S���]�A�d���҂�d�a�҂̐��ɂ������Ă͂��̉��{�ɂ��̂ڂ�Ƃ����ߍ����ł������炵���B���̂����Ȃ��������A�������Ď��ƍS���A����ɂ͐��₩�c�s�ȋ����J���̐��X�ƁA���H�J��̍�ƌ���͎��k�ɂƂ��č��ɂɂ�����ȏ�̏C����ƂȂ����̂ł������B
�@ �x�����������㖽�߂ł����������̉䂪���ɂ����ẮA���Ƃ������̎��S�҂�d���҂��ł��Ƃ��Ă��A�d�ߎ҂͍��y�J���̂��߂ɒ��p���ē��R���Ƃ���Ă����B�m�[�x���܍�ƃ\���W�F�j�[�c�B���́u�C�����E�f�j�[�\���B�b�`�̈���v��u���e���Q���v�Ƃ�������i�ɕ`����Ă���悤�ȁA�X�^�[��������ɂ����鋌�\�A�̃V�x���A�J���̎S��ƂȂ��ς��Ƃ��낪�Ȃ������̂��B���̗��̓r���Ŏ����������ԑ���k�����ӂ̓��H�Ȃǂ��A���Ƃ͂Ƃ����������k�����̑������ƈ��������ɊJ�����ꂽ���̂Ȃ̂ł������B
�@ �Љ���x�z���鋭�҂����́A���̎�������R�ƕ����ƒ����̖��̂��ƂɎ���̌��v��n�ʂ̕ۑS�ɓs���̂悢�̐���[�������肠����B�����āA�����̑̐���[�����I�݂ɗ��p�����肭���蔲�����肷���m�Ɍ�����l�X�́A�₪�ċ��R�ւƒǂ��l�߂��A��Y����]���A�����Ă��ɂ͕s���Ȑ��x�ɔ��t���d�߂����Ƃ��悤�ɂȂ�B���ЂƂ������̂����ׂ����̂��Ȃ��Ȃ����҂ɂƂ��āA���̐��̋K�͂͂����Ȃ���̂����ɓ������B�Ȃ�Ƃ��t���I�Șb�ł͂��邪�A�ނ�̍��͂��̋Ɍ��̒n���ɂ����Ă̂ݑ傢�Ȃ鎩�R��B
�@ ���̎x�z�҂����������̋��ɂ̎��R���������D���悤����Ȃ�A���R��搉̂��Ă���͂��̔ނ�̂ق����S���I�����I�ɍS������A�^�S�ËS�̓D���Ɋׂ��Ă��܂��Ƃ����p���h�b�N�X�ɑ�������������Ȃ��B�����Ȃ���A�ނ炪���@�I�Ə̂����i�������Ă��̑�������Y�Ȃ����͖��E���邵���Ȃ��Ȃ��Ă���B�����A���Y�Ƃ����E�Ƃ���������ȍs�ׂ́A�l�܂�Ƃ���A���ソ��ׂ��Љ�K�͂�Љ�ϗ��̔s�k���̂��̂ɂق��Ȃ�Ȃ��B���H�č����ԑ����k�����Ƃ��Ĕ����������̖ԑ��Y�����ЂƂɂ����Ă������A�ߋ��т�����Ȕߊ쌀���J��Ԃ���Ă����̂ł������B
�@ �A�肪���A�ʘH�e�ɗ��ЂƂ̐Δ肪�ڂɂƂ܂����B�ԑ��Y�����J��S���N���L�O���A������N�\���Ɍ��Ă�ꂽ�Ƃ������̔�ɂ́A�u�킽���̎�͌���������ǁA�킽���̐S�͈��ɖ����Ă���v�Ƃ����ꕶ�����܂�Ă����B�I�����_�̃A���X�e���_���ɂ���Y�����̖���̍�����|�����̂��Ƃ����B�Ȃ�قǂƂ͎v���Ȃ�����A�����ۂ��Ŏ��̋��̕Ћ��ɐ��ވӒn���ȐS�́A���������̕��ӂ��u�킽���̐S�͈��ɖ����Ă��邯��ǁA�킽���̎�͎c���Ȃ܂łɌ������v�Ƌt�]�����A�u�c���Ȃ܂łɁv�Ƃ����Z�����̌`�e���������킦���肵�Ă������B
�@
�@ �ԑ��Y�����̋߂��ɂ͖ԑ��č������ق�����B�L��ȕ~�n�������̔����قɂ́A�ڒz���邢�͕������ꂽ�����̖ԑ��č��̌�����W���{�݂̂ق��A�ߋ��S�\�N�ɋy�Ԗԑ��Y�����W�̍s�Y������č��j�����Ȃǂ��W������Ă���B���łȂ̂ł�����̂ق����K�˂Ă݂邱�Ƃɂ����̂����A�s���ό��X�|�b�g�̂ЂƂɂȂ��Ă��邱�Ƃ������āA�o�X�c�A�[�̒c�̋q���̑��A���K�҂͏��Ȃ��Ȃ������B��~�]�̓��ٗ����x�����ăQ�[�g��������Ƃ��A����҈�l�ЂƂ�ɃJ�����������Ă���j�̎p��ڂɂƂ߂����A�Ƃ��ɂ��̂��Ƃ��C�ɂ��邱�Ƃ��Ȃ��A���͂��̏��ʂ蔲�����B
�@ �䂤�ɓ�\����W��������W���{�݂�����ł����̂ŁA����炷�ׂĂ��Ԃ��Ɍ��w����Ƃ����킯�ɂ������Ȃ��������A�s�Y�����قȂǂ͂������ɂ���Ȃ�̌����������������B�������̎��k�����ɂ�钆�����H�J��W�̏ڍׂȎ����͌����ɋy���A�����̍��ɓ��ł̎��k��Ď��̐�����`���鎑���A�e��č��p��ށA�[�������݂�S�g�ɔ�߂��召�̃j�|�|�i���k�̎�ɂ��ؒ���̃A�C�k�l�`�j�Ȃǂ܂ł��A�Ƃ��닷���ƒ�W������Ă����B
�@�܂��A�����ɂ́A�����̒E�����A�ܐ��B�̓Ћg�ȂǂɊւ��鋻���[����������Ȃǂ��������B�E�����邱�Ǝ��ɘZ��A���鎞�Ȃǔނ́A���̔j����h�����ߓ��ʂɐ݂���ꂽ�O�d�č������j��A���l�I�Ȑg�̋@�\�������č��ɒʘH�̍����������ɂ悶�̂ڂ�ƁA���˂��Ō����������т����������̂��Ƃ����B����ɐ旧�E���̍ۂɂ́A�ܐ��i��\�܃Z���`�j�B�𑫂œ��ݔ������ɂ�������炸�A���̓B�̂������������܂\��L�����̓��̂�����������B�ܐ��B�̓Ћg�Ƃ����A�ǂ����،h�̔O���������������ٖ̈��́A����ȋ����ׂ����b�ɂ��Ȃ��̂ł���炵�������B
�@ �������H�J��̎���A�{���̍��ɂ��牓�����ꂽ��ƌ���Ȃǂɐ݂���ꂽ���h�Ɂu�x�����v���Č��������̂Ȃǂ��������B�J���ɋ��o���ꂽ���k��Ŏ��̓��g��͌^�Ƌ[�������܂ł����Ȃ���Ƃ�����̍��݂悤�ŁA�ނ�̏A�Q�̗l�q���͂��߂Ƃ��鐶���U���S���̌������Ȃǂ��ÂԂ��Ƃ��ł����B�����č��Ƃ��Ăꂽ���̋x�����́A���̖��̂Ƃ͈���āA���k���������S���ċx�蔑�܂����肷�邱�Ƃ��ł���悤�ȏꏊ�ł͂Ȃ������悤�ł���B
�@ �����̊Ďɓ�����̗l�q���Č����A���g��̐l�`�Ȃǂ�z�������̂Ȃǂ���ϋ����[�������B�吨�̎҂��Ȋ��̂��ƂŐQ�H�����ɂ��邽�߁A�畆�a�Ȃǂ����s���₷����������A�q���ʂ��������͌������Ȃ��ݔ��ł������B�܂������͎��Ď҂�ɂƂ��Ă��傫�Ȋy���݂̂ЂƂ������B�������A�������Ď��̂��Ƃł̎��k��̓������i�͂Ȃ�Ƃ����ς��Ȃ��̂ł������炵���B
�@ �\�l�قǂ̎҂���g�ɂȂ�A�E�ߏ�ňߕ���E���ʼn����ɕ��ԁB�����āA����Ȉ����������ł���B����͍L�������`�̋�ԂɂȂ��Ă���A���̏��ʂɂ͍ג����v�[����̗��������������Đݒu����Ă����B�����̊Ŏ炽���ɂ�錵�����Ď��̉��œ����������Ȃ��Ă������Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B
�@ �������ň��̊Ԋu���Ƃ�Ȃ��牡���ɕ������҂����́A���̂܂܈�ĂɑO�i���A��O�̗����Ɍܕ��O��̌���ꂽ���Ԃ����g�߂�B���ꂩ��Ŏ�̎w���ɏ]���Ă�͂�ג����O���̐�ɏオ��B���̂��Ƃɑ����Ď����̗�̎҂������A�O��̎҂����̔w�����݂邩�����ň�Ԗڂ̗����ɓ���B�ܕ��Ԃقǂ����đf������Őg�̂������O��̎҂����́A���̂��ƁA�O���ɂ����Ԗڂ̏オ�蓒�p�����ɓ���B�܂��ܕ��قǐg�̂����߂���A���̂܂܂���ɑO���̐@����ɂ�����A�g�̂�@���Ē��ߏ�ɓ���Ǝ葁�����߂��I����B�����āA���̈�A�̊�ȓ��������e�ƂɎ��X�ɌJ��Ԃ���Ă����Ƃ����킯�������B��ɑO�����̎p���ł̓����ŁA���p���Ԃ��e��\�ܕ������\���ɐ�������Ă����炵���B
�@ �ܗ����ˏ��ɖ[�ƌĂ�鍖�ɂ���ϒ��������̂������B�ŏ��̍��ɂ��Ď��������߁A�����l�\�ܔN�ɍČ����ꏺ�a�\��N�܂Ŏg�p����Ă������̂ŁA���̌�A���̔����قɈڒz���ꂽ�̂��Ƃ����B���ʓ������璆�ɓ����������̂Ƃ��낪�傫�Ȑ����p�`�\�����������菊�ɂȂ��Ă���A���ʂƂ��̗��e�̊Ŏ�T�����̂���O�ʂ��̂����ܖʂ���́A�ꍆ�ɂ���܍��ɂ܂ł̒���ȍ��ɂ����ˏ�ɂ̂т����Ă���B
�@ ���ꂼ��̍��ɂ̒����ɂ͎��A���\���[�g���ɂ킽��܂������ȒʘH�������āA���̍L��������ʘH�̗����ɓƖ[��G���[�ȂǑ召�̎ɖ[�������݂����Ă���B�v����ɁA���p�`�̌����菊�̒����ɗ��ĂA��ڂŌܓ��̍��ɂ̒ʘH�����܂Ō��n����\���ɂȂ��Ă����킯�ł���B�ʘH��̉����͂����Ԃ�ƍ����A��l�̔\�͂ł͂ǂ����~���Ă��悶�̂ڂ邱�Ƃ̂ł���悤�ȑ���ł͂Ȃ������B
�@ �������̍��[�͉��̂ق��܂łԂ��Ɍ��w�ł���悤�ɂȂ��Ă������A�Ƌ��[�͍L���l�E�㕽�����[�g���A�܂��A�O�`�ܐl�̎�Y�҂���炷�G���[�̍L���͋�E�㕽�����[�g���قǂŁA����������Ȗؑ��̍��[�������B�E����K�Ƃ̒E����h�����ߓ��ʂɑ���ꂽ�A��d�O�d�̌������ƕǂ�������Ɩ[�����J����Ă������A�E���̖��l�����͂���ł��j���ɐ��������炵���B�E���ɓq����ނ�̎��O�͂Ȃ�Ƃ����܂������̂������悤�ł���B
�@ ���Ƃ�����E���҂Ȃǂ́A���X�̐H���ɏo�閡�X�`��ݖ��A�H���Ȃǂ̉��������N�ɂ��n���č��C�悭�`�����̑����S�i�q�̍����ɂȂ�����A���ɕ��H�������̓S�i�q��܂�O���ĒE�������Ƃ����B�E�҂܂����̋Z�p�Ǝl�҂̔\�͂������č����ǂ�傫�Ȓ����悶�̂ڂ�A�V��≮���ɒ����Ԃ͂���E�����ʂ������҂��������������B
�@ �����ٕ~�n�̕Ћ��ɂ͎l�ʂ̕ǂ���������ʼn������������̒����p�Ƌ��[�Ȃǂ���������Ă����B���͂܂������Ȃ��A�����̌����h�A��߂�ƊO���̕����͊��S�ɎՒf����A�����͎����̈łɕ�܂��悤�ɂȂ��Ă����B���ɓ��őe�\�ȐU������������A�d��ȋK���ᔽ��������A���߂ɔw�����肵���҂����邽�߁A����A�������Ԃ����x�ɓ��[�����Ă����Ƃ����B
�@ �Ō�ɑ����^�̂͌Y�������̋����������������ŁA�����ɂ͖Ǝ��ی�̕��Ə̂�����F�i�@��t�̋ƐтȂǂ��Љ��Ă����B�����ʼn��ɂ���Ւd�ō����Ă��Q�肵�Ă���o���Ɍ������ĕ����Ă���ƁA���`�̎Ⴂ�����W���������ɋ߂Â��Ă��āA�u�����ق̎��ɎB�e�����ʐ^���o���������Ă܂���B�ƂĂ��悭�ʂ��Ă܂�����A�L�O�ɐ���@���ł����H�v�Ƃɂ��₩�ɘb�������Ă����B���َ҂���l�ЂƂ�B�e���Ă����̂͂��̂��߂������̂��B����痂������Ƃ��̂����Ȃ��B
�@ �f�낤�Ǝv�������A�����o���ꂽ�ʐ^������ƁA�Ȃ�قlj�Ȃ���ӊO�Ȃقǂɂ悭�ʂ��Ă���B�^�]�Ƌ��̎ʐ^�̂悤�Ȏʂ��������炻�̂܂ܑ���̊��U��U����Ă����̂��낤���A�܂�ł��Ȃ������̂ň�u�S���������B�����āA�����Ɍ����ɂ����܂�A���ǁA�����ٖԑ��č��ʐ^���ސ��Ȃ�G�t����̋L�O�ʐ^���~�Ŕ��킳���͂߂ɂȂ��Ă��܂����B
�@ �����̎p����ʂ��ɂȂ����ʐ^�̘e�ɂ͖ԑ��Y��������̏����ȉ����̎ʐ^���Y�����A���̉��Ɂu�o������暁@�E�V�Җԑ��č����Č��w���m���A���m���w�ԓx�_�����c�Ε׃j�t�L䢃j���̓��ȃb�e�o�������X�����m��@2001�N6��26���@�ԑ��č��v�Ƃ����ꕶ���t�L����Ă����B�m���Ɂu���w�ԓx�_�����Εׁv�ł�������������Ȃ��ȂƋ���Ȃ���A���͒��ԏ�Ɍ������čĂѕ����������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N10��3��
�k���S�i�E��q��
�@ �Η������o�Ē�q���i�Ă������j���쓒�߂��ɓ��������̂͌ߌ�\�����������B��q�������ӂ̒n���ɂ͖��邩�����̂ŁA�Â��Ȃ��e����}���ɓ����Ă������悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ������B���̈�т̒n���ɏڂ����̂́A��������ΘH�A���H�����Ȃǂ̑厩�R�ɖ������A�Ⴂ��������x�ƂȂ������^��ł������Ƃɂ���邪�A���܂ЂƂɂ́A��������ފ������`�����ꎞ�����̒n�ɋ����\���Ă�������ł��������B���̋`�������ɑ��E���A�`���Ɠ��̒햅�������F�����ߕӂɈڂ�Z��ł��܂����̂ŁA���܂ł͂���Ƃ����Ēm�l������킯�ł��Ȃ��̂����A���ɂƂ��ĉ����Ƒz���o�[���y�n�ł��邱�Ƃɂ͕ς��Ȃ������B
�@ �����R�̂����߂���ʂ�߂��A�쓒�̉���X���ċ��ΘH�ΔȂ̍����ɏo��ƁA��������Ԃ��~��ČΊ݂ւƌ��������B�����ĉ���̗N���o�����ӂɗ����ČΖʂɕY����̑�C��[�X�Ƌz�����B���Ԃ͊ό��q�œ��키�ΔȂ��A��x���Ƃ����Ă͂������ɐl�e�͌�������Ȃ������B�Â��Ζʂ������ƒ��߂Ă��邤���ɁA���t�ɂȂ�Ȃ��l�X�ȑz���������Ō������A�u���ɏ������錶�̃L�����o�X�̏�ɖ����̂Ȃ��S�ە��i�����X�ƕ`���o�����B
�@ ����o�g�Ŗk�C���̎��R��[���������`���́A���呠�ȍ������Ƃ��Ă̎d����ނ��ƁA����]��Ŏ��R�Ɍb�܂ꂽ���̒n�Ɉڂ�Z�݁A�\�N�߂����ƌ��������ω�ۗ{���u��Q���v�̎x�z�l�߂Ă����B���Ă͋����R�m���w�Z�o�g�̌R�l�ł��������`�����������A���Ў�`�I�ȂƂ���͂܂������݂��Ȃ���������łȂ��A���l�ɑ���v��������[���A�v�z�I�ɂ�����߂ă��x�����Ȑl���ł������B���Ђ���҂̉��\���◝�s�s�ȐU�����ɂ͊��R�Ɨ����������A��҂̂��߂ɂ͌Ȃ̕s���v��s�s�����ڂ݂��^�S�̂������s�����A����������ɂ��đ�������悤�Ȃ��Ƃ͂قƂ�ǂȂ������B
�@ ��q�����o�g�̖����j��Q�ɂ��Ȃ�ł��̖��O������ꂽ�Ƃ�����Q���̏h���q�̂Ȃ��ɂ́A���ƌ������㋉�E�⍑��c���Ƃ��Ă̒n�ʂ⌠�͂�@�ɂ����A�]�ƈ��⑼�̈�ʏh���q�ɑ��ĉ����ɂ܂�Ȃ��ԓx���Ƃ�҂Ȃǂ����Ȃ��Ȃ������B����Ȏ��A�`���͋B�R�Ƃ��ĐU�����A�������ē��ʈ��������肷��悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ������B�`���Ɍ����̔�������Ȃ߂��A���O�̎�Ȃǂ����ɂ�����Ă��Ƃ����藧�q��e�͂Ȃ��@���o���Ă��܂����悤�Ȃ��Ƃ��������B
�@ �����Ƃ��A����ȋ`���̋C�����`���Ɠ��A����ɂ͂��̒햅��ɂƂ��čK���������Ƃ����ƁA�K�����������Ƃ���Ƃ͌����Ȃ������ɈႢ�Ȃ��B���Ԃ�A�`���Ɠ���q�������́A�����Ȃ��Ƃ���ő傫��ᰊ������A���ꂪ���Ƃŗl�X�ȋ�J���������Ƃ��낤�B�P���ɂ��������ɂ��A����l�Ԃ��Ȃɂ�����̐M�O�◝�O��ʂ��Đ����悤�Ƃ���A�K���ǂ����ɂ���ᰊ���������̂����炾�B�ނ��A����́A�Ƃ�ɑ���Ȃ����̂Ȃ���A�M�O�̂�����炵�����̂����͐S�ɕ����Đ����Ă���䂪�g�ɂ����Ă͂܂邱�Ƃ������B
�@ ��̌Ί݂Ɋ邳���Ȃ݂̉��ɋL���̐[�w��h���Ԃ��Ă��A�ˑR�A���́A�d���ŏ㋞���������`���Ƃ̏��Ζʂ̓��̂��Ƃ�z���o�����B��������ӂꂽ���X�̈���ŁA�`���̓r�[���r�Ƌ�̃O���X��O�ɒu���A���߂Ȃ����̓W���[�X�̃O���X��O�ɂ��Ė����̂܂܂����ƌ����������Ă����B�Â������S�̉����˔����悤�ȉs�������Ŏ��̖ڂ����߂Ă����`���́A�₪�Ď����ŃO���X�Ƀr�[���𒍂��ƁA��������ɂ��Ȃ���A�u�{�c�N�A�����ǖk�C���ɗ����܂��A�Ɠ����҂��Ă���悤������v�ƈꌾ�����Z�������J�����̂������B�ߐe�҂Ȃǂ܂��������Ȃ����̓���炵�̐g�ŁA�����̓W�]���܂�ł����Ȃ��L�l�ł͂������̂����A�`���͂���ȏケ����̐g�セ�̑��ɂ��ċl�₵����F�������肷��悤�Ȃ��Ƃ͂��Ȃ������B
�@ ��q����K�˂邲�ƂɁA�`���͎���Ԃ̃n���h������ɂ��Ă��낢��ȂƂ���ւƎ����ē����Ă��ꂽ�B�n���̐l�������m����ΘH�▀���̎U��X�|�b�g�͌����܂ł��Ȃ��A�m�������⍪������A���H�����A����ɂ͈����A���y�A�k����тɂ܂ł��͈̔͂͋y�B�R����̂�ɘA��čs���Ă���邱�Ƃ������������B�����āA����Ȃӂ��Ɏ����ē����邩�����ŁA�`���́A�嗤�Ŏ���̌������펞���̐��S�ȏo�����Ȃǂɂ��āA�ǂ����d���������Ȃ�����A��݉B�����ƂȂ��b���Ă��ꂽ���̂������B�E�ƌR�l�Ƃ�������̂䂦�������Ƃ͂����A�`�����܂��A�������邱�Ƃ̂ł��Ȃ��푈�̏���S���[���ɔ�߉B���Đ�����l�Ԃ̈�l�ł��邱�Ƃ��A���̎����͏��߂Ēm�����悤�Ȃ킯�������B
�@ ����Ƃ��`���́A�����v�����̂��A�����������̊��Ȃǂ̂悤�Ȏ��ɂȂ���a�ɂ����������ɂ͕K�����̂��Ƃ����m���Ă����悤�ɂƌ������B���ꂩ�炸���Ƃ̂��̂��ƂɂȂ邪�A�É����ɓ��s�Ɉڂ��ė]���𑗂��Ă����`���́A�����B�Ɉُ���������A�����̋�a�@�ɓ��@�����B����ɂ��ڍׂȌ����̌��ʁA�ُ�̌����͈����̎����B���Ɣ����A�]�ڂ̋^�������邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B����ƂȂ����@�����`���͈�҂�`���Ɠ���ɕa��ɂ��Ė{���̂Ƃ���������Ă����悤�ɂƎ��X�ɔ��������A�N�����A�����������Ƃ͂���܂����Ə��Ă͂��̏ꗽ���̑Ή��ɏI�n���Ă����B
�@ ���x���̌������̍ۂɁA���܂��܋`���Ǝ��Ƃ���l�����ɂȂ邱�Ƃ��������B�`���͂܂�ł��̋@���҂��\���Ă������̂悤�Ɏ��̊�����߁A�P�������ɕa���Ƌq�ϓI�ȕa��Ƃ�u�˂Ă����B�u�����̊��Ȃǂɂ����������ɂ͕K�����̂��Ƃ����m���Ă����悤�Ɂv�Ƃ����`���̌��t��z���o���������́A��������ȏ�R�͂��Ȃ��ƊϔO�����B�s���`���̎������A����ȊO�̑I�������邱�Ƃ������Ă͂��ꂻ���ɂȂ������B���͗����Ɂu���Ȃ舫���̊��ł��v�Ɠ`�����̂������B�����āu���Ȃ�v�Ƃ��������������̂͌˘f���h�炮�Ȃ̐S�̏��̂��̂ɂق��Ȃ�Ȃ������B
�@ �`���͎��̌��t�ɖق����������B�����炩�ɂ��ׂĂ�������\��ł������B���ꂩ��قǂȂ��A�`���ɕa�������m�������Ƃ��`���Ɠ���ɐ����ɓ`�������A�K���N��������̍s�ׂ�ӂ߂���悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ������B���ꂩ��ꃖ���قǂ��āA�`���́A�S�g���ׂĂ̒ɂ݂����������悤�ɐÂ��ɑ��E�����B
�@ �Â��Ζʂ����߂Ȃ���`���ɂ܂�邻��ȏo��������z���Ă��邤���ɁA���������������Q���̐Ղ�K�˂Ă݂悤���Ƃ����v�����N���Ă����B���̉\�ŁA��Q���͕�����~�n�ƌ����͔���ɏo����Ă���Ƃ����b�����ɂ��Ă����̂ŁA���܂͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��낤���Ƃ����v���������Ă̂��Ƃ������B
�@ ���H��̎x���̂ЂƂ͋��ΘH���痬��o���Ă���B���̎x����n��A���H�Ɣ��y���Ȃ����������܂��ē�\���قǑ���ƒ�q���s�X�ɏo���B���Ă̂i�q�̉w�͒����Ƃ��Ȃ��u��q���v�ł��������A���܂ł́u�����v�Ƃ����w���ɕς���Ă���B���̒��͖����Ίό��̌���������A����ʂɐe���݂̂���w���ɂƂ������ƂŁA���̂悤�Ȗ��ɕύX���ꂽ�̂��낤�B�w�����ς���Ă������A����ȏ�ɕϖe���Ƃ��Ă����̂͒�q���̊X���݂��̂��̂������B��������ߑ㉻���A��Ԃł��s����݂ɖ��邭�Ȃ����X���݂ɂ́A���Ă̂悤�ȗ��D��U���k���̒����L�̕���Ȃǂ܂������������Ȃ������B
�@ �����⓹�H���͂��߁A���S�̂̌i�ς╵�͋C����������ϗe���Ă������߁A��Q���̂������ꏊ��T���o���̂ɏ��������Ԏ�����B�����A��Q�����̂��̂́A���l�ƂȂ�r��ʂĂĂ͂������̂̐̂̂܂܂ő��݂��Ă����B�����d������ɂ��ĕ~�n���ɓ���A���Ă͏h���q�œ�����Ă��������ؑ���K���Ă̌����̌���ɗ��ƁA�������ꂽ�h�A�̑O�ɉ��������f���������ꖇ�|�����Ă����B�����āA�����ɂ́A���̕��������o�����ł���A�₢���킹��͒�q�����쓒�̍��ƌ��������ω�ۗ{���ł���|�̕\�������Ă������B
�@ ���ƎG�����̂тق������ɂ̂т�������ւƐi�ނƁA���o���̂��鞾�̋������ꂽ�B��Q���̎�Ƃ������ׂ����ł���B���w�𑲋Ƃ����Ă̂���]�ƈ��̏��̎q���A���̎��㍂���ɂ̂ڂ�A�e���̉Ƃ̂�������������߂Ȃ��狃���Ă����Ƃ����`���̞��̖������B
�@ ���܂ł����ΖL���ȗ��_�n�тɂȂ��Ă��邪�A�p�C���b�g�E�t�@�[���ƌĂ�Ă������n���̊J��q��œ����҂̐����͍������ɂ߁A���������Ŗ铦�����N�������肷��قǂɔߎS�Ȃ��̂������B�`���͂���ȉƒ�̏��̎q�������ق��A�e�g�ɂȂ��ĉ䂪�q���l�Ɉ�ďグ�A��w��ʐM�����ʂ��Ă���Ȃ�̂��Ƃ��w���A����������]�E�����肷��ꍇ�����ꂱ��Ɛ��b���₢�Ă����B�����āA�ޏ��������������Ă��������Ƃ��A���Ƃ��邲�Ƃɑ��k�ɂ̂�����ʓ|���݂�������Ă����悤�ł���B����ł��Ȃ��A���w���ƌシ���ɐe���𗣂ꊵ��Ȃ��E��œ������Ƃ́A�ޏ������ɂƂ��đ�ςȂ��Ƃ������̂��낤�B
�@ �`���͂悭�]�ƈ��̏��̎q�����̎��Ƃɋߋ������˂Ĉ��A�ɏo���������A����Ȏ��Ȃǂɓ��s���Ă݂�ƁA���F����i���ۂ���Ȓn�����������j���Ԓn�ȂǂƂ������悤�ȁA�l�����������ꂽ�Ȃ�Ƃ���翂ȏꏊ��������������B��т��^���|�|�̉���F�ɕ����鏉�ĂȂǂ̌i�ς́A���l�̖ڂɂ͑f���炵�����̂ɉf����������A�����Ă��鋍�̐������Ȃ����Ƃ�A���~���̎��R�̖҈ЂȂǂ��l����ƁA���̐����̉ߍ����͗e�Ղɑz�������������B
�@ ����ɂ܂��A�|���Ȃǂ���`�����L���𗊂�ɉ���̌���̂������Ƃ����`���Ă݂����A��������[�����ނ�ɕ����A�͂�����Ɗm�F���邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�����͐₦�ԂȂ��M�����N���o�Ă������̂����A������������Ȃ�炩�̗��R�ʼn��͂�Ă��܂��̂�������Ȃ��B�`�����������Ă����R���Ƃ������̗����ȎG�팢��A���O�͖Y�ꂽ�����т̑傫�ȃA�C�k���Ȃǂ������A��ĕ~�n�̗���ɑ����R�ɕ�������A�R�؍̂����̂���������ƂȂǂ����������z���N�����ꂽ�B
�@ �����d����Ў�ɂ��������Ƃ�����p���ǂ����ŋ`�������Ă��邩�̂悤�ȋC���������́A�|�P�b�g����g�ѓd�b�����o���A����̉Ɠ����Ăяo�����B�����āA���ܑ�Q���ɂ���|�������A�����������ɂ��Ȃ���A������~�n���ӂ̕ϗe�Ԃ������������낵���Ԃ��ɓ`������������B���ȏ�ɂ��̒n�ɐ[���z���o�̂���Ɠ��Ȃǂ́A���S���ЂƂ����������ɈႢ�Ȃ��B
�@ ��Q�������Ƃɂ���ƁA���͂�����x���ΘH�ւƈ����Ԃ����B�������A����ǂ͍����ł͂Ȃ��A���ΘH�̓�݂���Β��ɂ̂т����a�Ք����Ɍ��������߂������B�S�̂��a�Ղ̌`�Ɏ��Ă��邽�߂ɂ��̖������邱�̏����Ȕ����̂Ȃ��قǂɂ́A���ł����R�ɓ����\�ȘI�V���C������B�ΔȂɖʂ������Ȃ�傫�ȓV�R�̉���ŁA�M�����炢�̂���������ƗN���o�Ă���A�������������͖����Ƃ��Ă���B����ł����߂Ȃ��炱�̘I�V���C�ɓ����āA�������ƈ���̊��𗬂����Ƃ������_�������B
�@ �a�Ք����ɒ������̂͌ߑO�뎞���������B�I�[�g�L�����v������Ă���Ԃ̉e�����䂩����ꂽ���A�I�V���C�ɂ͒n���̐l�炵����q����l�͂����Ă��邾���������B�葁������E���A���R�̊��g��łł������D�̒��ɔ�э��ނƁA�S�n�悢��̍��n�ɂǂ�����ƐK�������A�l�҂������ς��ɂ̂��Ėڂ��ނ����B�������̏����玞�܂������Ȑ����������Ă��邭�炢�ŁA������͐Î₻�̂��̂������B
�@ ���炭���Đ�q����������ƁA�L���I�V���C�͕����ʂ莄�̐�L���Ɖ������B���D�̒�����y���Ɍ��グ����ł́A�������I�R�Ƌ�̗͂���̒����H�����A���̋�͂��͂���ŘȂސD�P�ƌ����́A�i���Ɋ���ʗ��ƒm���Ă��m�炸���A�݂��ɐ���������Ȃ��炢�܂ł��u���Ăь��킵�����Ă����B
�@ ����ȐÎ�̂Ȃ��ɂ����đz���ׂ����Ƃ́A�{���Ȃ瑼�ɂ����Ă�����ׂ��͂��������B�����A���Ƃ����낤�ɁA���̎������z�������ׂ��̂́A���ʂ܂ŋ`�����S�̉���ɕ����������[���[�����̂��Ƃ������B�`�������O���ɂ��̘b�����Ă��ꂽ�^�ӂ��ǂ��ɂ������̂��͍��X�m�邷�ׂ��Ȃ��������A���炪�嗤�̐��ő̌��������S�������ȍs�ׂ��㐢�Ɍ��`���Ă����K�v������ƍl���Ă������Ƃ����͊m�����낤�B���Ď����������b�̈�[�͂��Ƃ��Ύ����̂悤�Ȃ��̂ł������B
�@ �`���̘b�ɂ��ƁA������N���������{���R�́A�n���s�ē��Ȓn��֍�핔����i�߂�Ƃ��K�����n�̖��Ԑl���Ă�œ��ē��������Ă����B�����āA�ē������Ă���Œ��͂����ς�ނ�Ƃɂ��₩�ɒk���A�H�Ƃ��^�����艌���������߂��肵�Ă������A��������p�ς݂ƂȂ�ƒ����ɂ��̏�ŎˎE�����B�ނ��A����͌R��w������̎��㖽�߂ŁA���̏������I���ƁA���R�̂悤�ɂ܂��ʂ̈ē��l���ĂсA�����ςݎ���܂����l�ɎˎE����Ƃ����s�ׂ��J��Ԃ��Ȃ���i�R���d�˂Ă������̂��Ƃ����B
�@ �����l�ߗ��̈��������C�̍����͎v���Ȃ����̂ł������悤���B��⋂��s�\���ł��������{�R�ɂ͐l�I�ɂ����I�ɂ������l�ߗ���{�������̗]�T�͂Ȃ������B���̂��߁A���R�i�ߕ��͍��ۖ@�ᔽ�����m�Ŋe�����ɕߗ������蓖�āA���Y������Ƃ�����i���Ƃ����B�e�����͊��蓖�Ă�ꂽ�ߗ��������R�p���̌P���⏉�N���̋����̂��߂ɗp�����Ƃ����B
�@ ����ɔ����Ď��R��D���A�֖҂ȌR�p���ɏP�������点�悤�Ƃ���ƁA�����o�債������R�̒����l�ߗ������͋��낵����Ō��ǂ����ɂ݂������B���̂��܂�ɐ��܂����`���ɋ������Ȃ��āA�������̌R�p���������ɂ͋߂Â����Ƃ͂��Ȃ������炵���B����Ȏ��A������w�����鏫�Z�����͌R���ŕߗ��̎���@�������A��������ɐH�킹�Č��̖����o�������Ă���P�������点���̂��Ƃ����B���̗l�q�����Ă����`���́A���ɂ�������ďP�킹�E�����͂ЂƂ������ɎE���Ă��܂����ق����ނ�̂��߂��ƍl���A�����̕����Ɋ��蓖�Ă�ꂽ�ߗ����R���Ő����Ɛh�����ɘb���Ă��ꂽ�B�`���̏ꍇ�́A�ɗ͕����ɂ���Ȕ؍s�������Ȃ��悤�ɂ��邽�߁A�Ȃ�ׂ������ŐӔC���Ƃ�悤�ɂ��Ă����炵���B
�@ ���Y����悤�Ƃ��鎞�A�����l�ߗ������͎��藎�Ƃ����Ɏh�E���Ă����悤�Ɉ��肵���Ƃ����B���g�̂���藣�����Ɛl�Ԃɐ��܂�ς�邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ����M�������̒����l�ɂ͂���������ł���炵���B���̂����ۂ��A�����l��O�́A����Ȏ��A�吨�W�܂��Ă��̐��S�Ȍ��i���O���璭�߂Ă���̂��킾�����悤�ł���B
�@ ���R�m���w�Z�Ȃǂ��I���A�V�l�m���Ƃ��Đ���ɑ���ꂽ�҂Ȃǂ́A�㊯�ɂ���Ă܂����l�̒����l�ߗ��̎��藎�Ƃ��悤������ꂽ���̂��Ƃ����B�ÎQ���Ȃǂ̕������w�����Đ퓬��W�J����ɂ́A���̒��x�̂��Ƃ͂������ʂɂł��Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƍl�����Ă������炾�����B�͂��߂Čܐl�̕ߗ��̎��藎�Ƃ����Ƃ��A�`���͓f���C�����您����T�Ԉȏ���H�����Ƃ�Ȃ���Ԃ������炵���B�������A�₪�Ă��������s�ׂɑ��錙��������Ⴢ��Ă������Ƌ`���͐����ɍ������Ă���B
�@ �����Ƃ��c�s�������͈̂�ÒS���̉q�����ŁA�Ȃɂ��ɂ��ߗ����E�Q�����Ƃ����B�V�䂩��t���݂�ɂ��č���ɂ����A���̂܂̂Ēu���ĊX�ֈ��݂ɂł������肷�邱�ƂȂǓ��풃�ю��ł������B�ނ��A���̊Ԃɕߗ������͊F����ł��܂��Ă����B
�@ �����l�ߗ��⋭���I�Ɏ�藧�Ă����n�J���҂����������܂ŘA�s���Ďg�����A�J�����I���Ǝ��X�ɎE���Ď��̂���������薄�߂��肷��̂́A���{�̕����������悭����Ă������Ƃł������B�Ƃ��낪�A����Ȏ��A�ǂ��ŒN���ǂ��蔤�𐮂���̂��͔���Ȃ��������A�K���ƌ����Ă悢�قǁA�����ɂȂ�ƈ�̂͐Ռ`���Ȃ������A�����ւƂ��Ȃ��^�ы����Ă����Ƃ����B
�@ �������A���ɂ͓��{���̕ߗ������c�Ȏp�Ŕ�������邱�Ƃ��������悤���B������K�܂ő����j����ʂ��ė��̂܂ܒ��ɒ݂邳��A���ؗ����̓̊ۏĂ������̂Ƃ��Ȃ��v�̂ŏĂ��グ��ꂽ��F��ڂɂ��A���R�Ƃ������Ƃ��������������B���̐l�ԐS���Ƃُ͈킩����Ȃ��̂ŁA����ȂƂ��ɂ͎��R�̎c�s�s�ׂȂǒI�ɏグ�A�ߕ��ƌ������G���S�ɋ��ꂽ���̂��Ƃ����B
�@ �푈�Ƃ͋��C���̂��́\�\���C�ɂȂ�˂ΐ푈�ɂ͑ς��Ă����Ȃ��A����Ȕ��f�͂��ӎ��I�ɎC�茸�炳�Ȃ�������푈�̂��Ȃ��������Ă������Ƃ͂ł��Ȃ��A����ُ͈킪����Ő��킪�ُ�ƂȂ鐢�E�Ȃ̂��ƁA�`���͌��t�����ݒ��߂�悤�Ɍ���Ă����B�Ɠ��̘b�ɂ��ƁA�`���͐Q�Ă��鎞�ȂǂɂЂǂ����Ȃ���邱�Ƃ�����������������A���Ԃ�A����Ȏ��Ȃlj������̐[���S�̏��������ƂȂ����S���Ă��Ă����̂ł��낤�B���A�W�A�Ⓦ��A�W�A��тœ��{�R�𗦂��������̏��Z�≺�m�������́A���̈Ӗ��ł͊F���ߎ҂ł���A�܂������S�̕����҂ł��������̂��낤�B
�@�u�����ɂ͐l��{��Ò����ł��������₩�Ȑl���c�c�����A����C�E���Ȃ��قǐ����ɐ[���،h�̔O������Ă���l�Ԃ��A���ɒ��ʂ����Ɍ���Ԃ̐��ł͋����قǂɕς���Ă��܂����̂Ȃ�B�ނ��낻��Ȑl�Ԃ̂ق����т����肷��قǗE���ɐ킢�A�������G�ɑ��ė�O�ɁA�����Ď��ɂ͎c�E���̂����Ȃ��U�������肷����̂ȂB�ǂ�Ȑl�Ԃ̐S�ɂ��S�∫��������ł���B�{�c�N�A�N�Ȃ���ꂾ�Ƃǂ��ς�邩���Ȃ����c�c�v
�@ ���ꂱ��Ɠ�l�̊Ԃł̉�b����z���邤���ɁA���������́A����Ƃ��`�������C�Ȃ��f��������Ȍ��t��z���o���Ă����B�m���Ɏ����̐S�ɂ��⍓����ȋS������ł���ɈႢ�Ȃ��B���̋S�U���点���܂܂ɂ��Ă������Ƃ��ł���K���ł͂��邵�A�܂��ɗ͂������������̂��Ƃ��v�������A��ɖڊo�߂邱�Ƃ��Ȃ��ƌ�����邾���̎��M�͂Ȃ������B�`���̌����Ƃ����Ƃ���́A�ꎞ��O�̖���u�l�Ԃ̏����v�̂������̃V�[���ɂ��̂܂d�Ȃ銴�������������B
�@
�@ ���G�ȑz���ɋ���Ȃ���I�V���C���o�����́A�Ԃɖ߂�Ƃ����ЂƑ��肵�Ė����̑�O�W�]�䒓�ԏ�Ɍ��������Ƃɂ����B�������A�C�������ւ��Ȃ���铹���삯�����A�����炵�̂������̏ꏊ�ň��𖾂������ƍl�������炾�����B�����A��������]���ɕ����яオ�����S���`���̏d�����t�́A�W�]�䒓�ԏ�ɒ����Ă��Ȃ��A�e�Ղɂ͈ӎ��̕��䗠�ւƏ��������Ă͂���Ȃ������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N10��10��
�k���S�i�F�E���̑�
�@ ���̓��̒��A�v�X�ɓW�]��ɗ����Ė����������낵�Ă݂����A���łɔZ�������������Ă��āA�Ζʂ̂����ꕔ�����ڂɂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�Ⴂ���o�����Ί݂̃J���C�k�v���i�����x�j�̎R�e�͂ނ��A�̒����ɕ����ԃJ���C�V�������������Ȃ������B���̖����Ƃ�����悤�ɁA�قǂ悢���͂��̌̉��o�Ɍ������Ȃ����̂̂ЂƂȂ̂����A�������߂�����͋y���邪���Ƃ��ŁA�قƂ�ǎ��E�̂����Ȃ��Z���ƂȂ�Ƙb�͕ʂł���B
�@ ���܂ɂ����A�ቺ�͂邩�ȌΖʂ������܂�ł��炩���^�Ȃ�~���l�߂ł��������̂悤�Ȕ����Z�����ɕ����邱�Ƃ�����B����Ȏ��̖����͐_��I�Ŕ������B����ɓ��̏o�◎�����d�Ȃ����肷��ƁA�����Ԃ�g�ɐ��܂��Ċ����͂��������傫�Ȃ��̂ɂȂ�B���������̉��Œ��߂閶�̖����Ȃǂ́u���z�I�v�̈��ɐs����B�����A���������������̎p��ڂɂ������Ǝv������A�V��̂ق��ɑ��z�⌎�̉^�s�ȂǁA���X�̏��������͂�����������ŏo�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���R�̂��ƂȂ���A�K�˂鎞�ԑт��ʏ�̊ό��q�̂���Ƃ͑傫�����ꂱ��ł��܂��B
�@ �����ɉf��������������߂悤�Ƃ������̓��̎v�f�͊O��Ă��܂����B�����A�����ɂ܂�������̖����̌i�ςɂ͉ߋ����x���o���������Ƃ��������̂ŁA�Ƃ��ɗ��_���邱�Ƃ��Ȃ������B�Ԓ��ɖ߂�A��A�O���Ԍ��e�����������ƁA���������炿����Ɠo�����Ƃ���ɂ��闠�����W�]��ɂ��܂���Ă݂����A������̂ق��͂����Ɛ[�����ɕ�܂�Ă��āA�܂��������E�͂����Ȃ������B�����ɂ̓J���C�k�v���̉��ɕ������悤�ɂ��Ĉ�ӏ��������������ȕl�ӂ����݂��Ă���B���E�̂������Ȃ�A���̗������W�]�䂩��́A���^�����D����ǂ����u����Ă��邻�̕l�ӂ̂������]�ނ��Ƃ��ł���B
�@
�@ �������W�]�䂩�獪��������ʂւƔ����A�{�V������A���W�ÁA�v�C�n��������C�̌����܂܂ɏ��������ƁA�W�����o�čĂђ�q���ɏo���B�����āA�ʂ肷����̂��X�ŗ[�H���Ƃ�ƁA�����Ε��ʂւƌ������đ��肾�����B�[�R��D�����̂�����̍�����钆�ɑ��s���Ă���ƁA�G�]�V�J��L�^�L�c�l�Ȃǂ����H�e���炢���Ȃ��яo���Ă���������Ȃ��Ȃ��B���H���悭�M�����Ȃ������ɒʍs���p���قƂ�ǂȂ��Ƃ��Ă��邩��A�ǂ����Ă��Ԃ̑��x���オ���Ă��܂��B����ȂƂ��G�]�V�J�ȂǂɂԂ���ꂽ�肵�悤���̂Ȃ�A������肩�A������̂ق��������ł͍ς܂Ȃ��B�r���ŔZ�������N���Ă����̂ŁA�w�b�h���C�g���r�[���ɂ������܂ܐT�d�ɃA�N�Z���ݑ������B
�@ �召�̃z�e����y�Y���X�̗������Ԉ����ΔȂ͂��̂܂ܒʉ߂��A���炭������ʂւƐi���ƁA���܂��ăI���l�g�[�ւƑ����ѓ��ɓ������B���͂�[�����ётɈ͂܂ꂽ�I���l�g�[�́A�R�o���g�u���[�̓����Ȑ���X���_��I�ȐF�̏��ŁA���̌Ζʂɂ͔w����ނ��鎓�����x�∢���x�m���������e�𗎂Ƃ��Ă���B�����A������Ȃ�ł��A����Ȗ�x�������ɃI���l�g�[��K�˂Ă݂����āA�i�F�����߂��悤�͂����Ȃ��B���ۂ̎��̑_���́A�I���l�g�[�̂��������ɂ���铒�u���̑�v�ňꕗ�C���т邱�Ƃ������B
�@ ���܂ł́A�I���l�g�[�T�K�̊ό��o�X�̉�]��ɂ��Ȃ��Ă��铒�̑�����̒��ԏ�ɒ������̂͌ߌ�\�����������B�������番�Ă��̒��ԏ�ɒ����܂łɎO�x�L�^�L�c�l�Ƒ��������B�L�^�L�c�l�͎Ԃ̑O��������Ƃ������̓����̂悤�Ƀo�l���������đf�������蔲������͂��Ȃ��B�����̑̂��x����l�{�̑������傱�܂��Ɠ������Ȃ���ʂ�߂��Ă����B������A���̂Ԃ��Ԃɝ��˂���m���������B
�@ �����x�m�̘[�̍L��Ȏ��ёт̉��ɂ��邽�߁A���Ԃł����K�҂̂قƂ�ǂȂ����̑���A����Ȏ����ɖK�˂�Ȃ�ċC�Ⴂ�������Ǝv���Ă��d�����Ȃ����A����ȋC�Ⴂ�����̑̌�������̂́A���ꂪ���߂Ă̂��Ƃł͂Ȃ������B���ړ��Ă̓��̑�܂ł́A�Ԏ~�߂̃Q�[�g�̌������ɑ����ѓ����������炳��Ɉ�L�����قǕ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�i�b�v�T�b�N�Ƀ^�I���⒅�ւ����l�ߍ��ނƁA���͉����d������ɂ��ĎԂ��~�肽�B�ނ��A���ɎԂ̉e�Ȃǂ��낤�͂����Ȃ������B
�@ �[�����т̒���D���ѓ��ɓ���ƁA������͕����ʂ莽���̈łƂȂ����B�����d���������ƁA�����͂��������̎�悳���������Ȃ��Í��̐��E�ł������B�����K���Ȃ��ƂɁA�c������B�̗����ňŖ�ɐe����ň�������ɂ́A�łɑ��鋰�|���Ȃǂ܂������Ȃ��B����ɁA�Ⴂ������o�R����ɂ��Ă�������A�Ŗ�ɎR������������ƂȂǂ���̂��̂������B
�@ ���邢���Ƃ͂������Ƃ��Ƃ�������̕����̂��Ƃɂ����āA�䂪���̖�̐��E����͐^�̈ł��قƂ�ǎp�������Ă��܂����B���܂ł́A�O�S�Z�\�x�����Ǝ�������n���Ă��l�H�̖����肪�܂�������������Ȃ��^�̈łƂ������̂�T�����Ƃ̂ق�������B�V�[���Ƃ����ł̉��������������鎽���̑�C�ɂ́A�݂����܊����s���S�点�Ă����s�v�c�ȗ͂����������̂����A�Èł̂�����ȓ������Y����Ă����v�����B�Ȃ̍זE�̋��X�ɂ܂ł��݂킽��A�����������������Ă����{���̈ł��v�X�ɑ̊����邱�Ƃ��ł��A���͂�������������Ȃ����B
�@ �X�̉�����͎��ܖ钹���s�������̖����������Ă����B�����Ɏ����X���Ȃ����A�O�\���ѓ�������ƁA�����߂��ŗ����̉��̂��邿����ƊJ�����ꏊ�ɂł��B�������ق��Ȃ�ʓ��̑ꂾ�����B����O���ɃU�[�U�[�Ɨ��ꗎ����ꂪ����A���̑�̐��͂��̎�O�̏��L���r�̒��ւƗ��ꍞ��ł���B����ɁA���̒r�̐��́A�ׂ����H�`���ɋ߂��̑�ւƗ���o���Ă����B
�@ ��͂�[��ɂ��̓��̑��K�˂��Ƃ��A���̑ꉺ�̒r�̂܂��̑��n�ɂ̓G�]�V�J�̌Q�����āA���C�g��������ƁA�ނ�̖ڂ���Ăɐ����F�ɋP���Č��������̂������B�����A���̖�͑�̐����������Ђ�����ł̒��ɂ����܂��Ă�����肾�����B�����d���������ĈÈł̒��ɗ����A�������Ђ炯������̋�����グ��ƁA�_�X�ƋP�����������X�̎p�����]���ꂽ�B�����̐��X�̏u���́A�܂�œV��͂邩�ȂƂ���ɂ��鑺�X�̓��̂悤�ɂ��v��ꂽ�B�����Ă��̌��́A���\���N���̎����đ̓��[���ɂ��܂�����A���������������̋L����h����܂��ł����Ă���邩�̂悤�������B
�@ �����Ȗ؋���n���đꉺ�ɋ߂Â��A���ꗎ���鐅�Ɏ�������o���ƁA�w��ɉ��������G���`����Ă����B������Ƃʂ�߂ł͂���̂����A���̑�Ƃ������̎����ʂ�ɁA����͉���̑�Ȃ̂������B�������A��̐��̒������ޒr�̐��̂ق��������������B���́A��̉E��̋}�Ζʂ�D���ד��`���Ɍ���̂���Ƃ���ڎw���ĕ����o�����B�O�A�l���قǓo�����Ƃ���ɂ͈ȑO�ɂ͂Ȃ����������ȊȈՍX�ߏ��Ƃ�����ŋ߂̂��̂炵���~�`�̘I�V���C���݂����Ă����B��Ԃɓ����҂����邱�ƂȂǂ͂Ȃ���z�肳��Ă��Ȃ�����A�ނ��Ɩ��̗ނ͂��������Ȃ��A�����d�����������肾�����B
�@ ���͂������炳��ɏ�ւƑ����}�ȓ����A�O���قǓo���Ă������B����ƌ��o���̂��铒�̑�̌��p�����킵���B�[�����тɕ���ꂽ�R�̎Ζʂ̈�p�ɂ��������V�R�̑��ň͂܂ꂽ�ג��������������āA�����ɂ���Ɖ��N���o�Ă���̂��B���C�g�Ă�ƈ�u�����ۂ������͂������A���ۂɂ͗ǎ��̓����ȉ���ł������B�N���o�Ă��邨���̉��x���l�\�x�キ�炢�Ȃ̂ŁA�̂�т�Ƃʂ�߂̓��ɂ���̂��D���Ȑl�Ȃǂɂ͂��傤�ǂ悢�B�@
�@ �ȑO�̂悤�ɂ��̌���̂����ɒ��ڐg�߁A������䂭�܂Ŕ���������Ƃ��ł�����Ǝv�����̂����A�c�O�Ȃ��Ƃɓ����̘e�ɂ͓����֎~�̕\���Ƃ��̗��R���L�������D�������Ă����B���̉��}���K����Ƃ�����ϒ������̂��̂��Ƃ������Ƃ͈ȑO����m���Ă����̂����A�k��Ȃǂɂ��ߔN�̌��������ɂ���Ċw�p�I�ɂ��ɂ߂ċM�d�ȑ��݂ł��邱�Ƃ������A�����ۑ����邽�ߓ����֎~�̑[�u���Ƃ���悤�ɂȂ����炵���B�ǂ���牺�̐V�I�V���C�͂��̑�ւƂ��đ���ꂽ���̂̂悤�������B
�@ ���̉���ɂ̓}���K�����n���Ă���̂����A���ނ̃}���K���_���ۂƂ��������������̃}���K���������_�������ς�����B���̂��߁A����t�߂ⓒ�̑�̗����ɂ͌��݂ł��_���}���K���z�����������Ȃ̂������ł���B���̂��͓̂����Ȃ̂ɍ����ۂ��F�Ɍ�����̂́A�}���K���_���ۂƂ���ɂ���Đ������ꂽ�_���}���K���z���ꕔ��ʂɕt�����邽�߂炵���B
�@ �����a������܂��Ԃ��Ȃ��O�\�����N�O�̎���ɂ́A�n����̂�����Ƃ���ł��̂悤�Ȍ��ۂ��N�����Ă����悤�ł���B�����A���݂ł͂��̂悤�Ȏ��ۂ�������Ƃ���͐��E�I�ɂ��ɂ߂ċH�ŁA����܂Ŕ������ꂽ���l�̃P�[�X�̂Ȃ��ł��A���̓��̑�̎���͍ő�K�͂̂��̂��Ƃ����B�k�嗝�w����H�ƋZ�p�@�̌����҂����܂������𑱂��Ă��邪�A�ŋ߂ł͊C�O�̐�匤���҂̗��K�������Ȃ��Ȃ��悤�ŁA���̓���Ȏ_���}���K���z�����e�[�}�Ɋw��Ȃǂ��J����Ă���炵�������B
�@ �N�����ĂȂ��Ȃ���������ǁA����Ȉꑽ������Ƃ����Ă͓�������킯�ɂ������Ȃ��B���̂��ߎ�������̒��ɍ������ꓒ�̉�������m���߂������ň����Ԃ����B�����āA���̂����ɐV�݂��ꂽ�I�V���C�̂Ƃ���ւ����ƁA��}���ŕ���E�����D�̒��ւƔ�э��B�₦�ԂȂ��N���o�邨���̉�������X�Ƃ����āA�܂��ɂ��̐��̓V�����̂��́A������������X�̒��̏������������ł�����̎p�߂Ă�����������Ȃ����A����Ȃ��ƂȂǂ��������C�ɂȂ�Ȃ������B
�@ �����ɉ����d���������Ă݂�ƁA��u�ɂ��Ă�����͔Z���łɕ�܂ꂽ���A���łɖڂ��łɂȂ�Ă����̂ŁA�����̎�悳���������Ȃ������̈ł̒��ɂ���Ƃ��������ł͂Ȃ������B����ɊJ�����܂邭�����Ȗ��ł́A�D�P�̖������Ս��̈ꓙ�����F�K���A���̈��b��i�������ł����邩�̂悤�ɐ���������Ă����B
�@ �Ԃɖ߂��Ă��̂܂ܖ���A�����㎞�ɖڊo�߂����́A������x���̑�ɏo�����Ē����C�𗁂т邱�Ƃɂ����B�[�X�Ɣɂ���X�̗ɂ���ď��ꂽ��C�͑u�₩���̂��̂������B���̑�t�߂ɂ́A�����ɂ���Ă����炵���O�A�l�l�̃c�[���X�g�̎p����������ꂽ�B���̂Ȃ��̈�l�������̗��ꍞ�ޒr�̒���`���Ă���̂ŁA�Ȃ낤�Ǝv���Ȃ��炻�̂ق��ɖڂ����ƁA���������Ƃɋ��̌Q���j������Ă���ł͂Ȃ����B�召�����̋��̂��ڂɂƂ܂������A�傫�����͎̂O�\�Z���`�قǂ�����悤�������B�ȑO�ɂ͋��e�炵�����̂ȂNJF���ł���������A�ǂ���炻���͍ŋ߂ɂȂ��đ�ɐB�������̂炵���B
�@ �k�C���̌k���Ƃ����Ƃ܂��v�������Ԃ̂̓C���i�̒��Ԃ̃I�V�����R�}�����A����Ȑ��ɐ��ރI�V�����R�}��������Ȃ�ł�����̓��̒��ɐ������Ă���킯���Ȃ��B�悭�悭�ώ@���Ă݂�ƁA�����Ŏ����Ă���M�ы��ɂǂ������Ă���B��������������ނ����ł͂Ȃ������������B�r�𐅌��Ƃ���ח��̂��������ɉ��i�ɂ��킽���Ėڂׂ̍����l�b�g�������Ă���Ƃ�����݂�ƁA���������ɓ����o���̂�h������Ȃ̂��낤�B�����̋���N���������ł����Ă���̂��낤���Ƃ��v�������A����ɂ��Ă͂ǂ����s���R�Ȋ����������B
�@ �r���牷���̗���o�鐅�H�����ɉ����ɕ����Ă݂�ƁA������Ƃ���ɑ̒���A�O�Z���`�̒t���炵�����̂̎p���������B���̐��H�͕S���[�g���قǂ������Ƃ���ł�͂萅���̍������Ȍk���ƍ������Ă�������A���̒n�_���牺�����ɂ����̋��͐������Ă���ɈႢ�Ȃ��B�ǂ���������ł���Ȃ��ƂɂȂ����̂��͂킩��Ȃ��������A��̐��Ԍn�ɑ傫�ȉe�����ł�̂ł͂Ȃ����ƐS�z�ɂȂ��Ă����B
�@ �C�����悭�����C�𗁂тĂ���r�̂Ƃ���ɂ���Ă���ƁA���傤�Ǘі쒡�̐X�ъĎ����炵���j������Ă��āA�Ȃɂ����ӂ̏��`�F�b�N���Ă���Ƃ��낾�����B�����ł�����Ɛ��������A�Ȃ��r�̒��ɋ�������̂��q�˂Ă݂��B����ƁA����͂Ȃ�Ƃ���X�������Ȍ����ŁA���̈ӊO�ȗ��R��������Ă��ꂽ�B
�@ �ނ̘b�ɂ��ƁA����r�ɐ������Ă���̂̓e���s�A��O�b�s�[�Ȃǂ̔M�ы��Ȃ̂������������B���N�O�A�S�Ȃ��N���������̋�������A���̌��ɐB���Ă���Ȃ��ƂɂȂ��Ă��܂����̂��Ƃ����̂ł���B�r�����������߁A�����ł��O�\�Z���`�ȏ�ɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ��̂����������A�������������邱�Ƃ͑�ύ���ł���炵�������B
�@ ���Ԍn�ւ̈��e���������ꂽ���������Ǘ����ǂ��A�ߋ��O�x���r�̐���r�����ɐB�������̊��S���������݂��悤�ł���B�����A�����̏����ȗ��܂Ŏ�菜�����Ƃ͕s�\�Ȃ����ɁA�M�ы��̗��͊����ɋ������߁A�r�ɉ������߂�Ǝc���ꂽ�����z�����Ă����܂����Ƃ̏�Ԃɂ��ǂ��Ă��܂��̂��������B���܂ł͕t�߂̌k���̂��Ȃ艺���܂ł��̐����͈͂��L�����Ă��邪�A�K�����n�_�����ł͐������}���ɉ����邽�ߐ������s�\�ŁA�Ȃ�Ƃ������������Ă���Ƃ����B
�@ ���̊Ď����͂���ɋV����悤�Șb�����Ă��ꂽ�B�܌����̗Z����ɓ~������ڊo�߂��q�O�}�́A�܂��R�ɉa�ƂȂ���̂������Ȃ����߁A���̒r�ɂ���Ă��Ē��̋���_���悤�ɂȂ��Ă��܂����Ƃ����̂ł���B�ό��q�ɖ���̂��Ƃ����������ς�����A�Ǘ����ǂ��_�o���g���Ă��邻�������A���S�̑Ή���͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��������B������т��ɕ����鍠�ɂȂ�Ɖa�ɕs���R�͂��Ȃ��Ȃ邩��A���̎����͑��v���Ƃ̂��Ƃ��������A���͓��S�M���b�Ƃ���������Ȃ������B
�@ �����Ƃ��m�炸�A�[��A�����̘I�V���C�ɓ����ĕ@�̋C�����������̗l�q���A�[�����т̉����炶���ƉM���Ă����q�O�}�Ȃǂ�������������Ȃ��B�܂��A���܂�E�}�����ɂ������Ȃ������낤���A�ƂĂ��ꏏ�ɉ���ɂ���C�ɂ��Ȃ�Ȃ��������낤����A����̂ق����������Ă��ꂽ�ɈႢ�Ȃ����A���������M�N���Ƃ�������Ȃ�Ƃ��N�}�����b�ł͂������B�����������ɁA��Ӓx���Ƃ�ł����ɂ���Ă��ĘI�V���C�ɓ����Ă����ȂǂƁA�Ď����ɐ����ɍ�������킯�ɂ������Ȃ������B
�@ �w�p����ɂ߂ċM�d�ȃ}���K�������邽�߁A�S�Ȃ��ό��q�ɂ���Ă���ȏ�t�߂̊����r�����͔̂����Ȃ���Ȃ�܂���B�܂��A�q�O�}�Ȃǂɂ�閜��̎��̂ɂ����Ȃ��Ȃ���Ȃ�܂���B������A�߂������ɉ�������͑S�ʋ֎~���A�V�݂̘I�V���C���X�ߏ����x�e�����������Ă��܂����ƂɂȂ��Ă��܂��\�\�Ď����̒j�͍Ō�ɂ���Ȍ��t��t���������B
�@ �ނ̌����S�Ȃ��ό��q�̈�l�ł��邩������Ȃ����́A���̌��t�������ق��ĕ��������Ȃ��������A���̑厩�R�̒��̖��������ꂪ���肨���߂��Ǝv���ƁA�Ȃ�Ƃ��c�O�łȂ�Ȃ������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N10��17��
�k���S�i�E�\���x�R�[
�@ �����Ϗ��q�`�ɂ���ė������́A��䂩��t�F���[�ł���Ă��鋳���q�̂r�N�̓�����҂����B���܂��ܓd�b���������Ƃ����������ŁA�C����ǂ����Ƃ����A�ǂ����Ȃ�k�C���ʼn���Ƃ������ƂɂȂ����̂������B�S�̕Ћ��ɂ́A�k�C���͏��߂Ă��Ƃ����r�N�ɎԂ̉^�]��C���A������͏���Ȃł̂�т�ƕ��i�ł��y�������Ƃ������_���������B�l���Ă݂�ƁA����ő��l�Ɏ����̎Ԃ��^�]���Ă��炢�A����ȂŃ{�[�b�Ƃ���Ȃ�Ă����Ȃ��������ƂȂ̂��B
�@ ���D���Ă����r�N���E���ƁA�݂��̈��A�����������ɕx�ǖ�ڎw���đ���o�����B�k�C���ɑ؍݂ł���̂͂��Ɠ�������Ƃ������Ƃ������āA�ǂ��ł���������A�C�͂Ƒ̗͂̑��������葖���낤�Ƃ������ƂɂȂ����̂������B��ʂ���x�ǖ�X���������쉈���ɖk��A�����A�芥�ƒʉ߂����Ƃ���Ńn���h�����r�N�ɈςˁA���Ƃ͂Ђ�����S�g�����E��Ԃɂ������Ƃɂ����B
�@ ��x�ǖ쒬�̋��R���߂������O�����ɂԂ������Ƃ���ʼnE�܁A�������炵�炭�s�����x�ǖ�s����[�̓��R�ō��܂����B�q�{����̃e���r�h���}�u�k�̍�����v�̕���Ƃ��Ė������[�����ʂւƑ������ɓ��邽�߂������B���̓��R�ō��܂����ɂ��炭�i�ނƓ�x�ǖ쒬���Ђɓ���B���̊��ЂƂ����Ƃ���́A�������߂Ėk�C���̑�n�݂��߂��z���o�[���ꏊ�ł��������B
�@ ���ɂ͏��w���̎��ȗ����ʂ𑱂��Ă�����ːM�j����Ƃ�����w�N��̗F�l���������B���������Ԃ�Ɛ̂̂��ƂɂȂ邪�A��˂���̌������ɏo�Ȃ��邽�ߓ�x�ǖ�ɂ���Ă������́A���Ђ̉w�ŔނƏ��߂đΖʂ����B���قŐ��A���D���~�荪���s���̗�ԂւƏ��p���ۂɃR���N���[�g���̒ʘH��v���b�g�t�H�[��������͂������A�����ʂ�̈Ӗ��Ŗk�C���̓y�̂͂��̎������߂Ă������B
�@ �������̉�z�ɂЂ����Ă��邤���ɁA�͂�Ԃ͘V�ߕz�ɍ����|����A����ɍ��킹�Ă������ɓW�]���J���Ă����B�Y��ȏ\���x�R�[�����ɍL�����q����_���K�˂�Ȃ�A���R���炱�̎R�[���ɓ���A�V�ߕz�A�[�����o�č����Â����ɔ��l�u�˂ւƔ�����̂��x���X�g�ł���B�̂ƈ���ē��H���f���炵���悭�Ȃ�������A���S�h���C�o�[�ł����Ȃ��B
�@ �ǂ��܂ł��q���n�┨�n�̍L������₩�ȋu�̌������ɂ́A�^���ȑ���w�i�ɂ��Ĕ����_�����������ƗN�������Ă���B�u���̋u���z�����Ƃ���ɂ͂��������ǂ�Ȑ��E���҂������Ă���̂��낤�H�v�\�\���l�̋��Ɉ��D���Ȃ����тт�����ȑz����N���N��������̂��A���̈�т̕��i�̓������B���[���b�p�̓c���n�т̕��i��ɒʂ�����̂������ɂ͂���B
�@ ���܂ł����ΖL���ȗ��_�n�тƂȂ��Ă��邪�A��˂���Ǝ��Ƃ����߂đΖʂ������ɂ́A���̋ߗׂ̊J��_�Ƃ̐����͂����ւ�Ɍ��������̂������B�u�k�̍�����v�̏�����i�ɕ`���ꂽ�h���n�����������A����ɉߍ��Ȍ����Ɛl�X�͌����������Ă����̂ł���B�����A�܂��Ⴉ������ːM�j����́A����u�肵�A�ꋉ�ƒn�ƌĂ��\���x�R�[���̕��Z�̋��t������Ă����B�~��ɂ͍���̂��ߊO���Ƃ̉������܂������ł��Ȃ��Ȃ邻�̕��Z�ŁA�ނ͖��N�Z�����߂����k�����Ƌ��������𑗂��Ă����B�e���𗣂꒷���~���炷���Z�̐��k�����́A�F�p�C���b�g�t�@�[���ƌĂ��J��_��]���҂̎q�������������B
�@ ��˂���́A�~��ɋً}���Ԃ��������Ƃ��ȂǁA�X�L�[���g���A�Ґ���̒������āA�������Ŗ{�Z�Ƃ̊Ԃ��������Ă����悤�ł���B�����ŃX�L�[����B���A���t�ɂȂ��Ă����X�L�[����ňꋉ���Ƃꂽ�Ə��Ă������̂��B����N�̓~�ɒ�˂��㋞�����Ƃ��A���y�Y�ɉ����������Ɛq�˂�ƁA�q�������ƈꏏ�ɗV�ׂ���̂��~�����Ƃ̂��Ƃ������B�����Ńf�p�[�g�ɍs���ăQ�[���Z�b�g�����݁A������v���[���g�������ƂȂǂ����܂͉��������z���N�����ꂽ�B
�@ ���Ă͂����F�ɕ�܂�Ă����x�ǖ��т��A���܂ł͖��邭�b�ݖL���ȓy�n�ւƕϖe�𐋂����B��˂��Q�H�����ɂ��Ĉ�Ă��q�������̊��l���́A���Ԃ�A���܂ł͂��̎��ӂ̑�_��̌o�c�҂ɂȂ��Ă���ɈႢ�Ȃ��B�������A���H�̐���������I�ɐi�݁A�ǂ��̉ƒ���Ԃ������A�������������قǂɌ��サ�����܂ł́A�ꋉ�ƒn�̕��Z�ȂǂƂ������͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂������Ƃ��낤�B��˂�������܂ł͈���s�ɋ����\���A���s�̒��w�ɋΖ����Ă���B�͂��ߍ���̋��t�������ނ́A���̌�A���y����Ƃ������y��{�i�I�Ɋw�сA���݂ł͖k�C���̑升���c���w�����鍂���ȉ��y���t�ɂȂ��Ă���B
�@ ���₩�ȗ̋N���̂ǂ��܂ł��Â����i�ɐ�������Ȃ��瑖���Ă��邤���ɁA�Ԃ͘[���̏W���ɓ��������B�u�k�̍�����v�̎B�e�ɗp����ꂽ�����̃Z�b�g�́A�ȑO�������ꏊ�Ƃ͈Ⴂ�A�[���̐X�Ƃ����L�����ёт̒��Ɉڂ���Ă���B�[���̐X�̓����ɂ͑�^�ό��o�X�Ȃǂ���������e�ł��钓�ԏ���݂����Ă����B����܂Łu�k�̍�����v�̎B�e�ŗp����ꂽ�e��Z�b�g�̌����́A��̐�����X�̒��ɓ_�X�Ɣz�u����Ă����B�r�N�ƂƂ��ɂ���ȐX�̒����߂���Ȃ���A�������̂Ȃ��ɐl��{�̌������Ɖ��������߂��q�{������̎p���ӂƑz�������ׂ���������B�@
�@ ���̒n��ɂ����h���}�u�k�̍�����v�ƕx�ǖ�m�̐��݂̐e�Ƃ��āA�x�ǖ�Ƃ����n����S���I�ɍL�߂��q�{����̌��т͑傫���B�������A�x�ǖ�́A�Y��Ȏ��R�̕�ɁA�W���K�C���A�J�{�`���A�g�E�����R�V�A�������Ȃǂ̍앨�̎Y�n�A���x���_�[���͂��߂Ƃ��钿�����Ԃ͔̍|�n�A����ɂ̓X�L�[�̍D�K�n�Ƃ��āA�̂���ꕔ�̐l�ɂ͒m���Ă����B�����A����炪�q�{����̔��M����h���}�̐��E�ƗL�@�I�A�d�w�I�Ɍ��т����Ƃɂ���āA�x�ǖ�̖��͈���S���I�ɒm����Ƃ���ƂȂ����̂������B�����ɂ����߂͂����̂�����A���̈�ʂ�����Ȃ�ɂ������ɂ͈Ⴂ�Ȃ����A���̂ق����͂邩�ɑ傫���������Ƃ��낤�B
�@ ���Ďዷ��ђ��̎�B��H���ɏ�����ł́A��Î҂ō�Ƃ̐���ׂ�����͂�ŁA���N�̂悤�ɗl�X�ȍÂ����J����Ă����B����Ȑ܂ȂǁA�q�{������́A�}���N�炳��A�i�Z�コ��A�D�J�����Y�����ƂƂ��ɁA�g�[�N�V���E�ɂ悭�o�ꂵ�Ă���ꂽ�B����搶�ɂ͂��낢��Ƃ����b�ɂȂ��Ă������Ƃ������āA��H���ɂōÂ���������Ƃ��ɂ́A�����g���ዷ�ɏo��������̗����߂Ă����B���鎞�A�q�{���A�x�ǖ�̘[���Ō}�������߂Ă̓~�̋�J�k���I���ꂽ���Ƃ��������̂����A���̍ۂ̘b�̈�[��ˑR���͑z���o�����B
�@ ������ˑR���ꂽ�n���̊���݂����Ȑl�ɁA�u�ǂ̕��ʂ̐��Y�W�̂��d���ł����H�v�q�˂��A��u�S�O�������ƁA��Z�Ɂu�h���}�̐��Y�W�ł��v�Ɖ�����ƁA����͍��f�����悤�ȕ\����ׂċ����čs�����Ƃ����B���ۂɕx�ǖ�ł̐����ɗn�����݁A�n���̐l�X�̑傫�ȐM�����������܂łɂ͑�ςȋ�J���������悤�ł���B
�@ �뉺�O�\�x�ɋ߂������̓��̂��ƁA�ƒ��̐����𓀌��j�������Ă��܂��A�g�C�����g���Ȃ��Ȃ����q�{����́A�ˊO�ɏo�Ē�̐�̏�ŗp�𑫂����Ƃɂ����Ƃ����B�Ƃ��낪�A�r�������V�����m�������܂��ł�������Ă��܂��ȂǂƂ͑z�������Ă��Ȃ��������߁A�����ɂ��A���̉s���������[���ɂ��K�����낵�A�Ђǂ�����������Ă��܂����Ƃ̂��������B�h���}�̓o��l�����A�o���o�D���̂��̂��A����ɂ͂��̕���ƂȂ�[���E�G�����ɕω����ϗe���Ă�������h���}�a���̗����ɂ́A�l�m��ʂ���ȋ�J�̐��X����߂��Ă����̂ł���B
�@
�@ �[�������Ƃɂ��A�z�D�ʁA�\���x����A�]�x��ƌo�Ĕ��l���ʂւƌ������r���A�\���A���w�ɂ����L�����̌������ɁA�|�v���̓Ɨ������|�c���Ɨ�������݂̕��i�ɂ߂��肠�����B��Ƀ��N���N�ƗN�����ϗ��_���A���|�I�ȗ͊��������Ă��̕��i����肢��������ې[�����̂Ɏd���ĂĂ����B
�@�u�J�����_�[�̎ʐ^�Ƃ�������ł��ˁI�v�ƁA�r�N�����Q�̐����������B�x�ǖ����l��т̕��i�͑O�c�^�O�̎ʐ^�ɂ���Đ��ɍL���m����Ƃ���ƂȂ����B�Ȃ��ł��L��Ȕ��n�Ƃ����ɐ�����|�v���̎��A����ɂ͂��̔w�i�̏\���A���E�s�Ȑϗ��_�Ȃǂ́A�J��Ԃ��J��Ԃ��ނ̍�i�̃��`�[�t�ƂȂ����B�r�N�́A�E��̃J�����_�[�Ŕ��l�u�˂̕��i�ʐ^��ڂɂ��Ĉȗ��A����Ƃ��k�C���ɍs�������Ǝv���悤�ɂȂ����Ƃ����B���̕��i�ʐ^�Ƃ����A�O�c�^�O�B�e�̍�i�������\���������B
�@ �ӂ���Ȃ�A�u�����̌i�F�̓J�����_�[�̎ʐ^�Ƃ�������ł��ˁv�ȂǂƂ��������z�����ɂ����r�[�A�u��������ƈႤ�������͂Ȃ��̂����H�A���O�����������̂��߂ɗ����Ă�I�v�ƕ���̂ЂƂ����т������Ȃ�Ƃ��낾���A���̎�����͎����ւ�ɔ[�����Ă��܂����B�O�c�^�O�̎ʐ^������ȊO�̕\���������ʂقnj����ɂ��̒n�̕��i���B�肫���Ă��邩�A�����Ȃ���A�����̕��i���A�N�̖ڂɂ��قƂ�Ǖς��Ȃ�������قǂɁA�N��ȓ����Ɗm�ł��鑶�݊����������킹�Ă��邩��Ȃ̂��낤�B
�@ ��O�ɔ���\���A������Ȃ���]�x����ӂ��U�I���A���l�u�˂�����n�߂鍠�ɂȂ�ƁA�݂�݂�V�}�ς��A�J���������~�肾�����B���̋�͗l�ł͈��x�R�[��K�˂Ă��d�����Ȃ��Ƃ����킯�ŁA�Ƃ肠��������ڎw���đ��肾�����B�����Ĉ���𑖂蔲���A�w�_�����ʂɒʂ��鍑���O�㍆�ɓ��鍠�ɂ́A�������Ă�����͂�������Â��Ȃ����B����������ɍ��킹�邩�̂悤�ɉJ���͂܂��܂����܂�A���ɐ₦�ԂȂ��M�������鐦�܂�������̗��J�ƂȂ����B�����A���D���ȉ�X��l�@�́A�v�X�ɏo�������͂���ȍ��J�̐���ƁA�������ŋ�Ɉ�Ȃ��`�����`�̖���������䂭�܂Ŋy���B��ԂȂǂ܂��������Ȃ��s���҂̎��ɂ���A�J�[�E�E�H�b�V���[�Ȃ݂̐����Œ@�����Ă��邻�̖҉J�́A�傢�Ɋ��}����Ƃ���ł��������B
�@ ����Ȑ���s���̂Ȃ��ʼn��C�Ȃ����̑�̘b�Ȃǂ������Ƃ���A�r�N������Ƃ����ꂩ�炻���܂ōs���āA�������ꕗ�C���тĂ݂����ƌ����o�����B���S�ł̓q�O�}���o�Ă��m��Ǝv�������A�N�}�����Ăǂ����H���Ȃ�Ⴍ�Ĕ��������Ȑl�Ԃ̂ق����悢���낤����A������܂Ŕ�Q���y�Ԃ��Ƃ͂Ȃ����낤�B����Ȃ�Ƃ����킯�ŁA�ēx���̑�Ɍ��������Ƃɓ��ӂ����B
�@ �����܂ł͂悩�����̂����A���̂��Ƃł�����Ƃ����v�Z�Ⴂ�ɋC�Â������͂߂ɂȂ����B���j�̗[���̂��Ƃ����A�R�[�X�͎�v�����`��������A�܂���ɂ�����ł������������邾�낤�Ƃ����킯�ŁA�c���ʎO���̈���w���R���v�����ڂɌ��Ȃ��爮���ʉ߂����B�Ƃ��낪�A���������ƂɁA�ǂ��܂ő����Ă����������S�����Ă���̂ł���B���ʒ��A��㒬�A�w�_���Ƌ�������T���Ȃ��瑖�������c�ƒ��̋������͊F���������B�w�_�����炳���͎R�x�H�ɂȂ�̂ŁA�����z���эL���̕��암�ɓ���܂ł͋������ȂǂȂ������ł������B
�@ ������Ƃ����Ĉ���܂ň����Ԃ��̂�ᛂȂ̂ŁA�R���v���ɂ݂Ȃ���A�Ƃ肠�����R�z�������A�эL���̏�m�y����ڎw�����ƌ��f�����B��m�y�܂ōs���A�����ŔR����ɂȂ����Ƃ��Ă��Ȃ�Ƃ��Ȃ邾�낤�Ƃ����Z�i�������B���_���t�߂ō����O�㍆�ɕʂ�������A�O���g���l�����čf���ΔȂɑ��������ɓ��������A���E�͂���߂Ĉ��������B�J�͂���A�����ɍ��x�̂���R�x�n�䂦�Z�����������߁A���H�̃Z���^�[���C���������Ă͂قƂ�lj��������Ȃ������B���R�A�E����ނ��A���ꂽ���Ȃ��Ԃł�����Ȃ�̓W�]���y���߂�Ƃ���Ȃ̂����A���̔ӂɂ������ẮA����ǂ���̘b�ł͂Ȃ������B
�@ �Ȃ�Ƃ���m�y�s�X�ɒH�蒅�����܂ł͂悩�������A�܂��ߌ�㎞�O���Ƃ����̂ɋ������͂�͂�ǂ������Ă����B���̑�̂���I���l�g�[�Ɍ������ɂ͑�����ʂ�ڎw���Ȃ���Ȃ�Ȃ��������A���̗l�q���Ƒ���t�߂̋��������݂ȕ��Ă������������B���낢��ƌ����������ʁA�����͈Ⴄ���эL�s�܂ōs�������Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ����B�����ŕS�L���ȏ�̖��ʓ��ɂȂ邵�A���������R�����эL�܂ł����ǂ������������������A��ނȂ��Ƃ������f�������B�R���ꂾ����Ƃi�`�e�ɂr�n�r�����߂�̂́A������Ȃ�ł���Ȃ����������A���Ƃ�����Ȃ��ƂɂȂ�ɂ��Ă��A�i�`�e�̏o����n�̂���эL�ɂ������ł��߂Â��Ă������ق����悳�����ł������B
�@ �_�ł��Ă������ʃ��j�^�[�̐ԃ����v���Ƃ��Ƃ��_�����ςȂ��ɂȂ�A�R���ꐡ�O�̏�ԂɊׂ������A�K���A�h�����đэL�̒��S�X�ɂ��鋋�����Ɋ��荞�ނ��Ƃ��ł����B�������Ȃ���A�W���ɂ���܂ł̌o�܂�b���ƁA�ŋ߂͖k�C���̋������̏ꍇ�A�s�s���̑�K�̓X�e�[�V�����������ẮA�E�B�[�N�f�C�ł��[���Z���ɂȂ�ƕ��Ă��܂��Ƃ̂��Ƃ������B
�@ ���������I���������Ԃ����Ԃ̃G���W������肽�ď�m�y�܂ň����Ԃ�����X�́A�������炳��ɃI���l�g�[�Ɍ������Ĕ������A�ߑO�뎞���ɓ��̑�����̒��ԏ�ɒ������B�[���̍��J���M�����Ȃ��قǂɏ��͐���n��A�����̐��X���u�Ŗ����グ���悤�ȉs�������Ă����B
�@ ���̑O�X���̖�x���A��l�����ŖK�˂����Ɠ��l�ɁA�����̈łɕ�܂ꂽ�[�����т̒�������ĉ�X��l�͓��̑�ւƌ��������B���ɂ����o���Ȃ��������A�����́A�����o�Ă����������Ȃ��قǂ̐^���Èłɂr�N���������肵�Ȃ����Ɠ��S�Ђ����ɋC���܂킵����������B�����A�w������ꉞ�͒T�����ɏ������Ă����Ƃ��������̂��Ƃ͂����āA�قǂȂ����̈Â��ɓK�����A�ł̐��E�̂����͂�����Ȃ�Ɋy���݂͂��߂��̂͂������������B
�@ ���̑�̘I�V���C�̓���S�n�͑����ς�炸�f���炵�������B�������芴�������l�q�œ��D�ɐg�߂�r�N�̘e�ŁA���͓��ɂ������܂�ɂ��Ă����n�[���j�J�𐁂����B�u���R���v��u�r��̌��v�Ȃlj����������Ȃ��\�Ȃقǂ����h���[�őt�ł��̂ŁA�N�O���̈ł̒��ł̉�������t�����t��Ƒ��������B���̃n�[���j�J���t���A���́A����ɔ����Ẵq�O�}�悯�����˂Ă������ƂȂǁA�C�����悳�����Ɏ����X����r�N�ɂ͑z�������Ȃ��������Ƃ��낤�B
�@ �쎟�n���_�̉�݂����Ȑg�ɂ���A���ꂪ�K���������̂��ǂ����͂킩��Ȃ����A�q�O�}�͂��납�A�G�]�V�J�ɂ��L�^�L�c�l�ɂ��t�N���E�ɂ��o�������ƂȂ��������I���A��X�͖����ɎԂ̂Ƃ���ւƖ߂蒅�����B�k�C�������̉Ă̖閾���͂Ƃ��ɑ����B�܂��ߑO���Ƃ����̂ɓ��̋�͂��������Ԃ�Ɩ����ł��āA�捏�܂ł��̋P�����֎����Ă������X���A���X�ɂ��̎p����߉B�����Ƃ��Ă���Ƃ��낾�����B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N10��24��
�k���S�i�E�ڎw���ϒO�����I
�@ �I���l�g�[�̐��ʂ͖��邢���̗z���̂��Ƃłǂ��܂ł������P���Ă����B���ӕ����G�������h�O���[���ɁA���̂����������W���R���u���[�ɁA����ɂ��̌������̐[�������T�t�@�C�A�F�ɍʂ�ꂽ���̏��̔������́A�����鑼�̏��X�̒ǐ��������Ȃ��B�Ί݂̌����т̂����w��ɂ͎������x�ƈ����x�m�̑o�A�܂�Ŏ��������̊Ԃɐ��܂ꂽ���������̂Ȃ������������ł����邩�̂悤�ɕ����ނ������Ă���B����A���ہA���̃I���l�g�[�݂����炵���̂́A�[���ł������G��Ȃ�����̉ΎR�Ȃ̂������B
�@ ���ۂɂ̓I���l�g�[�Ƃ����A�C�k��́u�V�������v���Ӗ����Ă��邩��A��̉ΎR�̊Ԃɐ��܂ꂽ�u�����v�Ƃ����\���͓K�łȂ���������Ȃ��B�������ɁA�Β��ɂ͐��v���ċv�������Ȃǂ����������邵�A�ӏH�Ȃǂɂ͌ΔȈ�тɕ��҂������͋C���Y������A�V�������Ƃ����ď̂̂ق����ӂ��킵���̂�������Ȃ��B�����A���邢���z�ɌΖʂ��Ƃ炳�ꂽ�V�Ί��̃I���l�g�[�́A�ǂ��݂Ă��u�V���v�Ƃ��������ł͂Ȃ��B
�@ ���c�͐s���Ȃ����A���ꂩ�疾���ɂ����ē����܂ł̈�働���O�����ɒ��܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�قǂقǂɎU����グ����X�́A�r�N����ڂ����ł����Ă݂����Ƃ��������Ζڎw���đ��肾�����B�r���̈����ɂ͐\������x�ɗ�����������������B�����ɒ����܂ł̊ԁA���̂ق��͏���Ȃ̃V�[�g�ɐ[���g�߁A�R�N���R�N���Ƌ����肵�Ă����B
�@ �����͂��̓������͗l�������B���̂ԂƖ����͌����Ȃ��Ɠǂ��́A�ܕS�~�̒��ԗ����������W�]����m���X�g�b�v�Œʉ߂��A�����Œ��Ԃł��A���߂̂ق��������Ă����O�W�]��ɎԂ𒓂߂�悤�Ɏw�����o�����B�N�������^���������ƂȂ̂����A���̂������ɂ͑��W�]��Ȃ���̂����݂��Ȃ��B���A��O�A����ɗ������̎O�W�]�䂪���邾���Ȃ̂��B
�@ �������ł�������Ăق����Ɗ肢�Ȃ���W�]��ɗ����Ă���ƁA�ቺ�͂邩�ɌQ�F�̌Ζʂ�������Ƃ��������Ă����B�������A���X�ƌΕǂ����z���A�}�s�ȎΖʂɂ����ČΖʂɗ��ꍞ�ޖ��̂��߂ɁA�Ȃ��Ȃ�����ȏ�ɂ͓W�]�������Ȃ������B�������߂邵���Ȃ��ȁ\�\�����v���������Ƃ��ł���A�ˑR�A�傫����������A��u�����A�ΐS�ɂ���J���C�V�������̂��Ƃ��ɂ��̎p���������B�����Ă܂��A�ĂїN���o�����̃��F�[���ɕ�܂�āA�����܂��p�������Ă������B������������A�����̎�ɂ��r�N�ւ̓��ʂȌv�炢�������̂�������Ȃ����A���ہA����͂Ȃ�Ƃ����ȉ��o�ł͂������B
�@ ��������C���悭�����r�N�̉^�]�Ԃ�͉������ɂ߂��B��O�W�]������Ƃɂ�����X�́A�����R�A�쓒�A����ɂ͋��ΘH�Ή����̍�����a�Ք������o�R���A����܂��������Z�Œm������y���ɓ��������B���Ɍ����_��������A�ቺ�̋��ΘH�̑Ί݂ɂ��鑔�ՎR���A���̉E�����Ɉʒu����Η��x���A�����Đ捏�܂ł����ɗ����Ă��������̊O�֎R���݂Ȗ��ɉ���Ō����Ȃ������B���ΘH�ɕ����Ԓ��V�������͂悭�����Ă������A�L��Ȗk������₻�̌������ɍL����I�z�[�c�N�C���قƂ�ǎp���B�����܂܂������B����ȏ��ɂ͂���������ǂ��A���߂Ĕ��y���ɗ��r�N�̖ڂɂ���A���̌i�ς͂���Ȃ�ɗY��Ȃ��̂ɉf�����悤�������B�@
�@ ���y������́A���y�s�X�ɉ��������Ə����ʂ̐�����ʂ��Ĕ\��ɉ��������ɍ����A���������܂��ăT���}�ΔȂ̃��b�J�����ԉ��ւƎԂ𑖂点���B���x�̗��Ŋ��Ɉ�x�K�˂����b�J�����ԉ����ĖK�����̂́A�ǂ����ЂƂ��炢�͖k�C���̎����������ԉ������ċA�肽���Ƃ����A�r�N�����Ă̊肢���Ȃ�Ƃ������Ă�邽�߂������B
�@ ���������̂����ɕ��ԋ߂Ȏ����ł����������߁A��x�ڂ̃��b�J�����ԉ��T�K�͂��Ȃ�Q�������̂ɂȂ����B�V����ܓV�͗l�ŕ����₽�������������낤���A�G�]�X�J�V�������G�]�[���e�C�J���A�ߓ��ɔ�ׁA�Ԃт�̒���ƐF���Ƃ��ǂ��ƂȂ���X�����ޏk���Č������B�ЂƂɂ͓����Ƃ��Ă��Ȃ����������ł��������̂��낤���A���Ƃ��ƌ��������̉��ɍ炭�k���̉ԁX�́A������߂���Ƃ��̐������ӊO�Ȃقǂɑ����̂��B�����ɂ���ȉԎ��̂̐����̂䂦�ł��������̂��낤�B�����Ƃ��A�r�N�͂���Ȃ��ƂȂǂ��܂�C�ɂ����A�k�C���Ȃ�ł͂̍L��Ȍ����ԉ��̕��͋C�Ƃ��̑f���炵�������\�������Ă���悤�������B
�@ �T���}�ΔȂ̂Ȃ��قǂɂ͌̒��]���y���݂Ȃ�������ł��鉷����B���b�J�����ԉ��̎U����I�������ƁA���O���Ẵ����O�����ɔ����ꕗ�C���тĂ������Ƃ������ƂɂȂ��āA�[�ł̔��鍠���̉���ɗ�������B�����āA�ꎞ�Ԃقǎ㉖��̓��ɐg�߂Ĕ����Ƃ������ƁA�Ăё��s���J�n�����B�O���̂��Ƃ��������̂ŁA�ނ��A�[�����ڂɔR���̕⋋�����邱�Ƃ��Y��Ȃ������B
�@ �N�ʂ���͒��N�ʁA���y���o�ď��~�n���ʂւƌ����������ɓ������B���������ɏ��M�t�߂ɓ��B�ł���A�ϒO�����̐�[���܂��A�j�Z�R�t�߂��o�āA�ߌ�O���߂����ق��o��t�F���[�ɂȂ�Ƃ��Ԃɍ������낤�Ƃ����v�Z�������B����Ȃ킯�ŁA�r�����܂��ܖڂɂ������������ɔ�э��݁A�[�H�Ƃ��Ă�����Ƃ����C�N�����ɐ�ۂ�ł������Ƃ́A�@���O���ĂЂ����瑖�葱���邱�ƂɂȂ����B
�@ ���y����ې��z���o�Ėk�����ɍ����|���鍠�ɂȂ�ƁA�r�N�̃n���h�����삪���Ȃ�������Ȃ��Ă����B�Ⴂ�Ƃ͂����A�O���̑�������̋��s�R�ł������ɔ�ꂪ�o�Ă����̂��낤�A�����^�]�������ƁA�����҂��Ă������̂悤�ɁA�t���b�g�ɂ����㕔�V�[�g�Ɉڂ��Ď��悤�ɖ����Ă��܂����B
�@ �[��̍������Ђ�����A��쒬���o�Ĉ���ɓ���ƁA��������͍������H�ɏオ��A�D�y�A���M���ʂ�ڎw���Ă��������ƃA�N�Z���ݍ��B������������Ɩ��C�������Ă����Ƃ���ł܂��r�N�Ɖ^�]����ւ��A�ߑO���O�ɏ��M�`�̐V���{�C�t�F���[����ɓ��������B�`�܂ł���Ă����̂̓t�F���[�ɏ�邽�߂ł͂Ȃ��A�n�q�q�̂��߂ɑ�������J���Ă���^�[�~�i���r���̃��X�g�����ŁA���M�`�߂Ȃ���x�e�����˂Čy�����H���Ƃ邾�߂������B
�@ ���H���Ƃ�Ȃ��炱�̓��̍s�����Č����������ʁA�_�Ж��܂ő����^�сA�ϒO�����̐�[���܂���Đ_�b���ւƔ����A����A�j�Z�R�A�������Ƃ������[�g���Ƃ��Ă��A�ߌ�O�����܂łɂ͔��ٍ`�ɒ����邾�낤�Ƃ������ƂɂȂ����B�����ŁA���M�^�͉����̑q�ɊX���ЂƂ܂�肵�����ƁA�]�s�ō����܍�����킩��ĐϒO�������C�����Ɉ�����铹�ւƓ������B�����āA�قǂȂ��]�s�ƌÕ��̊Ԃ̖L�l�Ƃ���������ɂ���g���l����ʉ߂����B�ȑO�ɑ傫�ȗ��Վ��̂��N����A������̎Ԃ���ʂ̓y�ɂ���ĉ����ׂ���Ă��܂����g���l���ŁA���܂ł͂��̈ʒu�͂������������Ɉڂ��Ă���B
�@ �����̐l��������ꂽ���̎��̂����������O�̂��Ƃ����A���̃g���l���̓����t�߂Ŏ��������Ƃ����ڂɑ��������Ƃ�����B���̎��͂��̓��Ƌt�����ɑ��s�����������A�㑱�̑��Ԃ����X�ɒǂ��z���҃X�s�[�h�Ŕw��ɔ����Ă�����p�ԂɁA�N���N�V������炵�ē�������Ƌ}�����Ă�ꂽ�B�����ȂƂ��돭�X�����������̂����A�������̃g���l�������̊C���ɂ͂��������ȑҔ��X�y�[�X���������̂ŁA�Ƃ����ɍ��Ɋ���ē����������B
�@ ������̎Ԃ����̎Ԃ�ǂ��z���g���l���ɔ�э������̏u�ԁA�ٗl�ȏՓˉ�����тɋ����n�����B�Ȃ�ƁA���̎Ԃ́A�g���l�����ł̒ǂ��z����������^�]�������Ŕ��ΎԐ����炱���瑤�̎Ԑ��Ɋ��荞�Ό��ԂƐ��ʏՓ˂��Ă��܂����̂������B���R�A�g���l���͒ʍs�~�߂ɂȂ�A�����҂��o�ċ~�}�Ԃ��삯���鑛���ɂ܂Ŕ��W�����̂����A�����Ŏ��͎��̂Ɋ������܂ꂸ�ɂ��̂ł���B���^�i�H�j�������ƌ��������܂ł����A�������炸���̂܂ܐ�Ƀg���l���ɓ˓����Ă�����A���܂���͂ǂ��Ȃ��Ă������킩��Ȃ��B
�@ ���ۂɑ����Ă݂�ƐϒO�����͒n�}�Ȃǂőz��������������Ƒ傫���ω��ɕx��ł���B���̒����w�ŕ��ɂ͐�O�S���[�g����̗]�ʊx���͂��߂Ƃ��A�烁�[�g���O��̍����̎R�X���A�Ȃ��Ă��邩��A���f�H���Õ��Ɛ_�b���Ƃ��Ȃ���{�����������݂��Ȃ��B�������A���̉��f�H���������R�z���̓������炻��Ȃ�Ɏ��Ԃ�������̂��B�܂��A�C�ݐ��̂قƂ�ǂ͋}�p�x�ŊC���ɐꗎ����s���ȊC�H�R�ɐ�߂��Ă���̂ŁA���̒f�R������D�����铹�͎����邲�Ƃɕs�ʂɂȂ邱�Ƃ������Ȃ��Ȃ��B���N�ɂ킽���Čv�擹�H�̌��ݍH�����i�߂��Ȃ���A�ŋ߂܂ŐϒO������[�����܂�铹�H�����J�ʂ������̂��A����Ȓn�`��̗��R�����Ă̂��Ƃ������B
�@ ���������������������āA�H��ɂ͑��Ԃ̉e�ȂǂȂ���������A�Õ��A�ϒO���Ə����ɑ��蔲���A�_�Ж������̒��ԏ�ւƓ��������B�ȑO�͍��������̑����Ƃ����Ƃ���ɎԂ𒓂߁A�������疦�ւƑ����ד����l�\���قǕ��������̂������B�������A�����Ƃ������̒n�_�ɂ́A�u���{�ň�ԗ[���̔������ꏊ�v�Ƃ����Ŕ����Ă��Ă����悤�ɋL�����Ă���B���܂ł́A���̏ꏊ���疦���ʂւƕ���ܑ����H�����݂���A���H�̏I�_�ɂ͔��X�Ȃǂ�����L�����ԏꂪ�����Ă����B
�@ �_�Ж��̐�[�܂ł͂��̒��ԏꂩ��A�b�v�_�E���̂��鏬��������ɓ�\���قǕ����˂Ȃ�Ȃ��B�O��̋��s�R�ł������ɔ�J�����o���Ă������́A��ɓƂ�Ŗ��̓˒[�Ɍ������ċ삯�o���r�N�̌�p��������Ȃ���A�}�C�y�[�X�ł̂�т�ƕ����o�����B���ւ̗V�����͈ȑO�Ƃ͌��Ⴆ��قǂɐ������s���͂��A�i�i�ɕ����₷���Ȃ��Ă����B�����A���̂Ԃ�A���Ă̎��R�炵�������Ȃ莸���Ă��܂����悤�ȋC�����Ȃ��ł͂Ȃ������B
�@ �ג����L�яo�����̔w�ŏ��`���V�����̗����ቺ�ɂ́A�V���R�^���u���[�ȂǂƂ��̂���鍮�ɂ̊C���L�����Ă����B�����āA���邢�����̍������ފC���ł́A���ΐF�̑召�̊�X�Ƃ����ɕt������C���ނ��A���z�I�ȐF�����������Ȃ��炩�����ɗh��߂������Ă����B�}�s�ȎΖʂɓ_�X�ƍ炭�G�]�J���]�E�̉ԁX�����ƋY���p�Ȃǂ���ې[�������B
�@ �O���̗V������������ŋ삯�o���Ă����r�N�̎p�����]���Ȃ���A�ӂƎ����̗̑͂̐����Ɏv���������B��ӂ��ӓO������悤���ǂ����悤���A�\�N���炢�O�܂ł́A���̒��x�̓��Ȃ炢�����ɋ삯���ő���ʂ����Ƃ��ł����B�������A�����s���Ɨ��̔��̏d�Ȃ������܂���Ȃ��Ƃ��������A�����������Ă��܂��͖̂ڂɌ����Ă����B�̗͓I�ɖ����̂Ȃ����x�ɏ����������𐮂��Ă��������ɁA����ł����Ȃ�����͏オ�����B�_�Ж���[�ɂ��铔��e�̓W�]��ɒ������r�N�́A��������Ă���ɂ͂܂��܂����Ԃ�������ƍl���Ă����炵���B������A�����W�]��Ɏp�����������ɂ́A�ӊO�����ȕ\����ׂȂ���A�u���H�A����Ȃɑ��������Ȃ�Ďv���ĂȂ������ł���v�Ɣ��Ί��S�����悤�ɐ��������Ă����B
�@ ���Ă̓S�c�S�c�������R�̊�ɕ����A���������ɐg���B���邭�炢�̌E�݂����������̍Ő�[���́A�ό��q�������₷���悤�ɃR���N���[�g���͂��A�����Ԃ�Ɨl�����ς���Ă����B�C�ʂ��炨�悻���\���[�g���̒f�R��Ɉʒu���邱�̖��́A�]�ˎ��㖖���̈����O�N���܂ł͏��l���̒n�ł������Ƃ����B�K���Ȃ��ƂɁA�������̊C���ɛ������鍂���l�A�\���[�g���̐_�Њ�̗̈e�ƁA���̑�����₦�ԂȂ��H�ތ��Q�̐�����������͐̂̂܂܂̂悤�������B
�@ ���̖����璭�߂�[���́A�v�킸������킹�����Ȃ�قǂɑ����ŁA�������������܂łɔ������B����Ȑ_�����̂��̂̐_�Њ₪�[����w�ɂ��č��X���ނ����L�l�́A�R����͂������Č���҂̍��𖣗�����B���邭�����̋P�������ɂ����āA����ȗ����̌��i��z�������ׂ�Ƃ����̂����Șb����������ǂ��A�[���z���b�N�̂��̐g�ɂ���A����͒v�������Ȃ����Ƃł͂������B
�@ �\�]�N�O�̉Ă̒��������������Ǝv�����A���͎R�c�◘����Ƃ����n���̖����Ď����̕��Ƃ��̏ꏊ�ł��܂��o���������Ƃ�����B���̎��A�R�c����́A�傫�Ȋ�̌E�݂���炾�����̂������A�_�Њ���ӂɕ����Ԓj���������̈ٗl�ȃ��W���[�{�[�g�̓�����o�ዾ�ł����ƊĎ����Ă���Ƃ��낾�����B�g�����V�[�o�łǂ����Ƌٖ��ɘA�����Ƃ�Ȃ���ނ�̓�����T�葱����R�c����̗l�q�͐^�����̂��̂������B����͖\�͒c�n�̈����Ȗ����O���[�v�ŁA�@���I�Ȃ��Ƃ܂ł��炩���ߌv�Z���s�������I������܂�Ȃ��������g���ăA���r��T�U�G�̖������邽�߁A�����͍�����ɂ߁A���̎��ӂ̋��������͐r��ȑ��Q�����Ă����̂ł���B
�@ �e�����Ȃ����R�c����A���͑o�ዾ�Ŋቺ�̃{�[�g�̗l�q���̂������Ă��������A�z����₷��悤�Ȗ����g�D�̎��Ԃɂ��Ęb�����Ă��������������B�����āA�̂��ɁA�ْ��u���ł̗��H�v�i���R�����Ёj�̒��Ȃǂł�����A�̋����ׂ����Ԃɂ��ďڂ����Љ��������������B���̌�A��т̖�����肪�ǂ��Ȃ����̂��͂킩��Ȃ����A����قǂ܂łɓW�]�䂪�������ꂽ���܂ƂȂ��ẮA�����Ď������g���B�����ɂ��A�t�߂ɂ͂���ɂӂ��킵����A��E�n�Ȃnj������肻���ɂ��Ȃ������������B
�@ �قǂȂ�������Ԃɖ߂�����X�́A�Ăэ����ɏo�����Ə��O�����ʂւƑ���o�����B���O�܂ł͈ȑO���瓹���ʂ��Ă����̂����A���ǂ̘A�Ȃ�n�т��т��Đ_�b���ւƎ���\��̃g���l�����H�̊J�ʂ͒x��A���K�˂Ă݂Ă��H�����Œʍs�s�\�ɂȂ��Ă����B�������A�ŋ߂悤�₭���̓��H���������A�ϒO�������C�`���Ɉ���ł���悤�ɂȂ����̂������B�@�@�@
�@ �g���l���̘A������V�������H���Ԃ͉����ɑ��葱�����B�ނ��A�������̐V���H�𑖂蔲����̂͏��߂Ă̂��Ƃ������B�k�C���̊O�����H�̂Ȃ��ŁA���̏��O�Ɛ_�b���Ԃ̓��H�����͍Ō�܂Ŏ����ʍs�ł����ɂ����Ƃ��낾��������ł���B�g���l������œW�]���قƂ�ǂ����Ȃ����߁A�i�F���y���ނƂ����킯�ɂ͂����Ȃ��������̂́A����ł����͂������[�����S�ɂЂ����Ă����B�����āA���ɎԂ��_�b�����̌��o���̂���n�_�ɓ��B�����Ƃ��A���́A�N�b����Ȃ��A���̒��Łu���ɂ�������I�v�Ƌ���ł����B���N�̌��Ă������k�C���O�����H�̊��S���s���悤�₭�ɂ��Đ������u�Ԃ����炾�����B
�@ �����Ȃ��Ƃ������Ȃ�A�鋫���̔鋫�A�m�������̒m���������́A�ԓ��͂������A�C�����ɖ��Ɏ�����s�H�������܂������Ȃ��L�l������A����͗�O�Ƃ���������Ȃ��B�����A�m�������Ɋւ��Ă��A�m�����f���H�͌����ɋy���A�m���ѓ��̏I�_��A���Ή���̂��锽�Α��̓��H�̍ŏI�n�_�A�����܂ł͍s�������Ƃ�����킯�����A�D�łȂ�m����������͂������Ƃ�����A�ꉞ�A�k�C���O�����H�S���j�B���ƍl���č����x���Ȃ����낤�B������ɂ���A�ϒO�����̎��s���B���ł����̂́A���̓x�̖k�C�����s�ő�̎��n�ł͂������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N10��31��
�k���S�i�E���k������
�@ �_�b���̊C�݂�C����тɂ͑召�l�X�Ȋ�₪��������ł���B�������ԑ����璭�߂Ȃ��瑖�s���邤���ɁA�E��O�����ނ���傫�ȎR�����Ă����B�~��ɂ̓X�L�[�̃��b�J�Ƃ��Ă��m����j�Z�R�A��̗Y�p�ł���B���̃j�Z�R�A����z���č����܍����ɍēx�������A���Y�p�݂̒������ɏo�悤���Ƃ����ƁA����ȗ~���������[�g���Ƃ��Ď��ԓI�ɊԂɍ����܂����ƁA�r�N��������ƕs�����ȕ\��Ŗ₢�Ԃ��Ă����B������ςȂ��Ȃ���v����Ǝ��͉��Ő��肽�āA���ǂ��̃R�[�X���Ƃ��Ĕ��قɌ��������Ƃɂ����B�j�Z�R�z���ɂ͏��X���Ԃ�v���邪�A�i�F�͂������A�����܍��ɏo�Ē������ɔ�������Ƃ͔��ق܂ňꑧ���B
�@ �j�Z�R�A���w�i�ɂ��čL�������̒��ɂ͖ؓc�����Y�̋Ɛт��L�O�������p�ق�����B���̔��p�قŋ߁X�m�l�̉�Ɠn�ӏ~����̌W���J����邱�ƂɂȂ��Ă����̂ŁA�ǂ�ȂƂ��납������Ă݂����Ƃ͎v�����̂����A���ԓI�ɓ�����������̂ł��̌��͒f�O����������Ȃ������B����s�X�𑖂蔲����Ƃ������ɍ��x�͏㏸���A�ቺ�ɂ̂т₩�ȗ̎R�[���L�������B���̌������ɂ͓��{�C�����P���A�z���ɉf����C�ʉz���ɂ́A���X�ƘA�Ȃ�ϒO�����̎R���݂��]�܂ꂽ�B
�@ �j�Z�R�A��̂��������ɂ͂��낢��ƌ����������̂����A�Ƃ肠���������̌����͏ȗ����A�W�����S���[�g���قǂ̍��x�̓����z����ƁA���z�����ʂɌ������ĂЂ����牺�邱�Ƃɂ����B�r���A���艓���ɗr���R�̓�������R�e�Ȃǂ��]�܂ꂽ�B�������������Ԃł�����A�j�Z�R������r���R�[���o�ē���Ζk���݂�������߂���A���c���ɔ��������Ƃ���Ȃ̂��������A�ǂ����Ă�����͖����Ȃ悤�������B
�@ ���z���ō����܍����ɍ������A�ꑖ�肵�Ē������s�X���߂���ƁA���Θp�̕ʏ̂�����L��ȓ��Y�p���A�X�ƋP�����̎p�������͂��߂��B���Y�p��傫�����݁A����͂邩�O���ɂЂƂ���傫���ނ���̂́A���݂��������̉ΎR��P�x�̗Y�p�������B���ꂩ����Y�p�����ĐX���Ɏ���A���̋�P�x�̐��R�[���o�Ĕ��قɌ��������Ƃ����킯�������B
�@ ���H�͑�������ł������A�a�Ƃ����قǂ̂��Ƃł��Ȃ������̂ŁA�قڗ\�莞���ʂ�ɐX����ʉ߂��A��P�x�̐��R�[�ɍ������������B��S�O�\�O���[�g���Ƌ�P�x�̕W���͂������킾���Ă���킯�ł͂Ȃ����A���Y�p�̊C�ʂ��炢�������ނ����Ɨ���Ȃ̂ŁA�W���ȏ�ɂ��̎R�e�͑傫�������ĈЁX����������B�ւ炩�ɂ��̂�̑��݂�i�����P�x�������Ȃ����H��ւƉ����Ă����ƁA�召�̏��Ƃ����̏��ɕ����ԕS�]���̏����Œm�����������̂��ɏo���B�������A���Ȃǂł��m���邱�̑��������т����Ă̍��ȂǂɎU��ƁA���낢��Ȕ����⊴���������ĂȂ��Ȃ��ɑf���炵���B
�@ ����������߂���Ɣ��ق܂ł͂����ق�̈ꑖ�肾�����B�t�F���[�o�q�\�莞���̎O�\���قǑO�ɔ��ٍ`�^�[�~�i���r���ɓ���������X�́A�����ɏ�D�葱�����I���A���k�����˒[�̑�ԍ`�s���t�F���[�ɏ�荞�B�f���ɐX�ɓn��̂ł͂Ȃ��A�ǂ����Ȃ牺�k�������݂�쉺���A�O��A�S�A���˂��o�R���ē��k�����ԓ��ɏo�悤�Ƃ������_�������B����Ȃ��ʁX���ƕ�����Ă��܂����������A���Ƃ��ҘH�ł����Ă��ő���ɖ쎟�n���_�����Ȃ���߂낤�Ƃ����킯�������B�܂��A�R�X�g�I�ɂ݂Ă����̂ق������オ�肾�����B
�@ �t�F���[�͓~�i�F�Ȃ�ʉČi�F�̒Ìy�C����n��A�ꎞ�Ԕ��قǂő�ԍ`�ɐڊ݂����B�r�N�͉��k���������߂ĂƂ������Ƃ������̂ŁA���D����Ƃ����ɖ{�B�Ŗk�[�̑�ԍ�Ɍ������A���̓W�]������Ìy�C���z���ɖk�C���T�c������т̎R���݂��������߂�����B��C������ł����̂œd�g���̗����َR�̎p�Ȃǂ��͂���Ɩ]�܂ꂽ�B
�@ ���̑�ԍ�W�]���̈�p�ɂ́A�u���C�̏����̈�̔����ɂ�ꋃ���ʂ�ĊI�Ƃ��͂ނ�v�Ƃ����A���̗L���Ȑΐ��̉̂�����ƁA���̔�̗R�����L����������݂����Ă���B��ԍ�̂������ɂ́A����̗��ٓV���Ƃ�������������̂����A������ɂ��ƁA��̂��̉̂̕���ƂȂ����̂́A�ق��Ȃ�ʂ��ٓ̕V���������̂������ł���B��؎��g���͂�����Ƃ����q�ׂĂ���킯�ł͂Ȃ��炵���̂����A�c���ꂽ�莆���̑��̕����ނ���l����ƁA�̒��́u���C�̏����v�Ƃ͂قڂ��̏����ɊԈႢ�Ȃ��Ƃ������Ƃ������B
�@ ����̑����C�����j���ł����Ȃ�������ٓV���ɂ͓n�ꂻ���ɂȂ��������A���Ƃ��n�ꂽ�Ƃ��Ă��A�����̂���l�ӂ�T�����āA�I�������ē˂����肵�Ă����̂ł͓������Ă��܂��B������ƒ��߂��Ƃ���ł́A���������ٓV���ɔ����̕l�ӂ�����̂��ǂ��������肩�łȂ������������B������쎟�n�����̉�݂����ȉ�X�����āA�������ɂ����܂ł͕t����������Ȃ��B�t�̈ꎞ���A��̉̂ɖ����ɂȂ������Ƃ�����g�ł͂��������A�����͂قǂقǂɑގU�����ق����悩�낤�ƍl���A�قǂȂ��唨���ʖڎw���đ���o�����B
�@ �n���h��������r�N�ɁA�u�ǂ�����A�厞�Ԃ܂łɒ����邩�ǂ����킩��Ȃ����ǁA���R�ɍs���Ă݂邩���H�v�Ɛq�˂�ƁA�u������ƊO���猩�邾���ł��c�c�v�Ƃ����Ԏ����߂��Ă����B���ꂶ��Ƃ������s���Ă݂邩�Ƃ������ƂɂȂ�A�唨���璼�ڂɗ����s�ւ͌����킸�A������o�ċ��R�ւƑ������ɓ������B�����āA������߂��A�T���Ƃ������ёт����˂��˂ƖD���i��ŁA�Ό��̉F�]���R�Ζk�݂Ɉʒu���鋰�R���̒��ԏ�ɓ��������B�����ɂ͋��R��ƌĂ�邱�̗��́A�㐢�I���Ɏ��o��t�~�m���J������̂��Ɠ`�����Ă���B
�@ �����������̂͂悩�������A�c�O�Ȃ��Ƃɂ��傤�ǖ傪�߂��A�����t�̌W�������ւƈ����g���Ă����Ƃ��낾�����B�����ۂ��F�̑e���ŕ���ꂽ�L��Ȓ��ԏ�ɂ́A�A��x�x�����Ă����q�̎Ԃ����Ƃ܂��Ă��邾���������B�����āA�قǂȂ����̎Ԃ����������Ă��܂��A���Ƃɂ͂ۂ�Ɖ�X�̎Ԃ������c���ꂽ�B
�@ �l���Ă݂�ƁA���N���O�Ɏዷ�̉�Ɠn�ӏ~������ē����Ă���Ă����̂��A�[���߂��̂��Ƃ������B���̎��͕�܂łɂ܂��O�\���قǂ������̂����A���삯���ōQ�����������߂���A����ɂ���Ñ�̓��Ƃ�������ɏ\���قǂ��������ƁA�g�̂�@���̂����������ɒ��ԏ�ւƋ삯�߂����B�����āA���̓��Ƃ͋t�̃R�[�X�����ǂ��āA�ґR�Ƒ�ԍ�ڎw���đ��肾�����B��C�̐��D�V�̈���������̂ŁA�ǂ����Ȃ��ԍ�Ŕ������[���߂悤�ƍl�������炾�����B
�@ ���߂Ă��̋��R��K�˂��̂͂����Ԃ�Ɛ̂̂��Ƃ����A���łɂ�����͐[�����łɕ�܂�A���傤�Ǔ����̊O�֎R�̏�ɁA�������������߂�������̌��������Ă���Ƃ��낾�����B�����������ƊO���̒��ԏ�Ƃ��d�钷����݂͐����Ă͂������A���܂̍����ď�v�ȑ���̔��ƈ���Đ\������x�̂��̂���������A���̋C�ɂȂ�ǂ�����ł����R�ɏo���肷�邱�Ƃ��ł����B���̎���������d���ƌ�������𗊂�ɁA���̖鎄�͗����ւƂ����ނ�ɑ��ݓ��ꂽ�̂������B
�@ �Ԓ����Ă���������ꂪ������Ȃ��đ傫�����˂�悤�ɍL����A�@���������̉����l���ɕY���A����ɂ͒n���̂�����������M���������o���Ă��鋰�R���́A���ԖK�˂Ă݂Ă����ɍr���Ƃ�������������B�܂��āA�l�̋C�z�̓r�₦����Ƃ����ẮA�W�������ɕ����Ԃ��̈ٗd�Ȍ��i�ɑz����₷�鐦�݂�����͓̂��R�̂��Ƃ������B������������ɂ�Č����͖��邳�𑝂��A���̒��ɕ����Ԃ悤�ɗ��������̉͌��̖����̐ΐς݂́A���ꂼ��ɐ[����߂�߂�������𗷐l�̂��̐g�ɐX�Ƒi�������Ă��邩�̂悤�ł������B
�@ ������Ƃ����e�𗎂Ƃ��Ēn����F�̗���R�̉A��D���ד����A�F�]���R�̌ΔȂɍ~�藧�ƁA�Â܂肩�������Ζʂɂ͑傫�Ȑl����z�킹�錎�e���Y���悤�ɉf���Ă����B�ɂ����čL�������̂т�Ήp���̔����̕l�ӂɑ��Ղ����݂Ȃ���������ƕ����Ă���ƁA�ˑR�T�[�b�ƕ����N����A����ɍ��킹��悤�ɂ��āA�J�T�J�T�A�J���J���Ƃ�����ȉ����ǂ�����Ƃ��Ȃ������Ă����B
�@ ��u�w�ɗ₽�����̂�����̂��o���Ȃ�����A�C�𗎂������ĕs�v�c�ȉ��̂���ق��ւƋ߂Â��Ă݂�ƁA���n�̏�ɗ��Ă�ꂽ���{���̒Z���_��̐�[�ʼn������J���J���Ɖ������ĂȂ������Ă����B�����d���ŏƂ炵�o���Č���ƁA�Ȃ�Ƃ����́A����K�Ȃ��l�X���A���܂͖S�����҂̗�ւ̒����̋F������߂ČΔȂɗ��Ă����Ԃ������B���m��ʕ��Ԃ���Ăɉ�肾�����Ƃ��ɋN����g�ł�����߂��悤�ȋ����́A�n�̒ꂩ��O���オ���Ă��鎀�҂����̔߈��ɖ������ꂫ�̂悤�Ɋ��������������̂��B
�@ �K���Ȃ��ƂɁA���̂Ȃ�Ƃ���������ʗ��p�j�ɂ�������炸�A���̌���䂪�g�ɂ͂Ƃ��ɕs�g�Ȃ��ƂȂlj����N����͂��Ȃ������B���܂�̐}�X�����ɁA���R��тɕY���썰������͂āA�������ɂ��Ē��߂ł����Ă����̂�������Ȃ��B
�@ ����Ȑ̂̑z���o���������݂Ȃ���A���肰�Ȃ��r�N�̕\����M���ƁA��������ڂ������`�����Ƃ��ł��Ȃ��͎̂c�O�ł��܂�Ȃ��Ƃł����������ł���B����ȗl�q�����Ă��邤���ɁA�Ȃ�Ƃ����Ă�낤�Ƃ����T�[�r�X���_���ނ�ނ�Ƌ����ɗN���Ă����B�����A�����͌����Ă��A�̂̂����������̍�Ƃ͈Ⴂ�A���݂̔��͂������肵�Ă��Č��Ԃ��Ȃ�����A��������z������C�蔲�����肷��͓̂�����������B�܂��A���Ƃ��\�ł������Ƃ��Ă��A����Ȍy�ƍ߂܂����̂��Ƃ܂ł͂������Ȃ��Ƃ����āA��������͂����Œ��߂����������B
�@ �����A���̉F�]���R�̒n�`�ɒʂ��Ă������́A��ӏ������ӊO�Ȏ��p�����邱�ƂɋC�������B�������A�ߋ��Ɏ��p�ƂȂ��Ă��邻�̃��[�g�̗��p���l�������Ƃ�����킯�ł͂Ȃ��������A���Ԃ�����ւƒʂ蔲�����邾�낤�Ƃ����z���͂����B�����ŁA�������������̒n�_�ɋ߂Â��ƁA�r�N�����Ƃɏ]���A������Ƃ������̔ɂ݂Ɛ[�����ނ�̑������n�тւƕ����������B
�@ ���炭�i�ނ����ɁA�Ă̒�A�n���̒N���ɂ���Ă���ꂽ�Ƃ��ڂ����A�������ȑ��̓��ݐՂ炵�����̂��ڂɂƂ܂����B���̂܂ܐi�߂ΉF�]���R�ΔȂ̔����̕l�ӂɔ�������ɈႢ�Ȃ��\�\�����m�M�������́A��������Ƒ��𑬂߂đ��ނ���i�B�����āA�قǂȂ��A���E���Ղ�悤�ɂ��čs����Ɍ��ꂽ�������z���A���̌��������ւƓ��ݓ������B��X�̊�O�ɍL�������̂́A�܂�����Ȃ��A��ʂ�嗱�̐Ήp���̔����ŕ���ꂽ�F�]���R�ΔȂ̔������l�ӂ������B
�@ ���̕l�ӂ̒��قǂ܂Ői��X�́A�����ɂ��炭�Ȃ�ŁA�������̎c���̂��ƂłȂ��Z���ɐ��P���F�]���R�̐Â��ȌΖʂɒ��߂������B���ӂ̂�����������͉��O���o���A����ƂƂ��ɕ����o���Ă��闰�����Ζʂ̈ꕔ�����ΐF�ɐ��߂Ȃ��琅���ɗn���o���Ă������B���ɐl�e�͂��낤�͂����Ȃ��A���Ɋ�g�̉����₦�āA������͐Î₻�̂��̂������B
�@ ��̋�����グ��ƁA���捏�܂ł܂����ۂ��F�����Ă����㌷�̌����A���̐[�܂�ƂƂ��ɂ���Ɛ��P���𑝂��Ă����Ƃ��낾�����B��O�̉F�]���R�Ζʂɉf�邻�̔����̉e�́A�܂�ł��ꂪ�H�E���Ƃ炵�o�����܂ЂƂ̏㌷�̌��ł��邩�̂悤�ȍ��o���������炵�������B�̉͌��̂����т�{�����ʂ����]�ł��鍂�݂ɂ�������Ƃ����̂ڂ��Ă݂����A�r���Ƃ��������̊��̂��������ŔM���������o���A�������R���A�����̏��C�������悭����ɗ�������ٗl�Ȍ��i�́A�����Ȃ��疻�E��z��������ɏ\���Ȃ��̂������B�@
�@ �����A����i����g���Ă̎��ԊO������w�������̂ŁA�������ɂ������n���߂�������A����ɐg���Ђ����Ƃ����킯�ɂ͂����Ȃ������B����łȂ��Ă��A���R�Ɋ�蓹�������Ƃŗ\�莞�Ԃ����Ȃ�I�[�o�[���Ă�������A���̂��Ƃ͖��O���Ẵm���X�g�b�v���s�œ����Ɍ����킴������Ȃ��ɂȂ��Ă����B������x�F�]���R�ΔȂɘȂ݁A�Ζʂɉf�錎�e�����������ƒ��߂����ƁA��X�͉��H�Ƃ��Ȃ��ד����t�ɂ��ǂ��ĎԂ̂Ƃ���ւƖ߂蒅�����B���鎞�ɂ������ݐՂ���������̂��Ƃł͂�����m�F���邱�Ƃ��ł�������A�Ƃ��ɖ������肷��悤�Ȃ��Ƃ��Ȃ������B
�@ ���R�����Ƃɂ�����X�́A�����s���獑���O�O�������ɓ���A��̉��k�������������ɓ��ݓ`���ɓ쉺�����B�L��ȌΏ��n�т�j���������{�݂̑��݂Œm����Z���������A���Ă͑����J���̊�n�Ƃ��ċr���𗁂тĂ������쌴�Ύ��ӂ������Ƃ����܂ɑ���߂��A�ČR�̊�n�Œm����O��s�ɓ������B�����āA�O��͕S�Β��Ɣ��ˎs���o�Ĕ��ˎ����ԓ��ɓ���A����œ��k�����ԓ��ɍ��������B�����{���ɖ߂蒅�����Ƃ��A���̗��ł̑��s�������͂قڎl���S�L���ɋy��ł����B�������A���H�Ƀt�F���[�ňړ������V�����珬�M�܂ł̋������͂��̒��Ɋ܂܂�Ă��Ȃ��B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N11��7��
�e�������ʑ[�u�@�ɂ�����
�@ �e�������ʑ[�u�@���O�Q���@��ʉ߂��A�A�t�K�j�X�^����p�L�X�^���ɓW�J����ČR���x������Ƃ������ڂŁA�C�O�ւ̎��q���h���������̂��̂ɂȂ낤�Ƃ��Ă���B��K�̓e�������߂邽�߂ɉ䂪�������ۓI�ȋ��͂�ɂ���ł͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ̂悤�����A���q���h�����A�t�K�j�X�^���̓��̃e���O���[�v�o�ł�A�t�K�j�X�^����~�ςɎ����I�ɖ𗧂��ǂ����̔��f���A���̐�D�̋@��𗘗p���A���q���̑��݂����Д��g�Ɍ��т��悤�Ƃ���ꕔ�̐l�X�̎��O�̂悤�Ȃ��̂�������s���Ă���悤�Ɋ������ĂȂ�Ȃ��B�l�I�ȏ����玨�ɂ���������ł��A����̃e�������ʖ@�Đ����܂ł̉ߒ��ɂ����ẮA�ڂɈ͂ޓ��t���[�W�҂��A���ۂɎ��q��������h�q�������̂ق����͂邩�ɐT�d����Âł������悤�ł���B
�@ �����������E�i�Ђキ�j���������悤�ł͂��邪�A���̂悤�ɏd�v�Ȗ@���̐����ƈ��������Ɏ��}���͂̊g���}�낤�Ƃ����A���܂�ɂ����������������I���������������ƂȂǂ́A�Ȃ�Ƃ���Ȃ�������ł������B��ʍ������ǂ��v�����ƁA�����̐����Ɋւ��҂ɂ͂���Ȃ�̔��������Ȃ�ʎ�����邵�A�����Ƃ������̂͂��Ƃ��Ƃ����������̂��Ƃ����̂������҂̖{���Ȃ̂�������Ȃ��B�����A�����Ƃ����ȕېg������ɂ��Ă����܂ŊJ������Ƃ����Ȃ�A��X�����ɂ�����Ȃ�̑Ή�������o�傪�K�v�ƂȂ��Ă��邾�낤�B
�@ �p�ݐ푈�ɂ����ċ��K�I�x���݂̂������Ȃ��l�I�v�������Ȃ��������{�́A�܂��Ƃ��ȍ��ۓI�]����ꂸ�A���̂䂦�ɂ����Ȃ���ʋ��J�𖡂�����Ƃ������Ƃł���B�������A���������ǂ��̍��̒N���ǂ̂悤�Ȃ������ƈӐ}�������ē��{�����̂悤�ɒႭ�]�������̂��A�܂��A���̂��߂ɍ����̒N����̓I�ɂǂ̂悤�ȋ��J���������̂��Ƃ������ƂɂȂ�ƁA���܂������ĉ���ߑR�Ƃ͂��Ă��Ȃ��B
�@ �����Ȃ��Ƃ��A���̎��ӂɂ͘p�ݐ푈��̍��ۓI�]���̒Ⴓ�ɂ���Ď��ۂɋ��J���𖡂�����Ƃ����l���قƂ�nj�������Ȃ��Ƃ�����݂�ƁA���J���ɏP��ꂽ�̂́A�命���̈�ʍ����ł͂Ȃ��A�s���ɂ������ꕔ�̍���c����O���W�҂����������Ƃ������ƂɂȂ�̂��낤�B�[�I�Ɍ����Ă��܂��A���ۓI�ɕ]������Ȃ������Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A�č�����т��̗F�D���̈ꕔ�ɕ]������Ȃ������Ƃ������ƂȂ̂��낤���A�꒛�~�ȏ�̋��K�I�x�������A�ČR�Ɍ���x����n����Ă����Ȃ���A���̈Ӌ`�ƕ��S�̑傫���ɂ��č��ێЉ�ɉ��ЂƂA�s�[�������Ă��Ȃ������s���ӔC�ҁA�Ƃ�킯�O���W�҂̖��\���Ԃ������Ă�����ׂ����낤�B
�@ �܂��e�������ʑ[�u�@���@�Ēi�K�ɂ������Ƃ��̂��Ƃ����A����e���r�ԑg�ɏo�����Ă���������A�����҂���u���������g�̂��q���p�L�X�^����A�t�K�j�X�^���ɍs���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����Ƃ���A�e�Ƃ��Ăǂ��v�����낤���H�v�Ƃ�����|�̎��₪�Ȃ��ꂽ�B���̖₢�����ɑ��A�͂܂Ƃ��ɂ͉����Ȃ���������łȂ��A�u����Ȏ���͎������Ⴂ�B�����������ۂɌ��n�ɏo�����͎̂��q�����ł���A�����͓������ɁA�C���Ƃ���ΐ����Ɋ댯���y�Ԃ悤�ȂƂ���ւ��o�����Ƃ����鐾�����������ő����ɂȂ��Ă���v�Ƃ����A���������_�_�̂��ꂽ�ԓ������Ă����B
�@ �����čD�ӓI�ɉ��߂���A���̎��́A���ƃ��x���̖����l����א��҂Ƃ��Ă̗��ꂩ�炷��ƁA���̂悤�Ȍl���x���̉��z�I����̓i���Z���X���ƍl�����邦�Ȃ��ƌ������������̂��낤�B�����A���͂��߂Ƃ��鍑��c������������قǎ����̍������O�������A����R�c�ɗՂ�ł���ȂǂƂ͓���v���Ȃ��B�쎟�A��A�s�^�ʖڂ��̂����Ȃ��ԓx�A�t���⊯���̉����ȓ��فA�l�ԓI��������ǎ��̃��[���A�̂����炷����������Ȃ��U���I�}�A�͂��߂��瑊��̈ӌ��ȂǕ���������Ȃ����炾�����ӂƕ̎��ɖ��������t�̐��X�ƁA�ǂ��Ɏ����̍����Ȃǂ��邩�ƌ��������Ȃ�̂́A�������ł͂Ȃ����낤�B
�@ �����͂��߂Ƃ��鐭�����s�̈�ʏ����́A�Ȃ�قǎ����̒Ⴂ���݂�������Ȃ��B�����̐g�̉��̂��Ƃ����l���邱�Ƃ̂ł��Ȃ��ڏ��Ȑl�ԂȂ̂�������Ȃ��B�������A�������炩�̍���������Ƃ��A�댯�����m�Ŏ��ۂɍőO���ɐg��u�����̓�ǂɗ����������̂́A���Ԃ�c�����g��ނ�̕ی쉺�ɂ���ꑰ�̎q���q���Ȃǂł͂Ȃ��B���̂悤�Ȕ�펞�ɂ����ċB�R�Ƃ���䅓�ɗ����������̂́A�������Ⴂ�ƌ����A���S�ł͋c����������~�[�n�[�I���ƕ̎�����Ă��邩������Ȃ���X�����A���邢�͂��̉Ƒ���q�ǂ������Ȃ̂��B
�@ ���Ƃ��炻�̂��Ƃ���������Ȃ����A�w���{�����u�t�@�[�X�g���f�B�v�ɑ���x�Ƃ����A���̕����悤�ȕ\���̈ꕶ�̉��ɓ��X�ƃT�C�������A���\���Ɂu�����ɕ��̂��ׂĂ�����v�Ƃ����q���̌��t��z���A���g�������ǂ݂ł��ʂ悤�Ƀr�j�[���Ŋ��S������ʐ^�W���̂��ق��Ȃ�ʏ����ł��邱�Ƃ����́A�ɂ��S���Ă����Ă����˂Ȃ�Ȃ����낤�B
�@ ���q�����͓������Ɂu�C���Ƃ���ΐ����Ɋ댯�̋y�Ԃ悤�ȂƂ���ɂ��o�����v�Ƃ�����������Ă���Ƃ̂��Ƃł��邪�A����͑����Ɍ`���I���邢�͋V���I�Ȃ��̂ł����āA�X�̑������ꂼ�ꂪ�����~�肩�����Ă��邩������Ȃ��g�̊댯��^������̓I�ɍl�����������Ő������̂ł͂Ȃ����낤�B������]�X����Ȃ�A�ق��Ȃ�ʍ���c���⍑�Ɗ���������̏A�C�ɍۂ��Ă͌��I�Ӗ����܂��Ƃ�����ƌ����萾���肵�Ă���͂����B�����ނ�̂����̂��������ǂꂾ���̎҂����ӂ������Ă��̌����������Ă���ƌ����邾�낤�B
�@ �c���⊯���������A����̂��Ƃ͒I�ɂ����A���q���������ɂ͓������̐鐾�����炵�A�E���ɒ����ł��邱�Ƃ�v������Ƃ���Ȃ�A�g������r�������Ƃ��������悤���Ȃ��B�܂��S�������āA���鎩�q����������ʂ�ɍs�����邱�ƂɂȂ���S�O�����Ȃ��Ƃ��Ă��A���̗��e��Ƒ��A���l�A�F�l��̕����s���͑z���ȏ�̂��̂ł���ɈႢ�Ȃ��B���ۓI�ȏ��炵�Ď��q���̊C�O�h������ނȂ����̂ł���Ƃ��Ă��A�����������S���锭����z�����K�v�ł͂Ȃ��낤���B
�@ ���݂ł͏͂��Ȃ����Ă��Ă���悤�����A���ẮA�h�q��w�̊w���◤�C��̎��q�����́A���̑�������B�A���k�A�k�C���Ȃǂ̒n���o�g�҂ɂ���Đ�߂��Ă����B�o�ϓI�Ɍb�܂�Ȃ��n���̏o�g�ŁA�\�͂�����w�ӗ~�������҂����́A���Ƃ����ꂪ�S�̒ꂩ��u�]�������ł͂Ȃ������Ƃ��Ă��A���q���W�̊w�Z�ւ̐i�w��I���̂Ȃ̂��B���Z����ɂ͊��ɂ��ׂĂ̓��e�������o�ϓI�ɂ������̋ɂ݂ɂ��������Ȃǂ��A���t����h�q��w�ւ̐i�w�����コ�ꂽ�肵�����̂��B���ʓI�ɂ͖h�q��ɐi�w�͂��Ȃ��������A������Ə�����Ă�����A�������ėE�܂����ȂȂ����̂悤�Ȏ҂����Ď��q���ɂȂ��Ă�����������Ȃ��̂��B
�@ ���̒m��͈͂ɂ������Ă��A���q�����邢�͂��̌o���҂ɂ͗D�ꂽ�l�ނ������Ȃ��Ȃ��B���Ƃ��Ɣ\�͂̂���Ƃ���ɂ����āA�����̎g����������Ȃ���e��̌��r��ς�ł��Ă��邩��A�������̎��q���Ƃ��Ȃ�Ɠ�A�O�J����͎��݂ɑ��邱�Ƃ��ł��邵�A���R�Ȋw��H�w�n�̐��m���͌����ɋy���A�@�w�A�o�ϊw�A�����w�A�Љ�w�A�S���w�Ƃ������Љ�Ȋw�n�̕���ɒʂ���҂��������B�������A�������q���̂��Ȃ�̎҂́A�K���Љ�ɑ����Ă���ɂ�������炸�A�ӊO�Ȃ��炢�ɏ_��Ŏv�z�I�ɂ����R�ł���A�l�ԂƂ��Ă͗L�͊����̊��������Ȃǂ���قǍD�������Ă�̂��B�����X�p�[�e�B�[�ɂ̍ݕ����Ƃ��Ċe���̓��{��g�ق��̑��ɋΖ������o���̂���҂Ȃǂ́A�݂����ʂ����Ă��閳�\�ȊO�����A�������A���荑�̕����s�����̑��̍���ɂ����ƒʂ��Ă�������̂��B
�@ ���{���^�̈Ӗ��Ŏ��q���̑��݈Ӌ`�������ɔF�������悤�Ɗ肤�̂Ȃ�A���̊ۂ��f���Ĕނ���C�O�ɑ���o�����ƂɎ��S����܂��ɂ��ׂ����Ƃ����邾�낤�B�������R�Ȃ������Ŕނ�̂��\�͂��L���Љ�̔��W�Ɋ��p���A���ԂƂ̕����������ʂł̌𗬂�[�߂Ă����悤�Ȕz�����ɂȂ��ׂ��Ȃ̂��B���̂��߂ɕK�v�Ƃ���A�ꎞ�I�ɐ�����E���Ŋ������邱�ƂȂǂ�������Ă�����ׂ����낤�B�ЊQ���̓��ʏo���≉�K���i�̌��J�A�����č���̂悤�ȓ��̊ۂ̌֎���ړI�ɂ��������̊C�O�h�������ɂ���āA���q���ɑ����ʍ����̍L���x���悤�Ƃ���̂͂ǂ��������Șb�ł���B
�@ �����������˂Ɏv���邩������Ȃ����A�E�܂������t��f���ăe�������ʑ[�u�@�̐����ɖz�����A���̊ۂ��f�������q���̊C�O�h�������X�Ƃ��Đ��肽�Ă�^�}����c�������ɂЂƂ�����Ă����Ă݂����B�\���ł���\���ł��悩������A�܂��E�C���邠�Ȃ��������A�p�L�X�^����A�t�K�j�X�^���ɏo�����A���Ԃ̃A�t�K�j�X�^����x�������ɎQ�����Ă��炢�����B�������A�n�q���؍ݔ�炢�͎����ŔP�o���Ă��炤�����Ȃ����낤�B������s�@�ɏ��̂��|���ȂǂƂ͍l������Ȃ���܂��B�e���r�Ȃǂō���R�c�����邩����A�\�����\���p���Ȃ��Ă��R�c�ɂȂ�̎x����Ȃ������ȋc���Ȃǂ�����悤������A�������������X����D��I�ɏo�����悤�ɂ��Ă��炢�����B
�@ ���ꂪ�s�\���Ƃ����̂Ȃ�A�p�L�X�^����A�t�K�j�X�^���ł�NPO������NGO�����ɐϋɓI�ɎQ�������苦�͂����肷��悤�ɁA��l�ł���l�ł�����̎q���q�����邢�͑������Ȃǂ�������邭�炢�̂��Ƃ͂��Ă��炢�����B�������������������Ƃ���������Ȃ�A���Y�c���ɑ��鍑���̐M���͑������Ƃ��낤���A���Ƃ����̎q���q���炪�����c���A�O���c���ɂȂ����Ƃ��Ă��A���̋M�d�Ȍo���͔ނ�̐��������̑傫�Ȏx���ɂȂ邱�Ƃ��낤�B�����̓A�O���c����ڎw������̐g�������͈��S�ȂƂ���Ɏ��u���A���l������E�܂������肽�Ă�Ƃ����̂ł͋��ʂ�Ȃ��B
�@ ��������O������̂͏��m�����A��O��O�ɂ��A���M���X�ɃR�����e�Ȍ����������鐭���Ƃ�]�_�ƂƂ������̂����͂��˂Ă��炠�܂�M�p���Ă��Ȃ��B���̂悤�ȃ^�C�v�̐l���Ƃ������͕̂\�ʓI�ɂ͉����ɂ��ʊ��ňӎu���������Ɍ�����̂����A���̎p�͈ӊO�ȂقǂɐƎ�ŁA�^�̊댯����O�ɂ���Ɖ��a�Ȏp��I�悷�邱�Ƃ������Ȃ��Ȃ��B�S���w�I�ɂ݂Ă��A���̎�̐l���͒n�ʂ⌠�͂ւ̎u����������߂ċ������ʂŁA������茠�Ђ���҂ɑ��Ă͏]�������ᔻ�ɐU���������ȂƂ��낪����B�����̍s�ׂ��������ʂ��������ꍇ�ȂǁA���X�ɓ����������A���̐ӔC���Ƃ낤�Ƃ��Ȃ��̂����̃^�C�v�̐l�X�̓����ł���悤���B����̃e�������ʑ[�u�@�̑��������������x����������c����]�_�Ƃ̖ʁX�ɁA����ȉe��тт��l���������Ԃ�ƌ���ꂽ���Ƃ͂��������C�ɂȂ�Ƃ���ł������B
�@ �O�q�����e���r�ԑg�̃L���X�^�[���A�Ō�ɁA�u�^�̗F�Ƃ́A���ɂ���Ă݂͌��ɋꌾ��悵�������Ƃ̂ł���W�ł�����Ƃ����邪�A����̏���ł́A�A�t�K�����ɂ��Ď̓u�b�V���đ哝�̂Ɏ��d�𑣂��悤�Ȃ��Ƃ����肤�邩�v�Ƃ����Ӗ��̂��Ƃ�₢���������A����ɑ��Ă��͐��ʂ��瓚���悤�Ƃ��Ȃ������B���ꂪ�Ӑ}�I�Ȃ��̂������̂��A����Ƃ����N�̂����ɐg�ɂ������̐l���L�̃X�^���X�̂Ƃ肩���Ȃ̂��͒m��Ȃ����A�������Ƃ���̂����͔��������Ƃ����v�����������͂����B������ɂ���A�ߋ��̌������݂邩����A����͗��l�ߌ^�̐l���ł͂Ȃ��������B
�@ ���Ԃ�A���̎́A�l�X�ȏ�ǖʂ��Â��_���I�ɍl�@�������̌��_���o���^�C�v�̐����Ƃł͂Ȃ��A���ϓI���邢�͊��o�I�ɂ܂����_���o���Ă����A���̌��_��i�삷�邽�߂ɗ��_������@���l���o���M���s�^�̐����ƂȂ̂��낤�B���̂悤�Ȑ����Ƃ��s���̒��_�ɗ��ꍇ�A���̒��ϓI���邢�͊��o�I���f�ƑI�����I�Ƀv���X�̕����ɂ͂��炢�Ă���Έ̋Ƃ����Ȃ����邾�낤���A�}�C�i�X�̕����ɂ͂��炭�悤���Ɗ낤�����܂��傫������A����Ȃ�̌x���͌������Ȃ��B
�@ �������Ă��̌��e�������i�߂Ă���ƁA���Ƃ����낤�ɁA�̕ꓰ���������ꂽ�Ƃ̕���э���ł����B������Ȃ���A�ꍑ���Ƃ��Ă܂��͌䖻�������F��\���グ�����B���̂Ƃ���̕\������Ԃ�ƌ������Ȃ�A��J�̉e���Z�������o�Ă���̂��C�ɂȂ��Ă������A����Ƃ����̂��A���Z�ȍ�����̐S�J�ɂ��킦�āA�ꓰ�̕a��ւ̐l�m��ʗJ���������Ă̂��Ƃ������̂�������Ȃ��B�A�C�����̍��Ƃ͈���āA���̂Ƃ��낿����Ɨ�ΓI�ŕ|�����̂�����������̌��t��\��ɁA�ꍏ�������l�ԓI�ȉ����݂��S���Ă��邱�Ƃ�����Ă�܂Ȃ�����ł���B
�@ ��̑I���ʼn�X�������ɑ��������̂́A�e�������ʑ[�u�@�̐���ł͂Ȃ��A�s���y�э\�����v�̒f�ł�����H�ł������͂����B��Ɍ��_���肫�̒f�ł��鏬�Ō��\�����A�܂��A�������������V�ł��Ȃ���Ή���ʗd�ȓ��������Q����绂��邱�̍��̉��v�͕s�\���낤����A����Ƃ����u���ѓO���Ă��炢�����̂��Ǝv���B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N11��14��
���P�c���̕i���͂ǂ��ɁH
�@ �炿�̂悢�l�Ƃ������̂́A�Ƃ�����Ɛ��Ԃ����J������Ȃ��Ƃ��A������m��Ȃ��Ƃ�����ꂪ���Ȃ��̂����A�����g�́A�ق�Ƃ��̈Ӗ��ł̈炿�̂悳�͂������Ĉ������Ƃł͂Ȃ��Ǝv���Ă���B�v�́A���̐l���炿�̂悳�������̐l���ɂǂ��������A�ǂ��Љ�Ɋւ���Ă������̖��Ȃ̂��Ǝv���B�Ⴂ���ɐS�J�̐₦�Ȃ��������Ȃǂ́A����䂦�Ɏ��������̂��f�O�������̂����Ȃ��Ȃ��B�o�ϓI����������Ɍb�܂�Ă����牓��肹���ɂ���������Ȃ��Ǝv�����Ƃ����Ă����Ԃ�Ƃ������B
�@ �������A����̈ӎv�Ɋւ��Ȃ��������������o��������Ȃ��������䂦�ɁA�͂��߂Đg�ɂ��邱�Ƃ��ł������Ƃ����X���������A���̂����ŋȂ���Ȃ�ɂ����܂������Đ����Ă���̂��Ƃ�������B�Ⴂ���̐����������ǃv���X�ƃ}�C�i�X�ǂ���ɂ���p�����������A�i�D�����āu�v���X�v�Ɠ��������Ȃ�Ƃ��낾���A�ق�Ƃ��̂Ƃ���͂悭����Ȃ��B����ɁA���܂����čj�n��l���𑗂��Ă��邱�Ƃɕς��͂Ȃ�����A�߂������A�j�̏ォ��܂��������܂ɓ]�����Ă��܂����Ƃ����čl������B
�@ �������A�}�C�i�X�܂݂̉^���̎��Ԃ����傫���}�C�i�X�̕����ɉ�]���Ă�����A�}�C�i�X������̐l�������Ă��肦���킯�����A�v���X�܂݂̊��Ɉ���Ă����Ȃ�A���܂Ƃ͌��Ⴂ�Ƀ_�C�i�~�b�N�Ȑl�����J���Ă�����������Ȃ��B������ɂ���A���ׂĂ͌��ʘ_�ł����āA���܂���u�������v�Ƃ�������̘b�����Ă݂��Ƃ���Ŏd�����Ȃ��B
�@ �����A�炿���悭�Ȃ���A����̓I�Ȍ�����������Ȃ�A�Ⴂ����Ɉ��̐�������o�ϓI�����Ɍb�܂�Ă��Ȃ�������ɂ����邱�Ƃ̓�����E�����݂��邱�Ƃ͎����ł���B���Ƃ��N���V�b�N���y�̐��E�Ȃǂ������ł��낤�B����Ȃ�̌o�ϓI�w�i���K�v�Ȃ����ɗc��������̓��ʂȃg���[�j���O���������Ȃ����̃W�������Ő�������ɂ́A�炿�̂悳�Ƃ������̂��A�\�������ł͂Ȃ��ɂ��Ă��K�v�����ł͂��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�ނ��A�炿�̂悳���x�[�X�ɃN���V�b�N���y�̐��E�ւƐi�ސl�����́A���ꂪ���������ɑ����ꂽ�Љ�I�������Ƃ킫�܂��A�����Ŋi�����A��Y���A���鎞�͍��܂����Ȃ���A����̉��y�\����ڎw���Đ��i���Ă��炦�悢�킯���B
�@ �×��A����חオ�����Ƃ���Ă������{�ł͕K�����������ł͂Ȃ��̂����A���[���b�p�Ȃǂł́A�w��̐��E���u���҂͈��̌o�Ϗ����⋳����Ɍb�܂�Ă��ē��R���ƍl�����Ă���悤���B�w��̐��E�ő听����ɂ́A�����̂��ƂȂǂ��������C�ɂ��������ɖv���ł���قǂ̌o�ϓI��Ղ̑��݂����R�̑O�Ƃ����̂ł���B���Ă̏ꍇ�A�����������l�������`���I�ɐ[���Љ�ɒ蒅���Ă��邪�䂦�ɁA�o�ϓI�ɂ͌b�܂�Ă��Ȃ������Q�̔\�͂����l�ނɋ�����鏧�w���̎x���z�Ȃǂ́A�K�v�z���\���ɖ��������̂ɂȂ��Ă���̂��낤�B���Ă̓��{��p��Ȃǂɂ݂钆�r���[�ȏ��w���̎x���Ԃ�ȂǂƂ́A���̓_�����Ԃ�ƈ���Ă���悤���B
�@ ���������w������̂��Ƃł��邪�A���܂��܉��̂���������ݓ����l��������{�q���g�̘b���������܂�A�u�N�������w��𑱂������Ȃ��ΓI�Ɍo�ϊ�Ղ̊m�����K�v�����炱�̘b��������ׂ����B�����łȂ���ΌN�ɏ����͂Ȃ��B�w��̐��E�Ő����ʂ����Ƃ͂��ꂾ�����������̂Ȃ̂��v�Ƌ����������ꂽ���Ƃ�����B���B�Ȃǂł͂����������A�h�v�V�����i�{�q���g�j�͂������ʂ̂��ƂȂ̂��Ƃ����̋����͗͐������B�ނ��A�ߐe�҂̂܂��������Ȃ����̐g����������炩���ߒ��ׂ������ł̂��Ƃ������B
�@ �R���ɕv�Ǝ��ʂ��A���q�����Ȃ��V�w�l�̎��Y�Ƃ������āA�Ƃ̏����������w�����炢�̗{�q���ق����Ƃ����b�ł͂������̂����A���낢��Ǝv�Ă���������A���ǁA���͂��̈ꌏ��f�����B���̊��߂ɉ����Ă���A�n�R�����҂̏�Ƃ��ē��X�̐����ɒǂ��邱�Ƃ��Ȃ��A�����͂܂��Ȑ��ʂ��グ�邱�Ƃ͂ł�����������Ȃ����A�����͌����Ă��A���Ƃ��Ƃ̎����Ɍ���̂������g�䂦�A��͂葽���͖]�ނׂ����Ȃ������ɈႢ�Ȃ��B����ǂ��납�A���܂���͂��̎��Y��H���Ԃ�����A���Y�Ǘ���������肵�āA����݂����Ƃ��ƕ����̎�ɂȂ��Ă����\�������Ă���B
�@ ����G���A�L�˔Ɏ��A������̓���O�Z��́A�����w�҂Ƃ��đ听���邽�߂̊��l����O��ɗ{�q�ɏo����A���̌��ʁA���ꂼ�ꂪ���{���\����w�҂ɂȂ������Ƃ͗L���Șb�ł���B���Ԃ�A���̐l�����͗c����������O�ꂽ���ݔ\�͂������Ă������̂��낤�B�܂����������炱���A���ٍ̈˂̊J�Ԃ��肤���e��{�����̊W�҂ɂ���āA��т��������肪�Ȃ��ꂽ�̂��낤�B
�@ �^�̈Ӗ��ň炿�̂悢�l�Ƃ������̂́A���~�▼�_�~�Ƃ����������I�~�]�����܂�Ȃ��A�����ꂽ�����I���l���f�\�͂�A���X�̌|�p�Ȃǂɑ���{���I�ȋ���͂����Ȃ��Ă��邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��B���Ԃ���͋�J�m�炸�Ǝv��ꂪ�������A�ӊO�Ƌt���ɂ������A������Ԃɏ�������\�͂������B���j��̊e��Љ�v�V�^����l�X�ȎЉ���^���Ȃǂɂ����Ď哱�I��������������A����̍v���������肵���l�X�ɁA�ljƂ̏o�g�҂������͍̂L���m����Ƃ���ł���B���S���ʂŌb�܂�Ĉ�����l�Ȃ�ł̗͂D�����A�̂т₩���A�����S�̂Ȃ��A�����̍L���A�D�ꂽ���A�挩�̖��Ȃǂ��傫���������䂦�Ȃ̂��낤�B�ނ��A�����ɂ�����͑��݂���킯�ŁA�炿���悢�ɂ�������炸�A�l�i�I�ɖ���������l�����Ȃ��炸���������͂���B
�@ �����ĂȂɂ��v�킹�Ԃ�Ȃ��Ƃ��������̂́A�炿�̂悢�͂��̓A�O���̐��P�c���ɂ���Ă��̑������߂��Ă�������̐��E�Ɉꌾ�G�ꂽ����������ł���B����A���c���[�����A�c���O���A�Ό��s�����v���A���������[��������͂��߂Ƃ��A�����t�ɂ͂����Ԃ�Ɛ��P�c�������������邵�A�^��}�̗L�͍���c���ɂ������ẮA���̑唼���A�O���̐��P�c���Ƃ����̂��A���܂����̂悤�ł���B�e����̒n�ՂƂ����o�b�N�{�[���������Ȃ��l�Ԃ��A�Ȃ̗݂͂̂𗊂�ɍ���c���ɓ��I����̂́A���݂̑I�����x���ł͑�ςɓ���B���Ƃ������ȃ��f�B�A�l�ł������Ƃ��Ă��A��قǏ���������Ȃ���������͂܂ʂ��ꂦ�Ȃ����Ƃ��낤�B
�@ �`���̉ƋƂł��ꉽ�ł���A�e�̐E�Ƃ����̂܂p���Ƃ������Ƃ́A�p�����鑤�ɂ�����Ȃ�̒�R������������̂����ʂł���A�p���҂̒f��ɂ����邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ����A����c���Ƃ����E�Ƃ͂��̓_�ł����قȑ��݂̂悤�ł���B��قNj��S�n�̂悢�E�ƂȂ̂��낤�B���Đ��̓��{���E�ɌN�ՁA煘r�������Ĉꐢ���r�����g�c�Ύ̏ꍇ�A���̗B��̒��j�g�c����́A�I�����E�ɋ����������A�D�ꂽ�p���w�҂Ƃ��Ă��̐��U���܂��Ƃ��������A���̂悤�Ȏ���͂ނ��뒿�����悤�ł���B���̑P�������͂Ƃ������A���܂⍑��Ƃ����Ƃ���́A�����Ƃ͈ꖡ�Ⴄ�A�u�炿�̂悢�v�͂��̐l�X�̊��������ɂȂ����ƌ����Ă��悢�B
�@ ����͂���ł悢�̂����A���������ƂɁA���̂Ƃ���̓A�O���̍���c���S�̂���˂��邩����A���̐l�ƂȂ�ɐ^�̈Ӗ��ł̈炿�̂悳��C�i�Ƃ��������̂����Ȃ����l���������قǂɏ��Ȃ��̂��B��O���܂������Ȃ��Ƃ͌���Ȃ����A�\�����̓A�d���Ƃ͗����̘������A�A�N�̋����A���M�ߏ肳�A����ɂ͗�ΓI�ԓx�Ƃ������悤�Ȃ��̂��������܂�ɂ��ڂɂ�������B�u�����Ȃ�ď��F�A�z�ȑ��݂ɂ����Ȃ��̂��I�v�Ƃ������t�ɂȂ�Ȃ����t���ނ�̋������畷�����Ă���悤�Ɋ�����͎̂������ł͂Ȃ����낤�B���Ȃ��A�O���̐��P�ł��A�l�i�҂������Ȃ��Ȃ����ƊE�̌p���҂����Ɣ�ׁA�Ȃ�����قǂɈႤ�̂��낤�B
�@ �����̐��E�Ƃ������̂͂��Ƃ��Ƃ����������̂�����A���Ƃ��炿�̂悢���P�c���ł͂����Ă��A���E�Ɋւ�鑶�݂ł��邩����A�����ɐl�ԂƂ��Ẳ�������i���̍��������߂Ă݂Ă����ʂł���Ƃ�������������̂́A�ނ��S�����m�ł���B�����ƂƂ��Ă̐e�̌��d�p���Ԃ��g�߂Ɍ��Ĉ炿�A�Ⴂ���ɗL�͋c���̔鏑�Ȃǂ߂Đ����̐��E�̉����邩���w�ׂA�K�R�I�ɂ����Ȃ炴������Ȃ����A�܂������łȂ���ΐ����ƂȂǖ��܂�Ȃ��Ƃ����l���ɂ��ꗝ����B������a����҂ɂ́A���ɂ����̔����K�v�ł��邱�Ƃ������ł���B
�@ �����A����ɂ��Ă��Ȃ��A�����̐��P�c���̗��O�Ȃ�������㵒p�S�̂�������Ȃ����ȕېg�Ԃ�͖ڂɗ]����̂�����B����̏�����t�̐��P�c���ɂ������Č����A��M���ɂ��Ă܂������܂��Ȃق��Ȃ̂�������Ȃ����A����S�̂ɂ����鐢�P�c���̎p�ƂȂ�Ƃǂ��ɂ��������������̂ł͂Ȃ��B���̎���������ɔ���圤���͂����̂��Ƃ͂����Ă��A���̌������N�̖ڂɂ��X���ɉf��ƂȂ�Ƙb�͂܂��ׂł���B�h�_�̋ɂ݂��o�A�P����������������̗͂ŋc���ɂȂ����҂Ȃ�Ƃ������A�����ł͂Ȃ��A�O���c���̂��ƂƂȂ�Ƃ�͂��肾�ƌ��킴������Ȃ��B
�@ ��ɒn���ւ̗��v�U���݂̂��c���ɋ��߁A���ƑS�̂̂��Ƃ��l���悤�Ƃ��Ȃ��I�����ɂ��ӔC�̈�[�͂���̂��낤�B�n���ւ̗��v�U���ɑ���I�����̉ߓx�̊��҂Ɨ~�����A���������̈炿�̂悳�Ƃ��̂䂦�̋C�i�Ƃ𐢏P�c�����玟�X�ɒD�����A�l�ԂƂ��Đ��n���A�^�̐����ƂƂ��đ听���邱�Ƃ�j�Q���Ă���̂͊ԈႢ�Ȃ��B
�@ �����ۂ��̓A�O���̋c���͋c���ŁA�x����̂ƂȂ��Ă���n���I������x���c�̂��牽������Ă����ᔻ�ōՂ�グ����̂��悢���ƂɁA���������̂�̖��n����Y��Đ��i��ӂ�A���ɂ́A�u����c���Ƃ��Č��݂̒n�ʂ��͎̂���̎��͂̂䂦�ɂق��Ȃ�Ȃ��v�ƍ��o����ɂ�����̂ł��낤�B�����Ȃ�Ƃ����A�����I�삯�����݂̂��g��̂�����u��������v�ɂȂ��Ă��܂��A�悢�Ӗ��ł̈炿�̂悳�Ȃǂǂ����������ł��܂��̂��B
�@ ���̂�̕ېg�ȂǍl�����A���S�����~�ʼnʊ��ɐ����̓�ǂɒ��݁A�}���}�����Đ^�̍����ɍv�����邱�Ƃ������A�炿�̂悢�A�O���c���ɖ{���]�܂�邱�ƂȂ̂����A���������p�̐��P�c�����قƂ�nj����Ȃ��Ȃ��Ă������Ƃ͂Ȃ�Ƃ��߂���������ł���B
�@ �O��̍����I���ō����̑�����������x�������̂́A���̐^��͂Ƃ������A�̎p��l�ƂȂ�ɋߔN�������炿�̂悳�ƁA�}���}���⎩�ȕېg�Ƃ����������I������݂ɑ����ʕi�������������炾�낤�B�̑I���n�Ղ����{���тƂ��������I���j�I�ɂ���Ɏ���̐�[�ɂ������n��ł��邱�Ƃ������W����̂�������Ȃ��B������ɂ���A���̐^��̂قǂ����������͉����Ȃ��B�ނ��A�l�I�ɂ͎̈炿�̂悳�Ƃ��̕i�i���{���ł��邱�Ƃ�����Ă�܂Ȃ�����ł���B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N11��28��
�L������賐헪�Ȃ邩�H
�@���Q���L�����́A�����Ŗ������l���\�쌹����̈�p�Ɉʒu���Ă���B���A�X���C�݂�A���̒n�`�𗘗p�����^��̗{�B�ȂǂŒm����F�a���s�̂��������ɂ������Ă���A�ː�����܂ł͉��B�ɒB�Ƃ̗�������މF�a���˂ɑ����Ă����B���̒n�ɂ́A�Î��L���Ȉɗ\�_�y��S�k���y�A�܂��x��ȂǂƂ���������������d�v�ȌÓT�|�\���c����Ă���B�ŋ߁A�L�����_�ƌ��Ђ̐V�{�����ɍۂ��A��j����̋M�d�Ȉ�Ղ��������ꂽ��������悤���B�������A�ߔN����ɂȂ����悤�ȝs����ՂȂǂł͂Ȃ��B
�@ �����ւj�[�N�Ȃ��̍L�������ȑO�Ɉ�x�K�˂����Ƃ�����̂����i���̎��̒T�K�L��2000�N10��11���`2000�N11��01���̃o�b�N�i���o�[�Q�Ɓj�A���̍ۂɂ�����Ƃ����b��ɂ̂ڂ����u賃v���W�F�N�g�v�̂��̌�̓W�J���C�ɂ͂Ȃ��Ă����B����賁i���{賂͒��b�ی�@�̐������ė{�B�ɂ͎g���Ȃ��̂��������j�̗{�B���ő�X�I�ɂ����Ȃ��A���������܂����ʃ��[�g�ɂ̂������A�����āA�ł���u賂̍L�����v�Ƃ����C���[�W��S���I�ɍL�������Ƃ����ꕗ�ς�����v���W�F�N�g�ŁA�ŋ߁A�ߑ�I��賂̉��H������Ȃǂ������ғ����n�߂��ƕ����Ă����B
�@ ����Ⓚ�Z�p�ƃI�y���[�V�����E���T�[�`�̐��ƂƂ��Ă��̃v���W�F�N�g�̌ږ�����Ă���m�l�̎O������ɁA�����̏ɂ��Đq�˂Ă݂��Ƃ���A���́u賎��v���W�F�N�g�v�Ƃ����ِF���i�J���v�悪�i�W���Ȃ̂��Ƃ̂��Ƃ������B���������u賎��v�Ƃ͂����Ȃ�V�����m�Ȃ̂��H�\�\���˂̂����ɍD��S�����͐l��{�����Ȏ��́A�Ȃɂ�瓾�̂̒m��Ȃ����̐��̂�T�����Ă݂悤�Ǝv���������B
�@ �������A���̃V�����m���A�����ʂ�́u���i�v�ł���Ȃ�A���̃A���R�[���}�ɂƂ��Ă���قǂ̘N��͂Ȃ����낤�B���̃R�����̑��_�̉i�䖾�h�N�^�[�Ȃǂ͋����Ċ�ԂɈႢ�Ȃ��B����ɁA�L�����̊F����ɂ͐�̖K��ʼn����Ƃ����b�ɂ��Ȃ������Ƃ䂦�A���̍ہA賎��v���W�F�N�g�Ȃ���̂̏Љ�Ɉ���Ă����̂������Ȃ��B�܂�����Ȃ悤�Ȃ킯�ŁA����̖��f�Ȃnjڂ݂���N�Ԃ�ɍL�����ւƗ��������B
�@ �������A�������B�̎O�����ꏏ���������A��B�Ƃ͂����Ă��A���̐l�̓i�r�Q�[�^�Ƃ��Ă����h���C�o�[�Ƃ��Ă��܂��������ɗ����Ȃ��B�Ƃ��낪�A�A���R�[���E���[���h�̊֘A���ƂȂ����r�[�ɓr�����Ȃ��\�͂�����Ƃ��Ă��邩��A�l�ԂƂ͂Ȃ�Ƃ��s�v�c�Ȃ��̂ł���B�L������賃v���W�F�N�g�ږ�Ƃ��āu賎��v���W�F�N�g�v�Ȃ���̂��l���o�����̂��A�ނ�̐l�ɂق��Ȃ�Ȃ��B�L�����⓯���ɋ��͂��閯�Ԋ�ƂɂƂ��Ė��̃v���W�F�N�g���g�Ƃł邩���Ƃł邩�ׂ͂Ƃ��āA�u賎��v�Ƃ������z���̂͂Ȃ��Ȃ��̂��̂ł���悤�Ɏv��ꂽ�B
�@ �L�����ł͂��łɐ擱���s�Ƃ��đ�������賂̗{�B�������Ȃ��Ă���A�܂邲�ƗⓀ���H���ꂽ���̂����Ɉꕔ�̔����[�g�ɂ̂���ꂽ������Ă���B�ڂ����b�͏ȗ����邪�i�����̂������2000�N11��01���̃o�b�N�i���o�[�u�L�����V�K���ƒT�K�L�v���Q�Ƃ��Ă��������j�A賃v���W�F�N�g�̂����܂��ȗ���͎����̂悤�Ȃ��̂ł���B
�@ ���c�̐����z���琬�{�݂�賂̗���l�H�z�����A�z�����������琗��ňꃖ���قLj�Ă�B�����̐��͒����̗{�B��]�̔_�Ƃɏ����A�e�_�ƂŐ����ɂȂ�܂ň�Ă���B�����Đ������Ăђ��������߂��B���̏��n���i�ƒ��̐������承�i�Ƃ̍��z���_�Ƃ̗��v�ƂȂ�̂͂����܂ł��Ȃ��B�L�����̂ق��͔����߂���賂c�̉��H������ŏ��i�����A�����炩�̒l�i����悹���Ĕ̔����[�g�ɗ����Ƃ����킯���B�������ʂ�賓������ʂ���悤�ɂȂ����Ȃ�ɍ̎Z�͍����炵���̂����A�{�i�I�Ƀv���W�F�N�g�������o���Ă���܂��Ԃ��Ȃ����݂́A�W�҂ɂƂ��Ă����ς琳�O��Ƃ����Ƃ���ł���炵���B
�@ ���������A����賃v���W�F�N�g�ɂ̓N���A���Ȃ���Ȃ�Ȃ���肪����݂��Ă����B���̂ЂƂ͓���Ȑ���������賓��̗Ⓚ�����Z�p��̖��A���܂ЂƂ�賗����̒����Z�p���܂߂�賓��̂����Ƃ����ȏܖ��@�̌����J���������B���ʗʂ����������Ȃ�賂̏ꍇ�A�ǂ����Ă��{�ȂǂɊr�ׂĈ�H������̔̔����i�������ɂȂ炴������Ȃ��B��������賂̑N�x�Ɩ���ۂ��A�����ۂ��ł��̊��������������Ă����ɂ́A������̓�����������K�v���������B
�@ �L������賃v���W�F�N�g�ږ�Ƃ��Ă��̖��̉����Ɏ��g�O������́A�n��Y�Ƃ̊W�҂�ΏۂɍL�����_�ƌ��ЂŊJ���ꂽ�u����ł��̌������ʂ�������A�Ȃ��Ȃ��ɂ��̘b�͖ʔ��������B
�@ �L���@�B���[�J�[���w�̌���������݂Œ��N�Ⓚ�Z�p�̌����Ɍg������O������̘b���ƁA�H�p�{�ށA���ށA�H���ނȂǂ̓��Ƃ������̂͒����Ⓚ�ۑ�����ύ���ł���炵���B�Ⓚ�������قǂ����ƁA�������ɍזE���̐������c�����邽�ߍזE���̂��̂������Ȃ��炸�j�Ă��܂��B�������A�������X�̔������ǂ��������X�Ɍ��������傫�Ȍ����ɐ�������̂ŁA���������זE�j�i��ł��܂��B���̂��߁A�𓀎��Ɏ|���������͂��߂Ƃ���זE���̏��������h���b�v�i�|���������܂ޑ��ʂ̐��H�j�ƂȂ��ė��o���A�����N�x���傫�������Ă��܂��̂��������B�Ƃ��ɁA�H���ނ̓����i�ʼn𓀎��Ƀh���b�v�̏o�Ȃ����i�̑��݂́A����܂ʼn䂪���ł͊m�F����Ă��Ȃ��Ƃ����B
�@ 賓��͌{���Ȃǂƈ���āA�ō��ɖ����悭�Ȃ���Ԃ���N�̂����̈�A���Ɍ�����B������A���̂悢賓���N�Ԃ�ʂ��ė��ʂ�����ɂ͗Ⓚ�ɂ�钷���ۑ����������Ȃ��B�����Ȃ�ƁA�h���b�v���ɗ͗}����Ⓚ�Z�p�̊m���͔����Ēʂ�Ȃ����ł������B�������A����ɂ��킦�āA賓��̗Ⓚ�Ɋւ��Ă͂��܂ЂƂ�����v�����₪�������B
�@ 賓��͏����シ���ɐH�ׂ���A����قǏn�������Ă���H�ׂ��ق��������������Ƃ͐̂���m���Ă����B�����ŁA�|���̎听���ł���C�m�V���_���̑�����Ԃ��Ȋw�I�ɕ��͂��Ă݂�ƁA��͂菈����l�\�����Ԃقnjo�߂����Ƃ��낪�n���̃s�[�N�ɂȂ�A���Ȃ킿�A���̎��_��賓����Ɋ܂܂��C�m�V���_���̑��̎|�������ʂ��ő�ɂȂ邱�Ƃ��m�F���ꂽ�B
�@ �������Ƃ���A������l�\�����Ԃقnjo�߂��Ă���Ⓚ��������̂��x�X�g���Ƃ������ƂɂȂ�̂����A�n���Ƃ͗v����ɏ��X�ɕ������邱�Ƃɂق��Ȃ�Ȃ�����A���̂Ԃ�咰�ۗނ������邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B�H�i�̉q���Ǘ��ɂ͌������@�I�K�����݂����Ă��邩��A�咰�ۗނ̐��͌��i�Ɋ�l�ȉ��ɗ}�����܂�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�咰�ۂ̑��B��}������ɂ͏�������ɋ}���Ⓚ����ɂ����邪�A��������ƁA���̗����関���n��賓��ɂȂ��Ă��܂��B
�@ �Z�p�I�ϓ_���炷��ƂȂ�Ƃ����Ȗ��ł͂��������A�O�������́A�܂��A���n�i�s�x�Ǝ��Ӊ��x�Ƃ̊W�A�咰�ۂ̑��B�x�Ǝ��Ӊ��x�Ƃ̊W���ڍׂɒ��ׂĂ݂��B�܂����̂����ۂ��ŁA�ߔN�قƂ�njڂ݂��邱�Ƃ̂Ȃ��Ȃ��Ă����t�̓����@�Ƃ����Ⓚ�@�ɍĒ��ڂ��A���낢��Ɨ\���������d�˂Ă݂��B�����āA���̌��ʁA�悤�₭�������ɑ��������Ƃ����̂ł���B
�@ 賓��̏n�����ɗ͐i�߂邢���ۂ��ő咰�ۂ̑��B���\�Ȍ���}����ɂ́A賂̏�����A�ێ����x�̒艷�̂��ƂŎl�\�����Ԃ˂����Ă����̂��œK�ł���Ɣ��������B�܂��A�𓀎��̃h���b�v���ŏ����ɗ}����ɂ́A���̂��ƃ}�C�i�X�O�\�x����}�C�i�X�O�\�ܓx�̃G�^�m�[���t����賂�Z���}������������̂��ŗǂł��邱�Ƃ��킩���Ă����B
�@ �قƂ�ǂ̗Ⓚ���H�H���ł́A���݁A�G�A�t���X�g�@�ɂ��u�ԗⓀ���嗬�ƂȂ��Ă���B�C�̂�p�������̕��@�́A�M�����������������߂ɁA�Ώە��̕\�ʂ����𓀌�������ɂ͂悢����ǁA�Ώە��̐[�����܂ł�Z���Ԃœ��������邱�Ƃ͓���B���̕��@�őΏە��̓������܂ł𓀌������悤�Ƃ���ƁA�����Ԃ�v���邤���ɁA���������X�̔�������������剻���J��Ԃ��A�ǂ�ǂ�זE�j���i�߂Ă��܂��Ƃ����B������Ƃ����ĕ\�ʂ�����Ⓚ�����̂ł́A�������̑N�x�ቺ�͔������Ȃ��B
�@ �Ƃ��낪�A�G�^�m�[����p�����t�̓����@�̏ꍇ�A��}�̔M���������傫�����߁A�Ώە��̓������܂ŋ}���ɒቷ�������i�ށB���̂��߁A�����̑N�x���ۂ�������łȂ��A�זE���ɐ�����X�����������̂܂܂ɂƂǂ܂�A�זE�j����ŏ����ł��ނƂ����B�������ʂ��܂Ƃ߂��f�[�^�����Ă݂Ă��A�܂��������Ȃ����x���ɂ܂Ńh���b�v�̔����͗}�����Ă���B
�@ �G�A�t���X�g�@�Ɖt�̓����@�ɂ�铀���Ȑ����r���Ă݂�ƁA�������x�̍��͈�ڗđR�Ƃ����Ă悢�B�t�̓����@�̏ꍇ�A�Ⓚ�T���v���̒��S�����x����x�O�ォ��}�C�i�X�\�O�x�܂ʼn�����̂ɎO�\�������v���Ȃ��̂ɑ��A���ݎ嗬�̃G�A�t���X�g�@�ł́A��x����}�C�i�X��A��x�̂܂܂̏�Ԃ���O���Ԃ������A��������l�\���قǂ������Ă悤�₭�}�C�i�X�\�O�x�قǂɉ������Ă���B�G�A�t���X�g�@�̏ꍇ�A�T���v���̒��S�����}�C�i�X�\�O�x�ɂȂ�܂łɎO���Ԏl�\�����������Ă��邱�ƂɂȂ�킯���B
�@ �ʔ������ƂɁA�t�̓����@��p����Ƒ咰�ۗނ̐��܂ł��Ⓚ�J�n�������������邱�Ƃ��킩���Ă����B�������A�Ⓚ�Ώە��ڂɗⓀ�t�ɐZ���̂ł͂Ȃ��A��}�ɐG��ʂ悤�ɐ^��p�b�N���ĐZ���킯������A�G�^�m�[���̎E�ۍ�p�ɂ����̂ł͂Ȃ��������B���̃��J�j�Y���͂��܂ЂƂ͂�����Ƃ��Ȃ��炵���̂����A���x�ቺ���}���Ȃ��߁A�咰�ۂ��זE����ʂ��Ă��炩���ߐ�������o�������c���ɔ����鎞�Ԃ��Ȃ����߂��낤�Ɛ�������Ă���悤���B�������ꋓ�ɓ����c�����čזE����j�A���̌��ʑ咰�ۂ�����ł��܂��̂ł͂Ȃ����Ƃ����킯���B
�@ �O�������́A���̉t�̓����@��p���Đ�s�\�������������Ȃ��A��������賂𗝑z�I�ȏ�ԂŖ�\�����Ԓ����Ⓚ�ۑ����邱�Ƃɐ��������B�������Ă悤�₭�A�L�����Ɂu賓������p�v�����g�E���C���v�����݁A�m���h���b�v�Ŏ|���������ő���ɕۂ���賓�������I�ɒʔN�����ł��錩�ʂ����������̂������B���̉t�̓����@��p������p�����@����������A賓�����łȂ��A�{���⋍���A�ؓ��A�����Ȃǂ̃m���h���b�v���������ۑ��ɂ��З͂����邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ������B��}�ɃG�^�m�[�����g�����߁A���̓����@�Ɋr�ׂă����j���O�R�X�g���Ⴍ�Ă��ނ��Ƃ��傫�ȗ��_�������B
�@
�@ �O������炪�����Ȃ����\�������̃f�[�^�����ƂɁA�G�^�m�[�����}�Ƃ��鍂���\�̉t�̋}�������@�̊J���ɒ��̂́A�_�ސ쌧���c���s�̒��J���H�Ƃ����@�탁�[�J�[�������B�_�ސ쌧���c���s�ɖ{�����������̒��J���H�O���[�v�͋ɂ߂č����H�Ɨp�@�퐻���Z�p�Ƃ����ꂽ���i�J���\�͂������Ă���B�e��̓���@�B����@��̐���Ɍg���ق��A�����̂b�c���Ր��Y�ɂ����đ��Ђ̒ǐ��������ʈ��|�I�V�F�A���ւ��Ă��邱�Ƃł��m���Ă���B���ԊO���Ƌ��U�������Z���~�b�N��f�ނɂ��A�����}�b�g��h���C�u�V�[�g�Ȃǂ̂悤�ȓƑn�I�ȏ��i�̌����J���ɂ��]�O���Ȃ��B
�@ �����f�[�^�͈ꉞ�o�������Ƃ͂����Ă��A���������ƂɎ��p�ɑς���@�B�삷��̂͗e�ՂłȂ��B���Ƃ��A��}�ƂȂ��ʂ̃G�^�m�[���t�����̒ቷ�ɕۂ��A�M����������I�ɂ����Ȃ��H�����������邾���ł���ςȂ��ƂȂ̂��B���̂ق��ɉq���Ǘ���̌��i�ȏ��������Ȃ���Ⓚ�Ώەi�������I�ɓ�����������H�v�Ȃǂ��K�v�����A�Ⓚ�����H��̃��C���S�̂Ƃ̊W�Ȃǂ��l�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A���J���H�̊J���Z�p�҂͂قڗ��z�ʂ�̉t�̋}���Ⓚ�@���������邱�Ƃɐ��������B
�@ ����������ꍆ�@�͍L�����ɐV�݂��ꂽ賉��H�����H��ɔ[�����ꂽ�B�������̍H������w�����Ă���������A�j�����A��̎��A�n�����A�N���[�����[���A�����ɂ���Ȃ铖�Y�{�݂͂���߂ċߑ�I�Ȃ��̂ŁA�������A���i�ȉq���Ǘ�����\���ɖ������\���ɂȂ��Ă���B�Ȃ��ł��A���މ�́A�E�ہA�^���A�\����p�A�}�������������Ȃ��N���[�����[���ɂ́A���ɗޗ�����Ȃ��قǂɌ������q���Ǘ��̐����~����Ă���B�L�����ɔ[�����ꂽ��ꍆ�t�̋}�������@�����̃N���[�����[���ɂ����߂��Ă���̂͌����܂ł��Ȃ��B
�@ ���܂ЂƂ��^�̉t�̓��������@���L�����ɔ[������Ă������A������̂ق��͂��肨�낵���R���̒����ۑ������Ɏ��p����Ă���炵���B���̓����@���g���Ă��肨�낵���R���𓀌��ۑ����Ă����ƁA�𓀂����ꍇ�ł��A���ƔS��C�͂قƂ�Ǒ��Ȃ��邱�Ƃ��Ȃ��Ƃ̂��Ƃł���B
�@ �䂪���̊ό��p��^�q�D�u�������v�ւ̒����p�^��̔[�������Ɉ����Ă���̂́A��x�����K�˂����Ƃ̂���G�����Y�Ƃ����F�a���̑�萅�Y�Ǝ҂����A���̋Ǝ҂��u�������v�֏o�ׂ���^��́A��͂�t�̋}�������@�ɂ���ē����ۑ����ꂽ���̂ł���Ƃ����B�u�������v�̃V�F�t���A�e�Ǝ҂̔[�������^���T�d�Ɏ��H���A�G�����Y�̐^���I���炾�Ȃ̂����������A���̏G���ɉt�̓����Z�p���Љ�w�������̂��O���m����ł���B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N12��5��
賎��v���W�F�N�g
�@ �ǎ���賓��̒����Ⓚ�ۑ��ƔN�Ԉ��苟���̖��͈ꉞ�̉������݂����A���܂ЂƂ������Ȃ���Ȃ�Ȃ���肪�������B賓��̘̔H�g��Ɍ������Ȃ����̒����@�Əܖ��@�̌����J���ł���B��ʂɂ悭�m���Ă���̂�賓�ŁA����͂���łȂ��Ȃ��̖��Ȃ̂����A��ɂ��邾���ł͂��܂�ɂ��H�v���Ȃ�������B
�@ �䂪�Ƃł��͂���ꂽ賂�Y�t�̃��V�s�ʂ�ɓ�ɂ��ĐH�ׂĂ݂����A�ϋl�߂�قǂɁA������������Q�̂Ȃ�Ƃ��R�N�̂���X�[�v�������i賏`���[�����Ȃǂ��������炳���������������Ƃ��낤�j�A�ґ�Ȃ��Ƃ��̂����Ȃ������B�����A���̂����ۂ��ŁA����������賓��Ȃ̂�����A賂Ȃ�ł͂̑@�ׂȖ��킢�𑶕��Ɋy���߂���ʂȒ����@�������Ă����������Ȃ��Ƃ����v���������B
�@ �×��A�c���Ȃǂł�賗������`������Ă��Ă���Ƃ����b�Ȃǂ�����Ȃ��ŁA�O�������͂��낢��Ɨ����Ɋւ���ߋ��̕����������Ă݂��炵�����A����賗����Ɋւ��ẮA����͂Ƃ���������L���͌�����Ȃ������悤�ł���B�����ʼn��l���̗��������Ƃɂ��q�˂Ă݂����A��͂茈��I�ȉ͓����Ȃ������B���Ƃ��Ɩ쐶��賂͕ߊl������A�e�Ղɓ���ł���悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ������̂ŁA�����@�̓`�����r�₦�����ɂȂ��Ă��܂����̂�������Ȃ��B
�@ �O������̂���̂����߂��ɂ́A�G�b�Z�C�X�g�ŁA���������ƂƂ��Ă������Ȗ{�Ԑ�}�q���Z��ł�����B�{�ԉƂƎO���ƂƂ̐e���͒��N�ɂ킽���Ă���A�{�Ԃ���ƎO������Ƃ͂��݂��C�S�̒m�ꂽ�ԕ��ł���B�܂��A�O������̉�������ȑO���痿�������Ƃ̑O�c�Ўq����̏���߂��肵�Ă��闿���̃v���ł���B����Ȃ��ƂȂǂ������āA�O������̎��ӂł�賓��̔������������@�̌������n�܂����B���낢��ƍH�v���d�˂��A�����A�����Ă��Ȃǂ��͂��߂Ƃ���A賓��̔��������ő�Ɋ������������̗����@�Ȃǂ��l�Ă��ꂽ�B
�@ ����ȂȂ��œ˔@�����яオ���Ă����̂��A���݂ł͌��̑��݂Ɖ������u賎��v�Ȃ�V�����m�Ȃ̂������B�������ォ�猻��ɂ�����܂ŋ{���ł͖��N�����̒���賎���������銵�킵�ɂȂ��Ă���Ƃ����L�^�����邵�A���a�ɓ����Ă�����A�����ꕔ�̎���ʂ̍D���Ƃ�ɂ���Ė�����賎������d����Ă����炵�����Ƃ��킩���Ă����B�����A���������ƂɁA�����璲�ׂĂ�賎��Ȃ���̂̑���������܂ЂƂ͂����肵�Ȃ������B
�@ 賎��͂�͂茶�̂܂܂ŏI���̂��ƒ��߂������܂��܁A�M�d�Ȏ�|�����^���Ă���镶�������ɔ������ꂽ�̂������B�O���������Ԃ�Ǝ��Ԃ������Č������A��J���ē��肵�����̕����Ƃ͏��їE�i���Z�O�`��㔪��j�̕M�ɂȂ�u賎��v�Ƃ����薼�̐��M�������B���їE�͊�g���X�̔��W�ɐs�����A�K�c�I����֓��g����͂��߂Ƃ��鑽���̍�Ƃ�w�҂̒���𐢂ɑ���o�����l���ł���B����Ȃ��������������т́A���E�ȕ��͂Œm���鐏�M�ƂƂ��Ă��������B
�@ ���̐��M�u賎��v�̒��ŁA���т́A�\�\�����̗����w���������̑�͓����q�A���̒�ʼn�Ƃ̑�͓��M�h�A��Ƃ̍K�c�I���A�����w�҂ō�Ƃ̎��c�ЕF�A����ɕM�Ҏ��g�̌ܐl���W�܂��ď��a�����̂���~�̖�Ɏ������J�����B���̎��A�u��賂��܁v�ƌĂ�A�����ɋ{���̋V���ŗp������Ƃ��������������o���ꂽ�B����́A賂̎�H����ړ��A�����Ȃǂ𔖂����Ă���Ă��A�قǂ悭�Ă��オ������������ɓ���ďォ�炨�������M�����𒍂��Ƃ������̂������B�������ݍ��ɂȂ�܂łɁA賓�������ݏo�����M�ȍ����������ƗZ�����āA�Ȃ�Ƃ������Ȃ��������F�����ɂȂ����B�h�i�q���j���A�C�l���i�R�m���^�j���ȂǂɊr�ׂ�͂邩�ɂ��܂��A�㓙�ŁA�I����賎����ܔt�A���������قƂ�Lj��܂Ȃ��ЕF���������������B����ɖ����߂����т�́A�����C�ۑ�̉��c�����A�����畽�̉Ȋw�ғ�l������������Ŋ��x��賎����y���\�\�Ƃ������悤�Ȃ��Ƃ��q�ׂĂ���B
�@ �����������Ƃ͂��Ă��Ă����������̂̂悤�ŁA�u��[�����A���ꂾ�I�v�ƈӋC����ł����O������̂Ƃ���ɁA���܂ЂƂv�������Ȃ��N�����炳�ꂽ�B賗����̃��V�s�Â���Ŏw�������ł���{�Ԑ�}�q����A�̂������悭賎���n��ł����A賎������ގ��ɗp����ꂽ��������̂܂c���Ă���A�Ƃ�������Ă��Ȃ���]���荞��ł����̂ł���B�@
�@ �{�Ԑ�}�q����ɂ��A賎��͕��N�����̃R���R�N�V�����i���������������j�������̂������ŁA���肩������������Ȃ��Ƃ����B賂̍��g�𔖂��O�����炢�ɍ킬���낵�A�㎿�̉����������ʂقǂ����Ă���Y���t��Ă��B�����āA����� �l�\�ܓx���炢�������̒��ɃW���b�Ƃ��A�܁A�Z���҂��Ă�����ނ̂��������B���N�̂��������ɖ{�Ԃ��g����������������Ƃ����邻���ŁA���̔��������͂Ȃ�Ƃ��`�e����Ƃ̂��Ƃ������B
�@ �O�q�������їE�̐��M���Ɍ�����賎��ƁA�ނ�������ɂ��������ȏ��������̎�l���`�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ƃ����{�Ԃ���̕��N��������賎��Ƃ͏��X�������قȂ��Ă͂������A�����܂Ŕ�����Ƃ͎�������݂̂������B�O������炪��������賎�����ɒ����Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B�����̎��s����͂������悤�����A���ʂ͑听���ł������B�O�҂�賎��ɂ͓Ɠ��̖��Ɛ[�݂�����A��҂�賎��ɂ͔�ނȂ���i���ƌ������������čb�������������A���̍��M�ȍ���Ɣ������͑o���ɋ��ʂ̂��̂ł��邱�Ƃ����������B�������A����賎��ɂ́A�������Ă���������ɂȂ�Ȃ��Ƃ������܂��܂ł��Ă����B
�@ ���������S�������̎��A�u賎��v�̔������ɎO�������͊m�M�����������A���掩�]�ɂȂ��Ă������Ȃ��Ƃ����킯�ŁA�T�d�̂����ɂ��T�d�������邱�Ƃɂ����B�����āA�{�Ԑ�}�q����̏��Ȃ���ʌv�炢�̂��ƁA�鍑�z�e���ŊJ���ꂽ�������̉�ɓo�ꂵ��賎��́A���ɂ��邳�����̓��̃v��������������ȕ]������Ƃ���ƂȂ����̂������B
�@ 賎��̍Č��ɐ��������O�������́A�����łƂǂ܂炸�A����ɂ����ЂƍH�v���݂Ă݂邱�Ƃɂ����B賎�������ɂ́A�ނ��A�Ⓚ����賓�����H���܂邲�ƍw�����A����������Œ������ėp����̂��őP�����A���R����Ȃ�Ɏ�Ԃ���p���������Ă��܂��B�����ŁA����y��賎����y����ł��炦��悤�ɁA���炩����賃G�L�X�����𒊏o���Ă����A��������������Ƃقǂ悭��������悤�ɂ�����ǂ����낤�ƍl�����B���ꂪ���������߂�ΐV���i�Ƃ��Ĕ���o�����Ƃ��ł��邵�A�L������賃v���W�F�N�g�����W�J���\�ɂȂ�Ƃ����킯�ł������������B
�@ �O�������͂��낢��ƌ������d�˂������ɓƎ��̒��o�@���l�Ă��A賓��̎|�������𒊏o�����㎿��賃G�L�X�����邱�Ƃɐ��������B�����āA���{�H�i���̓Z���^�[�Ɉ˗����A����賃G�L�X�̊ܗL�A�~�m�_�̕��͂����Ă��炤�ƁA�Ȃ�Ə\����ނ��̃A�~�m�_����ʂɊ܂܂�Ă��邱�Ƃ������ɂȂ����̂ł���B賎������Q�ɔ������A�������g�̂ɂ悢�閧���A�����\����̃A�~�m�_�ɂ��������Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B
�@ ���ۂɒ��o����賃G�L�X�𐴎��ƒ������Ď������Ă݂�ƁA���ڂ�賓���p�����ꍇ�Ɋr�ׂĂ�����Ȃɂ͑��F�Ȃ����ƍ���Ƃ��y���߂邱�Ƃ����������B�����ŋ߂ɂȂ��Ė���賃G�L�X�́u賎��̑f�v�Ƃ��āA���Q���L�����Ƃ��̋��͊�Ƃ�賎�{�܂Ƃɂ���ď��i������A���X�ɂ����s�̂���͂��߂Ă���悤���B
�@ �L�����Y�̍���賂̍��g�Ƌ������璊�o�����㎿��賃G�L�X����Ȃ�u賎��̑f�v�ɂ�����p�Ɨ��p�̓��ނ�����B����p�͐�����賎��̑f���X�F�P�̊����ŁA�܂����p�͐�����賎��̑f���R�F�P�̊����Œ������Ĉ��ނ̂����A���ꂼ��ɖ��킢�[�����̂�����Ƃ����B�������A�����Ŗ��키�̂�賎�{���̂��肩��������A�������ɂ�����邩���Ȃǂ�����p���������ق����悢���낤�B���łɏq�ׂĂ����ƁA賎�p�̐����ɂ͏��Ď��̒�����p����̂��őP�ł���炵���B����������Ȃǂ�p�����肷��ƁA���Ɋ܂܂�鍁�����̑����t���ʂ������炵�A����������賃G�L�X�̍��M�ȍ���□������������Ă��܂����Ƃɂ��Ȃ肩�˂Ȃ����炾�������B
�@ ���e���l�̂��a���ȗ��A�����ɂ͌c�ꃀ�[�h���L�����Ă��邪�A���̍ہA���ɖڂ̂Ȃ����X�́A����ȏj�ꃀ�[�h�ɕ֏悵�ē`����賎��ŏj�t���ȂǂƂ����͔̂@���Ȃ��̂��낤�B�{����賓���p���Ė{�i�I��賎��ŏj�t���Ƃ������́A�L�������Y�W���̔��{�݁u�X�̎O�p�ڂ����ihttp://sankaku-boushi.com�j�v�ɁA�܂��A��y��賎��̑f�ň�t�Ƃ������́A�u賎�{�܁ihttp://www.kijizake.com/�j�v�ɃA�N�Z�X���A賎��֘A������肳�ꂽ��悢���낤�B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N12��12��
���w�I�F���_�u���H
�@ �挎���̂��ƁA��錧�F�����ɂ����錧���猤�C�Z���^�[�ɏo�������B���Z���^�[�̐E���̕��X�A���Ȃ킿�A��錧���̏��A���A���̋������C�w���S���̃x�e�����w�������\�l�قǂ�Ώۂɂ����u����ɁA�u�t�Ƃ��Ĉ�������o����Ă��܂����̂��B�Ђ炽�������ΐ搶�̐搶�߂Ă�������X����̍u��������A�ߔN�A�m�������u�s���v�̐�߂�E�G�C�g�̂ق����傫���Ȃ������̐g�Ƃ��Ă͂��������C�����ꂷ��v���������B
�@ �łɂ���ɂ��Ȃ�Ȃ��y�����̍u���Ȃ�t���[�����X�̏�Ƃ��Ă���Ȃ�ɏꐔ��ł��Ă͂���B�������A����̐��Ƃ�ɂ����^�ʖڂȍu���ƂȂ�ƁA�����Ԃ�v���Ԃ�̂��Ƃł���B�t���[�����X�̐��E�ɐg�𓊂��Ă���Ƃ������́A�����łȂ��Ă��R����������̐��I�m����\�͓͂����ɑމ����A���̏ꂵ�̂��̖��R�Ƃ����G�w�I�f�{�������C�̂悤�ɐς����Ă��܂����B�������Ŋ̐S�̓��]�̂ق��̓X�|���W�A���܂��̕\�����������a��ԉ����A�w�p�I���邢�͋���I�ɗL�Ӌ`�ȍu���Ȃǂ܂Ƃ��ɂł���ł͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ă���B
�@ ����ȂƂ���ɁA�F���ɂ��ĉ����b���Ăق����ȂǂƂ����A�Ƃ�ł��Ȃ��˗�����������ł����̂�����A���������Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B����������錧�ɂ͓��{�̊w�p�����̒������Ȃ��}�g�����w���s�s�����邩��A�F���֘A�̗D�ꂽ��匤���҂Ȃǂ�����ł�����͂����B�F���J�����ƒc�����̒}�g�F���Z���^�[�����đ��݂��Ă���B����Ȉ�錧�̋��猤�C�Z���^�[�ɏo�����āA�������A���w�A�Ȋw�N�w�A���w�A����͋I�s�̌�����݂̃e�[�}�Ȃ�܂������A�{�����O�̉F���̘b������Ƃ����̂�����A�����̊ԈႢ���낤�Ǝv�킴������Ȃ������B
�@ ���Ƃ̔��[�́A���ٍ̐e�T���������ǂ�ł��������Ă���Ƃ������w�S���̋��猤�C�Z���^�[�E���A�����a�T���A�ْ��u�F���̕s�v�c���킩��{�v�i�O�}���[�j����ɂ��ꂽ���Ƃɂ������炵���B���̌��ʁA���Z���^�[�̎R���m�s�����Ƒ��k�̂����A�����Ăڂ��Ƃ������ƂɂȂ����悤�Ȃ̂��B�����Ȃ��A�o�ŎЂ̒��q�悢�U���ɏ���Ă���Ȗ{�Ȃ�����Ȃ������\�\�ȂǂƉ����ł݂Ă��A���͂��̍Ղ肾�����B
�@ ��錧���̑�w�⌤�����ɂ͂��̓��̐��Ƃ��吨���邩��A���̂Ȃ��̂ǂȂ����Ɉ˗�������ƈ�U�͎��ނ����̂����A�ǂ����Ă��Ƃ̘b�ł���B����Ȃ�A���ł͂Ȃ��A���Ǝ�q�����тɒ}�g�F���Z���^�[�����ŁA�O�q�̕��ɖ{�̋����ҁA�e�R�I�F����ł͂ǂ����낤�Ɠ`����ƁA���ۂɂ��̖{�����M�����̂͂��Ȃ��̂悤�����琥�肢�������ƁA����͂܂����������Ă����C�z���Ȃ��B
�@ ���Z�ȋe�R����ɑ����āA�O�������܂߉F���_�S�ʂɐG�ꂽ�����̈�͂���͂܂ł����M�����̂͊m���Ɏ������A���ۉF���X�e�[�V�������̋�̓I�ȉF���J���ɂ��ďq�ׂ��Z�͂Ǝ��͂��A�e�R����̐V�����e��u���^�������������ĕ��͉��������̂��B�����A���������ǂ����Ă���Ȃ��Ƃ܂ł킩�����̂��낤�B�ȑO�ɁA�u���{�b�`�R���ɂāv�Ƃ����ꕶ��{���Ɋ�e�����Ƃ��A������Ƃ�������炵�����Ƃ��q�ׂ͂������Ȃ��Ǝv���Ă���ƁA�Ȃ�ƁA�������d�b�̌������ŁA�u���̎��̕��͂ɖ������āA���͍��{�b�`�R�܂ōs���Ă݂���ł���v�Ƃ��������ł͂Ȃ����B�ƂĂ��l�l�Ɋ������Ă���������悤�ȕ��͂ł͂Ȃ������̂����A�����܂Ō�����Ƃ��������o���킯�ɂ������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B
�@ �����͎��Ԃɂ͂����Ԃ�Ɨ]�T�������Ď�����o�������̂����A�r���\�z�O�̑�a�ɑ������A�u�����̃Z���^�[���ԏ�ɒ������͍̂u���J�n�\�莞���̂킸���\�ܕ��O�Ƃ����L�l�������B�������ɒʂ���A�Ƃ肠�����R���m�s�����ƊȒP�Ȉ��A�����킵�����A���ɉ����ŏ_��Ȃ��l���̕��������B��錧���猤�C�Z���^�[�����Ƃ������������炵�āA�����ނ����u�����Y���݂����ȕ��ł����Ă����������Ȃ��Ƃ��z�����Ă����̂����A����͎��̎��z����J�ɉ߂��Ȃ������B�l���Ă݂�A���̂悤�ȕs�ǒ��N�\�����i���̂ԂƁA������͕s�ǁu�V�N�v�\�����ɂȂ��Ă��܂����Ƃ��낤�j���Z���^�[�E�����C�u�t�ɏ������Ƃ����̂�����A�����^�j��œx�ʂ̑傫�ȕ��ɂ͈Ⴂ�Ȃ��B�u�����Ȃ��A�Ȃ�ł����R�ɂ���ׂ��Ă�����č\���܂���v�Ƃ��������̈ꌾ�ŁA���͂�������C���y�ɂȂ����B
�@ �Z���^�[������\�����傤�ǂŎ��͍u�����̒d��ɗ����ƂɂȂ����B���悻��N�Ԃ�̃X�[�c�Ƀl�N�^�C�p�Ƃ����āA�X�[�c��l�N�^�C�̂ق����ʐH����ăI���I�����Ă��銴���������B�����̍u���ɐ旧���āA�u���w�_�I�F���_�u���v�Ƃ����u���e�[�}�ƍu���T�v�ɂ���A4�łŔ��y�[�W�قǂ̐}�œ��背�W�����g�����炩���ߑ��t���Ă������̂ŁA�Ƃ肠�����͂�����x�[�X�ɂ��Ęb��i�߂邱�ƂɂȂ����B
�@ �u���̖`���ɂ����āA�����g�͉F���_�̐��Ƃł͂Ȃ��̂ŁA�����Ȃ�p�E���I����ŁA������ɂ߂ē`���\�̗͂���p�E���I����Řb�������Ă��炤���ƂɂȂ�Ƃ�����|�̂��Ƃ��q�ׂ��B������ςȂ��瓦��������������Ȃƌ��������܂ł����A������o�����̂ɂ͎��͂���Ȃ�̗��R���������B�@���̐��E����łȂ��A�F���_���͂��߂Ƃ���e���[�Ȋw�̐��E�ɂ��A�L���X�g�i���c�j�I������S���l�X�ƃp�E���i�`���t�j�I������S���l�X�Ƃ��K�v���Ə�X���͊����Ă����B�m�l�̋��s��w����w���q�����������Ȃǂ̂悤�ɁA�����ƈȑO����A���ׂĂ̊w��ɂ̓L���X�g���ƃp�E�������K�v���ƒ������Ă����l�����邭�炢�ł���B
�@ �S�g�S����X���Đ[���ȋ��`�ݏo�����c�Ƃ��̋��`���킩��₷���l�X�ɐ����`���t���@���ɂƂ��ĕK�v�Ȃ悤�ɁA�Ȋw�E�ɂ����Ă��A�Ƒn�I�Ȑ�[�����ɑS�͂��X���鋳�c�I�����҂ƁA��[�����̐��ʂ��킩��₷����ʂ̐l�X�ɓ`����D�ꂽ�`���t�I�Ȋw����ҁi�T�C�G���X���C�^�[���j�̗������K�v�Ȃ��Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B
�@ ���c�ɂ�����l�����`���̎d�����I�m�ɂ��Ȃ���Η��z�I�ł͂���̂����A�����ɂ͂���͂قƂ�Ǖs�\�ɋ߂��B���ԓI��������邤���ɁA����̌����f�[�^����ɐ��I����i������e��L�����̉Ȋw�L�q����j��p���ė��_���\�z����\�͂ƁA�I�݂Ȕ�g��p�����肵�Ă��̘_���̊T�v����ʌ���ł킩��₷���`����\�͂Ƃ͂��Ƃ��Ƃׂ̂��̂����炾�B�A�C���V���^����z�[�L���O�̏��������ΐ����_��F���_�̉�����̈Ӗ�����Ƃ��낪���ǂ̂Ƃ����ʐl�ɂ͂悭�킩��Ȃ��̂́A���_���̂��̂̓�����ɂ��킦�āA�����ЂƂ��̂悤�Ȏ�����邩��ɂق��Ȃ�Ȃ��B
�@ �����A�Ȋw�E�ɂ��p�E���I�������K�v�ł���Ƃ͂����Ă��A����܂������e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ��̂ł���B���̖����߂�ɂ́A������x�܂Ő�[�Ȋw���_�̐��I�L�q�𗝉�������O���ꕶ�����܂ފ֘A������ǂ݂��Ȃ��\�͂̂ق��A�L�ĂȉȊw�N�w�I�f�{�Ɠ���I����ɂ���背�x���ȏ�̖������I�m�ȕ��͕\���\�͂����Ȃ��Ă��邱�Ƃ��O��ƂȂ�B
�@ �����҂��ۉ�̓��ɂ������Ă���悢����͏I���A��w��e�팤���@�ւƁA�Y�ƊE����ɂ͈�ʑ�O�Ƃ̋��͊W���s���ƂȂ������̎���A�Ȋw�̐��E�ɂ�����p�E���I�l�ނ̊m�ۂ͋}���Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv����B���Ăł͐̂���D�ꂽ�T�C�G���X�E���C�^�[�͂���Ȃ�̎Љ�I�]���Ƒҋ����Ă������A�䂪���ɂ����Ă͂��̓��̒��ڂ̐��Ƃł͂Ȃ��Ƃ������ƂŁA�T�C�G���X�E���C�^�[�͓Ɨ������E�ƂƂ��č����]������邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ������B�B���O������Ƃ���A���ԗ������炢�̂��̂ł͂Ȃ��낤���B�������A���Ԏ��̏ꍇ�̓T�C�G���X�E���C�^�[�Ƃ��Ă̊����͓����̎d���̈ꕔ�ɉ߂��Ȃ����A������ł̗D�ꂽ�ƐтƂ��̒m���x�Ƃ̊W�������ĉȊw�W�������ł̎d���������]������Ă���Ƃ����o�܂�����B
�@ ���l�Ƃ��ẮA���ꂩ���A�ꕔ�̑�w�Ȃǂɂ́A�Ȋw�̐��E�̃p�E���A���Ȃ킿�L�\�ȃT�C�G���X�E���C�^�[��Ȋw����҂�{������w�ȂȂǂ�ݗ����ׂ��ł͂Ȃ����Ƃ����l���Ă���B�����ŗ{�����ꂽ�l�ނ́A���Ƃ��T�C�G���X�E���C�^�[�ȂǂɂȂ�Ȃ��Ă��A��w���Ƃ̊e�팤���@�ւ̍L��S���҂�ΊO�I�ȏO�S���҂Ƃ��ďd�v�Ȗ������ʂ������Ƃ��ł��邾�낤�B
�@ �ȑO���瓌��⍑�ۃL���X�g����Ƃ����������ꕔ�̑�w�ɂ͋��{�w���i��ʋ��{�ߒ��̋��Ȃ��w�ԂƂ����Ӗ��ł̋��{�w���ł͂Ȃ��A�w�ۓI�ȑ����\�͂����l�ނ��琬������w���̂��Ƃł���j���݂����Ă���B���{�w���o�g�҂ɂ͉Ȋw�E�̓`���t�߂�Ɋi�D�̐l�ނ����Ȃ��͂Ȃ��̂��낤���A�䂪���ł͂���Ȋw���̑��݈Ӌ`���炱��܂łقƂ�Ǘ�������Ă��Ȃ������悤�ł���B
�@ �t���[�����X�ɓ]���Ă��̂����A�l�X�Ȉ�ʌ����̉Ȋw����Ȋw�L���̌��e���M�ɂ��g����Ă������A�Ȋw�Ɋւ���u���Ȃǂ����낢��Ƃ��Ȃ��Ă������A����Ȑ܂ɂ́A���\�ł����Ă��A���߂Ďl���ܗ��̓`���t���ǂ����炢�̎d���͂��������̂��ƐS�����Ă����B�t�ɂ����A�Ȋw�W�̐��E�ɂ����Ă��܂̎��ɂł���̂͂��̒��x�̂��Ƃ����Ȃ��Ƃ����킯�ł��������̂��B
�@
�@ �p�E���k�c�������Ȃ��Ă��܂������A����ȃX�^���X���Ƃ闝�R������������ƁA���͑����āu�Ȃ��F���_�͓���Ȃ̂��H�v�Ƃ����b�������B�F���_�Ƃ����z��̐��E�̔w��ɂ́A���̑O��ƂȂ�Ȋw�L�q����i�e�퐔����Ȋw�L���ށj��F���_�̍���I��`�Ɋւ��A��̐��E���B����Ă���B���̉A��̐��E�̈�[�ł��_�Ԍ��邱�Ƃ��ł���Ȃ�A�����Ȃ��Ƃ��F���_������ȗ��R�����͔[�����Ă��炦��B�F���_�̋L�q�ɂ͉���ʗd�Ȑ�����p����������Ȃ����ƁA���팾��ł�����L�q�����������肷��ɂ͂��̂�������E�����Ȃ����ƂȂǂ������炩�͂킩���Ă��炦�邩������Ȃ��B�܂��A����Ȃ悤�Ȃ��Ƃ��l�������炾�����B
�u�F���̕s�v�c���킩��{�v�ȂǂƂ����{�̕M�����������l���A�u���̖`���Łu�Ȃ��F���_�͓���Ȃ̂��H�v�ȂǂƂ����b������Ȃ�Ė{���^�|���r�����������肾���A�����ɂ��̂悤�ȃ^�C�g��������ꂽ�̂́A�u�킩��{�v�V���[�Y�����s���Ă���o�ŎЃT�C�h�̈ӌ��ɂ����̂ł���B�{���Ȃ�u�F���̕s�v�c���l����{�v�Ƃ��u�F���̕s�v�c�ɔ���{�v���炢�ɂ��Ă����ׂ��Ƃ���ł͂���̂��낤�B
�@ �ڍׂ͏ȗ����邪�A�A�C���V���^�C���Ɉ�ʑ��ΐ����_�̓W�J���\�Ȃ炵�߂��[�N���b�h�w�i���[�}���w�j�̒�`�َ̈�����A�l�Ԃ̔F���ړx�Ǝ��R�E�̖@���Ƃ̑����ɂ܂������s�\�Ȗ��̑��݁A����ɂ͂��̗��R�Ȃǂɂ��Ęb�������B�����āA�����Ȃ鎩�R�Ȋw�̖@�����F���ɂ�����q�ϓI����ΓI���݂ł͂��肦�Ȃ��Ƃ������ƁA�F���_�Ƃ́A���ǁA���w�Ɠ��l�ɐl�Ԃ̔F�����Öق̑O��Ƃ������̉F���`�ʁi�Ȋw����ɂ���ĉF�����r�O�q���j�ł��邱�ƂȂǂ��q�ׂ��B
�@ �܂��A��F���ɂ�����l�ނ̈ʒu�t���Ƃ��āA�u�l�ԂƂ͘c�A�����ē܂�������������Ȃ��B�������A����͂܂��A�F����������f�����邽�߂̊|���ւ��̂Ȃ����̂ЂƂɂق��Ȃ�Ȃ��B�F���̃h���}���ǂ�Ȃɑs�킩�[��������߂Ă��悤�Ƃ��A���̃h���}��F��������Ɋ������鑶�݂��Ȃ��Ȃ�A�����ɂ͎����̈łƉi���̖��Ƃ��L�����Ă������ł���v�Ƃ����A�����Ԃ������`���������l�ԍm��_���q�ׂ���������B
�@ �����āA���z�a1mm�̉~�u�B�v���Ɖ��肷��ƁA���̒��S���琅���܂ł�4,15cm�A�����܂ł�7.77cm�A�n���܂ł�10.7cm�A�ΐ��܂ł�16.4cm�A�ؐ��܂ł�55.9cm�A�y���܂ł�102.6cm�A�V�����܂ł�206.5cm�A�C�����܂ł�323.6cm�A�ʼn��̖������܂ł�452cm�Ƃ������ƂɂȂ�A���̏ꍇ�A���z�n�̂��悻�̒��a��900cm�ɂȂ�Ƃ��������������B�����Ă��̂��ƁA���̌v�Z�ł����Ɩ�10�����N�Ƃ������X�̋�͌n�̒��a�͂ǂ̂��炢�ɂȂ邾�낤���Ƃ�����������Ă݂��B
�@ ���Ȃ݂ɏq�ׂĂ����ƁA���̓�����68��km�ł���B���z�̒��a�͒n���̒��a��108�{������A�������n�����u�B�v�̑傫���ł���Ƃ���ƁA��͌n�̒��a��7344��km�Ƃ������ƂɂȂ�B��͌n�̒��S���̌�����2��5����N�قǂ��Ƃ����邩��A������̂ق���1836��km�ɑ������Ă���B�r�����Ȃ���͌n�̑傫����������x�͑z�����Ă��������邱�Ƃ���B��͌n��ł��̗L�l������A��͂����牭�����݂���Ƃ������̉F���̑傫���͑z���ɗ]��Ƃ����ق��Ȃ��B
�@ ���̂��Ƙb�́A����S�����̘c�݂̃C���[�W�̂������A�J�[���E�V���o���c�V���g���a�ƃu���b�N�z�[���̈Ӗ��A�t���[�h�}���̉F�����f���A�n�b�u���̖@���ƉF���̖c���A�_�[�N�}�^�[��O���C�g�A�g���N�^���A2.7��K�F���w�i���˂ƃr�b�O�o���Ƃ̊W�ȂǂƂ�������ɓW�J�����B����ɁA�F���͖�����a�������Ƃ���A���L�T���_�[�E�r�����L���̗ʎq�_������X�e�B�[�u���E�z�[�L���O�̖����E�F���_�Ȃǂ̌����F���̒a���Ɋւ�闝�_�A�^��G�l���M�[�̑��]�ڂƂ����T�O�ʼnF���c���̃��J�j�Y��������������F��O�[�X��̃C���t���[�V�������_�ɂ��Ĉ�ʂ�G�ꂽ�B
�@ �����āA�Ō���R�[�l����̃t�����N�E�h���C�N��ɂ���Ă͂��߂�ꂽSETI�iThe Search for Extraterrestrial Intelligence�A�n���O�m�I�����̒T���v��j�̘b�Ō��B���݂ł͑����̓V���w�҂�F�������w�҂��A�l�ވȊO�̒m�I�����̂̑��݂�M���Ă���Ƃ����Ă���B���̐���l���ɂ킩�ɐM����킯�ɂ͂����Ȃ����A�h���C�N�Ȃǂ͂��̋�͌n�����ł���O�S�̒m�I���������݂���ƍl���Ă��邭�炢�ł���B
�@ �u���ɐ旧���Ă̎��̍ő�̐S�z���́A����Șb����u�҂̕��X�̊i�D�̐����܂ɂȂ��Ă��܂��̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃł������B�����A�K���Ȃ��ƂɁA�������y����ł�������X�͂����킸���̂悤�������B������������A�����������ق��J���Ă������������������̂�������Ȃ����A�����͐}�X�����J�������Ċy�ώ�`�I���f�ɓO���邱�Ƃɂ����B
�@ �܂������܂ł͂悩�����̂����A�Ō�ɒd��ɗ������R���m�s�����̎��̘N�ǂɕs�ӂ�˂���A���͊��Ԃ�߂Ђ�����T���������ł������B�u���v�Ƃ������̈�т̎��͂��łɐ�łƂȂ��Ă���ْ��̍ŏI�͂ɂ����߂�ꂽ����̎�����������ł���B�ǂ����}���ق��ǂ����ł��炩���ߒ��ׂ����ꂽ���̂炵���B
�@ �Ȃ�Ƃ�������ʂ����I�������֖߂����̂ł��邪�A����A��������ƎR�������̂���l���炠�炽�߂Ă����Ղ����B�����Ă��ڂ̐ӔC�҂ł��鏼������Ɍ���f�������Ă��܂����̂ł͂Ɗ뜜���Ă����̂����A���ʓI�ɂ͂����ւ�D�]�������Ƃ��Łi�ق�Ƃ��͑�s�]�������̂�������Ȃ�����ǁj�A�Ƃ肠�����͋��ʼn��낵�����悾�����B
�@ ���̍ہA�p���������łɁA���́u���v�Ƃ����������Љ�Ă������B�����\�N�ȏ�O�ɒԂ������̎���i�̂ЂƂł���B���܂����Ƃ͂ƂĂ������Ȃ�������̂����A���Ȃ�ɐ[���z�����߁A��d�O�d�̊܂݂��߂ĉr���̂ɂ͊ԈႢ�Ȃ��B������ǂ������A�ǂ��ǂ݉����Ă������邩�͊F����ɂ��C�����邵���Ȃ��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
���������̏�����������ƂȂ������ŕ������悤�ȋC�����܂�
�����c�c�܂��c���������ł��@���������̂̂��Ƃł�
���ɑ����Ƃ��Ȃ���@��g�ɏ����ȌC��G�炵�Ȃ���c�c
�������Ă��܂����@�Ȃ����������@���̏����c�c
���̂Ƃ����Ȃ��͂ЂƂ荿���Ă��܂���
�����ߊ�ꂻ���Ł@����ł��Ăǂ����Ă��ߊ��Ȃ��Ƃ����
�������č��̏�Ŗ������悤�ȋC�����܂�
�ӂƋC�����Ƃ����[���ł���
�����C�ʂ��Ԏ��ɋP���Ă��܂���
�͂��Ƃ��Ă���������Ɓ@���Ɛ����ɓ�̑��Ղ��Â�
�C�̒��ւƏ����Ă��܂���
���̓����Ō�ł����@���Ȃ��̎p��ڂɂ����̂�
���ꂩ�炸���Ԃ�Ƃ������܂����@�����L���̂��̏����c�c
���Ɣg�Ɨ[�z�������Ă����悤�ȋC����������ł�
�킽���Ƃ����@���̏����ȑ��݂̕��������c�c
�����Ȃ������̂ł��ˁ@���Ȃ��ɂ�
���Ȃ��͂킴�Ɓ@���̂Ȃ���������n�����̂ł���
���̕l�ӂŁ@�c�������킽����
�����Ȃ����Ƃ��@�����K�v���Ȃ����Ƃ��m��Ȃ���
�������ł킽���͐����Ă��܂���
�����ȓ�������ǂ����ŋC�ɂ����Ȃ���
�킽�����܂��n���ׂ��Ȃ̂ł��傤��
�킽�����܂��c���ׂ��Ȃ̂ł��傤��
�����Ȃ��Ƃ킩���Ă��鑶�݂̕��������c�c
�����Ƃ������̐Ԃ��r�[�Y���ɂȂ�
�ڂɌ����Ȃ��ׂ��������Ƃ��āc�c
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N12��19��
�~�̓���
�@ �[�z���������G�߂ɂȂ��Ă����B���̏Z�ޓ����x�O�̒�����́A���̕��p�ɒO��R��ƂЂƂ��헬��ȕx�m�̎p�Ƃ��܂�d�Ȃ��Ė]�܂��B�ӏH����^�~�ɂ����Ă̎��߂́A���傤�Ǖx�m�R�̂�����ɗ[�z������ł����̂ŁA�Ƃ����܁A���^���ԂɔR���オ��R��������ۂނ悤�ȃV���G�b�g�ƂȂ��ĕ����яオ�邱�Ƃ�����B���ւ���������p���B�������Ƃ��A�����Ƃ������t�ʂ�ɑ����ȋP���̉��������c��A�₪�ē��F����[�����F�ɋ�̐F���ς�鍠�ɂ͏��̖����Ȃǂ�����������n�߂��������B�����̋���܂��܂��̂Ă����̂ł͂Ȃ��B
�@ ����Ȕ������[������Ȃ���A���̓~�͐l�S�̉���܂ł��₽�����Ă����炢�̐��܂������g������ė��邩������Ȃ��ȂƎv������������B�ł��A�l�ԂƂ������̂́A���̂����犴���̌������܂��ꂴ������Ȃ�����Ȏ������A���̂�̐�������𑣂��d�v�ȏo�����Ȃǂɑ����������Ȃ��̂ł͂Ȃ��낤���B�����̂����₩�Ȑl����U��Ԃ��Ă݂Ă��A�Ȃɂ�����O�i�̎�����������A�z��ʏo�����Ɍb�܂ꂽ�肷��̂́A�~�̋G�߂��قƂ�ǂ������B�ނ��A�����Ō����~�̋G�߂Ƃ͏ے��I�ȈӖ����������܂߂Ă̂��Ƃł����āA�����ʂ�̓~���݂̂������Ă����ł͂Ȃ��̂����c�c�B
�@ �~�̗��ɐS�Ђ���邱�Ƃ̂����Ȃ��Ȃ����݂����Ȑl�Ԃ̊Ⴉ�炷��ƁA���̊����G�߂͂܂��A�Ⴂ�������S�g�Ƃ��ɂЂƂ���������P���Č����鎞�ł�����B�t����N�n�̌����ɔw�������Ƃ�[���D����X���Ȃ���A���Ă��悤�Ȗk���̒����A�R�[�g�݂̋����āA����ł��Ȃ��B�R�Ƃ��ĕ���Ɍ������ĕ����Ă�������������̎p�����������肷��ƁA���킟�A�f�G���Ȃ��āA�������Ƃ�Ă��܂����Ƃ�����B
�@ �����\�N�ȏ�O�̘b�ɂȂ邪�A���̍��������قōÂ���Ă����S�ϊω��W�����ɍs�������Ƃ�����B�^�~�̗[���߂������Ƃ����āA�z�͂��������Ȃ�A�g�k������قǂ̗₽�����������قɒʂ���L���e�͂Ȃ����������Ă����B���̕��̒��𐴑^�Ȋ����̍��̃R�[�g���܂Ƃ����������A���̘B�����Â��邻�̂��Ȃ₩�Ȑg�̂���͂��Ƃ���悤�ȁu��C�v���Ȃ���A��͂荑�������قւƌ������Ă����Ƃ��낾�����B
�@ �َ��Ԓ��O�ł��������ƂȂǂ��K�����āA�S�ϊω��W�̉��͂قǂ悭�����Ă����B���������s�ސT�ł͂��������A�ϔY�������̐g�́A���������ꂽ�Ƃ��납���̕S�ϊω��������[���q�ς����Ă��炤���ƂɂȂ����B���̂����̂ЂƂ����g�̐l�Ԃ̎p�������S�ϊω��ł��������Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B
�@ ���������ق����Ƃɂ��钼�O�A�n���̔��X�Œ��b�Y��╽������G���̊G�t�����������Ă����̂����A�ӂƋC�����ƁA���g�̂ق��̕S�ϊω��l�����܂��܂��ɂ���Ă��āA���Ɠ����G�t������ɂ��Č��Ƃ�Ă�����ł͂Ȃ����B��u������ɂ������悤�Ȏv�����������A�����͂܂��C��������x���z���Ă͂����g�䂦�A�����ƐS�𗎂����A�e�̊G�̗t�����w���Ȃ���u���̊G�Ȃ��Ȃ������Ă܂���ˁv���Ęb�������Ă݂��B����Ƃ����ɁA�u��e����݂����ł��ˁA������āH�v�Ƃ����������̐����A�Â��Ȕ��݂ƂƂ��ɕԂ��Ă����B
�@ �s�v�c�ɋC�����������Ƃ������āA��삩��a�J�܂ŁA���̊Ԃ̎��Ԃł͂��������A���낢��Ƙb�����Ȃ���ꏏ�ɋA�����B������ςȂ���Ȃ�����Șb��ɂȂ��Ă��܂����̂��͖Y�ꂽ���A���[�O�i�[�̉��y�̐��E������B���̍�i���r�B�E�f�B�b�N�i���~�j�̎v�z�w�i�Ȃǂɂ��Ďn�܂����b�́A���������݂��̗��̃G�s�\�[�h�Ȃǂɂ܂ŋy��ł������B
�u���͂悭���܂��B�킽�����������~�ɁA��ƕX�̋P���r���Ƃ����k�ӂ̒n��l�m�ꂸ�����̂��D���Ȃ�ł��B��������x�����Ȃ����̐l���ł�����E�E�E�v
�@ �����b���ޏ��̌��t�ɂ͉��̋C�������������Ȃ������B�����Ȃ��ƂɁA�a�J�ł̕ʂꂬ��ɂȂ��Ă͂��߂ċC�������̂����A���������ƁA���̏����͒m�I�ȃC���[�W�Œm����^�������̂��B
�@ �����I���{���Ԃɏ���Ĉꏏ�ɉ������E�𗷂��܂��傤�ƁA���Ώ�k������̖����ĕʂꂽ�̂����A�C�O����l�����邱�Ƃ������Ƃ����ޏ��̂��ƁA�����������炢�܂���͉����ٍ��̋�̉��ɂ���̂�������Ȃ��B�����āA�����������Ƃ�����A�u�����𗷂���悤�ɂȂ��Ă͂��߂āA���{�̓`�������̑f���炵���⎩�R�̔����������݂��݂Ɗ�����悤�ɂȂ�܂����v�Ƃ������̎��̌��t�ʂ�ɁA�ޏ��́A���̓��{�̕����ɁA����ɂ͔������~�̈��F�̗[��ɉ����v����y���Ă���ɈႢ�Ȃ��B�@
�@ �l���͈�����c�c�l�ԂƐl�Ԃ̏o�����ȂǂƂ������̂́A���Ƃ����ꂪ�ق�̈�u�̏o�����ł����Ă��A���̒��ɖL���Ȏ��ԂƐ^���Ɍ����������S�Ƃ��Ïk����Ă���A����͂���őf���炵�����̂Ȃ̂��Ƃ����C�����ĂȂ�Ȃ��B
�@ ���̓��̋A�蓹�A���̖��ɕ����ԎO���������Ȃ�������Ă������́A�ȑO����ʂ�̐܂�ɉr�܂܋L���̒�ɖ��点�Ă�����̂��Ƃ��A�ˑR�ɑz���o�����B�@
�@�@�@�@�N�s����O�������銦�c���@
�@ ���̋���r�Ƃ��Ƃ��Ȃ��悤�ɁA���̖�����C���Ђǂ��g�ɂ��݂����炩������Ȃ��B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2001�N12��26��
�u�����賎��������
�@ 賎��Č��̔��Ď҂ł���O������Ǝ��̊ԂŁA�u���f�B�J���Y���L�v�����M���̉i�䖾����⌊���L���X�^�[��賎����������Ă��������A�Ƃ����b�������オ�����̂����Ƃ̔��[�������B������˗����ꂽ�����i�䎖�����ɓd�b���A�}�l�[�W�����g�S���̉Y�䂳��ɂ��̎|��������ƁA���������͑劽�}�ł��Ƃ̕Ԏ��ł������B
�@�����ŎO������ɓd�b���āA�ǂ����Ȃ瓌���O���̎O���@�œ��₩��賎���������Â�����ǂ����낤�Ǝ����������B����ƁA���l�����賗����Ȃǂ��o���邩�炻�̂ق����D�s�����Ƃ������ƂɂȂ�A�܂��͉i�䂳��̕Ԏ��҂��Ƃ������ƂɂȂ����B
�@ �قǂȂ��͂����i�䂳��̃��[���ɂ͏\�\�Z���̓��j������͂ǂ����낤�Ƃ������B���̓��͂��܂��܁A�{���s���U�w�K�Z���^�[�Łu�W���[�i���Y���̐��E�v�Ƃ����A���u���̍ŏI�Â���邱�ƂɂȂ��Ă���A�u�V���L�҂Ƃ����E�ƂƂ��̕]���v�Ƃ����e�[�}�ōu�������邱�ƂɂȂ��Ă����̂͂ق��Ȃ�ʌ����j�m�������B�܂��A�{���s����̈˗��Ŋ��R�[�f�B�l�[�g�Ɍg����������i��i�s���߂邱�ƂɂȂ��Ă����B
�@ ���ǁA�i�䂳�{�����U�w�K�Z���^�[�̍u���ɓ�������o������Ƃ������ƂɂȂ�A�u���I����A���̂܂��̎ԂŎO���@�ɐ���ꍞ�ގ蔤���������B�b�͂������A�����y�n���@���Łu�w�ْn���w�v���M�ҁA��X���M�v����ɂ��`���A�ꎞ�͋}篍L������Q���Ƃ������Ƃɂ��Ȃ肩�������A���ǁA�\�����܂ł͑�w�ł̎d��������̂Œf�O����������Ȃ��Ƃ̂��ƂŁA��X������̓o��͂܂��̋@��ɂƂ������ƂɂȂ����B����ł��A�i�䂳��̊Ď��������̉Y���A��������Ǝ��̋��ʂ̒m�l�̎O�X�A�Z�c�A��̎O���j�A����ɂ͊��ꖺ���������v��l���J�荞�����Ƃ����̂�����A���ƂȂ�O���Ƃ���ςȂ��Ƃł͂������B
�@ �A���R�[���̂܂������ʖڂȎ�����̂��������ނ̎��D���A������Ɉ��݉�����R�[�f�B�l�[�g����Ƃ����A���Ƃ������ȓW�J�Ƒ��������킯������A������Q���\��̐a�m�i�����������܂ЂƂs����@������Ȃ��ł������낤���Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B���Ƃ��ẮA���q���}�����O���Ɠ���̗m����̎����炵���u�J���ƁA�u賎��̌N�v�̎��͂̂قǂɂЂ�������҂��邵���Ȃ������������B
�@ �����̏\�Z���́A�����{���w�Ō�������Ɖi�䂳����E���A�ߌ�ꎞ�����ɕ{���s���U�w�K�Z���^�[�ɒ������B�u���͓��傤�ǂɎn�܂�A���̍u�t�Љ�ɑ����āA�Ɠ��̃��Y���ƃe���|�Ō������M�ق��ӂ邢�������B���������ƁA���̓��A��������͂��ɂȂ���@���������B
�@ �����V�����j�łɂ��̈�N�ԘA�ڂ���Ă����u������T�O�l�̋L�ҁv�Ƃ����T�K�L����]�����铊�����O���̒��������Ɍf�ڂ���Ă����B�K�c�^���Ƃ�����Ƃ̊�e�����ꕶ�ŁA�L�҂̑f�炪������ςɍD���̂��Ă��悾�����Ɛ�^�������e�̂��̂������B�������A�u�������̏\�Z���̓��j�łɌf�ڂ��ꂽ�D���m��L�҂́u�אl�v�Ƃ�����̓��{�T�K�L�����̍ŏI��ɂ������Ă����B�u������T�O�l�̋L�ҁv�̊��ҏW���ӔC�҂ł�������������̂������͂Ȃ��B���̓��e�L���̓R�s�[���Ď�u�҂ɂ��z�z����A���R���̓��̍u���̂Ȃ��ł��p����ꂽ�B
�@ �����̒��q����l���āA�f�b�h�{�[����r�[���{�[���Ƃ͂����Ȃ��Ă��A�J�[�u���t�H�[�N�{�[����̂̍u�����e�ɂȂ�̂ł͂Ǝv�������A���ۂɂ͗\�z�ɔ����X�g���[�g���S�̍u���ɂȂ����B���݂̐V���E�̌���Ə�����J�����A�����̍��̒����̎Ўj��������N�����A�i�n�ɑ��Y�̌��t�Ȃǂ�܂荞�݂Ȃ��烁�f�B�A�E�ɂ����钩���V���̗��j�I�Ӌ`��_���A����ɂ͍����̐V���L�҂̗ǐS�Ƌ�Y�������Ƃ����̂���܂��Șb�̗��ꂾ�����B�������u���̋����X�g���[�g��̂ɒ������Ă݂����u�K�c�^�����ʁv�͐�傾�����Ƃ����ق��Ȃ��B
�@ �����Ƃ��A�{��AIC�ɂ��Ă̘b�ɂȂ�ƁA�i��̎��ƗՎ����u�҂̉i�䂳��������J���ɂ��āA�����Ȃ���̗e�͂Ȃ��i�j�����c�b�R�~���n�܂����B�܂��A�C�S�̒m��Ă����X�����肾����悢����ǁA�����炱�ꂪ�{���̌��������Ƃ͂����Ă��A���Əꍇ��������Ƃ���ԈႦ����A�u�i���`���[�R�g���C�C�I���l���I�v�ȂǂƋC�F�ތ�m�����ꂩ�˂Ȃ����Ƃ��낤�B�c�b�R�~���͓��ӂ����{�P���͋��炵�����̋H�L�̍˔\�̎����傪�A�������{�P�̎����A�ׂ̌�����������A�������ꂽ��}��ꂽ�肵�Ă�����������A�l�m�ꂸ����̐S�����������s�G���̈�ʂ�����Ȃ�ɔ�߂����Ă����Ȃ�A���܂��뒩���̑�ŔL�҂ɂȂ��Ă�����������Ȃ��Ǝv���B��������{�l�ɂƂ��Ă��A�܂��A��X�ɂƂ��Ă��A���̂ق����悩�����̂��Ƃ������ƂɂȂ�ƁA�ނ��b�ׂ͂��ƌ��������Ȃɂ̂�����ǂ��c�c�B
�@ ��������̖��͓I�ȃL�����N�^�[�ɐG������Ă��A��u�҂̎��^�������������߁A�\�莞�����l�\�ܕ����I�[�o�[���Ă��̓��̍u���͏I�������B��������̖��͓I�ȃL�����N�^�[�ɎO���@�ł�賎�������ɎQ���\��̃����o�[�́A���̂��Ƃ����Ɏ��̃��S���Ԃɏ�荞�B�u�S�����߂����Ă���{���O���}�v�Ɛ捏�̍u���Ō���������Љ�ꂽ���S�������A�h���C�o�[�̎����܂ߔ��l�܂ł͏���B�i�䎖�����̉Y�䂳��͒��ڂɓd�ԂŎO���@�Ɍ������Ƃ������Ƃ������̂ŁA���ւ̈ړ��͎��̎Ԉ��ő��肽�B
�@ �O���܂ň�T�Ԃق�賂̗{�B�n�A���Q���L�����ɑ؍݂��Ă����O������́A���̓��A���H���̗Ⓚ賂Ɠ��ʂɒ��o����賃G�L�X���g���ċA���������肾�����B�O���@�ɓ���������X�͊��߂���܂܂Ƀe�[�u���ɒ������B�����Ĉ�ʂ�݂��̏Љ�I���ƁA���ꂼ��ɒk�����킵�Ȃ�������̑O����ɂƂ肩�������B
�@ �㎿�̏��Ď����Ȃ݂Ȃ݂Ƃ����傫�ȓy�r�����̂܂ܓ���ɓ���Ă������A�قǂ悢�Ƃ���œK�ʂ�賎��̑f�����Ďd�グ��ꂽ���́A�l�����̑傫�Ȃ������݂Ɏ��X�ƒ����ꂽ�B�����̂����Ă͂���̑����̉��Ȃ䂦�A�����ɑ傫�ȓy�r�������������Ă��܂��قǂŁA�����W�̎O������̎q���₻�̗F�l����Z���̗l�q�������B�͂��߂̂�����賎��̑f������܂��̎���賎��̑f�������������Ƃ̎��Ƃ����ݔ�ׂ��肵�āA���̌��������Ȃ��Ă������A�₪�Ė{�i�I��賎��̎�����Ɉڍs�����B
�@ �������̂��̂͂����Ԃ�Ɛ���オ�������A����賎��̂ق����Ȃ��Ȃ��D�]�̂悤�������̂ŁA���̏���R�[�f�B�l�[�g�������͈ꉞ���g�̋��ʼn��낵���悤�Ȏ��悾�����B�r������́A���J���H�J�����W����賎�{�܂�SSI���F�������t�ł�����I�؏��͂��͂�鏬�c������z�X�g�����R�ɓo��A���痠���ɂ܂����賎��̒������Ƃ��ތW�߂�Ƃ����W�J�ɂȂ����B���˂̐g�ŃA���R�[�����s�̎��ɂ͂��̎��ɋ����ꂽ賎��̖���_�]���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ŁA������̊��z�ɂ��ẮA�i�䂳��⌊��������ɂ�����ǂ����ŏq�ׂĂ��炤�����Ȃ����낤�B
�@ 賎����D�]���������A����ɗ�炸�f���炵�������̂́A�O������̉��l�肸�����賗����̖��������B���H����賂��ӂ�Ɏg���A���ؕ�賓������A賂̏����Ă��A賂̉����A������賂̃p�C�Ă��Ƃ��낢��ȍH�v���Â炵��賗��������X�Əo���ꂽ���A���ꂼ��ɓƓ��̕�����|���������Ĉꓯ�F���Q�������ł������B�Ƃ��ɁA���̓��͂��߂Ď��삵�Ă݂��Ƃ����A賈�H���܂邲�Ɨp�����p�C�Ă��͐�i�ŁA��̔삦���ꓯ���v�킸�������Ɛ���������قǂ̒����ł������B
�@ ���̂ق��ɁA�L�����̓Ďu�Ƃ̈�Ă��Ñ�āi���āj�ł����A賂̃X�[�v�Ŗ��t�����ꂽ�����A��͂�L�������Y�̌����ő��̎ϕ��A����ɂ͓����_�ƌ��Ђ̃n�E�X�Ő��k�͔|���ꂽ�Ƃ����嗱�Ŗ���������F���������ȃC�`�S�̃f�U�[�g�ƁA�����ʂ�L�����s�����̈��ł������B�f�U�[�g�̃C�`�S�́A���k�͔|�̓������������A���n���ɑS����������ĂĈ�Ă�ꂽ���̂ł��邽�߁A�P���悤�ȐF�������Ă��Đc�܂ŐԂ��_�炩���A�Ö������Q�ł������B�����ɂ����鐅�k�͔|�Z�p�̊v�V�I�i���̂������ŒʔN�̏o�ׂ��\�ɂȂ����̂������ł���B�߂������A賂ƂȂ��ōL�����̓��Y���ɂȂ�ɈႢ�Ȃ��B
�@ �Z���Ɏn�܂��������̉��͑傢�ɐ���オ��A�e�ޘb���s����Ƃ����m��Ȃ������ł͂������̂����A���������ɂǂ����Ă��͂����Ȃ��p��������Ƃ����������\���߂��ɎO���@�����Ƃɂ����B�{���͉i�䂳��̐��b���ł���Y�䂳����A�u���l���ʂɌ������^�N�V�[�ɏ悹��A�����̂��Ƃł��Ƃ͂Ȃ�Ƃ��{�\�ŋA�蒅���݂����ł�����v�Ƃ��Ƃ���X�ɑ����A���łɓV����V�j���̃h�N�^�[�̃T�|�[�g��������Ă��̂��Ƃ����ɋA���Ă������B
�@ ���ꂩ��ꎞ�Ԃقǂ��Ă���A�܂��c���Ă��������R�����ꂼ���]�̏ꏊ�܂ŎԂő���͂��A�Ăю����O���@�ɖ߂����Ƃ��ɂ͌ߑO�ꎞ�߂��ɂȂ��Ă����B�q�Ԃł͍s�i���̘I������͂���ŁA�i�䂳��ƎO������Ƃ�賎����킪�Ȃ����X�Ƒ����Ă����B���Ζʂł������ɂ�������炸�A�i�䂳��ƎO������Ƃ͂�������ӋC���������炵�������B���ɐl���s�ȏ�Ԃ̓�l�̊ԂŌJ�L������x���ŗ�ȃ��b�p���C��̉��V�͒������̂��̂ŁA�Ђ�������]����O������̉�����⑧�q�����̎p���Ȃ�Ƃ���ۓI�������B
�@ �ߑO�߂��A�����łȂ��l�����Ɏ���̐g�̂��x���Ă������Ƃ�����Ȃ��Ă����悤�������B�i�䂳��̂ق����܂��O������ɋߊ��A�������ɂ��O�̕G��݂��ƍ��}�𑗂�ƁA�������O������̍��G�ɓ����悹�C�����ǂ������ɖ��肱���Ă��܂����B����ƎO������̂ق������̂܂܂�����ɐg��|���A�����܂��Q�����Ă��܂����̂������B���炭����ƁA����ǂ͓�l���ǂ��z�������čK�������ɖ��荞�ޗL�l�������B�������ĉi��ΎO���͈̎��������ƂȂ����̂ł������B
�u���l���ʍs���̃^�N�V�[�ɏ悹��A���Ƃ͂Ȃ�Ƃ��{�\�ʼnƂɖ߂蒅���܂��v�Ƃ̉Y�䂳��̂����t���������A�����͌����Ă��S�z�łȂ�Ȃ������̂ŁA�i�䂳����N�����ĎԂɏ悹�A�����������̂���܂ő���͂��邱�Ƃɂ����B�i�䂳��̂���̏��ݒn�͒m��Ȃ��������A���̋ʐ�C���^�[�����O���l�ɏオ��`�k�C���^�[�ł����悢�Ƃ͕����Ă����̂ŁA�Ƃ肠�������̒ʂ�Ƀ��[�g���Ƃ邱�Ƃɂ����B
�@ ����ȂŊC�V�̂悤�ɐg���܂�ߎ����̖ʎ����Ŗ��荞��ł���i�䂳����ꎞ�I�ɗh��N�����A�`�k�C���^�[�o������̓�����q�˂�ƁA���������̓������Ȃ蕡�G�������ɂ�������炸�A�ӊO�Ȃقǂɂ������肵���Ԏ����߂��Ă����B�܂��ɋA���{�\�̂Ȃ���ƂƂ����ׂ����̂ŁA���肱���Ȃ�����v�����������艟���������̃i�r�Q�[�V�����Ԃ�́A�f�ʂł��Ԃ̃i�r�Q�[�^�ɂ͂܂�Ŗ𗧂����̎O������ɂ�����Ƃł����K�킹�������炢�̂��̂ł������B�����ɉi�䂳�������܂ő���͂��A�O����o�R�ŕ{���̉䂪�Ƃɖ߂����̂͂Ȃ�ƌߑO���߂��ɂȂ��Ă����B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2002�N1��2��
�씩��������̋ߋ�
�@ ���炭�Ԃ�ɎO��̂���ɐ씩���������K�˂Ă݂��B�锪�����̂��Ƃ��������A��������̐��Y����̈ē��Œʂ��ꂽ��K�̕����ŁA�씩����͂܂����n�[�T���𑱂��Ă���Ƃ��낾�����B�S�g���g�����������|�J���Ɍĉ����āA�ꎵ���Z�N����̖̂���K�_�j�[�j���A���̉���܂ł��݂Ƃ���悤�ȍ����������Ă����B
�@ �f�l�ڂɂ͂ǂ��ɂł����肻���ȌÂт����@�C�I�����ɂ��������Ȃ��̂����A�����씩����ɂ����r�[�ɁA���|�I�ȈЌ��Ƒ��݊�������͂��߂�̂�����s�v�c�Ȃ��̂ł���B���̃K�_�j�[�j�������ԋ߂Ŗڂɂ���̂����x�ڂ��ɂȂ邪�A�ǂ����Ă��̊y�킪����قǂɐ_���ȋ�������悤�ɂȂ�̂��Ǝ���X���������Ȃ�͎̂������ł͂���܂��B����Ƃ������̂́A����������ɑ����Ȑl���̑��݂����Ă����A���̉B����߂��^��������̂ł��낤�B
�@ �قǂȂ�������̋C�z���@�m���ă��@�C�I������e������Ƃ߂��씩����ɁA�u�ǂ����A���n�[�T���𑱂��Ă��������v�Ɠ`����ƁA�u������ł��A���K���Ă���Ƃ��肪����܂���v�Ƃ����A���₩���̉��əz�Ƃ������̂��߂��Ɠ��̐����Ԃ��Ă����B������A��N�قǂ̂����ɐ씩����ɂ͂����̕��i�����Ȃ���Ă����悤�Ɏv���B�ЂƂ̓����ɂ߂悤�ƂЂ����猤�r��ςސl�ɓ��L�ȑ��݊��Ƃł������ׂ����낤���B
�@ �ǂɂ͐̐씩���g���Ă����炵�����U��̃��@�C�I��������A�O��|�����Ă����B��������ڂŒ��߂Ȃ���A���݂̃K�_�j�[�j�Ń��@�C�I�����͉���ڂȂ̂���q�˂Ă݂�ƁA����ڂ��Ƃ��������������B�씩����̃\���X�g�Ƃ��Ă̐l���͂܂��n�܂�������ŁA�܂��܂����ꂩ��悪�����B����������Ƃ��܂̃��@�C�I�����Œʂ�����Ȃ̂��A����Ƃ����鎞����������ʂ̃��@�C�I�������g�����ƂɂȂ�̂��A�܂����̏ꍇ�ɂ͌��݂̃K�_�j�[�j�͂ǂ��Ȃ��Ă����̂��낤���B�t�҂Ɗy��Ƃ̑����̖����d�v�Ȃ悤������A���������ȗ��j�I����ł��肳������悢�Ƃ����킯�ɂ͂����Ȃ��ɈႢ�Ȃ��B
�@ ����ꏏ�ɐH�����Ƃ����씩�Ƃ̂��D�ӂɑ�����A���Ɠ��s�҂̊�䂳��Ƃ́A��������A�䗼�e�̐��Y����A��q����̎O�l�ƕ���ŐH����͂B�����āA��y���ɐ�ۂ�ł��Ȃ���G�k�ɉԂ��炩�������A����Ȓk��ʂ��āA�ŋ߂̐씩�Ƃ̌��J�̂قǂȂǂ��M���m�邱�Ƃ��ł����B���ʂ̎���ɂ��A�ŋ߁A�����}�l�[�W�����g��Ђ��ς�������߂ɁA����ɂƂ��Ȃ����㏈����V���ȓW�J�ւ̑Ή��������Ƒ�ςł���炵���B�܂��A���̐l�̏h���ƌ����Ă��܂�����܂ł����A�A���̒��n�[�h�X�P�W���[���̂䂦�ɑz��ʃn�b�v�j���O�Ȃǂ��N�������肵�Ă���悤�������B
�@ ��N�\�̊��q�ł̉��t��̂Ƃ��A�씩����͂Ђǂ����ׂɂ�����̒����ň��̏�Ԃ������B�������A������Ƃ����ĉ��t����ȒP�ɃL�����Z������킯�ɂ͂����Ȃ��B�����������ăX�e�[�W�ɗ������t���n�߂��܂ł͂悩�����̂����A���ׂ̉e���Ŏ��������̒��q�ł͂Ȃ��������߁A���t�҂̃s�A�m�̉������ۂ̉��������Ⴍ���������Ƃ����B���̂��߁A�s�A�m�̉�����ɂ��đt�ł���씩����̃��@�C�I�����̉��͖{������ׂ�������荂���Ȃ��Ă��܂����炵���B
�@ �W�҂��r���ł���ɋC�Â������߁A�}篁A���t�͒��~����A�c���ꂽ���Ԃ��g�[�N�łȂ��łȂ�Ƃ������̏�𗽂����̂��������B�ނ��A���̂悤�ȏꍇ�ɂ́A�����̒��O��ʂ̃R���T�[�g�Ȃǂɖ������҂����肵�ăJ�o�[����Ȃǂ̑Ή��Ƃ���炵���B���̗����͉������ꂽ�ʂ̉��ł̃R���T�[�g�������B��͂�̒��͂�������Ȃ������̂����������A�O���̂��Ƃ����P�ɂ��āA���ɕ������鉹�̍�������߂ɗ}���ă��@�C�I������e�����Ƃ���A���ʓI�ɂ͑�ϑf���炵�����t�ɂȂ����̂��Ƃ����B������������̐씩����炵���G�s�\�[�h�ł͂������B
�@ �ڂ̕s���R�Ȑ씩����ɂ́A�g�̉��̐��b�����邽�߁A��ɂ��ꂳ��̗�q�����s���Ă�����B���s�X�P�W���[���������Ă��邠����̖邱�ƁA���t���Î҂ɂ��ڑ҂������ƁA��q����Ɛ�������͌ߑO�뎞���Ɏl�J���痧����ʂɌ������������̓d�Ԃɏ�����B��������̐��Y����ɂ́A��q����A�������̉w�ɒ������ɓd�b����̂ʼnw�܂ŎԂŌ}���ɂ��Ăق����Ƃ����A���������Ă����B
�@ ���Y����͉Ƃ��o�鏀�������đ҂��Ă������A�\�莞���������Ԃ�Ɖ߂��Ă���q����̘A���͂Ȃ������B�S�z�ɂȂ������Y���Ƃ肠�����������̉w�ւƍs���Ă݂�ƁA�Ȃ�ƁA���@�C�I�����P�[�X�����ɂ�����������l�����[��̉w���D���̓����ɂۂ�Ɨ����Ă����̂��Ƃ����B�Q�Ă��������בR�ƍ\���Ă���Ƃ���Ȃǂ͂����ɂ���������炵���̂����A���Y����̋����͑�ςȂ��̂������炵���B�����A����ȏ�ɍQ�Ă��̂͗�q����̂ق��������ɈႢ�Ȃ��B
�@ �A��̓d�Ԃ����G���Ă������߁A�����������q����������Ɨ������ςȂ��������B�Ƃ��낪�A�������̂�������O�̉w�ł��܂��ܐȂ����̂ŗ�q����͂����ɍ������낵���B�����܂ł͂悩�����̂����A�A���̋��s�R�ŐS�g�Ƃ��ɔ�J�̋ɂ݂ɒB���Ă�����q����́A�s�o�ɂ����̂܂ܐ[������ɗ����Ă��܂����̂������B��q�������Ă��邱�ƂȂǒm��悵���Ȃ���������́A�����̂悤�ɕ������ʼn��Ԃ������A��q����̂ق��͂��̂܂��߂����Ă��܂����̂������B
�@ �����N�������̂��悭�킩��Ȃ���������́A�Ƃ肠�������͂ʼn��D���܂ł���Ă����B�����A�ؕ��͗�q���a�������܂܂��������A���������Ȃ������̂ŁA���̂܂܂����ŗ�q������Ă���̂�҂��Ă����̂��Ƃ����B�����Ƃ��A�ɗ͉������v���X�ɕς��čl���鐬������̂��Ƃ�����A�����������炻�̏�����Ȃ�Ɋy����ł͂����̂�������Ȃ��B�ؕ�����������q���ŏI�d�Ԃŕ������̉w�܂ň����Ԃ��A��l�̑҂��D���Ɏp���������̂́A���Y�����D���Ő�������̎p���݂��Ă��炸���Ԃ�Ƃ��������Ƃ̂��Ƃ������悤���B
�@ ��������ɂ́A���̖�A��Ă������薰�邢�Ƃ܂������Ȃ������B���������ɂ͓������đ��̉�Îᏼ�ɓ���A�ꎞ�Ԕ��قǂ̍u�������܂������ƉH�c�ɒ��s�A����̓ߔe�ɔ��œ��n�̉��t��ɗՂނƂ������s�R�ŁA�������g�̑̒��̂ق��A�C�ۏ����ɉe������₷�������Ȋy�탔�@�C�I�������A���̍����悻�O�\�x�Ƃ����ɒ[�ȉ��x�ω��ɂ��Ă����邩�ǂ������S�z�ł������炵���B
�@ ���k�̐���オ����łɁA���͐씩���q�ɂЂƂ��������Ԃ��Ă݂��B��Ґ��̌����y�c�̏ꍇ�ł��w���҂͒c���X�̊y��̉������ꂼ�ꐳ�m�ɔc�����Ă���Ƃ������A����͎����Ȃ̂��A�Ƃ������N���ɔ�߂Ă������₾�����B���Y����Ɛ�������Ƃő��������̑���͂��������̂́A���@�C�I������r�I���Ȃǂ̌��y��̏ꍇ�ɂ́A�������̑��ƂȂ��ċ����킽��̂ŁA��w���҂Ƃ����ǂ��X�t�҂̉��m�ɒ���������͓̂�����낤�Ƃ̂��Ƃł������B�ނ��A�\���y��̏ꍇ��A���y��ނł��w���҂�����̑t�҂Ɍ܊����W�����Ă���ꍇ�ɂ́A�b�͕ʂł���炵�������B
�@ ���̓��̓����ɐ씩����̃T�[�h�E�A���o���u���̈����݁v���r�N�^�[�Ђ��甭�����ꂽ���A�씩�Ƃɂ͂��łɂ���CD���͂��Ă����̂ŁA��������Ă��炢�Ȃ���A�S�n�悢�C���Ŏ���Y��Ċ��k�ɋ����邱�Ƃ��ł����B�t�@�[�X�g�E�A���o���u�̗̂��Ɂv���A�Z�J���h�E�A���o���u�A�x�}���A�v���f���炵���������A����V�����̂��̃T�[�h�E�A���o���͂���ȏ�ɑf���炵���ƌ����Ă悢��������Ȃ��B�|��̐搶�ł����邨������̐��Y������A�Ȗڂ̍D�݂͐l���ꂼ��Ȃ̂ŕʖ�肾���A���t���̂̏o���̓T�[�h�E�A���o������Ԃ悢�Ƃ̈ӌ��������B
�@ �������i���j�ɂ́A�ߌ㎵�����珉��̓����I�y���V�e�B�R���T�[�g�z�[���Ő씩����̃T�[�h�E�A���o�������L�O���@�C�I�������T�C�^�����J�Â����B�܂��A�O���O�\����i���j�ɂ͓����������I�y���V�e�B�z�[���œ��L�O���T�C�^���̒lj��������s�Ȃ��邱�ƂɂȂ��Ă���B�R���r��g�ރs�A�j�X�g���ł����̍����_�j�G���E�x���E�s�G�i�[���Ƃ��Ă��邩��A���̉��t�ɂ͂ƂĂ����҂����Ă������B�`�P�b�g�̗������S�Ȉꗥ�ŁACD�Ɠ����ō��ݎO��l�\�܉~�Ƃ����ւ�����B���̗����ł��̐��Ȃ鋿����������̂ł���Ό������Ƃ͂Ȃ��B
�@ ���݁A�씩����͈ꎞ�̃n�[�h�X�P�W���[������������A�V�t�̃��T�C�^���ɂ��Ȃ������h���Ő×{���Ȃ̂ŁA�����ƍ��x�̋L�O���T�C�^���ł͍ō��̉��t�����Ă��炦�邱�Ƃ��낤�B������������ς��A�S�C��]���ĐV���Ȕ���ڎw���씩������x����܂����߂ɂ��A��l�ł������̕��X�ɂ������肢�������̂ł���B�����g�������͉��������u���Ă����ɑ��^�Ԃ��Ƃɂ������ƍl���Ă���B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2002�N1��9��
�N���̎�
�@�@�@�@�@�������ƐV����
�l�����Ȃ����Y��Ɂ@���Ȃ���̖̂���������
���̐��ɐ����̂ł�
�Y��ɐ��܂ꂽ�҂͋����ł��@�����̂䂦�ɖ����܂�
���̐��̒����𗐂��̂́@���Ȃ�\�}�̋��Ԃ���
���܂ꂽ���̂̏h���i�����߁j�ł�
�͂��Ȃ��t�̉x�тƁ@�������~�̒ɂ݂���
���Ȃ���̂ɐӂ߂��ā@�Ȃ̐����Ƃ�
�����Ȃ�Ƃ��铔���@����̕�������̂�
�X�̂悤�ȗ܂ł��@�����̂悤�Ȍ��t�ł�
�X�̗܂͗͂ł��@�����̌��t�͎����ł�
�܂ƌ��t�͗��ݍ����@�ق̂��Ȉӎu���萶���܂�
�Ë��Ɩ��m�ŕ҂ݏグ���@�����̖Ԃɕ߂����
�������~���҂����Ɂ@�B�ЂƂ��������ꂽ
����͏����ȕ���Ȃ̂ł�
�łɂ����߂������́@���ׂɜւ����[��
�����̌��t�����ƂȂ��@�X�̗܂���Ƃ���
�邩�Ɉ�ĉB�����@�ӎu�Ƃ������̔O�삱��
���肵�҂ւ̒����́@�����҂ւ�櫏̉�
�@�@�@�@�@���閶�̍��ɂā�
�b���Ƃ�������b���܂����@���ׂƂ������狩�т܂���
�����Ă��ꂪ�@���Ȃ������̊肢�������Ⴀ��܂���H
�������ė~����������ł��傤�c�c�S�̉��ł́H
�����ł����@�����Ȃ�ł����@���̖閶�̍��͂����c�c
�����֍s������ł��I�@�ق�Ƃ��ɂ����N�����Ȃ���ł����H
�ˌ���߂đ����Ђ��߂Ă����ł���
�N������ĂȂ���Ȃ���ł���
������ł���@�҂����Ȃ���܂���
�|�����ĂȂ��܂���
����������Ɣ߂��������ł��@�������肵�Ă��邾���ł�
���������̐l���������ā@�����v���Ă��܂�������
���̖閶�����ׂĂ������Ă��܂���ł���
���炳��Ƃ������@���̍��ւ�
�w�悩�炳�炳��ƕ��ꗎ���Ă����܂��@�ɂ݂͂���܂���
�Y��Ȃ���ł����Ƃ����̂́@�Ȃɂ��S������܂���
���Ȃ������͂܂������Ă���̂ł��ˁ@��������Č˂̓�����
�����߂ɍ��ɂȂ�܂��@�閶���z���ĕ������܂�
�ӎ��������Ȃ��Ă��܂����@���낻��ł���
��������悤�@�ł́c�c
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2002�N1��16��
W���v����i1�j
�i��jW���v�o��܂ł̌o��
�@ �䂪�Ƃ̏���I�ɂ͍����u�����h�̊O�����r���v����A���Ƃ��Ȃ��ɓ]�����Ă���B�u�]�����Ă���v�Ƃ킴�킴�������̂́A�ނ��A�����̎��v�ɂ͂������Ă������x�̉��l�����Ȃ����炾�B�����܂ł��Ȃ����Ƃ����A���̎��v�͊䕨�ŁA�����������ɏo���̈�����u�����h���v�Ȃ̂ł���B�����A���̊䎞�v�ɂ́A���Ď��̐e�����F�ł�����W�ɂ��Ă̂�����Ƃ������b����߂��Ă���A���̂��߉䂪�Ƃł͂����W���v�ƌĂ�ł���B
�@ �����o�g�Ŏq�ǂ��̂��납��e��������W�́A�n���������̍��Z���I�������Ǝ��Ɠ��l�ɏ㋞���A�s���̂����w�𑲋ƁA�ƊE���s���Ă��鏬�V���ЂɏA�E�����B���w�N�ł��������M���������ނ́A���̐V���ЂłȂ��Ȃ��悢�d�������Ă����悤�ł���B�ނɂ͍��Z���㑊�v�����̏��������������A�ޏ��͂��̌㑼�̒j���ƌ������Ĉꏗ���������A����Ȃ�Ɉ��肵�������𑗂��Ă����B�����A�₪�Ĕޏ��͕v�Ɨ������A���Ƃ̗��lW�ƍč����A�A��q�̏����Ƃ��ǂ��ނ̌ːЂɓ��Ђ����B���̗����ƍč��̘A�����̉A�ɂ́A�ނ��A���O�ꂽ��M�Ƃł��������ނ̂ЂƂ����Ȃ�ʓ����������B����Ă������̂ł���B
�@ �ꎞ����W��Ƃ͌��邩��ɍK�����̂��̂ŁA���炭���Ĉ�l�̒j�����a�������B�q�ϔY�ʼnƑ��v���̔ނ͎q�ǂ�������S���������A���l�̉�����̊炩�牸�₩�ȏ݂������邱�Ƃ͉i���ɂȂ����̂悤�Ɏv��ꂽ�B�����A�����W��Ƃ̔w��ɈÉ_���������߂͂��߂��̂͌�����l�N�قǂ��Ă���̂��Ƃł������B
�@ W�̓������ˑR�ގЂ��A�����ʼn�Ђ�ݗ�����Ƃ����b�������オ�����̂����Ƃ̔��[�������B���̐V��Ђ̔��N�l�̂ЂƂ�Ƃ��ċ��͂����߂�ꂽ�l��Ƃ̔ނ́A���܂�����b�Ɉꖕ�̕s�����o���Ȃ�����A���Ǒ���̍���ɉ����邱�Ƃɂ����B��Ђ𗧂��グ��ɂ͎莝���������\���ł͂Ȃ��������߁A�ނ�̓T��������S���O��̋��������A����Őݗ������̕s������₤���Ƃɂ����B
�@ �ݗ�������Ђ͈�N�Ƃ��Ȃ������ɂ����Ȃ��j�]�A�؋��̊������ԍς͕s�\�ƂȂ��āA���R�̂悤��W���T������Ђ̗e�͂Ȃ���藧�Ăɒǂ��܂����邱�ƂɂȂ����B�@�O�ȋ����̂��ߎ؋��͂����܂����{�ɂ��c��オ��A�����̐E��≜������͂��߂Ƃ���e���ɂ܂ŋ������R�̌�������藧�Ă��y�Ԃɂ������ẮA�Ƃ�ׂ����͂ЂƂ����Ȃ��Ɣނ͍l�����悤�ł���B�ˑR��Ђ����߂��ނ́A������Ƃ��������A�q�ǂ�������������̂ق��Ɉς˂��܂܁A�ǂ��ւƂ��Ȃ��p������܂��Ă��܂����̂������B
�@ �ނ��A�����̓T������藧�Ă̒��ړI�e�����Ƒ��ɋy�Ԃ��Ƃ������ꂽ���炾�����悤�ŁA���ꂩ�炵�炭�A�ʂꂽ������̂��Ƃɂ́A�ǂ�����Ƃ��Ȃ����������炩�̎d���肪�Ȃ���Ă����悤�ł���B���̂Ƃ���ɂ��ʂꂽ�Ƒ��̂��Ƃ��ł���͈͂ł悢����X�������ނƂ����d�b�����x���������肵�����AW�͎����̋��ꏊ��d���ɂ��Ă͌��t������A�������ďڂ������Ƃ���낤�Ƃ͂��Ȃ������B�����āA�������A�ʗ������Ƒ��̂ւ̎d������r�₦�A�����͂��߂Ƃ���F�l�����ւ̘A�����܂������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂������B
�@ �������l�q�ōȂ�����������߂��Ă����̂͂��ꂩ�牽�N���̂��̂��Ƃł������B�Ȃ̌��Ƃ���ɂ��ƁA�Ȃ��W�炵���l�����w�O�̘I�X�ŊÌI���Ă���Ƃ����̂ł���B�܂����Ǝv���ĉw�O�܂ő����^�сA�X���ɗ��ÌI����̒j�̎p�����ڂɒ��߂Ă݂�ƁA����葫�������Ă����A�����Ԃ�ƕς��ʂĂ��l�������Ă͂������̂́A����͊ԈႢ�Ȃ�W���̐l�ł������̂��B���̓��͂ǂ����Ă��ނɐ��������邱�Ƃ��ł����A���̂܂܋A����B
�@ ���ꂩ��O���قǂ�W�Ƃ͈قȂ�j���I�X�̔Ԃ����Ă������A�l���ڂ̗[���ɍĂєނ��p���������B�q���̓r�₦���Ƃ���_���ċ}�����ŋ߂Â�����������ƁAW�͎��̊�����߂��܂܂�����債���B���̏�ł̗����b�͂�����Ƃ܂����̂ŋߓ����ɂ��炽�߂ĉ䂪�Ƃ�K�˂邩��A�Ƃ����ނ̌��t��M���A���̔ӂ͂��̂܂܋A����B���ꂩ�琔����̒��߂��A�ʂ�ނ͉䂪�Ƃɂ���Ă����BW�̌�����Ƃ���ɂ��ƁA�w�O�œV�ÊÌI���������ɂ�����܂ł̎��̎���͂��̂悤�Ȃ��̂ł������B
�@ ������Ɨ����������ƁA�T�����Ǝ҂̎�藧�Ă�邽�ߒN�ɂ�����������Ȃ��悤�ɓ]�X�Ƃ��Ȃ���A�H��������͂��߂Ƃ���l�X�ȓ��ق��J���̎d�����n������A�҂��������̈��z��ʂꂽ�Ƒ��Ɏd���肵�Ă����B�����A�d�J�������̌��������������ɒǂ��邤���ɁA����ɓ����̉Ƒ��ւ̐ӔC�����J���ӗ~�������ʂĂāA�킸���ł�������������A�J�����炵�̎��ɓM��A����ɂ̓p�`���R�A���n�A�q���}�[�W�����Ƃ������M�����u���ɐg���ς˂�悤�ɂȂ��Ă������B�܂��A�����܂łȂ琢�Ԃɂ�����ł�����b�����A�ނ̏ꍇ�͂��̂��Ƃ̐���s���������Ԃ�ƕς���Ă����B
�@ �����W�͂ЂƂ̕�W�L����ڂɂƂ߂��B����͘J�����Ԃ��Z������������~�ȏ�x������邤���ɁA�Z�ݍ��ݐH�����Ƃ����j�i�̏����̎d���ł������B�S�̕Ћ��ł͂܂��ʂꂽ�Ƒ��̂��Ƃ��C�ɂ����Ă����ނ́A����Ȃ�܂������̎d���肭�炢�͂ł��邩������Ȃ��ƁA�������Ȃ�����㩎d�|���̉a�ɋ����B
�@ �{�l�̈ӎu�̗L���ɂ������Ȃ��A�ʐړ����ɔނ̏A�J�͌��肵���B�ۉ��Ȃ������A�J������ꂽ�Ƃ������ق�����萳�m�ł͂������낤�B�ނ̔��������Ȃ�ʌl�I������@�m��������́A�J�����l�M��w�����Ă���Ă����Ǝv�����ɑ���Ȃ��B�����̋M�d�i����K���i�����[������^�g�����N�͒S�ۂƂ��ĉ�������A��������ނ͂��̕��ς��ȐE��œ�����������Ȃ��Ȃ����B
�@ ���܂���W���g��u�����ƂɂȂ������̏ꏊ�́A�����ł����̒m�ꂽ����t�O���[�v�P���̃^�R�����������B���K���̎d������n�܂�A����Ɏd���̂�肩�����d���܂�Ă������̂����������A�V���̘b�p�̎�����ł���ނ̘b���̂��̂͂Ȃ��Ȃ��ɖʔ��������B
�@ �\�l�قǂ��ЂƂ܂Ƃ܂�ɂȂ��ĐQ�N������^�R�����̘A���́A���߂�ꂽ�����Ɉ�ċN������ƁA�Ɖ��₻�̎��ӂ̑|���������Ȃ��A���ʂ��I�������ƐH��ɂ��ċ��ɒ��H���Ƃ����Ƃ����B��ԉ��ɂ͈��䂠��͈�����ƌh�ӂ������ČĂ�鍁��t��Ƃ̓���̑������w���A��ʎ҂���V�Q�҂܂ł��A���ʂɏ]���ďc���̃e�[�u�����͂B�V�Q�҂������ނ́A���R�A�ŏ��̂����͖��[�̐Ȃɍ��点��ꂽ�悤�ł���B
�@ �F�����H�̐Ȃɒ����ƁA������ɂ���܂��Ɉ���ƌĂ�鏗���Ɍ������ē��������A��ĂɊ��ӂ̌��t���q�ׂ�̂����킵�ɂȂ��Ă����炵���B���ꂪ�I���ƈ�ш�`�ɋ߂����M�i�������j���}���ő~�����݁A�H��������ŕЕt���Ă���d���̏����ɂƂ肩�������B���т͎��O�œK���ɂƂ�A�Ӕт͎d�����I����x���߂��Ă���A�p�ӂ���Ă�����̂����ꂼ��ɐH�ׂĂ����Ƃ����B���H���͂܂����������A��y���ƌĂԂɂ͒��������̂ł������悤���B�H�����I����ƐH���Еt���A�^�R�����ɖ߂�ƁA��قǗ]�͂ł��Ȃ�������͗����̎d���ɔ����ĂЂ����疰��B�Z�ݍ��ݐH�����ɂ͈Ⴂ�Ȃ��������A�l�Ԃ炵�������ɂ͒��������̂ł������B
�@ ��Ȏd���͂ӂ�����A�ЂƂ͂��������̉w�O��ɉ؊X�̘I�X�ɂ�����V�ÊÌI��^�R�Ă��Ȃǂ̐H�ו�����A���܂ЂƂ͊e�n�̐_�Ђ₨���Ȃǂ̂��Ղ�≏���ł̏o�X�̎d���������悤���B���Ղ�≏���Ȃǂ͖����K���ǂ����ōÂ���Ă��邩��A��قǂ̈��V��ł��Ȃ�������d�����x�݂ɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ������Ƃ����B���������ƕ������͂悢���A���̎��́A�قƂ�ǔN�Ԗ��x�ŋ����I�ɓ����Â߂ɂ�����ꂽ�Ƃ������Ƃ炵���B���������ۂ͔���ɉ������������ŁA����������ɂ���悤�ɂ��̊z������~�ɂȂ�͔̂N�Ԃ�ʂ��Ďl�A�ܓ�����������Ƃ��낾�����悤�ł���B���ς���Ɠ��ɐ�ܕS�~������~���炢�ɂ����Ȃ�Ȃ������Ƃ̂��Ƃł���B
�@ W�͘I�X����ł̎d���̎��Ԃɂ��Ă��b���Ă��ꂽ�B���Ƃ��A�w�O�Ȃǂ֓V�ÊÌI��ɏo�|����ꍇ�ɂ́A��ʂɎd����q�ɂɕۊǂ���Ă��鐶�I��K�v�ʉ^�ԏ����𐮂���B�Â��Ȃ�J�r�����������̂������Ԃ�Ƃ���炵���̂����A����Ȃ��ƂȂǂ��\���Ȃ��������Ƃ����B���I�������Ďd���ɏo�|����ۂɂ́A����Ȃ�l������Ă��オ�����V�ÊÌI�����邽�߂̎��܂̑���n���ꂽ�B��n����鎆�܂̖����͂�������ƃ`�F�b�N����Ă���A�d������߂������Ɏc���Ă��鎆�܂̖����Ƃ̍������ꂽ�����Ɣ��f�����B������A���������܂����Ă��܂����肷��ƁA���̕��ɑ���������z��S�z���ȕٍς��Ȃ���Ȃ�Ȃ��d�g�݂������B
�@ �S������w�O��ɉ؊X�ɏo�����ƁA�������y�����Ԃ��ĕt�߂ɒu���Ă��鉮���g�ݗ��āA����ꂽ���ƒ�߂�ꂽ�ꏊ�ɉ^�B�s���̎��ԂȂǂɔ�����l��g�Ŏd��������̂��킾�Ƃ������A�A�ѐӔC����~���Ă���ƂȂ����݂����Ď������킹�邱�Ƃɂ���āA�T�{�^�[�W���ⓦ�S��h���Ӗ����������炵���B
�@ �V�ÊÌI�����q�́A���̊Â������������Ɍ��f����č��z�̕R���ɂ߂邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��B������A�d�Ԃ��w�ɒ����ĉ��D������l�g���ǂ��Ɨ���o���̂ɍ��킹�ăU���������Ă��I�p�̘F���̏���ÌI���̂��̂ɂӂ肩����B����Ɣ������ƂƂ��ɂȂ�Ƃ������Ȃ��悢�������������тɗ�������̂��������B�������A�U�����͊ÌI�̕\�ʂ�F�̏������₩�Ɍ��点��ƂƂ��ɁA�ꕔ�͌I�̕\�炩������ɟ��ݍ���ŁA�H�p�����ɓƓ��̖��t��������̂ɂ��𗧂Ƃ����킯���B
�@ ��������^�R�����̎҂����́A�Ȑ������ł͂���ɂ���A�Ƃ������������ɂ���Ƃ肠���������Ă͂�����Ƃ������ƂŁA�����o�����Ƃ͂قƂ�ǂȂ������悤�ł���B�����o���Ƃ���A�I�X�œ����Ă���Ƃ����`�����X�������悤�ł��邪�A���܍���t�O���[�v�ƊW�̂���炵��������̂��Z�����������ƂȂ����Ă��ėl�q���M�������Ă���̂ŁA�E������ɂ͂���Ȃ�̊o����K�v�ł������炵���B
�@ ����t�̖��[�ɐg������Ă���Ƃ͂����Ă��A�ꉞ�͑�w�𑲋Ƃ��ƊE�V���̋L�҂܂ł�����j�̂��Ƃł���B�������ɂ��̂܂܂ł͚��������Ȃ��ƍl�������̂炵���B���炭�͉������Ȃ��������A���ꂩ��l�A�܃������Ă���̂��ƁA�ނ͓ˑR�ɉ䂪�ƂɎp���������̂������B�S�ۂƂ��ĉ�������Ă���g�����N�Ƃ��̒��g�͂��ׂĕ������A���_�ɓV�ÊÌI����̎d�����܂����Ă���Ԃɒ��̐g���̂܂܂Ō��ꂩ��h�������Ă����̂��Ƃ����B����̂��Ƃ�����Ƃ����Ȃ�����A������Ɏ������悤�Ȃ��Ƃ͂��Ȃ������Ƃ̂��Ƃ������B
�@ ���ꂩ��قǂȂ��AW�͎��̏Z�ޒ��̈���ɂ�����^�A��Ђ̑q�ɂɋ߂�悤�ɂȂ����B���̉�Ђ̓Ɛg���ɓ���A�Ζ��ԓx���^�ʖڂŁA���_�I�ɂ����Ȃ藎�����Ă����悤�ɂ݂����B�T������������Ă����ƁA����܂��ǂ����ő������ʓ|�Ȃ��ƂɂȂ��Ă������Ȃ��̂ŁA�m�l�ٌ̕�m�ɑ��k�ɏ���Ă��炢�A�@�I�ɂ�������Ə�������悤�ɑ����������B���Ƃ��Ǝq�ϔY�������ނ́A������x���������蒼���A���f���Ă����Ƒ��ւ̑������ł��邵�A�啝�Ɍ��z�ɂȂ����T�����̎c�����ԍςł���Ύq�ǂ������Ƃ̍ĉ���\�ɂȂ�Ƃ������ƂŁA�\��̂��̂��ʐl�̂悤�ɖ��邭�Ȃ����B
�@ �䂪�Ƃɂ��悭�p�����������A���X�ɂ����ȑO�̔ނɖ߂��Ă����悤�Ȋ����ŁA��������͎������g�̋��ʼn��낵���悤�Ȃ킯�������B�p�`���R�D�������͑��ς�炸���������A�ǂ��܂ł��̂߂荞�ނ悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ������悤�Ȃ̂ŁA�F�l�Ƃ��Ă��̒��x�͑�ڂɌ��Ă������Ƃɂ����B
�@ W���ˑR�Ɏp���������̂͂��ꂩ���N�قǂ��Ă��炾�����B�܂����⍚�R�ƍs��������܂����ނ�T���o�����Ǝv����������̂��Ƃ͂���Ă݂����A�ǂ����ǂ��T���Ă����̏�����m�邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�ނ̏Z��ł�����Ђ̓Ɛg���ɂ͐g�̉��̕i�����̂܂c����Ă���A�ގГ͂Ȃǂ��܂������o����Ă��Ȃ������B�������A�p�����������̕��̋��^������̂̂܂܂������B�ނ̐e�ʂ⑼�̗F�l�Ȃǂɂ��������Ă݂����A���ɂ����_�B����ԂŁA�Ȃ�̎����������Ȃ������B
�@ �p�����������Ƃ͋t�ɁA������̗[���A�˔@�䂪�Ƃ̌����W�����ꂽ�̂́A���ꂩ��O�N�قnjo���Ă���̂��Ƃł������B�ނ͕��ڂ����ŁA�ُ�ɓ��Ă��������̎p�ɂ͔��̐��Ƃ͗����̐[���S�g�̂�ꂪ�����Ƃꂽ���A���̊�ɂ͐̂Ȃ���̂ЂƂȂ����݂Ƃ����̈��g�̐F��������ł����B
�@ ���C�ɓ���A�H�����ς܂��A���ł����ɂȂ��悤�ɐQ�������炦�������ŁA�ނ̉ߋ��O�N�Ԃقǂ̑��Ղɂ��ďڂ����������ƂɂȂ����̂����A����́A�u�����͏���������Ȃ�v�Ƃ�������n�ł����悤�Șb�������B���K�̐܁A�ނ́A���[���b�p�������u�����h�̊䎞�v���A�܂������������䂪�Ƃ̎q�ǂ������̂��y�Y�ɂƎ��Q���Ă��ꂽ�̂����A�����ɂ�����܂ł̈�A�̕���͂�����̊䎞�v�ɐ[���܂����̂������̂��B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2002�N1��23��
W���v����i�Q�j
�i��j�^���̈��Y�Ƃ͌��������
�@ ���̏Z�ޒ��̈���ɂ���^�A��Ђ̑q�ɂœ����Ă���W�ɁA�Ăї\�����ʕs�^���~���ėN�����̂͂���_�Ђ̍Ղ̖�̂��Ƃ������B�N�����ē��₩�ȍՂ��������肷������ɏo�|���Ă݂����Ȃ�B���Ƃ��Ɛl��{�ՍD���Ȕނɂ���A���̂������͂ЂƂ����������ɈႢ�Ȃ��B���Ă������Ă������Ȃ��Ȃ����ނ��A�����̏o�X�œ��키�Q����l�g�ɂ܂���ĕ������̂��^�̐s���������B
�@ ���܂��܂��̏�ɋ����킹���̂̍���t���Ԃ̈�l��W�͌������Ă��܂����̂��B�����ɘA������荇��������t�O���[�v�́A�ނ̐Ղ����A�l�C�̂Ȃ��Ƃ���ŗL�������킳�����̐g�����S�����Ă��܂����̂ł���B���Ƃ̃^�R�����ɘA��߂��ꂽ�ނ́A���ꑊ���̎d�u�����Ȃ���ꂽ���ƁA���Ƃ��Ėk�������M�z���ʂœ���Ȏd�������Ă���P���̕ʑg�D�ւƑ��荞�܂ꂽ�B
�@ �ނ͂����Œ��Ԍܐl����g�ƂȂ��Ă����Ȃ������̍��\�����ɋ����]��������ꂽ�̂������B�ܐl�̈ꖡ�͈��̑�^��p�Ԃɏ���čs�������B�Ԃ��^�]�����l�����[�_�[�i�ł��ׂĂ��d��A�c��̎l�l�͖Ƌ��A�g�����͂��߂Ƃ��邢�������̏����i�D����A���K�����������Ƃ�������Ȃ������Ƃ����B
�@ �O���������u�����h���v�̊䕨�̔����ނ�̎�Ȏd���ł͂��������A���̎���͑����ɍI���Ȃ��̂������悤�ł���B�傽��^�[�Q�b�g�͒n���̒��X��_�����ݏZ�̏��p�Ȑl�X�ł������炵���B�Ԃ��^�]���郊�[�_�[�i�̒j���A�����͂Ǝv���Ƃ���ŎԂ𒓂߂�ƁA�l�l�̔���q�͈ꉞ����炵������ꂽ�䕨�̍����u�����h���v����̊��ƁA�����M�p�����邽�߂̖{���̍������v�������ĕt�߂̖��ƂɎU���Ă䂭�B����A�W�A���̂����䎞�v�͎��ۂɂ͌��n���Ɠ��~�����Ȃ��V�����m�������炵�����A�ꉞ�������݂͂��Ă����悤���B
�@ ����q�����́A���̎��v��~�ȉ��ł͔���Ȃ��悤�ɖ������Ă����B�ނ��A����ȏ�Ȃ炢���獂���Ă��悭�A���ۂɌܖ��~��\���~�Ŕ���邱�Ƃ��������Ƃ����B����Ă�����Ȃ��Ă��O�A�l�\���ȓ��ɂ͕K���Ԃɖ߂�悤�ɂƌ��d�Ɏw������Ă���A�l�l�̔���q�̒N������ł��䎞�v����ɐ�������A�����ɎԂ����Ă��̏�����Ƃɂ��A���Ȃ��Ƃ��O�\�L���ȏ�͗��ꂽ�ꏊ�Ɉړ������Ƃ����B�������A���������v���䕨���ƃo���Ď�z�����܂ł̎��Ԃ���������ƌv�Z�ɓ���Ă̍s���������B
�@ W���͂��߂Ƃ��锄��q�����́A���t�I�݂ɑ����U�����@�⑊��̐S���̓ǂݕ��A����̎�����A�����C�͂��邪����ɓ����̑���̎������킹���Ȃ��A�����������o���ɋ�s��X�ǂɏo�����ꍇ�̑Ώ��@�ȂǁA�䎞�v����̃m�E�n�E�����[�_�[�̒j�����ʂ茵�����@�����܂ꂽ�B�Ƃ��ɂ̓��[�_�[�i�̒j�₻��Ɠ��i�̒��Ԃ��V�Ă̔���q�s���A���n�̔��g���[�j���O�ɋy�Ԃ��Ƃ��������炵���B�䎞�v���ɓn�����Ƃő��������ɏo�����ȂǂƂ������Ƃ͊Ԉ���Ă����Ȃ������Ƃ����B
�@ ���\��������{���̂��Ƃ�p�������v�������������A�����ɂ�����Ƃ����G�点���肵�Ȃ���A����͐�ɔ��������Ɛ������݈����̊䎞�v�����̂��A�ނ�̊�{�I����ł���B�I���ȍ��\�̎���ɂӂ��܂����݂̂Ȃ��n���Z�܂��̐l�X�́A����q�̌������Ƃ���������M�����݁A���\���Ŕ����Ă��ꂽ�悤�ł���BW�������ɂ́A�䎞�v���Ă����̂́A�ق�Ƃ��ɉ������ĐS�̗D�����l�������肾�����Ƃ����B���܂�̐\����Ȃ���W�̐S�͂����Ԃ�ƒɂ݂������炵���B�ނ͂��̂��Ƃ����x���J��Ԃ��������Ă�������A���ۂ����������̂ł��낤�B
�@ ���[�_�[�i�̒j�́A����q�������䎞�v��J���ĎԂɖ߂��Ă���ƁA���낵���قǓI�m�ɔ��l�ĂĂ݂����Ƃ����B�Ȃ��Ȃ̂��͂킩��Ȃ��������A�ǂ����ɓ����킪�d�|�����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv�������Ȃ�قǂ̐��m���������炵���A���̂��ߔ��l�����܂�������̈ꕔ�𒅕����邱�ƂȂǐ�ɂł��Ȃ������Ƃ����B
�@ �ނ炪�䎞�v������n��́A�S���ǂ��ł��Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A�k������z��ɂ����Ă̈�тɌ����Ă����悤�ł���B��������̎d�������Ă��鑼�̃O���[�v�Ƃ̊ԂŃe���g���[�̒������Ȃ���Ă����炵���A�e���g���[�O�Ɉړ�����͕̂߂܂�댯���@�m���ꎞ�I�ɐg���B���Ƃ������������悤�ł���BW���S������Ă����O�N�߂��̊Ԃɏ��x�b�h�̂���܂Ƃ��ȏh�ɔ��܂����̂͂킸����A�O�x�ɂ����Ȃ������������B���[�_�[�̒j�����͖��Ӄz�e���◷�قȂǂɔ��܂������A����q�����l�l�͗��������������Ԃ̒��ŐQ���肳����ꂽ�B
�@ �܂��A�s����X�̌��O����Ȃǂʼn��������ƕ��C�ɓ��邱�Ƃ������ꂽ���A�Ď��̖ڂ͌����������悤�ł���B��������O�x�̐H����̓��[�_�[�̒j���S�z�x�����Ă����Ƃ������A�H���������ٓ��Ȃǂ��قƂ�ǂŁA�܂Ƃ��ȐH����X�g�����ɓ��������Ƃ͐�����قǂ����Ȃ������Ƃ����B�ߗފǗ�����Ȃǂ̏����͈ꕔ�����������ł����Ȃ��ق��A�e�n�ɓ_�݂���ꖡ�̋ɔ�̗���菊�œK���ȏ��u���Ȃ���Ă����炵���B
�@ ���[�_�[�̒j�͎��X�҂�������X�ǂ��s���獁��t�O���[�v�̏㕔�g�D�炵���Ƃ���ւƑ��������B�܂����i�̊䎞�v������ĂȂ��Ȃ肩����ƁA�����ǂ����ɓd�b�������ĐV���ȏ��i�̔������˗������B����ƌ��d�Ƀp�b�N���ꂽ���i�̊䎞�v���Ŋ�̋�`�ɒu�����߂ő����Ă���蔤�ɂȂ��Ă���A���Y��`�ɏo�����ă��[�_�[�̒j�����������A�܂��d���𑱂���Ƃ����V�X�e���������B
�@ W�̂���Șb���Ă���r���ŁA���́A���̋C�Ȃ炷�����݂ē����o�����Ƃ��ł������낤�ɁA�Ȃ��������Ȃ������̂��Ɛq�˂Ă݂��B����ƁA�ނ́A���̉Q���ɂ���҂ɂ����ق�Ƃ��̂Ƃ���͂悭�͂킩���Ă��炦�Ȃ��̂����ƌ����Ȃ���A���ݒ��߂�悤�Ȍ����ł��̗��R��b���Ă��ꂽ�B���ׂĂ͔ނ̈ӎu�͂ƌ��f�͂̎コ�̂䂦�ƒf���Ă��܂�����܂ł��������A����������ȏɒǂ����܂ꂽ��N�ɂ����ď\���N���蓾�邱�Ƃł͂���ȂƂ����v���͂����B
�@ W�͍Ղ̖�ɍS�����ꂽ���ƁA����R��̖\�s��������ꂽ�����ɁA���炭�̂������H����₽��Â������Ɋċւ��ꂽ�B�����āA����Ǔ����o���悤�Ȃ��Ƃ���������葫�̈�{���{�ǂ��납�������ĕۏ͂��Ȃ����Ɛ������ꂽ�������ɁA�m�l��F�l�Ƃ̘A���̂��ɂ������̊䎞�v����g�D�̎��̂Ƃ��Ėk�����ʂւƑ��荞�܂ꂽ�B�܂��g�ѓd�b�ȂǂȂ�����̂��Ƃ����A����ɂ���Ȃ��̂��������Ƃ��Ă��A���̂��܂��܂Ƃ��������i�ƈꏏ�ɂ��ׂĎ��グ���Ă��܂������낤����A������ɂ���A�F�l�m�l�ւ̘A���͕s�\�������ɈႢ�Ȃ��B
�@ �\�~�ʈ���������̎������킹�͂Ȃ���������A���������o���Ƃ���A�������݂Čx�@���Ԃɋ삯����ŕی�����߂邩�A�ʂ肷����̒N���ɏ��������߂邵���Ȃ����������B�͂��߂̂����͂���Ȃ��Ƃ����Ăł��Ȃ�Ƃ������o���Ȃ����̂��ƔނȂ�ɍl���͂����悤�ł���B
�@ �����A�x�@�����Ԃɕی�����߂邱�Ƃ͕|���Ăł��Ȃ������B���Ƃ����ꂪ�����v���ꂽ���̂ł������Ƃ͂��Ă��A���łɔނ͑������̍��\�s�ׂ������Ȃ��Ă��܂��Ă����B�����x�@�ɕی�����߂���A�������g���O��I�Ɏ�蒲�ׂ��A���\�߂𗝗R�ɔƍߎ҂Ƃ��đ�������邾�낤���Ƃ͊m�����������A���̍���t���Ԃɂ��{���̎肪�y�Ԃ��낤���Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��Ƃ��낾�����B�ނ��A����܂Ŕƍߗ��Ȃǂ܂������Ȃ��ނɂ���A�撲�ׂ���������邱�Ƃ͐S���I�ɂ��|�����Ƃ��������A����t�O���[�v�̎d�Ԃ��������낵�������B�܂��A����Ȃ��ƂɂȂ�����A���̉\�������ɂ��̋��̐l�X�ɓ`���A����łȂ��Ă��Ȃɂ��Ƒ傫�ȐS�z�������Ă���V���e����߂��܂��邾�낤�Ƃ����v�����������B
�@ ����t�O���[�v��[�_�[�i�̒j�Ȃǂ�����A�����x�@�ɐ��ꍞ�ނ悤�Ȃ��Ƃ���������A�ʂꂽ�Ȃ�q�ǂ���T�����Ăǂ��܂ł����܂Ƃ��Ă��Ƌ�������Ă����B�܂��A���Ƃ��x�@���ǂɕی삳��Ă��A������ꂽ�i�K�ōēx���O��T���o������Ȃ�̂���Q������Ă��ƓB���h����Ă������B
�@ ������Ƃ����Ď��͂œ����o���ē����ɖ߂�ɂ́A�ǂ����œ��ʕK�v�Ȃ������H�ʂ��A���ꂩ��w�ɍs���ēd�Ԃɏ��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�^�ǂ��e�Ȑl�ɂł��߂��肠���A�����Ă��炦��悢���A���̒����������Â��͂Ȃ����A�����������Ă݂Ă��e�Ղɂ͐M���Ă��炦�����ɂȂ������B�܂��A����Ȏ��ԂɂȂ�����A����t�O���[�v�����ԂƘA������荇���ĉw���̑�W�̗���肻���ȏꏊ��O��I�ɐ��낤����A�Ăѕ߂܂��Ă��܂��\�������������B���ꂻ���Ȃ�����ߎS�Ȍ��ʂɊׂ邾�낤���Ƃ͖ڂɌ����Ă����B
�@ ���ǁA�ނ͂���ȏ̂��ƂŎ��X���\�s�ׂɎ��݂��Â��邤���ɁA�����o���E�C���A����ɂ͎��炪�u����Ă���̐[�������l����C�͂�����A���ꂩ��O�N�ԋ߂����Ԓ������Ɗ䎞�v����̓��X�𑗂邱�ƂɂȂ����̂������B���̊Ԃɑ������̊䎞�v��܂������炵���̂����A�ނ����ނ����сi�H�j�������Ă��I�n�����̂܂܂ł����B���ɂ͌x�@�̌x���ԂɈ���������A�낤���Ƃ���œ����ɐ��������悤�Ȃ��Ƃ��������炵���B
�@ ����������W���ˑR�ɉ䂪�ƂɎp�����킷���T�ԂقǑO�A���܂����́A�V���n�����͂��߂Ƃ�����{�C���ݒn��ő�|����őg�D�I�ȍ��\�O���[�v����u�����h�̍������v������A��тɑ�ςȔ�Q�������炵�Ă���Ƃ̐V����ڂɂ��Ă����B�Ԃŋ@���I�ɓ��������̃O���[�v�����݂��Ă���悤�Ȋ������������A�܂������̈����W�������Ă���Ƃ͑z�����ɂ��Ă����Ȃ������B�Ȃɂ��Ȃ��ǂ��̋L���̂��Ӗ����͂�����Ƃ킩�����̂́A�ނ̘b�����Ȃ�̂Ƃ���܂ŕ����Ă���̂��Ƃł������B
�@ W�̘b�ɂ��ƁA�ނ��䎞�v����̃O���[�v���������ꂽ�͉̂䂪�ƂɌ�����A�O���O�̂��Ƃ������炵���B�V����������@�����Ƃ���A���ۂɂ͑{�����ǂ̒Njy���������Ȃ�A����ȏ�̎d���͖����Ɣ��f��������t��w���̎w���ŃO���[�v�̉��U�������Ȃ�ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂����A�ނ�����Ă��ꂽ�o�܂͂���Ƃ͏�������Ă����B
�@ W��������ꂽ���A�ނ�͐V�����̂���n���s�s�߂��ɂ����B���̓��̒��A�ˑR�A���[�_�[�i�̒j���A�u���O���O�N�߂������Ԃ�Ɗ撣���Ĕ���ɍv���������炱�̂ւ�Ŏ��R�ɂ��Ă�낤�v�ƌ��������A�ނ͍Ŋ�̉w�ŎԂ���~�낳�ꂽ�̂��Ƃ����B���̍ہA�j�́A�u�������ʂɖ߂�ɂ͏������炢�����v�邾�낤����A����ł������ċ�������Ȃ�v�ƌ����Y���āA�P�[�X����̓�̊䎞�v��ނɎ�n���Ă��ꂽ�̂��������B
�@ �l�Ԃ̐S���Ƃ͕s�v�c�Ȃ��̂ŁA������ꂽ�r�[�AW�͂���܂ł̎����̍s�ׂ��Ђǂ��|���Ȃ�A�茳�Ɏc������̊䍂���u�����h���v��J���ē����܂ł̗�����H�ʂ��邱�ƂȂǁA�ƂĂ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂��Ƃ����B���ǁA�ނ̓q�b�`�n�C�N�܂����̂��Ƃ����A�������g���b�N�̉^�]���̍D�ӂɏ�����ꂽ�肵�Ȃ��瓌���ɒH�蒅�����̂������B
�@ �O�N�߂��ɂ킽��ނ̐���ȑ̌��̏Ƃ������ׂ���̊䎞�v�́A����Ȍo�܂ŁA���܂͂������l���Ă���䂪�Ƃ̓�l�̎q�ǂ������ւ̎�y�Y�Ɖ������̂ł������BW���v�ƌĂ���Șr���v�����܂��Ȃ��䂪�Ƃ̒I�ɒu����Ă���̂͂���ȗ��R����ł���B���ꂩ����������Ԃ�ƔN�����o�߂������݁AW�͓s���̂��鏑�З��ʕ���̉�Ђ̑q�ɂœ����Ă���B���Ă̂悤�ɖ����̂����̗͎͂����Ă��܂������A����t�O���[�v�̃J���ɂ����悤�ȔN��ł��Ȃ��Ȃ����B���ɂ͔ނ����̐l���̌������̂܂ܕM�ɑ�����ł����Ȃ�ʔ�����i���ł������ȋC�����ĂȂ�Ȃ��̂����A����̊��߂ɂ�������炸�A���Ă̕��w�NW���M������͂��߂�C�z�͂܂������Ȃ��B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2002�N2��13��
���ł̓ޗLj�h
�@ ��y�̂x���A���Ζ����̊O���n�R���T���^���g��Ђ����قNjx�E���߁X�J���u�C���ʂɂł�����Ƃ����̂ŁA�ޏ������{�O�Ɉ�x����ĎG�k�ł����悤���Ƃ������ƂɂȂ����B�x����͉�������Ƃ悭���k��������̂����A����̎Ⴂ����̍l�����ȂǁA������������Ƌ���邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��̂ŁA�N���j���̕ʂƂ����������z�����t�������𑱂��Ă���B�܂���\��ʼn����ɂ��Ă��s���I�Ȕޏ��́A�m�f�n�̗Վ������o�[�Ƃ��ăL���[�o��R�X�^���J�Ȃǂ̎��R�������ی슈���ɎQ�����邱�ƂɂȂ����炵���B�������A�m�f�n�T�C�h����̎��������͂܂������Ȃ��A���n�ł̐���������ȕ��S�Ȃ̂��������B
�@ ����Ȃ�̔\�͂̂���l�ނƂ͂����A�Ζ����Ă܂����N�ƌo���Ȃ��ޏ����ݐЂ̂܂܂łm�f�n�����ɎQ�����邱�Ƃ�F�߂��Ƃ̂ق����Ȃ��Ȃ��̂��̂ł���B���Ԃ�A�����I�ɂ݂���̊�ƂɂƂ��Ă��v���X�ɂȂ�Ƃ������f�������Ă̂��ƂȂ̂ł͂��낤�B���Љ�ӎ����ω������������A�ߔN���̎�̘b���悭���ɂ���悤�ɂȂ��Ă������A��̑O�̍�����ƂȂǂȂ�Γ���l�����Ȃ��������Ƃł���B
�@ ���̂x������ߌ�ꎞ�߂������������a���w�ŏE���A�{�������C���^�[���璆���������ɓ����ď��{���ʖڎw���đ���o�����B�V�C���悢���ƂȂ̂ŁA�ǂ����Ȃ�~�̖k�A���v�X�̗[�i�ł����߂Ȃ���b�ł��Ƃ����̔ޏ��̊�]�������Ă̂��Ƃ������B���A��̗\��ɉ����A���r�̒Z���~���Ƃ����ē��v�܂ł��܂莞�Ԃ��Ȃ���������A�A�N�Z���ޒܐ�ɂ����̂�����͂��������B
�@ ���łɑ��z�������̋�ɍ����������Ă������Ƃ������āA�^�]�Ȃ̐^���ʂ���z���˂�����ł����B�~�̑��z�͉ĂɊr�ׂč��x���Ⴂ����A�ߌ���߂������炢�̎��ԑтł��z���͉^�]�Ȃ⏕��Ȃ��X�g���[�g�ɏƂ炵�o���Bῂ����Ă������͂��܂芴���Ȃ����߁A�����z�˂̋�����Y��Ă��܂��̂����A��C������ł��邤���Ɋ�ʂɑ�������̓��ˊp���傫���Ȃ邩��A�������肷��Ǝv��ʐ���𗁂т錋�ʂɂȂ肩�˂Ȃ��B�C�������Ƃ��ɂ́A��l�Ƃ���F���Ԃ��ۂ��ς��قǂɓ��Ă����Ă��܂��Ă����B
�@ �����Ղ���A���v�X�A��Ⓑ��Ȓ����R�n�̎R�X�����]���Ȃ���b�{�~�n�𑖂蔲���A������߂Â����ɂȂ�ƁA�E��ɂ͔����x�A��A�����č���ɂ͖P������b���x�ւƘA�Ȃ�W����甪�S���[�g���O��̕�X���傫�����̎p���������B��A���v�X�A��̖k�[�Ɉʒu����P���O�R��b���x�̉s���藧�k�ǂ́A�ǖʑS�̂������ɐቻ�ς���_�X��������̂������܂��������B
�@ �P���R�n�̒n�����x�̒���ɂ͍����O�\���[�g���قǂ̃I�x���X�N�i�s����̐듃�j������̂����A���E���ǍD�������̂ł��̐�����Ⓝ�̉e�����͂�����Ǝ��ʂ��邱�Ƃ��ł����B�㍂�n�̑��݂𐢂ɒm�炵�߁A���{�A���v�X�̖����C�O�ɍL�߂��E�H���^�[�E�E�G�X�g���́A���̒��u�ɓ��̗V����iThe playground of far east�j�v�i�R�ƌk�J�Њ��j�̒��ł��̒n�����x�̃I�x���X�N�Ƀ��[�v���g���ď��o�������ۂ̑z���o�Ȃǂ��q�ׂ��肵�Ă���B
�@ ����̖P����b���x�ɑ��A�E��̔����x�̂������܂��͕Ҋ}�x��ʂ̗Y��ȃX���[�v�Ƃ���ɑ����R�[�̍L���̂����������āA�݂邩��ɏ����I�Ȋ�������B���܂��R����т��_�ɕ���ꔪ���ڕt�߂��牺���������߂邱�Ƃ��ł��Ȃ������̂ŁA������������Ȉ�ۂ������c�����B�R���������炾�Ɠ�����A���쌧�̊����z�K���ʂ��炾�����ȎR���܂ޔ����x�A��̑S�e����]�̂��Ƃɂ����߂邱�Ƃ��ł���B�������ŁA�z�K�p�[�L���O�G���A�ɒ������ɂ́A�����x�A��̎R�����[�z�ɐԂ����܂�̂߂邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B�����Ƃ��A�����x�̎R����т͈ˑR�_�ɕ���ꂽ�܂܂������̂ŁA��̐ς�������X�̒������������я�A�Ȃ��ĐԂ��P���Ƃ���������ƕς�����[�i�F�ł͂������B
�@ ���쓹���ʂɕ��A���J�ō��������~��č�����\���`���ɉ��K�����z����ƁA�A���v�X�̓W�]��Ƃ��Ēm���鍂�{�b�`�R�֑����ѓ��ɓ������B���܂��܂Ƃ������H�܂Œm��s�������ѓ��ł͂��邪�A�H�ʂ̓K�`�K�`�ɓ��������ϐ�ŕ����Ă����̂ŁA�R�����ʂɐi�ނɂ͎l�쓮�ɐ؊����A�`�F�[��������K�v���������B�����A���ǁA���̂܂����i�Ƃ���ň����Ԃ������Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂����B�����̖k�A���v�X�A���т������_�ƃK�X�ɕ����A�܂������W�]�����������ɂȂ����Ƃ��킩��������ł���B���킦�ē��v���ԋ߂���������A����ȏ㖳�����ėѓ��[�����������Ă��d�����Ȃ��Ƃ������f���������B
�@ �k�A���v�X�̒��]���y���ނ��Ƃ͒��߂�������Ȃ��������A������Ƃ����Ă��̂܂܂���Ȃ蓌���֖߂�̂����܂�ɖ�����B����Ȃ킯�ŁA�}篁A�ړI�n��ύX�A���K�s�X���Ėؑ]�H�ɓ���A�ޗLj�h�A���ďh�A�n�ďh�Ȃǂ̋��h�꒬������A���ꂩ�璆�Ð�ɏo�Ē������o�R�œ����ɋA�낤�Ƃ������ƂɂȂ����B�����̗\������Ȃ蒴���������O�����̃h���C�u�ɂȂ肻�����������A���ɂ�������̂��Ƃ䂦�A�������ċC�ɂ��Ȃ�Ȃ������B
�@ �V�ς�菬��̂�����������ؑ]�H��쉺���A�ޗLj�h�ɓ������̂͌ߌ�Z�����������B���x�ƂȂ��ؑ]�H��K�˂����Ƃ̂��鎄�͂Ƃ������A���s�̂x����ɂƂ��Ă͖ؑ]�H�̗��͏��߂Ă̂��Ƃ������B������A�ˑR���ꂽ��O�̌��i�ɁA�ޏ����A���������ʎ����Łu�܂�Ń^�C���X���b�v�����݂����c�c�v�ƙꂢ���͓̂��R�̂��Ƃ������B
�@ �V�[�Y���I�t�Ȃ̂ɂ��킦�A���ɏ��ł̐[�܂鎞���Ƃ����āA�����̏h�꒬�̎p���̂܂܂Ɍ���A�˂�ƁX�́A�F���łɌ˒�����I���A�Ђ�����Â܂肩�����Ă����B�ߌ�Z���Ƃ����A������Ƃ������Ȃ�܂��ǂ��ł����Ȃ�̉���������̂����ʂȂ̂����A���X�����͂��ނ��̓ޗLj�h�̊X���݂ɐl�e�͂܂�������������Ȃ������B�����Ă��̂����ɁA�������ԉƁX�̌���ɓ_�X�Ɠ���Õ��Șa������p���̖����肪�A��������ق̂₩�ɏƂ炵�o���Ă����B���X����召�̘H�n�݂͂Ȑ�ŕ����ł߂��Ă������A���������̉ƁX�̊i�q�˂���R���������̐�ʂɒg�����A���������炩���f���Ă킽���Ă����B
�@ �H��ɐl�e���܂������Ȃ��ɂ�������炸�A����������Ɨ₦����ł���ɂ�������炸�A����قǂɐl�̉�����̊��������Ԃ����݂���Ƃ������Ƃ͕s�v�c�Ȃ��Ƃł������B�G���Ƒ����Ɉ�ꂩ�����Ă͂��邪�A�ǂ����r���������Ƃ������̂̕Y�����݂̓s��̋�ԂƂ���͑ɂɈʒu������̂̂悤�Ɏv��ꂽ�B
�@ �Ԃ���~��A���炭�̊ԁA��X�͐�݂��߂Ȃ���ޗLj�̊X���݂����������B�����āA�X�H����x���p�ɐ܂�Ȃ��鋌�h�꒬�ɓ��L�ȁu���̒ҁv�̂�������߂�������A�u�e�`�v�Ƃ����̂Ȃ���̋������ɗN�����鐴���ōA���������肵�Ȃ���A�����U����y���B
�@ ���܂������Œm���鑊�͉��̑O�ɂ́A�ƂĂ����g�̂����_���}���ЂƂۂ�Ɨ����Ă����B���̑傫�ȃ^�h���̖ڂ́A�܂�ʼn����������o���������ɁA�����Ƃ���������߂Ă����B�ޗLj�h�̊X���݂̂Ȃ��قǂɂ���܋�����X���ނ����Ă͂������A�X�̉��̂ق�����͂Ȃ�����̖��邢�����R��Ă��Ă����B
�@ ���Ԃ܂��u���Ă���Ǝv���̂����A�ȑO���̓X�ł͂Ȃ��Ȃ����������u�����Ă����B��������Ǝ���h���ĉ��₩�Ɏd�グ��ꂽ���U��Ō`�̂悢�Ɗy�̔��u���ŁA���̎��h�����ɂ��A���̂�������ԁA�A���A��Ȃǂ̋Ȑ��͗l�̑������قǂ����Ă���B�܌قǂ��Z�b�g�ɂȂ������̂��邵�A����̃o������̂��̂�����A�l�i�̂ق����荠�������B���͂悭���̓Ɗy�̔��u�������y�Y�Ƃ��ăZ�b�g�Ŕ������߁A�F�l��m�l�ɐi�悵�����̂ł���B
�@ ���̓Ɗy�̔��u�����Ȃɂ��������Ă���̂́A�P�ɕ��ς��Ȕ��u���Ƃ��Ďg�������łȂ��A�قǂ悢�d�ʊ��������āA�e�[�u���̏�ȂǂŎ��ɂ悭���̂��B���ہA���߂Ėڂɂ���l�ɂ��̔��u�����������n������A�F���F�A����͓Ɗy���Ǝv���ɈႢ�Ȃ��B���u�����ƍl����l�Ȃǂ܂����Ȃ����낤�B�H�O��H��ɁA�e�[�u�����͂މƑ��⒇�ԓ��m�œƊy����ׂ̗]�����y���ނ��Ƃ����Ăł���̂��B���̎���̒N�̒��z�ɂ����̂��͒m��Ȃ����A�V�ѐS�L���Ȃ��Ƃ��̂����Ȃ��B
�@ �ޗLj�h�̓쑤�ɂ́A�\���{�Ɨ����{�Ƃ̕����E�̈ꕔ���Ȃ��W������Z���[�g���̒��������ނ��Ă���B���܂Ȃ獑���\�㍆�`���ɒ����g���l������Ɠ�Ȃ����Α��̖����ɏo�邱�Ƃ��ł��邪�A�̂̐l�X�͂��̒�������k���ʼnz���Ă����B���R�����o�č]�˂Ɍ������喼�s��Ȃǂ��ނ�̓�����H�����̂��B���Ȃ蓹���g������A�Ԃ��ƒʂ��悤�ɂȂ��Ă��邪�A���܂��������ʂɒʂ��鋌���̖ʉe�͎c���Ă���̂ŁA�����̂���l�͖K�˂Ă݂�̂��悢���낤�B
�@ �ݔ��ȂǂȂ��̂́A���̒����������ɂ����푢��ɂ͈��̕��Ƒ̐����~����Ă����炵���B�ďꎼ�x�̍����Ȃ������{�m�z�Ȃǒ������ȓ�̏W���ł́A�ؒn�ǂ��ؔ��̂܂܂̎���ތ��^���肪�����Ȃ��A�����͒������Ȗk�̓ޗLj�╽��Ƃ������W���ɉ^��āA�����Ŏ��h��̎d�グ��Ƃ��Ȃ���Ă����B���h��̍�Ƃɂ͗���Ŋ��������C�ۏ������������Ȃ��B���ЂƂz���������Ȃ̂ɁA�ޗLj�h�╽��h�͖����h�Ȃǂɂ���ׂĂ����Ǝ��x���Ⴂ����A���h���d�オ��������̕ۑ��ɂ͊i�D�̓y�n���������̂��B
�@�u�܂��������߂��O���́@�ь�̂��ƂɌ������Ƃ��@�O�ɂ�������ԋ��́@�Ԃ��邫�݂Ǝv�Ђ���v�Ƃ����A���蓡���̗L���Ȏ��u�����v�ɏo�Ă��邨�䂤����̍����Ă����ԋ����A�×����낭���Ŗ����������Ō��^�ƂȂ���̂������A�ޗLj�ł���Ɏ���h�����葕�����قǂ������肵�Ďd�グ��ꂽ���̂������悤�ł���B
�@ �ޗLj�h�̎U����I���Ԃɖ߂�����X�́A�����g���l�����������ɑ��蔲���A�ؑ]�X�������āA�n�ĕ��ʂɌ������ē쉺�����B�ڎw�����Ă͓����̏����̐l�A���䂤����̉ł������e�{�w�̂���h�꒬�A�����Ă��܂ЂƂ̔n�Ă̂ق��͓��蓡�����̐l�Ƃ��䂤����Ƃ��Ƃ��ɐ��܂������h�꒬�ɂق��Ȃ�Ȃ������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2002�N2��20��
���ďh����n�ďh��
�@ �Y���`���̎c��㏼���Q�o�m���̒��c����ɂ������肵�Ă������߁A���ďh�ɒ������̂͌ߌ�㎞�����������B���ẮA�ޗLj�A�n�āi�܂��߁j�Ȃǂƕ���ł��܂Ȃ��̓��̏h�꒬�̖ʉe�𗯂߂�W���Ƃ��Ė������B�������A�����O�̋��h�꒬�̂Ȃ��ŁA�����̊X���݂̍\���╵�͋C�Ƃ��������̂������Ƃ��悭�c���Ă��邪���̍��ďh�ł���B
�@ ���Ȃ������R���̏h�꒬�Ƃ͂����Ă��A���ďh�͂����Ɠ�̒��Ð�߂��Ɉʒu���邩��A�ޗLj�Ȃǂɂ���ׂ�ΐ�͏��Ȃ��B���̖���W�����ӂ̘H��ɐϐ�炵�����̂͂܂�������������Ȃ������B�X��������������ɂ́A���̉_�̂����������r��A���̉_�̐�Ԃ���㌷�������炩���������������X����̂��������B�_�Ԃ��猎������ꗎ���͂��߂�Ƌ}�ɊX���݂͖��邳�𑝂��ĕ����オ��A�t�ɉ_�ɂ���Č������������ƊX���݂͍ĂшÂ�����ŁA�ƁX�̌���ɓ_�X�Ɠ��鉮������̊p���̂ق̂₩�ȋP�������̑��݂̓x�𑝂����B���̖��ẪR���g���X�g�̏����o���s�v�c�ȏ�i�́A�܂��ɂ��̏h�꒬�̖�Ȃ�ł͂̂��̂������B
�@ �������A���X�����͂���Ō���A�˂�ƁX�͂ǂ�����������ƌ˒�������ĐÂ܂肩����A�������疾����̘R��Ă���ƂȂǂ͂قƂ�nj�������Ȃ������B�����āA��ʂ������Ă���炵���e�Ƃ̎l�p���a�����茬���������A���̏h�꒬�ɏZ�ސl�X�̉��������Â������ԐړI�ɓ`���Ă����B���������^�~�̂���Ȏ����ɍ��Ă̊X��������Ƃ������Ƃ̂ق����q��ł͂Ȃ��̂��������A��O���킵���s�����Ƃ邪�䂦�ɂ����ڂɂ��邱�Ƃ̂ł��銴���I�ȏ�i�Ƃ������̂��܂����݂��Ă���B���̖���Ă̊X���݂Ɍ������̂͂܂��ɂ��̂悤�Ȍ��i�ł������ƌ����Ă悢�B
�@ ���݂͉��J���y�����قƂȂ��Ă��鋌�e�{�w��̂Ȃ���̌��̒҂̂��邠����𒆐S�ɁA�ЂƂ��̂Ȃ��X���݂��������������܂���Ă���ƁA�ˑR�����̂ق��ŃJ�`�J�`�J�`�Ɣ��q��ł��炵�Ȃ���u�̗p�S�I�v�Ƌ��Ԗ���̐����������Ă����B�̂Ȃ獑���̂�����Ƃ���Ō��邱�Ƃ̂ł������i�����A���܂ł͂���Ȗ���̎p�Ȃǂ߂����ɖڂɂ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ����B��X�͂����납�珙�X�ɋ߂Â��Ă��銣�������q�̋����Ɓu�̗p�S�I�v�Ƌ��Ԑ��Ƃ����������z���Ŏ��ɂ��Ȃ���A�傫�Ȍ���A�˂ė������ԓ�K���Ă̗��U�▯�Ƃ̎��ˁi���Ƃ݂ǁj��A�q�i�q�i��������j�A�����̌Õ��ȊŔȂǂ����Ă܂�����B
�@ �ςȎ����Ɍ�����ʓ�l�A�ꂪ�����Ă���̂��A�����납��߂Â��Ă������̒j���ǂ����������͒m��Ȃ����A����̂ق����玩�R�Ȓ��q�Łu�����́I�v�Ɛ����|���Ă��Ă��ꂽ�Ƃ�����݂�ƁA�Ƃ��ɉ������҂������Ƃ��v��Ȃ������̂ł��낤�B��X��ǂ��z��������̒j�́u�̗p�S�I�v�̐��Ɣ��q�̉������X�ɉ��������Ă����̂��Ȃ���A���͕s�v�c�Ȋ��S���o���Ă����B���������̂悤�ȏh�꒬�̈�p�ʼnЂ����������肵����A����ڂ���ƁX�͂����܂��ޏĂ��Ă��܂��ɈႢ�Ȃ��B����Ȏ��Ԃ�h�����߂ɂ��A�̂Ȃ���̖���̑��݂͂���Ȃ�ɈӖ����邱�ƂȂ̂��낤�B
�@ �����̏����̐l�A���䂤����̉ł������e�{�w�̌����́A��s�O�w����ō��ďh�̖��Ƃ̂Ȃ��ł��ЂƂ���傫���B����ȉB��������B���K�i�Ȃǂ��������肵�č\���I�ɂ���ϖʔ��������ł���B���݂͎����قɂȂ��Ă��邱�̌����̓����ɂ́A���Ắu�w��{���{�v�ƌ����A��{�f���̂��������ő�����Ƃ����قǂɋM�d�Ȟw�ނ�����ǁA�d��˂Ȃǂɂӂ�ɗp�����Ă���B�܂��A���蓡�������̖��𐬂����̂��ɂ��䂤����ɑ������Ƃ����u�����v�̎��̒��M�z�Ȃǂ������A�K�˂�҂̖ڂ��y���܂��Ă�����Ă���B
�@ ��ϕ��ς��Ŗʔ����̂́A�����V�c�s�K�̍ۓ��ʂɐ݂���ꂽ�Ƃ����e�[�u���ƃg�C�����낤�B�������̍��Ĉ�тɂ͗m���e�[�u����m���֎q�Ȃǂ����L����ƂȂǂȂ������̂ŁA�n���̑�H���ԐړI�ɕ����y�������Ƃɋ}篑g�ݗ��Ď��̗m��Ɨm�֎q�Ƃ������炦���炵���B�����V�c�͗瑕�p�R���ɒ��C�p�̂܂܂ł��̉����ɏオ��A�ɂ킩�d���Ẵe�[�u���ɂ�������̂��Ƃ����B
�@ ��������ʂɑ���ꂽ�Ƃ����g�C���̂ق��́A�V�c�̑؍ݎ��Ԃ��Z���������߁A���ۂɂ͎g�p����Ȃ������悤���B���̂��߁A���̏��~���̃g�C���͗R������u�g�킸�̃g�C���v�Ƃ��Č��݂܂ő�ɕۑ�����A���K�҂Ɍ��J����Ă���B�����L���Ƃ����ǂ��A�g�C�����ό��̖ڋʂ̂ЂƂɂȂ��Ă���̂́A���̍��Ă̎����ق��炢�̂��̂ł��낤�B
�@ ���܂ЂƂʔ�������Ƃ��ċL���Ɏc���Ă���̂͂��̘e�{�w�ŗp�����Ă����Ƃ�������ȓS���̐C��ł���B�ӂ���͏�̌��ԂȂǂɋr�����[�����肰�Ȃ���������ŗ��Ēu���A��[���̑�ɘX�C���Ďg���̂����A�����Ƃ����Ƃ����̐C������������t���܂ɂ��Ď��ƁA�����܂�����ɑ��ς�肷��Ƃ����V�����m�Ȃ̂��B�C��r���̍|�S����[�͉s���������܂���đ��̕��̂悤�ɂȂ��Ă���A���h���̏�Ԃ̂Ƃ����҂��ɕs�ӂ�˂��ꂽ�悤�ȏꍇ�ɂ́A�C����ĉ���ł���悤�ɂȂ��Ă����炵���B
�@ �������A��x���̂��Ƃ䂦�����ق̂Ȃ������w���邱�Ƃ͂��Ȃ�Ȃ������̂ŁA�x����ɂ���Ȏ����ٓ����̗l�q�Ȃǂ�b�����������肵�Ȃ���������ƎԂɖ߂����B�����čŌ�̒T�K�n�ł���n�ďh�ڎw���đ��肾�����B
�@ ���Ă����Ƃɂ���ƁA�����H�����o�ĈɓߒJ���ʂɌ������������������o��A��������E�ɕ��Ĕn�ē����ʂւƑ����R���ɓ������B���ĂƔn�Ă��Ȃ������R���͎��R�V�����Ƃ��Č��݂��f���I�ɕۑ��ێ�����Ă��邪�A�ԓ��̌��ݐ����Ȃǂ̂��߂�������l�ς�肵�A�̓��̕���͂��Ȃ莸���Ă��܂��Ă���B
�@ ���Ă͈�Ԑ��̃_�[�g�������ԓ��́A���܂ł͂�������g���ܑ�����A���s�җp�̋����R���Ɖ��x���������Ȃ���n�ē��ւƂ̂тĂ���B���Ɍ������ĎԂ̍��x���オ��ɂ�A���H�̗��e�₻��ɑ����R�̎Ζʂ̐ϐႪ�����Ă����B�������A���̐ϐ�́A���肩��̌����𗁂тĎ���ɂ��̔��X�Ƃ����P�������߂Ă������B���������͐���オ��A�����̋�Ɉʒu���錎��\���قǂ̂ӂ����炵�������̉e���A�����قǂɖ��邭������ῂ��������B
�@ �Ό��Ԃ��㑱�Ԃ��܂������Ȃ������̂ŁA�����ɎԂ̃��C�g�����ׂď����A��������Ɛᖾ�肾���𗊂�ɑ����Ă݂��B���ӂɓ��H����X���͂܂������Ȃ��A���Ƃ��F������������A�����ʂ莩�R���݂̂ɂ���ԑ��s�Ƃ����킯���������A�Ȃ�Ƃ����ꂪ���K���̂��̂Ȃ̂������B�̂�т�Ƒ��邩����A�^�]�ɂ͉��̎x����������Ȃ������B����ǂ��납�A�ǂ����_��I�ɂ����������錎���Ɛᖾ��݂̂�����̎R�H�̗��́A���̂����Ȃ��ґ�ł���悤�ɂ����v���ĂȂ�Ȃ������B
�@ ���炭��������đ����Ă���ƁA�����\�����̗ΐF�����������ɖڂɂ�����͂��߂��B�ʏ�Ȃ�܂������C�ɂȂ�Ȃ��قǂ̔����Ȃ̂����A�s�v�c�Ȃ��̂ł��̃O���[���̋P�����ӊO�Ȃقǂ�ῂ�����������̂��B���C�g�ނ͑S�������Ă���̂����A���̎����\���������̓G���W�����Ȃ��Ə����Ă���Ȃ��B��ނȂ��A�����\�����̕\�ʂɎ������킹�̖{�����Ԃ��Č����Ղ�ƁA����܂ł̈�a������������Ď��Ɏ��R�ȕ��͋C�ɂȂ����B
�@ �Ⴆ�����Ƃ��������Ɣ��X�Ƃ����ᖾ��ɐS�g�̍C���߂���悤�Ȏv���œ����z����ƁA�قǂȂ��n�ďh�̍�㑤�����ɒ������B�n�ďh�̏W���͐Ώ�̕~���ꂽ�}��̊X�������ɔ��B���Ă���B�����g�͉ߋ����x�����̏h�꒬����������Ƃ�����̂ŁA�x�������~�낵�A�≺���̓����ɎԂ��܂킵�Ă����Ŕޏ���҂��Ƃɂ����B
�@ �≺���̔n�ē����ɒ����ƁA�傫�����X�Ƃ����b�ߎR�̎p����������̂Ȃ��ɕ�����Ō������B���蓡���̐��n�Ƃ��Ēm���邱�̔n�ďh�́A�������N�ɑ�ɑ����A���̎��ɋ��\�̂قƂ�ǂ��Ď����Ă��܂����B�����猻�݂̖��Ƃ̌����͂̂��Ɍ��Ă�ꂽ���̂ł���B�����̐��Ƃ̂��������{�w�Վ��ӂ͌��ݓ��蓡���L�O�قƂȂ��Ă���A�����䂩��̕i�X������������Ă���B���̂ق��ɂ��Ɣn�������فA�n�ďh�ꋽ�y�فA�����������قȂǂ������āA�����Ɋւ��鎑���ɂ͎������Ȃ��B�����L�O�ً߂��̉i�����ɂ͓������g�̕�̂ق��A����u�閾���O�v�̎�l���R�����̃��f���ɂȂ��������̕��A���萳���̕�Ȃǂ�����B
�@ �x���Ȃ��Ȃ��~��Ă��Ȃ��̂ŁA��������Ώ�̍⓹���������������Ă݂��B�����䂩��̒n�ł�����A�܂��l�X�ȘV�܂�傫�ȏh������������ł��邱�Ƃ������āA���ԂȂ�O�̋��h�꒬�̂Ȃ��ł͂��̔n�ďh�̓��킢�̓x�������Ƃ��傫���B�����A���Ԃ����Ԃ������̂ł������ɐl�e�͌�������Ȃ������B�����Ă��̂����ɁA�}�ȍ⓹�̗��e�𗬂ꂭ����p���H�̐������A��̊X���݂ɂЂƂ��퍂�������L����킽���Ă����B
�@ �R�ԂɈʒu���鋌�h�꒬�ɋ��ʂȓ����́A�L���Ȑ��Ɍb�܂�Ă��āA����A�˂�ƁX�̑O�̑��a�������݂Ȃ�����Ă��邱�Ƃ��낤�B�����ɂ����ẮA���̐��͐����p���Ƃ��ĐH�ނ̉���ߗނ̐���ȂǂɎg���Ă����B���Ă̗p���H�̉ʂ����Ă��������Ȃǂ����Y�ꋎ���ċv�������A����ł��A�Â��W����K�˂��܂Ȃǂɂ��̖��c��ڂɂ����肷��ƁA �Ȃ��ق��Ƃ����C���ɂȂ�B������������A�c�����A���Ɛ[���ւ���Ĉ�����������̏���ȑz���ł͂���̂�������Ȃ����c�c�B
�@ �K�i��ɗ������Ԗ��Ƃ��ꌬ�ꌬ���������ɔ`�����݂Ȃ���⓹���~��Ă���x����̎p���悤�₭�����A�̂�т�Ƃ������̕��s�y�[�X�ɕt�������Ȃ���ԂւƖ߂����B�����̗\��ɂ͂܂������Ȃ��A���������ԊO��̋��h�꒬�T�K�ł��������A�ޏ��ɂƂ��Ă͖]�O�̋M�d�ȑ̌��ł������悤���B
�@�u���܂��܂ł����ǁA��x���ɖؑ]�H��K�˂Ă������Ă悩������������܂���ˁB���̖�̕��i�����Ă������A�h�꒬������Ă��Ă��悯���Ȃ��̂��ڂɂ͂���Ȃ�����A�������Ĉ�ۓI�Ɏv���āc�c�v�Ƃ����x����̌��t�ɂ́A���̓��ޏ��������������̂��ׂĂ����߂��Ă��銴���������B
�@ �Ăуn���h��������n�ďh�����Ƃɂ���ƁA���͈�H�����ڎw���đ��肾�����B���Ð삩�璆�����ɏオ��b�߃g���l�����������ɋ삯������ƁA�E�莋�E�����ς��ɍL��ȈɓߒJ�̉e�������яオ�����B�傫�����ɌX�������̌������̒J���ق̐��Ƃ炵�o���Ă���B�ɓߒJ�̌������ō��X�Ƃ����e��A�˂��A���v�X�A����A�Ő��̂����������⎇�F�ɋP�����鍶��̒����A���v�X�A����A�בR�ƍ\���ĂЂ����璾�ق�����肾�����B�r���ł�����Ƃ��薰�C�������Ă�������ǁA����ł��Ȃ�Ƃ����̂܂ܒ������𑖂�ʂ��A�����̎d���ɍ��x���Ȃ����炢�̎����܂łɂ͓����ɖ߂蒅�����B�ނ��ߑO�뎞�͂Ƃ����ɉ߂��Ă��܂��Ă����̂Ō����ȈӖ��ł̓��A��ł͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂������A����s���セ��͂�ނ����Ȃ����Ƃ������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2002�N2��27��
�L�O�p�[�e�B�G��
�@ �挎���{�̂��ƁA������蒬�̌o�c�A�r���E�S�[���f�����[���Ŗ����H�w�������̑n���O�\���N�L�O�p�[�e�B���Â��ꂽ�B�����H�w�������́A���݂ł͕����Ȋw�Ȃɓ������ꂽ���Ȋw�Z�p���ƊW�̐[�����c�@�l�ŁA��Ƃ��ĉȊw�Z�p�̈�̃v���W�F�N�g����Ƃ��鐭�{�n�V���N�^���N�̂ЂƂł���B�F���J�����ƒc�֘A�̎d���Ȃǂ��͂��߂Ƃ�����I�v���W�F�N�g�ɂ����Ă��D�ꂽ�Ɛт������Ă���B
�@ ���������Ԃ�Ɛ̂̂��ƂɂȂ邯��ǁA�����H�w��������Ẩ�ɏ������\�ꐢ�I�̏��Љ�̓W�]�ɂ��Ă̌��������߂�ꂽ��A���������P���̌����`�[������h�s�֘A�Z�p�̌���⏫���̗\���A����ɂ͖����̋���ɂ�����R���s���[�^�Z�p�̖����Ȃǂɂ��ĉ��x����������肵�����Ƃ��������B����Ȃ킯�ŁA���܂ł͂h�s���s��W�Ԃ������Ă��鎄�̂Ƃ���ւ����ҏ�������ł����̂ł���B
�@ �t���[�����X�ɓ]���Ă���́A�w�E���͂��߂Ƃ��邱�̎�̉�̏�Ɋ���o�����Ƃ͂قƂ�ǂȂ��Ȃ��Ă��܂��Ă���̂ŁA���R�A�o�Ȃ��悤���ǂ����Ɩ����͂����B�����A���܂��܋߂��܂ŏo�����p�������������A�������������Ă��ꂽ��C�����������܂ł͓��������̏����ɏA�C���Ă��邱�ƁA�����`�[���̈�����������������̂���C�������ɏ��i�A���݂ł�����[���̂��Ƃ肪���邱�ƂȂǂ��������̂ŁA�Ƃ��������ɑ����^��ł݂悤�Ƃ����C�ɂȂ����B
�@ �Ȋw�Z�p�̔��W�ɂ͂��͂≽�̖��ɂ������ʎ��Ȃǂ��o�Ȃ��Ă��A�Q���҂̖ڏ��ɂȂ����ł���B�����A���̕Ћ��ɐw����ĖفX�ƌ�y���ɂ�����Ă���Ԃ�ɂ͖��f��������܂��B�܂��A�Ⴂ�����҂�Z�p�҂Ȃǂ��o�Ȃ��Ă�����A�ނ炩��ŐV�Z�p�Ȃǂɂ��Ėʔ����b�̂ЂƂ�ӂ��͕������Ƃ��ł��邩������Ȃ����A���̒��̓��������Ă��������炢�͂킩�邾�낤�B�����Ɍ����A�܂��A����Ȏv���������Ă̎Q���ł͂������B
�@ �C�O�ł̌����҂̃p�[�e�B�̂悤�ɃW�[���Y�p�ȂǂŋC�y�Ɋ���o����悢�̂����A���̍��ł͎��̂悤�ȍ̐l�Ԃ�����Ȋi�D�ŏo�|���čs������A��t�ő�����O������H�炢���˂Ȃ��B�܂��ďꏊ���o�c�A�r���Ƃ����ẮA���̎�t�ɒH�蒅���O�Ƀr�������̃K�[�h�}���Ɍ������`�F�b�N����Ă��܂������ł���B�悵��Ή��ɓ��邱�Ƃ��ł����Ƃ��Ă��A�o�Ȃ̏������甒����ł݂���̂��������낤�B������������A����͂���Řb�̎�ɂ͂Ȃ�̂�������Ȃ����A�����܂ł��Đ��̐����ɋt�炤�C�ɂ͂������ɂȂ�Ȃ������B�����ŁA�v�X�Ƀl�N�^�C����߁A�X�[�c�ƃR�[�g��g�ɂ܂Ƃ��ĉ��ւƏo�������Ƃɂ����B�u�n�q�ɂ��ߏցv�A����A�u�t���[���C�^�[�ɂ��ߏցv�ł���B
�@ ���ۂɉ��ɗՂ�ł݂�ƁA�����Ȋw�Ȃ��͂��߂Ƃ��鏔�����̊��������A�m�s�s�h�R���В��ȉ��̑��Ƃ��[�Z�p��L��������Ƃ̊����A�A�����Ăs���j�傻�̑��̗L����w���������ȂǁA��Îґ������ւ̃p�[�e�B�ƒf���Ă���ɂ��Ă��B�X���郁���o�[�̏W�܂�ł������B�����ȂƂ���A���܂�Љ�̃S�~�ɂ����������Ȃǂ́A�܂�ŏ�Ⴂ�̂Ƃ���ւ���Ă����悤�ȋC�����ĂȂ�Ȃ������B
�@ �p�[�e�B�o�Ȏ҂͂��炩���ߗp�ӂ��ꂽ�����@�ւ⏊����Ж�����̃l�[���v���[�g��n����A��������ɂ��Ă������A������܂͂ǂ��ɂ��������Ă��Ȃ����̃v���[�g�͂������O���L���Ă��邾���������B���ɂ�����ق疼�O�����̐l������ꂽ���A���M�ɖ����������̐g�U��������͂̐l�X�̋C�̌����Ԃ肩��@����ƁA���������n�a����������ނ��������Ȍ������҂̕��X�ł͂Ȃ����Ǝv��ꂽ�B
�@ ���t�ɂ����͂�����Ƃ͏o����Ă��Ȃ��������̂́A�p�[�e�B���n�܂�܂�����A����T�����̂��������ł́A�u�����������̍��̂��̕����w�����Ă����̂ł��v�Ƃ��u���Ȃǂ͂��̋ƊE�̗��̗��܂Œm��s�����Ă��܂��v�Ƃ��������ӂ��ɂ���������v�킹�Ԃ�ȉ�b�����킳��Ă����B�p�[�e�B���n�܂��Ă�����A�݂��Ɋ猩�m��ł���炵�������̐l�X�̊ԂŌJ��Ԃ��J��Ԃ��݂��̌����Ԃ���m�F�������悤�Ȉ��A�̌������Ȃ���Ă����B
�@ �ʎ��̂��関���H�w�������̂���l�͗v�l�ւ̑Ή���p�[�e�B�̉^�c�ɑ��Z���ɂ߂Ă����悤�ŁA�Ō�܂Ŋԋ߂ɂ��̎p�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B���ҋq�͓�S���O��̂悤���������A���̎�̐��E�𗣂�ċv�������ɂ͒m�l�͊F���������̂ŁA�͂��߂̂����͉��̕Ћ��ɗ����ăp�[�e�B�̐���s����Ƃ肶���ƌ��Ă����B�����̋L����Ă��Ȃ����̃l�[���v���[�g�Ɏ��X���͂̎������������̂������͂������A���̂悤�Ȏ����ɑ��Ă͂Ђ����璾�ق����ʂ������Ȃ������B���������҂ł��邩�𖾂��ɂ��悤�ɂ��A�������������ɂ��ׂ����̂����ЂƂ������킹�Ă����Ȃ����炾�����B
�@ �����Ƃ��A���������₩�ȏꏊ�ɓƂ�ł���Ƃ����̂�����Ȃ�ɗ��_�͂�����̂��B���Ƃ��A���͂̐l�X�ɋC���˂Ȃ��A�p�ӂ��ꂽ���ݕ��◿���������̃y�[�X�ő����ɏܖ��ł��邱�ƂȂǂ��B�܂��A�Љ�̗v�l�Ɩڂ����l���̐l����A������抪���l�X�̐l�Ԗ͗l�Ƃ����ɉQ�������X�̎v�f�ȂǂɊώ@�ł����������B���̂悤�ȕ������̒[����ɂƂ��Ă���͕s���Ȃ��Ƃ�����A��ςɂ��肪�����B
�@ ���������̋@������Ƃ͂Ȃ��Ǝv���Ȃ����A�܂��͘a�H����m�H����ɂ͒��܂ł̌�y�����ӂ�ɕ��ԃe�[�u���ɑ����^�сA���ꂱ��Ǝ��L���Ă��̔����̂قǂ�S�䂭�܂Ŋy���܂��Ă��炤���Ƃɂ����B�����āA���̂����ۂ��ŁA���肰�Ȃ��A���������Ӑ[���A����Ƃ��ڂ����l���₻�̎��ӂ̐l�X�̈ꋓ�ꓮ�������A�R��Ă����b�ɂ����Ǝ����X�����B
�@ �ނ��A����͂���ł����Ԃ�Ɗy�����܂������̎��n���������̂����A���ɂ͂ЂƂ����ǂ����Ă��C�ɂȂ��ĂȂ�Ȃ����Ƃ��������B���{�̖����̈�[��S���d�v�ȉȊw�Z�p�n�V���N�^���N�̋L�O�p�[�e�B���Ƃ����̂ɁA������w�����ׂ���\��A�O�\��̎��̎p���܂������ƌ����Ă悢�قnj�������Ȃ������̂��B�o�Ȃ���O�͎Ⴂ�����҂�Z�p�҂���ʔ����b�Ȃǂ���Ǝv���Ă������̂����A���̓_�ɂ��Ă͂܂�Ŋ��҂͂��ꂾ�����B�܂��A������ɂ����鏗���̎Љ�i�o���ڊo��������Ȃ̂ɁA�̐S�̏����̎p���킸���l�A�ܖ��ɂ����Ȃ��Ƃ����̂������Ԃ�ƕs���R�Ɋ�����ꂽ�B
�@ �����̂��Ƃ�I�ɏグ�Ă���Ȃ��Ƃ��q�ׂ�̂��ǂ����Ƃ͎v���̂����A�Q���҂̂قƂ�ǂ͑����ȍ���҂ŁA�ߋ��ɂ����Č����ȋƐт��グ���l�X�ł͂���ɂ��Ă��A�݂��ɉ䂪���̖����������ɂ͂��͂�g�E�������߂��Ă���ƌ��킴������Ȃ������B�������A�\�Z����̃X�y�[�X�̊W���珵�ҎҐ����i��K�v���������̂ɂ��킦�A�ߋ��O�\�N�Ԃɂ����Ă��̃V���N�^���N�̔��W�Ɋ�^�����n�a��O���W�҂�N�㏇�ɌĂԂƂȂ�ƁA����Ғ��S�ɂȂ邱�Ƃ͔������Ȃ������̂ł��낤�B��Î҂̈��A�̒��Ɂu���ւ̃p�[�e�B�v���Ƃ����ꌾ�������킦��ꂽ�̂����̂悤�Ȏ������������ɈႢ�Ȃ��B
�@ �����A���Ƃ������ł����Ă��A���̂悤�Ȗ����̃v���W�F�N�g�Ɋւ��p�[�e�B�ɂ́A�����Ƃ܂ł͂����Ȃ��Ă��A���߂ē�O�����炢�͎����S���Ⴂ����̊����̂悢�l�ނ������Ăق������̂ł���B�������A�����̏o�ȎҐ��������Ƃ����Ƒ��₳�Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B�䂪���ɂ́A�L�\�Ȏ�茤���҂�Z�p�҂͂ނ��A�Ȋw�Z�p�����̕���ŗD�ꂽ�Ɛт������Ă��鏗���X�y�V�����X�g�������Ȃ��Ȃ��B�Ⴂ����̏ꍇ�Ȃǂ́A�Ƃ��ɋƐтȂǂȂ��Ă����ݓI�\�͂�������ꂾ���ŏ\�����Ǝv���B
�@ ����łȂ��Ă��A�䂪���ɂ����ẮA������w�����Ⴂ����̐l�ނ��A�w�E�̌��ЂƌĂ�錤���҂�A���������A���Ƃ̊����Ƃ������l�X�ƒ��ڂɑΘb������A�K�v�ɉ����Ĕނ�Ɏ��ȃA�s�[���������肷�邱�Ƃ̂ł���@��͂���߂Ă����Ȃ��B��啪�삪�݂��ɂ������ł�������肷��ƁA���̌X���͂��������傫�Ȃ��̂ƂȂ�B�\�ʓI�ɂ͂Ƃ������A���ۂɂ͋��ԑR�Ƃ�����吢�E�ɂ����Ēj���Ԃ̕ǂ�r�����Ȃ��傫���B
�@ ����̂悤�ȃp�[�e�B�̖����̂ЂƂ́A�Ɛт�n�ʁA�N��A���ʂȂǂ��ėl�X�Ȑl�X����̐l�ԂƂ��Ď��R�ɏo�����A�����Ȉӌ������Ȃǂ��o�āA�n���Ɣ��W�ɂȂ���V���ȊW��𗬂ނ��Ƃɂ���B�Ⴂ����͗D�ꂽ��l��������w�ԂƂ��낪�傫�����A�\�͂�������Α���̃��[�h��A�h�o�C�X�ɂ���Ď����̓����J���`�����X�ɂ��b�܂��B�t�ɁA���Ɍ����薼�������l�X�⌻�ݎw���I����ɂ���l�X�́A�Ⴂ����̎a�V�Ȕ��z�⊈�͂ɐG��A�Ƃ�����ƍd�������`�[���������Ȃ��̂�̎v�l���_��ɂ��A���ꂼ��̐�啪��ɂ����鎩���̖��������[�߂邱�Ƃ��ł���B
�@ ��N�A��͂薢���H�w��������Â̋L�O�u�����t�H�[�������Â���A�����̓W�]�ɂ��ĂȂ��Ȃ��ʔ����������\�Ȃǂ������Ȃ�ꂽ���A��͂�Q���҂̕��ϔN��͑����ɍ��������B���̎��ɂ͎��⏗���̎Q���҂����Ȃ�̐�����ꂽ���A����ł������͂����Ԃ�ƒႩ�����B���҂��������Q����U������\��̃X�y�V�����X�g���u�Ȃ���Ⴂ�ȏ��ɗ����݂����ł��ˁv�ƙꂢ���̂���ۓI�������B���̎����L�O�u���I����Ƀp�[�e�B���Â��ꂽ���A���̂ق��̏o�Ȏ҂͂�͂�j���̍���҂��قƂ�ǂ������B
�@ �C�O�̂��̎�̉��p�[�e�B�[�ł́A�Q���҂̕�����g�Ȃ�Ȃǂɂ�����Ƃ������K���͂Ȃ��A�F�v���������̊i�D�ŏo�Ȃ��邩��A�������͎��R�ȕ��͋C�ɕ�܂��B����ȕ��͋C�̂Ȃ��ŘV��j�����C�y�ɏo�����A�ӌ�������������������ɂ����Ȃ��A��������V���ȓW�J�����܂�Ă���B�䂪���ł����̂悤�ȋ@�^�����܂�邱�Ƃ��]�܂����̂����A���ӎ��̂����ɉE�֏K���̎��ȋK���̓����������̂��Ƃł́A�N�������[�_�[�V�b�v���Ƃ��ē���I�ɂ��̂悤�ȏ����܂��悤�ɓ���������K�v������̂��낤�B
�@ ���������瑊�Ȍ������ɂ͂Ȃ�̂����A�����H�w���������Љ�S���w�I�A����ɂ͑g�D�_�I�Ȍ������ʂ�啝�Ɏ�����A�V��j���̃X�y�V�����X�g���������R舒B�Ɍ𗬂ł���l�X�ȏ��ݒ肷�邱�Ƃɐ��������Ƃ��A���������̑��݈Ӌ`������I�ɍ��܂�A���̍��̖����ɂ��傫�ȓW�]���J����̂��낤�B������������A����̃p�[�e�B�ɏo�Ȃ��Ă������X�̑������A���S�ł͂����ƎႢ����̐l�X�⏗���̎Q�����]�܂����Ǝv���Ă���ꂽ�̂ł͂Ȃ��낤���B
�@ ��Îґ��̎���͂킩��Ȃ��ł��Ȃ��������A�����̓��{�̔��W���ɂ݁A�D�ꂽ�������ʂ��グ�Ă��関���w���̃V���N�^���N�̃p�[�e�B�ł����������ɁA���I�ȈӖ����炵�Ă��A���܂������J���I�ȕ��͋C�����Ȃ���Ă��Ăق��������Ƃ����̂������Ȋ��z�������B�����Ƃ��A����ȓ��S�̎v���������܂Ő����ɏq�ׂ����Ă�������ƂȂ�ƁA����̍Â����Ȃǂւ̏��҂����҂���͖̂����Ƃ������̂ł͂��낤�B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2002�N3��20��
��ؖ��̖{���́H
�@ ���̂Ƃ��냁�f�B�A�E�͗�؏@�j���ŕ����������Ă���B����ł̏ؐl���₪�I����Ă�������c���ɂ܂��^�f�����X�ɕ��サ�A���Ǘ�؋c���͎����}���}�̂�ނȂ��Ɏ��������A���̖��Ɋւ��ẮA�ЂƂ�̓��{�l�Ƃ��čl����������Ƃ��낪���Ȃ��Ȃ��B��؋c���̜����܂����̍s�ׂ₻�̐����������B�̔w�i�ɐ��ޗl�X�ȍ����^�f�����邱�ƂȂ���A�����ȏ�Ɏ����C�ɂȂ��Ďd�����Ȃ��̂́A���̎�̖��̍���ɂ����X���{�l�̗ϗ��I�����̂��Ƃł���B
�@ �l�ԂƂ������̂́A���̊����͂Ƃ������Ƃ��āA�N�������ƍ��̗��ʂ�S���ɋ��������Đ����Ă���B������O���C�]�[���Ȃ���̂��̂ɐS�̑唼���ς˂Ȃ���A����R�̂��ƂƂ��Đ����Ă���l�Ȃǂ����邭�炢���B�Ƃ��ɉ䂪���Ȃǂɂ����ẮA�u���������킹�ۂށv�Ƃ������t�ɏے������悤�ɁA���������̗v�f�R�Ƃ��ē����ɕ��������Ƃ����̔����Ƃ���l���̏Ƃ�����A����ɂ͎Љ�ɘa�������炷�錍�ł�����Ƃ��l�����Ă����B
�@ �P�ƈ��Ƃ̓_�Ɋ�Â��A���E�̍��X�𔒍��ǂ��炩�ɐF�������čl����A�����J�哝�̂�̎咣�Ɉ�a�����o����̂́A��X���{�l�̐S�̂ǂ����ɁA�O���C�]�[��������Ȃ�ɍm�肵�A����F�����Ȃ炸��������̂��̂Ƃ͌��Ȃ��Ȃ��`�����Ȃ����Â��Ă��邩��Ȃ̂��낤�B�A�t�K�j�X�^���ɂ݂�悤�ȕ��G�Ȑ������Ȃǂɂ����ẮA���{�l�̂����̂悤�Ȏ����̓v���X�ɂ͂��炫������̂��낤���A��؏@�j���̂悤�ȏꍇ�ɂ́A���̎����͑傫���}�C�i�X�ɍ�p���Ă��܂��B
�@ ���̂悤�ȓ��{�I���_�y��̉��ɂ����ẮA�����Ƃ⊯���A��ƌo�c�҂Ȃǂ̐S�ɑ��H�������v�f�̍ی��Ȃ����B�𖢑R�ɖh���͓̂���B��X���{�l�ɂ́A���̗v�f�������Ԃ�Ə��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ă��A���̐�߂銄���͂Ȃ��傫���Ɖߑ�]�����A�����v�f�̐�߂镔���ɂ͂Ђ�����ڂ��ނ��Ă��Ă��܂��X�������邩�炾�B
�@ ����Ȃ킯������A�����ƂȂǂ̐S���ɏ����ُ푝�B���\�������^�����ȉ肪�����������Ă��A���̒i�K�ł��̉��E�ݎ���Ă��܂����Ƃ͂܂��ł������߂����Ȃ��B���肪����F�ɐ��܂肫��A�g�̒����獕�����⍕�������o���悤�ɂȂ��Ă͂��߂āA��X�͎��̏d�傳��F������̂��ƂɂȂ�̂����A���̎��͊��Ɏ�x��ɂȂ��Ă��āA���̐l���̎��ӂ��Љ�S�̂����Ȃ���ʈ��Q�����Ă��܂��Ă���B
�@ ��؋c���ɂ܂�鏔�X�̋^�f�����ܕ���Ă���ʂ肾�����Ƃ��āA���c�������̂悤�Ȗ��@����܂�Ȃ���ԂɎ���̂��A���̎Љ�͖��R�ɖh�����Ƃ��ł������낤���B�c�O�Ȃ��瓚���̓m�[�ł���B���������킸�A��X���{�����͂��̂悤�Ȏ��Ԃ𖢑R�ɖh�����@���ϗ��I�������ϗ��I������܂��������킹�Ă��Ȃ����A�ߋ��̗��j�ɂ����Ă��̂悤�Ȗ��ɑΏ�������H�I�ȃg���[�j���O�������Ƃ��Ȃ����炾�B
�@ ���܋N�����Ă����A�̎��Ԃ́A���Ƃ��Ă����Ȃ�A�u�Љ�v�Ƃ������̐��̓��ɐ������d�x�́u�����K���a�v�ɂق��Ȃ�Ȃ��B�����K���a����������ɂ͓K�x�ȉ^����ې����K�v�����A������Ɏ��Ă͂�����̂̂��̎��͖���ɂ����������v�U���^�����ɂ�������A���܂�ɓx�̋֒f�Ǐ�Ɋׂ��Ă��܂��Ă��邱�̎Љ�ɁA�^����ې��ɑς����邾���̗̑͂ƈӎu�̋������c����Ă���Ƃ͎v���Ȃ��B���ɂ́A���{�l�����{�l�łȂ��Ȃ����Ƃ��ɂ������̐����K���a�͊������Ȃ��悤�ɂ��������ĂȂ�Ȃ��̂��B
�@ ��؋c���̋Ɛт₻�̉��b�̑傫�����̂���n���Z���̐��͂��܂��Ȃ����Ȃ��Ȃ��B��؋c�����l�ɁA�^�}�c���̂قƂ�ǂ́A���x�̈Ⴂ��������A�n���I����ւ̘I���ȗ��v�U���������Ȃ����Ƃ�����̎���̔C���ƐM���Ă����B�����āA���ꂼ��̒n��̏Z�������͂�������肪�������́A���邢�͓��R�̂��̂Ƃ��Ď���Ă����B
�@ ���ꂼ��̒n��ɋ����ɗU�����ꂽ�Љ�{�������悭�z���ėL�v�Ȏ��Y�����݁A���̌��ʂƂ��ē������{�̈ꕔ��t���I�ȗ������o�����X�悭���S�̂ɗ������Ҍ�����Ă��邤���͂���ł��܂��悢�B�����A���Ԍn��j�����ʼn��̐��Y���ɂ��Ȃ���Ȃ����ʂŏX���Ȍ������Ƃ��S���e�n�ł����Ȃ��A�ی��Ȃ������������I���Ɣ�̈ꕔ������c���Ɋҗ�����悤�ȍ\���ɂȂ�ƁA���͂�ǂ�Ȏ肾�Ă������Ă��Ă��~���悤���Ȃ��B
�@ �n��Z���͌������ƂƂ������̖���̒��Ŋ��҂ɂȂ��Ă��܂��āA���R�̂悤�ɂ���Ȃ閃���v����������B�����ۂ��ŁA�u�n��Z���̂��߂Ɂv�Ƃ������t���I�E���Ԃ��ɏ����Ȃ���A�c�������̓��N�U�̐e���܂����ɑ�ʂ̖���A���Ȃ킿�������Ƃ̓������͂���A������I�݂ɂ�܂��Ď������₵�A�n��Z����U�����ăS�b�h�t�@�[�U�[�I�Ȓn�ʂƌ��͂��m�����Ă����B
�@ �ǂ�ȂɔY�I�Ŕ��I�Ȃ��̂ł͂����Ă��A�������Ƃ������炳���ƈꎞ�I�ɂ͂��̒n��͑����Ƃ������B�����A���̂悤�Ȑ��Y���������I���l���Ȃ��������Ƃ��S���e�n�ő�ʂɂ����Ȃ���悤�ɂȂ�ƁA���̍������Ȃ���{���Ƃ�Љ�ۏᐧ�x�A�ی����x�A��Ð��x�A�������琧�x�ȂǁA���X�̍s�����x��s���T�[�r�X�ɑ����ᰊ��y�Ԃ��ƂɂȂ�B�܂��A���I�����Ɍ��������Y���̌��オ�Ȃ���A���S�̂Ƃ��Ă̌o�ς͔敾���Љ�s���͑��傷��B���̌��ʁA�������Ƃňꎞ�I�ɏ���������̒n��Z���́A���̉��{���̕s���v��ʂ̂������Ŕ�邱�ƂɂȂ�̂����A���������ƂɁA�������ƒ��łɂȂ����l�X�͂��̂��Ƃ��Ȃ��Ȃ��������悤�Ƃ��Ȃ��B
�@ ���܂�u�Q���ȁv�Ƃł����̂����炽�߂��ق����悳�����ȍ��J���̂̊O���Ȃ����A����ɂ��Ă��A��؏@�j�c���͂ǂ����Ă���قǂɁA�O���������͂��߂Ƃ��鏔�����������ӂ̂܂܂ɑ��邱�Ƃ��ł����̂��낤�B��؋c���̜����ɋ߂��ԓx�Ɉ炿�̂悢�G���[�g�����������Č����Ȃ�ɂȂ����Ȃǂƕ��ꂽ�肵�Ă��邪�A�����g�͂���Ȃ��Ƃ����̂܂ܐM����C�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�吺�œ{��ꂽ���炢�ŁA�ւ荂����������������������������Ă��ƂȂ��������܂܂ɂȂ�Ȃǂ��肦�Ȃ����ƂɎv���邩�炾�B
�@ �k���̓y�K�⎞�̐A���p�c�̌��u���ŁA�O���Ȃ̉ے��⍲����؋c�����牣��R��̖\�s�����ƕ��Ă��邪�A�����܂ňُ�ȍs�����Ƃ����Ƃ��Ă�����̐g�͈��ׂ��Ƃ������Ȏ��M�͂��������ǂ����炫�����̂Ȃ̂��낤�B���R�A�����̊O���Ȃ̏�w�����ӂ̂܂܂ɑ����Ƃ����m�M�������Ă̂��Ƃ������̂��낤���A����Ȃ��Ƃ͂�قǂ̗��t�����Ȃ���ł��Ȃ��͂��Ȃ̂��B
�@ ����͂܂������̌l�I�ȉ����ɂ����Ȃ����A����܂ŕ���Ă���ȏ�̉��������̐l�̔w��ɂ͉B����Ă����̂ł͂Ȃ��낤���B�����܂ł��\�̈���o�Ȃ����̂ł͂��邯��ǂ��A��؋c�����鏑�߂Ă�������c�������Y���o�������ȗ��A���̐l�ɂ͂����̈Â��e�����܂Ƃ��Ă����Ƃ������Ă���B����c���Ƃ��ẴX�^�[�g���_����A�q��ł͂Ȃ��s�C���Ȗ��̂悤�Ȃ��̂����̔w��ɂ͗���Ă����悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B
�@ ��؋c�����x�����̂̓��V�A�ʂ̍����D�Ƃ����L�\�ȊO�����ŁA���V�A�̋ɔ������肷�邱�Ƃɂ����Ă͂��̐l���̉E�ɂł���̂͂��Ȃ������Ƃ������Ă���B�Ȃɂ��Ȃ����������A�m���L�����A�g�ɂ�����ȗD�G�Ȑl���������̂��Ƃ��������̂��ƂŏI���Ƃ��낾���A�悭�l���Ă݂�ƁA���̘b�͂����P���Ȃ��Ƃł͂Ȃ��悤���B
�@ ���V�A�̋ɔ����I�m�ɓ���ł���Ƃ������Ƃ́A���̐l������KBG�Ȃǂ��͂��߂Ƃ��郍�V�A���@�ւ�V�A���{�v�l��Ɠ��ʂȊW�������Ă���Ƃ������Ƃɂق��Ȃ�Ȃ��B�������Ƃ���A�M�u�E�A���h�E�e�C�N���펯�̂��̐��E�Ń��V�A���������I�ɏd�v�����Ă����Ƃ͍l���ɂ����B���R�A���{����������Ƌ@���ɑ����������e�험���A���z�̎����Ȃǂ����V�A���Ɋҗ�����Ă����ƍl����ׂ����낤�B
�@ �����D�Ƃ����l���͑�ǓI�ɂ͓��{�ɗL���Ȏd���������̂�������Ȃ����A�����Ԃɂ�����ɔ�������̃p�C�v���Ƃ��āA��d�X�p�C�Ƃ͌���Ȃ��܂ł��A����ɋ߂���d����ттčs�����Ă����Ɛ��������B���̏ꍇ�A���V�A���ɗ��ꂽ���{�T�C�h�̋@������ǂ̂�����ɂ��������͌��킸�Ƃ��z�������Ƃ������̂��낤�B
�@ �䂪���ƊW�̂��鐢�E�̑卑���A�l�X�Ȏ�i��[�g��p���ē��{�̎�v����������L�͐����ƁA�L�����f�B�A�W�҂Ȃǂ̂Ȃ��Ɏ����̐e�h����Ă����A���̗͂���ċɔ�̂����ɍ��v�ɂȂ���O����W�J���悤�Ɖ��̂͏O�m�̂��Ƃł���B�č����������؍����k���N���A�����ă��V�A�����̗�O�ł͂��肦�Ȃ��B�������Ă݂�ƁA�����鐭���I�d���̃v���W�c�ł�������KGB�̑g�D�Ȃǂ����V�A���{�̗v���������A��؋c�������V�A�e�h�Ƃ��Ďx�����悤�Ƃ��Ă����Ƃ������Ƃ��܂�l�����ʘb�ł͂Ȃ��B���l�͔ے肷�邾�낤���A���V�A���{���ɔ�̂����ɗ�؋c���₻�̎��Ӌc���ɓ��ʂȗ��v���^���͂����Ă����Ƃ����\�������Ċ��S�ɂ͎̂Đ�Ȃ��B
�@ �܂��A��KGB�ȂǂƑ�U���Ȃ��ƂȂnj���Ȃ��Ă��A���ʂȒ����@�ւȂǂ����ėL�͐����Ƃ⍂�������A�L�͖��Ԋ�Ɗ����Ȃǂ̃X�L�����_����͂ނ��ƂȂǁA��؋c���̂悤�ȑ̎��̐l���ɂƂ��Ă͗e�ՂȂ��Ƃł������낤�B�ǂ�Ȑl�Ԃɂ����l�ɒm��ꂽ���Ȃ����̕���������͕̂��ʂ̂��Ƃ�����A������l�^�ɂ��ĈÖق̂����ɋ�������A�E�]�����v���ꂽ���R����̂͂������ėe�ՂłȂ����낤�B���낢��Ȃ������ł��肰�Ȃ����������点�A���������Ȃ�ʊW���ł����Ƃ���ő�����ӂ̂܂܂ɑ���Ƃ������Ƃ��\�������ɈႢ�Ȃ��B
�@ ������Ȃ�ł������܂ł�����Ƃ͎v�������Ȃ����A�ł̐��E�̗͂���Ď����ɕs�s���Ȑl���ɑ������̊댯������������鉉�o�������Ȃ��A����ɒ�m��ʕs�C���������������邱�Ƃɂ���āA���̔ᔻ�������𔗂�ȂǂƂ������Ƃ��A���Ԃ�s�\�ł͂Ȃ��������낤�B�K���s�K���A�u�ԐM���A�݂�Ȃœn��Ε|���Ȃ��v�Ƃ������傻������̏ɂȂ��ė�o�b�V���O�͂Ƃǂ܂�Ƃ����m��Ȃ����A��X�����͎��Ȕ��Ȃ̈Ӗ��������߂āA���̖��̖{���Ƃ��̑Ώ��@�ɂ��Ă��܈�x�[���l���Ȃ����Ă݂�K�v�����邾�낤�B
�@ ���̑I���ŗ�؋c���̍đI���Ȃ邩�ǂ����͂킩��Ȃ����A�������ċN���Ȃ�Ȃ�������A���߂āu��؏@�j��ژ^�v�̂悤�Ȃ��̂ł������A���E�̕��䗠�𔒓��̉��ɔ����Ă��炦�Ȃ����̂��Ǝv���B�����Ȃ�A����̕s�ˎ��͂Ƃ������A��؋c���̑��݈Ӌ`��A���c���łȂ���Ȃ����Ȃ���ژ^�̎d���ɑ���]���͑傢�ɍ��܂�ɈႢ�Ȃ��B
�@ ����ɂ��Ă��A�c�������ؖ��ɑ��鏬��́A������œ������ȁA�����Ċj�S���͂��炩���Ƃ��ȑΉ��Ԃ�͂ǂ����낤�B�ȑO�ɁA���������̔ᔻ�����߂Ȃ�����A���̐����p���ƕ\�����̐l�������{���ł���ƐM�������Ə����Ă݂͂����A�ŋ߂ł͊䕨�Ƃ�������ʂ������яオ���Ă����Ă���悤���B
�@ �i�D�悭�U�����A�А��悭�f��I�Ȍ��t��f���l���́A�ꌩ���f�͂������e�͂�����悤�Ɍ�����̂����A�S���w�̐����Ƃ���ɂ��A���̎�̐l���ɂ͕�q�����A���Ȍ��t�ł����}�U�R���̗v�f�����҂����Ȃ��Ȃ��Ƃ����B���̗��̎����́A���t�̌y���A�ӔC����A�����Ƃ����Ƃ��ٖ̕��ېg�A�������������҂ɑ���ӏ]�Ȃǂł���炵���B���}�U�R���ł���ȂǂƂ͎v��Ȃ����A���܂̂悤�ȏ�����������ƁA���̎����Ɏ���X����l�������Ȃ��Ă͂��邾�낤�B
�@ ��s�̕s�Ǎ������Ȃǂ͎��f���铖�ʂ̋}���ł���͂������A���̐l�̂���܂ł̌������s���ɑ���ǂ����������̑Ή������Ă���ƁA�̉B�ꂽ�x����̂����͗L�͓s�s��s�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ƃ����v���Ă���B�O�ɐi�߂Ɛ����炩�ɐ���Ȃ���A�i�����Ƃ���l�̃X�J�[�g�����瓥�ނƂ������������s�ׂ��A�s�s��s�̕s�Ǎ��������ł��N����Ȃ����Ƃ��Ђ�����肤����ł���B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2002�N3��27��
���ԗ]��
�@ �O���ɂ��Ăُ͈�Ȓg�����������Ă��邹�����낤�A�������ӂł͂������̉Ԃ��O���炫���炢�ɂ͂Ȃ��Ă���悤���B���ƈ�T�Ԃ�����A�s����т̂قƂ�ǂ̍��͖��J�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��낤�B���N�̍��̊J�ԓ��́A�ߋ��\�O�N�ɂ킽��ϑ��j������Ƃ����������Ȃǂƕ�ꂽ������Ă��邪�A���̒��q�ł����Ɨ��N����͂��������ǂ�Ȃ��ƂɂȂ�̂ł��낤�B
�@ ���ɂ͍��Ȃ�̎�������邱�Ƃ��낤����A�ނ������܂̂��s���ő����炫�����U��̂͂�ނ����܂��B�����A���̋G�߂��}���邲�Ƃɂ܂���N���߂������Ȃǂƍl����悤�ɂȂ������̐g�ɂ���ƁA��A��T�ԕ��l�����Z���Ȃ��Ă��܂����悤�ȋC�����Ă��邩�������ł͊�ׂȂ��B���̉Ԃ͎U��ۂ������Ȃ̂ŁA�������ł�҂͂��̂�̎U��ۂ����ɕ���Č����ɂƂ������Ƃɂ��Ȃ�̂�������Ȃ����A�U��ۂ��ُ�ȂقǂɊ������Ƃ����̂��܂����ł͂��邩������Ȃ��B
�@ �����̒��߂��A���܂����͓����x�O�̂Ƃ��������ʂ肩�������B�����̍����O���炫�قǂł��������A�܂肩��̗z���𗁂тĐ��X�����P���ԁX�́A�قǂȂ����ɎU��^���ɂ��邱�ƂȂǏ��������������Ȃ����炢�����͂Ɉ��Ă����B���̕��ؓ`���ɕ����Ă������́A��{�̑傫�ȍ��̖̑O�ő����Ƃ߂��B�ȑO�b�ɕ����Ă����̂́A�����������炱�̍��̖ł͂Ȃ����Ǝv��������ł���B
�@ �̂̋����q�̂ЂƂ��A����Ƃ�������������B���݂͌������A�̕�e�ɂȂ��Ă��邪�A�\�N�߂��O�܂ł́A�Љ�l��w���Ώۂ�IT�u���Ȃǂɂ����āA�܁X�A����Ȃǂ߂Ă�������肵�Ă����B�����A�ޏ��͋�s�n�̃V���N�^���N�ɋΖ�����L�\�ȃV�X�e���E�A�i���X�g�ŁA��������ςɈ炿���l�����悢���l�Ƃ��Ă�������A��u�҂̒j�������̊Ԃł̕]���͏�X�ł������B���Ɣޏ��Ƃ��������ǂ��炪�u�t�łǂ��炪����Ȃ̂��킩��Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��������������炢���B
�@ ����A���A�����ɂ��Ă��@�������S�̏��������[���ɔ�߂Ȃ��琶���Ă���̂�m�����̂́A�ޏ��Ƃ̂ӂƂ�����b����ł������B����́u�����͏���������Ȃ�v�Ƃ������t�ɂ��]��قǂɏՌ��I�Șb�ŁA�����̂��Ƃł͋����Ȃ������A�����Ⴊ�����^�����قǂł������B
�@ ���̐M����b��ł�������ꂽ����Ƃ����Ă��A���ɂ́AA����̂���̂Ȃ��v���ɐ܁X�����X���A�Ȃɂ��ɂ��ĐS�����܂��Ă����邭�炢�̂��Ƃ����ł��Ȃ������̂����A�K���A���܂ł͔ޏ��͂��̐[���S�̏��݂����S�ɍ������A��w�Ƃ��āA���Z�Ȓ��ɂ��[���������X�𑗂��Ă���悤���B��l�̂��q���������������ƈ���Ă���悤������A�܂��͂悩�����Ǝv���Ă���B��������������A����ɂ܂�邻��Șb�����J����C�ɂȂ����̂��A�ޏ��͂������v���Ɣ��f��������ɂق��Ȃ�Ȃ��B
�@ A����ɂ͊w�����ォ����ۂ��Ă����j�����������B��l�̊Ԃ͂��炭�͂��܂������Ă������A�₪�Ĕޏ��͔ނƂ̌��ۂ𑱂��Ă������Ƃ��d�ׂƂƂȂ�A�قǂȂ�����͋�ɂւƕς���Ă������BA����ɑ��鑊��̒j���̍S���Ԃ��x�z�~���ُ�Ƃ��������Ȃ���ԂɂȂ��Ă����̂ɂ��킦�A�ꌩ��e�͂�����Ǝv���Ă����ނ��A���ۂɂ͂��ׂĂɎ��Ȓ��S�I�ŁA���������̐��_��Ԃ��ɂ߂ĕs����ł��邱�Ƃ������������炾�����B����̉ƒ���q��ł͂Ȃ��炵�����Ƃ�A����̋C�ɂȂ�Ƃ���ł͂������B
�@ ��w�𑲋Ƃ��A�E�����ޏ��́A������_�@�ɔނƂ̕ʗ������ӂ��A���x���b�������������Ă��̎|��ɓ`���悤�Ƃ������A�ނ̂ق��͂܂���������݂����Ƃ��Ȃ������B��ނȂ�A����͎��炻�̒j�����ɗ͔�����悤�ɂȂ����̂����A����̓X�g�[�J�[�Ɖ����A��Ђ̍s���A��Ȃǂɔޏ���҂��������Ď��X�ɂ��܂Ƃ����B�����āA�����̂�����Ă���ꋫ�Ȃǂ����ꂱ��ƕ��ׂ��Ă�A����̓�����Ȃ���A���ۂ̕����𔗂葱�����B
�@ �ޏ��̂��Ƃɂ͔ނ���X�ƐS�̋ꂵ����i�����莆�Ȃǂ�����I�ɑ�������A�Ō�ɂ́A�u�ȑO�Ɠ��l�Ɍ��ۂ𑱂��Ă���Ȃ���Ύ��玀��I�Ԃ��Ƃ��}��Ȃ��B�܂��A���Ƃ������Ȃ����Ƃ��Ă��A���̐ӔC�͐��U���Ȃ����w�����ׂ��ŁA�������Ď����̐ӔC�ł͂Ȃ��v�Ƃ������悤�Ȏ�|�̕��ʂ�����������قǂɂ��̓��e�̓G�X�J���[�g���Ă������B
�@ �����S�̋���A����́A���ӂɕs�K�v�ȐS�z�������Ă������Ȃ��ƍl���A���̂悤�ȏɂȂ��Ă��邱�Ƃ��A��Ђ̓������i�ɂ͂ނ��A���e��e�F��ɂ������b���Ȃ������B�����āA���Ԃ������Ȃ���A�Ȃ�Ƃ����͂Ŏ��Ԃ̍D�]���͂��낤�Ƃ����B��������Ă���莆�͖���������J�������ɕԑ������肵�A��Ђ̍s���A��ɂ́A�����ɒʋΎ�����ʋ��[�g���������ς����肵�āA�j�Ƃ̐ڐG������������B����ȋ�J�Ɠw�͂������Ă��A�悤�₭������̒j�̉e����������A�ޏ����g���Ȃ�Ƃ��S���I�ɗ����������߂����Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B
�@ ���̋G�߂��}����������̑����AA����̏Z�ދ߂��̌x�@������ޏ��ɓˑR�̓d�b���������B���̓d�b�ڂɎ��ޏ��ɁA�x�@�̒S���҂́A�ً}���Ԃ��������̂ł����ɏ��܂ŏo�����Ăق����|�̗v����`�����B�����N�������̂��܂���������̂킩��Ȃ��܂܂ɁA�Ƃ肠�����ޏ��͌x�@���ɏo�������B
�@ �����̂Ƃ��镔���ɒʂ��ꂽA����͂��܂�̂��Ƃɐ�債�A���R�Ƃ��Ă��̏�ɗ����s�������B�ޏ��������Ŗڂɂ������̂́A���S��܂��Ԃ��Ȃ��Ⴂ�j���o���̂���������ł���B�ނ��A���̈�̂͂��Č��ۂ��Ă����j�̂��̂������B�x�@�͔ޏ��ɂ܂����̈�̂̐g���̊m�F�����߁A���̂��Ƃŏo�������߂�ɂ��������̐����Ɣޏ�����̎����������Ȃ����B
�@ �����ɂȂ�����A�̏͋����ׂ����̂ł������B�j�͂��̓��̖����AA�����̂����߂��̍����ɂ���Ă���ƁA�ޏ��̉Ƃ̌�������̖̈�{��I��ł悶�o��A���̎}�Ŏ��݂��Ď��疽�������̂��B�������A�ނ͂��̎��ɗՂ�ŁAA���^����ɂ��̈�̂��m�F����������Ȃ��Ȃ�悤�ɍI���Ȉ�v���Ă��Ă������B���̋G�߂ɔߌ��̕�������쎩�����A�ۉ��Ȃ�A��������̕���Ɉ������荞��ł��܂����̂������B
�@ �j�͎����̐g���ږ������悤�Ȃ��͉̂��ЂƂg���Ă��Ȃ������B���̂����ɔނ͐^�V�����蒠���ЂƂ����Ă����B�����āA���̎蒠�ɂ́A�Ȃ�ƁAA����̖��O�ƏZ���Ɠd�b�ԍ��������L������Ă����̂ł���B��ꔭ���҂���̒ʕ�ň�̂����e�����x�@�����ޏ��ɏo�������߂��͕̂K�R�̐���s���������̂��B
�@ ���ǁAA����͋ɓx�̐S���I������Ԃ̂܂܂ŁA�j�̑��V�ɂ܂Ŋ���o����������Ȃ��Ȃ����B�]�ނƖ]�܂���Ƃɂ�����炸�A�ޏ��͐��O�ɒj�̏���������ɍŌ�܂ł����킳���n���ɂȂ��Ă��܂����̂��B����̈ꑶ�����ŋ����ɐg����ȕ���̒��Ɏ�荞�܂�A�����l�m�ꂸ�w�����Đ����Ă����˂Ȃ�Ȃ��ޏ��̋����͎@����ɗ]�肠����̂ł͂������B
�@ ���̎����������Ă���Ƃ������́AA����͎���Ɖw�Ƃ����ԓ��ɂ��邻�̍�����ʂ�̂����낵���ĂȂ�Ȃ������Ƃ����B�Ƃ��ɁA�d���ŋA�肪�x���Ȃ����Ƃ��Ȃǂɂ́A���̋��|�̓x�͋ɂ݂ɒB���A�l��{�c�̋������̋C���������Ă��Ă�����ɑς���͎̂���̋Ƃł������炵���B�V���̂ɂ��₩���Ƃ͗����ɁA���ꂩ�炵�炭�́A�j���Ƃ������̂ɑ��邠���̕s�M�����a�����ǂ����Ă��@�����邱�Ƃ��ł��Ȃ������Ƃ����B���̌�A���Г�Ƃ������ׂ����̐��_�I�V���b�N����ޏ����������邱�Ƃ��ł����̂́A�s�K���̍K���������ƌ����ׂ����낤�B
�@ ���̓����R�ɁA����A����̎��Ƌ߂��ɂ��������ʂ肩�������̂������B�����āA�b�ɕ����Ă�����A�Z��X�ƍ����Ƃ̑��ΓI�Ȉʒu�W���炵�āA�قڂ���ɊԈႢ�Ȃ��Ǝv�����{�̍��̋������������Ƌ����邱�ƂɂȂ����B�傫���l���ɂ̂т��}�X�̐�ɂ͖������Q���o�Ԃ�҂��ĂЂ��߂������A���łɊJ�����������ԁX�́A���邢�z���ɋP�������āA���s���l�X�̖ڂ�]���Ƃ���Ȃ��D���Ă����B
�@ ���̍��̌Öɂ́A���ċN���������܂킵���o�����̋L���ȂǁA�����ǂ��ɂ��c���ĂȂ��悤�Ɏv��ꂽ�B�܂��A���Ƃ�����ȋL���̒f�Ђ��ǂ����Ɏc���Ă����Ƃ��Ă��A���̂�̎}��ɍ炭�ԁX�̂������悢�U��ۂ̔��w�Ƃ͈قȂ�A���������ώ��̋ɂ݂Ƃ������ׂ��U�肩���������ЂƂ�̒j�̕���ȂǁA���̖̂ق��ɂ��Ă݂�Ώ��F�ǂ��ł��悢���Ƃł͂������낤�B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2002�N4��3��
�h���L�����@�Ǒz�L�i��j
�@ �k�A���v�X�R�[�̍L��Ȑԏ��т�w�ɂ������̉��~�́A�s�v�c�ȐÂ����ɕ�܂�Ă����B���Ă��̉Ƃ̘V��́A�N�����߂Â��ƁA�@��𐧂���悤�ɉ��̂ق�����k�[�b�Ƃ��̎p�����킵�A�s�ӂ�˂��ꂽ���K�҂̂ق��́A�V���Ă������̏�ɗ����s���������̂������B�����\�̊Ď��J�����Ɖ������m�킪�����ɐݒu����Ă���A���ւ�x�b�h���[���ɋ��Ȃ���ɂ��Čˌ����ӂ̏�I�m�ɔc���ł���悤�ɂȂ��Ă�������Ȃ̂����A���̎d�|�����킩��܂ł́A�����g���ςɂ܂܂ꂽ�v���ʼn��x������X�������̂������B
�@ �O�����{�̂��̓��A�v�X�ɗ��K�������̑O�ɂ��Ẳ��~�傪���̎p�����킷���Ƃ͂����Ȃ������B���łɊĎ��J�����͎��O����A�d�C�A�K�X�A�����Ȃǂ̂̋������~�߂��Ă��܂��Ă����B���͕�������̉Ƃ̉E��ɉ��A�ԏ���G�S�m�L�̐����Ă����p�ɕ��ݓ������B�����ĎO�{�̐ԏ��Ɉ͂܂ꂽ�����ȃX�y�[�X�̐^���ɗ����A���߂Ă��̉��~�Ɉē����ꂽ���̂��Ƃ����������z���N�����B
�@ �ԏ��̊��ɂ͊��ȃt�b�N���܂����̂܂c����Ă����B���̃t�b�N�ɘV�厩���̑傫�ȃJ�i�_���n�����b�N���|���A����ɐg���ς˂Ȃ��������グ��̂́A�u�����̂����Ȃ����Ƃł��������B��l���O�l�قǂ͏���n�����b�N�ɋ����ɐQ���ׂ��Ă��̉��K����̊�����̂́A���̗��K�҂ɉۂ�����K�{�̋V���݂����Ȃ��̂ł��������B
�@ ���̃n�����b�N�́A�V��Ɛe���̂������ʐ^�Ǝs�쏟�O���̗v���œ����ɉ^�э��܂�A�W�p�Е��ɂ̐�`�|�X�^�[�ɗp����ꂽ��������B���̎��Ƀn�����b�N�ɐQ���ׂ��ă|�X�^�[�ʐ^�ɂ����܂����l���́A�ŋ߃t�����X�f��u�킳�сv�Ȃǂɂ��o�ꂵ�Ęb����܂����l�C���D�̍L�����q�������B
�@ ��N�܂ŁA�����߂��̌����ɂ͘V�厩���̎萻�ȈI�V���C�Ȃǂ��������̂����A���łɂ��̗����͎�蕥���A�y��̃u���b�N�Ɣr�����݂̂��c�邾���ɂȂ��Ă����B�܂��~�͂ꂵ���܂܂̒�߂Ȃ�����ܖ�ɖʂ��鉮�~�̕\���ɉ��ƁA�Ȃ�Ƃ����炩�Ȑ����������Ă����B���~�̂������ɂ͔_�Ɨp���H���݂����Ă��āA��N���₦�邱�ƂȂ����w�Ȑ�������Ă���B��ʂ̐������܂��������ŗ��ꂭ�����Ă��邩��A����Đ����ɗ������肵����ƂĂ������ł͂��܂Ȃ����낤�B
�@���̉��~�̃A�C�f���e�B�e�C�̂ЂƂł����邻��Ȑ������Ȃ���A�����ȐΒi���̂ڂ��Ē����̃K���X�˂ɋ߂Â��ƁA�����Ƃ���������J�����B�Ƃ̒��ɓ����悤�ɂ��Ă����Ăق����ƁA���݂̊Ǘ��҂̕��ɂ��炩���߂��肢���Ă������̂ŁA�K���X�˂Ɏ{���͂Ȃ���Ă��Ȃ������B
�@�܂������l�C�̂Ȃ������ɓ��������́A�[�����S�ɂЂ���Ȃ��炵�����̏�ɗ����s�������B�����āA����h���L�����V�l�Ə̂��A��������܂��h���L�������Ɛ��ߕ�����A���܂͖S���H��̊�l�̍��ɐS���ł����Ƌ��̑z������肩���Ă݂悤�Ƃ����B�����������₨�Ԃ������Ă݂Ă��A���邢�͂܂��삢�ď\���˂������Ă݂Ă����ł͂���Ȃ��ł��낤�V���̍����ɂ́A�������邵���Ȃ����낤�ƍl�������炾�����B
�@���������A���̓������Γc�@��K�˂��̂́A�M�����肩�����܂܂��܂��ɒE�e���Ă��Ȃ��V���̓`�L�A�u�����l�̐��U�v�̌㔼���������i�߂邽�߂ɁA���܂������m�F�����蒲�ׂ��肵�Ă����˂Ȃ�Ȃ����Ƃ����������炾�����B�Γc�B�v�������݂Ȃ����Ɋ������������ł������e�͏��ʂ̎���Œx��ɒx��A���ǁA���̐��O�ɂ��̎����͂Ȃ�Ȃ������B����ɂ��̌��ʂƂ��āA�a�����瑼�E�ɂ�����܂ł̕����ʂ�́u���U�v��`����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ�������w�������ނ͂߂ɂȂ����̂������B
�@ ��N������{�̂����x���̂��ƁA�ˑR�肾�����d�b�̃x���Ɏ��͖ڂ���܂��ꂽ�B�Q�ĂĎ�ɂ�����b�킩�痬��Ă����̂́A���ɂȂ���X�����A�����������ɉ�����i�������悤�Ƃ���䍂�̃h���L�������A���Ȃ킿�A�Γc�B�v�V���̐��ł������B
�@ �\�\����������ɗ��Ă���Ȃ����H�B�ǂ����Ă����Ȃ��ɉ���Ęb���������B�܂��̎҂��݂�Ȗl�̓������������ƌ����̂����A�����ł͂����͎v���Ă��Ȃ��B���Ȃ��ɉ���Ęb�����Ƃ��ł��A�����Ă���̂��ق�Ƃ��Ɏ����Ȃ̂������łȂ��̂��m�F���ł��邵�A�����ɂ��̔��f�����Ă��炤���Ƃ����Ăł���\�\
�@ �Γc���̓d�b�̓��e�́A�قڂ��̂悤�Ȏ�|�̂��̂������B�d�b�̐��̗l�q���炱��͐q��Ȃ��Ƃł͂Ȃ��Ɣ��f�������́A�������Ԃ̃n���h��������A�䍂���Ɍ������đ��肾�����B���˂��ˁA�{���̃h���L�����Ȃǂƌy����@���Ď��̂��Ƃ����炩���Ă����{�Ɩ{���̃h���L���������A���܂��Ƀh���L�������K���ɂ����Ȃ������̂��̐g���Ăъ�Ȃ�āA�������������N�������Ƃ����̂��낤�B���낢��Ƒz�����߂��点�Ă݂͂����̂́A�m���Ȃ��Ƃ͂��܂ЂƂ͂�����Ƃ͂��Ȃ������B
�@ �Γc�@�ɒ����Ă݂�ƁA���ɂ���̂͐Γc���{�l�Ɨ{�q�̐Γc�r�I����̓�l�����������B�Ⴂ������Ɛg����ʂ��Ă����Γc���́A�̂��̂��̂��Ƃ��l���A���Ȃ�ȑO�ɏr�I�����{�q�Ɍ}�����B�����A�Ԃňꎞ�Ԃقǂ̂Ƃ���ɏZ�ޏr�I����̉Ƒ��Ɠ������邱�Ƃ͂Ȃ��A���̕䍂�̉��~�œƂ�ŕ�炵�𑱂��Ă����B�ނ��A�����A����A�|���Ƃ������悤�Ȃ��Ƃ����ׂĎ����ł���Ă����B�l�ԊW��d���W�ɂ����ẮA�Γc�����{�q�̏r�I������݂��ɑ���̐��E�ɂ͂��������������炸�A�Ȃ�̊������Ȃ��Ƃ�����{���[�������炵�Ă����B
�@ �������͓̂�x�ڂ̏r�I����ƊȒP�Ȉ��A�����킵�����ƁA���͂����ɐΓc���̏��ւƃx�b�h���[�������˂������ɓ������B���̎p��ڂɂ����V���́A���̂܂܂łƂ������~�̌��t�ɂ͎���݂����A���͂Őg���N�����ƃx�b�h�̒[�ɍ����|�����B�����āA�u�₠�A���Ȃ�������̂�҂��Ă�����v�Ƃ��������ꂫ�A�ЂƂ傫���������ƁA�����Ƃ�����̊�����߂��B
�@ ���͂����ɁA�����Ɠy���������ĕ��ꗎ���鐡�O�̋���ȌÖ̎p�������B�傫�Ȋ��͂��łɋ����͂ꋀ���Ă��܂��Ă��邪�A�}��̂������̗t�͂Ȃ���ՓI�ɐ����̋P�����Ă���\�\����ȘV����̍Ŋ��̎p����O�̘V���ɏd�ˌ����̂������B�Γc���̐g�̂̈ꕔ�͖����ɐA�����������Ă����B�����A���O��ċ��x�Ȑ��_�͂Ɩ����Œm��ꂽ���]�Ƃ��A�g�̂��\������S�זE�₻�̋@�\���ׂĂ̐A�������拭�ɑj�~���Ă����B����́A������u�����v���o�Ă����Ԃɂ͈Ⴂ�Ȃ��������A���̐g�̂̓����łȂ��������������鐸�_�������ɁA�S��h�ӂ�\�����ɂ͂����Ȃ������B
�@ �V���̌��Ƃ�����ɗ͎��R�̂ŎƂ߁A���̎p������̂܂܂ɒ������悤�ƌ��ӂ������́A���炽�߂ăx�b�h�e�Ɉ֎q��������ƁA�����ނ�ɍ������낵�đ���̊�ɐÂ��Ɍ��������B���X����C���ł������r�ꂪ���ɔ�������Γc���̌��t�ɂ́A���Ă̂悤�Ȑ����Ɖs���ꖡ�͌����Ȃ������B�Ő�̌����̂悤�Ȏp��m�邱�̐g�ɂ�������������G�Ȏv�����������A������܂��A�Γc���Ǝ��Ƃ̉^���I�ȏo�����̋A����Ƃ���Ƃ����ނ����Ȃ����Ƃ������B
�@ �ڂ��������m��l����̂��ɕ������Ƃ���ɂ��ƁA���̐����O�A�����̌��ǔj��ɂ���ē˔@�Ђǂ��f���≺���ɏP��ꂽ�Γc���́A���̂܂��_��ԂɊׂ�A���܂��ܗ��K�����ߗ҂ɔ�������ĕa�@�ɒS�����܂ꂽ�B�K���A��t��̌����̎��Âɂ���ĂȂ�Ƃ��ꎞ�I�ɏ��N�����̂́A�ӎ������A������x�̗̑͂����߂��ƁA�V���̓x�b�h�Ō������\��?���A�g�̂ɕt����ꂽ��Ê��ނ��Ђ����������肵�āA����ȏ�̎��Â�f�ŋ��₵�悤�Ƃ����B
�@ �܂��A���X�ɋN����ُ�Ȍ��o�⌶�����������̂��̂��ƐM���ċ^��Ȃ������Γc���́A�����ɑς����Ȃ����玩��֖߂�Ƌ��d�Ɏ咣���ď��炸�A�䂵����Ȃ��Ȃ�����҂���͂̎҂����́A����×{����ނȂ��Ƃ������f���������B�������A���̔w�i�ɂ́A������ɂ��뎀���͂��������Ȃ��Ƃ������f�����������炾�����B�����A�V�������̓����ɐ^���Ȍ����Ō�����́A���R����Ƃ͂܂�ňقȂ���̂ł������B
�@ �\�\�����̓��@���Ă�����̘e�ɂ̓I�y���̗��K�p���䂪�����āA�j�����l���̃I�y���̎肪�A��������Ȃ���\�l���Ԏ������悤�ȑ吺�ŗ��K�����Ă����B�h�^���o�^���Ƃ������܂��������������Ă������A���܁A�x�b�h�̎����̂ق���`���Ă͊F�Ś}����悤�Ȑ������������肵���B�������������Ȃ肻���ŁA�ƂĂ������ĂȂ���Ȃ��̂ŁA���̏���҂�Ō�w�A�������q�Ȃǂɑi�����̂����A�N�����A��ɂ���Ȃ��Ƃ͂Ȃ��A����͐Γc��������ƍ������N�����Ă��邩�炾�ƌ������肾�����B�g�̒����ǂ��炯�ɂ���Ď��R��D��ꂽ�����ɁA����ȉ��̍���ɂ܂ő�������A�ƂĂ��䖝�Ȃł�����̂���Ȃ��B�F�͔ے肷�邯��ǁA����͐�Ɏ����������Ƃ��܂����͎v���Ă���B�a�@�͓s�����������玖�����B�����Ƃ��Ă����Ȃ����H�\�\
�@ ���Ƃ��ΘV���͂���Ȃ��Ƃ����ɓ`���A���̂��Ƃ��ǂ��v�����Ɛq�˂Ă����B���̂Ƃ����łɎ��ɂ́A���Ƃ��ǂ�Ȃ��Ƃł��낤�Ƃ��A�Γc���������ƐM����Ƃ�������ׂčm�肵�Ď���悤�Ƃ����S�̏������ł��Ă����B������A�������R�ɑ���̘b�Ɏ����X���A�����Ȃ��瓯�����A�����̂Ȃ��������ʼn�b��i�߂邱�Ƃ��ł����B
�@ �ނ��A�����Ή�����̂��x�X�g���ƍl��������ł����������A�V���̘b���̂��̂��A�a�@�ł̈ꌏ���̂����Ă͂�������Ȃ��̂ŁA�������������t�����炩�ɏo�Ă��Ȃ��̂��ׂɂ���A���������Ƃ���͂قƂ�ǂȂ������B�a�@�ł̃I�y���ɂ܂�錶�o�́A���N�p����BBC�̕����L�Ҍ��A�i�E���T�[�Ƃ��Ċ��A�V�F�[�N�X�s�A����Ȃǂɑ��ɂ��ʂ������Ƃ̂��邱�̐l���Ȃ�ł͂̂��̂������̂��낤�B���o�⌶���ł���Ƃ͂����A�a�@�̃x�b�h��Ŏ��ɂ����Ƃ����I�y���̋Ȗڂ�̎��܂ł͂�����ƋL�����Ă��邻�̈ٔ\�Ԃ�̂ق����A���ɂ͂�قNj����[�����ƂɎv��ꂽ�B
�@ �{�q�̏r�I����͌ߌォ��o�Ђ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������ƂŁA���炭����ƐΓc���Ǝ��̓�l�����ɂȂ����B���͋߂��̃X�[�p�[�}�[�P�b�g�܂ňꑖ�肵�āA�V���̍D�������߂��B�߂��Ă݂�ƁA�M�����Ȃ����ƂɁA�Γc���͎����ŗ����オ��A�①�ɂ����A�O�̕i�����o���ĎM�ɕ��ׁA���������čg�������鏀�������Ă���Ƃ��낾�����B
�@ �A�������������l�҂Ǝ�����тт����̑S���̂ɕڑł��ĂȂ��A���邾���̂��Ƃ͎��͂ł�낤�Ƃ��鐦��Ȃ܂ł̍s���͂Ɛ��_�͂ɁA���͂������|�������肾�����B�܂�ŃX���[���[�V�����̉f���ڂɂ��Ă���悤�ȓ����ŁA���邩��Ɋ�Ȃ����������������A���͂����Ă�����~�߂悤�Ƃ͂��Ȃ������B�~�߂Ă͂Ȃ�Ȃ��Ǝv�������炾�����B
�@ �x�b�h�̘e�̏����ȃe�[�u���ɐH�ו��ƈ��ݕ�����ׁA�C�̌����܂܂ɂ��������ɂ��Ȃ���A���ꂩ�炳��Ɍ܁A�Z���Ԃقlj�X�͓�l����Řb�𑱂����B���̊ԁA�Γc���͉��x���x�b�h�ɉ��ɂȂ�����A���͂Ńg�C���ɗ�������A���X����ɗ������肵�����A���͂�����������Ȃ��ƂȂNjC�ɂ����ɁA����̃y�[�X�ɍ��킹�ĉ����������B
�@ �����͓r�ꂪ���Ō��t�ɂ�����������Ă����Γc���̌������A���Ԃ��o�ɂ�Ď���Ɋ��炩�ɂȂ��Ă����͈̂ӊO�Ȃ��Ƃ������B�������A�y���܂ł���яo���͂��߂��̂ɂ͏��Ȃ��炸�������ꂽ�B�����āA���ɂ́A�u�ǂ����l�̓��̂ق������������Ȃ��Ă��ȁB���̓����g�̂��A�����������ɂ������Ă���ȁc�c�B���܂͂�����킩���Ă�����v�ƌ��������̂������B���Ԃ�A����́A�ꎞ�I�Ȃ��̂ł͂������ɂ���A�V���̐��_�����܈�x�{���̋P�������߂����u�Ԃł��������B
�@ �Еt���Ȃ���Ȃ�Ȃ��d�����������̂ŁA�ߓ����̍ĖK����������ŁA���̓��̗[���A���͕䍂���ē����ɖ߂����B�ʂ�ہA��������킵�Ȃ���A�u����A�܂��c�c�v�ƙꂢ���V���̊፷���ɂ́A�\�̌��t�Ƃ͗����ɁA�u��������Ƃ͂Ȃ����낤�c�c�v�Ƃ����Öق̃��b�Z�[�W�����߂��Ă����悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B���炽�߂ĕ䍂�Ɍ��������Ə����𐮂��Ă������ɁA���̓d�b���������Ă����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2002�N4��10��
�h���L�����@�Ǒz�L�i��j
�@ ��b����Ƃ�ƁA�������̒j���̐�������Ă����B�Γc��̋߂��ɏZ�ޓ��|�Ƃ̕��я�����Ƃ���������̓d�b�������B�Γc���Ɛe���̂��������т���́A�V������A�����̐g�ɂ������̂��Ƃ��������炻�̎|�����ɓ`����悤�ɂƗ��܂�Ă����̂ł���B���т���́A���̓��Ŕ߂��݂�}����悤�Ȑ��ŁA�u�Γc�������ߌ�l�����ɖS���Ȃ�܂����v�Ɠ`���Ă����B��Z�Z��N�����\�����A�Γc�B�v���͋��N���\�܍������ĕ䍂���L���̒n�Ő��������̂������B���̓��͂��܂��܋��j���ł͂��������A���O�V�����Ƃ��ɂ��C�ɓ��肾�����u�\�O���̋��j���v�ł͂Ȃ������B
�@ �����d�b����������̂͘V�������������Ƃ��Ă���O���Ԃقlj߂����ߌ㔪���O�̂��Ƃ������B�܂��Γc�@�ɂ���Ƃ������т���ɁA�䍂�ɒ����͖̂�x���ɂȂ�Ǝv������ǁA�o���̏������������悻����Ɍ�����Ɠ`����ƁA�ǂ����˘f�����悤�Ȑ�����b��̌��������狿���Ă����B���т���ɂ�����āA��͂�Γc���Ɛe�������Ƃ��ʎ��̂�����ܖ앶�ɂ̌o�c�ҎR�{���d�b�ɂł�ƁA��Z�ɂ��̏�̏������Ă��ꂽ�B
�@ �R�{����̘b�ɂ��ƁA�Γc���̈�̂͂قǂȂ��M�B��w����z�����ԂɎ��e����A����w��w���Ɍ��̂���邱�ƂɂȂ��Ă���A���܂���䍂�ɋ삯���Ă�����Ă��A������̂Ƃ̑Ζʂ͂��Ȃ�Ȃ��Ƃ̂��Ƃł������B���܂ЂƂ���悭�ۂݍ��߂Ȃ��������A�ǂ���瑒�V�Ȃǂ���؍s�Ȃ킸�A��̂͂��̂܂ܐM�B��w�ւƉ^���炵�������B�i�������V���̎p�������Ȃ���Γc�@�ɗ��܂��Ă���̂́A�r��̐Γc�r�I������܂ސ����̐l�X�ɂ����Ȃ����Ƃ����������B�u�܂��A�d���Ȃ����Ƃł��̂ŁA�����ꎄ���������ʼn�@���݂��A���O�̐Γc������ÂԂ��Ƃɂ��܂��傤�c�c�v�Ƃ����R�{����̐����Ō�ɂ��̓d�b�͐ꂽ�B
�@ �Γc���Ƃ̐e���͎����������ƒ������͌��ݏZ�̍����Ȏ������ƒJ���f�v����Ɠ����ݏZ�̃J�����}���s�쏟�O����̓�l�ɘA�����Ƃ������ʁA�����̌ߑO���ɏ��{�ő҂����킹�A�Ƃ������M���w���t���a�@��K�˂Ă݂悤�Ƃ������ƂɂȂ����B���̂��Əo���̏������I�������́A�ߑO�뎞���ɕ{�����Ĉꑫ��ɕ䍂���ւƌ��������Ƃɂ����B
�@ �ߑO�O���߂��ɂ͐Γc�@�ɒ������̂����A�Ƃ̌��ւ̔��ɂ͏�������A�Ђ�����Â܂肩��������������͘��Â������������ɘR��Ă��邾���ŁA�l�̋C�z�͂܂������������Ȃ������B������������A�{�q�̏r�I�����ɓƂ�ł�����̂ł͂Ȃ����Ƃ��v�������A����ɂ������Ƃ��Ă��A�ЂƂ����Ȃ�ʐS�J�̂䂦�ɔ����Ė����Ă�����ɈႢ�Ȃ��ƍl�����B
�@ �J�������Ƃ̏��{�ł̑҂����킹�܂łɂ͂܂������Ԃ�Ǝ��Ԃ��������̂ŁA�Γc���Ƃ̏��߂Ă̏o�������ÂтȂ���A���̂��������ƂȂ�����R���p�ّO��䍂�w�O��K�ˁA���̂��ƁA�܂��������ʕ䍂�̊X���݂�ʂ蔲���đ剤���T�r���ւƌ��������B�����āA�����T�r���̘e�𗬂�閜����i��낸������j�̂قƂ�ɓƂ�ȂB���V���̔ӔN�̍�i�A�u���v�̃��X�g�V�[���̃��P�n���Ȃ������̔�������ӂɈē����ꂽ�̂́A�V���Ə��߂ďo���������̗[���̂��Ƃ������B���̎��A��������l�́A���̐�̓y��������Ɍ������ĕ����Ȃ���A�����Ȃ����ɂǂ����������ł���������s�v�c�ȉ�b���J�L�����B
�@ ������̐�ʂ͂܂��Â��A�����̐����̋P�������ڂɂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��������A�f��̒��ɂ��o�ꂵ�����ԏ����̓��̐��Ԃ́A�����ς�炸�������Ƃ�����]�𑱂��Ă����B���V�́u���v�̃��X�g�V�[���ɓo�ꂷ�鑺�ł́A�����҂��V����S������̂͂߂ł������Ƃ��ƍl�����Ă���A���l�����̑��V�̗�͉₩�Ȃ��Ղ胀�[�h��F�ɕ�܂��̂ł��邪�A������������A�Γc���̍������̖��邭���₩�ȑ����̃V�[���ɕ��ꍞ��œV�ɏ����Ă����Ă��܂����̂ł͂Ȃ����Ǝv���������Ȃ�̂������B
�@ �Ԃɖ߂�Ȃ��牽�C�Ȃ����̕��������ƁA�قڐV���ɋ߂��ׂ����������閾���O�̋�ɏ����Ă����Ƃ��낾�����B���͂ǂ����Î��I�Ȋ����̂��邻�̌��̂������ƁA�s�C���ɂ�������Ԋ��F�̌��ɂ��炭�����������ƁA�قǂȂ��Ԓ��ʼn��ɂȂ肵�炭�̂������������Ƃ����B
�@ ��A�O���Ԃقǂ��Ėڊo�߂����͂�������䍂�����珼�{�܂œ쉺���A�����ŗ\��ʂ�ɒJ���A�s��̗����ƍ��������B���̂��Ɖ�X�O�l�́A���{�s�k���̐M�B��w��w���t���a�@��K�˂Ă݂��B�������܂��Γc���̈�̂��[�����ꂽ�܂܂̏�Ԃ�������A���߂Ĉ�ڂł��Ζʂ����Ă��炦�Ȃ����̂��Ǝv�������炾�����B
�@ �������Ȃ���A�c�O�Ȃ��Ƃɉ�X�̊肢�͊���Ȃ������B���Ɉ�̂̕ۑ����u���Ƃ��Ă��܂������Ƃ炵���A���Ƃ��e���Ƃ����ǂ��A���͂≥�̈�̂�ڂɂ���̂͋�����Ȃ��Ƃ̂��Ƃł������B�܂��A���̂��ꂽ��̂��Ăш⑰�̂��ƂɕԂ����̂͑����Ă��O�N�ȏ��̂��ƂŁA���ɂȂ邩�m���Ȃ��Ƃ͂킩��Ȃ��Ƃ�������ꂽ�B�ǂ���瓖���͐M�B��w��w���₻�̕t���a�@�Ɍ������č������邵���Ȃ��炵�������B�Ȃ�Ƃ��l��H�������̐Γc���̂��Ƃ�����A���܂���I�R�ƃA���R�[�����ɐg���ς˂Ȃ���A�u�z�����Ă������������Ɖ��K������A���O������̂��������ɗV�тɗ�����I�v�ȂǂƓŐ��f���Ă��邩������Ȃ��ˁA�Ƃ������t�܂ł��N�̌�����Ƃ��Ȃ���яo������������B
�@ �M�B��w�a�@�����Ƃɂ�����X�́A�Ƃɂ����A������x�Γc�@��K�˂ĘV���̍Ŋ��̗l�q���ڂ����u���Ă������Ƒ��k�������A�Ăѕ䍂���ւƌ������ĎԂ𑖂点���B�Γc�@�ł́A�{�q�̏r�I����������l�ŁA��X�O�l�̓�����҂��Ă��Ă��ꂽ�B�����Ō�ɐΓc���Ƙb�����������x�b�h���[���ɓ���ƁA�┯�����߂Ă���Ƃ������������Ȓق����z�ŕ�܂�A�x�b�h��ɂЂƂۂ�ƒu����Ă����B���̑O�ɂ͂������ʂ̏��M��p�����Ԃɍ��킹�̐������Ă������ł��邾���ŁA���̂ق��ɂ͉����u����Ă��Ȃ������B�ނ��A���������̗ނȂǂ�������ɂ͂܂�����������Ȃ������B
�@ ���˂��˃h���L�����������̂��Ĝ݂�Ȃ������V�l�̍������̂��Ƃ����ł���邩�ǂ����͋^�₾�������A�Ƃ��������A��X�͈┯����̏��ق̑O�ō������A�č����ĐS�̒��ŋF����������B�����Ă��ꂩ��A�Γc���̍Ŋ��̗L�l�Ȃǂ��r�I����ɏڂ����f���Ă݂邱�ƂɂȂ����B
�@ ������{�Ɏ����������ɂ���ė������ƁA�O�A�l�����Ă���Γc���͍Ăь����������̏o�����N�����ĕ䍂�a�@�ɍē��@�����̂��Ƃ����B�����A�܂�������͂̐��~������݂����Ƃ͂����A��Ê������������Ȃǂ��ĕa���Ō�������R���A�ǂ����Ă��Ƃɖ߂�ƌ����������炵���B�����܂œ��@��������̂ł���A�{�l�̊�]�ʂ�Ɏ���ōŊ����}������悤�ɂ����ق����悢�̂ł͂Ȃ����Ƃ�����t�̔��f�������āA���ǁA�V���͒��N�Z�݂Ȃꂽ���̉ƂւƖ߂��ꂽ�B
�@ �Γc���͍Ō�̍Ō�܂Ńg�C�������͎��͂ł��܂���ƌ����Ă����Ȃ������Ƃ����B�����ł�ނȂ��A�r�I����͐Q������x�b�h���^�яo���ăg�C���̂����e�ɍĔz�u���A�����ɘV����Q�������B�����āA�ړ������x�b�h�̂����̕ǖʂɋ}篎�����݂��A�g�C���ɗ��Ƃ��ȂǁA�g�̂̎������������ɒ͂܂��Đg���N�����₷���Ȃ�悤�ȍH�v�������B��X���K�˂��Ƃ��A�x�b�h�͂��łɃg�C���e���猳�̕����ɖ߂���Ă������A���t�����ĊԂ��Ȃ��V���������͂��̂܂܂ɂȂ��Ă����B
�@ ���Ȃ�W C�ł��A�u�n���I��i�Q�v���邢�́u�n���I�d���̏�v�Ƃ������悤�ȈӖ������߁AW��C�̓���ԐF�ɁA�c��̕��������F�ɂ��āuWORKS� CREATIVE�v�ƃg�C���̃h�A�ɕ\�L���ĉx�ɓ����Ă����Γc���́A���̃g�C���ɍŌ�܂ł������A�n���𑣂��h�A�̃A���t�@�x�b�g�Ɍ�����Ȃ���Â��ɑ�������������̂������B����́A�܂�ŁA����̐��U���̂��̂��ЂƂ̑n���I�|�p��i�ł������Ƃł��������ȉ����Ԃ�ł������̂��B
�@ �Γc���Əo�����A���߂Ă��̉��~�Ɉē����ꂽ���̖�A�g�C���ɓ��낤�Ƃ������́A�u�䂪�Ƃ̃g�C���ɂ͂�������A���Ȃ��A�ꎞ�Ԃ͏o�Ă����܂����v�ƌ����ĕԎ��ɋ����Ă��܂������̂��B�uWORKS� CREATIVE�v�Ƃ������̟������\�L�Ƀj�����Ƃ��Ȃ���g�C���Ɉ�����ݓ��������́A���̓V��Ǝl�ʂ̕ǂɐ݂���ꂽ������ׂ��H���i�Q�Ɉ��|���ꂽ�B����ɂ͂܂��A�g�C���b�g�y�[�p�[�ɍ��荞�܂�Ă���p��̃N���X���[�h�p�Y���ɓ����������������i�ڍׂ́A�o�b�N�i���o�[�u�l���͗l�W�O�\�[�p�Y���F2000�N4��26���j�v�Q�Ɓj�B���ɂƂ��Ă��z���o�[�����̃g�C���̃h�A�e�̋�Ԃ��A�V���́u���E�ւ̗��H�v�̏o���_�ɂȂ����Ƃ́A�Ȃ�Ƃ����^���̔���ƌ����ׂ��ł������낤���B
�@ �Ō�̏u�Ԃ��K�ꂽ�Ƃ��@���ɂ͓�l�����������Ƃ������A�����Ər�I����̎�����Ȃ���A�Ƃ��ɋꂵ�ނ��Ƃ��Ȃ��A�܂�����Ƃ��������t���c�����Ƃ��Ȃ��i���̖���ɂ����̂��Ƃ����B�Ō�܂ňӎ��͂͂����肵�Ă����炵�����A���E���钼�O�̘V���̐���Ԃ�͂�͂葊���Ȃ��̂ł������悤���B���̑s��Ȏp��l�ڂɔ����̂͐Γc���̔��w�ɂ�������̂ł͂Ȃ����ƍl�����r�I����́A���ǁA�N�ɂ���Ă̕����Ȃ������̂��Ƃ����B
�@ �ǂ��������̂��Ɩ����Ȃ�����A�ꉞ�͐S����̂��̂��Ƃ��v���A���炩���ߗp�ӂ��Ă������T�������o�����Ƃ���ƁA�r�I����͂��̎�����Ŏ����Ȃ���A�Ȃɂ�當���̋L���ꂽ�ꖇ�̗p���������Ă��ꂽ�B���M�����̂����ȒP�Ȃ��̂ł͂��������A����͐Γc�����炪���O�ɂ������߂��⌾��ɂق��Ȃ�Ȃ������B����ɖڂ�ʂ����Ă�������������́A�����ŏ��߂ĘV���������������ƂɂȂ��ꂽ��A�̑Ή��̗������m�����̂������B
�@ ���V�i�Γc�B�v�j�̎���͎��̂��Ƃ�����ĉ������B
��A���V���̑��̋V���͈�؍s�Ȃ�Ȃ����ƁB������ʔv�̗ނ���ؕs�p�̂��ƁB
��A���T�̗ނ���Ɏ���Ȃ����ƁB���̋C����������A�ǂ����̎��P�c�̂╟���c�̂Ɂ@�@ ��t���Ă��炤���ƁB
�O�A��̂͐M�B��w�Ɍ��̂��邱�ƁB�A����͏��{�s�����R���ڂP�|�P�A�M�B��w��w�����܁@�@ ������B
�l�A�y�n�������̑���̏��L���͗{�q�Γc�r�I�̂��̂Ƃ��邱�ƁB
�܁A���S�ʒm�͉��L�̂��̂Ɍ���B
�@�@�����ˑ��E�Ƃ���
�@�@ �i�ȉ��ȗ��j
�@ �r�I����͐Γc���̈⌾�𒉎��Ɏ�邱�Ƃɂ����B�M�B��w�ւ̌��̂��}�����̂́A��w�����ǂƂ̑��k�̌��ʁA�Ȃ�ׂ������ق����悢�Ƃ������ƂɂȂ������炾�����B�܂��A��̂����u���Ă����ƁA�\��`������������҂����T�⌣�Ԃ����Q���Ď��X�ɗ��K���A�������Ŏ����邾���ł��e�ՂłȂ��Ȃ邾�낤���Ƃ��뜜���ꂽ�̂��A���̂��}�������R�̂ЂƂł������悤���B�J������A�s�삳��A����Ɏ��̎O�l�ɂ́A�i�����O�Ɉ�x�͉���Ă�����Ă��邩��A�����Ċ��ɉ������p�����Ă��炤�K�v���Ȃ����낤�Ƃ������f�������Ă̂��Ƃ������炵���B
�@ ���S�ʒm�̑��t��Ƃ��Ďw�肳��Ă����̂��A����������ꂽ�����̐l���������ŁA���̓_�ł��Γc���͍Ō�܂œO�ꂵ�Ă����ƌ����Ă悢�B���Ȃ݂ɏq�ׂĂ����ƁA�ŏ��ɖ��O�̋������Ă�������v�Ȃ́A�Γc���ƌ����ɂ����ďI���[���W�̂��������X�ŁA�V�������ܖ�ɏZ�݂��悤�ɂȂ����̂����v�ȂƂ̐e�������ڂ̌_�@�ł������B
�@ �ߔN�͘V�q��q�Ȃǂɂ��Ă̎a�V�Ȓ���ł������������ˑ�����́A�ȑO�A�M�B��w�̏����������Ă���ꂽ�B���Z�ȉ�������̉p���w�|��̑����܁X���߂Ă������Γc���́A�������珼�{���ʂɎd���̑ł����킹�ɏo�������Ƃ����Ȃ��Ȃ������B���̂����ɂ�������M�Z�̕��y���C�ɓ������Γc���́A���ܖ�ɏZ�݂����Ƃ����ӂ����̂������B�����ۂ��̉�������́A���̂��Ɖ��l����̋����ɏ��ق���ĐM�Z�𗣂�邱�ƂɂȂ�A���ǁA�Γc���������M�B�Ɏc�邱�ƂɂȂ����̂������ł���B
�@ ������Ƃ����b���r�ꂩ�������Ƃ��A�r�I����͂ӂƎv���o�����悤�ɗ����オ��A�ꖇ�̏����Ȏ��Ђ����o���Ă����B���̂܂ɏ����ꂽ���̂��͒肩�łȂ����A����́A�V���̃x�b�h�̕Ћ�����r�I����̉������܂��܌����o�������̂Ȃ̂������ł������B���̂̒������c�����Z�����菑�����������A�a���ɂ����ĐΓc���������ɏ����L�������̂ɂ͈Ⴂ�Ȃ��悤�������B�����āA�����Ɏc���ꂽ�킸���l�s�̓�߂�������́A�����ɂ����̋H��̊�l�Ȃ�ł͂̂��Ƃ��ƌ����Ă悩�����B
�\�\��҂��R���A�Ō�w���R���A����R���A�����Ĉ�Ԃ̉R���͕a�C�\�\���̎��Ђɂ͂����L����Ă���������ł���B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2002�N4��17��
�h���L�����@�Ǒz�L�i�O�j
�@ �������Ԃ�ɑ��ݓ��ꂽ�Γc�@�̉����͐[�����قɕ�܂�A�Ђ�����Â܂�Ԃ��Ă����B�d�������Ă��ďƖ����͂��������g���Ȃ������̂ŁA�K���X�˂⏬�����獷�����ގ��R�����������肾�����B�Q�X�g���[����r���O�̗l�X�Ȓ��x�i��Ƌ�ނ͂��ׂĕЕt����ꂽ���ƂŁA�K�����Ƃ��������ɂ͈Â��₽����C�������d�X�����Y���Ă�����肾�����B
�@ �Ō�ɐΓc���Ɖ���������ɓ����Ă݂�ƁA���Ԃ�̖{�I�ЂƂ��̂����ẮA�V���̎d�������x�b�h���݂ȉ^�яo����Ă��܂��Ă����B�ǖʂ̂��������ɏ����Ă������p�ʐ^�Ⓙ�����|�X�^�[�̗ނȂǂ����ׂĊO���ꂽ�蔍�����ꂽ�肵�Ă���A���Ă��̕����ɐ���������l�̎p���Â�����̂͂����������݂��Ă��Ȃ��悤�Ɏv��ꂽ�B
�@ �������A�����̔�������ɖڂ����Ă���ƁA����Ȋ�l�����݂��Ă������Ƃ𖾗ĂɎ������Ղ��A���܂����̕����ɂ͓�����c����Ă��邱�Ƃ����������B���̂ЂƂ͏��Ԃ�Ȗ{�I�ɂ�������l�܂�����Ԃŗ������Ԑ��X�̗m���������B�����悭�Q���肵�Ă��������̖{�I��A�����ɕ���ł����a���ނ̂ق��͂����ǂ��ɂ���������Ȃ��������A�ǂ������킯���m���������Ӑ}�I�ɂ܂Ƃ߂��A�����Ɏc���ꂽ���̂̂悤�������B�ȑO�͗m���Ƙa���Ƃ����荬��������Ԃł��������̕����̒I�Ȃǂɕ��גu����Ă�������A�V���̐�����ɏr�I����̎�ŗm����������ӏ��ɏW�߂�ꂽ�̂ł��낤�B
�@ �Γc���́A�a�a�b�����L�҂Ƃ��ă����h���ɑ؍ݒ��A�̂��Ɍ����Ђ̉p�a���T�̕ҏW�҂Ƃ��Ă�����y����̏���F�j�����O��勳���������ɏZ�܂킹�����Ԗʓ|���݂Ă������Ƃ������āA�u����N�v�Ɓu�N�v�Â��ŌĂԂقǂɏ��쎁�Ƃ͐e���������B�܂��A�u���Ƌ��ɋ���ʁv�̖���҂Ƃ��Ēm����̑�v�ۍN�Y���Ƃ����m�̒����������A���łɏq�ׂ��悤�ɉ����ˑ������l���勳���ȂǂƂ����N�ɂ킽��e�����������B
�@ ����ȉ��������āA�C�M���X����A�����Ă���́A�����ł̎d���̈�Ƃ��āA���������������ȉp�ĕ��w�҂����̖|��̎d������`�����肵�Ă������B�����̖���\�ɏo�����Ƃ��������V���͋���҂Ƃ��Ċ��s���ɖ���A�˂邱�Ƃ͂Ȃ��������A�����I�ɉ������{�͔��\�]���ɋy��ł���B�V���[���b�N�E�z�[���Y���̂𒆐S�ɐΓc�����|����s���Ă�����v�ۍN�Y���̏ꍇ�́A���ŕ��̈�ł͂��ׂĘV���ɓn���A�Ĕňȍ~�̈�ł�{�l������悤�ɂ��Ă��������ł���B
�@ �{�I�ɕ��ԗm���Q�̔w�\����������ƌ�����������ŁA�����O�E���[�h�i�[�A�f�[�����E���j�A���A�A�K�T�E�N���X�e�B�A�R�i���E�h�C���A�T�}�Z�b�g�E���[���A�t�H�[�N�i�[�Ƃ������p�Ă̒����ȍ�Ƃ����̖��O�����X�ɖڂɔ�э���ł����B�Ƃ��ɁA�u��Y�ǂ��Ə������v��u�}���n�b�^������v�ȂǂŒm����f�[�����E���j�A���̖���ڂɂ������́A���̐܂��Γc���͂��̍�҂̒Z�҂��Ȃɂ���Ă���Œ���������ȂƁA���Ζʂ̓��̂��Ƃ����������z���o�����B
�@ �V�������Ă��̕����ŕ�炵�Ă������Ƃ̂��܂ЂƂ̏́A�ǖʂɒ���`���ꂽ��Ȏ��n�}�ƃO���t�A����ɁuTREES�v�Ƃ����^�C�g���̈�т̉p�����ł������B�Γc���́A���O�A���X�̕��s�����v�ŃJ�E���g���A����������Ɋ��Z�����f�[�^�����ƂɁA��Ȏ��n�}��ǂɕ`������ł������B�ڂ����`�惋�[���̐����͏ȗ����邪�A�v����ɁA���s�������̂т�ɂ����������`�}�̎}�����قȌ`���Ƃ�Ȃ��珙�X�ɐ�������d�g�݂ŁA�������̂��łɐL�ѐ����}�̐�[�ɂ͓��{�e�n�̓s�s�����\�L����Ă�����������B���łɂ��Ȃ�̑���ɂ܂Ő����𐋂��Ă������̈ٗl�Ȏ��n�}�́A�s�v�c�ȑ��݊��������ĉ�X���q�̖ڂ�D�������̂������B�������A�������̉����n�}�̎}������ȏ㐬�����邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ����B
�@ ���`�}�̏�ɉ����ɕ`���ꂽ���t�ڐ�����̐܂���O���t�́A�Γc���̊���̋N�������Ƃɂ������̃o�C�I���Y����}�����������̂ŁA�Ɠ��̐F�������Ȃ���Ă���A�����̎}��Ƃ̑�����ʂɂ���ĂȂɂ��~�X�e���A�X�ȕ��͋C�������ɏ����o���Ă����B���߂Ă̗��K�҂Ȃǂ������ł��̕s���ȕlj��i�Ɍ�����̂��A�V���̓j���j�����Ȃ��牡�ڂŒ��߂��肵�Ă������̂����A����������ߋ��̘b�ɂȂ��Ă��܂����̂������B
�@ �uTREES�v�Ƃ����p���͐Γc�����g�̍�������ł������B�p������R���݂ɑ��邱�Ƃ̂ł����V���́A���т��p���������Ă����悤�ł���B���̂Ȃ��̈�т����̃t�F���g�y����p���A������n�}�̉E���ɏ����L�����̂����̎��uTREES�v�ł������B���O�̐Γc���͑��Ԃ��������Ȃ������Ă����B�u�ߍ��̃h���L�����͔����̐������ł͂Ȃ��A��̎��t���z���悤�ɂȂ�����ł����ˁH�v�Ȃǂƌy����@�����肷��ƁA���́u����A�ߍ��͖l�̃p�T�p�T�Ɋ����������Ⴂ���ɋz������Ă��炤�̂������łˁI�v�Ɛ�Ԃ��Ă������̂��B
�@ �V�������ւ̐[���v����ǂݍ����́uTREES�v�̍Ō�̓�s�ɁA���̓����͂��炽�߂Č��������B����܂ł͂Ȃɂ��Ȃ��ǂݒʂ������ŁA���̌����Ƃ���Ƃ�������܂�[���l�����肷�邱�Ƃ��Ȃ��������A���̎�����͖��ɂ��̌��т̓�s�����ɋ������B����́A�uEven a fool like me can make a poem. But only God can make trees.�v�Ƃ������̂������B
�@ �h���L���������̂��A���̎��̎������̉a�H�ɂ��ꂽ�悤�ɁA�s������̗��l�����t�I�݂ɗU�����݁A�Ő�̂������s�����Ė|�M���H���s�������Ƃ��y���݂ɂ��Ă������̘V�����A�����ɒ��z�҂̑��݂��������Ă������Ƃ́A�l���Ă݂�ƂȂ�Ƃ����S�[�����Ƃł������B
�@ �h���L�������̐��߂�_�������Ȃ�_�ł������̂��͎��ɂ͂킩��Ȃ��B�����A���ꂪ�A�߉ނł��L���X�g�ł��A���[�ł��A�����Ă܂����{�×��̐_�X�ł��Ȃ��������Ƃ����͊m���ł���B�V���ɐu�˂邷�ׂ̂Ȃ��Ȃ������܂ƂȂ��ẮA���̐_�̓h���L�����_�Ƃł����Â���ׂ��V��̒��z�ҁA���邢�͒��z�T�O�ł������ƍl���邵���Ȃ��B
�@ �Ō�Ɏ��́A���܂��h�A�ɁuWORKS CREATIVE�v�̓��̂��邳�ꂽ�܂܂̃g�C���ɓ������B���Ă��̎l�ʂ̕ǂ������Ă������X�̎ʐ^��|�X�^�[�A�G�t���ނȂǂ݂͂Ȕ�������A�Ђ̐Ղ������ɁX�����c����Ă������A�������ꖇ�������̂܂܂ɂȂ��Ă���ʐ^���������B
�@ ����́A�ǂ��Ȃ̂��ꏊ�͒肩�ł͂Ȃ��������A�L�����u�̂悤�ȂƂ���������T���O���X���������啿�̘V�l�����̂悤�ɋ삯�����Ă���ʐ^�������B�������ȉe�ɂ��������̊�Ȑl���͑��d�ʂ��ɂȂ��Ă��āA���Ăȗ֊s�𑨂�����m������̂�c�������肷�邱�Ƃ͍���������A����ɂ�������炸�A���t�ł͌`�e���������Ɠ��̑��݊������킶��Ǝʐ^�̒�����Y���o�Ă��銴���������B
�@ �������A���̎ʐ^�̃��f���͐Γc�����̐l�ɂق��Ȃ�Ȃ��������A�|�p���̍������̈ꖇ�̎ʐ^�قǂɉ����̘V���̎p���悭�`������̂͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ����C�����ĂȂ�Ȃ������B���߂Ă��̃g�C���ɓ����������A���̎ʐ^�����Ď��͕s�v�c�Ȋ������o�������̂����A���̓������炽�߂Ă��̉f���ɂ����ƌ�����L�l�������B
�@ ���Ɠ��l�ɁA����ŋ��R�o�������V���̓ŋC�̗��ƂȂ����s�쏟�O�J�����}���́A�₪�āu�����̂��v�Ƃ����^�C�g���̟������ʐ^�W�����s����^�тɂȂ����B���̒��Ɏ��^����Ă��鐔�X�̎ʐ^�̔�ʑ̂͂��ׂĐΓc���Ƃ��̐g�ӂ̎����ɂ������A�ʐ^�W�̕��ς��ȃ^�C�g�����炵�ē@���̈�p�ɐ�����V�������̃G�S�m�L�ɂ��Ȃ��̂������B���̎ʐ^�͂����̒��̑�\�I�Ȉꖇ�ŁA�s�삳���̍�i�ł��������Ƃ����킯�ł���B
�@ ���܂́A�ʐ^�W�u�����̂��v���茳�ɂ�����A�C���������ł����̎ʐ^�����邱�Ƃ͂ł���̂ł��邪�A�����̑傫���Ƃ������ƂɂȂ�ƁA���̐Γc�@�́uWORKS �ECREATIVE�M�������[�v�ɂ�����ӏ܂ɂ͋y�Ԃׂ����Ȃ������B�����������炱�̏ꏊ�ł��̎ʐ^��ڂɂ���̂͂��ꂪ�Ōォ������Ȃ��ƍl���Ȃ���A���͂����ނ�Ƀg�C���̊O�ɏo���B����قǂɃg�C������o��̂��S�c��łȂ�Ȃ����ƂȂǁA�����̐l���̒��Ō�ɂ���ɂ����ꂪ��x����ɈႢ�Ȃ��Ƃ����v���������B
�@ �Γc�@�����Ƃɂ���ƁA���̐ԏ��т̒��𑖂蔲���V����Ƃ����������̑O�ɏo���B���̘V�܂̋������͘V���Ə��߂Ĉ��������̖�Ɉē����ꂽ�z���o�̓X�ł��������B�����A���̓��͂��܂��܋x�Ƃ������̂ŁA���ǁA�������炵�炭�������Ƃ���ɂ���㞊�Ƃ����������Ɍ��������Ƃɂ����B���̋������͐M�B��т̕������e�[�}�Ƃ����������ʐ^�Œm����n���̒����Ȏʐ^�ƁA�㞊��������o�c�̂��X�ł���B�ʐ^�ƂƂ��Ă̏㞊����ɂ́A�M�B�ݏZ�̍��C.W.�j�R������Ƌ����ŏo�ł��Ă���u�M�B�̎l�G�v�Ƃ�����i�W�Ȃǂ�����B
�@ ���̋������Ɏ����ē����A���̂��łɏ㞊����������Љ�Ă��ꂽ�̂��ق��Ȃ�ʐΓc���ł������B�������̋����E�l���������Ă�܂Ȃ��㞊����́A�S�g�S������߂ē��X�����ł��̎d���ɗ�ށB�����Ŕ[���̂����Ȃ������͂������ďo���Ȃ��Ƃ��������̂��Ƃ͂����āA�ׂ߂̋��������A����Ƃ����A���Ƃ����A���̋����Ƃ����A�܂��ɐ�i���̂��̂Ȃ̂��B
�@ ���邭�����������͋C�̓X���ɓ���A�������肵���ؐ��̃e�[�u���ɒ����ƁA���͂��̓X�������߂̓V�b�����𒍕������B���̋����𒍕�����ƁA�₽���^���ɑł����Ă̋��������ʕ������������̐������Ȃ���̂����ʕ�d�i�Ƃ��ďo����Ă���B���R�Ȃ܂܂̋����̖����q�ɂ��m���Ă��炢�����Ƃ����㞊����̋����N�w���A���̐������ɂ͂��肰�Ȃ����߂��Ă���ƌ����Ă悢�B�܂��͂��̐������𖡂킢�A���̂��Ƃŏ\��ނقǂ̋�����V�b�����ɔ�������킯�Ȃ̂����A���̂ꂪ�܂����ɔ������̂��B�V�̌b�݂Ƃ������ׂ��n���Y�̐V�N�ȐH�ނ��I�݂ɒ��������Ɠ��̋�ƁA�㞊�����̍��̂��鋼���Ƃ̃R���r�l�[�V���������Q�Ȃ̂ł���B
�@ �X��̏㞊����͉��̂ق��Ō����ɋ�����ł��Ă���Œ��炵�������̂ŁA�Γc�����ÂтȂ���V�b�������ܖ��������ƁA�㞊����̑f���炵�����i�ʐ^��i���W������Ă���ʓ��̃M�������[��q�����A���̂܂ܐÂ��ɓX�����Ƃɂ����B�l���Ă݂�ƁA���̏㞊�ŘV���Ƌ�����H�ׂ��̂͂�������x�������������A���̎��ɒ��������̂��������V�b�����������B
�@ �䍂�̒��𗣂��O�ɋv�X�ɖ�����̐��ʂł����߂Ă������Ǝv�������A�㞊�����Ƃɂ���Ƃ����ɑ剤���T�r�����ʂւƌ��������B�ό��V�[�Y�����͂���Ă���Ƃ����đ剤���T�r����тɐl�e�͂܂�ŁA������̂قƂ�ɘȂގ҂ȂǑ��ɂ͒N�����Ȃ������B�������������̂Ő��ʂ͂����̔����قǂ����Ȃ��������A�u�����v�Ƃ������ɒp�����A���������݂Ȃ�����A�����ł͑N�₩�ȐF�̗̐��������������ɍוR�̂悤�ȗt�X�ƐL���Ȃ���A�������Ɨh��Ă����B
�@ �����Ȃޒn�_�̂������㗬�ɂ�����̐��Ԃ́A�����ς�炸�������Ɖ�]�𑱂��Ă������A�يE�ւƋ����Ă������V�������̊ݕӂɗ����Ƃ͂����Ȃ������B���̓��̂��Ƃ��͂킩��Ȃ����A������͎����܂����̐��E�������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̓��܂ŁA����ɂ͂��̓��̂̂��܂ŁA���V�f��u���v�̃��X�g�V�[���ɓo�ꂵ���������̐��Ԃ͉�葱���Ă���̂��낤���\�\����ȂƂ�Ƃ߂��Ȃ��z���ɋ���Ȃ���A���͖���������Ƃɂ����B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2002�N5��8��
���F��˂���̑ސE
�@ �l�����̂��ƁA�k�C�������}�ւ��ЂƂ͂����B�����o���l���ɖڂ����ƁA�����ɂ͋��F��ːM�j����̖����������B�����낤�Ǝv���Ȃ��炷���ɕ�݂������Ă݂�ƁA�u��E���v�Ƃ������C���^�C�g���Ɂu�ܒj�E60�N�̋O�Ձv�Ƃ����T�u�^�C�g���̂�����������Ɠ�CD��������o�Ă����B�Y�t����Ă����莆��ǂނ܂ł��Ȃ��A���̒�����CD�������Ӗ����Ă���̂������ɂ킩�����B�ЂƂ����Ȃ�ʊ��S�������[���Ɋo���Ȃ���A�u�������A��˂���A��N�ސE�����ȁc�c�v�Ǝ��͎v�킸�ꂢ�Ă����B
�@ �l�\���N�̒����ɂ킽���˂���Ǝ��Ƃ̕��ς��Ȑe���ɂ��Č��s�����̂͗e�ՂłȂ��B���̏펯���猩�ĂȂɂ����܂��ς���Ă���̂́A�����I�ɂ��߂��e���ł���Ƃ����̂ɁA���̊Ԃɒ��ڂɉ�����̂����������\����x�ɂ����Ȃ��Ƃ������Ƃł��낤�B����ɂ�������炸�A�u�e�F�v�ȂǂƂ������t����z�������ȏ�̐S�̒ʂ��������A��X��l�̊Ԃɂ��������Ƃ����͊m���ł���B
�@�\�\���āA�����ƁA���̓x�O�\���N�Ԃɂ킽�鋳�E���������̎O���O�\����������Ė����ɏI���邱�Ƃ��ł��܂����B�������d�ɊF�l���̂����Ɗ��Ӓv���Ă���܂��B������_�@�Ɏ����j�ƋL�OCD���쐬�v���܂����̂Ō�Δ[�������\�\�����L���ꂽ��˂���̈��A���ɖڂ�ʂ����̔]�����A���������z���o�̐��X�����n���̂悤�Ɏ��X�Ƃ悬���Ă������B
�@ �Z�\�N�ɂ킽��ߋ��̋L�^��Ԃ��������j�Ɂu��E���v�Ƃ����^�C�g������������Ƃ����āA��˂��}�U�R���������킯�ł͂Ȃ��B���̒m�邩����A�Ⴂ�������˂���͐ӔC���Ǝ����S���l��{�����A�܂��Ɂu�j�̒��̒j�v�Ƃ������t���҂�����̐l���ł������B��˂������j�ɂ��̂悤�ȃ^�C�g���������̂́A����Ȃ�ɗ��R�������Ă̂��Ƃ������̂��B
�@ �I�풼��̏��a��\��N�͍����ɐԗ������������B�����āA�����܍�������˂���Ƃ��̕��e�̊O�g��������̉u�a�Ɋ������A�n���̕a�@�ɓ��@�����B�����A������̓���ȂǕs�\�����������̎���ɂ��킦�A���Âɂ��������V���l�̈�t�̊Ԃɂ͗Ö@�ɂ��Ĉӌ��̑��Ⴊ���������A���Ԃ͈����̈�r�����ǂ����B���V�̈�t�̂ق��͐H�����Ƃ点��ׂ��łȂ��ƍl���A�Ⴂ��t�̂ق��̗͑͂̏��Ղ�h�����ߐH���͎�点��ׂ����ƍl�����悤�ł���B���ǁA�V��t�̕��j���I�ꂽ�̂������ł��邪�A�O�g����̂ق��͂��ꂩ��܂��Ȃ��S���Ȃ��Ă��܂����B�܂��c��������˂���ɂ́A�ׂ̂�������̊�����z�������Ӗ����Ă���̂����������ł��Ȃ������Ƃ����B
�@ ��˂���̂ق����H��f����Ă������߁A�Ƃɂ������������ĕ��������Ăǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ������Ƃ̂��Ƃł���B�ǂ������ʂ��̂Ȃ�̌Ⴊ�q�ɂ��߂ĉ�����H�ׂ����Ă�낤�ƌ��ӂ�����e�̂Ƃ߂���́A�钆�Ɉ�҂̖ڂ𓐂�ŁA�H�Ɠ�̓����Ƃ��Ă͋M�d�ȍ����̂��������u�b�������v��^�����肵���B�Ƃ߂���̋�J�̎����ł��邻�́u�b�������v�̖������܂��Y����Ȃ��ƒ�˂���͌���Ă���B
�@ ���ꂩ��قǂȂ��A��t���瑧�q�̎����߂��Ƃ̐鍐���������Ƃ߂���́A�����������Ȃ��̂Ȃ玩��ɘA��ċA�낤�ƍl�����B�`���a�Ƃ������Ƃ��������̂ŁA�邱������ݕ���Ԃɏ悹�A�l�ڂ�E��Œ�˂�����ƂւƘA��߂����̂��Ƃ����B�A���������Ɖh�{�����ł��肬��̂Ƃ���܂ő̗͂����Ղ������A�����̉��������t���A��˂���͊�ՓI�Ɉꖽ���Ƃ�Ƃ߂��B
�@ �܂��A���Z�O�N�̎O���A��w���������Ƃ̋A��̎Ԓ��ł����̒��q�������Ȃ����B�A���͂��Ȃ�M���o�Ĉ����������̂ŁA���^���|�����ĐQ����ł����B����҂��ĂсA�������v��������G�f�����Ă�������肵�����A����ł��a�����킩�炸�A���̌���Ђ�����Q�Ă�����肾�����B
�@ �����A��e�Ȃ�ł͂̒����ő��q�̗l�q�������ł͂Ȃ��Ɣ��f�����Ƃ߂���́A���j���ł������ɂ�������炸��˂����x�ǖ�s�̑�a�@�ɘA��Ă����A���ʂɐf�@���˗������B�����͎Y�w�l�Ȉゾ�������A�G�f����Ƃ����ɒ��������������Ă���ꍏ�𑈂����Ɣ��f�A�ً}�ɊO�Ȉオ�Ă�Ď�p���Ƃ肨���Ȃ�ꂽ�B�������j�����O�ŁA�����������Ή����x�ꂽ�痎������Ƃ��낾�����Ƃ����B��p�̍������^���������߁A�O���O�Ӎ��M�ƒɂ݂ɂ��Ȃ���ꐇ���ł��Ȃ��������������A���̎�����e�Ƃ߂���̓I�m�Ȕ��f����˂���̈ꖽ���~�����̂������B
�@ ���̐��ɐ����������������ɁA���̌��x�ɂ킽���ĕ�e�̂Ƃ߂���ɖ����~��ꂽ��˂���́A�₪�āA�u�����̖��́A��̖����̂��̂��v�ƍl����悤�ɂȂ�A��w���ƌ�A�V�E�Ƃ������ׂ����E�ɏA���ƁA�S�g�S����X���ċ���̎d���ɐs�����Ă����B���a�\�Z�N�ɂƂ߂��S���Ȃ������Ƃ��A�ꂩ�����������͎��������̂��̂ł͂Ȃ��Ǝ�������߁A�܂��A�u���������đ��l�̂��߂ɐs�����v�Ƃ������A�O�g����̎c�������������Ȃ���A���X�ɐ�����d����̓�ɒ��݁A����ɔ������X�̍���ɑς��Ă����B
�@ �O�\���N�Ԃɂ킽���˂���̋O�Ղ̑S�e�������ŏЉ�邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A����҂Ƃ��Ă̂��̐^���ȓ����͗B�X�h���ɒl����B��˂���Əo�����A����҂Ƃ��Ă̕��тȂ����̏�M�ɐG��A������E�C�����������A�Ȃɂ��ƌ[�����ꂽ�肵�������q�̐��͂����Ȃ��Ȃ����Ƃ��낤�B
�@ �����A�����ꂽ����҂̏�Ƃ��āA������x������Ƒ��A�Ƃ��ɉ��l�̋�J�͕����̂��̂ł͂Ȃ������ɈႢ�Ȃ��B�M���V������̃\�N���e�X�ɂ݂�܂ł��Ȃ��A�×��A���g�I�ȋ���҂Ƃ������̂́A���S���ʂŎ����̉Ƒ��ɂЂƂ����Ȃ�ʋ�J����������̂Ƒ��ꂪ���܂��Ă��邩�炾�B����łȂ��Ă��A���t�Ƃ������̂́A�ǂ�ȂɌ��g�I�ɋ���ɐs�����Ă�����͋���҂Ƃ��ē��R�̂��Ƃ��Ƃ�������A�����ł��y���ȍs�ׂ┻�f�̌�肪�������ꍇ�ɂ͋���҂̂����ɂƐӂ߂���B����ɎO�\���N�ԂƂ͂������A����͒����Ȃ�����Y�Ɗ����̔N���ł��������ɈႢ�Ȃ��B
�@ ��A�Ƃ߂��S���Ȃ������ƁA�\�y�̒�����́A���w�Z���w�������w�𑲋Ƃ����������𑗂�悤�ɂȂ�܂łɒ�˂���������e�퐬�ѕ\���ނȂǂ����������B�@�Ƃ߂������ɔ�߂Â��Ă������O�̎����ւ̐[���v����z�������Ƃ��A��˂���́A���������炩�̌`�ŕ\�킵�c�����Ƃ��K�v�ł͂Ȃ����ƍl����悤�ɂȂ��Ă����B�����āA���̎O���̑ސE���@�ɁA�����j��Ҏ[���邱�Ƃɂ���āA���N�̌��Ă��������悤�ƌ��ӂ����̂������B�����ɂ���Ă͂�����ƈٗl�ɂ�����u��E���v�Ƃ������ς��ȃ^�C�g�����I�ꂽ�̂́A��˂��g�ɂ���Ȕw�i�����������炾�����B
�@ �k�C����x�ǖ쑺�ݏZ�̒�ːM�j�����l���̑��݂�m�����̂́A���������w�ٔ��s�̎G���̓ǎҗ���ʂ��Ă̂��Ƃ������B�������������̗����̏��w�Z�ɒʂ��Ă������́A�ǂ��������̒n���ɏZ�ސl�ƕ��ʂ��������Ǝv�������A�K���ȑ����T���Ă���Ƃ��낾�����B���V�i�C�ɕ����ԌǓ��̈�ӂʼn����y���Ȗ{�y�̉e�ɓ���鏭�N���������ɂƂ��āA���ʂ����́A�����Ƃ͖����ȕƒn�̏����Ɩ��m�̃h���}�Ɉ���L�����E�Ƃ��q���őP���B��̎�i���Ǝv�����������̂��B����Ȑ܁A���Z�̍Z�̂ɂ��ďq�ׂ���˂���̓��e�L�������܂��ܖڂɂƂ܂����̂ł���B
�@ ��˂���̂ق��ׂ͂ɕ��ʂȂǂ�]��œ��e�������킯�ł͂Ȃ������̂����A����������w�N�����̂��̐l�̂��Ƃ����ɋC�ɂȂ������́A���ǂ��ǂ������ʂƕM�Ղ̎莆�������Ĉ���I�ɕ��ʂ�\������ł݂��B���ꂪ�A�Ȍ�l�\���N�ɂ��y�Ԑe���ɔ��W���悤�ȂǂƂ́A�ނ��A���̎��ɂ͑z�������Ȃ����Ƃł������B���͂������ĉ^���_�҂Ȃǂł͂Ȃ��̂����A�l���ɂ͂܂�ɁA�N���̎�ł��炩���ߎd�|�����Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv�������Ȃ�قǂɕs�v�c�ȏo���������邱�Ƃ����͔F�߂�������Ȃ��B
�@ �莆�𓊔����Ă��牽�T�Ԃ����߂��A��͂�ʖڂ������̂��ƒ��߂��������ɂȂ��āA�悤�₭�k�C�������ʂ̎莆���͂����B�������̍����o���l���́u��ːM�j�v�ƂȂ��Ă����B���S����肵�Ȃ����}���ŕ����J���ƁA�ƂĂ���ΈႢ�̐l�����������̂Ƃ͎v���Ȃ��قǂɐ��������̂Ƃ������肵�����͂̎莆�������ꂽ�B�莆�ɂ́A�ˑR�̂��Ƃŋ���������ǁA���ʂ̌��͊��ŗ��������|�̂��Ƃ��L����A���̂ق��ɁA��˂���̉Ƒ��ɂ��Ă̊ȒP�ȏЉ�Ȃǂ��Ȃ���Ă����B
�@ ���ƂɂȂ��Ă킩�������Ƃ����A��˂�����܂��A���̍��͂܂��m��l�̂قƂ�ǂȂ������x�ǖ�~�n�̈���ɂ����āA�L�����E�𖧂��ɖ����鏭�N�������̂��B��ȉ��ł͂������̂����A�Ƃ������������āA�k�̑�n�̂Ȃ��قǂƓ�̂͂Ă̓��ɏZ�ޗc�����N��l�̕��ʂ��n�܂����̂������B
�@ ���ꂩ��Ƃ������́A��˂���Ǝ��Ƃ̕��ʂ͘A�ȂƑ����A�������\�ܔN����Ό������ꋎ�����B���̊ԂɋN���������݂��̋����قǂ̐g�ӂ̕ω��ɂ��ẮA���N�̎莆�̂��Ƃ��ʂ��ďn�m���Ă������A���ڂɊ�����킹��@��͈ˑR�Ƃ��Ĉ�x���Ȃ��܂܂Ɏ��͉߂��Ă������B���߂Ď莆�����킵���Ƃ��ɂ͗c�����N��������X�́A������\�㔼�Ή߂��̐N�ւƕϖe�𐋂��Ă����B���łɒn���̖k�C���Œ��w���t�ɂȂ��Ă�����˂���́A����u�肵�ĕ��C�����R�Ԃ̈ꋉ�ƒn�̊w�Z�ŗD�ꂽ��苳��҂Ƃ��Đ��X�̎��H��ς݁A���͂킽���ŁA���Ă͉��������̑��݂ɂ����Ȃ����������̒n�ɂ����āA�����₩�Ȃ������匤���̓�����݂͂��߂悤�Ƃ��Ă����B
�@ ���̔N�̌܌��̂��ƁA���N�̖������������D�̋@��K�ꂽ�B��˂���������Ƃ����̂ł���B���̃`�����X���Ă͂Ȃ�Ȃ��Ǝv�������́A�����ɏo���̏����𐮂��A�������o�Ȃ̂��ߋ}篖k�C���ւƗ������Ƃɂ����B���˂Ă���k�C���ɓn�������ƍŏ��ɓ��ޓy�͒�˂���̌̋��̂���ɂ��悤�ƌ��߂Ă�������A���ق�D�y�Ȃǂɂ͖ڂ����ꂸ�A�Ђ������Ԃ����p���ł܂����ʗF�̑҂�x�ǖ쑺���Љw�ւƒ��s�����B
�@ ��Ԃ��x�ǖ~�n�ɓ���ƁA�ԑ�����Ɏc���Ղ��Y��ȏ\���A��̎R���݂��������B���ꂪ�\���x���Ƌ����M���Ȃ�悤�Ȑ[���������o�������Ƃ����܂��͂���Ƒz���o���B�x�ǖ�s���班����ɉ������Ƃ���ɂ����x�ǖ�̊��Љw�ɍ~�藧�������́A�ɂ��₩�Ȕ��݂̂Ȃ��ɂ��Â��ȋْ����߂ĉw���ɘȂޖk�̗F�ƁA���ɔO��̑Ζʂ��ʂ������Ƃ��ł����̂������B���ɏ��a�l�\�l�N�܌��\���\�\���߂Ď莆�������������琔���Ă݂�ƁA���ɏ\�Z�N���̏t�H���Ƃǂ܂�Ƃ���Ȃ����J��Ԃ���Ă����B
�@ �����̌������̍ہA�i��҂��o�Ȃǂ����̈��A�̒��Łu���傤�Â�����A���傤�Â�����v�Ɖ�����J��Ԃ��̂��Ă��A���ꂪ�N�̂��ƂȂ̂������ɂ̓s���Ƃ��Ȃ������B���p���������b�����A���͂���܂ł̏\�Z�N�ԂƂ������́A�u��ˁv�Ƃ������́u�����Â��v�Ɠǂނ��̂Ƃ���v���Ă����̂ŁA�u���傤�Â�����v�Ƃ����������ɂ��Ă��A���炭�͂��ꂪ��˂���̂��Ƃ��Ƃ킩��Ȃ������̂ł���B�O���ɒ�˂���ƑΖʂ������ォ��A�u�����Â�����v��A�����Ă����͂��Ȃ̂����A�����̎��̋C������z�����Ă̂��Ƃ������̂��낤�A��˂�������̎��͂̐l�X���A�Ȃɂ��Ȃ�������Ď��̌ĂъԈႢ�������Ă���Ă����̂������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2002�N5��15��
���̎ʐ^�̐l���́H
�@ ��˂���̘Z�\�N�̋O�Ղ�H��ɐ旧���āA�Y�t����Ă������M�ɖڂ�ʂ��Ă���ƁA�Ō�̂ق��Ɂ\�\�����j�ɂ͒f��������A�ʐ^�ƕ��́A�Z�̂�����ɍڂ������Ă��������܂����B�������������\�\�Ə�����Ă����B���Ԃ�A���O�ɒʍ�����Ǝ��̂ق����K���݂��Ă��܂����˂Ȃ��ƍl�����̂��낤�A��˂���͎��㏳�������߂��ɂł��̂������B
�@ �G�b�A����ȁH�\�\�Ǝv���Ȃ���Q�Ăăp���p���ƃy�[�W���߂����Ă݂�ƁA�Ȃ�قǁA���������Ɂu�{�c�N�v�Ƃ������O���o�ꂵ�Ă���ł͂Ȃ����B���ꂠ��Ǝv���Ȃ���A��˂���\�����������̑��Ղ��L�����y�[�W���J�������́A������債���܂ܓ̎ʐ^�Ƃ��̘e�̈ꕶ�Ɍ��������B
�@ �\�\�������ɂ͖{�c�N���������痈�Ă���A���Ɋ��������B���ۂ̖ʉ�͂��̎������߂Ă��������A���Љw�ňꌩ���Ă����{�c�N�ƔF���ł����B���̓��i�\���j�́A�V���ƂȂ���c�Z��ɂē�l�ŐQ�H�����ɂ��A����܂ł̘b�ɉԂ��炢���B�\����̌ߑO���́A�ԂŐV���̉Ԍ��ɍs���Ă����\�\
�@ ���������A��˂���͌������������Ƃ����̂ɁA�����̌ߑO���Ɏ���Ԃ̃n���h���������āA�돟���₳��ɂ��̂ނ������ɂ���V���܂Ŏ����ē����Ă��ꂽ�B�������̖{�Ԃ��ߌ�ɍT���Ȃɂ��Ə��������邾�낤�ɂƁA������͋C���C�łȂ������̂����A�Ȃɂ��S�z���邱�Ƃ͂Ȃ�����ƌ����āA��˂���͎��̂��߂ɋM�d�Ȏ��Ԃ������Ă��ꂽ�̂������B
�@ ��˂���̕��͂��̂��̂͂Ȃ�Ƃ����S�[�����̂��������A���͂��̍���ɂ���̎ʐ^�̂ق��������B�Ȃ�ƁA�ꖇ�̎ʐ^�ɂ���l�݊w�����p�̐l���͏\���̎��̎����g�ɂق��Ȃ�Ȃ������B�������A�u��w���̖{�c���e�N�v�Ɛ������܂ŕt�L����Ă���B��w���ɎB���������菑�p�ʐ^����˂���ɑ����Ă����炵���̂����A����Ȏʐ^�Ȃǂ������̎茳�ɂ͎c���Ă��Ȃ��B�Ȃ�ł܂������낱��Ȏʐ^���Ɠ��S�Ԗʂ���v���ɋ���Ȃ�����A���́A�ʐl�Ƃ��������X�������̉ߋ��̌��e�����炭�Î����������B�����ɂ����^�����Ȃ��̍זʂ̎p�ɂ́A���N�\���������̂��邢�܂̎��̂ӂĂԂĂ����Ȃǔ��o���������Ȃ��̂������B
�@ �����ꖇ�̎ʐ^�ɂ́u�����������A�{�c�N�Ɓi�V���R�j�v�Ƃ������������Ă����B���̖ƎԂ��o�b�N�ɂ��ē�l����ŎB�����ʐ^�����A��˂�����������z�ɔR����N���̐^������Ƃ��������ŁA���z�̔R��������点�Đ����邢�܂ƂȂ��ẮA����܂��C�p�����������Ƃ��̂����Ȃ������B���߂Ă��̋~���́A�����̎ʐ^��ڂɂ���ł��낤�̂���˂��̊W�҂Ɍ�����ł��낤���Ƃ������B
�@ �ŋߌ�����������̖������܂��܉Ƃɖ߂��Ă��Ă��āA���̘e������̎ʐ^��`�����݂Ȃ���`���`�������Ă����B
�u�ց[���A�N���Ǝv������A���ꂪ�˂��c�c�A���܂�肸���ƃ��R�E���������I�v
�u����A���܂̓A�z����H�v
�u�܂��A�z�A���炢�̂Ƃ���ɂ��Ă������ȁc�c�v
�u�Ȃ����c�c����A���܂��̓z�A�̖�������A����ς�A�z����ȁI�v
�u�h�̎������Ȃ������ł����Ɋ��ӂ��Ȃ��Ƃ����Ȃ�����Ȃ��H�v
�u�h�̎������ƎO���炢�͂���Ɛe�Ƃ��Ă͔[���������I�v
�@ �v���������ʎʐ^�̓o��ɔ����낽���Ȃ���A���͖��Ƃ�������Ȃ��킢���Ȃ����t�̉��V���J��Ԃ��L�l�������B
�@ ��˂���̎����j�̂���ɂ��Ƃ̂ق��ɂ́A�ȑO�ɖk�C���𗷂����Ƃ�����Ȏ��ŏ����������Z�̎l��̃R�s�[�̂ق��A�ْ��A�u���ł̗��H�v�i���R�����Ёj�̒��́u�x�ǖ�̗F�v�Ɓu�ϖe���Ă����x�ǖ�v�������͂܂ł����^����Ă����B��˂���Ǝ��Ƃ̏o�����̎����猻�݂Ɏ���܂ł̓�l�̋O�Ղ���Z���ɂ܂Ƃ߂���i�ŁA�F�̑ސE���L�O���鎩���j�̒��ɏЉ���قǏo���̂悢������̂ł͂Ȃ��������A������̎��㏳����O��Ƃ������F�̎d�V�Ƃ������ƂɂȂ�Ƃ�ނ����Ȃ����Ƃł͂������B
�@ �͂��߉p��̋��t�Ƃ��ċ��d�ɗ����Ƃ̑���������˂���́A�₪�ĉ��y�A�Ȃ��ł����y�̓��ɖڊo�߁A�ЂƂ����Ȃ�ʌ��r��ς��ɁA���y�̋��t�Ƃ��đS���ɍL���m���鑶�݂ƂȂ��Ă������B�����āA1984�N�̈��썬�������c�̃J�i�_���t���s����ɁA1987�N�̈���s�������c���[���b�p���t���s�A1990�N�̃\�A�E�������t���s�A1993�N�̓��č����𗬎g�ߒc�i�k�C���������c�j�̃A�����J���t���s�A1996�N�̃g�D�C�}�[�_����j�������c�n�o���t�X�N���t���s�A2001�N�̓��{�E�C�^���A�����𗬎g�ߒc�C�^���A���t���s�ƁA���X�̍����c�C�O�����̎����ɐs�͂���B
�@ �Ȃ��ł��\�A�E���������A�A�����J�����A�n�o���t�X�N�����Ȃǂɂ����Ă͍����c�̎w���҂Ƃ�����łȂ������ǒ��Ƃ��Ă�煘r�������A�Ƃ��ɃA�����J���t���s�ɂ����ẮA���A�{���ł̌������͂��߂Ƃ���A�����J�e�n�ł̐��X�̌�����听���ɓ������B�����ɂ��Ă̍����Ȋ����L�^�Ȃǂ���˂���̎����j�Ɏ��߂��Ă������A���炽�߂Ă��̑��Ղ̑傫���ɐS�������v���ł��������B
�@ �����̋L�^�ɖڂ�ʂ������ɁA���́A���č����𗬎g�ߒc�A�����J�h���̑O�N�̏H�A�����a�J�̂��邨�X�ŁA���y�̎w���҂Ƃ��Đ��E�I�ɍ����ȃ��V�A�̃C�G���}�R�[�o���j���͂݁A��˂����A��͂�k�C���̒����ȉ��y�Ɩ���ڂ���ȂǂƂȂ��₩�Ɋ��k�����Ƃ��̂��Ƃ�z���o�����B���̐Ȃŋv�X�ɑΖʂ�����˂���́A�����Ԃ�Ƃ��̌����Ɋј\�����A����ɔ�Ⴗ�邩�̂悤�ɓ��t�������̈����������Ȃ��̂ɂȂ��Ă����B
�@ �����A����܂ʓw�͂̌��ʂƂ��āA�L�����E���삯�߂���Ƃ������N�̍�����̖����ʂ����A����ɂ͂��̖������傫�����肠����̂Ɉ�ĂĎႢ����ɓ`���������Ɛs�͂���p�ɁA���͓��S�����Ȃ���ʌh�ӂ��o�������̂������B�u���K�i�O�̏��N�v�ɂȂ�ʂĂĂ͂��Ă��A��˂���̐S�̖{�����̂��̂́A��X�����N�ł��������Ƃ��������ς�邱�ƂȂ������ł���^���ł��邱�Ƃ�m���āA���͐S��������������̂ł���B
�@ ���t���Ɗј\�ł͒�˂���ɉ���������͂�����̂́A�����܂�����̓Ő�ɂ͂����Ԃ�Ɩ����������A�����I�ŐԖʏǂ̌X�����������c�����̎p����傫���E�炷�邱�Ƃ��ł����B�E�炵�߂��Ď��ӂ̐l�X�Ɏv��ʖ��f�������Ă���̂ł͂Ȃ����Ɣ��Ȃ����Ă�����������A������ɂ������Ԃ̗���Ȃ����̐l���ɂ����ẮA�E���̂Ă��k��T���o���Z���Ȃ������ƂȂǂ��܂���ł���͂����Ȃ��B
�@ ��˂���Ƃ͑I�������@���܂�ňقȂ�͂������A���̂ق��͎��Ȃ�̂�肩���ŁA���ė����̈�ӂʼn������������E�̈ꕔ���炢�͌����̂��̂Ƃ��Ď���̑��œ��݂��߂邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B�����₩�ł͂��邪�A��������l�́A�Ƃ��������A���N�̍��ɕ������Ђ��₩�ȑz���̂����炩���ʂ������Ƃ����͂ł����B���]�Ȑ܂͂������ɂ��Ă��A���̂܂܂ŏI��点�Ȃ������Ƃ����Ӗ��ɂ����ẮA���݂��b�܂�Ă����ƌ����Ă��悢���낤�B
�@ �����j�ƂƂ��ɑ���ꂽ�̂b�c�̈ꖇ�́A���E�ސE�L�O�Ƃ��ē��ʂɍ쐬���ꂽ�u��ːM�j�̋ȏW�v�ł������B�V���[�}����V���[�x���Ƃ̉̋Ȃ����炩�Ɍ���ʼn̂�������o���g���̐��ɂ����Ƃ�Ƃ��Ȃ���A���͂���ɒ�˂���̋���҂Ƃ��Ă̑��Ղ�ǂ��������B�����j�̒��ɂ͋���҂Ƃ��Ċւ���Ă������k�����̐[���z���̂������L�̐��X��A����ɑ����˂���̊��z�Ȃǂ����^����Ă��āA�����[��������A�܂����S�[�����������B�����Ă܂��A����ɂ��܂ЂƂA��˂���̂����ꂽ����҂Ƃ��Ă̈�ʂ��M���m�邱�Ƃ̂ł��鎑�����A���͂��̍����Ȏ����j�̒��Ɍ��o�����Ƃ��ł����̂������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2002�N5��22��
���Ɛ��Ɍ����̎������F
�@ ��˂���͖��N��т̎���I�яo���A����𑗎��̑���Ƃ��đ��Ɛ������ɑ����Ă����̂������B�����O�̍����Ȏ��l�����̖�������ŁA�������A��X���ƂȂ����ɂƂ��Ă��������̊܈ӂ����݂Ƃ邱�Ƃ͗e�Ղł͂Ȃ������Ȏ����낢�ł��������A��˂���͓�����Ƃ�S�����m�ŁA�w���𑃗����k�����ɂ����̎����Ă����悤�Ȃ̂ł���B
�@ ���Ƃ��A�t���[�h���b�q�E�V���[�́u��]�v�A�͈䐌䪂́u�䂸��t�v�A�{���́u���k���N�Ɋ�v�A�n�C�l�́u�l���q�H�v�A�{�[�h���[���́u�ٖM�l�v�A�ΐ��́u��s�@�v�A�Q�[�e�́u�ʗ��v�ƁA������ƕ��ׂĂ݂������ł����Ȃ艜���[���ē��������ł��������A���Ԃ��˂���͓Ǝ��̂�肩���ł��̓��e���ł��邾���ق����A�������䂭���k�����ɂ����̑f���炵����`���悤�Ɠw�͂��Ă����̂��낤�B�����ɂ́A��X�A�����̋����q�����𖢏n�Ȓ��w���Ƃ݂Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�Ɨ������l�i�������h�Ȃ��ƂȂƂ��ĔF�߂悤�Ƃ��Ă�����˂���̊m�ł��鋳��p�����Â��̂��B
�@ ���܂����ɂ����̎��̂��ׂĂ��킩��Ȃ��Ă������A��X�̐l���̂ǂ����ɂ����Ă��̂悤�Ȏ����������Ƃ������Ƃ�N���ЂƂ�ł��悢����z���o���Ă��ꂳ����������A�����āA�K�v�Ȃ炻����S�̗Ƃɂ��Ăق����\�\�����炭�A��˂���̋����[���ɂ́A�������s�������q�����ɑ��邻��ȐȂ�肢�Ȃǂ����߂��Ă����ɈႢ�Ȃ��B
�@ �������A��˂��A�����Ȏ��l�̍쎌�ɂȂ�V���[�}����V���[�x���g�̉̋ȂN�̂������Ă����Ƃ����w�i�͂��邾�낤�B�����A���Ƃ��������Ƃ��Ă��A���܂ǂ����w���ɂ��̂悤�Ȏ���^���ȋC�����ő��낤�Ƃ��鋳�t�����������ǂꂾ�����邾�낤�B�܂��A�����������ꋳ�t�̋���ɑ���M�ӂ�]�������l���������������ǂ�قǑ��݂��邱�Ƃ��낤�B
�@ ���X�ɐ��̕s�i�C��Q���͂��Ă��A���̂���������A�̌��t�������̐��E�ɑ��Ă��d�v���ȂǁA�䂪���̑�l�����̂قƂ�ǂ͂��͂�ӂɉ�ĂȂǂ��Ȃ����Ƃ��낤�B���w���⍂�Z���̍���͂��͂��߂Ƃ���w�͂̒ቺ���뜜����Ă��邪�A����͂ЂƂ��ɑ�l�����̐ӔC�Ȃ̂ł����āA�������Ďq�ǂ������ɐӔC������킯�ł͂Ȃ��B�d�X�������̌����Ɛg�U��ɂ�������炸�A���̌ۓ��̔���ʌ��t�����f�����Ƃ̂Ȃ��ǂ����̍��̐����ƂȂǂ́A�����Ȑ�ł����܂�Ȃ�����A���w�Ȗ��̌��t�̗N���o�ł�^�̐��������x�T���Ȃ����Ăق������̂��B
�@ ���܂��̍��ɏd�v�Ȃ̂́u�ĕS�U�̐��_�v���̂��̂����u�ĕS�U�̐��_�v�ݏo�����Ƃ̂ł��鍪���I�ȓy��̈琬�̂ق��ł���A�x�X�g�Z���[��_�������X�̓��{��u�[���̏��Ђ��̂��̂����A�n���I�Ŋ����L���ȓ��{��ݏo���Љ��������̂ق��Ȃ̂ł���B���v���C���[�̌��I�ȉ^���t�H�[����^�����邱�Ƃ͂ł����Ƃ��Ă��A���̂悤�Ȍ����ȃt�H�[���ݏo����ؗ͂┽�ː_�o�A�o�����X���o�Ȃǂ�g�ɂ���̂͗e�ՂłȂ��B�������������̂́A�قǂ悢���_�I�Ȋ�����ْ����A����ɂ͐��X�̐g�̓I�ȃ��X�N������������R�Ȃ������ō��݂�����̒��ŁA����Ȃ�̒������Ԃ������ď��X�Ɍ`���������̂�����ł���B
�@
�@ ��������������A��˂����Ɛ��ɑ��������̂ЂƂA�{����́u���k���N�Ɋ�v�������ɏЉ�Ă������Ƃ������B���łɂ����m�̕��������낤���A���̂����ۂ��ŁA���߂Ă��̎���ڂɂ��A�S�����v���ł��̈�s���ɖ�������l���܂������Ȃ��Ȃ����Ƃ��낤�B�̑�ȋ���҂ł����������l�{���̎�����铴�@�͂ƁA���̎���I�яo������˂���̓I�m�ȑI����Ƃɂ��炽�߂Ď��͌h���������ł���B
�@ �Ȃ��A�u���k���N�Ɋ�v�Ƃ������̎��́A���Ƃ��ƑS�̂Ƃ��Ė��������������̂܂܂ŋ{���̎���m�[�g�̖����Ɏc����Ă������̂ł���B�ȉ��ɂ͒�˂����Ɛ��ɑ��������̂����̂܂ܓ]�ڂ��Ă������A���Ȓi�K�̎������܂ގ���m�[�g�L�ڂ̌����͂����肩�Ȃ蒷���A�e���̍\���Ɣz��������Ԃ�قȂ������̂ɂȂ��Ă��邱�Ƃ����f�肵�Ă��������B�܂��A�����ł͋����Ȍ����\�L���������̂����ォ�Ȍ����ɉ��߂��Ă���A���Ƃ͊����\�L�������������ꕔ���ȕ\�L�ɕς��炦�Ă�����B���Ԃ��˂������Ƃ��ėp�������Ђ̎��M�҂������̎�����Ƃ��錤���҂��ҏW�҂��A���Ƃ��Ă̂������𐮂���ʂɂ��ǂ݂₷�����邽�߂ɂ��̂悤�ɕҏW���Ȃ��������̂ł��낤�B
�@ �����̎��ɂ͊������ꂽ�������Ŏc���ꂽ���̂̂Ȃ��ɂ�����Ȃ��̂����Ȃ肠��A�������ɗp�����Ă��銿���➐��A����p��Ȃǂ��ǂ��ǂ݂ǂ������ׂ����ɂ��āA���̓��̐��Ƃł������˘f���Ƃ��낪�����Ȃ��Ȃ��B�n���w�̐��ƂŔ������L���̂��̂����������́A�@�،o���͂��߂Ƃ��鏔���T�Ⓦ���̗l�X�ȓN�w�v�z�A����ɂ͂��̎���̐�[�Ȋw�̐��E�ɐ[���ʂ��Ă���A�����Y���Ȓm�������݂ɋ�g���Ȃ���c��Ȏ���ɖv�����Ă����B����ɐ��ɏo�����̂̂ق�����������A�s���̓_�������̂��B
�@ ���k���N�Ɋ�@�@���{����
�@���̎l�P�N��
�@�킽�����ɂ͂ǂ�ȂɊy����������
�@�킽�����͖�����
�@���̂悤�ɋ����ł������Ă��炵��
�@����������
�@�킽�����͂��̎d����
�@�������ڂ������Ƃ͂Ȃ�
�@���N�据����̒n�������c��ݍ��܂�Ƃ���
�@���N�͂��̂Ȃ��ɖv���邱�Ƃ�~���邩
�@���ɏ��N�͂��̒n���ɂ�����
�@������`�̎R�x�łȂ���Ȃ��
�@���N�͂����D�u�i���������j����
�@���N�̖��������琁���Ă���
�@�����Ȑ����ȕ��������Ȃ��̂�
�@����͈�̑���ꂽ�����ł���
�@������ꂽ��̕��ł���
�@���N�͂��̎���ɋ�����ꗦ������
�@�z��̂悤�ɔE�]���邱�Ƃ�~���邩
�@�ނ��돔�N�悳��ɂ��炽�Ȑ��������E������
�@�F���͐₦������ɂ���ĕω�����
�@�����╗
�@�����鎩�R�̗͂�p���������Ƃ���ꑫ�i���
�@���N�͐V���Ȏ��R���`������̂ɓw�߂˂Ȃ��
�@�V��������̃R�y���j�N�X��
�@���܂�ɏd�ꂵ���d�̖͂@������
�@���̋�͌n����������
�@�V���Ȏ���̃}���N�X��
�@�����̖ӖڂȏՓ����瓮�����E��
�@���炵���������\���ɕς���
�@�V��������̃_�[�E�B����
�@����ɓ��m���Êς̃`�������W���[�ɂ̂���
�@��͌n��Ԃ̊O�ɂ�������
�@����ɓ����ɐ[���������n�j��
�@�������ꂽ�����w������Ɏ���
�@�Փ��̂悤�ɂ����s�Ȃ���
�@���ׂĂ̔_�ƘJ����
�@�₽�������ȉ�͂ɂ����
�@���̗�����̉e�Ƃ��������
�@���x�͈̔͂ɍ��߂�
�@�V���Ȏ��l��
�@�_��������痒����
�@�V���ȓ����ȃG�l���M�[������
�@�l�ƒn���ɂƂ�ׂ��`���Î�����
�@ ���Ȃ݂ɏq�ׂĂ����ƁA�`�������W���[�i�����ł̓L�������W���[�ƂȂ��Ă���j�Ƃ́A�ꔪ����N����ꔪ���Z�N�ɂ����đ����m�e�n��吼�m�̓씼�������Ŋw�p�������s�Ȃ����C�M���X�̊C�m�����D�̂��Ƃł���B�C�m�Ő[���̂���k�����m�̃`�������W���[�C���́A���̒����D�ɂ��Ȃ�ł��̖�������ꂽ�B�����Ƃ̂��ɕč��őł��グ��ꂽ�X�y�[�X�V���g�����`�������W���[�Ɩ������ꂽ���Ƃ́A�\���҂Ƃ��Ă̌������������f�i�Ƃ�����قǂɈ����߂��Ă��ĂȂ�Ƃ������[��������ł���B
�@ ��˂���̎����j�̍ŏI�y�[�W�ɂ́A�Ō�̐E��ɂȂ�������s���_�����K���w�Z�̊w�Z�ʐM�u���K�����v�̈ꕶ���]�ڂ���Ă���A���̕��͂́u�����邱�Ƃ͊w�Ԃ��Ƃł���ƁA���͒x�܂��Ȃ���������Ă���v�Ƃ������t�Ō���Ă���B����E�ł͐̂�����x�ƂȂ����ɂ���Ă������t�ł͂��邯��ǂ��A���N�ɂ킽���Đ��k�����Ɛ^�������𑱂��Ă�����˂����݂��݂ƌ�邻�̌��t�ɂ́A�������Ď蕨�Ȃǂł͂Ȃ��d�X�������������ĂȂ�Ȃ��̂������B
�@ �܂��A���˂��ˁA�����g���A�u������Ă�v�Ƃ����������̋������������u����v�Ƃ������t���́A�u����w�ш�v�Ƃ��������I�ȐF�����̔Z���u�w��v�Ƃ������t�̂ق��ɂ��D��������Ă����̂ŁA��˂���̑z���ɂ͐S�ꋤ�����邱�Ƃ��ł����B
�@ �����ɂ́A����̒p��E��Ō��J�ɓ��ݐ����Ƃ������A���A������̑S���ѕ\��ڍׂȐ����L�^�Ȃǂ̃R�s�[���Y�t����Ă������A������������˂���̌^�j��ȍs�ׂȂǂɂ����͑傢�ɍD���������Ƃ��ł����B�����⑽���̗F�l�m�l�A����ɂ͂��Ă̋����q���������ӂ�����ڂɂ��邾�낤���Ƃ�S�����m�ŁA��˂���͐����ɐ̂̎����̎p�����炯�����Č������̂��B�N�ɂł��w�Ɛ��т̑P�������͂���A���܂��܂ȎЉ�I�s���ʂł̓���s����͑��݂���B���t�͂��Ƃ��Ɩ��\�l�Ԃł͂��肦�Ȃ����A�܂������ł���K�v���Ȃ����Ƃ��A��˂���͂����Ď������������̂ł��낤�B
�@ �����j�́u���Ƃ����v�̍Ō�ɂ���u���ꂩ��̐l���������Ȃ���̂��̂��Ƃ͎v���܂����A�����Ȃ�ɐ���t�����Ă������Ƃ������ɐ����Č��тƂ������܂��v�Ƃ������t��ǂ݂Ȃ���A�u��˂���O�\���N�Ԃق�Ƃ��ɂ���J�l�ł����v�Ǝ��͐S�̒��řꂢ�Ă����B
�@�����āA�����ꂭ���̂������̂b�c�v���C���[����́A���Ē�˂��w����������s�����w�Z�}���h�������̑t�ł�Ȃ��A�܂�ł��̑ސE��߂��ݐɂ��ނ��̂悤�ɊÂ��Ȃ�����o�Ă����B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2002�N5��29��
�d����̓h�g�[���H
�@�u���e�������̂͂����ς炲����ł����H�v�Ɛl����u�˂�ꂽ�Ƃ��Ȃǂ́A�u�������A�Ԃ̒���X���̃J�t�F�ȂǂŎd�������邱�Ƃ������ł��v�Ɠ����邱�Ƃɂ��Ă���B����͔�����k���Ǝv���炵���̂����A�������Ă��̌��t�ɋU�肪����킯�ł͂Ȃ��B�ԂŎ�ނ����˂������ɏo��������L��������܂���Ă���Ƃ��Ȃǂ́A���ԂƂ�����舣�ԂƂ������ق����悢��������Ȃ��g���^�E���C�g�G�[�X�̒��Œ����ԃp�\�R����@���B�p�\�R�������̃o�b�e���[�����ł͈�莞�Ԉȏ�̍�Ƃ͕s�\������A�Ԃ̓d���̏\��u������S�u�̌𗬂ɕϊ�����R���o�[�^��ς�ł�����B
�@ ���ɏo�Ă��Ȃ��ꍇ�ɂ́A�߂��̃J�t�F�A���Ƃ��������{���w�\���̌[�������X�e�ɂ���h�g�[���Ȃǂ𗘗p���邱�Ƃ������Ȃ��Ȃ��B�������A��x�����ԑт�A��ʂ��ڍׂȎ��������ꂱ��ƒ��ׂ��肵�Ȃ��猴�e�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��ꍇ�ׂ͂ł���B����ȂƂ��ɂ͎���̏��ւ₠�������̐}���قȂǂ𗘗p���邪�A�����łȂ��Ƃ��́A���̂Ƃ���A��������イ�h�g�[���ɏo�����Ă���B���̂��X�͌y���H�����Ƃ�ĕ֗������A���q�ɑ���z�������܂₩�ŁA�����������T�[�r�X���Ȃ��Ȃ��悢�B�������ɏ��X�����邩��A������Ƃ��������ׂ��肵�������ɂ́A�ꎞ�I�ɐȂ𗧂��Ċ֘A���Ђ𗧂��ǂ݂����肷�邱�Ƃ��ł���B�q�̏o����̌������J�t�F�Ȃǂ́A�l�̊ώ@������̂ɂ��s�����悢�B�������ɂƂ��Đl�Ԃ̊ώ@�͌������Ȃ����Ƃ̂ЂƂ����炾�B
�@ ���ւŎd��������ƌ����Ε����͂悢���A������Ƃ̏��ւɂ������Ďd�����肵�Ă�����A�g�̂ɂ悢�킯���Ȃ��B���e�������Ƃ�����Ƃɂ͂���Ȃ�̃X�g���X�������̂Ȃ̂ŁA�K�x�̉^����C���]���͐�Ɍ������Ȃ��B�p�\�R����K�v�������i�b�v�T�b�N�ɋl�ߍ���Ŕw�����A�U�������˂ĊO�o����A����Ȃ�ɉ^���ɂ��Ȃ��đ̒��𐮂��邱�Ƃ��ł��邵�A���_�q���ォ�炵�Ă��A�O�C�ɐG��Ȃ���l�G�܁X�̕������C�̌����܂܂Ɋy���ނ̂͂������Ĉ������Ƃł͂Ȃ��B
�@ �����w���ӂ܂ŏo�����Ƃ��ɂ́A��قǂłȂ������莩�]�Ԃɂ͏��Ȃ��B���ꂪ�K���ɂȂ��Ă��܂��Ă��邩��A�}���̏ꍇ�Ȃǂɉw�܂Ŏ��]�Ԃɏ���ďo�������肷��ƁA�A��ɂ͎��]�Ԃ̂��ƂȂǂ�������Y��Ă��܂��B�Ƃɖ߂��Ă���A�Ƒ��̃q���V���N�����Ƃ͂�������A����Ȏ��ɂ́A�u���֏�̎��]�Ԃ̂��Ƃ�Y��Ȃ��ŁA�����Ə���ċA��悤�ɂȂ�����A������������؋������B���]�Ԃ�Y�����Ă��Ƃ́A�Ȃɂ������C�ȏ؋��Ȃ���I�v�ƛ���������ׂĊJ�����邱�Ƃɂ��Ă���B
�@ ����Ȃ킯������A�ߏ��ɏZ�ސl�X�̒��ɂ́A�������]�Ԃɏ��Ȃ����̂��Ǝv���Ă���҂�����悤�Ȃ̂��B���܂Ɏ������]�Ԃɏ���Ă���p�����������肷��ƁA���b�����Ȋ������l������̂͂��Ԃ̂����Ȃ̂��낤�B�Ⴂ������^���_�o�ɂ͎��M������������A���ۂɂ͂�����Ƃ������]�Ԃ̋ȏ�肭�炢�͂��܂ł��\���ł���̂����A�d�����������Ă����Ԃ̐l�͂���Ȃӂ��ɂ͌��Ă���Ȃ��悤�ł���B
�@ �J�t�F��Ԓ��Ȃǂł悭���e�������ƌ����ƁA���ɂ͂��܂��āu����ȂƂ���ł悭�d�����ł��܂��˂��B���邳��������A���������Ȃ������肵�܂��H�v�Ɛu�˂���B���������ƁA�ǂ�Ȋ����ɂ����Ă��W���͂����킸�d���ɐ�O�ł���͎̂��̓��Z�̂ЂƂł���B���Ƃ��K���K���Ɖ��y���苿���Ă����肵�Ă��A�q�̏o���肪�p�ɂŐl�X�̘b�������₦�Ȃ������Ƃ��Ă��A���������C�ɂȂ�����͂��Ȃ��B�܂�����Ƃ͋t�ɁA���ӂ��^���Âŕ����ЂƂ��Ȃ��^�钆�̐[�R��A�₵���r���Ƃ�������̂悤�ȂƂ���ł��A���_���W�������C�Ŏd���Ɍ��������Ƃ��ł���B
�@ ���X�̐����ɒǂ��Ȃ���w�˂Ȃ�Ȃ������Ⴂ����ɁA��ނȂ����āA�ǂ�Ȉ����̒��ł��{��ǂ�m�[�g���Ƃ�����[���v���ɒ^�����肷�邷�ׂ�g�ɂ��Ă��܂�������A���������݂Ȃ���X���̓��₩�ȃJ�t�F�Œ����Ԏd�������邱�ƂȂǃw�b�`�����Ȃ̂��B����Ȏd���Ԃ��m�����F�l��m�l��������������ꂽ��͂��邪�A�̂̌����������Ɋr�ׂ�ΓV���݂����Ȃ��̂Ȃ̂ŁA�{�l�͂������ĕ��C�Ȃ̂ł���B�m�l�̌���Ƃ̑�䏊�A�ʖ�������Ȃǂ���͂�i���X�����I�Ɏd����ɂ��Ă�����悤�����A�����Ƀv���̏�����Ǝv����l�����J�t�F�Ŏd�������Ă���p�Ȃǂ��悭�������邩��A���ۂɂ͂���Ȃɒ��������Ƃł͂Ȃ��̂ł͂Ȃ��낤���B
�@ ��X�ٍe��ǂ�ł��������Ă���ǎ҂̊F����ɂ͐\����Ȃ����A���̂悤�Ȃ킯������A���̂Ƃ��딭�\���Ă���G�b�Z�C�ނ̂قƂ�ǂ́u�h�g�[���ސ��v�A���邢�́u�g���^�E���C�g�G�[�X�ސ��v�Ƃ������ƂɂȂ�B�ǂ����Ȃ�u�鍑�z�e���ސ��v�Ƃ��u���[���X���C�X�ސ��v�Ƃ������悤�Ȉꗬ�u�����h���̂ق����]�܂����̂�������Ȃ����A������������i�̂ق��͂��܂��Ƃ��߂����ꗬ��ƘA�̂ق��ɂ��C�����邵���Ȃ����낤�B���������A���̂悤�Ȗ��\�ȍ�Ƃ��u�鍑�z�e���ސ��v��u���[���X���C�X�ސ��v�ɂ�����낤�Ƃ�����A�����܂������I�ɔj�]���������Ă��܂��ɈႢ�Ȃ��B
�@ �܂��A����Ɂu�鍑�z�e���ސ��v��u���[���X���C�X�ސ��v�̌��e�����������������Ƃ��Ă��A���˂��ˍ����u�����h�̐��E�ɊS�̂Ȃ����Ȃǂ́A���s�����Ȕ��H��g�ɗ]�鍋�ȕ��������Ă��܂��A���͂�Ԃ�ǂ���ł͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂����Ƃ��낤�B�l�ԂƂ������̂́A���˂��ˊ���Ă��Ȃ����Ƃ������肷��ƃ��N�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B�R�[�q�[��g����t�Œ����Ԃ˂��Ď��͂����ق̊�Ō����悤�ƁA�u�h�g�[���ސ��v�̃G�b�Z�C���M�ɓO����̂������ɍ����Ă��邵�A���������ĎԂ̒��Ŏd���ȂƏ��悤�ƁA�u�g���^�E���C�g�G�[�X�ސ��v�̋I�s�����M�ɐ�O����ق������̐g�ɂ͂ӂ��킵���B
�@ ����ɂ܂��A�鍑�z�e���̂悤�Ȉꗬ�z�e���̐������ꂽ�z�e���}���ɋC�����Ȃ���A�ؗ�Ȑl�X�̏W�����E�ɂ��ĕM���Ƃ���A�h�g�[���̂悤�ȊX�̃J�t�F�ŎႭ�Ă����̂悢�w���o�C�g��t���[�^�[�̓X����ƌ��t�����킵�Ȃ���A�����̂���Ȃ����E�ɂ��Ă̎��M�ɐ����o���ق����C�����悢�B�����Ԃɏ���Ċ��S�ܑ����H�̑���l�H���̐��E�Ɋ��Q�����͂�Ԃ���A�����炯�̂q�u�Ԃɏ���Ĉ��H��襘H�̑����厩�R�̒����߂���A���̋�J�̂قǂ⊴���̐[�����L�q����ق������ɂ͍����Ă���B�ނ��A�l�ɂ͂��ꂼ��̍D�݂�M��������킯������A�܂������t�̗�����Ƃ�l�X���������Ƃ��낤���A�܂��A����͂���Ō��\�Ȃ��Ƃł���B
�@ �L�����ɖ����Ȑl�Ԃ̕Ό��ƌ����������������Ȃ��̂����A���Ƃ����Ă����Ƃ��Ă��A�����������_�Ǝ�����ʂ��Ă��������Ȃ����E�����݂��邱�Ƃ��m���ł���B�����Ă܂��A����Ȑ��E��`���o�����ق����͂�ǂ�ł����l�X�������炩�͑��݂���̂��m���Ȃ��Ƃ̂悤�ł���B
�@ ������̂��Ƃ����A�h�g�[���ŗׂ荇�킹���l����ɂ��鐔���̕��̓R�s�[�ɉ��C�Ȃ��ڂ�������B�Ƃ��낪���������Ƃɂ́A�Ȃ�ƁA����͉i�䖾����̃��f�B�J���Y���L�Ǝ��̃}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�̃R�s�[�������̂��I�\�\�u���̕��͂̃��C�^�[�́c�c�v�ȂǂƗׂ��琺��������̂̓��{�������Ƃ���Ȃ̂ŁA�f�m��ʊ�Ńp�\�R���Ɍ����������Ă����̂����A���S�������悤�Ȓp���������悤�ȂȂ�Ƃ����G�ȋC���ł͂������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2002�N6��19��
�u�}���E�n���̖��p�t�����v
�������b
�@ ���N�̎O�����̂��ƁA�u���f�B�J���Y���L�v�̕M�ҁA�i�䖾����A�H�w�}���Ƃ������n���А��̏o�ŎЂɐe�����ҏW�҂�����̂ň�x����Ă��炦�Ȃ����Ƃ������[�����͂����B�ق��Ȃ�ʉi�䂳��̈˗��Ƃ������ƂŁA�����ɗ��������|�̕ԐM�𑗂����B���ꂩ�炵�炭���Ă킴�킴�{���܂ŖK�˂Ă��Ă��ꂽ�̂��A�H�w�}���̕ҏW�ґq�V�N�Ƃ������B�ꌩ���������ŐM���ɒl����l�����Ɗ������̂ŁA�����ɂ����������̂܂܂̎p�����炯�����A�������ꂱ��Ƙb�����B
�@ �q�V����f�����Ƃ���ł́A��ƂƂ��ăf�r���[�Ȃ��邷�����O�̂��ƁA�i�䂳��͎���o�c�҂ƂȂ菬���ȏo�ŎЂ𗧂��グ�悤�ƂȂ��������Ƃ��������炵���B�قǂȂ����āA�i�䂳��̎������A��t�⏬�o�ŎЂ̌o�c�҂Ȃǂ�����ƋƂ̂ق��ɓK���Ă���炵���Ɣ�������ƁA�i��В��ƃo�C�g�Ј���l�����̂��̉�Ђ͂����܂����ł��Ă��܂����̂��������B�܂�����c�̊w�����������A���̏o�ŎЂ̃o�C�g�]�ƈ��̂ЂƂ�߂Ă����̂��ق��Ȃ�ʑq�V�������Ƃ����킯�ł���B����܌��\�ܓ��Ɍf�ڂ��ꂽ�i�䂳��́u�_�b�J����n���r������v�̒��ɓo�ꂵ�Ă���K����Ƃ́A���̑q�V����̂��Ƃɂق��Ȃ�Ȃ��B
�@ ����ȏ��Ζʂ̐ȂŁA���͑q�V����Ȃɂ����琔�w����݂̖{�ł����M���Ă��炦�Ȃ����Ƃ����b������������ꂽ�B���鎞�������ɂ��āA���w���͂��߂Ƃ��鐔���Ȋw�W�̌��e���M����Ӑ}�I�ɉ���������鎄�́A�����A��发�A���邢�͂���ɋ߂������Ȋw�n�̖{�������̂͋C�̂肪���Ȃ��Ƒq�V����ɓ`�����B�����Ă܂��A���ݎ肪���Ă��鑼�̎d���Ƃ̊W������̂ŁA����ɕM������ɂ��Ă��A�����Ȋw�n�̍���I�����ɗ͓���I�ȕ��͂̂Ȃ��Ɏ�荞��ʓǎҌ����̌��e�ɂ������邾�낤�Ƃ��t���������B
�@ ����ƁA�q�V����́A��X���́u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v�Ȃǂɖڂ�ʂ��Ȃ��ŁA���������������낤�Ƃ������Ƃ͐��������Ă����̂ŁA�ׂɂ��̂悤�Ȍ��e�ł����܂�Ȃ��ƁA���������Ɉ��������Ă���邯�͂����Ȃ��B����ƊO�x�߂��Ă�������ȏ�̂Ȃ��ŁA���̏ꂵ�̂��̂��߂Ɏ��o�����̂�����̖|��{�������B�����������炱��Ȃ��Ƃ����낤���ƁA���炩���ߗp�ӂ����͂��Ă��Ă������̂��B
�@ ���͑q�V����Ɂu����͂�����Ƃ�����Ȃ�ł����A�H�w�}������͂���Ȗ{�̕����o�łȂɂ͊S�͂�����łȂ��ł��傤�ˁH�v�ƌ����Ȃ���A���̖|�������o�����B�uVICTORIAN� INVENTIONS�\19���I�̔����Ƃ����v�Ƃ����^�C�g���̂��̖{�́A���̖|���1977�N�ɃV�O�}�ЂƂ����Ƃ��납��o�ł��ꂽ���̂������BA4�ό`��200�y�[�W��A�P��1800�~�̑�^�}�Ŗ{�ŁA���s�����͊e��V����T�����Ȃǂ̏��]�ł��傫�����グ���A���Ѓ}�j�A�̂������ł͂�����Ƃ����]���ɂ��Ȃ����B
�@ ��Ƃ̍r���G����͊�\�I�̂Ȃ��Ƀ��X�g�A�b�v�����Ă�������B�����̍����Ȋw�����ق̍H�w�����؍��v����́A�u�|��̐��E�v�Ƃ����G���̏��]�̒��ŁA�u�����̓��e���炵�Ė|��ɂ͑����̍���Ƃ��Ȃ������낤�ɂ�������炸�A�|����D��Ă���A�Ȋw�j�̌��������Ƃ��ĉ�X�����҂ɂ��������ɖ��ɗ��v�Ƃ����A�g�ɗ]��悤�ȕ]�������������������B�܂��A�����̎��ʂ̘Z���������߂铺�ʼn����ؔʼn�̑n���̃��}���ɖ������}�G�̐��X�́A���p�f�U�C���W�҂̂������ł���D�]�����B�������̑}�G��A�O�_�����Ƃɐ��삵�A�s���̈ꕔ�̉w�Ȃǂɂ͂肾������`�p�|�X�^�[�́A�m��ʊԂɎ��X�ɔ�������A��������ꂽ��������B
�@ �����̊��s�����A���{�e���r�Ȃǂ͂��̖{�̒��ŏЉ��Ă��邢�����̊�z�V�O�Ȕ����i�Ȃǂ����A������l�^�ɔԑg��������������Ă����悤�ł���B�܂��A�������̑}�G�́A�����炩�f�t�H�������������ŁA�l�X�ȍÂ����̐�`�|�X�^�[�̐}����e�폤�ƍL���̃f�U�C���Ȃǂɂ��p����ꂽ�B�Ȃ��ɂ͖��f�g�p�̂��ꂽ�P�[�X�����Ȃ肠�����悤�ł���B��N�̉Ăɂ́A�t�W�e���r�n�̔[��������w�Ƃ����y�j�̒��Ԃ̌ܕ��Ԕԑg�ŁA�����̊G�ɃA�j���[�V�������̓������������̂����T���f���ꂽ��������B�u�R�䋳�Y����̃A�j���ɋV�I�v�i2000�N1��19���t���̏����̃o�b�N�i���o�[�Q�Ɓj�Ƃ����ٍe�̒��Ŏ��グ���^�C�v���C�^�[�̐}�łƂ��̉���L�������̖{�Ɏ��^����Ă�����̂��B
�@ ����Ȃ��Ƃ������ƁA�����������ꂽ�̂ł��낤�Ƒz���Ȃ��邩���������낤���A���ۂ̂Ƃ���͂����ł͂Ȃ������B���̋����[�����e�ɂ�������炸�A�o�Ŏ��̂��낢��Ȏ����A���̖{�͕s���ȉ^����H�炴������Ȃ���������ł���B�V�O�}�Ƃ��������ȉ�ЎВ��̔��Όl�I�Ȏ�ňϑ����ꂽ�d�������������ɁA���Ƃ��Ə��Љ�Ђł͂Ȃ����̉�Ђ́A���s����̔����[�g�ɂ̂���̂ɕK�v�ȏo�ŃR�[�h�����L���Ă��Ȃ������B������A���������{�͂ł���������S���̏��X�ɗ��ʂ������i�������Ă��Ȃ��������A�ނ��V����G���ȂǂɍL�������Ă邾���̎��͂��Ȃ������B
�@ ���̂��߁A�Ј����{�Ƃ̂������e�n�̖{�����ꌬ�ꌬ�܂���ẮA��������������Ŕ̔����ϑ����A����̉���ɂ��o�����Ƃ������肳�܂������B������A�s���̈ꕔ�̑发�X�ɏo���̂�����t�Ƃ����Ƃ���ł������B����ȏ���������A�����Ă����ł̂ق����|��ɔ�₵�����Ԃɂ͂ƂĂ�������ʒ��x�̂��̂ɂ����Ȃ��������A����ł������炩�͔���A���]�ȂǂɎ��グ��ꂽ�Ԃ�܂��ł͂�������������Ȃ��B�ނ��A�V�O�}�Ђ������ɂ킽���Ă���ȕs����ȏo�ŋƖ��𑱂��邱�Ƃ͓���A���������̖{�͐�łƂȂ�A����s�\�ɂȂ��Ă��܂����B
�@ ���ꂩ��15�N���1992�N�AJICC�o�Łi���݂̕Ёj�̍����M�O����i�u�c�ɕ�炵�̖{�v�̌��ҏW���j�̂͂��炢�ŁA�����́u�}���E�������̎���v�ƃ^�C�g�������߁A��������V���������œ��Ђ��畜�����ꂽ�B���̔łɂ͍r���G����̐������̋L���ꂽ�т܂ł����Ă����B�������Ȃ���A�����ł��܂��������̕s�^���d�Ȃ����B�������ł��������߁A���]�ȂǂɎ��グ�Ă��炤�̂�����A������JICC�o�ł̖{�Ƃ��Ă͈ٗ��A�S�ό`�łƂ�����^�{�ł��������߁A�����X�y�[�X�̊W�Ŗ{���̓X���ɒ����I�ɒu���Ă��炤���Ƃ͓�������B�܂��A���p���Ƃ��Ȋw���Ƃ���l�����̊G�{�Ƃ����ʊ�ł��邽�߁A�ǂ̃W�������ɕ��ނ������̂����X�����Ή��ɓ���Y�܂�����������炵���B
�@ �܂��C���^�[�l�b�g�ɂ�鏑�Џ����C���^�[�l�b�g���Д̔��ȂǂƂ����֗��Ȏ�i�̂Ȃ�����̂��Ƃ���������A�Ƃ��ɐ�`���̔����i���Ȃ���Ă��Ȃ��{���Ă��炤�Ƃ������Ƃ͗e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ��悤�������B����ł��K������蕪�͊��������̂����A�����ɂƂȂ肩�����Ƃ���ł܂��s���̎��Ԃ����������BJICC�o�ł����N�ɕЂƎЖ��ύX�ɂȂ����̂ɂƂ��Ȃ��A���t��\���̕\�L�Ƒ����̕ύX���K�v�ɂȂ����̂����A��������ɂ͐V���Ɏ�Ԃ���p�������Ԃ�Ƃ����邩��Ĕł͓���Ƃ������ƂɂȂ����B�������Ă܂������͔p�ł̂�ނȂ��ɂ��������̂ł���B�ˑR���̎|�̒ʒm��JICC�o�ł���͂��A�Q�Ăĉ���������肵�悤�Ɛ���ɘA������ꂽ�̂����A���̂Ƃ��ɂ͊��ɍɐ�ɂȂ��Ă���A���ǁA���̎茳�ɂ�JICC�Łu�}���E�������̎���v�͏��ł��ꕔ�����c��Ȃ������B
�@ ���̎����炳��ɏ\�N�̍Ό������ꋎ�������A���̊Ԃɂ��A���̖{�̑��݂�m��ꕔ���f�B�A�W�҂����W�ҁA����ɂ͉Ȋw�j�̌����҂Ȃǂ����łȂ̂��ǂ����̖⍇������������������B���̂����̂����������ɂ��̖|��ɂ͂����Ԃ�Ƌ�J��������A�����g�������ɂ͂ЂƂ����Ȃ�ʈ������������B������A�p�łɂȂ��Ă�����A�܂������ǂ��̏o�ŎЂ��畜���ł��o���Ă��炦�Ȃ����̂��Ƃ����v�������͂������̂��B
�@ �ŋ߂̓X�L���i�[�̐��\������I�Ɍ��サ�Ă��邱�Ƃ�����A���ł��p������Ă��Ă��A�ۑ���Ԃ̂悢�{��������A��������ƂɁA����ȂɌo����������������\�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ƃ����C�����Ă����B�܂��A�C���^�[�l�b�g����̓����̂������ŁA���܂Ȃ�A���o�ŎЂł����Ă������̊T�v���L���Љ���̖ʔ������F�ɒm���Ă��炤���Ƃ��ł��邩��A�r�W�l�X�Ƃ��Ă��\�����藧�̂ł͂Ȃ����ƍl���͂��߂Ă������B����ȂƂ���ɁA���܂��܍H�w�}���̑q�V�����ꂽ�Ƃ����킯�������B
�@ �K���b�̂ق��͑z�����Ă����ȏ�ɏ����ɐi�݁A�Ȃ�ׂ����������ɍH�w�}�������������Ă����Ƃ������ƂɂȂ����B�Ō��Ď擾�̖��́A�H�w�}���̊}�����В������N�u�k�ЂŊC�O���Е���̑����ӔC�҂߂Ă���ꂽ���Ƃ������āA��r�I�X���[�Y�ɉ������݂��B���̖����ł���ꕔ���͂̎蒼����⑫�̂ق����x�Ȃ����������B�����ł̐V���ȏ��������������̂����ɍl���Ă���ƈ˗����ꂽ�Ƃ��͂������ɏ��X�ł������A�Ȃ�Ƃ��������Ɂu�}���E�n���̖��p�t�����v�Ƃ����^�C�g�����Ђ˂肾�����Ƃ��ł����B
�@ ����ȏ̂Ȃ��őz���̂ق���J�����̂��A��̂��ĕ�����ƂɎg�����߂̌��{�̒��B�ł������B���̎茳�ɃV�O�}�ł̏��Ŗ{��JICC�ł̏��Ŗ{�Ƃ��ꕔ���c����Ă������A���܂ƂȂ��Ă͊|���ւ��̂Ȃ��{�Ȃ̂ł�����ׂ��킯�ɂ������Ȃ��B�����ŁA�F�l�ɗ��ݍ���ňȑO���悵�Ă������V�O�}�ł̉�����{����Ԃ��Ă��炢�A������Ɏ�������ł݂��̂����A���������ɕs�N���ȕ������������肵�A���܂ЂƂd�オ��̏�Ԃ͂悭�Ȃ��Ƃ������Ƃ������B
�@ �Ȃ�ׂ��Ȃ�ۑ���Ԃ̂悢�V�O�}�ł̏��Ŗ{���ǂ����炩����ł��Ȃ����Ƃ������ƂɂȂ�A�H�w�}���ł͊e��l�b�g���[�N����g���đS���e�n�̌Ï��X�ׂĂ݂��B�����A�X�̌Ï��X�ł悤�₭JICC�ł�����������������ŁA�V�O�}�ł�T���o�����Ƃ͂ł��Ȃ������B�Ƃ肠������}���ł���JICC�ł�X��������̂����������A�l�i�̂ق����ܐ�~�ȏサ���炵���B�܂��A�C�^�[�l�b�g�̃t���[�}�[�P�b�g�I�[�N�V�����u�y�V�v�ɂ����ĎO����̃V�O�}�ł��ꖜ�~�]�̒l�i�Ŕ����Ă���̂������A�����ɍw�����悤�Ǝ��݂����A������Ƃ̎��Ԃ̍��Ő�q�ɔ�������Ă��܂����Ƃ������Ƃ������B
�@ �O����łł�����Ȃɂ���̂Ȃ�A�V�O�}�ł����s���ꂽ�����ɏ��Ŗ{��S���قǔ�������ł����A���܂ɂȂ��Ă���y�V�ɂł�����ɏo���悩�������ȂǂƌƑ��Ȃ��Ƃ��l���Ă݂�����������A���ׂĂ͂��Ƃ̍Ղ�ł���B�����Ȃ�����A�킸����������茳�Ɏc�����A��������Ԃ����S�Ƃ͌�����V�O�}�ŏ��ł��тɍ����o�������Ȃ����ƍl���͂��߂��Ƃ��A�ˑR�v�������̂����F�̕]�_�Ƌڑ�r������B
�@ �ڑ�̂Ƃ���ɂ̓V�O�}�ŏ��ł̑���{���������͂��ł���B�����ɓd�b�������Ċm�F���Ă��炤�ƁA�������ɂ���Ƃ����B�ۑ���Ԃ��悢�Ƃ������ƂȂ̂ŁA�����b���ċ������A�厊�}���̂Ƃ���ւ��̏��Ŗ{�𑗂�͂��Ă��炤���Ƃɂ����B�ڑ�ɂ͕����ł��ł�����^����ɓ͂��邩��Ɩ������A�y�V�ł͎O����łł��ꖜ�~�ȏサ�Ă���炵���Ƃ͘b���Ȃ��ł������B���̏��Ŗ{�����Ƃɂ���������Ƃ̌��ʂ͏�X�ŁA�܂��ɁA�_�l�A���l�A�ڑ�l�ƂȂ����悤�Ȃ킯�ł������B�������{�Ƀ^�C�g���Ƒ�������V�����u�}���E�n���̖��p�t�����v�̃T���v���{���͂���ꂽ���A�����łȂ��ł̕������Ƃ͂������Ȃ��قǂɑf���炵���{�Ɏd�オ���Ă����B
�@ �Ƃ���ŁA�b�������܂łŏI���Ε����ʂ�n�b�s�[�G���h�Ƃ����킯�������̂����A�ǂ���炻���������Ȃ��Ȃ��Ă����B������Ƃ������I�����A���h�ȕ��������o���オ���Ă܂��Ȃ������肩��A�H�w�}���̊}�������q�V����̂ɂ��₩�Ȕ��݂����ɋC�ɂȂ肾���Ă�������ł���B���̔��̉��ɂ́A�u�����A�������̂ق��͏o���オ��������A�߂������Ɏ��̈˗����e�������Ă��炤���Ƃɂ��܂��傤�ˁB�^�C�g�������ł��Ȃ�ׂ����߂ɂ��肢���܂���I�v�Ƃ����Öق̗v�����B����Ă��邱�Ƃ͖��炩�������B�قǂȂ����āA�����b���������̂̓��u�w�r�ł������炵���ƌ�����̂����A���͂₷�ׂĂ͎�x��̂悤�������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2002�N6��26��
�{���̎莆
�@ ���̘Z���̖��T���j���̌ߌ�A�{���s���U�w�K�Z���^�[�ɂ����āA�s����ΏۂƂ����₳�����F���Ȋw�u���̍u�t�߂����Ă�����Ă���B�s�̍u�����S���҂���u�t�̈˗����������Ƃ��A�E�B�[�N�f�C�̌ߌ�́A�������A���傤�ǃ��[���h�J�b�v�E�T�b�J�[�Əd�Ȃ鎞�ԑтɁA�������ɂ͂Ȃ�̊W���Ȃ��F���Ȋw�u���Ɋ���o���Ă����l������̂��낤���ƁA�����ȂƂ�����S������ƐS�z�ɂȂ����B������ɂ擱���s�I�ȈӖ�����������̂Ŏ�u�҂̐��͂��܂�C�ɂ��Ȃ��łق����A�Ƃ����S���҂̌��t��M���Ĉꉞ�͗����������̂́A���̂����ۂ��ŁA����������҂��[���������炱����Ƃ��Ă��������Ȃ��ȂƂ������������������B
�@ �u���̎��ԑт����ԑтł���������A��u�҂̕��ϔN��Z�\��Ƃ��Ȃ荂�߂ɂȂ����̂͂�ނ����Ȃ����Ƃł��������A������̗\�z�ɔ����A�u�����ێ�����̂ɏ\���Ȑ��̎�u��]�҂��������B����̒j�������ɍ������Ď�w��Ⴂ�����̎p�Ȃǂ�����ق猩���A�K���ɂ��ē����̐S�z�͞X�J�ɏI������̂������B�u�`���܂�Ȃ�������A����Ȃ肷�����肵�A�r������W�c�Ö��p�̌��u���ɂȂ��Ă��܂�����ǂ����悤���Ƃ������������A���ۂɂ͑�ϔM�S�ɍu�`�Ɏ����X���Ă��炤���Ƃ��ł����̂ŁA���̓_�ł��܂��͈��g�����悤�Ȃ킯�������B
�@ ���̍u���̘b�̒��ł�����Ƃ����{���̉F���ςɐG��悤�Ǝv���A���˂̎������������Ă���ƁA�����Ԃ�̂ɒm�l��ʂ��ē��肵���������M�̎莆�̃R�s�[���݂������B����Ȃ��̂����������ƂȂǂ�������Y��Ă����̂����A�̑�Ȏ��l��Ƃ��ÂԂɂ͂܂��ƂȂ������Ȃ̂ŁA�b�̃^�l�ɂƁA��u�҂̊F����ɂ��Љ�Ă݂邱�Ƃɂ����B
�@ ����́A���a�Z�N�A�{�������������̐������Ƃ����Ƃ���ɂ������_�яȔ_��������Ζ��֖̊L���Y�Ƃ����l���Ɉ��Ă���ⳎO���قǂ̎��M�̃R�s�[�������B�{���̔N���ׂĂ݂��Ƃ���A�֖L���Y�Ƃ����l���͌��������������_�ъw�Z�����ȂɊw��ł������̉��t�ł��邱�Ƃ����������B�_�w���m�ł��������֖̊L���Y�w���̂��ƂŁA�܂���\��̌��w�S�����ȐN�����������́A�n���y��Ɣ엿�̌����Ɍg���A�B�ьS�̓y���������ϑ����ꂽ��������悤�ł�B���̎莆�̏����ꂽ���a�Z�N�ɂ͌����͎O�\�܍ɂȂ��Ă��邩��A���t�֖L���Y�Ɏw�����Ă��������炻�̎��܂łɏ\�O�N�̍Ό������ꋎ���Ă������ƂɂȂ�B
�@ ���̎莆�̕M�Ղɂ݂邩����A�����̎��͂����ւ�Ɍ��I�ł������Ƃ�����B�����̒m���l�̑������p�����������邢�͍s���ɂ��A�ȑ̂̕����ł͂Ȃ��A�����̌���l�̕M�Փ��l�A�ǂ��炩�Ƃ����ƞ����̂ɋ߂������ňꕶ���ꕶ���������������ɂ���Ă���B�Ɠ��̊ۂ݂�тсA�傫���Ă��Ȃ�A���o�����X�Ȃ��̕����́A�������ɂ��B�M�Ƃ͌��������ɂȂ��B�����̂��Ƃ�����A�\�ʓI�Ȃ��̂̌����������Ȃ���l�����Ȃ�A���\�ȍ����Ă���̂ɂȂ�Ƃ��t�قȕ������ƉA�������@�������Ƃł��낤�B�������A�悭�悭���߂Ă݂�ƁA�����͕s�v�c�ɂ��������݂̂��鎚�Ȃ̂ł���B
�@ �V�˂ƌĂ��l�Ԃɂ܂܂��肪���Ȃ���Ȏ��̂ŁA�����͕�ⳎO���ɂ킽�邻�̎莆�����ЂƂ����ɏ����グ���悤�ł���B���Ȃ葧�̒����莆���̗��ꂩ����A�܂��Ō�܂ł܂������i�������s���Ȃ��ɕ��͕��S�̂��Ԃ��Ă��邱�Ƃ�����A���̂��Ƃ��M���m�邱�Ƃ��ł���B�������߂�ׂ����͂̊T�v���u���ɓ��̒��ō\�z���A��Ⳃ��܂��ɂ��Ă��炷��ƕM���^�̂ł��낤�B������������A���i���Ŏ莆����Ԃ�̂͌����ɂƂ��ďK���I�Ȃ��Ƃ������̂�������Ȃ��B���ł�����A���̎莆�̑S�����Љ�Ă������Ƃɂ������B
�i�X������������������܂������A�{�N�͊�����̊O�����������̊��`�Ȃǂ�������ł������܂������搶���тɊF�l�ɂ͂���育�����܂���ł������B�i��ł��f�А\�������܂��B�M�i���āj���ʂ��Ȃ��Ă܂��Ƃɋ���i�����̂܂܁j����܂����A�N���̂��C�e�ɊÂ����w�}���������ꎖ�͖{�p���쑺���k�ӐH���莄�ɓ��H��̎d��������i�����ɓ����j�������Ɛ\���ĎQ��܂����V�ł������܂��B���H��͑�D�n����w�̒��O�ɂ���܂��āA����������̋u���ΊD��i�_���ΊD�l���j���̎悵�E�H�\��l����ŝ����ΊD�▖�y�Ǎޗ���������\�ӈʂÂ���ċ���܂��āA�����ւ͘Z���N�O����N�O�S�Ӂi�O�\�ԁj�Âo����N�͋{���p�_���̐����ɂ���ĉ₩�Ɉ�쓙�ւ����v�����₤�ɂȂ����Ƃ̂��Ƃł������܂��B�A�āi���܂��āj���̍ێ��ɏ���i�����ɓ����j�Ƃ��Đ��i�̉��P�ƒ����A�L�����̋N���A�Ƙ��̉��d���Ƃ��A�ꏊ�͂ǂ��ɋ��Ă����������N�Z�S�~���▖�ŝc�ӂƂ̂��Ƃł������܂��B����ʼnE�ɜ䂶�Ă�낵���������܂������A�_�Y�Z�p�č��̗����育�ӌ����R��������Ή��Ƃ��K�r�ɑ����܂��B���ΊD�▖�̌��ʂ͐�痱�q�̑召�ɂ���Ƒ����܂������Ȃǂɂ͊�~�����͊�Z���`�ʂ�⿁i�ӂ邢�j��p�ЂĂ�낵���������܂������A���Â�ɂ���Ă܂łɂ͎Q��q���������������ʂ��Ȃ��Ď���̒i�͏d�X���͂��˂��Џグ�܂��B�����p�̏ꍇ���Ƃ����������t�������v���u���܂����B�P�Ɉ���Ŗ��������閘�ł��˂��Ђ����܂��B�܂��́B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���a�Z�N���ܓ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{��
�@ �沑��Y�搶
�@ ���t�֖L���Y�Ɏd����̔��f��������߂Ď����I�Ȏ莆�ł͂��邪�A���̎莆�����������߂Ă����N����Ɍ��������E�������Ƃ��������ƁA�[�����S���o����������Ȃ��B�����͂��Ȃ�ȑO����]����N����Ă���A���̂Ƃ��܂łɊ��x���×{���J��Ԃ��Ă����B���̎莆�����t�ɏ����������O��A�ނ͈ꎞ�I�ɏ��N�Ă����悤�ł���B�֖L���Y���ǂ̂悤�ȕԐM�𑗂����̂��͒m��悵���Ȃ����A�O���ɓ����Đ����ɓ��k�ӐH��Z�t�ɏ�������Ă���Ƃ�����݂�ƁA���t�̊ւ���͂��̎d���������Ă݂���ǂ����Ƃ̕ԓ����������̂��낤�B
�@ �O�����甪���ɂ����āA�����͒Y�_�ΊD�̐��@���ǂƔ̔��̋Ɩ��ɏ]�����A��`�̂��ߏH�c�A�{��A�������͂��߂Ƃ��铌�k�e�n���߂���A�㌎�ɂ͓����܂ł��̑����̂��Ă���B�d���͂ǂ��ɂ��Ă���Ă���Ă��悢�Ƃ����������ŔN��Z�S�~�̑ҋ��Ƃ����Ɠ����Ƃ��Ă͂Ȃ��Ȃ��̂��̂����A�O�f�̎莆�ɂ݂邩����ΊD�▖�̌����x���������悤������A����J���Ȃ��Ă͂����ɂȂ�Ȃ������͂��ŁA���̓_�ł���J�͐s���Ȃ��������Ƃ��낤�B
�@ �㌎�ɓ���ƌ����͒Y�_�ΊD���i���{�Ȃǂ��g���ď㋞�����B�u�Ă܂łɂ͎Q��q���v�������v�Ǝ莆�ɂ������Ă���Ƃ�����݂�ƁA�\����͒x�ꂽ���̂́A���Ԃ�A���̎��Ɋ֖L���Y�ɂ������ł����̂��낤�B�������A�_�c��x�͑��b�꒬�\��Ԓn�i���݂̐��c��_�c�x�͑�꒚�ڎl�Ԓn�j�����قɓ����ƂƂ��ɔ��M�珰���A������ɂȂ�Ƃ��A�����邪�A�Ăё̒������������ɕ����Ă��܂����B
�@ �̂��ɂȂ��Ė��炩�ɂȂ������Ƃ����A�����̋߂����Ƃ��@�m���������́A���̏㋞�̍ۂɈ⌾�̏��Ȃ��������߂Ă���B�܂��A���N�̏\�ꌎ�ɂ́A����Ɉ⌾�̏��ȂƂƂ��ɔ������ꂽ�蒠�̒��ɁA�L���Ȏ��u�J�j���}�P�Y�v�������L���Ă�����B���N�̏��a���N���瑼�E�������X�N�̏��a���N�㌎�܂ŁA�����͕a���ɂ���Ȃ�����A�u�O�X�R�[�u�h���̓`�L�v���͂��߂Ƃ��鐔�X�̍�i�̎��M�ɐ������X�����B�`������Ƃ���ɂ��ƁA�ނ͂܂��A���̂悤�ȏ��ł̍�i���M�̍��ԂɁA�Ȃ�ƍ������w�����w�ڂ��Ƃ����̂��Ƃ����B���̗L�l�͂܂��ɁA�{���Ƃ����H��̐��_�̔��������������߂����Ō�̌�䊂Ƃ������ׂ����̂ł������B
�@ �m���ȑ����ō��X�Ɣ��藈�鎀�̉e���@�m���Ă��������̐S���́A�u�J�j���}�P�Y�v�Ƃ���������Ƃ��A���łɒB�ςƂ����O�Ƃ����ʗ̈�ɓ��ݓ����Ă����ɈႢ�Ȃ��B
����Ȕw�i��O���ɂ����Ȃ���A���̂��܂�ɂ��L���Ȏ���ǂ݂Ȃ����Ă݂�ƁA����܂łƂ͈ꖡ������V���Ȋ������N���オ���Ă���悤�ȋC�����ĂȂ�Ȃ��B���������Ă��A�o�����̕������炢���������Ă��Ȃ��Ƃ������������낤����A������x���̎��̑S�����L���Ă��̍e�̌��тƂ������B
���J�j���}�P�Y���@�@�@�{��
�J�j���}�P�Y
���j���}�P�Y
��j���ăm���T�j���}�P�k
��v�i�J���_�����`
�|�n�i�N
���V�e�сi�C�J�j���Y
�C�c���V�d�J�j�����b�e����
����j���Ďl���g
���X�g���V�m����^�x
�A�������R�g��
�W�u�����J���a���E�j�����Y�j
���N�~�L�L�V���J��
�\�V�e���X���Y
�쌴�m���m�уm���m
���T�i���u�L�m�����j���e
���j�a�C�m�R�h���A���o
�s�b�e�ŕa�V�e����
���j�c�J���^��A���o
�s�b�e�\�m��m�������q
��j���j�T�E�i�l�A���o
�s�b�e�R�n�K���i�N�e���C�C�g�C�q
�k�j�P���N�����\�V���E�K�A���o
�c�}���i�C�J���������g�C�q
�q�f���m�g�L�n�i�~�_���i�K�V
�T���T�m�i�c�n�I���I���A���L
�~���i�j�f�N�m�{�[�g���o��
�z���������Z�Y
�N�j���T���Y
�T�E�C�t���m�j
���^�V�n�i���^�C
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2002�N7��3��
�߂��猩���T�b�J�[��
�@ �h�C�c�ƃu���W���̌�����i�o�����܂�A���悢�惏�[���h�J�b�v�E�R���A�E�W���p�����t�B�i�[�����}���悤�Ƃ��Ă���B�ꃖ���]�ɂ킽��M������߂����Ƃ̃T�b�J�[�t�@���̋��E���ɂ͑z���ȏ�̂��̂�����ɈႢ�Ȃ��B���ɂ́A�u�T�b�J�[���Č��Ă��邾���Ŕ�����̂Ȃ�ł��˂��c�c�v�Ƃ������N��肽���̊��S�Ƃ������Ƃ����ʌ��t���Ȃ�Ƃ���ۓI�ł������B����ȏ���l���Ă݂�ƁA�C�O�̃T�b�J�[�����Ȃǂɂ����ẮA�����̂��܂蕮������t�@������������Ƃ����̂��\����������B
�@ ���{�ɂ����Ă����ׂ̊؍��ɂ����Ă��A�v�X�ɍ����Ƃ��Ă̈�̊��𖡂키���Ƃ��ł����Ƃ��������₦�Ȃ��悤���B�������Ɏ����g���A���{�`�[���ƊO���`�[���Ƃ̎������ϐ킵�Ă��āA���{�S�[������@�ɂ��炳�ꂽ��A�t�Ɏ����I�肪����S�[�������т₩�����肷�邽�тɃn���n���h�L�h�L�������Ă�������A�ɂ킩�����҂ɂȂ������Ƃ����͋^���]�n�̂Ȃ��Ƃ��낾�B
�@ ���荑�ɗL���Ȕ���ɂ͋q�ϓI�ɂ݂Đ����ȏꍇ�ł��u�[�C���O�𗁂т������A�����ɗL���Ȕ���ɂ͂��ꂪ���炩�Ɍ��ł����Ă��G�R�q�C�L�܂邾���Ŋ����������ĉ�������\�\�����܂ł��X�|�[�c�Ȃ̂�������Ȃ��ƌ���������Ƃ��炵���͂��邯��ǁA���������ÂɂȂ��ĕʂ̊p�x����l���Ă݂�ƁA����ȌȂ̐��_��Ԃ̉���ɂ͌��\�������̂�����ł���悤�ɂ���������B
�@ �܂��w�����������A���炩�ɍ��Д��g�Ǝ�҂̐�Ӎ��g��_�������������Y�̐펞���̎���ǂ݁A���یo�����L���������͂��̂��ꂾ���̒m���l���Ȃ�����Ȏ����������̂��낤���ƕs�v�c�Ɋ��������̂ł���B�����Y���g�����ɂȂ��Ă��炻�̂��Ƃ�[������݁A���Ȃ̈Ӗ��������āA���ԂƂ̌𗬂�₿���̑��r��R�[�ɂ����������Ƃ͂悭�m���Ă���Ƃ���ł���B���Ȃ݂ɏq�ׂĂ����ƁA�S���q�b�q���C���[�W���Đ��삵���Ƃ����\�a�c�ΔȂ̖L���ȏ����̗����͂��̂Ƃ��ɂ���ꂽ���̂ł���B
�@ �����Y����҂���ւƐ��肽�Ă鎍���������w�i�ɂ́A�R���ɂ��v�z�e�����̓���Ȏ�������������Ƃ��낤�B�܂��A�����Y�̓����ł́A���{�×��̓`���ɐ[�����Â��_���`�I���_�ƃ��_���ɏے������悤�Ȏ��R��`�I�ߑ㐸�_�Ƃ��A�܂�ł��݂��̑��݂��֎����ݍ�����C�̎ւ̂悤�ɂ����߂��Ă����悤�ł���B������A�����̐��E��풆�ɂ����ẮA�ނ̑̓��ɐ��ޑ�a���I�Ȑ_���`���_�̎ւ̂ق������܂��ܐ����𑝂��Ă����Ƃ������Ȃ����Ƃ͂Ȃ����낤�B
�@ �����A���̂Ƃ���̃T�b�J�[�����Ɏ�����������܂�邤���ɁA���͌����Y�����Д��g�Ɛ�Ӎ��g�̈Ӑ}�܂邾���̎����������S���������炩�킩��悤�ȋC�����Ă����B���ꂪ�T�b�J�[�ł��ꉽ�ł���A�����S�̂��������ɂނ����Ă�������M�����͂��߂�ƁA���̌���������̒��ɂ����ꂽ�҂́A���X�m���I���낤�������I���낤�������܂��Ȃ��A�������ɂ��̒����ɉ���������Ă��܂��̂ł͂Ȃ����Ǝv���悤�ɂȂ������炾�B����̖쎟�n���_�����������킹�Ȃ����̂悤�Ȑl�Ԃ������ɍR���ׂ����Ȃ��͓̂��R�̂��ƂȂ̂����A�ǂ��������Y�̂悤�Ȑ����Ȑ��_�����m���l�ł��A���̂悤�ȏɂ����ꂽ�痝�������Ŏ����ɓۂݍ��܂�Ă��܂����Ƃ�����悤�Ȃ̂��B
�@ �������\�N���O�̂��Ƃ����A�T�b�J�[��i���C�M���X�̍�ƃW���[�W�E�I�[�E�F���́A�T�b�J�[�ɔM������l�X�̐S���w�i���s�����͂����uThe Sporting Sprit�v�Ƃ�����т̃V���[�g�G�b�Z�C�\�����B����u�A�j�}���E�t�@�[���v�ɂ����āA���V�A�v���Ɗv�������̔ߎS�ȑO�r�����I�m�ȕ��h�������ĕ`�ʂ��\�����Ă݂������̍�ƂȂ�ł͂̃T�b�J�[�ς��A�����ɂ͔�������Ղ�ȕM�v�Ō��Ԃ��Ă���̂ł���B�����Ԃ�̂̍�i�ł���ɂ�������炸�A�����̃��[���h�J�b�v�������ɂ����̂܂܂҂����蓖�Ă͂܂�A�Ȃ�قǂƔ[����������Ƃ�������Ȃ��Ȃ��̂ŁA���̃T�b�J�[�ς�����������Љ�Ă݂邱�Ƃɂ������B
�@ ����Ƃ��A���\�r�G�g�A�M�̃T�b�J�[�`�[���A�_�C�i���X���e�P�����̂��߂ɓn�p���A�C�M���X�̖���`�[���A�A�[�Z�i����O���X�S�[�Ƒΐ킵�����A�A�[�Z�i���Ƃ̎����ł͓r���ŗ��`�[���̑I�蓯�m�ʼn��荇���ƂȂ�A�ϋq�̂ق���������ԂɊׂ����B�܂��A�O���X�S�[�Ƃ̎����͍ŏ�����Ȃ�ł�����̐��܂��������͗l�ƂȂ�A�F�D�e�P�ǂ���̑����ł͂Ȃ��Ȃ����B
�@ ����ɁA�\�A�l�����́u�A�[�Z�i���͎�����S�p�`�[���ł������v�Ǝ咣���A�����ۂ��̉p���l�����́u�A�[�Z�i���͑S�p�`�[���Ȃǂł͂Ȃ��ꃊ�[�O�`�[���ɉ߂��Ȃ������B�_�C�i���X���\����グ�}篋A�������̂́A�S�p�`�[���Ƃ̑ΐ������悤�Ƃ������炾�v�Ǝ咣�����B���̂��߁A�����날��l�X�́A���̂悤�ȃT�b�J�[�e�P�����͐s���邱�Ƃ̂Ȃ������̍����ƂȂ����ŁA�p�\�W���܂��܂����������A�����ԂɐV���ȓG�Έӎ��݂����炷�������ƈ��Ś������Ă����Ƃ����B
�@ ����ȏ��ɂ����āA�I�[�E�F���́A�u�T�b�J�[�̂悤�ȃX�|�[�c�͍��ƊԂ̗F�D�Ɛe�P��[�ߐ푈���������̂ɖ𗧂v�ȂǂƐ^��ŏ�����l�X�̋C������Ȃ��ƌ������Ă͂���Ȃ������B���Ƃ▯���̈АM��������W��A����������Ȃ��܂łɑł��̂߂��ď����Ƃɂ����Ӌ`������A�s�ꂽ��̖ʂ��������J�������ނ邱�ƂɂȂ�Ƃ���X�|�[�c�ł́A�K�R�I�ɂ����Ƃ���Ȑl�Ԃ̓����{�\�����N�����B������A���ۊԂł����Ȃ���T�b�J�[�̂悤�ȃX�|�[�c�͋[���푈���̂��̂ɂȂ炴������Ȃ��Ƃ����̂ł���B
�@ �I�[�E�F���͂܂��A�ق�Ƃ��ɖ��Ȃ̂́A�����ɂ�����I�肽���̖�ȍs�ׂ��̂��̂����A�����ɂ���Ă͔n�����Ă����鎎���ɔM���������A���Ƃ��ꎞ�I�ł͂����Ă��A�����Ƀ{�[����ǂ���������育�ƏR��܂��邱�Ƃ����Ɣ����̏ł���ƐM���Ă�܂Ȃ��ϏO��A���̔w��ɂ��鍑���̂ق����Ƃ��q�ׂĂ���B
�@ �T�b�J�[��i���̍����ȏ�ɃT�b�J�[�V�����̍����̂ق������ƈӎ��ƓG�Ӕ����o���ŋ����������Ȃ̂��T�b�J�[�Ƃ����Q�[���̓��F�ŁA�����`�[��������S�[���ɔ���ƈꕔ�̊ϏO���t�B�[���h�ɔ�яo���S�[���L�[�p�[�̓�����W�Q����Ƃ��������Ԃ����Ă͓���I�ɋN�����Ă����炵���B���������āA���ێ����ɂ�����ϏO���m�̖\���͂���������܂��̂��Ƃ������悤���B
�@ �����G�Ί�����N�����ƁA���[������낤�ȂǂƂ����ӎ��͂����܂��ǂ����������ł��܂��B�e�����͎����`�[�����������A���荑�`�[�������̂����Ȃ����J�𖡂키���Ƃ�M�]���邩��A�s���s�ׂɂ�鏟�����낤�����葤�I���t���[�ւ̊ϋq�ɂ�钼�ڊԐڂ̎��ЖW�Q�s�ׂɂ�鏟�����낤���A�Ƃɂ���������������悢�̂��Ƃ������ƂɂȂ�B
�@ �^�������̃X�|�[�c�Ƃ������̂͂��Ƃ��ƃt�F�A�v���C�Ƃ͖����ł���A���[���Ƃ͖��W�̑����A�i�݁A���ȑ��݂̌֎��A����ɂ͖\�͍s�ׂ�c�s�s�ׂ�ڂɂ������Ƃ����T�f�B�X�e�B�b�N�ȗ~�]�ȂǂƐ[�����т��Ă���B��������A����́A�uA war minus the shooting�v�A���Ȃ킿�A�u�e����̂Ȃ��푈�v�Ȃ̂��Ƃ����I�[�E�F���̌��t�͎��Ɏ茵�����B
�Ñォ��X�|�[�c�ɂ͎c�s���������̂���������ǂ��A�T�b�J�[�Ȃǂ̂悤�ȃX�|�[�c�������̐���@���ς̈قȂ鍑�Ƃ��邢�͖����Ԃ̏W�c�����ɂȂ���悤�ɂȂ����̂͋ߐ��̂��Ƃł���Ƃ��ނ͏q�ׁA���̌����́A���Ă̑卑����O�̌��n�I�ȓ����{�\�����N����X�|�[�c�𗘗p���A����ȕx�ޏ��Ɗ�������������Ƃɂ���Ƃ��Ă���B
�@ �����āA�I�[�E�F���͍Ō�ɁA�_�C�i���X�̐e�P�K�p�ɉ����ă\�A�ɉp����\�`�[���𑗂�Ȃ�A�����ŕK������`�[���ɔs��A�������p���l�̂ق��͂��ꂪ�S�p�`�[���ł͂Ȃ��Ǝ咣�ł���悤�ȓ̃`�[����h�����ׂ����Ɣ�������Ղ�ɒ�Ă��Ă���B����łȂ��Ă������̃^�l�̐₦�Ȃ������ɁA�҂苶���ϏO�̓{���̂Ȃ��Ŏ�҂������݂��������R�荇�����Ƃ���藧�Ă邱�Ƃɂ���āA����ɕ����̃^�l�𑝂₷�K�v�ȂǂȂ��Ƃ������Ƃ̂悤�ł���B
�@ �I�[�E�F���̎w�E��f���ɎƂ߂čl����ƁA���{�`�[���̎����̊ϐ�ɖ����ɂȂ����̂́A�������Ɏ����̐[���ɖ��錴�n�I�����{�\��G���S�����N���ꂽ����ɈႢ�Ȃ��B�e�������Ȃ�����ȑ㗝�푈����{�C���u���ɂ������Ă������ƂɂȂ�킯���B�����J�Í��̓��ؗ����������荑�̃`�[���̊���ɕ��G�ȋC����������A������ł������Ԃ��Ƃ��ł����ɂ����̂��A��ؓ�ł͂����Ȃ�����Ȑ[�w�S�����͂��炢�Ă������炾�낤�B
�@ ����I�Љ���̂Ȃ��Ŗ��ӎ��̂����ɗ}������Ă��錴�n�I�����{�\��T�f�B�X�e�B�b�N�Ȋ�]�A����ɂ͂����ɔ����X�g���X�Ȃǂ��A�����[���E�h�J�b�v�̎����ϐ��ʂ��ĉ������ꂽ�Ƃ����̂Ȃ�A����͂���ňӋ`���������ƌ����Ă��悢�B�����A�ȑO�ɂ��܂��ăX�g���X�����܂����Ƃ����Ȃ�A�����������ł͂��邾�낤�B
�@ �����Ƃ��A���l�̊��z�Ƃ��ẮA�I�[�E�F���̐h煂Ȍ��t�ɂ�������炸�A���[���h�J�b�v�̍����J�Âɂ͂���Ȃ�̎��n���������悤�ɂ������B���Ƃ��Α啪�����Í]���ɂ݂�J�����[���`�[���Ƒ��l�Ƃ̐e�P�𗬂�����ł���B���Ƃ��ƊO���l�Ƃ̌𗬂ȂǂقƂ�ǂȂ��R���̂��Ƃ�����A�����J�����[���`�[�������Í]���ɑ؍݂��邱�Ƃ��Ȃ�������A���F�̔������A�t���J�l�ɑ����a���₢���炩�̕Ό��Ȃǂ����l�̐S�̂ǂ����ɂȂ����݂Â������낤�Ƃ��l������B
�@ �������A����̃J�����[���`�[���̑؍݂ł���Ȉ�a����Ό��͂܂������Ȃ��Ȃ�A���l�Ƃ̐e�P�𗬂͂������ɐi�B���̍��̃`�[���̍��h�n�ł����l�̂��Ƃ��N���������Ƃ��낤�B�T�b�J�[�̎������̂��̂̏��s�Ƃ͒��ڂɊW�Ȃ����A���[���h�J�b�v�Ƃ������̈��t�F�X�e�B�o�������{�����ɂ����炵�����ېe�P���ʂ́A����Ȃ�ɕ]�������ׂ��Ȃ̂�������Ȃ��B�X�|�[�c��ʂ������ی𗬂Ƃ����Ƃ܂������ɃI�����s�b�N���������邪�A����Ƃ͂܂��ꖡ�Ⴄ�s�v�c�Ȃ͂��炫���T�b�J�[�̃��[���h�J�b�v�ɂ͂���悤���B������������A���n�I�����{�\�̗��Ԃ����ʂȂ̂��낤���B
�@ ���̓_�͂悢�̂����A���v�Nj���`��FIFA���������̑̎��ɂ́A���������̂���ȗF�D���[�h�ɐ�����������a�������ڂ����ĂȂ�Ȃ��B�o�C�����ЂƂ̖�������������������`�P�b�g�̔��̕s���Ɋւ���FIFA�����̑Ή��́A�܂��ɁA�g�D�̈АM����邱�Ƃ��ł��A���������̗��v�ɂȂ肳������Α���̗���Ȃǂǂ��ł��悢�Ƃ����A�T�b�J�[�̈����������{�\�܂邾���̏�Ԃ��̂܂܂��Ƃ����Ă悢�B������܂��A�T�b�J�[�Ƃ������̑㗝�푈��̌����Ă������䂦��FIFA�����A�̔߂������i�����j�Ȃ̂ł��낤���B
�@ ����؍����������܂Ői���Ƃɂ��A�l�N��̃h�C�c���ł͓��{�`�[�������������̔������҂���Ă���B�������Ȃ���A��苭���Ȃ�Ƃ������Ƃ́A����܂ňȏ�ɂ��邭�Ȃ�A�����Ƃ����Ƃ��͓��R�̂悤�ɐg�̂��ă��[�������̖W�Q�s�ׂ�����Ă̂���R�c���C�����邱�Ƃł�����悤���B�P�Ƀ{�[���R���g���[���̋Z�p�����߁A���x�ȃ`�[���v���[��g�ɂ��邾���ł̓T�b�J�[��i���ɏ����Ƃ͓���B
�@ �R���̌��Ă��Ȃ��Ƃ���ł͑���̃��j�z�[����������������g�̂����������肷�邱�Ƃ͂�����܂��A�S�[�������߂�ꂻ���ɂȂ�����Ӑg�̗͂����߂ďR��|���͓̂��R�̂��ƁA�{�[����ǂ��Ƃ݂��đ���̎�v�I��ɋ���ȑ̓���������킹�A����悭�Ε����ޏ���肤�͕̂s���Ȑ헪�\�\�ǂ���炻���̍����Z�p���}�X�^�[���������łȂ��ƁA������T�b�J�[�{���̋Z�p��g�ɂ��Ă�����ł͒ʗp���Ȃ����̂炵���B�ϋq�̂ق��������I��̌����Ȕ����v���[�ɐS�ꔏ��𑗂�邾���̃T�b�J�[��������Ȃ��Ɛ^�̈Ӗ��ŃQ�[�����y���ނ��Ƃ͂ł��Ȃ��炵���ƒm�����͎̂v��ʎ��n�ł������B
�@ �����O�̃`�[�����킸�A�ꗬ�Ƃ�����T�b�J�[�I��ɂ́A�g�̓I�ȋ��x����r�q���̂ق��ɒm�I�ȕ��͋C�����Ȃ��Ă���҂������Ȃ��Ȃ��B�ނ�̖ڂ̋P���ɂ́A�키���̓��L�̎����̉s������łȂ��A��ɓ��]�̂������s��������Ƃ�������������Ȃ��҂ɋ��ʂ̒m���̂���߂�����������B�Ⴂ�������ނ�̈ꋓ�ꓮ�ɖ����ɂȂ�̂�����ȗ��R����Ȃ̂ł��낤�B�����A�����������ނ�̂͂��肵��Ȃ����͂����Ƃ▯���̈АM��w�������[���푈�̌��ʐ��܂ꂽ���̂ł���Ƃ���A�Ȃ�Ƃ�����Ȃ��Ƃ��ƌ��킴������Ȃ����낤�B
�@ ���傤�ǂ����܂Ŗ{�e�������i�Ƃ���ŁA�؍��g���R�̎O�ʌ���킪�g���R�̏����ŏI�������B�Ō�܂ŗ��`�[��������ʌ��킾�����ɂ�������炸�A�܂�ɂ݂�قǂɊ����I�ŁA���������܂܂ŏ����Ă������Ƃ�^��������ے肷�邩�̂悤�ȃt�F�A�ȃQ�[���ł������B�܂����S�ɂ̓��[���b�p���ė��̃T�b�J�[�ɓł���Ă��Ȃ��A�W�A�`�[�����m�̎������������炩������Ȃ����A����ȃQ�[��������ɂ͂���Ƃ������Ƃ炵���B
�@ �Ƃ���Ŗ����̓u���W���h�C�c�̌�����\�\���̏ꍇ�ɂ͂Ƃ��ɂǂ���̃`�[���ɂ��z������͂Ȃ�����A���n�I�����{�\��I�肽���ɂ������n���n���h�L�h�L���Ȃ���ϐ킷��K�v�͂Ȃ��B�f��u���̘f���v�̂Ȃ��̏��R��A�z������h�C�c�̃J�[���I��ƁA�V�g�V�g�s�b�`�����V�g�s�b�`�����̕���ɂ����ɂ̓q�l�������u���W���̑�ܘY���i�E�h�I��̂ǂ���ɌR�z���������Ă��A��������_��������ÂɃe���r�Ɍ��������Ƃ��ł���̂́A���_�q�����ς悢���Ƃł͂���̂�������Ȃ��B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2002�N7��10��
��w�i�w���[�g�̑��l��
�Ɏv������
�@ ����܂ŁA���w���Ǝ��i�����Ȃ��҂⍂�Z���r�ފw�҂Ȃǂ���w������ɂ́A��w���w���i���莎�����A����ɍ��i���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�匟�͐�Ε]���Ɋ�Â������ŏo����e���e���Ȃ̊�b�I���������S�̎����ł��邩��A���ꎩ�̂͂������ē�����̂ł͂Ȃ��̂����A�����Ȗڂ������̋��Ȃɂ킽�邱�ƂȂǂ������āA���G�Ȑ��������S���̂��Ƃœ��X�𑗂��Ă����]�҂����̎����ɍ��i����̂͂��Ȃ炸�����e�Ղł͂Ȃ������B
�@ �w�Z����@�ɂ����ẮA��w���w�L���i�҂��u�����w�Z�⒆������w�Z���ƎҁA�܂��͂���Ɠ����ȏ�̊w�͂�����ƔF�߂�ꂽ�ҁv�ƒ�߂Ă���A���̏㔼�́u����Ɠ����ȏ�̊w�͂�����ƔF�߂�ꂽ�ҁv�Ƃ���������ɂ͑匟���i���K�v�ȏ����ł���Ƃ���Ă����B
�@ �����A�ߔN�̎Љ�̕ω��ɂƂ��Ȃ��A�����Ȋw�Ȃ�����܂ł̕��j���ꕔ�ύX���A�C���^�[�i�V���i���X�N�[���⒩�N�w�Z�ȂNJO���l�w�Z�̑��Ɛ��ɂ��Ă͑匟�ɍ��i���Ȃ��Ă���w��F�߂邱�Ƃɂ����悤�ł���B�܂��A���Z���ގ҂⒆�w���Ǝ҂ɂ��Ă��Ȃɂ�����̋~�Ϗ��u���u���A���Ȃ炷�����匟���i�������Ƃ��Ȃ��ő�w�ɗՂ߂�悤�ȃ��[�g��ݒ肷��悤������i�ߎn�߂��͗l�ł���B�������A������̂ق��ɂ��ẮA���_���o��܂łɂ܂����Ԃ�v����ƍl���Ă���̂��������B
�@ ����Ȑ܁A�����s����w���A��w���w���i�̂Ȃ��҂ł���w�w��̎��ƂōD���т������߂�Α�w���w���\�ƂȂ�u�`�������W�����v���Z�Z�l�N�x���瓱������Ɣ��\�����B����w�́A�u��w�ɂ����āA�����̔N��ɒB���A�����w�Z�𑲋Ƃ����҂Ɠ����ȏ�̊w�͂�����ƔF�߂��ҁv�Ƃ����w�Z����@�̎{�s�K���������ɂ��ēƎ��̓������x�����{����͉̂\���Ɣ��f�����悤���B
�@ �V���Ȃǂŕ���Ă���Ƃ���ɂ��ƁA���\���Έȏ�̃`�������W�����҂Ɏl�����甪���ɂ����ēs����w��̎��Ƃ���u���Ă��炢�A���C���т�ʐڂ܂��������Ŏ���̓��w��F�߂�̂��Ƃ����B��Z�Z�l�N�̓��w�ɂ��Ȃ��A�܂����t�͖@�w���Ɨ��w���œ������ɂ����̓o�^�������Ȃ���炵���B
�@�u���w���ƌ�ɍ��Z�i�w���Ȃ�������A���Z�ɂ��܂��Ȃ��߂��ɒ��r�ފw�����҂̂Ȃ��ɂ��A�Ȃ��w�Ԉӗ~�������Ă���҂͏��Ȃ��Ȃ��B���̂悤�Ȑl�X�ɓ����J���A�P�ɈËL�݂͂̂�L����w���ł͂Ȃ��A���ʓI�Ɏv�l�ł���悤�Ȋw����I�сA���̔\�͂�L�������v�Ƃ����̂��A�����s��s����w���̈ӌ��Ȃ̂��������B�N�̔��Ă��͒m��Ȃ����A�ێq��K�̎��Ȃ����`����Ƃ��Ă�������s�����ǎ҂ɂ��ẮA�����قǂɑ�_���a�V�ȑΉ��Ԃ肾�ƌ����Ă悢���낤�B
�@ �������A���̐V�K�̐��x�ɂ����w�Ґ��͂���������ꂽ���ɂȂ炴������Ȃ����낤���A���I�ȗ��ꂩ���]�҂̖{���I�Ȕ\�͂�₤�K�v��A�I�l��͌��������̂ƂȂ�A����Ȃ�ɍ��x�Ȓm���┻�f�̗͂L���Ȃǎ������ɈႢ�Ȃ��B�����A���Ƃ������ł������Ƃ��Ă��A���̂悤�ȓ������x���݂����邱�Ƃ͂������Ɋ��}���ׂ����Ƃł���B����w�ɂ��e���̋y�Ԗ�肾���ɂȂɂ��ƍׂ��Ȏ��O�������������Ȃ����Ƃ��낤���A���������̂��Ƃ�����A���ЂƂ������Ȋw�ȓ��ǂ̏_��ȑΉ������҂������B
�@ ���Q�L�Ƃ͖��W�ȓ������x���ɂ��ď����C�ɂȂ����̂́A�{���I�Ȕ\�͂�����ɂ�������炸�A��w���i���Ȃ���������ɁA��w�i�w��f�O������A��w�ɓ���܂łɂ����Ԃ�Ɛt�̋M�d�Ȏ��Ԃ�Q�����A�܂������łȂ��Ă��A���̔\�͂ɂ��Ĉꎞ�I�ɂ͕s���ȕ]��������҂����������Ԃ�ƒm���Ă��邩�炾�B�ڂ����o�܂��̓I���e�ɂ��ďq�ׂ�̂͂��̏�ł͍����T���������A�l�X�ȗ��R�Œ��w�⍂�Z���ɕs�o�Z��ԂɊׂ������k�����A���Z�̒��ގҁA����ɂ͂���Ƃ�����ˑR�w�Ԃ��Ƃɖڊo�߂������̎Љ�l�Ƃ������悤�Ȏ�҂����ɒ��ɐڂ��A���̖ʓ|���݂�@��ߋ����ɂ͂��낢��Ƃ������̂��B
�@ �w�Ԃ��ƂɂȂ������ӗ~����������҂⍂�Z���ގ҂Ȃǂ̂Ȃ��ɂ́A�傫�Ȑ��ݓI�\�͂��߂��҂����Ȃ��Ȃ��B�Ƃ��ɕ��G�ȉƒ�I�����o�ϓI����̂��߂ɏA�w��f�O�����n���o�g�̒����҂⍂�Z���ގ҂Ȃǂ̂Ȃ��ɂ́A���Ƃ��ƍ����w�K�\�͂����Ȃ������Ă���҂���������������ꂽ�������B�܂��A���Z�ł̎��Ƃ���ɓ���߂��s�o�Z��ԂɂȂ�A�P�ʕs���ȂǂɂȂ��Č��Ǒފw�̂�ނȂ��ɂ��������҂Ȃǂɂ́A�����̍�����{���ɓO��I�ɂ�����邶������^�̎v�l�^�C�v�����Ȃ��Ȃ��B������ʂ̕��삾���ɂ͔��Q�̔\�͂����邪���̕���̋��Ȃ͂܂�ł��߂Ƃ����A���o�����X�^��A�����́A�ώ@�́A�n���͂Ȃǂ͏G�łĂ�����̂́A�ËL�͈ˑ��̋��Ȃ͂ǂ�Ȃ��̂������I�Ɏ��Ȃ��Ƃ������{�I����K���s�\�^�Ȃǂ��������܂܂�Ă���悤���B
�@ ���r���[�Ȍ��f�͂��������Ȃ��������䂦�ɕs�o�Z�ɂ��Ȃ炸�ފw�����Ȃ��������A�����̍����ɂ�����鐫�i�̂��ɂ͐��т͂�������Ȃ��A���f����Ԃ����������g�̍��Z�����́A�����������ނ̎�҂����̏Ƃ��Ȃ�d�Ȃ�Ƃ��낪����B�����܂Ƃ��ȉp�ꋳ��ȂNJ��҂��ׂ����Ȃ����������̒��w�o�g�̎��́A�i�w�����������̍��Z�ł͉p��̗��������B�������ł����Ԃ�Ɨ��𖡂������������B���܂ł͂����N���M���Ă���͂��Ȃ��̂����A���ۂɂ����������̂ł���B
�@ �����̎��Ԃɂ́A�Ȃ��͂̑傫���� f��m�� �Ƃ������ŕ\�킳�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��ɂ������A���w�̎��Ԃɂ̓A�{�K�h�������Ȃɂ䂦����ȕςȐ��ɂȂ�̂��ƍl�����݁A�����Ƃ���ɐi�߂Ȃ������B�u����ȊȒP�Ȃ��Ƃ��킩��Ȃ��̂Ȃ痝�n�ɂ͌����Ȃ��B�d�����Ȃ����炻��Ȃ��̂��ƈËL����v�Ƃ����Ă��A�����������Ĕ[���������Ȃ����͔̂[�����������A�Ō�ɂ́u���܂��͖��������ĐX�����Ă��Ȃ��v�Ƃ��������t�܂Œ��Ղ����B����炪�������ĊȒP�Ȗ��Ȃǂł͂Ȃ��A���̒�`�␔�l�̌���ɂ͕����≻�w�̍����I�ȑ��肪�B����Ă��邱�ƁA��������u�X�����Ė��݂Ȃ��v���Ƃ��܂����ł��邱�Ƃ�m�����̂͂����Ƃ̂��̂��Ƃł���B
�@ �S�̎x�����ق����������ߏ����␏�M�̗ނ͗m�̓������킸���낢��Ȃ��̂�ǂ����Ă������A�Ǐ����z����앶����������̏h��͑�̋��ŁA��x���܂Ƃ��ɉۑ���o�����L�����Ȃ��B���ꂪ���܂������ċȂ���Ȃ�ɂ��l�l�ɓǂ�ł��炤���߂̕��͂�Ԃ��Ă���킯������A�l���Ƃ͂ق�Ƃ��ɂ킩��Ȃ����̂ł���B���E�j�̎��ԂȂǂɂ́A���X�̎������ڂ₻��炪�N�������N����Ђ�����L�����邱�Ƃ����A�ǂ�����Ă���ȉ����̂̂��܂��܂Ƃ����o����������قǂɋ^���]�n�̂Ȃ������Ƃ킩��̂���ƍl�����ނ��Ƃ̂ق������������B���̓��R�̌��ʂƂ��Ď����̓_���͎U�X�������B
�@ ���w�͂Ƃ����ƁA�Ƃ��Ƃ��`�ɂ�������Ă����悤�ɂ������B��`��藝������Ȃ��̂��Ǝ���Ă��܂��Ƃ肠�������x�Ȗ���������̂͂킩���Ă������A�Ȃ�ł���Ȓ�`�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��ƍl���͂��߂�Ǝ��E�����Ȃ��Ȃ����B�u�T�C�R���̂��ꂼ��̖ڂ��o��m���͂�������Z���̈�ł���v�Ƃ������Ƃ������ȈӖ��Ő��藧���߂ɂ́A�u�ǂ̖ڂ��ϓ��ɘZ���̈�̊����ŏo��T�C�R�������݂���Ƃ���v�Ƃ����Öق̑�O�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������ƂɋC�Â��ƁA�m���Ƃ������̂̈Ӗ����Ȃ��悭�킩��Ȃ��Ȃ�����������B���ǁA����́u�l�Ԃ͐l�Ԃł���v�Ƃ����g�[�g���W�C�i���ꔽ���j�Ɠ��ނł���Ƃ������ɂ�����Ɠ����ɁA���������A����ȃT�C�R����N���ǂ�����Ă���̂��Ƃ������{�I�ȋ^��ɂԂ���A���X�߂���Ɋׂ����B
�@ �܂��A����ȋ�ŁA���Z���̎��́A�ɕK�v�Ȓm��������Ȃ�Ǝ���A���������ɈËL����Ƃ����K���^�̗D�����ł͂Ȃ���������A�Ȃɂ��Ǝ�̂����鐶�k�ł͂������ɈႢ�Ȃ��B�����A����Ȍo���̂������ŁA�̂��ɂȂ��āA�w�Ԉӗ~��{���I�Ȏv�l�͂͂���ɂ�������炸�ʏ�̒�������R�[�X�ɂ��܂��K���ł��Ȃ�������A�͂��߂��疳���������肵����҂ɐڂ���@��������Ƃ��A�ނ�̂����ꂽ�S���I�̂����Ȃ�I�m�ɔc�����邱�Ƃ͂ł����̂������B
�@ �W���I����R�[�X����h���b�v�A�E�g�������k�����́A����ɐe���܂߂����͂̑�l����������߂̊፷���Ō�����悤�ɂȂ�A�₪�ď����ւ̉ߏ�Ȋ��҂�����f�ГI�Ȓm�����l�ߍ��ގ��炩�����������B�Ƃ��낪�ʔ������ƂɁA����ȏ�Ԃ��ނ�Ƀv���X�ɂ͂��炭���Ƃ�����B
�@ �ʏ�̊w�Z����J���L�����������āA���Ȃ�ɔނ���w�����邤���ɁA���̂Ȃ����炾���ł��l�X�Ȕ\�͂������҂����ꂽ�B���x���̐��w��ʂ�z����w���x���̐��w�̊w�K�ɖ����ɂȂ�ҁA�����Ȋw�̓���ȗ̈�ɕ��O��ċ����S�������ҁA�����A�G�b�Z�C�A�Љ�Ȋw���Ȃǂ̌������ǂ�ǂ�ǂݐi�ގҁA���x�ȕ��w����N�w���A���j���Ȃǂ�ǂ�ł́A�����Ɋւ��錴�e�p���\���S���̃��j�[�N�ȃ��|�[�g�����炷��Ə����Ă��܂��ҁA����ɂ͎O�S���߂��̎��쏬�����d�グ��҂ȂǂƂ��낢�낾�����B
�@ �����܂ł͂悩�����̂����A�I�[�����E���h�ł͂Ȃ�����nj��I�Ȕ\�͂������҂������A��荂�x�Ȋw�т̏���w�ɋ��߂悤�Ƃ����Ƃ��A�ނ�̑O�ɗ����͂��������̂��A��w�������i���莎���ƁA�G���ł₽��f�ГI�Ȓm�������߂��w���w�����Ƃ�����d�̑傫�ȕǂ������B���Ƃ��Ƃ��̎�̎����ɂ͐��i�I�ɕs�����ł��邤���ɁA���܂��牽���Ȃɂ��킽��ËL���S�̎��Ȃǂɂ͖߂�Ȃ��Ƃ��������v�����S�̉��ɂ͂��炭����A��قNJo�債�ĐS���I�Ë����͂���ʂ�����A���̕ǂ̓˔j�͔ނ�ɂƂ��ėe�Ղł͂Ȃ������B
�@ �������A�Ȃ�Ƃ����̓�d�̕ǂ�˔j���A���܂ł͑�w�̋����₳�܂��܂ȕ���̃X�y�V�����X�g�ɂȂ��Ă�����̂����Ȃ��Ȃ��B�������A�����ɂ͂��������̔\�͂��J�����������Ȃ�����܂��Ă������҂̂ق����͂邩�ɑ��������B���Ƃ��A�������Ȃ�̂̂��Ƃł͂��邪�A���Z���ގ҂ł������ɂ�������炸�A���w�̂��镪��̂���߂č��x�Ȓm���C���Ɉӗ~��R�₷�\���̒j�̎q�ɏo���������Ƃ�����B���炩�ɓ��قȍ˔\�������Ă����Ǝv���邱�̐��k�́A���łɕ��ʂ̐��w�Ȃ̑�w���Ȃǂ����͂��������Ƃ�����ꂽ�̂����A���ǂ̂Ƃ���A���ɂ͔ނ̑O�r���Ђ炢�Ă�邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B���x�̕ǂ̂䂦�ɍ��܂����ނ͈ꎞ�����[�������̓X���߂��肵�Ă����炵���̂����A�₪�Ă��̏����͂킩��Ȃ��Ȃ����B
�@ �܂��A���s�I�Ȃ��̂ł���ɂ���A����̓����s����w�ɂ�����`�������W�����̓����͑�ϕ]�����ׂ����̂ł���Ǝ����g�͍l����B����łȂ��Ă��s�o�Z�҂̐������債�Ă�������̏��������ƁA����ɑΉ��������l�ȑ�w�i�w���[�g�������Ă�����ׂ����낤�B�����̑�w�����l�̐��x�̓����ɊS�������悤�ɂȂ�A���ʂ̃��[�g����͂�������h���b�v�A�E�g�����Ƃ͂����A�{���I�ɂ͒ʏ�̑�w�i�w�҂ɏ���Ƃ����ʔ\�͂�����҂��~�ςł���悤�ɂȂ�ɈႢ�Ȃ��B����͂܂��A���ڊԐڂ��킸�A�����̉䂪���̔��W�ɂ��Ȃ��邱�Ƃł����邾�낤�B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2002�N7��31��
�T�b�|���r�[���𒍂�������́H
�@ �Z�����{�̂��ƁA�V���̑��z�e���ōÂ��ꂽ�������ӍݏZ�ґΏۂ̍��Z������ɏo�Ȃ����B�����g�͂��낢��ƍÂ���邱�̎�̉�ɐϋɓI�ɎQ������^�C�v�̐l�Ԃł͂Ȃ��̂����A���܂ɂ͂������낤�Ƃ���������o���Ă݂��̂������B���̑�L�Ԃɂ͍��N���Z�𑲋Ƃ���w�ɓ���������̃t���b�V���}�����玵�\������y�܂Ŏl�S�l�߂����W�܂�A����Ȃ�ɐ����ł������B
�@ ���H�p�[�e�B�`���̉��ɂ͓�\�قǂ̉~�^�e�[�u�����z����Ă��āA���ꂼ��̃e�[�u���ɂ́A���Ƃ��Α����A��\����A���\����A��O�\����Ƃ�������ɁA�\�N�Ⴂ�̊e�N��w�̉�����W�܂�A���݂��ɔN������𗬂����Ă�悤�ȍH�v�Ɣz�����Ȃ���Ă����B
�@ �����U�蓖�Ă�ꂽ�A�����A��\����A���\����Ƃ���������p�̃e�[�u���͂��܂��Q���҂����Ȃ��A�܂��ʒu�I�ɂ����̉E�����Ɉʒu���Ă����̂ŁA���̃e�[�u���Ɗr�ׂ�ƐÂ��ŗ������������͋C�������B�J��O�ɂȂ��āA���\�ΑO�ォ�Ƃ������镨�Â��Ȋ����̐l�����A�u�����͘V�l�����Ă��\��Ȃ��Ȃł����c�c�v�ƌ����Ȃ���Ⴂ�����ŋ߂Â��Ă��āA���ׂ̗ɂ����Ƃ������B
�@ ������X���ɂ��J��̎��ɑ����A�������̕�Z���珵�҂��ꂽ�w�Z�W�ҁA����ɂ͓�������A�̈��A���I���A�܂��͊F�Ŋ��t�Ƃ����i���ɂȂ����B�e�e�[�u���ɗ₦���T�b�|���r�[�������{���^��Ă����̂ŁA���͂��̂����̈�{����ɂ���ƁA�������ܗׂ̑��y�Ƃ��ڂ����l���̂��O���X�Ƀr�[���𒍂��ł������B�Ȃ��Ή��������Ɏ��̂��ނ������Ă��ꂽ���̐l���́A��������O���X���e�[�u���ɂ��낷�ƁA���x�͎������r�[���r����ɂƂ��Ď��̃O���X�Ƀr�[���𒍂��ł��ꂽ�B���͉��˂ŃA���R�[���͂قƂ�ǂ��߂Ȃ̂����A�Ƃ肠�������t�̉����ɍ��킹�ăO���X���f���A�ׂ̐l�����͂��߂Ƃ��铯���e�[�u���̐l�����Ƃ��݂��ɃO���X���d�ˁA�����������y�����������B
�@ ���̑��y�ł���炵�����̐l���́A�u�������N�Ŏ��\�ɂȂ�܂��Ă˂��c�c�v�ƓA�d�Ȍ����Őe�����ɘb�������Ă����B���ꂩ��A��������l�́A�ߔN�̕�Z�̗l�q�Ȃǂ��Љ�����[�t���b�g�ɖڂ�ʂ��Ȃ���A�����A���킢���Ȃ��y����b�������������B�����A���̑���̎��R�Ȑg�U�����̉��ɂȂ�ƂȂ��������ꂽ���̂������n�߂Ă������́A���炭����ƁA���̐l���͂ǂ������L�����A�̎�����Ȃ̂��낤���Ə��X�C�ɂȂ肾�����B�����A������Ƃ����āA�u���d���́H�v���́A�u����܂łǂ�Ȃ��Ƃ��Ȃ����Ă�����ł����H�v���̂ƑF���ӎ����܂邾���ɂ��ėՂނ̂��݂��ĂȂ�Ȃ������B
�@ �Ƃ��낪�ł���B�����Ă���Ƃ��ɂ͌����Ȃ������̂����A������ƈʒu���ς�����Ƃ��ɂ��肰�Ȃ�����̋��̃l�[���v���[�g�Ɏ����𑗂�ƁA�v�����������u�}�������v�Ƃ����l�����̖��O���ڂɔ�э���ł����B����ȁc�c�܂����c�c���������Ƃ������Ƃ����Ă��邵�Ȃ��c�c�����ȋƊE�l�Ƃ��Ă��̖��O�����͂��˂��ˎ��ɂ͂��Ă�������ǁA�����������̐l�͎����̏o�g���Z�̐�y�����������H�c�c�����������Ƃ���A����ɋC�Â��Ĉ��A�ɗ���҂������Ă��悳�����Ȃ��̂����Ȃ��\�\�����ʼnQ��������Ȍ˘f�����������͌䂵���˂Ă����B�݂��Ƀr�[���𒍂������O���X���d�ˍ��킹�����肪�ق�Ƃ��ɂ��̐l���ł���Ƃ���A���܂�ɂ��b���o���߂��Ă���Ƃ������������炾�����B
�@ �Ăт��̐l���ׂ̗ɕ���ŗ��������́A���̗͂l�q���M���A��l�����ɂȂ����^�C�~���O���݂͂�����������ŁA�v�����ď����ł����Ɛq�˂������B
�@�u���̂��c�c������������A�T�b�|���r�[���̎}����������ł�������Ⴂ�܂����H�v
����̐l���͕s�ӂ�˂��ꂽ�悤�ɂ�����Ǝ��̂ق�������ƁA�����Ƀe�[�u���̏�Ɍy�������𗎂Ƃ��A�����̂������ق荞�B�\�b���\�ܕb���炢�͂��̒��ق��������̂ł͂Ȃ��낤���B��͂�l�Ⴂ�������̂��ȁA�������Ƃ���Ȃ��\����Ȃ����Ƃ����Ă��܂������ȁ\�\���̋����ɂ���Ȃ��������N���オ��͂��߂�����ɂȂ��Ă���A����͂悤�₭�����J�����B�����āA�ꌾ�����A�u�͂��A�����ł��c�c�v�ƒႭ�����悤�Ɍ������B�킸���O�\�b���炸�̊Ԃ̂��Ƃ肾�������A���T�b�|���r�[���В��Ō��݂ł͓��Ђ̖��_�ږ���Ƃ߂Ă�����}����������̂��l�����悭�Â��ł����Ƃł͂������B
�@ ����ɂ��Ă��Ȃ�Ƃ������Ƃ��낤�A���˂̎������܂��܌��T�b�|���r�[���В��Ɨ��킹�A�����Ƃ͒m�炸�ɃT�b�|���r�[����̃O���X�ɒ����A���肩��������̃O���X�ɃT�b�|���r�[���𒍂��ł��炢�A�O���X�����킹�Ċ��t����\�\�C�܂���Ƃ������Ȃ�Ƃ������A�_�l�Ƃ������̂́A���ɂȂ�Ƃ����Ȑl���̉��o�����Ă������̂ł���B
�@ �����l�[���v���[�g�̂��̖������˂��ˎ��ɂ��Ă��Ȃ�������A�܂����ł���������Ƃ��Ă��܂��Ă�����A�T�b�|���r�[���𒍂����������̐l�����N�ł��������ȂǍŌ�܂Œm�邱�Ƃ͂Ȃ������ł��낤�B���̂��Ǝ���������ƐȂ��͂������m�̌�y�Ƙb�����I���ăe�[�u���ɖ߂����Ƃ��ɂ́A�}������̎p�͂��łɉ�ꂩ������Ă��܂��Ă����B���̂悤�ɃX�[�b�Ɨ��������Ă��������̂炵���B�����̗F�l�������A�u���̓�����p�ɃT�b�|���r�[�������Ă��ꂽ�͎̂}����������炵����v�Ƃ����̂ŁA�u���܂܂Ō�{�l�������ɂ�������Ȃ��v�Ƃ����ƁA�N�����ςɂ܂܂ꂽ�悤�Ȋ���������悤�ȗL�l�������B
�@ ���ƂŐْ���������悷��ƁA�݂邩��ɒB�M�ȃy�����̗�����Ă����B�A�d�ȕ��ʂ̋��X�ɂ�����܂ŁA���Ζʂ̌�y�̎��ɑ��邱�̂����Ȃ��������v������ƐS�z��Ɉ��Ă��āA�Ȃ�Ƃ��S������������ł͂������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2002�N8��7��
�ς��ʂĂ����O�ʌk�J
�@ �������w�̐����Œm��ꂽ�O�ʐ�Ƃ��̎��ӂ̌i�ς����Ȃ�ϖe���Ă��邾�낤�Ƃ͑z�����Ă����B�������A���̕ϖe�Ԃ�͎��̑z�����͂邩�ɒ�������̂ł������B�O�ʌk�J��傫���ׂ��V�݂̋���ɗ��������́A������債���܂ܕ�R�Ɗቺ�̉��O�ʃ_���̌Ζʂ߂�����B�߂������̎O�ʌk�J�̐��̐F�ɂ͎��Ă������ʊD���F�̌ΐ��́A�Ă̑��z�̉��ł���ɂ�������炸�d�����Â�����ł��āA���Ă̐��C�̖��c�Ȃǂ܂�Ŋ������Ȃ������B�_�����������X�����n�܂钼�O�̓�Z�Z�Z�N�㌎���ɂ��̒n��K��Ă���܂���N�\�����قǂ����o���Ă��Ȃ��Ƃ����̂ɁA���̖��c�Ƃ��������悤�̂Ȃ��ς��悤�͂ǂ����낤�B���͋����Ō�������[�������݂ƕ����������Ƃ��ǂ����邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�i2000�N9��20���`10��4���̃o�b�N�i���o�[�Q�Ɓj
�@ �ȑO�ɂ͓��{���w�̎��R�̕�ɂ�搂��A�_��I�ȐF�ɂ���߂������A�ΖL���ȐX��сA�i���ɕx�މ��[���k�J�A�ꕶ�̈�ՌQ�A����ɂ͂���炷�ׂĂ������ޒ����R�n�̎R�X�Œm��ꂽ���O�ʂ̒n�́A���͂⊴���̂����炳�����o���邱�Ƃ̂ł��Ȃ����}�ŎE���i�ȋ���l���Ɖ����Ă����B�㍂�n����̐��̐������������������R�o���g�u���[�̐����̑啔�������O�ʃ_���̌Β�[���ɒ���ł��A���Ă̖ʉe�̂����炩���炢�͎Âׂ�ł��낤�Ɗ��҂��Ȃ��玄�͂����ւ���ė����B�������A����ȒW�����҂͏u���ɂ��Đ������ł��܂����̂������B
�@ �����Ɏc����Ă����͉̂��O�ʂ̒J�X�̈������S�[�ɂ����Ȃ������B�����̑�����̏㗬�ɂ��鏬�͓��_���̐��̐F�ł������A���ܖڂɂ��Ă��鉜�O�ʃ_���̌ΐ��̐F���͂����Ƃ܂����Ƃ����킴������Ȃ������B�_������܂���N���炸�������Ԃ��o�߂��Ă��Ȃ��Ƃ����̂ɁA����قǂ܂łɎ��ӊ�����ς��Ă��܂����Ƃ���������ڂ̓�����ɂ��āA���͐S�ꜱ�R�Ƃ���ƂƂ��ɁA���������R�̐삪���ʂƂ������Ƃ��ǂ��������Ƃł���̂������炽�߂Ďv���m�炳������ł������B
�@ �k���̎R�x�n�тł́A�c��ȗʂ̐�Z�����ƂƂ��ɑ�ʂ̓y����A�����̕��t�y�A���X�̗��t�⏬�}�A�|�ؗނȂǂ����X�Ɍk�����ɗ��ꍞ�ށB�����A���Ƃ������ł����Ă��A�ȑO�̂悤�ɐ삪�����Ă��Đ�ԂȂ��������ꓮ���Ă���Ƃ��ɂ͋��͂Ȏ��R�̏͂������A�����ɂ킽���Đ�����������D���F�ɑ������肷��悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B���̂����ۂ��A��^�_���̏o���ɂ���Đ����������~�߂�ꐅ�̓����̂Ƃ܂����ΐ��ł́A�y���╅�t�y�͎��X�ƌΒ�ɒ��b���A�㗬���痬�ꍞ�ޑ��ʂ̗L�@���̂��߁A���Ƃ��Ƃ͂ǂ�Ȃɐ����ł����Ă��}���ɕx�h�{�����i�݁A�����܂������x�������Ă��܂��̂��B�ނ��A����Ȃ��ƂȂǗ����Ƃ��Ă͂Ƃ����ɒm���Ă͂������Ƃ����A���̐��܂����ϗe�Ԃ�������ɖڂɂ��Ă݂�ƁA���������Ռ��̑傫���͂܂��z���ȏ�̂��̂ł͂������B
�@ ��Z�Z�Z�N�̏\���ܓ��ɎO�ʃ_���̒X�����͂��܂�ƃ_�����ӂւ̈�ʐl�̗�������͋֎~���ꂽ�B���̌�̗l�q��m�肽���Ƃ������A��N�Z���̂����x���ɒ����X�[�p�[�ѓ�������_�����ʂ֓��낤�Ƃ����̂����A�܂��ʍs�~�߂ɂȂ��Ă���ړI���ʂ������Ƃ͂ł��Ȃ������B�������A���̎��́A�܂������̋��R����A�����ʂ�̎�Ԃ��ԂŁA����ɂ͐܂���̑̒��̈����������Ē����X�[�p�[�ѓ����̐����Ɉʒu������R�ɋ��s�o�R����n���ɂȂ����̂������B�i�o�b�N�i���o�[�A2001�N6��20���`7��4���Q�Ɓj
�@ ���ǁA��N�͂��̂��Ɖ��O�ʂ�K�˂�@��Ɍb�܂�Ȃ������̂ŁA���N�͂Ȃ�Ƃ��Ă��Ƃ������A�����̏��{�ɍĖK�����݂��悤�Ȃ킯�������B����͑���s���璩���X�[�p�[�ѓ��`���ɓ��邢���̃R�[�X�ł͂Ȃ��A�R�`���암�̏�������ܖ���̉��ւƑ������𑖂�A�r������k�ɕ���ׂ��ѓ��ɓ����Ęn�����z���A���O�ʃ_���{����ʂւƂ�����R�[�X���Ƃ����B
�@ �n���z���̗ѓ��͐[���т�D�������_�[�g�̓��ŁA�r���A�}��Ƌ}�J�[�u�̑������H���������A���ӂ̌i�ς͂Ȃ��Ȃ��ω��ɕx��ł���A���ё����L���Ȃ������̂ŁA�����Ă��ċ�ɂȂ�悤�Ȃ��Ƃ͂܂������Ȃ������B�n�����z���A�u�����Ќv�Ɩ������ꂽ�Ƃ������Ă��鉜�O�ʃ_���ɉ���܂ŁA�����ȂƂ���A���́A����Ȃ�ɂ͐��Ζʂ�������̂��낤�ƍl���Ă����B�������A������I���l�g�[�Ɍ���悤�Ȑ^���ɐ��ΐ��̐F�����҂��Ă����킯�ł͂Ȃ��������A�_���̒X�����͂��܂�ȑO�̎O�ʐ��{���̐����̐��P����m��g�Ƃ��ẮA�����炩�ł��������ʂ̋P�����c���Ă���悤�ɂƊ�킴������Ȃ������B
�@�������Ȃ���A���ۂɎ���҂��Ă������̂́A�D���F�������Ζʂ݂̓����P�������������̂��B���v�������O�ʌk�J��傫���ׂ����݂̐V�������́A������Z�Z�Z�N�㌎���ɂ��̒n��K�˂��Ƃ��ɂ͂܂��������ł������B�O�ʐ쉈���̓���J���ւƌ������đ���Ȃ���A�͂邩����ł����Ȃ��Ă����|����ȉˋ���ƂG�Ȃ������ŋ��������̂ł���B����Ȃ��ƂɁA�����͂��̐V���̏ォ��A���ē��H�̂������Ƃ������邠����̐��������������ƌ����낷���ƂɂȂ����̂ł������B�������A������������Ƃ����Đ���[���ɒ�������O�ʐ�̉͌��Ȃǂ�������͂����Ȃ����Ƃ͂킩���Ă����B���ۂ̂Ƃ���́A���Ƃ��ǂ�Ȋ�Ղ��N�������Ƃ��Ă��A����ꂽ���̂����Ă̎p���̂܂܂��S�邱�Ƃ͂����Ȃ��̂��Ǝ���ɂ����������������Ă����̂ł���B
�@ ���̐V�������̒[�ɂ����̎x���ɂ́A���ꂼ��Ƀ}�^�M�ƃJ���V�J�̃����[�t���Ƃ߂��܂�Ă������A�������������z���̂��̂���X����������ł͂���Ƃ�����ꂽ�B���Ă̓}�^�M��J���V�J�����̉��O�ʂ̒J�̏ے��ł������ƌ����`�����������̂ł��낤���A�����ŋ߂܂ŋȂ���Ȃ�ɂ������Ă������̔������J������Ȗ��c�Ȏp�ɕς������l�����̎�ɂ���āA���R�ւ̈،h�̂����炳�����������Ȃ�����ȏ����̍H���Ȃ��ꂽ���ƂɎ��͂���̂Ȃ�������o����������Ȃ������B
�@ ��N�O�ɐ��v���O�̉��O�ʂ�K�ꂽ�Ƃ��A����_���̍H������ɂ́A�u���炩�ȎO�ʐ�A���̂ʼn����ȃ_�����ԁv�Ƒ发�����傫�ȉ��f���������Ă����B�N���l���o�����W��Ȃ̂��͒m��悵���Ȃ��������A���͂��̂���ׂ����̎��R�]���̌��t�̗����ɐ��ޖ��_�o���ɗB�X����ʂĂ����ł��������Ƃ�z���o���B�����O�\�N���̉䂪���̑�K�͌������Ƃƌ��ݍs���̎��Ԃ�����قǂɏے����Ă��錾�t�͂Ȃ��Ɗ��������炾�����̂����A����Ƃ܂��������Ȃ��悤�Ȗ��_�o���������̂Ƃ��Ă����悤�ȃ����[�t�Ɋ��������Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B
�@ �l�ގj�̗���̂Ȃ��ɂ����āA�K�v�ɉ����Ď��R�����X�ɉ�������A����ɂ���Ď��R�{���̎p���������ϗe���Ă������Ƃ͎d���̂Ȃ����Ƃ��Ƃ͂������B�ЊQ����n��Z������邽�߂̎����A�_�Ɨp������p���̊m�ہA����ɂ͕N������d�͎���̊ɘa�ɋ���_������ΕK�v�ł���A�n��Z�������A�Z�X�����g�̐��Ƃ����̂��Ƃ��\���ɔ[�����Ă���Ƃ����Ȃ�A�_�����݂Ɋ����Ĕ��͂��Ȃ��B
�@ �������A���̉��O�ʃ_�����݂Ɋւ��ẮA���߂���I���܂ł܂�Ŕ[�������������Ƃ����������B���ݐ��i�W�҂ɂƂ��Ă͎������p���m�ۂ��d�͋��������ۂ̂Ƃ���͂ǂ��ł��悭�A���炩�Ƀ_���邱�Ǝ��̂�ړI�ɂ����A��萳�m�Ɍ����_�����݂�ʂ��ċ��z�̂������������Ƃ�����_�����_�����݂���������ł���B�ߔN�̍s�����v��\�����v�̋C�^�̍��܂�ɂ��^�_�����݂̌������_�Ȃǂ���яo���Ȃ��ŁA�O�\�N���̉��O�ʃ_���̊����ƒX�����ُ�Ȃ܂łɋ}���ꂽ���ɂ͂���Ȃ�̎���������ɈႢ�Ȃ��B
�@ �����L���̖L���Ȏ��R�Ɍb�܂ꂽ�O�ʏW�������I�ɑS�ʈړ]�����A�������Ɛ����Ɗ�̐��X����Ȃ�L��Ȍk�J�𐅖v�����A���̑r������Ƃ��ɂ������~��т̋M�d�ȓꕶ��Ղ����ł����Ă܂Ō��݂��ꂽ���̃_���́A���ア�������ǂ�قǂɒn��Z���̐����ɖ𗧂Ƃ����̂ł��낤�B���̃_���̌��ݖړI���A�����p�A�����p���m�ۗp�A����ɂ͔��d�p�Ƃ��̎��X�̓s���ł��邭��ς�������Ƃ��炵�Ă��A���̕K�v������̂��̂ł͂Ȃ��������Ƃ��M����B
�@ �V��������s�̖k�����o�ē��{�C�ɒ����O�ʐ쐅�n�ɂ́A���łɑ�^�̎O�ʃ_���Ɖ��c�@�_���Ƃ������Ă���A������e��p���m�ۂ̖����͂�����̃_���ɂ���ď\���ɉʂ�����Ă����B�e���ʂ��炻�̖ړI�̞B������ᔻ���ꂽ�V�����⋌���ݏȂ̊W���ǂ́A���ǁA���̉��O�ʃ_���d�p�_�����ƈʒu�Â��邱�Ƃɂ����̂��������A�f�l�ڂɂ����̎咣�ɐ����͂�����ȂǂƂ͂������Ȃ��B
�@ ���O�ʃ_���ɂ���ĐV���ɐ��ݏo�����d�͔͂N�Ԗ�ꉭ�O�疜�L�����b�g���Ƃ̂��ƂŁA��������z�Ɋ��Z����ƔN�Ԃ��悻�\�����~�ɂȂ�Ƃ����B�O�ʃ_���̌��݂₻�̈ێ��Ǘ���ɓ������ꂽ�����͂��łɈ�牭�~���Ă��邩��A���̎����������҂��邾���ł��P���v�Z�ŕS�N�߂����v���邱�ƂɂȂ�B�����ɂ͓��������ɗ����������邱�Ƃ��낤���A�_���̑ϗp�N���͕S�N�O��ł��̊Ԃɔ��d�{�݂̂ق����V�������Ă��܂�����A�ƂĂ��̎Z�̍����b�ł͂Ȃ��B
�@ �������A���łɐ������̐��͔��d��������d�͎���������͂Ȃ��V�������A���̃_���̔��d�\�͂ɂ���قLjˑ����Ȃ���Ȃ�Ȃ������Ƃ͍l�����Ȃ��B�܂��A�����g������قǂ܂łɂƋ����قǂɕς��ʂĂ���O�̕��i�́A�ƂĂ��ό������Ȃǂɂ͂Ȃ肻���ɂ��Ȃ��B�X���J�n���N���炸�ł��̗L�l������A�Β�ɂ͂ǂ�ǂ�D�y�����܂�A�����͗L�@�����Ď��Ԃ͂������������Ȃ邢���ۂ����낤�B
�@ ��肫��Ȃ��z���ɋ���Ȃ�����A���͂��܈�x�Ȃ�Ƃ��C�������������A�ȑO�ɕ����܂�����O�ʌk�J�̏㗬�n�т��ĖK���Ă݂邱�Ƃɂ����B�_���̌Ζʂ��J���̂ǂ̂�����ɂ܂ŒB���Ă���̂��A�X���J�n���O�ɓn�������̑z���o�[���݂苴�₻�̉��𗬂�Ă��������͂ǂ��Ȃ��Ă��܂����̂��A�I�т₻�̂���ɒJ���ɂ���u�i�т͂��Ă̂܂܂Ŏc���Ă���̂��ȂǁA���낢��ƋC�ɂȂ邱�Ƃ����������炾�����B�����āA�Ȃ��ł��Ƃ��ɋC�|���肾�����̂́A��Z�Z�Z�N�㌎���̒T�K�̍ۂɋ}�Ζʂɐ�����u�i�т̐[���M�n��~�������ō~�藧�����������k����͌����A���̌�ǂ��Ȃ��Ă��邩�Ƃ������Ƃ������B
�@ ���̂Ƃ��j�����R�o���g�u���[�̕���Ήp���̔����Ə����̋ʐ���Ȃ�͏��͂��܂ǂ��Ȃ��Ă���̂��낤���A����ɂ܂��A���̉͏��̏���T���T���Ɖ������𗧂ĂȂ��炫��߂����ꉺ���Ă����A���̐������z�I�Ȑ����͂Ȃ������݂Ȃ̂��낤���\�\���͂����̑��݂̖������F��Ȃ���A���v�����O�ʌk�J�̍������㗬�Ɍ������đk�s���͂��߂��B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2002�N8��14��
��W�Ƃ��Ẳ��O�ʃ_��
�@ ��N�قǑO�܂ł͂��̗̈e���ւ��Ă��������~�ꕶ��ՌQ�̑啔���͐��v���Ă��܂��Ă������A��Ղ̍ŏ�i���ɂ�����Ƃ��낾���͌��݂�������Ƃ�Ă��銴���ł������B�����A���ڂɒ��߂邻�̍r��ʂĂ��l�q���炷��ƁA��Z�Z�Z�N�̏H�ɒX�����J�n����Ă��炢�������ՑS�̂������ɒ��݁A���̌�̃_���̐��ʒቺ�ɂƂ��Ȃ��čēx���̕����������p�����킵�����̂̂悤�ɂ�������ꂽ�B���Ȃ����̂Ȃ猻��܂ŋ߂Â��ďڂ������ώ@���Ă݂����Ƃ����C�͂������A�_���̑Ί݂ɂ��邻�̒n�_�ɓn�邱�Ƃ̓{�[�g�ł��Ȃ�����͂�s�\�Ȃ��Ƃ������B�@�@
�@ �����ł����������̋M�d�Ȉ�Ղ���邽�߁A�Ȃ�Ƃ����ʂ̒���������H�v�����ł����Ăق����Ƃ����̂��ꕔ���Ƃ̂����₩�Ȑ��ł��������̂����A���d�p�Ƃ��Ẵ_���@�\�̈ێ��ォ�����Ղ̑S�ʐ��v�͔������Ȃ��ƊW���ǂ͎咣���A�\��ʂ�X���͋��s���ꂽ�B����ɂ�������炸�A���̈ꕔ���������r���[�Ȃ������Ő��ʏ�ɖ��c�Ȏp�����炵�Ă���̂́A����ɔE�тȂ������肾�����B
�@ �X���J�n���O�ɖK�ꂽ�Ƃ��܂ł͎c���Ă������O�ʖ����̌Õ��ŃX�������_�̖ؑ��݂苴�����łɂ��̉e�͌����Ȃ������B���̎��̒T�K����ɁA�������ɔp�����R�ɂȂ��Ă������݂̒苴���Ō�ɓn�����͎̂������������Ƃ������ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ə���������������A���ۂɂ����������Ƃ������̂ł͂Ȃ��낤���B���̎��͂܂����̉�������߂��悤�Ȑ����������悭����Ă������A�ނ��A��т͐��v������ł������萶�C�������������d�����Y������ł������B
�@ �V�����݂���ꂽ�_�������ܑ̕����H���ʼn��܂ŋl�߁A�����ŎԂ��~���ƁA�[�X�Ƒ��ނ��r��ʂĂ��ׂ����o�R����J�̉��ւƌ������Đi��ł������B�K���ȑO���炠�����L��ȌI�т͐��v��Ƃ�A���܂��̂̂܂܂̎p���Ƃǂ߂Ă����B�r�q�ŗ͋����������݂������̏��^�̐Ԋ^�̐��ޑ�����݂������B�o�R�������炭�䂭�ƁA�ȓ��x���ʂ��牺�R���̓o�R�ғ�A�O�l�Ƃ��������B���ꂩ��قǂȂ����͐[���u�i�т̒��ւƓ������B�o�R�����ӂ̃u�i�т����Ă̂܂܂̎p���Ƃǂ߂Ă����̂ŁA���̋C�����͏������薾�邭�Ȃ����B�����āA���̂ԂƁA��N�O�̋㌎�ɉj�������Ƃ̂�������[�����₠�̃R�o���g�u���[�̌��z�I�ȐF�̐����A����ɂ�ῂ����P�������̉͏��A�Y��ȏ��̉͌��Ȃǂ����܂����̂܂c���Ă���̂ł͂Ȃ����ƁA�����₩�Ȋ��҂�����͂��߂��̂������B
�@ �u�i�т̉��̌��o���̂���n�_�܂ł���Ă���ƁA���͎��щ����M��~�������Ȃ���}�Ζʂ�J��̕��ւƌ������ĉ����Ă������B�������A���Ə����Ƃ����Ƃ���܂ŗ��āA�Ȃ��ȑO�Ɨl�q���ς���Ă��܂��Ă��邱�ƂɋC�Â����̂������B�Ζʂ��h���h���ɂȂ��Ăʂ������芊�����肵�A�������A�O�����قڐ����ɂ�����Ă��܂��Ă��ĉ͌��ɍ~��郋�[�g��T�����Ƃ��ł��Ȃ������B����ǂ��납�A���������͌��炵�����̂�����������Ȃ��̂������B����n�_���ԈႦ���̂��ȂƂ������A�܂��Ζʂ��悶�̂ڂ��ēo�R���܂ň����Ԃ��ƁA�������̂ق��ւƒn�_��ς��A�ēx��������݂��B�������Ȃ���A���ʂ͂܂�ł��Ȃ��������B
�@ ���������Ȃ�ƈӒn�ł���B���͂����Ă�����x�A�^�b�N�����݂邱�Ƃɂ����B�����A�O�x�ڂ͒J�̏㗬�����ւƑ傫���ړ����A�K���ȎΖʂ�I��ł�������~�����͂��߂��B���̎Ζʂ̒J��߂��̈�т���͂�c���c���h���h���ŁA�������Y�u�Y�u�Ƃʂ��������A�D�ɂȂ�̂��o��ł����ꂽ�n�`������Ɉړ����Ȃ��猜���Ƀ��[�g��T���Ă��邤���ɁA�Ȃ�Ƃ��k���ɖʂ���n�_�ɍ~�藧���Ƃ��ł����B�����āA���̏�ɘȂ��́A�قǂȂ����ĉ����N�������̂����͂�����ƌ�����̂������B
�@ �k�J�̐��͂������Ɨ���Ă���A�����Đ��͊m���ɐ���ł����B���ʂ̐�̐��Ȃǂ��͊i�i���Y��ŁA���߂Ă��̌k����ڂɂ����l�Ȃ炻��Ȃ�ɔ������Ɗ������ɈႢ�Ȃ��B�����A�ȑO�̔�������ʂ̋P����m��҂̖ڂɂƂ��ẮA����͎��ʂĂ��O�ʌk�J�̎p�ȊO�̂Ȃɂ��̂ł��Ȃ��̂������B���̐_��I�ȐF�̃R�o���g�u���[�̐����́A����ł͂�����̗̂��������F�̐��ւƕς��A���낤�Ƃ��ĉj���Ƒ傫���쉺�����ւƗ������قƂɐ����̂悩���������́A�킸���ɓ������x�̗��������Ƃǂ߂Ă��Ȃ��L�l�������B
�@ �ڂ��Â炵�Ă悭����ƁA�ȑO���L�������Đ[���Ȃ����k���̐���ɂ͗Ί��F�̓D�y���������a���Ă���A�Ήp���̔����̉͏��Ȃǂ��͂�ǂ��ɂ���������Ȃ������B����ɂ܂��A�Ζʂ̗�����㗬�悩�痬��o���D�y���ς����Ă��܂����W�ŁA�k�J�̂��������ɍL�����Ă������Ă̔������͌��͂��ׂď��ł��Ă��܂��Ă����B
�@ ���̑����͂ʂ����ăh���h����Ԃ������B���Ԃ�A�Z����̑�ʂ̐�Z�����̂��߂Ɉ�т̌k�J�̐��ʂ��オ��A���ꂪ�Ƃ܂��ēy����D�y�����a�A���̌�ɐ��ʂ��������Ă��̂悤�Ȗ��c�ȏɂȂ����̂��낤�Ɛ������ꂽ�B�����Ƀ_�����ł��������Ƃ܂�����A�����łȂ��Ă��������������肵�Ď��R�̃o�����X������Ă��܂��ƁA���̂悤�Ȃ��ƂɂȂ��Ă��܂��̂��B��N���炸�ł��̗L�l������A����͂܂��܂��Ђǂ���ԂɂȂ��Ă������Ƃ��낤�B���̂����₩�Ȋ��҂��ނȂ����A�X���O�ɖڂɂ������̌��z�I�Ȍ��i�͂��łɎ����Ă��܂��Ă���A���ꂪ�S�邱�ƂȂǂ�����x�ƂȂ��Ƃ����킯�Ȃ̂ł������B
�@
�@ �W�[���Y�̐���C�̈�ʂɃh���h���̓y��t���������܂܁A���̏��}����J���M��~�������ċ}�Ζʂ�o��R���ւƖ߂鎄�̑����͏d���������B������x�Ƃ��̎Ζʂ����邱�Ƃ͂Ȃ����낤�Ƃ������Ɣ߂������������B���߂ă}�X���f�B�A�̎�ސw���X���O�̂��̌k�J�̌����Ƃ��܂������i���r�f�I�ɂł����^���Ďc���Ă����Ă��ꂽ�Ȃ�A���݂̓����̌��i�Ɣ�r���f���邱�Ƃɂ���āA�_���Ƃ������̂��@���ɒZ���ԂŊ|���ւ��̂Ȃ����R��j�Ă��܂�����l�X�ɑi�������邱�Ƃ��ł����̂����c�c�B
�@ ���v���O�Ɍ����~�̓ꕶ��Ղ̎�ނɋ삯�����ꕔ�̒n�����f�B�A�̕w���A�����肸���Ə㗬�Ɉʒu���Ă��ē������m��l�̏��Ȃ��������̒n�_�܂Ŏ�ނɗ��邱�Ƃ͂܂��Ȃ������ɈႢ�Ȃ��B�܂��A���Ƃ���������̏��Ă����Ƃ��Ă��A�J������S���A��J���Ă킴�킴����ȂƂ���܂ŎB�e�ɓ��邱�ƂȂǂȂ������ł��낤�B�������Ə��ƃx�[�X�݂̂ɏd����������������{�̃}�X���f�B�A�͂̕�p���Ȃ�ď��F����Ȃ��̂Ȃ̂��낤�Ƃ������ƁA��肫��Ȃ��C���ɂ��Ȃ炴������Ȃ������B
�@ ���̉��O�ʃ_���Ƃ܂��������l�̎Љ�I�\�}����I�w�i�������A�����̏Z������ی�c�̂̎��ƌ������v���̐�������ɂ�������炸�A�W���ǂɂ���Ē���^�_���̊������}����悤�Ƃ��Ă���̂��A��B�̋�����㗬�̐�Ӑ�_���Ɗ��k���̓��R�_���̓�ł���B��Ӑ�_���̏ꍇ�ɂ͗����т̓��A�����Ԃ̑傫�ȕω���A������̐싛���┪��C�i�s�m�ΊC�j���݂̐��Y�Ƃւ̈��e�����뜜����Ă���B�܂��A�����ۂ��̓��R�_���ɂ��ẮA���O�ʃ_���̏ꍇ�������ł������悤�ɁA�厩�R�̕�ɂƂ��Ēm���A�����̎��R���D�҂ɐɂ��܂ꑱ���Ă��������R���S��𐅖v�����邱�Ƃ̐���≺����̐����ω��̐�����Ă���B���R�_�����ݗ\��n�̏ꍇ�A���N���O�܂ł͈�ʂ̗���������\�ŁA�������̎��R�̑f���炵����ڂɂ��Ă������ƈ�A��x�K�˂����Ƃ����邪�A���݂͊W�҈ȊO�̗�������͋֎~����A�}�s�b�`�Ń_���̊������}����Ă���悤���B
�@ �ǂ���̃_�����ݎ��Ƃ��A�����_��搂��������o�u���o�ς̐Ⓒ���Ɍ������ē��{�Љ�S�̂�����o���������Ɍv�悳�ꂽ���̂�����A���Ƃɂ�鋐�厑�{������̊m�ۂƂ��̌o�ϓI���ʂ⎑���^�p�����̃A�b�v�ɖ𗧂��Ƃ����ŁA���R���ɑ���z����{���I�Ȏ��ƖړI�̐���ȂǓ�̎��̖��ɉ߂��Ȃ������̂��B�������A�o�u���o�ϕ���ȍ~�̎Љ�̕ω��ɂƂ��Ȃ��A����_�����݂̖ړI��K�v�����e���ʂ���^�⎋�����悤�ɂ��Ȃ��Ă����B���ƌv��𐄐i�����W���ǎ҂�́A������̕K�v����d�͎����J���A�e��p���̊m�ہA�n���o�ς̊������Ȃǂ����ݗ��R�ɂ������肵�Ĉ���������_���̊������Ɗ���Ă͂���悤�����A���̎咣�ɂ͈�ѐ����Ȃ��A�Љ�̐��ڂɂ�Đ����͂Ɍ�����悤�ɂȂ��Ă��Ă���̂͂��łɏO�m�̒ʂ�ł���B
�@ �W���ǎ҂�W�����̂̎��ƐӔC�҂����āA���S�͎Љ�̕ω����@���_�����݂����s���邱�Ƃɉ��^�I�ɂ͂Ȃ�͂��߂Ă͂���̂�������Ȃ����A�s����̐ӔC��肪�������邱�ƂȂǂ������āA���ɖc��Ȏ����𓊓����Ă��܂����v��𒆎~���錈�f�����������ƂȂǂ��ł����ɂ���ɈႢ�Ȃ��B���Ƃ�����܂ł̓��������ʂɂȂ����Ƃ��Ă��A�̂��ɐ����鑹���̑傫�����������Ύ��ƌv��̒��~���ӂ��킵���Ɣ��f�����P�[�X�͏��Ȃ��Ȃ����Ƃ��낤�B�����c�O�Ȃ��ƂɁA������������������R�Ƃ��ĉ�����悤�Ȑ����N�w�ƐӔC���������������Ƃ�s���҂Ƃ������̂́A�䂪���ɂ͉ߋ��ɂ����݂ɂ��قƂ�Ǒ��݂��Ă��Ȃ��B
�@ ���ܒ��쌧�̌����͑O�m���̒E�_���錾�����[�ƂȂ��đ�h��ɗh��Ă���B�������̂��ׂẴ_���v��𒆒f�Ȃ����͒��~����Ƃ����O�m���̐������j���S�ʓI�ɐ������K�Ȃ��̂ł���̂��ǂ����́A����炷�ׂẴ_���v�掖��ɒʂ��Ă��Ȃ����ɂ͔��f�������˂�B�������Ȃ���A�����Ȃ��Ƃ������_�����ƌv��̂����̓�A�O�̂��̂��A���݂̎Љ����ӊ��̗l�q���炵�Ă��K�v�̂Ȃ����̂ł��邱�Ƃ����͂悭�킩��B
�@ �C���i�ނ��R�؍̂�A�����Ȃǂ����˂Ē��쌧���͂��߂Ƃ���e�n�̐[����ɓ��邱�Ƃ̑������́A�قƂ�ǐl�ՋH�Ől�ڂɂӂ�邱�Ƃ��Ȃɂ悤�ȂƂ���ɁA����Ȕ�p���������d�ɂ�����ꂽ���h�_���⎡���_���ɍs�������邱�Ƃ�����B�������ɕK�v���Ƃ�������_��������̂����������A�����ۂ��ł��̎�̃_�����ӂ̍r��ʂĂ�������I�Ȗ��@�\���v�Ԃ肩�画�f���A���݂���Ȃ������ق��������Ƒ����������낤�Ƃ�������悤�Ȃ��̂����Ȃ��Ȃ��B�ꌩ���������ŁA�Ȃ�����ȂƂ���ɂ���Ȃ��̂����̂��Ǝ���X�������Ȃ�悤�ȃV�����m�����Ă����Ԃ�Ƒ��݂��Ă���̂ł���B
�@ ���c���s�M�C���c��˂�����ꎸ�E�����O���쌧�m���͍ēx�m���I�ɗ���₵�A�E�_�������͂��߂Ƃ���s�����j�⎩��̔\�͂�l�i�ɑ��錧���̐M���ēx�₤���肾�Ƃ����B�L�͂ȑR�n�����ꂩ���Ă�����悤������A���̌��ʂɂ��Ă͗\�f�̋�����Ȃ��Ƃ��낾���A���̉e���͑�������łȂ������S�̂ɂ��y�Ԃ��Ƃ��낤����A���쌧�̕��X�ɂ͍����̏⏫���̎Љ���\���ɏn�����������ł̓��[�����肢���������̂ł���B
�@
�@ �������藎�_�������ĎԂɖ߂������́A���߂ĕς��ʂĂ����O�ʂ̒n�̖��c�Ȏp����������Ɣ]���ɍ��݂��Ă��������Ƃ������A�_���{�̂̂��鉺�������ւƑ��肾�����B������̋���ȃA�[�`���_����ɍ��������鏭����O�̒n�_�ɂ́A�傫�ȐΔ�̗��W�]�䕗�̃X�y�[�X���݂����Ă����B�Ȃ낤�Ƃ������Ԃ���~��Ă��̐Δ�̑O�ɘȂ�ł݂�ƁA�����ɂ́u�O�ʂ����ɂ��肫�v�Ƃ����Z���������������̕����A�傫���A�����Đ[�����܂�Ă����̂������B
�@ �݂肵���̎O�ʏW�������܂��Âԋ��Z�������̐[���z��������Ō��Ă�ꂽ��Ȃ̂ł��낤���A���ɂ͂��ꂪ�A�Β�ɖ��鋌�O�ʏW���̕�W�ł������łȂ��A�L��ȉ��O�ʌk�J�̎��R�́A����ɂ͓��{�Ƃ����������ėL�������E�L���̔��������R���̂��̂̕�W�ł�����悤�ɂ������ĂȂ�Ȃ������B�܂��A���̎������ł����邩�̂悤�ɁA
�ቺ�ɍL���鉜�O�ʃ_���̐��ʂ͑�ʂ̍g����n�������悤�ȐF�����Ă��āA�Ђ�����d�����A�����Ăǂ��܂ł��Â������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2002�N8��21��
���ɏo���ēǂ݂����Ȃ����{��
�@ �o�ŊE�͂��܂�����Ƃ������{��u�[���̂悤�ł���B�X���̖{���̓X���Ɋe��̓��{��W�̐V�������R�ς݂ɂȂ��Ă���̂͊F������悭�����m���낤�B�������A���̉����ƂȂ����̂́A�ē��F���́u���ɏo���ēǂ݂������{��v�Ƃ����{�ł���B���̖{����]���ƂȂ������߂ɁA���̉��̓D�Ӂi�ǂ��傤�j��_���Ă��A�u���{�l�Ȃ�m���Ă����������{��v���́u�펯�Ƃ��Ēm���Ă����������{��v���̂Ƃ������A�u�Ȃ�Ƃ�����Ƃ����������{��v�Ȃ�ޏ������X�ƓX���ɕ��т͂��߂��B�������ł͂Ȃ��A�u�Ȃ�Ƃ�����Ƃ����������v�A�u�Ȃ�Ƃ�����Ƃ������������v�Ƃ������悤�Ȗ{�܂ł��������ŏo�ł����悤�ɂȂ��Ă��Ă���B�@�@
�@ �����Ȃ��Ă���Ƃ����A�d�����P���F�Ƃ�ǂ�̃l�I���̂�������ʂŎ��X�ɂ��q��U�����ލ����e�n�̃��u�z�e���Q�̂���悤�Ƃ��������Ⴂ���Ȃ��Ȃ��Ă���B�悭���܂������܂ł���Ȃ��A�Ƃ��������������邢���ۂ��ŁA���悢�悻���܂ł������Ƃ����뜜�����������Ȃ����Ȃ��B�u���{��A���{��v�̑升���́A�u�j�b�|���A�j�b�|���v�̃T�b�J�[�̑吺���ɒʂ��A�₪�āu���̊ۖ��I�A���{�������I�A�V�c�É����I�v�̈�句�a�ւƌ������ĔM���̓x�𑝂��Ă������˂Ȃ���������������������B
�@ �ނ��A���̎�̖{�̕M�҂�ɂ��̂悤�ȈӐ}��_��������Ƃ����̂ł͂Ȃ��̂�����ǂ��A���̍��ɂ́A����ȏ��a�̐������܈�x�����ɍ��炩�ɋ����킽�邱�Ƃ���i�����˂��j���l�������Ȃ��Ȃ��͎̂����ł���B���S�ł́u���ɏo���ēǂ݂������{��v�̂Ȃ��ɋ��璺����w�P�����^���Ăق����Ƃ������Ă���l�����Ă��邾�낤�B
�@ ���������A�u���ɏo���ēǂ݂����Ȃ����{��v���������Ȃ����̂悤�ȖA�����C�^�[���A�u���ɏo���ēǂ݂������{��v�ɂ��Ă��ꂱ��Əq�ׂ�̂͂ǂ����Ƃ��������B�������Ȃ���A���̎�̖{�������l�X�̓��{�ꕶ���̂��̂��u���ɏo���ēǂ݂������{��v�ł���̂��ǂ����͂܂����̂�����ʖ��ł��낤����A�����Ă��̂悤�ȑʕ���Ԃ邱�Ƃ����ɂ������Ă��炤���Ƃɂ������B
�@ �������낢���ƂɁA�u���ɏo���ēǂ݂������{��v�ɂ͌����Ƃ̕��͈͂�т����^����Ă��Ȃ��B�����̒��Ɏ��^����Ă���̂́A�O���R�I�v���[�N���ȑO�̕��͂���Ȃ̂ł���B������Ȃ�ł������Ƃ̕��͂����ׂĂ��u���ɏo���ēǂ݂����Ȃ����{��v�ł���킯�ł��Ȃ����낤����i�������������Ƃ�����A���ꂱ������ł���j�A�����Ȃ��Ă��܂������Ƃ̗��ɂ͂���Ȃ�̂�ނ����ʎ���������ɈႢ�Ȃ��B
�@ �����Ƃ̕��͂̏ꍇ�ɂ͒��쌠���łȂǂ̊W�ň��p����̂�����Ƃ��������悤�Ȏ�����������̂��낤�B�܂��A���Ƃ����͂̎��^���\�ł���ꍇ�ł��A���̕��͂�I���������R�₻�̑I��@�A���f��Ȃǂ̐�����邱�ƂɂȂ肩�˂Ȃ��Ƃ������悤�Ȗ����������ɈႢ�Ȃ��B�ނ���Ƃ����y�ڂ����ڊԐڂ̉e���Ȃǂɂ��Ă̔z�����Ȃ��ꂽ���Ƃ��낤�B��������ł��Ȃ��A�����Ƃ̕��͂��܂��������^����Ă��Ȃ��Ƃ����̂͂Ȃ�ƂȂ��S�ɂЂ�������B���Ȃ�u���ɏo���ēǂ݂����Ȃ����{��v�Ɗ�����悤�Ȃ��̂Ȃǂ��ꕔ�Ɏ��^����Ă���̂��C�ɂ͂Ȃ�B
�@ �����ۂ��u���ɏo���ēǂ݂������{��v�̒��ɂ́A���N����N���ɈÏ����������������▼���A���́A����Ȃǂ����������^����Ă���A�����̖����▼�����̗̂ނ��玄���g�������ɉe���������Ƃ��m���ł���B����ȒZ�̂��r�肷�邱�Ƃ������āA���t�̂��C����Y���ɂ͏�X���Ȃ肱�����ق��ł���B���͂������Ƃ��ɂ��A���ۂɐ��ɂ����o���Ȃ����A���ɏo���ēǂƂ��Ă��Ȃ�ׂ����R�ȋ����Ɨ���ɂȂ��ĕ�����悤�ɂƁA�S���Ő����o�����Y�����`�F�b�N���Ȃ���M��i�߂�悤�ɐS�����Ă���B����ȏꍇ�ɋ��菊�ƂȂ��Ă���̂͐��N���ɐe�������▼�����̂̃��Y���⋿���Ȃ̂�����A�ē��F���̎咣�ɂ͋������o����Ƃ���������Ȃ��Ȃ��B
�@ �����A�����Ȃ��Ƃ��������̐���̏ꍇ�ɂ́A�厩�R�₻�̒��ł̎�������ʂ��ē����鏔�X�̐[���������сA�߂��݁A�ꂵ�݂Ƃ������悤�Ȃ��̂���ɂ���A������\������ɂ͂��܂�ɖ��n�Ȍ��t���������Ȃ��������ȏ��N�N�Ƃ��Ă̂��̂ꂪ��ɑ��݂��Ă����B����ȏ̒��Ő�l�̖����▼�����̂ɂ߂��肠�����Ƃɂ���āA���t�̗͂ɐS���犴�����A�l�X�ȐS�ۂ�I�m�ɕ\������Z�p�ɂ������ÂJ�Ⴕ�Ă��������̂ł���B��Ղ̖��ɏ��閞���̔�������m���Ă͂��������̔�������\�����邷�ׂ������Ȃ������c�Ɉ炿�̏��N���A�y��Ӑ��́u�r��̌��v�̉̎��ɏ��߂ďo�����A���t�̗͂Ɉ��|����A����J���ꂽ���i��z�����Ă��炦�悢�ł��낤�B
�@ �������Ȃ���A���܂⎞��͂�������ς���Ă��܂����悤�ł���B���R�̒��ł̑̌����Ȃ��A�̂̂悤�Ȑ������o�����Ȃ��Ă��Ȃ��q�ǂ������̐S�̒��ɁA���Ȃ莞��I�ɂ͂���̂��閼���▼�����̂̈�[��N�ǂ����Ï������Ă܂����荞�ނ��Ƃ����コ���B����Ɏ��M�����������t�����̂���҂́A����K���Ƃ���ɐ�������Ă��̎�̖{���w�����A���ᔻ�Ȃ܂܂ɂ��̎�@�P�A����̌���ő������H���悤�Ƃ���B�������Ȃ����͂܂��ł��邱�Ƃ͊m�������A����Ȗ����▼�����̂�̓��[���ɍ��荞�܂ꂽ�q�ǂ������͐�X�ǂ�Ȏ��R�ς���ς��`�����Ă����̂ł��낤�B�܂��ނ�͏����ǂ̂悤�Ȕ��������{����g�����Ȃ��A�ǂ̂悤�Ȗ����������Ԃ�悤�ɂȂ�̂��낤�B���̎q�ǂ��������A�����A�_��ǂ݂̘_��m�炸�ɂȂ�Ȃ���悢���Ƃ������̂͂��̎������Ȃ̂��낤���B
�@�u�Ǐ��̓X�|�[�c���v�Ǝ咣����ē��F���́A���������{��Ȃ���̂��J��Ԃ����ɏo���ēǂ݁A���̋�����S�g�ɒ@�����ނ��Ƃɂ���āA���S�����N�Ȑ��_�̎�������琬���邱�Ƃ��ł���Ƃ��l���Ă���悤���B����̏��ł��邱�Ƃ������āA���̎咣�ɂ͂���Ȃ�̐����͂��������Ȃ����Ƃ��Ȃ��B�����Ȃ��Ƃ�����i�Ƃ��āA���邢�͎��s�I�ȃv���W�F�N�g�Ƃ��Ĉꕔ�ɂ��̂悤�Ȍ��ꋳ��@�����݂��Ă��悢�̂�������Ȃ��Ƃ͂������B
�@ �������Ȃ���A���w�̐��E�Ȃǂ����Ė����▼�����̂Ƃ�������̂̂قƂ�ǂ́A�Љ���ɓK���ł����[�����������_��A�ő��A�s���A���|�A��Y�A������A�a��A�����A���i�A�s�k�A���]�A���O�Ƃ������悤�ȁA���Ȃ��}�����ꂽ�l�ԐS���̂��Ƃɂ����Đ��ݏo����Ă����ƌ����Ă悢�B�����̖����▼�����̂̑n��҂����̑唼�́A�������Č��S�ł����N�ł��Ȃ��������낤�ƍl������̂��B�����Ȃ��Ƃ����̂��Ƃ����͖Y��Ȃ��悤�ɂ��Ă������Ƃ��K�v���낤�B
�@�u���ɏo���ēǂ݂����Ȃ����{��v���������Ȃ����́A�������ł����Ȍ[�������悤���Ƃ������ď��X�ɏo�����A�u���{�l�Ȃ�m���Ă����������{��v��A�u�펯�Ƃ��Ēm���Ă����������{��v�A�u���m�ɒm���Ă����������{��v�A�u���܂ł��Y�ꂽ���Ȃ����{��v�ȂǂƂ������{�����X�Ɏ�Ɏ�藧���ǂ݂��Ă݂��B���̌��ʁA���͎������A���{�l�ł��Ȃ��A�펯�l�ł��Ȃ��A����ɂ͔��������{������m�ȓ��{����m��Ȃ��l�Ԃł��邱�Ƃ���炳�ꂽ�B���炩�Ƀ��C�^�[�Ƃ��Ă͎��i���ƌ����ق��Ȃ��B
�@ �ǂ����A�����C�^�[�Ƃ��Ă̎��Ɏc���ꂽ���́A�u�w�Ȃ�Ƃ�����Ƃ����������{��x�̖{���������l�����̓��{��v�Ƃ����{�����s�����̂�҂��Ă�����n�ǂ��A���̂�̋��{�Ɠ��{��̕\���͂����߂�ׂ��A�ēx���͏C�s�ɋ��ނ��Ƃł���炵���B����ɂ��Ă��A�u���ɏo���ēǂ݂������{��v�͔���ɔ���Ă��邻�������A�u�ǎ҂̂����Ŏ��ۂɐ��ɏo���ēǂl�͂��������ǂ̂��炢����̂ł��낤���c�c�B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2002�N9��11��
���̎n�܂�͍u����
�@ �������{�̂�����̌ߌ�A��錧�F�����ɂ��铯���̋��猤�C�Z���^�[�ւƏo�������B���̐��̒��Ƃ������̂͂Ȃ�Ƃ��C�܂���ɂł��Ă��āA�܁X�A���̂悤�Ȃ킯�̂킩��ʕY���l�Ԃ̘b�����Œ����Ă������낤�Ƃ�������W�҂��������������B�����˗������͈̂�錧�����w�Z�����C��ł̍u���ŁA�������̌��������w�Z�̍Z���搶����O�ɂ��āA�u���̕����Ă������v�Ƃ�������̂��Ƃɂ��ꂱ��Ƙb����������n���ɂȂ����B�����Ƌ����ԍ����w�Z����ɂ���ȉ���Ŗ��ӔC�Șb������ق�������ق��ł��邪�A���݂����Ȃ��������Ȑl�Ԃ��Z�����C��ɌĂ�ŁA����Șb�����Ăق����ƈ˗�����ق����˗�����ق��ł���Ƃ�����ꂽ�B
�@ ���������̂ŁA�����Ȃ����T�V���c�ɃW�[���Y�Ƃ����o�ŗ����ʼn��d�ɗ��̂��ǂ����Ƃ������A���Ȃ�ɋC�������ď㉺�̃X�[�c�Ƀl�N�^�C�Ƃ����i�D�ň�錧���猤�C�Z���^�[�ւƌ��������B�t���[�����X�ɓ]���Ă���́A�X�[�c�𒅗p���l�N�^�C����߂�Ƃ������ƂȂǖő��ɂȂ�����A�S�g���d�����������ɂȂ�A���̂ԂƎ����̓f�����t�̈����܂ł��K�`�K�`�Ɍł܂��Ă��܂��̂ł͂Ȃ����Ƃ����뜜�������������B�����A�R���Z���^�[�����A���уZ���^�[�����A�u�����S���̉i�ˋ���w���厖�A����ɂ͂���AIC�̔M�S�ȓǎ҂ł�����Ƃ�����������w���厖�Ȃǂ̉������Ή��������āA����ȐS�z�͂����܂��������ł��܂����̂������B
�@ �u���̈˗����������Ƃ��A�v���t�B�[���͂ǂ����܂����Ɖi�ˎw���厖�ɐq�˂��A�u�߂�ǂ��ł�����A�����炢�̗��l���C�^�[�Ƃ������Ƃɂł����Ă����Ă��������v�Ɣ��Ώ�k�ɓ����Ă������Ƃ���A���C��Q���̍Z���搶���ɂ��炩���ߔz��ꂽ�������ɂ����Ă��A���ɂ��Ă͎��ۂɂ��������������̒Z���Љ�����Ȃ���Ă����悤�ł���B�Ȃ�ׂ��A�b�g�E�z�[���ȕ��͋C�̂Ȃ��ŁA���R�̂̂܂܂ɍu�����ł���悤�ɂƂ̌��C�Z���^�[�T�C�h�̔z���������Ă̂��Ƃ������̂��낤���A�����ł�������A����Ȃ��ƂȂ�X�[�c�p�łȂ����Ȃ������Ƃ������قǂɋC���y�ɂȂ�A�����Ԃ�ƊJ�������������œ����̘b��i�߂邱�Ƃ��ł����B
�@ ���̓������܂��ܐl���̋��ڂƂ�������a�����̗��X�����������Ƃ������āA���̍ێ����̐����p����炢�����Ă݂�̂������̂ł͂Ȃ����Ǝv�������A����Ȃ�Ɋo������߂ĉ��d�ɏ�����悤�Ȃ킯�������B�����āA���N�̊ԋ��̉��ɕ��Ă����䂪�g�ɂ܂��ߊ삱�������ȉߋ��̏o�����Ȃǂ��������Љ���Ȃǂɖʔ������������߂Ȃ���A���Ȃ�̎v���点�Ă��炤���ƂɂȂ����B�����Ȃ�̂ŋ�̓I�Șb�̓��e�͊������邪�A��������������蕠��������A�ƂĂ�����I�Ƃ͌����Ȃ��̌��k�Ȃǂ������ꂱ��ƌ����Ȃ���̍u���ƂȂ����悤�Ȏ��悾�����B
�@ �����A���̂��Ƃ��t�ɍK�������Ƃ݂��A���̍Z���搶�����F����݂��J���A�܁X�����������Ȃ��玄�̐ق��b�ɕ��������Ă����������B���k�ɂ����k�����Œʂ��̂��ǂ����Ƃ͂��������̂ŁA�����̌���`����v�l�`���A����ɂ͎v�z�`���̃v���Z�X�ȂǑ����͋���ɗ��ނ��ƂȂǂɂ��Ă��b���L�����̂����A���ʂ����ċX��������Ȗ�肾�������グ��̂ł͂Ȃ��A���R�ȗ���������Ă��肰�Ȃ��b���[�߂�悤�ɐS���������Ƃ��A�����Ȃ�Ƃ�����t���錋�ʂɂ͂Ȃ����̂�������Ȃ��B
�@ ���̋�C���Ȃ��܂����߂ɍu���̖`���Ȃǂōu���҂�����W���[�N�̂��Ƃ��p���icebreaker�ȂǂƂ������A�u���҂ƒ��O�̑o�����ٗl�ɋْ����₽����C�̕Y���u�����Ȃǂɂ����ẮA����icebreaker�̂͂��炫�͂Ƃ��ɏd�v���Ƃ����Ă悢�B���܂�������g�����Ȃ��邩�ǂ����ɂ���Ă��̌�̃X�s�[�`�̐����x�����E����邱�Ƃ����Ă��邾�낤�B�܂��܂�icebreaker�̊��p�ɖ��n�Ȏ��Ȃǂ́A����ȃX�s�[�`�𑱂��Ȃ���A�����Ƃ��̎g�������ɏK�n����K�v������Ɠ��S�Ŕ��Ȃ�����L�l�������B
�@ ���̋��̂ق��ɂ���Ȃ�����A�M�S�Ɏ��̘b�Ɏ����X���Ă��������Ă��鏗���̍Z���搶���̎p�������ւ�Ɉ�ۓI�ł������B�������Z���̍��܂ł́A�������Z�̍Z���������̐搶�����߂�ȂǂƂ������Ƃ͂قƂ�Ǎl�����Ȃ����Ƃł��������A�����̎Љ�i�o���ڊo���������A�䂪���̋���E�̏͊m���ɕω����Ă��Ă���悤�ł���B�Ƃ�����Ƌ����I�Ȕ��z�ɔ����d�����Ă��܂������ȋ���E�ɁA�j���Љ�̗���C����|����V�����������ނ̂͂������Ɋ��}���ׂ����Ƃ��ƁA����珗���̍Z���搶���̑傢�Ȃ銈���S�̒ꂩ��F�炸�ɂ͂����Ȃ��C�����ł������B
�\�\���̍u�����I�����炷���Ɏ��͒��ԏ�̎Ԃɖ߂�A�l�N�^�C���͂����X�[�c��E����T�V���c�ƃW�[���Y�ɒ��ւ��܂��B�����Ă��ꂩ��A�����A�{��A�R�`���ʂ�ڎw���Ėk�シ�����ł��B�ɗ͌o���ߖ��ԂŐQ����̗��ł�����C�܂܂Ȃ��̂Ȃ̂ł����A���̂Ԃ�s���܂����ɂ��Ȃ�܂�����A���ۂɂ��̂��Ɖ������ǂ������邱�ƂɂȂ�̂��͂킩��܂���B�ߔN�͗��Ƃ����ƊC�O���s�Ƒ��ꂪ���܂��Ă���悤�ł����A�I�s���Ȃǂ��C�O���̂��قƂ�ǂ̂悤�Ȃ̂ł����A�Ȃ������͓��{�̗��ɂ�������Ă��܂��B�ЂƂɂ́A���{��ɂ��\���̑ΏۂƂ��Ă͂�͂���{�̕��y�������Ƃ����������ƁA���˂��ˍl���Ă��Ă��邩��Ȃ̂�������܂���B�܂��A�ǂ�ȏ����ȓ��{�̕��i�ɂ����E�̂����镗�i�ɋ��ʂ�����́A��������A���E���̕��i�̏k�}�Ƃł������ׂ�������߂��Ă���Ƃ������̂ł��B����ȕ��i�̏k�}�������o���A���̖{����I�m�ɕ`�ʂ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ���A���ǁA���ɂ͋I�s���ȂǏ������������i���Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��ł��傤�\�\�Ō�ɂ��̂悤�ȈӖ��̂��Ƃ��q�ׂāA���͂��̓��̍u�����Ȃ�Ƃ�����ɒ��ߊ������B
�@ �u�����I���Ƃ����ɁA�R���m�s���C�Z���^�[�����Ə����a�T����w���厖�̂���l�̐擱�ōu����ꂩ��Ԃňꑖ�肵���Ƃ���ɂ���}�ԓ������p�قɌ��������ƂɂȂ����B�u�t�T�����ɖ߂邢�Ƃ܂��Ȃ��܂܂̈ړ��ōQ����������ł͂��������A��A�O�l�̏����Z�����܂ސ��l�̕��X�̓A�d�Ȃ�������������Ȃ���A���͈�錧���C�Z���^�[�̌��ւ����Ƃɂ����B
�@ �F�����Ɨׂ荇���}�Ԏs�̈���Ɉʒu����}�ԓ������p�قł́A���܂��ܕx�m�R���e�[�}�ɂ����ʐ^�W���Â���Ă����B�W������Ă��鎵�\�]�_�̍�i�͊F�A�}�`���A�ʐ^�Ƃɂ��ʐ^����Ȃ̂��������������A�ǂ�������R�ƍK�^�̓����Ƃ��������悤�̂Ȃ���u�̃V���b�^�[�`�����X�Ɍb�܂�Ȃ���Γ���B�e�s�\�ȁA��Ղɂ��߂��f���炵����i����ł������B�ē��ɗ����Ă��������������p�َ����ǒ��̒���������̘b�ɂ��ƁA�����͂����ƓW���_�����i�荞�����Ƃ����������A�c�������̂͂�������b������������I�Ȏʐ^����Ȃ̂ŁA���ǂ����̍�i���ׂĂ�W�����邱�Ƃɂ����̂��Ƃ����B
�@ ���Ƃ��_���Ă����Ƃ��Ă���������\���͋ɂ߂ĒႢ�ɈႢ�Ȃ����̎�̕��i�ʐ^�̎B�e�́A�v���̎ʐ^�ƂɂƂ��Ă����A�ނ���A���U�Ɉ�x���邩�Ȃ����̃`�����X�ɓq����A�}�`���A�ʐ^�ƂɌ������d���ł͂���̂�������Ȃ��B����ɂ��Ă��A���Ȃ��x�m�R���G�߂�C�ۏ�������ɂ͎����̕ω��Ȃǂɉ����Ă���قǂɑ��l�Ȋ��p��������Ƃ́A���˂��˗l�X�Ȋp�x����x�m�R�̒��]��ڂɂ��Ă��Ă��鎄�ɂƂ��Ă��傫�ȋ����ł������B
�@ �����̎ʐ^���ꖇ�����܂����߂Ȃ���ٓ����߂��邤���ɁA����͗���x�m�̉B�������Ȃ鐢�E�̉ʂĂ��Ȃ����H���̂��̂ɂق��Ȃ�Ȃ��Ƃ����z�����N���Ă����B�u���̌��тɂ����āA�u�ǂ�Ȃɏ����ȓ��{�̕��i�ɂ������鐢�E�̕��i�ɋ��ʂ�����́A��������A���E���̕��i�̏k�}�Ƃł������ׂ����̂���߂��Ă���v�Əq�ׂĂ������肾�������A�܂��ɂ��̂��Ƃ��ے�����悤�ȕx�m�R�̕��i�ʐ^�W�ł͂������B�ꑫ��ɂ��̎ʐ^�W���ɑ����^�ѓ��l�̊��S�������Ă���ꂽ�R���Z���^�[�����́A���̊����������������Ƃ����킯�ŁA���Z�Ȏ��Ԃ������Ă킴�킴�����}�ԓ������p�قւƈē����Ă����������悤�Ȃ킯�������B
�@ ���̊}�ԓ������p�ق̈�K�W�����̒������ɂ͊O���Ɍ������ĎO�p�`��ɓ˂��o����Ԃ������āA�ǖʂ��S�ʃK���X����ɂȂ��Ă���A���̃K���X�̕ǖʂ̌������ɐ^�|���Џ@�|�Ƃ�������|�т�]�ނ��Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă����B�܂��A���̎O�p�`�̋�Ԃ̒����ɂ̓W���R���b�e�B��̍ג����u�����Y������̂����z�u����Ă����B���̟�������Ԃ̍\���Ɖ��o�Ɋ��Q���Ȃ���K���X�z���ɊO�̒|�т߂邤���ɁA���͂��Ă悭�K�˂���B��H���ɂ̎Ԉ֎q����̂��Ƃ����������z���o�����B�Ԉ֎q����̕��䉜�͑S�ʑ��K���X����ɂȂ��Ă��āA���̃K���X�̕ǖʂ�ʂ��Č��ꗠ��̒�̒|�т�]�ނ��Ƃ��ł������̂������B���҂̓��قȋ�ԍ\���Ɍ����邱�̗ގ����͂܂������̋��R�Ȃ̂��ǂ낤���Ƃ������������A��u���̔]���ɕ����яオ������������B
�@ �x�m�R�ʐ^�W�̌��w���I�����p�٘e�̒��ԏ�ɖ߂����������O�l�́A�߂��̎����̔��@�ł��ꂼ��Ɋʓ���̈��ݕ����ăx���`�ɍ���A���������ʂ�̂�������ɂ��Ă����̂������b�����B�����Ƃ������ڎ���i�����Ȃǂł͂Ȃ��A���݂��E�[��������W���[�X�̊ʂ���ɂ����܂܉��̕ϓN���Ȃ��V��̃x���`�ɍ����Ă̂��ʂ�̂����Ƃ����̂́A�����ɂ���Ă͐��Ȃ��Ƃ��̂����Ȃ��v�炢�ł��������B�����āA���̏_�����錧����E�̎w�����ɂ��邩����́A���̌��̋���ɂ����鏫���̓W�]�͖��邢�̂ł͂Ȃ��낤���Ƃ�����ꂽ�B
�@ ���ꂩ��قǂȂ����ăx���`�𗧂����������͂��̏�ŕʂ�̈��A�����������A��Ɍ��C�Z���^�[�ւƈ����Ԃ��Ă����R�������Ə�������w���厖�̏��Ԃ����͒��ԏ�Ō��������B���ꂩ��Ԓ��ɖ߂�A�l�N�^�C���͂����X�[�c��E���Ƃ����ɂs�V���c�ƃW�[���Y�ɒ��ւ��A���X�ɗ[���̔���͂��߂���ʍ����𐅌˕��ʂɌ������đ��肾�����B�����Đ��ˎs���Ŗk�ɐi�H��ς��A�C�ݐ��߂������ʂւƂ̂т鍑���U���`���ɁA���ƕ��������̖ܗ��A����ɂ͂��̐�̏����l���ʂ�ڎw���Ĉ��Ԃ̃A�N�Z���ݑ������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2002�N9��18��
�錴����V���q�l��
�@ �����s�ɍ��������邱��ɂ͂�������������A���̋�u�~�̂悤�ɂ܂邢�v�Ƃ������t���̂܂܂̑傫�Ȍ��������Ă����B�^�̂悢���ƂɁA���܂��ܖ����̖�ɂ������Ă����Ƃ����킯�������B���̖]�O�̃`�����X����͂Ȃ��ƍl�������́A�ǂ����C�̌�����Ƃ���ɏo�āA���邢�����Ɩ�̒��̂���߂�����Ȃ����f�I�ȏ�i���y�������ƍl�����B
�@ ���炭����ƁA�C�����Ɉꌬ��������h�̂���k��ؒ��̈錴�Ƃ����Ƃ���ɏo���B���̒n���̒ʂ�ɂ��������C�������̂ŁA�����ŎԂ𒓂߁A�����ނ�ɕl�ӂɍ~�藧�����B�����m��͂邩�ȂƂ���ɂ���䕗�̉e���Ȃ̂��낤�A�C�͂��Ȃ�r��Ă��āA��ԂȂ���g���ݕӂɌ������đł��Ă��Ă����B�l�ӂ̂����߂��ɂ��鏬���̈�̂ق�����͂Ƃ�킯�������ӂ��U��r�g�̉��������Ă����B���̍��X�Ƃ���������Ă��邤���ɁA�C�ɂ܂�鉓�����̋L���̒f�Ђ��ˑR���S���Ă��͂��߂��B��z�̒��Œ��߂�镗�i�Ƃ������̂́A�����ɂ���߂������̔����ɂ��ǂ��������u���Ԃ̍��v�ɏ���A�悯���Ȃ��̂��킬���Ƃ���Ă��܂��Ă��邩��A�s�v�c�Ȃقǂɔ����������I�ɂ݂����肷��B
�@ ���炭���̕l�ӂɘȂ�ł��邤���ɁA�����̌��̂��Ƃő傫�����˂�P����O�̊C�ʂ̌��i�ƁA���̔�������ȂǂɘE�𑆂��œn������̓��̊C�̉��������L���Ƃ���Ȃ܂łɌ����������A���̌��ʁA�����Ƃ����Ƃ����ʂ��܂ЂƂ̐V���ȐS�ە��i�����̋����Ɍ`�����ꂽ�B
�@ �r����N�����Đ���]���̌������~��錴�̊C
�@ ���ԁA���邢���z�̂��ƂŒ��߂���A���Ԃ�A���̈錴�̕l�ӂ₻�̌������ɍL����C�̕��i�͂�������ӂꂽ���̂ɂ����Ȃ����Ƃ��낤�B�������A���镗�i��ڂɂ��A���������X���S�Ŋ������S�ە��i�Ƃ������̂́A�����̕��i�Ƃ͈قȂ��Ă��邱�Ƃ������Ȃ��Ȃ��B�ꌩ�����Ƃ���Ȃ�ł��Ȃ��悤�ȕ��i�����ƂɈ̑�ȊG���i�ݏo�����Ƃ��Ȃǂ������肷���Ƃ����̂��Ƃ��������A�ׂ���s�v�c�Ȃ��Ƃł��Ȃ��B���Ƃ��ƕ��i�Ƃ͌X�̐l�Ԃ�����������̂ł���̂�������Ȃ��B
�@ �̂̐l�X���A�����̎p�̔�������������u��ځA���ځA�P�̓��v�Ȃǂƌ����\�킵���̂��A������j������̏���炤�S�����u�A�o�^���G�N�{�v�ƌ������肷��̂��A�{���I�ɂ͂���Ƃ��Ȃ����ƂȂ̂��낤�B
�@ �悭�悭�l���Ă݂�ƁA���������u�����̕��i�v�Ȃ���̂����݂���̂��ǂ������������������̂ł���B�������Œ��߂�̂��^�̌��i�ł����āA������[�z�̒W�����̂��ƂŁA����ɂ͌����������̂��ƂŖڂɂ��邻��͐^�̌��i�ł͂Ȃ��Ȃǂƌ������Ƃ��ł��邾�낤���B�����̂�������������ȕ��i�ł���A����̏������Ō��镗�i�������ق�Ƃ��̕��i���ȂǂƂ������Ƃ͂��肦�Ȃ��B�S�l�̐l������Ƃ��A�����̒��̓���̐l���������w���āu���ꂪ�^�̐l�Ԃł���v�ƒf�肷�邱�ƂȂǒN�ɂ��ł��Ȃ��̂Ƃ��Ȃ��悤�Ɂc�c�B
�@ �錴�����Ƃɂ���ƁA�����Z�����炷�����͂��ꂽ�Ƃ���ɂ���܉Y�̂�������߂�������������B���ꂩ��Ăэ����ɖ߂�ƁA�u��������ܗ��̊ւƂ����ւǂ��݂������ɎU��R���ԁv�Ƃ����������Y�`�Ƃ̉̂Ŗ������ܗ���ʉ߂��ĕ������ɓ������B��ӏ����|���̂���Z�I�I�łǂ����v�킹�Ԃ�Ȃ��̉̂́A�͂��炸���̂��̌������A�`�o��ꑰ�̎q���̉^�����Î����Ă���悤�ł�����B
�@ ����܂������Ă��Ă����Ȃ�A���̉Ԃ��܂����ꂩ��Ƃ������̖ܗ��̊ւɐ����Ă���悤�Ȃ炱�̊ւ̐�ɂ͒ʂ��Ă͂��܂����\�\�����������Ă݂͂������́A����ȉ䂪�肢�����A�ܗ��̊ւ𐁂�������t�̗��̂��߂ɁA���J�̓����ނ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��܂܂ɍׂ������R�H��ʂɎR���̉Ԃ��U���Ă������Ƃ�
�@ �䗬�̉���ȉ��߂�����A�ǂ���炻�̂悤�Ȃ��Ƃ������Ƃ��Ă���炵�����̉̂��r���`�Ƃ́A�ܗ��̊ւ�n�ɏ���ĉz���A�����ڈΒn�ƌĂꂽ���k�n����т̎x�z�ҁA�����ꑰ�ɐ킢�̂������B
�@ �����ۂ��A��������ߑ㕶���ɓł��ꂽ����l�̎��̂ق��́A���Ȃ��l���ł��n�Ȃ�ʎԂɏ���āA�Ă̖�̖ܗ����ЂƂ����ɑ��蔲�����B�����āA�����l��ʉ߂��A�֏�i���킫�j�s�̓����Ɉʒu����V���q�l�ւƏo���B�������ɂ�����Ɩ��C���Â������Ă������̂ŁA�l�����̋n�̈�p�ɎԂ𒓂߂�ƁA�C���]�������˂čL��Ȗ��l�̍��l�ւƑ��ݓ���Ă݂邱�Ƃɂ����B
�@ ��V�����ɏ���߂������̌��͂�������ƍႦ�n��A��k�ɉ����̂т鍻�l�𖾂邭�Ƃ炵�o���Ă����B���₩�ɗ�����̑�C�͑u�₩���̂��̂ŁA���������Ɛ[�������ɑ��Ղ����ݍ��݂Ȃ���A�����̕l�ӂ�Ƃ��߂ɂ��ĕ����܂��͎̂��ɂ����C���������B�Ƃ��낪�A�g�ł�����ɋ߂Â��Ċ��������g�ƋY��邤���ɓ˔@�������ۂ��Â��͂��߂��B�߂��ɂ͂�������p�̎{�݂炵�����̂͌�������Ȃ������B
�@ ���̂ɂ͉䖝�̌��E�Ƃ������̂����邩��A�����ƂȂ�����Ƃ�ׂ���i�͂ЂƂ����Ȃ��B�R���łȂ璿�������Ȃ����Ƃ����A�L���l�ӂłƂ������ƂɂȂ�ƍŋ߂ł͂��܂肻�̎�̋L���͂Ȃ��B�����Ƃ��A���̍r���l�ӂ��삯�߂����Ă������N����̂��ƂƂ��Ȃ�Ƙb�ׂ͂ł���B���̏������ɕ`�ʂ���킯�ɂ������Ȃ����A�Ƃɂ����A�����̒��Ŏ��R�ɐg�ɂ�������Ȃ�̒m�b�ƍH�v�ɗ����Ă������̂������B
�@ �܂�����Ȃ킯�������āA�����͂ǂ����Ȃ�ƓV�^ࣖ����������N����̋C���ɖ߂��Ă������ɊJ�����邱�Ƃɂ����B���X�ƏƂ�f���閞�����̍L��Ȗ��l�̍��l�ŁA����߂��C�ʂ߁A����ɂ͍��炩�ɋ����g�����Ȃ�����C�x���g�����s���邱�ƂɂȂ����̂͌����܂ł��Ȃ��B�����l�̕��ꂽ�悤�șꂫ����̂ق�����R�ꕷ���Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ������������A���̍ۂ���Ȃ��ƂȂNjC�ɂȂ��Ă������Ȃ������B
�@ �l���悤�ɂ���ẮA�l�ԂɂƂ��Ă���قǂ��ґ�͂Ȃ��̂�������Ȃ��Ȃ��\�\�ӂ����Ă���ƌ����Ă��܂�����܂ł����A�C�x���g�̐i�s���ɂ���Ȃ���������u�]�����悬������������B����ɂ܂��A�J�^���V�X�Ƃ����L���Ȍ��t�����邪�A���̌��t�͂܂��ɂ��̂悤�ȐS���I����ɂ͐g�̓I�̂��Ƃ��Ӗ����Ă���̂�������Ȃ��Ƃ�����ȑz���ɂ���ꂽ��������B
�@ �[��̐V���q�l�����������Ɯp�j�����̕���ƌi�ς�S�䂭�܂Ŋy�����ƁA�Ԃɖ߂��ē�A�O�l�̒m�l���Ăɂd���[����ł����B�����̗���Ƃ������̂͂��������ꍇ�ɂ͂����ւ�ɗL���B�؎��t�������߂���|�X�g��T�����肷�邱�ƂȂǂȂ��A��������芪�����݂̏����A���^�C���Œ��ڑ���ɓ`���邱�Ƃ��ł��邩��A���܂��g���Ȃ�Ƃ��Տꊴ������̂��Ƃ肪�\�ɂȂ�B�����A������ƌ����āA���̎��̂d���[���Œm�l�����Ɍ����̐V���q�l�ł̓��ʃC�x���g�̗L�l���Ԃ��Ƀ��|�[�g�����Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B�J�^���V�X�]�X�͂����܂ł����̌l�I�ȑ̌��ɂƂ��Ȃ���ۂȂ̂ł����āA���l�̒m��Ƃ���ł͂Ȃ����炾�B
�@ ���[���𑗐M���I�����Ƃ��A���j�͂��傤�njߑO���w�����Ƃ��Ă���Ƃ��낾�����B�������ɓ����{�[�b�Ƃ��Ă����̂ŁA����ȏ㖳�����Đ���}�����Ƃ��Ȃ��낤�ƍl���A���̂܂ܖ���ɂ����Ƃɂ����B��������N�O�̍��ɂ����āA�͂邩�ȓV��Ő��P�����e�������A��u����Ƃ��Ƃǂ܂邱�ƂȂ��Ǎ��̗��𑱂��Ă����B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2002�N9��25��
�����G����������ߓ�����
�@ �����͘Z�����ɋN�����A�������Ɉ����G�R�n�̂Ȃ��قǂɂ���ꍪ���ڎw���đ��肾�����B���ړ��Ă͓����ɂ��鈢���G���ł���B�H�F���◳���͂��߁A�����ɂ���߂ڂ����ߓ����ɂ͂قƂ�Ǎs�������Ƃ�����̂����A�����G�������͂܂���x���K�˂����Ƃ��Ȃ������B���܂��Ԓ����������V���q�l�̂����肩��͂��������Ȃ��Ƃ���̂悤�Ȃ̂ŁA���̋@��ɐ���K�˂Ă݂悤�Ǝv���������悤�Ȃ킯�������B�r���Œ��H���Ƃ����肵�Ȃ���Ĉ��k�J�`���ɂ��˂��˂ƎR�Ԃ�D�����H���̂�т�Ƒ��������A����ł��ߑO�㎞���ɂ͈����G���O�̒��ԏ�ɓ��������B�ꍪ���ɋ߂Â��ƁA��������ł��ΊD�������������Ղ����X���������傫�Ȋ�R��������̂����A�����G���̓����͂��̊�R�̒���������Ɉʒu���Ă���B
�@ �����G�����������ꂽ�͔̂�r�I�ŋ߂̂��Ƃ̂悤���B���Z��N�i���a�l�\�l�N�j�A�ΊD��̍̌@���ɂ��܂��ܔ������ꂽ���̂炵���B�����L���̋K�͂����ߓ����ŁA���J����Ă��镔���̓��̒������Z�S���[�g���A�����J�����̓��̉��s���͓��ܕS���[�g���ɂ��y��ł���Ƃ����B�����J�����̓����ɂ́A�V��̍�����\���[�g���ɂ��y�ԑ�z�[������{����ւ鍂���l�\�܃��[�g���̃t���[�X�g�[���Ȃǂ����݂��邱�Ƃ��m�F����Ă���B�ʏ�R�[�X���S�~�A�T���R�[�X���܂߂�Ɛ�l�S�~�Ƃ������w���͂�����ƍ����Ƃ����C�����Ȃ��ł͂Ȃ��������A���̗������K�Ȃ̂��ۂ��͎��ۂɓ������Ă݂Ă���łȂ��Ɣ���Ȃ��̂ŁA�܂��͑f���ɗ������x�����ē����ɓ������B
�@ �L���傫�ȓ����͂悭�������s���͂��Ă���A���ڊԐڂ̏Ɩ��ɂ������╶���ɂ�����ɂ����ꂱ��ƍH�v���Â炳��Ă��銴���������B�����Ђ����Ԃ�������ȗd����A�z������d���̓��A�ꍪ��a�Ɩ������ꂽ������\�チ�[�g���̑�z�[���₻�̂Ȃ��Ő����P�������̑����ȐΒ��Ɛ�⡌Q�A�j�̂悤�Ȍ`�̌������������Ăł����C�̎X�肻������̓����X��A����ɂ́A���A�ǖʂ𗬂ꗎ����n�����̐ΊD�����Č�������̂悤�Ȍ`�ɂȂ����t���[�X�g�[���ȂǁA�����Ɍ��鎩�R�̑��`�̖��͂Ȃ�Ƃ��f���炵�������肾�����B
�@ ���̈����G���̏ߓ��̑S�̓I�ȓ����͂��̐F��`�̑@�ׂ��ŁA�Ȃ��ł��㕔���琂�ꉺ����悤�ɐL�эL���郔�F�[�����J�[�e����̏ߓ��͑��̏ߓ����ł͂��܂茩�����邱�Ƃ̂Ȃ����������̂ł������B�N���X�^���J�[�e���ƌĂ�锖��̐��ꖋ��ߓ��Ȃǂ͂����̑�\�I�Ȃ��̂ŁA�\���Ɍ��Ă�Ƃ��̓����͗l�Ȃǂ����ώ@�ł���Ƃ������Ƃł������B
�@ �e��̃t���[�X�g�[���╡�G�Ȍ`��̐Β���⡌Q�̗������ԗ��{�a�����̖��ɒp���ʉؗ킳�𑑌������ւ��Ă����B�܂��A���ʂ�召�����̃c������ߓ��ΌQ�ŕ�������ꂽ�����⡂Ȃǂɂ̓N���X�}�X�c���[�Ƃ����X�Ƃ���������������Ă��āA�����������ۂނ���̔������ł������B
�@ �����ʘH�̕Ћ��ɐ݂���ꂽ�x���`�ɍ��|���A�������̓��A��a�̌����Ȑ̑������ɂ݂Ƃ�Ȃ���A���̑�ߓ������`�������܂ł̒����Ȃ������Ԃ̂��Ƃ�������������B�ߓ����⡂��킸����Z���`�L�т�̂ɂ������r���̂Ȃ����Ԃ�v����Ƃ����̂��ƂŁA���̊�̌�a�����݂̂悤�Ȍ`���Ƃ�悤�ɂȂ�܂łɂ��������C�̉����Ȃ�悤�Ȏ��Ԃ̗���ɂ���ׁA���̂�̖��̂Ȃ�ƒZ���R�����Ƃ��낤�B
�@ �������A�S���\���N�Ƃ����F���a���ȗ��̓V���w�I���ԂɊr�ׂ�����ƒZ���ɈႢ�Ȃ����A����ł����疜�N����ɂ͉����N�ɂ��̂ڂ�Ƃ����ߓ����`���܂ł̎��Ԃ̏W�ς������ɓr�����Ȃ����̂ł��邩�́A�ߓ��̐�[�ɕt���������H���Ԃ������ă|�g���|�g���Ɛ��ꗎ����l�q�����Ă���Ƃ��̂�����[���������B
�@ ������Ȃ����̓H�̐������邱�̊�a�ɖ��͂��Ȃ�
�@ ���哴�A�̒��ŐÂ��ɂ����������ɌJ�L�����Ă���s��Ȏ��Ԃ̃h���}�Ɉ��|����Ȃ���A��������͂���ȉ̂��r�肵�����̂́A�l�Ԃ̖��ȂǂƂ������̂͒�����悢�Ƃ������̂ł͂Ȃ��Ƃ��炽�߂Ďv���Ȃ����A���͂����ނ�ɗ����オ�����B���̐��E�̒��ɂ����ẮA��X�̒Z�����ɂ͒Z�����Ȃ�̖����ƈӋ`�Ƃ�����͂����B���̂ЂƂ́A���Ƃ��A���̏ߓ����̒��ɂ݂�悤�Ȏ��R�̈��y�C�W�F���g�̑��݂�F�����A�����ɔ�߂�ꂽ��F���̃��b�Z�[�W�ɐ[�������Ƌ����o���邱�Ƃ��낤�B���Ƃ��ƈÍ��ɕ�܂ꂽ�[�������ɑ��Â����Ԃ̌|�p�Ƃ������̂́A���Ƃ����ꂪ�ǂ�Ȃɑf���炵�����̂ł��낤�Ƃ��A���̑f���炵����m�o���������S��h���Ԃ��鐶���̂��Ȃ�������A���F���ɓ������ɈႢ�Ȃ��B���̈Ӗ��ł͑s��ȉF�����܂����Ȃ��ł���Ƃ����Ă��悢�B
�@ ���ɂ��Ȃ�����ȑ�Ȃ��ƂȂǂ��l���Ȃ���A�����T�K�R�[�X�̍Ō�ɂ��錎�̐��E�Ȃ�Ƃ���ւƏo���B�������s���̂���n���Ԃ������āA��⡁A�Β��A�����X�g�[���A�ߓ��ǁA�t���[�X�g�[���A���F�[����ߓ��ȂǑ��푽�l�ȏߓ��ΌQ���������сA�܂�Ō����E���Ȃɂ��ɂ��܂����s�v�c�ȕ��͋C�������������Ă���B������A�閾������[���ɂ�����܂ł̌��̉��������o�ł��镑��Ɩ��p�̒����V�X�e���Ń��C�g�A�b�v���Ă��邩��A�Ȃ��Ȃ��Ɍ����������������B
�@ �����G������ʂ�߂���I�������́A����Ȃ��l�S�~�̓��������܂��d�����Ȃ����Ƃ������Ȃ���O�֏o���B�����āA�Ƃ�����������Ŗ��K��̂܂c���Ă��������G���̒T�K���������邱�Ƃ��ł����Ƃ��������₩�ȒB�����ɂЂ���Ȃ���A�Ȃɂ��Ȃ����ӂ̊ό��ē����[�t���b�g�߂�����B����ƁA�u�����ߓ����v�Ƃ����ςȖ��O�̏ߓ����̏Љ�L�����ڂɔ�э���ł����̂ł���B
�@ �ȂɁ[���A���シ�����傤�ɂイ�ǂ������āH�A�܂�Ő̂̐l���g�����̏�ɂ��Ă����ߓ����݂��������I�\�\����Ȃ���������u�]�����悬������������B�����A���̏ߓ����̏Љ�ɂ悭�ڂ�ʂ��Ă��邤���ɁA�ǂ����u�ɂイ�������傤�ɂイ�ǂ��v�Ɠǂނ炵�����Ƃ����������B������Ƃ����P�[�r���O�C�������킦��ߓ������Ƃ̂��ƂŁA������N��������Ă���A�G��������܂ł𐅒��ɓ���Ȃ��瓴���T�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���Ȗ��������Ă���炵�������B
�@ �����͐^���Âŋ����Ƃ��낪�قƂ�ǂȂ̂ŁA�����Ń��C�g�����Q���邩�����ŘX�C����邩���A����ő������Ƃ炵�Ȃ��牜�ւƐi�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��炵���B�܂��V�䂪���ʒႭ�Ȃ��Ă���Ƃ���Ȃǂł́A�����g���܂邲�Ɨ₽�������ɂ��Ȃ���A����������l���ɂȂ����肵�Ȃ���ړ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��悤�ł��������B�g�x�x�Ɋւ��ẮA�����g�͔G��Ă��\��Ȃ��Z�p�����C�p���ɑ������T���_�������A�㔼�g�ɂ͖h���̌������A�m���b�N���J���H���͂��邩�A�����Ȃ���ΔG��Ă������V���c�ނ𒅂Ă����K�v������݂����������B
�@ ���[��A����͖ʔ��������Ȃ��A������Ƒ�ς�������Ȃ�����ǁA�܂��ƂȂ��`�����X������`�������W���Ă݂邱�Ƃɂ��邩�\�\�ނ�ނ�ƗN���オ�邢���Ȃ���̖쎟�n������}���ꂸ�A�����̍��l�����ɂ������f�����悤�Ȃ킯�������B�ߍ��́A���������[���o������ڑO�ɂ����悤�ȂƂ��A�u����͂܂����̋@��Ɂc�c�v�ȂǂƂ������ӂ��ɐ摗�肷�邱�Ƃ͂��Ȃ��悤�ɂȂ��Ă��Ă���B����Ƃ͋t�ɁA���Ԃꂪ�Ō�̋@��ŁA���̋@��������x�ƃ`�����X�Ɍb�܂�邱�Ƃ͂Ȃ����낤�ƍl���邱�Ƃ̂ق��������B
�@ �ǂ���玄���u������v�Ƃ������t�̂��d�݂�Ɋ�����N���ɓ��B�����Ƃ������ƂȂ̂��낤�B����Ȃ�A�����ɂ��g��T��ŕ��Q�Ȃǂ͂�߁A�c���ꂽ���Ԃ������ƈӖ����邱�ƂƂ̏o�����ɔ�₷�S���������邩�Ƃ����Ƃ����ł��Ȃ��B�g�̂̓��������ɍs����Ƃ���͍s���Ă������ƁA�܂��܂��e�H�ƎԒ����������ς�̌o��ߌ��̗��ɐg���ς˂邱�ƂɂȂ�̂�����n���������B
�@ �����G������Ԃœ�\���قǑ������Ƃ���ɂ�������ߓ����̒��ԏ�ɒ����ƁA�����ɔG��Ă������Z�p���ƃX�j�J�[�ɗ����ւ��A�s�V���c�̏�ɓo�R�p�̃t�[�h�t���A�m���b�N���͂���h�����C�g����ɂ��ē������ւƌ��������B�����ւƌ������������ɂ���H����y�Y���X�ł́A�������̂Ȃ�������]�҂ɁA�����⍇�H�A�Ɩ��p�X�C�Ȃǂ�݂��o���Ă���悤�ł��������B�܂��A�������e�̎�t�������ɗאڂ��Ēj���ʂ̍X�ߎ��Ȃǂ��݂����Ă������B
�@ �\�z�O�������̂́A�����̌��w�R�[�X��A�AB�AC�A�̎O�R�[�X�ɂ킯���Ă��āA����ɉ����ĎO�i�K�̗����ݒ肪�Ȃ���Ă��邱�Ƃ������B�����̂����Ƃ���O�̕������������w���Ė߂�A�R�[�X�͌ܕS�~�A����ɂ��̉��̃J�{�`����܂ł���������Г��Z�S���[�g����B�R�[�X�͎��S�~�̓������ɂȂ��Ă����B�Ƃ��낪B�R�[�X�̏I�_���炳��ɎO�S���[�g�����܂Ői�ޕГ���S���[�g����C�R�[�X�����͓��ʂŁA�댯�x�������Ƃ������R����ē��l�t���łȂ��ƒT�K��������Ȃ��悤�ɂȂ��Ă����B���������̗��������A�ꖼ�`�ܖ��܂ł��l��Z�S�~�ꗥ�ɂȂ��Ă����B�ܖ��̃O���[�v�Ȃ��l�������S��\�~�ƂȂ�AB�R�[�X����S��\�~���������Ȃ̂����A��l���Ǝl��Z�S�~���܂�܂鎩���Ŏx����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@ �N��C�R�[�X����]���闈�K�҂����ɂ���ΐ��������Ċ��芨�łƂ��������A���炭��t�������O�ŗl�q���M���Ă������AC�R�[�X�͌����ɋy���AB�R�[�X����]����҂����قƂ�nj���Ȃ��L�l�������B�E�C�[�N�f�C���������Ƃ������āA���K�҂����������͂Ȃ��������Ƃ����̌����������̂��낤�B�ǂ��������̂��Ƃ������Ȃ���ē��\���̉���Ȃǂ�ǂ�ł݂�ƁAB�R�[�X�̃J�{�`����܂łł������͂���Ȃ�ɑ�ςŁA�P�[�r���O�̕��͋C�����Ȃ炻��ł��\���ɖ��키���Ƃ��\�炵���Ƃ킩���Ă����B����Ȃ�Ƃ����킯�ŁA���̍�C�R�[�X�͒f�O��B�R�[�X�ʼn䖝���Ă������Ƃɂ����B
�@ ������̐��_�ɂ̂��Ƃ�A�����̍ʼn��܂ł���������`�����X�͂����Ȃ����������炱�̍ۖ��킸C�R�[�X���ƌ��f���ׂ��Ƃ��낾���A�������n�R�l�̏�Ȃ��Ƃ���ŁA�l��Z�S�~���ɂ����Ȃ��Ă��܂����Ƃ����̂������ȂƂ��낾�����B������̐��_��������ō��E���ꂽ�Ƃ����킯������Ȃ�Ƃ��i�D�̂��Ȃ��b�ł���B���Ƃ������H�ׂ���̂��Ȃ��Ȃ����Ƃ��Ă���������ׂ����̂͌��Ă����Ƃ��������S�����Ă��Ԃɂ܂œ��B���Ȃ�������A���̈�����̐��_�͏��F�䕨�ɉ߂��ʂ̂�������Ȃ��ƁA���ƂɂȂ��ď��X���Ȃ�������ł��������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2002�N10��2��
�����ߓ����T�K�L
�@ ��t�������œ��������ƁA�����Ă��ꂽ�Ⴂ�����W���͂����ɁA�Ɩ��������Q���Ă��邩�ǂ�����q�˂Ă����B���̃`�F�b�N���I���ƁA�Â��Ĕޏ��͑傫�ȓ����ē��}�����o���A������w�������Ȃ��炠�ꂱ��ƒ��ӂ��ׂ�������������Ă��ꂽ�B����ɂ��ƁA�����ɂ͐����\�x�̗␅������Ă���A��������ƍŏ��͗₽�������邪���炭����Ɗ���Ă���Ƃ������Ƃł������B����ɁA�␅�ɂ�鑫�̂��тꂪ�ǂ����Ă������܂�Ȃ��悤�ȏꍇ�ɂ́A�T���𒆎~�������Ԃ��Ăق����Ƃ����⑫�Ȃǂ��t��������ꂽ�B
�@ �܂��A�����͈Â������Ƃ��낪�قƂ�ǂȂ̂Ŋ�ɓ����Ԃ����葫�����芊�炵���肵�Ȃ��悤�ɂ��邱�ƁA�V�䂪�Ⴍ�������ߎl���ɂȂ邩�K�����ʂɂ��邩���Ȃ���Βʉ߂ł��Ȃ��Ƃ��낪����A�����ʼn����g�͊ԈႢ�Ȃ����ԔG��ɂȂ��Ă��܂����ƁA���̓����҂Ƃ���Ⴄ�Ƃ��ɂ݂͌��ɓ������荇�����菕���������肵�Ă��炢�������ƂȂǂ̒��ӂ��Ȃ��ꂽ�B
�@ ����ɁA�J�{�`����̂Ƃ��낪B�R�[�X�̈����Ԃ��n�_�Ȃ̂ŁA�ē��l�Ȃ��ɂ͂��������ɂ͐i��ł͂Ȃ�Ȃ����ƂȂǂ����炽�߂ē`�����A�Ō�ɃS���ւ̂����ԍ��D����n���ꂽ�B�����҂̐��Ƃ��̈��S���`�F�b�N���邽�߂̔ԍ��D�Ȃ̂ŁA�T�����I���ĊO�ɏo����K���Ǘ��������̌W���ɕԋp����悤�ɂƂ̎w�����������B
�@ �h�����C�g��Ў�ɏƖ��̂Ȃ��Â������ɓ���ƁA�����ɐg�k������قǂ̗�C�ɑS�g���܂ꂽ�B���O�̋C�����O�\�x���Ă���̂ɑ��A�����̉��x�͔N�Ԃ�ʂ��ď\�l�x�ƈ�肵�Ă���A���x�r�����\�ܓx�ȏ������̂�����ŏ�����������̂������͂Ȃ��B�����Ƃ��A���ꂪ�~�ꂾ������t�ɉ������������ɈႢ�Ȃ��B
�@ ���炭�i�ނƂ��Ȃ�̐��ʂ������킹���̉��������Ă����B�߂Â��ĉ��̕������Ă���ق������C�g�ŏƂ炵�o���Ă݂�ƁA�����悭�������ꗎ���Ă���̂��ڂɂƂ܂����B���ۂɂ͉�����z�������قǂɑ傫�ȑ�ł͂Ȃ������̂����A���̉������̒��ŋ������艽�x�����ǂŔ��˂��ꂽ�肷�邱�Ƃɂ���āA���{�ɂ��傫�ȉ��ɂȂ��ĕ�����̂ł��낤�B�����Ƀ��C�g�������Ă݂�ƁA�����͂����܂��^���ÂɂȂ�A��̉��������[���ł������݂ɗh����k�킹�Ă����B
�@ ���̉��̂ق��ɂ�����ɂ������̑ꂪ���������A�����̂Ȃ��ōł��傫�Ȃ��͍̂����Z���[�g��������Ƃ����s���̑ꂾ�����B�ʘH���炷�������܂����Ƃ���ɂ��邽�߂Ƀ��C�g�ŏƂ炵�Ă݂Ă����̑S�e��ڂɂ���̂͂ł��Ȃ��������A���ۂɐ��ʂ̂ق������Ȃ肠��悤�ŁA���X�Ƃ��������̉��������̏d������C���������h���Ԃ蓮�����Ă����B
�@ ���C�g�ɕ����ԓ����̏ߓ��̗l�q�Ȃǂ��Ԃ��Ɋώ@���Ȃ���㉺���E�ɂ��˂�ʘH�����ւƒH��ƁA��x���Ƃ������̂������z�[����̂Ƃ���ɏo���B���������͋}�ɒʘH�������Ȃ��Ă���B���H�ɂ���炵����s�����҂̐����O������S���[���S���[���Ƌ����Ă����̂ŁA���C�g���������܂܂��炭�����ő��肪����Ă���̂�҂��Ƃɂ����B
�@ ���炭����ƁA�ł̉��Ƀ{�[�b�ƋP���_�������ꂽ�B�Ȃ�Ƃ���͈�{�̗��X�C�̌��������B�^���Âȏߓ����̉��̂ق����珙�X�ɋ߂Â��Ă���X�C�̌��Ƃ������̂ɂ͓Ɠ��̕��͋C�����܂Ƃ��B���a���j�̏����u���摺�v�̃N���C�}�N�X�V�[���ł͂Ȃ����A���ۂɑ̌����Ă݂�ƂȂ�Ƃ��d�����s�v�c�Ȋ����̂�����̂Ȃ̂��B
�@ �قǂȂ��X�C�̌��͎l�ɑ����A����Ƃ��̌��̗ւ��L���Ȃ��玄�̘Ȃ�ł���n�_�ւƌ������Ă����B�ł̒�����k�[�b�Ɗ���o���đ�����������̂������̂ŁA���̂ق������C�g���ē_�������邭�O�����Ƃ炵�o�����B���ꂽ�̂͒j�����l�̃O���[�v�ŁA�����ɂ���ꂽ�ƌ��������ȕ\��̏����̎p���Ȃ�Ƃ���ۓI�ł͂������B
�@ �l�̘X�C�Ƃ�����ꂽ���A���ۂɂ͂��̂����̂ЂƂ̓L�����v�p�̏��^�K�X���̂悤�������B���̃K�X������ɂ����j�Ƃ���Ⴂ�Ȃ��爥�A�����킵�A���łɁA���ɂ܂������҂�����̂��Ɛq�˂�ƁA���Ԃ�����N�����Ȃ��͂����Ƃ����Ƃ����ԓ����߂��Ă����B�ׂɂ���������킯�ł��Ȃ��̂����A�ǂ���炻�������͎K���̖ڗ����͂��߂����̂�̐g�̂ɕڑł��Ă̓����P�ƍs�Ƃ������ƂɂȂ肻���������B�����K���Ȃ��ƂɁA�u�Èł͗c�Ȃ��݂̂��F�B�v�Ƃ����ς�������o�̎�����Ȃ̂ŁA�S���I�ȋ��|���Ȃǂ͂܂������Ȃ������B
�@ �}�ɋ����Ȃ����ʘH�������������i�ނƂ��悢��u�������v�Ƃ͑��������B��u�₽���Ƃ������o���ܐ�ɑ��������A���̗₽���ɂ͂������ꂽ�B�����������炢�܂ł̐[���̗����ɂ���Ȃ����l�ЂƂ肪���傤�ǒʂ�邭�炢�̒ʘH������Ă����ƁA�X���������傫���Ȃ�}�ɑ����̐��̗��ꂪ�����Ȃ����B����Ő���~�������Ȃ���㗬�Ɍ������Đi�ނ̂����A���̊��G���Ȃ�Ƃ��S�n���悢�B���̐��̊��G�ɂ͊o��������\�\�������������̏u�ԁA�₽�������̗���鏬��Ő�V�т����Ă������̉��������L�����S�g���т��悤���S�����B
�@ �����~�߁A���C�g�ŋ��������̏��ʂ⍶�E�̕ǖʂ����炽�߂ďƂ炵�������͂��̔������ɑ���ۂB���݂��������������悭����Ă���ג������������̕ǖʂ��A���ׂď����̑嗝�̊�Ղ���Ȃ��Ă�������ł���B�ǂ���炱�̕t�߂ɂ����ẮA�ׂ����������嗝�̊�Ցw�̂Ȃ����т��Ă���炵���̂��B���C�g�̌��𗁂тĐ^�����ɋP�����₩�ȕǖʂ����ŕ��ł���A�����ɖ�����ăL���L�����銊�炩�ȏ��ʂ��ׁX�Ɗώ@�����肵�Ȃ���A�������͖]�O�Ƃ������ׂ����̎��R�̉��o��������䂭�܂Ŋy���B�@
�@ ���C�g�������Ɠ����͎����̈łƂȂ�A�����𗬂�鐅�������������ɐS�n�悭�����Ă����B���̏ߓ��������������܂ł́A���̂悤�Ȏ����̈ł̒��ŁA�C�̉����Ȃ�قǂɒ������Ԃ������Ȃ��痬���ɂ���咤�����c�X�Ƒ������Ă������ƂȂǒN���m��Ȃ������킯�ł���B���Ԃ���{�����ɂ����Ă����ł��A�܂���x���l�ڂɐG�ꂽ���Ƃ̂Ȃ��������V�R���A���n��̈ł̉��ɐ����������āA���܂Ȃ��Â��ɖ���Â��Ă���̂��낤�B�����Í��̏ߓ������ɂ����Ƃ肠���āA���ꂪ�a������܂ł̎��Ԃ�z���̂͂Ȃ�Ƃ��s�v�c�ȋC���̂�����̂ł������B
�@ �������炳��ɂ��炭�i�ނƉ��y���ƌĂ��Ƃ���ɏo���B���[�����ʂ����Ȃ肠�邻�̓��A���͑����L���Ȃ��Ă���A�\���I�ɂ݂ĂƂĂ��������悳�����������B�V�䂩�琂�ꉺ����ߓ����y���R���R���ƒ@���Ƃ悢�����������Ƃ�A�s�`�����A�s�`�����Ɛ��ꗎ���鐅�H�̋����ɂ�������������������ꂽ���Ƃ��炷��ƁA���y���Ƃ������������̗R�����Ȃ�قǂ������悤�Ƃ������̂������B���̏ߓ����̑f���炵���̂ЂƂ́A���B���̑召���܂��܂ȏߓ������R�Ɏ�ŐG���Ă݂邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ��낤�B�P�[�r���O�C���𖡂킢�Ȃ���ߓ����̐����ߒ��Ȃǂ�̊��I�Ɋw�Ԃ��Ƃ��ł���_�ŁA���̓����ߓ����͂܂��ƂȂ��̌��w�K�X�|�b�g�ł�����Ƃ����������������B
�@ ���y���̖��ɂ��₩���āA���C�g�������^���Âȓ����ʼn���ȉ̂ł��吺�ł��Ȃ����肷��Ζ��̎�ɂł��Ȃ����C��������̂�������Ȃ��Ƃ��l�������A�N�����Ƃ������Ă��Ă����肵���炢�������i�D�����̂ŁA�������ɂ��ꂾ���͎v���Ƃǂ܂����B�ЂƂɂ͈����̂��߂ɓ����̊�Ղ��ُ�ȐU�����ĕ��A�o�����ǂ���Ă��܂����炽���ւƂ������Ƃ�����������ł���B
�@ ���[���G���߂��܂ł���[�����̊ۂ݂��������ߓ��́A���̎�G��Ƃ����F���Ƃ����Ȃ��Ȃ��̂��̂��������A���̐[��������������ɂ��ĒʘH�͈�i�Ƌ��܂�A�V����}�ɒႭ�Ȃ��Ă����B���������ߓ���Ⴍ���Ē��Ӑ[�������Ȃ��ƁA��p�Őg�̂̂����������K�c�[���Ƃ���Ă��܂������������B���ہA�C�����Đi��ł����ɂ�������炸�A���ꂩ��قǂȂ��E�O�����ɋ���Ȋ�̃p���`���ꔭ��������n���ɂȂ����B�܂��ɖڂ���ΉԂ���юU��Ƃ��������ŁA���̉ΉԂœ��������邭�Ȃ�Ȃ��̂��s�v�c�Ȃ��炢�ł͂������B
�@ �����d���Ȃǂōs������Ƃ炵�Ȃ��璆���őO�i����ꍇ�A�ǂ����Ă��������O�������Ɍ������邱�ƂɂȂ邩�瓪��̎��ӂ̒��ӂ��������낻���ɂȂ��Ă��܂��B�����̐g�̂̏㉺���E�͈łɕ�܂�Ă��܂��Ă��邽�߁A�\���ɒ��ӂ��Ă������ł���p�ɓ���ł����Ă��܂��̂��B���������ƁA���̓�������������ԂɎO�x����p�ɓ����Ԃ��^���R�u�������Ă��܂����B�w�����b�g�ł����Ԃ��Ă���Βɂ������������Ȃ��Ă����ނ̂ł��낤���A���̗p�ӂ̂Ȃ��ߓ����T�K�҂Ȃǂ́A��x���x�͓����S�c�\����邱�Ƃ����炩���ߊo������Ă������ق����悢���낤�B
�@ ����������Ȃ���A����ł��߂����ɂǂ�ǂ̂ق��ւƐi��ł����ƁA�ٓ�������ƌĂ�Ă���ɒ[�ɒʘH�̋��܂��Ă���n�_�ɏo���B�������ɂȂ��Đl�ЂƂ肪�Ȃ�Ƃ����蔲�����邭�炢�̊�̗ڂ����C�g�Ў�ɒʉ߂��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���悩��͂���Ɖ����g���҂�����Ɗ�Ԃɋ��܂��ē����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����Ƃ�����̂ŁA�K�����̂ق����炳���ɂ͂���悤�ɂƒ��ӂ̂������ӏ��ł���B�ł��邾���g���k�ߔ�������悤�ɂ��Ă��̊�Ԃ�ʂ蔲�������A�������l��g�̂̓������܂܂Ȃ�Ȃ�����҂Ȃǂɂ͂���ȏ�̑O�i�͍���ł���ɈႢ�Ȃ��Ƃ�������ꂽ�B
�@ �E��Ƀ��C�g�����������ǖʂɌy���G��Ȃ���[������܂��Đi��ł����Ƃa�R�[�X�ő�̓�ւƏo���B���ٓ�������ł���B�V��̊�Ղ��ɒ[�ɒႭ�Ȃ��Ă��܂��Ă��邽�߁A�l���ɂȂ��Đi�ނ��A�����Ȃ���ΌӍ����������K�����G��܂�Ȃ��邩�����i�D�œ�\���[�g���قǂ̋�����������悤�ɐi�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����A���ʂ𗬂�鐅�̐[�����O�\�Z���`�قǂ͂���̂ŁA�ǂ�����Ă������g�͂��ԔG��ɂȂ��Ă��܂��̂��B��l�̏ꍇ���ƁA��l��������ʉ߂���Ԃ�����l��������ŒʘH���Ƃ炵�o�����Ƃ��ł���̂����A�P�ƍs�Ƃ����Ă͂������䂩�Ȃ��B
�@ �����K���Ȃ��ƂɌg�s���Ă����̂��h�����C�g�������̂ŁA�_���������܂܂���𐅒��ɓ���A�l���ɂȂ��Ă��̒n�_���ʉ߂��邱�Ƃ��ł����B�������A�����g�͂��ԔG��ɂȂ��Ă��܂������A�����̒B�����̂悤�Ȃ��̂���������������A������������悤�Ȃ��Ƃ͂܂������Ȃ������B
�@ ���̂��Ƃ��A�Ⴍ�����Ȃ�����ω��ɕx�����̌i�ς��y���݂Ȃ���ǂ�ǂ�Ɛi��ł����ƁA���ɐi�s�����E��ɑ傫�ȃJ�{�`���l�̊₪���ꂽ�B�a�R�[�X�̍ŏI�n�_�J�{�`����ł���B�J�{�`����̌��������͂���Ƃ������ɂȂ��Ă���A���̒n�_����͂���ɉ��̂ق��ւƌ������Ă��ׂ����������������Ă����B���G��������Ⴍ������ԂłȂ���ΑO�i�ł������ɂȂ��^���Âȓ��������C�g�ŏƂ炵�o���Ă݂����A��A�O�\���[�g����̂Ƃ���ō������ɓ����J�[�u���Ă���炵���A�c�O�Ȃ��炻��ȏ㉜�̂ق������ʂ����Ƃ͂ł��Ȃ������B
�@ ����ł��J�{�`���₩��\���[�g���]�̂Ƃ���܂ł͂b�R�[�X�ɑ��ݓ���Ă݂��B�������Ȃ���A�ē��l���Ōܐl�܂Ŏl��Z�S�~�Ƃ����b�R�[�X�̓��������Ă��Ȃ��g�Ƃ��ẮA����ȏ�̒T����f�O����������Ȃ������B�S�̕Ћ��ł́A�N�����Ă��Ȃ����Ƃ����炻�̂܂܂b�R�[�X�ɓ˂��i��ł݂���ǂ����Ƃ����������Ȃ��͂Ȃ��������A����������������Ǘ��҂ɖ��f�������邵�A���������ᔽ�s�ׂ͂悭�Ȃ����Ƃ��Ƃ����ǐS�̐��̂ق�������A���ǂ͂��̐��ɏ]�����悤�Ȃ킯�ł������B
�@ �����ւƈ����Ԃ��܂��ɁA���̓J�{�`����ɍ���������|���ă��C�g�������A�����ʂ�ꐡ��������Ȃ��ł̒��ł����ґz�ɒ^���邱�Ƃɂ����B���ꂩ��܁A�Z���قnjo���������낤���A�N����������ɋ߂Â��Ă��邯�͂��������B�����Ă��ꂩ��قǂȂ����Ďp���������͎̂Ⴂ�v�w�A��炵����g�̒j���ł������B��l�̉�b�̗l�q���炷��ƒj���̂ق��͉��x�����̏ߓ�����K�˂����Ƃ�����炵���������A�����̂ق��͏��߂Ă炵���A�����ɓ��O�ɖ߂�邩�ǂ������X�s�����ȗl�q�������B
�@ �����d���ŏƂ炵�����Ȃ��炨�݂��Ɉ��A�����킵�����ƁA���͓�l�̎��Q�����J�����ŃJ�{�`������o�b�N�ɋL�O�B�e�����Ă������B��l�͂��炩���ߐ��ɔG��Ȃ��悤�ɂ��̃J������h���p�p�b�N�ɓ���Čg�s���Ă������̂̂悤�������B���̃J��������ɂ��ĎB�e��S�����鎄�̂ق��́A�K�R�I�ɕ��̂��鑤�ɐg���ĒႭ�\���˂Ȃ�Ȃ��Ȃ������߁A�ǂ��Ղ�Ɖ����g�����ɂ����Ă��܂��L�l�������B
�@ �J�{�`���₩��̕��H�͎Ⴂ�v�w����ɗ����A�����������Ƃ��̂��Ƃ�ǂ��������ɂȂ����B��x�H�������������Ԃ������Ȃ̂łƂ��ɑ傫�Ȗ��͂Ȃ��������A��s����v�w�̒j���̂ق����ˑR�����ɂԂ���S�c�[���Ƃ����݂��������Ă��B����ɑ����āu�C�e�[�b�I�A�C�e�[�b�I�v�Ƃ����ߖ������������Ƃ���@����ƁA�ǂ����ނ͊�p�ɂЂǂ�����ł����Ă��܂����悤�������B�����āA���̐��ɋC���Ƃ�ꂽ���̏u�ԁA����ǂ͎����̓��̂ق��ɂ܂�����S�c�[���Ƃ����Ռ����������B���̐c�܂ŃN���N������悤�Ȍ��ɂɕK���ɂȂ��Ċ����Ȃ���A�ēx�ɂ킽�鎩���̕s���ӂ������ł݂͂����̂́A���ׂĂ͂��Ƃ̍Ղ�ł������B
�@ �������ւƖ߂�r���ŁA�V���ɉ���ڎw���l�l�̉Ƒ��A��Ƃ��������B�܂����w����w�N�Ƃ��ڂ�����l�̒j�̎q�����́A�g�̂��������r�q�Ȃ����ɓ����ł̓����͌y�₩�ŁA���m�̓��A�T����S��y����ł���l�q�������B���Ƃɑ������e�̂ق��͂��Ȃ舫��ꓬ���Ă���悤�ł͂��������A����ł����̕��ς��ȏߓ����ɑ���D��S�̂ق������̋ꓬ�Ԃ���͂邩�ɏ����Ă��銴���������B
�@ ������Ƃ����`���S�̂���q�ǂ������Ȃ���т����������A���܂ł��z���o�Ɏc�邾�낤���Ƃ����������Ȃ̂ŁA�t�B�[���h���[�N�D���̉Ƒ��ɂ͂��̓����ߓ����̒T�������ЂƂ��������߂��������̂ł���B�n���w�̑̌��w�K�����˂Ă̒T���Ȃ�����������n�͑������Ƃ��낤�B
�@ �����ɓ��O�ɏo��Ƙr�ɂ��Ă������ԍ��D���Ǘ��������ɕԋp���A���ɔG�ꂽ�V���c��p���c�𒅑ւ��邽�ߋ}���ŎԂւƖ߂������A���ʂƂ��Ă͂Ȃ�Ƃ��[�����̂���ߓ����T�K�ł͂������B�����œ��ɂ�������̑傫�ȃR�u��������̂ɓ�A�O����v�����̂ƁA�����̕s���R�Ȏp�����Ԉđ�����������Ȃ������̂������ł��炭���̂����������ɂ̂͌v�Z�O�������̂����A����]��Œ������P�[�r���O�̑̌��̑㏞�Ƃ��ẮA�����͂�ނ����Ȃ����Ƃł͂������̂��낤�B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2002�N10��9��
�쑽���̒����Č�����
�@ �쑽�������ƃ��[�����̒����Ƃ������Ƃ͈ȑO���炩��悭�m���Ă����B�����A���̐܂̗��ɂ����āA��Îᏼ����đ�ɔ�����r����������쑽���ł͑z��ʔ������������������B�쑽���s���̈�p�ɂ́A���Ďs���̂��������Ɍ����Ă������X���ڒz���A���̓����Ɋe��̗��j�����▯����������W�������u�쑽�����̗��v�Ƃ��������ق����݂��Ă���B�����đ傫�Ȋ��҂��������ɂ��̎����ق�K�˂����́A�����Ŋ쑽���Ƃ������̔�߂�ӊO�Ȉ�ʂ��܂̂�����ɂ��A�����Ȃ��炸��������邱�ƂɂȂ����B
�@ �c���l�N�Ɍ��Ă�ꂽ�����ƍ������Ɛ����̂��鑠���ɂ́A���Ă͂��̒n�̌ւ�`���E�l�Z�|�ł�������Ì^���쐬�ɂ��Ă̋Z�p�������W������Ă����B�^���Ƃ͒����̕z�n�Ɏ�X�̊G�����l����ߕt���邽�߂̐��F�p���^���̂��Ƃł���B�����ꂽ�^���Z�p���������Ƃ������Ƃ́A���R���̒n�ł͕z�n�̐��F�����������Ƃ��Ӗ����Ă���B�]�ˎ���ɂ����Ă͒N�ł����R�Ɍ^���邱�Ƃ��ł����킯�ł͂Ȃ��A���{������ʂɋ��̂���Ă���ɐ��A�]�ˁA����ɂ��̉�Ê쑽���̐E�l�����������̐���Ɍg��邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�������Ă���Ƃ���ɂ��ƁA�ꎞ���܂ł͈ɐ��n���̐E�l�W�c�����̐�L�Z�p�ł������Ƃ������B�쑽���^���Z�p��`�����͈̂ɐ��̐E�l�����������ŁA���̌㖋�{������ʂȔF������A��Ô˂̊NJ��̂��Ƃɖ{�i�I�Ȍ^�����肪�����Ȃ���悤�ɂȂ����悤�ł���B
�@ �^����ɐ旧���āA�E�l�����͂܂����̒n����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�n���͏㎿�̘a�����`�a�ŎO���ڒ����đ���A����ɐE�l�����ߌ^�荞�ށB���k�Ȑ��ߌ^������A�����������I�Ȍ^���Ő��ߕt���������Ȃ����肷��Ƃ��Ɍ^���ꂪ�������肵�Ȃ��悤�ɁA�R����Ƃ����\��Ƃ�����������ȏ����Ȃǂ��{����Ă����炵���B
�@ �W�������ɂ��ƁA�^������ɂ́A�����A�Ȓ���A������A�˂�����̎l�ʂ�̕��@���������悤���B�����Ƃ́A�E�l���l�X�Ȑn�`�̒�������K�v�ɉ����Ď��삵�A������g���Ēn����ł������悤�ɐ}����͗l��Z�@�̂��Ƃ��A�܂��A�Ȓ���Ƃ́A��K�ɒ������̐n�āA�����O�Ɉ����ċϓ��ɋؖ͗l��Z�@�̂��Ƃ��������炵���B������Ƃ͏����ȉ~�`�̌����ɘA�˂Ė�l��Z�@�ŁA��[�������Ȕ��~�`�̍אn��]�����Ēn��������ł����Ƃ����B�Ō�̓˂�����̏ꍇ�́A��o���`�̒�������p���A�O���ɐn�������o���悤�ɂ��čׂ��Ȗ͗l�荏�̂��������B
�@ �^������Ɏg�p���ꂽ�������ނ⊮�������^���Ȃǂ��W������Ă������A�_������Ƃł������ق��Ȃ������̓V�ːE�l�����̋Z�ɂЂ����犴�Q�������ł������B����Ȃǂ̐��t���ɗp����ꂽ�^���Ȃǂ͌��Ă��邾���ł��C�̉����Ȃ肻���Ȃ��炢�ɐ��k������߂Ă������炾�B�����S���̎���ɂ����鐈�ȕ��͗l���\�\���㕗�ɂ����Ő�[�t�@�b�V�����A���邢�͍ŗ��s�t�@�b�V������n�����x�z���邽�߂̍����Z�p�������킯������A���{���^������Ɍ������K����݂��Ă����̂����R�̂��Ƃ�������������B
�@ �쑽���Y�̌^���͉�Ì^���ƌĂ�A����ɂ���Đ��ߕt����ꂽ���n�ނ͍L�����k�n����тɏo����Ă����悤���B�쑽���̐E�l�����͂₪�Ė{��̈ɐ��^�������������������I�Ȍ^���ݏo���悤�ɂȂ��Ă������悤�����A�ߑ�ɓ���v�����g�Z�p�ɂ��z�n�̐��ߕt�������y�������߂ɁA�^���Z�@�ɂ��`���I�Ȑ��ߕt���@�͔p��A�Z�p��`������E�l�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����Ƃ����B���ׂĂ͎���̗���Ƃ��������Ȃ��̂��낤���A�Ȃ�Ƃ��ɂ����C�����ĂȂ�Ȃ������B
�@ ���̗��ɂ͍������̂ق��ɂ��A���X���A���葠�A�̑��A���A���~���A�X���Ƃ������悤�ȗl�X�ȑ����ڒz�W������Ă����B�����āA��������ʂ茩�Ă��������ɁA�쑽���̑��X�͒P�Ȃ钙���ɂƂ��Ă̑��ł͂Ȃ��A�e�퐶�Y��Ə�p�A�䏊�p�A�g�C���p�A�Z���p�A���q�ڑҍ��~�p�A���X�p�ȂǓ��퐶���S�ʂƐ[�����т����݂ł��������Ƃ��킩���Ă����B�n���o�g�̎ʐ^�Ƃ̌̋��c���́A�ߑ㉻�̒��Ŏ����䂭�쑽����т̑��X��ɂ��݁A���̏�i���ʐ^�ɂ��čL���S���ɏЉ���B���̂��Ƃ����[�ƂȂ��Ċ쑽���̑��͑����̐l�X�ɒm����Ƃ���ƂȂ�A���ʓI�ɖ���������Y�Ƃ��Ă̑��ۑ������������̂����A�����Ȃ������Ƃ̔w�i�ɂ́A���̒n�̑����P�Ȃ钙���ɂł͂Ȃ������Ƃ���������Ȃǂ��������̂��낤�B
�@ ���Ȃ݂ɏq�ׂĂ����ƁA�쑽�������[�����ŗL���ɂȂ����̂����c���̂������ł���B���������X�̎ʐ^���L���Љ�ꂽ�̂��_�@�ɁA�쑽���ɂ͑S�����瑽���̎ʐ^�Ƃ〈���q�Ȃǂ��K���悤�ɂȂ����B�����쑽���ɂ͂������������K�҂��H�����Ƃ�邨�X�Ȃǂ��قƂ�ǂȂ��A��ނȂ����Ĕނ�͋߂��ɂ������ꌬ�̃��[�������ɗ����悤�ɂȂ����炵���B���܂��܂����̓X�ŏo�����[���������������������ߕ]���ƂȂ�A���ꂪ�Ăѐ��ƂȂ��Ď����悤�ȃ��[�����������X�Ɍ���A�Ǝ��̖��������悤�ɂȂ����悤���B�����āA���ɂ͊쑽�����[�����Ƃ����u�����h�܂ł����܂��ɂ��������̂��Ƃ����B
�@ ���𗘗p�����W���ق̒��ɂ́A���m�̃i�C�`���Q�[����搂�ꂽ�Z����q�̔N���ƋƐт�����R�[�i�[��A�ꎞ��O�ɓƓ��̋��痝�O�̎��H�Ŗ���y��������Ҙ@����O�̋Ɛт��̂��鎑�����Ȃǂ��������B�����g�ɂ���A�ǂ����Ŗ��O���炢�������������Ƃ̂Ȃ��l���������������A��l�Ƃ����̊쑽���n���̈̐l�Ȃ̂������ł���B���܂��܂̂��Ƃ��������A�悢�@��ł͂������̂ŁA���̑��Ղ������[���q�������Ă��炤���Ƃɂ����B
�@ �Z����q�Ƃ����l���́A��C�푈�Ȃǂɂ����đ����̕����҂�G�����ւ��ĂȂ��~�ς����̂���n�߂Ƃ��A�n���~�ςȂǗl�X�ȎЉ���^���ɐ��U�����������I�������������Ƃł������悤���B�ɂ͔ޏ��̋Ɛт��L�O���������������Ă��邻���ŁA���̔蕶�͏a��h��̊��|�ɂȂ���̂��Ƃ����B
�@ �\�O�����̕���������W�Ȃǂ��邱�Ƃ���m��Ȃ���������Ƙ@����O�ɂ��āA���̈̋Ƃ��������]�����肷�鎑�i�Ȃǂ��̐g�ɂ��낤�͂����Ȃ����A����͂Ƃ������A���Γ`���I�Ƃ����������Ȕނɂ܂��G�s�\�[�h���̂��̂͂Ȃ��Ȃ��ɖʔ��������B������ɂ��ƁA�@����O�͖����\�ܔN��\��ߑO�O���߂��A���̂��Ȃ��A���[�̌ӓ��̖̂��ƂŐ��܂ꂽ�̂��Ƃ����B�v�̎��ƂɓƂ�ň��A�ɍs������e���A�r�̎R���œˑR�Y�C�Â��A�N�̏������Ȃ��܂܂ɐ��ɐ��ݗ��Ƃ��ꂽ�̂��������B�a���̏u�Ԃ��炻�̐l���͂����낵�����I�������Ƃ����킯�ł���B
�@ ����Ȕނ̒a���̋�J��m���Ă��m�炸���A�ނ��c�������Ɏ����͉Ƃ��o�z���s���s���ɂȂ��Ă��܂��B�ł���̔z���������Ă��̌ア�낢��ȍč��b�����ӂ��玝���オ��̂����A��e�͊�Ƃ��Ă����̘b��f��A�`����ɐs�����X�𑗂����B�₪�ĕ�e�͍������鐶�����x���邽�ߑ��ƂɏZ�ݍ��݉�����������悤�ɂȂ�̂����A�������ɂ��T���Ƃ͂����Ȃ��������̉Ƃ̎�͗c����O���䂪�q�̂悤�ɉ������Ă��ꂽ�̂��Ƃ����B���̗l�q�����Ă�����e�́A����܂ł̂������Ȃȑԓx��ς��A���̑���ƍč����邱�Ƃ����ӂ����B�@���Ƃ������͕�e���č�������̂��̂ł������Ƃ����B
�@ ��߂��d�˂ɏd�˂Ȃ��琬��������O�́A�₪�Č��w�S�ɔR���ď㋞���A���݂̓����w�|��w�ɓ��w�A���̊w�������Ƌ��ɗ������𑗂�悤�ɂȂ�B�I�ꂽ�w���Ƃ������̓����ӎ��������o���J���̔��w���ւ闾���������y���ŗ����ɓ��ݓ��邱�ƂȂǏ�̂��ƂŁA���̂��ߌ��ւ�L���Ȃǂ͉���ق������ł������B����Ȓ��Ŗ�O�����́A���̗����̎̕���}�����̂Ƃ������A�������������������Ƃ�ŎG�Ђ������͂��߂Ƃ��鐴�|�ɐ�O���A�����̔����ɓw�߂��̂��Ƃ����B�@
�@ ����Ȃ�����A�ߘJ��������̒����������Ă����ނ́A�|���̍Œ��ɍ��M���o���A����f���ē|��Ă��܂��B����ł��Ȃ��K���Ɋ撣�낤�Ƃ����O�̎p�ɁA����܂Ŕނ̍s����⎋���Ă��������̗��������������������Ɣ��ȁA�Ȍ�A�ނƋ��ɗ����̔�����Ƃɋ��ނ悤�ɂȂ����B�����āA���������̔����^���͊w�����S�̂ɍL����A�F�����悵�ė����̐��ڂƔ����ɓw�߂�܂łɂȂ��Ă������̂��Ƃ����B
�@ �ǂ�ȏ����Ȑ��ӂƂ����ǂ��A���߂��ɂ����ςݏd�ˑ����Ă����₪�Ă���͑傫�ȗ͂ƂȂ��ĎЉ�����悤���ɂȂ�\�\����Ȃӂ��ɂ��ǂݎ���@����O�̋��痝�O�̍������A���̃G�s�\�[�h�Ȃǂ͂悭�ے����Ă���̂��낤�B���h�Ȃ��Ƃ��̂����Ȃ��̂ł͂��邪�A���������Ȃ����ɁA����Љ�̌l��`�I�Ȋ��ɂ�������ł���Ă��܂������Ȃǂɂ͂ƂĂ��^�����ł������ɂȂ��B�����Ȃ��Ƃ��A�ӂ�ӂ�Ɨ������Ȃ��珟��Ȃ��Ƃ�Ԃ��Ă���g����������ƋC�y�ɋ߂Â����Ƃ̂ł���悤�Ȏ荇���ł͂Ȃ��������B
�@ �̂��ɏC�{�c�^���Ȃǂ�ʂ��ċ���ʂō��ۓI�ɂ��v�������Ƃ����@����O�́A���a�\�ܔN�ɑ��E�����B�ӔN�͓V�c�̑O�Ō�i�u�Ȃǂ�����h�_�ɂ��b�܂ꂽ�Ƃ������Ƃ��B�ނ��c�����Ƃ������t���������̕ǂɕ\�����Ă������̂ŁA���łɂ�����Љ�Ă������B���̎����W�����̗l�q���炷��ƁA���̂悤�ȋC�܂���ȗ��l�����܂ɂӂ�ӂ�Ƃ���Ă��āA��������˂��������ł��������Ɨ�������̂��悢�Ƃ���ł͂Ȃ����Ƃ��������邩��A����Ȃ��������ȏЉ�ł��A�����炩�͘@����O�搶�̗�̈Ԃ߂ɂȂ邩������Ȃ��B
�l����߂�@���߂Ĉ��ɋA��
���Ȃ��l���͈Í��Ȃ�
���ɋF���
���ׂĂ̐l�Ɛe����
�킪�Z�ދ���
��l�̑��ӎ҂��Ȃ��܂ł�
�l��N�Ă�@�N���Ċ��ɋA��
���Ȃ��Љ�͑��Ȃ�
���ɋF���
���ׂĂ̐l�Ɠ���
�킪�Z�ޗ���
��l�̑ӂ��҂��Ȃ��܂ł�
�@�@�@�@�@�i�@����O�j
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2002�N10��16��
����ɏ����Ȕ����Əo������
�@ �쑽�����̗��̎����قɂ͂����ЂƂ����[���W�������������B�����\�ܔN�ɋN�������쑽�������̎����ł���B���̖������{�͉�ÎO�����H�̊J������s���悤�Ƃ��Ă����B��ÎO�����H�Ƃ͉�Â���R�`���ɒʂ���H�B�X���A�Ȗ،��ɒʂ����B�X���A�����ĐV�����ւƒʂ���z��X���̂��ƂŁA��������������R�x�n�т�D���т����H�ł��������߁A�����̋Z�p�̂��Ƃł͑�ςȓ�H�����\�z����Ă����B
�@ ���̎���R�`�ƕ����̗����߂����˂Ă����F���o�g�̎O���ʗf�́A��È�т̔_�����������p�����̓��H�J��ɂ����点�����A���܂�ɂ���O���킵����H�����������߁A�Ђǂ��_�����ꂵ�߂邱�ƂɂȂ�A�ނ�̊Ԃɂ͕K�R�I�ɑҋ����P�̗v���^���⓹�H���̂��̂̊J��ɔ�����^�����u�������B�����āA���̉^�����x�����A���{������ɂ�鈳���ɒ�R���邽�߁A�n���⍑���e�n�̎��R�����v�z�ƗL�u�������쑽���̑�����떃�S���ӂɏW�������B����ɑ��A���߂̎O���ʗf�͓����F���o�g�Ōx��������x���̍����u�Y�S�Ƃ��ĕ������떃�S���ɏ��ق��A���Ύ҂̓O��e���ɂ����点���B
�@ �����\�ܔN�A�O���̎w�����������͊��������Ĉ�т̑����̔_���⎩�R�����Ƃ����X�ɑߕߓ������A�e�͂Ȃ������Ɩ����v�z�e�������݂��B���ꂪ���ɂ����쑽�������ɂق��Ȃ�Ȃ��B�ߕ߂��ꂽ�_���▯���Ƃ����͌��Ǎٔ��Ŗ��߂ƂȂ邪�A�O�����߂炪�ӔC�����邱�Ƃ͍Ō�܂łȂ������悤�ł���B���Ƃ̋ߑ㉻���ŗD�悳���Ă����������{�ɂ́A���H�����s�ɂƂ��Ȃ����O�̑���ȋꂵ�݂�َE���Ă��A�܂��͓��H�̊������}�����Ƃ����Öق̕��j������������Ȃ̂��낤�B
�@ ���̊쑽���������_�@�Ƃ��Ď��R�����^���͖��O�̊Ԃł���ɍL������݂��A�_�ޏ���̓o����݂邱�ƂɂȂ�̂����A����ɔ�Ⴗ�邩�̂悤�ɐ��{���ǂ⊯���ɂ��K�����������𑝂��Ă������悤�ł���B�쑽�������Ɋւ��铖���̖c��ȍٔ��������K���X�P�[�X�ɕۊǓW������Ă������A�N�ł����R�ɂ�������ɂƂ��ĉ{���ł���悤�ɂȂ��Ă����̂������ɂ��Î��I�ŁA���ɂ͂����ւ��[��������ꂽ�B�������������Ԃ�����Ζn�����ꂽ�����̎����ɂ������Ɩڂ�ʂ��Ă݂����Ƃ����C�����Ȃ��ł͂Ȃ��������A�ǂ��l���Ă��e�Ղɂł���悤�Ȃ��Ƃł͂Ȃ������̂ŁA�������ɂ���͒f�O����������Ȃ������B
�@ �����̂ЂƂƂ��āA���L�d�����u�Ԋ���v�̑}�G�ŁA�u�ᒆ�S���̐}�v�Ȃ���̂��W������Ă������A���̊G�}�Ȃǂ͋����[�����Ƃ��̂����Ȃ������B���Ⴋ�̒��������ɂ���Ď��R�����Ƃ��������Ă��Ă����Ƃ����`�����G�}�Ȃ̂����A����|�����Ă���ɂ�������炸�B�R�Ƃ��������p�̖����Ƃ́A���ɔ����t�������A�߂̐����͂��߂����Ȃ���A���낵���`���őO�����ɂ�ŗ����Ă���B����̒��ł���ɂ�������炸�A�S�����ꂽ����͕I���炳���������o���ŁA�����͂Ȃ�Ɨ����̂܂܂ł���B����ɑ��A�O�l�̊����̂ق��́A�������X�̂����Ɍ����O�����͂���A���܂ɔ�̒��C�Ƃ����o�ŗ����Ȃ̂����A�Ȃ�Ƃ���Ȃ������ȕ\����ׁA�S�g�Ɏ��M�̂Ȃ������ȗl�q��Y�킹�Ȃ���K�^�K�^�Ɛ�ɐk���Ă���B���̑}�G�t���ӂ��ޓ����̉�Ö��O�̊����ւ̓��Ȃ邨���������̊G�}�ɂ��̂܂��ڂ��Ă��銴���ł������B
�@ �����R��Ƃ����A�|����p�ٕۑ��́u���v�Ƃ�����i�ōL���m���鍂���Ȏʎ���Ƃł���B���̍����R��͓��ǂ���O�����H��������̕��i�������ɕ`���悤�Ɉ˗�����Ă������̂炵���B�ނ̕`�������H�Ƃ��̎��ӂ̌i�ϐ}�����Ȃ�̖����W������Ă������A�����̊G�}����������ɎO�����H�̊J�킪��H���ł����������M���m�邱�Ƃ��ł����B�������̒n���ŋ�����Ƃɗp�����Ă������ȏC���i���މ^���p�̖ؐ����A���̒n���ł́u�V���v�ƌĂ�Ă����j�Ȃǂ����ׂ��Ă������A���̂悤�ȏC���̓I���m���̖Ƃ����d���瑢���Ă����炵���B�I���m���Ƃ́u���܂�v���a�������t�Ȃ̂������ŁA�����܂�Ă��܂��قǂɍd���Ȃ̂ł����Ă�Ă����Ƃ����B�����A�I���m���̖͋M�d�Ȏ��Ƃ��đ�Ɏ���A���\�N�Ɉ�x�Ƃ�������ɁA���̔��͕̂K�v�ŏ����ɂ��������Ȃ��Ă��Ȃ������悤�ł���B
�@ �쑽�����̗��̂����߂��ɂ͊쑽���s�����p�ق��������B��O�̍Â����ē�������ƁA���܂��܁u�����������`�������{�̎��R�v�Ƃ������i��W���Â���Ă���Ƃ���炵�������B�ӊO�ȂƂ��Ƃ�Ŏv�������Ȃ����i��W�ɂ߂��舧�������́A�������������͂Ȃ��Ƃ������ܓ��ق��A�f���炵����i�̐��X�ɑΖʂ����B���{��d�ɃL�����̂��Ƃ��P�������ȉ�Ƃ����̕`�������i��͂�������f���炵����i�����ŁA�b���������������������B�e�n�̍���������`������i�����Ȃ�̐����������A�Ȃ��ɂ͂��łɎ����Ă��܂��������Ԃ�̂̕��i�Ȃǂ������ĉ�������������ł������B
�@ �W����i�̂Ȃ��ɂ͍�{�ɓ�Y�̕`�����u�����v�Ƃ�����̏��߂Ėڂɂ��镗�i��Ȃǂ��������B�����ĒW���̐F���ŕ`����Ă���A�e�[�}�ƂȂ��Ă���Ώە��̗֊s���ځ[���Ƃ��Ă��āA���܂ɂ��w�i�̐��E�ɗn�����ݓ������Ă��܂������ɂ��݂���̂́A���̍�i�ɂ����ʂ����{�̊G�̑傫�ȓ����ƌ������B�Ⴂ���͂ǂ����e�̔��������̂����{�ɓ�Y�̊G�ɂ��܂ЂƂ���߂Ȃ��ł����̂����A���鎞�������ɁA�������Č������̑��݂��咣���悤�Ƃ͂��Ȃ����̉拫���Ȃ�ƂȂ��킩��悤�ɂȂ��Ă����B�\�̏��ʂ�`������i���ނɂ͂���̂����A���܂��ܖڂɂ������̏��ʂ̊G�̐��݂Ɉ��|���ꂽ�̂��A������{�ɓ�Y�̐��E�ɂ̂߂荞�ނЂƂ̑傫�ȓ]�@�ƂȂ����B
�@ �u�C�̍K�v�Œm����ؔɂ̐e�F�ŁA����������O�̐��Ȃɂ��ƉA�Ŏx�����Ƃ�����{�ɓ�Y�́A������_�ŐƂ͑ΏƓI�Ȑl���������炵���B����Ɍ����u���v�̐ɑ��āu�Áv�̍�{�\�\����ƂŎu�����̋��������ƈ���č�{�̂ق��͉��₩�ŁA����߂Ď��ȗ}���̂������l���������悤�ł���B�V�˂�搂�ꎩ����V�˂��������Ȃ���A����ȍ\�}�ƐF�ʂ����G���Ïk���ꂽ���Ԃ̒��ŕ`���đ��������A�����ۂ��A�n�����������Ȑl�������R�̂Ő��������A�ǂ����͂�Ă��ė����悤�ȍ\�}�ƒW���F�ʂ̊G��`���đ听���A���\��I�ɒ�����V�����܂��Ƃ����Đ�������{�ƁA��ƂƂ��Ă̓�l�̐l�����܂�����߂đΏƓI�������݂����ł���B�݂��Ɉَ��ȑ��݂��������䂦�ɂ����A�������p�w�Z�i�������|�p��w�j����̐ƍ�{�̊Ԃɂ͐[���F����J���萶�����̂ł��낤�B
�@ ��{�ɓ�Y�͂悭�n�̂��镗�i��`���Ă��邪�A�����̊G�̂������������҂̐S�ɂȂ�Ƃ��s�v�c�Ȉ�ۂ��Ă�����B�����ɂ���Ă͉����������z���̂悤�ɂ͂��Ȃ����̂̂Ȃ����݂ɂ��������Ă��܂������ȊG�ł��邩�炾�B�ނ̕`�����G�̂Ȃ��ɂ͐��F�������n������A��F�������n������B�����Ă܂��A�t�ɁA�n�̐F��������������A�n�̐F����������B
�@ �I�v�̑厩�R�̂Ȃ��ɂ����Ă͂��܂�ɂ��R���e�̂悤�ȑ��̊Ԃ̐��A�������Ȃ��炻�̒W���e�̂悤�Ȉ�u�̐��Ȃ����Ă͈Ӗ����Ȃ����݂������Ȃ����R�E�\�\��{�ɓ�Y�́A���m�v�z�̉e����傫�����z���C�g�w�b�h�̓N�w�̐����悤�Ȑ[���Ȑ��E�ς��A���Ԃ���G�ɂ���킻���Ƃ����̂��낤�B�f������R�E�Ƃ̘A�����̂Ȃ��ŁA�O�E�Ƃ̋��E�̒肩�łȂ��܂܂ɒW���ق̂��ɕ����яオ�鐶���̐_��A����ɂ͂��̌��̉e�̂��Ƃ�������ʂ��Ă̂ݔF�������ʂĂ��Ȃ��O�E�̍L����A�����������悤�Ȃ��̂���{�͂��̑�z�����R����̂ނ����ɓǂ݂Ƃ��Ă����ɈႢ�Ȃ��B
�@ ���܂��܊쑽���̒n�ł߂��舧������{�ɓ�Y�̑f���炵���ꖇ�̕��i���ʂ��āA���Ċ����������낢��ȍ�{��i������������z���A�����₩�ȑz����[�߂邱�Ƃ��ł����̂͂��̗��̎��n�̂ЂƂł��������B
�@ ���ł�����A���̐܂ɋL���̌Ñw����ˑR���S������Ƃ�������z���o�̂��Ƃɂ�����Ƃ����G��Ă������B�����c����������Ɉꐢ���r�����m�g�j�̃��W�I�h���}�u�J�������q�v�̂Ȃ��ȂǂŔ������ڔ��̉������ꂽ�肷��ƁA���łɎ��������̍����̒n�Ŏ��̕a�̏��ɏA���Ă�����́A�u��������������������̎ڔ����c�c�v�ƙꂫ�Ȃ���A����ɕ����������Ă������̂��B���c�����Ƃ͓J�������q�̂ق��A�����̋R�m�ȂǓ����̐��X�̃��W�I�h���}�̉��y��S�����A���̖���m��ꂽ�l���ł���B
�@ ���l���܂�̉��l�炿��������́A���������ƎႢ�����c�����v�Ȃ̉Ƃ̂����ׂɏZ��ł����B���̊W�ŕ��c�ƂƂ͈ꎞ�Ƒ�����݂̌��ۂ��������悤�ł���B���c�����v�l�͐��O�q�Ƃ��������̗L���Ȕ��l���D�ŁA��̌`���̃A���o���ɂ͕��c�v�Ȃƈꏏ�ɎB�����傫�Ȏʐ^�Ȃǂ��\���Ă���B���O�q���M�̃T�C������̎ʐ^�Ȃǂ��c���Ă���悤���B���ĕꂪ�b���Ă��ꂽ�Ƃ���ɂ��ƁA�Y��Ȍ��̖�Ȃǂɂ͗������̑t�ł�������ڔ��̉����낤�낤�Ƌ����Ă������̂������Ƃ����B
�@ �ނ��A����ȉ������̋L���������}�ɑz���o�����̂ɂ͂���Ȃ�̗��R���������B���c�����Ƃ́A��{�ɓ�Y�̐e�F�������ؔɂ̑��q�A���c�K�F�̂��Ƃ�����ł���B�������̎�����m�����̂͂����Ƃ̂��ɂȂ��Ă���̂��Ƃ��������A���̕ꓰ�͂ނ�c���ˁ\�\�ؔɂ̗��l�ŁA�u�C�̍K�v�ɕ`����Ă��闇�̂̏����̃��f���ɂȂ����ƌ����Ă��邠�̐l���ɂق��Ȃ�Ȃ��B��{�ɓ�Y�̕��i��u�����v�����[�ƂȂ�A�A�z���A�z���ʁA�L���̒�ɒ���ł����z���o���S���Ă����悤�Ȃ킯���������A�Ƃɂ������s�v�c�ȗ��̈���ł͂������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2002�N10��23��
���̍ד��E�R�������l
�@ �R�`�~�n��k�Ɍ������đ��蔲�����ԑ�ɓ���ƁA�����ō����\�O���ɕʂ�������A���H�����̉H�O�ԑq�w�t�߂ւƒʂ��錧���ɎԂ������ꂽ�B���ړ��Ă͉��̍ד��ŗL���ȎR�������i�Ȃ�����Ƃ����j�������B���܂͂�������g���������ꂽ���̓����A�m�Ԉ�s�͌��݂̉H�O�ԑq�����肩��t�ɒH���Ĕ��ԑ���ʂւƏo���B���̌����͋ߔN���S�ܑ�����A�����̎R�������z���̓���ʂ炸�����̃g���l�����Đԑq������ʂɒʍs�ł���悤�ɂȂ��Ă���B����Ȃ킯����������A���炭�����𑖂������ƁA�g���l���̂�������O�ʼnE��ɕ���ׂ������ɓ������B��Ԑ������Ȃ��ׂ��������ꉞ�ܑ��͂Ȃ���Ă���B
�@ ���������߂��Ƃ���ɂ͂������J�����X�y�[�X������A�����������Ȓ��ԏ�ɂȂ��Ă���B���̒��ԏ�ŎԂ��~��Ėؗ���D���ד��������������ƁA�m�Ԃ��ʂ��������̂܂܂̎R�H�����܂����������c���Ă���{���̓����̂Ƃ���֏o���B���̎R�������ɂ͍��t�����̓r���ŗ�������̂����A���̎��͂܂��c�Ⴊ�����Ċ��X�Ƃ��Ă���A�������[���̎����߂��Ƃ������Ƃ������Ă�����͈Â��W�]�������Ȃ������B
�@ �K�����̓��͓V����悭�A�܂��ߑO���̎��ԑтƂ������Ƃ������āA���ԑ̖ؗ��̊Ԃ���͌��R�A��̑傫�ȎR�e���]�܂ꂽ�B�̗t�̐ς���̂Ȃ���ׂ̍������̘e�ɂ͎q���n�����K���ЂƂ���B���̋߂��ɂ͔m�ԉ��̌����肪�����Ă����B���̎q���n�����K�͂��Ȃ�̂��炱�̒n�ɂ��������̂炵������A�m�Ԉ�s�����̓����z�������ɂ��A���݂̂��̂Ƃ��Ȃ��ł͂Ȃ��ɂ��Ă������悤�Ȓn�����̂悤�Ȃ��̂��J���Ă����̂ł��낤�B���R�����̂��ׂ͍̂�����ǂ���������Ɠ��ł߂��Ă���A�J�T�J�T�Ɨ����t�ݖ炵�Ȃ��炻�̓���H��̂͂Ȃ��Ȃ��C���̂������̂������B
�@ �Ԃɖ߂�ƁA�����̂Ƃ͔��Α��̐ԑq������ʂւƉ��������A�����瑤�͂��Ȃ�̋}�Ζʂœ������˂��˂Ƃ��˂��Ă���A���H�̗����̐X�т��[�X�Ƃ��������������B�ł����̋����͑���o���ĂقǂȂ��捏�̌����ɍ��������B���̏ォ�猧���Ƃ̍����n�_�܂ł̍��x���͕S���[�g�����炢�̂��̂������낤���B�Ăь����`���ɉH�O�ԑq�w���ʂւƑ��肾���������������A����ȂȂ��œˑR�����ɂ���f�p�ȋ^�₪�N���オ���Ă����B���̍ד��̓����ɂ����čő�̓�������Ƃ��`�����A�̂̌ÓT�̎��ƂȂǂɂ����Ă��m�Ԉ�s����ςȓ�V�����ĉz�����Ƌ�����ꂽ���̎R�������̏ɂ��āA���ۂ̂Ƃ���͂ǂ��������̂��Ƃ����z��������������ł���B
�@ ���̍ד��̖{�����ɂ��]�ǐ��s���L�ɂ��R�z���������|�̋L�q�����邾���ŁA��̓I�ɂ͂��̖��̂̋L����Ă��Ȃ��R�������́A�W�����㎵���[�g���̑�X�R�ƕW�����Z�[�g���̋��R���Ȃ��Ő��̈ƕ��ɂ�����A���̍����͊C���l��Z���[�g���قǂł���B�m�Ԃ炪���������Ƃ������l�̉Ƃ̂�������c�t�߂̊C�����x��n�}�Œ��ׂĂ݂�ƎO�A�l�S���[�g���قǂ�����A���x���͂���������S���[�g�����炸�̂��̂��낤�B���̍ד��̍s���L�^�ׂĂ݂�ƁA�m�Ԃ�͌��݂̘Z�����{���ɂ����鎞���ɁA��c������ԑ�܂Ŗ�O�\�L�����[�g���̓��̂����������ĕ����Ă���B
�@ ��c�ƎR�������ԏ\��L���قǂ̓��̂��������Ƃ����x�̒Ⴂ�Ƃ���͌��݂̐ԑq����t�߂ŁA�C���O�S���[�g�����̂悤�ł���B�������Ƃ���A�m�Ԉ�s�͍�c���o�����Ƃ��₩�ȍ⓹�`���ɕS���[�g���قǍ��x�������A���ꂩ��܂����X�ɓ�S���[�g���قǍ��x�グ�ē����z���A���ԑ�ւƉ����Ă��������ƂɂȂ�B
�@ ���ۂɎ����̖ڂŊm���߂Ă݂�������ł́A���̂��炢�̌������ƍ����̓����z����R�H�Ȃ瓖���ǂ��ɂł��������ɈႢ�Ȃ��Ƃ����̂������Ȉ�ۂ������B�ނ��A�����͂���Ȃ�ɗ҂����Ƃ���ł͂�������������Ȃ����A�n�`�I�ɂ݂�������ł́A���Ƃ����\����̂��Ƃł͂������Ƃ��Ă��A���ꂪ�z����₷��قǂɏs���ȓ�H�������Ƃ͍l���ɂ����B�������A�m�Ԃ́A�u�A�O�̊ցv�̏͂̂Ƃ���Ŏ��̂悤�Ȃ��Ƃ��q�ׂĂ���B
�@
�@ �h�̎�l�ɂ��A��������o�H�̍��ɏo��ꍇ�A�r���ɑ傫�ȎR�������ē����͂����肵�Ă��Ȃ�����A�����ē����Ă����҂𗊂݁A���̎҂̐擱�ŎR�z���������ق����悢�Ƃ������Ƃł���B����Ȃ�Ɛl�𗊂Ƃ���A���ē��ɂ͂����Ă����̗���������҂�����Ă��āA�n�̔������R�������ɍ����~�̏����ɂ����p�ʼn�X��擱���Ă��ꂽ�B��X�́A�u���������͂����Ɗ�Ȃ��ڂɑ����ɂ������Ȃ��v�Ƃ͂�͂炵�A�܂����̂����ɐh���ꂵ���v�����d�˂Ȃ��炻�̂��Ƃɂ��čs�����B�h�̎�̌������ʂ�A���̍��R�͐X�ՂƂ��Ă��Ē��̖����ЂƂ��������A�����T���Ɣɂ��Ă��邽�ߎ����̓��͂Ђǂ��Â��A�܂�Ŗ铹������Ă���悤�Ȋ����ł���B�u�_�[�ɂ��ӂ�v�Ƃ����m��̎��̈�߂����z���o���قǂɔ��Â��Đ��܂����L�l�ŁA�����̒��ݕ������ݕ����O�i���A�����n���������T�����肷�邲�Ƃɗ�⊾�Ŕ��g��G�炵�Ȃ���A����Ƃ̂��Ƃōŏ�̏��ɏo���B�ē��̒j�́A�u���̓���ʂ鎞�ɂ͂��܂��č��������Ƃ��N����̂ł����A�����͖����ɂ�����\���グ�邱�Ƃ��ł��K���ł����v�ƌ����c���A���ŋA���čs�����B���̌��t�����͖̂����ɓ������I���Ă���ł͂�����������A�����ǂ��ǂ����ĂȂ�Ȃ������B
�@ ��c������ԑ���ʂւƔ����邱�̎R����т�����قǏs���Ȓn�`�ł͂Ȃ������ɂ��Ă��A�����͂���߂Đl�ՋH�ȂƂ���ŁA�[�����т��M�n�A���R�Ȃǂ�~�������蕪�����Ȃ���i�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��������Ƃ��A�ǔ����Ȃǂ��펞�o�v���Ă��Ċ댯���̂����Ȃ������Ƃ����̂Ȃ�b�͂킩��Ȃ��ł��Ȃ��B���ہA���Љ�����̍ד��̋L�q�����̂܂����Ƃ����Ƃ�Ȃ�A�m�Ԉ�s���ʂ����R�H�͂��̂悤�Ȋ댯������ȏ��ɂ������悤�ɂ��v����B
�@ �������Ȃ���A���낢�뒲�ׂĂ݂�Ƃ��̓_�ɂ��Ă����������^�₪�����Ă���B���A�Ί����ʂ����o�R�A�q���o�ďo�H�̏M�`��V���Ɏ���k�H�O�X���́A���\����͌����ɋy���A�]�ˎ���̂����ƈȑO���牜�H�n���ɂ�����d�v�Ȍ��H�ł������B�A�O�̊ւȂǂ��݂����Ă������ƂȂǂ����̂��Ƃ��悭������Ă��悤�B�������Ƃ���A�q�A��c�A�M�`�A�V�����Ȃ����R�z���̊X���͂���Ȃ�ɂ͒ʍs�҂�����A���ݐՂ��������肵�����ł������ɈႢ�Ȃ��B�ō��n�_�ł��C���l�S���[�g�����x�ŁA�q�̒��̂��邠����̍��x�����łɓ�S���[�g���ȏ�͂��邩��A�����ɂ͓�H�Ƃ����قǂ̂��̂ł͂Ȃ������悤�ł���B����l�Ȃǂ����͂邩�Ɍ��r�������Ƒz������铖���̗��l�����ɂƂ��āA���R�z��������قljߍ��Ȃ��̂������Ƃ͂ƂĂ��l�����Ȃ����炾�B
�@ ��c�̕��l�̉Ƃ��o�������m�Ԃ�́A�V�����ʂɌ������Ėk�H�O�X����Z�L���قǐi�݁A���݂̉H�O�ԑq�w�ɋ߂����_�Ƃ����n���̂�����ō��ɕ��A�R���������z�����ԑ�Ɍ������R���ɓ��������̂Ǝv����B�n�}������Ζ��炩�����A�M�`��V���ɏo�Ă�����ԑ���ʂւƌ��������[�g���Ƃ�Ȃ������̂́A���ԑ�ւ̒��ڃ��[�g�̂ق��������قǂ̍s���ł��݁A�V����M�`���I���肸���Ƌߓ����������炾�낤�B���܂ЂƂɂ́A���ԑ痧�Ύ��̂���R�`���ʂɓ쉺���A���̂��ƍŏ�쉈���ɏM�`�A�V���̒����o�āA�������炳��ɍŏ����̎�c�ւƏo�悤�ƍl��������ł��������낤�B
�@ �m�Ԉ�s�͂Ƃ������Ƃ��Ă��A�����̍s���l���̑��̗��l�Ȃ�A�q�����c���o�Č��Ղ̗v�Ղł��������ԑ�ւƌ������ꍇ�A���R���̎R�������z���̎R�H��H�����ł��낤���Ƃ͑z���ɓ�Ȃ����A�S�̓I�ȏ��炵�Ă����̓��z�����[�g�͑����ɌÂ����ォ�瑶�݂��Ă����ƍl����̂����R���낤�B���������A�m�Ԃ炪�R�����z����I�̂��A�n������s���l�炪���̎R�����g���Ă�������ɈႢ�Ȃ��B�R�������ɂ͌��\����ȑO����n�����J���K�Ȃǂ��������炵�����Ƃ��A�܁X�ʍs�҂����������Ƃ̖T�ɂ͂Ȃ邾�낤�B
�@ ���ԑ�Ŕm�Ԃ͖剺�̐����̉��~�ɔ��܂��Ă���B�g�ԏ��l�ł������������͔��ԑ�̍�������������A���R�A�q�A��o�R�A����ɂ͐Ί��A�����ʂ̏��l�����Ƃ����������������͂��ł���B�ނ��A���ԑ�͂���Ȃ�ɉh���Ă������Ƃ��낤����A�����P���̗p�l�������͂��߂Ƃ�����ԑ�̏��l��͔��ԑ�ƍ�c�Ƃ̒��ڃ��[�g�𗘗p���Ă����ɑ���Ȃ��B�������Ƃ���A�m�Ԃ����ԑ�ɓ������邩�Ȃ�ȑO���琴���Ƃ͘A�������Ă���A��c����͂��̃��[�g���Ƃ�悤�ɂƂ��炩���ߏ����Ă����ƍl����̂����R�̂��Ƃł͂Ȃ��낤���B
�@ ���������ꂪ���ۂ̏ł������Ƃ���A�Ȃ��m�Ԃ͂����ĉ��̍ד��Ƃ����I�s���̒��ŁA���̂悤�ȑ�U���Ƃ�������L�q�������̂��낤�B���R����ɂ͂���Ȃ�̖������Ǝv����B�m�Ԍ����̐��Ƃ����ɂƂ��Ă͊��ɉ����ς݂̖��Ȃ̂ł��낤���A���̂悤�Ȃ��̓��̑f�l�ɂ͂��������C�ɂȂ邱�Ƃł͂������B���̗��R�Ȃ���̂ɂ��ꂱ��ƂƂ�Ƃ߂��Ȃ��z�����߂��炵�͂��߂����́A�ȑO�ɔq���������Ƃ̂���h�i���h�E�L�[�����̉��̍ד����e�[�}�ɂ����u���̂��Ƃ�z���o�����B�����āA�Ȃ�قǂ�͂肻���������̂��Ƃ��̔w�i�������[�������C���ɂȂ����B����Ȃ��Ƃ������āA�Ƃɂ������ꂩ�炷���ɁA��c�ɂ��܂��c��Ƃ����u���l�̉Ɓv��K�˂Ă݂悤�Ǝv���������悤�Ȃ킯�������B�u�a�l�n�̔A�i��j���閍���Ɓv�̈��Ŗ��������l�̉Ƃ�K�˂Ă݂�A�����Č֒��Ƃ��݂���L�q�������Ȃ����m�Ԃ̐^�ӂ��A�f�l�̎��ɂ��͂�����Ɨ����ł���̂ł͂Ȃ����Ƃ����C�����Ă������炾�����B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2002�N10��30��
���̍ד��E���l�̉ƍl
�@ ���̍ד��A�O�̊ւ̏͂Ɂu��R���̂ڂ��ē����ɕ�ꂯ��A���l�̉Ƃ��������ĎɁi��ǂ�j�����ށB�O�����J����Ă悵�Ȃ��R���ɐ������v�ƋL�q����Ă��镕�l�̉Ƃ́A�d�v�������̎w��������A���݂��R�`���ŏ㒬��c�Ɏc�鋌�L�H�ƏZ��ł���ƌ����Ă���B���V��̂��߁A��ނȂ��m�Ԉ�s�͎O���Ԃ��̕��l�̉Ƃɑ؍݂��A�V��̉�҂��Ă����킯�ł���B�����āA���̊Ԃɉr�܂ꂽ�̂��u�a�l�n�̔A���閍���Ɓv�Ƃ����L���Ȉ��ɂق��Ȃ�Ȃ��B�a�A�l�A�A�Ƃ������悤�ȁA�l�X�������Ƃ��������Ώە�������̂܂܂ɋ�ɉr�ݍ��݁A���̍ד��̕��͂̂Ȃ��قǂɕ��R�Ɣz�����m�Ԃ̔o�~���_�̒B�ςԂ���A�m�Ԍ����̐��Ƃ����͊F������č����]�����Ă�����悤���B
�@ �Ƃ���Łu��R���̂ڂ��ē����ɕ�ꂯ��v�Ƃ���Ƃ���́u��R���̂ڂ��āv�Ƃ͖q����A�O�̊ւ��o�č�c�Ɏ��钆�R�z���̓��������̂����A���ɏ������悤�ɖq�̒��Ɠr���̓��̍ō��n�_�Ƃ̍��x���͓�S���[�g�����炢�̂��̂�����A�����ɂ͂���قǂ̓�H�������Ƃ͎v���Ȃ��B���Ȃ�ȑO�ɉ�Ƃ̓n�ӏ~����Ɠ�l�ŁA�m�Ԉ�s�����R�z���̂Ƃ��ɒʂ����ƌ������[��̘Z�Ȃ���̌Ó����\�ܕ��قǕ����Ă݂����Ƃ�����B���̂Ƃ��́A����ȓ������X�Ƒ����Ă�����傫�ȓ����z����̂͌��\��ςȂ��Ƃ������낤�ȂƂ͎v�����̂����A���Ƃł悭�悭�n�}�����Ȃ���l���Ȃ����Ă݂�ƁA�}�Ȃ̂ڂ�̂���ȑ͍s�����̂����ꕔ�ɂ����Ȃ������悤�ł���B
�@ �܂��A���̈���f���ɓǂނƁA�m�Ԉ�s�����܂����̂́A�@�����ď������e���Șm�����݂����ȂƂ���ŁA�s���ȏ����̒��ɂ͔a���l���E�W���E�W�����Ă���A�g�̒����y���Ȃ��Ė���ǂ���̑����ł͂Ȃ������悤�Ȋ�����������B�������A���������̒��Ŏ����Ă���ʔn�������ƂŃW���[�W���[�ƕ��A����n���Ȃ̂�����A�ƂĂ������ł���悤�ȏł͂Ȃ������낤�Ƃ��z���������Ȃ�B
�@ �������Ȃ���A���̓����߂ĖK�˂Ă݂����l�̉Ƃ̂������܂��́A��ɉr�ݍ��܂�Ă���̂Ƃ͂܂�ňقȂ���̂ł������B���������A���l�̉ƂƂ͗��O���̂Əo�H�V���̂Ƃ̍���������l�̉Ƃ̂��Ƃ��Ӗ����Ă���B���ۂ̍l�ł́A�V���̍�c���̓����̏����̉ƁA�܂�A���̋��L�H�ƏZ��ł������Ƃ����Ă���B������ɂ���A���̂ƐV���̂Ƃ����ԏd�v�Ȍ��H�A�k�H�O�X���̗v�Ղ̏W���Ȃ̂�����A���̒n��a�����l�⏯���̉Ƃ�����قǂɑe���Ȃ��̂ł��낤�͂����Ȃ��B
�@ ���ۂɖڂɂ������̉Ɖ��́A�������̉����������W�P�i�Q�V�O�������[�g���j���̗��h�Ȍ����ł������B�قړ����ɂ̂т钷���`�̌����̖k�����������t����\��̏��~�����̊ԁA���̓쑤�ɂ�����쓌�����\��������~���̓���̍��~�A����̍��~�̓�������͂���~���\��̒����~�A�����āA���̊Ԃ̓����A���Ȃ킿�����~�̖k�����\���̔~���[�˂̊ԂɂȂ��Ă����B�܂��A�[�˂̊Ԃƒ����~�̊Ԃ̓����ɂ͖�\����̑��~���̊Ԃ������āA���̂Ȃ��قǂɂ͑傫�Ȉ͘F�������炦���Ă����B��������������I�Ɏg���Ă������Ԃ������炵���A�͘F���ɂ͂��̓����ԁX�ƒY����������Ă���A���R�ɐg�̂��g�܂��Ă��̂�����S���炮�����ł������B����ɁA����̍��~�A�����~�A�͘F���̂���~���̊Ԃ̓쑤�ɂ͒ʂ��̑�L���������āA���̘L���̓���̍��~�ɖʂ���ӏ��̊O���Ɍ��ւ��݂����Ă����B
�@ �ł͖��̉X�������ɂ������̂��Ƃ����ƁA���ۂɁA���h�ȑ���̂��X���O���݂����Ă����̂ł���B�\����̔~�����Ԃ̓����ɂ͖ʐϏ\�ܒi�O�\��j���䂤�ɒ������y�Ԃ������āA�����ɂ͐����p�̑��}�␅���i����˂Ȃǂ̂��鐶���p����j���̂̂܂܂Ɏc����Ă����B���Ă��̂悤�ȓy�Ԃ́A������A��A�e���Ə�A�����ۑ���ȂǂƂ��đ��l�Ȏg�������Ȃ���Ă����悤�ł���B�����āA���̓y�Ԃ̓����A���Ȃ킿�Ɖ��̍œ��[�ɁA�l�i����j�قǂ̉X����ƎO�i�Z��j�قǂ̉X������єz����Ă����̂ł���B
�@ ���������ƌĂ�Ă����ŏ㒬��т͒����ȗ��̗L���Ȕn�Y�n�ŁA�]�ˎ���ɂ͐V���˂̕ی쏧��̂��ƂɁA���m�����ɋ������p�n���Y�o���Ă����B���̏����n���ł͉��n�i�Y�n�j���e�n�ɑ���o���Ă���A�u������v�ƌĂ邻���̔n�́A�����]�˂�z�O�n���ɂ܂ňڏo����A�d�p����Ă����̂��Ƃ����B���̂悤�Ȃ킯������A���̉X�Ŏ����Ă����n�����͔_�k�p�̑ʔn�Ȃǂł͂Ȃ��A�䂪�q�̂悤�Ɉ���[����Ă�ꂽ�����n�ł������悤�Ȃ̂��B�m�Ԃ�̐������ɉ����̔n�������Ă����̂��͂킩��Ȃ����A�������ς肵�������O�̉X�ɂ�����A�����Ȃ��Ƃ��܁A�Z���̔n�̎��e���\�������̂ł͂Ȃ����낤���B
�@ �ʏ�A�ʼn��̏��̊Ԃ������~�̊Ԃ͎g�p����Ă��炸�A�܁X�X����ʂ�喼�₻��ɏ]�����ʂ̕��m�����̋x�e��h���ɋ�����Ă����炵���B���܂��܋��������Ǘ��l�ɁA�m�Ԉ�s�͂ǂ̕����ɔ��܂����̂��Ɛu�˂Ă݂�ƁA�����~�����������ł��Ƃ����Ԏ����߂��Ă����B�ŏ�̊Ԃł͂Ȃ������ɂ��Ă��A����Ɏ����Ȃ��Ȃ����h�ȏ��~���̍��~������A�a���l�����������o���Ƃ͎v���Ȃ��B�Q����āA�����Ȃ��̂ł͂Ȃ������ɂ��Ă�����Ȃ�ɐ����Ȃ��̂����ꂽ�ƍl����̂����R���낤�B�n�̔A�ɂ������ẮA���̉����͂�����ƕ����������ǂ��������^��ł���B�����~����X�܂ł͂����Ȃ��Ƃ��Z�Ԕ��i11.7m�j�͂��邩��A�����ƂŔn�����A����Ƃ����ɂ͂��悻�����������ƌ����Ă悢�B
�@ �Ƃ������������Ď��ۂɌ����K�ˁA���̉Ƃ̍\�����䂪�ڂŊm���߂Ă݂����ʁA�R�������ɂ��Ă̏��q�Ɠ��l�ɁA�u�a�l�n�̔A���閍���Ɓv�Ɖr�܂ꂽ���l�̉Ƃ͎̏����Ƃ͂����Ԃ�قȂ��Ă����炵�����Ƃ����������B���R�z���╕�l�̉Ƃ̕`�ʁA����ɂ͎R�������z���̋L�q�̂�������Ƃ��Ă��A�����Ԃ�ƌ֒����ꂽ�\���̑������Ƃ����́A���͂�f�l�ڂɂ����炩�ł������B
�@ �����Ă��̎��_�ŁA���͍Ăєm�Ԃ��Ȃ����̂悤�Ɏ����Ƃ͂����Ԃ�قȂ�L�q�������ď����c�����̂��Ƃ����^��ɗ����߂邱�ƂɂȂ����B�����Ƃ��A���̎��ɂ͂����A�m�Ԃ̐��E�ɂ��Ƃ����ɂ��������ɂ��̓����炵�����̂�����Ȃ�ɂ͔���͂��߂Ă͂����̂ł���B�^������̎����ƂȂ����̂́A�����Ԃ�ȑO�ɒ������h�i���h�E�L�[�����̉��̍ד��ɂ��Ă̍u���̋L���������B
�@ ���̍u���ɂ����āA�h�i���h�E�L�[�����́A�u�t�B�N�V�������������邩��Ƃ����ĉ��̍ד��̕��w�I�ȉ��l��������킯�ł͂Ȃ��B�ނ��낻��ɂ���Ă��̌|�p���͈�i�ƍ��߂��Ă���v�Ƃ��炩���ߒf����������ŁA���̂Ƃ��뉜�̍ד��ɂ͂������̃t�B�N�V�����̕��������邱�Ƃ���̓I�Ɏw�E���Ă݂����B�܂��A�����ɂ��ƁA����̍�i��[���䂭�܂Ő��l���A���x���蒼������Ƃ����͔̂m�Ԃ̏�ł������̂������ŁA���X�̗L���Ȕm�Ԃ̋�̂Ȃ��ɂ͑�����͂قƂ�Ǒ��݂��Ă��Ȃ��Ƃ̂��Ƃł��������B
�@ �R�`���̎R���ɂ��闧�Ύ��ʼnr�Ƃ����L���Ȉ��A�u�Ղ����ɂ��ݓ����̐��v
�͊����Ɏ���܂łɏ��Ȃ��Ƃ��O��͎蒼������A�ŏI�I�ɂ͓����̋�Ƃ͂��Ȃ��������̂ɂȂ����Ƃ������A�������ɍۂ�������̐l�X�Ƃ̕ʂ��ɂ��݂Ȃ����Z������ʼnr�Ƃ�����A�u�s���t�Ⓓ�e�����̖ڂ͟��v�ɂ������ẮA���̍ד��̗����I�����̂��ɉr�݉�����ꂽ���̂ł���Ƃ����B
�@ ���炩�Ƀt�B�N�V�����Ƃ킩��̂́A�����ʼnr�܂ꂽ�A�u���炽�ӂƐt��t�̓��̌��v
�Ƃ������Ȃ̂������ŁA�]�Ǔ��L���̑��̎����Ȃǂ����Ƃɏڂ����l���Ă݂�ƁA�m�Ԉ�s�������𗈖K�������͉J�����ŁA�t��t�����̌��𗁂тċP���Ȃǂ��Ă����͂����Ȃ��Ƃ̂��Ƃ������B
�@ �u�̊��v�̒i�ɂ́A�u�R�[���t������������Ă悤�₭�ɉh������߂�̊��̒��ɂ������A�Ȃ��Ȃ����߂Ă��炦��Ƃ��낪������Ȃ��B����ƌ������n�������Ƃɔ��߂Ă��炢�A�邪�����Ă���A�܂��m��Ȃ���������Ȃ�������Ă������v�Ƃ������e�̋L�q������B�Ƃ��낪�A���ۂɂ́A�������łɈɒB�˂̗v�`�������̊����ӂ̓��H�͏\���ɐ������s���͂��Ă��Ė����悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ������͂������A���܂����Ƃ��ق�Ƃ��͒n���̍����̗��h�ȓ@������Ƃ����̂ł���B�m�Ԃ������Ď����ƈقȂ�L�q�������̂́A�̊����ӂ̉h�Ԃ肪���痝�z�Ƃ��đz���`���Ă��������̏�i�Ƃ͈�������̂���������ł͂Ȃ��������Ƃ������Ƃł������B
�@ �����ɋP�������������Ɋ������ĉr�Ƃ�����u�܌��J�̍~��̂����Ă�����v�̋�Ɋւ��Ă��A�u�]�Ǔ��L�ɂ��ƁA�������ݎ�镢�����ɂ͏������낳��Ă��āA���ۂɂ͔m�Ԃ����͉����݂邱�Ƃ��ł��Ȃ������悤�Ȃ̂ł��v�Ƃ����L�[�����̎w�E���������B�ǂ����A���̍ד��̃N���C�}�b�N�X�̈�Ƃ��Č������Ȃ������̏�i��m�Ԃ͑z���͂���g���ĐS��œ������A���̐S�ە��i������߂Č|�p���̍������j�I�Ȗ���Ƃ��ĉr�݂������Ƃ������Ƃł���炵���B����͂���ł܂������Ƃ��������ق��͂Ȃ��悤�Șb�ł͂������B
�@ �m�Ԃ͎l�S���l�ߌ��e�p���ŎO�\�ܖ��قǂɑ������鉜�̍ד��̑S��������������̂ɌܔN���̍Ό����������̂��Ƃ����B���̗��R�́A��̕�������łȂ��A�U�������܂߂����̍�i�S�̂��A����߂Ċ����x�̍������тȂ����͎�����Ƃ��Ďd�グ�悤�Ƃ����Ӑ}�����������炾�낤�Ƃ����̂��A�h�i���h�E�L�[�����̌����������B���͂��̍u�����Ȃ���A�u����ȗ��H�ɂ����鐔�X�̎��̌����m�ԂƂ����H��̓V�˂̐S��ʂ��Ĉ�x�h���������A���ꂪ�[�����������ɂ̐S�ە��i�ƂȂ��āA�w���̍ד��x�Ƃ������Ր��̍�����i�ւƌ��������̂��v�Ƃ������ƂȂ̂��낤�Ɨ��������B���̍ד������O�ł��L�����ǂ���Ă���Ƃ����̂��A�����l������̂�����[���̂������Ƃł͂������B
�@ ���̍ד��̐����ɂ����Ď����Ƃ͈قȂ�L�q���Ȃ��ꂽ��A��U���Ƃ��v����\�����p����ꂽ�肵�Ă���̂́A�͂��߂���m�Ԃɂ͎���������������̂܂܂ɋL�q����Ӑ}���Ȃ��������A�܂����̕K�v�����Ȃ���������ɈႢ�Ȃ��\�\����̎R�������╕�l�̉Ƃ̒T�K��ʂ��āA�܂�Ƃ��뎄�͂����m�M����ɂ��������̂������B�I�s���ȂǂƂ����ƁA�Ȃɂ������������ɑ����č��������m�ɋL�q���Ȃ���Ȃ�Ȃ��悤�Ɏv��ꂪ�������A����͌���I�ȋI�s���ɓł��ꂽ��X�̏���Ȏv�����݂��Ƃ�������B���̍ד��Ƃ�����i�̋L�q�Ɏ����Ƃ̈�v�����߂邱�Ƃ��̂��̂����Ӗ��Ȃ��ƂȂ̂ł���B
�@ �ꗬ�̉�ƂƂ������̂́A�ЂƂ̌����̕��i��ڂ̑O�ɂ��Ă��̉�ƂȂ�̐S�ە��i�����肠���A������L�����o�X�ɕ`���Ƃ߂�B��۔h�̍�i�̏ꍇ�͂ނ���A���Ƃ��ʎ���`�̉�Ƃ̍�i�������Ƃ��Ă��A���͂₻��͌����ȈӖ��ł̎ʎ��Ƃ͈قȂ��Ă���͂��ł���B���̂悤�Ȃ킯������A�G��̐��E�ł͂Ȃ�ł��Ȃ����i�����Ƃɂ��Č㐢�Ɏc��悤�Ȋ����I�Ȗ��삪���ݏo����邱�Ƃ����Ă����Ȃ��Ȃ��B���̂悤�ȏꍇ�A���������G�̕��i�������̕��i�Ƃ͈قȂ邩��Ƃ����āA���̊G�̕]�����Ⴍ�Ȃ�悤�Ȃ��Ƃ͂܂������čl�����Ȃ����Ƃ��낤�B
�@ �m�Ԃ̉��̍ד��𗤉��̗����ނɂ����ꕝ�̊G���A���������߂Ċ����x�̍����G�����ꂾ�ƍl���Ă݂�Ȃ�A���ׂĂ͐����̂����Ƃł���B����́A���ۂ̗��̏o������f�ނɂ����S�ۍ�i�A�ׂ̌�����������Ȃ�A�m���t�B�N�V�������x�[�X�ɂ������̂����Ȃ��ǎ��ȃt�B�N�V�����Ȃ̂��Ƃ������ƂɂȂ�̂��낤�B�m�ԂƂ����H��́u���t�̊G�t�v�Ɉ̑�ȊG�����t�̎p���d�ˌ���Ȃ�A�����[���������Ƃ����킯�Ȃ̂��B
�@ �����������ÂсA�̐l���s�@�t�̗��̐S�ɌX�|���Ă����Ƃ�����m�Ԃ́A���̍ד��̗��H�̂Ȃ��ɐ�l�������H��K�˂��̂Ȃ���̕����╗������߂悤�Ƃ����ɈႢ�Ȃ��B�����A����Ō����ɔm�Ԃ��ڂɂ������i�́A���Ȃ炸�����ނ̊��҂ɓY���悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ������̂ł͂Ȃ��낤���B
�@ ���\�Ƃ������̐V��������̔g���A�s����X�̌i�ς�P���Ӗ��ł������Ӗ��ł��傫���ς��Ă��܂��Ă������낤���Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B����̉�X���m�Ԃ�̕������Ó��▼�����Ղ�H��Ƃ��A�̖̂ʉe�Ȃǂǂ��ɂ��Ȃ����܂�̕ϗe�Ԃ�ɒV������̂͂悭���邱�Ƃł���B����Ɠ��l�̎v�������\����̔m�Ԃɂ������Ȃ��炸�������ƍl���Ă݂�̂����R�Ȃ��Ƃł͂��邾�낤�B�������Ƃ���A���̍ד�������������ɂ������āA�m�Ԃ��I�n�S�ە��i�̋L�q�ɓO���ʂ������ƁA���Ȃ킿�A���ۂ̗���f�ނɂ������t�B�N�V�����̑n��ɐ�O�������Ƃ́A���R�̐���s���ł������ƌ����ׂ����낤�B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2002�N11��6��
���̃t�B�i�[���͉���ŁI
�@ ���q�̌Âт����ٓc������Ɉꔑ�������ƁA��ԟ[��Ŗ������S���ʉ߂��A����ɂ͗������������͋C�ƐÎ₳�Œm����H�̋{������o�R���ďH�c���̗Y�����ւƑ��蔲�����B���̂Ƃ��͂܂��G�߂��������čg�t�͖]�ނׂ����Ȃ��������A�H�̐���̍��Ɍ��邱�̈�т̌k�J�̍g�t���͑f���炵���̈��ɐs����B�m��l���������Ȃ����A�W�����S���[�g���̋S���z���鋌�����璭�߂�H�̌i�ς͕����ʂ葧��ۂނ���ł���B
�@ �Y��������͓���ւƌ������Ă���������k�サ�A����Ƃ����Ƃ��납�珬�������ʂւƑ������ɓ������B���삩�珬�����܂ł͓�\�܃L���قǂ̓��̂肾�����B
�@ �������̓��̉w�ɗ����ƁA�N�ł��������Ŏ��R�ɂ͂���銘���Ƒ����Ƃ��������B�ǂ����Ȃ�ƈ��̗���~�������Ċ����̂��镔����`���Ă݂�ƁA��x�ɓ�l���炢�͓��ꂻ���Ȑ̕��̑劘�^���D�����炦���Ă��Ă���ł͂Ȃ����B�����ɂ͋߂��̌��������Ă����������������ɂ͂��Ă���B�������������͂Ȃ��ƍl�������́A���Ɋό��q�����Ȃ������̂��������ƂɊ������Ȃ��Ȃ��ƓƐ肵�A���������قǂ悢���̂�����S�䂭�܂Ŋy���̂������B
�@ �������o��ƁA�������̍L��̎Ő��ɐQ�]�����ď��ꎞ�Ԃقǒ��Q�����A���̂��ƕ����ď\���قǂ̂Ƃ���ɂ��鏬�����̖����A�啬���K�˂Ă݂��B�������̋}�s�ȎΖʂ��W�O�U�N�ɖD��������������ƁA�قǂȂ��k�J�̒ꕔ�ɏo���B��Ղ̂�����������͍����̉��N���o�Ă���A����炪����̍ח��ƂȂ��Đ[�������Ȃ��k�J�{���ւƗ��ꍞ��ł����B�������̂������쉺�ɂ�����Ƃ���ł����ƕ��̐��Ɏ������Ă݂�ƁA���̕\�w���͂قǂ悢�������ɂȂ��Ă����B
�@ ��������㗬�����ւނ����Ă��炭�i�ނƁA�S�[�S�[�Ƃ������������Ă����B���C���Ȃɂ��������������オ���Ă��銴���ł���B�قǂȂ��A��ʂɂ��������Ɠ������������߁A�����C������̉��������悭���o���Ă���Ƃ���ւƏo���B�ԟ[��ƈ���Đ�ԂȂ���ʂ̔M���������オ��A�������̕��ւƗ��ꍞ��ł���B�e�n�̉���������Ԃ�Ƃ߂�������Ă��Ă��鎄�ɂƂ��Ă��A�[���k�J�̒f�R���猃�����N���o�邱�̂悤�ȑ啬���ڂɂ���̂͒��������Ƃ������B�啬������w���Ă���̋A�蓹�A���܂��ܓ��H�̂����e�ɓƓ��̌`�ƐF�������^�}�S�_�P�������Ă���̂��������̂ŁA������̂��ĎԂɖ߂����B
�@ ���������炳��ɒJ�����ɑk�s���A�H�c�Ƌ{��̌����ɂ�����ԎR���ʂւƌ������Đi�ނƁA�哒�Ƃ����V���ȉ���n�ɍ������������B�ƂĂ��������������͋C�̏h�����������Ă��āA���̂����߂��ɂ͌��邩��ɕ���ɕx�V�R�I�V���C�Ȃǂ���������������B�����A������ƑO�ɒ��X�Ɖ���ɂ����Ă������肾�����̂ŁA�������ɂ����͎��ӂ���ʂ茩�w���邾���ɂƂǂ߁A����ɉ��ւƌ������čĂюԂ𑖂点���B
�@ �����O�㔪���`���ɉԎR�����z���ċ{�錧���ɓ���O�ɁA���{�S���R�̂ЂƂI��R�̖k���ʂ�D���I��H�ւ̕���_�ɍ������������B���̂܂ܒʉ߂��悤���Ƃ��l�������A���������̂��Ƃ�����Ǝv�������A������Ƃ�����蓹���Đ{�쉷��܂ł̉��������݂邱�Ƃɂ����B�������z�͑傫�����̋�ւƌX���Ă������A�ቺ�͂邩�ɍL����Y��ȎR�x���i���y���݂Ȃ���I��R�k�ʂ̍����n�т���������͉̂��K���̂����Ȃ����Ƃ������B��i�ƓW�]�̂����r���̃I�[�v���X�y�[�X�ɎԂ𒓂߂ċx�e��������A�R�����ƃR�b�t�F�������o���Ă��������A�捏�̂��Ă����^�}�S�^�P����̃C���X�^���g�X�[�v�������Ĉ���ł݂����A�Ȃ��Ȃ��ɔ����őS�g�����܂��Ă��銴���������B
�@ ��ւƓ���Ƃ����ԎO�l���Ƃ̍����_�ɂ���{�쉷��܂ōs���Ƃ����ň����Ԃ��A������x�O�㔪�����ɖ߂����B�����āA���̂��Ƃ������ɍ��x���グ�A�ԎR�����z���ċ{�錧���ɓ������B�ԎR�����炷�������艺���Ă����ƁA���蓹�H�e�ɒ��ԏ�炵�������ȃX�y�[�X�������āA���̈�p�ɓ��l��������Ƃ����\���������Ă���̂��ڂɂƂ܂����B�ǂ���獶��̐[���J�̉��ɉ���h���ꌬ����炵���A�����܂ōs���ɂ͎R��������ē�A�O�\���قǂ̎��Ԃ�v����炵�������B
�@ ����������͔��Â��Ȃ肩���Ă������A���̔ӂɂ͓��k�𗧂��ē����ւ̋A�r�ɒ������肾�����̂ŁA���̃t�B�i�[��������Ӗ��ł������ꕗ�C���тĂ������Ƃ����C�ɂȂ����B�����āA�^�I���ނ̂ق��ɋA��̈Â���ɔ����ĉ����d����p�ӂ��A�[���u�i�т̉���D���ׂ��}�ȎR����`���ĒJ��̕��ւƉ����Ă������B�J��𗬂��k������������A���̌k�������ɏh�̂���Ƃ�������ق��ւƌ��������ɂ͂�����͂�������Â��Ȃ����B�r���ɖ��ӂ�閳�l�̘I�V���C������̂����������A����������Ɣ`���������ł��̂܂ܒʂ�߂��A�������炳��ɏ\���قǕ����ƁA�J���Ɉꌬ�����ۂ�ƌ������ȉ���h�̑O�ɏo���B
�@ �ˑR�̖K��ɂ��킦���������Ԃ����Ԃ���������A�h�̎�l�͂�����Ƌ������悤�ȗl�q���݂������A���������Ăق����Ɛ\���o��Ƒ���͂ɂ��₩�ȏΊ�ł��̈˗��ɉ��������Ă��ꂽ�B�m��l���m��R���̔铒�Ƃ��������̉���h�ŁA�Ɩ��p�d�͂Ȃǂ͂����������Ɣ��d�ɂ���ċ�������Ă���悤�������B���֘e�̈ē������Ȃǂ��炷��ƁA�ǂ���炷�����O�܂ł͂����郉���v�̏h�ł������炵���B���X�Ƃ�����X�����w�̓��D��Ɛ肵�A�@�̂܂���ŗ��̔����̂�т�Ɩ������Ƃ��ł����̂́A�]�O�Ƃ������ׂ��K���ł��������B
�@ �������I������h�̌��ւ����Ƃɂ������ɂ́A�ނ�܂ЂƂ��ׂ����Ƃ��������B�����d���̖�����𗊂�ɐ^���ÂȎR���������Ԃ��A�捏���������I�V���C�̂Ƃ���܂ł���Ă���ƁA���͂܂���}���ŗ��ɂȂ蓖�R�̂悤�ɂ��̓��D�ɔ�э��B������Ƃ�����Z�͒E�ߒ��}�ɉ����d���̒��q�����������Ȃ�A�^���Èł̒��œ�������������Ȃ��Ȃ������Ƃ��������A���̒��x�̂��Ƃł��܂���W�^�o�^����悤�Ȑg�ł��Ȃ������̂ŁA�Q�Ă��������[�X�Ɠ��D�ɂ���t�B�i�[���̓��Ɵ������B�����d�����g�����ɂȂ�Ȃ��Ȃ��Ă��܂������߁A�I�V���C����オ�������Ɗ��𗊂�ɍׂ��R����H��̂͏��X��V���������̂́A�Ƃ��ɗ�����������悤�Ȃ��Ƃ��Ȃ������Ԃɖ߂蒅�����B
�@ ���̍Ō�̈���́A�͂��炸������A����A�܂�����A����ł����肸�ɂ܂�����Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂������A����L���ȌI��R���ӂ̔铒�̗L�l�����̖ڂł�������Ɗm���߂邱�Ƃ��ł����̂͑傫�Ȏ��n�ł��������B�I��R�̓�Ɉʒu�����̉ԎR���𑖂蔲���Ȃ���A���̖����铒�n�ւ̍ēx�̗������ЂƂ��������悤�Ǝ��͋��̉��Ő����Ă����B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2002�N11��13��
�ɓ��A���搶�̑z���o
�@ �\���N�O�̂���ӏH�̓��̂��Ƃ������悤�ɂ������B�V�h�I�ɍ����l�K�̉�L�ɂӂ���Ɨ���������́A���̂����Ȃ�������̂���A����ł��Ă��������ɒ�m��ʑ��݊����߂��s�v�c�Ȓb����i�Q�ɑ��������B�Ñ�̑q�����Â�����Ȃǂ́A���ꂪ�S�ő���ꂽ���̂��Ƃ͐M�����Ȃ��قǂɂ��炩�����₩�ȋP��������Ă����B���̈���ɂ͂����̍�i�̐���҂Ƃ��ڂ�����������Ƃ����̋�̒��N�j����������Ă��āA��u�����������ƁA�ዾ�̉��̑o������������肩���ł����邩�̂悤�ɂ����ƌ������B�s������ǂ��l�̐S��D������������݂��ށA�Ȃ�Ƃ��s�v�c�ȋP���ɖ��������������B
�@ ���̓��͂Ȃ����q�������Ȃ��A���̂Ƃ��W���ɂ����̂͂��܂��܉�X��l�����������B�S�⓺�Ƃ�����������f�ނɂ����ꍇ�ł��A����قǂɔ��������炩�ȐF����C��������i�ݏo������̂Ȃ̂��Ɗ��Q���Ȃ���A���͉��ɕ��ԑ召�l�X�ȃI�u�W�F����ЂƂ��J�Ɍ��Ă܂�����B���̂悤�ȍs������́A���������̐��E�ɂ͂܂�Ŗ����Ȑl�Ԃ̖ڂƐS������قǂ܂łɎ䂫���ė����Ȃ��Ƃ������Ƃ́A����Ԃ������̍�i�������ɑf���炵�����̂ł��������Ƃ������Ƃ̏ł��������B
�@ ������i����ʂ�ӏ܂��I����̂��݂͂�����āA���̐���҂Ƃ��ڂ����l���́A�u�悩������ǂ����c�c�v�ƌ����Ȃ����t�̂����������߂Ă��ꂽ�B����������̐l���̐S����̂����߂������Ȃ�����邱�Ƃɂ����B�u�b���v�Ƃ������t���̂��̂��炵�ď����ɓ������������́A���m�Ȃ�ł͂̌����܂������������ƂɁA���͂����ւ�ȕ��ł����������̐l���ɂ��ꂱ��Ə����I�Ȏ���𗁂т��������B
�@ ����Ƒ���́A������̋��ɂ����Ȋ�ЂƂ������J�ɓ����Ă��ꂽ�̂ł���B�A�[���ƌĂ�����ȓS���H��Ȃǂ�p���Ĕ��������炩�ȋȖʂ�ł��o���H���Ȃǂɂ��Ă��A���ꂱ��Əڂ������������Ă��炤���Ƃ��ł����B���̓Ɠ��̌��t�̋����ɂ́A��|�ɒʂ����l�Ȃ�ł̗͂͋����Ɗm�M�̐[�����M��ꂽ�B��������̂͂��A���̐l���Ƃ́A�䂪�����w�̒b����ƂƂ��č����Ȉɓ��A�������|�p��w�����i�����������j�������̂��B����́A�܂ł܂�ňقȂ鐢�E���Ă����킽��������l�̂Ȃ�Ƃ���ȁA�������ǂ�������^���̎��̑��݂̊������Ȃ����Ȃ��o�����ł͂������B
�@ �قǂȂ����͐搶���炨�萻�̋˔������̂����ۂ݂Ղ��A���̂���ɂƂ�������������A�O���i�悵���B���Ƃ��Ɖ��˂̐g�ł����������ɁA�����łȂ��Ă����i�Ɏg���ɂ͈ꑽ���M�d�ȍ�i���Ǝv�������́A���̋�̂����ۂ݂��Ɏd���������A�ɓ��搶�̂ق��ْ͐��ɂ�������Ɩڂ�ʂ��Ă����������悤�ł���B���ꂪ�_�@�ƂȂ��āA���X���͋q���u�t�Ƃ��Č|���w�@�̔��p���猤���Ȃɏo�����A�F�m�Ȋw��Ȋw�N�w�A�R���s���[�^�T�C�G���X�W�̏������e�[�}�ɂ����₩�ȍu�`�Ȃǂ�����悤�ɂȂ����B�����A�������瓯�����e�̍u�`�͂��Ȃ��Ƃ������Ȃ�̕��j���т��ʂ������Ƃ������āA�̂��ɂ͍u�`���e���\���_�⋳��_�A����ɂ͕��w�_�ɂ܂ōL�����Ă����L�l�ƂȂ����B
�@ ���p�̐��E�ɂ͂܂����������ł����������A�|��Ƃ������{�̌|�p����̒��j�Ɉʒu�����w�Ɋւ��������Ƃ��ł����̂́A�ЂƂ��Ɉɓ��搶�̂������ł���B���o�����b����Ƃł���������łȂ��A�����ւ�D�ꂽ����҂ł�����ꂽ�搶�̐^���ȋ��痝�O�ɋ������A���͂Ȑg�Ȃ�����ł��邩����̋��͂͂����Ă����������ƌ��ӂ������́A�W���u�`�Ƃ�������ȏ������ł͂���������ǂ��A���̂�̔\�͂̂������s���Đ��S���Ӎu�`�������Ȃ����ƍl�����B���p���猤���Ȃ̎�C�����ł��������ɓ��搶�͂���Ȑق����̍u�`���@�������ƈꏏ�ɖ��u���Ă������������̂ł���B�{���̐�啪��̍u�`��ʂ��Ċւ���Ă�������܂ł̑�w�Ƃ͂�����_�ňقȂ�|��ł̍u�`�o���́A���ɂƂ��Ă������ւ�M�d�Ȃ��̂ƂȂ����B
�@ �I�ɍ����ł̏o���������N�قnjo���Ă���̂��Ƃ������Ƃ��������A���͐܁X��ʌ����R�s�ɂ���H�[�ɂ��ז����A�ɓ��搶�̓Ƒn�I�Ȃ��d���̂ЂƂł������ؖڋ��i�����߂��ˁj�̍�i����H���Ȃǂ��Ԃ��ɔq�������肷��悤�ɂȂ����B�܂��搶���X�̂����߂Ȃǂ������āA���鎞����͏����I�Ȓb����i����ɒ��킷��悤�ɂ��Ȃ����B�܂������̑f�l�̐g�����̓��̑�搶�̍H�[�̐^�����̂��A���葫���̎w���̂��Ƃŋ�t����������킯������A�Ȃ�Ƃ�����ʂĂ��b�ł͂���B
�@ ����߂��́A���Y��Ŏ��������V���Ђ���˗����ꂽ�Г��e�j�X���p�̑��t����ł������B���͂ЂƉċ��R�̍H�[�ɒʂ��l�߂Đ搶�̍��Ȃ��w���������Ȃ��痧�h�ȑ��t�������������B���̕��䗠�̎�����������Ă����ƁA�\�����͎��̍�ł��������炢�͈ɓ��搶�̎�ɂȂ���̂���������A�����������t�������ȏo���h���ł��邱�Ƃ͓��R�̂��Ƃ������B���̑��t�����Ɋւ��Ă͂`�h�b�̌����j�m�L���X�^�[���ꖇ����ł��������ƂȂ̂ŁA���Ԃ̂�����͎��̃o�b�N�i���o�[�������t�Łu�M�̒��v1999�N8��4���t�������Q�Ƃ��Ă������������B
�@ �Ȃ�Ƃ��c�O�Ȃ��ƂɁA�ɓ��A���|�勳���͂��܂���l�N�O�̕����\�N�\�A�ʋΓr���̓d�Ԃɂ����ăN�������o���œ|��A���̂܂܈ӎ������邱�Ƃ��Ȃ����E���ꂽ�B�����搶�͕����Ȃ̋���J���L���������ϓ��ɂƂ��Ȃ����p�H�|���ȊW�̑�\�ψ��߂Ă���ꂽ���A�ꕔ�ɂ͔��p�H�|���ȕs�v�_�̂悤�ȋɘ_����������Ȃ��ŁA�����Ȃ̖�l�⑼���Ȃ̊W�ψ���������̕s����ȐՂ�Ή��ɂ����Ԃ�Ƃ���J�Ȃ����Ă���l�q�������B�w���O�ɂ킽��ߓx�Ȍ����ɒ[����ɓx�̃X�g���X��ߘJ���}���̌����̂ЂƂ��Ɛ��@����邾���ɁA���܂��Ȃ��r���S�c��łȂ�Ȃ��B
�@ ���E�Ȃ���ꃖ���قǑO�ɍH�[�ɂ��f�������Ƃ��̂��ƁA�搶�́A�u��w��ފ����A���܂̂��̖Z�������������ꂽ��̋��̍����ɖ߂��ăA�g���G���\���A�S��y���݂Ȃ��玩�R�̂őf�ނƌ��������A�悢��i�肽����ł���B���܂͂��̓�������������������Ă���邱�Ƃ�S�҂��ɂ��Ă����ł��B���̎��͎l���ɗ��āA�搶����i����ɋ����Ă��������v�Ƃ������t�����肰�Ȃ��R�炳��������B���Ԃ�͐搶�̋U��ʐS���ł������ɈႢ�Ȃ��B������A���܂�ɂ��ˑR�̈ɓ��搶�̂������́A���ɂƂ��ėB�X�Ռ��̈��ɐs�����B
�@ ���݁A���̈ɓ��搶�̈��W�u�b���E�ɓ��A���̐��E�v�����̓����|�p��w���p�ْ�قŊJ�Â���Ă���B���W�͍�����\�l���܂ł̗\��ŁA���ꗿ�͖����ƂȂ��Ă���B�搶�͕����V�c���ʂ̋V���ɕK�v�ȋ���p��̐���ɂ��g���ꂽ�B�܂��ؖڋ��i�����߂��ˁj�̍�i����Z�p���͂��߂Ƃ��邻�̓Ƒn�I�ȋ��H�Z�p�͊C�O�ɂ����Ă������]������Ă����B���ɂ͐搶�̐��U�ɂ킽���\�씪�\�_�قǂ��W������Ă���̂ŁA���̋@��Ɉ�l�ł������̕��X�ɂ��̌����ȍ�i�Q���䗗���������������̂��Ƃ������B���炩�ȃ��C����Ȗʂ���̂Ƃ����ӔN�̍�i���f���炵�����A�Ñ�_�b���e�[�}�ɂ����Ⴂ����̋S�C�����i�Ȃǂ����Ɋ����I�ł���B���܂͖S���ɓ��搶�̌��т��̂��A���̂���u���㐢�ɏ����p���Ӗ��ł��A���̈��W������������߂邱�Ƃ�S�������Ă�܂Ȃ�����ł���B
�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����\�l�N�\�ꌎ�\�O��
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2002�N11��20��
���̃{�N���H�̑�g�ɁH
�ߓ��A���Q���L�������珼�Y�r�꒬���ȉ��O���̕��X���㋞���ꂽ�܁A�������̗v���������Ă������s�Ƃ�������k����@��������B�����肷�����ȑO�ɁA�L�����ł́u�H�̑�g�v�Ƃ������̑ΊO�L����ʑ㗝�l�݂����Ȃ��̂�C�����邱�ƂɂȂ�A���̌��̈�l�Ɏ����m�~�l�[�g�����̂ŁA���̍ۂ��ЂƂ�������Ăق����Ƃ����Őf���������B
���̂Ƃ��̘b�ł́A������l�̌��҂̓G�b�Z�C�X�g�ŗ��������ƂƂ��Ă��������{�Ԑ�}�q����ł���Ƃ������Ƃ������B�{�Ԑ�}�q����͐H�Ɋւ���L���Ȑ��Ƃł������邩�甒�H�̖�������͓̂��R���Ƃ��Ă��A���X�e�H�ɊÂĐ����邱�̎��̂ق��́A���悻�H�ʂɂ͒��������݂ł���B������d�b��ʂ��đ�g�A�C�̑Őf���������Ƃ��A�ǂ��l���Ă݂����Ă��̐g�ɂ���ȑ�������܂�킯���Ȃ����낤�ƁA���������˘f�����o������肾�����B
���Ƃ��H�̑�g�Ȃ���̂ɏA�C�����Ƃ��Ă��A�������������ǂ�Ȃӂ��ɂ��Ȃ�����悢���̂��F�ڌ��������Ȃ��B���̂ւ�̂��Ƃ����ɖ₢���킹��ƁA�u�܂��[�A����܂����l���Ȃ��œK���ɂ���Ă�������Ό��\�ł��B���������ł��A�K���ł����ł�����Ɂc�c�v�Ƃ����Ȃ�Ƃ��v�̂Ȃ��Ԏ��Ȃ̂ł���B�u�K���ł����ł�����Ɂv�ƌ����Ă��Ȃ��ƁA������̂ق��͂܂��܂������������ł��܂����肳�܂������B
�����܂��A�u�����͍L�������Y�̍���賏\�H��賓��̖��X�Ђ��\�p�b�N�𑗂��Ă��������B�����͐��k�͔|�̑嗱�C�`�S��\�p�b�N���A������ɂ͖��Y�ő��u�Q���v���O�\�p�b�N���肢���܂��B���̎����̓��ɂ͕r����ǎ��E�R�������\�ƁA���̔��Q�̖��̗M�q�|���|�ƗM�q�����̋l�ߍ��킹�w�䂸�̗��x���\�Z�b�g�قǂ��͂��肢�����ł��˂��B���������A�����_�@�Ő��Y������̔������Ă��Y��Ȃ��ł��炦��Ί������ł��B���ꂩ������ЂƂA�S�k���R�����\�{�قǁc�c�B�{�N�͐H�̑�g�Ȃ�ł�����A�������A�݂�ȑ���Ƃ������ł��肢�ł����ł���ˁI�v�Ȃ�Ă��Ƃ��ł���Ȃ�H�̑�g�������͂Ȃ����A����ł͉��H�̑�g�ǂ��납���E�̑�g�ɂȂ��Ă��܂��Bዂ��Ă��͂�Ă��ǂ����̍��̈ꕔ�̊O�����݂����Ȑ^�������͂������Ȃ��B
����ɁA����Ȃ��ƂɂȂ��Ă��܂�����A�L�����͔j�Y���Ă��܂��c�c���ĂȂ��Ƃ͂܂��Ȃ���������Ȃ�����ǂ��A�l�I��������ӔC���Ƃ����킯�ŁA�����ȉ��̊W�҂����Ă����ł͂��܂Ȃ����Ƃ��낤�B�����Ŗ������l���\��̌����͐�L����Ȃǂ́A���̔��ςŒm���閼�������Ă��܂����Ƃɂ��Ȃ�B
�L����������H�̑�g�ɔC�����悤�ƍl�����̂́A���́u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v���͂��߂Ƃ��邢�����̃��f�B�A�ŁA�����̎��R����l�X�ȕ����A�Y���Ȃǂɂ��ĂȂɂ��ƏЉ�����Ƃ�����������ł���炵���B�L������賃v���W�F�N�g�����賗Ⓚ���H��̋Z�p�ږ�߂�e�����m�l�A�O���m����̎�莝������������̂��̂Ɣ��[�ł͂������B
������������^�v�[�����j������Ă���悤�Ȃ��̕s�v�c�Ȑl���̑劈��c�c�Ƃ������͂ƂĂ��Ȃ����������i�H�j������t���A�L�����͌��\�L���ɂȂ�A����賃v���W�F�N�g��賗����A賎��Ȃǂ͒����V���̓y�j�ła����m�g�j�̋���e���r�Ȃǂł��Љ��A�����ɍL���m��n��Ƃ���ƂȂ����B
���̎O���m�Ƃ������l���A���ď������쏊�Ȃǂɂ��Ζ����A�����ւ�D�ꂽ�d�������Ă������ƂȂǂ�����̂����A���̂����ƈȑO�ɂ͓������牫��̐��\���ɈڏZ���Ė{�i�I�ȋ��t�ƂȂ�A���̂�����疯�h�̌o�c�Ɍg����Ă������B�����ł͐����Ȃ��X�L���[�o�_�C�r���O�̏㋉���ۃ��C�Z���X�̎�����ŁA�V�l�_�C�o�[�̗{���ɂ��s�͂��Ă����炵���̂����A���������ǂ��łǂ�����ă_�C�r���O�X�N�[���̐��k����w�����Ă������̂Ȃ̂��A���܂��Ɏ����D�ɗ����Ȃ��B���̐��̂ǂ����ɂ������E�C�X�L�[�łł����閧�̑�C�������āA���Ԃ��Ń_�C�r���O�̋ɔ�w���������Ȃ��Ă���̂��낤�B
����A���̕��Q�L�����܂��ܓǂƂ������Ă̋����q�����[��������A�u�O������͎��̃X�L���[�o�_�C�r���O�̐搶�ł����v�Ɠ`���Ă��Ă��ꂽ�Ƃ��납�炷��ƁA�ŔɋU�肪�Ȃ����Ƃ����͊m���炵���B���x���̋����q�Ɖ�@��ł���������A����̃X�P�W���[���̂����A�_�C�r���O�̎w�����ԂƃA���R�[���̎w�����ԂƂ̊������ǂ��Ȃ��Ă����̂����܂߁A���̏ڂ�������Ȃǐq�˂Ă݂邱�Ƃɂ������Ƃ������B
���\���Ɉڂ苙�t�ƂȂ�O�́A�Ȃ�Ɠ��{�J����s�ɋΖ�����D�G�ȃI�y���[�V�����E���T�[�`�̃X�y�V�����X�g�ŁA���ܘb��̒|���������Z�S����b�͂��̓����̓����������B�O������̌������Œ|����b�͎t���߂Ă����Ƃ����̂�����͘b�͂܂��܂���₱�����B�u�������A�m�����v�ƌĂэ������͂��̌�������Ƒ����Ă����炵���̂����A������A�u���͔��m����b���v�ǂ���ł͂Ȃ��u���͔��m����b���v�����łɌ����̂��̂Ƃ��A�����ۂ��͂Ƃ����ƁA�u���̓A�������Ђ��v�̓�����}�i���Ƃ��Ă���B���̃M���b�v�����������ǂ��l������悢���̂Ȃ̂��낤�B
�|����b���a������ȑO����A�O������́A�u�������͐l�ԂƂ��Ă͂ƂĂ�����������ǁA�Ȃ�p�w�҂�����A�ނ̌o�ϊw�͂�����A������ł���v�ȂǂƁA�悭��k�܂���Ɍ��������肵�Ă������̂��B���̂Ƃ���A���̌o�ϐ��Ȃɂ��Ɣᔻ�𗁂сA�l�ʑ^�̋C���̒|�������A���̐����s�ɏI������肷��悤�Ȃ�A����͂��̎O��������s���`�q�b�^�[�ɓo�p������ǂ����낤�B�A���R�[�����̓Ђ���o�ϐ���͈ӊO�Ɍ���t���邩������Ȃ��c�c�ł��܂��A���̒��������܂��͂Ȃ����c�c�B
�P�Ȃ�A���R�[�����ł�Ђ�����ǂ��Ȃ�A�����Ԃ�ė��ŐQ�悤���g����݂�����悤�����͂��m����ŕ����Ă����̂����A�ւ�ɂ��낢��ȍ˔\���������肵�A���ꂪ�܂����\���̒��̖��ɗ������肷����̂�����b�͂Ȃ�Ƃ����Ȃ̂ł���B���̂܂ɂ��A���������L�����̖��_�����ɂ����܂����肵�Ă���̂��A���̌��g�I�Ȏd���A���⌣��I�Ȏd���Ԃ肪�����]������Ă̂��ƂȂ̂ł��낤�B�{�Ԑ�}�q����Ǝ��Ƃ��L�����́u�H�̑�g�v�Ƀm�~�l�[�g���ꂽ�w�i�ɁA���̋K�i�O�̖��_�����a�̂����Ȃ���ʖz�������������낤���Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B
���ł����珑���Ă����ƁA�V����Ƃ̂��̎O��������A�ǂ����{�Ԑ�}�q����ɂ����͓����オ��Ȃ��炵���B�O��s�ɂ���{�Ԃ���̂��Z�܂��͎O���@�Ɨאڂ��Ă��āA�O�������N������������A�{�Ԃ���ɂ͉����ɂ��Ă����b�ɂȂ��Ă����炵���B������A�ǂ�Ȃɐ����ς���Ă��Ă��A�{�Ԃ��u�O���N�I�v�ƈꐺ�����������Łu�͂����I�v�Ƃ���ɒ����s���̎p�����Ƃ肩�˂Ȃ��قǂ̌X�|�Ԃ�Ȃ̂ł���B�{�Ԃ���͂����ւ�Ȑ�҂Ŏ��Ɉ߂𒅂��ʕ��������Ȃ��邤���ɁA���̍L�������ɗ��ł����ꂽ���l���⑶�݊������Q�Ƃ��Ă��邩��A����łȂ��Ă��O�����h�ӂ��͂炤�͓̂��R�̂��Ƃł͂���̂��낤�B
�Ƃ����������A���̂悤�Ȃ킯�ŁA���ǁA���͍L�����̐H�̑�g�Ȃ���̂�������������͂߂ɂȂ����B�u��g�v�ł͂��������ׂ��d������ǂ��A�܂��u���g�v���炢�Ȃ�Ȃ�Ƃ����܂邩������Ȃ��Ƃ����������������Ă̂��Ƃ������B���܂ЂƂɂ́A���Y��������t�ے���A������W�҂̂��������̂Ԃ����Ƃ���̂Ȃ������I�Ȃ��l����A�悻�҂ɂ��D�����������L�����̊F����̒������ɓq����M�ӂ̂قǂ��A����܂ł̖K���ʂ��Ď����g�ɂ��قǂɊ����Ƃ��Ă�������ł��������B
�O������ɗU���ď��߂čL�����̒n�Ƃ�����A���͂��̒��̂��Ɠ��̋�C�̂悤�Ȃ��̂����Ă����B���R����w�i�ɂ����Â��`�������ւ̌h�ӂ̔O�ƌ����I���v������ʐi��̋C�s�Ƃ��o�����X�悭�������A�s�v�c�Ȓ��a��ۂ��Ă��邱�Ƃ��Ȃ�Ƃ���ۓI�������̂��B���̂��Ƃ͂܂��A���̒n�̐H�����ɂ��F�Z������Ă���悤�ɂ�����ꂽ�B���Ԃ�A����́A�אڂ���F�a���s�ƂƂ��ɋ��F�a���˂̓��قȗ��j�ƕ������p���L�����Ȃ�ł͂̂��Ƃł�����̂��낤�B��͂Ȃ����ɉ��l���܂�Ŏ������̗����炿�̂��̎����ɉ����ł���̂͂��܂��ɋ^��Ȃ̂ł͂��������A�{�Ԃ������g�����������ɂȂ�Ƃ������Ƃ������̂ŁA���͂��̐��s���ɂł��ƍl�����悤�Ȃ킯�ł���B�i���T�ɂÂ��j
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2002�N11��27��
�Ȃ�Ƃ܂��_��w�̌䕪�g���I
���Y�r��L���������s�Ɗ��k���������A�{�Ԑ�}�q����Ǝ��Ƃ͊z�����ꂽ�H�̑�g�̔C���؏�����蒼�ڂɎ��^���ꂽ�B�傫�Ȋz�ɓ������㎿�̘a�����̏؏��ɂ́u�Ɛ����̒��A�S�k�̗��A�L���̐H�����ɑ��w���[���A�H�ɐ��ʂ���Ă���M�a�Ɂw�L�����H�̑�g�x�̏A�C�����肢�v���܂��v�Ƃ����ꕶ���n�����Ă������B�؏��̏���ɂ͓������Y��賂̊G���`���Y���炦�Ă������B
�ߋ����x���L������K�˒n���̐V�N�ŖL�x�ȐH�ו��ɐ�ۂ�ł����͎̂��������A�u�H�����ɑ��w���[���A�H�ɐ��ʂ���Ă���M�a�v�Ƃ������ƂɂȂ�ƁA����͂����Ԗʂ��̂ł���B�����A����ł��A�u�H�v�̎����u�F�v�ɕς��A�u�F�����ɑ��w���[���A�F�ɐ��ʂ���Ă���M�a�v�Ǝ����グ��������͂邩�Ƀ}�V���Ƃ͂��������̂ŁA�Ƃ肠�����͂��̂��Ƃɂ͖ڂ��ނ��Ă������Ƃɂ����B�����āA�^�̈Ӗ��ōL�����̐H�����ɐ��ʂ���悤�ɍ��シ�����͓w�͂��悤�Ƃ��l�����悤�Ȃ킯�������B
�H�̑�g�̔F�菑�ƂƂ��ɔ�����̗��h�Ȟw�̒u���Ƒ傫�Ȟw�̕\�D��ꂽ�̂����A���������Ƃ����̕����i�͂����ւ�Ȉ�i�������̂ł���B�Ɠ��̖F�������������̞w�A���傻����̂����̞w�Ƃ͂킯��������̂��B���悳�ꂽ���̞w�̒u���ƕ\�D�ɂ͈����N���s�̒n�����A�F�a���V���̗[���L���̃R�s�[�ƒn���Ȋw�������̍쐬�����N�㑪�茋�ʕ\�Ȃ���̂��Y�t����Ă����B
�u�}�j�A���̂ǂ���肪�c�c�_��w������v�Ƃ������o���Ŏn�܂邻�̗[���L���ɂ��ƁA���̔N�A�L�������̓c��ڂ̒n���ꃁ�[�g������l���[�g���̒n�����A������E�܃��[�g���A���a�Z�\�Z���`���[�g���ƁA�����Z���[�g���A���a�l�\�܃Z���`���[�g���̓�{�̌Â��w���������ꂽ�̂��Ƃ����B�����҂͓����ōH���X���c�ސ��Ɩ���ŁA�O�N�O�ɂ����l�̖��������Ă������Ƃ���A�t�߂�T���Ă����Ƃ̂������ł������B�L���̎ʐ^�ɂ͔������ꂽ�_��w�ƁA���̑傫�ȍ������̕����Ɏ�������ė����Ɩ���̎p���ʂ��Ă������B
�������l�S�N�ȏ�Ƃ��������̞w�͓V�ЂȂǂ̉e���ł�������ɓy���ɖ��܂��Ă��܂������̂��낤�Ɛ�������A�����𑽂��܂ޔS�y���̓y��̂������ŕ��邱�ƂȂ�����܂Ŏc���Ă������̂炵���Ƃ������B�܂��A���������A�\�ʂ���[���O�Z���`���炢�܂ł̕����̓X�|���W��ɂȂ��Ă������A�c�̕����͌��łȂ܂܂Ő����F�����Ă���A���܂��w���L�̍��������Ă���Ƃ��L����Ă����B�����āA�����ꂽ�N��͂͂����蕪����Ȃ����̂̑����ɌÂ����Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��A�}�j�A�����̒��i�����ɁA���Ɏg���̂������Řb��ɂȂ��Ă���ƌ���ł��������B
�Ȃ�ƁA���ɑ���ꂽ�w�̒u���ƕ\�D�͂����̋M�d�Ȑ_��w�ł���ꂽ���̂������̂��B���Ɏg���̂��Ƙb��ɂȂ�A�}�j�A�����̓I�ł������Ƃ������u���i�w�l�v�̌䕪�g���A���Ƃ����낤�ɂ��݂̂��ڂ炵���䂪�Ƃɒ����܂��܂����Ƃ����̂�����A����͂��������ւ�Ȃ��Ƃ��ƌ����ق��Ȃ������B
���̂悤�ɍd���ł܂������̞w�̌Ö̕\�ʂłȂ���A���������ǂ̂��炢�o���Ă���̂��낤�Ƃ��ꂱ��z�����߂��点���B���ꂩ�炨���ނ�ɒn���Ȋw�������ɂ��N�㑪��f�[�^�\���J���Ă݂��B�����ɂ͕��ː����ʌ��f�J�[�{��14�̔�������p�����N�㑪�茋�ʂ��L����Ă����̂����A���̐��l�ɖڂ���������͋����̂��܂�v�킸����ۂB
NO.1�Ǝ����ԍ��̂Ă���w�̐��炵�͂��߂�����̐����N�オ�Ȃ�ƋI���O����Z�N�A������NO.2�̎����ԍ��̂����w�̂ق������炵�͂��߂�����̐����N��͋I���O�ꎵ�O�ܔN�A�N�㐄��덷�̓v���X�E�}�C�i�X���\�N�ƋL�ڂ���Ă��������炾�I
���N���I����Z�Z��N������A���܂���O���S�\��N�O�ƎO�玵�S�O�\���N�O�̞w�Ƃ������ƂɂȂ�B���炩�̗��R�łǂ���̞w���������ɒn���ɖ��v�����炵���Ƃ������茋�ʂ����L����Ă����B�_��w�Ƃ����\�����������ăI�[�o�[�łȂ��قǂ̌Ö������Ƃ����킯�Ȃ̂��B���܂��炨�悻�l��N�O�Ƃ����A���{�̓ꕶ����̌���ɑ������Ă���A�G�W�v�g�ł͒������̉h��������A�����ł����Οu�����̐����ɉ��S�N���旧������̐������ɂ������Ă���B
�w�̒u�������Ԃ̈�p�ɐ�����ƕ��������ς��ɖF�������肪�Y���͂��߂��B�Ȃɂ��l��N�߂��ȑO�̍���A��萳�m�ɂ����u����̉��v�Ȃ̂ł���B�S�g�̔畆�̂�����Ƃ��납��̓��[���ɂ��݂킽��悤�Ȃ��̍���ɕ�܂�Ȃ���A���͂܂����̞w���t��ɂ点�Ă������̉����̂ɑz�����߂��点���B���̖��@�̍��肪����ꕶ����ւƏu�Ԉړ������Ă����̂ł͂Ȃ����Ƃ����C���ɂ����Ȃ��Ă����B���̐_��w���������蕪���ă}�j�A�ɔ�������Ќ��𗽂����Ƃ��ł��邩�ȂȂǂƂ����n�R�l�̌Ƒ��ȑz���́A���̐_���ȍ���ɂ���Ă����܂�����A���X�̑ӑĂȐ����Œo�݂͂Ă��S�g���Ȃɂ��s�[���ƈ������߂Ȃ�����銴���ł��������B
�������傫�ȕ\�D�̂ق��������ւ�ȑ��݊���Y�킹�Ă����B�ނ��A�܂����O�͕\�L����Ă��炸�A�����ōD�݂̕������L�����荏�肷�悤�ɂȂ��Ă����̂����A����ɂ���Ȃ��Ƃ���낤���̂Ȃ�A���̌y�����O�ȂǕ\�D�{�̂̕��Ќ��Ɉ��|����A�����܂��������ł��܂������Ȃ������������B���̕\�D�̂ق��͂��܂����悳�ꂽ�Ƃ��̂܂܂ő�ɕۑ����Ă���̂����A����ɂȂ�Ƃ����܂������̖��O���L���Č���ɂɊ|���邱�Ƃł��ł���悤�Ȃ�A���̌䗘�v�ƌ�Ќ���w�ɉ���N�����������邱�Ƃ��ł邩������Ȃ��B
�ł��܂��A�܂���Ԉ���Ă���Ȃ��Ƃɂł��Ȃ����肵����A���f����̂͐��̒��̂ق�������A�����͌Ȃ̕��ۂ��킫�܂����d����̂���Ԃ��낤�B����łȂ��Ă��A���܂��̍��ɂ͘V�X�Ƃ����\�����҂�����̊���p���������݂����ȘV��c���Ȃǂ����āA�ŋC��f���Ȃ���傫�ȑԓx�Ő��E����������������Ă���̂�����A����ȏ�̘V�Q�͍��̏����ɂƂ��Ė��f�疜�Ȃ��Ƃ��낤�B�������ގ��ɐ_��w�̕��F�������q�m�L�`�I�[�����L���Ȃ獑��ɐ_��w�̒u���������ɂ�����͂������Ƃ��낾���A����������������ł͂Ȃ�����n���������B�ٌ`�蕨�ɂ��̎肱�̎�ł��˂��˂Ɨ����Ɋ��������̘A���́A�_�㓡���_��ӂ݂����Ȃ��̂��o�b�N�{�[���ɂł����Ă���̂��낤���B
����A���삳��Ƃ����L��������Ζ��̏����E�������S�ɂȂ��ăf�U�C�������u�H�̑�g�v�̖��h���茳�ɓ͂���ꂽ�B����܂œ�A�O�x����������Ƃ�����̂����A���삳��͂����ւ�ɃZ���X�̂�����ŁA�L��������ɂ����ẮA�����Ȃ�ł͂̂��܂₩�����������A���s���S�̗̂�����I�݂ɒ����R���g���[�������E�ɏA���Ă���B
���̖��h�͋ߔN�͂��̃g���p�����i���̊G�����j�������ăf�U�C�����ꂽ�Ȃ��Ȃ��������V�����m�������B������Ɂu�H�ׂ�v�u�b���v�u����v�Ƃ����Ӗ���\�킷�l�`�͗l�̎O�̃g���p�������傫���z����A���������ɓ������\��̃g���p���������ׂ��Ă���B���̕����̈Ӗ�����Ƃ���́A�u�̎R�A��̐��A�������y�n�A�����łƂꂽ��A�ʕ��A賂Ȃǂ̐H�ށ\�\�����L���Ȏ��n���̖���`���A�����̐H��v�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃł���炵���B�������A�L�����̃C���[�W���g���p�����ŕ\�킵�����̂ŁA�����\��̃g���p�����̈Ӗ��͖��h�̗��ʂɒʏ�̕����ŋL����Ă������B
�܂����h�̕\�ʂ̈�ԉ��ɒʏ�̕����ŁA�u���Q���L�����H�̑�g�E�{�c���e�v�ƋL����Ă���A���ʂ̂��Ȃ����ʼn��i�ɂ����������u��798-1395�@���Q���k�F�a�S�L�����厚�߉i800�Ԓn1�L��������_�щ� 0895-45-1111�v�ƘA���悪������Ă����B�ނ��A���͂��̕��ς��Ȗ��h���ƂĂ��C�ɓ������B���Ԃ�A�{�Ԑ�}�q����������ł͂Ȃ����낤���Ǝv���B�ǂ����Ȃ�A���̌��������u�H�̏��g�v�Ƃ��u�H�̘Q�m�v�Ƃ����Ăق��������B�����\�L����Ă���������ƋC�ɓ������ɈႢ�Ȃ��B
�e��p�[�e�B���̂悤�ȑ吨�̐l�����ނ낷�Ƃ���֑����^�Ԃ̂͌����D���Ȃق��ł͂Ȃ��̂����A��ނȂ����Ă��̂悤�ȏ�Ɋ���o���@�����Ƃ��ɂ͂��̖��h���g�s���A�u�H�̏��g�v���炢�̖����͉ʂ��������Ǝv���Ă���B�L�����̓��Y�����̑��ɊS�̂�����͑O�q�̔_�щۂɖ₢���킹�Ă��悢���A�����̓��̉w�ɂ���L�����̕��Y�W���̔��{�݁u�X�̎O�p�ڂ����v�ɃA�N�Z�X�������̓I�ȏ��������邵�A���i�̒����Ȃǂ��\�ł���B
�Ⓚ賁A賂̖��X�ЁA賃X�[�v�A賎��̑f�A���k�͔|�̑嗱�C�`�S�A�S�k���R���A�E�R���y�уE�R������e����H�i�A�S�k�āA�����_�@�āA���Y�ő��u�Q���v�A���I�f�ނ����Ƃɂ����M�q�|���|��M�q�����A�e�퐶�N��ؗށA����ɂ́A�����̉Ԃ�؍H���i�ނȂǐH�i�ȊO�̓��Y���\�\������̕i���n���̐l�X���O�����߂Đ��Y�������̂ł������łȂ��A���̔̔����i�������ւ�ǐS�I�ł���B
�L�����̏��Y�r�꒬���́A�u�L���̓��Y���̔��{�݂ł͐�ɖ{����������Ȃ��悤�ɂ��܂��B�{���������������悤�Ƃ���ƁA���ɂ͂Ђǂ������s���Ɋׂ��Ă��q�l�ɖ��f�������邱�Ƃ�����܂��B�ł������őË����A�ꎞ�����ɒn���̏����Y�i�ł͂Ȃ��܂������𗬒ʂ������肵����A���ǐM�p�𗎂Ƃ����ׂĂ��䖳���ɂȂ��Ă��܂��܂�����c�c�v�Ƃ��̌��ӂ̂قǂ�����Ă���ꂽ�B���������̂��̌��t�ƔM�ӂ̂قǂ�M���A�����₩�Ȃ�����L�����Љ�̂���`�������Ă����������̂��Ǝv���Ă���B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2002�N12��4��
�D���������A
����Lj��^���܂������I
���݂������ӏH�̐�̉��A�������������Ђ����琼�ւƎ������鎄�̋C���͐���₩�������B�{�����甪���q�A���͌A�匎�ƌo�čb�{�~�n�ւƌ������ԁA�Ƃ�����ԑ�����Ɏp��������x�m�͐V���Ղ��ď����ɋP���A�Ȃ�Ƃ��_�X��������ł͂������B�������߂��b�{�~�n�ɓ���ƁA�O���ɓ�A���v�X�A��̔����s���Ő�����������ƕ����яオ��A�E��ɂ͘A�ȂƂ�Ȃ钁���A��̎R���݂��ւ炩�ɂ��̗̈e������킵�͂��߂��B
��C�̐��ӏH�Ƃ����ǂ��A����قǂɂ͂�����Ɖ����̎R�X�߂邱�Ƃ��ł���̂͂߂��炵���B����ɔ��P�O�R��b���P�x�̐藧��X���A�E��ɂ͂ǂ������珗���I�Ȋ����̂��锪���x�������Ȃ��珬�����ʉ߂���ƁA�z�K�Ε��ʂɂނ����Ă�������ƃA�N�Z���ݍ��B����s�t�߂܂ł�����ƁA�����قǂƂ͈Ⴂ�����x�A��𐼑�����]�ނ��Ƃ��ł���悤�ɂȂ������A�����炩��ڂɂ����X�͂��ł�ῂ�����̔���F�̎p�ɕϖe�𐋂��Ă����B��������Ɛቻ�ς�������������т̂��₩�ȗŐ������ɂ̂т₩�ŁA���̓�����͂��̖��ƈ���Ė��ɂ������̂悤�ł������B�z�K�~�n���͂�����ނ��鍂�{�b�`�R�̌������ł́A��ƁA�䍂�A���Ƒ����k�A���v�X�A��̎R�X���A�������������R�x���i�̐^�ł��ƌ�������ɏs���Ȃ��̎R�e���֎����Ă����B
�z�K�����J�̃C���^�[�`�F���W�ō�����������A���̂܂܂����ɍ��{�b�`�R�ɏオ��ΎO�S�Z�\�x�̎R�x�p�m���}���y���ނ��Ƃ��ł���̂͂킩���Ă������A���̓�����͂�������킯�ɂ������Ȃ������B�䂪���Ԃ̌㕔�ɂ͉ߓ������ōÂ��ꂽ�n�ӏ~�攌�̌W�o�W��i��\���_���ς܂�Ă�������ł���B������ȊG����ዷ�܂ʼn^�сA�����ɕԋp����̂����̓��̎��̐Ӗ��ł������B���N�ɂ킽��t�������̂悵�݂������āA���܂��|����Ȕ�����Ƃ�K�v�Ƃ��Ȃ��ꍇ�Ȃǂɂ́A�n�ӂ���̊G��ڂɗa�����ĉ����܂ʼn^�肷�邱�Ƃ�����B���̓������܂��܂�����Ȗ�ڂ������ĎԂ𑖂点�Ă���Ƃ��낾�����B
�m���X�g�b�v�Őz�K��ʉ߂��ɓߒJ�ɓ���ƁA�Ăэ���ɔ����A�Ȃ��A���v�X�A�p���������B���P�x�A�k�x�A�Ԃ̊x�A�_���x�A�ԐΊx�A�r��x�ȂǕW���O�烁�[�g�������A�Ȃ������ނ������A�e�����������L�l�͂����Ă��s�ς̈��ɐs����B������ӂɍ���������ƁA���x�͂�������ɒ����A���v�X�̖���ؑ]��P�x�̑傫�ȎR�e�������Ă����B�s���V���w���̓���A�ď�ɂ͍��R�A���̍炫�������̒����̐���~�J�[����т͐�ɕ����Ĕ���ɋP���A�͂�^�~�̌������������܂��ւƕϖe�𐋂��Ă����B
���X�Ǝԑ��𗬂�䂭�������R�x���i�ɂ݂Ƃ�Ȃ��玄�͉����Ƀn���h���������A�C�����悭�A�N�Z���ݑ������B�u�D���������v�Ƃ͂������̂́A���̎��܂ʼn����������������̂��̂������̂�����A���������N���肩���Ă���Ȃǐ_�Ȃ�ʐg�ɒm��悤�̂��낤�͂����Ȃ������B
���q�p�[�L���O�G���A���߂�����Ɍb�߃g���l�����߂Â��͂��߂����������Ǝv���A�ˑR�A�p�V���Ɖ������e����Ԃ悤�ȉ��������B��u������Ƃ͎v�������A�H�ʏ�̏����Ȉٕ������������˔��Ń{�f�B�ɂԂ����������������̂ŁA�����ċC�ɂ��������̂܂ܑ��x�𗎂Ƃ����ƂȂ����s���������B���ꂩ��قǂȂ��Ԃ͑S�����E�Z�L�����[�g���̌b�߃g���l���ւƓ˓������B�E�C�[�N�f�C�Ƃ������Ƃ������Ă����s�Ԃ͂����Ȃ��A�g���l�����̎Ԃ̗�����X���[�Y�������̂ŁA�O�����䂭�Ԃ̔�����ǂ������Ȃ��玄�͋C�����悭�A�N�Z���ݍ��B
���̂Ƃ��ɂ��łɈُ��m�点��x�������_���Ă����̂�������Ȃ����A�����g���l���̒��ɂ����đO���𒍈Ӑ[���ɂ݁A�S���[�g���قǐ�𑖂郏�S���̐Ԃ��e�[�������v�Ɏ������W�����Ă������Ƃ������āA�s�o�ɂ����̂��Ƃɂ͂܂�ŋC�����Ȃ������B���Ƃ��x�����̓_���ɋC�Â����Ƃ��Ă��A�Ƃ肠�����Ԃ͕S�L�����鑬�x�ʼn����ɑ����Ă����̂ŁA�����ɂ͉����N�������̂����f�����Ȃ������ɈႢ�Ȃ��B�܂��A�}篎Ԃ��~�߂��Ƃ��Ă��A�ꏊ���ꏊ�����������ɒǓ˂����댯��������A���㏈�����ӂ��߂Ď��Ԃ͐[�����ʓ|���̂����Ȃ��W�J�ɂȂ��Ă������Ƃ��낤�B����ɁA���̎��_�ł͂܂��m�炸�ɂ������A�~�߂悤�ɂ��Ԃ̂ق����������ɂ͎~�܂��Ă���Ȃ������낤����A�O���̎Ԃ��a�������ŋ}�ɑ��x�𗎂Ƃ��Ă�����Ǔ˂͔������Ȃ������ɈႢ�Ȃ��B
���ٕ̈ςɂ��C�Â��ʂ܂܂Ɍb�߃g���l���𑖂蔲�������́A���̒���ɁA���E�ɑ傫���J�[�u���Ȃ��璆�Ð���ʂւƉ���}��ɍ������������B�����Ƃ������Ƃ������āA�����S��\�L���قǂ̃X�s�[�h���o�Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�傫�ȃJ�[�u�̎�O�őO�����s���Ԃ����x�𗎂Ƃ����̂ŁA����ɍ��킹�Ă�������u���[�L�B�Ƃ��낪�Ȃ�ƁA�u���[�L���܂�ō쓮���Ȃ��̂��I�\�\�����狭������ł݂Ă��u���[�L�y�_���̓s�N���Ƃ����Ȃ��̂������B�����Ƃ����܂ɔ����Ă��������т̃K�[�h���[������O�ɂ��āA���̐g�͍̂d�����A�u���ɔw����������B
�������A���̐l���A�����K�����邩�킩��Ȃ��B�́A�m�l�Ƀv���̃J�[���[�T�[�����āA���͔ނ���V�є����ő��s���x�𗎂Ƃ����ɃJ�[�u���Ȃ���e�N�j�b�N������������Ƃ��������B�n���h�������E�ɏ����݂ɐU��Ȃ���A�u���[�L�ނ����ɃA�N�Z�����قǂ悭���ݍ���ŁA���S�͂Ƌ��S�͂̃o�����X�𗘗p���Ȃ���J�[�u���Ȃ��肫��̂ł���B�e�P�̃��[�T�[����������Ă��邠�̃n���h���������v�������ׂĂ��炦�悢���낤�B�ӊO�Ɏv���邩������Ȃ����A�n���h�������E�ɏ����݂ɐU��Ȃ���A�N�Z����ʼn�������ƎԂ����肵���܂��J�[�u���Ȃ��邱�Ƃ��ł���̂��B
�m�l�ɂ��̃e�N�j�b�N������������Ǝ��ۂɉ��x���̌����A���̃R�c�����͓ۂݍ���ł����������ŁA�^�悭����l�ɐg�̂����������B�����������݂Ƀn���h����U��Ȃ���v�����ăA�N�Z���ݍ��ނƁA�K�[�h���[���Ɍ��˂��鐡�O�łȂ�Ƃ����̃J�[�u���Ȃ��肫�邱�Ƃ��ł����̂������B�J�[�u���Ȃ���I��������Ɏl�A�܃��[�g���̋����܂őO���̎Ԃɐڋ߂������A�����ł������܃M���𗎂Ƃ��G���W���u���[�L�����������̂ŒǓ˂̂ق��������ɂ��B�����ł̃J�[�u���s�̃e�N�j�b�N��������Ă��Ȃ�������A���܂���n�Ӊ攌�̊G��Ƃ��ǂ��O�V���O�V���ɂȂ��Ă�����������Ȃ��B
�������܃n�U�[�h�����v��_�ł����A�G���W���u���[�L�ƃT�C�h�u���[�L�p���Ȃ���H�����̂Ƃ���������\�L���قǂő��s�����B�x�������S���_��������ԂɂȂ��Ă���ɋC�������̂͂��̂Ƃ��������B�u���[�L�I�C���n���̃p�C�v���������j���̂�������Ȃ��Ǝv�������A�Ƃ肠�����Ԃ͓����̂ŁA�Ŋ�̌b�߃T�[�r�X�G���A�܂ł��̂܂܂Ȃ�Ƃ����s���Ă݂邱�Ƃɂ����B���ƂŔ����������炷��ƁA�r���ŃG���W�����I�[�o�[�q�[�g���Ă����������Ȃ���Ԃ������̂����A���܂��ܑ�C�����Ⴉ�������ƂȂǂ��K�������悤���B�r���̒��Ð�̃C���^�[�`�F���W�ł���悤���Ƃ��l�����̂����A�u���[�L�̂����Ȃ���Ԃŗ��������Q�[�g�܂ł�����A��ʓ��ɏo�Ă���Ή����u���Ƃ낤�Ƃ���Ƃ������Ėʓ|�Ȃ��ƂɂȂ肻���������̂ŁA���̂܂ܓ�\�L���قǂ�T�d�ɑ���Ȃ�Ƃ��b�ߒJ�T�[�r�X�G���A�ւƂ��ǂ�����B
�����ɃG���W�����[�����J���Ă݂�ƁA�Ȃ�Ƃu�x���g�̈�{���o���o���ɂȂ��Ă��܂��Ă����B����_���͂����������Ă���̂����A�����̌����łu�x���g���ˑR�ؒf����Ă��܂������̂炵���B�b�߃g���l���ɓ����O�Ńp�V���Ƃ������������̂́A���̃x���g���ؒf�������炾�����̂��B�u�x���g�����Ɨ�p�t�@�����~�܂��ăG���W�����ߔM�������łȂ��A�t�b�g�u���[�L���쓮����������|���v�������Ȃ��Ă��܂�����A�ˑR�Ƀu���[�L�������Ȃ��Ȃ����̂����R�̂��Ƃł͂������B����ɂ��Ă��A�u�x���g����Ă��獂�����s�Ōb�߃g���l���ɓ���A�g���l�����������Œʉ߂��A�u���[�L�ُ̈�ɋC�Â��Ă���������Z�\�L���قǂœ�\�L���߂����ꂽ�b�ߒJ�T�[�r�X�G���A�܂ő������Ƃ����̂ɁA�G���W�����I�[�o�[�q�[�g���Ȃ��������̈��^�̋����ɂ͉�Ȃ�����������悾�����B
�b�߃T�[�r�X�G���A�̃K�\�����X�^���h�ł͏C���s�\���Ƃ����̂ŁA�i�`�e�ɘA�����Ƃ�A���p���Ƒ�Ԃɍڂ��Čb�ߎs���̊g���^�̃T�[�r�X�H��܂ʼn^�����Ă��炢�A�����ŏC�������Ă��炤���ƂɂȂ����B���Ƃɂ������b�ߎs�ňꔑ���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ɗo��������̂����A�K���O���Ԃقǂ���Ό����p�t�@���x���g�����邱�Ƃ��ł���Ƃ������Ƃ������̂ŁA�T�[�r�X���[���Ŗ{��ǂ�t�߂���������肵�Ďl���Ԃقǂ��߂����A�����ɏC�����I���̂�҂����B
���łɏ\�����L���𑖔j�����䂪���Ԃ́A�������Ă܂��̏Ⴉ��l���Ԍ�Ɋ�Ղ̕����𐋂����̂������B�ዷ��ђ��̓n�Ӊ攌�̃A�g���G�R�����ɓ��������̂͌ߌ�㎞���ɂȂ��Ă��܂������A�Ƃ��������M�d�ȍ�i��ԋp����Ƃ�����C���ʂ������Ƃ��ł������A�����g���Ȃ�Ƃ������ł��B�ԂőS���𑖂����Ă��邱�Ƃ������āA�����ȂƂ���A�����Ƃ����ڂɑ������̂͂��ꂪ��x���x�ł͂Ȃ��B�ق��ɂ��ߋ����x���M�����Ȃ��悤�ȑ̌������Ă��邪�A����܂ł̂Ƃ���Ȃ�Ƃ������ɐ������тĂ��Ă͂���B
���܂͂������胊���b�N�X�����C���ɂȂ�A�R�����̒g�����R�^�c�̂Ȃ��ł��̌��e�������Ă���B���̔w��ɂ͊����ԋ߂ȓ�S�l�\���̑��u�J�̑��v�̑�L�����o�X���������Ă��āA��ʂ����ς��ɕ`���ꂽ�攌�䂩��̐��[���R�X���A�L�[�{�[�h��@�����̎p���̂܂܌����낵�Ă���B���̓������{���̎�����o�Ďዷ�̂��̃A�g���G�Ɏ���܂ł̏ɂ�����Ƃł������������Ă�����A���͂��̉攌�̑��ƑΖʂ��邱�Ƃ͂Ȃ�������������Ȃ��B���Â��l�Ԃ̉^���Ƃ������͕̂s�v�c�Ȃ��̂ł���Ǝv���B�^���ǂ��̂������̂��͂悭�킩��Ȃ����A�������Ă܂����͐�������Ȃ��C�܂���ȗ��H�ɐg���ςˁA���̖͂��f��������݂��ɂ��̕��Q�L���Ȃ��Ԃ葱���邱�ƂɂȂ����̂������B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2002�N12��11��
���[�X�g�Z���[��Ƃ̋Y��
����o�ŎЂ���˗����ꂢ���l�S���߂��̌��e���悤�₭�����I�����Ƃ���ł���B�Ȋw�N�w�̍�������e�[�}�ɂ������e�����������ɁA�������������v�l�\�͂Ȃǎ������킹�Ă��Ȃ��g�ɂ���ߔN�ɂȂ��n�[�h�Ȏd���ł͂������B����ɁA���̂Ƃ��낸���ƁA�y���ʕ�����������Ԃ���X�������Ă����̂Łi�Ƃ����Ă��A���̂`�h�b�̓ǎ҂̕��X�����낻���ɂ��Ă�������͂���܂���̂ŁA���̓_�͌���Ȃ��悤�Ɂj�A�ア�]���X���܂��܂��ӂ₯�Ă��܂��Ă��āA�[���v����O�ꂵ�����Ȃ�v���錴�e�Ȃǂ�e�ՂɎ��M�ł����Ԃł͂Ȃ������B������A�悯���Ɏ��M��Ƃ͑�ς������B
����ł��Ȃ�Ƃ��E�e�ɂ܂ő������邱�Ƃ��ł����̂́A������x���g���������肵��������Δ���Ȃ��{�ł����s����̂͂�Ԃ����łȂ��Ƃ���o�ŎЃT�C�h�̈ӌ��ƁA�S���ҏW�҂̂ЂƂ����Ȃ�ʔM�ӂƂ����������炾�����B�܂��A���N�Z���ɂ��̏o�ŎЂ���ٖ�̊�u�n���̖��p�t�����v�����s���Ă�������ۂɁA���͂������Ƃ����������e�������Ƃ����Öق̖݂����Ȃ��̂��������Ă��܂��Ă������Ƃ����܂ЂƂ̗��R�������B�i���Ԃ̂������2002�N6��19���t�o�b�N�i���o�[���Q�Ƃ��Ă��������j
���܂ǂ��Ȋw�N�w����݂̖{���o�ł��Ă���悤�Ƃ����̂�����A���[�X�g�Z���[��Ƃ̐g�Ƃ��Ă͕���̂�����؍����ł��Ȃ��̂����A�v�X�ɏ����Ȕ]�����Ƃ��Ƃg�������Ƃ������āA���܉䂪�g�͈��̋��E���ɏP���Ă���B�����͍��l�߂Ėʓ|�Ȏd���ȂǓ����͂���C�ɂȂ�Ȃ���ԂȂ̂��B
����ȋC���̉����������āA�[���v����l�@�̂Ƃ��Ȃ������N�w��Ȋw���_����݂̌��e���M�͂������̂ւ�ōŌ�ɂ������ƕҏW�҂ɍ�����ƁA�u���₠�A����Ȃ��ƌ���Ȃ��ł���������v�Ƃ����Ȃ߂��������B��X�ǂ��Ȃ邩�͂킩��Ȃ��̂����A�ډ��̂Ƃ���A����ȕ��̐S���I�Ɏ�����������Ă��邱�Ƃ����͊ԈႢ�Ȃ��B
�b�͔�Ԃ��A���ܕ{���s�̐��U�w�K�Z���^�[�ł́A��N�������R�[�f�B�l�[�g�y�юi��i�s���ϑ�����Ă���H�̍u�����J����Ă���B�����V�������{�ЎЉ�f�X�N�A���_���ψ����o�Č��݂͒����V���ҏW���̓��X������ɂ͂��܂������N�̍u�����A�\�����̕]�_�Ƌڑ�r���ɂ��ŏI�u���Ŗ������Ƃ������ƂȂ�B�O��̏\����́A���Y�t�H�Б��o�ŋǒ��̕������O������}���Ắu�x�X�g�Z���[�ɂ݂�Љ�ہv�Ƃ����e�[�}�ł̍u���������B�T�����t�ҏW���A���Y�t�H�ҏW�����o�Č��E�ɂ��镽������́A���R�Ȃ���x�X�g�Z���[����̒B�l�̈�l�ŁA���낢��ȑ啨��ƂƂ̕t�������������B����ȕ�������������Ă��Ă��A�{�̔���s����I�m�ɗ\�����邱�Ƃ͎���̋Ƃł���Ƃ����B
���ł�����q�ׂĂ����ƁA���܂��������\�N�ȏ�O�̂��ƁA���N�̗F�l�ł�����ڑ�r���˗����A�|�A���J���[���́u�Ȋw�Ɖ����v����сu�Ȋw�ƕ��@�v�Ƃ�������̖{���e�L�X�g�ɁA�Ȋw���_��Ȋw�N�w�Ɋւ��邩�Ȃ�n�[�h�ȘA���u�`���������Ƃ��������B�ڑ�̂ق��A�]�_�Ƃ̕đ�d�����ʖؖ��������߂�u�ނ̉�v�Ƃ�������̃����o�[���Ώۂ̍u�`���������A�������Y�t�H�Ђ̎�蒆���Ј�������������������܂��܂��̃����o�[�̈�l�������B��������Ƃ͂��̎��ȗ��̕t�������ł���B
�啨��ƂƂ̂��Ƃ��o�ŋƊE�̂��̎肱�̎�̐헪�ȂǁA�ƊE�ɂ��Ă̕�������̗��b�͎��ɖʔ��������̂����A�b���Β����قǂɎ��Ȃǂ̓x�X�g�Z���[��ƂƂ͖����ȑ��݂ł���ƒɊ������������ł������B�����܂ł͂����肻�̂��Ƃ�������ƂȂ�ƁA�c�铹�̓��[�X�g�Z���[�ɓO���邵���Ȃ��̂����A�悭�悭�l���Ă݂�ƁA�ق�Ƃ��̈Ӗ��ł̃��[�X�g��ƂɂȂ邱�Ƃ͂���܂��Ȃ��Ȃ��ɓ�����ƂȂ̂��B
�Ƃ肠�����A���̍�Ƃ̖{���Œ����͏o�ł����̂łȂ���ȂȂ�Ȃ��B�Ƃɂ����{���o�ł���Ȃ����Ƃɂ͍�ƂƂ͂����Ȃ����炾�B�{���o�ł��ꂽ�����ň��������Ȃ��Ƃ����̂��p�[�t�F�N�g�ȃ��[�X�g�Z���[��ƂƂ������ƂɂȂ�̂��낤���A��Ɩ{�l���Ӓn�ł�������炢�͔������낤����A�����ɂ͂܂����̂悤�Ȃ��Ƃ͋N����Ȃ����낤�B�������Ƃ���A���[�X�g�Z���[�̃��[�X�g�Ԃ�̊�Ƃ��Ă͂��������ǂ̂悤�ȃ��x����z�肵�Ă����悢���̂Ȃ̂��낤�B���[�X�g�Z���[��Ƃ����F���鎄�̏ꍇ�ł��A���Ŕ��s������畔���炢�̍Œ�C���̎d�����������Ƃ͂�����̂́A�K���Ƃ����ׂ����A���ł�����c�����Ƃ����o���͂���܂ł̂Ƃ��낢���ǂ��Ȃ��B
�l�N�]�ɂ킽���Ė��T�x�݂Ȃ������Ԃ��Ă������Q�L�̌��e�͓�琔�S���ɂ̂ڂ��Ă���B�G���ɒǂ���܂܂ɁA�������������̂܂܂ɂ��Ă��邪�A�Ȃ��ɂ͂����炩�܂Ƃ��ȕ��͂����邱�ƂȂ̂ŁA���������炢�͐������đ����͂܂��Ȉ��������Ă��炦��o�ŎЂ�T�������Ƃ͎v���Ă���B����̍u���I����A����������w�܂Ō�����Ȃ���A�����������璩���ŏ��������e���Y�t�H�Ђ���o���Ă��炤�Ȃ�Ă��Ƃ����肩�ȂȂǂƈ�����k���l�������A�\�����̗��Ђ̓���W���炷��ƁA������Ȃ�ł���k�������Ƃ������̂��낤�B�܂��A���Ƃ�����Ȃ��Ƃ����悤�Ƃ��Ă��A�����܂���O������H���Ă��܂��̂������ɂ͈Ⴂ�Ȃ��B
�̂���̒m�l�A�F�l�A�����q�Ȃǂő�V���Ђ���o�ŎЂȂǂɋΖ�����҂Ȃǂ͂�������ɂ͂���̂����A���̂悤�Ȍl�I���ۂ���݂̃c�e��R�l�𗊂��Ď����̍�i�����s���Ă��炤�悤�Ȃ��Ƃ͐��������čD���ł͂Ȃ��B���[�X�g�Z���[��Ƃƌ����悤�������܂����A�����܂ł���i�{�ʂ̕]�������Ă����Ƃ���Ǝd�������������A���̂悤�ȑ��肪����Ȃ炻�ꂪ�����m��ʏ��o�ŎЂł����������ɍ\��Ȃ��B����ȂƂ����������Ȃ��Ƃ���A���C�^�[�Ƃ��Ă̌Ȃ̗͗ʕs���ƒ��߁A���Ȗ����̏Ƃ��Č��e�����̂܂R�ς��ĕ����Ă������A�����Ȃ���ΕM��܂�݂̂ł���B
�u�}�Z�}�e�B�b�N���Q�L�v
2002�N12��18��
�v�X�̐�i�F�ɑz������
�@�Ⴊ�~���Ă���B�e���r�Ȃǂł�����Ă���悤�ɁA�����ŏ\�\���O��ɐϐ���݂�̂͋v���Ԃ�̂��Ƃł���B�\�N�قǑO�܂ł͐������ƂȂ�ƂȂ��킭�킭�����C���ɂȂ��Ă������A�ߍ��́A�u�Ⴉ���c�c�A��������O�ɂł邪�Ȃ�ƂȂ��������Ȃ��v�ȂǂƂ����C�����̂ق�����ɗ����A�ˊO�ɏo�錈�f������܂łɂ�����Ƃ������Ԃ�������悤�ɂȂ����B���ꂪ�A�u�Ⴉ���A�O�͂Ђǂ��������낤�Ȃ��c�c�A�X�g�[�u�����A�R�^�c�ɓ����ă{�[�b�Ƃ��Ă���̂������c�c�v�Ȃ�Ă��ƂɂȂ��Ă�����A���̐l�������낻��I��肪�߂Â����Ƃ������ƂɂȂ�̂��낤�B�K���Ƃ������A�ډ��̂Ƃ���͂܂������܂ł͂����Ă��Ȃ��B
�@���E�I�ȑ�C���̏㏸���`������ߔN�ɂ����Ă͂����Ԃ�Ə�����Ă��Ă���̂��낤���A���������w�����������܂ł́A�썑�������̗����ł����܂ɂ͐Ⴊ�~��ς������B���w�Z�̍Z��ŐႾ��܍���������ፇ��������肵�Ă͂��Ⴌ�܂�������ƂȂǂ����܂ƂȂ��Ă͂����ւ�ɉ��������B�������~�肵�����߂Ă��邤���ɁA�Ȃ����ˑR���͂���ȉ������̏�i��z���o�����B
�@��������������͓��V�i�C�ɕ����ԗ����̂ЂƂŁA�����������ؖ�s�̐����l�\�L���قǂ̂Ƃ���ɂ���B�F�{���V�����ɂ��鋍�[�s�̓���O�\�L���]�̊C��Ɉʒu���Ă���Ƃ������ق����킩��₷����������Ȃ��B�^�~�ɑ嗤���琁����k���̋G�ߕ����܂Ƃ��ɂ�����ʒu�ɂ��邩��A�썑�̓��Ƃ͂����Ă��A���̋������Ȃǂ͌��\���������L��������B�~�R�o�R��~�G�̖k�����s�ȂLjꎞ�I�ȃP�[�X���̂����A����܂ł̐l���̒��œ~�̎��������Ƃ������Ɗ������̂́A�ӊO�Ȃ��Ƃɂ��̍����ł̏��w�Z����Ȃ̂ł���B�������A�~�̕��ϋC���̒Ⴓ���炷��Ɠ����𗣂�Ĉȗ���炵�Ă��������e�n�̂ق��������Ɗ��������͂��Ȃ̂����A�����Ƃ��Ă͂��̍��̊�����������L���Ɏc���Ă���B�ނ��A�������������Ƃɂ͂���Ȃ�̗��R���������̂ł͂��邯��ǂ��c�c�B
�@�����A�䂪���͂܂������Ԃ�ƕn������������A�����̏��w�Z�̍Z�ɂȂǂ݂͂Ȗؑ��ŁA��������O����̌Â����������������B�G�A�R���f�B�V���i�[�Ȃǖ����̎���̂��Ƃ�����A�Ă��������B�e�n�̓����̍Z�ɂ́A�݂ȕ��ʂ��̂悢�Č����̑���ɂȂ��Ă����B���������͂������������Ԃ��炯�̈�ʂ̔���A�����Ċ����֎q���ÂтČ����炯�����炯�������B���̍��̍����ł͗[�����痂���܂ł������d�������Ȃ��Ă��Ȃ���������i���̂�����́A�Ȃɂ�炢�ܘb��ƂȂ��Ă���k���N�̓d�͎���Ƃ�������ł���j�A�w�Z�̋����ł͎��R�������𗊂�ɂ��Ď��Ƃ������Ȃ��Ă������̂ł���B
�@���R�����ő���ɍ̌����邽�߂ɁA�����̍��E���ʂɂ͎l�p���Ĕ��������K���X���������͂߂��K���X�˂��������ĕ��ׂ��Ă����B�Ƃ��낪�A�Â��ؐ��̑��i�q�͘c�菝�肵�Ă��邽�߂ɁA�����̃K���X���̂�����Ƃ��낪���Ԃ��炯�ɂȂ��Ă���A�܂��A�펞���ӏ����͊��ꂽ�܂ܕ��u����Ă���Ƃ����̂�����ł������B�������g�p����Ă��鑋�K���X�݂͂Ȃ����������̂��肾�����B
�@����Ȃ킯������^�~�ɂȂ�ƌ��ԕ����������݁A�܂������łȂ��Ă��������͂���Ɨ₦�킽�����B�������A���̊����ɓ����̓��̕n�������������������̔��Ԃ��������B���k�����͋������ł݂͂ȗ����������B�������A�C���ȂǗ������Ƃ͋�����Ȃ��������A���Ƃ��������ɂ��C���ȂǂȂ����k���قƂ�ǂ������B�������w�Z���w�N�ɂȂ鍠�܂ł͌C�������Ă��鐶�k���̂��̂������킸���ŁA�^�~�ł������Œʊw����̂��������ʂ̂��Ƃ������B���Ƃ��C�������Ă��Ă��A����𗚂��Ēʊw����̂��݂�ꂳ���������̂ł���B
�@�����Z��ł����Ȃ��钩����A���Ƃ��n�ʂ�������悤�ȓ��ł����Ă����t�ȊO�͑S�Z���k�����A�̈�̎��Ԃ͂����ɂ�����A�^����Ȃǂ̂悤�ȍÂ����Ȃǂ��݂ȗ����ł̎Q�����`���Â����Ă����B���̎���݂͂Ȃ������������A���߂��͂Ȃ͂��e���Ȃ��̂Ŗh�����Ȃǖ]�ނׂ����Ȃ���������A�₦�₦�Ƃ��������ɂ����ƍ����Ă��邾���Œܐ�₨�K�̂ق����犦�C������[���ƑS�g�ɓ`����Ă������̂������B
�@�w�Z�ŗ������`���Â����Ă����̂́A�L�����������������Ƃ������O�̂ق��ɁA�����̐��k�����̐�������ւ̔z���Ȃǂ��Ȃ���Ă�������ł�����̂��낤�B�����ꕔ�̐��k�������C��C���𗚂��Ă�����s�������Ȃǂ������ĂȂɂ��Ɩ�肪�������ɈႢ�Ȃ��B�u���ǂ��͕��̎q�v���́u���������v���̂Ƃ��������t�������͂����Ԃ���Ă͂₳�ꂽ�肵�����A�Ӓn���ȉ��߂�����A�{���̂Ƃ���́A�u���ǂ��Ȃ���A���̂��炢�̊����͉䖝�����I�v�Ƃ��A�u�n�R�ł��d���Ȃ�����撣���ȁI�v�Ƃ��������悤�Ȃ��Ƃ������Ƃ��l�����Ȃ��͂Ȃ��B
�@�Ƃ��������A���̂悤�ȏ��ł̊w�Z��������������A�^�~�Ȃǂ͎��ƒ��Ɏ肪��������ʼn��M�����܂����ĂȂ����Ƃ������������B���R�A�����̎w����������Ŋ��o���Ȃ��Ȃ邱�Ƃ���������イ�������B���ƒ��ɗ���◼���̎w���������C�荇���A�Ȃ�Ƃ����Ă������w���L�����o�����߂����ƕK���ɂȂ������ƂȂǂ��N���ɋL���̒��Ɏc���Ă���B�����Ƃ��A�ǂ�ȏ��ɂ����Ă������̒m�b�͗N���o�Ă�����̂ŁA�x�ݎ��ԂƂ��Ȃ�ƁA���k�����͂��݂��Ɍ������g�̂��Ԃ���������C�肠�����肷��V�т����낢��ƍl�������A���̏�𗽂������̂������B
�@�`���ɂ��������悤�ɁA����Ȃ�ɍ��Ƃ��Ă��܂��������ŁA���܂͌��\������ɂȂ��Ă��܂������A�썑�炿�ł���ɂ�������炸�A����N��܂ł͊����ɂ͋����ق��������B�Ƃ��ɁA����[���Ɛg�̑S�̂��₦���ނ悤�Ȋ����ɑ��ẮA�k���炿�̐l�X�Ȃǂ��������Ƌ���������������Ȃ��B�Ɠ��͖k�C���炿�����A�����̓~�̊����ɑ��Ă͂��܂ł����炩�Ɏ��̓K���\�͂̂ق��������B�k���͌ˊO�̉��x�͂ƂĂ��Ⴂ����ǁA�Ƃ̑��肪�~�����ɂȂ��Ă���A�̂���h����ɏ\���ȍH�v�Ɣz���Ƃ��Ȃ���Ă��Ă��邩��A���̂悤�Ȋ��ň�����l�X�́A�ĊO�A�����ɂ�����悤�Ȋ����ɂ͎ア�̂�������Ȃ���Ȃ��B
�@�Ⴂ���A�ϐ���̖k�A���v�X�ŖҐ���ɏP��ꑘ����������Ƃ��A���Ԃ̊F�����Ȃ�Ђǂ������ɂȂ����ɂ�������炸�A�������͖j�Ɍy���������������ł��݁A������قǂȂ��������Ă��̍��͂܂������c��Ȃ������B�э��ǂ��l��{���B���Ă������炾�Ƃ�����ꂽ�肵�����A������������A���̍����̓~�̊����ɏ������邽�߂Ɏ��R�ɑ̓��̖э��ǂ����B�����̂�������Ȃ��B�������Ƃ���A�����ł̏��w�Z�����ɂ����Ċ������������������Ƃ͂����ւ�ɗL���o���������Ƃ������Ƃɂ��Ȃ�B
�@�����̒ÁX�Y�X�𗷂���ɂ��Ă��A�ߔN�̏����w�Z�̌�����ݔ��͂����Ԃ�Ɨ��h�ɂȂ������̂��Ƃ������B���ƒ��Ɏ肪��������ʼn��M�����ĂȂ��Ȃ�悤�Ȃ��ƂȂǁA���܂ł͂ǂ�ȓc�ɂ̊w�Z�ł����ċN��������͂��Ȃ����낤�B�ł́A�̂ɔ�ׂ�Ɗi�i�Ɍb�܂ꂽ����ȋ�����̒��ŁA�����w�Z�̐��k�����̖{���I�Ȋ�b�w�͂����ꑊ���Ɍ��サ���̂��ƂȂ�ƁA���Ԃ��́u�m�[�v�ł���悤�ȋC�����ĂȂ�Ȃ��B
�@�n�����͂���������ǂ��A�A�t�K�j�X�^���̂��ǂ������̓��������ł���悤�ɁA�܂��c�����������������̏��w���̑o�Ƃ́A���m�̂��̂ւ̓�����߃L���L���Ɛ��P���Ă����ɈႢ�Ȃ��B�ł́A���ǂ������̓��̋P�������߂����߂ɁA���{�Љ�͂��܂����ǐ̂̂悤�ɕn�����Ȃ����ق����悢�Ƃ����̂ł��낤���H�\�\�u�C�G�X�v�Ƃ͂ǂ����Ă������Ȃ��Ƃ��낪���̖��̖��ȂƂ���ł���B�����̐i���̗��ꂪ�k�s�s�\�ł���悤�ɁA�����j�̎��Ԏ����t�s�����邱�Ƃ��܂��s�\�Ȃ��Ƃł���B����ɁA���܂��炻��Ȃӂ��ɐ̂��₽������������Ă݂Ă��A���m�ȃA�i�N���j�Y���Ɋׂ�̂��ւ̎R�ł͂��邾�낤�B����̖�����������ɂ́A���ǂ̂Ƃ��낻�̎���Ȃ�̒m�b�ƍH�v�ɗ��邵���Ȃ��B
