やがてゆく吾が奥津城(おくつき)か風寒き
信濃の野辺に昴きらめく(信州安曇野にて)
気の向くままにふらりと訪ねた真冬の安曇野は一面白い雪に覆われていた。安曇野の冬空にしては珍しいほどに空は晴れてわったっていたが、吹き抜ける風は心の奥底までもがたちまち凍てついてしまいそうなほどに冷たかった。峻険な北アルプスの山陰に太陽が沈むと、大気温はさらに下がり、それまで冬の野を凛として彩っていた光は、一帯の空が黄昏から宵闇へと移るなかでいっきにその輝きを失った。そして宵闇がどんどん深まるにつれて、冬の星座が夜空いっぱいにその存在をひときわ青々と誇示しはじめた。私の脳裏に「砥石で磨き上げたような星々の輝き」というメルヴィル作「モヴィディック(白鯨)」の中の一文が現実味を帯びながら甦ってきたほどだった。
煌き揺れるそれら美しい星々をなにげなく仰ぎ見るうちに、なぜか私は突然奇妙な幻想に捉われた。あるものは群をなし、またあるものはひとつだけぽつんと離れて明滅する星明りのいずれもが、頭上はるかなところに位置する天空の村々の民家の灯であるように思われてきたのである。そして、いつしか私はそれらの星々の輝きに不思議な懐かしさとでも言うべきものを覚えはじめたのだった。
その時の気持ちをいったいどう表現したらよいのだろう――そう、あえて一口に言えば、それら天の灯火の揺れ瞬く遠い遠い村々に、私というこの不可思議な存在のほんとうのルーツを発見しでもしたかのような懐かしさを感じたのだった。四十億年近く前にこの地球上のどこかに誕生し、現在の私の命の根源となった原初生命体のさらなる源を探しあてたような思いになったというのがより正確なところだったかもしれない。
そんな夢想に駆られながら、身を切るような寒さも忘れて冬空を見上げているうちに、天の奥にあってひときわ澄んだ光を発する群星が目にとまった。それは清少納言の枕草子にも登場する昴(すばる)だった。よく知られているように、「すばる」という呼称は「統(す)ばる」、すなわち、「ひとつにまとまる」という意味をもつ古い和語がもとになったと言われる。また、「すばる」に「昴」という漢字が当てられているのは、この星団のが中国では古来「昴宿(ぼうしゅく)」と呼ばれていたからである。
天文学の世界で「プレアデス散開星団」として知られる昴は、牡牛座の一等星アルデバランの近くにあり、肉眼では数個の青い星々の集団に見える。実際には120個ほどの恒星からなる星団で、解像度のよい双眼鏡などを用いれば70個前後の星々を確認することができる。距離は意外に近く、地球から410光年ほどのところに位置している。宇宙の中では新しい星に属し、誕生してからまだ6000万年ほどしか経っていないと考えられている。肉眼でも見えるいくつかの青白い星々は太陽の十数倍もの質量があって、その猛烈な活動のゆえに寿命はあと1000万年ほどであり、最後には超新星爆発を起こして宇宙に飛散し消滅すると予想されている。
もっとも、この晩の私にとっては、昴という散開星団についてのそんな天文学的知識などはどうでもよいことであった。安曇野の一隅に立って神秘的な輝きを放つ昴をじっと仰ぎ見ているうちに、いつしか私は、死後に自らの魂が行きつくところがあるとすれば、昴の瞬くあのあたりなのではなかろうかという夢想とも妄想ともつかないおもいへと沈んでいった。
私は、死んだあとのことは死んでみてからでなければわからないという不可知論者だから、べつに死後も自分の魂が存在し続けるであろうなどと信じているわけではない。ただ、もしもそんなことがありうるとするならば、この小さく愚かなおのれの魂の行き着き眠る奥津城(おくつき)、すなわち終の墓所となるべきに地は、昴の瞬くあのあたりこそが相応しいのではないかという気がしたのだった。そうすれば、昴をかたちづくる星々がやがて超新星爆発によって無窮の大宇宙へと飛散し消滅していくときには、私の魂もまた粉々になって母なる大宇宙の胎内に再び回帰していくことになるに違いないとも思われたからである。

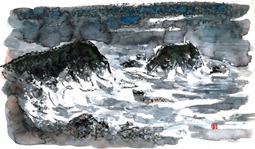
 RSS
RSS