石田がミサと再会したのは、それからさらに三年ほどが経った秋の終わりの頃だった。お互い何かと忙しく、なかなか再会の機会を持てずにいたのだが、ネダーマン夫妻が仕事の関係でたまたま上京するというので、その時ちょうど都合のよかった石田のほうもそれに合わせて東京へと向った。そして、夫妻の泊まっている有楽町のホテルのティー・ルームで待ち合わせた。すこし早目に着いた石田が本を読みながらしばらく時をやり過ごしていると、見るからにセンスのいいグリーンのコートを肩から軽く羽織るように着流した中年の女性が現れ、颯爽とした足取りで真っ直ぐに彼のほうへと近づいてきた。
むろん、それはほかならぬミサの姿であった。石田より一歳年長のミサはすでに六十の峠を越えていた。ただ、髪の毛にちらほら白髪が混じってはいたものの、その姿はまだまだ若々しさを内に秘めていて、四十代半ばくらいの年齢にも見えるほどだった。以前にくらべ全体的にかなり太った感じを受けはしたが、その身体からは長年にわたって世界を駆け巡った気丈な女性ならではの存在感のようなものが漂い出てもいた。
「タッツァン、ほんとうにお久しぶりだわね!」 先に言葉をかけたのはミサのほうだった。読みかけの本を閉じてテーブルに置くと、石田もすぐに立ち上がった。英国仕立ての上質のウールのスーツを着こなした石田もまた、もう六十歳になったとは思われぬほどにかくしゃくとして見えた。固い握手を交す二人には、互いの手の温もりを通して、二十年余にわたる波瀾に満ちたそれぞれの人生の歩みがじわじわと伝わってくる感じだった。
再びシートに腰をおろすと、石田はすぐさまミサに向かって毒舌を浴びせかけ始めた。ある意味でそれは相手に対する石田流の愛情の表現でもあったし、その点はミサのほうも心得たものだった。 「若狭の田舎の景色のいい海辺でジョンと二人杖を突きながら静かな隠居暮らしをしているのかと思ったら、結構まだしゃんとして世間を引っ掻きまわしている感じだよねえ。これじゃ閻魔様だって持て余してしまうわけだ!」 「そうそう、『縁間様』っていうわけなのよ、まだ縁をもつには間があると言う意味でね。タッツァンだってずいぶんと閻魔様から迷惑がられている風にも見えるけどね!」 「そりゃまあ、近頃こちらは周囲の人たちからドラキュラって呼ばれてる身なんだし、また自分でもそう称してるんだから、閻魔様から敬遠されてもおかしくはないさ」 「たしかに閻魔様がドラキュラを捌くことになったら困るわよね。地獄へ送ったりしたらドラキュラのほうは我が意を得たりとかえって喜んじゃうだろうし、天国へ送って蓮の花の上に坐らせてみたって様になんかならないしねえ……ふふふふふ」
折々手紙のやりとりをしたり、電話を掛け合ったりしていたこともあってのうえだったとはいえ、冒頭のそんな会話は、二十四余年ぶりに再会した二人の間で交されているものだとはとても思えなかった。とりとめもない掛け合いをそれからもしばらく続けてから、ようやく、ミサは日本に戻ってからの石田の生活ぶりについて問いかけた。
「じゃ、タッツァンはイギリスから日本に戻ったあとまた英会話学校を開いたんだ。憲兵隊に潰された上海時代のあの学校みたいに繁盛してる?……あの頃は五百名くらい受講生がいたわよね」 「日本に戻ってなんとなく一年ほどなく暮したあと、BBC日本語部にもう一度雇用してくれるように申請したんだけど、結局、返事がこないままになってしまってね……。まあ、時代の流れもあって、日本の若い現役の放送局員などを呼ぼうといようということになったらしいんだけど。それも二、三年ごとに人材の入れ替えをしながらね」 「そりゃBBCだってさ、和製のドラキュラなんかいらないわよ!」 「それで、東京でちょっとした英会話塾なんか開いて、あとは、大久保君や加島君から依頼される翻訳の仕事の手伝いなどを気の向くままにやったりしてたんだ。しばらくの間だったけど、映画の友の淀川長冶とも一緒に仕事なんかやってたよ。フランス映画部門の紹介などは僕が担当してね……」
「でもさあ、タッツァンが松本に移住したって知ったときはどういう風の吹きまわしかと思ったのよ。松本ってよくは知らないところだったけど、都会生活好みだったタッツァンがずいぶんと田舎に引っ込むことにしたもんだって……。ワーズ・ワースの世界にかぶれてしまったのかとも思ったわ」 「手紙にもちょっとだけ書いたけどさ、加島君が信州大学の助教授になって松本に移ったんで、翻訳の仕事の打ち合わせでちょくちょく信州にやってくるようになってね。そうこうするうちに、松本を中心とした安曇野一帯が気に入ってね……、加島君も勧めてくれたんで結局松本に住むことにしたんだよ」
「それで、仕事は順調なのね?……、どうせタッツァンのことだから、周辺のみんなを毎日煙に巻いて暮してるんでしょうけど!」 「最初のうちは、幼児の英才教育、例の『鈴木メソッド』で知られる鈴木慎一主宰の英語教室で英会話を教えてたんだけど、教育方針などで意見が食い違うようになってしまってね。それで独立してESSMを開設したんだよ。石田ドラキュラの吐く毒気に当たって幻惑されたせいなのか、近所の信大の教官夫人連中やその子供、学生などでESSMは結構盛況でね。あと、大久保君と加島君から頼まれる翻訳もずいぶんとやってるから、まあ、先のことはともかく、いまのところ生活にはそうそう困らない」
石田のそんな返答に聞き入りながら、ミサはしばし紅茶をすすり、ケーキを頬張ったあと、さらに尋ねた。 「それで、タッツァン、養子もらったっていうことだけど、どういう風の吹きまわしなの?」 「松本城で彼を偶然ハントしてね。まあ、のちのちのこともあるから、そろそろ二人で生活するのもいいかと思ってね、なにかと細々したことを手伝ってもらうということもあったりすしてね……」 「独り善がりでスノッブなタッツァンらしくないわよねえ!……、ドラキュラが聞いて呆れるわ!」 「実はね、佐々木家のほう……そう、養子の俊ちゃんの両親がね、いろいろ僕のことを伝え聞いてあれこれ調べたらしいんだ。それで、どうせなら息子を養子に貰ってくれないかという熱心な申し入れなどもあったりしてね。そこまで見込まれたのなら、まあ、この際だからそれもいいかと……」 「ふーん、そういうことだったの?……、怪しげなこと言って旅の途中の青年をたぶらかした付けがまわってきたみたいなものね」 「でもね、俊ちゃんはなかなかいい青年なんで、一緒に仲良くやってるよ」 「そうやって、その俊ちゃんとやらをドラキュラ二世にでも仕上げるつもりなの?」
すると、そんなミサの言葉を遮りでもするかのように今度は石田が問いかけた。 「それはそうと、ミサのほうはどうだったんだい?、まさか日本に舞い戻ってくるなんてねえ……、お互い腐れ縁とはいえ、よくもまあ!」 「細々話すと長くなるから今日はやめておくけど、私もいろいろあったわよ。ジョンの仕事の関係で、結構世界中を飛び回ってたわ。イギリスのほか、フランス、ドイツ、イタリア、アメリカとあちこちで長期滞在しながらね……。そして、行く先々でずいぶんいろいろな著名人に出会ったりもしたわ。もちろん、途方に暮れてしまうようなハップニングにもね」 「それにしても、ジョンと離婚なんかしないでよくここまでやってきたよね?」 「あの人、優れた能力がある割にはとても謙虚で穏やかだし、ともかく人畜無害だから……」
「でもさあ、人畜無害ったってさ、原発の仕事って下手すると人畜有害になってもしまうだろう、大丈夫なのかい? 死神の手先になってしまう惧れだってないわけじゃないだろうからさ!……まさか、ジョンと二人で東京まで放射能をばらまきに来たわけじゃないよね?」 「タッツァンはもう手遅れだわ。私とさっき握手した時に、いっぱい放射能をプレゼントしておいたから。でもさ、ドラキュラが十字架じゃなっくて放射能で参っちゃうようなら、それって世紀の大発見だわね」
そこまで言うと、ミサはまた紅茶をすすりながらしばし沈黙し、ケーキの残りをうまそうに平らげた。石田もそれに合わせるようにティー・カップを手にし、紅茶を口に含みながらさりげなくミサのほうを見やった。コートとお揃いのグリーンのスーツの着こなしも、品のいいアクセサリー類の纏いかたも実に洗練されていて、内心さすがだという思いがした。ちょっとした仕草や身振舞いにも日本人離れしたところがあり、しかもそれがすこしも厭味を感じさせないところなどは、外国人を夫にもち、長い海外生活を経験した者ならではのものだった。
いっぽう、そんな石田の視線に気づいたのか、ミサはそれをかわしでもするかのように再び口を開いた。 「原発の専門的な技術のことは私にはさっぱりわからないんだけど、夫のジョンはジョンなりに一生懸命だわ。原発が完成し操業が開始されるまで、すべてのことに責任があるわけだし、人命にも関わることだから、とても慎重に行動しているようだわ」 「それはそうだろうね。それにしても、ジョンが原発技術者だったなんて想像もしていなかったよ。そうと知った時はさすがに驚いたなあ」 「もちろん、スターティング・アップ・マネージャーとして日本に派遣される前も世界のあちこちで原発の建設に従事し、いろいろな経験を積んできたわけなのよ。ただ、若狭周辺には原発反対の人々も多いから、いろいろ神経を使うことも多いし、冷たい視線を浴びせられたり、原発建設中止を呼びかけるデモに遭ったりすることもあるのよ。なかなか難しい問題よね」
「それで、若狭での日常生活そのものにはとくに不便はないのかい?」 「もちろん、欧米とは生活習慣や生活環境が大きく異なってるし、手に入る食品類にもなにかと制約があったり違いがあったりするから、最初戸惑いもあったけど、もうずいぶんと慣れてきたわ。ジョンはもともと適応能力の高い人だし、それに彼、日本の風土や日本人の生活振りがすっかり気に入ったみたいだわ。私のリードもあってのことなんだけど、食べ物だって、いろいろな日本食を好んで食べるようにもなったことだしね。それにね、私が原発技術者の家族だとわかっていても高浜周辺の人々のほとんどはとても親切にしてくれてるわ」
「それで、ジョンの若狭での原発の仕事が終わったら、今度はどこに行くことになるんだい?……またイギリスに戻るのかな、それともウエスティング・ハウスの本社のあるアメリカかなのかな?」 「どうするかまだ先のことははっきり決めていないんだけど、ジョンは、日本での原発関係の仕事が無事に終わったら、そろそろ会社を辞めて余生をのんびりと過ごすようにしたいとも考えているみたいなの。イギリスの家だけでなく、既にフランスにも永住できるような別荘を既に入手してあるんだけど、そのほか日本にも住まいを確保したいと思ってるのよ。日本は私の母国だし、ジョンも日本がすっかり気に入ったらしくって、是非そうしたほうがいいって賛成してくれてるのよ」
「さすが、ブルジョワは違うなあ……。三カ国を股にかけての悠々自適の隠居生活かあ」 「信州安曇野のドラキュラになろうっていうタッツァンが何羨ましがってるのよ!」 ロンドンで別れて以来二十年余にも及ぶそれぞれの人生にまつわる珍会話は、こうしていつ果てるともなく続いたが、まるでそれは、ドラキュラと魔女との時空を超越した掛け合い漫談にも似た趣きがあった。

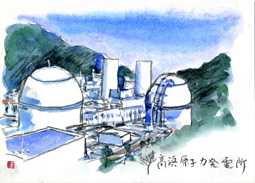
 RSS
RSS